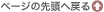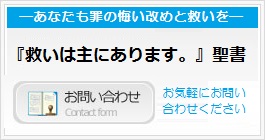説教:ガラテヤ人への手紙
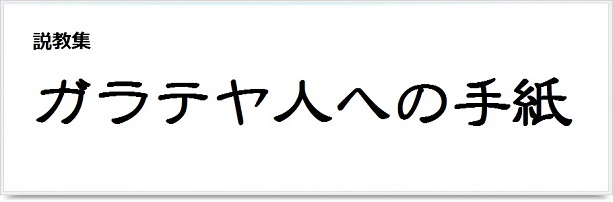
以前、礼拝で行なわれた「ガラテヤ人への手紙」における説教の文章を全文アップしました。ぜひ、神様のお書きになられた聖なる書物である聖書からのメッセージをお読みください。
ガラテヤ人への手紙1章1~3節(2015/11/22説教)
『使徒となったパウロ―私が使徒となったのは、人間から出たことでなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストと、キリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によったのです。―および私とともにいるすべての兄弟たちから、ガラテヤの諸教会へ。どうか、私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安があなたがたの上にありますように。』(ガラテヤ1章1~3節)
今週からは、ガラテヤ人への手紙(※2016/03/27追加)からの説教となる。この手紙は全部で6つの章と149の節(※①参照)があるが、一つ一つ詳しく見ていきたいと考えている。この手紙において、パウロは、律法の行ないによって義と認められるなどと主張する律法主義者どもに対抗し、彼らを念頭に置きつつ、受け身の信仰、(行ないによるのではない)信仰による義について力強く論じている。ここでパウロは、哀れな状態にあったガラテヤのキリスト者に対して、大胆かつ峻烈に語っている。(※大胆かつ峻烈に書かれているのは、パウロを通した書かれたガラテヤ書だけでなく、聖書のほかの巻についても同じことがいえる)もし自分の愛する家族が、ふざけた凶暴な者どもに襲われたりかき乱されていたりしたとしたら、その家族たちを助け出そうと激しくならない父親は恐らくいないことだろう。そのようにパウロも、愛する家族を危害から守ろうとする者のごとき心に満たされてこの手紙を書いたのではないかと私には思える。このパウロが兄弟姉妹に対してどれだけ熱心な思いを抱いていたかは、彼が書いた書簡を見たらよく分かるからである(※②参照)。愛する者たちが危機的な状況にあるというのに、なにも動揺せず、まったく穏やかでいられるような人がどこにいるだろうか。
①『使徒となったパウロ※2016/03/06追加―私が使徒となったのは、人間から出たことでなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストと、キリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によったのです。―』(1章1節)
まずパウロは自分の使徒的権威をここで主張している。彼は、自分が使徒になったのは、人間によるのではなく、ただ神によったのだと述べている。彼がこのように自分の使徒としての権威を神という至高の存在に結び付けることで、より彼の言葉には神的な輝きが帯びることになる。「パウロは神から遣わされた使徒だ。」ということが分かったのならば、パウロの言葉を聞く人たちは、より彼の言うことに熱心に耳を傾けることにもなろう。もし我々のところに、どこかの国の王から遣わされた立派な使節が訪ねてきたとしたら、我々はその人が王の命令のゆえに訪ねてきたというので、その人を尊重し、その人が言うことに注意することであろう。王の権威と命令のゆえに、その使節に対する我々の気持ちが引き締まったものとなるのである。パウロが自分のことについて「私は神の御心による使徒なのだ。」と述べるのも、これと似たようなものである。このパウロは他にも、ローマ書、コリント第一および第二の書、エペソ書、コロサイ書、テモテ第一および第二の書、テトス書においても、自分の使徒としての立場を主なる神とその御心に基づかせている(※③参照)。事実、パウロが使徒となったのは、神の聖なる御心によるものであった。
パウロはここで「私が使徒となったのは人間から出たことではない。」と述べているが、これは、パウロが召されてもいないのに自分自身の意志で勝手に使徒となったのではないということを示している。彼は、本当は召されていないのに勝手に使徒の名を名乗っている不遜な「にせ使徒」では無かった。また彼は「私が使徒となったのは人間の手を通したことではない。」とも述べているが、これは、主から直接的に使徒として遣わされたということを意味している。つまり、誰かほかの使徒がパウロに対して「あなたは使徒としてこれから歩みなさい。」と言ったので使徒となったのではなく、主が彼に任命されたからこそ使徒となったのである。牧師として歩む場合、その人には神から与えられた召命が必要であるが、それに加えて、人間から受ける按手も必要となる。それゆえ牧師として歩む場合、ある意味「人の手を通して」牧師として歩むことになると言えなくもない。しかし使徒パウロの場合、そのように人の手を通して使徒として歩むに至ったのでは無かった。
パウロはここで使徒的権威を読者に提示することによって、不遜な態度になり、愚かにも高圧的になっているのではない。つまり「俺は神からの使徒だ。お前らとは違うのだ。さあ、俺の前にひざまづいて俺の意のままに動け。俺は専制的な王で、お前たちは惨めな奴隷のごとき存在なのだから。」というような愛のない、高飛車な精神で手紙を書いているというのではない。『誇る者は主にあって誇れ。』(Ⅰコリント1章31節)とあるように、彼は主にあっては誇っていただろうが、自分で自分自身を誇るようなことはしていなかった。
この使徒という職務(使徒はギリシャ語ではapostolosであり、原義は「遣わされた者」である。)はパウロ以外に12人いたが、この職務における尊厳の度合いは、伝道師や牧師よりも上である。パウロは教会における職務について語っている箇所で、使徒職を一番最初に位置させている(※④参照)。聖なる教会とは、いにしえの預言者に加え、使徒の教説の上に建て上げられていると言われているのだから(※⑤参照)、その職務における重大性は測り知れないものがあると言える。また、使徒職が今のこの時代にもあるなどと勘違いをしている人たちがいるが、それは間違っており、今の時代にはもう使徒としての召しを受ける人は存在していない。「私はキリストの使徒として召されています。」などと言いだす人がいたとすれば、その人の口は切り取られるべきであろう。何故なら、滅びへと落ちていったイスカリオテのユダの代わりの使徒を決める際、代わりとなる使徒は、『いつも私たち(※つまり使徒)と行動をともにした者の中から』(使徒の働き1章22節)決められなければならない、と言われているからだ。つまり使徒とは、主イエスとその奇蹟とをその目でまざまざと確認した人物でなければいけないのである。それゆえ、今の時代において、主にあって「使徒」であると正当に名乗れる人物は存在していない。
ここに『使徒となったパウロ』と書いてあるが、彼は以前は使徒では無かったのに、『イエス・キリストと、キリストを死者の中からよみがえらせた父なる神』のゆえに使徒とされたのである。使徒になる以前のパウロは、教会を迫害し、クリスチャンたちを死に至らせたほどの凶暴な反キリスト、神の敵対者であったのだが、神の大いなる憐れみと恵みによって使徒とされたのだ。この神の憐れみと恵みによるキリストの使徒パウロが、聖霊により、惨めな状態にあったガラテヤの聖徒たちに書いたのが今回の説教箇所における「ガラテヤ人への手紙」である。
パウロはこのガラテヤ人に対する手紙の中で、自分が使徒となったのは、『イエス・キリストと、キリストを死者のよみがえられた父なる神によった』と書いているが、パウロはこう言うことも出来た。「私が使徒となったのは、この世界を造られ、保ち、今も全ての生物を恵み深く養っておられる神によったのです。」しかしパウロはこのようには言わず、「キリストとキリストを蘇らせた父なる神によった」と述べている。これは、パウロの心にキリスト・イエスについての思いが充満していたことを意味している。主は『心に満ちていることを口が話すのです。』(マタイ12章34節)と言われたが、パウロの心にキリストについての思いがあったからこそ、このようにキリストとその御父について記述しているのである。
さて、パウロは神の御心によって使徒とされたのだが、救われる以前のパウロは、まさか自分がキリストの使徒になるなどとは夢にも思わなかっただろう。救われる以前のパウロは、クリスチャンであれば『男も女も縛って牢に投じ、死にまでも至らせた』(使徒の働き22章4節)ほどの人物であった。しかし、神の御心は教会を迫害していたパウロが使徒になることであり、その御心のゆえにパウロは使徒となるに至ったのである。これはイザヤ書にこう書いてある通りである。『わたしの思いは、あなたがたの思いと異なり、わたしの道は、あなたがたの道と異なるからだ。―ヤーヴェの御告げ。―天が地よりも高いように、わたしの道は、あなたがたの道よりも高く、わたしの思いは、あなたがたの思いよりも高い。』(イザヤ55章8~9節)この聖句から分かるように、神は、我々ちっぽけな人間が考えもつかないような考えを持っておられ、その考えに基づいて我々が想像もしなかったようなことをなされる。1517年に、ルターは腐敗していたカトリック教会の免罪符に対して批判をしたが、ルターは単に免罪符を攻撃しただけであって、大きな反響をひき起こそうとか、宗教改革運動を始めようとか、そういった思いはまったく持っていなかった。しかし神は、このルターの批判を大いに用いられる御計画を持っておられ、この免罪符に対する批判を通して宗教改革の幕開けとさせられた。カルヴァンも最初は宗教改革運動に参加するつもりはなく、研究を続けたかった。しかし神は、牧師ファレルの言葉を通してカルヴァンに働きかけ、カルヴァンは自分の意に反して宗教改革運動に協力することになった。平民であったダビデも、まさか自分がイスラエルの王になるなどとは、まったく考えていなかっただろう。しかし神のダビデに対する御心は、ダビデがイスラエルを治める君主となることであった。これらのことなどから分かるように、我々の主なる神は、我々人間が思いもつかないようなことをなされる御方なのである。
2節目に進みたい。
②『および私とともにいるすべての兄弟たちから、』(1章2節)
パウロはここで、この手紙に書いてあることが自分だけでなく、ほかの聖徒たちによるものでもあると言っている。つまりパウロは「ここに書いてあることは他の聖徒たちも同意していることだ。この手紙は私個人だけというのではなく、私たちみんながあなたがたに対して送っているものなのだ。」と言いたいのである。すなわちこの手紙はパウロが自分自身の手で書いたのではあるが(※⑥参照)、多くの聖徒たちの署名がびっしりと付いているということである(※2016/05/15追加)。
③『ガラテヤの諸教会へ。』(1章2節)
この手紙の受取人は、ガラテヤにある多くの教会及びその教会に属しているキリスト者たちである。パウロはこのガラテヤの地方に福音を宣教しており(※⑦参照)、救われたキリスト者たちの霊的共同体(つまり教会)がこの地方には多く存在していた(※2016/03/27追加)。パウロは手紙の読者に対しては説教をしたことがあり、この手紙を受け取った聖徒たちはパウロのことはすでに知っていた。推定であるが、この手紙が書かれたのは紀元48年頃であると考えられている。パウロが回心したのが紀元33年頃であるから、救われてからおよそ15年後に書いたものであるということになる。このガラテヤの地方は、現在におけるトルコの場所にあり、そこには首都アンカラがある。
この手紙は、直接的・第一義的には、当時のガラテヤ人に対して書かれたものである(※2016/03/27追加)。しかし、パウロは、真の著者であられる聖霊により真理の言葉を語っている。真理は不変であり、いつの時代にも有効であるから適用されねばならないものだ。それゆえ、ここで書かれている神の言葉は、現代の我々に対しても語られているものであると認識すべきである。「当時のガラテヤ人に対して書かれたものだから、今の私たちには関係ないものだ。」などと考えるべきではない。これはガラテヤ書だけでなく、聖書のほかの巻についても同じことが言える。
神は、ガラテヤ人たちに、パウロを通してこの聖なる手紙をお与えになった。神は、ガラテヤにいた兄弟姉妹たちを無視されず、彼らに心を配っておられた。というのも、ガラテヤの兄弟姉妹たちは、パウロが教会を建てたあとに湧いて出てきた律法主義者という化物どもに大いに惑わされていたからである。この化物は、救われるためには割礼を受けたりするなど律法の行ないが必要だなどと主張する行為義認論者であった。パウロはこのような異端者に対して、『いっそのこと不具になってしまうほうがよい』(ガラテヤ5章12節)また『さばきを受ける』(ガラテヤ5章10節)などと、かなり厳しいことを書いている。神は、このような危機的かつ悲惨な状況にあったガラテヤ人に対し、パウロを通して信仰義認という聖なる教理を豊かに伝えられたのである。これは、神の大きな憐れみによるものである。その上、神はこの手紙により、当時のガラテヤ人だけでなく、この時代以降に生まれることになる新約時代の聖徒たち(※2015年に生きている我々も含まれる)をも教えようと計画された。この神の御計画と御計らいのゆえに、我々も、この手紙から聖なることについて学ぶことが出来るのである。特に「律法の行ないによる義認の教理は間違いであり、信仰による義認の教理こそ聖なる正しいものである。」ということについて豊かに弁え知ることが出来るであろう。これは、何という大きな恵みであろうか。我々は、このようなことについて神に感謝すべきであろう。
ところでこの手紙、パウロは、このガラテヤの兄弟たちの共同体について「教会」であると言っているが、これは考えさせられることである。ガラテヤ人たちは律法主義に惑わされ、行ないによる能動的な義認の考えに陥り、パウロからこのように言われてしまうほどであった。『律法によって義と認められようとしているあなたがたは、キリストから離れ、恵みから落ちてしまったのです。』(ガラテヤ5章4節)キリストから離れて恵みから落ちるとは、実に恐るべき緊急事態であるといえよう。しかしパウロは、あくまで彼らについて「教会」であると確かに書いている。このことについては、ヒエロニムス(今でも語られることの多い3~4世紀における有名な教父。聖書のラテン語訳である「ウルガタ」を完成させた。342頃―420)も「なぜパウロは教会でもないものを教会と呼んでいるのか。」(ガラテヤ書注解)と疑問を抱いている。我々の場合、どこかのプロテスタント教会内で行為義認論者になる者が多く生じた際、「あそこは異端になってしまった。」などと言うこともあるだろう。我々はそのような集団を異端視したり、不敬虔な集団として警戒することだろう。しかしパウロは、そのように異端的な状態になってしまったガラテヤ人の集団に対して、あくまで「教会」と言っている。行ないによる義認の考えに迷いこみ、キリストから離れ、自分を召して下さった父なる神を見捨てて他の福音に移ってしまったのにも関わらず、である。パウロは他に、罪に満ちていた悲惨なコリント人たちの集団に対しても『神の教会』(Ⅰコリント1章2節)と書いている。我々がこのことについてどう考えようと、確実に言えるのは、パウロが悲惨な状態にあったガラテヤとコリントの集団を「キリストの教会」であると認識していることだ。どちらの教会も非常に不敬虔な状態にあったが、しかし、まだ完全に捨てられてはいなかった、ということなのだろう。何故なら、もし完全に見離されていたとしたら、パウロはそこが「教会」であるとはもう言えなかったはずだからである。(※2016/03/06追加)
これはガラテヤ人への手紙以外の書簡についても同じことが言えるのだが、パウロが自分の手で書いた手紙そのものは、もうすでに無くなってしまっている。今存在しているのは、パウロの書いたものを書き写した無数の写本のみである。今はもうパウロの書いた原本が存在しておらず、それは完全に失われてしまっているが、彼を通して語られた神の言葉が失われてしまったのでは全くない。写本の数は本当に沢山あり、全ての写本同士が完全に合致した内容を保っているというのでもないが、しかし神はそれらの写本のうちに御自身の言葉を十全に保持しておられる。いったい、神が語られた聖なる言葉がどうして消滅してしまうことがあるだろうか。御言葉がこの世界から消えてしまう……こういうことは絶対にありえないことだ。また、我々がいま日本語で読んでいる聖書とは、その写本から翻訳されたものであるが、翻訳されたものだからといって何か疑ったり不安になったりすべきではない。たとえ翻訳されたものであったとしても、我々がその目で見、その耳で聞いているものは、紛れもない神の真理の言葉なのである。
④『どうか、私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安があなたがたの上にありますように。』※2016/04/24追加(1章3節)
これは、パウロ御決まりの使徒的挨拶である。彼が書いた手紙のすべてにこの挨拶が用いられている(※⑧参照)。テモテへの2つの手紙においては、「恵み」と「平安」だけでなく「憐れみ」も加えられている。
ここでパウロは、ガラテヤの聖徒たちに恵みと平安があるように願っているが、この2つのものはキリストを信じるクリスチャンにとって非常に重要なものである。まず「恵み」だが、この恵みによって我々には様々な面における幸いが生じることになる。神のキリストにある恵みによって、我々の犯してしまった罪が赦される。もしこの恵みが無ければ、我々は悲惨にならざるを得ないだろう。「平安」だが、これが我々にあることによって、我々の魂は心地よさのうちに安らぐことが出来る。もし平安が無ければ、またこの平安が取り上げられたなら、我々は恐怖し、怯え、落ち着きが無くなってしまうことにもなる。この恵みと平安があるのであれば、我々は、たとえ大きな困難が襲いかかってきた際にも豊かに忍耐することが出来るであろう。それゆえ、この恵みと平安とは非常に望ましく喜ぶべきものであって、決して軽んじるべきものではないということが分かる。
パウロは、このように幸いなものが聖徒たちの上にあるようにと書いている。つまり、パウロは手紙の読者であるガラテヤの聖徒たちに熱心であり、彼らを愛していたのである。もしそうでなかったとすれば、どうして彼らに恵みと平安という幸いなものがあるようにと願うだろうか。例えば、普通、サタンと悪霊どもに対して恵みと平安があるようにと願う愚かな者はいないだろう(サタニストや狂った者は別である)。憎悪すべき者に幸いがあるようにと願う者の精神は絶対にまともではない。それは彼らが憎むべき者であって、彼らに幸いがあることを望むべきではないからだ。しかし愛すべき者の場合、その愛する者に対して幸いを願うのは何も不思議なことではない。何故ならその者を本当に愛しており、その者が幸せになるのを願っているからである。それゆえ、ここで聖徒たちに幸いがあるのを願っているパウロは、本当に彼らのことを愛していたのである。
この恵みと平安が『私たちの父なる神と主イエス・キリストから』あるようにとパウロは言っている。つまり、パウロはここで「神とキリストがガラテヤ人に対して恵みと平安をお与え下さるように。」と願っているのである。「ちっぽけな被造物から」ではなく、「自分自身から」でもなく、「この世から」というのでもない。『神とキリストから』と彼は言うのである。我々の主なるキリストは御自身がお与えになる平安について、こう言っておられる。『わたしは、あなたがたにわたしの平安を与えます。わたしがあなたがたに与えるのは、世が与えるのとは違います。』(ヨハネ14章27節)キリストが下さる平安は、この世が与える平安などとは比べ物にならないほどまさっている。キリストが平安を満たして下さったのならば、その人の魂は死のときすらも安心に満ちあふれるだろうし、その平安は消えることなく、その後も永遠に続くであろう。この世が与える平安は、金による平安とか、安全による平安とか、家族が幸せなことによって生じる平安とか、色々な平安があるだろう。しかしこの世が与える平安は、死のときには消え去ってしまうかもしれないし、この肉体が朽ちてから後は続くこともない。それゆえ、キリストが下さる平安とは我々にとって非常に望ましいものである。キリストが下さる恵みも、平安と同じく非常に望ましいものである。しかも、これらのものはキリストだけでなく、「御父からも」与えられる。つまり、パウロは、本当に望ましく喜ばしいものをガラテヤ人に対して願っていたということになる。神とキリストから与えられるこれらのものは、当然ながら我々にとっても非常に好ましいものであるのは言うまでもない。
エペソ書には『すべての聖徒のために、忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。』(6章18節)とあるが、我々は互いのために祈りあうべきである。互いのことについて祈祷する際、我々は自分の兄弟姉妹に恵みと平安があるようにと祈るべきであろう。しかも、パウロのように『父なる神と主イエス・キリストから』恵みと平安があるようにと願えるのならば、それは非常に望ましい。パウロは、聖徒たちに恵みと平安があるよう「聖霊によって」願っている。つまり、罪深き肉の思いによって願ったのではない。この「肉」は自分の兄弟姉妹を愛することが出来ないものであるから、兄弟姉妹に恵みと平安があるようにと願うことは絶対に出来ない。それゆえ、このように願うのは御霊の働きによるのであって、それは確実に神の御心にかなったことである。『何事でも神のみこころにかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださる』(Ⅰヨハネ5章14節)とあるから、確かに神はそのような願いを聞いてくださることだろう。キリストの聖なる血によって買い取られた自分の同胞である愛する兄弟姉妹に恵みと平安が満たされるのは、なんと喜ばしいことだろうか。神とキリストも、そのようになるのを喜ばれることであろう。我々が自分の仲間に幸いが満たされているのを喜ぶのであれば、尚更のこと、その幸いをお与えくださった御方が喜んでおられるだろうことは間違いない。
ここでパウロは、恵みと平安という幸いなものの出所を、父なる神だけでなくキリストにも帰している。このことから分かるのは、キリストがただの人だけの存在なのではなく、被造物でもなく、真の神であられたということである。アリウスなど、かつて狂った異端者どもが言ったように、もしキリストが被造物であり、また単なる人でしかなかったなどと言うのであれば、そのような存在を恵みと平安の発出者として父なる神と共に並べ立てるのは変ではないだろうか。キリストは神ではなく単なる人間にすぎない、または被造物であるなどと言うのであれば、どうしてそのような存在が御父と共に、恵みと平安を我々に与えることが出来ようか。もしそれが本当だったとすれば、父なる神は「神ではない存在」に対してかくも大きな地位・権能・尊厳を与えたものだ。恵みと平安を神と一緒になって注ぐというその人間あるいは被造物に過ぎない者とは一体何者なのか。しかし我々の主なるキリストは、真の人であられただけでなく真の神でもあられたから、恵みと平安の発出者であると言われるのは何も不思議なことではない。キリストは『万物の上にあり、とこしえにほめたたえられる神』(ローマ9章5節)であられるから、父なる神と同じく「恵みと平安を与える存在」なのである。もしキリストが神では無かったというのであれば、パウロはここで、キリストを父なる神と並べて書くことが出来なかったであろう。
⑤終わりに
パウロはこの手紙で、律法の行ないによって救われようとする行為義認論者に反対し、キリストを信じる信仰によって救われるという信仰義認の教理を大胆に論じている。パウロはこの裁かれるべき律法主義者・ユダヤ主義者たちに翻弄されているガラテヤ人のことを本当に心配に思っていた。それは、あたかも自分の愛する子どもが邪悪な男から危ない目にあわされているのを心配している母親のようである。かつて2世紀に現われた異端のモンタヌス派は、イタリヤやアフリカで一時的に勢力を得、テルトゥリアヌス(160―220)も加わったほどであるが、6世紀には消滅した。中世に現われた異端のカタリ派も、二元論や現世否定などふざけたことを主張したが、14世紀末には消滅してしまった。反三位一体論者で有名なセルベトゥスも、狂ったことを喚き立てていたが、1553年にカルヴァンによって焚刑に処せられ地獄に落ちていった。ローマ・カトリックなど、行為義認の思想をもっている宗教グループは今でも少なくない。この行為義認という思想は、すぐさまモンタヌス派やカタリ派のように消滅し、非常な勢いをもってセルベトゥスのごとく地獄に投げ込まれてほしいものである。
我々は、行為義認の思想をもっているローマ・カトリックに迎合することは絶対に出来ない。何故なら、自分の行ないによって義認を獲得しようとする者たちは、パウロも言っているように、キリストから離れて恵みから落ちてしまっているからである(※⑨参照)。一体、そのようなグループとどうして仲良くできるというのだろうか。現在、エキュメニズムを肯定する多くのプロテスタントにおける教師たちがカトリックとその誤謬に対して激しくなっていないが、これは不思議なことだ。行為義認であれ、ミサであれ、煉獄の教理であれ、教皇制であれ、もしカトリックの信じているものをまじまじと我々が見つめるのならば、批判・否定せずにはいられない。どうしてこのような教えを肯定したり、「まあ、そういうものもありますね。人それぞれ考え方がありますよね。」などと言えるだろうか。このぐらいのことは、エキュメニズム推進派の教師たちも弁えているはずだ。彼らはプロテスタントなのだから、カトリックにおける異端的・非聖書的な教理を受け入れられるはずがない。しかし、多くの教師たちはカトリックの誤謬に対して厳しい態度をとっておらず目をつぶってしまっている、と私には感じられる。カトリックについて良いことを言ったり、褒めたりしている教師もいるほどだ。つまり、妥協し、女々しくなり、真理への愛および誤謬への憎悪が隅へと追いやられてしまっているということなのだろう。我々は、このカトリック教であれ、他の宗教であれ、自分の行ないによって救いを得ようする行為義認の思想をもった異端グループと合同することをしない。
何であれ、自分の行ないによって義認を得ようとする思想は、腐臭を放つどす黒い毒物である。信仰義認に立っているキリスト者がその毒物を飲むのならば、その人の霊は滅びに至ることであろう。何故なら、行ない・功績・自分自身によって救いを獲得しようとするのであれば、原理的に「キリストなど必要ない。」ということなってしまうからだ。たとえ少しだけでも自分の行ないを義認に結びつけるのであれば、少しだけでも救い主なるキリストを自分から退けることになってしまう。だから、そのような人は十全にキリスト・イエスの救いを自分に受けているとは言えない。パウロの主にある伝道によって当時ガラテヤの地方には御国が大いに拡がったのだが、そのすぐ後でサタンが自分の兵士によって、拡大された御国を破壊・縮小させようとした。その兵士とはこの書簡で言われている「かき乱す者」のことであって、このかきみだす者の武器は「行為義認」であった。つまり、パウロはこのかき乱されていたガラテヤ人たちに対して手紙を書くことによって、御国の破壊・縮小を食い止めようとしたわけである。言うまでもなく、この行為義認という考えは、聖書の教えているものではない。キリスト・イエスが選ばれた者のために御自身を永遠の犠牲とし、今キリスト者である我々は恵みのゆえに、行ないなしに、信仰によって救われ義と認められるに至った。これが聖書の教える義認の内容であって、パウロが次のように言うとおりである。『あなたがたは、恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それは、自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行ないによるのではありません。』(エペソ2章8~9節)『人は律法の行ないによっては義と認められず、ただキリスト・イエスを信じる信仰によって義と認められる、ということを知ったからこそ、私たちもキリスト・イエスを信じたのです。これは、律法の行ないによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら、律法の行ないによって義と認められる者は、ひとりもいないからです。』(ガラテヤ2章16節)行ないによって義と認められようとしても、ルターやその他の修道士たちがそうだったように、解決できない不安に悩まされるだけであろう。
※2016/03/27追加
「ガラテヤ人への手紙」などと我々は言っているが、このタイトルは、後代の人たちが独自につけたものに他ならない。これは標識としてつけられたものに過ぎないから、「使徒パウロによって送られたガラテヤ人への聖なる手紙」とか「神が使徒パウロを通してガラテヤ人に送られた手紙」などといったタイトルをつけたとしても別に構わないわけである。実際、我々が「伝道者の書」と呼んでいるソロモンの文書を、ある人々は「コヘレトの言葉」などと呼んでいるが、違う呼ばれ方をしていても通常は論争が生じたりすることもない。また、我々が「出エジプト記」などと呼んでいる文書がユダヤ教では「脱出」などと呼ばれていたが、単に呼び名が異なるだけであるから、別にどちらの名前で呼ばれても構わないのである。これらのことは些細な事柄かもしれないが、認識の幅が強化されるかと思ったので、追補したのである。
[本文に戻る]
※①
聖書を「節」に区切るようになったのは16~17世紀以降である。それ以前の時代には「節」として区切っていなかったので、説教者や著述家が聖句を引用する場合、ただ「章」を言ったり書いたりするだけであった。例:「イザヤ書の1章には~~~と書いてありますが…」など。
[本文に戻る]
※②
例えば、次の聖句からパウロがコリントの聖徒たちに熱心な思いを抱いていたことが分かる。『私があなたがたのことを思うのと同じ熱心を、テトスの心にも与えてくださった神に感謝します。』(Ⅱコリント8章16節)また『私はあなたがたのことを思わぬ時はなく、…』とローマ1章9節でパウロが言っているように、パウロはローマにいる聖徒たちのことをいつも思っていた。更に『すべての聖徒のために、忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。』(エペソ6章18節)と命じたパウロだが、このように命じたということは、パウロ自身が全ての聖徒たちのために忍耐をもって祈っていたということを示している。このようなことを考えればすぐに分かるように、パウロは聖徒たちに対する兄弟愛に満ちていた人物であった。その兄弟愛とは、パウロ自身から出たというのではなく、御霊による、神の恵みに基づいたものであったのは言うまでもない。
[本文に戻る]
※2016/03/06追加
パウロの職業は「使徒」であった。職業、と言われたのを聞いて多少違和感を感じられる方もおられるかもしれない。しかし、牧師が職業の一つであるという認識を持たぬ人はいないと思うが、もし牧師が職業であるのを認めるのであれば、使徒という役割も職業の一つとして認識すべきであろう。もし使徒職が職業であるとしないのであれば、牧師も職業とはいえなくなる。何故なら、使徒と牧師はどちらも、神によって召され、信徒たちの霊的共同体のために仕事をする、という点で共通しているからである。
[聖句に戻る]
※③
『神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリスト・イエスのしもべパウロ、…このパウロから、ローマにいるすべての、神に愛されている人々、召された聖徒たちへ。』(ローマ1章1、7節)
『神のみこころによってキリスト・イエスの使徒として召されたパウロと、兄弟ソステネから、コリントにある神の教会へ。』(Ⅰコリント1章1~2節)
『神のみこころによるキリスト・イエスの使徒パウロ、および兄弟テモテから、コリントにある神の教会、ならびにアカヤ全土にいるすべての聖徒たちへ。』(Ⅱコリント1章1節)
『神のみこころによるキリスト・イエスの使徒パウロから、キリスト・イエスにある忠実なエペソの聖徒たちへ。』(エペソ1章1節)
『神のみこころによる、キリスト・イエスの使徒パウロ、および兄弟テモテから、コロサイにいる聖徒たちで、キリストにある忠実な兄弟たちへ。』(コロサイ1章1~2節)
『私たちの救い主なる神と私たちの望みなるキリスト・イエスとの命令による、キリスト・イエスの使徒パウロから、信仰による真実のわが子テモテへ。』(Ⅰテモテ1章1~2節)
『神のみこころにより、キリスト・イエスにあるいのちの約束によって、キリスト・イエスの使徒となったパウロから、愛する子テモテへ。』(Ⅱテモテ1章1~2節)
『神のしもべ、また、イエス・キリストの使徒パウロ―私は、神に選ばれた人々の信仰と、敬虔にふさわさしい真理の知識とのために使徒とされたのです。…―このパウロから、同じ信仰による真実のわが子テトスへ。』(テトス1章1、3~4節)
[本文に戻る]
※④
『こうして、キリストご自身が、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師として、お立てになったのです。』(エペソ4章11節)
[本文に戻る]
※⑤
『あなたがたは使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリスト・イエスご自身がその礎石です。』(エペソ2章20節)
[本文に戻る]
※⑥
『ご覧のとおり、私は今こんなに大きな字で、自分のこの手であなたがたに書いています。』(ガラテヤ6章11節)
[本文に戻る]
※2016/05/15追加
この「署名」とは、実際的な署名のことを言っているのではない。パウロと共にいた多くの聖徒たちがこの手紙の内容に精神的に同意している、という意味において私はこのように書いたのである。つまり、簡単に言ってしまえば「多くの聖徒たちがこの手紙に心において署名している。」ということである。
[本文に戻る]
※⑦
次の聖句が示すとおり、パウロはガラテヤの人たちに福音を伝えていた。『ご承知のとおり、私が最初あなたがに福音を伝えたのは、…』(ガラテヤ4章13節)
[本文に戻る]
※2016/03/27追加
多く存在していたとはいっても、一体どれだけの数の教会があったのか具体的には分からない。絶対確実に分かるのは、『諸教会』と書いてあるがゆえ、1つとか3つなどといった少ない数ではなかった、ということである。
[本文に戻る]
※2016/03/27追加
だからといって、我々はこの文書がただの個人的な手紙に過ぎないなどと絶対に考えるべきではない。長老派の著名な新約学者でありウェストミンスター神学校の創設者であるメイチェン(1881―1937)は、パウロの書簡について「エジプトのごみの山に発見された手紙のように、捨て去られるつもりの単なる個人的な覚書ではなく、一人の使徒が神の教会に宛てた手紙である。」(ニューライフ出版社:J・グレシャム・メイチェン「新約聖書ギリシャ語原点入門」p6)と言っている。この文書は、神が使徒を通して書かれた聖なる文書なのである。それゆえ我々は、パウロを通して書かれた手紙を崇高・神聖なものとして認識せねばならない。これをただの個人的な手紙に過ぎないと考えたり、また、聖書が他の書物と何ら変わらないものであると感じている者たちは、その非霊的な認識により、自分をみずから真理への敵対者としてしまっている。
[本文に戻る]
※2016/03/06追加
参考までに、この箇所におけるカルヴァンの注解は以下の通り。
「ガラテヤはかなり広大な一地方であり、従ってそこには多数の教会があちこちと散在していた。しかし、ガラテヤ人はキリストに反逆しているといわれてもよいような状態だったのだから、そのガラテヤ人に教会の名が与えられているという事実は、驚くべきことである。教会の在るところには、信仰の一致があるはずではないか。わたしはこう答える。そこでもキリスト教信仰が告白され、唯一の神への祈りがなされ、聖礼典が守られ、いくらかの仕事がなされていたのだから、まだ、若干教会のしるしはあったのだと。たしかに、教会はいつでも望ましい純粋な状態にあるというものではない。最も純粋な教会でさえも、なお何らかの欠点や汚点をもっているのであり、いわんや一般の教会にいたっては、欠点があるどころの話ではない、ほとんど見るに耐えない状態である。それゆえわれわれは、ある集会に何か自分の気に入らぬ点があったからといって、それですぐにその集会を教会と呼ぶことをやめてしまうというように、教えや行ないの欠陥にあまりに気を取られすぎてはならない。パウロがここでわれわれに教えているのは、むしろ寛大さなのである。ただし、何らかの欠陥をもっている集会でも、なおキリストの教会と認められるからといって、われわれが教会にあるすべての過ちを非難することをやめてはならない。ともかくも教会というものが存在しさえすれば、そこには教会において望むべきすべてのことが完成されているのだ、というように考えるべきでは断じてない。」
(新教出版社:カルヴァン・新約聖書注解Ⅹ ガラテヤ・エペソ書p20)
[本文に戻る]
※2016/04/24追加
平安があるように願う、ということは我々クリスチャンにとって非常に重要である。聖書では、相手の平安が願われている箇所が多くある。アロンとその子供たちは、イスラエル人に神からの平安があるように祈れと命じられた(民数記6:22~27)。ダビデはナバルに対して『あなたに平安がありますように。あなたの家に平安がありますように。また、あなたのすべてのものに平安がありますように。』(Ⅰサムエル25章6節)と言うよう、若者たちに命じている。復活された主も、弟子たちに対して2度『平安があなたがたにあるように。』(ヨハネ20章19、21節)と言われた。パウロの全ての手紙でも、読者に平安があるようにと言われている。ペテロも、読者に対して平安を願っている(Ⅰペテロ1:3)。主は、70人の者たちに対して『どんな家にはいっても、まず、『この家に平安があるように。』と言いなさい。』(ルカ10章5節)と命じられた。このように多くの箇所で平安を願うことについて書かれているのだから、誰かに平安があるように願うのは、重要なことであるのが分かる。それが重要なことだからこそ、聖書の多くの箇所では、相手の平安を願うことについて記されているのである。
[本文に戻る]
※⑧
ローマ人への手紙1章7節
『私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなたがたの上にありますように。』
Ⅰコリント人への手紙1章3節
『私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安があなたがたの上にありますように。』
Ⅱコリント人への手紙1章2節
『私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安があなたがたの上にありますように。』
エペソ人への手紙1章2節
『私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安があなたがたの上にありますように。』
ピリピ人への手紙1章2節
『どうか、私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安があなたがたの上にありますように。』
コロサイ人への手紙1章2節
『どうか、私たちの父なる神から、恵みと平安があなたがたの上にありますように。』
Ⅰテサロニケ人への手紙1章1節
『恵みと平安があなたがたの上にありますように。』
Ⅱテサロニケ人への手紙1章2節
『父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安があなたがたの上にありますように。』
Ⅰテモテへの手紙1章2節
『父なる神と私たちの主なるキリスト・イエスから、恵みとあわれみと平安とがありますように。』
Ⅱテモテへの手紙1章2節
『父なる神および私たちの主キリスト・イエスから、恵みとあわれみと平安がありますように。』
テトスへの手紙1章4節
『父なる神および私たちの救い主なるキリスト・イエスから、恵みと平安がありますように。』
ピレモンへの手紙
『私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安があなたがたの上にありますように。』
[本文に戻る]
※⑨
『律法によって義と認められようとしているあなたがたは、キリストから離れ、恵みから落ちてしまったのです。』(ガラテヤ5章4節)
[本文に戻る]
ガラテヤ人への手紙1章4節(2015/11/29説教)
『キリストは、今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。』(ガラテヤ1章4節)
先週の説教でも述べたように、神はこの手紙を通してガラテヤ人たちを教えられただけでなく、新約時代におけるクリスチャン一人一人をも教えようと計画された。つまり、この手紙は今の時代を生きている我々に対しても向けられているものである。それゆえ、ここに書いてある輝かしい真理の言葉は、我々に対する神からの贈り物であると言える。この手紙をざっと見るだけでも分かるように、聖書の文体は非常に平易なものであり、学者の難しい研究文書でもあるかのように高度な文体ではない。カルヴァンの場合、聖書の文体について「人から卑しめられるような身を低くした言葉遣い」また「粗削りと言えるほどに単純」であると言っている(※①参照)。文体が平易であって難しいものでないからこそ、未信者の方は、この聖書とそこに書いてある福音を卑(いや)しいものとみなしてまうことになる。救われる以前のアウグスティヌスも、聖書の平易さに触れた際、自分の期待していたものがそこに無かったので辟易してしまったという。しかし、神は、御自身の真理をやさしくその民に伝えられるのを望まれた。今回の箇所も、文体的に平易であって、「書かれている事柄そのものがどのようなことなのか認識できない。」などと思う人はいないだろう。我々の神は恵み豊かな方であるから、誰にでも書かれていることが理解できるようにと、愛の御配慮から文体が難しいものとなるようにはなさらなかったのであろう。
本日、この1章4節における箇所から説教がなされるのは、神が永遠の昔からお定めになった御計画に基づくものである。先週1章1節~3節における箇所から語られたのも、同じように、神がそうなるよう定められたからであった。もしそうでなかったのであれば、先週も今週も、どこか違う箇所から説教がなされていたことだろう。説教の時に聞くのであれ、家で自主的に学ぶのであれ、御言葉に触れる際に必要な態度とは、言うまでもなく「へりくだり」である。我々はこの聖なる御言葉の前に自分の心と精神をひざまづかさせ、『みことばのすべてはまことです。』(詩篇119篇160節)また『あなたのみことばは真理です。』(ヨハネ17章17節)と書いてある通りの態度をもって読んだり聞いたりすべきである。「なにが真理だ。どうせ間違ったことも書いてあるのだろう。俺はこれが神の言葉などとは絶対に信じない。」などという傲慢な態度をもってこの聖書に向かうのであれば、それは決して神に喜ばれることではない。謙遜な態度をもち、書いてあることを真に正しいものとして受け入れるのでなければ、神はそのような人に御自身の真理を体得させては下さらないだろう。「私たちは、これをどれほど深い尊敬の念をもって受け取るべきか!」とピューリタン牧師のトマス・ワトソンは言っているが、「敬意」の念も「謙遜」と同じように欠くことは出来ない。
先週、写本の話をしたが、パウロが実際に書いた手紙の言語はギリシャ語であり、これは「コイネー」(共通語)と言われ、当時の世界における標準語であった。この写本だが、B・M・メツガーというアメリカの聖書学者(1914―2007)によると全部で5000を超えるといい、本当に多くの写本があることが分かる。それら無数の写本を研究したり考えたりして元通りの姿を求める作業を学者たちが行なうわけだが、そのようにして復元されたのものを「聖書本文」(せいしょほんもん)という。つまり、「これこそパウロが、ペテロが、ヨハネが、実際に書いたであろう文章に違いない。」というものが聖書本文である。この聖書本文はいくつか種類があって、一つだけというのではない。この本文をしっかりと確定させる作業は、今も絶えず行なわれ続けている。この聖書本文から日本語に翻訳され、今我々がその目で見ているのが、この聖書、そして本日の箇所における「ガラテヤ人への手紙」ということである。
ある学者は、この手紙がパウロによるものであるということに疑問を抱いている。ウィキペディアでも「使徒パウロの手によるとされるパウロ書簡の一つ」と書かれており、「使徒パウロによるパウロ書簡の一つ」というふうに断定的には書かれていない。しかし、我々はこの手紙がパウロによるものであるとすべきである。もしそうでなかったとすれば、聖書には嘘が書いてあることになってしまうからだ。確かにこの手紙の1章1~2節では『使徒となったパウロ…から、ガラテヤの諸教会へ。』と書いてあるのである。神は、ふざけた、偽りの文章を御自身の民にお与えになるお方ではない。また、よく言われることだが、この手紙は「ローマ人への手紙」と同じく、パウロの救いにおける神学がもっともよく明らかになっている書簡である。
それでは、先週に引き続き4節目を見ていきたいと思う。本日は、この4節目における前半部分だけとなる。
①『キリストは、今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。』(1章4節)
パウロはまず、この手紙の最初の部分において、キリストの救いのことを提示している。これは、歪められた『ほかの福音』(ガラテヤ1章6節)に惑わされてしまったガラテヤ人に対する、聖なる宣言文のようなものである。悲惨な霊的状態のうちにあったガラテヤ人たちは真に正しい救いの教理について教えられる必要があり、そのため、まずはガラテヤ人たちの心が救いのことについて豊かに傾けられる必要があった。それで、ここではまず最初に、キリストの救いのことが簡潔に語られているのである。
『キリストは、今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、』…ここでこのように言われている対象は、言うまでもなく未信者ではなく、信者である。この箇所から、ガラテヤ人たちであれ、我々であれ、クリスチャンとは「悪の世界から救われた存在」であることが分かる。それゆえ「クリスチャンとはどういう存在なのか。」と聞かれたら、「悪の世界から救い出された人たちだ。」と答えることが出来るだろう。
パウロは自分が生きていた当時(つまり今から2千年前)について「悪の世界」と言っているが、これは今の時代(つまり21世紀)でも同じである。この「悪の世界」とは一体どのようなものなのか。我々はこの悪の世界から救い出されたのであるから、もはや悪の世界には属していない。つまり、クリスチャンではない人たちが生きているその生き方・歩み・世界観、またその人生そのものが「悪の世界」または「悪の世界に生きている」と言うことになる。簡単に言ってしまうと、ノンクリスチャンは暗やみの世界観に生きる住民であり、クリスチャンは聖なる世界観に生きる住民であると言えよう。聖書を規範とし、イエスを主とし、神とその栄光のために生きているクリスチャンは聖なる国、つまり神の御国のうちに歩んでいる。しかしノンクリスチャンの場合は、聖書を規範とせず、イエスを主とせず、神とその栄光を求めないのであるから、悪の世界、つまりサタンの暗やみの支配のうちに歩んでいるのだ(※②参照)。
今話したことから分かることだが、この地上には「悪の世界/サタンの支配」と「聖なる世界/キリストの御支配」の2つが存在している。この4節目の聖句から分かるように、我々クリスチャンは、このサタンに属する悪しき世界から救い出され、キリストに属する聖なる世界へと移されたのである。このことについては、コロサイ書における1章13説を見たらよく分かるであろう。次のように書いてある。『神は、私たちを暗やみの圧政から救い出して、愛する御子のご支配のうちに移してくださいました。』言うまでもないことだが、キリストによって救われておらず、まだ光の世界に移されてはいないノンクリスチャンの方々は、今も悪の世界のうちに歩んでいる。
この悪の世界について、もう少しだけ語りたい。神の支配のうちに歩まず悪の世界のうちに歩んでいる未信者の方々は、先程も述べたように聖書を規範とはしておらず、自分の心によって歩んだり、聖書以外のものを原理原則として生きている。詩篇119篇105節には『あなたのみことばは、私の足のともしび、私の道の光です。』とあるが、この御言葉に書いてあるように、御言葉を自分の人生における光とすることがない。何か悪いことをしてしまったと心で感じることがあっても、神に向かって悔い改めることはない。神に生きるとか、神を愛するとか、神の栄光を求めるとか、神の御国の拡大を願うとか、そんなものははっきり言ってどうでもよいと感じている。回心した人が「救われる以前は自分が主であるかのように歩んでいた。」と言っていることがあるが、神ではなく、自分自身が自分の神となってしまっている。このようなことを考えれば分かるように、神の国にいまだ導かれていない方々は、まさに「暗やみの中に歩んでいる。」という言葉が相応しい。暗やみの中に歩んでいるのだから、そのような方々は「悪の世界に住んでいる住人」と言わねばならない。
キリストは、この悪の世界・サタンの支配から我々を解放させようとして、ご自身を罪のために永遠の犠牲としてくだった。というのも、忌まわしい暗やみの穴から我々が引き上げられてキリストが支配される光の世界に移されるためには、どうしてもキリストが罪のためにご自身を捧げられる必要があったからである。だれかが聖なる光の御支配のうちに新しく移されるというのであれば、その人は、かならずキリストの犠牲のゆえに罪の赦しを受け、聖められ、義と認められ、神の民とされねばならない。つまり、キリストがご自身を我々の罪のために捨てられたからこそ、我々は、新しい世界へと移されることが出来るようになったのだ。それゆえ、我々が忌まわしい悪の世界から救い出されて聖なる新しい世界に移されたのは、ただキリスト・イエスの犠牲のゆえに実現したのだということが分かる。もしキリストがご自身を捨てられなかったとすれば、我々一人一人は他の人たちと同じように今も悪の世界にいただろうし、恐るべき地獄に向かって突き進む人生を歩んでいたことだろう。
この世界(つまり地上)には、悪の世界「だけ」があるのだと思うべきではない。我々が住んでいるこの世界には、この悪の世界に対するものとして、「光の世界」または「神の国」が存在している。この地上では、この2つの世界がせめぎ合い、互いに陣取り合戦をしているのである。悪の世界における頭はサタンであり、光の支配における頭はキリストである。キリストは大宣教命令において『あらゆる国の人々を弟子としなさい。』(マタイ28章19節)と言われたが、これは「すべての国の人々が悪の世界から神の支配のうちに移されるようにせよ。」と言われたも等しい。つまり福音宣教とは、「まだ救われていない悪の世界にいる方々が神の国に移されるようになるための活動」であると言える。
ここで言われているように、我々が悪の世界から救われるためにキリストはご自身を犠牲にして下ったのだが、これは、キリストの我々に対するその測り知れない愛のゆえであった。エペソ書3章19節では『人知をはるかに超えたキリストの愛』と言われているが、正にこれである。聖書に書いてあるように、キリストはご自身の民を愛しておられ(※③参照)、その愛はご自身の命を捨てられるほどに大きなものであった。このキリストにおける愛とは最高の愛であって、この愛よりも優れた愛は存在していない。主はご自身の民のことを「友」と呼ばれ、その友である存在に対してこのように言われた。『人がその友のためにいのちを捨てるという、これよりも大きな愛はだれも持っていません。』(ヨハネ15章13節)もしこのキリストが我々のことを愛しておられなかったとしたら、この御方が我々のためにご自身を捨てられることも無かっただろう。
また、パウロはここで、人が救われるのはキリスト・イエスによるということを我々に教えている。キリストが我々のために罪の身代わりとなられ、我々の代わりに罪となって下さったからこそ(※④参照)、我々は救われることが出来た。つまり、我々が救われたのは「自分の行ない」また「功績」によるのではない、ということである。もし人が行ないによって救われることが出来るのであれば、パウロはここで、そのことについて語れたはずであるが、そのようにはしていない。彼は、ただキリスト・イエスによる救いのことだけを言っている。それは、人が救われるのは行ないによるのではなく、ただ救い主なるキリスト・イエスによるからである。行ないでは救われないというのは、このガラテヤ書だけでなくパウロの他の書簡においても言われていることであるし、御霊と御言葉によって教えられている我々も知っているところである。我々一人一人は日々、数えきれないほどの罪を犯すというのに、それらの罪をどうして自分の行ないによって消し去ることが出来るというのだろうか。考えてもみてほしい。たとえ我々が良い行ないをしたとても、その行ないの中には多かれ少なかれ「罪」「愚かさ」「肉の思い」「弱さ」といったものが含まれてしまっている。そのような完全完璧であるとは言えない行ないが、どうして罪をきよめる働きをするだろうか。到底不可能である。
それで、いま述べたこの罪とは『律法に逆らうこと』(Ⅰヨハネ3章4節)であるが、我々は本当に罪深い存在である。我々一人一人は日々、一体どれだけ罪を犯してしまっているだろうか。神への不信・疑念・反逆・軽視・不遜、また悪い思い、高慢、妬み、虚栄、不正、憎悪、激怒、無礼、利己心、復讐心、愛なき言動…アダムにおいて堕落してしまった我々はあまりにも罪深いので、毎日本当に多くの罪を犯してしまっている。しかも、自分が犯してしまっている数々の罪を悟ることすら出来ない。ダビデが『だれが自分の数々のあやまちを悟ることができましょう。』(詩篇19篇12節)と言っている通りである。罪を犯しても自分では気付いていなかったり、それが罪であると認識できていない場合も多いのだ。だから、全てを御存知の神が、我々が日々犯してしまっている罪を一つ一つ数え上げて「これがお前の犯した罪だ。」と我々に向かって言われたとしたら、我々は絶望的になって気も狂わんばかりになるだろうし、中には気絶してしまう人もいることだろう。また、我々が今までに犯した罪を書きならべたリストを作るとしたら、(リストに書かれる文字の大きさによっても変わるだろうが)恐らくその紙の長さは太陽までも届くほどの長さだろう。我々の主なるキリストは、この無限とも言うべき大量極まりない罪の赦しのために、御自身の命をみずからお捨てになったのである。実に、キリストの十字架における聖なる贖いとは、我々の犯した一つ一つの罪のためになされたものである。
ここで、キリストが悪の世界から救いだそうとされた対象は、『私たち』であると言われている。つまり、永遠の昔から救われるように選ばれているクリスチャン全員である。パウロとか、ステパノとか、「彼らだったら救われるに値するのではないだろうか。」と思ってしまう人もいるであろう聖なる人物ではなく、<クリスチャンであれば誰でも>と彼は言っている。実に、キリストが御自身を犠牲にされたのは、『私たち』全て、つまり選びの子ら全てのためであったということが分かる。
この4節目から更に分かるのは、キリストによらねば、誰も、悪の世界から救いだされることは出来ないということである。大哲学者であるプラトン(前427ー前347)は、今に至るまで測り知れない影響を世界に及ぼし続けてきた。キケロ、デカルト、ニーチェなど、このプラトンから影響を受けた人物は数えきれない。彼の弟子であったアリストテレス(前384年―前322)も同じである。ユダヤ人の大思想家であるマイモニデスや、トマス・アクィナス、ガリレオやコペルニクスも、このアリストテレスから影響を受けている。しかし、この偉大であるとみなされているプラトンとアリストテレスは、キリストによって悪の世界から救いだされていなかったのだから、今は地獄で苦しんでいる。実に、今地獄にいる彼らは「悪の世界の住民」だったわけである。今彼らは、『私はこの炎の中で、苦しくてたまりません。』(ルカ16章24節)と叫んだ金持ちと同じ状態に至っているのである。つまり、どれだけこの世界に影響を及ぼしたとしても、どれだけ人から認められていたとしても、もしキリストの救いを受けていないのであれば、その行きつく先は地獄である。プラトンやアリストテレスといった名高い人物でさえ、恐るべき地獄に行かねばならないのである。「この世界に大きな影響を及ぼした彼らは人間的に偉大であるから、神も、その功績のゆえに彼らを天国に入れてくださるだろう。」ということは有り得ない。もし、悪の世界から救い出されて地獄に行かなくなるのを望むのであれば、その人はキリストにこそ救いを求めねばならないのだ。聖書は、キリストこそが唯一の救いの道であると教えている。ペテロが、『この方以外には、だれによっても救いはありません。』(使徒4章12節)と言っている通りである。
我々の敵である邪悪なサタンは、このキリストの救い、聖なる福音のことを嫌い、憎んでいる。どうしてだろうか。まず、キリストが言われるようにサタンは真理に立っておらず『彼のうちには真理がない』(ヨハネ8章44節)のであるから、この邪悪な者は、真理である福音をそれ自体において憎んでいる。また、キリストによるこの救いは、サタンの陣営を滅ぼすものだからである。もし誰かが今の悪の世界からキリストによって救いだされるのであれば、その救われた人は、サタンの陣営から離れてキリストの陣営に移ることになる。その救われた人は、以前はサタンの支配下にいた―つまりサタンに敵対するものではなかった―のだが、救われたことによってサタンの支配から解放され、サタンを攻撃するようにすらなる。そうしたら、それだけサタンの勢力が破壊・縮小されることになるが、キリストの勢力はそれだけ拡大・強化されることになる。つまり、キリストの救いのゆえに、自分の味方であった者が、神の国という敵の陣営にまわって自分に反対する者になってしまうわけだ。だから、サタンにとって誰かが福音を信じるというのは、非常に危機的なことである。このサタンが『不信者の思いをくらませて、神のかたちであるキリストの栄光にかかわる福音の光を輝かせないようにしている』(Ⅱコリント4章4節)のは理由なきことではない。彼は、誰かがキリストの福音によって自分の陣営から離れていくのを、何とかして阻止したいのである。それゆえ、サタンがこの聖なる救いを非常な不快感をもちつつ嫌悪しているのは確かなことであろう。
この世に属している生まれながらの人間はこの救いのことについて決して信じることが出来ない。何故なら、その人には、御霊が与えられていないからである。『御霊のことは御霊によってわきまえるもの』(Ⅰコリント2章14節)とパウロが言うように、御霊によらねば救いのことは絶対に信じれない。どれだけ知恵と知識があろうと、また人間的に偉大であると思われている賢者であったとしても、キリストの救いを確かなものとして信じることは不可能である。御霊が与えられていないのならば、この救いのことについて聞いても、パウロがⅠコリント1章22節で言っているように(※⑤参照)、ユダヤ人のようにつまづいたり、異邦人のように愚かに感じてしまうことだろう。
我々は、キリストが悪の世界から救い出してくださったこの救いについて、豊かに感謝すべきであろう。自分の目の前に1000兆円の束が1000兆個積み上げられて、「これを全部君に上げよう。遠慮せずに受け取ってくれたまえ。」と言われたならば、感謝しない人はいないだろう。しかし、キリストの救いは、これ以上に感謝すべきものである。どうしてかといえば、たとえ1000兆円を1000兆個分もらったとしても地獄を免れることは出来ないが、キリストの救いを受けるのであれば、この恐るべき地獄を免れることが出来るからだ。キリストの犠牲のゆえに救われて地獄を免れておきながら、この救いのことを感謝しないとは一体どういう信仰をもっているのであろうか。キリストは御自身を我々のためにお捨てになられたのである!!また、神がキリストによって我々を救ってくださった目的の一つは、救われた我々がその救いを感謝し、救ってくださった神を豊かに褒めたたえるようになるためであった。パウロは、神が永遠の昔から救われるよう我々をキリストによって選んでくださったその理由を、このように述べている。『神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が、ほめたたえられるためです。』(エペソ1章6節)我々がキリストの救いに感謝し、キリストによって救ってくださった父なる神を賛美することによって、神のキリストにある恵みの栄光および神の素晴らしさが豊かにあらわされるのである。パウロは『すべての事について、感謝しなさい。』(Ⅰテサロニケ5章18節)と命じているが、救われた我々クリスチャンが最も感謝すべきことは、このキリストによる救い、つまりキリストが我々を悪の世界から救いだしてくださったことであろう。このこと以上に、我々が神に対して感謝すべきことが他にあるだろうか?もしクリスチャンと呼ばれる方の中で、誰かが「ある。」と言うのであれば、それが一体何であるのか聞いてみたいものである。我々がこの救いについて全く感謝しないのであれば、その人は父なる神から「この者は忘恩の民だ。」と言われてしまいかねない。
また、このキリストの救いにおける恵みは、最も偉大な輝かしい恵みであって、人が受けることが出来る恵みの中でこれに勝るものは他にはない。救いにおける恵みという点について考えるのであれば、どれだけ優れた賜物も、莫大な財産も、ソロモンのごとき英知も、輝かしい栄誉や地位も、幸いな境遇も、まったき健康と長寿および平和も、夫婦や家庭における円満も、救いにおける恵みとは全然比べられない。人がキリストによって悪の世界から救いだされるという素晴らしい恵みに勝る恵みなど、他にあるだろうか?そのようなものは有りえないであろう。
ここまで、悪の世界とこの悪の世界から我々が救いだされたことに関して詳しく語ったが、この悪の世界から救いだされたクリスチャンとは、「勝利者」である。キリストによって悪の世界から光に満ちた聖なる世界のうちに移されたならば、その人はすでに勝利者となっている。『神は、私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。』(Ⅰコリント15章57節)とパウロは言っている。我々は勝利者となったのだが、それは我々が自分自身によって勝利者となったというのではなく、父なる神がキリストによって我々を勝利者とさせてくださったのである。すなわち、キリストが我々の罪のために御自身を永遠のいけにえとしてくださったことにより、我々は勝利したのである。この勝利についてだが、キリストによって、我々は「この世」に対して勝利した。キリストは『わたしはすでに世に勝ったのです。』(ヨハネ16章33節)と宣言された。キリストが世に勝利されたのだから、この御方に属しているクリスチャンもこの世に打ち勝った存在である。ヨハネも、我々が世に勝ったのだということを述べている。『なぜなら、神によって生まれた者はみな、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ、世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とはだれでしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。』(Ⅰヨハネ5章4~5節)我々は、キリストにより、悪魔に対しても勝利している。ヘブル書の著者が述べるように、キリストは『その死によって、悪魔という、死の力を持つ者を滅ぼし』(ヘブル2章14節)てくださったのだが、我々はこの悪魔を滅ぼされたキリストと契約的に一体なのであるから、我々もキリストにあって悪魔に打ち勝っている。ヤコブが『悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば、悪魔はあなたがたから逃げ去ります。』(ヤコブ4章7節)と言ったのは、クリスチャンがキリストにあってすでに悪魔に勝利しているからに他ならない。もしクリスチャンが悪魔に対する勝利者でなかったのならば、ヤコブはこのように書けなかったであろう。つまりは、悪魔に勝利しているからこそ、悪魔は我々から逃げ去るということなのである。また、『キリストは死を滅ぼし…』(Ⅱテモテ1章10節)とあるが、我々はキリストによって、死にも打ち勝っている。キリストが死を滅ぼし、死に対する勝利を得られたのであれば、このキリストにつくクリスチャンも死に対して勝利していることになる。だから、我々のこの身体はいずれ朽ちるであろうが、この肉体の死の際において、死が我々を圧倒的な恐怖で満たし、屈服させてしまうことは決してない。ノンクリスチャンの場合、死は彼らを恐れさせ、恐怖と悲しみのうちに死の門をくぐることになるであろう。彼らが死に勝利していないからである。我々は死に勝利しているのだから、肉体が朽ちる際に絶望的になることも無いばかりか、この肉体が朽ちたあとも生き続け、もはや死が存在することのない永遠の世界に存在し続けることになるのである。今語られたこれらの勝利は、すべてキリストのゆえに与えられた。本日の御言葉で言われているように、キリストは我々を悪の世界から救い出そうとして、御自身を我々の罪のために捨ててくださったが、そのゆえに我々は勝利者となることが出来たのである。
最後になるが、罪と汚れと暗黒に満ちた「悪の世界」から救われたということは、つまり、我々が良い行ないをする存在へと造り変えられたことを意味する。『私たちは神の作品であって、良い行ないをするためにキリスト・イエスにあって造られたのです。』(エペソ2章10節)とパウロが言うとおりである。良い行ないとは、すなわち、御霊と御言葉による、愛ときよい心に基づいてなされる神の喜ばれる行ないのことである。救われたクリスチャンはこのような行ないを神の恵みのゆえにするが、未信者の人たちはそうではない。彼らはいまだ悪の世界におり、暗やみの中を歩んでいるので、神の御心にかなった聖なる行ないをすることがどうしても出来ないのだ。クリスチャンは悪の世界から救いだされて輝かしいキリストの御支配に移されたのだから、それに相応しく、良い行ないに富むべきであろう。そうすれば、つまり良い行ないに励めば励むほど、その人は自分が悪の世界から救われたことが豊かに分かるようになる。何故なら、そのように良い行ないに満ちるのであれば、それはその人が悪の世界から光の世界へと移されたことを証明するからである。『もし、私たちが神の命令を守るなら、それによって、私たちは神を知っていることがわかります。』(Ⅰヨハネ2章3節)とヨハネは言っているが、神の命令を守り、良い行ないに富み、主イエスの御心を実行し、神の御国を求めるのであれば、そのような言動により、自分が神を知っていること、また自分が救われたということが豊かに確信できるようになるのだ。それは、その人が救われて悪の世界から引き離されたからこそ、聖なる幸いな言動をするようになるからである。だから、我々一人一人が良い行ないを求め、自分の遣わされている場所にキリストの御国が拡がるようにするのであれば、それは自分が救われた神の民であるということを実感させるだろうし、神の御心にかなっていることである。しかし、ここで注意せねばならないのは、決して良い行ないを救いの根拠としてはならないということである。つまり、(これは今までに何度も語っていることであるが)「行ないこそが人を救い、義と認めるのだ。」などと考えるべきではない。良い行ないは救いの根拠ではなく「救いの果実」であって、救われて聖霊が注がれたからこそクリスチャンは良い行ないに歩むのである。今語ったようにクリスチャンは良い行ないに富んで敬虔に歩むべきであるが、しかし、もし行ないが救いのためには必要だなどと考えるのであれば、パウロがこの手紙で批判している「かき乱す者ども」(つまり律法の行ないによって救いを得ようとしている行為義認論者ども)と同じになってしまう。
※①
実際、天国の気高い奥義が、大部分において人から卑しめられるような身を低くした言葉遣いによって伝えられるということは、神の特別な摂理なしには起こらなかったのである。これがもしも素晴らしい美辞麗句で述べられていたならば、不敬虔な者は、聖書の力はただその文体にあるに過ぎないと皮肉ったかもしれない。ところが、聖書の飾り気ない粗削りとも言えるほどの単純さが、世のいかなる修辞家の文章も為し得ないほどに我々を感動させ、聖書に対する尊敬を起こさせるのであるから、聖書には言葉の技巧を必要とせぬ、もっと強力な真理の力があると断定して差し支えないのではなかろうか。(キリスト教綱要改訳版・第1篇、第8章1節:新教出版社)
[本文に戻る]
※②
ノンクリスチャンがサタンの支配のうちに歩んでいるということは、パウロがエペソの聖徒たちに対し、クリスチャンの救われる以前の状態について言った次の箇所を見れば、よく分かる。『あなたがたは自分の罪過と罪との中に死んでいた者であって、そのころは、それらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今の不従順の子らの中に働いている霊に従って、歩んでいました。』(エペソ2章1~2節)
[本文に戻る]
※③
『イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また、私たちを王とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。』(黙示録1章5~6節)
[本文に戻る]
※④
『神は、罪を知らない方を、私たちの代わりに罪とされました。それは、私たちが、この方にあって、神の義となるためです。』(Ⅱコリント5章21節)
[本文に戻る]
※⑤
『しかし、私たちは十字架につけられたキリストを宣べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかし、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとっては、キリストは神の力、神の知恵なのです。』(Ⅰコリント1章23~24節)
[本文に戻る]
ガラテヤ人への手紙1章4~7節(2015/12/06説教)
『私たちの神であり父である方のみこころによったのです。どうか、この神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。私は、キリストの恵みをもってあなたがたを召してくださったその方を、あなたがたがそんなにも急に見捨てて、ほかの福音に移って行くのに驚いています。ほかの福音といっても、もう一つ別に福音があるのではありません。あなたがたをかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。』(ガラテヤ1章4~7節)
まったく問題を抱えていない家族が少ないように、何一つ問題がそのうちに存在しない教会は珍しい。今現在においては、教理的に悲惨な状況にある教会が非常に多い。例えば、プレミレニアリズムの終末論や、反セオノミー、進化論などがそうである。教理的にはかなり良かったとしても、内部に問題や悩みを抱えていたりする。カルヴァンの場合、その牧会していたサン・ピエール教会において、毎週聖餐式を行いたかったのだが、不幸なことに年に3回しか出来なかった。ガラテヤの諸教会も律法主義という異端思想に惑わされており、致命的・危機的な問題をもっていた。そのような悲惨な状態にあったガラテヤの教会に対してパウロが書いた手紙から、今週も見ていきたい。
我々が見ているのはまだ1章目であり、ガラテヤ書には全部で6章あるが、この章による区分けは13世紀以降に定着した。節による区分が行われるようになったのは16~17世紀以降であると以前の説教で述べたが、章と節がセットで区分されるようになったのは、英語訳聖書では1560年のジュネーヴ聖書以降である。つまり、我々が当たり前のように感じている聖書の章と節における区分は、ずっと昔には行われていなかったということである。説教には色々なスタイルがあるが、この区分された節を一つ一つ見ていく説教方法は、我々の記憶に対して良い作用を及ぼす。ピューリタン神学者のトマス・ワトソンも言っているが、聖書を秩序立てて見ていくのは我々の記憶を助けるのである。他にも、同じ書を毎週連続して見ていくのであれば、内容の流れを掴むことが出来るので、理解もし易くなるなるのではなかろうか。
それでは、さっそく4節目から始めていきたいと思う。
①『私たちの神であり父である方のみこころによったのです。』(1章4節)
まずここで言われている『私たち』とは「神」と「父」の両方にかかっている。つまり、「私たちの神」また「私たちの父」ということである。それで、我々がこの御方を神また父と呼ぶことが出来るのは、ただ主なるキリストのゆえにそうなのである。我々の贖いとなられたキリストのゆえに、我々はこの御方を神・父として持つことが出来るのであって、もし主なるキリストが除外されるのであれば我々はこの御方を神また父として持つことが出来ない。
先週はこの4節目における前半部分から、我々が悪の世界から救いだされたことについてかなり詳しく見たが、パウロはここで、その救いはただ神の御心によるのであると述べる。つまり、救いは、我々の意思や行ないによるのではないということである。父なる神が、一方的に我々を愛し、選び、憐れみ、キリスト・イエスにあってご自分の子となるのを欲されたからこそ、我々は悪の世界から救いだされてキリストのものとされるに至った。我々の意志とか欲求とか行ないとか家柄とかではなく、一方的な神の御心と御意思のゆえに救われたのだということは、ヨハネが真のクリスチャンについてこう述べていることからも分かる。『この人々は、血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ、神によって生まれたのである。』(ヨハネ1章13節)このことについては、キリストが言われた御言葉を見たなら、更によく分かるであろう。主は弟子たちにこう言われた。『あたながたがわたしを選んだのではありません。わたしがあなたがたを選び、あなたがたを任命したのです。』(ヨハネ15章16節)すなわち、我々の救いにおける全ては、何もかも、ただ神の御心、神による選びにかかっているのである。
パウロは、ここで我々の救いを主なる神にだけ結びつけているが、彼はこのように書いている時、救いを人間の行ないに結びつけている律法主義者・行為義認論者どもを念頭に置いていたに違いない。何故なら「救いはただ神の御心によるのだ。」と述べるのは、換言すれば「救いは行ないにはよらない。」ということに他ならないからだ。我々は、パウロがこの手紙において、人間の行ないによって救われようとしている呪われるべき異端者どもに対抗しているのだということを忘れるべきではない。
また、ここでは「我々が救われたのは父なる神の御心のゆえである。」ということが言われているが、それは、キリストが父なる神の御心に従われたということを示している。どうしてかといえば、パウロがこう言うのは、暗に「キリストは父なる神の御心を実現するために、父なる神に従われた。」と言っているのも等しいからだ。このことは、まことである。聖書が教えているように確かにキリストは、父なる神の立てられた救いの御計画を実現するため、父なる神に完全に従われ、その救いのために永遠の贖い成し遂げられたのである。(※2016/04/03追加)
5節目に行くが、ここでパウロは大いなる感動をもって唐突にこう祈る。
②『どうか、この神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。』(1章5節)
ヘブル人たちは、神の栄光および尊厳などについて、文書中に書きしるす特徴を持っていた。これもその一つである。そのように神やその栄光を願ったり求めたりしている箇所は、他にも沢山存在している。例えば、ローマ11章36節。『というのは、すべてのことが、神から発し、神によって成り、神に至るからです。どうか、この神に、栄光がとこしえにありますように。アーメン。』また、ピリピ4章19~20節。『また、私の神は、キリスト・イエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなたがたの必要をすべて満たしてくださいます。どうか、私たちの父なる神に御栄えがとこしえにありますように。』他には、ユダ書の24~25節、黙示録の1章5~6節などもそうである(※①参照)。
神の輝かしい栄光が、被造物である時間(また空間)という流れの中で、永遠にあらわされることこそ、神がこの世界を造られた目的・理由であった。この世界とは、神の栄光、神の聖なる御性質がとこしえまでも明らかにされるためにこそ、創造されたのである。だから、パウロやその他の聖書記者たちがこのように神の栄光を求めているのは、まことに理に適っていることであるのが分かる。ある牧師は「神に栄光がありますように!」と叫んでいた。カルヴァンのキリスト教綱要における最後の文章は「神に賛美あれ。」であった。これらの例のように神に栄光があるようにとか、神が褒めたたえられますようにとか願うのは、非常に好ましいことである。神の栄光こそ求められるべきものであり、またこの世界は神の栄光のためにこそ造られたのであるから、我々も自分の人生における視点を神とその栄光に据えるべきであろう。
6節目に行きたい。
③『私は、キリストの恵みをもってあなたがたを召してくださったその方を、』(1章6節)
この言葉は、「あなたがたが救われたのはただ神の恵みによるのだ。」ということを教えている。パウロは4節目で言ったのと同じようにここでも、クリスチャンの救いにおける理由・要因を、ただひたすら主なる神に結び付けている。このようにパウロが言っているのは、人間の行ないによって救われるなどと誘惑してガラテヤ人たちをかき乱していた愚か者どもとは、まったく正反対である。
④『あなたがたがそんなにも急に見捨てて、ほかの福音に移って行くのに』(1章6節)
パウロは、ガラテヤ人たちが神を見捨たその「スピード」のことについて言っている。「ガラテヤ人たちよ。あなたがたは超特急で正しい道から逸れてしまった!!!」と、あからさまに彼は言うのである。
以前の説教でこのガラテヤの諸教会はパウロによって建てられたということについて述べたが(厳密には「キリストがパウロを通して建てられた。」というのが正しい)、パウロの建てた教会でさえ、この有り様である。このパウロは使徒として特別に選ばれた傑出したクリスチャンである。それゆえ、多くの人が「あのパウロによって建てられた教会だから大丈夫に違いない。堅実に成長していくことであろう。」と思ったとしても不思議ではない。しかし、そのようなことは無かった。パウロによって建て上げられた教会でさえ、かき乱され、惑わされ、悲惨な状況になってしまった。パウロの教会でさえこうなのだから、使徒ではない教師によって建てられた教会がこのようになってしまった場合(つまり異端的になること)があったとしても、何も不思議ではない。これは、非常に嘆くべきことである。
このパウロは『すべての聖徒のために、忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。』(エペソ6章18節)と言ったのだから、当然、ガラテヤ人のことも祈っていたことは確かである。パウロの主にある伝道によって救われたガラテヤの聖徒たちの霊と信仰に関して、心から祈っていたことであろう。『お互いの霊的成長に役立つこととを追い求めましょう。』(ローマ14章19節)とパウロ自身が述べているのだから、パウロがガラテヤの聖徒たちにおける霊と信仰のことについて祈っていたのは確実である。しかし、パウロが祈っていたにも関わらず、神の御計画はガラテヤの聖徒たちが異端者どもに翻弄されてしまうことであった。我々の神は、ガラテヤ人たちがかき乱されるようになるのを、永遠の昔からお定めになっておられた。だからこそ、このようにガラテヤの諸教会は悲惨な状態になってしまったのだ。しかし、そのようになるのは、神が御自身の聖なる御心を遂行するためであった。つまり、ガラテヤ人たちが翻弄されることによってパウロがそのガラテヤ人たちに対して信仰義認に関する手紙を書くことになり、この時代以降に生まれる全てのクリスチャンがその手紙によって真理を学ぶという御心である。これは、もしガラテヤ人たちが愚か者どもに惑わされなかったなら、一体どうなっていたかと考えたらよく分かるであろう。もしガラテヤの諸教会が誰にもかき乱されずまったく平和でいられたとしたら、パウロもこのような手紙を書く必要が無かったから、ガラテヤ人も我々もこの手紙から学んでいることが無かったのだ。すなわち、全ては神の摂理によって起きたことなのである。
ものすごい速度をもって神を見捨ててしまったこのガラテヤ人のことを考えたら分かるように、人間とは非常に弱く、惨めな存在である。特に、救われてからまだ少ししか経っていない兄弟姉妹は、ほんのささいなことにも揺り動かされやすい。ある救われたばかりの兄弟は、ラジオから流れてくる仏教の輪廻転生の教えを聞いて、信仰がグラついてしまった。もし神が守って下さるのでなければ、我々もこのガラテヤ人たちと同じ有り様になってしまうであろう。
それでは、このガラテヤ人たちが真理から離れてしまったその不敬虔の理由はいったい何であろうか。それは、彼らがキリスト・イエスの御救いをしっかりと直視していなかったからである。何故なら、もしキリストにある贖いの恵みについて正しく考え、それを揺るぐことなく自分自身のうちに保つのであれば、訳の分からない間違った教えに迷いこむことなど無いからである。ヘブル書の著者は『兄弟たち。あなたがたの中では、だれも悪い不信仰の心になって生ける神から離れる者がないように気をつけなさい。』(ヘブル3章12節)と言っている。この御言葉から分かるように、信仰によって神についての理解や真理といったものをしっかりと抱きしめ、直視し続けるのでなければ、それらのものから離れてしまうことになったとしても不思議ではない。ガラテヤ人たちは、キリストとその救いを信仰によって理解・把握・認識する力に欠けていたので、やすやすと、超特急で、正しい道から逸れてしまったのだ。これは、自分の妻のことを一心に愛していない愚かで不貞な夫が、他の女性をいとも簡単に心に慕ってしまうのと似ている。妻を一途に見つめているのであれば他の女性と不倫をすることなど心に思うことすらしないだろうが(なぜなら真に貞潔な夫であればそのようなことは嫌悪するはずだからである)、妻に対する愛が弱いか、妻への愛に純粋さが欠けているがゆえに、不品行という忌むべき悪事に簡単に誘い込まれてしまうのである。同じように、ガラテヤ人たちもキリストに対する愛と信仰と貞潔さが弱々しかったため、不倫をする者のように、簡単にキリストから離れてしまった。
⑤『驚いています。』(1章6節)
聞いただろうか。パウロは、キリストから離れ、父なる神を見捨て、真理に従わなくなってしまった(※②参照)『愚かなガラテヤ人』(ガラテヤ3章1節)に対し、愛をもって優しく接している。彼は激怒しつつ強烈な雷撃をガラテヤ人に対してあびせることも出来た。例えば、彼は軽蔑しつつこう言うことも出来たであろう。「程度の低い、ふざけた、不忠実で不信仰な惨め極まりないガラテヤ人たち。あなたがたは自分が一体どのような状態にあるのか分かっているのか。あなたがたはあまりにも酷すぎる。まさか地獄に行きたいというのでもあるまい。自分たちがどれだけ神に対して愚かなことをしているのか弁えなさい。そして恥じ入り、泣き悲しみなさい。私は非常に怒っている。異端に陥ってしまったことを悔い改めるのだ。さもないと、私は、舌の鞭をもってあなたがをますます打ちたたこう。」しかし、彼はこのようには言わないで、穏やかな態度をもって『驚いています。』と優しく語りかけるのである。彼は6章1節で『もしだれかがあやまちに陥ったなら、御霊の人であるあなたがたは、柔和な心でその人を正してあげなさい。』と言っており、惑わされてしまったガラテヤ人が正しい道に復帰できるようにとさえ、御霊の愛をもって願うのである。つまり、『私の子どもたちよ。』(ガラテヤ4章19節)とパウロがガラテヤ人に対して言っていることからも分かるように、彼は、あたかも母親であるかのように慈愛と穏やかさをもってガラテヤ人に語りかけているのだ。この『驚いています。』という穏やかな言葉は、パウロのガラテヤ人に対する慈愛および兄弟愛を豊かに明かしている。
パウロが、行為義認に陥ってしまったにも関わらずガラテヤ人に対して『驚いています。』と言ったのは、ガラテヤ人たちが悔い改めるならば赦されるということを教えている。パウロはガラテヤ人たちに対して「あなたがたは行為義認に陥ってしまったから神の子どもでは無いことが明らかになった。あなたがたは救われたように見えたが、実は救われていなかったのだ。」とは言っていないからだ。彼はガラテヤ人に対して『兄弟たち』(ガラテヤ1章11節、3章15節、4章12節)また『私の子どもたち』(4章19節)更には『神による相続人』(ガラテヤ4章7節)とすら言っている。つまり、ガラテヤ人のことを救われているクリスチャンであるとパウロは認識しているのである。このことから、何が分かるだろうか。それは、もしクリスチャンと呼ばれる者の誰かが、弱さや愚かさ、また未熟さのゆえに行為義認の信仰に迷いこんでしまったとしても、もし悔い改めるのであれば必ず赦されるということである。使徒であるパウロは、行為義認に惑わされてしまったガラテヤ人に悔い改めへの道を閉ざしてしまってはおらず、むしろ、正しい信仰に復帰できるようにさえ願っている。だから、同じように、我々の仲間のうち誰かが行為義認の信仰に陥ってしまったとしても、もしその人が行為義認を捨てるのであれば確実に赦される。例えば、あるプロテスタントの教会のクリスチャンが、ローマ・カトリックに騙されて行為義認の信仰に陥ってしまったとする。彼は、カトリック教会の教えのほうが正しいと感じたので、毎週カトリック教会に通うようになってしまった。この場合、このカトリック教会に行ってしまった人に対して正しい教理である信仰義認を伝えるなどして、その人が行為義認を捨て去るのであれば、そのカトリック教会に行ってしまった人は赦されるであろう。しかし、もしその行為義認に迷いこんでしまった人がどれだけ説明されても一向に異端的信仰から離れず、死に至るまでも悔い改めないのであれば、その場合は彼が本当は救われていなかったことが明らかになってしまう。ここで我々は「ほう、そうか。行為義認に陥ってしまったとしても、悔い改めるならば赦されるのか。」などと思って、気を緩めるべきではない。確かにガラテヤ人たちのように行ないによる義認の教理に騙されてしまったとしても、もしそれを捨てるのならば正しい道に復帰することが出来るのだが、あくまでも我々はこの異端思想に警戒し、それを自分から遠ざける必要がある。それは、罪を犯しても悔い改めれば赦されるというので、罪を犯したり、また罪を避けるようにしなくても良いということにはならないのと同じである。
次は7節目である。
⑥『ほかの福音といっても、もう一つ別に福音があるのではありません。』(1章7節)
パウロは6節目で『ほかの福音』と言っているが、この7節目において、そのようなものは本来的には福音ではないのだと教える。言うまでもなく、我々の主なるイエス・キリストの聖なる福音は唯一であって、複数あるのではない。もし真の福音でなければ、そんなものは福音ではない。それは、聞いても救いを受けさせることのない、ただの紛い物に他ならない。つまり『ほかの福音』とはすなわち、「にせの福音」ということである。すなわちパウロはここでガラテヤ人に対して、こう言いたいわけである。「あなたがたは福音でも何でもないものを信じてしまった。あなたがたが信じてしまったのは福音とは全く言えないものだ。それは福音の<にせもの>なのである。」このようにガラテヤ人が「偽物の福音」に騙されてしまったと言ったあとで、パウロは、その偽物の福音が異端者どもによるものであると説明する。その説明とは、7節目の後半部分である。
⑦『あなたがたをかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。』(1章7節)
いま語った「偽の福音」とは、かき乱す者たちがキリストの福音を歪めてしまおうとすることによってもたらされたものである。
それで、福音を歪めてガラテヤ人たちをかき乱すこの異端者どもの目的とは、キリストの聖徒たちを救いから引き離し、神の御国を破壊することである。彼らは自分自身で意識していたとしてもしていなかったとしても、サタンに味方しており、悪魔の陣営を拡大あるいは強化させようとしている。そのようなことは、決して神の御心に適ったことではない。それはサタンの喜ぶことに他ならない。キリストの福音を変えようとする彼らは、何と忌まわしいことだろうか。パウロが『いっそのこと不具になってしまうほうがよい』(ガラテヤ5章12節)と彼らに対して言うのは、もっともである。彼らは言うなれば、呪わるべき異端者、狂った霊的障害者、キリストの敵、闇の使い、猛毒をまき散らす邪悪な者どもである。このような者どもは、地獄に投げ込まれてサタンとともに永遠に裁かれるであろう。キリストの福音を変えることへの報酬は「永遠の火による苦痛」である。
『あなたがたをかき乱す者たちがいて、』…とパウロは言う。つまり「ガラテヤ人たちは、かき乱す者たちからかき乱されてしまっている。」ということだ。ここから分かるのは、パウロがガラテヤ人に対しては「被害者」、かき乱す者どもに対しては「加害者」という認識を持っているということである。だから、パウロは被害者であるガラテヤ人に対しては、あたかも悪人に騙されて非行に走ってしまった少年を愛をもって叱責する大人でもあるかのように振る舞う。他方、加害者であるかきみだす者に対しては、あたかも少年を非行に走らせるという悪事を行なった愚か者に対して警察官がどなり声をあげるかのように敵対する。このことは、このガラテヤ書をざっと見るのであればすぐにも分かることだろう。「被害者であるガラテヤ人」に対して「加害者であるかき乱す者ども」がいるという、この構図が分かるならば、この手紙がますます理解しやすくなるに違いない。
当時ガラテヤの諸教会で起こっていたこのようなことは、霊的な戦いであって、神の陣営と悪魔の陣営における戦争であった。神の陣営にいるガラテヤ人たちは、行ないによって救われようとする呪われるべき愚者どもに騙され、霊的な攻撃を受けていた。この状況において、パウロはこの呪われるべき愚者どもからガラテヤ人たちを守り、この異端者どもを追い払おうとしているのだ。これは肉における戦いではなく霊における戦いであるが、それは、パウロがエペソ書においてこう語っている通りである。『私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗やみの世界の支配者たち、また、天にいるもろもろの悪霊に対するものです。』(エペソ6章12節)当時、闇の勢力に属している敵どもが、ガラテヤ人たちを光の世界から引き離そうとして霊的な攻撃を加えていたのである。
⑧最後に:我々も警戒すべきである
我々は、行ないによって救いを獲得しようとする思想に注意すべきである。自分の行ないによって救われることができると思っているカトリックは勘違いをしており、自分たちが霊的に盲目であることをみずから示している。キリスト教に次ぐ宗教人口をもつイスラム教(2007年時点で13億8700万人:ブリタニカ・オンライン・エンサイクロペディアより)も、人間の努力によって天国に入れるのだと信じている。彼らは1日5回の礼拝を行ない、礼拝・施し・食物・その他いろいろな守るべき規定に従わなければならない。イスラム教の開祖であるマホメット(570?―632)によると、イスラム教信仰のために戦争で死んだ信者たちはみな、即刻パラダイスに行くとされていた。それゆえイスラム教徒たちは戦争の際に天国のことを思いつつ、死という恐怖の障壁に妨げられることもなく、みずから大胆に突撃していったのである。この手紙でパウロが対抗している律法主義者どもも、律法の行ないによって人は救われるのだと夢想していた。このように行ないによって救いを得ようとするとは、何という思い違い、何という霊的盲目であろうか。しかし、彼らが自分の行ないや功績によって救いを得られるなどと考えているのは、一体どういった理由によるのだろうか。それは、(先ほどもいくらか述べたことだが)彼らがキリスト・イエスとその救いを、一心に、真面目に、純粋に直視していないからである。もしキリストとその救いに満足しているのであれば、行ないによる救いに心を傾けることもない。しかし救い主なるキリスト・イエスに満足していないのであれば、その人の心は行ないにやすやすと誘い込まれてしまう。ルターもガラテヤ書講解の中で言っていることだが、人はキリストか行ないか、どちらか一つしか取ることが出来ない。もしキリストを取るならば行ないによる救いは退けられ、行ないを取るならばキリストによる贖いの恵みは退けられてしまうのだ。ルターと私も同じ意見であるが、両方とも我々が取ることなど出来ないのである。だから、キリスト・イエスとその救いをしっかりと自分のものとしていない者らは、必然的に行ないによる救いの思想に落ち込むのである。それで、キリストではなく行ないによって永遠の命を得ようとしている者たちは、「業の契約」(※③参照)を神と結んでいた堕落以前のアダムのようである。堕落する前のアダムは完全な状態であり、神に対する完全な服従を貫き通すのであれば、自分自身の行ないによって救いを獲得することが出来た。しかしアダムが罪を犯したことにより堕落して不完全な存在となってしまったので、人類はもはや業の契約によって救いを得るということにおいて不適格な存在となってしまった。アダムが堕落してから神は「恵みの契約」によって人が救いを得られるよう定められた。この契約は簡単に言ってしまえば、神のキリスト・イエスにある恵みのゆえに、信仰によって、人は救いの契約のうちに招き入れられることが出来る、というものである。つまり、この恵みの契約における救いでは、行ないは求められていない。人類が「業の契約」によって救いを得られる時代は、とうの昔、つまり今から6000年前におけるエデンの園での堕落の時に、過ぎ去った。今は、キリスト・イエスによる恵みの契約を神と結ぶことによって救いを得られる時代である。もし恵みによって救われると信じているのでなければ、その人の魂には、キリストにある平和と安心感は存在していない。信仰義認に立っているクリスチャンの場合、信仰によっていわば受動的にキリストを受けているのだから、(いかなる時もそうとは限らないが)その魂は平安を感じることが出来る。しかし、キリストではなく人間の行ないによって救われると勘違いしている者らはそうではない。彼らは、不完全かつ罪深い自分自身の行ないに救いを基づかせているのだから、まったき平安を得ることなど出来るはずがないからである。罪深く惨めな堕落している人間とその行ないに救いがかかっているのであれば、どうして安心したり、救いにおける心地のよい感覚を味わうことが出来るだろうか。絶対に不可能なことである。それは、今にも倒壊してしまいそうな家に住んでいて安心することが出来ないのに似ている。最後になるが、我々が良い行ないに富み、キリストの御心を実行し、聖書に喜んで従い、敬虔な人生を送っていると、サタンが「おい、行ないによってお前は救われることが出来るのではないか。」とささやいてくることもあるかもしれない。しかし、キリストの民である我々は騙されるべきではなく、思い違いをすべきでもない。我々は行為義認という誤謬を警戒し、聖なる信仰義認の教理に堅く立ち続けよう。我々の主なるキリスト・イエスは御自身の民が行ないによらず、恵みのゆえに、信仰によって救われることが出来るようにと御自身の命を犠牲にして下さったのである。
※2016/04/03追加
確かに、御子キリストは御父の御心と御命令とに完全に従われた。実に、この御子と御父における聖なる親子関係のゆえに、聖書では『両親に従いなさい。』(エペソ6章1節)とか『あなたを生んだ父の言うことを聞け。』(箴言23章22節)と命じられている。何故なら、この世界は、神の御性質を被造物を通してあたかも鏡のようにあらわすためにこそ造られたからである。それゆえ、御子が御父に従われるかのごとく自分の親に従う子どもは幸いであって、その子どもは神の御心に適うことをしているがゆえに祝福を受けるであろう(もちろん、子が親に従うべきなのは聖書が命じる命令に違反しない限りにおいてであって、親に従うことが神に反逆する言動となるのであれば従う必要はない)。
[本文に戻る]
※①
『あなたがたを、つまずかないように守ることができ、傷のない者として、大きな喜びをもって栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち、私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威が、私たちの主イエス・キリストを通して、永遠の先にも、今も、また世々限りなくありますように。アーメン。』(ユダ24~25節)
『イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また、私たちを王とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とが、とこしえにあるように。アーメン』(黙示録1章5~6節)
[本文に戻る]
※②
『あなたがたはよく走っていたのに、だれがあなたがたを妨げて、真理に従わなくさせたのですか。』(ガラテヤ5章7節)
[本文に戻る]
※③
「業の契約」と「恵みの契約」については、ウェストミンスター信仰告白7章<人間との神の契約について>において、こう書いてある。
Ⅰ.
神と被造物との間の距離は甚だ大きく、理性的被造物は彼らの創造主としての神に服従する義務を負わされているにも拘らず、神が契約によって表わすことをよしとしたもう神の側の自発的な何らかの懇切さによるほか、神から何らかの成果を、彼らの祝福また報いとして、獲得することは決してできなかったほどである。
Ⅱ.
人間との間に結ばれた最初の契約は、業の契約であり、それによって、完全な、そして個人的な服従を条件として、生命がアダムに、さらに彼を通じて彼の子孫に約束された。
Ⅲ.
自身の堕落によって、この契約による生命に、自身を不適格なものとした人間に、主は第二の、普通に恩恵の契約と呼ばれる契約をなすことをよしとしたもうた。これによって、主は、罪人に、イエス・キリストによる生と救いとを無償で提供したまい、彼らが救われるためには彼を信ずる事を彼らに要求し、生命に定められたすべてのものに、彼らをして信ずることを喜びとし、信ずることを得せしめんがために彼の聖霊を与えたもうた。
Ⅳ.
この恩恵の契約は、遺言者イエス・キリストの死と、永遠の遺産とに関連して、それに属し、そこに教えられるすべての事物と共に、遺言の名によって、聖書の中にしばしば示されている。
Ⅴ.
この契約は、律法の時代と福音の時代とにおいて異なって実行された。律法の下に在っては、それは、約束、預言、犠牲、過越の子羊。その他ユダヤ人達に教えられた形式や儀式によって実行された。それらはすべて、来るべきキリストを予示するものであり、聖霊の働きによって、選ばれた者たちを、彼らに全き罪の赦しと永遠の救いとを得させたところの約束されたメシヤへの信仰に導き、養い育てるのに、その時代にとっては充分であり、有効であった。そしてそれは旧約と呼ばれる。
Ⅵ.
福音の下に、その実体なるキリストが現示されたとき、この契約が実行される様式は、言葉の説教と、洗礼と主の晩餐との礼典との執行である。それらは、数においてはより少なく、実施されるときはより単純であり、栄えにおいて劣っているが、契約は、これらにおいてユダヤ人と異邦人とを問わず、すべての民に、勝れた完全さと明白さと、霊的効果とにおいて呈示される。そしてそれは新約と呼ばれる。従って本質において異なる恩恵の二つの契約があるのではなく、様々な配剤の下に一つの同じ契約があるのである。
(信教出版社「信条集 後篇」p189―190)
[本文に戻る]
ガラテヤ人への手紙1章8~12節(2015/12/13説教)
『しかし、私たちであろうと、天の御使いであろうと、もし私たちが宣べ伝えた福音に反することをあなたがたに宣べ伝えるなら、その者はのろわれるべきです。私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います。もしだれかが、あなたがたの受けた福音に反することを、あなたがたに宣べ伝えているなら、その者はのろわれるべきです。いま私は人に取り入ろうとしているのでしょうか。いや。神に、でしょう。あるいはまた、人の歓心を買おうと努めているのでしょうか。もし私がいまなお人の歓心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。兄弟たちよ。私はあなたがたに知らせましょう。私が宣べ伝えた福音は、人間によるものではありません。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。』(ガラテヤ1章8~12節)
今現在、我々が使っているこの新改訳聖書だが、今の時点においてはこの訳がもっとも良いだろうと思われる。というのも、消去法でこの新改訳聖書にせざるを得ないからである。文語訳聖書は格調が高く、霊的な影響という点についても致命的な問題はないと感じられるし、今に至るまで良い評価をされてきた訳なのだが、訳における文体が今の時代になじみにくい。新共同訳聖書は多くの教会で使われているが、カトリックと(プロテスタントの)共同翻訳であるから、我々は採用することをしない。口語訳聖書は文体的に読みやすく、新改訳を見て分からなかった箇所を口語訳で確認すると意味が分かるようになるケースが多くあるが、神学的にはリベラルであって、キリストの神性を否定しているので、霊的な影響を考慮して我々は使うべきではないと考える。この口語訳聖書にリベラルの傾向があったからこそ、聖書信仰に立った翻訳聖書―つまり新改訳聖書が生まれることになったのだ。聖霊派の現改訳聖書はビザンチン写本から訳しており、この点については好ましいのだが、まだ確認していない。他にも新契約聖書とか、尾山令仁師による現代訳聖書などがあるが、こちらのほうも今のところ、まだ確認していない。これらの翻訳聖書はこれから確認したいと思っているが、おそらく様々な理由により、今後使うことにはならないだろう。このように消去法で考えるならば、この新改訳聖書こそ今のところ最適であると感じられる。
最近は再び説教の際、原稿を用意するようになったが、書いてあることを全て語れておらず、いくらか飛ばしつつ語っている。主の恵みにより教会のホームページに原稿をそのまま載せてあるので、もし神に導かれるのであれば、こちらの方も確認してほしい。原稿のほうが口で語るより文章表現が的確であり、語調もきびきびとしている。
それでは先週に引き続き、8節目から見ていきたいと思う。
①『しかし、私たちであろうと、天の御使いであろうと、もし私たちが宣べ伝えた福音(※2016/04/03追加)に反することをあなたがたに宣べ伝えるなら、その者はのろわれるべきです。』(1章8節)
真理の敵対者、呪われるべき異端者というべき「かき乱す者」たちに対してパウロはこの手紙で対抗しているのだが、彼は、この偽使徒たちに対抗するために聖なる御使いすらも持ちだしている。もしキリストの福音を間違って伝えるのであれば、天使たちでさえ呪われてしまうとパウロは言う。つまり福音とは、きよく、汚れもない聖なる天使たちでさえもし歪めるならば呪いを受けてしまうほどに神聖なものであるということだ。この御使いのことだが、彼らは聖なる被造物であって、罪や悪や不正や愚かなことを行なうことがないのだから、福音を歪めて伝えるということは万が一にも行わないはずである。天使が福音を間違って伝えるというのは、悪魔が真にきよい愛の心をもって親切なことを語るのと同じぐらいあり得ないことだ。しかし、パウロはあえてこの天使を持ちだす。つまり、パウロはここでこう言いたいのである。「御使いたちでさえ間違って福音を伝えるならば呪われるのを避けられないのだ。だから福音を歪めるということは許しがたい極悪である。このことから、福音のあまりの神聖さが君たちにも理解できるだろう。またこの福音を曲げることは絶対にしてはならないことが分かるだろう。」間違うことのない天使たちをすら「言論の武器」として持ち出し、また呪いについても言及しているということから、パウロがかき乱す者どもに対して、どれだけ激しく敵対しているかが分かる。
パウロはここで「呪われるべき者ども」のことについて言っているが、これは明らかに、当時ガラテヤ人たちを惑わしていた偽使徒たちのことである。この手紙を受け取ったガラテヤ人たちも、行ないによって義と認められるなどと主張している律法主義者たちのことをパウロが言っていることが分かったであろう。
『その者はのろわれるべきです。』とパウロは言う。ここで使われている呪いという言葉は、新改訳聖書の下の箇所にある※印を見れば分かるが、ギリシャ語で「アナテマ」(αναθεμα)であり、ヘブル語では「ヘレーム」という言葉がこれに当たる。英語訳聖書では、「anathema」「accursed」「cursed」などと訳されている。このアナテマという言葉は、「呪われる」「どかされる」「引き離される」「斥けられる」また「神との関係から閉め出される」「神との交わりから断たれる」などといった意味をもっている。この言葉が他に新約聖書で使われている箇所は、Ⅰコリント12章3節。『神の御霊によって語る者はだれも、「イエスはのろわれよ。」と言わず、…』また、Ⅰコリント16章22節。『主を愛さない者はだれでも、のろわれよ。』他にはローマ9章3節もそうである。『もしできることなら、私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて、のろわれた者となることさえ願いたいのです。』新約聖書でこの「アナテマ」という言葉が使われているのは、いま挙げた3つの箇所と、いま我々が見ているガラテヤ書のこの2つの箇所、つまり計5つである。ヘブル語のヘレームの場合、旧約聖書では、聖絶することなどに関して使われている(※2016/03/06追加)。このアナテマという言葉は非常に恐るべきものであり、それは致命的・破壊的・殺傷的な内容を持ったものである。何故ならこの言葉が言われるということは、その言われた者を完全に断罪することであって、その者が神の民・キリストのものではないということを宣言するのも同じだからである。
パウロは、ガラテヤ人たちを惑わしていた偽使徒どもが呪われるべきだと、ここで大胆に言う。それはつまり、偽使徒どもがもうまったく神から引き離され、永遠に斥けられたままでいるように、ということに他ならない。だから、このように言うことは霊的な死刑宣言である。このようにアナテマが宣言されるということは、当時ガラテヤ人をかき乱していた律法主義者たちが選ばれていない者たちであったことを示している。彼らは、「悪魔の民」「永遠的な真理の敵対者」「地獄の相続人」「救いに予定されていない不幸な人たち」であった。このように「偽使徒どもは選ばれていない呪われし者だったのである。」と断言するのは私だけではない。カルヴァンも、この箇所でパウロが「自分の福音と異なった福音をもたらすものは、すべて悪魔であるとみなすように命じている。」(カルヴァン・新約聖書注解p26)と説明している。何故なら、先程アナテマという言葉を説明した時に述べたように、この言葉が発せられるということは、つまりこの言葉が向けられている対象に完全なる断罪を与えることも等しいからである。それゆえ、パウロが偽使徒たちにここまで激しく対抗し、『あなたがたをかき乱す者どもは、いっそのこと不具になってしまうほうがよいのです。』(ガラテヤ5章12節)とすら言っているのは理由なきことではないのが分かる。すなわち、彼ら<偽使徒ども>が呪われるべき地獄の民であるからこそ、パウロはこのように強い意志と確信をもって敵対しているのである。(※2016/04/17追加)
ルターはガラテヤ書講解の中で、忌まわしい教義を伝えている偽使徒たちだけでなく、その教義を受ける者たちも呪われるべきであると言っている。真理を愛する者であれば、ルターがこう言っているのは理解できないことではないだろう。しかし、ここでは確信をもって宣べ伝えた者たちにだけアナテマが宣言されており、それを受けたガラテヤ人に対しては呪いの言葉は言われていない。もし間違った福音を受入れてしまった人たちも(それを伝えた者どもと同じように)呪われて神から永遠に斥けられるべきだとすれば、悔い改めの余地が無くなってしまうことになる。だが、パウロはこの手紙において、弱さや愚かさや未熟さのゆえに異端思想を受入れてしまった人たちに悔い改めの道を閉ざしてはおらず、むしろ彼らが正しい道に復帰できるようにさえ願っている。だから、ここで言われている呪われるべき者とは、福音を歪めてそれを伝えた偽使徒どもにだけ限定されていると考えるべきである。これは、使徒ヤコブが『多くの者が教師になってはいけません。私たち教師は、格別きびしいさばきを受けるのです。』(ヤコブ3章1節)と言っていることからも分かるだろう。つまり、教えを受けるだけの信徒らはたとえ間違っても正しい道に復帰できるよう神が優しく導いて下さるのだが、確信をもって教えたり伝えたりする教師らは厳しく断罪されることも珍しくなく、呪いを宣言されてしまう者も中にはいるということである。恐らく、ルターは「福音を曲げられるということの忌まわしさ」という点に着目していたから、その曲げられた福音を受けた者たちも呪われるべきであると言ったのだと思われる。正しい福音に激しく固執していた彼にとっては(これは我々も見習うべき態度であるが)、信仰義認の真理を愛するあまり、曲げられた福音であれば、それを伝える者も受ける者も、ともに忌まわしい存在であると感じられたのであろう。あまり信仰義認の思想が感じられないのでヤコブ書を低く評価してしまったルターらしい言説である。しかし、ここでは神から永遠に断絶されるという呪いの言葉が書かれているのであるから、そのことを考慮すべきであろう。
カトリックは行為義認の思想をもったグループである。多くの信者たちが、自分の行ないによって天国に入ることが出来るのだと考えている。カトリックであれ、他のキリスト教教派であれ、行いによる救いの教理を伝える教師たちは、ここでパウロが言っている「呪われるべき者」と同じ存在である。パウロがここでアナテマの対象としているのは当時ガラテヤ人を惑わしていた偽使徒どもかもしれないが、この偽使徒どもと同じことをしている者らもアナテマに値するだろうことは確かである。ただ教えを受けるだけのカトリック信者たちにアナテマを宣告するのは行きすぎであると私は思う。一般信徒である彼らはプロテスタントである我々の仲間とは言いがたいが、ある意味においてはガラテヤ人たちと同じであり、もし行為義認の信仰を捨ててプロテスタントに改宗するのであれば正しい道に歩めるようになるからだ。だが、確信をもちつつ歪められた福音を伝えて人々を惑わす聖職者たちに対しては、パウロと共にこう言わねばならないだろう。『その者はのろわれるべきです。』イギリス国教会における有名な39ヶ条(聖公会大綱:1563年、1571年)の第18条目でも、同じようにこう言われている。「あらゆる人がその信ずるところの戒律または宗派によって救われる、従ってその戒律に従って、また自然の光に従って、勉めて品行を正しくすべきであるとみだりに言う者達は、呪わるべきである。」これは簡単に言ってしまえば「行為義認を伝える者どもは呪われよ。」ということである。行為義認に関して言及されたものではないのだが、ピューリタン神学者のトマス・ワトソンも、ローマ教会は呪われるべき者たちなのであると述べている(※①参照)。教会を訪ねては「イエスではなく、エホバこそ神なのです。」などと、ふざけた異端神観を教師たちに信じさせようとするエホバの証人どもにも、同じくこう言わねばならないだろう。『その者はのろわれるべきです。』
ここまで呪いのことについて語ったが、この8節目においてパウロは、使徒だけでなく天使たちですら、もし福音を曲げるのであればアナテマを免れないのだと述べる。これはつまり、「使徒や天使たちが呪われるほうが、福音が歪められるより遥かに良いことである。」ということに他ならない。このことから、ここでパウロがキリストの福音を天高く引き上げ、その唯一性・重要性を明らかにしていることが分かる。すなわち、福音には神聖さを保たねばならず、それを傷つけたり、曲げたり、誤って語ったりすることは絶対にしてはならないということである(※2016/04/24追加)。
この8節目で呪いのことについて書いた後、パウロは9節目においても同じ内容のことを繰り返してこう述べる。
②『私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います。もしだれかが、あなたがたの受けた福音に反することを、あなたがたに宣べ伝えているなら、その者はのろわれるべきです。』(1章9節)
ほぼ同じ内容のことが繰り返されるということは、その言われたことにおける重要性の高さを示している。キリストも、ルカ13章1~5節の箇所において、同じ内容のことを繰り返して言っておられる。『ちょうどそのとき、ある人たちがやって来て、イエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちのささげるいけにえに混ぜたというのである。イエスは彼らに答えて言われた。「そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、ほかのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない。わたしはあなたがたに言います。あなたがたも悔い改めないなら、みな同じように滅びます。また、シロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの十八人は、エルサレムに住んでいるだれよりも罪深い人たちだったとでも思うのですが。そうではない。わたしはあなたがたに言います。あなたがたも悔い改めないなら、みな同じように滅びます。」』2回も連続で言うのであるから、その言われたことは大変重要なことであって、この手紙を読んでいる我々もその重要性を感じることが出来るであろう。あまりにも重要であるからこそ、2回も連続で語るのである。今見ているこのガラテヤ書の箇所の場合、「福音を歪めたり変えてしまう行為は何があってもしてはならない!!!」ということが悟れるのではないだろうか。(※2016/02/07追加の文章)
ここでは2回も同じことを繰り返して語り、その言っている内容は同一であるのだが、1回目と2回目とでは少し言い方が変わっている。1回目(8節)では「私たちが伝えた福音に反することを述べる者は呪われよ。」と言い、2回目(9節)では「あなたがたの受けた福音に反することを述べる者は呪われよ。」と言っている。つまり、1回目では福音を伝えたパウロたちが基点となっており、2回目では福音を聞いたガラテヤ人が基点となって語られているのが分かる。しかし、1回目も2回目もパウロが言いたいことは「偽使徒どもは呪われよ!!」ということに他ならない。
また、パウロは8節目と9節目で『私』ではなく『私たち』と言っている。8節目では『私たちが宣べ伝えた福音…』と言い、9節目では『私たちが前に言ったように、…』と言っている。ここでパウロが「私」ではなく「私たち」と言ったのは、パウロとその仲間が信じている福音を、ガラテヤ人たちが精神的に強く感じられるようにしたのだと思われる。人間は誰でも「私(だけ)が信じている。」と言われるよりも、「(私一人だけでなく)こんなにも大勢の人たちが信じている。」と言われるほうが、より耳を傾けるものである。「こんなにも沢山の人たちが信じているのだから、そのゆえにあなたがたも私たちが伝えた福音に戻りなさい。」などと、信じる者の多さのゆえに正しい福音を信じるようにさせたのではなかっただろうが、しかし「私たち」と言うことによって、よりガラテヤ人がパウロたちの信じている福音に心を傾けるようにさせたのだろう。パウロはとにかくガラテヤ人たちを自分たちが伝えた福音に戻したかったのであるから、このように私が考えるのはふざけたことではない。これは以前、1章2節目における聖句を説明した際に語った原理と同じものである。
10節目に行きたい。
③『いま私は人に取り入ろうとしているのでしょうか。いや。神に、でしょう。あるいはまた、人の歓心を買おうと努めているのでしょうか。もし私がいまなお人の歓心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。』(1章10節)
ここでパウロは自己自身の弁護をしている。パウロはこの手紙において、1~2章までを自己弁護および偽使徒どもに対抗することに費やしている。これは一体どうしてなのか。それは、偽使徒たちに惑わされていたガラテヤ人に真の使徒であるパウロのことを認めさせ、当時教会をかき乱していた者たちをガラテヤ人の精神から遠ざけるためである。もっと簡単に言ってしまえば、パウロは、当時ガラテヤ人がパウロに対して抱いていた疑念をことごとく取り払おうとしたということである。
パウロはここで、自分には何の野心もないのだと述べている。パウロが人の歓心を求めず、ただ神に喜ばれようとして語っていたということは、彼が他の手紙で書いている箇所から分かる。彼はⅠテサロニケ2章4節においてこう述べている。『私たちは神に認められて福音をゆだねられた者ですから、それにふさわしく、人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。』ここで自己弁護をしているパウロは、つまりこう言いたいのである。「私は人からの愛顧を求めて語っているのではない。私はただ神の栄光を求めて語っているのだ。だから私の語っていることは純粋であり健全なものである。」ここで、キリストが語られた御言葉を思い浮かべる方もおられるかもしれない。すなわち、ヨハネの福音書7章18節である。『自分から語る者は、自分の栄光を求めます。しかし自分を遣わした方の栄光を求める者は真実であり、その人には不正がありません。』この御言葉から分かるように、その人が神の栄光を求めているなら、その人の語ることは純正・真実なものとなるであろう。しかし、人の歓心を買おうとしたり、愛顧を得ようとしたりするならば、その人の語ることには不正・誤謬が含まれかねない。カルヴァンも言うように、異端や誤謬といったものは、良くない心から生じるからである。
教師として召されている者は、人からの栄誉を得るという目的をもって語るべきではない。この10節目の御言葉から分かると思うが、もし人の歓心を買おうとするならば、その人はキリストに仕えることが出来ないであろう。確かに、人から反発されることを恐れず、真理を大胆に語るのであれば、それを聞いて気分が悪くなってしまった人たちが自分の敵対者となってしまうだろう。だが、そうなるのは仕方がないことだ。気を悪くした人たちが自分の属している陣営から遠ざかっていくかもしれない。カルヴァンも迫害の最中にある信仰者たちに対して容赦なく語ったので、色々と文句を言われて、多くの人たちがカルヴァンから遠ざかってしまった。(つまり、迫害されている信仰者に対して殉教を覚悟せねばならないという内容のことを大胆に言ったので、「カルヴァンは色々と言っているが、我々のように迫害における苦しい状況の中にいるのではないだろう。口で言うだけならば誰でも出来ることだ。」などと思われて非常に反発されたのである。)もし人の歓心を得ようとして妥協し、真理を曲げるのであれば、敵対者はほとんど生じないかもしれない。しかし、そうであってはならない。それは、キリストのしもべとして相応しくないことだからである。
このことから分かるのは、我々が「いかに人の歓心を買おうとしていないか。」という点についてある教師を見るのならば、その教師がどれだけキリストに忠実な教師であるかが知れるということである。もし、ある教師がまったく人の歓心を買おうとせず、とにかく真理をまっすぐに、また恐れず大胆に語っているのであれば、その教師は忠実な教師であろう。そういう教師は『キリストのしもべ、また神の奥義の管理者』(Ⅰコリント4章1節)なる教師として実に相応しいと言える。アウグスティヌスにカルヴァンやルター、クレルヴォーのベルナルドゥス、ピューリタン牧師およびジョナサン・エドワーズやスポルジョンなどはかなり厳しいことを大胆に語っているが、彼らは、間違いなく忠実な教師と言えるであろう。ここ日本では、真理に基づいて辛辣なことを言っている教師はあまり見られない。これとは逆に、もし人の歓心を買おうとしてばかりいるのであれば、その教師はキリストに喜ばれる教師とは言えない。異教徒に受入れられようとして自分のほうから進んで異教の思想・神学・風習などに迎合し、そのようにして真理に混ぜ物をする自由主義神学者たちがいるが、そのような者たちはキリストのしもべとは言えない。
11~12節目に行きたい。
④『兄弟たちよ。私はあなたがたに知らせましょう。私が宣べ伝えた福音は、人間によるものではありません。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。』(1章11~12節)
パウロはここで、自分が伝えた福音はイエス・キリストから直接的に受けたものであることを分からせようとする。パウロはガラテヤ人に伝えられた福音について、『私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。』と述べる。ここでパウロは、福音という救いを得させる聖なる使信における、その神聖性・天上性を、ガラテヤ人に対して伝えようとしているのではない。つまり、「福音はあまりにも素晴らしいものなのだ!!!」ということを説明しようとしているのではない。何故なら、そのようなことは言うまでもなく、もう分かりきっていることだからである。ここでパウロが言いたいこととは、「私の伝えた福音は(人間からではなく)キリストから受けたものであるから、絶対的に尊重されねばならず、あなたがたは私が伝えた福音に大いに注意を払わねばならない。」ということに他ならない。
『使徒の働き』の9章における箇所から、「パウロはアナニヤから福音を教えられたのではないのか。」と考える人もいるかもしれない。たとえそのように人間から教えられたかのように考えるのだとしても、パウロがただキリストの啓示によって福音を受けたということを妨げはしない。物理的・可視的にはアナニヤがパウロを教えたのだとしても、神がみずから御自身の福音をパウロに直接啓示して下さったのである。しかし、このことについてどのように考えるにせよ、もしパウロが福音を人間から受けたとか、人間から教えられたなどと考えるのであれば、ここでパウロが言っていることを否定することになってしまうだろう。
それで、ここでパウロが福音をイエス・キリストの啓示によって受けたと言うのは、歪められた福音に惑わされていたガラテヤ人たちを警戒させるためであった。何故なら、パウロの伝えた福音がキリストによるものであるというのであれば、パウロが伝えた福音とは違うことを教える福音は「まがい物」ということになるからだ。以前の説教でも言ったが、当時ガラテヤ人たちは、本当は福音でも何でもない「にせもの」の福音に騙されていた。だから、パウロは自分の伝えた福音こそキリストから受けた<真に正しいもの>なのだと言うことによって、ガラテヤ人から「福音もどき」を遠ざける必要があったのだ。
最後になるが、2つほど語って終わりにしたい。
⑤偶像崇拝者である行為義認論者
ある調査によると、アメリカにおけるカトリック教徒のうち43%もの人が「善行によって天国に入る。」などと信じている(Christianity Today.May.1980)。我々が今見ている手紙で言われているガラテヤ人たちを惑わしていた偽使徒どもも、行ないによって救われるなどという考えをもっていた。このように自分の行ないによって救いを得ようとする者たちは、みな偶像崇拝者である。何故なら、彼らは「イエス・キリストを信じる信仰によって救われる。」という神の教理よりも、「人間の行ないによって救われる。」という人間の教理を上に位置させているからである。神が定められた救いの方法よりも人間の考えによる救いを採用するということはつまり、(真の神ではなく)人間を神としていることも等しい。もし真の神を神としていたとしたら、その人は、神がお定めになった救いの手段を人間的な考えに優先させていたことだろう。だから、行為義認という偽りの教理を信じる者らは自分を神とする偶像崇拝者であると言える。
⑥信条と信仰義認とカトリックについて
今までプロテスタントの教会では、その信条において信仰義認の教理を正しく告白してきた。プロテスタントの信条は沢山あり、救いの教理以外の教理においては互いに内容が異なっていることも珍しくないのだが、この信仰義認の教理だけはどの信条もみな一致しており、聖書的である。例えば、改革派で有名な信条の中に、ブリンガーによる第二スイス信条(1564年)というものがあるが、そこではこう書かれている。「われわれは各人のわざによってではなく、神の憐れみと、イエス・キリストによる信仰によって義とせられるゆえに、使徒と共に、罪人は律法の行為や、わざによってではなく、信仰によってのみ義とせられると教え、かつ信じる。」(第15章:4)同じく改革派の有名な信条であるベルギー信条(1561年)でも、「われらは正しくパウロとともに、人の義とせらるるは律法の行為によらず、信仰によるなりという。」(第22条)と告白されている。これも有名なものだが、ルター派教会で今も採用され続けているアウクスブルク信仰告白(1530年)でもこう告白している。「人は、自分の力、功績、あるいは業によって神の前に義とせられることは出来ず、キリストのゆえに、信仰によって、代償なく、神の恩恵により義とせられる。」(第4条)アイルランド聖公会の信条だが、カルヴァン主義的であり、ウェストミンスター信仰告白に大きな影響を与えた「アイルランド聖公会大綱」(1615年)でも信仰による義認の教理が書かれている。「われわれは、われわれ自身の働きや功績のゆえでなく、われわれの主なる救い主イエス・キリストの功績によってのみ、信仰によって、神の前に義として数えられる。」(34条:義認と信仰について)他のプロテスタント信条でも、行ないによる義認が斥けられ、信仰による義認の教理が告白されている(※②参照)。それらの条項はどれも聖書に基づいたものであり、それゆえ「アーメン。」と言うに相応しいものである。確かに聖書では、御言葉が言っているように、信仰による義認が教えられている。すなわち、次の御言葉である。『人が義と認められるのは、律法の行ないによるのではなく、信仰による』(ローマ3章28節)『もしアブラハムが行ないによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし、神の御前では、そうではありません。聖書は何と言っていますか。「それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされた。」とあります。働く者のばあいに、その報酬は恵みでなくて、当然支払うべきものとみなされます。何の働きもない者が、不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。』(ローマ4章2~5節)このように信仰義認のことを言うと、行ないのことについて書いてある聖書の箇所を持ち出したり、ヤコブ書の行ないについて書いてある箇所を思い浮かべる方もいるかもしれないが、それらの箇所についての説明は昔の神学者たちがすでに行っているし、私はまた他の機会に語ることにしたい。それで最後の最後になるが、行為義認に立っているカトリック陣営が拡大したとしても、キリストの御国が拡大しているかどうか定かではない。何故なら、カトリック派は教会ではないか、または教会であるかどうか分からないのであって、一つだけ確実に言えることはそこが「聖書的な教会ではない。」ということだからである。果たしてこのような勢力に信者が増し加えられたといって「御国が拡大した。」と言えるのか。私には疑問に感じられる。我々が「御国が拡大した。」と自信をもって言えるケースは、信仰義認に立っているプロテスタント勢力に信者が増やされた場合である。今後、信仰義認に立つ教会が建てられ、信仰義認を信じるクリスチャンが増え、信仰義認を死守する教師が沢山になり、信仰義認を告白する信条が作られ(また告白され)、信仰義認を堅持する教派が増大するように願うものである。どうか、選民の罪のためにみずからを永遠の犠牲としてくださった我々の救い主なるキリストが、行為義認という異端思想を滅ぼし、信仰義認の教理を地に満たしてくださるように。アーメン。
※2016/04/03追加
パウロは、ガラテヤ4:13や1:11では「私が福音を宣べ伝えた。」と言っているが、この箇所では「私たちが福音を宣べ伝えた。」と言われている。ここで「私たち」と書かれているのだから、ガラテヤ人に伝道したのはパウロ一人だけではない。すなわち、ガラテヤの地方への伝道は、パウロの他にも複数の聖徒たちが動員されたということである。つまり、この箇所と9節目に書いてある『私たち』とは明らかに、ガラテヤ人にとって顔見知りの人たちである。
[聖句に戻る]
※2016/03/06追加
ヘレームという言葉が使われている旧約聖書の箇所は、たとえば次の箇所がそうである。「聖絶」という訳がなされている。
■レビ27:21
『その畑がヨベルの年に渡されるとき、それは聖絶された畑としてヤーヴェの聖なるものとなり、祭司の所有地となる。』
■レビ27:28
『しかし、人であっても、家畜であっても、自分の所有の畑であっても、人が自分の持っているすべてのもののうちヤーヴェのために絶滅すべき聖絶のものは何でも、それを売ることはできない。また買い戻すこともできない。すべて聖絶のものは最も聖なるものであり、ヤーヴェのものである。』
■民数記18:14
『イスラエルのうちで、聖絶のものはみな、あなたのものになる。』
■申命記7:2
『あなたの神、ヤーヴェは、彼らをあなたに渡し、あなたがこれを打つとき、あなたは彼らを聖絶しなければならない。』
■申命記20:17
『すなわち、ヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人は、あなたの神、ヤーヴェが命じられたとおり、必ず聖絶しなければならない。』
■ヨシュア6:17~18
『この町と町の中のすべてのものを、ヤーヴェのために聖絶しなさい。ただし遊女ラハブと、その家に共にいる者たちは、すべて生かしておかなければならない。あの女は私たちの送った使者たちをかくまってくれたからだ。ただ、あなたがたは、聖絶のものに手を出すな。聖絶のものにしないため、聖絶のものを取って、イスラエルの宿営を聖絶のものにし、これにわざわいをもたらさないためである。』
■Ⅰサムエル15:3
『今、行って、アマレクを打ち、そのすべてのものを聖絶せよ。容赦してはならない。男も女も、子どもも乳飲み子も、牛も羊も、らくだもろばも殺せ。』
新共同訳聖書では「滅ぼし尽くす」などと訳されている箇所もある。つまり、ギリシャ語のアナテマにあたるヘブル語『ヘレーム』とは、全く分離する、完全に断絶する、などといった意味をもつ言葉である。
[本文に戻る]
※2016/04/17追加
「だが、もし偽使徒どもが悔い改めて異端を捨てたとしたら一体どうなるのか。」と思われるかもしれない。私は言うが、偽使徒どもは悔い改めに至らせる神の憐れみを受けることを考慮されるべきではない段階にまで堕ちていたので、パウロは一貫して彼らを断罪しているのである。パウロの頭には、もしかしたら偽使徒どもも改悛するかもしれない、などという思念はまったく存在していない。それどころかパウロは、彼らを呪い、彼らが不具になることさえ望んでいる。つまり、ガラテヤ人を惑わしていた邪悪な者たちは、永遠の裁きを恐れながら待つより他ない、最終的な段階にまで行き着いていたのである。こういった者どもは憐れみを受けることなく地獄に突入していくのである。「もしも彼らが悔い改めたなら…」と思われる方は、キリストの福音を曲げるという罪がどれほど大きい邪悪であるか考えていただきたい。
[本文に戻る]
※①
トリエント公会議の述べるところ、ローマ教会の伝承は、pari pietatis affectu、すなわち、聖書を受け入れるのと同じほどの敬慕をもって受け入れられなくてはならないという。このようにして彼らは、自らを呪われるべき者としているのである。
http://homepage2.nifty.com/grapes/Wat104.htm
⇒「聖書は完全な基準か」の項目
[本文に戻る]
※2016/04/24追加
プロテスタントである我々がキリストの福音を隣人に伝える際、我々はパウロのように大胆に語るべきであるが、しかし神学的にはよく注意して語るべきであって、決して軽々しく語るべきではない。何故なら、福音を歪めるという過ちは致命的な過ちだからである。この福音伝道以上に思慮深く語らねばならない事柄はおそらく無いと思われる。もし福音を曲げるならば、偽使徒どものように呪われるに相応しい者とされるからである。もちろん、御霊がその人のうちにおられるのであれば福音を間違って語ることは出来ないだろうが、しかし、だからといっていい加減に語るべきではなく、あくまでも誤らないように慎重になるべきである。
[本文に戻る]
※②
■フランス信条(1559年:カルヴァン)
「イエス・キリストはかれを信じるものが亡びないように、われらに救いをえさせるために苦しみを受けたもうたといわれるごとく、われらはただ信仰によって義とされるとわれらは信じる。」(4―20:信仰により義とされること)
■第一スイス信条(1536年:ブリンガー)
「神の恩恵のかくも貴き大なる慈愛と神の御霊による真の聖潔とを、われらはわれらの功績や力によってではなくて、神から純粋に賜わり贈られた信仰によって得るのである。」(13条:キリストの恩恵とその功績がいかにしてわれらに与えられるか、そしてそのことからいかなる結実がもたらされるか)
■第二ロンドン信仰告白(1677年:バプテスト派)
「神は、効果的に召したもう人々を、また自由に義としたもう。これは、彼らに義を注ぎこむことによってでなく、彼らの罪を赦し、彼らの人格を義なるものと認め、受けいれることによってである。彼らのうちに何かが行われたとか、彼らが何かをしたとかのゆえにではなく、ただキリストのゆえにである。信仰そのものとか、信ずる行為とか、何かほかの福音的服従を彼らの義として彼らに帰することによるのでなく、律法全体に対するキリストの能動的服従や、その死における受動的服従をば彼らの唯一の義として彼らに帰することによってであり、彼らが信仰によってキリストとその義をうけ、これに依り頼むことによってである。この信仰も、彼らは自分でもつのでなく、神の賜物なのである。」(第11章、義認について:1節目)
■シュマルカルデン条項(1537年:マルティン・ルター)
「われらの神にして主なるイエス・キリストはわれらの罪のために死にわたされ、われらの義のために復活し給うた(ローマ4:25)。彼こそが「世の罪をのぞく神の子羊」(ヨハネ1:29)そして「神はわれらすべての者の不義を彼の上に置き」給うた(イザヤ53:6)。更に「全ての人、罪を犯したれば神の栄光を受くるに足らず、功なくして神の恵により、キリスト・イエスにあるあがないによりて義とせらるるなり…」(ローマ3:23以下)。この故にわれらはこのことを信じなくてはならない。聖パウロがローマ3章28節で「われらは思う、人の義とせらるるは、律法の行為によらず、信仰によるなり」、といい、更に(13:26)「自ら義たらんため、またイエスを信ずる者を義とし給わんためなり」といっているように、如何なる業、律法、あるいは功績によっては到達することも獲得することも出来ない、ただこの信仰によってのみ義とせられるということは明確である。」(第二部:第一の主要なる条項)
■和協信条(1576年:ルター派)
「Ⅱ.ゆえに、われらは、次のように、信じ、教え、また告白する。われらの過去・現在・未来の行為、功績、価値に関係なく、全く恩恵から、われらの罪をわれらに赦したうということそのものが、神の前におけるわれらの義である。なぜなら、神は、キリストの服従の義をわれらに付興し、また負わせたもうからである。そしてその義のために、われらは、神によって恩恵に受けいれられ、義と見なされる。Ⅲ.われらは、また、次のように、信じ、教え、告白する。信仰のみが、われらがキリストを、従ってキリストにおいて神の前に価値あるような義をとらえ得ることが出来るための手段また道具である。」(第3条:神の前における信仰の義について)
(新教出版社・信条集より)
[本文に戻る]
※2016/02/07追加の文章
我々が聖書の記述内容を真似して同じように行なうのはどうだろうか。つまり、重要なことを繰り返して語ったり書いたりするのはどうだろうか。別に悪いことではないし、人それぞれ行なうのは自由である。「お願いします。お願いします。」と言う人は珍しくないが、もし本当に願っていることであれば、人は自然と繰り返してしまうものである。参考までにアウグスティヌスの場合、手紙のなかで「祈ってくれ。」と繰り返し要請しているものがある。「とはいえ、もしあなたが滅びの内にいるわたしを見出されるなら、わたしが衰退して行かないで、完成されるようにお祈りください。祈って下さい、わが子よ、祈って下さい。…あなただけでなく、あなたの言葉からわたしを愛するようになられたすべての人たちも、わたしのために祈って下さい。…わたしたちのためにお祈り下さい。」(書簡231:ダリウスへの手紙Ⅱ)
[本文に戻る]
ガラテヤ人への手紙1章13~15節(2015/12/20説教)
『以前ユダヤ教徒であったころの私の行動は、あなたがたがすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。また私は、自分と同族で同年輩の多くの者たちに比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心でした。けれども、生まれたときから私を選び分け、恵みをもって召してくださった方が、』(ガラテヤ1章13~15節)
今はクリスマスの時期だが、このクリスマスに対してどのような思いを持っているだろうか。駅前のにぎやかな場所に行けばクリスマスの雰囲気が漂っており、街を歩けは多くの家の玄関のところにクリスマスリースが飾られているのが分かるし、テレビやインターネットを見てもクリスマスの時期なのだと感じさせられる。恋人たちは互いにプレゼントを贈りあい、家の中にクリスマスツリーを飾ったり(これは19世紀以降に行われるようになった)、美味しいものを食べたりする家庭も多いことだろう。企業も、利益のために「クリスマス」を大いに活用している。この家のすぐ近くにはモスバーガーがあるが、あそこなどは「メリークリスモス」などと言っている。コンビニなどでも、セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・サークルK・ミニストップ・デイリーヤマザキなど、あらゆる企業が「クリスマス」という言葉を使って人々の心とその欲求に働きかけている。多くの人がこのクリスマスの時期は、どこか楽しい感じがするのではないだろうか。人それぞれかもしれないが、気分が悪くなるという日本人はあまりいないのではないだろうか。多くの日本人がこのクリスマスの時期には何か美味しいものを食べたりするかもしれないが、確かなことを言ってしまえば、このクリスマスとは「キリストの誕生を祝うキリスト教の祝祭日」である。それゆえ、この日本では多くの教会がこのクリスマスの時期に、人々が教会に来れるようにと誘ったりチラシを配ったりしている。以前いた教派でも、クリスマスになるとちらほら未信者の方が教会に来ていたようだった。それでこのクリスマスという名前だが、これは「Christ(キリスト)」+「Mass(ミサ)」から成っており、『キリストのミサ』という意味である。紀元336年頃にはすでにローマでクリスマスが祝われているから、かなり長い歴史があることが分かる。このクリスマスは12月25日に祝われ、プロテスタントである我々およびローマ・カトリックもこの日をクリスマスとして定めているのだが、東方正教会というキリスト教の教派(これはプロテステントとカトリックと並ぶキリスト教3大教派の一つである)では、1月6日に祝われている。また、イースター(復活祭)という4月ごろに行われるキリスト教の祝祭日があるが、クリスマスはこのイースターと共にキリスト教最大の祝祭日となっている。それで本日は、今現在我々が見ている『ガラテヤ人への手紙』という聖書の箇所を説明するとともに、(クリスマスの時期に相応しく)イエス・キリストの生誕のことについても語りたいと思っている。
今現在我々が見ているこの『ガラテヤ人への手紙』だが、これはパウロという使徒が、今から2千年前にガラテヤという地方にいた沢山のクリスチャンに書いた手紙である。このガラテヤ人たちは「人間は律法という神の命令に従うことによって救われることができる。」などと間違ったことを教える偽教師たちに惑わされていたのだが、正しい教師であった使徒パウロは「いや、そうではない。人間が救われるのはイエス・キリストを信じることによるのである。」ということを教えるために、ガラテヤ人たちに対して手紙を書いたのである。パウロはこの間違ったことを教える偽教師たちに対して『いっそのこと不具になってしまうほうがよいのです。』(ガラテヤ5章12節)と書いており、彼らに激しく敵対していることが分かる。先程も言ったように、クリスマスとはイエス・キリストが御生まれになったのを祝う祝祭日だが、このイエス・キリストを信じることについてこの手紙では論じている。本日の箇所(1章13~15節目)では、パウロがクリスチャンになる前の自分のことと、どのようにして今の自分となったのかということについて簡潔・大胆に書かれている。それでは早速13節目から見ていきたいと思う。
①『以前ユダヤ教徒であったころの私の行動は、あなたがたがすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。※2016/03/20追加』(1章13節)
パウロはこの13節目から、自分のことについて赤裸々に語り始める。このパウロは、とにかくガラテヤ人から自分に対する疑いの念を取り払いたかった。
ここでパウロが書いているように、ガラテヤ人は回心する前のパウロのことを知っていた。『私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。』とパウロは自分の回心前の行状についてあからさまに言う。パウロがどのようにしてキリストの教会を滅ぼそうとしたかは、『使徒の働き』という巻に詳しく書かれている通りである。そこでは、回心前にキリスト者たちを憎悪していた頃のパウロについて、こう書かれている。『さてサウロは、なおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて、大祭司のところに行き、ダマスコの諸会堂あての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それは、この道の者であれば男でも女でも、見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いて来るためであった。』(使徒の働き9章1~2節)アナニヤは、パウロのことについて主にこう言っている。『主よ。私は多くの人々から、この人がエルサレムで、あなたの聖徒たちにどんなひどいことをしたかを聞きました。彼はここでも、あなたの御名を呼ぶ者たちをみな捕縛する権限を、祭司長たちから授けられているのです。』(使徒の働き9章13~14節)パウロは、クリスチャンであれば『男も女も縛って牢に投じ、死にまでも至らせた』(使徒の働き22章4節)と、自分の過去について隠すことなく告白している。このように、回心する前のパウロはクリスチャンの敵であり、その行状は実に凄まじいものであった。
ここでは何も隠さず書かれており、他の場所でも赤裸々に語られている箇所がたくさん聖書には存在しているが、これは、聖書が神の御霊によって書かれたことを証明する際に用いられる言説の一つである。つまり、「神の御霊によって書かれたからこそ、自分がどのように思われることになったのだとしても、何一つ包み隠さず書かれているのだ。もし人間自身が書いたというのであれば、自分が悪く思われたり、書いたことによって恥ずかしくなってしまうような内容は決して書けないだろう。」という論理である。これはもっともな考え方であると私は思う。神の御霊によって書いたからこそ、恐れの感情に妨げられることもなく、ありのままに書かれているのだ。この他の箇所においても聖書では、モーセなどが自分に悪い思いが抱かれてしまうことになるにも関わらず、大胆・率直な記述をしている。
14節目においても、パウロは引き続き自分自身の過去について述べる。
②『また私は、自分と同族で同年輩の多くの者たちに比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、』(1章14節)
これは書かれている通りの内容であって、回心前におけるパウロがパリサイ人の超エリートだったということは我々がすでに知っているところである。パウロは救われる以前の自分について、『律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのない者です。』(ピリピ3章5~6節)と書いており、彼がどれだけ熱心なパリサイ人であったかが分かる。
③『先祖からの伝承に人一倍熱心でした。』(1章14節)
『先祖からの伝承』とある。この部分において、新改訳聖書の下の部分に示されている聖句を確認すると、どれも人間的・パリサイ的な伝承のことを言っている聖句が参照されている(※①参照)。ということはつまり、このガラテヤ書の翻訳者(松尾武1908―1967:日本カルヴィニスト協会の発会者)は、この部分が人間的な言い伝えのことを言っているのだと考えているのだろうか。しかし、ヒエロニムスやルター、またカルヴァンは、この部分が人間的・パリサイ的な伝承のことではなく、聖なるモーセ律法のことを言っているのだと断言している(※②参照)。果たしてこの部分は、新改訳聖書の参照聖句にあるような、主が厳しく批判されたようなパリサイ的な伝承のことを言っているのだろうか、またはカルヴァンらが言うように神の律法のことを言っているのだろうか。「新改訳聖書の参照聖句がこうだから」とか「カルヴァンがこう言っているから」とかではなく、我々自身は一体どのように解釈すべきだろうか。この手紙では、パリサイ的な伝承を問題としているのではなく<律法遵守による義>という非常に重要な内容が論じられているのだから、十戒をはじめとした聖なる律法について言われていると考えるのが適切であろう。(※2016/02/14追加)
パウロがこの13節目~14節目の箇所で一体なにを言いたいかといえば、つまりこういうことである。「兄弟たち。あなたがたを惑わしている偽使徒どもは律法遵守による救いに熱心になっているようだが、回心前の私は彼ら以上に律法による義に熱狂的であった。今あなたがたを惑わしている彼ら以上に行ないによる救いに夢中になっていたこの私がそのような考え方から離れたのだから、あなたがたを翻弄している者どもが主張している行為義認思想が幻想であるということが分からないだろうか?」例えば、あるカルト宗教で超エリートと言われている優秀な信者がいたとして、その信者が自分の信じていたカルト宗教から脱退したとする。その脱退した元信者が、今もまだカルト宗教を信じている信者たちに対して「諸君。私は本当に熱狂的な信者であり、超エリートと言われるほどであったが、今はもうこの宗教とは縁を切った。どうしてかといえば、この宗教が邪悪であって間違っているということに気付いたからだ。」と言ったならば、それを聞いた多くの信者たちが大いに心を揺るがされるかもしれない。何故なら、かつては非常に熱心だった人が、今となってはその熱心だったものを完全否定しているからである。「あんなに優秀だったあの人が今となっては脱会し、このようなことを言うようになるとは…。もしかしたらあの人が言っていることは本当なのかもしれない…。」などと多くの信者が感じ、そのカルト宗教に疑念を抱くようになったとしても不思議ではない。もし、ただの一般信徒に過ぎなかった信者が脱退してこのようなことを言うのであれば、超優秀だった元信者がこのように言う場合と比べて、より心を動かされることにはならないだろうことは明白である。これはどうしてかといえば、一般信徒と超エリート信徒とではカルト宗教に対するその熱狂度が段違いだったがゆえに、その発言力も段違いとなるからである。パウロがここで「こんなにも優秀であった私でさえもその熱狂していたものから遠ざかったのだ。」と言っているのは、これと同じことである。
次は15節目である。
④『けれども、生まれたときから私を選び分け、』(1章15節)
ここでパウロは、自分が生まれた時にすでに、使徒となるように神によって定められていたのだと言う。つまり、パウロは自分が使徒となったことの原因を、完全に神に結び付けているのだ。これは我々が以前確認したこの手紙の1章1節において、パウロが使徒となったのは『イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によった』と言っているのとよく似ている。この1章1節目で言われているのと同じように、ここでもパウロは自分が使徒となったのは人間によるのではないと言っていることが分かる。
これは我々についても同じである。クリスチャンである我々も「生まれた時からクリスチャンとなるように定められていた。」と言うことができるのだ。そのように定められていたからこそ、我々は主の恵みのゆえにクリスチャンとなったのである。もし定められていなかったとしたら、定められていないがゆえに、クリスチャンとなっていることは決して無かっただろう。つまりは、パウロが使徒となったことであれ、我々がクリスチャンとなったことであれ、すべては神の御計画に基づいているのである。
⑤『恵みをもって召してくださった方が、』(1章15節)
パウロが使徒となるように予定していた神の定めは、このパウロが(紀元33年頃に)実際的に使徒となることによって明確に実現された。パウロが使徒となるまでは、神が使徒となるように定めておられたにも関わらずまだその定めが実現していなかったのだが、定められた時が訪れた時点においてその定めが確かなものとなった、ということである。
『恵みをもって』…とパウロは言う。この言葉から分かるのは、パウロであれ、クリスチャンであれ、すべての召しは神の恵みによるものであるということである。つまり、召しにおける原因は、人間の力とか功績とか行ないなどでは全くない。すなわち人間が何かを行ったからとか、その人が偉大だからとかではなく、ただ神の恵みのゆえにこそ人は召されるのだ。ところで、パウロはここでも自分が今の状態になったことをひたすら主なる神にのみ結び付けているのに気付かれるだろう。今まで我々はパウロが、自分が使徒となったこと、また人が救われることの原因を完全に(人間ではなく)神にだけ結び合わせているのを見てきた。このことから、「人は神の恵みによらなければ救われることも何かの働きに召されることも出来ない。」という考えをパウロが疑うことなく自分自身のうちに堅持していたのだということが分かる。
ここで言われていることからも分かるように、神は恵みをもって人を召して下さる御方であるが、一体どうして神は恵みをもって人を召して下さるのであろうか。それは神が賛美され、この御方の栄光・素晴らしさ・偉大さが明らかにされるためである。つまり、『ヤーヴェに感謝せよ。主はまことにいつくしみ深い。その恵みはとこしえまで。』(詩篇107篇1節)また『わがたましいよ。ヤーヴェをほめたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ。聖なる御名をほめたたえよ。わがたましいよ。ヤーヴェをほめたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。』(詩篇103篇1~2節)と我々が声高らかに言うためである。例えば、誰かが我々を大事故から救ってくれて、そのゆえに死を免れることが出来たとしたらどうだろうか。その救ってくれた人は我々にとって「命の恩人」である。我々はその人に心を尽くして感謝し、「この人はなんて優しい人なのだろうか。まさに愛の人と言うにふさわしい。」と思うことだろう。そうしたら、その人が感謝されるうえ、その人の素晴らしさが明らかになるようになる。もしその人が我々を救おうとしなかったなら、その人が感謝されたりするようなことも無かった。その人が救おうとして我々のために行動を起こしてくれたからこそ、その人が感謝され、その人の素晴らしさが分かるようになったのである。神が恵みをもって人を召して下さるのも、これと同じである。クリスマスの時期に相応しく、このことについてこれから語りたいと思う。
⑥罪ある人間
先程13節目で見たように、パウロは『激しく』教会を迫害し、充満された憎しみをもってそれを滅亡させようとした。いったい、教会はパウロを怒らせるような悪事を何か行ったとでもいうのか。そのようなことは無かった。パウロはただ、クリスチャンが持っているその信仰のゆえに、教会を大いに攻撃したのだ。「奴らはふざけたことを信じている。何と忌まわしいことか。彼らは地上から抹殺されるべきだ!!!」という思いによってパウロは迫害したのである。だから、パウロは教会に対してひどい愚行をしたことになる。パウロ自身が次のように言っており、愚かなことをしていたのを認めている。『私は以前は、神をけがす者、迫害する者、暴力をふるう者でした。』(Ⅰテモテ1章13節)それゆえパウロは自分自身について『罪人のかしら』(Ⅰテモテ1章15節)であると告白している。つまり、このように言っているパウロは「大犯罪人」であったということになる。
クリスチャンになる以前のパウロはこのように罪深い愚行をしていたのだが、罪人であるという点については、パウロも他の人間も変わらない。聖書は、すべての人間が罪深い存在であると教えており、聖書のある巻では『義人はいない、ひとりもいない。』(ローマ3章10節)と書いてある。では、どうして人間は罪深いのだろうか、どうして人間は義人ではないのだろうか。それは、神の命令である「神の律法」を万人が破っているからである。聖書では『罪とは律法に逆らうこと』(Ⅰヨハネ3章4節)と言われているが、この律法を守れていないのであれば、その人は罪人であるということになる。神の律法とは、たとえば十戒で定められているものであれば、このようなものである。『あなたの父と母を敬え。』『殺してはならない。』『姦淫してはならない。』『偽りの証言をしてはならない。』『すべてあなたの隣人のものを、欲しがってはならない。』(出エジプト20章12~17節)ある未信者の方が「こんなの守れるわけが無いだろう…。」と言っていた。もし神の律法を完全完璧に守れるのであれば、そのような人は罪人ではなく義人であると言えるが、この未信者の方が言っているように、そんな人は私たちのうちには存在していない。知恵の王として知られるソロモンは、『この地上には、善を行ない、罪を犯さない正しい人はひとりもいない』(伝道者の書7章20節)と言っている。それゆえ、極悪を行ったパウロであれ他の人であれ、聖書では全ての人間が罪人であると確言されているのである。
⑦永遠の裁きと地獄について
罪ある人間は、永遠の裁きを受けねばならないと聖書は教えている。つまり、地獄での燃えさかる火炎の中で、<永遠に>狂い喚かねばならない。罪人であれば誰でもこの恐るべき地獄に行かねばならないのである。この地獄は苦しみと暗やみに満ちた場所であるが、この場所とここに行く人たちについて、聖書ではこのように言われている。『彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。』(黙示録20章10節)『そこでは、彼らを食ううじは、尽きることがなく、火は消えることがありません。』(マルコ9章48節)『まっ暗なやみが、彼らのために永遠に用意されています。』(ユダ13節)罪人たちに対して、神が微笑んでおられるなどと考えてはならない。『怒りは、いまにも燃えようとしている。』(詩篇2篇12節)と書いてあるが、神は罪人に対して激しく憤っておられるのである。それで、この神は、罪人たちに対して容赦なくこう言われるであろう。『のろわれた者ども。わたしから離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火にはいれ。』(マタイ25章41節)罪人は、悪魔とともに永遠の火で焼かれるのだ!!神は、罪深い人間のために永遠の地獄をお造りになられた。いったい何故なのか。罪人たちを永遠に地獄という恐怖の場所でお裁きになるためである。この地獄において、火は永遠に燃え続ける。いったい何故なのか。罪人たちを永遠に焼き尽くすためである!!
⑧イエス・キリストの救い
聖書は今語ったようなことを確かに教えている。罪人である人間とは、本当に悲惨極まりない状態にある存在なのである。日々多くの罪を犯している完全な存在でないうえ、神の激しい怒りのもとにあり、当然の報いとして地獄の刑罰を受けねばならないのである。これほどまでに悲惨な存在がほかにあるだろうか。悲惨さという点において罪人と動物とを比較するのであれば、動物のほうがましであると言える。どうしてかといえば、罪人たちは地獄の罰を喰らわねばならないが、動物は死んだらそこで終わりであって、地獄に投げ込まれることはないからである。ペットは死んだら一体どうなるのか、ペットも天国とか地獄に行くのだろうか、ということについて心配する人がこの世界にはいるかもしれないが、ペットであれ動物園で飼育されている公開用の動物であれ、動物は死んだらそこで完全に全てが終わるからである。罪人たちのように恐るべき地獄に行くぐらいならば、動物のように全てが「無」になってしまうほうが遥かに優っている。だから、動物よりも罪ある人間のほうが比べ物にならないほど悲惨であると言えるのだ。
今はクリスマスの時期であり、このクリスマスとは先にも言ったようにキリストの生誕を祝う行事であるが、このキリストが御生まれになったのは、ほかでもない、このような悲惨な状態にある地獄こそ相応しい罪人たちを救うためであった。キリストは今から2千年前(正確には紀元前4年ごろ)にダビデの町で御生まれになったが、キリスト生誕の際、天使たちがキリストのことを「救い主」と呼んでこのように言っている。『きょうダビデの町で、あなたがたのために、救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。』(ルカ2章11節)罪人たちを救うために御生まれなったからこそ「救い主」と言うわけである。聖書の他の場所でも、ハッキリとこう言われている。『キリスト・イエスは、罪人を救うためにこの世に来られた。』(Ⅰテモテ1章15節)それゆえ、先程クリスマスとは「キリストの生誕を祝うもの」であると言ったが、もっと正確に言えばクリスマスとは「罪人を救うために罪なき御方として御生まれになったキリストの生誕を祝うもの」ということになる。私は今「罪なき御方」…つまりキリストには罪が一切ないのだということを述べた。聖書では確かに、キリストには何の罪もないのだと教えている。この罪なきキリストは、我々の罪を背負い、我々の罪の身代わりとして十字架の上で御自身の命を捨ててくださった。このことを信じるならば、その人はイエス・キリストのゆえに罪が赦されて地獄と永遠の刑罰を免れることが出来るのだ。『この方を信じる者はだれでも、その名によって罪の赦しが受けられる』(使徒の働き10章43節)と聖書に記されている通りである。また、次の聖書の言葉から分かるように、このキリスト以外に救われる道は一切存在していないと聖書は教えている。すなわち、「使徒の働き」という巻における言葉である。『この方以外によっては、だれによっても救いはありません。』(使徒の働き4章12節)今現在我々が見ているこの「ガラテヤ人への手紙」の内容では、私が今述べたこのことに反したことを主張している偽教師たちが問題となっている。この偽教師たちはこのように言っている。「人はイエス・キリストを信じることによってではなく、自分の努力とか行ないとかによってこそ救われることが出来るのだ。」しかし、そのようなことは決して無いし、パウロもこの手紙で偽教師たちとその主張を激しく攻撃している。もう一度言うが、『キリスト・イエスは、罪人を救うためにこの世に来られた。』(Ⅰテモテ1章15節)のであって、このキリストを信じるのであれば、キリストがその人の罪の身代わりとして死んで下さったがゆえに、その人は救われて罪に対する神の恐るべき裁きを免れることが出来るのである。これこそ、キリストの生誕を祝うクリスマスにおける精髄・本質である。何故なら、キリストが生誕されたのは、罪人たちの無限ともいうべき罪の数々をその身に背負うためであったからである。
先程、大事故から救いだしてくれた命の恩人についての話をした。たった今、罪人とその罪人を救うためにこの地上に来られたキリストについての話をした。このキリストは、罪人を地獄という永遠の苦しみから免れさせてくださるのだから、信じる人たちにとっては「命の恩人」であると言えよう。もし大事故から救いだしてくれた人にさえ大いに感謝するのであれば、地獄から救いだしてくれたキリストに対しては、尚更のこと感謝がされるはずであろう。事実、クリスチャンたちは自分を救ってくださったこの救い主である御方に対して大いに感謝している。それで、もしキリストを信じるのであれば、その人はキリストを命の恩人とするのである。何故なら、キリストがその人の罪のために犠牲となられ、そのゆえに、その人は地獄に行かずに済むからだ。その人には、神の祝福がとこしえまでも注がれ続けるようになる。天国で、神からの恵みを永遠に受け続けるのである。しかし、イエス・キリストを信ぜず、罪を悔い改めないのであれば地獄は免れないと聖書は教える。キリストはこのように言っておられる。『わたしはあなたがたに言います。あなたがたも悔い改めないなら、みな同じように滅びます。』(ルカ13章3、5節)もし悔い改めないのであれば、永遠の滅びを受けねばならないのだ。誰かが大事故に巻き込まれてしまったにも関わらず、自分を助けようとして走ってくる優しい人を突き放して拒否したとしたら、その人は「死を愛する人」であると言えよう。何故なら、自分を救おうとして大急ぎで走ってきた人を退けたからだ。それと同じように、神の律法を破るという罪にまみれきっている罪人を救おうとしてこの地上に来てくださった愛の御方であるキリストを拒否するのであれば、その人は「地獄を愛する人」であると言えよう。何故なら、救いのため、罪の赦しのため、地獄を免れさせるためにこの世界にやってこられた御方を退けたからだ。最後になるが、厳密な意味においてのクリスマスとは「罪人を救うためにこそ御生まれになったキリストの生誕を祝うキリスト教の祝祭日」である。どこかの店や雑誌、またインターネットやコマーシャルなどを見ればすぐに分かるように、わが国においても、本当に多くの日本人の方々がこのクリスマスの時期には楽しんだり味わったり喜んだりしている。このような時期に、本当に多くの日本人の方々がイエス・キリストを信じ、真の意味においてクリスマスを祝うようになるのを願うものである。
※2016/03/20追加
パウロは憎悪に満ちた激しい迫害によって教会を攻撃したが、神の憐れみにより、それらの暴虐行為は赦された。敬虔なテオドシウス帝(347―395)は、テサロニケの市民たちに演劇を見せてやるぞと言って呼び集め、兵士たちに命じて7000人もの民衆を処刑させたが、そののち悔改めるに至ったテオドシウス帝を、神はお赦しになった。ダビデも、バテ・シェバの夫であったウリヤを亡き者とし、他人の妻を欲望につき動かされるままに奪ったが、神によって赦しが与えられた。これらの事例から分かるのは、神の憐れみの大きさは測り知れず、神は赦しに富んでおられる、ということである。出エジプト34:6~7で神は、『ヤーヴェは、あわれみ深く、情け深い神、…咎とそむきと罪を赦す者』と御自身について宣言しておられる。神の無限の憐れみは、イエス・キリストとその贖罪のゆえに、大きな罪にも豊かに赦しを与える。しかし、神が我々の罪をキリストにあって赦して下さるからといって、我々は決して調子に乗ったりすべきではないし、また、我々が罪を犯してもよいということにはならない。つまり、「どうせ赦されるのだから少しぐらい罪を犯しても大丈夫だろう…」などと絶対に考えるべきではない。確かに神は「赦しの神」であって人の罪をお赦しになるが、我々は罪を憎み、この罪から自分を遠ざけるようにすべきである。そうしないと、神の怒りがその人にむかって燃え上がることにもなりかねない。神は「裁きの神」でもあられるのだから。
[聖句に戻る]
※①
『そのころ、パリサイ人や律法学者たちが、エルサレムからイエスのところに来て、言った。「あなたの弟子たちは、なぜ昔の先祖たちの言い伝えを犯すのですか。パンを食べるときに手を洗っていないではありませんか。」そこで、イエスは彼らに答えて言われた。「なぜ、あなたがたも、自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか。…』(マタイ15章1~3節)
『―パリサイ人をはじめユダヤ人はみな、昔の人たちの言い伝えを堅く守って、手をよく洗わないでは食事をせず、また、市場から帰ったときには、からだをきよめてからでないと食事をしない。まだこのほかにも、杯、水差し、銅器を洗うことなど、堅く守るように伝えられた、しきたりがたくさんある。―』(マルコ7章3~4節)
『あのむなしい、だましごとの哲学によってだれのとりこにもならぬよう、注意しなさい。そのようなものは、人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではありません。』(コロサイ2章8節)
[本文に戻る]
※②
「父たちの言伝え(※または「先祖たち」)というのは、神の律法を堕落させることになった付加物のことをいっているのではなく、かれが幼時から養われ、父母やその他の祖先の手から手へと伝えられてかれが受けた神の律法そのもののことである。」(カルヴァン・新約聖書注解p30)
[本文に戻る]
※2016/02/14追加
ヨセフスなど、ユダヤ人の著作では、モーセ律法を指して「先祖からの教え」とか「父祖の伝承」などといっている箇所が無数にある。フィロンもそうである。ユダヤ人には律法をこのように言う慣習があったのであろう。それゆえ、ここで言われているのは、モーセを通してイスラエルに与えられた聖なる律法のことだと考えるべきであろう。
[本文に戻る]
ガラテヤ人への手紙1章16~21節(2015/12/27説教)
『異邦人の間に御子を宣べ伝えさせるために、御子を私のうちに啓示することをよしとされたとき、私はすぐに、人には相談せず、先輩の使徒たちに会うためにエルサレムにも上らず、アラビヤに出て行き、またダマスコに戻りました。それから3年後に、私はケパをたずねてエルサレムに上り、彼のもとに15日間滞在しました。しかし、主の兄弟ヤコブは別として、ほかの使徒にはだれにも会いませんでした。私があなたがたに書いていることには、神の御前で申しますが、偽りはありません。それから、私はシリヤおよびキリキヤの地方に行きました。』(ガラテヤ1章16~21節)
先週は、血に飢えた猛獣でもあるかのように教会を荒らしまわっていたパウロが神の恵みによって今の自分となったことについて説明されたが、パウロは本日の箇所でも引き続き自分の過去について述べている。まずは16節目からである。
①『異邦人の間に御子を宣べ伝えさせるために、御子を私のうちに啓示することをよしとされたとき、』(1章16節)
『御子を私のうちに啓示することをよしとされたとき、』…ここでもパウロは、自分がキリストについて悟れたのは、ただ神の第一位格である御父によったのだと言う。つまり、1章12節の箇所の場合と同じように、ここでも「私がキリストのことを知れたのは人間によるのではない。」とパウロは述べている。パウロだけでなく、ペテロにキリストが啓示されたのも、これと同じであった。ペテロがキリストのことを「神の御子」であると悟れたのは、人間によるのではなく、父なる神の啓示によるのであった。すなわち、ペテロがキリストに対して『あなたは、生ける神の御子キリストです。』(マタイ16章16節)と言うと、それをお聞きになったキリストはペテロに対して『バルヨナ・シモン。あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいますわたしの父です。』(マタイ16章17節)と言われたのである。神は『わたしは自分のあわれむ者をあわれみ、自分のいつくしむ者をいつくしむ。』(ローマ9章15節)と言われた。この神は、御自身の憐れみによって救おうと予定された者に対し、その慈しみをもって御子を悟れるよう聖霊によって働きかけて下さるのだ。この箇所や今まで見てきた箇所からも分かると思うが、パウロは繰り返し繰り返し、幸いなことをただ神とその恵みに結び付けている。まるで「人間が自分自身によってどうして救われることが出来ようか。そんなことはあり得ないことだ。全ては神の恵みなのである。」とでも言っているかのようである。
それでは、神がパウロに対して御子を啓示してくださったのは一体どうしてなのか。それは神がパウロに『異邦人の間に御子を宣べ伝えさせるため』であった。つまり、パウロにおいて「御子による救い」と「異邦人に福音を宣教すること」という2つのものは、互いに結びついたものであった。どういうことかといえば、もし神がパウロに対して「この人間(つまりパウロ)を通して異邦人に御子を伝えさせる」という御計画を立てておられなかったとしたら、パウロが救われていたかどうかは分からないということである。何故なら、確かにこの箇所では「パウロに御子が啓示されたのは、パウロが異邦人に御子を伝えるようになるためであった。」と言われているから。救いと召命とが密接に繋がっているということについては、ペテロも「我々クリスチャンがキリストのゆえに神の国の住民とされたのは我々がキリストを人々に伝えるようになるためであった。」ということを手紙の中で言っている。すなわち、Ⅰペテロ2章9節の箇所である。『しかし、あなたがたは、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それは、あなたがたを、やみの中から、ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方のすばらしいみわざを、あなたがたが宣べ伝えるためなのです。』ここまで語ったことから、<救い>と<召し>という2つのものが一体となっているのがよく分かるであろう。
この箇所から分かるように、パウロは異邦人に対して遣わされている使徒であった。パウロは割礼を受けたユダヤ人に対して遣わされている使徒ではなかった。この手紙の2章で言われている言葉からも分かるように、ユダヤ人への使徒として召されているのはペテロであった。「神は、ペテロをユダヤ人に対する使徒に、パウロを非ユダヤ人に対する使徒とされた。」とこの手紙の2章8節で言われている。『ペテロにみわざをなして、割礼を受けた者への使徒としてなさった方が、私にもみわざをなして、異邦人への使徒としてくださったのです。』(2章8節)つまり神は、ペテロという使徒を通してユダヤ人に、また、パウロという使徒を通して異邦人にキリストの福音を知らせようと欲されたわけである。
我々一人一人にも、神から与えられた召しにおける役割というものが存在している。牧師であれば、ある人は国内宣教のために召されているが、別の人は国外宣教のために召されている。男性信徒であれば、ある人は職人として召されており、ある人はどこかの団体の職員として召されており、ある人は機械の整備士として召されており、ある人は医者として召されており、学者として召されている人も存在する。助け手としての妻の場合、その召されているところはラッシュドューニーが『聖書律法綱要』の中で言っているように「夫」である(※2016/02/07追加)。いかに夫の助け手として機能できるか、また、自分の存在のゆえにいかに夫の召しにおける歩みが幸いになるよう作用することができるか、ということが大事である※2016/03/20追加(何故なら妻とは助け手として造られたからである※①参照)。人それぞれ役割があるのだということを、パウロはⅠコリント12章29~30節の箇所で我々に教えている。『みなが使徒でしょうか。みなが預言者でしょうか。みなが教師でしょうか。みなが奇蹟を行なう者でしょうか。みながいやしの賜物を持っているでしょうか。みなが異言を語るでしょうか。みなが解き明かしをするでしょうか。』ペテロがユダヤ人に対して福音を伝える役割をもっており、パウロが非ユダヤ人に対して福音を伝える役割をもっていたように、我々もそれぞれ自分に割り当てられている役割に従って歩むべきであろう。自分が遣わされているところで主にあって頑張り、そこにキリストの御国が拡がるようにするのであれば、その人は自分に与えられた召しに相応しく歩んでいることになる。※②参照
次は、16節の後半と17節全体に行きたい。
②『私はすぐに、人には相談せず、先輩の使徒たちに会うためにエルサレムにも上らず、アラビヤに出て行き、またダマスコに戻りました。』(1章16~17節)
これは、パウロの最初の旅行のことである。パウロはアラビヤ及びダマスコで一体なにをしていたのか、と思われるかもしれない。文脈から考えれば分かるように、パウロは、アラビヤとダマスコでキリストの福音を伝える活動をしていた。何故なら、16節目で「福音を伝えさせるためにこそ私は救われて使徒となったのだ。」と言ったすぐあとの箇所(17節)で、『アラビヤに出て行き、またダマスコに戻りました。』と書いているからだ。パウロは、このアラビヤとダマスコにおいて、怠けて遊んでいたり、楽しく休んでいたり、社会的な事務手続きに熱中していたのではない。パウロは自分が救われてから『すぐに』アラビヤに行ってダマスコに向かったと言っているが、彼は救われたのち、本当にすぐにも宣教活動を行なうようになったのである。
『人』(16節後半)という言葉に新改訳聖書では※印がついており、下のほうを確認すると【※直訳「血肉」】と書いてある。これは原文では「αιματι」であり、「人間の体」また「肉体」という意味をもっている。この部分は「人」ではなく「血肉」とも読めるが、どちらの言葉を採用するにせよ、パウロがここで言いたいことは「周りの人たち全般」ということである。ただ知り合いだけというのではなく、自分に関連するいっさいの人たちについてパウロはここで言っているのだ。何故なら、この箇所でパウロが言おうとしていることは「私は神の召命以外にはどんな人たちからも左右されてはいない!!」ということだからである。
それで『人には相談せず、先輩の使徒たちに会うためにエルサレムにも上らず、』とは、つまり、パウロが誰からも左右されず、指導されず、勧められず、ただ神の召しに基づくということによってのみ、使徒としての活動を開始するようになった、ということである。つまり、「私は相談したり誰かに言われたからというので使徒としての活動をするようになったのではない。私がそのようにすることになったのは、ただ神がそうするように導かれたからに他ならない。誰一人として人間は関与していないのだ!!」と言いたいわけである。パウロはこのように言うことによって、自分の使徒としての純粋性・正統性を強力に主張し、ガラテヤ人たちに「神に遣わされた者である使徒パウロ」のことを認めさせようとしている。偽使徒どもがガラテヤ人にパウロのことを疑わせようとしていたので、それに対する対処として、パウロはこのように自分のことを認めてもらうべく色々と書く必要があったのだろう。
③『それから三年後に、私はケパをたずねてエルサレムに上り、彼のもとに十五日間滞在しました。しかし、主の兄弟ヤコブは別として、ほかの使徒にはだれにも会いませんでした。』(1章18~19節)
ここで言われている「ケパ」とは、使徒ペテロのことである。主がヨナの子シモンに対して直々に付けられた名前である(※③参照)。
この18節では、<3年>および<15日>という数字が出てくる。15日という期間について、ヒエロニムスは「パウロはペテロから8と7の神秘を示されたのだ。」などと考えているようだが、私には特に隠れた意味があるとは感じられない。パウロがペテロのもとに15日間滞在した、ただそれだけのことであろう。3年という期間においても、なにか霊的な意味が隠されているようには思われないが、しかし、3年という期間からそれなりに時間が経過したのだということを理解することができる。
この3年という期間であるが、「使徒の働き」の巻ではよく記されておらず、パウロがこの期間に行った実際の言動について詳しく知ることは出来ない。詳細は分からないが一つ確実に言えるのは、この3年の間にパウロが使徒として活動し、キリストの福音を伝えていたということである。
パウロはここでも、自分の使徒としての権威をガラテヤ人に対して暗に主張している。使徒になってから3年後にペテロに会いに行ったと彼は述べるが、このことから、パウロが使徒ペテロによって左右されず、指導されず、重要な影響も受けていないのだということが分かる。もし使徒になってから数ヵ月後にペテロをたずねたのだとすれば、「パウロは使徒ペテロから色々と教えられたのだ。それだからパウロはあのように活動するようになったのだ。」などと思われてしまいかねない。そうしたら、パウロの使徒としての輝きが大いに失われてしまう。そうなれば、ガラテヤ人たちはますます使徒としてのパウロのことを認めなくなってしまう。こんなことになれば、ますますガラテヤ人たちはパウロの伝えた福音の真理から遠ざかってしまうことにもなる。それゆえ、パウロはこのように言うことで、自分の使徒としての独立性・純粋性・正統性を強く示しているのである。19節で「自分はペテロおよびヤコブの他にはどの使徒とも会っていない。」と言われているのも、いま説明したことと同じである。「使徒である私とその働きはどの使徒からも影響を受けてはいない。私は、誰かから教えられたり命じられたり指導されたからというので活動を開始したのではないのだ。つまり使徒である私パウロは、二流の使徒なのではない。従属的な使徒なのでもない。幼稚な使徒なのでもない。私は他の使徒たちと同じように、一人前また大人の使徒なのである。どうか私のことを正統な使徒として認めてくれ!!」とパウロは言いたいわけである。
それで、パウロがペテロのもとに行ったのはただ彼に会いに行っただけであって、ペテロから何かを学ぼうとか、相談をするために行ったのではない。15日間滞在したと書かれているが、この期間にパウロの進路に大きな影響を及ぼすようなことが話されたというのではない。
19節には『主の兄弟ヤコブ』がでてくる。カルヴァンによるとこの人物のことを、「エルサレム教会の牧師であったオブリアス」とか「ヨセフが他の女性との間に生んだ子ども」などと考えていた人たちもいるようである。しかし、この19節の文章における内容を考えるならば、これは明らかに主が使徒として任命された『アルパヨの子ヤコブ』(マタイ10章3節)であろう。
(2016/03/06追加)パウロが主の兄弟ヤコブに会った理由は一体なんであろうか。聖書に書かれていないので、どういった理由からパウロがヤコブと会ったのかは不明である。しかし、このヤコブは非常に敬虔な人物であり、パウロがペテロよりも上に位置させるほどの使徒なのであるから、面会すべきそれなりの理由があったのだと考えられる。ここで、このような定かでない事柄に対し「これこれこういった理由からパウロはヤコブに会ったのだ。」と断言してしまうような教師は多く、あのスポルジョンもそういった教師の一人であるが、このような場合においては、(聖書から確実な証明ができないゆえに)はっきり「これこれこうなのだ。」などと言い切ることは出来ない。このことについては、私もよく注意せねばならない。
次の20節の箇所で、パウロは、自分は嘘を言っているのではないのだと誓いつつ強力に断言する。
④『私があなたがたに書いていることには、神の御前で申しますが、偽りはありません。』(1章20節)
パウロは、神を証人としてまで自分は嘘をついていないのだと断言する。このことから、パウロがどれだけガラテヤ人たちに自分のことを認めさせたかったかが分かる。また、ガラテヤ人たちがパウロに対し、多かれ少なかれ疑いや不安の感情を抱いていたことが分かる。何故なら、パウロは神を持ちだしてまでガラテヤ人たちの心を獲得しようとしているからである。もしガラテヤにいた聖徒たちが何もパウロに疑念の心をもっていなかったのだとすれば、どうしてパウロは自分のことを色々な言説をもって認めさせる必要があっただろうか。神をすら証人とする必要などさらさら無かったはずである。
ヒエロニムス(※④参照)は、このガラテヤ人への手紙において、パウロが嘘をついているという見解をもっていた。ヒエロニムスは、パウロがガラテヤ人たちに役立つために偽りを言っていたのだと言う。「嘘も方便」という言葉があるが、まさにこれであるというわけだ。しかし、パウロはこの箇所(20節)で自分は嘘をついていないのだと確言しているのだから、我々にとって多少理解しにくい部分があったとしても、パウロが嘘を言っているなどとは塵ほども考えるべきではない。聖書では『偽証してはならない。』(申命記5章20節)と言われている。ということはつまり、聖霊なる神は、偽証を憎まれ、偽証を喜ばれず、偽証を決してされない御方であるということになる。何故なら、聖書は聖霊によって書かれたからである。この手紙とは聖霊がパウロを通して書かれたものであり、聖霊は決して偽証をなさらない御方であるから、この手紙に偽りが含まれているはずがどうしてあるだろうか。聖書が神によって書かれたという信仰を持っているのであれば、その人は、(このガラテヤ人の手紙だけでなく)聖書のどの巻においても嘘や偽りが書いてあるなどとは絶対に思うべきではない。
この誓いであるが、もし神を証人として呼びだしつつ何かを断言するのであれば、それは紛れもない誓いの言葉である。それで、パウロがここで誓っているからというので、そのことを聞いた我々は軽率に誓ったりすべきではない。パウロがここで誓いつつ述べているのは、そうする必要がどうしてもあったからであり、しかもその誓いは神への恐れと誠実な精神に基づいたものであった。この誓いというものは、もし軽々しく行われるのであれば自分自身に破滅を招くことに繋がるのであるから、我々は絶対に無思慮に行うべきではない。誓いとは、神への全き恐れと敬虔および真理への愛また誠実な精神という土台に立ったうえでなされるべきものである。
次は21節目の箇所である。
⑤『それから、私はシリヤおよびキリキヤの地方に行きました。』(1章21節)
このシリヤとキリキヤは、互いに隣接している地方である。パウロはここで一体なにをしていたのだろうか。先程17節目の箇所で見たように、我々は、パウロがここでも主にある福音伝道の働きをしていたのだと理解すべきであろう。
1章目における最後の部分(22~24節)に行きたいところだが、時間がかなり長くなってしまうことが予想されるので来週にまわすこととし、もうそろそろ最後としたい。
⑥福音宣教と神の栄光および聖なる御救いについて
我々が本日見たように、パウロは使徒となってから各地でキリストの福音を伝えたのだが、神はこの2千年間の間、パウロであれ他の人であれ、御自身の民を通して各地に福音を満たし続けてこられた。そのようにして、この世界では信じる者が豊かに起こされてきたのである。この日本にも福音を伝える者たちが神によって遣わされたからこそ、キリスト者と呼ばれる人々が増えてきたのである。もしこの日本に誰も宣教者が送られなかったとしたら、キリスト者が増えることも無かったかもしれないし、我々も福音に触れることが出来ていたかどうか分からない。それで、我々は以前パウロが『どうか、この神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。』(ガラテヤ1章5節)と書いているのを学んだ。我々は、神の栄光がますますあらわされるようになるため、ますます聖なる福音が地に満たされキリストの弟子が増えていくようになるのを望むべきである。ジュネーヴ信仰問答の267番目の項目でも言われているように、神の無限の栄光はそれ自体において増えたり減ったりすることはない(※⑤参照)。しかし我々は、「神の栄光があるべき姿のままにあらわされるように」(ジュネーヴ信仰問答:問267への答え)また「神の栄光がすべての場所で、すべての事柄において、たたえられるように」(同:問266への答え)なるのを願うべきである。1人よりも10人、10人よりも100人、100人よりも1000人の人たちが神の栄光を求めるようになるのが望ましいことは言うまでもない。より多くのクリスチャンがいれば、それだけ多くの人が神の栄光を願うようになるのだ。そのようになるのは非常に喜ばしい。だから、神の栄光が豊かにあらわされるようになるためにも、神を愛する我々はますます各地に福音が満たされるようになるのを願うべきであろう。
「我々の罪のために十字架の上で犠牲となられた救い主なるキリスト・イエスを信じ、受け入れ、この御方を自分の主とすること。」「神の御前に悔い改めること。」…これを教会は人々に対して望んでいる。罪なき主イエスは、その無限の愛をもって、我々の罪のために御自身の命をみずから捨ててくださった。この御方は、我々の罪の身代わりとして死なれたのである。このことを信じるのであれば、その人は救われ、義と認められ、聖なる者とされ、十字架の贖いのゆえに罪の赦しが受けられ、『主キリスト・イエスにある永遠のいのち』(ローマ6章23節)が与えられる。神の子であるキリスト御自身がこう言っておられる。『まことに、まことに、あなたがたに告げます。信じる者は永遠のいのちを持ちます。』(ヨハネ6章47節)『御子を信じる者は永遠のいのちを持つ』(ヨハネ3章36節)とも書いてある。その人はキリストの打ち傷のゆえに癒され(※⑥参照)、聖なる永遠の契約のうちに導き入れられ、とこしえまでも神の栄光のために生き続けるであろう。そのようになる人は幸いである。しかし、信じない人は神の燃え上がる怒りを避けることができず、永遠に罪ある者として裁かれ続けるようになる。『信じない者は罪に定められます。』(マルコ16章16節)とキリストは言っておられる。是非、罪を悔い改め、キリストを信じ、この御方を自分の主とするように我々は心を一つにして願っている。「信じるならば救われるとでもいうのか?たったそれだけで?信じるだけだと???」…こう聞く人もいるかもしれない。その通りである。この聖書では、もし信じるならばその人は救われると教えている。『先生がた。救われるためには、何をしなければいけませんか。』(使徒の働き16章30節)と聞いた看守に対して、パウロは『主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われます。』(使徒の働き16章31節)と答えている。我々は信仰を強制するようなことはしないが、しかし、この機会にぜひ信仰を持たれることをお勧めしたい。どうか、神がこれからキリストの福音を世界中にますます満たし、更に信者の数が増やされ、多くの人たちが神の栄光を求めるようになり、救い主なる御方の聖なる陣営が勢いをもって拡大していきますように。アーメン。
※①
『その後、神であるヤーヴェは仰せられた。「人が、ひとりでいるのは良くない。わたしは彼のために、彼にふさわしい助け手を造ろう。」』(創世記2章18節)
[本文に戻る]
※2016/02/07追加
ラッシュドゥーニーは聖書律法綱要のなかで、「女性の召命が夫と家庭であるのに対し、…」と述べている。
[本文に戻る]
※2016/03/20追加
「うちらの場合、共働きをしなければとてもじゃないがやっていけない。妻が家事に専念したら生活していけない。」などと思われる方もいるかもしれない。この場合、妻が多くの時間を仕事に費やさないと生活していけないのだから、仕方がないかもしれない。しかし、聖書では妻の職務が助け手であるといわれており、また、女性が社会において台頭すればするほど今の日本のように男性が草食化される傾向が増進されてしまう、ということを我々は忘れるべきではない。クリスチャン夫婦においては、妻が専業主婦としての職務に専念し(※たとえ専業主婦であっても、例えば清掃員、店舗の受付係、シール貼り、ポスティングスタッフなど、内職は禁止されておらず―どうしてそう言えるかといえば、箴言31:10~31の箇所にでてくる妻が、着物や帯を作るなどといった内職をしているからである―、行なうのも行なわないのも自由である。)、その妻の存在のゆえに夫の召しにおける統治領域が拡大される、ということを理想とすべきである。
[本文に戻る]
※②
自分に与えられた召しを明確に理解している兄弟姉妹もおられるが、まだ自分がどのような歩みに召されているか分からない兄弟姉妹も多くおられることと思われる。そのような場合は、召しのことについて神に伺い、「私の願うところではなくあなたの遣わされるところに歩めるようお恵みください。」などと祈りつつ懇願し(※この祈りの文章は一つの例にすぎない)、主に導かれるまま御霊によって歩むべきであろう。召しについての認識が堅固でないと、確かな意思をもって力強く歩めないことに繋がり、(男性の場合)昇進・昇給および仕事における能率の向上などが自分から遠ざかるので、御国の拡大が実現しにくくなってしまう。言うまでもなく、自分に与えられている召しを確信しており「私はこの仕事をするように導かれている!!」と心のなかで主にあって思っている人であれば、そのような人の仕事における歩みは臆することのないものにされるだろうし、強い意志を持てるがゆえに努力と誠実と忍耐の面において大きな益がもたらされるようにもなり、ますます自分が遣わされている場所に神の御心と聖なる言動とが満たされるよう作用することが出来るようにもなるのである。そのような人であれば高い地位に就けるようになる可能性はそれだけ上がることになるが、もしそれが実現したならば、その高い地位における強力な力のゆえに、その団体にある邪悪な規則や制度などを廃して聖なる決まりごとを制定できるようにもなるだろう。そうしたら、それだけ地上では神の御心が多く行なわれるようになって、「主の祈り」における第3番目の項目で言われている内容がこの地上に実現されるようになる。それゆえ、自分に与えられている召しを確信できるのあれば、それはキリストの御国にとっては非常に喜ばしいことなのである。どうか、神が御自身の民一人一人をその召しにふさわしく歩ませてくださるように。
[本文に戻る]
※③
『イエスはシモンに目を留めて言われた。「あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ(訳すとペテロ)と呼ぶことにします。」』(ヨハネ1章42節)
[本文に戻る]
※④
ヒエロニムス(342頃―420)は名高い教父であり、聖書のラテン語訳であるウルガタ聖書を完成させたことで知られる。古代キリスト教最大の教父であるアウグスティヌス(354―430)はヒエロニムスに対して「もっとも誠実なる愛の献身をもって仕えかつ抱擁すべき、わたしの最愛のご主人、兄弟、同僚司祭」(書簡28)また「もっとも敬愛しとても憧れている主人にしてキリストにあって尊敬すべき兄弟にして同僚の司祭」(書簡67)また「願わしい聖なる兄弟」(書簡71)と言っている。アウグスティヌスはヒエロニムスに対して「才能の点でわたしに優っておられます」(書簡71)と書いているが、非常に学識豊富な聖書学者であった。このヒエロニムスはルターの尊敬する人物であり(卓上語録:ワイマール版1巻、項目584、1533年頃)、カルヴァンも聖書注解の中で言及している。
[本文に戻る]
※⑤
「主の祈り」の1番目の項目『御名があがめられますように。』(マタイ6章9節)について説明している箇所ではこう書いてある。
<問266>
では第一の祈りを説明してごらんなさい。
<答>
神のみ名とは、それをもって、神が人々の間にたたえられる神の名声であります。でありますから、われわれは神の栄光がすべての場所で、すべての事柄において、たたえられるように願うのであります。
<問267>
神の栄光が増大したり減少したりしうるとあなたは考えますか。
<答>
それ自体ではそのようなことはありません。しかし、神の栄光があるべき姿のままにあらわされるように、また神が何事をなさっても、すべてそのみ業があるがままに輝かしくあらわれ、かくしてあらゆる仕方において、神があがめられるようにということであります。
ジュネーブ教会信仰問答
[本文に戻る]
※⑥
『キリストの打ち傷のゆえに、あなたがたは、いやされたのです。』(Ⅰペテロ2章24節)
[本文に戻る]
ガラテヤ人への手紙1章22~2章3節(2016/01/03説教)
『しかし、キリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られていませんでした。けれども、「以前私たちを迫害した者が、そのとき滅ぼそうとした信仰を今は宣べ伝えている。」と聞いてだけはいたので、彼らは私のことで神をあがめていました。それから十四年たって、私は、バルナバといっしょに、テトスも連れて、再びエルサレムに上りました。それは啓示によって上ったのです。そして、異邦人の間で私の宣べている福音を、人々の前に示し、おもだった人たちには個人的にそうしました。それは、私が力を尽くしていま走っていること、またすでに走ったことが、むだにならないためでした。しかし、私といっしょにいたテトスでさえ、ギリシャ人であったのに、割礼を強いられませんでした。』(ガラテヤ1章22節~2章3節)
2016年もこうして礼拝が行なわれ、神の言葉を学べる幸いを主に感謝したいと思う。
本日は、先週に引き続き「ガラテヤ人への手紙」からであり、1章22節目からである。パウロは自分の使徒としての権威と正統性を主張するため、過ぎ去った過去の出来事について色々と記している。
①『しかし、キリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られていませんでした。けれども、「以前私たちを迫害した者が、そのとき滅ぼそうとした信仰を今は宣べ伝えている。」と聞いてだけはいたので、彼らは私のことで神をあがめていました。』(1章22~24節)
この箇所は書いてある通りの内容であるが、ここではシリヤおよびキリキヤの地方における教会のことが言われている。我々は1章13節の箇所で、当時のガラテヤの地方にいた聖徒たちが回心前のパウロの行状について聞いていたのだということを以前の説教で確認した。それと同じようにシリヤとキリキヤにおける『ユダヤの諸教会』にいた聖徒たちも、凶暴だった昔のパウロの行動について聞かされていた。あれほどまでの凶悪性をもった回心前のパウロであったから、ガラテヤであれシリヤであれキリキヤであれ、当時の多くの教会にパウロの残虐行為が知れわたっていただろうことは容易に推測できる。
回心前のパウロはクリスチャンの信仰を滅ぼそうとしていた、と言われている。パウロはユダヤ教に熱心になるあまり、初代教会のキリスト者たちが持っていた信仰を消し去ろうとし、それを地上から滅亡させようとしていた。彼は、自分が間違っていると感じていたキリスト者の信仰を破壊するために大いに努力していたのである。
そのような邪悪な行動をパウロがしていたにも関わらず、ユダヤの諸教会にいた聖徒たちは神を崇めていた。彼らはパウロの愚行の数々を聞いて、「なんだと。あいつはもともと我々の勢力を迫害していた大犯罪人だったのか。それが今では救われて福音を伝えるようになったと?私にはとても信じられない。そんな奴が救われるとは…。」などと、ぶつぶつ言うことも出来た。しかし、この地方にいた聖徒たちはそのようにはせず、パウロに起こった神の恵み豊かなみわざを通して神を賛美した。これは、なんと敬虔な信仰であろうか。つまり、回心前のパウロにおける残虐行為に心を傾けるというよりも、むしろ彼を回心させてくださった神の大いなる御恵みにこそ心を留めたわけである。だからこそ、ユダヤの諸教会にいた聖徒たちはパウロという存在を通して神に賛美を捧げることが出来た。パウロが神の恵みによって救われたことよりも、むしろパウロが悪事を行ったということにこそ目を向けていたとしたら、彼らが神を賛美していたかどうかは定かではない(※2016/02/14追加)。これは、大変不幸な目にあったにも関わらず、ぶつぶつ言うどころか『ヤーヴェの御名はほむべきかな。』(ヨブ1章21節)と言って神をほめたたえたヨブの信仰と似ているところがある。我々も、このような信仰を見習いたいものである。
ここの教会にいた聖徒たちのことだが、彼らは、神の恵みによる愛の精神をもっていた。どうしてかといえばパウロが過去に愚かなことをしていたのを聞いていたにも関わらず、そのことを追及したり批判したりしようとはしていなかったからである。『(愛は)人のした悪を思わず』(Ⅰコリント13章5節)とあるが、誰かが過去に行なった解決済みの悪事を根掘り葉掘り尋ねたり批判したりしないのは、愛の精神に他ならない。もし愛がなかったとすれば、彼らはパウロのした愚行について「おい、お前はあんなことをかつて行なっていたのだろう。一体なんということをしていたのか。お前は本当にふざけている。お前は信用できないやつだ。」などと言っていたかもしれない。実に、愛があるからこそ人のした悪を思わないのである。このように彼らには神の恵みによって愛が与えられていたが、この愛を与えた神こそ、もっとも人のした悪を思われない愛の御方である。というより神は愛そのものである。この愛なる神は、罪の中に死んでいたみじめな我々を御子イエス・キリストのゆえに恵みによって救い、我々の犯した罪を御子の血により赦し、我々が過去に行なった悪事をキリストのゆえに忘れてくださった。この御方は愛の存在であられるので、我々が過去に行なった罪を根に持たれることはされず、大きな恵みによりそれを忘れてくださる。『わたし、このわたしは、わたし自身のためにあなたのそむきの罪をぬぐい去り、もうあなたの罪を思い出さない。』(イザヤ章43節25)と言われている通りである。もし神が愛ではなかったとすれば、我々が過去に犯してしまった罪は大いに追及・批判されていただろうから、我々は恐怖と不安で絶望していたに違いない。誰かの愚行を一度許したにも関わらず後になって再びその愚行を責めてくる人も人間のなかには存在するし、我々クリスチャンといえども肉の中に放置されるのであればこのようなことをいとも簡単に行なってしまうものだが、神は愛であられるから、そのようなことはされないのだ。我々は「愛とは人が過去にしてしまった解決済みの悪事を根に持たないということ。」また「神は人のした悪を根に持たれない愛の御方であること。」という2つのことについて知るべきであろう。
また、ここでもパウロは自分の使徒としての権威を暗に主張しているのが分かる。何故なら、この地方にあったユダヤの諸教会にいた聖徒たちはパウロのことを認め、このパウロを通して神を賛美することさえしていたからである。つまり、パウロはここでガラテヤ人に対してこう言いたいのだと思われる。「あの地方にいる聖徒たちは私のことを認め、私のことを通して神を賛美することさえしている。彼らは私のことを疑ったり否定してはいない。これは、私の使徒としての正統性を証明するものではないだろうか。もし私が本当に疑わしい人物であったならば、こういうことは起こらなかったはずではないか。」
1章目が全て終わったので、2章目に行きたいと思う。
②『それから十四年たって、私は、バルナバといっしょに、テトスも連れて、再びエルサレムに上りました。』(2章1節)
14年たってパウロは再びエルサレムに上ったと書いている。カルヴァンによると、この14年とは、パウロが救われてから3年後に初めてペテロをたずねてエルサレムに上った時から計算した年数ではなく、回心した時から数えた年数であるという(※①参照)。これが救われてから14年後のことを言っているのであれば、この手紙が紀元48年ごろ―つまりパウロが紀元33年ごろに救われてから15年後―に書かれたという見解は間違っていないことになる。しかし、これが救われて3年後にエルサレムに行ってから14年後のことを言っているとすれば、この手紙が紀元48年ごろに書かれたという見解はとれなくなってしまう。すなわち、紀元50年以降に書かれたと推定せざるを得なくなってしまう。ルターの場合、カルヴァンとは違って「14年」とは救われてからの年数ではなく、救われてから3年後にエルサレムに行ってからの年数であると考えている。この箇所で言われている年数が、パウロが救われてから17年後(3年+14年)であると考えるにせよ、14年後であると考えるにせよ、いずれにしても致命的な問題ではない。このような問題で激しく議論し合って決別するのというのであれば、分派が無限に生じてしまうであろう。
ここで出てくるバルナバとは、「使徒の働き」4章36節によると『キプロス生まれのレビ人で、使徒たちによってバルナバ(訳すと、慰めの子)と呼ばれていたヨセフ』であって、彼はユダヤ人であった。このバルナバは、パウロのことを他の使徒たちに紹介した人物である(※②参照)。テトスとは、この手紙の2章3節で言われているようにギリシャ人―つまり異邦人であって、パウロが書いた「テトスへの手紙」の受取人である。このテトスは、「テトスへの手紙」の1章5節に書いてあるとおりパウロから長老たちを任命するよう指図されたのだが(※③参照)、このことからも分かるように、彼は大司教であった。パウロは、このバルナバとテトスという2人の人物を証人として連れていったのだと考えることができよう。
それで、パウロは一体どういうふうにしてエルサレムに再び上ったのであろうか。このことについて、次の節ではこのように書いてある。
③『それは啓示によって上ったのです。』(2章2節)
つまり、自分の意思や願望とかではなく、神からの啓示があったからこそエルサレムに向かったということである。パウロは、神によってこそエルサレムに再び行ったのだ。この啓示をもって、ここでもパウロは自分の使徒としての権威を論証していると思われる。すなわち、「神から啓示があったからこそ私は使徒としてエルサレムに行ったのだ。」と言うことによって、自分の使徒としての働きの正当性を神によって主張しようとしているのだ。
しかし、神からの啓示が無かったのであればパウロがエルサレムに再び上っていたかどうか、我々には分からない。一つだけ確実に言えるのは、パウロがエルサレムに向かったのは神からの啓示があったからだということである。確かにパウロは啓示のゆえにこそエルサレムに行ったのだ。『私にとっては、生きることはキリスト』(ピリピ1章21節)と言ったパウロは、もしキリストの父なる神が啓示されるのであれば、エルサレムであれ、地の果てであれ、宇宙の果てであれ、迷うことなく向かっていったことだろう。彼が、神の啓示によって動き、生き、喋り、また何かを行なう人間であったことは間違いない。我々も神が示される御心によってこそ歩めるように祈るべきであろう。
④『そして、異邦人の間で私の宣べている福音を、人々の前に示し、おもだった人たちには個人的にそうしました。』(2章2節)
パウロがどうしてエルサレムに行ったかといえば、自分が伝えているキリストの福音を多くの人たちに示し、使徒をはじめ、おもだった人たちと聖なる協議を行なうためであった。我々がすでに知っているように、パウロは「人が救われるのは律法の行ないによるのではない。人はイエス・キリストを信じる信仰によってこそ救われる。律法によっては人は救われることなど出来ない。」という救いについての正しい理解を、神の恵みにより会得していた。これは、パウロがこの手紙で強力に主張しているものであって、我々の救いにとって根本的なものである。我々は誰一人として自分の行ないによっては救われず、イエス・キリストを信じることなしには永遠の命はまったくあり得ない。実に、パウロはこのような重要なことのためにこそエルサレムに行くよう神の啓示によって動かされたのである。
『示し』…と言われているが、この言葉に注目すべきである。パウロは、使徒やほかの人たちに対して、自分の伝えている福音を「示した」のである。つまり、パウロが伝えていた福音は、使徒やだれか別の人たちからの受け売りではないということだ。何故なら、もし受け売りだったとしたら、「示した」などとは言えなかっただろうから。もし誰からが教えられたからというのでキリストの福音を宣べるようになったのだとしたら、次のように言わねばならなかっただろう。「私は自分に教えられた福音を自分自身のうちに堅持し、それを宣べていることを使徒やほかの人たちに伝え知らせた。」ただイエス・キリストの啓示によって受けたからこそ、つまり人から教えられたからというので福音を知ったのでは無かったからこそ、ここで「私は自分の信じている福音を多くの人たちに示した。」と言っているのである。だから、1章11~12節目の箇所と同じようにパウロはここでも「私の伝えている福音は人間によるものではない。」ということを暗に主張していると言えよう。
では、どうしてパウロはエルサレムに行って、多くの人々にキリストから啓示された福音についての話をする必要があったのだろうか。その理由は一体なんなのだろうか。パウロは2節目の後半部分でこのように言っている。
⑤『それは、私が力を尽くしていま走っていること、またすでに走ったことが、むだにならないためでした。』(2章2節)
律法の行ないによって救いを獲得できるなどという間違った理解をもっていた偽使徒どもが、聖なる純粋な福音の真理を、暗やみで覆ってしまわないためにもパウロはエルサレムに上って自分の伝えている福音を公に示す必要があったのである。もしそうしなかったのであれば、偽使徒たちがキリストの福音におけるその光をかき消し、歪められた福音を更に充満させようとしていたことだろう。そうなれば、パウロに反対する者たちは、パウロが行なっている福音伝道の働きを無駄なものとして認識しかねない。このようなことに警戒し、危機感を抱いたからこそ、パウロは神からの啓示によってエルサレムに上ったのである。
ところで、パウロは自分が『力を尽くして』使徒としての活動を行なっているのだと、ここで言っている。それはつまり、パウロが勤勉で怠らず霊に燃えて主から与えられた召命に相応しく歩んでいた(※④参照)ということを示している。神の御国のために自分に与えられた召しの道を熱心になって歩むというのは、なんと聖書的で、敬虔なことであろうか。我々も使徒としてこの世に派遣されたパウロを見習い、自分に定められている役割を力を尽くして全うしていくべきであろう。カルヴァンも影響を受けた宗教改革者のマルティン・ブツァー(1491―1551)は、「神はただに使徒たちをこの世に派遣されただけではなく、すべての者をそれぞれ自分の天職・業務・職務へと派遣されます。」(※⑤参照)と言っておりこれは正にその通りの言葉である。神は、使徒だけでなく、御自身の聖徒たちをみなそれぞれ定められた場所へと遣わしてくださる。聖徒たちがそれぞれ自分の遣わされている場所で主にあって頑張るのであれば、それは喜ばしいことであり、いずれ天で受けることになる報いの度合いを増し加えることにもなるだろう。
パウロが使徒たちと福音に関する協議を行なった結果、テトスなど異邦人たちに対して割礼を強いるべきではないとの決定がなされた。このことが2章3節の箇所で書かれている。
⑥『しかし、私といっしょにいたテトスでさえ、ギリシャ人であったのに、割礼を強いられませんでした。』(2章3節)
すでに我々が見たことであるが、ガラテヤ人たちは偽使徒どもに惑わされており、この偽使徒どもは割礼をするなど律法の行ないによって救われるなどという間違ったことを教えていた。異邦人であったテトスに割礼を強いる必要がないとの判断が下されたのは、惑わされていたガラテヤ人と偽使徒どもに対する強力な打撃であって、彼らの口を完全に封じ込めるものであった。何故なら、テトスであれ他の誰かであれ、異邦人が救われるため割礼を受ける必要はないとの決定がなされたのは、パウロだけでなくペテロやヨハネなど複数の使徒たちによるものだからである。ペテロやヨハネなどの使徒たちが「救いのためには律法の行ないは必要なし。」との決断を下したと聞くのであれば、たとえ偽使徒どもが調子にのっていたのだとしても、もう反論することは出来なくなってしまうのである。パウロはこのようにして、律法の行ないがなければ救いはあり得ないとする考え方を完全完璧に退けてしまっているのだ。
最後になるが、救いのことついて語りたく思う。
⑦聖なる救いについて
本日は、エルサレムに上ったパウロが使徒たちと、救いに関する聖なる協議をしたということについて確認した。これは、本来であれば全世界すべての人たちが真剣に協議すべきものであると言える。果たして人は行ないによって天国に行けるのか、それとも信仰によってこそ天国に行けるのか。天国がかかっているのであれば、人間にとってこんなにも重要なものは他にないであろう。救いとか天国とかいったものに関心があまりない人は、永遠の灼熱のなかで苦しむことになってから後悔してもすでに遅い。その人は地獄を自分の永遠の住まいとし、神がその人に向かって『怒りを激しく燃やし、火の炎をもって責めたてる』(イザヤ66章15節)ことをお止めにならないであろう。『ヤーヴェに刺し殺される者は多い。』(イザヤ66章16節)と言われているが、これは多くの者たちが聖なる救いを求めず、永遠に滅ぼされることを示している。救いを求めない者たちが多いからこそ、神によって永遠に滅ぼされ続ける者たちが多いというわけである。救いや天国について笑い、無視し、蔑むというのであれば、それだけ自分が地獄において受ける苦しみの度合いは増し加えられる。笑えば笑うほど、無視すれば無視するほど、蔑めば蔑むほど、それだけその人は呻き、苦しみ、泣き、歯ぎしりすることになろう。死後に行かねばならない恐るべき地獄が怖いのであれば、その人は救いに心を傾けるべきである。それで、人は行ないによっては救われることが出来ない。行ないによって救われようとする者は、地獄に行くべき者である。もし救われたいと思うならば、その人は、神のキリストにある憐れみに飛びつき、これによりすがらねばならない。神がこの地上に遣わしてくださった神の子イエス・キリストを信じる信仰によってこそ人は救われるのだと聖書は教える。『御子を信じる者は永遠のいのちを持つ』(ヨハネ3章36節)と書かれている通りである。自分が何か素晴らしいことをしたとか、高貴な生まれだとか、偉大な功績があるとかではなく、神がその人をキリスト・イエスとその聖なる贖罪のゆえに憐れんで下さるのでなければ、罪の赦しは決してあり得ない。それゆえ、キリスト・イエスを信じるというのでなければ、天国はまったくあり得ない。何故なら、その人の罪が十字架において流されたキリストの聖なる血によって赦されておらず、罪が赦されていないがゆえに、地獄で永遠の断罪をその身に喰らわねばならないからである。救われたいのであれば、人間や人間の行ないに心を傾けるのではなく、イエス・キリストにこそ心を傾けねばならない。偉大なる贖い主イエス・キリストは我々の罪のために十字架にかかられ、我々の罪をことごとくその身に負ってくださった。実に、このことを信じるならば人は救われ、罪の赦しを受けることが出来るのである。『この方(※つまりキリスト)を信じる者はだれでも、その名によって罪の赦しが受けられる』(使徒の働き10章43節)と書かれている通りである。どうか憐れみ深い神が、多くの人たちの心を救いに対して傾けさせ、行ないによっては人は救われないということを悟らせ、イエス・キリストを信じる信仰によって尊い救いへとお導き下さいますように。アーメン。
※2016/02/14追加
アウグスティヌスはこの箇所で、ユダヤの諸教会の聖徒たちは邪悪だった頃のパウロが神に立ち返れるように祈っていた、だからこそ回心したパウロを通して神を賛美したのだ、と考えている。アウグスティヌスのこの考えはあり得ないことではない。何故なら、『自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。』(マタイ5章44節)と主が言っておられるからである。
[本文に戻る]
※①
この十四年というのは、パウロが初めにエルサレムにのぼったときから次の上京の折までのことではなく、つねにかれの回心から始めて計算されている、とわたしは理解する。そうすると、再度の旅行の間には十一年が経過していることになる。(カルヴァン・
p37)
[本文に戻る]
※②
『ところが、バルナバは彼を引き受けて、使徒たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や、主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの御名を大胆に宣べた様子などを彼らに説明した。』(使徒の働き9章27節)
[本文に戻る]
※③
『私があなたをクレテに残したのは、あなたが残っている仕事の整理をし、また、私が指図したように、町ごとに長老たちを任命するためでした。』(テトス1章5節)
[本文に戻る]
※④
『勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。』(ローマ12章11節)
[本文に戻る]
※⑤
教文館 宗教改革時代の説教(シリーズ・世界の説教)
「アウクスブルクでの説教」p285
⇒amazon.co.jp
■この書物は、マルティン・ルター、ジャン・カルヴァン、マルティン・ブツァー、ジョン・ノックス、トマス・クランマーなど宗教改革者たちの説教がたくさん収録されており、ルターによって異端者とされたトマス・ミュンツァーや再洗礼派のメノー・シモンズの説教まで載せられているが、全体的に考えるならば、何の益にもならないどころか読者の信仰を引き下げる効果すらもたらす書物が沢山あふれている今の日本において、かなり良い部類に属する書物であると思われる。ルターやカルヴァンは言うまでもないが、ノックスやクランマーの説教も実に素晴らしく驚嘆させられる。
[本文に戻る]
ガラテヤ人への手紙2章4~8節(2016/01/10説教)
『実は、忍びこんだにせ兄弟たちがいたので、強いられる恐れがあったのです。彼らは私たちを奴隷に引き落とそうとして、キリスト・イエスにあって私たちの持つ自由をうかがうために忍び込んでいたのです。私たちは彼らに一時も譲歩しませんでした。それは福音の真理があなたがたの間で常に保たれるためです。そして、おもだった者と見られていた人たちからは、―彼らがどれほどの人たちであるにしても、私には問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません。―そのおもだった人たちは、私に対して、何もつけ加えることをしませんでした。それどころか、ペテロが割礼を受けた者への福音をゆだねられているように、私が割礼を受けない者への福音をゆだねられていることを理解してくれました。ペテロにみわざをなして、割礼を受けた者への使徒となさった方が、私にもみわざをなして、異邦人への使徒としてくださったのです。』(ガラテヤ2章4~8節)
先週は、エルサレムに上ったパウロが使徒たちと福音についての話し合いをしたことについて確認したが、今週はそのエルサレム滞在の時に起こった出来事について語られている箇所の続きである。まず4節目だが、パウロはエルサレムにいた際、にせ兄弟たちがいたことについて語っている。
①『実は、忍びこんだにせ兄弟たちがいたので、』(2章4節)
『にせ兄弟たち』とは、すなわちクリスチャンではない、神とキリストに属するのではない暗やみの子どもたちのことである。彼らは、キリスト者であると口では自称していたかもしれないが、しかし本当はキリスト者ではなく、神の民の仲間では決してない。パウロが当時の教会の長老たちに対して、神の群れを荒らしまわる邪悪な者どもがこれから出現するだろうと語っている箇所があるが、にせ兄弟たちもこのような忌むべき者どもと同種の存在である。『私が出発したあと、凶暴な狼があなたがたの中にはいり込んで来て、群れを荒らし回ることを、私は知っています。あなたがた自身の中からも、いろいろな曲がったことを語って、弟子たちを自分のほうに引き込もうとする者たちが起こるでしょう。』(使徒の働き20章29~30節)このような者どもは、パウロの時代だけではなく、中世であれ現代であれ、いつの時代にも存在している。アウグスティヌス(354―430)の時代にはドナトゥス派という教会もどきが存在していたし、16世紀にはミゲル・セルベトゥス(1511―1553)という狂った反三位一体論者(※①参照)が間違った教えを広めようとしていた。今の時代にはエホバの証人という異端者どもがあたかもクリスチャンでもあるかのように堂々と活動している。彼らは忌まわしく、キリストの教会にとって敵である存在である。このような者たちは、日本であれ、他の国であれ、世界中どこの教会においても出現する可能性がある。彼らは我々をキリストから引き離そうとしたり異端に迷い込ませようとするのであるから、もし現れたのであれば、固く信仰に立って大いに警戒する必要があるだろう。
②『強いられる恐れがあったのです。』(2章4節)
このにせ兄弟たちは、人が救われるためには割礼を受けるなど律法の行ないが絶対に必要であるなどと考えており、それゆえそのような考えを主張し、誰かの救いのためにはそのようにするよう強いるような人たちであった。「人が救われたいと思うのであれば割礼を受けねばならない。君たちはまだ割礼を受けていないようだから、さあ、すぐにでも受けるようにしなさい。そうしないと救われることは出来ないだろう。」…実際にこの通りに言ったかどうかは分からないが、こんなことを言うような者たちであったと私は推測する。それでは、彼らは一体どのような理由から割礼を行なうように聖徒たちに強いようとしたのだろうか。パウロは4節目の後半部分でこう書いている。
③『彼らは私たちを奴隷に引き落とそうとして、キリスト・イエスにあって私たちの持つ自由をうかがうために忍び込んでいたのです。』(2章4節)
もし誰かが、救われるためには割礼をするなど律法の行ないが必要だなどと思い違いをしているのであれば、その人は「救いのためには律法遵守の必要あり。」と考えているわけだから、律法の様々な規定に縛り付けられており、それを行なうように強制されているがゆえに、いわば『律法の奴隷』である。しかし、キリストに対する信仰によって神の民とされた者は、律法の行ない無しにすでに救われており、割礼であれ安息日の遵守であれ律法において規定されているものに縛られてはいないから、それを行なうように強制されていないがゆえに、いわば『自由の民』である。にせ兄弟どもは、せっかく律法の儀式的規定からキリストにあって自由にされたキリスト者たちを、ふたたび律法の規定に隷属させるべく割礼を受けさせようと企んでいたのである。これこそ彼らの目的であった。それゆえ、パウロは、救いのためには律法の規定を行なわねばならないということから自由にされたガラテヤの聖徒たちに対して「律法の行ないなしには救いはあり得ないなどという考えに迷いこんではならない。」とこの手紙の5章1節で述べている。『キリストは、自由を得させるために、私たちを解放してくださいました。ですから、あなたがたは、しっかり立って、またと奴隷のくびきを負わせられないようにしなさい。』
「律法から自由にされた。」といっても、それは永遠の刑罰を容赦なく宣告する宣告者としての律法から自由にされたという意味であって、行動規範という意味においては今現在であっても我々は道徳的律法を行なう必要がある。すなわち、我々は、義と認められることを求めて律法を行なおうとすべきではないが、しかし、人生の規範としては律法を守るようにすべきである。以前から何度も語っていることであるが、我々が行なうべき律法は「道徳的律法」であって、生贄を捧げたりする「儀式的律法」については行なう必要はない。詩篇には『あなたのみことばは、私の足のともしび、私の道の光です。』(119篇105節)とあるが、これは我々が道徳的律法を行なうべきことを教えている。新約時代においても道徳的律法を行なう必要があるということは、パウロや他の使徒たちが新約時代の聖徒たちに律法を提示しつつ命令しているということから明らかに分かるであろう(※②参照)。もし新約時代においては行なう必要がないのだとすれば、どうして使徒たちは律法によって命じたり教えたりしたのであろうか。今現在であっても道徳的律法が我々の人生における規範となるべきだということは、歴史的な信条でも言われているとおりである(※③参照)。我々は、律法から自由にされたと聞いて、律法は十戒であれ、こまごまとした戒めであれ、何であっても行なわなくてよいことになったなどと考えるべきではない。もしそういうふうに考える人がいれば、その人は神とその法への反逆者であって、キリストに敵対する者・真理にそむく者であると言わねばならない。
次の5節目の箇所から分かるように、パウロはこの惑わす者どもに対して毅然とした態度をもって対応し、彼らとその思想に妥協することをしなかった。
④『私たちは彼らに一時も譲歩しませんでした。』(2章5節)
ガラテヤの諸教会はかき乱す者どもと霊的な戦闘状態にあったのだが、このエルサレム滞在においても霊的な戦いがあった。以前の説教でも語ったが、パウロがエペソ6章12節で書いているように、教会・クリスチャンには肉的ではない、霊の戦いがある。『私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗やみの世界の支配者たち、また、天にいるもろもろの悪霊に対するものです。』アウグスティヌスの時代にはペラギウス(360?―420?)とその異端思想との戦いがあった。宗教改革時代には教皇主義者たちとの戦いがあり、多くの新教徒たちが殉教した。近代においては自由主義神学との戦いがあり、スポルジョンも彼らの陣営に激しく敵対した。教会の歴史とはいわば霊的戦闘の歴史であって、永遠の世界が到来するまでその戦いは決して止まないであろう。
霊的な防衛者であったパウロは、にせ兄弟たちが主張していた異端思想を警戒し、断固としてそれに譲歩することをしなかった。ここでは『私たち』と書かれているが、パウロ一人だけでなく、パウロと一緒にいた仲間たちもパウロと同じように妥協しなかった。最近でも、リベラルであれ、フェデラル・ヴィジョン神学であれ、ディスペンセーション主義であれ、異端また異端的思想が沢山ある。これからもふざけた思想が続々と登場してくるだろうが、我々は目を覚まして、異端または異端的なものには警戒すべきである。何故なら、クリスチャンとは真理に固執すべき者たちであるから。箴言には『真理を買え。それを売ってはならない。』(23章23節)と書いてあるが、これは真理の重要性について我々に教えている聖句であり、我々は真理を売ったりそれから離れたりすべきではないのだ。
5節目の後半部分であるが、ここに書いてあることからも分かるように、パウロは聖徒たちの信仰が異端的・異常なものにならないよう注意していた。
⑤『それは福音の真理があなたがたの間で常に保たれるためです。』(2章5節)
『福音の真理』と書いてあるが、これは「内容的に純粋な福音」のことである。もし誰かが聖書が述べている通りの福音を会得しているのであれば(これこそ真のクリスチャンのことである)、その人のうちには福音の真理が保たれている。にせ兄弟どもは「人は自分の行ないによって義認を得られるのだ。」などと破滅的な思い違いをしていたが、そのようなものは歪められた福音であって、そんなものは福音とはいえない。それゆえ彼らは福音をもってはおらず、彼らのうちに福音の真理は存在していなかった。我々は福音を信じれるように大きな恵みが与えられた者として、自分自身のうちに福音の真理が保たれるようにせねばならない。もし我々が福音の真理から遠ざかってしまうのであればもはや我々のうちには真理は無く、我々はキリスト者ではなくなってしまうであろう。これは非常に重要なことである。あまりにも重要だからこそ、パウロは聖徒たちに福音の真理が保たれるために断固として譲歩することをしなかったのである。
次は6節目の御言葉である。
⑥『そして、おもだった者と見られていた人たちからは、―彼らがどれほどの人たちであるにしても、私には問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません。―そのおもだった人たちは、私に対して、何もつけ加えることをしませんでした。』(2章6節)
『おもだった人たち』という言葉は2章2節の箇所でも使われているが、これは、文脈から考えるならば明らかに使徒たちのことを言っている。(私の個人的・独善的・自分勝手な解釈ではないことを理解していただくために言うが)カルヴァンとルターもそのように理解している。
『彼らがどれほどの人たちであるにしても、私には問題ではありません。』とパウロは書いている。パウロはこのように言いたいのであろう。「私以外の使徒が一体なんだというのか。確かに彼らは私よりも先に使徒とされたかもしれないし、マッテヤ以外の使徒は偉大なる御方<キリスト>から直接任命されている。しかし、私も彼らと同じ真の使徒なのである。神の御前において、彼らが使徒であるという事実は、私が真の使徒であるという事実に何の影響も及ぼしはしない。」聖徒たちを惑わしていた偽キリスト者どもが、パウロが真の使徒であることを疑わせようとしていたので、パウロはこのように他の使徒たちをぶっきらぼうに取り扱うことによって自己弁護する必要があったのである。「ペテロなどの使徒たちに比べてパウロは何だか怪しいぞ。」などと思われたり言われたりしていたのだと思われるが、パウロはこれに対して「ペテロなどの使徒たちが一体なんだというのだ。彼らがどのような存在であったとしても、神にあって私が使徒であることは変わらない。」と言うことによって弁明する必要を感じたのである。とはいっても、パウロは他の使徒たちを真の意味において見下したり蔑んでいたというのではない。パウロはここで自分を弁護するため、あえて他の使徒たちを押しのけるという手法を使っているのだ。この聖なる神の器たる偉大な使徒が、キリストが直接任命された使徒たちの存在自体を愚弄することがどうしてあるだろうか。
ところで、ここで我々は、パウロの使徒としてのプライドに驚かされないだろうか。彼は、自分の使徒としての権威が曇らされているのを不快に感じ、その権威を認めさせるために他の使徒を軽んじることさえあえて行なっている。こんなにも自分に与えられた職務に自負の念を抱いている人物は他にいないのではないかとすら、私には感じられる。しかし、パウロがもっていた使徒としての自負とは、自分自身から使徒になったからというので生じた自負ではなく、神がパウロを使徒としてくださったがゆえに生じた自負である。つまり、パウロがもっていたプライドは正当なものであって不純なものではなく、それは「主にあるプライド」であった。
『神は人を分け隔てなさいません。』…確かに、パウロ以外の(マッテヤを除いた)11使徒たちは直接キリストか選ばれており、以前から使徒としての活動を行なっていた。それに比べて、使徒としてのパウロの誕生は時間的には11使徒よりも遅く、パウロは物理的・可視的な意味においてキリストから直接任命されたのでもない。だから、パウロが他の使徒たちと比べて「二流の使徒」であると見られてもおかしくはなかった。だが、パウロはここで、時間的・境遇的な違いはあったとしても、神にあってはどの使徒もみな使徒であることには変わらないと述べている。これは使徒だけでなく、クリスチャン全員にも言えることである。少し考えればすぐ分かるように、どの聖徒たちにも一様に賜物が与えられているというわけではなく、カルヴァンやヴァン・ティルのように優れた霊性が与えられているキリスト者もいるし、神学的に難しいものはあまり分からないという方も多くおられる。また、多くの善行や献金および御国のための甚大な努力・貢献などのゆえに永遠の報酬を豊かに受けるようになる人がいれば、あまり多くの報酬を受けることにはならない人も存在する。このように人それぞれ神から与えられた恵みの度合いや取り扱いの違いはあれど、どの聖徒も例外なく神の子どもであり、キリストから愛されており、その人のうちには聖霊が住んでおられる。複数の使徒たちがおり、無数の聖徒たちがいるのであるが、人それぞれ境遇や賜物の違いがあったとしても、神は彼らをその根本的存在において区別されることをなさらない。実に、この意味において、神は人をえこひいきされることをされない。つまり、神にとって、使徒は誰であっても「使徒」であり、キリスト者は誰であっても「キリスト者」なのである。
『神は人を分け隔てなさいません。』という聖句だが、これは旧約聖書からの引用であるとルターは考えているようである(※④参照)。カルヴァンの場合、このことについて何も言っていない。果たしてどうなのだろうか。確かなことは分からないが、もしかしたらルターが言っているように、パウロは旧約聖書の聖句を心に浮かべつつ書いていたのかもしれない。
『そのおもだった人たちは、私に対して、何もつけ加えることをしませんでした。』と6節目の後半部分に記されている。これは簡単に言ってしまえば、ペテロやヨハネなどの使徒たちがパウロのことを使徒として認め、受け入れ、拒否することをしなかった、ということである。使徒たちはパウロのことを「おお、確かに彼は神によって定められている使徒だ。」というような思いをもって肯定的に受容したのである。これは、パウロが使徒であることを疑わせようと企んでいる偽キリスト者どもに対する、強力な打撃となったことであろう。何故なら、キリストに任命された使徒たちがパウロのことを使徒として受け入れたのであれば、誰であってもパウロが使徒であることを認めざるを得ないからである。もし使徒たちがパウロのことを使徒として認めたにも関わらず、偽キリスト者どもがそれを認めなかったのであれば、偽キリスト者どもは自分たちが疑わしい人物であることをみずから暴露してしまうのであるから、偽キリスト者どもはパウロが真の使徒であることを否定できないのである。
⑦『それどころか、ペテロが割礼を受けた者への福音をゆだねられているように、私が割礼を受けない者への福音をゆだねられていることを理解してくれました。ペテロにみわざをなして、割礼を受けた者への使徒となさった方が、私にもみわざをなして、異邦人への使徒としてくださったのです。』(2章7~8節)
ここでは、パウロが使徒となったことと彼にゆだねられた福音という2つのものが、完全に(人にではなく)神に結び付けられている。パウロはあたかも次のように言いたいかのようである。「人間ではないのだ。私が使徒となったのも、私に福音がゆだねられたのも、人間によるのではないのである。それらは全て神によるものなのである。」
パウロであれペテロであれ、彼らが使徒になるように導かれたのは、ただ神の恵みによる。パウロやペテロは、選ばれた神の器であって、真理を委ねられており、その教説は預言者とともに教会の土台とすらされたのであるから(※⑤参照)、人間的に考えればあまりにも偉大な人物であって、プラトンやアリストテレスよりも1000倍も偉大であると言えよう。しかしパウロやペテロであっても、神の恵みによって使徒とされたに過ぎず、もし神が使徒になるよう彼らに働きかけて下さらなかったならば彼らもただの「一キリスト者」に過ぎなかった。つまり、神とその恵みのゆえに、彼らは人間的に偉大なのである。ルターも言っているように、我々は、その人物の存在そのものを見がちであり、その人にある神の恵みを見忘れ易いものである。我々は、アウグスティヌスが、カルヴァンが、カイパーが、ヴァン・ティルが、ラッシュドューニーが、などとすぐに言いがちである。確かに彼らは大きな功績・影響力をもっているかもしれないが、それは神の恵みのゆえにそうなのであって、もし神の恵みがなければ彼らもただの獣に過ぎなかった。そもそも、神の恵みがなければ彼らは救われてすらいなかった(これは我々にも同じことがいえる)。我々は偉大であるとみなされている人物をいつも重んじたりしがちであるが、しかし、その人のうちにある神の働きを忘れてしまわないようにすべきであろう。神にこそ栄光と恵みと知恵とが帰されるように。アーメン。
(2016/04/03追加)神は、使徒や宣教師など人間を用いられずに御自身の御声をもって直接人間に福音を告げることもお出来になったはずである。しかし、神はそうなさらず、使徒であれ宣教師であれ牧師であれ一般信徒であれ人の声を通して我々人間に福音を伝えるという方法を、今も昔も取っておられる。これはどうしてかといえば、神が我々人間に合わせてくださっている、というのがその答えである。小さい子どもに何かを伝えたい際、大人の男ではなく女性か子どもが派遣されるというケースが往々にしてある。神が人間とその声を用いて我々に福音を伝えられるのは、これと似たようなものである。小さい子どもに大人の男が語りかけたならばその子どもは恐がったり泣いたりしてしまう場合があるだろうが、それと同じように、神が直接その雷の御声でもって人間に語りかけるのであれば、我々人間は戦慄しつつたじろいでしまうことになるのは間違いないのである。このゆえに神は人間を用いられ、人を通して我々の身の丈に合わせつつ御自身の真理を伝えて下さっておられるのである。
⑧信仰と行ないについて
「人が救われるのは信仰のみによる。」と今まで何度も語ってきた。これは確かに聖書が述べていることである。確かに、我々が義と認められるのはただキリストを信じる信仰のみによるが、しかし、もし信仰をもったのであればその人にはかならず行ないが見られるようになるのだということを我々は覚えるべきであろう。もし誰かが信仰をもったにも関わらず、なにも行ないが見られないのであれば、我々はその人が本当に信仰をもったのかどうか分からない。例えば、ある人が主イエスを自分の救い主として信じたように見えたのだが、信じたと言っているにもかかわらず、毎週教会に来ようとせず、バプテスマを受けることを拒否し、聖書も読まず、なにも祈らず、神の御言葉に従う人生をまったく願わないのであれば、その人が本当にキリストに対する信仰をもったのかどうか我々には不明である。「あの人はイエス様を信じたのに教会に来ようとしてないけれど、本当に信仰をもっているのかな。」などと疑われてしまうことにもなる。使徒ヤコブも、もし行ないが見られないのであれば、その信仰はないも等しいと教えている。『私の兄弟たち。だれかが自分には信仰があると言っても、その人に行ないがないなら、何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。もし、兄弟また姉妹のだれかが、着る者がなく、また、毎日の食べ物にもこと欠いているようなときに、あなたがたのうちだれかが、その人たちに、「安心して行きなさい。暖かになり、十分に食べなさい。」と言っても、もしからだに必要な物を与えないなら、何の役に立つでしょう。それと同じように、信仰も、もし行ないがなかったら、それだけでは死んだものです。』(ヤコブ2章14~17節)『ああ愚かな人よ。あなたは行ないのない信仰がむなしいことを知りたいと思いますか。』(同2章20節)『たましいを離れたからだが、死んだものであるのと同様に、行ないのない信仰は、死んでいるのです。』(同2章26節)もし誰かが本当に信仰をもったのであれば、その信仰のゆえに、その人はキリスト教的な歩みをするようになるはずなのである。スポルジョンによると、ある荒くれ水夫がキリストを信じたのだが、その水夫はクリスチャンになってからはまったく正しい生活をするようになったという。つまり、品行の悪かったその水夫が信仰をもち、本当にキリストを自分の主としたので、聖書に従って清く歩むという言行が生じるようになったのである。もし信仰という種が本当に蒔かれたのであれば、その種はかならず行ないという木を生じさせる。行ないという木が見られないのは、じつは、信仰という種が蒔かれていなかったからである。けれども我々は真に信仰をもってはいても罪に腐敗した肉の身体をもっているので、神の恵みによって悪が抑制されなければ、悪徳に妨げられて良い行ないをすることが出来ない。しかし、我々は信仰をもつ者として神の恵みに助けられつつ良い行ないに励むべきであるし、良い行ないは聖書が命じているものである(※⑥参照)。我々一人一人にキリスト・イエスに対する信仰を与え、神に喜ばれる良い行ないをするための聖なる作品としてくださった父なる神に(※⑦参照)栄光と誉れがとこしえにありますように。アーメン。(※2016/02/07追加)
※①
スペインの医学者、神学者。血液の肺循環を発見。キリスト教の解釈、三位一体説を批判し、極端な人間中心的信仰を説いたため新旧両派から異端として迫害され、カルヴァンによってジュネーヴで火刑。
(百科事典 マイペディア)
[本文に戻る]
※②
『教会では、妻たちは黙っていなさい。彼らは語ることを許されていません。律法も言うように、服従しなさい。』(Ⅰコリント14章34節)
『よく指導の任に当たっている長老は、二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。みことばと教えとのためにほねおっている長老は特にそうです。聖書に「穀物をこなしている牛に、くつこを掛けてはいけない。」また、「働き手が報酬を受けることは当然である。」と言われているからです。』(Ⅰテモテ5章17~18節)
[本文に戻る]
※③
道徳的律法は、義とされた人々をも他の人々をもすべて同様に、永久的にそれへの服従に拘束する。そのことはただにその中に含まれている内容に関してのみでなく、それを与えたもうた創造主なる神の権威に関しても同様である。キリストは福音においていささかもこれをこぼつことなく、この義務を著しく強化し給うた。
(ウェストミンスター信仰告白:第19章「神の律法について」第5節)
[本文に戻る]
※④
パウロは、一度ならず用いられているモーセからのあの箇所を引用する。「あなたは裁きのときには、偉い人であろうと、貧しい人であろうとかたより見てはならない」などという箇所である。
(ルター著作集 第二集11 ガラテヤ大講解・上p143)
[本文に戻る]
※⑤
『あなたがたは使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリスト・イエスご自身がその礎石です。』(エペソ2章20節)
[本文に戻る]
※⑥
『善を行なうのに飽いてはいけません。失望せずにいれば、時期が来て、刈り取ることになります。』(ガラテヤ6章9節)
『しかしあなたがたは、たゆむことなく善を行ないなさい。兄弟たちよ。』(Ⅱテサロニケ3章13節)
[本文に戻る]
※⑦
『私たちは神の作品であって、良い行ないをするためにキリスト・イエスにあって造られたのです。神は、私たちが良い行ないに歩むように、その良い行ないをもあらかじめ備えてくださったのです。』(エペソ2章10節)
[本文に戻る]
※2016/02/07追加
1.信仰によって救われたからこそ善行が生じるということは、アウグスティヌスも次のように述べている。
したがって、恩恵は召すかたによって与えられるのであるが、善行はその恩恵を受けた者が後からなすのである。そして善行が恩恵を生み出すのではなく、むしろそれは恩恵によって生み出されるのである。というのは、火は、熱くなるために燃えるのではなく、熱いから燃えるのである。車輪は、丸くなるためにまわるのではなく、丸いから、よくまわるのである。それと同様に、だれも恩恵を受けるために善行をするのではなく、恩恵を受けたから、善行をするのである。いったい、すでに義とされていない者が、どうして正しく生きることができようか。すでに聖化されていない者が、どうして聖く生きることができようか。あるいは、すでに生かされていない者が、どうして真実の意味で生きることができようか。だが、義とされた者が正しく生きることができるために、恩恵が義とするのである。それゆえ、恩恵が第一であって、善行は第二である。(アウグスティヌス「シンプリキアヌスへ」第2問 パウロの恩恵論 釈義10-11節<3>)
教文館:アウグスティヌス著作集4 神学論集p150―151
2.ルターも、信じて聖霊を受けた者にはさまざまな良い行ないが生じるようになるのだと述べている。
それゆえわれわれはパウロとともに、キリストを信じる信仰のみが、律法も行ないもなしに義とすると結論する。人は、信仰によって義とされ、今や信仰によってキリストを所有し、キリストが自らの義であり、いのちであることを知るようになってのちはじめて、なにもしないでいるのではなく、よい木がよい実を結ぶようになるのである。なぜなら信じる者は聖霊をもつからである。聖霊がおられるところ、人がなにもしないのをお許しにならず、信仰のすべての訓練や、神への愛や、苦難の忍耐や、祈りや感謝や、すべての人への愛の実践へと人を動かしてくださるからである。
聖文社:「ルター著作集」第2集11 ガラテヤ大講解・上p231
[本文に戻る]
ガラテヤ人への手紙2章7~15節(2016/01/17説教)
『それどころか、ペテロが割礼を受けた者への福音をゆだねられているように、私が割礼を受けない者への福音をゆだねられていることを理解してくれました。ペテロにみわざをなして、割礼を受けた者への使徒となさった方が、私にもみわざをなして、異邦人への使徒としてくださったのです。そして、私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネが、私とバルナバに、交わりのしるしとして右手を差し伸べました。それは、私たちが異邦人のところへ行き、彼らが割礼を受けた人々のところへ行くためです。ただ私たちが貧しい人たちをいつも顧みるようにとのことでしたが、そのことなら私も大いに努めて来たところです。ところが、ケパがアンテオケに来たとき、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。なぜなら、彼は、ある人々がヤコブのところから来る前は異邦人といっしょに食事をしていたのに、その人々が来ると、割礼派の人々を恐れて、だんだんと異邦人から身を引き、離れて行ったからです。そして、ほかのユダヤ人たちも、彼といっしょに本心を偽った行動をとり、バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。しかし、彼らが福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て、私はみなの面前でケパにこう言いました。「あなたは、自分がユダヤ人でありながらユダヤ人のようには生活せず、異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対して、ユダヤ人の生活を強いるのですか。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。』(ガラテヤ2章7~15節)
先週は7~8節目の聖句について十分に話せなかったので、本日は先週に引き続いて7~8節目の箇所から始まる説教である。パウロが使徒としての自分をガラテヤ人たちに認めさせようとして、エルサレム滞在の時の出来事について色々と書いている。
①『それどころか、ペテロが割礼を受けた者への福音をゆだねられているように、私が割礼を受けない者への福音をゆだねられていることを理解してくれました。ペテロにみわざをなして、割礼を受けた者への使徒となさった方が、私にもみわざをなして、異邦人への使徒としてくださったのです。』(2章7~8節)
1章16節の箇所でも確認したことだが、人にはそれぞれ神から与えられた役割というものがある。ここの箇所では、パウロが異邦人に福音を伝える役割が与えられており、ペテロはユダヤ人に福音を伝える役割が与えられているということがいわれている。各人にはおのおの与えられた役割があるのだということは、聖書の中で明瞭に言われている通りである。例えば、次のような聖句である。『私たちは、与えられた恵みに従って、異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば、その信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行なう人は喜んでそれをしなさい。』(ローマ12章6~8節)『神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち、第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行なう者、それからいやしの賜物をもつ者、助ける者、治める者、異言を語る者などです。』(Ⅰコリント12章28節)『それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて、互いに仕え合いなさい。語る人があれば、神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば、神が豊かに備えてくださる力によって、それにふさわしく奉仕しなさい。』(Ⅰペテロ4章10~11節)今の時代においては、料理とか家事ができるような夫が良く言われていることがあるが、もし仕事が上手にできるというのであれば、妻が行なうべきであるこのようなことは別にできなくても構わないのである(もし夫にそういうことが出来るのであれば、それはそれで良いことではある)。我々は一人一人、神に従い、それぞれに定められている職務にふさわしく歩むべきであろう。まだ自分に定められている役割がなにか分からないという人は、神に祈るべきであって、それが何であるか分かるまでは拙速になるべきではない。
この7~8節の箇所では、パウロが異邦人に定められている使徒であり、ペテロがユダヤ人に定められている使徒であると言われているが、これは原則的なことについて語られているのだということを我々はわきまえる必要がある。つまり、パウロが異邦人への使徒だからというのでユダヤ人には伝道してはいけなかったというのではなく、ペテロもユダヤ人への使徒だからというので異邦人に伝道してはいけなかったというのではない。実際、パウロは異邦人に遣わされている使徒でありながら、ユダヤ人に対しても福音を伝えている(※①参照)。
次に、9節目の前半部分にはこう書いてある。
②『そして、私に与えられたこの恵みを認め、』(2章9節)
ここでは、完全に、ほかの使徒たちがパウロのことを受容したのだと言われている。これも、以前の聖句において確認したのと同じように、パウロのことを疑わしく思っていた人たちに対する破壊的な言論攻撃であったことだろう。ペテロなどの偉大な使徒たちがパウロを認めていたとことが分かるのであれば、パウロが使徒であることを否定できる者など誰もいないのだ。このように自分の使徒としての職務の正当性を認めさせようとしているパウロの言説には一切の隙がなく、正しく反論することは不可能である。論争家として有名だったカルヴァンから非難されたとしたら、その非難された人はたまったものではないだろうが、パウロから非難された場合はその1000倍も悲惨であると私には思える。
③『柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネが、(※2016/04/03追加)』(2章9節)
ここで、使徒の中ではこの3人が指導的な力をもっていたのだと言われている。もちろん使徒はみな使徒であることには変わらないのだが、この3人はその指導性において傑出していたということである。ここで言われているヤコブとは、1章19節でも言われている『アルパヨの子ヤコブ』(マタイ10章3節)と同じ人物であって、ヘロデに殺されたヨハネの兄弟のヤコブではない(※②参照)。カルヴァンはこの箇所から、ヤコブのほうがペテロよりも格上であったと考えている(※③参照)。ヤコブのほうがペテロよりも順序的に先に書かれているから、カルヴァンはこのように理解したのだろうか。聖書では、書かれている順序が先であればあるほど地位や尊厳が高いことを示している箇所があるが(※④参照)、ここではその書かれている順序によって格の高さが違うなどとは考えにくいように私には思われる。(※2016/02/14追加)
御存知のように、ローマ・カトリックでは、「ペテロの後継者」とされる教皇がもっとも高い地位・尊厳をもっている。この非聖書的な考えに満ちた教派において、教皇に並びたつ者はほかには存在していない。しかし、この教皇が自分の祖先とするペテロでさえ、ペテロ自身のほかにヤコブとヨハネまたパウロという3人もの並びたつ人物が存在していた。ペテロでさえ他に3人もの力ある人物に取り囲まれていたというのに、このペテロの後継者であるとされる教皇には他に肩を並べる人物がいないとは一体どういうことなのか。もし教皇が本当にペテロの地位を受け継ぐ者であるのならば、ローマ・カトリックは他にも教皇に匹敵する人物を2名であれ3名であれ作りあげ、教皇がペテロと同じ境遇になるように工夫すべきではないのか。彼が真にペテロの後継者であるというのならば、隅々に至るまでペテロにならうようにすべきであると私は思うのである。もしペテロが自分の後継者とされている今の教皇について知ったとしたら次のように思ったことであろう。「彼が私の後継者だと?ほかにもリーダー的な立場にある使徒に囲まれていた私はここまで専横的な権力は持っていなかったのだが…。」
④『私とバルナバに、交わりのしるしとして右手を差し伸べました。』(2章9節)
これは、ヤコブとペテロとヨハネの3人の使徒たちが、パウロおよびバルナバを神によって立てられた働き人であると認めたということである。以前の箇所で我々が見たのと同じように、ここでも、パウロを疑わしい人物であるとみなす者たちに対する強烈な言説攻撃が暗になされている。それで、この3人の使徒たちがバウロとバルナバを認可・受容したのは、次の目的のためであった。すなわち、9節目の後半部分に書いてある目的のことである。
⑤『それは、私たちが異邦人のところへ行き、彼らが割礼を受けた人々のところへ行くためです。』(2章9節)
「私たちはユダヤ人の救いのために、パウロたちは異邦人の救いのためにそれぞれ歩むこととしよう。」…こういった思いをもってペテロたちはパウロたちとそれぞれ役割分担をしたのである。前にも述べたが、ここで言われている役割とはあくまで原則的なことであって、「ペテロたちはかならずユダヤ人に福音を伝え、パウロたちはかならず異邦人に福音を伝えなければならない。」というように強力な拘束力があったというわけではない。また、ユダヤ人の使徒(ペテロやヤコブなど)のほうが地位が上だとか、異邦人の使徒(パウロ)のほうが職務的に優れているとか、そういった優劣における差も存在していない。ペテロなどユダヤ人の使徒も、異邦人の使徒であったパウロも、どちらも地位的には対等である。
10節目においても、パウロは自分がほかの使徒たちと同等な地位にあったことを示している。
⑥『ただ私たちが貧しい人たちをいつも顧みるようにとのことでしたが、そのことなら私も大いに努めて来たところです。』(2章10節)
ここではペテロが貧しい人たちを無視しないようにパウロに促しているが、もしここでパウロが「確かにあなたの言うとおりだ。そのとおりにするとしよう。」などと言っていたとしたら、ガラテヤ人たちはパウロをペテロに劣る使徒として認識されていたかもしれない。つまり「パウロはペテロから手ほどきを受けているぞ。」などと思われてパウロを見くびっていたかもしれない。しかし、パウロはここでそのようには言っていない。彼はペテロから貧しい人たちのことについて言われた際、「そのようなことならあなたに言われるまでもなく既に私は行なっている。そんなことは忠告されなくても分かりきっていることだ。」と言っている。こう言っているのを聞くならば、ガラテヤ人たちは、パウロがペテロに劣った使徒だとは思いにくくなる。それゆえ、パウロがこのように書いているのは、パウロの使徒としての尊厳をガラテヤ人たちに認めさせるためには非常に有益であった。
『貧しい人たち』と言われているが、この頃、ユダヤの貧しい兄弟たちが存在しており、ここでは彼らのことについて言われている。貧しく困っている兄弟たちに心を配るのは、使徒たちにとっては義務のようなものだったことであろう。この使徒たちが貧しい人たちを心にかけていたということは、ある女が主に対して高価な香油を注いだ際、弟子たちが次のように憤慨しつつ言っていることからも十分に分かるであろう。『何のために、こんなむだなことをするのか。この香油なら、高く売れて、貧乏な人たちに施しができたのに。』(マタイ26章8~9節)この香油を注いだ女は主が言われるように『りっぱなことをしてくれた』(マタイ26章10節)のであって、弟子たちはこの女に対して憤慨すべきではなかったのだが、しかし、貧しい人たちのことを思っていたからこそ弟子たちはこのように香油を売ることを考えたのであった。
『貧しい人たちをいつも顧みるように』という言葉は、我々にも言われているものとして受け取るのが望ましい。キリスト者とは「貧しい人たちを顧みる人たち」と言ってよい。我々の模範であり主であるキリスト御自身が、貧しい人たちを気にしておられた御方だったのである(※⑤参照)。聖書に無知ではないかぎり、聖書が貧しい人たちに多くの言及をしているということを知らないキリスト者はいない(※⑥参照)。聖なる律法でも、貧しい兄弟に対して憐れみの心をもつよう言われている。『あなたの神、ヤーヴェがあなたに与えようとしておられる地で、あなたのどの町囲みのうちででも、あなたの兄弟のひとりが、もし貧しかったなら、その貧しい兄弟に対して、あなたの心を閉ざしてはならない。また手を閉じてはならない。進んであなたの手を彼に開き、その必要としているものを十分に貸し与えなければならない。あなたは心に邪念をいだき、「第七年、免除の年が近づいた。」と言って、貧しい兄弟に物惜しみして、これに何も与えないことのないように気をつけなさい。その人があなたのことでヤーヴェに訴えるなら、あなたは有罪となる。必ず彼に与えなさい。また与えるとき、心に未練を持ってはならない。このことのために、あなたの神、ヤーヴェは、あなたのすべての働きと手のわざを祝福してくださる。貧しい者が国のうちから絶えることはないであろうから、私はあなたに命じて言う。「国のうちにいるあなたの兄弟の悩んでいる者と貧しい者に、必ずあなたの手を開かなければならない。」』(申命記15章7~11節)箴言でもこのように言われている。『貧しい者に施す者は不足することがない。しかし目をそむける者は多くののろいを受ける。』(箴言28章27節)『寄るべのない者に施しをするのは、ヤーヴェに貸すことだ。主がその善行に報いてくださる。』(箴言19章17節)『貧しい者をあわれむ人は幸いだ。』(箴言14章21節)もしキリスト者と呼ばれている人で、貧しい人、特に貧しかったり困っている聖徒たちに対して金銭的援助を拒否する人がいたとしたら、その人はクリスチャンであるのか疑われたとしても文句はいえない。それは、ヨハネがこう言っていることからも分かるであろう。『世の富を持ちながら、兄弟が困っているのを見ても、あわれみの心を閉ざすような者に、どうして神の愛がとどまっているでしょう。』(Ⅰヨハネ3章17節)その人は、貧しい兄弟を無視するという行ないによって自分がクリスチャンであることを否定しているようなものだからである。今の時代の説教では貧しい人たちに対する言及はあまりされていないように感じられるが、古代教会においては貧困者への援助について大いに言われたものであった。また、教会の歴史を見るならば、今まで教会が多くの援助を貧しい人たちにしてきたことが分かるが、それは正しい聖書的な行ないであった。スポルジョンも多くの慈善活動に力と財とを投入したものであった。我々クリスチャンは、決して貧しい人たちを無視するべきではない。
11節目からは、愚行をしてしまったペテロ及びそのペテロの悪を責めているパウロのことについて書かれている。
⑦『ところが、ケパがアンテオケに来たとき、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。なぜなら、彼は、ある人々がヤコブのところから来る前は異邦人といっしょに食事をしていたのに、その人々が来ると、割礼派の人々を恐れて、だんだんと異邦人から身を引き、離れて行ったからです。』(2章11~12節)
愚行をしてしまったペテロに対してパウロが抗議したのだが、ペテロは一体どんな悪いことをしたというのだろうか。このペテロはある時期までは『異邦人といっしょに食事をしていた』(12節)のであるが、これはつまり、ペテロが律法で禁止されている動物をなんら気にすることなく異邦人といっしょに食べていた、ということである。新約時代においては律法に定められている食物規定(※⑦参照)を守る必要はもうなくなっていたので、ペテロは救われた異邦人クリスチャンたちと共に律法を無視して自由な食事をしていたのである。しかし、割礼派のユダヤ人たちはいまだに律法に書かれている食物規定を守るべきであるという考えをもっていた。ペテロはこの古い考えをもっていた割礼派のユダヤ人たちを恐れたため、異邦人たちと一緒に律法を無視して自由な食事をするのを止めてしまったのである。何故なら、もしずっと異邦人たちと一緒に自由な食事をし続けていたのであれば、思い違いをしているユダヤ人たちに良く思われないと判断したからである。
ペテロは無知のゆえにこのような過ちに陥ってしまったというのではない。彼は、新約時代では律法の食物規定を気にせず何でも食べてよいということを知っていながら、自分の理解に反した行動をしたのである。使徒の働きの巻に書かれているように、神はペテロに対して「今の時代となってはもう何でも食べてよい。」と言っておられた(※⑧参照)。それゆえペテロは「新約時代においては律法の食物規定に忠実になる必要はない。」という理解を確かにもっていたはずである。だからこそペテロは異邦人たちと一緒に何でも自分の好むままに食事をしていたのである。しかし、それにもかかわらずペテロは割礼派の者たちの反応を気にし、びくびくと恐がり、間違った考えをもっている人たちに悪く思われないようにと異邦人と食事をすることを止め、この異邦人からだんだんと離れて行ってしまった。このような行ないは批判されるべきものであって、ペテロの臆病から生じた罪であった(※2016/04/24追加)。
このようなペテロの悪事にほかのユダヤ人たちもつられてしまったことが、次の13節に書かれている。
⑧『そして、ほかのユダヤ人たちも、彼といっしょに本心を偽った行動をとり、バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。』(2章13節)
使徒時代でさえ、また、聖性と敬虔と信仰において全てのクリスチャンを凌駕していただろう使徒たちのリーダー的存在であったペテロでさえ、このような偽りに陥ってしまった。ペテロやバルナバでさえこのようになってしまったのであれば、今の時代ではどのようなことが起こるであろうか。彼らでさえ悲惨を免れなかったのだから、我々はなおさらのこと悪と愚かさと誤謬とに陥ってしまうであろう。実際、今のプロテスタント教会をみたら、このことは明らかである。ディスペンセーショナリズム、無律法主義、アルミニウス主義、バルト、リベラル、浸礼ではないバプテスマに対して異常なほど憤激するグループ、幼児洗礼に対して異常なほど気を激しくする教師…このようなものが考えればいくらでも出てくるのである。そして、当然ながらこの教会も例外ではない。我々は聖書的な教会であるのを願っているのであるが、しかし「我々だけは絶対に大丈夫だ。」などとは言えない。私はこの教会が聖書的な神学および思想に満たされ、それらのうちに保たれるのをいつも願っており、(言うまでもないことだが)これからも聖書的になるようにするつもりである。しかし、そうではあっても神の御前においては多くの愚かさがこの教会にも存在しているに違いないのである。それゆえ、我々は神に祈らねばならないだろう。神が御自身の教会を守り、誤謬から遠ざけ、豊かに真理を満たしてくださるようにと。
使徒たちの柱として重んじられていたペテロが引き金となって聖徒たちに悪が拡がってしまったのであるが、このことからどのようなことが分かるだろうか。それは「力がある者ほど、その悪徳を周りの人たちに伝播しやすい。」ということである。悪を行なった者がリーダー的な存在であればあるほど、その者に対して従属的な立場にいる人々に悪い影響を及ぼしてしまうことになる。箴言に『支配者が偽りのことばに聞き入るなら、従者たちもみな悪者になる。』(29章12節)と書いてある通りである。普通の人が悪を行なったことによりその人が所属している団体全体に悪が伝染してしまう可能性は、リーダー的な人の場合のそれよりも少ない。つまり、牧師の悪は信徒たちに伝播しやすく、リーダーの不正も部下たちに悪影響を及ぼしやすく、父の愚かさも子どもに移りやすく、権威者の罪も彼を重んじる人たちに害を与えやすく、ペテロの悪徳もほかのユダヤ人たちを引きこませやすい。この逆の現象は(まったく起こらないということではないが)いま述べたこれらの場合よりは起こりにくい。それゆえ、高い地位や大きな影響力をもっている人たちの責任は非常に大きいがゆえに、よく注意しないと多くの人たちを不幸にしてしまうことになりかねない。
次の14節において、このペテロをパウロが実際に責めている場面が書かれている。
⑨『しかし、彼らが福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て、私はみなの面前でケパにこう言いました。「あなたは、自分がユダヤ人でありながらユダヤ人のようには生活せず、異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対して、ユダヤ人の生活を強いるのですか。』(2章14節)
ペテロがどうして責められたかといえば、ペテロの偽りの行ないが、周りの人たちを福音の真理から逸らす性質をもったものだったからだ。さきほど述べたように、このペテロは最初は、律法で禁止されている動物を気にすることもなく異邦人たちと一緒に食べていた。しかし、彼はある時から割礼派の人たちを恐がって、ふたたび律法に書かれている食物規定を守るようになった。このようなペテロの変化を見た周りの人たちが次のように思ったとしても不思議ではない。「あれ、ペテロは律法で禁止されている動物を食べないようになってしまったけれど一体どうしたのだろうか。あのペテロがこういうことをするようになったのだから、やっぱり救われるためには信仰だけではなく律法の行ないも必要だということなのだろう。」つまり、ペテロは自分の偽りの行ないによって、暗に周りの人たちに「救いのためには律法を守らなければいけない。」と叫んでいたのである。我々の場合においても、自分自身の行ないを通して暗になにかを誰かに教えてしまうことがある。例えば、毎日からだに悪いものばかり食べていた人が急に健康的なものばかり食べるようになったら、その人は自分の行ないによって周りの人に「健康は大事だ。身体に悪いものはよくない。」と暗に伝えていることにならないだろうか。このペテロは自分の振る舞いによって周りの人たちを勘違いさせてしまうような行ないに陥ってしまったのであるが、それは福音に関する事柄であるから、ペテロの愚行は非常に恐るべき事態を生じさせてしまうものであり、彼は当然非難されるべきことをしてしまったのである。
ここでパウロが公然とペテロを非難している理由を更に詳しく考えるならば、我々はその理由を3つほど見出せるように思われる。まず一つ目は、たった今語ったように、ペテロの行ない自体が責められるべきものだったからである。ペテロの愚行は福音の真理に関わっていたため、妨げられることなく批判されなければいけないものだった。二つ目は、ペテロが仲間たちの前で公然と責められることによって、それを見た人たちが間接的に責められ教えられるためであったと思われる。この状況において改善されるべき者はペテロ一人だけでなく、ペテロにつられてしまった多くの者たちも改善される必要があったのは言うまでもないからだ。三つ目の理由は、ペテロが非難されているのを多くの人たちが見ることによって、それを見た人たちがペテロと同じ過ちをふたたびしてしまわないように恐れるためであったと思われる。もしペテロに対するパウロの抗議を見たのであれば、その人は自分もペテロのように抗議されるのを恐れて、ふたたび愚行に陥らないよう警戒することになるだろう。この第三の理由は、パウロが次のように書いていることからも分かるであろう。『罪を犯している者をすべての人の前で責めなさい。ほかの人をも恐れさせるためです。』(Ⅰテモテ5章20節)
ここではペテロがパウロの抗議に対してどのような反応をしたかについては書かれていないが、神に用いられたペテロという聖なる器のことを考えるのであれば、おそらく素直になってパウロの言うことを認めたであろうと思われる。何故なら、パウロの抗議は実に正当なものであったし、ペテロの行ないは非難されて当然のものだったからだ。このペテロが「なんだと!あなたは実に生意気な態度を私にとっている。この私を批判するとはどういうことか?私は神に遣わされた使徒なのだぞ!!?」などと言って反発したとは考えにくい。むしろ、ペテロは自分を責めてくれたパウロに対して兄弟愛を深めたのではないかと私は推測する。『知恵のある者を責めよ。そうすれば、彼はあなたを愛するだろう。』(箴言9章8節)と言われているからである。
また、いま我々が見ているここの箇所からも、パウロの使徒としての権威が輝かされているのが分かる。何故なら、ペテロほどの人物に対して臆することもなくパウロが責めているからである。このような出来事があったと知れば、「パウロがあのペテロをすら責めているとは…。」などとガラテヤ人たちが関心の念をパウロに抱いたとしても不思議ではない。また、もしパウロが真の使徒ではなかったとすれば、「あいつは使徒でもないのにあのペテロを大胆に責めているが、いったい何様なのだ。」などと思われても不思議ではない。しかしパウロは真の使徒だったのであり、真の使徒だったからこそペテロを対等な者として認識しつつ責めたのである。パウロが一信徒に過ぎなかったのであれば、ペテロという神の聖なる使徒をこのように大胆に責めるのは僭越すぎる行ないだったであろう。それゆえ、このようなことについて書かれている文章をガラテヤ人たちが読むのであれば、そこに書いてある出来事の真実性と力強さのゆえに、彼らはパウロのことを真の使徒として認めざるを得なかったことであろう。
ここまで、ペテロが恐れのゆえ真理に対して不正を働いてしまった出来事を見てきたが、「恐れ」とは真理への忠実さを奪い去らせてしまう性質をもっていることを我々は覚えねばならないだろう。キリスト教の歴史において、死や苦痛や非難に対する恐れのために真理を裏切ってしまった人たちは少なくない。これは主にカトリックに関わる出来事であるが、1628年頃に導入された踏絵制度によって(1858年廃止)、キリシタンと呼ばれていたカトリック信者たちが自分の信仰に反した行ないをしてしまった。キリストの姿が刻まれた像を踏んでしまった人たちは、恐れのゆえにそうしてしまったのである。この踏絵制度やペテロの例からも分かるように、恐れの感情は信仰を棄てさせ、自分の思想信条に違反した偽りの行ないを生じさせてしまうのだ。どうか神が、我々を『おくびょうの霊』(Ⅱテモテ1章7節)に惑わされないよう守ってくださるように。
次は本日の最後の箇所である15節目であるが、このように書かれている。
⑩『私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。』(2章15節)
パウロやペテロなどのユダヤ人たちは、生まれながら神の律法に生きるべき契約の民として人生を開始したのであって、それゆえ契約の民のメンバーの印である割礼を生後8日目に受けたわけである。つまり、彼らは誕生した時点からすでに「律法の義に歩むべき神の民」であった。彼らも堕落している罪人であることは他の民族と変わらなかったが、彼らは他の民族とは違って「罪人だが神に選ばれた聖なる民族」であった。しかし異邦人と呼ばれる他の民族は、ユダヤ人のように神の律法に生きるべき者として生まれたのではなく、神と律法とはまったく無縁の存在としてこの世に生を受けた。つまり異邦人の場合はユダヤ人とは違い、生まれながらにして神に敵対・反逆するまったくの罪人としてこの世に誕生した。たった今ユダヤ人は「罪人だが神に選ばれた聖なる民族」であると言ったが、これに対して異邦人は「神とその契約からまったく疎外された惨め極まりない罪人」または「救いから除外された地獄を相続すべき罪の中に死んでいる民族」であると言える。この15節では、こういった意味において―つまり神の御前における契約的な相違という観点において―2種類の人たち(ユダヤ人と異邦人)のことが言われている。
ここでパウロは「我々ユダヤ人とは生まれながらにして律法の義に歩むべき神の民である。」と言っているが、この節に続く16節目からは、この15節目の内容を土台として次のような福音的論説が展開されている。「確かに我々ユダヤ人は律法の義に生きるべき民族として生まれたのだが、しかし、我々は律法の行ないによって義と認められるのではない。我々が律法の民としてこの世に生を受けたとしても、律法によって義認を得られるなどという考えは退けるべき誤謬に他ならない。我々が義と認められるためには律法の行ないではなく、ただイエス・キリストを信じる信仰こそがなければならないのである。」本日はこの15節目で終わりであるから、これらのことは次週、神の恵みによって語られることになるだろう。ルターも言っているが、キリストの救いについてはどれだけ語っても語りすぎるということはない。福音を完全に知り尽くしていると自負しているキリスト者のことをルターは非常に驚いているが、ルターであれ我々であれ、この福音を隅から隅まで完全完璧に捉えきっているわけではないからである。私にしても年数が経つにつれ福音についての理解は深まっていると感じるが、それは福音を限界まで窮めていないことの証拠であって(なぜならもし限界まで窮め尽くしていたとしたら理解が深まるなどという現象は起こらないはずだからである)、福音を窮め尽くしてはいないということは全てのクリスチャンに言えることである。この「福音」とは「三位一体神への信仰」および「聖書信仰」と共にクリスチャンをクリスチャンたらしめている最も大きな要素の一つである。三位一体の教理を間違って理解しているか信じていない人がクリスチャンとは言えないように、また聖書を神の言葉として信じていない人が我々の仲間とは言えないように、福音を信じていなかったり歪められた福音を信じていたりする人は我々の仲間であるクリスチャンとは言えないのである。来週は恐らく、このキリストの福音のことについて詳しく語られることになるであろう。どうか主なる神が、聖書の真理に対する我々の理解をさらに深めてくださるように。
※①
『兄弟たちは、すぐさま、夜のうちにパウロとシラスをベレヤに送り出した。ふたりはそこに着くと、ユダヤ人の会堂にはいって行った。ここのユダヤ人は、テサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、、非常に熱心にみことばを聞き、はたしてそのとおりかどうかと毎日聖書を調べた。』(使徒の働き17章10~11節)
[本文に戻る]
※2016/04/03追加
使徒たちはこの聖句でいわれているように指導力・プレゼンスにおいて差があったが、その権威・尊厳においては平等であった。実に、平等であったからこそ、新参また後輩の使徒であったパウロは筆頭使徒の一人であるペテロに面と向かって抗議できたのである。使徒たちが互いに平等であったように、真の牧師たちもその権威・尊厳において互いに平等であるとすべきである。正統的な改革派信条でもこのように言われている。「すべての真の牧師は、いかなる場所にあっても、ただ一人の首長、ただ一人の君主、全教会の監督なるイエス・キリストのもとにおなじ権威とおなじ力をもつ」。(『フランス信条』:30<牧師の平等なること>※新教出版社「信条集」前篇p326)「神の言の教役者については、かれらがいかなる地位にあるにせよ、かれらはすべて唯一の総監督また唯一の教会の首長なるイエス・キリストの教役者であるならば、同じ権力と権威を持つのである」。(『ベルギー信条』:第31条<教会の教役者の職務について>※新教出版社「信条集」前篇p351)しかしながら、牧師たちがみな平等であるにも関わらずリーダーシップなどにおいては差があったとしても何ら非難されたりすべきではない。何故なら、互いに平等であるにも関わらず使徒たちの間にはプレゼンスの面で差があった(すなわちヤコブとケパとヨハネの三人が柱として重んじられていた)からである。
[聖句に戻る]
※②
『そのころ、ヘロデ王は、教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。』(使徒の働き12章2節)
[本文に戻る]
※③
なお、ここでは権威が問題なのであるが、ヤコブのほうがペテロ以上に重んぜられているという事実は、驚くべきことである。おそらくそれは、ヤコブがエルサレム教会を監督していたからなのであろう。
(カルヴァン・新約聖書注解p47)
[本文に戻る]
※④
例えば次の箇所は、先に書かれているほど職務における尊厳のレベルが大きいと思われる(※伝道者を使徒に次ぐほどの職務として考える教派の場合における理解。バプテスト派など、伝道者がたくさん存在しており牧師よりも低く扱われがちな教派もある。)。
『こうして、キリストご自身が、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。』(エペソ4章11節)
[本文に戻る]
※2016/02/14追加
この時、私はカルヴァンの考えるように書かれている順序が権威の高さを示しているとは考えられないのではないかなどと述べ、その後も多少曖昧であった理解のまま思いあぐねていたが、やはり、ここでは書かれている順に重んじられていたのだという理解に確定したいと思う。しかし、カルヴァンの言うようにヤコブのほうがペテロよりも重んじられていたのだとしても、ヤコブという人物について思案するのであれば、この事実はそれほど驚くべきことであるというわけでもない。というのは、「義人」と呼ばれていたこの使徒ヤコブはほかの使徒たちによってエルサレム教会の最初の監督に選ばれた人物であり、凄まじいほどの聖性と敬虔とを持っていたからである。エウセビオスの「教会史」第Ⅱ巻23章によると、このヤコブは「哲学と敬虔の生活によって達した高みのために、すべての者からもっとも義しい人物と見なされていた」(講談社学術文庫:エウセビオス「教会史」上p131)「立派な人物で、その義のためにすべての者に知られていた」(同p135)のだという。エウセビオスはこの書物の中で、ヘゲシップスという2世紀のユダヤ人キリスト教史家が述べているヤコブの説明を次のように引用している。「主の兄弟ヤコブは、使徒たちとともに教会を継承した。彼は、主のときからわたしたちまでのすべての人びとから義人と呼ばれた。ヤコブという名の人物が大ぜいいたからである。彼は母の胎内にいるときから聖別され、ぶどう酒や濃い酒を飲まず、命あるものも食べず、かみそりを頭にあてることもなかった。彼はオリーブ油を塗りもしなければ風呂にも入らなかった。彼だけに聖所に入ることが許された。彼が毛ではなく、極上の亜麻布をまとっていたからである。彼はただ一人で神殿に入って跪き、民の赦しを祈るのだった。そして絶えず跪いて神に祈り、民のために赦しを乞うために、彼の膝頭はらくだのように固くなった。彼は正義が横溢していたために、「ディカイオスにしてオーブリアス」と呼ばれた。…」(同p132)このヘゲシップスによると、ヤコブは殉教する際、キリストやステパノのように自分を迫害する者たちの赦しを神に祈り求めながらこの人生を終了させた(同p134参照)。ヨセフスも、ヤコブのことを「もっともすぐれた義人」と述べている。これらの言説を真なるものとするならば、ヤコブは非常に信仰深いキリスト者だったうえ、エルサレム教会の初代監督として使徒たちによって任命されたほどの大人物なのであるから、パウロが、ヤコブをペテロよりも上に位置させていたとしても何も不思議ではない。
[本文に戻る]
※⑤
『イエスは、彼に言われた。「もし、あなたが完全になりたいなら、帰って、あなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。』(マタイ19章21節)
[本文に戻る]
※⑥
例えば次の御言葉など。
『主は、弱い者をちりから起こし、貧しい人をあくたから引き上げ、彼らを、君主たちとともに、御民の君主たちとともに、王座に着かせられる。』(詩篇113篇7~8節)
『主は君主たちをさげすみ、道なき荒れ地に彼らをさまよわせる。しかし、貧しい者を悩みから高く上げ、その一族を羊の群れのようにされる。』(詩篇107篇40~41節)
[本文に戻る]
※⑦
『あなたは忌みきらうべきものを、いっさい食べてはならない。あなたがたが食べることのできる獣は、牛、羊、やぎ、鹿、かもしか、のろじか、野やぎ、くじか、おおじか、野羊。および、ひづめが分かれ、完全に二つに分かれているもので、反芻するものは、すべて食べることができる。反芻するもの、または、ひづめの分かれたもののうち、らくだ、野うさぎ、岩だぬきは、食べてはならない。これらは反芻するが、ひづめが分かれていない。それは、あなたがたには汚れたものである。豚もそうである。ひづめは分かれているが、反芻しないから、あなたがたには汚れたものである。その肉を食べてはならない。またその死体にも触れてはならない。すべて水の中にいるもののうち、次のものをあなたがたは食べることができる。すべて、ひれとうろこのあるものは食べることができる。ひれとうろこのないものは何も食べてはならない。それは、あなたがたには汚れたものである。すべて、きよい鳥は食べることができる。食べてはならないものは、はげわし、はげたか、黒はげたか、黒とび、はやぶさ、とびの類、烏の類全部、だちょう、よたか、かもめ、たかの類、ふくろう、みみずく、白ふくろう、ペリカン、野がん、う、こうのとり、さぎの類、やつがしら、こうもり。羽があって群生するものは、すべてあなたがたには汚れたものである。羽のあるきよいものはどれも食べることができる。』(申命記14章3~20節)
[本文に戻る]
※⑧
『その翌日、この人たちが旅を続けて、町の近くまで来たころ、ペテロは祈りをするために屋上に上った。昼の十二時ごろであった。すると彼は非常に空腹を覚え、食事をしたくなった。ところが、食事の用意がされている間に、彼はうっとりと夢ごこちになった。見ると、天が開けており、大きな敷布のような入れ物が、四隅をつるされて地上に降りて来た。その中には、地上のあらゆる種類の四つ足の動物や、はうもの、また、空の鳥などがいた。そして、彼に、「ペテロ。さあ、ほふって食べなさい。」という声が聞こえた。しかしペテロは言った。「主よ。それはできません。私はまた一度も、きよくない物や汚れた物を食べたことがありません。」すると、再び声があって、彼にこう言った。「神がきよめた物を、きよくないと言ってはならない。」こんなことが三回あって後、その入れ物はすぐ天に引き上げられた。』(使徒の働き10章9~16節)
[本文に戻る]
※2016/04/24追加
このペテロの過ちは、まさに『人を恐れるとわなにかかる。』(箴言29章25節)という御言葉の通りである。ペテロは割礼派の人々を恐れてしまった。それゆえ彼は、誤謬に惑わされて異邦人から遠ざかるという罠に陥ってしまったのである。もしペテロが人を恐れなかったならば罠にかかることも無かったであろう。我々は、ペテロのこの過ちから「人を恐れるならば害が生じる。」という教訓を得るべきであろう。
[本文に戻る]
ガラテヤ人への手紙2章16節(2016/01/24説教)
『しかし、人は律法の行ないによっては義と認められず、ただキリスト・イエスを信じる信仰によって義と認められる、ということを知ったからこそ、私たちもキリスト・イエスを信じたのです。これは、律法の行ないによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら、律法の行ないによって義と認められる者は、ひとりもいないからです。』(ガラテヤ2章16節)
■聖句の概要
本日の聖句は、生まれながらにして律法という神の戒めを行なうべくこの世に生を受けたユダヤ人であっても律法を守るという行ないが人を救うのではないということについて使徒パウロが論じている箇所である。「ユダヤ人という生まれながら律法を人生の規範とするよう定められた民族だからといって、この律法が自分たちを救うなどという思い違いをしてはならない。我々ユダヤ人がどれだけ聖なる戒めを守ろうとも救われないし、いかに律法に歩んでいる人であっても罪人であることには変わらない。何故なら人が救われるのは律法の行ないによるのではなく、イエス・キリストを信じることによるからだ。」と使徒パウロは言いたいのである。
■聖句の構成
この聖句における論述は、3つの部分から組み立てられている。まず初めに本題が述べられている。『しかし、人は律法の行ないによっては義と認められず、ただキリスト・イエスを信じる信仰によって義と認められる、ということを知ったからこそ、私たちもキリスト・イエスを信じたのです。』まず「律法を行なうことではなくキリストを信じることによって救われるということを知ったからこそキリストを信じた。」と使徒パウロは言っている。次に、パウロたちがキリストを信じことについての説明がなされる。『これは、律法の行ないによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。』ここでは「私たちがキリストを信じたのは、律法を行なうことではなく、キリストを信じることによって救われるためだ。」との説明がされている。最後に、キリストを信じた理由について述べられている。『なぜなら、律法の行ないによって義と認められる者は、ひとりもいないからです。』つまり「律法を行なっても人は救われることができないからこそ、救われようとしてキリストを我々は信じたのだ。」ということである。
■説教の内容
本日の説教は3つの項目から成り立っている。まず第一に罪と地獄のことについて語られ、次に義認という救いについての話がなされ、最後に義認の方法についての説明が行なわれる。いつもの説教では聖句をひとつひとつ説明して我々の人生に真理が適用されるような内容となっているが、本日はいつもとは違い、聖句と共に救いについての説明が行なわれる説教となっている。我々の主なる神がこの時間を祝福してくださるように願いつつ、祈りをもってはじめたいと思う。
【Ⅰ.罪と地獄について】
1:罪を理解する必要性
まず、罪とその罪に対する永遠の刑罰についての話がなされねばならない(※①参照)。何故なら、罪とか死後に行くべき地獄とかいったものについての理解が抜け落ちているのであれば、救いとかイエス・キリストの十字架とかいったものについての説明を聞くための素地が欠けてしまっているからである。もし罪とか地獄および天国などといったものについての思いがまったく無い人がいたとしたら、そのような人に救いについての話がされても空想話のように感じられてしまうだろう。「救い?はっはっは。なにを言っているのかね、君は。」などと思いかねない。罪とか地獄などといったものについての概念が心のうちに存在しているからこそ、救いとか天国とかいったものについての思考が有効に働くようになるのだ。言うまでもなく、使徒パウロも本日の聖句において「地獄に行くべき罪深い人間」という理解を前提・土台としつつ語っている。
2:罪人である人間
聖書では、イエス・キリストを除くすべての人間が罪人であると教えられている。もし悪いことをまったくしたことのない人がこの世界に誰かいたとしたら、その人は「義人」であると言えよう。それゆえ「この世界には義人がいくらか存在している。アメリカのオハイオ州にいる○○氏とガーナにいる○○社長と日本にいる○○議員などがそうだ。」などと言えたであろう。しかし聖書はそれを否定している。『義人はいない。ひとりもいない。』(ローマ3章10節)と書いてあるとおりである。ある宗教では、人の心を清いものだとみなしているが、そのようなことはない。いったい、誰が自分の心について堂々と「清い」と言えるであろうか。もし本当に「清い」と豪語するのであれば、その人は、かつて邪悪極まりない思いを抱いてしまった時の心の状況を、隠さずに皆に公開していただきたい。「こんな悪い思いをこの人は抱いたのか。これはひどいものだ。」などと思われてしまうほどに邪悪なことを思った時の心における状況を語れる人などいないだろう。まさか、そのように決して公開できないほどの悪い思いを心に抱いたことのない人もいないだろう。もし「自分こそその人である。」などと言う人がいたとしたら、その人は嘘をついているのだ。誰でも人に言えないような思いを心に抱いてしまったことがある。そうであるならば、そのような思いを抱いてしまう心をもっている人間とは罪深い存在と言わねばならないのではないだろうか。
3:律法違反という罪
それでは具体的に罪とはどういうふうに定義されるべきなのか。例えば、貧しい人たちのために金持ちから財産を盗んだ人物がいたとしたら、ある人は「いくら貧しい人たちのためであったとしても泥棒行為には変わらないから彼は悪いことをしたのだ。」と考え、別の人は「彼は貧しい人のことを思ってああいうことをしたのだから犯罪行為をしたのではない。それゆえ彼は罰せられるべきではない。」と考えるだろう。また、今の日本では一夫多妻は社会的に容認されておらず沢山の妻をもっている人などまったく見られないほどだが、昔においては、それが欲望のためではなく子どもを多く産むためであるならば容認されている社会もあった。このようなことについて考えると、必然的に「人間にとって絶対的な罪とはいったい何なのか。」という思いが生じることにもなる。不動の規範がそこにないので、社会や人間の違いによって何が罪であるかという定義が変わってしまっているのを感じるからある。今の社会でも、ある事柄について「それは犯罪的だよ。」と言っている人がいれば、「それは悪いことでは決してない。」などと言う人もいる。しかし、聖書は、何が罪であって何が罪でないかという定義をしっかりと教えている。聖書は、神に従おうとせず聖なる律法に違反することこそ罪であって悪いことであると教えている。『罪とは律法に逆らうこと』(Ⅰヨハネ3章4節)と書かれている通りである。例えば、律法では『殺してはならない。』(出エジプト20章13節)と言われているが、これは外面的なことだけを言っているのではなく、内面―つまり心においても誰かをいっさい傷つけたりしないことを求めている。『欲しがってはならない。』(出エジプト20章17節)と言われているが、これは書かれている言葉の通りであって、もし心の中で誰かのものを羨んだとすれば、その人は罪を犯してしまったことになる。この律法は心・精神の面においてもそれを守るように求めているが、内面的にも完全完璧に守れる人など存在していない。それで、もし内面に関しても律法を守れないのであれば、その人は神の前に悪いことをしているのである。だから、外面的にだけでなく内面的にも完全に律法を守れない我々人間は日々、神の前に大量の悪を行なっているのであって、それゆえ全ての人間が(律法を守れないがゆえに)神の前に罪人であると聖書は教えている。クリスチャンであれ、未信者の方々であれ、律法を忠実に行なえないのだから、神の前に誰であっても罪人なのである。
4:人間的に優れていても罪人であることには変わらないことについて
徳が高かったり、その人間性の卓越さのゆえに称賛された人たちが昔も今も存在している。アナクサゴラス(前500頃―前428頃)とデモクリトス(前460頃―前370頃)という哲学者は、哲学に打ち込んだがゆえに、自分たちの財産を家畜たちに食い荒らせるにまかせた。それゆえ、ギリシャ人は彼らのことを称賛した。彼らが金銭を超越しており、物質的なものの奴隷ではないのを見たからである(※②参照)。彼らとは違って、ある哲学者たちは自分の財産を家畜によって無駄にさせてしまうのではなく人々に恵み与えることによって、自分が金銭に隷属しているのではないことを証明した。それゆえ、他人を財産によって、自分を哲学によって益したその哲学者たちのことがユダヤの大哲学者であるフィロンによって称賛されている(※③参照)。確かに、金銭は必要であって大事なものではあるのだが、それの奴隷ではないということは認められるべき精神性の高さをもっている人物であると言えよう。他にも、自由を愛する不屈の精神のゆえに奴隷的になるよりは命を捨てることを選んだ人も、卓越した人物であると特定の人々から称賛された(※④参照)。エレアのゼノンという有名な哲学者(前490頃―前430頃)は、拷問を受けた際、明かしてはならない事柄を己の意志に反して無理矢理喋らされないようにと、自分の舌を噛み切って拷問をしている者に対して吐きかけた。それゆえ、彼もその忍耐と意思の力強さにおける卓越性を認められている。これらは昔の人たちの話であるが、今の時代においても、例えば人類社会のために自分の命をすら惜しまなかった人たちが賛美されるのは珍しいことではない。優れた誠実さや品性の高さのゆえに称賛されている人たちもいる。これは有名な話であるが、マッカーサーも昭和天皇のことを称賛した。第二次世界大戦が終結した後、昭和20年9月27日に昭和天皇は米国大使館を訪問されたのだが、その時マッカーサーは「天皇が、敗戦国の君主が通常そうするように戦争犯罪者として起訴されないよう訴えるのではないか?」との懸念を抱いた。しかしその時、天皇は命乞いをするどころか「戦争の全責任は私にある。私は死刑も覚悟しており、私の命はすべて司令部に委ねる。どうか国民が生活に困らぬよう連合国にお願いしたい。」と言われたという。この廉直な高い精神性のゆえにマッカーサーは天皇を「日本の最上の紳士」であると認識し、後には「あんな誠実な人間は見たことがない!」と語ったのである。このように徳の高さや優れた品性のゆえに称賛される人たちがこの世界には存在しており感嘆させられることも多いのであるが、しかし、聖書によると、たとえどれだけ素晴らしい人間性をもっていたとしても神の前に罪人であることは誰であっても同じである。それは、いかに人間的に高い品性をもっていても、神の律法を完全に守れていないからである。神が万人に守るよう求めておられる聖なる律法を守れていないのであれば、その人は、神の前に義人であるとは決して言えない。それゆえ、いかに称賛すべき優れた人たちであっても神にとってはただの罪深い人間にすぎないのだ。
5:罪に対する永遠の刑罰―地獄
罪に満ちた人間に対して、裁判者なる神は永遠の有罪を宣告される。この世界において、動かぬ証拠が揃っている状況の際、裁判官は悪を行なった人物に対して有罪判決を言い渡すだろう。それと同じように、罪についての無数の証拠をもっている人間に対して、神は有罪の判決を容赦なく下される。神は、人間が行なった律法への違反をことごとく見ておられるのであって、その違反を全く明瞭に覚えておられる。そして、その違反という罪のゆえに、人は永遠の地獄の中で焼き尽くされるという刑罰を受けねばならない。その時、審判者なる神は罪人である人間にこのように言われる。『のろわれた者ども。わたしから離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火にはいれ。』(マタイ25章41節)この神に対して、言い訳は通用しない。「そんな。私は良いことも結構しましたし、他の悪人どものように大きな犯罪行為はしていません。人間の中では正しく生きたほうです。それでも永遠の火にはいらなければならないのですか。」などと言っても無駄である。これが人間だったら「まあ、確かにお前はまともな人生を送っていたし良いことも沢山していたから、永遠の刑罰は免れさせてやろう。」ということにもなるが、神の場合はそうではない。何故なら、神とは完全であって、聖であって、義なる御方だからである。例えば、完全なものしか収集しない完全主義のコレクターがいたとして、彼は一つも傷のない完全なもの以外は買おうとせず、自分のコレクションの中のあるものが傷ついたならそれを廃棄してしまうほどに完全であろうとする。このような完全主義の人と同じように神は完全な存在であって、たとえ少しであっても罪に汚されているのであれば、神はその罪に汚れている人間を地獄に投げ込んで永遠に捨ててしまわれるのである。それゆえ、罪に汚れている人間は誰でも神による地獄の刑罰を避けられない。
【Ⅱ.義認について】
1:義認について説明する必要性
ここまで罪と地獄についての話がされた。この罪とか地獄とかいったものについて何か考えたりするのであれば、必然的に「では我々人間は救われる必要があるのだろうか。地獄を避けて天国に行ける方法があれば、それは一体どのようなものだろうか。」などという救いのついての考えが展開されることにもなる。それゆえ、罪と地獄について1番目の項目で語られたことの展開として、2番目の項目では義認という救いについての話がなされることになる。実に、この義認という救いについての事柄が、本日の聖書の箇所では論じられているのである。
2:義認とは何なのか
「義認」とは、神がその恵みによって汚らわしい罪人を義、つまり全く正しい存在として認めて下さることを言う。つまり、義認とは簡単に言ってしまえば「救い」のことである。もし誰かが救われて義と認められるのであれば、その人は罪の赦しを受けるのだから、罪が赦されているがゆえに永遠の刑罰を受けることもなく天国に行くようになる。しかし義と認められていないのであれば、その人は救われておらず罪の赦しも受けいていないのだから、罪が赦されていないがゆえに罪に対する神の恐るべき刑罰をその身に受けねばならない。これらのことを短い言葉でまとめるならばこういうことになる。「義と認められるならば天国に行き、義と認められなければ地獄に行く。」それゆえ、この義認とは我々の死後に関わるものであるがゆえ、あまりにも重大なものであることが分かる。
3:義認についての詳細
本日の箇所では『義と認められる』と書かれていることに注目してほしい。『義と認められる』と書いてあり、「義にされる」―つまり義そのものとされる―とは書かれていない。聖書の他の箇所でも「義と認められる」という書かれ方になっている(※⑤参照)。つまり、義と認められた人は、神がその人を義人であると見なして下さるのであって、その人自身が義そのものになるということではないのである。たとえ義と認められ、神に義人であると認識されていたとしても、その人自身について考えるならばその人はあわれな罪人にすぎない。ルターという宗教改革者が『真面目なクリスチャン』などと呼ばれて歴史の教科書に出てくるが、この真面目なルターも言うように「義と認められたが同時に罪人」である。また、神が義をその人に<注入>するというのでもない(※⑥参照)。もし義が注ぎ込まれることによって救われるというのであれば、義がその人に注ぎ入れられたがゆえに、その人は義そのものになってしまうのであるからもはや罪人ではなくなってしまう。しかしそうではない。神からの義が注入されるというのではなく、義が上からその人を全く覆うことによって義なる存在として見なされるようになるということである(※⑦参照)。我々はこの点についてよくわきまえる必要がある。
4:義と認められることの重要性
本日の箇所では、神の前に汚らわしい罪人が義と認められることについて書かれている。使徒パウロも、自分が義と認められて救われることを求めたのであった。そして実際、彼は義と認められてクリスチャンとなったのであった。義と認められていない方々は、パウロと同じように義と認められるのを求めるべきであろう。何故なら、もし義と認められていないのであれば、その人は永遠の地獄に投げ込まれてしまうからである。義と認められておらず神の前に汚らわしい状態のままでいるのであれば、我々人間が腐った不要物を容赦なく火で焼いてしまうように、神によって地獄の激しい炎で永遠に焼かれることになっても文句は言えないであろう。地獄で『永遠に昼も夜も苦しみを受ける』(黙示録20章10節)のを避けたいのであれば、義と認められることを求めねばならない。
【Ⅲ.義認の方法について】
1:義認の方法
人間が義と認められる必要があるということを述べたのであれば、必然的に「もし義と認められる必要があるというのならばそれは一体どのような方法によるのか?」という考えが展開されることになる。3番目の項目では、この義と認められる方法について詳しく論じられる。我々が見ている本日の聖書の箇所では、この方法が一体どのようなものであるのかということについてこそ書かれている。それで、人が義と認められるための方法には2種類の考え方がある。すなわち、「自分の行ないによるか」または「イエス・キリストを信じる信仰によるか」。義と認められることにおいて、両方とも選ぶなどということは出来ない。何故なら、もし信仰を取るのであれば行ないを捨てねばならず、それとは逆に、行ないを取るのであれば信仰が殺されてしまうからである。また、両方とも正しい考え方であるということもなく、正しい考え方は2つのうち1つしかない。何故なら、もし信仰によって義と認められるという考えを正しいとするならば行ないの方を否定せねばならず、それとは逆に、行ないによって義と認められるという考えを正しいとするならば信仰の方を蔑ろにせねばならないからである。
2:信仰義認か行為義認か
さて、それでは行ないによる義認と信じることによる義認の2つのうち、一体どちらが正しいのであろうか。聖書は明らかに後者、つまり信じることによる義認の方を教えている。本日の箇所でも明らかにそのように言われている。その箇所をふたたび確認することにしたい。『しかし、人は律法の行ないによっては義と認められず、ただキリスト・イエスを信じる信仰によって義と認められる、ということを知ったからこそ、私たちもキリスト・イエスを信じたのです。これは、律法の行ないによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら、律法の行ないによって義と認められる者は、ひとりもいないからです。』確かに、ここでは信仰による義認が正しいとされ、行ないによる義認は否定されている。この信仰による義認はルターも言うように「キリスト教の根拠」であって、真のキリスト教を見分けるための印のようなものである。B・B・ウォーフィールドという有名なカルヴァン主義の神学者(※⑧参照)も、信仰義認は真理であると断言している。彼らがこのように言うのはまったく正しい。何故なら、信仰によって義と認められて救われるという考え方こそ聖書に書いてあることだからである。
3:行為によっては義と認められない
本日の箇所では『律法の行ないによって義と認められる者は、ひとりもいない』と書かれているが、ここから我々が理解すべきことは、律法であれ、何らかの功績であれ、称賛されるべき偉大さであれ、愛に基づいた良い行ないであれ、―つまり人間自身に関する事柄全般によっては―人は決して義認に至れないということである。もし、そのような人間的なものによって義と認められて救われるという考えを持つのならば、その人は神と聖書に真っ向から反対していることになる。人間が自分の行ないによって救われようとしてどれだけ頑張ったとしても、神がその人を義と認められることは決してない。もし人間が自分自身の力によって救いを獲得できるとしたら誇ることができてしまうが、神は、そのように人間を誇らせないために行ないによっては救われないように定められた。それゆえ、使徒パウロは、救われた者たちが救われたその救いが行ないによるものではないということについて次のように書いている。『行ないによるのではありません。だれも誇ることのないためです。』(エペソ2章9節)
4:信仰による義認について
義認の原因は信仰であって行ないではない。本日の箇所でパウロが言っているように、人は『ただ、キリスト・イエスを信じる信仰によって義と認められる』のである。キリストは我々の罪のために十字架の上で身代わりとして死なれ、我々の罪の赦しのために御自身の聖なる血を流された。実に、このキリストの血によって信じる者たちの罪が赦され、義と認められることになるのである。この救いを受けた信仰者たちに対してパウロは次のように言っている。『私たちは、この御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の赦しを受けているのです。』(エペソ1章7節)聖書が教えるこの救いとは、ただ神の恵みによって与えられた信仰によるのであって、人間自身の行ないによるのではない。それゆえパウロは救われた者たちに対してこのように言っている。『あなたがたは、恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それは、自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行ないによるのではありません。』(エペソ2章8~9節)もし行ないによって義と認められ救われるというのであれば、キリストとキリストに対する信仰は必要でなくなってしまう。それゆえ、救われたいと願う者は自己自身を無にし、行ないや功績などといった自分に関することをまったく無視し、信仰によって全的にキリスト・イエスを受けなければならない。無限の愛によってキリストは、信じる者たちの救いのために御自身の命を十字架の上でお捨てになられた。それゆえこのキリストを信じる者は、キリストのゆえに、その信仰によって義と認められ、救われ、罪の赦しを受け、永遠の命を相続する者とされるのである。これらのものはただ信仰によらねば受けることが全くできず、行ないによって得ようとしても決して得られることはない。どうか、この機会にキリストを、このキリストに対する信仰によって神から義と認められることを、ぜひ求めてほしい。
5:信仰は功徳ではない
信仰によって義と認められるといっても、信仰自体を自分の功徳とするということではない。つまり、自分がキリストを信じたというその信仰を、自分自身の力に帰すことはできない。何故なら、もし信仰を人間の力に基づかせるのであれば次のように思うこともできてしまうからだ。「私が自分自身の力によって信じたからこそ私は救われたのだ。神は、私が信仰を持たなければ私を救うことが出来なかっただろう。それゆえ私が救われたのは私自身から出たことであって、私は大いに誇ることが出来るのだ。」これでは信仰によって救われたというより、(信仰という名の)自分自身の行ないによって救われたと言うほうが正しいことになる。だからこのようなものは信仰義認ではなく、実質的には行為義認に分類されるものであろう。確かに人は信仰によって救われるのだが、その信仰は神が恵みによって与えてくださるものであって、もし神が与えてくださらなければその人は信仰を持つことが出来なかった。それゆえ信仰とは神によって与えられるものであるがゆえに、我々は信仰を自分自身から出たもの、また自分自身の功徳とすることができない。最後になるが、もし神が信仰を与えてくださるのであれば、その人は、神の恵みのゆえにキリスト・イエスに対する信仰を持つようになるだろう。多くの方々が、我々の罪のために死なれたキリスト・イエスの十字架における犠牲の死を受けいれ、自分自身の行ないとか功績とかではなく、このキリストに対する信仰によって義と認められ救われるようになるのを願うものである。
※①
約4万回もの説教を行なったメソジストの創始者ジョン・ウェウレー(1703―1791)は「わたしは愛を説教する前に、罪と審判について説教しなければならない。」と言った。我々は彼のアルミニウス思想を受けいれず、強く反対するが、この伝道説教に関する言葉自体は至言である。ジョナサン・エドワーズの説教「怒れる神の御手のうちにある罪人」では、神の恐るべき裁きが大胆に語られたからこそ、多くの回心者が起こされた。大説教家スポルジョンも、福音が語られる説教の中で、地獄と神の裁きについて大胆に語ることを忘れてはいない。ルターも「真の悔い改めは、恐れと神の裁きから始まる。」とガラテヤ書講解の中で述べている。
[本文に戻る]
※②
アナクサゴラスとデモクリトスが哲学に打ち込んだ結果、財産を家畜の食い荒らすにまかせた、というのでギリシアの人々は彼らを誉め称える。私もまた、金銭を超越したこの人々を称賛するにやぶさかでない。(フィロン「観想的生活」第2章14節)
※教文館 ユダヤ古典叢書「観想的生活・自由論」p10
[本文に戻る]
※③
それにくらべて、この者たちは、はるかに優れ、はるかに驚嘆すべき人々である。この人々の哲学にかける情熱は、かの人々と比較して決して劣ることはなく、怠ることなく、寛厚な精神を尊び、財産を消滅させるのではなく、人々に恵み与えて、自他共に―他の人々は豊かな資産によって、自分自身は哲学によって―益するようにはかるのである。と言うのも、金銭や所有財産への配慮は結構時間をつぶすものであり、時間を大切にするのは立派なことなのだから。実際、医者ヒッポクラテスも言うとおり、「人生は短く、(医)術は長い」のである。(フィロン「観想的生活」第2章16節)
※教文館 ユダヤ古典叢書「観想的生活・自由論」p10
[本文に戻る]
※④
ラコニアの少年の、生まれあるいは本性に由来する不屈の精神が、諸徳を探究することを慣いとしている人々によって、称賛されている。と言うのも、彼は、アンティゴノスの部下の一人によって捕虜として連行された際に、自由人たるにふさわしい仕事は甘受して耐えたが、奴隷的な仕事は、「私は奴隷になるつもりはない」と宣言して、拒んだのである。そしてさらに、その年齢の故にリュクルゴスの法によってしっかりと育てられることは不可能であって、それらを少々かじったに過ぎなかったけれども、現在の耐え難い生よりも死の方が幸せだと判断して、解放されることをあきらめ、喜んで自殺したのである。(フィロン「自由論」第17章114節)
※教文館 ユダヤ古典叢書「観想的生活・自由論」p63
[本文に戻る]
※⑤
『人が義と認められるのは、律法の行ないによるのではなく、信仰によるというのが、私たちの考えです。』(ローマ3章28節)
『ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって、神との平和を持っています。』(ローマ5章1節)
[本文に戻る]
※⑥
神は、彼が効果的に召したもうものたちをさらに値なくして義としたもう。それは、義を彼らの中に注入することによってではなく、彼らの罪を赦したもうことによってであり、彼らの人格を義なるものと見なし、受け容れたもうことによってであり、彼らの中になされ、あるいは彼らによってなされた何事かのゆえにではなく、キリストのゆえのみであり、信仰自体、信ずる行為、あるいはそれらに対する他の何らかの福音的な従順を彼らの義として、彼らに帰することによってでもなく、キリストの従順と償いとを彼らに帰したもうことによってであり、彼らが信仰によって彼の義を受け、それに憩うことによってであり、この信仰は彼ら自身に持つものではなく神の賜物である。(ウェストミンスター信仰告白 第11章:義認について 第1節)
※新教出版社「信条集」後篇p193
[本文に戻る]
※⑦
救われた者は『義なるイエス・キリスト』(Ⅰヨハネ2章1節)を信仰によって自分自身に受けたのであって、我々はこの義なる御方をその身に着た。『バプテスマを受けてキリストにつく者とされたあなたがたはみな、キリストをその身に着たのです。』(ガラテヤ3章27節)とパウロが言うとおりである。つまり、キリスト者である我々とは、義なるキリストによって完全に覆われた存在である。また、我々は、この救い主であり義である御方と契約的に一体である。それゆえ、神は、この義なる御方のゆえにこそ我々を義なる存在としてみなして下さるのである。
[本文に戻る]
※⑧
ヘルマン・バーヴィングとアブラハム・カイパーとともに19~20世紀における三大カルヴァン主義神学者として知られる、アメリカの著名な神学者。ウェストミンスター信仰告白の擁護に力を尽くし、聖書の霊感について強力に論証した。非常に学究肌の人であり、学識豊かな教師だった。
⇒ウィキペディア「ベンジャミン・ウォーフィールド」
[本文に戻る]
ガラテヤ人への手紙2章17~20節(2016/01/31説教)
『しかし、もし私たちが、キリストにあって義と認められることを求めながら、私たち自身も罪人であることがわかるのなら、キリストは罪の助成者なのでしょうか。そんなことは絶対にありえないことです。けれども、もし私が前に打ちこわしたものをもう一度建てるなら、私は自分自身を違反者にしてしまうのです。しかし私は、神に生きるために、律法によって律法に死にました。私はキリストとともに十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。いま私が、この世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。』(ガラテヤ2章17~20節)
本日は先週の箇所に引き続き、パウロが自己弁明をしている箇所である。パウロが実際に書いた手紙には章も節もつけられていなかったが、我々が便宜上つけている章と節における区分の2章21節の箇所まで、このパウロの自己弁明が続いている。パウロもユダヤ人であったが、前の説教でも言ったようにユダヤ人とは生まれながら律法を行なうように定められている者たちであって、異邦人とは違い、彼らにとって律法を守るということは「当たり前」であった。今でもそうだが、このユダヤ人たちにとって、律法に背いた歩みをすることなどもってのほかである。あるディスペンセーション主義のクリスチャンがユダヤ人に対して「今はもう律法を行なう必要はない。」という内容のことを言うと、それを聞いたユダヤ人たちは唖然としてぽかんとしてしまったという話がある。このようなユダヤ人に対して「思い違いをするな。我々ユダヤ人であろうと律法の行ないによって救われるのではない。」と言われているのが、我々がいま見ている2章の後ろのほうの箇所で言われている内容である。
①『しかし、もし私たちが、キリストにあって義と認められることを求めながら、私たち自身も罪人であることがわかるのなら、キリストは罪の助成者なのでしょうか。』(2章17節)
ここでは、キリストの救いが我々の罪深さを明らかにするのであればキリストとは罪に協力する存在なのか、という疑問について言われている。パウロなどのユダヤ人たちは異邦人とは違って、律法を人生の規範として生きている聖別された神の民であった。しかし、彼らにキリストの救いについての事柄が提示されるのであれば、ユダヤ人であっても異邦人と変わらぬ汚らわしい罪人であるという事実が明らかになってしまう。何故なら、キリストの救いの前では、ユダヤ人も異邦人も関係なく、みなひっくるめて「汚らわしい罪人」とされるからである。だから律法に従っている敬虔なユダヤ人たちの前にキリストの救いが差し出されるのならば、「我々もみな異邦人と同じく罪人なのか。では我々が罪人であることを明らかにするキリストとは罪を推進する方なのか。」という疑問が生じることにもなる。今の我々の社会においてはこういう疑問をもつ人はいないだろうが、当時は、このように考える人たちがいたのであろう。このような疑問に対してパウロは次のように言っている。
②『そんなことは絶対にありえないことです。』(2章17節)
たとえキリストの救いについて聞くことによってユダヤ人たちも罪人であるということが明らかになるのだとしても、キリストは罪に協力する御方ではない。この聖なる救い主である御方が、どうして悪いものの推進者なのであろうか。たとえキリストの救いを聞いた人たちが罪人であるという事実が明らかになるのだとしても、それはこの御方のせいではなく我々人間が罪深いからである、ということは言うまでもないことである。
そして、この17節に続く18節ではこのように書いてある。
③『けれども、もし私が前に打ちこわしたものをもう一度建てるなら、』(2章18節)
今やキリスト者となったパウロは信仰義認の考えを自己のうちに保持していたのであって、言うまでもなく、行為義認の思想からはすでに遠ざかっていた。つまり、パウロはかつては行為義認という名の建物の中に住んでいたのだが、ある時からこの建物を打ちこわして、信仰義認という名の新しい建物の中に移り住んだのである。信仰義認の立場に立っている我々もパウロと同じように、信仰義認という建物の中に住んでいる。ここでは、パウロがかつて住んでいたが今はすでに破壊されているこの行為義認という建物をふたたび復活させるならば一体どういうことになるのか、ということについて言われている。これは、我々が行為義認の建物に移り住むことになってしまった場合、つまり我々が行為義認の信仰に迷い込んでしまった場合についても言えることである。それでは、もし行為義認の家を復活させるならば一体どうなるのか。パウロはこう言っている。
④『私は自分自身を違反者にしてしまうのです。』(2章18節)
これは当然である。せっかく信仰義認の教理に導かれたのに、異端思想である行為義認の教理に陥ってしまったなら、その人はキリストの救いを自分から斥ける異端的存在となってしまうからである。行ないによって救いを得ようとする者は、キリストの救いに関する違反者でなくて何であろうか。我々も、行ないによって救済に至ろうなどという理解に陥ってしまうのであれば自分自身を違反者としてしまうのだから、固く信仰義認の教理に立ち続けねばならない。
⑤『しかし私は、神に生きるために、律法によって律法に死にました。』(2章19節)
これは、「神に生きるとはモーセの律法を忠実に守ることだ。」と考えていた偽使徒たちにとって驚くべき言説である。ここでパウロは偽使徒たちが唖然とするようなことを大胆に語っている。すなわち、パウロはここで彼らの理解とは正反対のこと、つまり「神に生きるためには律法に死ななければいけない。」と神の霊によって語るのである。
それでは、律法によって律法に死ぬとは一体どういうことであろうか。それはつまり、律法による義を追い求めていたパウロが律法による義認は不可能であることを知り、それを知ったがゆえに律法による義認の思想に対して死んだ、ということである。すなわちパウロは次のように言いたいわけである。「律法よ、聞いていただきたい。私はあなたによって、あなたが私に義を得させられないということを知った。だから私はあなたによって義を得るという考えに対して死ぬことにしよう。」律法の行ないによって義を追い求めている者たちは、律法によって義とされるという理解にしばられているのだから、律法に対して生きているのであって死んではいない。しかし、我々のようにキリストに対する信仰によってすでに義と認められている者たちは、律法の行ないによって義と認められるなどということとは無縁であり、それゆえ律法に対して死んでいることになる。もし本当に神に生きるようになりたいのであれば律法による義認の考えに死に、そのような理解に別れをつげ、キリストを信じる信仰による義認の考えを新しく求めなければならない、とパウロはここで言いたいわけである。
確かにすべてのキリスト者は律法にすでに死んでいるのだが、だからといって、十戒など道徳的な律法を守らなくてもよくなったなどと考えるべきではない。ここで言われているテーマは『義認』についてだということを我々は弁えなければならない。すなわち、我々は、律法によって義と認められるということに対してはすでに死んでおり、(キリストに対する信仰のゆえに)道徳的律法に違反してしまっても律法によって死と呪いとを宣告されることはもうないのだが、規範としては道徳的律法を行なわねばならない(※2016/04/17追加)。このことについては前から何度も説明しているので、本日、ここでふたたび詳しく論じる必要はないだろう。
それで、このパウロは神に生きるために律法に対して死に、また、キリストとともに十字架につけられた。このことについて書かれている20節に行きたい。彼はこう言っている。
⑥『私はキリストとともに十字架につけられました。』(2章20節)
パウロだけでなく、すべてのクリスチャンはキリストとともに十字架につけられた。何故なら、我々クリスチャンとは、自分の主である御方と一体だからである。それゆえ、我々はキリストとともに十字架につけられただけでなく、キリストとともに葬られ(※①参照)、キリストが蘇られたように新しい生命のうちに蘇らされ(※②参照)、キリストとともに天に引き上げられ(※③参照)、引き上げられたがゆえにキリストとともに天のところに座らされている(※④参照)。お分かりだろうか。我々は主なるキリストと契約的に一つであるがゆえ、キリストが経験されたことを我々もキリストと同じように経験しているのである。つまり、我々は、キリストに起こった出来事にともにあずかっているわけである。確かに聖書では、キリストに起こったことが我々にも起こったのだと書いてあるのだから、私がいま話しているこのことを否定することはできない。この理解は非常に重要なものである。私はこのことをアウグスティヌスの文章によって明瞭・的確に認識させられるに至った(※⑤参照)。我々のうちにキリストにおいて起こったこの数々の出来事の中で、「十字架につけられた」ということがここで言われている。
それで、我々がキリストとともに十字架につけられたとは、つまり、我々が十字架においてキリストにあって罪と肉と古い人とに死んだ、ということである。パウロはローマ6章6節で『私たちの古い人がキリストとともに十字架につけられた』と言っている。彼はガラテヤ5章24節でもこう言っている。『キリスト・イエスにつく者は、自分の肉を、さまざまの情欲や欲望とともに、十字架につけてしまったのです。』このようにキリストに属する我々はすでに十字架において自己自身の罪とか邪欲とかいったものに死んでおり、今や、キリストにある聖なる人生を歩む者へと変えられた存在である。それゆえ、我々の人生とは「我々自身による人生」というのではなく、「キリストによる人生」と言わねばならない。だから、パウロは次のように言うわけである。
⑦『もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。』(2章20節)
キリスト者と呼ばれる人たちのうちには、キリストによる生命が形造られている。実に、クリスチャンには、キリストがその内に生命を持っておられるのである。何故なら、その人は、キリストに生きる「キリストにある人生」を歩むようにキリストによって変えられた、キリストに属する存在だからである。だから我々の人生とは、我々が自分自身によって生きている人生ではなく、キリストがそのうちに生きておられる人生なのである。聖書で、すべてのことをキリストによって行なえとか(※⑥参照)、我々の人生はキリストを目的とせねばならない(※⑦参照)などと言われているのは、我々の生命・人生・存在がすべてキリストを根拠・理由・土台としているからに他ならない。それゆえ、キリスト者にとって生きるとはキリストのために生き、動き、存在することであると言えよう。このことから、キリスト者であるパウロが『私にとっては、生きることはキリスト』(ピリピ1章21節)と言ったのは、必然的な言説であることが分かる。何故なら、キリスト者にとって生きるとは、すべてがキリストを目的・理由とされるべきものだからである。
このキリストにある我々の人生について、更に詳しくパウロは説明している。
⑧『いま私が、<この世に生きているのは>、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。』(2章20節)
<>の場所だが、新改訳聖書の第2版では『この世に生きているのは』となっているが、第3版では『肉にあって生きているのは』となっている。口語訳でも『肉にあって生きているのは』という訳であり、文語訳でも『肉体に在りて生くるは』となっており、カルヴァンおよびルターの場合も同一の訳としている。肉とかこの世とか訳されている原語σαρκι は「肉に属する」とか「肉体的な」という意味であるが、本日は、第2版ではなく第3版のほうの訳を前提として語ることにしたい。それで『肉にあって生きる』とは、愚かな肉によって罪深い人生を歩んでいる、という意味ではなく、ただ単に物理的・実際的な意味においてこの地上に生きている、というふうに理解すべきである。この箇所における文脈から考えても、このように理解するのが妥当であろう。
パウロの当時の人生とは、キリストを信じる信仰による人生であった。彼はキリストを信じたからこそキリストにある新しい人生を開始できたのであって、もしキリストへの信仰をもっていなかったとしたら、そのような人生は彼になかった。それで、ここでも、義認を行ないに基づかせようとする連中に反対する言及がなされ、そのような異端的存在が斥けられているのが分かる。何故なら、「私の今の人生はキリストへの信仰によるものだ。」と言うことは、つまり「私の今の人生は行ないによる義認に基づいたものではない。」と言うことだからである。もしこれを書いている時のパウロの人生が行為義認によって生じたものだとしたら、彼はこのようには書けなかったことだろう。
言うまでもなく、パウロ以外のクリスチャンの人生も、キリストを信じる信仰によって生じた人生である。我々キリスト者の人生とは、キリストへの信仰によって開始され、その人生を歩む者たちはキリストとその御国、またこの御方の喜びを求め、自分の救い主である御方に対する信仰のうちに保たれつつ天の故郷(※⑧参照)に帰っていく。これは、キリストという御方が我々の人生の根底におられるのだから、当然のことであると言える。それゆえ、我々はこの御方とその王国に、自分の人生における視点を据えるべきである。そうすることは、存在する人生のうち、真に幸いな正しい人生を送ることである。いったい、キリストとその御国のために生きるという人生よりも優(まさ)った人生がほかにあるだろうか。
もうそろそろ最後になるが、この箇所の『私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子』という部分に注目してみたい。キリストは我々の罪のために御自身をお捨てになられたが、この犠牲における重大さはあまりにも大きいものである。我々のために犠牲となられた神の御子を信じる信仰という宝は天と地よりも価値が高い、とルターは言っているが正にその通りである。キリスト以外の宝をどれだけ手に入れたとしても地獄を避けられないが、キリストへの信仰という宝は天国の扉をひらく。ということはつまり、この地上のすべての宝よりも、キリストへの信仰という宝のほうが価値があるということになる。このことは我々の救いという観点からみた理解であるが、キリストの犠牲そのものについて考えるならばどうだろうか。キリストは罪を犯したことがなく(※⑨参照)、我々のようにいずれ死んでしまうような存在ではなかった。我々の場合、寿命によってであれ病気によってであれ、いずれかならず死に至ってしまう。しかしキリストは罪に対する報酬である死(※⑩参照)を受ける必要のない御方なのだから、もし十字架にかかられなかったなら死なれることもなく、いつまでもこの地上に生き続けておられた。このように本来であれば死なれる必要のなかった御方が、我々の救いのために死を必要なものとして御自身に引き受けて下さったのである。つまり、自分の犯した罪のゆえにいずれ自然に死んでしまうような罪人が身代わりとして死んだのではなく、罪のない、本来であれば死なれる必要のない聖なる御方が、みずから死に臨んで下さったのである。この救いにおける恵みはあまりにも大きい。詩篇には『主の恵みはとこしえまで。』と言うように書かれている箇所があるが(※⑪参照)、もっともこの言葉が言われなければならないもの、それはキリストの救いにおける恵みであろう。
また、この部分からは、カルヴァン主義の5特質(※⑫参照)の一つである「限定的贖罪」の教理を見出すことができる。これは、「キリストは救われるように選ばれている者たちだけのために死なれた。」という聖書的理解である。確かにここで選ばれた人であるパウロは『私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子』と書いており、選ばれていない滅びの子たちのためにキリストがご自身をお捨てになった、とは書いていない。この考えに反対する人たちは、キリストの犠牲は文字通りすべての人たちを対象としていると考えているが、それは間違っている。選びにおける神の愛とキリストの犠牲とは渾然一体であり、愛されている人たちが愛されているがゆえ、キリストはその人たちのために犠牲となられた。兄弟を殺したカイン、一杯の煮物と引きかえに長子の権利を売ったエサウ、主を売ったイスカリオテのユダ、暴君ネロ、こういった呪われた者たちは、キリストが御自身を捨てられるほどに愛された対象ではない。神が誰かを愛されたのであればキリストはその人のために犠牲となり、キリストが誰かの犠牲となられたのであればその人は神から愛されている。神から憎まれている人のためにキリストが御自身を捨てられたり、キリストが誰かのために犠牲となられたのに、その犠牲の対象とされている人が神から愛されていないということはない。それで、キリストは我々のためにこそ御自身を犠牲としてくださったのだから、この犠牲のゆえに救われた我々は神に感謝し、永遠に至るまでも神に感謝を捧げるのである。この限定的贖罪の教理については、機会があればまた詳しく話すことにしたい。
※2016/04/17追加
このことについては、ツヴィングリもこのように説明している。
参考までに。
「内的人間に関するかぎりは、律法のすべては廃せられることなく存続する。このことは実例によって証示されよう。例えば、「盗んではならない」は永遠の戒めである。しかし、もしだれかが盗みを働き、あなたが裁判で彼を絞首刑から救ったとすれば、その男は律法から、すなわち律法による処罰から救われたことになる。しかも彼は今後は律法を犯して、自由に盗んでも良くなるために救われたわけではない。たとえしばしば盗みを働いても、絞首刑は免れるかもしれないが、だからと言って律法を守らなくともよいほど自由にされたわけではない。そこで、たとえキリストが私たちの罪の代わりに永遠の贖いを成しとげてくださったとしても、しかも律法は確固として存続する。しかも、キリストを信頼するならば、律法によって滅びに定められることは決してないのである。それが律法の廃絶の一面である。つまり、私たちが律法による処罰から救い出されていることである。それは私たちがわれらの救い主、イエス・キリストに信頼を寄せているからである。」
ツヴィングリ「キリスト教信仰入門」四、律法の廃絶について
教文館:宗教改革著作集6 ツヴィングリとその周辺Ⅱp30
[本文に戻る]
※①
『それとも、あなたがたは知らないのですか。キリスト・イエスにつくバプテスマを受けた私たちはみな、その死にあずかるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちは、キリストの死にあずかるバプテスマによって、キリストとともに葬られたのです。』(ローマ6章3~4節)
[本文に戻る]
※②
『それは、キリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも、いのちにあって新しい歩みをするためです。』(ローマ6章4節)
『だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古い者は過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。』(Ⅱコリント5章17節)
[本文に戻る]
※③
『わたしが地上から上げられるなら、わたしはすべての人を自分のところに引き寄せます。』(ヨハネ12章32節)
[本文に戻る]
※④
『しかし、あわれみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪過の中に死んでいたこの私たちをキリストとともに生かし、…キリスト・イエスにおいて、ともによみがえらせ、ともに天の所にすわらせてくださいました。』(エペソ2章4~6節)
[本文に戻る]
※⑤
したがって、キリストの十字架、埋葬、三日目の復活、昇天、父の右の座において起こったことはすべて、この世におけるキリスト者の生活がただ単に神秘的な言葉においてだけでなく、現実そのものにおいても、これに倣ってなされるために、起こったのである。すなわち、彼の十字架のゆえに「しかしキリスト・イエスに属する者は、自分の肉を、その情と欲と共に十字架につけてしまったのである」(ガラテヤ5:24)と言われているからである。また埋葬のゆえに「わたしたちは、バプテスマによって、キリストと共に死の中に葬られたのである」と言われ、復活のゆえに「キリストが父の栄光によって、死人の中からよみがえったように、わたしたちもまた、新しいいのちに歩むためである」と言われている。昇天と父の右の座とのゆえに次のように言われている、「しかし、もしあながたがたキリストと共によみがえったのであれば、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右に座しておられるのである。あなたがたは上にあるものを思うべきであって、地上のものを思ってはならない。なぜなら、あなたがたはすでに死んだものであって、あなたがたのいのちは、キリストと共に神のうちに隠されているからである。」(アウグスティヌス「信仰・希望・愛」第3部、救済の受領 第2章、義とされること 四<53>)
※教文館:アウグスティヌス著作集4 神学論集p253~254
http://www.kyobunkwan.co.jp/publishing/archives/7187
[本文に戻る]
※⑥
『あなたがたのすることは、ことばによると行ないによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。』(コロサイ3章17節)
[本文に戻る]
※⑦
『私たちの中でだれひとりとして、自分のために生きている者はなく、また自分のために死ぬ者もありません。もし生きるなら、主のために生き、もし死ぬなら、主のために死ぬのです。』(ローマ14章7~8節)
[本文に戻る]
※⑧
1.ノアやアブラハムなど、天に故郷をもっていた昔の信仰者たちについて次のように言われているが、天に故郷があるということは全キリスト者に共通していることである。
『これらの人々はみな、信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって、自分の故郷を求めていることを示しています。もし、出て来た故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし、事実、彼らは、さらにすぐれた故郷、すなわ天の故郷にあこがれていたのです。』(ヘブル11章13~16節)
2.次のようにも書かれている。
『私たちの国籍は天にあります。』(ピリピ3章20節)
[本文に戻る]
※⑨
『キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見いだされませんでした。』(Ⅰペテロ2章22節)
[本文に戻る]
※⑩
『罪から来る報酬は死です。』(ローマ6章23節)
[本文に戻る]
※⑪
『ヤーウェに感謝せよ。主はまことにいつくしみ深い。その恵みはとこしえまで。さあ。イスラエルよ、言え。「主の恵みはとこしえまで。」と。さあ。アロンの家よ、言え。「主の恵みはとこしえまで。」と。さあ。ヤーウェを恐れる者たちよ、言え。「主の恵みはとこしえまで。」と』(詩篇118篇1~4節)
[本文に戻る]
※⑫
【1.全的堕落】
堕落後の人間は完全に腐敗しており、自分の力によって神に立ち返ったり、神に仕えたりすることはできない。
【2.無条件的選び】
人間の行状や価値などは前提的に考慮されることなく、神はただ御自身の欲するままに、ある人を永遠の救いに、ある人を永遠の滅びにお定めになった。
【3.限定的贖罪】
イエス・キリストの贖いは、救いに予定された者たちだけを対象としている。
【4.不可抵抗的恩恵】
救われるよう予定されている者は、神の救いにおける恵みを拒否することができない。
【5.聖徒の永遠堅持】
救いに定められている者は、救われてから後、この地上の人生における最後の瞬間に至るまでキリストとキリストに対する信仰のうちに保たれ続ける。
[本文に戻る]
ガラテヤ人への手紙2章21節(2016/02/07説教)
『私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。』(ガラテヤ2章21節)
ガラテヤ人たちの心から疑いを払いのけようとしてなされるパウロの自己弁明および使徒としての権威の主張は、本日の(2章)21節にて終わる。この聖書は、はるか昔の時代に書かれたものであり、当時の人たちを直接的な対象としたものだから、説明がされなければ豊かな理解には至りにくい。それゆえ、教会では聖書の説き明かしがされなければならない。宗教改革の時代においては、説教の代わりにアリストテレスの講解をしていたカトリックの教師もいたようであるが(※①参照)、アリストテレスとかプラトンとかではなく、聖書こそが説明されなければならない。全ヨーロッパの改革派教会に影響を与えたブリンガー(1504―1575)という宗教改革者は、数十年かけて聖書全巻を説き明かしたが、このような姿勢は我々も見習わなければならないものであろう。それでは、さっそく21節からみていきたいと思う。
①『私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。』(2章21節)
『もし義が律法によって得られるとしたら』、キリストの贖いなど必要でなくなってしまう。もし律法による義認の思想が真実なものだったとしたら、パウロも言うように、キリストは無意味に死なれたことになる。それゆえ、律法の行ないによって義を得ようとするならば、それはキリストの贖罪を否定することである。「かくて、自分の清さ、赦し、浄め、義および解放を、行ないに帰するものはすべて、キリストの死を徒らにし、これを空しくする。」(新教出版社:カルヴァン・新約聖書注解Ⅹ ガラテヤ・エペソ書p61)のである。
たとえ少しであっても、部分的であっても、もし罪の赦しや義認や救いを自分の行ないに基づかせるのであれば、その人はいくらかでもキリストの贖罪を冒涜していることになる。ローマ・カトリックは最初、つまりクリスチャンになる時においては「恵みのみ」「信仰のみ」によって救われると言うが、救われてからは、罪の赦しを人間の行ないに基づかせている。つまり、救われたのちに犯してしまった罪は、自分の行ないによって償わなければ赦されないなどと彼らは考えるのである。だから、罪の赦しを行ないに基づかせている彼らは、多かれ少なかれ、部分的にであってもキリストの贖罪を否定している。ローマ・カトリックであれ、キリスト教と呼ばれているほかのグループであれ、少しであっても行ないによる罪の赦しの思想をもっているのであれば、その集団は暗に「キリストの贖いなど罪の赦しに必要ない。」と叫んでいる。我々は騙されてはならない。赦し、義認、救い、解放、こういったものはすべて、キリストとその贖罪を原因とせねばならないし、実際、キリストとその贖罪がそれらのものの原因なのである。
律法や良い行ないによって義が得られるなどと考えるのであれば、それは、神のキリストにある恵みを無にすることである。神の恵みのなかで最大のものは、言うまでもなく、キリストの救いにおける恵みである。この恵みを無にすることほど大きな忘恩がほかにあるであろうか。ここでパウロは『私は神の恵みを無にはしません。』と言って、行為義認の思想によりキリストにある神の恵みを無駄にすることはしていない。我々もパウロとともに信仰義認に固く立ち、行為義認の思想によって神の恵みを斥けてしまわないように警戒せねばならない。
ここで、行ないによる救いの思想によって神の恵みを無にしてしまっている人たちのことを実際にみてみたい。ルターはガラテヤ書講解のなかで、カトリックの修道士による罪の赦しに関する言葉を紹介している。「兄弟よ、神があなたを赦してくださいます、われわれの主イエス・キリストの受難の功績、永遠のおとめ、祝福されたマリアとすべての聖人の功績、修道会の功績、修道士たちの負う重荷、あなたの告悔の謙遜、心の通悔、われわれの主イエス・キリストへの愛によってあなたが行なった、また、行なうであろうよい行ない、これらのものがあなたにとって、罪の赦し、功績と恵みの増加、永遠のいのちの報酬となります、アーメン。」(聖文社:「ルター著作集」第2集11 ガラテヤ大講解・上p230)ここで修道士はキリストの功績のことについて言ってはいるが、しかし、ルターも指摘するように「キリストがここでは明らかに大したことをしておらず、義とし、救うかたという栄光と名とが彼から奪われて、修道士としての行ないに帰せられていることがわかる」(同)のである。しかし、このルターもかつては、「主イエスよ、私はみもとにきて、祈ります。どうか私の修道会の負う重荷が私の罪のための償いとなりますように」(同)と祈っていた。このような者たちは、キリストの贖罪を信じているように見えるが、その一方では、行ないによる罪の赦しの考えによってキリストの贖罪を愚弄している。結局、彼らは罪の赦しをキリストの贖罪に全的に基づかせていないのだから、キリストの贖罪にある神の恵みを蔑ろにしてしまっていることになる。また、ルターによると、ベネディクト派やフランシスコ派などの修道会における会則の中には「キリストを信じる信仰については一音節たりともなく、ただ「この会則を遵守する者は永遠のいのちを持つ」と強調されているだけ」(同p211)だったという。修道会の会則という行ないによって永遠のいのちを得ようとする修道士たちも、神のキリストにある贖罪の恵みを無にし、完全に斥けてしまっている。また、かつて教皇ボニファティウス8世は教勅「ウナム・サンクタム」(1302年)の中で、次のように述べた。「すべての人は救いのために教皇に対する服従が絶対必要であると、われわれは宣言し、明記し、定義する。」教皇に服従するという行ないがなければ救いはありえないとするこの宣言も、キリストの神にある恵みを蔑ろにしてしまっている。もし教皇に従えば救われるというのが本当ならば、キリストの救いなど我々に必要ないではないか!!また、アリストテレスは「ニコマコス倫理学」(2:3、3:7)において、「多くの良いことを行なう者は、これによって良い者になる」と言う。人が良い者、つまり聖なる者と神から見られるようになるのは、良い行ないではなく、ただキリスト・イエスを信じる信仰による。それゆえ、アリストテレスのように良い行ないによって良い者になろうなどと考える者たちも、良い者となるためにはキリスト・イエスこそが必要だと考えていないわけだから、贖い主なるキリストにある神の恵みを無駄にしてしまっていることになる。
②1~2章における総括
パウロがこの箇所(1~2章)で何を目的としているかといえば、「自分が真の使徒であることをガラテヤ人に分からせること」および「行為義認ではなく信仰義認こそが正しい考えであることをガラテヤ人に分からせること」の2つである。信仰義認の正しさだけを論じたとしても、パウロ自身が疑われたままでいたならば、パウロの言うことに耳がふさがれてしまうわけだから、どうしてもパウロの使徒としての正当性および権威を認めさせる必要があった。またパウロが真の使徒であるということだけを伝えても、義認についてなにも説明しないのであれば、ガラテヤ人たちが異端思想に沈みこんだままの状況はなにも変わらないのであるから、義認についての説明がどうしても行なわれる必要がある。それゆえ、パウロはこの2つをセットにして語らねばならなかった。
ここでのパウロの言説は、完全なものである。ここではステパノのように知恵と御霊によって語られているので(※②参照)、だれもパウロに対抗することはできず、その内容には一点の隙もない。これは、この箇所を少し考えただけでもすぐに分かるであろう。まず、ペテロなどの偉大な使徒たちがパウロのことを認めているので、このパウロを認めている使徒たちを否定するというのでもなければ、パウロが使徒であるということを否定することはできない。しかも、このパウロは使徒たちに認められている上、「自分は神によって使徒とされた」(1章1節、2章8節)とまで言っているのであるから、パウロが真の使徒であるという事実はますます確かなものとされる。また、真の使徒であるこのパウロが宣べている福音はイエス・キリストからのものであると言い(1章12節)、信仰義認でなければ救いはありえないと断言し(2章16節)、行為義認の思想を伝えている偽使徒どもは呪われるべきであるとさえ書いているのだから(1章8~9節)、パウロがガラテヤ人たちに伝えた福音また信仰義認の思想とは、正に真理であることが強力に論証されているのが分かる。これらの言説は、人間自身によるものではなく、神がパウロという人間を通してなされたものである。だからこそ、ここでの内容はこれほどまでに完全なのである。
ここでは、1.律法の行ないによって義を追い求めている律法主義者と、2.彼らの考えに巻き込まれてしまっているガラテヤ人、という2種類の人たちのことが言われている。パウロは前者のほうをその考えとともに斥け、後者のほうは正しい教えに戻れるようにしている。この前者のほう、つまり律法によって救われようとしている者たちが、律法の行ないによって義が得られるなどという勘違いをしていたのは、ユダヤ人の律法に対する態度を考えてみたら必然的なものであるとも言えよう。というのも、前にも言ったようにユダヤ人たちにとって律法を守るとは「当然」のことであり、彼らの精神には【律法>命】という構図が存在していたからである。このことは、ユダヤ人についての話を聞いたり知ったりするならば、強く感じさせられることである。例えば、紀元40年ごろ、『史上最も悪名の高い皇帝の一人』(角川:世界史辞典)と言われるカリグラ(12―41)が聖所の中に自分自身の像を立てさせようとしたのだが、これは明らかに偶像を禁止している律法に違反するものである。カリグラのこの神聖冒涜的行為に対して律法を規範としていたユダヤ人たちは、律法のためならどんなことでも耐え忍ぶ用意があると大声で叫び、次のように言った。「われわれは日に二度、カイサルさまとローマの市民のために犠牲をささげておりますが、もしカイサルさまが像を設置しようとされるならば、彼はまずユダヤの民族全体を犠牲としてささげねばなりません。われわれは、子供たちや妻たちと一緒に、いつでも殺される用意ができております。」(ちくま学芸文庫:フラウィウス・ヨセフス「ユダヤ戦記」①―第2巻10章4節p296)つまり、律法のためなら我々はいつでも死ぬ用意をしている、もし我々の律法を犯すのであれば我々ユダヤ民族を殺してからにせよ、と言うことにより、彼らは自分たちの命よりも律法のほうが大事であるということを示したのである。この当時アレクサンドリアのユダヤ人社会で代表的な人物とされていたフィロンも、この事件に関して記している文書のなかで、ユダヤ人たちが「父祖たちの慣習のひとつたりといえども―たとえそれがどんなに小さなものであっても―破壊されるのを黙過できず、死が不死であるかのように、それを進んで受け入れることに慣れている」(フィロン「ガイウスへの使節:16章117節」※③参照)と書いている。ユダヤ人であったこのフィロンは「律法を守るための真に高貴な死こそが生なのだ。」(同29章192節」※④参照)とすら言っている。また、紀元前4年ごろには、当時イスラエルで最高の敬意を払われていた有名な2人のラビが「たとえ危険を伴っても、父祖の律法のために死ぬことは高貴な行為だ。」(ちくま学芸文庫:フラウィウス・ヨセフス「ユダヤ戦記」①―第1巻33章2節p235)と言っている。つまり、ヘロデが聖所の中に偶像を置いたのだが、それは律法に反したことだから、たとえヘロデに処刑されることになったとしてもこの偶像を取り壊すべきだと、このラビたちは言ったのである。さらに、ヘブル人に対する手紙の中でもこう書かれている。『だれでもモーセの律法を無視する者は、二、三の証人のことばに基づいて、あわれみを受けることなく死刑に処せられます。』(ヘブル10章28節)つまり、律法を守らないような者は、死に値する人物だということである。このようにユダヤ人たちの律法に対する精神は非常に高い宗教性をもったものであり(これは親が小さい頃から子どもたちが律法を守るように育ててきたためであろう)、律法という神の言葉に対する彼らの忠実性は、異邦人クリスチャンである我々にとって驚くべきものである。「律法を少しでも裏切るぐらいならば死んだほうがましだ!」という心を彼らは持っており、このユダヤ人たちは神の律法を、自分の人生において徹底的に前提としていたのである。それゆえ、律法に対してこのような態度をもっていたユダヤ人であったがゆえ、律法によって救われるなどと勘違いをしている者たちが彼らのうちにおおぜいいたとしても何も不思議ではない。つまり、彼らにとって神の御前に生きるとは律法に従うことであったから、もし律法に従って生きているにも関わらず神が自分たちを救ってくれないのだとしたら、「どうして律法に従っている私たちを神は永遠の生命に入れてくれないのか!?」という疑問が生じるのは自然なことであり、律法によって救われるという思想が前提としてあるからこそ、このような疑問が生じることになるのである。この手紙で出てくる偽使徒たちも、そのような者であった。しかし、そのような考えは間違ったものであった。だからこそ、パウロはこの1~2章の箇所で、律法によって救われるなどという考えを偽使徒とともに完全に否定しているのである。
この1~2章に続く3章からはガラテヤ人に対する厳しい追及がなされるが、パウロは初めから責め立てるのではなく、まずは優しく語ることから行ない、自分自身についての弁明および義認についての説明を行なっている。これは知恵の手法である。というのは、まず穏やかに開始することをせず、いきなりガラテヤ人たちを叱るのであれば、ガラテヤ人たちの心はすぐにもパウロから離反していただろうから、書かれている文章をよい心で読んでもらうことなどできなくなってしまうからである。それゆえ、初めは刺激のあまりない、やわらかな記述をなしてガラテヤ人の心をパウロに同調させ(1~2章)、そうしてから言説を強化させているのである(3章~)。
③最後に
最後に、この1~2章の箇所から、3つほど話して終わりにしたい。
1.神的事柄の説得の際に人間的なものを使うことについて
パウロが神から遣わされた真の使徒であったのは、疑うことのできない事実である。このパウロは、自分に疑念を抱いていたガラテヤ人に対して「私は神から遣わされた真の使徒である。」と言うだけで済ますこともできた。しかし、彼は自分が神によって立てられた使徒であるということに加えて、「ほかの使徒たちも私が使徒であると認めている。」という人間的な説得をすることも躊躇せずに行なっている。すなわち、「ペテロなどほかの使徒たちも私パウロのことを認めているぞ。それなのに、ガラテヤ人よ、あなたがたは私のことを認めないというのか?」と彼は言うのである。このようにパウロでさえ信仰的な言説に加え、人間的なものによっても説得しているのだから、我々が神的・霊的な問題を論じるさいに、彼の手法を真似たとしても問題はない。例えば、祈りが聞かれて奇跡的な出来事が神によって起こされた場合、奇跡が起こるように祈っていたその人は、周りの人たちに分からせようとするさい、「私の祈りが聞かれたので神がこういう出来事を起こしてくださった。」と言うだけで本来的には充分である。何故なら、この場合、神が祈りを聞かれたがゆえに奇跡的出来事が起こったのが確かだからある。しかし、パウロがそうしているのと同じように、より理解させるという意図をもって「周りの先生方も私の祈りが聞かれたからこそこういうことが起こったと口を揃えて言っています。」などと、人間的な説得を加えても問題はない。だがここで我々が留意すべきなのは、このような人間的なものがその出来事の原因なのではなく、あくまでもその出来事の原因は神に帰されねばならないということである。つまり、この状況の場合「先生方もあのように言っている。」という言説はあくまでも説得のためになされるものにすぎない。もし周りの人たちが「神がこの出来事を起こされた。」と言っただけで十分に信じてくれるのであれば、先生方のことについての話は、別に持ちださなくても困りはしないからである。
2.義認についての区別
この手紙では義認について論じられているが、我々は、義認についての明確な区分をすべきであろう。すなわち、信仰義認のグループを「信仰義認のグループ」として、行為義認のグループを「行為義認のグループ」として明確に認識すべきである。前者のほうは我々プロテスタント陣営が、後者のほうはローマ・カトリック陣営やユダヤ教、イスラム教などが該当する。そのようにしっかりと区別しつつ認識することは、境界意識を強め、その人の精神を異端的集団に容易に迎合しないようにさせる。また、行為義認のグループの中でも、2つの区分を設けるべきである。すなわち、「行為義認の思想を確信をもって伝えている聖職者たち」と「聖職者たちから教えられる一般信徒」の2種類である。前者のほうは呪わるべき悲惨な者たちであるが、後者のほうに対しては前者ほどに厳しい認識をもつべきではない。パウロも行為義認の思想を伝えている偽使徒どもには呪いを宣告することさえしているが、ただ惑わされているにすぎなかったガラテヤ人たちにはそのようにはしていない。また、信仰義認のグループの中でも、2つの区分を設けるべきである。すなわち、「信仰義認に固執する信仰者たち」と「信仰義認に立ってはいるが行為義認に妥協的な信仰者たち」の2種類である。義認に関して、前者のほうと接しても我々の信仰に惑乱をもたらすことはないだろうと思うが、後者のほうと親しく接するならば健全な理解に良からぬ影響をおよぼす恐れがある。
3.それぞれの召しにふさわしく歩むことについて
この手紙からも分かるように、ペテロはユダヤ人へと遣わされており、パウロは異邦人へと遣わされていた。これは少し強引な言説かもしれないが、ペテロやパウロと同じように、星は輝くために遣わされており、時間は流れ、また進むために遣わされており、雲は動き、景色を作り、雨を降らすために遣わされている。また、ペテロはユダヤ人への使徒であって異邦人への使徒ではなく、パウロは異邦人への使徒であってユダヤ人への使徒ではなかった。それと同じように、太陽は太陽であって人間ではなく、魚は魚であって鳥ではなく、植物は植物であって動物ではない。これらのことから分かるのは、被造物には、神から定められている役割および、それぞれの存在における固有の概念があるということである。それゆえ、我々も、それぞれ自分の遣わされている場所において、特有の役割が与えられている者としてふさわしく、自分がキリストを信じる信仰によって神の民とされた存在ということをわきまえつつ歩んでいくべきであろう。どうか、我々の救い主なるイエス・キリストの恵みが、聖徒ひとりひとりの上に豊かにありますように。アーメン。
※①
メランヒトン(1497―1560:ドイツの宗教改革者でルターの同僚・協力者)は当時のローマ・カトリック教会の状況について「福音が放逐せられて、ある者は説教の代わりにアリストテレスの倫理学を講解しているということをわれらは聞いている。」(「アウクスブルク信仰告白の弁証:第4条 義認について」※新教出版社「信条集 前後篇」p62)と書いている。
[本文に戻る]
※②
『しかし、彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった。』(使徒の働き6章10節)
[本文に戻る]
※③
京都大学学術出版会:フィロン「フラックスへの反論 ガイウスへの使節」(秦剛平訳)
西洋古典叢書 第Ⅱ期第5回配本p127
[本文に戻る]
※④
京都大学学術出版会:フィロン「フラックスへの反論 ガイウスへの使節」(秦剛平訳)
西洋古典叢書 第Ⅱ期第5回配本p156
[本文に戻る]
ガラテヤ人への手紙3章1~3節(2016/02/14説教)
『ああ愚かなガラテヤ人。十字架につけられたイエス・キリストが、あなたがたの目の前にあんなにはっきり示されたのに、だれがあなたがたを迷わせたのですか。ただこれだけをあなたがたから聞いておきたい。あなたがたが御霊を受けたのは、律法を行ったからですか。それとも信仰をもって聞いたからですか。あなたがたはどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなたがたが、いま肉によって完成されるというのですか。』(ガラテヤ3章1~3節)
今週から3章に突入する。パウロは1~2章においてはガラテヤ人たちを直に責め立てはしなかったが、この3章からは、ガラテヤ人に視点をまっすぐに合わせて猛追及をしている。パウロがガラテヤ人を叱ったり責めたりしているのは、ガラテヤ人を憎んでいるからというのではなく、彼らを愛し、正しい理解に戻ってほしいという願いをもっているからであった。ちょうど、親が子どもを、師が弟子たちを、先輩が後輩に激しくなるのと同じである。それでは、早速、1節目から見ていきたい。
①『ああ愚かなガラテヤ人。』(※2016/05/01追加)(3章1節)
まず『愚かな』と『ガラテヤ人』という2つの言葉について、大まかな説明をしたいと思う。『愚かな』と訳されている原語ανοητοι とは、「物分かりの悪い」「無知な」「馬鹿な」といった意味をもつ言葉である。カルヴァンは「あさはかな」と訳している。他には、「無分別な」とか「軽率な」などと訳することもできる。ルターは、ガラテヤ人が民族的に愚かな性質をもっていたのだろうと言っているが(※①参照)、私はそうなのかどうか知らない。それで、このガラテヤ人とは言うまでもなくガラテヤの地方―現在のトルコの首都がある高原地帯―にいた民族であって、バベルにおいて言葉が混乱させられた時期(創世記11章)には「ゴメルの子ら」と呼ばれている民族であった(ちくま学芸文庫:フラウィウス・ヨセフス「ユダヤ古代誌①」第1巻6章1節p60参照)。
それにしても、嘆きに満ちた大胆な言説である。パウロは、自分がいつも大胆に語れるように強く願っていた。この大胆さは聖書特有のものであって、パウロだけでなく、聖書記者はみな例外なく大胆な記述をなしている。真理が真理として保たれるためには、大胆さが絶対的に必要である。それゆえ、聖書の真の著者である神は、聖書記者を通して大胆にお語りになっているわけである。
それでは、このガラテヤ人が「愚か」なのは一体どうしてなのか。言うまでもなく、彼らが救いについての正しい理解から逸れてしまったからである。パウロは彼らが些細な問題で誤ってしまったからというのでこのように言っているのではない。「義認」という最も重要であるといえる問題で誤ってしまったからこそ、「愚かな者たちよ。」と大胆に言っているのである。確かに、信仰義認から行為義認の思想へと移ってしまったのであれば、それは「愚か」であると言わねばならない。
ここで、「パウロはガラテヤ人たちを裁いている!」などと我々は批判的な思いをもつべきではない。ヒエロニムスなどは、パウロは間違っていたとか、勘違いしていたとか、聖書に対する批判的なことを平気で言っているが、我々はそのようにすべきではない。何であれ、この聖なる書物に対して文句をつけることがどうして許されるであろうか。今のプロテスタント教会では、『さばいてはいけません。』(ルカ6章37節)という主の御言葉に基づいて、何もかも裁いてはならないと考える傾向がある。しかし、主は『うわべによって人をさばかないで、正しいさばきをしなさい。』(ヨハネ7章24節)と他の箇所で言っておられるし、パウロはここで「愚かな者たちよ。」といって裁いているのだから、たとえ何であっても裁くのはいけない、ということではない。アウグスティヌスも、ルターもカルヴァンも、スポルジョンも、パウロと同じようにみな裁いているではないか。主御自身も、辛辣に裁いておられる。ここでパウロが裁いているのは、愛に基づいているのであって、また、非難されるに相応しい状態にあったガラテヤ人は裁かれることによって行為義認という泥沼から引き出される必要があったのだから、我々は「裁いている。」などと言ってパウロおよび聖書を非難すべきではない。(※2016/02/28追加)
また、ここでパウロが「愚かな者たちだ。」と言っているのを聞いて、主のあの御言葉を心に思い浮かべる方もおられるかもしれない。すなわち、山上の説教におけるマタイ福音書のあの箇所である。『兄弟に向かって『能なし』と言うような者は、最高議会に引き渡されます。また、『ばか者。』と言うような者は燃えるゲヘナに投げ込まれます。』(マタイ5章22節)パウロはここで「能なし」とか「ばか者」といった意味をもつ言葉を使ってガラテヤにおける兄弟を責めている。はたして、パウロはここで主の御言葉に違反した内容のことを言ってしまっているのであろうか。決してそうではない。主がマタイ福音書の箇所で言っておられるのは、ただ単に相手に害を与えることに関して言われているものである。すなわち、もし愛に基づかず、単にそれを聞いた相手にダメージを喰らわせるという目的をもって攻撃的な言葉が兄弟に向けられた場合、それは主の御言葉に違反してしまっている。だが、パウロがここで「無能な者たちよ。」あるいは「愚劣な者たちよ。」などと言っているのは愛に基づいたものであって、ガラテヤ人たちを単に傷つけるなどという意図はまったくなかったのであるから、パウロは主の御言葉に違反しているのではない。しかし、もしパウロがここでガラテヤ人たちを正しい信仰に引き戻すという目的をなにも持たず、ただ単にガラテヤ人を蔑もうとしてこう言っていたのだとしたら、それは主の御言葉に反したものだったことであろう。
(2016/05/01追加)パウロがガラテヤ人に『愚か』と言ったのだから、ガラテヤ人もパウロに対して同じようなことを言っていたのであろう。「パウロは愚かだ。彼は自分の教えに酔い痴れている。」と。どうしてこう言えるがといえば、人は自分のした通りのことを自分にもされる、と聖書が教えているからである。『あなたがしたように、あなたにもされる。』とオバデヤ書(15節)には書かれているし、他にもこのような聖句が書かれている箇所は多い(例えばエレミヤ50:15、29 ホセア4:6など)。70人の王たちの手足の親指を切り取ったことのあるアドニ・ベゼクは、自分も同じようにされたのでこのように言った。『神は私がしたとおりのことを、私に報いられた。』(士師記1章7節)このように聖書は報いの原理について教えているのだから、「ガラテヤ人たちが愚かであると言われたのは彼らに対する報いなのだろう。」と私が推測するのは荒唐無稽ではない。ガラテヤ人たちがパウロについて悪口を言っていたということは、別にこのような解釈をしようとしなくても、この手紙を読めば十分に推測できることであろう。
②『十字架につけられたイエス・キリストが、あなたがたの目の前にあんなにはっきり示されたのに、』(3章1節)
これは、十字架につけられているキリストの幻がガラテヤ人の前に示されて、ガラテヤ人たちが視覚的にキリストの贖罪の場面をその目で見たというのではない。そうではなく、これは、パウロの福音の説教によって、ガラテヤ人がイエス・キリストの十字架の犠牲をあたかもその目で実際に見たかのようにまざまざと知った、ということに他ならない。すなわち、ガラテヤ人たちはキリストについての御言葉を聞いて、本当に自分の目の前でキリストの犠牲を見ていると言えるほどにキリストの贖罪を認識し、それを信じたのである。例えばキリストの贖罪を信じて涙を流す人がいれば、その人の目の前には十字架につけられたイエス・キリストがはっきり示されたのであって、あたかもキリストの十字架の場面を実際にその目で見たといえるほどに強く認識し理解し把握したからこそ、心が揺り動かされて涙を流すに至ったわけである。
パウロは続けてこう言っている。
③『だれがあなたがたを迷わせたのですか。』(3章1節)
暗に、ガラテヤ人を惑わしている偽りの使徒たちのことをパウロはここで言っている。ここで、次のように考える者があってはならない。「ガラテヤ人は惑わされていたに過ぎなかったのだから、パウロがここまで厳しく責め立てるのはやりすぎだ。」確かにガラテヤ人は被害者といわれるべき境遇にあったが、しかし、彼らが陥ってしまった誤謬における問題は致命的な悲惨さをもったものであったから、大胆かつ峻烈に責められる必要があったのである。
パウロの説教を聞いて福音を受けいれたガラテヤ人は最初は正しい信仰を保っていたが、時間がたつと、惑わす者たちによって間違った信仰に迷い込まされるに至った。異端的信仰に陥ってしまったこのガラテヤ人たちは、結婚した夫婦に似ているように私は思う。新婚ほやほやの夫婦の愛は激しく純粋なものであるが、子どもも産まれて時間がたつならば、かつての純烈な愛はもうそこにはない。異性を恋してから脳内に生じる激しい愛の成分はおよそ3年ほど有効だといわれているが、この成分がでている期間に激烈で盲目的な愛が形成されるのであろう。ある人は、この期間が終わってから、その男女の愛における本当の姿が明らかになるという。ある男女はかつてほどの激しさはないにしても変わらず愛し続けるが、ある男女の場合は真の愛が欠けていたたために、飽きたり不倫に走ったりしてしまう。ガラテヤ人たちは後者の人たちのようであって、信仰義認という真理を真に愛せていなかったため、一定の時間が経過したさい、容易に行為義認という異端思想に不倫をしてしまったのである。
そしてパウロは『ただこれだけをあなたがたから聞いておきたい。』と言って(※2016/05/01追加)、2節目でもガラテヤ人に対する詰問を続けている。
④『あなたがたが御霊を受けたのは、律法を行ったからですか。それとも信仰をもって聞いたからですか。』(3章2節)
『御霊を受けた』とは、「救われている」とか「義と認められた」とか「罪の赦しを受けた」とか「サタンの民からキリストの民となった」などといった言葉と同義である。このように言われているガラテヤ人たちは確かに救われており、永遠の昔から神の民となるよう選ばれていた。なぜなら、選ばれていなければ誰も御霊を受けて救われた存在になることはできないからである。それで、ここではガラテヤ人が御霊を受けたといわれているが、ガラテヤ人の全てが御霊を受けていたというのではなく、御霊を受けてはいない滅びの子らも中にはいたのだということは、少し考えれば分かることであろう。ここでパウロが御霊を受けたと言って語りかけているのは、広義にはガラテヤ人という集団全体に対してであるが、狭義には選ばれている神の子らのみに対してである。
ここでパウロは、ガラテヤ人が福音を聞いて救われた時の記憶に訴えている。「ガラテヤ人たちよ、あなたがたは救われて御霊を受けた時のことを覚えているだろう。どうか、当時のことを思い返してほしい。あなたがたが御霊を受けたのは、律法を行ったからではなく、キリストについての御言葉を信仰をもって聞いたからではなかっただろうか?」と言うかのようである。
ここでは、御霊を受けたのは律法によるのか、または信仰によるのか、という問いだけがなされており、その答えはまだ明らかにされていない。しかし、数節後(6節)において、信仰の人アブラハムを例として「御霊を受けたのは外でもない、信仰によるのだ。」という答えが明らかにされている。確かに人が御霊を受けて神の所有の民とされるのは、律法とか善を行なったからではなく、ただ信仰をもって、キリストについて言われている御言葉を聞くことによる。このことは、使徒の働きの10章44節で、キリストについての御言葉を聞いていた人たちに御霊がお下りになった出来事について記されている箇所からも分かるであろう。このように書いてある。『ペテロがなおもこれらのことばを話し続けているとき、みことばに耳を傾けていたすべての人々に、聖霊がお下りになった。』ここで言われている人たちが御霊を受けたのは、律法を行なったからではなくて、ただ信仰をもって御言葉を聞いたからであった。
この世界には高い徳をもった人たちが存在しており、昔の哲学者の中にも超絶的ともいうべき有徳の士がたくさんいた。キケロなどの哲学者は、人に評価されるために徳を追及するのではなく有徳であるがために徳を追及すべきである、つまり人に全く見られなかったとしても正義を求めるべきである、と言っており、哲学者たちの精神性の高さには驚かされることが多い(※しかし、神とか宗教的なことに関する彼らの発言は、愚昧な妄想話しか聞かれないものである)。偽善・見せ掛けではなく、称賛のためでもなく、真の意味において徳を窮(きわ)めようとしているのである。カルヴァンも「キリスト教綱要」のなかで哲学者たちの廉直な精神性について語っているが、彼らはクリスチャン顔負けというべき倫理観の持ち主たちである。(※2016/03/13追加)しかし、いかに高い徳をもっていようが、どれだけ律法を敬虔に守っていようが、もし信仰をもってキリスト・イエスの十字架の言葉を聞けないのであれば、その人は御霊を受けられはしない。はっきりと言うが、もし信仰をもって聞かないのであれば、あと数年あるいは数十年後には地獄を自分の住処とするようになってしまう。つまり、キリストを信じないのであれば、地獄で永遠の裁きをその身に喰らわねばならない。だから、もし徳の高さや素晴らしい精神性をもっているがゆえにキリストについての御言葉を信仰をもって聞けないようであれば、つまり、そのようなものが信仰を持つのを妨げてしまうようであれば、そんなものは無くてもよいからキリストに対する信仰を持てたほうがはるかにいい。もちろん、ここで私は徳とか精神性とかいったものを否定しているのではない。しかし、賢者だがキリストを信じないのと、愚者だがキリストを信じるのとでは、後者の人のほうが幸せである。前者は地獄に投げ込まれるが、後者は天国に導きいれられるからである。聖書には、神の御子キリストとその救いについて、次のように書いてある。『神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。』(ヨハネ3章16節)『私たちは、キリストに代わって、あなたがたに願います。神の和解を受け入れなさい。神は、罪を知らない方を、私たちの代わりに罪とされました。それは、私たちが、この方にあって、神の義となるためです。』(Ⅱコリント5章20~21節)『主イエスは、私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために、よみがえられた』(ローマ4章25節)『御子イエスの血はすべての罪から私たちをきよめます。もし、罪はないと言うなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし、私たちが自分の罪を言い表わすなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての悪から私たちをきよめてくださいます。』(Ⅰヨハネ1章7~9節)未信者の方々はぜひ、私たちの罪のために十字架の上で犠牲となられたキリスト・イエスについての御言葉を、信仰をもって聞く人になってほしい。
パウロは、3節目でもガラテヤ人に対する追及の手をゆるめない。
⑤『あなたがたはどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなたがたが、いま肉によって完成されるというのですか。』(3章3節)
ここでは、「御霊」と「肉」という2つの言葉が、完全に対立させられている。『御霊で始まった』とは、つまり(御霊の御働きによって)キリストに対する信仰をもって救われた、ということである。『肉によって完成される』とは、愚かな肉に基づいた救いに関する間違った理解のうちに安住しきる、ということであろう。すなわち、パウロはここでこう言いたいのである。「ガラテヤ人たちよ、あなたがたは最初は御霊による正しい信仰によって救われたはずだが、今や肉による間違った信仰のうちに沈みきってしまっている。一体どういうことなのだ、気が狂っているとでもいうのか。」
偉大なる御国の土台とは、御霊によって始まり、御霊による信仰の救いの教理のうちに保たれ続けることにある。もし、ガラテヤ人のように最初は御霊によって始まったとしても、途中で肉による救いの教理に落ちてしまうなら、御国の前進はストップしてしまう。もし我々のうちだれかが、行為義認の教理に陥ってしまったとすれば、御国前進におけるスピードは確実に遅くなる。また、もし、御霊によって始まることがないのであれば、そもそも御国が始まることはない。例えば、誰かが「行ないによって人は救われる。」などと考える宗教グループ―それがキリスト教と呼ばれるものであれ、そうではない宗教であれ―に入信するならば、どうして神の支配がこの地上に拡大するのだろうか。ありえない話である。それゆえ、神の恵みにより御霊で始まった我々は、御霊による救いの教理のうちに踏みとどまり続けねばならない。しかし、弱く惨めな我々は、神の恵みのうちに保たれなければ容易に異端的教理に迷い込んでしまう。だから、神が我々を真理のうちに保ってくださるように、我々は祈らねばならないであろう。恵みの神が、多くの人たちを御霊によって新しい人生に生きることを始めさせ、増え拡がったキリストの民が御霊のうちに歩み続けられるようにして下さり、ますます御国が拡大していくようになるのを願うものである。
※2016/05/01追加
パウロは自分の兄弟である者に向かって「愚かだ」と言っているが、我々はこのように言っていいのだろうか。例えば、エホバの証人に騙されて異端信仰に陥ってしまったガラテヤ人のような兄弟がいた場合、我々はこの兄弟に対して「君は一体どうしたというのか、本当に鈍くて愚かとしか言いようがない。」などと責めていいのだろうか。もしその兄弟を真に愛しているというのであればこのように言ったとしても非難されるべきではない、と私は考える。キリストも弟子たちに対して『信仰の薄い人たち。』(マタイ6章30節)と率直に言っておられるし、使徒ヤコブも読者に対して『貞操のない人たち。』(ヤコブ4章4節)と厳しく書いている。しかし、このように厳しい言葉を口にする場合、2つのことに我々は注意せねばならない。まず第一に、我々は、その兄弟が愛すべき主の兄弟であるということを決して忘れてはならない。パウロも『愚かなガラテヤ人』と厳しく言ったものの、ガラテヤ人たちが愛すべき者たちであるということを忘れてはいなかったはずである。自分の仲間である者を非難するのだから、あたかも裏切り者ユダにそうするかのように容赦のない刺々しさを伴わせるべきではない。第二に、このように言うのは、より敬意を払われるべき立場にある者だけに許可されるべきである。つまり、パウロがガラテヤ人たちに、牧師が一般信徒たちに、教師が学生たちに、親が子供たちに、成熟したクリスチャンがまだ幼いクリスチャンに対してだけこのように言えるのであって、これとは逆のケースが起こるべきではない。たとえ過ちに陥ってしまったとしても、敬意を抱かれるべき者たちに対しては、あまりにも辛辣な発言にならないよう自分の舌を抑えるようにすべきである。パウロも大祭司アナニヤを彼が大祭司だとは知らずに罵ったさい、厳しい言葉を口にしたことについて弁明している(使徒の働き23:1~5参照)。
[聖句に戻る]
※①
ここでは「ガラテヤ人」という言葉に強調点がある。ほかの場合のように、兄弟とは呼ばずに、その土地の名まえをもって呼んでいる。クレテ人はうそつきであるように、愚かであることがこの民族に特有の欠点であったように思える。
聖文社:「ルター著作集」第2集11 ガラテヤ大講解・上p282
[本文に戻る]
※2016/02/28追加
では、『さばいてはいけません。』(ルカ6章37節)と言われた主の御言葉はどのように解釈すべきなのか。主も使徒たちも明らかに裁いているのだから、この御言葉がどのような意味で言われているのか我々は考えねばならない。まず、この御言葉はルカ6章以外ではマタイ7章に聖置されており、どちらも「あなたが行なった通りにあなたにもされるであろう。」という文脈の中で語られている。『あなたがたがさばくとおりに、あなたがたもさばかれ、あなたがたが量るとおりに、あなたがたも量られるからです。』(マタイ7章2節)と言われている通りである。つまり、ここで主が「裁くな」と言われているのは、文脈から考えるならば「あなたがたがした通りの行ないがいずれ自分の身に返ってくるのだから、自分も裁かれたくないのであれば裁くな、また、自分も裁かれることを考え、軽率で愚かな裁きをするな。」という意味である。こういうふうに理解するのでなければ、「裁きをなしている主と使徒たち」および「裁いてはならないという主の御言葉」という一見矛盾しているかのように思われる2つの事柄をどのように調和させるというのか。このように解釈する以外にどういった解釈をするというのだろうか。確かに、パウロは自分が『主にあって』裁きを行なったことを『神の霊によって』語っているのである。『私のほうでは、からだはそこにいなくても心はそこにおり、現にそこにいるのと同じように、そのような行ないをした者を主イエスの御名によってすでにさばきました。』(Ⅰコリント5章3節)さらにパウロは、我々が教会の中にいる人たちを裁くべきことすら『キリストの御霊によって』述べている。『外部の人たちをさばくことは、私のすべきことでしょうか。あなたがたがさばくべき者は、内部の人たちではありませんか。』(Ⅰコリント5章12節)キリストと御霊なる神が、どうして矛盾した内容の言葉を語られるのだろうか。あり得ない話である。だから、我々は、裁くべき時には主にあって裁かねばならないといことを、弁えねばならないであろう。また、我々は、自分も裁かれたくないのであれば、もしくは愚鈍な精神に基づいては、マタイ福音書とルカ福音書に書かれてある主の御言葉の通りに裁くことを差し控えるべきであるということを、弁えねばならないであろう。
[本文に戻る]
※2016/05/01追加
この御言葉に我々は注目すべきであろう。パウロは『ただこれだけをあなたがたから聞いておきたい。』と言っている。つまり、パウロがこの手紙の中で眼目としていたのは、行為義認が正しいのか、それとも信仰義認が正しいのか、という点をガラテヤ人たちに明らかにすることであった。すなわちパウロがこの手紙で最も言いたいこと、それは、「ガラテヤ人たちよ、行為義認と信仰義認のどちらが正しいのか白黒をつけようではないか。私の文章を見て、正しい教理に立ち返れ。そして間違った考えから離れされ。」というものだったのである。
[本文に戻る]
※2016/03/13追加
とはいっても、彼らがどれだけ良い行ないに富んでいたとしても、神に喜ばれることはできない。何故なら、彼らは神に敵対し、神を拒否し、神を憎んでいるからである。また、彼らがいかに善行に励んでいたとしても、それは聖書的な意味における善行ではない。善行とは聖書的にいえば、神また隣人のために、イエス・キリストにあって、愛に基づいてなされた、信仰による聖書的な行ないのことである。哲学者らは善行によって自分の魂がきよめられると夢想しているが、彼らの魂はその身体とともに永遠に焼き尽くされる。神と和解していなかった彼らの善行は、どれだけ人間的に素晴らしかったとしても、神の怒りを燃やす結果以外のことを生じさせなかった。彼らがキリスト・イエスによって贖われていなかったからである。
[本文に戻る]
ガラテヤ人への手紙3章4~7節(2016/02/21説教)
『あなたがたがあれほどのことを経験したのは、むだだったのでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょうが。とすれば、あなたがたに御霊を与え、あなたがたの間で奇蹟を行なわれた方は、あなたがたが律法を行なったから、そうなさったのですか。それともあなたがたが信仰をもって聞いたからですか。アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました。それと同じことです。ですから、信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。』(ガラテヤ3章4~7節)
先週に引き続き、パウロがガラテヤ人に正しい信仰の理解を知らせている箇所である。1~2章目までは、パウロは遠まわし、または間接的にガラテヤ人たちに真理の教えを訴えかけるだけであったが、3章目からはしっかりとガラテヤ人に的をあてて語るようにしている。それでは早速、4節目から見ていきたい。
①『あなたがたがあれほどのことを経験したのは、むだだったのでしょうか。』(3章4節)
これは一体どういうことであろうか。我々が使用している新改訳聖書の下の欄のところで示されているように、この部分は『あれほど苦しみを受けたことが無意味なことだったのでしょうか。』とも訳せる。カルヴァンはこのように訳している。それで、ここで言われているのは、ガラテヤ人たちが救われたのちに経験した信仰の試練、または霊的な戦いのことである。『あなたがたは、キリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜わったのです。』(ピリピ1章29節)と言われているように、信仰者はキリストと信仰のゆえに生じる戦いを避けられない。「信仰者に真の信仰があるかどうか神は試される。人間が自分の創作物の耐久力をテストするように。」という内容のことをスポルジョンは言っているが、信仰のあるところにはかならず、神が試練を起こされることにより困難・問題・苦痛などが生じるものである。ガラテヤ人たちも、正しい信仰をもったがゆえに試練・霊的な苦痛および困難を受けるに至った。
すぐに続けてパウロはこう言っている。
②『万が一にもそんなことはないでしょうが。』(3章4節)
パウロはここで、こう言っているかのようである。「あなたがたはかつて信仰のゆえにあれほどの苦しみを経験したが、それが無駄だったはずがどうしてあるだろうか。絶対にありえないことである。この手紙を読んでいるあなたがたもそのくらいのことは分かるだろう。あなたがたは正しい信仰をもったからこそ、あのような苦痛を味わったのだ。もし正しい信仰をもっていなければ苦しい戦いも経験しなかったことであろう。どうか気づいてほしい。」…このように言うことで、パウロはガラテヤ人の心が真理の高みへと引き上げられるように励ましている。なぜなら、彼らが苦痛を味わったのは正しい教理のゆえであったのだから、もしずっと偽りの教理に沈みこんだままでいるのであれば、「我々は一体なんのためにあのような苦痛を経験したのだろうか?」ということになってしまうからである。
③『とすれば、あなたがたに御霊を与え、あなたがたの間で奇蹟を行なわれた方は、あなたがたが律法を行なったから、そうなさったのですか。それともあなたがたが信仰をもって聞いたからですか。』(3章5節)
3章の2節目でなされたのと同じ問いが、ここでも繰り返されている。この2節目の問いにおいて『ただこれだけをあなたがたから聞いておきたい。』と言われているように、パウロが問題としていたのは、救いは律法遵守によるのか、それとも信仰によるのか、という一点にあった。人は、重要であると感じている事柄については、意図したとしてもしなかったとしても、何度も繰り返して聞いたり語ったりするものである。ここでパウロが再度同一の内容を繰り返して述べているということから、彼がこの問題にどれほど心を傾けていたかが分かるであろう。
そしてパウロは6節目において、自分が問いかけた問いに対する答え―すなわち救いは律法によるのか、あるいは信仰によるのかという問いに対する答え―をアブラハムを例として出しつつ明らかにしている。
④『アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました。それと同じことです。』(3章6節)
ここでは、我々がよく知っている旧約聖書のあの箇所をなぞりつつ語られている。すなわち、創世記15章6節の『彼はヤーヴェを信じた。主はそれを彼の義と認められた。』という信仰者アブラハムについての聖句である。パウロは、義認について論じているローマ4章の最初のほうのところでも、この聖句を引用している(※①参照)。
ここで言われているように、アブラハムは信仰をもったからこそ義と認められたのであり、それは行為によるのではない。神は、人が行ないにはよらず信仰をもつことによって義と認定されるようにお定めになった。もちろん、神は行ないによって我々人間が義を得られるようにもできたが、そうはなさらなかった。それは、我々が信仰によってキリスト・イエスの救いをいただくことにより、救いとその救いにおける栄誉・功績・恩寵が完全完璧に神にのみ帰されるようにするために他ならない。我々が信仰によってイエス・キリストによる神の救いを全的に上から受けるからこそ、救いにおける一切の幸いが100%の割合で神に結び付けられる。それは、我々が、信仰によって救いにおける一切の幸いを神から完全なる受身の状態でいただくからである。しかし、もし信仰ではなく行ないによっても救いを得られるのだとすれば、100%の割合でもって幸いなものが神に帰されることはない。救いにおける功績の内訳に、人間の行ないが割合を占めるようになればなるほど、神に捧げられる栄誉・讃美・感謝の割合がそれだけ少なくなってしまうのは火を見るよりも明らかである。例えば、救いの内訳が「神の恩寵100%」だった場合は「人間の行為による功績は0%」だが、「神の恩寵が99%」だったら「人間の行為による功績は1%」となってしまうであろう。もし「神の恩寵が70%」だったら「人間の行為による功績は30%」となってしまうであろう。このように前者、つまり神の恩寵の割合が少なくなればなるほど、それに比例して後者、つまり人間が帰される功績の部分は大きくなる。言うまでもなく、後者の行ないにおける割合が増大すればするほど、栄誉であれ功績であれ感謝であれ、救いにおける幸いなものが神に帰されることはなくなってしまう。それで、神は、御自身に全ての幸いなものが完全完璧に帰されるのを欲されたからこそ、我々人間が行ないによっては救われないように定められたのである。それは、救いが我々人間の行ないにまったく帰されない場合にのみ、つまり完全に神にだけ帰される場合にのみ、我々人間がなにも誇ることなく、また、神のみが純粋に讃美されるようになるからである。これらのことが実現されるためには、どうしても我々人間が信仰によって救われるようになっていなければならない。それゆえ、神は行ないによる救いを人類に対して設定されなかった。パウロが我々の救いについて、『行ないによるのではありません。だれも誇ることのないためです。』(エペソ2章9節)と言っている通りである。
ここで少し信仰についての話をしたい。まず、この信仰による救いについての教理は、愚かな肉によっては把握されない。罪深い肉とその思いによっては、聖なる真理を正しく捉えることは出来ず、肉に属している人間がそれを理解して自分のものとすることは不可能である。肉はその性質上、神の御前に高慢にならざるを得ないため、救いにおけるあらゆる幸いを神にだけ帰し、自分自身は救いにおける栄誉・功績などといったものを完全に放棄するという謙虚な振る舞いには到底耐えられない。それゆえ、肉にある人間は救いについての正しい教理を純粋に受け入れられず、悟れず、信じれず、それを拒否する以外にはできない。これらのものは御霊によらなければ理解し把握し受容することができず、我々も、御霊を受けていなかった時には信じることができなかった。
また、「信じる」などと我々は単に言ったり聞いたりしているが、我々はこの信仰を具体的に理解せねばならない。もしキリストの十字架の出来事そのものが実際にあったということだけを情報として、つまり歴史上の出来事として信じているだけならば、それは、キリスト教における真の信仰ではない。つまり、キリストの贖罪について、今から2千年前にイエス・キリストが十字架にかかられた、という出来事が本当にあったものとして信じているだけだとしても、その人は我々クリスチャンのように信仰者とはふつう言われない。つまり、聖書が教え、我々がそうだと理解している信仰とは、ただ単にその出来事における歴史性・実際性を認めるということではない。キリスト教で言われている信仰とは、その出来事の歴史性・実際性を認めるだけでなく、それが、自分のためになされたものであることを真に認め、受け入れ、把握し、決して疑うことなくそれを自分のものとすることに他ならない。すなわち、キリストの贖罪の場合、「イエス・キリストは確かに紀元30年ごろに十字架につけられた。」ということを史実的な意味において信じるだけでなく、それに加えて「その十字架における死は私を対象としてなされた永遠・完全なる犠牲の死である。」ということを信じること、これこそ、我々の属するキリスト教における正しい信仰の内容である。だから、信仰とは、単なる思弁においてその事柄を把握するだけでなく、それが自分のためにこそなされたということを聖霊によって体験的・経験的に把握することであると言えよう。キリストが十字架にかけられた、という歴史的な出来事についてならば、獣のごとき悪魔の手下どもでさえそう信じているのである。(※2016/02/28追加)/(※2016/03/13追加)
この信仰とはあまりにも重要なものであって、信仰とは、神に栄誉を帰するための道具のようなものである。それとは逆に、不信仰とは忌まわしいものであって、不信仰とは、神を愚弄し、侮辱するものである。例えば、アブラハムは「神は死んだイサクを復活させることぐらい造作なくできる。」という神の全能に対する信仰をもっていたからこそ、神の命令にしたがい、イサクを犠牲に捧げようとした。このことについて、ヘブル書の著者はこう言っている。『信仰によって、アブラハムは、試みられたときイサクをささげました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただひとりの子をささげたのです。神はアブラハムに対して、「イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれる。」と言われたのですが、彼は、神には人を死者の中からよみがえらせることもできる、と考えました。』(ヘブル11章17~19節)つまり、神とその全能に対する信仰があるがゆえに、このアブラハムの場合であれば「イサクが死んだからなんだというのだ。神は死んだイサクをよみがえらせることができないとでも言うのか?ありえない話である。神はなんなく死者をよみがえらせることが出来るであろう。神は全能なのだから。」などと考えることが出来るのである。つまり、アブラハムはその信仰に基づいた行ないによって「神は全能である。」という告白をなし、神に栄誉と尊厳と全能と御力とを帰したわけである。これとは逆の、不信仰な人物が聖書のなかに存在している。すなわち、エリシャが飢饉のときに『あすの今ごろ、サマリヤの門で、大麦2セアが1シェケルで、上等の小麦粉1セアが1シェケルで売られるようになる。』(Ⅱ列王記7章18節)という神の言葉を語ったにもかかわらず、それを信ぜずに『たとい、ヤーヴェが天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうか。』(同7章19節)という不信仰な言葉を吐いた、王の侍従である。道理の分からないこの侍従は、その不信仰な言葉によって「神は無能である。」または「神には出来ないこともある。」という告白をなし、神とその全能に侮辱を加えたのである。それで、もし信仰があるならばその人は神に喜ばれるだけでなく報いをいただくことも出来るが、不信仰な人は神から嫌われるだけでなく罰として苦痛を味わわされてしまう。不信仰な人は、場合によっては王の侍従のように死の罰を喰らうことになる(この侍従は不信仰な言葉を吐いたので民に踏みつけられて死んでしまったのである)。ヘブル書では次のように言われているが、これは大いに心に留めるべき御言葉であると私には思われる。『信仰がなくては、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを、信じなければならないのです。』(11章6節)我々はいかなる時であっても神とその全能を信じ、この神に栄誉と尊厳と全能と御力とを帰し、神から豊かな報いをいただけるようにしよう。まさか、不信仰の徒になって神の怒りと裁きとをその身に喰らいたいなどと感じる兄弟姉妹もおるまい。
本日の箇所で言われているアブラハムとその信仰のことに話を戻すが、このアブラハムは神に対する真の信仰によって、義と認められるに至った。彼が義と認められた、ということはつまり、アブラハムがキリストを信じており、キリストによって救われていた、ということを意味する。というのも、聖書が教えているように、人はイエス・キリストによらなければ義認・救済・新生・解放・赦免、こういったものを決して受けられないからである。主は、次のように言っておられる。『わたしを通してでなければ、だれひとり父のみもとに来ることはありません。』(ヨハネ14章6節)この御言葉から分かるように、キリストによらなければ誰も父なる神のところに行くことはできず、救われることも、義と認められることもできない。人が義と認められるのは、ただイエス・キリストだけによる。このアブラハムがキリストに対する信仰をもっていたということは、主がユダヤ人に対して次のように言っておられる御言葉からも分かる。『あなたがたの父アブラハムは、わたしの日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て、喜んだのです。』(ヨハネ8章56節)この御言葉から分かるように、アブラハムは、キリストとキリストが来られる時のことを大いに信じていた。我々はすでに来られたキリストを信じているが、アブラハムやその他の旧約の聖徒たちは、いずれ来たるべきキリストを期待しつつ信じていたのである。もしアブラハムがキリストを信じていなかったというのならば、彼は義と認められていなかったであろう。つまり、キリストを信じていたアブラハムは、我々と同じように『キリスト者』だったのである。
この信仰によって義と認められたアブラハムを持ち出して、パウロはガラテヤ人たちを納得させようとしているのである。これは実に強力な説得手段であるといえる。なぜかといえば、聖書にそう書いてあるがゆえに、アブラハムが信仰によって義と認められたのを疑うことは絶対にできないからである。アブラハムの救いが信仰義認によるものだったということが不動の事実であるならば、ガラテヤ人たちが行為義認を首肯し続けるかぎり、その首肯そのものによってガラテヤ人たちは聖書に敵対することになってしまう。ガラテヤ人たちが正しいと考えている思想(つまり行為義認の思想)が、完全に聖書の記述に反しているからである。だから、「アブラハムは信仰義認であった。」などと聖書の記述に基づいて語られるのであれば、もうまったく反論の余地はなくなってしまうのであって、このパウロの言説によって、おそらくガラテヤ人たちは大きな衝撃を受けたのではないかと私には思われる。
また、ここでは「義とされました。」ではなく『義とみなされました。』と言われている。このことについては2章16節の説教のときにも話したから、繰り返しになってしまうが、人はキリストに対する信仰によってその存在が義そのものになってしまうというのではなく、「義なる存在であるという認定を神から受ける。」のである。この箇所でもそうだが、「義と認められた。」または「義とみなされた。」という記述になっているのに我々は注意すべきであろう。(※2016/02/28追加)
続く7節においてパウロはこう言っている。
⑤『ですから、信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。』(3章7節)
言うまでもなく、肉によるアブラハムの子孫はユダヤ人である。だから、肉的な意味において「ユダヤ人はアブラハムの子孫である。」と言うのは正しい。しかし、霊的な意味において、真の意味において、キリスト教的な意味において、また、神の御前においてはそうではない。このような意味におけるアブラハムの子孫とは、『信仰による人々』―すなわち信仰義認のキリスト者である。それゆえ、ユダヤ人たちは肉においてはアブラハムを祖先とする民族かもしれないが、真の意味においてはアブラハムを自分の祖先としているのではない。何故なら、ここでパウロが言っているように、キリストを信じる信仰が与えられている者たちこそ真のアブラハムの子孫だからである。具体的に把握できるように例を2人ほどあげてみたい。まず一人目の例はイスカリオテのユダであるが、ユダヤ人だった彼は肉的にはアブラハムの子孫であったにも関わらず、霊的には、また、真の意味においては、『信仰による人々』、つまりアブラハムの子孫ではなかった。というのも、滅びに定められていた彼が『信仰による人々』の一人だったとみなすことは許されないがゆえ、彼がアブラハムの子孫だったと考えるのは不可能だからである。二人目は、当時のユダヤ社会で非常な尊敬を受けていたアレクサンドリアのフィロンである。彼もユダヤ人であり、彼は使徒ペテロにも会ったと言われている。このフィロンは、フォティウスという9世紀のコンスタンティノポリス大主教によると「キリスト教に改宗し、後になって悲しみと怒りのうちに教会を後にしたと言われる。」(ビブリオテーカ86a―86b)※②が、この言説の真偽についてはここでは論じないとして、もし彼が、教会をいちど離れた後にふたたび戻っていたのだとしたら、彼は肉においてだけでなく、霊的な意味においても、アブラハムの子孫だったということになる。しかし、教会から遠ざかったままの状態で人生を終えていたのだとしたら、彼は肉的にはアブラハムの子孫だったとしても、真の意味においてはアブラハムの子孫ではなかったということになる。すなわち、真のアブラハムの子孫とは、肉的な意味において判断されるべきではなく、その人がキリストに対する正しい信仰をもっているかどうかという点において判断されるべきなのである。
信仰義認の人たちこそアブラハムの真の子孫なのであれば、この命題に対立する命題として、「行為義認の人たちはアブラハムの子孫でない。」ということが分かる。この命題について考えるならば、この聖句は、ガラテヤ人に対する厳しい警告が暗になされている聖句であると言える。すなわち次のような警告である。「もし信仰による人たちこそがアブラハムの子孫なのであれば、ガラテヤ人たちよ、あなたがたが行為義認にこれからも留まり続けることにより、あなたがたが本当はアブラハムの子孫ではなかったということを暴露してしまうであろう。何故なら、行為義認の徒はアブラハムの子孫ではないからである。それゆえ、もしこのままあなたがたが行為義認から離れないのであれば、あなたがたが本当はアブラハムの子孫ではなかったということが明らかになってしまうが、それでもよいのだろうか?」ルターも言うように「聖書は対立命題でいっぱい」(聖文社:「ルター著作集」第2集11 ガラテヤ大講解・上p366)であって、この箇所もそうである。そして、この対立命題について考えるのならば、この箇所では、ガラテヤ人に対する密かな警告が実施されているとも考えられるのである。
神の恵みによって信仰による人々の一人とされた我々は、パウロが言うように『アブラハムの子孫』である。信仰者アブラハムが神の恵みによりとこしえまでも御国を相続するように、信仰による我々にも同じ恵みが注がれるよう定められている。ユダヤ人たちが『われわれの先祖はアブラハムだ。』(マタイ3章9節)と心の中で考えていたとしても、もし彼らがキリストに対する信仰を持たないのであれば、アブラハムに与えられる永遠の祝福をアブラハムと共に受けることは不可能である。今現在の彼らは父なる神に敵対しており、父なる神が遣わされたキリスト・イエスに対して「裏切り者」などと言い、キリストを憎むあまり「4」の数字を書くさい十字架の形が中央部分に現れないような書き方をする者たちもいる。また、イエス・キリストが旧約聖書で預言されていた御方であることを彼らは信じておらず、それゆえ、まだ救済者は現れていないと考えている。そのため、彼らはこれから預言されている救済者が来られるのだと本当に信じ、考えている。このような状態であれば、彼らユダヤ人がどうしてキリストの民であったアブラハムの子孫なのであろうか。あり得ないことである。しかし、今はこのような状態にある彼らであっても、ローマ11章に書かれているように、これから民族的な意味においてキリスト・イエスに立ち返るようになるであろう。彼らの民族的回心は『死者の中から生き返ること』(ローマ11章15節)であると言われているのだから、ユダヤ民族の回復によって未曾有の祝福が世界に注がれるようになるのであろう。キリストを信じる信仰が与えられて我々が「信仰による人々」とされたように、彼らユダヤ人にも信仰が与えられて「信仰による人々」とされるようになるのを切に願うものである。どうか、神が、ユダヤ民族を憐れんで下さって、彼らが偉大なる救い主イエス・キリストに立ち返れるようにして下さるように。アーメン。
※①
『もしアブラハムが行ないによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし、神の御前では、そうではありません。聖書は何と言っていますか。「それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされた。」とあります。』(ローマ4章2~3節)
[本文に戻る]
※2016/02/28追加
更に言えば、異端者どもでさえイエス・キリストを信じている、と告白している。例えば、エホバの証人どもは自分たちがキリストを信じていると我々クリスチャンと同じように告白する。しかし、どれだけ彼らがキリストを信じていると叫んでも、彼らの集団のうちに御子の救いは存在していない。また、悪霊どもでさえ、我々の主が神の子であると信じている。悪霊どもは墓場に住んでいた男を通して、『神の子よ。』(マタイ8章29節)また『いと高き神の子、イエスさま。』(ルカ8章28節)と、主に対して言っている。しかし、悪霊どもが何と言おうと、たとえ主が神の御子であると信じていたのだとしても、悪霊どもが永遠の刑罰を免れることは不可能である。このような例から分かるように、「信じています。」と自分の口で言っていたのだとしても、その信仰が永遠の救いを生じさせる信仰でないのならば、そのような信仰には何の意味があるであろうか。
[本文に戻る]
※2016/03/13追加
この事柄については、カルヴァンもこう言っている。
「キリスト教信仰とは、心に触れることなく頭をあちこちととび廻る、神についてのむき出しの単なる認識、あるいは聖書の知識であるかのように考えるべきではない。或る真実らしい理屈によってわれわれに立証される物事についての見解なら一般にそのとおりである。しかし信仰は確かで堅固な心の信頼であり、それによってわれわれは福音がわれわれに約束している神の憐れみに確乎としてとどまるのである。かくして信仰の定義は約束の実体から導き出されねばならず、その信仰は基礎が取り除かれるやいなやたちまち崩壊しあるいはむしろ消えうせるほどにその基礎に支えられているのである。それゆえ主がその福音の約束によってわれわれにその憐れみを示すとき、もしわれわれが確実にまた何のためらいもなくその約束の主であるキリストに依り頼むならば、われわれは信仰によってそのことばを理解した、といわれる。そしてこの定義は使徒の定義(ヘブル11・1)と異なるものではない。使徒はその定義において、信仰とは望むべきものの実体であり表れていないものの啓示されることだと教えている。つまり彼は神によって約束されたものをしかと確実に所有すること、また表れていないものすなわち永遠のいのちの明証と解しており、その永遠のいのちに関しては福音を通してわれわれに与えられている神の善に信頼することによってわれわれは希望を抱くのである。さてこのように神のあらゆる約束はキリストにおいて固められいわば支えられ成就されるのだから、キリストが信仰の永遠の対象であり、また信仰は神の憐れみのすべての富をキリストに観想する、ということは、疑いもなく明らかである。」
ジャン・カルヴァン 『信仰の手引と告白』―真の信仰とは何か
教文館:「宗教改革著作集 第14巻」p231~232
[本文に戻る]
※2016/02/28追加
ここに書いてある文章を読んで、次の箇所が気になる方がおられるだろうか。すなわち、Ⅱコリント5章21節の箇所である。『神は、罪を知らない方を、私たちの代わりに罪とされました。それは、私たちが、この方にあって、神の義となるためです。』…ここでは『神の義となるためです。』と書いてあるが、これは「我々が義と認められた。」と言われているよりは、むしろ「我々が義とされた。」と言われているように感じられるかもしれない。何故ならこの箇所では「神により義と認められるためです。」ではなく、『神の義となるためです。』と書かれているからである。しかし、このように書かれていたとしても我々は不思議に思うべきではない。それはどうしてなのか。それは、我々がキリストにあって義と認められた、というその義認の状態に着目するならば、「神の義とされた。」という言い方をすることも可能だからである。このⅡコリント書の聖句では、このような観点から「我々が神の義とされる。」という言い方がされているのだと思われる。しかしながら、基本的・原則的に聖書では「義と認められた。」もしくは「義とみなされた。」という書き方になっていることを我々は弁えるべきである。
[本文に戻る]
※②
京都大学学術出版会:フィロン「フラックスへの反論 ガイウスへの使節」(秦剛平訳)
西洋古典叢書 第Ⅱ期第5回配本p246
[本文に戻る]
ガラテヤ人への手紙3章8~11節(2016/02/28説教)
『聖書は、神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを、前から知っていたので、アブラハムに対し、「あなたによってすべての国民が祝福される。」と前もって福音を告げたのです。そういうわけで、信仰による人々が、信仰の人アブラハムとともに、祝福を受けるのです。というのは、律法の行ないによる人々はすべて、のろいのもとにあるからです。こう書いてあります。「律法の書に書いてある、すべてのことを堅く守って実行しなければ、だれでもみな、のろわれる。」ところが、律法によって神の前に義と認められる者が、だれもいないということは明らかです。「義人は信仰によって生きる。」のだからです。』(ガラテヤ3章8~11節)
このガラテヤ人への手紙もそうだが、新約聖書における言葉はフィロンのような学者的なものではなく、普通の、自然な、通俗的なものであった。「日常的な言葉で語られていた。」といえば分かりやすいだろうか。J・G・メイチェンもこう言っている。「疑いもなく新約聖書の言語は書物にあるような技巧的なものでも、ユダヤ的ギリシャ語という変則語でもなくその時代の自然な活きた言語である。」「新約聖書の著者たちは、その時代の通俗な生きている言語を用いた。」(※①参照)この聖書の文体にキケロのごとき天才的技術がちりばめられていないからといって、我々は、高慢な者と同じようになって不満を持つべきではない。この聖書とは、神の言葉、聖なる言葉、真理の言葉、永劫不滅の言葉、輝かしい光の言葉なのだから。
この手紙を書いたパウロは、行為義認という異端に陥ってしまったガラテヤ人を真理に引き戻すために、「追及し、教えつつ説得する」という手法をとった。つまり、ガラテヤ人に対して何もせずに放置したり、ただ祈りつつ神がガラテヤ人の目を覚ましてくれるようになるのを待つだけだったり、間接的にガラテヤ人に真理の教えを気付かせようとする、というのではなく、みずから問題が渦巻いている戦場に乗り込むという方法を選んだ。これはつまり、こうすることこそ神の御心の方法だったということである。何故なら、パウロは神の御霊によってこの聖なる手紙をガラテヤ人に送ったからである。また、手紙を書いて直接的に当事者(ガラテヤ人)に迫るというこの手法は、この手法こそ最善の手法だったということを意味している。というのは、もし他の手法のほうが良かったのであれば、知恵と思慮の神はパウロにこのようにはさせず、更に幸いな手法を選ばせていただろうからである。「無知を病み愚劣な欲望に沈殿した魂には、ただこれを敢然と叱責する言葉のほかにいかなる妙薬もない」とはイソクラテスの言葉だが、異端という恐るべき眠りの中にぐうぐうと安らいでいる無知な魂に対しては、「教理の伴った追及・叱責」という聖なる衝撃を加え、その危険な眠りから覚まさせる必要があるのである。
それでは早速、8節目から見ていきたい。
①『聖書は、神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを、前から知っていたので、』(3章8節)
『前から知っていたので』とあるが、これは旧約時代のことである。新約時代になるまでは、ユダヤ人だけに救いが与えられており、異邦人には天国の扉が開かれていなかった。もちろん、異邦人であっても割礼を受けてユダヤ民族の一員になるのであれば神の救いに導きいれられることが可能であったが、民族としては救われることができなかった。新約時代には異邦人も神の民となれるようになったというので多くのユダヤ人たちが戸惑いを隠せなかったことからも分かるように、旧約時代の聖徒たちにとって、異邦人に救いが与えられるようになるなどとは考えにくいことであった。しかし、旧約時代の聖徒たちがどのように思ったのだとしても、神の思いは人の思いをはるかに超えていた(※②参照)。すなわち、神は旧約時代からすでに―というより永遠の昔からすでに―、異邦人にも義認の恵みが与えられるようになることを定めておられた。だから、ここでは、そのことを聖書が、また聖書を記された神が『前から知っていた』と言われているのである。
ここで、「どうして神は旧約時代には異邦人が救われるようにされなかったのだろうか。」という疑問を持たれる方がいるかもしれない。確かに、神はユダヤ人と共に異邦人も旧約時代から神の民となれるようにすることがおできになったのだが、そうはなされなかった。つまり、我々異邦人が救われるようになるためには新約時代になるまで待たねばならなかった。神がそのようにされた理由は、神が、まずユダヤ人を救いに導き、そのあと我々異邦人を救いに導かれようとされたからに他ならない。ソロモンは神の霊によって語っている。『天の下では、何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。』(伝道者の書3章1節)すなわち、異邦人に天国の扉が開かれるようになるのに時があったのである。旧約時代は、我々異邦人が救われるようになるのに、まだ時では無かったのである。兄より時間的に遅く生まれた弟で、「どうして俺は兄よりも遅く生まれたのか!?」などと親に文句を吐く者がどこにいるだろうか。弟が兄より遅く誕生したのと同じように、我々異邦人もユダヤ人たちの後に神の民となれるようになったのである。
続けてパウロはこう言っている。
②『アブラハムに対し、「あなたによってすべての国民が祝福される。」と前もって福音を告げたのです。』(3章8節)
ここでは、創世記に書かれている御言葉が語られている。すなわち、創世記の12章3節、『地上のすべての民族は、あなたによって祝福される。』また18章18節、『地のすべての国々は、彼によって祝福される。』22章18節もそうである、『あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。』なお、この内容の御言葉はアブラハムだけでなく、イサクおよびヤコブに対しても語られている(※③参照)。
パウロはこの創世記の御言葉が『福音』であると言う。このように言われているのを、我々は不思議に思うべきではない。というのも、福音とは「イエス・キリストの救いについての聖なる音信」のことだからである。つまり、ここでは『あなたによってすべての国民が祝福される。』と言われており、これはガラテヤ3:14にあるように『アブラハムへの祝福が、キリスト・イエスによって異邦人に及ぶ』ということであるから、すなわち、これはイエス・キリストの福音について語られている言葉に他ならない。何故なら、『あなたによってすべての国民が祝福される。』とアブラハムに告げられたのは、つまり「あなたに与えられた祝福がイエス・キリストを信じる全ての国民に注がれるようになる。」ということだからである。
ここで、『あなたによってすべての国民が祝福される。』という御言葉について詳しく考えてみたい。この御言葉は、たった今言われたように「アブラハムへの祝福が、ユダヤ人だけでなくイエス・キリストを信じる全ての異邦人にも注がれるようになる。」ということについて言われたものに他ならない。だから、「全ての国民が祝福されるようになるといっても、今の時代を見るならば、あらゆる国の人々にアブラハムへの祝福が注がれているようには思われないのですが…?」という疑問は斥けられる。何故なら、この聖句で言われていることは、「すぐにもその言われたことが全ての国民に対して実現される。」という意味ではなく、「その言われたことは諸国民がキリストを信じることによって実現されていく。」という意味だからである。それで、このことは今から2千年前、すなわち新約時代が到来してから実現されるようになった。それが実現されるようになってから2千年の歴史の間、この御言葉は時間の経過と共にますます実現されるようになっている。このことは、この新約時代における歴史を少し考えるならばよく分かるであろう。この日本においても、元々はキリスト者と呼ばれる人たちなどほとんど存在していなかったが、今ではプロテスタント教徒が約65万人(2004年時点)も存在するようにまでなった。アメリカでも500年ほど前にはクリスチャンなどいなかっただろうが、今ではプロテスタントだけでも数千万人の信者が存在するようになった。決して偽りを告げることのない真実で正しい神が「あらゆる国々が祝福されるようになる。」と告げられたのだから、これからもますますこの御言葉が諸国民に実現されるようになっていくのだということを、ポストミレニアリズムの終末論に立つ我々は固く信じるべきであろう。また、この御言葉は、これからユダヤ人の民族的回心という出来事が起こるのであれば、その実現に加速度がますますつくようになるのだと私には思われる。主が御語りになった以上、この歴史において、ユダヤ人であれ、日本人であれ、中国人であれ、インド人であれ、あらゆる民族にアブラハムへの祝福がイエス・キリストを通して注がれるようになっていくのだということは確実である。
続く9節でパウロはこう言っている。
③『そういうわけで、信仰による人々が、信仰の人アブラハムとともに、祝福を受けるのです。』(3章9節)
2節前の7節目の箇所と内容的に似ている言説である。7節目では、まず6節目で「アブラハムが信仰義認だったように、ガラテヤ人たちよ、あなたがたの救いも信仰義認によるのだ。」と言われてから、「それゆえ、信仰義認であるガラテヤ人たちは信仰義認であるアブラハムの子孫なのである。」と語られている。9節目では、まず8節目で「アブラハムへの祝福がイエス・キリストによって全民族に注がれるという福音は、旧約時代から告げられていたものだ。」と言われてから、「それゆえ、この福音の通りにキリストによる祝福を受けたガラテヤ人たちは、アブラハムと同じ祝福に浸っている者なのである。」と語られている。どちらも、聖書とアブラハムという人物に基づいて述べられている言説である。ここで見られるような、「聖書がこう言っている、アブラハムはこうだった、それゆえあなたがたに私は告げる。云々」というパウロの論法は非常に力強いものであって、真理によって説得させようとするこのような説得手法は、聖書を己の規範とすることを願う信仰者であれば反論できないものである。
ところで、ここでは「祝福」と言われているが、これはどういった意味であろうか。「祝福」と一口に言っても、生活に対する祝福、知性に対する祝福、人生に対する祝福、また(これは最大の祝福であるが)救いにおける祝福など、いろいろな種類があるから、一体どのような祝福を指してここでは「祝福」と言われているのか明らかにせねばならない。10節目以降の箇所では「律法の呪い」について語られているが、文脈から明らかに分かるように、この呪いに対立するものとしての祝福こそ、ここで言われている祝福に他ならない。まず、「律法の呪い」とは一体なんなのか。それは、簡単に、また粗雑に言えば「地獄に行くべきこと」あるいは「地獄に行かねばならない非再生者たち」に関することである。それで、この呪いに対立する概念がここで言われている祝福なのだから、ここで言われている祝福とは、すなわち「天国に行けるようになること」あるいは「天国にいずれ行き着く再生者たち」に関することである。つまりは「イエス・キリストの救いにおける祝福」こそ、ここで言われている祝福の意味である。だから、ここで言われているのは、本義的には、生活に対する祝福とか知性に対する祝福などといった諸々の祝福を意味していない。しかし、キリストによって救われるという祝福にそのような諸々の祝福も含まれている、あるいは救いにおける祝福にそのような祝福が付随する、というふうに考えることも可能ではある。
この箇所から分かるのは、ガラテヤ人であれ我々日本人クリスチャンであれ、信仰義認のキリスト者とは「祝福された者たち」であるということである。というのは、我々が罪深いにもかかわらず神はキリスト・イエスの救いにおける祝福を我々に与えてくださり、今現在もその祝福のうちに保ってくださり、これからもその祝福から除外するようなことはなされないからである。祝福された者たちは、イエス・キリストによる聖なる祝福によって始まり、保たれた祝福のうちに歩み、喜ばしい永遠の祝福に満ちた世界(つまり天国)に至るのである。しかし、選ばれていない方々、選ばれているがまだ救われていない方々は「祝福された者たち」ではなく、「呪われている者たち」である。信仰による人々とはすなわち祝福された者たちということがこの箇所から分かるのだから、この命題に対立する命題として、信仰によらない人々とはすなわち呪われた者たちということが明らかに分かるのである。先にも述べたように、この祝福とは「イエス・キリストによる祝福」であり、呪いとは「律法の呪い」である。10節目以降ではこの祝福と呪いについての事柄が詳しく論じられているが、それこそ、我々がこれから見ていく内容である。まずパウロは10節目で、この律法の呪いについての事柄をガラテヤ人に意識させることから始めている。
④『というのは、律法の行ないによる人々はすべて、のろいのもとにあるからです。こう書いてあります。「律法の書に書いてある、すべてのことを堅く守って実行しなければ、だれでもみな、のろわれる。」』(3章10節)
ここで、パウロはまた聖書の御言葉を引用している。すなわち、申命記27章26節の『このみおしえのことばを守ろうとせず、これを実行しない者はのろわれる。』という御言葉である。
パウロはこの申命記の御言葉に基づき、『律法の行ないによる人々』すなわち律法の遵守によって義を獲得しようとしている者たちが全て呪われた状態にあるのだと述べている。これは、つまりこういうことである。1.律法は、それを守れない者たちに呪いを宣告する。2.人が律法を遵守することを追い求めても、誰も完全に守ることなどできない。3.それゆえ、律法の行ないによって義を得ようとしている全ての者たちに対して律法は恐るべき呪いを宣言する。
この律法の呪いとは、先に話された「イエス・キリストによる救いの祝福」と正反対の概念である。つまり、律法の呪いのもとにある全ての者は、イエス・キリストによる救いから除外されており、呪いのもとにあるがゆえに最後には永遠の地獄に至る。もし律法を完全に守れるような人がいれば、その人は律法違反のゆえに「おお、律法を守れない罪深い不法な者よ。お前には永遠の呪い、燃える地獄の刑罰こそ相応しい。」という恐るべき宣告を律法によって突きつけられることもないが、そのような人は我々のうちに一人も存在しない。もし我々のうち誰かが律法を忠実に行なおうとしても、時間の経過と共に新たな罪が次から次へと噴出するばかりであって、律法を窮めようとするどころか、ますます呪われるに相応しい罪人になってしまう。もし律法を窮めようとする人がこうなのであれば、律法を行なう意志のない人たち、また律法に対する真面目な精神を持っていない人たちは尚更のこと、時間が経つにつれてますます呪われるに相応しい存在となってしまうであろう。それゆえ、神の聖者なるイエス・キリストを除く万人は、「律法の行ないによる人々」だけでなく、律法を行なう意志のない人たち及び律法に対する真面目な精神を持っていない人たちも、例外なく、律法の前において呪われるべき存在である。
ここで「誰しも律法を一点の落ち度もなく守れないがゆえ、律法主義者たちは律法の前において呪われた者である。」ということを述べたパウロは、続く11節でこのように言っている。
⑤『ところが、律法によって神の前に義と認められる者が、だれもいないということは明らかです。「義人は信仰によって生きる。」のだからです。』(3章11節)
パウロはまたも聖書の御言葉を引用しつつ語っている。ここに書かれている『義人は信仰によって生きる。』という御言葉はハバクク書2:4からの引用である。パウロはこの聖句をローマ1:17(※④参照)でも引用しており、この手紙はパウロが著者であるかどうか定かではないが「ヘブル人への手紙」の10章38節(※⑤参照)でも語られている。
このハバクク書の聖句に基づき、パウロは『律法によって神の前に義と認められる者が、だれもいないということは明らかです。』と述べる。これは、ハバクク書の御言葉が明らかに、義および義人を(律法の行ないではなく)信仰に結びつけているからに他ならない。つまり、聖書がこのように信仰義認の教理を主張しているのであれば、自ずと「人が義と認められるのは律法の行ないによる。」と主張する行為義認の教理は斥けられる、ということである。もし人が律法や自分の行ないによって義を獲得できるのであれば、ハバクク書であれ他の箇所であれ、聖書は『義人は行ない(または律法)によって生きる。』と述べていたはずである。しかし、そうではなく聖書は『義人は信仰によって生きる。』と述べている。それゆえ、ここでは聖書の信仰義認の主張に基づいて、行為義認の教理また律法主義の思想が完全に否定されてしまっていることが分かる。
本日はこの11節までであり、次週は12節目からの始まりとなる。このガラテヤ書における説教ももう中ごろになってきたが、何はともあれ、この説教文章をご覧になっておられる兄弟姉妹の方がたに、主からの霊的祝福が豊かにありますように。
※①
ニューライフ出版社:J・グレシャム・メイチェン「新約聖書ギリシャ語原点入門」p5
[本文に戻る]
※②
『わたしの思いは、あなたがたの思いと異なり、わたしの道は、あなたがたの道と異なるからだ。―ヤーヴェの御告げ。―天が地よりも高いように、わたしの道は、あなたがたの道よりも高く、わたしの思いは、あなたがたの思いよりも高い。』(イザヤ55章8~9節)
[本文に戻る]
※③
■イサクに対して
『こうして地のすべての国々は、あなたの子孫によって祝福される。』(創世記26章4節)
■ヤコブに対して
『地上のすべての民族は、あなたとあなたの子孫によって祝福される。』(創世記28章14節)
[本文に戻る]
※④
『なぜなら、福音のうちには神の義が啓示されていて、その義は、信仰に始まり信仰に進ませるからです。「義人は信仰によって生きる。」と書いてあるとおりです。』
[本文に戻る]
※⑤
『わたしの義人は信仰によって生きる。もし、恐れ退くなら、わたしのこころは彼を喜ばない。』
[本文に戻る]
ガラテヤ人への手紙3章12~15節(2016/03/06説教)
『しかし律法は、「信仰による。」のではありません。「律法を行なう者はこの律法によって生きる。」のです。キリストは、私たちのためにのろわれたものとなって、私たちを律法ののろいから贖い出してくださいました。なぜなら、「木にかけられる者はすべてのろわれたものである。」と書いてあるからです。このことは、アブラハムへの祝福が、キリスト・イエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。兄弟たち。人間のばあいにたとえてみましょう。人間の契約でも、いったん結ばれたら、だれもそれを無効にしたり、それにつけ加えたりはしません。』(ガラテヤ3章12~15節)
カルヴァンの牧会していたサン・ピエール教会の会員の多くが、先週の説教の内容を記憶のうちに蘇らせられなかったという。カルヴァンの説教は神学書とは違ってかなり平易であり、霊的な幼児であっても理解しやすい内容であった。しかし、それにも関わらず、7日前の説教で話された内容をよく覚えていない教会員が少なくなかった。カルヴァンの分かりやすい説教ですらこうであった。私はこのことを鑑みて、最近では説教の冒頭にて7日前に語られた内容を簡潔に繰り返すようにしている。この教会の説教を聞いておられる皆様においては、どうであろうか。7日前の説教の内容を覚えておられるだろうか。今後どうなるか分からないが、もし多くの兄弟姉妹が先週の説教の内容を忘れてしまっているというのであれば、説教の冒頭において簡単な復習をするのは有益であろう。今現在この教会でなされているように、聖書の箇所を連続で説教するスタイルの場合は、特に有益であり必要であろう。
それで、先週の説教では、祝福と呪いという2つの概念について語られ、この祝福とは「イエス・キリストの救いにおける祝福」であり、呪いとは「律法を守れないことによって定められる死の呪い」を意味するということについて述べられた。本日は、この事柄を論じている箇所の続きである。まずは12節目からである。
①『しかし律法は、「信仰による。」のではありません。「律法を行なう者はこの律法によって生きる。」のです。』(3章12節)
またもやパウロは、旧約聖書の御言葉をもって論じている。『律法を行なう者はこの律法によって生きる。』とは、レビ記18:5の箇所から語られている言葉である。そこには、『あなたがたは、わたしのおきてとわたしの定めを守りなさい。それを行なう人は、それによって生きる。』と書いてある。同じ内容のことはエゼキエル書などにも記されており、エゼキエル書20:11では『それを実行すれば生きることのできるそのわたしの定め』などと言われている。
パウロはこの旧約聖書の御言葉に基づき、『律法は、「信仰による。」のではありません。』と言う。この論法は11節目のそれと同じであり、11節目では「義認および義人とされるのは信仰によると聖書では言われているがゆえに、律法の行ないによって義と認められたり、義人となることはできない。」と述べられており、この12節目では「律法によって生きる者はこの律法の行ないによって生きると聖書では言われているがゆえに、律法によって生きることは信仰によって生きることではない。」と述べられている。この12節目で言われている内容は、非常に論理的なものである。つまり、もし我々のうちに律法を完全に行なえるような超人がいたとしたら、その聖なる人物は律法の義を行なうことによって永遠に生き続けられるわけだから、そのような行ないによる義人は自分の行ないで事足りているがゆえに、別に、義と認められたり義人となるために信仰をもったりする必要など無いのである。
我々が見ている今現在の箇所では、「信仰による義」と「律法による義」という2つの事柄が対立的な概念として論じられていることに留意すべきである。この2つのものが対立的に言われているということはつまり、信仰による義を是認するならば律法による義が斥けられ、それとは逆に、律法による義を是認するならば信仰による義が斥けられる、ということである。それで、ここでは『義認』という観点から律法の行ないが論じられているということを我々は弁えるべきである。そうしないと、『義認』という分野において「信仰による義のゆえに律法による義は斥けられる。」と考えるのに伴って、「道徳的な規範として今現在も行なうべき律法」という観念も共に斥けられてしまう恐れがあるからである。私が注意を促しているのは、すなわち、義認という観点においては律法の行ないは遠ざけられるべきだが、道徳的規範という観点においては律法の行ないは遠ざけられるべきではない、ということである。実際、このことについて弁えていないため、義認という分野において律法の行ないを自分から遠ざけるだけに留まらず、規範としての律法の行ないすらも自分から遠ざけてしまう方々が多く存在している。このような方々は「無律法主義者」などと言われている。これは非常に重要なことである。それゆえ、これと同じ内容を前に一度語ったことがあるにも関わらず、今ここで繰り返し語ることにしたのである。
次の13節目では、律法の呪いからの解放について書かれている。この聖句は、我々クリスチャンの救いに関して述べられている重要な箇所である。パウロは次のように述べている。
②『キリストは、私たちのためにのろわれたものとなって、私たちを律法ののろいから贖い出してくださいました。なぜなら、「木にかけられる者はすべてのろわれたものである。」と書いてあるからです。』(3章13節)
ここでもパウロは旧約聖書の御言葉をもって語っている。「」で囲まれている部分がそうであるが、これは申命記21章23節に書かれている御言葉である。そこでは、『木につるされた者は、神にのろわれた者だからである。』と記されている。
パウロはこの旧約聖書の御言葉に基づき、『キリストは、私たちのためにのろわれたものとなって、私たちを律法ののろいから贖い出してくださいました。』と述べる。先に語られたように、万人には律法の恐るべき呪いが宣告されている。律法を完全に守れる人など存在しないがゆえ、律法は全ての人に対して永遠の呪いを突きつけている。しかし、キリストは我々に突きつけられているこの律法の呪いを、十字架の上で死なれることによって、御自身の上に引き受けてくださった。つまり、我々信仰者に対して宣告されていた律法の呪いが、キリストの上に完全に転嫁された。それゆえ、キリストを信じる者には、もはや律法の呪いが宣告されず、信仰者たちは律法の呪いからキリストのゆえに完全に解放されている。例えば、死刑を宣告された死刑囚が死刑を受ける代わりに誰か潔白な人が死刑を受けるのだとしたら、その潔白な人が死刑囚の身代わりに死刑を受けたがゆえに、もはや死刑囚に対する死刑宣告は無効になってしまうであろう。それと同じで、キリストが我々に宣告されていた律法の呪いを身代わりに受けてくださったので、もはや我々はキリストのゆえに律法から呪いを突きつけられることがない。これこそ、キリストの死によって実現し、我々に与えられた聖なる救い、すなわち律法の呪いからの解放である。
このキリストによる救い、律法の呪いからの解放は、『人知をはるかに超えたキリストの愛』(エペソ3章19節)によって実現された。罪をもたず(※①参照)、罪を何も犯したことのない(※②参照)聖なる御方が、救いようのない我々罪人のために苦しまれ、死なれ、呪われたものとなり、黄泉に降られ、永遠の刑罰を我々のために身代わりとしてお受けになってくださったからである。これは、罪人である存在が誰かのために身代わりとしてただ単に死んだ、というのではない。キリストの身代わりの死は、このようなものとは訳が違う。罪のない聖なる御方が、選ばれた民すべてのために身代わりとして死なれ、呪われたものとして地獄に行って永遠の罰を引き受けられたのである。これほどまでの大きな愛がほかにあるであろうか。決してない。だから、我々が救われ、律法の呪いから解放されたのは、偉大なる主キリストの無限の愛によるものなのである。
今でもキリストを信じていない全ての人には、律法が恐るべき永遠の呪いを宣告している。すなわち、「あなたがたは聖なる律法を守れないがゆえに永遠の呪いに値する者たちである。それゆえ、いずれ神なる御方から『のろわれた者ども。わたしから離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火にはいれ。』(マタイ25章41節)と言われる時が来るであろう。つまり、あなたがたは呪いのもとにあるがゆえ、永遠の火の刑罰を受けねばならないのである。」という宣告が律法によって突きつけられている。この呪いを回避するためには、我々を愛して、十字架の上で呪われたものとなられたイエス・キリストを信じる以外には何一つ解決方法が存在しない。もしキリストに対する信仰を持つのであれば、その人はキリストのゆえに救われ、もはや律法から「あなたがた呪われた者たち、永遠の刑罰を受けるべき者たちよ。」という呪いの宣告をされることもなくなる。何故なら、その信じた人に対して突きつけられていた律法の呪いは、イエス・キリストがその呪いを身代わりに引き受けてくださったがゆえに、完全に無効とされるからである。未信者の方がたには、イエス・キリストを信じる信仰によって律法の呪いから解放されるという永遠の救いを望み欲するようになることを、お勧めしたい。
ところで、『木にかけられる者はすべてのろわれたものである。』というパウロが引用している旧約聖書の御言葉のゆえに、主イエス・キリストの犠牲の死は十字架の上で実現されたことが分かる。何故なら、我々に突きつけられている呪いがキリストの上に移されるためには、どうしてもキリストが木にかけられて呪われたものとならねばならなかったからである。もしキリストの死が、たとえば飢えとか斬首とか拷問によるものだったとしたら、木にかけられていないがゆえにキリストが呪われたものとはされなかっただろうから、我々に突きつけられている律法の呪いがキリストの上に転嫁されることはなかったであろう。つまり、キリストが木にかけられて呪われたものとして死なれるからこそ、選ばれた者たちの呪いがキリストの上に転嫁されるという贖いの死が実現されるのである。だから、律法に『木にかけられる者はすべてのろわれたものである。』と書いてあるがゆえに、どうしてもキリストの犠牲の死は木にかけられること、すなわち十字架刑による必要があった。
(2016/03/13追加)「それでは、木にかけられる方法であれば、十字架刑以外の方法による贖罪もありえたのか。」と思われる方がいるかもしれない。もろもろの預言が成就されるというのであれば、十字架刑でない方法による木にかけられる方法もあり得たのかもしれないが、神は十字架刑による方法でもって贖罪を実現された。これには、十字架のマークをキリスト教における目印・記号とするなど、様々な理由があったのだと思われる。実際、今でも人々は十字架のマークがなにかに描かれているのを見たら、多くの場合、それがキリスト教に関連したものだと認識する。何はともあれ、神は十字架刑において御子が木にかけられるのを望まれたのであるから、我々はそのことに深入りしすぎて心を煩わすべきではない。
これに続く14節目は、この13節目で言われている内容を展開したものである。まずは前半部分からになるが、このように書かれている。
③『このことは、アブラハムへの祝福が、キリスト・イエスによって異邦人に及ぶためであり、』(3章14節)
これはすなわち、キリストの十字架上における贖罪とは、すべての民族がキリストに対する信仰によってアブラハムの祝福を受けられるようになるためであった、という説明である。すなわち、我々の主は、ユダヤ人以外の民らも永遠の祝福を受けられるようにと、御自身みずから十字架の上で呪われたものとなってくださったのである。この贖罪の出来事が今から2千年前に実現してのち新約時代が始まり、異邦人にも天国の扉が開かれるようになった。今や、未開の地にいる人たちであろうと先進的な都市に住んでいる人たちであろうと、ユダヤ人であろうギリシャ人であろうと、どんな民族・種類の人たちでもキリスト・イエスを信じるならば救われることができるようになった。言うまでもなく、それはキリスト・イエスの贖罪のゆえに実現されるようになったものである。このキリストに、栄光がとこしえにあるように。アーメン。
すぐに続けてパウロはこう言っている。
④『その結果、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。』(3章14節)
たったいま話されたように、今から2千年前において全ての民族は信仰をもつならば救われることができるようになったが、救われる、とは『御霊を受ける』ということである。何故なら、御霊を受けないようであれば、当然ながら救いも無いだろうから。御霊を受けていない人を、どうして「救いを受けたキリストのものである信仰者」と呼べるのであろうか。『キリストの御霊を持たない人は、キリストのものではありません。』(ローマ8章10節)とパウロが言っているではないか。それで、この御霊は、キリストの昇天後に信仰者たちに与えられるようになった。キリストは御自身が天に昇られてのち、助け主なる聖霊を信仰者たちに遣わしてくださるということについて、ヨハネ福音書16:7の箇所でこう言っておられる。『わたしは真実を言います。わたしが去って行くことは、あなたがたにとって益なのです。それは、もしわたしが去って行かなければ、助け主があなたがたのところに来ないからです。しかし、もし行けば、わたしは助け主をあなたがたのところに遣わします。』だから、キリストの贖罪とは、我々が約束の御霊を受けられるようになるためになされたものである、とも言えよう。何故なら、キリストが永遠の犠牲となられたのちに復活して昇天されなかったとすれば、我々が約束の御霊を受けられるようにはならなかったからである。行ないではなく信仰によって御霊を受けるのだということについては、前に3章2節の箇所で話した内容であるから、ここで再び説明することはしない。
この14節目の後半部分でもパウロは、『信仰によって』我々が御霊を受ける、また救われるのだと述べている。つまり彼は義認の原因を教えるさい、『信仰によって』と言うのであって、決して「行ないによって」とは言わない。ここまで我々がこの手紙を見てきて分かるのは、パウロは繰り返し繰り返し「信仰によって」と書いていることである。この後の箇所でも、引き続きパウロは「信仰によって」「信仰によって」などと繰り返している。『心に満ちていることを口が話す』(マタイ12章34節)と主は言われたが、この聖なる御言葉は、口で話すことだけでなく文章を書くことについても当てはまる。それゆえ、この手紙を書いていたパウロの心に「ガラテヤ人たちが信仰による救いの教理に気づくようになってほしい。」という愛の思いが満ちていたのだということは絶対確実である。
⑤6~13節目の箇所について
6~13節目までの箇所で、パウロは畳み掛けるかのように連続で旧約聖書からの引用を行なっている。この部分は全部で8節あるが、8節中なんと6節もの箇所(6、8、10、11、12、13)で御言葉の引用がなされている。3章6節よりも前の箇所をざっと見ていただけると分かると思うが、この箇所になるまでは聖書からの引用はなされていない。パウロがどのような意図をもってこのように急に連続で引用したのか正確なところは分からないが、しかし、急に怒涛のごとき聖句の引用が行なわれることによって、内容とその調子にかなりメリハリが感じられるようになっている。
次は15節目である。
⑥『兄弟たち。』(3章15節)※2013/03/13追加
この呼びかけは、行為義認・律法主義という異端思想に陥ってしまったガラテヤ人が真の聖徒たちであり、彼らが真の聖徒たちであるがゆえにパウロは愛をもって教え諭(さと)そうとしているのだということを我々に教える。何故なら、もしガラテヤ人たちの不敬虔があたかもイスカリオテのユダのごとき致命的なものであったとしたならば、パウロは彼らに対して『兄弟たち』などとは決して言えなかっただろうからである。
こう呼びかけたのち、パウロは『人間のばあいにたとえてみましょう。』と言って、人間の契約という身近なものを通して分かりやすくガラテヤ人に悟らせようとする。
⑦『人間の契約でも、いったん結ばれたら、だれもそれを無効にしたり、それにつけ加えたりはしません。』(3章15節)
『契約』とあるが、これは新改訳聖書の下の欄の箇所で示されているように『遺言』とも訳せる。この語句は、つまり、人間社会における「協約」全般のことである。今現在の我々の社会でいえば、労働契約、賃貸契約、電話回線の契約、インターネット利用の際の契約など、契約といわれるものなら考えればいくらでも出てくるであろう。結婚も、ある男子とある女子の間において結ばれる性的な契約に他ならず、それは「夫婦契約」という名の契約である(※2013/03/13追加)。
この箇所でパウロが言いたいことは、こうである。「ガラテヤ人たちよ、我々人間社会の契約では、それを無効にしたり、それに何かを付加したりはしない。人間の間での契約がそうなのであれば、尚更のこと、神と人間との間での契約では無効とか付加とかいったものはあり得ないであろう。何故なら、人間との契約よりも、神との契約のほうが、はるかに大切であり尊重されるべきものだからである。それなのに、ガラテヤ人たち、あなたがたは神との契約をないがしろにしてしまっている。こんなことが果たしてあってよいものであろうか…?」このように人間社会の約束事を通して分かりやすく語ることによって、パウロはガラテヤ人たちを恥じ入らせようとしているのだと思われる。というのは、人間と結ばれた契約は当たり前のように尊重するのに神と結ばれた救いの契約のほうは尊重しないということは、神の民であるガラテヤの聖徒たちにとって、あるまじき愚行に他ならないからである。
ガラテヤ人たちは、神が彼らと結んでくださったキリストにある救いの契約を重んじることができないでいたが、神の側においてはそうではなく、神はガラテヤ人に対して結ばれた契約に徹底的に忠実であられた。神は御自身が結ばれた契約をあくまでも完全に保たれ続ける。『わたしは、わたしの契約を破らない。』(詩篇89篇34節)と神御自身が言っておられる通りである。この神は、いったん誰かと救いの契約を結ばれたのならば、その人が最後までその契約のうちに留まるようになされる。これは我々カルヴァン主義者の「聖徒の堅忍」の教理からも分かることであって、この教理とはすなわち、「神はいったんキリストにある恵みの契約に導きいれた信仰者を、永遠にその契約から除外されることはない。」といっているものに他ならない。我々クリスチャンはキリストを信じる信仰によって、恵みの契約―もしくは救いの契約、または聖なる契約と言ってもよい―すなわちキリストにある契約のうちに招き入れられた。我々人間が、誰かと結ばれた契約を堅く守り続けるのであれば、尚更のこと、神は御自身が結ばれた契約に忠実であられる。それゆえ、恵みによって我々と救いの契約を結んでくださった神は、契約のうちに導きいれられた我々をその契約から追い出されるようなことは絶対になさらない。だから、我々が招き入れられたキリストにある救いの契約は、神のゆえに永遠に磐石である。もし神が選ばれた者に対して結ばれた契約を破棄されるのであれば、神は御自身を否定されることになってしまうが、そういうことは絶対にあり得ないのである。最後になるが、御心のままをなされる神が多くの人びとをキリストにある救いの契約に招いてくださって、ますます御国が進展するようになるのを願うものである。次週は16節からとなる。
※①
『キリストには何の罪もありません。』(Ⅰヨハネ3章5節)
[本文に戻る]
※②
『キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見いだされませんでした。』(Ⅰペテロ2章22節)
[本文に戻る]
※2013/03/13追加
ここでは『兄弟たち』と書いてあるが、「姉妹たち」という言葉は含まれていない。聖書は、一見すれば分かることだが、第一義的な対象として男性を念頭において書かれている。例えば、山上の説教における次の箇所などは、明らかに男性を念頭において語られ、書かれている。『『姦淫してはならない。』と言われたのを、あなたがたは聞いています。しかし、わたしはあなたがたに言います。だれでも情欲を抱いて女を見る者は、すでに心の中で姦淫を犯したのです。』(マタイ5章27~28節)『また『だれでも、妻を離別する者は、妻に離婚状を与えよ。』と言われています。しかし、わたしはあなたがたに言います。だれであっても、不貞以外の理由で妻を離別する者は、妻に姦淫を犯させるのです。また、だれでも、離別された女と結婚すれば、姦淫を犯すのです。』(マタイ5章31~32節)もちろん、女性だけを対象として書かれている箇所もある。それで、もし聖書で「兄弟たち」と呼びかけられていたとしても、そこで言われている内容が性的に限定されたものでないならば、それは当然、姉妹たちも聞き従うべきものとして受け取るべきである。例えば「兄弟たち。祈りなさい。」などと書かれていたのであれば、これは兄弟たちだけなく、姉妹たちもその言われている内容に従うべきである。何故なら、この場合、その言われていることは性的に限定された内容ではないからである。兄弟たち、としか呼びかけられていないからというので、姉妹たちはそこに書かれている真理に従わなくてもよいのだ、というふうに考えないように我々は注意すべきである。
[聖句に戻る]
※2013/03/13追加
この契約により、その男とその女とは心も身体も共に一つとなり、一心同体なる夫婦として歩むようになるのである。この契約を結んだ夫婦は、キリストも言われるように『もはやふたりではなく、ひとり』(マタイ19章6節)である。
[本文に戻る]
ガラテヤ人への手紙3章16~20節(2016/03/13説教)
『ところで、約束は、アブラハムとそのひとりの子孫に告げられました。神は「子孫たちに」と言って、多数をさすことはせず、ひとりをさして、「あなたの子孫に」と言っておられます。その方はキリストです。私の言おうとすることはこうです。先に神によって結ばれた契約は、その後四百三十年たってできた律法によって取り消されたり、その約束が無効とされたりすることがないということです。なぜなら、相続がもし律法によるのなら、もはや約束によるのではないからです。ところが、神は約束を通してアブラハムに相続の恵みを下さったのです。では、律法とは何でしょうか。それは約束をお受けになった、この子孫が来られるときまで、違反を示すためにつけ加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたのです。仲介者は一方だけに属するものではありません。しかし約束を賜る神は唯一者です。』(ガラテヤ3章16~20節)
先週の説教では、イエス・キリストの犠牲の死によって我々が律法の呪いから贖い出された、という我々の救いのことについて語られた。特に13節目の箇所では、我々に与えられた救いがどのようなものであるかという内容が具体的に明らかにされているのを見た。クリスチャンにとって、イエス・キリストとその救いほど重要なものは他にない。それゆえ、主が実現してくださった救いについて明瞭に語られているこの13節目の箇所は、特に心に刻みつけられるべき聖句であると言えよう。
早速、16節目から見ていきたい。
①『ところで、約束は、アブラハムとそのひとりの子孫に告げられました。神は「子孫たちに」と言って、多数をさすことはせず、ひとりをさして、「あなたの子孫に」と言っておられます。』(3章16節)
ここで言われている『約束』とはいったい何であろうか。これは、(3章)8節目でパウロが引用している旧約聖書に書いてある『あなたによってすべての国民が祝福される。』というアブラハムへの御言葉、すなわち、14節目に書かれている『アブラハムへの祝福が、キリスト・イエスによって異邦人に及ぶ』という神の約束に他ならない。
このアブラハムに告げられた約束の言葉では、「子孫たちに」ではなく「子孫に」と言われているがゆえに、それは多数を対象としたものではなくある特定の存在を対象としているものなのだとパウロはここで説明している。実際に、旧約聖書の御言葉を見てみよう。神は創世記22:17~18において、キリストの福音を、アブラハムに対して前もって告げられた。次の通りである。『あなたの子孫は、その敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。』ここではパウロが言っているように、確かに『子孫』と個人に対して言われているのが分かる。このことについては、パウロが書いている通りであって、詳しい説明が必要なほど難解な内容でもないから、多言は不要であろう。
それでは、約束の言葉の中で言われている『子孫』とはいったい誰を指しているのか。パウロはこう言っている。
②『その方はキリストです。』(3章16節)
つまり、約束とは、イエス・キリストに基づく神の救いの契約のことであるのが分かる。何故なら、約束は今から2千年前にキリストがこの地上に来られたことによって実現され、また、人はイエス・キリストを通して救いの契約に招き入れられるからである。すなわち、イエス・キリストという御方なくして神の約束も、我々が導きいれられた契約もあり得ないのである。この御方のゆえに、この御方に基づいて、約束が告げられ、全ての民族が契約に入れるようになったのである。我々は、約束であれ、契約であれ、救いであれ、赦免であれ、和解であれ、解放であれ、イエス・キリストという御方を徹底的に前提とせねばならない。
そしてパウロは17節目で『私の言おうとすることはこうです。』と言って、契約の不動性・十全性について説明する。
③『先に神によって結ばれた契約は、その後四百三十年たってできた律法によって取り消されたり、その約束が無効とされたりすることがないということです。』(3章17節)
アブラハムに告げられた神の約束は不動のものであるから、約束が告げられてから430年後に制定された律法によっても揺り動かされはしない。とすれば、約束によってすでに救いを受けていたアブラハムの事例が示している通り、救いを受けるのは律法によるのではなく約束によることになる。何故なら、偽使徒たちがそれによって義と救いを得ようとしている律法が登場する430年も前に、もう義と救いは約束によってアブラハムに与えられていたからである。約束による相続の恵みが不動のものだとすれば、必然的に、律法の行ないによって相続を勝ち取ろうとする思想は斥けられてしまうのである。
しかしながら、もし神がアブラハムと契約を結んでから430年後にできた律法が、その契約を取り消したり無効にしたりするのであれば、その場合は、(神の恵みではなく)律法の行ないによって救い・義認が得られる、ということになっていたかもしれない。つまり、「律法が現われたのでアブラハムに与えられた約束による相続の恵みはもう無効とされた。今からは律法を完全に行なうことによってのみ、救い・義認を自分のものとできるようになった。律法を遵守できない者に天国はあり得ない。」ということになっていたかもしれない。しかしそうではない。だから、我々は、神の告げられた約束こそを中心・基点としてここで論じられている内容を考えるべきであって、律法や律法の登場という出来事によってこの約束を決して揺り動かしたり歪めてしまわないように注意すべきである。
続けてパウロは18節目でこう言う。
④『なぜなら、相続がもし律法によるのなら、もはや約束によるのではないからです。』(3章18節)
ここでは明らかに、相続が約束によるものであると言われている。もしそうであるならば、律法は決して、相続の原因・理由ではないであろう。相続における要因が、律法によるが、しかし約束にもよる、ということはあり得ない。それは、「あの人は東のほうに顔を向けているが、しかし西のほうにも同時に顔を向けている。」などと理解不可能なことを言うようなものである。相続は、律法によるか約束によるか、どちらか一つしかない。もし律法によるのであれば約束によるのではないし、もし約束によるのであれば律法によるのではない。パウロはここで、「相続は律法によるのではなく約束によるのだ。」と我々に教えている。18節目の後半部分では、このことについて、ふたたびアブラハムの例を提示することで強力な論証がなされている。
⑤『ところが、神は約束を通してアブラハムに相続の恵みを下さったのです。』(3章18節)
神は、相続の恵みを約束によってこそお与えになるのであって、そのことは、アブラハムに対して実際そのようにされた事実から明らかである。アブラハムが律法ではなく約束によって相続の恵みを受けた、というこの事実は、律法主義者たちの妄想、すなわち行為義認の思想を完全に粉砕してしまう。どうしてか。それは、律法が存在するようになる前にすでにアブラハムは律法なしに義と認められていたからである。つまり、律法主義者たちがそれによって義認を得ようとしている律法が制定されるより前の時代にもう信仰による救い・義認・相続が存在していたのであるから、律法による救い・義認・相続は幻想であるということになるのである。「律法がまだ制定される前の時代にアブラハムは(律法なしに)救いを受けていたというのに、どうしてあなたがたは律法によって救いを得ようとするのか。」という質問がなされるならば、偽使徒たちは困惑したに違いない。何故なら、アブラハムが律法の行ないなしに相続の恵みを受けたというその事実が、偽使徒たちの奉じる律法主義の思想と矛盾しているからである。それゆえ、アブラハムの例から明らかに分かるように、相続・救い・義認などは、人間自身の行ないではなくて、神の恵みによってもたらされるものなのである。
そしてパウロは続く19節において、「もし相続が約束だけによって与えられたのであれば、律法とは一体なんのためにあるのか。」との問いに答えている。
⑥『では、律法とは何でしょうか。それは約束をお受けになった、この子孫が来られるときまで、』(3章19節)
まずは律法制定の時期について説明がなされる。つまり、律法は、イエス・キリストが来られて新約時代が開始される時まで用いられるために制定された、ということである。次に、律法の目的および性質についてこう言われる。
⑦『違反を示すためにつけ加えられたもので、』(3章19節)
律法は違反を暴露するために制定された。この律法の数々の戒めを聞くならば、イスラエル人たちはそれらの戒めを忠実に守れないがゆえ、自分自身の罪および自分が罪深い存在であるということを大いに痛感させられてしまう。戒めを聞けば聞くほど、それらを完全に行なえないために、自分が違反に満ちた罪深い存在であるということを実感するようになる。例えば、誰かの所有物を心の中で欲しがってしまう人が『欲しがってはならない。』(出エジプト20章17節)という戒めを聞くまではあまり自分が罪深い思いを心に抱いていると感じなかったとしても、もしこの戒めを聞いて羨望・嫉妬が悪であるということを知ったならば、「ああ、他人のものを欲しがってしまう私はなんて罪深い存在なのだろうか。」と思って、自分が惨めな罪人であることを大いに痛感するようにもなる。つまり、戒めがそこにあるからこそ、ますます我々人間の罪、違反、愚かさ、また惨めさが明らかにされてしまう。それは、戒めそのものが「お前は悪いことをしている。」と我々に向かって語りかけるからである。これと同じ内容のことをパウロも多くの箇所で言っている。『律法がなければ、罪は死んだものです。』(ローマ7章8節)『律法によらないでは、私は罪を知ることがなかったでしょう。律法が、「むさぼってはならない。」と言わなかったら、私はむさぼりを知らなかったでしょう。』(ローマ7章7節)『罪は、何かの律法がなければ、認められないものです。』(ローマ5章13節)『律法によっては、かえって罪の意識が生じる』(ローマ3章20節)『律法がはいって来たのは、違反が増し加わるためです。』(ローマ5章20節)パウロが言っているように、もしも律法が何もなかったとすれば、イスラエル人であれ、我々であれ、自分がこんなにも罪深い存在であるという実感を持つことは出来なかったであろう。
つまり、律法とは、イエス・キリストが来られて新約時代が始まるまで、イスラエル人たちの違反・罪・悪を大いに示し、彼らが律法の呪いのもとにいる罪深い存在であるということを明らかにするために制定されたのである。このことは、救い主がやがて来られるという約束に心を向けさせるために、非常に有益であった。何故なら、律法を聞いて己が罪深い違反者であると痛感したならば、イスラエル人たちは「約束を受けられた罪からの解放者がどうか来られますように!」と、罪からの救い主の到来を大いに待望するようになるからである。つまり、非常に簡単に言ってしまえば、「罪を清めてくださる救済主を待ち望むようにさせるために律法は定められた。」ということである。だからこそ、ここでは「律法はイエス・キリストの到来の時までつけ加えられた。」と言われているのである。このことについては、主も『律法は…ヨハネまでです。』(ルカ16章16節)と言われ、律法が新約時代にまるまで作用させるために制定されたということについて語っておられる。
ここの箇所で我々が絶対に注意せねばならないのは、これらのことは律法の第一効用に関して言われている、ということである。我々の改革派およびルター派では、律法には3つの役割があるのだと理解する(※①参照)。第一の役割は、『律法を聞いて自分が罪深い存在であることを実感することによって、罪からの救済主イエス・キリストを希求するようになる』という教育的用途である。どうして「教育的用途」と言うかといえば、罪を実感させる律法がキリストへ導くために教導の役割を果たすからである。第二の役割は、『律法を聞いた人たちに恐れを生じさせて悪の発露を押さえつける』という抑制的用途である。例えば、未信者の方がたであっても、「律法に違反したら誰でも神の裁きを免れない。」と聞かされ、「おお、そうなのか。恐ろしいことだ。」と思って恐れを抱いたのであれば、その人はいくらかでも律法違反をしないように注意するようにもなるであろう。第三の役割は、『律法は神の民が指針とすべき聖なる掟である』という規範的用途である。『あなたのみことばは、私の足のともしび、私の道の光です。』(詩篇119篇105節)と書いてあるように、聖書律法とはクリスチャンが規範として守るべき、義なる神の規準なのである。この箇所では、第二および第三の用途について言われているのではなく、第一の用途に限定して言われている、ということを我々はわきまえるべきであろう。このことについて弁えていないと、律法が『約束をお受けになった、この子孫が来られるときまで、違反を示すためにつけ加えられたもの』であるからというので、もうキリストが来られた今となっては何もかも律法は無効となってしまった、規範として守る必要もないのだ、などと思いかねない。これは、無知な教職者が陥ってしまいやすい誤謬である。
最後にパウロは、律法はどのようにして、また誰によって定められたのか、ということについて述べている。
⑧『御使いたちを通して仲介者の手で定められたのです。』(3章19節)
まず律法は、『御使いたちを通して』制定された。このことついては、異論を唱える者はいないであろう。カルヴァンも「キリスト教綱要」の中で詳しく論じているが、神は、御使いたちを通して御自身の御心をなされる。例えば、死んだラザロをアブラハムのふところに連れて行ったのは、御使いたちであった(※②参照)。また、(この箇所における終末論思想には本日は触れないが)マタイ13:49~50に書いてあるように、悪い者を正しい者の中からえり分けて火の中に投げ入れるのも、御使いたちの仕事である(※③参照)。シナイ山における律法の授与もそれと同じで、ここでパウロが言っているように、神は御使いたちを御自身の道具として用いられることによって律法をお定めになったのである。
『たち』と書いてあるから、ただ一人の御使いではなく、複数の御使いたちが律法制定のために動員されたことが分かる。いったいどのぐらいの数の御使いたちが働いていたのか、と尋ねる人があれば、「分からない。」と答えるしかない。この箇所における御使いたちの詳しい数について、聖書はなにも明らかにしていないのだから。
また律法は、パウロが言っているように『仲介者の手で定められた』。ここで言われている『仲介者』という存在には2通りの解釈がある。一つ目はルターのように仲介者とはモーセのことを指しているとする解釈、もう一つはカルヴァンのようにこれはキリストを指しているとする解釈である。さて、一体どちらの理解のほうが正しいのであろうか。その答えは、明らかにキリストを指しているという理解のほうであろう。何故かといえば、もしこの仲介者という存在がキリストであると理解しなければ、20節目の『仲介者は一方だけに属するものではありません。』という聖句を正しく解釈できなくなってしまうからである。このことについては、後ほど説明がなされる。
『手』と書いてあるが、これは「職務」のことを意味する。すなわち、律法授与者であられるキリストが、御自身みずから律法をイスラエル人にお与えになったのである。
それで、キリストが律法を定められた、ということはつまり、律法とは『キリストの律法』であるということである。すなわち、私が言いたいのは、律法をお定めになった御方の名を冠して『キリストの律法』と呼ぶのは非常に理に適っている、ということに他ならない。パウロも『キリストの律法』(ガラテヤ6章2節、Ⅰコリント9章21節)と言っている。この律法とはすなわち『キリストの律法』であるから、この律法には主キリストの御心が啓示されていることが分かるのである。もしキリストの御心がそこに示されていないのであれば、パウロであれ、私であれ、『キリストの律法』などとは呼ばなかったであろう。
律法は悪霊によって定められた、などと言う人がいるが、これはとんでもないことである。パウロは律法についてこう言っている。『ですから、律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しく、また良いものなのです。』(ローマ7章12節)聖なる律法が悪霊によってもたらされるなどというのは、甚だしい狂言である。このような言説は、「無律法主義」と「無知」と「傲慢」という悪徳の三位一体が生みだした恐るべき結晶である。一体どのようにしたら律法が悪霊によって与えられたなどという結論に行きつくのであろうか。聖なるものを悪霊どもに帰しては決してならない!!!
20節目に進みたい。
⑨『仲介者は一方だけに属するものではありません。』(3章20節)
これは、19節でもいわれている『仲介者』という存在が明らかに分かるようになる聖句である。まず、この20節目でいわれていることは、「仲介者は、旧約の契約と新約の契約という2つの契約に属している方である。」ということに他ならない。だから、仲介者は旧約の契約か新約の契約か、どちらか一方だけに属しているのではない、とパウロはここで書いているのである。それで、もし『仲介者』がモーセを指しているとすると、モーセが旧約の契約にも新約の契約にも属している、ということになるから正しい理解にはならない。何故なら、旧約時代の民であるモーセが属していたのは旧約の契約だけだったからである。しかし、『仲介者』がキリストを指しているとすると、キリストは旧約の契約にも新約の契約にも属している、というすっきりとした理解になる。確かにキリストは旧約と新約という2つの契約の制定者・仲介者・主なのであるから、やはりこの『仲介者』という言葉はモーセではなく、キリストであると我々は解釈すべきである。
⑩『しかし約束を賜る神は唯一者です。』(3章20節)
これはつまり、キリストは旧約と新約という2つの契約における仲介者であるが、だからといって神およびキリストが2つも存在しているというのではない、ということである。この御言葉は、「キリストが旧約と新約という2つの契約の制定者だというのであれば、2つの契約の制定者が、2つの主が、2つのキリストが、2つの仲介者が存在しているのか?」という素朴な疑問に対する答えとなっている。もちろん、パウロの言葉から分かるように、そのようなことはない。つまり、キリストは、旧約と新約という2つの契約における、同一の主・制定者・仲介者であられる。これは、旧約時代と新約時代という2つの時代区分があるからといって、2つの神がいるのではないのと全く同じことである。旧約時代と新約時代という2つの区分があったとしても全ての時代における神はおひとりだけであるのと同じで、旧約の契約と新約の契約という2つの契約があったとしても、両契約における主・制定者・仲介者が2種類おられるというわけではない。
新改訳聖書の『約束を賜わる』という部分における※印が示しているように、この文章は本文につけ加えられた補足である。それゆえ、文語訳聖書でも、口語訳聖書でも、このような文章は存在していない(※④参照)。この新改訳聖書における補足は、翻訳者あるいは発行者サイドが分かりやすくなるようにと工夫したものであろう。我々の使っている新改訳聖書では、他にも同じようなことがなされている箇所がいくつも存在している(出エジプト18:13、22:13~14など)。なお、ここで補足されている文章は、内容的に間違っていたり、正しい解釈を妨げてしまうようなものではない。
来週は21節目からとなる。多くの方々が、約束されていた御方イエス・キリストとその救いの御業を通して、律法の呪いから贖い出されるようになるのを願うものである。キリストに、栄光と尊厳とが永遠に至るまでもあるように。アーメン。
※①
律法の三用益は、メランヒトン(1497―1560)によって論じ始められた。ルター派では、改革派における第一用益と第二用益の順番が逆さまになっているのが見られるが、単に順番が入れ替わっているだけで、内容的には同一であるから問題はない。カルヴァンは「第三の用益こそ主要なもの」(新教出版社:「キリスト教綱要 改訳版 第1篇・第2篇」第2篇7章12節p396)といって3番目の用益を強調するのに対し、ルターは第一用益と第二用益に対して「これこそ律法の真の、本来の用法である」(聖文社:「ルター著作集」第2集12 ガラテヤ大講解・下p71)といって1番目と2番目の用益を―特に1番目の用益を―、強調する。
[本文に戻る]
※②
『さて、この貧乏人は死んで、御使いたちによってアブラハムのふところに連れて行かれた。』(ルカ16章22節)
[本文に戻る]
※③
『御使いたちが来て、正しい者の中から悪い者をえり分け、火の燃える炉に投げ込みます。』
[本文に戻る]
※④
■文語訳聖書
『中仲は一方のみの者にあらず、然れど神は唯一に在せり』
■口語訳聖書
『仲介者なるものは、一方だけに属する者ではない。しかし、神はひとりである。』
[本文に戻る]
ガラテヤ人への手紙3章21~28節(2016/03/20説教)
『とすると、律法は神の約束に反するのでしょうか。絶対にそんなことはありません。もしも、与えられた律法がいのちを与えることのできるものであったなら、義は確かに律法によるものだったでしょう。しかし聖書は、逆に、すべての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束が、イエス・キリストに対する信仰によって、信じる人々に与えられるためです。信仰が現われる以前には、私たちは律法の監督の下に置かれ、閉じ込められていましたが、それは、やがて示される信仰が得られるためでした。こうして、律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。しかし、信仰が現われた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。あなたがたはみな、キリスト・イエスに対する信仰によって、神の子どもです。バプテスマを受けてキリストにつく者とされたあなたがたはみな、キリストをその身に着たのです。ユダヤ人もギリシヤ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜなら、あなたがたはみな、キリスト・イエスにあって、一つだからです。』(ガラテヤ3章21~28節)
先週の説教では、約束の不動性はたとえ律法によっても左右されないということ、また、律法制定の理由や期間などについて、(3章)16~20節の箇所から話された。本日は先週のこの箇所に引き続き、21節目からである。まず、なんらかの質問を提示してすぐさまその質問をみずから否定するという、パウロ特有の言い方をもって本日の箇所は始まる。
①『とすると、律法は神の約束に反するのでしょうか。絶対にそんなことはありません。』(3章21節)
相続の恵みが約束だけによって得られ、律法の行ないは別に求められていないのであれば、必然的に、「約束と律法は互いに対立しているのか?」という疑問が生じる。パウロが『絶対にそんなことはありません。』と言っているように、約束と律法は互いに反したものではない。何故なら、先週も話したように、律法はそれを聞いた者たちに自分の罪深さを痛感させることによって、約束による相続の恵みをみずから求めるようにさせるからである。
②『もしも、与えられた律法がいのちを与えることのできるものであったなら、義は確かに律法によるものだったでしょう。』(3章21節)
まず『与えられた律法』という部分に注目したい。律法はキリストによって御民イスラエルに『与えられた』のであって、それは神からの恵み、また贈り物である。だから、律法が与えられたことに負の感情を抱く方がたは、甚だしい思い違いをしてしまっている。神が御自身の『宝の民』(申命記7章6節)とされた者たちに、どうして悪いものを与えたり、悪いことをされたりするのであろうか。神が、聖き幸いなる義の基準である律法を恵みによってお与えくださったからこそ、詩篇119篇ではあれほどまでに神の律法が讃美されているのである。そこでは、『どんなにか私は、あなたのみおしえを愛していることでしょう。これが一日中、私の思いとなっています。』(97節)また『私は、金よりも、純金よりも、あなたの仰せを愛します。』(127節)などと律法について言われている。
この与えられた律法があたかも永遠の生命を与えることのできないものであるかのように、パウロはここで語っている。しかし、さまざまな聖句が示している通り、律法はもしそれを完全に守れるのならば永遠の生命を与えるものである。律法では『それを行なう人は、それによって生きる。』(レビ18章5節)と言われているし、主も『いのちにはいりたいと思うなら、戒めを守りなさい。』(マタイ19章17節)と言っておられる。では、どうしてパウロは、この律法によっては永劫の命が獲得できないかのように言っているのであろうか。それは、我々のうちにはだれひとり、律法を完全に遵守できるような超人が存在していないからである。つまり、(主キリストを除いては)たった一人でさえも律法の要求を全うできないのだから、パウロは思いきって「律法によっては誰もいのちを獲得できはしない。」と大胆に言っているのである。だから当然、彼は、もし律法をキリストのごとく守り行なえるならば、その人は律法によって義を得られるということを疑ってはいなかった。これは、誰もまともに操縦することのできないほど運転が難しい自動車に関して、「誰もあの自動車ではどこにも行けやしない。」などと言うのと似ている。このように言う人はあたかもその自動車によっては誰もどこにも移動ができないかのように言っているが、それは、誰ひとりとしてその自動車を上手に運転できないからそう言っているのであって、もし誰かしっかりと運転できる人がいれば、その人はその自動車によってどこかに移動することが出来るのである。
③『しかし聖書は、逆に、すべての人を罪の下に閉じ込めました。』(3章22節)
ここでの『聖書』とは、つまり律法のことである。律法は人間にいのちを与えるどころか、あらゆる人たちを永遠の断罪にふさわしい罪ある者として定めた、とパウロはここで言っている。
『すべての人』と書いてあるが、これは文字通りに受け取らねばならない。すなわち、ユダヤ人も、ギリシャ人も、日本人も、インド人も、エジプト人も、イギリス人も、ありとあらゆる民族である。パウロはローマ3:9で『ユダヤ人もギリシャ人も、すべての人が罪の下にある』と言っており、罪の下にある者たちを特定の民族に限定していない。だから、今でもすべての再生していない人びとは、律法によって罪と永遠の呪いが宣告されている状態のうちにあるのである。
それでは、律法がすべての人たちを罪の下に閉じ込めた理由・目的は一体なんなのか。パウロはこう言っている。
④『それは約束が、イエス・キリストに対する信仰によって、信じる人々に与えられるためです。』(3章22節)
もうお分かりであろう。前の説教でも話されたように、律法によって罪が暴かれ示されるからこそ、人は「罪からの救い主、律法の呪いからの解放者よ。どうか私を助け、お救いください。」と心のなかで思って、救済主なるイエス・キリストを求めるようになるのである。もし律法が存在しないがゆえに我々の罪深さが明らかにされないのだとすれば、それだけ罪の清め主を求めなくなってしまう度合いが強まるだろうことは言うまでもない。「私たちが罪深いから救い主が必要だって?私は自分がそこまで罪深いとは思いません。私はなんの法律違反もしてなければ、他人に迷惑もほとんどかけていません。」などと思っている不信者の例が示しているように、もし罪を実感しないのであれば、それだけ救い主を希求することもなくなってしまうのである。
ここでもパウロは『信仰によって』と言っており、ガラテヤ人たちが騙されてしまった行ないによる救いの思想を完全に斥けてしまっている。「教えに必要な事柄は、鈍い人々に対しては繰り返し示されねばならない」とアウグスティヌスは書いているが(※①参照)、『ああ愚かなガラテヤ人。』(ガラテヤ3章1節)とパウロも言っているように、ガラテヤ人たちが愚かで鈍かったからこそ、ここまで信仰によって、信仰によって、信仰によって、と繰り返し聞かされる必要があったのだろう。実に、彼らが霊的に鈍かったからこそ、行為義認などというふざけた思想に迷い込んでしまったのである。
⑤『信仰が現われる以前には、私たちは律法の監督の下に置かれ、閉じ込められていましたが、』(3章23節)
律法が監督に例えられており、人間はこの監督によって支配されている、とパウロは言っている。この23節と24節では、律法が監督・牢獄・養育係・家庭教師・教導役などといったものに例えられている。このように表現されるというのはつまり、救いに選ばれている誰かが律法の呪いのもとに閉じ込められているのは一時的な期間に過ぎない、ということである。何故なら、その選ばれている人がキリストに対する信仰を持つならば、もうその人は律法の呪いから完全に解放されるからである。今でもすべての非再生者たちは例外なく律法という監督の下に閉じ込められている。人は、信仰によって律法の呪いから解放されることにより、律法の呪いという監獄から抜けだすに至るのである。実にこのためにこそ、つまり信仰による救いが実現されるためにこそ、この律法は制定されたのである。それゆえ、23節目の後半部分ではこう言われている。
⑥『それは、やがて示される信仰が得られるためでした。』(3章23節)
パウロはローマ書でもこう言っている。『神は、すべての人をあわれもうとして、すべての人を不従順のうちに閉じ込められた』(11章32節)すなわち、神は、救い・解放・癒し・憐れみ・赦免などを実現させるために、我々人間が律法の呪い・不従順のうちに閉じ込められるのを欲されたのである。なぜなら、もし我々人間が悲惨な状態のうちに閉じ込めれていなかったのであれば、我々がその悲惨から救出されることによって、救いであれ解放であれ憐れみであれ、神に属する幸いなものが明らかにされなくなってしまうからである。
⑦『こうして、律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。』(3章24節)
律法によって我々は信仰を求めるに至るようになる、という事柄についてはひととおり話したので、この箇所ではパウロがまたもや『信仰によって』と書いていることに注目したい。ここまで繰り返して『信仰によって』といわれているのを見ると、箴言のあの御言葉に抵触するのではないか、などと心配される方もいるかもしれない。『同じことをくり返して言う者は、親しい友を離れさせる。』(箴言17章9節)確かにすでに一度聞いたことのある内容の話をふたたび聞かされると、もう満腹になったのにも関わらずさらに強制的に食べさせられるのに似て、「またか。」と思わされることにもなりかねないのだが、パウロがここまで信仰義認の思想を繰り返しているのはこの御言葉には抵触していない。何故なら、箴言の御言葉で言われているのは一回だけ聞けば十分に弁えられるような日常的な話などについてのことであって、何度も話される必要があるほどの重要性をもった言葉については当てはまらないからである。致命的誤謬に陥ってしまった鈍いガラテヤ人たちに分からせるために、パウロはどうしても繰り返して『信仰によって』と言わねばならなかったのである。
⑧『しかし、信仰が現われた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。』(3章25節)
これはすなわち、信仰者たちに突きつけられていた律法の呪いはすでに主イエス・キリストの上に完全に移されてしまっているので、もはや信仰者たちは律法の呪いのもとには置かれていない、ということである。
ルターのガラテヤ書講解を読んでいると、律法から解放された、律法の獄から救われた、などとあまりにも力強く論じられているので、成熟していない兄弟姉妹が読んだならば「私たちは律法からことごとく無関係になったのだ(※つまり律法の第三効用とも無関係になったということである)。」などと思いかねないほどの勢いである。今のプロテスンタント界でも、「律法から解放された。」と言うだけで第三効用については何も論じていない人が多く存在している。そればかりではなく、「律法から解放されたクリスチャンは何もかも自由に行なってもよいのだ。」などとすら軽率に語られているのが見られる。これとは違ってルターの場合は第三効用を否定していないし、今でも道徳的律法を我々は行なわねばならない、などとルターは語っているのだが、それでも第三効用について話されているのは量的には非常に少ない。この第三効用のことについて私は繰り返し話してきたし、今ここでもう一度言うのだが、「キリスト者は律法から解放された。」と言われているからといって、律法の第三効用からもキリスト者は解放された、などと思わないよう我々は注意すべきである。
26節目では、信仰をもった者たちはもはや律法の監獄のもとに閉じ込められてはおらず神の子どもなのである、ということが述べられている。
⑨『あなたがたはみな、キリスト・イエスに対する信仰によって、神の子どもです。』(3章26節)
ここでは明らかに、「信仰」と「神の子ども」という2つの事柄が結び合わされている。ここで言われている「信仰義認の者こそ神の子どもである。」という命題に対する命題は、「行為義認の者は神の子どもではない。」というものである。だから、この箇所でも行為義認の思想が否定され、信仰義認の思想が主張・肯定されているのが分かる。
この26節から分かるのは、ガラテヤ人たちは、永遠の昔から救われるように選ばれた真のキリスト者たちであった、ということである。何故なら、人間自身が書いた手紙ではなく、御霊によって書かれた手紙のなかで「ガラテヤ人たちよ、あなたがたは神の子どもである。」などと言われているからである。まさか、御霊によって語られた言葉を否定するクリスチャンもおるまい。つまりは、神の子らであるガラテヤ人たちは一時的に異端思想に陥ってしまっただけなのであって、パウロがこの手紙を送ってのち、その手紙を読んだ者たちの多くが正しい真理の教えに回帰したはずである。神は、パウロにこの手紙を書かせて我々を含めた新約時代のクリスチャンたちに益を与えるというその目的のために、ガラテヤの聖徒たちがサタンと異端者どもに惑わされて行為義認に迷い込むということを許可されたのである。御霊がガラテヤ人たちに対して『神の子ども』と言っておられるのだから、このように考えるのが間違っているとどうして言えるだろうか。それゆえ、我々は、やがてこの手紙の直接の読者であったガラテヤの聖徒たちと顔を会わせることになるであろう。彼らは我々の兄弟なのであって、天に国籍をもつ人たちだからである。もちろん、彼らのうちにいた毒麦ども―つまり偽クリスチャンどもについては別なのであるが。
ここで言われている内容から分かるように、人は、信仰によって「神の子ども」とされるに至る。「神の子ども」でなければ、その人は「悪魔の子ども」である。キリストが御自身を信じない人たちに対して『あなたがたは、あなたがたの父である悪魔から出た者』(ヨハネ8章44節)と言っておられる箇所がある。しかし今は悪魔を父とする人たちであっても、もし『キリスト・イエスに対する信仰』を持つならば、神を自分の父とするようになる。『この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子どもとされる特権をお与えになった。』(ヨハネ1章12節)と言われている通りである。未信者の方がたには、悪魔の子として地獄に投げ込まれて苦しみつつ後悔しないため、ぜひキリスト・イエスに対する信仰によって神の子どもとされるようになるのをおすすめしたい。
続く27節目において、パウロは聖なるバプテスマの事柄について書いている。
⑩『バプテスマを受けてキリストにつく者とされたあなたがたはみな、キリストをその身に着たのです。』(3章27節)
パウロが言うように、バプテスマを受けた者たちとは、キリストをその身に着ている者たちである。キリストという聖なる衣を身につけることによって、人は、父なる神から聖なる存在として取り扱われるようになる。この着物の比喩から分かるのは、人間が裸であるのはキリストという衣を身につけていない状態を象徴し、他方、服を着ているのはキリストという衣を身につけている状態を象徴する、ということである。神の御前にキリストを着ていないという悲惨な状態を象徴するからこそ「裸」は恥ずかしいのであって、神の御前にキリストを着ているという正しい状態を象徴しているからこそ「着衣」の人は堂々と振舞えるのである。このことについては、動物の場合を考えるならますます良く分かるであろう。動物たちは罪をもっていないがゆえに裸の状態でも恥ずかしくない。また、動物には罪がないがゆえに、罪の清め主なるイエス・キリストを象徴する衣服を身につける必要もない。もし動物たちに罪があったならば、我々人間のようにキリストを象徴する衣服をその身体につけねばならなかったであろう。もちろん、このことがあくまでも「象徴」にすぎないのだということは言うまでもない。たとえキリストを象徴する衣服をこの地上において物理的に着ていたとしても、もし真にキリストを着ることがなければ―つまりキリストに対する信仰を持たないのであれば―、その人は神の御前では恥ずべき悲惨な裸の状態なのであるから、かならず地獄に投げ込まれてしまうのである。
バプテスマを受けて制度的教会に属してはいても、真にキリストをその身に着ていない毒麦どもが存在している。彼らは真の信仰をもっていないので、やがて教会から遠ざかり、本当はキリストをその身につけていなかったことをみずから明らかにする。ヨハネはこのような偽クリスチャンについて次のように書いている。『彼らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちといっしょにとどまっていたことでしょう。しかし、そうなったのは、彼らがみな私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。』(Ⅰヨハネ2章19節)しかし、教会に所属している者のうちいったい誰がユダのごとき毒麦・偽善者であるのか、正体が暴露されるまで我々には分からない。ジョナサン・エドワーズも言っているように、「彼はきっと毒麦だろう。」と思っていた者がじつは真のクリスチャンであった、という事例は往々にしてあるのである(これとは逆に、「彼はきっと大丈夫だろう。」と思っていた者がじつは毒麦であった、というケースもある)。イスカリオテ・ユダが毒麦であると気づかなかった使徒たちの例からも分かるように、我々人間の目には、だれが麦でだれが毒麦であるのか判別不可能である。それゆえ、我々は、毒麦がその正体を現わすまでは、疑ったり探り合ったりせず、兄弟姉妹と呼ばれている者たちを主にある仲間として認識して大いに愛し合うべきである。
ローマ13:14にも『主イエス・キリストを着なさい。』と書いてあるが、このローマ書の御言葉の場合、ガラテヤ書の箇所とは違った意味で言われている。文脈から明らかに分かるように、ローマ書においてキリストを着るべし、と言われているのは、キリストをその身に着ることによってキリストが聖い歩みをされたごとくに聖い歩みをしなければならない、という意味である。ここではもうすでにキリストをその身に着てクリスチャンとなったローマ人たちを対象として語られているのだから、このように理解すべきであろう。
⑪『ユダヤ人もギリシヤ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜなら、あなたがたはみな、キリスト・イエスにあって、一つだからです。』(3章28節)
『ユダヤ人』とはアブラハムを肉の先祖としてもつイスラエルの民のことであり、『ギリシヤ人』とは異邦人全体を示している言葉である。『ユダヤ人』という言葉を律法主義者、『ギリシヤ人』という言葉を哲学者だとする考えもあるが、適切ではない。ここでは明らかに民族的な意味で、ユダヤ人とギリシア人という言葉が使われている。
我々クリスチャンは、キリスト・イエスにあって契約的に一体であり、それは民族・立場・性別などの外的要素によって妨げられることがない。それは、同じ両親から生まれた大勢の子どもたちが「俺たち全員があのお父さんとお母さんの子どもであるという事実は、兄とか弟とか姉とか妹とかいった俺たち一人一人の生まれの順序によって変えられたり歪められたりするものではない。」と言うようなものである。彼らは、生まれた順序によって長子とか次女とか兄とか妹などと呼ばれているが、呼ばれ方・年齢・性別はそれぞれ違えど、みな同じ親から生まれた子どもたちである。最初のキリスト教皇帝であるコンスタンティヌス一世(274頃―337)は、このことをよく弁えていたキリスト者であった。皇帝という輝かしい地位にあった彼は、司教たちがキリスト・イエスにある自分の同胞であって尊重するに値する者たちだからというので、彼らがみすぼらしい服装をしているにも関わらず、多くの司教たちを自分の食事の席に列座させて愛のうちに懇談したのである。また、江戸幕府がキリスト教とその普及に恐れを抱いたのも、このことが理由であった。すなわち、キリストにあって自分たちを一体・同胞同士とするキリシタンが多くなれば、領主すらも「兄弟たち」などと言われるようになり、諸々の秩序と体制とが転覆されかねない、と幕府の者らは心配したのである。
もちろん、聖徒たちが外的な事柄に関係なくキリスト・イエスにあって契約的に一つであるからというので、もはや種々の外的区別は撤廃しなければならない、というふうに我々は受け取るべきではない。パウロは、『夫たちよ。』(エペソ5章25節)とか『奴隷たちよ。』(コロサイ3章22節)とか『先輩』(ガラテヤ1章17節)などと、その人の立場・地位・状態に応じて区別を設けている。この箇所では、「キリストにあって聖徒たちは問答無用に一体なのである。」という視点に基づいて言われていることに我々は留意すべきである。
次週は29節目からとなる。恵みと平安が、聖徒たちすべてにありますように。
※①
アウグスティヌス「洗礼論」第2巻1章1節
教文館:アウグスティヌス著作集8 ドナティスト駁論集p69
[本文に戻る]
ガラテヤ人への手紙3章29節~4章5節(2016/03/27説教)
『もしあなたがたがキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。ところが、相続人というものは、全財産の持ち主なのに、子どものうちは、奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは、後見人や管理者の下にあります。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時には、この世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、この方を、女から生まれた者、また律法の下にある者となさいました。これは律法の下にある者を贖い出すためで、その結果、私たちが子としての身分を受けるようになるためです。』(ガラテヤ3章29節~4章5節)
この辺りの箇所は、非常に神学的な内容となっているので、教義面にどうしても精神が集中されやすい。じっくり考えないと、正しい理解が得られないような箇所もある。だから、パウロが語っている言葉における教理の内容にだけ心が傾けられてしまい、この手紙の直接の読者であるガラテヤ人の存在を忘れてしまいかねない。しかし、我々はそこで言われている教義的内容に心を注視させるのだとしても、この手紙はガラテヤ人に送られたものなのだ、ということを忘れるべきではない。何故なら、聖書のどの巻でもそうであるが、その文章が書かれた背景をまったく無視してしまうのであれば、そこで言われている真理の事柄を正しく捉えられなくなってしまいかねないからである。
先週の箇所は3章の20~28節目であったが、律法と信仰における関連性、人は信仰によって神の子とされること、バプテスマとキリスト者の契約的一体などの事柄について語られた。本日は29節目からである。
①『もしあなたがたがキリストのものであれば、』(3章29節)
パウロは、ガラテヤの地方にいた聖徒たちがキリストの所有の民なのだと言っている。彼は、コリントの聖徒たちに対しても『あなたがたはキリストのもの』(Ⅰコリント3章23節)と言っている。主キリストは、御自身の弟子たちのことについて父なる神に『あなたが世から取り出してわたしに下さった人々』(ヨハネ17章6節)と言っておられる。つまり、信仰をもった人はキリストに対する信仰によってこの世から取り出されてキリストに与えられるので、キリストの所有とされるのである。我々一人一人も、ガラテヤ人やコリント人や使徒たちと同じく、信仰によってキリストのものとされた民である。
②『それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。』(3章29節)
キリストのものである人たちは、すなわち『アブラハムの子孫』また『約束による相続人』である。まず第一に『アブラハムの子孫』とあるが、ここではキリスト者たちこそが真の意味における『アブラハムの子孫』なのであって、ゆえに、肉的なアブラハムの子孫であるユダヤ人たちが斥けられている。当時、アブラハムを肉における先祖としてもっているからというので喜びつつ誇っているユダヤ人が存在していたが、パウロは彼らに対して「あなたがたは真のアブラハムの子孫とはいえない。なぜなら、あなたがたはアブラハムのように信仰義認の者ではないし、キリストを知ってもいないからだ。たとえ異邦人であっても、アブラハムがそうであったように信仰義認であり、キリストを主としている者たちこそが本当のアブラハムの子孫なのだ。」と、ここで暗に言っているのである。次に『約束による相続人』とあるが、我々が『約束による相続人』であるならば、我々は「律法の行ないによる相続人」ではない、ということがこの言葉から分かる。我々人間が相続者となれるのは、ただ信仰・約束だけによるのであって、それは律法・行ないによるのではないのである。
神の恵みによって3章の箇所がすべて終わったので、ここから4章目となる。まずパウロは29節目で言われた『約束による相続人』という存在をピックアップし、たとえをもって説明し始める(※2016/04/10追加)。
③『ところが、相続人というものは、全財産の持ち主なのに、子どものうちは、奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは、後見人や管理者の下にあります。』(4章1~2節)
相続人である父の子どもは、父の全財産をやがて自分のものにできるので、今はその全財産における裁量権をもっていなかったとしても、その全財産の持ち主・主人であると言える。つまり相続人は、父の全財産における「未来の所有者」ではあっても、「現在の所有者」ではない。または、今は「法的な所有者」であるが、「実際的な所有者」ではない、という表現もできるだろう。奴隷の場合は相続人とは違って未来になっても全財産を自分の所有とすることができないが、しかし、「現在の所有者ではない」また「実際的な所有者ではない」という点については、奴隷も相続人もどちらも同じである。それゆえ、パウロはここで、相続人が全財産を受けつぐ日が到来するまでは「全財産に対する支配権をもっていない」という点において、相続人も奴隷も何ら変わらない、と言っている。
そしてパウロは3節目で、「かつて我々は、全財産を受けつぐ日がくるまで奴隷と同一の状態にあったこの相続人のようであった。」ということについて書いている。
④『私たちもそれと同じで、まだ小さかった時には、この世の幼稚な教えの下に奴隷となっていました。』(4章3節)
『小さかった時』とはまだ信仰が現われていなかった時代、すなわちユダヤ人たちが律法の監督の下に閉じ込められていたその状態のことであり、『この世の幼稚な教え』とは律法および律法で命じられている種々の儀式を行なうことである。信仰がまだ現われていなかった旧約時代において、ユダヤ人たちには律法の儀式を行なうことによってキリストの贖いが適用されていたのだが、この時代にはまだキリストの永遠の贖いが実現されていなかったのだから、このようにする以外に道はなかった。しかし、パウロは、そのような時代に行なわれていた儀式の遵守のことを『幼稚な教え』であると言う。ここで、「旧約時代には律法が命じている動物犠牲などの儀式を行なうことを通してキリストによる罪の赦しを受けるしか道がなかったというのに、パウロはどうしてここで律法の儀式に対して『幼稚』などと否定的な形容をしてしまっているのか。」という思いをもたれる方は多いかもしれない。もちろん、旧約時代になされていたその儀式自体を単体としてみるならば、それは仕方なかったことであるから、パウロも否定しなかったであろう。しかし、キリストが永遠の贖いを実現してくださった新約時代においては、もはや様々な儀式は不要となったのであり、もしキリストが贖罪を成し遂げられたにも関わらず儀式を行なうのであればそれはキリストの贖いを否定する行為となってしまう。つまり、キリストの贖罪が実現された新約時代にあっては、律法の儀式は斥けられるべき、もはや行なう必要のない過去のものとされている。だからパウロがここでキリストの贖いのゆえに「律法の儀式は今となっては幼稚なものである。かつてあなたがたはそのようなものの奴隷となっていたのであった。」と言っているのは何も不思議なことではない。『幼稚』と書いているからといって、パウロはこの箇所で律法を侮辱・冒涜しているというわけではない。
この奴隷の状態から我々を解放してくださる救い主の到来およびその定めの時のことについて、パウロは4節目で語っている。
⑤『しかし定めの時が来たので、』(4章4節)
『定めの時』とは、厳密にいえば紀元前4年、すなわちキリストが誕生されたその年である。ソロモンは『天の下では、何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。』(伝道者の書3章1節)と言っているが、この時代において、遂に「御子がこの世界においでになる時」が到来したのである。そして、この定めの時が到来したがゆえに、神は大いなること―聖なる御子の派遣―をなされた。次のように書いてある。
⑥『神はご自分の御子を遣わし、』(4章4節)
すなわち、神の第一位格なる御父によって、神の第二位格なる御子がこの世界に送られた、ということである。このことから2つのことが分かる。まず第一に、御子は御自身が遣わされる時代以前からずっと存在しておられた、ということである。もし遣わされる前にはおられなかったのであれば、どうして存在していないにも関わらず遣わされるということが起こりえようか。第二は、御父が受肉するように命令し、御子がその命令に完全に従われた、ということである。御父が命令し、御子が従われるというこの親子の関係は、ヨハネ12:49~50におけるキリストの御言葉からも分かるであろう。『わたしを遣わした父ご自身が、わたしが何を言い、何を話すべきかをお命じになりました。わたしは、父の命令が永遠のいのちであることを知っています。それゆえ、わたしが話していることは、父がわたしに言われたとおりを、そのままに話しているのです。』
4節目の後半部分では、この御子がどのようにして遣わされたのかが説明されている。
⑦『この方を、女から生まれた者、また律法の下にある者となさいました。』(4章4節)
まず御子は、『女』―すなわちキリストの母であるマリヤから、『生まれた』。確かに主はマリヤという一人の女性から御生まれになったのだが、ここでは「マリヤ」と書いて特定の女性を示すことはせずに、たた概括的に『女』とだけ書かれている。それで、キリストは我々一人一人と同じように女の胎から誕生することによって遣わされる、というのが神の御心であった。御子は、たとえば天使でもあるかのように空中の高い場所から輝きをもって降臨されたり、どこかの場所に成人の姿でいきなり出現されたり、アダムがそうだったように土地の塵によって人間となられる、などといった方法によってこの世界に来られることも出来たのだが、神はそうされず、人間から生まれさせるという方法を選ばれた。神がこの方法によって御子を遣わされたのは、キリストはダビデの子孫として生まれる、という神御自身の語られた預言のゆえであった。また、御子は『女から生まれた』のだから、この御方がまことの人間であられたことが分かる。確かに聖書では、キリストは真の人であったと言われている(※①参照)。それゆえ、御子がまことの神であるのは信じるが、まことの人であるということについては否定するふざけた異端者どもを、我々は聖書によって断罪する。私は思うのだが(これを読んでおられる方もそう思われるだろうが)、御自身が作られた被造物・人間・堕落している者・不完全な存在・女―すなわちマリヤから産まれるという御子の受肉は、なんというへりくだりであろうか。このキリストの人知を遥かに超えた謙遜と聖なる従順について、パウロは次のように言っている。『キリストは、神の御姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして、仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質をもって現われ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。』(ピリピ2章6~8節)女から生まれた謙遜な御方キリストは、我々の聖なる模範であられる。
また御子は『律法の下にある者』、つまり、生まれながらにしてモーセ律法を遵守すべき民族であるユダヤ人として御生まれになった。人としてのキリストと他のユダヤ人は、罪を犯すか犯さないか、という点では異なっているが、律法に服すべき存在であるという点では同一であった。ではどうして御子は『律法の下にある者』また『女から生まれた者』として遣わされねばならなかったのだろうか。パウロは5節目でこう言っている。
⑧『これは律法の下にある者を贖い出すためで、』(4章5節)
すなわち、律法の呪いの下に奴隷となっている選ばれている者たちを、その律法の呪いから解放して救いだすために御子はまことの人となられた。我々がガラテヤ3:13の箇所で見たように、キリストが木にかけられて我々に突きつけられていた律法の呪いを御自身の上に引き受けて下さったからこそ、我々は律法の呪いから贖い出されたのである。この贖いが実現されるために、どうしても御子は真の人間とならねばならなかった。何故なら、もし御子が神でしかなかったのならば、律法の呪いを御自身に引き受けることが出来なかったからである。神性は神性であるがゆえに呪いを身代わりとして負うことができない。呪いを引き受けるのは人性でなけれはできない。それゆえ、御子は人性において我々に宣告されていた呪いを御自分の上に移すために、まことの人間として誕生されねばならなかった。それで、この贖いがどのような結果をもたらしたのか、ということについてパウロは5節目の後半部分でこう言っている。
⑨『その結果、私たちが子としての身分を受けるようになるためです。』(4章5節)
御子とその贖いのゆえに、選ばれた者たちは神の子としての身分を受けられるようになった。実に、我々が子となれるためにこそ、神の第二位格なる御子は人として生まれ、律法を完全に遵守され、十字架において永遠の贖いを成し遂げられたのである。我々は、我々のためになされたこの救いの御業のうちに、神の無限の愛が示されているのを見る。神の愛のゆえに御子が世に遣わされ、この尊い救いが実現されたからである。
神の子とされるためには律法の下から贖いだされねばならず、イエス・キリストに対する信仰が必要である。教皇派であれユダヤ教であれイスラム教であれ古代ギリシャであれ、どこもかしこも自力による良い行ないを通して義と認められようとしているが、そんな考えはサタンのまやかしにすぎない。修道士や哲学者などがどれだけ善行を積んだとしても、神の前に正しい存在となることは全く不可能である。未信者の方がたには、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められて神の子とされるようになるのを、ぜひおすすめしたい。もし我々の罪のために贖いとなられたイエス・キリストを信じるならば、律法の呪いから解放されて神の子とされる特権が与えられるであろう。『この方を受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には、神の子どもとされる特権をお与えになった。』(ヨハネ1章12節)と言われている通りである。
⑩この手紙について
最後に、いくらかこの手紙について話したい。
この「ガラテヤ人への手紙」とは、パウロがあらゆる手法を使ってガラテヤ人たちを正しい教えに復帰させようとしている、説得・改善の手紙である。パウロはこの手紙で、敵対者どもへの呪詛、聖句による教説、罵倒と批判、叱責、懇願、行為義認の完全否定、たとえ等、あらゆる方法を用いて、ガラテヤ人たちを信仰義認に目覚めさせようとしている。これらのものはすべて、彼らを正しい教義に引き戻す、という聖なる目的を実現させるために行なわれている。これはつまり、ガラテヤ人の目を覚まさせるためにはどうしても多種多様な方法を駆使せねばならなかった、ということである。致命的な異端の穴に沈み込んでしまった者に対しては、出来るかぎり多くの手法をもって多角的に説得することにより、その穴から引き出されるようにする必要があるのだ。カルヴァンも言っていたが、誤謬のうちに安住している者らは、何か少しでも自分たちの奉じている誤謬を支える思想的土台があると、その誤謬がもっともらしい堅固な根拠の上に建てられていると勝手に思い込み、「俺たちの信じている教えは論拠のあるものなのだ。」などと感じて安心してしまう。つまり、思想的な逃げ道が少しであっても存在するならば、誤謬に洗脳されている者らはその誤謬からなかなか離れようとしない。たとえ100もの指摘・批判をされて反論できなかったとしても、そうである。だから、パウロはあらゆる方法を使うことによってガラテヤ人たちから思想的な逃げ道を完全に奪い、もうまったく弁解の余地を無くしてしまう必要がどうしてもあったのである。それで、我々の共同体のうちから異端・致命的な誤謬に陥るガラテヤ人のような者が誰か生じたとしたら、その時は、パウロのこの手紙のことを思い返してみるべきであろう。その時の状況にもよるが、そのような者はなかなか過ちから離れようとしないだろうから、我々はパウロのごとく完全に反論・弁明の余地が無くなるよう多くの手法を駆使し、その過ちに陥ってしまった者が悪から離れて真理に復帰する以外にはできないようにすべきであろう。そうしないと、「俺の信じている教義にだって別に根拠がないわけでは無いのだ。」という思いがその人を誤謬から離れなくさせるので、悪い教義に迷い込んだまま滅びに至ってしまいかねない。
次週は6節目からである。これからもキリストの御国が大いに進展していくように。アーメン。
※2016/04/10追加
「たとえ」は聖書の中で多く用いられているものだが、よく論じられるように、これは理解の助けに有益となる強力なものである。何故なら、「たとえ」が理解のための足掛かり・糸口の役割を果たすからである。これを使えば霊的な幼児であっても真理を把握できるように導かれるのであるから、教職者がこれを使わない手はないと私には思える。
[本文に戻る]
※①
『また、神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリスト・イエスです。』(Ⅰテモテ2章5節)
『人となって来たイエス・キリストを告白する霊はみな、神からのものです。』(Ⅰヨハネ4章2節)
『なぜお願いするかと言えば、人を惑わす者、すなわち、イエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大ぜい世に出て行ったからです。こういう者は惑わす者であり、反キリストです。』(Ⅱヨハネ7節)
[本文に戻る]
ガラテヤ人への手紙4章6節~8節(2016/04/03説教)
『そして、あなたがたは子であるゆえに、神は、「アバ、父。」と呼ぶ、御子の御霊を、私たちの心に遣わしてくださいました。ですから、あなたがたはもはや奴隷ではなく、子です。子ならば、神による相続人です。しかし、神を知らなかった当時、あなたがたは本来は神でない神々の奴隷でした。』(ガラテヤ4章6~8節)
先週は、ガラテヤ人たちがキリストの所有の民であること、相続人の比喩による奴隷状態の説明、御子の派遣、律法の呪いからの解放などといった事柄について話された。本日は、先週に引きつづき6節目からである。
①『そして、あなたがたは子であるゆえに、』(4章6節)
ガラテヤ人らは、律法の儀式に拘束されている奴隷状態からキリストによって解放されて自由になったので、もはや奴隷ではなく子どもである。信仰をもった彼らは相続の恵みを受けたのだから、もう奴隷のごとき状態にある存在ではなく、完全に子である者たちなのである。このガラテヤ人たちに神が御霊をお与えになったのは、彼らが真の子たちであるがゆえであった、ということが6節目の後半部分で言われている。
②『神は、「アバ、父。」と呼ぶ、御子の御霊を、私たちの心に遣わしてくださいました。』(4章6節)
まず、この6節目の個所では「ガラテヤ人たちよ、あなたがたは子であって、私たちには御霊が与えられたのだ。」と言われているのだから、ガラテヤ人たちの多くは永遠の昔から救われるように選ばれていた者だった、ということが分かる。何故なら、神が御霊をお与えになるのは、世界の基の置かれる前からキリストにあって選ばれていた幸いな人たちだけだからである。
この聖句に基づいて、クリスチャンとは「御霊が心に遣わされている者たち」であるという定義をなすことができよう。御霊がその心に遣わされていない人はクリスチャンではない。ルターによると、16世紀当時の堕落しきっていた教皇派の連中は「たとえ聖く生き、すべてのことをしても、私が恵みの中にあり、聖いもので、聖霊をもっていると確信するには、ほど遠い。」(聖文社:「ルター著作集」第2集12 ガラテヤ大講解・下p128)などと言っていたようである。彼らは「誰かが神のみ霊をもっていると言うと、これを悪しき僭越だといって非難する」(新教出版社:カルヴァン・新約聖書注解Ⅹ ガラテヤ・エペソ書 p97)連中であったとカルヴァンは言っている。それゆえ、当時の腐敗していたカトリック陣営の者たちは真のクリスチャンではなかった、ということが明らかに分かる。何故なら、聖書が言っているように、真のクリスチャンたちは自分のうちに遣わされた御霊なるお方の存在について多かれ少なかれ感じたことがあるはずだからである。キリストは、御霊と御霊が与えられた神の子らについて次のように言っておられる。『しかし、あなたがたはその方を知っています。その方はあなたがたとともに住み、あなたがたのうちにおられるからです。』(ヨハネ14章17節)クリスチャンであれば自分のうちにおられる御霊のことを知っている、とこの聖句のなかで主が言っておられるのにも関わらず、カトリック教徒らは「我々のうちには御霊がおられるかどうか分からない。」などと言うのだから、彼らが御霊をもたない非再生者たちであったのは絶対確実である。スポルジョンはこれらのことに基づき、ある人がクリスチャンであるかどうか確かめるために「あなたは自分のうちに御霊がおられるのを感じたことがありますか?」という質問をしていたようだが、これは実に至当な聖書的質問である。もし誰かが真のクリスチャンであるというのならば、その人には絶対に御霊が遣わされているはずだからである。
聖書の他の箇所でも、クリスチャンには御霊が与えられたのだと言われている(※①参照)。それらの箇所では、単に「御霊が私たちに与えられた。」と言われているだけであるが、我々が今現在見ているこの箇所によると、御霊が与えられた場所は我々の『心』の部分である。我々の『心』に御霊が与えられた、ということは、すなわち我々の存在そのものに御霊が与えられた、ということを意味する。何故なら、心というものは我々人間の根幹をなしているものであって、心はその人そのものだからである。だからこそ聖書の多くの箇所では、「御霊が心に与えられた。」という局所的・部分的な言い方ではなく、「御霊が私たちに与えられた。」という全体的・総合的な言い方がなされているのである。
この聖句から分かるように、我々は、我々のうちにおられる御霊によって『アバ、父。』とか「私たちの父なる神さま。」などと呼び求めたりする。『聖霊によるのでなければ、だれも、「イエスは主です。」と言うことはできません。』(Ⅰコリント12章3節)とパウロは他の箇所で言っているが、これと同じで、御霊によるのでなければ誰も『アバ、父。』と言うことは出来ない。しかし、ここで次のように思われる方がいるかもしれない。「滅びに至る偽善者であってもクリスチャンと同じように『アバ、父。』とか『イエスは主です。』という言葉を口にするけど、これは一体どういうことなのだろう。」これは確かにその通りであって、偽クリスチャンたちも真のクリスチャンであるかのようにこういう言葉を発するのであるが、偽善者である彼らは、御霊によって心からそう言っているわけではない。つまり、彼らの口にする信仰的な言葉とその心はまったく調和していない。すなわち、偽善者たちは『アバ、父。』と口では言ってもその心は父と和解しておらず、『イエスは主です。』と告白してもその心は主に敵対したままなのである。しかし、御霊の与えられている真のクリスチャンがこういう言葉を口にした場合、その言説と心は完全に調和している。
ここでは『アバ』という言葉があるが、これはヘブル語で「父」を意味する言葉である。だから、この箇所ではヘブル語とギリシャ語の2つの言語において「父、父。」と言われていることになる。アウグスティヌスは、これはユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンという2種類のクリスチャンを念頭に置いて書かれているものだと考えているが、それは検討に値する一つの解釈であろう。『アバ、父。』と書かれている箇所は他にもローマ8:15があり、主もゲツセマネという場所で『アバ、父よ。』(マルコ14章36節)と祈っておられる。新約時代においては、もはやヘブル人だけが神を父とする存在ではなく、ギリシャ人をはじめとして全ての民族が神を父とすることが出来るようになったのだから、やはりアウグスティヌスが考えるように、ヘブル人と異邦人という2つの存在を前提としつつこのように書かれたり言われたりしているのであろう。
ここでは『呼ぶ』という言葉が出てくるが、我々の使っている新改訳聖書だけでなく文語訳聖書および口語訳聖書でもこのように訳されている。訳されている「κραζον」という原語は写本間において違いがないが、この言葉は『呼ぶ』のほかに『叫ぶ』とも訳せる。宗教改革者たちは当然でもあるかのように『叫ぶ』と訳しており、ルターの場合、『呼ぶ』と訳されることは念頭にすら置かれていない(※②参照)。他にもこの原語が「叫ぶ」という言葉でもって訳されているのは、マルコ5:7における汚れた霊につかれた人、また、マタイ15:23におけるカナン人の女についての話の箇所である。詳細は不明であるが、日本語訳における翻訳者たちはこの箇所の翻訳に際して、上に挙げたマルコとマタイの人物においててなされているのと同じ表現を避けようとしたがゆえに、あえて『叫ぶ』ではなく『呼ぶ』と訳したのであろうか。しかし、バプテスマのヨハネにおいても(現在完了の言い方ではあるが)この言葉が使用されており、彼についてヨハネ1:15では『叫んで言った。』と書かれている。それゆえ、『叫ぶ』と訳しても何ら問題はないはずである。私としては、『叫ぶ』という訳のほうが、御民の霊のためには良いだろうと思う。何故なら、そのほうが我々の霊に聖なる刺激がもたらされるだろうと考えられるし、また、我々クリスチャンは御霊によって心から御父を呼び求めるとき、叫ぶようにして「父なる神さま!」とか「御父よ!」などと言うものであるから。
我々は、ニカイア・コンスタンティノポリス信条およびアタナシオス信条にも書いてあるように(※③参照)、御霊が「御父と御子から出る」と信じているが、御霊が「御父から出る」ということは信じても、「御子から出る」ということについては否定するキリスト教グループが存在している。しかし、この箇所に『御子の御霊』と書いてあるのだから、御霊が御父からだけでなく御子からも出るということは明らかである。もし御子からも出るというのでなければ、どうして『御子の御霊』などと言われるのだろうか。御霊は御子からも出るのだからこそ、『御子の御霊』と言われているのである。「御霊は御父からしか出ない。」などという考えを、我々は非なる見解として斥ける。
7節目に行きたい。
③『ですから、あなたがたはもはや奴隷ではなく、子です。子ならば、神による相続人です。』(4章7節)
5節目においてガラテヤ人たちはキリスト・イエスによって贖われたがゆえに子なのであり、6節目においてガラテヤ人たちは子であるゆえに御霊が与えられた存在である、と言ったパウロは、この7節目で彼らが神の子らであるということを再び強調する。彼らが神の子であるというのは3節26節の箇所において前に話されており、また彼らが相続人であるということも既に語られたことであったが、パウロはこのように繰り返して論じることにより、鈍いガラテヤ人たちに真理を悟らせようとしているのである。我々も、イエス・キリストによって贖われたがゆえにもはや自分が奴隷ではなく神の子であり、相続人であるということを再び心に銘記すべきであろう。
ところで、我々が使っているこの新改訳および文語訳・口語訳の聖書では『神による相続人です。』(κληρονομοs δια θεου)と訳されており、これはアレクサンドリア型の写本に基づいている。しかし、ビザンチン型の写本では『キリストによる神の相続人です。』(κληρονομοs θεου δια χριστου)となっている。どうしてアレクサンドリア型写本では、「キリスト」(χριστου)という御名が書かれていないのか。他にもアレクサンドリア型写本には、ビザンチン型写本であれば書かれている御名が存在していない箇所が多い。このような小さからぬ問題があるため、我々はアレクサンドリア写本に対してあまりいい感情を持っていない。最近では聖霊派がビザンチン写本から訳された『現改訳』なる聖書を出しているが、やはりビザンチン型の写本から訳すべきであろう。
8節目でパウロは、ガラテヤ人たちの回心前の時のことについて言及している。
④『しかし、神を知らなかった当時、あなたがたは本来は神でない神々の奴隷でした。』(4章8節)
ガラテヤ人たちは救われる以前、偶像崇拝をしている異教の民であった。古代においてはゼウスやヘラといった神々の存在が一般的・普遍的に認められており、それらの神々は当たり前でもあるかのように崇拝されていた。ローマの地にも神々をまつる神殿がいくつも建てられていた(※2016/04/10追加)。プラトン思想にもデミウルゴスなる神の存在がでてくるし、ソクラテスも神々に祈りを捧げていた。神々の存在を否定するような者は気が狂っているとみなされないだろうか、などと言っている者も古代にはいた。ガラテヤ人たちも例外ではなく、人間の頭で勝手に考え出された神々を崇める偶像崇拝者たちであった。
パウロはここで、三位一体神以外の神と呼ばれる存在を完全に否定している。すなわち彼は、本質が一つであって父・子・聖霊という3つの位格があるのではない神は、すべて偽りの神であると言う。律法には『あなたには、わたしのほかに、ほかの神々があってはならない。』(出エジプト20章3節)と書いてあるが、これはつまり、聖書の神以外に真の神は存在しないということである。だから、ゼウスであれアラーであれシヴァ神・ブラフマー神・ヴィシュヌ神(※ヒンドゥー教の主要な三神)であれ、偽の神に他ならない。それゆえ、嘘の神々を崇拝をしていた回心前のガラテヤ人たちは、その当時『神を知らなかった』のであり、また『本来は神でない神々の奴隷』であったのだと、パウロはここで大胆に指摘している。
聖書は三位一体神ではない神の存在を、完全に斥け、否定している。今我々が見ているこの箇所では「聖書の神以外の神は神でもなんでもない。」と言われているし、イザヤ2:18では『偽りの神々は消えうせる。』と書かれている。他にも聖書では『天と地を造らなかった神々は、地からも、これらの天の下からも滅びる。』(エレミヤ10章11節)と言われており、『まことに、国々の民の神々はみな、むなしい。』(詩篇96篇5節)と書かれている箇所もある。それゆえ、聖書の弟子であるのを望む者たちは、本当は神ではない嘘の神々を嫌悪し、否定し、それらのものが滅ぼし尽くされるのを願うべきであろう。何故なら、聖書の弟子であるのを望む者たちは、自分の心を聖書思想に完全に合致させるのを望むべきだからである。聖書の弟子であったパウロも、アテネの地に満ちていた偶像の神に対して憤りを感じている(※④参照)。しかし、だからといって、クリスチャンは偶像崇拝者・異教徒たちの目前で敵意と不快感をむき出しにして、「あなたがたは本当に不信仰な方々だと私は思います。どうして自分たちが偽りの神々を信じているのに気づかれないのでしょうか!?私は前からずっと不思議に感じていました。」などと言ったりして攻撃的になるべきではない。パウロも、アテネの異教徒たちが拝んでいた偶像についての考えを穏やかに正そうとはしたが、敵対心をもって激しく批判するようなことはしていない。しかし、どうして我々は心の中では偶像を否定しつつも、偶像崇拝者と相対した際には偶像に対する敵意を隠して穏やかに接するべきなのか。それは、偶像崇拝者たちがイエス・キリストによって救われ、その拝んでいた偶像から離れるようになってほしいという愛の思いを我々が持つべきだからである。最初から敵意をあらわにして彼らに向かうならば、彼らは我々に対して抵抗感をもつだろうから、我々が何を言っても耳を塞がれてしまうことになりかねないのである。
次週は4章9節目からである。つい先日まで学生だった方など、4月になってから新しい歩みを始められる方がたが多いと思うが、それと同じように、これから新しいクリスチャン・新しい働き人・新しい教会がますます地上に増えていくようになるのを願うものである。
※①
『神は私たちに御霊を与えてくださいました。』(Ⅰヨハネ4章13節)
『神は、この聖霊を、私たちの救い主なるイエス・キリストによって、私たちに豊かに注いでくださったのです。』(テトス3章6節)
『あなたがたは、人を再び恐怖に陥れるような、奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。』(ローマ8章15節)
[本文に戻る]
※②
パウロは、「神はみ子の霊をわれわれの心の中に送って、『アバ、父よ』と呼ばせた」と言うこともできた。だが、彼はわざと「叫ばせた」と言っている。
(聖文社:「ルター著作集」第2集12 ガラテヤ大講解・下p132)
[本文に戻る]
※③
■ニカイア・コンスタンティノポリス信条
また、我らは、聖霊、主となり活かし、御父と御子とより出で、御父と御子とともに礼拝せられ崇められ預言者らを通して語り給う御方を信ずる。
(新教出版社「信条集」前篇p6)
■アタナシオス信条
聖霊は、御父と御子とより出で、形成されたのでもなく、創造されたのでもなく、生まれたのでもなく、発生したのである。
(新教出版社「信条集」前篇p9)
[本文に戻る]
※2016/04/10追加
「キケロー選集」(岩波書店)の巻末にある資料によると、紀元前1世紀のローマ市街中心部には以下の神殿が建てられていた。近接した場所(2平方キロメートル内)に計14もの神殿が存在しており、その多さに驚かされる。
1. ユーノー・モネータ神殿
2. ユッピテル・カピトーリーヌス神殿
3. フォルトゥーナとマーテル・マートゥータ神殿
4. ポルトゥーヌス神殿
5. ヘルクレース・ウィクトル神殿
6. キュペレー(マグナ・マーテル)神殿
7. アポッローとベッローナの神殿
8. クイリーヌス神殿
9. ディアーナ神殿
10.ユーノー・レーギーナ神殿
11.コンコルディア神殿
12.サートゥルヌス神殿
13.ウェスタ神殿
14.カストル神殿
[本文に戻る]
※④
『さて、アテネでふたりを待っていたパウロは、町が偶像でいっぱいなのを見て、心に憤りを感じた。』(使徒の働き17章16節)
[本文に戻る]
ガラテヤ人への手紙4章9~12節(2016/04/10説教)
『ところが、今では神を知っているのに、いや、むしろ神に知られているのに、どうしてあの無力、無価値の幼稚な教えに逆戻りして、再び新たにその奴隷になろうとするのですか。あなたがたは、各種の日と月と季節と年とを守っています。あなたがたのために私の労したことは、むだだったのではないか、と私はあなたがたのことを案じています。お願いです。兄弟たち。私のようになってください。私もあなたがたのようになったのですから。あなたがたは私に何一つ悪いことをしていません。』(ガラテヤ4章9~12節)
孟子の考えに「去る者は追わず、来る者は拒まず」という有名なものがあるが、この精神に立つならば、パウロは異端思想に陥ってしまったガラテヤ人らを気にかけず放置したままでいるべきであった、ということになるように思われる。何故なら、ガラテヤ人たちはパウロおよびパウロが伝えた福音から霊的に遠ざかってしまっていたからである。しかし、パウロであれ他の使徒であれ牧師であれ長老であれ、教会を指導する職務に召されている者たちは「去る者を引き戻し、来る者には注意を払う」という精神―つまり孟子の考えとまったく逆の思想―に立つべき存在である。というのは監督たちはその職務にふさわしく、迷いでてしまった羊を群れのなかに戻さねばならず、また、教会を健全な教理のうちに保たせるために入会者を厳格に吟味すべきだからである。エウセビオスの教会史によれば、使徒ヨハネも堕落して教会から離れ去ってしまった男性信徒を命をかけて追いかけ、真理に引き戻そうとしたようである。監督たる者が「去る者は追わず」という精神に立つならば迷ってしまった羊は迷ったままなのであり、また「来る者は拒まず」という思想を持つならば教会は毒麦どもで満たされかねない。教会から離れ去ってしまった人に手紙を書いたりその人の家を訪ねたりする牧師はどこの地域でも見られるものだが、その人が教会から離れた理由はともかく、そのような言動は牧師の職務に適ったものである。この手紙では、異端思想に迷い込んでしまったガラテヤ人のごとき羊たちをどのようにして真理に復帰させればいいのか、という事柄についての聖なる手本が示されている。
早速、9節目から見て行きたい。
①『ところが、今では神を知っているのに、いや、むしろ神に知られているのに、』(4章9節)
パウロたちの伝道活動によってガラテヤ人たちは真の神を知るに至った。しかしパウロはそのことについて言った後すぐに『いや、むしろ』と言い直して、ガラテヤ人らが神を知っているということよりも、神がガラテヤ人を知っている、ということの方を強調する。彼はここで、ガラテヤ人側を中心とした視点ではなく、神の側を中心とした視点を前面に押し出している。パウロがこのように言い直しているのは、愚かで鈍いガラテヤ人たちに「俺たちは神を知っている。だから偉いのだ。」という不敬虔な誇りを抱かせないためであったのだろう。
そしてパウロは、神を知り、神に知られているこのガラテヤ人たちのはなはだしい忘恩について9節目の後半部分で言及している。
②『どうしてあの無力、無価値の幼稚な教えに逆戻りして、再び新たにその奴隷になろうとするのですか。』(4章9節)
4章3節目で我々が見たのと同じように、ここでもパウロは、律法の儀式とその儀式を遵守することについて『無力、無価値の幼稚な教え』などと言っている。確かに、イエス・キリストの贖罪が実現した新約時代にあっては、一時的なものに過ぎなかった祭儀律法は、もはや行なう必要のない過去のものである。だから、ここでパウロが律法を否定的に形容しているのは、キリストの贖罪という観点からみれば何も悪いことではない。実に、ガラテヤ人たちはこのような過ぎ去った過去の理念に陥ってしまっていたのである。これは、イエス・キリストとその救いを蔑ろにし、神の恵みによる義認にみずから遠ざかる愚劣な行為に他ならない。ガラテヤ人に対して『あなたがたは、キリストから離れ、恵みから落ちてしまった』(ガラテヤ5章4節)と、パウロが言っている通りである。
ここではガラテヤ人たちが儀式的な律法によって義を獲得するという思想に『逆戻り』している、と言われているが、これは考察されるべき表現である。言うまでもなく異邦人であったガラテヤ人たちはユダヤ人とは違い、今までに律法主義者だった時期はなかった。例えばパウロは元は律法主義者だったのだから、仮にパウロが律法主義の思想に戻ってしまっていたとしたら、「パウロは律法主義に『逆戻り』してしまった…。」などと言えたであろう。しかし、ガラテヤ人はかつて律法主義を奉じるような者たちでは無かったのだから、彼らが律法主義の思想に陥ってしまったとしても、「ガラテヤ人たちは律法主義に『逆戻り』してしまった…。」とは言えないであろう。それにも関わらず、パウロはここでガラテヤ人たちが律法による義認の考えに『逆戻り』してしまったと述べている。どうしてパウロはここでこのような表現をしているのだろうか。私としては、この表現は、ガラテヤ人らを厳しく批判して恥じ入らせるためになされたのではないかと思われる。
10節目では、ガラテヤ人らが陥ってしまっていた祭儀律法の宗教的遵守がどのようなものであったか明らかにされている。
③『あなたがたは、各種の日と月と季節と年とを守っています。』(4章10節)
ここで言われているのは、律法が定めている安息日や安息年などを宗教的な意味において、つまりそれを救いに必要なものとして遵守することについてである。ヘブル10:1でも言われているように、このような祭儀律法は実物における『影』に過ぎないものであった。本体であるキリストが現われた新約時代においては、もはやこの本体を指し示す「象徴」に過ぎなかった影は行なう必要がなくなった。このことについてはコロサイ2:16~17の箇所でもこう言われている。『こういうわけですから、食べ物や飲み物について、あるいは、祭りや新月や安息日のことについて、だれにもあなたがたを批評させてはなりません。これらは、次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。』旧約時代においてはこの影を通して実体であるイエス・キリストによる恵みを受けねばならなかったためにどうしても遵守する必要があったのだが、実体が現われた新約時代においてはもはや影ではなく実体そのものによって恵みを受けられるようになったのだから、必然的に影の必要性はまったく無くなったのである。21世紀に生きる我々であれガラテヤ人であれ、今や、影なしに実体における恵みを受けられる時代となった。それなのに、盲目な偽使徒どもは「諸々の儀式律法を遵守することが我々の救いのためには必要である。」などと言って人々を惑わしていたのであって、ガラテヤ人もこの連中に翻弄されてしまったがゆえに儀式的律法、すなわち諸々の宗教的規定を救いのために守るようになってしまっていたのである。
我々も、毎週日曜日は仕事を休んだり、クリスマスおよびイースターなどの祭日を祝ったりしているが、このようなものは、ガラテヤ人たちが非難されているような類いのものではない。これらのものは、救いのためにではなく、習慣的・規律的なものとして守っているに過ぎないからである。しかし、主の日であれクリスマス行事であれ、これらの日をガラテヤ人のように救われるために必要な行ないとして守るようであれば、我々も、ガラテヤ人のごとく責められるべき行為義認の徒になってしまうであろう。
そしてパウロは11節目で、未だに旧約時代でもあるかのように律法の儀式に拘泥していたガラテヤ人たちに対して溜息を漏らしている。
④『あなたがたのために私の労したことは、むだだったのではないか、と私はあなたがたのことを案じています。』(4章11節)
ここでは、ガラテヤ人のあまりの霊的悲惨さに対するパウロの嘆きと憂慮とが明らかにされている。自分(※パウロ)の主にある労苦によって多くの人たちが救われたのに、その人たちが真理から甚だしく遠ざかってしまった。せっかく沢山の家を建てたのにも関わらずそれらのものが一挙に倒壊してしまったとしたらほとんど全ての人は嘆くと思うが、それと同じようにパウロも、せっかく神の言葉によって建設されたのにも関わらず霊的に倒壊してしまったガラテヤ人たちに対して嘆かざるを得なかった。
しかしながら、パウロは自分の憂慮の念を怒りの言葉をもって発散させようとはしていない。彼はここで愚かなガラテヤ人に対して「まったくふざけた不敬虔な者たちだ、異端に陥ったりして。あなたがたはそんなに地獄に行きたいのか?」などと怒りに満ちた攻撃的な調子にはならず、むしろ『私はあなたがたのことを案じています。』と穏やかに言っている。『(愛は)怒らず』(Ⅰコリント13章5節)と書いてあるが、パウロはガラテヤ人たちを愛していたからこそ、彼らの不敬虔に対する怒りを抑制させているわけである。また、ここまでガラテヤ人たちを厳しく責めすぎてしまったのではないかと心配したがゆえにパウロはここで優しい調子になっている、などとルターは言っているが、そのように考えるのも一つの解釈であろう。
そして12節目で、パウロはガラテヤ人に対して懇願の言葉を発している。
⑤『お願いです。兄弟たち。私のようになってください。私もあなたがたのようになったのですから。あなたがたは私に何一つ悪いことをしていません。』(4章12節)
パウロは『兄弟たち』と呼びかけるが、これは愛に基づいている。すなわち、ここまで厳しい指摘と批判をしてきたのでガラテヤ人たちが「もしパウロの言うように俺たちがそんなにも愚かであれば俺たちは本当に神の民なのだろうか…」などと思って自分のことを神の民ではないと認識してしまうのを恐れたために、パウロはここで『兄弟たち』と言って彼らが神の民であるという認識から遠ざからないようにしているわけである。
この12節目では言説における調子が急に変わっている。以前も話したが、パウロはこの手紙において実に多種多様な調子、論法、話題、言い方を駆使しつつガラテヤ人らを真理に引き戻そうとしている。「神の真理にガラテヤ人を復帰させる」という聖なる目的のために多角的な説得を行なっているパウロとこの手紙に驚かされるばかりである。
それで、この箇所でパウロはガラテヤ人たちに自分のようになってほしいと願っているのだが、この箇所を読んで聖書のあの箇所を思い浮かべるクリスチャンの方は多いかもしれない。すなわち、Ⅰコリント9:19~22の箇所である。ここでパウロは『すべての人に、すべてのものとなりました。それは、何とかして、幾人かでも救うためです。』(22節)と言っている。我々が今見ているこの箇所の文脈から考えるならば、パウロはガラテヤ人たちに伝道した際、ガラテヤ人たちの救いのために彼らに自分自身を合わせたのであろう。このパウロがガラテヤ人の救いのために自分をガラテヤ人に対して従順にさせ奴隷のごとき者となったのだから、それに報いてガラテヤ人たちもパウロおよびパウロが伝えた真理に対して奴隷のように従順になってほしい、とここでは言われている。このパウロは、誰かが何かを行なったのであればその行ないに対する返礼を受ける権利がその人にはある、ということをよく弁えていた人物であった。それゆえ、パウロはここで「ガラテヤ人に対して従順になった」というその行ないのゆえに、「ガラテヤ人もパウロに対して従順になる」という行ないを報いとしてガラテヤ人に求めているのである。しかし、言うまでもなく、パウロがここで自分がしたようにされたく願っているのは、ただ単にそのような応対を自分が受けたいからというのではなく、ガラテヤ人たちがそうすることによって真理に立ち返れるように導くためであった。
『あなたがたは私に何一つ悪いことをしていません。』とあるが、これは一体どういう意味なのか。パウロがこの文章によって伝えたいのはつまり、こういうことである。「私パウロがあなたがたを批判したり罵倒したり叱責したりしているのは、あなたがたが私に対して悪い行ないをしたからではない。この点について誤解しないでほしい。私がこのように強烈な言説をなしているのは、あなたがたが敵の罠に陥ってしまったからに他ならない。」パウロはこのように自分の行ないの原因をガラテヤ人たちに結びつけることにより、彼らが己の過ちにしっかりと心を向けるように計らっているのである。
⑥至上の真理なる福音と救いについての懇願
パウロは実に熱心になってガラテヤ人らを福音の真理に引き戻すべく説得しているが、この福音とは何よりも価値あるものである。この福音は、もろもろの財産、名誉、良きものに遥かに勝っていると我々は考える。それは、たとえ自分のすべての所有物を犠牲にしたとしても己のものとすべき聖なるものである。何故なら、この福音が述べているキリストの御救いを受けないのであれば、その人は燃えさかる地獄の中に放り込まれてしまうからである。もしキリストによる罪の赦しを受けて地獄を避けられるのであれば、あらゆる所有物が無くなってしまうことなど何であろうか。もちろん所有物を全部放棄したからといってキリストを信じないのであれば地獄を回避することはできない。しかし、私が今述べたこのことから、福音とはたとえ全ての財物を失ったとしても信じるべき至上の真理であるということがお分かりいただけるのではないだろうか。それゆえ、この輝かしいキリストの贖罪における真理をすべての民族が受け入れるようになってほしいと願う我々教会勢力は、使徒パウロと共にこのように未信者の方々に願うのである。『私たちは、キリストに代わって、あなたがたに願います。神の和解を受け入れなさい。神は、罪を知らない方を、私たちの代わりに罪とされました。それは、私たちが、この方にあって、神の義となるためです。』(Ⅱコリント5章21節)赦しと憐れみに満ちておられる神が、多くの人びとを贖い主なるイエス・キリストに対する信仰のゆえに義と認め、御自身と和解させて下さるよう切に願うものである。そして、これからも日に日に信者の数が増やされ、キリストの聖なる陣営が地の上に満ち拡がっていくよう神が働きかけて下さいますように。アーメン。
ガラテヤ人への手紙4章13~18節(2016/04/17説教)
『ご承知のとおり、私が最初あなたがたに福音を伝えたのは、私の肉体が弱かったためでした。そして私の肉体には、あなたがたにとって試練となるものがあったのに、あなたがたは軽蔑したり、きらったりしないで、かえって神の御使いのように、またキリスト・イエスご自身であるかのように、私を迎えてくれました。それなのに、あなたがたのあの喜びは、今どこにあるのですか。私はあなたがたのためにあかししますが、あなたがたは、もしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか。それでは、私は、あなたがたに真理を語ったために、あなたがたの敵になったのでしょうか。あなたがたに対するあの人々の熱心は正しいものではありません。彼らはあなたがたを自分たちに熱心にならせようとして、あなたがたを福音の恵みから締め出そうとしているのです。良いことで熱心に慕われるのは、いつであっても良いものです。それは私があなたがたといっしょにいるときだけではありません。』(ガラテヤ4章13~18節)
無知・勉強不足である場合は別として、聖書の箇所で分からない事柄について「分からない。」とはっきり言うのは、正しい教職者を見分ける一つの印である。例えば、キリストの聖なる復活について、「確かにキリストは蘇られたのだが、一体どのようにして復活されたのかという、その場景については不明であり、述べることはできない。」と言う教師はまともである。何故なら、キリストの復活の場面における詳細は聖書の中で具体的に書かれておらず、それゆえ我々には不明だからである。不明な事柄であるにも関わらず何でも分かるかのようにあれやこれやと論じるのであれば、それは僭越のなせる業である。だから、どうしても分からない事柄について『分からない。』と教師たちが言っていたとしても、我々は「駄目な教師だな。」とか「牧師ならば調べたり考えたりすべきではないのだろうか。」などと思うべきではない。
①『ご承知のとおり、私が最初あなたがたに福音を伝えたのは、私の肉体が弱かったためでした。』(4章13節)
パウロは、ガラテヤ人たちに福音を宣べ伝えた際のことについて言及し始める。
ここではパウロの肉体が弱かったためにガラテヤ人らに福音が宣教された、と言われているが、これは一体どういう意味なのか。このパウロは、ユダヤ人には福音のゆえに反発され、兄弟たちには本当に使徒であるのか疑われ、敬虔に歩んでいたために多くの迫害を受けた(※①参照)。それゆえ、パウロは外面的・肉体的・人間的には「悲惨」であると言うべき弱い人物であった。しかしパウロが肉的な意味において弱かったからこそ、神とその力が彼に対して豊かに働きかけて下さったのであり、霊に燃えて福音伝道の働きに邁進することができたのである。このことについては、パウロ自身が他の手紙の中でこのように言っている。『しかし、主は、「わたしの恵みは、あなたに十分である。というのは、わたしの力は、弱さのうちに完全に現われるからである。」と言われたのです。ですから、私は、キリストの力が私をおおうために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから、私は、キリストのために、弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら、私が弱いときにこそ、私は強いからです。』(Ⅱコリント12章9~10節)人間の性質は、肉において苦痛を味わえば味わうほど、霊の事柄に対して心が向けられるように造られている。これはクリスチャンだけでなく、ノンクリスチャンにも言えることである。例えば、ノンクリスチャンでも悲惨の極みに至った時には、普段は神など呼び求めたりしないにも関わらず、「神さま。もしおられるのであればどうかこの私を助けてください。」などと言ったりするものである。
次にこう言われている。
②『そして私の肉体には、あなたがたにとって試練となるものがあったのに、』(4章14節)
ここで言われているパウロの肉体にあった試練となるもの、とは一体なんなのか。ヒエロニムスや教皇派の連中などは、この試練とは『性欲』を指していると考えていた。しかしこの理解はいかがなものだろうか。ガラテヤ人たちがパウロの性欲に躓いた、というのは考えにくいように私には思われる。それではこの試練とは一体なにを言っているかといえば、パウロの肉体における全体的または部分的な醜さ、または特異な身体的特徴、などといったものが考えられる。しかし、明確なことは何も書かれていないのだから、この試練という言葉が具体的に何を指しているのか我々には不明である。
しかしながら、ガラテヤ人らは、自分たちにとって試練となるものを己の身に纏わせているこのパウロを喜びをもって歓迎してくれた。こうパウロは言っている。
③『あなたがたは軽蔑したり、きらったりしないで、かえって神の御使いのように、またキリスト・イエスご自身であるかのように、私を迎えてくれました。』(4章14節)
愛とは『すべてをがまんし』、『すべてを耐え忍びます』(Ⅰコリント13章7節)と定義されているが、もし人に愛があるならば、その愛のゆえに誰かの不快感・マイナス面がベールのように覆われ、掻き消されてしまう。酷い疾患のために耐えられないような悪臭を放っている病人に対し、医者であれ身内の人であれ、多くの人たちが嫌悪感や不快の念を率直に言い表わしたりしないのは、その病人に対する愛のゆえである。その病人をどうでもいいと考えている人は、愛の欠如のゆえに侮辱的な言葉を吐いて、その病人から遠くに立ち去っていくだろう。ガラテヤ人たちもその兄弟愛のゆえに、パウロの肉体にあった試練について嫌悪の念をあらわにしなかった。それどころか、彼らはこのパウロを快く迎え入れてくれた。パウロはそのような愛に基づくガラテヤ人の応対・態度をここで褒めている。
この箇所を読んで、「人に過ぎない存在に対してキリストや天使でもあるかのごとく聖なる天的な存在としての認識を抱いてもよいものだろうか。」などと思われる方もいるかもしれない。パウロは、自分のことをキリストや天使でもあるかのように歓迎してくれたガラテヤ人たちの応対をこの箇所で何も否定していない。だから、パウロであれペテロであれルターであれ他の教師たちであれ、神の働き人を天上的な存在でもあるかのように尊重したりする人がいたとしても、我々はその人を非難すべきではない。しかし、神の器であるその教職者を天上的人物であるかのように尊重するあまり、コルネリオがペテロを拝んでしまったように偶像視してしまうのであれば(※②参照)、それは行き過ぎである。我々に許されているのはその教師を「キリストや天使でもあるかのように尊重する」という段階までであって、「神でもあるかのように崇拝する」という段階にまで進んでしまってはならない。
たとえパウロのように躓きをもたらす点が見られたとしても教職者たちは彼らを派遣してくださったキリストのゆえに敬意の念を持たれるべきであるということを、我々は学ぶべきであろう。異端的信仰を持っているのでもなく、怠惰な生活をしているのでもないのに、情熱をもって教職者としての働きをなしている者たちを敬わないのであれば、それは悪を行なうことである。パウロは、確かに真面目な教師たちには敬意をもつようにと命じている。『よく指導の任に当たっている長老は、二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。みことばと教えのためにほねおっている長老は特にそうです。聖書に「穀物をこなしている牛に、くつこを掛けてはいけない。」また、「働き手が報酬を受けることは当然である。」と言われているからです。』(Ⅰテモテ5章17~18節)私は、自分が敬われたいからというので教師たちが敬意を持たれるべきであると言っているのではない。正直にいえば、私などが敬われるのは、私としては身に過ぎるように感じられてしまう。しかし、聖書が教職者たちは敬われるべき存在であると述べているがゆえ、このように私は率直に言うのである。アダム・スミスが教会の教職者たちにとって名誉は報酬であると言っていたが、これは的を射た理解である。パウロは先に挙げた聖句の中で『働き手が報酬を受けることは当然である。』という御言葉のゆえに真面目な教師らは敬意を受けるべきであると言っていたが、これはつまり、忠実な教職者たちにとって名誉や敬意といったものはその職務における報いであるということに他ならないのである。
④『それなのに、あなたがたのあの喜びは、今どこにあるのですか。私はあなたがたのためにあかししますが、あなたがたは、もしできれば自分の目をえぐり出して私に与えたいとさえ思ったではありませんか。』(4章15節)
ガラテヤ人たちのパウロに対する当初の喜び、愛、敬意といった良い感情は、自分たちの目をパウロに上げたいとさえ願わせる程のものであった。古代の哲学者たちは目、つまり視覚を身体における最高の感覚であると考えていたが、程度の差はあれ、この目という器官を重要であり大切であると思わない人などほとんどいないであろう。ガラテヤ人はそのような大事なものをパウロのためになら犠牲にしてもよいと考えていたのだから、彼らのパウロの対する感情は非常に幸いなものであったことが分かる。
しかし、ガラテヤ人のそのような感情は今やどこかに行ってしまっていた。それは、偽使徒どもの奸詐によって、ガラテヤ人らがパウロとパウロが伝えた福音を疑わしいものとして認識するようになっていたからである。だから、パウロがここで『あなたがたのあの喜びは、今どこにあるのですか。』と嘆きつつ言うのは、無理もないことである。ガラテヤ人たちは今やパウロとその福音よりも偽使徒とその異端のほうに己の精神を傾けていたのであって、パウロからすれば自分の主にある労苦によってクリスチャンとなった人たちが横取りされてしまったようなものであるから。
⑤『それでは、私は、あなたがたに真理を語ったために、あなたがたの敵になったのでしょうか。』(4章16節)
もし真理を告げるのであれば、敵対されたり、反発されてしまうのは何も珍しいことではない。キリストや使徒たちがそうだったし、ルターなど宗教改革者らも正しい教理のゆえに異端的存在とされてしまったし、我々もポストミレニアリズムを語ったために反発され悪口を言われたのである(※我々は何かおかしなことを言ったから悪口を言われたというのではない。そうではなく、数々の聖書的な指摘によってプレミレニアリズムの誤謬を突いたからこそ大いに反発されたのである)。つまり、多くの人たちは、真理を告げる者たちを有罪とし、その真理を聞いて反発してしまう自分たちを無罪とするのである。しかし、言うまでもなく、無罪なのは真理を語るほうの人たちであり、有罪なのは真理に対して反発するほうの人たちである。このガラテヤ人たちも、パウロとパウロが知らせた真理に反発するに至ってしまった。
17節目では、偽使徒と彼らの奸詐のことについて言われている。
⑥『あなたがたに対するあの人々の熱心は正しいものではありません。彼らはあなたがたを自分たちに熱心にならせようとして、あなたがたを福音の恵みから締め出そうとしているのです。』(4章17節)
パウロは偽使徒どものことを『あの人々』などと呼んでおり、実名を出そうとはしていない。この手紙におけるパウロの偽使徒に対する認識は完全に一貫しており、パウロは、御国を破壊しようとする彼らに対して激しい敵意と嫌悪の念をもっていたようである。そうでなければ彼らに対して、『その者はのろわれるべきです』(1章8節)とか『いっそのこと不具になってしまうほうがよい』(5章12節)などとは言わなかったであろう。だから、ここで彼らの実名を書いていないのは、「彼らの名は口にするのも書いたりすることさえ嫌だ。」というような彼らに対する憎悪の精神に基づくものであると私には思われる。
この忌まわしい連中がしていた愚行とはガラテヤ人たちを『福音の恵みから締め出そうとしている』というものであった。つまり、この偽使徒どもはサタンの望みが実現するような行ないをしていたのである(もちろん、彼らは自分たちがサタンの願いを叶えようとしているなどとは塵ほども思っていなかっただろうが)。正しい信仰者たちを聖なる福音から引き離そうとするのは、明らかに神およびキリストの御霊によるものではなく、サタンおよび忌まわしい悪霊どもによる働きである。ガラテヤ人たちは、サタンと悪霊どもが喜ぶようなことをしていたこの偽使徒どもに騙されてしまっていた。それゆえパウロは、自分の使徒としての職務にふさわしくこのような手紙を書き、ガラテヤ人らを邪悪な連中から引き離し、守ろうとしたのである。
偽使徒どもがガラテヤ人たちに邪悪な誘惑を仕掛けていたのは、野心に基づくものであった。ある人も言うように、野心であれ何であれ、不義とは異端・誤謬の母である。偽使徒はガラテヤ人たちを『自分たちに熱心にならせよう』という欲望をその心に持っていたからこそ、正しい教師であるパウロと聖なる福音からガラテヤ人たちを引き離そうとしたわけである。何故なら、もし自分たちの愚かな教説にガラテヤ人らを引き込むことが出来たならば、偽使徒たちはガラテヤ人にとって尊重されるべき者・重要である者となれるからである。また、パウロは勘違いをしていた偽使徒たちが熱心だったと言っているが、彼らの知識なしの熱心がここでは非難されている。『熱心だけで知識のないのはよくない。急ぎ足の者はつまずく。』(箴言19章2節)とソロモンの書に記されているが、これは偽使徒どもについて言われているかのような聖句である。もし偽使徒のように勢いだけあっても正しい理解や知識がないのであれば、その人は異端の闇と野心の欲という罠にみずから掛かってしまうことになりかねない。偽使徒のごとく戯(たわ)けた理解と愚行とに陥らないよう我々は思慮をもちつつ注意すべきであろう。
⑦『良いことで熱心に慕われるのは、いつであっても良いものです。それは私があなたがたといっしょにいるときだけではありません。』(4章18節)
17節目でパウロは偽使徒どもの悪しき熱心を批判したが、だからといって熱心という性質自体までも否定しているのではないということを分からせるために、彼はここで短く書いている。言うまでもなく、良いことであれば熱心になったり熱心に慕われたりするのは問題ではないが、悪いことであれば熱心になったり熱心に慕われたりするのは大いに問題である。つまり、熱心というものはその関わっている事柄に応じて、善し悪しが判断されるべきである。例えばボランティアに熱心になっている人の熱心は称賛されるべきであるし、不正行為に熱心になっている人の熱心は非難されるべきである。この箇所は、パウロが偽使徒どもの熱心を批判したからというので彼が熱心という性質すらも批判していると見られないために書かれたものであり、このようなことは言わなくても分かるようなことであるが、パウロは鈍く愚かなガラテヤ人たちが勘違いをしないようにと、ここで注意深く書いているのである。
⑧福音とサタンの働きについて
福音のあるところには、我々の敵であるサタンが働く。それは、福音を伝える者たちであれ、福音を聞く者たちであれ、福音を信じている我々であれ、例外はない。ガラテヤ人たちも福音を信じてのち、サタンの心を行なう敵ども(すなわち偽使徒ども)に惑わされてしまった。どうしてサタンが福音のあるところに働くかといえば、彼は、福音の伝播・弟子の増加・御国の拡大などといった聖なる現象を忌み嫌っているからである。我々が忌まわしい異端と異端者どもを攻撃するように、サタンも自分の嫌悪しているものに対して攻撃を加える。しかし敵どもが悪しき妨害をするなどして働こうとも、我々は福音が地に満ち拡がり、主の弟子が日に日に増加し、御国が大いに進展するようになるのをあくまでも願い求めねばならない。さて、聖書では『主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われます。』(使徒の働き16章31節)と言われているが、未信者の方がたには、我々の罪のために十字架の上で犠牲となられた主イエス・キリストを信じて救われるようになってほしいものである。このように言われるとサタンとその悪霊どもが未信者の方がたに信仰を持たせないように悪しき思いを入れてくるかもしれないが、もし信じないのであれば聖書も言っているように、自分の罪のために地獄の中で永遠の苦しみを味わうことなってしまうであろう。
※①
『何というひどい迫害に私は耐えて来たことでしょう。しかし、主はいっさいのことから私を救い出してくださいました。確かに、キリスト・イエスにあって敬虔に生きようと願う者はみな、迫害を受けます。』(Ⅱテモテ3章11~12節)
[本文に戻る]
※②
『ペテロが着くと、コルネリオは出迎えて、彼の足もとにひれ伏して拝んだ。』(使徒の働き10章25節)
[本文に戻る]
ガラテヤ人への手紙4章19~21節(2016/04/24説教)
『私の子どもたちよ。あなたがたのうちにキリストが形造られるまで、私は再びあなたがたのために産みの苦しみをしています。それで、今あなたがたといっしょにいることができたら、そしてこんな語調でなく話せたらと思います。あなたがたのことをどうしたらよいかと困っているのです。律法の下にいたいと思う人たちは、私に答えてください。あなたがたは律法の言うことを聞かないのですか。』(ガラテヤ4章19~21節)
この手紙におけるパウロのガラテヤ人に対する認識は一貫しており、それは「仲間」という認識である。一方、偽使徒たちに対しては「部外者」また「敵対者」という認識が貫かれている。パウロが偽使徒に対して厳しくなるのは当然だが(何故なら彼らは呪われるべき敵どもだからである)、ガラテヤ人に対して厳しくなっているからといって、このガラテヤ人がパウロにとって敵であるというわけではない。つまり、パウロは、偽使徒どもには敵であるからこそ厳しくなっているのであり、ガラテヤ人に対しては彼らが味方であるからこそ真理に引き戻そうとして厳しくなっている、ということである。
先週の箇所は13~18節目だったが、パウロが最初ガラテヤ人に福音を伝えた時のこと、ガラテヤ人のパウロに対する良い対応、偽使徒どもの野心のことなどについて話された。本日は19~21節目の箇所である。パウロは引き続き、様々な言い方や表現方法を用いつつガラテヤ人らを説得しようとしている。
①『私の子どもたちよ。あなたがたのうちにキリストが形造られるまで、私は再びあなたがたのために産みの苦しみをしています。』(4章19節)
パウロは、ガラテヤ人のためなら何でも行うし、どのような表現方法も使う。ここの箇所では、パウロが母親に、ガラテヤ人が子どもに例えられている。ソロモンもパウロと同じように読者のことを「子どもたちよ」と呼んでいる(箴言1:8、2:1、3:1、4:1など)。ソロモンの場合は、著者である自分があたかも子どもを訓戒する親でもあるかのように教えているので、読者に対して「子どもたちよ」と書かれている。パウロの場合、神がパウロの伝えた福音により、キリストにあってガラテヤ人たちを聖徒として生まれさせたがゆえに、『私の子どもたちよ。』と言っている。コリント人たちもガラテヤ人と同じで、パウロが語った福音を聞いたことにより、キリスト・イエスにあって神の民として新生するに至った。だから、コリント人たちもパウロにとっては子どものような存在である。パウロはコリント人に対してこう言っている。『たといあなたがたに、キリストにある養育係が一万人あろうとも、父は多くあるはずがありません。この私が福音によって、キリスト・イエスにあって、あなたがたを生んだのです。』(Ⅰコリント4章15節)例えば、Aさんという未信者の方がある教職者の説教を聞いてキリストによって救われたのであれば、このAさんにとってその教職者は親のような存在であり、その教職者にとってAさんは子どものような存在であると言えよう。もちろん、これは霊的・信仰的・現象的な意味においてそうなのであって、肉的・物理的な意味において親子関係が生じたというのではない。使徒ヨハネも読者のことを多くの箇所で『子どもたち』(Ⅰヨハネ2:1、3:7、5:21、Ⅲヨハネ4など)と呼んでいるが、これも肉的な意味においてではなく霊的な意味において言われているものである。
『あなたがたのうちにキリストが形造られるまで』と言われているが、これは、ガラテヤ人らがキリストの救いについての確固たる認識を抱けるようになる、ということである。ガラテヤ人たちはキリストとその救いを知る知識において、まだ全き大人の状態とはなっていなかった。だからこそ、彼らはゆらゆらと動く海でもあるかのように、異端的教理のほうに流れていってしまったのである。我々はこのガラテヤ人の過ちから、「救いについて誤らないためにはキリストの救いに関する聖書的教理を十全に理解する必要がある。」ということを弁え知るべきであろう。
パウロはガラテヤ人たちがキリストの救いについて堅固な理解を持てるようにと奮闘していたが、彼はこの奮闘のことを、出産と出産における苦しみに例えている。女性における産みの苦しみは凄まじいものなのであろうが、出産しない男たちにとって、その苦しみがどれほどのものなのか理解しにくいものである。この苦痛について、ある女性は「大型トラックに何度も突撃されたかのような激痛」と言い、別の女性は「ひどい便秘の時に感じる激しい腹痛のよう」などと語っている。他にも、あまり痛みを感じなかった、苦しくても平気だった、何度も出産しているので苦痛に慣れてしまった、などと色々な所感が述べられるものだが、やはり「大変だった。」と言っている女性が多いように思える。旧約聖書でもこの産みの苦しみについて語られている箇所は多いが(※①参照)、出産とは大変なものであるのだと感じさせられる。それで、パウロがガラテヤ人のうちにキリストについての正しい認識を形成させるために努力しているのは、女性が子どもを産むかのように苦しく、様々な不安や悩みを生じさせるものであった。というのは、まだ信仰的に成人となっていない羊たちにキリストについての正しい理解を得させる際には、妊婦が自分の身体を気づかうように細心の注意を払わねばならないし、女性が出産の際に色々と思いわずらったりするかのように心配したり悩まねばならず、多大な労苦と苦痛とが生じるものだからである。だからパウロがこの仕事のことを『産みの苦しみ』になぞらえているのは、もっともである。また、ガラテヤ人のような羊であれば、堅固な信仰を持たせるために生じる教職者らの苦しみはいっそう増加する。何故なら、ガラテヤ人のように鈍ければ鈍いほど、それだけ正しい信仰理解を持たせるためには困難や苦痛などが生じてしまうものだからである。
(2016/05/01追加)ところで、パウロはガラテヤ人のために『再び』産みの苦しみをしていると言っているのだから、この手紙を彼らに送る以前にも、ガラテヤ人のために産みの苦しみをした時があるということが分かる。その時とは一体いつなのか。「パウロが最初ガラテヤ人たちに福音を伝えた時である。」と理解するのが自然な解釈であろう。このように、ガラテヤ人は自分を産んでくれた親であるパウロに『再び』産みの苦しみを経験させるような子たちであったのだから、パウロが彼らに対して『ああ、愚かなガラテヤ人。』(3章1節)などと責めているのは当然のことであったと言えよう。
次の節でパウロは、自分の心の思いを打ち明けている。
②『それで、今あなたがたといっしょにいることができたら、そしてこんな語調でなく話せたらと思います。』(4章20節)
ガラテヤ人と実際に会って話がしたい、という思いがパウロの心にはあった。しかしこの手紙を書いている当時はまだガラテヤ人と対面しつつ語り合うことは出来ないでいた。それゆえ、パウロは「実際にガラテヤ人と面会して話し合えたらいいのに…」とここで告白しているのである。手紙であれメールであれ、たとえ文書であっても何かを伝えることが出来るのだが、やはり、生の声を通して語ったほうが益が大きいように思われる。このことについては、イソクラテスが、ディオニシオスというシラクサの僭主(前430頃―前367)に対して次のように述べている。「さて、建策を試みるにあたっては、書かれた文字を通してでなく、じかに対面して言葉をかわすほうがはるかにまさることを私は承知しております。それも同じ主題についてなら、面と向かって述べるほうが、書簡で説明するよりも簡単だからというだけではありません。また誰もが、書かれたものよりは実際に語られる言葉のほうを信用し、後者は提案として聞くけれども、前者はこしらえものだとして本気で相手にはしないというだけでもありません。それだけでなく、直接に話をかわせば、発言の中でわからないことや信じがたいことが出てきても、その話の語り手が居合わせて、いずれの場合にも助けになるのに対して、手紙に書かれたものは、そのようなことが起こった場合に、正してくれる者がいないからです。著者がその場にいないので、孤立無援の状態に置かれるのです。」(※②参照)おそらくパウロの心にも、このような思念がいくらかでもあったのだと考えられる。
次にパウロはこう言っている。
③『あなたがたのことをどうしたらよいかと困っているのです。』(4章20節)
ここで『困っている』とあるが、これは、異端に陥ったガラテヤ人らをどのように裁くべきか、またいかに断罪すべきか、という意味において『困っている』と言われているのではない。そうではなく、これは「どうしたらガラテヤ人らを正しい道に引き戻せるだろうか…」という意味における困惑である。パウロのガラテヤ人に関する悩み・嘆きはどれだけ大きいものだっただろうか。コリント人の肉に基づく不敬虔も凄まじかったが、ガラテヤ人の過ちは、神を見捨て、キリストから離れ、真理を裏切るという致命的なものであったから、コリント人とガラテヤ人はどちらの方が酷かったか、と聞かれるならば、「ガラテヤ人の方である。」という答えになるだろう。それゆえ、パウロのガラテヤ人に関する困惑の大きさは、パウロと同じ境遇を経験したことのない我々にとっては推測し難いほど大きいものであったと言えよう。
愚かな教説に陥ってしまっていたガラテヤ人に困惑していたパウロだが、ここでは『困っている』と言うだけにとどめ、厳しい調子で裁いたり責めたりしていない。パウロはこの手紙の1:6の箇所でもガラテヤ人に対して『驚いています。』と言うだけで、彼らに対する憤りや不快の念をむき出しにしなかった。我々がここから学ぶべきことは、訓戒・説得などの際には、厳しさだけではなく柔和さも必要だということである。何故なら、もし峻厳な態度ばかりがずっと続くのであれば、聞いている人たちの精神が疲れ果てたり反発してしまいかねないからである。逆に、柔和さだけあって厳しさが何もないというのも避けねばならない。もし優しさだけしかないのであれば、聞いている人たちの精神が刺激されず、改悛へとその心が動かされにくくなるからである。
次は21節目である。
12節目の箇所と同じように、ここでも急に話の調子が変わっている。ルターは、20節目で一度終了させようと思ったのだが話すべきことを急に思いついたのでパウロは再び書き始めたのだ、などと述べており(※③参照)、これも一つの解釈ではあるが、実際はどうだったのか定かなことは分からない。
④『律法の下にいたいと思う人たちは、私に答えてください。』(4章21節)
今度はパウロは、聖書に基づく尋問をし始める。これはあたかも次のように言っているかのようである。「ガラテヤ人諸君、私は聖書の記述に基づいて質問するからどうか答えてほしい。私は聖書の内容をもってあなたがたに聞くのだから、屁理屈をこねたりせず真面目に答えてほしい。もし正しく応答できないようであれば、それはあなたがたが間違った教理に陥ってしまっている証拠である。その場合はどうか、私が伝えた教理―以前あなたがたが信じていたあの教理―に立ち返ってほしい。」
⑤『あなたがたは律法の言うことを聞かないのですか。』(4章21節)
この21節目では『律法』という言葉が2つ出てくるが、初めの方のそれが「モーセ律法および律法が命じる儀式の遵守」を指すのに対し、2番目に書かれている方のそれは「聖書」を指している。新約聖書では、単にモーセ律法を指して「律法」と言われることも、旧約聖書全体を指して「律法」と言われることもある。それで、この箇所で聖書を指して『律法』と言われているということは、文脈を見れば明らかであろう。何故なら、まずこの21節目で『あなたがたは律法の言うことを聞かないのですか。』と言われた後に、『そこ(※つまり律法)には、』(22節)と言って、創世記に書いてあるアブラハムの子どもたちの話が開始されているからである。
⑥多くの方がたが真理を求めますように
ガラテヤ人であれ世の人々であれ、多くの人たちが真理そのものであられるキリスト・イエスから遠ざかってしまっている。これは、多くの人たちが主キリストを求めていないということを示している。パウロが次のように言う通りである。『だれもみな自分自身のことを求めるだけで、キリスト・イエスのことを求めてはいません。』(ピリピ2章21節)しかし誰であれ、もし真剣になって求めるならば、キリストについての正しい聖書的理解が神から与えられるであろう。主が『求めなさい。そうすれば与えられます。』(マタイ7章7節)と言っておられる通りである。確かに心から求めるならば真理が得られるのだが、この日本にいる多くの人たちは求めようとしておらず、求める人たちは今のところ少ししかいない状況である。しかし、神により、多くの方がたが真理なるキリスト・イエスを求めるようになるのを願うものである。我々の罪のために贖いとなられた主イエス・キリストの聖なる福音によってあらゆる民族は弟子とされるのであって、我々は『あらゆる国の人々を弟子としなさい。』(マタイ28章19節)という主の御命令の通り、あくまでも全民族弟子化の実現を求めてゆかねばならない。どうか主が、御国の進展におけるスピードの度合いをますます加速させて下さいますように。アーメン。
※①
例えば以下の聖句がそうであるが、産みの苦しみについて言及されている箇所は他にも多くある。
『彼らはおじ惑い、子を産む女が身もだえするように、苦しみと、ひどい痛みが彼らを襲う。』(イザヤ13章8節)
『それゆえ、私の腰は苦痛で満ちた。女の産みの苦しみのような苦しみが私を捕えた。』(イザヤ21章3節)
[本文に戻る]
※②
『書簡一 ディオニュシオス一世宛』2~3節
京都大学学術出版会:イソクラテス「弁論集2」西洋古典叢書 第Ⅱ期第21回配本 p348~349
[本文に戻る]
※③
パウロはここで手紙を閉じようと思った。これ以上に書こうとは思わず、むしろ、自ら出向いて、ガラテヤ人に語りたいと思った。しかし、この問題で心が不安であるので、彼はここでこの比喩を取り上げる。急に思いついたのである。なぜなら、比喩とかたとえとかは、一般に大きな効果をもつからである。
聖文舎:「ルター著作集」第2集12 ガラテヤ大講解・下p208
[本文に戻る]
ガラテヤ人への手紙4章22~26節(2016/05/01説教)
『そこには、アブラハムにふたりの子があって、ひとりは女奴隷から、ひとりは自由の女から生まれた、と書かれています。女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の女の子は約束によって生まれたのです。このことには比喩があります。この女たちは二つの契約です。一つはシナイ山から出ており、奴隷となる子を産みます。その女はハガルです。このハガルは、アラビヤにあるシナイ山のことで、今のエルサレムに当たります。なぜなら、彼女はその子どもたちとともに奴隷だからです。しかし、上にあるエルサレムは自由であり、私たちの母です。』(ガラテヤ4章22~26節)
『大胆に、少しも妨げられることなく、神の国を宣べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。』(使徒行伝28章31節)とパウロの働きについて、聖書には書かれている。我々が今見ているガラテヤ人への手紙でも、パウロは妨げられることなく真理の言葉を書いている。このパウロという偉大な教師を見れば分かるように、教職者には「大胆さ」が必要である。これを持っていない人は、教職者としての性質が欠如していると言わねばならない。信徒の中には、あまり大胆に語られるのはちょっと…、と思われる方もおられるかもしれない。しかし、真理を伝えるべき教会の教師たちはその職務にふさわしく大胆に語らねばならない、ということをどうか弁えてほしい。神に用いられた教師は、パウロだけでなく、アウグスティヌスもカルヴァンもルターもエドワーズもスポルジョンも、みな大胆に論じる人たちだったのである。
先週の箇所は19~21節目だったが、パウロの奮闘が産みの苦しみになぞらえられていること、彼のガラテヤ人に関する困惑、21節目に書いてある「律法」という言葉の説明などについて語られた。本日は22節目から始まるが、パウロは、ガラテヤ人らを聖書の記述によって説得しようとしている。
彼は『そこには、』とまず言って、アブラハムとその2人の子どもに関する聖書の話をし始める。
①『そこには、アブラハムにふたりの子があって、ひとりは女奴隷から、ひとりは自由の女から生まれた、と書かれています。』(4章22節)
どうしてパウロは、女奴隷ハガルの子イシュマエルおよび自由の女サラの子イサクについて語っているのだろうか。それは、奴隷の子イシュマエルによって肉による民のことを、自由の子イサクによって御霊による民のことをガラテヤ人に説明するためである。つまりパウロはこう言いたいのである。「今も律法の儀式の奴隷となっている肉的な者たちは奴隷の子イシュマエルがそうだったように相続できない者たちである。しかし、律法による義認から自由となっている霊的な者たちは自由の子イサクがそうだったように相続できる者たちである。ガラテヤ人たちよ、あなたがたはイシュマエルのごとき相続不可能な奴隷の子ではなく、イサクのごとき相続可能な自由の子である。」
このイサクとイシュマエルの出生について、23節目でこう言われている。
②『女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の女の子は約束によって生まれたのです。』(4章23節)
女奴隷ハガルは本来アブラハムの妻ではなかったが、サラのゆえに、アブラハムと一つになり彼の子を産むに至った。不妊だったサラが自分の奴隷ハガルの肉体を通してアブラハムとの間に子どもを作ろうして、この女奴隷をアブラハムに妻として与えたのである。サラがアブラハムに対して次のように言った通りである。『ご存じのように、ヤーヴェは私が子どもを産めないようにしておられます。どうぞ、私の女奴隷のところにおはいりください。たぶん彼女によって、私は子どもの母になれるでしょう。』(創世記16章2節)このようにハガルは何の約束も無しに子どもを産んだのだから、彼女が産んだ子イシュマエルは「肉による子」であった。これに対し、サラは肉ではなく、神の霊的な約束のゆえに子どもを産むに至った。すなわち、彼女は高齢のゆえにすでに子どもを産めるような身体では無くなっていたのだが、神が「サラはアブラハムの子を産むであろう。」と約束されたがゆえに、彼女は子どもを産むことが出来た。つまり、サラは神の約束によって子どもを産んだのだから、彼女が産んだ子イサクは「御霊による子」であった。
アブラハムの2人の子どもたちについて話されているこの箇所では、奴隷の子と自由の子という2人の子どもが、明らかに峻別されている。奴隷の子は自由の子ではなく、自由の子は奴隷の子ではない。それで、自由の子イサクはガラテヤ人たちに当てはめられている。『兄弟たちよ。あなたがたはイサクのように約束の子どもです。』(4章28節)とガラテヤ人に対して言われている通りである。これは、ガラテヤ人たちがイサクのように「相続する者」だからである。一方、奴隷の子イシュマエルは偽使徒どもに当てはめられるであろう。何故なら、地獄の子らである偽使徒どもはイシュマエルのように何も相続できないからである。
次の節で、この2人の女たちには比喩があるのだとパウロは言う。
③『このことには比喩があります。』(4章24節)
パウロはこの手紙の4章の初めのところでも、相続人の比喩を使って真理の事柄を説明していた。この比喩というものは、事柄の理解のためには非常に有益なものである。何故なら、この比喩というのは相手のよく知っている物事を借りてきて、それになぞらえて表現するものだから、たとえ難しい事柄であってもすんなり分かるようにさせられるからである。
パウロはこの女たちに比喩を見出しているが、我々は、パウロがここで比喩的解釈をしているからというので、この比喩的解釈を全的に肯定すべきではない。パウロがここで比喩的解釈をしているのは、この女たちの事柄に比喩を見出すことが正しいものだからである。しかし、だからといって、我々は何でもかんでも聖書の箇所を比喩的に解釈しようとすべきではない。この比喩的解釈で有名なのは、ユダヤ人ではフィロン、教父ではオリゲネスやクレメンス(※①参照)などがおり、アウグスティヌスも天地創造の記事を比喩的に解釈しているが、彼らの比喩的聖書理解は訳の分からない異様なものである。この比喩的解釈について否定するのは私だけというのではなく、クリュソストモスやカルヴァンやルターなどの教師らも激しく否定している。それでこの比喩的解釈とは、聖書の記述を字義通りに受け取るのではなく、そこで比喩が語られていると見なすものである。たとえば創世記の天地創造の記事における7日間の出来事であれば、これを世界の創造記事として見るというよりは、むしろその各日がそれぞれ世界の歴史区分を表示している、と理解するのがこの解釈方法である。この比喩的解釈をしている人たちの聖書理解を見ると、彼らがとんでもない理解をしていることに驚くことだろう。それゆえ、我々は、何もかもこの比喩的解釈によって聖書に記されていることを理解しようとすべきではない。
それで、パウロはこの2人の女たちに正しく比喩を見出している。その比喩とは、ハガルが奴隷の者・地上的エルサレム・肉的な契約を示しており、サラが自由の者・天上的エルサレム・霊的な契約を示している、というものである。
④『この女たちは二つの契約です。』(4章24節)
パウロはここで、ハガルが肉的な契約を表わしており、サラが霊的な契約を表わしていると述べている。これは、つまりこういうことである。(1)行ないによって義認が得られるとする肉の契約のうちに留まっている者たちはハガルとその子どものように奴隷であるから何も相続することが出来ない。(2)信仰によって義と認められるという霊の契約に属する者たちはサラとその子どものように自由な身分の者であるから相続することが出来る。つまり、分かりやすく示すと次のようになる。A「ハガル=奴隷の身分=肉的契約=律法による義認に固執すること=相続不可能」B「サラ=自由の身分=霊的契約=信仰による義認に固執すること=相続可能」
この2つの契約について、パウロはまず女奴隷ハガルの方から説明し始める。
⑤『一つはシナイ山から出ており、奴隷となる子を産みます。その女はハガルです。このハガルは、アラビヤにあるシナイ山のことで、今のエルサレムに当たります。なぜなら、彼女はその子どもたちとともに奴隷だからです。』(4章24~25節)
奴隷の女から生まれるのは、必然的に奴隷の子である。奴隷から自由身分の子は生まれない。それは、鶏が鶏を生み、決して人間を生まないのと同じである。それで、未だにモーセ律法の儀式に奴隷でもあるかのように固執していた偽使徒のような者たちは、この女奴隷ハガルを自分の生母とする者たちである。何故なら、このハガルは、儀式の遵守によって義を得ようとする肉的・奴隷的な者たちの根源的存在として例えられているからである。
25節目では『今のエルサレム』と言われているが、これは霊的・天的ではない、肉的・地上的な王国のことである。この王国とは言うまでもなく、女奴隷ハガルとその子どもを指している。愚かな偽使徒どももこの肉的な王国に属する者たちであった。この地上的なエルサレムとは肉的なものであって、これに属する者たちはハガルのように奴隷的な存在であるから、ハガルとその子どもが相続できなかったように、何も相続することが出来ないのである。
⑥『しかし、上にあるエルサレムは自由であり、私たちの母です。』(4章26節)
ここでは『上にあるエルサレム』と言われており、これは25節目に書いてある『今のエルサレム』という言葉と対置されるべきものである。それゆえ、25節目で言われていた『今のエルサレム』とは、すなわち「下にあるエルサレム」ということになる。この2つのエルサレムは完全に対立した概念であって、その性質を互いに異にしている。つまり、「下にあるエルサレム」が肉・地上の国・奴隷・律法義認・相続不可能なハガルの子を表わすのに対して、「上にあるエルサレム」は霊・天上の国・自由・信仰義認・相続可能なサラの子を表わしている。
先に、下にあるエルサレムに属する者たちは女奴隷ハガルを自分の母とする者たちであると述べた。これは偽使徒どものように律法の奴隷となっている者たちの住まう肉的な王国である。しかしこれとは逆に、上にあるエルサレムに属する者たちは自由の女サラを自分の母とする者たちである。これはパウロやガラテヤ人たちのようにキリストによって自由にされた者たちの住まう霊的な王国である。ここにいる我々も、パウロやガラテヤ人たちと同じように霊的王国である上のエルサレムを母とする自由の者であるから、イサクのように神の相続人である。しかし、カトリック教徒やユダヤ教徒などの「行ないによる者たち」は、偽使徒どものように肉的王国である下のエルサレムを母とする奴隷の者である。何故なら、彼らはイシュマエルが奴隷だったように、自分の行ないによって義を獲得できるという異端教理の奴隷となっているからである。それゆえ、イシュマエルのような奴隷の者たちは、その誤った考えを改めないかぎり、神による御国の相続者とはなれないであろう。
⑦人類の2区分とキリストによる救いについて
聖書は、人間には2つの種類があると教えている。まず一つめはパウロやガラテヤ人たちのようにイエス・キリストを信じるクリスチャンであり、二つめはイエス・キリストを信じていないノンクリスチャンである。もしクリスチャンならばその人はノンクリスチャンではなく、もしノンクリスチャンならばその人はクリスチャンではない。クリスチャンでもノンクリスチャンでもない中間的な人物は誰もいないのである。自分のことをノンクリスチャンであると思う人たちは、是非、聖書の言うことに耳を傾けてほしい。この聖書が言うこととは、イエス・キリストが我々の罪のために十字架の上で御自身の命をお捨てになった、ということである。『主イエスは、私たちの罪のために死に渡され(た)』(ローマ4章25節)、また『自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。』(Ⅰペテロ2章24節)などと聖書の中でキリストの死について言われている通りである。もしこのイエス・キリストの贖いを信じるのであれば、その人はイエス・キリストのゆえに罪の赦しを受けて救われ、新しい種類の人へと変えられる。つまり、信じる前はノンクリスチャンという種類の人だったのだが、信じた後はキリストのゆえにクリスチャンという種類の人になるのである。キリストを信じなければ人は地獄に行かねばならないと聖書は教えるが、この地獄での苦しみほど恐ろしいものは他にない。地獄での恐怖を永遠に味わいたいだろうか?嫌だろう。それゆえ未信者の方がたには、自分が地獄に行くべき種類の人では無くなり、罪の赦しを受けた地獄に行かない種類の人に変えられるように望まれるのを、お勧めしたい。もし信仰を持つならば、その人にはイエス・キリストの名による罪の赦しが与えられるであろう。『この方を信じる者はだれでも、その名によって罪の赦しが受けられる』(使徒の働き10章43節)
※①
<150頃―215頃>アレクサンドリアの教父。広いギリシャ的教養を生かし、知識人に向けキリスト教を弁論した。ロゴス―キリストを教育者に見たて、キリスト教の教えを真のグノーシスと主張した。著「ギリシャ人への勧告」「教育者」など。
(スーパー大辞林)
[本文に戻る]
ガラテヤ人への手紙4章27~31節(2016/05/08説教)
『すなわち、こう書いてあります。「喜べ。子を産まない不妊の女よ。声をあげて呼ばわれ。産みの苦しみを知らない女よ。夫に捨てられた女の産む子どもは、夫のある女の産む子どもよりも多い。」兄弟たちよ。あなたがたはイサクのように約束の子どもです。しかし、かつて肉によって生まれた者が、御霊によって生まれた者を迫害したように、今もそのとおりです。しかし、聖書は何と言っていますか。「奴隷の女とその子どもを追い出せ。奴隷の女の子どもは決して自由の女の子どもとともに相続人になってはならない。」こういうわけで、兄弟たちよ。私たちは奴隷の女の子どもではなく、自由の女の子どもです。』(ガラテヤ4章27~31節)
古代においては、今のように黙読の習慣はなく、音読または朗読されたものを聴くのが一般的であった。アウグスティヌスの『告白録』の中では、何か特別な読書方法をしているとでも言わんばかりに黙読をしていたアンブロシウスについて書かれているが、これは、黙読が今のように一般的に行なわれていなかった時代背景があったからである。このガラテヤ人の手紙も、当時の人たちは声に出して読んだり読まれたものを聴いたのであろう。黙読するのが当たり前となっている我々はどうしても黙読をしているガラテヤ人たちの姿をイメージしてしまうかもしれないが、そのようなイメージは正確性に欠けると言わねばならない。
本日は、パウロがガラテヤ人のことを自由の女サラの子イサクのような約束による相続人であると教えている箇所の続きである。このアブラハムの子どもたちについての話がされている箇所は、4章21~31節目までである
本日の最初の箇所では、パウロは『すなわち、こう書いてあります。』と言って、イザヤ書54:1の箇所を引用している。この預言書の聖句は、神御自身が語られたものである。
①『喜べ。子を産まない不妊の女よ。声をあげて呼ばわれ。産みの苦しみを知らない女よ。』(4章27節)
ここでは、出産したことも陣痛を経験したこともない女に対して『喜べ。』と言われている。普通であれば、多産であったり子どもを産んだことのある女に対して『喜べ。』と言われるものだが、この箇所ではそうではない。どうしてここでは不妊の女が歓喜するように命じられているのか。この理由について、27節目の後半部分にはこう書いてある。
②『夫に捨てられた女の産む子どもは、夫のある女の産む子どもよりも多い。』(4章27節)
ここでは、『夫に捨てられた女』がハガルに、『夫のある女』がサラに対応している。サラを母とするイサクのような御霊による者は、信仰的には正しいかもしれないが、その数は決して多くない。他方、ハガルを母とするイシュマエルのような肉による者は、正しい信仰を持っていないが、その数は非常に多い。今の時代でも、絶対に正しい信仰を持っていないと確言できる者たちは66億人もいるのに対し、正しい信仰を持っていると言えるような者たち(すなわちプロテスタント教徒)は4億人しかいない(※もちろん、プロテスタントの中にも正しいとは言えない信仰を持っている者が多くいるだろうが)。つまり、いつの時代も、サラの子イサクのような御霊による者たちの数は少ないが、ハガルの子イシュマエルのような肉による者たちの数は多いのである。当時ガラテヤ人たちは異端的信仰に陥ってしまっていたものの、彼らのようにイサクのごとき者であると言えるような人たちは比率的にいえば決して多数派では無かった。このように、当時ガラテヤ人のような御霊による者たちの数は少なかったのだが、しかし彼らは相続することのできる幸いな種類の人たちであったのだから、そのような幸いな人たちの母とされているサラは、たとえ子沢山ではなかったとしても喜ぶよう、ここで命じられているのである。
③『兄弟たちよ。あなたがたはイサクのように約束の子どもです。』(4章28節)
即ち、ガラテヤ人は律法の儀式に縛られている奴隷のごとき者たちではないのだ、と言われている。何故なら、もしガラテヤ人が約束による者たちであったならば、それは彼らが律法・行ないによる者たちでは無いことを意味しているからである。ところで、ここでもパウロはガラテヤ人たちが神に属する者たちであると述べている。パウロは、以前もガラテヤ人たちが神の民であるということを、この箇所とは違った語り方で伝えていた。このように、ある重要な事柄を、様々な表現・内容をもって多角的に伝えるのは、鈍い者たちに対しては有益な説得手段である。
④『しかし、かつて肉によって生まれた者が、御霊によって生まれた者を迫害したように、今もそのとおりです。』(4章29節)
ここで『肉によって生まれた者』がイシュマエルを、『御霊によって生まれた者』がイサクを指しているのは、もうお分かりであろう。また、前者のほうは偽使徒どものような肉的教義の奴隷となっている非再生者たちを、後者のほうは霊的教義に固く立っているキリストによる再生者たちと対応している。この2つの存在は互いに対立しているのであって、もし前者であれば後者ではなく、もし後者であれば前者ではない。
パウロがここで言うように、イサクのような御霊による子らはイシュマエルのような肉による子らに迫害されてしまう。これは当時もそうであったし、いつの時代でもそうである。例えば、パウロや他の使徒たちは、彼らに反発する肉的な者たちから多くの迫害を受けた。今から500年前には宗教改革者たちが肉的な教えと行ないに満ちていたローマ・カトリック教徒らに迫害された。1572年にフランスで起こったサンバルテルミの虐殺では、カトリック教徒によってプロテスタント教徒が一万人(※死者数には諸説ある)も殺害された。基本的にイサクのような自由の女の子は、イシュマエルのような奴隷の女の子に迫害されるよう定められているのである。どうしてこのように定められているかといえば、御霊による者たちがキリストによって選ばれたキリストの所有の民であり、肉による者たちがキリストによって召されていないキリストに属さない民だからである。つまり、御霊による子たちがキリストに選ばれた神の国民だからというので、―この理由のゆえに―御霊によらない子たちは御霊による子たちに迫害を加えるのである。世が聖徒たちを憎むのは聖徒たちがキリストによって世から選ばれたがゆえである、と主も言っておられる(※①参照)。
それで、この箇所でパウロが言いたいことはつまりこうである。「私パウロであれ誰であれ、御霊によって生まれた者は肉によって生まれた者に迫害されてしまう。それは、かつて肉の子イシュマエルが霊の子イサクを迫害したのと同じである。ガラテヤ人たちよ、偽使徒どもは誹謗中傷するなどして私パウロを迫害しているかもしれないが、彼らに騙されてはならない。私パウロがそのように偽使徒どもから迫害されているのは、彼らがイシュマエルのごとき肉の子らであって、私がイサクのごとき霊の子であるという明白な証拠なのだから。」
ところで、パウロはここでイシュマエルがイサクを迫害したと言っているが、この迫害は一体どのようなものだったのか。これは、新改訳聖書の参照部分で示されているように、創世記のあの箇所に書いてある出来事であろう。そこには次のように書いてある。『そのとき、サラは、エジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子が、自分の子イサクをからかっているのを見た。』(創世記21章9節)ここで不敬虔・不信仰な者たちは、「パウロはからかわれたり笑われたりするのが迫害だと言っているのか。」などと思うかもしれない。このように思う者たちは、迫害というものが、例えば暴行を受けたり石を投げられたり略奪されるなど、小さからぬ災厄のことだけを指すと考えている。だから「ただ侮辱されただけで迫害と言えるのか?」と心に感じるのである。しかし、もし神・真理・霊的事柄などのために痛みを受けるのであれば、たとえ笑われたり馬鹿にされたりするだけだったとしても、その人は迫害を受けていると言えるのである。だから、パウロがからかわれた(または笑われた)イサクのことを念頭に置いて「彼は迫害された。」と言っていたとしても、何も不思議なことはない。
⑤『しかし、聖書は何と言っていますか。「奴隷の女とその子どもを追い出せ。奴隷の女の子どもは決して自由の女の子どもとともに相続人になってはならない。」』(4章30節)
たとえ奴隷の子らの数が非常に多かったとしても、また奴隷の子らが自由の子らを攻撃していたとしても、まったく無益なことである。彼らの状態・言動がどのようなものであったとしても、イシュマエルのように奴隷であれば、容赦なく追い出されてしまうのだ。神は、イシュマエルのような奴隷的存在が、キリストによって自由にされたイサクのごとき者のように相続人となるのを許されない。それゆえ、偽使徒どものような奴隷の子らはずっと御国から追放されたままの状態であって、彼らは永遠に相続不可能な者たちなのである。これはいつの時代でもそうであって、我々が生きている今の時代でも同じことがいえる。すなわち、プロテスタントに属している約束の子らはイサクのように相続できるが、カトリックに属している奴隷の子らはイシュマエルのように相続できない。ユダヤ教徒やイスラム教徒もカトリック教徒と同じく行ないの奴隷となっている者たちであるから、奴隷イシュマエルのように相続不可能である。
心の優しい人はこの箇所を読んで、「イシュマエルも追い出されることなくイサクと一緒に相続できたらいいのに。そうしたら2人とも幸いになれるから。」などと思われるかもしれない。しかし、聖書とそこに書いてある真理は峻厳である。聖書は言う、滅ぼされるべき者たちは憐れみを受けることなく滅ぼされ、追い出されるべき者たちは容赦なく追い出される、と。神の御意志がかならず実現されるべきであれば、そこには峻厳さが見られるはずである。もしそこに何の厳しさも見出されないとすれば、神は御自身の御心を完璧には行えなかったであろう。何故なら、神は御自身の望まれることを為されるため、必然的に物々しいことを行わねばならないからである。それゆえ、神を愛する者たちは、聖書に書いてある神の御心における峻厳さに決して異を唱えたりすべきではない。
ここには『決して』という言葉がある。この言葉によって、イシュマエルがイサクと共に相続してはならないという神の御意志が強調されている。つまり、イシュマエルや彼のような奴隷の者たちは絶対に相続してはならない、彼らが相続するのは絶対に不可能である、ということである。
⑥『こういうわけで、兄弟たちよ。私たちは奴隷の女の子どもではなく、自由の女の子どもです。』(4章31節)
パウロはまたもガラテヤ人たちがサラの子どもであると、ここで強調している。ガラテヤ人たちが自由の者であって奴隷の者ではない、ということはつまり、彼らが律法によって義を得ようとする教えの奴隷であるべきでは無いということを示している。何故なら、律法義認の奴隷となっているのは奴隷女ハガルの子どもだけなのであって、自由の女サラの子はそうではないし、また、そうであってはならないからである。それゆえこの箇所では、自由の子らでありながら異端教理の奴隷になってしまっていたガラテヤ人たちの不敬虔および偽使徒どもが伝えていた奴隷的思想が、暗に否定・非難されていると言えよう。
⑦奴隷と相続人、また選ばれている人たちについて
イシュマエルのような奴隷の者たちは一時的に父の家にいるだけであって、いずれ家から追い出され、彼らが相続することは決してない。彼らがイエス・キリストによって自由の子イサクのようにされていない、つまり奴隷の状態のままだからである。これは、イシュマエルであれユダであれローマ教皇であれ、キリスト・イエスの民でない全ての者たちに言えることである。しかし、キリストによって自由にされたイサクのごとき者たちはずっと父の家にいるのであって、追放されることもなく、彼らは相続することができる。何故なら、彼らが何も相続できない奴隷の者イシュマエルのような者ではなく、相続人イサクのような者だからである。ここにいる我々はかつて奴隷イシュマエルのようであったが、今や相続人イサクのようにされている。つまり我々は、奴隷・イシュマエル・相続できない者から自由の者・イサク・相続人へと変えられたのである。このように変えられたのは、神の憐れみのゆえ、キリスト・イエスによる贖いのゆえであって、我々が何かを行なったからというのではない。もし我々の素晴らしい行ないや生き方などのゆえに奴隷から自由の子へと変えられたなどと勘違いをしている人がいたとすれば、その人はいまだにイシュマエルなのである。選ばれている人たちは、今はイシュマエルのような奴隷的存在(つまり非キリスト者)であったとしても、やがて御子によりイサクのような自由の子(つまりキリスト者)とされるであろう。それは、我々が以前イシュマエルであったのに、今はイサクへと変えられているのと同じである。どうか主が、選ばれている人たちにイエス・キリストによって自由を得させ、彼らを相続できない奴隷の者から相続できる自由の者へと変えて下さいますように。アーメン。
※①
『しかし、あなたがたは世のものではなく、かえってわたしが世からあなたがたを選び出したのです。それで世はあなたがたを憎むのです。』(ヨハネ15章19節)
[本文に戻る]
ガラテヤ人への手紙5章1~3節(2016/05/15説教)
『キリストは、自由を得させるために、私たちを解放してくださいました。ですから、あなたがたは、しっかり立って、またと奴隷のくびきを負わせられないようにしなさい。よく聞いてください。このパウロがあなたがたに言います。もし、あなたがたが割礼を受けるなら、キリストは、あなたがたにとって、何の益もないのです。割礼を受けるすべての人に、私は再びあかしします。その人は律法の全体を行なう義務があります。』(ガラテヤ5章1~3節)
今週から5章目に入る。と言っても、前にも述べたように章と節の区分けは便宜上なされたものに過ぎないから、5章目になったからといって、何か霊的に特別な意味があるということではない。私がこの手紙を読んでいて感じるのは、この手紙は神によって記されたものに他ならない、ということである。兄弟姉妹の方であれば、誰でも、私と同様の思いを心に抱かれるであろう。神の御霊によるのでなければ、どうしてこのような天上的文章が書かれるであろうか。あり得ないことである。
早速1節目から見ていきたい。
①『キリストは、自由を得させるために、私たちを解放してくださいました。』(5章1節)
キリストは御民に対して自由と解放を与えられた、と言われているが、これは一体どういう意味なのだろうか。これはつまり、律法の儀式に縛りつけられている奴隷的状態にあったガラテヤ人たちをキリストが解放して自由にして下さった、ということである。少し前の箇所に書いてあるように、『信仰が現れる以前には、私たちは律法の監督の下に置かれ、閉じ込められて』(3章23節)いたのだが、信仰が現れてからは、この信仰によって律法の監督から自由になれるようになった。すなわち、イエス・キリストに対する信仰のゆえに、律法を遵守しなければ義は得られないという奴隷的観念から解放されるようになった。ここから、キリスト者と非キリスト者について次のように定義できるであろう。すなわち、(1)「キリスト者=キリストへの信仰によって奴隷状態から解放された自由の民」、(2)「非キリスト者=キリストへの信仰を持たない奴隷状態のままでいる肉的な民」という定義である。
この自由・解放は、イエス・キリストの贖いに基づいている。キリストが十字架の上で犠牲となられたからこそ、信じる者たちは、このキリストのゆえに奴隷状態から解放されて自由になれるようになったのである。この自由と解放は、決して人の行ないにはよってはもたらされない。もし自分の良い行ないによってキリストのみが得させてくださる自由を獲得しようとするのであれば、その人は、自分が奴隷的存在であることをますます明らかにするだけである。
②『ですから、あなたがたは、しっかり立って、またと奴隷のくびきを負わせられないようにしなさい。』(5章1節)
パウロはガラテヤ人に対して、せっかく自由の者とされたのだから再び奴隷の状態に戻ってはならない、と忠告する。これは、免許を取得した人に対して「せっかく車に乗れるようになったのだから免許を失効させないように気をつけなさい。」などと言うのによく似ている。何故なら、キリストによって自由にされたガラテヤ人も、免許を取得した人も、どちらも幸いな状態に至ることのできた人であるが、そのような人に対して「前の状態に戻ってはならない。」と言われているからである。幸いな状態に至ったのに前の状態に引き戻されてしまうのは、悲しむべきことである。もっとも、キリストによって自由にされた人と免許を取った人とでは、享受した幸いの度合いが天と地ほども違うのではあるが。
『しっかり立って』とあるが、ガラテヤ人たちが異端という邪悪な石につまずいてよろめいていたからこそ、つまり彼らがしっかり立っていなかったからこそ、パウロはこのように書いている。ガラテヤ人であれ誰であれ、よろめいている哀れな信仰者たちに対して「キリスト・イエスに対する正しい信仰のうちに堅く立ちなさい。」という忠告がなされるのは、至極当然のことである。ここにいる我々一人一人は、もし自分が正統的信仰のうちに立てていると感じるのであれば、ガラテヤ人のように異端的信仰に揺るがされてしまわないように気をつけるべきであろう。どうして気をつけるべきかといえば、自分が正しい信仰に立てているからというので、気をゆるめ安心しきってしまうのであれば、それだけ悪しき神学に惑わされ易くなるからである。我々は、Ⅰコリント10:12におけるパウロの忠告に心を留めるべきであろう。『立っていると思う者は、倒れないように気をつけなさい。』
パウロはガラテヤ人たちをキリストに対する正しい信仰に堅く立たせようとしているが、聖徒たちがしっかりと立てるように計らうのは、教職者たちの重要な任務である。パウロであれ誰であれ教師である者たちは、あたかも親が幼児をしっかりと歩けるようにするごとく、まだ未熟である教えられる者たちがちゃんと立てるようにせねばならない。もし聖徒たちがキリストを信じる信仰に正しく立てていないのであれば、どうして地の塩・世の光として豊かに役立てられることが出来ようか。もし堅く立てていないのであれば、この世にあって輝くどころか満足に歩くことさえ出来ないのであるから、まず教職者たちは聖書的信仰に堅く立てるよう幼い聖徒たちに働きかけるべきなのである。
③『よく聞いてください。このパウロがあなたがたに言います。』(5章2節)
この箇所でパウロはまず『よく聞いてください。』と言って、これから書かれることに注目するように促している。次に『このパウロがあなたがたに言います。』と言われるが、これは、使徒的権威の通告である。つまり、彼はこう言いたいわけである。「キリストの使徒であるこの私パウロがあなたがたに言う。あなたがたはよく弁えなさい、普通の人が語っているのではない。使徒である者が語るのである。だから、あなたがたは書かれている内容をしっかりと読み、よく理解しなければならない。」例えば、「皇帝である私が汝らに告げる。」と言われたら民衆はその語られる内容に耳を傾けるだろうし、「僕が野球について考えていることを言うと…」とイチローが言えば野球に興味のある人たちはその述べられる言葉を侮りはしないであろう。これは、その語っている者に少なからぬ権威が備わっているからである。これと同じように、パウロは自分の使徒的権威を掲げ、読者たちの心を書かれている言葉に集中させようとしているのである。
④『もし、あなたがたが割礼を受けるなら、キリストは、あなたがたにとって、何の益もないのです。』(5章2節)
つまり、<ガラテヤ人たちが割礼を受けるという行ないによって義を得ようとするのであれば、キリスト・イエスは彼らにとってまったく不要になる>ということである。パウロはこの手紙の少し前の箇所でもこう言っていた。『もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。』(2章21節)もし律法の行ないによって義と認められるとすれば、律法の行ないによって義を得られるわけだから、キリストによる義認は必要でないことになってしまう。これはキリスト者にとってあまりにも重要な問題であって、その人がキリスト者であるかそうでないか、ということを左右させるほどのものである。すなわち、律法によって義と認められると信じているのであればその人はキリスト者ではなく、律法ではなくキリストに対する信仰によって義と認められると信じているのであればその人はキリスト者である。ガラテヤ人たちはこの重大な問題において正しい理解を持てておらず、「人が義と認められるためには絶対に割礼を受けねばならない。」という異端信仰こそが正しいのではないか?と考えていた。だからこそ、パウロはここでガラテヤ人に対して『あなたがたが割礼を受けるなら、キリストは、あなたがたにとって、何の益もないのです。』と言い、彼らが惑わされている異端信仰が誤りであってキリスト否定であることに気付かせようとしているわけである。
この箇所におけるパウロの言説は、ガラテヤ人に対する脅迫である。この脅迫とは聖書に反するものではないから、ここでパウロが脅迫的言説をしているからといって、我々は驚くべきではない。神も、ヒゼキヤ王の寿命を増し加えるため、この王に対して脅迫的預言をなされた(イザヤ38章参照)。
パウロがこの箇所で言いたいことは、つまりこうである。「ガラテヤ人たちよ、もし割礼を受けるという行ないによって義を得ようとするのであれば、あなたがたにとってキリストは無意味となってしまう。そんなことで本当にいいのだろうか。嫌だろう。であるならば、救いのためには割礼を受けねばならないなどと教える者たちの考えに騙されるべきではない。そのような考えからあなたがたは離れ去るべきである。」
ところで、パウロはここで「割礼はキリストを無益・無意味にする。」と言っているにも関わらず、テモテに対して割礼を受けさせているが、これは一体どういうことだろうか。『パウロは、このテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前、彼に割礼を受けさせた。』(使徒の働き16章3節)と書かれている。割礼を受けさせられたテモテにとってキリストは何の益も無くなってしまったのであろうか、また、パウロはテモテに対してキリストを否定させるような異端的行為を行なったのであろうか。絶対にそのようなことはない。パウロがテモテに割礼を受けさせたのは、割礼を受けることを当たり前のこととしていたユダヤ人たちを躓かせないためであった。つまり、パウロは『テモテを連れて行きたかった』のであるが、その際、ユダヤ人たちが「パウロは無割礼の者を連れて行ったぞ。一体どういうことなのだ。何を考えているのか分からないが、けしからん奴だ。」などと不信感を抱かないようにするためであった。パウロはユダヤ人たちの救いのためになら『キリストから引き離されて、のろわれた者となることさえ願いたい』(ローマ9章3節)ほどであったから、彼らがキリスト教から心を遠ざけてしまわないよう、テモテに形式的な意味において割礼を受けさせたのである。この場合の割礼はあくまでも外面的・表面的な行ないに過ぎず、救いのために行なわれたものではなかったから、何も問題はなかった。パウロは自分の言葉に反したことをテモテに対して行なったのではない。
次の3節目でも割礼に関することが語られている。
⑤『割礼を受けるすべての人に、私は再びあかしします。』(5章3節)
これは、救いのためには割礼を受けねばならないと考えている全てのガラテヤ人たちに言われているものである。偽使徒たちも割礼による律法義認を信じていたのであるから、この言葉は、(ガラテヤ人だけでなく)偽使徒たちにも言われたものであると考える人がいるかもしれない。何故なら『割礼を受けるすべての人に』と言われているからである。しかし、この手紙の読者はガラテヤの聖徒たちであって、偽使徒たちではない。それゆえ、ここで対象とされているのはガラテヤ人だけであると考えるべきである。
⑥『その人は律法の全体を行なう義務があります。』(5章3節)
もし偽使徒たちのように割礼によって義を得ようとするならば、その人は、割礼だけでなく律法に書いてある諸々のことを実行せねばならない。割礼だけでなく、十戒も、色々な祭儀律法も、何もかも全部である。もし律法によって義と認められたいのであれば割礼だけを行なえばそれで良い、ということは決してない。パウロが言うように、『律法の全体を行なう義務が』ある。もし全ての律法を完全に行なえる人がいたのであれば、その人は、この律法によって義と認められるであろう。しかし、そのような聖人はキリストを除いては一人もいない。全ての律法を行なえないようであれば、律法によって義を得ようとしても、得られるのは「増し加わる呪い」だけである。『律法の書に書いてある、すべてのことを守って実行しなければ、だれでもみな、のろわれる。』(3章10節)と書いてあるから、律法によって義を得ようとしている人たちは、(律法を守れないがゆえに)呪いのもとに留まり続ける以外にはない。だから、ここで割礼によって義を得ようとしている者たちに対して『その人は律法の全体を行なう義務があります』と言われているのは、換言すれば「律法によって義を得ようとする者たちは呪いのもとにおり、永遠の裁きを受けねばならない。」ということである。それゆえ、パウロはこの箇所でも律法による義認の思想を斥けていることになる。
最後になるが、もし律法によって義を得たいのであればその人は律法を完全に行なわねばならない、ということを我々は再認識すべきである。律法はそれ自体としては、もし全てを完璧に守れるのであれば義を得させられるものである。だが、我々の人生には厖大な律法違反が満ちている。キリストを除いては、すべての人が例外なく律法を守れない罪人である。言うまでもなく、我々が犯してしまったこの律法違反という罪に対する刑罰は、本来であれば我々自身が受けねばならない。自身によって悪いことをしたのであるから、自身が処罰を受けるのは至極当然である。しかし、主キリストは、我々が本来であれば受けるべきこの刑罰と多くの罪を、身代わりとして御自身に引き受けてくださった。『まことに、彼は私たちの病を負い、私たちの痛みをになった。だが、私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし、彼は、私たちのそむきの罪のために刺し通され、私たちの咎のために砕かれた。』(イザヤ53章4~5節)と書いてある通りである。このキリストの贖罪ほど我々に対する神の大きな見計らいはなく、キリスト以外には誰も我々の罪を負うことなど出来ない。キリストが罪のために贖いとなられたのにも関わらず、多くの人たちはこの救いを受けいれようとはしない。キリストとその救いを求めず、良い行ないによって自分を清いものにしようとしている人たちの数は少なくない。しかし、これから多くの人たちがイエス・キリストのゆえに律法違反という罪から清められ、義と認められるようになるのを願うものである。聖なる救いを伝える福音が世界中の民族をことごとくキリストの弟子にしていくのを妨げることは誰にも出来ない。どうか、全能の神が福音を速やかに全世界の国々に満たし、キリストの弟子を大いに増やして下さいますように。アーメン。
ガラテヤ人への手紙5章4~7節(2016/05/22説教)
『律法によって義と認められようとしているあなたがたは、キリストから離れ、恵みから落ちてしまったのです。私たちは、信仰により、御霊によって、義をいただく望みを熱心に抱いているのです。キリスト・イエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。あなたがたはよく走っていたのに、だれがあなたがたを妨げて、真理に従わなくさせたのですか。』(ガラテヤ5章4~7節)
先週は5章1~3節目の箇所だったが、キリストによって実現された自由・解放のことについて、割礼を受けるならばキリストを無益にしてしまうということについて、律法によって義を得ようとするならばその人は律法を完全完璧に行なわねばならないことについて、などが語られた。本日は4節目からである。この箇所でもまだガラテヤ人に対するパウロの追及が続いている。しかし、間もなく、キリストによって救われた者たちが当然なすべき歩み・行ないについて語られるようになる。(1)まず救いについて十分に説明する(2)そののち救われた者たちがなすべき義務について述べる、という語り方がパウロのやり方であった。パウロはこの手紙だけでなく、ローマ書やエペソ書でもそのようにしている。
①『律法によって義と認められようとしているあなたがたは、キリストから離れ、恵みから落ちてしまったのです。』(5章4節)
何という大胆さだろうか。今の時代の多くの教職者たちであれば、信徒たちに配慮し、信徒たちが逃げていくのを恐れるがゆえに、決して言えないような大胆さである。スポルジョンやラッシュドゥーニーなどはこの箇所でパウロが言っているのと同じぐらい厳しく大胆なことを平気で言っているが、今の日本において、そのように大胆に語れる牧師たちは少ないように思える。教師たちはパウロの大胆さを見習わねばならないであろう。私の場合、もし聞くならば反発されたり私に抵抗感を持つようになるような内容であっても、それが語らねばならないことであれば容赦なく語ってきたつもりである。これは主の恵みである。どうか、主がもっと大胆に語らせて下さいますように。
それにしても、これは恐るべき言説である。キリストの聖徒・恵みの民である者に対して『キリストから離れ、恵みから落ちてしまった』などと言われるのは、魂を揺るがす衝撃である。考えてみてほしい。我々クリスチャンとはキリストに属し、恵みのうちに保たれているからこそ、「クリスチャン」なのである。しかし、そのような人たちが『キリストから離れ、恵みから落ちてしまった』と言われたら、一体どういうことになるのか。このように言われるということはつまり、その人が真のクリスチャンではない、または真のクリスチャンであるかどうか分からない、ということにならないだろうか。このような言説はクリスチャンの存在そのものに関わる根本的なものであるから、パウロがこのように言うのは、ガラテヤ人たちを根底から揺るがすものである。
ここではガラテヤ人たちに対して『キリストから離れ、恵みから落ちてしまった』と言われているが、これは、彼らがキリストと絶縁して神の国から永久的に追い出されてしまった、ということではない。このように厳しく言われてしまったガラテヤ人であったが、彼らはあくまでもクリスチャンであった。それは、パウロが彼らに対して『兄弟たち』と親しく呼びかけていることからも明らかである。しかし、この箇所で言われている内容は、まさしくその通りであった。つまり、ガラテヤ人たちはキリストの民であるにも関わらずキリストから離れてしまっており、恵みの子であるにも関わらず恵みから落ちてしまっていたのである。この状態は、キリストの弟子でありながらキリストを裏切ったペテロや、父から離れてしまっていた放蕩息子に似ていると言えよう。パウロがどうしてこのように辛辣に述べたかといえば、ガラテヤ人に聖なる衝撃を与えるためであった。すなわち、厳しく衝撃的な言葉をもってガラテヤ人に自分が陥っている悲惨な状態を驚きのうちに気づかせ、そのように気づかせることにより、彼らが正しい道に戻れるようにしたかったわけである。
ここで言われている『律法によって義と認められようとしている』ということと、『キリストから離れ、恵みから落ちてしま(う)』ということは、互いに大きな関係がある。この2つの事柄は、密接に連動している。すなわち、もし律法・行ないによって義を得ようとするのであれば、その人は、キリストとその恵みによる救いを自分から遠ざけてしまう。何故なら、その人が自分自身の行為によって救われようとするので、必然的にキリストによる救いが不要になるからである。また、キリストとその恵みによる救いを蔑ろにするのであれば、その人は、律法であれ善行であれ何らかの行ないによって自分を清めようとする考えに導かれる。例えば教皇派の連中は、キリストに対する信仰による義認をプロテスタントのように重視していないので、自分の行ないによって罪の赦しを得られると思っている。それゆえ我々は、2つの事柄を大いに注意すべきである。まず一つめは、「絶対に律法によって義と認められようとしてはならない。」ということである。我々は、人が義と認められるのはイエス・キリストに対する信仰によるのみである、という聖書的教義から一歩も逸れてはならない。『異端者』『行ないの徒』などと言われたいのでない限り、偽使徒どものようになってはならない。二つめは、「キリストとその恵みによる救いから遠ざかってはならない。」ということである。もし真に『キリストから離れ、恵みから落ちてしまった』のであれば、永遠の命を失うからである。「彼は背教した」「キリストを裏切った」などと言われたいのでない限り、神が下さった聖なる御恵みを捨ててはならない。どうか神が、これらの破滅的な過ちから、我々一人一人をキリストにあって守ってくださいますように。
次は5節目である。パウロはこう言っている。
②『私たちは、信仰により、御霊によって、義をいただく望みを熱心に抱いているのです。』(5章5節)
ここでは『行ないにより、肉によって、義をいただく望みを熱心に抱いている』とは言われてはいない。そうではなく、『信仰により、御霊によって、義をいただく望みを熱心に抱いている』と言われている。つまり、ここでもパウロは行為義認を斥け、正しい教えである信仰義認について述べていることになる。今までこの手紙をずっと見てきたからもう分かると思うが、パウロはここでも繰り返して信仰による救いを論じているのである。
この箇所を読んで「クリスチャンにとって義は未来、つまり御霊の体が与えられる時にこそ得られるものなのだろうか。」と思われる方がいるかもしれない。どうしてこのような疑問が生じるかといえば、この箇所では、あたかも義がこれから後の時間において得られるものであるかのように言われているからである。しかし、聖書では、クリスチャンである者はすでに義と認められている者なのであると教えられている。では、この箇所で『義をいただく望みを熱心に抱いている』などと書かれ、義が未来に現れるかのように言われているのは一体どういうことなのだろうか。ここで言われているのは、すなわち「私たちは義と認められるということを御霊によって生じる信仰に基づかせている。」という意味である。つまり、パウロがここで何よりも意図しているのは信仰による義認を伝えることであって、彼はこう言うことによって行為による義認をガラテヤ人の精神から追い払いたかったのである。
御霊によるプロテスタント教徒たちは、『義をいただく望みを熱心に抱(く)』ということを、御霊によって与えられた信仰に基づかせている。しかし、肉による偽使徒どものような者たちは、『義をいただく望みを熱心に抱(く)』ということを、肉によって生じた行為義認の思想に基づかせている。ここに、「御霊・信仰による民」と「肉・行為による民」における本質的な違いがある。すなわち、義認の根拠を我々プロテスタント教徒たちが御霊による信仰に置くのに対し、偽使徒のような者たちは肉による行為や功績に置く。言うまでもなく、キリストに対する信仰こそ義と認められる唯一の道である。もしこのことを信じていないのであれば、その人は地獄に行かねばならない。行ないによって義と認められようとする者たちは、サタンと共に永遠の裁きを受けることになるであろう。我々はもし自分が信仰義認に立っていると思うのであれば、恵みから落ちて地獄に行くことにならないよう、行為義認の異端によくよく警戒すべきである。
6節目に行きたい。
③『キリスト・イエスにあっては、割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。』(5章6節)
ガラテヤ書の中では、特に引用されることの多い聖句である。『愛によって働く信仰だけが大事』という言葉が我々の霊を強く引きつけるがゆえ、多く引用されるのだと思われる。また、我々にとって愛に基づいた信仰の行ないが非常に大事なものであるからこそ、ここまで引用されるのであろう。この愛に基づく信仰についての事柄は、後ほど話されることになる。
カトリックの詭弁家は、この箇所に基づいて「愛こそが人を義とする。」などと考えている。つまり、この箇所を読んで「人が義とされるのは割礼などによるのではなく愛に基づいた信仰の行ないによるのだ。」などと考えるわけである。しかし、愛の行ないこそが義のためには必要などと考えるのは、愚かな行為義認の考えである。この箇所で言われているのは、義認についてのことではない。この箇所で言われているのは、クリスチャン人生についてのことである。パウロはここでこう言いたいのである。「ガラテヤ人たちよ、我々にとって割礼を受けるか受けないかなどはどうでも良いことだ。割礼を受けるとか受けないとか以前に、我々はもうすでにキリストに対する信仰によって救われて神の民とされているではないか。だから、神の民である存在にふさわしく、愛に基づいた信仰によって歩もうではないか。我々クリスチャンの人生においては割礼などの儀式ではなく、愛による信仰の行ないこそを求め、重視すべきなのである。」
もし愛が土台にないのであれば、どれだけ強い信仰に基づいた行ないであっても、無意味な行ないにしかならない。例えば「神がかならず人々を回心へと導いて下さるに違いない。」という強い信仰に基づき、ヘリコプターで上空から福音の書かれた100万枚のトラクトを街に投下したとしても、そこには愛がないから無意味な行ないになってしまう。いや、愛がないから無意味になるだけでなく人々に害をさえ与えてしまう。何故なら、100万枚も上からトラクトが降ってくるのだから街中がトラクトで一杯になってしまい、人々が溢れかえったトラクトの掃除や処理に悩まされることになるからである。こうなれば愛がないから無意味になるだけでなく人々に害を与えるうえ、キリスト教やクリスチャンが嫌悪される結果まで生みだしてしまう。こう考えると、『愛によって働く信仰』が我々にとってどれだけ大事であるかよく分かるであろう。愛が根底にあるからこそ信仰の行ないが有効に作用するようになり、神に喜ばれる幸いなものとなる。もし愛が無ければ何にもならない。だから、我々にとって『愛によって働く信仰』とはあまりにも重要なものである。
次にパウロはこう言っている。
④『あなたがたはよく走っていたのに、だれがあなたがたを妨げて、真理に従わなくさせたのですか。』(5章7節)
パウロは「走っていた」と言っているが、これは、信仰の歩みに熱心になっている状態のことを意味している。燃える信仰による人生が「走る」と言われている箇所は、他にもある。ガラテヤ2:2の箇所では、パウロの霊的な働きが走ることに例えられている。『それは、私が力を尽くしていま走っていること、またすでに走ったことが、むだにならないためでした。』またⅠコリント9:24の箇所でも、クリスチャンにおける信仰によって歩む霊的人生が、競技場で走るランナーに例えられている。『競技場で走る人たちは、みな走っても、賞を受けられるのはただひとりだ、ということを知っているでしょう。ですから、あなたがたも、賞を受けられるように走りなさい。』これらの聖句から分かるように、どこかに敬虔な心をもっていつも聖書的な歩みに励んでいる真面目なクリスチャンがいたとしたら、その人は「走っている」と言えることになる。
ここでパウロが言っているように、かつてガラテヤ人たちはよく走っていた。つまり、健全な信仰を持っており、霊に燃えて聖書的クリスチャンとして相応しい歩みをしていた。しかし、忌まわしい偽使徒どもがガラテヤ人を惑わしたので、ガラテヤの聖徒たちはイエス・キリストから遠ざけられて真面目に走れなくなってしまった。だからこそ、パウロはここでこう言っているのである。『あなたがたはよく走っていたのに、だれがあなたがたを妨げて、真理に従わなくさせたのですか。』このパウロの言葉を読んだガラテヤ人たちは、ここで偽使徒どものことが言われているのに気づいたであろう。『だれがあなたがたを妨げて、真理に従わなくさせたのですか。』という言葉が、偽使徒どもについて言われているのは明らかである。それゆえ、この言葉はガラテヤ人にとって「あなたがたを妨げ、真理に従わなくさせたのは、あの偽使徒どもである。」と言われているのと全く同じである。もしここでガラテヤ人を惑わしたのが偽使徒どもであると言われているのであれば、それは、ガラテヤ人たちに偽使徒どもから離れるように勧告されているのも等しい。だから、パウロはここでもガラテヤ人たちを偽使徒どもから遠ざけようとしていることになる。
神の御民を、イエス・キリストから引き離そうとするものは一体なにか。それは、「サタン」と「罪深い肉の心」の二つである。サタンは御民を憎んでいるので、御民が何とかしてキリストから離されて地獄に行くようになるのを願っている。もし我々が地獄に行くのを望んでいるのでなければサタンは我々を憎んでいないことになるが、そうではない。彼は、心の底から我々を憎悪している。その憎しみは純粋そのものである。それゆえ、サタンは邪悪な策略をもってクリスチャンたちをキリストから引き離し、地獄に投げ込まれるようにと企んでいるわけである。また、我々の忌まわしい肉の思いも、我々をイエス・キリストから引き離す大きな原因となる。もし我々の信仰が弱まり、不信仰な肉の心が満ちるようになるのであれば、我々は自分自身の愚かさによってキリストから離れてしまいかねない。このことのゆえに、ヘブル書では次のような忠告がなされている。『兄弟たち。あなたがたの中では、だれも悪い不信仰の心になって生ける神から離れる者がないように気をつけなさい。』(ヘブル3章12節)もちろん「聖徒の堅忍」の教理に立っている我々は、選ばれている者たちがキリストから完全に引き離されることは絶対にあり得ないと信じている。しかし、選ばれている者たちが最終的・決定的な意味においてキリストから遠ざけられてしまうことがあり得なかったとしても、もし不信仰な肉の心がそのうちに満ちてしまうのであれば、ガラテヤ人のように一時的にキリストから遠ざかってしまうことも十分に起こりうる話である。当時ガラテヤ人たちは、サタンの心を行なう偽使徒どもに騙され、自分の肉的な思いを斥けられなかったために、イエス・キリストから離れてしまっていた。ガラテヤ人であれ他のクリスチャンであれ、聖徒たちがイエス・キリストから遠ざかってしまうことは、悲しむべき霊的不幸である。我々を救って下さったキリストは、我々の罪の贖いとなるため十字架における死にみずから臨んで下さったのであって、この御方とその贖罪のゆえに我々は罪の赦しを受けて義と認められたのである。このことを少しでも考えるのであれば、キリストから離れるということが我々にとってどれだけ大きな忘恩であるか、またどれだけ大きな愚行であるか、よく分かるであろう。それゆえ、我々は、行為義認の教理や異端神観などをもって迫ってくるサタンの惑わしによく警戒し、ヘブル書でも言われているように悪い不信仰の心になって神から遠ざかってしまわないように注意し、あくまでもキリストに根差し続けるべきである。どうか神が、我々一人ひとりを憐れみ、最後まで主イエス・キリストのうちに保たせて下さいますように。アーメン。
ガラテヤ人への手紙5章8~10節(2016/05/29説教)
『そのような勧めは、あなたがたを召してくださった方から出たものではありません。わずかのパン種が、こねた粉の全体を発酵させるのです。私は主にあって、あなたがたが少しも違った考えを持っていないと確信しています。しかし、あなたがたをかき乱す者は、だれであろうと、さばきを受けるのです。』(ガラテヤ5章8~10節)
先週は、義認や愛によって働く信仰の行ないなどについてのことが語られた。本日は8節目からである。色々な方法をもって真理に引き戻そうとするパウロのガラテヤ人に対する説得が、まだ続けられている。
まずは8節目からである。
①『そのような勧めは、あなたがたを召してくださった方から出たものではありません。』(5章8節)
まず『そのような勧め』と書いてあるが、これは、偽使徒どもが説いていた教義―律法によって義と認められようとする行為義認の思想―のことである。
パウロは、この行為義認の教えについて「あなたがたを召してくださった方から出たものではない」と言う。つまり、この忌まわしい教義は、神から出た神聖な教義というのでは決してない。この教義を我々の主である三位一体神は決して首肯されず、大いに否認される。それでは、この行為義認という異端教義は、いったい誰から出たのであろうか。それは、言うまでもなく敵なるサタンからである。いま私が言ったこのこと(つまり行為義認とはサタンによるものであるということ)は、真のクリスチャンであれば誰も否定できないだろう。何故なら、ここでパウロが『そのような勧めは、あなたがたを召してくださった方から出たものではありません。』と言っているのは、すなわち「行為義認の教えはサタンから出たものなのです。」と言っているのも等しいからである。
サタンの心を行なう偽使徒どもによる行為義認の罠に、当時ガラテヤ人たちは陥ってしまっていた。この手紙が書かれた2千年前の当時もそうであったが、今の時代においてもあちらこちらにサタンの罠が蔓延(はびこ)ってしまっている。進化論、自由主義神学、ディスペンセーショナリズムなど、敵どもによる惑わしが世界には山ほど満ちており、一つ一つ挙げれば切りがない。我々は、ガラテヤ人のように騙されてしまわないよう、敵どもの策略を大いに警戒すべきである。
ここでパウロが「行為義認の教理とは悪しき者から出たものである」と言っているということは、つまり、行為義認の教理が攻撃され排斥されているということである。もしそうであれば、パウロはここでもガラテヤ人たちが悪しき教えから離れてほしいと言っていることになる。何故なら、「あなたがたは悪い教えに惑わされている。」と言うことは、すなわち「その悪い教えから離れてほしい。」と暗に言うことだからである。それゆえ、「異端から離れて真理に戻ってほしい。」というガラテヤ人に対するパウロの思いが、この箇所からも伝わってくる。実に、パウロは「真理への回帰」という目的を達成すべく、ガラテヤ人のために一心になって筆を執っていたわけである。
次は9節目である。パウロはこう言っている。
②『わずかのパン種が、こねた粉の全体を発酵させるのです。』(5章9節)
言うまでもないが、ここでは、パンを膨らませるイーストそのものについて説明しているのではない。ここで説明されているのは、食べ物のこと、物質的なことではなく、霊的なこと、教義のこと、共同体のこと、である。このパン種というものは、たとえ少しであっても粉のかたまり全体を膨らませてしまう性質をもっている。それと同じように、異端というパン種がある集団のうちに少しでも存在しているのならば、やがて広がり、その集団全体に満たされるようになってしまう。量は関係ない。異端というパン種がわずかでもあったならば既にアウトである。もし砂の一粒ほどでも異端があるならば、その異端はパン種のごとくに膨らまざるを得ない。ここでパウロがパン種について書いているのは、このように書くことによって、ガラテヤ人たちに警鐘を与えるという意図があったのだろう。つまり、この手紙が書かれた当時、ガラテヤの諸教会には「異端教理という悪しきパン種」がまだ完全には広まっていなかったのだが、もしこのまま放置するのであればガラテヤの諸教会全体が完全に異端教理で汚染されてしまうことになるのは明白であったから、そのような状態になってしまうのを恐れてパウロはこのように書いたのだと思われる。すなわち、パウロはこう言いたいのだと思われる。「ガラテヤ人たちよ、このままだとパン種が膨らむように異端があなたがたの教会に満ちるようになるぞ。それでもいいのか。嫌に決まっているだろう。もし嫌ならば、異端が充満してしまう前に異端を完全に取り去るべきである。」
我々はこの箇所から何を学ぶべきか。それは、<異端というパン種は教会から速やかに除き去らねばならないものである>ということである。もし少しであっても教会に異端教理が入りこむならば、事は重大であって、それは霊的な緊急事態である。これらのことは特に教会の管理者たちに関わることであるが、もし異端の芽が見えたならばすぐにも取りのぞき、教会内に異端が膨れ上がってしまわないようにすべきである。これは、無視しても構わないような取るに足らない問題ではない。「新改訳聖書がそうしているように<ピリピ書>と呼ぶべきなのか、それとも新共同約聖書がそうしているように<フィリピ書>と呼ぶべきなのか。」というような問題であれば、そこまで重要であるとは言えないだろう。このような小さな問題の場合、たとえ放置していたとしても致命的な事態に発展する可能性は非常に少ない。しかし、異端という問題は、無視したり放置したりすることが絶対に許されない問題である。もし異端を放置したままにするならば、教会が忌まわしい教義に汚染されるので、キリストの御身体なる教会に大きなダメージがもたらされてしまう。この異端とは、その集団が真に聖書的な教会であるか、または異端的な教会であるか、ということにおける判断を左右させるものである。もし異端に完全に毒されてしまうのであれば、もはやその集団は真の教会とは言いがたい。しかし、妥協せずに異端を斥けるのであれば、その集団は聖書的な教会として保たれるだろう。この異端という問題は教会にとってあまりにも重要なものであるから、我々―特に教師たち―は大いに警戒せねばならない。私も、この異端についてはいつも目を光らせている。
次は10節目である。
③『私は主にあって、あなたがたが少しも違った考えを持っていないと確信しています。』(5章10節)
この箇所を読んで、すぐにあることに気づかれるかもしれない。それは、以前パウロが「ガラテヤ人たちは違った考えに陥ってしまっている。」と言っていながら、ここでは「ガラテヤ人たちが違った考えに陥ってしまっているとは信じない。」と言っていること、つまり一見すると矛盾しているかのように感じられる点である。パウロは、5章4節目でガラテヤ人たちが『律法によって義と認められようしている』と述べたが、これは「ガラテヤ人たちは間違った教えを信じてしまっている。」と述べているのも同じである。更に、5章7節目ではガラテヤ人たちが「真理に従わなくなってしまっている。」とパウロは言ったが、これは「ガラテヤ人たちは非聖書的な教理に陥ってしまった。」と言っているのも同じである。しかし、パウロはここでガラテヤ人について『あなたがたが少しも違った考えを持っていないと確信しています。』と書いている。つまり、パウロは「ガラテヤ人は間違った教えに陥ってしまった。」と言いながら「ガラテヤ人が間違った教えに陥ってしまったとは信じない。」とも言っている。はたしてパウロはここで矛盾したことを書いてしまったのだろうか?絶対にそんなことはあり得ない話である。ここでパウロが言っているのは、「ガラテヤ人たちが完全に異端教理に染まったなどとは信じない。」ということである。つまり、『少しも違った考えを持っていないと確信しています。』とここで言われているのは、本質的・決定的・究極的な意味においてである。すなわち、「私は、あなたがたガラテヤ人たちが真の意味において異端を信じているなどとは思わない。あなたがたは異端を本当に信じているかのように見えるが、実はそうではなく、単に一時的に騙されてしまっているに過ぎないのだ。」とパウロは言いたいのである。
この箇所もそうだが、聖書には一見すると矛盾しているように思われる箇所が多くある。例えば、Ⅰサムエル15章の箇所がそうである。ここでは「神は悔いることがない」と言われているが、「神は悔やまれた」とも言われており、一見すると矛盾しているかのように感じられる。このように矛盾しているように感じられる箇所が聖書には多くあるのだが、しかし、何か意味不明なことが書かれているわけではない。どの箇所も、よく考えるなら、実は矛盾していないのだということが分かるようになる。それゆえ、我々はこの箇所のように矛盾しているかのように思われる箇所に出会ったなら、まずは落ち着くべきであって、急いだために判断を誤って「聖書には変なことが書かれている。」などと不敬虔な思いを抱かないように気をつけるべきである。
それで、パウロはこの箇所で『主にあって』ガラテヤ人たちが異端に完全には毒されていないと確信している、と言っている。ここで『主にあって』と言われているのは一体どういうことなのか。もしガラテヤ人が主にあって救われてクリスチャンに変えられたのであれば、それは、彼らが永遠の昔から選ばれていた者たちであったことを示す。もし彼らが主にあって救われるように選ばれていたのであれば、そのような者たちが真に異端に染められてしまうことはあり得ない話である。もし完全完璧に異端の信仰になってしまったのであれば、そういう人は、もともと選ばれていなかったのである。だからこそ、パウロはここで『主にあって』ガラテヤ人たちが異端信仰に完全に染まってしまったとは思えない、と言うのである。ここでパウロが述べている言葉を分かりやすく表現すれば、次のようになる。「ガラテヤ人たちよ、あなたがたは救われて主のものとされたのだから、決定的・究極的な意味において異端に染められてしまうことはあり得ない。何故なら、主は御自身のものである民を完全完璧に異端に引き渡されるようなことはされないからである。それゆえ、私は主のゆえにあなたがたが真に異端信仰に陥ってしまったとは信じないし、そのようなことはあり得ない話である。」
いま説明されたように、主は御自身の所有の民を、徹底的な意味において異端に引き渡されるようなことは絶対に為さらない。我々キリスト者が異端に完全に引き渡されるということは―つまり我々が異端者になってしまうということは―、すなわち我々が神から見離され、捨てられてしまうということに他ならない。何故なら、異端者という存在は天国には行けず、地獄で永遠の刑罰を受けるからである。しかし、主は選ばれている人たちを異端に引き渡して捨てられてしまうような御方ではない。『わたしは決してあなたを離れず、また、あなたを捨てない。』(ヘブル13章5節)と主が言われる通りである。もし神が許されるのであれば、選ばれている者たちがガラテヤ人たちがそうであったごとく一時的に異端信仰に引き渡されてしまうこともあり得る。しかし、彼らが異端信仰に究極的な意味において引き渡されることはないから、時がくれば、かならず正しい信仰に復帰するはずである。選ばれているのに、どうして異端に染まって滅びに至るということが起こるだろうか。ここにいる我々一人一人も、異端の深みに沈み落とされて永遠の滅びに至る、という結末を迎えることは決してない。どうしてこう言えるかといえば、我々一人一人が主にあって選ばれていると私が信じているからである。もし我々一人一人が選ばれている人たちであると私が信じているのでなければ、どうしてこのように言えようか。
次は10節目の後半部分である。ユダヤ主義の異端者、割礼主義者、行為義認論者、すなわち偽使徒どもに対する厳しい言葉が書かれている。
④『しかし、あなたがたをかき乱す者は、だれであろうと、さばきを受けるのです。』(5章10節)
パウロはここで、偽使徒どもが裁かれるのだと断言している。確かに彼らは裁かれねばならない忌まわしい愚物どもであった。ここで「パウロには憐れみがない。」などと思う兄弟姉妹がいてはならない。もしこのように思うとしたら、考えを改めるべきである。何故なら、もしパウロが偽使徒どもを憐れんでいたとしたら、それは、彼らに惑わされていたガラテヤ人たちを蔑ろにすることだからである。例えば、自分の家族が襲われていたとして、暴れ回っている狂人を憐れみ何もしないとしたら、その人は、自分の家族よりも狂人のほうを大事にしていることになる。もし狂人よりも自分の家族を大事にしていたとしたら、その人は暴力を振るったり武器を使うなどして、狂人を容赦なく追い払おうとするはずである。そのようにしなければ、家族に大きなダメージが加えられることになるからである。パウロが偽使徒どもに対して呪われよ、裁かれよ、切り取られよ、などと言ってガラテヤ人から遠ざけようとしているのは、これと同じことである。言うまでもなくパウロは、偽使徒(つまり狂人)よりもガラテヤ人(つまり家族)のほうを大事にしていた。だからこそ、パウロは、父親が家族のために狂人を打ち負かして追い払うがごとくに、ガラテヤ人に霊的攻撃を加えていた偽使徒どもに厳しい言葉を浴びせかけて斥けようとしているのである。
また、パウロはここで『だれであろうと』かき乱す者どもは裁かれるであろうと書いている。これはつまり、教会をかき乱す者たちは例外なく裁きを受けねばならない、ということである。誰であれ教会勢力を異端によって惑わす偽キリスト者どもは、神の裁きを受ける直前の状態にまで行きついた者たちである。裁かれる者たちは、「裁きの時」がくれば、かならず裁かれることになる。偽使徒どもは裁かれるべき者たちであったが、パウロがこの手紙を書いた当時、彼らに裁かれる時が近づいていた。だからこそ、彼らは自分に定められた当然の裁きを受けるべく、神の教会において、裁かれるべき愚行―異端教理の宣伝および普及活動―を行なうに至ったのである。それゆえ、裁かれるべき悪を行なったこの偽使徒どもは、パウロがこの手紙を書いてのち、何らかの裁きを受けたことであろう。確かにパウロはここで「偽使徒どもは裁きを受ける。」と言っているのだから、このことを疑うことは出来ない。
最後になるが、偽使徒どものように異端教理によって教会を惑わすという罪は、凄まじい極悪である。これは、キリストの御身体に<癌>を生じさせる行ないである。聖なる共同体のうちに死に至らせる恐ろしい病が生じる。誰がこれを切除せずにいられるだろうか。もしこの悪しき疾患が教会から除かれるのを望まないのであれば、その人は、キリストの御身体などどうでもいいと感じている人である。異端という悪によって教会勢力を攪乱(かくらん)する者どもは、切り取られるべきである。セルベトゥスは反三位一体という異端をもって教会を惑わしたが、このような者たちは容赦なく裁かれ、切除されねばならない。実際、カルヴァンは彼を焚刑によって教会から切除し、永遠の地獄へと送り込んだ。聖書では悪を憎むように命じられている。例えば、詩篇97:10では『悪を憎め。』と書かれており、ローマ12:9では『悪を憎み(なさい)』と言われている。行為義認であれ反三位一体論であれ、異端とはれっきとした悪に他ならない。それゆえ我々プロテスタント教徒たちは、悪である異端を憎むべきである。実に、異端とはサタンの悪であって、憎むべき霊的毒物である。どうか、神がこの異端をことごとく滅ぼし尽くして下さいますように。
ガラテヤ人への手紙5章11~13節(2016/06/05説教)
『兄弟たち。もし私が今でも割礼を宣べ伝えているなら、どうして今なお迫害を受けることがありましょう。それなら、十字架のつまずきは取り除かれているはずです。あなたがたをかき乱す者は、いっそのこと不具になってしまうほうがよいのです。兄弟たち。あなたがたは、自由を与えられるために召されたのです。ただ、その自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに仕えなさい。』(ガラテヤ5章11~13節)
先週の箇所(8~10節目)では、特に異端のことについて話された。本日は11節目からである。
①『兄弟たち。もし私が今でも割礼を宣べ伝えているなら、どうして今なお迫害を受けることがありましょう。それなら、十字架のつまずきは取り除かれているはずです。』(5章11節)
まずは言葉の説明からである。前半部分の方に『割礼を宣べ伝えているなら』と書いてある。『割礼』とは、すなわち「義のためには割礼を受けねばならないという教え(つまり行為義認の異端)」のことである。だから、これは「行為義認の教理を告げているなら」という意味である。また、後半部分の方には『十字架のつまずき』と書かれている。これは、「十字架につけられたイエス・キリストに対する信仰のゆえに受ける苦難・妨げ」のことである。つまり、ごく簡単に言えば「迫害」という意味である。
言葉の説明が終わったので、次は内容のほうを見ていきたい。この箇所でパウロが言いたいことを別の言葉で表現すれば、次のようになる。「ガラテヤ人たちよ、私が今でも行為義認の信仰を伝えているなら、私は迫害を受けていなかっただろう。何故なら、行為義認とは真理では無いからである。真理を伝えていないのであれば、敵どもが憤ることもないから、敵どもから迫害を受けることもない。しかし、私は(行為義認ではなく)信仰義認を告げているがゆえに、迫害を受けている。真理を伝えているから、真理を憎む敵どもが憤って私に迫害を加えるのである。それゆえ、私が迫害されていることとは、私が真理を告げている明白な証拠である。私たちの主も真理を語られたがゆえに多くの迫害を受けられたではないか。」
パウロはここで、行ないによって義を得ようとする教えを伝えていたのであれば自分は迫害を受けてはいなかったであろう、と言っている。この行為義認の思想は、キリストを信じていなかったユダヤ人たちが持っていた思想に反するものではない。ユダヤ人たちは自分の行ないによって魂に救いが与えられるという考えを持っていたが、この考えは行為義認の思想であるから、もしパウロがこの考えを伝えていたとしたら、ユダヤ人から迫害を受けることは無かっただろう。通常の場合、自分たちと似たような思想を持っている者に対して激しい攻撃を加えるということはほとんど無い。しかし、パウロは「人は信仰によって救われる。」というユダヤ人にとって受け入れがたい教えを伝えていた。だからこそ、ユダヤ人たちはパウロに反発し、彼を迫害するに至ったのである。
次は12節目である。
②『あなたがたをかき乱す者は、いっそのこと不具になってしまうほうがよいのです。』(5章12節)
『不具になってしまうほうがよい』と訳されているが、この部分は※印が示しているように『切り取ってしまうほうがよい』と読むことも出来る。私の使っている第2版の新改訳聖書では『不具になってしまうほうがよい』と書かれているが、第3版では『切り取ってしまうほうがよい』という文章になっている。どちらも内容的にはほぼ同じだから、「不具」としても良いだろうし、「切り取る」という訳の方を選んでも良いだろう。
この箇所は、10節目の後半部分の箇所と非常に似ている内容である。そこには『あなたがたをかき乱す者は、だれであろうと、さばきを受けるのです。』と書かれている。聖書思想では、2回、3回と繰り返すことは、その事柄を強調したり証明したりすることである。この手紙の1:8~9では、偽使徒どもに対して2回も『のろわれるべきです。』と言われているのを我々は以前確認した。偽使徒どもが絶対に呪われねばならない悪者だったからこそ、ここでは2回も繰り返してアナテマが宣告されたのである。我々が今見ているこの12節目と10節目でも、似たような内容が2回も繰り返して書かれている。ここでは、どうして2回も偽使徒どもが痛めつけられるように繰り返して言われているのだろうか。それは、偽使徒という極悪人どもは絶対に裁かれて痛めつけられねばならない存在だったからである。
この箇所から、パウロの偽使徒どもに対する激しい憤りの念が伝わってこないだろうか。彼らに対して怒っているからこそ、パウロはこのように厳しいことを大胆に書いているのである。パウロはあたかもこう言いたいかのようである。「偽使徒どもは割礼を受けさせて包皮を切り取ろうとしているが、彼らこそこの世界から切り取られて無くなってしまうべきである。」「偽使徒どもはあなたがたに割礼を受けさせようとしているが、このような者たちの性器は切除されて不具になるべきである。」つまり、パウロは偽使徒どもが自分の行ないに対する当然の報いを受けるようにと、ここで言っているのである。私もこのパウロにならって、教会および人々を惑わしているエホバの証人どもにこう言いたいものである。「エホバの証人どもは痴呆になり、自分の子供が人間であるとはもはや認識できなくなってしまうほうがよい。」狂った神学に立っている彼らは、神の第二位格である御子が「神」であると認めていない。それゆえ、彼らは当然の報いを受け、自分の子供が「人間」であることをまったく認められなくなってしまうほうがよいのである。彼らは神の御子を正しく認識していないのだから、自分の子供も正しく認識できなくなってしまうがよい。
これを書いている時、パウロの頭の中には、御国・キリストの教会の事柄しか無かったのではないかと思われる。「もしかしたら偽使徒も悔改めるかもしれない」とか、「彼らにも情けをかけてやらねばならない」などといった憐れみの念はパウロの心に無かったに違いない。だからこそ、このように偽使徒どもを容赦なく取り扱っているのである。「このままでは神の教会が大変なことになってしまう。何とかして聖徒たちをかき乱している異端者どもを追い払わないといけない。」このような思いを抱きつつパウロはこの文章を書いていたのだと私は推測する。もし憐れみの感情が少しでもあったならば、どうしてこのように辛辣かつ断罪的な文章が書けるであろうか。
次は13節目である。
③『兄弟たち。あなたがたは、自由を与えられるために召されたのです。』(5章13節)
5章1節目でも「キリストが私たちに自由を得させて下さった。」と書かれていたが、(この13節目の箇所と)内容的に似ている箇所である。ガラテヤ人たちは主イエス・キリストのゆえに自由の民とされるに至った。いったい何から自由にされたかといえば、前にも説明したことだが、律法の隷属状態から解放されたという意味における自由である。ここにいる我々も、キリストのゆえに自由の民とされており、もはや奴隷の民ではなくなった。それゆえ、ガラテヤ人であれ我々であれ自由の民である者たちには、「律法の儀式を行なわなければ義と認められることはないぞ。」という恐ろしい奴隷的宣告がなされることは、もはや無い。それで、自由にされたキリストの民は、自由にされた存在に相応しく、神に喜ばれる聖書的な歩みをしなければならない。その歩みとは、「愛に基づいた言動に満ちた人生」また「我々が互いに愛しあい仕えあう人生」である。このことについて、パウロは13節目の後半部分の箇所でこう言っている。
④『ただ、その自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに仕えなさい。』(5章13節)
我々が自由にされたからというので、我々はもはや何でも行なって良い、好き放題しても構わないのだ、などと平気で考えている方々がいる。このように考える人たちは、次のように言う。「私たちは、肉的な行ないであれ忌わしい言動であれ、何であっても行なって良い。たとえ盗みであっても不倫であっても我々は行なって良いのだ。何故なら私たちは自由にされたのだから。」しかし、自由の民にされたのだから肉的な行ないをしても良くなった、ということは決してない。我々は思い違いをすべきではない。我々は、パウロがここで「キリストによって与えれた自由を肉の働く機会としてはいけない。」と言っているのを心に留めるべきである。もし「自由にされた=肉的言動が許されるようになった」と考えている人がいれば、その人は、我々を自由にして下さった主を蔑ろにしてしまっている。何故なら、キリストが選ばれた者たちを贖って自由の民として下さったのは、彼らが聖潔に進んでますます主に似たものとされ、忌わしい肉的言動から次第に遠ざかっていく聖書的人生へと変えられるためであったからである。『神が私たちを召されたのは、汚れを行なわせるためではなく、聖潔を得させるためです。』(Ⅰテサロニケ4章7節)と言われている通りである。それゆえ、キリストによって自由にされた=肉的言動をしても良くなった、という理解は非聖書的であって、誤りである。
言うまでもなく、キリストによって与えられた自由は、肉的言動ではなく愛の言動のために用いられねばならない。パウロもここでそのように命じている。例えば、自動車の免許を取って自動車を自由に運転できるようになった人が気儘な暴走運転をするのであれば、その人は非難されるべきだろう。その人は、車を運転できるようになった自由を、不適切なことのために用いている。免許を取得して自動車を運転できるようになった自由は、暴走運転のためにではなく、安全運転のために使われるべきである。それと同じように、キリスト者に与えられている自由も、暴走する肉の行ないのためにではなく愛のために使われるべきである。しかし、我々は罪深い存在なので、もし神の恵みが無ければ、与えられた自由を愛のために用いることなど出来ない。クリスチャンであっても堕落した肉的精神が働くならば、愛ではなく、肉の行ないのために自由を使ってしまう。このゆえに、パウロはローマ7章の箇所で、愚かな肉の行ないに歩んでしまう自分のことを嘆いているのである。もしパウロが完全完璧に肉を避けて愛の行ないに歩めたのであれば、『私は、ほんとうにみじめな人間です。』(ローマ7章24節)とは言わなかったであろう。我々は神の恵みがなければ肉を避けて愛の行ないに歩めないのであるから、与えられた自由を愛の言動のために使えるよう、主なる神に祈るべきである。
パウロはここで『互に仕えなさい。』と書いているが、これは一体どういうことだろうか。ペテロの手紙には次のように言われている箇所がある。『それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて、互いに仕え合いなさい。』(Ⅰペテロ4章10節)このペテロを通して語られた御言葉の内容によって我々がいま見ている箇所を解釈するのであれば、次のような解釈になるであろう。「キリストによって与えられた自由に基づき、それぞれが持っている賜物を使って互いに仕えるべきである。」賜物を用いて互いに仕えあう、ということは、新訳聖書全体が我々に教えているクリスチャンの行動原理である。例えば、私のように『語る人』(Ⅰペテロ4章11節)であれば、語るために与えられた賜物を用いて聖書的な教育をすることにより、聖徒たちに仕えていることになる。スポルジョンも『語る人』であったが、彼は説教をして教えたり励ましたりすることによって、聖徒たちに仕えていた。彼はこのゆえに、自分のことを「聖徒たちの僕」と呼んでいる。もし、『語る人』であるのに語ったり教えたりしないのであれば、その人は、聖徒に仕える真の教師であるとは言えない。また、金持ちのクリスチャンは明らかに『分け与える人』(ローマ12章8節)であるから、自分の財物を困っている貧しい聖徒たちのために分与することで、聖徒たちに仕えることが出来る。私がこう言っても、金持ちの精神とは高ぶりやすいものであるから、分け与えることに対して抵抗を感じるかもしれない。「私が努力して自分で稼いだお金なのに稼ぐ能力のない貧乏な人たちに与えなければならないのか…。」と。私は言うが、あくまでもこのような思いを持ち続けるならば、その人は金を自分の神としている偶像崇拝者である。彼らは、金持ちに対して聖書が次のように命じているのを心に留めねばならない。『人の益を計り、良い行ないに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように。』(Ⅰテモテ6章18節)Ⅰヨハネ3:17でも言われている通り、世の富を持ちながら困っている聖徒たちを助けて仕えようとしない者たちには、永遠の命などあり得ない。また、『奉仕する人』(Ⅰペテロ4章11節)であれば、『神が豊かに備えてくださる力によって、それにふさわしく奉仕』(Ⅰペテロ4章11節)することにより、聖徒たちに仕えることが出来る。奉仕の種類はたくさんあるが、教会内の活動であれば、例えば日曜学校の教師とか聖歌隊における指導・管理などがそうである。このような活動において何らかの奉仕をするのであれば、その人は、その働きによって聖徒たちに仕えていることになる。KGK(キリスト者学生会)という団体があるが、この団体において集会や聖書研究会などの奉仕をしたり、この団体で行なわれる何かの活動に協力したりしている兄弟姉妹も、聖徒たちに仕えていることになる。牧師の働きや活動に協力している兄弟姉妹も、牧師という聖徒に仕えていることになる。もし、『奉仕する人』として何かの奉仕しているにも関わらず、嫌々ながら、また不快感をもってその奉仕を行なうのであれば、それは、神に喜ばれない無意味な奉仕となってしまうから注意が必要である。「心」の伴っていないパリサイ的奉仕は、神の御心に適った奉仕ではないことを覚えるべきであろう。
今いろいろと仕えることについて話したが、この「我々が互いに仕えあう」ということは非常に重要なことである。
我々クリスチャンが互いに仕えあう際、仕えあう動機はどのようなものであるべきだろうか、また我々が仕えあう目的とは一体なんなのだろうか。まず、我々が互いに仕えあう動機は、「愛」に基づいているべきである。『愛をもって互いに仕えなさい。』とパウロが命じる通りである。彼は他の箇所でも、『いっさいのことを愛をもって行いなさい。』(Ⅰコリント16章14節)また『愛を追い求めなさい。』(Ⅰコリント14章1節)と命じている。もし聖徒たちが愛を動機として仕えあうのでなければ、外面的には仕えあっているかのように見えても、本質的な意味において仕えあっているとは言えない。たとえ仕えあっているように見えても、そこに愛が無ければ、ただ何らかの動作をロボットでもあるかのようにしているに過ぎない。「これを行なえばあの聖徒の利益になるだろう。」「こうしておけばあの姉妹に役立つに違いない。」我々は、こういった愛の思いに基づいて仕えあうことが望まれている。ここで、「私たちは惨めな罪人に過ぎないのに、どうして常に完全完璧な愛をもって仕えあえるだろうか。」と思われる方もいるかもしれない。確かにその通りである。だが、我々が不完全で罪深い存在だからといって、「難しいから諦めよう。」などと感じ、愛に基づいて互いに仕えあうことを放棄してしまうようであれば、それは誤りである。我々は、もし神の御心に従えずに愚かな行ないをしたのであれば悔改め、聖書が命じている愛の歩みに進めるよう御霊によって導かれるべきである。次に、我々が互いに仕えあうのは一体なにを目的としているのだろうか。その答えは「キリストの御身体を建て上げること」である。パウロはエペソ4:12~16の箇所でこう書いている。『それは、聖徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストのからだを建て上げるためであり、ついに、私たちがみな、信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全におとなになって、キリストの満ち満ちた身たけにまで達するためです。それは、私たちはもはや、子どもではなくて、人の悪巧みや、人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ、愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、かしらなるキリストに達することができるためなのです。キリストによって、からだ全体は、一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また、備えられたあらゆる結び目によって、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して、愛のうちに建てられるのです。』ここでは、聖徒たちが互いに仕えあうことによってキリストの御身体が建て上げられる、ということが言われている。我々が互いに愛をもって仕えあうのであれば、それだけキリストの御身体が建て上げられて完成に近づくようになるだろう。我々は、自分たちが『キリストのからだであって、ひとりひとりは各器官』(Ⅰコリント12章27節)であるということを思い出すべきである。教職者たちは聖徒を教えることによって、キリストの身体である多くの部分を成長させ、健全にし、病気にならないように働きかけている。困っている聖徒を助ける兄弟姉妹がいれば、その兄弟姉妹は、今にも崩れてしまいそうなキリストの身体の部分を治療し、介護し、正常になるように働きかけている。つまり、我々が愛をもって互いに仕えあうということは、キリストの御身体を建て上げているということに他ならない。だから、もし聖徒たちが全く互いに仕えあわなかったとしたら、キリストの御身体が建て上げられることはなく、朽ちていくばかりであろう。
本日の箇所はここまでである。今回は、11節目から13節目までであった。次週は14節目からとなる。
ガラテヤ人への手紙5章14~15節(2016/06/12説教)
『律法の全体は、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」という一語をもって全うされるのです。もし互いにかみ合ったり、食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。』(ガラテヤ5章14~15節)
先週の説教箇所は5:11~13であった。11節目ではもしパウロが行為義認の教えを伝えているならば迫害されていなかったということについて、12節目では裁かれるべき偽使徒どもについて、13節目ではキリストにあって我々に与えられた自由のことについて、またこの自由を愛のためにこそ用いるべきことについて語られた。本日は14節目からである。パウロは13節目から、救われたクリスチャンが当然なすべき歩み・行ないについて論じ始めている。
ルターもカルヴァンも、教える際に最も重要なことの一つは「分かりやすさ」であると考えていた。私も文章を作成する際には、なるべく分かりやすくなるようにと心がけている。私が自分の文章について個人的に感じることを言うと、もう少し説明を加えた方が更に分かりやすくなると感じることが多いが、全体的にはまあ分かりやすいのではないかと感じる。しかしキケロも言うように「自分のことは自分がいちばん知らないものであり、自分で自分について評価を下すのは最もむずかしいこと」(岩波書店:「キケロー選集7 弁論家について」(第3巻)9章33節p349)であるから、これ以上自分自身の文章に評価を下すのはやめるべきだろう。誰であれ、自分自身について自分が思っているのと同じように大多数の人たちが思っているかのかどうか、私たちには分からないのである。商売など特にそうだが、自分が「良い」と思っているのに周りの人たちは「良くない」と思っていたり、自分が「良くない」と思っているのに周りの人たちは「良い」と思っていたりするケースが往々にしてある。何はともあれ、これからも分かりやすい文章を心がけていきたいものである。もし書かれている文章の内容が不明瞭であれば、何を言いたいのか全く分からなくなってしまうのだから。
まずは14節目からである。
①『律法の全体は、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」という一語をもって全うされるのです。』(5章14節)
5:6の箇所もそうだが、我々が今見ているこの5:14の箇所も、ガラテヤ書の中では最も引用されたり語られたりすることの多い場所である。私にしても、この箇所は何度も引用したり語ったりしたものである。どうして引用される頻度が多いのかといえば、この聖句は、我々クリスチャンが行動原理とすべき道徳律法の本質を大変素晴らしく説明しているからであろう。この聖句で言われている内容は、全ての聖書的クリスチャンが十分に弁えるべき内容である。この聖句は、内容的にローマ13:9の箇所と非常に類似している(※①参照)。
ここでパウロが言っているように、諸々の律法が目的としているのは隣人愛である。すなわち、数々の戒めは、外面的にであれ内面的にであれ『あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。』という聖句に帰着する。例えば、律法では『偽証してはならない。』(申命記5章20節)と命じられているが、この律法は隣人への愛を目的としている。何故なら、もし偽って語るのであれば、それを聞いた人たちが惑わされて損害を受けてしまうからである。だから、隣人を愛するのであれば、その人が具体的に行なわねばならないことは「偽証しない」ということである。『偽証してはならない。』という律法を守り、隣人に害を与えてしまう嘘をつかないからこそ、『あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。』という聖句が行なわれることになる。つまり、律法とは、言い換えれば「隣人を愛するための聖なる規範」と言えよう。我々は、律法とは愛を目的としているものなのだということを、再び心に覚えるべきであろう。
この箇所に書かれている『律法』とは、言うまでもなく「道徳的な律法」を指している。ここでは「儀式的な律法」を念頭に置いて『律法』と言われているのではない。このことは、文脈から考えても明らかである。 今、この箇所では道徳的な律法について言われていると述べたが、この道徳的な律法とは「十戒」だけを指しているのではない。ここでは「十戒」もそうだが、「十戒以外の様々な戒め」も含まれている。現在もそうだが、今の時代に至るまでプロテスタント界では、「道徳的な律法」=「十戒」としか考えない傾向が存在している。つまり、「道徳的な律法」=「十戒」+「十戒以外の諸々の戒め」とは考えない傾向がある。だから、教会では十戒について語られることはあっても、細々とした道徳的な戒めについてはほとんど教えられてこなかった。それゆえ、今のプロテスタント界においては、この箇所で『律法』と言われているのを見ても、「十戒」のことしか思い浮かべないかもしれない。しかし、「道徳的律法」という言葉の中には、十戒だけでなく、その他の諸々の道徳的な戒めも当然ながら含まれている。我々は、ここで『律法』と言われているのが、「全ての道徳的律法」を指しているということを知るべきであろう。
キリストを信じていないユダヤ人たちは、この箇所の内容を理解できない。彼らは律法を守るには守るが、表面的に守るだけであって、その根底には愛がない。彼らの聖典であるタルムードには、律法をどのように遵守すればいいのかということについて実に詳しく書かれているが、ただ機械的な遵守の方法が書いてあるだけであって、愛の念がそこには全く感じられない。「どうしたら私たちは律法を隅々に至るまで完全に守れるだろうか。」という宗教的精神は伝わってくるのだが、「どうしたら私たちは神に喜ばれる精神をもって律法を守れるだろうか。」という念は全く感じられない。もし外面的に律法を行なえるのであれば、心の状態はどうでもいいかのようである。このような愛なき精神を持っていたからこそ、キリストはパリサイ人たちを厳しく責められたのである。我々は愛のないパリサイ的律法遵守の精神を自分から斥け、ここでパウロが言っているように、律法の本質が「隣人愛」であることを弁えるべきであろう。
この14節目および13節目の箇所では、明らかにガラテヤ人たちが互いに愛しあうようにと命じられている。13節目ではキリストによって与えられた自由を愛のために用いるように言われており、この14節目では律法の本質が人への愛にあると教えられているからである。どうしてこのように語られたかといえば、当時、ガラテヤの教会には愛の交わりが欠如していたからではないかと思われる。すなわち、ガラテヤの教会にいた聖徒たちに愛が欠如していたからこそ、パウロは愛に基づいた行ないが満ちるようにせよと聖徒たちに書いているわけである。この理解は、次の15節目を見るならばますます確かなものとなるだろう。パウロはこう言っている。
②『もし互いにかみ合ったり、食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。』(5章15節)
この聖句の内容から考えるならば、恐らく、当時のガラテヤ教会には『互いにかみ合ったり、食い合ったりしている』状態があったのだろう。または、そのような愛のない状態が生じそうな兆候があった。だからこそ、パウロはここで「あなたがたは互いにかみ合ったり、食い合ったりするな。」と忠告しているのである。このように忠告されているのだから、やはり、ガラテヤの教会には愛の交わりが十分に存在していなかったと考えられるのである。
この箇所から分かるように、我々が互いにかみ合ったり食い合ったりすることに対する裁きは「滅亡」である。「かみ合う」とか「食い合う」というのは、教会員たちが教理面であれ精神面であれ、互いに敵同士でもあるかのごとく愛のない対立に陥ることに他ならない。まだ肉に属していたコリント人たちは、『私はパウロにつく。』(Ⅰコリント3章4節)とか『私はアポロに。』(同)などと言って、互いに妬んだり争ったりしていた。このコリント人たちは『互いにかみ合ったり、食い合ったりしている』状態にあったと言って良いだろう。先にも話したことだが、恐らくガラテヤ人たちの間にも多かれ少なかれ愛のない対立状態が存在していた。このように対立しあうことは、夫婦や兄弟姉妹である者が互いに喧嘩をするのと似ている。このように近い間柄にある者たちが言い争うのであれば、最悪の場合、離婚をしたり疎遠状態になってしまいかねない。実際、互いにかみ合ったために離婚してしまった夫婦や、ほとんど縁を切ったのも同然の状態になった兄弟姉妹が今の時代にも存在している。これと同じように、キリストにあって互いに同胞である教会員たちの間に愛のない争乱が生じるならば、教会が分裂してしまったりするなどして目茶目茶な状態が生じかねない。
我々は、かみ合ったり食い合ったりして滅亡しないよう、自分の所属している教会内において愛の一致が保たれるようにすべきである。この15節目の箇所は、そっくりそのまま今の時代の教会に対しても言われている命令である。教会内に何か小さな問題が生じた時、もしその問題が致命的とはいえない事柄であれば、ある程度は妥協する精神も必要である。例えば、「使徒パウロは結婚していたのか、それとも独身だったのか。」という致命的とは言えない問題であれば、我々は、互いにかみ合ったり食い合ったりすべきではない。先週も話したが、「フィリピ書か、またはピリピ書なのか。」という問題でも、互いに敵対し合うべきではない。このように致命的とは言えない問題で対立して争ってばかりいたら、パウロが言うように、その教会は滅亡するに至るであろう。
「我々は、互いにかみ合ったり食い合ったりすべきではない。クリスチャンが喧嘩をし合って目茶目茶な状態になるのは避けるべきである。よって、カトリックもプロテスタントも仲良くやっていくべきである。」この15節目の箇所を読んで、このようなエキュメニズム的思念を我々は心に抱くべきではない。確かにパウロは、我々クリスチャンが争乱的になって滅亡すべきではない、気をつけよ、とこの箇所で命じている。だが、この箇所で言われている命令は、信仰・教派を超越した命令であるというわけではない。この命令は、信仰の一致する限りにおいて、また教派内において、我々が遵守すべきものである。ガラテヤの諸教会であれ改革派のあるグループであれ、その集団内においてはこの御言葉を心に留めるべきである。そうしないと、ここでパウロが警告しているように、その集団が争乱のゆえに滅んだりして目茶目茶になってしまいかねない。しかし、カトリックとプロテスタント、またカルヴァン主義の教会やアルミニウス主義の教会など、信仰的に一致していない間柄においては、話が別である。考えてほしい。信仰的に一致していないからこそ、また信仰的に一致できずに論争・不和が生じてしまうからこそ、ここまで沢山のキリスト教グループが存在している。プロテスタント勢力がカトリック教会から出たように、我々がバプテスト派から出たように、信仰が違っているからこそ様々な教派・教会が生じていくのである。もしこの箇所を読んで「カトリックもプロテスタントも敵対し合ってはならない。」などと考えるのであれば、いっそのこと、カトリックとプロテスタントを統一して同じグループにしてしまうべきである。思いきって、教派名も信奉する神学も一緒にしてしばえばよい。そうすれば本当に心から仲良くできるに違いない。しかし、両者が立っている神学はかなり違うのであって、我々プロテスタント教徒たちがカトリックの誤った神学を認めることは出来ないことである。もし神学を無視してまで合同と親愛を優先させるのであれば、それは真理を蔑ろにする行為に他ならない。あくまでも真理に拘る敬虔な精神を殺さない限り、真理よりも合同と親愛を上に位置させることは出来ないからである。だからエキュメニズム賛成論者とは、「真理よりも人間の親愛関係を優先させている妥協的信仰者」なのである。彼らは、真理にしがみついていない。真理への愛を蔑ろにして人間関係の方を大事にしている。それゆえ、我々はここで言われている命令を、信仰の一致する限りにおいて、また自分の属している教派内において、大いに遵守すべきである。異なった信仰を持っている教派と仲良くするのは非常に難しい。もし妥協するというのであれば、異なった信仰を持っているグループと、問題もなく穏やかにやっていけるかもしれない。しかし妥協せず真理に固執するのであれば、穏やかになるのは不可能に近い。最初のうちは平和であっても、いつか必ず、論争や不和といった分裂を引き起こす要因が芽を出すことだろう。信仰的に一致できないにも拘わらず教会合同を願っている方がたは、暗にこう言っているのも等しい。「エキュメニズムだ。一致こそが何より大事だ。カトリックもプロテスタントも仲良くやろう。御言葉や真理や信仰よりも統一関係こそが重要だから。」しかし、御言葉や真理や信仰を蔑ろにしてまで統一を求めることは出来ない。宗教改革者のブツァーは次のように書いている。「宗教上の不一致のあるところでは、いかにして統一を期待できましょうか。」(※②参照)ルターも次のように正しく言っている。「神のことばが危うくされても保たれねばならない愛と一致は呪われよ」(※③参照)。このルターによると、カトリックなどの異常な信仰を持っている存在と一致することは「われわれが真の教えを失ったたしかなしるし」である(※④参照)。宗教改革者たちが今の時代における仲良し主義、すなわちエキュメニカル運動について知ったならば愕然とするに違いない。我々はこの15節目の箇所を読んで、エキュメニズムを肯定したり、「いがみ合ってばかりいないでカトリックとも仲良くしないといけないな。」などと思うべきではない。
③パウロの大胆な叱責および追及について
我々が今見ているこの手紙を見ただけでも明らかに分かることだが、パウロは実に辛辣な言葉をもって叱ったり指摘したりしている。これは他の使徒たち、またキリストにおいても同様である。使徒であれ誰であれ、真理を伝える教師に特徴的なのは「大胆さ」である。例えばヤコブは『貞操のない人たち。』(ヤコブ4章4節)また『ああ愚かな人よ。』(ヤコブ2章20節)などと容赦なく言っており、非常に大胆である。今の時代では、厳しいことを言ったり叱責したりするなどといった行為は、あまり見られなくなっている傾向がある。「今日の大学はあまり叱らないのです。親は叱らない、先輩は叱らない、先生も叱らない。会社へ入っても会社は叱らない。やめられたら困るから、なんとかご機嫌をとる。」これは昭和44年に松下幸之助が口にした言葉だが(※⑤参照)、このように言われてから50年近く経った今でも、ほとんど状況は変わっていない。どこもかしこも叱ったり叱られたりするのを避けている有様である。叱る側の人間は辞められたり嫌われたり逃げられたりするのを恐れて、叱ることに抵抗感をもつ。叱られる側の人間も、叱られるのが気に入らないから、叱られたら反発したり敵意を持ったりする。叱られる側が叱られたことにより反発すると分かれば、叱る立場にある人間は反発されたくないので叱らないようになる。教会でも、事態は同様である。今の教会では、ほとんど叱責がなされない傾向がある。だが、パウロのごとく過ちに対して厳しい言葉を発する、という行為は忌避されるべき行ないではない。パウロや他の使徒たち、またキリストのように、悪徳を大胆に責めるからこそ、責められた人たちは自分の過ちや未熟さに気づいて改善できるようになる。もし率直に追及されないのであれば、それだけ兄弟姉妹が自分の悪徳に気づいて改善するようになる確率は低まる。例えば、スポルジョンは「あなたがたは聖書を読んでいない。あなたがたの家の隅に置いてある聖書は、埃まみれになっているではないか。おお、なんという有様か。」また「あなたがたは全然祈っていない。神との交わりをどうして望まないのか?おお、何という状態であることか。」という内容のことを平気で言っていたが、これは容赦のない大胆な言説である。このように厳しく言われるからこそ、言われた人たちは自分の至らなさに気付けるようになるのである。このスポルジョンの場合であれば、大胆に言われたことにより、聖書を読んでいなかった人たちは埃まみれになっている聖書を読むようになるかもしれないし、あまり祈っていなかった人はよく祈るようになるかもしれない。何故なら、「あなたは聖書を読んでいない。」「あなたは祈っていない。」と率直に言われたので、自分が聖書を読んでいなかったこと・祈っていなかったことを痛切に実感するからである。今の社会が、叱ることに抵抗感を抱いている傾向にあるのは確かである。自分の子どもに懲らしめを与えるのであれば、虐待だ、暴力だ、異常だ、などと思われかねない。このような現代社会において、世の光たる教会こそが、パウロのごとく、不敬虔や過ちを正すということを大胆に行なわねばならないと思える。教会の教師たちが、指導・叱責・矯正を大胆になって行なった使徒たちに倣うのは悪いことではないであろう。パウロのように大胆な聖書的教師たちが沢山いるのであれば、教会もより幸いな状態になっていくであろう。もし知恵もなく無思慮に、また愛のない精神に基づいて厳しいことを言うのであれば、険悪に満ちた不和が教会内に満ちることにもなりかねない。しかし、パウロのごとく知恵をもって、また愛に基づいた精神によって悪徳を正すべく大胆に言うのであれば、より聖徒たちがキリストに喜ばれる敬虔な歩みをすることが出来るようにもなるであろう。
※①
『「姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな。」という戒め、またほかにどんな戒めがあっても、それらは、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」とうことばの中に要約されているからです。』
[本文に戻る]
※②
マルティン・ブツァー「四都市信仰告白」 むすび
教文館:「宗教改革著作集 14信仰告白・信仰問答」p157
[本文に戻る]
※③
聖文舎:「ルター著作集」第2集12 ガラテヤ大講解・下 p195
[本文に戻る]
※④
それだから、教皇や司教や諸侯や熱狂主義者がわれわれとひとつ心になることを、私は望まない。その一致は、われわれが真の教えを失ったたしかなしるしとなるからである。
聖文舎:「ルター著作集」第2集12 ガラテヤ大講解・下 第5章(12)p307~308
[本文に戻る]
※⑤
PHP研究所:松下幸之助「かえりみて明日を思う」 日本を見直す(昭和44年12月14日)p111
[本文に戻る]
ガラテヤ人への手紙5章16~17節(2016/06/19説教)
『私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら、肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなたがたは、自分のしたいと思うことをすることができないのです。』(ガラテヤ5章16~17節)
先週の箇所は14~15節目であった。14節目では、律法の本質が隣人愛であるということについて語られた。『あなたがたは互いに愛し合いなさい。』(ヨハネ13章34節)とキリストが命じておられる通り、互いに同胞である兄弟姉妹は愛し合わねばならない。もしそうしないのであれば、聖徒たちには本来あるべき本質的な性質が一つ欠けていることになってしまう。15節目では、我々は滅びないため互いにかみ合ったり食い合ったりすべきではないが、これは同じ信仰を持った集団内において適用されるべき事柄であるということについて語られた。我々は、同じ信仰を持った仲間の間においては、あたかも敵同士であるかのように互いにかみ合ったり食い合ったりすべきではない。しかし、『友だちが悪ければ、良い習慣がそこなわれ』(Ⅰコリント15章33節)てしまうのだから、真理に基づく良い習慣を破壊してしまう忌わしい神学をもった非聖書主義者たちのグループとは、仲良くすべきではない。例えば、最高の指導者である教皇がイエス・キリスト以外にもマリヤという仲保者を認めるような教派と、どうして仲良くやっていけるというのか。真理に対する忠誠心を捨てない限り、このような団体とは親愛的な関係を結ぶことは出来ないと私には思われる。本日は16節目からである。
①『私は言います。』(5章16節)
5:2の箇所でも『このパウロがあなたがたに言います。』と言われているのを以前、我々は見た。このように言われるのは、つまり「使徒であるこのパウロがあなたがたに告げるのだから、よく注意して聞きなさい。」ということである。主も、たびたび『まことに、あなたがたに告げます。』と言われてから、重要な事柄について告げておられるのが福音書を見ると分かる。主がこのように言っておられるのと、パウロが『私は言います。』と言っているのは、非常によく似ている。どちらも、これから語られることになる重要な事柄をよく注意して聞かせるため、事前に「私はあなたがたに告げる。」と言っている。
②『御霊によって歩みなさい。』(5章16節)
御霊によって歩むとは一体どういうことか。それは、我々のうちにおられる御霊によって聖書に記されている神の御心を正しく実行するということである。『聖書はすべて、神の霊感によるもの』(Ⅱテモテ3章16節)と書いてあるが、つまり聖書とは御霊によって書かれたものであるから、そこに書かれている命令を御霊によって行なうことこそ「御霊によって歩む」ということである。例えば、『盗んではならない。』(出エジプト20章15節)という御霊によって記された命令を、御霊によって我々クリスチャンが守るならば、その人は御霊によって歩んでいる。御霊によって歩む人は、かならず御霊によって記された命令を守るからである。しかし、『盗んではならない。』という命令を守らず他者の所有物を盗むクリスチャンがいたのであれば、その人は御霊によって歩んではいない。周りの兄弟姉妹がそのクリスチャンに対して、「彼は確かに御霊によって歩んでいる。」と言ったとしても無駄である。何故なら、その人は、御霊が記された命令に反した行為をしているからである。御霊によって書かれた命令に従っていないのに、どうして「御霊によって歩んでいる。」などと言えるだろうか。
③『そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。』(5章16節)
もし我々が御霊によって歩むのならば、罪深い肉の行ないに歩むことはない。先に語られたように、『盗んではならない。』という御霊による命令を守って人の物をかすめないのは、「御霊によって歩む」ということである。しかし『盗んではならない。』という御霊による命令を守らず人の物を奪うのは、「肉によって歩む」ということである。我々は、この2つの行ないのうち、どちらか一方の行ないしか出来ない。すなわち、御霊に従って「盗まない」という行ないをするか、肉に従い「盗む」という行ないをするか、どちらか一つしか選べない。前者の方を行なえば後者が退けられ、後者の方を行なえば前者が退けられる。「盗まない」が「盗む」とか、「盗む」が「盗まない」という矛盾した行ないはあり得ない。それゆえ、もし御霊に従って盗まないのであれば、必然的に、肉による行ないである「盗む」という行ないに歩むことは無い。だから、ここでパウロも言っているように、もし我々が御霊によって歩むのであれば、必然的に忌わしい肉的行為から遠ざけられるのである。そういう人であれば、『決して肉の欲望を満足させるようなことはない』であろう。
もし御霊によって神の言葉に従うのならば、我々が肉の行ないに歩むことはない。このことについて、内容的によく似ている聖句が詩篇にある。その箇所とは詩篇119:9である。次のように書いてある。『どのようにして若い人は自分の道をきよく保てるでしょうか。あなたのことばに従ってそれを守ることです。』ここでは、もし若い人が御言葉に従うのなら清い道を歩み続けられるだろう、すなわち肉の道に歩むことはないだろう、と言われている。我々が今見ているガラテヤ書の箇所も、この詩篇の箇所も、どちらも「もし御霊によって御言葉に歩むのであれば肉的言動は斥けられるであろう。」ということが言われている。キリストの為に生きるべく召された我々は、神の御言葉に歩むならば肉の行ないを防止できるということを知るべきであろう。御言葉の遵守に全神経を集中させるならば、自ずから罪深い肉の行ないは窒息して消えさる。
我々クリスチャンには、霊的な戦いが常にある。すなわち、我々の内には、御霊によって御言葉に従って歩むか、それとも肉の欲望を満足させる行ないに歩むか、という霊的な葛藤がいつもある。キリスト者であれば、この問題に悩まない人はいない。ローマ7章を見れば分かるように、使徒パウロでさえこの問題に苦しめられていた。敬虔に歩んでいたパウロでさえ罪深い肉的な行ないと無縁でなかったすれば、我々は尚更のこと、無縁ではないであろう。しかし、この箇所では「御霊によって歩むことにより肉の欲望を満足させないようにすべきである。」と命じられている。それゆえ、我々はここで言われている命令を心に留め、肉ではなく御霊によって歩むようにせねばならない。だが、我々が御霊によって歩むことを願ったとしても、往々にして『自分でしたいと思う善を行なわないで、かえって、したくない悪を行なって』(ローマ7章19節)しまうものである。肉に唆(そそのか)されて罪を犯してしまわない人など、我々の中に一人すらもいない。どれだけ敬虔な信仰者であっても、肉に動かされて何らかの罪を犯してしまう。それは、我々のうちに罪の残滓があるからである。もし我々が御霊によって歩めず肉に歩んでしまったのであれば、その時はどうすればいいのか。その時は、『神さま。こんな罪人の私をあわれんでください。』(ルカ18章13節)と言った取税人のように我々の心を低くし、神の御前に悔い改めねばならない。
我々が御霊に歩まないで肉に歩むのは、『新しい人』(コロサイ3章10節)を破壊することである。肉の行ないとは『古い人』(コロサイ3章9節)としての性質に属するものであって、『新しい人』である我々には相応しくないものである。キリストによって救われた我々は新しい人を着たのであるから、パウロが言うように『造り主のかたちに似せられてますます新しくされ』(コロサイ3章10節)るべきである。その為には、この箇所でパウロが言うように、御霊によって歩まねばならない。ますます御霊によって歩めるようになれば、それだけ忌わしい肉の行ないから遠ざかる傾向が強まるであろう。このような歩みが実現されるからこそ、我々は、キリストに似たものとして更に刷新されていくのである。もし我々が肉の行ないから遠ざからないのであれば、つまり、ますます御霊によって歩めるようになっていかないのであれば、我々が更に新しくなっていくのは難しいであろう。我々クリスチャンとはますます新しくなっていくべき存在であるから、ますます御霊によって歩み、ますます肉による歩みが殺されていくということを追い求めるべきである。
「あなたがたは御霊によって歩むべきであり、肉の欲望を満足させるべきではない。」…ここでパウロがこのように言っているのだから、恐らく、ガラテヤ人たちはコリント人のように肉的な行ないに歩んでいたのではないかと思われる。つまり、ガラテヤの諸教会に肉的な言動が満ちていたからこそ、この箇所でパウロは注意を喚起しているのだと考えられる。もしガラテヤ人が素晴らしい敬虔な歩みをしていたのであれば、恐らくパウロはこのように言っていなかったと私は思う。もしガラテヤの諸教会に素晴らしい敬虔な信仰が満ちていたのであれば、パウロは、主が百人隊長の信仰を褒められたようにガラテヤ人たちの信仰を称賛していたであろう。しかしパウロはそうはせず、「御霊によって歩め。肉の欲望を満足させるな。」と命じている。この16節目以降の箇所を見ても、ガラテヤの諸教会には肉的な傾向があったように思われる。文の流れや内容から考えるならば、やはり、ガラテヤ人たちには肉的な傾向があったのだと理解するのが妥当であろう。
ここでパウロは『肉の欲望』と書いているが、誤謬に満ちたカトリックは、この言葉が「性欲」を指していると考えていた。言うまでもないが、ここでは「性欲」のみを指して『肉の欲望』と言われているのではない。そうではなく、ここでは「聖書に反した人間的な言動および思念全般」を指して『肉の欲望』と言われている。つまり、持つべきではない不適切な情欲だけでなく、嫉妬であれ傲慢であれ暴虐であれ偽証であれ不信であれ放埓であれ、あらゆる非聖書的な言動および思念を指して『肉の欲望』と言われている。普通に考えれば、『肉の欲望』=「非聖書的な忌わしい願望および言動」という理解になるはずである。どうして彼らは、『肉の欲望』=「(不適切な)欲情のみ」という理解をするのか。我々は、盲目的理解に満ちたカトリック派でもあるかのように、ここでは不正な性欲についてだけ言われているのだと考えるべきではない。
次は17節目である。
④『なぜなら、肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなたがたは、自分のしたいと思うことをすることができないのです。』(5章17節)
先にも述べたように、我々は「肉の願うことに従って御霊に逆らうか」、または「御霊に従って肉の願うことに逆らうか」という2つの内、どちらか一つしか選べない。前者を取れば後者を退け、後者を取れば前者が退けられる。永遠の世界においては、聖徒たちは御霊による言動以外をすることが無いから、常に御霊によって歩むであろう。しかし、今の人生においては、我々の身体のうちに『悪が宿っている』(ローマ7章21節)ために、「御霊に従うか、それとも肉に従うか」という葛藤における霊的な戦いが存在している。もし我々が肉を殺し、御霊によって歩むならば神から祝福される。しかし、我々が御霊によって歩まないで肉に従えば罰は免れない。我々がどちらの方を選ぶべきかはあまりにも明白である。我々は、御霊による行ないに進み、神からの祝福を頂けるようにすべきである。我々が御霊による行ないではなく罪深い肉の行ないに歩んでしまった場合、肉の行ないをしたその時は心が偽りの満足で満たされるかもしれないが、後には裁きが襲い掛かるであろう。例えば、肉に従って不倫をしたのであれば、その時は喜悦を味わえるかもしれないが、後には夫婦間の不和または離婚という悲惨な状態に陥ることになる。また、肉に歩んで店の商品を盗んだのであれば、その時は嬉しいかもしれないが、やがて見つかったならば恥と損害というダメージを食らうことになる。我々が御霊によって歩むことは神からの祝福を求めることであり、肉によって歩むことは神からの祝福を遠ざけることである。この聖書的原理を、神の民である我々はよく弁えるべきであろう。
神は、イエス・キリストによって御霊を我々に豊かに注いで下さった。これは、つまり救われてクリスチャンとされた我々が御霊によって歩むのを神が望んでおられるということである。言うまでもなく、我々を救って下さった主キリストも、聖徒たちが御霊によって歩むのを願っておられる。我々は、「御霊による道」と「肉による道」という2つの道があった場合、どちらか一方に歩まねばならない。御霊の御心は、我々が「御霊による道」の方に進むことである。我々クリスチャンの信仰人生における基本原理とは、「御霊によって歩み、肉の行ないを殺す」というものである。つまり、我々が御霊によって歩むのであれば、我々はクリスチャンとして相応しい、神の御心に適った歩みをしていることになる。もし御霊によって歩まず肉にばかり歩んでいるコリント人のようであれば、クリスチャンとしての歩みをしているとは言い難い。キリストによって救われた神の民である聖徒たちは、御霊によって歩めるように心から願うべきである。どうか、慈愛に満ちた神が、我々一人一人が肉ではなく御霊によって歩めるように、いつも御恵みを施して下さいますように。アーメン。
ガラテヤ人への手紙5章18~21節(2016/06/26説教)
『しかし、御霊によって導かれるなら、あなたがたは律法の下にはいません。肉の行ないは明白であって、次のようなものです。不品行、汚れ、好色、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、ねたみ、酩酊、遊興、そういった類のものです。』(5章18~21節)
先週は、我々が肉ではなく御霊によってこそ歩むべきことについて語られた。クリスチャンの信仰人生では、肉が殺され御霊によって歩むようになる度合いが増されていかねばならない。本日は18節目からである。
①『しかし、御霊によって導かれるなら、あなたがたは律法の下にはいません。』(5章18節)
御霊によって神の御心の道に歩んでいる人の内には、御霊がおられる。何故なら、その人の内に御霊が住んでおられないのであれば、御霊によって歩むことなど出来ないからである。もし御霊がその人の内におられるのであれば、その人はイエス・キリストによって救われている存在である。何故なら、イエス・キリストによって救われた人には、かならず御霊が注がれているからである。もしイエス・キリストによって救われているのであれば、その人は、律法に隷属する奴隷状態から解放されて自由になっている。何故なら、救われている人は、律法の奴隷となっている状態からイエス・キリストによって贖い出されたからである。それゆえ、御霊によって歩んでいる救われているクリスチャンとは、律法の隷属状態から贖いだされた自由の民なのである。だから、パウロがここで言っているように、「御霊によって導かれている人」とは即ち「律法の下にいない人」ということになる。つまり、我々が御霊によって歩んでいるのならば、それは我々が律法の下にいないことの明白な証拠である。
クリスチャンが御霊によって歩むということは、つまり「肉によって歩まない」ということである。何故なら、先週も話されたように、我々は「御霊に従って歩むのか」「肉の行ないによって歩むのか」という2つの選択肢の内、どちらか一つしか取れないからである。御霊によって歩むのならば肉の行ないによっては歩めず、肉の行ないによって歩むのならば御霊によっては歩めないのである。この「肉による行ない」というものが一体どのようなものなのか、パウロは19~21節目において具体的に書いている。
この肉の行ないについて説明するにあたり、パウロはまずこう言っている。
②『肉の行ないは明白であって、次のようなものです。』(5章19節)
肉の行ないとは明らかに見分けられるようなものであると、パウロは言っている。もし霊的に鈍感になっていないのであれば、我々は聖書によって肉的な行ないを見分けられるであろう。しかし、霊的認識能力が衰えてしまったのであれば、本来であれば見分けられる肉の行ないを見分けられなくなってしまう。例えば不倫行為は明らかに肉の行ないであるが、霊的に鈍くなれば、このような行ないが為されているのを見ても何も感じなくなってしまう。実際、ドイツのある町では牧師が愛人を作ったという話が広まったのにも拘わらず、その町の人たちは霊的な道理が分からなかったので、悪く思うどころか安心してしまった。
それでは、パウロが挙げている肉の行ないについて見て行きたい。
③『不品行、汚れ、好色、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、ねたみ、酩酊、遊興、そういった類のものです。』(5章19~21節)
『そういった類のものです。』とパウロが言っているように、ここに挙げられているのは少数の例にすぎない。つまり、全ての肉の行ないが列挙されているのではない。しかし、ここに書かれている幾つかの肉的な行ないを見るならば、「肉的な行ないとは一体どのような種類のものなのか」ということについて、我々は察することが出来るであろう。
ここでパウロが挙げている肉の行ないは、4つのカテゴリーに分類できる。一つ目は『不品行、汚れ、好色』であり、これは「貞潔を破壊する性的汚濁」に関することである。二つ目は『偶像礼拝、魔術』であり、これは「神に対する反逆・不信・不敬」に関することである。三つ目は『敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派』であり、これは「教会における愛の交わり」に関することである。四つ目は『ねたみ、酩酊、遊興』であり、これは「肉的な愚かさ」に関することである。
4つのカテゴリーの内、聖徒たちの交わりに関する事柄が、最も多く書かれている(即ち『敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派』である)。これは、前にも話したことだが、ガラテヤの諸教会に愛の交わりが欠如していたことを示していると考えられる。つまり、ガラテヤ人の間には多かれ少なかれ愛なき争乱が存在していたからこそ、ここでは「聖徒の交わりに関する事柄」が最も多く挙げられているのだと思われる。
ここで挙げられている事柄を、カテゴリーごとに見て行きたい。
■不品行、汚れ、好色
『姦淫してはならない。』(出エジプト20章14節)と十戒では命じられている。また、『不品行を避けなさい。』(Ⅰコリント6章18節)と神はパウロを通して命じておられる。神は、我々に純潔を望んでおられるのである。神は聖であられるから、神の民である聖徒たちも聖くなければならないのである。不倫、ポルノ、性風俗などといったものは、我々の純潔を破壊する肉的なものである。これらのものに歩む者は、肉の行ないをしている。もしこのような肉の行ないに歩むのならば、裁きは免れないであろう。『神は不品行な者と姦淫を行なう者とをさばかれる』(ヘブル13章4節)と言われている通りである。
■偶像礼拝、魔術
十戒には次のように書かれている。『あなたには、わたしのほかに、ほかの神々があってはならない。あなたは、自分のために、偶像を造ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも造ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。』(出エジプト20章3~5節)神以外の存在を神とする偶像崇拝者は、偶像崇拝という反逆的な肉の行ないによって真の神を侮辱し、斥け、否定している。その人が本来崇拝されるべき当然の神を自分から遠ざけ、他の存在を神の位置に据えているからである。神は御自身に並びたつ存在を許容できない御方であるから、最終的に、偽りの神々や偶像はことごとく滅ぼされるであろう。神ではない存在を拝んでいる偶像崇拝者も忌わしい肉の行ないをしているのだから、真の神によって裁かれるであろう。『魔術』という肉の行ないも、悪魔であれ悪霊であれ偽りの神々であれ神秘的な存在であれ、神以外の存在から超越的な力を得ようとするのだから、神への反逆行為である。魔術を行なっている者たちは、その行ないによって、自分が偶像崇拝者であることを示している。何故なら、彼らは人知を超えた驚くべき力や能力を、神ではない存在にこそ求めているからである。魔術を行なう者たちは神を退け、神ではない存在にこそ素晴らしい力を願うのであるから、真の神に代えて神ではない存在を認め、尊重しているのである。これが偶像崇拝でなくて何であろうか。今話された、この『偶像礼拝』および『魔術』とは、パウロが言うように『肉の行ない』である。それは御霊による行ないではない。
■敵意、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派
この手紙の5:15で、「互いにかみ合ったり食い合ったりしないように気をつけよ。」と言われているのを我々は見た。それは、我々が敵対しあって滅びないためである。我々が互いに敵対しあったり、致命的でない問題で争いあったり、「何であの人ばかり…」などとそねんだり、兄弟姉妹に対して憤怒したり、コリント人のように党派心を抱いたり、愚かになって分裂したり、自分勝手に分派を作り出そうとするのは、『肉の行ない』である。このような肉の行ないに歩んで争乱が生じるのであれば、パウロが言っているように、我々は滅びに至ってしまうであろう。『あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。』(レビ19章18節)と律法では命じられている。つまり、我々クリスチャンはこの世の人々を愛さなければならない。もし我々がこの世の人々をも愛するべきなのであれば、尚更のこと、兄弟姉妹である者たちを愛さねばならないのは言うまでもない。我々クリスチャンは互いに愛し合うべきであるから、教会の内に、愚かな争乱状態が生じるのは望ましいことではない。神は、我々クリスチャンの間に、愛と平和が存在しているのを望んでおられるのである。
■ねたみ、酩酊、遊興
この3つのものは、弱々しい未熟な心から生じる愚かな行ない、また心の状態である。どうしてそう言えるかといえば、もし神によって心が強められるならば、我々はこれらのものを避けることが出来るからである。これらのものは、ノンクリスチャンにおいては悪とは見なされていないが、我々クリスチャンにおいてはれっきとした悪として認識せねばならない。まず説明するのは『ねたみ』についてであるが、十戒で『すべてあなたの隣人のものを、欲しがってはならない。』(出エジプト20章17節)と命じられていることからも分かるように、嫉妬とは非聖書的な御心に適わない心の思いである。ヨセフはどの兄弟たちよりも父ヤコブから愛されていたので、兄たちの心にはヨセフに対する妬みがあった。この妬みのゆえに、兄たちはヨセフを憎み、殺意すら抱くようになった。このように、「妬み」とは悪い感情を自然に引きおこす性質をもったものである。これは非常に恐ろしいことである。何故なら、もし妬みという肉の思いを心に持つならば、悪い感情が起こったのに基づき、悪しき肉の行ないが生じかねないからである。『酩酊』とは、泥酔して狂った妖怪のようになってしまうことである。ここで注意せねばならないことがある。それは、「酒は飲んではならないものだ。」と勘違いしている教派が非常に多いが、聖書では酒を飲むこと自体は禁止されていない、ということである。聖書が禁じているのは、「酒を飲む」ことではなく、「泥酔して理性を失ってしまう」ことである。主も酒を飲まれたのだから、聖書が飲酒自体は禁止していないのは明らかである。それゆえ、飲酒自体はここで言われている『酩酊』にはあたらず、ゆえに『肉の行ない』ではない。酒に酔って異常な状態になってしまうのが『酩酊』なのであって、これこそ『肉の行ない』である。『遊興』と書いてあるが、これは愚かさに満ちた宴会や度を越した娯楽パーティーなどのことであろう。例えば、どこかの旅館で宴会が開かれ、すべきではない愚かな話が平気で交され、踊り子に卑猥な振る舞いをさせ、酒に酔って理性を失った人が沢山おり、気儘放題な雰囲気が漂っている、という目茶目茶な状態があれば、それは明らかに『遊興』と言うべきものである。このような混沌とした状態にある宴会に参加している際、自分も一緒になって愚かな振る舞いをするようであれば、それは『肉の行ない』である。このような宴会が肉的なものであることは、誰が見ても明らかであろう。しかし、「宴会」と名のつく全ての集まりが『遊興』また『肉の行ない』であると言うわけではない。もし節度を弁えた紳士的な集まりであれば、それは『遊興』と言うべき宴会ではないし、『肉の行ない』でもない。我々の主も食事会において色々と食べたり飲んだりされ、多くの人と共に交遊されたのである。つまり、ふざけた馬鹿騒ぎの伴う愚かさに満ちた宴会こそ『遊興』なのであって、理性に支配された紳士的・常識的な宴会は『遊興』ではない。
キリスト者の内には、ここで挙げられているような肉の行ないは存在すべきではない。何故かといえば、我々は汚らわしい肉の行ないから遠ざかり、聖潔から聖潔に向かって歩むような人生へと変えられるために召されたからである。『神が私たちを召されたのは、汚れを行なわせるためではなく、聖潔を得させるためです。』(Ⅰテサロニケ4章7節)と書かれている通りである。だが、堕落している我々は、自力によって肉の行ないを忌避し、聖なる行ないを選び取ることは出来ない。罪深い我々は、神の恵みがなくては、悪徳から悪徳に向かって進むのみである。このことは、聖く歩むべき者でありながら大きな悪に陥ってしまったダビデの例を考えれば、明らかに分かるであろう。彼は、肉に動かされて本来であればすべきではない大きな悪事を為してしまったのである。我々は神の恵みが無ければ肉の行ないから遠ざかれないのだから、常に、神の恵みを願い求める必要がある。そうすれば、我々自体は罪深く愚かであっても、神の恵みにゆえに聖潔から聖潔へと進めるようになるであろう。『何事でも神のみこころにかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださる』(Ⅰヨハネ5章14節)と書かれているように、我々が聖潔という神の御心に適ったものを願い求めるならば、神はその願いを叶えて下さるからである。
永遠の天国には、ここに挙げられているような肉の行ないは塵ほども存在しない。何故なら、天国とは悪がまったく存在しない、聖なる世界だからである。だから、天国にいる聖徒たちが肉の行ないをすることは全くない。何故なら、天国にいる聖徒たちはもはや何の罪をも犯さず、永遠に聖い行ないのみをするからである。もし天国にいる聖徒が罪を犯すのであれば、その聖徒はエデンの園から追い出されたアダムとエバのように天国から追い出されねばならないが、そのようなことはあり得ない。何故なら、天国にいる聖徒は、神の恵みによって悪から完全に守られているからである。このような聖なる世界に、クリスチャンである我々はいずれ導き入れられるのである。真のクリスチャンであれば、この人生が終わった後、天に凱旋するのである。これは、主イエス・キリストの尊い贖いのゆえに、我々が贖われ、聖められ、罪の赦しを受けたからに他ならない。主キリストによって救われたからこそ、我々は救われた者として天国という至福の世界へと導かれるのである。もし、我々がイエス・キリストに対する信仰によって救われるように選ばれていなかったとしたら、救われることが無いのだから、天国にも導かれなかったことであろう。しかし、我々はキリストによって救われるように選ばれていたからこそ救われ、いずれ天国に導かれることになる種族とされたのである。それゆえ、我々を地獄から免れさせ天国へと行けるようにして下さった主イエス・キリストに対して、我々は永遠に感謝を捧げねばならない。どうか、我々の救いのためにイエス・キリストを与えて下さった父なる神に、栄光が永遠にありますように。アーメン。
ガラテヤ人への手紙5章21~23節(2016/07/03説教)
『前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなたがたにあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。』(5章21~23節)
先週は18~21節目の箇所から、我々が忌避すべき「肉の行ない」について話された。本日は21節目の途中の箇所からである。
①『前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなたがたにあらかじめ言っておきます。』(5章21節)
この手紙の1:9でも『私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います。』と書かれていたが、この箇所と、我々が今見ているこの21節目の箇所は内容的によく似ているのが分かる。パウロは、ガラテヤ人が正しく歩めるようになるために、以前話された内容を繰り返して話すことを厭(いと)わなかった。この手紙を見れば分かるように、パウロはガラテヤ人のためなら10回でも20回でも同じ内容を繰り返して語ったであろう。それは、何度も言わなければ分からないほどガラテヤ人の霊的感性が鈍かったからである。
②『こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。』(5章21節)
ここでパウロは、もし肉の行ないに歩み続けるのであれば永遠の命はその人にあり得ない、と言っている。これは、読者に対する恐るべき霊的脅迫である。このように言うのは、あたかも大音量の恐るべき雷を鳴り響かせているかのようである。パウロはどうして、このように言ってガラテヤ人を恐れさせようとしているのだろうか。それは、ガラテヤ人たちの魂を強く揺り動かすためであった。いかにガラテヤ人のように霊的に鈍かったとしても、「もし肉の行ないをしているのであれば御国の相続などあり得ないのだ。」などという恐ろしい言葉を聞いたのであれば、その言われている内容に強く反応せざるを得ない。つまり、「俺たちは肉の行ないに歩んでしまっているだろうか?」などと自分自身の歩みを省察するように動かされざるを得ない。このように、パウロはガラテヤ人たちの心を動かせるため、ここで恐るべき脅迫の言葉を書いているのである。鈍い人たちを動かそうとする場合、このような恐ろしい警告は非常に効果的である。このような霊的脅迫は、パウロだけでなく、使徒ヨハネもその第一の手紙において行なっているものである。
ここで言われているのは、「もし一回でも肉の行ないに歩んだならば、その人には御国の相続はあり得ない。」ということではない。もしこのような意味で言われたのだとしたら、我々は絶望するしかなかったであろう。はたして、不品行に陥ってしまったダビデ、酒に酔って異常になってしまったノア、対立し合っていたコリント人たちは、肉の行ないに歩んでしまったから神の国を継ぐことが出来なかったのだろうか?絶対にそんなことはあり得ないことである。ダビデとノアおよび選ばれていたコリント人たちは、確かに肉的な行ないをしてしまったが、あくまでも御国を継ぐために選ばれていた人たちだったはずである。ここで言われているのは、「一回でもミスをしたらアウト」ということではない。そうではなく、ここで言われているのは、「いつまでも頑なな心のまま肉の行ないに歩み続けている者には御国の相続はあり得ない」ということである。つまり、短期的な意味において言われているのではなく、長期的な意味において言われているのである。もし少しだけでも肉の行ないをしたなら我々から御国が取り上げられてしまうのであれば、我々のうち、誰一人として御国を継ぐ者はいなかったであろう。
我々は、ここで言われているパウロの警告を心に留め、肉の行ないを忌避する精神をますます強く持たねばならないであろう。パウロが言うように、肉の行ないに歩み続ける頑なな人生に陥ってしまっている者たちは、神の国を継ぐことが無いのだから。
次は22~23節目である。
③『しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。』(5章22~23節)
今度は、パウロは、御霊の結ぶ実について具体的に挙げている。ここで挙げられているものも、肉の行ないについて列挙された時(19~21節目)と同じように、何もかも網羅されているというのではない。ここで並べ立てられているのは、一部分だけである。ここで数え上げられているものを見るならば、御霊の実が一体どのようなものなのか、我々は感覚的に察することが出来るであろう。例えば、この箇所で列挙されているものを見るならば、他にも「憐れみ」「慈しみ」「情け」「平和」といったものが御霊の実であるということを類推できるであろう。
ここで挙げられている『御霊の実』は、全部で9つある。一つ一つ見て行きたい。
■愛
愛が一番最初に挙げられているが、これは、クリスチャン人生における最高の原理が「愛」でなければいけないからであろう。つまり、我々クリスチャンにとって「愛」というものがあまりにも重要なものであるがゆえに、ここでは「愛」が何よりもまず第一に挙げられているのである。パウロが言うように、もし愛がなければ何もかもが無益・無価値・無意味となってしまうのだから、その重要性は測り知れないものがある。この愛の性質については、Ⅰコリント13:4~7に具体的に書かれている。御霊によって歩む者は、必然的に、愛に満ちた実を生じさせる。
■喜び
御霊によって歩む者、すなわち御霊によって聖書の御言葉に歩む者には、聖なる喜びがある。どうしてかと言えば、その人が御霊によって良い歩み・良い行ないをしているからである。悪い行ないをすれば腐敗した喜びが生まれるだけだが、良い行ないをすれば真の喜びが生まれるものである。もし我々が御霊によって神の命令のうちに歩むのであれば、必然的に、幸いに満ちた喜びを得られることであろう。詩篇記者も、次のように書いている。『私に、あなたの仰せの道を踏み行かせてください。私はその道を喜んでいますから。』(詩篇119篇35節)この御言葉からも分かるように、我々が御霊によって神の御心を行なうならば、その行ない自体によって喜びが発生するであろう。
■平安
御霊によって神の命令の内に歩むのならば、喜ばしい平安が生じるようになる。何故なら、その人が神に喜ばれる歩みをしているからである。『あなたのみおしえを愛する者には豊かな平和があり、つまずきがありません。』と詩篇記者も述べている(119篇165節)が、神の道に歩むならば、霊的な平穏を享受できるようになる。魚は水の中で生きるように造られているので、水の中を動いている時だけ、平安がある。釣られて水のない場所に置かれるならば、魚には平安が無いだろう。それと同じように、人間も神のために生きるように造られたので、御霊によって神の道に歩んでいる時には平安が生じるのである。しかし、御霊に歩まず肉の行ないに歩むのであれば、その人に真の平安はない。その人が成すべきこと―神の御心―を行なっていないからである。もし肉の行ないに歩んで平安を感じたとしても、それは偽りの平安にすぎない。
■寛容
御霊は、我々クリスチャンを寛容な性質にさせて下さる。つまり、聖書に違反しない限りは多様性を認め、悪い行ないでなければ突飛な言動に対して激怒しないようにさせて下さる。簡単に言ってしまえば、「心の広い、受容性に富んだ性質を持たせて下さる。」ということである。例えば、暴走しそうなほど元気な子供を見たら、その溌剌(はつらつ)な性向を否定したり批判したりしないようになる。何故なら、子供における元気さとは神が備えられた性質であって、それは受容すべき性質だからである。
■親切
御霊は、愛の神であられる。それゆえ、御霊によって歩む聖徒たちは必然的に隣人を愛するようになり、親切な行ないを心掛けるようになる。だから、我々が御霊によって歩む度合いが強まるならば、それだけ「親切という果実」を多く生みだすようになるであろう。
■善意
御霊は、我々の心に良い思いを起こさせて下さる。先にも述べたように御霊は愛の神であられるので、我々が御霊によって歩むのならば、必然的に愛に基づく幸いな思い、感情、また志が生じるようになるのである。この善意も先に話された『親切』と同じように、我々が御霊によって歩めば歩むほど、実として結ばれるようになる度合いが増されるであろう。
■誠実
御霊は、我々を誠実にして下さる。聖書には、御霊によって『偽証してはならない。』(申命記5章20節)また『欺いてはならない。互いに偽ってはならない。』(レビ記19章11節)と書かれている。御霊は、我々が誠実であることを望んでおられるのである。それゆえ、御霊によって歩む者は、必然的に、その精神が誠実になるように導かれる。救われる以前には嘘と偽りに対する強い抵抗が無かったのに、クリスチャンになった途端に「誠実な人」になったという事例はよく聞かれるものである。これは、御霊がその人を誠実にさせて下さったからに他ならない。御霊は、我々に「誠実」という実を結ばせて下さるのである。
■柔和
邪悪さのない優しい心は、御霊によって歩むクリスチャンの特質である。我々が御霊によって歩むならば、我々には柔和さが備えられるであろう。
■自制
御霊は、我々に自己制御力を備えて下さる。この御霊による自制心により、我々は、暴走した怒りであれ、情けない怠惰であれ、忌わしい不正であれ、道理に反する不遜であれ、非聖書的な良くないものを自分から退けられるようになるであろう。また、非聖書的なものを自分から遠ざけるだけでなく、聖書的なものを積極的に選び取れるようになるであろう。成熟したクリスチャンに特徴的な性質の一つは、「強い自己管理能力」である。私の見るところ、彼らは多くの事柄に関して、肉の思いの赴くままに進もうとはせず、制御された心によって正しいものを選び取ろうとしている。数十年も牧師をしているクリスチャンなどが、特にそうである。長老を務めているクリスチャンにも、このような傾向が強く存在しているように思える。これは、彼らが御霊によって歩んでいる為であろう。御霊は、我々が自分自身を管理し、正しい聖書的な選択が出来るような自制力を持てるように働きかけて下さるのである。
本日はここまでである。次週は23節目の後半部分からになる。どうか、我々一人一人の人生が、御霊によって結ぶ実に満たされた幸いな歩みとなるように。
ガラテヤ人への手紙5章23~26節(2016/07/10説教)
『このようなものを禁ずる律法はありません。キリスト・イエスにつく者は、自分の肉を、さまざまの情欲や欲望とともに、十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて、進もうではありませんか。互いにいどみ合ったり、そねみ合ったりして、虚栄に走ることのないようにしましょう。』(ガラテヤ5章23~26節)
先週は、御霊の結ぶ実について具体的に説明された。本日は、先週の箇所に引き続き、23節目の途中からとなる。
22~23節目に挙げられているものは、天国の性質である。天国にいる聖徒たちは、常に御霊によって結ぶ実に満たされた歩みをしている。彼らは、御霊によって結ぶ実に満ちた歩み以外は決してしない。そこには御霊の実を何ら結ばない聖徒など一人もいない。我々は、今はまだ天国の聖徒たちのようには十全に御霊の実を結べないかもしれないが、しかし、より豊かに御霊による実が結ばれるようになるのを望み求めるべきであろう。そのように願うのは、贖われた我々クリスチャンにとって相応しいことである。もし神の恵みによって我々が肉を殺すならば、それだけ豊かに御霊の実が結ばれる歩みとなるであろう。
①『このようなものを禁ずる律法はありません。』(5章23節)
ここでは22~23節目で挙げられている9つの御霊の実を指して『このようなもの』と言われている。この言い方は、先週話されたように、22~23節目において列挙されていた『御霊の実』が、あくまでも一例に過ぎないことを示している。何故なら『このようなもの』という言い方は、概括的・抽象的に物事を取り扱う際に用いられる言い方だからである。
パウロがここで言うように、御霊によって結ばれる幸いな実は、律法の禁ずるものではない。22~23節目に挙げられている御霊の実を、律法は決して否定していない。それらのものは、律法の目的とするもの、また律法を行なうにあたって追い求められねばならないもの、である。パリサイ人たちは律法を行なってはいたが、このような本質的に求められねばならないものを蔑ろにしていたので、主から激しく責められたのである。『忌わしいものだ。偽善の律法学者、パリサイ人たち。あなたがたは、はっか、いのんど、クミンなどの十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、すなわち正義もあわれみも誠実もおろそかにしているのです。』(マタイ23章23節)と、主は彼らに対して言われた。我々が聖なる道徳律法を行なう際には、22~23節目に書いてあるようなものが必ず伴っていなければならない。そうしないと、我々もパリサイ人たちのような偽善者となってしまうであろう。パリサイ人たちは律法を守ってはいたが、御霊の実は結んでいなかった。もし我々が御霊によって神の命令のうちに歩むのであれば、必然的に、律法遵守と共に御霊の実が生じるであろう。
次は24節目である。
②『キリスト・イエスにつく者は、自分の肉を、さまざまの情欲や欲望とともに、十字架につけてしまったのです。』(5章24節)
まず、ここに書かれている言葉を個別的に見ていきたい。『キリスト・イエスにつく者』とは、キリストを信じる信仰によって救われたクリスチャンのことである。これが、偽使徒ども、アリウスやペラギウスやセルベトゥスなどの異端者ども、最近の人たちであればエホバの証人ども、またふざけたことばかり口にしている教皇たち、すなわち選ばれていない非再生者たちについても言われている言葉だと思うべきではない。『自分の肉』とは、聖書に反した人間的な悪しき言動のことである。これがどのようなものであるかということについて、我々は19~21節で挙げられている『肉の行ない』の一例を通して、以前学んだ。『情欲や欲望』とは、肉的な言動に繋がってしまう、あらゆる危険かつ邪悪な思念であると思われる。つまり、聖書に反した行ないに結びついてしまう全ての思いは、どれほど些細なものであっても『情欲や欲望』に当たると思われる。『十字架につけてしまった』とは、我々の悪しき肉が、ことごとくキリスト・イエスと共に十字架の上で死んだ、ということである。つまり、我々の肉は、キリスト・イエスの十字架の贖いによって過去のものとして葬り去られた、ということである。
救われたクリスチャンの肉は、古い人と共に十字架につけられたので、既に死んでしまっている。我々の古い人における肉は、もう既にキリスト・イエスとその十字架にあって葬り去られたのである。『私たちの古い人がキリストとともに十字架につけられた』(ローマ6章6節)とパウロが言っている通りである。そのようになったのは、どのような目的があったのであろうか。それはパウロが言うように『罪のからだが滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるため』(ローマ6章6節)であった。それゆえ、肉において死んでしまった我々クリスチャンには、肉の行ないに歩まず御霊によって進むことが求められているのである。我々が肉において死んだ、ということは、つまり我々が御霊によって生きることになった、ということを意味するのである。
③『もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて、進もうではありませんか。』(5章25節)
信仰によって救われたクリスチャンとは、御霊が与えられた存在である。もし御霊が与えられているのならば、その人は、御霊によって歩むべき存在である。御霊によって歩むべき存在であるということは、すなわち、その人が御霊によって御言葉を遵守しなければいけない存在であることを意味する。前の説教でも述べたように、「御霊によって歩む」とは「御霊によって御言葉を行なう」ということである。だから、パウロがここで言いたいことを簡単に言い表わすと、「御霊によって御言葉を遵守せよ。」ということである。
さて、この箇所を読むと、パウロの言葉が、何だか「勧め」であるかのように感じられる方がいるかもしれない。つまり、文章的に「命令」であるとは感じられないかもしれない。しかし、ここで言われている内容は、たとえ「勧め」であるかのように感じられたとしても、あくまでも「緩やかな語調の命令」であると思うべきである。この箇所もそうだが、聖書を読む際には、いかにそこから神の御心および神の命令が何であるかを察することが出来るかが大切である。つまり、勧めのように見える箇所であれ、何も命じていないように思われる箇所であれ、多くの箇所において、そこから神の御旨とするところが何であるかを悟れるように霊的察知能力を働かせるのである。そうすれば、ますます神の恵みによる知恵・悟りがその人のうちに増し加えられるであろう。
ここで『進もうではありませんか。』と書いてあるのを読んで、「一体どこへ行くというのだろうか。」と思われる方もいるかもしれない。しかし、ここでは「場所的」な意味で言われているのではなく、「我々の人生における歩み」という意味において言われているということを我々は弁えるべきである。つまり、ここでは「このように生きなければならない。」また「こういう歩みをすべきである。」という意味で、『進もうではありませんか。』と言われているのである。しかし、この箇所を場所的な意味で言われているものとして受け取りたい方がいたとしても、その行くべき場所が「天国」または「最高に聖潔な状態」として設定されているのであれば、私はその人の理解を厳しく否定することはしない。何故なら、確かに我々は、至福の天国に、また素晴らしい聖潔が存在している状態へと日々、歩んでいくべき存在なのであるから。
次は26節目である。
④『互いにいどみ合ったり、そねみ合ったりして、虚栄に走ることのないようにしましょう。』(5章26節)
ここでパウロが言いたいことを簡単に言い表わすならば、「些細なことで不和に陥って愚かにならないようにせよ。」ということである。ここでもパウロは、前に書いたのと同じ内容のことを、繰り返して述べている。前に我々が見た(5章)15節目の箇所を、もう一度見てみたい。そこには次のように書いてある。『もし互いにかみ合ったり、食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。』(5章15節)我々が今見ている26節目の箇所と、類似しているのが分かる。どちらの箇所も、争わないようにと言われている。前の説教の時にも話されたように、ガラテヤ人たちは霊的に凄まじく鈍い人たちだったのであり、そのゆえに、パウロはここでも繰り返して同じ内容のことを述べているわけである。つまり、彼らは、何度も何度も言わなければ十分に理解できないような性質を持っていたのである。
【争乱】と【虚栄】とは、互いに密接な繋がりがある。もし『互いにいどみ合ったり、そねみ合ったり』するのであれば、「俺たちの方が彼らよりも優れているのだ。」などと思って虚栄を張るようにもなる。これは「争乱」が「虚栄」を生むケースである。これとは逆に、もし『虚栄に走る』のであれば、仲間を見下したりして対立関係が生じてしまいかねない。これは「虚栄」が「争乱」を生むケースである。それゆえ、次のように言えるであろう。すなわち、もし虚栄を避けたいのであれば、対立状態に陥らないようにすべきである、ということである。また、もし争いを避けたいのであれば、虚栄心を持たないようにすべきである。「争乱」と「虚栄」。この2つのどちらか一方を避けるのであれば、必然的に、もう一方の事柄を避けられるであろう。
パウロはここで、ガラテヤ人たちが互いに争い合わないようにと指導している。キリストの御身体である教会に争乱状態があるのは決して望ましいことではない。些細なことで喧嘩ばかりしているなら、その教会が破壊されるばかりである。我々が教会内においてなるべく争いを避けようとするのは、知恵であり、誉れである。しかし、すぐに争いを起こそうとするのは、愚かであり、恥である。ソロモンが次のように言う通りである。『争いを避けることは人の誉れ、愚か者はみな争いを引き起こす。』(箴言20章3節)また彼はこのようにも言っている。『争いの初めは水が吹き出すようなものだ。争いが起こらないうちに争いをやめよ。』(箴言17章14節)これは、水がポコポコ吹き出すのを見たならば、すぐにも水の噴出を塞ぐべきであるということである。つまり、争いが起こりそうであると察知したならば、早急に解決策を考えるべきであるということである。だから、もし教会内に「争いの芽」が生じたならば、それが成長しきらない内に除き去ってしまうことが求められる。教会に争乱状態があるのは適切ではない。神は『平和の神』(ローマ15章33節)である。それゆえ、神の教会のうちには(争乱ではなく)平和があることこそ望ましい。我々は、教会内における平和の重要性をよく弁えるべきであろう。
ガラテヤ人への手紙6章1~2節(2016/07/17説教)
『兄弟たちよ。もしだれかがあやまちに陥ったなら、御霊の人であるあなたがたは、柔和な心でその人を正してあげなさい。また、自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。』(6章1~2節)
先週の箇所は23~26節目であった。23節目では「律法は御霊が結ばせて下さる実を否定しない」ということが、24節目では「我々の罪深い肉は十字架において過去のものとして葬り去られた」ということが、25節目では「御霊によって生きる者たちは、御霊によって御言葉を行なうべきである」ということが、26節目では「教会内に争乱があるのは相応しくない」ということが、話された。今週から6章目に突入する。この手紙も、残すところあと僅かとなった。
早速、1節目から見て行きたい。
①『兄弟たちよ。もしだれかがあやまちに陥ったなら、』(6章1節)
我々は、神の恵みによって守られていなければ、すぐに過ちに陥ってしまうものである。我々はすでにキリストによって救われているのだが、我々の内には「罪の残滓」があるので、罪深い肉の行ないを完全に避けるのは原理的に不可能である。それは、パウロやダビデでさえ罪に陥ってしまったことを考えれば、明らかに分かるであろう。それゆえ、過ちとは無縁でいられない我々のこの地上における人生は、惨めであると言える。パウロもこのことを良く弁えていた。彼は、キリスト者は罪に陥るべきではないと考えていたが、しかし、キリスト者が罪とは無縁でいられないことも知っていた。だから、彼はここで「あなたがたは絶対に過ちに陥ってはならない!!」とは言っていない。むしろ、『もしだれかがあやまちに陥ったなら、』と言っている。つまり、キリスト者は過ちに陥ってしまうものであるという前提に基づいた記述をなしている。我々は、たとえ贖われて神の民とされてはいても、多くの過ちに陥ってしまう弱くて惨めな存在である。
それでは、もし兄弟姉妹である者が過ちに陥ってしまったのを知った場合、我々は一体どうしたらいいのだろうか。パウロは、ガラテヤ人にこのように言っている。
②『御霊の人であるあなたがたは、柔和な心でその人を正してあげなさい。』(6章1節)
兄弟姉妹が過ちに陥ってしまったならば、周りの聖徒たちは、その人が正しい歩みに復帰できるように祈りつつ働きかけねばならない。『正してあげなさい。』とパウロはここで言っている。つまり、過ちに陥るというのは、すなわち「曲がる」ことであるから、周りの人たちは「真っ直ぐ」になるように正さねばならないわけである。例えば、ある兄弟が盗みを長期に渡って行なっているのを知ったとしよう。その兄弟は『盗んではならない。』(出エジプト20章15節)という神の命令に背いているのだから、曲がった行ないをしている。それゆえ、その兄弟が盗んでいるのを知っている周りの聖徒たちは、その人が盗みを止めるように、祈りつつ正さねばならない。また、ある学生のクリスチャン(※彼は男性である)が女装をして楽しんでいたとしよう。その兄弟は『男は女の着物を着てはならない。』(申命記22章5節)という律法に違反しているのだから、歪んだ行ないに歩んでしまっていることが分かる。それゆえ、その学生のクリスチャンが女装をしているのを知っている友達は、彼が2度と女装などしないように、祈りつつ正さねばならない。
『柔和な心で』と、パウロはここで書いている。つまり、我々が兄弟姉妹を矯正する際には、優しい心が必要である。人は、相手の態度に応じた態度を取るものである。経験からも明らかだと思うが、激しい態度を持って接するならば相手も激しくなりがちであり、静かな態度を持って接するならば相手も穏やかに応対してくれるものである。もし我々が厳しい面持ちで兄弟姉妹を矯正しようとするならば、大いに反発されてしまいかねない。しかし、優しい穏やかな態度で正そうとするならば、相手も従順な態度で応対しやすくなる。もし反発されるような態度で向かうならば矯正できなくなってしまうかもしれないが、穏和な態度で向かうならば、それだけ従順になれるようにもなる。それゆえ、パウロも言うように、我々が兄弟姉妹を正そうとする際には『柔和な心』が欠かせない。
『御霊の人であるあなたがは、』とパウロは言っている。つまり、御霊が与えられているのであれば、その人は悪徳に陥ってしまった兄弟姉妹を正すべきである、ということである。パウロは他の箇所でこのように書いている。『神が私たちに与えてくださったものは、おくびょうの霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。』(Ⅱテモテ1章7節)この聖句から分かるように、神の霊とは『おくびょうの霊ではなく、力と愛と慎みとの霊』である。それゆえ、神の霊が注がれた我々クリスチャンは、兄弟姉妹を正そうとする際に臆病になるのではなくて、むしろ力と愛と慎みとを持って矯正しようとすべきなのである。それこそ、御霊の人に相応しい行ないである。
ところで、パウロはこの箇所で、ガラテヤ人たちに対して『御霊の人』と言っている。パウロがこのように言っているのだから、ふざけた信仰に陥ってしまっていたとしても、やはりガラテヤ人たちは選ばれたキリストの民であったということが分かる。もしそうでないのならば、どうしてパウロは神の霊によってガラテヤ人たちに『御霊の人』と言っているのだろうか。もしガラテヤ人たちが選びの民では無かったとしたら、御霊は彼らのことを『御霊の人』とは言われなかったはずである。これらのことは前にも話した内容であるから、これ以上の説明は不要であろう。
③『また、自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。』(6章1節)
もし他者を正しておきながら自分も過ちに陥ってしまったなら、それは困ったこと、見苦しいことである。そのような人に、他者を堂々と矯正できる正当性と権利はない。何故なら、その人は、他者を正そうとする前に、まず自分自身を正さねばならないからである。まず第一に自分自身のことをしっかりさせてからこそ、他者を改善させられる正当性が生じる。このことについて、主も次のように言っておられる。『なぜあなたは、兄弟の目の中のちりに目をつけるが、自分の目の中の梁には気がつかないのですか。兄弟に向かって、『あなたの目のちりを取らせてください。』などとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には梁があるではありませんか。偽善者たち。まず自分の目から梁を取りのけなさい。そうすれば、はっきり見えて、兄弟の目からも、ちりを取り除くことができます。』(マタイ7章3~5節)自分自身がしっかりしていないというのに、どうして自分を差し置いて他者をしっかりさせようとするのだろうか?まず先に正すべきは自分であろう。それゆえ、もし我々が兄弟姉妹を正そうとするのであれば、ここでパウロが言うように、我々は自分自身が悪に歩んでしまわないように注意せねばならない。
次は2節目である。
④『互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。』(6章2節)
まずは、言葉の説明から始めていきたい。
まず『互いの重荷』とは一体なんであろうか。アウグスティヌスは、これは「罪」であると考えている(説教164:2章4節)。しかし、私はこれは、クリスチャン一人一人が聖徒として当然なすべき義務の行ない・仕事であると考える。例えば、日曜学校で教師をしているクリスチャンがいたならば、毎週子供たちを教えることこそ、その人の『重荷』である。また、体の不自由な兄弟を教会に送り迎えしているクリスチャンがいたならば、毎週送迎を行なうことこそ、その人の『重荷』である。私は『重荷』という言葉を、このように理解する。それゆえ、この言葉をアウグスティヌスのように「罪」と解釈するのは、今現在の私としては、あまり正しいものではないと感じられる。
次に『キリストの律法を全う(する)』とは、どういう意味であろうか。この『キリストの律法』という言葉は、Ⅰコリント9:21の箇所でも使われている。これは、キリストが命じられた通りに我々が互いに愛し合うという目的をもって、聖なる律法の原理を前提とした愛の言動を行なう、という意味である。例えば、困窮している兄弟がいたのならば、愛をもってその兄弟を助け、困らないようにすること。こうするのは、『キリストの律法を全う』することである。何故なら、その人は、キリストの命令の通りに兄弟を愛しているのであり、「貧しい兄弟を無視するな」という律法(申命記15:7~11)を行なっているからである。
個別的な言葉の説明は以上で終わりである。
さて、ここでパウロが言うように、我々が互いの重荷を負い合うのは、キリストの律法を全うすることである。このことを具体的に理解するために、先に話した例で考えてみよう。日曜学校で教師をしているクリスチャンが何かの事情により数週間のあいだ子供たちを教えられない場合、他の人が、このクリスチャンに代わって子供たちを教えること。また、体の不自由な兄弟の送迎をしているクリスチャンがどうしても送迎を行なえない場合、他の人が、そのクリスチャンに代わって送り迎えの任務を引き受けること。こうするのは、互いの重荷を負い合うことであり、キリストの律法を全うすることである。もしこのようにしない場合、つまり我々が互いの重荷を負い合わない場合、我々はキリストの律法を全うすることが出来ない。
基本的に、我々は自分自身に定められている重荷を、自分自身によって負うようにすべきである。『人にはおのおの、負うべき自分自身の重荷があるのです。』(5節)とパウロが少し後の箇所で言っている通りである。その人に定められている重荷とは、本来的にはその人自身が解消すべきものである。しかしながら、我々は「自分の重荷はすべて自分で負いなさい。」などと思って全く他者の重荷に関与しないというのではなく、むしろ他の人の重荷を負ってあげる姿勢を豊かに持つべきである。つまり、他人の重荷を代わりに負うべきであると判断したならば、容易に、その人の重荷を負えるような精神を持っているべきである。このような態度を持っているのは、互いに愛し合うべきクリスチャンとして実に相応しいことである。また、他の人が自分の重荷を負ってくれるからというので、その援助に甘えすぎるべきでもない。何故なら、もし甘えの精神が養われるのであれば、自分自身の重荷を自分自身によって負うための力が失われかねないからである。もしそうなってしまったならば、クリスチャンとしての尊厳が失われ、何事も他人に頼ってしまう奴隷的な精神が生じかねない。
我々が自分自身の重荷を負い、仲間の重荷を負い合うことによって、キリストの教会が建て上げられていくであろう。何故なら、為すべきことがしっかりと為されているからである。もし「重荷などどうでもいい。」などと思って、負うべき重荷を投げ出してばかりいるのであれば、教会は健全に建て上げられていかない。キリストの民である我々一人一人には、自分の負うべき重荷を負い、また互いの重荷を負い合って、これからの日々を歩んでいくことが求められている。
ガラテヤ人への手紙6章3~5節(2016/07/24説教)
『だれでも、りっぱでもない自分を何かりっぱでもあるかのように思うなら、自分を欺いているのです。おのおの自分の行ないをよく調べてみなさい。そうすれば、誇れると思ったことも、ただ自分だけの誇りで、ほかの人に対して誇れることではないでしょう。人にはおのおの、負うべき自分自身の重荷があるのです。』(ガラテヤ6章3~5節)
先週の箇所は(6章)1~2節目であった。悪徳に陥ってしまった兄弟姉妹を矯正すること、また互いに重荷を負い合うことについて話された。本日は3節目からである。
最近の説教では、クリスチャンの行動原理について話される比率が多くなっている。我々が今見ているこの辺りの箇所は、主に行ないについて書かれている箇所だから、内容的に行ないに関する話が多くなるのは必然である。クリスチャンの行動原理について考える際に我々が注意すべきことは、何か良い行ないをしたからというので人が義と認められるということではない、ということである。我々が善を行なったからこそ義と認められるのではなくて、信仰によって救われからこそ、『神の作品』(エペソ2章10節)として善に励むようになるのである。世の中や様々な文章を見ていると、(プロテスタントではなく)カトリックによるものばかりが目に付くことが多い。この静岡市を歩いてみても、教会以外の建物で目に入ってくるのは、カトリック系の学校・幼稚園・養護施設ばかりである(しかし、教会の建物だけはプロテスタントの方が多く見られる)。世の人たちが名を挙げるのも、ローマ法王やマザー・テレサやジョルジュ・ルメートルなど、カトリックの人物ばかりである。信仰義認に立つ我々プロテスタント勢力はカトリックの行為義認を憎むべき誤謬として認識せねばならないが、しかし、カトリックが結んでいる実の度合いを凌駕できるように望まねばならないと思う。何故なら、選ばれているかどうか定かではない異端的な勢力であるカトリックではなく、信仰義認に立つ我々プロテスタント陣営が、神の民である我々プロテスタント教徒こそが、世にあって豊かな実を結んでいかねばならないと考えるからである。
まずは3節目からである。
①『だれでも、りっぱでもない自分を何かりっぱでもあるかのように思うなら、自分を欺いているのです。』(6章3節)
パウロは、ガラテヤ人が高ぶらないように抑制させようとしている。愚かな誇りであれ、優越感であれ、もし高慢になるならば、その人は罪の行ないに接近している。高慢があるところには、罪も溢れでる。謙虚さを失った傲慢な暴君の振る舞いを見たら、このことは良く分かるであろう(例えばネロやカリグラがそうである)。壮年期の男性が店員に対してぶっきらぼうに振る舞うのも、「俺は客だ。この店を利用してやっているのだ。」という類の高慢な精神を持っているからである。高慢は罪をもたらすので危険である。それゆえ、罪を避けるべき我々クリスチャンは、ここでパウロが言っている言葉を良く弁えなければならないであろう。
『りっぱでもない自分』と書いてあるが、これは、ガラテヤ人だけでなく、全ての聖徒たちが自分についてそのように思うべきものである。たとえダビデやヤコブなど、人間的には偉大であると言える聖徒たちであっても、神の御前においては立派であるとは言えない。何故なら、彼らを偉大であると思わせている諸々の要因は、彼ら自身から出たというのではなく、神の恵みによって与えられた賜物だからである。もし神の恵みのゆえに人間的に偉大であると思われているならば、人間の前では「素晴らしい」と思われるかもしれないが、立派にさせて下さった神の御前においては誇れないであろう。我々の内にある全ての良いものは、神の恵みによって与えられたものである。だから、我々が良いものを持っていたとしても、「俺は他の人たちよりも凄いのだ。」などと誇ることは出来ない。我々は、ただ天の神による恵みによって良いものを持つことが出来たに過ぎないからである。それゆえ、どれだけ優れているかのように見える人であっても本質的な意味においては何も立派な存在ではない、ということが分かる。我々は、取るに足らない、ちっぽけな存在に過ぎないのである。だから、この箇所で言われているように、我々は自分自身のことを『りっぱでもない自分』などと思うべきである。
パウロがここで言うように、『りっぱでもない自分を何かりっぱでもなるかのように思う』のは、自分を欺くことである。何であれ愚かな誇りを持つ人は、勘違いをしているのである。我々は、自分のことについて思い違いをすることなしには、愚かな誇りを持つことは出来ない。思い違いをしているからこそ自分を何か立派であるかのように思ってしまうのである。「思い違い」と「愚かな誇り」という、この2つの事柄は互いに深い関わりがある。すなわち、思い違いをしているからこそ愚かな誇りが生じてしまう。また、愚かな誇りを持っているということは、思い違いをしている証拠である。
パウロは次の4節目で、我々が愚かな誇りを抱かないようになるために自分自身のことを良く考察すべきであると言っている。彼はこのように書いている。
②『おのおの自分の行ないをよく調べてみなさい。そうすれば、誇れると思ったことも、ただ自分だけの誇りで、ほかの人に対して誇れることではないでしょう。』(6章4節)
「自分の行ないをよく調べよ」というのは、文脈から考えるならば、「自分自身の負うべき重荷について考えてみよ」ということである。5節目で言われているように『人にはおのおの、負うべき自分自身の重荷がある』。我々に定められている重荷とは、(他の人ではなく)自分自身が負わねばならない義務的な行ないである。だから、自分に定められている重荷を自分自身によって負ったとしても、その人は、ただ為すべきことをしているに過ぎない。その人が当然行なうべき任務を成し遂げたからといって、どうして他者に対して誇れるであろうか。例えば、牧師として働いているクリスチャンと学者として働いているクリスチャンが、自分自身の為すべき職務を全うしたとしても、互いに対して誇ることは出来ない。何故なら、この人たちは、神によって定められた重荷を、当然為すべき義務として自分自身で負っているに過ぎないからである。もし当たり前のことをしているに過ぎないのであれば、たとえ何かをしても、他人に対して誇ることは出来ないのは自明である。
また、他人との比較において考量するならば、ますます我々は誇れなくなってしまうことが分かる。何故なら、どの分野にも上には上がいるからである。例えば、凄まじい働きをしている牧師がこの日本にいたとしよう。この牧師は、日本にいる他の牧師に対しては誇れるような働きをしているかもしれない。しかし、歴史を見るならば、カルヴァンやルターなど、もっと凄い働きをしている人たちが見いだされるだろう。このような優れた人たちと自分を比較するのであれば、その人の持っていた誇りは打ち消されてしまうであろう。いかに優れた活動をしている牧師といえども、もしカルヴァンやルターと比べるならば、やはり誇り高ぶることが出来なくなってしまうに違いない。精神が異常になっていない限り、この牧師は「私はカルヴァンやルターよりも優れた働きをしている。」などとは言わない、否、言えないはずである。教会活動に熱心に協力している聖徒についても、同じことが言える。その聖徒は素晴らしいことをしているのだから、一般的な聖徒たちと比較する限りにおいては、誇れるかもしれない。しかし、他の教会の中には、この聖徒と同等か、この聖徒以上の協力をしている人が必ず存在するはずである。そのような聖徒と比較するならば、いかに自分が素晴らしい協力をしていたとしても、大いに誇れることは無くなってしまうだろう。このように、自分よりも上であると思われる人との比較において自分自身を考量するのは、愚かな誇りを抑制できる一つの手段である。
害をもたらす愚かな誇りについては、我々は抑制すべき必要がある。そのような誇りは神の御心に適ったものではない。しかし、我々が主にあって自分自身のことを誇るのは間違ったことではない。つまり、「私は主の恵みのゆえにこの職務を行なうことが出来ている。それゆえ、主が私にこのことを行なわせてくださっているのは、私にとっての誇りである。」などと言うのは間違っていない。我々は、主にあって誇るのならば、誇っても良い。『誇る者は、主にあって誇りなさい。』(Ⅱコリント10章17節)と書かれている通りである。
次は5節目である。
③『人にはおのおの、負うべき自分自身の重荷があるのです。』(6章5節)
ここでも2節目の箇所と同じように『重荷』と書かれている。2節目の箇所を説明する際にも話されたが、やはり『重荷』とは「罪」として解釈すべきではないと思われる。アウグスティヌスのように『重荷』=「罪」であると考えると、あまり適切とは言えない理解に陥る。つまり、「罪とは自分自身の負うべき重荷である。」という理解が生じる。しかし、罪を「負うべきもの」と表現するのは、あまり正しいとは言えないのではないだろうか。何故なら、罪とは、嘆き、悔改め、捨て去り、自分から斥けるべきものだからである。「罪」という、自分が遠ざかるべきものについて「負うべきもの」と言うのは適切とは言えないであろう。それゆえ、前の説教でも話されたように、『重荷』とは即ち「クリスチャンとして当然なすべき義務的な言動」であると解釈すべきである。
この箇所で言われているように、我々一人一人には、各人に定められている任務―つまり重荷が存在している。それは、神が負うようにと我々に定められたものである。使徒であれば使徒としての職務を果たし、パン屋であればパン作りの仕事を行ない、主婦であれば主婦が為すべき働きを全うする。もし使徒がパン作りの仕事に熱心になろうとしたり、パン屋が主婦として歩もうとしたり、主婦が使徒でもあるかのように働こうとするのであれば、それは自分自身の負うべき重荷を弁えていないことを示す。その人に与えられている重荷を自分自身によって全うするのは、その人の本分である。もちろん、だからといって、誰かが誰かの負うべき重荷を肩代わりすることは否定されるべきことではない。否定されないどころか、むしろ、我々は積極的に互いの重荷を負い合うべきである。パウロが2節目の箇所で『互いの重荷を負いあい(なさい)』と述べている通りである。しかし、各々に定められている重荷とは、パウロがこの箇所で言っているように、本来的にはその人自身が負うべきものであると考えるべきである。
④高ぶりの危険性は最高クラスである
本日の箇所では、愚かな高ぶりに関することが主に話された。この「高ぶり」というものについて幾らか語って、本日の説教を終わりにしたい。
高ぶる者は、たとえ上に高く昇ろうとしても、下に引き降ろされることになる。神が、高ぶる者を下の方へと落とされるからである。ルシファーは『私は天に上ろう。神の星々のはるか上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山にすわろう。密雲の頂に上り、いと高き方のようになろう。』(イザヤ14章13~14節)と、心の中で言った。しかし、彼は神に嫌悪されつつ『よみに落とされ、穴の底に落とされ』(イザヤ14章15節)てしまった。ルシファーのように高ぶって上に行こうとしても、結局は下に行き着くことになるだけである。この世界には「高ぶる者は破滅に至る」という法則が存在する。何故なら、神がそのようにされるからである。『高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。』(箴言16章18節)と言われている通りである。
この高ぶりは、罪に直結する性質を持つ。もし高ぶるならば、邪悪・不信仰・愚鈍・狂気など、あらゆる悪徳を生じさせるのである。だから、高ぶりとは「悪徳製造装置」であると言うべきものである。高ぶった人が実際にどのような悪徳に陥ってしまうかということについては、いちいち例を挙げなくてもお分かりいただけると思う。我々は、自分であれ他者であれ、高ぶりによって多くの悪徳が生じてしまったケースを今までに何度も見ているはずだからである。この高ぶりは多くの罪を生じさせるのだから、この高ぶりを避けるならば、一挙に多くの罪を避けることになる。つまり、高ぶりを避けるのは、悪の発生源を封じることである。それゆえ、高ぶりを避けることにおける重要性の大きさは、我々にとって測り知れないものがある。人間とは高ぶりやすい存在であって、それは、我々クリスチャンであっても変わらない。しかし、神の言葉は、我々クリスチャンが高ぶらないように求めている。だから、我々は、愚かな高慢から自分を遠ざけることを願うべきである。どうか、神が我々一人一人の心を謙遜にし、その状態を豊かに保ち続けて下さいますように。
ガラテヤ人への手紙6章6~7節(2016/07/31説教)
『みことばを教えられる人は、教える人とすべての良いものを分け合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種を蒔けば、その刈り取りもすることになります。』(ガラテヤ6章6~7節)
先週は、我々が愚かな誇りの念を抱くべきではないことについて話された。先週の箇所は、3~5節目であった。本日は6節目からである。
早速、6節目から見て行きたい。パウロはこう書いている。
①『みことばを教えられる人は、教える人とすべての良いものを分け合いなさい。』(6章6節)
まずは語句の個別的な説明である。『みことばを教えられる人』とは、教会に籍を置いている一般信徒の方がたのことである。『教える人』とは、牧師や教師、また伝道師(※教派によっては伝道師の職務が無いところもある)として遣わされている、教会内で「先生」と呼ばれるような人たちである。『すべての良いもの』とは、金銭であれ物品であれ、神が我々に与えてくださった所有物全般のことを指す。
この箇所で言われているのは、すなわち「信徒たちは自分の属する教会にいる真面目に働いている牧師を支えなさい。」ということである。
恐らく、ガラテヤの諸教会にいた牧師たちは、信徒からの支えが乏しいために経済的に困っていたのかもしれない。だからこそ、パウロはここで牧師たちを経済的に支えることについて命じているのだと思われる(あくまでも推測に過ぎないが)。ガラテヤ人たちは『愚か』(3章1節)だったのだから、牧師を助ける必要性が分からなかったとしても無理はない。彼らは異端信仰に陥ってしまうほど霊的に鈍かったのであるから、教会で働いている者たちを支えることの重要性を理解できなかったのであろう。ルターは、ガラテヤ人たちが牧師を十分に支えていなかったことこそ、彼らが異端神学に惑わされてしまった原因であると『ガラテヤ大講解』の中で述べている。つまり、ガラテヤの諸教会にいた牧師たちが経済的に十分に支えられていなかったので教育の働きが不完全なものとなりガラテヤ人たちは正しく教えられていなかった、だからガラテヤ人たちはやすやすと偽使徒どもの異端に陥ってしまった、ということである。このように考えるルターの理解は非常に大胆なものであるが、これは有りえない解釈、荒唐無稽な解釈ではない。もしかしたら、本当にルターの言うとおり、牧師たちの経済的困窮がガラテヤ人の異端化へと結びついたのかもしれない。
今から2千年前の初代教会の時代に教職者たちが経済的に困っていたのだとしたら、キリスト教の歴史において、今までずっと教職者たちは悩まされ続けてきたことになる。何故なら、これまでの歴史において経済的に困窮した教職者たちの例は、枚挙に遑(いとま)がないからである。これは、『みことばを教えられる人』すなわち信徒たちが、『教える人とすべての良いものを分け合』うことをしなかったからである。もしそうでなかったとしたら、教職者たちは経済的に悩まされはしなかったであろう。支えがないために餓死した司祭がいる。ルターも一時期、経済的に困ったことがある。ジョナサン・エドワーズも牧師である自分を支えるように信徒たちに訴えている。この日本でも、アルバイトをしながら教会の仕事をしている牧師が多く存在する。もちろん、全ての牧師たちが全て、貧窮に苦しめられているというわけではない。この日本にも、十分に支えられている牧師たちが多く存在している。しかし、経済的に十分に支えられていない牧師たちの数は少なくない。
残念なことだが、牧師が支えられるべきことにおける重要性が分からない兄弟姉妹の方がたは非常に多い。中には「献金で食わせてもらっているくせに。」などと口にする兄弟の方もいる。先にも述べたが、恐らく、ガラテヤ人たちもこのことが分からなかったと思われる。だからこそ、パウロはこの箇所で、教える人が教えられる人とすべての良いものを分け合うようにとの命令を出していると考えられるのである。牧師や牧師の職務を経験したことのある人、また教職者の子どもであれば、牧師が支えられることの必要性を弁えられる人がほとんどである。父が牧師であったイギリスの哲学者トマス・ホッブズ(1588―1679)も、牧師たちが経済的に支えられるべきことの必要性を弁えていた。しかし、そうでない兄弟姉妹の方がたにおいては、牧師が経済的に困らないようにすることに関する重要性を中々理解しにくいようである。恐らく、経済的に自分を支えるようにと要求している牧師(こういう牧師は今でも多く見られる)を見て<貪欲>であると思う兄弟姉妹の方がたは多いと思う。「あの先生はお金を欲しがっている。何だか卑しい感じがする。」などと思われる兄弟姉妹の方もいるのではないか。このように思ってしまうのは残念なことであるが、しかしある意味、仕方がないと言えなくもない。何故なら、牧師が経済的に支えられるべきことの重要性が分からないということは、霊的な道理が総体的に分からないことを示しているからである。霊的な道理が総体的に分からないからこそ、そのような信徒たちを牧師は豊かに教えていく必要があるのである。もし霊的な道理の分かる信徒ばかりが集っていたならば、牧師が豊かに教えていく必要性もそれだけ無くなっていたであろう。
『教えられる人』が『教える人とすべての良いものを分け合』うようにするのは、当然なすべき行ないである。教えられている人たちは、「俺たちの献金で生活しているのだろう?」などという不敬虔な思いを牧師に対して持つべきではない。そうではなく、「牧師が献金によって生活するのは当然である。」と思うべきである。牧師の生活が支えられ、彼らが報酬を受けるのは「当たり前」である。聖書の御言葉を見てみよう。主は、御自身の遣わされた福音の伝道師たちに対して、次のように言われた。『働く者が報酬を受けるのは、当然だからです。』(ルカ10章7節)パウロも、真面目に働いている牧師について、同じことを言っている。『働き手が報酬を受けることは当然である。』(Ⅰテモテ5章18節)また彼は、御霊のものを撒く教師たちは物質的な報酬を受ける当然の権利があると、Ⅰコリント9:11の箇所で書いている。『もし私たちが、あなたがたに御霊のものを撒いたのであれば、あなたがたから物質的なものを刈り取ることは行き過ぎでしょうか。』この少し後の箇所で言われているように、牧師が信徒たちによって支えられるのは「主の定め」であり、それゆえに当然なされるべきことである。『主も、福音を宣べ伝える者が、福音の働きによって生活のささえを得るように定めておられます。』(Ⅰコリント9章14節)以上の説明によって牧師が支えられるのは当然であることが十分に分かると思うが、歴史的な信条からの引用により、更に説明の度合いを強化することにしたい。かの有名な「第二スイス信条」(ブリンガー)の中では、次のように書かれている。「すべての信仰深き教職者は、良き働き人として、彼らの報酬を受けることは当然である。そして、彼らの保証と彼ら及びその家族に対する必要なすべての物を受けることは、決して罪を犯すことではない。コリント前書9章、テモテ前章5章、その他にあるように、使徒は、それが教会によって正しく与えられ、教職者が正しく受けたことを示している。教職者が彼らの職能によって生活することを罰し、侮辱する、再洗礼派の人たちもまた、使徒の教義によって罰せられたのである。」(第18章:第23節※①参照)彼(ブリンガー)がこのように言うのは、誠に正しい。
自分の属する教会で教えている真面目な牧師を支えようとしない兄弟姉妹の方は、多くの報いを受ける。まず、牧師を支えようとしないことによって、自分が霊的な道理の分からない者であるということを、みずから示すことになる。また、牧師が生活に困るのであれば教育の働きが不完全なものとなることに繋がるので、牧師の行なう毎週の礼拝説教やその他の教育の働きを通して、霊的なダメージを受けてしまうようになる。更に、牧師が経済的に支えられるようにしないことにより、実際的な害を受けるようになる。例えば、当然なすべき献金をしないことによって自分が自由に使えるお金の量が増加するのであれば、美味しいのだが身体に悪いものをより多く食べることにもなるかもしれない。「お金に余裕があるから新しく出来たあの店に行ってみようか。」と。そうすれば、身体に悪いものをより多く食べることにより、病気にかかったり寿命が縮ったりするようになるかもしれない。本来であれば牧師を助けるために使うべきであったお金を自分の腹のために使うのであれば、健康と寿命に呪いが注がれたとしても何の不思議もない。神の働き人である牧師を経済的に攻撃するのは、神御自身を攻撃するのも等しい。もしそうであれば、どうして神からの報いを受けずに済むであろうか。
我々は、自分の属する教会において、かならず十一献金を捧げるべきである。神は御自身に捧げられたこの十一献金によって、教会の働き人たちを扶養して下さる。しかし、しっかり十一献金がなされているにもかかわらず、牧師が経済的に困っているようであれば(こういう牧師は今の日本では往々にして見られるものである)、その牧師が真面目に働いている限り、出来る範囲内で自主的に援助するようにすべきである。それは、『みことばを教えられる人は、教える人とすべての良いものを分け合いなさい。』とパウロが言っているからである。そのように牧師に対して良いことをしている人は、キリストに対して良いことをしているのである。何故なら、牧師とはキリストに遣わされて教会で仕事をしている者たちだからである。『もし世があなたがたを憎むなら、世はあなたがたよりもわたしを先に憎んだことを知っておきなさい。』(ヨハネ15章18節)と主は言っておられるが、クリスチャンに対する態度―とりわけ働き人に対する態度―は、キリストに対する態度を示すものである。今の日本のプロテスタント界は、牧師不足、霊的衰弱、悲観的終末論による力の喪失などにより弱々しくなっており、悲惨な状況である。このような悲惨な状況にあって、牧師が経済的に悩まされるのであれば、ますます劣悪な状況が生じてしまうことに繋がる。例えば、牧師になれば経済的に困るなどと信徒の方がたが考えるのであれば、ますます牧師になろうとする人が少なくなるから、プロテスタント界は更なる牧師不足に悩まされるであろう。つまり、牧師を経済的に困らせるのは、新たな牧師を出現させないようにすることなのである。真面目に働いている牧師に対して「献金で食わせてもらっているのでしょう?」などと口にする兄弟の方がいたとしたら、その兄弟は、このようなことを言わせてしまう不敬虔な心を嘆くべきである。このように言う人は、休暇を返上し、キリストの教会とそこにいる真面目な牧師を経済的に支えることが出来るように、もっと稼げるようにすべきである。キリストとその牧師たちを侮るべきではない。
次は7節目である。
②『思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種を蒔けば、その刈り取りもすることになります。』(6章7節)
神は報いられる御方であると聖書は教えている。『神は、ひとりひとりに、その人の行ないに従って報いをお与えになります。』(ローマ2章6節)また『神は、善であれ悪であれ、すべての隠れたことについて、すべてのわざを裁かれる』(伝道者の書12章14節)などと書いてある通りである。我々の神は、善に対して祝福を与えることによって御自身が善を喜ばれる存在であることを、また悪に対して罰を与えることによって御自身が悪を憎まれる存在であることをお示しになられる。つまり、我々の主なる神は「報いの神」なのである。だから、ここでパウロが言うように、我々が良い種を蒔けば良い実を刈り取ることになるだろうし、悪い種を蒔けば悪い実を刈り取ることになるであろう。
我々が善の行ないをするのは、未来において良い思いをすることである。『あなたのパンを水の上に投げよ。ずっと後の日になって、あなたはそれを見いだそう。』(伝道者の書11章1節)とソロモンは言っている。『パンを水の上に投げる』―すなわち自分自身を犠牲にした善の行ないをするのであれば、『ずっと後の日になって、あなたはそれを見いだ』すであろう。神が、その善の行ないに対して報いて下さるからである。これとは逆に、我々が悪の行ないをするのは、未来において悪い思いをすることである。パウロはⅡテモテ4:14の箇所で、『銅細工人のアレキサンデルが私をひどく苦しめました。そのしわざに応じて主が彼に報いられます。』と言っている。我々がアレキサンデルのように悪の行ないをするのであれば、主によって罰が与えられるであろう。何故なら、報いの神は、悪の行ないに裁きを与えられる御方だからである。我々は、善の行ないであれ悪の行ないであれ、自分の蒔いた種の刈り取りをせねばならない。
我々は、善や自分を犠牲にした行ないや施しをすることに対して、何だか「損」であると感じてはいないだろうか。このようなことをしても、ただ自分にとってマイナスになるだけで、未来において何の報いも与えられないかのように考えていないだろうか。もし霊的に鈍くなっている人であれば、このように考えてしまうであろう。しかし、パウロはこの箇所で「神は必ず報いられるのだから思い違いをするな。」と我々に教えている。だから、我々は、何か良い行ないをするに際して「損」であるなどとは思うべきでない。むしろ、報いが将来あることを覚えて良い思いを持つべきである。いずれ、神がその行ないに対して報いを与えて下さる、つまり我々の蒔いた種の刈り取りをすることが出来るように計らって下さるのだから。もし豊かに実を刈り取りたいのであれば、豊かに善を行なうべきである。少しだけしか善を行なわないのであれば、少しだけしか実を刈り取れないであろう。パウロがこう書いている通りである。『私はこう考えます。少しだけ蒔く者は、少しだけ刈り取り、豊かに蒔く者は、豊かに刈り取ります。』(Ⅱコリント9章6節)
ガラテヤ人への手紙6章8~10節(2016/08/07説教)
『自分の肉のために蒔く者は、肉から滅びを刈り取り、御霊のために蒔く者は、御霊から永遠のいのちを刈り取るのです。善を行なうのに飽いてはいけません。失望せずにいれば、時期が来て、刈り取ることになります。ですから、私たちは、機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行ないましょう。』(ガラテヤ6章8~10節)
先週の箇所は6~7節目であったが、信徒たちは教職者と全ての良いものを分け合うべきことについて、また我々は蒔いた種の刈り取りをせねばならないことについて話された。本日は8節目からである。
最近知ったことであるが、この手紙の読者であるガラテヤ人たちは、生まれつき勇気のある民族であった。彼らは勇敢ではあったかもしれないが、しかし、霊的には非常に鈍かった。もし豪胆ではあっても理解力が乏しいのであれば、ガラテヤ人たちのように多くの過ちに陥ってしまう可能性が高まる。ガラテヤ人たちの場合、頭脳的に優れていなかったからこそ、異端信仰に迷い込んでしまったのである。それゆえ、勇敢という性質を否定するのではないが、やはり理解力の方が勇敢さよりも重要なものであると私は思う。何故なら、たとえ勇敢であっても理解力が乏しいゆえに誤った考えを持ってしまうのであれば、間違った事柄に熱心になってしまいかねないからである。
まずは8節目からであるが、先週確認した7節目の箇所に引き続き「刈り取り」のことについて語られている。
①『自分の肉のために蒔く者は、肉から滅びを刈り取り、御霊のために蒔く者は、御霊から永遠のいのちを刈り取るのです。』(6章8節)
この箇所では明らかに、『肉』と『御霊』という言葉が対立的に書かれていることが分かる。『肉のために蒔く』とは、本来なすべきことのために時間・労力・金銭・物品を使うのではなく、「自分自身の欲求」のためにそれらのものを使ってしまうことである。私は今ここで、我々が持つ欲求そのものを否定したわけでは決してない。欲求自体を否定しているのではなく、本来なすべきことを放棄してまで自分自身を満足させようとすることを否定しているのである。何故なら、そのようにするのは『肉のために蒔く』ことであるから。次に『御霊のために蒔く』とは、良い事柄のために、時間であれ労力であれ金銭であれ物品であれ、自分自身の持っている物を費やすことである。例えば、誰かがロシアであれ中国であれ他の国であれ、聖書配布の働きをするために時間や労力や精神などを使ったとしよう。このようにするのは間違いなく「善」の行ないであって、それは聖書に違反する行ないではない。このようにするのは明らかに『御霊のために蒔く』行為である。
『肉のために蒔く』のと『御霊のために蒔く』という2つの事柄は、決して両立し得ない。何故なら、もし『肉のために蒔く』のであれば『御霊のために蒔く』ことは出来ず、また『御霊のために蒔く』のであれば『肉のために蒔く』ことは出来なくなるからである。我々は、『肉のために蒔く』のと『御霊のために蒔く』という2つの事柄のうち、どちらか一方しか選び取れない。
さて、この箇所には『御霊のために蒔く者は、御霊から永遠のいのちを刈り取る』と書いてあるが、これは何だか行為義認を教えているかのように感じられるかもしれない。しかし、この御言葉は行為義認を教えているものではない。我々はこの箇所を読んで、「我々は御霊のために蒔くという行ないによって義と認められて永遠の命を受けるようになる。」という理解を持つべきではない。我々は、<義認・救いは行ないによるのではない>と聖書が教えていることを知っている。では、ここで言われている内容は一体どういう意味なのだろうか。ここで言われているのは、つまり「いずれ我々は永遠の命を与えられた者として永遠に生き続けるようになるのだから、そのような者に相応しく、御霊のために蒔くという行ないに励むべきである。」ということである。
文脈から考えるならば、この箇所で言われているのは「善行によって天に宝を積み上げる」ということである。つまり、御霊のために蒔くという善の行ないによって天で受けることになる永遠の報酬を増し加えよ、ということである。このことは、次の箇所である9節目を考えてみても分かるであろう。7節目と9節目で「刈り取る」ということについて言われているのは、文脈から考えるならば「天国において刈り取る」ということなのである。パウロは、いずれ我々が行きつく所である天国を対象として語っている。しかし、我々が刈り取ることになるのは<天国においてだけ>というのではなく、この世においてもそうであるということは確かである。聖書は、確かに我々がこの世においても、自分の行ないに対する報いを受けるであろうと教えているからである。
次は9節目である。パウロはこのように書いている。
②『善を行なうのに飽いてはいけません。失望せずにいれば、時期が来て、刈り取ることになります。』(6章9節)
我々は天国とこの地上において、自分の蒔いた種の刈り取りをすることになるであろう。ここで、「この箇所では(この地上ではなく)天国において刈り取りをすることを教えているのだ。」などと言いたい人がいるかもしれない。その通りである。文脈からはそう考えるがいい。しかし、我々は(天国だけでなく)この地上においても自分の蒔いた種の刈り取りをすることになるのは確かである。だから「クリスチャンはこの地上では蒔いた種の刈り取りをしない。刈り取りをするのは天国においてだけだ。」などと考えるのは誤りである。
『飽いてはいけません』また『失望せずにいれば』、とパウロはこの箇所で述べている。我々は何か善の行ないをするに際して、時には飽いてしまったり失望してしまったりする場合があるかもしれない。我々が善を行なう時に、何らかの妨げが生じたことのある経験は誰でも持っているのではないかと思う。例えば、善を行なっているのにあまり良い反応が無いので善を行なう熱心さが削がれてしまう、というのがそれである。しかし、我々は自分の行なっている善の行ないが神の御心に適ったものである限りにおいて、忍耐を持ちつつその善の行ないを継続させる必要がある。もし善の行ないを継続させるのであれば、やがて『時期が来て、刈り取ることになる』であろう。しかし、善の行ないを中断させてしまうのであれば、少しだけしか刈り取ることが出来なかったり、最悪の場合、何も刈り取れなくなってしまうようになる結末を迎えることにもなりかねない。
スポルジョンのことを考えてみよう。スポルジョンはプロテスタントの中では名声があり、知っている人が多い人物であるから、彼の名前を出すならば、聴衆の関心をその話されている内容に引き込みやすくなる効果があると思われる。それゆえ、たびたび私は彼のことについて言及しているのである。このスポルジョンは霊に燃えて説教を行ない、多くの慈善活動に精を出した。彼は、(肉のためではなく)御霊のために種を蒔いていたと言えよう。それゆえ、彼は今ごろ天国において多くの実を刈り取って喜んでいるに違いない。もし彼が豊かに善を行なったのであれば、豊かに実を刈り取っているであろう。これは、スポルジョン以外の人物でも同じことが言える。もし「豊かに実を刈り取りたい」と思うのであれば、その人は、スポルジョンや他の聖徒たちのように豊かに善を行なう必要がある。我々一人一人は、豊かな実を刈り取れるようになることを望み求め、豊かに善を行なっていくべきであろう。そうすれば、やがて『時期が来て、刈り取ることになる』ので、いずれ大いに喜ぶことが出来るようになるであろう。いずれ我々が豊かな実を刈り取れるようになるとしたら、それは何と幸いなことだろうか。
次は10節目である。
③『ですから、私たちは、機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行ないましょう。』(6章10節)
まず『すべての人』と書いてあるが、これは信者も未信者も、味方も敵も、同国人も外国人も、財産家も貧者も、あらゆる種類の人たちのことである。つまり、人間全体を指して『すべての人』と言われている。次に『信仰の家族の人たち』と書いてあるが、これはキリストを信じる兄弟姉妹のことである。パウロはエペソ2:19の箇所で、聖徒たちについて『神の家族』と言っているが、神の民である我々クリスチャンはキリストにあって互いに家族同士なのである。
この箇所を読めば分かるように、我々は兄弟姉妹である者に対する善を、兄弟姉妹でない者に対する善よりも優先させねばならない。何故ならパウロがこの箇所で「私たちは特に兄弟姉妹に対して善を行なうべきである。」と命じているからである。人は通常の場合、家族よりも只の知り合いに過ぎない人を、友達よりも友達ではない者を、妻よりも同僚を、親しい仲間よりも見ず知らずの人を優先させはしないであろう。これと同じように、我々が善を行なう際には、クリスチャンよりもノンクリスチャンの方を優先させるべきではない。我々クリスチャンとは一人一人、主にあって契約的に一体である者たちである。我々は契約的に一つであって、一人一人はキリストの身体の部分である。『あなたがたはキリストのからだであって、ひとりひとりは各器官なのです。』(Ⅰコリント12章27節)というパウロの言葉からも、このことは分かるであろう。もしそうであれば、どうしてクリスチャンよりもノンクリスチャンの方を優先させていいわけがあるだろうか。確かに我々は、クリスチャンである者に対して特に善を行なうべきである。しかし、我々はノンクリスチャンの方がたに対する善の行ないを蔑ろにしたり、否定したり、忘れたりすべきではない。我々の主なる神は御自身の民ではない者たちにも恵みを与え、彼らを日々養って下さっておられるが、そのように、我々も神の民ではない方がたに対して善の行ないをしていかねばならないのである。ただ、ノンクリスチャンに対する善の行ないに熱心になるばかりにクリスチャンに対する善の行ないが蔑ろにされてしまった、という事態が生じるのは出来るだけ避けられるべきである。
次週は11節目からである。本日は8~10節目の箇所であった。どうか主なる神が、キリストにあって造られた『神の作品』(エペソ2章10節)である御自身の民を、ますます善の行ないに富ませて下さいますように。
ガラテヤ人への手紙6章11~14節(2016/08/14説教)
『ご覧のとおり、私は今こんなに大きな字で、自分のこの手であなたがたに書いています。あなたがたに割礼を強制する人たちは、肉において外見を良くしたい人たちです。彼らはただ、キリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのです。なぜなら、割礼を受けた人たちは、自分自身が律法を守っていません。それなのに彼らがあなたがたに割礼を受けさせようとするのは、あなたがたの肉を誇りたいためなのです。しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって、世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。』(ガラテヤ6章11~14節)
先週は、我々が倦まず弛まずに御霊のために蒔くべきであるということについて話された。本日は11節目からである。
①『ご覧のとおり、私は今こんなに大きな字で、自分のこの手であなたがたに書いています。』(6章11節)
パウロは大きい文字でこの手紙を書いた。それは一体どうしてなのか。それは、ガラテヤ人が異端から遠ざかってほしいというパウロの思いが非常に強かった為であろう。我々は、どうしても知らせねばならない重要な事柄を人々に伝える時、大きな声をもって伝えるものである。絶対に言わねばならない重要な事柄であるのに、か細い声で話す人はあまりいないものである。それと同じように、パウロは何が何でも信仰義認の教理をガラテヤ人たちに伝えたかったので、必然的に文字が大きくなったのである。つまり、簡単に言ってしまえば、この手紙では「文字の大きさ」が「気持ちの大きさ」を表しているということである。
また、パウロはこの手紙を自分の手で書いた。ここで、「どうして手紙を自分自身の手で書くことをあなたは取り上げるのか。手紙を自分の手で書くことなど当たり前ではないか。別に特別のものとして説明する必要もないように感じるが…。」などと私に対して思われる方がおられるかもしれない。もちろん、今の時代においては、当然のように誰でも自分自身の手によって手紙を書くであろう。しかし、パウロが生きていた当時は今のように全ての手紙が全て自分自身の手によって書かれるというのではなく、他の者によって代筆されるというケースが多くあった。例えば、キケロ(前106―前43)はアッティクス宛の手紙のいくつかを奴隷の手によって書かせている。また、我々のよく知っている『ローマ人への手紙』は、パウロが完全に他の人物(テルテオ)によって代筆させたものである。しかし、この手紙は、完全にパウロの手によって筆記されたものである。どうしてパウロはこの手紙を『ローマ人への手紙』のように他人に書かせずに自分の手で書いたのであろうか。その理由は、ガラテヤ人たちが陥ってしまった事態が非常に深刻なものだった為であろう。つまり、ガラテヤ人たちはあまりにも悲惨な状態にあったので、パウロは(他の者ではなく)自分の手でこそ手紙を記さねばならないと考え、それゆえに自筆を選択したのではないかと思われるのである。我々は何か重大な出来事があったりした場合、他の者を現場に行かせるのではなく自分自身が出かけるようにするものであるが、パウロが自分自身の手でこの手紙を書いたのはそれと同じである。
しかしながら、この手紙は、最後だけパウロの自筆だったのではないかと考える人たちもいる。コリント書Ⅰ、コロサイ書、テサロニケⅡなどの書簡が、最後だけパウロの手によって書かれた手紙であったことは確かであろう(このことについては次の聖句を参照されたい。Ⅰコリント16:21、コロサイ4:18、Ⅱテサロニケ3:17)。しかし、この『ガラテヤ人への手紙』は、最後だけパウロが書いたのではなく、初めから終わりまでパウロの手によって書かれた手紙であると私は考える。どうしてそう思うかといえば、ガラテヤ人たちの陥ってしまっていた状態があまりにも悲惨なものだったからである。このガラテヤ人たちは神を捨て、キリストから離れ、真理に背いてしまっていたのである。こんなにも悲惨な状態に陥ってしまっていたガラテヤ人たちを正しい道に引き戻そうとして手紙を書くのであれば、どうして自分の手によって書かず、他人の手によって書くようにするだろうか。
②『あなたがたに割礼を強制する人たちは、肉において外見を良くしたい人たちです。彼らはただ、キリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのです。』(6章12節)
何という率直な言い方だろうか。パウロは何の容赦もせずに偽使徒どもの悪徳を指摘し、責め、裁いている。今の時代に教職者たちがこんな大胆な言い方をするのであれば、「裁いている。」とか「ちょっと厳しすぎると思う。」などと言われてしまいそうである。しかし我々は、偽使徒とかエホバの証人といった異端者どもが、兄弟姉妹から遠ざけられるべき邪悪な存在であるということを忘れるべきではない。彼らは教会勢力にとって「非常に忌まわしい存在」である。それゆえ、偽使徒とかエホバの証人などといった異端者どもを激しく非難するということは、忌避されたり批判されたりすべきではない。神に用いられたカルヴァンやルターやスポルジョンなどの教師たちも、キリストや使徒たちと同じように邪悪な者どもを激しく指弾しているではないか。教会をかき乱すふざけた異端者どもを激しく批判するのは、別に間違ったことではないし、悪いことでもないのである。
この箇所から分かるように、偽使徒どもが割礼を重視していたのは見栄のためであった。もし偽使徒どもが割礼を受けるのであれば、周りにいる割礼主義者たちから「アイツらは割礼を受けていないぞ。」などと悪く思われずに済むようになる。実に、偽使徒どもは他の人たちから非難されないためにこそ割礼を受け、外見を良くするという見栄を張っていたのである。このような悪徳をパウロはここで厳しく批判している。「割礼主義の人たちから悪く思われたり非難されたくない。一体どうしたら良いだろうか。そうだ。割礼主義の人たちの心に適うように割礼を重視するようにすればいいのだ。」…このような臆病な精神が、偽使徒どもを割礼を重視する輩にしてしまったのである。
「嫌われたくない。」「批判されたくない。」「仲間外れにされるのは嫌だ。」「迫害されるのが恐い。」…こういった自愛の念が真理を曲げてしまう。ペテロも自愛の念のゆえに真理に背いてしまったが、そのことを我々は以前、この手紙の2章の箇所において見た。そこではペテロが割礼派の人々を恐れてしまった為に異邦人から遠ざかり、福音の真理に背いてしまった出来事が記されていた(2章11~14節を参照)。このペテロや偽使徒どもの事例から分かるように、我々に真理よりも自己保身を優先させるような思いがあれば、真理に対する忠誠心は容易に失われてしまうであろう。もし真理よりも自分を愛する思いの方を選んだのであれば、真理への愛を退けなければならなくなるのは必然である。真理よりも自分の方を選んでしまった人が、偽使徒どもやペテロのように異端や誤謬や悪徳などに陥ってしまうのは、神からの当然の報いであると言えよう。真理の道に歩まなかったのであれば、どうしても悪の道へと歩まねばならなくなってしまうのは当然である。東に行けば西には行けず、西に行けば東には行けないのと同じで、真理の道に行けば悪の道へは行けず、悪の道に行けば真理の道へは行けないのである。神は真理を愛さない者に対して報いを与えられる。その報いは恐ろしいものである。
次は13節目である。パウロは更に偽使徒どもの悪徳を追及している。
③『なぜなら、割礼を受けた人たちは、自分自身が律法を守っていません。それなのに彼らがあなたがたに割礼を受けさせようとするのは、あなたがたの肉を誇りたいためなのです。』(6章13節)
偽使徒どもは割礼を受けることによって律法の要求を全うしていると感じていたが、それは思い違いであった。前にも述べたが、律法の要求を全うするには、割礼以外の命令をも完全に守り行なわねばならないからである。また、彼らは割礼を受けたことによって虚しい誇りを抱いていた。そして、ガラテヤ人にも自分たちが正しいと信じる割礼を受けさせることにより、この虚しい誇りを更に増し加えようとしていた。更に、偽使徒どもがガラテヤ人に割礼を受けさせようとしたのは、愚かな野心と臆病な精神に基づくものであった。つまり、偽使徒とは「どうしようもない邪悪な連中」であった。こういう輩がどうして非難されずに済むだろうか。どうしてこのような連中が教会から遠ざけられずにいて良いだろうか。このような者どもは当然のこととして非難され、教会から追い払われなければならないであろう。今の日本でこの偽使徒どもに該当するのはエホバの証人どもであると私には思われる。彼らはガラテヤ人を惑わした偽使徒どものように、我々プロテスタント教徒たちを惑わそうとする。教職者たちは教会勢力をかき乱そうとするエホバの証人のような忌まわしい異端者どもをパウロがしたのと同じように非難し、聖徒たちの精神が彼らの方になびいてしまわないようにせねばならないであろう。それは、御民一人一人が豊かに守られるためである。
次は14節目である。
④『しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって、世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。』(6章14節)
まず、『イエス・キリストの十字架』とは一体どのような意味なのか。これは、「私たちの古い人はイエス・キリストと共に十字架の上で葬られ、私たちはキリストにある被造物として新しい生命のうちに歩むようになった。」ということを言っているものである。つまり『イエス・キリストの十字架』という言葉は、主イエス・キリストが我々のために実現して下さった十字架における救いを総体的・概観的に表現したものである。
先にも述べたように、偽使徒どもは割礼を受けたことによって自分自身の肉を誇っていた。しかし、パウロは彼らの愚かな誇りを否定し、「我々はキリストとその十字架以外においては誇るべきでないのだ。」と述べる。次のようにパウロは言っている。『私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。』パウロがここで言うように、我々は自分自身の行ないを通して肉的に誇るべきではなく、ただイエス・キリストが我々のために贖いとなって下さったということをこそ誇るべきである。前にも述べたが、『誇る者は主にあって誇れ。』(Ⅰコリント1章31節)と書いてあるように、我々が主において誇ることについては禁止されていないのだ。しかし、我々が主において誇ることをせず、肉に基づいて誇るのであれば、それは愚かな高慢のなせる業である。
『この十字架によって、世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられた』と書かれている。これは、我々が主の十字架によって『今の悪の世界から』(ガラテヤ1章4節)救い出され、<この世の民>から<御国の民>へと新しく変えられたという意味である。『この世と調子を合わせてはいけません。』(ローマ12章2節)と書かれているのは、この理由による。つまり、聖徒という存在がこの世から乖離させられた者たちであるからこそ、聖徒たちはこの世と調子を合わせるべきではないと言われているのである。もしこの世から救い出されて神の国の住民となったのであれば、確かに、我々がこの世とそこに満ちた様々な悪に迎合すべきではないことは自明である。更に、もし我々が御国の民とされたのであれば、我々はこの世と調子を合わせないだけでなく、世にあって光り輝き、神の国の拡大を大いに望むようにすべきであろう。何故なら、そのようにするのは、神の民として相応しいことだからである。「我々はこの世から乖離させられたのだからこの世の事柄には触れるべきではない」などと我々は考えるべきではない。今のプロテスタント界のクリスチャンはこのように考えてしまいがちである。しかし我々はこのように考えるのではなく、むしろ、この世の悪が無くなっていくようになることを、また教会が世にあって指導力を発揮していけるようになることを、積極的に望むべきである。何故なら、キリストによって贖われた我々とは『世の光』(マタイ5章14節)また『地の塩』(同5章13節)とされた存在だからである。他のプロテスタント教会がどのように考えようが、当教会はあくまでも『世の光』『地の塩』として歩めるようになるのを願い求めていくであろう。イエス・キリストの十字架によって悪しき世から救い出された我々は、この世と調子を合わせず、地球全体が神の御心に適ったものへと変えられていくようになるのを望むべきである。
ガラテヤ人への手紙6章15~16節(2016/08/21説教)
『割礼を受けているか受けていないかは、大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。どうか、この基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に、平安とあわれみがありますように。』(ガラテヤ6章15~16節)
先週の箇所は11~14節目であった。この手紙に対するパウロの言及(11節)、偽使徒どもへの批判と悪徳の暴露(12~13節)、イエス・キリストの十字架こそを誇るべきことや聖徒たちはこの世から乖離させられた存在であること(14節)、などについて語られた。本日は15節目からである。
ここまで『ガラテヤ人への手紙』を見てきたが、御言葉とは実に深淵なものであると強く感じさせられるものである。恐らく、他の方がたも私と同じように感じておられるのではないかと思う。この御言葉とは真理であって、その深淵さを測り知ることは出来ない。御言葉が深淵であるからこそ、我々は御言葉を完全完璧に把握することが出来ない。それゆえ、我々が聖書を読む度に新しい発見があるのは必然である。また、御言葉とはすなわち「神による天上的な言葉」であるから、どれだけ読んでも決して擦り切れることがない。人間が書いた地上的な言葉であれば、何回も読んでいる間に擦り切れて飽きてしまうことにもなるが、御言葉は天上的なものであるから、そういうことがない。神の真理の言葉であるにもかかわらず、どうして擦り切れることがあるだろうか。私の場合、聖書はいつ読んでも常に新鮮であるように感じられる。これは、御言葉が擦り切れることのない天上の性質を持っているからに他ならない。もし御言葉が地上的なものであったならば、何回も読んでいる内に飽きてしまったことであろう。ルターは毎年3回も聖書を読了していたが、もし御言葉が神による言葉でなかったのだとしたら、年に3回も読めなかったであろう。我々はこの御言葉が天上的なものであり、聖なるものであることを知っている。この御言葉を聞いたり読んだりすることが出来るのは、またこの御言葉を考え、理解し、実行したりすることが出来るのは、神の大きな恵みによるものである。もし神の恵みが無ければ、我々は、他の多くの人たちと同じように、御言葉に心を傾けることが出来無かったであろう。
それでは本日の聖句を見ていきたい。まずは15節目からである。
①『割礼を受けているか受けていないかは、大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。』(6章15節)
偽使徒どもは割礼を大事なものとして認識していた。彼らが割礼を重視していたからこそ、ガラテヤ人にも自分たちと同じように割礼を受けさせようとしたわけである。しかし、パウロはこの箇所で「割礼を受けているかどうかは重要なことではない。そんなものは別にどうだっていいのだ。」と言う。パウロは他の箇所でもこう言っている。『割礼は取るに足らぬこと、無割礼も取るに足らぬことです。』(Ⅰコリント7章19節)旧約時代においては、割礼を受けていることに重要な意味があった。当時は、割礼を受けていなければ神の民として認められなかったのである。当時は、神の民であるというのであれば、どうしても割礼を受けている必要があった。しかし新約時代においては、主イエス・キリストに対する信仰によって神の民とされるのであるから、割礼を受けるか受けないかということは別にどうてもいいことである。それゆえ、パウロはここで割礼の必要性・重要性を否定し、割礼を「どうでもいいもの」として扱っている。
『新しい創造』と書いてある。これは即ち、「イエス・キリストによって新しい被造物とされる」ということである。人は、キリストに対する信仰を持つのであれば救われ、キリストによって新しく創造された種族へと変えられる。パウロは、これこそ大事なことであると述べている。たとえ偽使徒どものように割礼を受け、自分自身の肉や行ないを誇ったとしても、もしイエス・キリストを信じて新しく創造されないのであれば、一体なんの意味があるだろうか。その人が最後に行きつく所は永遠の暗闇、地獄である。しかし、割礼を受けておらず、自分の中には何一つ誇るべきものが無かったとしても、イエス・キリストを信じて新しい被造物とされるのであれば、その行きつく先は至福に満ちた永遠の天国である。それゆえ、全ての人にとって究極的に大事なこととは、何かの行ないをして自分自身を誇るなどということではなく、イエス・キリストを信じて新しい被造物(すなわち神の民)とされることである。我々はこのことを神の恵みのゆえに知っているが、この世の人びとは知らず、それを悟ることすら出来ない。多くの人びとがイエス・キリストによって新しい被造物とされることの重要性に無知なままでいるのは、またイエス・キリストによって新しい被造物とされないままでいるのは、大変不幸な状態であると言える。
ところで、この箇所の翻訳についての話だが、我々が使っている新改訳聖書の元となっているアレクサンドリア型写本では、「キリスト・イエス」という言葉が存在していない。しかし、教会がその歴史の大半において使用してきたビザンチン型写本では、「キリスト・イエス」という言葉が存在している。すなわち、ビザンチン型写本では『割礼を受けているか受けていないかは、大事なことではありません。』という文章の前に、『キリスト・イエスにあっては』という文章が付いている。この『キリスト・イエスにあっては』という文章が、アレクサンドリア型写本には無い。前にも話したことだが、この箇所でも、アレクサンドリア型写本にはキリストの御名が存在していない。ビザンチン型写本にはキリストの御名があるのに、アレクサンドリア型写本には存在していないという箇所は他にもある。前々から思っていたのだが、アレクサンドリア型写本には人為的な書き直し、削除がなされているように感じられる。もし本来は写本にキリストの御名が書かれていたのにもかかわらず、それを消したというのであれば、実に忌々しき、許しがたい愚行であると言わねばならない。もしそういうことをした者がいたのであれば、その者は呪われるべきである。何故なら、その人は、神の聖なる言葉を削除したからである。前から感じていることだが、やはりビザンチン型写本の方が正当な写本ではないかと、私には感じられる。これから、聖霊派がそうしたごとくに、ビザンチン型写本に基づく翻訳聖書が出版されてほしいものである。
次は16節目である。
②『どうか、この基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に、平安とあわれみがありますように。』(6章16節)
ここでパウロが語りかけている対象は、偽使徒どもではなく、クリスチャンではないユダヤ人たちでもない。ここでパウロが対象としているのは、明らかにガラテヤの諸教会にいた真のクリスチャンたちである。また、この箇所で言われている対象はガラテヤ人だけでなく、プロテスタント教徒である我々にも及んでいると理解すべきである。というのは、パウロがここで語っているのは、神の民である者たちに対してだからである。もしカトリック教徒がこの箇所を自分たちにも言われているものとして考えるとしたら、そのように考えるのは如何(いかが)かと私は思う。何故なら、カトリック派には看過できない異端的教理が多く存在しているがゆえに、彼らカトリック教徒たちが真のクリスチャンであるとは言い難いからである。もし彼らが真のクリスチャンであるとは言い難いとしたら、この箇所で言われていることがカトリック教徒にも及んでいるとは言いにくいであろう。何故なら、(繰り返しになるが)この箇所は真のクリスチャンである者たちを対象としているからである。
さて、パウロはガラテヤ人に対して『神のイスラエル』と述べている。真のクリスチャンであれば、ガラテヤ人であれパウロであれ誰であれ『神のイスラエル』である。私は言うが、真のクリスチャンこそが『神のイスラエル』なのであって、ノンクリスチャンであるユダヤ人たちは『神のイスラエル』ではない。このような言葉を当時のユダヤ人たちが聞いたならば、次のように反論したかもしれない。「ふざけたことを言うな。我々ユダヤ人こそが神のイスラエルだ。」しかし、パウロはこの箇所で、真のクリスチャンこそが『神のイスラエル』なのであると我々に教えている。それゆえ『神のイスラエル』と言える種族はただ一つ、クリスチャンだけなのである。ユダヤ人たちは民族的にはイスラエルであるが、もしキリストを信じていないのであれば『神のイスラエル』ではない。
この『神のイスラエル』とは、聖句から分かるように『この基準に従って進む人々』である。さて、ここで言われている『この基準』とは一体なんなのだろうか。これは文脈から考えるならば、「イエス・キリストの十字架による救いの原理」に関する事柄であろう。すなわち、イエス・キリストの十字架における救いを信じ、信仰による義認の教理のうちに保たれ、キリストの十字架を誇りとしている人物であれば、その人は『この基準に従って進む人々』である。しかし、キリストの救いを正しく信じておらず、信仰義認の教理にも立っておらず、キリストの十字架を誇りとしていない人物であれば、その人は『この基準に従って進む人々』であるとは言えない。何故なら、その人はキリストの救いに関する事柄を否定してしまっているからである。
ここで言われている『神のイスラエル』すなわち『この基準に従って進む人々』とは、今の時代においては、我々プロテスタント教徒だけに該当すると私には思われる。何故なら、キリストによる救い・再生・義認・罪の赦しに関する教義を正しく信じているのは、プロテスタント教徒だけだからである。ローマ教の信徒たちは、数多くの異端的教義を何の抵抗もなく信じているから、彼らが真に『神のイスラエル』であるとは言い難い。クリスチャンではないユダヤ人たちは、先にも述べたように民族的にはイスラエルかもしれないが、キリストの救いを信じていないのだから、『神のイスラエル』であるとは言えない。他の宗教の人たちも、明らかに『神のイスラエル』ではない。無宗教である未信者の方がたの場合は、誰がどのように考えても『神のイスラエル』であるとは言えないであろう。それゆえ真に『神のイスラエル』と言えるのは、今の時代では、我々プロテスタント教徒たちだけである。
この『神のイスラエル』である者たちは、パウロの述べる聖なる基準に固く根ざし続けるべきである。何故なら、この基準に固く立ち、その基準の内に歩み続けるのが『神のイスラエル』だからである。もし我々がこの基準から逸れてしまうのであれば、『神のイスラエル』であるとは言えなくなってしまうであろう。
パウロは聖徒に対して『平安とあわれみがありますように。』と書いている。『平安』とは、キリストにあって与えられる平安のゆえに穏やかでいられる精神状態について言われているものである。『あわれみ』とは、聖徒たちの霊と肉体に対する神の豊かな守りのことを言っているものであると思われる。パウロはこの箇所で聖徒たちに『平安とあわれみ』を願っているが、もしこの『平安とあわれみ』がなければ、我々は悲惨である。何故なら、これらのものが無かったならば、我々の心は騒ぎ、様々な悪徳から守られなくなってしまうだろうからである。我々に平安があるからこそ心を騒がせずに済み、憐れみがあるからこそ悪に迷い込まずに済むのである。この『平安とあわれみ』というものが幸いなものであることは明らかである。それゆえ、パウロはここで、御霊の愛によって聖徒たちに幸いを願っていることが分かる。聖徒たちが幸いであることを望んでいるからこそ、『平安とあわれみ』があるように願っているわけである。互いに愛し合うべき我々クリスチャンは、このパウロに倣(なら)い、自分の仲間である兄弟姉妹たちに『平安とあわれみ』があるのを願うべきであろう。
本日の箇所は15~16節目であった。次週は17~18節目である。
ガラテヤ人への手紙6章17~18節(2016/08/28説教)
『これからは、だれも私を煩わさないようにしてください。私は、この身に、イエスの焼き印を帯びているのですから。どうか、私たちの主イエス・キリストの恵みが、兄弟たちよ、あなたがたの霊とともにありますように。アーメン。』(ガラテヤ6章17~18節)
「ガラテヤ人への手紙」からの説教は、本日で最後である。本日は17~18節目となる。先週の箇所は15~16節目であった。新しい創造のことや神のイスラエルのことなどについて語られた説教であった。それでは早速、本日の箇所を見ていきたい。
①『これからは、だれも私を煩わさないようにしてください。私は、この身に、イエスの焼き印を帯びているのですから。』(6章17節)
この箇所でパウロは自分の心の思いを吐露している。「私に面倒をかけさせないでくれ」と。この大胆さ・率直さ・直裁さは、聖書特有のものである。この箇所もそうだが、聖書では、何も妨げられることのない記述がなされている。
さて、ここで『だれも私を煩わさないようにしてください。』と言われているのは、偽使徒どもに対してである。何故なら、偽使徒どもが全ての元凶だからである。この偽使徒どもがいなければ、ガラテヤ人たちが惑わされることによりパウロに煩いが生じることは無かったであろう。だから、この箇所では偽使徒どもが対象とされていると私は考える。つまり、パウロはここでこう言いたいのである。「異端者である偽使徒どもよ。主に遣わされた使徒である私に手間をかけさせるなかれ。」
今、私はこの箇所で言われているのは「偽使徒ども」に対してであると述べたが、偽使徒どもだけでなく「ガラテヤ人」も含まれていると考える人がいるかもしれない。つまり、ここでは、偽使徒どもとガラテヤ人という2者を対象として『私を煩わさないようにしてください。』と言われていると思う人がいるかもしれない。確かに、そのような解釈をすることも出来ないわけではない。私は、そのような解釈をする人がいても、否定したり批判したりはしない。
ところで『イエスの焼き印を帯びている』と書いてあるが、これは一体どういう意味だろうか。これは、一言でいえば「信仰のゆえに受けた物理的患難」のことである。パウロはキリストを信じる信仰のゆえに鞭で打たれたり、石で傷つけられたり、飢え渇いたりするなど、多くの身体的苦痛を受けた。彼は真に敬虔な信仰を持っていたので、それだけ受けることになった苦痛も大きかったのである。信仰のゆえに受けるこの苦痛を指して、ここでは『イエスの焼き印』と言われている。
パウロは「イエスの焼き印を帯びているからこそ誰も私を煩わしてはならない。」とこの箇所で述べている。一体どうしてパウロは「イエスの焼き印を帯びているから」という理由のゆえに、煩わされることを嫌に思って避けようとしているのだろうか。その理由は2つ考えられる。まず一つ目は、もう十分にイエスの焼き印を帯びているのだから更なる焼き印を帯びる必要性は感じられない、という理由である。つまり、パウロは他の聖徒たちよりも多くイエスの焼き印を帯びているのだから、どうしてこれ以上イエスの焼き印を帯びる必要があるだろうか、ということである。これは、戦争で負った多くの傷のために勇敢な戦士であることが証明された人が、更なる傷を負わなくても勇敢であることが十分に分かるというのと同じである。この人はもう既に十分に傷を持っているのだから、更なる傷を負わなくても勇敢な戦士であることは誰の目にも明らかだからである。もう一つ目は、イエスの焼き印を帯びている使徒である者を困らせてはならない、という理由である。つまり、「どうしてイエスの焼き印を帯びている使徒を煩わせようとするのか。いったい私を何だと思っているのか。私はイエスの焼き印を帯びた使徒である。このような者である私を困らせるとは一体どういうことなのか。」ということである。これは、高貴であったり地位が高かったり尊敬されている人物が、「誰も私に迷惑をかけないで下さい。」というのと同じである。この人は、強い自負心のゆえに自分に迷惑をかけないようにと要求している。それと同じように、パウロもキリストにある自負心のゆえに、自分に迷惑をかけないように要求しているのだと考えられる。人は、強い自負心を持っているのであれば、愚かな人たちから迷惑をかけられるのを強く厭うものである。
②『どうか、私たちの主イエス・キリストの恵みが、兄弟たちよ、あなたがたの霊とともにありますように。アーメン。』(6章18節)
この手紙の最後の箇所である。
パウロは聖徒たちの霊に恵みがあるようにと、この箇所で願っている。これはつまり聖徒たちの霊がキリストにあって守られ、健全な状態に保たれ、より研ぎ澄まされたものとなるように、ということである。ところで、ここでパウロはただ単に「恵みがあるように。」と言うのではなく、「霊とともに恵みがあるように。」と言っている。どうして「霊とともに」とパウロは言ったのだろうか。別に、「霊とともに」と言わなくても十分に意味は伝わるはずである。パウロが「霊とともに」と言ったのは、ガラテヤ人が霊的に悲惨な状態にあったからだと思われる。つまり、パウロはガラテヤ人の霊を心配していたからこそ、ここで「霊とともに恵みがあるように。」と願っているわけである。
手紙の最後の部分で「恵みがあるように。」と願うのは、パウロの手紙の特徴である。パウロの書簡では全て、最後の箇所で「恵みがあるように。」と言われている(ローマ16:20、Ⅰコリント16:22、Ⅱコリント13:13、エペソ6:24、ピリピ4:23、コロサイ4:18、Ⅰテサロニケ5:28、Ⅱテサロニケ3:18、Ⅰテモテ6:21、Ⅱテモテ4:22、テトス3:15、ピレモン25)。ヘブル人への手紙の著者が誰であるか我々は知らないが、もしこの手紙がパウロによるものであったとしたら、このヘブル人への手紙でもパウロは最後の箇所で「恵みがありますように。」と書いていることになる(ヘブル13:25)。パウロ以外の新約聖書記者は、ヨハネ黙示録とヘブル書を除けば最後に恵みを願う言葉を書いてはいない。ヘブル書の箇所はたった今確認した通りだが、ヨハネの黙示録の最後の部分でも恵みが願われている(黙示録22:21)。パウロが全ての手紙における最後の箇所で「恵みがあるように。」と願っているのは、非常に特徴的である。
恵みが聖徒たちに注がれるのは非常に喜ばしいことである。自分の兄弟姉妹である者たちに恵みが与えられるのを喜ばないクリスチャンはいないはずである。パウロも、それが喜ばしいことであるがゆえに、聖徒たちに恵みがあるようにと願っているのである。我々も、自分の同胞である聖徒たちにキリストの恵みが豊かに施されるようになるのを願うべきであろう。
パウロがここで言っていることを別の言葉で言い換えれば次のようになる。「主イエス・キリストによる恵みがあなたがたの霊に注がれますように。そして、その状態(すなわち霊に恵みが注がれている状態)が保たれますように。」つまり、ここで言われているのは、パウロから恵みが注がれるということではなく、キリストから恵みが注がれるということである。パウロは自分自身の力によっては聖徒たちの霊に恵みを施すことが出来ない。聖徒たちの霊に恵みを施されるのは常に神であられる。私たちも、ここでパウロが言っているのと同じことを祈ったり告げたりすることがある。「○○さんの上に主の恵みがありますように」と。これは、今説明したことから分かると思うが、我々から恵みが注がれるようにと言っているのではなく、主から恵みが注がれるようにと言っているものである。
パウロは『アーメン。』という言葉でこの手紙を終わらせている。これは、その言われたことに同意の念を示すものである。原義はヘブル語で「そうあれかし」である。これは我々が日本語で「然り、その通りです。」と口にするのと同じである。このアーメンという言葉はキリスト者があまりいないこの日本でもよく知られており、ノンクリスチャンの方であってもふざけて「アーメン」などと言う人がいるほどである。ノンクリスチャンの方がこの言葉の意味を十分に弁えているかどうかは定かではないが、とにかくよく知られた言葉である。なお、パウロは「ローマ書」と「Ⅰコリント書」の最後の部分もこの言葉で終わらせている。『アーメン。』という言葉で終わっているパウロ書簡は、我々が今見ているガラテヤ書とローマ書およびⅠコリント書の3書だけである。これ以外のパウロ書簡は『アーメン。』という言葉で終わっていない。
③終わりに
この手紙が送られた後、ガラテヤの諸教会の状態は一体どのようになったのであろうか。具体的にどうなったか詳しいことは分からない。しかし、確実に言えることがいくつかある。それは、まず、この手紙を読んだ者のうち、信仰が強められるように定められていた人は信仰が強められ、偽使徒に騙されてしまっていたが信仰義認の教えに戻るように定められていた人は信仰義認の教えに戻り、パウロに反発するように定められていた人はパウロに嫌悪感を持つようになり、この手紙の内容を受け入れられずに真理から背くように定められていた人はますます真理から遠ざかった、ということである。この手紙を読んだガラテヤ人は、各々が神の定めた通りの状態に導かれたことであろう。またもう一つ確実に言えるのは、この手紙はパウロが送った後に複製されて多くの聖徒たちに読まれた、ということである。
この手紙では、イエス・キリストの聖なる救いが多角的に論じられている。ガラテヤ人たちは鈍かったので、色々な言い方、様々な表現方法、種々の内容によって教えられ、説得される必要があった。我々は、この手紙から『聖書的な説得方法』を学ぶことが出来るであろう。その方法とは、異端に陥った者、不敬虔な者、無知・鈍感な者―つまりガラテヤ人のような者―に対しては、多種多様な手段をもって教えたり目覚めさせたりせねばならない、ということである。つまり、「数を尽くして働きかける」ということである。もしパウロのように沢山の表現方法、また多くの話題をもって働きかけるならば、その内のどれか一つが語りかけられた人の霊を揺るがし、正しい教えに目覚めるようになるかもしれないからである。沢山やればやるほど、目標物を捉えられる可能性はそれだけ増す。教会のトラクトも、たとえそれがどのような内容であったとしても、数万枚も配布すれば1人ぐらいは教会に来てくれるものである(もちろん、どれだけ配布しても誰も来ない場合もあるが)。数を尽くすからこそ期待していたものを獲得できるようになる度合いも増すわけである。しかし数を尽くさなければ、それだけ目標物を捉えられるようになる度合いは低下する。
本日で『ガラテヤ人への手紙』からの説教は終わりである。この手紙を全部確認するのに10ヶ月程かかった。カルヴァンやブリンガーも聖書を順々に説明する説教をしていたが、彼らの説教と比べるとかなり遅いスピードである。一つ一つの聖句内容を詳しく見たので、ゆっくりと進行する説教であった。最後になるが、ここまで『ガラテヤ人への手紙』からの説教を行なわせ、この手紙を通して我々に恵みを注いで下さった神に感謝と讃美を捧げる。この説教のために書かれた文章は教会HPにも掲載してあるので、神が豊かに用いて下さいますように。当教会の聖徒たちに、またこの説教文章を読んでおられる聖徒の方がたに、イエス・キリストの恵みが豊かにありますように。アーメン。