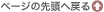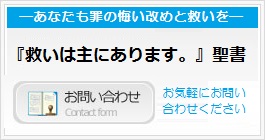再臨論
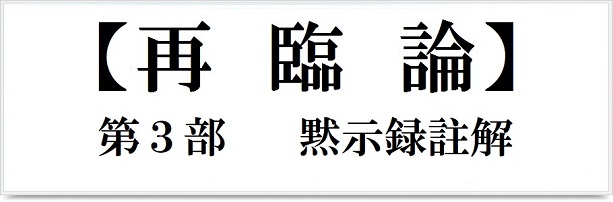
稲野晴也
目次
はじめに 本作品の目的
凡例
【第1部 既に起きた再臨】
第1章 再臨に対する一般的・歴史的な見解
第2章 既に起きた再臨
第3章 再臨の起きた年
第4章 本当にすぐに起きた再臨
第5章 宣教命令が成就してから起きる再臨
第6章 実際の身体をもって再臨されたキリスト
第7章 再臨の証拠
第8章 再臨に関する御言葉を信じることができない理由
第9章 再臨は2度起こるのではないかという疑問
第10章 今まで教会に再臨を正しく理解する解釈の恵みが与えられなかった理由
第11章 再臨に関する悔い改めについて
第12章 この再臨論に対する教職者の反応と態度
【第2部 再臨と再臨の前後に起きた諸々の出来事の詳細およびその順序】
第1章 第2部の説明
第2章 再臨と再臨の前後に起きた出来事の順序
第3章 ①教会による42ヶ月の預言活動(紀元61年6月~64年12月)
第4章 ②ネロによる42ヶ月の迫害(紀元64年12月~68年6月9日)
第5章 ③再臨(紀元68年6月9日)
第6章 ④エルサレムの包囲と滅亡(紀元68年6月9日~70年9月)
第7章 これから世界はどうなるのか
第8章 聖徒の信仰生活について
第9章 重大な懸念
第10章 真理のありか
【第3部 黙示録註解】
第1章 黙示録を理解する必要性
第2章 黙示録の筆記年代
第3章 事前に知っておくべきこと
第4章 ①1章:プロローグ
第5章 ②2~3章:7つの教会に対するキリストの称賛と勧告と約束
第6章 ③4章:天における場景
第7章 ④5章:7つの封印を解くことになったキリスト
第8章 ⑤6章:キリストによる6つの封印の解除
第9章 ⑥7章:間奏―神の配慮と耐え忍んだ者に与えられる天での恵み
第10章 ⑦8章1節:キリストによる7つ目の封印の解除
第11章 ⑧8章2節~9章21節:6つのラッパによる預言
第12章 ⑨10章1節~11章13節:挿入―ネロによる大患難の前に起きる出来事から再臨の日に起こる携挙の出来事までについての預言
第13章 ⑩11章14節~19節:残された7つ目のラッパによる預言
第14章 ⑪12章:ネロによる大患難からサタンがローマ軍を招集する出来事までについての預言
第15章 ⑫13章:ネロと偽預言者についての預言
第16章 ⑬14章1~5節:天国の情景
第17章 ⑭14章6~13節:裁きの日に向けた色々な預言
第18章 ⑮14章14~20節:2度の携挙
第19章 ⑯15~16章:7つの鉢による裁き
第20章 ⑰17章:開示されるイスラエルとローマ皇帝ネロの秘儀
第21章 ⑱18章:ユダヤの裁きについて言われた霊的な預言
第22章 ⑲19章1~10節:ユダヤが陥落してから起きた天での出来事
第23章 ⑳19章11~21節:再臨および再臨の際に起きた2つの裁き
第24章 2120章1~6節:復活と携挙と裁きと荒野の期間
第25章 2220章7~10節:解放されたサタンとローマ軍による都の包囲/サタンとローマ軍に対する裁き
第26章 2320章11~15節:第二の復活、第二の携挙、空中の大審判について
第27章 2421章1節~22章5節:天国について
第28章 2522章6~21節:エピローグ
第29章 ヨハネが黙示録を書いた理由
第30章 黙示録の註解における真実―濃密な文章は正しい見解の証拠
補章 マサダの要塞および第2次ユダヤ戦争における記述について
【第4部 部分註解】
第1章 十全な再臨理解のために必要な聖句の部分註解
第2章 第4部の記述について
第3章 1:創世記
第4章 2:出エジプト記
第5章 3:レビ記
第6章 4:民数記
第7章 5:申命記
第8章 6:ヨシュア記
第9章 7:士師記
第10章 8:ルツ記
第11章 9:Ⅰサムエル記
第12章 10:Ⅱサムエル記
第13章 11:Ⅰ列王記
第14章 12:Ⅱ列王記
第15章 13:Ⅰ歴代誌
第16章 14:Ⅱ歴代誌
第17章 15:エズラ記
第18章 16:ネヘミヤ記
第19章 17:エステル記
第20章 18:ヨブ記
第21章 19:詩篇
第22章 20:箴言
第23章 21:伝道者の書
第24章 22:雅歌
第25章 23:イザヤ書
第26章 24:エレミヤ書
第27章 25:哀歌
第28章 26:エゼキエル書
第29章 27:ダニエル書
第30章 28:ホセア書
第31章 29:ヨエル書
第32章 30:アモス書
第33章 31:オバデヤ書
第34章 32:ヨナ書
第35章 33:ミカ書
第36章 34:ナホム書
第37章 35:ハバクク書
第38章 36:ゼパニヤ書
第39章 37:ハガイ書
第40章 38:ゼカリヤ書
第41章 39:マラキ書
第42章 40:マタイの福音書
第43章 41:マルコの福音書
第44章 42:ルカの福音書
第45章 43:ヨハネの福音書
第46章 44:使徒の働き
第47章 45:ローマ人への手紙
第48章 46:コリント人への手紙Ⅰ
第49章 47:コリント人への手紙Ⅱ
第50章 48:ガラテヤ人への手紙
第51章 49:エペソ人への手紙
第52章 50:ピリピ人への手紙
第53章 51:コロサイ人への手紙
第54章 52:テサロニケ人への手紙Ⅰ
第55章 53:テサロニケ人への手紙Ⅱ
第56章 54:テモテへの手紙Ⅰ
第57章 55:テモテへの手紙Ⅱ
第58章 56:テトスへの手紙
第59章 57:ピレモンへの手紙
第60章 58:ヘブル人への手紙
第61章 59:ヤコブの手紙
第62章 60:ペテロの手紙Ⅰ
第63章 61:ペテロの手紙Ⅱ
第64章 62:ヨハネの手紙Ⅰ
第65章 63:ヨハネの手紙Ⅱ
第66章 64:ヨハネの手紙Ⅲ
第67章 65:ユダの手紙
第68章 第4部の最後に
第69章 聖書に書かれているユダヤ戦争について
【後記】
【資料】
【リンク】
【付録】
【作品情報】
はじめに 本作品の目的
この作品は、聖書が教えている再臨の真理を聖書に基づいて明らかにすることを目的としている。この作品に、それ以外の目的はない。それゆえ、この作品の記述は、ことごとく読者に再臨を正しく理解していただくという一点にこそ向けられている。よって、この作品には再臨以外にも、再臨と関わりを持つ出来事であれば、その出来事が書き記されている。それは読者が再臨と関わりを持つ出来事をも詳しく知ることにより、より豊かに再臨のことを理解できるようになるためである。再臨と関わる出来事をも再臨と併せて知ることで、より再臨の詳細を把握できるようになるというのは言うまでもないことであろう。
この作品の構成について書きたい。まず第1部であるが、ここでは聖書から既に再臨は起きているということに関する真実性を論証することが目的とされている。ここは再臨が既に起きたという真実性を証明する箇所だから、まだ再臨や再臨の前後に起こる出来事の内容およびその順序については詳しく論じられない。第2部は、再臨は既に起きたということを聖書によって理解した読者が、再臨や再臨の前後に起こる出来事の詳細およびその順序を把握することを目的とする。それは、ますます読者が再臨のことを理解できるようになるためである。第3部は、黙示録の註解を通して再臨を更に豊かに理解できるようになることを目的とした内容である。これは非常に豊かな内容であり、徹底的な記述となっている。第4部以降は、それが書かれるの書かれないかということさえ、2020年2月22日(土)である今現在は何も確定的なことを語らないでおきたい。とうのも、今はまだそのことについて語るべき段階にはないからである。ソロモンも言うように、『何事にも定まった時期』(伝道者の書3章1節)がある。人は、知恵と思慮とを持つべきである。これから確定的なことを語るべき時期が訪れたならば、その時にはこの箇所で、そのことについて語られることになるであろう。以上、ここまで第3部までの構成について不足なく簡潔に語られたことにしたい。
最後に、この作品の中で書かれていることの重大性について書いておきたい。この作品で書かれていることを読んだ方は、初めは、まだその重大性がどれほどのものか、よく悟れないのではないかと思う。「ふーん、そうなのか。」としか思えない方も多いはずである。誰でも最初は、事の重大性があまりにも大きすぎるので、逆にほとんど重大性を感じ取れないのである。それは、ちょうど、目の前から1mぐらいの場所に月が急に出現したのだが、月が近付き過ぎているために、何が起きているのか分からずきょとんとしてしまうようなものである。しかし、時間が経つにつれ、徐々にその重大性が分かるようになっていく。そうしてある一線を越えると、この事柄がどれほど重大であるのかということを真に悟れるようになる。その時、その人は、この問題をどうあっても無視できない状態に至ることになる。ちょうど、離婚した親の子どもが新しく親となった人物のことを大いに気にするように、養子として入ってきた血の繋がりのない家族を既にいた子どもたちが注意するように、この事柄に心を傾けるであろう。例えはあまり良くないが、この新しい親また養子とは、すなわち、この作品の中で説明される再臨の真理のことである。しかし、読者は事の重大性を感じ取っても驚き慌てたりせず、どうか常に冷静さを保ってほしい。そうするのが英知ある姿勢だからである。箴言17:27には『心の冷静な人は英知のある者』と記されている。また、よく考えつつ読み進めて行くことをお勧めしたい。私がこの作品で取り扱っていることは、非常に重大なことであり、よく考えねばならないことだからである。また、途中で速断したりせずに、最後までしっかりと読むことも重要である。最後まで読んでこそ、最善の判断を得られるからである。多くの知識を得なければ、それだけ判断を誤る確率が高まるのは言うまでもない。何よりも大切なのは、神の言葉にこそ根差し、真理を求めて真摯に祈り願うことである。そうすれば、聖書が教える再臨の真理を十全に把握できるようにもなるであろう。神の言葉に立たず、真理のために祈りもしないのであれば、真理を把握できなかったとしても自然なことである。真理とは神の言葉なくして悟れず、また神は真摯に祈る者の願いを聞き入れて下さるからである。未だに分からない真理のために祈るということについては、アウグスティヌスも次のように言っている。「あなたがたの精神を集中させても未だ到達できない事柄については、それが何であれ、あなたがたの間に平安と慈愛を守り続けながら、主によって理解させていただけるよう祈りなさい。そして、あなたがたが未だ理解できていない事柄については、主ご自身が導いてくださるまで、あなたがたが到達しえた所を歩んでゆきなさい。」(『アウグスティヌス著作集10 ペラギウス派駁論集(2)』恩恵と自由意志 第1章 1 p16:教文館)真理の味は誠に心地良い。確かに真理を得てそれを保持し続けたために、何らかの苦しみを受けるということはあるかもしれない。しかし、それではあっても、真理の味そのものは、あまりにも喜ばしい。願わくは、多くの読者が、この素晴らしき真理の美酒に酔いしれんことを。アーメン。
2019年6月14日(金)
稲野晴也
凡例
◎この作品で筆者が想定している対象は、今の時代に生きる全ての聖徒たちと、未来に生きる全ての聖徒たちである。私は日本人であるが、現代に生きる日本人だけを対象としていたのでは、通俗性も力も失われてしまいかねない。商売の世界を見れば分かるように、強大な通俗性と力を持っているのは、2019年の今で言えばアップルやマイクロソフトやアマゾンやネスレやジョンソン・アンド・ジョンソンなど、どこも自国だけではなく全世界を相手に商売をしている多国籍企業である。私がしているのは商売ではないが、しかし現代の日本人だけを対象としたのであれば、その対象の規模に相応しく、やはり、それだけのものしか出来上がらないであろう。また筆者である私は、この作品を、キリスト教界とその未来のため、すなわち教会の歴史のために書いている。よって、想定する対象は、必然的に今と未来に生きる全ての聖徒たちにならざるを得ない。
◎この作品の中には、色々な書物からの引用や言及がされているが、信仰があまり強くないと感じる人は、たとえその書物が気になったとしても、無闇に読まないほうがいいであろう。それは、その人の信仰がおかしくなってしまわないためである。例えば、本作品ではイルミナティでありユダヤ教徒の手駒であった哲学者ニーチェの『反キリスト』という作品が言及されているが、これは信仰に自信のある強い霊を持った人でなければ読まないほうがよい。タイトルからして既にサタン的な内容であることが分かると思うが、どういうことが書いてあるか気になるからといって、霊的に未熟な人がこれを読めば、霊がおかしくなったり、動揺してしまったり、躓いたりしてしまいかねない(※)。特に、この作品は、信者になったばかりの人は絶対に読んではいけない。また、本作品では外典や偽典もよく引用されているが、これも強い霊を持っておらず聖書の知識が十分にない人は、あまり読まないほうがいいかもしれない。そのような人が外典や偽典を読めば、正典に関わる様々な知識が頭に入ってくることにより、動揺したり正しい判断が取れなくなって悩んだり、また正典を純粋に直視できなくなってしまう、ということが起こりかねない。霊的に熟練していない人は、正典を読んでいるだけで十分であり、そうするのが無難である。筆者である私は、教えと神学の賜物が恵みにより与えられているがゆえに、信仰を乱しかねなかったりサタン性の強い書物を読んでも、平気であり害を受けずに済んでいるということを言っておきたい。しかし、クリスチャンの中にはそのような人ばかりではないのである。変な書物を読んだために、信仰がおかしくなってしまう人も多い。いずれにせよ、何といっても我々は聖書にこそ心を傾けねばならないということを、私はルターと共に言っておこう。何故なら、この聖書にこそ神の真理が書かれているからである。だから、カルヴァンも言うように「わたしたちは常に主の口に聞かなければならない」(『新約聖書註解Ⅴ 使徒行伝 上』10:15 p312:新教出版社)のである。もちろん他の書物を読むことも有益ではあるが、他の書物ばかり読んでいたのでは、どうにもならない。聖書の真理を正しく理解しようとして聖書以外の書物を読み漁るのだが、そのために聖書をあまり読まなくなってしまったというのでは、本末転倒もいいところである。
(※)
例えば、著者自身でさえ生前の刊行を避けたこの邪悪な作品には、以下のようなふざけたことが書かれている。この弱犬の遠吠えを反駁するのは私にとっては容易いことであるが、読者の中でその内容を見たくないと思われる人は、以下の引用文を読まずに避けるがよい(※引用文は読みたくない人のために赤色にしておいた)。
「弱者と出来損ないは亡びるべし。―これはわれわれの人間愛の第一命題。彼らの滅亡に手を貸すことは、さらにわれわれの義務である。およそ悪徳よりも有害なものは何か?―すべての出来損ない的人間と弱者に対する同情的行為―キリスト教……」(『偶像の黄昏/アンチクリスト』アンチクリスト 二 p162:白水社)
「「我まことに汝らに告げん、此に立つものの中に、神の国の、権威をもて来るを見るまでは、死ざる者あり。」(マルコ9/1)―うまく嘘をつきましたね、獅子<シェイクスピア『夏の夜の夢』第5第1場の句「うまく吠えましたね、獅子」をもじる。獅子はマルコの象徴。>」(同 四五 p227:白水社)
「「汝らは神の殿にして、神の御霊なんじらの中に在すことを、知らざる乎。もし人、神の殿を毀たば、神かれを毀たん。そは、神の殿は聖きものなればなり。この殿は即ち汝らなり。」(パウロ、コリント前書3:16)―こういったたぐいは、いくら軽蔑しても軽蔑しすぎることはない。……」(同 四五 p228:白水社)
「―以上において私は結論に達したので、私の判決を下すことにしよう。私はキリスト教に有罪の判決を下す。私はキリスト教会に対して、かつて告訴人なるものが口にした限りの告訴のうちで、最も恐ろしい告訴を行おうとする者である。キリスト教教会とは、私には考えられるいっさいの腐敗のうち最たるものに思われる。キリスト教教会は、最後の、およそ可能な限りの腐敗への意志を持っていた。キリスト教教会は、いかなるものをも己れの堕落と無関係に済ませることはなかった。それはあらゆる価値を無価値とし、あらゆる真理を嘘と化し、あらゆる誠実を魂の卑劣と変えて来た。」(同 六二 p267:白水社)
「キリスト教に反発する律法
救済の日に、第一年の最初の日に(―偽りの時の計算法に依れば1888年9月30日に)公布される。
悪徳に対し決戦を挑む。悪徳とはキリスト教のことなり。
第一命題―あらゆる種類の反自然は悪徳なり。最も悪徳を具えし種類の人間は僧侶なり。僧侶は反自然を教えるがゆえなり。僧侶には反抗する謂われはなく、刑務所あるのみなり。
第二命題―いかなる礼拝に参列するも、公の道義に対する暗殺行為なり。カトリック教徒に対するよりも、プロテスタント教徒に対して、いっそう酷薄苛烈に当るべし。信仰堅固なるプロテスタント教徒に対してよりも自由寛大(リベラール)なるプロテスタントに対して、いっそう酷薄苛烈に当るべし。(※引用者註:彼がキリスト教の中で最もリベラルを敵視しているのは、ユダヤ教徒の手駒らしいと言えよう。何故ならリベラルの徒は、ユダヤ教徒の聖典である旧約聖書を単なる歴史的な文書としか見做さず、その神聖性を認めていないからである。)キリスト教徒たることにおける犯罪性は、世人が学問に近づくその度合いに応じ、ますます増大せん。故に、犯罪者中の犯罪者は哲学者なり。
第三命題―キリスト教が怪蛇バジリスクのの卵を孵化せし呪ふべき地は、完膚なきまでに破壊さるべし。其処は極悪非道の場所として、後世のあらゆる人々の恐怖となるべし。その地にて毒蛇の飼育に当るべし。
第四命題―純潔童貞への説教は、反自然への公然たる扇動なり。性生活のいかなる侮蔑も、また「不潔」といふ概念による性生活のいかなる不潔化も生の聖なる精神に反抗する本来の罪なり。(※引用者註:このようにニーチェが言ったのはニーチェ自身が性的に異常だったからという可能性がある。それは彼のゲイ的な顔を見ても分かるし―ゲイであったフレディ・マーキュリーとそっくりである―、彼がSMプレイを嗜んでいたという情報もある。つまり彼自身がしている異常な性的行為また性的嗜好に叱責が与えられることを嫌悪したのではないかということが、この文章の背景として考えられるのである。)
第五命題―僧侶と食卓を共にする者は、追放の憂き目に会はん。これにより、実直誠実なる社会から村八分にされることも起こらん。僧侶はわれらがチャンダーラなり。―僧侶の法律的保護を停止し、僧侶の糧道を断ち、僧侶を何方なりと荒野へ追い払ふべし。
第六命題―謂わゆる「聖なる」歴史は、それにふさわしき名称をもって、呪われし歴史として、呼ばれるべし。「神」「救世主」「救ひ主」「聖者」なる語は、罵讒謗の言葉に、犯罪者用の記章マークに、利用さるべし。
第七命題―残余の事はそこから必ずや生ぜん。」(同 四五 p269~270:白水社)
[本文に戻る]
◎この作品で展開されている解釈は、それが正しい解釈であるにもかかわらず、地動説が長い間隠され続けてきたのと同じように、今まで教会に対して長い間隠され続けてきた解釈であるから、多くの箇所において読者はなかなか理解できないかもしれない。しかし、理解できない箇所があっても慌てたり、早計に判断したりしてはならず、冷静になり、知恵と理解の霊が与えられるよう神に祈り求めるべきである。もし知識も理解も足りていないのに速断するのであれば、いとも簡単に誤謬へと陥ることになるであろう。途中で分からない箇所があれば、その時は分からないままで我慢し、そこにいつまでも留まらずに次の箇所へと読み進めていくという選択をすることも重要である。何故なら、そのようにして次に次にと読み進めていけば、後の箇所で得た理解や知識が手がかりとなり、今までは分からなかった箇所が紐解けるようにもなるからである。カルヴァンが『キリスト教綱要』の中で「書物の内容が理解できない人があっても、気落ちしてはならない。その人は、一つの文章が前にあった文章に一層良き解明を与えることを期待して、先へと読み進むべきである。」(『キリスト教綱要 改訳版 第1篇・第2篇』本書の梗概 p13:新教出版社)と勧めたのは、本作品でも同じことが言える。また読者が本作品を読むにあたり絶対に心がけておかねばならないことは、聖書にこそ固着せねばならず、人間理性や常識や歴史的な通念といったものに縛られてはいけないということである。
◎聖書の真理を正しく悟るためには、何よりも信仰が必要であるということを、ここで言っておかねばならない。重要なのは、神の御言葉を、子どものように素直で純粋な信仰を持って信じるということである。それは何故か。それは、そのようにしないと、真理を知解することができないからである。聖徒の中には、この再臨の真理に関して、まず知解してから信じようとする人が、あまりにも多くいる。このような人たちは、知解するまでは、決して信じようとはしない。つまり、「分かったら信じるよ。」という精神がそこにはある。まず第一に知解、その次に第二段階として信仰。このような精神を多くの聖徒が持っている。しかし、このような精神を持っていると、いつまでも真理を知解することはできない。実際、このような精神を持っている人は、ずっと知解することを求めているのだが、信仰を持とうとしないため、いつまで経っても知解できず、延々と理解の暗闇に留まり続けている。アウグスティヌスは、イザヤ7:9における70人訳聖書の翻訳に基づいて、たびたび「知れるようになるために信ぜよ。」と教えたものである。アンセルムスも「知解せんがために我信ず。」と言った。彼らがこのように言ったのは正しい。この2人が言っているように、もし本当に真理を知解したければ、まず第一に信じることが必要である。事柄は超越的な内容を持っているのだから、まずそれを信じなければ、決して正しい知解に至ることはない。超越的な事柄は、人間理性の機能だけでは把握できない性質を持っているから、まず信仰によってそれを捉えない限り、絶対に知解することができない。すなわち、信仰により、初めてその事柄を把捉できるようになる。まず第一に知解を求める人たちは、信仰を抜きにした人間理性の力だけで超越的な事柄を掴もうとしていることになるが、そのような方法で知解を求めても理解の光は決して与えられないであろう。私は読者に言っておこう。御言葉が確実な意味を持つことを言っていたのであれば、それを今の段階では理解できなくても、まずその言われている通りのことを信ぜよ。そうすれば、今はまだ意味が分からなかったとしても、その信仰に対する報いとして正しい知解が与えられるようになる。つまり、『義人は信仰によって生きる。』(ローマ1章17節)という言葉は、聖書解釈においても同じことが言えるのである。信仰の人でありたいと思う人は、受胎告知を受けた際に理解できなかったものの問答無用で言われたことを信じたあのマリヤのようにならなければいけない。そうすれば、キリストを生むことで御使いの言葉が実現されたことを知ったマリヤのように、後ほど正しい理解が与えられることになるであろう。
◎この作品は、2020年5月20日現在、Operaのブラウザーで表示の確認をしている。多くの場合特に問題はないと思うが、これ以外の動作環境でこの作品を見た場合、表示がしっかりされない、また非常に見にくいなどといった不具合が生じることもあるかもしれない。以前はMicrosoft Edgeとインターネット・エクスプローラーで表示の確認をしていたが、何も問題はなかった。
◎この作品に書かれている内容は、悪意に基づいていたり犯罪などのためにというのでなければ、事前の連絡なしに、ご自由に引用していただいて構わない。しかし、この作品は多くの改訂が行なわれる作品である。だから、たとい引用したとしても、引用してから後ほど、その引用した内容が本作品の中から削り取られてしまっているという場合もあるかもしれない。私は真理のために今持っている自説を、それが間違いであると気付けば、すぐにも捨てるつもりでいるから、そのようになる可能性がないわけではない。引用される方は、あらかじめ、この点について留意してほしいと思う。
◎この作品が載せられているページへのリンクは、事前の連絡なしに、自由にしていただいて構わない。このページのURLは以下の通りである。
http://sbkcc.net/sairin.html
第1部 既に起きた再臨
第1章 再臨に対する一般的・歴史的な見解
プロテスタント、カトリック、東方正教会を問わず、キリスト教が西暦21世紀の現在に至るまで抱いてきた再臨に対する見解は、次の通りである。「これから我々の住む世界にキリストが雲に乗って再臨される。」このような見解を教会が今まで抱いてきたのは、聖書の中に、このような見解を抱かせる聖句が無数に満ちているからに他ならない。例えば、パウロはピリピ4:20の箇所で、こう書いている。『けれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを、私たちは待ち望んでいます。』このパウロは、コリント人に対しても、こう書いている。『その結果、あなたがたはどんな賜物にも欠けるところがなく、また、熱心に私たちの主イエス・キリストの現われを待っています。』(Ⅰコリント1章7節)また、全世界にある多くの教会が聖書的な信条として採用・承認する「使徒信条」の中でも、こう書かれている。「主は…天に昇り、全能の父なる神の右に坐したえり、かしこより来りて生ける者と死ねる者とを審きたまわん。」(※①)また、エイレナイオス、ユスティノス、テルトゥリアヌス、アレクサンドリアのクレメンス、ローマのヒッポリュトス、オリゲネス、バシレイオス、ナジアンゾスのグレゴリウス、ニュッサのグレゴリウス、アタナシオス、キプリアヌス、ポワティエのヒラリウス、アンブロシウス、アウグスティヌス、ヒエロニムス、アレクサンドリアのキュリロス、クレルヴォ―のベルナルドゥス、エックハルト(※②)、ペトルス・ロンバルドゥス、トマス・アクィナス、ルター、メランヒトン、カルヴァン、ブリンガー、ジョン・ノックス、ギイ・ド・ブレイ、ジェームズ・アッシャー、ジョン・ウェスレー、ジョナサン・エドワーズ、スポルジョン、アブラハム・カイパー、J・G・メイチェン、コーネリウス・ヴァン・ティル、バルト(※③)をはじめとした高名な教師たちも、例外なく再臨がこれから起きるのだと信じてきた(※④)。「修道生活の父」と呼ばれるアントニオスも、古代教会最大のラテン詩人であるプルデンティウスも同様であった。著名な天文学者であるルター派のケプラーやイエズス会の創設者イグナチウス・デ・ロヨヤや自然魔術師として有名なデッラ・ポルタや奇人エリファス・レヴィや数学者のパスカルや日本の著名なキリスト者である内村鑑三も同様である。更に言えば、忌まわしい邪悪な異端の徒でさえ、正統派信仰の聖徒たちと全く同様に、再臨はこれから起こる出来事であると信じていた(※⑤)。ビザンティン思想の著述家たちも、例外なく皆そうである。パット・ロバートソンやハル・リンゼイをはじめとした米国の著名なテレビ伝道師たちも、例外ではない。要するに、現在に至るまで、右も左も上も下もキリスト教は「キリストの再臨はいまだに起きていない。」と理解してきた。もし、この一般的・歴史的な理解を持たない教会や聖徒がいたとすれば、そのような教会や聖徒は「異端」とみなされるか、そうでなければ「異常」と思われることであろう。再臨に関し、健全な理解を持っているとみなされることは、まずない(※⑥)。また、このような再臨に対する理解を教会が抱いていることは、教会に属さない未信者でさえも知っていることである。
(※①)
無学な聖徒たちのために、他の有名な信条においても再臨がまだ起きていないとされていることを、参考情報として以下に記したい。
■ニカイア信条:「また主は…天に昇り、生きている者と死んでいる者とを審くために来り給うのである。」
■アタナシオス信条(39―40):「(主は)天に昇り、全能の御父の右に坐し給う。そこより、生きている者と死んでいる者とを審くために来り給うのである。」
■ウェストミンスター信仰告白(第8章/仲保者なるキリストについて:4):「第三日に、彼は、受難のままの身体をもって死からよみがえり、そのままの身体をもって天に昇り、かしこに在って彼の父の右に座し、執成をなし、世の終わりに、人と天使とを審くために再び来りたもう。」
■ベルギー信条(第37条/最後の審判、身体の復活、および永生について):「われらの主イエス・キリストは大いなる栄光と尊厳をもって天に昇り給いしごとく、肉体をもって目に見えて天から来り(使徒行伝1:11)、…」
■聖公会大綱<39か条>(第4条/キリストの蘇えりについて):「キリストは死から蘇えり、肉と骨及び完全な人生に属するすべてのものを持つ身体を再び取って天に昇られた。そして、終わりの日にすべての人々を審くため、再び来られるまで、かの所に座していられるのである。」
■アウクスブルク信仰告白(第17条/審判のためにキリストが再び来り給うことについて):「また、われらの諸教会は、かく教える。終末の日に、われらの主イエス・キリストは、審判するために現われ、…」
引用元―「新教セミナーブック4/信条集 前後篇(新教出版社)」
[本文に戻る]
(※②)
ここでエックハルトの名前が出ているからといって、筆者である私が彼の神秘主義に共鳴しているなどとは思わないでいただきたいと思う。私は、どれだけ多くの高名な教師たちが、再臨がまだ起きていないと信じてきたかを示そうとして、このようにエックハルトの名前を書いただけに過ぎないのである。
[本文に戻る]
(※③)
ここでバルトの名前が出ているからといって、筆者である私がバルト主義者だとは思わないでいただきたいと思う。私は、どれだけ多くの高名な教師たちが、再臨がまだ起きていないと信じてきたかを示そうとして、このようにバルトの名前を書いただけに過ぎないのである。
[本文に戻る]
(※④)
<Ⅰ>
アウグスティヌスは次のように書いている。「主は聖霊と処女マリヤとから生れ、十字架につけられ、葬られ、復活し、天に昇られた。これらはすでに起こったことである。終りの世に死者の復活があった後、生ける者と死せる者とを裁くために再臨される。これはなお将来のこととして預言されるのである。」(『アウグスティヌス著作集17 創世記注解(2)』未完の創世記逐語注解/第1章4節 p160:教文館)ルターは、まだ教皇制の中にいた時の自分を思い出して、こう言っている。「キリストが、生きている者と死んだ者、義しい者と神なき者を裁くために、来るであろうことは、よく知っていた。」(『ルター著作集 第二集7 ヨハネ福音書第3章・第4章説教』第49説教 第3章(35以下)p355:LITHON)この再臨理解は、ルターが一生涯持ち続けたものであった。バルトも次のように言うことで、まだキリストの再臨が起きていないと信じていたことを我々に知らせている。「このように私たちは、われらの主イエス・キリストの御名において、感謝し祈ります。そのお方によって、あなたは、私たちがこの地上に立ち、天が開かれるのを見、やがてそのお方が、すべてを新たにするために、偉大なる栄光の中に来たりたもうのを、喜び待つようにして下さいました。アーメン。」(『カール・バルト説教選集12 1959―1968』あなたを憐れまれる主 1959年12月27日、バーゼル刑務所にて p35:日本基督教団出版局)「主よ、私共の愛する神よ。あなたは私共に、待ちまた急ぐように命ぜられます。世界の中で、また私共人間の中で、またあなたの教会の中で、また私共の心の中で、また私共の生活の中でも、あなたが完全に現われ、あなたの救いが示される、あの大いなる日に目を注ぎつつ、待ちまた急ぐように命ぜられます。」(同 二重の待降節の使信 1962年12月23日、バーゼル刑務所にて p117)アタナシオスも、読者に対して次のように書いている。「また、この方の第二の、栄光に包まれた、真に神的なわれわれの許への顕現をもあなたは学ばれよう。その時、もはや卑しい<姿>でではなく、本来の崇高さの内に来られる。その時、もはや苦しみを受けられるためではなく、ご自分の十字架の実り―私の言わんとするのは復活と不滅のことである―をすべてのものに賦与されるために来られるのである。」(『中世原典思想集成2 盛期ギリシア教父』言の受肉 56(3) p136:平凡社)バシレイオスも「かの恐ろしく突然私たちを見舞う主の日のことを目の前に置こうとしないのか。」(『中世原典思想集成2 盛期ギリシア教父』修道士大規定 序文 p183:平凡社)と言っているから、主の日という再臨の起こる日がまだ訪れていないと考えていたことが分かる。ナジアンゾスのグレゴリウスも、やはり再臨がこれから起こるに違いないと信じていた。彼はキリストについて「生者と死者を裁くために、…再びやって来られるのである。」(『中世原典思想集成2 盛期ギリシア教父』神学講話 第3講話 20 p358:平凡社)と言っている。ユスティノスも、再臨はこれから起こるのだと信じていた。彼はこう言っている。「キリストへの信仰によって敬虔で義なる者となったわれわれは、彼の再臨を心待ちにしている」(『中世原典思想集成1 初期ギリシア教父』ユダヤ人トリュフォンとの対話 52(4) p59:平凡社)「またキリストはわれわれのために人となり、苦難と侮辱に耐え、再び栄光のうちに来臨するはずなのです。」(『キリスト教教父著作集1 ユスティノス』『第一弁明』50:1 p65:教文館)オリゲネスも、キリストが「卑しい到来の後の栄光に包まれた第二の到来をわれわれに示すとき、…」(『中世原典思想集成1 初期ギリシア教父』出エジプト記講話 第6講話(1) p567:平凡社)と言っているから、まだ「第二の到来」すなわち再臨は起きていないと信じていたことが分かる。ローマのヒッポリュトスも、「(キリストは)父の右の座に着き、生ける者と死せる者とを裁くために来るのである。」(『中世原典思想集成1 初期ギリシア教父』ノエトス駁論 18(9) p493:平凡社)と言っており、再臨をこれから起こる出来事として信じていた。キプリアヌスも自分たちが「主の到来が速やかに実現するように待ち望んでいる」(『中世思想原典集成4 初期ラテン教父』主の祈りについて 第13章 p156:平凡社)と他の教師たちと同じことを言っている。彼はまた兄弟たちが「キリストの再臨を祈り願う」(同 第35章 p175)べきだとも言っている。ノラのパウリヌスも次のように言っている。「われわれはさらに、天から戻るキリストに望みを寄せるようにと、命じられています。まるでこのキリストが父の許に赴くのを、われわれがこの目で見たかのように。」(『中世思想原典集成4 初期ラテン教父』歌謡31 第3部 399―400 p864:平凡社)カルヴァンも他の教師たちと同様に、再臨を願望し大いに期待していた。彼は次のように言っている。「それ故、我々は精神を一層健全にして、肉の盲目的かつ愚鈍な欲望に対抗し、主の来臨を、単に願望するのみでなく呻きと嘆息をもって全ての内で最も祝福されたこととして期待するのをためらってはならない。我々をこの禍いと悲惨の底なしの深淵から救い出して、彼の命と栄光の祝福された嗣業に入れたもう贖い主が来られるからである。」(『キリスト教綱要 改訳版 第3篇』第3篇 第9章 第5節 p203:新教出版社)「したがって、我々は「この世で慎ましく、公正に、敬虔に生きて、幸いなる望みを望み、大いなる神にして我が救い主なるイエス・キリストの栄光の来臨を待ち望む」状態にある(テトス2:12―13)。」(同 第25章 第1節 p504)アレクサンドリアのキュリロスも、やはり同様であった。彼は、キリストが「聖書に記されているように、義をもって全地を裁くために、定められた時に、御父の栄光のうちに、ひとりの子、主として来られるでしょう。」(『中世思想原典集成3 後期ギリシア教父・ビザンティン思想』書簡集 第17書簡 p114:平凡社)と言っている。ヴァン・ティルも、次の言葉が示すように、まだ再臨が起きていないと考えていた。「しかし、時が経ち、神が原理と原理とが対立することを許されるこの世界の終わりに向かうにつれて、外形的には正しいと見えていた者が次第に正しくない者であることが明らかとなる。そのとき、自分を神の律法の上に高める「不法の人」「不義の人」が現れ、正しくない者たちが不法の人を礼拝し、正しい者たちにその礼拝を強制するであろう。しかし、そのときにはまた、正しいお方として屠られたがゆえに第七の封印を開くに値するお方が、義のための勝利を達成するために、正しくない者また正しくない者たちを、律法も秩序もないがゆえに底なしである穴に投げ込み、神の律法に従う人々を、律法と秩序があるがゆえに、安息の領域に受け入れるために、出現なさるであろう。」(『ヴァン・ティルの十戒』第十戒 p204:いのちのことば社)ビザンティン思想の著述家であるダマスコのヨアンネスも、キリストは「また再び来られることになるであろう」(『中世思想原典集成3 後期ギリシア教父・ビザンティン思想』知識の泉 第3部 第2章 p602:平凡社)と言っている。堕落していた暗黒期におけるキリスト教の教師も、再臨がまだ起きていないと考えている点では、その他の時代に生きた教師たちと何も変わらなかったのである。
<Ⅱ>
私がこのように引用文を多く書き記すのは、読者に知識と情報をもたらすというだけでなく、私が公平に論じているということを示すためでもある。キケロとJ・S・ミルは、反駁したい場合、相手の生の声また実際の文章を知るべきだと言った。キケロについて言えば、彼は法廷弁論を依頼された際、相手側の情報をまず徹底的に調べて熟知するまでは、実際の弁論に臨もうとはしなかった。これは正にその通りであって、反駁したい見解を実際に体感するからこそ、公平な論述が可能となるのである。つまり、私は自分が反駁する見解を、よく知り、観察し、考慮しているということである。この2人の知者も言っていることだが、世の中には自分が反駁したい者が発している生の見解を故意に無視する者が多いのである。例えば、マルクスを反駁しているのに「資本論」と「共産党宣言」は全く読んだことがない、という人がそうである(こういう人はかなり多いと思われる)。要するに、この2人はマルクスの場合で言えば、もしマルクスを反駁したいのならばまずは「資本論」「共産党宣言」を読めと言ったわけである。そうしてこそ真に公平な論述となるからである。単に風評や一般的な見識だけに基づいて論じ、実地に当たらないというのではお話にならないのだ。私は相手側からのジャブを受けた上でカウンターを放ちたい。
[本文に戻る]
(※⑤)
例えばアリウスがそうである。彼は大帝コンスタンティヌスに対する手紙の中で、次のように書いている。「私どもは信じます。…天に昇られ、生ける者と死せる者とを裁くために再び来られる方を。」(『中世原典思想集成2 盛期ギリシア教父』コンスタンティヌス帝への手紙 2 p36:平凡社)ペラギウスも、デメトリアスという若い処女が霊肉ともに聖いままで「主の来臨を待ち望む」(『中世思想原典集成4 初期ラテン教父』デメトリアスへの手紙 第10章 p945:平凡社)べきだと勧めている。このように、悪臭を放つ腐った異端者どもも、その多くが、再臨についての考えは正統派の教師たちと何も変わらないのである。
[本文に戻る]
(※⑥)
パウル・ティリッヒのように再臨をはじめとした終末の事柄を「神話」として片づける者も存在するが、このような者は一般的にはほとんど見られない。
[本文に戻る]
このような誰でも知っている当たり前のことが、今、どうして書かれたのか。読者の方は、「このようなことは言うまでもないことだ。」と思われたかもしれない。今、このようなことが書かれたのは、本作品が、この当たり前の見解を聖書から根本的に考察するものだからである。筆者である私は、これから「再臨」という名の霊的素材を、「聖書」という料理道具を使って、神に祈りつつ、読者の前で調理する。それゆえ、私は、今、これから調理される素材をあらかじめ読者の前に眺めさせようとして提示したわけである。つまり、この最初の章で書かれたことは「前置き」であると思ってもらえればそれでよい。
さて、それでは前置きが終わったので、これから「再臨」という教会にとってあまりにも重要な事象を、徹底的に聖書から考察していくことにしたい。全能の神が、本作品を通して、我々に霊的な恵みを豊かに注いで下さるように。アーメン。『どうか、あなたがたがあらゆる霊的な知恵と理解力によって、神のみこころに関する真の知識に満たされますように。』(コロサイ1章9節)
第2章 既に起きた再臨
前章で述べられたように、今に至るまでキリスト教では再臨がいまだに起きていないと理解されてきたが、確かなところ、聖書は既に再臨が起きたのだと我々に教えている。こう言われると多くの聖徒たちが驚き、疑いの念を抱くであろうが、私が今述べたこのことが、本当なのかどうか聖書から見てみよう。ここでは4つの聖句を読者に提示することにしたい。まず我々の主は、今から2千年前に、ご自身の前に立っていた紀元1世紀のユダヤ人に対して次のように言われた。『まことに、あなたがたに告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が御国とともに来るのを見るまでは、決して死を味わわない人々がいます。』(マタイ16章28節)まず我々がこの主の言葉に異を唱えるようなことは、絶対にあってはならない。というのもカルヴァンも言うように、「わたしたちは、かれがたったひと言でも言ったことはすべて、少しも疑うことなく胸に抱きしめなければならない」(『新約聖書註解Ⅳ ヨハネ福音書 下』14:11 p469:新教出版社)からである。もし主の言葉を疑うような人であれば、この作品を読むべきではない。この作品は主の言葉を己の規範とする者に対して書かれているのだから。さて、この聖句の中で、主は紛れもなく明白に、当時のユダヤ人が生存している間に再臨があると言っておられる。この聖句は、そのように解釈する以外にはなく、何とかして他の解釈を試みようと思っても合理的な解釈をすることができない(※①)。私と論じ合ったバプテスト派の牧師も、これは紀元1世紀のユダヤ人のみを対象としている聖句であると、しぶしぶながら認めざるを得なかった。主がこのように言われたのは、紀元30年頃であると思われる。その時、主の目の前に立っていたある者が仮に10歳だとしよう。その者が120歳まで生きる可能性は、普通に考えれば、ほとんどないと考えられる。とすると、主の御言葉によれば、その当時10歳であった者が120歳になるまでには確実に再臨があることになる。そうであれば、主の再臨は、主がこのように言われてからもっとも長く見積もっても110年の間に起こることになる。このように聖書から考えると、再臨は既に起きていたことが分かるであろう。また主は、当時生きていた大祭司カヤパおよびカヤパと共にいた律法学者また長老たちに対して、このように言われた。『なお、あなたがたに言っておきますが、今からのち、人の子が、力ある方の右の座に着き、天の雲に乗ってくるのを、あなたがたは見ることになります。』(マタイ26章64節)ここでも主は紀元1世紀の人たちが生存している間に再臨があると断言しておられる。もし主の言われた通りにならなかったのであれば、カヤパや他の指導者たちは、主を大いに愚弄しペテン師扱いしていたに違いない。ところでエリサベツは聖霊に満たされてこう言っている。『主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は、何と幸いなことでしょう。』(ルカ1章45節)信仰深く敬虔な人は、いつの時代であれ、主の語られたことが実現すると確信するものである。当時の信仰深い人も、主の語られたことが必ず実現すると信じたはずである。すなわち、主の言われた通りに再臨が当時の人たちの存命中に起きると信じきったはずである。イザヤ書46:10で神は『わたしのはかりごとは成就し、わたしの望む事をすべて成し遂げる。』と言われた。主はご自身の語られたことを必ず行なわれる方であるから、主が当時の時代に再臨という「はかりごと」を成就され、その再臨という「望む事」を成し遂げられたのは確実である。そうであれば、やはり再臨は既に起きたということになる。アウグスティヌスも、「神の約束は決して欺くことはありません。」(『アウグスティヌス著作集26 パウロの手紙・ヨハネの手紙説教』説教157 第1章1 p156:教文館)と言っている。神がなされた再臨の約束も、その他の約束と同様に欺くことがないから、やはり、その約束の通り、紀元1世紀当時の人たちが生きている間に再臨が起きたと我々は考えなければいけない。また、御霊はヨハネを通して黙示録1:7で、このように言われた。『見よ、彼が、雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが、彼を見る。』ここで言われている『彼を突き刺した者たち』とは、言うまでもなく、ゴルゴダの丘でキリストに槍を突き刺した兵士のことである(※②)。この兵士が生きていたのは紀元1世紀である。御霊はこの兵士たちがキリストの再臨を見ると言われたのだから、誰でも少し考えれば分かるように、再臨は既にあったことになる。もし御霊の言われたことを否定したくないのであれば、このことを信じなければいけない。またパウロは再臨に関して次のように紀元1世紀のテサロニケ人へ書き送っている。『私たちは主のみことばのとおりに言いますが、主が再び来られるときまで生き残っている私たちが…』(Ⅰテサロニケ4章15節)パウロは、紀元1世紀の聖徒たちが再臨のある時まで生きていると、ここで述べている。これは、主が当時の人たちの存命中に再臨が起こると述べられたのと同じである。この箇所におけるパウロの言葉については、カルヴァンも「彼は最後の日まで生きるであろうひとびとのなかに、自分自身をおいている。」(『新約聖書註解ⅩⅠ ピリピ・コロサイ・テサロニケ書』Ⅰテサロニケ4:15 p216:新教出版社)と言っている。つまり、カルヴァンさえも、パウロは自分の存命中に最後の日、すなわち再臨の起こる日が到来すると言っていたと考えていたことになる。これは当然である。何故なら、この箇所はそのようにしか理解できないからである。繰り返すが、確かにパウロは自分とその仲間たちが生きている間に再臨が起こると言ったのである。そうであれば、再臨が既に起きたという説は、キリストの御言葉だけからではなく、パウロの語ったことからも支持されることになる。どうであろうか。私は、今、4つの聖句に基づいて再臨のことを詳しく考察した。読者がどのように思われたのか私は知らないが、確かに聖書は再臨が既に起きたと教えているのである。
(※①)
<Ⅰ>
アウグスティヌスは、説教の中で、この聖句はすぐ後に続く17章1~8節目までのことを言ったものだという解釈をしているが、これは誠に特異な解釈であって、検討する価値さえない間違った解釈である。今の時代にこのような解釈をとる教師や一般信徒は、恐らく一人もいないのではないかと思われる。彼はマタイ17:1~8の説教における冒頭部分で、こう言っている。「愛する兄弟姉妹の皆さん、わたしたちは、主が山上で示された光景に深く目を注ぎ、それをとりあげ、論じなければなりません。主ご自身がそれについてこう言われております。「よくよくあなたがたに言っておく。ここに一緒にいる人々の中には、人の子がその国と共に来るのを見るまでは、決して死なない者がいる」(16・28)と。ただいま朗読されましたこの箇所―つまり「このように言われたとき、すなわち、6日の後、イエスは、ペトロと、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて、高い山に登られた」という箇所はこのところ<16・28>から始まっているのであります。<ですから>「人の子がその国と共に来るのを見るまでは、決して死なない者がいる」と言われている「死なない者」とはまさにこの3人のことなのであります。ここにあるのは小さな問題ではありません。なぜなら、この山はその国の全体とは理解されにくいからです。天国を持っている方にとって山とは何でしょうか。…」(『アウグスティヌス著作集21 共観福音書説教(1)』説教78 1節 p344:教文館)東方教父のグレゴリオス・パラマス(1196頃―1359)もアウグスティヌスと同様、このマタイ16:28の聖句は数日以内に起こる出来事が記されているという頓珍漢な理解をしていた。私はこのような解釈が持てることに驚きを隠せない。この博士はこう言っている。「ではまず始めに、少しのあいだ今日読まれる福音書の言葉に耳を傾け、その神秘を解明し、真理を明らかにしよう。「6日の後、イエスは、ペトロ、それにヤコブとその兄弟だけを連れて、高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝いた」。まず福音書の語っていることをよく注意してみなければならない。キリストの弟子や福音書記者マタイが、どの日から数えて主の変容の日が6日目だとしているのであろうか。いつから。それは主が弟子たちに次のように言って数えている日の後である。すなわち、「人の子は父の栄光に輝いて来る」、またそれに付け加えて、「ここにいっしょにいる人々のなかには、人の子がその王国と共に来るのを見るまではけっして死なない者がいる」。つまり彼の変容の光を父の栄光とその王国と呼んでいるわけである。…」(『中世思想原典集成3 後期ギリシア教父・ビザンティン思想』講話集 講和第34 p879~880:平凡社)
<Ⅱ>
確かに、上で示されたアウグスティヌスとパラマスの見解は、取り扱うまでもない無価値な見解である。彼らの見解は「こじつけ」であって、それゆえ「異常」であると言ってよい。いったい誰が彼らのような見解を持つのであろうか。実際、このマタイ16:28の聖句を、彼らのように解する人は、今となってはいない。しかしながら、私はここで、彼らの見解を文章により退け、打ち砕いておくことにしたい。というのも、この作品は、再臨を徹底的に考究することが最大の目的の一つとされているからだ。また読者の中には、この問題を取り扱わなければ不満に思う人がいるかもしれない。「どうしてこの問題については詳しく取り扱わないのか」と。そういう人のためにも、この取るに足りない見解を取り扱っておくのが良いと考えた。さて、それでは、この2人の誤った見解について具体的に見ていきたい。既に述べたように、彼らが、キリストがマタイ16:28で言われたのは6日後の出来事についてであると考えたのは完全な誤りであった。彼らが、キリストの言われたのはその時にキリストを見ていた人についてである、と考えていた点は間違いではなかった。何故なら、キリストは目の前にいた人たちに限って、すなわち『ここに立っている人々』(16:28)に限って、このことを言われたからである。しかし、その出来事が6日後の出来事であると考えたのは異常なことであった。何故そう言えるのか。この2人の見解は具体的にどういうわけなので、誤りだと言えるのか。その理由は4つある。まず、6日後の出来事では、16:27で言われているようにキリストが『御使いたちとともに』来てはいない。山上の変貌において書かれている17:1~8の箇所で、御使いがキリストと共に来たとは、どこにも言われていない。共に来たと言えるのは、エリヤとモーセだけである(17:3)。キリストが言われたのは、御自身が御使いと共に来る、ということであった。6日後の出来事では御使いが共に来てはいなかったのだから、キリストが言われたのは6日後の出来事ではなかったことになる。また、6日後の出来事では、裁きがなされていない。キリストは御自身が来られる際には、人々に『報いをします。』(16:27)と言われた。しかし、山上の出来事において、裁きらしい出来事はまったく見られない。そこにおいて『報い』が行われていない以上、キリストが言われたのは6日後の出来事では無かったことになる。また、6日後の出来事では、キリストの国が『力をもって』(マルコ9:1)到来したとは見做しがたい。聖書が教えるように、キリストが御国と共に再臨される際には『雷と地震と大きな音…、つむじ風と暴風と焼き尽くす火の炎』(イザヤ29章6節)という力ある現象が伴うはずである。しかし、6日後の出来事では、そのように大いなる力は感じられない。この山上の変貌がイザヤ29:6で言われているような『力をもって』実現されたと見做せない以上、キリストが言われたのは6日後の出来事では無かったことになる。また、キリストの言われたのが6日後の出来事についてだったとすれば、キリストの言葉に違和感が生じてしまう。たった6日後に起こるにもかかわらず、「その出来事が起こるまではここに死なない者がいるであろう。」などとは通常の場合、言われない。何故なら、自然な感覚からすれば、目の前にいる人が6日後にも生き残っているだろうということは、当たり前のように前提できるからである。戦争や自然災害や伝染病が起きていれば話は別だが、この時は、そのようなことが起きている状況では無かった。それゆえ、キリストが言われたのは6日後の出来事では無かったことになる。もし6日後の出来事について言われていたとすれば、キリストはわざわざ「ここにいる者たちの中に死なない者がいる。」などと言われなかったはずだ。なお、アウグスティヌスも、この山上の変貌においては御国が感じられにくい、と隠すこともなく告白している。彼がこの出来事のうちに御国を感じられなかったのは当然である。キリストが言われたた御国の到来とは、山上の変貌のことではないのだから。以上の4点から、アウグスティヌスとパラマスの見解は完全に非とされ、断罪されるべきである。この2人がマタイ16:28の前後における箇所を考慮したのは、すなわち文脈を検討したのは、それ自体として非難されるべきではない。何故なら、前後の話を考慮するのは、聖書解釈にとって非常に重要だからである。しかし、彼らは前後の箇所に心を完全に奪われたので、このマタイ16:28と再臨との関連性を見落としてしまった。つまり、彼らは文脈に意識を100%奪われたので、再臨との関わりにおいて解釈するという意識を持つことが出来なかった。確かなところ、このマタイ16:28の箇所における内容は、17:1~8の内容とは繋がっていない。16:28の内容が繋がっているのは、17:1~8の内容ではなく、むしろ「再臨」である。確かに、キリストがこの箇所で言われたのは、再臨の出来事についてであった。何故なら、それが17:1~8のことを言ったのではないとすれば、必然的にそれは再臨のことを言ったとせざるを得ないからである。実際、マタイ16:28で言われているのが再臨についてであるというのは、少し考えれば分かることである。これが再臨の出来事だとすれば、先に見た4つの問題も起こらない。すなわち、1つ目について言えば、再臨の際には御使いがキリストと共に来る。2つ目について言えば、再臨の際には裁きが実際に下される。3つ目について言えば、再臨は物凄い力を伴って実現される。4つ目について言えば、もしこれが再臨について言われた言葉だとすれば、キリストの言葉には何の違和感もなくなる。それというのも、再臨が起こる際には、キリストの目の前に立っていた人々の中で、既に死んでしまっている人も多くいたはずだからである。そのようなことだったと受け取れば、キリストがここで「再臨の時までここにいる者たちの中には生き残っている者がいるであろう。」と言われたのを聞いても、何も違和感が起こらない。それだから、読者は、この2人の見解になびかないようにしてもらいたい。マタイ16:28で言われたのは、再臨の出来事以外ではないからである。
[本文に戻る]
(※②)
『それで、兵士たちが来て、イエスといっしょに十字架につけられた第一の者と、もうひとりの者とのすねを折った。しかし、イエスのところに来ると、イエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかった。しかし、兵士のうちのひとりがイエスのわき腹を槍で突き刺した。』(ヨハネ19章32~34節)※ここで言われている「わき腹を槍で突き刺した兵士」とは、ニコデモ福音書(ピラト行伝)12:1によればユダヤ人の兵士だったようである(※A)。その兵士の名は「ロンギノス」という名であったという(ニコデモ福音書16:7)。つまりローマ兵ではない。しかしこの文書は外典であって信仰の基準ではないから、あくまでも参考情報としてのみ捉えていただきたいと思う。
(※A)
「ユダヤ人達は、イエスの屍をヨセフが願い受けたと聞いて、ヨセフを探した。また、イエスが不倫の関係の生れではないと主張した12人と、ニコデモと、ピラトの前に出て来てイエスの良い業を明らかにした他の大勢の者を探した。しかし他の者は皆かくれてしまい、ニコデモだけがユダヤ人の前に現れた。ニコデモはユダヤ人の役人だったからである。ニコデモは彼らに言う、「どうしてあなた方はこの会堂に集って来たのですか。」ユダヤ人達は言う、「お前はどうしてこの会堂にはいって来たのか。お前はあの男の証人で、来世ではあの男と運命を共にするはずではなかったのか。」ニコデモは言う、「まことに、まことに。」ヨセフもまた(かくれていたところから)出て来て彼らに言った、「イエスの屍を乞い受けたからといって、どうしてあなた方が私のことを怒る必要があるのですか。私はあの方を清潔な亜麻布にぬくるんで、私の新しい墓に埋葬してさしあげたのですよ。岩穴の入口には石をころがしてふたをしてあります。あなた方はあの義人に対して正しからぬことをなさった。十字架につけたことを後悔なさらなかったばかりか、槍で突きさすようなことまでなさった。」…」(『聖書外典偽典6 新約外典Ⅰ』ニコデモ福音書(ピラト行伝)第章12節1節 p192~193:教文館)
[本文に戻る]
今引用された聖句を考えるならば、西暦21世紀の時代になっても再臨が起きていないとすることは、絶対にできない。それは聖句を直視しないことであり、神の言われたことを否定することである。私ははっきりと言おう。今に至るまで、教会は、再臨という事象に関して、キリストと使徒たちとを「出鱈目を言う者」に仕立てあげてきた。「いや、そのようなことはない。」と多くの聖徒は言われるかもしれないが、再臨がまだ起きていないと理解するのは、暗にそのように仕立てあげているのも同然なのである。つまり、意識していなかったとしても、事実上そうしてしまっているということである。2千年経過してもまだ起きないような遥か未来の事象を、キリストと使徒たちが自分と同時代に生きている人たちがさも見るかのように断言したと考えるのは、彼らを「出鱈目を言う者」に仕立て上げることでなくて何であろうか。
確かなところ、今に至るまで2千年間も教会が誤ってきたのは、再臨に関する御言葉を、あたかも自分たちを直接的な対象としているかのように捉えてきたということである。例えば、ヤコブは、キリストの再臨について、その手紙の中で次のように述べている。『あなたがたも耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。』(5章8節)今まで教会は、ここでヤコブが述べている『あなたがた』という対象を、ヤコブよりも後の時代の人間である自分たちであると当然のように思って何も疑わなかった。だから、あらゆる時代の教会が、キリストの再臨はもう間もなく起こると考え、信じ、語ってきた。確かに、再臨についての御言葉が、あらゆる時代の教会に対して共通的なものとして言われたとすれば、今までの教会がキリストの再臨はもう間もなく起こると考え、信じ、語ってきたのは正しいことであった。何故なら、再臨の御言葉があらゆる時代の教会に言われているというのは、すなわち神が、あらゆる時代の聖徒たちに再臨が間もなく起こると期待するように望んでおられることを意味しているからである。そうだった場合、私もこのような作品を作ることをせず、他の聖徒たちと同じように、再臨がすぐに起こると大きな声で叫んでいたはずである。しかし、大変嘆かわしいことに、今まで教会は、再臨についての御言葉には時期がしっかりと規定されているということを、完全に―そう完全に―見落としてきた。すなわち、今まで教会は、聖書がキリストの栄光の再臨はキリストの目の前に立っていた人たちが生きている間に起こり(マタイ16:28)、パウロと共にいたテサロニケ教会の聖徒たちが生き残っている間に起こり(Ⅰテサロニケ4:15)、神殿崩壊をそのクライマックスとするユダヤ戦争<66-70>の時期に起こる(マタイ24章)と教えていることに、まったく気付いてこなかった。実に、本当に文字通りに誰一人として、この重要な点に心が向かなかったのである。それは、アウグスティヌスやルターのような高名で有能な教師たちといえども例外ではない。それは、ちょうど天動説の誤りに、並はずれた知性を持つ学者たちがコペルニクスの登場まで数千年の間、気付けなかったのと同じことである。どうして今まで神に用いられた教師たちが、このような重要な点に気付けなかったのかということは、後ほど語られることになる(第1部:第10章)。聖書には、時期性を問わない、あらゆる時代に適用また実戦されるべき普遍的な命令や教えが多く存在しているのは確かである。例えば、『盗んではならない。』という戒めは、時期性を問わない普遍的な命令であって、それはあらゆる時代の聖徒たちが行なうべき戒めである。これは、明らかに普遍的な内容を持っているから、時期性を限定して理解することは許されない。すなわち、「この戒めはモーセと共にいたイスラエル人たちに与えられたものだから、それ以降の時代に生きる聖徒たちは行なう必要のないものだ。」などと言うことは絶対に許されない。これは神学の学びをある程度している者であれば、誰でも分かることである。もしこのように言う者がいたとすれば、その者は絶対に悔い改める必要がある。再臨について語られている御言葉の場合、それとはまったく逆である。再臨についての御言葉の場合、時期性が明らかに規定されているから、その時期性を取り除いて普遍的な内容を持っていると理解することはできない。すなわち、「再臨はあらゆる時代の聖徒たちがすぐにも起こるべき出来事として捉えねばならないのだ。」などと考えたり言ったりすることはできない。何故なら、キリストもパウロも、明らかに自分と一緒にいた人たちが存命中に再臨が起こると言って、再臨という出来事にそれが起こる時期を設けたからである。だから、再臨についての御言葉から時期性を除く者たちは(今まで全ての聖徒たちがそのようにしてきた)、時期性をよく考慮しなかったことについて悔い改める必要がある。今まで優秀な教師たちが、再臨について語られている御言葉に見られる時期性を注意してこなかったのは本当に驚きである。このことを聞かされたならば、アウグスティヌスであれその他の教師であれ、大いに気付かされて深く考究していたはずである。実際、私からこのことを聞かされた教師たちは、誰もが例外なく初耳であって、驚いたりキョトンとしたりし、そうしてから考えたり納得したり反論したりするなど多くの反応を見せる。今までの時代にこのことに気付く教師たちがいたとすれば、とっくの昔に、私が今述べているようなことを述べる教師が現われていたことであろう。しかし、新約聖書が書かれてから2千年経つまでは、私のようなことを述べる者は誰も現われなかった。読者は、私が今述べたこのこと、すなわち再臨についての御言葉には実現される時期が大まかにではあるが規定されているということについて、時間をかけてじっくりと考察していただきたい。多くの者を教える立場にある教師たちには、このことを特に要請したい。
しかし、聖句が再臨は既に起きたということを明瞭に示してはいても、それを信じることができずに「確かに再臨が当時において起きると言われているが、再臨は<遅延>しているのだ。だから再臨はいまだに起きてはいないと信じるべきである。」などと言う人もいるであろう。実際、世の中にはこのように言う人が少なからず存在する。彼らが何と言おうとも、このようなつけ足しを聖句に対してすることはできない。神は、そのようなつけ足しを嫌われるお方であると聖書は教えている。申命記12:32で神は御言葉に『つけ加えてはならない。』と言われた。御霊は、黙示録について、こう言われた。『もし、これにつけ加える者があれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。』(黙示録22章18節)自分の心が聖句で言われている事柄を信じられないからといって、聖句を受容可能なものとするために曲げることは、神の御前において合法ではない。そのような傲慢で自己中心的な態度は、神に喜ばれる態度ではない。神は『わたしが目を留める者は、へりくだって心砕かれ、わたしのことばにおののく者だ。』(イザヤ66章2節)と言われたのである。確かにグレゴリウスも言うように、「神は決して自らの熟慮したことを変えない」。キリストの再臨が、当時の時代の聖徒が生きている間に起こると定められたのは、明らかに神の熟慮、しかも完全極まりない熟慮に基づいている。それゆえ、そのような熟慮に基づいた神の再臨に関する決定が「遅延」するなどというのは間違っても考えられないことである。神の言葉を好き勝手に捻じ曲げるのは止めていただきたい。しかしながら、このように言われても、まだ抗弁する姿勢を崩さない人が、世の中には多くいるのではないかと思う。そのような人は、Ⅱペテロ3:7~9を提示して「やはり今の世は終わりの日に起こる再臨の時までずっと保持されているのだ。」などと言う(※)。しかし、この箇所を挙げて反論しても無駄である。というのは、どれだけ主がその忍耐深さにより、再臨の日を選ばれた者のために遅らせたとしても、再臨の日が紀元1世紀に生きている人たちが死ぬ前までに訪れるということは、先に挙げたキリストの聖句から明らかだからである。もし紀元1世紀の人たちが存命中に再臨が起きなかったとすれば、主の言われたことを偽りだったとせねばならなくなる。神は、ご自身の御言葉を偽りにしてまでも再臨の日を数千年も遅延させられるような方ではない。もし、そのようなことがあれば、御言葉の絶対性が揺らぎ、御言葉を聖徒たちの究極的な規範とすることができなくなってしまうであろう。私がこのように言っても、まだ御言葉を素直に信じられない人がいるのではないかと思われる。そのような人は、旧約聖書のある箇所を挙げて、次のように反論するかもしれない。「確かに神はご自身の言われたことを基本的には曲げられないが、ヒゼキヤ王の例を見れば分かるように、例外的に御言葉をそのまま行なわれないこともあるのではないか。ヒゼキヤ王に告げられた預言が取り消されてそのまま実現されることがなかったように、再臨に関する預言も、その言葉通りに実現されることはなかったということではないのか。」確かに、神は死にかけていたヒゼキヤ王に『あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ。直らない。』(イザヤ38章1節)と預言されたのにもかかわらず、この王の涙に動かされて預言を取り消し、そればかりでなくヒゼキヤの寿命を15年も増し加えられた。これは私たちが既に知っている通りのことである。しかし、この例外的なケースを、再臨の預言に当てはめることはできない。何故なら、神がヒゼキヤになされた死の預言とは、そもそも最初からヒゼキヤの寿命を延ばすという目的をもってなされたものだからである。神は、この預言を聞いたヒゼキヤが大声で泣くことを予知しておられ、その号泣のゆえに寿命を増し加えるという計画を行なわれるためにこそ、あえてこのような預言をされた。これはカルヴァンの「キリスト教綱要」で十全に解説されていることだから、私がこれ以上の説明をする必要はあるまい。キリストの再臨を告げた新約聖書の預言は、当然ながらヒゼキヤになされた預言と同じような性質を持ったものではない。後者のほうは最初から無効にされる意図をもってなされ、前者のほうは必ず実現される意図をもってなされた。それゆえ、ヒゼキヤの例を提示して、再臨の遅延を論証することはできない。もし再臨が今に至るまで遅延し続けているというのであれば、再臨に関する無数の聖句につけ足しをせねばならなくなり、聖書全体、特に新約聖書を歪めねばならなくなってしまう。そればかりでなく、神により聖なることを語った聖書記者たちを「偽証者」とせねばならなくなってしまう。果たして、神は、ご自身の御言葉をそのまま素直に受け入れようとしない者を喜ばれるであろうか。
(※)
『しかし、今の天と地は、同じみことばによって、火に焼かれるためにとっておかれ、不敬虔な者どものさばきと滅びとの日まで、保たれているのです。しかし、愛する人たち。あなたがたは、この一事を見落としてはいけません。すなわち、主の御前では、一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主は、ある人たちがおそいと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえって、あなたがたに対して忍耐深くあられるのであって、ひとりでも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。』
[本文に戻る]
再臨が既に起きたというこのことを、私は、ジョナサン・エドワーズについて語ることによっても論証することにしたい。とはいっても、その論証は直接的な論証ではなく、あくまでも間接的な、すなわち遠回し的な論証である。つまり、実際にエドワーズが再臨は既に起きたと考えていたり、述べたりしたということではない。しかし、エドワーズについて私がここで語るならば、その語ることにより、間接的に再臨が既に起きたということが論証される結果となる。そのような間接的な論証ではあるが、私は、そのような間接的な論証によっても、読者が再臨について正しい理解を持てるようにしたい。何となれば、この作品は、再臨という事象を徹底的に考究し論述することを最大の目的の一つとしているのだから。まずジョナサン・エドワーズという人間であるが、彼は超一級の神学者であって、その学識と影響力は大変大きなものがあり、非常に恵まれた人であった。彼の有名な説教「神の怒れる御手の中にある羊」は、アメリカの公立学校の教科書にも採用されている。また彼はプリンストン大学の学長でもあった。正統的な信仰を持つプロテスタントの教師であれば、エドワーズを神学的な権威として認めない人は、恐らくほとんどいないはずである。エドワーズはあのスポルジョンも高く評価していた神学者であった。さて、この権威あるエドワーズがマタイ24章の箇所を、紀元66~70年におけるユダヤ戦争を預言した箇所だと理解していたということは、この再臨論にとって、また我々の再臨に対する理解にとって非常に大きな意味を持つ。エドワーズがマタイ24章の箇所をユダヤ戦争について言われた箇所だと理解していたということは、つまり彼が、マタイ24章は既に成就していることが書かれた箇所だと認識していたことを意味する(※)。何故なら、マタイ24章がユダヤ戦争のことを言ったものだとすれば、その箇所は既に実現していることになるからである。誰がこのことを疑うであろうか。ユダヤ戦争は既に過ぎ去った昔の出来事なのだ。エドワーズの『原罪論』第1部の第2章の箇所を見ると、彼が、マタイ24章およびマタイ24章との並行箇所であるルカ21章は、今から2千年前に起きたユダヤ戦争のことを言っていると理解していたことがよく分かる。後の箇所でも説明されるが、このユダヤ戦争の際には、エルサレムが徹底的に破壊されることになった。彼はこの「エルサレムの最後の破壊の出来事」について、こう述べている。「それは、ソドムやネブカドネザルの時代のエルサレムの破壊よりも、はるかに悲惨であり、より大きな神の怒りを証言する出来事であった。それはこの世の始まりから当時に至る歴史のなかで都市や人々に対して起こった最も悲惨な出来事であった。「マタイによる福音書」24章21節、「ルカによる福音書」21章22―23節に記されている通りである。…新約聖書では、キリストが弟子たちの保護のためになしたまう特別な配慮について記されている。すなわち、キリストは彼らにエルサレムの破壊が近づいたことを知らせる徴候を示し、都市の内部にいる者たちを山に逃れさせた。そして歴史が告げるように、その指示に従ったキリスト教徒たちは、ペラと呼ばれた山岳地に逃れて惨禍を免れたのであった。…」(『ジョナサン・エドワーズ選集3 原罪論』第1部 第2章 p145:新教出版社)この文章を見れば分かるように、明らかにエドワーズは、マタイ24章(およびルカ21章)がユダヤ戦争について記された箇所であったと理解していた。「キリストは彼らに…都市の内部にいる者たちを山に逃れさせた。」と書いてあるのは、マタイ24:16の『そのときは、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。』という御言葉と、ルカ21:21の『そのとき、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる人々は、そこから立ちのきなさい。いなかにいる者たちは、都にはいってはいけません。』という御言葉のことを指している。もしマタイ24章がユダヤ戦争の時期のことを言ったものだと理解していなかったとすれば、エドワーズが、このような文章を書くことはなかったはずである。エドワーズが、マタイ24章をこのように理解していたのは、正しかった。何故なら、この箇所は確かにネロにより引き起こされウェスパシアヌスがティトゥスに遂行させたユダヤ戦争のことを述べている箇所だからである。今の時代の教師たちも、このマタイ24章がユダヤ戦争のことを言った箇所だと説明されると、それまではまだマタイ24章が実現していない箇所であると信じていたとしても、納得して「確かにそうだ。これはユダヤ戦争のことを書いたものだ。」などと言う。というのも、普通に考えれば、これはユダヤ戦争以外のことではないと分かるからである。さて、エドワーズがマタイ24章とはすなわちユダヤ戦争のことを述べた箇所だと理解していたということは、一体どういうことであろうか。彼のこの理解は、どういった意味を持っているのであろうか。それは、つまり、エドワーズが事実上、キリストの再臨はユダヤ戦争の時期に起きたと主張しているのも同然だということである。ここで驚きの念を抱かれる読者が多くいるかもしれないが、慌てないで、冷静に読み進めていただきたい。読者、ことに教職者である読者が反発するだろうことは、私には既に分かっている。しかし、冷静にならねば、本来であれば理解できることも理解できなくなってしまう。心における激しい情動が、理性の正しい働きを妨げてしまうからである。さて、どうしてエドワーズが事実上、マタイ24章に記されているユダヤ戦争の時期に再臨が起きたと主張していることになるかと言えば、それはマタイ24章の箇所で、キリストの再臨のことが述べられているからである。もしマタイ24章がユダヤ戦争のことを述べた箇所であり、その戦争が既に実現していると理解するのであれば、普通に考えて、その箇所に書かれている再臨もユダヤ戦争と共に実現したと考えなければいけない。マタイ24章に書かれているユダヤ戦争に関する史実的な記述だけが既に実現したと理解し、他方ではそこに書かれている再臨のことはまだ実現していないと理解するのは、明らかに普通ではない。それは論理的ではない。理性が正常に働いている人であれば、誰もこのことは疑わないはずである。もしマタイ24章の内容のうち、ユダヤ戦争について言われている部分は既に実現したが、再臨について言われている部分はまだ実現していないと理解する人がいたら、その人は愚か者とか精神障害者だと見做されても文句は言えない。言うまでもなく、マタイ24章が既に起きたユダヤ戦争のことを言っている箇所だと理解するのであれば、そこで語られている再臨のことも既に起きたと理解しなければいけない。もちろん、エドワーズは、意識的には再臨が既に起きたとは理解していなかった。それは彼の書いたものを読めば誰でも分かることである。彼は、他の無数の教師たちと同じように、まだキリストの再臨が起きていないと理解し、そのように語っている。しかしながら、マタイ24章が既に起きたユダヤ戦争のことを言った箇所だと考えるのであれば、それは再臨もユダヤ戦争の時期に起きたと考えていることを意味しているのである。この卓越した神学者であるエドワーズは、この問題について、大いに悩んだに違いない。「マタイ24章が既に起きたユダヤ戦争について言っているということは理解できるのだが、その箇所でキリストの再臨について書かれていることが何故なのか分からない、一体どうしてここで再臨が起こると書かれているのだろうか。ここでは再臨についてどのようなことが言われているのか。公同の信条も述べているように、まだ再臨は起きていないはずである。私はこの箇所をどのように解釈すべきなのか…。」このような神学的な思い煩いが、彼の心に多かれ少なかれ生じたであろうことは、決して疑えない。ロックに匹敵するほどの深遠性と思考力とを持ったこの神学者が、この問題に気付いていなかったということは、まったく考えられない話である。しかし、エドワーズの霊と精神に、再臨の真理が会得させられることは遂になかった。彼の時代には、まだ再臨の真理が、隠されていたからである。だから、エドワーズは思慮深い学者に相応しく、この件については何も語ることをしていない。すなわち、よく理解できていないのであえて堂々と語るという無謀を冒すことをせず、「判断停止」の選択をしたわけである。もし仮に筆者である私がエドワーズにこのことを教え説くことができていたとすれば、彼は最初のうちは驚いたり、怪しいと思ったり、反発したりするであろうが、徐々に納得していき、最終的には再臨が既に起きたと認めるに至っていたことであろう。というのも、マタイ24章の箇所がユダヤ戦争のことを述べた箇所だと理解するのであれば、その箇所に書かれている再臨もユダヤ戦争の時に起きたと理解しなければいけないということが、彼にはよく分かっただろうからである。エドワーズは御霊の人であり、洞察力と思考力に富んでいたから、確かにそのようになったに違いないと私は思う。もっとも、彼の生きた時代には、まだ私のような者は一人も世に起こされていなかったのであるが。というわけで、エドワーズは潜在的には、この『再臨論』に書かれている内容に同意する神学者である。実際には同意していないかもしれないが、「事実上」同意している。何故なら、マタイ24章がユダヤ戦争のことを述べているなどと言うのは、暗に「再臨はユダヤ戦争の時期に起きたのだ。」と言っていることになるからである。エドワーズ以外の教師また一般信徒においても、もしマタイ24章がユダヤ戦争のことを述べた箇所だと信じているのであれば、その人は潜在的な私の味方また賛同者である。その人も、暗に、また遠回し的に「再臨はユダヤ戦争の時期に起きた。」と言っているからである。読者は、このエドワーズを通しての間接的な論証からも、再臨が既に起きたということを理解すべきである。まだマタイ24章がユダヤ戦争のことを述べたと理解していない者は、まずそのことを理解するにようにせよ。そのことを理解したならば、そこに書かれている再臨の事象も、ユダヤ戦争と共に既に実現したのだと知れ。また、もし再臨が起きていないと考えるのであれば、再臨について語られているマタイ24章の箇所も、まだ起きていないと考えなければいけないが、そのように考えるとマタイ24章で記されているユダヤ戦争もまだ起きていないと考えなければいけなくなることに気付け。論理的に考えれば、マタイ24章の記述に関して、我々は次のうちの、どちらか一つしか選べない。すなわち、1.ユダヤ戦争は既に起きたから再臨も既に起きたと理解すること、2.ユダヤ戦争はまだ起きていないから再臨も既に起きていないと理解すること、の2つである。正しいのは言うまでもなく1のほうである。ユダヤ戦争と再臨というこの2つの出来事はマタイ24章の箇所で一緒に纏められて語られているのだから、ユダヤ戦争のほうは既に起きたが再臨はまだ起きていない、または再臨のほうは既に起きたがユダヤ戦争はまだ起きていない、などと考えることは絶対にできないのである。
(※)
私と対論したある牧師も、マタイ24章がユダヤ戦争のことを預言している箇所だと認めた。認めざるを得なかったのである。この箇所は、どう考えても明らかにユダヤ戦争の時期に起こる悲惨な出来事を預言した箇所だからである。オリゲネスも、マタイ24章がユダヤ戦争のことを預言した箇所だと理解していた。というのも、彼はマタイ24章の並行箇所であるルカ21章に書かれている文章が、エルサレム包囲について言われたことだと述べているからである。ルカ21章が既に起きたことを認めるのであれば、それと同じ内容が記されているマタイ24章も既に起きたと認めていることになるのは、誰でも分かることである。そのことについて彼はこう言っている。「ケルソスのユダヤ人は、イエスが自分に起こったすべてを予知していたことを信じないので、次のことも考慮してもらいたい。すなわちエルサレムがまだ存続しており、全ユダヤの崇拝がこの地で行なわれていたときに、ローマによってこの地に引き起こされた出来事をイエスがどのように予告したのか。というのも、確かにイエス自身に従った人々や聴衆が福音の教えを文書化せずに伝えたとか、イエスに関する文字で書かれた覚え書きを抜きにして、弟子たちのことを後代に残したとは言われていないからである。それらにおいては確かに、「エルサレムが軍隊に包囲されるのを見たなら、そのときその滅亡が近いことを知りなさい」(ルカ21・20)と記されている。そのときエルサレムを包囲し、封鎖し、封じ込める軍隊はなかった。すなわちそれが始まったのはネロがまだ統治していたときで、それはウェスパシアヌス帝の治世まで続いていた。そのむすこのティトゥスは、ヨセフスが記述しているように、キリストといわれるイエスの兄弟、義人ヤコブのゆえにイスラエルを滅ぼしたのだ。だが真相は、神のキリストなるイエスのゆえであったのだ。」(『キリスト教教父著作集8 オリゲネス3 ケルソス駁論Ⅰ』第2巻 13 p104:教文館)コーネリウス・ヴァン・ティルも、マタイ24章の出来事が紀元1世紀に実現すると理解していたように見える。何故なら、彼の書いた次の文章は、明らかにマタイ24章で言われている「荒らす者」からの逃避がすぐに実現すると理解していなければ書けないはずだからである。「週の終わりの日から初めの日への移行は、徐々になされた。イエスは明らかに、御自分に従う者たちが当分の間はユダヤ人の安息日を守ることを望んでおられた。「逃げるのが、冬や安息日にならぬよう祈りなさい」(マタイ24・20)。」(『ヴァン・ティルの「十戒」』第4戒 安息日 Eキリスト教の主の日 p118:いのちのことば社)
[本文に戻る]
続いてパウル・ティリッヒについても語ることにより、既に再臨が起きたということを論証したい。とはいっても、エドワーズの場合と同じで、これもまた間接的な論証となる。私が間接的であると言うのは、ティリッヒの言説から遠回し的に再臨が既に起きたという聖書の真理を論証することができるものの、当のティリッヒ自身は既に再臨が起きたと信じていないということである。しかし、たとえそのような論証ではあっても、私が述べた説をいくらかでも補強することにはなるから、私はここでその論証を臆せずにすることにしたい。そうすれば、ますます再臨の真理が豊かに論じられ、読者もそれだけ再臨の真理を理解しやすくなるのである。特に、ティリッヒを敬愛する先生方にとっては、ここで語られる論証は、強い説得力となるのではないかと思う(※)。なお、このティリッヒもエドワーズと同様に、著名であり影響力の強い学者である。さて、この著名な学者のことであるが、彼は、キリストの再臨が、初臨が起きてからあまり年月の経たない間に起こる出来事であると理解していた。つまり、ティリッヒは、使徒たちが再臨は「すぐに」起こると語ったことについて、それが文字通りの「すぐ」であると捉えていた。彼の「プロテスタンティズムにとってのカトリック教会の永続的意義」という論文の中では、次のように書かれている。「キリスト教の最初期以来、カトリシズムは漸次、使徒時代の非常な緊張感、すなわち、われわれはキリストの第一の来臨と第二の来臨のあいだの短いがしかし重要な時期を生きているのだという感情を排除してきた。」(『ティリッヒ著作集 第5巻 プロテスタント時代の終焉』p165~166:白水社)下線部に注目すべきである。この文章を見れば分かるが、ティリッヒは明らかに、使徒たちは再臨(第二の来臨)が初臨(第一の来臨)から長くない間に起こるのだと考えていたという理解を持っていた。というのは、この文章の中では、再臨と初臨の間の時間が「短い」と言われているからである。すなわち、彼は、他の多くの学者たちとは違って、再臨が初臨から数百年後、数千年後に起こる出来事であるとは考えていなかった。そうでなければ、再臨と初臨の間の時間を「短い」などと言うことはなかったはずである。彼が、このように再臨を捉えていたのは正しかった。というのは、聖書を時代背景やその語られた状況を考慮しつつ読むのであれば、初臨の次に起こるキリストの現われとしての再臨は、本当に文字通りに「すぐに」起こるとしか理解できないからである。確かにティリッヒの文章の中で言われているように、「初臨と再臨の間の時期は短い」。我々が日常生活において「すぐに」とか「短い間に」などと言う場合、それは文字通りのことを言っているのであって、そのように言うことで数百年後、数千年後を言い表わすことはほとんどない。通常の場合、「すぐに」とか「短い間に」という言葉は、数日か数カ月か2~3年ぐらいであり、長かったとしても30年ぐらいを意味するだけである。使徒たちが再臨について「すぐに起こる」などと教えたのも、それと同じであった。このようにティリッヒは、再臨が初臨に続いてすぐに起こると理解していたのではあるが、そのように聖書が教えているということ自体は信じていても、実際に使徒の時代に再臨が起きたということについては信じていなかった。彼には、再臨の真理を信じる恵みが注がれていなかったのである。彼は、再臨が初臨のすぐ後で起こると聖書には書かれているものの、実際に当時において再臨が本当に起きたとは信じれなかった。このように、この学者は、再臨がすぐに起こると聖書の中では語られているのにもかかわらず、それが既に起こったことだとは信じれなかったので、驚くべきことに、再臨を含めた終末の事柄が「神話」であると理解してしまった。だから、彼は自分が理解できず信じることのできなかった再臨と再臨にかかわる終末の事柄を純粋に解明することを拒み、それがキリスト教神学における重要な課題ではないと判断するに至った。このように彼が判断したのは彼に対して再臨の真理が隠されていたためであるから仕方がないといえば仕方がなかったかもしれないが、あまりにも愚かであり、批判されるべきことである。分からないから、また信じられないからといって、再臨にかかわる終末の事柄を神話化していいはずがどうしてあろうか。神が、聖書の中に神話を書かれるはずが、どうしてあろうか。確かなところ、この再臨の事柄こそが、現代のキリスト教神学における最も考究され解明されるべき事柄なのである。この盲目的な学者は、次のように言うことで、自分に再臨を理解する恵みが与えられていないことを自ら公にしている。「…ユダヤ的・原始キリスト教的な終末神話を弁護したり解明したりすることは、プロテスタント神学の課題ではない。むしろ次のように問うことがその課題である。すべての歴史的行為に内在している究極的な意味とは何であるのか。われわれはいかに時間を、そのなかに侵入してきた永遠の光のなかで解釈するのか。「時の終わり」を時間の一要素として、正しく、前方に向かっている、意味にあふれた、救済史的な時間の要素として見ることが大事である。」(同 プロテスタント的形成 p86)ここで読者は2つのことを知るべきである。すなわち、まず第一にティリッヒは再臨が初臨に続いてすぐに起こると考えていたということ、第二にそのように考えるのは聖書を正しく捉えることであるということ、この2つである。上に述べたようにティリッヒは再臨が使徒たちの時代に起きたと信じられなかったが、だからといって自分の考えを変えて、他の学者たちと同じように再臨は遥か後の時代に起こるべき出来事として記されたのだという見解を持つには至らなかった。何故なら、聖書は明らかに、再臨が使徒たちの時代に起こるものとして記しているからである。この理解を固持した点では、彼は正しかったと言える。多くの人の場合、聖書では再臨が使徒たちの時代に起こるものとして記されていると理解しても、実際に使徒たちの時代に再臨が起きたとは思えないので、考えを切り替えて、再臨はずっと後に起こるものとして記されたという既存の見解を持つに至る。ティリッヒよ、自分が終末の事柄を正しく理解できないからといって、それを神話として処理してしまうあなたは一体何様なのか。あなたは神の啓示を素直に信じることをせず、自分の理性を自分の判断基準とした。あなたは神を神とせず、自分を神としたのだ。だから、あなたには裁きとして惑わしの霊が送られ、その霊の惑わしにより、聖書の啓示を神話として考えるという罰が下されたのである。読者の方は、このティリッヒのようにならないように、よく注意してほしい。御言葉を素直に信じなければ、この学者のように裁きを受け、聖なる啓示を神話にまで引きずりおろすという致命的な愚を犯すことになりかねない。
(※)
私の場合、ティリッヒにはバルトや近代における他の学者と同様に、あまり首肯的な評価を持っていないが。
[本文に戻る]
ところでアウグスティヌスは、再臨について触れられているヨハネの福音書21章の箇所で、どれだけ狼狽したことか。彼は、他の全ての教師たちと同じように再臨が未だに起きていないと考えており、まさか再臨が聖書に書いてある通りに本当に『すぐに』(黙示録22章20節)起こるなどとは想定することさえできなかったので(このように聖書に書いてある通りのことを信じないのは不信仰また不敬虔である)、福音書の中でキリストが「もしヨハネの生きている間に再臨が起きたとしたら」と言っておられるのを読んで、ひどく動揺してしまった。キリストは福音書の中で、ペテロがヨハネについて『主よ。この人はどうですか。』(21章21節)と言ったのに対して、次のように答えられた。『わたしの来るまで彼が生きながらえるのをわたしが望むとしても、それがあなたに何のかかわりがありますか。』(21章22節)アウグスティヌスは再臨が既に起きているなどとは夢にも思っていなかったので、このキリストの御言葉が、まったく意味不明に思えてしまった。この狼狽ぶりを確認したい人は、彼の『ヨハネ福音書講解説教』における21章の部分を見るといい。結局、彼はどうしてキリストがヨハネの生きている間に再臨が起こるかのように言われたのか―実際にはヨハネの時代に再臨が起こったのであるが―、理解できないままに終わった。これは、彼にとっては当然であったと言えるかもしれない。何故なら、まだ再臨の真理が隠されていた時代にあっては、神の摂理により、聖徒たちは再臨が既に起きたという考えを心の中に抱くことさえ禁じられていたからである。だから、アウグスティヌスは既に再臨が起きたということを想定することさえ出来なかった(※)。多くの教師たちは、自分にはまだ分からない事柄があれば、それを何も語らないでおくという選択をするのが常である。再臨に関する事柄においても、それは例外ではない。例えば、カルヴァンは黙示録がよく理解できなかったので、誰でも分かるような簡単なことを除けば、この文書に書いてあることに深く言及することはしなかったし、彼が新約聖書の中で註解書を書かなかったのはこの文書とヨハネの手紙ⅡとⅢだけであった。彼が黙示録の註解を書かなかった理由は不明とされているが、私から見れば、黙示録が分からなかったからであるのは間違いない。彼が黙示録の聖句を引用している文章を見ると、彼は黙示録について無知で盲目だったことが分かる。彼も他の無数の神学者たちと同様、その引用している黙示録の聖句が、誰でも容易に理解できるような簡単な聖句に留まっているのだ。私はそのような引用の背景に、いつも黙示録に対する無知の匂いを嗅ぎ取っている。ジョナサン・エドワーズも、マタイ24章が紀元1世紀のユダヤ戦争について預言した箇所であることを知っていたが、その中でどうして再臨のことが預言されているのかまったく理解できなかったので、あえてその謎―私のような者たちにとっては謎ではないが―に触れることはしなかった。しかし、この教父はといえば、分からないことがあればしっかりと分からないと告白し、分からないながらも様々な考察をしていることを多くの人に対して開陳し、分かるようになるために聴衆や読者に議論して答えを出してくれるようにと要請さえするほどであった。こういう教師は非常に珍しい。アウグスティヌスがこういう教師だったからこそ、我々は、彼がヨハネの福音書21書の箇所で狼狽していたことをその残された作品によって知ることが出来ているのである。だから、本当はもっと多くの人たちが、このヨハネの福音書21章の箇所で狼狽しているはずである。ただ、その人たちは、自分が狼狽していることをアウグスティヌスのように表に出さなかっただけに過ぎない。世の中には、恥ずかしかったり、引け目を感じたり、自分の権威が損なわれることを厭うなどといった理由により、分からない事柄については完全な沈黙を保つ人が多い。それゆえ、これを読んでいる読者の中にも、周りの人に言いはしないものの、どうしてこの21章の箇所でキリストがこのように言われたのか分からずに悩んだことのある教師や一般信徒が、多くいるはずである。だが、既に再臨が起きたと信じるのであれば、この箇所には何の違和感もなくなる。何故なら、キリストがこのようにヨハネが生きている間に再臨が起きることもあり得るという含みを持たせたことを言われたのは、本当に使徒の時代に再臨が起きることになっていたからである。この言葉を聞いた弟子たちは、キリストが言われたことに対して、何の違和感も持たなかったはずである。というのも、キリストはあらかじめ、ご自身の目の前に立っている人たちが生きている間に再臨が起こると言っておられたからである(マタイ16:28)。キリストがそのように言われたのだから、使徒の時代に再臨が起きるという考えが当時の弟子たちの間にあったのは疑えない。そのことを知っており、また信じている私のような者たちも、このキリストの言葉を読んでアウグスティヌスのように狼狽することはない。そもそも、今まで全ての教師たちがそう考えてきたように、再臨がキリストの時代から数百年、数千年経過しても起きていないというのであれば、キリストはペテロに対してこのようには言われなかったはずである。非常に長い時間が経過しても起きないような遥か未来の出来事を、あたかも自分の目の前にいる人間―ヨハネ―が生きている間に起こるかのように語るということほど、愚かなことが他にあるであろうか。読者は、ここまで説明されたように、再臨は既に起きたと信じるべきである。そうすれば、たった今見たこの福音書の箇所を読んでも、違和感を心に抱くことはなくなるであろう。
(※)
これはカルヴァンも同様である。彼の著書を読むと、再臨が既に起きたなどとは塵ほども思っていなかったことが分かる。恐らく頭の中に、そのような考えが一瞬だけでもよぎったことさえなかったことであろう。実際、彼の書いたヨハネ福音書の註解における21:22~23の箇所では、再臨について全く触れられてはいない。カルヴァンは自分には理解できない事柄は、分からないことでも堂々と告白するアウグスティヌスと違って完全に沈黙する人だったから、この箇所で何が言われているのか全く悟れていなかったことが分かる。というのも、もし少しでも悟れていれば、彼が多くの箇所でそうしているのと同様に、大胆に力強く語っていたことであろうから。だから、彼はこの箇所の註解では、自分の理解できる再臨以外の事柄を長々と語って、その場をやり過ごそうとしている。そのため、私は彼のこの箇所における註解を読んで「どうして再臨のことには何も触れようとしないのか?」と大いに思ったものである。だから、多くの教職者と同様に、彼も私の言っていることを聞いたら「きょとん」として思考が止まったことであろう。
[本文に戻る]
それではどうなのか。全ての教会と全ての聖徒たちは、私がここまで述べたように、既に再臨が起きたと信じなければならないというのであろうか。その通りである。とはいっても、そのように信ぜよと命じるのは私ではない。命じるのは私ではなく「神とその御言葉」である。何故なら、御言葉は既に再臨が起きたと明瞭に教えているのであって、神は全ての教会と全ての聖徒たちに御言葉を信じるように命じておられるからである。
このように聖書は再臨がもう実現されたと教えているのだから、「使徒信条」の再臨に関する部分は、我々においては誤りであるとせねばならない。この信条の制作年代がいつだったかということは別問題として、この信条における再臨の部分は、まだ再臨が起きていない時までは、誤りではなかった。しかし、再臨が起きてから後は、既に再臨が起きたのだから、この信条の述べる再臨の部分を我々に直接かかわりのあるものとすることはできなくなった。既に再臨が起きたのに、「かしこより来りて生ける者と死ねる者とを審きたまわん。」と唱えるのは、理に適ったことではない。もちろん、この信条の再臨以外の部分は、我々においても正しいことを述べているとせねばならない。それらの部分は、まったく聖書的な内容だからである。なお、他の諸信条においても、再臨がまだ起きていないと述べている部分については間違っているとせねばならないが、これは言うまでもないことであろう。
たった今、使徒信条について小さからぬ内容のことを述べたが、ここで使徒信条を部分的にではあったとしても否定しているのを読んだ読者の中で、「怪しい」などと感じる人は多いだろうと私は思う。何せ使徒信条と言えば、聖書に次ぐ権威を持った文書として教会の中で1500年以上も尊重されてきた文書である。そのような文書であれば、たとえその文書の中に誤りがあると理知的に説明されたとしても、多くの人たちが訝ったとしてもそれほど不思議ではないと言えるかもしれない。人間とは歴史や伝統に縛られやすい生き物だからである。しかし、読者は2つの点をよく弁えるべきである。まず一つ目は、私は使徒信条における再臨の箇所だけが間違っていると言っているということである。つまり、先にも述べたが私は再臨の箇所を除けば、使徒信条の内容にまったく同意している。しかも、本書を読めば分かるが、私には使徒信条の再臨の部分が誤っていると言えるだけの十分な理由を持っている。要するに、私は何の根拠もなしに信条の再臨の部分が誤っていると言っているわけではないのだ。二つ目は、使徒信条は聖書ではないということである。使徒信条はほとんど聖書同然の取り扱いを受けているが、これはあくまでも人間が作った文書に他ならない。人間が作った文書だからこそ、特にバプテスト派などがそうだが、あまりこの信条に心を傾けない教派また教会もあるわけである。これは、特に「信条ではなく聖書だ」と言う傾向を持つ教派また教会に多い。人間は神ではなく、誤りから完全に免れている人間などこの地上においては存在していない。だから、使徒信条の中で、再臨の部分だけが誤っていたとしても、それほど驚くには値しない。つまり、こういうことだ。神は御自身の御言葉だけが神聖視されるようにと、つまり使徒信条があたかも聖書でもあるかのように見做されないようにと、使徒信条の中に一つだけ誤謬が書かれることを望まれ実際にそのように取り計られたのである。もし使徒信条の中に一つも誤りが無かったとすれば、それは誤りが無いという点では聖書と一緒になってしまう。しかし、神は人間の作った文書が、聖書と肩を並べることをお望みではない。そうしたら、聖書からそれだけ輝きが失われてしまうからである。唯一無二であるからこそ、そこに大きな輝きが伴うのである。それだから、我々は使徒信条に誤謬が一つだけ含まれることが神の御心であったということを知るべきである。以上このように私は理知的に説明をしたのだから、使徒信条に誤りが含まれていると言われたからといって読者は問答無用で拒絶することをせず、シッカリと聖書に基づいて使徒信条の当該部分を吟味してほしいものである。私は御言葉に基づいて説明をしているのだ。そのような説明を果たして無視していいものであろうか。
さて、ここまで書かれた文章を読んで、「もし再臨が既に起きたというのであれば再臨の証拠は存在するのか?もしあるとすればどのような証拠が?」などと思われる人が多くいるに違いないが、これについては第7章になるまで待ってほしい。今はまだこのことを論じないが、やがて7章になれば詳細に考察されるであろう。読者は、少なくとも今の段階では、この証拠の問題のことで心が落ち着かなくなったとしても、御言葉を疑うことはすべきではない。すなわち、証拠の問題は取りあえず隅に置いておき、御言葉が既に再臨は実現済みだと教えているということ自体は確かなこととすべきである。また後の箇所で述べることになるが、証拠も何も御言葉が既に再臨が起きたと我々に教えているのだから、御言葉に立つべき我々がどうして御言葉で言われていることを否定してよいであろうか。まだ証拠に関する説明を十全に聞いていないにもかかわらず、今の時点で速断してしまい、不十分な見解のまま再臨の真理を否定してしまうのは実に危険である。思慮ある者は、まずは私が後ほど説明する再臨の証拠についての論述をしっかりと読みたまえ。まだ説明を聞いていないのに、「再臨が既に起きたなどとは信じがたいことだ!」などと最終的な判断を下すのは無思慮も甚だしい。アウグスティヌスも言うように「これはとても深淵な問題であるがゆえに、決して結論を急いではならない。」(『アウグスティヌス著作集30 ペラギウス派駁論集(4)』ユリアヌス駁論 第6巻 第15章 45節 p397:教文館)のであって、ソロモンも言うように『急ぎ足の者はつまずく。』(箴言19章2節)のである。というわけで、再臨の証拠が気になる方は、そのことについて論じられる箇所が来るまで今しばらく待っていてほしい。
第3章 再臨の起きた年
これまで見てきたように、再臨が既に起きたというのは聖書から明らかであるが、それでは再臨が起きたのは一体いつであろうか。すなわち、再臨の起きた正確な年代はいつであろうか。この重要極まりない疑問を聖書から解決することにしたい。
説明に入る前に、まず読者の懸念を解決しておきたいと思う。多くの読者は、キリストが再臨の日は誰も知らないのだと言われた聖句を提示して、再臨の日を特定することなどできるのか?という疑問を持つことであろう。何か心配に思う人もいるはずである。確かにキリストは次のように再臨の日について言われた。『ただし、その日、その時がいつであるかは、だれも知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。』(マタイ24章36節)確かに、再臨が起きるまでは、父なる神以外には誰も再臨の日がいつなのか知ることはまったくできなかった。それは人としてのキリストでさえ例外ではなかった。しかし、これは再臨が起きるまでの期間についてのみ、そう言えることである。我々が聖句から見たように、間違いなく既に再臨は起きている。であれば、その再臨が起きた日を特定することは、神の恵みがあれば不可能ではないであろう。もし既に再臨があったのであれば、聖書的な考察により、神の恵みによって、その日を特定することが可能であると私は考える。多くの人たちが信じているように、いまだに再臨が起きていないというのであれば、再臨の日を特定することは誰にもできないと私も認める。しかし今や既に再臨は起きたのであるから、我々はその日がいつだったのか霊的に考究するべきではないか。もしその日が特定できたのであれば、それは我々にとって大きな喜びとなるに違いない。再臨の起きた時期を特定すると聞いて何か心配に思う人は、既に再臨は起きたのだという第2章で述べられたことを、もう一度よく心に留めていただきたい。
我々が再臨の起きた年を知るために注目せねばならない箇所の一つは、マタイ24章である。この箇所を考究すれば、完全とまではいえないものの、再臨の起きた年をある程度まで正確に知ることができる。まず第一に、今も多くの教会が注目しているこの箇所は、これから起こることが預言されている箇所ではない、ということを我々は知らねばならない。今もこの箇所は未来のことを言っている箇所だと思われているが、確かなところ、ここで言われているのは紀元66~70年に起きた第一次ユダヤ戦争とその戦争が始まるいくらか前に起きる出来事のことである。ここでキリストが言われたことを見ればすぐに、それは分かる。例えば主は『『荒らす憎むべき者』が、聖なる所に立つのを見たならば』(マタイ24章15節)と言われたすぐ後で、次のように言われた。『そのときは、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。屋上にいる者は家の中の物を持ち出そうと下に降りてはいけません。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だが、その日、悲惨なのは身重の女と乳飲み子を持つ女です。ただ、あなたがたの逃げるのが、冬や安息日にならぬよう祈りなさい。』(マタイ24章16~20節)主は、当時ユダヤにいたユダヤ人に苦難が襲い掛かるというので、その苦難から免れるために山へ逃げなさいと言われたのである。また、兵士らがユダヤの地を攻めるからこそ、家の中に入ったり、服を取りに戻ってはいけない、と言われたのである。何故なら、そんなことをしている余裕は、ローマ軍がユダヤを包囲した時にはまったくないからである。お分かりであろうか。主は、ユダヤ戦争における苦難について、ここで預言されたのであって、今の時代に生きる我々に対して、このように警告しておられるのではない。今の教会は、この箇所をまったく誤解しており、そのため自分たちに当然の報いを招いているが、ここではそのことには触れないでおきたい。この有名な戦争がどれだけ悲惨であったか知りたい者は、ヨセフスの「ユダヤ戦記」を読むべきである。この書を読めば、主が預言された苦難が一体どのようなものであったか、よく分かるであろう。この時には、多くのユダヤ人が殺され、キリスト者は迫害され、食糧不足のために母が幼子を煮て食べたり動物の糞や木の皮をさえも食べるほどであり、気の狂った者が現われ、最後には世界で最も有名な建築物であったエルサレム神殿が完全に滅ぼしつくされた。主が、この戦争における苦難を予告し警戒させるために、このような預言をされたと考えれば、この24章の箇所は我々にとって理解できない箇所ではなくなる。しかし、この箇所が2千年経過しても実現していない苦難を預言したものだとすれば―今の教会のほぼ全てはそのように理解している―、この箇所は我々にとって意味の分からない箇所となる。その場合、主は、2千年経っても起きない出来事について警戒するように、当時の人たちに色々と言われたことになるからである。「君たちの時代には決して起きない出来事ではあるが、しかし数千年以上経過してから起こる出来事であるから、そのことを思って、よく心構えをしたまえ。」などと言う人がいれば、一体誰がそのように言う人を信用するであろうか。ところが、今の教会は、事実上、主がこのように言ったことにしてしまっているのである。更に、マタイ24章がユダヤ戦争のことを預言しているという見解は、マタイ24:34の箇所からも論証できる。ここで主はこう言われた。『まことに、あなたがたに告げます。これらのことが全部起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。』この箇所にある「時代」という言葉の原語は「γενεα」(※ゲネア)であり(※①)、これは「世代」という意味である。KJVでは「ジェネレーション」と訳されている(※②)。「世代」とは、どのような辞書を見ても、いかなる世の学者の説明を聞いても、例外なく「およそ30~40年」すなわち「生まれた子が大人になって子を産み始めるようになるぐらいの期間」という意味であるとされている。古代ギリシャの歴史家であるあのポリュビオス(前200-前118)も、そのように理解していた(『歴史』)。いつの時代であれ、これが数百年とか数千年といった長い期間であるとされることは、まずない。アウグスティヌスも、このゲネアという言葉について次のように言っている。「「代」をギリシア人はゲネアと言っている。これは一番短く考えると15年で終わるとされ、それは人が子孫を残すことのできる歳である。」(『アウグスティヌス著作集20/Ⅰ 詩篇註解(5)』詩篇104篇 p199:教文館)また、この言葉は新約聖書の中で15回使用されているが、どこの箇所でも「今のその時代」という意味合いで使用されている(マタイ12:39、45、16:4、17:17、24:34、マルコ8:12、38、9:19、13:30、ルカ9:41、11:29、30、21:32、使徒行伝13:36、ヘブル3:10※③)。これらの箇所を見ても分かるが、この「ゲネア」という言葉が、2千年以上も経過した時代を意味しているというのは絶対に有り得ない。これは、あくまでも「当時代」という意味である。だから、マタイ24:34の箇所では、1世代という意味で『時代』(ゲネア)と言われているとすべきである。1世代とは確かに『この時代』でなくて何であろうか。ということはつまり、こういうことになる。キリストがマタイ24章で預言された年は、恐らく紀元33年頃であろう。そうすると、ここで預言されている苦難は、「γενεα」後、つまりおよそ「30~40年」後に実現するということになる。ユダヤ戦争の時期は、紀元66~70年である。紀元33年に「30~40年」を加えると紀元63~73年となる。どうであろうか。このように考えると、本当に主が預言されたことが、主の言われたように、一世代(γενεα)経過する間に起きたことが分かるであろう。それゆえ、マタイ24章がユダヤ戦争についての預言でないと信じている者、またルターのようにこのマタイ24章が「最近の…時代」(『ルター著作集 第一集 4』修道誓願について 誓願は保たれるべきかどうかではなく、… p271:聖文舎)のことを預言した箇所であるなどと考えている者は、正しい考えに切り替えるのが望ましい。このような理解を前提としてこの24章の箇所を読むと、キリストの再臨の時期が、かなり具体的に分かるようになる。聖句から見ていこう。まず、主はエルサレム神殿を指し示した弟子たち(24:1)に対して、24:2の箇所でこう答えられた。『このすべての物に目をみはっているのでしょう。まことに、あなたがたに告げます。ここでは、石がくずされずに、積まれたまま残ることは決してありません。』これは、すなわち、紀元70年に神殿が跡形もなくなることである。主がこのように答えられた後に、その答えを聞いていた弟子たちは、、主に次のような質問をした(24:3)。『お話しください。いつ、そのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりには、どんな前兆があるのでしょう。』この質問からは、神殿崩壊の時期にこそ『あなたの来られる時』つまりキリストの再臨が実現するという理解を弟子が持っていたことが分かる。何故なら、この質問の中では、明らかに『そのようなこと』(※神殿崩壊)と『あなたの来られる時』(※再臨)という2つの事象の結びつきが認められるからである。つまり、この弟子は神殿が崩壊する時期にこそ再臨が起こるという理解を持っていたからこそ、このような質問をしたということである。このような弟子の再臨に対する理解を、主はまったく諌められなかったし、問題にもされなかった。それどころか、弟子のこの理解に沿う形で、4節目から『人に惑わされないように気をつけなさい。…』と返答をしておられる。もし弟子の再臨理解が間違っていたとすれば、主は弟子の質問に返答される前に、まずその理解を正しておられたに違いない。主は、弟子たちの理解に誤りがあった場合、その誤りを率直に正しておられたということを、私たちは既に福音書から知っている。要するに、キリスト御自身も、弟子と同じように、神殿崩壊の時期に再臨もまた起きると考えていたということになる。それでは、神殿の完全な滅亡をそのクライマックスとするユダヤ戦争が起きた時期はいつか。それは先にも書いたように紀元66~70年である。繰り返すが、弟子はこの時期にこそ『あなたの来られる時』(24章3節)が訪れると考えており、またそのように述べた。よって、キリストの再臨された年は、間違いなく紀元66~70年の間だったことになる。確かに主も、これから一世代の間に起きることを預言したマタイ24章の中で、ご自身が再臨されることを明瞭に述べているから(24:30)、この期間に再臨が起きたことは確かであるとせねばならない。しかしながら、今論じられた箇所であるマタイ24章だけしか考察しないと、再臨が紀元66~70年の間の「いつ」に起きたのかということまでは分からない。この箇所およびこの箇所と並行する箇所(ルカ21章、マルコ13章)から、再臨の起きた年をピンポイントで特定するのは非常に難しい。
(※①)
ビザンチン型写本による原文は以下の通り。
αμήν λέγω υμίν (οτι)※ ου μη παρελκή η γενεά αυτή ιώβ αν πάντα ταύτα γένηται
※()内の文はアレクサンドリア型にだけある言葉
[本文に戻る]
(※②)
Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.
[本文に戻る]
(※③)
『しかし、イエスは答えて言われた。「悪い、姦淫の時代はしるしを求めています。だが預言者ヨナのしるしのほかには、しるしは与えられません。』(マタイ12章39節)
『そこで、出かけて行って、自分よりも悪いほかの霊を7つ連れて来て、みなはいり込んでそこに住みつくのです。そうなると、その人の後の状態は、初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまた、そういうことになるのです。』(マタイ12章45節)
『悪い、姦淫の時代はしるしを求めています。しかし、ヨナのしるしのほかには、しるしは与えられません。』(マタイ16章4節)
『イエスは答えて言われた。「ああ、不信仰な、曲がった今の世だ。いつまであなたがたといっしょにいなければならないのでしょう。いつまであなたがたにがまんしていなければならないのでしょう。…』(マタイ17章17節)
『まことに、あなたがたに告げます。これらのことが全部起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。』(マタイ24章34節)
『イエスは、心の中で深く嘆息して、こう言われた。「なぜ、今の時代はしるしを求めるのか。まことに、あなたがたに告げます。今の時代には、しるしは絶対に与えられません。」』(マルコ8章12節)
『このような姦淫と罪の時代にあって、わたしとわたしのことばを恥じるような者なら、人の子も、父の栄光を帯びて聖なる御使いたちとともに来るときには、そのような人のことを恥じます。』(マルコ8章38節)
『イエスは答えて言われた。「ああ、不信仰な世だ。いつまであなたがたといっしょにいなければならないのでしょう。いつまであなたがたにがまんしていなければならないのでしょう。…』(マルコ9章19節)
『まことに、あなたがたに告げます。これらのことが全部起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。』(マルコ13章30節)
『イエスは答えて言われた。「ああ、不信仰な、曲がった今の世だ。いつまであなたがたといっしょにいて、あなたがたにがまんしていなければならないのでしょう。…』(ルカ9章41節)
『さて、群衆の数がふえて来ると、イエスは話し始められた。「この時代は悪い時代です。しるしを求めているが、ヨナのしるしのほかには、しるしは与えられません。』(ルカ11章29節)
『というのは、ヨナがニネベの人々のために、しるしとなったように、人の子がこの時代のために、しるしとなるからです。』(ルカ11章30節)
『まことに、あなたがたに告げます。すべてのことが起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。』(ルカ21章32節)
『ダビデは、その生きていた時代において神のみこころに仕えて後、死んで先祖の仲間に加えられ、ついに朽ち果てました。』(使徒行伝13章36節)
『だから、わたしはその時代を憤って言った。彼らは常に心が迷い、わたしの道を悟らなかった。』(ヘブル3章10節)
[本文に戻る]
それでは、もっと正しく再臨の起きた年を特定することは可能なのであろうか。それは可能である。そのためには、我々は、Ⅱテサロニケ書の2章に出てくるあの『不法の人、すなわち滅びの子』(2章3節)に注目する必要がある。何故かといえば、この邪悪な人物は、パウロによれば主の再臨により殺されることになっているからである。パウロは、この不法の人が再臨によって死ぬだろうと述べているが、それは次のように書いてある通りである。『その時になると、不法の人が現われますが、主は御口の息をもって彼を殺し、来臨の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。』(Ⅱテサロニケ2章8節)(※①)確かにパウロが言うように不法の人は再臨により死ぬのであるから、再臨の時期をより正しく知りたいのであれば、この不法の人が誰なのかということを考えればよいことになる。すなわち、この不法の人が誰であるかを知り、その人物が死んだ年を知れるのであれば、その死んだ年から再臨の起きた年をかなり詳しく知ることができる。では一体この『不法の人』とは誰か。答えから先に言えば、この人物はかの有名な「ネロ」である。まずはこの『不法の人』が「ネロ」であるということから論証していきたい。論証抜きに断定するのは、このような作品や私のような教師にとっては、相応しくない態度だからである。まず我々が知っておくべきなのは、Ⅱテサロニケ書にでてくる『不法の人』とは、すなわち黙示録13章にでてくる「海から上ってきた一匹の獣」であるということである。一体どうしてこう言えるかといえば、それは、この2人(実際は同一人物であるが)に関して言われている記述の内容が、実によく似ているからである。まず第一に、Ⅱテサロニケ書のほうで、この邪悪な人物は非常に傲慢であり、神に敵対的な態度を取る者であると説明されている。すなわち次のように書いてある。『彼は、すべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。』(Ⅱテサロニケ2章4節)このような性質があるということが、黙示録13章の獣に対しても言われている。この獣に関する黙示録の記述はこうである。『この獣は、傲慢なことを言い、けがしごとを言う口を与えられ…た。そこで、彼はその口を開いて、神に対するけがしごとを言い始めた。すなわち、神の御名と、その幕屋、すなわち、天に住む者たちをののしった。』(黙示録13章5~6節)どちらの聖句でも、神に反抗的な高ぶった人物だと言われているのが分かる。次は第二の説明であるが、それは『不法の人』と「獣」が、どちらもサタンの働きかけを受けているということである。パウロは『不法の人の到来は、サタンの働きによるのであって、…』(Ⅱテサロニケ2章9節)と言っている。同様に黙示録13章の「獣」も、竜すなわちサタン(※②)の働きかけがあったと言われている。黙示録のほうでは次のように書いてある。『竜はこの獣に、自分の力と位と大きな権威とを与えた。…そこで、全地は驚いて、その獣に従い、そして、竜を拝んだ。獣に権威を与えたのが竜だからである。また、彼らは獣をも拝んで、…』(黙示録13章3~4節)つまり、『不法の人』も「獣」も、どちらのほうもサタンの働きかけがなければ現われなかったということである。第三の説明、それは、どちらの人物も、キリストの再臨によって殺されると言われていることである。『不法の人』のほうについてはⅡテサロニケ2:8の箇所から既に確認した通りである。同じように、黙示録の「獣」も、再臨のキリストによって滅ぼされると言われている(※③)。次は第四の説明である。我々は、『不法の人』と「獣」が同一の人物であることを知れるために、『不法の人』がキリストの言われた『荒らす憎むべき者』(マタイ24章15節)でもあると知らなければいけない。この2つの存在は同一の人間である。というのは、どちらも、聖なる場所を愚かにも占拠すると言われているからである。すなわち、『不法の人』については『神の宮の中に座を設け』(Ⅱテサロニケ2章3節)と言われており、『荒らす憎むべき者』についても同じように『(荒らす憎むべき者が)聖なる所に立つのを見たならば』(マタイ24章15節)と言われている。これは、どちらも同じことを言ったものだと考えられる。よって、これでまず『不法の人』(Ⅱテサロニケ2章)=『荒らす憎むべき者』(マタイ24章)だということが分かったのではないかと思う。もしかしたらこの理解を疑う人がいるかもしれないから、念のためルターもⅡテサロニケ2章とマタイ24章で言われている邪悪な者は同一の人物だったと理解していたということを、補足として書いておきたい(『ルター著作集 第一集8』キリストの聖餐について p330:聖文舎)。このルターの理解は正しい理解であった。さて、キリストはマタイ24章においてダニエル書で預言されていた者のことを述べたのだが、この者には、ダニエル書によれば現われてから1290日の期間が用意されているという。ダニエル書にはこう書いてある。『常供のささげ物が除かれ、荒らす忌むべき者が据えられる時から1290日がある。』(ダニエル12章11節)「1290日」とは、すなわち約42ヶ月間である。この42ヶ月間が、黙示録13章の「獣」にも用意されていると、ヨハネは述べている(※黙示録13:5)。ヨハネがダニエル書の『荒らす憎むべき者』を黙示録13章の「獣」として書いたのは疑い得ない。だからこそ、どちらのほうでも同じ期間(1290日=42ヶ月)が書かれているのである。つまり、キリストとダニエルの述べた『荒らす憎むべき者』とは、黙示録13章の「獣」と同一の人物なのである。つい先ほど、『不法の人』とは「獣」であると説明された。要するに、聖書が教えているのは、『不法の人』=『獣』=『荒らす憎むべき者』だということである。さて、今までに述べた4つの説明から、Ⅱテサロニケの『不法の人』が、黙示録13章の「獣」であることがお分かりいただけたのではないかと思う。どちらからも傲慢な印象が感じられるのは、同一人物のことを言っているからに他ならない。次に我々は、この邪悪な者が本当にネロなのかどうか、ということを考察せねばならない。これは、さほど難しい問題ではない。何故なら、黙示録13:18の箇所を読み解くならば、この邪悪な者がネロだということが、すぐにも分かるからである。この箇所でヨハネは獣についてこう述べている。『ここに知恵がある。思慮ある者はその獣の数字を数えなさい。その数字は人間をさしているからである。その数字は666である。』ヨハネはここで、獣には「666」の数字があると書いているが、正にネロこそがそれなのである。一体どういうことであろうか。まずネロ・カエサルというギリシャ語「Νερων Καισαρ」を、ヘブル語に置き換える。そうしてから次に、―ヘブル語のアルファベットにはそれぞれ数字が割り当てられているのだが―(※④)、このヘブル語に置き換えられたネロの名におけるアルファベットを、一つ一つその割り当てられた数字に変換する。その変換された数字は50、200、6、50、100、60、200であるが、これらの数字を合計するとヨハネの述べた「666」となる(※⑤)。ヨハネが、『思慮ある者』に獣の数字を数えよと命じたのは、もっともなことであったと言える。これは確かに『ここに知恵がある。』と言うべきことであって、思慮がない者には絶対に分からないだろうからである。しかし、思慮があれば、このようにネロの名を数えて「666」を把握できるのである。これで、黙示録13章の「獣」がネロだと分かったのではないかと思う。であれば、Ⅱテサロニケ2章にでてくる『不法の人』(=黙示録13章の獣)もこのネロだったということになる。この『不法の人』と「獣」また『荒らす憎むべき者』がネロだったというのは、このような詳しい考察を抜きに考えても、「なるほど」と思える解釈ではないかと私には感じられる。何せこの皇帝の暴虐と凶暴性は、2千年経った今ですら、語られたり注目されたりするほどのものだったのであるから。話を元に戻したい。私はこの箇所の冒頭の部分で、『不法の人』が死ぬ時期を知れば、再臨の時期をかなり正確に特定できると述べた。何故なら、繰り返しになるが、この者は再臨によってこそ殺されるとパウロが述べているからである。今この者が「ネロ」だと我々は知ったが、ネロが死んだのは紀元68年6月9日であった。スエトニウスはこう記している。「ネロは32歳の年(※68年)に、かつてオクタウィアを殺害したその日(※6月9日)に亡くなった。」(『ローマ皇帝伝(下)』第6巻 ネロ p197:岩波文庫)つまり、パウロによる聖句に基づいて考えれば、この日にネロは再臨のキリストにより殺されたことになる。よって、紀元68年6月9日になるまでには、キリストが再臨されていたというのは間違いない。すなわち、この日になった時には、再臨が確実に起きていた。パウロは『不法の人』であるネロが再臨の輝きにより殺され滅ぼされると述べたのだから(Ⅱテサロニケ2:8)、ネロの死んだこの日以降になっても再臨が起きていないというのは、絶対に考えられないことである。(※⑥)
(※①)
パウロは、この御言葉を明らかにイザヤ11:4の『くちびるの息で悪者を殺す。』という預言に基づいて述べている。
[本文に戻る]
(※②)
次の聖句を見れば分かるように、黙示録において「竜」とはサタンを意味している。『こうして、この巨大な竜、すなわち、悪魔とか、サタンとか呼ばれて、全世界を惑わす、あの古い蛇は投げ落とされた。』(黙示録12章9節)
[本文に戻る]
(※③)
『また私は、獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。すると、獣は捕えられた。…そして、…硫黄の燃えている火の池に、生きたままで投げ込まれた。』(黙示録19章19~20節)
[本文に戻る]
(※④)
א 1
ב 2
ג 3
ד 4
ה 5
ו 6
ז 7
ח 8
ט 9
י 10
כ 20
ל 30
מ 40
נ 50
ס 60
ע 70
פ 80
צ 90
ק 100
ר 200
ש 300
ת 400
[本文に戻る]
(※⑤)
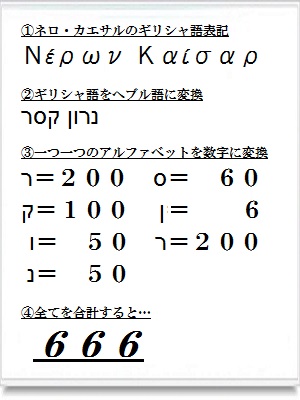
[本文に戻る]
(※⑥)
この註の箇所で、『不法の人』また「獣」また『荒らす憎むべき者』は、ネロ以外には考えられないということを書いておきたい。というのは、もしかしたら該当するのはネロ以外の人物ではないのか、と疑問に感じる方が必ずいるだろうからである。さて、まずネロ以外の候補として挙げられる者の筆頭はティトゥスであろう。彼は紀元70年にエルサレム神殿の至聖所の中に入ってローマの旗を打ち立てたのであるから、『神の宮の中に座を設け』(Ⅱテサロニケ2章3節)ると言われている不法の人であると思われる方も多いかもしれない。実際、私も以前はティトゥスこそが不法の人であると考えていた。しかし、彼は再臨が起きると言われた時期であるユダヤ戦争の時期には死んでいないし(彼が死んだのは81年である)、その名の中にも666は隠されていないと思われる。上で述べられたように、不法の人はユダヤ戦争の時期に再臨により殺されるのであって、またその名には666の数字が隠されているのだから、不法の人がティトゥスではないことは明らかである。同様の理由から、ネロにユダヤ鎮圧を命じられたウェスパシアヌスも不法の人ではありえない。また、この2人はエルサレムとその神殿を本心では破壊したいとは思っておらず―それはあまりにも素晴らしかったからである―、むしろ何度も何度もそれを救おうとしたのであって、仕方なく都と神殿の破壊を命じたに過ぎないということも考慮されるべきである。つまり、この2人は本質的に『荒らす憎むべき者』ではあり得ない。ティトゥスについて言えば、彼は次の言葉が示すように神殿を残したく願っていた。「たとえユダヤ人たちが聖所に登って戦いを仕かけてきても、予はこの男たちの代わりに生命なき物件に復讐するつもりはないし、どんなことがあってもこれほどの造営物を焼き払うつもりもない。それはローマ人の損害にもなる。聖所が残れば、帝国の飾りとなるからだ」(『ユダヤ戦記3』ⅤⅠ iv3:241 p060:ちくま学芸文庫)。それではドミティアヌスはどうか。彼は傲慢不遜にも「主にして神」(dominus et deus)と自称して(スエトニウス「ローマ皇帝伝」第8巻:13)、キリスト教徒を迫害したのだから、『自分こそ神であると宣言します。』(Ⅱテサロニケ2章3節)と言われている当の人物ではないかと思う人もいるであろう。しかし、彼もティトゥスと同様の理由から不法の人ではないとせねばならない。ガルバ、オト、ウッティリウスという3人の皇帝も違うと思われる。何故なら、このような「小物」に過ぎない皇帝のことをパウロやヨハネが述べたとは考えにくいからである。また不法の人には42ヶ月間活動する権威が与えられるが(※黙示録13:5)、この3人の在位期間はそれぞれ1年にも満たないから(ガルバ=7ヶ月6日、オト=5ヶ月1日、ウッティリウス=7ヶ月1日)、彼らは完全に候補から除外されるべきである。「臆病者で、自信のない人であった」(スエトニウス『ローマ皇帝伝(下)』第5巻 クラウディウス p120:岩波文庫)弱々しいクラウディウス帝は、問題外である。カリグラ(在位37―41)は、非常に凶悪であるという点で「不法の人」のイメージに合致しているが、時期的に早すぎるために除外されねばならない。カリグラの前の皇帝であるティベリウス(在位14―37)も同様である。また今まで教会がそう考えてきたように、不法の人がパウロの時代から数百年後また数千年後の時代に出てくる人物であると考えることもできない。宗教改革の時代には、ルターなどにより教皇こそ該当する人物だと思われていた。確かにルターは「聖パウロが、教皇を罪の人間、またはほろびの子(第二テサロニケ2・3)と名づけ、さらに、キリストが憎むべき者(マタイ24・15)、あらゆる罪とほろびの頭と名づけるのに、…」(『ルター著作集 第一集 4』大勅書に対するルターの弁明と根拠 第36 p126:聖文舎)と言っており、正に教皇こそパウロの語った邪悪な人物だと考えていた。昨今においてはヒトラーやEUの指導者がそうだと言われたこともある。このような推測はどれも問題外である。紀元1世紀に生きていたパウロは、Ⅱテサロニケ2章の箇所で『いま引きとめている者』(6節)が不法の人を『引きとめている』(7節)と述べているから、明らかに不法の人とはパウロと同時代の人物である。この引きとめている者とは当時の皇帝であったクラウディウス帝のことであって、彼が皇帝としてのネロの現れを引きとめているのであるが、もし不法の人が遥か未来の人物だとすれば、訳が分からなくなる。例えば世界政府の首長が「不法の人」だったとしよう。そうだとすると、その人物が、パウロの時代から、『いま引きとめている者』によって引きとめられていたというのであろうか。もしそうだとすると、その人物は今現在約2000歳だということになるが、こんなおかしなことを誰が真面目に考えるであろうか。またヒトラーが不法の人だったとして、ヒトラーがパウロの時代からある人物によって引きとめられていたというのであろうか。これも、あまりにも馬鹿らしい話である。パウロが当時の人間を念頭に置いているのは火を見るよりも明らかである。よって、「不法の人」が、パウロの時代に生きていた人たちが確認不可能な人物ではなかったことは明らかである。学識あるB・B・ウォーフィールドも、この邪悪な人物はパウロと同時代の人だったと述べている。このように考えると、やはり該当するのは「ネロ」以外には考えられないということが理解できるのではないかと思う。ちなみにオリゲネスは、『出エジプト記講話』(第6講話/1)で、この不法の人が「悪魔」だと言っているが、これはお話しにならない。誰がこのようなふざけた理解を受け入れられるであろうか。パウロはⅡテサロニケ2章の箇所で、明らかに不法の人がその名の通り「人」であって、しかもそれは『サタンの働きによ(り)』(9節)到来すると言っているのだから、どうしてこの存在が悪魔そのものであると言うのか私には理解できない。なお、知識と思考力があるうえ非常に鋭い人であれば、この『荒らす憎むべき者』とはあのシモンとヨアンネスのことではないかと疑問を持つかもしれない。というのも、この愚かな2人の不法者は神殿を荒らしに荒らし回ったからである。私はここでこの2人が『荒らす憎むべき者』ではないと言っておくが、これについては第4部の中で再び考察されることになるから、その時が来るまで待っていただきたい。ひとまず、ここでは『荒らす憎むべき者』がこの2人ではないとだけ知っていればそれで十分である。
[本文に戻る]
さて、ここで、たった今考察した「不法の人」と「反キリスト」における関係性をいくらか取り扱っておくことは、無益ではなかろう。やや横道に逸れる感はあるものの、しかし「不法の人」と関わりがあることであるから、聖徒たちの聖書に対する見識が更によくなるために、今ここでそのことを取り扱うことにしたい。流れを重視されたい方は、この挿入的な節を飛ばして読んでも何も問題はない。さて、今に至るまで教会は、この不法の人がすなわち「反キリスト」であると、ずっと語ってきた。今までどれだけ多くの教師たちが、語ってきたことであろうか。「不法の人こそ反キリストなのである」と。例えばスルピキウス・セウェルスは、不法の人が出てくるⅡテサロニケ2章の箇所を頭に置きつつ、反キリストの到来について次のように述べた。「多くの兄弟たちによれば、この頃東方でも、自分がヨハネであると自惚れる者が現れたと言われる。こうした偽りの預言者たちの出現を考えると、われわれは反キリストが今にも到来しようとしていると考えざるをえない。反キリストはすでにこれらの哀れな者たちに不法の秘密を働いているのである。」(『中世思想原典集成4 初期ラテン教父』聖マルティヌス伝 第24章(3) p916:平凡社)ここでは明らかに「不法の人」=「反キリスト」という構図が彼の脳内にあるのが分かる。ウェストミンスター信仰告白25:6の箇所でも、やはりローマ教皇こそが「反キリスト」である「不法の人」だと書かれている(※①)。そこでは反キリストである教皇こそ「キリストと神に召されたすべてのものとにそむき」と書いてあり、これは間違いなく不法の人について言われているⅡテサロニケ2:4に基づいた文章だから(※②)、やはりこの有名な信仰告白でも「不法の人」=「反キリスト」という構図が見られることが分かる。カルヴァンも例外ではなく、Ⅱテサロニケ2章の箇所を念頭に置いて「ついに反キリストを御口の息によって討ち滅ぼし」(『キリスト教綱要 改訳版 第3篇』第3篇 第20章 第42節 p409:新教出版社)と言っている。彼の頭の中には、明らかに「反キリスト=不法の人」という認識があった。ルターも同様に教皇こそⅡテサロニケ2章で書かれている「不法の人」であって、また「反キリスト」(『後期スコラ神学批判文書集』『第1章 ラトムスの序文に対する回答』 p113 知泉学術叢書6)であると考えていた。神学書を読み慣れた人であれば、他の多くの教師たちも、不法の人こそ反キリストであると述べていることを知っているであろう。この不法の人がネロであるということは、既に説明されているから、ここで再び説明することはしない。問題なのは、今まで多くの教師たちが、この不法の人こそが正に反キリストであると語ってきたことである。それらの教師たちの頭には、「不法の人」=「反キリスト」という固定観念が、強力に根づいてしまっている。それは、あたかも反キリストであるのは不法の人だけだと言わんばかりである。要するに、今まで教師たちは、反キリストであるのはⅡテサロニケ2章に出てくる不法の人「一人」だけであると聞く者たちが感じてしまうかのように語ってきた。オリゲネスも「ケルソス駁論」の2巻50節目の箇所で、「ダニエル書からも反キリストに関する預言を引用することができる」(『キリスト教教父著作集8 オリゲネス3 ケルソス駁論Ⅰ』p137:教文館)と反キリストがあたかも特定の個人に過ぎない存在だと誤認させるような言い方をしている。しかし、確かなところ、この「反キリスト」という言葉は特定の一者を指すために存在している言葉ではない。それは、不特定多数の存在を指す普遍的な言葉である。例えば、この言葉は「インド人」とか「金持ち」などといった多くの人を纏めて指すために存在している言葉と同じである。それなのに、今まで教会は、この言葉が特定の邪悪な個人だけを指すためだけに存在しているかのような言葉として使ってきた。上で引用した文章の中で、セウェルスが「われわれは反キリストが今にも到来しようとしていると考えざるをえない。」と言っていた通りである。グレゴリウスも、「私は確信をもって言うが、普遍的祭司と自称し、あるいはそう呼ばれることを願う者は誰であれ、己れを他の人の上に立てる思い上がりの故に、その高ぶりによって反キリストの先駆となる」(皇帝マウリキウス宛 「書簡」第7巻 第30)と言っているが、これは明らかに邪悪な特定の個人だけを頭に思い浮かばせるかのような言い方である。聖書はこの「反キリスト」という言葉について、どのように言っているのか。ヨハネは、この言葉について次のように言っている。『小さい者たちよ。今は終わりの時です。あなたがたが反キリストの来ることを聞いていたとおり、今や多くの反キリストが現われています。』(Ⅰヨハネ2章18節)『偽り者とは、イエスがキリストであることを否定する者でなくてだれでしょう。御父と御子を否認する者、それが反キリストです。』(同2章22節)『なぜお願いするかと言えば、人を惑わす者、すなわち、イエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大ぜい世に出て行ったからです。こういう者は惑わす者であり、反キリストです。』(Ⅱヨハネ7節)これらの聖句では難しいことは何も言われていない。つまり、反キリストとは、単に神の第二位格であられる御子が受肉して人となられたということを否定して退ける者たちのことだと、ヨハネは言っている。だから、もし子なる神が人として世に来られたことを否認しているのであれば、あの人も、この人も、どの人も例外なく歴とした反キリストなのである。具体的な例を見よう。ヒュームは無神論者であり、当然ながらキリストを否認していたから、彼は反キリストであった。イルミナティであったニーチェは、自分を手駒として使っていたユダヤ教徒たちの聖典である旧約聖書は首肯していたものの(『ツァラストゥスラかく語りき』を読めば一目瞭然である)、新約聖書は否定しており、当然ながらキリストを信じていなかった。だから彼も反キリストであった。実際、彼は『反キリスト』という生前には出版を避けたほどに有害な本を書いた。セックス・ピストルズのジョニー・ロットンは「アナーキー・イン・ザ・UK」という曲で、「アイ アム ア アンチキリスト」と軽快に歌っている。私は彼がキリスト教徒であるかどうか知らない。だが、このように歌うぐらいなのだから、恐らく彼も反キリストだったのであろう。エクストリームメタルの始祖的存在であるヴェノムというバンドは、「アンチキリスト」という名前の曲の中で「アンチキリスト」と大声で歌っている(※収録されているアルバムは「メタルブラック」)。このバンドのヴォーカリストであるクロノスは「単なるジョークだよ」と言っているが、このバンドの曲やイメージから察するに、彼はアンチキリストに違いないと思われる。キリスト教徒の多いイギリスにおいて、サタンの子供が「ジョークだよ」と言って聖なる者たちからの非難をかわそうとするのは当然である。もしアンチキリストでなければ、どうしてサタン的な曲を作ったり、邪悪なイメージを出すことに耐えられるのであろうか。もしヴェノムのメンバーがキリスト教徒であるとすれば、非常に驚きである。野良仕事をしている無名の農夫も、キリストを否んでいれば立派な反キリストである。このように大きい者から小さい者まで、世界は反キリストで満ちているのである。ヨハネも紀元1世紀の時点で既に『多くの反キリストが現われています。』と証言している。だから今まで教会が、「反キリスト」という言葉が不法の人だけを指す言葉であるかのように語ってきたのは、とんでもない誤りであった。確かに、Ⅱテサロニケ2章に出てくる不法の人も「反キリスト」であることには間違いない。しかし、この不法の人も、数多く存在している反キリストの一人に過ぎなかった。よって、今まで教会は誤解を抱かせるような使い方でこの「反キリスト」という言葉を使ってきたことになる。もし不法の人が反キリストであると言いたいのであれば、教師たちは次のような思慮深い言い方をすべきであった。「不法の人は間違いなく反キリストである。しかし、反キリストは他にも多く存在しているのであって、不法の人一者だけだというのではない。彼は反キリストの一人に過ぎないのだ。何故なら、反キリストとは、ヨハネも言っているように、キリストを告白せずに否認するあらゆる人間を指す言葉なのだから。」そもそも、不特定多数の存在を指す反キリストという言葉を不法の人という特定の個人に深く結び付けようとすること自体が、どうかしている。反キリストという言葉の意味を厳密に認識しないからこそ、このような誤りが犯された。古代にいた教師の誰かが、他の教師に先駆けてまずこの反キリストという言葉を不法の人に強力に結び付けて、「不法の人こそ反キリストだ。これからその反キリストが現われるのだ。今はまだ現われていないがその現われの時は迫っている。」などと誤解を招くような言い方をしたのであろう。そうして後、その言い方が他の多くの教師たちにも使われるようになり今日に至っている。もし今まで教師たちがこの反キリストという言葉を厳密に認識していたとすれば、私のように反キリストと不法の人を特定的に結びつけるようなことはしなかったはずである。実際、私は不法の人だけが反キリストであるかのように思えてしまうような言い方をしたことは今までに一度もないし、これからもそのような誤解を招く言い方はしないはずである。今や、誰も反キリストという言葉の釈義をしっかりとすることさえしていない。誰も彼も、ただ盲目的に「不法の人こそ反キリストなのだ。」などと思っているだけである。もししっかりと釈義をしていたら、今までおかしな言い方がされていたことにすぐにも気付いたはずである。このことを考えると、人間の持つ帯同性、慣れ、風習、慣用、常識といったものは実に恐ろしいと言わねばならない。多くの人が間違った行為をしていたとしても、それが間違いであることに誰も気付かなくなってしまうのである。超然とした見方をする者が鋭い指摘をして人々に気付かせない限り、そのようなおかしい状況が改善されることはない。それゆえ聖徒たちは、もう反キリストが不法の人だけを指しているかのように感じられる言い方をすべきではない。私は、聖徒たちに対して、不法の人がネロであるという理解を持つと共に、反キリストという言葉の意味を聖書からしっかりと認識するように要請したい。私が「不法の人」と「反キリスト」という言葉の関係性について語りたかったことは以上である。というわけで、一時的に話がやや横道に逸れてしまったから、再び話の内容を本線へと戻すことにしたい。
(※①)
「イエス・キリストの外に教会の首はなく、ローマの教皇もいかなる意味においても、その首ではあり得ず、彼こそキリストと神に召されたすべてのものとにそむき、教会において己れを高うする非キリストであり、不法の人、滅亡の子である。」(『新教セミナーブック4 信条集 後篇』p205:新教出版社)
[本文に戻る]
(※②)
『彼は、すべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。』
[本文に戻る]
既になされた説明から、紀元68年6月9日というネロの死んだ日には、確実に再臨が起きていたことが確定したが、ここで問題が生じる。その問題とは、こういうものである。すなわち、キリストが再臨されたのは紀元68年6月9日なのであろうか、それともこの日よりもっと前の日に再臨があり、この日はただ空中におられる既に再臨されたキリストによってネロが殺された日に過ぎないものなのか、という問題である。この日に再臨があったということであれば、何も説明する必要はない。しかし、この日よりも前にキリストが再臨されていたというのは、いくらか説明が必要であろう。これは、つまり、ネロの命日以前にキリストが再臨しており、ネロの命日になるまでずっと空中に留まっていたということである。この場合、キリストは6月9日よりも前からずっと空中におられたが、ネロの命日が訪れた時にネロを死なせられた、ということになる。この問題を解決するためには、黙示録の19:11~20:6の箇所を見ればよい。この箇所は、19:11~21までがキリストの再臨とネロの滅亡を、20:1~6までがキリスト者における第一の復活を、書き記している。この箇所の内容における順序を示せば、①再臨、②ネロの滅亡、③第一の復活、ということになる。パウロによる御言葉によれば、再臨(①)から第一の復活(③)までの期間は一日以内、つまり同日中に起きたことが分かる。パウロの言った言葉を見てみよう。まず彼はある箇所でこう言っている。『主は、号令と、御使いのかしらの声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者が、まず初めによみがえり、次に、生き残っている私たちが、たちまち彼らといっしょに雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。』(Ⅰテサロニケ4章16~17節)ここでパウロは、『神のラッパの響きのうちに』キリストが再臨されると、『キリストにある死者が、まず初めによみがえり』と述べている。つまり、黙示録19:11~21に書いてある再臨が起こると、それから後に黙示録20:1~6に書いてある「第一の復活」が起こるということである。パウロは別の箇所で、ラッパと共に起こる再臨(つまり①)と復活の出来事(つまり③)とは、ほぼ同時に起こると書いている。それはⅠコリント15:51~52の箇所である。パウロはここで当時の聖徒たちに次のように述べている。『聞きなさい。私はあなたがたに奥義を告げましょう。私たちはみなが眠ってしまうのではなく、みな変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち、一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。』確かにパウロは、ここで再臨のラッパが鳴ると『たちまち、一瞬のうちに』復活が起きると断言している。つい先ほど、まず再臨が起き(①)、次にネロが殺され(②)、そうしてから復活が起きる(③)ということを示した。そしてたった今、再臨が起きたら(①)即座に第一の復活が起きる(③)ということを、パウロの聖句から確認した。この2つの出来事(①と③)がほとんど同時に起きるのであれば、普通に考えれば誰でも分かるように、この2つの出来事にはさまれた出来事であるネロの死も(つまり②)、この2つの出来事とほとんど同時に起きるということになる。我々が黙示録19:11~20:6の箇所を実際に起きる順序通りに書かれたものだと理解するのであれば、私が今述べたように考えねばならない。①と③がほぼ同時に起きたのに、その中間に位置する②も同時に起きていないと考えることはできない。つまり、再臨もネロの死も第一の復活も、同日中に起きることが分かる。それゆえ、ネロの死んだその日に再臨があったことになるのだから、再臨の起きた日は紀元68年6月9日だったことになる。この日よりも前の日にキリストが再臨して空中にずっと留まっていたという考えは、以上の説明から斥けられねばならない。
さて、ある千年王国論者たちは、再臨の起きた年が「紀元70年」だと主張しているが、今までの説明から分かるように、この主張はかなり良い線にまでは行っているもののいくらか正確さに欠けていると言わねばならない。我々は、再臨の起きた年を、これまで述べられたように「紀元68年」だとせねばならない。彼らは、再臨の正確な時期を厳密に考察するという恵みを神から受けていないと思われる。もし恵みを受けていれば、神から与えられたその恵みにより、緻密な考察をするよう導かれていたことであろう。私の場合、神の恵みにより、「再臨の起きた日をどうか教えてください。この日なのでしょうか。どうか正しく知ることができますように。」と祈った。そうしたら、私の思考がこの事柄のために動かされ、今述べたように再臨の起きた年と日とを知るに至らされたのである。神は、聖書のことを知りたい悟りたいという私の真摯な願いを、大きな恵みにより叶えてくださった。この神に私は感謝を捧げる。読者の中で、本当に再臨の起きた年を知りたいと思う者、またそのことを信じ受け入れたいと願う者は、私のように具体的に、しかも心から祈るべきであろう。そうすれば恵みの主が豊かに私たちに働きかけてくださるであろう。
しかし、ネロが再臨のキリストにより死に至らされたといっても、一体どのようにして殺されたのであろうか。確かにパウロはネロが再臨のキリストにより殺されると断言しているが、書き残された記録を見ると、ネロは剣で自殺することにより死んでいる。すなわち、元老院から「国家の敵」と呼ばれて逃げている際に、持っていた剣で自殺を試みたが死にきれなかったので、解放奴隷に剣で止めを刺すようにさせた。このような歴史の記録を見ると、はたして本当にネロが再臨のキリストにより滅ぼされたのかどうか、疑問に思われる方もいるに違いないと私は思う。しかし、ネロが再臨されたキリストにより死に至らされたということは疑えない。実に、ネロのこの死に方こそが、再臨のキリストによる殺し方だったのである。一体どういうことなのか説明したい。聖書の多くの箇所で言われているように、キリストは御言葉という剣(※①)を使われる方であり(※②)、この御言葉を振り回すことで戦ったり悪しき人間を死に至らせたりする方である(※③)。紀元68年6月9日に実際に再臨されたキリストは、この日に、逃げ回っていたネロに対してご自身の口から出ている御言葉の剣を強烈に突き刺された。その御言葉の剣とは次のようなものである。『人の血を流す者は、人によって、血を流される。』(創世記9章6節)『かりそめにも人を打ち殺す者は、必ず殺される。』(レビ記24章17節)『剣を取る者はみな剣で滅びます。』(マタイ26章52節)『剣で殺す者は、自分も剣で殺されなければならない。』(黙示録13章10節)この日に今挙げた御言葉をキリストがネロに真っ直ぐ突き刺したのである。つまり、このような御言葉がネロに裁きとして適用された。私は読者の方が霊の人であることを望んでいるが、御言葉を突き刺すとは、霊的に考えれば、すなわち御言葉が裁きとして適用されるということに他ならない。このために、今までに多くの人を剣で殺してきたネロは、裁きとして、御言葉で言われているように自分も剣で死ぬことになったわけである。確かに『人の血を流す者は、人によって、血を流される。』と書いてあるように、多くの人の血を流したネロは解放奴隷により血を流された。確かに『かりそめにも人を打ち殺す者は、必ず殺される。』と書いてあるように、かりそめにも人を殺したネロは裁きとして死に至らされた。確かに『剣を取る者はみな剣で滅びます。』と書いてあるように、剣を取って人殺しをしたネロは自分と解放奴隷の持つ剣で滅ぼされた。確かに『剣で殺す者は、自分も剣で殺されなければならない。』と書いてあるように、剣で何度も人を殺したネロは自分も剣で殺されることになった(※④)。それゆえ、このように考えるならば、本当にキリストは再臨された際に御言葉の剣によりネロを滅ぼされたことが分かる。もう一度言うが、御言葉の剣を刺して殺すということは、つまり御言葉を裁きとして適用させて死なせるということである。ネロは、そのようにしてキリストに殺された。まさか、実際にキリストが「御言葉」という文字の書いてある剣を口にくわえており、その口にくわえた剣を誰かに突き刺して殺される、というように想像する人はいないであろう。このように考えるのは、実に滑稽であり、肉的な理解をすることであり、キリストを愚弄することである。我々は聖書を霊的に解釈すべきであるから、自分が霊の人だと思う方は、私が今述べたような考え方をしなければいけない。私の推測では、恐らくローマ大火の罪をキリスト者になすりつけた際に、ネロは捕えられたキリスト者から、上に挙げた御言葉のどれかを明瞭に聞かされたのではないかと思う。「ネロよ。あなたは今まで多くの人を剣で殺したが、あなたもいずれきっとそのようにされるであろう。『人の血を流す者は、人によって、血を流される。』と神が言っておられる。」などと。これは十分に考えられる話である。そして、このようなことを聞かされたネロの脳裏に、御言葉が忘れ難いほど強く刻まれた。そうして後、ネロが死ぬ直前に脳内にこの御言葉が鳴り響き、それからネロが剣で死ぬことになった。その御言葉が鳴り響いたのは、再臨されたキリストが御言葉の剣をネロに対して振り回したからであった。とはいっても、実際にネロの脳にこの御言葉が鳴り響いていたのかどうかは分からない。これはあくまでも推測である。しかし、ネロの脳で御言葉が鳴り響いたとしてもそうではなかったとしても、再臨のキリストが御言葉の剣で突き刺す、つまり御言葉を裁きとして適用(執行と言ってもよいであろう)させることにより、ネロを滅ぼされたのは間違いない。このようにしてネロは再臨されたキリストの御言葉により殺されたのである。これは、ダニエル書に記されているネロ(※ダニエル書においては『荒らす忌むべき者』)の死に関する記述とも何ら矛盾していない(※⑤)。
(※①)
パウロが書いているように、聖書において御言葉とは霊的な剣である。『また御霊の与える剣である、神のことばを受け取りなさい。』(エペソ6章17節)
[本文に戻る]
(※②)
ヨハネはキリストの口から御言葉という剣が出ていると書いている。『それらの燭台の真中には、…人の子のような方が見えた。…また、…口からは鋭い両刃の剣が出ており、…』(黙示録1章13、16節)また黙示録の中では、キリストが『鋭い、両刃の剣を持つ方』(2章12節)とも言われている。
[本文に戻る]
(※③)
黙示録2:16におけるキリストの御言葉。『だから、悔い改めなさい。もしそうしないなら、わたしは、すぐにあなたのところに行き、わたしの剣をもって彼らと戦おう。』黙示録19:15。『この方の口からは諸国の民を打つために、鋭い剣が出ていた。』黙示録19:21。『残りの者たちも、馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が、彼らの肉を飽きるほどに食べた。』イザヤ66:16。『実に、主は…その剣ですべての肉なる者をさばく。主に刺し殺される者は多い。』
[本文に戻る]
(※④)
この黙示録の御言葉は、恐らくネロの死に方を預言したものではないかと思われる。というのは、ネロについての説明が一通りされた最後の部分で、このように書かれているからである。実際、これはネロのことだと理解することが十分に可能であるし、ネロは本当にこの御言葉の通りになったのである。
[本文に戻る]
(※⑤)
このダニエル書によると、ネロには『さばきが行なわれ、彼の主権は奪われて、彼は永久に絶やされ、滅ぼされる。』(ダニエル7章26節)が、確かにネロにはキリストが裁きを行なわれ、その皇帝としての主権はガルバへと移され、ネロはその時に永遠に地から消え果て、滅ぼされることになったのである。またネロは『人手によらずに、彼は砕かれる。』(ダニエル8章25節)が、確かにネロは解放奴隷という他者の力を借りて死にはしたものの、その死は自殺の域を越え出るものではないから、人手によらずに砕かれたといえよう。またネロについては、『ついに彼の終わりが来て、彼を助ける者はひとりもない。』(ダニエル11章45節)とも書かれている。確かにネロが死ぬ時、彼を助ける者はまったくいなかった。このように見ると、再臨により自殺という裁きを受けたネロの死に様は、ダニエル書のネロに関する記述とよく調和することが分かるであろう。
[本文に戻る]
ここまで再臨の起きた正確な年を聖書から導き出し論証したが、再臨が紀元68年6月9日、すなわち紀元1世紀に起きたということは、偽典によっても証明できる。確かなところ、本来であれば、再臨という神聖な教義を正典ではなく偽典によって証明するというのは明らかに違法である。何故なら、教会で教えられる事柄は、正典によってこそ証明されるべきものだからである。もし正典に加えて偽典を信仰の拠り所とする教会があったとすれば、それは真の教会とは言い難い。真の教会であれば、ルターのように「聖書のみ」という姿勢を持っているからである。私も、当然ながら偽典を信仰の規範とするつもりは毛頭ない。そういうことは正しくない姿勢である。しかし、私が今しようとしているのは、既に正典から証明された事柄を、それが既に証明済みであるという確固な前提に基づいて、今度は偽典によって論じるということである。つまり、既に正典から証明済みである事柄を、偽典によって言わば追認するということである。こうするのであれば、偽典からも論じたとしても問題はないはずである。何故なら、私は偽典を規範としているのでもないし、まず第一に偽典から証明しようとしているのでもないからである。繰り返し言うが、私はそのようなことをするつもりはまったくない。私が今しようとしているのは、聖書から論じられた証明済みであることを、同じことを述べている偽典によって補強し、更に論証の力を増し加えようとしているに過ぎない。さて、再臨が紀元1世紀に起きたと示唆している偽典は、2つある。それは「アダムとエバの生涯」と「エチオピア語エノク書」である。一つずつ見ていくことにしたい。まずは「アダムとエバの生涯」という偽典である。この作品の中で、アダムは病気で死にかかっている。そして、その時、天使ミカエルが現われて、エデンにある命の木からアダムのために油を取りに行こうとしていたセツに対してこう言っている。「わたしはそなたに言う。5500年が満たされた終わりの日々でなければ、どんなことをしてもその(樹)から受け取ることはできないのである。その時になれば、きわめて愛すべき神の子キリストが、アダムの身体を復活させ、また彼とともに死者たちの身体を復活させるために、地上にやって来るであろう。」(『聖書外典偽典 別巻 補遺Ⅰ』アダムとエバの生涯42 p228 教文館)世界創世の年についての見解は人によってもかなり違うが(※①)、前5500年だとすることもできる。実際、世界創世の年をヨセフスは前5555年、ヘイルスは前5402年だったとしている。仮に世界が造られた年を前5500年だとすれば、再臨が起こるのは、この偽典によれば、世界が造られた年から5500年後の紀元1世紀だということになる。これは、聖書の教えと合致している。であれば、聖書の教えている再臨の起きた年は、この偽典によっても証明されることになる。次は「エチオピア語エノク書」である。この偽典は、ユダの引用したエノクの預言(ユダ14)が収められている文書である。この文書には、大洪水の時に罪を犯した悪しき御使いたちが審判の日まで暗やみの牢獄に繋がれる期間が、「70世代」だと言われている(※②)。1世代とは約30年であるから、70世代とは約2100年である。ノアの大洪水が起きたのは、いつか。それは、人や算出方法によってもいくらかの違いはあるが、だいたい前2100年頃である。終わりの審判が行なわれる日とは、キリストの再臨が起こる日に他ならない。つまり、この文書は、大洪水が起きてから2100年後に終わりの審判を伴う再臨が起こると言っている。その時、大洪水の元凶となったあの御使いたちが、裁かれることになった。これも「アダムとエバの生涯」と同じで聖書が教えている再臨の起きた年と異なることを言っているのではない。よって、聖書が教えている再臨の起きた年は、このエノク書からも論証できることになる。このエノク書からはあのユダさえも正典に引用しているほどなのだから、たとえ偽典であるとは言っても、その論証力はかなりのものではないかと私は思う。このように、この2つの偽典も、聖書が教えている通りのこと、すなわち再臨は紀元1世紀に起こるのだということを言っている。確かに、これは言うまでもないことだが、偽典自体として考えれば、そこには何の証明力も存在していない。それは正典ではなく信仰の規範たり得ないからである。しかし、正典の確かな教えを事後的に追認するという形であれば、偽典もそれなりの証明力を持つことになる。それは、聖書の教えていることをアウグスティヌスやその他の教父たち、また初代教会の長老たちの言った言葉によって事後的に追認するのと同じである。そのようなことであれば、今までに多くの人たちがしてきた。誤解を避けるために再び言うが、私は、聖書を隅に追いやり、まず偽典を基準として再臨の事柄について証明するということであれば、絶対にしていなかった。私は今、聖書で証明済みのことを更に証明するために、偽典を持ち出したに過ぎない。というわけで、再臨が紀元1世紀に起きたという聖書の教えは、このように正典に加えて偽典からも証明できるものなのだということを、読者の方は知っておいていただきたい。
(※①)
今までに持たれてきた見解を知りたい人は、この作品の【資料】を参照されたい。
[本文に戻る]
(※②)
この文書では、神がミカエルに対し、シェミハザをはじめとした堕落した天使たち―彼らは人間の女たちと交わり堕落の原因となった巨人たちを産んだとされている:創世記6章1~4節―が暗やみの獄に繋がれている期間が70世代だということを言っている。次のように書かれている通りである。「神はミカエルに言われた。「シェミハザとその同輩で女たちとぐるになり、ありとあらゆるけがらわしいことをして自堕落な生活をした者たちにふれよ。彼らの子孫が斬りむすんで果て、愛児の滅亡を見たら、彼らを70世代、彼らの審判と終末の日、永遠の審判が終了するまで、大地の丘の下につないでおけ。その日彼らは拷問の火の下をくぐらされ、永久に獄舎に閉じこめられるであろう。…」(『聖書外典偽典4 旧約偽典Ⅱ』エチオピア語エノク書 第10章11~13節 p180:教文館)
[本文に戻る]
さて、以上の論述から、やはり再臨は初代教会の聖徒たちが生きている間に起こると確言したパウロの御言葉は、真実であったことがよく分かる。その御言葉とはⅠテサロニケ4:15のことである。この箇所は本作品のキーとなる、あまりにも重要な箇所だから、ぜひ聖徒たちは本作品を読むにあたり、この箇所を記憶しておいてもらいたいものである。パウロがⅠテサロニケ4:15の箇所で、自分たちが『生き残っている』間に、『主が再び来られる』と確言したことを、再び考察してみるとどうであろうか。パウロがこの第一の手紙を書いたのは、クラウディウス帝(41年1月24日―54年10月13日)の治世下においてであった。この手紙を受けた当時におけるテサロニケ教会にいるある聖徒の年齢が、40歳だったとしよう。上で見たように再臨が起きたのは紀元68年6月9日であった。そうるすと、パウロから手紙が送られた当時において40歳だった聖徒は、再臨が起きる時には、だいたい55~70歳の間だったことになる。55~70歳ぐらいであれば、平均寿命が短かった紀元1世紀であったとしても、十分に再臨が起こるまで生き延びることが可能である。手紙が送られた時に40歳だった人でさえ再臨の時まで生きていることが出来るのだから、40歳以下の人であれば、尚更のこと再臨の時まで生きていることが出来たはずである。例えば手紙が送られた時に20歳だった人であれば、まず間違いなく再臨の起きる紀元68年まで生きていたであろう。このように、再臨の起きた時が紀元68年6月9日だと分かると、本当にパウロの御言葉は真実なことを言っていたのであったということも同時に分かるようになる。聖徒たちは、私が述べたようにパウロの御言葉を解釈すべきである。何故なら、これこそが正しい解釈だからである。今の聖徒たちは、再臨はパウロの仲間たちが『生き残っている』間に起きたとは考えておらず、2000年経過しても未だに起きていないなどと平気で言っている。私は忠告するが、これでは永遠にパウロの御言葉を正しく理解できない。何故なら、パウロの時代に再臨が起きたと信じてこそ、この御言葉を正しく捉えることが可能になるからだ。今の聖徒たちは、パウロの言っている通りに御言葉を理解していないので、その当然の罰として、パウロが言っていることを正しく捉えることが出来ていないでいるが、それは自業自得であるから仕方がないと言えば仕方がないかもしれない。今の聖徒たちは、私が色々と再臨のことについて言っても耳を傾けようとはしないのだから。ちなみに、パウロが言った『主が再び来られる時まで生き残っている私たちが』という言葉は、パウロ自身には実現されなかった。すなわち、パウロは再臨が起こるまで『生き残っている』ことが出来なかった。何故なら、パウロはどうやらネロの大迫害(64~68)の際に殉教したようだからである。しかし、そうだったとしても何も問題はない。何故なら、パウロが「我々は主の再臨の時まで生きているであろう、テサロニケ人たちよ。」と言ったのは、あくまでも全体的なことであって、パウロ自身について特定的に言われたことではないからである。もしこれがパウロ自身について言われたことだとすれば大いに問題だったが、これはテサロニケ教会の聖徒たち全体について言われたことだから、パウロ自身は自分の言ったことから除外されてしまったとしても別に支障はなかった。
第4章 本当にすぐに起きた再臨
再臨が68年に起きたのだから、一体どうして聖書記者たちが速やかに再臨が起きると繰り返し述べたのか、もう読者にはお分かりであろう。すなわち、当時の聖徒たちにとって本当にすぐに再臨が起こるからこそ、速やかにキリストが来られると何度も言われたのである。ここでは、その例を3つ挙げたいと思う。一つ目。パウロはピリピ人たちに対して次のように言った。『あなたがたの寛容な心を、すべての人に知らせなさい。主は近いのです。』(ピリピ4章5節)これは、主の再臨が近いのだから、キリスト者の寛容さを示すことで多くの人が救いに引き寄せられるようにと、また再臨の際には平安をもってキリストの御前に立てるような精神を持っているべきだということであろう。パウロがこの手紙を書いた時期を、厳密な検証などせず、伝承で言われている通りに61~62年だったとしよう。そうすると、6~7年後に再臨があったことになるから、本当に主の再臨が近かったということが分かる。(※私はここでパウロの言っていることが、詩篇145:18、119:151、34:18などの箇所で言われているように神の親近性についてだと捉える解釈があるのを知っているが、ここではそうではなく再臨の切迫性についてだと捉えていることに留意してほしい。これを神の親近性についてだと捉える人が教会の中には多いが、これをたとえ再臨の切迫性についてだと捉えても意味上の問題は何も生じない。)二つ目。ヤコブ書には次のように書かれている。『あなたがたも耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。』(5章8節)この巻を記したヤコブがどのヤコブかという検証はここでは隅に置いておき、これが仮に50年代に書かれたとする。そうすると、紀元68年にキリストが来られたのだから、20年以内に再臨があったことになり、本当に当時の聖徒たちにとって再臨が近かったことが分かる。三つ目。黙示録の中でキリストご自身が次のように、『アジヤにある7つの教会』(1章4節)にいる聖徒たちに言っておられる。『見よ。わたしはすぐに来る。』(22章7節)ヨハネが黙示録を書いたのは、カリグラ帝(37―41)の時であったから(※①)、再臨が起きるのはヨハネが黙示録を書いてから約30年後である。これも先の2つの例と同様で、本当にキリストはすぐに来られたということが分かるであろう。もし再臨が近くなかったのであれば、再臨が近いなどとは言われていなかったに違いない。しかし、ここで6~7年は問題ないとしても、20年や30年という期間は果たして「すぐに」と言えるのかという疑問を持つ方がおられるであろう。人によっても感覚が違うから、もしかしたら6~7年でも「すぐに」と言われることに疑問を抱く人も、もしかしたらいるかもしれない。私の見解としては、キリストの再臨までの期間が30年であれば「すぐに」と言われたとしても、まったく許容範囲内であると思われる。それが大きな出来事であればあるほど、日常では長いと思われる年数でも、短いとされる傾向がある。例えば、新しい服を買う場合、40年後まで待たなければいけないと言われたら、誰でも長いと感じるであろう。何故なら、服を買うという行為は、それほど大きな出来事ではないからである。しかし、これから世界が40年後にビッグクランチに転じると聞かされたら、どうであろうか。40年もしたら宇宙が収縮に転じ、全ての天体が宇宙の中心に向かって集められることになるのだから、誰でも「そんなに早く起こるのか」と思うはずである。これはビッグクランチという事象があまりにも大きな出来事だからである。我々が今考究している再臨はといえば、こんなにも偉大で注目すべき大きな出来事は他にないとさえ言えるほどの出来事である。この再臨の時には聖書が述べるように世界が改まるのだから(※②)、これはビッグクランチと同じぐらいか、もしくはそれ以上に重大な出来事であると言えよう。であれば、そのような重要極まりない出来事が30年後に起こるのだから、それは「すぐに」と言うべき期間である。30年では長過ぎると思われる方は、恐らく再臨という出来事の偉大性がよく分かっていないのではないか。つまり、再臨という出来事が服を買うぐらいの小さな出来事であると認識しているからこそ、30年という期間が長過ぎると思うのであろう。これが100年後とか1000年後とかであれば話はまだ分かるが、30年ぐらいであれば「すぐに」と言われるべき期間だとすべきである。何よりも、神の御霊が当時において再臨が起きるまでは近いのだ、と言っておられることを我々は忘れてはいけない。もしキリストの再臨が近いと言われているにもかかわらず「近くない」または「長過ぎる」と言うのであれば、その人は御霊に言い逆らうことになってしまう。
(※①)
このことについては後の箇所(第3部2章)で語られる。
[本文に戻る]
(※②)
既に我々が知っているように再臨の時にはキリストが栄光の座に着かれるが、その時こそ正に世が改まる時であるとキリストは述べておられる。それは、『世が改まって人の子が栄光の座に着く時、…』(マタイ19章28節)と書いてある通りである。次の御言葉からも、キリストが天から再臨される時こそ正に世界更新の時であるということが分かる。『このイエスは、神が昔から、聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られた、あの万物の改まる時まで、天にとどまっていなければなりません。』(使徒行伝3章21節)この万物の改まりについて今は述べることをしないが、もし主の御心であれば、後ほど語られることになるであろう。
[本文に戻る]
このようにキリストの再臨は本当にすぐに起きたわけだが、今に至るまでキリスト教では、再臨がすぐには起きていないと思うどころか、いまだに起きていないとすら信じられ続けてきた。これは誠に嘆かわしいことであったと言わねばならない。何故なら、教会は今まで聖書記者たちをおかしなことを言う者に仕立てあげてきたからである。もし再臨がいまだに起きていないとすれば、聖書記者たちは2千年経過しても起こらない再臨について「それはすぐにも起こることなのだ。」と述べたことになる。2千年経過しても起こらない出来事について「すぐに」とか「近い」などと語るのは、少し変わった人以外にはいないと思われる。再臨について誤解しているキリスト者であっても、もし自分の周りに、数千年経過しても起きないことを「すぐに起こる」などと述べている人がいたら、異常な人物だと認識するはずである。実にこのような認識を、今に至るまで教会は聖書記者たちに持って来たのである。いや、そういうことはない、と多くの人が言うかもしれない。確かにそういうことをしている意識はまったくないかもしれないが、無意識的に、また事実上、ほとんど全ての兄弟はそのようにしてしまっているのである。もし長い期間が経過しても起きないことをすぐに起きると言う人を異常だと思うのであれば、どうして聖書記者たちのことは異常と思わないのか。もし前者のほうが異常だとすれば、後者のほうも異常だということにならないであろうか。また、もし聖書記者たちが異常であると思わないのであれば、長い期間が経過しても起きないことをすぐに起きると言う人をも異常であると思うべきではない。前者が異常でないのであれば、後者も異常ではないからである。もし再臨が当時においてすぐに起きたと信じないというのであれば、その人は、前者と後者のどちらをも異常とするか、または異常ではないとするか、一貫性を持たせるべきであろう。どちらか一方だけを正しい、または異常であるとするのは、論理的な一貫性に欠けており、理に適っていない。いずれにせよ、今述べられたことからも分かるように、現今の教会が持つ再臨に対する理解は、まったく未熟な状態にある。聖書が再臨は近いと教えており、実際に再臨が本当にすぐにも起きたのに、それを信じておらず、それどころか聖書記者たちを異常なことを言う者に事実上仕立てあげ、しかもそのように仕立てあげていることに気付いてさえいない。ぜひ、聖書記者たちを「とんでもないことを言った者」に仕立て上げるのは、もう止めていただきたいものである。
第5章 宣教命令が成就してから起きる再臨
マタイ24章の箇所で、キリストは、世界中に福音の宣教がなされない限りは再臨が起こることはないと示しておられる。その箇所とは、マタイ24:14であり、そこにはこう書かれてある。『この御国の福音は全世界に宣べ伝えられて、すべての国民にあかしされ、それから、終わりの日が来ます。』ここで言われている『終わりの日』とは、他の箇所では『かの日』(Ⅱテモテ4章8節)とか『主の日』(Ⅱテサロニケ2章3節)とか『報復の日』(ルカ21章22節)とか『その日』(Ⅰコリント3章13節)などと書かれており(※①)、つまり再臨が起きるある特定の1日のことを指している(※②)。だから、この日を『再臨の日』と言ったとしても誤りではない。要するに、上に挙げたマタイ24:14の箇所で、キリストは宣教命令(※③)が成就してから再臨が起こるのだと言っておられる。つまり、こういうことになる。もし宣教命令が成就したのであれば必ず再臨が起こり、もし再臨が起きたのであれば、その時には宣教命令は既に成就されている。宣教が世界中になされたのに再臨が起きないことは絶対にないし、再臨が起きたにもかかわらず、まだ宣教が世界中になされていないということも絶対にない。キリストの御言葉によれば、この「再臨」と「宣教命令の成就」という2つの事象はセットであり、切り離して考えることができないものなのである。
(※①)
旧約聖書の中でも『終わりの日』(イザヤ2章2節)、『万軍のヤハウェの日』(イザヤ2章12節)、『仇に復讐する復讐の日』(エレミヤ46章10節)、『わたしが事を行なう日』(マラキ4章3節)、『ヤハウェの大いなる恐ろしい日』(マラキ4章5節)などと書かれている。
[本文に戻る]
(※②)
これは「1日」すなわち24時間をその長さとする時間の区切りとしか理解できないと私はここで言っておきたい。何故なら、この日について言及されている箇所は、どれも1日の間に起こることしか書かれていないからである。単数形で言われていることからも、これは言える。これがもし2日以上であれば「日々」などと複数形で言われていただろうし、もっと長い期間であれば「月々」とか「年」などと言われていたに違いない。具体的には、これは第3章で説明した起源68年6月9日のことである。
[本文に戻る]
(※③)
『全世界に出て行き、すべての造られた者に、福音を宣べ伝えなさい。』(マルコ16章15節)
『それゆえ、あなたがたは行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。』(マタイ28章19節)
[本文に戻る]
ではどうなのか。私は再臨が紀元1世紀に既に起きたと説明したが、それはつまり、既に宣教命令も成就したということを意味するのか。すなわち、当時において既に世界中に宣教がなされたとでもいうのか。これは正にその通りである。当時において既に宣教命令は完全に成就していた。「そんなことが本当にあったのだろうか…。」と思われる方もいるだろうが、これは私の自分勝手な理解ではなく、聖書がそのように教えているのである。例えば、パウロはコロサイ人にこう書いている。『この福音は、あなたがたが神の恵みを聞き、それをほんとうに理解したとき以来、あなたがたの間でも見られるとおりの勢いをもって、世界中で、実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあながたがに届いたのです。』(コロサイ1章6節)世界中で福音が実を結び広がり続けていたのだから、当時において既に福音が世界中に宣べ伝えられていたことになる。パウロはローマ人にも次のように述べた。『まず第一に、あなたがたすべてのために、私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。それは、あなたがたの信仰が全世界に言い伝えられているからです。』(ローマ1章8節)ローマ人の信仰とは、言うまでもなく福音に対する信仰のことである。よってローマ人の信仰を福音と切り離して考えることはまったくできない。そのような信仰が当時において既に『全世界に言い伝えられている』とパウロは明言しているのだから、パウロの時代に宣教命令が成就していたと考えても間違ってはいないであろう。マルコの箇所は更に明瞭である。そこでは、主が弟子たちに『すべての造られた者に、福音を宣べ伝えなさい。』(16章15節)と命じられた後、この命令を受けた弟子たちが次のようにしたと書かれている。『そこで、彼らは出て行って、至る所で福音を宣べ伝えた。主は彼らとともに働き、みことばに伴うしるしをもって、みことばを確かなものとされた。(別の追加分)さて、女たちは、命じられたすべてのことを、ペテロとその仲間の人々にさっそく知らせた。その後、イエスご自身、彼らによって、きよく、朽ちることのない、永遠の救いのおとずれを、東の果てから、西の果てまで送り届けられた。』(マルコ16章20節および別の追加分)ここでは疑いもないほど明瞭に、キリストが弟子たちを通して福音を『東の果てから、西の果てまで』すなわち全世界に満ち広げられたと言われている。使徒行伝のある箇所からも、既に宣教命令は成就しているということを証明できる。そこでは昇天される前のキリストが使徒たちに次のように言っておられる。『しかし、聖霊があなたがたの上に臨まれるとき、あなたがたは力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、および地の果てにまで、わたしの証人となります。』(1章8節)ここで『わたしの証人となります。』とあるのは、つまりイエスがキリストであることを証明する福音の伝え人となるという意味である。主は、そのような者として使徒たちが『地の果てにまで』遣わされるであろうと、ここで言っておられる。実際、使徒の一人であるパウロは『それは私を通してみことばが余すところなく宣べ伝えられ、すべての国の人々がみことばを聞くようになるためでした。』(Ⅱテモテ4章17節)と書いているが、これはつまりキリストの御言葉が本当に使徒たちにおいて実現されていたことを意味している。であれば、確かに使徒たちの生きている時代に、もう全世界に福音は宣べ伝えられていたことになる。これで、読者はもうお分かりであろう。つまり、紀元68年6月9日までに宣教命令が成就されたからこそ、キリストが言われたように終わりの日が訪れ、再臨が起こったのである。もしこの日までに宣教命令が成就していなかったとすれば、終わりの日も再臨も起きてはいなかったであろう。私たちの理性がどう思おうとも、聖書の御言葉に基づいて考えれば、確かにそういうことになる。であれば確かに当時そういうことになったのである。というのも神の言葉には何の偽りもないからである。『あなたのみことばは真理です。』(ヨハネ17章17節)また『みことばのすべてはまことです。』(詩篇119篇160節)という聖句を聖徒の中で誰が疑うのであろうか。「信仰のみ」「聖書のみ」という原則に固執したルターも、私の述べたことをもし聞けたのであれば、それに同意したであろう。何故なら、私は今、まったく徹底的に聖書の御言葉に基づいた信仰的な説明をしたからである。ちなみに、既に世界中に福音が宣べ伝えられていたという点について、昔の多くの教師たちは正しく信じることができていた。アウグスティヌスをはじめ著名な教師の多くが、使徒たちにより既に福音が世界中に広まっていたと著書の中で書いている。彼らがこのように語ったのは当然であった。というのも御言葉がそう言っているからである。もっとも、彼らは再臨が既に起こったというほうの点については、正しい見解を持つことができていなかったのであるが(※)。
(※)
これは例えばルターがその一人である。彼はこう書いている。「ペトロが、ペンテコステの日、初めての説教をエルサレムで行ったとき、人々は聖霊を受けた後、喜んでみことばを受け入れ、「およそ三千人が洗礼を受けた」と、ルカは使徒言行録第二章で言っている。その後、エルサレムでは使徒の説教により、それよりはるかに多くの人々が回心し、その信仰は、エルサレム市外にも、国内では言うまでもなく、ローマ帝国の他の地方、ペルシアやその他の地域にも、世界中あちらこちらに広められ、また、使徒やその弟子たちの説教によりこちらまで伝えられた。」(『ルター著作集 第二集6 ヨハネ福音書第1章・第2章説教』第五説教 第1章(10―12)p128:LITHON)アウグスティヌスも「使徒たちはキリストの復活を諸々の国民に告げ知らせました。」(『アウグスティヌス著作集21 共観福音書説教(1)』説教51 3 p16:教文館)とか「(既に)福音が地の果てにいたるまで広められている」(『アウグスティヌス著作集29 ペラギウス派駁論集(3)』ペラギウス派の2書簡駁論 第3巻 第4章 第9節 p384:教文館)などと言っている。彼も聖書が述べている通りに、既に福音が使徒により世界中に告げ知らされていたという正しい理解を持っていたのである。エウセビオスも、既に福音は世界中に、しかも短期間の間に宣教されたと信じていた。彼はこう言っている。「それゆえ福音は、異邦人への証しのために短期間に全世界に宣べ伝えられ、ギリシア人も非ギリシア人もイエスについての書を祖国の文字、祖国の言語に翻訳したのである。」(『中世原典思想集成1 初期ギリシア教父』福音の論証 第3巻 第7章(15) p759:平凡社)彼は他の箇所でも、キリストの弟子たちが「かくも短い時間に全地を巡り行き、あらゆる場所を世の救い主に関する尊い教えで満たした」(同 第3巻 第1章(4) p705:平凡社)と言っている。オリゲネスも同様に、既に福音は世界中に宣教されていたと考えていた。彼はこう言っている。「また、イエスによって語られたことに即してイエス・キリストの福音が、「天が下に存在する<すべての被造物>に」(コロ1・23)、「ギリシア人にも非ギリシア人にも、知者にも無知な者にも」(ロマ1・14)既に宣べ伝えられていることを考慮するならば、驚嘆せずにおられるだろうか。というのも、力をもって語られた御言葉はすべての人類を打ち負かしたので、イエスの教えを受け取ることを免れている人類を見ることはできないからである。」(『キリスト教教父著作集8 オリゲネス3 ケルソス駁論Ⅰ』第2巻 13 p103:教文館)カルヴァンも、使徒により福音が全世界に宣教されたと考えていた。彼は使徒の職務を論じる箇所で次のように言っている。「使徒の機能は、「行って全ての被造物に福音を宣べ伝えよ」との命令によって明らかである(マルコ16・15)。彼らには一定の境域が定められず、全世界をキリストへの服従に帰せしめるように指定されたので、彼らは至る所で福音を広め、御国を建てることができた。そこでパウロは自分が使徒であることを証明しようとした時、自分はどこか一つの町をキリストのために得たと言わず、遠くまた広く福音を宣伝したことを強調し、他の人の据えた基礎の上には手を加えず、主の名が聞かれなかった所に教会を植え付けたと言う(ローマ15:19、20)。したがって、世界を神に対する背反から真の服従へと立ち返らせた使徒は、派遣されて福音の説教によって至る所に神の支配を打ち建てたのであり、もしそう言いたければ、全地に教会の基礎を据えた教会の最初の建築師のようなものである。」(『キリスト教綱要 改訳版 第4篇』第4篇 第3章 第4節 p58:新教出版社)また彼はコロサイ1:5の註解でも、既に福音が「この世のすべての国に広が」(『新約聖書註解ⅩⅠ ピリピ・コロサイ・テサロニケ書』p96:新教出版社)っていると言っている。コロサイ1:23の註解でも同様のことが言われている。既に福音が全世界に宣教されたと考える点で、昔の優秀な教師たちは何と一致していることか。
[本文に戻る]
以上のような聖書からの説明を聞いても、紀元1世紀の時に福音が世界中に宣べ伝えられていたということを理解できず、信じることもできない者がいるはずである。このような者は聞く耳を持っておらず、聖書が明白に紀元1世紀に福音が全世界に伝えられていたと述べているにもかかわらず、「でも福音はまだ全ての場所に伝えられていませんよね?」などと平気で口にする。このような者は、神が言われたことよりも、自分の思いのほうを優先させている。彼にとって御言葉は権威でも何でもなく、自分の思いこそが最高の権威である。だからこそ御言葉ではなく自分の思いのほうにこそ立脚するわけである。このような者は教会から出て行けばよい。何故なら、教会とは御言葉を最高の権威とする者たちの集まりだからである。もし教会に居続けたいのであれば、悔い改めて神の言葉に立脚せねばならない。我々神の民である者たちは、御言葉で言われているように、既に福音は使徒の時代に全世界に言い広められていたと信じなければいけない。そうしないのは、自分が聖書を信じない者であり、不敬虔な者であり、理性をこそ神とする者だということを暗に周りの者に告白しているのも等しい。しかし、御言葉を理解しがたいと感じる不信仰な方が御言葉を受け入れられるようになる可能性を高めるのために、いくらかの説明を試みることにしたい。もし御言葉で言われていることが理解しがたいと感じられたならば、その人は現代の世界を定規として古代の世界を考察するということをせず、今の世界に関する意識を捨て、ただ古代の世界だけを直視してみるといい。というのは、その人は古代を現代というフィルターを通じて見ている可能性が高いからである。つまり、古代が現代と同じような状態だと知らず知らずのうちに認識しているからこそ、聖書で言われている古代のことがよく理解できない。使徒たちの生きていた古代がどういった時代だったかといえば、まだ世界人口が3億人ぐらいしかなかった(※①)。また当時の人たちは、ニーチェにより「神は死んだ」などとされた無神論的な現代とは違い、非常に有神論的であった。更に当時の使徒たちやその他の弟子たちには奇跡や不思議な業を行なう力が与えられており(※②)、死者を生き返らせたり、瞬間移動をした者さえいた(※③)。このような古代の状態を知るならば、今とはかなり違う時代だったということが分かるのではないかと思う。さて、古代はまだ3億人しか人間がいなかったのであるから、宣教命令が出された紀元33年頃から再臨の起こる68年までの35年間があれば、世界中の全ての人たちに伝道をするのは十分に可能だったであろう。使徒のトマスなどはインドにまで宣教に行ったと伝えられているし(※④)、12使徒以外にも福音を伝える者は多くいたのである。しかも当時の弟子たちは、今とは違って非常に純粋で熱烈な信仰を持っていた。これが現代のように70億人の人口であったのであれば話は別だっただろうが、たったの3億人ぐらいであれば、35年以内で宣教命令が成就されたとしても何も不思議なことではない。また当時の人たちは有神論的な人ばかりであって、今とは違って無神論者はほとんどいなかったのだから、伝道がしやすく、多くの人たちが信じやすく、その信仰が連鎖的に伝播しやすい状況であったと推測できる。古代は、あまり信仰的な傾向がない現代とは、かなり違う宗教性が多くの民族のうちにあったのである。また当時の弟子たちが素晴らしい奇跡により福音の御言葉を確証できたという点も考慮せねばならない。そのようにして弟子たちが奇跡という徴と共に伝道をしたのであれば、話題になり、多くの人がキリストを信じ、すぐにも福音が普及するといった効果が生じたであろうことは想像に難くない。今の時代の人でも、もし目の前で復活の奇跡が行なわれるのを見せられたならば、実に多くの人が信仰に入るであろう。つまり我々は、当時の福音宣教において、『主は彼らとともに働き、みことばに伴うしるしをもって、みことばを確かなものとされた』(マルコ16章20節)ということをよく弁えるべきである。当時は、御言葉に奇跡という徴が伴うことの珍な現代とは、状況がかなり違っていたのである。更にピリポの例が示すように使徒たちは瞬間移動もできたのだから、移動の難しさも、それほど問題にはならなかっただろうと思われる。もし神が働かれたならば、使徒はヨーロッパからアメリカ大陸にさえも移動することができたのである。このような奇跡や超自然的な現象が当時にはあったのだから、福音が世界中で実を結び広がり続けているというパウロの言葉は、正に真実であったと我々は信じなければならない。このように、奇跡などがほとんど見られなくなった現代とは、かなり異なった状態が古代にはあったのである。どうであろうか。このように古代を現代の状況に当てはめて考えるということをせず、徹底的に古代という時代の状況を直視して考察するのであれば、御言葉で言われていることが理解しがたいと感じた人も、少しは御言葉が真実なことを言っているということが分からないであろうか。このような説明を聞いて「確かに再臨の起こる条件である宣教命令の成就は既に使徒の時代において実現していたのだ。」と分かるようになれば、それでよい。しかし、今書かれたことを読んでも、まだ「既に世界中に宣教がなされたなどとは信じがたい話だ。」などと思うのであれば、もはや手のうちようがない。その人は、御霊を受けておらず、真の信仰を持っておらず、そのために聖書の明瞭な証言を受け入れられないのだと考えられる。そのような者については、放っておく以外にはない。キリストも御言葉が分からないパリサイ人たちについて『彼らのことは放っておきなさい。』(マタイ15章14節)と言われたのである。
(※①)
様々な研究者による紀元1年の世界人口における推測値は以下の通りである。
3億(Haub, Carl, 2007, "2007 World Population Data Sheet)
3億(国連経済社会局(United Nations Department of Economic and Social Affairs)―2006)
2億3082万(Angus Maddison, 2003, "World Economy: Historical Statistics", Vol. 2, OECD, Paris)
2億5500万(Jean-Noel Biraben, 1980, "An Essay Concerning Mankind's Evolution", Population, Selected Papers, Vol. 4, pp. 1~13.―1980)
1億7000万(Colin McEvedy and Richard Jones, 1978, "Atlas of World Population History," Facts on File, New York)
2億(Ralph Thomlinson, 1975, "Demographic Problems: Controversy over population control," 2nd Ed., Dickenson Publishing Company, Ecino, CA)
2億7000万~3億3000万(John D. Durand, 1974, "Historical Estimates of World Population: An Evaluation," University of Pennsylvania, Population Center, Analytical and Technical Reports, Number 10.)
■引用元:ウィキペディア「世界人口」―世界人口推定・予測値(https://ja.wikipedia.org/wiki/世界人口#世界人口推定・予測値
[本文に戻る]
(※②)
キリストの言われた通り、当時の弟子たちには素晴らしいことをする力が与えられていた。『信じる人々には次のようなしるしが伴います。すなわち、わたしの何よって悪霊を追い出し、新しいことばを語り、蛇をもつかみ、たとい毒を飲んでも決して害を受けず、また、病人に手を置けば病人はいやされます。』(マルコ16章17~18節)とマルコが記している通りである。確かにルカが記しているように、パウロは病人を癒すという奇跡をキリストの恵みにより行なっていたのである。使徒行伝28:8~9。『たまたまポプリオの父が、熱病と下痢とで床に着いていた。そこでパウロは、その人のもとに行き、祈ってから、彼の上に手を置いて直してやった。このことがあってから、島のほかの病人たちも来て、直してもらった。』
[本文に戻る]
(※③)
これは使徒ピリポのことである。ルカは、ピリポが宦官にバプテスマを授けた後で御霊により連れ去られたので見えなくなった、と書いている。使徒行伝8:39~40。『そして馬車を止めさせ、ピリポも宦官も水の中へ降りて行き、ピリポは宦官にバプテスマを授けた。水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去れたので、宦官はそれから後彼を見なかったが、喜びながら帰って行った。それからピリポはアゾトに現われ、…』
[本文に戻る]
(※④)
これは外典の「トマス行伝」による。この外典では、トマスがキリストに売られてインドに行かされたと書かれている。もっとも、私はこの外典の内容を、実話だと見ていない。何故なら、この外典ではトマスの言っていることが聖書的ではないからである。もしこれが本物のトマスであればパウロのように配偶者とは離別すべきではないと言ったであろうが(Ⅰコリント7章)、ここでのトマスは信者になった者を配偶者から引き離している。これは恐らく2~3世紀頃の禁欲的なキリスト者が創作したものだと思われる。もちろん、この外典を考慮しなくても、トマスがインドやインド以東の地域に行った可能性は十分にあるが。
[本文に戻る]
さて、それでは再臨が既に起きて宣教命令も成就しているのであれば、もはや教会は宣教をする必要がないのであろうか。そのようなことは絶対にない。何故なら、福音を世界中の人に宣べ伝えて弟子が増えるようにするというのは、地上に生きる聖徒たちに対する神の永遠の御心だからである。このようなことは少し考えればすぐにも分かることではないかと私には思われる。今の時代にも、永遠の昔から救われるようにと定められている人が、世界のどこかに必ず存在している。そのような人たちがキリストの救いを受けるようになるためにも伝道がなされなければならない、というのは火を見るよりも明らかであろう。これを読んでいる聖徒たちも筆者である私も、そのようにして伝道がなされたからこそ、キリストの救いを受けるように導かれたはずである。我々は、もし全く伝道が行なわれなかったとすれば、恐らく救われていなかったかもしれない。このことから考えても分かると思うが、もし全く伝道がなされるべきでないとすれば、誰も救われることができなくなってしまう。聖霊を受けた者であれば、こんなことにはとてもではないが我慢できないはずである。それは、聖霊を受けた者であれば、必ず、大いに伝道がなされて弟子が増えるようになるのを願うだろうからである。もし再臨が既に起きて宣教命令も成就しているからというので、宣教がなされるべきでないとすれば、信徒が減り、教会が衰退し、キリスト教が滅亡することになる。このようなことは明らかに神の喜ばれることではない。それゆえ、再臨が起きたがゆえに宣教はもはやする必要がなくなったなどと考えるのは、愚の骨頂であると言わねばならない。
第6章 実際の身体をもって再臨されたキリスト
今から2千年前にキリストが再臨された際、その再臨の様子は一体どのようなものだったのであろうか。その様子は、何か幻想的なものではなく、単なる概念上のものでもなく、実際的なものであった。すなわち、物理的な肉体をもって復活されたキリストが(※①)、その物理的な肉体を有したまま天からおいでになられた。つまり、もし再臨されて空中におられるキリストの御身体に触れることができたとすれば、我々が誰かの身体に触った際に物理的な感触を感じるように、物理的な感触を感じることができた。これは疑えないことである。というのは、使徒行伝を見ると、そのように考える以外にはないからである。ルカは聖書のこの巻でこう書いている。『こう言ってから、イエスは彼らが見ている間に上げられ、雲に包まれて、見えなくなられた。イエスが上がって行かれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると、見よ、白い衣を着た人がふたり、彼らのそばに立っていた。そして、こう言った。「ガリラヤの人たち。なぜ天を見上げて立っているのですか。あなたがたを離れて天に上げられたこのイエスは、天に上って行かれるのをあなたがたが見たときと同じ有様で、またおいでになります。」』(1章9~11節)キリストはこの時、物理的な肉体を持ちながら天に上げられた。それゆえ、御使いの言葉から分かるように、再臨される時も物理的な肉体を持ちながら天から降りて来られたことになる。紀元68年6月9日に生きていたキリストの弟子たちは、この光景を、自分の目でまざまざと見たであろう(※マタイ16:28)。大祭司カヤパ、律法学者、長老たちも、キリストの再臨を目撃したはずである(※マタイ26:64)。キリストを槍で刺した兵士も、同じように再臨を見ただろうことは疑えない(※黙示録1:7)。他にも多くの人たちが、この日に、キリストの再臨を見たはずである。何故なら、御言葉にそう書いてあるからであり、御言葉を素直に信じるならば(※②)、そのようになったと理解せねばならないからである。しかし、世の中には、再臨が紀元1世紀に起こったことは信じても、その再臨が実際的なものだっとは考えない人たちがいる。彼らは、この紀元1世紀に起きた再臨が霊的なものだったとか法的なものだったなどと主張し、ルカにより書かれた御言葉をねじ曲げている。正常な精神を持っている人であれば誰でも分かるように、ルカは明らかに再臨の様子が実際的なものだったと書いているのであって、それが霊的だとか法的だとか言ったわけではない。このように御言葉を曲げるならば、御言葉をそのまま信じている聖徒たちから、不審がられても文句は言えない。このルカによる聖句を、そのまま文字通りに捉えないというのは、明らかに普通ではない。よって、この時に起きた再臨が実際的なものではなかったという考えは、御言葉のゆえに斥けられねばならない。自分が御言葉で言われていることを素直に信じれないからといって、受け入れられるようにと御言葉の内容を改変させるというのは、神の御前における霊的な犯罪行為である。
(※①)
キリストの復活された身体が霊とか幽霊とか概念的なものではなかったことは、ルカ24:36~43を見るだけでも十分に分かる。これは既に我々にとっては明らかなことであり、本作品で論じられるべき内容でもないから、ここでこの問題について取り扱うことはしない。
[本文に戻る]
(※②)
キリストは、『子どものように神の国を受け入れる者でなければ、決してそこに、はいることはできません。』(ルカ18章17節)と言われた。子どものように受け入れる、というのは神の国以外のことについて述べられた種々の御言葉についても同様である。すなわち、あらゆる御言葉に対して、我々には素直にそれを信じる態度が求められているのである。
[本文に戻る]
再臨の様子に関してもっと詳しく知りたいと思われる方がいるかもしれない。しかし、この場所では、とりあえず上に書かれたことを知るだけで十分であるとしてほしい。というのは、再臨の様子における詳細については、後ほど語られることになるからである。少しもやもやとする読者もおられるかもしれないが、そのような読者は、今しばらく待っていただきたい。ソロモンも述べるように、何事にも時というものが存在するのである。
第7章 再臨の証拠
聖書の御言葉を考えるならば確かに再臨は紀元1世紀に起きたと信じなければいけないが、再臨が既にあったというのであれば、その証拠は果たしてあるのであろうか。あのような注目すべき大きな出来事であったのだから何か少しぐらいは証拠があるに違いない、と思われる方も多いはずである。これは避けて通れない重要な問題であるから、この章で今このことを語ることにしたい。まず結論から先に言えば、キリストの再臨に関する史実的また科学的な証拠を提示することはできない。例えば、タキトゥスであれ大プリニウスであれ紀元68年に生きていた著述家たちの書いたものから、再臨の証拠を示すことはできない。何故なら、再臨が起きたことについて書き記された書物や文書は、まったく存在しないからである。キリストがピラトにより磔刑に処せられたということであれば、例えばタキトゥス(55年頃~120年頃)の「年代記」に書いてあるから、その箇所を提示できる(※①)。キリストが実在しておられたということであれば、紀元1世紀の著述家であるスエトニウスが「ユダヤ人は、クレストゥスの煽動により、年がら年中、騒動を起こしていたので、ローマから追放される。」(『ローマ皇帝伝(下)』第5巻 クラウディウス p110:岩波文庫)と書いている。ユスティノスも紀元2世紀におけるローマの元老院に宛てた文書の中でこう言っている。「イエス・キリストはここで生れました。この事実は、ユダヤにおけるあなたがたの初代総督、クレニオの時代に行われた人口調査の登記簿からもお知りになることができます。」(『キリスト教教父著作集1 ユスティノス』『第一弁明』34:2 p50:教文館)「また彼を十字架につけた人々は、十字架につけたのち彼の「着物のくじ引にし」、自分たちの間で分けたのです。以上のことが事実起ったことは、ポンテオ・ピラトの時代に作られた公務記録からお知りになることができます。」(同 35:8~9 p51)「次に、私共のキリストがあらゆる病をいやし、死人を立たせるであろうとの予言について、語られている言葉をお聞きください。このように述べております。「彼の来臨の時、足の不自由な者が、しかのように飛び走り、もつれた舌はほどけるであろう。見えぬ目は開き、らい病人はきよまり、死人はよみがえって歩くであろう。」彼が事実これを行ったことは、ポンテオ・ピラトの時代の公務記録から確かめていただくことができます。」(同 48:1~3 p64)モーセの実在性と古代性についてであれば、オリゲネスがこう言っている。「モーセは、何人かのギリシアの著述家によって、ポロネウスの子イナコスの時代に生きていたことが、語られている。また彼の古代性は、エジプト人や、フェニキア史の編纂者たちによっても同意されている。」(『キリスト教教父著作集9 オリゲネス4 ケルソス駁論Ⅱ』ケルソス駁論 第4巻 11 p87:教文館)…が、再臨の場合、残念ながらそのようなものはない。これは一体どういうことかといえば、神が再臨を記録させることを許されなかったということである。ゼノンやエピクロスの書いた大量の著書が世に一冊たりとも残されることを神が望まれなかったように、再臨が起きたことについて何かが書かれることも、神は望まれなかった。しかし、今まで見てきたことから分かると思うが、御言葉は疑いもないほど明白に当時再臨が起きたことを我々に教示している。つまり、我々は史実的また科学的な証拠抜きに、すなわちただ御言葉の内容だけを直視することにより、再臨が既に起きたということを信じる信仰を求められている。神は、この再臨については、ただ御言葉のみにより信じるようにと願っておられるのではないかと私は考えている。多くの人たちは、御言葉が既に再臨が起きたと教えていることは認めても、証拠の不在によって大いにつまづいてしまう。私と論争した牧師も、再臨が紀元1世紀に起きたと認めたが―認めざるを得なかったのである―、証拠がないからというので不信仰の闇に陥ってしまった。確かに「証拠」がない、というのは多くの聖徒にとっては無視できない大きな障害となることであろう。しかし考えてほしい。証拠がないからといって、御言葉で言われていることを否定してもよいものであろうか。証拠抜きに、つまり私たちがしっかりと理性により捉えられる実際的・物理的な物や状況や情報抜きに、神の言われたある事柄を真なるものとして受け入れるというのが「信仰」なのではないのか。ヘブル書では次のように言われている。『信仰は…目に見えないものを確信させるものです。』(11章1節)もし目の前に何かがあって、その存在を信じるというのであれば、そのような心の働きを「信仰」と呼ぶことはできない。それは目の前にあるのだから信じるも何もないからである。目に見えないもの、確認できないもの、信じるかしないもの、こういったものを真なるものとして認めるのが「信仰」である。再臨はこのような種類に属するものであり、御言葉しか証拠として提示できないのだから、我々は御言葉のゆえ、たとえこの世的な証拠がなかったとしても再臨のことを信じるべきなのである。もし御言葉以外に証拠がなければ信じないというのであれば、あなたはどうして天国や永遠の生命や天使といったものを信じているのか。天使の場合は恵まれた人であれば、その存在を実際に見ることができたり感じたりできるから、自分だけの証拠を持っている人もいるかもしれないが、天国や永遠の生命について何かの証拠を持っている人は一人もいないはずである。多くの聖徒たちは、このような目に見えないものを、何も証拠がないにもかかわらず、ただ御言葉がそう言っているからというだけの理由で心の底から信じているであろう。もし誰かから「天国や永遠の生命がある証拠を提示してほしい。」と言われても、御言葉以外の証拠は提示できないはずである。確かに、このようなものは御言葉だけが証拠であって、史実的また科学的な証拠は存在していない。あなたは、御言葉以外に証拠がないからというので、天国や永遠の生命といったものの存在を疑うことはしないはずである。何故なら、確かにこの世的な証拠はないが、神が御言葉の中でこのようなものがあると明瞭に言っておられるからである。そうであれば、どうして再臨の場合は、証拠がないと信じないのであろうか。もし天国などのことを証拠抜きに御言葉だけで信じるべきだとすれば、再臨もそのようにすべきではないのか。もちろん、そうであろう。確かに御言葉は既に再臨が起きたと教えているのだから、たとえ証拠がなかったとしても、我々は既に再臨が起きたということを信じるべきである。証拠がないので再臨を信じない人は、証拠がないので天国の存在を信じない人と同じである。何よりも我々が知るべきなのは、御言葉こそが我々にとってもっとも強力な証拠だということである。確かなところ、この御言葉こそ至高の、究極の、完全な、絶対である証拠である。何故なら、御言葉とは全ての上におられる超越神の言われた言葉だからである。神の言われたものに優るものが他に何かあろうか。要するに、この御言葉に優る権威などは、この世に存在していない。御言葉こそが、万物における最高の権威である。キリストはこの御言葉によって世界を保っておられ(※②)、この御言葉には『この世の神』(Ⅱコリント4:4)であるサタンさえも打ち勝つことができない。そのように力強く大いなるものである御言葉という証拠が「既に再臨は紀元1世紀に起きている」と我々に教えているのである。であれば、我々は、そのように信じるべきであろう。この世的な証拠がないために御言葉を拒絶する者は、もっとも高い権威を持つ神の言葉を愚弄し、それを偽りであるとさえしている。もし我々が御言葉の権威を疑ったり否定したりする不信の徒でないのであれば、たとえ歴史的な証拠がなかったとしても、御言葉という証拠のみにより私が上で述べた再臨のことを信じなければならない。カルヴァンも、アモス1:13~15の箇所で預言されているアモン国に降り注がれる災いを証明することのできる「歴史は存在しませんが、この預言が実現したことを疑ってはなりません。」(『アモス書講義』第1章 p42:新教出版社)と言っているではないか。カルヴァンは、アモンの災いを証明できる歴史が書き残されていないからと言って、アモス書の預言を疑うべきだったろうか。とんでもないことである。敬虔な者にとっては聖書が述べていれば、ただそれだけでOKなのである。これを書いている私は御言葉に書かれていることを素直にそのまま信じ、あなたはそのようにせず不信仰な思いを心に抱いている。どちらの態度が神の御心にかなったものであるか、よく考えてほしいと思う。ベルナルドゥスも「信仰は理性・知覚・経験を超越する」と言って、信仰によってこそ物事を捉えるようにと言っている。彼の言葉はこうである。「信仰は、感覚が知らず、経験が見いださないことを、確実に捉える。「わたしに触れてはならない」(ヨハエ20・17)と主は言われる。つまり、こうした誤りがちな感覚から自分を解き放しなさい、言葉に寄りかかりなさい、信仰に親しみなさい。信仰は欺瞞を知らない。信仰は目に見えないものを把握し、感覚知覚の欠乏を感じない。つまり信仰は人間的な理性の領域、自然の必要、経験の限界を乗り越えていく。目には不可能なことの何かをあなたは目に尋ねるのか。また、手の力を超えたことを手に説明するように試みるのか。目や手が知らせることができるものは僅かである。確かに信仰は、わたしの偉大さを低めることなく、わたしについてあなたに知らせるであろう。信仰が説得するであろうことを、もっと確信を懐いてそれをもつように、もっと安全にそれを追求するように、学びなさい。「わたしに触れてはならない。わたしは御父のもとに未だ昇っていないから」(ヨハ20・17)。」(『キリスト教神秘主義著作集2 ベルナール』雅歌の説教28 9 p180:教文館)御言葉という明白な証拠があるにも関わらず、歴史的な証拠を求める人は、キリストの復活体に触れなければ、すなわち物的な証拠を感覚により会得しなければ、信じようとはしなかったあの女のようである。
(※①)
「それは、日頃から忌わしい行為で世人から恨み憎まれ、「クリストゥス信奉者」と呼ばれていた者たちである。この一派の呼び名の起因となったクリストゥスなる者は、ティベリウスの治世下に、元首属吏ポンティウス・ピラトゥスによって処刑されていた。その当座は、この有害きわまりない迷信も、一時鎮まっていたのだが、最近になってふたたび、この禍悪の発生地ユダヤにおいてのみならず、世界中からおぞましい破廉恥なものがことごとく流れ込んでもてはやされるこの都においてすら、猖獗をきわめていたのである。」(『年代記(下)』第15巻 44 p269:岩波文庫33―408―3)
[本文に戻る]
(※②)
『御子は…その力あるみことばによって万物を保っておられます。』(ヘブル1章3節)
[本文に戻る]
以上のように説明されても、いまいち納得できない方がおられるかもしれない。それは、御言葉のゆえに再臨に関する証拠がなくても問題にするなと言われただけであって、どうして証拠がないかという具体的な理由は何も語られていないからである。確かに再臨の証拠がないのはその通りであるが、やはり証拠がない理由も考察されるべきであろう。そのようにしないのは学術的また神学的であるとは言えない。それは、例えばヘラクレイトスの著書が残されていないと言うだけで、どうして彼の著書が残されていないのか考察しないようなものである。一般の人であれば彼の著書が残っていない理由などはどうでもいいかもしれないが、学者や専門家や教養人であれば、やはりその理由をいくらかでも詳しく知りたいはずである。我々はそのような人たちのように再臨のことを知りたく願っているのだから―敬虔な読者であればみなそうであろう―、再臨のことが更に詳しく語られるべきであろう。そうすれば、たとえ再臨の証拠がなかったとしても、わだかまりが残らず全てがスッキリする、ということにもなるであろう。さて、再臨の証拠を何も提示できないのには多くの理由がある。その理由とは一体どのようなものなのか。一つ一つ考察していきたい。まず我々は第一に、紀元68年に起きた再臨の際、永遠の救いに定められていた聖徒たちが、天へと引き上げられたことについてよく考えねばならない。再臨の時、当時生きていた聖徒たちは、地上から再臨されたキリストのおられる空中へと携挙された。それはパウロが『次に、生き残っている私たちが、たちまち彼らといっしょに雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。』(Ⅰテサロニケ4章17節)と書いている通りである。ここではまだ詳しく説明しないが、この空中に携挙された聖徒たちが、それからのちキリストと共に天に引き上げられたのは間違いないことである。というのもパウロが『私たちの国籍は天にあります。』(ピリピ3章20節)と書いているからである。聖徒たちの国籍が天にあるというのであれば、どうしてそこに帰って行かないことがあるであろうか。携挙された聖徒たちが空中に留まっていたままで、『天の故郷』(ヘブル11章16節)に帰らなかったというのはまったく考えられない。もしそのようにして天へと当時の聖徒が行ったのであれば、天に行ったのであるから、この地上で再臨のことを言い広めたり書き残すことは絶対にできない。天に存在するにもかかわらず、地上でそのようなことをするというのは、普通に考えればあり得ないし、聖書からもそのような考えは導き出せない。それゆえ、紀元68年までに生きていた聖徒たちによる再臨の伝承や記録が何も残されていないのは当然である。これで当時の聖徒たちがどうして再臨について何も証拠となる情報を残していないのか、分かっていただけたであろう。つまり、そもそも彼らは再臨が起きた時にはもう地上に存在していなかったのである。次に考えるべきは、携挙されはしたものの天の御国に引き上げられることがなく、永遠の火に投じられた偽信者のことである。この者たちは携挙されて空中に行った際、そこにいたキリストから、このように言われてしまった。『のろわれた者ども。わたしから離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火にはいれ。』(マタイ25章41節)ここで言われている『永遠の火』については今はまだ説明しないが、このように言われた彼らがキリストの御言葉の通りに火に投げ込まれたのは確かである。天国に引き上げられた聖徒たちの場合と同じで、この滅びの子らも火の中に投げ込まれたのだから、自分の見た再臨を誰かに言い広めたり書き残すことはできない。火に投げ入れられたのに、そのようにできたというのは、少し理解し難いことだと私には思われる。であれば、当時生きていた偽信者たちが、実際に再臨を見たにもかかわらず、再臨に関する証拠を何も世に残していなかったとしても不思議なことではない。あの3人のように火に投げ入れられても生きていられたというのであれば話は別だったかもしれないが(ダニエル書3章)、神に遺棄されるべく生まれた滅びの子らに、そのような超自然的現象が起きたとはまったく考えられない。よって、我々はキリストの恐るべき宣告を受けたあの山羊どもによる再臨の証拠が残されていなかったとしても、驚いたり疑問に感じたりすべきではない。第三に考察すべきは、再臨の際に携挙されないで地へと残されたままだった不信者また異教徒たちのことである。キリストの御言葉によれば、再臨が起きた時に携挙されなかった者がいたというのは疑えない。それは次のように主が言われたからである。『そのとき、畑にふたりいると、ひとりは取られ、ひとりは残されます。ふたりの女が臼をひいていると、ひとりは取られ、ひとりは残されます。』(マタイ24章40~41節)ここで問題となるのは、この地上に残された者たちが再臨の証拠を何か残していないのか、ということである。この不幸な者たちが、空中に再臨されたキリストをその目で見たことは間違いない。キリストは再臨の時の様子について次のように言われた。『そのとき、人の子のしるしが天に現われます。すると、地上のあらゆる種族は、悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見るのです。』(マタイ24章30節)ヨハネもこう書いている。『見よ、彼が、雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが、彼を見る。地上の諸族はみな、彼のゆえに嘆く。しかり。アーメン。』(黙示録1章7節)確かに、今引用した聖句から、地に残された滅びの子らもキリストの再臨を見たということが分かる。その者たちは、再臨されたキリストを見て悲しみ、嘆いたのである。では一体どうなのか。この再臨を見た滅びの子らは、再臨を実際にその目で見たのだから、その大いなる光景を誰かに言ったり記録として残したりすることが可能だったはずである。もし彼らがそういうことをしたのであれば、その証言や記述を、再臨の証拠として提示することが私にはできたであろう。しかし、そのようなものは一切残されていない。つまり、彼らは再臨を見たにもかかわらず、それを何らかの形で世に残さなかった。まったくそうしなかったのである。読者は、私が今このように書いたのを読んで、「ほら、やっぱり再臨なんて当時には起こらなかったのだよ。もし本当に起きていたら、それを見た不信者たちが何か書き残していただろうから。」などと早計にも思ってはならない。彼らが再臨を見たのに何も述べていないのには、しっかりとした理由がある。どういうことかと言えば、彼らは救われるために真理を受け入れなかったので、神の裁きにより惑わされたということである。パウロはある箇所で、再臨により滅ぼされるネロが現われた時には、救いを拒絶した携挙されない人々が偽りを信じるようになると述べている。その箇所とはⅡテサロニケ2:9~12であり、そこにはこう書いてある。『不法の人の到来は、サタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、しるし、不思議がそれに伴い、また、滅びる人たち対するあらゆる悪の欺きが行なわれます。なぜなら、彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は、彼らが偽りを信じるように、惑わす力を送り込まれます。それは、真理を信じないで、悪を喜んでいたすべての者が、さばかれるためです。』パウロの言うように携挙されなかった者が惑わされて偽りを信じるように裁かれたというのであれば、たとえ最初は再臨を見て悲しんだり嘆いたりしたとしても、後になってから再臨の出来事を否定したり夢また幻だと思ったとしても何もおかしなことはない。彼らは惑わされ偽りを信じるようにされたのだから、このようになったというのは十分に予測可能である。当時は迷信深い人たちが多かったから―あのキケロでさえ鳥占いをしている―、惑わしの力を受けたことにより、再臨を何か一種の超常現象として捉え―あのタキトゥスでさえ様々な超常現象について書き記している―、あまり重要ではないこととして忘れてしまった、という可能性がある。実際には、少しぐらいは仲間の間で話し合われたのかもしれないが、記録として書き残すほどのものとしては意識されなかったという考えをすることもできる。そうであれば、裁かれた彼らにより再臨の証拠が残されていなかったとしても、それほど驚くべきことではないといえよう。地に残された者らによる再臨の証拠がないと言って反論する人たちには、私は今書かれたように答える。このように反論する者たちも、惑わす力が不信者たちに送られたということを考慮すれば、それを不信者による証拠がない理由の一つとして考えることができるのではないかと思う。さて、ここまで書かれたことには納得できても、「しかし、それでは再臨の時に起こる天変地異は一体どうなのか?」と問う人がいるであろう。つまり、人の声や文章による証拠は残っていなくても、再臨の時には前代未聞の天変地異が起こるのだから、その天変地異が再臨の証拠となるはずだが、紀元1世紀の歴史を見てもそのような天変地異が起きてはいないではないか、という問いである。確かにキリストが再臨の際に凄まじい天変地異が起こると言われたのは間違いない。キリストはマタイ24:29の箇所でこう言われた。『だが、これらの日の苦難に続いてすぐに、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。』ペテロも、再臨の日に起こる天変地異について、こう書いている。『その日には、天は大きな響きをたてて消えうせ、天の万象は焼けてくずれ去り、地と地のいろいろなわざは焼き尽くされます。』(Ⅱペテロ3章10節)これらの天変地異に関する預言は明らかにイザヤ34:4と対応しており、そのイザヤ書のほうではこう言われている。『天の万象は朽ち果て、天は巻き物のように巻かれる。その万象は、枯れ落ちる。ぶどうの木から葉が枯れ落ちるように。いちじくの木から葉が枯れ落ちるように。』読者がまず考慮すべきなのは、キリストの預言された天変地異は、間違いなく紀元1世紀に起きたということである。私は先に第3章でマタイ24章で書かれている出来事はその世代(γενεα)のうちに起こると説明したが、そのマタイ24章の中で天変地異が起こると言われているからである。そうであれば、同じことが言われているⅡペテロ3章とイザヤ34章の預言も、既に紀元1世紀において成就していることになる。確かに聖書から考えればそういうことになる。しかし、読者の方は、紀元1世紀にそのような天変地異が起きたとは到底思えないかもしれない。確かに歴史を見ても、このようなことが文字通りには起きていないのを私も認める。だが、このような読者は、預言で語られている天変地異がどういったものなのか、よく悟れていない。一体どういうことか。それはつまり、これらの預言で語られているのは、確かに紀元1世紀に起きたことではあるが、全世界的なものではなく、ユダヤ戦争と神殿崩壊の際に起きる凄まじい出来事を象徴的に表現したものだということである。この時期にキリストの再臨が起きて世界全体も改められるのだからこそ、それを全世界的な規模であると思ってしまう人もいるほどの表現をもって語られているのである。アインシュタインなどは、このような聖書の表現を「誇張だ」などと言って批判する。だが、我々聖徒である者たちは、神がその偉大性や凄まじさを教えようとしてこのような象徴表現をされたのだと捉えるべきである。聖書には誇張表現があると非難する不信者たちも、自分の愛する者にはとてつもない誇張表現を使って愛を伝えようとするのだから(ラブレターが良い例である)、実際のところ、聖書の象徴表現を批判できないと私は思う。このように預言された天変地異とは、ユダヤ滅亡の際に起こる凄まじい悲惨な出来事を象徴的に言い表わしたものだから、紀元1世紀を見てもそのような天変地異が伴う再臨が起きたとは信じられないなどと反論することはできない。私がこのように言ってもまだ考えを変えないようであれば、つまり天変地異の記述が象徴表現であるということを信じられないようであれば、その人に私は聞きたい。すなわち、ペテロが成就したと述べているヨエル書における預言は果たして象徴表現が使われたものではなかったのか、と。確かにペテロはペンテコステの際、ヨエル書の預言が成就したのだと明白に述べている。彼はその時こう言った。『これは、預言者ヨエルによって語られた事です。『神は言われる。…主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽はやみとなり、月は血に変わる。』』(使徒行伝2章16、17、20節)ペテロがこう述べた時に、実際に太陽が暗くなったり月が血の色に変わったりしなかったのは確かである。というのも、これは象徴表現であって、つまりこのペンテコステの出来事は太陽が輝きを失い、月も血に染まってしまうぐらいの驚くべき出来事なのだ、と言おうとしたものだからである。確かに、実際このペンテコステの出来事を見たユダヤ人たちは『驚きあきれてしまった』(使徒行伝2章6節)のである。それは、あたかも太陽が闇となり月が血に変わる際に持つ驚きのような驚きであった。今私が論述の対象としている「考えを変えない人」も、もちろんこのヨエル書の預言が象徴であると認めるであろう。カルヴァンもこのヨエル書の預言は「隠喩的表現」であって、実際的な現象を述べたものではないと言っているが、彼がそのように説明したのは正しかった(『新約聖書註解Ⅴ 使徒行伝 上』2:19及び20 p61:新教出版社)。しかし、もしマタイ24章の天変地異が象徴表現でなかったと言うのであれば、どうしてヨエル書のほうは象徴表現が使われていると認めるのであろうか。明らかに、どちらも似たようなことを言っているではないか。もしヨエル書で象徴表現が使われているとすれば、同様にマタイ24章などの預言のほうも象徴表現だと捉えるべきではないであろうか。つまり、天が焼けて無くなるとか地の業が燃やされるなどと言われているのは、エルサレムの炎上や再臨がどれほど凄まじいものであるのかということを意味しており、またそれはその際に起こる世界の更新を示すものとしての意味も含まれているのである。このようにマタイ24章の天変地異には象徴表現が使われているのだが、そのように考えるならば、この天変地異の記述を盾に取って反論することもできなくなると私は言いたい。ちなみに、この天変地異は今述べたようにユダヤ戦争の時期に起きたのだから、それを再臨の証拠とすることができるかもしれない。これは誰かの証言や書き残された記録のように認識しやすい証拠というわけではないし、中にはこれが証拠だなどとは思えない人も多くいるだろうが、証拠と言えるようなものといえばこれぐらいなものである。キリストは当時のユダヤ人にやがて再臨が起きる際には大異変が起こると述べられた、それがユダヤ戦争の時に実現された、それゆえそれこそが正に再臨の間接的な証拠なのである。―要するにこういうことである。ここまで再臨の証拠がない理由を具体的に考察してきたが、ここまで読んでもまだ再臨が紀元68年に起きたと信じられない人は、神の御言葉に言い逆らうことになるというのをよく覚えておいていただきたい。確かに、既に第2章で説明されたように、キリストや使徒たちは、当時の人たちが生き残っている間に再臨が起こると明白に述べた。証拠の不在のゆえにそのことを信じないのは、神に向かって「あなたの言われたことは違っていた。」と文句を言うのも等しい。このように言うのは実に不遜である。私が今再臨の証拠がない理由を詳しく説明したのだから、自分が聖徒であると思う人は、証拠の不在を理由として既に再臨が起きたことを否定すべきではない。我々が重視すべきなのはこの世的な証拠ではなく、御言葉に対する信仰である。『信仰がなくては、神に喜ばれることはできません。』(ヘブル11章6節)と聖書では言われているではないか。
しかしながら、この証拠の不在について、もう少し別の論証をしてみたい。地上における不信者たちがキリストの再臨をその目で見たにもかかわらず、その光景を何も記録として書き残さなかったというのは、聖書のある箇所からも言えることである。その箇所とは、イザヤ29:1~8である。まず、この箇所がどのようなことを述べているのか見ていく。まず、このイザヤ29章は、紀元66~70年に起きたユダヤ戦争を預言した箇所である。何故なら、この箇所では、聖都エルサレムを敵である多くの兵士たちが包囲すると書かれているからである。すなわち、ここでは神がエルサレムに対してこのように言っておられる。『わたしは、あなたの回りに陣を敷き、あなたを前哨部隊で囲み、あなたに対して塁を築く。』(3節)また、この章では敵たちがエルサレムを『攻めて、これを取り囲み、これをしいたげる』(7節)とも言われている。確かに、ユダヤ戦争において、エルサレムは無数のローマ軍に包囲され、多大なる攻撃を受けた。ここで『アリエル』(1節)と言われているのは、『ダビデが陣を敷いた都』(同)であって、すなわちエルサレムのことである。戦いのイメージを強くするために、ここではエルサレムが、ダビデにより戦陣が敷かれた都として語られているのである。確かにエルサレムの崩壊に至るユダヤ戦争とは戦いそのものであるから、単にエルサレムと言わず、『アリエル』と言い表わしたのは実に適切であった。次に、このイザヤ29章は、再臨について預言した箇所でもある。何故なら、この章の中では、次のように書かれているからである。『万軍の主は、雷と地震と大きな音をもって、つむじ風と暴風と焼き尽くす火の炎をもって、あなたを訪れる。』(6節)『あなたを訪れる。』と書いてあるから、これは明らかに再臨についての預言である。すなわち、これは主が受肉された際にこの世に来られた初臨の時のことを預言したものではない。このような激しい力動的な表現がなされるのは、間違いなく再臨について預言されているからに他ならない。つまり、このイザヤ29章では紀元66~70年におけるユダヤ戦争の時期に再臨が起こると言われていることになるが、それはマタイ24章の内容と完全に一致している。先にも見たように、マタイ24章もユダヤ戦争を預言した箇所であって、そこでは再臨のことが預言されていた。しかし、このイザヤ29章は、紀元前585年にネブカデレザルがエルサレムを包囲した時のことを預言した箇所ではないか、と思われる方がいるかもしれない。確かに紀元前6世紀にも、ネブカデレザルの軍隊によりエルサレムが包囲されたのは歴史の事実である。だが、確かなところ、ここで預言されているのは、紀元前6世紀のほうの包囲ではなく、紀元1世紀のほうの包囲である。というのも、この箇所における6節目では、キリストの再臨のことが預言されているからである。前6世紀の包囲の際には包囲は起きたが、再臨は起きなかった。一方、紀元1世紀の包囲の際には包囲と共に再臨も起きた。だから、このイザヤ29章で預言されているのは、ネブカデレザルの包囲のことではなく、ティトゥス率いるローマ軍の包囲のことであると考えねばならない。まさか、紀元前6世紀の時に、キリストが『雷と地震と大きな音をもって、つむじ風と暴風と焼き尽くす火の炎をもって』再臨されたなどと考える人はいないであろう。そのように考える人がいたとすれば、気がおかしくなっていると思われたとしても文句は言えない。紀元前6世紀にキリストの再臨が起きるとは一体どういうことであろうか……。これで、このイザヤ29章が、ユダヤ戦争とその時期に起こる再臨について預言した箇所だということが確定した。さて、このイザヤの箇所では、エルサレムを包囲している際に再臨されたキリストとその軍勢を見た敵であるローマ兵たちにとって、その光景は『夢のよう』また『夜の幻のよう』であったと言われている。ここでは、エルサレムを包囲しているローマ兵たちの見た再臨と無数の聖なる者たちが彼らにとって幻影のように思われたということについて、次のように言われている。『アリエルに戦いをいどむすべての民の群れ、これを攻めて、これを取り囲み、これをしいたげる者たちはみな、夢のようになり、夜の幻のようになる。飢えた者が、夢の中で食べ、目がさめると、その腹はからであるように、渇いている者が、夢の中で飲み、目がさめると、なんとも疲れて、のどが干からびているように、シオンの山に戦いをいどむすべての民の群れも、そのようになる。』(7~8節)この部分(7~8節)は、再臨が起こると言われた部分(6節)のすぐ次の部分だから、再臨されたキリストにローマ軍が対峙しているということになる。聞いたであろうか。不信者たちにとって、その見た再臨の光景は、あたかも夢を見ているかのようであったと、ここでは言われている。つまり、彼らにとって再臨と空中にいた聖なる者たちの光景は、現実だとは思えなかったということである。これは私が自分勝手にこう述べているのではなく、聖書の記述に基づいて、このように述べているということを忘れてはならない。読者の方は、ここでよく考えていただきたい。再臨を見た不信者たちが、再臨の光景を幻影であると認識したというのは、一体どういうことであろうか。このことから分かるのは、こういうことである。すなわち、不信者たちにとって再臨と空中にいた聖なる者たちは幻影であるように思われたので、あまり重要であるとは思えず、脳における短期記憶の領域にそのイメージが格納され(※)、取るに足りないものとして記録されることがなかった、ということである。通常の場合、夢や幻を見て、それを記録として書き残そうとする人は、あまりいない。いちいち自分の見た夢や日中に頭に生じた幻をしっかりとメモする人は、変わった人だと思われても不思議ではないし、実際にそのような人はこの世にほとんど見られない。私の場合、そのようなことをする人を今まで一度も聞いたことがない。だから、不信者たちが幻影であると感じられた再臨の光景を記録として書き残さなかったとしても、何も驚くには当たらない。仮にエルサレムを包囲していた兵士たちが記録として再臨のことを書き残していたとしても、それは取るに足りないものとして後世にまで伝えられることなく散逸してしまっていたことであろう。事実、そのような記録は何も知られていない。数千冊にも及ぶ書物を読み漁ったギボンの『ローマ帝国衰亡史』でも、そのような記録にはまったく触れられていない。一体誰が無名のローマ兵が書いたものを、後世にまで残そうとするであろうか。また彼らが自分たちの見た再臨の光景を仲間内で話し合ったり、将軍であるティトゥスに報告したということがあったかもしれないが、しかしそれは幻影だと思えるものだったのだから、やはり後世にまで言い伝えられることがなかった。夢のように思えることを、一体誰が重要な事柄として後世にまで言い伝えられるようにするであろうか。そういうことだから、不信者たちが再臨を見たにもかかわらず、それを記録として残さなかったというのは、今書かれたように聖書からも論証できるのである。多くの聖徒たちは、私がたった今書いたことを読むまでは、次のように言っていたことであろう。「紀元1世紀の不信者たちが再臨を見たというのであれば、自分たちの見た再臨の光景を文章として書き残さなかったのはあり得ないことだ。あんなにも力動的な現象である再臨を見ておきながら、それを記録しないとはまったく考えられない。」このように言うのは、理性の感覚に基づいている。それは聖書に基づいた感覚ではなく、人間一般の感覚による。しかし、イザヤ書29章に基づいて考えると、こう言わねばならないことになる。「紀元1世紀の不信者たちは再臨を見たにもかかわらず、それを記録として書き残すことはしなかった。何故なら、彼らにとって再臨はあたかも夢や幻を見ているかのようだったからだ。いちいち夢や幻を記録として残すような人は、この世に珍しいのである。」聖徒たちのほとんど全ては、再臨について考究する際、このイザヤ29章の内容をまったく考慮していないはずである。だから、再臨を見た不信者が再臨のことを記録しなかったと聞かされても納得できない。しかし、このイザヤ29章の内容を考慮して再臨のことを考えると、どうであろうか。このイザヤの箇所では、再臨が不信者たちにとっては幻影だと感じられると言われている。であれば、むしろ再臨を記録として書き残していたほうがおかしいということに、ならないであろうか。もちろん、そうなるであろう。詰まる所、聖書から言えば、不信者たちが自分の目で見た再臨の光景を記録していなかったとしても、何もおかしいことはないのである。
(※)
長期記憶とは違って、短期記憶はすぐにも忘れ去られてしまう。不信者たちが再臨を幻影だと思ったのであれば、その再臨のイメージが短期記憶に納められたのは間違いない。この領域には、例えば朝食がそうだが、あまり重要だとは感じられないことが納められるからである。
[本文に戻る]
第8章 再臨に関する御言葉を信じることができない理由
これまでに書かれたことを読んでも、聖句で言われている再臨のことを信じれない人が、多くいるのではないかと思われる。そのような人たちが信じれない理由は、大きく分けて3つあると私は考える。以下にその3つの理由を記す。
まず一つ目は、その人が御霊を受けていないという理由である。御言葉という御霊に属することは、パウロも言うように、御霊によって弁えるべきものである。パウロはⅠコリント2:14でこう書いている。『生まれながらの人間は、神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。また、それを悟ることができません。なぜなら、御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。』もし御霊を受けていたとすれば、御霊の恵み深い働きかけにより、御言葉で言われている再臨のことが悟れるはずである。それは御霊を受けている人が、キリストの贖罪に関する御言葉を悟れるのと同じことである。しかし、御霊を受けていない生まれながらの人間は、御言葉で言われていることを受け入れず、愚かに思い、決して悟ることがない。その人には御霊による働きかけがまったく与えられないからである。犬が人間の言葉を、発達した言語を持たない未開人が文明人の言語を、知的障害者が正常な人間の喋ることを理解できないように、御霊を受けていない人も神の言葉を理解することができない。これは原理的なものであって、努力や時間の経過などによりどうにかなるというものではない。すなわち、原理的な意味において、御霊を受けていない者が、御言葉を悟ることは何であれ不可能なのである。それゆえ、再臨について述べられている聖句を信じられなかったり悟れなかったりする聖徒は、実のところ御霊を受けていなかったという可能性がある。
二つ目だが、それは「肉の思い」が聖書に対する真っ直ぐな信仰を妨げる、という理由である。肉の思いが多ければ多いほど、またその思いの度合いが強力であれば強力であるほど、当然ながら信仰が邪魔される傾向も高まってしまう。今取り扱われている再臨の場合、自分の立場や評価に関する肉の思いにより聖句を純粋に信じられない、というケースが多いはずである。それは例えば次のような思いである。「確かに再臨は既に起きたと聖書は教えているが、しかし、そのように信じたとすれば私の状態は一体どうなるのか?周りの兄弟から非難されたり問題になるのは目に見えている。そうなれば今いる教派や教会には、とてもではないがいられなくなる。そのようなことになるのであれば、仕方がないが、今のままの聖書理解でいるとしよう。」読者の方は分かったであろう。肉を殺すことができなかったからこそ、このように神の言葉に対する信仰が妨害されてしまったのである。このような人は御霊を受けてはいても、その御霊により再臨を正しく信じるという恵みのほうは受けていない。このような人は、肉によって再臨に関する真理を正しく信じようとしなかったのであるから、それから後、再臨に関する偽りの教義を信じるように惑わされるという罰を受け(※)、また真理を信じなかったのだから当然ながら天国で受ける栄光の輝きが減らされることであろう。
(※)
次のパウロによる御言葉が示す通り、何であれ真理である神の言葉を受け入れない者は、裁きとして偽りを信じるように惑わされることになる。『それゆえ神は、彼らが偽りを信じるように、惑わす力を送り込まれます。それは、真理を信じないで、悪を喜んでいたすべての者が、さばかれるためです。』(Ⅱテサロニケ2章11~12節)カルヴァンも言うように「神の言葉ほど尊いものはないので、それをあなどることを神が罰せずに置かれることはあり得ない」(『新約聖書註解Ⅴ 使徒行伝 上』3:23 p113:新教出版社)のであり、また「み言葉が軽蔑されることほど、神が怒られることはない」(『新約聖書註解Ⅰ 共観福音書 上』マタイ10:14 p347:新教出版社)。神の言葉を受け入れないとは、それを愚弄し軽んじることでなくて何であろうか。それは、神の言葉が真理でないと暗に告白しているのも同然なのだから。そのような者が裁きを受けるのは当然である。カルヴァンの次の言葉は心に留めておくに値する。「私たちが神の言葉から遠ざかれば、間違いなく、多くの偽りに身を任せることになってしまいます。そして、必ず道を踏み外すことになるのです。このことは覚えておきましょう。」(『アモス書講義』第2章 p52:新教出版社)
[本文に戻る]
三つ目は、御霊を受けているし、肉的な思いに信仰を妨げられるような人物でもないが、単に聖句で言われていることをよく理解できていなかったり、生来的に理解力が乏しいという理由が考えられる。聖句で言われていることをそもそもよく頭で理解していないのであれば、私が述べた再臨のことを信じれなかったとしても不思議ではない。自分がよく分かっていない事柄を、どうして意識的に信じられるであろうか。何だかよく分かっていないことを信じるのは、信仰とは言い難い。事柄を理性的に認識した上で信じるというのが「信仰」である。であるから、これは、そもそも信仰以前の問題だと言うべきことかもしれない。このような人は、事柄の理解に問題があるだけだから、十分な理解を持ったならば、上で述べられたことを信じられるであろう。
このように、もし御霊を受けているのであれば、神の恵みにより、再臨に対する聖書的な信仰を持つことができる。その人は再臨を正しく信じることが許された人である。しかし、御霊を受けていないか、肉の思いが妨げとなるか、理解が足りない、という問題があると再臨のことを正しく信じることはできない。その人は、たとえ御霊を受けてはいたとしても、再臨については正しく信じることが許されていない。だからこそ真の聖徒であるにもかかわらず、聖書における再臨の部分だけは正しく信じることができない。もし再臨を正しく信じられる人がいたら、その信仰は神から与えられた恵みによるものだから、何か自分を優れているかのように思って高ぶるべきではない。その人は、『高ぶらないで、かえって恐れなさい。』(ローマ11章20節)という神の言葉を心に留めるべきである。たとい多くの人が再臨を誤解しているからといって高ぶるのであれば、あのネブカデネザル王のように罰を受けたとしても文句は言えない(ダニエル書4章)。今は再臨を正しく信じている我々とて、神の恵みがなければ、他の人たちと同じように再臨を正しく信じることなどできなかったのである。
第9章 再臨は2度起こるのではないかという疑問
聖句がまざまざと再臨は既に起きたと教えていることを、御霊を受けた敬虔な聖徒であれば、認めざるを得なくさせられるであろう。それゆえ、そのような聖徒は、何か特別な理由でもない限り、聖句で言われている通りに、既に再臨は紀元1世紀に起きたという考えを持つに至る。実際、決して多い数ではないにしても、そのような考えに切り替えた聖徒たちを、私は今まで見てきた。しかし、ここで少なからぬ聖徒が混乱に陥り、再臨は2度起きるという奇妙な発明をしてしまう。再臨が既に起きたと知ると、どうしても人の心は、もう一度再臨が起きるという考えに導かれるようである。私と論争をした牧師も、再臨は2度起こるのではないかと言っていた。だが、再臨が2度起きるという理解は、まったく誤りであると言わねばならない。何故かといえば、聖書で言われていることからは、再臨が一度限り起こるとしか読めないからである。実際、私の述べたことを聞いて再臨が既に起きたと信じた人も、もし再臨が既に起きたと信じなかったとすれば―つまり以前のままの信仰であったとすれば―、まさか再臨が2度あるなどとは塵ほども考えなかったはずである。そのような考えは、思いつくことさえできなかったであろう。それは、聖書が再臨を一回限りのものとして書いているからに他ならない。再臨が既に起きたという新しく正しい理解に切り替えたからこそ、自分の持っていた過去の信仰とのつじつまを合わせるために、もう1度再臨が起きるに違いないなどと不思議な発想をするに至ってしまった。その人は、もし私が今ここで述べていることを全く知らなかったとすれば、たとえ再臨が2度あるなどという考えを聞かされたとしても、それを微笑しつつ無視していただろうと思われる。昔の教師たちも、それがアウグスティヌスであれテルトゥリアヌスであれクレメンスであれベルナルドゥスであれルターであれカルヴァンであれホィットフィールドであれ、誰一人として再臨が2度あるなどとは塵ほども考えていなかった。彼らにとって、そのようなことは思いつきもしなかったことである。ある教師の見解について言えば(この教師は既に再臨が起きたと信じている)、再臨が2度起きるという新奇な理解を、律法により論証している。この教師は、律法では清めが2回必要だと書いてあるからというので再臨も2回起こるなどと、何の躊躇もなく言い立てている。確かに律法では汚れを清めるためには2回の清めがなければいけないと書かれているが(※①)、だからといって再臨も2回起こるということにはならない。もしこの律法を根拠として再臨が2回起きると述べるのであれば、どうして他の事柄については2回でなくなてもよいとされているのか。例えば、どうして罪を犯した場合に悔い改めるのが1回でよいのか。確かに罪を犯した場合、悔い改めは1回だけでよく、その1回の悔い改めをすれば既にキリストにおいて罪は赦されている。罪の赦しを得るために悔い改めが2度必要だなどと述べるまともな教師は誰もいない。律法のゆえに再臨が2度起こるとせねばならないのであれば、我々における悔い改めと犯した罪の赦しも2度されなければいけない、ということにならないであろうか。もしこの律法のゆえに再臨の起きる回数を2倍にすることが可能であれば、原理的また論理的に言って、清めや更新や回復に関わる事象および行ないを何でもかんでも2倍にすることが可能となる。この教師は、律法における「清め」に関する記述のゆえに、再臨という「世界の改まり」に関する事象も2度なければいけないと述べているからである。このような見解は、単に自分独自の説を論証しようとして律法を勝手に利用しているに過ぎないものだから、受け入れるべきものではない。珍奇な私的解釈を聖なる律法によって支持させようとするとは、実に恐ろしいことである。これは自分勝手な非聖書的教義を周りの人に押し付けようとする者が行なう常套手段である。はっきりと言いたい。もし本当に2回再臨があるのだとすれば、神はそのことを聖書の中で、しっかりと書いておられたはずである。例えば、「贖い」はある意味において2回あるから、神はそのことを明瞭に聖書の中で書き記しておられる。すなわち、この地上で起こる贖いが書かれている箇所があれば(例えばエペソ1:7、コロサイ1:14)、今の身体が新しい御霊の身体に切り替えられるという未来に起こる贖いが書かれている箇所もあるが(ルカ21:28)、これは初心の聖徒でなければ、すぐにも見分けがつくものである。再臨に関する聖句の場合、このような区別はまったくなく、またそのように区別することもできず、ただ1回限りのものとしか解釈することができない(※②)。それは今まで2千年間の聖徒たちが、再臨を1回限りのものとしてのみ信じていたことからも分かる。つまり、誰一人として聖書から再臨が2度あるなどとは解せなかったのである。これは一体どういうことなのか。つまり、本当に再臨は1回しか起きないということである。だからこそ、再臨が2回もあるなどとはとてもではないが解釈できないような聖句以外には見つからないのである(※③)。さて、再臨が既に起きたと認めた聖徒が2回目の再臨を発明してしまうのは、つまる所、「肉」が最大の原因であると私は見ている。もし再臨が既に起きたとすれば、既に再臨が終わったのだから、論理的に考えて当然ながら再臨はもう起きないと考えざるを得ない。しかし、そんな考えを持っていることを他の聖徒たちに知られたら、どうなるのか。まず間違いなく驚かれて「異常」だと思われるだろうし、中には「異端」だと言いだす教師もいるはずである。そのような考えは今までに誰も持ってこなかったし、あの「使徒信条」の内容をも否定せねばならないことになるからである。再臨が既に起きたと知った聖徒たちは、そのような未来における危険を、意識的にであれ無意識的にであれ頭の中で感じる。聖徒たちにある肉は、そのような見解を持つことにより異端的な存在だとみなされることを大いに恐れる。すなわち、「再臨がもう起きないなどと言ったら批判の的になるのは目に見えている。使徒信条も唱えられなくなるから異端視されてしまう。一体どうすればよいのか。困ったことになったぞ。」という感情が、その聖徒の中に生じる。そのような状態になるのは大変苦しく悲惨なことである。人間の自然の情として、そのような状態になるのは出来れば避けたいことである。だからこそ、肉の働きがそのような状態に自分を至らせることを避けようとして、問題をなくすために、2度目の再臨などという考えを発明してしまうのである。そのようにして2度目の再臨があるなどと考え公言していれば、他の教会と同じようにこれから再臨が起こるという考えを持っていることになるのだから、それほど批判の対象になることもなくなり、その人は多かれ少なかれ安全な状態を享受できるようになる。もうお分かりであろう。要するに、2度目の再臨について主張する者たちは、「肉による弱さ」のために今までに誰も考えなかったような考えを発明してしまったのである。我々は、彼らのような見解を持つことをせず、再臨は一度限りの事象であったと信じるべきである。聖書が再臨について2度起こると示唆していたり明瞭に述べていれば話は別だっただろうが、そのようなことはないのである。
(※①)
『どのような死体にでも触れる者は、七日間、汚れる。その者は3日目と7日目に、汚れをきよめる水で罪の身をきよめ、きよくならなければならない。3日目と7日目に罪の身をきよめないなら、きよくなることはできない。』(民数記19章11~12節)
[本文に戻る]
(※②)
前述の教師は、一時期、マタイ25:14~30と25:31~46の箇所を、1回目の再臨と2回目の再臨に区別するという無謀を行なっていたことがあった。すなわちタラントが出てくるほうが紀元1世紀の再臨であり、羊と山羊が出てくるほうがまだ起きていない再臨という区別である。はっきり言えば、この区別は、完全に恣意的なものであって、聖書的な区別だとは間違っても言えない。再臨に関する諸々の聖句を見れば分かるように、第1回目の再臨の時に―とはいっても再臨は1回しかないのであるが―、キリストがその栄光の座に着かれることになる。これは全てのキリスト者が認めることである。第1回目の再臨が起きた時に、キリストが栄光の座に着かれないなどということが、どうしてあるであろうか。そのような再臨の仕方は、聖書が教えている再臨の仕方とは違っている。キリスト者ならば誰でも分かるように、「再臨」と「栄光の座への着座」という2つの出来事はセットであって、切り離して考えることはできない。であれば、この教師がかつて2回目だと思い違いをしていたマタイ25:31~46の再臨は、実は第1回目の再臨だったことになる―とはいっても再臨は1回しかないのであるが―。というのも、この箇所では『人の子が、その栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴って来るとき、人の子はその栄光の位に着きます。』(25章31節)と書いてあるからである。キリストが再臨される時には必ず栄光の座への着座があるのだから、キリストが栄光の座に着くと教えられている25:31~46の箇所が1回目の再臨を書いたものであるということは疑えない。もっとも、この教師は、後になってから25:31~46の箇所も紀元1世紀の再臨(つまり第1回目)のことではないのかという考えを持つに至ったようではある。今はどのような考えを持っているか私は知らないが、どうもこの教師は、自分の願望に聖句を合わせようとする傾向があると言わねばならない。
[本文に戻る]
(※③)
しかしながら<到来>であれば、2度起こると聖書は述べている。すなわち、それは受肉の時における「初臨」と、死者の復活が起こる時における「再臨」という2度の<到来>のことである。オリゲネスも、異端者のケルソスを反駁している書物の中で、次のように正しく説明している通りである。「ケルソスと彼のユダヤ人、そしてイエスを信じるに至っていないすべての人々は、預言がキリストの到来は2度あると語っているのを見逃しているが、最初のそれは、より人間の苦難に関わり、より謙遜なもので、キリストが人間たちと共にいることにより、神の道をたどることを教え、この世の人々の誰にも将来の審判について知らなかったという弁明の機会を残さないためである。もうひとつのそれは、栄光に満ち、唯一の神的な到来であって、人間の苦難がその神性には混合されていない。」(『キリスト教教父著作集8 オリゲネス3 ケルソス駁論Ⅰ』第1巻 56 p65:教文館)
[本文に戻る]
それでは、我々はもうキリストの再臨を待ち望むべきではないのであろうか。これは、その通りである。我々は、紀元1世紀の聖徒がそう言ったように『主イエスよ。来てください。』(黙示録22章20節)などと言うべきではない。紀元68年に再臨が起きるまでは、このようには言うのは正しいことだったし、それどころか、このように言わねばならないと命じられてさえいた。確かに黙示録の中では、神が『これを聞く者は、「来てください。」と言いなさい。』(22章17節)と命じておられる。何故なら、当時はまだ再臨が起きていなかったのだから、再臨がすぐに起こるようにと待ち望むべきだったからである。しかし今やキリストは再臨されたのであるから、我々がこのように言って再臨を待望するのは間違っている。既にキリストが来られたのに、またもう再臨は起きないのに、再臨を待ち望むというのは一体どういうことであろうか。そのようにするのは明らかに普通ではない。我々が再臨を誤解して『来てください。』などとどれだけ叫んでも、キリストが再臨されることはない。それは意味のないことを口にして時間と精神を無駄遣いすることに他ならないのである。
さて、もし再臨が起きて世界が改まったのであれば、これからこの世界はどうなっていくのであろうか、また我々はどのようにしていけばよいのであろうか。これは大変重要な事柄ではあるが、今はまだ語ることをしないでおきたい。読者の方は、もうしばらく待っていただきたい。というのも、この第一部は、再臨が既に起きたということに関する真実性を聖書から論証することを目的とした場所であって、「これからは一体どうなるのか」という未来に関する事柄を説明する場所ではないからである。そのような事柄は第二部において書かれるであろう。ここでは、とりあえず「既に再臨は起こった」という見解が証明されるだけで満足してほしい。何にでも時と秩序というものがある。ジャン・カルヴァンも「キリスト教綱要」では、まず神のことを、次にキリストのことを、そうしてから聖霊なる神のことを、というふうに事柄を順序立てて個別的に論じたものである。アウグスティヌスも「あらゆる場合にあらゆることを語るべきではない」(『アウグスティヌス著作集9 ペラギウス派駁論集(1)』自然と恩恵 第53章 62 p212:教文館)と正しいことを言っている。何も私は十分に説明できないから語るのを避けているということをしているわけではないのだから、読者はもう少しの間我慢してほしい。
第10章 今まで教会に再臨を正しく理解する解釈の恵みが与えられなかった理由
上で説明された見解は真に聖書的な解釈に基づくものだと私は信じているが、この見解が神の御心にかなった見解だとすると、教会は今まで2千年もの間、再臨の領域において誤謬の闇の中に放置されてきたことになる。すなわち、あらゆる聖徒たちは誠に長い期間、再臨を正しく理解する解釈の恵みを神から受けていなかったことになる。これは大変驚くべきことであり、多くの兄弟の心を動揺させることではないかと私には感じられる。何故なら、今まで聖徒たちが悲惨な誤謬に陥っているにもかかわらず、神がそれをそのままにしておかれたからである。これが一体どういうことなのかといえば、つまりまだ単に「時」ではなかったということである。ソロモンは何であれこの世界には時期というものがあると教えているが、それは次のように書いてある通りである。『天の下では、何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。』(伝道者の書3章1節)再臨を聖徒たちが正しく信じる「時」は今に至るまで、まだ訪れていなかった。しかし最近になって、その時が遂に訪れた。だからこそ、このようにして再臨の正しい解釈が神の恵みにより明らかにされることになった。―簡単に言えば、こういうことなのであろう。このことは、他のことでも同様である。例えば、20世紀になるまでは人類に自分たちの住む地球がどのような姿をしているのか、まだ神は明らかにしておられなかった。しかし20世紀になって時が来たので、神の恵みにより、我々は青くて美しい地球の姿を明瞭に見ることができるようになった。つまり、それまで約6000年の間に生きていた全ての人間は、地球の姿を目で見るという恵みをまだ神から受けることができないでいたのである。これは地球の姿以外にも、遺伝子や銀河や原子といった存在でも、まったく同じことがいえる。再臨の正しい理解が今まで隠されてきたことに動揺する兄弟は、他にもそのような例が多くあるということを知って、不安や混乱や疑念を抑えるべきである。神は、このようなやり方により、真理や本当の姿といったものを人間に明かされる方である。神は、ご自身の時に、ご自身の御心にかなったことをされるのである。一体誰が神に向かって「あなたはどうして今まで再臨を聖徒たちが正しく信じられないように誤謬の闇に放置してきてこられたのですか。」などと言えるであろうか。
しかし、このように思われる方も、もしかしたらいるかもしれない。「神が御民を本当に愛しておられるのだとすれば、再臨を正しく信じられないままの状態に留まらせておかれたというのは実におかしな話ではないか。もし神が我々に恵み深い方であれば、2千年もの間、再臨を誤解したままでいるようにはされなかったはずだ。そんなにも長い期間、誤謬を放置させておくとは、憐れみの神には相応しくないと言わねばならない。」このように言う気持ちは分からないでもないが、ではどうして聖徒たちは16世紀もの間、正典を正しく認識することが許されなかったのであろうか。正典とは神が聖徒たちに与えられた誠に重要で大切なものであって、この正典抜きには我々の信仰もまったくありえなかった。そのような重大極まりないものを、神は1500年もの間、教会で緻密に確定させることをさせないでこられた。カルヴァンも言うように「古代教父の間では正典に関する見解が殆ど確立していない」(『キリスト教綱要 改訳版 第4篇』第4篇 第9章 第14節 p192:新教出版社)状態が見られた。この古代教父の時代から約1000年経った16世紀の人であるルターでさえ、正典は全部で66巻だという認識を持てておらず、「シラの書」や「知恵の書」さえも正典に含まれていると考えていた(※①)。カトリックお気に入りのトマス・アクィナスも、神秘主義者のエックハルトも、この2つの巻を正典として認識していた。またあのジャン・カルヴァンでさえ、「ヨハネの手紙Ⅱ・Ⅲ」をある時までは、それが本当に正典に含められるべきものかどうか疑問に感じていた(最終的には正典であると認めるに至ったが)。既にキリスト教の歴史が1500年も経過しているのに、このような巨人たちでさえ、正典が66巻であると認識できていなかったのである。このように神は1500年もの間、聖徒たちが正典の数をしっかりと確定できないのを放置しておられたことになるが、このことについても我々は問題にすべきであろうか。つまり、「神が本当に御民を愛しておられるのだとすれば、正典を1500年も正しく確定できなかったことを放置しておかれるはずがどうしてあるだろうか。そのようにする神は恵み深くも憐れみ深くもない神だと言わねばならない。」などと悪く言うべきであろうか。当然ながら、こんなふざけたことを言う者は批判されても文句はいえないし、このように言うのは神に対する不敬である。また、このような文句を言ってもよいとすれば、他にも神が地球の姿や遺伝子や銀河といった存在を人類に長い間隠してこられたことを悪く言わねばならないことになる。「数千年もこのようなものを隠し続けてこられた神は愛のない酷いお方である。」などと。しかし、そのように文句を言う人がいたら、やはり批判されたとしても文句は言えないし、またそのように文句を言うのは間違っている。16世紀におけるカトリックも、ルターをはじめとした宗教改革者たちが出て来た際に、その信仰義認の教理をいぶかしげに思い、「もし信仰義認が真理であれば神はどうして長い間、教会にそれを隠し続けてこられたのか。なぜ、神はそんなに長い時代にわたって教会をさ迷わせ続けられたのか。」などと批判をしたものであった。しかし、このような批判は誤っており、誤っているがゆえに宗教改革者たちに打撃を与える批判とはならなかったのを我々は知っている。だから、我々に2千年間も再臨の正しい解釈が隠されてきたからといって、神に文句を言い立てるのは敬虔な態度に基づくものではないと言わねばならない(※②)。我々人間の親も、子どもに何かを与える際には、それを与える時期を選ぶ。車は非常に良いものであるが、それが良いものだからといって7歳の子に与える親はいない。その際、子どもが車を与えてくれないことに文句を言ったら、親である我々はどう思うであろうか。当然ながら、「まだ駄目なのだ。」というような思いを抱くであろう。神に対して再臨についての文句を言う人は、車を与えてくれないからというので親に文句を言う子どもとよく似ている。人間の親が子に何かを与える裁量権を持っているように、神も人間に何かを与える裁量権を持っておられる。子どもは「7歳の子に車を与えるのはまだよくない。」という親の心を尊重すべきである。神という我々の親にも「この理解を聖徒また人類に与えるのはまだよくない。」という御心があるのは誰にでも分かるはずである。人間の子が親の心を尊重すべきであれば、聖徒も自分たちの父である神の御心を尊重すべきである。たとえ神が再臨の正しい理解を2千年間も隠してこられたからといって(※③)、聖徒たちに対して恵み深くないということにはならない。神は、聖徒たちにキリストを与え、そのキリストのうちに保ち、日々多くの恵みを与えて下さっておられるではないか。それなのに再臨を隠してこられたという一つの点だけで、神を恵み深くない方だと認識してしまうのは、いかがなものかと私には思われる。
(※①)
特に、この「シラの書」は、聖徒たちが1000年以上もの間、正典であることを全く疑わなかった厄介な文書である。今から500年前になるまで、教会はこの文書に心を大いに奪われてきたといってよい。今では考えられないことだが、これまでこの外典から、それがあたかも神の言葉であるかのように多くの説教がなされてきた。アウグスティヌスにおいては、あまりにも酷かった。語るのも辛いほどであるが、彼が晩年になって聖徒向けの聖句集を編んだ時、もっとも引用されたのはこの「シラの書」からであった!アウグスティヌスほどに恵みを受けていた者が、聖句集の中に、実際は聖句ではないガラクタをもっとも多く組み入れたというのは、聞くことすら耐え難い悲劇である。しかし驚くなかれ、神がアウグスティヌスにこのような醜態を演じることを許されたのである。また現在では正典から外されてしまったが、かつてはソロモンの筆によると見做されてきた「知恵の書」について、アウグスティヌスはこのように言っている。「…知恵の書は、かくも多年にわたってキリスト教会において朗読されるに値していたものであって、不当な取り扱いを受けるべきではない。なぜなら、知恵の書は、人間の功績を主張して誤りに陥り、そのため最も明瞭な神の恩恵に対抗するようになる人たちに講義しているからである。」(『アウグスティヌス著作集10 ペラギウス派駁論集(2)』聖徒の予定 第14章 29 p220:教文館)「…この知恵書そのものを、すべての釈義家よりも優先させるようにしなければならない。なぜなら、使徒たちの時代にもっとも近い卓越した釈義家たちといえども、自分自身よりもこの書を優先させており、この書を証人として立てる場合には、ほかならない神的証言に諮っていると信じていたからである。」(同 28 p219)「…事情がこのようであるから、『知恵の書』から引用された聖句は拒絶されてはならなかったのである。この書物はキリストの教会において教会の講壇からかくも古から長年月にわたって朗読するに値したものであり、すべてのキリスト教徒によって、つまり司教から下ってもっとも低い平信徒、悔罪者、洗礼志願者にいたるまで、神的権威に対する尊崇の念をもって傾聴するに値したものである。」(同 27 p217)今では考えられないことだが、アウグスティヌスはこの『知恵の書』を正典と見做しており、そこに書かれている言葉を「聖句」だと何の疑いもなく言っている。この思い違いはルターの時代まで続き、カルヴァンの時代になってやっとこの書の正典性が疑われるようになった。これは何を意味するのか。それは、つまり約1500年もの間、神がその愛する全ての聖徒たちに思い違いをさせるのを許可されたということである。
[本文に戻る]
(※②)
このように真理が隠され誤謬の泥沼に沈んだたままの状態が許されたのは、あの「免償」の教理でも同様のことが言える。カルヴァンは、この免償の教理が長い間罰せられずに放置されたままでいたことについて、次のように言っている。「確かに、免償がかくも長い時代にわたって無傷で存続し、こんなに久しい間罰せられないままに無節度かつ狂暴な恣意を押し通して来たのは、人々がいかに深く誤謬の闇に沈んでいたかの証拠である。」(『キリスト教綱要 改訳版 第3篇』第3篇 第5章 第1節 p153:新教出版社)
[本文に戻る]
(※③)
このように神が隠されてきた聖書の教理や理解や箇所は、再臨についての他にも存在している。例えば、ローマ1:3~4の正しい理解がそうであった。ルターによれば、ルターの時代まで1500年の間、この聖句の正しい理解は聖徒たちに隠されたままであった。ルターさえも、このローマ書の箇所を、恐る恐る解き明かしている。彼はこの箇所について、こう書いている。「この箇所は、私の知るかぎり、だれからも真に、また、正しく解き明かされたことがない。初代教会の解釈者たちを不適切さが、最近の解釈者たちを霊の欠如が妨げてきた。」(『ルター著作集 第二集 第8巻(ローマ書講義・上)』スコリエ 第1章3~4 166 p225 聖文舎)
[本文に戻る]
それでは一体どうして神は、今まで2千年も明らかにされてこなかったことを、これを書いている私を通して明らかにしようとしておられるのであろうか。どうしてビリー・グラハムやマーティン・ロイドジョンズをはじめとした有名な牧師やバルトのような偉大と見なされている神学者ではなく、名もよく知られていない私により、このような正しい解釈が書き記されることになったのか。その理由は、はっきり言って私にも分からない。確かに私は自分に正しい聖書解釈が与えられていると自分では感じている。実際、私と話し合った人は、私の言ったことに答えられずに沈黙してしまうし、私の言うことを聖書的な見解として認めさえする。だが「一体なぜ私が?」という思いが前からあったのである。一つ言えるのは、私が無名であり、取るに足りない存在だからであろう(※①)。神はそのような存在にこそ真理を与えられる。それは聖書を見ても分かることである。使徒のほとんどは無名で取るに足りない漁師や取税人だったし、あのパウロも元はといえば教会を迫害するどうしようもない獣のごとき存在であった。ルターも同様であって、彼は注目されることもないただの一修道士に過ぎなかったが、キリスト教のために大いに用いられることになった。すなわち神は教皇や皇帝のようなビッグネームではなく、ルターという小さな存在をこそ教会のために選ばれたのである。神が、どうでもいいような存在を使われるということについては、他にも多くの例があるのを我々は知っている。だから、私がこの作品で本当に再臨の正しい解釈を述べているのであれば、それは神がこの世的には偉大ではない私を、その再臨の正しい解釈が伝えられるようになるために用いられたということになるのであろう。いずれにせよ、読者の方は、このような考察に値すると思われる見解を聞いて、人ではなくその書かれた内容にこそ注目してほしいと私は願うものである。神が私を通して再臨の正しい解釈を明らかにしておられるのであれば、私という人につまづいたがゆえにその書かれた内容を取り損なってしまうというのでは、大変悲惨である。しかし、内容のほうにこそ注目すれば、私という者がいかなる存在であれ、神の明かされた真理を取り損なうこともなくなる。それは、その人が内容を直視しているために、私という存在により内容が妨げられないからである。教皇と教皇主義者たちは、ルターの「人」につまづいたからこそ聖書の正しい解釈を取り損ねてしまった、ということを我々は忘れるべきではない。高慢な彼らは、真理を語るルターのことを「こんな修道士に過ぎない小物が口を大きく開いて生意気なことを言っているぞ。」などと思ったものである。神が私により再臨のことを聖徒たちに伝えようとしておられるのだとすれば、私をルターのように軽く取り扱うのは、あまりにも不幸なことである。
(※①)
ここで、筆者である私が知恵深いからこそ、このように分かることができているのだ、などと思う人があってはならない。私にはそれほど自覚がないのだが、確かに、今まで多くの人が私のことを賢いと評してきたのは事実である。しかし、だからといって、聖書の真理を正しく理解することができないのは明白である。もし頭が良いからというので真理を悟れるというのであれば、どうしてセネカは、ヒュームは、アダム・スミスは、ヴォルテールは、J・S・ミルは、アインシュタインは、聖書を悟れなかったのであろうか。彼らのうちで聖書の真理を悟れた者は一人もいない。もし知恵深いからといって真理を悟れるのであれば、最高の知者と言うべきこのような者たちが、聖書を悟れないのは説明がつかない。確かなところ、真理を理解できるのは、神が恵みを与えられるからに他ならない。知恵があろうがなかろうが、真理を理解できる人は理解でき、理解できない人は理解できない。つまり、神が理解させようと欲された者は理解できるが、そうでない者は誤謬の闇に留めさせられる。そこにおいて、人間の知力は一切考量されていない。神により恵みが与えられるか与えられないか。事はただこれだけである。我々は『人は、天から与えられるのでなければ、何も受けることはできません。』(ヨハネ3章27節)という聖書の言葉を、よく考えるべきである。聖書の真理に対する正しい理解は、人間の知性にではなく、神の恵みにだけ帰されねばならない。
[本文に戻る]
第11章 再臨に関する悔い改めについて
これまでに書かれた説明を読んで、再臨の正しい解釈を知ることができた者は、自分の今までの解釈を捨て、神の御前で悔い改めるべきであろう。再臨を待望する信仰が強力であればあったほど、その人は大いに悔い改めなければいけない。その人は間違った見解を強力に信じていたのだから、悔い改めも、当然ながらそれに応じたものでなければいけない。また、再臨の誤った考えを多くの人に伝えたり教えたりしていればいるほど、大いに悔い改めなければいけない。これは牧師や神学者や教師や伝道師などが、特にそうである。このような者は、周りにいる多くの人を誤謬の穴に引きずり込んだわけだから、悔い改めもそれに応じたものであるべきである。それは世の中において、その犯した罪の度合いが大きければ大きいほど、また多くの罪を犯せば犯すほど、悔い改めも大いになされねばいけないのと同じである。ただ教えを聞いているだけの聖徒であれば、教えている者に求められているほどの深い悔い改めは求められていないと私は思う。何故なら、その人は多くの人に聖書を誤って伝えたわけではないし、こういうと問題があるが言わば被害者的な面もあるからである。しかし、だからといって教えられるだけの者も、教職者ほどの深さは求められていなかったとしても、真剣な悔い改めが求められていることは言うまでもない。その人も、聖書を誤って信じていたことについては教職者と変わらないからである。つまり、教職者は責任が重いのであるから、それだけ悔悛の念も深くなければいけないということである。もし、あなたが悔い改めるならば、神はキリストにあってその誤りを赦して下さる。何故なら、神は憐れみ深く、『御子イエスの血はすべての罪から私たちをきよめ』(Ⅰヨハネ1章7節)るからである。本当に誤謬を奉じていたことを悔い改めたのに、神が赦して下さらないというのは、あり得ないことである。そうであれば、神は『咎とそむきと罪を赦す者』(出エジプト34章7節)ではないことになってしまう。それでは、もし悔い改めなかったら、どうなるというのか。再臨の正しい解釈を聞いても悔い改めないのは、実に危険である。その人は、報いとして真理から遠ざけられ、誤謬の闇に歩むことになる。真理と誤謬という2つの道は、前方に分かれている右と左という2つの道と似ている。もし人が右に進むならば左の道に進むことはできず、左の道に進むならば右の道に進むことはできない。それと同じように、もし誰かが真理の道に進むならば誤謬のほうに進むことはできず、誤謬の道に進むならば真理のほうに進むことはできない。我々は、どちらか一つしか選ぶことができない。すなわち、真理のコースに進んで真理の道を歩み続けるか、誤謬のコースに進んで誤謬の道を歩み続けるか、どちらかしか選べない。悔い改めるならば真理の道に進めるが、悔い改めなければ誤謬の道を突き進むことになり、神学の領域において呪われる。ますます誤謬の深みに入り込みたくなければ、その人は、悔い改めて真理を自分のものとしなければいけない。私がこのように書いても、自分の奉じる説が正しいと思うので悔い改める必要などないと感じる人もいるかもしれない。そのような人は、第8章でも説明されたように、御霊を受けていないか、肉の思いがあるか、私の述べたことをよく理解できていない。このような人は、恐らく神の恵みにより悔い改めるようにと定められていない。それゆえ、そのような人は悔い改めて正しい解釈を奉じることもなく、延々と誤謬の中に留まり続けることになる。
再臨に関して悔い改めた聖徒は、再臨の正しい解釈を、周りの人に伝え知らせるべきなのであろうか。もし、そのようにできるならば、そうするのが望ましいと私は思う。自分では伝える力がないというのであれば、この作品を見てもらえるようにするというだけでも、よいであろう。アロンのようなよく話す仲間がいるのであれば、その人に語ってもらってもよいであろう(出エジプト4:14~16)。もっとも、一番望ましいのは神から与えられた自分の力で伝えることではあるが。確かに神は、多くの人たちが聖書の真理を知るようになるのを望んでおられる。だからこそ、キリストは『全世界に出て行き、すべての造られた者に、福音を宣べ伝えなさい。』(マルコ16章15節)と言われたのだし、パウロも『みことばを宣べ伝えなさい。』(Ⅱテモテ3章2節)とテモテに命じたのである。そうであれば、神が多くの聖徒たちに再臨を正しく理解するようにと願っておられるのは、間違いないことである。何故なら、再臨の事柄も聖書の真理のうちの一つとして含まれているからである。今となっては再臨の真理が既に明らかにされているのだから、それを神が聖徒たちに知ってほしくないと思っておられることがどうしてあるであろうか。真理が明かされたということは、すなわち、その真理が多くの聖徒たちに知らされるべきだということであろう。何にせよ、まず我々がすべきなのは、ここで説明されたことをよく把握し、悔い改め、自分の信仰的な立場を変えることである。そうしてから初めて再臨のことを周囲の人に知らせることができるようになる。理解が足らず、悔い改めてもおらず、立場も変えていないというのに、どうして他者を説得させることができようか。自分の状態が何も変わっていなければ、他の人の状態を変えることもできないであろう。また、周りの人に知らせる際には、祈り、思慮を持つということを忘れるべきではない。というのは、祈らなければ神が働きかけて下さらず、思慮がなければ愚かな言行をしてしまいかねないからである。古代イスラエル人は、神に祈って指示をあおがなかったので、異邦人を自分たちの集団に受け入れるという害をこうむることになった(ヨシュア記9章)。ソロモンは『愚か者は思慮がないために死ぬ。』(箴言10章21節)と書いている。聖徒であれば誰でも、神の働きかけと共に何かをしたいと思うだろうし、思慮がないために死んだりするなどといったことはできれば避けたいと感じるであろう。であれば、再臨の正しい解釈を伝える際には、絶対に祈り、必ず思慮を持つべきだということになる。これは今の教会にとってはあまりにも刺激的なことだから、祈らなかったりやり方を間違えると、大変なことになりかねないのである。しかし、祈り、そのうえ思慮をもつのであれば、たとえ大きな論争に発展した場合でも最善の結果を享受することができるであろう。
しかし、そうはいっても、やはり、ここで書かれた再臨の見解を伝えたことにより生じると想定される論争や軋轢や諸々の問題が心の煩いとなり、誰かにこのことを伝えるのを躊躇してしまうという聖徒も実際多くいるのではないかと思われる。実際、私もこの見解を伝えたら、無視できない問題となり、大きな論争へと発展してしまった。ある牧師は、この見解を奉じたために所属していた教派から追い出されることになった。この見解を伝えても、今まで通りの状態でいることができないのは、既に伝える前から十分に予測可能である。こんなにも我々の心が捉われてしまう霊的な見解は、非常に珍しいからである。もしこのことを伝えた場合に何かの問題が起きたとしても、それは仕方がないことだと受け止めるべきであろう。真理を伝えると何かの問題が生じたり、大変な状態に陥ってしまうというのは、昔から世の常であったのを我々は知っている。あのエリヤは神の預言を告げたために、どれだけ大変な目にあったことか。キリストも真理を大胆に語られたので、凄まじい迫害を受け、最後には十字架へと渡されてしまった。三位一体の教義に大きく貢献したアタナシオスは、逃亡を続ける生活を送っていた。ルターは福音のゆえにカトリックから憎まれ、殺されても何も不思議ではない状況のうちに歩んだ。カルヴァンも宗教改革の最中にあって、ほら穴の中で集会と聖餐式を行なっていた。このように真理を伝えると大変なことになるのが自然の成り行きであるが、これは私が説明した再臨の見解についても同様のことがいえる。だが、だからといって真理を伝えるのを差し止めるべきであるということにはならない。我々は、キリストの言われた次の御言葉に耳を傾けるべきである。『義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。わたしのために、ののしられたり、迫害されたり、また、ありもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなたがたは幸いです。喜びなさい。喜びおどりなさい。天においてあなたがたの報いは大きいのだから。あなたがたより前に来た預言者たちも、そのように迫害されました。』(マタイ5章10~12節)我々の理性は「正しいことのために悪い状態になるのは不幸である。」と思う。これに対しキリストは「いや、そうではない。正しいことのために悪い状態になるのは幸いなことである。」と言われる。このようにキリストが言われたことを心に留めれば、多かれ少なかれ再臨の真理を伝えることに抵抗感がなくなるのではないかと私は思う。そのようにして真理を伝えれば、たとえこの世においてはより不幸になったとしても、いずれ行き着く天で受ける幸いの度合いはそのぶん増し加えられるのだから。どうか、再臨の真理を悟った聖徒たちの多くが、その真理を周りの者に伝えることができるよう神が働きかけて下さいますように。アーメン。
第12章 この再臨論に対する教職者の反応と態度
この章では、この再臨論を聞いた教職たちが、それに対してどのような反応や態度をとったのか書き記したい。どうしてかといえば、まず読者の情報が増えるようになるためである。私が本作品で取り扱っている問題は、実に重要であり、注目に値するものであるから、そのことに関する情報が増えるのは望ましいことではないかと私には思える。そして情報が増えることで、読者が、この問題に正しく対応できるようになるためでもある。もし情報が増えるのであれば、無知による偏見もなくなり、自分が理解してさえいない問題をさも知っているかのように堂々と批判するという愚を犯すこともなくなるであろう。もし情報が少なければ、それだけ事柄を把握できず、思慮もなく愚かな批判をしてしまう可能性が高まる。これは批判だけでなく質問や評価などをする場合も同様である。色々な情報があるからこそ、批判や質問や評価を正しく行なえるようにもなるということは言うまでもない。よって、本質的なことであるとは言えないが、私がここでこのような情報を読者に伝えるのは少なくとも無駄にはならないはずである。
まず第一に書くのは、私と激しい論争を行なったMT牧師である。この牧師は、再臨が既に起きたという見解を知った際に「私は今まで30年の間何をしてきたというのか。」と口からこぼした。彼がこのように言ったのは、恐らく再臨の正しい見解を真に悟ったからだと思われる。つまり、その見解を受け入れてしまえば今まで信じてきた見解をまったく捨てねばならず、自分が過去に言ってきたことも全て否定しなければならず、これまでにしてきたことが何もかも無駄だったように感じられたがゆえに、こうこぼしたのであろう。実際にはどう思ったか分からないが、いずれにせよ、この見解が正しいと感じたことだけは間違いない。そうでなければ一体どうしてこんなことを言ったのであろうか。確かにこの牧師は、私の説明を聞いて、再臨が既に起こったと聖書が教えていることを認めた。というのもマタイ16:28で言われている『ここに立っている人々』という言葉を、この牧師は紀元1世紀の人間であったと認めざるを得なかったからである。キリストはそれらの人々が生きている間に再臨が起こると言われたのだから、当然ながら『ここに立っている人々』がすなわち当時の人間であったとすれば、彼らが生きている紀元1世紀に再臨が起きたことになる。だからこそ彼は再臨が既に起きたことを認めたのである。もちろん彼がこのように考えたのは正解であった。しかしながら、彼は再臨が紀元1世紀に起きたことは認めたものの、もう再臨が起こらないという教会の常識に反したことは言えなかったために、教会の常識に合わせようとして2度目の再臨を開発してしまった。確かにこの牧師は「これから2度目の再臨もあるのだ。」と述べた。第9章でも説明されたが、彼は、常識の力や周りの人からの評価に関する懸念に屈服させられてしまったのである。真理を直視しようとせず、この世の威力に屈したがゆえにまともではない見解を発明してしまうのは、人間が弱いからである。その後、彼は証拠の不在につまづいたために、一度は既に再臨が起きたことを認めたにもかかわらず、自分が長い間信じ続けてきた見解に戻ってしまった。これは私がまだ証拠の不在について彼に詳しく説明できるほどに理解が進んでいなかったからであるが、彼がこの証拠の問題により、御言葉で言われていることを拒絶してしまったのは確かである。そうしてから、この牧師は自分の以前の見解を強烈に主張するだけになってしまった。聖句の内容を慎重に考察したり一つ一つの言葉にこだわることもせず、ただ聖句で「キリストの再臨が近い」と言われているからというので、「キリストの再臨が近い」と言うだけになった。聖句でこう言われているのは、パウロの時代に生きていた聖徒たちがすぐにも再臨を見ることになるからであったのだが…。つまり、彼は私のした説明をまったく考慮せず、その説明を脳内から切り捨ててしまい、ただ自分の見解に無我夢中でしがみつくだけになったのである。これは彼が真理を受け入れなかったために下された神学的な罰である。パウロが述べたように、真理を拒絶したからこそ偽りを信じるようになってしまったわけである。彼は真理の道を選ばずに偽りの道を選んだのだから、その偽りの道に突き進み、もう2度と真理の道に入ることはできないであろう。聖書を直視し真理を我が物としたく願う者は、この牧師から教訓を得なければいけない。我々は、この牧師のように証拠がないからといって御言葉を素直に信じないということがあってはならない。アウグスティヌスも言ったように「知るためにまず信ぜよ」。そうすれば、信じた後に、様々なことが知れるようにもなろう。この牧師も、天国という場所を真に知るために、天国へと人を導くイエス・キリストをまず信じたはずである。まずキリストを信じたからこそ、やがて天国を本当の意味で知れるようにもなる。まず天国に行って自分の目で確かめることにより証拠を得なければキリストを信じないという人は、決して天国には入れない。まず信仰があり、次に知識がやってくる。ここで説明されている再臨の見解も同様である。再臨の真実を詳しく知りたいならば、まず既に再臨が起きたことを信じなければならない。「証拠がないから信じない」と抵抗する人は、「天国を自分の目で確かめない限りキリストの救いを信じない」と抵抗する人と、本質的には何も変わらない。先に知識という果実を求めてどうするのか。その果実は、信仰という種を蒔かなければ得られないのである。
このような牧師もいる。それは私の説明を最終的には受け入れた牧師である。この牧師は、私が初めて説明した時には、まったく無反応であった。手応えのようなものがなく、私は空を打っているかのようであった。この牧師が言うには、私の説明を聞いても「何を言っているかよく分からなかった。」ということである。これは無理もなかったといえるかもしれない。何故なら、このような再臨に関する見解は、今まで一度たりとも聞いたことがなかったのだから。恐らく、他の多くの牧師も、私の説明を聞いた際、この牧師と同じような反応を示すのではないかと思われる。この見解は、驚きを通り越して思考が停止してしまうぐらいに今のキリスト教界では聞きなれない見解なのである。しかしながら、私がもう駄目かと諦めかけていた時期に、この牧師は自分の見解を変えた。すなわち、自分の今までの見解を捨て、再臨が既に起きたということを聖書により信じた。神がこの牧師に働きかけて下さったのである。そうでなければ誰がこのような見解を受け入れられるであろうか。聖書の真理は、たとえクリスチャンであっても、それを悟れるように定められていなければ、与えられないものである。それはバプテスマのヨハネが『人は、天から与えられるのでなければ、何も受けることはできません。』(ヨハネ3章27節)と言っている通りである。このことには多くの例がある。あのキプリアヌスは洗礼の1回性を信じることができなかったし(彼は再洗礼主義者であった)、ジョナサン・エドワーズも律法の第三効用を受け入れていなかった(彼は無律法主義者であった)。実に、このような高名な教師たちでさえ、神の恵みがなければ聖書の真理を受け入れられないのである。私が述べているこの再臨論もまったく同様のことが言える。この牧師は新しい見解に切り替えた時、「目からウロコが落ちるようだった。」とか「暗闇のベールが取り去られた。」などと言っていた。これは正にその通りだったであろう。再臨を正しく理解できたので、聖書、特に新約聖書の多くの部分が何を言っているのか分かるようになったからである。例を少し挙げよう。この牧師は、かつては再臨がこれから起こると信じていたので、一体どうして使徒たちが2千年経過しても起きないような出来事を当時の人たちに速やかに起こるかのように述べていたのか疑問に感じていた。しかし、それではあっても、他の多くの牧師たちと同じように、再臨がこれから起こると信じ、語ることを止めはしなかった。何故なら、これは教会の常識的な見解であって、その見解が正しいものであると教会および神学校で教えられたからである。だが、私の説明を聞いて再臨が既に起きたと理解した途端に、どうして使徒たちが再臨がすぐにも起こると述べたのか容易に理解できるようになった。もちろん、そのように述べられたのは本当にすぐに再臨が起きるからであった。それゆえ、この牧師は「なるほど、そういうことだったのか。」と思って解釈の眠りから目覚めることが出来たのである。これ以降、この牧師は以前の解釈には二度と後戻りすることがなくなった。この牧師は、今でもこの解釈を正しいものとして奉じ続けている。いや、神の恵みが、そのようにさせて下さっておられると言ったほうが正しいかもしれない。よって今後も、この牧師は、前の見解に再び戻るようなことは決してないであろう。この牧師は、真理の道を選んだのだから、その道に突き進むしかないのであって、誤謬の道のほうには移ろうとも移れないのである。
私とよく食事をしたある幼馴染みの伝道師は、私の説明に真っ向から向き合わなかった。私が何かを述べると、その述べられたことに、しっかりと答えてくれなかった。いや、正確には答えられなかったというべきであるが、私は真正面から答えが返ってこないので、もやもやとしたものである。彼は、私と堂々と向き合うことはせず、ただ自分の見解を主張するのみであった。「僕はこのように信じています。」と。彼は自分の見解を私に知らせるために、ジョージ・ラッドの『神の国の福音』から数十枚印刷して私にその紙を渡してきたこともあった。このぐらいの著者であれば、実際に話し合えた場合、私は何度でもその口を封じることができるのだが。このような伝道師は、私の説明に対抗できないものの、しかし私の見解を受け入れたくもなく、ずっと今の信仰に留まっていたいと思う人に多い。だからこそ、私の土俵に上がってこようとしないのである。もし私の土俵に上がれば、論戦に負けてしまうのが目に見えているからである。それゆえ、このような教職者は、自分の見解を一方的に主張することで、私に一応返答したつもりになっており、またそうすることで自分の信仰が揺るがないようにする。しかも、この伝道師は、私がカルヴァンやルターなどの教師らをよく引き合いに出しているのを聞いて、彼らを「ちょっと批判的すぎる」などと言った。今のなよなよしたキリスト教界に頭の先までつかっているこの伝道師にとって、ルターをはじめとした神の選びの器たちは愛がなく、野蛮な戦士とでも感じられたのであろう。彼はルターが「私が辛辣で復讐心が強いと、私を非難する。」(『ルター著作集 第一集 3』ローマの教皇制について p176:聖文舎)と言ったところの真理なき教皇主義者と同類の徒なのであろうか。私は彼らの攻撃的な面を批判するこの伝道師に驚いてしまった。というのも、カルヴァンであれルターであれ、あそこまで激しくなったのは真理への愛ゆえだったからである。この伝道師は、このように批判することで、自分が真理よりも優しさや寛容性といったものを第一にする人物であることを暗に告白している。そういった精神を持っていなければ、つまり聖書の真理を何よりも第一とする精神を持っているというのでなければ、ルターやカルヴァンの攻撃的な面を問題にすることなどできなかったであろう。彼にとっては愛や親和が何よりも大事であって(もちろんこのようなものが大事であることは間違いないが)、真理は二の次なのである。ルターやカルヴァンを批判する彼は、自分の愛する主も、邪悪なパリサイ人どもをこれ以上ないほど辛辣に批判されたことを忘れているか、そうでなけれ意識的に考えないようにしている。我々の主ほど忌まわしい者どもを辛辣に批判された方が他にいるであろうか。いないであろう(※)。また彼はスポルジョンを他の多くの教師たちと同じように高く見ており、そのスポルジョンの本を私にプレゼントしてくれたこともある。この伝道師は、このスポルジョンが強烈極まりない批判家であり、牧師・一般信徒を問わずクリスチャンである者をさえも厳しく批判し、「牧師殺し」とまで呼ばれた事実を知らなかったのであろうか。彼は知識量においては地方教会の伝道師としてはまあ合格ラインに達していたから、まさか知らなかったということはないと思われる。恐らく意識的に考えないようにしていたか、すっかり忘れていたのかもしれない。もしこの伝道師がカルヴァンやルターの攻撃性を批判したのであれば、今述べた主やスポルジョンをも批判しなければいけないのは確かである。何故なら、主はカルヴァンとルターよりも辛辣な批判を行なわれた方であり、スポルジョンはこの2人の宗教改革者と同等程度の批判家だったからである。彼はスポルジョンのほうは批判できたかもしれないが、主を批判することは間違ってもできなかったであろう。一体誰が「主はあまりにも批判的であった。」などと言えるであろうか。であれば主よりも批判性の少なかったカルヴァンとルターとスポルジョンをも批判すべきではなかったはずである。このようにこの伝道師は真理よりも安住や平和といったものを愛する人物であり、また私の説明をよく把握しているにもかかわらず真正面から対応しようとしなかったが、真の伝道師や牧師でありたいと願う者は、このようであってはならない。彼は、私の述べたことにしっかりと対面すべきであったし、もし批判できず沈黙させられてしまうようであれば、私の述べたことにへりくだって聞き従うべきであった。キケロやJ・S・ミルといった超一級の著述家であれば、このような「逃げ」の姿勢は取らなかったであろう。こう述べている私の基本姿勢も、相手の述べたことに一つ一つ対応し、認めざるを得ないことは認めて受け入れるというものである。預言者や使徒たちのように真理を愛する聖徒たちは、今のように交わりをこそ重視するなよなよしたキリスト教界の傾向を超越し、またこの伝道師を自分の教訓とし、真理を徹底的に愛し恋い慕うべきである。真理を愛する聖徒は「アーメン」と言うべきである。
(※)
この聖なる救い主が述べたパリサイ人に対する言葉はこうである。『忌まわしいものだ。目の見えぬ手引きども。』(マタイ23章16節)『愚かで、目の見えぬ人たち。』(同17節)『忌まわしいものだ。偽善の律法学者、パリサイ人たち。』(同23節)『あなたがたは、杯や皿の外側はきよめるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。』(同25節)『あなたがたは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は、死人の骨や、あらゆる汚れたものがいっぱいなように、あなたがたも、外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。』(同27~28節)『おまえたち蛇ども、まむしのすえども。おまえたちは、ゲヘナの刑罰をどうしてのがれることができよう。』(同33節)
[本文に戻る]
ある伝道師は、恐らく私の説明したことをよく理解できていなかったと思う。だから、この伝道師はこの問題について多くを語らなかった。私は今でも彼が、私の述べたこといついてどの程度の理解を持っていたのか分からないでいる。もし彼がこの問題をよく理解していたのに何も言わなかったとすれば、真理のために戦うことを恐れ、交わりのために真理を隅に押しやっていたことになる。すなわち、交わりをこそ全てに勝る至上のものとしていたことになる。実際はどうだったか判定できないのだが、もし彼がよく理解できていなかっただけならば情状酌量の余地があると私としては思う。理解力があまりなく、よく理解できなかったのであれば、たとえこの問題にタッチしない傾向があったとしても、大いに責められるべきだとは言えないであろう。カルヴァンもよく分からなかった黙示録の注解書をあえて書こうとはしなかったし、それ以外にも理解が足りないことについては多くを語らなかった。しかし、事柄をよく理解していたにもかかわらず真理よりも交わりのほうを優先させていたのだとすれば、これは大いに批判されるべきである。もし交わりよりも真理を優先させるべきだとすれば、預言者は何も預言できなかっただろうし、キリストも真理を大胆にお語りにならなかっただろうし、ルターも有名になっていなかったであろう。真理のほうが交わりよりも上に置かれるべきだということは、敬虔な人であれば誰も疑わないはずである。交わりを否定するのではないが、真理よりも交わりを上にするのは、明らかに間違っていると言わねばならない。実際はどうか分からないが、もし彼が本当にそのようにしていたのだとすれば、実に問題である。ルターはこう言った。「真理なき愛は消えうせよ」と。プルデンティウスもこう言った。「真理への愛よりも崇高なものはありません」(『聖アンブロシウスの賛歌』プルデンティウス「ペリステファノン・リベル」 p190:サンパウロ)と。真理を愛する者は、この2人の言葉をよく弁えるべきであろう。伝道者が真理を蔑ろにして交わりこそを重視すべきだとすれば、テレビに出てくる芸人のほうがよい伝道者になれるであろう。実際、面白い芸人たちは大衆の心を掴み、人とのコミュニケーション能力も優れたものを持っているのだから。
書き記すに値するのは、現段階では、このぐらいである。他にも私の話を聞いた教職者や一般信徒は多くいるが、取り立てて紹介するほどの反応を示したとは言い難い(※)。これからも書き記すに相応しい教職者が現われたならば、この章に加筆することで、読者に紹介したいと思っている。それは、些末であるといえばそうかもしれないが、この再臨論に関する読者の情報量が増し加えられるためである。これは本質的な情報とは言えないが、しかしまったく無駄な情報だというのでもないのである。これを書いている私自身も、ここに書かれたような不信仰な者とならないように注意せねばならない。『私がほかの人に宣べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるようなことのないため』(Ⅰコリント9章27節)である。
(※)
牧師たちについて言えば、その多くは私が何かを言っても、ほとんど無反応である。実際、私がこの見解を伝えると、はっきりとした反応が返ってくることは珍しい。未信者に福音を宣べ伝えると、じっとしたまま眉一つ動かさないという無反応の態度を示す場合が多い。牧師であれば、これはよく経験しているはずである。私がこの見解を伝えても無反応であるのは、これと全く同じである。だから私がこの見解を伝えていると、私のうちにはあたかも未信者に福音を宣べ伝えているかのような錯覚が生じてしまう。しかし、どうしてこのような反応となってしまうのか。それは、人間という被造物が、まったく新しいことに触れるとフリーズするように設計されているからである。これは誰でも経験したことがあるはずである。つまり、私の述べた見解が新しく感じられ、それに対してどのように対応したらよいか分からないので、大きな反応を示すことが出来ないのである。時間の経過と共に徐々にこの見解を掴めるようになっていくが、かなり掴めるようになっても、この見解を受け容れようとする牧師は非常に少ない。何故か。「今までに誰もそのようなことは言っていなかったから。」である。なんということか!!真理の判定基準が、歴史における人々の同意にかかっているとでもいうのか!!それはとんでもないことである!思い返してもみてほしい。「誰も今までにそんなことを言う者はいなかったぞ。」などと思われたり言われたりしたがゆえに、キリストもルターもコペルニクスも拒絶されたではないか。確かなところ、今までに誰にも語られなかったとしても(これはこの再臨論がそうである)、今までに語られはしたが否定され続けてきたとしても(これは近代になるまでの原子論がそうである)、今までにも今も公然と受け入れられているとしても(これは三位一体論がそうである)、真理が真理であることには変わらない。真理は人々の同意を超越しているということを、私は聖徒たちによく覚えてほしいと思う。真理が人々の同意にかかっているとすれば、人々の同意こそが真理だということになり、真理は人間理性に服する隷属者に引き下げられてしまうのである。カルヴァンも言うように、「その賢さがただの虚栄以外の何物でもない人間の判断に、神の真理を委ねることほど馬鹿げたことは全くない」(『新約聖書註解Ⅰ 共観福音書 上』ルカ7:29 p379:新教出版社)。敬虔なユスティノスもこう言っている。「真理の基準に照らして敬虔な者、また愛知者であるなら、昔の人々の意見がもし間違っている時は、これに従うことを拒否し、ただ真実だけを重んじ愛すべきことをロゴスは命じております。」(『キリスト教教父著作集1 ユスティノス』『第一弁明』2:1 p17:教文館)それゆえ牧師たちは、周りの人々が持つ判断や今までの歴史がどうであれ、もしこの見解が真理であると悟れたならば、それを受け入れるのが望ましいということは確かである。真理が根本的に人間の同意や歴史の常識にかかっていると考える道理の分からない人であれば話は別であるが…。少し厳しいことを言うようであるが、今の時代の牧師たちは、もし真理よりも人間のほうを優先させるというのであれば、あの悪霊(ダイモーン)に憑かれた青少年好きのソクラテス以下と呼ばれてしまってもよいのであろうか。この思索力だけは達者な哲学者は、偶像崇拝をしている異教徒なのに「しかしたしかに、真理よりも人間の方が尊重さるべきではないのだ。」(※プラトン『国家』X595c 山本光雄訳)などと心に留めるべきことを言ったのである。
[本文に戻る]
第1部 既に起きた再臨 [了]
第2部 再臨と再臨の前後に起きた諸々の出来事の詳細およびその順序
第1章 第2部の説明
第1部では、聖書は既に再臨が起きたと我々に教えているということが、聖書に基づいて信仰的に論証された。霊の人であれば、第1部で説明されたことを悟り、認め、受け入れることができたであろう。その人は霊的な人であって、徹底的に聖書から思考できる恵みを受けているからである。しかし、私の説明がよく分からなかった人は、何かがおかしいと思っていただきたい。すなわち、私の説明に問題があるというのではなく、その人の霊や信仰の状態に何らかの問題がある。だからこそ、私の霊的な論証を素直に受け入れられなかったり、よく理解できなかったのである。私はとにかく聖書に基づいて説明をしたのだから、もし徹底的に聖書から考えるのであれば、確かに既に再臨が起きたと考えざるを得ないのである。
私はまだ再臨と再臨の前後に起きる出来事の詳細とその起こる順序については、詳しいことを語っていない。というのは、第1部では、ただ再臨が既に起きたという見解の真実性を論証することだけを目的としていたからである。そこでは、この作品の構成から言えば、まだ再臨と再臨の前後に起きる出来事を詳しく説明するべきではなかった。しかし今や、そのことを語るべき時が到来した。このことは読者がより豊かに再臨を理解できるようになるためにも、入念に説明されねばならない。読者がこの第2部で書かれる説明をよく理解するのであれば、読者の持つ再臨理解における輪郭がますます明瞭になるであろう。今はまだ多くの読者が「もやもや」とした輪郭のハッキリしない再臨理解しか持てていないと思うが、その「もやもや」が取り除かれることになるわけである。
それでは私は神が書ける恵みを与えて下さる限りにおいて、いったい再臨とその前後に起きる出来事とはどのようなものであったのかということを、今からこの第2部で書いていくことにしたい。願わくば、神が我々に理解できるよう霊的な知恵と理解力とを豊かに与えて下さいますように。アーメン。
第2章 再臨と再臨の前後に起きた出来事の順序
既に目次の場所で一通り書いたのではあるが、まずは再び再臨と再臨の前後に起きた出来事の順序を大まかに示すことにしたい。それは、これから書かれるべき事柄をあらかじめ眺めることで、読者が内容をより把握しやすくなるためである。事前に語られるべき事柄を俯瞰できたほうが、言うまでもなく、よりよく理解するためには良い。この第2部で、これから書かれることになる内容の順序は以下の通りである。この第2部は、この順序に従って一つ一つ説明されることになる。
①教会による42ヶ月の預言活動(紀元61年6月~64年12月)
②ネロによる42ヶ月の迫害(紀元64年12月~68年6月9日)
③再臨(紀元68年6月9日)
④エルサレムの包囲と滅亡(紀元68年6月9日~70年9月)
第3章 ①教会による42ヶ月の預言活動(紀元61年6月~64年12月)
まず最初に書かれるのは、教会が42ヶ月の間行なった預言活動のことである。これは紀元61年6月~64年12月の間のことである。どうして、この出来事から書くかといえば、そのようにするのが自然であり相応しいからである。この出来事よりも前の出来事は、取り立てて書き記すに値するものとは私には思えない。いや、カリグラがエルサレム神殿の中にゼウス像を安置しようとした事件をはじめ、それ自体としては書き記すに相応しいものが多くあるにはある。しかし、そのような出来事であっても、再臨を中心的な題目とする本作品においては書くに適したものとは言えない。つまり、本作品は再臨と再臨の前後に起きた出来事にスポットライトを当てるものだから、そのような内容に相応しい出来事しか書き記さないということである。よって、この60年代前半に行なわれた預言活動よりも前に起きた出来事は、全て省略しても差し支えないものである。私はそのような出来事をも書くことで、この作品を冗長なものにしたくはない。
さて、60年代の前半に42ヶ月教会が預言活動をするというのは、黙示録11:3に書いてあることである。そこではこう言われている。『それから、わたしがわたしのふたりの証人に許すと、彼らは荒布を着て1260日の間預言する。』1260日とは、第1部でも書いたように『42ヶ月』である。この2人の証人について、続く11:4の箇所ではこう説明されている。『彼らは全地の主の御前にある2本のオリーブの木、また二つの燭台である。』まず、2つの燭台とは何か。キリストは黙示録1:20で『七つの燭台は七つの教会である。』と言われた。それゆえ『二つの燭台』とは、つまり「2つの教会」のことである。次に、2本のオリーブの木とは何か。これは間違いなくゼカリヤ書に基づく記述であり、そのゼカリヤ書によれば『全地の主のそばに立つ、ふたりの油そそがれた者』(4章14節)である。この2つの存在が何を指すのかは、様々なことが考えられる。私は以前、この2人の証人における諸々の見解に関して次のように書いた。<まず異邦人の教会とユダヤ人の教会という2つの教会を示すことで、教会全体を指していると考えることが可能である。もしくはエルサレム教会とローマ教会という2つの有名な教会を指していると考えることもできる。あるいはある2つの教会にいる代表的な預言者を指すと考えることもできるであろう。パウロとペテロを指していると考えることもできなくはない。これ以外に興味深いものとしては「ニコデモ福音書」の記述がある。その記述に基づいて考えると、この2人の証人とはエリヤとエノクだということになる。少し長いが、その記述を引用することにしよう。「さて主は父祖アダムを手でつかんで天国におもむかれ、大天使ミカエルに手わたし給うた。他のすべての義人達をもわたし給うた。彼らが天国の門をはいると、そこで、2人の高齢の人に出会った。聖なる父祖達はこの2人に言った、「死ぬことがなく、従ってハデスにくだったこともなく、肉体も精神もそのままにこの天国に住んでおいでになるあなた方はどなたですか。」そのうちの一人が答えて言った、「私は神様のお気に入りのエノクです。神様が私をここに移して下さったのです。またこちらはテシベ人のエリヤさんで、私達二人は世の終りまで生きることになっているのです。世の終りになると反キリストが起こるのですが、その時に私達は神様によってつかわされ、反キリストによって殺されます。けれども三日後には復活して、雲にのって主にお会いするために連れられてくることになっています。」」(『聖書外典偽典6 新約外典Ⅰ』ニコデモ福音書(ピラト行伝)第章25節(第9章)1節 p217:教文館)今引用した外典の記述は、明らかに黙示録11章の箇所と対応している。2人の証人がエリヤとエノクだというのは、何だかもっともらしく感じられる理解である。というのも、この2人の有名な人物は黙示録11:3~12に出てくる2人の証人と、どこか似通っているように思えるからである。エリファス・レヴィも、この2人の証人はエリヤとエノクであるなどと外典に基づいて言っている(『高等魔術の教理と祭儀 教理篇』神殿の支柱 p70:人文書院)。このエリヤとエノクは、どちらも神により生きたままで天に上げられた(※①)。黙示録11:12でも、2人の証人が『雲に乗って天に上った』と書かれている。またエリヤとエノクは、どちらも紛れもない預言者であった。黙示録11章に出てくる証人も預言をしている。つまり、預言者であるという点でエリヤとエノクは、この黙示録の証人と同じである。またエリヤは、火を天から降らせることにより、敵であった多くの者たちに打ち勝った(Ⅰ列王記18章)。黙示録11:5でも、証人が火により敵を滅ぼし尽くすということが書かれている。火により敵対者を死に至らしめるという点で、どちらも一緒である。また黙示録11:6では『この人たちは、預言をしている期間は雨が降らないように天を閉じる力を持っており』と書いてあるが、エノクは別として、これは正にエリヤそのものである。我々が既に知っているように、エリヤは雨が降らないようにと天を祈りにより閉じたのである。また黙示録11:6では、証人に凄まじい業を行なう力が与えられていることが分かるが、エリヤも数々の奇跡を行なったということを我々は知っている。驚くべき業を行なえるという点で、黙示録の証人もエリヤも同じである。エノクが奇跡を行なったことについては聖書に何も書かれていないが、彼は神に喜ばれる人だったのだから、エリヤのように奇跡を行なっていたとしても何もおかしなことではない。また、エリヤとエノクが生きたまま天に上げられたのは、我々が今見ているこの42ヶ月間の時のために生命を言わば留保させられたのだと考えることも出来なくはない。つまり、エリヤとエノクが自分たちの時代においては死を味わわなかったのは、やがてこの42ヶ月の活動のために遣わされるためであり、その活動を終えた後にこそ死を味わうようにと死を後回しにさせられたのではないか、という見解である。すなわち、これはエリヤとエノクの死が遥か未来に「ずらされた」ということである。神の名は『不思議』(士師記13章18節)だから、このように不思議に思えるようなことを神が為されたとしても、何もおかしいことではない。確かに、この2人の証人をエリヤとエノクだと考えると、この箇所がよく理解できそうではある。しかし、だからといって本当にそうだと言えるのであろうか。多くの類似性が見られるからといって、必ずしも同一人物だということにはならない。何故なら、ただ単に似ているだけで実際は違うという可能性もあるからである。私としては、この証人がエリヤとエノクだという見解には、非常に心が強く惹かれることを告白する。何よりも問題なのは、この「ニコデモ福音書」が正典ではないということである。もしこの文書が正典であれば、この2人の証人がエリヤとエノクだということは100%確定する。しかし、これは外典に過ぎず、あくまでも参考情報としての意味しか持たないのであるから、この外典に基づいて証人をエリヤとエノクだと断定することは難しい。私としては「可能性としては十分にあり得る」としか言えないと思う。一つ言えるのは、この証人がエリヤとエノクだとする見解は、何も聖書の内容に違反しないということである。そればかりでなく、そのような見解は、この黙示録11章の記述とよく合致するとさえ言える。それは「なるほど」と感じられるような見解なのである。もし、この2つの存在が本当にエリヤとエノクであったとすれば、神が我々に悟りと確信とを与えて下さらんことを。事のついでに書いておくが、この2人の証人が、バプテスマのヨハネや義人ノアだったのではないかと考える人もいるかもしれないが、エリヤとエノクであれば話はまだ分かるものの、ヨハネとノアは私としては考えられないと思う。というのも、聖書には彼らが2人の証人だと匂わせる箇所はないし、またこの2人の証人がヨハネとノアだったとはどうしても思えないからである。もしヨハネとノアだと考えるのであれば、エリヤとエノクの2人のほうが、可能性としては遥かに高い。これはヨハネとノア以外の人であっても、―例えばアダムやヨブやイザヤなど―、同じことが言える。いずれにせよ、これがある2つの教会か2人の預言者たち、そうでなければ教会および聖徒たち全体のことを指しているのは確かである。この存在を、ひとまず「教会勢力」と呼んでおくことにしても特に問題はないであろう。意味はやや曖昧であるが、何か間違ったことを言っているというのでもないからである。>……私は以前、まだ黙示録の理解が進んでいなかったため、このように書いたのであったが、黙示録の註解を神の恵みにより書き終えた今では、この2人の証人が聖徒たち全体を意味しているという解に至っている。これは、エリヤとエノクなどではない。何故なら、外典の中で言われているのは単なる空想に過ぎない作り話だから。今になって思えば、この外典の著者は、明らかにエリヤが再来すると教えている旧約の預言を正しく理解していないために誤りを書くというミスを犯した。つまり、この著者は、エリヤが再び遣わされるというマラキ書の預言(4:5)を、バプテスマのヨハネについて言われたことだと理解していなかった。だからこそ、エリヤの到来についての預言を黙示録に書かれている2人の証人に結び付けてしまったのである。少し考えれば分かるが、再来したエリヤがバプテスマのヨハネであれば、そのエリヤは黙示録に書かれている2人の証人(のうちの一人)では有りえない。それだから、この2人の証人を外典などという神の言葉でない矮小な制作物によって検討していたのは、私の大きなミスであった。私は何をしていたのかよく分からない。パウロのように、『私には、自分のしていることがわかりません。』(ローマ7章15節)と言いたいところである。またこれは、パウロとペテロでもない。何故なら、黙示録11:7~8の箇所によれば、この2人の証人はエルサレムで死ぬことになるからである。多くの人により伝えられた話によれば、パウロとペテロが死んだ場所はエルサレムではなくローマである(※②)。もしこの2人の証人がローマで死んだパウロとペテロだったとすれば、黙示録では2人の証人がエルサレムで死ぬことになるなどとは書かれていなかったであろう。またこれは、その他の有力な2人の個人的な聖徒でもない。ある特定の有名な2つの教会でもない。この2人の証人についての詳細は、第3部の黙示録註解における当該箇所の中で論じられているから、今すぐに見るにせよ後ほど見るにせよ、そちらのほうで確認していただきたい。なお、この2人の証人はすなわち聖徒の全体を意味しているから、私が以前述べたように、これを「教会勢力」と呼んだとしても何も問題にはならない。さて、この教会勢力が、黙示録に書いてあるように42ヵ月の間許された預言する活動を、紀元61年6月~64年12月に行なった。これは本当の意味での預言だったと考えられる。すなわち、これからすぐにも訪れることになるネロの大迫害およびあの悲惨なユダヤ戦争のことを、多くの人たちに向かって預言したのだと考えられる。つまり、ここで言われている『預言』とは文字通りに捉えるべきものだと私は考える。もうあと3年と半年もすれば邪悪なネロが聖徒たちを迫害するようになるのだから、そのことをあらかじめ知らせるために、神が彼らに預言させたのだとしても何もおかしくはない。『神は愛』(Ⅰヨハネ4章8、16節)であられるから、聖徒たちが突然の苦難に慌てないようにと、事前に預言を通して心の準備をさせて下さったと考えるのは荒唐無稽とは言えないであろう。彼らが預言をしている期間、彼らは凄まじい力を持っていた。黙示録11:5では次のように書いてある。『彼らに害を加えようとする者があれば、火が彼らの口から出て、敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとする者があれば、必ずこのように殺される。』ここに書いてある『火』とは、御言葉による裁きのことであろう。この42ヶ月の間に教会に害を加えようとする者たちは、聖徒たちの口から出る御言葉の火によって裁かれ、殺されてしまった。これは、ちょうどエリシャを侮辱した42人の子どもたちが、エリシャの口から出た呪いの言葉により殺されてしまったのと同じである(※③)。また、彼らの凄まじい力については、他にもこのように書かれている。『この人たちは、預言をしている期間は雨が降らないように天を閉じる力を持っており、また、水を血に変え、そのうえ、思うままに、何度でも、あらゆる災害をもって地を打つ力を持っている。』(黙示録11章6節)彼らは、祈りにより天を閉じたり開いたりしたエリヤのように(※④)、祈ることで天候に働きかけることができた。また『水を血に変え』ることもできたが、これは聖徒たちの血を流した者に対する報いのことであろう。聖徒の血を流した者は、神からの報いとして、自分自身の血で自分を酔わせることになる。つまり、自分が血を流したように自分も血を流されてしまう。そのことが「水が血に変わる」と表現されている。これは黙示録15:4~6を見ると、よく理解できる(※⑤)。要するに、これは血の復讐のことである。この表現は黙示録ではよく使われる表現だから、心に留めておくのが望ましい。『あらゆる災害をもって地を打つ』と書いてあるのは、そのまま受け取るべきであろう。当時のような世の終わりの時期にあっては、神が聖徒たちを通して多くの災害を地に送られたとしても、何も不思議なことはない。今の時代とは違い、当時はまだ恐るべき奇跡や不思議な業などといった多くの超自然的現象が聖徒により起こされていたということも考慮すべきである。もしこれが物理的な現象を述べたものでないのだとすれば、御言葉による人々への霊的な攻撃を、物理的な表現に変換して語ったものであろう。このような凄まじい力が与えられていた2人の証人に、当時の人たちは苦しめられた。『このふたりの預言者が、地に住む人々を苦しめた』(黙示録11章10節)と書いてある通りである。また人々はこの聖徒たちに打ち勝つことができなかった。もし聖徒たちに無謀にも対抗しようとすれば、『火が彼らの口から出て、敵を滅ぼし尽くす』(黙示録11章5節)からである。教会が42ヶ月もの間、このような力ある状態と活動に与かることができたのは、神がそのようになることを許可され恵みを注がれたからである。そうでなければ、どうしてこのような状態と活動に与かることができようか。
(※①)
エリヤの昇天についての記述は次の通り。『こうして、彼らがなお進みながら話していると、なんと、一台の火の戦車と火の馬とが現われ、このふたりの間を分け隔て、エリヤは、たつまきに乗って天へ上って行った。』(Ⅱ列王記2章11節)エノクの昇天についてはこう書かれている。『エノクは神とともに歩んだ。神が彼を取られたので、彼はいなくなった。』(創世記5章24節)『信仰によって、エノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて、見えなくなりました。移される前に、彼は神に喜ばれていることが、あかしされていました。』(ヘブル11章5節)
[本文に戻る]
(※②)
<1>
古代教会最大のラテン詩人であるプルデンティウスは、パウロとペテロの死について次のように言っている。
「(6-10:ペテロはネロ帝治下に、バチカン丘上のネロ帝円形競技場で逆十字架刑にされ、パウロはオスティア街道沿いのアクアェ・サルヴィアェ(トレ・フォンタネ)で斬首されたと伝えられている)
最初にペトロがネロ皇帝の宣告で
高い木に吊り下げられるよう命じられました
しかしペトロは高くそびえる木の上での処刑で
偉大な師の栄光を得ようとすることを恐れて
頭を下にし、足を上にして
こうして頭のてっぺんが一番下の方を見るように要求しました
それゆえペトロの手は下の方で縛られ、足は頂上へ向けて縛られ
彼の一層気高い精神が、より卑しい姿勢になりました
ペトロは天が低いところから、より一層早く到達されるのがならわしであるのを知っていて
彼の魂を任せるために、頭を下げました
移り行く年月の円周軌道が完全に円を走行して
のぼる太陽が再び同じ日に回帰したとき
ネロ皇帝は異教者たちの教師が打ち首にされるよう命令して
燃える激しい怒りをパウロの首に吐き出しました
パウロ自身がこの世を去る時が近づいていることを、前もってこう言っています。
『わたしはキリストのところへ行かなければなりません。世を去る時が近づきました』
パウロは直ちに逮捕され、処刑が宣告され、剣で首を切られました
予定通りの日時でした
テベレ河は2人の遺骨を分かち
神聖に清められた墓地の間を流れながらその両岸は聖別されています」
(『聖アンブロシウスの賛歌』プルデンティウス「ペリステファノン・リベル」 12 使徒ペトロとパウロの受難 p245~246:サンパウロ)
<2>
ペテロの死についてカルヴァンはこう言っている。
「ペテロがローマで死んだことについては著作家たちが一致しているので、私はその点では反対しない」(『キリスト教綱要 改訳版 第4篇』第4篇 第6章 第15節 p121:新教出版社)
[本文に戻る]
(※③)
『エリシャはそこからベテルへ上って行った。彼が道を上って行くと、この町から小さい子どもたちが出て来て、彼をからかって、「上って来い、はげ頭。上って来い。はげ頭。」と言ったので、彼は振り向いて、彼らをにらみ、主の名によって彼らをのろった。すると、森の中から二頭の雌熊が出て来て、彼らのうち、42人の子どもをかき裂いた。』(Ⅱ列王記2章23~24節)
[本文に戻る]
(※④)
ヤコブはエリヤについて次のように書いている。『エリヤは、私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると、三年六か月の間、地に雨が降りませんでした。そして、再び祈ると、天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。』(ヤコブ5章17~18節)
[本文に戻る]
(※⑤)
『第三の御使いが鉢を川と水の源にぶちまけた。すると、それらは血になった。また私は、水をつかさどる御使いがこう言うのを聞いた。「常にいまし、昔います聖なる方。あなたは正しい方です。なぜならあなたは、このようなさばきをなさったからです。彼らは聖徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたは、その血を彼らに飲ませました。彼らは、そうされるにふさわしい者たちです。」』
[本文に戻る]
42ヶ月の期間が紀元61年6月~64年12月であるというのは、一体どういった考えから導き出されたのか、と問う人がいるであろう。これは説明されねばならないことである。もし何の根拠も論理もなく、このような期間を考え出したのだとすれば、私は愚かであって大いに批判されるべきだからである。42ヶ月がこの期間であるのは、ネロの死が68年6月だったからである。ネロが聖徒たちを蹂躙する権威を持てるのは42ヶ月間である。黙示録13:5で『この獣は、…42ヶ月間活動する権威を与えられた。』と書いてあるのは、すなわちネロが聖徒たちを屈服させる期間についてのことである。この権威がネロの死により取り上げられたと考えるのは何もおかしいことではない。死んだのであれば当然ながら権威も失われるからである。とすれば、このように考えると、ネロの聖徒たちに対する許された活動期間は、64年12月~68年6月だったということになる。すなわち64年12月に活動の権威が与えられ、42ヶ月経過した68年6月の死によりその権威が取り上げられた。黙示録11:7によれば、42ヶ月間預言することが許された二人の預言者は、ネロに活動の権威が与えられた時に殺される。すなわちネロが64年12月に聖徒たちを蹂躙し始めた時に殺戮されてしまう。このことについてヨハネはこう書いている。『そして彼らがあかしを終えると、底知れぬ所から上って来る獣が、彼らと戦って勝ち、彼らを殺す。』(黙示録11章7節)ここで『彼ら』とあるのは二人の預言者であり、『底知れぬ所から上って来る獣』とはネロを指している。『あかしを終えると』とは42ヶ月間預言する期間が全うされたことであり、『底知れぬ所から上って来る』とはネロが聖徒たちに対する弾圧を開始したことである。そうであれば、ネロが出てきて聖徒たちを殺し始める紀元64年12月に至るまで、聖徒たちは42ヶ月間預言の活動をしていたことになる。何故なら、聖徒たちが42ヶ月間の活動を完全に終えた後で、42ヶ月間活動する権威を受けたネロがその権威により聖徒たちを大いに殺すからである。それゆえ、聖徒たちが預言の活動をしていた時期はネロの迫害が始まる42ヶ月前までの期間、すなわち紀元61年6月~64年12月だったことになる。このようにネロの死んだ年月から逆算して考察すると、聖徒たちの預言していた期間が分かるのである。
この『42ヶ月』という期間を、我々は象徴として理解すべきではない。これは象徴ではなく実際の年月を述べた期間である。というのは、この期間を文字通りに捉えると、聖書をすんなりと理解できるし、歴史の事実にもよく合致するからである。しかし、これを象徴として捉えると、聖書の内容がよく分からなくなるだけでなく、歴史の事実にもそぐわなくなる。これから本作品を読み進めていけば、確かにこの期間は実際の期間を示すということが、よく分かるようになるであろう。もしヨハネが象徴として書いていた場合、ヨハネはもっと象徴的な数字を用いていたはずである。例えば黙示録20:4に書いてある『千年』などというように。後ほど詳しく説明されるであろうが、こちらの方は、この『42ヶ月』とは違って完全に象徴的な期間なのである。
それでは一体どうして『42ヶ月』なのであろうか。神は、どうして教会の預言活動を『42ヶ月』として永遠の昔に定められたのであろうか。また、この期間には何かの隠された意味があるのであろうか。分析をすることは可能なのか。まず一つ確実に言えるのは、神がこの期間であるのを欲されたということである。これは間違いないことである。神は欲するままに期間を定められ、定められたままにその期間を実現させられる。では『42ヶ月』という数字を我々は分析できるのであろうか。少し考えてみよう。まず、この数字は「6×7」または「7×6」と解せるのであろうか。私としては、そのように解すべきではないと思う。確かに不完全数である6が完全数である7回繰り返されることで、真に不完全である、すなわち「まったく少ない」と読むこともできなくはない。また完全数である7が不完全数である6回繰り返されることで、「足りない」と読むことも可能といえば可能ではある。しかし、これはいまいち納得し難い解釈だと言わねばならないであろう。「もやもや」とした感があるのは否めないのである。では「21×2」なのであろうか。この解釈も斥けられるべきであろう。何故なら意味が分からないからである。「14×3」はどうであろうか。これこそ正しい『42ヶ月』の分析である。というのも、マタイの福音書では、アブラハムからダビデまでが14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代だと言われているからである(※)。アブラハムからキリストまでが「42」(代)であるというのは、すなわち「十分な期間また量」であることを示す。何故ならアブラハムからキリストまでの42代に及ぶ期間は、不足の感じられない期間だったからである。42というこの数字は、このアブラハムからキリストまでの不足なき期間を象徴する数字であるから、「これだけあれば十分」と言い表わすための数字なのである。一体誰が、アブラハムからキリストまでの42代に及ぶ期間を十分なだけの期間だと感じないであろうか。この期間は約1700年だったのである。もっとも、だからといって42で示されている期間や量が、単なる象徴だけに留まらないということは確かである。つまり、それは実際の期間や量であると共に象徴としての意味も持つものなのである。確かに、今我々が考察している教会の預言期間が『42ヶ月』だったのも、ネロによる聖徒の迫害期間が『42ヶ月』(13章5節)だったのも、また異邦人がエルサレムを踏みにじる期間が『42ヶ月』(黙示録11章2節)だったのも、十分だと感じられるほどの期間であった。エリヤが『雨が降らないように祈ると、3年6ヶ月の間(※42ヶ月)、地に雨が降りませんでした』(ヤコブ5章17節)のも、「もう十分だろう」と感じられる期間であった。エリシャの呪いにより『42人の子ども』(Ⅱ列王記2章24節)が裂かれたのも人数としては不足を感じさせるものではなかった。このように聖書には、明らかに42という数字が多く書かれているのが分かるが、それはどれもあの聖なる系譜の42代を間接的に示すものなのである。それゆえ、この数字を「全うされた期間や量」と理解しても間違ってはいない。何故ならアブラハムからキリストまでの42代は全うされた期間だったからである。また、この『42ヶ月』という期間が実に使いやすいから多用されているという理解を持ったとしても問題ないであろう。この期間は、他の箇所では『1260日』(黙示録11章3節)、『ひと時とふた時と半時』(ダニエル12章7節)すなわち「3年6ヶ月」などと言い換えられている。このように言い換えられた数字や期間を見れば分かるが、それらはどれもかなり整った印象があり、秘儀を表わしたり、知恵を隠すためには実に適している。神は、ダニエル書や黙示録において、読み解ける者だけが読み解けるようにと、多くの「謎」を秘めることを望まれた。実際この2つの文書には無数の「秘密」が満ちており、知恵と思慮を受けた者でなければ読み解けないようになっている。だからこそ、神は他にも特徴的な言い換えが可能であり、しかもそのどれもが整った印象を与えることになる『42ヶ月』という期間を設定されたのだと考えられる。この期間であれば、秘儀を示すには実に相応しいと言えるのである。もしこれが「37」とか「43」とかだったら、どうであろうか。特徴的な言い換えもできず、整った印象も与えず、秘儀を示すには全然相応しくないのは明らかである。要するに、全能なる神の知恵は秘儀と恵みを受けた者たちのために、この『42』という数字を永遠の昔から設定され、世界の歴史の中に組み込まれたということである。だからこそ、アブラハムからキリストまでの期間が「42代」であり、ネロの活動期間が「42ヶ月」であり、エリシャを通して罰を受けた子どもの数も「42人」だったのである。このような使い勝手のよい数字を歴史において用いるために選定するというのは、確かに神の知恵に相応しいと感じられないであろうか。私はこの数字について考察したのであるが、私が今述べたこの2つ以外の解釈は恐らくできないと思われる。この「42」という数字は、これからも本作品の中で多く出てくるから、「1260日」また「ひと時とふた時と半時」また「3年6ヶ月」という別の言い方と共に、忘れないでいてもらいたいと思う。もし忘れてしまったら、思い返すために再びこの箇所を読むべきである。
(※)
『それで、アブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になる。』(マタイ1章17節)
[本文に戻る]
教会が42ヶ月もの間、その預言活動により多くの人々を苦しめたので、それから後、教会も報いとして42ヶ月の間苦しめられることになった。すなわち、42ヶ月の間聖徒に対して活動する権威を与えられたネロにより、教会は苦しめられることになった。聖書は神が誰かの行ないにそのまま報いられる方だと教えている。例えばオバデヤ書15では『あなたがしたように、あなたにもされる。あなたの報いは、あなたの頭上に返る。』と書かれている。詩篇18:25~26でもこう言われている。『あなたは、恵み深い者には、恵み深く、全き者には、全くあられ、きよい者には、きよく、曲がった者には、ねじ曲げる方。』手足の親指を切り取られたアドニ・ベゼクも、このように言った。『私の食卓の下で、手足の親指を切り取られた70人の王たちが、パンくずを集めていたものだ。神は私がしたとおりのことを、私に報いられた。』(士師記1章7節)報いの神は、教会が42ヶ月の間人々を苦しめたので、その苦しめたのと同じ期間、教会も苦しめられることを許されたのである。正に教会は自分たちがした通りのことを自分たちにもされたことになる。ここに神による報いの原理を私たちは見ることができよう。もっとも、教会が自分たちが苦しめたのと同じだけの期間の苦しみを受けたのは、当然ながら刑罰としての報いではない。教会は神の御心にかなったことをしたのだから、どうして罰の意味を持つ報いを受けることがあろうか。神は善に対して罰を与えられる方ではない。教会が報いとして受けたのは、刑罰としての報いではなく、ただ言行をそのまま返されるという意味しか持たない賞罰的に言えば無色透明の報いであった。
この42ヶ月間の預言活動を記した当時の文書は何か残されているのか、と問う人がいるかもしれない。そのようなものが残っていれば実に良いと思うのではあるが、残念ながら私は、そのようなものを知らない。しかし、このことに関する証拠としての文書が残されていないからといって、我々は驚いたり怪しんだりすべきではない。それは第1部で再臨の証拠について説明されたのと同じことである。再臨のこの世的な証拠が不在であるのと同様に、この42ヶ月の預言活動の証拠も、御言葉という証拠を除けば存在していない。当時この預言活動を見ていた聖徒たちは、もう間もなくネロの迫害を受け、それから3年半後に携挙されるのだから、何も証拠としての文書を書かなかったとしてもそれほど変だとは思われない。そのような危険な時期に、どうして悠長に書き物をしている余裕があるであろうか。偽者の聖徒たちも、この42ヶ月の活動が起きてから数年以内に携挙されはするものの、火に投じられてしまうのだから、何も書き残していなかったとしても不思議ではない。この活動を見ていた世の人々も、神が許さなかったので、この活動について何かを書き残すことがなかった。それは、キリストが多くの奇跡を行なわれたことがユダヤ以外の地域にも当然知られていたはずなのに、その奇跡について当時生きていた世の人々が何一つ言及していないのと同じことである。神は、キリストの奇跡と同様に、聖徒たちが御言葉のみによりこの預言活動のことを信じるように願っておられるのだと思われる。だからこそ、この活動について何もこの世的な証拠が残されなかったのである。確かに御言葉は、この預言活動のことを書き記しているのだから、御言葉を信仰の基準とするクリスチャンである者は、たとい何らかの文書が残されていなかったとしても、この預言活動が42ヶ月の間起きたということを信じるべきである。
第4章 ②ネロによる42ヶ月の迫害(紀元64年12月~68年6月9日)
ネロの治世である紀元64年7月19日に、ローマの大火が起きた。この大火災は大規模なものであり、ローマ市の70%が焼失したほどであった。当時のローマ市は木造の建築物が多く、しかも非常に密集した構成になっていたので、火災が容易に広がり、ここまでの火災となったのである。それまでも、ローマ市には火災が起きることが少なくなかったが、この時に起きた大火災は今までにないほどに大きいものであった。そのような驚くべき大火災であるから、この事件は、今に至るまでも語り継がれ続けているし、これからも語られることであろう。今の時代に起きた出来事で例えるとすれば、2001年9月11日に起きたニューヨークの同時多発テロであろうか。その被害の大きさという点で、後世にまで延々と伝えられるという点で、非常に驚くべき事件であるという点で、どちらもよく似ている。当時のローマ人は、この大火災はネロが放火したから起きたのではないかと思った。ネロの邪悪性は誰もが知るところであったから、ネロが犯人に違いないと多くの人が感じたのである。「ネロはあの大火災を前に、琴を弾きながらトロイア陥落の詩を吟じていた。」などという噂も広がった(※)。ネロがこの大火災の犯人だったかどうかということについては、後ほど考察することになる。この有名な歴史的事件は、世の終わりに関して預言された黙示録やマタイ24章などの箇所を理解するための重要なキーとなるものだから、聖書を正しく解釈したいと願う読者はよく心に留めていただきたい。この出来事を考慮しないと、それだけ聖書の預言が理解しにくくなってしまう。
(※)
ネロは音楽をはじめとした芸術の愛好家であった。自分の演奏を披露する「ネロ祭」というコンサートも開催している。
[本文に戻る]
民衆がネロこそローマ大火の犯人だと疑い続けたので、この邪悪な暴君は、自分に咎が帰せられないようにと、大火災の罪をキリスト教徒になすりつけた。もちろん、当時のキリスト教徒が大火災の犯人でなかったのは言うまでもない。確かに当時キリスト教徒たちは偏見と無知のため何の根拠もなく民衆から憎悪されていたが、神に従う彼らが、このような大事件を起こすことなど到底あり得なかった。これが狂信的なイスラム教徒や邪悪な宗教の信者や暴動ばかり起こしていたユダヤ人(※)であれば話は別だったろうが、そうではなかったのである。小プリニウスも述べているように、当時のキリスト教徒は、穏やかで平和的な人たちであった。この罪のなすりつけから、ネロの聖徒に対する42ヶ月間の蹂躙が開始された。この期間について黙示録では、こう書かれている。『この獣は、傲慢なことを言い、けがしごとを言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。そこで、彼はその口を開いて、神に対するけがしごとを言い始めた。すなわち、神の御名と、その幕屋、すなわち、天に住む者たちをののしった。彼はまた聖徒たちに戦いをいどんで打ち勝つことが許され、…』(13章5~7節)この箇所で特に注目すべきは『聖徒たちに戦いをいどんで打ち勝つことが許され』という部分であろう。これはネロがキリスト教徒らを捕らえて屈服させることを言ったものである。このネロによる蹂躙の期間である42ヶ月とは、紀元64年12月~68年6月9日である。この大迫害の時、キリスト教徒はネロによる罪のなすりつけのために、各地から捕えられてしまった。ネロとその暴虐について説明されている黙示録の箇所で『とりこになるべき者は、とりこにされて行く。』(13章10節)と書いてある通りである。すなわち、世の初めからネロに捕えられるようにと定めを受けていた聖徒は、皆その定めの通りに捕えられてしまった。そして、この捕えられた聖徒たちは、犯してもいない罪のために大量に処刑されることになった。この時にどれだけの聖徒が処刑されたのかは分からない。タキトゥスもスエトニウスも具体的な数字を何も記していない。無数の歴史書を読み漁ったギボンの本にも、処刑された人数は書かれていない。しかし、聖書の記述や大火災の規模を考えると、かなりの人数のキリスト教徒が処刑されたと推測される。もし小規模なものだったとすれば、ここまで有名な出来事として記憶されることにはならなかったと思われる。これこそが、今に至るまで語り継がれるあの有名な大迫害なのである。このような忌むべき迫害を行なったネロは、皇帝としては初めてキリスト教徒を迫害した皇帝であった。
(※)
ニコデモ福音書にはこう書かれている。「ピラトは怒ってユダヤ人に言う、「お前達ユダヤ人はいつも暴動を好み、お前達に良いことをしてくれる人達に逆らってばかりいる。」…」(『聖書外典偽典6 新約外典Ⅰ』ニコデモ福音書(ピラト行伝)第章9節2節 p189:教文館)あの第一次ユダヤ戦争も、ユダヤ人の暴動を鎮圧するためにこそ行なわれたのである。
[本文に戻る]
マタイ24章におけるキリストの預言が、この大迫害において成就された。それは次のような預言である。『そのとき、人々は、あなたがたを苦しいめに会わせ、殺します。また、わたしの名のために、あなたがたはすべての国の人々に憎まれます。また、そのときは、人々が大ぜいつまづき、互いに裏切り、憎み合います。』(9~10節)同じことが預言されているマタイ10:18~22の箇所も、この時に成就した。そこにはこう書いてある。『また、あなたがたは、わたしのゆえに、総督たちや王たちの前に連れて行かれます。それは、彼らと異邦人たちにあかしをするためです。人々があなたがたを引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことは、そのとき示されるからです。というのは、話すのはあなたがたではなく、あなたがたのうちにあって話されるあなたがたの父の御霊だからです。兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子どもたちは両親に立ち逆らって、彼らを死なせます。また、わたしの名のために、あなたがたはすべての人々に憎まれます。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われます。』これらの預言は、聖徒がネロの命令によって捕えられ、ある者たちは信仰の証をし、ある者たちは自己保身のために聖徒である家族を見放し、そのようにして大量の処刑が行なわれることを告げたものである。そうであれば、既に第1部で説明されたように、やはりマタイ24章はその世代(ゲネアー)の間に実現した箇所だということが分かる。キリストが紀元30年頃にマタイ24章でネロの暴虐を預言されてから、約1世代後(30~40年)の64年に預言されていたことが実現した。このように考えると、マタイ24章が既に成就された箇所だと理解することしかできなくなる。実際、その理解は間違っていない。読者の方は、今ここで、マタイ24章の一部の箇所は確かにネロの暴虐において成就したのだということを心に留めてほしい。もし、未だにマタイ24章が実現されていないことを預言した箇所だと考えているのであれば、その考えを捨てるべきである。
ネロがその権威により42ヶ月の間聖徒たちを苦しめたので、世の人びとは大いに喜びを感じた。何故なら、それまで42ヶ月の間、聖徒たちが世の人びとに霊的な苦痛を与えたからである。このことについて黙示録11:10ではこう書かれている。『また地に住む人々は、彼らのことで喜び祝って、互いに贈り物を贈り合う。それは、このふたりの預言者が、地に住む人々を苦しめたからである。』肉的には苦しめられたキリスト教徒たちを可哀そうに感じた人が少なからずいたが、それは肉的にはということであって、霊的には非常な喜びを感じていたということは疑えない。何故なら、世の人びととは霊的に言えばサタンの子らであって、神の子らである者たちをその主であるキリストと共に憎んでいるからである。霊的に憎んでいるのならば、その憎んでいる対象の苦難を喜ばないということはないはずである。キリスト者のことをよく考えていただきたい。キリスト者とは、滅びの子らにとっては『死から出て死に至らせるかおり』(Ⅱコリント2章16節)である。またキリスト者とは、最強の剣である鋭い御言葉を、勢いよく降りまわす霊的な戦士である。更にキリスト者とは、使徒たちが手紙の中でそうしているのと同じように、世を容赦なく糾弾する「口による裁き人」である。キリスト者がこのような存在であれば、キリスト者がネロに苦しめられたことを霊的な意味にいおて喜ばない死人たちがどこにいるであろうか。確かに御言葉は世の人びとが喜んだと教えているのだから、御言葉を規範とする我々は、実際に当時そのようになったと信じなければいけない。もっとも、神の御前においては、彼らの聖徒に対する微笑みは単にその邪悪さと不敬虔さとを如実に示すものでしかないのではあるが。
この42ヶ月の苦難において聖徒たちは大いに試された。黙示録ではネロの迫害が行なわれることについて、『ここに聖徒の忍耐と信仰がある。』(13章10節)と書かれている。これは当時の聖徒にとって言わば最後の試練であった。その時、聖徒たちの忍耐と信仰が、目に見える形で如実に現れ出ることとなった。ネロに屈せず忍耐して信仰を守り続けた聖徒たちは、永遠の救いを失なうことがなかった。その人には真の忍耐と真の信仰とが与えられていたからである。しかし、ネロの前に引き出された際に忍耐できず、信仰に留まれなかった者らは、自分がそれまでは持っていたと感じていた永遠の救いを失ってしまった。彼らには忍耐と信仰とが与えられていなかったのである。だからこそネロに屈服させられてしまったのである。そもそも彼らには初めから永遠の救いなど与えられてはいなかった。もしそれが与えられていたとすれば、忍耐と信仰も与えられていたはずなのである。このようにこの42ヶ月の苦難の際に、教会に属していた者たちは、「命を捨てて天国を取る者」と「信仰を捨てて命を取る者」の2種類により分けられた。前者は信仰のゆえに天国の恵みを受けることになり、後者は不信仰のゆえに永遠の裁きを受けることになってしまったのである。
最後にネロの教会迫害の規模について言及しておきたい。世の中には、ネロの迫害が、実際にはそれほど大規模なものではなかったと考える者が、いくらか存在する。しかし、聖書を読むならば、ネロの迫害はかなりの規模のものだったと考えざるを得ない。だからこそ、黙示録やマタイ24章の中では、非常に悲惨だと感じられるような迫害に関する記述がされているのである。もしこれが小規模な取るに足りないものであれば、あのような語り方はされなかっただろうし、ここまで豊かに語られはしなかったはずである。考えてもみてほしい。先に書かれたように、ローマの大火災は市街地の70%を焼失させるほどの凄まじい事件だったのである。それは今に至るまで語り継がれることになるほどの大きな事件であった。そうであれば、この大火災の罪が聖徒になすり付けられた際に行なわれた迫害の度合いも、やはり大きいものだったと考えるべきであろう。ネロの迫害の度合いは、この大火災の度合いに応じたものであったと考えるのが自然である。こんなにも大きい事件を契機として聖徒たちが犯人として扱われたのだから、ネロも堂々と暴虐を行なえるのであって、それにもかかわらず小規模な迫害しか行なわれなかったというのは考えにくい。ネロの邪悪性を考慮すれば、尚更のこと、このように言える。暴君の代名詞であるあのネロが、このような機会を捉えて、小さな苦しみしか与えなかったということが一体どうしてあるであろうか。もちろん、学問的な意味においては、この迫害が非常に大きな規模だったことを願う気持ちが私にはある(※①)。他の聖徒もそうであろう。だから、どうしてもネロの迫害が大規模だったに違いないという結論に思考が向いてしまう傾向があるのは間違いない。また、聖書において、神が事柄の素晴らしさや凄まじさなどを悟らせるために、非常な強調表現を多くの箇所でしておられることも確かである(※②)。しかし、このような点を考慮しても、やはり聖書から考えれば、また大火災の事件における凄まじさを考えれば、ネロの迫害は大規模なものだったと考えざるを得ない。もし本当に小規模だったというのであれば、私を承服させるために、学術的な論拠を示していただきたい。可能であれば当時生きていた人の書いた文書または公的な記録を提示してもらえるとありがたい。それが反論不可能なほどに真実性の強いものであれば、私は聖書の記述に逆らうことにならない範囲において、自分の理解を多かれ少なかれ修正することにしたい。
(※①)
注意していただきたいが、これはあくまでも「学問的な意味」においてのことである。実際には、このようなことは起きてほしくなかったと私が思っていることは、言うまでもない。一体どこの聖徒が、自分の仲間である聖徒たちの悲惨を願うであろうか。
[本文に戻る]
(※②)
このことの良い例は次の聖句である。『イエスが行なわれたことは、ほかにもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書きしるすなら、世界も、書かれた書物を入れることができまい、と私は思う。』(ヨハネ21章25節)※これは主の行なわれた素晴らしく注目すべき行為が、どれだけ量的に多かったか、またそれがどれだけ書き記すに値するものだったか、ということを悟らせようとして言われたものである。
[本文に戻る]
第5章 ③再臨(紀元68年6月9日)
ネロの最後の数カ月間は誠に悲惨であった。紀元68年に入ると、元老院により「国家の敵」と宣言され、事実上帝位を奪われた状態となった。それ以降、もはや、かつてのように好きなことが出来なくなったのは言うまでもない。ネロは元老院に敵視されたので、殺されないようにと逃げ回らざるを得なくさせられた。更に、自分の最も忠実な臣下であるティゲリヌスからも裏切られてしまった。そのように逃亡を続ける惨めな日々を送ったネロだが、遂に最期の時が訪れることになった。ネロがある家に隠れていたところ、元老院から送られてきた騎馬兵の足音がネロの耳に入ってきたのである。これは絶体絶命と言うべき状況であった。もう駄目だと諦めたネロは、既に第1章でも書いたことだが、自殺を試みたのだが死にきれなかったので解放奴隷に剣を使わせることで絶命した。これがあの有名な暴君の末路であった。享年30歳であった。このようにして死んだネロは、神の定められた通りに「自分のおるべき場所」へと下って行ったのである。
前章で見たように、旧約聖書に書かれている全ての預言は、再臨の日に成就された。またこの日に、ユダヤに対する恐るべき裁きが下され、ユダヤが破滅に至ることになった。それは我々が歴史の中で見る通りである。その破滅のクライマックスは紀元70年9月に起きた神殿崩壊の出来事である。裁きが再臨されたキリストと聖徒たちにより下されたので、このようなことになってしまったのである。本章では、再臨の後で起きたこの悲惨な出来事を取り扱う。それは、読者の再臨についての理解が更に深まるようになるためである。
キリストは既に再臨された。世の終わりも紀元1世紀に到来した。死人の復活と携挙も使徒の時代に起きた。最後の審判も実施された。新しい時代が訪れた。マタイ24章や黙示録をはじめ新約聖書に書かれている預言も既に成就した。旧約聖書に書かれている預言も、ことごとく成就している。さて、それでは一体、この世界はこれからどのようになるのであろうか。これは多くの聖徒が是非とも知りたいと願うことではないかと思う。再臨に関する事柄を取り扱う本作品において、このことを書かずに済ますことはできない。まず結論から言えば、この世界は、これからも我々の知っている今のような状態が永遠にわたって続くことになる。というのは、今の世界は、既にもう新しい世界となっているからである。預言書では、その新しい世界が永遠に続くと言われている。すなわちイザヤ66:22で、神は次のように言っておられる。『わたしの造る新しい天と新しい地が、わたしの前にいつまでも続くように、―主の御告げ。―あなたがたの子孫と、あなたがたの名もいつまでも続く。』もし新しい世界に終わりや中断があれば、そのことを神は啓示されたであろうが、そうではなく神は新しい世界が『いつまでも続く』と言われた。創世記9:22には、『地の続くかぎり、種蒔きと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜とは、やむことがない。』と書かれている。この聖句で言われていることが、これからこの世界にずっと実現し続けるのである。その永遠に継続されるこの世界において、神は本質的には何も変わらない種々の事象を、永遠にいつまでも繰り返して起こされる。本質的な意味において、何か異なったことや前にはあり得なかったことが、神により起こされるということはない。それはソロモンが次のように言った通りである。『私は知った。神のなさることはみな永遠に変わらないことを。それに何かをつけ加えることも、それから何かを取り去ることもできない。神がこのことをされたのだ。人は神を恐れなければならない。今あることは、すでにあったこと。これからあることも、すでにあったこと。神は、すでに追い求められたことをこれからも捜し求められる。』(伝道者の書3章14~15節)ここで言われているのが「本質的な意味において」であるということを理解しないと、何が言われているのか分からなくなるから注意しなければいけない。確かに外面的また感じられ方においては新しく思えることも多くあるであろうが、本質的な意味においては、この世界で起こる事象は、全てが例外なく過去の繰り返しである。伝道者の書1:9~10に次のように書かれているのも、そのような意味においてである。『昔あったものは、これからもあり、昔起こったことは、これからも起こる、日の下には新しいものは一つもない。「これを見よ。これは新しい。」と言われるものがあっても、それは、私たちよりはるか先の時代に、すでにあったものだ。』ところで聖書には、『主であるわたしは変わることがない。』(マラキ3章6節)また『イエス・キリストは、きのうもきょうも、いつまでも、同じです。』(ヘブル13章8節)また『父には移り変わりや、移り行く影はありません。』(ヤコブ1章17節)と書かれている。神は完全な存在であられるから、我々のように更に良くなろうとして変化される必要性がまったくない。つまり、もう既に完全であるから、ずっとそのままの状態で変わらずにいても何も問題ないわけである。そのように完全であるからこそ、神がお求めになることも、未来永劫変わることがない。そのような完全な方である神が求められることは、ご自身の存在と同じように完全で変わる必要性がないから、神はいつでも同じことを永遠に至るまでも追い求め続けられるのである。もし存在の変化があれば、その存在の変化に応じて求めることも変化するであろうが―これは我々人間にはよくあることである―、神にはそのような変化はまったくないのである。確かに世の中を見ても、既に完全に達している存在は、本質的な意味においてはずっと同じものを求めたり同じことを行なったりするものである。例えば今の我々の時代には、AC/DCという世界中に多くのファンを持つロックバンドが存在している。このバンドの音楽性は既に完全であり変える必要が少しもないから、数十年の間、まったく同じに感じられる作品しか作っていない。これを「マンネリ」などと言って批判する人もいるが、存在的に完全な域に達しているのであれば、その完全な域に自分たちを保たせている限りは、ずっと同じものしか出さなかったとしてもそれは自然なことである。何故なら、それがベストだからである。神を世俗のロックバンドに例えるのはいかがなものかと感じるのではあるが、理解のためには、このようなロックバンドの例をもって説明したとしても許してもらえるであろう。それでは、神が永遠に同じ事象を繰り返して起こされる理由は一体なんなのであろうか。神は何のために、永遠に至るまでもこの世界で同じことを繰り返して行なわれるのか。それはご自身の素晴らしい栄光を、その繰り返しの事象を通して、いついつまでも現わされるために他ならない。神は、例えば救いに選ばれた者たちを滅びからキリストにより救ったり、多くの人々に種々様々な恵みを与えられる、ということを永遠に繰り返されることで、ご自信の恵みの栄光をこの地上において、とこしえまでも現わされる。それは、そのような恵みが現わされることで、いつの時代にも神に感謝が捧げられたり、神が崇められるようになるためである。そうすれば、それが、いつの時代においても神の栄光となるのである。また神は、滅びに定められた者たちを永遠の滅びや偽りの闇に追いやったり、罪を犯した者たちに罰を下されたりする、ということを永遠に繰り返されることで、審判者としての義の栄光を、この地上において未来永劫までも現わされる。それは、いつの時代でも神が正しく真実な方であり、悪には義の裁きをもって報いられるということが知られるようになるためである。そのようになれば、いつの時代であっても、人間が神の正しさ、聖性、その恐ろしさと威厳とを知ることになり、それが神の栄光となるのである。実に、神はこのようにご自身の栄光を永遠に地上の事象を通して現わすためにこそ、この地上で未来永劫同じことを行なわれ続けるのである。神は永遠のお方であられるから、その栄光も時間の中において永遠に現わされなければならない。それゆえ、その栄光が時間的な意味において永遠に現わされるために、この地上が永遠に続き、そこで起こることも永遠に繰り返され続けることになるわけである。その繰り返しについての具体的な例をいくらか見てみたい。まず、神はかつてソドムを永遠に滅ぼされ、それから約1700年後に再びソドム同然のユダヤを永遠に滅ぼされたが、これからも神はこのような滅びをどこかの場所や民族に与えられるであろう。またその際には、滅びを下される中にあって、ロトや少数の選ばれたユダヤ人のように救いが与えられる者が現われることであろう。ある存在を徹底的に容赦なく滅ぼすのと同時に、その滅ぼされる存在の中から一部の者たちを滅びから免れさせる。これこそ神がこの地上において永遠に繰り返して起こされる事象の一つである。このようにするのが、神がご自身の栄光を現わすために取られる手段なのである。また後にも再び書かれることになるが、ある個人を通して、神が多くの者たちに霊的・知的・物質的な恵みを授与されるということも、神が永遠に繰り返される事象の一つである。この事象は今までに無数の事例が存在している。例えば、神はノア一人を通して、当時生きていた多くの人々にご自身の真理を告げ知らされた。またヨセフ一人を通して、非常に多くの人々を飢饉の悲惨から物質的に救助された。モーセ一人を通して、数多くのユダヤ人がエジプトから脱出させられた。キリストお一人を通して、無数の人間が救いに導かれるようになった。大帝コンスタンティヌス一人を通して、ローマがキリスト教を受容するに至らされ、多くのキリスト教徒たちが迫害と苦難から解放されることになった。コペルニクス一人を通して、人類が天動説の闇から抜け出せるようになった。ルター一人を通して、キリスト教界が改新されることになった。アインシュタイン一人を通して、物理学全体が変わることになった。フォード一人を通して、自動車の大量生産が実現するようになり、そのため多くの人が車に乗れるようになった。リークワンユー一人を通して、シンガポールが世界に名立たる繁栄した都市に変えられることになった。もしこれらの人が現われなかったならば、ある場所や特定の領域は、まったく何も変わらずに昔の状態のままでいたことであろう。このような例からも分かるように、神は往々にしてある一人の人間に莫大な恵みを与え、その者を通して世とそこに住む人々に働きかけられる。要するに、世界を良くするためには、恵みの泉となる言わばシンボル的またアイコン的な存在を登場させられるというのが、神の好まれるやり方なのである。これは、昔も今も変わっていない。これからも、神はそのようなことを繰り返して、人類に恵みを与え続けられることであろう。今挙げた例はこの2つだけだが、神はその他のことも、同じようにこの地上で繰り返し繰り返し行なわれ続ける。1000年経過しても、1000億年経過しても、その繰り返しの事象が起こされることは変わることがない。神の栄光が時間の中において永遠に現わされるために、永遠に至るまでも、それは継続させられるのである。もう一度言うが、これは「永遠」である。我々はこのことに驚いたりすべきではない。何故なら、このことは我々人間の精神には非常に受け容れ易いものだからである。クリスチャン、ノンクリスチャン問わず、進化論を奉じている人々を見るとよい。彼らは進化論が教える宇宙の存在年数を、何の疑いもなくそのまま受け入れている。その年数とは128億年である。これは誠に長い年数であるが、だからといってその気の遠くなるような年数に異を唱えている人などまったく見られないのである。それどころか、どの人も本当に宇宙は128億年も存在し続けてきたと信じ続けている。これは人間の精神が、宇宙の存在における継続年数がいかに長かったとしても受容できるように創造されていることを示すものである。だからこそ、誰も128億年という長い年数を不思議に思ったり拒絶したりしないわけである。たとえこれが128億年ではなく例えば7800億年だったとしても、事は同じであったであろう。そのように人間の精神が造られているとすれば、それはこの世界が永遠に続くからであるというのが理由でなくて何であろうか。つまり、この世界が永遠に続くからこそ、神は人間の精神がそのような長い継続年数を容易に受容できるようにされたということである。もしそうでなかったとすれば、今頃多くの人たちが、進化論の教える長大な時間スケールを拒絶していたに違いない。このように、不信仰な世の人々でさえ、偽りの理論が教える宇宙の長い継続年数を何の疑いもなく受け入れている。であれば、我々は尚更のこと、そのような長い継続年数を拒絶したりすべきではないことになる。何故なら、我々に対して世界が永遠に続くと教えているのは偽りの理論ではなく、神の聖書だからである。世の人々が偽りの理論から教えられて長い継続年数を受けて入れているのだから、聖書から教えられるべき我々が、どうしてそのような長い継続年数のことに対して反発していいはずがあろうか。偽りの理論による教えでさえ何の疑問もなく信じられているのであれば、尚のこと、我々が神聖な書物の教えに基づいてそのような長い継続年数を受容しなければいけないのは明白である。
キリストの再臨により改められた新しい世界に生きる聖徒は、どのような人生を営めばよいのであろうか。再臨が既に起きたと信じる聖徒と、再臨がまだ起きていないと信じる聖徒では、その取るべき信仰生活においてどのような違いがあるのであろうか。これは、これまでに述べられたことに比べれば、それほど難しい問題ではない。何故なら、これは、今までに言われたことに基づいて考えれば自然に答えが出てくるような事柄だからである。よって、読者は、このことについて、容易に受け入れられるのではないかと思う。この第8章では、このような我々の人生に直接関わることについて論じられる。
この章では、再臨を正しく理解しようとして考究する際に我々の心に生じるであろう重大な懸念を、取り扱うことにしたい。その懸念とは、次のようなものである。「確かに再臨を正しく理解することは大変重要ではあるが、しかしそのことの考究に心を費やすのであれば、そのことにかかりきりになってしまい、キリスト者にとってもっとも重要である救いのことが蔑ろにされてしまうのではないか。」まず言うまでもなく、本作品で考究されている再臨の問題は、あまりにも重要である。私の経験から明らかであるが、この問題は、神の聖徒たちの心を完全に捉えて離さなくさせる力を持っている。それは、この問題に心が捉われたために、他のことを考えられなくなってしまうほどである。実に多くの人たちが、この問題の虜になっている。心を大いに悩ませる聖徒も多いはずである。ある牧師は、この問題で悩み過ぎたため、短い間に多くの白髪が出てしまった。上手に理解したいのだが、どうしても上手に理解できないという、霊的また精神的なもどかしさ。人間の矮小な理性では測り知れない真理の高さ、深さ、その奥深さに接して、我々の心は驚いたり、動じたり、喜んだり、不安になったり、訳が分からなくなったりしてしまう。この問題に近付いておきながら、神学的な意味において、何の悩みも持たない人は一人もいないはずである。また、この問題がどこかの教派や教会に投げ込まれたら、高い確率で論争や分裂や動揺が起きてしまう。実際、これを書いている私の所属していた教派や教会がそうであった。キリストは家族の間に剣をもたらすべく来られたと言われたが(※)、これは救いに関することであった。この再臨の問題の場合、それは教派や教会に投げ込まれる剣であると言ってよい。剣が投げ込まれるので、そこには普通ではない状況が生まれるのである。それは、この問題が、我々にとって言葉では言い表わせないぐらいの重要性を持っているからである。この問題が投げ込まれたにもかかわらず、いつまで経っても今までと何も変わらない状態を保っている教派や教会があるとすれば、それは例えるならば3兆円の遺産をめぐる遺書の難しい解釈を子どもや親族たちが延々と放っておくようなものである。つまり、この問題とは、すなわち神学的な動乱をもたらす荒れ狂う剣なのである。この作品で考究されているのは、このような尋常ではない問題であるから、この問題に心を費やすことにより救いが隅に押しやられてしまうことになるのではないかと懸念する人がいたとしても不思議ではない。普通の牧師であれば、この問題を処理しきれず困り果て、「このような難しい問題に苦労しなくてもよいから、ただ主イエスの救いだけを正しく信じていれば、それでいいのではないか。そうすれば、やがて天国に入れるのだから。」と思われる方もいるであろう。一般信徒や求道者であれば、このような問題により様々な話し合いや動乱が起きているのを見て、つまずいてしまう方もいるかもしれない。そのような方の中には、キリストから離れはしないものの、何だかキリスト教や教会が嫌に思ってしまう人もいるかもしれない。
再臨を正しく悟りたいというのであれば、何よりも聖書を読まなければいけない。カルヴァンが「私は言う、御言葉にこそ赴かねばならない」(『キリスト教綱要 改訳版 第1篇・第2篇』第1篇 第6章3 p76:新教出版社)と言ったのは、再臨の真理を求める場合でも当然ながら同様のことが言える。何故なら、この聖書にこそ、再臨のことが啓示されているからである。このカルヴァンが他の箇所で言ったように「およそキリスト教に関わることの一切は聖書に記され聖書に含まれる」(『キリスト教綱要 改訳版 第4篇』第4篇 第19章 第9節 p501:新教出版社)のだ。確かな所、神は、聖書以外の書物において、再臨のことを啓示してはおられない。であるから、もし聖書に再臨の事柄を求めないというのであれば、どこに求めるというのか。聖書以外の書物に再臨の事柄を求める人は、「無」に向かって何かを求めているようなものである。カルヴァンは「キリストは聖書によって以外には、ただしく知られ得ない」、それゆえ「キリストを知りたいと思うなら、聖書のうちにその知識を求めなければならない」と言ったが(『新約聖書註解Ⅲ ヨハネ福音書 上』5:39 p181:新教出版社)、これは再臨の事柄でも同様のことが言える。つまり、我々は再臨を理解することにおいて「神の御口から出るものによってのみ養われていくこと」(カルヴァン『アモス書講義』第2章 p51:新教出版社)が求められている。そのようにして我々が聖書にこそ再臨を求めるのであれば、我々は霊的な祝福を神からいただくことができる。神が、その人を喜ばれるからである。しかも、聖書に求めれば求めるほど、祝福の度合いは増し加えられる。神が、その人を豊かに喜ばれるからである。神が聖書にこそ解を求める人に祝福を注がれるというのは、疑えない。ルターもそのようにしたからこそ、神の祝福をいただき、教皇の腐った糞便から解放されるようになった。そのようにして祝福をいただけたのであれば、我々は再臨のことをよく理解できるようになるであろう。神の祝福が、我々に再臨のことを正しく理解できるようにして下さるからである。それゆえ、再臨を誤りなく悟りたいと願う人は、聖書にこそ再臨のことを求めなければいけないということを、よく心に留めなければいけない。再臨における真理のありかは、聖書にこそあるのである。
第2部 再臨と再臨の前後に起きた諸々の出来事の詳細およびその順序 [了]
再臨を十全に把握したいのであれば、黙示録を徹底的に理解する必要がある。何故なら、黙示録は、再臨と大いに関わりがある文書だからである。黙示録は、再臨に至るまでの歴史的な経緯がどのようなものであったかということを、記している。それだから、黙示録を十分に読み解けないと、再臨がどのような出来事を経て起きたかということが曖昧なままとなる。黙示録を理解していない人の再臨理解は、どうしても不十分なものとならざるを得ない。
気になる人も多いと思うが、黙示録が記された年代は、いつ頃なのであろうか。註解に入る前に、まずこのことを述べておかねばならない。これは、黙示録を正しく理解するためには、あまりにも重要なことである。あまりにも重要だからこそ、ここで、そのことのために章を割り当てているのである。というのも、筆記年代をどこに定めるかによって、黙示録の理解がかなり違ってきてしまうからである。黙示録は、実際の歴史やローマ皇帝のことについて多くを記している。よって、筆記年代をいつに設定するかで、我々の解釈が大きく変動させられてしまう。例えば、黙示録がウッティリウス帝の69年に書かれたとすれば、13章に出てくる獣は、2代後の皇帝である「ティトゥス」だということになる。何故なら、13章の獣とは、すなわちヨハネが黙示録を書いている当時の皇帝から数えて2代後の皇帝のことだからである。黙示録17:9~11。またウェスパシアヌス帝の69~79年に書かれたとすると、獣は「ドミティニアヌス」だということになる。トラヤヌス帝(98~117年)であれば、獣は「アントニヌス・ピウス」となる。このように、筆記年代の設定次第で、大きな解釈の違いが我々に生じる。これは無視してもよい小さな問題ではない。
黙示録の註解に入る前に、事前に知っておくべきことを、いくらか書いておきたい。このような難しい文書を理解するにあたっては、前提となるべき基礎的な認識や知識を、あらかじめ持っておくのが益となる。それは、あたかもタイトル戦に出場する前のボクサーが、身体を慣らすために準備運動をするようなものである。言うまでもなく、準備運動をするかしないかで、結果はかなり違ってくるものである。
1章目は、言うなればプロローグである。聖書以外の本でいえば、「序文」または「前書き」が、それにあたる。言うまでもなく、ヨハネが記した原文には、第1章などという区切りは存在していない。これは後世の人間が、便宜のため、人為的に振り分けた区切りである(※①)。それは、黙示録の2章目以降においても、他の聖書の巻においても同じである。よって、我々は、この1章という区切りさえも、神の霊感により振り分けられたものだと考えるべきではない。聖書の中には、あまり適切とは言えない区切りもある(※②)。しかし、黙示録1章という区切りにおいては、非常に適切な区切りであると言える。このように区切ることで、分かりやすくなるという効果が生じている。また、それは非常に取り扱いやすい区切りでもある。この区切りは、黙示録を語りやすくさせてくれる。この第1章では、主に4つの事柄が語られている。すなわち、黙示録はキリストにより示されたものだということ、黙示録はヨハネにより記されたものだということ、またそれは当時の教会に宛てられているということ、そしてここで示されているのは当時において間近に迫っている出来事だということ、この4つである。この第1章は、それほど難しい部分ではない。12章や20章と比べれば、遥かに優しい部分である。それでは、早速、1節目から見ていくことにしたい。どうか、我々が黙示録を悟れるように、主が豊かに霊的な恵みを与えて下さるように。アーメン。コロサイ1章9節。
1章に続くこの2~3章では、キリストがアジアの7つの教会に対して称賛と勧告と約束とを告げておられることについて、書かれている。まず「称賛」とは、その教会が持っている美徳が褒められることである。例えばテアテラの教会に、次のように言われたのが、それにあたる。『わたしは、あなたの行ないとあなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っており、また、あなたの近ごろの行ないが初めの行ないにまさっていることも知っている。』(2章19節)ここでは実際の褒め言葉は書かれていないが、このように言われるのは、事実上、称賛がされていることである。この称賛は、サルデスとラオデキヤの教会には、少しもされていない。「勧告」とは、すなわち、その教会に見られる悪徳や至らなさが改善されるように何かが言われたり、これから起こる苦難に耐えるようにと忠告がされることである。例えば、エペソ教会に次のように言われたのが、これにあたる。『しかし、あなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それで、あなたは、どこから落ちたかを思い出し、悔い改めて、初めの行ないをしなさい。』(2章4~5節)この勧告は7つの全ての教会に対して言われている。「約束」とは、最後まで信仰を守り通したら祝福の報いが与えられるという期待を持たせる言葉のことである。例えばエペソ教会には、こう言われた。『勝利を得る者に、わたしは神のパラダイスにあるいのちの木の実を食べさせよう。』(2章7節)これは全ての教会に対して、最後のほうの部分で言われている。これらの言葉は、言うまでもなく直接的には、紀元1世紀のアジヤにある7つの教会に言われたものである。しかし、その言葉が直接的には個々の教会に対して言われたものであっても、そこで言われていることを、他の教会もあたかも自分に対して言われているかのように考えなければいけなかったことは確かである。何故なら、どの教会に対して言われている箇所でも、最後のほうで『耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。』と書かれているからである。この2~3章で言われていることは、直接的には個々の教会に言われたものだが、それはもっと幅広く捉えられるべきものであって、あらゆる教会に与えられたものでもあると理解する必要がある。だから、これら7つの教会ではない他の教会が、そこで言われていることが自分たちの教会にも当てはまると感じたならば、当然ながら改善したり反省したりする必要があった。また更に言えば、この7つの教会に言われていることは、紀元1世紀以降の時代における教会に対しても語られていると考えるべきである。何故なら、ここで語られている内容は多くの普遍的な内容を含んでおり、そのため紀元1世紀以降の教会にとっても無関係なものではないからである。それゆえ、もし自分たちの教会が、ここで言われていることに該当していると感じたらならば、やはり悔い改めたり改善したりする必要があるのである。これらの記述が自分たちに言われたものだと考えつつ読んでみるとよい。そうすれば、多かれ少なかれ自分たちにも当てはまる部分が必ずあるはずである。
4章目におけるこの11節分を1章分として区切るのは、適切であったと言える。しかし、この4章目は5章目と内容的に纏めることができるから、11節しかないということを考慮して、この2つの章を1章分として区切っても問題とはならなかった。6章目は、それ以前の部分とは内容的に明らかに区切るべき箇所だから、4章目と5章目は一区切りにできても、4章目と5章目に合わせて纏めて区切ることは決してできない。とはいっても、このような内容の区切りに関する問題は本質的な問題ではないから、深く考察する価値がない。私もこれぐらいで、このことについての記述を終わらせねばならない。言うまでもなく、深く考察せねばならないのは、我々の聖書理解に重要な影響を及ぼす複雑であったり解釈が難しかったりする箇所である。
5章目では、誰も解けなかった封印を、死からの復活により勝利されたキリストが解くようなった場面が描かれている。この章は、後に出てくる難しい章に比べると、そこまで難しいとは言えない。
6章目からは、本格的に預言が書き記されることになる。黙示録が難解という名の霧に包まれるようになるのは、実にこの章からである。6章目までは、そこまで難しいとは言えない部分も多かったが、6章目からは極度に難解さが増している。読者は、この難解さに呑み込まれてしまわないために、思考する努力を怠ってはならない。
7章目は、挿入的な箇所であって、ここでは2つのことが書かれている。一つ目は神の聖徒たちに対する配所について書かれており(7:1~8)、二つ目は耐え忍んだ聖徒たちがやがて天で享受できるようになる幸いな状態について書かれている(7:9~17)。この箇所を1章分として区切ったのは、適切だったと思う。
【8:1】
7つのラッパによる出来事も、やはり預言である。一つのラッパが吹き鳴らされると、一つの預言が幻として示される。この預言の示し方自体は非常に単純であって、そこに難解さは何もない。難しいのは、その預言の内容が何を言っているのかということである。これこそ正に解明されねばならないことである。私は、神の恵みにより、その解明をすることにしたい。聖徒たちが、その解明により、更に黙示録および再臨の事柄について精通することができるように。アーメン。
10:1~11:13の箇所は、それまでの流れに沿わない挿入箇所である。どうして、この箇所が挿入箇所だと言えるのか。その理由は、それまでは再臨の後に起こる出来事が記されていたが(9:1~21)、10章に入ると再臨の起こる前の出来事が11章13節目までに記されているからである。9章からの記述を考慮すれば、9章から語られる災いは時間的に順序立てて語られねばならないはずである。すなわち、第一の災い、第二の災い、第三の災いというように、時間の流れに純粋に沿った記述がなされねばならない。それは『第一のわざわいは過ぎ去った。見よ。この後なお二つのわざわいが来る。』(9:12)と言われているからである。しかし10章に入ると明らかに今までの流れに反した預言、すなわち時間の流れに逆行する預言が11章13節目までに書かれているのだから、10:1~11:13の箇所は挿入として加えられていると考えなければいけない。もしこのように考えないと、どうして急に時間的に前の出来事に関する預言が挿入されたのか理解できなくなってしまう。更に、この箇所が挿入された箇所だということは、そこで書き記されているのが『巻き物』による預言だということからも論証できる。これが『巻き物』による預言だということは、つまり『ラッパ』による預言ではないということである。誰がこれを疑うであろうか。この預言がラッパによる預言ではないとすれば、それは今までの流れとは別のタイプの預言だということになるのだから、そのような預言は挿入として加えられた預言だと考えるのが望ましいと言える。
再び、ラッパによる預言の記述に戻ることになった。14節目を見ると分かるように、6つ目のラッパによる預言の末尾部分から記述が再開されている。
この12章は、11章からの続きではない。この章は、すぐ前の章まで書かれていた7つのラッパ(8:2~9:21、11:14~19)とは、明確に区別せねばならない箇所である。11章から12章に続く流れは、テレビで例えるならば2、3時間の番組が終わって、別の番組が30分または1時間ぐらい放映されるようなものである。12章からは新しい別の番組が始まるのだ。とはいっても、扱っている内容がどちらも「再臨の時期に起こる出来事」という点では何も変わらないのではあるが。12章を11章としっかり区別しないと、つまり12章が11章からの続きであると理解すると、黙示録をちゃんと理解できなくなってしまう。それゆえ、黙示録を理解したいと思う聖徒は、12章をそれまでの章としっかり区別しなければいけない。
13章である。この章は、前の12章と比べると理解するのが簡単である。何故なら、この章は12章のように象徴や比喩のレベルが極端に高いというわけではないからである。そのため私も、喜ばしく註解の文章を書くことができる。12章では、100本の木を背に積みながら急な坂道を上るかのようであった。とはいっても、この13章が簡単だというのは、あくまでも比較の上でそう言えるだけである。それそのものとしては、この13章も難しいことは確かである。その難しさの度合いは、5段階で言ったとして、12章が「5」、2~3章が「1」だとすると、この12章は「2.5」ぐらいであろうか。
ここでは天国の場景が描かれている。内容的にも量的にも7:9~17の箇所と、かなり似ている。両方の箇所を比べれば、それは一目瞭然である。7章のほうを「第1部」とすれば、こちらのほうは「第2部」といったところであろうか。この14:1~5の箇所は、13章でネロとその迫害について語られたすぐ後に書き記されている。これは、つまりネロの苦難に聖徒たちが耐えられるようにと希望を持たせる意味で書かれていると考えられる。つまり、こういうことである。「聖徒たちよ。あなたがたは、これからネロにより苦しめられることになるが、しっかりと耐え忍びなさい(13章)。そうすれば、やがてこのような素晴らしい天国に入ることができるのだから(14章)。」実際、ネロの迫害が開始されてから『42ヶ月間』が経過するとキリストの再臨が起こり、復活した聖徒たちが天国で永遠に住まうようになったのである。この14:1~5の箇所を読んだ聖徒たちがより強い心をもって忍耐できたであろうことは想像に難くない。さて、この箇所は非常な慰めに満ちている。我々も、やがてこのような場所に行くことになる。聖徒たちが、この箇所によって天国を思うならば、多かれ少なかれ信仰の益となるであろう。
ここではユダヤ戦争の時期に行なわれる裁きの時に向けて、様々な預言がなされている。ここでは色々と言われているので雑多な印象が感じられる。
この箇所では、2度の携挙が取り扱われている。一度目は14:14~16で、二度目は14:17~20で記されている。この2つの区分を、しっかりと我々は把握せねばならない。ここで携挙について書かれたのも、やはり紀元1世紀当時の聖徒たちに信仰の益を与えるためであった。何故なら、もし携挙が起こるということを御言葉により強く認識するならば、それだけ信仰に希望が加えられるようになるからである。そうすれば忍耐も強くなるはずである。だから、この箇所も、神がご自身の聖徒たちのために書いて下さった箇所だということになる。
ここでは7つの鉢がぶちまけられることによる裁きについて書かれている。ここでは、2つに話を区分するのがよいだろう。すなわち、15章を「1話目」とし、16章を「2話目」として認識する。何故なら、そのようにすると分かりやすいからだ。1話目では『7人の御使い』に『7つの金の鉢』が渡されたことについて、2話目ではその渡された鉢がぶちまけられることについて、書かれている。この15章と16章の章区分は適切である。ただこの2つの章を1つの章として纏めると、なお分かりやすくなったと私は思う。だから私は、本作品でこの2つの章を一纏めにして、しかし2つの話に区切って取り扱うことにした。これまでの内容を読み解けるのであれば、この箇所は極端に難しいというわけではない。しかし、それでも難しいということには変わらない。神が、その恵みにより、我々にこの箇所をも解読させて下さるように。アーメン。
17章では、イスラエルとローマ皇帝ネロについての秘儀を、御使いがヨハネに明らかにしてくれている。ここではまず17:1~6の箇所でイスラエルの秘儀が、次に17:7~14の箇所でローマとネロにおける秘儀が、最後の17:14~18の箇所でローマがユダヤを焼き滅ぼすことについて記されている。この17章は、解説的・辞書的な箇所である。この箇所で言われている秘儀を理解するのは非常に重要である。というのも、ここで言われている秘儀を理解しなければ、黙示録の多くの部分が読み解きにくくなってしまうからである。黙示録を理解したいと願うのならば、まず率先的にこの箇所を理解しておく必要がある。確かなところ、この箇所はゲームで言えば攻略本のようなものである。攻略本を読めばゲームが楽々と進められるように、17章を理解すれば黙示録もそれだけ容易に解読できるようになる。だからこそ、私は13章の註解において、本来であれば17章で註解すべき事柄を先駆けて既に註解してしまったのである。なお、この章では聖徒たちが付随的には取り扱われているが(17:6、14)、メインの内容としては取り扱われていない。つまり、この章は聖徒たちに関することが言われている箇所ではない。また、ここでの章区分は実に適切であった。何故ならここに書かれている18節分の内容は、一纏まりの内容となっているからである。
18章では、ユダヤの裁きに関する預言が語られている。これは紀元70年9月の出来事である。これも、やはり『すぐに起こるべき事』(22:6)だったことに心を留めるべきである。
この箇所では、ユダヤが裁かれた際に天で見られた光景について描かれている。これも、やはり紀元70年9月のことであった。先の18章では地上にスポットライトが当てられていたのに対し、この箇所では天上にスポットライトが当てられている。その点で、先の18章とここは、まったく違っている。
この箇所では、再臨と再臨の際にネロたちが裁きを受けた出来事について預言されている。この箇所は、2つの部分に区切ることができる。一つ目は19:11~16である。ここでは、遂にキリストが聖徒たちを引き連れて再臨されることになったシーンが描かれている。二つ目は19:17~21である。そこでは、実際にキリストが再臨され敵どもを裁かれているシーンが描かれている。この箇所も、やはり『すぐに起こるはずの事』(1:1)であった。この理解を拒絶する者は、聖霊の言われたことに言い逆らうことになるから、よくよく注意していただきたい。聖霊に言い逆らうというのは、誠に恐ろしいことである。
この箇所では、サタンが封じられ、聖徒たちが王として統御するという、秘儀的な表現で言い表されている期間について預言されている。この箇所も、黙示録の他の箇所と同様、内容が秘儀に満ちている。
ここからは千年すなわち1260日が終わってから起こる出来事について書かれている。
この箇所では、主に空中の大審判についての出来事が書かれている。今まで幾度となく教師たちに語られてきたマタイ25章における注目すべき大審判が、ここで預言されているのである。
この箇所では、天国のことについて啓示されている。この箇所は、聖徒たちにとって、黙示録の中で最も喜ばしいことが書かれている箇所である。というのは、我々にとって天国以上に喜ばしい場所がどこかにあるであろうか。ない。その天国が、この箇所では大いに啓示されているのだ。だから、この箇所は、黙示録の中で最も我々にとって喜ぶべきことが書かれていると結論すべきである。キリストは、我々をこの喜ぶべき場所に招き入れるためにこそ、御自身を永遠の犠牲として父なる神にお捧げになったのである。
22:5~21の箇所は、黙示録の最後の部分に相応しくエピローグとなっている。これは、この箇所の内容を見れば誰でも分かることである。何かの作品では最後にエピローグを置くというのが、世の常であるが、ヨハネもそれに倣ったのである。
ヨハネが黙示録を書いた理由は何だったのであろうか。ヨハネが黙示録を書いたことにおける神の御心は、一体どのようなものだったのであろうか。これは、敬虔な聖徒たちにとって知っておいても損にはならない、いやむしろ是非とも知っておくべき事柄だと思われる。何故なら、これは神の文書にかかわることだからである。本章において、この事柄を簡潔に取り扱っておきたいと思う。
最後に、黙示録の註解に関する真実について書くことで、この第3部を終えたいと思う。これは、私が黙示録を研究していく中で、真に気付かされたことである。黙示録という文書は、その註解の度合いと理解の度合いとが、まったく比例している文書である。すなわち、黙示録を豊かに註解できる人は、黙示録を正しく理解することができている。逆に黙示録を註解できない人は、黙示録を正しく理解できていない。他の聖書の巻であれば、たとえ分からないことがあったとしても、多かれ少なかれ註解できてしまうものである。具体的な例を挙げてみたい。20:8の箇所で書かれている『地の四方にある諸国の民』という言葉であれば、どうか。これが紀元1世紀におけるローマ軍の隠喩表現だと分かれば、これが何か理解しているのだから、この言葉に関わる事柄について豊かに論じることが可能となる。私が神の恵みにより、この言葉について豊かに論じた通りである。しかし、これが何か分かっていないと、そもそも何を意味しているのか分からないのだから、どうしても論じることができない。たとえ論じようとしても、分からないから口を慎まざるを得なくなるか、無理に論じて曖昧なことを短く論じるだけとなる。それは今までの教師たちが、この言葉について、何も論じていないのを見ればよく分かることである。14:14~20の箇所であれば、どうか。これが2回の携挙についてのことだと理解していれば、それがどういうことか分かっているのだから、この箇所について豊かに論じることができる。しかし、これがよく分かっていないと、分かっていないのだから論じようにも論じられなくなってしまう。これは一体どういうことなのか。これは、つまり黙示録とは、理解しない限りは説明できない仕組みになっているということである。今まで教師たちは黙示録を何も理解できなかったので、その無知に相応しく、黙示録を解き明かすこともできなかった。理解していなければ、どうして解き明かすことができようか。しかし、理解していれば、その理解に基づき、黙示録を解き明かせるようになる。それは、私がこれまで註解を書いたのを見れば分かる通りである。要するに、事は世の学問の場合と同じである。相対性理論を理解していない者は何も相対性理論について論じられないように、黙示録を理解していない者は黙示録について論じることができないのである。
ここまで黙示録に関して語らねばならない事柄を十全に語ったのであるが、最後に補章として、多くの人が疑問に感じるだろうと思われる事柄を短く取り扱っておきたい。その疑問とはこうである。「黙示録はマサダの要塞における出来事および第2次ユダヤ戦争について何か語っているのか。」まず、この2つの出来事はどういった内容のものだったか。前者は、神殿崩壊後に生き残ったユダヤ人たちがマサダという有名な要塞に立てこもり、幾らかの者を除いては最後に総自殺してしまった悲惨な出来事である。世の中には、この出来事をユダヤ戦争に含める者と、含めない者がいる。含める者はユダヤ戦争が72年まで続いたと認識し、含めない者は神殿の崩壊した70年までであったと認識する。辞書を見ても、ユダヤ戦争の時期が66~70年と書かれているものがあれば、66~72年と書かれているものもある。私の場合、このマサダの立てこもりについては、ユダヤ戦争に含めて考えていない。何故なら、これは言わば「おまけ」のような出来事であって、ユダヤ戦争の本体部分ではないと考えるからだ。ヨセフスの「ユダヤ戦記」では、これは第7巻で取り扱われている。後者は、自称メシアのバル・コクバという狂ったユダヤ人に心奪われたユダヤ人たちが再びローマ帝国に反逆したことにより引き起こされた戦争である。当然ながら、この戦いでもユダヤ側が負けてしまった。神は、もはや捨てられたユダヤ人たちに味方しては下さらなかったのである。この戦争は、紀元66~70年のユダヤ戦争が1回目とされるのに対し、2回目に起こったので「第二次ユダヤ戦争」と呼ばれている。しかし、単に「ユダヤ戦争」とだけ言われたら、普通は第1回目のほうを指すことが多い。というのも1回目のほうが、知名度と規模において勝っているからである。歴史において、特にキリスト教界において、この2回目の戦争が言及されることはあまりない。ヨセフスの書において、この戦争はまったく書き記されてはいない。何故なら、ヨセフスは第2次ユダヤ戦争が起きた時には既に他界していたからである。この2つの出来事における詳細を更に知りたい人がいれば、各自で調べるのが望ましい。何故こう言うかといえば、この2つの出来事は本書で本来的に取り扱うべき出来事ではないからである。本書でこの2つの出来事を取り扱うのは、例えるならばカルヴァンの「キリスト教綱要」とアウグスティヌスの「神の国」の中でタルムードを取り扱うようなものである。別にこの2つの書物の中でタルムードが取り扱われていたとしても不思議ではなかったが、しかし、ややピントが外れていると言わざるを得ないのである。だからこそ、この2つの出来事を、私は「補章」の中で補足的に取り扱うことにしたわけである。
第3部 黙示録註解 [了]
第4部では、再臨を十全に理解するために、黙示録以外の聖書の巻に書かれている再臨に関する聖句が註解されることになる。第4部の題名である「部分註解」とは、黙示録以外の聖書の巻から再臨に関する聖句を取り出して部分的に註解するからである。
第4部の記述内容は以下の通り。
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★☆☆☆☆☆☆☆(3/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★★★☆☆☆(7/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★☆☆☆☆☆☆☆☆(2/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★☆☆☆☆☆☆☆☆(2/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★☆☆☆☆☆☆☆(3/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆(1/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★☆☆☆☆☆☆☆☆(2/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆(1/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆(1/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆(1/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆(1/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★☆☆☆☆☆☆☆☆(2/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆(1/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★☆☆☆☆☆☆☆☆(2/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆(1/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆(1/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆(1/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★☆☆☆☆☆☆☆☆(2/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★★★★☆☆(8/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆(1/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★☆☆☆☆☆☆☆☆(2/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆(1/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★★★★★★(10/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★★★★★★(10/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆(1/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★★★★★★(10/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★★★★★★(10/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★★★☆☆☆(7/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★★★★★★(10/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆(1/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★★★★★★(10/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆(1/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★★★☆☆☆(7/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆(1/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆(1/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★★★☆☆☆(7/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆(1/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★★★★★★(10/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★☆☆☆☆☆☆☆(3/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★★★★★★(10/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★★★★★★(10/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★★★★★★(10/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★★★★★★(10/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★★★★☆☆(8/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★☆☆☆☆☆(5/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★★★★★☆(9/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆(1/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆(1/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★☆☆☆☆☆(5/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★★☆☆☆☆(6/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★☆☆☆☆☆☆☆(3/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★★★★★★(10/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★★★★★★(10/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★☆☆☆☆☆☆☆☆(2/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★☆☆☆☆☆☆☆☆(2/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★☆☆☆☆☆☆☆☆(2/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆(1/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★★★★★☆(9/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★☆☆☆☆☆(5/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★☆☆☆☆☆(5/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★★★★☆☆(8/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★☆☆☆☆☆(5/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★☆☆☆☆☆☆☆☆(2/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★☆☆☆☆☆☆☆☆(2/10)
<再臨理解のために研究する必要性> ★★★★★★★★☆☆(8/10)
ここまで、再臨に関わりのある聖句が一つ一つ註解された。再臨を更に豊かに理解するために必要な註解すべき箇所は、恐らく全て取り上げることが出来たのではないかと思う。もしまだ取り上げるべき聖句が残っており、その聖句の存在に私が気付いていたならば、私はその聖句を註解していたであろう。しかし、私とて全知の存在ではない。私も有限な認識と知識しか持ち得ない人間である。それゆえ、本来であればこの第4部で註解すべき聖句がまだあるにもかかわらず、私がその聖句に気付いていない可能性がある。その聖句の数は1つだけかもしれないし、非常にたくさんあるかもしれないし、もしかしたらそのような聖句はもうないということも考えられる。もしそのような聖句があれば、ぜひ私に知らせていただきたいと思う。そうしたら、私はその聖句を註解して、この第4部を増補するであろう。本書は再臨を完全なレベルにまで考究することを目的としているのだから、そのような聖句を取り逃すわけにはいかないのである。
再臨理解のために聖書を考究していると、あることに気付かされる。それは、聖書ではそこら中にユダヤ戦争の記述が見られる、ということである。これは再臨を知ろうとして聖書を研究しなければ気付けないと思われる。例えば、マタイ24章とその2つの並行箇所はユダヤ戦争について預言された箇所である。黙示録でも、ユダヤ戦争に関して大いに語られている。エゼキエル書38・39章もそうである。イザヤ29:1~8の箇所もそうである。ゼカリヤ書14章も。更にダニエル書でもユダヤ戦争について語られている。今挙げたこれらの箇所は、ユダヤ戦争が直接的
に語られている箇所である。間接的に語られている箇所も含めれば、その数はあまりにも多くなる。例えば、Ⅰテサロニケ5:1~4の箇所がそうである。そこではユダヤ戦争の時期に起こる事柄が語られているからだ。
第4部 部分註解 [了]
[1]
[ローマ帝政期における皇帝の在位期間]
<70人訳聖書>
[再臨に関する重大な25の項目]
[本書の梗概]
ネロの自殺による死は、自殺による死であると同時に再臨によりもたらされた死でもあった。すなわち、再臨されたキリストが裁きを下されたのでネロは自殺により死ぬことになった。これは紀元68年6月9日のことである。このことについては既に第1部で説明済みだから、もうこれ以上説明する必要はないであろう。忘れてしまったり理解がまだ足りていない方は、第1部の該当箇所を再び読み返していただきたい。
このネロは、再臨による自殺の死という刑罰を受けた後、この世とは別の空間または次元にある永遠の火に投げ込まれることになった。彼は、そこで火により昼も夜も焼かれることになり、2000年経過した今でも火で苦しめられており、これからも永遠に火で苦しめられる。それは黙示録19:20の箇所で、ネロが『硫黄の燃えている火の池に、生きたままで投げ込まれた。』と書かれている通りである。先に述べた「自分のおるべき場所」とは、この火の池のことである。ダニエル書7:11でも、『その獣は殺され、からだはそこなわれて、燃える火に投げ込まれる』と預言されていたが、これはネロが再臨により殺されて火の池に投じられることを言ったものに他ならない。この黙示録19:20とダニエル書7:11は、明らかに似ており、同一のことを言っているのは間違いない。それゆえヨハネは、このダニエル書の記述に基づいてネロの悲惨な末路を預言したのだと我々は考えるべきであろう。この火の池については、また後ほど詳しく説明されることになる。話の流れとしては、今ここで書かないほうが相応しいからである。今は、この火の池が「永遠の刑罰を受ける場所」とか単に「地獄」とだけ理解していれば、それで充分である。
さて、再臨が起きる直前の時期には、多くの驚くべき出来事があった。その時には、『にせキリスト、にせ預言者たちが現われて、できれば選民をも惑わそうとして、大きなしるしや不思議なことをして見せ』(マタイ24章24節)た。すなわち、サタンに動かされた滅びの使いどもが、選ばれた聖徒を信仰から何とか離そうとして、大いに惑わしを行なった。真の聖徒は、この惑わしに惑わされてはならなかった。何故なら、キリストが『人に惑わされないように気をつけなさい。』(マタイ24章4節)と事前に命じておられたからである。また『エルサレムが軍隊に囲まれ』(ルカ21章20節)た。ネロの命令によりユダヤ鎮圧の使命を受けたウェスパシアヌスが(ウェスパシアヌス派遣が決まったのは紀元66年の冬である)、その子ティトゥスを遣わし―ウェスパシアヌス自身はアレクサンドリアの問題を処理する仕事があったのでティトゥスに代行させた―(「ユダヤ戦記」第4巻/xi4:657 文庫)、エルサレム市が無数のローマ軍に包囲されることになったのである。これは誰も疑うことのできない歴史の事実である。この時の状況についてタキトゥスは次のように書いている。「ティトゥスはユダエアで、第5、第10、第15の3箇軍団、いずれもウェスパシアヌスの古い兵士を受け継いだ。これにシュリアから第12軍団と、アレクサンドリアから連れて来た第22と第3軍団を加えた。さらに手許には、同盟部族の援軍歩兵20箇大隊と騎兵8箇中隊。同時にアグリッパ王とソハエムス王とアンティオコス王の援軍。近隣同士間によくある憎悪から、ユダエアに敵意を燃やしていたアラビア人の部隊、そして誰もまだ獲得していない元首の好意を手に入れたいと希望し、首都やイタリアから馳せつけた人も大勢いた。ティトゥスは、これらの軍勢を率いて整然と行軍し、敵地に入った。予めすべての状況を偵察し、臨戦態勢を整え、ヒエロソリュマ(※引用者註―エルサレム)から遠くない地点に陣営を築く。」(『同時代史』第5巻 1:1 p267~268:筑摩書房)このような包囲を見て、当時の聖徒は再臨が近いと真に悟ったことであろう。ところで、タキトゥスはこの時に「包囲されたユダエア人は、老幼男女合せて60万人いたと言われる。」(『同時代史』第5巻 13 p276:筑摩書房)と書いている。これはユダヤの国全体にいた人の数ではなく、首都エルサレム市の中にいた人の数だけであることに注意すべきである。また『不法がはびこるので、多くの人たちの愛は冷たくな』(マタイ24章12節)った。当時のユダヤには異邦人が多くおり、尊敬されていた指導者のパリサイ人も堕落しており、御心に適わないことがいっぱい行なわれていた。そこには愛をその本質とする神の律法が、真の意味において実践されていなかった。だからこそ多くの人たちから愛が失われてしまったのである。律法とは愛の戒めであるから(※)、不法の満ちている所には、当然ながら愛も無くなってしまう。また『荒らす憎むべき者』(マタイ24章15節)であるネロが、ダニエル書で預言されていた通りに現われた。この暴君は聖徒にとって、とんでもない存在であった。また『戦争のことや、戦争のうわさ』(マタイ24章6節)が耳に入ってきた。これは具体的には第一次ユダヤ戦争のことである。当時のユダヤはローマのくび木を打ち破ろうとして、どうしようもない犬のように飼い主と言うべきローマに牙を剥いていたのだから、いずれユダヤとローマとの間に戦争が起きるだろうという噂が広がったとしても何もおかしなことはなかった。実際、その噂は紀元66~70年に現実のものとなったのである。このように再臨の前には普通ではないことが多く起きたのだが、それは、あたかも間もなく死に至る病気に侵された人体のようであった。癌や糖尿病の人は、死の直前になると、身体に多くの異変が起こり、そうしてから死に至ってしまう。ユダヤという人体も、もう間もなく死んで滅ぼされる末期の状態であったから、末期の状態にある病人のように、多くの異変が起きたのである。その後、確かにユダヤは紀元70年9月に完全に滅ぼされることになってしまった。つまり人体で言えばユダヤは、この時に死んだことになる。今まで教会は、このような異変が未だに起きていない、つまりこれから起きると信じてきたが、既に説明されたことから分かるように、それらの異変は既に起きたことである。再臨が既に起きたと正しく理解すれば、その再臨の前に起きる多くの異常な出来事も、既に起きたことが分かるのである。このような異変がまだ未実現だと信じている人は、勘違いをしているので、即刻自分の考えを改めねばならない。
(※)
『律法の全体は、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」という一語をもって全うされるのです。』(ガラテヤ5章14節)
『「姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな。」という戒め、またほかにどんな戒めがあっても、それらは、「あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。」ということばの中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ、愛は律法を全うします。』(ローマ13章9~10節)
[本文に戻る]
この再臨の様子は次のようなものであった。まずキリストは『天の雲に乗って』(マタイ24章30節)来られた。雲とは、聖書では権威を象徴する。主がこの雲に乗って来られたのは、主が天地万物における至高の権威者だからでなくて何であろうか。確かに主は、『わたしには天においても、地においても、いっさいの権威が与えられています。』(マタイ28章18節)と宣言されたのである。そのような権威ある方が、権威を象徴する雲に乗って来られるのは実に相応しいことである。古代キリスト教最大のラテン詩人であるプルデンティウス(384-405以後)は、その詩の中でキリストが「赤い火のような天の雲に乗って来る」(『聖アンブロシウスの賛歌』プルデンティウス「ペリステファノン・リベル」 p106:サンパウロ)と言っているが、これは出鱈目である。聖書には、キリストが「赤い火のような」雲に乗って来るとは書かれていない。キリストの再臨の際の光景において赤いことが確実に分かるのは「雲」ではなく「火」である。またキリストは『ご自身天から下って来られ』(Ⅰテサロニケ4章16節)た。すなわち、キリストは自らの意思により再臨された。それは御父の命令によるものではあったが、御父と御子とは『一つ』(ヨハネ10章30節)であるから、再臨は御父の命令であると共に御子の意志でもあった。キリストは何かに強いられて嫌々ながら天から下って来られたというのではないのだ。またキリストは『号令と、御使いのかしらの声と、神のラッパの響きのうちに』(Ⅰテサロニケ4章16節)再臨された。これは象徴としての音ではなく、実際の音のことを言ったものである。この時どれだけ大きな音が鳴ったのか正確には分からない。私としては、考えられないほど非常に巨大な音が鳴り響いたと推測する。まさか、ほとんど誰も聞き取れないような小さな音だったということはないであろう。そのようなみすぼらしい音は、キリストの再臨という偉大な事象には相応しくないからである。またキリストの再臨は、稲妻でもあるかのようであった。キリストは、『人の子の来るのは、いなずまが東から出て、西にひらめくように、ちょうどそのように来る』(マタイ24章27節)と言っておられる。これは、つまり再臨は稲妻でもあるかのように突如として閃光と共に起こるということである。すなわち、再臨は津波のように徐々に迫って来る現象ではなかった。またキリストは『炎の中に』(Ⅱテサロニケ1章7節)天から下って来られた。これも音と同じで、象徴として言われているのではなく、実際の炎のことを言ったものであろう。火とは神の存在を示すものであるから(※①)、そのようなものを伴って神である方が再臨されるのは、実に相応しいことである。なお、この時、キリストがご自身の近くにある火から火傷や苦痛などといった害を受けなかったことは言うまでもない。この火は、再臨を演出するための忠実な使いであるから、キリストには害を与えないのである。またキリストは天から下って来られた際に、空中すなわち今で言えば飛行機が飛んでいる場所に留まられた。何故ならパウロは自分たちが携挙される時には、『雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。』(Ⅰテサロニケ4章17節)と述べているからである。聖徒が空中におられるキリストの所に引き上げられるとパウロは書いているのだから、このことを疑う聖徒がいるのであろうか。誰もいないであろう。言うまでもないことだが、キリストが地上まで降りて来られたなどと考える人があってはならない。それは聖書に反した夢想である。またキリストは『力ある御使いたちを従えて』(Ⅱテサロニケ1章7節)再臨された。黙示録5:11によれば、御使いたちの数は『万の幾万倍、千の幾千倍』である。万の幾万倍とは「少なくとも1億以上」であり、千の幾千倍とは「少なくとも100万以上」である。これは、つまり「とにかく多い」ということである。マタイ25:31によれば、キリストは『すべての御使いたちを伴って来る』。聞いたであろうか、キリストは『すべての御使いたち』と言っておられる。すなわち、再臨の際には、天で留守番をしている御使いは一人すらもいなかった。だから、再臨の際には、考えられないぐらいに多くの御使いがキリストと共にやって来たということが分かる。それは目がくらんでしまうぐらいに多い数だったことであろう。またキリストは、無数の聖徒と共に再臨された。エノクの預言はこうであった。『見よ。主は千万の聖徒を引き連れて来られる。』(ユダ14節)ここで言われている『千万』とは、実際の数ではなく、「非常に多い」ということを象徴的に言い表わしたものであろう。ユダが引用したこのエノクの預言の本文では「1万人」と書かれているが(※②)、1万であれ『千万』であれ、数の多さを示す象徴数であることには変わらない。パウロも数は明記していないが、キリストは聖徒たちを伴って再臨されると述べている。Ⅰテサロニケ4:14。『それならば、神はまたそのように、イエスにあって眠った人々をイエスといっしょに連れて来られるはずです。』主は、御使いだけではなく、聖徒たちをも再臨の際には伴われるのである。どうであろうか。このように再臨の様子を聖句に基づいて眺めてみると、実に壮大で驚くべきものだったということが分かるのではないだろうか。私としては、こんなにも凄まじい光景は他にないと感じられる。再臨を描いた映画であれば話は別だが、いかなる映画であれ、これほどまでのシーンを作り出すことは恐らくできないと思われる。このような雄大で感動的な光景は、キリストの再臨という偉大な出来事には、実に相応しいと言えよう。
(※①)
『私たちの神は焼き尽くす火です。』(ヘブル12章29節)
『きょう、知りなさい。あなたの神、主ご自身が、焼き尽くす火として、あなたの前に進まれ、主が彼らを根絶やしにされる。』(申命記9章3節)
[本文に戻る]
(※②)
「見よ、彼は1万人の聖者をひきつれて来られた。それは彼らに審きを行なうためである。彼は不敬虔な者たちを滅ぼし、すべて肉なる者、すなわち罪人たちと不敬虔な者たちが彼に対して働いたいっさいの不義を告発されるであろう。」(『聖書外典偽典4 旧約偽典Ⅱ』エチオピア語エノク書 第1章9節 p172:教文館)
[本文に戻る]
上で再臨の際には無数の聖徒がキリストと共にやって来るとエノクが預言しているのを確認したが、この聖徒は一体どのような存在なのであろうか。天にいなければキリストの再臨と共にやって来ることができないのは明らかだが、それでは、彼らはどのようにして天に上げられたのであろうか。まずこの聖徒たちは、キリストを「影」を通して信じていた旧約時代のユダヤ人のことである。すなわち、キリストが公生涯を開始される前までに、「ナザレのイエス」という存在としてはキリストを認識していなかった全ての選ばれていたユダヤ人である。これは例えばアブラハムやモーセやヨシュアやダビデやエレミヤが、そうである。旧約時代にキリストを「影」の形で信じていた選ばれたユダヤ人は、死んだ後、その魂がハデスの中へと入れられた。それはヤコブが自分の子らに、『あなたがたは、このしらが頭の私を、悲しみながらよみに下らせることになるのだ。』(創世記42章38節)また『私は、泣き悲しみながら、よみにいるわが子のところに下って行きたい。』(同37章35節)と言っていることから分かる。ダビデも死んでしまった子のことについて、『私はあの子のところに行くだろうが、あの子は私のところに戻っては来ない。』(Ⅱサムエル12章23節)と言っている。ここでダビデが言っている『あの子のところ』とはハデスである。これはヤコブもダビデも、自分の魂が死んでからハデスに入れられると信じていたことを示している。実際、旧約時代の聖徒の魂はハデスへと移されることになっていた。まだこの頃は、聖徒の魂が天に引き上げられる段階は訪れていなかったのである。とはいっても、聖徒の魂はハデスに置かれたからといって、火による苦しみを受けるわけではない。悪者の魂はハデスの火で焼かれるが、聖徒の場合はそうではない。キリストの話(ルカ16:19~31)によると、ハデスには2つのスペースがあるのが分かる。すなわち、アブラハムやラザロなど聖徒たちの魂が移される「良いスペース」と、あの金持ちと同じ滅びの子らの魂が移される「苦しみのスペース」である。この2つのスペースは完全に区切られており、一方のスペースからもう一方のスペースへと移ることはできない。良いスペースにいたアブラハムは、悪いスペースで苦しんでいたあの金持ちにこう言っている。『そればかりでなく、私たちとおまえたちの間には、大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても、渡れないし、そこからこちらへ越えて来ることもできないのです。』(ルカ16章26節)それゆえ、聖徒の魂がハデスに置かれたからといって、悪者の魂と同じように苦しめられていたと考えるのは誤りである。確かにラザロはハデスに入れられはしたが、しかし、そこにある「良いスペース」で『慰められ』(ルカ16章25節)ていたのである。しかし、キリストが死なれてからハデスに下られた際、キリストはハデスの力に打ち勝たれてハデスから抜け出られたのだから、この時にハデスにいた旧約時代のユダヤ人もハデスから解放されることになった。要するにキリストがハデスを屈服させることで、そこに閉じ込められていた聖徒たちを出られるようにして下さったということである。それ以降、今まではハデスにいた聖徒たちの魂は、もはやハデスに縛られることがなくなった。このハデスからの解放については、このように預言されていた。『まことに、あなたは、私のたましいを、よみに捨ておかず、…』(詩篇16篇10節)『しかし神は私のたましいをよみの手から買い戻される。神が私を受け入れてくださるからだ。』(同49篇15節)『あなたが私のたましいを、よみの深みから救い出してくださったからです。』(同86篇13節)キリストはご自身の力と勝利によりハデスから解放されたこの魂たちを、上げられる時に天へと引き連れて行かれた。それは、『高い所に上られたとき、彼は多くの捕虜を引き連れ』(エペソ4章8節)とキリストの昇天について書かれている通りである。ここで言われている『捕虜』とは、ハデスの捕虜にされている聖徒でなくて何であろうか。そのようにして天へ上げられた聖徒の魂は、再臨の日が訪れるまで、その魂のままに留め置かれた。すなわち紀元68年6月9日までは、御霊の身体が与えられることもなく、ただ魂だけの状態であった。再臨の日が遂に訪れると、この魂だけの状態だった天にいる聖徒は御霊の身体を受けて復活し、その復活した状態でキリストと共に天からやって来ることになった。注意しなければならないのは、この再臨の日よりも前に、天にいる聖徒が御霊の身体を受けて復活することはなかったということである。そのように考えるのは誤っている。何故なら、御霊の身体による復活が始めて起きるのは、キリストの再臨されるその日だからである。キリストはヨハネ6章で、終わりの日すなわち再臨の起こる日に聖徒が復活させられると何回も言われたのだから、その日よりも前に復活が起きたというのは考えられないことである。そして、その日になると、聖徒たちは物理的にしっかりと復活した状態で、キリストと共に空中へと降りて来る。つまり、魂だけの状態で空中にひとまず下りて来て、空中に来てから物理的に復活するのではない。聖徒が空中に来る時には、既に御霊の身体が与えられた状態となっている。何故なら、エノクもパウロも、再臨の際にはキリストが聖徒を引き連れて来られると言っているからである。そうであれば、必ず、地上にいる人たちが天からやって来る聖徒を物理的に認識できなければいけないはずである。もし聖徒が魂だけの状態でキリストに連れて来られるとすれば、どうして、その魂だけでしかない聖徒を物理的に認識できるであろうか。それはできないことである。よって、我々は天にいる聖徒が天であらかじめ復活してからキリストと共に空中に降りて来たか、そうでなければ天から出たその瞬間に復活した、と考えなければならない。降りて来るその時にも、まだ魂だけの状態だったというのは考えられない話である。当然ながら、この天から降りて来た聖徒の中に、キリストを「実体」として、つまり「ナザレ育ちのイエス」という存在として信じていた聖徒―例えばペテロやパウロやバルナバ―は一人も含まれていなかった。何故なら、もう少ししたら説明されるように、彼らは地上において復活に与かり、それから再臨されたキリストのおられる空中へと引き上げられるからである。
この無数の聖徒を伴う再臨を見た多くの人たちは、大いに嘆くことになった。『地上の諸族はみな、彼のゆえに嘆く。』(黙示録1章7節)『すると、地上のあらゆる種族は、悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見る』(マタイ24章30節)と預言された通りである。再臨されたキリストは『天に上って行かれるのをあなたがたが見たときと同じ有様で』(使徒行伝1章11節)来られたのだから、尚更のこと、人々の嘆きは大きかったはずである。つまり、本当に肉体を持ってキリストが来られたのだから、それが幽霊や幻だった場合に比べて、遥かに大きな情動が心に生じたはずである。もし再臨が幽霊や幻の形で起きたとすれば、嘆きの度合いが弱かったか、そうでなければ全く嘆かれなかったということも考えられる。そこには生々しさがないからである。確かに当時生きていた人たちは再臨を見て嘆いたのであるが、それがどれほど大きな嘆きだったかということは想像に難くない。何故なら、再臨されたキリストを見たことにより、ユダヤ人とキリスト教徒が妄想を抱いていたのではないということが分かっただろうからである。「彼らが言っていたことは本当だったとは…」と。もっとも、この嘆いた人たちは、再臨の光景を見て嘆いたからといって、キリストに対する信仰を持ったわけではないことは言うまでもない。それは、様々な事象と証言を通してキリストが聖なる使者だったことを認めざるを得なくさせられたものの、実際にはキリストを信じて悔い改めることがなかったパリサイ人や長老たちと同じである(※)。
(※)
参考情報として挙げておくが、当時のユダヤ人たちは、カリヌスとレウキウスによる証言を聞いてキリストにおける神の働きを認めたものの、信仰を持って悔い改めることは出来なかったようである。外典の「ニコデモ福音書」の中では、このことについて次のように書かれている。「以上読み終ると、みながこれを聞いてひれふし、いたく泣き、おのれの胸をひどく打ち叩き、叫んでそれぞれ言った、「我らにわざわいあれ。どうしてこういうことがみじめなわれらに起こってしまったのか。」ピラトが逃げ、アンナとカヤパが逃げ、祭司レビ人達が逃げ、さらにユダヤ国民が、泣きながら「みじめな我らにわざわいあれ。我らは聖なる血を大地に流してしまった」と言いつつ、逃げた。かくして三日三晩、パンも水も全然とらず、また誰一人とて会堂にもどってくる者はいなかった。しかしまた三日目に会議が召集され、今後はレウキウスの文が読みあげられた。けれどもそれはカリヌスの書いたものが含んでいることと一字一句同じで、一語も多くも少なくもなかった。そこで会議は混乱に陥り、四十日四十夜喪に服し、神から滅亡と罰とを与えられるのではないかと恐れた。けれども、かの憐みに富み給う至高者は、ただちに彼らを滅ぼすことはなされず、悔い改める機会を大幅に与えられた。けれども彼らは主に対して悔い改めることのできる者ではなかった。…」(『聖書外典偽典6 新約外典Ⅰ』ニコデモ福音書(ピラト行伝)第章27節(第11章) p228:教文館)
[本文に戻る]
無数の聖徒を伴うこの再臨が起こると、裁きの座が備えられ、その座に多くの者が着いた。黙示録20:4にはこう書かれている。『また私は、多くの座を見た。彼らはその上にすわった。そしてさばきを行なう権威が彼らに与えられた。』ここで言われている座に着いた『彼ら』とは誰であろうか。直前の箇所である20:1~3に出てくる『御使い』(20章1節)であろうか。そうではない。聖書は御使いが裁きの座に着くとは教えていないし、『彼ら』と複数形で書かれているのに対し、『御使い』は単数形だからである。ここで言われている『彼ら』とは、少し前の箇所である19:19の『馬に乗った方とその軍勢』、すなわちキリストとキリストに付き添う聖徒たちのことである。この人々は、先に説明されたように、非常に多くの人数であり、単数形ではなく複数形で表現されるに相応しい人たちである。それゆえ、この人々こそ『多くの座』に『すわった』『彼ら』だということになる。これから説明されるが、確かに聖書は聖徒たちこそ裁きの座に着く者たちであると教えている。さて、それではこの聖なる人々は座に着いて一体何を裁くというのであろうか。彼らが裁く対象は、全部で3つある。一つ目は、キリストを否んだユダヤ人である。キリストは弟子たちに対して次のように言われた。『まことに、あなたがたに告げます。世が改まって人の子がその栄光の座に着く時、わたしに従って来たあなたがたも12の座に着いて、イスラエルの12の部族をさばくのです。』(マタイ19章28節)イスラエルの12部族は、今までに多くの血を流した上に、遂に来られた預言されていたメシアをさえも否んで殺したので、報いとして裁かれねばならなかった。このようなイスラエルが裁かれないことは、あり得ないことであった。二つ目は、世界すなわち諸国の民である。パウロは、コリント人たちにこう言った。『あなたがたは、聖徒が世界をさばくようになることを知らないのですか。世界があなたがたによってさばかれるはずなのに、…』(Ⅰコリント6章2節)当時の世界にいた人々は、キリストの福音が大いに宣べ伝えられたにもかかわらず、それを受け入れなかったので、裁かれねばならなかった。御子を否んでおきながら、裁かれないままでいることがどうしてあろうか。この2つの裁きはカルヴァンも「関連させるべきこと」(『新約聖書註解Ⅷ コリント前書』6:2 p134 新教出版社)、すなわち同時的に起こるべきことであると言っているが、それは正しい見方であった。三つ目は、サタンである。パウロは『私たちは御使いたちをもさばくべき者だ、ということを知らないのですか。』(Ⅰコリント6章3節)とコリント人に言っている。サタンは、それまで数千年間も悪事を行ない続けてきたので、キリストと聖徒による裁きを受けねばならなかった。人類は、このサタンの惑わしにより堕落に至らしめられたのである。それでは一体どうして、聖徒たちは被造物に過ぎない身分であるにもかかわらず、キリストと同じように裁きの座に着いて、キリストと同じように裁きを執行するのであろうか。それは、キリストが聖徒たちを愛しているからであって、ご自身に与えられた状態と権威とを聖徒たちにも与えて下さるからである。キリストは聖徒のために命をさえ犠牲にされた恵み深いお方だから、ご自身の受ける状態と権威を聖徒にも与からせて下さるのである。それゆえ、キリストは聖徒たちにこう言っている。『勝利を得る者を、わたしとともにわたしの座に着かせよう。それは、わたしが勝利を得て、わたしの父とともに父に御座に着いたのと同じである。』(黙示録3章21節)『勝利を得る者、また最後までわたしのわざを守る者には、諸国の民を支配する権威を与えよう。彼は、鉄の杖をもって土の器を打ち砕くようにして彼らを治める。わたし自身が父から支配の権威を受けているのと同じである。』(黙示録2章26~27節)実際の裁きがどのようなものであったかということについての詳細は、後ほどまだ語られることになる。何故なら、順序的にそうするのが相応しいからである。ひとまず、ここでは再臨の際に裁きの座が備えられて、その上に聖なる人々が座り、彼らに裁きを行なう権威が与えられた、ということだけを述べるに留めたい。
先
に再臨の際に天上において、または天から降りて来る時に御霊の身体を受けて復活した聖徒のことが説明されたが、再臨の際には、地上において復活に与かる聖徒もいる。彼らは上のほうの場所で復活することがなく、復活した状態で再臨のキリストに引き連れられるということもない。これは、キリストを「ナザレのイエス」として、つまり影ではなく実体として信じていた全ての聖徒のことである。正確に言えば、キリストが公生涯を開始された紀元30年頃から紀元68年6月9日までの間に、キリストを信じた全ての人である。この時に起こる復活こそ、正にあの「第一の復活」である。黙示録20:4~5ではこう書かれている。『また私は、イエスのあかしと神のことばとのゆえに首をはねられた人たちのたましいと、獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返って、キリストとともに、千年の間王となった。そのほかの死者は、千年の終わるまでは、生き返らなかった。これが第一の復活である。』この復活は、地上において生き返る聖徒の復活だけでなく、上のほうの場所で生き返ってキリストと共に降りて来る聖徒の復活のことも含まれている。簡単に言えば、この第一の復活とは、ある人の魂に御霊の身体が与えられることである。地上でこの復活に与かる聖徒と、上のほうの場所でこの復活に与かる聖徒は、どちらのほうが時間的に早く復活に与かったのであろうか。地上の聖徒のほうが先であろうか、それとも天上の聖徒のほうが先であろうか。私としては、両方とも同時期であったと理解する。というのは、パウロがこう言っているからである。『私たちは主のみことばのとおりに言いますが、主が再び来られるときまで生き残っている私たちが、死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。』(Ⅰテサロニケ4章15節)これは、パウロと共に生きていた聖徒の復活が、再臨の際に連れて来られる聖徒の復活に先んじることはないと述べたものであろう。そうであれば、逆に、天上にいる聖徒の復活が、地上にいる聖徒の復活より先んじるということもないと考えられる。そうすると、両方の復活は同時期であったということになる。さて、地上において第一の復活に与かる聖徒は2種類に分けられる。それは、当時既に死んでいた聖徒と、まだ生きていた聖徒の2種類である。まずは死んでいた聖徒のほうから説明する。紀元68年6月9日までに死んだ聖徒の魂は、旧約時代の聖徒のようにハデスに入れられることもなければ、天に引き上げられるというのでもない。その魂は、地上に残され、そのままに留め置かれた。しかし、再臨の日が訪れると、この墓の中にいた聖徒たちは命の息を受けて第一の復活に与かり、墓の中から出てくることになった。その墓から復活した聖徒の数がどれほどであったのかは分からない。かなり少なかったということはないと思われる。当時は多くのキリスト者が殉教したのだから、当然ながら墓から出てきた聖徒の数も多かったと考えるべきであろう。次は生きていた聖徒の復活である。紀元68年6月9日に生きていた聖徒は、その持っていた身体がそのまま新しい御霊の身体に切り替えられるという形で、第一の復活に与かった。その切り替えは一瞬の間に行なわれた。パウロはこのことについて、コリント人にこう言っている。『聞きなさい。私はあなたがたに奥義を告げましょう。私たちはみなが眠ってしまうのではなく、みな変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち、一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。』(Ⅰコリント15章51~52節)確かにパウロが言うように、『血肉のからだは神の国を相続できません。』(Ⅰコリント15章50節)キリストもこう言っておられる。『人は、新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。』(ヨハネ3章3節)もうお分かりであろう。当時の聖徒が持っていた血肉の身体では天の御国に入ることができなかったので、御霊の身体を受けて物質的に新しく生まれなければいけなかったのである。この時にキリストが再臨されたのは、聖徒たちを天の御国に引き入れるためであったということは言うまでもない。地上において生きたまま第一の復活に与かったこの聖徒の数も、墓から出てきた聖徒の数と同じように、かなり多かったと思われる。このように地上における第一の復活には2種類あるが、これこそ、キリストが終わりの日に聖徒を蘇えらせると言っておられたことに他ならない。既に述べたように、終わりの日とは、すなわち再臨の起こる日のことであって、既に過ぎ去っている(※①)。キリストが言われた御言葉はこうであった。『わたしを遣わした方のみこころは、わたしに与えてくださったすべての者を、わたしがひとりも失うことなく、ひとりひとりを終わりの日によみがえらせることです。事実、わたしの父のみこころは、子を見て信じる者がみな永遠のいのちを持つことです。わたしはその人たちをひとりひとり終わりの日によみがえらせます。』(ヨハネ6章39~40節)『わたしを遣わした父が引き寄せられないかぎり、だれもわたしのところに来ることはできません。わたしは終わりの日にその人をよみがえらせます。』(同44節)『わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む者は、永遠のいのちを持っています。わたしは終わりの日にその人をよみがえらせます。』(同54節)これらのキリストの御言葉は、再臨の起きた紀元68年6月9日に成就された。まだこの御言葉が一度も成就していないと考えるのは誤っている。最後に、私に反抗したある兄弟のことを書きたい。ある兄弟は、私が既に復活が起きたと信じていることを知り、このように吠えかかってきた。それは、すなわち、こういうことであった。「あなたは「復活はすでに起こったと言って、ある人たちの信仰をくつがえしている」のではありませんか。あなたこそ、パウロの言っていたこの人なのではありませんか。」この兄弟が引用した聖句は言うまでもなくⅡテモテ2:18のものである。この不信仰な兄弟は、聖書が教える復活のことをよく弁えていない。彼は不信仰のゆえに私を愚かにも非難している。Ⅰテサロニケ4:15~17を見れば分かるように、パウロは当時の聖徒たちが『生き残っている』(4:15、17)間に、『主が再び来られ』(4:15)、『それからキリストにある死者が、まず初めによみがえ』(4:16)る、と言っているではないか。『生き残っている』とは、どういう意味か。言うまでもなく、「生存中に」また「死ぬことになるまでに」という意味である。つまり、パウロは明らかに紀元1世紀の聖徒が生きている間に、死ぬことになる前に、死者の復活があると言っていることになる。彼の使ったⅡテモテ2:18の聖句は、まだ復活が起きていなかった当時には正にその通りであったが、既に復活は起きたのだから、今の時代においてこの聖句を使って私を非難することはできない。さあ、不信仰な者よ、パウロを通して語られた神の言葉を否定できるならばしてみよ。パウロが当時の人たちが生きている間に復活があると明らかに述べたことに、もしできるというのならば、言い逆らってみよ。できるのか。もしできるというのならば、この兄弟は御霊の言われたことに抗弁することになる。この兄弟が、このように愚かにも私を非難したことは完全に間違っていた。実際、私がこの非難に対して聖書から答えると、この兄弟は答えられず、それ以降何も言わなくなってきた。私が答えたその文章はこうであった。私の書いた文章をそのまま転載しよう。「私が「復活は既に起こった」ということを信じていることを批判し問題にされるのでしょうか。パウロは、再臨が起きた際にまず「復活」が起こり、そうしてから当時生きていた紀元1世紀の聖徒たちが携挙されると書いたのではありませんか。パウロはこう言っています。「私たちは主のみことばのとおりに言いますが、主が再び来られるときまで生き残っている私たちが、死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は、号令と、御使いのかしらの声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者が、まず初めによみがえり、次に、生き残っている私たちが、たちまち彼らといっしょに雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。」(Ⅰテサロニケ4:15~17)この御言葉の中で、明らかにパウロは当時の聖徒たちが「生き残っている」時に、再臨および復活があると述べています。また私たちが既に成就したと信じている旧約聖書の預言の中でも、死者の復活のことが言われています(ダニエル12:2)。もし旧約聖書の預言が全て成就したのであれば、ダニエル書12:2に書いてある復活も既に成就していることにならないでしょうか。」私の述べた聖書的な答えに抗弁すれば、神が言われたことに抗弁することになるのだから、この兄弟が何も答えられなくなってしまったのは自然なことであった。キリスト者であると思われている人の中で一体誰が「パウロの言っていたことは間違っていた。すなわち、パウロと共にいた聖徒たちが生き残っている間に死者の復活が起こることはなかった。」などと言えるであろうか…。私はパウロの語った御言葉をそのまま素直に信じているが、この兄弟はそうせず、そればかりか御言葉を素直に信じている私を批判しさえする。どちらの態度のほうが神に喜ばれるのか考えてほしいものである。クリスチャンとは、御言葉をそのまま素直に信じるべき人たちのことである。この兄弟は、パウロの語ったことをよく理解できていなかったと認め、神の御前に悔い改めなければいけない。そうして、「当時の人たちが『生き残っている』時に復活が起きた。」ということを、パウロの御言葉に基づいて信じなければいけない。他の人たちも、この兄弟のように復活のことに関して不信仰にならないように、よくよく気をつけていただきたい。
(※①)
次の引用文が示すように、アウグスティヌスは復活の起こるこの終わりの日がまだ到来していないと考えていたが、それは彼の無知に基づく誤謬であった。「最後には、ある人たちはこの死を突然の変化によって味わうことなく、復活する人たちと共に空中でキリストと会うために雲のなかに拉し去られ、こうして主と共にいつまでも生きるであろうということが、終わりの日に授けられるであろう(Ⅰテサ4・16参照)。」(『アウグスティヌス著作集29 ペラギウス派駁論集(3)』罪の報いと赦し、および幼児洗礼 第2巻 第31章 第50節 p146:教文館)
[本文に戻る]
この第一の復活に与かった地上の聖徒は、裁きを行なう王として、先に述べられた裁きの座に着いた空中のキリストおよび聖徒と共に、聖なる裁きを執行した。この裁きこそ、『キリストとともに、千年の間王となった。』(黙示録20章4節)という御言葉の意味である。これは、つまり第一の復活に与かった聖徒が、裁きを行なう王になったことを預言したものである。黙示録では『千年』と言われているが、これは象徴表現であって、実際には非常に短い時間を指している。多くの者らは、この千年という期間が未だに訪れていないか、または今がその期間であると考えている。もし、そうだとすると、今の時代はまだ黙示録20:1~6の箇所まで至っていないか、または今が20:1~6の時代だということになる。実際、今のほとんど全ての教会は、このどちらかの見解を持っている。どちらの見解であっても、まだ黙示録には起きていない箇所があると信じていることには変わらない。すなわち、まだ20:1~6の箇所まで至っていないと考える者は少なくとも20:1以降の箇所はまだ起きていないと信じており、今が20:1~6の箇所だと考えている者は20:7以降の箇所がまだ起きていないと信じている。しかし、御霊はヨハネを通して、黙示録で示されたことについてこう言われた。『御使いはまた私に、「これらのことばは、信ずべきものであり、真実なのです。」と言った。預言者たちのたましいの神である主は、その御使いを遣わし、すぐに起こるべき事を、そのしもべたちに示そうとされたのである。』(黙示録22章6節)この聖句で言われているように、黙示録に示されている全てのことは『すぐに起こるべき事』である。多くの者らが考えているように、もし黙示録にまだ実現していない箇所があるとすれば、御霊の言われたことと明らかに矛盾してしまう。黙示録には『すぐに起こるべき事』が示されていると言われた御霊が偽りを言われることはあり得ないから、黙示録は20:1~6の箇所も、それ以前の箇所も、20:7以降の箇所も、すぐに起きたことになる。それらの箇所が当時においてすぐに起きたというのであれば、そこに書かれている『千年』という期間も短かったと、つまりそれは象徴表現であったと考えねばいけないことになる。では、千年という表現で言い表わされている裁きの期間は具体的にはどれぐらいの期間なのであろうか。それは「1日以内」である。何故なら、再臨の起こる日とは『書かれているすべてのことが成就する報復の日』(ルカ21章22節)だからである。この日に旧約聖書に書かれている全ての預言が成就した。つまり、エゼキエル書38章でゴグがイスラエルを攻めると言われている預言も、当然ながら、この日に成就した。このエゼキエル書38章の内容と、黙示録20:7~10の内容が、非常に似ていることを疑う人は誰もいないはずである。どちらのほうにも『ゴグ』『マゴグ』「火が降って来る」「多くの集団が集められる」「イスラエルが攻められることになる」などといった同じことが多く書かれている。もしこの2つの箇所を非常に似ていると思わない人がいれば、その人は気の狂った馬鹿者か精神障害者であると思われる。つまり、ヨハネはエゼキエル書38章のことを黙示録20:7~10で預言したのである。それで、エゼキエル書38章が再臨の日に成就したとすれば、同じことを書いている黙示録20:7~10の箇所も再臨の日に成就したことになる。もし黙示録20:7~10の箇所が再臨の日に成就したのであれば、その前の箇所である20:4~6に書かれている『千年』という期間も再臨の日における24時間以内のことであったと考えなければいけない。何故なら、千年の終わりになるとサタンが多くの軍勢を動員させてエゼキエル書38章と対応した箇所である黙示録20:7~10の出来事を実現させるからである。千年の期間は再臨の日に起きた第一の復活の時から始まり、エゼキエル書38章(=黙示録20:7~10)の出来事が実現するための条件である千年の終わりの到来も再臨の日に起こる。そうして千年の終わりが到来すると、すぐにもサタンがエゼキエル書38章(=黙示録20:7~10)を実現させるために軍勢を動員させるのだから、その動員の出来事によりエゼキエル書38章(=黙示録20:7~10)が成就することになり、千年の期間も終わりを告げる。それゆえ、『千年』という期間は非常に短い期間、しかも1日以内の期間であると考えなければいけないことになる。御言葉に基づいて考えるならば、このように理解する以外にはない。理性により考える者たちは、まだ千年が終わっていないか、まだ訪れていないと信じているが、そのように理解すると御言葉に言い逆らうことになる。すなわち、黙示録に示されていることは『すぐに起こるべき事』であると言われた御言葉に抗弁しなければいけないことになる。御言葉は理性により弁えるべきものでなく、御霊により弁えるべきものである。御霊により御言葉を弁えられない者は、御霊を実は受けていない可能性がある。だからこそ御霊ではなく理性により御言葉を弁えようとするのである。御霊を受けていないのに、どうして御霊によって御言葉を弁えられるというのか。御霊を受けていない者は、神の民ではないから、キリストの教会から退場すればよかろう。そこは御霊を持たない生まれながらの人間が籍を置くべき組織ではないのだから。御霊により御霊に属する御言葉を弁えたいと願う者は、次のパウロの聖句を心に留めるべきである。『生まれながらの人間は、神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。また、それを悟ることができません。なぜなら、御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。』(Ⅰコリント2章14節)さて、それではヨハネは一体どうして、短い期間を『千年』などと記したのであろうか。黙示録は、無数の謎と秘儀が隠されている書物だから、たとえ1日を『千年』と言い換えたとしても何も不思議なことはない。しかし、その言い換えた理由はどのようなものだったのか。その一つとして考えられるのは、再臨と復活の起きた日が、千年と言い換えられるに相応しい1日だったということである。1日を千年と言い換えることや、千年を1日と言い換えることは、確かなところ、聖書的なことである。何故ならペテロがこう言っているからである。『すなわち、主の御前では、1日は千年のようであり、千年は1日のようです。』(Ⅱペテロ3章8節)神にとっては、1日は千年のように感じられるものでもあり、千年は1日のように早く過ぎ去るものであるかのようである。それでは、この再臨と復活の起きた紀元68年6月9日とは、どのような1日であったのか。それは、あまりにも驚くべきことが何回も起こる、前代未聞の大いなる日、聖なる日、特別な日、2度と訪れない日である。そのような2度と訪れることのない素晴らしい1日における偉大性や特殊性を悟らせるためには、千年と表現するのが相応しい。そうするのは優れた英知によるものである。本当は1日であるのに千年などと言われたら、誰でもその日が何か特別な日であると感じるはずである。しかし1日を「1日」とだけしか表現しないのであれば、それほど特別な感じは受けないし、偉大な1日を表現する言葉としては何か物足りない感じもしてしまう。このために、ヨハネが1日を「千年」と表現したというのが、この言い換えの理由として考えられる理由の一つである。簡単に言えば、ヨハネは「1日」という期間に表現における当然なすべき聖なる誇張を仕掛けたということである。または「この1日は千年にも感じられるほどに長い1日なのだ。」ということを言い表わそうとしたとも考えられる。誰でも、驚くべきことが色々と起きる日は体感的に長く感じるものであるが、再臨と復活の起きたこの1日ほど長く感じられるような日が他にあるであろうか。ないであろう。もう一つの理由として考えられるのは、この裁きの時間における完全性また絶対性を示そうとして『千年』と言い換えられたというものである。つまり、その完全性と絶対性を教えようとして、「10×10×10」=『1000年』と表現したということである。聖書において10は完全数であるから、それが三つ掛け合わされた1000という数字は、完全の極みということであり、究極的な絶対性がそこに存在しているということを意味する。聖徒たちの王としての裁きには、言うまでもなく完全性と絶対性とが、そこにはある。そうでなければ、どうして聖徒たちが世を裁くことになるという御言葉が実現されようか。完全で絶対でなければ全き裁きもできないであろう。聖徒たちの裁きが完全的なもの、絶対的なものであったとすれば、そのような裁きの期間を『千年』と表現するのは実に相応しいことである。このように「1000」を10の三乗と考えるのは、カルヴァンの見解でもあった。もちろん、だからといって、この見解が真に正しいと言うことになるのではないが。カルヴァンも誤謬を持った一人の人間に過ぎないのである。しかしプロテスタントの権威であるカルヴァンもそう考えていたということは、この見解をもっともらしく思わせてくれる要素の一つであるということは確かである。このように『千年』と言い換えられた理由は2つ考えられるのだが、どちらが正しいかということは、今の私にはまだ確かなことはいえない。どちらか一方が正しいかもしれないし、両方とも正しいのかもしれない。ただ一つ確実に言えるのは、この『千年』という言葉が1000年か、またはそれ以上の長い期間を指しているのではないということである。そのように考えるのは誤謬であり、御霊の御言葉に言い逆らうことになる。この期間については、今の時点では、以上のことを語るだけにしたい。また後ほど、再び、この期間について詳しく論じることになるであろう。さて、地上で第一の復活に与かった聖徒たちと空中の座に着いているキリストおよび無数の聖徒たちは、この再臨の日に、大いなる裁きを行なった。その裁きが行なわれる時とは、『千年の終わりに、サタンはその牢から解き放され』(黙示録20章7節)た時である。すなわち、サタンが多くの軍勢を召集して『聖徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ』(黙示録20章9節)時に、裁きが執行される。何故なら、そうなってから色々な裁きが下されているのが確認できるからである(黙示録20:7~10)。この裁きが行なわれる時間は、非常に短い。それは、後ほど説明される「最後の審判」における審判の時間が、非常に短いのと同じである。これは数日、数週間、数年、数千年と時間がかかるようなものではない。また、この裁きが行なわれている最中は、まだ千年の期間が終わることがない。つまり、千年の期間の間に、裁きが行なわれるということである。何故なら、復活した聖徒たちが王として裁きを行なう期間が「千年」なのだからである。先に3種類の対象が裁かれると書かれたが、それを一つ一つ見ていくことにしよう。まず初めに見ていくのは「全世界」つまり諸国の民である。これは、つまりローマの軍隊のことである。すなわち、ローマの軍隊により全世界また諸国の民が表示される。これはローマの軍隊がエルサレム包囲のために召集されることについて、こう書かれていることからも分かる。『しかし千年の終わりに、サタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわち、ゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海べの砂のようである。』(黙示録20章7~8節)これはエルサレム包囲について書かれている箇所だから、召集された『地の四方にある諸国の民』とはローマの軍隊以外のことではない。当時はローマと言うことで慣用的に全世界を表わしたのだから、ローマの軍隊により全世界の民が表示されているとしても何も不思議なことはない。つまり、この諸国の民を表示させる存在であるローマ軍に裁きが下されることで、全世界に裁きが下されることになったのである。神は、非常に多くの存在や場所における諸々の悪に対する裁きを、ある一つの存在や場所に裁きを下されることで全うさせようとされるお方である。それは、それまでに多くの場所で流された無数の義人の血に対する報いが、紀元1世紀におけるイスラエルという一つの存在および場所に纏めて下されることで全うされたことからも分かる。つまり、神は今までに積み重ねられた悪に対する裁きを留保しており、ある時点になると、ある一つの存在や場所に纏めて下されることでその溜め込まれた裁きを解放されるということである。キリストは確かに次のようにパリサイ人に対して言われたのである。『だから、わたしが預言者、知者、律法学者たちを遣わすと、おまえたちはそのうちのある者を殺し、十字架につけ、またある者を会堂でむち打ち、町から町へと迫害して行くのです。それは、義人アベルの血からこのかた、神殿と祭壇との間で殺されたバラキヤの子ザカリヤの血に至るまで、地上で流されるすべての正しい血の報復があなたがたの上に来るためです。まことに、あなたがたに告げます。これらの報いはみな、この時代の上に来ます。』(マタイ23章34~36節)よって、全世界を表示させるローマ軍に裁きが下されることにより、それまでに福音を信じなかった全ての国民に対する裁きが代わりに下されたことになるのである。このような裁きが聖徒たちにより下されたので、このローマ軍は全世界に対する裁きを受ける者として、エルサレムの炎上の中に巻き込まれることになった。『すると、天から火が降って来て、彼らを焼き尽くした。』(黙示録20章9節)と書いてある通りである。当時、ローマ軍のいたエルサレムが火の海に包まれたのは、歴史の事実である。Ⅰコリント6:2の『あなたがたは、聖徒が世界をさばくようになることを知らないのですか。』という聖句は、このようにして成就した。確かにパウロが言ったように、この聖句を読んだであろう当時のコリント人たちは、紀元68年6月9日に復活して世界を裁くようになったのである。次は「サタン」に対する裁きである。このサタンも再臨の日に復活した王である聖徒たちから裁きを下され、その後、永遠の火に投げ込まれることになった。『そして、彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。』(黙示録20章9節)と書いてある通りである。これは、つまり簡単に言えば別世界または別の次元にある地獄のことであるが、このことについては後ほどまた詳しく説明されることになる。この黙示録20:9の出来事については、その箇所に来るまで、早まった判断をしないで待っていてほしい。その箇所に来たら、このことについて詳しい説明がされることであろう。この地獄には、少し前の時間に、既にネロが投げ込まれていた。これによりⅠコリント6:3の『私たちは御使いをもさばくべき者だ、ということを、知らないのですか。』というパウロのコリント人に対する聖句は成就された。ここで言われている『御使い』とは、言うまでもなく「罪を犯した悪しき御使い」すなわちルシファーのことでなくて何であろうか。ミカエルやガブリエルなどといった罪を犯していない聖なる御使いが裁かれるということが、どうしてあるであろうか。そのようなことは決してない。それゆえ、この御使いという言葉を我々は正しく理解しなければいけない。この御使いを「聖なる御使い」であると考えるのは誤りである。このように考えると、確かにパウロの語ったように、本当に当時のコリント人が御使いを裁くことになったということが分かるであろう。パウロは、この時のことをコリント人に言っていたのである。最後は「ユダヤ人」の裁きである。先にマタイ23:34~36の箇所で確認した通り、当時のユダヤ人は、それまでに流された義人の血に対する溜め込まれた裁きを纏めて喰らう役割―何という悲惨な役割であることか!―を担っていた。その纏めて放出される裁きを、ユダヤ人はこの時に受けることになったのである。その裁きのため、ユダヤ戦争において最高で110万人とも推定されるユダヤ人が殺され、エルサレムが紀元70年に完全に跡形も無くなることになり、このユダヤ人たちで生き残った者らは全世界に散らされて放浪することになった。そうしてこのユダヤ人たちは、今に至るまで放浪の民として、世界中に散らされたままである。あのエルサレムにあった神殿の場所も禍々しい岩のドームに占領されてしまっており、まるでユダヤを侮辱しているかのように陣取っている。彼らは今に至るまで実に多くの迫害を受けて苦しめられてきた。彼らにはもはや、レビ族もユダ族もイッサカル族もゼブルン族もナフタリ族もベニヤミン族もヨセフ族もルベン族もシメオン族もダン族もガド族もアシェル族も、何の区別もない。更には、アブラハムの血を持たない非純正のユダヤ人まで多く混入されることにさえなった。このようになったのは紀元68年6月9日に彼らが裁きを受けたからに他ならない。ああ、彼らが裁きを受けていることを否定する者がどこにいるであろうか。彼らが裁きにより呪いを受けているのは明らかである。実に、裁きを受けたというのでなければ、このような悲惨な境遇は考えられないのである。このユダヤ人に対する裁きは、先に述べられた全世界とサタンに対する裁きとは異なり、非常に分かりやすいものではないかと思う。目に見える非常に明瞭な形で、彼らに悲惨が降りかかっているのが分かるからである。この時の裁きにより、キリストの言われた『わたしに従ってきたあなたがたも12の座に着いて、イスラエルの12の部族をさばくのです。』(マタイ19章28節)という預言が成就されることになった。確かにキリストの目の前でこの預言を聞いていた弟子たちは、紀元68年6月9日に復活して、キリストの言われた通りに大いなる裁きをイスラエル人たちに下したのである。このように、紀元68年6月9日において、3つの対象に対するキリストと聖徒たちの裁きが執行された。それは『千年の間』として表現された非常に短いが偉大な時間の間に行なわれたことであった。この裁きの完了と共に、『千年』と言い換えられた報復としての短い時間は終わることになった。
この裁きの時間である『千年』が終わると、その時、「第二の復活」が起こる。一体どうして、千年が終わると2回目の復活が起こるのであろうか。それは、『そのほかの死者は、千年の終わるまでは、生き返らなかった。これが第一の復活である。』(黙示録20章5節)と書いてあるからである。これはつまり、千年が終われば第二の復活が起きるということを意味する。この「第二の復活」という言葉が、聖書には書かれていないからといって、我々はこの復活がないなどと考えるべきではない。『第一の復活』があるのであれば、当然ながら「第二の復活」もあるはずだからである。たとえ文字的には書いてないからといって、それが存在しないことにはならない。それは、「時間が造られた」と文字としては聖書に書かれていないからといって、神が時間を造られなかったことにはならないのと同じである。それでは、この第二の復活を受けるのは、どのような種類の者であろうか。それは「悪者」つまり滅びの子らである。ヨハネが書いたように、『第一の復活にあずかる者は幸いな者、聖なる者』(黙示録20章6節)であった。この1回目の復活では、救いに選ばれていた正しい者たちが復活したからである。そうであれば、2回目の復活のほうは、正しい者でない者たち、すなわち悪者たちの復活だということになる。要するに、第二の復活とは、あまり喜ばしくない復活のことである。これは第一の復活が、非常に喜ばしい復活であったのと対照的である。しかし、悪者が復活するといっても、一体どのような悪者が復活するのであろうか。具体的には、その悪者とはどのような人たちを指しているのであろうか。それは、復活した後でキリストのおられる空中に携挙されることになる悪者である。キリストは、再臨の日には、携挙される者と携挙されない者がいると言われた。すなわち、それは次のような御言葉である。『そのとき、畑にふたりいると、ひとりは取られ、ひとりは残されます。ふたりの女が臼をひいていると、ひとりは取られ、ひとりは残されます。』(マタイ24章40~41節)復活する悪者とは、このうちの『取られ』るほうの者であり、『残されます』ほうの者は復活しない。というのは、復活する悪者たちは、第二の復活により復活してから御座の前における空中の裁きを受けることになっていたからである。確かにキリストは、復活のことについて、このように言っておられた。『墓の中にいる者がみな、子の声を聞いて出て来る時が来ます。…悪を行なった者は、よみがえってさばきを受けるのです。』(ヨハネ5章28~29節)ここで言われている『さばき』とは空中における裁きのことであろう。この空中の裁きを受けることになる者は、それが空中で執行されるがゆえに、当然ながら携挙されることになる者たちであるのは言うまでもない。携挙されない者たちは、そもそも空中にさえ上げられないのだから、どうして空中の裁きを受けられるであろうか。その者たちは地に『残され』るのである。確かに悪者どもは復活したら空中の裁きを受けることになるのだから、第二の復活を受ける悪者とは、すなわち空中へと携挙されることになる悪者だけである。それでは、そのような悪者とは一体どういう者たちなのであろうか。もう少し詳しく説明してほしいと感じる方が多くいるのではないかと思う。その悪者とは『山羊』と呼ばれる悪者である。空中の裁きが描かれているマタイ25:31~46の箇所を見ると、審判者なるキリストの御前に『羊』と『山羊』が立たされているのが分かる。この後者の『山羊』こそが復活して携挙されることになる悪者である。この山羊なる悪者は、「ナザレのイエス」という紀元1世紀にこの地上におられた聖なる存在をよく知っており、そのためにキリストに対して『主よ。』(マタイ25:44)と口にする。つまり、この悪者とはキリストのおられた紀元1世紀に生きていた者のことである。また、この悪者は『御国』すなわち地上の教会に属していた者でもある。何故なら、マタイ13:41~42を見ても分かるように、空中の裁きのために携挙されて裁かれることになる悪者とは、地上の御国の中にいる者だからである。このマタイの箇所ではこう言われている。『人の子はその御使いたちを遣わします。彼らは、つまずきを与える者や不法を行なう者たちをみな、御国から取り集めて、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。』ここで言われているように、裁きのために空中へと御使いにより携挙される『つまずきを与える者や不法を行なう者』などといった悪者たちは、『御国』すなわち地上の教会の中から取り集められる。そうしてから、後ほど詳しく説明されることになるが、この悪者たちは裁きを受けて『火の燃える炉に投げ込』まれることになる。つまり、地上の教会に属していなかった悪者たちは、確かに悪者ではあるのだが、この第二の復活により復活することはなかった。要するに、第二の復活を受けるのは、使徒の時代に教会に籍を置いていた全ての再生していなかったキリスト教徒である。これは、簡単に言ってしまえば「毒麦」のことである。この毒麦たちが、当時生きていた者も、既に死んでいた者も、第二の復活を受けてよみがえることになったのである。この教会に蒔かれていた本当は神の民ではない毒麦どもは、火の池に投げ込まれて永遠に苦しめられるために、第二の復活により新しい「滅びの身体」を受けることになった。これは、永遠に焼かれ続けることができる刑罰のために用意された身体である。紀元68年6月9日の時点で生きていた毒麦どもには、生きたままの状態で即座に、この身体への切り替えが起こった。それは、たちまち、一瞬のうちに起こったことであった。一方、既に死んで墓の中にいた毒麦どもは、墓の中でこの新しい身体を受けて復活し、そうしてから墓より出てくることになった。この墓の中にいた毒麦どもの復活も、一瞬の間になされたことである。この第二の復活による新しい身体の授与は、第一の復活による新しい身体の授与と、現象的には同じことである。どちらも即座に身体の切り替えが行なわれた。違うのは、第二の復活のほうが時期的には少し遅いということと、その与えられる身体の性質がまったく異なっているということである。黙示録20:13で『海はその中にいる死者を出し、死もハデスも、その中にいる死者を出した。』と書かれているのは、この第二の復活のことである。『海はその中にいる死者を出し』とは、海として象徴される生存中の非再生者すなわち霊的な死者が、第二の復活により新しい身体の切り替えに与かるということである。『死もハデスも、その中にいる死者を出した。』とは、死んでハデスの中に放り込まれた死亡中の非再生者すなわち霊的な死者が、第二の復活により新しい身体を受けて墓から出てくるということである。ここで言われている『死者』とは、すなわちキリストが生存中の者に対して『死人』と言われた意味における死んだ者のことである(※①)。つまり、この『死者』とは霊的な死者のことであって、肉体の死者のことを言っているのではない。肉体の死は、『海』および『死』また『ハデス』という部分で区別されている。こちらのほうこそ肉体の生死を分けている指標であり、こちらのほうは霊的な死を言ったものではない。つまり『海』が肉体的に生存中であるという指標であり、『死』また『ハデス』が肉体的な死亡者であるという指標になっている。この箇所については、後ほどまた説明されることになるであろう。今はこれだけ説明されれば事柄の理解のためには十分である。さて、この箇所の最後で言っておかねばならないことがある。それは実に多くの人たちが、復活の際には「あらゆる悪者」が復活することになると考えているということについてである。今に至るまでほとんど全ての聖徒たちは再臨や復活のことなどについて聖書を詳しく研究することをせず、最後の審判を受けるべく「全ての悪者」が例外なく復活するのだと考えてきた。すなわち、教会では今まで最後の審判を受けるべく復活することになるのは「狼」、つまり地上の教会には属していない不信者や異教徒たちも含まれると盲目的に考えられてきた(※②)。ところでこの「狼」とは、カルヴァンも言うように「神のあわれみの聖霊によって全く再生されない者」また「福音の敵である者たち」(『新約聖書註解Ⅰ 共観福音書 上』マタイ10:16 p349:新教出版社)を指す。しかし、この「狼」である不信者や異教徒さえもが、紀元68年に起きた最後の審判を受けるために復活すると考えるのは誤っている。それが誤りであるということは、しっかりと聖書から証明できる。まず「狼」でさえも復活して携挙されてから空中の裁きを受けるというのであれば、空中の裁きを描いているマタイ25:31~46の箇所で、『羊と山羊』すなわちクリスチャンと偽クリスチャンしか出てこないのはどういうわけか。興味深いことに、この箇所では羊と山羊だけしか登場しておらず、教会と関わりを持たない不信者なる狼は描かれていない。もし全ての種類の人が空中で最後の審判を受けるというのならば、当然ながら「狼」も空中に引き上げられることになるだろうから、このマタイの箇所では「狼」も登場していたはずである。しかし、この箇所によれば最後の審判を受けるのは「羊と山羊のみ」である。つまり、最後の審判が行なわれる空中に狼が引き出されることはないのである。また、もし狼も空中で審判を受けるとしたら、彼らは自分の前におられるキリストに向かって『主よ。』(マタイ25章44節)などと言うのであろうか。そのようなことはない。狼はキリストを主と認めず、むしろ「有害な唾棄すべきクリストゥス信者どもの頭よ。」(※③)とか「キリスト野郎」(※④)などと言うであろう。当然ながら『主よ。』と言うのは羊と山羊だけである。よって、キリストを否む狼たちは最後の審判を受けなかったことが分かる。更に言えば、審判を受けるのは『御国から取り集め』(マタイ13章41節)られた者だけであるから、そもそも御国と関わりを持たない狼たちが、どうして携挙されて最後の審判を受けることがあろうか。まさか狼も御国に属する者たちだなどと言う人はいないであろう。極めつけの証拠は、キリストが携挙の際には『残され』(マタイ24:40、41)る者がいると言っておられることである。もし狼を含めたあらゆる者が携挙されて最後の審判を受けるというのであれば、どうして地上に残される者がいるのであろうか。そのようなことが起これば、地上には誰も残されなくなる。しかしキリストは地上に残されて空中の審判を受けない者がいると言われたのだから、狼も含めた全ての者が最後の審判を受けると考えるのは誤りであることが分かる。すなわち、先にも述べたように携挙されるのは羊と山羊だけであって、狼たちは地上に残されるのだから御前における空中の審判を受けることはないのである。最後の審判の際には『すべての国々の民が、その御前に集められます。』(マタイ25章32節)と書いてあるのを盾に取っても無駄である。ここで言われている『すべての国々の民』とは、あくまでも携挙されることになる者たちのことだからである。すなわち、ここで言われているのは「携挙されることになる者たちにおけるすべての国々の民」ということである。もしこれが文字通り全ての国民だと解するべきだとすれば、ペテロが成就したと言ったヨエル書に書かれている『わたしの霊をすべての人に注ぐ。』(使徒行伝2章17節)という預言も、そのように考えるべきなのであろうか。すなわち、本当に文字通り『すべての人』に神の霊が注がれたのであろうか。そのようなことはなかった。ここで『すべての人』と言われているのは、言うまでもなく異教徒は含まれていない。このヨエル書の箇所を、文字通りに捉えるべきではないのと同様に、マタイ25:32も文字通りに捉えるべきではない。マタイ25:32の後では『すべての国々の民』が、すなわち『羊と山羊』だと言われているのだから、これはクリスチャンと偽クリスチャンのことだけについて言われたものである。もし、この『すべての国々の民』という言葉を文字通りに捉えると、既に説明されたことからも分かるように、他の箇所と調和できなくなってしまう。アウグスティヌスもエレミヤ31:34に書かれている「すべて、わたしを知るであろうから」という御言葉の「すべて」という部分が、すなわち全人類ではなく「イスラエルの家とユダの家を指す。」(『アウグスティヌス著作集9 ペラギウス派駁論集(1)』霊と文字 第24章 40 p70:教文館)と言っており、カルヴァンもヨハネ12:32で書かれている「わたしは、地上からあげられる時、すべてのひとたちを…」という御言葉について「すべてと言っているが、それは当然、神の羊の群れに属する神の子供たちに結びつけて考えなければならない。」(『新約聖書註解Ⅳ ヨハネ福音書 下』12:32 p421:新教出版社)と言っており、また同じヨハネ6:45で書かれている「かれらはすべて神から教えられるだろう、と」という御言葉について「このすべてという語は、教会の正当な子供たちであるえらばれたひとたちにだけ、限定されなければならない。」(『新約聖書註解Ⅲ ヨハネ福音書 上』6:45 p215:新教出版社)と言っているが、このエレミヤ書の箇所やヨハネ福音書の2つの箇所や今取り扱っているマタイ25:32の箇所や先のヨエル書の箇所のように、聖書において「すべて」と言われながら実際にはかなり限定された範囲内の存在を対象としている箇所は多い(※⑤)。聖書をよく研究している人であれば、このことに既に気付いておられるはずである。よって、このマタイ25:32による反論も私の説明を揺るがすものとはならない。このように「最後の審判の際には全ての者たちが空中にいるキリストの御前に立たされるであろう。」という教会が今まで信じてきた一般的な見解は、聖書研究をしていないために陥ってしまった謬見であって、それが謬見であることを今まで教会はいくらかでも察することさえしなかったのである。このように考えると、聖書の教えに沿わなくなってしまうのは、今なされた説明から分かったはずである。確かに今まで教会は、「審判を受けるのはどのような種類の者か?」「地上に残される者たちは空中に上げられないから最後の審判を受けることもないのではないか?」「キリストを憎んでいる者も審判の際には『主よ。』などと言うのだろうか?」といったことを何も考察してこなかった。それは第1章でも言われたように、まだ再臨と再臨に関わる事柄が明らかにされる時期が到来していなかったからである。しかし、今ここで説明されたことを読んだ読者は、復活と携挙と審判のことがよく分かったはずである。それゆえ、「最後の審判の際には全ての者が復活させられるのだ。」という考察の欠如した一般的な見解はもう捨てられるべきである。『主よ。』と言わず御国にも属していない狼なる不信者たちは、空中の審判のために携挙されるべく第二の復活を受けることがないのである。
(※①)
『まことに、まことに、あなたがたに告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。』(ヨハネ5章25節)
[本文に戻る]
(※②)
例えば今に至るまで多くの教会が採用してきたアタナシウス信条では、キリストの再臨の際に「すべての人間は、その身体をもって蘇えり。」(41節目)と書いてある。つまり、狼を含めたあらゆる人間が復活して、携挙され、空中に立たされ、キリストの御前で裁かれる、というのである。これは再臨や再臨に関する出来事について、まったく聖書研究をしていないことが分かる記述である。私からすれば、これは誠に幼稚な理解であり、表面的であり、何の考察もされておらず、実に盲目的であると感じられる。もちろん、私とて、もし神の御恵みが注がれなかったならば、このような未熟な理解のままに留まっていたのではあるが…。
[本文に戻る]
(※③)
これはスエトニウスが言いそうである。というのも彼はキリスト者について、「前代未聞の有害な迷信に囚われた人種であるクリストゥス信奉者」(『ローマ皇帝伝(下)』第6巻 ネロ p150:岩波文庫)などと侮蔑的な言い方をしているからである。キリスト者に対してこう言うのであれば、尚のこと、キリスト者の主であるキリストには侮蔑的な言い方をするはずである。
[本文に戻る]
(※④)
本当にこう言ったのかどうか定かではないが、長官アグリッパは「ペテロ行伝」33章の中でこのように口にしている。参照:『聖書外典偽典7 新約外典Ⅱ』ペテロ行伝 第33章 p79 教文館
[本文に戻る]
(※⑤)
このアウグスティヌスは、この範囲の限定性のことについて、こうも述べている。「たとえば、「あなたがたはあらゆる野菜の十分の一を納めている」(ルカ11・42)とパリサイ人に言われていますが、そこでは彼らの持っているすべてだけであると解釈しなければなりません。実際、彼らは全地上のあらゆる野菜の十分の一を納めはしなかったのです。「わたしもまた、すべてのことについて、すべての人を喜ばせているように」(Ⅰコリ10・33)と言われているのは、この表現法に倣っているのです。これを述べた人は、彼を迫害するあれほど多くの人々に、実際喜ばれていたでしょうか。しかるに彼は、キリストの教会が結集するあらゆる種類の人間―すでにそのうちにいる者も、これから教会に導き入れられることになっていた者も―に喜ばれていたのでした。」(『アウグスティヌス著作集10 ペラギウス派駁論集(2)』譴責と恩寵 第14章 44 p155~156:教文館)
[本文に戻る]
理解が更に深まるために、もう少し携挙される対象者についての論証をしたい。確かに、今の時代に至るまで、携挙の際には、あらゆる人間が上に引き上げられる対象であると考えられてきた。そう、文字通り「あらゆる人間」である。それは、携挙について今までに語られてきた教師たちの文章を見れば、一目瞭然である。今まで教師たちは、何の例外も設けずに「あらゆる人間」が上に引き上げられると語ってきた。しかし、上で説明されたように、実際には携挙の際にあらゆる人間が引き上げられるのではない。このことを、今度は、実際の歴史から論証することとしたい。その論証の際に、検証する対象は3者、すなわち「異邦人」(=狼)と「ユダヤ人」(=狼)と「キリスト者」(=羊および山羊)である。まずは「異邦人」から検証するが、携挙の際に上に引き上げられると多くの聖徒たちから思われてきたこの存在は、実際の歴史においては携挙されることがなかった。何故なら、携挙の起きた紀元68年を過ぎても、多くの異邦人たちが以前と変わらず人生を送ったからである。例えば「博物誌」で知られる大プリニウスの生きた年は、23~79年であった。また今でもよく語られる歴史家のタキトゥスが生きた年は、55年頃~115年頃であった。もし多くの者が考えているように、携挙の時に異邦人も上に引き上げられるとすれば、この2人の異邦人は、携挙の起きた紀元68年にこの地上から去っていたはずである。というのも、もし彼らが携挙された場合、キリストを信じていなかったがゆえに、間違いなく左のほうにより分けられ(マタイ25:41~45)、地獄に移されていただろうからである。彼らが携挙されていた場合、『わたしから離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火にはいれ。』(マタイ25章41節)とキリストから言われなかったはずがどうしてあろうか。しかし、彼らは紀元68年を過ぎても、相も変わらず前から続いていた人生を地上において送った。今までの携挙に関する考察不足の見解に基づいて考えると、この大プリニウスとタキトウスは携挙の起きた紀元68年にその地上における人生を終わらせていたはずである。しかし、そのようなことはなかった。これは、つまり、狼である異邦人は携挙される対象ではないということを意味している。やはり、先に説明されたように、携挙の日には地上に『残される』(マタイ24章40~41節)者がおり、空中の審判に羊でも山羊でもない異邦人という狼たちは集められないのである(マタイ25:31~46)。この大プリニウスとタキトゥスは、携挙の対象に異邦人が含まれていないということを証明してくれる人間である。次は「ユダヤ人」である。このユダヤ人たちも再臨の日には携挙されると多くの者が考えているが、実際には、彼らが携挙されることはなかった。何故なら、ユダヤ戦争(66~70)において死ななかったユダヤ人であるヨセフスが、携挙の起きた紀元68年を過ぎても、ずっと生き続けたからである。このユダヤ人のヨセフスが生きた年は、37年頃~100年頃であった。もしユダヤ人も携挙されるのであれば、携挙の年である紀元68年になった時、ヨセフスは空中に引き上げられていただろうから、その年に自分の地上での人生を終わらせていたはずである。しかし、ヨセフスは携挙の年を過ぎても生き続けたのだから、ユダヤ人は携挙の対象として含まれていなかったということになる。ここで彼の『ユダヤ古代誌』に書かれている有名な「キリスト証言」のことを思い浮かべる読者がいると思うが(※①)、これは明らかに後世の挿入だから、我々が今取り扱っていることにおいては何も問題にならない。もしこの「キリスト証言」が本当にヨセフスが書いた文章だとすれば、彼がキリスト者だったという可能性が生じ、もしキリスト者であったならば、このヨセフスはキリスト者であるがゆえに紀元68年の時点でこの地上から去っていなければならなかった。しかし、ヨセフスは紀元68年を過ぎても生き続けていたのだから、この有名な文章が別の者による文章であるということは確かであって、それゆえ彼がキリスト者でなかったということも確かである。もしこれがヨセフスの手による文章だったとすれば、キリスト者であるヨセフスがキリスト者であるにもかかわらず再臨の日に携挙されなかったという致命的な問題が生じることになり、私の述べる携挙の見解が偽りであるか、聖書の教えが偽りであるかということになっていたであろう。もちろん、私の述べる見解も聖書の教えも真理であって、偽りであるのは挿入された箇所のほうであるのは言うまでもない。もっとも、キリスト者であったユダヤ人であれば、話は別である。ユダヤ人でもキリスト者であれば、その者は携挙の対象に含まれていたから、紀元68年に上に引き上げられたはずである。というのも、携挙されるのは、福音書も教えるように御国という海の中で泳いでいる良い魚と悪い魚だからである(マタイ13:41~42、47~50)。つまり、携挙の対象となるのは、簡単に言えば「キリスト者」と呼ばれ教会に通っている全ての者であった。最後は「キリスト者」であるが、彼らが紀元68年に実際に携挙されたのは、もう読者には明らかであろう。誰であれ、キリスト者と呼ばれる者は、紀元68年にこの地上での人生を終わらせた。彼らは携挙されてから、天国に移されるにせよ地獄に移されるにせよ、もはや再びこの地上に戻りはしなかったからである。しかし読者の中には、「紀元68年を過ぎてもこの地上に生き続けたキリスト者の存在はどうなるのか?」と実に鋭い質問を心の中に持たれる方がいるかもしれない。私が言っているのは、ローマのクレメンス(30~101)をはじめとした、紀元68年でその地上での生涯を終わらせていない聖徒たちのことである。このような聖徒たちが、紀元68年を過ぎても生き続けたというのは、誰も疑うべきでないし、私もあえてそれを否定することはしない。この鋭い質問を解決するのは、簡単なことである。つまり、彼らは携挙の年を過ぎてから信仰を持ってキリスト者になったのである。彼らは、携挙の起きた紀元68年の時には、そもそもキリスト者ではなく不信者だった。だから、彼らは、聖徒でありながら紀元68年を過ぎても地上から取り去られていなかったのである。先にも言ったように不信者たちは、紀元68年の時に携挙されることがない。もしローマのクレメンスであれその他の聖徒であれ、紀元68年までにキリスト者となっていたとすれば、紀元68年に携挙されていただろうから、その年に地上からいなくなっていたであろう。学識と意欲のある読者は、紀元68年を過ぎても生き残っていた古代の聖徒たちの生涯を、よく調べていただきたい。そうすれば、その聖徒たちが携挙の起きた紀元68年以降にキリスト者になったのであって、それ以前は不信者だったことが分かるはずである。もし紀元68年の時点でキリスト者でありながら携挙されなかった聖徒がいたとすれば、この『再臨論』における見解は根底から覆されることになり、私もこの説を捨てるか理解を大幅に変更せねばならなくなるであろうが、そのようなことは絶対にないであろう。このように実際の歴史からの検証を受けても、この携挙の見解が堂々と耐えられることが、読者にはお分かりいただけたのではないかと思う。これは、この携挙の見解が、聖書に基づいた真理の見解だからに他ならない。真理だからこそ、実際の歴史の検証に打ち負けたりしないのである。もしそうでなければ、実際の歴史の検証に耐えられず、看過できない矛盾を引き起こし、大きな問題となっていたはずである。真理でなければ、どうして実際の歴史との関係において矛盾が生じないままで済むであろうか。事実、進化論は真理でないからこそ、実際の歴史と多くの点で矛盾を引き起こしているのである。そういうことだから、携挙があらゆる種類の人たちを対象としているという見解は誤謬に他ならない。この携挙に関する誤謬は、聖書研究の不足、検証の不足、思索の不足がその原因である。もし聖書をよく研究し、検証に臆病にならず、思索を熱心にしていたとすれば、このような誤謬に陥らなくて済んでいたはずである。このことから、誤謬の原因である努力不足が、どれだけ悲惨であるかということが分かるのではないかと思う。神の恵みにより努力をしようとしないからこそ(努力できるのは神の恵みに他ならない)、その怠惰に対する罰として誤謬の闇に落とされてしまう。もし神からの恵みを受けて色々と考究していれば、神の恵みにより色々と分かるので、神の恵みのゆえに誤謬から遠ざかれるようになるのである。今までの教会は、この携挙や再臨をはじめとした古い世の終末のことについて努力不足であったと言わざるを得ない。それは、私が今神の恵みにより書き記しているこのような作品が、最近になるまで世にまったく出てこなかったことからも分かる。
(※①)
「さてその頃、イエスという賢人―実に、彼を人と呼ぶことが許されるならば―が現れた。彼は不思議な業の数々を行う者であり、真理を尊ぶ人たちの教師でもあった。そして、多くのユダヤ人と少なからざるギリシア人とを帰依させた。彼こそはキリストだったのである。ピラトは、彼がわれわれの指導者たちによって告発されると、十字架刑の判決を下したが、彼を最初に愛するようになった者たちは、彼を見捨てようとはしなかった。すると、彼は三日目に復活して、彼らの中にその姿を見せた。すでに神の預言者たちは、このことや、さらに彼に関するその他多数の驚嘆すべき事柄を語っていたが、それが実現したのである。なお、キリスト者と呼ばれる族は、その後現在に至るまで連綿として残っている。」(ヨセフス『ユダヤ古代誌』18.3.3)
[本文に戻る]
さて、この紀元68年の時に第一の復活に与かった聖徒は、地上から、キリストのおられる空中まで携挙された。その携挙は目にも止まらぬ速さで行なわれた。『たちまち…雲の中に一挙に引き上げられ』(Ⅰテサロニケ4章17節)とパウロが書いている通りである。恐らく、携挙された聖徒は気付いたら既に空中に上げられていたと推測される。聖徒を空中まで携挙させたのは、キリストが遣わされた御使いたちであった。それは、マタイ24:31にこう書かれている通りである。『人の子は大きなラッパの響きとともに、御使いたちを遣わします。すると御使いたちは、天の果てから果てまで、四方からその選びの民を集めます。』つまり、聖徒たちは、何か見えない力や上昇する空気などによって空中へと引き上げられたのではなかった。御霊が、聖徒たちを空中に移して下さったというのでもなかった。そうではなく、この仕事を任されていた御使いたちが、その手で一人一人の聖徒を上のほうまで運んだのである。ここでは『御使いたち』と言われていることに注意すべきである。すなわち、キリストから遣わされた御使いは一人ではなく何人もいたということを見落とすべきではない。そうして空中に上げられた聖徒たちは、既に空中に再臨されていたキリストと会った。これが感動的な対面であったのは間違いない。新約聖書に書かれている多くの聖句は、この時のことを言ったものである。例えばⅡテサロニケ2:1。『さて兄弟たちよ。私たちの主イエス・キリストが再び来られることと、私たちが主のみもとに集められることに関して、あなたがたにお願いすることがあります。』またⅠテサロニケ2:19。『私たちの主イエスが再び来られるとき、御前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのはだれでしょう。あなたがたではありませんか。』Ⅰヨハネ2:28もそうである。『そこで、子どもたちよ。キリストのうちにとどまっていなさい。それは、キリストが現われるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに、御前で恥じ入るということのないためです。』これらはどれも、携挙された聖徒が空中で主の御前に立つ時のことである。また、この携挙の時にマタイ24:40~41の御言葉が実現した。この箇所でキリストはこう言っておられる。『そのとき、畑にふたりいると、ひとりは取られ、ひとりは残されます。ふたりの女が臼をひいていると、ひとりは取られ、ひとりは残されます。』つまり、再臨の起きた紀元68年6月9日には、携挙されるべき者が急に消え去り、携挙されるべきでない者は地上にそのまま残された。この日、地上に残された不幸な者たちは、ある人たちが突然目の前からいなくなったのを見たのである。その時の驚きがどれほどのものであったかということは、想像に難くない。
キリストは再臨が起こる時について『その日、その時がいつであるかは、だれも知りません。』(マタイ24章36節)と言われたが、これは正にその通りであった。一体当時の誰が紀元68年6月9日に再臨が起こるなどと考えたであろうか。誰も考えなかったであろう。確かに先に書かれたように、再臨の前兆となる出来事は、あらかじめ預言により知らされていた。その一つとしては、『にせキリスト、にせ預言者たちが現われて、できれば選民をも惑わそうとして、大きなしるしや不思議なことをして見せ』(マタイ24章24節)る、というのがそうであった。『エルサレムが軍隊に囲まれる』(ルカ21章20節)というのもそうである。この包囲の出来事は非常に明瞭な前兆であった。『『荒らす憎むべき者』が、聖なる所に立つ』(マタイ24章15節)というのもそうであって、これはネロの迫害のことだから、誰でも明白に認識できる前兆であった。しかし、前兆はかなり知ることができたものの、再臨の起こる正確な日時は誰一人として分からなかった。というのも『人の子の来るのは、いなずまが東から出て、西にひらめくように、ちょうどそのように来る』(マタイ24章27節)からである。稲妻の発生を誰も予知できないように、再臨の発生も誰も予知できなかった。ところでカエサルは、いつ暗殺されてもおかしくない状態にあったが、自分がいつ死ぬことになるかは全く知らなかった。彼は、気付いた時にはブルータスをはじめとした多くの暗殺者たちから刺されている自分の姿を見た。彼はこうなることをある程度予想していたから冷静さを保ちはしたが、まさかその日(紀元前44年3月15日)に殺されるとは予測できなかったであろう。キリストの再臨される日が隠されていたのは、ちょうどこのカエサルの暗殺のようなものであったと言える。だから、再臨の起こる日は確かに当時の人たちにとっては『いつ起こるかをだれも告げることはできない』(伝道者の書8章7節)類のものであった。神は、人の意表を突くような日を、再臨の起こる日として定められたのである。
再臨の起きた場所は、地理的に言ってどこだったのであろうか。再臨の起きた場所は、エルサレムの上空だったと考えるべきである。何故こう言えるかといえば、主は大祭司や律法学者や長老たちが再臨を見ると言われたからである(マタイ26:64)。これらの者たちがエルサレム市にいたということは疑えない。もしエルサレムから遠く離れた場所の上空で再臨が起きたとすれば、このエルサレムにいた指導者たちが再臨を目撃することは、恐らくできなかったのではないか。しかしエルサレムにいたとすれば、確実に、キリストの再臨を見ることができる。エルサレムの上空にキリストが降りて来られたならば、この指導者たちだけでなく、他にも再臨を見ると言われていた弟子たち(マタイ16:28)やあのロンギノスという兵士も(黙示録1:7)再臨を見ることができる。再臨が起きた時にはまだ多くの弟子がエルサレムにいただろうし、ロンギノスも兵士なのだから―といってももう老兵士になっていただろうが―エルサレムというユダヤの中でもっとも重要な街にいたと考えても何もおかしくはない。よって我々は、エルサレムこそ再臨が起きた直下の場所であったと考えるべきである。このエルサレムとは非常に重要な意味を持つ街なのだから、その上空にキリストが来られたと考えるのは、荒唐無稽な理解とは言えないはずである。もし「主が再臨される場所はどこがもっとも相応しいか?」と問われるならば、その答えは間違いなく「それはエルサレムである。」というものになるであろう。読者もこの答えにはうなずくはずである。であれば、やはり再臨が起きた直下の場所はエルサレムだったと考えるべきだということになる。それでは、聖書の御言葉は、どこの場所にキリストが再臨されたと教えているのであろうか。やはり、この件についても聖書が何と言っているのか、ということを我々は見なければいけない。何故なら、この聖書こそが、我々の知識と判断における基準だからである。敬虔な読者の方であれば、聖書の御言葉から論じられなければ、満足することができないはずである。これまで論じられたのは、聖書の御言葉から直接的に論じるというよりは、言わば間接的な推論に過ぎないものであった。私は聖書の御言葉から、この件についての答えを提示しよう。聖書は、再臨の起きた場所がエルサレムであると教えている。つまり、聖書は、私が先に述べた推論と同じことを述べている。旧約聖書の多くの箇所では、キリストの再臨される場所が「シオン」であると言われている。その御言葉は次の通りである。『しかし、シオンには贖い主として来る。』(イザヤ59章20節)『彼らは、主がシオンに帰られるのを、まのあたりに見るからだ。』(イザヤ52章8節)シオンとはエルサレムの南東にある丘であって、すなわちエルサレムを指す。またキリストが再臨される場所は「オリーブ山」であるとも聖書は教えている。その御言葉は次の通りである。『その日、主の足は、エルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。』(ゼカリヤ14章4節)オリーブ山とはエルサレム神殿のすぐ近くに位置する場所であって、すなわちエルサレムである。主が再臨される場所は空中であるから、その下にある場所はシオンの山であるとも言えるしオリーブ山であるとも言える。何故なら、空中の広い場所に降りて来られるために、どちらを直下の場所としても問題ないからである。例えば、キリストがもし日本の皇居と東京駅の中間の場所を直下として持つ上空に再臨されたとすれば、「皇居の上に再臨された。」と言うことができるし、「東京駅の上に再臨された。」と言うこともできる。ゼカリヤの預言においては、再臨が起こる際、主の足がオリーブ山にある地表に触れるかのように書かれているが、これは実際に足が地表に触れるというのではなく、ただ主の足の下にその地表が置かれるという意味に解するべきである。このように聖書は、主の再臨される直下の場所が、エルサレムであると教えていることが分かっていただけたのではないかと思う。それゆえ、我々は、主の再臨される場所が、エルサレム以外の場所であると考えるべきではない。聖書では、主がエルサレムの上空に再臨されるからこそ、シオンの山やオリーブ山に主が再臨されると言われているのである。もしエルサレム以外の場所に主が再臨されるとすれば、聖書は、その場所にこそ主が再び来られると書いていたはずである。例えば、その場所を仮にローマだとすれば、聖書は「主はローマの地に来られる。」などと書いていたはずである。以上、理性による推論からも、聖書の御言葉からも、主の再臨される場所はエルサレムの上空に他ならないということが論じられた。それでは再臨の規模は、どの程度のものだったのであろうか。まずキリストが天から再臨されたということについて言えば、それは局所的な規模であったと言わねばならない。何故なら、主は『天に上って行かれるのをあなたがたが見たときと同じ有様で』(使徒行伝1章11節)再臨されたからである。キリストが天に上って行かれたのは当然ながら局所的なものであったから、御使いの言葉に基づいて考えると、昇天と同様に再臨も局所的なものであったことになる。再臨が全世界的な規模であったと言うのであれば、遠くの地域に住んでいた人は、一体どうなるのか。エルサレムのある地球の部分の裏側に住んでいる人は、どのようにして再臨を見たのか。当時は、今のようにビデオカメラで全世界に中継するなどということはできなかった。地球では、ある場所で起きていることを、その反対側の場所にいる人が見ることはできないというのは誰でも知っていることである。アメリカにいる人は、アメリカの反対側の地域であるインド辺りの上空で起きていることを見れないし、イギリスにいる人も、イギリスの反対側の地域であるアンティポディーズ諸島の上空で起きていることを見れない。再臨されたキリストの「視像」が、地球全土の空中部分に幻のように投影されたというのも考えにくい。このように地理的な要素を考慮するならば、やはりキリストが降りて来られたという点においては、局所的であったとせねばならない。当時は地球の全土が平面であったと言うのであれば話は別であるが。しかし、再臨に伴って起こる復活と携挙について言えば、それは全世界的な規模であったと言わねばならない。第1部でも説明されたように、当時既にキリストの福音は世界中で実を結んで広がっていた。つまり、当時の時点で、既に世界中にキリストを信じる信仰者たちがいた。その人たちが生きているのであれ既に死んだのであれ、再臨の時には復活に与かり、その後に携挙されるというのは確かである。当時、中国にいた聖徒も、日本にいた聖徒も、アメリカ大陸にいた聖徒も、例外ではない。であれば、キリストの再臨の際に起こる復活と携挙も、全世界的な規模だったということになる。この復活と携挙は全世界にいる聖徒たちを対象としたものだからである。当時において世界中で福音が実を結んでいたというパウロの御言葉を信じる兄弟は、もし本当に御言葉を信じているというのであれば、このように考えなければいけない。キリストが天から降りて来られたということを全世界的な規模であると理解したり、また復活と携挙が局所的な規模であると理解するのは、以上の説明から非とされねばならない。だが、このように質問する人もいることであろう。すなわち、キリストの再臨の際には『あらゆる種族』(マタイ24章30節)が、『人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見る』(同)のではないのか、と。つまり、これは地球の全ての場所にいる民族がキリストの再臨を見ることになると考えるべきではないかという質問である。このように考える場合、再臨を全世界的な規模のものとして捉えねばならなくなる。確かに『あらゆる種族』と書いてあるのは間違いない。しかし、これは当時の時代における慣用を考慮せねばならない。例えば、紀元1世紀のヨーロッパ世界において「全世界」という言葉は、慣用的にはヨーロッパ世界だけのことであり、中国や日本までは含まれていなかった。その証拠となるのはルカ2:1である。そこには『そのころ、全世界の住民登録をせよという勅令が、皇帝アウグストから出た。』と記されている。確かにアウグストゥスは「全世界」の住民登録をしたのだが、これがローマの支配が及ぶ地域だけを指しており、ヨーロッパとは完全に断絶したアジアの国々を含めていないのは、それほど学のない者でも分かるはずである。「全世界」と書いてあるからというので、アウグストゥスが中国や日本の住民登録もしたと考えるのは、完全な間違いなのである(※)。当時のヨーロッパ人において「世界」とは、つまりヨーロッパだけだと認識されており、ヨーロッパ以外の地域は存在しないも同然の異世界だと思われていたのだから、ルカは当時の常識的な言い方に沿って『全世界』と述べたに過ぎないのである。だから、再臨を『あらゆる種族』が見て悲しむと言われているのも、当時の人たちが「世界」と認識していたヨーロッパ地域における『あらゆる種族』として理解すべきだと私は考える。そのように考えると、キリストの再臨は地理的に考えて少なくとも当時の「全世界」であったヨーロッパ地域に住んでいた全ての民族には視認されたであろうから、確かに当時の言い方からすれば『あらゆる種族』に見られたことになる。もし私がこのように説明しても、これが文字通り世界中全ての民族を指していると言い張るのであれば、ネロについて書かれている聖句も、そのように考えるのであろうか。その聖句とはこうである。『彼はまた…あらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。』(黙示録13章7節)ここではネロがあらゆる部族や国民などを支配する権威を持つと言われているが、果たして、ネロは文字通り全ての部族や国民を支配できたのであろうか。例えば、天皇が支配していた日本もネロは支配できたのであろうか。ネロによるローマの支配が、日本にまでも及んだというのは歴史の事実にまったく反している。この黙示録で言われている『あらゆる部族、民族、国語、国民』とは、先に述べたのと同じで、当時の人たちにとっての「全世界」すなわちヨーロッパ社会における範囲内のことに他ならない。もし私の説明に納得できないのであれば、当時のローマにおける支配の範囲が、文字通り全ての国々に及んでいたことを証明してほしい。そんなことは誰にもできないことである。であれば、この黙示録の文章は、当時の慣用表現を弁えて理解せねばならないことになる。それならば、同じようにマタイ24章の『あらゆる種族』という言葉も、慣用を考慮すべきことになるであろう。そのように時代的な慣用表現を考慮するとなれば、やはり私が言ったように、これは当時における「全世界」の範囲内のことを言ったものだと理解すべきことになる。よって、キリストが再臨により降りて来たということを局所的な規模だったと考えても何も問題にはならないことが分かる。たとい再臨が局所的な規模だったとしても、慣用的に理解すれば『あらゆる種族』がキリストの再臨を見たことになるのである。昔から教会は、聖書の時代における慣用表現をよく考慮せず、その書かれていることを自分の生きている時代の慣用(!)を通して解釈する傾向を持ってきたが、これがあまりよくない傾向であることは火を見るよりも明らかである。もしそういうことが許されるのであれば、我々はアウグストゥスが文字通り地球全土の国々の住民登録をしたと理解せねばならなくなる。「アウグストゥスが全世界の住民登録をしたと書いてあるから当時の日本にもローマから役人がやって来たのだ。」などと言って。こんなふざけた理解をしていいはずがどうしてあるであろうか。要するに、聖書は今の我々にとっては「古典」なのだから、古代の時代性を考慮しつつ読み解いていかねばならないのである。
(※)
例えば中国がローマから支配の間接的な作用さえ受けていなかったのは、前2000年頃~後8年までの歴史を取り扱った「史記」や、前2000年頃~紀元960年までの歴史を取り扱った「18史略」を見れば明らかに分かる。そこにはローマの「ロ」の字さえ出てこない。すなわち、中国とヨーロッパは完全に断絶しており、接触さえほとんどしないような間柄であった。そうであれば、これこそ中国まではアウグストゥスの支配が行き届いていなかったことの証明になる。もしローマの支配が中国にまでも及んでいたとすれば、これらの歴史書に、そのことを匂わせる文章がいくらかでも記されていたであろう。また、中国がローマの支配を受けていなかったのであれば、当然ながら、中国より東に位置する日本もローマの支配を受けてはいなかったはずである。
[本文に戻る]
さて、千年の期間が終わってから空中に携挙された聖徒と毒麦たちは、キリストの御前に立たされ、聖なる審判を受けることになった。これこそ、あの「最後の審判」である。この出来事については、マタイ25:31~46に詳しく書かれている。審判が行われる際には、キリストが羊である聖徒と山羊である毒麦たちを、まずご自身の両側に区別して置かれた。『彼は、羊飼いが羊と山羊とを分けるように、彼らをより分け、羊を自分の右に、山羊を左に置きます。』(マタイ25章32~33節)と書かれている通りである。一体どうして右と左に彼らは分けられたのであろうか。それは宣言のためである。すなわち、キリストは羊たちには良い宣言を、山羊たちには恐るべき宣言をされるために、彼らを別々の位置に置かれたのである。もし彼らがごちゃ混ぜの位置にいたとすれば、どうして両者に対して正しく宣言できるであろうか。我々も、日常生活において、何かを行ないやすくしようとして別々の場所に区別するということが往々にある。褒めるべき人を前に連れて来させ、そうでない人は席に座らせたままにしておく教師のように。これは単に便宜的な意味しか持たないものであるから、これ以上深く考える必要は感じられない。2種類の者がこのように両側に分けられると、まず初めに右にいる聖徒たちへ宣言がなされる。この聖徒に対して、キリストは次のようなことを言われた。『『さあ、わたしの父に祝福された人たち。世の初めから、あなたがたのために備えられた御国を継ぎなさい。あなたがたは、わたしが空腹であったとき、わたしに食べる物を与え、わたしが渇いていたとき、わたしに飲ませ、わたしが旅人であったとき、わたしに宿を貸し、わたしが裸のとき、わたしに着る物を与え、わたしが病気をしたとき、わたしを見舞い、わたしが牢にいたとき、わたしをたずねてくれたからです。』すると、その正しい人たちは、答えて言います。『主よ。いつ、私たちは、あなたが空腹なのを見て、食べる物を差し上げ、渇いておられるのを見て、飲ませてあげましたか。いつ、あなたが旅をしておられるときに、泊まらせてあげ、裸なのを見て、着る物を差し上げましたか。また、いつ、私たちは、あなたのご病気やあなたが牢におられるのを見て、おたずねしましたか。』すると、王は彼らに答えて言います。『まことに、あなたがたに告げます。あなたがたが、これらのわたしの兄弟たち、しかも最も小さい者たちのひとりにしたのは、わたしにしたのです。』』(マタイ25章34~40節)羊である聖徒たちは、このような宣言を受けた後、『永遠のいのちにはいる』(25章46節)ことになり、御国を継ぐこととなった。これは、彼らが御国を継いで永遠に生きるようにと、神により世の初めから選ばれていたからである。次に、キリストは左に置かれた山羊である毒麦たちに対して、このような恐るべき宣言をなされる。『『のろわれた者ども。わたしから離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火にはいれ。おまえたちは、わたしが空腹であったとき、食べる物をくれず、渇いていたときにも飲ませず、わたしが旅人であったときにも泊まらせず、裸であったときにも着る物をくれず、病気のときや牢にいたときにもたずねてくれなかった。』そのとき、彼らも答えて言います。『主よ。いつ、私たちは、あなたが空腹であり、渇き、旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見て、お世話をしなかったのでしょうか。』すると、王は彼らに答えて言います。『まことに、おまえたちに告げます。おまえたちが、この最も小さい者たちのひとりにしなかったのは、わたしにしなかったのです。』』(マタイ25章41~45節)山羊である彼らは、このように言われた後、火の池に投げ込まれ、永遠の刑罰を受けることになった。彼らは永遠の裁きを受けるようにと定められていたので、このような宣言を受けることになったのである。ちなみに、キリストがこのような宣言をされてから、山羊たちを火の池に投げ込んだのは御使いたちであった。それはマタイ13:49の箇所で、『御使いたちが来て、正しい者の中から悪い者をえり分け、火の燃える炉に投げ込みます。』と書いてある通りである。つまり、山羊たちは重力のような力で火の池に落とされたとか、神の目に見えない不思議な力によって火の池に移動されたのではない。そうではなく御使いたちが、この呪われた者たちを自分たちの手により、『毒麦が集められて火で焼かれるように』(マタイ13章40節)火の中に投げ込んだのである。これは、携挙が御使いたちに任されていたのと同じことである。この空中の審判が起きたのは、携挙が起きたその直後、すなわち紀元68年6月9日である。どうしてこう言えるのであろうか。まず、第一の復活について記されている黙示録20:4~6の箇所が、再臨の日に起きたということは、もうここまで読まれた読者にとっては明白であろう。そして、この20:4~6の後に書かれている21章の箇所も、再臨の日に起きたということは明らかである。というのも、再臨の起こる日は、先にも書かれたように『書かれているすべてのことが成就する報復の日』(ルカ21章22節)だからである。キリストの言われたように再臨の日とは、旧約聖書のあらゆる預言が全て成就される日であるから、当然ながらイザヤ65:17の新天新地の創造に関する預言も、この日に成就されたことになる。その預言とはこうである。『見よ。まことにわたしは新しい天と新しい地を創造する。』キリストの御言葉を信じる神の子らは、この新天新地の創造について言われたイザヤ書65:17の預言も、再臨の日であり『報復の日』である紀元68年6月9日に成就したと信じなければいけない(※①)。理解の鈍い人のためにもう一度言うが、キリストはルカ21:22の箇所で、この日こそ、旧約聖書の全ての預言が成就する日であると言われたのである。とすれば、新天新地のことが書かれている黙示録21章以降の箇所も、再臨の日に成就したことになる。何故なら、イザヤ65:17の箇所と黙示録21章以降の箇所は、どちらも同じ新天新地の創造について述べられているからである。この2つの箇所が同じことを言っていることを疑う人が果たしているであろうか。文章的に多くの似たことが言われているのである。先に見た黙示録20:4~6の箇所は再臨の日に成就したが、今説明されたように黙示録21章以降の箇所も再臨の日に成就したのだから、その真中に挟まれている箇所である20:11~15の箇所も再臨の日に成就したことは確かである。20:4~6と黙示録21章は再臨の日に成就したが、その真中に挟まれている20:11~15の箇所は再臨の日には成就していなかった、ということが一体どうしてあるであろうか。20章~21章の箇所が、その起きた順序通りに書かれているというのであれば、確かにこのように考えねばならないことになる。そして、この真中の箇所である20:11~15とは、少し見れば分かるように明らかにマタイ25:31~46に書かれている最後の審判のことである。どちらも滅びの子らが裁かれて『火』(マタイ25章41節、黙示録20章15節)に投げ込まれることについて書かれているから、この2つの箇所は間違いなく同一の出来事を描いた箇所である。であれば、論理的に考えて、この空中の審判は再臨のあった日に起きたことになるのである。携挙があれば、その直後には審判が起きると聖書は教えているのだから、携挙が起きたその日に審判も起きたと考えるべきである。携挙が起きたにもかかわらず、空中で審判が行われないままに留まるということは考えられない。パウロも、当時の聖徒たちが『キリストのさばきの座に現われて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになる』(Ⅱコリント5章10節)と言ったのだから、やはり当時の聖徒が携挙された直後に裁きが行われたと考えるのが自然である。また、このように理解すると、黙示録20:11~15に書いてある最後の審判が紀元68年6月9日に起きたことになり、黙示録には『すぐに起こるべき事』(黙示録22章6節)が示されていると言われた御霊にも言い逆らわずに済む。この20:11~15の審判が紀元68年に起きたのであれば、どうであろうか?―本当に御霊が言われたように黙示録には『すぐに起こるべき事』が書かれていることになるではないか。それゆえ、この審判は既に紀元68年に実現したと考えるのが正しく、黙示録の内容にも沿っているということが分かるのではないかと思う。今まで教会は、例外なく、この最後の審判が未だに起きていないと当然のように考えてきた(※②)。しかし、私に言わせてもらえば、今まで教会は、再臨に伴う審判の出来事をよく弁えていなかった。再臨がまだ起きていないと信じていたので、再臨の直後に起きる審判もまだ起きていないと信じていたのである。今まで何と多くの聖徒たちが、審判の書かれた箇所を目では読みながら心と霊において正しく悟れていなかったことか。今まで教会は、この再臨に伴う審判のことに関し、盲目であったと言わねばならない。私の場合、神の恵みのゆえに、今説明したように、この審判が既に実現したということを神の御言葉に基づいて信じている。それゆえ、この事柄で論争することがこれからあったとしても、私が動じることはないであろう。たとい、まだ生きていた時のアウグスティヌスやベルナルドゥスやルターやカルヴァンやベザやその他の高名な神学者が、私と論争するために現われたとしても恐れはしない。私と論争すれば、私の降りまわす御言葉の剣により、彼らの口が何度も封じられることになるだろうから。ステパノと同じように、神が塵に過ぎない私に知恵と御霊により語らせて下さる恵みを注がれるので、私に対抗することなどできないのである(※③)。
(※①)
ルターは、まだ再臨が起きていないと誤って信じていたので、当然ながら新天新地もまだ造られていないと考えていた。確かなところ、再臨が既に起きたということは聖書の言葉から明らかなのだから、その再臨の際に新天新地も造られたことになる。彼は説教の中で次のように言っている。「そして、天と地は火で変えられるときが、すなわち、新しい天が造られるときが、本当に来るであろう。」(『ルター著作集 第二集7 ヨハネ福音書第3章・第4章説教』第49説教 第3章(35以下)p356:LITHON)
[本文に戻る]
(※②)
使徒信条、ニカイア・コンスタンティノポリス信条、アタナシウス信条をはじめ諸々の信条を見れば、このことは明らかである。教父のヒッポリュトスも、ノンクリスチャンに対して「もしその真理を知るならば、君たちは来るべき火による審判での滅びを免れるであろう。」(『キリスト教教父著作集19 ヒッポリュトス』『全異端反駁』第10巻 p424 教文館)と述べることで、まだ最後の審判は起きていないという信仰を持っていたことを示している。ボナヴェントゥーラも、これから最後の審判が起きるということについて、次のように述べている。「更に我々は信仰によって、世界が最後の審判によって終末を迎えることを信じる。」(『魂の神への道程』第1章12節 p17:創文社)ジョナサン・エドワーズも、次の文章が示すように、まだ最後の審判は起きていないと信じていた。「世界全体が善と悪に分かれており、審判の日に人類の誰もが義人として認められるか、悪人として告発されるか、どちらかであること、神の国の子として栄光にはいるか、邪悪な王国の子として火に投げ込まれるかどちらかであること。これについては、聖書に十分な証拠があるので、キリスト教徒であると自認する人は、誰もそれを否定しないと思う。」(『ジョナサン・エドワーズ選集3 原罪論』第1部 第1章 第7節 p80~81:新教出版社)「「マタイによる福音書」25章に描かれる審判の日には、そうなる。要求されていたことを行なわなかった罪によって、邪悪な者は有罪とされ、呪われ、消えることのない火に投げ込まれる。」(同 第5節 p60)カルヴァンも「この件について…十分な証拠は最後の審判で明らかになるであろう。」(『キリスト教綱要 改訳版 第1篇・第2篇』第2篇 第15章 5 p545:新教出版社)と書いていることから、まだ最後の審判は実現していないと考えていたことが分かる。というのも、もし最後の審判が既に実現したと考えていれば、このような文章は決して書けないからである。テルトゥリアヌスは、魂に対して「あなたは…最後の裁きの日を待ち望む」(『中世思想原典集成4 初期ラテン教父』魂の証言について 第4章(1) p87:平凡社)と書いている。彼も、他の教師と同様に、最後の審判がまだ起きていないと考えていた。ヴァン・ティルも「審判の日の後までは来ないであろう。」(『ヴァン・ティルの十戒』第四戒 p118:いのちのことば社)と審判の日を未来の出来事として語っているから、まだ最後の審判が起きていないと考えていたことが分かる。
[本文に戻る]
(※③)
『ところが、いわゆるリベルテンの会堂に属する人々で、クレネ人、アレキサンドリヤ人、キリキヤやアジヤから来た人々などが立ち上がって、ステパノと議論した。しかし、彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった。』(使徒行伝6章9~10節)
[本文に戻る]
毒麦たちは、このように空中の審判において、キリストから恐るべき宣言を受けたのだが、それではこの者たちは、それからどのようになったのであろうか。『永遠の火にはいれ。』(マタイ25章41節)と書かれているから、毒麦が永遠の火に投げ込まれたのは間違いないが、それが一体どのようなことであるのか詳しく説明されねばならないと私は思う。というのも、これは語らずに放置しておくべきことではないからである。これが知るべき誠に重要なことであるのは言うまでもない。まず最初に言っておくべきなのは、毒麦たちは、この世界ではない別の空間にある刑罰専用の場所へと移されたということである。つまり、この『永遠の火』が燃えている場所とは、この宇宙空間のどこかに存在しているというのではない。たとえ光速を遥かに越える速度を出せる宇宙船が開発されたとしても、この宇宙にその場所を見いだすことはできないであろう。この場所は、人間が死なない限りは行けないようになっているのである。また、これは単なる概念的なことを言っただけのものでもなく、象徴として何かが言われたのでもない。本当にある場所、素粒子の集合体としての物質的領域、実際的な空間を指して『永遠の火』また『火の池』(黙示録20章15節)などと言われているのである。我々は、この『火の池』という別の空間にある実際的な場所を、「ハデス」と理解してはならない。そのように理解するのは誤っている。『火の池』と「ハデス」とは別々の場所であって、一緒にしてはならず、しっかりと区分して考えなければならない。確かに、この「ハデス」とは死と共に『火の池』に投げ込まれて滅ぼされてしまったものだから、どうしてこの2つの場所を区別しなくていいはずがあるであろうか。もし一緒のものであったとすれば、どうしてハデスが『火の池』に滅ぼされてしまうのであろうか。これを誰も上手に説明できないのは言うまでもないことである。このことについては、黙示録20:14で次のように書かれている通りである。『それから、死とハデスとは、火の池に投げ込まれた。』さて、それではハデスと火の池とは、どのような違いを持っているのであろうか。この2つが一緒の内容を持っていないということは、恐らく誰にでも何となく分かるのではないかと思う。まずハデスであるが、これは死んだ者の魂のみが、火で焼き尽くされる空間のことである。この空間においては、魂だけが火で焼かれるのであって、そこに肉体を持ったままで苦しめられる者は存在しない。しかし、もう一方の火の池のほうは、魂と身体とが一体になった状態で火による苦しみが与えられる。こちらのほうにいる者たちは、皆、例外なく魂だけでなく肉体をも持っている。毒麦たちが第二の復活によって刑罰のための身体を新しく魂に結びつけられたのは、実に、この火の池において魂だけでなく身体をも焼かれることになるためであった。もしキリストが『永遠の火にはいれ。』とは言われず、「ハデスの火にはいれ。」と言われていたとすれば、毒麦に第二の復活による新しい身体が与えられることはなかったであろう。何故なら、もしハデスで苦しむだけならば、魂だけが存在していればよいのであって、新しい身体が与えられる必要などないからである。しかし、毒麦は火の池に投げ込まれることになっていたのだから、第二の復活により新しい身体を受けることになったのである。『それから、死とハデスとは、火の池に投げ込まれた。』(黙示録20章14節)という御言葉は、空中の審判により毒麦たちが火の池に投げ込まれることが起こった日に、成就された。この御言葉は、すなわち、この日において「死とハデス」が「第二の死と火の池」に置き換えられたことを我々に教える御言葉である。それは一体どういうことなのであろうか。それは、つまりこういうことである。この日になるまでは、「死」とは魂が肉体から分離されてハデスへと投げ込まれることを意味していた。また「ハデス」とは死により肉体から分離された魂が火で苦しめられることになる場所であった。しかし、この日になると、この「死」と「ハデス」はその役割を終えることになった。この日以降は、「第二の死」と「火の池」が、この「死」と「ハデス」にとって代わることになった。「第二の死」とは何か。これは、ある人が死んだらかつての死のように魂が身体から分離されることもなく、身体を持ったそのままの状態で刑罰の場所である「火の池」に移されることである。ある人が死んだその瞬間に、その人の身体が新しい滅びの身体に瞬時に切り替わるのと同時に別の空間へと移されることになる。これはそれまでの死の形とはまったく違っている。それまでは死んだら魂だけが身体を置き去りにして別の空間へと移されることになっていた。つまり、これは今までにはなかった新種の「死」である。それゆえ、このような新しい死の形が「第二の死」と呼ばれているのである。この日以降、人類が「第一の死」を味わうことはなくなった。すなわち、全ての人が「第二の死」という死を味わわねばならなくなった。この死による身体の瞬間的な切り替えと同時に移されることになる空間が『火の池』である。そこは「ハデス」のように魂だけが存在する空間ではない。このような死と刑罰の場所における置き換えのことを、ヨハネは「死とハデスは火の池に投げ込まれて滅ぼされるであろう。」と表現したのである。確かに置き換えられてもはや存在しなくなるということは、つまり滅ぼされると見なしても間違ってはいないから、ヨハネがこのように表現したのは誠にもっともなことであった。ネロが『火の池に、生きたままで投げ込まれた。』(黙示録19章20節)と書いてあるのも、ネロが今説明された新しい形の死により死んだからに他ならない。ネロの身体は死と共に瞬時に新しい身体へと切り替わり、その切り替えと同時にネロは火の池に移されたのだから、『生きたままで』火の池に投げ込まれたと書かれているのである。火の池に移される際、ネロの身体が物理的に存在し続けているという点において、そこには一瞬の断絶も中断もなかった。それゆえ、それは『生きたままで』と表現されるのに相応しい現象であった。このような場所である『火の池』に、毒麦どもは審判を受けてから投げ込まれることになったのである。毒麦どもが投げ込まれた時には、既にこの火の池にネロが入っていた。ネロは毒麦どもが第二の復活により復活する前に、既に火の池に投げ込まれていたのである。それは黙示録19:20を見れば分かる通りである。毒麦が火の池に投げ込まれることになる黙示録20:11~15の箇所は、ネロが火の池に投げ込まれているこの19:20の箇所よりも、いくらか後に起こる箇所である。つまり、ネロは火の池に投げ込まれた最初の人間であった。また、毒麦が火の池に投げ込まれた時には、サタンも既にそこに投げ込まれていた。それは、サタンが火の池に投げ込まれている箇所が黙示録20:10であることから分かる。この箇所は、ネロが火の池に投げ込まれている箇所よりも後であり、毒麦が火の池に投げ込まれている箇所よりも前である。つまり、サタンはネロよりは遅かったが毒麦よりは早かった。黙示録を見ると、このように、まず第一にネロが、第二にサタンが、第三に毒麦が、火の池に投げ込まれたということが分かる。しかし、この三つの存在が火に投げ込まれたのは、どれも同日中、すなわち紀元68年6月9日のことであった。確かにこの三つの存在が火に投げ込まれたことについて時間的な差はあったが、その差は大したものではなかった。さて、ここで一つの非常に重大な疑問が生じることになるのに気付かれる人もいるであろう。その疑問とは、つまり「サタンが既に火の池に投げ込まれたというのであれば、一体どうしてサタンは今の世界にも働いているのか?もしサタンが火の池に投げ込まれたのであれば、サタンはもう世界に働きかけられなくなっていたはずではないのか?」という疑問である。私は以前、この問題について次のように書いた。少し長いが、私の前の見解を読者に知ってもらうため、削除せずそのまま残すことにしたい。<この重大な疑問は次の答えにより解決できる。それは、すなわち「サタンは霊的な存在であったのだが新しく魂と身体とを与えられた状態で物質的な意味において火の池に投げ込まれた。」という答えである。つまり、サタンは刑罰のために魂と身体とを新しく受けて物質的な状態としては火の池に投げ込まれることになったのだが、霊においてはいまだに世界に働きかけることが許されている、ということである。先に述べたように『火の池』とは身体と魂とが共に苦しむ物質的な場所であるから、霊的な存在であるサタンが火の池に投げ込まれたというのであれば、魂と身体がサタンにも与えられたということになろう。このように考えるならば、サタンが霊においては今も世界で活動を続けていることの理由が、よく分かるようになる。彼は霊においては今も世界に働いているのだが、身体と魂を持った物質的な状態としては火の池で苦しめられているので、物質的な状態としては何も出来ず火の池でもがき続けるのみである。これは、神である御子が受肉されて人となられことを考えれば更によく分かる。御子は確かに肉を取られて人となられた。この御子は人としては物質的な意味において特定のある場所に存在しているのみであった。一体どこの誰が人としてのキリストがエルサレムにもローマにもインドにもおられたなどと言うであろうか。魂と肉体を持った人としてのキリストは、エルサレムであればエルサレム、ローマであればローマ、インドであればインド、というようにある特定の場所に存在しているだけである。しかし、神としてのキリストは世界のどこにでも普遍的に存在しておられた。『天にも地にも、わたしは満ちているではないか。』(エレミヤ23章24節)と主ご自身が言っておられる通りである。人としてのキリストがある特定の場所だけにしか位置していないからといって、神としてのキリストが霊的な意味において全世界におられるということを疑う人はいないであろう。人としてのキリストが肉的にある特定の場所に制限されていたとしても、キリストというお方は、霊的な存在として世界のどこにでも存在しておられる。サタンが魂と肉体を受けて物質的な意味において火の池に投げ込まれたのも、これと同じことであって、たとえサタンが火の池に物質的な存在としては位置しているからといって、霊的な存在としては世界全体にいないということにはならない。キリストが肉的にはある位置に制約されつつも霊的には全世界におられるのと同様に、サタンも肉的には火の池という場所に制約されつつも霊の存在として全世界にいることができている。つまり、我々はサタンがキリストのように受肉した―サタンの場合は受肉させられたと言うべきである―のだと考えればよい。サタンは火の池に投げ込まれて物質的に苦しむためにこそ受肉させられたのである。それは、キリストが人類の贖いを実現させるためにこそ受肉されたのと同じである。それゆえ、もし「サタンは火の池に投げ込まれたのだからもう世界全体に働きかけることはできないはずだ。」と言うのであれば、その人はキリストにもこう言わなければならないことになる。「御子なるキリストは人としてユダヤの地に来られたのだから世界全体に遍在しておられることはあり得ない。」と。キリストについて、こんなことを言う兄弟は恐らくいないであろう。無知な兄弟でなければ、しっかりとキリストの肉における限定性と、霊における神としての普遍性を区別して考えられるはずである。であれば、サタンの場合でも、そのようなことは言うべきではないことになる。サタンが火の池に投げ込まれたのなら今の世界でまだ働いているのはどういうわけか、と問う人は、サタンがキリストのように受肉した上で火の池に投げ込まれたということをまったく考えていない。しかし、サタンが受肉した上で火の池に投げ込まれて物質的な意味においてはそこにおり、霊においては全世界に遍在していると考えるのであれば(※①)、問題はすべて解決されることになる。我々は、このようにサタンが霊的な存在であるということと、サタンは受肉した上で火の池に投げ込まれたという2つのことをよく考えなければいけない。この2つのことが考慮されていないと、この問題を解決することはできないからである。今取り扱ったこのサタンと火の池に関する問題は、私の見るところ、聖書において最も解決するのが難しい問題の一つである。恐らく、これ以上に解決の難しい問題は他にはないのではないかと思われる。私のこの解決方法が正しいとすれば、―私はこの解決方法が正しいと思っているが―、それは神の恵みによるものである。ある者らは、この最大級に難しい問題につまづいてしまい、御霊の言われたことに言い逆らってしまった。その者らは、御霊が黙示録に示されていることは『すぐに起こるべき事』(黙示録22章6節)であると明白に言われたにもかかわらず、この問題を解決できなかったので、何と御霊の言われたことを否定してしまった!!!すなわち、彼らはサタンが火に投げ込まれたのに今も活動している理由が分からなかったので、黙示録20:10で言われているサタンが火に投げ込まれるという出来事がいまだに起きていないと主張するに至った。「自分の理性によっては理解できないからまだ起きていないことにしてしまおう。」というわけである。御霊は、この黙示録20:10の箇所も含めて黙示録に示されていることは『すぐに起こるべき事』だと言われたのである。よって、この者らはサタンが2000年経過した今でもまだ火に投げ込まれていないと主張することにより、「御霊が言われたことは本当ではないのだ。黙示録にはすぐに起こらない事も示されているのだ。御霊は出鱈目なことを言われた。」と暗に述べていることになる。自分の理性では理解できないからといって、神の言われたことを否定し、自分の都合に合わせて聖書を読み込むとは何という態度であることか!アウグスティヌスも言うように聖書は「人間的なすべての思考よりも優先されるべき」(『アウグスティヌス著作集29 ペラギウス派駁論集(3)』罪の報いと赦し、および幼児洗礼 第1巻 第23章 第33節 p47:教文館)である。重要であるから繰り返すが、確かに御霊はサタンが火の池に投げ込まれるという出来事が書かれた20:10の箇所も含めて、黙示録には『すぐに起こるべき事』が示されていると言われたのである。であれば確かにサタンは黙示録が書かれてからすぐにも『火と硫黄との池に投げ込まれた』(黙示録20章10節)ことになる。つまり既にサタンは火に投じられたのである。しかし、今の世界でも相変わらずサタンは活動を続けている。ここにおいて多くの者に致命的な難問が襲い掛かることになる。多くの者はこの難問を解決することができない。しかし、私の説明したように考えれば、この頭を悩ませる問題を解決することができる。この説明は合理的であって荒唐無稽なものではない。それゆえ、読者は私が今説明したようにして、この問題を解決すべきである。サタンは受肉体として火に投げ込まれて物質的な位格においてそこで苦しんでいるに過ぎないのである。彼は霊的な位格においては全世界に働くことが今でも許されているのである。私は、このような説明をもって、この難しい問題が解決されたことにしたい。ネロや毒麦が火に投げ込まれたことについては、このサタンの問題とは違い、我々の頭を悩まさせるようなものではない。>これが以前の私の見解であった。しかし今の私は、この見解が誤っていたことに気付いている。確かなことを言うが、サタンが受肉したという私の以前持っていた見解は、単なる「こじつけ」に他ならない。このような見解は、愚かであり、虚しく、価値がなく、聖書的だとは言えない。私は真心から黙示録の正しい解釈を得たいと思っているから、このように以前の自分の見解が間違っていたことを素直に認め、それを公然と晒し、貶すことさえも厭わない。私にとって間違った解釈とは捨てるべきゴミなのだから。サタンが火の池に投げ込まれたというのは、つまり単なる表現に過ぎず、これはユダヤに対するサタンの働きの停止を意味しているのである。これは聖書から証明できるのであって、聖書においてサタンが滅びた、殺された、追い出された、燃やされた、無くなってしまった、と言われているのは、どれもサタンが支配権を失ったり、ある分野や対象における働きの力が消失させられた、ということを教えているのだ。聖書に深く精通している人であれば、これは明らかである。この件については、第3部の黙示録註解における20章の註解箇所で詳しい説明がされているから、そちらのほうを見ていただきたい。これがどういうことなのか、すぐにも知りたいと思う方は、先駆けて第3部における当該の部分を見るとよい。さて、それではこの火の池とは具体的にはどのような場所なのであろうか。まず火の池とは、滅びの子らが投げ込まれる場所である。そこには永遠の刑罰に定められた者しかおらず、聖なる者はただの一人もいない。何故なら、この場所は悪者たちに備えられた刑罰専用の場所だからである。一体どうして選ばれた聖徒が刑罰の場所に投げ込まれるであろうか。またこの火の池にいる者たちは、永遠に至るまでも苦しめられる。『彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。』と黙示録20:10に書いてある通りである。1000年経っても、1000億年経っても、彼らの苦しみは続く。その苦しみが終わることはない。外典である「パウロの黙示録」には、この火で苦しむ者たちに少しだけ安息の時が与えられると書いてあるが、そのような考えは聖書に書かれていないから拒絶せねばならない(※②)。タルムードの中では、この火の池すなわち「ゲヒンノム」における「悪人の裁きは12か月間である。」(『タルムード モエードの巻』シャバット 第2章 33b ミシュナ6/ゲマラ p110:三貴)と書かれているが、これは検討にも値しない謬見である。また彼らは苦しみながら『泣いて歯ぎしりする』(マタイ13章50節)。永遠の悲しみが、尽きぬ苦しみと共に与えられるのである。火の池には、大きな絶叫や哀れな泣き声が四六時中鳴り響いているに違いない。これは、想像するだけでも辛くなるような恐るべき光景である。また火の池とは、火と蛆とが存在する場所である。『そこでは、彼らを食ううじは、尽きることがなく、火は消えることがありません。』(マルコ9章48節)と主は言っておられる。火で焼かれつつ蛆に食われ続けるという光景は、正に永遠の刑罰が注がれる場所に相応しいと言えよう。先に挙げた「パウロの黙示録」では、この場所には雪のある冷たい場所も存在していると書かれているが(※③)、そのようなことは聖書の正典の中では言われていない。雪のある場所が火の池に存在していることは恐らくないと思われる。あったとしても、そのことは聖書に何も書かれていない。我々は、安全な理解に留まり続けるために、火の池には「火」と「蛆」が存在していると理解するだけで十分である。やがて我々が天に引き上げられたならば、火の池に雪が存在しているのかどうか知れるようになるであろう。また火の池に投げ込まれた者たちは、そこから出ることはできない。つまり、未来永劫そこに留まり続けることになる。最近では「セカンドチャンス論」を唱える者らが増えて来たが、私としては、この考えには否定的である。何故なら、火の池に投げ込まれた者たちは、永遠の昔から滅びるようにと定められていたからこそ、そこに投げ込まれることになったからである。つまり、その者が火の池にいることこそが、その者が永遠の滅びに定められていた証拠であるというわけである。もし永遠の救いに選ばれていたというのであれば、そのような者は、そもそも一度たりとも恐るべき火の池に投げ込まれるということさえないと思われる。キリストにあって愛された神の子どもである者が、火と蛆に少しでも苦しめられることがあるというのは非常に考えにくいと言わざるを得ない。『永遠に昼も夜も苦しみを受ける。』と書いてあるから、やはりそこに入った者には再び救いのチャンスが与えられることもなく永遠にそこに居続けることになると理解するのが、もっとも正しいと私は思う。またこの火の池に入った者たちは、とこしえまでも忌み嫌われることになる。イザヤ66:24にはこう書かれている。『彼らは出て行って、わたしにそむいた者たちのしかばねを見る。そのうじは死なず、その火も消えず、それは全ての人に、忌みきらわれる。』つまり、この地上から出て行って故郷である天国に凱旋した聖徒たちは、火の池で火と蛆に苦しめられている生きた死人たちを嫌な思いで見ることになる。呪われた者らは、天国にいる聖徒たちから忌み嫌われて恥辱を受けるという苦しみをも受けることになるのである。この『忌みきらわれる』という不名誉による苦痛も、神から彼らに与えられる刑罰の一つである。また、この火の池という場所は、先にも述べられたように、実際的な場所である。そこは幻想の世界でも、概念的な世界でも、霊だけの世界でもなく、今我々が住んでいる世界のような原子の集合体としての世界である。時間や感触や距離感といったものも当然ながら、そこにはある。もし我々が住んでいる世界のようでなかったとすれば、そこはハデスということになるが、このハデスは既に廃止されているのだから、この火の池とはハデスのような場所ではない。そこは真に実在的な物質空間なのである。この火の池がハデスのようではない実際的な場所であるということについて、これ以上の説明をする必要はないであろう。これは誰でも分かるような簡単なことなのだから。また世の中にはサタンがこの『火の池』の主人であるなどと言ったり、サタンが火の池で悪者たちを苦しめているなどと考えている人が多くいたし、今でも多くいるが、そのように考えるのは完全な誤りである。何故なら、黙示録20:10を見れば分かるように、サタンは火の池において苦しむ側であって、苦しめる側の存在ではないからである。私はどうして、このような謬見が世に満ちているのか不思議に思う。もしサタンが火の池で刑罰執行人として振る舞っているのであれば、サタンは火の池で苦しむ存在ではないことになる。しかし、黙示録はそのようには教えていない。つまり、サタンはただこの火の池で罰を受ける以外には何もできないのである。それゆえ、我々は世の人々の空想に惑わされてしまわないよう注意しなければいけない。世の人々は聖書から知識を得ていないからこそ、このような聖書に書かれていないことを平気で空想してしまうのである。とはいっても、サタンが火の池で苦しむというのは、先に述べたように単なる表現であって、実際のことを言っているのではないのだが。またこの火の池で燃えている火と硫黄の温度や形状や色といったものは、我々に何も知らされていない。もしかしたら1000度ぐらいの温度であり、黄金色の火であり、果てしなく上方にまで燃え上がっているのかもしれないが、定かなことは何も言えない。何故なら、その火の様子について、聖書は具体的なことを何も教えていないからである。これは火だけでなくうじも同様である。前述の「パウロの黙示録」では、うじの長さが1キュビトあると書いてあるが、本当にそうなのかどうかは分からない。正典の中にそのように書いてあれば確かにその通りであろうが、これはただの外典に過ぎないものである。外典を正典のように規範とするのは避けねばならない(※④)。我々は愚かな空想家になって神でもあるかのように何かを勝手に定めたりしないようにしよう。また愚かなイグナチウス・デ・ロヨラは地獄についての黙想を命じた第5霊操の中で「鼻で、地獄の噴煙と硫黄の悪臭と、ごみ溜めや腐敗物の悪臭をかぐ。」(『霊操』第1週 p114:岩波文庫33-820-1)と書いているが、地獄における匂いについては聖書で全く触れられていないので、この匂いについて何か確定的に言うことはできない。ロヨラは地獄の匂いを想像の中で勝手に嗅いでいるが、もしかしたら地獄には何の匂いもない可能性だってあるのである。またこの場所は『まっ暗なやみ』(ユダ13)に満ちた場所である。そこには僅かな光さえもない。神は、滅びの子らから光の恵みを完全に取り上げられる。この地獄における闇については、また再び第4部において語られることになる。というわけで、第二の復活により復活してから携挙され、空中の審判により恐るべき宣言を受けた毒麦どもは、このような場所である『火の池』に投げ込まれることになったのである。『火の燃える炉に投げ込みます。』(マタイ13章42、50節)とか『わたしから離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火にはいれ。』(マタイ25章41節)とか『いのちの書に名のしるされていない者はみな、この火の池に投げ込まれた。』(黙示録20章15節)などといった毒麦どもに関する恐るべきことが言われた御言葉は、このようにして紀元68年6月9日に成就することになったのである。なお、この永遠の苦しみが与えられる場所を「地獄」と一般的な呼び方で呼ぶのは何も問題ない。しかし先にも述べたように「ハデス」と呼ぶのは間違っている。「地獄」でも別に構わないのだが、より正確に言うのであれば聖書の記述通りに『火の池』と言わなければならないことになる。
(※①)
サタンが霊において全世界に遍在しているというのは、サタンがまったく同一の時間に、世界の様々な場所にいる人間に同時に働きかけることを考えればよく分かる。例えば、昼の12時45分36秒という時間において、サタンはイギリスで畑仕事をしているジョンに誘惑をしかけると同時に、中国で車を運転中のリーにも精神的な攻撃を仕掛ける。この同じ時間に、サタンは日本の小林にも、アメリカのピーターにも、イスラエルにいるイサクにも、宇宙空間にいるジェイコブにも、霊的な働きかけをしている。これはサタンが霊において全世界に遍在していると考えなければ理解できないことである。もしサタンがある一定の場所にしか霊において存在していないというのであれば、ある一定の時間において、あるどこかの場所にいる一人かまたはそれほど多くない人数に対してしか働きかけることができなかったはずである。つまり、サタンは神ではないが、しかし神が全世界に遍在しておられるように、全世界に遍在することを許されているということである。サタンは霊の存在であるから、彼を霊において理解するのであれば、彼が何か物質的な存在でもあるかのようにどこか一つの場所に縛られているといった考え方をしてはいけないのである。
[本文に戻る]
(※②)
この外典では、地獄で苦しんでいる者たちに対して、『罰を司る意地の悪い天使たち』―これはよく分からない存在である―が「お前たちはしかし、お前たちのところに下って来た、神にこよなく愛されているパウロに免じて、日曜日には日夜、安息という大きな恵みを与えられた」(『聖書外典偽典6 新約外典Ⅰ』パウロの黙示録 第44節 p310:教文館)と言っている箇所がある。このような安息が与えられたことに対して、この者たちはキリストに「神の子よ。あなたをほめたたえます。あなたが一日一夜の安息をお与えくださったことを。わたしたちにとっては、この1日の安息は、地上で送ったわたしたちの生涯のすべての時にまさってよいものです。」などと言っている。このようなものは単なる空想の産物に他ならない。たとえパウロが大声で泣き叫びながら神に懇願したとしても、地獄にいる者たちには、たとえ僅かでも安息が与えられることはないであろう。
[本文に戻る]
(※③)
「次いでわたしは北のほうから西のほうを眺めたが、そこには休みを知らぬうじ虫が見えた。そしてその場所には歯ぎしりがあった。うじ虫は長さが1キュビトあり、それには二つの頭があった。そこにはまた男たち女たちが、寒いところで歯ぎしりているのが見えた。わたしはたずねて、「主よ、この場所にいるこの人たちはだれですか」と言った。すると彼は、「この人たちはキリストは死人の中から復活しなかった、また、この肉が復活することはないと主張する人々だ」と言った。わたしはたずねて、「主よ、この場所には火や温かいものはないのですか」と言った。すると彼はわたしに、「この場所には霜と雪以外は何一つ存しないと言い、また、「この場所の霜と雪とがあまりに多いので、彼らの上にたとい太陽が上っても彼らは温かくはならない」と言った。」(『聖書外典偽典6 新約外典Ⅰ』パウロの黙示録 第42節 p307:教文館)
[本文に戻る]
(※④)
このような霊感されていない文書は、別に容赦なく疑ったり、その真偽性を問題にしても構わないものである。ルターも、スタンプレンシスが外典を引用しつつ論証したことを、容赦なく否定している。ローマ書15章のグロッセにおける欄外註の40。「使徒はイスパニアに行ったのかどうかが問題となる。スタプレンシスは、行ったと答えて、外典を引用している。しかし、私は行かなかったと信じている。」(『ルター著作集 第二集 第8巻(ローマ書講義・上)』グロッセ 第15章(37―40) p203 聖文舎)ちなみに、この『パウロの黙示録』なる文書は、アウグスティヌスにより否定的に見做されている。我々も彼の見解通りに、この文書を懐疑的に見做すべきであろう。この文書に対するアウグスティヌスの記述はこうである。「霊の人たちの間でも、たしかに他の者たちよりも能力がありすぐれている者がいて、彼らの中のある者は、人間には語ることの許されないことに到達するほどである。それを口実にして、うぬぼれの強い者たちが、健全な教会が受け入れてはいない何か作り話に満ちたパウロの黙示録なるものを、きわめて愚かしい僭越さによって捏造し、これこそがパウロが第三の天に連れ去られて(Ⅱコリ12・2)、そこで人間には語ることの許されないことばを聞いた(同12・4)、と言っているものだと主張している。」(『アウグスティヌス著作集25 ヨハネによる福音書講解説教(3)』第98説教(16章12―13節、続き)8 p260:教文館)
[本文に戻る]
さて、それでは第二の復活によりハデスから出されず、墓からも上がらず、携挙もされず、それゆえに空中の審判を受けなかった死亡者たちは一体どうなったのであろうか。つまり、使徒の時代にいた毒麦ではない全てのハデスにいた悪者どものことである。まず、この者らが、ハデスで苦しんでいたのは確かである。この者らは、ハデスからある者たちが空中の審判を受けるために引き出されて行ったのを見た後、そのままハデスに居続けたのであろうか。そのようなことはない。何故なら、ハデスはそこにいた毒麦たちがハデスから引き出されて空中に上げられたその日に、火の池に投げ込まれて滅ぼされたからである。ハデスはこの日に完全に廃止されている。ハデスから引き出されずそこに残されたこの悪者どもは、再臨の日に、ハデスと共に火の池に投げ込まれたと考えるべきである。この悪者たちはハデスごと火の池に投げ込まれるその時に、第二の復活を受けた。つまり、ハデスから火の池に移行させられるその瞬間に新しい身体を付与された。先に第二の復活により復活したのは使徒の時代にいた毒麦だけだと私は言ったが、それは、あくまでも空中の審判に引き出されるために墓から出て来ることになった者たちのことに限られる。確かに、墓から出て来ることになるハデスにいた死亡者という観点から言えば、第二の復活を受けるのは使徒の時代にいた毒麦だけであったと言っても間違いではない。しかし、この第二の復活は、全体として言えば、つまり限定なしに言えば、ハデスから出されずそこに残された者たちも受けたのだと私はここで言っておきたい。この者たちにおける第二の復活は、空中の審判を経ないでそのまま火の池に直行させられたという点で、先に述べた毒麦どもにおける第二の復活と異なっている。どちらも第二の復活を受けてから火の池に投げ込まれるという点では何も変わらない。こちらのほうの悪者たちが火の池に投げ込まれた時も、ハデスから出された毒麦たちが空中から火の池に投げ込まれた時と同じである。というのは、毒麦たちが恐るべき宣言を受けて空中から火の池に投げ込まれる時こそ、『ハデス…は、火の池に投げ込まれた。』(黙示録20章14節)という預言が成就した時だからである。毒麦とハデスが火の池に投げ込まれた時間において何も変わらないのであれば、そのハデスの中にいた悪者たちも毒麦と同じ時間に火の池に投げ込まれたのだということは、思推の出来る者であれば誰でも分かることである。
こ
こで『火の池』のことを述べたついでに、この場所が一体どのようにして造られたのか、またそれはいつ造られたのか、ということをいくらか考察してみたい。何故なら、これはあまり重要な問題とは言えないものの、気になる方もいるかもしれないからである。そのような方のために、私はここで短く筆を取ることにする。まず、この『火の池』とは、死とハデスが滅びることになる再臨の日に創造されたのであろうか。つまり、再臨の日よりも前には創造されておらず、それゆえ存在していなかったのであろうか。これは可能性としてはあり得る、としか言いようがない。もしかしたら火の池が創造されたのは、この日なのかもしれないし、そうではないのかもしれない。では、この場所は、再臨の日よりも前に既に創造されていたのであろうか。つまり、再臨の日よりも前に創造されて存在していたが、まだハデスが機能していたために、この火の池は存在していても機能する必要がなく、そのためそこは無人状態のままに保たれ続けていたのであろうか。これも先に述べたのと同じで、可能性としてはあり得るとしか言えない。というのも、火の池がいつ造られたのかということを聖書は何も教えていないからである。それでは、もしかして火の池とは元はハデスであって、ヨハネはハデスの性質が再臨の日以降変えられたことを言おうとして『ハデス…は、火の池に投げ込まれた。』(黙示録20章14節)と書いたのであろうか。これはいくらか興味深い見解ではあるが、しかし何とも言えないと私には思える。このように考えることもできなくはないが、あまりしっくりせず、「そうなのだ。」と確信を持つこともできない。私は、どちらかと言えば、この見解には否定的である。というわけで、このように私は聖書がこのことについて何も語っていないがゆえに、確定的に論じることができない。聖書が何も教えていないのに、どうして「こうだ。」と言えようか。私はハデスと火の池とを造った神ではないのである。ただ一つ言えるのは、この火の池も被造物であって、再臨の日まで使われていたハデスにとって代わった場所であるということである。ハデスは再臨の日まで使われていたが、その日以降は火の池に刑罰の役割を譲ることになった。他方、火の池は再臨の日までは機能していなかったか、または存在すらしていなかったが、その日以降ハデスの代わりに刑罰の職務を遂行することになった。これは間違いないことである。しかし、火の池の創造についてのことはよく分からない。このような聖書に書かれていないことを断定的に論じるのは、キリストの教師としては正しくない態度である。それゆえ私が何もしっかりと答えていないからといって、私は責められるべきではないし、むしろ正しいことをしているとさえ見なされるべきである。私のような者たちは、天使の位階を好き勝手に空想して紙の無駄使いをしたあの傲慢な古代の暇人(※)のようになるべきではない。明らかにされたことは我々のものであるが、隠されていることは神のものであって、我々にはどうすることもできない。それは、『隠されていることは、私たちの神、主のものである。しかし、現わされたことは、永遠に、私たちと私たちの子孫のものであり、…』(申命記29章29節)と書いてある通りである。それゆえ、神のものが我々に与えられておらず、我々がその事柄を知ることを許されていない時は、「分からない。」と言うのが正しいのである。今取り扱われたこのことが気になる人もいるかもしれないが、このような次第であるから、事を了承していただきたいと思う。冷たいことを言うようだが、別にこのような些細な事柄を知らなくても、信仰に影響は出ないだろうし、救いが失われることもないし、何か致命的な問題が生じるわけでもないのである。
(※)
もちろん私が言っているのは、『天上位階論』という偽書の著者であるディオニシウス・アレオパギテースのことである。この書物とその著者については、カルヴァンも『キリスト教綱要』第1篇・第14章・第4節の箇所で言及している。このディオニシウスの文書群は「聖書に次ぐ権威を持つ」とすら言われたほどに有名となったものであり、ダンテさえも影響を受けたものだが、その内容は新プラトン主義的であり、正統的で健全な信仰を持った聖徒にとってはあまり益にはならないように思われる。日本人でこの文書を確認したい方がいれば、平凡社から出ている『中世思想原典集成3 後期ギリシア教父・ビザンティン思想』という本で読むことが出来る。
[本文に戻る]
それでは、この空中においてキリストから喜ばしい宣言を受けた聖徒たちは、それから後、どのようになったのであろうか。これは放置しておいてはならない問題である。放置しておけば、再臨についての理解が、それだけ乏しいままに保たれてしまうからである。一つ一つ考察していきたい。まず空中にいるこの聖徒たちは、空中の場所から、地上へと降りて来たのであろうか。これは考えられないことである。何故なら、聖書には、そのようなことが何も教えられていないからである。もしキリストと無数の聖徒が地上に降りて来たとすれば、大きな騒ぎとなり、再臨に関するこの世的な証拠がいくらかでも残されることになっていたであろう。それでは、どこにも移動せず、そのまま実体的に空中に留まっていたのであろうか。これも考えられない話である。聖書は、そのように語ってはいないからである。もしこのようであったとすれば、聖書はそのことを、しっかりと記していたであろう。では、実体としてではなく「幻影体」として空中に留まっていたということは考えられないであろうか。実体であろうが幻影体としてであろうが、そもそも彼らが空中に留まっているという理解そのものが聖書の教えではないのだから、幻影体として空中に留まっていたと考えることも当然ながらできない。異端の人であれば、この空中における出来事が、そもそも単なる概念的なことを述べたものに過ぎないと考えるかもしれない。このような腐った妄想も、これまでに述べたことと同様、退けられねばならない。この空中における出来事は、実際の出来事を述べたものであって、概念的なものなどではない。それは、キリストの復活が真に実際的なものであり、単なる概念的なものではなかったのと同様である。悪魔の妄想は速やかに消え去れ。また、この空中における出来事が、そもそも未だに起きていないと考えることもできない。何故なら、パウロは自分たちが『生き残っている』(Ⅰテサロニケ4章17節)時に携挙が起こると言ったからである。携挙があれば、その後で起こるのは空中の審判である。紀元1世紀に生きていた聖徒が携挙されて空中に上げられたのだから、その時に空中の審判も起きたと考えるべきである。ここまで読んでも、また空中における出来事が既に起きたと信じれない聖徒は、不信仰であるか、そうでなければ理解が足りていない。不信仰のほうはどうしようもないが、ただ理解不足なだけであれば、やがて分かるようになる可能性があるから、今までに書かれた説明を理解できるようによく読み返してほしい。それでは空中にいる聖徒は一体どうなったというのであろうか。結論を述べる。彼らは上のほうにある天に引き上げられたのである。何故かと言えば、天こそ聖徒たちのおるべき場所だからである。パウロは『私たちの国籍は天にあります。』(ピリピ3章20節)と言った。天にこそ聖徒の国籍があるのであれば、どうして聖徒がそこに行かないわけがあろうか。まさか、神が聖徒たちにいじわるをして、聖徒を国籍のある天へと行かせないようにしておられるというのでもあるまい。我々は『神は愛』(Ⅰヨハネ4章8、16節)であることを知っている。ヘブル書の著者も、信仰の人々として死んだ者たちのことについて、こう述べている。『これらの人々はみな、信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことで、自分の故郷を求めていることを示しています。もし、出て来た故郷のことを思っていれば、帰る機会はあったでしょう。しかし、事実、彼らは、さらにすぐれた故郷、すなわち天の故郷にあこがれていたのです。』(ヘブル11章13~16節)ここで言われているように、信仰の人々はこの地上においては『旅人であり寄留者』であって、『自分の故郷』すなわち『天の故郷』を持っている。聖徒の故郷が天だというのであれば、聖徒がその故郷へと連れて行かれないはずがどうしてあるであろうか。神は、聖徒をその故郷へと行かせて下さらない「いじわるなお方」ではない。更に我々は、キリストが天に上げられたのは、天に聖徒の住まいを用意するためであったということも考えるべきであろう。キリストはヨハネ14:2~3の箇所で次のように言われた。『わたしの父の家には、住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなたがたに言っておいたでしょう。あなたがたのために、わたしは場所を備えに行くのです。わたしが行って、あなたがたに場所を備えたら、また来て、あなたがたをわたしのもとに迎えます。わたしのいる所に、あなたがたをもおらせるためです。』ここで言われているように、キリストは、聖徒の場所を備えるために御父のおられる天へと行かれた。そうして場所が用意できたので、―『また来て、あなたがたをわたしのもとに迎えます。』―、聖徒たちを迎えるために天から再臨された。すなわち、紀元68年6月9日に用意が整ったので、もはや天で待機される必要がなくなり、再臨されたのである。であれば、空中に上げられた聖徒たちが、どうして天の場所に連れて行かれないはずがあろうか。キリストは聖徒を天に備えられた住まいへ住ませるために、天から聖徒を迎えるべく降りて来て下さったのである!もし聖徒が空中から天に連れて行かれなかったとすれば、いったいキリストは何のために天に聖徒の住まいを備えに行かれたのか、ということになるのである。更にルターの文章も引用しよう。彼は説教の中でこう言っている。「われわれの住まいは…天にある。」「そこ天では、市民権を得て、われわれの名は、天使の都市台帳の中に書き留められているのである。」(『ルター著作集 第二集6 ヨハネ福音書第1章・第2章説教』第16説教 第1章(51)p307、310 LITHON)ルターよ。あなたの言ったことは誠に正しい。確かにルターも言ったように、我々の住まいは天にあり、我々は既に天の市民権を持っている存在である。そうであれば、どうして聖徒たちがそのような天へと引き連れて行かれないのであろうか。言うまでもなく、天の市民権を持っている聖徒たちは、その住まいのある天へと引き連れて行かれたと考えるのが自然な理解である。このように言ったルターも、ここで今されている私の説明を聞いたならば頷いて同意したことであろう。それゆえ、以上の説明から、聖徒たちは幸いな宣言を受けた後、天へと引き上げられたということが分かる(※)。つまり、『正しい人たちは永遠のいのちにはいるのです。』(マタイ25章46節)と言われたのは、このように言われた後、聖徒たちが空中から天に引き上げられてそこで永遠に生き続けることになるという意味に他ならない。実際、聖徒たちはこのように言われた後、空中から天に引き上げられてそこで永遠に生き続けることになった。この天のことを詳しく説明しているのが、黙示録21章以降の箇所である。この天のことについては、これから詳しく論じられることになるであろう。
(※)
聖徒が天に上げられたのも、やはり携挙および毒麦が火の池に投げ込まれたのと同様に、御使いに任されていた仕事だったのであろうか。これについては何とも言えない。というのも、聖書にはこのことについての明白な記述がないからである。携挙と火の池への投下は明白な記述があるから、こちらのほうは確定的なことが言える。天に上げられることのほうは、もしかしたら天使が連れて行ったのかもしれないし、そうではないかもしれない。つまりキリストが昇天された時のように、不思議な力により聖徒たちが天へと連れ去れたのかもしれない。いずれにせよ、私はこのことについて確定的なことを言わないでおきたい。
[本文に戻る]
聖徒たちがキリストと共に引き上げられた天とは、次のような場所であった。全部で8つの項目に分けて説明したい。一、天とは、父なる神とキリストと御霊と贖われた聖徒と御使いとヨハネが黙示録で描いている天上の生き物だけが住まう場所である。そこにはサタンや悪霊どもや悪者たちはまったく存在していない。これは火の池に、裁かれるお方を別としては(※)、邪悪な存在しかいないのとは正反対である。この場所は聖なる場所であって、聖なる存在しか存在しない、いや、してはならない場所なのである。『しかし、すべて汚れた者や、憎むべきことと偽りとを行なう者は、決して都にはいれない。子羊のいのちの書に名が書いてある者だけが、はいることができる。』(黙示録21章27節)と書かれている通りである。二、天は永遠に続く場所である。神はイザヤ66:22で『わたしの造る新しい天と新しい地が、わたしの前にいつまでも続くように。』と言われた。この預言は先に説明されたように既に成就しているのだが、ここで言われているように、天は神の御前に未来永劫存続し続ける場所である。御子を信じて救われた聖徒たちも、当然ながら、この天で永遠に存続し続ける。何故なら、キリストは『信じる者は永遠のいのちを持ちます。』(ヨハネ6章47節)と言われたからである。この天とそこにいる者たちが、消えていなくなったり、一時的に存在を中断させられるということはあり得ない。天という神の聖なる空間から、愛された聖徒が失われるということがどうしてあり得ようか。三、天には良いものや良いことしかなく、そこには悪かったり不快感をもたらすようなものはまったくない。それは黙示録21:4で『もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。』と天について書かれている通りである。祝福、幸せ、喜び、楽しみ、讃美、光栄、栄光、名誉、元気、健康、笑顔、円満、力能、順調、希望、愛徳、柔和、善意、親和、従順、尊敬、平和、平安、―このような幸いだと感じられるものが天には満ちている。そこには、贖われた聖徒たちが共に住まう幸いもある。これは大変素晴らしい幸いである。ダビデはこう書いている。『見よ。兄弟たちが一つになって共に住むことは、なんというしあわせ、なんという楽しさであろう。』(詩篇133篇1節)ここで言われている『兄弟』とは聖徒のことでなくて何であろうか。アダムやエノクやノアやアブラハムやモーセやダビデやエリヤやマリヤやペテロやパウロといった我々のよく知る聖徒たちがそこにはおり、皆がキリストと共に生き続けるのである。これは少し想像しただけでも素晴らしいと感じられる場景である。このような天における幸いは、火の池に不幸なことしか存在していないのとは真逆である。そこは幸いだけが満ちた至福の空間なのである。タルムードの中では、「来たるべき世における満ち足りた思いの1時間は、この世における全生涯よりもすばらしい。」(『タルムード ネズィキーンの巻』アヴォード 第4章 11b ミシュナ17 p29:三貴)と言われているが、これは間違っていない。四、天とは実際的な物理空間である。すなわち、手で何かを触り、ある物体との間に距離感を感じ、音の粒子が飛んでくれば音を認識できる、そういった物質的な空間である。何故なら、この天には肉体的に復活されたキリストが昇天されたのであって、そこから使徒行伝1:11で言われているようにキリストが肉体的に降りて来られ、そうしてからこの天に肉体を持ったキリストと共に聖徒たちが引き上げられたのだからである。キリストであれ聖徒たちであれ、天に引き上げられたら肉体が失われてしまうなどということがどうしてあるであろうか。そのようなことは考えられない。この天が実際的な物理空間ではなく、幻想的であるとか、霊的な場所に過ぎないとか、単なる概念として言われたなどと考えるのは誤りである。もしここが実際的な物理空間ではないとしたら、聖徒たちが『キリストの復活とも同じようになる』(ローマ6章5節)と教えたパウロの聖句は偽りだったということになる。キリストが実際的に復活されたように聖徒も実際的に復活するというのであれば、その聖徒が引き上げられた天の世界も実際的であるというのは確かである。聖徒であるにもかかわらず、天が実際的な場所でないと信じるのであれば、そのような聖徒は天に至った際に自分だけ幽霊のようにされたとしても文句は言えまい。五、天が実際的な場所であるとはいっても、我々は、そこが具体的にどのような性質を持った場所であるのか知りえない。天の都には『これを照らす太陽も月もいらない。』(黙示録21章23節)とヨハネは書いている。つまり、天国とは我々が今存在している宇宙空間のようではない。太陽も月もないのであれば、そこには恒星も惑星も銀河も天の川も公転も自転も引力作用もないことになる。また、そこには『もはや海もない。』(黙示録21章1節)これは、天国が地しかない場所であるということを教えた聖句であると思われる。つまり、地形的に言えば月や火星のように、どこを見渡しても一面地続きの場所であるということなのかもしれない。しかし、天における「地」が一体どのような性質のものなのか、我々にはまだ何も知らされていない。一つ確実に言えるのは、天国にはタイタニック号がその上を進んだあの巨大な液体物質は見られないということである。また天には『もはや夜がない。』(黙示録22章5節)天に太陽や惑星や自転がないというのであれば、当然ながら夜もないことになる。夜というのは惑星が自転することにより太陽に照らされなくなる暗黒領域のことを意味しているからである。つまり、天では明るい昼のような状態がずっと続くということである。我々はこのような驚くべき現象をまだ一度も体験したことがない。このように天とは我々の感覚では捉えきれない場所であって、その詳細を具体的に伝えることは地上に住まう人間にはできないことである。一つ確実に言えるのは、天がこの今の世界とは違って驚くべき性質を持った場所であるということである。そこは我々が想像さえできないような場所であるのは間違いない。六、天というパラダイスは最初のパラダイスのように汚され腐敗させられることがない。最初のパラダイスはアダムの犯した罪により堕落の巻き添えを受け、呪われてしまった。これは、『被造物が虚無に服した』(ローマ8章20節)とパウロが言っている通りである。しかし天では『もはや、のろわれるものは何もない。』(黙示録22章3節)と神は教えておられる。つまり、そこは常に完全に聖なる空間なのであって、塵ほども罪や汚れや腐敗といった忌まわしいものは入り込む余地がないということである。もしそのようなことがあれば、天は一瞬のうちに汚れの巻き添えを受けることになり、もはや聖なる空間ではなくなってしまうであろう。しかし、神はそのようなことが起きるのを決してお許しにはならない。そこは未来永劫完全に聖であることが定められた空間だからである。七、天に上げられた聖徒たちは、栄光に満ちて輝かしい光を放っている。キリストは、天に上げられた聖徒について次のように言われた。『そのとき、正しい者たちは、天の父の御国で太陽のように輝きます。』(マタイ13章43節)聖徒が太陽のように輝くというのは素晴らしいことである。しかし、どうして聖徒たちは輝くのであろうか。まず考えられるのは、神がその光をもって聖徒を照らされるので、聖徒たちが神から受けた光を反射することにより輝くということである。このことについては黙示録でこう書かれている。『神である主が彼らを照らされるので、彼らにはともしびの光も太陽の光もいらない。』(22章5節)この聖句から分かるように、聖徒たちが神の光を反射させるというのは間違いないことである。しかし、それでは聖徒たち自身としては光を放たないのであろうか。つまり月のように外部(太陽)から届いた光を反射させて輝くだけであり、自分自身としては何も光を放たない闇の存在に留まるのであろうか。私としては、聖徒たちも自ら太陽のように光を放出するのではないかと推測する。というのは、まだ新しい身体を受けていなかった死すべきあのモーセでさえ、神と話したことにより自ら光を輝き放ったからである。出エジプト記にはこう書かれている。『彼は、主と話したので自分の顔のはだが光を放ったのを知らなかった。アロンとすべてのイスラエル人はモーセを見た。なんと彼の顔のはだが光を放つではないか。…イスラエル人はモーセの顔を見た。まことに、モーセの顔のはだは光を放った。』(34章29~30、35節)罪の残滓をまだ持つあのモーセでさえ、自分自身から光を放ったというのであれば、常に神と共にいる栄光体の聖徒たちは尚更のこと自ら光を放つのではないか。原理的また論理的に言えば確かにそういうことになる。何故なら、まだ地上にいたモーセよりも天上に引き上げられた聖徒のほうが、遥かに輝きを放出すべき聖なる存在だからである。誰がこのことを疑うであろうか。であれば、天の聖徒も自ら光を放つという可能性はかなり高いと見てよいであろう。八、この天における聖徒の持つ輝きの度合いは一様ではない。すなわち、人によりそれぞれ輝きの差がある。ある聖徒は考えられないぐらいに大きな光を放ち、ある聖徒は天上においては平均的な光度の光を放つ。これはヘブル11:35に『さらにすぐれたよみがえりを得るために』と書いてあることから分かる。確かにヘブル書で言われているように、ある者らはより素晴らしい復活を受けるためにあえて苦しみを甘受したのであるが、これは復活体における輝きの度合いを増し加えることについて言ったものである。そうでなかったとすれば、それらの聖徒たちは一体何のためにあえて苦しみを甘受したのか、ということになる。神が報いに差をつけられるというのは、この地上のことを考えても分かる。この地上では非常に多くの幸いを受ける聖徒がいれば、普通程度の幸いしか受けない聖徒もいる。パウロは霊的に凄まじい恵みを受けたが、行為義認の教えに惑わされていたガラテヤ教会の聖徒や腐敗に満ちていたコリント教会の聖徒は、間違いなくパウロほどには霊的な恵みを受けてはいなかった。誰がこのことを疑うであろうか。天においてもそれは同様であって、大いに輝く聖徒がいれば、普通程度にしか輝かない聖徒もいるのである。トマス・アクィナスのようなスコラ的詮索をすることになるが、それでは一体、天でもっとも輝くことになる聖徒は誰であろうか。これは推測の域を出ないが、私としてはバプテスマのヨハネがそうではないかと思う。何故なら、キリストは彼について『女から生まれた者の中で、バプテスマのヨハネよりすぐれた人は出ませんでした。』(マタイ11章11節)と言われたからである。つまり、このヨハネはアベル、エノク、ノア、アブラハム、イサク、ヤコブ、モーセ、ヨシュア、ギデオン、サムソン、サムエル、ダビデ、エリヤ、エレミヤなどといった父祖たちよりも偉大な人間であった。ヨハネはキリストの先駆者であり、驚くべきことに神であるお方にバプテスマを授けることさえした。しかも、生涯に渡って敬虔な態度を貫き通した。このような人物が、地上だけでなく天上においてももっとも偉大な人間であったとしても何も驚くべきことではない。しかし、先にも言ったようにこれは確定的にそうだと言えることではなく、あくまでも推測に過ぎない。ただ可能性として十分にあり得るということは、読者の方にも認めていただけるのではないかと思う。もちろん、もしかしたらパウロのほうが彼より輝いているという可能性も十分に考えられるのではあるが。というわけで、天国とはざっと見るならばこのような場所であるが、我々人間にとって、この場所は実に計り知りがたい。そこは、今の我々の理性からすれば、把握したくてもできないような事柄に満ちている。それは、あたかも街にいる浮浪者が、黄金の宮殿に住んでいる金持ちの生活を知りえないようなものである。確かに天国について聖書はいくらかのことを啓示しているが、それはあくまでも限られた範囲内のことであって、その啓示と啓示に基づいて得られる知識はそれほど多くない。神は、天国に関する一部のことだけしか今の我々に知識としては与えておられないのである。我々がパウロのように『第三の天にまで引き上げられ』(Ⅱコリント12章2節)たというのであれば話は別だっただろうが、我々の中で、そのような恵みを受けた者は一人もいない。それゆえ、我々はまだ天のパラダイスに至っていないがゆえ、この天のことについて経験に基づいて何かを述べることもできない。いい加減な馬鹿げた考えを言うことならば誰にでも好きなだけできるが、もし神の民であるという自覚を持っているならば、そのようなことをすることは絶対にできない。それは神の喜ばれない愚行に他ならないからである。このように、我々が天について知れること、語れることは、今の人生においては非常に限られており、もやもやとした感があるのは否めない。これは神が天のことをそこまで多くは啓示しておられないのだから仕方がないと諦めねばならない面もある。しかし、我々もやがて天に引き上げられたならば、その時には、天国について分からなかった全てのことが明白に分かるようになるであろう。それはパウロがこう言っている通りである。『今、私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今、私は一部分しか知りませんが、その時には、私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。』(Ⅰコリント13章12節)パウロも言うように、今の我々はぼんやりとしか天国のことを認知できていないが、やがて完全に知れるようになるということに希望と喜びを覚え、今の時点では聖書で啓示されている範囲内に基づいた知識を持つことだけで満足すべきである。それは、我々が愚かで傲慢な夢想家になって神の御心を損ねないためである。今まで実に多くの夢想家たちが腐った夢想を撒き散らして、無知で弱い人々を大いに誤謬へと導いてきたことを、我々は既に知っているのである。
(※)
神が御使いたちに火とうじによる苦痛の投与を委ねておられるというのであったとすれば、当然ながら御使いも含まれる。
[本文に戻る]
今のキリスト教界にとって重要な話に移りたい。それは、神の御国が、この再臨の日に力をもって到来したということである。つまり、この再臨の日に、天上におけるキリストの御国が正式にスタートすることになった。この日になるまでは、まだ天の御国は到来しておらず、また開始されていなかった。このようなことが言われたのを聞いて、読者は驚くべきではない。何故なら、これは私の個人的な見解ではなく、聖書がそのように教えていることだからである。確かに、キリストは再臨と共に御国が到来すると明白に言われた。それはマタイ18:26の御言葉のことである。そこにはこう書いてある。『まことに、あなたがたに告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が御国とともに来るのを見るまでは、決して死を味わわない人々がいます。』既に論じられたように、再臨はネロの命日である紀元68年6月9日に起きたのだから、キリストがマタイ18:26で言っておられるように、この日に天の御国も到来したことになるのである。この見解に反対すると、聖書の御言葉に反対することになるから読者の方はよく注意されたい。つまり、多くの兄弟が考えているように、天の御国はいまだに到来していないなどと考えるのは誤りである。多くの教派と教会は、御国の到来に関して自分たちの考えを改めねばならない。ベザの場合、御国が到来したのはキリストの復活された時だと考えていた。つまり紀元33年頃だということである。御国の到来を紀元1世紀だとする点では、つまり御国が既に到来済みだと考える点では、ベザに誤りはなかった。しかし、キリストが言われたように御国は再臨と共に来るのであって、この再臨はネロの命日に起こった。それゆえ、ベザの見解には日付の正確性という点で問題があったことになる。またベザの考えに従うと、パウロがキリストの復活よりも後の時期に『私たちが神の国にはいるには、多くの苦しみを経なければならない。』(使徒行伝14章22節)と弟子たちに言ったことを上手に理解できなくなってしまう。もし主の復活の際に御国が到来したのであれば、どうしてパウロはここで、まだ御国が到来していないかのように言ったのであろうか。パウロがこう言ったのは、もちろん、まだ御国がその時には到来していなかったからに他ならない。つまり、パウロはここで「これから到来することになる御国に入れるよう君たちは多くの苦しみに耐えなければいけないのだ。」と言いたかったのである。もし復活の時に御国が来たのであれば、パウロはこのようには言っていなかったであろう。それゆえ、ベザの見解は時期的にいくらか早すぎたと言わねばならない。ここまで読み進められた読者には、もうお分かりだと思うが、この御国の到来を紀元68年6月9日に設定しない全ての見解は偽りの見解である。しかし、「地上の御国」であれば再臨の日以前にも既にこの世に存在していたと言える。何故なら、地上の御国とはすなわち地球上に存在しているキリストの教会のことだからである。マタイ13:41に書いてある『御国』とは、このような意味としての御国である。しかし、「天上の御国」の場合は、再臨の日以前にも既に存在していたと言うことはできない。そのように考えると、諸々の聖句が上手に理解できなくなるからである。それは先に述べたパウロの聖句(使徒行伝14:22)がそうだし、キリストがユダヤ戦争の時期に起こる色々な凶兆を見たら『神の国は近いと知りなさい。』(ルカ21章31節)と言われた聖句もそうである。このような聖句は、天上の御国が再臨の日になるまでは、まだ到来していなかったことを教える聖句である。要するに、地上の御国は天上の御国を指し示す存在ではあるが、再臨の日になるまではその天上の御国がまだ正式に開始されていなかったということである。
そ
れでは、我々は「主の祈り」の中にある『御国が来ますように。』(マタイ6章9節)という条項を、もはや祈らなくてもよくなったのであろうか。これは、その通りであると私は言いたい。聖書ではなく教会の常識的な見解に盲目的に従ったり、権威を鵜呑みにする人たちが、こう言われたのを聞いて反発することは既に分かりきっている。彼らは聖書を直視するというよりは、むしろ人の目や常識のほうを上に置く人たちだから、この聖書的な主張には大いに敵対するであろう。しかし、私は今、確かに聖書からこのように言ったのである。何故なら、聖書は既に御国がキリストの再臨と共に到来したと教えているからである。もし御国が既に到来したというのであれば、どうしてその既に到来した御国が到来するようにと祈らなければいけないのであろうか。既に来たものを「来ますように。」と祈り願うのは、普通に考えて理に適っていない。それは、ある人が既に皇帝になったのに、その人が皇帝になれますようにと願うようなものである。我々は、この条項を「地上の御国が拡大しますように。」と言い換えて祈るべきだと私は思う(※①)。『御国が来ますように。』と祈っても、その祈りは無効的である。何故なら、神はもう遥か昔にそのような祈りを実現させて下さったからである。キリストの時代にいた聖徒たちが『御国が来ますように。』と祈ったことを我々はよく考えるべきである。驚くなかれ、その祈りは紀元68年6月9日に叶えられた(※②)。この祈りは、一度叶えられたならば、もうそれ以上祈り求める必要のないものである。しかし、「地上の御国が拡大しますように。」という祈りであれば、それは有効的な祈りである。何故なら、これは地上にある教会が強くなったり数的に増加したりするのを願う祈りであって、そのように祈るのは理に適っているからである。御国が来るようにと祈っても再び御国が開始されるわけではないが、このように祈るのであれば、実際に教会に良い変化が訪れることになるであろう。しかし、私がこのように説明したとしても、まだ多くの人が私の説明を聞き入れず、悟らず、自分の態度を変えようとしないであろう。私も、このような不敬虔な態度を多くの人が取るのは自然であることを認めるのに吝かではない。何せ、このように祈るのはキリスト教会の常識であって、今まで2千年もの間、あらゆる聖徒たちが『御国が来ますように。』と祈るのを義務としてきたからである。これは、「キリスト教とは何か?」と尋ねられたら、「『御国が来ますように。』と願う宗教である。」と答えてもいいぐらいのことである。つまり、それほどまでにこの祈りとキリスト教における常識的な見解は強く結びついている。それゆえ、たとえこのように聖書から説明されたとしても、一日一夜で多くの聖徒たちが自分の考えを変えられるとは思われない。アウグスティヌスやルターでさえ、私の言ったことを受け入れるまでには多くの時間を要するであろう。もちろん、神が働きかけて下さるのであれば、一瞬の間に、実に多くの人たちが自分の考えを変えることになるのは間違いないことではあるが。確かに多くの人は、私に対して「何を言われるのですか。主が祈れと言われたのだからこのように祈らなければいけないのです。」と言うであろう。もちろん、主が『御国が来ますように。』と祈るよう当時の聖徒たちに命じられたのは私も知っている。しかし、主が当時の聖徒たちに祈れと命じられたからというので我々も祈らねばならないとすれば、『ただ、あなたがたの逃げるのが、冬や安息日にならぬよう祈りなさい。』(マタイ24章20節)という命令も、我々は行なうべきであろうか。もし主が当時の聖徒に命じられたことは何であれ我々もしなければいけないとすれば、当然ながら、この命令も我々は行なわなければいけないことになる。マタイ24章がまだ実現していないと勘違いをしている聖徒であれば、尚のこと、そのようにしなければならない。すなわち、我々、ことにマタイ24章がこれから起こると勘違いをしている聖徒たちは、本当に心から日々「私たちの逃げるのが冬や安息日にならないようにして下さい。」とキリストが命じられたように祈らなければいけないことになる。しかし、こんなことを祈っている聖徒を、私は今まで一人も見たことがない。多くの教会は、こんな祈りを唱えることさえしないであろう。もし唱えるとすれば、私はもう既に、そのような教会や聖徒のことを知っていたはずである。このように聖徒が祈らないのは、無意識的にこのように祈るべきではないことを感じているからに他ならない。実際、このマタイ24章の箇所は既に説明されたように紀元1世紀当時のことを言った箇所だから、当時の人には当てはまっても、今の時代に生きる我々には当てはまらないことが多かれ少なかれある。主がこのように祈れと言われたのはユダヤ戦争の恐るべき時期を念頭に置かれてのことだったから、その戦争が終わってからは、もはや冬や安息日に逃げることにならないようにと祈る必要はなくなったのである。誰がこのことを疑うであろうか。これは当時のユダヤ人と聖徒たちだけが祈るべきだったものである。このマタイ24章の命令を当時の時代背景を弁えつつ考慮するならば、もう我々がこの主の命令を行なわなくてもよいということは確かである。つまり、この祈りは主が『祈りなさい。』と言われたにもかかわらず、我々はその命令に従って祈らなくてもよい。たとえ祈らなかったとしても罪にはならない。むしろ、そのように祈るのは知識と理解の欠けを露呈することであり、神に対して荒唐無稽な祈りを捧げることである。であれば、時代背景を弁えつつ聖句を考慮すべき我々にとって、『御国が来ますように。』という祈りの条項もマタイ24:20の箇所と同様に既に祈らなくてよくなったということになる。何故なら、―重要だから繰り返すが―御国は既に紀元1世紀に来たからである。しかしながら、その他の主の祈りの条項は、たとえ時代背景を考慮したとしても、まだ我々にとって祈るべき義務となるものである。何故なら、それらの条項は今の時代にも問題なく当てはまる普遍的な内容だからである。確かに、今の時代でも主の祈りそのものを祈るべきであるということは、紀元1世紀の時代と何も変わらない。というのも、この祈りは「型」というべき祈りの模範であって、主がそのように祈るべきだと我々に教えて下さっておられるからである。だが、そのうち2番目の項目だけは既に完全に成就したのだから、そのことを弁えて、我々はこの2番目の項目を言い換える必要がある、というのが私の言いたいことである。私は何も主の祈りそのものを否定しているわけではない。ただ2番目の項目を聖書的に考察した上で今の我々には言い換えが必要となっている、と主張しているだけである。そのように言い換えれば、何も問題はなくなるし、聖書の教えともよく調和することになる。読者の方は、私が愚かにも何か勝手な変更を理性の思いに基づいて提案しているのではないということを、よく理解してほしい。
(※①)
例えばルターが次のように祈ったのと同じようにして祈るのがよいと思われる。「み国が来たり、広がりますように。悪魔によって盲目となり、悪魔の国にとらえられているすべての罪人が、み子イエス・キリストに対する正しい信仰の知識をとらえ、キリスト者の数が大いに増加しますように。」(『ルター著作集 第1集6』ドイツミサと礼拝の順序 p438:聖文舎)
[本文に戻る]
(※②)
アウグスティヌスは、この祈りの項目について、こう言っている。「「御国を来らせ給え」。わたしたちは誰に言っているのでしょうか。もしわたしたちが願い求めなければ神の国は来ないのでしょうか。なぜなら、世の終りの後で到来するであろう神の国について言われているからであります。」(『アウグスティヌス著作集21 共観福音書説教(1)』説教56 6 p108:教文館)アウグスティヌスであれ他の教師であれ、再臨の日に世が終焉を迎え、その時に御国が到来するという理解では、誰もが一致している。何故なら、主がマタイ16:28の箇所で、再臨と共に御国が到来すると言っておられるからである。既に説明されたように再臨は紀元68年に起きた。その時に古い世が終わり改まった。だから、その年に御国が到来したことになる。このように、再臨が既に起きたと考えると、御国も既に到来したと考えざるを得ないが、そのように考えるのは聖書の言葉に基づいた論理的な結果であるから、何も間違ってはいない。
[本文に戻る]
再臨の起きたこの日には、世の改まりが起こった。それは、キリストが栄光の座に着かれる再臨の日について『世が改まって人の子がその栄光の座に着く時、…』(マタイ19章28節)と言われていることから分かる。再臨が起こると世が改まり、世が改まるというのはその日に再臨が起きたことを意味する。確かに紀元68年6月9日には、再臨が起こり、復活と空中の審判も起こり、天上の御国がスタートし、死と地獄の形態も大いに変わることになった。またこの日には『見よ。まことにわたしは新しい天と新しい地を創造する。』(イザヤ65章17節)という預言も成就された。このようなことが起きた大いなる特別な日に、世界が改まったことを認めない人があるであろうか。この日こそ、正に世が改まったと言うに相応しい日である。もしそう言うべきでないとすれば、一体いかなる日が世の改まりと呼ぶに相応しい日なのであろうか。まさか、この日以上に凄まじい出来事が多く起こる日があるなどとは誰も言うまい。確かに惨めな人間の矮小な理性によっては、この日に世が改まったことは認め難いかもしれない。しかし、聖書はキリストの再臨の日に世が改まると明白に教えている。その再臨は紀元68年6月9日に起きた。それゆえ聖書を己の規範とする神の聖徒たちは、再臨の起きたその日こそ世が改まった日であると信じなければいけない。
世が改まったこの再臨の日こそ、世界が終わった日である。一体どうして、こう言えるのか。これは今のキリスト教界にとっては非常に重要なことであるから、先入観や偏見を捨てて、聖書に立ちつつじっくりと考察してもらいたいと思う。神の言葉を直視しない者は、再臨に関する真理を悟ることが出来ないであろう。まず世が既に紀元1世紀に終わったということは、マタイ24:1~3の箇所から証明できる。第1部で見たように、ここでは主が神殿崩壊について言われたことに対し、弟子がその時に起こる前兆を主に尋ねている。この弟子はこの神殿崩壊が起こる時期こそが、『
(※)
例えばルターは、度々これから終わりが来るとか、今が世の終わりだとか平気で言っていた。再臨のことを何も理解できていなかったからである。次の文章はそのうちの一つである。「われわれは、終わりの日にわれわれがなりたいと望んでいるような完全な聖人に、まだなっていない。そして、神は、死によって、われわれを聖めることを始められ、われわれは炭とちりになるが、終わりの日の火が来て、すべてを聖めるのをわれわれは待たなければならない。それだから、墓の中の腐敗によっては、われわれは、傷も染みもないほどに聖くならない。その終わりの日が来ると、われわれは明るい太陽のように、まさに天使のようになるのである。しかし、そのようなことはまだ起こっていない。それが起こるまで、われわれは今それを信じて待ち、それを望みつつ死ぬのである。そして、われわれは、この地上で、そのことを知って、信じて生きており、古いアダムが完全に聖められるのを待ち望んでいる。」(『ルター著作集 第二集6 ヨハネ福音書第1章・第2章説教』第21説教 第2章(24―25)p397 LITHON)世界信条の一つであるカルケドン信条では、「この終わりの時代には、主は我らのためにまた我らの救いのために、神の母である処女マリヤより生まれ給うた。」と言われている。この信条を作成した者たちも、この信条が作成された紀元451年10月が正に終わりの時代であると理解していた。アウグスティヌスもカルケドン信条と同様の理解であった。彼もキリストの時代から再臨が起こるまでの期間が「終わりの時代」であると考えていた。しかも彼はこのように考えて少したりともおかしいとは思わなかった。再臨は主の御言葉の通りに当時の弟子たちが生きている時に起こったのであるが…。更に酷いことにアウグスティヌスは、この終わりの時代を終わらせる「最後の日」が「ずっと先」(『アウグスティヌス著作集24 ヨハネによる福音書講解説教(2)』第52説教 7 413年 p386:教文館)に「来るはず」(同)だと考えていた。このように終わりの日がずっと後に来ると考えるのは、聖書の否定である。何故なら、ペテロが『万物の終わりが近づきました。』(Ⅰペテロ4章7節)と言っていることからも分かるように、聖書は明らかに終わりの日が「間近に」「すぐに」起こると教えているからである。つまりこの教父は聖書が言っているのと真逆のことを言っているのだ!このことからも、アウグスティヌスが終わりの時代や終わりの日について、何も正しい理解を持てていなかったことが分かる。ちなみに、このことについてはカルヴァンも「キリスト示現までの長い時日」(『新約聖書註解ⅩⅠ ピリピ・コロサイ・テサロニケ書』Ⅰテサロニケ1:3 p176:新教出版社)とか、「この日が遠い」(同 5:4 p220)などと言って致命的な誤りを犯している。彼も「再臨が起こる終わりの日までの期間は短い」と言われた聖書にまったく反したことを言っていたのだ。彼は、どうやらキリストが『わたしは、すぐに来る。』(黙示録3章11節)と言っておられたのを知らなかったようである。もしカルヴァンの言ったことが正しいとすれば、キリストは「わたしが来るのは遥か未来のことであって「すぐ」ではない。」と言っておられたであろう!蛇足になるが、ルターは終わりの日が「遠い」とは言わない点では(彼は度々「近い、近い」と言っている)、カルヴァンよりはましであった。ちなみに、ベルナルドゥスも主の日が来るまでの時間が「それは長く、余りにも長すぎる時間である。」(『キリスト教神秘主義著作集2 ベルナール』雅歌の説教74 4 p298:教文館)などと御言葉で言われているのと異なることを言っている。トマス・アクィナスも「だが、「世の成就」は、『マタイ福音書』第13章にいうごとく、世界の終りにおいて齎らされるであろう。」(『神学大全Ⅴ』Qu.73,art.1 p119 創文社)という彼の文章から分かるように、まだ世の終わりが訪れていないと信じていた。エイレナイオスも、まだこの世の終わりが来ていないと信じていた。彼は次のように言っている。「この世の終わりの時には、火によってなされる裁きが、信じなかった人々にとっての滅びとなるであろう。」(『中世原典思想集成1 初期ギリシア教父』使徒たちの使信の説明 69 p250:平凡社)カルヴァンも天使の階級と人数について論じている箇所で、その天使の階級と人数における「完全な啓示は終わりの日まで延ばされていると信じよう。」(『キリスト教綱要 改訳版 第1篇・第2篇』第1篇 第14章 8 p185:新教出版社)と書いているから、他の者たちと同様に未だに終わりの日は訪れていないと考えていたことが分かる。彼は他の箇所でも、「我々の待ち望む終わりの日」(『キリスト教綱要 改訳版 第3篇』第3篇 第25章 第7節 p518:新教出版社)などと言っている。このカルヴァンは、終わりの日の時間的な範囲について次のような理解を持っていた。「そういうわけで、キリストがご自身の福音を我々に宣べ伝えるために現われたもうて以来、裁きの日までが、終わりの時刻、終わりの時、終りの日として規定されるようになった」(『キリスト教綱要 改訳版 第4篇』第4篇 第8章 第7節 p165:新教出版社)。テルトゥリアヌスも、教会が「この世の終わりに…平安を再び取り戻されるのである。」(『中世思想原典集成4 初期ラテン教父』洗礼について 第12章(7) p57:平凡社)と言っており、まだこの世の終わりが到来していないと信じていた。ポワティエのヒラリウスも「この贈り物は、世の終わりまでわれれとともにあり、…」(『中世思想原典集成4 初期ラテン教父』三位一体論 第2巻 35 p500:平凡社)と言っているから、まだ世の終わりが来ていないと考えていた。キリストが既に再臨されたのだから、既に古い世も終わって改まったことになるのであるが…。アンブロシウスも「来たるべきこの世の終わりについては、…」(『中世思想原典集成4 初期ラテン教父』エクサメロン 第1巻 第3章 10 p557:平凡社)と言っている。ヒエロニムスもダマススに対して「あなたはというと、世の終わりには、あなた自身のために、反キリストとしての子山羊を犠牲にしようとすることでしょう。」(『中世思想原典集成4 初期ラテン教父』書簡21(35) p666:平凡社)と書き送っている。このように、多くの教師たちや信条の制作者たちは、終わりの日が既に過ぎ去ったと言わないことにより、自分たちが再臨に関する領域においては盲人であったことをみずから示しているのである。
[本文に戻る]
ここで、『世の終わり』という言葉の意味について、更に詳しく論じておきたい。この言葉は、非常に重要であり、聖書では頻繁に見られる言葉である。それゆえ、この言葉は、是非とも正しく理解しておかねばならない。そうしなければ、聖書全体の理解に大きな悪影響が生じることにもなりかねない。今まで教会は、この『世の終わり』という言葉を、文字通りに捉えてきた。すなわち、この地球全土が文字通りの意味で破滅すると今まで考えられ、また主張されてきた。これは今までに書かれた神学書を読めば、分かることである。例外と呼ぶべき人はいなかったと言ってよい。アウグスティヌスもルターもカルヴァンも、そうである。この文章を読んでいる読者も、そうであるに違いない。だから、今まで教会は『世の終わり』がこれから来て、全世界が大変なことになるということについて何の疑いも持たなかった。それは、聖書の多くの箇所で『世の終わり』が訪れると書かれているからである。しかし、世が終わる、世が終わる、などと力強く言いはするものの、黙示録については何も理解できていなかった。カルヴァンも、黙示録の註解書を書くことが出来なかった。この黙示録とは、少し読めば誰でも分かるように、世の終わりについて預言された文書である。世の終わりについて熱心に語りながら、世の終わりについて預言している黙示録を理解できていないとは、どういうことであるか。それは世の終わりについて、よく理解できていないということである。何故なら、もし世の終わりがよく理解できていたとすれば、世の終わりについて預言されている黙示録を豊かに理解することができていただろうから。私は言うが、今まで教会は、この『世の終わり』の理解を誤っていた。これはハッキリと断言できる。どうして断言できるのか。それは私が聖書を研究し、再臨に関わることを深く思索しているからである。研究と思索のゆえに、私はこのように言うことができる。しかし、今まで教会は、この言葉について研究と思索が足りていなかったと私には思われる。だからこそ、これまで『世の終わり』について教会は誤り続けてきたのだ。さて、『世の終わり』とは、文字通りに全世界が終わるというのではない。これは「ユダヤ世界における世が終わる」ということである。マタイ24:1~3の箇所を見ると、エルサレム神殿の崩壊する時期に『世の終わり』(マタイ24章3節)が訪れると言われていることが分かる。このマタイ24章が、ユダヤ戦争についての預言を書き記した箇所だということについては既に語られている。これはエドワーズも、そう考えていたことである。エルサレム神殿の崩壊した時にユダヤが破滅したというのは、歴史の事実であって、愚か者でもない限り疑う人は誰もいない。つまり、マタイ24章を読むと、ユダヤの破滅が『世の終わり』と言われていることが理解できる。要するに、世が終わるとはユダヤのことなのだ。このユダヤの破滅は、スエトニウスが「ローマ皇帝伝」の中で書いているように、紀元70年9月2日であった。それは使徒時代の聖徒たちにとって間近に迫っていた。もう数十年もすれば、ユダヤ世界が滅ぼされて、神から完全に見放されてしまう。だからこそ、使徒たちは「世の終わりが近い」と言ったわけである。ペテロはその手紙の4章7節でこう言っている。『万物の終わりが近づきました。』このようにペテロが言ったのは、もう少しでユダヤが終わりを迎えるからである。つまり、これは「ユダヤにおける万物の終わりが近づいた。」という意味である。それでは、ペテロが次のように言ったのは、どういう意味か。『キリストは、世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時に、あなたがたのために、現われてくださいました。』(Ⅰペテロ1章20節)これは、ユダヤが終わりを迎える時期にキリストが、この世に来て下さった、という意味である。確かにキリストはユダヤの世界が破滅する70年ぐらい前に降誕されたのだから、「終わりの時に現われて下さった。」とペテロが言ったのは間違っていない。ではパウロがコリント人にこう言ったのは、どういう意味か。『この私たちに世の終わりが来ています。』(Ⅰコリント10章11節)これは、もう間もなくキリストの再臨に伴うユダヤの破滅が訪れる、という意味である。パウロがこう書いてからユダヤは数十年後に終わったのだから、これは何もおかしいことではない。これ以外に『世の終わり』について書かれている箇所でも、私が今言ったのと同様のことが言える。もし今まで教会がそう考えてきたように、この『世の終わり』という言葉が文字通りに捉えるべき言葉であり、西暦2020年になった今でもまだ世が終わっていないと理解せねばならないとすれば、大きな問題が生じる。何故なら、聖書では世の終わりがすぐに来ると教えられているのに、2000年経過してもまだ世が終わっていないことになるからである。これは明らかにおかしいと言わねばならない。聖徒たちも、世の終わりが近いと聖書で教えられながら2千年も実現していないことについて、いくらかでも違和感を持っているはずだ。「確かに違和感がある。」などと口に出しては言わないだろうが、実はちょっと微妙に感じているはずだと私は思う。つまり、多くの聖徒たちは無理をして、世の終わりがすぐにも来ると信じている。私が「世の終わりはすぐに来た」と言うと、それを受け入れられない聖徒たちは「いやいや、神にとっては千年も1日のごとし、だ。神にとっては数千年の期間も<すぐ>なのだよ。」などと言うのを常にする。しかし、この反論は根拠に乏しい。まず千年も神にとっては1日のごとしと言われたⅡペテロの箇所から終末を神の感覚により捉えるべきだとは言えないし、聖書の多くの箇所から世の終わりは紀元1世紀に実現したと証明できるからである。確かにキリストもパウロも、当時の聖徒たちが生きている間に再臨が起こると断言したのだ。そうであれば、世の終わりも紀元1世紀に起きたことになろう。というのも、再臨と世の終わりとはセットだからである。一方、私が今述べたように『世の終わり』という言葉が「ユダヤ世界の終わり」を意味していると理解すれば、何も問題は起こらない。確かにマタイ24章の中では神殿の崩壊する時が世の終わる時であると言われているし(これは決して疑えない)、使徒が言った通り、本当にユダヤの世はすぐにも終わりを迎えたからである。このように世の終わりがユダヤのことだと考えると、全てがスッキリと理解できるようになることに気付かないであろうか。私の『世の終わり』に対する見解のほうが、今までの教会の見解よりも聖書的であり正しいのは、火を見るよりも明らかである。
第6章 ④エルサレムの包囲と滅亡(紀元68年6月9日~70年9月)
まず、この時期に悲惨がユダヤにもたらされた歴史的な背景を、いくらか見ていきたい。一体どのようにして、ユダヤは危難に陥ったのであろうか。当時のユダヤ人は、宗主国であるローマの支配に屈しており、そのため不満を抱いていた。彼らはローマにとっては非常に反逆的だと思われる言わば不良的な存在であった。ユダヤ人たちは、いつもローマに従順な姿勢を見せることがなかったのである。そのようなユダヤ人はローマのくび木を取り除けようと前から暴動や問題ばかりを起こしていたのだが、60年代に入ると、彼らの反逆的な態度が一定の線を越えてしまった。シリア州のローマ総督であったフロールスとケスティウスをユダヤ人が打ち負かしたのである(ユダヤ戦記2巻)。この知らせを聞いたネロは「密かなる驚愕と恐怖に襲われた」(『ユダヤ戦記2』Ⅲ i1:1 p013:ちくま学芸文庫)とヨセフスは言っている。しかしネロは動じつつも獣のように発奮した傲慢なユダヤ人を鎮圧すべく、ユダヤの地域に軍隊を遣わすことを決定した。この時に任務を任されたのが、後の皇帝ウェスパシアヌスである。彼は「若いときから軍功とともに齢を重ねてきた」(『ユダヤ戦記』第3巻/i2:4)のでユダヤ制圧の任務を帯びるに相応しいと見做された(※①)。このウェスパシアヌスは自分の子であるティトゥス(彼も後に皇帝となる)にローマ軍を率いらせ、ユダヤ鎮圧のために彼を属州ユダヤへと送り込んだ。そうしてこのティトゥス率いるローマ軍が、ユダヤを取り囲み、あの有名なユダヤ戦争が勃発することとなった―それはネロの治世の第12年目であった(※②)。これは今に至るまで語り継がれることになる注目すべき戦争であった。このようにネロを原因として、ユダヤ戦争が始まったかのように感じられるが、ネロがユダヤ鎮圧を命じたということは、元はといえばサタンがネロに働きかけたからに他ならない。確かにネロがサタンの働きかけにより邪悪な存在として登場したというのは、既に第1部で我々が見た通りである。つまり、ユダヤの滅亡はネロというよりは、サタンを第一の元凶として発出したものだということである。要するにサタンがユダヤの滅亡を望んだがゆえに、自分の強い支配の中にいるネロを通して、その望みを実現させようとしたということである。これはサタンがユダを通してキリストを敵に渡されるようにしたのと同じである。またサタンがこのような望みをネロを通して実現させたということは、神がその望みの実現を許可されたということを意味する。何故なら、サタンが何を望もうが、神の許可なしには何も起こらないからである。それは、ヨブ記において、サタンが神の許可によりヨブを打つことができたのを見ても分かる。キリストも『雀の一羽でも、あなたがたの父のお許しなしには地に落ちることはありません。』(マタイ10章29節)と言っておられる。それでは神がサタンの望みを許可されたのは一体どうしてなのか。それは、神の御心が実現するためであった。神がユダヤの滅びを望まれたからこそ、サタンのユダヤを滅ぼすという望みが、許可されたのである。またネロとその周りの者たちの心にユダヤを滅ぼすという望みが生じたのも、神が働きかけられたからであった。それはネロと周囲の者たちがユダヤを滅亡させる望みを持ったのは、神が『神のみこころを行なう思いを彼らの心に起こさせ』(黙示録17章17節)られたからであると言われている通りである。つまり、神がユダヤの荒廃を欲し、そのためにサタンとネロたちがユダヤの荒廃を欲するようになり、そのようにしてユダヤに悲惨がもたらされることになったということである。さて、このユダヤとローマの注目すべき戦争は、最初から勝敗が決まっていたような戦争であった。ローマ軍と言えば世界最強の軍隊として有名であった。ローマ兵らは、休みらしい休みも取らず、激しい訓練で流した汗を川で一生懸命泳ぐことにより洗い流していたほどであった。当時のローマ軍は「実戦であるかのように訓練し、訓練するかのように実戦した」。モンテスキューは、彼の時代の兵士に見られたなよなよしさと古代ローマ兵の屈強さにおける違いの理由を、この休息に見出している。つまり、休むことさえ必要としないほどに当時のローマ兵は力に満ちていたというわけである。モンテスキューの時代の兵士は、しっかりと休みを取ったので、それが屈強さの欠如を招いたとモンテスキューは述べている。ヨセフスの場合、ローマ兵の屈強さは「とくに命令への服従と武器使用の訓練の賜物である」(『ユダヤ戦記Ⅰ』Ⅱ xx7:577 p395:ちくま学芸文庫)と言っている。このヨセフスはローマ軍について次のようにも書いている。「なぜなら、ローマ人たちは戦争になってはじめて武器を手にするのではないからである。彼らは平時に漫然と生活し危急のときにはじめて手を動かすというのではなく、あたかも武器を手にして成長してきたかのように、訓練の手を休めることは決してなく、とって実戦さながらの激しいものである。兵士一人ひとりが日々、戦場におけるかのごとくに、全勢力を傾注して訓練に励んでいる。そのため彼らはどんな戦闘にもやすやすと耐えることができる。彼らは訓練時の隊形を崩して逃げ出すことはなく、恐怖におののいて大混乱に陥ることもなく、またどんな労苦にも疲れ果てることはない。その結果、しっかりとした訓練を受けていない者たちを相手にすれば、勝利がつねにローマ兵たちに舞い込む。実際、彼らの軍事訓練を流血抜きの戦闘、戦闘を流血の軍事訓練と呼んだとしても、それはあながち間違いではないであろう。」(『ユダヤ戦記2』Ⅲ v1:72~75 p028:ちくま学芸文庫)ヨセフスがこのようなローマ兵たちは「全世界とでもいうべき世界を支配している」(『ユダヤ戦記』2巻/xx7:580)と評したのは決して言い過ぎではなかった(※③)。一方、このように屈強なローマ兵と戦うユダヤ人はといえば、戦いだというのに愚かにも仲間割れをしており、戦争をするに相応しい状態にすらなかった。一致を保っていない上に、最強のローマ軍が相手であるのだから、負け以外にはあり得ない状況がそこにはあった。しかし実際には驚くべきことに、ユダヤ人たちはいくらかローマ兵に善戦することができた。技術力や統率力やチームワークではローマ軍にまったく及ばなかったが、しかしユダヤ人たちの持つ猛獣のような勢いが、ローマ軍とまともな戦いをさせることになった。ローマ兵たちはこのユダヤ人の無謀とも言うべき恐れ知らずの勢いに、かなり手こずらされ、いくらか怯みもした。これは激しい勢いのネコが大型の獅子に飛び掛って大慌てさせるようなものであったと言ってよい。ヨセフスはこの時の戦いについて次のように書いている。「ユダヤ人たちはしばしば城門から打って出て白兵戦を挑んだ。彼らはローマ軍の戦術に不慣れなため、接近戦では城壁に押し戻され敗北を喫したが、城壁の上からの戦闘では優勢だった。兵力に裏付けられた経験がローマ兵たちを勇気づけ、恐怖に育まれた大胆さと、災禍に直面したときに発揮される生来の不暁不屈の精神がユダヤ人たちを支えた。ユダヤ人たちは救いの望みをまだもちつづけ、逆にローマ兵たちは速やかな制圧を望んでいた。そのため、双方は倦むことなく戦い、終日、城壁での戦い、隊伍を組んでの出撃などが繰り返された。あらゆる種類の交戦方法が用いられた。戦闘は夜明けとともにはじまったが、夜になってひと息つくということはほとんどなかった。双方とも不眠不休で、昼間より苛酷だった。一方は城壁が攻め落とされるのではないかと四六時中恐れ、他方はユダヤ人たちが陣営に侵入してくるのではないかと恐れた。そのため双方とも、武装したままで夜を明かし、最初の曙光のもとで戦闘準備を整えた。」(『ユダヤ戦記2』Ⅴ vii3:305~308 p332~333:ちくま学芸文庫)しかし、最終的には洗練された戦争の技能がモノを言った。やはりと言うべきであろうか、ローマ軍はユダヤ人たちを完全に屈服させるに至ったのである。これはあたかも子どもが大人に立ち向かうようなものだから、当然のことであった。神が働いて下さったのであれば、『たぶん、主がわれわれに味方してくださるであろう。』(Ⅰサムエル14章6節)と言ったヨナタンと道具持ちのように少人数であってもユダヤに勝利がもたらされたであろうが、神はこの時ユダヤに味方しては下さらなかった。神はユダヤ人と共におられず、むしろユダヤ人が敗北させられるのをお望みになったのである。神はローマに勝利を、ユダヤに敗北を与えられた。
(※①)
ヨセフスはこう書いている。「ネロンはこれらの軍功を幸先のよいしるしと見なし、経験と年齢からくる安定さを買い、その子息たちはウェスパシアヌスの忠誠心を保証する大きな人質となり、その働き盛りは父親の思い通りの手足となることを見て取ると―神は、多分、このときすでに帝国の未来を先取りして経営されておられた―、この危難にさいして必要なその気にさせる賛辞を浴びせてご機嫌を取った後、ウェスパシアヌスをシリアに駐留する軍団の指揮権を取らせるために遣わした。」(『ユダヤ戦記2』Ⅲ i3:6~7 p014:ちくま学芸文庫)
[本文に戻る]
(※②)
「戦争が勃発したのは、ネロン帝統治の第12年、アグリッパス王の第17年のアルテミシオスの月(66年5月ころ)だった。」(ヨセフス『ユダヤ戦記Ⅰ』Ⅱ xiv4:284 p320:ちくま学芸文庫)
[本文に戻る]
(※③)
とはいっても実際にはローマ帝国の境界は「東はエウフラテス、西は大西洋、南はもっとも肥沃なリビア、そして北はイストロスやレノス川」(『ユダヤ戦記2』Ⅲ v7:107 p036:ちくま学芸文庫)であった。つまりローマが世界を支配していたと言えるのは、あくまでも慣用的な意味においてだけである。もちろん、当時の世界観は非常に狭かったので、その慣用表現がすなわち実際的な意味であると無意識的に見なされていたのではあるが。
[本文に戻る]
このユダヤに対する悲惨は、神の裁きであった。我々は、これを単なる戦争による悲劇に過ぎないものだと捉えるべきではない。何故なら、聖書が、このような悲惨が起きたのは神の裁きのゆえであったと教えているからである。聖書の子である者は、聖書の教えるように、これが神による災難であったと考えなければいけない。考えていただきたい。当時のイスラエルはどのような状態であったか。それは、神の前に堕落した状態、忌まわしい状態、投げ捨てられるべき状態であった。紀元1世紀のユダヤでは、あの神の神殿の中で、本来であれば為されるべきでなかった商売が堂々と行なわれていた。そこには何と『牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちがすわって』(ヨハネ2章14節)いた。キリストが言われたように、彼らは神の家を『商売の家』(同16節)としていたのである。また当時のユダヤ人を指導していた指導者たちは、神の戒めではなく人間の戒めにこだわってそれを行ない、霊的にまともだとは言えなかった。そのため彼らは、『こうしてあなたがたは、自分たちの言い伝えのために、神のことばを無にしてしまいました。』(マタイ15章6節)と主から言われてしまったのである。しかも、彼らは偽善に満ちており、ただ外面的に民衆からよく思われたらそれでよしとするような精神を持っていた。つまり、心の敬虔に関心を持たず、神のことなどどうでもよくなっていた。イザヤを通して語られた『この民は、口先ではわたしを敬うが、その心は、わたしから遠く離れている。彼らが、わたしを拝んでも、むだなことである。人間の教えを、教えとして教えるだけだから。』(マタイ15章8~9節)という預言は、正に彼らのことを言ったものであった。主がマタイ23章の箇所で、あれほどまでにこの指導者たちを厳しく非難されたのは、理由のないことではなかったのである。また当時のユダヤ人は、ローマの支配を覆そうと願うばかりに、血気盛んな傾向があった。彼らにはローマの支配から抜け出したいという願いが強くあったので、あの使徒たちでさえ、メシアとはローマから社会的な意味において解放して下さるキュロス的な存在なのだと思っていたほどである。それは主が昇天する前の時に、使徒たちが主に対して『主よ。今こそ、イスラエルのために国を再興してくださるのですか。』(使徒行伝1章6節)と言ったことから分かる。このようなユダヤ人独特の自立精神のゆえに―ヨセフスはこれを「孤立主義」と呼んだ―、彼らは宗主国ローマから異端的かつ反逆的な民族だと思われていた。異邦人であったピラトもユダヤ人に対して「お前達ユダヤ人はいつも暴動を好み、お前達に良いことをしてくれる人達に逆らってばかりいる。」(ニコデモ福音書9:2)と言っている。ニコラオスという人も、「この国民は御しがたく、王たちにたいして反抗的だった」(ヨセフス『ユダヤ戦記Ⅰ』Ⅱ vi2:92 p268:ちくま学芸文庫)と言ってユダヤ人たちをカエサルに告発している。しかし、主が言われたように、彼らは暴動を起こしたりするなどして反逆的になるべきではなかった。ユダヤ人らは謙遜になり、『自分を打つ者に頬を与え、十分そしりを受けよ。』(哀歌3章20節)という神の言葉を守るべきであった。また、彼らは自分たちが前から待望していたメシアが遂に現われたというのに、その方を木にかけて殺してしまった。ユダヤ人はメシアの到来をどれだけ待ち望んだことであろうか。確かに彼らはメシアの到来を死ぬほどに待望していた。それなのにメシアがメシアだと分からず、そのメシアを死に追いやってしまったというのは、彼らが霊的に堕落していたことを示すものとして見ていいであろう。もし当時のユダヤに多くの「霊の人」がいたとすれば、メシアを殺すということは恐らくしなかったと思われる。『そして、彼らはみな神によって教えられる。』(ヨハネ6章45節)と預言者は言ったが、もし神に教えられた霊の人ばかりがいたとすれば、どうしてメシアを否んで殺すということがあるであろうか。イスラエルがこのような堕落した状態だったので、主はこの時代を『悪い、姦淫の時代』(マタイ12章39節、16章4節)と呼ばれた。実際、当時のイスラエルは自分の夫である神を捨て、蛇のほうを恋い慕っていたのだから、姦淫していたなどと言われても文句を言えなかった。黙示録においては『大バビロン』『大淫婦』『すべての淫婦と地の憎むべきものとの母』(17章)などと呼ばれてしまうほどに堕落していた。これは驚くべきことである。神に愛された民、選ばれた人々、聖書の筆記人とされた存在であるあのイスラエルが、このような忌まわしい名前で呼ばれてしまったからである。世の人々は、このように黙示録で呼ばれている「都」とはローマであると理解する人が少なくない。クリスチャンの中でも、ユダヤがこのように言われることを理解できない人が少なからずいるかもしれない。しかし、これがイスラエルを指した呼び名だということは、聖句のゆえに疑うことができない。というのは、黙示録でこのように呼ばれている「都」とは、ローマという肉的な理解による都ではなく、エルサレムという霊的な理解による都のことだからである。黙示録11:8では、この都とは、すなわちキリストが十字架につけられた場所であると言われている。すなわち、このように書いてある。『彼らの死体は、霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの主もその都で十字架につけられたのである。』主が十字架にかかられたのは言うまでもなくエルサレムというユダヤにおける都である。ヨハネはその都こそ、ソドムやエジプトと化した邪悪なイスラエルだと言っているのである。もしこの都がローマだとすれば、キリストはローマで磔刑にされたことになるが、実際はそうではなかったので、黙示録で悪く言われている都とはユダヤの都だということになるのである。このように悪い名で呼ばれてしまっていることからも、当時のユダヤがどれだけ腐敗していたかが分かるであろう。また、当時のイスラエルは、今まで流した義人たちの血を神の前に積み重ねている状態にあった。すなわち多くの義人たちの血が、自分たちを殺したユダヤ人に対し、神からの復讐はまだなのかと叫んでいたのである。血が復讐を求めて叫ぶというのは、カインに流されたアベルの血について、神が『聞け。あなたの弟の血が、その土地からわたしに叫んでいる。』(創世記4章10節)とカインに対して言われたことから分かる。エルサレムでは多くの正しい者の血が流されたが、その血がエルサレムに対する報復を願って叫んでいた。ユダヤがこのように異常な状態になっていたので、神の裁きが遂に、この時に至って発動されることになった。これほどまでに多くの裁かれるべき要素が、神の御前に置かれていたのである。だから神の裁きが、この時にユダヤへと注がれたのは自然なことであったと言える。確かにキリストが言われたように、今までに流された血の報復は、この時に至って纏めて当時のイスラエルの上に注がれることになった。それはマタイ23:34~36で主がこう言われた通りである。『だから、わたしが預言者、知者、律法学者たちを遣わすと、おまえたちはそのうちのある者を殺し、十字架につけ、またある者を会堂でむち打ち、町から町へと迫害して行くのです。それは、義人アベルの血からこのかた、神殿と祭壇との間で殺されたバラキヤの子ザカリヤの血に至るまで、地上で流されるすべての正しい血の報復があなたがたの上に来るためです。まことに、あなたがたに告げます。これらの報いはみな、この時代の上に来ます。』しかし、どうして紀元1世紀になるまで、神はユダヤに対する裁きを留保しておられたのであろうか。何故、この時に至ってダムを一気に放出させるかのごとくに裁きのダムを放出させたのであろうか。それは、神が忍耐強く、ご自身の怒りをこの時代に至るまで抑えておられたからである。聖書は神が『怒るのに遅く』(詩篇145篇8節、出エジプト34章6節)あられる方だと教えている。それゆえ、この時になるまでは、まだ罪に対する裁きを下さずに待っておられた。何を待っていたのであろうか。それは彼らが悔い改めて神に立ち帰るようになることをである。しかし、今までに遣わされたご自身の僕たちに酷い仕打ちをされたのには我慢された神であったが、御子が殺されたことには神は我慢されなかった。せっかくご自身の御子が遣わされたにもかかわらず、その御子でさえ酷い目に合わされたのであるから、ここにおいて神の忍耐は限界に達した。神のいとし子を殺されたとあっては、それまでは忍耐強くあられた神も、もはや忍耐を続けることは欲されなかったのである。それゆえ、この御子の殺害により、イスラエルには神の裁きが下されることが確定してしまったのである。この裁きが御子の磔刑からおよそ1世代後に実現されたのが、我々が今見ているユダヤの悲惨のことである。だが、神に愛されたユダヤがこのように厳しい裁きを受けたことを疑問に感じる方も、もしかしたらいるかもしれない。「神はどうしてご自身の選ばれたユダヤを滅ぼしてしまわれたのか?」と。まず神がご自身の民でさえ、もし邪悪に染まっていたならば容赦なく捨てられたり、敵に渡されたり、滅ぼされたりされるお方だというのは、ユダ王国とイスラエル王国の例を考えれば誰でも分かることである。この2つの王国は偶像崇拝を行なって神に反逆し続けていたので、南王国ユダは前585年にバビロンへと捕囚され、北王国イスラエルは前720年にアッシリアへと捕囚されてしまった。これは間違いなく裁きにより引き起こされた悲劇であった。神が、その怒りにより、この2つの王国を敵の手に渡されたのである。このような前例がしっかりあるのだから、我々は紀元1世紀の堕落していたユダヤに大いなる裁きが下されたことを何か不思議に思うべきではない。神は、悪に満ちていたとすれば、ご自身の愛された民に対してでさえ容赦はされない。いや、ご自身が愛された民であるからこそ、かえって他の民よりも大きな裁きをさえお与えになる。というのもユダヤは神に選ばれた民だったのだから、本来的に神に従って生きる義務を負っていたからである。そのような義務があるからこそ、邪悪になった場合、かえって裁きは他の民族に対するものよりも大きくなってしまう。神に対して責任が大きいぶん、神から注がれる裁きの度合いも大きくなるというのは理に適ったことである。それは、普通の人が万引きをしたらそこまで社会的な不名誉を受けずに済むのに対し、大統領や大臣といった地位の高い人の場合は取り返しがつかないほどの不名誉が生じてしまうのと同じことである。義務の度合いと罰の度合いは正比例するのが世の常である。だから、他の民族であればそれほど裁きが下されないことであっても、ユダヤの場合は恐るべき裁きを受けることにもなる。当時のユダヤは考えられないぐらいに堕落していたのだから、これでもかといわんばかりの裁きがユダヤに下されたのは、何もおかしなことではなかった(※①)。彼らは神に選ばれた聖く生きるべき義務を負った民だったのだから、その凄まじい堕落に対して致命的な裁きが下されないのは、あり得ないことだったのである。それゆえ、我々は、ユダヤに対するこの神の裁きは下されて当然のことであったと理解するべきである。
(※①)
ジョナサン・エドワーズも、このように堕落していたユダヤ人たちには、神の恐るべき怒りの裁きが下されて当然だったと考えていた。彼はこの裁きについてこう言っている。「彼らは栄光の主を悪意と残忍な心で十字架にかけ、主に従う者たちを迫害した。彼らは神に喜ばれず、人々に敵対し、悪を重ねて罪を最大まで犯したので、恐ろしい罰がくだり、滅ぼされて、神の眼前から消え去った。神がこれほど嫌悪と怒りを顕わにされたことはなく、その怒りはネブカドネザルの時代と比べてもはるかに大きかった。ユダヤ人の多くが殺され、残った者は地上の最も裏寂れた場所に離散した。彼らは、今日もなお、キリストと福音に対して同じ不信と悪意の精神を持ち、惨めな離散状態に留まっている。」(『ジョナサン・エドワーズ選集3 原罪論』第1部 第1章 p106:新教出版社)
[本文に戻る]
この裁きの時に、ユダヤのエルサレムにもたらされた悲惨は誠に凄まじかった。まず、ユダヤ人たちは外部から食糧を補給していなかったので、大量の餓死者が出た。人々は、まともな食糧がないので、木の皮、草、靴、更には自分の幼子でさえも口にしなければいけなかった(幼子を食べた事件については「ユダヤ戦記」第6巻/iii3:208~213に書かれている)。街に空腹でお腹の膨らんだ人が多く見られた。この時には「下水溝をあさり、古くなった牛の糞を探し、それに交じっている籾殻を口にする者さえいた」のであって、「かつては見るも汚らわしかったものが、そのときは食べ物になった」(『ユダヤ戦記2』Ⅴ xiii7:571 p390:ちくま学芸文庫)のである。1メトロンの穀物が1タラントで売られることにもなったが、これは非常に大まかに言えば手で掴めるぐらいの量の小麦が6000日分の給料によって買われるということである(1タラント=6000デナリ=6000日分の給料)。空腹で気のおかしくなった一部の狂暴な男たちが、食糧を探して家々に入り込み、食糧を隠しているかどうか尋ねたが、あれば取り上げ、嘘をついていると見做した時はその家の者の尻の穴に「ひよこ豆」を流し込んで告白するまで大いに苦しめた。これは誠に苛酷な拷問であり、大きな叫び声が響き渡ったという(※①)。母親が自分の煮た幼子を皆と一緒に食べようとして笑顔で勧めたが、流石にこれは他の人たちに遠慮されたようである。この時の悲惨についてヨセフスはこう書いている。「他の場合ならば敬意を払われて当然のものが、このような状況では軽視された。妻は夫から、子供は父から食べ物を奪い取った。もっとも悲惨だったのは、母親が自分の幼子の口から食べ物を奪い取る光景だった。彼女たちは最愛の子が自分の腕の中で息を引き取ろうとしているときでも、その生命に必要な最後の一片の食べ物を奪うことをためらわなかった。人びとはこうして糧を漁ったが、監視の目を逃れることだけは難しかった。叛徒たちが至る所にこれらの者たちの略奪物をもって姿を見せたからである。閉め切った人家があれば、それは叛徒たちにとって中の者が食べ物にありついている証拠だった。そこで彼らは即刻戸口を打ち破って押し入り、家人の喉を絞めんばかりにして、わずかばかりの食べ物を吐き出させた。老人たちは殴打されても食べ物を手放さず、女たちは髪の毛をつかまれて引きずり回されても、掌中に隠し持ったものを手放さなかった。白髪の者にも幼子にも憐憫の情はまったくかけられなかった。実際、叛徒たちは一片の食べ物を握りしめている幼子を抱き上げると、地面にたたきつけたりもした。叛徒たちの闖入を予期して略奪されそうな食べ物を呑み込んだ者たちもいたが、彼らはそういう者たちにたいして不正を働かれたと考えて一層残酷になった。」(『ユダヤ戦記2』Ⅴ x3:429~434 p361:ちくま学芸文庫)「飢えはますます深刻となり、市民たちを家ごとに、あるいは一族ごとに呑み込んでいった。屋上という屋上は赤子を抱えるぐったりとした女たちで溢れ、路地という路地は年老いた者たちの屍で埋まり、栄養失調で腹の膨れ上がった子供や若者たちが市場の中を幽霊のように徘徊した。力尽きてそこに倒れる者もいた。」(同 xii3:512~513 p377~378)「都の中では飢えのために無数の者が次つぎと倒れていったが、その災禍は言葉では言い尽くせぬものだった。どこかに食べ物のある気配でもすれば、どこの家でも戦争があった。もっとも親しい者たち同士がほんのわずかの命の糧をめぐって奪い合いをした。瀕死の者でさえ食べ物を隠し持っているのではないかと疑われた。そのため、野盗たちは最期の息をしている者たちをさえ調べ上げた。衣服の下の胸の辺りに食べ物を隠して死んだふりをしているのではないかと疑ったからである。彼らは、飢えのために、狂った犬のように口を開け、家の戸口を泥酔漢のように激しく叩き、どうしていいか分からず、そのため同じ家に1時間たらずのうちに2度も3度も入り込んでくる始末だった。あまりの空腹に耐えかねて、人びとは手に入る者は何でも口に入れ、理性のない生き物のうちでもっとも汚らわしい獣でさえ口にしない物を拾い集めては食べたりした。そして最後には、皮の帯や下履きを口にするようになり、長楯の革ひもを引きちぎっては噛み砕いて食べた。一部の者たちには一握りの古くなった干し草が食べ物だった。実際、干し草を拾い集めては、一束4アッティカ・ドラクメーで売る者もいた。」(『ユダヤ戦記3』ⅤⅠ i3:193~198 p048~049:ちくま学芸文庫)また、その時にはローマ軍に勝つために、女性さえも自ら武器を取って戦うほどであった。また、ローマの強力な破城錘がエルサレムの城壁を打ち破ろうとして何度も城壁にぶつかったので―この城壁は堅固だったのでウェスパシアヌスも悩まされた―、全エルサレムを心身ともに震撼させた。城壁を破壊されたら最後、ローマ兵がエルサレムに流れ込んで来るからであった。タキトゥスはこの城壁について言う。「神殿は要塞の如く固有の塁壁を持ち、塁壁は費やした労力と工夫を凝らした技において他に類を見なかった。神殿を囲む柱廊ですら、実に見事な防御施設であった。」(『同時代史』第5巻 12 p275:筑摩書房)この堅固極まりない城壁を壊そうとした破城錘は「雄羊」と呼ばれるが、これについてヨセフスはこう書いている。「この装置は船の帆柱に似た途轍もなく大きな桁で、先端が雄羊の頭の形をした―そこから「雄羊」と呼ばれている―鉄のかたまりで補強されていた。その槌は、天秤の竿のように、もう1本の横桁の中央部分で網で吊るされ、その横桁の両端は(土中に)打ち込まれた縦木で支えられている。「雄羊」は大ぜいの男たちによって後方に牽引され、次に男たちがまたひとつとなって前方に押し出すと、先端に突出している鉄のかたまりが壁に一撃を加えるのである。そのためどんな堅固な塔やどんなに厚い壁も、最初の一撃に耐えられても、続けざまに打たれればそれに耐えることはできない。ローマ軍の指揮官がこの手段に訴えたのは、ユダヤ人たちがおとなしくしていないことと相俟って包囲が思うようにいかなかったからであり、また何としてでも町を陥落させたかったからである。」(『ユダヤ戦記2』Ⅲ v19:214~218 p057~058:ちくま学芸文庫)そうしてこの「雄羊」が「間断なく城壁を打ち」(「ユダヤ戦記」第5巻/vii2:298 文庫)続けた末、遂にその城壁が破壊されてしまい、ユダヤ人たちが慌てて逃げ惑う中で(「ユダヤ戦記」第5巻/vii2:301)、都に乗り込んだローマ兵により大量のユダヤ人が殺されることになった。この時こそエルサレムが攻略された時であった。この時の悲惨についてヨセフスはこう書いている。「ローマ兵たちは剣を手に狭い路地に雪崩れ込むと、出会った者たちを容赦なく殺し、人家へ逃げ込んだ者たちをひとり残らず家もろとも焼き払った。略奪のために人家に押し入ると、全家族がすでに死体となり、屋内には飢えの犠牲者がごろごろしていた。そのような光景に接すると彼らは、何も手にせずに、身震いしながら外に飛び出してくるのだった。ローマ兵たちはこのような仕方で滅んだ者たちに憐れみを覚えたが、生き残った者たちにそのような感情を示すことはなかった。ローマ兵たちは出会った者を剣で突き刺しながら進んだ。そのため路地という路地には死体の山が築かれ、都中が血で氾濫し、火炎の多くがその血で消えるほどだった。」(『ユダヤ戦記3』ⅤⅠ viii5:404~406 p094~095:ちくま学芸文庫)またタルムードでは、ローマ軍の城壁破壊によりユダヤが攻略されたことについて、こう言われている。「彼らは一基の怒砲をエルサレムの周壁に沿って引き揚げ、彼のもとに運んで来た。彼らは杉板を彼のもとに運んで来たので、彼はそれらを怒砲に取り付けた。彼はこれらを用いて周壁を打ったので、やがてそれ(周壁)に亀裂が生じた。彼らは豚の頭を運んで来てそれを怒砲に取り付けた、彼はそれを祭壇の上の(供犠用の動物の)肢体に向けて発射した。その時、エルサレムが攻略された。」(『タルムード ネズィキーンの巻』アヴォード・デ・ラビ・ナタン 第4章 5 20a p30:三貴)ローマ兵が雪崩れ込んだ都の中には、大量の死者が山のように積み上げられ、神殿の中まで「屍でいっぱい」(「ユダヤ戦記」第6巻/ii1:110)になったので、あまりの腐臭に気がおかしくなるほどであった。多くの血もそこら中に撒き散らされた。阿鼻叫喚がそこには満ちていた。シリア全土において「埋葬されていない死体いっぱいの町々を、幼子の死体の傍らに投げ捨てられた年老いた者たちの死体を、恥部を隠す一片の覆いすら剥ぎ取られた女たちを、名状しがたい災禍でいっぱいの地方一帯を」(『ユダヤ戦記Ⅰ』Ⅱ xviii2:465 p368:ちくま学芸文庫)目にすることが出来た。この時に見られた次のような状態は、正に神から下された呪いにより生じた光景である。「都の中の至る所に積み上げられた死体の山は身の毛のよだつ光景を呈し、疫病のときのような異臭を放っていたが、加えてそれは戦闘要員たちにとって出撃の邪魔になるほどのものだった。彼らは、戦場で無数の屍に無感覚になった者たちのように、屍を踏んで行かねばならなかった。屍を踏み越えて行く者たちは、身震いもせず、憐れみも覚えず、逝ってしまった者たちへ加えた自分たちの侮辱に何のためらいも感じなかった。」(『ユダヤ戦記3』ⅤⅠ i1:2~3 p011:ちくま学芸文庫)ユダヤ軍の将軍でありまた「祭司であり、祭司一族の者だった」(『ユダヤ戦記2』Ⅲ viii3:352 p084:ちくま学芸文庫)ヨセフスは投降したために助かることになったが、こういう者はほとんどいなかった。ユダヤ人の持つ異邦人嫌いの気質を考えれば分かるが、あのローマ人に対して膝をかがめることなど、ユダヤ人のプライドが許さなかったのである(※②)。ヨセフスと一緒に穴の中に隠れていた部下たちもローマに投降するぐらいならば火で焼死しようと言ったのだが、ヨセフスはユダヤ人としては珍しいと言うべきだろうか(※③)、「自殺するのは神の御心にかなわないことだ。」と言って部下たちを説き伏せようとしたのである(「ユダヤ戦記」3巻/viii5)。―余談であるが、キリスト教が自殺を悪と見做すことになったのは、このヨセフスの説教に基づいて教父が自殺を悪としたことに端を発する。―この説得にそこにいた「人びとは絶望感から聞く耳を持たなかった」(『ユダヤ戦記2』Ⅲ viii6:384 p090:ちくま学芸文庫)のではあったが、神の摂理により、ヨセフスは例外的にもう一人の男と共に自殺せずに済んだ。このユダヤ人としては珍しく投降したヨセフスがウェスパシアヌスが皇帝になると預言し(「ユダヤ戦記」3巻/viii9:400~402)、後のウェスパシアヌス帝からの寵愛を受け、あの有名な「ユダヤ戦記」を記すに至ったのは既に我々の知っているところである。このような諸々の悲惨は、正に「神の裁き」と呼ぶに相応しいものである。この時に死んだユダヤ人の数は、最高で推定110万人とされる。当時の世界人口がまだ2~3億人であったことを考えると、これは実に大きな数だと言える。仮に当時の世界人口を2億人だとすると、ユダヤ人が110万人死んだというのは、21世紀の今で言えば3500万人が死んだのと比率的には同じである。これがどれだけ大きな数であるかということは誰にでも分かるのではないかと思う。しかも、これは2度の世界大戦のように各地における死者の総計ではなく、まったく局所的な一つの地域における死者の総計である。恐らく、ある一つの地域だけにこれほどまでの壊滅と悲惨が起こったのは―これは「全滅」と言っても言い過ぎではない(※④)―、歴史においてほとんど類例がないと思われる。唯一あるとすればソドムとゴモラの滅亡ぐらいであろうか、否、ソドムとゴモラの滅亡さえもユダヤの滅亡と比べたら小さなものであったと言わねばならない(※⑤)。これは正に悲惨の極みであったと言えよう。遂に、この時、神の裁きがユダヤに下されてしまったのである。ユダヤ人は今でもこの大いなる民族的な悲惨を、嘆くべき事象として強く心に留め続けている。
(※①)
ヨセフスはこの拷問について書いている。「叛徒たちは食べ物を探し出すために恐ろしい拷問の方法を考え出し、恐怖におののく犠牲者たちの肛門にひよこ豆を詰め込み、先の尖った棒をそこに押し込むのだった。人びとは犠牲者の苦しみの声を聞いて震え上がり、ひと切れのパンを持っていればそれを告白し、わずかな量の大麦を隠し持っていれば、その隠し場所を漏らすのだった。」(『ユダヤ戦記2』Ⅴ x3:435 p362:ちくま学芸文庫)
[本文に戻る]
(※②)
このユダヤ人の異邦人嫌いについては、タルムードを見れば、よく分かる。特に偶像崇拝についての口伝律法を纏めた「アヴォダー・ザラー篇」を読むと、どれだけユダヤ人が異邦人を嫌悪しているかが分かる。そこでは、例えばユダヤ人は異邦人に自分の髪を刈らせてはならないとか、異邦人は男女ともに獣姦をする恐れがあるので獣を異邦人と一緒にしてはならないとか、階段を異邦人と歩く時にはユダヤ人が下になってはならないとか、異邦人が手をつけた酒は全て捨てなければならないとか、とにかく異邦人を汚らわしい存在として見做している記述が多く見られる。それは、ちょうど健康な人が新型コロナウィルスに感染した人を危険な存在として取り扱うようなものである。確かなところ、彼らにとって異邦人は正にウィルスのように見做されているのだ。これは、もちろん全世界の支配者であったローマ人たちも例外ではなかった。タキトゥスの場合、ユダヤ人が「彼ら以外のすべての人間には敵意と憎悪を抱く。」(『同時代史』第5巻 5 p270:筑摩書房)と書いている。これは、我々プロテスタントのキリスト者で言えば、エホバの証人どもを酷く嫌悪し近くにいることさえ避けようとするのと似ている。
[本文に戻る]
(※③)
多くの事例から分かるように、ユダヤ人はこういう時には、死んだほうが1000倍良いと考えるものである。敬神や信仰が問われる際、例えば律法遵守が問われている時であれば、ユダヤ人たちは往々にして「わたしたちの父祖たちの神の誡めを踏みはずすよりも、むしろ死のう。」(『聖書外典偽典 別巻 補遺Ⅰ』『モーセの遺訓』9:6 p176 教文館)とか「たとえ危険を伴っても、父祖の律法のために死ぬことは高貴な行為だ。」(『ユダヤ戦記Ⅰ』Ⅰ xxiii2:650 p235:ちくま学芸文庫)などと言うものである。ピラトがエルサレムにカエサルの軍旗を持ち込もうとした時にも、ユダヤ人たちは積極的に死のうとした。ヨセフスはこの件について次のように書いている。「ユダヤ人たちは三重の隊列に取り囲まれ、予想もしなかった光景に呆然となったが、ピラトスは、もしカイサルの像を受け入れなければ斬り殺すぞと脅し、兵士たちに剣を抜くよう合図を送った。他方、ユダヤ人たちは、あたかも示し合わせたかのように一体となって地に伏し、自らの首を差し出し、律法を侵すよりは死を選ぶ覚悟があると叫んだ。彼らの不屈の敬神の念に驚いたピラトスは、即刻、軍旗をエルサレムから撤去するよう命じた。」(『ユダヤ戦記Ⅰ』Ⅱ ix3:173~174 p289~290:ちくま学芸文庫)このような徹底的な敬虔さは異邦人にはまったく理解できないものであった。ヨセフスはこのようなユダヤ人の振る舞いを「他に例を見ぬ献身と死に立ち向かう不屈の勇気」(『ユダヤ戦記Ⅰ』Ⅱ x4:168 p296:ちくま学芸文庫)などと言っている。
[本文に戻る]
(※④)
これはヨセフスの「ユダヤ戦記」を読めば分かる通りである。
[本文に戻る]
(※⑤)
<Ⅰ>
ジョナサン・エドワーズの場合、このユダヤの大破滅は、それまでに起きた出来事の中でもっとも悲惨であったと考えていた。確かに、この壊滅は、そのように言われるに相応しいほどに惨たらしいものであった。エドワーズはこう言っている。「それはソドムやネブカドネザルの時代のエルサレムの破壊よりも、はるかに悲惨であり、より大きな神の怒りを証言する出来事であった。それはこの世の始まりから当時に至る歴史のなかで都市や人々に対して起こった最も悲惨な出来事であった。」(『ジョナサン・エドワーズ選集3 原罪論』第1部 第2章 p145:新教出版社)
<Ⅱ>
読者の中には、ノアの大洪水はどうなのか、と疑問を持つ人がいるかもしれない。つまり、ノアの大洪水のほうがユダヤの破滅よりも悲惨の度合いが大きかったのではないか、あれは世界的な破滅であって生き残ったのはたったの8人だけしかいなかったのだから、と。確かに、一見するとあの大洪水のほうがユダヤの破滅よりも悲惨であったように感じられる。何故なら、感覚的に言えば、何となくそのように思えるからである。だが、我々の感覚がどのように思おうと、ノアの大洪水よりもユダヤの破滅のほうが酷い出来事だったと理解せねばならない。何故なら、キリストがこのユダヤの破滅について、こう言われたからである。『そのときには、世の初めから、今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないような、ひどい苦難があるからです。』(マタイ24章21節)このキリストの言葉は決定的である。ここでキリストは、ローマ軍によるユダヤの苦難が、ノアの大洪水よりも大きな苦難であると断言しておられるからである。だから、ノアの大洪水のほうが悲惨だったのではないか、という疑問は即座に解決されたことになる。御言葉に反する感覚的な理解は聖徒たちの中から消え去れ。我々は次のように考えたらよい。すなわち、ノアの大洪水が起きた紀元前2300年頃の時代は、まだ世界の総人口が少なかったと。つまり、ユダヤ戦争で殺された110万人のユダヤ人のほうが、ノアの時代の世界人口よりも多かったと考えるのである。このように考えれば、何も問題はなくなる。何故なら、こう考えれば、キリストの御言葉には何の偽りもないことになるからである。それでは、ユダヤ陥落が起こるよりも前に、ノアの大洪水以外の出来事で、ユダヤ陥落よりも酷い出来事が何か他にあったのであろうか。これも無かったとすべきである。というのも、もし何かそのような出来事があったとすれば、キリストが偽りを言われたことになってしまうからである。しかし、キリストは真実なことを言われたのだから、ノアの大洪水以外でも、ユダヤ陥落を越える悲劇は無かったと考えるべきである。実際、歴史を振り返ってみても、そのような悲劇は一つも見られないのである。ヨセフスが、この悲劇を生じさせた戦争について「わたしたちの時代においてばかりか、わたしたちが耳にしたかぎり、都市が都市にたいして、あるいは民族が民族にたいして戦った戦争の中でも最大規模のものであったローマ人にたいするユダヤ人の戦争」と言ったのは間違いではなかった(『ユダヤ戦記Ⅰ』はじめに p019:ちくま学芸文庫)。
[本文に戻る]
エルサレム神殿の徹底的な破滅は、ユダヤに対する悲惨の数々の中で、特に注目に値する。心の割礼を受けていない呪われた彼らにとって、何がこの戦争の中でもっとも悲惨だったかといえば、やはりこの神殿崩壊ではなかろうか。このエルサレム神殿は、当時の世界で一番有名な建築物であった。その美しさは実に素晴らしいものであった。バビロニア・タルムードの中では、この破壊された神殿について「ユダヤの神殿を見たことのない者は美しいものを見たことがない人だ。」と言われているが(※①)、これは言い過ぎではなかった。多くの王や指導者たちが、この神殿を見て感心したものである(※②)。ネロからユダヤ鎮圧を任されていたウェスパシアヌスも、この神殿を打ち壊すべきかどうかということで非常に悩まされた。というのは、もしこれほどまでに有名で美しい建築物を破壊したら、世界中の人々から極悪非道の理性なき獣と見做されて非難の対象となるのではないかと感じたからである。人の美を愛好する性質は今も昔も変わらない。あのヒトラーでさえ、パリには多くの美があるからというので、そこを避けて爆撃するようにと命じたほどである。マンハッタン計画においても、日本に原爆投下する際には、歴史的な建造物が多くあるからというので京都には投下しないようにと考えた計画の参与者が多くいた。プリニウスが言っているように「デメトリオス王が、1枚の絵の焼失を避けるため、その絵が保存されている側からのみ攻略できたロドスに火をかけることを控え、そしてその1枚の絵の安全を考慮することによって勝利の機を逸した」(『プリニウスの博物誌Ⅲ』第35巻36<104> p1429:雄山閣)のも、「イアリュソス」という素晴らしい絵画のためであった。このような例が示す通り、あまりにも美しいものは、何かを守る防壁としての役割を果たす。要するに、この神殿は破壊されることが躊躇されるほどの美しさを持ったもの、つまり「美の極み」と言うべき建築物だったのである。読者は私が偽りを述べていると思うべきではない。福音書の中でも、弟子が神殿の素晴らしさに感嘆しつつキリストに対して、『先生。これはまあ、何とみごとな石でしょう。何とすばらしい建物でしょう。』(マルコ13章1節)と言っているではないか。この弟子の言葉は誇張でも偽りでもなかった。ヨセフスもこの神殿の外観的な驚異性について次のように書いている。「聖所の外側の正面部分は、見る者の心や目をただただ圧倒するものであった。すべての側面が厚い金の板金で覆われていたため、太陽が昇ると、燃え盛る炎のような輝きを反射させた。そのためそれを無理矢理見ようとする者たちも、直射日光のように、その反射光を直視することはできなかった。聖所に近づいてくる外国の者たちには、それは遠方からは雪をかぶった山のように見えた。というのも、金の板金で覆われていない部分が純白だったからである。」(『ユダヤ戦記2』Ⅴ v6:222~224 p311~312:ちくま学芸文庫)この記述からも、神殿がどれだけ美麗であったかよく分かるのではないかと思う。ヨセフスはこの神殿について「わたしたちがかつてこの目で見、この耳で聞いたもっとも驚嘆すべき造営物」(「ユダヤ戦記」第6巻/i8:267)とも言っている。また、この神殿は『建てるのに46年』(ヨハネ2章20節)も要した。このような長い年数がかかったのは敵の妨害があったからであるが、しかし妨害がなかったとしても10年ぐらいはかかったことであろう(※③)。ソロモンの場合は、『20年』(Ⅱ歴代誌8章1節)を要した。そのような長い年月が建築に必要だったのだから、やはり、この神殿はそれだけの外観を持つ建築物だったのである。この神殿は21世紀の今で言えば、バチカンのサン・ピエトロ大聖堂、ヴェルサイユ宮殿、中国の万里の長城などよりも、遥かに価値と意義のあるものであった。これらのものを合わせても、この神殿には到底及ばないであろう。というのも、これは世界一有名な唯一無二の建築物であり、万物の創造者である神の家だったからである。しかし、そのような素晴らしく貴重な神殿が、この時に跡形もなくなってしまった。これがどれだけ衝撃的な事件だったかということは、それほど深く考えずとも分かるのではないかと思う。主も、ルカ20:41~44の箇所で、このことについて泣きながら嘆いておられる。また当然ながら、この神殿の崩壊に至る全過程も神からの裁きのうちの一つであるのだが、この裁きがまた霊的に無割礼であるユダヤ人にとっては実に痛々しいものであった。まず神殿が破壊される前に、ティトゥスとその部下の幾人かが、神殿のうち最も神聖な場所であった至聖所の中に入り込んでしまった。昔の人もそうだったように、ティトゥスとその部下たちは、せっかく至聖所に入ったのに、そこに契約の箱しか置かれていなかったので驚嘆してしまった。つまり、ユダヤ人が目に見えない神を拝んでいるということに驚いたわけである。確かに、金や銀や石などの物体を神として拝む異邦人からすれば、ユダヤ人の神とは得体が知れなかったし、またそのような神を彼らが拝んでいることは理解し難いことであった。しかも彼らは至聖所に入っただけでなく、そこの床にローマの旗を力強く打ち付けた。つまり、神殿は我々ローマが占領したのだという宣言を行なった。これはユダヤ人にとっては耐え難いことであった。というのも、この至聖所とは、大祭司でさえ年に一度しか入ることが許されていない神聖極まりない場所だったからである(※④)。ユダヤ教の最高指導者でさえ年に1度以上は入れないというのに、真の神を知らない異邦人が堂々とこの場所に入って旗を打ち付けたというのは、ユダヤ人に対する侮辱以外でなくて何であろうか。しかも彼らは、至聖所に入るために必要だった生贄の血も携えていなかった―彼らは血の代わりに武器を携えていた。そして、それから後、ある無名の兵士が何気なく火を街の中に放り投げると、その火がエルサレム神殿を焼き尽くすことになった。ヨセフスはこの衝撃的な出来事についてこう書いている。「そのとき、ひとりの兵士が、命令を待たずに、またその結果がどんなに恐ろしいものであるかも顧慮せずに、ダイモニオンか何かに憑かれたかのように、燃え盛る松明を手にした。そして仲間の兵士によって持ち上げられると、黄金の入り口から―そこを通れば北側から、聖所の周囲に建てられた建物に入ることができた―それを投げ込んだ。火の手が上がると、その悲劇的最後にふさわしいユダヤ人たちの叫び声が上がった。彼らは身の危険や労を惜しまず、死に物狂いになって火を消そうとした。それまで寝ずの番で警戒をしてきた造営物がまさに焼け落ちようとしたからである。」(『ユダヤ戦記3』ⅤⅠ i5:252~253 p062:ちくま学芸文庫)この燃え盛る火の勢いたるや凄まじく、エルサレム中を火の海と化させるほどであった。このようにしてあの美しい神殿は火で滅ぼされることになったのである。サタンに動かされたローマ人が『彼女を火で焼き尽くすようになります。』(黙示録17章16節)と言われていたのは、こういうことだったのである。この時、天では大きな声が『ハレルヤ。彼女の煙は永遠に立ち上る。』と言ったと黙示録19:3には書かれている。ヨセフスによれば、神殿はあまりにも激しく火で焼かれたので、そこには草1本さえも残っておらず「広場」となり(「ユダヤ戦記」第6巻/v4:311)、そこにかつて神殿があったことを誰も認められないほどであったという。これは確かに、キリストが神殿について『ここでは、石がくずされずに、積まれたまま残ることは決してありません。』(マタイ24章2節)と預言された通りであった。文字通りに真っ平らとなってしまったわけである。ユダヤ人たちは自分たちの愛していた素晴らしい神殿を、このようにして滅ぼされてしまった。もうそこには何も残っておらず、もはやユダヤ人は神殿の記憶を呼び起こして悲しい思い出にふけることしかできなくなってしまった。このような裁きの仕打ちは、彼らの精神にとって実に強烈な打撃をもたらすものであった。その証拠として、先にも述べたように、今でもユダヤ人はこの時の出来事を記憶に留め続けている。もし神殿が残されるのであれば、彼らは1000回でも死ぬほうを選んだことであろう。このような痛々しい裁きが下されたのも、彼らが堕落した状態から神に立ち返ろうとしなかったからである。このような痛々しい悲劇は、この事件一つだけでも簡単に詩集が10冊は出来てしまうほどの悲惨さを持った出来事であった。神殿が崩壊するとは、それほどまでに衝撃的で注目に値する出来事なのである。ヨセフスが、この時に起きた騒擾を「最大規模のものだった」と言っているのは正しい(『ユダヤ戦記Ⅰ』はじめに p020:ちくま学芸文庫)。ある人も言っているように「彼らにとってこの戦争の結末ほど悲劇的なものはなかった」のである。さて、このように神殿が消滅してしまったのは、つまり神がもう石造りの神殿を必要とされなくなったことを意味している。もう不要になったからこそ神は神殿を滅ぼし尽くされたのである。もし不要なために滅ぼされたのでなければ、今頃とっくの昔に、神殿は再建されていたことであろう。もしくは、そもそも滅ぼされることさえなかったかもしれない。それでは一体どうして神は神殿をもう必要とされなくなったのであろうか。それはキリストの復活以降、神が石造りの神殿のうちに歩むことをお止めになられたからである-それまで神は神殿の至聖所を御自身の住まいとしておられた。それは、少し例えがよくないが、大きくなった子どもがもう乗らなくなった三輪車を廃棄処分してしまうようなものである。今や神の神殿とは、石造りの建築物ではなく、キリストを信じるクリスチャンのことである。パウロはこう言っている。『あなたがたは神の神殿であり、神の御霊があなたがたに宿っておられることを知らないのですか。』(Ⅰコリント3章16節)『私たちは生ける神の宮なのです。』(Ⅱコリント6章16節)ニーチェは、このパウロの言葉を「反キリスト」という邪悪な作品の中で、あざ笑っている。これは肉に属するサタンの子らが、神殿のことを霊的に理解できないというよい証拠である。我々は死人であるニーチェのような肉的感覚を持ってはならない。パウロがキリスト者こそ神殿であると御霊により述べたのである。であれば確かにその通りなのである(※⑤)。神の御霊がどうして偽りを言われるであろうか。事は霊的に理解されるべきである。つまり、神は新しい神殿であるキリスト者の中を、紀元1世紀以降においては歩まれるようになったということである。このような新しい神殿が登場するようになったがゆえに、不要となった古い石造りの神殿は燃やされて完全に消し去られることになったわけである。確かに、神が聖徒の中をこそご自身の神殿とされるというのは、旧約聖書で預言されていたことである。それはエゼキエル37:26~28にこう書かれている通りである。『わたしは…わたしの聖所を彼らのうちに永遠に置く。わたしの住まいは彼らとともにあり、わたしは彼らの神となり、彼らはわたしの民となる。わたしの聖所が永遠に彼らのうちにあるとき、…』この預言に書いてある通り、今や神の聖所があるのは聖徒の身体である。石造りの神殿はもはや聖所となるべきものではなくなった。西暦21世紀の今でも、ユダヤ人たちは、かつて神殿があったあの場所に再び神殿を建てたいと望んでいる。今までに何度かあの場所に神殿を再建させる計画が実行されたことがあったが、どれも完全な失敗に終わってしまった。神が起こされたとしか思えない天変地異が起きて建設が邪魔されたこともあったとギボンは述べている。私は言うが、できるはずがないのである。神殿を再建することは、昔も今も未来も、決してできない。何故なら、神がそれをお許しにならないからである。今は神殿のあった場所にイスラム教の「岩のドーム」が陣取っているが、このままである可能性が高いと私は思う。たとえあのドームが無くなったとしても、そこには何も建てられないままの状態が続くか、ユダヤの神殿ではない他の建築物が再び占領することであろう。永遠にあの場所には、また他の場所であっても、ユダヤの神殿が再び建設されることはない。何故なら、神はキリスト者をご自身の神殿とされたからである。もし石造りの神殿が再建されたならば、そのような神殿紛いの建築物―それは神の神殿とは言えない―が存在することにより、キリスト者という神の真の神殿におけるその唯一性・特殊性・神聖性・契約性が侵害されてしまう。それは、イギリスに偽女王が、アメリカに偽大統領が、日本に偽天皇が出現するようなものである。そのような偽物の存在が許されたら、女王や大統領や天皇の存在が侵害されるのは確かである。偽神殿が建てられるのもこれと同じことである。神がそのようなことを許されるはずがない。実際、今に至るまでそのようなことは一度も起こっていない。「今や神は聖徒の身体をこそ神殿とされた。」というのが世界の真理である。それゆえ、ユダヤ人らが愚かにも神殿を再建させたいと願っているのは、神と真理と真の神殿である聖徒たちに対する忌まわしい冒涜であると言わねばならない。もし彼らが神殿を欲するというのであれば、我々と同じように神の聖なる民となるがよい。そうすれば彼らも自分たちの欲している神殿を自分たちの身体において見出すことであろう。キリストに帰依して神の国民になることこそ、ユダヤ人にとっての神殿なのである。
(※①)
これは自由な引用であるが、文意は何も変わっていない。実際の文章とその前後にある文章は、次の通りである。「華麗であったエルサレムを見たことのない者は、決して好ましい町を見たことがなかった。建立された聖所を見たことのない者は、決して麗しい建物を見たことはない。どの聖所のことなのか。アバイェ、あるいはラヴ・ヒスダが言った、「これはヘロデの神殿のことである」と。どのような材料で建築されたのか。ラヴァは、「黄色い石と白の大理石で」と言った。ある人は、「黄色い石と黒い大理石と白い大理石であろう」とも言う。彼は縁ごとに出っ張らせたり引っ込めたりして、漆喰の抑えとした。ヘロデは金で建物を覆いたかったのであるが、ラビたちは彼に「そのままであったほうがよい。そのままのほうがずっと麗しい。それはまるで海から湧き上がる波のようである」と言った。」(『タルムード モエードの巻』スッカー/第5章 ミシュナ4―ゲマラ p207~208:三貴)タルムードでは他の箇所でも「エルサレムの美のような美はない。」(『タルムード ネズィキーンの巻』アヴォード・デ・ラビ・ナタン 第28章 1 28a p101:三貴)とか「美の10カブがこの世に降った。9カブをエルサレムが取り、そして1つを全世界が取った。」(『タルムード ナシームの巻』キドゥシーン 第2章 49b ミシュナ2/ゲマラ p179:三貴)など言われているが、エルサレムとその神殿は切っても切り離せない関係を持っているから、これも神殿の美しさについての言及と見てよいであろう。
[本文に戻る]
(※②)
例えば異邦人であったプトレマイオス王が神殿の巣晴らしさに驚嘆したということについて、『Ⅲマカベア書』では次のように書かれている。「彼はエルサレムにはいり、大いなる神に犠牲獣を献げ、感謝の献げ物を献げ、その場所にふさわしい行為をなしたが、さらにその場所の中にはいると、そのすばらしい美しさに驚嘆し、また聖所の秩序整然たるさまにも驚いて、神殿の中にはいりたいものだと思いめぐらした。」(『聖書外典偽典 別巻 補遺Ⅰ』Ⅲマカベア書1:9~10 p34 教文館)
[本文に戻る]
(※③)
ルターの場合、妨害抜きであれば6~7年もあればよかったと述べている。「…神殿建築の始めから終わりまで46年かかったのである。なぜなら、ユダヤの民は戦争によって、また、周囲の諸民族によってしばしば妨害され、異邦人たちは彼らに一時の安らぎも平和も許さなかったからである。そうでなかったら、彼らはそのような神殿をおそらく6、7年で建てたことであろう。…建設自体は、妨害ほど困難ではなかったからである。」(『ルター著作集 第二集6 ヨハネ福音書第1章・第2章説教』第19説教 第2章(18―22)p369 LITHON)
[本文に戻る]
(※④)
『第二の幕屋には、大祭司だけが年に一度だけはいります。そのとき、血を携えずにはいるようなことはありません。』(ヘブル9章7節)
[本文に戻る]
(※⑤)
アウグスティヌスも「われわれがそれによって神の神殿へと変化せしめられるところの聖化は、再び生まれる者たちにのみ属するのである」(Epistola CLXXXⅦ ad Dardanum,10,PL 33,844.)と述べたことから分かるように、聖徒たちの身体こそが今や神の神殿だという正しい聖書的な理解を持っていた。彼は「個々人もまさに神の宮であり、…」とも述べている(『アウグスティヌス著作集21 共観福音書説教(1)』説教63 1節 p206:教文館)。アレクサンドリアのクレメンスも、聖徒たちは神を宿す神殿であると理解していたが、これは正しい理解であった。彼はパウロの聖句を引用しつつ、こう書いている。「使徒は次のように言う。「あなたがたは知らないのか。あなたがたが神の殿堂であるということを」。実に、覚知者は神的でありすでに聖なる者であって、神を宿し神の息吹を受けた人物である。」(『キリスト教教父著作集―4/Ⅱ―アレクサンドリアのクレメンス2 ストロマテイス(綴織)Ⅱ』第7巻 82:2 p366 教文館)
[本文に戻る]
さて、この裁きを受けてから、西暦21世紀の今に至るまで、ユダヤ人はどのような歩みをしたのであろうか。この2千年の間、神はもうかつてのようにユダヤの民と共に歩まれなかった。彼らは、もう『主がわれわれと共におられる。』(マタイ1章23節)とは言えなくなった。というのも、彼らはもはや真のイスラエルではないからである。霊的に理解すれば、今や真のイスラエルはキリストの聖徒たちである。パウロは、聖徒こそが『神のイスラエル』(ガラテヤ6章16節)であると述べた。2千年前から、キリストにある者こそが、神の民であるイスラエルになったのである。それゆえ、もはや肉のユダヤ人たちは、キリストを信じるユダヤ人は別であるが、神のイスラエルではない。彼らは神から捨てられて聖なる牧場から離れたのだから、サタンの家畜となった。今や彼らの主はサタンである。だからこそ、サタンと同じように、彼らは御子と聖徒たちに敵対するのである。であるから、神が彼らと共におられなかったとしても不思議なことはない。このような彼らが歩んだ2千年の歴史は、霊的にも肉的にも悲惨であったと言える。すなわち、霊的には神がもはや共におられないという意味において、肉的には多くの迫害を受けて苦しめられたという意味において、彼らは悲惨であった。まずユダヤ人たちは、紀元68年に裁きを受けて後、ドミティアヌス帝による迫害を受けた。このローマ皇帝は、「主にして神」などと自称し、傲慢な態度をもってユダヤ人を苦しめた。その後、第2次ユダヤ戦争が起きたが、ユダヤ人はこの戦争において敗北を喫した。神が彼らと共におられなかったので、負ける以外の運命にはなかったのである。それから、ユダヤ人たちは金貸しや銀行家など、人々から嫌われる職業に従事することになった。当時は今のように利息をつけてお金を貸すことが合法的だとは思われていなかったので、キリストを殺害した民族という負の認識との相乗効果により、ますます忌み嫌われることになった。今でもロックフェラーをはじめユダヤ人と銀行業との関わりは非常に深い傾向があるが、それは、昔から金を貸す職業に従事してきたという歴史が一つの要因である。このユダヤ人たちはエルサレム神殿を再建しようと試みたこともあったが、不思議な力が働いて阻止されてしまった。モーゼス・マイモニデスという学識ある聡明な者が現われた。彼は今でも言及されることの多い人物だが、やはり死人らしく、旧約聖書を正しく読めていなかった。また、アブラハムの血を持たない偽者のユダヤ人が大量に現われることになった。彼らはキリストの時代には異邦人だったのに、今や正式なユダヤ人として世に認められることにさえなっている。宗教改革の頃になると、コロンブスがアメリカ大陸を始めて発見したということにされた(実際はコロンブスより数百年前に既にアメリカ大陸を発見した人が存在していた)。このコロンブスの航海には、ユダヤ人が大いに関与していたという話があるが、これはなかなか興味深く感じられる話である。この時代にはルターがユダヤ人たちを回心させるべく福音を彼らに宣べ伝えたのだが、ユダヤ人たちが反発したので、ルターはユダヤ人を激しく非難するようになった。ルターの説教をると、彼はこれでもかといわんばかりにユダヤ人を攻撃している。このルターの反ユダヤ主義を、後のヒトラーのユダヤ迫害におけるファクターとして捉えることも可能であると私には思える。ヒトラーの場合がどうであれ、少なくともルターの反ユダヤ主義が、世界の反ユダヤ主義に多かれ少なかれ影響を及ぼしたことは疑えない。それはルターほど強い影響力を世界に与え続けている人物は、非常に珍しいからである。あのマルクスという巨人さえもルターの本を読み漁っていたことを考えれば、このことはよく分かるであろう。また17世紀になるとスピノザが現われた。18世紀の革命が起こるまでに、ここまで学術界において有名なユダヤ人が登場したのは、かなり珍しいことである。彼はキリストの復活をさえ信じたが、その信仰は異端のそれであり、正しい神理解を持っていたとも言えなかった。更にこの時期には、サバタイ・ツィヴィという名の異常なユダヤ教徒も出現した。彼の出現は、明らかにサタンの働きかけによるものであった。この狂った病的な者は、自分こそ預言されていたメシアだと自称し、ユダヤ教サバタイ派の創始者となった。この一派は、今のユダヤ教において少なからぬ影響力を持っており、考究に値する存在である。18世紀になると、ユダヤ人を解放させるためのフランス革命が起こされた。この革命により、かつては奴隷のように社会のもたらす鎖で縛られていたユダヤ人たちが、自由に、そして活発に活動できるようになった。そのため、彼らはこの革命を境として大いに台頭することになった。これは、この革命の前後に現われたユダヤの著名人の数を考えれば一目瞭然である。それまでは、紀元1世紀以降のユダヤ人でよく知られていたのはマイモニデスとかスピノザぐらいしかいないようなものであった。しかし、この革命以降は、マルクスやアインシュタインやリカードやミーゼスやロックフェラーをはじめ、著名なユダヤ人が実に数多く出現した。これはこの革命がユダヤ人の解放を主眼としていたものだったからでなくて何であろうか。解放されたからこそ、ここまで活発に活動できるようになったのである。また20世紀になると、我々がよく知っているように、ヒトラーがユダヤ人を大々的に迫害した。ヒトラーは、ユダヤ人の世界支配の計画を危惧したために、このような迫害を行なった。確かにタルムードがユダヤ人による世界支配を書き記しているのは事実である。この世界支配のことについては、ここで詳しく取り扱うことをしない。中にはこのヒトラーがユダヤ人であって陰謀に荷担していたと主張する人もいるが、これは誤りであろう。何故なら、当時において、まだユダヤの陰謀家たちは自分たちの計画を大胆に暴露するようなことはしなかったからである。今では自分たちの側から工作員を使って陰謀を暴露するようにもなったが、それはつい最近、正確に言えば20世紀の後半になってからのことである。ヒトラーの時代では、まだ陰謀を自ら大胆に開示して人々が誤認するように働きかけるということはされていなかったので、そのようなことをしたら、高い確率で容赦なく抹殺されていたことであろう。しかしヒトラーは「我が闘争」という本の中で、これでもかといわんばかりにユダヤの陰謀を暴露している。もしヒトラーがユダヤの工作員であったとすれば、その時代にあって、このようなことをするのはまったく考えられない。しかし彼が工作員ではなく、ユダヤの陰謀を本当に危険視していたというのであれば、このような暴露をしたことは容易に納得できる。それゆえヒトラーは陰謀を企むユダヤ人の一味ではないということになる。ここ100年の間には、シオニズム運動が推し進められている。この運動により、正式な国家と認められないこともあるが、イスラエルが建てられた。これは金融資産家でありユダヤ教徒であるロスチャイルドの願望がバルフォアを通して実現されたものであるが、このユダヤ教徒は紛れもない陰謀家であるから、このシオニズムを首肯することはすべきではない。何故なら、タルムードの記述を実現させるためにこそ、このシオニズムは企まれたのだからである。純粋なユダヤ人はこの運動には否定的であって、そのことを裏づける証拠であるが、この運動により生じたイスラエルに住んでいるユダヤ人の大半は偽のユダヤ人たちである。つまりアブラハムの肉の子らは、その多くが、別にあの地域に造られた国家に戻りたいなどとは思っていないのである。このような偽のユダヤ人たちが、あたかも本物のユダヤ人であるかのように色々と世を騒がせているのも、純粋なユダヤ人に対する裁きの一つとして見てよいであろう。18世紀のユダヤ人解放のための革命以降に活躍しているユダヤ人は、そのほとんどが生来的にはユダヤ人でない者たちであると思われる。著名なユダヤ人の顔を見ると、マルクスであれミーゼスであれリカードであれアシモフであれクリントンであれマーク・ザッカーバーグであれ、そのほとんどはヤペテ系の顔だちである。純粋なユダヤ人はセム系の顔だちであって、例えば今のイランやサウジアラビアなどにいる中東系の人たちのようである。そのようなユダヤ人は、私の今の知識に基づいて言えば、恐らくあまり活躍できていないのではなかろうか。非常にしんみりしている、というのが私の個人的な所感である。アブラハムの子孫たちのことを言えば、彼らのこの2千年間の歴史は、放浪と悲惨と孤独という言葉に尽きる。この2千年の間、彼らに恵みが注がれているようには感じられない。むしろ、呪いを受けていると思われることが多い。読者の方も、彼らの受けた迫害や苦難のことを考えれば、恐らくそのように思われるのではないか。これは当然といえば当然である。何故なら、キリストが再臨された紀元68年の時に裁きを受けたために、彼らはこのような苦しみを受けることになったのだからである。
事のついでに、これからアブラハムの肉の子孫であるユダヤ人がどうなるのかということについて、いくらか考察してみたい。今後、彼らがどうなっていくかということは、なかなか興味深いことだと思われる。まず、アブラハムの遺伝子を持った純正のユダヤ人たちが、かつてのように一つ所に所在を定めるということはこれから起こらない。先に書かれたように、彼らの大部分はシオニズムには否定的である。それゆえ、かつてのように純粋なイスラエル国家がこれから登場することもないであろう。アブラハムの肉の子らによる国家的な共同体は、紀元70年9月の時をもって最後であり、今も存在せず、今後も生まれない。それでは彼らは、ずっと今のままの状態でいるのであろうか。その通りである。彼らは今まで2千年の間そうだったように、これからも流浪の民であり続ける。永遠にそうである。というのも、紀元68年6月9日にこの大いなるゴモラが受けた刑罰とは、この地上において永遠に続けられるものだからである。この裁きの時、その汚れと堕落と反逆に対して罰が注がれた大淫婦バビロンについて、天ではこういう声が鳴り響いたのである。『ハレルヤ。彼女の煙は永遠に立ち上る。』(黙示録19章3節)神の民は、この声に対して「アーメン。」と言わなければならない。この声が言ったように娼婦イスラエルの煙は『永遠に』消えないのだから、それは彼らに対する刑罰が永遠に続くということを意味しているのである。それはソドムとゴモラに対して、永遠の刑罰が注がれたのと同様である(※①)。また彼らが待ち望んでいるメシアがこれから到来し、そのメシアがユダヤ人たちの状態を大幅に変えるということも起こらない。何故なら、そのメシアとはイエス・キリストであって、その方は既に来られたからである。既に来られた方を、まだ来ていないと考えるのは間違っている。彼らは旧約聖書をよく理解できていないのである。メシアが2回も受肉されるということが、どうしてあるであろうか。同様に、彼らがいずれ成就されるだろうと信じているエゼキエル書の第三神殿に関する預言も成就しない。何故なら、あの預言は紀元68年に成就しているからである。あれは天の都に存在する神と子羊という神殿のことでなくて何であろうか(※②)。しかし、このように言われるのを聞くと、神が永遠にユダヤ人を裁かれるというのは少し酷いのではないか、と思われる方もいるかもしれない。このように思われる方は、ユダヤ人が何をしたかをよく考えてみるとよい。彼らは神を裏切り、サタンのほうに走り、バアルやアシュタロテなどといった異教の神々を拝み、律法を蔑ろにし、不信仰になり、神を怒らせ、異邦人と混合し、主の鞭を厭い、神の使いたちを何人も殺し、遂に来られたメシアをさえ十字架につけた。このようなことを見ても分かるが、酷いことをしたのは、元はといえばユダヤ人のほうである。神はユダヤ人をせっかくご自身の『宝の民』(申命記7章6節)としてお選びになったのである。そして、彼らにご自身の聖なる戒めを与えて、彼らがそれに従って聖く歩むようにさせて下さった。また多くの神聖な啓示をも彼らに与えられた―このような素晴らしい恵みを受けた民が他にどこにいるであろうか。つまり、神はこの民にとんでもなく良くして下さったのである。それにもかかわらず、この反逆者たちは、自分たちに良くしてくれた神に逆らってばかりいた。これでは、この地上において永遠に裁かれることになっても文句は言えないであろう。彼らがこのような酷い状態にあったので、それに応じて神も彼らを永遠に捨てられたというのは、行き過ぎであろうか。もちろん、そのようなことはない。ユダヤ人が神に酷いことばかりをしていたので、神も永遠に裁かれるという仕返しを彼らにお与えになったのである。人の親でさえ、愚かな子供を家から追い出して、もはや子供とは認めないのである。我々は、酷いのは永遠の刑罰を与えられた神ではなく、ユダヤ人のほうであったと理解すべきである。神はただ正しく報いておられるだけに過ぎない。また、ユダヤ人に永遠の報いを与えられた神が酷いと感じるのであれば、火の池で滅びの子らに永遠の刑罰が与えられるということは、どうなのか。もしユダヤに永遠の刑罰が与えられたからというので神を酷い方だと非難するのであれば、神が無数の人間たちを火で永遠に裁かれるということも、当然ながら非難せねばならないことになる。何故なら、どちらも人間に永遠の刑罰が与えられているという点では変わらないからである。しかし、聖書に立つ聖徒の中で、いったい誰が滅びの子たちに対する永遠の裁きを通して神を非難するであろうか。例えば、イスカリオテのユダが永遠に火で焼かれるからというので、神を残虐な悪魔でもあるかのように非難する聖徒がどこかにいるであろうか。まともな信仰を持っていれば、そのような聖徒はいないはずである。むしろ、多くの聖徒が、ユダに対する永遠の刑罰の妥当性を認めるであろう。というのは、ユダは非常に悪いことをしたので、永遠の刑罰に値すると誰でも思うだろうからである。であれば、同じ永遠の刑罰を受けたユダヤにおいても、我々は神を非難すべきではないことになる。ユダの刑罰に文句を言わないのであれば、ユダヤに対する刑罰にも文句を言うべきではない。すなわち、ユダの刑罰における妥当性を認めるのであれば、ユダヤの刑罰における妥当性をも認めるべきである。どちらも、永遠に断罪されるに相応しいことをして、神を怒らせたのであるから。このように純正のユダヤ人たちは、これからも永遠に呪いの民として各地を放浪し続ける運命を持っている。非純正のユダヤ人たちの未来については、私はさほど興味を持っていない。何故なら彼らは本来はユダヤ人ではなく、肉と血においてアブラハムを父祖として持たず、それゆえに神に選ばれた者たちとは言えないからである。紀元68年の裁きを受けなかった偽者のユダヤ人たちを本作品で取り扱うのは、あまり必要性を感じないし、意義のあることだとも思われない。それゆえ、彼らについては、少なくとも今の時点ではここに書くことをしないでおきたい。
(※①)
ソドムとゴモラなどの堕落した町々は、アブラハムの時代から永遠に刑罰を受けることになった。それゆえ、今もあの地域は荒廃しており、栄えや潤いとは無縁である。イスラエルもこのような永遠に及ぶ刑罰を受けることになったのである。ソドムとゴモラなどの町々に対する永遠の刑罰については、ユダが次のように書いている通りである。『また、ソドム、ゴモラおよび周囲の町々も彼らと同じように、好色にふけり、不自然な肉欲を追い求めたので、永遠の火の刑罰を受けて、みせしめにされています。』(ユダ7節)
[本文に戻る]
(※②)
『私は、この都の中に神殿を見なかった。それは、万物の支配者である、神であられる主と、子羊とが都の神殿だからである。』(黙示録21章22節)
[本文に戻る]
重要な問題に移りたい。それは、ユダヤ人の回復については一体どうなるのであろうか、という問題である。今まで、多くの教会が、やがてユダヤ人は民族全体としてキリストに立ち帰るようになると信じ、望んできた。ジョナサン・エドワーズやサミュエル・ラザフォードもその一人である。西暦21世紀の今でも、多くの教会がこのように信じ、望んでいる。この文章を書いている私も、かつてはその一人であった。このユダヤ人の大々的な回心についての一般的な見解は、次のようなものである。すなわち、キリストが再臨された時か、再臨される直前の時期になると、今はキリストを否んでいるユダヤ人が(※①)民族全体としてキリストに帰依することになるという見解である。つまり、福音のゆえに捨てられて不従順になっている彼らも、時が来れば、その福音に戻ってきて不信仰な状態から従順にさせられるということである(※②)。このような見解は、次に挙げる聖句に基づいている。『もし彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら、彼らの受けられることは、死者の中から生き返ることでなくて何でしょう。』(ローマ11章15節)『ちょうどあなたがたが、かつては神に不従順であったが、今は、彼らの不従順のゆえに、あわれみを受けているのと同様に、彼らも、今は不従順になっていますが、それは、あなたがたの受けたあわれみによって、今や、彼ら自身もあわれみを受けるためなのです。』(同30~31節)多くの聖徒は、この見解を聞いて「アーメン。」と言うであろう。確かに、まだ再臨が起きておらず、これから再臨が起こるというのであれば、この見解は誠に正しいと言わねばならない。何故なら、確かに再臨の時期には、ユダヤの回復が起こると聖書は教えているからである。このように聖書が教えていることを疑うことはできない。しかし、既に説明されたように、キリストはキリストを目の前で見ていた人たちが死を見る前に再臨された。よって、ユダヤ人は、キリストが再臨された紀元68年6月9日にもう回復させられたことになる。再臨がこの日に起きたのであれば、確かにそのようになったことは絶対に疑えない。何故なら、ペテロは当時のユダヤ人に対して次のように言ったからである。『そういうわけですから、あなたがたの罪をぬぐい去っていただくために、悔い改めて、神に立ち返りなさい。それは、主の御前から回復の時が来て、あなたがたのためにメシヤと定められたイエスを、主が遣わしてくださるためなのです。このイエスは、神が昔から、聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られた、あの万物の改まる時まで、天にとどまっていなければなりません。』(使徒行伝3章19~21節)ここでペテロはユダヤ人の回復が来ると、ユダヤ人のためにメシヤと定められたキリストが天から再臨されると言っている。つまり、キリストは既に再臨されたので、既にユダヤの回復も起こったことになる。それゆえ、多くの聖徒たちが願っているユダヤの回復に関する問題は、もう遥か昔に解決されているということになる。しかし、ここで、このように言って反論される方もいるはずである。すなわち、今の世界を見てもユダヤ人が回復されたようには感じられないから、まだ再臨は起きていないのだ、という反論である。しかし我々人間の理性が何を思おうとも、聖書は再臨が既に起きたと我々に対して教えている。このことについては、既に充分論じたので、繰り返して説明しなくてもよいであろう。聖書が教えているように再臨が既に起きたのであれば、ユダヤも既に回復したことになるから、このような反論は聖書によって打ち負かされてしまう。ではユダヤの回復とは一体どのような意味なのであろうか。キリストが再臨されたことで、ユダヤはどのような回復を神から受けたのであろうか。これは絶対に説明する必要がある。それは、ユダヤの中にいた選ばれた者たちが再臨の日に贖いを受けることにより、天国における神の御前でユダヤが回復されるに至る、という意味の回復である。旧約聖書を見ると分かるが、ユダヤ人の回復とは、すなわち選ばれたユダヤ人たちが再臨の日になると神の元に集められるということである。例えば旧約聖書では再臨の日に起こるイスラエル人の携挙について、こう預言されている。『その日、主はユーフラテス川からエジプト川までの穀物の穂を打ち落とされる。イスラエルの子らよ。あなたがたは、ひとりひとり拾い上げられる。その日、大きな角笛が鳴り渡り、アッシリヤの地に失われていた者や、エジプトの地に散らされていた者たちが来て、エルサレムの聖なる山で、主を礼拝する。』(イザヤ27章12~13節)次の預言も、同じ携挙のことが言われている。『わたしは東から、あなたの子孫を来させ、西から、あなたを集める。わたしは、北に向かって『引き渡せ。』と言い、南に向かって『引き止めるな。』と言う。わたしの子らを遠くから来させ、わたしの娘らを地の果てから来させよ。』(イザヤ43章5~6節)ユダヤ人の中にいた選ばれし子らが神の元に東西南北から携挙されて集められ、そのようにして神の御前においてユダヤ人の回復が実現する。この回復の時にこそ、ユダヤに憐みと赦しが与えられ、彼らの犯した罪の問題が全て解決されることになった。それはパウロがこう書いている通りである。『…こうして、イスラエルはみな救われる、ということです。こう書かれているとおりです。「救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬虔を取り払う。これこそ、彼らに与えたわたしの契約である。それは、わたしが彼らの罪を取り除く時である。」』(ローマ11章26~27節)この聖句から、キリストがシオンの山から再臨された時こそが、ヤコブらの悪が除かれる時であるということは疑えない。裁かれるべきユダヤ人については、この回復の恵みにあずかれない。このユダヤ人のほうは回復とは何の関係もない。彼らに関係があるのは回復のほうではなく、遺棄されるという裁きのほうである。我々はユダヤには回復が与えられると同時に、遺棄の呪いも与えられるということを理解すべきである。私が今ここで取り扱っているのは、このうち回復のほうである。遺棄のほうについては既に多くのことが語られた。要するに、ユダヤの回復とは、あらゆるユダヤ人が神に立ち帰るという意味の回復ではない。今述べたように回復にあずかれるのは選ばれたユダヤ人のみである。そのユダヤ人が回復されたのであれば、神の御前においてユダヤ全体が回復されたことにもなるのである。それは、先に語られた呪われしユダヤ人たちが裁かれることにより、ユダヤ全体が捨てられてしまったのと同じである。我々は、神がある一つの対象に対して、複数の働きかけをなさる方だということをよく知るべきである。その最もよい例は、キリストの贖いである。キリストが十字架につけられるように神がされたのは、神の人類に対する愛のためであり、聖なる計画を遂行するためであり、サタンとイスラエルと使徒ユダが悪を行なうことで裁きが彼らに与えられるためであった。このユダヤの場合は、紀元68年の時に、回復が与えられるのと同時に呪いが与えられるという働きかけがなされた。この2つの働きかけは妨げ合うことがなかった。何故なら、回復されたほうの人は天に挙げられ、呪われたほうの人とその子孫は地において苦難を受けたからである。だからこそ、聖書は再臨の日には、ユダヤが赦されるとも処罰されるとも書かれているのである。我々はこの2面性をよく弁えねばならない。すなわち、回復のほうだけを見て「回復するのだから裁かれることはない。」などと言ったり、処罰のほうだけを見て「処罰されるのだから回復されることがどうしてあろうか。」などと言うべきではない(※③)。では、これからユダヤの回復は起こらないのであろうか。それは起こらない。すなわち、多くのキリスト者が考えているような奇跡的な民族的大回復は起きないであろう。何故なら、今地上に生きているユダヤ人とは、ことごとく呪われて捨てられたユダヤ人たちの子孫であるから。そのような者たちが民族全体として回復するというのは非常に考えにくい。事実今に至るまで、彼らはほとんど救われていない。それどころか、彼らは救いから大いに離れたままの状態を今でも続けており、キリストに近付く気配さえ見せていない。オリゲネスがユダヤ人について次のように言っていることは正しい。「わたしたちは敢えて、彼らはもはや回復されることはないと言おう。というのも彼らはすべてのうちで最も畏れを知らない罪、すなわち人類の救い主に対して、しかも大いなる神秘の象徴である習慣的祭儀を、神のために行うまさにその都で、陰謀を企てるという罪を犯したからである。それゆえに、イエスがそのような苦難を被ったこの都は、ことごとく滅亡した。さらにユダヤの国民は破滅し、神による至福への招きは他の人々、つまりキリスト教徒に移行した…」(『キリスト教教父著作集9 オリゲネス4 ケルソス駁論Ⅱ』ケルソス駁論 第4巻 22 p98:教文館)。しかしながら、それなりに多くのユダヤ人が纏まって救われるということであれば、時には起こることもあるかもしれない。例えば100人、1000人ぐらいのユダヤ人がある地域でクリスチャンになった、ということであれば、可能性としては起こりえると思われる。しかし、彼らは呪われた子孫なのだから民族的な大回復と呼べるほどの救いは与えられないはずである。それは呪われしユダまたエサウが、心から悔い改めて神に立ち帰るようなものである。それでは教会は、もはやユダヤ人の回復を求めるべきではないのであろうか。我々は、ユダヤ人の救いそのものは願い求めるべきであるが、それは他の異邦人と同じように願い求められるべきである。ユダヤ人だからといって何か特別扱いをするべきではない。何故なら、彼らは神の御前において今や異邦人と同等の者たちであり、彼らの回復に関する問題は既に解決されているからである。よって我々は、宗教的な意味において預言が成就することを求めて、彼らが救われるようにとは願い求めるべきではない。もう既にユダヤが回復されたというのに、どうしていまだに回復されていないかのように、彼らの回復を願い求めなければいけないのであろうか。彼らは既に宗教的な意味において回復したのだから、宗教的な意味において彼らが回復されるのを願うことはすべきではない。それは我々が安息日を宗教的な意味において守るべきではないのと同じことである。カルヴァンも「キリスト教綱要」の中述べたように、安息日は既にキリストにより成就されたのだから、安息日を宗教的に守るのはキリストという安息日の実体を蔑ろにすることである。それゆえ、今や安息日は「主の日」として、身体の休息のため、また霊的な修養や生活に心を向けるために守るのが望ましい日とされている。それと同じように、我々はユダヤ人が宗教的な意味において大々的に回心するのを求めるべきではなく、―もし彼らの大々的な回心を求めるというのであれば―、他の異邦人が大々的に回心するのを求めるのと同じような態度と精神で彼らの大々的な回心を求めるべきなのである。というわけで神学者諸君、牧師諸君、また一般信徒である兄弟たちに私は言いたい。あなたがたはユダヤの回復について考えを改めるべきである。再臨が既に起きたということが聖書から本作品の中で明らかにされたのだから、その再臨の時期に起きるユダヤ人の回復についても、我々は考えを正しいものへと変えなければいけないのである。
(※①)
昔から今に至るまで、往々にしてユダヤ人はキリスト嫌いである。マルクス(本名はモーゼス・モルデカイ・レヴィ)をはじめとしたキリスト教徒であるユダヤ人は別であるが、彼らがキリストについて口にすることと言えば、悪いこと、不信仰なこと、冒涜的なことばかりである。例えばキリストのことを「あいつは裏切り者だ。」などと罵ったりする。いまだにキリストを不貞の子と見做す者も存在する。中にはキリストとキリスト教を忌み嫌うあまり、数字の「4」を十字が含まれないように書く者さえいる。つまり「U」の右下に「I」をくっつけるような形で「4」を書く。何故なら、4を普通に書くと十字架がそこに含まれるかのような形状になるからである。タルムードでもキリスト教が「異端」(ミーン/複数形:ミーニーム)として取り扱われている(バビロニア・タルムード/ソーター篇 9章 ミシュナ15 49b)。
[本文に戻る]
(※②)
ルターもこう考えていた。彼はこう言っている。「こうしてすべてのイスラエル、すなわち、救われるべき、イスラエルのすべての者が救われるであろう。こう書かれているとおりである。イザヤ書59章、初穂の残りにおいてなさったように、救うかたがシオンから来て、すなわち、キリストが肉において来て、ヤコブから不信心を、すなわち、ユダヤ人の不信仰を取り去る。彼は世の終わりにこれをする。」(『ルター著作集 第二集 第8巻(ローマ書講義・上)』グロッセ 第11章 113~114 p158 聖文舎)
[本文に戻る]
(※③)
ルターも、再臨の起こる終わりの日は、2つの対極すること、すなわち良いことと悪いことが同時に起こる日であると言っている。彼が持っていたこの理解は聖書的で正しいものであった。ただ、この日がまだ起きていないと考えている点では非聖書的で誤っていたと言わねばならないが…。彼は、そのことについて次のように言っている。「終わりの日は怒りとあわれみの日、苦難と平和の日、破壊と栄光の日と呼ばれる。その日不信仰者は罰せられ、混乱させられるが、信仰者は報酬を受け、誉れを受ける。同じように、信仰の光におって信仰者の心のなかにある霊的な日もまた、怒りと恵みの日、救いと滅びの日と呼ばれる。詩篇第109篇に「主はあなたの右にあって、その怒りの日に王たちを粉砕する」、すなわち、今がそうである、恵みの日と時に、とあるとおりである。また、ゼパニヤ書第1章には「主の日の声は苦い。強い者(すなわち、力ある、ごう慢な者)もそこで苦しむ。その日は怒りの日、苦しみと悩みの日、災いと不幸の日、暗黒と闇の日、雲と旋風の日、ラッパとその響きの日である」などとある。」(『ルター著作集 第二集 第8巻(ローマ書講義・上)』スコリエ 第2章(5) p265 聖文舎)カルヴァンも、このことについて次のように述べている。「さて、最後の審判の日は、「怒りの日」と呼ばれる。不信仰なものについて言われるときには、そうである。しかし、信仰者にとっては、この日は「贖いの日」である。やはり同じように、主の他のすべての訪れもみな、悪しきものに対しては、つねに、恐るべく、また威嚇に満ちたものとして記されている。しかし、その反対に、信仰者に対しては、これは、慈しみと恵みとにみちたものと書かれているのである。」(『新約聖書註解Ⅶ ローマ書』2:5 p57 新教出版社)
[本文に戻る]
第7章 これから世界はどうなるのか
このように世界がこれから永遠に続くと言われたのを聞いて、それはゾロアスター教の善悪二元論だなどと批判する人たちがいる。この人たちは我々のことを、これから永遠に神とサタンという2つの相反する究極的な原理が互いに対立し合うという理解を持っているなどと言って、批判するのである。確かに、我々が善なる神と悪なるサタンとの永遠の対立を主張しているのであれば、このような批判はもっともであった。というのも、それは異教であるゾロアスター的な思想に他ならないからである。しかし、批判者たちは自分の批判する対象を失って残念かもしれないが、我々はそもそもそのような善悪二元論を信じているわけではない。つまり、我々は、ゾロアスター教やその他の異教のように、善なる存在と悪なる存在が永遠に至るまでも対立し争い合うなどといった考えは持っていない。我々の考え―というよりは聖書の考えと言ったほうが正しいが―では、サタンは神のために用いられている言わば「道具」に過ぎない。我々は、サタンが単なる神の役者または不幸な仕え人であると理解する。それは詳しく言えば一体どういうことであろうか。それは、つまりこういうことである。「神は永遠に至るまでもご自身の栄光を最大限に現わされるためにこそ、あえてサタンの存在と彼の行なう悪を永遠に至るまでも許容し続けられる。」この理解においては、サタンが神に対立する言わば永遠のライバルとして理解されているのではないことに注意されたい。サタンやサタンの悪、またサタンに動かされた人間たちの罪深い行ないがこの地上に存在するからこそ、神の栄光がもっとも豊かに現わされるようになるという理解は、既にライプニッツが「弁神論」の中で(※①)、またジョナサン・エドワーズが「自由意志論」第4部/第9章の箇所で実に正しく論じている通りである。アウグスティヌスも「神は悪者どもの悪しきわざを善用したもう。」(『アウグスティヌス著作集24 ヨハネによる福音書講解説教(2)』第27説教 10 413年 p66:教文館)と言っている。このような考えは、正に聖書が教えている考えである。分かりやすい例をいくつか挙げよう。まず第一は、あのヨセフの例である。ヨセフは彼を妬んだ兄弟たちから売られてしまうという悪を受けたが(創世記37章)、しかし、そのような悪をヨセフが受けたからこそ、後になって大飢饉が起こった際、神によりヨセフを通して多くの人たちが助けられることになった。つまり、ヨセフが悪を受けたからこそ、神の大きな恵みがヨセフを通して人々に与えられることになったのである。それゆえ、ヨセフは創世記50:20の箇所で、このように兄弟たちに言っている。『あなたがたは、私に悪を計りましたが、神はそれを、良いことのための計らいとなさいました。それはきょうのようにして、多くの人々を生かしておくためでした。』この素晴らしい神の取り計らいから、悪が存在するからこそ、神の恵みが大いに現われることになるのが分かるであろう。もしヨセフの兄弟たちが人身売買をするという悪を行なわなければ、ヨセフはエジプトの支配者になっていなかっただろうから、このようにして多くの人々がヨセフを通して大きな恵みを神から受けるということもなかったはずである。第二の例は、我々の主なるお方の例である。主は、サタンとユダの悪により、敵どもの手に渡されて十字架につけられることになった。これは実に忌まわしい悪であったが、サタンとユダがこのような悪を行なったからこそ、キリストが人類の贖いとなられるというこれ以上考えられないほどの善が実現することになった。これは神が悪を用いて、素晴らしい善を生じさせるということの、もっとも良い例だと言ってもいいかもしれない。もしサタンとユダがこのような悪を行なわないか、またはそもそもサタンとユダが存在していなかったとすれば、キリストが我々のために十字架上で救いとなられるという究極の善も実現されなかったかもしれない(※②)。悪が存在するからこそ、神が実現させて下さる善の度合いもそれだけ巨大なものとなるのだ。第三の例は、「Ⅳマカベア書」で描かれている7人の少年たちである。この敬虔な少年たちは、邪悪なエピファネスの悪により亡き者とされたが、しかし、このような悪が行なわれたからこそ、御民イスラエルだけでなく異邦人たちでさえ、大きな恵みを受けることになった。この少年たちが死んだからこそ、ユダヤ人たちの持つ敬神の念が更に研ぎ澄まされ、異邦人たちもユダヤ人の信仰深さに感嘆させられたのである。更にはエピファネスの軍隊ですら、この少年たちから精神的に良い影響を受けることになった。そればかりでなく、この出来事はヒエロニムスやナジアンゾスのグレゴリオス、クリュソストモス、アンブロシウスといった後の時代の信仰者たちにも、良い作用を与えることになった。アンブロシウスは「小さな義務について」という作品でこの出来事を語り、クリュソストモスは、この少年たちを殉教者の模範として称えている。これは、非常に広範囲に及ぶ恵みであった。悪が存在するからこそ、恵みもそれだけ広範囲に行き渡るようになるのである。もしエピファネスがこのような悪を行なわなかったなら、またはエピファネスという邪悪な君主が存在していなかったなら、このような種々の恵みが、イスラエル人と異邦人、更には後世の人間にさえ及ぼされることはなかったであろう。このことは聖書以外にも、多くの事例がある。その一つは、日本に落とされた原爆である。原爆を人の住む地域に落とすというのは、それ自体として考えれば誠に由々しき悪行であるが、しかしそのような悪が1945年に行なわれたからこそ、それ以降今に至るまで核兵器が人の住む地で使われるという悲惨が起こらずに住んでいる。それは、広島と長崎に行なわれた悪の記憶が、誰かの持つ核兵器を使いたいという欲望を抑制させているからである。つまり神は、あの原爆投下という悪を用いて、長い間核兵器が使われないようにさせるという平和の恵みを我々人類に与えて下さったわけである。もちろん、だからといって私が原爆投下を首肯しているというのではないが、しかしこのような悪が行なわれなければ、一体この世界はどうなっていたことであろうか。もし原爆があの時に落とされなかったとしたら、もっと破壊力のある核兵器が最初から使われていたかもしれないし、いきなり核戦争が起こって地球の大部分が破滅していたかもしれない。実際はどうなっていたか分からないのではあるが、しかしこのようになっていた可能性は十分にある。いずれにせよ、あの2つの原爆投下が、非常に長い間抑止力を生じさせるために用いられていることは確かである。このような例から分かるように、神の恵みが最大限に現わされるためには、悪い者の存在や悪が行なわれることが必要となる。もし悪がなかったとすれば、ヨセフの善行も、キリストの贖いも、戦後における核の不使用も、起こらなかったかもしれないのである(※③)。このようなことのために、神は永遠に至るまでもサタンが存在することと、彼が悪を行なうことを許されるのである。それは、神の栄光がこの地上において、もっとも豊かに現わされるようになるためである。つまり、サタンは神の計画のために動かされている奴隷のような存在に過ぎない。我々をゾロアスター教だなどと言って批判する者たちは、このようなことを何も理解していない。我々は、サタンが単なる神の栄光の仕え人だと考えているだけであって、サタンが神と永遠に対立し続ける究極のライバル的な存在だなどとは塵ほども考えてはいない。このような批判者たちは、カルヴァン主義をその予定説のゆえに「ストア派の運命論」だと言って揶揄したアルミニウス主義者たちと非常によく似ている。アルミニウス主義者たちは、次のように言ってカルヴァン主義者たちを批判したものである。すなわち、カルヴァン主義によれば救いも永遠の滅びも既に永遠の昔から確定しているのだから、我々人間がどれだけ善を行なおうが怠惰になろうが最終的な運命は絶対に不変であり、そのため人間を不敬虔や怠惰の悪徳に陥らせてしまう、と。しかし、アルミニウス主義者は荒唐無稽なことを言っていた。彼らは聖書もカルヴァン主義のこともよく理解できていなかった。確かにカルヴァン主義は人間の最終的な運命が不変であると考えるが―何故ならそれは人が生まれたその瞬間から既に決まっているのだから―、だからといって、人を不敬虔や怠惰の悪徳に陥らせてしまうということにはならない。このアルミニウス主義者たちと同じように、我々をゾロアスター教の善悪二元論だなどと言って批判する者たちも、荒唐無稽なことを言っている。彼らは、我々がどのようなことを考えているのか、よく理解していない。今言われたことからも分かるように、もししっかりと理解していたとすれば、このような批判をすることはできなかったであろう。彼らは、サタンの存在と悪い行ないを神がこの地上において永遠に許容され続けることについて、何か誤解をしている。先にも述べたように、神の栄光が最大限に顕現されるためには、そのような悪い存在がどうしてもなくてはならないのである。もし神がご自身の栄光のために悪を許容させられることが気に入らないのであれば、今までに実現された、神の悪を用いた素晴らしい御業をも全て否定しなければいけなくなる。ヨセフの例も、キリストの例も、否定しなければいけなくなる。一体どこの誰が、このような神により起こされた出来事を批判できるであろうか。聖徒であれば絶対にできないはずである。もし批判できないというのであれば、神がご自身の栄光のために悪を許容されるお方であるということを、事実上認めていることになる。であれば、神が永遠にそのようにして悪を許容され続けると主張する我々をも、批判できないことになる。「蜂の寓話」で有名なマンデヴィルもこのように社会のためには悪が必要だなどと言って大いに批判されたものだが、マンデヴィルは批判されても、神がそのようにされることは批判すべきではない。神が、ご自身の栄光や善のためにあえて悪をお許しになられるのだ。誰がそのことを批判してよいであろうか。もし批判する人がいたら、その人は、自分がそのように神の行ないを批判するという悪をも神が許容しておられることに気付いていないのである。
(※①)
この本はキリスト教の知識を増加させるためには、いくらか役立つであろう。この本では、ディドロも死にたくなったほどの学識を持つライプニッツのキリスト教に関する知識が、これでもかといわんばかりに並べ立てられている。ライプニッツはルター派であった。
[本文に戻る]
(※②)
神が、サタンに動かされたユダの極悪を善に変えて用いられたというこのことについては、アウグスティヌスもこう言っている。「…神が善であればあるほど、ますますわたしたちのなした悪事を善用したもう。ユダよりも悪いものは何であろうか。先生に帰依していたすべての人のなかで、また12弟子の中で、金袋が彼に委ねられ、貧しい人たちへの扶助が割当てられていた。このように大きな寵愛とこのように大きな名誉に感謝しないで、金を彼は受け取り、正義を失った。彼は死んでいたので命を裏切った。彼は弟子として従ったかたを敵とみなして迫害した。これがユダのなした悪事の全体であったが、主は彼の悪事を善用したもうた。主はわたしたちを贖うために、自分が裏切られるのに耐えられた。見よ、ユダの悪事は善に変えられた。」このように言った後、アウグスティヌスはユダからサタンの悪に視点を移して、同じ事柄についての話を続ける。「サタンがどれほど多くの殉教者たちを迫害したか。もしサタンが迫害するのをやめていたら、わたしたちは今日聖ラウレンティウスのかくも栄誉ある王冠を祝うことができないであろう。したがって、もし神が悪魔そのものの悪しきわざを善用しないとしたら、悪人が悪用してなすものは自分自身を害しても、神の善性を反駁することにはならない。神は制作者として悪魔をも用いたもう。また神は偉大な制作者として悪魔を用いることを知らなかったとしたら、悪魔の存在を許したまわなかったであろう。」(『アウグスティヌス著作集24 ヨハネによる福音書講解説教(2)』第27説教 10 413年 p67~68:教文館)
[本文に戻る]
(※③)
神は、このような意味においては、つまり善の最大化のために悪が必要となるという英知の観点からは、悪を欲される。もちろん、神が悪を、それ自体として欲しておられるのではないことは言うまでもない。このことについては、ルターもこう言っている。「神が悪または罪を欲しておられるということは真である。…神はほかの仕方で悪を欲する。すなわち、悪は神のそとにあり、人にせよ悪魔にせよ、ほかのものが悪を行なうのである。…このように神はなにかほかのあることのために罪をお望みになる。すなわち、ご自身の栄光のため、選ばれた者のためである。以下で、神がパロを立てて、頑なにしたのは、彼においてご自身の力を示すためであったと、パウロが言うとき、このことは明白になるであろう。また同じく、「私は、私が欲する者をあわれむ」ともある。このように、ユダヤ人の咎によって救いが異邦人のものとなる。神はそのあわれみを異邦人により明らかに示すために、ユダヤ人をして墜落せしめたのである。神がお許しになるのであければ、どのようにして彼らは悪であり、悪を行なうことなどできようか。神は、お望みになるのでなければ、どうしてお許しになるだろうか。神は欲しないでこれをなさるのではなく、欲してこれをお許しになる。神はこれを欲して、反対の善がいよいよ輝くようになさる。…」(『ルター著作集 第二集 第8巻(ローマ書講義・上)』スコリエ 第1章(付論) p247~248 聖文舎)次の文章も、同様のことが言われている。「聖徒たちにはすべてのことがよいことへと働くのだから、いわんやましてキリストと神には悪でさえもよいことへと働くのである。事実、神が働いておられれば、悪は溢れるばかりに善に貢献する。他者の善にばかりでなく、悪に関わる人自身の善にも貢献する。」(『ルター著作集 第二集 第9巻(ローマ書講義・下)』スコリエ 第11章(11) p240 LITHON)
[本文に戻る]
しかし、これから今のような世界がずっと続くというのは異端の理解ではないのか。このように思う人に、私は問いたい。再臨の日に、旧約聖書の預言は、すべて成就されたのではないのか。確かにキリストは、『これは、書かれているすべてのことが成就する報復の日だからです。』(ルカ21章22節)と言われた。ここで言われている『報復の日』がユダヤ戦争の時期に訪れたのは、この御言葉が書かれているルカ21章やその並行箇所であるマタイ24章の文脈を考えれば明らかである。主は『エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら』(ルカ21章20節)、その日が訪れると言われた。エルサレムが軍隊に囲まれるというのは、ローマ軍がエルサレムを包囲したあのユダヤ戦争の時期のことでなくて何であろうか。もし、その日に旧約聖書の預言がみな成就したのであれば、当然ながら、その日には『見よ。まことにわたしは新しい天と新しい地を創造する。』(イザヤ65章17節)また『わたしの造る新しい天と新しい地が、わたしの前にいつまでも続くように、』(同66章22節)という預言も成就したことにならないであろうか。もちろん、聖書を信じる者であれば、そのことは認めざるを得ないはずである。もしそうでなかったとすれば、主がルカ21:22で言われたことは、偽りだったということになってしまうからである。そうであれば、聖書はこの日に新しく造られた天と地が、いつまでもずっと続くと教えていることになる。聖書からこのように合理的に説明する私が、異端などと言われるのは、いかがなものであるかと感じられる。しかし、このように正しいがその当時にあっては受け容れ難い説を唱える者は、異端視されるのが世の常である。例えばキリストがそうであった。主は、真理ではあるが衝撃的なことを多く教えられたので、それを受け入れられない当時の人たちは大いに反発したものである。中には主が悪霊に憑かれているなどと口にした者もいたほどである。パウロもユダヤ人には受け容れ難いことを教えたので、『この人は、律法にそむいて神を拝むことを、人々に説き勧めています。』(使徒行伝18章13節)などと言われて訴えられたものである。ウィクリフも、ただ聖書にだけ従うべきだと正しいことを主張したが、当時のローマ・カトリックの反発を買って殺されてしまった。まともなことを言ったら、異常者扱いをされてしまったのである。16世紀頃の地動説論者たちも、気の狂った異端者だと見做された。コペルニクスは当時の人々に反発されるのを恐れて、「天球回転論」という地動説に関する歴史的な作品の出版を差し控えたものである。ケプラーも、正しいことを考えたり言ったりしたために、非常な孤独感を味わわされた。ガリレオが宗教裁判において自説を撤回させられたことは、誰でも知っているはずである。ルターとカルヴァンでさえ―宇宙の真実について神の言葉から正しいことを教えるように望まれていたこの2人の教師たちでさえ―、地動説論者たちを異常視して辛辣に批判したほどである。冷遇されてばかりいたコペルニクス自身が言っているように、当時の著作家たちは、天動説と「反対のことを思うことが考ええないこと、あるいは笑うべきこととさえ見なしているいるほど」(『コペルニクス天文学集成 完訳 天球回転論』第1巻 第5章 p30:みすず書房)であった。しかし、地動説論者であった彼らはみな悪く言われたにもかかわらず、実は真実なことを教えていたのである。このように、真実なことを主張する者が異端者であると見做されるのは、今までの歴史を考えれば何も不思議なことではない。むしろ、真理に疎い傾向を持つ人間の性質を考えれば、真実な考えが登場した際に、それを拒絶してしまうのはかえって自然なことであるとさえ言えよう。もし教会の常識的な見解に反しているというだけの理由で、私を異端視するというのであれば、その人はルターを異端視したカトリック教徒と同じことをしている。ルターは、ただ教皇の教えに服従しないからというだけの理由で、カトリックから異端者だと宣言されたのである(※)。何故なら、教皇に従わないのはカトリックにおいて破門に値する重罪だったからである。教皇に服従しないのは、カトリックの常識に反することであった。つまり、カトリックは聖書を聖書とするのではなく、教皇の教えをこそ聖書としていたと言える。それと同じように、常識に適合しないからというだけの理由で私を非難する人は、聖書ではなく常識をこそ聖書としている。その人の聖書である常識に適合しないからこそ、その常識にそぐわないことを教える私を異端視するわけである。このような人は聖書に立てていないから、聖書に立つことを求める私と議論する相手としては相応しくない。そもそも議論の前提となる土台が異なっているからである。常識を土台とする人と、聖書を土台とする人。この2者がまともな議論を行なえないことは明白である。つまり、前提がお互いに違うので、話がかみ合わない。それゆえ、このような人は聖書を考究するという点においては、「お話しにならない。」と言わねばならない。もし教会の常識的な見解に適合していないからというので私のことを異端だなどと言うのであれば、その人は何とでも叫んでおればよい。私の言ったことが間違っていなかったということは、これから歴史が証明してくれることであろう。
(※)
ルターは教皇の教えに反する説教をしたので、正しい説教をしたにもかかわらず、異端者だと認定されてしまった。次のようにルター自身が言っている通りである。「この説教が罪と死からの贖いをもたらすのに、それにもかかわらず異端者呼ばわりされて、人々がこのような助け主を今なお迫害していることを聞くのは、恐るべきことである。今やわれわれは毎日この説教を訴えているのに、ことがこんな具合に進んでいることをなお見ているのである。私が語っていることは、乳飲み子の乳しゃぶりではない。キリストご自身が語っておられることをあなたがたは聞いているのである。それなのに、異端者呼ばわりされることになる。」(『ルター著作集 第二集7 ヨハネ福音書第3章・第4章説教』第33説教 第3章(19)p170 LITHON)
[本文に戻る]
さて、キリストや使徒が言ったように、紀元1世紀の人々が生き残っている間に主の再臨が起きたと信じるならば、そのように信じる人はある2つの未来観のうち、どちらか一方の未来観を持つことになる。その一方は誤謬であり、もう一方は真実な理解であって、どちらも真実であるとか誤謬であるということはない。その人は、もし考えを留保させるのでなければ、この2つのうち、必ず、どちらか一方の未来観を持たざるを得ない。第3の未来観は恐らく存在しないと思われる。たとい何とかして第3の見解を考え出したとしても、それは真実な理解に基づく未来観ではないはずである。その2つの未来観とはどういったものか。まず一つ目は、従来の未来観をほとんど変えないことである。このような人たちには、自分が前から持っている未来観を捨てたくないという固執の欲望と、教会の一般的な未来観に背きたくないという弱さに基づく恐れがある。そのため、彼らはこれからキリストが再臨されるという教会の常識的な未来観に反する未来観を持たないように、2度目の再臨があるなどと主張している。また彼らは2度目の再臨があると共に、2度目の終末もあると考えている。何故なら、もし再臨が2度あるのであれば、その再臨の前には悲惨な終末も訪れるだろうからである。それゆえ、彼らはこれからサタンが解放された後で2回目の再臨が起こるなどと信じ、そのように主張している。このような未来観は、今までに教会が持ってきた常識的な未来観と、ほとんど変わることがない。どちらも、これからキリストが再臨されると信じている点では何も異なっていない。それゆえ、彼らは、その偽造の罪のために、多くの教会からの反発を免れていることができている。それは彼らが常識的な未来観に抵触することを言っていないからである。昔から不敬虔に振る舞えば世俗の非難を避けられるというのが世の常であったが、彼らもそのようにしていると言えよう。2度目の再臨があるなどという自分勝手で非聖書的と言うべき見解を発明したからこそ、多くの教会からそれほど非難されずに済むわけである。しかし、このような未来観は誤謬である。次は2つ目だが、それは教会の一般的な未来観を気にしたり恐れたりしないことによる未来観である。この人たちは、自分が前から持っていた未来観に固執したり、教会の常識的な未来観から外れることを恐れたりせず、ただ聖書が何と言っているかということにこそこだわる。そのため、頑固さや弱さに基づく恐れのゆえに、2度目の再臨があるなどとは考えない。だから、この人たちは必然的に、これから世界が永遠に今のような状態のままで継続されると考え、信じ、そのように主張する。何故なら、2度目の再臨がないのであれば、そのように理解する他はないからである。この人たちの未来観は、これから今の世界がずっと続くという未来観であるから、当然ながら従来の一般的な未来観とはかなり異なっている。それゆえ、このような人たちは、多くの教会から非難を受けてしまうことになる。何故なら、今までに教会が信じてきたこととは別のことを言っているからである。しかし、こちらのほうの未来観こそ、真実な理解に基づく正しい未来観である。このように、再臨が既に紀元1世紀において起きたと理解するのであれば、これから再び再臨が起こるのかどうかという見解の違いにより、2つの未来観に分かれることになる。もし2度目の再臨が起こるという見解を取れば従来の未来観が保たれ、もし再臨は1度きりの事象であるという見解を取れば今までとは異なる未来観を奉じるに至る。この2つの未来観のうち、どちらが正しいかは火を見るよりも明らかである。すなわち、正しいのは今までとは全く異なる未来観のほうである。というのも聖書を読むならば、第1部でも既に述べられたように、再臨は1度だけしかないとしか解せないからである。一体どのようにすれば、再臨が2度起こるなどという考えを生み出せるのか。今では再臨が2度起こるなどと考えている者たちも、以前であれば、再臨が2度起こるなどとは塵ほども考えなかったはずである。そのようなことを言う者がいれば、彼らは、その人を無視したり批判したり大いに軽蔑していたりしたことであろう。というのも再臨が2度起こるなどとは、どうあっても聖書から読み込めないからである。彼らは、頑固と恐れのために、勝手に2度目の再臨を発明し、従来の未来観に留まり続けようとしている。これは安全と平安のために真理を犠牲にすることである。しかし正しく認識するのであれば、再臨は1度限りの現象であるとしか理解しないはずである。再臨が1度限りしかないとすれば、必然的に、今の世界がこれから永遠に続くと考えざるを得なくさせられる。よって、再臨が既に起きたと信じる者たちにおいては、従来の未来観を保つのは誤りであり、従来の未来観とは異なる未来観を持つのが正解だということになる。
それでは、教会の歴史にける繁栄と衰退については、どういうことが言えるのであろうか。これから教会はその勢力と力とを増し加えていくのであろうか、それとも徐々に衰えていくのであろうか。まず、多くの教会がそうなると信じているように、これから教会が、悪魔の勢力に屈服させられて、見るも無残な状態に陥るということはない。何故かと言えば、そのようなことが預言されているマタイ24章や黙示録は、既に成就しているからである。もしこれらの文書がまだ成就していないことを預言していたとすれば、確かに、これから邪悪な存在が出てきて教会を徹底的に打ち負かすことになっていたであろう。よく言われる「反キリスト」のことである。しかし既に十分なだけ説明されたように、これらの文書に書かれている預言は既に成就したのだから、そのようなことがこれから起こるとは考えられない。よって、マタイ24章や黙示録に基づいて恐るべき未来がこれから訪れると信じている兄弟は、自分の考えを捨て去らなければいけない。まだ思想的に堅固あるいは頑固になる50代後半になっていない人であれば、自分が昔から持っている考えを捨て去るのは、それほど難しいことではないはずである。聡明なリークワンユーも、50になるまではまだ変われるチャンスがあると述べている。特に10代、20代の若い方がたは今のうちに目を覚ますべきである。さて、これから教会がどうなっていくのかと言えば、それはこのようである。すなわち、神は教会勢力を長らく悲惨で不幸な状態の中に留めさせておかれ、『時期』(伝道者の書3章1節)が来ると大きな恵みを注がれて大々的な回復が実現させられる、ということである。神は、教会の歴史に、このようにして繰り返し繰り返し永遠に至るまでも働きかけられる。このような教会における素晴らしい回復の出来事は、既にもう2回ほど起こっている。1回目は、ローマに縛られ苦しめられていたキリスト教徒たちが、コンスタンティヌス帝の登場により、一挙に幸いな状態を享受することになった出来事である。この皇帝が登場するまで、聖徒たちは約300年の間、迫害と困難に長らく苦しんできた。しかし回復の時が来たので、神がコンスタンティヌス帝を起こされ、この皇帝により聖徒たちの状態を天地が逆さになるぐらいに変わるようにして下さった。これは、長い苦しみから神により解放されることであった。当時の聖徒たちは、この良き変転をどれだけ喜んだことであろうか。2回目は、堕落していた教会が、ルターの登場により根本的に刷新されることになった出来事である。アウグスティヌスが没してからルターが出るまで教会は1000年間も堕落した状態に留まっていた。それゆえ、この期間にはクレルヴォーのベルナルドゥスぐらいしか恵まれた指導者が現われなかった。トマス・アクィナスなどの有名なスコラ学者も出るには出たが、彼らは学はあっても愚かにもアリストテレス哲学をキリスト教に混入させたのだから、彼らの存在は教会が堕落していたことを示すものとして見做されるべきであろう。今でも彼らはよく揶揄されるものである。しかし、暗黒の時代が終わる時が遂に訪れたので、神が無名の修道士に過ぎなかったルターを起こされ、教会が新しいステージに移行するようにして下さった。その移行先のステージとしての教派が、我々のプロテスタントなのである。これもコンスタンティヌス帝の場合と同じ大変転であって、霊的な腐敗からの大いなる解放であった。神がこのようにして下さらなければ、我々は今でもサタンのシナゴーグの中で種々様々な汚物にまみれていたことであろう。バルトはどうか、と言われる方がいるかもしれない。バルトの登場は、このような回復の働きに含めることができない。というのは、バルトの登場は、コンスタンティヌスやルターの場合とは、かなり内容的に異なっているからである。バルトは確かに教会に大きな影響を与えたが、教会を堕落や腐敗から引き上げたというのではなく、むしろ更に悲惨な状態にさせた人物だからである。彼の神学はつまり万人救済主義の異端なのだから、どうしてこのような者を、神の歴史的な働きに用いられた者として見做すことができようか。バルトの愛好者には残念かもしれないが、彼はコンスタンティヌスやルターのような恵みを受けて用いられた人物だとは言い難い。では、改革派で高く評価されることの多いコーネリウス・ヴァン・ティルはどうであろうか。彼のことをキリスト教で最大の神学者だと呼ぶ人もいる。しかし残念ながら彼も、そうではない。何故なら、神は教会の歴史に働きかけられる際、その勢力の全体を回復の恵みに浸らせられるからである。コンスタンティヌスとルターが正にそのようであった。しかしヴァン・ティルという神学者は、その神学は注目すべきではあるもののプロテスタント全体を刷新させたとは言い難い。事実、彼のことをあまり知らない教師も少なからずいることから分かるが、彼の影響は部分的に留まっていると言わねばならないのである。このような教会のダイナミックな回復は、まだ2回しか起こされていない。しかし、これからも神はこのようなことを教会に実現させて下さるはずである。次に来る3回目は、プロテスタントもカトリックも東方正教会も、全ての教派が全体的に大きな衝撃また影響を受けることになる回復となるであろう。その3回目の時にも、やはりコンスタンティヌスやルターのような言わばシンボルまたアイコン的な存在が目に見える形で現われるだろうから、多くのキリスト教徒がその人物に注目し、何か尋常ではないことが起きていることに気付くはずである。神は、教会の歴史に対し、このようにして永遠に至るまでも働き続けられる。それゆえ、教会にはこれからも、長らく悲惨を味わった後で急変的な回復の恵みにあずかるということが繰り返される。何故なら、これこそが神の取られるやり方だからである。長らく非常に苦しんでいる状態にある教会を、ご自身の恵みを与える仲介者となる者を通して大いに癒されたり改善させられたりする。こうすることこそ、もっとも神の栄光が現わされることに繋がるゆえに、神はこのような手法を取られるのである。神がこのようなやり方を好まれるというのは、旧約聖書の士師記を見ても分かる。この書物では、イスラエル人が長い間苦しんだ末に助けを呼び求めると神による救助者が与えられて苦しみから解放されることになった、という話が繰り返し繰り返し記されている。神がモーセというご自身の使いを通して430年の間苦しめられていたイスラエルを遂に解放させられたというのも、同様のことである。このような長い苦しみからの聖なる解放劇が、これからの教会の歴史において起こされる出来事であって、それは永遠に繰り返されるのである。神は、そのようにして教会の歴史の中で、ご自身の栄光をとこしえまでも現わされ続けるのである。また、このような手法は、教会以外の領域、すなわちこの世の領域においても神が取られる手法である。そのもっとも良い例は、コペルニクスにより全世界の宇宙観が完全に変えられたことである。コペルニクスが現われるまで、この世界は数千年もの間、天動説という誤謬から抜け出せずにいた。そもそも、それが誤謬であることすら見抜けなかった。何かがおかしいと天文学者たちは感じていたのではあるが、それでも天動説が誤謬であるという認識には至らなかった。しかし、神がコペルニクスを登場させたことにより、人類はこの誤謬から遂に解放されて、地動説という真実な理論を享受できるようになった。これは霊的であるか自然科学的であるかという点を除けば、コンスタンティヌスやルターの場合と、本質的に言って何も変わらないことであったと言える。どちらも、神の起こされた救助者により、世界が大幅に変えられることになった。それゆえ、この世の領域においても、教会の歴史と同じように、神はある一人の者を通して悲惨な状態を改善させられる恵みを与えられることを好まれるということが分かるであろう。それでは、教会は歴史において拡大していくのではないということであろうか。キリストは、御国が拡がったり大きくなったりすると言われたのではなかったか。確かに主は、マタイ13:31~33の箇所で、御国についてそのように言われた。そこには次のように書いてある。『イエスは、また別のたとえを彼らに示して言われた。「天の御国は、からし種のようなものです。それを取って、畑に蒔くと、どんな種よりも小さいのですが、生長すると、どの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て、その枝に巣を作るほどの木になります。」イエスは、また別のたとえを話された。「天の御国は、パン種のようなものです。女が、パン種を取って、3サトンの粉の中に入れると、全体がふくらんで来ます。」』まず言っておかねばならないのは、これは紀元1世紀の時点で既に実現しているということである。それは、この箇所の文脈を見れば明らかである。ここでは、今から2千年前に過ぎ去った世の終わりの時期のことが言われている。すなわち、再臨が起こる終わりの日までに御国はこの地上で大きく発展するであろう、ということがここでは教えられている。実際、既に我々がパウロによる聖句から見たように、使徒の時代において御国は地上で豊かに拡がり満ちていた。主は、まだ実現していなかったことではあるが、ここでパウロが言ったのと同じことを言われたのである。すなわち、主はこれから未来に実現されることをあらかじめ言われ、パウロは主の言われたことが正に実現されていることを言った。しかしながら、この主の御言葉では御国の性質、すなわち原理的なことが言われているのだから、再臨以降の時代における教会にも当てはめて考えることができる。すなわち、天の御国の福音を宣教する地上の教会は、いつの時代であれ『からし種』や『パン種』のように巨大化する性質を原理的に持っているということである。それゆえ、教会は人数的な面において増え広がる傾向を持っている。それは、この2千年間の歴史を見ても分かるであろう。人数的に言えば、教会は今に至るまで増え広がる傾向を持っている。主の御言葉から察せられるように、神は、教会が大きな木や膨張したパンのような状態にあることをお望みである。それゆえ、そのような状態になるまでは、教会がこの世界において人数的に増し加えられることが許されている。しかし、そのような巨大な状態になると、それは既に神の満足される教会の状態なのであるから、それ以降、あまり人数的には増えなくなってしまうことになる。それは、ここ数十年の間、キリスト教の信徒数が20億人程度からほとんど変化していないことからも分かる。たとい人数が減って木やパンのような状態でなくなったとしても、やがて再び元の状態に戻ることになる。何故なら、教会とはこの世界において本来的に木やパンのような状態であるべき存在だからである。もちろん、もし教会が罪や不信仰や怠惰に陥るのであれば、短い期間であれ長い期間であれ、人数的にかなり衰えてしまうことになってしまうのは言うまでもない。そのようになるのは裁きが下されるためであるから、仕方がない。しかし、この場合も、もし罪や不信仰や怠惰が教会から取り除かれるのであれば、再び元の大きな状態へ戻れるようになる。このように教会は人数的には大きな存在に保たれるまで増えることになるが、しかし、その中身すなわち内実においては常に堕落する傾向を持っている。それは教会が罪人の集まりだからである。そのような内面の堕落を改善させるためにこそ、神は教会の歴史において、その悲惨な状態を良くする救助者が起こるようにされるのである。我々は、教会の歴史における数の変化と内実の改善という2つの事象を、しっかりと弁えつつ理解しなければならない。すなわち、教会はその数においては罪が見られない限り一定の状態にまで拡充される。しかし内実のほうは必ず腐敗してしまうので、ある一定の線にまで達すると神がその状況を改善させるべく介入される。よって、教会が数的に増加しているからというので今後も数的に増加し続けるだろうとか、内面における堕落の傾向が止まらないから今後も教会は堕落し続けて滅亡に至ってしまう、などと考えることはできない。増加の現象には限度があるし、堕落の現象にも「ここまで。」という線が存在している。多くの人は、人数における拡大の現象を見ては拡大が続くと信じ、堕落の傾向を見ては堕落が止むことはない、もう教会は駄目なのだ、と思いがちである。というわけで、教会がこれから歴史においてどのようになっていくのか、という事柄については以上で必要十分なだけ語られたことにしたい。また何かこの箇所で付け加えるべき内容が出てきたら、その都度、その内容が付け加えられることになるであろう。
この新しい時代において、そこに生きる選ばれた聖徒たちは、最終的にどうなるのであろうか。キリストにつく彼らは、その地上における命の限度に達した時、天の御国へと引き上げられる。それは生きたままであり、『たちまち、一瞬のうちに』(Ⅰコリント15章52節)起こるであろう。つまり、古い身体から新しい身体に切り替わるその瞬間に、同時に天へと存在が移行させられる。この天への引き上げが、御使いたちの手によるものかどうかということについては、よく分からない。前にも書かれたが、携挙および火の池へ投下する仕事は御使いたちに委ねられているが、天へ引き上げることまでも彼らに委ねられていることは聖書から証明できない。聖書には、天への引き上げも御使いたちの仕事であるなどとは明白に書かれていないからである。しかし、この天への引き上げも御使いたちに委ねられている可能性は十分にある。いずれにせよ、我々が天に上げられた時、このことについての真実を明白に知るようになるはずである。要するに、新しい時代の聖徒は、古い時代の聖徒がそうだったように、この地上での人生を終える際に、魂と身体が分離されるという現象が起こらない。そのような現象は、あの「主の日」を境として終わったのである。今の聖徒がそのままの状態で天へ移行させられるということは、既に紀元1世紀の時代に生きていた聖徒たちが前例として存在しているから、我々はこのことを何か不思議がったりすべきではない。我々も、パウロと共に生きていた聖徒たちが生きたままで上へ引き上げられたように、やがて上へ引き上げられるようになるのである。新しい時代の聖徒は、この地上の人生を終えたその時、いつの間にか天に上げられていることに気付くことになる。そうして後、その聖徒は、天の御国でキリストと多くの聖徒たちと共に永遠に至福のうちに生きることになる。この天国については、既に第5章で多くのことが論じられた。それでは、滅びに定められた者らは、最終的にどのようになるのか。この者たちは、死んだその時、燃える火の池の中に投じられることになる。それは、生きたままの状態で起こり、瞬く間にそのようになる。つまり、死んだその瞬間に新しい滅びの身体を受け、その身体を受けると同時に火の池の中に投げ込まれてしまう。古い身体は、魂なき死体として、この地上の世界に置き去りにされることになる。これは言わば「抜け殻」のようなものである。既にその人の魂は新しい身体と共に、別の世界へと移されているのである。滅びに至る彼らにも、やはり聖徒の場合と同じように、もはや古い時代のような現象は起こらない。新しい時代の不信者たちも、死んだ際、かつてのように魂が身体から離れて完全に孤立するということはない。また魂だけがハデスに投じるということもない。もう既に、第一の死とハデスとは、第二の死と火の池に置き換えられてしまっているからである。また毒麦たちが空中から御使いたちの手により、火の池に投げ込まれたように、新しい時代に生きる不信者たちも死んだ際には御使いたちの手により火の池に投げ込まれてしまう。神の御前における腐敗物を処理するのは、御使いたちに任された仕事なのである。それは、あたかも大屋敷の主人が、ゴミ捨ての仕事を自分の使用人に行なわせるようなものである。このような破滅的終末を受けた者についても、既に明白な前例が存在している。それはネロと空中に上げられたが罰を受けることになった毒麦どもである。新しい時代の不信者たちは、このネロや毒麦たち、また今までに死んだ全ての不信者たちが苦しんでいる火の池に投げ込まれるのである。そこに生きたままの状態で投げ込まれた彼らは、そこで永遠に至るまでも苦しみと裁きとを受け続ける。この火の池についても、天国と同じように既に多くのことが語られたから、ここで再論する必要はないであろう。
第8章 聖徒の信仰生活について
まず聖徒である者は、この新しい時代において、多くの聖徒がそうしているように再臨を待望するべきではない。何故なら、再臨は既に起こったからである。今まで2千年の間、ほとんど全ての聖徒が「再臨は近い。それゆえ我々は再臨を待ち望まなければならない。」などと考えたり、言ったりしてきた。しかし、そのように考えたり言ったりしたのは、―私はハッキリと言うが―、すべて意味のないことであった。何故なら、この2千年の間、アウグスティヌスであれルターであれ実に多くの聖徒が再臨を待望したが、再臨はまったく起こらなかったからである。これは当たり前である。既に再臨は起きたのだから、どれだけ再臨を待ち望んでも、再臨が起こることなどないのである。ここまで読み進められた方は、このように意味のないことを願うのが、聖書の理解不足に基づいていることをよく理解できるであろう。聖書をよく理解できていないからこそ、再臨についても、意味のないことを言ったり願ったりするわけである。だから、これから再臨が起こるなどと願っても、それは我々にとってはまったく無意味なことである。もう一度はっきりと言うが、今の聖徒たちは起こりもしないことを無意味に願い求めているのである。今の聖徒たちは、まだ再臨が起きていなかった紀元68年6月9日以前の時代に生きていた初代教会の聖徒にでもなったつもりでいるのか、と私は少し冷たいようではあるが思うのである。だが、再臨がこれから起きなかったとしても、悲しむ必要はない。何故なら、我々はこれから数年後、数十年後には、主に会うことができるからである。再臨を待ち望まないからといって、主に会うことができなくなるというわけではない。たとい再臨を待望しなくても、我々がやがて天に行って栄光のキリストを見ることができるということは、何も変わらない。再臨がなくても、やがてキリストに会えるのであるから、我々はそのことだけでもって十分に満足するべきであろう。再臨を待望しなければ何か致命的な問題が生じるというわけでもないのだから。また聖徒たちは、これから世が終わるなどとも考えるべきではない。既に世の終わりはキリストの再臨された日に訪れ、過ぎ去ったからである。既に2千年前に過ぎ去った終末を、まだ訪れていないかのように考えるのは、間違っている。我々がこれから終末が来るなどと考えても、そのような終末が来ることはない。実際、今まで2千年の間、実に多くの聖徒が終末が近いと考えたり言ったりしてきたが、そのような終末はまったく来なかったではないか。また実に多くの聖徒がこれまで「今」(※その聖徒が生きているその時代における「今」)こそ終末の時代だなどと考えたり言ったりしてきたが、世が終わることなどなかったではないか。もしこれから世の終わりが来るとか今こそ終わりの時であるなどと考えるならば、そのような人には、霊的な罰が与えられる。その罰とは、とんでもない誤解をすることで心を煩わせるという罰である。その良い例はルターである。ルターは自分の生きている16世紀こそが終末の時だと心から信じていたので、そのような誤った聖書理解に対する罰として、教皇こそが終末に現われる「反キリスト」であるなどと本当に信じてしまった。これはルターの著書を読めば誰でも分かることである。確かに彼は「反キリスト」ではあったが、しかし終末時に現われるあの666なる獣ではなかった。それは既に我々が見たように、ネロ帝のことであった。このような誤解のために、ルターの心から平安が多かれ少なかれ失われてしまったことは間違いない。ルターが終末を正しく理解し、教皇が終末時に出てくる凶悪な反キリストであるなどと誤解していなければ、どれだけ彼の心は平安を持つことができたであろうか。これはヒトラーやEUの首領などを終末時に出てくる邪悪な権力者だと信じてしまう聖徒も、同じことである。彼らは終末が既に過ぎ去ったことを知らないので、「ヒトラー(またEU大統領)こそあの預言されていた反キリストではないのか?そうだ!もう世界の終わりが近付いているのだ!これから世界は大変なことになるだろう!」などと慌てたり平安を失ったりしてしまうのである。中にはパニック状態になる聖徒もいるかもしれない。このようになるのは、世の終わりがまだ起きていないという誤った聖書理解を持っているからである。このようにして聖書の預言とは無関係の人物に動揺させられてしまうのは霊的な罰が下されることでなくて何であろうか。もし、このような誤解をして精神状態を悪くさせたくないというのであれば、その聖徒は世がこれから終わるなどという非聖書的なことを考えたり言ったりしてはならない。また聖徒たちは、無数の人間が携挙されて後に行なわれるあの大々的な審判のことも、待ち望むべきではない。これも再臨や世の終わりと同じように、紀元1世紀の時に実現している出来事だからである。もし再び再臨が起こるのであれば、この大々的な審判ももう1度起こることになるが、既に説明されたように、2度目の再臨が起こることはない。しかし、我々の個人的な復活については話が別である。我々がこれから個々的に復活するということは、再臨や世の終わりとは違って、信じるべきことであり、望むべきことである。我々も、紀元1世紀の聖徒たちが復活して天に引き上げられたように、これから復活して天に引き上げられるようになる。再臨や世の終わりがこれから起こるのを信じるのは誤りであるが、この復活のほうまでもう起こらないと考えると、大変なことになってしまう。もし我々がこれから復活しないのであれば、我々が信仰を持っている意味はなくなる。もしそうであれば、我々はこの世界でもっとも惨めな存在になることであろう。何故なら、キリストをただ信じているだけであって、その信仰は何の益も効果ももたらさないからである。それは、パウロが『もし、私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは、すべての人の中で一番哀れな者です。』(Ⅰコリント15章19節)と言っている通りである。この聖徒の復活については、既に本作品の中で十分なだけ説明がされているから、これ以上書く必要はないであろう。さて、このように再臨や世の終わりを待望したりしないのは、少し驚かれる人もいるかもしれないが、聖徒に対する恵みである。というのは、そのようなものを待望しないことで、無気力また怠惰になったり、不安になったりしなくて済むようになるからである。多くの聖徒を見れば分かるように、このようなものを待ち望むと、往々にして、どうしても精神が落ちつかなくなったり改進的な姿勢が持てなくなってしまうことに繋がる。キリストがもうすぐにも再臨されると心から信じていたら、論理的に考えて、何か素晴らしいことをしてもすぐに置き捨てなければいけなくなるということになるから、建設的な人生を送れなくなる傾向が生じてしまう。中には再臨を待望しても建設的な人生を送ろうとする人もいるが、しかし傾向としては、確かにこのように言える。明日にも再臨が起こるかもしれないなどと本当に考えている人が、どうして偉大なことを実現させるために長期的なプランを立てられようか。ウェルギリウスが「アエーネイス」に10年の歳月を費やしたように、アダム・スミスも「国富論」を10年かけて書いたように、エルサレム神殿が46年また20年かけて建設されたように、偉大な仕事は往々にして長期的な視点が必要となるものである。明日か、または数週間後か、そうでなければ数年後に再臨が起こって自分のしていた仕事が中止されてしまうと考えれば、仕事やライフワークに大きな悪影響が及ぼされるのは言うまでもないことである。それは、あたかも明日死ぬかもしれないと怯えて過ごしている人が、何も力を持って行なえないという悲惨な状態に自分を陥らせているのとよく似ている。それゆえ、この「再臨論」の中で論じられている再臨の教義を受け入れることは、我々にとって大きなメリットがあるということが分かるのではないかと思う。再臨を正しく信じるのであれば、誤解することがなくなり、未来観を正しく持てるようにもなり、建設的な人生が送れなくなるという害を受けずに済むようになる。これこそ我々が再臨を正しく信じることによって生じる大きな益の一つである。残念ながら、今までの教会は再臨を正しく信じてこなかった。それゆえ、誰一人として気付いていなかったかもしれないが、再臨を誤って理解することで、教会からはかなり力と勢いが失われていたはずである。もし教会がこの作品の中で言われているように再臨のことを理解していたとすれば、もっと教会はエネルギーに満ちていたはずである。何故なら、再臨を待望しないので、聖徒が「抑制の鎖」に縛られないで済んだからである。つまり、再臨を待望しないので、「もう再臨が近付いているから静かに生きていよう。」などと思って人生全体が押さえつけられずに済んだわけである。まだこれまでに書かれたことを受け入れていない兄弟は、ぜひ、素直になって再臨のことを正しく信じるようにすることをお勧めしたい。もし多くの聖徒が再臨を正しく信じるのであれば、教会全体に力と勢いが増し加えられることになるであろう。聖徒たちが再臨を正しく理解しているので、神が教会に対して霊的な祝福をお与えくださるからである。神は、聖書を正しく信じる者の近くにこそいて下さる。
この新しい時代においては、預言が成就するようにと、ユダヤの民族的な大回心も求められるべきではない。キリストの再臨された日に、ユダヤの回復についての問題は、完全に解決されたからである。このことについては、もう既に十分なだけ論じられた。これ以上ここでこのことを論じるのは無意味な冗長であろう。
福音伝道については、どうか。この福音伝道は、言うまでもなく、今の新しい世界においても為され続けなければいけない。確かに、パウロやルカが記したことからも分かるように、使徒の時代においてキリストの伝道命令は既に成就していた。これは信仰と理性を持っている聖徒であれば、誰も疑えないことである。しかし、福音が宣べ伝えられて信者が増えて行くようになるというのは、地上の聖徒に対する神の永遠の御心である。つまり、『すべての国民を弟子とせよ。』(マタイ28章18節)また『全世界に出て行き、すべての造られた者に福音を宣べ伝えなさい。』(マルコ16章15節)という主の命令は、既に成就されてはいるものの、そこには神の永遠の御心が示されているのだから、使徒の時代以降に生きる聖徒に対しても命じられていると我々は考えなければいけない。よって、我々は新しい世界が到来したからといって、福音伝道を止めたりすべきではない。今になっても、まだこの世界に神がキリスト教会を置かれ続けているというのは、誰の目にも明らかである。もしそうでなければ、この世界に教会などという存在は今頃、無かったかもしれない。またこの新しい世界においても、救いに定められてはいるが今はまだ失われたままの状態でいる人が多く存在しているということも、疑えない。そのような人が世界のどこかに存在しているからこそ、この世界では日々、多くの救われる人が起こされているのである。そうであれば、神によって存在させられている教会が、そのような選びの子どもたちを捜し求めて伝道をせずに呆けていてもよい、ということがどうしてあっていいであろうか。教会が失われている者の救いを求めて飽きることもなく伝道していかねばならないのは、言うまでもない。もし教会が伝道しなくてもいいというのであれば、教会はたちまち滅亡してしまうことになる。何故なら、伝道をしないので信者が増えず、既に教会にいる人たちは寿命や病気などにより減ってしまうだけとなるからである。そうなれば、数十年の間に教会が急激に縮小し、やがて誰も教会にはいなくなってしまうという事態に陥りかねない。このようなことがあって、どうしていいはずがあるであろうか。またもし伝道活動がされなくてもいいと言うというのであれば、それは我々自身の存在とも大いに関わるということを知らなければいけない。もし伝道活動がされなくてもいいということであったら、我々がクリスチャンになっていたかどうかは定かではない。何故なら、大昔から今に至るまで継続して伝道がなされてきたからこそ、我々にも福音が届けられることになり、その届けられた福音により我々が救われるようになったからである。であるから、クリスチャンであるにもかかわらず福音は宣教されなくてもよい、などと言うのはとんでもないことであるのが分かる。その人は、遠回しに福音宣教が行なわれたからこそ救われた自分自身の存在をも否定していることになる。もしその人の言うように福音宣教が行なわれなかったとすれば、その人は恐らくクリスチャンになっていなかっただろうからである。このように今の時代でも、昔と変わらず福音を伝えていかねばならないのだが、しかし再臨やこの世の終わりを求めて伝道するべきではない。今の時代に生きる多くの教会は、主が「福音が世界中に宣教されてから終わりの日が来る」とマタイ福音書の中で言われたからというので、早くその日を来させようとして伝道に邁進している。しかし、パウロが言っているように既に福音は世界中に宣教されている。そのようにして世界中に福音が宣教されたから終わりの日も訪れた。その終わりの日が訪れた時にはキリストの再臨も起きた。つまり聖書を正しく理解するのであれば、再臨や世の終わりなどを求めて福音伝道をするというのは、まったくの誤りであることが分かる。要するに、そのようなものを求めて伝道することができたのは紀元68年6月9日よりも前の時代に生きていた聖徒たちだけであって、それ以降の聖徒がそのような伝道の仕方をするのは、その聖徒が聖書を正しく理解していないことを意味している。我々は既に新しい世界が到来しているということを、よく理解しなければいけない。我々は、ただ人々の救いを求めて伝道していけば、それでよい。そこには再臨や世の終わりの思想が伴っている必要はない。いや、そのような思想を伴わせて伝道の活動が行なわれるべきではない。たとい再臨を早めようとして熱心に伝道したとしても、その熱心さが大いに用いられることはあっても、その人の願っている再臨が起こることはない。何故なら、再臨はもう既に起こっているからである。冷たいことを言うようではあるが、伝道の際に再臨が速やかに起こるようになるのを願い求めても、そのように願うのは意味のないことである。再臨の速やかな到来を願うことに心の力を費やすぐらいであれば、そのように願わないだけ、人々の回心を願うことに心の力を回したほうがよいであろう。
神の戒めについては、どのように考えるべきであろうか。聖書の律法は、新しい世界においても、守られなければならない。これは言うまでもないことである。何故なら、神の命令を守るのは、地上に生きる聖徒たちに対する神の永遠の御心だからである。それは、『神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。』(伝道者の書12章13節)と書いてあることからも分かる。それでは、聖徒たちは、どのような種類の律法を守ればよいのであろうか。これについては、改革派やルター派の持つ理解と、何も変わらない。つまり、この「再臨論」の見解は、多くの教派と同じように律法の第三効用を否定することはない。要するに、十戒などの道徳的な律法は現代においても規範として遵守されなければいけない、ということである。私は、十戒に関する次のルターの言葉に、心から同意する。「こうして、われらは十戒を所有しているが、これは、われらの全生涯が神によろこばれるものとなるためには何をなすべきかという、神の教えの摘要であって、そこから善き行為と考えられるすべてのものが流れ出で、また、そこへかえっていくべき、正しき泉、また通路である。」(『信条集 前篇 新教セミナーブック4』大教理問答書 十戒の結論 p139 新教出版社)もし新しい世界に改まったからというので、聖なる戒めを守らなくてもよくなったなどと無律法主義者のようなことを言うのであれば、その者は天国において小さい者とされる。しかし、そのようなふざけたことを言わず、神の律法を守り、またそれを守るように教える者は、天国で大きな栄光と報いとを受ける。それはキリストがこう言われた通りである。『だから、戒めのうち最も小さいものの一つでも、これを破ったり、また破るように人に教えたりする者は、天の御国で、最も小さい者と呼ばれます。しかし、それを守り、また守るように教える者は、天の御国で、偉大な者と呼ばれます。』(マタイ5章19節)というわけで、今の時代でも道徳的な神の戒めを謹んで行なわなければいけないという点で、この「再臨論」の見解は、他の諸教派が持つ見解と何も変わらない。これは、既に多くの教師たちが何度も教えてきたことである。それゆえ、このことについては、ここでもうこれ以上説明する必要はないであろう。もし、このことについて詳しく学びたいという聖徒がいれば、カルヴァンの「キリスト教綱要」やルターの「大教理問答書」などを読めばよかろう。
祈り、聖徒の交わり、讃美、十一献金、毎週礼拝に集うこと、聖書を読むこと、善の実行、こういった事柄については従来と何も変わらない。これは、いちいち書くまでもないことである。
それでは聖餐式は、この新しい世界において、どのようにすべきであろうか。これは、少しばかりの思考を要する問題である。教会に定められている2つの聖礼典のうち、バプテスマのほうは、何も問題は生じない。というのは、新しい世界になっても、バプテスマを信者になった者に施せば、ただそれだけでよいからである。そこにおいて、神学的な障壁はまったく起こらない。しかし、聖餐式のほうは、少々厄介な神学的障壁が起きてしまう。それは一体どのようなものであろうか。それは、パウロが、聖餐式を行なうのはキリストが再臨される時までであるとコリント人に対して、述べていることである。パウロは、まだ再臨が起きていなかった紀元68年以前の時代に生きていた聖徒たちに対して、次のように書き送った。『ですから、あなたがたは、このパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られるまで、主の死を告げ知らせるのです。』(Ⅰコリント11章26節)確かに、ここでパウロは『主が来られるまで』すなわち再臨が起こるその時まで、主の死を告げ知らせるべく聖餐式を執行すべきなのだと言っている。既に我々が確認したように、主の再臨は既に起こった。それは、パウロが手紙を書き送ったこのコリント人たちが生きている間のことであった。つまり、彼らが生き残っている間に主が再び来られるからというので、パウロはこのように書いたのである。それではどうなのであろうか。キリストや使徒の言ったことから分かるように、再臨が既に起きたというのであれば、キリストが再臨されてから後の時代に生きる聖徒たちは、もう聖餐式を行なわなくてもよくなったのであろうか。そのように考えるのは、とんでもないことである。聖餐式は、キリストが再臨されたからといって、もう執行しなくてもよくなったというのではない。我々は、事の詳細をよく弁えなければいけない。聖徒たちが聖餐式を行なうべきであったのは、この地上に生きている間は、まだキリストが肉的には聖徒たちと共におられなかったからである。もちろん、霊においてキリストは聖徒たちと常に共にいて下さるのだが、肉においてはそうではない。聖徒が肉においてもキリストと共にいるようになるのは、言うまでもなく天の御国においてである。そのようにこの地上ではキリストがまだ肉において聖徒たちと共におられないので、この地上に生きる聖徒たちは聖餐のパンとぶどう酒という外的な徴を通して、キリストとの契約的な一体性を強め確認しなければいけない。つまり、地上の聖徒は今はまだキリストが肉においては共におられないので、パンとぶどう酒を通して、信仰によって、キリストの実際的な肉と血とにあずかるわけである。地上の聖徒たちの霊と信仰は弱い状態にあるので、このようにして物質的なものを通してキリストを受けなければいけないのである。これは、今まで多くの教師たちが十分過ぎるほど論じてきたことである。つまり、聖餐式という聖礼典は、キリストが肉的にはまだ共におられない聖徒たちのために定められている。聖徒たちが天に挙げられたのであれば、その聖徒たちは肉においてもキリストと共に過ごすことになるから、もはや聖餐式を通してキリストにあずかる必要もなくなる。今、この地上に生きる我々の状態はどうであろうか。キリストが肉的な意味において我々と共におられないのは、誰でも分かることである。そうであれば、再臨が起きて新しい世界になったとしても、聖徒たちは聖餐式を行なわなければいけないことになる。もしキリストがこの地上のどこかにおられるのであれば話は別だっただろうが、この地上に今キリストは肉的な意味において存在しておられないのである。つまり、キリストが『これはあなたがたのための、わたしのからだです。わたしを覚えて、これを行ないなさい。…この杯は、わたしの血による新しい契約です。これを飲むたびに、わたしを覚えて、これを行ないなさい。』(Ⅰコリント11章24~25節)と命じられたのは、地上の聖徒に対する神の永遠の御心だということになる。地上に生きる聖徒たちは、永遠に至るまでも、この聖餐式に関する主の御言葉を覚えて聖餐式を執行しなければいけない。この聖餐式に関するキリストの命令は、再臨以降の時代に生きる聖徒たちにも向けられているのである。再臨が既に起きたからといって、またパウロが「再臨が起きるまで我々は聖餐式を行なうのだ。」と言ったからといって、再臨以降の時代はもはや聖餐式を執行しなくてもよくなったというわけではない。我々は、このことによく注意する必要がある。もし再臨がもう起きたからというので、聖餐式を執行しなくてもよくなったなどと考えるのであれば、そのような教会はあまりにも悲惨である。その教会は、聖餐式という真の教会の印を持たないので、偽りの教会だと見做されても文句は言えない(※①)。「偽りの教会だから聖餐式を執行しないのだ。」などと批判されても、自業自得である。また、その教会にいる信徒たちは、聖餐式を行なわないのだから、霊と信仰が弱まったり堕落したりするという報いを受けてしまう。何故なら、神は聖餐式により、聖餐を受ける聖徒たちの信仰を強め、その霊の状態を健全にするという恵みを与えて下さるからである。またその教会は、聖餐式という教会の義務を蔑ろにしていることで、自分たちが霊的に堕落していることをみずから外部に対して示している。堕落しているからこそ、キリストの永遠の御心である聖餐式を行なおうとしないわけである(※②)。それは道徳的に堕落している家長である者が、自分の家族を養おうとしないのと、よく似ている。その家長は堕落しているからこそ、自分の家族を養おうとせずに放っておくのである。また、聖餐式を執行しない教会は、聖餐式を行なえというキリストの重要な命令にさえ従わないような教会なのだから、この聖餐式に関する命令以外の命令にも聞き従わないであろう。他の命令には聞き従うが、この聖餐式についての命令だけは例外的に従っていないだけ、ということは考えにくい。つまり、その教会は根本的にキリストに不忠実な精神を持っているからこそ、聖餐式に関する命令であれその他の命令であれ行なおうとしない、というわけである。というわけで、再臨が起きて新しい世界に改まったからといって聖餐式を執行しない教会は、わざわいである。そのような教会は多くの呪いを受けるであろう。いや、既に呪われているといってもいいかもしれない。つまり既に呪われているからこそ、その呪われていることの現われとして、聖餐式を執行することがないのである。
(※①)
宗教改革期に制作された有名な信条の中のいくつかでは、真の教会の印を「御言葉の宣教」および「聖礼典の執行」という2つに定めている(フランス信条、アウクスブルク信仰告白、Ⅱスイス信条)。つまり、この2つがしっかりと確認できれば、その教会は「真の教会」に他ならないということである。このような考えには私も同意する。確かに真の教会であれば、そこには、この2つのものがしっかり見られるだろうからである。中には、この2つに加えて「聖徒たちの訓導」を定める信条もある(第一スコットランド信条、ベルギー信条、Ⅰスイス信条)。
[本文に戻る]
(※②)
それでは聖餐式を行なわない日本の無教会派の者たちも堕落しているのか、と問う人がいるかもしれない。彼らが堕落しているのかどうかといえば、それには一考の余地があるが、しかし彼らは聖餐式を行なっていないのであるから、私は前々から彼らに対してあまり良い思いを抱いていない。というのも、キリストが聖餐式を執行せよと命じられたのだから、あらゆる聖徒たちは聖餐式を執行すべきだからである。それなのにキリストに従って聖餐式を執行しないとは、おかしな話ではないか。私が今何か愚かなことを言ったとは思えない。宗教改革者たちも、無教会派のことを知ったら、多かれ少なかれいぶかしげに感じていたことであろう。「キリストに従わない教会は、教会ではないからである。」とはルターの言葉である(『ルター著作集 第二集7 ヨハネ福音書第3章・第4章説教』第41説教 第3章(29)p261 LITHON)。
[本文に戻る]
この新しい世界において、聖徒である救われた者たちは、何よりも天の御国に入れなくならないようにすることを求めなければいけない。これこそ、聖徒たちが何よりも第一に求めなければいけないことである。何故なら、キリストがこう言われたからである。『神の国…をまず第一に求めなさい。』(マタイ6章33節)『何はともあれ、あなたがたは、神の国を求めなさい。』(ルカ12章31節)この至福の場所から排除されないようにすることを第一に求めるというのは、この地上に生きる聖徒に対する、神の永遠の御心である。もし我々が天の御国に引き上げられないとすれば、それは火の池に投げ落とされることを意味する。天の御国にも引き上げられず、火の池にも投げ入れられない、ということはない。天国でも火の池でもない第3の永遠の場所があるということもない。我々は、この火の池がどれだけ悲惨な場所であるかということを、既に確認した。この火の池に行くことは、考えられる限り究極の不幸である。そこで永遠に苦しむのは不幸の極致であるから、そのような場所に投げ込まれることがあってはならない。よって聖徒たちは何よりも、神の御国にやがて入れなくなるということがないようにすることを、第一に求めなければいけないことになる。キリストが再臨されて新しい世界が始まったからというので、もはや天国に入れるようにすることを求めなくてもよくなった、ということにはならない。そのように考えるのは、ふざけていると言わねばならない。このことについても、先に述べた律法と同じで、この「再臨論」の見解は、他の諸教会が持つ一般的な見解と何も変わらない。またこのことは、教会の説教でいくらでも論じられることであるし、これを読んでおられる聖徒たちも既に何度も聞いているのではないかと思う。それゆえ、このことについては、もうこれ以上の説明は必要ないであろう。
第9章 重大な懸念
(※)
『わたしが来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。わたしは、平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら、わたしは人をその父に、娘をその母に、嫁をそのしゅうとめに逆らわせるために来たからです。さらに、家族の者がその人の敵となります。』(マタイ10章34~36節)
[本文に戻る]
この再臨の事象を正しく理解するのは、我々の救いにとって害になるのではなく、むしろ益となる。もし、かなりの程度まで理解できるというのであれば、確かにそうである。それは具体的にはどういうことであろうか。もし我々が再臨を正しく理解できるのであれば、我々は救い主が述べたことが正に真実だったということを、明白に知ることができる。「主が再臨について言われたことは正に真実であった。」などと心に思うことができる。そうすれば、我々はより救い主を信頼できるようになる。何故なら、主が確かなことを言われたということを、より豊かに知るようになるからである。ある人が正しいことを言っていると思えば思うほど、その人に対する信頼が強くなるのは言うまでもない。そのようにして我々が救い主をより信頼するようになれば、それだけ我々が持つ救い主とその救いに対する信仰は、固くされる。これは、間接的に我々の救いに対する信仰が堅固にされることである。また我々が再臨を正しく理解するのであれば、再臨について多くを語っている聖書に対する信頼も、ますます豊かなものとなる。それは先に述べたのと同じで、聖書が正しいことを語っているということを、より豊かに知れるからである。そうすれば、その聖書をお書きになられた神に対する信頼も、ますます深まる。何故なら、神が真実なことを言われたということが、我々の信仰において更に確かなものとなるからである。そのようにして神に対する信頼が深まれば、その神が御子を通して与えて下さった救いに対する信仰を、我々はますます豊かに持てるようになる。もし神に対する信頼が深まるのであれば、それと同時に、その神による救いに更に豊かに立てるようになるのは確かである。これは我々の持つ救いに対する信仰にとって、大きな益である。更に再臨を正しく理解すれば、我々に与えられた救いの知識が増し加わることにもなる。つまり、我々がこの地上での生命を終えた後にどのようになるのかということが、具体的に分かるようになる。それは、救いの知識に関する輪郭が更にクッキリすることである。そうなれば、救いに関して不明瞭な部分が、それだけ我々の信仰からは除かれることになる。そのようになれば、我々の救いに関する信仰は、更に堅固なものとなるであろう。これは我々の救いにもたらされる直接的な益である。どうであろうか。このように見ると、再臨を正しく弁えることは、我々の救いにとって大きなメリットとなることが分かるのではなかろうか。再臨を考究すると必然的に救いの領域が疎かにされるなどと感じる人は、どれだけ考究しても正しい理解に至れないからであると私は思う。そのような人は、どれだけ思考しても再臨の事象を正しく理解できないので、その結果、救いに対して何の益も得られないままの状態に留まる。これは当然である。何故なら、再臨をある程度の段階まで正しく理解して始めて、救いに直接的・間接的な益がもたらされることになるからである。そのようにして何も理解できないままでいると、せっかく多くの精神的労苦を払ったにもかかわらず何の益も生じないので、無駄骨を折らされたかのように感じてしまう。しかも、再臨のことを熱心に考究していたその時に、魂の救いについては、あまり多くのことを考えることができていなかった。それは、再臨の考究だけで、心が一杯になっていたからである。つまり、再臨のことで無駄骨を折ったのと同時に、大事な救いの領域のことも蔑ろにされたと感じる。そうすると、どれだけ労力を払っても再臨のことが分からず、また再臨の正しい理解が救いに関わるとも思えない、という状態がいつまでも続くことになる。このような状態になれば「再臨のことを考えても一体なんになるのであろうか。」などと思って、うんざりすることにもなる。このような経緯があるために、多くの人たちは「再臨の考究に心を費やすのであれば、それにかかりきりになって救いが蔑ろにされてしまう。しかも、どれだけ考えても結局は分からないままだ。このような難しいことは考えなくてもいいから、ただ救いに固く立っていればよいのだ。」などと考えたり言ったりするのではないかと、私には思われる。もちろん人によっても状況は違うだろうが、このような経緯により再臨の考究を敬遠することになった人は、必ずいるはずである。間違いなく言えるのは、このようなことを考えたり言ったりする者たちも、もしこの再臨のことを正しく理解できていたのであれば、このようなことは考えたり言ったりしていなかったということである。つまり、どれだけ考えても分からないからこそ、多くの者たちには「諦め感」が生じてしまい、このように考えたり言ったりすることになるのである。
むしろ、再臨のことを正しく理解しないほうが、かえって我々の救いにとって害をもたらすと言える。それは一体どういうことであろうか。もし聖徒が、再臨のことを正しく弁えられないのであれば、それだけ救い主の言われた再臨に関する御言葉も分からなくなってしまう。「主は再臨が紀元1世紀の人たちの生きている間に起こると言われたが、これは一体どういうことなのだろうか。主は何を弟子に言いたかったのか。」などと思って、心の中には「?」マークが無数に生じることになる。これは、今に至るまで無数の聖徒たちに起きたことである。今まで教会は再臨を正しく理解してこなかったのだから、主の言われた再臨に関する御言葉を正しく理解することができていなかった。それゆえ、聖徒たちは再臨についての御言葉に「?」と感じる他はないのである。何か分かっているかのように再臨のことを堂々と論じていたとしても、心の中では、分からないことが多いと意識的にであれ無意識的にであれ感じていたはずである。そのようにして主の言われた御言葉がよく分からないと、それだけ救い主に対する信頼も強く持てないことに繋がる傾向が生じる。そのようにして救い主に強い信頼を持てないと、それだけ救い主の実現して下さった救いに対する信仰も堅固なものとならないことに結びついてしまう。これは救いに対する信仰に間接的な害がもたらされることである。また、これは聖書に対する信頼についても同じである。すなわち再臨のことを正しく理解していないので、聖書に対する信頼が揺らぎ、その結果、聖書の啓示している救いに対して堅固な信仰が持てなくなることになりかねない。中には、どれだけ聖書を読んでも再臨のことが分からないから、聖書を読むのが嫌になってしまったという人もいるかもしれない。また、再臨を正しく理解しないと、それだけ救いに関する輪郭が明白なものではなくなる。例えば再臨をよく理解していない人は、もう既に第一の復活が起きたことや、我々もこれから第一の復活に与かって生きたまま天に挙げられることになるということが、よく分からないままである。再臨を正しく理解していないのに、どうしてこのような救いにかかわることを、十全に把握できるであろうか。言うまでもなく、再臨を正しく理解してこそ、このようなことを始めて正しく把握できるようになるのである。そのように再臨をよく理解できておらず、またそのため救いについても不明瞭な点が残されたままでいると、やはりそれだけ救いに対する堅固な信仰を持てなくなることに繋がる傾向が生じる。救いの信仰を固く持てないのは、信仰者にとって良いことではない。よって再臨を正しく理解しないのは、我々の救いにとって直接的な害をもたらすということが分かる。どうであろうか。このように見ると、再臨のことを敬遠すればするほど、救いにとって直接的また間接的な害をもたらすということが分からないであろうか。確かに、どれだけ考究しても再臨を正しく理解できないというのであれば、再臨のことを延々と思考し続けてもあまり意味がないということは私も認める。その人が精神的な無駄骨を折ったと感じたとしても無理はない。せっかく多くの労力を払ったのに、何の収穫も無かったのだから。しかし、もし再臨を正しく理解できるというのであれば、再臨の正しい理解のために多くの労力を払うべきである。それは、再臨を正しく理解できるという益があるだけでなく、我々の救いにとっても大きな益をもたらす。今この時、読者の目の前には、再臨を正しく理解できるための文章が置かれている。それは本作品のことである。この作品を読んで考究し、よく理解すれば、読者は神の恵みによって再臨のことを正しく悟れるようになる。そのような作品がここにあるのだから、読者はこの機会を取り逃さず、聖書が再臨について何と言っているかということをよく考究していただきたい。そのようにして正しい理解を持てるようになれば、再臨のことを正しく理解していないために、救いの信仰を堅固なものにできなくなるという害からも免れるようになる。
もし再臨の考究に時間を費やすと、それだけで心が一杯になって魂の救いが疎かにされると言うのであれば、日々忙しくしている信仰者はどうなるのであろうか。例えば、仕事で忙し過ぎて聖書すら読んでいる暇がないという聖徒は、どうなるのであろうか。彼は、仕事の多忙さにより救いのことに心を集中させる余裕がほとんどない。また世俗のことに関する何かを一生懸命研究している学者の聖徒は、どうなるのであろうか。彼も、自分の研究していることで心が一杯になるから、あくまでも傾向としてだが救いが隅に押しやられがちになる。また多くの子どもがいるために家事で働き回っている母親は、どうであろうか。彼女も、子どもや家のことで忙し過ぎるので、なかなか霊的な事柄を静かに思考する余裕がない。もし再臨の考究のために救いが蔑ろにされはしないかと言う人がいれば、このような人たちに対しても同じように言わねばならなくなる。「忙しく仕事ばかりしていると救いのことが疎かになりますよ。」などと。しかし、世の中に、このような忙しいクリスチャンはいくらでも存在している。彼らは、霊的なことを考究したくても、自分の仕事に縛られているために、なかなかそれができないでいる。しかし、この再臨のことは、たとえどれだけ考究したとしても仕事のように救いを隅に押しやるというものではなく、かえって救いに益がもたらされることになるものである。つまり、私がこの作品の中で論じているのは、仕事のようなものではないのだから、それにかかりきりになると救いが蔑ろにされてしまうなどと懸念されるべき性質を持ったものではない。これが救いに何の益ももたらさないものであれば話は別だったであろうが、これは救いに益をもたらすものなのである。それゆえ、この再臨のことについて、人はそれがあたかも救いのことを考えられなくさせる世の仕事でもあるかのように何かを言うべきではない。教会は多くの場合、仕事で忙しくしている人に対して「仕事は救いのためによくないから控え目にしたほうがよい。」などとは言わない。救いを考えさせる余裕を奪う仕事に対してでさえ、普通であれば、このようには言われないのである。であれば、尚更のこと、救いに益をもたらす結果を生じさせる再臨の考究に対しては、そのように言われるべきではない。このことについては、もうこれ以上言う必要はないであろう。聖徒たちにとって、救い以上に大事なものは他にないのだから。
これは真実なことであるが、どれだけ多くの牧師が再臨の考究を敬遠したとしても、この再臨の真理は、絶対に求められ、神の恵みより得られるべきものである。真理を愛する人であれば、この意見に異を唱えることはしないはずである。ソロモンは箴言23:23の箇所で、『真理を買え。それを売ってはならない。』と書いている。再臨という聖書の教える聖なる事象は、言うまでもなく真理である。それゆえ、聖書に従う者たちは、真理である再臨をソロモンが言っているように買わなければいけない。つまり、我々は、再臨を正しく理解するために時間や労力という犠牲を払い、神から再臨の真理をいただくことができるようにと願い求めなければいけない。そのようにしない人は、真理を売っているのも同然である。何故なら、その人は真理を愚かにも売って遠くへ追いやったユダと同じように、真理を自分の手元に置いておこうとしないからである。真理を売る人も、真理を考究して求めない人も、真理を拒絶しているという点では何も変わらない。牧師の中で、面倒だからというので再臨を考究したくないと思う方が、誰かいるであろうか。霊的に衰えている傾向を持つ現今の教会において、このような思いを抱く牧師は、かなりいるのではないかと思う。もし、再臨の真理を考究するという手間を厭うのであれば、その牧師は、あまり神学には向いていない。もし考えるのすらまったく嫌だと言うのであれば、その牧師は、神学だけでなく教職者にも向いていない。確かに、このような難しい問題を考えるのは精神的に大変であるというのはあるかもしれない。しかし、まったく真理の考究を拒むという態度をキリストの教師である牧師が持つというのは、いただけない。それはキリストに召された教師のあるべき姿ではない。何故なら、キリストはご自身の教師たちが、多くの聖徒たちに真理を教えることを望んでおられるからである。であれば、どうして真理を考究しなくていいということがあろうか。面倒だからといって真理を考究しなければ、真理が分からないままなのだから、その結果、真理を聖徒たちに教えられなくなってしまう。それは主の御心にかなったことではない。よって、自分が召された牧師であるという自覚を持つ人は、真理の考究を厭うべきではない。言うまでもなく、真理を熱心に考究するというのが、キリストの教師に相応しい姿勢である。さて、牧師であれ一般信徒であれ、聖徒たちには再臨の真理が満ちるべきである。主も、そのことを望んでおられるのは言うまでもない。パウロも書いたように、『神は、すべての人が…真理を知るようになるのを望んでおられ』(Ⅰテモテ2章4節)る。だから、聖徒である者は、再臨の真理を得られるようにと神に求めるべきである。もし心から求めるというのであれば、神はそれを与えて下さるであろう。再臨の真理を捜すならば見つかるであろう。再臨の真理が隠されている部屋の扉を叩けば開かれるであろう。それはキリストが、次のように言われた通りである。『求めなさい。そうすれば与えられます。捜しなさい。そうすれば見つかります。たたきなさい。そうすれば開かれます。だれであれ、求める者は受け、捜す者は見つけ出し、たたく者には開かれます。』(マタイ7章7~8節)再臨の真理を得られないのは、その人が求めず、捜さず、叩かないからである。何も得ようとしないのに、どうして受け、見つかり、開かれるであろうか。神は得ようと切に願う者にこそ、恵みにより、再臨の真理を得させて下さる。
第10章 真理のありか
しかしながら、特に教職者がそうなのであるが、聖徒の中で、真理をより良く理解しようとして、聖書以外の本を読もうとする人は数多い。私はこのことについては、ルターとまったく同じ考えを持っている。すなわち、聖書こそを何よりも聖徒は読まねばならないのであるが、聖書を理解するための助けとしては聖書以外の書物を読むことも益になる、しかしながら聖書以外の書物を読み過ぎて聖書を読まないようでは本末転倒となる、という考えである。ルターも教父たちの本やキケロまたアリストテレスなどといった古代人の本をよく読んでいた。確かに、通常の場合であれば、聖書以外の書物を読むことは益になるし、否定されるべきでもない。例えばアウグスティヌスやカルヴァンの書物を読めば、聖書の理解が増進されることになる。しかしながら、この再臨のことについては、驚く方も多いかもしれないが、話がまったく違う。この再臨の場合、救済論や三位一体論などと違って、聖書以外の書物を読んでも、ほとんど意味がない。これは私の経験から言えることである。というのは、ここまで書かれた内容を読んだ方であれば分かると思うが、今まで教会と聖徒たちはこの再臨について完全に誤った理解を持っていたからである。そのような人たちが書いた書物の中には、再臨に関する誤謬が満ち満ちている。再臨についてだけ言えば、そこには誤謬しかないと言ってよい。アウグスティヌスもルターも、その他の教師たちも、そうである。彼らは徹底的に再臨の領域において誤っており、ほとんど盲人であると言ってよく、誰一人として再臨を正しく理解している人はいなかった。それゆえ、聖書以外の書物を読んで再臨を正しく理解しようとしても、正しく理解できるどころか、更に誤謬の穴に沈み込んでしまうばかりとなる。しかし、まったく読むべき書物が存在しないというわけでもない。再臨を理解するために読むべき書物も、数は少ないが、いくらか存在している。再臨を理解するために読むべき聖書以外の書物は、2つに分けられる。まず一つ目は、この作品のような、再臨を徹底的に聖書から考察した作品である。このようなものは、再臨を正しく理解するためには大きな益となる。しかし、残念なことではあるが、このような作品は今まで世の中にまったく見られなかった。二つ目は、間接的に再臨の理解に役立つ作品である。例えば、ヨセフスの『ユダヤ戦記』やタキトゥスの『同時代史』などが、そうである。このような作品は、再臨のことを直接的に取り扱っているのではないが、キリストや使徒の時代における歴史的な知識が得られるので、間接的に再臨を正しく理解できることへと結びつく。新約聖書が書かれた紀元1世紀当時の時代背景を知っていればいるほど、それだけ再臨の事柄が理解しやすくなるのは確かなことである。このような読むべき聖書以外の書物を、数はあまり多くないが、本作品の末尾に掲載しておいた。読みたい人は読むがよかろう。もし読むならば、再臨の理解のために、多かれ少なかれ益となるはずである。
第3部 黙示録註解
第1章 黙示録を理解する必要性
この第3部では、黙示録の註解が記される。それは、聖徒たちが、より豊かに再臨を理解できるようになるためである。この黙示録を読み解けるようになれば、それに伴い、再臨もより深く悟れるようになるのは確かである。私は、この黙示録註解を、別冊にしたり、または本作品とは独立した作品にすることも考えたが、この作品の中に組み入れることにした。どうしてこうしたかと言えば、それはまず利便性のためである。再臨を取り扱う本作品の中で、黙示録の註解を行なえば、それだけ読み易くなるのは間違いない。何故なら、黙示録の註解がセット品として組み込まれているからである。繋がっていれば読み易くなるのは、誰でも分かることである。またこの註解を第3部にあてれば、本作品において、再臨を多角面から見れるようになるという幸いな作用が生じる。すなわち、第1部では再臨を「真実性」という観点から眺め、第2部では「詳細および順序」という観点から眺め、そしてこの第3部では「黙示録」を通して再臨を眺められるようになる。このように3つの違った方面から再臨を見るのであれば、それだけ再臨の事柄が理解しやすくなると思われる。主イエスの生涯を記した福音書においても、そのような手法が取られている。すなわち、マタイから見たイエス像、マルコから見たイエス像、ルカから見たイエス像、ヨハネから見たイエス像、というように、全福音書では4人の視点から主イエスの事柄が認識できるようにされている。そのように多角面からキリストを見ることで、より我々はキリストのことが立体的に分かるようになるのである。本作品でも、そのように異なった視点から再臨を見ることで、より再臨を立体的に理解・把握できるようになることを求めた。つまり、そのようにして違った方面から再臨を理解しようとすれば、相乗効果があると私には思われたのである。もし黙示録の註解を第3部に組み入れないで独立した作品にすれば、それだけ読みにくくなってしまう。何故なら、その註解が本作品とはセットになっていないため、心がすんなりとそちらの註解のほうに向かうかどうかは定かでないからである。また、第3部に組み入れなければ、本作品において多角面から再臨を見るという作用も生じなくなる。そうすると、私の求める相乗効果も、やはり生じなくなるはずである。このような難しい問題においては、相乗効果や積み重ね、繰り返しといった要素が大変重要である。事柄が複雑で難しいために、そのような要素がなければ、なかなか十全に理解できないことに繋がる。それゆえ、私としては、このように黙示録註解を第3部に組み入れたのは正解であると感じている。少なくとも、これを書いている今の時点ではそうである。なお、この第3部では、既に語られたことが再び繰り返されることも多いということを、あらかじめ書いておきたい。黙示録の註解を記す際には、どうしても以前に語ったことと重複することを書かねばならないからである。もし繰り返しはよくないからといって重複を避けていたら、不完全な註解となってしまうであろう。「大事なことは何度でも」という昔の諺に免じて、読者は、この点について大目に見てほしい。この再臨の事柄が、聖徒である者にとって、非常に大事なことであるのは言うまでもない。大事だというのであれば、やはり何度でも聞くべきだということにもなる。そのようにして繰り返し学ぶからこそ、難しい部分が紐解けるようになるということにもなる。実際、私自身がそうである。聖書も、大事なことは何度も繰り返して書いている。至高の書物である聖書でさえそうなのだから、本作品に重複があったとしても、それは咎められるべきではないはずである。私は何も、わざと重複させようとしているのではなく、自然とそうならざるを得ないからこそ、そのようにするに過ぎないのである。
第2章 黙示録の筆記年代
新約外典の「ヨハネ伝」の中では、ヨハネがパトモス島に流されたのは、トラヤヌス帝の治世(98~117年)であったと記されている。黙示録1:9でヨハネは、『神のことばとイエスのあかしのゆえに、パトモスという島にいた。』と自分の今の状況について記している。このパトモス島にいた時に、ヨハネは幻を見せられ、その幻を書き記すようにと命じられた(黙示録1:11、19)。つまり、この外典によれば、ヨハネが黙示録を書いたのは98~117年の間だったことになる。つまり、ヨハネがキリストと共にいた紀元30年頃の年齢を仮に20歳だとすると、88~107歳の時に、ヨハネは黙示録を書いたことになる。これは、かなり高齢での筆記作業である。しかし、高齢であったということは何も問題にはならない。健康と頭脳が恵まれているのであれば、高齢になっても高度な内容の本を書くことは可能だからである。実際、今の時代でも、バートランド・ラッセルやピーター・ドラッカーといった知者たちが、80代、90代になっても、しっかりとした本を書いている。彼らは高齢になっても知性が衰えていないことを、その晩年の書物において公に示している。この場合、我々はヨハネが高齢になっても、かなり壮健であったと信じなければいけなくなる。そうでなければ、誰が、このような複雑極まる知的に高度な文書を80代にもなって書けるであろうか。エイレナイオス(130頃~200頃)も、ヨハネはトラヤヌス帝の時代まで生きていたと述べている(※)
。とすると、彼も、トラヤヌス帝の時代に黙示録が書かれたと考えていたことになる。しかし、エイレナイオスが「ヨハネ伝」を読んだから、ヨハネがトラヤヌスの時代まで生きていたと考えていたかどうかは定かではない。しかし、この外典を読んだがゆえに、そのような考えを持った可能性は十分にある。教会の中でも、今までに、ヨハネが高齢になって黙示録を書いたというこの見解を取ってきた者は少なくない。今でも、そのように考えたり言ったり書いたりする人たちが多い。今の新約聖書学では、黙示録の筆記年代は「ドミティアヌス帝の治世の終わりのこと」とするのが定説である。このドミティアヌスは紀元96年9月18日に暗殺された。しかし、我々はこの外典が、あくまでも外典に過ぎないものだということを弁えなければいけない。すなわち、この「ヨハネ伝」なる文書は、神の書かれた聖書ではない。よって、この外典が何と言おうとも、我々はそれをそのまま鵜呑みにすることはできない。それは人間の手による文書に過ぎないのであって、もしかしたら出鱈目が書かれている可能性もあるのである。古代においては、出鱈目が書かれた多くの文書があったことを我々は知るべきである。例えば「シビュラの託宣」がそうである。この文書には、いい加減なことが多く書かれている。もし「ヨハネ伝」という外典の記述を信じるべきだというのであれば、他の外典で言われていることも、信じなければいけなくなる。例えば「トマス伝」で言われているようにトマスがインドに売られたとか、「ニコデモ福音書」で言われているようにキリストがハデスの中に十字架を置いて出て行かれたとか、「パウロの黙示録」で言われているようにパウロが地獄の見学旅行をした、ということも信じなければいけなくなる。しかし、これらの出来事が本当にあったのかどうかは定かではない。もしかしたら本当にあったかもしれないし、ただの出鱈目だということも十分にあり得る。それゆえ、この「ヨハネ伝」の中で言われているようにヨハネがトラヤヌス帝の頃まで生きていたということを、我々が絶対に信じなければいけないということはない。我々は外典はあくまでも外典に過ぎないことを弁えるべきである。それは人の手によるものであって、神に霊感されていない。よって、外典をあたかも正典でもあるかのように理解と知識の基盤に据えるのは、よくないことである。我々の基盤となるべきなのは正典の66巻だけだからである。外典はあくまでも参考情報としての意味以外にはなく、懐疑的に見られるべきものであることを忘れてはいけない。
(※)
「さらには、アジア州で主の弟子のヨハネに会ったことのある長老たちも全員そろって、ヨハネは同じことを自分たちに伝えてくれたと証言している。このヨハネは皇帝トラヤヌスの時代まで、彼らと一緒に生きたからである。彼らのうちの何人かはヨハネだけではなくて、他の使徒たちにも会ったことがあって、同じことを彼らからも聞いており、事実そういう事情であったことを証言しているのである。彼ら以上に信をおくべき者が他にいるだろうか。今述べたような者たちを信じるべきか、それともプトレマイオスを信じるべきなのか。プトレマイオスは使徒たちに一度も会ったことがないばかりか、夢の中でさえ、使徒のだれかの足跡をたどったことがないのである。」(『キリスト教教父著作集 2/Ⅱ エイレナイオス2 異端反駁Ⅱ』『異端反駁』第2巻 22:5 p105 教文館)
[本文に戻る]
さて、ヨハネが高齢になってから黙示録を記したというキリスト教界の通説は、完全な誤りである。それが誤りであることは聖書から証明できる。私が今から書くその証明は、ここまで読み進められた方であれば、それほど苦もなく理解できるのではないかと思う。我々は、『不法の人』(Ⅱテサロニケ2章8節)がキリストの再臨により殺されると聖書には書かれているということを、既に第1部の箇所で確認した。この不法の人とは、パウロによれば紀元1世紀当時においてその『秘密はすでに働いて』(Ⅱテサロニケ2章7節)おり、それはすなわちネロ帝のことであった。既に我々が見たように、パウロはⅡテサロニケ2章の箇所で、今はまだクラウディウスが帝位にあるから、それゆえネロが皇帝に就くのはまだ留められていると言ったのである。このネロが殺される時に再臨が起きた。そして、その再臨の時には、聖徒たちの携挙も起きた。それはパウロがⅠテサロニケ4:15~17で、再臨が起こると携挙も起こると書いている通りである。それは紀元68年6月9日のことであった。この携挙の際、ヨハネも空中に引き上げられたのは確かである。まさか、携挙の際に他の聖徒たちは上げられているのに、ヨハネだけは地上に残されたなどと考える兄弟はいないはずである。携挙の際にヨハネだけが仲間外れにされたなどというのは考えられない。ヨハネ自身も、自分が再臨の現場に直面するであろうと手紙の中で書いている。Ⅰヨハネ2:28。『それは、キリストが現われるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに、御前で恥じ入るということのないためです。』またⅠヨハネ3:2もそうである。『しかし、キリストが現われたなら、私たちはキリストに似た者となることがわかっています。なぜならそのとき、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。』ヨハネがネロの命日に携挙されて地上から『取られ』(マタイ24章40、41節)たのであれば、どうしてトラヤヌス帝の時代まで地上にいたのであろうか。もちろん、ヨハネがトラヤヌス帝の時代には、この地上に存在していなかったのは言うまでもない。であれば、トラヤヌスの治世である98~117年の間に黙示録が書かれたという通説は、間違っていることになる。既に世に存在していない人物が、どうして今も存在しているかのように、何かを記すことができるのであろうか。ヨハネがトラヤヌス帝の時まで生きていたと書いている「ヨハネ伝」も、ただの創作に過ぎないものである。というのは、ここで描かれているヨハネは、黙示録で言われているようなことを何も言っていないからである。ヨハネは、これから『すぐに』(黙示録1章1節、22章6節)獣や破滅的な終末が到来するからというので、その『時が近づいている』(同1章3節)からというので、黙示録において多くの警告をしたのである。本当に大変な恐るべき事態が間近に迫っているからこそ、ヨハネはそれを聖徒たちに非常な緊迫感をもって伝えた。しかし、この外典に描かれているヨハネは、そのような事態を何も想定していないかのように感じられる。何もそこには緊迫感がなく、あたかも獣や終末のことなど頭にないかのようである。実際、そこに描かれているヨハネは、そのようなことを何も言っていない。これは黙示録で多くの警告をしたヨハネのことを考えれば、理解できないことである。「時が近い。もう破滅が間近である。君たちは悲惨が訪れるのを覚悟しなければいけない。」このように言ったヨハネが、何もそのようなことを言わないというのは、一体どういうことなのか。ヨハネは黙示録で書いたことを、高齢のために、すぐに忘却してしまったのであろうか。そういうことは恐らくなかったと思われる。何故なら、すぐにも自分の書いたことを忘却してしまうほどに頭脳が衰えていたとすれば、そもそも黙示録という難解な文書を書くことさえ出来なかっただろうからである。これは、つまり、この外典が実話を書いたものではないことを意味している。これを作った作者は、私が今言ったこのような点を、まったく考慮していなかったからこそ、このような腑抜けたヨハネを描くことになったのであろう。これが本当に実話であったとすれば、ヨハネはいくらかでも獣や終末のことを、周りの人に対して話していたはずである。また周りの人たちも、そのことをヨハネに色々と尋ねていたはずである。しかし、この外典にそのような記述はまったくない。またエイレナイオスの時代にいた長老たちが会ったヨハネも、偽者であろう。何故なら、もしこの長老たちが会ったヨハネが本物の使徒であったとすれば、いくらかでも奇跡を行なっただろうからである。例えば死人を蘇えらせたり、病人を癒したり、悪霊を追い出したりしたはずである。高齢になっていたから奇跡はもう行なえなくなっていたと考えることはできない。モーセも、80代になってから色々な奇跡を行なったからである。しかしエイレナイオスの書いている文章を見る限りでは、その長老たちはどうやら奇跡のことについては、何も言わなかったようである。もし奇跡が行なわれたのを見ていたら長老たちはそのことをエイレナイオスに話していただろうから、エイレナイオスも、長老たちから聞いたその奇跡のことにいくらかでも言及したはずである。しかしそのような言及はない。それは、その長老たちの会ったヨハネが偽者だったからに他ならない。この長老たちは、偽ヨハネにまんまと騙されてしまったのである。『にせキリスト』(マタイ24章24節)が実際に現われたことを考えれば、ヨハネに扮装する者が現われたとしても何も不思議なことはない。神であるキリストにさえ化けることが可能なのであれば、尚更のこと、人にしか過ぎないヨハネに化けることは容易にできるだろうからである。もし偽ヨハネに長老たちが会ったというのでなければ、長老たちが嘘を言っていたのであろう。パウロは再臨が起こる終わりの日が到来すると、忌まわしい者たちが多く出てくる時代がやってくるとⅡテモテ3:1~5で言った(※)。パウロが列挙している者の中には「嘘をつく者」とは書かれていないが、それはただ書いていないだけであって、「嘘をつく者」も含まれていることは言うまでもない。そのような者たちが多く出てくる時代が再臨の日と共に来たのだから、その時代にいた長老たちが嘘を言ったとしても驚くべきではない。この場合、エイレナイオスは愚かな長老たちに、まんまと騙されてしまったことになる。それでは一体どうして、今までキリスト教界は、ヨハネがトラヤヌス帝の時まで生きていたなどという謬説に惑わされてきたのであろうか。それは、神が、西暦21世紀の今に至るその時まで、聖徒たちに再臨や終末の事柄を隠されたいと欲されたからだと私は推測する。「ヨハネ伝」やエイレナイオスという巨人がヨハネは高齢まで生きていたなどと言えば、そのことを聞いた聖徒たちが「なるほど、そうだったのか。」と納得してしまうのは必然である。有名人の言った言葉がよく受け入れられるのと同じで、外典や巨人の述べたことは、人間にとっては力強いものである。そのようにして聖徒たちが外典や巨人に納得させられてしまえば、再臨や終末の事柄について、致命的な誤りに陥ることになる。すなわち、再臨や終末はまだ起きていないと誤解させられることになる。そうなれば、聖徒たちには再臨や終末の事柄が、いつまでも隠されたままとなる。神はそのような状況を欲されたからこそ、外典や巨人の言説に、教会が呑み込まれるようにされたのだと思われる。しかし今や、遂に再臨や終末のことが明らかにされる時期が到来した。もう今はそれらの事柄が隠されるべき必要はなくなった。だからこそ、このようにしてヨハネは高齢まで生きていたという通説が打破されることになった。私の今の考えでは、事情はつまりこういうことなのではないかと思う。実際はどうであったにせよ、一つ確実に言えるのは「ヨハネがトラヤヌス帝の時代まで生きていたことはあり得ない。」ということである。
(※)
『終わりの日には困難な時代がやって来ることをよく承知しておきなさい。そのときに人々は、自分を愛する者、金を愛する者、大言壮語する者、不遜な者、神をけがす者、両親に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう見ずな者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは敬虔であっても、その実を否定する者になるからです。』
[本文に戻る]
それでは、ヨハネが黙示録を記した年代はいつなのであろうか。私は確かなことを言うが、それはカリグラの治世である37~41年の間である。何故かと言えば、既に確認したように13章で記されている666の獣が、すなわちネロだからである。このネロは、黙示録17:11によれば『8番目』の支配者である。ヨハネは17:10の箇所で、ヨハネが黙示録を書いている時点での皇帝が、ネロの2代前、すなわち「6番目」であったと言っている。この6番目の支配者は『今おり』(17章10節)、7番目の支配者が来れば『しばらくの間とどまる』(同)ことになる。そうしてから「8番目」のネロが遂に到来して滅びに至る。この6番目の皇帝が誰かと言えば、それは「カリグラ」である。だから、ヨハネはカリグラが帝位に就いていた37~41年の時に、黙示録を記したことになる。しかし、このように聞かされると、「ネロは8番目ではないしカリグラも6番目ではないではないか?」などと疑問に思う人が多くいるはずである。確かに普通に考えれば、正にその疑問の通りである。歴史を調べれば誰でも分かるように、ローマの帝政においてネロは5番目の皇帝であり、カリグラは3番目である。明らかに3つ順位が違う。しかし、確かなところ、黙示録においてネロは8番目であり、しかも最初の1番目でもある。それは、17:11でネロについて、『彼は8番目でもありますが、先の7人のうちのひとりです。』と言われている通りである。読者の頭の中には今「?」が多く生じているだろうが、ここは、まだこのことについて詳しく語るべき場所ではない。その場所が来れば、その時には、このことがどういうことなのか詳しく語られることになる。だから読者の方は、その時が来るまで、今しばらくの間待っていただきたい。今の段階では、ネロが8番目かつ1番目だということを知っていれば、それで十分である。もし、どうしても今すぐにこのことを知りたいと思われるのであれば、その人は、この註解における17章の部分を先に見ればよい。このように我々がカリグラの時代に黙示録が記されたと考えるならば、黙示録が、驚くほどすんなりと読み解けるようになる。これは正しい理解を主の恵みにより持てたがゆえである。しかし、カリグラだと考えないと、黙示録を上手に読み解けなくなってしまう。例えばドミティアヌス帝(81年―96年)の頃に書かれたと考えれば、どうして既にドミティアヌスの治世には滅ぼされていた聖都エルサレムが出てくるのか、という重大な疑問が出てきてしまう。そうすれば「既に無くなっていた都のことを記すとはどういうことなのか?」などと思い悩むことになるが、どれだけ考えてもすんなりと解が出てこないので―これは当然である―、この都は新約の教会を指しているなどという強引な解釈を取ることになる。このようにカリグラ以外の治世を想定すると、誤謬が誤謬を生みだし、まったく黙示録を読み解けなくなることに繋がる。これは筆記年代を正しく悟れなかったことに対する報いである。大変嘆かわしいことではあるが、今まで全ての教師たちが、このように誤った筆記年代を想定することにより、黙示録を隅から隅まで誤解しなければいけない羽目に陥ってきたのである。カリグラの治世に筆記年代を設定しない限り、黙示録を合理的に読み解くことは絶対にできない。読者の方は、このことを強く心に留めていただきたいと思う(※)。
(※)
アレクサンドリアのクレメンスによる「主の使徒たちの教えは、パウロによる宣教に始まってネロ帝の頃に終わる。」(『キリスト教教父著作集―4/Ⅱ― アレクサンドリアのクレメンス2 ストロマテイス(綴織)Ⅱ』第7巻 第17章106:4 p388 教文館)という記述も、私の説に味方している。何故なら、クレメンスは、ここでヨハネを含めた使徒たちの教説はネロ帝の治世において完結すると言っているからである。そうであれば、どうして使徒であるヨハネが黙示録における教説を、ドミティアヌス帝やトラヤヌス帝の治世に書き記したことになるのであろうか。
[本文に戻る]
第3章 事前に知っておくべきこと
黙示録は、非常に霊的な文書である。キリストが言われたように、『神は霊』(ヨハネ4章24節)である。全聖書は、この霊なる神によって、聖なる霊感のうちに記された。それはパウロが『聖書はすべて、神の霊感によるもの』(Ⅱテモテ3章16節)と書いている通りである。その霊感された聖書の諸巻の中で、もっとも霊的であると言えるのがこの「黙示録」である。それは、黙示録を一度でも読んだことのある人であれば、誰でも分かることである。この黙示録以上に霊的な傾向の強い文書は、他にない。イザヤ書やエゼキエル書やゼカリヤ書よりも、黙示録は霊的である。このように黙示録ほど霊的な文書は他にないのだから、我々は、この文書に霊的な目をもって取り組まなければいけない。すなわち、肉の目をもって取り組むということがあってはならない。これは聖書の他の巻でも同じことが言えるが、特にこの黙示録において、そのように言える。もし黙示録を我々が肉的に解釈しようとするのであれば、必ずや、御心にかなわない理解に陥ることになる。何故なら、肉は霊に対して、常に、必ず、徹底的に反発するものだからである。肉は霊的な事柄に対して、反発する以外のことはできない。それは聖書で『肉の思いは神に対して反抗するものだからです。』(ローマ8章7節)とか、『肉の願うことは御霊に逆らい、…』(ガラテヤ5章17節)などと言われている通りである。このことについての分かりやすい例を一つ挙げよう。黙示録の中では、キリストが『7つの金の燭台』(1章12節)の真中におられたと書かれている。肉的に理解すれば、この燭台とは、どこかの店に売っているような人の手による物体だと考えてしまう。しかし、キリストによれば、この7つの燭台とは『7つの教会』(1章20節)のことである。よって霊的に理解すれば、この燭台とは何かの物体ではなくて、教会だと考えることになる。「何かの物体」と「教会」とでは、かなりの違いがある。もし肉的に理解するのであれば、その人は、いつまで経っても燭台のことを悟れないままである。「どうしてキリストの周りに燭台が置かれているのだろうか…」などと思って、永遠に悩み続けることになる。しかし、これを霊的に捉えれば、そのような問題は何もなくなる。霊の事柄を霊によって捉えているからである。黙示録には、このような霊的な表現や思想が満ちているから、我々はそれを霊的に考えなければいけないのである。
また我々は、黙示録が神によって記された文書であるということも、よく弁えなければならない。もちろん実際に手を使って書いたのはヨハネではあるが、神がヨハネとその手を使って黙示録をお書きになられたのである。それゆえ、究極的に言えば、黙示録はヨハネの著作と言うべきではない。それは「神の著作」なのである。よって、我々は思い違いをして、この黙示録を何か他の人間的な文書でもあるかのように取り扱うべきではない。それは神の著書なのであるから、神の著書として取り扱わなければいけない。もし人間の文書と同じように取り扱うのであれば、その人は、当然受けるべき罰を受けることになる。すなわち、考古学的にしか聖書を読もうとしない自由主義神学者たちのように、まったく異常な理解を持つに至る。そうすれば、いつまで経っても黙示録を正しく理解できないままになってしまう。
ヨハネは、黙示録の多くの部分を、旧約聖書の記述に基づいて書いている。だから、黙示録には旧約聖書を思わせる内容が非常に多くある。というよりは、神が旧約聖書の出来事に基づいてヨハネに多くの幻を示されたと考えるほうが正しい。だからこそ、ヨハネの書いている文章は、旧約聖書の文章と非常に似通っているものが多いのである。黙示録と旧約聖書を読み慣れた方であれば、これは、すぐにも気付くことである。例えば、黙示録には、海が血となり、そのために海の中にいた生物が死んでしまった、と書かれている(8章8~9節、16章3節)。これは明らかに出エジプト記7章に書いてある出来事に基づいている。そこでは、モーセが神によりナイル川を打つと、川がことごとく血に変わり、そこにいた魚が死んでしまったと書かれている。また黙示録の6章では、4つの異なった色を持つ馬が登場する。これも明らかに旧約聖書のゼカリヤ書6章に基づいている。このゼカリヤ書でも、4匹の異なった色を持つ馬が出てくる。しかも、3つの馬の色はどちらの文書でも同じであり、ただ1つの馬だけが異なった表現をされているだけである。ヨハネがゼカリヤ書の記述を念頭に置いて黙示録6章を書いたのは間違いないことである。今はこの2つの例だけを挙げたが、これはほんの少しだけであって、黙示録にはこのような旧約聖書に基づいた記述がそこら中に満ちている。それゆえ、もし黙示録を徹底的に理解したいと願うならば、旧約聖書をよく読まなければいけない。できれば旧約聖書の文章を脳に記憶させ、そらで言えることが望ましい。旧約聖書に精通していればいるほど、その人は、黙示録をより良く理解できるようになる。紀元1世紀のユダヤ人たちも日々シナゴーグにおいて聖書の言葉を頭に刻み込んでおいたからこそ、キリストが何かを言われたり行なわれたりした際に、ハッと気付いたのである。「ああ、これは聖書に書いてあることだ。間違いない。」などと。それはキリストが神殿の商人たちを追い出された際にそれを見た弟子たちが、『あなたの家を思う熱心がわたしを食い尽くす。』(ヨハネ2章17節)という詩篇の文章を思い起こしたと、福音書に書いてある通りである。黙示録を読む際、心に旧約聖書の文章がインプットされているのも、これと同じことである。インプットされていればいるほど、それだけ黙示録の内容を悟れる度合いも高まる。しかし旧約聖書を知らなければ知らないほど、黙示録を理解するのは難しくなる。ヨハネが旧約聖書に基づいて多くのことを書いているのだから、これは当然といえば当然である。その人は、あたかも地図を何も見ないで、まだ1度も言ったことのない遠くにある場所へたどり着こうとする人に似ている。その人は何とかして目的地へ行けるかもしれないが、それはかなりの時間と労力を要するのであって、場合によってはいつまで経っても目的地へ着けない可能性も十分にある。旧約聖書を知らずに黙示録を読み解こうとする人は、地図をあらかじめ確認しないで遠い地に行こうとする人のように、準備と思慮が足りないと言わねばならない。その人は「無謀者」だと言われても文句はいえない。我々が特に精通しておくべき旧約聖書の巻は、預言書と出エジプト記である。何故ならヨハネはこれらの巻に基づいて、多くの文章を記しているからである。これ以外の巻においては、創世記に書いてあるソドムとゴモラの記述などいくらかの箇所を除けば、黙示録を理解するためには、それほど熟読する必要はないと思われる。特に箴言やヨブ記やエステル記などといった巻は、たとえそれほど知らなかったとしても、致命的な問題にはならないであろう。というのも、これらのような巻は、ほとんど黙示録と関係する内容を持たないからである。また同じ理由から預言書の中でも、マラキ書やヨナ書などといった巻は、黙示録の研究のためには、あまり読まなかったとしても大きな問題は生じない。新約聖書においては、福音書に精通しておかねばならない。それは、ヨハネが福音書と対応する文章を多く記しているからである。例えば、マタイ25:31~46と黙示録20:11~15、マタイ23:34~36と黙示録16:4~7および18:24が、そうである。福音書以外では、Ⅱペテロ3章、Ⅱテサロニケ2章1~12節、Ⅰテサロニケ4章13~18節、Ⅰコリント15章20~28、50~56節を頭に叩き込んでおかなければいけない。これらの箇所は、黙示録の内容と大いに関係している箇所だからである。
また我々は、黙示録に、無数のユダヤ的な象徴や言い方が満ちていることを心に留めなければいけない。これは黙示録を少しでも読めば誰でも分かることである。ヨハネは純粋なユダヤ人だったのであるから、これは当然と言えば当然である。それゆえ、我々が黙示録を十全に理解するためには、我々が紀元1世紀の時代に生きていたユダヤ人に知的・精神的な意味においてなりきるのが、もっとも望ましい。もし我々が当時のユダヤ人そのもののようになれば、黙示録をそれだけ理解しやすくなるのは明らかだからである。しかし、このようにするのは非常に難しい。今のユダヤ人ですら、そういうことは出来ないであろう。だから、我々は何とかして、旧約聖書におけるユダヤ的な象徴や言い方を知り、それに精通し、また慣れる必要がある。そのように出来るのであれば、それだけ我々は黙示録のことをよく弁えられるようになる。しかし、そのように出来なければ、それだけ象徴や今の時代からすれば少し変わった言い方を理解するのは困難となる。
確かなところ、黙示録は、相対性理論よりも難解であり、弁えることが困難である。アインシュタインにより主張された相対性理論は、難しいと昔から言われてきた。アインシュタインが論文を発表した頃は、相対性理論を理解できるのは世界に5人しかいないと言われた。時代が進んだ今においては、かなりの人が理解できるようになっている。しかし、黙示録を十全に理解している人は、今の世の中に一人もいない。黙示録を完全に理解できるようにと神に願い求めている私でさえ、十全に理解することができていない。色々と本を読めば分かるが、高名な神学者や牧師たちの黙示録理解は、誤解のオンパレードである。卓越した神学者であるカルヴァンも、黙示録がよく理解できないので、この文書にだけは手を出さなかった。すなわち、彼は黙示録の註解書を記すことがなかった。アウグスティヌスも、黙示録の解き明かしをしようとはしていない。エリファス・レヴィは黙示録を教会が解明しようとしないことに驚いており、この文書は「敬虔なキリスト教信徒には7つの封印で閉ざされている」(『高等魔術の教理と祭儀 教理篇』序章 p10:人文書院)などと率直に言っているが、この奇人魔術師の言っていることには一理ある。彼の言っているように、教会からは「黙示録を解明する鍵」また「ソロモンの学問を解明する鍵」が失われてしまっているのだ。これは認めなければならない。詰まるところ、今まで誰も彼も黙示録のことを、まったく悟れていなかったのである(※)。今までに黙示録を完全に理解したことがあるのは、著者であるヨハネ一人だけである。ヨハネと共にいた他の使徒たちや、ヨハネから直々に教えを受けた聖徒たちも、十全には理解できなかったはずである。何故なら、それがあまりにも高度で複雑で謎に満ちているからである。黙示録を完全に把握するよりは、相対性理論をマスターするほうが、遥かに優しい。我々は、最初から黙示録を理解することなど人間業では不可能だという前提で、黙示録の研究に臨んだほうがいいかもしれない。今までの2000年間の例を見れば分かるように、黙示録は理解できないのが当然なのである。実際、今までに黙示録を理解した者は、ヨハネという例外を除けば、誰もいなかった。このような前提で研究に臨めば、たとい理解できずに思い悩んだとしても、その前提が我々をいくらかでも慰めてくれることになる。しかし、人間の理性と力では黙示録を理解できなかったとしても、神の恵みが注がれるのであれば、我々は黙示録をその恵みにより理解できるようになる。何故なら、神の恵みが、我々に黙示録を理解できるようにと働きかけて下さるからである。神はその恵みにより、人間にとっては不可能なことを、可能として下さる。それはキリストが『人にはできないことが、神にはできるのです。』(ルカ19章27節)と言われた通りである。それゆえ、我々は、黙示録の正しい理解が徹頭徹尾神の恵みにかかっているということを知らなければいけない。神の恵みだけが、人に黙示録を理解できるようにして下さるのである。だから、もし黙示録を正しく理解できたのであれば、その人は、黙示録を理解できた恵みを神に感謝すべきである。
(※)
本屋や図書館または教会に置いてある本棚に行って、片っ端から黙示録を取り扱っている書物を見てみるがよい。私は断言するが、そのどれもが根本的な誤謬に基づいて記されている。正しい理解に基づいて記されている書物は、一つすらもない。
[本文に戻る]
最後になるが、もし黙示録を正しく理解したければ、その人は徹底的に謙遜な精神を持たなければいけない。アウグスティヌスは「キリスト教の要諦は何か?」と聞かれた際に、デモステネスの有名な返答(※①)に則して次のように答えた。「第一に謙遜、第二に謙遜、第三に謙遜」と。それと同じように、もし私に「黙示録を正しく理解するための要諦は何か?」と聞く人があれば、私はデモステネスとアウグスティヌスの答えに則してこう言うであろう。「第一に謙遜。第二に謙遜。第三に謙遜。」と。高慢な人は、自分の理解を、神の御心に適った正しい理解よりも優先させてしまう。その人が高慢であって自分の理解こそを第一とするからである。その人は自分の理解こそを神としている。だから、神がその人の心に正しい理解を生じさせても、最終的にその理解を拒絶するに至る。それは、あたかもキリストが譬えの中で、心に蒔かれた御言葉の種を悟らないと悪魔である鳥が来てその種を持っていってしまうと言われた人のようである(※②)。この譬えでは、サタンが良いものを心から取り去ってしまうのだが、黙示録の正しい理解が心に蒔かれてもそれを拒絶する人は、自分自身がサタンのようなことをしている。その人は、サタンのように良いものを心から除き去っているのである。だから、高慢な人は、いつまで経っても黙示録を悟ることができない。我々は、聖書に『神は、高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。』(ヤコブ4章6節)と書いてあることに心を留めるべきである。つまり神は、高ぶる者には黙示録の正しい理解を与えられないのであって、へりくだる者にこそそれを持たせて下さるのである。黙示録を正しく理解したい兄弟は、謙遜になって神に祈るがよい。「私は天から受けるのでなければ何も悟れない鈍い者ですから、どうか恵みにより悟りを与えてください。」などと。そうすれば、『へりくだる者に恵みをお授けになる』神が、我々に正しい理解を持たせて下さることであろう。
(※①)
最高の雄弁家であるデモステネスは「雄弁の要諦は何か?」と聞かれた際に、「第一に身振り、第二に身振り、第三に身振り」と答えたといわれる。
[本文に戻る]
(※②)
『種を蒔く人が種蒔きに出かけた。蒔いているとき、道ばたに落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。…御国のことばを聞いても悟らないと、悪い者が来て、その人の心に蒔かれたものを奪って行きます。道ばたに蒔かれるとは、このような人のことです。』(マタイ13章3~4、19節)
[本文に戻る]
第4章 ①1章:プロローグ
(※①)
「節」は、ルターの時代以降に区分されるのが一般化した。ルターの時にはまだ節での区切りがなされておらず、ルターも聖書を引用する際には章だけしか述べていない。
[本文に戻る]
(※②)
例えば、黙示録の2章と3章がそうである。この2つの章は、どちらも7つの教会に対してキリストからの言葉が伝えられるという同じ内容を持つのだから、1つの章に纏めるべきであった。「そうするとかなり長い章となってしまわないだろうか。」などと思う方もいるかもしれないが、これぐらいの長さの章であれば、聖書の他の箇所にも存在しているので、特に問題だとは思われない。例えば詩篇119篇は非常に長く176節まであるし、申命記28章も長く全部で68節もある。また読者は、私がこのように章の区切りについて文句を付けることに驚いてはいけない。いい加減な区切りであれば、それは文句を付けるべきである。カルヴァンも次に示す通り、章の区切りについて大いに文句を言っている。「…だれだか知らないが、章節の区分をした人は、ここでは無分別な分けかたをしたものである。なぜなら、…」(『新約聖書註解Ⅸ コリント後書』2:1 p39:新教出版社)「使徒の手紙を各章に区分した人は、むしろ、ここで第5章をはじめるべきであった。」(『新約聖書註解Ⅷ コリント前書』4:21 p116 新教出版社)「章の分けかたがいかにでたらめであるかは、これをみても明らかである。だいたい、この聖句は、前出の各句につらなるものであるが、それが切りはなされ、この句と何の共通点もない後続の各句に結びつけられているのである。だから、これは、前章の結論であるという仮定をとることにしたい。」(『新約聖書註解Ⅷ コリント前書』11:1 p249~250 新教出版社)「この章の区分が実にでたらめなされかたなので、わたしは、どうしてもその変更をしないわけにはいかなかった。それに、そうしないことには、その適切な解釈もできない始末だったからである。…」(『新約聖書註解Ⅷ コリント前書』13章 p301 新教出版社)「読者は章の区切りの不手際に煩わされないため、この文章が前章の最後の二節に続くものとして読んでもらいたい。…」(『旧約聖書註解 創世記Ⅰ』12:1 p223:新教出版社)
[本文に戻る]
【1:1】
『イエス・キリストの黙示。』
これは、聖書でよくなされる書き方である。これと似たような書き方がされているのは、他にも、次の箇所がある。『神の子イエス・キリストの福音のはじめ。』(マルコ1章1節)『エルサレムでの王、ダビデの子、伝道者のことば。』(伝道者の書1章1節)『イスラエルの王、ダビデの子、ソロモンの箴言。』(箴言1章1節)『ユダの王、アモンの子ヨシヤの時代に、クシの子ゼパニヤにあった主のことば。』(ゼパニヤ1章1節)『ニネベに対する宣告。エルコシュ人ナホムの幻の書。』(ナホム1章1節)聖書は、どの巻も、神の宣言文である。だからこそ、このような宣言文が、冒頭で書かれている。もちろん、このような宣言文が冒頭で書かれていない巻もあるが、だからといって、それが神の宣言文でないということにはならない。また、この簡潔な言葉は、その文書の内容を一言で言い表わす要約的なものでもある。
『黙示』とは、原文では「αποκαλυψιs」(アポカリュプス)である。英語では「revelation」と訳される。これは、「神の真理や奥義が公にされる」という意味である。「隠されていたことが明らかにされる」とか「被いが取り除かれる」という意味でもある。(※)だから『イエス・キリストの黙示』とは、すなわち「イエス・キリストが示された未来に関する秘密」という意味となる。これは、あたかも「イエス・キリストがこれから起こる様々な出来事を遂に開示して下さるのだぞ。」とでも言おうとしているかのようである。確かに、これはその通りである。これから書かれる註解を読めば、正にこの文書が『黙示』に他ならないということがよく分かるようになるであろう。それは、黙示録を少しパラパラと眺めているだけでも、感覚的に把握できることである。確かに、この文書では、ヨハネの時代にとっての未来の事柄、すなわち再臨の時期に起こる諸々の出来事が預言されている。だからこそ、私は、本作品の第3部で黙示録の註解を組み入れることにしたのだ。それというのも、この作品は再臨を徹底的に考究することが目的とされているからである。この黙示録には再臨の時期に起こる出来事が豊かに書かれているのだから、この黙示録を理解することなしに、再臨を十全に理解することは非常に難しいと言わねばならない。
(※)
黙示録は世俗においても有名な文書であり、その名を知らない人がいないほどであって、この文書の中に見られる内容や名前がよくファンタジー作品の中で使われているのを見かける。日本で言えば世界的に有名なゲームであるファイナルファンタジーというシリーズの中で、アポカリプスという名前が幾つも使われている。他にもドラゴンクエストやモンスターハンターやモンスターストライクというゲームの中でも、アポカリプスという名前が使われている。世界で最も有名なトレーディングカードゲームの「マジック・ザ・ギャザリング」の中でも、このアポカリプスという名前が使われている。BABYMETALという日本の有名なバンドのメンバーズサイトは、かつて「APOCALYPSE WEB」という名前であった。ラルク・アン・シエルという日本のバンドのアルバムの中にも「REVELATION」という名の曲がある。2020年に発売の「ゼルダ無双」というゲームにおけるサブタイトルは「厄災の黙示録」である。今挙げたのはほんの少数の例であって、他にも探せば、この名前が使われている作品はいくらでも見つかるであろう。もちろん、アポカリプスという名前を黙示録から取っている人たちは、単に名前の響きや印象を理由としてこの名前を取り入れている。何故なら、この名前は、武器や魔物や特技などに付けられており、ほとんど言葉の意味が適合するかどうかということは考慮されていないからである。アポカリプスという名前の魔物や武器とは一体何なのであろうか…。このように黙示録は世俗からすればファンタジー系の作品と相性が良いように感じられるかもしれないが、黙示録が世俗の作品などよりも遥かに卓越しており崇高であることは言うまでもない。
[本文に戻る]
『これは、すぐに起こるはずの事をそのしもべたちに示すため、』
黙示録に示されているのは、すぐに起こるはずのことである。その『すぐ』とは、もちろん、ヨハネが黙示録を書いている当時にとっての『すぐ』である。この言葉は文字通りに捉えなければいけない。我々の日常的な感覚に基づいて、この『すぐ』という言葉を捉えても差し支えない。事実、ヨハネは自分の日常的な感覚に基づいて『すぐ』と書いている。注意しなければいけないのは、これは神にとっての『すぐ』と考えるべきではないということである。神にとっては『千年は1日のよう』(Ⅱペテロ3章8節)だから、たとえ千年でも、いや千万年であったとしても「すぐ」だということになる。しかし、これは言うまでもなく、人間的な感覚から言った『すぐ』である。今の教会には、これを神の感覚から言った『すぐ』だと捉えたがる人が多いから、そうしないよう注意しなければいけない。第3部の2章で言われたように、ヨハネが黙示録を書いたのは、紀元37~41年の間である。13章に書かれているネロの教会迫害は紀元64年に始まるのだから、ヨハネが黙示録を書いてから23~27年後にそれは起こったことになる。また20:7~10に書かれているエルサレム包囲は紀元66~70年の間のことだから、それは、ヨハネが黙示録を書いてから約30年後に起こったことになる。確かにヨハネは本当にすぐに実現することを、この文書の中で書いたのである。しかし、30年が『すぐ』だとは思えない方も、読者の中にはもしかしたらおられるかもしれない。人にはそれぞれ感覚があるから、30年をすぐだと思えない人がいたとしても不思議ではない。しかし、聖書はこの30年を『すぐ』だと言っているのだから、聖徒である者は、この期間を「すぐ」だと捉えなければいけない。もし捉えられなければ、強引に自分の理性をねじ曲げよ。そうしなければ神に喜ばれることはできない。既に語られたように、その事象が大きければ大きいほど、日常であれば長いと感じられる期間でも非常に短く感じられることになる。例えば、これから30年後に、人口およそ3500万人のカナダやアルジェリアに巨大な隕石が落ちるとすれば、どうか。その時、3500万の人が、すべて死んでしまう。これは非常に大きい出来事であるから、日常では長いと感じられる30年後であったとしても、短いと感じられるのではないかと思う。「そんなにすぐにカナダやアルジェリアが滅亡してしまうのか?」と思う人も多いはずである。黙示録で預言されているユダヤの滅亡も、非常に大きな出来事である。紀元1世紀にユダヤが滅亡した際には、最高で110万人の人が死んだと言われる(※)。これは2019年の今でいえば、比率的に言って3500万人と同じ数であり、カナダやアルジェリアが一挙に滅亡するのと同じことである。このような前代未聞の悲劇がこれから30年後に訪れるというのだから、これを『すぐに』と言わずして何と言えばいいであろうか。これが小さい出来事であれば30年後を「すぐ」と言うのは適切ではなかったが、ユダヤの滅亡は小さい出来事ではないのである。あの神の聖なる民における集団が、一挙に滅ぼし尽くされてしまうのだから。
(※)
これは推定上の最高数であって、他にもユダヤ人の死者数には異なる見解がある。オロシウスの場合、「60万人のユダエア人がこの戦争で殺されたと、コルネリウス・タキトゥスとスエトニウスは伝えている。」(「世界史梗概」7・9・7)と言っている。
[本文に戻る]
この『すぐに起こる』という短い文を、今まで教会は、まったく注目してこなかった。今までにいた高名な教職者で、この文に多くの注意を払った人は、恐らく一人もいなかったはずである。もしいたら私に知らせてほしいものである。今に至るまで、この黙示録は闇に包まれた文書であった。黙示録の全体がそうであった。だから、今まで教職者たちが、このような些細だと思われる部分に着目してこなかったのは、自然なことであると言えるかもしれない。それは、あたかも人が真っ暗な倉庫の中に入って、人類の秘密が隠された太古の文書を探し出して読むようなものである。今まで教会はこの部分に着目して来なかったから、黙示録には『すぐに起こるはずの事』が示されているということに、まったく気付くことができなかった。それゆえ、今まで教会は、黙示録には「すぐには起こらない事」また「(自分たちが生きている時代を基点として)これから起こる事」が示されているのだと思い続けてきた。例えば、ある人たちは8:11に書いてある『苦よもぎ』による死が、チェルノブイリ事故のことを言っていると考えてしまった。ある人は、12:7に書いてある「ミカエルたちと竜の戦い」が、教会と異端との戦いを霊的に示していると愚かにも考えた。ある人は11:4の『オリーブの木』が、プロテスタントにおける改革派の教会を示しているなどと考えた。ある千年王国論者は20:7~10に書いてあるのは「ロスチャイルドのこと」ではないかと考えてしまった。どれもこれも大変素晴らしい解釈である!タルムードに書いてあるように「よくぞ彼らは言った!」(シャバット篇:第1章、ミシュナ3)と私は彼らに言ってやりたいと思う。というのも、どうすればこのような曲芸的な解釈ができるのか私にはよく分からないからである。このような解釈ができるのは、ある意味、非常に凄いと言える。もちろん、私が褒めているのではないことは言うまでもない。しかし、ヨハネは黙示録が書かれているその当時から考えて『すぐに』と言っている。今挙げた妄想的な解釈は、どれもこれも、ヨハネの時から考えて明らかに『すぐに』ではない。それらの出来事は「ずっと後になって起こること」である。理性が与えられている者ならば、これは誰でも分かることである。よって今まで教会が黙示録の記述に基づいて起こると考えてきた出来事、また既に起きたと考えた出来事は、ことごとく誤りだったことになる。黙示録には、チェルノブイリのことも、改革派の教会のことも、真理と異端との戦いも、ロスチャイルドのことも、何も書かれてはいないのである。このような妄想を今まで聖徒たちが抱いてしまった究極的な原因は、この『すぐに起こるはずの事』という部分を直視してこなかったからである。もしこの部分を直視してよく考えていたのであれば、ヨハネが書いてもいないような出来事を妄想として心に抱くこともなかったことであろう。この部分は小さく心に留めにくい部分ではあるが、実は非常に重要な部分である。この部分は、黙示録の全内容を規定し、我々の解釈を大きく左右させる根本的な部分である。それゆえ、我々がどれだけこの部分に心を留めたとしても、留めすぎるということには決してならない。
『示す』とは、すなわち、ヨハネに幻の形で預言が示されたという意味である。それは幻であって、ヨハネは何か実際の物質現象を見たというのではない。それでは、その幻とは、ヨハネの脳内において視像として示されたのであろうか。それとも、ヨハネの周りの空間に他の人には見えないバーチャル映像のような形として示されたのであろうか(※①)。これは、我々にはよく分からない。1章12節目では『振り向くと、七つの金の燭台が見えた。』と書いてあるから、ヨハネのいたパトモス島に、ヨハネだけが見れるバーチャル映像が示されたということなのかもしれない(※②)。しかし、ヨハネは天の場景を見せられたのだから、脳内における視像として幻が示されただけだという可能性もある。もしくは、脳内にも示されたし、バーチャル映像として周りの空間にも示された、ということなのかもしれない。いずれにせよ、これはあまり黙示録の理解においては重要な問題ではない。一つ確実に言えるのは、これが神の示された幻であったということである。ヨハネは、何かの空想を頭に思い描いたというのではない。世の中にはモーセが麻薬を使っていたなどと根拠もなしに言っている人がいるが、そのように麻薬を使ったからというので、このような普通ではない幻を見たということでもない。そのような考えを抱く人たちは、神の呪いを受けている。神の呪いを受けているからこそ、そのような愚かな考えを持つのである。
(※①)
例えば、空間上に現われたキリストの幻をダニエルだけが見たように(ダニエル10:7)。
[本文に戻る]
(※②)
技術の進歩した昨今ではコンサート会場などでリアルなバーチャル映像が投影されることがあるが、私が言っているのは、このような映像として示される幻のことである。
[本文に戻る]
神は、どうして幻を示されたのか。それは聖徒たちのためであった。ヨハネが黙示録を書いている時には、聖徒たちに襲い掛かる苦難の時が、もう間近に迫っていた。それは1:3で『時が近づいている』と書いてある通りである。ネロによる大虐殺が、もう30年もすれば、聖徒たちにやって来る。これは誠に悲惨なことである。神は、このような出来事の到来を、あらかじめ聖徒たちに示されることを欲された。往々にして人は、事前に未来の事柄を知っていればいるほど、それだけ準備が出来るし、また突然悲惨が襲いかかってきたからというので慌ててしまうこともなくなる。これは誰でも分かることであろう。中にはカエサルのように突然の悲惨を望む強い人もいるが(※①)、パウロが言っていることからも分かるように、聖徒たちには弱い人が多いのだから(※②)、やはり聖徒たちにとっては未来の事柄をあらかじめ知っておいたほうがいいということになる。つまり神は、やがて訪れる悲惨な出来事を聖徒たちにあらかじめ示すことで、聖徒たちが心の準備をしたり、急に襲いかかってきた悲惨に動乱することがないようにされたのである。もし黙示録で未来の事柄が示されなかったとすれば、聖徒が心の準備をしたり、動乱しないで済むようなことには、ならなかったであろう。要するに、『神は愛』(Ⅰヨハネ4章8、16節)であるから、聖徒たちに親切なことをして下さったのである。パウロも言うように『愛は親切』(Ⅰコリント13章4節)である。だから、この「示し」のうちに、神の聖徒に対する愛が現われていることが分かる。神は優しく慈しみに富んでおられるから、聖徒に予告して下さったのである。また、幻が示された理由は、もう一つある。それは、神が、あらかじめ預言されることなしには何事もなさらないお方だということである。アモス3:7には、こう書かれている。『まことに、神である主は、そのはかりごとを、ご自分のしもべ、預言者たちに示さないでは、何事もなさらない。』事前に未来のことを示されてから何かをするというのが、神のやり方なのである。何故なら、そのようにすれば、神の栄光が現われるようになるからである。神が語られたことが実際に起きたならば、我々は驚いたり、感嘆の念を持ったり、神を恐れたり讃美したりしないであろうか。敬虔な人であれば、恐らくそうするであろう。そうすれば、そこにおいて神の素晴らしさや偉大性、また真実性といったことが、実際に顕現されることになる。
(※①)
カエサルは「どのような死に方が一番理想的か。」と聞かれた際、「予期せぬ突然の死。」と答えた(※A)。実際、この言葉の通り、カエサルはブルートゥスらによる予期せぬ突然の暗殺により死ぬことになった。彼のように徹底的な強さを持った人は、意識的にであれ無意識的にであれ常に強くあることを望むから、死の兆候を感じることにより弱くならないことを求める。病気などにより死の接近を感じて弱まるのであれば、強さに基づく優位性や尊厳が、それだけ失われてしまうからである。
(※A)
「あのような死に方がカエサルの願望にかなっていたという見解では、ほぼすべての人が一致している。というのもカエサルはかつてクセノポンの中で、キュロス王が死に際の病床で、自分の葬儀についていくつかの指示を与えたというくだりを読んだとき「こんな悠長な死に方はまっぴらごめんだ。私なら不意に一息で死にたい」と言ったという。刺殺される前日にも、マルクス・レピドゥス邸での晩餐会の最中、たまたま、いかなる最期が最も好ましいかということが話題になったとき、カエサルは「突然の予期せざる死がいい」と言っていた。」(スエトニウス『ローマ皇帝伝(上)』第1巻 カエサル p91:岩波文庫)
[本文に戻る]
(※②)
Ⅰコリント1:26~28。
[本文に戻る]
『そのしもべたち』とは、もちろん紀元1世紀に生きていた神の聖徒のことである。黙示録は、第一次的・直接的には、言うまでもなく当時の聖徒を対象として書かれたものである。ネロの到来を、この文書は預言しているのだから、このことは疑えない。しかし第二次的・副次的な意味においては、この紀元1世紀以降の神のしもべたちをも対象としている。それは、つまり紀元1世紀以降の聖徒たちにとって、この黙示録が益となるためである。その益とは、すなわちヨハネの時代に迫害を受けた聖徒たちから忍耐を教訓として得ること、また神の聖徒に対する愛を豊かに知るようになること、また神とその預言における真実を知れるようになること、また天国や永遠の刑罰のことを豊かに悟れるようになること、この4つである。だから、我々は、この黙示録が直接的には昔の聖徒を対象としたものであったとしても、何か残念に思ったりすべきではない。というのは、確かにこの手紙は直接的には昔の聖徒に宛てられたものだが、それは今の時代に生きる我々に与えられたものでもあるからである。この黙示録は、ヨハネの時代の聖徒に対する贈り物であり、我々に対する贈り物でもある。
『神がキリストにお与えになったものである。』
これは、つまり父なる神が、人としてのキリストに預言をお与えになったということである。人としてのキリストは、神からこの預言を受けるまでは、黙示録に示されていることを知っておられなかった。それは、人としてのキリストが、再臨の起こる日がいつであるのか知っておられなかったのと同じである。マタイ24:36を見れば明らかなように(※)、人としてのキリストには、再臨の日がいつであるのか父なる神はお示しになっておられなかった。しかし、神としてのキリストは、父なる神と同じように、永遠の昔から黙示録に示される出来事を何もかも知っておられた。それは聖霊なる神も同じである。我々は、ここで言われているのが人としてのキリストについてであるということを知らねばならない。
(※)
『ただし、その日、その時がいつであるかは、だれも知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。』
[本文に戻る]
どうして父なる神は、預言をキリストにお与えになったのか。すなわち、どうして聖徒に預言を直に与えられず、まずキリストにお与えになり、そうしてからキリストを通して聖徒にお与えになるようにされたのか。それは、父なる神が、御子を通して何かをされるお方であるからであり、また全てはこの御子のために存在し、この御子のために起こるからである。確かに、聖書は万物が御子を通して創造されたと教えている。ヨハネは福音書の1:3で、このことについて、こう書いている。『すべてのものは、この方によって造られた。造られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。』救われて父なる神の御元に至ることも、御子を通してでなければいけない。福音書の14:6で、キリスト御自身がこう言っておられる。『わたしを通してでなければ、だれひとり父のみもとに来ることはありません。』またパウロも言うように、『万物は…御子のために造られた』(コロサイ1章16節)。つまり父なる神は、あらゆる事柄において、御子を媒介者とされるのである。それは父なる神が、ご自身の御子を愛しておられるからである。このようなことのために、父なる神は、まず初めに預言をキリストにお与えになったのである。もしそうされず、直接的に聖徒に預言をお与えになっていたとすれば、父なる神は御子のためにこそ万物をお造りになったのではないということになる。しかし万物は御子のためにこそ造られ、存在している。だから、父なる神が直接、聖徒に対して預言をお与えになるのは御心ではなかった。
『そしてキリストは、その御使いを遣わして、これをしもべヨハネにお告げになった。』
主は、御使いにより、ご自身の与えられた預言をヨハネにお与えになった。それは、例えるならば、ある会社の社長が経理やデザインの仕事を、それを専門とする者に任せるようなものである。「きみ、これをやってくれ。頼んだよ。」と。聖書の他の箇所でも、キリストがその御使いたちにより、何かを行なわれるということが書かれている。マタイ24:31では、キリストが御使いたちに携挙の仕事を行なわせることが書かれている。マタイ13:40~41によれば、悪しき者を火の池に投げ込むのは、御使いに委ねられていた。ガラテヤ3:19では、仲介者なるキリストの手で律法が定められたのは、御使いたちを通してであったと書かれている。牢に閉じ込められていたペテロを主が救い出されたのも、やはり御使いを通してであった。ペテロは使徒行伝12:11でこう言っている。『今、確かにわかった。主は御使いを遣わして、ヘロデの手から、また、ユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから、私を救い出してくださったのだ。』今引用した箇所からも分かるように、御使いたちに何かの仕事を任せられる、というのがキリストのやり方なのである。
聖書では、悪しき御使いを指して「御使い」と言われている箇所もある(Ⅰコリント6:3、ユダ6)。しかし、ここで言われているのは、もちろん「聖なる御使い」である。御使いは色々と存在しているが、キリストが遣わされたこの御使いが、どの御使いだったのかは分からない。何故なら黙示録は、この御使いがミカエルなのかガブリエルなのかラファエルなのかウリエルなのかレミエルなのかドキエルなのかピュルエルなのかエズラエルなのかゼルエルなのかナタニエルなのか(※)、また火をつかさどる御使いなのか水をつかさどる御使いなのか、何も書いていないからである。申命記29:29に書いてあるように、『隠されていることは、私たちの神、主のものである。』この御使いが誰なのかということは隠されているのだから、我々は、そのことを無謀にも詮索すべきではないし、たとい詮索しても分からないままであろう。それゆえ、我々は喜んで、この謎を謎のまま放置しておくべきである。もし無謀にもこの御使いの存在を確定しようとする人がいれば、その人は傲慢である。我々は、カルヴァンも言ったように「知ることが与えられておらずまた許されていないものについては、無知こそが博識であり、知りたいという欲求は一種の狂気」(『キリスト教綱要 改訳版 第3篇』第3篇 第23章 第8節 p467:新教出版社)だということをよく弁えよう。
(※)
ここで挙げた御使いの中には外典や偽典に出てくる御使いも含まれているが、正典に出てくる御使いはミカエルとガブリエルとラファエルの3人だけであるという点に注意してほしい。
[本文に戻る]
キリストは、ヨハネにこそ、この預言をお与えになった。それはヨハネが、キリストから受けた預言を書き記して、それを聖徒たちに知らせるためであった。しかし、どうしてヨハネなのか。それは我々には分からない。ところで次の質問に答えられる人がいるであろうか。どうしてマリヤが主の母として選ばれていたのか。どうしてユダヤ人が神の民として選び取られたのか。どうしてダビデがイスラエルの王に定められていたのか。どうしてヤコブは愛されエサウは憎まれたのか。これらは、どれも主がそのように欲されたからというのがその理由ではあるが、その欲された当の理由というのは、我々には分からない。この問題は、既に多くの著作家たちが論じてきたことである。それと同じで、どうしてヨハネが黙示録の筆記人として選ばれていたのか、我々には不明である。しかし、その理由が不明であったとしても、黙示録の理解のために何か障害が生じるということはないから、その点は安心すべきである。
黙示録では、ここで初めてヨハネという名前が出てくる。教会における今までの一般的な理解は、このヨハネが使徒であり福音書記者でもあるヨハネであったというものである。私もそのように考えている。というのも、これは使徒であり福音書を書いたあのヨハネ以外には考えられないからである(※)。他にキリストから貴重な啓示を受けるような別のヨハネがいたとは思われない。それではヨハネはこの文書を、自分の手で記したのか、それとも口述により記したのか。ローマ16:22を見れば分かるように、ローマ書の場合、それはパウロが『テルテオ』に口述筆記させたものであった。今ではあまり考えられないが、古代のギリシャやローマにおいて、文書を代わりに書かせるのは何も珍しいことではなかった。キケロもアッティクスへの手紙を、奴隷に代筆させている。少し前の時代でも、ゲーテが口述により文章を書いているし、チェッリーニの有名な自伝も口述によるものである。しかし、この黙示録の場合、ヨハネが自分自身の手で記したと考えるべきであろう。何故なら、ヨハネに対して大きな声が『あなたの見ることを巻き物にしるして』(1章11節)と言っているし、キリストもヨハネに『書きしるせ。』(1章19節)と命じておられるからである。このように言われたのに、ヨハネが誰かに口述筆記させたというのは、非常に考えにくい。このような聖なる命令があるにもかかわらず、代筆させたのであれば、ヨハネが不忠実また不誠実な人間だということにならないであろうか。
(※)
アウグスティヌスも、黙示録を書いたのは、このヨハネであったと考えていた。アウグスティヌスの説教の中に、「黙示録のある箇所で、天使が福音書記者ヨハネに何かを示したとき、…」(『アウグスティヌス著作集23 ヨハネによる福音書講解説教(1)』第13説教 2 413年 p222:教文館)と書かれていることから、彼がヨハネこそ黙示録の著者であったと考えていたことが分かる。トマス・アクィナスも「黙示録での福音史家ヨハネにおいては…」(『中世思想原典集成 第Ⅱ期1 トマス・アクィナス 真理論 上』第13問題第2項 p927:平凡社)と言っており、この文書がヨハネによるものだと理解していた。バウルおよびテュービンゲン派の学者たちも(※私は彼らの神学には否定的である)、黙示録を書いたのは使徒のヨハネだったと理解していた。しかし、ルターは黙示録を書いたのはヨハネではないと考えていた。これは、とんでもない見解である。この聖なる文書は、「ヨハネ」こそがその著者であると、紛れもないほど明瞭に教えている。神が、ご自身の文書に偽りを書くとでもいうのであろうか。そのようなことは、考えるだけでもふざけた話である。ルターは用いられた神の器であったが、この見解については受け入れるべきではない。ルターも黙示録においては、ただの盲人だったのだ。私が最近見た「図説 ローマ帝国衰亡史(東京書籍)」というギボンの歴史書を図において編集した書物の中でも、黙示録の著者はヨハネではないと言われていた。この本の訳者によると黙示録を書いたのは「一預言者」なのだということである。何も黙示録を理解できていない無知な者が、さも十分に弁えているかのように堂々とこのように語っているのは、滑稽であり失笑を禁じ得ない。私の推測では、この訳者は黙示録というこの注目される秘儀に満ちた文書について知者ぶって語ることで、人々から優れた者・知恵ある人間であると思われたいと密かに感じているのではあるまいか。いずれにせよ、ルターもこの訳者も、黙示録を十分に研究してから著者について何事かを言うようにすべきであった。こんなに難しい文書を十分な研究抜きに理解し語れるとでも思っているのか。黙示録を舐めるのはやめていただきたいものである。それゆえ、我々は黙示録の著者がヨハネではなかったなどというこの誤った見解を完全に脳内から斥けるべきである。黙示録の正式名称が「偽ヨハネによる黙示録」となるべきだとでも言うのであろうか…。
[本文に戻る]
【1:2】
『ヨハネは、神のことばとイエス・キリストのあかし、すなわち、彼の見たすべての事をあかしした。』
黙示録に書かれているのは、ヨハネに見せられた幻の『すべて』であった。すなわち、ヨハネがこの文書の中で、うっかりして書き忘れたことは一つもない。またヨハネが見たにもかかわらず、それを隠して書かないでおいたというものも一つもない。神は、ヨハネに対して過不足なく、幻を示された。だから、我々は黙示録を読んで、「何か足りない」とか「ちょっと冗長すぎるのでは…」などとは間違っても思うべきではない。全てのことを正しく適切に行なわれる神は、ヨハネに対して必要充分なだけの量の幻を示されたのである。その幻を、ヨハネは漏れなく書き記したのである。
黙示録に書かれているヨハネの証は、すなわち『神のことばとイエス・キリストのあかし』である。何故なら、ヨハネは自分に示された神からの幻を、そのまま書き記したからである。聖書の他の巻もそうであるが、黙示録が天上の匂いを放っているのは、これが理由である。すなわち、それが神から出たものであるがゆえに、必然的に天上の匂いが放たれざるを得ない。そのように崇高で神聖な証がここには記されているのだから、この文書の取り扱いには注意を要する。それは単なる人間の文章に過ぎないものではない。それは、例えばどこかの国の王族から受けた貴重な手紙よりも、その重要性において優っている。それゆえ、どれだけこの文書に対して慎重になったとしても、慎重になり過ぎるということにはならない。我々は、誤りに陥らないためにも、この文書を取り扱う際には、非常に慎重になるのが望ましい(※)。神の言葉で誤るのは実に悲惨なことである。
(※)
喜劇作家のメナンドロスもこう言っている。「最も知恵ある人々は言っている、『すべて探求には注意深さが必要だ』と。」(断片164、ケルテ編)
[本文に戻る]
【1:3】
『この預言のことばを朗読する者と、それを聞いて、そこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。』
ヨハネの時代において、「書物」と言えば、それは巻き物を意味していた。当時は、まだ我々の知っているような形としての書物は、存在していなかった。キリストが会堂で手渡されたイザヤ書も、巻き物であった(ルカ4:16~17)。この黙示録も、やはり巻き物であったはずである。これだけ長いのだから、正方形や長方形のパピルス紙1枚か2枚だけのはずがない。また古代において、本を読むとは、朗読のことであった。驚く人も多いかもしれないが、今のような黙読という読書方法は、まだ古代では一般的ではなかった(※)。アウグスティヌスの「告白」を見ると、アウグスティヌスが黙読をしているアンブロシウスに驚いていることが分かる。つまり、ここで言われているのは、ヨハネから届けられた黙示録という巻き物を誰かが朗読し、それを皆で集まって一緒に聞く、ということである。まだ文盲の人が多かった古代において、書物は、このようにして衆人に読み聞かされるのが一般的であった。
(※)
大グレゴリウスの「対話」2巻で語られているヌルシアのベネディクトゥス(480頃―547/60頃)は戒律の中で「聖なる読書に喜んで耳を傾けること。」(『中世思想原典集成5 後期ラテン教父』戒律 第4章(55) p257:平凡社)と言っている。今の時代に「読書に耳を傾ける」と言われることは、あまりない。つまり、これは古代においては音読が主流だったことを我々に知らせている。
[本文に戻る]
ヨハネは、どのような人たちが、黙示録を朗読し、聞き、心に留めるようにと願っていたのか。それは、ヨハネの時代の聖徒たちである。もう少し具体的に言えば『アジヤにある7つの教会』(黙示録1章4節)にいた聖徒たちである。もちろん、そのようにすべきなのは、アジヤにいるのではない聖徒たちも同様であった。何故なら、キリストが『耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。』(黙示録2章7節)と言われたからである。つまり、黙示録は直接的な宛て先としてはアジヤの教会なのであるが、それはアジヤの教会以外の『諸教会』も心を傾けるべきものであったのである。また、紀元1世紀以降に生きる聖徒たちも、黙示録を朗読し、聞き、心に留めるべきであるということは確かである。この文書は直接的には紀元1世紀以降の聖徒に宛てられたのではないにしても、またそこに書かれていることは既に実現済みのことであるにしても、それは全ての時代の聖徒に与えられているからである。
ここでは命令形として記述されているのではない。しかし、これが事実上、命令であったのは間違いない。何故なら、黙示録を朗読したり、聞いたり、心に留めたりするというのは、すべての聖徒に対する神の御心だからである。聖徒に対する神の御心は、そこに命令としての言葉がなかったとしても、それを命令として受け取るべきである。神が、聖徒たちに、そのようにするのを望んでおられるからである。例えば、キリストは『あわれみ深い者は幸いです。』(マタイ5章7節)と言っておられるが、ここに命令はない。しかし、そこに命令がないにしても、これを「あわれみ深くせよ」という命令として我々は受け取るべきである。何故なら、キリストがあわれみ深くあることを聖徒に望んでおられるのは、明らかだからである。だからこそ、キリストはこのように言われたのである。神の御心がそこに示されていれば、それは我々にとって命令となる。というのも、聖徒とは、神の御心を行なうことを義務とする存在だからである。だから、このようにヨハネが書いているのを読んだ当時の聖徒たちは、そこに命令としての言葉がなかったとしても、黙示録を朗読して、聞いて、心に留めなければいけなかった。これは確かなことである。実際、彼らはそのようにしたことであろう。誰がこれを疑うであろうか。
ここでヨハネが書いている通りにした人たちは幸いであった。何故なら『時か近づいている』からである。もし黙示録に心を傾けるのであれば、その聖徒は、やがて訪れる苦難の時に向けて色々と精神的な準備をしたり、未来のことをいち早く知ることができたり、またそのようにすることで神に感謝したりできる。だからこそ、時が近づいている出来事について口にしたり聞いたり心に留めることは、幸いなのである。これは神やヨハネにとって幸いであるというよりは、手紙の読者である聖徒たちにとって幸いだと言えることであった。しかし、そのようにしない人たちは不幸であった。何故なら、その人たちは黙示録に心を傾けないことにより、準備をしたり、未来のことを知ったり、神に感謝したりすることができないからである。そのような人たちは、今の時代で言えば、やがてニューヨークの同時多発テロが起こると前々から聞かされていたにもかかわらず(※)、それを心に留めなかったマンハッタン住まいの人に似ている。その人たちは、事前に予告されていた出来事に心を留めなかったので、警戒や退避の準備をすることもできず、あの大事件に巻き込まれてしまうのである。その時、彼らは「あっ、あの予告は本当だったのか。しくじった。」などと思わされることになる。それと同じように黙示録を心に留めなかった人たちも、自分たちが心に留めなかった出来事が本当にすぐに訪れたので、準備もできずただ驚くばかりで不幸だったのである。
(※)
言うまでもなく2001年9月11日に起きた歴史的な事件のことである。
[本文に戻る]
『この預言のことば』というのは、黙示録の全ての箇所を言ったものではない。これは、黙示録を大まかに言った言葉である。言うまでもなく、黙示録の中には、預言ではない箇所も多くある。例えば1:9でヨハネがパトモス島にいたというのは、預言ではない。4:1でラッパのような声がヨハネに『ここに上れ。』と言っているのも、預言ではない。12:5に書かれているキリストの携挙は、預言であるどころか、過去のことである。22:8でヨハネが御使いの足もとにひれ伏して拝もうとしているシーンも、預言ではなかった。しかし、それ以外の箇所は、どれもみな預言である。すなわち、ヨハネが黙示録を書いている時に、まだそのことは起きていなかった。だが、我々からすれば、その預言は既に成就されているということを、我々は知るべきである。―すべてが例外なくそうなのか?―そうである。例外はない。
【1:4】
『ヨハネから、アジヤにある七つの教会へ。』
『アジヤ』とは、今のトルコの地域である。パウロが手紙を送ったガラテヤやエペソやコロサイも、この地域であった。ここも他の多くの地域と同じように、ローマの属領であった。この地域では、偶像崇拝が蔓延していた。エペソには有名なアルテミス神殿があったし、ガラテヤ人たちもキリスト者になる前は偶像崇拝者であったとパウロは言っている(ガラテヤ4:8)。とはいっても、古代においては他の地域でも偶像崇拝が蔓延していたから、この地域だけが何か特別であったというのではない。この7つの教会とは、1:11によれば『エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィヤ、ラオデキヤ』である。エペソはトルコの最西端にあり、エーゲ海に面している。このエペソは戦略的に恵まれた都市であった。ポリュビオスは言っている。「というのもエペソスは、海路にせよ陸路にせよ、イオニア地方やヘレスポントス沿岸の諸都市に攻め寄せるとき、そのための城砦のような位置にあるばかりか、アジアを治める王がヨーロッパからの攻勢を阻もうとするときには、いつでもそのための絶好の防衛拠点になると期待できた」(『歴史3』第18巻:41a、2 p474:京都大学学術出版会 西洋古典叢書 2011第4回配本)。スミルナはエペソから北に100km以内の場所にある。このスミルナは、教父のエイレナイオス(130頃―200頃)の出身地だとされている。ペルガモはスミルナから北に100kmほど行った場所にある。テアテラはペルガモから東に100kmほどの所に位置する。サルデスはテアテラから南に50kmほどの所にある。このサルデスは、かつて硬貨を世界で最初に導入したことで知られるリュディア王国(前547年滅亡)の王都であった。フィラデルフィヤはサルデスから東に50kmほど離れている。ラオデキヤはフェラデルフィヤから南東に100kmほどの場所である。地図を見ると分かるが、これらの地域は、どれも小アジヤの西側に集中している(※)。ヨハネは小アジヤの中部と東部にある町の名前は何も出していない。
(※)
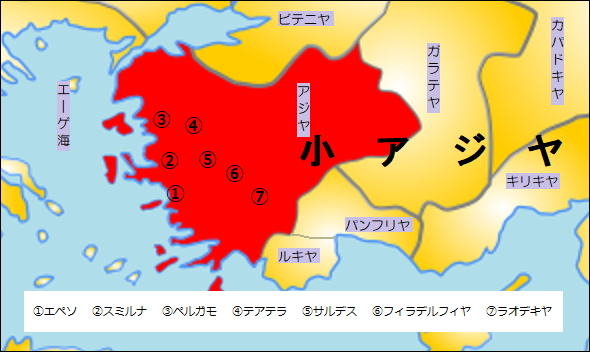
この7つの教会のある位置は、非常に整っており、何かの意図を感じさせられる。エペソとスミルナの教会が左に整列しており、それ以外の5つの教会が右に整列している。これはギリシャ語のΛを少し左に傾けたかのような並びである。地図を確認できる人は確認してみてほしい。神は、この7つの教会の位置において、何らかの意志を隠しておられるのだろうか。その可能性は十分にあり得る。私にはこの並びが、あたかも「ローマの街を見よ(エペソおよびスミルナを辿る線がローマを指し示している)。このローマが南東に下ってエルサレムを攻撃するのだ(5つの教会の位置は明らかに南東を示す線である)。」と言っているように見える。確かに、7つの教会をその語られる順に辿っていくならば、その地理的な線が、そのように言っていると解することは不可能ではない。我々は、聖書の言葉が徹底的に霊感されているということを忘れるべきではない。
[本文に戻る]
ヨハネはどうして7つの教会を挙げているのか。まず「7」という数字は、聖書では完全であったり聖であったりすることを意味している(※①)。カルヴァンも「聖書ではこれは完全数である」(『キリスト教綱要 改訳版 第1篇・第2篇』第2篇 第8章 30 p433:新教出版社)と正しいことを言っている。また彼は「聖書において、7という数は無限を意味します。また周知の如く、7という数は巨大な数として理解できます。」(『アモス書講義』第1章 p24:新教出版社)とも言っている。神は、創造の業を7日目に休まれ、その日を聖とされた(※②)。詩篇12:6では『主のみことばは混じりけのないことば。土の炉で七回もためされて、純化された銀。』と書いてある。ここでは「7回」と言うことで、その「炉による試し」が完全であることを示している。詩篇79:12でも『主よ。あなたをそしった、そのそしりの七倍を、私たちの隣人らの胸に返してください。』と書かれている。ここでは「七倍」と言うことで、完全だと感じられるほどの倍化が望まれている。アウグスティヌスも、7という数字が完全を象徴する数字だと述べている。彼はこう言っている。「と申しますのは、この数によって大いにしばしば完全が象徴されているからであります。例えば詩篇に「日に7たび、わたしはあなたを讃美します」(詩119・164)とはどうしてでありましょうか。かくもしばしば主を讃える人が誤ちを犯すことがどうしてあるでありましょうか。でありますから、「7たび讃美ます」とは、「讃美することを決して止めない」ということ以外の何でしょうか。「7たび」と詩篇の記者が言うとき、彼は「あらゆるすべての時」という意味を指しているのです。世界は7日の循環的な運行によって回転しているからであります。ですから、「日に7たび、わたしはあなたを讃美します」とは、「わたしの口で常に主を讃美します」と他のところで言われている(詩34・3)以外のことではないのであります。」(『アウグスティヌス著作集22 共観福音書説教(2)』説教95 p209~210:教文館)ヨハネはここで7という完全な数の教会を挙げることで、地上の諸教会が完全であり聖なる存在であるということを言いたいのだと思われる。アウグスティヌスも「こうした完全数を考慮してヨハネは7つの教会に手紙を書いているのであります。」(前同 p210)と述べている。先に述べたように、この文書は直接的な宛て先としては7つの教会が挙げられているが、それはその7つの教会以外の『諸教会』(黙示録2章29節)にも語られているものなのである。要するに神は、この7つの教会を、言わば抽出したのである。すなわち、そのようにして抽出して7つの名前を出すことで、全ての教会が表示されるようにしたということである。簡単に言えば、これらは全ての教会を表わすために代表として選ばれたに過ぎないということである。神が、あまり有名ではない教会を抽出されたのは、他の教会にいる聖徒たちが距離感を感じないためだったと私は推測する。神は、これらの7つの教会に対して色々と言われているのを他の教会にいた聖徒が知ることにより、その聖徒が教えられたり幸いな益を受けることを欲された。もし大きくて有名な教会―例えばローマ教会やエルサレム教会―ばかりが抽出されていたとすれば、その大きさと特別性のゆえに、自分たちとは関係がないと思いかねない。しかし、それほど有名でもなければ、それだけ関わりがあると感じられることになりやすい。往々にして人は、自分と同じような存在であればあるほど、問題意識や親近感を持ちやすくなるものである。当時の教会は、―いつの時代もそうであるが―、大きくて有名な教会ばかりではなかった。だからこそ、あえて有名であったり特別であったりするのではない7つの教会が選ばれたのではないかと考えられる。
(※①)
この7という数字は、ユダヤ教・キリスト教だけでなく、古代から今に至るまで、多くの民族において良い意味を示す数字とされてきた。例えば、古代ギリシャの哲学者であるソロンは、70年の人生を、「7」年という周期で10に区切って考察している。恐らくノアの洪水後からあまり経たないうちに記されたであろうギルガメシュ叙事詩の中でも、不思議なぐらいに多く「7」という数字が何らかの期間や回数を示すために使われている。アウルス・ゲッリウスもその著書の中で「10、自然界の多くの事象に、7という数のもつ、ある種の力と効能が認められ、その力について、マルクス・ウァッローが、『7という数』で、詳細に論じていること」という項目を書いている。ローマ人の中で最高の学識を持っていたあのウァロさえも<7>に着目していたという事実は非常に興味深いので、迷信めいた記述も幾らか見られるが、少し長いものの引用したい。ゲッリウスはこう書いている。「マルクス・ウァッローは、『7という数』、別名『肖像について』と題された書の中で、ギリシア人がヘプドマスと呼ぶ、7という数のもつ多様な力と効力を語っている。彼は言う、「事実、7という数は、天空で、大熊、小熊の2つの星座を形成し、同様に、ギリシア人がプレイアデスと呼ぶ『昴』や、さらに他の人たちは『迷い星』と呼び、プブリウス・ニギディウスは『放浪者』と呼ぶ惑星を形作っている」。また、天空には、天軸の縦線の周囲に7の円があり、その内の最も小さい円は、天軸の両端に触れているもので、ポロイと呼ばれるが、これは、径が小さいために、クリコーテーと呼ばれる天球の中には含まれないという。また、十二宮そのものも、7という数と無関係ではない。なぜなら、夏至は冬至から数えて7番目の宮で起こり、冬至は夏至から数えて7番目の宮で、春分は秋分から、秋分は春分から数えて7番目の宮で起こるからである。加えて、翡翠が、冬、海上に巣を作る例の日数もまた7日間である、とウァッローは言う。さらに、その記すところでは、月の周回軌道は7という数の丸々4倍の日数で辿り終えられるとされる。「というのも」とウァッローは言う、「月は28日目に出発点に戻るからである」。ウァッローはそう言い、この見解の権威として、サモスのアリステイデスを挙げている。この点に関して、ウァッローは、単に、月が7の4倍、すなわち28の日数で道程を辿り終えるという事実のみならず、7という数が、1から初めて7まで進むあいだに通過するすべての数と、7そのものをも積算すれば、28となる数であり、その数が月の周期に一致するという事実にも留意しなければならない、と言う。また、7という数の力は人間の誕生にも関係し、影響を及ぼすとされる。「なぜなら、生命の種が女性の宮に宿されると、最初の7日間で凝縮、凝固して、姿形を形成するのに適したものとなるからである。そのあと、続いて、4週目に、男性性器となるものと頭と背中にある背骨とが形成される。一方、子宮で人の全体が完成するのは、およそ7週目、つまり49日目である」。ウァッローはまた、この数のもつ次のような力にも言及している。すなわち、男子でも女子でも、7か月未満の胎児は、健全で、自然的に生まれることはなく、最も正常な胎内期間を経過する胎児は、胚胎後、273日を経過して、言い換えれば、40週に入った時に生まれるという。さらに、カルダイオイ人が「厄年」と呼ぶ、あらゆる人の生や運の危機も、最も重大なものは、7の倍数の節目に生じるとされる。そのほかにも、人の身長の成長の限度は7ペースであると、ウァッローは言う。思うに、この見解のほうが、ホメロスがそう考えたように、往古の人間の身体は今よりは大きくて高く、現在は、言わば世界が老化したために、物や人間も縮小した、というのではないかぎり、土に埋もれて発見されたオレステスの身長が7クビトゥム、ペースで換算すれば、12と四分の1ペースであったと述べる、四方山話の語り手ヘロドトスの『歴史』第1巻の記述よりも真実であろう。歯もまた、最初の7か月で上下に7本ずつ生え、7年目に抜け落ちて、ほぼ7の2倍の年数で奥歯が付け加わるという。また、ウァッローは言う、音楽療法を施す医者たちの言では、人の血管、というより、むしろ動脈も、7という数に関係して脈動し、この療法を、医者たち自身は、重なる4つの音によってなされる「4つの協和音を通じての療法」と呼んでいる、と。さらに、ウァッローの考えでは、病の危機は、病勢が嵩じる7の倍数日に訪れ、特に、どの日よりも、第一、第二、第三の倍数日が、医者の呼称で言えば、「危機日」のように思われる、という。また、彼は、7という数の力と効能をさらに証する事実として、食を断って自殺しようと考える人が7日目にしてようやく死を迎えるという事実も取り上げている。以上が、いかにも博捜ぶりを発揮した、ウァッローの記述である。しかし、そこには、このほかに、いささか他愛ない事例も列挙されている。世界には7つの不思議があるとか、往古の賢人は7人であったとか、円形競技場での通常の周回は7周であるとか、テバイ攻めに選ばれた将は7名であったとかいった事例である。ウァッローはまた、自分の年齢が7を11度重ねて12度目に入ったばかりで、その日までに物した書の巻数が7の70倍にのぼるが、これらの書は、かなりの数のものが、彼が市民権剥奪、財産没収の宣告を受けた時に、私設の文庫が略奪されて、失せてしまった、とも書き添えている。」(『アッティカの夜1』第3巻 10 p206~209/京都大学学術出版会 西洋古典叢書 2015第6回配本)21世紀の現在においても、例えばスロットで大当たりとされているのは「777」である。この7という数字に完全性また神聖性が感じられるようになっているのは、神がこの世界に組み入れられた概念的な基本原理なのであろう。実際、神が考え出された虹やプリズムは「7」色に分類される。これは、神がこの世界に「7」を特別な概念として組み入れておられるというよい証拠であると思われる。もちろん、虹やプリズムを7色に分類しない国や人も多く存在するから、これを事柄の論拠とするには非常に弱弱しいということを言っておかねばならないのではあるが(少なくともニュートンや我が日本においては7色として分類している)。
[本文に戻る]
(※②)
『それで神は、第七日目に、なさっていたわざの完成を告げられた。すなわち、第七日目に、なさっていたすべてのわざを休まれた。神はその第七日目を祝福し、この日を聖であるとされた。』(創世記2章2~3節)
[本文に戻る]
ヨハネがこの7つの教会に送った文書は、もちろんギリシャ語で書かれていた。紀元1世紀において、このギリシャ語は、世界共通語(コイネー)であった。2019年の今で言えば英語がそれにあたる。だから、この7つの教会にいた聖徒たちは、ヨハネがギリシャ語で書いた文書を、文盲の人は別として、よく理解して読むことができたであろう。そうして後、他の教会に回し読みされたり、写本が作られたりしたはずである。これは今で言えば、日本の天皇が英語でアメリカ大統領に手紙を書き、それを大統領が読み、読んだ後で公開されたりコピーがとられたり重要な文書として大切に保管されたりするようなものである。当然ながら、他の聖書の巻と同じように、ヨハネが書いた黙示録の原書は既に失われてしまっている。いつ失われたのかということは、まったく分からない。今、残っているのは、黙示録を書き写した無数の写本だけである。我々は、その無数の写本から校訂された校訂文が訳された黙示録を読んでいる。ここで原書が失われたということを聞いて、我々は何か不安になったりすべきではない(これは初信であったり霊的に弱い聖徒が陥りやすいことである)。というのも、神は写本の中において、ご自身の言葉を十全に保っておられるからである。神がご自身の発された御言葉を、人間のミスや愚かさによって失わせることを許可されるはずがどうしてあろうか。イザヤも言っているように『神のことばは永遠に立つ。』(イザヤ40章8節)のである。永遠に立つべき御言葉が少しでも失われるということは、つまり御言葉が倒れるということだから、それは絶対にありえない。よって、読者は、黙示録の原書が既に存在していなかったとしても安心すべきである。これは黙示録以外の聖書の巻でも同じことが言える。
ヨハネは、一つだけの文書をある教会に送り、その一つの文書が他の教会に回されたり多くの写本として流布することになったのか。それとも、最初に同じ内容が書かれた7つの文書を7つの教会に送ったのか。これは我々には不明である。教父たちの書いたものを読んでも、確かなことは分からない。それでは、この文書は、どのようにして7つの教会に送り届けられたのか。これも定かなことは何も言えない。ヨハネが実際に自分で届けたのかもしれない。またはヨハネが弟子や知り合いに届けさせたのかもしれない。それ以外の不思議な方法、例えば神の流された風に乗せられて届けられたり、鳥に運ばせたりした、という可能性もある。このようなことは、我々が天国に行った際に、ヨハネに聞く以外にはない。しかし、たとえこのようなことを知らなかったとしても、我々の信仰や黙示録の理解には、特に問題は生じない。この点については、我々は安心すべきである。
【1:4~5】
『常にいまし、昔いまし、後に来られる方から、』
『常にいまし』とは、キリストが、いついかなる時も、存在しておられるという意味である。キリストは、時間という被造物のどこの位置においても、常に現在しておられる。このお方が、現在していない時間は少したりともない。『昔いまし』とは、キリストが過去のすべての時間帯の中に、存在しておられたということである。『後に来られる』とは、言うまでもなく再臨のことである。ヨハネがこの黙示録を書いているその時には、まだ再臨が起きていなかったから、このように書かれている。しかし、今や再臨は過去の出来事となっている。よって、聖徒たちは、ヨハネがここで『後に来られる』と言っているからといって、これから再臨が起こるのだと考えるべきではない。それは、キリストの受肉について預言されている箇所を見て、これからキリストが受肉されるのだと考えてしまう人と同じである。そのような人は、聖書をよく弁えていない。ここでは、キリストが時間的な要素と共に語られている。このように言われることで、キリストが実に生々しく感じられるという効果が生じている。ヨハネはここで、「キリストは真に生き、存在し、動かれるお方なのだぞ。」とでも言いたいかのようである。これは、キリストをただ信仰上の存在として概念的にしか捉えないという状態から、聖徒を遠ざけるためには実に有効的な言葉である。何故なら、この言い方は実に動的で生き生きとしているからである。
『また、その御座の前におられる七つの御霊から、』
ヨハネは、神の御前には7つの御霊がおられると言っている。ここで我々は、御霊の数が7つしか存在しておられないなどとは、間違っても思うべきではない。神であるお方を、7つに制約するというのは、誤りである。というのは、御霊なる神は、無限なお方だからである。それはヨハネ3:34に、『神が御霊を無限に与えられる』と書いてあることからも分かる。『無限』という数は、明らかに「7」ではない。ここで御霊が『七つ』と言われているのは、御霊が完全なるお方だという意味に捉えるべきである。先にも述べたように「7」とは完全を示す数字である(※)。ヨハネは天に上げられた際(黙示録4:1)、神の御前に御霊がおられる場景をその目で見たのであろう。だからこそ、このように書いた。そうでなければ、このことをキリストから直接教えられたか、パウロや他の使徒から聞いたか、または天から啓示をダイレクトに受けたか、のどれかである。ヨハネが自分自身によって、このようなことを悟れたというのではない。何故なら、天のことについては神の啓示がない限り、人間にはまったく分からないからである。プラトンの例を見ても分かるように、啓示抜きで、つまり理性の考究のみで神や神に属する事柄を探ろうとしても、ただただ誤りに陥るばかりなのである。先にはキリストのことが語られたが、今度は御霊のことが語られている。ヨハネはここで、あたかも「キリストだけでなく御霊もあなたがたのことを思っておられるのだぞ。」と言いたいかのようである。このように御霊のことも語られることで、聖徒たちの霊に幸いな益が生じたのは確かである。というのは、御霊も聖徒たちに心を配って下さっておられることが、このように言われることで、分かるからである。このことは、この部分がもしなければどうだったのか、ということを考えればよく分かるのではないかと思う。
(※)
アウグスティヌスの場合、御霊が『7つ』であられるというのは、イザヤ11:2に書かれている7つの霊のことであると言っている。彼の使用していたウルガダ訳聖書とその底本であるビザンチン写本の場合、このイザヤ書の箇所で書かれているのは7つの霊だということである。そこでは、「知恵と悟りの霊、深慮と剛毅の霊、知識と敬虔の霊、主を恐れる霊」という7つの霊が書かれている。しかし私の使用している新改訳聖書とその底本であるアレクサンドリア写本の場合、そこに書かれているのは6つの霊である。すなわち、1.知恵の霊、2.悟りの霊、3.はかりごとの霊、4.能力の霊、5.主を知る知識の霊、6.主を恐れる霊、の6つである。アウグスティヌスの使っていた聖書と比べると、6番目の「敬虔の霊」が欠けている。カルヴァンもイザヤ11:2で書かれているのは6つの霊だと言っている(※A)。こちらのほうの場合、我々が今見ている黙示録の箇所を、イザヤ11:2の箇所を助けとして解釈することはできないことになる。というのは、黙示録のほうで「7」と言われているのに、イザヤ書のほうでは「6」と言われており、数が異なっているからである。いずれにせよ、これは底本と翻訳に全てがかかっている。ヨハネが黙示録で「7つ」と書いているのは何も問題がない。問題となるのは、イザヤ本人が6つの霊について書いたのか、それとも7つの霊について書いたのか、ということである。もしイザヤが6つの霊を書いたのであれば、我々が今見ている黙示録の箇所の助けとすることはできないが、もし7つの霊を書いたとすれば、それは大いに考察すべきことである。―この註は、今の状態では満足できない内容である。読者の方も、これでは不十分だと感じるであろう。また後ほど、この註を、満足できるようなものに書き換えたいと思っている。
(※A)
「…イザヤ書で読まれるのは6つより多くないのに(イザヤ11:2)、しかも預言者はここで賜物の全てを総括しようとしたのでないのに、それを7つと読んだとみえて聖霊の賜物は7つであるとする。…ここでは「知恵、悟り、謀、力あること、主を知り、恐れる霊」と記されている。」(『キリスト教綱要 改訳版 第4篇』第4篇 第19章 第22節 p516:新教出版社)
[本文に戻る]
『また、忠実な証人、死者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから、』
『忠実な証人』とは、キリストが、神の真理を偽りなく語られる方だという意味である。主は、この地上におられた時、真理をまったく正しく語られた。ペテロがキリストについて、『その口に何の偽りも見いだされませんでした。』(Ⅰペテロ2章22節)と言っている通りである。だから、この黙示録でヨハネが証しているキリストの証にも、当然ながら嘘や偽りはまったくない。『偽証してはならない。』(申命記5章20節)と言われた当のお方が、どうして偽証されることがあろうか。それはあり得ない話である。『死者の中から最初によみがえられた方』というのは、つまりキリストが御霊の身体により復活した最初の人間だという意味である。すなわち、これはキリストが十字架につけられてから3日目に蘇えったあの復活のことを指している。キリスト以前に、このような形での復活にあずかった人間は、一人もいなかった。一応は復活したが御霊の身体による復活ではなかったので、やがて身体が朽ちて死ぬことにならねばならないという形での復活であれば、キリスト以前にもいくらか起こった。例えば、エリヤと一緒にいたやもめの息子がそうである(Ⅰ列王記17:22)。キリストによみがえらされたラザロも、このような形での復活であった。ここでヨハネが言っているのは、このような形での復活のことではない。『地上の王たちの支配者であるイエス・キリスト』とは、どういう意味であろうか。ここに書いてある『地上の王たち』という言葉は、少し考える必要がある。この王とは、アレンクサンドロスやネロといった社会的な意味における王のことであろうか。それとも、聖徒のことであろうか。ペテロによれば、聖徒もキリストにあって『王』(Ⅰペテロ2章9節)である。社会的な王か、聖徒という王か、正だしい解釈は一つである。この解釈に悩む人は多いと思うが、ここで言われているのは、実際的な意味における王のことである。つまり聖徒のことではない。何故なら、キリストが王を支配する支配者であると聖書で言われている場合、その王とは、どこの箇所でも実際的な王を指しているからである。例えば、黙示録17:14では『子羊は主の主、王の王』と言われている。これは簡単に言えばキリストが世の支配者の支配者だということである。それは、『主の主』と言われているからである。この『主』とは、間違いなくこの世的な意味における支配者また権威者のことである。この『主』というのが、聖徒のことではないのは明らかである。そのようなこの世の支配者を示す言葉が使われている文と並べて『王の王』と言われているのだから、やはり、ここで言われているのは社会的な意味における王だということになる。我々が今見ている箇所で言われている『地上の王』というのも、そのような意味である。聖徒たちを「王」と呼び、その上で、その王である聖徒たちをキリストが支配しておられるという意味で『王の王』とキリストについて言われている箇所は、聖書にはない。確かにそのような意味でキリストについて『王の王』、つまり聖徒たちという王の王であるキリスト、と言うこともできるが、聖書はそのような言い方を用いていない。キリストが王として聖徒たちを支配していると言う場合、聖書は、例えば『大牧者』(Ⅰペテロ5章4節)とか『監督者』(同2章25節)などと言うのが常である。確かにヨハネも言うように、キリストは地上の王たちを支配しておられるお方である。キリストは支配を支配しておられる究極の支配者であられる。それはペテロがその手紙の3:22の箇所で、キリストは『もろもろの権威と権力を従えて』いる、と言っている通りである。またこのことは、キリスト御自身が『わたしには天においても、地においても、いっさいの権威が与えられています。』(マタイ28章18節)と言っておられることからも分かる。キリストは王の王権さえも支配しておられるから、王を新しくするのも、王権を取り上げるのも、御心のままに行なえる。キリストが望まれればある者が王となり、キリストが望まれなければ今どこかにいる王は王位から遠ざけられるのである。それはダニエルが主について、『神は…王を廃し、王を立て』(ダニエル2章21節)と言っている通りである。このように言うのは、非常に力強いことであり、聖徒たちが強められることである。何故なら、ここではキリストが地上の王たちをさえ支配しておられると言われているからである。そのような王の王であられる方が、聖徒たちの主なのである。であれば、このようなことを聞かされて、霊に良い作用を受けないような聖徒が誰かいるであろうか。一人もいないに違いないと私は思う。さて、この部分では、キリストがその特異性において語られている。このような素晴らしく注目に値する特異性をお持ちの方から云々…などと言われたら、やはり聖徒たちにとって励ましとなるのは確かである。ヨハネはこれからすぐにも訪れる苦難に際して聖徒たちに準備をさせるべくこの手紙を書いたのだから、このような励ましとなるような言い方がされているのである。ただ「キリストから云々」とだけ短く言われたよりは、このように特異性を前面に押し出した豊かな言い方がされたほうが励みや力になるのは、言うまでもない。これは、あたかもまだ未熟さの残る研究中の若手科学者たちの元に、ニュートンとマッハとアインシュタインが訪ねてくるようなものである。このような大物たちが励ましにやって来るのと同じような効果を持つことを、ヨハネはここで書いている。
『恵みと平安が、あなたがたにあるように。』
手紙の最初の箇所で、このように書くのは、パウロがよく行なうやり方であった。パウロも、例えばローマ1:7やⅠコリント1:3やピリピ1:2などで、このように書いている。最初にこのように平安などを祈るのは、キリストも弟子たちが伝道をする際に命じておられたことである(※)。スタート地点から平安を。最初の時点でこのように祈るのは、誠に良い挨拶である。パウロの言い方と違うのは、パウロが多くの場合に神とキリストから恵みと平安を願っているのに対し、ヨハネはキリストと御霊からそのように願っているということである。パウロは『父なる神から』また『キリストから』とは言っても、『御霊から』とは言わなかった。他方、ヨハネは『父なる神から』とは言っていない。すなわちパウロは第三位格を語らず、ヨハネは第一位格を語らない。そこで挙げられている位格が何であれ、これはつまり纏めて言えば「神から」ということである。何故なら、パウロのように父と子だけを挙げようが、ヨハネのように子と聖霊だけを挙げようが、『主はただひとり』(申命記6章4節)だからである。ヨハネはここで、まずキリストを、次に御霊を、最後にはまたキリストを、という言い方をしているが、これは実に豊かな言い方である。ヨハネには、黙示録で、これからやがて訪れる苦難の時を伝えるという目的があった。その苦難とは、実に悲惨であり、忍耐を必要とするものであった。だからこそ、ヨハネはこのように豊かな言い方をすることで、聖徒たちの霊に幸いがもたらされるようにしたのである。このように言われた聖徒たちが、この豊かな言い方を通して、大きな励ましや力を受けたことは確かである。
(※)
『その家にはいるときは、平安を祈るあいさつをしなさい。』(マタイ10章12節)
[本文に戻る]
『恵み』とは、霊的・精神的・物質的を問わず、諸々の幸いのことである。神から恵みが与えれたら、その人には、色々な幸いがもたらされる。『平安』とは、要するに心の安らかさのことを指す。聖書で、平安があるようにと言われている箇所は、実に多い。ヘブル人は、昔から相手に平安があるようにと祈るのを常としている(※)。今でも「シャローム」などと言って、相手が安らかであるのを願ったりするものである。このように「平安」という言葉が聖書の多くの箇所で言われているのは、これが、どれだけ聖徒に、またあらゆる人々にとって大切であるかということを示している。というのも、もし心に平安がなければ、すべてが悪く思えるようになり、絶望の淵に立たされて目茶目茶な精神状態になりかねないからである。ヨハネは、このような2つの大事なものが、キリストと御霊から聖徒たちに与えられるようにと、ここで願っている。それは、もちろん御霊の愛から出た聖なる願いであった。
(※)
バビロニア・タルムードの中でも、安息年に異邦人がしている農作業の手助けをする際には「彼らに対して平和のために挨拶する。」(シュヴィイート篇:第5章、ミシュナ9)と言われている。
[本文に戻る]
『イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、』
これまでは、神がどのようなお方であるかという視点から、ヨハネは語っていた。今度は、ヨハネは神が聖徒たちにどのようなことをして下さったのかという視点から、語っている。この1:4~6の箇所を、じっくりと読んでみるとよい。そうすれば、明らかに2つの視点から語られていることが分かるはずである。
『人知をはるかに超えたキリストの愛』(エペソ3章19節)により、聖徒たちは血による清めを受け、罪から解放されて自由の民とされるに至った。それは、キリストが『自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われ』(Ⅰペテロ2章24節)たからである。このキリストの愛と救いがなければ、聖徒とされた者たちが新しい人生のうちに歩むことはなかった。救われた者たちは、このことを、再び強く心に留めるべきであろう。
【1:6】
『また、私たちを王とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。』
ここにある『王』という言葉は『王国』とも訳せる。キリストは、聖徒たちを王または王国として下さった。聖徒はすなわち王であるから、霊的に言って、神以外のどのような存在からも支配されない。ルターも『キリスト者の自由』という作品の中で、「キリスト者は王であって誰からも支配されない」と書いている。これは今までに殉教した殉教者たちのことを考えれば分かる。彼らは、死に至るまでも、神以外の存在に屈服させられることがなかった。彼らを屈服させようとした者たちは、結局そのようにできず、打ち勝てないまま敗北するに至ったのである。その際には、敵対していた多くの者たちが、キリスト者に対して驚いたり、自分たちのほうこそが参ってしまったほどである。つまり、キリスト者である彼らが王であったからこそ、屈服させることができなかったのである。しかし、キリスト者が王とされたからといって、実際に社会的な意味において王となったのではない。実際的な意味においては、キリスト者は、一般の状態や地位にあるままである。もちろん、そのキリスト者がキリスト者になったことにより、王となることがあれば、話はその限りではないが。またキリスト者は王でありながら、この世の制度や為政者に従う。何故なら、神がそうするように命じておられるからである。ペテロはこう言っている。『人の立てたすべての制度に、主のゆえに従いなさい。』(Ⅰペテロ2章13節)パウロもこう言う。『人はみな、上に立つ権威に従うべきです。』(ローマ13章1節)しかし、この世の制度や為政者に従うとはいっても、もしそのようにすることが神に反逆したり罪を犯したりすることになる場合は、従わない。それは、そのようにすることは神の喜ばれないことだからである。だから、その場合は『人に従うより、神に従うべきです。』(使徒行伝5章29節)ということになる。このように言った当の使徒たちも、議会の決定によりもう宣教してはならないと言い渡されたにもかかわらず、それに従わないで宣教をし続けた(使徒行伝5:40~42)。またキリスト者たちは王であるだけでなく、『王国』とされた存在でもある。すなわち、キリストの救いにより、神は聖徒たちをご自身の住まわれる王国とされた。キリストが『神の国は、あなたがたのただ中にある』(ルカ17章21節)と言われたのは、このような意味においてであった。キリスト者は神の王国とされたのだから、神の支配に従い、神の御心に適ったことを行なう。そこにおいて、神の支配する国が聖徒たちの中にまざまざと現われる。神は、そのようにして聖徒たちを、ご自身の王国として統治されるのである。それゆえ、聖徒という存在は、永遠に神ご自身の相続地また割り当ての領域である。それはレビ族が、神ご自身の割り当ての地だったのと同じである。また聖徒たちは『祭司』にもされた。この箇所は、プロテスタントの「万人祭司説」を証明する箇所である。かつて、聖徒は、レビ人である祭司たちに神への執り成しを頼むしかなかった。しかし今や、キリストを信じる全ての者が、そのような祭司とされている。だから、今の時代にあっては、祭司に執り成しを頼む必要がなく、ただ自分だけで神に祈ればそれで済むようになった。もちろん、牧師に執り成しの祈りを頼む人もいるが、基本的には、祭司である自分だけが神に祈りを捧げれば、それだけで事は済まされる。また、これは「賛美と感謝を捧げる祭司、要するに自己と自己に属するものを捧ぐべき祭司」(『キリスト教綱要 改訳版 第4篇』第4篇 第19章 第28節 p523:新教出版社)という意味でもある。キリストが血を流されたのは、このように聖徒たちを神のために祭司とするためでもあった。我々が今見ているこの部分は、出エジプト記19:6に書いてある『あなたがたはわたしにとって祭司の王国、聖なる国民となる。』という御言葉を思わせる。この出エジプト記の御言葉は旧約時代のユダヤ人に対して言われた。その時代には、祭司の王国とは、すなわちユダヤ人だけであった。だが、今やキリストの贖いを受けた全ての聖徒たちが、祭司の王国とされる時代である。もはやかつての祭司の王国であったユダヤ人は、キリストを信じるのでない限り、祭司の王国ではなくなっている。ヨハネは、ここで、このようなことを言いたいのである。
ここでヨハネは、あかたも「このような素晴らしい幸いをお与え下さったイエス・キリストから恵みと平安があるようにと私は、あなたがたに願っているのだ。」とでも言いたいかのようである。確かにこのように素晴らしい幸いを与えて下さったキリストから云々…などと言われたら、聖徒たちもそのように言われたことに呼応して、「そのようなお方であるキリストから恵みと平安があるようにと願ってくれるとは…」などという感謝と畏敬の混じった精神状態にされることにもなる。そうなれば、やはり霊も強められることになる。先にも述べたことだが、ヨハネがそのようにして聖徒たちに霊的な幸いを与えようとして、このように書いたのは確かである。
『キリストに栄光と力とが、とこしえにあるように。』
聖徒たちは、そのうちに住まわれる御霊によって、キリストの幸いと利益とを願う。それは、聖徒たちが、万物はキリストのためにこそ存在しており、全てはキリストを目的としていることを知っているからである。聖徒たちが聖徒とされたのも、当然ながらキリストのためであった。それはパウロがⅡコリント5:15でこう書いている通りである。『キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々が、もはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。』キリストのために贖われた聖徒は、キリストのために存在しているのだから、キリストの幸いと利益を願うのである。ヨハネがここで言っているのも、そういうことである。ところで、ヨハネがキリストに栄光と力が永遠にあるようにと願ったのは、なぜなのであろうか。たといヨハネがこう願わなくても、キリストに栄光と力がとこしえにあるのは言うまでもない。聖徒が願わなければキリストに栄光と力が永遠にないというのであれば、それはキリストに相応しくないことである。何故なら、そのような栄光と力は、聖徒が願っているということにかかっており、また支えられていることになるからである。別に願わなくても実現され続けることをヨハネやその他の聖徒が口にして願うのは、我々が、キリストの益を願い求めるべき存在だということを知り、確認し、告白するためである。それは別に祈らなかったとしても与えられるのに、我々が日々『私たちの日ごとの糧をきょうもお与えください。』(マタイ6章11節)と祈るのと同じことである。我々は、このように願わなくても与えられるものについて祈ることで、神こそが我々に食物を与えて下さるお方であるということを知り、確認し、告白している。これは既にカルヴァンが『キリスト教綱要』の中で述べている。ヨハネが、ここでキリストの幸いを願っているのも、それと同じことである。ヨハネは、願わなくても実現され続けることを願うことで、無意味な愚行をしているというのではない。何にせよ、キリストは永遠に至るまでも、ご自身の栄光と力とを現わして下さる。たとい聖徒たちがそのように祈らなかったとしても、である。何故なら、そのようにすることこそ、この世界がキリストにあって造られ存在している目的の一つだからである。我々は、キリストが永遠に栄光と力とを現わされることを喜ぼう。それは、大変素晴らしいことであり、讃美されるべきことであるのだから。
『アーメン。』
これは、「しかり」とか「その通りです」などといった同意していることを示す言葉である。この短い言葉は、旧約聖書で多く使われており、本来はヘブル語であるが、ギリシャ語でもそのままの言い方で使われている。黙示録では、この箇所を含めると、全部で8回「アーメン」という言葉が使われている(1:6、1:7、3:14、5:14、7:12、19:4、22:20、22:21)。
【1:7】
『見よ、』
これは修辞的な短い掛け声である。この言葉で、ヨハネは「さあ、私に聞かされたこと、示されたことを、あなたがたも知り、心に留めよ。」と言いたいのである。この言葉は、黙示録の中では非常に多く使われている。
『彼が、雲に乗って来られる。』
再臨のキリストが雲に乗っておられるということには、2つの意味がある。すなわち、実際的な意味と、象徴的な意味の2つである。実際的というのは、文字通りキリストが雲を伴って天から来られるということである。それはキリストがご自身の再臨の際には『天の雲に乗って来る』(マタイ26章64節)と言われた通りである。山上の変貌が起きた際には、キリストの周りに雲がわき起こったが(ルカ9:34)、再臨の際にも、そのような実際の雲が現われたのである。象徴的というのは、雲がキリストの権威を示しているということである。聖書において、雲は権威を象徴している。神はモーセと会われる際に、濃い雲のうちに降りて来られたが(出エジプト記19章)、それは神が至高の権威者だからであった。キリストは神であられるから、ご自身の再臨の際には雲を伴わせることを欲され、そのように定められた。これは至高の権威者であられるキリストにとっては、実に相応しいことであった。このようにして主が来られるということは、旧約聖書の時代から預言されており、またキリスト御自身とヨハネ以外の使徒たちもあらかじめ預言していたことであった。
この再臨を、まだ起きていない出来事だと思ってはならない。というのも、ヨハネが黙示録の中で書いていることは『すぐに起こるはずの事』(1章1節)であって、ヨハネが黙示録を書いている時には『時が近づいてい』(1章3節)たからである。既に何度も私は述べてきたが、再臨は紀元68年6月9日に起こっている。よって、ここでヨハネが書いているのは、既に我々にとっては実現済みのことだとせねばならない。
『すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが、彼を見る。地上の諸族はみな、彼のゆえに嘆く。しかり。アーメン。』
ここで『見る』とか『嘆く』などと言われているのは、ユダヤ人のことである。すなわち、『すべての目』というのも、『地上の諸族』というのも、ユダヤ人におけるそれである。これはユダヤ人という範囲内で言われていることであり、異邦人のことを言ったものではない。何故なら、ヨハネは明らかに、この部分をゼカリヤの預言に基づいて書いているからである。そのゼカリヤの預言の中で語られているのは、どう考えてもユダヤ人のことだけである。それゆえ、ゼカリヤの預言と対応しているこの黙示録の箇所も、ユダヤ人のことが言われているということになる。そのゼカリヤの預言は次のようなものである。『わたしは、ダビデの家とエルサレムの住民の上に、恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは、自分たちが突き刺した者、わたしを仰ぎ見、ひとり子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣く。その日、エルサレムでの嘆きは、メギドの平地のハダデ・リモンのための嘆きのように大きいであろう。この地はあの氏族もこの氏族もひとり嘆く。ダビデの家の氏族はひとり嘆き、その妻たちもひとり嘆く。ナタンの家の氏族はひとり嘆き、その妻たちもひとり嘆く。レビの家の氏族はひとり嘆き、その妻たちもひとり嘆く。シムイの氏族はひとり嘆き、その妻たちもひとり嘆く。残りのすべての氏族はあの氏族もこの氏族もひとり嘆き、その妻たちもひとり嘆く。』(ゼカリヤ12章10~14節)この預言を見れば、ヨハネの言っていることが、ユダヤという民族また地における『すべて』『諸族』だということが分かる。人間理性で判断する限り、この箇所は、文字通り地球全土に住む全ての人間や民族であると考えてしまう。しかし、聖書の預言を見ると、これはユダヤにおいて言われているということが分かる。聖書は人間理性によってではなく聖書によって解されねばならない。それゆえ、我々は、この箇所があらゆる人間や民族のことを言っていると考えてはならない。この箇所や、この箇所と対応しているゼカリヤ書の預言で『突き刺した者』と言われているのは、直接的・実際的に言えばあのロンギヌスという兵士のことである。福音書に書いてあるように、この兵士は、十字架につけられているキリストを自分の持っていた槍で突き刺した(ヨハネ19:34)。しかし、この2つの箇所では、この一人の兵士によりユダヤ人全体が表示されている。すなわち、ロンギヌス一人がキリストを槍で突き刺したのは、つまりユダヤ人全体がキリストを槍で突き刺したことなのである。それゆえ、この『突き刺した者』とは、ロンギヌスでありユダヤ人全体のことでもある。このように言われるのは何もおかしいことではない。我々もこのような言い方をする時が往々にしてある。例えば、A国のある一人の人物がB国の皇帝を刺し殺したので、B国の人たちやその他の国の人たちが「A国民族は邪悪な輩だ。」などと非難するのが、それである。この例では実際には一人が皇帝を刺し殺したに過ぎないのに、その殺人者の属する国民全体が邪悪視されてしまっているが、これは慣用的には何も変ではない。ここでロンギヌス一人の行為がユダヤ人全員の行為に帰されているのも、それと同じように何も変ではないのである。ここで書かれている通り、紀元1世紀に再臨が起きた時には、全てのユダヤ人に大きな嘆きが起きたはずである。それは、彼らが再臨されたキリストを見て、キリストの預言に関する真理を全て悟っただろうからである。「ああ、遂に預言されていたあのことが起きてしまったのだ。」と。キリストも再臨の際には彼らが嘆くということについて、『すると、地上のあらゆる種族は、悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見るのです。』(マタイ24章30節)と言っておられた。しかし、彼らが真理を察して嘆いたとしても、もう時は遅かった。何故なら、彼らが再臨を見て嘆いたその日は、彼らに裁きが与えられる日だったからである。嘆いているその時には、もはや悔い改めている余裕はなかった。彼らは嘆きつつ、悔い改めることもできずに、永遠の断罪を受けるに至ったのである。あたかもエリヤに打ち負かされたバアルの預言者たちが、エリヤの神こそが真の神であるという真実をまざまざと見せ付けられたにもかかわらず、悔い改めることもできずに皆殺しにされたように(Ⅰ列王記19:40)。すなわち、彼らは嘆いた後ですぐに上に挙げられて空中の審判を受け、キリストから断罪されて火の池に投げ込まれることになったのである。
ヨハネは、同意を示す言葉を、ここで2回も続けて書いている。『しかり』とはすなわちアーメンと同じ意味だから、ここでヨハネはアーメン。アーメン。と言っているのも等しい。つまり、これは非常に強い同意を示す記述である。このことは、ヨハネがどれだけキリストの再臨に心を傾けていたかということを、またどれだけその出来事を待ち望んでいたかということを示している。
【1:8】
『神である主、常にいまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる。』
1:4~5と同じで、ここでもヨハネはキリストについて豊かな言い方をしている。このように豊かに言っているのは、ヨハネがそれだけ豊かにキリストのことを伝え、読者に強く感じさせたいからに他ならない。ここではキリストについて3つのことが言われている。まず『神である主』とは、すなわち主なるキリストが本来的・生来的な意味における神だということである。異端者らがかつて考えたように、キリストは、本来は神ではなく、ある時から神とされたというのではない。そのように考えるのは間違っている。キリストは永遠の昔から神であられた。ヨハネは、ここで「キリストは単なる人に過ぎない存在ではないのだぞ。彼は人であり神でもあられるのだ。」とでも言いたいかのようである。次に『常にいまし、昔いまし、後に来られる方』とは、先に1:4の箇所で見たのと同じである。最後の『万物の支配者』とは、文字通り、キリストがあらゆる被造物を支配しておられるということを言っている。ヘブル1:3でも言われているように、キリストは『その力あるみことばによって万物を保っておられ』、彼の支配を免れている被造物はただの一つもない。あらゆる被造物は、このお方に左右され、作用され、縛られている。ヨハネは少し前の1:5の箇所では『地上の王たちの支配者』とキリストについて書いたが、今度は『万物の支配者』と書いている。明らかに『地上の王たち』よりも『万物』のほうが、その規模と意味において大きな広がりを持っている。ヨハネは、キリストの支配しておられるのが地上の王たちだけではなく、キリストは万物さえも支配しておられるのだと悟らせようとして、このように言ったのだと思われる。何故なら、このようにキリストは万物をも支配しておられると言わなければ、キリストは地上の王たちを支配しているということ以上には何も考えない聖徒たちも、多くいただろうからである。しかし、このように言えば、キリストが王だけでなく万物をも支配しておられるという認識が、多くの聖徒たちの頭の中に生じることになる。よってヨハネが、ここでこのように書いたのは実に適切であった。
『「わたしはアルファであり、オメガである。」』
ここでキリストは、ご自身がギリシャ語の最初のアルファベットであるΑであり、最後のアルファベットであるΩであると言っておられる。これは、黙示録の他の箇所でも、書かれていることである。例えば22:13で、キリストはこう言っておられる。『わたしはアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。初めであり、終わりである。』これは一体どういうことであろうか。可能な解釈としては2つがある(※①)。まず一つ目は、アルファというのは、すなわちキリストが『死者の中から最初によみがえられた方』(黙示録1章5節)であり、オメガというのは、すなわちキリストが『最後のアダム』(Ⅰコリント15章45節)だという解釈である。この解釈の場合、キリストは「私は復活した者のうちで第一の者であり、アダムを型とする最後の者(※②)である。」と言っておられることになる。二つ目は、これは、キリストの永遠性について言われているという解釈である。永遠という理性では捉えられない無限の時間帯において、キリストは永遠の初めにも、終わりにも存在しておられる。つまり、キリストは永遠の時間の中で、いつまでも変わることなく常に存在し続けておられる。この解釈の場合だと、キリストは「私は永遠に存在している者である。」と、ここで言っておられることになる。これはどちらの解釈も可能であり、どちらとも聖書に反するものではない。一つ確かに言えることは、この御言葉が、イザヤ書の御言葉とまったく同じものだということである。イザヤ書で神はこう言っておられた。『わたしは初めであり、わたしは終わりである。』(44章6節)ここでキリストは、あたかも「私こそイザヤ書で語っていたあの神なのだ。」と言っておられるかのようである。実際、確かにイザヤ書の中で語っておられたのはキリスト御自身であった。何故なら、キリストは神だからである。このようにイザヤ書と同じ御言葉をキリストが言われたのは、ご自身の栄光が現わされるためであったと私は考える。キリストのこの御言葉から、キリストこそイザヤ書で語っておられた神だと知るのであれば、敬虔な聖徒たちにキリストに対する崇敬の念が生じるのは確かである。そのような崇敬の念が、キリストの栄光となるのである。
(※①)
ボナヴェントゥーラの場合、キリストがアルファでありオメガであるのは、キリストが「隣人にして同時に神であり、兄弟にして同時に主であり、また王にして同時に友であり、造られざる御言でありつつ同時に受肉した御言であり、我々を形造る方にして同時に我々を再び新たに造り直す方」だからだと述べている(『魂の神への道程』第4章 p53~54:創文社)。この見解は意味が分からず、そこには何の論理性もなく、考察不足であると言わねばならない。
[本文に戻る]
(※②)
『アダムはきたるべき方のひな型です。』(ローマ5章14節)
[本文に戻る]
【1:9】
『私ヨハネは、あなたがたの兄弟であり、あなたがたとともにイエスにある苦難と御国と忍耐とにあずかっている者であって、』
ヨハネは聖徒たちに対して兄弟愛に基づく連帯感を持っており、その連帯感をここで聖徒たちにも持ってもらおうとしている。そのような連帯感は、往々にして、力や励ましとなる。人は群れることで、その集団性から益を受けるものだからである。よって、このような連帯感は、特にヨハネの時代のような危急の時にあっては、非常に大切なものであったと言える。このような連帯感は、『互いに一つ心にな』(ローマ12章16節)ることが命じられている聖徒たちが、是非とも持たねばならないものである。ヨハネはアジヤにある7つの教会にいたこの聖徒たちを『兄弟』だと見做している。たとい、この7つの教会がどのような状態であったとしても、ヨハネにとって、そこにいた聖徒たちは主にある兄弟であった。その教会がどれだけ罪に満ちていたとしても、どれだけ不完全な状態にあったとしても、神の支配のうちにあるのであれば、そこはれっきとした教会であり、そこにいるのは紛れもない神の聖徒たちなのである。パウロも、異端に陥っていたガラテヤ教会にいた信仰者たちを『兄弟』(ガラテヤ3章15節)と呼んだ。黙示録の2~3章を見ると、この7つの教会には少なからぬ悪徳や不完全さがあったようだが、それにもかかわらず、そこにいた者たちが『兄弟』と呼ばれるべき者であったことには変わらない。ヨハネは、ここでその兄弟たちがあずかる3つのものについて述べている。それは『苦難と御国と忍耐』である。キリストの信仰を持つのであれば、『苦難』は避けられない。キリスト信仰を持つと、神からの試練やサタンの攻撃が、その人にもたらされるからである。パウロも、聖徒たちに次のように言っている。『あなたがたは、キリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜わったのです。』(ピリピ1章29節)しかし、キリスト信仰には、『御国』に入れるという恵みも伴っている。神は、キリストを信じる者たちを、その信仰のゆえに御国へと導いて下さるのである。だが、この御国に入るためには、そこに入るまでの間に多くの苦難があるから、必然的に『忍耐』が必要となる。この忍耐を持つことなしには、襲い掛かる苦難により信仰から脱落してしまうから、御国に入れることもなくなる。『私たちが神の国にはいるには、多くの苦しみを経なければならない。』(使徒行伝14章22節)とパウロが言ったように、聖徒に必要なのは苦難に対する忍耐なのである。ヨハネが書いたこの3つのものは、信仰を持った者に、必ず付いてくるものである。それはヨハネの時代に生きていた聖徒だけではなく、あらゆる時代に生きる聖徒たちに共通している。アジヤにいた聖徒であれ、今の時代に生きる聖徒であれ、信仰者でありながら、この3つのものを受けないような人は一人もいない。もちろん、ヨハネの時代の聖徒たちは、2019年に生きる今の聖徒たちよりも、御国はともかく、苦難と忍耐については多くのものを要求されていたということは間違いない。何故なら、ヨハネの時代には、ヨハネが黙示録の中で書いているように、もう間もなく恐るべき悲惨な出来事が聖徒たちにやって来ることになっていたのだから。
『神のことばとイエスのあかしとのゆえに、パトモスという島にいた。』
パトモス島とは、エーゲ海にある無数の小島の中の一つである。この島は、ヨハネが黙示録の中で書いたのでなければ、ずっと誰からも言及されないままだったであろう。この島はアジヤ西岸から遠く離れていない。ヨハネがアジアの西側の地域にあった教会にこの文書を届けたのは、恐らく距離的に近かったというのも理由の一つとしてあったのだろうと考えられる。近くにあるそれらの教会にだけ送り届ければ、そこから東西南北にある多くの教会に拡散されるだろうとヨハネが考えたと推測することも、十分に可能である。
ヨハネは、どうしてパトモスにいたのか。この黙示録やその他の聖書の巻では、ヨハネがパトモスにいた理由について、何も述べられていない。通説では、ドミティアヌスに島流しにされたということになっている。ドミティアヌス帝の治世にヨハネは地上にいなかったのだから、ドミティアヌス帝の治世だと考えるのは間違っているが、島流しにされたという理解自体は、間違っていないと私は思う。何故なら、そのようにしか理解できないからである。『神のことばとイエスのあかしとのゆえに』誰にも語られることのないような島にいたというのだから、これは島流しが理由でなくて何であろうか。つまり、ヨハネはカリグラ帝の治世に、皇帝かユダヤの王あるいは総督により、この島に送り飛ばされたということである。しかし、バプテスマのヨハネやアントニヌスが荒野で生活していたように、世の汚れに触れないようにと、ヨハネがパトモス島に自ら逃れたということは考えられないか。これは、まったく想定することが不可能というわけではない。何故なら、そのようにして島に逃れるのも、ある意味『神のことばとイエスのあかしとのゆえに』と言えるからである。つまり、主から与えられた真理を持っていると迫害されてしまうので、迫害を逃れて島に行ったということである。しかし、この考えは想定可能なものではあるものの、退けねばならない。何故なら、ヨハネは聖徒たちに『私たちは、互いに愛し合いましょう。』(Ⅰヨハネ4章7節)と言ったからである。このように言った愛を重視するヨハネが、兄弟愛に基づく主にある交わりを諦めてまで、パトモスという島に行ったというのは考えにくい。パトモスという島にいたのであれば、話すことも善を行なうこともできないのだから、どうして互いに愛し合うことができようか。またヨハネには『全世界に出て行き、すべての造られた者に、福音を宣べ伝えなさい。』(マルコ16章15節)という命令も与えられていた。ヨハネのような者が、キリストから与えられた宣教についての命令を行なわないで、パトモスという島に自ら閉じこもるということは考えられない。そういうことをすれば、ヨハネはキリストとキリストから与えられた使命を蔑ろにすることになる。それゆえ、やはりヨハネは世の権威者により島流しにされたと考えるのが、もっとも理に適った理解だということになる。
【1:10】
『私は、主の日に』
『主の日』というのは、皆で礼拝するために用意された毎週の日曜日のことである。今、我々が日曜日を『主の日』と呼ぶのと同じ意味で、ヨハネは『主の日』と言っている。旧約時代においては土曜日が礼拝の日であったが、新約時代になってからは、キリストの復活された日曜日に置き換えられている。この『主の日』とは、既に説明されたように、聖書においては再臨の起こる日を指して多用されている。しかし、ここではそのような意味で言われたのではない。もしそのような意味で言われたとすれば、ヨハネがパトモス島で幻を見せられた日に、キリストの再臨が起きたことになってしまう。そのようなことがどうしてあろうか。それでは、どうして神は、このような日にヨハネに幻を示されたのか。それは『主の日』が、霊的なことに心を使うべき日だったからであろう。確かに旧約聖書において、この週に1度の休みの日は『聖なる会合の日』(レビ23章3節)だと言われていた。この日は、聖なることが啓示されるには実に相応しい日なのである。しかし、この日に、黙示録に書かれている全ての幻がヨハネに啓示されたのであろうか。これは気になることではあるが、黙示録には何も詳しく書かれていないので、我々にはよく分からない。もしかしたら、1日では終わらず、日をまたいで啓示が続けられたという可能性もある。というのも、黙示録に書かれている啓示の総量は、1日で啓示されるにしては、あまりにも多いと思えるからである。8:1の1節だけでも『半時間』、すなわち30分の時間が経過している。ここだけで30分も経過しているのであれば、黙示録の幻が全て啓示されるのは、相当長い時間が必要だったに違いない。黙示録はこのような豊富な量であるのだから、たとえ1日で終わったとしても、朝から晩まで幻が示され続けたのではないかと考えられる。このような多くの幻が、2時間や3時間の間に全て示されたとは思えない。しかし、いずれにせよ、これは黙示録の理解にとっては、あまり本質的なことではない。
『御霊に感じ、私のうしろにラッパの音のような大きな声を聞いた。』
これは、御霊が感じさせて下さったので、ヨハネの耳に大きなラッパのような音が入ってきたということである。これは、霊的にしか感じられない音であり、ヨハネ以外には聞こえない音だったと思われる。あたかもエリシャと若い者の二人だけが、霊的な光景を見ることができたように(Ⅱ列王記6:15~23)。もしヨハネが御霊により感じなかったとしたら、このような音を聞くことはなかったはずである。何故なら、御霊の働きかけがなければ、どうしてこのような霊的な声が聞こえるであろうか。この世を見れば分かるように、霊的でない人々は、霊的なことには無頓着であるのが常である。
ラッパの音により大きな声が聞こえたのは、何故か。それは、ヨハネに対して啓示される神の預言が、よく注意して聞かれるべきだったからである。主が律法を授与するためにシナイ山に降りて来られた時にも、『角笛の音が非常に高く鳴り響いた』(出エジプト19章16節)と書いてある。ラッパとか角笛といった大きな音を出すものは、人の精神を、その出されている音に引きつけるためには非常に役立つ。誰でもラッパや角笛が大きく鳴らされたら、嫌でもそちらのほうに理性が傾けられてしまう。そこには精神を動かす強制力がある。神の啓示は言うまでもなく精神が強く傾けられるべきものだから、そのことが実現されるべく、ラッパの音が鳴らされたのである。また、これはラッパというものが、神に相応しいという理由もある。地を揺るがすようなラッパの強い響きは、神とその威厳に非常に適っている。これがラッパではなくリコーダーやハーモニカやウクレレやアコースティックギターだったらどうだったか、と考えてみるとよい。もしそのような音が鳴ったのであれば、神とその威厳に相応しくなかったのは明らかである。というのも、このような楽器の音は、穏やかで親しみやすいというのはあるかもしれないが、威厳や壮大さをあまり我々に感じさせないからである。またそのような音であれば、大してその発される声に注意を向けることもできなかったかもしれない。
【1:11】
『その声はこう言った。「あなたの見ることを巻き物にしるして、7つの教会、すなわち、エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィヤ、ラオデキヤに送りなさい。」』
この声の主はキリストである。それは、御父でも、御霊でも、御使いでも、天にいる4つの生き物でも、既に世を去った聖徒でも、アダムの子らである罪人でもない。何故なら、すぐ後の箇所を見れば分かるように、この声を見ようとしてヨハネが振り向くと、そこにはキリストがおられたからである。
ここからヨハネは、自分の前にキリストが現われたことについて書いている。これは、記述の信憑性を高めることであった。何故なら、このように書かれれば、本当にヨハネの前に現われたキリストが預言としての幻を示して下さったということがよく分かるからである。キリストがお示し下さったということ以上に、そこで言われていることの信憑性を高めるものはない。
【1:12】
『そこで私は、私に語りかける声を見ようとして振り向いた。』
『声を見ようとして』とは、すなわち「声の発生源また発出者を目で確認しようとした」という意味である。つまり、ここでは、声が実際に目に見えるものだと言われているのではない。
『振り向くと、7つの金の燭台が見えた。』
『7つの金の燭台』とは、キリストが黙示録1:20で言われるように『7つの教会』を指す。すなわち、1:11に書いてあるアジヤにある7つの教会である。これを、明かりを灯すただの製作品に過ぎないと思ってはならない。しかし、一体どうして教会が燭台に例えられているのであろうか。それは、教会という存在が、燭台が多くの人々を照らすように、人々を照らす存在だからである。燭台なる教会がこの世に存在しなければ、人々は闇の中に留まり、決して光を見ることがない。何故なら、真理を語る存在がどこにもいないからである。光である真理を語ってこの闇の世を照らすのは、キリストの教会の他にはない。だから、教会が燭台に例えられているのは、実に理に適っていることが分かる。このことは、キリストもマタイ5:15の箇所で、聖徒たちのことをこう言っている通りである。『あなたがたは世界の光です。山の上にある町は隠れる事ができません。また、あかりをつけて、それを枡の下に置く者はありません。燭台の上に置きます。そうすれば、家にいる人々全部を照らします。』
ヨハネが振り向き、そこに金色の燭台が見えたからといって、そこに触れば感触があるような実際の物質体があったというのではない。ヨハネが振り向いて見たのは、あくまでも、幻としての物体に過ぎない。しかし、それが幻だからといって、明瞭に認識できない、何かもやもやとしたようなものではなかった。もしもやもやとしていたとすれば、しっかりと認識できないから、このように具体的に自分の見たことを記すことはできなかったであろう。幻でありながらも、確かな認識を持てるようなものであったからこそ、ヨハネは正確に自分の見たことを書き記しているのである。このことは、これ以降に出てくる幻についても、同じことが言える。
金の燭台は教会を指すのだが、どうして「金」なのか。それは、教会が神にとっては、金が高価で尊いように、高価で尊いからである。誰でも金を持っていたならば、それを大事にするものである。神も、そのように教会を大事にされる。確かに、神はご自身の民に『わたしの目には、あなたは高価で尊い。』(イザヤ43章3節)と言っておられる。また、もう一つの理由は、教会という神のおられる存在は、金で象徴されるのが相応しいからである。神は栄光の王であられるから、そのような方がおられる場所を金だとするのは、実に適切である。旧約時代に神が住んでおられた神殿も、その全体が隅々まで金で張られていた(Ⅰ列王記6:22)。もっとも、教会は旧約の神殿とは違い、実際には金で満たされているのではないが。神は、ここで銀や銅や鉄などとは言っておられない。燭台がそのような物質において語られていたとすれば、それは神の住まわれる教会の表現としては相応しくなかったのである。
【1:13】
『それらの燭台の真中には、足までたれた衣を着て、胸に金の帯を締めた、人の子のような方が見えた。』
ここから、ヨハネは自分の見た燭台の真中におられるキリストが、どのような様子だったのかということを書いている。この説明は16節まで続く。
どうしてキリストは燭台である教会の真中におられたのか。それは、キリストが教会の主であり支配者だからである。キリストは教会を支配する牧者だから、『七つの金の燭台の間を歩く』(黙示録2章1節)ということをされる。教会はキリストの所有であるから、キリストがこのようにされるのは実に相応しいことである。往々にして、人は自分の所有する領域を、それが自分の所有であるからというので、四方八方に動き回るものである。そこが、自分の好きなようにできる領域だからである。アブラハムも、自分とその子孫に与えられると言われた地を歩き回るように、神から命じられた(創世記13:17)。神が『園を歩き回られる』(創世記3章8節)と言われたのも、エデンの園が神の所有する領域だったからである。もしキリストが教会の主でなければ、キリストが燭台の真中におられるということはなかったはずである。何故なら、主でないということは、すなわちそれを所有していないということだからである。自分の所有していない領域の真中に一体誰が常駐することができようか、またそこを一体誰が自由に動き回れるであろうか。主でも所有者でもなければ、そういうことはできない。なお、キリストはアジヤにあった7つの教会の真中にだけおられるなどと考えるべきではない。何故なら、このアジヤにある7つの教会とは、諸教会を表示しているからである。それゆえ、キリストは当然ながらこの7つの教会の真中におられただけでなく、地上に存在する全ての教会の真中におられた。
キリストが『足までたれた衣を着て』おられた理由は、定かではない。どうして長い衣をキリストが着ておられるのかということについて、聖書は何も説明していないからである。19:13のほうに出てくるキリストは『血に染まった衣』を着ておられる。しかし、ここでのキリストが着ておられた衣は、まだ血に染まっていなかったと考えるべきである。というのも、19章のキリストが血に染まった衣を着ておられるのは、大患難の時に殺された聖徒たちの血がキリストの衣に降りかかったために、そうなったからである。だが、この1章の箇所では、まだ大患難は起きていない。だから、ヨハネがここで見たキリストの衣も、まだ血に染まっていなかったことになる。もしこの時、既にキリストの衣が血に染まっていたとすれば、ヨハネはそのことについて、しっかりと書いていたはずである。
15:6に出てくる7人の御使いも、キリストと同じように『金の帯』を締めていた。どうしてキリストと御使いが金の帯を締めているかといえば、それは、キリストと御使いが教会を保護し管理する存在だからだと思われる。だからこそ、教会を表示する燭台の物質である金を使った帯を締めている。これは、ある施設の管理人が、その施設が描かれたバッジを胸につけているようなものである。そのバッジを見れば、誰でもその人がその施設の管理人だということが分かる。それと同じように、キリストと御使いたちも金の帯を締めていることにより、金の燭台である教会の保護者・管理者であるということが分かるようになっている。この『金の帯』とは、つまり、こういうことであると私は考えている。だからこそ、聖徒たちのほうは胸に金の帯を締めていると書かれていないのである。何故なら、聖徒たちは保護され管理される側の存在、つまり先の例えで言えば施設だからである。保護また管理される施設がバッジをつけるということが、どうしてあるであろうか。
ここでは『人の子のような方が見えた。』と書いてあるが、このキリストは恐らく立っておられたと思われる。もし座っておられたならば、そのことが分かるように書かれていただろうからである。例えば、ダニエル書7:9(※①)やマタイ19:28(※②)などのように。
(※①)
『私が見ていると、幾つかの御座が備えられ、年を経た方が座に着かれた。』
[本文に戻る]
(※②)
『「…世が改まって人の子がその栄光の座に着く時、…』
[本文に戻る]
【1:14】
『その頭と髪の毛は、白い羊毛のように、また雪のように白く、』
キリストの頭部が白かったのは、キリストの光栄と正義を示している。箴言16:31には、次のように書いてある。『しらがは光栄の冠。それは正義の道に見いだされる。』キリストは、光栄の光栄であり、正義そのものである。よって、キリストの頭部が白かったのは自然なことであった。キリストの光栄と正義は完全であって、そこには少しの欠けもない。それゆえ、我々はキリストの頭部には黒い毛が1本も無かったと考えるべきである。ダニエル書7:9によれば、キリストの御父は、白髪であり、『年を経た方』であると言われている。この御父の場合、白髪であるから、年を経ていると言われるのは誰でも納得できる。何故なら、白髪とは、老人にこそ生えるものだからである。ではキリストの場合はどうなのであろうか。ここでキリストの髪の毛は白髪であると言われているが、髪の毛が白髪であれば、ここでのキリストは老人のようだったのであろうか。白髪であるのだから、やはり白髪を持っていることに相応しく、ここでのキリストは老人だったと考える人もいるであろう。だが、私はそうは考えない。何故なら、確かに、ここでのキリストは白髪を持っておられるものの、非常に生き生きとしており、とても老人のようには感じられないからである。ここでは、キリストの目が燃えているとか、足が光り輝いているとか、顔が太陽のようだったとか、爆発的な生気を持っているかのように描かれている。このような生気は、老人の気質とはかけ離れている。つまり、ここでのキリストは単に髪が白かったというだけで、別に年を経ていたということではないと私には思われる。日本のある皇族の方がそうだが、まだ若いにもかかわらず白髪を持っている人は、数はそこまで多くはないものの、世の中に存在している。だから、キリストが白髪であったにもかかわらず老人のようではなかったと考えるのは、荒唐無稽だということにはならない。
『その目は、燃える炎のようであった。』
主の目が炎のように燃えていたのは、主の生気が豊かであったことを示す。これは、『レアの目は弱々しかった』(創世記29章17節)のと対極的である。レアは、キリストとは違い、生気に満ちてはいなかったのである。往々にして人の意気や生命力といったものは、目の力によって知られるものである。読者の中には、この目についての記述を、神が火であられるという聖書の啓示から解したいと思う方もいるかもしれない。確かに、聖書は、神が燃える火であられると教えている(※)。しかし、ここでは神が火であられるという観点から解釈をすべきではない。何故なら、ヨハネはここで、明らかにキリストの生き生きとした様子を書こうとしているからである。すなわち、ヨハネは、ここでキリストが火を持って裁かれるお方であると言いたくて、このように書いているのではない。ここでは、裁き主としての教示がされていると考えるべきではない。もちろん、キリストが裁き主であると考えること自体は、何も間違ってはいないのであるが。
(※)
『私たちの神は焼き尽くす火です。』(ヘブル12章29節)
[本文に戻る]
【1:15】
『その足は、炉で精錬されて光り輝くしんちゅうのようであり、』
キリストの足が輝く真鍮のようであったというのは、キリストの力強さを現わしている。これは実にキリストにとっては相応しい表現である。何故なら、キリストは神であられ、力そのものであられるからである。この箇所と対応しているダニエル書10:6のほうでは、キリストの足が『みがきあげた青銅のよう』であったと書かれている。これも、ヨハネが『精錬されて光り輝く真鍮のよう』と言っているのと同じで、キリストの力強さを示している。しかし、ヨハネのほうが、より優った言い方をしている。ダニエル書のほうでは、足だけでなく腕についても書かれており、その腕は足と同じようであったと言われている。このダニエル書と我々が今見ている黙示録の箇所は対応しているから、黙示録のほうのキリストも、青銅であるか真鍮であるかという違いはあるが、腕が足と同じようであったと考えるべきであろう。つまり、黙示録のほうでは、単に足のほうしか書かれていないだけであって、実際には腕も足と同じようであったということである。黙示録には、このように旧約聖書の対応する箇所と、僅かではあるものの無視できない微妙な差異が見られるので複雑になっていたり我々の頭脳を混乱させる聖句が多くあるから、注意すべきである。そのような聖句に出会った場合、もし黙示録を正しく理解したいというのであれば、我々はじっくりと考えなければいけない(※)。
(※)
旧約聖書の箇所と対応している黙示録の箇所に出会った際、その内容が全体的には非常に似ているものの部分的には明白な差異が見られる場合、我々は、どちらか一方の記述が偽りであるなどと誤解したり、矛盾しているなどと疑ったりしてはいけない。聖書の真の筆記者であられる神が、どうして偽りや矛盾したことを書かれるはずがあろうか。詩篇記者も言うように、『みことばのすべてはまこと』(119篇160節)である。ヴァン・ティルも言っているように「聖書は矛盾していない」(『ヴァン・ティルの十戒』第一戒 p42:いのちのことば社)のだ。もしこのような箇所に出会った際、我々は、どちらも正しいことを言っていると考えるべきである。黙示録の箇所と旧約聖書の箇所がそれぞれ部分的に違っている場合、本質的には同じ意味を持つが視像的には違った幻が示されていたり、それぞれ異なった観点から語られているのではないかと、よく考えねばならない。そうすれば、どちらも正しいことが言われていることに気付くであろう。例えば、我々が今見ているこの1:15の箇所とダニエル書10章の箇所であれば、なるほど、確かに全体的には類似しているが部分的には明瞭な違いが認められる。ヨハネは真鍮を見たが、ダニエルは青銅を見た。しかし、ヨハネに示された幻とダニエルに示された幻のどちらか一方が偽りであるというわけではない。この2つの幻は、部分的にはいくらか違うかもしれないが、どちらも本質的には真である。つまり、この2つの箇所ではキリストの本質が示されることが目的とされているのだから、その本質さえ分かるようであれば、その見せられた幻にいくらかの違いがあったとしても問題にはならないわけである。たとえキリストの幻における足が真鍮であれ青銅であれ、キリストの力強さと特異性が示されていることには変わらないのだから、どちらも本質的には正しい幻が見せられている。このような多少異なる2つの箇所に出会った際、聖書には偽りや矛盾があるなどと考えてしまう人は、キリスト者として終わっている。何故なら、その人は、神が偽りや矛盾を語られる信頼に値しない存在であると考えているからである。我々は霊的な破滅を避けるために、このような箇所に出会った際には、慌てて愚かな判断をしたりせず、冷静になってよく考えるべきであろう。もしよく考えても解決が得られない場合は、少しもどかしかったとしても、未解決のまま保留にしておくのが無難である。アウグスティヌスも分からない箇所があれば、分かるようになるまでは、分からないままの状態で我慢したものである。
[本文に戻る]
ここで一つの疑問が生じる。先に13節の箇所で、キリストが『足までたれた衣を着て』おられたと書いてあったのに、ヨハネはどうしてキリストの足がどのようであったか知ることができたのであろうか。足までたれた長い衣を着ていたのであれば、足が衣で隠されてしまうのであるから、足の様子を知ることはできないはずである。それなのに、ヨハネは、あたかも足までたれた衣をキリストが着ておられなかったかのように、キリストの足の様子を詳しく書いている。この問題を解決するのは簡単である。つまり、キリストは確かに長い衣を着ておられたのではあるが、それは足の様子がまったく分からなくなるほどの長さではなかったということである。すなわち、衣の下からは、わずかではあったかもしれないが、キリストの足がどのようであるか見ることができた。だからこそ、ヨハネはキリストの足について、このように具体的に書いているのである。もし、この衣が足を完全に覆うほどの長さであったとすれば、ヨハネがこのように足の詳細を書くことはできていなかったはずである。我々は、先の13節の箇所で、ただ『足までたれた衣』とだけ書かれており、「足を完全に覆っている衣」とは書かれていないことを考えるべきである。つまり、『足までたれた衣』という記述は、足が衣により隠れて見えなくなっていることを意味していないのである。
『その声は大水の音のようであった。』
キリストの声が『大水の音』のようだったというのは、キリストの偉大性と力強さを現わしている。これは、男から造られ、力強さを持たない女性の声がか弱いのとは対極的である。キリストは女性のようではないから、女性のような声は出さない。福音書に書いてあるように、天から神の声が聞こえた時に、群集は『雷が鳴ったのだと言った。』(ヨハネ12章29節)雷も、大水と同じように、偉大性と力強さがそこに感じられる音を出す。要するに、雷のようであろうが大水のようであろうが、神は圧倒的だと思える声を発されるということである。
【1:16】
『また、右手に7つの星を持ち、』
この『7つの星』とは、キリストが1:20の箇所で言っておられるように『7つの教会の御使いたち』である。これは象徴表現であるから、本当の星だとか、御使いや星以外の被造物であるなどと考えてはいけない。キリストの手が教会の御使いたちを持っていたということには、2つの意味がある。まず第一は、キリストが、御使いたちを手に持っている道具でもあるかのようにお使いになられる、ということである。既に説明されたように、キリストは何かを行なわれる際、御使いにそれを委ねるというやり方を往々にしてとられる。第二は、キリストが、その御手の中にある道具としての御使いを通して、教会に働きかけられるということである。黙示録の中でも、キリストが7つの教会に何かを通達される時には、まず各々の教会の御使いたちに伝えるべきことを書き送らせるという手法をとっておられる(2~3章)。なお、黙示録で『星』と書いてある場合、それは御使いを指している場合もあるが、全ての箇所がそうだというわけではない。例えば、8:12では『星の三分の一とが打たれた』と書いてあるが、ここでの星は御使いを指してはいない。
『口からは鋭い両刃の剣が出ており、』
この『両刃の剣』とは、つまり御言葉のことである。聖書は、御言葉のことを剣と言い表わしている。例えば、パウロは『御霊の与える剣である、神のことば』(エペソ6章17節)と言っている。この御言葉は、それを聞いた人を刺し通し、その隠された本性を現われ出させるものである。ヘブル4:12では、こう言われている。『神のことばは生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、たましいと霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し通し、心のいろいろな考えやはかりごとを判別することができます。』また、この御言葉という剣が振り回されることは、その御言葉が振り回された対象に裁きとして適用されるということである。既に見たように、ネロはこのような仕方でもって、キリストにより殺されてしまった。キリストは、この口から出ている鋭い霊の剣によって、戦われるお方である。それはイザヤ書66:16において、主が『その剣ですべての肉なる者をさばく。主に刺し殺される者は多い。』と書かれている通りである。この御言葉の剣が振り回されて裁かれると、その裁かれた人は、裁かれて悲惨な状態になってしまう。呪われた者たちは空中の審判の際、キリストの口から出た『わたしから離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火にはいれ。』(マタイ25章41節)という御言葉の剣により裁かれ、永遠の火に投げ込まれることになってしまった。なお、我々は、この記述を肉的に捉えるべきではない。この記述は霊的に捉えられるべきものである。もし肉においてこの記述を捉えると、キリストが実際にその口で御言葉という名の物体的な剣をくわえていることになってしまう。この場合、剣を口から離さないように力を口に入れ続けていなければならず、口が剣の柄で埋まっているから上手に喋ることもできず、舌から自然に生じる唾液が剣を伝ってこぼれてしまうことになる。これは実に滑稽に思えることである。肉において捉えると、このようにコミック的なシーンを想像しなければいけなくなる。このように想像することは、キリストに対する侮辱だと言わねばならない。よって、ここで言われていることを肉的に捉えるのは誤りである。
『顔は強く照り輝く太陽のようであった。』
これはキリストの威光の輝きが、いかに大きかったかということを言っている。キリストの御顔における威光は、太陽のように、いや、太陽以上に照り輝いている。ヨハネが黙示録を書いている紀元1世紀の時代においては、太陽が知られている星の中でもっとも光度が大きいと認識されていたから、そのような星をもってキリストの御顔の輝きを言い表わすのは実に相応しいことであった。この太陽をもってキリストの輝きを語れば、非常に分かりやすいのである。しかし、太陽のような輝きではあっても、太陽よりも光度が大きい星よりは輝きが劣っているというわけではない。これは言うまでもないことであろう。天文学が進んだ今では、太陽よりも何十倍も輝いている星がいくつもあるこということは周知の事実である。キリストの御顔の輝きが、太陽よりも輝いているそれらの星のどれよりも、その光度において優っているのは間違いない。何故なら、それらのものも、キリストにより造られたからである。その方において造られた被造物が、当の造られたお方よりも輝いているというのは絶対に考えられないことである。言うまでもなく、創造者であるお方は、もっとも高い光度を持つ星よりも、輝かしい光を持っておられるお方である。その御顔における威光の輝きは凄まじいものであるから、その御前では、誰もが低められて輝きと尊厳とを失い、暗い場所に入って逃げ隠れたくなるほどのものである。それは、主が再臨されて人々の前にその御姿を現わす時において、『人々は主の恐るべき御顔を避け、ご威光の輝きを避けて、岩のほら穴や、土の穴にはいる。』(イザヤ2章19節)と言われている通りである。すぐ後の箇所でも見るが、人は、主の御顔のご威光に耐えることが決してできない。
ここまでヨハネが書いたキリストの様子は、全部で10であった。すなわち、(1)長い衣を着ている、(2)金の帯を締めている、(3)正にキリストの外貌をしている、(4)頭部が白かった、(5)炎のような目であった、(6)輝く真鍮のような足を持っていた、(7)声が大水のようであった、(8)7つの星を右手に持っていた、(9)口から御言葉の剣が出ていた、(10)太陽のような顔であった、という10の様子である。聖書で、無意味だと思われるような書き方で書かれている箇所は、非常に少ない。この箇所で、キリストの様子が10挙げられているのも、恐らく何かの意味を持つ可能性が高い。もしこの箇所に隠された意味があるとすれば、それは10の様子を挙げることにより、キリストの完全性を示すという意味であろう。聖書において「10」とは完全であることを示す数字である。しかし、10の項目の配列については、その順序に何か深い意味が隠されているようには思われない。ヨハネは、特に意識せず、ただ心のおもむくままにキリストの様子を一つ一つ列挙しただけだという印象を私は受ける。というのも、その10の順序のうちには、意味を持つ整った秩序のようなものが何も見出されないからである。しかし、ここではキリストの様子を列挙することが目的とされているのだから、特に配列の順序に意味が無かったとしても、何も問題にはならない。
この13~16節目の箇所は、明らかにダニエル書10:5~9の箇所と類似している。ヨハネは、ダニエル書の箇所に基づいて、この箇所を書いたのである。いや、むしろ、神がダニエル書の記述に類似した幻をヨハネに見せられたと言ったほうがいいかもしれない。それでは、この黙示録の箇所とダニエル書の箇所に見られる違いは、どのようなものであるのか。いくらか見てみたい。まずヨハネは足までたれた衣をキリストが着ておられたとだけしか書いていないが、ダニエルは亜麻布の衣を着ているとしか書いていない(10:5)。ヨハネはキリストには金の帯が胸にあったと言っているが、ダニエル書のほうには腰にウファズの金の帯が締められていたと書いてある(10:5)。金という点に違いはないが、「ウファズの」と書いてあるかないかという点で、また胸か帯かという点で、違いがあるのが分かる。ダニエルがキリストの身体を『緑柱石のよう』(10:6)と言っているのに対し、ヨハネの場合、身体のことには何も触れていない。顔は、どちらも輝いていたと書いているが、ヨハネのほうは「太陽のよう」と言い、ダニエルは「いなずまのよう」(10:6)と言っている。目も両方とも燃えていると書いているが、ヨハネは「燃える炎」と言い、ダニエルは「燃えるたいまつ」と言っている(10:6)。腕と足については、先に見た通りである。声については、ヨハネが「大水の音」と言っており、ダニエルは「群集の声」と言っているが(10:6)、どちらも言っていることは同じである。すなわち、キリストの声は巨大で多重的であるということである。キリストを見た時に倒れてしまったというのも、両方とも同じである。今見たこのような比較から、この2つの箇所が対応しているということが分からない人は恐らくいないと思う。この2つの幻は、どちらが正しくて、どちらが間違っているということはない。どちらも、神が与えられた純粋で真実な幻である。この2つの幻にいくらかの違いが見られるのは、その幻の示され方が単に少し違っているだけであって、どちらのほうも真のキリスト像が示されていることには変わらない。我々は、このように類似した箇所を比較しつつ考察することで、ますます黙示録の理解が深まるようになるということを知るべきである。
【1:17】
『それで私は、この方を見たとき、その足もとに倒れて死者のようになった。』
これは、キリストの威光が、人の精神に耐え得るものではなかったからである。神は、モーセに対して『人はわたしを見て、なお生きていることはできない』(出エジプト33章20節)と言われた。神は、被造物を超越したお方であり、被造物がその精神により把捉できる存在ではないから、神を見てもなお正常なままでいられる人はいない。そのような存在である神をヨハネは目の前で見た。だからこそ、ここでヨハネは倒れて死者のようになってしまったのである。ダニエルも同様に、キリストの幻を見た時、『意識を失って、うつぶせに地に倒れ』てしまった(ダニエル10章5~9節)。我々は、この箇所を読んで、倒れてしまったヨハネが軟弱な人だったなどと思ってはならない。たとえカエサルであれゼノンであれサムソンであれアキレスであれ、キリストの威光を見ながら、意識を失って倒れてしまわない人は、誰一人としていないのである。
『しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。』
キリストは、倒れたヨハネの上に手を置いて、ご自分の語るべきことをヨハネに知らせようとされた。主は、ヨハネに告げ知らせるべきことを告げ知らせるためにこそ現われたのだから、ヨハネが倒れたのは仕方がなかったとしても、ヨハネは倒れている場合ではなかったのである。キリストが左ではなく右の手をヨハネに置かれたのは、キリストがヨハネを蔑ろにしておられなかったからである。昔から今に至るまで、この世界では左よりも右のほうが優越していると認識される傾向があるが、聖書も、そのように右のほうを優越した方向また部位として扱っている傾向を持っている。例えば、キリストが父なる神の隣に座したのは、左ではなく右であったと聖書は教えている。詩篇でも、次のように書かれている。『あなたの愛する者が助けだされるために、あなたの右の手で救ってください。』(108篇6節)『主の右の手は力ある働きをする。主の右の手は高く上げられ、主の右の手は力ある働きをする。』(118篇15~16節)『そこでも、あなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕えます。』(139篇10節)この世で右のほうが優越していると思われがちなのは、右利きの人が多いというのが理由の一つであるかもしれないが、神がそのように思えるように世界に働きかけられたからというのも一つの理由としてあると思われる。もしそうでなければ、これほどこの世界において右のほうが優越していると思われることはなかっただろうし、聖書もそのように右ばかりを強調して書くことはなかったはずである。であるから、キリストが右の手こそをヨハネに置かれたのは、キリストもそのような思想を背景として持っておられたことを意味している。これが左の手だったらと考えると、どうであろうか。どこかキリストがヨハネのことをあまり重視しておられないと感じられるのではなかろうか。もちろん人によっても感じ方は違うだろうが、少なくとも右であると書かれている場合よりは、いくらかでも違和感を持つはずであると私は思う。
『「恐れるな。』
これは、聖徒たちが神や天使たちを見て恐怖に満たされた際に告げられるのを常とする、なだめの言葉である。モーセも、イスラエル人が神の到来を恐れた際に、『恐れてはいけません。』(出エジプト20章20節)と言った。キリストを見た際に気絶してしまったダニエルにも、『恐れるな。ダニエル。』(ダニエル10章12節)とか『恐れるな。安心せよ。強くあれ。強くあれ。』(同19節)などと言われた。一方、聖書では『神を恐れよ。』(伝道者の書12章13節)とも命じている。これは、神とその裁きとを恐れ、そのようにして悪から離れて敬虔に歩めという命令である。しかし、ここで言われているのは、それとは逆のことである。他の箇所では恐れよと言われながら、ここでは恐れるなと言われているが、これは何も矛盾していない。つまり、ヨハネに対して『恐れるな。』と言われたのは、あたかも神を苦しみを与える恐るべき奴隷主であるかのように思って戦々恐々とするな、という意味である。これは、軍隊がやって来たので恐れおののいている群集に対して、その軍隊の将軍が「恐れてはならない。私たちは、あなたがたを滅ぼすためにではなく助けるために、また守るために来たのだ。勘違いをしてはならない。私たちは敵ではなく味方なのである。」などと言うのと似ている。確かに、その町の群集はその軍隊を敵や奴隷主でもあるかのように恐れる必要はないのだが、しかし、悪いことや反逆的なことをすれば処罰をもたらす言わば警察的な存在としては当然ながら恐れなければいけない。聖書で「神を神を恐れよ。」と命じられながら、この箇所で書かれているように神のことを『恐れるな。』とも言われているのは、つまりこういうことなのである。もっと分かりやすく言えば、聖徒たちは神を懲らしめを与える父としては恐れるべきなのだが、拷問を与える奴隷主でもあるかのようには恐れるべきでない。何故なら、聖徒たちにとって神とは父ではあるが、奴隷主ではないからである。しかし、ここでのヨハネは仕方がなかったにせよ、神をあたかも恐怖の大王でもあるかのように恐れてしまった。だからキリストは、ここで『恐れるな。』と不適切な反応を示したヨハネに言われたのである。
【1:17~18】
『わたしは、最初であり、最後であり、生きている者である。わたしは死んだが、見よ、いつまでも生きている。』
これは、非常に生き生きとした、真の、流動的なキリスト認識を聖徒たちが持てるような記述である。このような言い方は、先に見た1:4と1:8の箇所でも、既に行なわれていた。キリストは、仏像のように不動だと感じられるようなお方ではないし、そのように感じてはならないのである。
【1:18】
『また、死とハデスとのかぎを持っている。』
キリストは、死の扉とハデスの扉とを開けることのできる鍵を持っておられる。この鍵を持っておられるのは、キリスト以外にはいない。キリストがその鍵を使うと、死とハデスが開かれるので、死んでハデスに行くべき者が、そこに投げ込まれる。つまり、これは、誰かが死ぬのも死んでハデスに送られるのも、すべてはキリストにかかっているということである。また、ここでは死とハデスと言われているが、この2つのものは、既に説明されたように、第二の死と火の池に置き換えられている。ヨハネにキリストが語りかけておられる時点では、まだこの2つのものが、滅ぼされて不要にされてはいなかった。だからこそ、ここでは『死とハデス』と言われているのである。今は既にこの2つのものが新しい死と新しい刑罰の場とに置き換えられているから、我々は、そのことに気をつけるべきである。―では今のキリストは「第二の死と火の池の鍵」を持っていることになるのか?―恐らく。しかし、そのことが文章として聖書の中で教えられているというのではないが。 さて、もしかしたら読者の中には、この箇所を「セカンドチャンス論」の論証として使える箇所ではないかと考える方もいるかもしれない。すなわち、「キリストは死とハデスを自由に開け閉めできるお方だが、これは苦しみの場所で焼かれている人たちの中で、そこから出してもらえる人がいることを意味しているのではないか。」と考える方がいるかもしれない。確かにキリストが地獄の鍵を持っているというこの啓示は、中には地獄から救い出される人もいると考えたいセカンドチャンス論者にとっては、少なからず論証の武器として使える啓示であると言える。しかし私としては、たとえこの啓示を考慮しても、セカンドチャンス論を確証することはできないと思う。何故なら、これはただキリストが地獄を開ける鍵を持っておられるということだけしか教えていないのであって、地獄にいる者にも救いの余地があるということについては何も言っていないからである。実に、このセカンドチャンス論においては、このこと、すなわち地獄にいる者にも救われるチャンスがあるということを証拠付けられなければ、強い説得力が生じない。よって、この箇所をセカンドチャンスの論証のために使っても、それほど論証力の強化とはならず、それゆえに反対する者たちを納得させることもできないであろう。なお、この「鍵」というのが実際上のものではないということは、言うまでもない。これは、キリストが死とハデスを人々に与える権威また裁量権を持っておられるということを、「鍵」という象徴表現で言い表わしているに過ぎない。つまり、鍵の持ち主が好きなようなその鍵に適合する扉を開け閉めできるように、キリストは人々を好きなように殺してハデスに送ることができるということである。もしこの鍵を実際的なものだと考えると、愚かな詮索家たちのように「鍵はどのような材質だったのか。」とか「キリストがその鍵を無くされた場合はどうなるのか。」などといった些末な空想にふけることにもなる。我々はそのような愚に陥らないために、この「鍵」という言葉を霊的に理解しなければいけない。黙示録には、このように実際上のものを通して、ある事柄を言い表わしている箇所が非常に多くあるから、我々はそのことによく注意する必要がある。そのような箇所に出会った場合、霊的に捉えないと、いつまで経っても正しい理解に至れないままとなってしまうのである。
【1:19】
『そこで、あなたの見た事、今ある事、この後に起こる事を書きしるせ。』
どうしてキリストは、このようなことを書き記すようにと命じられたのか。それは、既に述べられたように、紀元1世紀のアジヤにいた聖徒たちにあらかじめ様々な事柄を告げることで、聖徒たちが心の準備をして患難が襲ってきても慌てないようにするためであり、またそのようなことが告げられることで、神が恐れられたり、讃美されたり、更に愛されたりするようになるためであった。神は全てを意図的に行なわれるお方であって、この箇所における命令も、意味なく命じられたものではない。
ここに書いてある『見た事』とは、ヨハネに見せられた幻の全てを指す。ヨハネは、そのことについて、『私は見た。』などと書いて自分の見た通りのことを黙示録の中で記している。『今ある事』とは、ヨハネの現在の時における状況のことである。例えば、ヨハネが現在パトモス島にいたこと、その時の皇帝は黙示録において言えば「6番目」であったこと(17:10)、というのがそうである。『この後に起こる事』とは、ヨハネに見せられた幻の中で、まだ起きていなかった部分のことを言っている。黙示録の多くの箇所は、これに該当している。つまり、これは「ヨハネに見せられた全ての幻」という大区分の中にある、「まだ未実現の部分」という小区分のことである。よって、これは幻の中の預言ではない部分については該当していない。
【1:20】
『わたしの右の手の中に見えた7つの星と、7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会である。』
ここではキリストが、『星』と『燭台』という象徴表現としての言葉を、それがどういう意味なのか理解できるように説明して下さっておられる。このような解き明かしがされている箇所は、他にも17章がある。ここでは御使いが「頭」や「角」などのことについて詳しく説明している。このように意味が解明されていると、我々は黙示録で言われていることの意味を簡単に理解できるようになる。しかし、黙示録で、このような解明が行なわれているのは非常に少ない。黙示録に書かれていることのほとんどは、あまり解明されていないか、まったく解明されていない。例えば、11:13の『7000人』や多くの箇所で出てくる『3分の1』という言葉は、まったく何の説明もされていない。このような場合、我々は真面目になって深く考えないと、そこに隠されている意味をいつまで経っても理解できないままに留まることになる。いくら考えても結局は分からないままでいるという部分も、かなり多い。これこそ、黙示録が難解である理由の一つである。つまり、この文書は謎に満ちているのである。そのため、ほとんど全ての人が、今まで黙示録を理解できなかったのである。この1:20の箇所のようにいちいち説明がされてあれば、ここまで黙示録が難しく感じられることはなかっただろうが、そうではない。しかし、だからといって我々が、「何の説明も書かれなかった神は親切でないお方だ。愛がない。」などと言って神を責めることがあってはいけない。そのように神を責めるのは不遜である。神は、分かる者だけが分かればそれでよいと思われたので、このように多くの箇所が謎に包まれるままにしておかれたのである(※)。邪悪だが知性は高かったアレスター・クロウリーは、「<達人>の秘密とは凡人には明かされることがないのである。」(『アレスター・クロウリー著作集5 777の書』777 p18:国書刊行会)と言ったが、これは黙示録でも同様のことが言える。すなわち、「<神という真理の達人>の秘密は霊的な恵みを受けていない解釈的な意味における凡人には明らかにされることがない」のである。だからこそ、黙示録は謎に次ぐ謎で満ちているのだ。そのように謎に包まれたままにしておけば、神に恵まれ導かれた少数の者だけが、黙示録を理解できるだけとなる。キリストも、そのようにして、多くのことを謎に包む形でお語りになられた。だから、弟子たちはキリストに尋ねでもしない限り、その意味が分からないままであった。これは福音書の中で我々が既に見ている通りである。要するに、「悟れる者だけが悟れ。他の者は読むが読むな。すなわち文章を認識しはするが、その意味を理解するな。真理の知解は少数の者にだけ与えられるのだ。」ということである。それはキリストが『耳のある者は聞きなさい。』と言われたのと同じことである。
(※)
アレクサンドリアのクレメンスもこう言っている。「実に聖書は、そのすべてが誰にでも全く明瞭に伝えられることを望みはしない。」(『キリスト教教父著作集―4/Ⅱ―アレクサンドリアのクレメンス2 ストロマテイス(綴織)Ⅱ』第5巻 57:2 p58 教文館)
[本文に戻る]
ここで1章目として区切られた箇所は終わる。この1章目で特に考察されるべきなのは、1~3節目と7節目である。1~3節目は、黙示録全体の理解を規定し左右させる、実に重要な箇所である。7節目は、再臨についての理解を更に深めるために、是非とも考究されるべき箇所である。
第5章 ②2~3章:7つの教会に対するキリストの称賛と勧告と約束
これら3つのことは、どれも再臨の日のために書かれている。「称賛」がされているのは、聖徒たちの美点・徳が再臨のある日まで保たれ、更に増し加えられるようになるためである。そうすれば、それだけ良い心持ちでキリストの前に立つことができる。より自信を持ってキリストの前に立てたほうがよいのは、言うまでもないことである。「勧告」は、聖徒たちが不敬虔なまま歩んだり、これから訪れる悲惨に耐えられなかったりしたために、救いから漏れないようにするためにされている。もし勧告を聞かず、救いから漏れるようなことでもあれば、再臨のキリストに出会った際には、大変なことになってしまうのである。そうなれば、キリストから大いに非難されることにもなる。これは、使徒たちも、そうならないようにと勧告していることであった。パウロは『主イエス・キリストの来臨のとき、責められるところのないように』(Ⅰテサロニケ5章23節)と聖徒たちに言っている。ペテロも聖徒にこう言っている。『愛する人たち。…しみも傷もない者として、平安をもって御前に出られるように、励みなさい。』(Ⅱペテロ3章14節)同様にヨハネもその手紙の2:28で聖徒たちが『来臨のとき、御前で恥じ入るということのないため』に勧告をしている。「約束」がされているのは、聖徒たちが再臨の起こる日まで大いに努力し、その努力が継続されるようになるためである。努力すれば、キリストが再臨された時には、それだけ良い報いを受けることができる。往々にして人は、目の前に報酬を伴う約束が提示されたら、大いに頑張る気になるものである。アレクサンドリアのクレメンスも言うように、「約束は、従順を追及する上での端緒である。」((『キリスト教教父著作集―4/Ⅱ―アレクサンドリアのクレメンス2 ストロマテイス(綴織)Ⅱ』第6巻 98:3 p239 教文館))今書かれたこれら3つのことは、どれも神の愛から出ている。つまり『神は愛』であるから、聖徒たちがキリストの再臨の際に良い状態で御前に出られるように、そしてキリストから良いことを言われて永遠の報酬をより豊かに受けるようになってほしいと思われたのであって、それゆえに、このように聖徒たちの改善と徳性と忍耐と努力に益することを親切に語ってくださったのである。
この2~3章目の箇所においては、それぞれの教会に対して、例外なく『知っている。』と言われることから語りかけが始まっている(※)。どうしてキリストは、まず聖徒たちのことを知っていると言われることから、語りかけを始められたのか。それは、キリストが聖徒たちの監督者であり支配者であるということを、聖徒たちによく分からせるためだったと思われる。最初にそのように言われたら、聖徒たちは、キリストこそが自分たちの管理者なのだということをよく認識するようになるはずだからである。このように最初に言うのは、あたかも「私こそがあなたがたを常に見て知っている牧者なのだ。」とでも言っているかのようである。
(※)
エペソ教会に対して 「私は知っている」―行ないと労苦と忍耐と自称使徒を試したことを
スミルナ教会に対して 「私は知っている」―苦しみと貧しさと悪者からののしられていることを
ペルガモ教会に対して 「私は知っている」―その住んでいる所を
テアテラ教会に対して 「私は知っている」―行ないと愛と信仰と奉仕と忍耐とより良い状態になっていることを
サルデス教会に対して 「私は知っている」―その行ないを
フィラデルフィヤ教会に対して 「私は知っている」―その行ないを
ラオデキヤ教会に対して 「私は知っている」―その行ないを
[本文に戻る]
さて、それでは2章の1節目から見て行くことにしたい。
【2:1】
『エペソにある教会の御使いに書き送れ。』
まずはエペソ教会から、書き送るようにと命じられている。この2~3章の箇所で、書き送られることになる教会の順番は、1:11で言われた教会の順番と、まったく同じである。では一体どうしてエペソ教会が第一に置かれているのか。これは分からない。このように聞くのは、「どうして最初の人間はアダムだったのか。」と聞くのと同じであり、不毛な疑問であると言わねばならない。
この記述から、個々の教会には、それぞれ固有の御使いが担当者として割り当てられていることが分かる。それは、一つ一つの国に御使いが割り当てられているのと(ダニエル10:20)、また一人一人の聖徒に御使いがつけられているのと(マタイ18:10、使徒行伝12:15)、同じことである。全世界に教会は数え切れないぐらいに多く存在するが、御使いの数は『万の幾万倍、千の幾千倍』(黙示録5章11節)なのだから、教会に割り当てる御使いが足りなくて困り果てるということは起こらない。神はそのような不足の悲惨が起こらないようにと、御使いを非常に多くお造りになった。御使いが創造された理由の一つは、間違いなく、このように個々の教会を担当させるためであった。今、あなたの属している教会にも、神から割り当てられた担当者としての御使いが存在している。この『御使い』という言葉を、教会の牧師また長老だと解したい人もいるかもしれないが、私は少なくとも今の時点はそのようには見ていない。何故なら、新約聖書の中では、牧師や長老が御使いだとは言われていないからである。新約聖書においては、そのような役職にある者を、その役職名の通りに記すのが常である。もしこれが牧師や長老だったとすれば、新約聖書の書き方に逸れないように、その役職名の通りに記されていたはずである。「○○○にある教会の長老に書き送れ」と。しかし、どうしてキリストはまず御使いたちに、それぞれの教会に告げるべきことを告げられたのであろうか。それは、その御使いたちを通して、それぞれの教会に告げられるべきことが告げられるためであった。先にも述べたように、キリストは御使いをご自身の召使いとされるお方であって、このようなことにおいても御使いたちをご自身の仲介者とされるのである。
『『右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。』
このような文章は、それぞれの教会に対して、その冒頭の箇所で例外なく書かれている。このように冒頭でいちいち書かれたのは、この文書の読者である聖徒たちが、7つのどの教会に対してもキリストが語っておられるということを、よく理解するためであった。この冒頭で言われているキリストの言われ方は、7つの教会のどれにおいても、それぞれ全体的には異なっており、一つの例外を除いては一致する部分が何もない。その例外とは、エペソとサルデスの箇所である。この2つの箇所では、どちらもキリストが『7つの星を持つ』(2:1、3:1)と言われている。また、その言われ方は、5つの部分を除けば、既に語られたことと同じである。その5つとは、すなわち、神の7つの御霊を持っておられるということ(3:1)、聖なる方(3:7)、ダビデのかぎを持っている方(同)、アーメンである方(3:14)、神に造られたものの根源である方(同)、という5つの部分である。これら5つの部分は、これまではまだ語られていないことであった。このキリストの言われ方と、その教会とは、何か関連があるのであろうか。つまり、「その教会」だからこそ、その冒頭部分で、「その教会」に適合したキリストの言われ方がされているのであろうか。きっとそうに違いない、と思われる方がいくらかいるかもしれない。私もそのように思う。例えば、このエペソ教会に対する箇所の冒頭でキリストが『右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方』という言われ方をしているのは、『初めの愛から離れてしまった』(2章4節)エペソ人たちに、『悔い改めることをしないならば、わたしは、あなたのところに行って、あなたの燭台をその置かれたところから取りはずしてしまおう。』(2章5節)と言われたのと関連があるのは明らかである。つまり、これは「エペソ人たち、キリストは燭台の中を歩まれる方なのだ。その方が、あなたがたの燭台を取り外してしまってもいいとでもいうのか。もし嫌だというのならば、悔い改めるがよい。そうすれば、燭台の中を歩まれる方が、いつまでもあなたがたの燭台の中を歩んで下さろう。」ということである。他の教会に言われている箇所でも、やはり冒頭におけるキリストの言われ方と、その教会に対して言われていることの内容には、多かれ少なかれ何らかの関連性や一致が見られる。つまり、ヨハネは冒頭の部分において、7つの教会に対して、それぞれ意味もなくキリストの言われ方を変えたというのではない。そうではなく、ヨハネは意図的に、それぞれの教会に相応しい言い方をもってキリストの言い表わし方を変えたのである。だから、この冒頭におけるキリストの言われ方と、その教会に対して言われたことの内容には、一貫性がある。
【2:2~3】
『「わたしは、あなたの行ないとあなたの労苦と忍耐を知っている。また、あなたが、悪い者たちをがまんすることができず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちをためして、その偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して、わたしの名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。』
エペソ教会の聖徒は、その信仰の歩みにおいて、良い傾向を持っていたようである。彼らは、真面目であったと言ってよい。そこには、コリント教会のような酷い罪や恐るべき悪徳はなかったし、ガラテヤ教会のような異端も見られなかった。これは彼らに送られたパウロの手紙を見れば明らかである。であるから、主も、そのような面においては一定の評価をしておられる。では、ここで言われている労苦や忍耐は、どのようなものだったのか。それは、エペソの教会を悩ましていた悪しき者たちにかかわっている労苦や忍耐だったと考えられる。すなわち、そのような邪悪な者たちに引きこまれないようにするための忍耐や、またそのような者たちを撃退するために払った労苦のことではないかと思われる。この箇所から分かるのは、主がそのような労苦や忍耐を喜ばれ、評価されるということである。よって、エペソ教会に言われたことを聞いて、我々もそのような労苦や忍耐とは無縁でいないように求めていかねばならない。何故なら、パウロも言うように聖徒たちにとって『念願とするところは、主に喜ばれること』(Ⅱコリント5章9節)だからである。
エペソ教会の聖徒たちには、偽使徒の問題があったようである。ここでは『使徒と自称しているが実はそうでない者たち』という記述の前に『悪い者たち』のことが書いてあるが、偽使徒たちがこの『悪い者たち』であると解することができるし、そのように解さないことも可能である。そのように解さない場合、ここでは偽使徒たちと悪い者たちという別の2つの事柄が言われていると解することになる。キリストは、エペソ人たちがこの自称使徒たちに対抗したことを、ここで評価しておられる。再臨が間近に迫っている古い世の終末においては、このような偽者の使徒たちが聖徒たちの前に現われた。パウロもこのような偽使徒に煩わされた。このような偽使徒は、再臨が起きた後の時代においても、ちらほらと現われたようである。例えば、エイレナイオスと共にいた高齢の長老たちが会って話をしたというヨハネがそうである。エイレナイオスによれば、この高齢の長老たちは、老人になっていたヨハネと思われる人物がキリストから聞いたことを色々と話したということだが(※)、これは間違いなく偽ヨハネであった。既に述べたことだが、再臨と共に携挙されて地上からいなくなったヨハネが、どうして高齢になるまでこの地上にいたというのか。それはあり得ないことである。キリストが『人に惑わされないように気をつけなさい。』(マタイ24章4節)と言われたのは、このような偽使徒が終末の時期に現われるからであった。もしそのような者に惑わされてしまえば、聖徒たちは救いを失い、再臨されたキリストから非難されてしまうことにもなる。だからこそ、キリストが言われたように、聖徒たちは人に惑わされないように気をつけねばいけなかったのである。よって、ここで言われているように、エペソの聖徒たちが、滅びと混乱をもたらす偽使徒たちを試してその偽りを見抜いたことは、主の御心に適ったことであった。
(※)
このことはエイレナイオスの『異端反駁』第5巻に書かれている。
[本文に戻る]
ここで主はエペソ人たちのことを『知っている』と言っておられるが、これは主が、エペソ人たちの教会を、いつも見ておられることを示している。だからこそ、主は、エペソ人たちの様子をこのように詳しく語っておられるのである。もし、そうでなければ、主はどうしてこのように言えたであろうか。ここでキリストが言われたエペソ教会の様子は、一点の偽りも含まれていない事実であった。キリストは決して偽りを言われないお方だからである。それゆえ、この記述は、また2~3章に書いてある他の教会における記述は、初代教会の実情を知るためには超一級の資料となるものである。キリストの証言以上に確かな資料が他にあろうか。そのようなものはない。よって、初代教会の詳細を確実に知りたい読者は、この2~3章に書いてあるキリストの言葉を黄金の資料とするがよい。
【2:4~5】
『しかし、あなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それで、あなたは、どこから落ちたかを思い出し、悔い改めて、初めの行ないをしなさい。もしそうでなく、悔い改めることをしないならば、わたしは、あなたのところに行って、あなたの燭台をその置かれた所から取りはずしてしまおう。』
エペソ教会には、2~3節目で言われているように労苦と忍耐という美徳が見られたものの、非難されるべき点もあった。それは、信仰を持った当初の激しい愛が衰えてしまうという、肉の悪徳であった。このことは、パウロによる『エペソ人への手紙』の内容を見ても分かる。つまり、エペソ人のキリストに対する愛が衰えて悲惨な状態にあったからこそ、パウロは手紙の中でエペソ人にキリストの愛を思い起こさせ、そのようにしてエペソ人たちが再び神への愛に燃え上がるように書いたのである。すなわち、パウロはエペソ人にこう書いた。『こうしてキリストが、あなたがたの信仰によって、あなたがたの心のうちに住んでいてくださいますように。また、愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなたがたが、すべての聖徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに越えたキリストの愛を知ることができますように。』(エペソ3章17~19節)結婚した最初のうちは愛が激しく燃え上がっているのだが、数年も経つと愛の炎が多かれ少なかれ衰え弱まってしまうようになる夫婦は、世の中に少なくない。読者の方も、そのような夫婦を、今までに多く見てきたのではないかと思う。夫婦の愛とは、友情とは違って、努力したり保たれるように工夫しなければ、自然の傾向として衰えてしまうものである。キリストを夫として持つ妻であるエペソ教会の聖徒たちも、世の中の夫婦と同じように、初めに持っていた夫なる神への愛が失われてしまっていたのである。これは、非難されて当然のことであった。何故なら、キリストは全ての聖徒たちのために、ご自身の命をさえ惜しまずに犠牲にして下さったからである。それはエペソ教会の聖徒たちにおいてもそうである。そのような犠牲をもって救いを与えて下さったキリストに対する愛が失われてしまうというのは、あってはならないことである。また、神は律法の中で『心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。』(マタイ22章37節)と命じられた。このように神が命じられたのだから、エペソ人のように神への愛を激しく持たないのは御心に適わないことであり、罪である。だから、神に対する愛の炎が衰えていたエペソ人は、当然のこととして、このように非難されるべきであった。
このように非難されたエペソ人は、悔い改めて、当初の愛に復帰しなければいけなかった。ところで、命の恩人に対して、あたかも命を助けてもらわなかったかのように無礼な振る舞いをする人がいたとすれば、命の恩人はその愚かな人に対して何と言うであろうか。「あなたは私に命を助けてもらっておきながら、私に対して取るべき態度を取っていない。これは由々しきことである。あなたは、あなたの命を助けた私に対してもっと誠実に振る舞わなければならない。」などと言うのではなかろうか。もちろん人によっても言う内容は違うだろうが、このように言う人がいたとしても何も不思議ではないし、ネットで探せばどこかにこのように言った人が見つかるかもしれない。ここで悔い改めを求めておられるキリストは、命の恩人に対して無礼な振る舞いをした人にしっかりした態度を取るように謝罪と改善を求める人と似ている。キリストも聖徒にとっては命の恩人であるのだから、キリストがこのようにエペソ人に悔い改めを求めたのは当然のことであった。命を受けておきながら、その命を与えてくれた人に対して愛を持たなくなるというのがどれだけ非人道的なことであるかということは、少し考えれば誰でも分かることではないかと思う。なお、ここでキリストが言っておられるのは「勧告」ではなく、行なうべき義務を持った強制的な「命令」である。つまり、エペソ人たちは「絶対に」悔い改めなければいけなかった。
キリストはここで、もしエペソ人が悔い改めなければ『行って』、『燭台をその置かれた所から取りはずしてしま』う、と脅迫しておられる。この脅迫は、悔い改めさせようとして言われた「見せかけ」の言葉ではなかった。すなわち、エペソ人が悔い改めなければ、本当に脅迫した内容の通りのことが実現されることになっていた。キリストは、その言われたことを確実に実現させられるお方であって、単なる「見せかけ屋」ではない。『あなたがたのところに行って』とは、もし悔い改めなければ裁きが下されるであろう、ということである。すなわち、これはキリストが裁きにおいてエペソ人の所に行かれる、という意味である。『燭台をその置かれた所から取りはずしてしまおう。』とは、つまり、エペソ教会が御前から捨てられるということである。霊的に考えれば、そこに金の燭台が置かれているからこそ、そこはキリストの教会であると言える。すなわち金の燭台の存在は、霊的に捉えるならば、そこが真の教会であるという証拠また徴である。そのような教会の霊的なシンボルをキリストが取り外されるということは、そこが教会ではなくなり、『サタンの会衆』(2章9節)と化すことを意味する。したがって、ここでキリストは「もし悔い改めなければ、お前たちはサタンの陣営に捨てられるであろう。」と言っておられることになる。これは実に恐ろしい脅迫である。キリストはこのような戦慄すべき脅迫をすることで、エペソ人たちが悔い改めに導かれるようにと、ここで言っておられるのである。
【2:6】
『しかし、あなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行ないを憎んでいる。わたしもそれを憎んでいる。』
このニコライ派とは、使徒行伝6:5に書いてある『アンテオケの改宗者ニコラオ』の創始したグループである。ただ『改宗者ニコラオ』とルカが書いているように、創始者であるニコラオ自身は、既にヨハネが黙示録を書いている時にはニコライ派に属していなかった。このニコラオという人は、『御霊と知恵とに満ちた、評判の良い人たち7人』(使徒行伝6章3節)の一人に選ばれたほどの人であるから、改宗後は非常に敬虔に歩んだ人である。もちろん、彼の創始したグループは、この箇所でエペソ人とキリストから憎まれているように、ニコラオが抜け出てからも忌まわしい行ないをしていた。このニコライ派については、ペルガモ教会について語られている個所にも書かれている(2:15)。
ここで、このようなことが書かれていることに、少し違和感を持たれる方がいるかもしれない。何故なら、4~5節目の箇所で悔い改めよと言われたすぐ後で、急にエペソ人たちを褒めるかのような記述が出てくるからである。これは2~3節目の内容に組み入れたほうが違和感を感じないと思われる方もいるはずである。ここで急にこのようなことが書かれたのは、4~5節目で行なわれた脅迫によって生じるであろう畏怖の念を和らげるためであった。つまり、これは、エペソ人がその恐るべき脅迫のゆえに、キリストを拷問を加える奴隷主でもあるかのように感じないためになされた記述である。このようにして再びエペソ人を称賛するかのようなことを言えば、先になされた脅迫による衝撃が抑制され、キリストを無意味に、また過剰に恐れることもなくなる。これは、例えるならば遅刻ばかりする生徒に対して先生が、こう言うようなものである。「君はいつも遅刻ばかりしているが、次に遅刻した時にはもう容赦しない。その時には、全ての生徒の前で君の名前と遅刻の悪徳が言い表わされ、君は大いに恥を見ることになる。その時、君は死んでしまいたいと思うことになるだろう。/しかし、君が優秀であることを私は前から評価している。君は優秀な生徒なのだから、遅刻しないようにすることも出来るはずなのだ。こんなにも優秀なのに、どうして遅刻を改善できないはずがあるだろうか。」この先生が/で区切られた後の部分を言わなければ、この生徒は大いに先生を恐がることになっていただろうが、/よりも後の部分を言うのであれば、その先生に対する恐怖が抑えられるようにもなる。というのも、恐ろしいことを言われたすぐ後で、気を和らげることが言われたからである。エペソ教会に対するこの記述も、これと同じことである。しかし、ペルガモ教会の場合は、このような「和らげ」の言葉はない。この教会のほうは、エペソ教会とは違い、恐ろしいことを言われたら、ただそれきりであり、何も恐怖の発生を抑制させるような言葉が加えられていない。この違いはどういうわけなのか。それは、エペソの聖徒たちの場合、そのような「和らげ」の言葉がなければ、恐怖に圧倒されてしまうというのが理由でなくて何であろうか。またペルガモ教会の場合は、そのような工夫がなくても大丈夫だったというのが、その理由でなくて何であろうか。エペソの聖徒とペルガモの聖徒の精神状態や気質は同一ではなく、それゆえ、キリストから告げられるべきことも違っていたことは言うまでもない。だからこそ、エペソ教会に対しては「和らげ」の言葉があり、ペルガモ教会に対してはそのような言葉がないのである。
ここではニコライ派の人々の『行ない』が憎まれていることに、注意すべきである。悪い行ないを憎むことは、何も問題ないし、聖書ではそのようにすることが命じられている。すなわち、詩篇では神が聖徒に対して『悪を憎め。』(97篇10節)と命じておられる。もし悪を憎まなければ、その人は堕落しており、正義の敵である。そのような人は、正義である神に喜ばれることができない。つまり、我々は、ここでニコライ派の人たちそのものが憎まれているのではないことに、気付くべきである。ここで憎んでいるとキリストが言われたのは『行ない』であって、「人そのもの」ではない。『自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。』(マタイ5章44節)と言われたキリストは、ニコライ派の人々そのものは憎んでおられなかったのである。そうでなければ、主は、ご自身の言われたことに反することをされることになっていた。敵を愛せよと言われたキリストが、どうして敵を憎まれるであろうか。このお方は、ご自分を十字架につけた者らさえも愛されたのである。だから、エペソ人たちも、ニコライ派の人々自体は憎んでいなかったはずである。もちろん、エペソ教会の中には、ニコライ派の人そのものを憎んでいた者が、少しぐらいはいたことであろう(これはあくまでも推測の域を出ないが)。それは、その者が、「敵を愛せよ」という主の御言葉を知らなかったか、知っていたが忘れてしまったか、蔑ろにしていたからである。しかし、エペソ教会の中の主に従う聖徒たちであれば、確かにニコライ派の人々そのものを憎むことはしなかったはずである。要するに、これはよく言われるように「悪を憎んで人を憎まない」ということである。それだから、我々は、この箇所で『憎んでいる』と書かれていることを、何か不思議に思ったり、疑問に感じたりすべきではない。
【2:7】
『耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。』
これは、つまり『耳のある者は聞きなさい。』(マタイ13章43節)ということである。キリストは、福音書の中で言われたことを、この黙示録においても言っておられる。このように言われたのは、簡単に言えば「悟れる者だけが悟れ。」ということである。神は、ここで、あたかも次のように言っておられるかのようである。「これらの言説は、耳のある選ばれた者だけが分かればよいものだ。他の者たちは、読むには読むが、分からないままに留まればよい。真理とその理解は少数の者にだけ与えられるものなのである。」だから、『あなたがたは確かに聞きはするが、決して悟らない。』(イザヤ13章14節)というイザヤの預言で言われたことは、この黙示録においても当てはまる。耳のない者にとって、この黙示録で言われていることは、理解できないことばかりである。この文書を受けた紀元1世紀の聖徒たちは、恐らく、この黙示録で言われていることを、よく理解できたのではないかと私は推測する。つまり彼らの大部分は『耳のある者』であった。何故そう推測するかといえば、この文書を受けた当時の人たちは、ヨハネと同じ時代に生きており、ヨハネと同じ時代感覚や認識の幅また常識を持っていたはずだからである。だから、ヨハネが言ったことに対して「ああ、これはこういうことなのだな。」などと思えたに違いない。しかし、紀元1世紀以降の聖徒たちは、この黙示録をまったく理解できていない。つまり、紀元1世紀以降の聖徒たちは、黙示録の領域においては完全に『耳のない者』である。誰も彼もこの黙示録を正しく読めていなかったということは、私がここまで書いた内容を読めば、よく分かるはずである。だから、今までに存在した聖徒たちにとって、この文書は謎に満ちており、どうあがいても誤謬と無知と混乱の闇に留まるしかなかった。
ここでヨハネは「御霊が言われることを聞け」と書いているが、これはキリストが言われたことではなかったのか、という疑問を持つ人がいるかもしれない。確かに、2:1の箇所では、これがキリストの言われたことであると書かれていた。一体どうして、キリストが言われたことなのに、御霊が言われたことになっているのであろうか。この疑問を解決するのは難しくはない。つまり、これは、キリストが御霊において言われたものだということである。御霊の御思いと、キリストの御思いとは、まったく同じであり、それゆえそのお語りになられることも完全に一致している。何故なら、三位は3つあろうとも、その三位はすなわち一人の神だからである。それぞれの位格の御思いとその語られることが矛盾するということはあり得ない。だから、キリストが御霊において言われたことは、御霊ご自身が言われたことでもある。よって、ヨハネがこのようにキリストの言葉を御霊が言われたこととして記しているのは、何もおかしいことではない。すなわち、これはキリストの言葉であると同時に、御霊の言葉でもあるのである。
ここで言われている言葉は、それぞれの教会に対し、その箇所の最後の部分で例外なく言われている(2:7、11、17、29、3:6、13、22)。しかし、どうして7つの教会に対して、いちいち最後の部分でこのように言われたのか。それは、どの教会に対する言説も、その教会だけでなく、その教会以外の全ての教会にも語られているということを、聖徒たちによく分からせるためであった。このように、いちいち末尾で「…聞きなさい。」などと言われたら、誰でもこれがあらゆる教会に与えられた言説だということに気付くことができる。経験も証するように、我々人間の精神は弱くて鈍く、何度も繰り返して言われなければ気付けなかったり、理解できなかったりすることが多い。人間とその精神の造り主である神は、もっともそのことをよく知っておられるお方である。だからこそ、神は、聖徒たちにこのことを気づかせるべく、このようにいちいち同じことをそれぞれの箇所の最後で書き記すようにされたわけである。
『勝利を得る者に、』
『勝利を得る』とは、つまり再臨の起きる日までキリストに留まり続けて信仰の道を全うする、という意味である。それは2:26の箇所で、『勝利を得る者』と言われてから、『また最後までわたしのわざを守る者』と言われていることから分かる。つまり、勝利者とは、最後までキリストの信仰を持ち続ける者ということである。我々は、この言葉を肉的に捉えるべきではない。しかし、どうして最後まで信仰者として歩み続けることが、勝利することなのであろうか。それは、その人を、サタンも罪も肉も死も地獄も屈服させることができなかったからである。これらのようなものに屈服させられないというのは、つまりこれらのようなものに打ち勝つということだから、すなわち『勝利を得る者』ということになる。世の中では、よく誘惑や攻撃に悩まされている不幸な人に対して「いいか、絶対に打ち負けては駄目だぞ。」などと言われるものである。この不幸な人が最終的に誘惑や攻撃に屈しなかったことが示されると、周りの人たちは、その不幸な人について「彼は最後まで屈服することがなかった。」などと言って、その人を勝利者扱いする。実際、彼は屈服しなかったことにより、事実上の勝利者となったと言えよう。7つの教会の聖徒に対して『勝利を得る者に』などと言われているのも、つまりは、それと同じことである。
このエペソ教会や他の6つの教会には『勝利を得る者に』と言われているが、このように言われているからといって、聖徒たちが自らの力で勝利を獲得できるなどと考えるべきではない。ヨハネは『人は、天から与えられるのでなければ、何も受けることはできません。』(ヨハネ3章27節)と言った。パウロも『あなたには、何か、もらったのでないものがあるのですか。』(Ⅰコリント4章7節)と言っている。このように聖書では教えられているのだから、聖徒たちが勝利できるのは、聖徒たち自身の力のゆえではなく、神から貰い受けた恵みのゆえであると考えなければいけない。では、どうして黙示録の中では聖徒たちが自分自身の力によって勝利できるかのように言われているのか。この疑問に対しては、「これは実際的な現象面から言われた言い方に過ぎない。」と答えることができる。つまり、究極的に言えば聖徒が勝利できるのは神の恵みのゆえなのではあるが、実際的な現象面に基づいて言えば、「聖徒たちが勝利を得る」という言い方をすることも不可能ではないのである。これはパウロが自分について『使徒となったパウロ』(ガラテヤ1章1節)と言ったのを考えても分かる。パウロはこの箇所で「私は使徒になったのだ。」とあたかも自分自身から使徒になったかのように言っているが、しかし究極的に言えば、パウロが使徒となったのは神が恵みによりパウロを使徒として召されたからに他ならない。パウロは当然ながらこのことをよく理解していたので、『使徒となったパウロ』と言ったすぐ後で、『―私が使徒となったのは、人間から出たことでなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストと、キリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によったのです。―』という言葉を付け加えている。我々も「自分がこれをした。」などと言うことが多くあるが、それが良いことであれば、そのようにできたのは自分の力によるというよりは神の恵みによりそのようにできたのだということを決して忘れてはならない。栄光と良きものを神に帰さない者は、神の怒りを買い、呪われ、不幸に陥る。
『わたしは神のパラダイスにあるいのちの木の実を食べさせよう。」』』
最後まで信仰を保ち続けた勝利者は、神のパラダイスに導かれ、そこにあるいのちの木の実を食べることができる。これは、大変魅力的で素晴らしい約束である。『神のパラダイス』とは、天国のことを指す。『いのちの木の実を食べさせよう。』とは、つまり聖徒たちの永生のことを言っている。この天国といのちの木のことは21~22章の箇所で詳しく書かれている。この2つのことについては、その時が来たら、また詳しく論じることにしたい。この木が果たして実際的なことを言っているのか、それとも象徴的な意味で言われているのか、ということについても、まだ論じないでおく。何故なら、そのことは、ここで論じるよりも21~22章の箇所で論じたほうが、より適切であり、また秩序に適っているからである。パウロもⅠコリント14:40の箇所で、『ただ、すべてのことを適切に、秩序をもって行ないなさい。』と命じている。
我々は次のことに注意しなければいけない。すなわち、この約束は、既に、しかも遥か昔の時代に、成就しているということである。つまり、この約束が与えられた紀元1世紀のエペソ人たちは、既に天国に行って、そこにある素晴らしい木の実を食べ、今もそれを食べ続けている。何故こう言えるかといえば、御霊はこの約束の箇所も含めて、黙示録で言われていることは『すぐに起こるはずの事』(1:1)と言われたからである。もしこの約束が、ヨハネの時代に生きていたエペソ人たちにとって『すぐに起こるはずの事』でなかったとすれば、神はヨハネを通して偽りを言われたことになってしまう。そんなことがどうしてあるであろうか。聖徒である読者は、御霊の言われたことに言い逆らったり、不信仰になったりしないようにせよ。もう一度言うが、この約束はこの約束が告げられたエペソ人にとって『すぐに』実現されたことだったのである。すなわち、キリストの再臨が起きた紀元68年6月9日に、この約束が彼らに果たされた。その日、エペソ人たちは―エペソ人だけでなくその他の全ての聖徒たちも―、再臨されたキリストにより神のパラダイスなる天国に引き上げられ、そこで素晴らしい実を食べた。神の子である聖徒たちは、このように、この箇所を理解しなければいけない。何故なら、これこそが、この箇所における正しい理解だからである。
しかしながら、この約束は、紀元1世紀のエペソ人たちだけでなく、それ以降の時代に生きる全ての聖徒たちにも言われているものである。何故なら、この約束は、普遍的なものであって、時代を問わない内容だからである。紀元1世紀当時のエペソ人たちだけでなく、あらゆる聖徒たちは、最後まで信仰を保って勝利者となるならば、ここで言われている通りの恵みを受けられる。すなわち、その者は、神のパラダイスである天国に入れられ、そこにあるいのちの木から実を取って食べることにより永遠に生きられるようになる。しかし、最後まで信仰を保たない者は、勝利者ではないから、そのような恵みは決して受けられない。実に、天国とは勝利者だけが入れる場所なのである。パウロが言うように『神の御霊に導かれる人は、だれでも神の子ども』(ローマ8章14節)であって、その人は必ず勝利者となる。何故なら、神の子は、必ず勝利するようにと定められているからである。それゆえ、神の御霊によって歩む勝利者となるべき者は、神に感謝すべきである。その人は、やがてここで言われている約束の恵みを受けられるようになるのだから。
さて、このエペソ教会に語られている2:1~7の箇所だけでなく、2~3章の中では、どの教会に語られている箇所でも、聖徒たちが『あなた』と言われている。つまり、聖徒たちの呼ばれ方は単数形であって複数形ではない。このことを疑問に感じる方がいるかもしれない。「キリストはどうして多くの聖徒たちに対して、聖徒たちが大勢いるにもかかわらず、あたかも一人しかいないように『あなた』と呼びかけておられるか?」と。確かに、普通に考えれば、聖徒たちは多くいるのだから、「あなた」よりは「あなたがた」と言われたほうが適切であると感じられるかもしれない。日常の場でも、複数の人に対しては「あなたがた」などと言われる。この疑問は契約のことを考えれば、簡単に解決できる。エペソ教会であれ他の教会であれ、そこには多くの人々がいるが、契約的に見ればそれは一人であると捉えることができる。だから、多くの人々を持つ教会に対しては「あなたがた」と言うことができるだけでなく、契約的な意味においては『あなた』と単数形で言うことも可能である。これは、多くの社員を抱える企業が、実際的には多くの人数がいるのではあっても、法人格としては単体的に取り扱われるのと同じことである。神は契約的に何かを取り扱われるお方であるから、ここで多くの聖徒たちに対して『あなた』と単体的に呼びかけておられるわけである。だから、我々は、ここで多くの聖徒が一人でもあるかのように見做されていることに驚いたり、戸惑ったりすべきではない。契約的に考えれば、これは何もおかしな表現ではないのである。なお、このような例は、旧約聖書の中でも見られる。旧約聖書の多くの箇所で、神は、イスラエル人たちを『あなた』とか『お前』などと言って、あたかも単体者であるかのように取り扱っておられる。これも上に述べたのと同じで、イスラエル人たちは実際的な意味においては数十万人もいたのではあるが、しかし契約的な意味においては神の御前に一人の単体者として存在していたがゆえであった。だから、旧約聖書ではイスラエル人に対し、ある時は『あなた』と言われ、ある時は『あなたがた』と言われている。
【2:8】
『また、スミルナにある教会の御使いに書き送れ。『初めであり、終わりである方、死んで、また生きた方が言われる。』
ここでのキリストの言われ方は、非常に生き生きとしており、その生命感が、すなわち死にも屈されずに真に生きておられるという生の躍動感が、前面に押し出されている。この言われ方は、既に1:17~18の箇所で言われていた言い方である。エペソ人に対するキリストの言われ方はエペソ人に相応しいものであったが、このスミルナ人に対しても、やはりスミルナ人に相応しい言われ方がされている。一体どうしてスミルナの聖徒には、このようにキリストが生命感ある言い方で言い表わされたのであろうか。それはすぐ後の10節目を見れば分かるように、スミルナ人たちには、死の試練が間近に迫っていたからである。すなわち、スミルナ人には、死による信仰の試みが襲い掛かることになっていた。キリストは、そのような運命が待ち受けているスミルナ人たちに備えを与えようとして、彼らが生命そのものであられるご自身に固着するようにと、ここでご自身を『初めであり、終わりである方、死んで、また生きた方』などと言い表わすように命じられたのである。そのようにしてスミルナ人が生命の主であるキリストに固着できたならば、キリストが永遠に生きておられ、また死んだにもかかわらず復活して再び生きられたということに基づき、自分たちもそのようにキリストにおいて永遠に生きられるということがよく分かる。そのようなことが分かれば、自分たちもキリストのように永遠に生きられることが分かっているのだから、やがて訪れることになる死の試練を恐れることもなくなる。それどころか、中には、死ぬことを喜ぶ者さえいるはずである。キリストは、これから苦難が待ち受けているスミルナ人たちのことを思って、このように聖徒たちがご自分に固着することができるような言い方をされたわけである。これは分かりやすく言い換えれば、こういうことである。「スミルナの聖徒たちよ。あなたがたはこれから死の試練を受けることになるが、しかし、あなたがたは私と共に永遠に生きるのだということを忘れてはならない。たといあなたがたが死んだとしても、私が死んでまた生きたのと同じように、あなたがたも再び生きるようになるのだから。だから、あなたがたはそのことを覚えて、これから受けることになる苦しみを恐れたり、私に対する信仰を捨てたりしてはならない。」このようなことが言われていることが分かったスミルナ人たちは、非常に励まされたのではないかと私には思える。
【2:9】
『「わたしは、あなたの苦しみと貧しさとを知っている。―しかしあなたは実際は富んでいる。―』
スミルナの聖徒たちには、苦しみと貧しさとがあった。この苦しみとは、恐らく、すぐ後に書かれている『サタンの会衆』による口撃だったのではないかと思われる。この箇所を見る限りでは、そのように考えたとしても何もおかしくはないが、しかし、これが他の苦しみのことを言っている可能性も、もちろんある。他の苦しみの場合、我々は、その苦しみがどのようなものであったか知ることは難しい。というのも、聖書では、何もそのことについて書かれていないからである。『貧しさ』とは、文字通りの貧しさ、すなわち物質的な困窮のことであろう。神は、貧しい人にこそ心を留められ救いに導かれるのだから、スミルナ人たちが貧しかったとしても、それは自然なことである。しかしながら、そのような貧しいスミルナ人に対して、キリストは『実際は富んでいる。』と言われる。これは一体どういうことか。これは、つまり霊的なことである。パウロは、『キリストのうちに、知恵と知識との宝がすべて隠されている』(コロサイ2章3節)と書いている。スミルナの聖徒たちは、宝に満ちたこのようなお方を、神の恵みにより持っていた。霊的に考えるならば、御子を自分のうちに持つことは、あらゆる物を持ち、豊かに富むことも等しい。だからこそ、キリストは霊的な意味においてスミルナの聖徒が『実際は富んでいる。』と言われたのである。よって、スミルナの聖徒は―スミルナの聖徒だけでなく他の全ての聖徒も―、霊的に言えば、どのような金持ちよりも富んでいることになる。万物の所有者であられるキリストを持つこと以上に富むことが、何か他にあろうか。
このように言われるのは、スミルナ人にとっては、非常に幸いなことであった。何故なら、間もなく終末の悲惨が訪れるこの時期にあって、キリストが自分たちのことをご覧になっておられるということを知らされたならば、慰めと励ましとが与えられるからである。キリストは、人とその心をお造りになられた神であられる。このキリストは、ご自身の造られた人であるスミルナ人たちに対して言うべきことを、完全に弁えておられた。だからこそ、このように心を良くする言葉を語ることができたのである。これは、例えるならば、ある高貴な王侯がこれから大変なことが起こることになっている人々の前にやって来て、「私はあなたがたのことを、いつもニュースで見ており、心に思っています。」などと言うようなものである。そうするとこのように言われた人々は感動したり感謝したりするであろうが、ここでキリストが言われたのも、それとよく似ていると言える。
『またユダヤ人だと自称しているが、実はそうでなく、かえってサタンの会衆である人たちから、ののしられていることも知っている。』
この自称ユダヤ人はスミルナ人たちの敵である。この敵は、真正なユダヤ人ではない。その敵は『ユダヤ人だと自称している』に過ぎないからである。またこの敵は、神の子らでもない。何故なら、その敵は『サタンの会衆』と言われているからである。しかし、これは一体どのような者たちだったのであろうか。聖書には詳しく書かれていないから、確定的なことは何も言えない。しかし、これが忌まわしい腐敗した存在だったということだけは間違いないことである。聖徒をののしるということは、すなわち神をののしることも同じなのであるから。
ここで言われているように、スミルナ人たちは、サタンの会衆に属する者たちから、口による攻撃―ののしり―を受けていた。つまり、スミルナの教会には迫害があった。キリストの聖徒たちにこのような口による迫害がされるのは、何も珍しいことではない。その聖徒たちが敬虔に歩んでいれば、確かに、それは珍しくないし、それどころか「必然的なこと」であるとさえ言える。何故ならパウロも言うように、『確かに、キリスト・イエスにあって敬虔に生きようと願う者はみな、迫害を受け』(Ⅱテモテ3章12節)るからである。敬虔と迫害とは切っても切り離せない関係にある。このことから、ののしりという迫害を受けていたスミルナ人たちが、敬虔に歩んでいたということが分かる。教会とはサタンにとって敵対勢力であり、攻撃対象の一つである組織である。神がサタンに許可を出されると、サタンは神の許可の範囲内において、教会に攻撃を加えることが可能となる。それは、ヨブ記の内容を通して我々が既に知っている通りである。このスミルナ人に対しても神からの許可がサタンに出されたからこそ、サタンは自分の支配する子らに働きかけ、その子らを通してスミルナ人をののしることができた。その子らは、ここで『ユダヤ人だと自称している』と言われているが、これは実にサタンの子らしい振る舞いである。というのも、サタンはⅡコリント11章で書かれているように、変装の名人であり、変装を好むからである(※)。つまり、サタンとは「なりすましの父」である。このサタンがなりすましを常套手段とするように、その子らも、自分たちがユダヤ人でないにもかかわらずユダヤ人であるかのようになりすましていた。「子はその父に似る」という言葉は真実である。もっとも、キリストの前においては、そのような擬装は何の意味も持たなかったのであるが。
(※)
『しかし、驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。ですから、サタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても、格別なことはありません。』(Ⅱコリント11章14~15節)
[本文に戻る]
【2:10】
『あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ。悪魔はあなたがたをためすために、あなたがたのうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなたがたは十日の間苦しみを受ける。』
キリストは、スミルナの聖徒が、これから苦しみを受けることになると予告する。その苦しみとは、悪魔による試みであり、牢獄に投げ込まれることであり、10日の間続くものであった。この節では『死』について言われているから、この苦しみにより、死ぬ人が多かれ少なかれ出たはずである。この悪魔による苦難は、前節に出てきた『サタンの会衆である人たち』を通してのものだと私は考える。というのも、そのように解するのが、文脈を考慮すれば自然だからである。この悪魔による苦難の時、スミルナの聖徒たちの信仰が問われた。スミルナの聖徒たちが真の信仰を持っていれば、苦難に屈することもなかったであろう。しかし偽りの信仰を持っていたのであれば、多くの者が脱落したはずである。このことについて、実際はどのような結末に終わったのか、我々には分からない。神はどうしてサタンによる試みをお許しになられたのか。それは、この試みにより、スミルナ人の持つ信仰がどのようなものか顕わになるためであった。すなわち、神は既に試みが与えられる前からスミルナ人の信仰を完全に知っておられたが、このスミルナ人たちの信仰を、スミルナ人と他の者たちがよく知るようになるために、このような試みに許可を出されたのである。何故なら、このような試みがあれば、その試みによってスミルナ人の信仰における真実が明らかになるからである。それは、試練を受けたアブラハムがイサクを捧げたことにより、このアブラハムの信仰が、アブラハムとその他の人たちに対して顕わにされたのと同じことである。神は、このように聖徒たちに試練を与えることで、隠されていたことが明らかになるようにされる。
キリストはここで『苦しみを恐れてはいけない。』と言われる。これは勧めではなく命令である。この箇所で言われている苦難においては、スミルナ人たちの最終的な運命がかかっていた。もし恐れたために信仰から外れてしまったならば、スミルナ人たちは御国を継ぐことができなかった。つまり、永遠の地獄に投げ落とされてしまう。キリストがスミルナ人たちに信仰を与えたのは、もちろん彼らが御国を継ぐことができるようになるためであった。言うまでもなく、スミルナ人たちが御国を継げなくなるようなことがあってはならない。だからこそ、キリストはここで『恐れてはいけない。』と命じ、スミルナ人がしっかりと最後まで信仰に留まるように計らって下さったのである。なお、この『恐れてはいけない。』という命令は、聖書の全体で命じられている普遍的な命令であって、この箇所だけで特別的に言われているというのではない。
『死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば、わたしはあなたにいのちの冠を与えよう。』
スミルナ人たちは、死に至るまでもキリストに留まり続けるならば、『いのちの冠』を受けることができた。この『いのちの冠』とは、すなわちキリストにある永生を意味している。つまり、これは永遠に生き続けられるということを象徴的に言い表わしている。これが象徴的な意味だけではなく、実際上のことも言っていると考える人がいるかもしれない。すなわち、天国においてスミルナ人たちの頭には本当に物質的な『いのちの冠』が乗っていると。しかし、これが実際上のことを言ったものだとは私には思われない。何故なら、聖書の他の箇所では、そのようなことが言われていないからである。今現在の私の場合、これはキリストの口から両刃の剣が出ているという記述と同様に、象徴的な言い方がされているに過ぎないものだと考えたい。このような約束を言われたスミルナ人たちは、大いに強められたのではないかと思われる。何故なら、このように言われたならば、もし死んでも永遠に生き続けられるようになるということを強く思えるようになるから、死を恐れなくなるからである。死が永生への入口だと認識している者が、どうして死を恐れることがあるであろうか。人の精神を造られた神は、スミルナ人たちがどのようなことを言われたら苦難に耐えられるようになるかということを、完全に知っておられたのである。
我々は、この約束が、紀元1世紀以降の時代に生きる聖徒たちに対しても言われたものであると受け取らねばならない(※)。というのも、この約束は普遍的なものであって、時代的な制約を持たないからである。我々も、死に至るまで忠実であれば、ここで約束されている通りに、いのちの冠を得ることができる。
(※)
私の以前いた教会の礼拝堂には、この聖句を記した額が掲げてあった。このようにして、この聖句が自分たちにも言われていると受け取るのは、正しいことである。もっとも、当時そこにいた人たちは、誰も黙示録のことをよく理解できていなかったのではあるが。
[本文に戻る]
【2:11】
『耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者は、決して第二の死によってそこなわれることはない。』
『第二の死』という言葉は、黙示録だけに出てくる言葉であり、黙示録ではここで初めてこの言葉が出てくる。この言葉は、この箇所を含めると、黙示録では全部で4回でてくる(2:11、20:6、20:14、21:8)。これは既に説明されたように、4000年間続いた第一の死に取って代わる新しい形の死である。この死においては、魂だけが苦しみの状態に投げ込まれることはなく、魂も身体も共に苦しめられることになる。この『第二の死』については、かなり後になってから、再び説明することにしたい。というのは、そのようにしたほうが、作品の流れとしては適切だからである。
キリストは、スミルナ人たちが、もし最後まで信仰を保って勝利するならば、この恐るべき死を受けることは決してないと約束された。何故なら、勝利して天に凱旋する者たちに、この死は何も効力を持たないからである。このような約束をキリストから受けたスミルナ人たちは、幸いであった。何故なら、この黙示録が送り届けられた時代は、古い世における終末の時代であって、またそれだけでなくスミルナ人たちには『サタンの会衆』(2章9節)による苦難が待っていたからである。この約束を受けたスミルナ人たちは、もし彼らがその約束を真に確かなものとして受け取ったのであれば、死の苦難を恐れることはなかったはずである。自分たちが『第二の死』により損なわれないと本当に信じていたのであれば、死の向こう側には希望と生命と安息と喜びと幸いとがあるということもよく分かるからである。だから、スミルナ人たちは、むしろ恐れるどころか喜んで死を甘受したということも十分に考えられる。今までに出た多くの殉教者たちは、実に、自分たちが死んでも第二の死によって損なわれないと信じていたからこそ、平安と喜びのうちに死んでいったのである。
この約束も、先に見たエペソ人への約束と同じように、既に成就している。すなわち、勝利する者たちが確定する紀元68年6月9日に、この約束は完全に成就された。何故なら、黙示録で書かれていることは、何度も述べているように『すぐに起こるべき事』(22章6節)だからである。この箇所における約束も、当然ながら『すぐに』起こることであり、それは紀元1世紀に起こることであった。
また、この約束は、エペソ人に対する約束と同じように、紀元1世紀以降の時代に生きる全ての聖徒たちにも言われていると捉えなければいけない。これも、やはり普遍的な内容を持つ約束だからである。今の時代に生きる我々は、勝利の道を歩み続けるならば、やがて完全な勝利者となり、もはや第二の死によって損なわれることのない状態に至る。それゆえ、第二の死により損なわれたくないと思う聖徒は、今歩んでいる勝利の道を変わることなく歩み続けるがよい。もし勝利の道から外れて敗北者となるのであれば、勝利者として天に凱旋することもできず、第二の死により永遠に損なわれることになるであろう。
【2:12】
『また、ペルガモにある教会の御使いに書き送れ。『鋭い、両刃の剣を持つ方がこう言われる。』
ここでは、どうしてペルガモ教会に、このようなキリストの言われ方がされたのか。これも、やはりペルガモ教会に相応しいキリストの言われ方となっている。キリストがペルガモ教会に対してこう言われたのは、2:16に書いてあるように、もしペルガモ人たちが悔い改めなければ、キリストが剣をもって襲い掛かってくることになっていたからである。ペルガモ人が悔い改めるためには、キリストが剣を持った力ある裁き主であるという認識を持ち、キリストに敬虔な恐れが抱かれる必要があった。何故なら、往々にして「恐れ」とは悔い改めをもたらすからである。―多くの人は地獄における神の刑罰を恐れるがゆえに信仰に入るのである― ペルガモ人たちは悔い改める必要があったので、キリストに対する恐れから悔い改めに進めるようにと、キリストがこのような言われ方をしている。このようにキリストが言われたら、それだけキリストが恐れられることになるのは明らかであろう。剣を持っておられる方を恐れない者が、誰かいるであろうか。―それでは、もしペルガモ人たちに悔い改める必要がなければ、キリストがこのように言われることはなかったのか。―その通りである。その場合は、キリストが他の言い方をもって言われていたはずである。 なお、このキリストの言われ方は、既に1:16の箇所で言われていたことである。
【2:13】
『「わたしは、あなたの住んでいる所を知っている。そこにはサタンの王座がある。』
『サタンの王座』とは、そこにサタンの支配が強く働いていることを意味している。ペルガモは、あたかもサタンが王として君臨する「サタン国」とでも言うべき地域だったからこそ、このように言われている。21世紀の今で言えば、サウジアラビヤやイラクをはじめとしたイスラム教の国家が、そうである。このような国にはサタンがイスラム教という自分の宗教を使って無数の人々を支配しているので、そこにいる人々はキリストを信ぜず、敵視し、無視し続けている。だから、そのような所には教会も少ないし、伝道も非常に行ないにくい。このようなイスラム教の国家は、ペルガモと同じように、『サタンの王座がある』とか「サタンが住んでいる」などと言われるべき所である。もちろん、ペルガモであれイスラム教の国であれ、サタンの王座がそこにあるとは言っても、キリストがその上におられるということを、我々は忘れてはならない。もしキリストが働きかけられたならば、すぐにもサタンはそこからどかされてしまうのだ。サタンがそこで支配できているのは、神がご自身のご計画を遂行するために、サタンの王座が据えられることを許可しておられるに過ぎない。これは、エジプト人がユダヤ人を支配することを神が許しておられたのだが、時が来たので、すぐにもユダヤ人がエジプト人から解放されることになったのを考えれば、よく分かるのではないかと思う。つまり、エジプト人にせよペルガモを支配していたサタンにせよ、究極的な支配者だというのではなく、ただ神により道具として使われているだけなのである。
『しかしあなたは、わたしの名を堅く保って、わたしの忠実な証人アンテパスがサタンの住むあなたがたのところで殺されたときでも、わたしに対する信仰を捨てなかった。』
この『アンテパス』なる人物の詳細は、我々には不明である。一つ言えるのは、この人物が、キリストに選ばれた真の聖徒だったということである。我々は、やがて天国に行った際に、この聖徒のことを知れるようになるであろう。既に見たように、黙示録は直接的には紀元1世紀のアジヤにある教会に届けられた文書であるから、このような我々にとっては知ることのできない当事者性の強い箇所があったとしても、何も驚くには当たらない。ヨハネは、後世の聖徒たちを考慮して、この文書を記す責任を何も負っていなかったのだから。
真の信仰を持っていない者は、仲間であったり身近にいたりする聖徒が酷い目に会わされると、それを見て、キリストから離れてしまう。自分も、同じ酷い目に会わされるのではないかと思ってしまうからである。たとえ実際は苦しまなかったとしても、苦しむかもしれないというその可能性が恐怖をもたらし―それが僅かな可能性であったとしても―、信仰の道から外れるようになる。その人は真の信仰を持っていないので、苦しむかもしれないという可能性だけであっても、その人が信仰から離脱してしまうのには十分なのである。これは、まだ真の信仰を持てていなかったあのペテロがそうであった。我々が既に知っているように、ペテロはキリストが捕らえられた際、自分も酷い目に会うのではないかと恐れ、キリストを3度も否んでしまった。しかし、このペルガモ人たちは、そうではなかった。だからアンテパスが殺されたのを見ても、恐れを抱いて信仰から離れることをしなかった。これはペテロが恐れのゆえにキリストを否んだのとは大違いであった。このペルガモ人たちは、真の信仰を持てていた、すなわち神から真の信仰を与えられていた。そうでなければ、彼らもペテロのように惨めな様を見せていたことであろう。このようなペルガモ人たちの信仰を、ここでキリストは評価しておられる。このような信仰は、主に喜ばれる、御心にかなった信仰である。このペルガモの聖徒には、スミルナの聖徒のように『恐れてはいけない。』(2:10)と言われる必要はなかった。何故なら、既にアンテパスの件により、ペルガモ人たちが恐れることのない者たちであるということが証明済みだからである。彼らは、自分の命よりもキリストに対する信仰を優先させる人たちであった。
【2:14~15】
『しかし、あなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちに、バラムの教えを奉じている人々がいる。バラムはバラクに教えて、イスラエルの人々に、つまずきの石を置き、偶像の神にささげた物を食べさせ、また不品行を行なわせた。それと同じように、あなたのところにもニコライ派の教えを奉じている人々がいる。』
ペルガモ人は恐れを抱かないという点では良かったが、しかし非難されるべき点もあった。それは、ここでキリストが言っておられるように、ペルガモ教会の中にニコライ派の教えに迎合している人たちがいたことである。それではペルガモ教会の中で、一体どのぐらいの人数が、ニコライ派の教えを奉じていたのであろうか。これは具体的には分からないが、それなりに多くいたのではないかと考えられる。このことは、黙示録の中において、エペソ教会に対しても、このニコライ派のことが言及されていることからも、そうだと言える。つまり、当時のアジヤにおける西側の地域には、ニコライ派の存在がかなり目立っていたということである。そのニコライ派という名の大風に、ペルガモ教会にいた者たちも巻き込まれてしまっていたのである。そうでなければ、つまりこの派が取り立てて言及するほどには目立っていなかったのであれば、ここで、このように言われることもなかったのではないかと私には思える。
しかし、どうしてニコライ派の教えを奉じている人たちを教会に抱えていることが、悪かったのであろうか。それはニコライ派的な人たちがバラム的な邪悪さを持っていたからであった。キリストもここで言っておられるように、バラムはイスラエル人たちを惑わして、罪に迷いこませた。これは実に忌々しきことである。何故なら、神はご自身の民が罪から離れて、義に歩むことをこそ望んでおられるからである。バラムは、その逆をイスラエルに行なわせた。ニコライ派もこのバラムと同じように、聖徒たちを惑わして、罪に迷いこませていた。これは明らかに御心に適わないことである。だからこそ、キリストはここでそのニコライ派の者たちのことについて、非難しておられるのである。これは絶対に非難されるべきことであった。それは例えるならば、ある王族の少年に、柄の悪い不良たちが悪いことや法に違反する犯罪行為や夜の遊びをさせるようなものである。このようなことが発覚したら、王室や国や国民は、その不良に対して大きな怒りを発するに違いない。何故なら、それはあってはならないことだからである。神という王の子らであるペルガモ人たちをニコライ派の教えを奉じている不良どもが惑わして罪に陥れていたのは、これと非常によく似ている。
【2:16】
『だから、悔い改めなさい。もしそうしないなら、わたしは、すぐにあなたのところに行き、わたしの口の剣をもって彼らと戦おう。』
このような状態が見られたペルガモ教会の聖徒たちに、ここでキリストは悔い改めを命じておられる。しかし、ニコライ派的な者を教会に抱えていることについて悔い改めるとは、一体どういうことなのか。すなわち、キリストはここで、どのようなことを悔い改めるようにと言っておられるのか。それは、ペルガモ教会にいたまともな聖徒たちが、自分の周りにいたニコライ派的な者たちを、その者たちがニコライ派的であると知りながらも放置し続け、追い出さなかったということである。このような者たちは、教会に悪い影響を及ぼす言わば腐敗したペストのような存在であるから、絶対に追い出さなければいけなかった。もしそうしなければ、パン種が膨らむように、また種がどんどんと大きくなるように、ペルガモ教会を汚染してしまうことになる。実際はどうだったのか知る術がないのだが、もしかしたら既に汚染されていたということもあり得る。しかし、ペルガモ人たちは、追い払うべき彼らを追い払わないままでいた。これは明らかに罪であり、御心に適わないことであった。だからこそ、ここでキリストは、この件について悔い改め、ペルガモ教会にいた追い出すべき者たちを追い出すようにと語っておられるのである。しかし、どうしてこれが「罪」だと言えるのか。邪悪な者たちを追い払わないのが罪であると、はたして聖書から言えるのであろうか。「然り」と私は言う。聖書によれば、罪は律法によって判断される(※①)。ニコライ派的な者たちはペルガモ教会にいたまともな聖徒を、神から遠ざけて霊的な不品行に陥らせていたのだから、彼らを除外しないで放置し続けるのは、明らかに申命記13章の律法に違反している。旧約聖書を見れば分かるように、この申命記13章の律法では、神から聖徒を引き離そうとする邪悪な者たちを殺して除外するようにと命じている―それがたとえ兄弟や子や愛妻や親友であっても―。旧約時代においてはこのような者たちが実際に殺されたこともあったであろうが、新約の時代においては、このような者たちは殺すのでなく教会から追い出すべきであると今の私には思われる。カルヴァンの場合、教会を惑わしていたあの忌まわしいセルベトゥスを実際に火で焼いて殺したが、これには賛否両論があり、この件について今現在の私はまだ確かな判断ができないでいる。仮にカルヴァンがこの糞のような者を殺したのが問題であったとしても、教会に悪い影響を及ぼす者が除外されたという点自体については、正しいことが行なわれたと言える(※②)。いずれにせよ、ペルガモの聖徒が自分たちの教会にいたニコライ派的な者たちを追い出さなかったのは、この申命記における律法に違反しているので罪であり、それゆえに彼らは悔い改めなければいけなかったのである。
(※①)
『罪とは律法に逆らうことなのです。』(Ⅰヨハネ3章4節)
『罪は、何かの律法がなければ、認められないものです。』(ローマ5章13節)
[本文に戻る]
(※②)
最近―この註解箇所を書いてから恐らく10か月ぐらい後―、私はカルヴァンの手紙を読んだのだが、どうやらカルヴァンはセルベトゥスに与えられる刑罰が緩やかになるようにと願っていたようである。カルヴァンは出来るならばセルベトゥスが死刑にならないように願っていたというのが本当らしく思われる。また、この異端者に厳しい処罰が下されるように願っていた者たちがカルヴァンの他にも多くいた。メランヒトンをはじめとした多くの神学者たちは、セルベトゥスの死刑を当然の裁きとして是認していた。それゆえ、この問題はカルヴァンだけに注意が向かいがちであるが、個人的な問題としてではなく、もっと全体的な幅広い問題として捉える必要があるのではないかと私には思われる。ただ2つのことは確実に言える。一つ目はセルベトゥスが消え失せることは神の定めであったということ、二つ目はセルベトゥスが消されたのは結果的に教会にとって益となったということ、である。
[本文に戻る]
ここで悔い改めるように命じられているのが、すなわちニコライ派的な者たちを追い出さなかったということだったというのは、テアテラ教会の箇所(2:18~29)を考えてもそうだと言える。このテアテラ教会では、イゼベルという偽預言者のことが問題にされている。すなわち、キリストは、テアテラ教会の聖徒たちがこのイゼベルを追い払わなかったことを、この教会の聖徒たちに非難している。邪悪な者、害を波及させる者を教会から追い出さないのは、明らかに悪であり、御心に適わないことなのである。そうであれば、テアテラ教会に対して邪悪な者を追い出していないことが非難されているのだから、やはり我々が今見ているペルガモ教会に対しては、邪悪なニコライ派的な者たちが追い出されていないことについて悔い改めが命じられていることになる。ペルガモ教会に対するこの箇所では、文字的にそのことを悔い改めるようにとは言われていないが、ここでそのことを悔い改めるようにと言われているのは間違いない。ここで文字的には悔い改めるべき事柄が書かれていないのは、その事柄を書かなくても、ペルガモ人たちには悔い改めるべき事柄がよく分かっただろうからである。他方、テアテラ人たちに対しては「悪者を放置していることがいけないのだ。」と明瞭に言われているが、こちらのほうでは、しっかりとその罪状を述べることが神の御心であった。ペルガモ人に対して、悔い改めるべき罪状が明白に文字として書かれていないのも、やはりそのように書かれるのが神の御心だったからである。我々も具体的なことを何も言わずに相手に伝えるべきことが伝わるようにすることが往々にあるが、神はここで、そのような語り方をしておられるのである。だから、この箇所におけるヨハネの文章が説明不足だなどと言って非難することはできない。
キリストは、もしこのことについて悔い改めなければ、剣により裁きを下されると言っておられる。これは脅迫であるが、エペソ人に対して言われたのと同じで、単なる見せかけの言葉ではない。『口の剣』というのは、ここまで読み進められた読者に対しては説明不要であるが、『彼ら』というのは誰を指すのか。これは、ニコライ派的な者たちと、彼らを除外しようとせずに放置し続けている聖徒たちのことである。私がこの『彼ら』という言葉に、聖徒たちも含めているのに驚くべきではない。何故なら、忌まわしい異端分子を除外しようとするなどして敵対しないのであれば、それは事実上、その異端分子の仲間であるのも同然だからである。キリストは、『わたしたちに反対しない者は、わたしたちの味方です。』(マルコ9章40節)と言われた。反対しないのは味方であるのも等しい。つまり、この論理を今我々が見ている黙示録の箇所に当てはめて考えれば、ニコライ派的な者に反対しない者たちは、たとえそれが聖徒と一般的に呼ばれる者であろうとも、事実上はニコライ派的な者たちの味方だということになる。要するに、味方だからこそ、その味方である者たちを敵視したり、除外しようとしないというわけである。だから、この『彼ら』というのは、ニコライ派の教えを奉じている者たちに敵対しない聖徒―それは聖徒ではないかもしれないが―も含めねばならない。ここで言われているように、ペルガモ人たちが悔い改めて異端分子を除外しようとしなかったならば、キリストが御言葉の剣をもって襲いかかってくることになっていた。これを肉的に捉えて実際の剣だと考えるべきではなく、霊的に捉えて御言葉による裁きが下されると考えねばならないのは、言うまでもないことであろう。それでは、キリストはどのような御言葉の剣を使って、彼らを裁かれるのであろうか。それは先に見た申命記13章の御言葉である。もしペルガモ教会が悔い改めなかった場合、キリストは、この申命記13章における御言葉の剣を彼らに対して振り回され、その御言葉の中で言われているように、ペルガモ教会の中にいた追い出されるべき者どもをご自身みずから追い出されることになっていた。要するに、ペルガモ教会の聖徒たちが律法の中で命じられている神の命令を遂行しないので、キリストが代わりにその律法を裁きとして遂行されるということである。それゆえ、もしペルガモ人たちが悔い改めていなかったとすれば、この教会には、死者や追放される者や悲惨な状態に陥ることになる者たちが多く出ていたはずである。しかし、実際に彼らがキリストの勧告を聞いて悔い改めたかどうかは、不明である。我々が天国に行ってペルガモ教会の聖徒に会う日が来れば、このことについて、やがて知れるようになるであろう。今はまだ何も分からなかったとしても、致命的な問題が生じるわけではないから、その点については安心すべきである。
エペソ人とは違い、このペルガモ人には、このような恐るべき脅迫がなされた後で、霊と精神を和らげるための言葉が付け加えられていない。これは、ペルガモ人には、そのような和らげの言葉を付け加えなくても、何も問題なかったからである。ペルガモ人たちはキリストに対する堅固な信仰を持っていたので、たとい強烈な脅迫がなされても、戦慄してキリストに過重な恐れを抱くという危険はなかった。他方、先に見たように、エペソ人たちはペルガモ人よりは「ヤワ」な性向を持っていたので、恐怖を和らげるための言葉がどうしても必要であった。全てを知っておられるキリストは、エペソ人にはエペソ人に相応しい仕方で述べ、ペルガモ人にはペルガモ人に相応しい仕方で述べられたのである。
【2:17】
『耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。わたしは勝利を得る者に隠れたマナを与える。』
『マナ』とは、すなわちキリストのことである。何故なら、キリストとは、真の食物である霊的なマナまたパンだからである。確かにキリストは、ご自身のことを、そのように言われた。すなわちヨハネの福音書6:48~51の箇所である。そこでキリストは、ユダヤ人に対してこう言っておられる。『わたしはいのちのパンです。あなたがたの先祖は荒野でマナを食べたが、死にました。しかし、これは天から下って来たパンで、それを食べると死ぬことがないのです。わたしは、天から下って来た生けるパンです。だれでもこのパンを食べるなら、永遠に生きます。またわたしが与えようとするパンは、世のいのちのための、わたしの肉です。』確かにキリストはご自身のことをマナであると教えておられる。だから、我々はこの『マナ』という言葉を肉的に捉えて、単なる物体的な食物のことだと考えてはいけない。つまり「マナが与えられる」とは、真のマナであられるイエス・キリストという永遠の命が与えられ、そのマナにより永遠に生き続けられるようになる、という意味である。これは簡単に言えば「永遠の命」である。確かに、キリストこそが人を永遠に生きられるようにする真の食物なるマナである。人は、このマナを受けることなしには、永遠に生き続けることができない。「勝利するならば真のマナが受けられるのだから忍耐のうちに保たれるようにせよ。」―ここでキリストはペルガモ人に対して、このように言っておられるのである。
このマナが隠れていると言われているのは、少数の選ばれた者を除いて、人間は、キリストが真のマナであられるということを理解できないからである。御霊を受けていない者に対し、キリストがマナであられるという真実なことは、理解できないように隠されている。それは、御霊により、キリストこそ真のマナであるということを悟れないからである。だからこそ、ここではキリストが『隠れた』マナであると言われている。主の時代にいた多くの者たちは、この隠されたマナであるキリストのことを、真に悟れなかった。だから、キリストがご自身のことをマナだと言われたのを聞くと、実に多くの人たちがつまづき、キリストから離れてしまった。これはヨハネの福音書6章に書いてある通りである。要するに、キリストは「万人に明らかにされているマナ」ではないということである。
『また、彼に白い石を与える。その石には、それを受ける者のほかはだれも知らない、新しい名が書かれている。』
『白い石』とは、すなわちキリストのことである。何故なら、キリストは、聖書において石(また岩※)として象徴的に語られているからである。キリストは詩篇を引用しつつ、ユダヤ人に対して、ご自身についてこう言われた。『「あなたがたは、次の聖書のことばを読んだことがないのですか。『家を建てる者たちの見捨てた石。それが礎の石になった。…』…また、この石の上に落ちる者は、粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛ばしてしまいます。」』(マタイ21章42、44節)確かに、ここでキリストはご自身が石であると言っておられる。ペテロも、キリストについてこう言っている。『主は、人には捨てられたが、神の目には、選ばれた、尊い、生ける石です。』(Ⅰペテロ2章4節)それでは、どうして、ここではキリストという石が白いと言われているのか。それはキリストの清さを表わすために他ならない。黙示録においては、この箇所もそうだが、色が重要な意味を持っているので、我々はたかが色だなどと思って軽んじるべきではない。すなわち、黙示録の中で「色」が出てきたら、その色が一体どのようなことを意味しているのかと深く考えて、正しい理解を得られるようにせねばならない。白い石が受けられるというのは、つまり、白い石であられるキリストの救いを受けられる、ということである。この『白い石』とは、キリストにある永遠の命を象徴している。ここでは、もしペルガモ人たちが勝利するならば、そのような素晴らしい石を受けられると約束されている。再臨の日に勝利者であることが確定したペルガモ人たちは、実際に、この白い石なる永遠の命を、天国においてキリストから受け取ったことであろう。
(※)
パウロは、荒野でユダヤ人について来た岩とはすなわちキリストであったと言っている。『というのは、彼らについて来た御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。』(Ⅰコリント10章4節)
[本文に戻る]
どうして、このキリストという白い石には、それを受け取る人以外には誰も知らない新しい名が書かれているのか。これは、3つのことを示していると考えられる。まず一つ目は、勝利して天国に入れられる者には、実際的な意味での新しい名が付与されるということである。聖書を見れば分かるが、神は、ある転機がご自身の選ばれた子らに訪れると、その者の名を変更されるということをされるお方である。例えば、アブラハムとサラが、そうであった。アブラハムは神と契約を結んだ際に「アブラム」という名を変えられ(創世記17:4~5)、その際にはサラも「サライ」という名から変えられた(創世記17:15)。本当かどうかは定かではないが、偽典によれば、モーセは天に挙げられた際、新しく「メルキ」という名を与えられたという。この地上における転機が訪れた時でさえ名前の変更がなされるのであれば、天国に行くという大いなる転機が訪れた場合は、尚更のこと、名前が変えられるべきであると言えよう。何故なら、天国に行って新しい人生を送ることになるというほどに大きな転機は、他に存在しないからである。2つ目は、勝利した者は、天国においてキリストに完全に固着するようになるということである。その人は、天国に行ってからは、契約的な意味においてキリストと完全に一体化する。その時、その人はペテロにようにキリストを否んだり、キリストから離れたりするということは、まったくなくなる。何故なら、ここでは、勝利する者が新しい名においてキリストという石に書き込まれると言われているからである。これは契約における一体性を教えるものでなくて何であろうか。3つ目。ここで石に書かれている名がその当人以外には知られないというのは、つまり、新しい名が与えられることになる救いは、その人にだけ与えられているということを示していると思われる。勝利することになるある人に与えられるキリストの救いは、その人にだけ与えられるものであって、その人以外の誰かに与えられはしない。すなわち、他の人は誰であっても、その人に与えられるその人を対象とした救いにあずかることはない。それは、ある人に与えられた命がその人だけを対象とした命であって、その人の命に、その人以外の誰かがあずかるわけではないのと同じである。つまり、ここで石に書かれた新しい名がその石を受け取る人以外には知られないと言われているのは、勝利する者一人一人に対して与えられる救いの限定性・一者性のことを言っている。これを分かりやすく言い変えれば、「あなたに与えられる救いは他でもないあなただけを対象としているものなのだ。他の人はあなたを対象とした救いにあずからない。」ということである。天国に行った者たちに新しい名が与えられるとして、その新しい名は天国にいる全ての人々に知られることになるはずだから、ここで言われていることは、私が今述べたように理解すべきである。そのように理解しないと、この箇所を上手に理解することは非常に難しいと思われる。
ここまで説明されたように、マナも石もどちらもキリストのことであるから、ここではキリストによる恵みが与えられるということが2回繰り返して言われていることになる。「マナを与える。そして白い石も与える。」とは、すなわち「キリストを与える。そしてキリストも与える。」ということである。このように同じことを2回繰り返すのは、ヘブル人が文意を強調するために行なう語法である。彼らは昔から、よくこのような語法を使っている。キリストは、もちろん人としてはヘブル人であった。だから、聖書の他の箇所でも、キリストが2回連続で同じことを繰り返して言っておられることについて記されている(※)。―とはいっても、バビロン捕囚が起きてからは言語的にも大きな変化が起きたので、このようなヘブル流の語法が使われることは捕囚前の時代に比べるとかなり少なくなったのではあるが。―つまり、ここでは「勝利者にはキリストによる恵みが与えられる。」という約束が、2回同じことが言われることにより、非常に強く語られていることになる。それゆえ、我々は、ここで2回も「キリストが与えられる。」と繰り返し言われていることを、何か不思議に思うべきではない。ヘブル人の特性を考えれば、このような語り方をするのは、何も珍しくはないからである。なお、バビロニア・タルムードのゲマラでは、ラビ・イシュマエル学派が「(聖書において)何かが言われて繰り返される文節はすべて、何かその中に新しいことがあるがゆえに繰り返されるのである」(『タルムード ナシームの巻 ソーター篇』第1章3b p10:三貴)などと教えているが、これは間違っている。聖書の中では、繰り返されている箇所の全てが、新しいことを含んでいるというわけではないからである。
(※)
例えばルカ13:2~4がそうである。『イエスは彼らに答えて言われた。「そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、ほかのどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない。わたしはあなたがたに言います。あなたがたも悔い改めないなら、みな同じように滅びます。また、シロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいるだれよりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない。わたしはあなたがたに言います。あなたがたも悔い改めないなら、みな同じように滅びます。」』
[本文に戻る]
我々も、勝利者となるならば、この2つのものをキリストから受け取ることができる。このマナと石を受けることができるのは、勝利する者たちにだけ与えられる特権である。それゆえ、この2つのものを願う者たちは、勝利の道を歩み続け、最終的な勝利者となれるようにせねばならない。もし敗北者となるのであれば、この2つのものを受けることは絶対にできない。敗北者に幸いな恵みが与えられることが、どうしてあるであろうか。
【2:18】
『また、テアテラにある教会の御使いに書き送れ。『燃える炎のような目を持ち、その足は光り輝くしんちゅうのような、神の子が言われる。』
ここでも、やはりその教会に適合した言い方によってキリストが言い表わされている。テアテラ教会に対してキリストの目が燃える炎のようであると言われているのは、この教会にいたイゼベルという女の不品行を、キリストがしっかりと見ておられるということを強く認識させるためだと思われる。この女の不品行をキリストの力強い目が監視していると聞かされるのであれば、この女も、またこの女を放置しているテアテラ人たちも、たまったものではないはず。もしキリストがそのような醜態を力強く監視しておられると知ったならば、やはり、それだけキリストに対する恐れを抱くようにもなる。つまり、キリストは悪を裁かれる裁き主としての認識を、ここで強くテアテラ人たちに持たせようとしているのだと考えられる。要するに、「私の燃える炎の目が、あなたがたの罪と醜態を見逃すことは決してない。」ということである。またキリストがここで真鍮のような輝く足を持っておられると言われているのは、キリストの力強さと堅固さとを、イゼベルによく認識させるためではないかと思われる。キリストがそのような特異で毅然とした印象を抱かせる足を持っておられると聞かされたならば、悪に凝っているイゼベルが調子に乗ってキリストを軽んじたり無視したりすることも、それだけなくなるのは確かである。キリストがこのように普通ではない足を持っておられると聞かされたならば、人間の自然の情として、いくらかでもそのような足を持っておられるお方に対して恐怖を抱くようにもなる。人間は、何だかよく分からないものや理解を超えたものには、往々にして恐怖を抱くものだからである。要するに、これはイゼベルという邪悪な女に対して、威圧感を与えようとして言われた言い方であると考えられる。私はここでのキリストの言われ方をこのように説明したが、この言われ方は、これまでに見た3つの教会に対するキリストの言われ方を解読することに比べると、かなり解読における難易度が高い。なお、この箇所における2つの言われ方は、既に1:14~15で言われていた言い方である。
【2:19】
『「わたしは、あなたの行ないとあなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っており、また、あなたの近ごろの行ないが初めの行ないにまさっていることも知っている。』
テアテラの聖徒たちは霊的に恵まれており、多くの美点を持っていた。ここでキリストが、彼らの行ないと愛と信仰と奉仕と忍耐とを評価しておられる通りである。しかも、このテアテラ人たちは、信仰を持った最初の頃の状態よりも更によくなっていた。これは、初めの頃の愛を失っていたエペソ人たちとは大違いである。このことから分かることだが、テアテラ教会にいた聖徒たちの多くは、コリント教会の聖徒たちとは違い、あまり肉的ではなかったのであろう。というのも、肉とは、神への愛を衰えさせる性質を持っているからである。もしテアテラの聖徒たちが全体的に見て肉的であったとすれば、初めの頃の状態よりも良い状態になるなどということは考えられないのである。
【2:20】
『しかし、あなたには非難すべきことがある。あなたは、イゼベルという女をなすがままにさせている。この女は、預言者だと自称しているが、わたしのしもべたちを教えて誤りに導き、不品行を行なわせ、偶像の神にささげた物を食べさせている。』
テアテラ人には多くの美点があったものの、非難されるべき汚点も持っていた。それはイゼベルという名の偽預言者を放置し続けていたということである。この女は、テアテラ教会にいた聖徒たちを惑わして、神から離すという霊的な姦淫を行なわせていた。これは誠に由々しきことであった。このような女は、先に見たペルガモ教会のニコライ派的な者たちが追い出されるべきであったのと同様に、テアテラ教会から追い出されるべきであった。しかし、テアテラの聖徒たちは、そのようにせず、このイゼベルが自由に行動するままにさせていた。これはテアテラの聖徒たちの罪であり、主の御心に適わないことであった。だからこそ、主は、ここでテアテラ人たちが『イゼベルという女をなすがままにさせている』ことについて非難をしておられるのである。なお、主が気をつけよと福音書の中で言われたのは、このような偽預言者のことであった(※)。この終末の時期には、このような忌まわしい偽預言者が多く出現したに違いない。だからこそ、主はあらかじめ、そのような者たちを警戒するようにと言われたのである。
(※)
『にせ預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやって来るが、うちは貪欲な狼です。…』(マタイ7章15節)
[本文に戻る]
ところで、このイゼベルという偽預言者は、アハブの妻であったイゼベルと何か霊的な関連性があるのであろうか。すなわち、摂理的な意味において、何らかの繋がりや連関があるのであろうか。この2人の女は、邪悪という点では、どちらも一致している。両方とも神の民にとっては有害な敵対者である。聖書が教えているのは、この世界において偶然に起こることは何一つないということである。キリストも言われたように、一羽の小さい雀が地に落ちることにさえ、神の働きかけがある。だから、この偽預言者があの邪悪なアハブの妻と同名であるということも偶然ではないと考えるのが望ましい。この女がアハブの妻と同じ名前なのは、アハブの妻とその邪悪性を、この女において想起させるためであったと思われる。この偽預言者がアハブの妻と同じ名前であれば、この偽預言者がより邪悪であると思えるようにもなる。何故なら、あのイゼベルと同じ名前を、この偽預言者が持っているからである。神は、この偽預言者の邪悪性を誰でも理解できるようにするために、この偽預言者にあのイゼベルと同じ名前が付けられるようにと永遠の昔から定めておられたと考えられる。つまり、この偽預言者は世の始まる前から邪悪なことをするようにと決まっていたので、邪悪であったアハブの妻と同じ名前が付けられるように、神が欲されたということである。「アハブの妻と同名なのは単なる偶然に過ぎない。」などと考えるのは、この世的な態度であって、霊的な態度とは言えない。
【2:21】
『わたしは悔い改める機会を与えたが、この女は不品行を悔い改めようとしない。』
神は、罪人たちが悔い改めて破滅に陥らないようにと、罪人たちに悔い改める機会をお与え下さる。それは神が、憐み深いお方だからである。神は、たとえ邪悪に染まっている者であっても、悔い改めて救われるようになることを望んでおられる。神により送られた牧師や神父たちが死刑囚に悔い改めて救われるようにと勧めるのは、神が罪人たちを憐れんでおられることのよい証拠である。神が、神に対して不敬なことばかり口にしていたアインシュタインに多くのキリスト教徒から送られた手紙を通して悔い改めを促しておられたということも、神が罪人を憐れんでおられることのよい証拠である。その機会が与えられた際、もし悔い改めるならば、その人は最終的な破滅を免れることができる。しかし、悔い改めないならば、パロのように心が頑なにされ、神に敵対したままで死に、永遠の破滅に至る。このような悔い改めの機会が、この忌まわしいイゼベルにも与えられた。これはイゼベルに対する神の慈しみのゆえであった。実に、神は、ご自身に敵対するこの邪悪な偽預言者をも憐れんでおられたのである。
しかしながら、せっかく悔い改めの機会が与えられたにもかかわらず、このイゼベルという女は悔い改めようとしなかった。この女は、せっかくの機会を台無しにしてしまった。これは、無期懲役の刑に服して監獄の中にいる囚人に、そこから出ることができる恩赦の提示がされたにもかかわらず、その囚人があくまでも監獄の中にい続けることを願うようなものである。イゼベルは罪という監獄から抜け出せる恵みを、キリストという恩赦を与えるお方から提示されたにもかかわらず、あくまでも罪のうちに留まり続けていた。この女が悔い改めようとしなかったのには、大きく分けて2つの理由がある。まず一つ目は、イゼベルが罪の闇にいつまでも留まり続けていたいと願ったからである。悔い改めるとは、人間性を低くさせる恥ずかしいことであり、自らに屈辱を与える行為である。ゆえに、高慢であればあるほど、人間は悔い改めることが難しくなる(逆に謙遜な人であればあるほど、すぐに悔い改めることができる)。イゼベルは、他の多くの人と同じく高慢であったので、悔い改めることを望まず、いつまでも暗闇の中に歩み続けることを願ったのである。二つ目は、神がイゼベルに悔い改めの恵みを、与えられなかったということである。人が悔い改めるのは、ただ神の恵みによらねばできない。神は、イゼベルが悔い改めることを望まれたが望まれなかった。すなわち、悔い改めを望まれたがゆえに悔い改めの機会を彼女にお与えになったが、彼女がその機会を蔑ろにしたので、もはや悔い改めるようになることをお望みにはならなかった。それゆえ、イゼベルには悔い改めの恵みが与えられることもなく、彼女は悔い改めないままに留まったのである。しかし、我々は、ここでイゼベルが悔い改められなかったことにおける非を、神が悔い改めの恵みをお与えにならなかったことに帰してはならない。つまり、「イゼベルが悔い改められなかったのは、神が彼女に悔い改めるように恵みを与えられなかったがゆえであるから、悪いのはイゼベルではなく神である。」などと考えてはいけない。それは、「パロの心が頑なになったのは神がそのように働きかけたからだ。」などと言って、パロではなく神を非難するのと同じことである。確かにパロの心を頑なにさせたのは神であったが(※)、だからといってパロではなく神を非難すべきではない。何故なら、実際に心を頑なにさせたのはパロであって、悪の責任はパロにこそ求められなければいけないからである。それと同じように、イゼベルが悔い改めなかったのは究極的に言えば神が悔い改めの恵みを彼女に与えられなかったからであるが、しかし、だからといって神を非難してはならない。これもパロの場合と同じで、悪いのは神ではなくイゼベルのほうであり、それゆえに悔い改めなかった責任はイゼベルにこそ求められなければいけないのである。
(※)
『しかし、主はパロの心をかたくなにされた。』(出エジプト記10章27節)―出エジプト記における他の多くの箇所でも同じ内容のことが言われている。
[本文に戻る]
【2:22~23】
『見よ。わたしは、この女を病の床に投げ込もう。また、この女と姦淫を行なう者たちも、この女の行ないを離れて悔い改めなければ、大きな患難の中に投げ込もう。また、わたしは、この女の子どもたちをも死病によって殺す。』
イゼベルは悔い改めなかったので病を罰として受ける、とここでは言われている。これは実際的な病のことであろう。主は、悔い改めない者には、容赦なく罪に対する裁きをお与えになる。しかし、イゼベルがこの箇所で言われている裁きのことを読んだか他の人から聞いたことにより、裁きに対する恐れを抱いて悔い改めたのであれば、病が下されることはなかったはずである。何故なら、罰が下される前に悔い改めたからである。またイゼベルの同調者たちも、連帯責任として、罪に対する裁きを受けることになっていた。何故なら、同調者たちも、イゼベルと同じように罪に問われるからである。しかし、やはり同調者たちも、もし悔い改めるのであれば、裁きを回避することができた。更に、ここではイゼベルの子どもたちにも、イゼベルの罪に対する裁きが波及されると言われている。イゼベルの子らが死病によって殺されるのは、親であるイゼベルに精神的な裁きが下されるためである。主は、イゼベルに病という身体的な苦痛だけでなく、子を失うという精神的な苦痛をも裁きとして与えようとしておられた。この子たちが、イゼベルの罪を行なっていたかどうかということについては、何も書かれていないので、我々には不明である。だが、その子たちがイゼベルの罪をしていようがしていなかろうが、その子たちは裁きにより殺されることになっていた。もし子どもたちがイゼベルのように罪を犯していたならば、死病により殺されるという裁きは、誰でも納得できることであろう。その子たちが悪いことをしているからである。しかし、もし子たちが罪を犯していなかった場合でも殺されるということであれば、納得できない人もいるかもしれない。だが、我々は、あのダビデに懲らしめが与えられるために、彼に生まれた幼児がすぐにも殺されたことを思い返すべきである。あの殺された幼児は、まだ生まれてから1ヶ月も経っていなかったのだから、実際的に悪を行なったのではなかった。それにもかかわらず、あの幼児は、ダビデが懲らしめを受けるために容赦なく殺されたのである。それはダビデが、自分の犯した罪のゆえに、懲らしめとしての精神的な苦痛を受けるためであった。懲らしめか裁きかという違いはあるものの、このイゼベルの場合も、同様である。つまり懲らしめの場合であれ裁きの場合であれ、神は罪を犯したある人に精神的な苦痛を与えるために、その人に近い誰かが罪を実際には犯していないにもかかわらず苦しみに陥ることをお許しになられる。それは罪を犯したその人が、自分の周りの人が苦しみを味わうことにより、自分の犯した罪の苦味をよく知るためである。「ああ、私の罪のために実際には罪を犯していないあの人が裁きとしてあのように苦しめられることになるとは。一体、私は何ということをしてしまったのか。」―このように思って嘆きの念を抱くためにこそ、神は罪を犯した人に対する裁きあるいは懲らしめとして―イゼベルの場合は裁きである―、その罪人に関連する人物を苦しめられるのである。
このような裁きは、神の怒りの表れであった。すなわち、神がイゼベルの罪に怒っておられたからこそ、このような裁きが下されることになったのである。もしイゼベルの罪に神が怒りを持っておられなかったとすれば、このような裁きが下されることもなかったであろう。確かなところ、神の怒りと裁きの度合いは、正比例している。つまり神が怒っておられればおられるほど、その与えられる裁きも悲惨なものとなる。その分かりやすい例は、ユダヤの滅亡である。紀元1世紀のユダヤは神の怒りが頂点に達するほどにまで邪悪に染まっていたので、その怒りの表れとして、ユダヤには恐るべき滅びの裁きが下されることになった。ここで言われているイゼベルの悪も、神の前において非常に大きく、神の怒りもそれだけ大きいものであった。だからこそ、ここで言われているように、イゼベルには、病という身体的な苦痛と、子らの消失という精神的な苦痛という2つの大きな悲惨が与えられようとしていたのである。
ここで書かれている神の裁きを受ける者たちは、裁きを原因として死んだ者たちであれ、裁きを受けて死にはしなかったものの頑ななまま歩んで悔い改めようとしなかった者たちであれ、地獄に投げ込まれたと考えるべきである。前者のほうは死んだ瞬間に地獄に行き、後者のほうは、再臨の日までに死んだならばその死んだ日に地獄に行き、再臨の日まで生き残っていたのであれば、1.教会に留まり続けていた者は携挙されて空中の審判を受け、2.教会から離脱した者であれば携挙されることなく地上において永遠の死を受けるべき者として確定された。どうしてこう言えるかといえば、今書かれたような者たちは、死の時まで罪を悔い改めなかったからである。言うまでもなく、罪が残されたままの状態にある人間が、天国に入れるという恵みを受けることはない。イゼベルであれ彼女の子らであれイゼベルの行ないをしていた者たちであれ、我々がこの地上から出て天国に行った際には、その天国において、ここで書かれている者たちが地獄の中で苦しんでいる凄まじい光景をまざまざと見ることになるであろう。それはイザヤ書66:24の箇所で、『彼らは出て行って、わたしにそむいた者たちのしかばねを見る。そのうじは死なず、その火も消えず、それはすべての人に、忌みきらわれる。』と言われている通りである。
【2:23】
『こうして全教会は、わたしが人の思いと心を探る者であることを知るようになる。』
これは、キリストがイゼベルおよびイゼベルと共に裁きを受けるべき者たちに罰を与えることで、あらゆる教会の聖徒たちが、キリストが報いのために人の内面を詮索されるお方であるということをよく認識するようになる、という意味である。イゼベルとその共犯者たちに恐るべき罰が下されるのであれば、その時、聖徒たちはキリストが秘密の詮索者であられるということを明瞭に悟るに至る。何故なら、罰という詮索の実を見ることになるからである。しかし、罰が下されるまでは、キリストが詮索者であられるということは、それほどよく認識されない。何故なら、その時には、まだ罰という詮索の実が見られないからである。これは、警察が覆面捜査によりマフィアの一団を壊滅させたというニュースが流れたことで、そのニュースを見た多くの人々が、警察とは悪い集団に潜伏してまで探りを入れる組織であるということをよく理解するようなものである。マフィアを壊滅させたという覆面捜査の実が公に現われたからこそ、人々は、このように警察のことをよく知るようになる。それまでは、たとえ警察が覆面捜査をする組織だと分かってはいても、あまりそのことが意識の領域には上ってこない、つまり漠然とした認識しか持てていない。しかしニュースが流れると、意識の領域にそのことがしっかりと上ってくることになる。キリストがここで言っておられるのは、つまりはこれと同じことである。キリストは、このようにご自身がどのような存在であるのか聖徒たちに知らせるためにも、イゼベルとその共犯者たちに罰をお与えになった。
『また、わたしは、あなたがたの行ないに応じてひとりひとりに報いよう。』
ここでは、テアテラ人たちにも報いが与えられることを忘れさせないために、このように言われている。つまり、テアテラ人たちが、報いを受けるのはイゼベルとイゼベルにかかわる悪者たちだけなのだと思い込んでしまわないために、このようにキリストは言われた。人間は鈍くて愚かであるから、このようにいちいち言われないと、よく理解できなかったり気付けなかったりすることが多い。それが普通に考えれば誰でも分かりそうな内容のことであっても、である。だから、もしキリストがこのようにテアテラ人にも報いがあるのだと言っておられなければ、テアテラ人たちは、自分たちはイゼベルたちと違って報いを受けなくても済むと勘違いしてしまっていたかもしれない。確かに、イゼベルのような悪者だけでなく、正しく歩んでいる聖徒たちにも、神の報いが与えられることになる。それは、『神は、善であれ悪であれ、すべての隠れたことについて、すべてのわざをさばかれる』(伝道者の書12章14節)とか『神は、ひとりひとりに、その人の行ないに従って報いをお与えになります。』(ローマ2章6節)などと書かれている通りである。
この報いとは、具体的に言えば、再臨の起きた紀元68年6月9日に行なわれる最後の審判における報いである。この日における空中の審判を指して、キリストは『ひとりひとりに報いよう。』と言っておられるのである。これはマタイの福音書で言えば、25:31~46の箇所のことを言っている。黙示録では、20:11~15のことである。この黙示録の箇所で『そして人々はおのおの自分の行ないに応じてさばかれた。』(20:13)と書いてあるのは、我々が今見ている箇所の『あなたがたの行ないに応じてひとりひとりに報いよう。』という言葉と対応している。ここで言われているように、テアテラの聖徒たちは、この審判の時、その行ないに応じて報いをキリストから受けた。キリストは、テアテラ人たちが徳に励み、悪徳から離れるようにと、ここでこのように言っておられる。というのは、未来に報いがあると強く意識するのであれば、それだけ善を行ない悪から離れる傾向性が生じることになるからである。キリストは聖徒たちがより良い報いを受けてほしいと願っておられたので、ここで、このように愛徳を助長させることを言われたのである。もし、このような言葉が言われていなければ、報いに対する希望を善の原動力とすることができないので、それだけテアテラ人たちが幸いな歩みをすることは難しくなっていた。
この言葉は、普遍的な内容として捉えるならば、我々に対しても言われていると考えることができる。確かに、我々も、この地上の幕屋を脱ぎ捨ててから後に、それぞれが神からの報いを受けることになる。その時、我々は、地上の人生において行なった良い行ないに応じて、報いを受ける。すなわち、大いに善行をした者は非常に輝かしい栄光体として復活し、それなりに多く善を行なった者はそれなりに多い輝きをもった栄光体として復活し、普通程度の善しか行なわなかった者は普通程度の輝きしか持たない栄光体として復活する。しかし、その中のもっとも輝きの小さな者でさえ、人類の中でもっとも偉大とされたあのバプテスマのヨハネより偉大である(※)。何故なら、天国に行った聖徒は報いを受けて栄光の身体に蘇えらされた状態だが、地上にいたバプテスマのヨハネはまだ肉の身体を脱ぎ捨てていなかったからである。つまり、安価な栄光の身体のほうが、高価な地上の身体よりも、遥かに優っているということである。高価な栄光の身体を報いとしてやがて受けたいと願う聖徒は、大きな報いを受けられるように努力するがよい。
(※)
『まことに、あなたがたに告げます。女から生まれた者の中で、バプテスマのヨハネよりすぐれた人は出ませんでした。しかも、天の御国の一番小さい者でも、彼より偉大です。』(マタイ11章11節)
[本文に戻る]
【2:24~25】
『しかし、テアテラにいる人たちの中で、この教えを受け入れておらず、彼らの言うサタンの深いところをまだ知っていないあなたがたに言う。わたしはあなたがたに、ほかの重荷を負わせない。ただ、あなたがたの持っているものを、わたしが行くまで、しっかりと持っていなさい。』
ここで『サタンの深いところ』をまだ知っていないと言われているのは、どういう意味か。これは、要するに、サタンの邪悪にまだ染まっていないので、サタンの邪悪性を実体験していない、すなわちサタンがどれほどに悪いのかということを真に体感してはいない、という意味である。多くの密儀宗教では、熟練した信仰者でなければ、その宗教における秘儀を開示しない。ピュタゴラス教団にも、そのような面があった。フリーメイソンも、かなり上位の階級に進まない限り、その組織における本質と秘密とが開陳されることはない。このような者たちは、ある少数の者しか知らない特定の秘儀を知っていることに、喜びと優越感を覚える。その秘密性に伴う優越の快楽が、秘儀が公のものとされないように防ぐという効果をもたらす。イゼベルたちの言う『サタンの深いところ』というのも、要するに、このような性質を持ったものだったと考えられる。サタンに従う邪悪の徒は、このようなことを好むものである。テアテラ人のうち、イゼベルの罪を行なっていた者たちは、既にこの『サタンの深いところ』を知っていたと見てよいであろう。そのような者たちは、サタンに属する悪を行なっているので、サタンの邪悪性をよく体感できるからである。一方、まだイゼベルの罪を行なっていない聖徒たちは、このサタンの深みを知っていなかったと考えるべきである。その者たちは、サタンの悪を行なっていないので、まだサタンの邪悪性における深みを体感的には知らないからである。
『重荷』とは、悔い改めてイゼベルたちを教会から追い出すという負担のことである。テアテラ人たちは、イゼベルたちを追い出すことを、恐れたりにせよ、嫌がったにせよ、怠惰になっていたにせよ、とにかく避けていた。それは彼らにとっては負担に感じられることだったからである。これは、あたかも大変なので夏休みの宿題をいつまでもやらずに放ったままにしておく子どものようである。子どもが夏休みの宿題を重荷に感じるように、テアテラ人たちも、イゼベルの件は重荷であると感じられるものであった。『あなたがたの持っているもの』とは、キリストが2:19の箇所で称賛しておられるテアテラ人たちの『行ない』と『愛と信仰と奉仕と忍耐』および『近ごろの行ないが初めの行ないにまさっていること』である。つまり、これはテアテラ人の持つ美点のことである。これを何かの物質的な持ち物であると考えてはならない。キリストは、テアテラの聖徒たちに、ここで2つのことしか求めておられない。その2つとは、1.悔い改めてイゼベルたちを教会から追放すること、2.再臨が起こるまで今まで通りの状態をしっかりと保ち続けること、である。つまり、テアテラ人たちは悔い改めてイゼベルとその同調者たちを教会から追い払ったならば、それ以降は、それまでの状態を保ったまま歩み続ければ、もうそれだけで全てがよくなっていた。というのも、イゼベルの件を除けば、テアテラ人たちは良い状態を持っていたからである。だから、テアテラ人たちはイゼベルを除いた後、そのままの状態で歩んでいれば、キリストが紀元68年に再臨された際には、『さあ、わたしの父に祝福された人たち。世の初めから、あなたがたのために備えられた御国を継ぎなさい。』(マタイ25章34節)などとキリストから言われることができた。しかし、ここで「本当にそれだけでよかったのか。」などと思われる方もいるかもしれない。本当にそれだけでよかったのである。何故なら、ここでキリストが求めておられるのは、この2つのことだけだからである。キリストの言われた通りにしたにもかかわらず、キリストから称賛の言葉を受けられないということが、どうしてあるであろうか。主権者の言葉を、過不足なく実行することが、称賛を受けるための方法であるということは、誰にでも分かることである。しかし、もしテアテラの聖徒たちが、キリストの言われた通りにしていなかったとすれば、称賛の言葉をもらえるどころか、非難され、裁かれることにさえなっていた。何故なら、テアテラの聖徒がキリストに従わず、教会から汚物を取り除くことをしなかっただけでなく、自分たちの持っている種々の美点を保つこともしなかったからである。キリストに従わない者たちが、キリストから幸いな処遇と褒美を受けられないというのは、言うまでもないことであろう。
この箇所から分かるのは、キリストが慈しみ深いお方であられ、聖徒たちに負いきれない重荷を負わせられることをしないということである。もし過重な重荷を聖徒たちに負わせるのであれば、聖徒たちはその重荷を負いきれず、押しつぶされてしまう。キリストは、聖徒がそのようにならないようにと、必ず、その聖徒の限界を超越することがないほどの重荷しか負わせられない。10の重荷が限度である人は、10を越す重荷は決して負わされず、100まで重荷を負える人は、100までの重荷は負わされるかもしれないが、100を越える重荷は決して負わされない。全ての人を完全に知っておられるキリストは、それぞれの聖徒の限度を弁えた上で、おのおのに適切な分量の重荷を負わせられる。このキリストは『わたしのくびきは負いやすく、わたしの荷は軽い』(マタイ11章30節)というご自身の御言葉を、決して曲げられない。この御言葉は絶対不動である。すなわち、キリストはその聖徒が負いきれるだけの重荷しか、聖徒に負わせられない。それゆえ、全ての聖徒たちはキリストにあって安心すべきである。今現在、あなたの負っている重荷は、あなたの負いきれない重荷では決してないのである。もしそれが負いきれない重荷であるとすれば、そもそもキリストは、あなたにその重荷を負わせられはしなかったであろう。だから、あなたは今自分が負っている重荷をしっかりと負うべきであるし、それは必ず負いきることのできる重荷なのである。
さて、この箇所にある『ただ、あなたがたの持っているものを、わたしが行くまで、しっかりと持っていなさい。』という御言葉は、再臨が既に起きたことを、強力に論証する箇所である。すなわち、この箇所から、テアテラ人たちが生きている間にキリストが再び来られたと断言することができる。何故なら、ここではキリストが来られるまで、テアテラ人たちがしっかり自分の持っている多くの美点を保つようにと言われているからである。このように言われたのは、もちろん、テアテラ人たちが生きている間にキリストが再臨されることになっていたからである。つまりキリストは、テアテラ人たちが再臨の際に良い状態で御前に立てるようになるために、ここでテアテラ人たちが良いものを保つようにと言っておられるわけである。再臨が起きた時に良い状態であれば良い状態であるほど、キリストの御前に幸いな状態で出られるようになるということは、言うまでもない。もし、今まで全ての教師たちが誤解してきたように再臨が未だに起きていないのであれば、ここでキリストはテアテラ人たちに愚かなこと、偽りであることを告げたことになる。というのは、2千年経った今でもまだ再臨が起きていないとすれば、ここでキリストはテアテラ人が生きていた時代にはまだ起きない遥か未来の出来事を、あたかもテアテラ人が生きている間に起こるかのように語ったことになるからである。このように言うのが愚かであり偽りであることは誰が考えても明らかである。この場合、キリストはペテン師として語ったことになってしまう。しかし、キリストは愚かではないし、偽りを語られるお方でもない。つまり、ここで語られたことは正に真実なことであった。ここで言われていることからも分かるように、本当にキリストは、テアテラ人たちが生きている間に再び来られたのである。このように論理的に御言葉から説明されても、再臨が既に起きたということが、まだ分からないであろうか。そのような読者は、自分がこのテアテラ教会に属する古代のキリスト者だったと想定してみるとよい。あなたはテアテラ人である。そのあなたの属するテアテラ教会にヨハネから黙示が記された文書が届けられ、その文書の中では、キリストがあなたとあなたの周りにいる兄弟姉妹に対して『ただ、あなたがたの持っているものを、わたしが行くまで、しっかりと持っていなさい。』と言っておられる。そうすると、どうであろうか。あなたは、自分たちの生きている間に、キリストが再びおいでになると理解し、そのようになることを期待するはずである。「キリストがやがて来られるのだから、この文書の中で言われているように、私たちが持っているものをしっかりと持ち続けなければいけない。」などと他のテアテラ人たちと一緒に心の中で思うはずである。何故なら、あなたはキリストが決して偽りを言われることのないお方であると知っているからである。だとすれば、あなたがテアテラ人として生きている紀元1世紀の間に、やはりキリストが再臨されるということになる。もしそうでなかったとすれば、テアテラ人であるあなたも、あなたの周りにいる他のテアテラ人たちも、キリストが嘘を言われたと思うことになるであろう。何故なら、キリストが自分たちに向けて「再臨があるまでしっかりとやるように。」と言われたにもかかわらず、実際は再臨が起こらなかったからである。そういうことであったとすれば、多くのテアテラ人たちがキリストとヨハネとその文書(黙示録)から離れていくことになっていたに違いない。実際は起こりもしない偽りを述べる存在や文書を、誰が信じられようか。しかし、ここでキリストが言っておられるように、確かに再臨はテアテラ人が生きている時代に起こった。御言葉がそのように我々に教え示しているのだから、そのように信じる以外にはない。既に第1章でも説明されたが、その再臨についての歴史的な証拠が神の摂理により残されていないので、多くの聖徒たちは再臨が既に起きたということを信じていないだけなのである。しかし歴史的な証拠がなくとも、御言葉という証拠があるゆえに、既に再臨が起きたのは明らかである。御霊を受けている聖徒たちは、この箇所によっても、再臨の真理を悟り、弁えるようにしていただきたい。御言葉で言われていることを信じようとしないのは、歴とした罪である。
【2:26~27】
『勝利を得る者、また最後までわたしのわざを守る者には、諸国の民を支配する権威を与えよう。彼は、鉄の杖をもって土の器を打ち砕くようにして彼らを治める。わたし自身が父から支配の権威を受けているのと同じである。』
これは、最後まで信仰を保って勝利した聖徒たちが、全世界の民を勝利者として裁くということである。これは具体的に言えば、紀元1世紀のことである。紀元68年6月9日に復活した聖徒たちは、その復活した状態で、自分たちの周りを取り囲んでいた全人類を表示するローマ兵たちにキリストにある裁きを下した。その裁きにより、ローマ兵すなわち全人類は裁きを受け、永遠の罪に定められ、神とキリストと聖徒たちの前に低められることになった。これは黙示録で言えば、20:9の箇所のことである。この箇所では、第一の復活にあずかったテアテラ人をはじめとした当時の聖徒たちが、自分たちを取り囲んでいるゴグとマゴグなるローマ兵(=諸国の民=全人類)に、天から御言葉という火を降り注いで霊的に焼き尽くしていることについて記されている。この20:9における天から降ってきた火とはすなわち御言葉である。また詳しく説明されることになるが、実際に聖徒たちと都エルサレムが包囲されたユダヤ戦争において―この歴史的な事実を疑うことはできない―、『聖徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ』(20:9)ローマ兵の上に火が降ってきて多くの死者が出たという出来事は、実際の歴史に適合していないので、この火とは霊的に理解すべきもの、すなわち御言葉という名の火であると捉えなければいけない。聖書で、御言葉を火と言い表わすのは、よくあることである。また、この箇所で言われていることは、Ⅰコリント書6:2の御言葉のことでもある。そこでは紀元1世紀の聖徒に対して、『あなたがたは、聖徒が世界をさばくようになることを知らないのですか。』と言われている。このコリント書の御言葉と、我々が今見ている黙示録の箇所で言われていることは、同じことを言っている。すなわち、紀元68年6月9日に復活した聖徒たちは、当時の全世界をキリストにあって裁いたのである。この2つの箇所がまだ実現していないとほとんど全ての聖徒たちが考えているが、そのように考えるのは誤りである。というのは、ヨハネもパウロも、自分の生きている時代にいた聖徒たちに、このような裁きの権が与えられるようになると言っているからである。「あなたがたが世界を裁くようになる。」と言われながら、そのように言われたのを聞いた聖徒たちに、そのことが起こらなかったというのはあり得ない。また、ここで言われている聖徒たちによる統御の期間を、長い期間であると捉えるべきではない。何故なら、ここでは『土の器を打ち砕くようにして』と書かれているからである。この言葉は、統御また裁きの期間が、一瞬の間であることを教えている。それは我々が、自分の支配する所有物である土の器を打ち砕く期間が、ほんの一瞬の間に過ぎないのと同じことである。言うまでもないことだが、自分の持っている土の器を打ち砕くのに、1年、10年、またはそれ以上の時間を費やす人は誰もいない。ここで『土の器を打ち砕くようにして』と言われているのは、非常に重要である(※)。この支配の期間が一瞬であると考えれば、黙示録、ことに20章の箇所とよく調和することになり、黙示録を上手にすんなりと理解できるようになる。しかし、これを10年であれ100年であれ1000年であれそれ以上の年数であれ長い期間であると捉えると、様々な矛盾が生じ、黙示録を上手に読み解けなくなってしまう。その場合、ここで言われている支配とは20章に書かれている『千年』(20:4)の時代のことであると考えるようになり、そのように考えると、必然的に20:7以降の箇所はまだ起きていないと理解しなければいけなくなってしまうが、そうすると、黙示録には『すぐに起こるべき事』(22章6節)が書き記されているという神の明瞭な言葉を否定することになってしまう。千年王国論者たちは、ただ感覚的に『千年』を長い期間だと捉えているに過ぎないのであって、深く聖書研究をした結果、そのような結論を出したというのではまったくない。しかし黙示録を時間をかけて考究すれば、この期間とは、すなわちほんの短い時間を意味しているに過ぎないことが分かる。この支配の期間を長いと考える者たちは、既に何度も述べたことであるが、神の明瞭な言葉、すなわち黙示録1:1および22:6における御言葉に言い逆らうことになってしまう。この聖徒たちによる支配のことについては、20章の箇所まで註解が進んだ際、更に詳しく論じられることになるであろう。また注意が必要だが、この箇所で言われている支配権の授与は、既に紀元68年6月9日において成就している出来事である。この箇所が未だに成就していないと考えることは許されない。何故なら、神の霊は、この箇所も含めて黙示録で言われていることは『すぐに起こるはずの事』(1章1節)であると言われたからである。神が黙示録で書かれていることは「すぐに起こるものだ。」と言われたにもかかわらず、それを否定して、「黙示録に書いてあることはすぐに起こらないこともある。」とか「黙示録の多くの箇所はすぐには起こらないことだ。」などと言うのか。口と心を慎みたまえ。聖徒であると見做されているにもかかわらず、神が言われたことをそのまま素直に信じようとしないあなたは一体何者なのか。そのような者は、もしかしたら御霊を受けていないということも十分にあり得る。なぜなら、御霊を受けていない者が、神の言葉をそのまま素直に受け入れることは絶対にできないからである。
(※)
ここで、「土の器は堅いので打ち砕くのに非常に長い時間がかかる。だから支配の期間は非常に長いのだ。」などと抗弁する者があってはならない。それは勝手な思い込みであって、普通に考えれば、この打ち砕きは一瞬にして終わるはずだからである。また「長い時間をかけて徐々に土の器を打ち砕いていくのだ。だから支配の期間も非常に長い。」などと考えることもすべきではない。そのように考えるのは屁理屈である。聖徒たちの鉄の杖とは力強いものであって、土の器とはすぐにも打ち砕かれてしまうものである。それゆえ、ここで言われているのが打ち砕きにおける一瞬性のことであるというのは疑えない。実際に考えてみれば分かるが、土の器を打ち砕くのに長い時間をかけるような人が、世界のどこにいるのか。そのような人がもしいたとすれば、変わった人であると思われたとしても文句は言えないのである。
[本文に戻る]
ご自身の命を永遠の犠牲として神にお捧げになられた我々の救い主は、テアテラ人をはじめとした紀元1世紀の聖徒たちに、ご自身が受けたのと同じ支配権を、紀元68年の再臨の時にお与えになった。キリストは、ご自身が受けた恵みに、ご自身に連なる聖徒たちをも与からせて下さる。それは、キリストが恵み深いお方であって、ご自身の民を愛しておられるからである。すなわち、ここでキリストがご自身に与えられたのと同じ支配の権を聖徒たちにお与えになると言っておられるのは、キリストの聖徒たちに対する恵みと愛の現われである。もしキリストが恵み深いお方でなく、聖徒たちを愛しておられなかったとすれば、聖徒たちにも幸いな恵みを味わわせようとされることはなかったはずである。このようなことは、黙示録3:21の箇所でも言われている。こちらのほうでは、キリストが輝かしい座に着いたのと同じように、聖徒たちも輝かしい座に着かせてもらえることについて書かれている。
【2:28~29】
『また、彼に明けの明星を与えよう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。」』』
『明けの明星』とは、すなわちキリストのことである。それはキリスト御自身が、黙示録22:16の箇所で『わたしは…輝く明けの明星である。』と言っておられる通りである。なお、聖書においては『明けの明星』がサタンを意味する場合もある(イザヤ14:12)。しかし、ここではサタンのことが言われているのではない。もしこれがサタンのことであるとすれば、キリストが最後まで信仰を保ち続けた勝利者にサタンを与えることになってしまうが、これは笑うべき解釈である。また、これが実際の物理的な天体を指すと考えてもいけない。これを実際的な天体であると考えると、キリストが勝利した信仰者たちに、天国において大きな星を手渡すことになる。このように解釈するのは、妄想的であり、ふざけている。黙示録を漫画物語にしてはならない。ここで言われているのは、つまり「勝利者にはキリストにある永遠の命が与えられる。」という意味に他ならない。
【3:1】
『また、サルデスにある教会の御使いに書き送れ。『神の七つの御霊、および七つの星を持つ方がこう言われる。』
これは、どのような意味を持った言い方であろうか。これは、つまりキリストが御霊により、また御使い(=星)を用いて教会を支配される主権者であられるということを分からせようとした言い方であると思われる。サルデス人たちは、神を自分たちの主権者とはしておらず、自分たちが自分たちに対する主権者であるかのように歩んでいた。これは良くないことであった。だからこそ、ここではキリストがご自身こそ御霊と御使いによってサルデス教会を支配する主権者なのだということを悟らせようとしている、というのが一つの可能な解釈である。これは、つまり次のように言っているのも同じである。「サルデス人たちよ。あなたがたは自分たちこそが支配者であるかのように死んだ歩みをしているが、そのような態度と精神は誤っている。あなたがたの支配者であるのは、御霊と御使いを持っているこの私なのだ。あなたがたはよく弁えよ。勘違いをしてはいけない。さあ、私から出た聖なる御霊に従い、またあなたがたの教会に割り当てられている御使いの導きに歩みなさい。」読者の中には、私が今書いたのとは違う解釈をする方もいるかもしれない。その解釈が、聖書に反しておらず、またまともであると感じられるものであれば、私はその人の解釈を否定することはしない。なお、ここで「神の7つの御霊を持つ」とキリストについて言われているのは、黙示録の中では、この箇所が初めてである。「7つの星を持つ」と言われているのは、既に1:16、1:20、2:1の箇所で言われていたことであった。
『「わたしは、あなたの行ないを知っている。あなたは、生きているとされているが、実は死んでいる。』
サルデスの教会に対しては、美点が何も言及されていない。何も美点が無かったので美点が挙げられていないのか、多かれ少なかれ美点は存在していたが単に挙げられていないだけなのか、我々には不明である。美点が何も言及されていないのは、黙示録に記されている7つの教会のうち、ラオデキヤとこの教会だけである。このサルデス教会に対して言われているキリストの言葉を読めば分かるが、この教会は、あまりキリストに喜ばれるような状態にはなかったように思われる。
このサルデス教会にいた聖徒たちは、聖徒らしい行ないをしてはいたのだが、その行ないには生きた誠実な心が伴っていなかった。それは、あたかも心のない死体が、操り人形のように動かされ、ただ外面的に良いと見られる善行をしているようなものであった。だから、ここでそのようなサルデス人に対して、キリストは『あなたは、生きているとされているが、実は死んでいる。』と言われたのである。つまり、サルデスの聖徒は生きてはいるものの、霊的に言えば死んでいるのも同然だということである。このようなことをキリストから言われたのは、サルデスの聖徒にとって、非常に大きな打撃であった。何故なら、キリストがこのように自分たちの真の姿を見抜いて大胆にそれを告げられただけでなく、そのような恥ずべき醜態が、他の諸教会にまで知られ渡ることになってしまったからである。しかも、愚かなことも嘘も言われないキリストが、全てを見ておられるキリストが、このように言われたのだから、言い訳をして自己防衛することもできない。これは、現代のことで例えるならば、多くのスターを育てたレコード会社のボスが、テレビ番組に出演して、自分の育てたスターについてこう言うようなものである。「あいつはニコニコしながら皆の前で踊ったり歌ったりしているが、アレは実は表面だけであって、心は伴っていないんだ。俺は前から、このことを知っていたし、またあいつに注意してもきた。だが、あいつは何も聞き入れなかった。心なんて分かりゃしないんだから大丈夫なんて言ってな。でも、もうこれ以上あのような精神でやっていくのなら、残念だけど、あいつを解雇することになる。客に対して心を入れられないようじゃ、プロとして問題があるからな。」このように言われてしまったスターは、ボスに対する恩と敬意と恐れとのゆえに、またこのことが真実であって客に対する申し訳ないという気持ちがあるゆえに、何も言い返せず縮こまるばかりである。ボスであるキリストからこのように真の姿が暴露されてしまったサルデス人たちも、このスターのように縮こまるしかなかったに違いない。もし聖徒らしい良い行ないをしていても、このサルデスの聖徒たちのように、そこに心が伴っていなければ、神から評価されることはない。いや、評価されないというより、「マイナス評価を受ける」と言ったほうが正しい。サルデス人たちは、そのようなマイナス評価を受けるような、あまり良いとは言えない状態にあった。読者である聖徒たちは、このようなサルデス人たちのようにならないよう、よくよく注意しなければいけない。
この箇所を読むと、『人はうわべを見るが、主は心を見る。』(Ⅰサムエル16章7節)という御言葉が思い起こされる。人間の目からすればよく見えても、神の目からすれば邪悪であったり愚かであったりするということは、世の中に少なくない。このサルデス人たちが正にそうであった。そうなると、主から『あなたは、生きているとされているが、実は死んでいる。』などと言われてしまうことにもなる。聖徒たちは、神から見られていることをよく覚え、人ではなくこの神からこそ評価されることを求めるようにすべきである。人からの栄誉を受けるよりも、神からの栄誉を受けるほうが、遥かに優っている。というのも、人の栄誉よりも神からの栄誉のほうが、素晴らしく、また価値があるからである。だから、人からは悪く思われるが神からは良く思われるほうが、神からは悪く思われるが人からは良く思われることよりも、よい。霊的でない人は、このことを悟ることはできない。サルデス人たちは、心を見抜けない人間からは悪く思われていなかったが、心を見抜かれる神からは悪く思われていた。これを読んでいる読者が、このサルデス人たちのようにならないことを私は願うものである。福音書に出てくるあの指導者たちは、人の栄誉を求めたからこそ『彼らは、神からの栄誉よりも、人の栄誉を愛した』(ヨハネ12章43節)などと言われて非難されてしまったのである。
【3:2~3】
『目をさましなさい。そして死にかけているほかの人たちを力づけなさい。わたしは、あなたの行ないが、わたしの神の御前に全うされたとは見ていない。だから、あなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを堅く守り、また悔い改めなさい。』
死人も同然の状態になっている悲惨なサルデス人たちは、悔い改めて、真の聖徒に相応しい生きた行ないをしなければいけなかった。彼らが悔い改めなければいけなかったのは当然である。何故なら、彼らは聖徒の守るべき最大の律法、すなわち『心を尽くし、知力を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。』という律法に違反していたからである。だから、キリストが彼らに対して悔い改めを命じられないということは、あり得ないことであった。異常な状態になってはいたにせよ、あくまでもサルデス人たちは、キリストという師につく弟子だったのである。自分の弟子が悲惨な状態になっているのにもかかわらず、その状態を改善させようとしない師が、どこにいるであろうか。そのようにしない師がいたとすれば、それは師とは言い難い。
『もし、目をさまさなければ、わたしは盗人のように来る。あなたには、わたしがいつあなたのところに来るか、決してわからない。』
もしサルデスの聖徒たちが悔い改めなかったとすれば、キリストが『盗人のように来る』という結果が彼らを待っていた。これはつまり、「もしあなたがたが悔い改めなければ私は思いがけない時に再臨して、悪い歩みをしているあなたがたを裁くことになるであろう。」ということである。キリストが盗人のように突如として来るというのは、詳しく言えば、紀元68年6月9日における再臨の時のことである。この箇所やマタイ24:42で言われているように、確かに、当時の人たちは誰一人として―人としてキリストでさえ―紀元68年6月9日にキリストの再臨が起こるということは分からなかった。再臨がこの日に起きた際、当時の人たちは仰天したに違いない。盗人が侵入して来た際には誰でも仰天してしまうように。もしサルデス人たちがこのように言われたにもかかわらず悔い改めていなかったとすれば、再臨の日に彼らが空中へ携挙された際には、左のほうにより分けられていたはずである。何故なら、悔い改めない者について、キリストがこのように言われたからである。『あなたがたも悔い改めないなら、みな同じように滅びます。』(ルカ13章3、5節)悔い改めない者には滅びあるのみ。実際にこのサルデス人たちが悔い改めたかどうかについては、我々が天国に行った際、知れるようになるであろう。今はこのことついて何も言うことはできない。キリストはここで実にサラッと述べておられるが、これはつまり悔い改めなければ滅ぼされるということであるから、実に恐るべき威嚇であったと言える。これを「死の宣告」と呼ばずして何と呼んだらよいであろうか。
【3:4】
『しかし、サルデスには、その衣を汚さなかった者が幾人かいる。』
衣を汚すというのは、やがて着せられることになる天上における栄光の身体を損なう、すなわち自分をやがて着せられることになるはずだった栄光の身体に相応しくない者としてしまう、という意味であると私は解する。確かに、死人も同然であったサルデス人たちは、天上の身体を着るに相応しくない歩みをすることで、その天上の身体を汚す、つまり損なってしまっていた。このように解すると、この箇所ではかなり難しい言い方がなされていることになるが、聖書の中には難しい言い方が満ちているので、たとい難しい言い方がされていることになろうとも誤りであるとは必ずしも言えないし、私が今述べた解釈が荒唐無稽であるというわけでもない。このように解するのは、十分に可能であって、そこに強引さや矛盾性はない。ここで言われている『衣』を天上の身体でない衣、つまり地上における聖徒たちの身体という衣であると捉えることはできない。この衣が本来的に聖徒たち自身のものであるとすれば、おかしなことになってしまう。何故なら、聖徒たちが本来的に持つ自分の身体という衣は、原罪により、また日々犯す罪により、生まれた初めの時から既に汚れているからである。既に汚れている衣について、『その衣を汚さなかった者が幾人かいる。』などと言われるのは、明らかに普通ではない。我々は、この箇所においては、本来は汚されていなかったが罪や愚かさなどが原因となり汚されてしまった衣について言われているということに、よく留意せねばならない。つまり、ここでは最初から、また本来的に、あるいは既に汚されている衣について言われているのではない。
この箇所から分かるのは、サルデス教会には、まともな聖徒がほとんどいなかったということである。何故こう言えるかといえば、ここでキリストが『衣を汚さなかった者』は『幾人』すなわち少しばかりしかいないと述べておられるからである。まともでない聖徒の比率がどのぐらいであったかは分からないが、この御言葉から推測すれば、大多数がまともではなかったと思われる。今までキリスト教の歴史においては実に多くの教師たちが初代教会の聖性・純粋さ・その敬虔の度合いを称賛し、それを見習うように教えたり述べたりしたものだが、死人のような聖徒が多かったこのサルデス教会や、異端に陥っていたガラテヤ教会や、異邦人にさえ見られないほどの悪徳が見られたコリント教会や、初めの愛を失っていたエペソ教会や、忌まわしい偽預言者を放置し続けていたテアテラ教会といった初代教会のことを考えると、いくらか初代教会に対して過剰な評価をしている面があったのではないかと私には思える。「初代教会は素晴らしい聖性に満ちていた。」と言いたい気持ちはよく分かるのだが、当時の教会には、異端や大きな悪徳や見過ごせない未熟さの見られた教会が少なくなかった、というのが真実である。しかも、あの使徒たちが直接的に監督していたにもかかわらず、である。それゆえ、初代教会に対する賛美の度合いは、その過剰さをいくらか抑えるべきであると私は考える。初代教会を高く評価している人に、「それではサルデス教会またガラテヤ教会といった初代教会も私たちは見習うべきなのでしょうか。」などと問えば、その人は絶対に頷くことをしないはずである。
『彼らは白い衣を着て、』
『白い衣』とは、すなわち御霊の身体のことを指す。『白い』と言われているのは、御霊の身体における清さと聖性のゆえである。ヴァン・ティルはこの衣について言う。「この衣は、もはや罪のぬかるみに触れることはない。義の環境の中で、永遠に完全なものであり続ける。」(『ヴァン・ティルの十戒』第十戒 p203:いのちのことば社)この衣がすなわち御霊の身体であるということを、黙示録から示すと、こういうことである。まず『白い衣』とは、19:14によれば『きよい麻布』のことである。この『きよい麻布』とは、19:8によれば『聖徒たちの正しい行ない』である。この『正しい行ない』と呼ばれている『きよい麻布』(=『白い衣』)が、正に御霊の身体のことなのである。何故なら、御霊の身体とは正しい行ないしかしないのであって、この身体は正しい行ないをするために存在しているからである。つまり、この白い衣なる御霊の身体を着た聖徒たちは、もはや罪を犯すことがなく、正しい行ないだけをするようになる。この言葉は黙示録の他の箇所でも使われているから(3:5、3:18、4:4、6:11、7:9、7:14)、今ここで、その意味をよく覚えておくのが望ましい。どの箇所でも、その意味は「御霊の身体」である。
【3:4~6】
『わたしとともに歩む。彼らはそれにふさわしい者だからである。勝利を得る者は、このように白い衣を着せられる。そして、わたしは、彼の名をいのちの書から消すようなことは決してしない。わたしは彼の名をわたしの父の御前と御使いたちの前で言い表わす。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。』
ここでは、最後まで信仰を保って勝利する者たちに対して与えられる、種々の恵みの約束についてキリストが語っておられる。その約束は、全部で4つに分けられる。一。勝利者には、『白い衣』なる御霊の身体が着せられることになる。再臨の起こる紀元68年6月9日までに死んだ聖徒は、再臨の起こる日までは身体のない魂だけの状態となるが、再臨の日になると、その魂に御霊の身体が与えられることになる。再臨が起こるその日まで生き残っている聖徒の場合、再臨の際に鳴るラッパの響きと共に、たちまちにして古い身体が滅びて新しい身体が着せられることになる。『ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。』(Ⅰコリント15章52節)とパウロが言っている通りである。二。勝利して白い衣を着せられた者は、天国において、いついつまでもキリストと共に歩むようになる。何故か。それは『彼らはそれにふさわしい者だから』である。キリストは、ご自身を否まずに勝利する者たちを愛され、その者たちをご自身の永遠の友とされる。それは、あたかも王が戦いに勝利して凱旋した将軍を愛し、その将軍と生涯に渡って深い親交を結ぶようになるようなものである。もちろん、この世の王と将軍における親交が一時的なものに過ぎないのに対し、王の王であられるキリストと聖徒における親交は永遠に至るまで続く、という大きな違いがあるのではあるが。三。勝利者は、その名が『いのちの書』から消し去られることが決してない。つまり、勝利する者には、永遠の命という定めが取り消されることはない。その者は、いついつまでも生き続けることができる。この『いのちの書』という言葉は、永遠の命に定められているというその定めのことを、人の名が書き記される名簿という物質的なものを通して、象徴的に言い表わした言葉である。すなわち、この言葉は、永遠の命に定められている人たちの全てを、書物という形で総体的に表現した言葉である(※①)。カトリックお気に入りのトマス・アクィナスのこの書に対する理解は、私と同じである。彼はこの書について次のように言っているが、これは正しい理解である。「神において書は比喩的にのみ語ることができる。そうした比喩的意味で、生命の一覧表自体が生命の書と言われるのである。」(『中世思想原典集成 第Ⅱ期1 トマス・アクィナス 真理論 上』第7問題第1項 p449:平凡社)「生命の書とは、生命を授ける者が或る人についてあらかじめ秩序づけられていることに即して生命を授けるとき、その者がそれに即して導かれる一種の記載表のことである。」(同 第7問題第5項 p463)アウグスティヌスの場合、「神の国」20巻において、この書について「生命の書は誤りえない神の予知である。」と言っているが、これは悪くない理解である。彼が同書の中で次のように言っているのも、私の気に入らない理解ではない。「(生命の書とは)或る神的な力が理解されるべきであって、その力によって各人は善かれ悪しかれすべての行いを思い起こすことになる。この神的な力は確かに書という名称が与えられている」。また、この『いのちの書』という言葉は、いくらか言われ方が違う場合もあるが、聖書の他の箇所でも使われている(※②)。主が『ただあなたがたの名が天に書き記されていることを喜びなさい。』(ルカ10章20節)と言われたのも、この『いのちの書』という言葉と意味内容としては同じである。なおトマスは、この書について「生命の書は神において本質的に語られるか、あるはペルソナ的に語られるか、が問われる。」(『中世思想原典集成 第Ⅱ期1 トマス・アクィナス 真理論 上』第7問題第2項 p454:平凡社)などと言っているが、これは些末な問題であって修道士的な暇潰しに他ならないから、本質的な事柄をこそ真っ直ぐに考究すべき我々は問題にしなくてもよい。また、彼が「生命の書と同様、死の書が語られるか、が問われる。」(同 第7問題第8項 p471)と言っているのも同様である。四。勝利する者は、キリストが神と御使いたちの前で、その者の名を言い表わして下さる。キリストは何を言い表わされるというのか。それは、その者がご自身と共に永遠に生きるに相応しい者であるということを、である。その者は、その口により、神と御使いたちとが見ている前でキリストを否むことがなかったので、キリストもその者を神と御使いたちとの前で否まれることをされない。むしろ、その者はキリストが主であるということを神と御使いたちが見ている前で告白したので、キリストも、その者がご自身の民であるということを神と御使いたちが見ている前で告白して下さる。キリスト御自身がマタイ10:32でこう言っておられる。『わたしを人の前で認める者はみな、わたしも、天におられるわたしの父の前でその人を認めます。』オバデヤ書15では『あなたがしたように、あなたにもされる。』と書かれているが、キリストは聖徒がした通りのことを、その聖徒に返されるのである。しかし、神と御使いたちとが見ている前でキリストを否んだ者に対しては、キリストも神と御使いたちとが見ている前でその者の名を否まれる。すなわち、「この者は私に相応しい者ではありません。」という意味のことを言われる。それは、キリストが『人の前でわたしを知らないと言うような者なら、わたしも天におられるわたしの父の前で、そんな者は知らないと言います。』(マタイ10章33節)と言われた通りである。なお、この種々の約束は、直接的には、紀元68年の再臨の日のことを対象として言われた約束である。
(※①)
霊性の高い人であったグレゴリウスは、この書について「やがて到来する審判者自身が生命の書である。というのも、彼を見るであろう人は誰でも、彼の為したことをすぐに思い起こすであろう。」(Moralia XXIV,cap.8,PL76,295B)と言っている。この理解は私としては嫌いではないが、しかしこの書はキリスト御自身として捉えるよりは、キリストにある永遠の命の定めのことであると理解すべきであろう。
[本文に戻る]
(※②)
例えば詩篇69:28。『彼らがいのちの書から消し去られ、正しい者と並べて、書き記されることがありませんように。』
[本文に戻る]
しかしながら、これらの恵みは普遍的な意味内容を持っているから、当時の聖徒たちだけではなく、21世紀の時代に生きる我々に対しても言われていると捉えなければいけない。最後まで信仰を保ってキリストにある勝利者とならなければ、このような素晴らしい恵みが我々に与えられることはないであろう。
【3:7】
『また、フィラデルフィヤにある教会の御使いに書き送れ。『聖なる方、真実な方、ダビデのかぎを持っている方、彼が開くとだれも閉じる者がなく、彼が閉じるとだれも開く者がいない、その方がこう言われる。』
ここでは、キリストが3つの言われ方により、言い表わされている。『聖なる方』とは、『キリストには何の罪もない』(Ⅰヨハネ3章5節)、つまりキリストが清く崇高な存在であるということである。このキリストを言い表わした言葉は、黙示録では、まだ出てきていない。『真実な方』とは、キリストが『その口に何の偽りも見いだされませんでした。』(Ⅰペテロ2章22節)ということ、つまりキリストが嘘や偽りを言われない真っ直ぐな存在であるということである。この言葉は、1:5に出てきた『忠実な証人』という言葉と意味としては同じであるから、既出であると言える。『ダビデのかぎを持っている方』と『彼が開くとだれも閉じる者がなく、彼が閉じるとだれも開く者がいない』という言葉は、明らかにイザヤ22:22の箇所と対応した言葉である。イザヤ書ではこう書かれている。『わたしはまた、ダビデの家のかぎを彼の肩に置く。彼が開くと、閉じる者はなく、彼が閉じると、開く者はない。』これは間違いなくキリストについて言われたことである。『ダビデのかぎ』とは、つまりキリストの王権のことである。すなわち、これは、ダビデのような王権を持っているキリスト以外には誰も天国の門を開け閉めすることができない、ということを教える言葉に他ならない。天国の門を開け閉めできる王としての権はキリスト以外には誰も持っていないので、キリストが天国の門を開けるならば誰も閉じることができず、閉めるならば誰も開けることはできない。だから、ここで『彼が開くとだれも閉じる者がなく、彼が閉じるとだれも開く者がいない』などと天国の門について言われているのは真実である。つまり、これは、キリストが天国を開け閉めできる王としての権力を持っておられるということを、キリストの予表としての王であるダビデの名において、鍵として言い表わした言葉なのである。ダビデは、有名で偉大な王である上、キリストを指し示す意味を持った王であった。それゆえ、キリストの王権を示す鍵が、そのダビデの名により言い表わされたのは実に適切なことであった。この『ダビデのかぎ』という言葉の解読はかなり難しいが、私が今述べた以外の解読は、恐らくできないと思われる。これは、天国を開閉できる権を象徴的に言い表わした表現だと捉えるのが望ましい。なお、この言葉が出てくるのは、黙示録ではここが初めてである。すなわち、この言葉は既出ではない。それでは、この箇所では、どうしてフィラデルフィラ教会に対してキリストがこのように言い表わされているのか。それは、フィラデルフィヤ教会に対して書かれた文章との関連性を考えれば、すぐに分かる。このフィラデルフィヤ教会の聖徒には、キリストがその王権をもって彼らのために天国の門を開いて下さったということが言われている(8節)。つまり、冒頭でこのようにキリストが言い表わされているのは、キリストが天国の門を開いて下さったということの真実性が、強調されるためであった。何故なら、キリストが聖であり、真実であって、しかもそのような方がダビデの鍵を持っておられると言われたならば、それだけキリストが天国の門を開かれたということにおける真実性の度合いが強められるからである。ここでこのように言われているのは、言い換えれば、次のように言っていることである。「フィラデルフィヤの聖徒たちよ。私はあなたがたのために天国の門を開いておいた。私はダビデの鍵、すなわち天国を開くことのできる王権を持っているから、そのようにできるのだ。これは嘘ではない。というのも、私は聖であって真実な存在だからである。そのような存在である私が、どうしてあなたがたに嘘を言うであろうか。私が聖であり真実であると信じるのなら、そのような私がダビデの鍵を使って天国の門を開いたと言ったことを、確かなこととして信じなさい。」
【3:8】
『「わたしは、あなたの行ないを知っている。見よ。わたしは、だれも閉じることのできない門を、あなたの前に開いておいた。なぜなら、あなたには少しばかりの力があって、わたしのことばを守り、わたしの名を否まなかったからである。』
フィラデルフィヤの聖徒は、わずかではあったが真の信仰を持っていた。その信仰の力により、彼らはキリストとその御言葉とを斥けることをしなかった。このようなフィラデルフィヤの聖徒を、キリストはここで評価しておられる。キリストとその御言葉とを尊重することは、神の御心にかなったことであり、非常に良いことである。
このフィラデルフィヤの聖徒たちは、キリストとその御言葉を斥けなかったので、彼らのために天国の門が開かれているという希望を持たせる言葉がここでは語られている。これは、つまりフィラデルフィヤの聖徒たちが天国に入れる資格を持っているということ―その資格は神からのものである―、またそのままの状態を彼らが続けるならば天国に入れるようになるということである。実際に、この教会の聖徒たちは、もしそのままの状態で歩み続けていたというのであれば、再臨の起こった紀元68年6月9日に、既に開かれている天国の門をくぐって天国に入ったはずである。何故なら、キリストが天国の門を開かれたのは、フィラデルフィヤの聖徒たちのような者がそこに入れるようにするためだったからである。もしそうでなかったとすれば、一体なんのために天国の門が開かれたのか分からなくなってしまう。なお、キリストがダビデの鍵、すなわち天国を開く王権を使われたのは、キリストの昇天の時、つまり紀元33年ぐらいのことである。この時、キリストが天に入られるのと同時に、天国の門が開かれることになった。それ以降、この天国の門は、選ばれた者たちがそこに入れるようになるために、ずっと開かれたままである。天国の門が開かれたままであるというこのことについては、後ほど、また詳しく語られることになるはずである。
【3:9】
『見よ。サタンの会衆に属する者、すなわち、ユダヤ人だと自称しながら実はそうでなくて、うそを言っている者たちに、わたしはこうする。見よ。彼らをあなたの足もとに来てひれ伏させ、わたしがあなたを愛していることを知らせる。』
フィラデルフィヤの聖徒たちの周りには、『サタンの会衆に属する者』、すなわち自分が救い主の出たユダヤ民族であると自称することで、優越感の喜びを抱いていた愚かな俗物どもがいた。ここでキリストが言っておられるように、彼らは『ユダヤ人だと自称』しているだけであって、肉的な意味でも霊的な意味でも(※)ユダヤ人ではなかった。このような愚か者たちは、神の子らではなかったから、サタンに属する子らであった。自己を他の何者かに偽装させる者たちには常のことだが、この『サタンの会衆に属する者』たちは聖徒たちに屈辱を与えることで高ぶりの喜悦を楽しんでいた者であろうから、フィラデルフィヤの聖徒たちは彼らに悩まされていたか、そうでなければ多かれ少なかれ不快感を抱かされていたに違いないと私は思う。この自称ユダヤ人なる俗物たちは、スミルナ教会の箇所でも言及されている(2:9)。恐らく、この時代のアジヤ西部には、このような者たちがそれなりに多くいたのであろう。ちょうど、今の時代で言えば、世界各地で異端者や新興宗教に属する者たちが世の顰蹙を買いながらも公然と活動しているように。
(※)
霊的な意味におけるユダヤ人とはクリスチャンのことである。
[本文に戻る]
自分たちの出自がキリストと同じであると偽ることで優越感の喜びと偽りの誇りとを抱いていたこの者たちには、やがて裁きが下されることになると、ここでキリストは言っておられる。その裁きとは、この偽り者たちが自分たちの見下しているフィラデルフィヤの聖徒たちの前に来てひれ伏し、主に喜ばれているのは、実は自分たちではなくフィラデルフィヤの聖徒たちのほうだったということが明らかにされる、という裁きである。この偽り者たちは、キリストと同じ出自を誇ることで自分たちこそがキリストに喜ばれる者であると感じていただろうから、このような逆転の裁きが下された際には、大いに驚いたのではないかと思われる。誠に、『ああ、彼らにわざわいあれ。彼らは悪の報いを受けるからだ。…悪者にはわざわいあれ。』(イザヤ3章9、11節)という悪者について語られた御言葉は、真実である。彼らはユダヤ人たちだと自称して神の御前に悪く振る舞っていたので、このような裁きを受けることになってしまったのである。また、『だれでも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされる』(ルカ18章14節)というキリストの御言葉も、正に真実である。ここで言われている自称ユダヤ人たちは自分たちを高めたがゆえに墜落して低くされ、他方、自称ユダヤ人たちから屈辱を味わわされ低められていた聖徒たちはキリストにより高くされた。それでは、ここで言われている自称ユダヤ人たちに対する裁きとは、いつのことであろうか。これには2つが考えられる。まず一つ目は、これは再臨の日の裁きのことを言っているという考えである。つまり、再臨の起きた紀元68年6月9日の時に、空中において自称ユダヤ人たちがフィラデルフィヤの聖徒たちの前に来させられて屈辱を味わわされることになった、ということである。2つ目は、これは再臨が起こる前の日に起きた裁きなのだと考えることである。この2つ目のほうが現実的に思えるのではあるが、しかし、1つ目のほうの考えを完全に退けることはできない。もしかしたら、この裁きとは、再臨の日のことを言っているという可能性も十分にあるからである。どちらが正しかったにせよ、一つだけ確かに言えることは、この箇所で言われている裁きは、既に実現済みであるということである。すなわち、自分たちをユダヤ人になりすませている者たちは、既に遥か昔の時において、フィラデルフィヤの聖徒たちの前にひれ伏している。これは、我々にとっては、もう起こったことなのである。この裁きが、黙示録が書かれてから2千年も経過した今になっても未だに起きていないなどと考えてはいけない。
主は、この箇所で『見よ。』と2回も言っておられる。この言葉は強調の意味を持っているが、つまり、ここでは非常に力強く悪者の裁きについて語られていることになる。この箇所で主は、あたかも次のように言っておられるかのようである。「いいか。思い違いをしてはならない。あなたがたの周りにいる自称ユダヤ人たちが裁きを受けないままでいることは絶対にあり得ない。フィラデルフィヤの聖徒たち。よく聞きなさい。彼らはいずれ必ず裁きを受けることになるであろう。あなたがたは、このことをよく覚えておかなければいけない。」
主が、ここで悪い者たちに対する裁きを語られたのは、古い時代の終末に生きるフィラデルフィヤの聖徒たちにとっては、非常な励ましと慰めと力になったと思われる。何故なら、全世界の王であるキリストが、自分たちにとって有害な存在である悪者たちが裁かれると約束して下さったからである。一方、この裁きの言葉は、裁きを受ける当の本人たちにとっては、当然のことではあるが、良く思えるものではなかったはずである。何故なら、ここではやがて自分たちに対して裁きが下されることになると言われているからである。
【3:10】
『あなたが、わたしの忍耐について言ったことばを守ったから、わたしも、地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時には、あなたを守ろう。』
この箇所で言われている『試練の時』とは、すなわちネロによる42ヶ月の迫害を指している。この期間は非常に長いというのではないが、しかし、その期間において行なわれる迫害の度合いは誠に凄まじいものであった。実に、その迫害が凄まじいからこそ、神はヨハネを通して、このような警告の文書を当時の聖徒たちにお与えになったのである。ここではその試練が『全世界に来ようとしている』と言われているが、この『全世界』という言葉は、慣用的に、すなわち当時のヨーロッパおよび中東の周辺を指した意味を持つものとして捉えねばならない。つまり、これは21世紀の時代に生きる我々が考えるような意味における全世界のことではない。既に第2部で説明されたように、当時における『全世界』という言葉は、慣用的に捉えるべきであって、それは地球の全土を指しているのではない。黙示録13:7ではネロが『あらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた』と書かれているが、これは文字通りではなく慣用的に捉えなければいけない。それと同じように、我々が今見ているこの箇所における『全世界』という言葉も、慣用的に捉えなければいけない。もしこの試練が文字通りの意味における『全世界』に来るというのであれば、それは歴史の事実にそぐわないことである。読者は、ルカ2:1で書かれている『全世界』という言葉が文字通りに捉えられるべきものではないと第2部で説明されたことを思い返してほしい。今の時代の聖徒であれば、その多くは、ここで言われている試練が未だに起きていないと信じていることであろう。しかし、そのように信じることはできない。何故なら、ヨハネは、紀元1世紀の聖徒に対し、すぐにも起こるべきことを語っているからである。それがすぐにも起こるからこそ、ヨハネは、この黙示録の中で、それをすぐにも起こるべきこととして語っているのである。もし、すぐにも起こらないことが言われているとしたら、ヨハネは当時生きていた聖徒たちに対して何を言ったというのか。遥か未来に起こる出来事を、あたかもすぐにも起こる出来事であるかのように、それも非常な切迫感を持って語ったとでもいうのか。聖徒たちは、そのような荒唐無稽なことを考えるべきではない。そのように考えるのは、神とヨハネを詐欺師に仕立て上げるのも等しいことである。
この厳しい試練が訪れた際には、フィラデルフィヤの聖徒たちが守られることになる、とここでキリストは約束しておられる。それは、彼らがキリストの御言葉を守ったからであった。『わたしを愛する者を、わたしは愛する。』(箴言8章17節)と主は言っておられる。フィラデルフィヤの聖徒は、主を愛してその御言葉を守ったので、主も彼らを愛して、ご自身の御言葉を守った彼らが守られるようにして下さるのである。もし彼らが主の御言葉を守っていなければ、試練の際に守られることはなかったはずである。何故なら、彼らが主を愛さず、その御言葉を守らなかったからである。聖徒たちが主を愛さなければ、その態度に応じて、主も聖徒たちを愛されはしない。サムエル記15:23には、『まことに、そむくことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。』と書かれている。フィラデルフィヤの聖徒が主に従っていなければ、それは彼らが占いや偶像崇拝の罪を犯すことであった。占いや偶像礼拝の罪を行なう者を、どうして主が守って下さるであろうか。それでは、ここで『守ろう。』と言われているのは何のことか。すなわち、キリストは何を対象として『守ろう。』と言われたのか。これが聖徒たちを対象としていることは明白であるが、聖徒たちの「身」が守られると言われたのか、それとも「信仰」が守られると言われたのか。主がここで守られると言われたのは、聖徒たちの「信仰」のことであった。というのも、たとえ身体は守られなくても、信仰が守られるのであれば、それは真の意味において守られたと言えるからである。しかし、身体のほうは守られても、信仰のほうは守られなかったとすれば、それは一見すると守られているかのように思えるが、実は守られていないことになる。何故なら、その場合、身体は守られたものの、信仰が守られなかったために最終的には地獄に投げ込まれてしまうからである。はて、地獄に行くことになるのに、「守られた。」などと言えるのであろうか。決して言えないであろう。このように、ここで守られると言われたのを、身体のことに限定して考えることはできない。しかし、信仰と共に身体も守られた、と考えるのであれば、それは不可能な解釈ではない。私は今ここで守られるのは「信仰」であると述べたが、信仰と共に身体のほうも守られたという可能性も十分にある。いずれにせよ、実際にフィラデルフィヤの聖徒たちは、ここでキリストが約束しておられる通り、試練が訪れた際には守られたことであろう。キリストが偽りを言われることは決してないからである。
【3:11】
『わたしは、すぐに来る。あなたの冠をだれにも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。』
前の節で言われたように、確かにキリストは聖徒たちの信仰を守って下さるのであるが、しかし、聖徒たち自身も、自分で自分の信仰を保持するようにと、ここでは言われている。これは、キリストが守って下さるからといって、聖徒たち自身が自己の信仰を堅く保とうしないのは愚かで怠惰なことだからである。キリストが守られるからというので、何もしないで呆けているのは、明らかに愛と礼節の義務に違反している。これはパウロが選ばれている信仰者に対して、その信仰者が選ばれているにもかかわらず『立っていると思う者は、倒れないように気をつけなさい。』(Ⅰコリント10章12節)と言ったのと同じことである。その信仰者は選ばれているため信仰から脱落するということはあり得ないのではあるが、それにもかかわらず、パウロはその信仰者が愚かで怠惰な者にならないように、こう言ったのである。もしこのように言わなければ、選ばれているということに安心しきってしまい、その安心感が多くの悲惨をもたらすことに繋がりかねない。それと同じように、キリストも守りをしっかりと与えて下さるにせよ、聖徒たちが悲惨にならないように、聖徒たち自身も自分で自分を防衛するようにと言われた。もしそのように言われなければ、フィラデルフィヤの教会には、「キリストが守って下さるのだから俺たちは何も頑張らなくてもよいのだ。寝ていようが遊んでいようがキリストが守って下さることには変わりない。さあ、楽にしていよう。」などと思って安逸を貪る怠惰な者が多く出てしまっていたに違いない。だから、ここではあたかも、このように言われているかのようである。「フィラデルフィヤの聖徒たちよ。私はあなたがたを確かに守ろう。しかし、だからといってあなたがた自身が自分で自分の信仰を保持しようと努力しなくてもよい、ということではない。確かに私があなたがたを守るにせよ、あなたがたも信仰の努力を怠ってはいけない。私が再臨するのは、もう間もなくのことなのだ。だから、その短い間において、しっかりとやりなさい。まさか、そんなに短い時間だけでも、私のために努力できないということではあるまい。少しの間だけ、あなたがたは信仰の努力をすれば、それでよいのだ。私は何も非常に厳しく難しいことを、あなたがたに言っているわけではないのである。このことをしっかりと心に覚えよ。」語句の解説に移りたい。ここで言われている『冠』とは、すなわち「約束において既に与えられている命の冠」を指す。地上に生きる聖徒たちは、まだ天国に入っていないのだから、実際的な意味においては命の冠を持っていない。しかし、約束においては、また希望においては、既にどの聖徒も命の冠を持っている。つまり、ここで『あなたの冠をだれにも奪われないように』と言われているのは、他の誰かによって命の冠を与える信仰を失うことがないようにせよ、という意味である。『あなたの持っているもの』とは、すなわち「信仰」のことである。こちらのほうが『冠』という言葉よりも、幅広い意味を持つ。すなわち『冠』という言葉が「命の冠」だけを限定的に指しているのに対し、『あなたの持っているもの』という言葉は、信仰全般のことを指している。ここで『あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。』と言われているのは、つまり「あなたがたの持つ信仰を最後まで堅く保持せよ。」という意味である。
この箇所では『わたしは、すぐに来る。』と書かれている。この聖句は、既に再臨が起きたことを明瞭に証明する聖句の一つである。紀元1世紀の時代に生きていたフィラデルフィヤの聖徒に対して、キリストがこのように言われたのである。であれば紀元1世紀の時点での意味における『すぐ』、すなわち今から2千年前の時代にキリストが再臨されたことになる。このように言われたフィラデルフィヤの聖徒たちは、間違いなく、キリストが言われた通り、キリストは本当に『すぐに来る。』と信じたはずである。誰がこのことを疑うであろうか。そうであれば、キリストがすぐに再び来られると約束された以上、彼らの生きている間に再臨が起こらなければ、おかしいことになってしまう。今まで教会は、このようにキリスト御自身が再臨はすぐに起こると言われたにもかかわらず―偽ることのない神がそのように言われたにもかかわらず―、再臨が未だに起きていないと信じ続けてきた。今の時代の教会も、あいかわらず、そのように信じ続けている。今に至るまで聖徒たちは、キリストの語られた再臨についての御言葉とその御言葉を信じた紀元1世紀の聖徒たちに対し、罪を犯し続けてきたと言ってよい。その罪とは、キリストの言われたことを素直に信ぜず、またキリストの言われたことを信じた初代教会の聖徒たちを無意味な期待を抱く愚か者に事実上仕立て上げてきた、という罪である。今まで聖徒たちは、再臨が未だに起きていないと信じることにより、暗に次のように言っていたのも同然であった。すなわち、こうである。「キリストは再臨がすぐに起こると言われたが、それは嘘であった。再臨はすぐに起きておらず、それどころか未だに起きていないのだから。また再臨がすぐに起きると言われたことを信じた初代教会の聖徒たちも、無意味な期待を抱いていた。何故なら、彼らは再臨がすぐには起きないにもかかわらず、すぐにも起こるかのように信じていたからだ。実際、彼らは再臨がすぐに起こると信じていたが、彼らの生きている時代に再臨は起きなかったではないか。」いや、こういうことを私たちは言っていない、と多くの聖徒たちが思うであろう。確かに、実際に聖徒たちがこのように言っているというのではない。しかし、実際にはこのように言っていなかったとしても、再臨はすぐには起きなかったと信じるのは、事実上このように言っているのも等しい。すなわち、「再臨はすぐには起きなかった。」というその信仰自体が、上で言われたようなことを事実上告白している。それでは、今までどうして聖徒たちには、再臨の真理が隠され続けてきたのであろうか。それは既に第1部でも説明されたように、まだ再臨の真理が明らかにされる「時」が訪れていなかったからである。これは例えるならば、成人になるまでは飲酒が禁止されているために、子どもには、まだ酒の味が分からないようなものである。時が来て成人になれば酒の味が理解できるようになるのと同じで、キリスト教にも時が来たので、遂に再臨の真理という名の酒が味わえるようになったのである。もう再臨の真理が明らかにされる「時」が来たのだから、聖徒たちは、再臨を正しく理解し信じるようにしてほしい。
【3:12】
『勝利を得る者を、わたしの神の聖所の柱としよう。彼はもはや決して外に出て行くことはない。』
これは、勝利を得て天国に入れられた聖徒が、天国における聖所から決して遠ざけられることはない、という意味である。どこかの宮殿にある柱は、不動であり、ずっとそこにあり続ける。そのように聖徒たちも、天国において存在的な意味で不動であり、ずっとそこに居続ける。そこから離れない、いつまでもそこに存在している、という意味において、天国の聖徒たちは正に「柱」である。我々は、この箇所を読んで、聖徒たちが本当に柱のようになってしまうなどと考えてはいけない。これは、あくまでも象徴として捉えねばならない。また、聖徒たちが柱になると聞いて、聖徒たちがあたかも柱のようにじっと留まったままでいると考えてもいけない。つまり、動くことも喋ることもできない像のようになるなどと考えはいけない。黙示録7:15では、天国の聖徒たちが『昼も夜も、神に仕えている』と言われている。つまり、勝利して天国に入った聖徒たちは、そこから追い出されないという意味では正に柱そのものなのだが、勤勉に働くという意味では柱のようでない。紀元68年の再臨の日までキリストに保たれて勝利した聖徒たちは、ここでキリストが言っておられるように、天国の聖所における柱とされた。彼らは今に至るまで天国から離れることがなかったし、今も離れていないし、これからも離れることがない。何故なら、彼らは聖所における柱だからである。紀元1世紀以降の聖徒たちも、勝利するのであれば、天国の柱にしてもらえる。そのような柱となれば、その聖徒は、永遠に天国から離れることがない。そのような不動の柱になりたいと願う聖徒は、最後まで信仰を保ち、キリストにある勝利者となれるように努力奮迅せねばならない。
【3:12~13】
『わたしは彼の上にわたしの神の御名と、わたしの神の都、すなわち、わたしの神のもとを出て天から下って来る新しいエルサレムの名と、わたしの新しい名とを書きしるす。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。』
勝利した聖徒たちの額には、3つの名が刻まれることになる。まず一つ目は『神の御名』、すなわちキリストの父なる神の御名である。旧約聖書の中では、神の御名がいくつも書かれており、一つに限定されてはいない。その複数の御名のうちどれが聖徒の額に刻まれることになるかは、我々には分からない。何故なら、ここでは神の御名が書かれると言われているだけで、どの御名が書かれるのかということは、何も言われていないからである。聖書に何も書いていないのに、どうして「この御名だ。」などと我々が断定できようか。しかし、可能性として最も高いと感じられるのは、やはりあの聖四文字(YHVH)である(※①)。というのも、旧約聖書の多くの箇所では、神がこの御名により語られているからである。旧約聖書を開けば、至る所に「神であるヤハウェは…」などと書かれているのを我々は知っている。二つ目は『新しいエルサレムの名』である。このエルサレムの名が、どのような名前で、またどのような文字により書かれるのかは不明である。なお、この新しいエルサレムは、黙示録21章の箇所で詳しく説明されている。三つ目は『わたしの新しい名』、すなわちキリストの新しい御名である。はて、我々の主であるキリストは、天国では新しい御名を持っておられるのであろうか。つまり、天国においてキリストは「イエス・キリスト」などとは、もはや呼ばれないのであろうか。どうやら、そのようである。ここでは主が、ご自身には新しい名があると言っておられるのだから、我々はそのことを信じるべきであろう。しかし、それがどのような御名であるのかは、現時点の我々には知らされていない。先に2:17の箇所では、聖徒たちに新しい名が与えられると言われているということを、我々は確認した。つまり、天国に行った者は、キリストであれ聖徒たちであれ、地上にいた時とは違う新しい名を持つことになるのだ。天国に入るとは、今までとはまったく違う人生を送ることであるから、新しい名がつけられるというのは、そのような変化に相応しいと言える。天国に行って新しい名を与えられた聖徒たちの額には、新しい名を持たれたキリストの新しい名が、先に見た2つの名と共に刻まれることになる。ここで聖徒たちにこのような3つの名が書かれると言われているのを、我々は象徴として捉えるべきではない。つまり、これは文字通りに捉えるべきである。勝利して天国に行った聖徒たちの額には、本当にこのような3つの名が書かれることになる。それは、ちょうど神が石の板に10の戒めを書き記されたのと同じことである。これを文字通りに捉えねばならないというのは、黙示録22:4の箇所からも、そのように言える。すなわち、この箇所でも聖徒たちについて『彼らの額には神の名がついている。』と書かれているが、これは文字通りに受け取るべき箇所である。もし聖徒の額に何も書き記されないのであれば、このようには書かれていなかったはずである。さて、この3つの聖なる名は、聖徒たちの額に横文字で、縦3列に並べて書き記されると思われる(※②)。というのも、人間の額は横方向に長く拡がっているのであって、縦3列に横文字で書かれるのがもっとも自然だと思えるからである。もしそうでなく、縦文字で横3列に並べて記されるとすると、どこか不自然である(※③)。しかも、この場合、文字が額のスペースに収まりきるのか分からないという心配が出てくる。この場合、額の小さい人であれば、眉毛の部分まで文字が達してしまうということにもなりかねない。そうすれば、美観的に非常に惨めだと感じられることにもなる。美と調和の神が、そのようにされるとは考えにくい。また、この3つの名が額に書き記される順序は、ここでキリストが言っておられるのと同じ順であると思われる。つまり、キリストは、この箇所で実際に書き記されることになる順番通りに、その名を書き記しておられるのだと思われる。そのように理解するのが、もっとも理に適っており、また無難である。
(※①)
ヘブル語には母音が存在していないので、この御名が実際に、どのような発音で呼ばれていたのか今となってはまったく不明である。それゆえ、この聖四文字は人によって「ヤハウェ」「ヤーヴェ」「ヤーウェ」などと違った呼ばれ方をされているが、どれも間違ってはいない。私も「ヤハウェ」と呼ぶ時があれば、「ヤーウェ」と呼ぶ時もある。
[本文に戻る]
(※②)
つまり、以下のように書き記されるということである。
―――――――――
神の御名
エルサレムの名
キリストの御名
―――――――――
[本文に戻る]
(※③)
以下のようだと、額が横長であるのと適合しておらず、どこか不自然に感じられてしまう。
―――――――――
神 エ キ
の ル リ
御 サ ス
名 レ ト
ム の
の 御
名 名
―――――――――
[本文に戻る]
ここで勝利した聖徒たちの額に名が記されると教えられているからといって、我々は、いずれ自分の額に神からの名が記されることになるのを、恐れたり、驚いたり、嫌がったりしてはならない。神が聖徒たちの額に名を記すのは、聖徒たちが神の所有物であるからに他ならない。もし聖徒たちが神の所有物でなければ、その額に名が記されることもなかったであろう。だから、自分の額に神からの名が記されることになるのを厭う者は、自分が神の所有の民であることに不快感を持っていることになる。その人は、神の所有の民であることを不快に感じるからこそ、所有の証拠として名が筆記されるのも嫌だと思うのである。神の民である者が、自分が神の所有物であることを嫌がっていいはずが、どうしてあるであろうか。そのように嫌がるのは、良くないことである。聖徒である者は、聖徒の額に名が記されるということを聞いて、むしろそのことを喜び、期待し、神に感謝すべきである。神は、聖徒たちを愛しておられるからこそ、そのように名を額に刻んで下さる。額における名の筆記は愛の証拠であると言ってよいであろう。もし我々がサタンの子らであったとすれば、永遠の昔から憎まれていたのであるから、そのような愛と所有の証拠としての名が記されることもないのである。ところで、我々が自分の所有物に、それが自分の所有であることを示すための名を記す際、その所有物がバラムのロバのように理性を持って「名を記すのは止めて下さい。」などと反抗したらどうであろうか。恐らく、多くの人が驚きの伴った不快感を持つのではなかろうか。もし我々が自分の額に神からの名が記されることを拒むのであれば、神も、そのように驚きの伴った不快感を我々に対して持たれるはずである。どちらの場合も、自分の所有物である存在が、傲慢にも反抗しているからである。それゆえ、我々が神から不快感を持たれたくないのであれば、自分の額に名が記されることを嫌がるべきではない。
我々人間の額は、元から聖なる名を書き記すためのスペースとして造られていると思われる。つまり神は、人間の額を名前を書き記すためのスペースとして、最初の人であるアダムを造られた時から備えておられたということである。というのも、この額とは、正に何かの文字を書き記すための場所としか考えられないからである。こんなにもマジックで何かを書き記しやすい場所が、手の甲を除いて、他にどこにあるであろうか。もちろん、神が文字を書き記すのはマジックによるのではないことは言うまでもない。しかも、この額という場所には、筆記以外の用途があるとは思えない。この地上における今の状態では、神がまだ誰が真に神の子どもであるのかということを万人に対して明らかにしておられないために、誰の額にも何かが書かれていることがない。神は、この地上世界では、誰が真の選民であるかということを隠しておられる。だからこそ、この地上世界においては、たとえ真の聖徒であっても、まだその額には何も書かれていないわけである。しかし、天国では全ての人が聖徒であるということが自明であり、誰が真の聖徒であるかということを隠す必要がまったくない。だから天国においては、あらゆる人間の額に聖なる名が書き記されているのである。もしこの地上世界で誰かの額に既に聖なる名が刻まれていたとすれば、また天国にいる人間の額に聖なる名が刻まれていなかったとすれば、それはどちらもおかしいことである。それは、地上世界という場所がまだ額に何も記すべきではない場所であって、天国という場所のほうは額に何かが記されているべき場所だからである。だから、今の地上世界に生きている人間の額に何も書かれていないからといって、天国にいる人間の額にも何も書かれていないと思ってはいけない。聖書は、天国にいる人間の額には聖なる名が記されていると教えている。よって、今の世界ではまだ人間の額に何も記されていなかったとしても、天国においては人間の額に名が記されることになるのだと我々は信じるべきである。
それでは、天国に行った人間の額に聖なる名が記されるというのであれば、地獄に投げ込まれた人間の額にも、聖なる名ではないにしても、何らかの名が記されるのか。その可能性は非常に高い。何故なら、地獄も天国と同様に、そこにいる者たちがどのような種類の者であるか明白に分かっており、額に選びの秘密を隠す必要がまったくないからである。天国で額に名が記されるのであるから、地獄でも、そこにいる者の額には名が記される、と考えるのは荒唐無稽ではない。それでは、もし地獄で人間の額に名が記されるとすれば、それはどのような名であろうか。天国にいる者たちの額に記されるのが、そこにいる者たちの主人の名とその場所の名であるのだから、地獄にいる者たちの額にも、そこにいる者たちの主人の名とその場所の名が記されるはずである。すなわち、そこにいる呪われた子らの額には、サタンの名と地獄の名が記されることになる。そのように記されることで、彼らがサタンの子らであり、地獄の住民であるということが、明らかに示されるのである。その記され方は、天国の場合と同じで、恐らく横文字で縦2列に並べた記され方になるはずである。しかし、それがどのような名前で記されるのか、また文字の言語はどのようなものか、ということについては、まったく分からない。―その額に記された名が燃える炎により消えてしまうことはないのか。答え。そのようなことはないであろう。―そのようにして額に邪悪な名が記されたら、もう2度とその名を消してもらうことはできないのか。答え。セカンドチャンスが存在しないとすれば、そのようなことはないであろう。
【3:14】
『また、ラオデキヤにある教会の御使いに書き送れ。『アーメンである方、忠実で、真実な証人、神に造られたものの根源である方がこう言われる。』
ラオデキヤ教会にいる聖徒たちに対しては、キリストが3つの言い方により言い表わされている。まず最初に『アーメンである方』と言われている。これはキリストが、全てのことについて、ことに神の約束について「然り」すなわち「アーメン」以外ではあり得ない存在であるという意味である。確かに、このお方にとっては、「しかり」でありながら「否」でもあるということは、まったくあり得ない。これは、パウロがコリント人に対してこう言った通りである。『私たち、すなわち、私とシルワノとテモテとが、あなたがたに宣べ伝えた神の子キリスト・イエスは、「しかり。」と同時に「否。」であるような方ではありません。この方には「しかり。」だけがあるのです。神の約束はことごとく、この方において「しかり。」となりました。それで私たちは、この方によって「アーメン。」と言い、神に栄光を記するのです。』(Ⅱコリント1章19~20節)これは、黙示録では初めて出てくるキリストの言われ方である。次は『忠実で、真実な証人』と言われている。これはキリストが偽ることのない純粋な存在であるという意味である。これは既に1:5および3:7の箇所で言われていた言い方である。最後は『神に造られたものの根源である方』と言われている。これは、つまり『すべてのものは、この方によって造られた。』(ヨハネ1章3節)ということである。被造物の中で、キリストを根源としていない存在は、一つもない。サタンでさえも、元を辿ればキリストを根源として持っている。何故なら、サタンもキリストを通して創造されたからである。我々人間もキリストを根源としているということは、言うまでもない。『造られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。』(同)と書かれている通りである。この言われ方は、黙示録では、ここで初めて出てくる。それでは、どうしてラオデキヤ教会には、キリストがこのような言われ方により言い表わされたのか。それは、生ぬるい歩みをしていたラオデキヤ人たちが、キリストの威厳や卓越性を豊かに感じられるようにするためであったと考えられる。悲惨な状態のラオデキヤ人たちが、このようにキリストが言われているのを聞けば、キリストの偉大さを再認識し、心を入れ替えて敬虔に歩めるようにもなる。この箇所では、あたかも、このように言われているかのようである。「ラオデキヤ人たちよ。キリストは全てにおいて「アーメン」であられる。またこのお方は純粋そのものであられる。そして、このお方こそ万物の根源者であられる。このように偉大なキリストが、あなたがたに御言葉を賜わるのだ。謹んで聞きなさい。聞いて悟りなさい。悟ったならば悔い改めなさい。そして敬虔に歩むようにせよ。このような卓越したお方の御告げを無駄に受け取ってはならない。」
【3:15~17】
『「わたしは、あなたの行ないを知っている。あなたは、冷たくもなく、熱くもない。わたしはむしろ、あなたが冷たいか、熱いかであってほしい。このように、あなたはなまぬるく、熱くも冷たくもないので、わたしの口からあなたを吐き出そう。あなたは、自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分がみじめで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸の者であることを知らない。』
ラオデキヤの聖徒たちには、美点が何も言及されていない。美点がいくらかでもあったが言及されていないのか、何も無かったから言及されていないのかは、我々には不明である。サルデス教会と同じで、このラオデキヤ教会は、あまり主に喜ばれるような状態にはなかった。しかし、それであっても、この教会があくまでもキリストの肢体であることには変わらなかった。我々は、あのコリント教会でさえ、パウロにより『神の教会』(Ⅰコリント1章2節)と呼ばれたことを思い返すべきである。コリント教会や、このラオデキヤ教会のようにたとえ異常な状態にあっても、そこが神の支配のうちにあるのであれば、そこは歴としたキリストの教会なのである。このラオデキヤ教会は、例えるならば、親の手を焼かせる未熟な子どものようであった。異常で未熟であっても、それが子どもであれば、やはり、あくまでも子どもなのである。
このラオデキヤ人たちは「生ぬるい」状態にあった。つまり、暑い日に食べる冷たい食べ物のように、また寒い日に食べる熱い食べ物のように、好ましいと感じられるようではなかった。誰でも猛暑なのに冷たくない物を口にしたり、極寒の地にいるのに熱い物を食べられなかったりすれば、やはりその生ぬるさのゆえに不満を感じるはずである。「もっと冷たければ(または熱ければ)どれだけ良いことだろうか。」などと残念に思うはずである。生ぬるい歩みをしていたラオデキヤ人たちは、神にとっては、正にそのような満足できない食べ物も同然であったわけである。しかし「生ぬるい」とは具体的には、どういうことか。それは簡単に言えばパウロのようではなかったということである。ラオデキヤ人たちは、パウロのように敬虔な歩みをしておらず、愛も信仰も純粋さも足りなかった。つまり学生で言えば、上の学年に上がれない劣等生のようであった。このようなラオデキヤ人たちが肉的な歩みをしていた、すなわち御霊によって歩めていなかったことは間違いない。
そのような惨めな歩みをしていたラオデキヤ人たちに対して、キリストは『わたしの口からあなたを吐き出そう。』と言っておられる。キリストは、ラオデキヤ人たちが生ぬるかったので、口の中から吐き出してしまいたいと思っておられた。これは、つまりラオデキヤ人たちがキリストから切り離されて、サタンに餌として与えられるということである。何故なら、もしキリストの口から彼らが吐き出されるのであれば、もう口の中には存在していないので、もはやキリストと一体ではないからである。そのように吐き出されると、サタンに餌として食われてしまうから、サタンの会衆と化してしまうのである。つまりサタンの口に入れられるのだから、サタンと契約的に一体化してしまうわけである。だから、ここで『吐き出そう』と言われているのは「キリストの御国から追い出そう。」ということに他ならない。これは実に恐ろしい威嚇の御告げである。ここでは『わたしの口からあなたを吐き出そう。』と言われているが、これはすぐにも吐き出されるということではない。これは、「吐き出したくて仕方がないから、もし悔い改めが見られなかったならば容赦なく吐き出すことにしよう。」という意味に捉えるべきである。キリストはすぐ後の箇所で悔い改めを命じておられるのだから(19節)、もし彼らが悔い改めたならば、吐き出されずに済んだのは明らかである。このような威嚇を受けたラオデキヤ人たちは、戦慄したことであろう。しかし、このような威嚇を受けたのは、彼らが生ぬるかったのが原因であるから、自業自得であると言える。もしラオデキヤ人たちが生ぬるくなければ、このように言われることはなかった。
また、このラオデキヤ人たちは、とんでもない思い違いをしている自惚れ屋であった。彼らは自分たちが『富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もない』と思ったり言ったりしていた。すなわち、自分たちは暑い日の冷たい食べ物や、寒い日の熱い食べ物のように、神にとって喜ばしい存在であると、本当はそうでないにもかかわらず、勝手に思っていた。しかしキリストは彼らの思いとは逆に、彼らが『みじめで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸の者である』と言われる。つまり、キリストは彼らが、神に喜ばれる食べ物のようではなく、むしろ神から嫌だと思われるような生ぬるい食べ物のようであると言っておられる。このような思い違いを彼らがしていたのは、誠に愚かで悲惨だったと言わねばならない。しかしながら、このような誤った自己評価は、人間には特に珍しいものではない。自分の肉眼で自分の姿を見ることができないように、人は往々にして自分のことを正しく評定できないものである。多くの場合、自分を客観的に見るのは、至難の業である。キケロも「自分のことを正しく評価するのは難しい。」と言ったが、彼がこのように言ったのは間違っていない。
この箇所から分かることだが、キリストは本質的な部分をこそ重視され、問題にされる。何故なら、キリストは、もし本質的な部分が悪ければ、全てが悪いということをよく弁えておられるからである。誰かがラオデキヤ人たちのように自分たちを高く見ていても、キリストはその本当の姿をご存知であられる。もし自分を誤って評価し、ラオデキヤ人のように不当に認識しているのであれば、やがてキリストから責められることにもなりかねない。世の中にいる人の中で、どれだけ多くの人が、このラオデキヤ人のように自分を誤って評価しているであろうか。我々は、全てを見抜かれる神の目を恐れ、その御前に高ぶらず謙遜に歩まねばならない。そうしなければ、このラオデキヤ人のような自惚れ屋になりかねない。
【3:18】
『わたしはあなたに忠告する。』
キリストがラオデキヤの聖徒に忠告されるのは、もちろん彼らのためであった。すなわち、キリストはラオデキヤ人たちが改善できるようにと、彼らのことを思って、このような忠告をされた。『キリストでさえ、ご自身を喜ばせることはなさらなかった』(ローマ15章3節)と言われているお方が、自分を喜ばせようとして、つまり高圧的に語ることで優越感を得ようとして、このように語ったのではないことは言うまでもない。『神は愛』(Ⅰヨハネ4:8)であるから、全てのことを愛をもって行なわれるのであって、ここで忠告をしておられるのも例外ではない。もしラオデキヤの聖徒たちが知恵のある者であったとすれば、このような忠告を聞いて受け入れ、悔い改めると同時にキリストを愛していたことであろう。それは、『知恵のある者を責めよ。そうすれば、彼はあなたを愛するだろう。』(箴言9章8節)と書かれているからである。しかし彼らが愚かな滅びの子であったとすれば、忠告に反発し、キリストを憎んでいたであろう。『あざける者を責めるな。おそらく、彼はあなたを憎むだろう。』(同)と書かれているからである。このようにキリストが彼らを責めつつ忠告されたのは、一見すると悲惨なように見えるかもしれないが、実は彼らにとって幸いなことであった。ヨブ記5:17でも、『ああ、幸いなことよ。神に責められるその人は。』と言われている。何故なら、このように責められるからこそ、改善できるようにもなるからである。もしラオデキヤの聖徒たちに、このような忠告がされなかったとすれば、それこそ彼らにとっては不幸なことであった。それは災難である。何故なら、責められたり忠告されたりしないので、悪徳に気付かないまま改善することもできず、最終的には滅びに至ってしまうからである。もちろん、このような忠告を受けねばならないその状態そのものは惨めであった。私が幸いだと言っているのは、その惨めな状態のことではなく、その惨めな状態を改善できるようにと忠告を受けられることである。それゆえ、彼らは惨めであったが幸いであり、幸いであるが惨めであったと言える。
『豊かな者となるために、火で精錬された金をわたしから買いなさい。また、あなたの裸の恥を現わさないために着る白い衣を買いなさい。また、目が見えるようになるため、目に塗る目薬を買いなさい。』
この箇所では、物理的なことが言われていると思ってはいけない。つまり、この箇所では、どこかにある店に行って金や衣や目薬を買うようにと命じられているのではない。そのように捉えるのは実に肉的である。キリストの前にいて話を聞いていたユダヤ人たちは、キリストの言われたことを肉的に捉えたので、キリストの言われたことを誤解して躓くことになった。例えば、彼らはキリストがご自身の神殿について言われたにもかかわらず石造りの神殿について言われたと勘違いしたり(ヨハネ2:17~22)、キリストの肉を食べることについても料理屋で食事を食べるかのように思い違いをしてしまった(ヨハネ6:52)。我々は、このように肉的な人たちが陥った愚に陥らないようにしよう。実際、この文書を受け取ったラオデキヤ人やその他の教会にいた聖徒たちのいくらかは、ここでキリストが言われていることを読んで肉的に捉え、「どうして主は金や衣や目薬を買えと言われたのか。」などと疑問に感じたはずである。このような捉え方をするのは、誤っている。事柄は霊的にこそ捉えねばならない。ここにおいて、「選び」が大いにかかわってくる。すなわち、選ばれている人は事柄を霊的に捉えて正しい解を得るに至るが、選ばれていない人は事柄を肉的に捉えるので、いつまでも正しく悟ることがない。それゆえ、選ばれている人は、この箇所を霊的に捉えて正しい解を悟るべきである。そして正しい解を悟ったならば、主なる神に感謝せよ。神の恵みがなければ、選ばれることも、霊的に捉えることも、正しい解を得ることも、まったくあり得ないことだからである。
ここで『買いなさい。』と命じられているのは、買うようにと言われているその対象物を、獲得したり、使ったり、自分に適用させたりする、という意味である。箴言には、『真理を買え。』(23章23節)と書かれている。これは、物理的な購買行為のことを言っているのではなく、「真理を自分のものとせよ。」という意味に他ならない。我々が今見ているこの箇所で『買いなさい。』と言われているのも、そのような意味に捉えなければならない。しかし、何を支払うことによって買えというのか。それは、時間・意志・精神・努力などといった目に見えないものによって、である。このような目に見えない代金を支払うことにより、ラオデキヤ人たちは、買えと言われている対象物を自分のものにすることができた。もし彼らが何も支払うことなしに、つまりは怠惰になって何もしないでいたのであれば、その対象物を手に入れられなかったのは言うまでもない。ただ呆けているだけの人が、何を手に入れられるであろうか。ところで、注意してほしいのだが、私がここで支払うことにより命じられたものを買えると言ったからといって、行為義認のことを言ったのではない。私が言ったのは、あくまでも呆けていたのであれば何も起こり得ない、ということであって、何らかの行ないにより義認や救いや天国に入れる特権が獲得できるということでは決してない。それと同様に、ここでキリストが『買いなさい。』と言っておられるからといって、キリストが行為義認の教理を教えているなどと考えてはいけない。すなわち、ここでは何かの犠牲を払うという行いにより救済が得られると教えられている、などと思ってはいけない。
聖書をよく読み慣れた読者であれば、ここで言われていることを解読するのは、それほど難しいことではない。とはいっても、もちろん解読できるのは神の恵みによるのであって、たとえどれだけ簡単な箇所であっても、我々は神の恵みなしには決して御言葉を解読することができないのではあるが。ここでは3つのものを買いなさいとキリストが言っておられる。まず『豊かな者となるために、火で精錬された金をわたしから買いなさい。』と言われているが、これは、試練という名の火に耐えられるような力強い信仰を持ちなさい、という意味である。『火』とは試練を指している。何故なら試練とは火で焼かれるように苦しいものだからである。ペテロも、次の御言葉が示すように、苦しみの伴う試練を「火」に例えている。『愛する者たち。あなたがたを試みるためにあなたがたの間に燃えさかる火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろ、キリストの苦しみにあずかれるのですから、喜んでいなさい。』(Ⅰペテロ4章12~13節)『精錬された金』とは、試練により研ぎ澄まされた信仰を指す。何故なら、研ぎ澄まされた信仰とは、精錬された金のように尊く、輝かしく、価値があり、重要なものだからである。確かに研ぎ澄まされた信仰とは精錬された金そのものであると言えるのだが、しかし金以上に尊いとも言える。ここでキリストは信仰を金に例えておられるが、ペテロの場合は、金よりも尊いと言っており、どちらかが間違っているというわけではない。このペテロの場合、『信仰の試練は、火を通して精錬されてもなお朽ちて行く金よりも尊い』(Ⅰペテロ1章7節)と言っている。弱々しい信仰しか持てていなかった惨めなラオデキヤ人たちは、主に喜ばれない状態にあった。そのような状態は良いとは言えず、当然ながら改善されねばならない。だからこそ、主に喜ばれるために、精錬された金のような筋金入りの信仰を持つ必要があったわけである。『裸の恥を現わさないために着る白い衣を買いなさい。』とは、すなわち白い衣を自分にもたらすことになる信仰をしっかりと持ちなさい、という意味である。しっかりとした信仰を持つ者は、希望において既に白い衣を、その身に着ていると言える。何故なら、そのしっかりとした信仰が、その人にやがて白い衣が与えられることを確証しているからである。それは、まだ聖徒たちが実際には天の座に着いていないにもかかわらず、希望においては既に着いているので、あたかも今の時点で着いているかのように言われたのと同じである(エペソ2:6)(※)。このラオデキヤ人たちは、しっかりとした信仰を持てていなかったので、白い衣を希望において着ることができておらず、それゆえ神の御前に恥ずべき裸も同然の状態であった。神の御前における真の服装とは霊的に言えば白い衣だけであるから、この白い衣を希望においてさえ着ていない者は、神から裸の状態にあると見做されている。ラオデキヤ人たちは、キリストの民であったのだから、そのような裸の状態であってはいけなかった。それゆえ、ここでキリストはしっかりとした信仰を持つことで、彼らが希望において白い衣をしっかりと着るように言われたわけである。『目が見えるようになるため、目に塗る目薬を買いなさい。』とは、御霊によって歩めという意味である。ここで『目に塗る目薬』と言われているのは、恐らく御霊のことであろう。ラオデキヤ人たちは肉的な死んだ目を持っていたので、何も正しく認識できず、それゆえ正しく歩むことができていなかった。だから、彼らは御霊という目薬を肉の目に注すことで、物事を正しく認識し―物事を正しく認識するとは御霊によって認識することに他ならない―、その正しい認識に基づいて正しく歩むようになる必要があった。だからこそ、キリストはここで、肉的な死んだ目ではなく御霊による生きた目を持つようにと言っておられるわけである。もし御霊という目薬を目に注すのであれば、肉の死んだ目が回復し、よく見えるようになるからである。このように、この箇所では3つのことが命じられているのだが、ラオデキヤ人たちが実際にこの命令に聞き従ったかどうかということは、何も記録が残されていないので我々には分からない。実際にはどうだったか不明ではあるが、ラオデキヤ人たちはこのように言われてしまうほどに惨めな状態にあったのだから、多くの者がキリストの命令に反発して従わなかったということも十分にあり得る。
(※)
このことについては、アウグスティヌスもこう言っている。「将来起こるのを疑わない事柄がすでに起こったと見なすことは、むなしいことではなく、信仰深いことである。」(『アウグスティヌス著作集25 ヨハネによる福音書講解説教(3)』第111説教(17章24―26節)2 p345:教文館)
[本文に戻る]
【3:19】
『わたしは、愛する者をしかったり、懲らしめたりする。』
キリストは、ラオデキヤの聖徒たちを愛しておられた。もちろん、キリストが愛しておられたのは、この教会にいる選ばれていた聖徒たちだけである。この教会にいた者のうち、聖徒であると見做されてはいても、使徒でありながら実は滅びの子であったユダのような者たちは、当然ながら愛されてはいなかった。その者たちは、キリストから愛されているどころか、むしろエサウのように憎まれていた。この教会にいた本当に愛されている聖徒の数が、またその比率が、どれほどであったかということについては、分からない。我々はこの時代にいたわけではないし、全てを知っておられる神でもないのだから、もしその数と比率を知れたとしたら驚くべきことである。しかし、これは些細な問題に過ぎないから、このことが分からなかったとしても思い悩んだりする必要はない。もしラオデキヤ教会にいた者が、すべて滅びの子であったとすれば、この黙示録において7つの教会の一つに選ばれることはなかったはずである。というのも、サタンの子らしかいない教会に何かを書き送ったとしても一体何になるであろうか。そのようなことをするのは、無意味なことであると思われる。しかし、このようにラオデキヤ教会は、7つの教会の中の一つとして選ばれている。これは、つまり、この教会にいくらかでも真の聖徒がいたことを意味している。なお、ここで言われている「愛する者」とは、すなわち「永遠の昔から天国に至るように選ばれていた者」のことを言っている。
キリストはラオデキヤ教会の聖徒たちを愛しておられたからこそ、彼らに叱責や懲らしめを、お与えになられる。それは人間の親が、自分の子を愛しているからこそ、その子のために叱責や懲らしめを与えるのと同じことである。もし子に叱責や懲らしめを与えないのであれば、それはその子が悪徳に留まるのを許容することを意味しているから、たとえその子を愛していると口では言っていても、実のところ愛してはいない。だから、叱責や懲らしめというのは、愛の証拠であると言ってよい。すなわち、それらのものは愛の具体的な表われなのである。私が今述べたこのことについては、聖書で次のように言われている。『わが子よ。主の懲らしめをないがしろにするな。その叱責をいとうな。父がかわいがる子をしかるように、主は愛する者をしかる。』(箴言3章11~12節)『むちを控える者はその子を憎む者である。子を愛する者はつとめてこれを懲らしめる。』(箴言13章24節)それゆえ、もしラオデキヤの聖徒が愛されていなかったとすれば、キリストが彼らに叱責や懲らしめをお与えになることはなかったであろう。憎んでいる者を、どうして改善させて良い状態にすべく、叱責したり懲らしめたりするであろうか。
『だから、熱心になって、悔い改めなさい。』
愛の証拠としての叱責や懲らしめをラオデキヤ人が受けたならば、それに応じて、彼らは悔い改めなければいけなかった。何故なら、キリストはラオデキヤ人が改善されるようにと、叱ったり懲らしめたりされるからである。もしキリストがそのようにされたにもかかわらず、悔い改めないようであれば、キリストが何のためにそのようにされたのか分からなくなってしまう。またラオデキヤ人たちは、ただ悔い改めれば良かったというのではなく、『熱心になって』悔い改めなければいけなかった。すなわち、ダニエルが灰をかぶったように(ダニエル9:3)、ネヘミヤが泣いたり断食をしたように(ネヘミヤ1:4)、心からの態度を伴った悔い改めが求められていた。それは何故なのか。それは、ラオデキヤ人たちが、かなり悲惨な状態に陥っていたからである。彼らは不敬虔という名のどす黒い闇の霧に覆われて霊的に窒息せんばかりだったのだから、熱心に悔い改めることにより、その厄介な霧を強力に吹き飛ばす必要があったわけである。一般の社会においても、その犯した罪の量や度合いが多大であればあるほど、より豊かな反省の念が要求される。それと同じように、このラオデキヤ人たちには、より豊かな悔い改めが要求されていたのである。また、この『熱心になって』という短い言葉から、ラオデキヤ教会が、どれだけ悲惨な状態に陥っていたかがよく分かる。というのも、この2~3章の箇所では他の教会にも悔い改めるようにと命じられてはいるのだが(2:5、2:16、2:22、3:3)、それらの教会にはただ悔い改めるようにと言われているだけで、このラオデキヤ教会のように『熱心になって』悔い改めるようにとは言われていないからである。この『熱心になって』という短い言葉は、ラオデキヤ教会がその他の教会よりも惨めな状態であったことを示す言葉であると考えるべきではないかと思う。読者の中で、悔い改めねばならない悪徳に陥っている人が、いるであろうか。その人は、ラオデキヤ人に悔い改めるようにと言われているキリストの御言葉を聞いて、自分も悔い改めるべきである。そうすれば、その悪徳に対する赦しがキリストから与えられるであろう。何故ならキリストは、悔い改める者に対しては、愛をもって赦しをお与えになるお方だからである。
もしラオデキヤ人たちが、悔い改めよと命じられたにもかかわらず悔い改めなかったとすれば、どうなっていたのか。その場合、彼らは永遠の滅びに至ることになっていた。何故なら、主は『あなたがたも悔い改めないなら、みな同じように滅びます。』(ルカ13章3、5節)と言われたからである。罪を悔い改めないならば、その人の罪はキリストにおいて赦されていないのだから、罪があるままの状態に残ってしまう。そうすると、その罪のゆえに、地獄に投げ込まれて永遠に滅ぼされることになってしまう。キリストにより罪を処理しておかなかったので、その罪の処理を自分でしなければいけなくなるのだ。悔い改めなかったラオデキヤ人たちは、地獄に投げ込まれて滅び、今もそこで火による苦しみを受けている。このことから、悔い改めないということが、どれだけ愚かで悲惨であるかということが、よく分かる。つまり、悔い改めないとは、みずから地獄を選択するのも等しいことなのである。これ以上の愚かさと悲惨が他にあろうか。
【3:20】
『見よ。わたしは、戸の外に立ってたたく。』
ここで『戸』と言われているのは、天国の戸ではなく、ラオデキヤ教会の教会堂に付けられていた戸でもなく、聖徒たちの心における戸を意味している。ラオデキヤ人たちは、キリストに対して心の戸を閉ざしていた。彼らは、心の中に、まだ本当の意味でキリストを受け入れてはいなかった。つまりパウロが『こうしてキリストが、あなたがたの信仰によって、あなたがたの心のうちに住んでいてくださいますように。』(エペソ3章17節)と言ったことは、まだラオデキヤ人には実現されていなかった。だから、彼らが思ったり行なったりすることは、すべてキリストとその名に基づいてはいなかった。心の中にキリストがいて下さらないのに、どうしてキリストにあって生きることができるであろうか。このように彼らは自分の心からキリストを締め出していたので、キリストのことを真に考慮してはおらず、キリスト抜きで王となっていた。だから、彼らが思ったり行なったりすることは、すべて自分自身という主権者によっていた。これがキリストに喜ばれる状態でなかったことは言うまでもない。何故なら、キリストこそが聖徒たちの主権者だからである。
キリストは、ご自身を真の意味で受け入れようとしていなかったラオデキヤ人たちの心を、外に立って叩かれた。それは、彼らが心の戸を開いて、キリストを受け入れるようになるためであった。ラオデキヤ人たちが、このように叩かれるキリストに応じ、心の戸を開くべきであったということは言うまでもない。もし王が臣下の家を訪ねて、その戸を開くようにと叩き続けたのであれば、その王を受け入れるために戸を開かない臣下は恐らくいないはずである。もし王のために戸を開かなかったのであれば、その臣下は不忠実の悪徳を罰せられても文句は言えない。そのようにキリストという王に戸を叩かれた臣下であるラオデキヤ人たちも、キリストという王を受け入れるべく戸を開かなければいけなかった。もしラオデキヤの人々が、御霊を受けていたのであれば、キリストのために戸を開けたことであろう。何故なら、御霊は、聖徒たちがキリストを受け入れるように働きかけられるお方だからである。しかし彼らが御霊を受けていなければ、キリストを戸の外に放置し続けていたことであろう。御霊を受けていない者は、サタンの霊に突き動かされているがゆえに(エペソ2:1~2)、キリストを受け入れることが決してできないからである。例のごとく、ラオデキヤ教会にいた人たちがキリストに対して戸を開いたかどうかは、実際には分からない。
『だれでも、わたしの声を聞いて戸をあけるなら、わたしは、彼のところにはいって、彼とともに食事をし、彼もわたしとともに食事をする。』
もしラオデキヤの人々たちが、せっかくキリストが戸を叩かれたにもかかわらず、戸を開かなかったとすれば、一体どうなっていたであろうか。その場合、彼らは、キリストから拒絶されることになった。何故なら、キリストとはすなわち「報いの神」であられるから(※)、聖徒たちの行ないや振る舞いに対して、そのまま報いられるお方だからである。ラオデキヤ人がキリストを拒絶して受け入れなければ、それに応じて、キリストもラオデキヤ人を拒絶して受け入れられなかった。具体的に言えば、その拒絶とは、どのようなことであろうか。それは、こういうことである。つまり、ラオデキヤ人が戸を閉ざしてキリストを中に入れることもなく外に放置し続けていたので、キリストも天国という戸を彼らに対して閉ざし、彼らが外の暗やみに放置されるままにされる。その時、ラオデキヤ人たちは暗やみの中に放り出されるので、泣いて歯ぎしりするのである。しかし、そのようになるのは、彼らがキリストを自分の心の外に放置し続けたことに対する当然の報いであるから、自業自得であって文句は言えない。その時、彼らは、かつて自分がした通りのことを自分にもされたアドニ・ベゼクが嘆いて言ったように、『神は私がしたとおりのことを、私にも報いられた。』(士師記1章7節)と言わねばならない状態に至らされることになるのである。心の戸を閉ざしてキリストを受け入れないままでいる者たちは、自分がしたのと同じように、自分もキリストのおられる天国に受け入れてもらえることがない。もし我々がキリストから戸を閉ざされたくないのであれば、我々の心の戸をキリストのために開け続けておかなければいけない。キリストは、我々のした通りに我々にも返されるお方であるということを、我々はよく心に留めねばいけない。
(※)
詩篇18:25~27でダビデが次のように言っている通りである。『あなたは、恵み深い者には、恵み深く、全き者には、全くあられ、きよい者には、きよく、曲がったものには、ねじ曲げる方。』
[本文に戻る]
この箇所で、『彼とともに食事をし、彼もわたしとともに食事をする。』と書かれているのは、いくらか注目に値する。ここでは、『彼とともに食事を(する)』と言われればそれで意味内容としては十分であったにもかかわらず、それに加えて『彼もわたしとともに食事をする。』とも言われている。つまり、キリストの側を主体とした言葉に加えて、聖徒たちの側を主体とした言葉も書かれており、食事をするということが二重に言われていることが分かる。このような言い方には、キリストと聖徒の関係における双方性または対等性が示されている。すなわち、キリストと聖徒の関係が主君と臣下のような上下関係ではないということが、この二重の言い方では示されている。つまり、キリストは、聖徒たちと親しい友としての関係を結びたく思っておられるということである。だからこそ、ここでは「私は彼と共に食事をする。また彼も私と共に食事をする。」などと両方の側を基点とした二重の言い方がなされているのである。もしキリストが完全に優越する支配関係が結ばれるべきだとすれば、ここでは「私は彼と共に食事をする。」という一方の側を基点とした言い方しかされていなかったであろう。これは、キリストが福音書の中で、聖徒たちを僕ではなく「友」であると言われたことと完全に適合している(※)。つまり、キリストは本当に聖徒たちを対等の関係を持つ友とされたいと思っておられるわけである。
(※)
『わたしはもはや、あなたがたをしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。わたしはあなたがたを友と呼びました。』(ヨハネ15章15節)
[本文に戻る]
さて、ここまでラオデキヤ人には多くの要求が与えられたが、このように悔い改めと改善が命じられたのは、キリストの再臨が間近に迫っていたからであるということを、我々はよく考えるべきである。もう間もなく実現される再臨が起きた際、もしラオデキヤ人たちが生ぬるいままで歩んでいたとすれば、空中の場所で左側にえり分けられることにもなりかねなかった。キリストがこのように命じられた時は、当時存命していた全ての聖徒たちが、再臨されたキリストの御前に立つことになる日がさし迫っていた。一部の聖徒たちではなく<全ての聖徒たち>が、もう間もなく審判を受けることになっていたのである。つまり、もはや再臨を待ち望む必要の無くなった今の時代とは状況がまったく違かったわけである。今の時代では、この世を去った人は個別的に審判を受けることになるが、あらゆる人が同時期において一挙に審判を受けるということは、もはやない。だから、このようにラオデキヤ教会に対して、直接的に悔い改めと改善が命令されたのは、ごく自然なことであったと言える。このように多くの要求が彼らに対してなされたのは、理由なきことではなかったのである。もちろん、この教会に対して言われていることは普遍的な内容を多く含んでいるから、今の時代に生きる我々に対しても適用すべきことが言われているというのは言うまでもない。
【3:21~22】
『勝利を得る者を、わたしとともにわたしの座に着かせよう。それは、わたしが勝利を得て、わたしの父とともに父の御座に着いたのと同じである。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。」』」』
勝利した者は、勝利した者として、キリストと共に座に着いて裁きの業を遂行できると、ここでは言われている。つまり、ここで言われているのは、2:26~27と内容的には同一のことである。「勝利した者が座に着いて鉄の杖で全世界を裁く。」ということについて、この3:21の箇所と2:26~27の箇所は、どちらも部分的に説明している。すなわち、我々が今見ているこの3:21の箇所では、座に着くということだけが説明され、鉄の杖で全世界を裁くということのほうは説明していない。もう一方の2:26~27の箇所では、我々が今見ている箇所とは逆に、鉄の杖で全世界を裁くということについては説明されているが、座に着くということは説明していない。我々が今見ているこの箇所は、黙示録20:4の箇所で、更に詳しく説明されている。そこでは、こう書かれている。『また私は、多くの座を見た。彼らはその上にすわった。そしてさばきを行なう権威が彼らに与えられた。』この2つの箇所が対応しているのは、そこで言われていることの類似性を考えれば、誰の目にも明らかであろう。また、この3:21~22の箇所は、Ⅰコリント6:2~3およびマタイ19:28の箇所とも対応している。何故なら、勝利した聖徒たちが座に着くとは、すなわち『聖徒が世界をさばくようになること』(Ⅰコリント6章2節)であり、『イスラエルの12の部族をさばく』(マタイ19章28節)ことだからである。なお、この3:21~22の箇所も、例のごとく、既に実現済みの箇所である。というのは、この箇所を更に詳しく説明している20:4の箇所で示されている幻は、既に私が何度も言っているように『すぐに起こるはずの事』(黙示録1章1節)だからである。確かに神は、黙示録で示されている幻は、すぐにも実現されることであると明白に教えておられる。『すぐに起こるはずの事』という御言葉は曖昧な内容ではないから、決して疑うことはできないし、私が言った意味以外の意味に捉えることもできない。すなわち、これは文字通り「すぐに起こる」という以外の意味ではない。このような意味の明白な言葉を否定するのは、神の言葉を否定することだから、その人はクリスチャンではない可能性がある。もし真のクリスチャンであれば、御霊の働きかけにより、神の言葉で言われていることを素直に信じるだろうからである。つまり、真のクリスチャンではなく、御霊を受けていないからこそ、御言葉で言われていることを受け入れられないということである。
ここで言われていることからも分かるように、キリストは、ご自身が受けた恵みを、ご自身のものである聖徒たちにも味わわせて下さる。それは、キリストが、ご自身の命をさえ捨てられるほどに、聖徒たちを愛しておられるからである。これほどまでに慈しみ深い存在が他にあるであろうか。愛情深い親や師匠でさえ、このキリストほどの慈しみは持っていない。このことについては、既に2:26~27の箇所で説明済みだから、これ以上の説明は不要である。
これ以降の箇所では、この7つの教会について言及されることは、もうない。すなわち、7つの教会について黙示録で語られているのは、この2~3章だけである。この2つの章で7つの教会について語られたのは、キリストが、この7つの教会において表示される全ての教会を心にかけておられるということを、聖徒たちによく分からせるためであった。試しに、この2つの章が無かったと想定してみられるとよい。そうすると、キリストが何だか教会に対して無関心であるかのように感じられるのではないかと思う。つまり、このようにしっかりと7つの教会に対して色々と言われることにより、誰でもキリストが教会を重要視しておられるということが、分かるようになっている。また、この2つの章でこのように書かれているのは、当時の教会が、やがて訪れることになる苦難に対して心構えがしっかりとできるようになるためでもあった。このように教会に対して色々と言われることで、教会は、自分たちにこそこの文書が向けられているのだということを明瞭に意識するようになり、その結果、精神的な準備ができるようになる。もし色々なことがこの2つの章で言われていなければ、それだけ当時の教会は、これから訪れる危難に対してあまり関心を持てなくなっていたことであろう。その場合、聖徒たちは、この文書があまり自分たちに向けられたものだとは思えなくなってしまうからである。要するに、この2つの章は、理由なしに書かれた章ではないのである。
最後に、ヨハネが「7つ」の教会に対して文書を書き送ったことについて、いくらか書いておきたい。これまで我々が見たように、ヨハネは7つの教会にこのように書き送ったわけだが、7つであったのは既に説明されたように完全性を示すためであったのだから、「10」だったとしても問題はなかったはずである。何故なら「10」も「7」と同様に完全であることを示す数字だからである。しかしヨハネが書き送ったのは「10」ではなく「7」に対してであった。これは一体どうしてであろうか。なぜ「10」ではなく「7」であったのか。その理由として考えられるのは、7にするのが、10にするよりも適切だったということである。この文書では一つ一つの教会に対して、かなりの内容量を持った文章が書かれるのだから、10にすると分量的に煩わしくなりかねない。この文書では、かなり長い量の文章が個々の教会に対して書かれているのだから、7にしたほうが、明らかに分量的に適切であるのは誰の目にも明らかである。だからこそ、ヨハネはあまりにも長々しくなるのを避けて10ではなく7にしたということなのであろう。だから、もし一つ一つの教会に対する文章がそれほど長くなかったとすれば、7ではなく10の教会が選ばれていたという可能性も十分にある。何故なら、その場合、個々の教会に対する文章があまり長くないのだから、たとえ10の教会に対して文章が書き送られたとしても、それほど煩わしく感じられないだろうからである。もちろん、「7か10か」というこのことは本質的な問題であるというのではない。はっきり言えば、これは些細な問題である。しかし、たとえ些細な問題であったにせよ、まったく考察するのが無意味というわけでもない。何故なら、たとえ些細な問題であったにせよ、それが御心にかかわることであるならば、その問題を探ることはすなわち神の御心を探ることに他ならないからである。この問題を探る場合であれば、それは7の教会が選ばれたということの背景に存在する神の御心を探ることであるから、ますます我々には神に関する知識が増し加えられることになる。それが望ましいことであるのは言うまでもないであろう。神の御心を知ることは非常に重要であるがゆえに、私は今この場所で、このように些細な問題であっても論じることを差し控えなかったのである。
この2~3章からは多くの教訓を得ることが可能である。聖徒たちは、これらの章から普遍的なことを汲み取り、自分の信仰の益となるようにするのが望ましい。このような教訓の宝庫を見過ごして放ったままにしておくのは、非常に勿体ない。
これにて7つの教会に対して語られた箇所である、黙示録2~3章の註解が終わった。以上で、この2~3章の箇所についての解き明かしが必要十分なだけ述べられたことにしたい。
第6章 ③4章:天における場景
この4章目からは、場面が切り替わり、天で幻が示されるようになる。これまで、ヨハネの精神は、地上に置かれていた。しかし、この章からは、地上ではなく天上にヨハネの精神が据えられるようになる。それは、ヨハネの精神が天へと引き上げられたからである(4:1~2)。この「天」とは、大気圏という意味における天のことではない。少し考えれば分かるように、これは、我々が住んでいる宇宙空間には存在していない別の空間にある霊的な場所のことである。つまり、この天とは、聖徒たちがこの世での生を終えた後に行く場所、世俗的に言えば「あの世」のことである。
しかし、この章から天で幻が啓示されるようになった理由は何なのか。その理由は2つある。まず第一の理由は、ヨハネに告げられるべき幻は、内容的に天上の出来事がその大部分を占めているからである。黙示録で示されている幻には、例えば天での戦い(12:7)や天における大群衆の賛美(19:6)など、天上にかかわる内容を持ったものが非常に多い。このような幻は、やはり天でこそ啓示されるのが望ましい。だから、地上で幻が示されるのは、非常に難しいことであった。第二の理由は、天で幻が示されることになると、崇高だからである。ヨハネに告げられるべき幻は、実に神的であり、厳かで、そこには天上的な匂い以外には漂っていない。そのような幻は崇高な内容を持ったものであるから、崇高な場所である天でこそ示されるのが望ましい。それゆえ、我々は、神がこの崇高な幻を崇高な場所である天上において啓示されるということ以外の選択肢を持ってはおられなかったと考えるべきである。試しに、黙示録で示されている幻が、天上ではなく地上で啓示されたと想像してみると、どうであろうか。そのように想像すると、すぐにも適切ではないと思われるはずである。よって、この文書における大部分の幻が、地上で啓示されるというのはあり得ないことであった。
【4:1】
『その後、私は見た。見よ。天に一つの開いた門があった。』
ここから、ヨハネには天における幻が示されることになる。この天とは、もちろん象徴的なものだと解するべきではない。これは実際的に、また文字通りに解するべきである。この天を象徴としか解さない者は、創世記におけるエデンの園の話を神話であると解する者とほとんど同族であって、その解釈は実に忌まわしい。
この箇所でヨハネに見せられている幻は、まだ天の外側の部分だけである。何故なら、ここでは明らかに、一つの開いた門を持つ天が視像的に外部から示されているからである。確かに、ここでヨハネは開いた門を持つ天を、外の位置から見ている。天の内部を見せられるようになるのは、2節目からとなる。
ここでヨハネは一つの門が開かれている天を見ているが、この門は黙示録21:12~13によれば全部で12の門である。その箇所には、『東に三つの門、北に三つの門、南に三つの門、西に三つの門があった。』(21:13)と書かれている。この天にある12の門は、ヨハネがこの幻を見せられている時点で、既に全て開かれていた。というのは、キリストが紀元33年頃に昇天された際、『ダビデのかぎ』(黙示録3章7節)を使って、その門を開かれたからである。それは、選ばれた者たちが、地上から上げられてこの門をくぐって天国に入れるようになるためであった。ヨハネがここで天に一つの門が開かれているのを見たと言っているのを読んで、12の門の中で、開かれている門は一つだけであったなどと考えるべきではない。この箇所では、一つしか天の門が開かれていないということを言っているのではない。つまり、ここでは既に開いている天の門は12あるのだが、ヨハネが見たのはそのうちの一つであった、ということが言われているわけである。キリストが昇天された際に、12ある門のうち、たった一つしか門を開けられなかったというのは少し考えにくい話である。黙示録21:25でも教えられているように、この12の門は、キリストに開かれてからは、もはや決して閉じられることがない。もしその門が閉じられることがあれば、地上から贖われた聖徒たちが、天に入るようにと定められているにもかかわらず、天に入れなくなってしまうからである。この門は、2019年の今でも、ずっと開かれたままになっている。
『また、先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえたあの初めの声が言った。「ここに上れ。この後、必ず起こる事をあなたに示そう。」』
ここで言われているラッパのような声とは、既に1:10~12で書かれていたあの声である。これは神の声、すなわちキリストの声であって、ただの人間に過ぎない者や天使の声ではない。
このように言われてから、ヨハネの精神は完全に天の場所に据えられることになった。それは、ヨハネが天上の幻を見、書き記し、それを聖徒たちに送り届けるようになるためであった。
ここでキリストの声は、これから示される幻が『必ず起こる事』であると告げておられる。そして、それは『必ず起こる事』であると共に、『すぐに起こるはずの事』(1章1節)でもあった。つまり、黙示録に書いてある幻は「すぐにも絶対に実現される」ということである。確かに、黙示録を正しく解釈するのであれば、この文書で示されている幻は、実際の歴史においてすぐにも起きたということが分かる。神が言われたことは、正に真実だったのである。しかし今に至るまで、聖徒の中には、黙示録で示されている幻が未だに起きていないと考えている者が多い。多い、というよりはほとんど全ての者がそうである。彼らの中の多くは「黙示録に示されている幻はずっと後に起こることだ。その幻にはまだ実現されていないことも多い。チェルノブイリが、ロックフェラーが、獣が、EUの首領が、666が云々…」などと起こりもしない終末を思いつつ妄想しているのだが、このように考えるのが神の御言葉に反していることに、多くの者は気付いていない。神はその幻が『すぐに』(1:1、22:6)起こると言われたのである。この『すぐに』という言葉と、彼らの考えている「ずっと後に」という言葉が、どうすれば調和するのか私には全く分からない。果たして『すぐに』とは「ずっと後に」という意味であろうか。また「ずっと後に」という言葉は『すぐに』という言葉と同一の意味を持つのであろうか。理性を失っていないと言うのであれば、この2つの言葉がかなり違う意味を持っているということに、どうか気付いてほしいものである。
ここで大きな問題を取り扱っておきたい。それは、こういう問題である。すなわち、この箇所で言われているように、ヨハネが天に引き上げられたのは間違いないが、ヨハネは天の「どこに」引き上げられたのか。すなわち、ヨハネは天のどの階層に引き上げられたのか。これは解決が難しいが、軽んじるべき問題ではない。パウロの場合、自分が『第三の天にまで』(Ⅱコリント12章3節)引き上げられたと言っている。この『第三』という言葉は、比喩ではなく、実際的なことを言った言葉であると思われる。今まで多くの教師たちが、そのように考えてきた。カルヴァンの場合、パウロが言った『第三』という言葉は「<至高の・まったく完全な>と言うかわりに用いられている」(『新約聖書註解Ⅸ コリント後書』12:2 p208:新教出版社)と言っており、完全性を比喩させる意味しか持たないと考えていたようだが、これが実際的なことを意味する言葉であると解したとしても荒唐無稽な解釈とは言えない。とすれば、天の階層は少なくとも三段は存在しているということになる。すなわち、天は人間社会で例えれば3階建ての建物のようになっているということである。しかし、第三よりも上の天があるかどうかは、パウロのこの言葉からだけでは何とも言えない。聖書の他の箇所では、天について『もろもろの天』(エペソ4章10節、ヘブル4章14節)と言われている。この言葉からも、やはり天には複数の階層があると考えられる。何故なら、『もろもろ』とは、すなわち「いくつもある」という意味の言葉だからである。しかし、この言葉からも、やはり天にどの程度の階層があるのかは分からない。アウグスティヌスも「すべての諸天」(『アウグスティヌス著作集26 パウロの手紙・ヨハネの手紙説教』説教171 第3章3 p319:教文館)と言っているが、これは聖書に沿った言い方である。更に―私は外典を挙げるのはあまり気が進まないのだが―外典でも、天には複数の階層が存在すると書かれている。ある外典では、天が7層存在すると言われている。しかし、外典はあくまでも外典であって、正典のように霊感されていないから、そこに書かれている記述を理解の根拠とすることはできない。だが、天には複数の階層があると言っている点では、正典の内容と一致している。エイレナイオスも「地は7つの天に包み込まれている。」(『中世原典思想集成1 初期ギリシア教父』使徒たちの使信の説明 9 p209:平凡社)と言っているが、これも後期ユダヤ教文書から取られた知識だから、天が複数あると言っている点は問題ないが、7つあるかどうかは懐疑的に捉えるべきである。以上のことを考えると、天には複数の階層が、正確に言えば少なくとも3つの階層が存在する可能性が高い。しかしながら、ヨハネがその階層の中のどの階層に引き上げられたのかは不明である。パウロのように第三の天に引き上げられたのかもしれないし、それよりも下の階層かもしれないし、もしかしたら3段目よりも上の階層に引き上げられたのかもしれない。ヨハネがどの階層に引き上げられたかというこのことについては、どれだけ思索しても分からないだろうから、我々はあのティオニシウスのような空想家になることを恐れて、喜んで分からないままにしておくべきであろう。聖書が啓示していないにもかかわらず、あたかも啓示されたかのように確定的なことを語るのは、あまりにも僭越だからである。
次に、更に大きな問題を取り扱うことにしたい。それはこのような問題である。すなわち、パウロは自分が引き上げられた天について語ることを許されなかったのに(Ⅱコリント12:4)、ヨハネのほうは天について大胆に語っているのは、一体どういうことなのか。これは無視できない重要な問題である。まず一体どうしてパウロは、自分が引き上げられた天のことについて語ることを許可されなかったのか。それは、パウロは、そもそも天で見せられることを預言するために、天に引き上げられたのではないからである。神は、パウロに天での幻を預言させるためにこそ彼を天に引き上げたのではなく、彼の霊を天の場景を見させることで言わば研ぎ澄ませようとして、天に引き上げられた。この天とは、我々の住んでいる地上とは違って、徹底的に神に属する領域である。またパウロには、この天のことを語るようにと、神からの指示が出ていたのでもなかった。だから、パウロにとって、天で見せられたことを勝手に語るのは、実に僭越なことであった。それは例えるならば、隠された秘密を勝手に暴露することである。だからこそ、パウロは自分には天で見たことを語ることが許可されていないと言ったのである。一方、ヨハネのほうは、そもそもの始めから天で啓示される幻を語らせるためにこそ、天へと引き上げられた。ヨハネの場合、天で見たことを語らないということは、許されないことであった。だからこそ、ヨハネはパウロとは違って、自分が天で見たことを大胆に語っているのである。ヨハネは、パウロが「語る」ことを許可されていなかったのとは正反対に、「語らない」ということのほうが許可されていなかった。それゆえ、我々は、パウロが天のことを語るのは人間には許されていない、と言っているからといって、天がまったく語ってはいけない場所であると考えてはならない。もし本当に天が語ってはいけない場所であるとすれば、ヨハネに天で見せられたことを語るようにと命じられてはいなかっただろうし、ヨブ記でも天の様子が記されることはなかったであろう。パウロが言っているのは、「天は語ってはならない場所なのである。」ということではない。それは、パウロ自身が、天のことを許可されている範囲内で語っていることからも分かる(エペソ2:6、6:12)。要するに、もし神からの許可が出ているならば、天はその許可の範囲内においてならば語ってもいい場所なのである。
【4:2~3】
『たちまち私は御霊に感じた。すると見よ。天に一つの御座があり、その御座に着いている方があり、その方は、碧玉や赤めのうのように見え、その御座の回りには、緑玉のように見える虹があった。』
『たちまち私は御霊に感じた。』とは、御霊がヨハネの精神に働きかけて下さったので、彼の精神が天に引き上げられて、そこにおける幻を見ることができるようになった、という意味である。この言葉は言い換えれば次のようになる。「御霊が働きかけられたので私の精神は天に引き上げられた。だからこそ、私は天での場景を見ることができたのだ。これは御霊のゆえであって、私の力や努力によるのではない。御霊が働きかけて下さらないのに、どうして人の精神が天に突入できようか。」聖書には、このような難しい言い方をしている箇所が多いから、そのような箇所に出会った際、我々はそれがどのような意味を持っているのか、聖書に立ちつつよく考える必要がある。
『御座に着いている方』とは、父なる神である。御霊は2節後の5節目で、御子は5章目で出てくる。ここで、どうしてこのような順番で三つの位格が出てくるのか疑問に感じられる方がいるかもしれない。すなわち、どうして御父、御霊、御子という順番なのか、という疑問である。三位は本質としては同質であるが、位格の順番としては、御父、御子、御霊という順である。そうであれば、やはりその順番通りにそれぞれの位格が登場するのが自然ではないのか。キリストもマタイ28:19の箇所で『父、子、聖霊』などと3つの位格をその順番通りに語っておられる。しかし、ここでは御父は三位の順番通りではあるものの、御子と御霊の順番のほうは逆になっている。これは、ここでは話の流れとして、そのような順番として語られるのが相応しかったからである。つまり、ここでは位格の順序を教えることが目的とはされていない。だから、たとえ位格がその順番通りに記されていなかったとしても何も問題とはならない。たとえ位格の記述における順序があべこべになっていても、実際の位格に何らかの影響が出るというのでもない。つまり書き方がどうであれ、神の位格における順序が、御父、御子、御霊という順序であることには変わりないのである。以上、あまり本質的な問題であるとはいえないが、気になる方もいるかもしれないと思われたので、ここでこの問題を短く取り上げておいた。
ここで御父が『碧玉や赤めのうのよう』であったと言われているのは、神の栄光が示されるためである。我々は、碧玉や赤めのうを見たら、その美しさのゆえに、やはり素晴らしいと感じるはずである。神の栄光の輝きも、そのように素晴らしいと感じられる性質を持っている。つまり、ここでは目に見えない神の栄光が、目に見える物質を通して、視覚的に理解できるように語られている。そのように物質を通して語られたならば、我々は、完全とは言えないにせよ、ある程度までは神の栄光を物質的な存在を足がかりとして掴むことができる。神の栄光は実に感嘆とさせられるものだから、碧玉や赤めのうにより語られているのは、実に相応しいことである。しかし、神は碧玉や赤めのうの創作者であって、実際にはそれらのものよりも遥かに豊かな輝きを持っておられる。碧玉や赤めのうの創作者が、それらのものよりも素晴らしい輝きを持っておられないということが、どうしてあるであろうか。要するに、これは物質を補助手段として理解させることを目的とした「例え」である。それは旧約聖書の中で、神が実際には手や翼を持っておられないにもかかわらず、神がどのような存在であるのかを我々に理解させようとして、あたかも神に手や翼があるかのように語られているのと同じことである(詩篇139:10、申命記32:10~11)。だから、我々はこの箇所を読んで、神が目に見える物質的な存在者であられるなどと思ってはならない。キリストも言われたように『神は霊』(ヨハネ4章24節)であって、我々人間のような物質者として捉えられてはいけないのである。
『御座の回りには、緑玉のように見える虹があった。』と言われているのも、やはり神の栄光が示されている。神は、ご自身の周りにさえも、ご自身の栄光を持っておられる。すなわち、神の栄光は、神の内部にだけ限定されるものではなく、その外側にまで波及されている。この『緑玉のように見える虹』という表現には、我々を恍惚とさせる響きがあり、どこか神秘的な印象がある。実際、神の栄光は理性では測り知れない神秘性を持つのであって、我々を恍惚とさせる印象を持つものである。
しかし、この箇所で父なる神が描かれているのは、一体どういうことなのであろうか。ここで御父が出てくるのは、御父が万物の主権者であられるからである。つまり、崇高な幻が啓示される際には、崇高なお方がその幻と共に示されることが理に適っているがゆえに、ここでは御父が出てくるのである。試しに、ここで御父が描かれていなかったと想定してみるがよい。そうすれば、黙示録で示されている諸々の幻からいくらかでも神聖な印象が失われてしまうのではなかろうか。私の場合、そのように感じられる。崇高な幻が啓示される際には、その崇高性が保たれるために、崇高なお方が出てくるのが望ましい。偉大な式典が開催される際には、偉大な人物が参席しているのが望ましいのと同じである。
【4:4】
『また、御座の回りに24の座があった。これらの座には、白い衣を着て、金の冠を頭にかぶった24人の長老たちがすわっていた。』
『24人の長老たち』とは、すなわち天上にある教会のことである。旧約における神の民は、イズラエルの12部族で表示されるべきである。一方、新約における神の民は、12使徒により表示されるべきである。この2つの「12」を足すと24となる。つまり、この24とは旧約時代と新約時代における神の民が集っている天上の教会のことである。この天上の教会を表示する24人の長老たちが『白い衣を着て』いたのは、天上の教会に属する聖徒たちが身体の贖いを受けており、御霊の身体を持っているからである。この白い衣が御霊の身体を意味しているということは、既に説明済みである。また彼らがかぶっている『金の冠』とは、天上の聖徒がかぶっている『いのちの冠』のことである。つまり、天にいる聖徒たちは、この『いのちの冠』により象徴されている永遠の命を持っているということである。また彼らが座に座っているのは、天の聖徒たちが王だからである。黙示録22:5でも言われているように、天にいる聖徒たちは『永遠に王である。』王だからこそ、彼らは座に着いているのである。何故なら、王というのは座に着いているのが相応しい存在だからである。もし彼らが王でなかったとすれば、座に着いていることもなかったであろう。我々は、ここで言われている『24人の長老たち』という言葉を24人の個人的な存在ではなく、天上の教会を表示させるための象徴表現であると捉えるべきである。
天上にも地上と同じように教会が存在するということは、聖書が教えていることである。それは、ヘブル12:23の箇所で『天に登録されている長子たちの教会』と言われている通りである。もし天に教会がなければ、ヘブル書では、このように言われていなかったであろう。この地上にさえ教会が存在しているのであれば、尚更のこと、天上には教会がなければいけないことになる。何故なら、教会とは聖なる存在だからである。罪に満ちたこの世にさえ教会があるのだから、聖そのものである天上に教会がないのは、おかしいことである。教会は、罪深さに満ちた地上よりも、聖なる場所であるこの天のほうが存在的により相応しいのである。
【4:5】
『御座からいなずまと声と雷鳴が起こった。7つのともしびが御座の前で燃えていた。神の7つの御霊である。』
ここでは『7つの』御霊が、御座の前におられたと書いてあるが、先にも説明されたように「7」というのは実際の数ではなく、御霊の無限性を示している。すなわち、御霊は、神の御座の前で無限的な存在者として存在しておられるということである。人間に過ぎない我々は、この場景を、視覚的また物理的に把捉することができない。何故なら、この場景は霊的な場景であって、理性では捉えきれず、認識の限界を遥かに超えているからである。
この御霊なる神は、燃えている灯として、ここでは描かれている。これは、御霊が、神の霊だからである。霊が、燃えている灯のようであるということは、聖徒であれば誰でも異を唱えはしないと思う。世俗のファンタジー作品を見ても分かるが、霊的な死人であるノンクリスチャンでさえ、霊が灯のようなものであると捉えている。「それでは、その灯の勢いはどれぐらいなのであろうか。」と問う人がいるであろうか。この問いには、「非常に激しい。」と答えることができる。何故なら、御霊なる神は、力と勢いに満ちておられるお方だからである。『万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。』(イザヤ9章7節)と言われているお方が、激しい勢いで燃えている灯でないということが、どうしてあるであろうか。「それでは、その灯の色はどのようなものであろうか。」と問う人がいるであろうか。この問いは不当であって、答える必要がない。何故なら、これは真面目な問いというよりは、むしろ好奇心から出た問いだからである。このような本質的ではない問いを許したら、例えば「地獄の炎は何色なのか。」とか「善悪の知識の木の実はどのような形状をしていたのか。」とか「キリストの喋り方はゆっくりだったか、それとも普通の速さだったか。」とか「キリストの背の高さはどれぐらいだったか。」とか「サタンが園で入った蛇はどのような種類の蛇だったのか。」などといった他の些末な問いをも許さねばならなくなり、知恵のない詮索家となりかねない。誠に、カルヴァンが次のように言ったことは正しい。「御霊は常に我々に益を与えたもうのであるから、信仰の確立に殆ど役に立たないことについては全く沈黙するか、もしくは軽く駆け足で触れるに留め、我々の務めとしても益のないことは喜んで知らぬままでおくとしよう。」(『キリスト教綱要 改訳版 第1篇・第2篇』第1篇 第14章3 p180:新教出版社)
御座から『いなずまと声と雷鳴が起こった。』のは、御霊の神性と尊厳が示されるためである。基本的に、神がその栄光をもって現われる時には、このような要素が付随して現われるのが常である。このような要素は、偉大な神の偉大性が示されるためには実に相応しいものなのである。神がシナイ山に降りて来られた時には『山の上に雷といなずまと密雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いた』(出エジプト記19章16節)し、キリストも今から2千年前に『雷と地震と大きな音をもって、つむじ風と暴風と焼き尽くす火の炎をもって』(イザヤ29章6節)再臨された。御霊も神であられるので、その現われの際には、ご自身の偉大さを示す要素を伴われるわけである。
ここで御霊について描かれているのは何故であろうか。それは、先の箇所で述べたのと同じで、御霊は万物の主権者であられるからである。黙示録に書かれるような神聖で深遠で崇高で偉大な幻が啓示される際に、万物の主権者であられる栄光の御霊が描かれるのは、実に相応しいことである。偉大なことが示される時には、偉大な存在が現われるのが理に適っているというのは、世の中を見ても分かる。例えば、偉大な功績をあげた人を表彰する式典が開催される際には、往々にして、王や大統領や首相といった権威ある人たちが招かれるものである。
【4:6】
『御座の前は、水晶に似たガラスの海のようであった。』
これも先に語られたのと同じで、神の栄光が示されている。神は、その御座の前ですら、輝かしい栄光をお持ちのお方であられる。栄光の神にとっては、その御前の状態においてでさえ、栄光を持たれることが相応しいのである。実際に我々が御座の前における『水晶に似たガラスの海のよう』な状態を見ることができたとすれば、思わず息を呑んでしまうに違いない。誰がこのような清らかな光景に心を揺り動かされないであろうか。出エジプト記の場合、神の『御足の下にはサファイアを敷いたようなものがあり、透き通っていて青空のようであった。』(24章10節)と書かれている。『御座の前』と『御足の下』という記述の違いがあるが、どちらも神の面前に広がっている光景を描いている。この御前の状態についても、いくらか記述の違いがあるが、つまり一方は『水晶に似たガラスの海のよう』と言っており、もう一方は『サファイアを敷いたようなもの』また『透き通っていて青空のよう』と言っているが、どちらも神の澄み切った栄光を示そうとしていることには変わらない。どちらも神の栄光を示すという目的が達成されているのだから、記述にいくらかの違いがあっても、何も問題とはならない。だから、「ヨハネが描いた御前の状態とモーセが描いた御前の状態はどちらがより正確なのか。」と問う人がいれば、その人には「どちらも誤ってはおらず、どちらも完全に正しい。」という答えが与えられることになる。なお、この箇所は、恐らくエゼキエル書10:1とも関わりがあるのではないかと思われる。そこでは、『ケルビムの頭の上の大空に、サファイヤのような何か王座に似たものがあって、』と書かれている。神のおられる場所において何か神秘的な光景が見られた、という点で今示されたエゼキエル書の箇所は、我々が今見ている箇所と出エジプト記24:10の箇所と共通している。黙示録はエゼキエル書と似ている部分が非常に多く見られるから(これは両方の巻をよく読んでみれば明らかである)、ヨハネが4:6の文章を書いていた時に、このエゼキエル書10:1の言葉が頭に浮かんでいたという可能性はかなり高い。
【4:6~8】
『御座の中央と御座の回りに、前もうしろも目で満ちた4つの生き物がいた。第一の生き物は、ししのようであり、第二の生き物は雄牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶわしのようであった。この4つの生き物には、それぞれ6つの翼があり、その回りも内側も目で満ちていた。』
黙示録では、ここで初めて『4つの生き物』が出てくる。この生き物は、これからも、たびたび出てくることになる。よって、この生き物が何であるかを知っておくのは、非常に重要である。この4つの生き物は、我々の感覚からすれば、どこか得体が知れない。アーサー・C・クラークの『宇宙のランデヴー』の最後には、得体の知れない正体不明の存在が出てくるが、この『4つの生き物』はそれ以上に得体が知れないと私には感じられる。しかし、その得体の知れなさが、神の近くにいる生き物としては相応しいと言える。何故なら、神とは『不思議』(士師記13章18節)という名のお方であって、不思議なことをなされるお方だからである。この士師記の箇所で、『主はマノアとその妻が見ているところで、不思議なことをされた。』(13章19節)と書かれている通りである。つまり、不思議である神は不思議なことをなされるお方なので、その御座の回りの場所にも不思議であると思えるような生き物を置かれたのである。
まず、この『4つの生き物』が被造物であったことは間違いない。何故なら、この生き物は神の御前にひれ伏して、神を拝んでいるからである(黙示録19:4)。被造物だからこそ、このように神を崇拝するわけである。というのも、神に選ばれた理性ある被造物は、このようにして神を拝み、神の栄光を現わすためにこそ造られ、また存在しているからである。この生き物が神であれば、このような崇拝を神に捧げていることもなかったはずである。被造物でないのに、つまり神でありながら、神に賛美を捧げるなどして神の栄光を現わすのは、人としてのキリスト以外にはおられない。福音書にも書いてあるように、キリストは、人としては神に賛美や感謝や誉れを捧げられるなどして、崇拝の行為をされた。しかし、この『4つの生き物』は、言うまでもなくキリストではなく、キリストを象徴する生き物でもない。それゆえ、この生き物は被造物であったと考えなければいけない。
エゼキエル書1章でも、我々が今見ているこの箇所に出てくるのと同じような4つの生き物が出てくる。私は以前、このエゼキエル書における4つの生き物について次のように書いた。<黙示録およびエゼキエル書における4つの生き物について記された箇所を読み比べてみるならば、その類似性を、誰も疑うことはできないはずである。まず、この2つの文書に出てくる4つの生き物について、確実に言えることは次の通りである。1.どちらの箇所で示されている生き物も神の啓示によるということ。2.内容にいくらかの違いがあっても、どちらも本質的には同一のことを教示しようとしていること。3.どちらのほうがより正しいなどということはなく、どちらのほうにも誤りがないということ。この2つの箇所で示されている生き物における同一の点は、次の通りである。まず、どちらのほうもその生き物の数は「4」である。また、どちらのほうでも複数の翼が描かれている。また、どちらのほうでもその示されている被造物の種類は4つであり、それはどちらも内容的に同じである。すなわち、黙示録でもエゼキエル書でも、その示されている被造物は「人間」「獅子」「牛」「鷲」の4つである。違う点は次の通りである。まず、黙示録で示されている生き物がそれぞれ違う外観を持っているのに対し、エゼキエル書で示されている生き物は、それぞれ同じ外観を持っている。また、黙示録の生き物が『6つの翼』(4章8節)を持っているのに対し、エゼキエル書の生き物は『4つの翼』(1章6節)を持っている。またエゼキエル書の生き物の傍には『輪』(1章15節)があるが、黙示録の生き物には、そのような輪があるなどとは言われていない。このように、この2つの文書における『4つの生き物』についての記述には、同じ点があれば違っている点もある。なお、この4つの生き物は、外典・偽典には書かれていない。世俗のファンタジー作品やSF作品にも、このような不思議な生物は描かれていない。私の思うところ、神の聖なる啓示によるのでなければ、このような不思議に思える生き物を描くことができないのは確かである。>私は以前このように書いたのであり、エゼキエル書と黙示録における4つの生き物は同一の存在だと思っていた。しかし、このエゼキエル書における4つの生き物は、黙示録における4つの生き物とは似ているものの完全な別物である。というのも、エゼキエル書における生き物には4つの翼しかないのに対し、黙示録における生き物には6つの翼があるからだ。今の時点では、ひとまずエゼキエル書と黙示録の生き物がそれぞれ違った種類の存在であるという点だけを弁えていれば、それで良い。すぐ後ほど、これが一体どういうことなのか話されるであろう。
まだ信仰的に純粋であった頃の古代教会では、この『4つの生き物』が、4つの福音書また4人の福音書記者として解されていた。その解釈の内容を読むと、確かに「なるほど。」と思えるような内容となっている。この解釈についてアウグスティヌスは次のように言っている。「預言者エゼキエルでも、この福音書を書いた同じヨハネの手になる黙示録においても、人間・若い牛・獅子・鷲という四つの顔をもった四重の動物のことが述べられている(エゼ1:5~10、黙4:6~7)。私たちよりも前に聖書の秘儀について研究したことのある人たちは、たいていこの動物で、むしろこれらの動物たちのことで、四つの福音書を理解していた。彼らは獅子がその力と恐ろしい勇猛さのために、ある意味で動物たちの王であると思われているゆえに、王の代わりに立てられていると理解した。この獅子の顔付きはマタイに適用されている。なぜなら、彼は、どのように主が王の家系によりダビデ王の血統から出ているかを、主の家系図により王の系統を追跡しているからである。しかしルカは、牛とみなされた洗礼者ヨハネの父について語りながら、祭司ザカリヤの祭司職から開始しているので、牛の代わりに立てられている。なぜなら、祭司の捧げる犠牲の中で最大の供物は牛であったから。マルコには人なるキリストが至当にも配当されている。なぜなら、彼は王者としての尊厳からも、祭司としての尊厳からも開始しないで、単純に人なるキリストから出発してるからである。これらの人たちは皆、ほぼ地上的なものから、すなわちわたしたちの主イエス・キリストが地上にあったとき行われたことから遠ざかっていなかった。あたかも地上を主と共に彼らは歩んだかのように、キリストの神性について語ることきわめて少なかった。鷲がまだ残っている。ヨハネがそれであって、彼は崇高なことを宣べ伝え、内的で永遠的な光を確固たる目をもって観照しているのである。なぜなら、鷲の雛は両親の爪で吊され、太陽の光にさらされて、親たちからためされると言われているから。もし雛がしかと光を見るならば、子として認められ、目がぴくつく場合には、真正な子でないかのように爪先から落とされる。それゆえ今や、鷲になぞらえられた人がいかに崇高な事柄を語らなければならないかと考えてみなさい。」(『アウグスティヌス著作集24 ヨハネによる福音書講解説教(2)』第36説教 5 413年 p164~165:教文館)カシオドルスも、このように言っている。「四福音書については、「エゼキエル書」において「またその中から4つの生き物の形が出てきた」(エゼ1:5)と伝えられている。」(『中世思想原典集成5 後期ラテン教父』綱要 第2巻第5章 p388:平凡社)セビリャのイシドルスも次のように言っている。「以上が四福音書であり、聖霊は彼らのことを、エゼキエルを通して4つの動物のうちに示した。さらに彼らが4つの動物であるのは、キリスト教の信仰が彼らの告知によって世界の4つの部分に広まったからである。彼らが「動物」(animal)とされるのは、キリストの福音が人間の「魂」(anima)のため告知されているからである。なぜなら、それらの動物は内にも外にも眼力に富み、預言者たちによって語られ、以前に約束された福音を予見しているからである。彼らの脚はまっすぐである。福音には曲がったことは一つもないからである。彼らは6つずつの翼をもち、脚と顔とを覆い隠している。それまで隠されていたことがキリストの到来において啓示されたからである。」(『中世思想原典集成5 後期ラテン教父』語源 第6巻第2章 p519:平凡社)「福音書」と名のつく古代の文書であれば多く存在しているが、神に霊感された真の福音書は、マタイとマルコとルカとヨハネによる4つの福音書だけである。神は、この4人による福音書だけを真の福音書として世に残されようと、永遠の昔から計画しておられた。そのような聖なる文書またはその文書における著者を、神が『4つの生き物』として象徴的に描いておられたとしても、何もおかしいことはない。何故なら、聖書を見れば分かるように、神は、ある存在を何かに「例える」ということを、よくなされるお方だからである。例えば聖書の中では、キリストが『太陽』(マラキ4章2節)として、バプテスマのヨハネが『エリヤ』(同4章5節)として、ネロは『獣』(ダニエル7章11節)として描かれている。だから、福音書または福音書の著者が『4つの生き物』として描かれていたとしても不思議ではないことになる。要するに、この生き物を「福音書または福音書の著者」であると解釈するのは、不可能なことではない。
今述べた「福音書または福音書の著者」の他に、この4つの生き物についての可能な解釈があるのか。もしあるとすれば、それはどのような解釈であるか。その解釈は「存在する」。その解釈の一つとしては、この生き物が「文字通りの生物そのもの」であるという解釈である。つまり、この生き物は、天にだけ存在する特殊な生き物であるということである。このように解する場合、この生き物は、神に崇拝や賛美を捧げるためにだけ造られた被造物であるということになる。何故なら、この生き物は黙示録4:8に書いてあるように『昼も夜も絶え間なく叫び続け』ているからである。四六時中同じことをしているというのは、そのことをするためだけに創造されたということを意味している。『4つの生き物』をこのように解釈したとしても、黙示録の理解に致命的な問題が生じるわけではない。だから、このように解するのは「可能」である。しかし、このように解するよりは、上で説明されたように「福音書または福音書の著者」であると解したほうが、より望ましいと私は思う。というのは、これを福音書と解したほうが霊的であって、そのように解釈する信仰者の霊を研ぎ澄まさせることになるだろうからである。
しかし、確かなことを私は言おう。この『4つの生き物』は、福音書や福音書の著者ではなく、天上にだけ存在する特殊な生き物でもない。まず、この生き物を「福音書」と解するのは、完全な誤りである。これを福音書と解するのは、古代の教父たちが持っていたその思考力の高さを示すものではあるが、しかしいくらか強引な解釈である。この解釈は確かに説得力があるように感じられるが、一方では違和感も感じられる。これが理性による解釈であることは間違いない。すなわち、これは聖書に基づいた見解ではない。次に、この生き物は「天上にだけ存在する特殊な生き物」でもない。これも、やはり理性による解釈である。この解釈には、聖書の裏付けがまったくない。それでは、この生き物は何なのか。この生き物は、聖書から言えば「セラフィム」である(※①)。何故こう言えるかといえば、イザヤ書6章に出てくるセラフィムと、黙示録に出てくるこの『4つの生き物』は、非常に類似しているからである。これをセラフィムと解するのは、先に見た2つの解釈とは違って、聖書に基づく解釈である。ヨハネの描いた生き物には『6つの翼』があったが、イザヤ書に出てくるセラフィムにも『6つの翼』(6章2節)が描かれている(※②)。また黙示録の生き物は主の近くにいるが、イザヤ書のセラフィムも、やはり主の近くに立っている。また黙示録の生き物は『聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。』と主の聖性を3回続けて叫んでいるが、イザヤ書のセラフィムも同様に『聖なる、聖なる、聖なる、万軍の主。』(6章3節)と言っている。これらのことを聞いて、黙示録に出てくる生き物とイザヤ書に出てくるセラフィムが似ていると思わない人はいないはずである。よって以上の類似点から考えると、この『4つの生き物』は間違いなくセラフィムである。既に説明されたように、ヨハネは黙示録の多くの箇所を旧約聖書の箇所に基づいて書いているのだから、この『4つの生き物』が出てくる箇所も、イザヤ書6章に対応しているとすべきであろう。しかし、イザヤ書のセラフィムのほうには、黙示録におけるセラフィムについて書かれていることが書かれていないのは、どういうわけなのか。それはイザヤ書のほうでは、単に黙示録のほうでは書かれていることが、書かれていないだけである。先に見た黙示録1:13~16とダニエル書10章におけるキリスト像でも、一方では描かれているのに、もう一方のほうでは描かれていないことがあった。すなわち、黙示録のキリストにおいては口から鋭い剣が出ていたが、この箇所と対応しているダニエル書のキリストにおいてはそのようなことは描かれていなかった。しかし、どちらの幻も、同じキリストであった。それと同じように、イザヤ書のセラフィムには黙示録のセラフィムには書かれていない内容があるが、どちらも同じセラフィムであることには変わらない。というわけで、この『4つの生き物』がセラフィムであるということが、以上の説明からお分かりいただけたのではないかと思う。
(※①)
このセラフィムという御使いは、偽ディオニュソス・アレオパギテースによれば、次のような御使いであった。私はこの説明には否定的ではない。「実際、「セラフィム(熾天使)」という名称が明白に教えていることは、彼らが、神に属する事柄の周りを永遠に動いていて終わりがないということであり、隣接した不変でそれることのない永遠なる運動の熱、鋭さ、あふれる沸騰であるということであり、また下位のものたちを沸騰させ再び燃え立たせて同じ熱さにすることで彼らを積極的に引き上げて似たものにするということであり、さらにまた燃やして完全に焼き尽くすことによって浄化するということであり、曇りなく明らかで、不滅で、常に同じままに輝いて照明するという特性を有しているということであり、光のない暗い闇を作るものをすべて追い払って消滅させるものであるということである。」(『中世思想原典集成3 後期ギリシア教父・ビザンティン思想』天上位階論 p376:平凡社)
[本文に戻る]
(※②)
偽ディオニシウス・アレオパギテースは、この6つの翼について「最初と中間と最後の思推によってあの神に属する事柄へ向かう絶対的な最高の上昇を意味している。」と言っているが、このような勝手極まる推測は退けられるべきである。
[本文に戻る]
それにしても、まだ信仰が純粋であった頃の古代教会の聖徒たちが、しかもアウグスティヌスさえもが、このように誤って解釈をしていたということは、今に至るまで本当に黙示録が正しく解釈されてこなかったことを、よく分からせてくれることではないかと思う。敬虔と思索力に富んでいた、まだ今のように世俗化していなかった時代の聖徒たちでさえ、このように黙示録を誤って理解していた。であれば論理的に考えて、世俗化に悩まされている今の時代の聖徒たちは、尚更のこと、黙示録を正しく理解できないないことになる。実際、今の時代の聖徒たちは、黙示録を不思議なぐらい正しく解釈することができていない。しかし、今や黙示録を正しく解釈できるような時代が到来している。今まで、聖徒たちはこの黙示録において盲人も同然であった。だが、もう聖徒たちの目が黙示録に対して開かれる恵みを受けられるようになってきている。だからこそ、このようにして黙示録が、今までの時代とは比較にならないぐらいの正確さをもって解析されているわけである。我々が、もし黙示録を正しく悟れたのであれば、その解釈の恵みを神に感謝せねばならない。神の恵みがなければ、黙示録だけでなく聖書の諸巻を正しく理解することは決してできないのである。
さて、ヨハネはここでセラフィムがセラフィムであることを隠しつつ書いているが、それは何故だったのか。それは、分かる者だけがこの『4つの生き物』の正体を知れたらよいからである。つまり、『聞く耳のある者は聞きなさい。』ということである。悟れない者は、この生き物の正体を悟れないままでいれば、それでよかった。悟れる者だけが悟れたらいいという事柄が、聖書の中には多くあるが、この生物もその中の一つである。だから、ヨハネは分からない人たちが分かるようにと配慮する義務を負っていなかった。それゆえ、ヨハネはこのように隠しつつセラフィムのことを書いたわけである。このようなことを聞いて、ヨハネが意地の悪いことをしたとか、ヨハネには愛がないなどと思ってはいけない。確かにヨハネは、一見するとこれがセラフィムだとはほとんど分からないような書き方で、このセラフィムを書いた。しかし神が、このような書き方をヨハネにさせるのを望まれたのである。もしヨハネがこのようにセラフィムを隠しつつ書いたことについて批判するのであれば、同様の理由から、キリストをも批判せねばならなくなってしまうから注意すべきである。キリストも、多くのことについて、それがそれであることを明らかにしないで語られたのである。
しかし、このセラフィムが『前もうしろも目で満ち』ていたのは何故なのか。それはセラフィムが、その与えられた無数の目により、神の栄光を見るためである。言うまでもなく、神の栄光を賛美するためには、神の栄光を見ることができなければいけない。何故なら、神の栄光を見るからこそ、神の栄光の素晴らしさが分かり、口から賛美が出るようになるからである。そして神の栄光は、より豊かに見られ、より豊かに賛美されるべきである。だからこそ、神を賛美することを主な役割とするこのセラフィムには、神の栄光を豊かに認識できるようにと、多くの目が与えられているのである。しかし、イザヤ書のほうではセラフィムに目があると書かれていないが、それは何故なのか。それは、イザヤ書のほうでは単に目があると書かれていないだけである。つまり、イザヤ書のほうでは目について書かれていないだけであって、実際には目があったということである。それゆえ、目には今書かれたような意味があるのだから、我々はセラフィムに目がついているということを聞いて、我々を驚かせるためにこのように書かれているなどと思ったり、意味もなく目がついているなどと考えたりすべきではない。神が、ご自身の創造物であるセラフィムにおいて、ただ我々を驚かせるためにだけ目をつけたり、意味もなく目をつけたりされるということが、どうしてあるであろうか。ところで、アレクサンドリアのキュリロスはこのセラフィムが「天使、大天使、そして彼らよりも上位にある」(『中世思想原典集成3 後期ギリシア教父・ビザンティン思想』キリストはひとりであること p163:平凡社)と言っているが、これには何の根拠もない。私はキュリロスがどうして、このように言ったのかよく分からない。聖徒たちはセラフィムの位階を勝手に定めたりしないように注意すべきである。
では、このセラフィムが4つの被造物のような外観(人間、獅子、雄牛、鷲)を持っていると言われているのは、どういうことなのか。セラフィムの外観が4つの被造物のようであると言われているのは、我々が、この生き物を神であるかのように考えないためである。ヨハネはこのセラフィムをそれがセラフィムであることを隠しつつ書いたが、そのようにするとこの生き物に何か神秘的な印象が生じることになり、その印象がこの生き物を神または神をそのまま具現化した生物ではないかと思わせることに繋がる。多くの例が示すように、人間という存在は、そこに神秘性が現われていると、すぐにも無意識的に神性または神的な事柄と結びつけてしまう傾向を持つ存在である。ヨハネは、そのような思い違いを防止させようとして、この生き物が4つの被造物のような外観を持っていると書いたのである。そのようにすれば、この生き物が神であるとは思いにくくなる。何故なら、その生き物には被造物としての外形が示されているのであって、神とは被造物ではないからである。人間、獅子、雄牛、鷲といった被造物がその造り主である神であるはずが、どうしてあろうか。もしこのような4つの被造物について書かれていなかったとすれば、多くの人が、この4つの生き物を神的な存在であると思ってしまったに違いない。エリファス・レヴィの場合、この4つの外観は、人間が「条理」を、獅子が「闘いと征服」を、雄牛が「諦念と勤勉」を、鷲が「信仰」を表わしているなどと言っているが、ただ好き勝手に生物と観念を結び付けているだけである。こういった奇人の妄想的な聖書解釈にはよく気を付けなければならない!ちなみに、この4つのセラフィムは、エゼキエル書における4つの生き物とは同一の生き物ではない。私は以前、セラフィムとエゼキエル書の生き物が同一の存在だと思っていたから、次のように書いたのであった。<それだから、この4つの被造物を通して示されている黙示録のセラフィムとエゼキエル書のセラフィムの外観がそれぞれ違っていたとしても、何も問題にはならない。確かに、先に見たように、黙示録のセラフィムはそれぞれ4つとも外観が違うのに対しエゼキエル書のセラフィムは4つとも外観が同じであった。つまり、この2つの文書において4つの被造物が描かれた目的は、この4つの生き物が「神ではない。」ということが示されるためであったから、その目的さえ達成していれば、外観がいくらか異なっていても構わなかったのである。確かに、4つとも外観が異なっていても(これは黙示録のセラフィムである)、どれもみな同じ外観であっても(これはエゼキエル書のセラフィムである)、その生き物たちが「被造物である。」ということが示されているのには変わらない。だから、黙示録とエゼキエル書のセラフィムにおける外観がそれぞれ違っていても、どちらの記述のほうが正しいとか、間違っているとか、そういうことはないのである。先に見た黙示録1:13~16の箇所におけるキリスト像も、その箇所と対応しているダニエル書におけるキリスト像と若干の違いがあったが、本質的には同一のことが示されているので、外見上にいくらかの違いがあっても特に問題ではなかった。それと同じことが、我々が今見ている黙示録とエゼキエル書におけるセラフィム像についても言える。要するに、幻というものは、そこで示されている事柄が同一でありさえすれば、その幻と対応している他の幻と内容的な違いがあっても問題ではないということである。それは、ある人が長袖を着ていても半袖を着ていても、または長髪であっても短髪であっても、そこに存在しているのはその人そのものであることには変わらないのと同じである。ある2つの対応した幻において示されている事柄が同一であるにもかかわらず、いくらか視像的な違いがあるからといって騒ぎ立てたり不信仰になったりするのは、ある人が前の日とは違う服装をしているからといって、「この人は本当に前の日にいた人と同一の人なのだろうか。前の日とは服装が異なっているが…。」などと悩んでしまう愚か者に例えることができよう。>私は前にこう書いたのであるが、エゼキエル書の生き物は実はセラフィムではない。先にも述べたように、エゼキエル書の生き物はセラフィムのように6つの翼を持っていないからである。では、エゼキエル書の生き物がセラフィムでないとすれば、それは何なのか。その答えは『ケルビム』である(※)。エゼキエル書において、4つの翼を持っているのはケルビムだと明示されている。すなわちエゼキエル書10:20~22で、エゼキエルはこの4つの生き物について次のように言っている。『彼らは、かつて私がケバル川のほとりで、イスラエルの神の下に見た生きものであった。私は彼らがケルビムであることを知った。彼らはおのおの4つずつ顔を持ち、おのおの4つの翼を持っていた。その翼の下には、人間の手のようなものがあった。彼らの顔かたちは、私がかつてケバル川のほとりでその容貌としるしを見たとおりの顔であった。彼らはみな、前のほうへまっすぐ進んで行った。』私は以前、このエゼキエル書10:20~22の箇所を失念していたのであった。だからこそ、エゼキエル書1章だけしか見ておらず、そのためこれがケルビムだと気付かなかったわけである。しかし、今はもう、これがセラフィムであると考えることはできない。その理解は完全な誤りだからである。これはセラフィムではなくケルビムなのだ。それゆえ、黙示録に出てくる4つの生き物は、エゼキエル書の4つの生き物とは全く対応していない。両者は全く別の御使いであるのだから。エリファス・レヴィは黙示録の生き物とエゼキエル書の生き物を同一視しているが(『高等魔術の教理と祭儀 教理篇』媚薬と呪い p246:人文書院)、研究不足な者らしく完全に間違っている。読者は、6つの翼を持つのがセラフィムで(これは黙示録とイザヤ書の生き物である)、4つの翼を持つのがケルビムだという理解(これはエゼキエル書の生き物である)を持つようにしてほしい。このように私は、自分の思い違いを今、隠し続けることなく訂正した。教師のほとんど全ては自分が誤っていたと気付いても誤っていたことを認めようとはしないものだが(というのもそのようにするのは恥ずかしく苛立たしく教師としてのプライドにかかわることだから)、他の教師がどうであれ、私はアウグスティヌスと同じように、誤りをシッカリと認め、それを訂正していかねばならないのである。というのも、そうすることが正しい姿勢であり、そうしないと自分も教えられる者も誤りから解放されないままとなってしまうからである。誤っているのに気付いても誤りを是正しようとしない人は、真理よりも自己愛を上に置いているわけだから、神からの恵みを受けていないのである。
(※)
偽ディオニシウス・アレオパギテースによれば、このケルビムは次のような御使いであった。エゼキエル書の記述から推測可能な内容に限って言えば、私はこの説明に首肯的である。「あるいはまた、「ケルビム(智天使)」という名称が教えているのは、彼らが神を見ることができ、光の最高の賜物を受け取って、第一次的に与えられた力で神性の根源の整然たる美しさを観想することができる認識能力であり、また知恵を与える分与の働きに満たされて、与えられた知恵を注ぎだ出すことにより第二位のものに惜しみなく分け与えることができるということである。」(『中世思想原典集成3 後期ギリシア教父・ビザンティン思想』天上位階論 p376:平凡社)
[本文に戻る]
ちなみに、この4つの被造物が描かれているのは、セラフィムの力強さを示していると考えることもできる。何故なら、箴言にはこう書かれているからである。『歩きぶりの堂々としているものが3つある。いや、その歩みの堂々としているものが4つある。獣のうちで最も強く、何ものからも退かない雄獅子、いばって歩くおんどりと、雄やぎ、軍隊を率いる王である。』(30章29~31節)我々が今見ている箇所とこの箴言の箇所を比べると、人と獅子という2つの被造物は同一だが、残りの2つは種類が異なっている。恐らくヨハネは、雄鶏を『鷲』に、雄山羊を『雄牛』として言い換えたのだと思われる。そうすれば、よりセラフィムの堂々とした雰囲気を伝えることができるからである。雄鶏よりも鷲のほうが、雄山羊よりも雄牛のほうが、より堂々としている印象があるのは確かである。既に説明されたように、黙示録には旧約聖書のある箇所と全体的には似ているが細部においていくらか異なっている箇所が多くあるのだから、ここでも、そのような細部における微妙な言い換えがなされていると考えるのは荒唐無稽な見解ではない。つまり、その場合、神がセラフィムの力強さを示そうとして、箴言の箇所に基づいた幻をヨハネに啓示されたということになる。セラフィムが堂々とした存在だというのは、誰でも分かることであろう。神を賛美する役割を持つ天使が弱々しくて、どうしていいはずがあるであろうか。軍隊の音楽隊が力強い演奏をすべきであるのと同じように、『ヤハウェの軍の将』(ヨシュア5章15節)であられる神の賛美部隊であるセラフィムも力強くなければいけないというのは確かである。私が今この4つの被造物について箴言の箇所から述べた見解が正しい可能性は、黙示録の秘儀的な内容を考えると、かなり高いと思われる。
『彼らは、昼も夜も絶え間なく叫び続けた。「聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。神であられる主、万物の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来られる方。」』
ここではセラフィムが、絶えることなく神に対して、良き言葉を叫び続けている様子が記されている。セラフィムはこのように叫び続けて飽きることがなく、このように言われる神も、セラフィムが良き言葉を叫び続けることに飽きることがない。何故なら、神は永遠に昼も夜も褒め称えられるべきお方であって、セラフィムはその神に良き言葉を捧げることを喜びとするからである。
『聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。』と言われているのは、イザヤ書6章でセラフィムが言っているのと同じである(※)。この4つの生き物が、イザヤ書6章のセラフィムと同様のことを言っているということから、この生き物がセラフィムだと分かるようにされている。神は、イザヤ書6章を頼りにこの4つの生き物がどのような存在であるのか、聖徒たちが知れるようにして下さった。つまり、この4つの生き物が、正にイザヤ書に出てくるあのセラフィムだからこそ、イザヤ書でセラフィムが言っているのと同じことをここで4つの生き物は言っているわけである。ここで『聖なるかな』という言葉が3回も繰り返されているのは、神の聖性を強調するためである。神の聖性は無限であられるから、このように強調して豊かに言い表わされるのが好ましい。聖書において3回の繰り返しは、その言われていることを強調する意味がある。エレミヤ書22:29では『地よ、地よ、地よ。』と言われているが、これは地に力強く語りかけていることを示している。これは今の時代の人たちで言えば、文章の最後に「!」をつけるようなものだと考えればよい。ヘブル人たちは、何かを強調して語りたい場合、「!」などという記号を使うのではなく、連続で同じ言葉を繰り返すという語法を使っていた。要するに、ここでは「神の聖性はあまりにも素晴らしい。」ということが言われている。このようにセラフィムが言っている対象は、キリストである。というのも、このように言ったすぐ後で、セラフィムは『後に来られる方』と言っているからである。『後に来られる方』とはすなわち「これから再臨されるキリスト」という意味だから、ここで口にされている聖性の対象となっているのはキリストである。しかし、ここでキリストについてその聖性が言い表わされているからといって、御父と御霊には聖性が存在していないというのではない。確かに、ここで『聖なるかな』と言われているのはキリストのことである。だが、ここではただキリストにだけこう言われているだけであって、御父と御霊には聖性が存在していないということが言われているのではない。御父と御霊も、キリストと同様に『聖なるかな』と言われるべき存在であるのは確かである。誰がこのことを疑うであろうか。なお、イザヤ6:4の箇所によれば、セラフィムは叫びつつこのように言っていた。セラフィムが叫んだのは神の聖性が非常に重要だからである。
(※)
この言葉は、非常に印象深く、特徴的である。多くの人の脳裏に残るような言葉である。邪悪なアレスター・クロウリーでさえ、その著作の中で、この言葉をそのまま使っているぐらいである(例えば「おぼこ連のための物語」や「霊視と幻聴」など)。
[本文に戻る]
『神であられる主、万物の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来られる方。』という言葉は、既出であり、その意味は既に説明された通りである。前出の箇所との違いは、ただこのように言っている存在者が違うという点だけであって、その相違点は大いに考察すべきであるとか非常に重要であるというわけではない。それゆえ、この部分は、もうこれ以上の説明をする必要がない。
【4:9】
『また、これらの生き物が、永遠に生きておられる、御座に着いている方に、栄光、誉れ、感謝をささげるとき、』
セラフィムは『栄枯、誉れ、感謝』といった良きものを、神に捧げるために存在している。何故なら、そのようにするためにこそ、神はこのセラフィムをお造りになったからである。これはセラフィムが、昼も夜も絶え間なく神に良き言葉を叫び続けていることから分かる。つまり、先にも述べたが、四六時中神に良き言葉を捧げているというのは、すなわち、そのようにする役割を持つ生き物として造られているということを意味しているのである。
とはいっても、セラフィムは何か自動装置のように機械的な賛美を捧げているというのではない。何故なら、そのような賛美は、賛美とは言えないからである。それは賛美というよりは、むしろ愚弄であるというべきものである。この世の王侯たちは、口先だけの機械的な称賛を望まないものである。それが上辺だけの言葉に過ぎない虚無的なものだからである。王侯たちでさえそうであれば、尚更のこと、王侯たちの王であられる神はそのような機械的な言葉を望まれない。セラフィムがこのような良きものを神に捧げるのは、心からである。彼らは理性的に、しっかりと意味を弁えつつ、偽りのない心でもって神に栄光や誉れや感謝を捧げる。セラフィムたちは神に良きものを捧げるために造られたのだから、確かにこのように考えなければいけない。神が、上辺だけの言葉を口にする存在としてセラフィムを造られたということが、どうしてあるであろうか。そのようなことは決してない。もしそういうことであったとすれば、神はこの上もなく愚かな存在であるということになってしまうであろう。
【4:10】
『24人の長老は御座に着いている方の御前にひれ伏して、永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出して言った。』
ここでは、24人の長老として表示されている天上の教会に属する聖徒たちが、神の御前に崇拝を捧げている場面が描かれている。これは一時的、この場限りの崇拝行為であると考えてはならない。これは永遠に至るまで行なわれ続けることである。何故なら、神は永遠に崇められるべきお方であって、ご自身が崇められるためにこそ、聖徒たちを救ってご自身の民とされたのだからである。だから、ここで神に崇拝を捧げている教会が、強制的・奴隷的・無意識的・機械的に崇拝を捧げているなどと思ってはならない。この崇拝行為は、自主的・積極的・意識的・理性的・親愛的なものである。何故なら、聖徒たちは『主をおのれの喜びと』(詩篇37篇4節)するからである。パウロも、『私たちの念願とするところは、主に喜ばれることです。』(Ⅱコリント5章9節)と言っている。聖徒たちは、その与えられた聖霊によって、神を喜び、神の喜びをこそ求める。よって、天上の聖徒たちが無理強いさせられた崇拝を奴隷的に行なうということは、決してない。その崇拝は、あたかも子が父に仕えたり、妻が夫のために何かをしたりするようなものである。つまり、それは何の重荷にもならないということである。確かにヨハネもその第一の手紙(5:3)の中で言っているように、神を愛することは何の重荷にもならないのである。それゆえ、このような崇拝行為が永遠になされるということを聞いて、聖徒である者は、何か大変そうであるなどと思うべきではない。
この箇所で教会が自分の冠を神の御前に投げ出しているのは、栄光に満ちておられる神の御前において、名誉や権威や立場といったものは何の意味も持たないからである。神の輝かしい栄光の前では、月も太陽も、その持っていた輝きを失い、輝いていないのも同然の状態となってしまう。何故なら、それほど神の栄光は輝かしいからである。イザヤ24:23の箇所では、神の『栄光がその長老たちの前に輝く』と、『月ははずかしめを受け、日も恥を見る。』と言われている。つまり、神の輝きは、月や太陽が劣等感を覚えてしまうほどのものだということである。これは、月も太陽も神の創造物であるから当然である。それらのものを造られた神が、それらのものよりも輝いておられないということが、どうしてあるであろうか。確かなところ、神は、月や太陽の数万倍、数億倍、いやそれ以上の輝きを持っておられる。要するに、神の御前では、どれだけ輝かしいものであれ、暗黒や無に等しくなってしまう。だからこそ、ここで長老たちは、自分たちが王であることを示す権威の冠を御前に投げ出しているわけである。この冠は、それそのものとしては輝かしいものであるが、輝きの極致であられる神の御前においては、何の価値も持っていないと言わねばならないのである。ちょうど、世界タイトルのチャンピオンベルトを持っているプロボクサーの前では、あまり有名でない大会におけるチャンピオンベルトを持っているアマチュアボクサーが、その比較において、小さく見えたり取るに足らないと思えてしまうのと同じである。
【4:11】
『「主よ。われらの神よ。あなたは、栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたのみこころゆえに、万物は存在し、また創造されたのですから。」』
この章の9節目の箇所でセラフィムたちは『栄光、誉れ、<感謝>』を捧げていたが、ここで長老たちは神に対して『栄光と誉れと<力>』と言っている。つまり、1番目と2番目の言葉はどちらも同じなのだが、3番目の言葉が違っている。しかし、『感謝』と言われていようと『力』と言われていようと、どちらかが間違っているというわけではない。何故なら、神は感謝も力も共に受けるべき当然のお方だからである。
ここで長老たちが言っているように、神はその万物における創造と保持のゆえに、『栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方』である。まず、神は万物のゆえに栄光を受けるに相応しい。万物には、それぞれ神の栄光が鏡のように現われ出ている。すなわち、人間はそのうちにある神の似像において神の栄光を現わし、チーターはその速さによって神の俊敏さにおける栄光を現わし、象はその大きな力によって神の御力における栄光を現わしている。個々の被造物に見られる神の現われとしての素晴らしさ、すなわち栄光は、当然ながらその創作者であられる神にこそ結び付けられるのが相応しい。だから、神は、その万物を通して栄光を受けるべき当然のお方なのである。次に、神は、誉れを受けるに相応しいお方である。万物は、神の創造物であって、そこには神の知恵が満ちており、それは喫驚に値する素晴らしい構造や性質を有している。それは、他でもない神が巧みに創造されたものである。だから、神は、その万物を通して誉れを受けるに相応しいお方である。我々が、素晴らしい商品を開発した開発者に、「あなたは素晴らしいことをした。」と言って誉れを与えるのと同じことである。最後に、神は力を受けられるべきお方である。というのは、万物は、神の御力によってこそ造られ、また日々神の御力のゆえに保持されているからである。この神の御力なしには、万物が造られることもなかったし、造られた万物が保持されることもなかった。だから、神には、その万物を通して力が帰されなければいけない。このように万物と神とのかかわりと考えるならば、神には『栄光と誉れと力』が捧げられるに相応しいということが分かる。我々も、神の造られた万物を通して、神に良きものを帰し、捧げるべきである。それは主の御心に適ったことであり、主に喜ばれることなのである。
第7章 ④5章:7つの封印を解くことになったキリスト
【5:1】
『また、私は、御座にすわっておられる方の右の手に巻き物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書きしるされ、7つの封印で封じられていた。』
ここで主が右手に持っておられるのは、預言の書き記された巻物である。その預言の内容は、全部で7つである。だからこそ、その一つ一つの預言が『7つの封印で封じられていた』のである。この巻物は、封印が解かれると、その解かれた預言が公に開示されるという仕組みになっている。一つ目の封印を解けば一つ目の預言が開示され、2つの目の封印が解かれたら2つ目の預言が開示される。同様に3つ目、4つ目…と続けられる。この7つの預言が開示されている場面は、6章目で描かれている。
ここで、この巻物に書かれている文字は何語なのか、その文字における神の筆跡はどのような感じであったのか、巻物の大きさはどれほどであったのか、またその全長は短かったのか、それとも長かったのか、というような疑問を持たれる方がいるであろうか。このようなことは本質的ではなく、熱心になって探求したりすべきであるとか、知って大いに有益となるというようなものではない。それは、キリストの身長がどれぐらいであったかとか、パウロの髪の色は何色だったかなどと問うのが些細で重要ではないのと同様に、些細で重要ではない。それゆえ、このような疑問は取り扱わなかったとしても特に問題にはならない。我々は自分の精神と思索の力とを、もっと重要で本質的な事柄に振り分けなければいけないのである。
神の手に巻物があったのは、この巻物が神によるものだということを意味している。つまり、神がそれを作られたからこそ、神の手にそれがあるのである。確かに、この巻物に記されている預言は『神がキリストにお与えになったもの』(1章1節)だから、その預言が記されている巻物は、他でもない神が制作者であられる。この巻物が神の『右の手に』あったのは、この巻物とそこに記されている預言が、重要であったことを教えている。もし重要ではなかったとすれば、左の手に巻物があったということもありえる。我々人間は、そのほとんど全ての人が右利きであって、それゆえ重要な物があれば、より使いやすい右の手でそれを持ったり動かしたりする傾向があると言っても間違いではないはずである。神は目に見えないお方であるから、実際には物質的な手を持っておられないが、ここでは比喩として、右利きの多い我々人間に分かりやすいようにと、神がその右手で巻物を持っておられたと言われているわけである。先に見た1:17の箇所でも、キリストが倒れてしまったヨハネの上に『右手』を置かれていたが、それはキリストにとってヨハネが重要な存在だからであった。
ここでは巻物に記されている預言が『7つの封印で封じられていた』と書かれているが、どうして巻物の預言が7つに定められたかといえば、それはその預言が聖であり、必ず完全に実現されるべき預言だったからである。すなわち、ここでも「7」という数字により、預言の聖性と完全性とが示されている。ここでは預言の聖性と完全性を示すことが目的とされているのだから、預言とその封印の数が7ではなく10でも問題はなかった。しかし、神は10ではなく7のほうを選ばれた。それは、明らかに7にしたほうが分量的に、また啓示としてより相応しいからであった。もしこれが10だったとすれば、いくらか煩わしくなり、不適切になっていたはずである。
ところでタルムードの中では、巻き物の表と裏について書かれている箇所がある。すなわち、「アヴォード・デ・ラビ・ナタン」では次のように書かれている。「「表」はこの世を指し、「裏」は来るべき世を指す。もう一つの解釈。「表」はこの世における義人の苦難とこの世における悪人の繁栄を指す。「裏」は来るべき世における義人の報いとゲヒンノムでの悪人の懲らしめを指す。」(『タルムード ネズィキーンの巻』第25章 1 27a p92:三貴)我々が今見ている箇所に出てくる巻き物にも表と裏に文字が書き記されているが、ここでは表に何が書かれており裏に何が書かれているか、ということを正しく理解することは難しい。というのも、そのことについて我々には何も知らされていないからである。
【5:2】
『また私は、ひとりの強い御使いが、大声でふれ広めて、「巻き物を開いて、封印を解くのにふさわしい者はだれか。」と言っているのを見た。』
『強い御使い』というのは、どのような御使いか。それはミカエルなのか、ガブリエルなのか、それともラファエルなのか。聖書には明確に記されていないから、この御使いが、どのような名を持っているのか我々には分からない。僭越になるべきではない我々は、この御使いがただ『強い』性質を持っていると知るだけで満足すべきであろう。
しかし、この『強い御使い』はセラフィムではないかと思われる方もいるかもしれない。上の箇所で、この御使いがどのような存在か分からないと書かれたのだが、確かにこの御使いがセラフィムである可能性はないわけではない。というのも、ここでその御使いは『強い』と言われているが、先に4章7節目で示されていたセラフィムにおける4つの被造物は、堂々とした、つまり強いと言える存在について記している箴言30:29~31の箇所と関連している可能性があるからである。もし本当にセラフィムにおける4つの被造物が箴言30:29~31の箇所に関連しているとすれば、4:7の箇所ではセラフィムが堂々とした強い存在であると示していることになるのだから、我々が今見ている箇所に出てくる『強い御使い』もセラフィムであることになる。問題となるのは、4:7の箇所が箴言30:29~31と関連しているのかどうか、というこの一点に尽きる。いずれにせよ、今現在の私は、この問題について確定的なことを言わないでおきたい。
この強い御使いが大声で巻物を解くべき者を見つけようとしているのは、この御使いが、封印された預言の内容を切に知りたがっていたということである。それは当然ながら、この御使いだけでなく他の御使いたちも、また24人の長老たちも、そうだったであろう。もしそうでなければ、大声でこのようなことを言うこともなかったはずである。一体、どこの誰がどうでもいいと思っていることを知るために、大声でふれ広めてそれを知ろうとするであろうか。この預言は、再臨や古い世の終末や復活や審判に関する、あまりにも重要かつ神聖な預言であった。だから、この強い御使いが、それを知ろうとしてこのように大声でふれ広めたのは自然なことであった。この世でも、絶対に捕まえて尋問すべき極悪人は、往々にして指名手配され、人々に周知されるものである。例えがあまりにも悪いのだが、ここで御使いがしているのは、つまりはそれと似たようなことであったと言える。
【5:3】
『しかし、天にも、地にも、地の下にも、だれひとりその巻き物を開くことのできる者はなく、見ることのできる者もいなかった。』
この巻物は、全知全能の神が、その制作者であった。それは人間の手によるものではなかったのである。だから、誰一人として巻物を開いたり見たりできなかったのは当然であった。神が封印されたその封印を、被造物に過ぎない存在が、どうして自分の力や知恵や権能によって解いたりできるであろうか。そのようなことは決してありえない。それは、世界一のハッカーが仕組んだ秘密の封印プログラムを、PCの素人が解除しようとしても無駄な徒労に終わるようなものである。
【5:4】
『巻き物を開くのにも、見るのにも、ふさわしい者がだれも見つからなかったので、私は激しく泣いていた。』
ヨハネが『激しく泣いていた』のは、巻物を開いて見たかったのに、残念ながらそのようにすることのできる者がいなかったからである。ほとんど全ての人は、どうしても見たいのに見ることができなかったので悲しくなった経験を持っているはずである。そのような経験を持っている人は、ここでヨハネが感じている悲しみに、多かれ少なかれ同感できるのではなかろうか。どうしても見たいのに見れないということほどに、残念なことが他にあろうか。
ヨハネが巻物を見れなかったというので激しく泣いていたということは、ヨハネの霊性の高さを如実に語っている。ヨハネは非常に高い霊性を持っていたからこそ、この巻物とそこに書かれている文字の測り知れない重要性を悟ることができた。だからこそ、重要であるその巻物が見れないからというので、激しく泣いてしまったのである。もしヨハネの霊性が高くなかったとすれば、激しく泣いたりすることもなかったであろう。何故なら、霊性が高くないので、巻物の重要性を悟れないからである。そうであれば、巻物が重要だと思っていないのだから、たとえ巻物が見れなかったとしても、激しく泣くということは起こりえない。「ふーん、そうなのか。見れないのか。」と思うぐらいで終わってしまう。これは、ちょうど邪悪な死人たちが、聖書の重要性をまったく理解できないので、聖書の中に非常に重要で難解な箇所があると知っても、あまり関心を持とうとしないのと同じことである。しかし、ヨハネのように敬虔な聖徒であれば、そのような箇所があると知った際、非常に残念に思って大いなる関心を示すのである。
【5:5】
『すると、長老のひとりが、私に言った。「泣いてはいけない。見なさい。ユダ族から出たしし、ダビデの根が勝利を得たので、その巻き物を開いて、7つの封印を解くことができます。」』
『ユダ族から出たしし』とは、キリストのことであり、そのキリストがユダ族の出であって、聖書では獅子として象徴されているからである(※)。創世記49章で、ユダの子孫であられるキリストが『雄獅子のように、また雌獅子のように』(9節)と言われている通りである。『ダビデの根』とは、キリストがダビデの子孫だということである。パウロが『御子は、肉によればダビデの子孫として生まれ』(ローマ1章3節)と書いている通りである。これらは初歩的な知識であって、もう既に何度も語られてきたことだから、もうこれ以上の説明は不要であろう。
(※)
Ⅰペテロ5:8の箇所にも書かれているように、聖書において『獅子』とはサタンをも象徴する言葉である。この動物が、キリストを象徴する動物であると共にサタンをも象徴する動物であるということに注意せよ。また、これは蛇の場合も同様である。
[本文に戻る]
ここでキリストが『勝利を得た』と言われているのは、すなわち、キリストが死と罪とサタンとこの世とに打ち勝たれたことを意味している(※)。それらの勝利は、十字架における贖いと3日目の復活により実現された。その勝利は完全なものであった。キリストが勝利されなかったものは、一つもない。
(※)
キリストが死に勝利されたというのは、『キリストは死を滅ぼし、…』(Ⅱテモテ1章10節)と書いてある通りである。罪に勝利されたというのは、キリストが『いろいろな定めのために私たちに不利な、いや、私たちを責め立てている債務証書を無効にされた』(コロサイ2章14節)と書いてある通りである。キリストがサタンに勝利されたというのは、キリストが『その死によって、悪魔という、死の力を持つ者を滅ぼし、…』(ヘブル2章14節)と書いてある通りである。キリストがこの世に勝利されたというのは、キリストが『わたしはすでに世に勝ったのです。』(ヨハネ16章33節)と言われた通りである。
[本文に戻る]
このような勝利をキリストが得られたので、キリストは、いや、キリストだけが、神に封印されていた預言の巻物を解くに相応しいとされたのであった。キリストは死に至るまでも従順であられ、完全な勝利を得られたので、そのようなお方として相応しく、神の巻物を解く資格を持っておられたのである。
だからこそ、ここでは長老が『泣いてはいけない。』と言って、大いに悲しんでいたヨハネを慰めているのである。何故なら、キリストという巻物を解くに相応しいお方がいたので、もはや巻物の中身が見れないということはなくなったからである。この時のヨハネの喜びは、どれほどだったであろうか。切に見たいと願っていた巻物が見れるようになり、しかも自分の愛する救い主がそれを解いて下さることになったのである。ただの被造物に過ぎない人間ではなく、人となられた神なるキリスト・イエスが、である。であるから、この長老の声を聞いたヨハネは、測り知れない喜びに満たされたに違いない。
【5:6】
『さらに私は、御座―そこには、4つの生き物がいる。―と、長老たちとの間に、ほふられたと見える子羊が立っているのを見た。』
『子羊』すなわちキリストが『ほふられたと見える』と書かれているのは、キリストが御父にご自分を永遠の犠牲として罪のためにお捧げになった、という意味である。ここでは『子羊』と言われているが、我々は、御父の前に本当に動物のような姿をしたキリストが立っておられたというイメージを頭に描いてはならない。『子羊』という言葉は、あくまでもキリストを象徴的に言い表わした言葉だからである。事柄は霊的に捉えねばならない。しかしながら、キリストが実際的な動物としての子羊ではなかったにせよ、キリストが真の意味における犠牲としての子羊だったということは間違いない。というのも、神の御前に捧げられるべき本来的な唯一の犠牲は、旧約の時代に多く捧げられた動物としての子羊などではなく、キリストという霊的な子羊お一人だけだからである。バプテスマのヨハネも、この意味において『見よ、世の罪を取り除く神の子羊。』(ヨハネ1章29節)とキリストを指して言っている。古い時代に捧げられた子羊という犠牲は、キリストという実体の『影』(ヘブル10章1節)に過ぎなかったから、神の御前において真の犠牲物であるとは言えないのである。影に過ぎない一過性を持つ犠牲物が、どうして真の犠牲物であると言えるであろうか。この霊的な子羊であるキリストが、このように御父の近くにおられるようになったのは、紀元33年頃であった。この頃に、キリストが天に入れられ、御父の近くに位置されるようなったのである。それはマルコが、『主イエスは、彼らにこう話されて後、天に上げられて神の右の座に着かれた。』(マルコ16章19節)と書いている通りである。しかし、ここでいくらか難しい問題が生じる。この箇所ではキリストが御座の前に立っていたと言われているが、キリストは他の多くの箇所で言われているように、「御座の前に立っておられる」のではなく、「御座の右に座しておられる」のではなかったのか(マルコ16:19、ヘブル8:1、Ⅰペテロ3:22、コロサイ3:1、詩篇110:1その他多数)。どうしてヨハネは、他の箇所で言われていることと異なった描写をここでしているのか。この問題を解決するのは、それほど難しいことではない。すなわち、預言や幻と同じように天という霊的な空間を描写する際にも、その本質部分が同じでありさえすれば、幾つかの聖句箇所においてそれぞれ微妙な差異が見られたとしても特に問題にはならないのである。聖書は、我々に対して、天におられるキリストが御父の側近くにいて統御しておられるということを示そうとしているのであるから、その点さえ固守されていれば、天におられるキリストの様子が幾つかの聖句箇所においていくらか違っていたとしても問題ではない。我々が今見ているこの黙示録の箇所ではキリストが御父の前に立っておられたと言われているが、そのような描写は、キリストが天において御父の側近くで統御しておられるということと何も矛盾していないから、他の多くの箇所のように「キリストは御父の右の座に着いておられる。」と書かれていなかったとしても問題にはならない。というのは、たとえ御父の右に座しておられるとは言われておらず、御父の前に立っておられたと言われているとしても、御父の側近くで統御しておられることには変わらないからである。だから、ヨハネがここで書いているキリストの描写を誤りだと思ってはならない。ステパノが殉教する際に、『神の右に立っておられるイエスを』(使徒行伝7章55節)見たと書かれているのも、同様のことが言える。ステパノは神の右に立っておられる―座しておられるのではない―キリストを見たのだが、それは聖書が伝えようとしている本質部分において誤っていない光景であったから、何も問題はなかったのである(※)。しかし、この箇所(黙示録5:6)や使徒行伝7:55~56で記されているような描写は誤りではないものの、聖書において一般的にはこのような描写はほとんどされていないということは言っておかねばならない。多くの箇所において、聖書はキリストが「御父の右に座っておられた。」と言っている。もしキリストが例えば神の「左に」座しておられたとか、神の「遠くに」立っておられたなどと書かれていれば、それは完全な誤りであった。というのも、この場合は、聖書が伝えようとしている本質的な点から意味内容が完全に逸脱しているからである。
(※)
カルヴァンも、このような微妙な違いは、そこにおいて同じ一つの事柄さえ言い表わされていれば何も問題にはならないと論じている。彼はステパノが殉教の際に見たキリストに関する箇所で、こう註解している。「ほかのところでイエスは座しておいでになると言われているのに、なぜ立っておいでになるイエスをステパノは見たのだろうとの疑問もここで起こるかもしれない。アウグスティヌスは(時として必要以上に精密であるから)、キリストは裁判官としてすわっておられるが、その次に弁護人としてお立ちになるのであると述べている。しかしわたしとしては、こうした言い方は種々あろうとも、それらは同じ一つの事を意味していると考える。イエス・キリストがすわっておいてになる、あるいは立っておいでになるのは、そのからだの姿勢を示しているのではなく、彼の権力と国とに関係があるのであるから。その右手の場所を少しも考えるべきではないように、神はあらゆる物に満ちたもうのであるから、イエス・キリストが神の右手に座したもうその玉座は、彼のためにいったいどこに設けられたよいのか。だから、人の子は父の右に立っておられる、あるいは座しておられると言われているのは、その主題全体が隠喩であるのだ。」(『新約聖書註解Ⅴ 使徒行伝 上』7:56 p230:新教出版社)
[本文に戻る]
『これに7つの角と7つの目があった。その目は、全世界に遣わされた神の7つの御霊である。』
キリストに『角』があったというのは、すなわち、キリストの王権を意味している。黙示録17:12では、大淫婦なる女が乗っていた獣の角について、こう書かれている。『あなたが見た10本の角は、10人の王たちで、彼らは、まだ国を受けてはいませんが、獣とともに、一時だけ王の権威を受けます。』これは忌まわしい存在の持つ角について言われたことだが、角が王権を意味しているという点は、キリストにおいても同様のことが言える。キリストにあったこの角を王権ではなく、「王」すなわちキリスト者という王を意味していると考えることも可能だが、そのように考える場合は、キリストが王としての聖徒たちを有している存在だという意味となる。しかし、私としては、これが「王権」を意味していると考えたほうがよいと思う。いずれにせよ、この『角』は、王権か、そうでなければ王を意味していると考えることしかできない。これを、キリストには実際の物理的な角が生えているなどと考えるのは、おかしいことだから注意せねばならない。何故なら、この箇所で言われている『角』とは、あくまでも象徴的な表現として捉えるべき言葉だからである。これを実際の角であると捉えなければ、王権であると捉えても王であると捉えても、どちらでも構わないと今現在の私は考える。また、この角が『7つ』あるのは、角が王権であると捉えた場合、キリストという王の持つ支配権が完全かつ神聖であることを示している。確かにキリストとは『王の王』(Ⅰテモテ6章15節)であられ、その統治は『海から海に至るまで、また、川から地の果て果てに至るまで』(詩篇72篇8節)に及ぶのだから、そのようなお方の持つ支配権が『7』という完全数で言い表わされているのは実に相応しいことである。この角をキリスト者という王であると捉えた場合、角が7つあるのは、キリストの有する聖徒たちがキリストにおいて完全かつ神聖であるという意味になる。確かに、キリスト者たちは、キリストにあって完全で神聖な存在である。何故なら、キリスト者は、キリストの贖いにより清められ聖とされているからである。
キリストに『7つの目があった』のは、キリストに、目であられる御霊が「7つ」すなわち無限に与えられているということである。福音書に書かれているように、御父は御子に『御霊を無限に与えられ』(ヨハネ3章34節)た。先に見た箇所もそうだったが、ここでも御霊が『無限』と言われる代わりに『7つ』と言われているのである。キリストはその与えられた無限の御霊という目なるお方において全世界を隅々に至るまでもご覧になられる。それは詩篇33:13~14で、『主は天から目を注ぎ、人の子らを残らずご覧になる。御住まいの所から、地に住むすべての者に目を注がれる。』と書かれている通りである。つまり、我々が今見ているこの箇所で「キリストの持つ7つの目とは、すなわち全世界に遣わされた神の御霊である。」と言われているのは、すなわち「キリストがその与えられた無限の御霊において全世界をご覧になっておられる。」という意味である。例のごとく、これも実際にキリストが7つの物理的な目を持っていると考えるべきではない。これも、やはり霊的に捉えなければいけないことだからである。
【5:7】
『子羊は近づいて、御座にすわる方の右の手から、巻き物を受け取った。』
キリストに巻物が渡されたのは、この巻物がキリストに与えられるべきものであり、それをキリストが解くことになっていたからである。他の存在が、この巻物を受けるということは、あり得ないことであった。
しかし、どうして御父ではなくキリストが巻物の預言を開示すべきだったのか。それは、御父が、御子にこそ巻物の封印を解くようにと願われたからであった。御父は、空中におけるあの裁きを、ご自身が行なわれるのではなく御子に任せられた。『父はさばきを行なう権を子に与えられました。』(ヨハネ5章27節)とキリストが言っておられる通りである。それと同じように、巻物が開示されることも、父は子に委ねられたのである。御父が巻物を解除できなかったというのではない。つまり、御父が巻物を解除できなかったので、御子にそれをやってもらおうとして巻物を渡されたというのではない。『神にとって不可能なことは一つもありません。』(ルカ1章37節)と書かれていることからも分かるように、神であられる御父はご自身でも巻物を解除できたのであるが、ただそれをご自身では行なわれず、御子にやらせようとされただけである。御父が巻物を解けなかったと考えるのは、愚かの極みであると言わねばならない。
ここで、「どうして巻物の開示を第1章目の始めから書き記さなかったのか。」などと疑問に思われる方がいるかもしれない。「このように長々とした記述をせず、早々と預言を記せばよかったと思うのだが…」と。これは愚かな疑問であって、我々はこのような疑問を発すべきではない。物事には順序や秩序といったものがある。実は枝が出てから生り、読書は文字を識別できるようになってから可能となり、小説にも起承転結という流れがある。キリストもアダムが堕落してからすぐさま受肉されることをせず、多くの年月が経ってから、また数々の預言が語られてから、受肉された。それと同様に、黙示録において預言が開示されるということにも、流れというものがあるのを弁えねばならない。もし第1章目からいきなり巻物の預言を書き記していたとすれば、いくらか不自然になっていたであろうし、それは『すべてのことを適切に、秩序をもって行ないなさい。』(Ⅰコリント14章40節)と言われた主の御心に適わないことであった。すぐにも巻物の預言が書かれなかったことに疑問を抱くのは、例えば「どうして人間は成人の状態で生まれてこないのか。」とか「どうしてこの映画はクライマックスから始まらないのか。」などと問う人に似ている。このように問う人には、順序や秩序を弁える精神がない。聖徒たちは、神が欲された啓示および記述の流れに異を唱えたりしないように注意せよ。神の書かれ方に文句をつけるとは何様のつもりなのか。
【5:8】
『彼が巻き物を受け取ったとき、4つの生き物と24人の長老は、おのおの、立琴と、香のいっぱいはいった金の鉢とを持って、子羊の前にひれ伏した。この香は聖徒たちの祈りである。』
どうしてキリストが巻物を御父の手から受け取った時、彼らはキリストに崇拝の行為を捧げたのか。それは、その出来事があまりにも素晴らしかったからである。キリストにしか解くことのできない巻物が、キリストの手に渡され、それが遂に開かれて解かれることになった。これは、只ならぬことである。だから、天上の住民たちが、この出来事を見て、崇拝の行為を捧げないというのはあり得ないことであった。どうしてこの時に彼らがキリストの前にひれ伏したのか分からないか、あるいは違和感を持つ人は、まだ肉の人であるということを覚えるがよい。その人は肉的な人だから、霊的なことが分からず、それゆえどうして彼らが御前にひれ伏すのか分からないのである。天上の出来事は霊的であるから、霊的な人でないと、よく理解できないのである。
彼らが『立琴』を持っていたのは、この楽器が、神を賛美するのに相応しいからである。ダビデも、立琴を奏でつつ神に賛美を捧げた。この楽器は、誠に流麗で神妙な音を出すのであるから、神の輝かしい栄光とよく調和している。このように天上の住民が、またダビデが、神を讃えるために立琴を使用しているのだから、教会でもっとこの楽器が使用されてもよいのではないかと私は考える。ダビデだけでなく、天国にいる者たちでさえ、この楽器を使っているからである。そうすれば、より賛美が幸いなものとなるはずである。今の教会が、立琴をほとんど使用せず、ピアノやオルガンのほうを使用しているのは残念なことだと思う。天上の住民もダビデも、そのような楽器を使用してはいない。ピアノやオルガンも悪いとは言わないが、立琴のほうがより賛美に相応しいのは確かである。しかも、立琴の使用には聖書に明白な根拠がある。しかし、ピアノやオルガンのほうはない。もっとも立琴の場合、弾き手が不足するという問題が生じることは避けられないかもしれないが。
『香のいっぱいはいった金の鉢』とは、すなわち聖徒たちの祈りを有機的に象徴させた言い方である。天上の住民たちは、地上の聖徒たちが捧げる祈りを運ぶことで、神に仕え続ける。その祈りは神にとっては香であって、それは神の喜ばれるものである。我々が香しい匂いを嗅いで喜びを感じるように、神も祈りという匂いを嗅いで喜びを感じられる。その香である祈りの入った鉢が『金』だったのは、心からの祈りは、神の御前で金のように価値あるものだからである。そのような祈りは、神の目に価値あるものであるから、神はその祈りを聞いて下さる。金の鉢に入った祈りの香が放たれるのであれば、それを嗅いだ神が心を動かして下さるのは確かである。天上の住民たちは、このように聖徒たちの祈りを運ぶという行為を、何ら重荷としない。何故なら、彼らにとって、神に仕えるのは喜ばしいことだからである。だから、彼らにとっては、このような行為は、むしろ進んで行ないたいとさえ思えるものである。彼らは、地上に住む腐敗した者たちとは、性質がその根底部分からして違うのである。我々は地上における肉的な感覚を通して、天上に属することを推し量ったりしないようにすべきである。
我々の祈りが『香』だと知るのは、良いことである。何故なら、自分の捧げる祈りがすなわち神にとって香であると分かれば、それだけ祈りに益と幸いがもたらされるようになるからである。聖徒が祈るとは、すなわち神に香を捧げることである。であれば、そのことを知っている聖徒が、どうしてより祈りに進もうとしないであろうか。神への愛があるのであれば、より素晴らしい香を捧げようとするに違いない。よって、神を愛する聖徒たちは、より良い香を祈りにより天の神へと送り届けるようにすべきである。
ここでセラフィムと長老たちが、共に神の御前で崇拝を捧げているのは、注目に値する。というのも、この崇拝から、我々はどれだけ神が崇拝されねばならないお方であるかということを学ばせられるからである。ここに記されている崇拝は、言わば崇拝における模範である。確かに神は、大いに、心からの態度を持って、十全的に崇拝されねばならないお方である。我々は、世俗に呑まれて、神を崇拝する精神が失われたり衰えたりしないように注意せねばならない。我々も、やがてこのような天上の住民の一員に加えられることになるのだから。
【5:9】
『彼らは、新しい歌を歌って言った。』
これは旧約聖書の御言葉と内容的にほぼ同じ内容である。イザヤ42:10にはこう書いてある。『主に向かって新しい歌を歌え』。詩篇96:2。『新しい歌を主に歌え。』詩篇40:3。『主は、私の口に、新しい歌、われらの神への賛美を授けられた。』ヨハネは、昔の預言者たちと内容的に同じことを記したのである。
この箇所から分かるように、天においては『新しい歌』が神に対して歌われる。古びた過去の歌は、常に生き生きとしておられる神には、相応しくないのである。ここで『新しい歌』と言われているのは、2つの捉え方ができる。まず一つ目は、これは新しい時代に適した今までにはなかった歌を指していると捉えることである。キリストの贖いと復活により、古い契約は新しい契約へと更新されたのであるから、新しい契約が現れた時代においては、もはや古い契約の時代に歌われていた歌は歌われるべきではなくなった。それは古い契約に属する歌であり、新しい時代には適していないからである。つまり、これは「新しい契約の時代に相応しい歌」という意味だと考えられる。二つ目は、これが単に今までには歌われていなかった新しい歌だと捉えることである。今の時代で言えば「ニューシングル」がリリースされるようなものである。この2つのうち、正しいのはどちらか一つかもしれないし、もしかするとどちらも正しいということもありえる。一つ確かに言えるのは、これが新しい歌であって、神には新しい歌が捧げられるべきであるということである。目新しさを求めて珍奇に堕してしまうのは良くないが、我々も、神に対して新しい歌を歌うべきではなかろうか。神には、永遠に新しい歌が歌われるべきだと私には思える。
【5:9~10】
『「あなたは、巻き物を受け取って、その封印を解くのにふさわしい方です。あなたは、ほふられて、その血により、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から、神のために人々を贖い、私たちの神のために、この人々を王国とし、祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。」』
キリストは、御父から巻物を受け取って開き、その封印を解くのに相応しいお方であった。何故なら、キリストは、永遠の昔から選ばれていた人たちを神の王国また祭司とするために、ご自身を犠牲として捧げられたからである。命をさえ捨てられた従順な神の子羊は、巻物を受け取り、その封印を解く正当な資格を持っておられたのである。キリスト以外に、このような行為をした存在はいないから、キリスト以外にこのような資格を持つ者は一人もいなかった。
ここで聖徒たちが「王国また祭司とされた」と言われているのは、既に1:5~6の箇所で言われていたことである。
聖徒たちが王国にされたと言われているのは、贖われた者たちが、神の支配する王国としての存在に変えられたからである。古い契約の時代において、神の王国は、ユダヤ人の中にしか存在しなかった。しかし、今現在のユダヤ人からは御国が取り去られ、彼らは神の王国どろこか、サタンの王国となってしまっている。新しい契約の時代になった今では、キリストに贖われた全ての人間が、神の支配領域としての王国に変えられるようになったのである。また聖徒たちが祭司にされたと言われているのは、聖徒たちが文字通りの意味において神に仕える祭司とされたということである。旧約時代では、ユダヤ人、しかもレビ族であるユダヤ人しか神の祭司になることはできなかった。しかし今現在のユダヤ人は、神の祭司であるどころか、ベリアルの祭司にすらなってしまっている。実に、この犬たちはベリアルの祭司だからこそ、神の子であるキリストを憎み、そのお方の宗教を大いに嫌悪しているのである。今の時代では、昔の時代と違って、キリストに贖われた全ての者が、神の祭司に変えられるようになっている。とはいっても、聖徒たちは、自分の力によって神の王国また祭司となれたのではない。聖徒が神の王国また祭司になれたのは、ただただキリスト・イエスの贖いのゆえである。子羊なるキリストの救いがなければ、我々は未だにサタンの王国であり、またベリアルの祭司たちであった。我々は、自分が神の王国また祭司となれたのはキリストの恵みゆえであることを覚えて、その恵みを与えて下さった神に感謝すべきである。
聖徒たちが『地上を治める』と言われているのは、2:26~27および3:21の箇所と内容的に同じであって、20:4~6の「千年」として象徴される完全完璧な支配のことを指している。すなわち、ここで言われているのは、紀元68年6月9日に携挙されて支配の座に着いた聖徒たちが、全世界を神的な権威により裁くことである。私はしつこいぐらいに言うのだが、黙示録に示されている全ての幻は『すぐに起こるはずの事』(1章1節)だから、この千年として象徴される短い支配の期間も既に終わっている。この期間を長大な期間として捉える者たちは、聖書の研究不足であり、恐らくこの期間がどのような意味内容を持つのか神に尋ねていない。『祈りを聞かれる方』(詩篇65篇2節)にこの期間を尋ねたならば、神の恵みにより、私のように、この期間がどのような意味内容を持つのか必ず分かるようになるはずなのだ。『求めよ。さすれば与えられん。』と言われた神は、真理を求める者に、解を与えて下さらないお方ではない。私は求めたから恵みにより与えられたのである。しかし、この支配の期間については、今はまだ詳しく語られるべき時ではない。後ほど、この期間については、詳しく説明されることになるであろう。
【5:11】
『また私は見た。私は、御座と生き物と長老たちとの回りに、多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。』
御座と生き物と長老たちとの周辺には、無数の御使いたちがいた。その数は『万の幾万倍、千の幾千倍』、すなわち1億(10000×10000)また100万(1000×1000)であった。この数字は、具体的なものとして捉えるべきではなく、「あまりにも多い」という意味に捉えるべきである。つまり、この言葉は、数の多さを象徴的に言い表わしていると考えねばならない。ところで、この言葉は明らかにダニエル書7:10の箇所に基づいて書かれている。そこでは御使いについてこう言われていた。『幾千のものがこの方に仕え、幾万のものがその前に立っていた。』ここでダニエルは『幾千…幾万』と書いているが、ヨハネはダニエルが御使いたちにおける数の多さを示しかったことを悟ったので、より数の多さが伝わるように『万の幾万倍、千の幾千倍』などと更に表現を強調して書いたのだと私は考える。というわけで、今は地上にいる我々も、やがて天国に行ったならば、この無数の御使いたちをその目で見ることになるであろう。実に、聖書で『万軍の主』と神について言われているのは、これが理由である。神が、幾万もの御使いたちを統率する天の大軍の将だからこそ、『万軍の主』と言われているのである。このように聖書で言われているのは、理由なきことではないのである。このように聖書は神が無数の大軍の将であることを示そうとして『万軍の主』と言っているのだから、別の言葉にすることもできた。例えば、「億軍の主」とか「兆軍の主」などと言うこともできた。このような言葉でも、確かに、神が無数の御使いを統率しているということが示されている。しかし、神が聖書に記されるべき適切な言葉として選んだのは『万軍の主』であった。
【5:12】
『彼らは大声で言った。』
神の御使いたちが、大声で神を讃えたのは、神を讃えるということが非常に大切なことだったからである。キリストも、真理を大声で語られた(ヨハネ12:44)。我々も、大切な事柄は、傾向として声を大きくして語るものである。大切な事柄とは、よく聞かれ、よく認識されるべき事柄なのだから、大声で語られるのは理に適っている。小さな声で語られたならば、あまり聞き取れず、よく認識できないことにもなってしまう。神を賛美するという行為は、間違いなく、あまりにも大切な事柄である。だからこそ、御使いたちは神を賛美する際に『大声で言った』のである。
『「ほふられた子羊は、力と、富と、知恵と、勢いと、誉れと、栄光と、賛美を受けるにふさわしい方です。」』
キリストは、あらゆる良きものを受けるに相応しいお方である。何故なら、キリストは、御父に従われてご自身みずからほふられた子羊となられたからである。ここで御使いたちは、7つの良きものがキリストに相応しいと言っている。「7」だから、例のごとく、ここではキリストに捧げられるべき良きものの完全性また神聖性を示しているのだと思われる。とはいっても、この4~5章に出てくる4つの被造物のうちで(セラフィム、長老、天使、あらゆる被造物)、キリストに捧げられるべきものを「7つ」にしている被造物は、この天使たちしかいないのではあるが。セラフィムは3つ(4:8)、長老たちも3つ(4:11)、あらゆる被造物は4つ(5:13)、神に良きものを帰している。この箇所で言われている7つの良きものについて、一つ一つ見ていきたい。<力>キリストはその御力によって多くの奇跡を行なわれ、その御力により永遠の贖いを成し遂げられた。またイザヤはキリストのことを『力ある神』(イザヤ9章6節)と言っている。キリストは神であって、ダニエルも言うように『力は神のもの』(ダニエル2章20節)である。よって、キリストには力が帰されるべきである。<富>この世界にいる王には、名誉や称賛と共に富が捧げられるべきであろう。そうであれば、尚更のこと、キリストには富が捧げられなければいけないことになる。何故なら、キリストは『地上の王たちの支配者』(黙示録1章5節)すなわち『王の王』(Ⅰテモテ6章15節)だからである。それゆえ、キリストには富が捧げられるべきなのである。ソロモンも、キリストについて『彼にシェバの黄金がささげられますように。』(詩篇72篇15節)と言っている。<知恵>キリストは知恵そのものであられ、ソロモンよりも知恵のあるお方である。ソロモンに知恵を与えられたお方が、ソロモンより知恵深くないわけがどうしてあろうか。またキリストは神であって、ダニエルも言うように『知恵…は神のもの。』(ダニエル2章20節)である。だから、キリストは知恵を受けるに相応しい。<勢い>イザヤは万軍の主であられるキリストについて、『万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。』(イザヤ9章7節)と言っている。主が熱心であられるということは、つまり主が「勢い」に満ちておられるということでなくて何であろうか。キリストは勢いに満ちておられる、いや勢いそのものであられるお方なのだから、勢いがこのお方に帰されるのは当然のことである。<誉れ>キリストはご自身の命を犠牲にされて、神のために選ばれていた人たちを王国とし祭司とされた。その贖いの御業は、誠に誉れのある行為であった。よって、そのような御業を成し遂げられたキリストは、誉れを受けるに相応しいお方である。<栄光>キリストは神であられ(ヨハネ1:1)、万物はことごとくこのお方によって創造され(ヨハネ1:3)、またそれらのものはこのお方により常に保たれている(ヘブル1:3)。このようなお方が栄光を受けるに相応しいということは、言うまでもないことである。<賛美>パウロはキリストについてこう言った。『このキリストは万物の上にあり、とこしえにほめたたえられる神です。アーメン。』(ローマ9章5節)パウロが言うようにキリストは『とこしえにほめたたえられる』神なのだから、『賛美を受けるにふさわしい方』である。以上、キリストに帰されるべき7つの良きものについて、簡潔に書き記された。なお、キリストに帰されるべき良きものは、ここで記されている7つのものだけに限定されない。ここでは、キリストに帰されるべき多くの良きもののうち、ただ7つのことだけが書き記されているだけに過ぎない。他にもキリストに帰されるべき良きものは、知識、英知、主権、権威、尊厳、威光、聖性、愛徳など多く存在している。
【5:13】
『また私は、天と地と、地の下と、海の上のあらゆる造られたもの、およびその中にある生き物がこう言うのを聞いた。「御座にすわる方と、子羊とに、賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。」』
ここでは、あらゆる被造物が、神とキリストとを讃えているということが言われている。神がキリストを世に遣わされ、その遣わされたキリストが子羊としてご自身を永遠の生贄にされたので、神とキリストはあらゆる生命体に讃えられるようになった。パウロも、キリストの受難のゆえに、キリストとキリストの御父が、あらゆる被造物に讃えられるべきであると言っている。『それは、イエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが、ひざをかがめ、すべての口が、「イエス・キリストは主である。」と告白して、父なる神がほめたたえられるためです。』(ピリピ2章10~11節)と書かれている通りである。ここで、「しかし、実際には口または心において神とキリストを讃えていない被造物が多く存在しているではないか。」と思われる方もいるであろう。確かに口と心において神とキリストを讃えていない被造物が多く存在しているが、しかし、そのような被造物であっても、霊的に考えれば神とキリストとを讃えていると言わねばならない。何故なら、聖書が教えるように御子の十字架における血によって万物は神と和解したのであって(コロサイ1:19~20)、万物が神と和解したというのは、つまり万物がその存在を通して否応なしに神とキリストを讃えていることになるからである。すなわち、その和解の事実そのものが、その和解された被造物を神への賛美と変化させた。万物は和解されたのだから、万物の存在そのものが今や神への賛美となっている。それは、生まれた自分の子供が、その存在自体によって親である者を否応なしに讃えているのと同じことである。子とはすなわち親の栄光の現われだから、その存在自体が、たとえ口や心では親を憎悪していたとしても、事実上親を讃えていることになるのだ。万物も神の和解を受けたのだから、その存在自体が、神を讃える意味を持つものとされたわけである。カルヴァンの場合、「これは世界の各部分が、天の頂きから地の中心まで、それぞれの方式で創造主の栄光を物語るということを確認させるものにほかならない。」(『キリスト教綱要 改訳版 第3篇』第3篇 第5章 第8節 p161~162:新教出版社)と言っているが、これは私が言いたいこととさほど変わらない。それゆえ、神の造られた万物は今や例外なくその存在において、『御座にすわる方と、子羊とに、賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。』という声を暗黙の内に、それぞれの方式で発している。私が今述べたこのことは、霊的に捉えなければならない。そうしないと、この箇所で言われていることは、正しく理解できない。この箇所で言われていることを、実際に口や心の中で意識的に神とキリストとを讃えることだと捉えてはならない。そのように捉えるのは肉的であり、誤っている。
黙示録の性質からして、この箇所も、恐らく旧約聖書の他の箇所と対応していると思われる。その箇所とはイザヤ45:23~24である。そこではこう書かれている。『すべてのひざはわたしに向かってかがみ、すべての舌は誓い、わたしについて、『ただ、主にだけ正義と力がある。』と言う。』我々が今見ている箇所とこのイザヤ書の箇所は、どちらも全ての存在が神に良きものを帰しているという共通点がある。
【5:14】
『また、4つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。』
セラフィムと長老たちも、御使いたちとあらゆる被造物の発する賛美に同調し、神を崇拝した。何故なら、御使いたちと天地における被造物が発した賛美は良きものであって、神は賛美されるに相応しいお方だからである。もしここでセラフィムと長老たちが同調して崇拝しなかったとすれば、すなわち沈黙し不動であったとすれば、神に対する崇拝の精神と畏敬の念を抱いていなかったと見做されていたに違いない。『死人は主をほめたたえることがない。沈黙へ下る者もそうだ。』(詩篇115篇17節)と言われている通りである。
4~5章を見ると分かるが、これらの箇所では、あらゆる被造物が神を崇拝している。すなわち、セラフィムが4:8~9で、長老たちが4:10~11で、御使いたちが5:11~12で、天地における被造物が5:13で、神に崇拝を捧げている。あれも、これも、誰もが神を讃えているのである。これは何という神聖で厳かな光景であろうか。あまりにも崇高であり、それは知解の限度を越えており、言葉で説明することができないほどである。
聖徒とされた我々も、今はまだ地上にいるのではあるが、神に崇拝を捧げねばならない。この神は、聖なる存在であられ、万物を創造し保持しておられ、全ての良きものを受けるに相応しく、御子を世に遣わされ、その遣わされた御子により選ばれた人たちを王国また祭司とされたのである。このような神を知りながら、崇拝を捧げようとしないとは、どういうことであろうか。神のこのような素晴らしさを知りながら、その神に崇拝を捧げない者は、気が狂っていると言わねばならない。そのような者は、理性なき獣も同然なのである。
これで4~5章目の箇所における註解が終わった。この4~5章からは、天上における多くの知識を得ることができる。我々がやがて行きつくことになる場所の啓示が、ここではなされている。よって、この2つの章を熟読して理解するのであれば、それだけ我々は自分がやがて住まうことになる天上の世界について把握できるようになるであろう。
第8章 ⑤6章:キリストによる6つの封印の解除
この6章目では、7つの封印のうち6つの封印が解かれている。7つ目の封印は、7章目をまたいで8章目の1節目で解かれている。どうして7つ目の封印だけが別の箇所に書かれているかといえば、7つ目の預言は他の6つの預言と内容的にかなり異なっているからである。もし7つ目の預言もその他の6つの預言と内容的に似ていたのであれば、この6章の箇所に纏めて書かれていたはずである。つまり、内容的な区別を示すために、7つ目の預言だけ別の箇所(8:1)で書かれている。
【6:1】
『また、私は見た。子羊が7つの封印の一つを解いたとき、4つの生き物の一つが、雷のような声で「来なさい。」と言うのを私は聞いた。』
まずは第一番目の封印が解除される。
巻物の封印が解除される仕組みは、このようである。すなわち、キリストが封印を解除されると、その封印されていた預言が開示されることになる。この解除が一挙になされることはなく、一つ一つなされる。それは、この6章目と8章1節目を見れば一目瞭然である。どうして一挙にではなく一つ一つ解除がなされるかといえば、それは秩序と分かりやすさのためである。『ただ、すべてのことを適切に、秩序をもって行ないなさい。』(Ⅰコリント14章40節)と命じられた神は、そのように整った解除がなされるのを欲されたのである。
7つの封印のうち最初の4つまでは、キリストが封印を解除されると、その後すぐにセラフィムと馬が出てくる。この馬は、その預言が迅速に実現また実行されることを意味している。何故なら、馬とは速い生き物だからである。確かに黙示録で示されている預言は、『すぐに起こるはずの事』(1章1節)だから、その預言は素早い生き物である馬によって示されるのが相応しい。馬は、ある場所に「すぐに」到達するのだから。また馬は、その預言が確実絶対に成し遂げられることを意味している。何故なら、馬とは忠実な生き物だからである。この世で馬と同等の忠実さを持つ生き物は、犬と象ぐらいしかいないものである。また馬は、神が報復のために戦われることを意味している。何故なら、馬とは戦いのために使われる生き物だからである。車や自転車やその他の乗り物が普及している今の時代ではあまり使われていないが、昔は戦争によく馬が使われた。後ほどまた説明されるが、この4つの馬が出てくる黙示録の箇所(6:1~8)と対応しているゼカリヤ書6:1~8の箇所では、馬が出てくるだけでなくその馬が戦車を引いている(ゼカリヤ6:2~3)。「戦車」とは、明らかに「戦い」でなくて何であろうか。神は、古い世の終末において、報復のために戦われたのである。すなわち、その時、神は不信仰な諸国民、棄てられたユダヤ人、忌まわしいサタンの軍勢と戦われた。確かに黙示録19:11の箇所では、白い馬に乗ったキリストが『戦いをされる。』と書かれている。つまり、「戦い」だから「馬」だということである。このように、ここで出てくる馬は3つの意味を持っている。なお、ある人は黙示録におけるこの馬が「ローマクラブ」が「解き放った」「地球を駆けめぐる」「経済破壊と飢饉、そして疫病」であり、しかも「馬小屋のドア」が開かれることにより解放されたなどとふざけたことを言っているが(いったい黙示録のどこに「馬小屋」が出てくるのだろうか…)(※①)、黙示録についてこのようないい加減なことを言っている人は世の中に本当に多くいるから、読者は惑わされないようによく注意してほしい。この人を見ても思うのだが、黙示録をよく研究していない人は、黙示録について語らないほうがよい。100%誤るから(※②)。
(※①)
ジョン・コールマン博士(『鳥インフルエンザの正体』第2章 大量殺戮計画「グローバル2000」の加速度 p59:成甲書房)
[本文に戻る]
(※②)
黙示録をろくに知りもしないのに、さも知っているかのように論じる聖書の教師たちは、だいたいカシオドルスが次のように言った通りのことを言うことになる。このカシオドルスの黙示録の理解を見ても分かるが、はっきり言って何も分かっていない。もし分かっていたとすれば、どうして黙示録を註解できないのであろうか。註解できないということは、つまり何も分かっていないのである。分かっていれば註解できていただろうから。彼の無知に基づく黙示録理解はこうである。「「黙示録」を読む者は、この世界もまたキリストの命令によって統治されており、キリストが望むならば、終末の時にはより善いものへと変化するはずであることを理解する。次いで、天使が喇叭を鳴らすと死者たちが再び起き上がり、長いあいだ埋葬されていた人間は新たな生において復活させられるであろう。キリスト自身も、雷鳴と稲妻を先導として畏敬の念を呼び起こし、不正の子を滅ぼし、最初の顕現においては摂理にもとづいて無差別には示されないことにした自らの徳を明らかにし、世界を裁くために現れる。その後、読者は教会がどれほど大きな苦役と災厄から解放されて主とともに永遠に幸福となるか、そしてどのような正義によって悪魔の命令に従う人々が悪魔とともに滅ぶのかを理解する。こうした事柄を完全に調べ終えたとき(引用者註:私から見れば全く調べ終えていない)、読者は大いなる喜びに満たされる。さて、こうしたことの後に、聖書に記されているように「新しい天と新しい地」(黙21:1)があるであろう。もしわれわれが惑わされることなく確固として信じるなら、キリストの報いによってかの栄光を見渡せるようになろう。」(『中世思想原典集成5 後期ラテン教父』綱要 第2巻結論 p401~402:平凡社)―この誤解に満ちた文章に対して反駁するとすれば300ページぐらいの本が1冊できてしまう。つまり、それほどに誤謬が多い。未信者も、よく黙示録について言及しているのを見かけるが、やはり黙示録について研究していないのに恥ずかしげもなく堂々と語っている。だから、訳の分からないことや、間違ったことばかりを言っている。アレイスター・クロウリーもその一人であった。この邪悪な魔術師は黙示録について何も分かっていないのに、次のようにあたかも何かを知っているかのように語ったが、滑稽千万である。「また、私に分ることは、『黙示録』とは1ダース位の全く関連のない寓話を校訂し、継ぎ合わせ、その上で容赦なく削ぎ落し、筋の通った話にした、ということだけである。その肯定とは、キリスト教に都合のいいように書き改めたり、編集したりすることであった。」(『アレイスター・クロウリー著作集4 霊視と幻聴』アルンと呼ばれる第二番目のアエティールの叫び p159:国書刊行会)このような無知な言説は反駁する値打ちすらないので、排水溝に流れ込んでいく惨めな害虫を見つけた時のように、軽蔑の伴った微笑をもって無視するのが望ましい。更にエリファス・レヴィも、黙示録について何かを悟っているかのように誇らしげな言い方で語っているが、お笑いとしか言いようがない。詰まる所、どの人も黙示録という秘儀的な文書について語れば何だか秘密めいた格好良さが生じるので、この文書について語りたがるのだと私には思える。確かに黙示録を使用すれば、その使用が神秘的な装飾となるのは確かである。誰も彼も何も理解していないのだから多かれ少なかれ注意を惹くのは間違いない。だけれども、結局は黙示録の内容をぜんぜん理解していないのだから、よく考えれば多くの人たちのしている黙示録への言及は非常に利己的であって「みっともない」ということになるのだ。
[本文に戻る]
それでは子羊なるキリストは、どのようにして封印を解いたのであろうか。これは、そこまで重要とは言えない疑問である。我々は、ただキリストが封印を解いたということだけを知れば、それでよい。それだけ知っていれば十分であり、黙示録の理解に関して何か大きな問題が生じることもない。些細なことであり、また考えても分からないようなことを深く知ろうとするのは、あまり敬虔な態度とは言えない。
セラフィムが『雷のような声』を発したのは、セラフィムが神の権威により声を発したからである。神の権威に基づいて声を発したからこそ、神のような声がセラフィムから出たのである。そうでなければ、これは神がセラフィムを通して声を発されたということである。ちょうど預言者の口を通して神がその言葉を公布されたのと同じように。解がどちらであるにせよ、セラフィムが『雷のような声』を出したのは、このセラフィムにおいて神がかかわっていることを示している。何故なら、雷のような声を持っておられるのは、神以外にはいないからである。
セラフィムが『来なさい。』と言ったのは、恐らく福音書の出来事とかかわりがあると考えられる。福音書では、キリストがペテロに『来なさい。』と呼びかけている箇所がある。そのキリストの呼びかけに応じたペテロは、不信仰のゆえに、水の中へ沈んでしまった。その時、キリストはペテロに『信仰の薄い人だな。なぜ疑うのか。』と言われたのであった。この出来事は、マタイ14:22~33の箇所に記されている。我々が今見ている箇所でセラフィムがキリストと同じように『来なさい。』と言っているのは、この呼びかけによってやって来る馬が、ペテロのように途中でその歩みを中断させないということを示そうとしているのであろう。神による馬が、ペテロのように不信仰になることは、絶対にあり得ないからである。つまり、この馬は、ペテロとは違い、しっかりと声の主のもとに辿り着く。ペテロの場合は、不信仰だったから声の主のもとにその歩みを中断することなく辿り着くことができなかったが、この馬はそのようではない。このようなことをこの『来なさい。』という呼びかけは教えようとしている、というのが一つの可能な解釈である。既に説明されたように黙示録には聖書の他の箇所と対応している箇所が無数にあるのだから、この箇所が福音書のあの箇所と関連していたとしても何も不思議ではない。言葉や状況の類似性を考えれば、マタイ14:22~33とこの箇所とが関連している可能性は高い。
【6:2】
『私は見た。見よ。白い馬であった。』
この白い馬に乗っておられたのはキリストである。実際にキリストが乗っていたとは書かれていないが、この白い馬にキリストが乗っておられたのは明らかである。白い馬に乗っておられるのがキリストでなければ、他に誰が乗っているというのであろうか。黙示録19:11の箇所でも、キリストがやはり白い馬に乗っておられる。これは、つまり白い馬に乗ったキリストが、天から現れて裁きと戦いのために再臨されるという預言である。再臨について記されている19:11~16の箇所で、キリストが『義をもってさばきをし、戦いをされる。』(19章11節)と言われている通りである。この第一の預言は、紀元68年6月9日に成就された。この日、白い馬に乗ったキリストが再臨され、不信仰な世を霊的に裁かれ、ローマ軍において表示された諸国の民と戦われた。なお、この再臨の際には、無数の聖徒たちも白い馬に乗ってキリストと一緒に天から降ってきた。それは次のように書かれている通りである。『天にある軍勢はまっ白な、きよい麻布を着て、白い馬に乗って彼につき従った。』(黙示録19章14節)『私の神、主が来られる。すべての聖徒たちも主とともに来る。』(ゼカリヤ14章5節)『見よ。主は千万の聖徒を引き連れて来られる。』(ユダ14節)とはいっても、地上に残されたままの状態で再臨のキリストを見たサタンの国の子らは(マタイ24:40~41)、再臨が夢また幻であるかのように思えたので(イザヤ29:1~8)、誰一人として自分の見た再臨の光景を記録として書き留めなかったのだから、我々はこの点をよく留意すべきである。すなわち、第1部でも説明されたように、再臨の史実的な証拠が存在していないのは、聖書からもそのように言えるということである。
この馬が白かったのは、キリストの清らかさを示す。キリストは『何の罪もない。』(Ⅰヨハネ3章5節)のだから、そのような罪のないお方の乗っている馬は、清らかさを示す白であるのが相応しい。聖書において、白が清らかさを示すというのは、他の箇所でもそうである(黙示録19:14、マルコ9:3、マタイ28:3、詩篇51:7、イザヤ1:18その他多数)。
『それに乗っている者は弓を持っていた。』
キリストが弓を持っていたのは、悔い改めない不信の者たちを、裁きの矢で断罪するためである。神であるキリストが裁きのために弓をその手に持っておられるということは、詩篇でこのように言われている。『神は正しい審判者、日々、怒る神。悔い改めない者には剣をとぎ、弓を張って、ねらいを定め、その者に向かって、死の武器を構え、矢を燃える矢とされる。』(7篇11~13節)つまり、弓とは裁きのことである。福音を拒絶した者たちは、裁きの矢で断罪されて『罪に定められる』(マルコ16章16節)ので、真理に盲目な者となってただ地獄に突き進むだけの豚のようになる。すなわち、その者たちは『彼らの最後は滅びです。』(ピリピ3章19節)と言われるような状態となる。紀元68年に再臨が起きた際、キリストはその手に持っておられる弓を射かけ、悔い改めない不信仰な者たちを容赦なく断罪されたのである。その時、多くの者たちが裁かれて鳥なる悪霊どもに喰われたので(黙示録19:21)、真理に暗い地獄に突き進むだけの豚と化した。
『彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出て行った。』
再臨の際にキリストが冠を受けるというのは、すなわち敵どもを裁かれる王権を持たれるということである。再臨の時、キリストは敵を裁かれる権威を受けたのだが、その権威がここでは『冠』として表現されている。―その冠という権威を受けたのはどのようなキリストであったのか。答え。それは人としてのキリストであった。―それではその冠を人としてのキリストに授けたのは誰であったのか。答え。父なる神以外に誰が考えられるであろうか。―ではその冠はどのようなものであったか。答え。先にも述べたように、これは権威の霊的な表現であるから、このような問いは不毛であって答える必要がない。
ここではキリストが更なる勝利、すなわち2度目の勝利を得ようとして出て行ったと言われている。キリストが最初に勝利を得られたのは、十字架と復活の時であった。この十字架と復活により、キリストは、死と罪とサタンとこの世とに対する十全の勝利を獲得された。これが第一の勝利であった。この第一の勝利に続く第二の勝利は、再臨の時に、諸々の敵どもを裁かれることで実現された。何故なら、裁きを与えるとは敵を屈服させることであって、それはその裁かれた敵どもに対する勝利に他ならないからである。誠に、神は裁かれる時、勝利を得られる。だから、ここでは『勝利の上にさらに勝利を得ようとして出て行った。』と預言されているのである。このことから、キリストの再臨には「勝利」の要素も含まれているということがよく分かる。すなわち、キリストが再臨される目的の一つは、キリストが敵どもに勝利されることである。再臨と聞くと「携挙」や「復活」や「審判」や「時代の区切り」ぐらいしか思い浮かべないような読者は、ぜひ再臨という出来事に「勝利」という観念をも結びつけるべきである。
ここでは過去形の言葉で預言が語られているが、既に起きたかのように預言が語られるのは、聖書では特に珍しいことではない(※)。例えば、過去形で預言されているのは、他にも次のような箇所がある。『主は、私の主に仰せられる。「わたしがあなたの敵をあなたの足台とするまでは、わたしの右の座に着いていよ。」』(詩篇110篇1節)―ここでは、まだ御父がキリストに右の座に着くようにと言っておられないのに、既に言ったかのように預言されている。『倒れた。大バビロンが倒れた。そして、悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの巣くつ、あらゆる汚れた、憎むべき鳥どもの巣くつとなった。』(黙示録18章2節)―ここでは、まだ大バビロンなるエルサレムが滅亡していないのに、すでに滅亡したかのように預言がなされている。『聞け。…敵に報復しておられる主の御声を。』(イザヤ66章6節)―ここでも、まだ敵に報復されていないのに、もう報復がされているかのように預言がされている。永遠の立場におられる神はあらゆる時間帯を正に「今」としてご覧になられるので、神にとっては、まだ我々にとっては未来の事柄であっても既に起きたかのように捉えられている。よって、我々が今見ているこの箇所やその他の多くの箇所では、もう既に起きているかのような言い方で預言が語られているのである。そういうことだから、ここでは過去形の言い方がされているが、ヨハネがこの箇所を記した時には未だに起きていないことであった。
(※)
アウグスティヌスも次のように言っている。「聖書には、将来のことに過去の時制が用いられることがよくあるが、同じように、霊の予見によって、来たるべきことが既に起こったことであるかのように書かれていることもよくある。だから別の詩篇の、まるで福音書が読み上げられているかのような箇所を、わたしたち誰でもが知っている。「彼らはわたしの手足を突き刺し、わたしの骨をすべて数えた。わたしの衣を賭けてくじを引いた」(21・17-19)。すべてがまるで既に起こったことであるかのように記されているが、もちろんその時はまだ、将来のこととして見られていたのである。」(『アウグスティヌス著作集20/Ⅰ 詩篇註解(5)』詩篇103篇 説教2 p127~128:教文館)ユスティノスも次のように言っている。「予言の霊は、未来に起るべき事象を既に起ったかのように語る場合があります。…未来に起るということが完全に分っている場合、それが既に起ったかのように予言の霊は予告します。」(『キリスト教教父著作集1 ユスティノス』『第一弁明』42:1、2 p57:教文館)
[本文に戻る]
この第一の封印が解かれた際に、『ししのよう』(4:7)な第一のセラフィムが、白い馬に乗ったキリストを御父にあって呼び寄せたのには、深い関連性があるのであろう。獅子のセラフィムだからこそ、獅子なるキリストを呼んだのである。これには明らかに関連性があるとしか思えない。もし第一のセラフィムが『ししのよう』でなければ、獅子なるキリストの乗った馬が出てくることはなかったであろう。何故なら、そこにはセラフィムと馬とに関連性が見られないからである。御言葉とは実に深いものである。
【6:3~4】
『子羊が第二の封印を解いたとき、私は、第二の生き物が、「来なさい。」と言うのを聞いた。すると、別の、火のように赤い馬が出て来た。』
この赤い馬が登場したのは、地上に争いや騒乱がもたらされるという預言である。実際、ネロによる42ヶ月の大迫害の時に、この預言は実現された。歴史も言うように、その時、多くの争いや混乱や不和や殺戮が起きたのである。だから、この預言がまだ成就されていないと考えることはできない。この預言も、神が言われたように『すぐに起こるべき事』(22章6節)だったからである。神が黙示録の預言は『すぐに起こるべき事』だと言われたのに、それを信じようとしない者は、信仰の国から退去して不信仰の王国に入りたいとでもいうのであろうか…。
この馬が赤かったのは、争いや不和や分裂をもたらすからである。何故なら、そのようなものは、激しく燃える火に例えることができるからである。キリストも、分裂や不和とはすなわち燃える火であると言っておられる。『わたしが来たのは、地に火を投げ込むためです。だから、その火が燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。…あなたがたは、地に平和を与えるためにわたしが来たと思っているのですか。そうではありません。あなたがたに言いますが、むしろ分裂です。今から、一家5人は、3人がふたりに、ふたりが3人に対抗して分かれるようになります。父は息子に、息子は父に対抗し、母は娘に、娘は母に対抗し、しゅうとめは嫁に、嫁はしゅうとめに対抗して分かれるようになります。』(ルカ12章49~53節)このような分裂は、喧嘩や激怒といった火のような激しさを伴うものであり、またそれは火のように苦痛をもたらす。だから、この馬はそのような不和や分裂をもたらす存在として赤かったのである。
また、この馬が赤かったのは、「血」を意味すると考えることもできる。何故なら、この馬は『人々が、互いに殺し合うようになるため』に出て行くからである。人々が互いに殺し合えば、当然ながら血が大量に飛び散る。その血は赤色である。その赤色をもたらしたのは、この第二の封印における馬である。だから、この馬は血を示すために赤色であったと考えることができる。
【6:4】
『これに乗っている者は、地上から平和を奪い取ることが許された。人々が、互いに殺し合うようになるためであった。』
この預言は、古い世の終末において既に実現した。その時に起こることについて、キリストは次のように言われた。『民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、…また兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち、彼らを死に至らせます。』(マルコ13章8、12節)このように、あらかじめ預言がなされたのは、聖徒たちが後に訪れる苦難の時のために心構えをするためであった。前もって苦難が起こると聞かされるのは、苦痛が和らげるための緩衝材となるからである。神は、聖徒たちにそのような緩衝材を与えるために、あらかじめこのような預言をなされたのである。
この箇所からは普遍的なことを学ぶことができる。ここで言われているように、平和が消失するのは、神がそれを『許された』からであった。つまり、神が平和の消失を命令されたからこそ、平和が消失されるのである。もし神の許可が出たのでなければ、平和が消失することは決してない。何故なら、その場合、神は平和が消失することを許可されないからである。その場合、神が命令しておられるのは平和の存続である。キリストが『雀の一羽でも、あなたがたの父のお許しなしには地に落ちることはありません。』(マタイ10:29)と言われたのは、この世の真実である。雀などという小さな生物が地に落ちることさえ神の許しなしには起こらないとすれば、尚更のこと、平和が消失するのは神の許しなしに起こらないことは確かである。だから我々はこの箇所から、平和の存続も平和の消失も、全ては神の許しと命令のうちに起きているのだということを知るべきである。神が平和の存続を命令されたら平和の消失は許可されず、平和の消失が命令されたら平和の存続は許可されない。
『また、彼に大きな剣が与えられた。』
この『大きな剣』とは、争いや分裂の象徴である。すなわち、剣が投じられると、人々の間に騒乱や仲違いや暴力や殺戮や平和の崩壊が起こる。この剣がそのようなことを象徴しているというのは、キリストの御言葉からも分かる。キリストは、剣の投下により平和が消失してしまうことについて、次のように言われた。『わたしが来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。わたしは、平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら、わたしは人をその父に、娘をその母に、嫁をそのしゅうとめに逆らわせるために来たからです。さらに、家族の者がその人の敵となります。』(マタイ10章34~36節)
この剣を物質的な剣であると捉えてはならない。何故なら、これは霊的に、すなわち象徴的に捉えるべきものだからである。これを物質的に捉える人は、自分が肉的な人であるということをみずから証明している。もしこれが物質的に捉えられねばならないものだとすれば、この箇所と同様にキリストの口からも物質的な剣が出ていると考えなければいけないことになる(黙示録1:16)。地上に空から剣が実際に投げ込まれ、キリストの口から物理的な剣が出ている―このように捉えるのは、何と滑稽で空想的なことか。
第二の封印が解かれた際は、『雄牛のよう』(4章7節)な第二のセラフィムが呼び出しを行なったからこそ、雄牛のように地上を踏み荒らす赤い馬が出てきたのであろう。雄牛とは力強く地上を踏み荒らす存在だから、争いと殺戮とを地上にもたらして目茶目茶な状態を生じさせる赤い馬が適合している。雄牛のようだったセラフィムが、赤い馬を呼んだのは、これが理由だとしか考えられない。もしこれ以外の理由があるとすれば、それは一体どのようなものであろうか…。この第二の封印の場合はセラフィムと馬との関連性はないのではないか、などと思われる方がおられるであろうか。しかし、第一の封印の場合はセラフィムと呼び出された馬とに明らかな関連性があったのだから、同様に第二の封印の場合も関連性があると考えるべきであろう。同様に、第三と第四の封印の場合でも、やはりセラフィムと馬とには関連性があることは間違いない。
【6:5~6】
『子羊が第三の封印を解いたとき、私は、第三の生き物が、「来なさい。」と言うのを聞いた。私は見た。見よ。黒い馬であった。これに乗っている者は量りを手に持っていた。すると私は、一つの声のようなものが、4つの生き物の間で、こう言うのを聞いた。「小麦一枡は1デナリ。大麦三枡も1デナリ。』
ここで『一つの声のようなものが』麦とデナリについて言ったのは、間違いなく福音書におけるキリストのたとえと対応している。キリストは、マタイ20:1~16の箇所で、このようなたとえを語られた。『天の御国は、自分のぶどう園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。彼は、労務者たちと1日1デナリの約束ができると、彼らをぶどう園にやった。それから、9時ごろに出かけてみると、別の人たちが市場に立っており、何もしないでいた。そこで、彼はその人たちに言った。『あなたがたも、ぶどう園に行きなさい。相当のものを上げるから。』彼らは出て行った。それからまた、12時ごろと3時ごろに出かけて行って、同じようにした。また、5時ごと出かけてみると、別の人たちが立っていたので、彼らに言った。『なぜ1日中仕事もしないでここにいるのですか。』彼らは言った。『だれも雇ってくれないからです。』彼は言った。『あなたがたも、ぶどう園に行きなさい。』こうして、夕方になったので、ぶどう園の主人は、監督に言った。『労務者たちを呼んで、最後に来た者たちから順に、最初に来た者たちにまで、賃金を払ってやりなさい。』そこで、5時ごとに雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつもらった。最初の者たちがもらいに来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らもやはりひとり1デナリずつであった。そこで、彼らはそれを受け取ると、主人に文句をつけて、言った。『この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは1日中、労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。』しかし、彼はそのひとりに答えて言った。『私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と1デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としては、この最後の人にも、あなたと同じだけ上げたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか。それとも、私が気前がいいので、あなたの目にはねたましく思われるのですか。』このように、あとの者が先になり、先の者があとになるものです。』声のようなものが言ったのは、キリストのたとえと比べて、内容的に非常に圧縮されており、労働の時間を労働の実(麦)に言い換えている。どちらも意味としては何も変わらない。すなわち、これはどちらの箇所も、聖徒がどれだけこの地上において主のために労苦したとしても、同じ1デナリという救いが共通に与えられることには変わらない、ということを教えている。たといパウロのように『ほかのすべての使徒たちよりも多く働き』(Ⅰコリント15章10節)をしたとしても、何もこの地上では主のために労苦できなかった十字架上で救われた強盗であっても、1デナリとして表わされる同一の救いを差別なく受けることになる。それは、人を救われる神が、全ての聖徒に同一の救い、すなわち1デナリを与えたいと欲されたからに他ならない。実に、『神にはえこひいきなどはない』(ローマ2章11節)のである。それゆえ、もし労苦の度合いにかかわらず同一の救いが与えられることに異を唱える不遜な聖徒がいたとすれば、その聖徒は、神から『私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と1デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。』と言われてしまうであろう。神がパウロのように労苦した人にも十字架上の強盗のように働きをほとんどしていないような人にも1デナリなる救いを与えようと決められたのだから、誰がそのことに異を唱えてよいであろうか。
この箇所と対応している福音書のたとえの中では、1デナリという救いが労働に対する報酬として描かれているが、行為による救い(行為義認)は聖書の教えではないから、よく注意しなければいけない。行為義認は、救いが『行ないによるのではありません。』(エペソ2章9節)というパウロの言葉によって、聖書の中では否定されている。この福音書のたとえでは、正しい歩みをした聖徒たちに救いが与えられるからこそ、あたかもその救いが正しい歩みに対する報酬でもあるかのよう描かれているに過ぎない。聖書が教えているのは、信じることによる救い(信仰義認)であって、それは次のように書かれている通りである。『あなたがたは、恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それは、自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。』(エペソ2章8節)救いが恵みでありながら報酬と言い表わされていることについては、アウグスティヌスもこう言っている。「かくして、親愛なる方方よ、もしわたしたちの善き生活が、神の恩恵以外の何物でもないとすれば、永遠の生命もまた、善き生活に応じて与えられはしますが、疑いもなく、神の恩恵なのです。そこで永遠の生命も、実際無償で与えられるのです。なぜなら、永遠の生命が与えられる当の善き生活も無償で与えてくださったからです。しかし与えられる先の善き生活は端的に恩恵なのですが、それに対して与えられるこの永遠の生命は、善き生活に対する報酬なのですから、いわば正義に対する報酬のように恩恵に対する恩恵なのです。「神は各人にその行いに応じて報いられる」(ロマ2・6)ということは、真実なのですから、真実となります。」(『アウグスティヌス著作集10 ペラギウス派駁論集(2)』恩恵と自由意志 第8章 20 p44~45:教文館)
ここで黒い馬が出てくるのは、そのような同一の救いが聖徒たちにもたらされるという預言である。この預言は、再臨の日に成就された。その時、労苦して『大麦1枡』分の働きをした聖徒も、あまり労苦しなかったので『小麦1枡』分の働きしかしなかった聖徒も、1デナリという同一の救いを受け、『たちまち、一瞬のうちに』(Ⅰコリント15章52節)罪の身体から御霊の身体へと変えられたのである。この預言も、やはり例のごとく『すぐに起こるべき事』(22章6節)であった。もちろん、ここで言われている究極的な救いは、再臨より後の時代に生きる全ての聖徒たちにも同じことが言える。再臨以降のいかなる時代の聖徒であれ、どれだけ主のために労苦したとしても、またはあまり主のために労苦しなかったとしても、同一の救い―1デナリ―を受けることになる。アウグスティヌスやルターのように多く労苦した人も、世俗の仕事が忙しくてあまり霊的な奉仕ができなかった人も、まったく同じ救いを受けられることには変わらない。このことは、全ての時代に通用する普遍的なことである。
この馬に乗っている者が『量りを手に持っていた』のは、再臨が起きた際に、地上にいた聖徒たちがどれだけ主のために労苦したかを計測するためであった。その時、この聖徒は大麦三枡分の働きをした、あの聖徒は小麦1枡分の働きしかしなかった、あそこにいる聖徒は…、というように働きの査定が行なわれた。とはいっても、どの聖徒にも同じ1デナリが与えられることになったのではあるが。それゆえ、この馬に乗っている者の名前は「量り」または「救い」または「労務者たちの主人」だと考えてよい。
この馬に乗っている者に与えられた『量り』を肉的に捉えて、物質的な量りを頭の中に思い浮かべてはならない。これは、先に見た『弓』(6:2)や『剣』(6:4)と同様に、比喩的な表現として捉えるべきである。事柄は肉的に捉えられてはいけない。
この馬が『黒い』色をしていたのは、非常に解読が難しい。神の恵みを受けなければ、どうしてこの馬が黒色だったかということの理由を知ることは出来ないであろう。この馬が黒かったのは、量りにより量られるべきまだ身体の贖いを受けていなかった聖徒たちの顔が黒かったからである。『雅歌』によれば、身体の贖いをまだ受けていない状態にある聖徒たちの顔は『日に焼けて、黒い』(1章6節)。だから、その醜い黒さを隠すために『顔おおいをつけた女のようにしていなければならない』(1章7節)。この顔覆いは、聖徒たちにまだ身体の贖いという究極的な救いが隠されていることを意味している。しかし、聖徒たちが天上においてキリストの花嫁として迎え入れられる時に、その頬は『ざくろの片割れのよう』(6章7節)になる。すなわち、薄いピンクがかった血色が現われるほどに肌が白くなる。天上において新しい身体を着せられたので、完全に清くなり、もはや黒くは無くなったのである。つまり、ここで黒い馬が預言として現われたのは、まだ白くなる前の状態にある黒い聖徒たちを対象とした預言だからに他ならない。すなわち、黒い馬と聖徒たちの黒い顔は対応しているのである。そのような対応が両者にあるのは、黙示録の読者がこの箇所と雅歌との関わりに気づけるようになるための、配慮であった。馬が黒く、この預言が身体の贖いを受ける前の聖徒たちを対象としているからこそ、雅歌との関わりを悟れるようにもなるのだ。よって、この馬は、理由なしに黒かったのではないことが分かる。御言葉とは実に深いものである。
『オリーブ油とぶどう酒に害を与えてはいけない。」』
ここで言われている『オリーブ油とぶどう酒』とは、聖徒たちの結ぶ「実」のことである。オリーブ油とはオリーブの木から採られ、ぶどう酒とはぶどうの枝が結ぶ実から作られるものである。聖書において、聖徒はオリーブの木(※①)やぶどうの枝(※②)に例えられている。よって、『オリーブ油とぶどう酒』とは、オリーブの木またぶどうの枝である聖徒たちが生じさせる「実」であることが分かる。しかし、その「実」とは一体なんなのか。それは、聖徒たちが行なったりこの世に残したりする良い行ないのことである。何故なら、『オリーブ油とぶどう酒』とは明らかに良いと思えるものだからである。
(※①)
ダビデはこう言っている。『しかし、この私は、神の家にあるおおい茂るオリーブの木のようだ。』(詩篇52篇8節)
[本文に戻る]
(※②)
キリストは聖徒たちにこう言われた。『わたしはぶどうの木で、あなたがたは枝です。』(ヨハネ15章5節)
[本文に戻る]
ここで言われている言葉は、つまり、聖徒たちの結ぶ「実」には裁きが下されるのではなく、むしろ良き報いが与えられるということを教えている。確かに、聖徒たちの結んだ実には、幸いな見返りが天にて与えられる。だから、ここでこのように言われることで、聖徒たちは自分たちの結ぶ実に損害がもたらされないということが、分かるのである。もちろん、あらゆる聖徒に同一の1デナリという救いが与えられるにしても、おのおのが結んだ実の度合いに応じて、天での見返りが違うのは確かである。すなわち、パウロも十字架にかかった強盗も同一の1デナリという救いを受けるのだが、天における祝福の度合いは、それぞれ異なっている。この2人の聖徒の場合、パウロのほうが強盗よりも天での祝福をより多く受けられるのは火を見るよりも明らかである。このように聖徒が結んだ実の度合いに応じて、天で受けられる祝福の度合いが変化するというのは、キリストが『宝を天に積み上げなさい。』(ルカ12章33節)と命じられたことからも分かる。宝をどれだけ天に積み上げたかによって天で受ける祝福の度合いが違ってくるのだから、キリストはこう言われたのである。もし天での祝福の度合いが、どの人も同一だったとすれば、キリストはこのように言われなかったであろう。要するに、救われるという点ではどの聖徒も同一の1デナリを受けるのだが、その結んだ実に対する報いという点では、どの聖徒も1デナリを受けるのではない。その報いにおいては、1000デナリを受ける聖徒もいれば、10デナリしか受けない聖徒もいる。聖徒である我々は、自分たちの結んだ実に応じて天で受けられる祝福が違ってくるということを心に留め、より多くの『オリーブ油とぶどう酒』を生み出していくべきである。そうすれば、それだけ天で受けられる祝福の度合いが増し加えられる。神は、その結ばれた実に対して『害を与えてはいけない。』と言われる。だから、聖徒たちは、安心して『オリーブ油とぶどう酒』とを、その良い行ないにおいて産出していくがよい。そうすれば、その良い行ないによる実は、やがて天における報酬へと変化させられることで永遠に残るものとなろう。実に、キリストが聖徒たちを選んで召されたのは、聖徒たちが『実を結び』(ヨハネ15章16節)、その『実が残るため』(同)であったのだから。
この第三の封印解除の箇所で、『人間のような顔を持』(4章7節)っている第三のセラフィムが、第三の黒い馬を呼び出したのは、この黒い馬が、顔の黒い聖徒たちを対象とした預言だからでなくて何であろうか。つまり、人の顔を持っていたセラフィムが黒い馬を呼んだのは、この馬が黒い顔の人間に向かって行くのと関係している。人の顔を持ったセラフィム=黒い顔の人たちに向かって出て行く黒い馬。実際には書かれていないからどうか分からないのではあるが、恐らくこの第三のセラフィムの顔も、馬と聖徒たちの色と同じように黒かったのではないか。先にも説明されたように、セラフィムとそのセラフィムに呼び出される馬には深い関連性があるのだから、この箇所の場合、私が今説明したように解するのが望ましいと思われる。というのも、今説明された以外の関連性を、このセラフィムと馬とに見出すのは難しいと感じられるからである。
ここでは『一つの声のようなものが、4つの生き物の間で』麦とデナリについて語っているが、この声の主は、父なる神であると思われる。何故なら、『4つの生き物』であるセラフィムの間から、この声が聞こえてきたからである。4:6の箇所でも言われていたように、この4人のセラフィムは『御座の中央と御座の回り』にいたのだから、そのセラフィムの間から出た声は、御座に座っておられる父なる神の声だということになる。もしそうでなかったとすれば、この声の主はキリストだということになろう。何故なら、この麦とデナリの発言は、キリストがかつて福音書の中で言われたのと本質的には同じ内容だからである。しかし、キリストは5:6の箇所からも分かるように、セラフィムの間には立っておられなかったのだから、やはりこの声の主は父なる神だったと解すべきであろう。黙示録の中には、無意味な箇所や言葉は一つたりともない。この文書においては、あらゆる箇所と言葉が、何らかの明確な意味を持っている(※)。もし何の意味もないと感じられる箇所や言葉があったとすれば、それは、その人がその部分をよく理解できていないからに他ならない。ここで声が出たと言われているのも同様であって、そこには明確な意味があるのだから、黙示録を究めたいと願う聖徒は、この箇所であれ他の箇所であれ、そこで言われていることの意味を探るための努力を怠ってはならない。
(※)
これは黙示録以外の聖書の巻でも同様のことが言える。ルターもこう言っている。「聖書においては一点一画も無駄に書かれていないことは確かだからである。」(『キリスト教神秘主義著作集11 シュタウピッツとルター』第二回詩篇講義 p247:教文館)
[本文に戻る]
【6:7~8】
『子羊が第四の封印を解いたとき、私は、第四の生き物の声が、「来なさい。」と言うのを聞いた。私は見た。見よ。青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は死といい、そのあとにはハデスがつき従った。彼らに地上の4分の1を剣とききんと死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。』
『剣とききんと死病と地上の獣によって殺す』とは、ユダヤが滅ぼされるという預言である。預言者の書には、4つの恐るべきものによってユダヤに滅びの裁きが与えられると預言されている箇所が多くある。例えば、かつてユダヤには次のような預言がなされた。『わたしはあなたがたにききんと、悪い獣を送る。彼らはあなたに子を失わせる。疫病と虐殺とがあなたのうちに起こる。わたしはあなたに剣を臨ませる。主であるわたしがこれを告げる。』(エゼキエル5章17節)『まことに、神である主はこう仰せられる。人間や獣を断ち滅ぼすために、わたしが剣とききんと悪い獣と疫病との4つのひどい刑罰をエルサレムに送るとき、…』(エゼキエル14章21節)我々が今見ている黙示録のこの箇所が、預言書の箇所と対応しているのは間違いない。ユダヤの滅亡について預言している預言の中には、4つではなく3つのものによる滅亡が語られている箇所も多いが(※)、4つでも3つでも意味としては何も変わらない。どちらも酷い滅亡が襲い掛かるという意味である。この預言には、神の激しい怒りが示されている。すなわち、神が激しく怒っておられるので、その怒りの現われとして、4つあるいは3つのものによって滅びの裁きが下されるということである。この預言は既にユダヤ戦争の時期に成就された。その時、ユダヤはローマ軍の剣によって打たれ、包囲の際の食糧不足による飢饉で苦しめられ、不衛生のために病が生じ、死体が獣によって引き裂かれ、遂には滅亡するに至った。これは我々が歴史の中で見ている通りである。キリストも、このような滅亡を預言して、あらかじめ次のように言っておられた。『その日、悲惨なのは身重の女と乳飲み子を持つ女です。この地に大きな苦難が臨み、この民に御怒りが臨むからです。』(ルカ21章23節)『その日は、神が天地を創造された初めから、今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないような苦難の日だからです。』(マルコ13章19節)『やがておまえの敵が、おまえに対して塁を築き、回りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしておまえとその中の子どもたちを地にたたきつけ、おまえの中で、一つの石もほかの石の上に積まれたままでは残されない日が、やって来る。』(ルカ19章43~44節)この預言も、やはり『すぐに起こるべき事』(22章6節)であった。この預言が書かれてから、数十年以内に、ユダヤが滅んで大量の死者が出たのだから。それゆえ、この青ざめた馬による預言がまだ起きていないと考える者は、御言葉に対抗しており、傲慢であって、その心の中には不信仰がある。
(※)
3つの場合の預言は次のようなものがある。『わたしは彼らのうちに剣と、ききんと、疫病を送り、彼らとその先祖に与えた地から彼らを滅ぼし尽くす。』(エレミヤ24章10節)―ここでは「獣」が語られていない。『あなたの3分の1はあなたのうちで疫病で死ぬか、あるいは、ききんで滅び、3分の1はあなたの回りで剣に倒れ、残りの3分の1を、わたしは四方に散らし、剣を抜いて彼らのあとを追う。』(エゼキエル5章12節)―ここでも「獣」が語られていない。
[本文に戻る]
上でこの預言に出てくる『地上の獣』は動物としての獣であると書いたが、これが実際の動物ではなく、ネロだと解することもできるのではないか、と思われる方がいるかもしれない。それというのも、彼も聖書では「獣」と呼ばれているからである。すなわち、このネロは黙示録13章で『獣』と言われている。だから、この『地上の獣』をネロであると解せるのではないか、ということである。しかし、この獣がどちらの意味でもあるということはない。何故なら、この獣が実際の動物を指していると同時にネロという比喩的な獣をも指していると考えるのは、かなり難しいと感じられるからである。この『地上の獣』とは、どちらか一方のことを言っていると解するのが自然な理解である。私は言うが、この『地上の獣』を、ネロという比喩としての獣だと解することはできない。何故なら、ネロはキリストの乗っておられる白い馬が出て来る第一の預言および赤い馬が出て来る第二の預言の時に殺されるのであって、我々が今見ている第四の馬が出て来る時には、既にこの世から消えているからである。確かに第一と第二の馬が出てくる6:1~4の箇所と対応している19:11~21の箇所では、ネロがキリストの軍勢により殺されている(19:19~20)。第一と第二の馬が出て来た時にネロが殺されたのであれば、どうして時間的に後の出来事である第四の馬が出て来る時まで、ネロという獣が生き残っているのであろうか。それはあり得ないことである。よって、我々が今見ている箇所で書かれている『地上の獣』を「ネロ」だと解するのは、黙示録の啓示に反している。それゆえ、この『地上の獣』とは上で書かれたように文字通りの動物であるか、ユダヤを滅ぼすローマ兵のことを言い表わしているか、そうでなければ神の怒りを<殺す獣>という表現で比喩的に言い表わしている。実際の歴史も教えるように、紀元70年9月にユダヤが滅ぼされた時、すなわち青ざめた第4の馬により死滅の裁きが下された時、ネロという獣は約2年前(紀元68年6月9日)にこの世を去っていた。だから、この獣がネロだと考えるのは、実際の歴史からしても退けられねばならない。ネロはユダヤ戦争が始まった元凶であるものの、第4の馬が示しているユダヤの滅亡には直接的に関わっていないのである。なお、陰謀論で有名な博学のジョン・コールマン博士が言っている『地上の獣』についての見解は、子供じみており、黙示録に対する無知がその背景に垣間見え、はっきり言ってお話にならない。しかし彼はキリスト教の教師ではないから、大目に見てやりたいと思う。彼はこう言っている。「黙示録に出てくる「地上の獣」とは巨大な動物のことではなく、死の疫病を広める能力をもった小動物を指す。「獣」とはまさに死のウイルスのことだと考える学派もある。スコットランドには「幽霊と小鬼と小動物」についての狂詩がある。さらに、一部の聖書学者は、人口の4分の1がペストと「地上の獣」によって死ぬ、と言っている(引用者註:これは大変素晴らしい卓越した聖書学者である。いつも黙示録が理解できるようにと祈りを積み重ねているに違いない)。」(『鳥インフルエンザの正体』第1章 全世界に死と恐怖をもたらす遺伝子操作ウイルス p29~30:成甲書房)(※)
(※)
なお、この博士は「千年」という期間についても何一つ分かっていない。彼はこの期間について次のように言っている。「…ダービーの教えのなかには「千年紀」―キリスト教原理主義思想の重要な要素―についての教えがあるが、この言葉は聖書のどこにも出ていない。」(『9・11 陰謀は魔法のように世界を変えた』謎を解くための参考資料 9・11にまつわる公式情報への反論を要約すると p261:成甲書房)期間の長さをどう理解するかということについては別問題として、この「千年」という言葉および概念自体は、黙示録20:1~6の箇所で明白に記されている。そこに書かれている「千年」という言葉から、「千年紀」という概念を導き出すことは不可能ではない。この期間については、本註解書における当該の箇所が来たら、詳しく説明されることになる。それにしても、コールマン博士は、黙示録については門外漢なのに、よくもここまで堂々と語れるものだと思う。黙示録を読めば、この言葉が出てくることぐらい、誰でも分かるはずなのだが…。更に彼はローマ軍に打ち壊されたのは「ダヴィデの神殿」(『石油の戦争とパレスチナの闇』日本民族が知らされないパレスチナ、その怨磋の歴史 p91:成甲書房)と書いているが、これだけでも彼が聖書について生半可な知識しかないことは明らかである。何故なら、「ダヴィデの神殿」などいう建造物は存在していないからである。別の箇所でも彼は「紀元70年にローマ将軍ティトゥスによってソロモンの神殿が破壊されて以来、…」(『石油の戦争とパレスチナの闇』日本民族が知らされないパレスチナ、その怨磋の歴史 p88:成甲書房)などと言っている。ティトゥスが破壊した神殿はヘロデ神殿であって、ソロモン神殿を破壊したのはネブカデレザルなのだが…。彼は「ロトはアンモン人とモアブ人の血を引いている。…エサウはエドム人の血を引いている。」(『石油の戦争とパレスチナの闇』はたしてユダヤとは何か、ユダヤ人とは誰か p283:成甲書房)とも言っている。この文章からも彼が聖書に全く精通していないことは明らかである。これらは神学の素人が聖書について語ると一体どういうことになるか、というよい例である。一般大衆は聖書のことをあまり知らないから、こういった博士が言っていることを鵜呑みにして「ほお、そうなのか。」などと聖書について間違った情報を獲得してしまうのである。
[本文に戻る]
『地上の4分の1』とは、すなわち「南」を意味する。東西南北は4つに分けられており、比率的に言えば、それぞれ4分の1である。すなわち北が4分の1、東が4分の1、西が4分の1、南が4分の1である。どうしてこの第四の馬が「南」を対象としているかと言えば、この黙示録の箇所(6:1~8)と対応しているゼカリヤ書6章(6:1~8)の箇所における第四の馬が、南の方角に出て行っているからである。そこでは、第四の馬が『南の地へ出て行く。』(ゼカリヤ6:6)と書かれている。このゼカリヤ書6章は後ほど説明されることになるが、この第四の馬が黙示録とゼカリヤ書とでは言い方こそ異なっているものの、どちらも同じ馬であることは間違いない。すなわち、この第四の馬について黙示録のほうでは『青ざめた馬』、ゼカリヤ書のほうでは『まだら毛の強い馬』(6:3)と言われているが、これは単に言い方が違うだけであって、同一の馬である。この第四の馬が『地上の4分の1』すなわち『南の地』へ出て行くというのは、ユダヤが滅ぼされることを意味している。古い世の終末に関して語られている聖書の箇所で「南」と出てきたら、それはユダヤの滅亡を意味していると知るべきである。聖書は「南」と言ってユダヤの滅亡を語っている。確かに、南の方角に出て行くこの第4の馬はユダヤの民に死とハデスをもたらす存在なのだから、このことからしても、南がユダヤの滅亡を意味しているということが分かる。しかし黙示録では、あえて「南」と言わずに『4分の1』と表現している。それとは逆の方角である「北」が何を意味しているかということは、また後ほど述べることにしたい。今説明されたことを考えても、やはり黙示録は、聖書の研究抜きには解読できない文書だということがよく分かるのではないかと思う。この文書は、実に深淵であり、それは底の見えない深い穴のようである。要するに、この文書は、ただ分かるようになる者だけが分かればよいという精神でもって記されているということになる。『耳のある者は聞きなさい。』という御言葉は、この黙示録においても同様のことが言えるのである。
どうして死が乗っている馬の後にハデスがつき従っているかと言えば、死が人を殺した後で、その殺された人をハデスが飲み込むからである。つまり、これは「殺されて死んだ人はハデスに捕えられる。」という意味である。これは簡単なことであって、何も難しく考える必要はない。それゆえ、ハデスが乗っている馬の後に死がつき従っていたのではない。これはあり得ないことである。何故なら、これは順序を転倒させており、意味が分からないからである。ハデスがまず人を飲み込んで、その後でその飲み込まれた人が死ぬとは、一体どういうことであろうか。また、このハデスが馬に乗っていたのか、ということについてはよく分からない。どのような様子をしていたのかということも、よく分からない。何故なら、このハデスについては『そのあとにはハデスがつき従った。』としか書かれていないからである。
この第四の馬が『青ざめた』状態だったのは、この馬に死が乗っているからでなくて何であろうか。死が乗っているからこそ、馬が死んだように青ざめているのである。それゆえ、この馬が青ざめていたのは自然なことであった。更にこの馬の後にはハデスもつき従っている。自分に死が乗っている上にハデスも追いかけてくるとは、何と不気味なことであろうか。だから、この馬は青ざめていなかったほうが、むしろおかしいと言える状態にあった。
『わしのよう』(4:7)な第4のセラフィムが、この青ざめた馬を呼び寄せたのは、この馬に乗る死が、勢いある鷲のようにユダヤに襲い掛かるからであった。つまり、神がもたらされる死による滅亡の裁きが、襲い掛かる鷲のように猛烈な勢いでユダヤに下されるからこそ、第4の馬は『わしのよう』なセラフィムが呼び寄せたのである。確かに、ユダヤの滅亡は、敵であるローマ軍を通して、恐るべき鷲のような猛烈さをもって実現された。確かに、聖書の中では、神が敵たちを罰せられるべき者たちに鷲のように襲い掛からせると言われている(※)。我々は、ユダヤ戦争の時にユダヤに下されたローマ軍による滅亡の裁きは、正に獲物を目がけて突進する鷲のような猛烈さを有していたことを知るべきである。「最強」と呼ばれたローマ軍が『わしのよう』であったことを疑う人が誰かいるであろうか。古代ローマはその軍隊の持つ鷲のような力強さのゆえに、全世界の支配者となったのである。これはアグリッパ王がローマ軍について、「彼らの兵力は世界の至る所で無敵ではないか?」(『ユダヤ戦記Ⅰ』Ⅱ xvi4:362 p341:ちくま学芸文庫)とユダヤ人に対して語っている通りである。ティトゥスも「今日に至るまで、この世界に住む民族の中で我々の手を逃れ得た民族はなかった。」(「ユダヤ戦記」第3巻/x2:473)と言っている。ヨセフスもローマ軍には「無限の兵力」(「ユダヤ戦記」第2巻/xvii10:453)があったと述べている。実際、古代ローマ軍のシンボルは鷲であり、スエトニウスも書いているようにその旗は「鷲旗」(『ローマ皇帝伝(上)』第2巻 アウグストゥス p103:岩波文庫)であった。この「鷲旗」についてはヨセフスもこう言っている。「鷲はすべての鳥たちの王であり、もっとも獰猛であるので、ローマ軍ではこの鷲(の軍旗)がすべての軍団の先頭に立つ。この鷲(の軍旗)はローマ兵たちにとって帝国の象徴であり、また戦う相手が誰であれ、勝利の吉兆だった。」(『ユダヤ戦記2』Ⅲ vi2:123 p040:ちくま学芸文庫)であるから、ここでも、やはりセラフィムと呼び出された馬とには深い関連性があったことが分かる。
(※)
『主は、遠く地の果てから、わしが飛びかかるように、一つの国民にあなたを襲わせる。』(申命記28章49節)―これはローマがユダヤを滅ぼすということでなくて何であろうか。『角笛を口に当てよ。鷲のように敵は主の宮を襲う。彼らがわたしの契約を破り、わたしのおしえにそむいたからだ。』(ホセア8章1節)―これもローマがユダヤとそこにあった宮を滅ぼすことを言ったものでなくて何であろうか。
[本文に戻る]
ところで、ユダヤにこのような恐るべき裁きが下されるのは冷酷ではないかと思われる方が、もしかしたら読者の中にはおられるかもしれない。しかし、ユダヤ人のしたことをよく考えていただきたい。彼らは、自分たちを『エジプトの国、奴隷の家から連れ出し』(出エジプト20章2節)て下さった救い主なる神に対して延々と背き続け、律法も守るには守るがただ外面的に守るだけであってそこには神の求めておられる『正義もあわれみも誠実も』(マタイ23章23節)見られず、自分たちに送られた預言者たちを何人も殺したり迫害したりし、最後には遂に来られた約束のメシア、神の御子、ユダヤ人の王をさえも拒絶してしまった。このような不敬虔な民に、滅亡という裁きが下されたのは当然だったということを、読者は知るべきである。『御言葉を蔑む者は身を滅ぼす。』(箴言13:13)という神の言葉は、正に真理であった。彼らは神の御言葉を蔑ろにしたので、民族としての身を滅ぼしたのである。もしどこかに人を殺す者がいたとすれば、その者は死刑になってこの世から取り去られないであろうか。そうなるであろう。ユダヤは、その背きの罪により、神を契約的に殺してしまった。すなわち、彼らは神との契約を破り、自分たちと神との関係を愚かにも断ち殺した。だから、神もそのようにしたユダヤの民に報いられ、彼らを容赦なく殺滅されたのである。つまり、ユダヤが滅ぼされたのは根拠なきことではなかった。だから、このような裁きが冷酷だったなどと言って神を批判することはできない。
先にも説明されたように、7つの封印が解除される際、セラフィムが馬を呼び寄せることについて描かれているのは、ここまで見た4つの封印解除の時だけである。これ以降に書かれる3つの封印解除においては、もはやセラフィムと馬は出て来ない。
さて、先にも触れたことだが、この6:1~8の箇所とゼカリヤ6:1~8の箇所は間違いなく対応している。しかしながら、黙示録における他の多くの箇所と同じように、この2つの箇所には、3つほど微妙に異なった点が見られる。それは次に示す通りである。<1>この2つの箇所では、第4番目の馬だけ言い方が異なっている。すなわち、この第4番目の馬は、黙示録のほうでは『青ざめた馬』と言われているが、ゼカリヤ書のほうでは『まだら毛の強い馬』(6:3)と言われている。それ以外の3つの馬については、どちらのほうでも、まったく同じ言い方がされている(赤い、黒い、白い)。<2>黙示録のほうでは、馬が出て来るだけで、ゼカリヤ書のように馬が戦車を率いてはいない。<3>黙示録とゼカリヤ書とでは、馬の出てくる順序が異なっている。第4の馬だけは4番目に登場しており、どちらも同じ順序であるが、それ以外の3つの馬においては順序が違う。すなわち、黙示録のほうでは「白、赤、黒、第4の馬」という順だが、ゼカリヤ書のほうでは「赤、黒、白、第4の馬」という順になっている。3番目までの順序が、まったくあべこべになっているのが分かる。
<1について>4番目の馬だけ言い方が異なっているのは、ただ言い方が異なっているだけであり、どちらも同一の馬であることには変わらない。三つ目までの馬がどちらも一緒の馬なのであるから、4番目の馬も一緒の馬だと考えるべきであろう。『青ざめた』(黙示録)と『まだら毛の強い』(ゼカリヤ書)という言い方は、不調和を引き起こしていない。何故なら、青ざめていながら毛がまだらであるということは可能な様態だからである。つまり、この第4の馬においては、同じ馬に対して違った観点から2つのことが言われてるに過ぎない。もし不調和を引き起こすような2つの言い方がされていたとすれば、この2つの箇所に出てくる第4の馬は別々の馬だったということにもなるが、ここで不調和は引き起こされていないのである。それは例えば、ジョン・ロックに対して「長髪の人」と言っても「痩せている人」と言っても、同じロックについて言われているのには変わらないのと同じである。というのも、「長髪」と「痩身」は不調和を引き起こす様態ではないから。
<2について>黙示録のほうでは馬が戦車を率いているとは言われていないが、これは特に問題にはならない。何故なら、この2つの箇所による預言では、その預言が「主の戦いまた報復」であることを教示する目的が達成されていれば、それで良いからである。馬がそのまま出て来るにせよ、戦車を率いているにせよ、その預言が主の戦いまた報復であることは十分に理解できる。先にも述べたように馬とは古代では、戦いや報復のために使われる生きた道具だったからである。我々は、この2つの箇所における預言の中で何が示されているのかということを十分に考えるべきである。預言とは、その本質部分さえ堅持されていれば、それぞれ対応している2つの箇所で細部において微妙な差異が見られたとしても問題にはならないのである。
<3について>正しい順序は、黙示録のほうであって、ゼカリヤ書のほうではない。何故なら、この黙示録6:1~8の箇所に出て来る馬の順序は、馬による神の働きかけが実際に起きる通りの順序を記している19:11~20:10の箇所と、まったく同じだからである。読者は、この黙示録6:1~8の箇所と19:11~20:10の箇所が互いに対応していることに気付くべきである。確かに、実際に起きる通りの順が記された19:11~20:10の箇所においては、まず第一に白い馬に乗ったキリストが現われ(19:11~16)、第二に赤い馬が示している争いと殺し合いとが起こり(19:19~21)、第三に黒い馬が示している究極的な贖いが起こり(20:1~6)、第4に青ざめた馬により示されているユダヤの死滅が起きている(20:7~10)。このように見ると黙示録6:1~8と19:11~20:10が調和していることが分かるであろう。一方、ゼカリヤ書のほうの順序は、黙示録19:11~20:10で示されている順序と調和していない。ゼカリヤ書のほうの順序においては、まず第一に赤い馬による騒乱が起こり(19:19~21)、第二に黒い馬による聖徒たちの最終的な救いが実現され(20:1~6)、第三に白い馬に乗った再臨のキリストが現われ(19:11~16)、第四に第4の馬によるユダヤの破滅が起こることになる(20:7~10)。この場合、第四の順序だけは正しいが、第1~第3までの順序は明らかにおかしい。ネロと再臨されたキリストとの戦いがまずあり(赤い馬)、その次に再臨の直後に起こる究極的な贖いが起こり(黒い馬)、そうしてからキリストが再臨される(白い馬)とは一体どういうことであろうか。それでは、どうしてゼカリヤ書の馬の順序は、黙示録で出て来る馬の順序とは違い、実際の順序と異なっているのであろうか。その理由は、ゼカリヤ書のほうでは、ただ古い世の終末に起こる出来事の言わば輪郭部分だけが啓示されたに過ぎないからである。すなわち、ゼカリヤ書のほうでは、単に古い世の終末の時には馬による神の働きかけが起こるということの報知だけが啓示の目的とされていたのであって、順序を正確に示すことまでは考量されていなかった。つまり、ゼカリヤ書の預言においては、ただ「神が馬によりご自身の民と敵どもに報復されるのだ。」ということだけが示されていればよかった。このように黙示録と旧約聖書において、細部において微妙な差異が見られる対応し合った箇所は少なくない、ということについては既に説明された通りである。もしゼカリヤ書の順序のほうを実際の順序だと理解すれば、実際に起きたこと及び黙示録の啓示と適合しなくなってしまい、何が何だか分からなくなってしまうので注意しなければいけない。要するに、実際に起こる出来事の順序を啓示しているのは黙示録のほうだけであり、ゼカリヤ書は事象の啓示だけであって順序の啓示までは含まれていない。
なお、このゼカリヤ書については、黙示録の理解向上のため、第4部も見て学んでいただきたい。ここでは黙示録を基点にしてゼカリヤ書が語られたが、第4部のほうではゼカリヤ書を基点にして黙示録が語られている。黙示録の正しく深い理解のためには、黙示録と対応している他の箇所も十全に知っておかねばならない。これは言うまでもないであろう。
【6:9】
『子羊が第五の封印を解いたとき、私は、神のことばと、自分たちが立てたあかしとのために殺された人々のたましいが祭壇の下にいるのを見た。』
魂が置かれている『祭壇』の場所は天であった。8:3にはこの祭壇が『御座の前にある』と書かれており、9:13でも『神の御前にある金の祭壇』と書かれている。つまり、これは地上のどこかにある祭壇のことではない。
この祭壇が金の色だったのは、永遠の贖いを成し遂げられた子羊と、その子羊に贖われた聖徒たちが、御父にとって尊く高価だったからである。確かに、屠られた子羊が御父にとって尊く高価だったのは間違いない。誰がこれを疑うであろうか。また子羊に贖われた聖徒たちにおいても、同じことが言える。何故なら、神はイザヤ43:4の箇所で、聖徒たちに対して『わたしの目には、あなたは高価で尊い。』と言っておられるからである。それだからこそ、子羊が永遠の贖いを成し遂げられたことを示すものであり、またその子羊に贖われたことを指し示すものである祭壇は金の色をしていたのであった。それゆえ、この祭壇が金でない色をしているということはあり得なかった。何故なら、金というものは、尊く高価であることを示す物質としてはもっとも相応しいものだからである。
この箇所で言われている神の御前にある祭壇にいた魂とは、メシアをナザレのイエスとしては認識していなかった昔の殉教者たちの魂のことである。まだメシアがナザレのイエスとして公に現われていなかった時の聖徒たちは、神の言葉と聖なる証しとのために殉教した際、その魂が神の御前にある祭壇に移された。イザヤやエレミヤをはじめとした預言者たちも、そのようにして魂が神の御許へと移された。これはソロモンが、『霊はこれを下さった神に帰る。』(伝道者の書12章7節)また『人の子らの霊は上に上り、』(同3章21節)と書いた通りである。霊とはすなわち「魂」のことでなくて何であろうか。この黙示録の箇所では殉教者の魂のことしか書かれていないが、殉教せずに死んだ昔の聖徒たちの魂も、神の御前にある祭壇の下に移されたことは間違いない。何故なら、ソロモンが霊は神の御許に行くと断言しているからである。であれば、やはり殉教していない聖徒たちの魂も祭壇の下に置かれることになるはずである。殉教した聖徒の魂だけが神の御許にある祭壇の下に引き上げられ、殉教しなかった聖徒の魂はそのようにならない、というのは非常に考えにくい。『神は人を分け隔てなさらない。』(ガラテヤ2章6節)のだから、どうして殉教しなかった聖徒たちだけは仲間外れにされてしまうのであろうか。しかし、メシアをナザレのイエスとして認識していた紀元30年以降の聖徒たちは、死んでもその魂が神の御許に引き上げられることはなく、その魂は再臨の起こる日まで地上に延々と留め置かれていた。何故なら、ナザレのイエスを認識していた死んだ聖徒たちの場合、再臨の起こる紀元68年の時に、天ではなく地上で死者の中から復活することになっていたからである(Ⅰテサロニケ4:16~17)。パウロも言うように再臨の日には地上において死から復活する聖徒が存在したのであって、それは、たった今述べたような聖徒であった。一方、ナザレのイエスという具体的なメシア認識を持っていなかった昔の聖徒たちは、再臨の日に、地上ではなく天上において復活することになっていた。そのようにして天で復活してから、その聖徒たちはキリストと共に天から降りてきたのである(ユダ14、Ⅰテサロニケ4:14)。そのやがて天から降りて来る聖徒たちの魂のことが、我々が今見ている箇所では言われている。だから、この箇所で言われている聖徒たち、すなわちナザレのイエスという人物においてメシアを認識していたのではなかった昔の聖徒たちは、死んでからその魂が地上に横たわるということがなかった。もしそういうことであったとしたら、旧約の聖徒たちの魂は全て地に留め置かれるのだから、天で復活する聖徒たちが誰もいなくなり、再臨の際にキリストが復活した無数の聖徒たちを天から引き連れて来られるということもなかった。これはおかしなことであり、聖書の啓示に反することである。我々は、紀元30年までに死んだ聖徒の魂は天に引き上げられ、紀元30年以降にナザレのイエスを知りつつ死んだ聖徒の魂は、紀元68年6月9日という古い世界の終わりの日になるまでは地上に留め置かれたということをよく覚えるべきである。
この9節目の箇所でヨハネが見ている光景そのものは、預言としての光景ではなかった。この箇所においては、ヨハネが幻を啓示された正にその時にある現実の光景が描かれている。つまり、ヨハネが祭壇の下に聖徒たちの魂が置かれているのを見たのは『今ある事』(1:19)であった。すなわち、この9節目の箇所は『この後に起こる事』(同)ではない。このように黙示録では、『今ある事』としての光景が描かれている箇所も存在している。
【6:10】
『彼らは大声で叫んで言った。「聖なる、真実な主よ。いつまでさばきを行なわず、地に住む者たちに私たちの血の復讐をなさらないのですか。」』
祭壇の下に置かれていた魂たちは、自分たちの血に対する復讐がなされるようにと、ここで叫んでいる。アベルから4000年の間、ずっとその復讐が果たされないままの状態だったからである。だからこそ、彼らはこのように神に向かって大きな声を上げたのである。というのも、人間とは、自分に害を加えた者に対して至当な復讐が果たされることを望む存在だからである。あのダビデでさえ、自分に悪を行なったナバルに対して復讐がなされることを欲したのを、我々はよく知っている(Ⅰサムエル25章)。それでは、ここで復讐が果たされるようにと叫んでいる殉教者たちの魂の数は、どれぐらいだったのであろうか。これについては、何も書かれていないので、よく分からない。21世紀に生きる我々の感覚からすれば、非常に多いと感じられる数だったかもしれないし、あまり多いとは感じられない数だったかもしれない。
彼らが『大声で叫んで言った』のは、神に復讐していただきたいという願望が非常に強かったことを示している。もしその願望が強くなかったとすれば、このように大声で叫んでいなかったであろう。何せ、アベルの時からおよそ4000年もの間、義人の血に対する裁きが遂行されないままであった。であるから、彼らが復讐がなされるようにと大声で叫んだのは無理もなかったと言える。こんなにも長い間、復讐が果たされないでいるのに、どうして大声で叫ばずにいられるであろうか。
この叫びの声は、すぐにも神に叶えられることになった。すなわち、神は紀元66~70年のユダヤ戦争において、今までに流されてきた義人たちの血に対する復讐を、ユダヤを滅ぼすことで一挙に全うされた。この溜め込まれてきた復讐がユダヤにおいて放出されることについて、キリストは次のように言われた。『それは、義人アベルの血からこのかた、神殿と祭壇との間で殺されたバラキヤの子ザカリヤの血に至るまで、地上で流されるすべての正しい血の報復があなたがたの上に来るためです。まことに、あなたがたに告げます。これらの報いはみな、この時代の上に来ます。』(マタイ23章35~36節)神は、このように留保されてきた復讐を、ある時にたちまち注がれるお方である。それは、例えるならば、怒りという名のダムが長い間注ぎ込まれてきた怒りという名の雨により決壊したために、多くの水が一挙に放出されて街々が壊滅してしまうなものだ。この時、ユダヤにおいて神の復讐が全うされることにより、神の怒りは鎮められることとなった。このユダヤの滅亡を見れば、この時に注がれた神の怒りがどれほどに大きかったかがよく分かる。実に、それは一つの民と都市とが致命的な壊滅に至らされるほどのものであった。神の怒りの度合いは、その滅亡の度合いに反映されていたのである。
この復讐を見ても分かるが、神は、復讐を大きな度合いにより実行される。神は偉大で巨大なお方だから、その存在に相応しく、復讐の度合いも大きいものとされる。それは偉大な王が、その偉大さに相応しく、贈り物をする際には常に価値の高い物品を贈るのと同じことである。もしある王が小さな贈り物しかしないとすれば、その王は大いなる存在だとは見做されないであろう。何故なら、その場合、その小さな贈り物に応じて王の価値が判定されるからである。神もそれと同様であって、人間がご自身を軽んじないようにするために、基本的な傾向として復讐の度合いを大きくなされるのである。もし神が復讐を小さくなされることしかされないとすれば、その小さな復讐に応じて神が判定されてしまうので、神が恐れられたり尊重されることもそれだけなくなってしまう。ソドムとゴモラに対しても、そのように大きな復讐が果たされたのを我々は既によく知っている。しかしながら、これはあくまでも基本的な傾向なのであって、悔い改める余地のあるご自身の聖徒に対しては、神はその復讐を留保されることはなく、むしろ小さな度合いながらもすぐに損害をもたらされる。それは、その聖徒たちが、すぐにも悔い改めて心を変え、もう2度とその悪に歩まないようにするためである。神は、正しい者たちに対しては憐み深いのである。一方、悔い改める余地のない邪悪かつ不敬虔な者に対しては、神はそのようにされない。ここに彼らの悲惨がある。彼らは悪を行なっても復讐を受けることがなく、復讐を受けないので調子に乗り、いつまでもそのまま悪に突き進むようにされている。このような者に対してこそ、神は復讐を溜め込んで置かれるのである。だから、忌まわしい悪者たちは、溜め込まれた復讐が最終的に下されることによりユダヤが滅んだごとくとなる。ソロモンが『悪い行ないに対する宣告がすぐ下されないので、人の子らの心は悪を行なう思いで満ちている。』(伝道者8章11節)と言ったのは、見放された者たちに特によくあてはまる。それゆえ、悪に突き進むばかりの悪者たちは実にわざわいである。彼らは最後に全滅するためにこそ、悪の行ないが途中で中断させられないように放置されているのだから。すなわち、神は、最後に破滅的な復讐を注ごうとしておられるからこそ、あえて彼らに小さな復讐をちまちまと注がれることをされないのである。もしそのような小さな復讐が悪を行なうごとに注がれていたとすれば、彼らの悪が定期的に中断されることにもなり、彼らが破滅して消え去るということもなくなってしまうではないか。神は滅ぼそうと欲しておられる者たちに対しては、その復讐を最後まで引き延ばされるのである。
【6:11】
『すると、彼らのひとりひとりに白い衣が与えられた。そして彼らは、「あなたがたと同じしもべ、また兄弟たちで、あなたがたと同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間、休んでいなさい。」と言い渡された。』
ここで『彼らのひとりひとりに白い衣が与えられた。』と言われているのは、過去形で語られた未来に起こる預言である。聖書には過去形で語られる預言も存在している、ということについては既に説明された。だから、この預言が語られた時点で天にいる魂たちに御霊の身体である『白い衣』が与えられたと考えてはならない。そのように考えるのは、聖書の教えてと矛盾している。聖書は再臨の起きる時に、永遠の肉体が与えられると教えている。それなのに再臨が起きる数十年も前の時に、つまりヨハネがこの預言を書き記している正にその時に、新しい永遠の肉体が聖徒たちに与えられることになるとは一体どいうことであろうか…。
この預言は、再臨の起きた紀元68年に成就された。その時、天に置かれていた魂たちは、御霊の身体である白い衣を着せられることで復活の恵みに与った。そうしてから、パウロやエノクが預言していたように、天からキリストと共に空中へと降りて来たのである(Ⅰテサロニケ4:14、ユダ14)。ここで言われているように、天にいる聖徒の魂たちは時が来るまで、魂のままで休んでいなければならなかった。その時とは、すなわち『あなたがたと同じしもべ、また兄弟たちで、あなたがたと同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで』であった。つまり、これはネロによる42カ月の迫害期間が終わるまで、ということである。その迫害期間が終わると、紀元68年6月9日という驚くべき日に至り、今までに殺された殉教者たちと同じように殺されるはずの人々の数が満ちたのである。ソロモンも言うように、『何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある』(伝道者の書3章1節)のである。つまり、白い衣が天の魂に与えられるようになる<時>は、<再臨の時>であった。この預言が成就して以降、聖徒たちは、もはやそれ以前の時代のように死んでも魂だけの状態になることがなくなった。その時以降、聖徒たちの魂は、死んだら『たちまち、一瞬のうちに』(Ⅰコリント15章52節)古い身体から抜け出て新しい身体へと移されるようになった。今やそのような死後経験に与れる時代が到来している。我々も、死んだならば、すぐにも魂が新しい身体へと移行されることになる。これは古い時代とはまったく違う死後経験である。
ここで『休んでいなさい。』と語っている声の主は、神であろう。その語る声が御父か、御子か、御霊か、ということは分からないが、いずれにせよ「神」であることは間違いない。何故なら、神でなければ、どうしてこのようなことを語れるであろうか。もしこれが被造物に過ぎない者の声だとすれば、その者はなんと傲慢で自分の身を弁えていないことであろうか。もしこれが神でない者の声であれば、「あなたは神でもないのに、どうしてこのようなことを言うのか。」などと文句を言われてしまうことにもなるのである。
【6:12】
『私は見た。子羊が第6の封印を解いたとき、大きな地震が起こった。』
第6の封印による預言は、そこまで解読が難しいというわけではない。というのは、ここでの預言は、旧約の預言をほとんど一緒の形になぞることで語られているといってよいからである。だから聖書、特にイザヤ書を読み慣れた人であれば、この第6の封印の箇所を読んだ際、すぐにも対応する別の箇所が頭の中に浮かぶのではないかと思う。
とことで、ヨハネがこの箇所や他の箇所で『私は見た。』と書いているのは、あたかも次のように言っているかのようである。「私はキリストに選ばれた使徒であって、そのキリストから預言としての幻を受けて、皆にそれを伝えている。そのような私が伝える預言を、まさか聖徒である君たちは、否定したり疑ったりはしないであろう。もしそのようにするとすれば、君たちは実に不敬虔だということになる。何故なら、使徒であるこの私ヨハネがキリストから与えられた預言を、まざまざと伝えているのだから。それゆえ、君たちは、私が見て伝えるこれらの預言としての幻を決して否定したり疑ったりしないようにせねばならない。」
ここで『大きな地震が起こった。』と言われているのは、キリストの再臨が起こるという預言である。聖書では、キリストが再臨される際には、大きな地震が起こると教えている。例えば、イザヤ29:6の箇所ではキリストが再臨されることについて、『万軍の主は、…地震…をもって、…あなたを訪れる。』と言っている。一体どうして再臨の際には地震が起きるかと言えば、<地>が、自分の上に乗っている人々を裁こうとして来られるキリストを迎えるからである。地が自分の上に乗っている人々を裁こうとして来られる審判者なるキリストを迎えるのだから、地は自分の創造主なるお方を前にして文字通り震撼するわけである。つまり、この地震とは、地が自分という場所に向かって来られるキリストの前に恐れ戦くことを意味している。その恐れ戦く状態が、地震として現われ出るのである。我々も恐怖を感じるとガタガタと震えて小さな地震を周囲に生じさせるが、地が再臨の際に恐がってガタガタと地震を引き起こすのは、それと同じことである。
『そして、太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。』
これは、再臨されたキリストの威光が、あまりにも凄まじいということを教えている。再臨されたキリストの威光はあまりにも輝かしかったので、まばゆい太陽でさえも黒いと感じられるほどであり、また月もその輝かしさを前にして驚愕するほどであった。月においては、その驚愕が、血まみれになるということで表現されている。これは例えるならば、素人のゴルフ大会で獲得した優勝者のベルトが、それ自体としては輝かしいものであり自慢できるものの、タイガー・ウッズの前においては、まったく輝きが失われて無にも等しいただのベルトに過ぎなくなるようなものである。タイガー・ウッズと比較するならば、そのようなベルトなど何の意味があるであろうか。それと同じように、キリストの威光と比較するならば、太陽も月もそれ自体としては輝かしいのではあるが、その比較において虚しい存在に過ぎなくされてしまったのである。このことについては、いくらか言い方が違っているが、イザヤ書の中でこう言われている。『見よ。主の日が来る。残酷な日だ。…太陽は日の出から暗く、月も光を放たない。』(12章9~10節)『わたしは天をやみでおおい、荒布をそのおおいとする。』(50章3節)『月ははずかしめを受け、日も恥を見る。』(24章23節)同様にキストも、ご自身が再臨される際には『太陽は暗くなり、月は光を放た』(マタイ24章29節)なくなると言われた。
【6:13】
『そして天の星が地上に落ちた。それは、いちじくが、大風に揺られて、青い実を振り落とすようであった。』
これを文字通りに捉えるのは変である。星が地上に落ちてくるというのは、明らかに象徴としての言い方だからである。遠くにある恒星や惑星が、地球に向かって突進してくるとでもいうのか。そのような愚かしい空想は止めるべきである。ここで『天の星が地上に落ちた。』と言われているのは、再臨の際に、イスラエルが究極的な救いから除外されたということを意味している。実際、イスラエル人たちは再臨が起こった際、あの復活の恵みに与かることが出来ず、身体の贖いという究極的な救いから『大風に揺られて、青い実を振り落とすよう』に遠ざけられた。それゆえ、ここで『天の星』と言われているのはイスラエルを指していることが分かる。何故なら、この星は『いちじくが、大風に揺られて、青い実を振り落とすよう』にして再臨の時に実現された救いから落とされたからである。「いちじく」とは聖書ではイスラエルのことである。読者は、黙示録において『星』という言葉が多様な意味を持っていることを知るべきである。我々が今見ているこの箇所では、それは「イスラエル」である。キリストの右の手に握られている星は『教会の御使いたち』(1:20)である。12:4の箇所で竜が地上に投げ落とした星は「キリスト者」である。8:4で書かれている星は、「文字通りの星」である。星が一通りの意味だけしかないと思って、星について言及されている黙示録の箇所を理解しようとした場合、その一通りの意味しかないと思っている意味と整合する箇所であれば問題はないのだが、そうでない箇所であれば間違った理解を持つに至るので注意が必要である。だから、読者は黙示録を解読する際、星と書かれている箇所があれば、その星がどのような意味で言われているのかということをよく考えなければいけない。この箇所の後半部分は、表現こそ違うものの、明らかにイザヤ34:4と対応している。そこでは『いちじくの木から葉が枯れ落ちるように。』と書かれている。前半部分においては、キリストが再臨の際には『星が天から落ち』(マタイ24章29節)るだろうと言っておられるのと対応している。
【6:14】
『天は、巻物が巻かれるように消えてなくなり、』
これは、世界が刷新されるということを、象徴的に表現した預言である。これを文字通りに捉えるのは、狂気に陥ることである。この預言の通り、キリストが再臨された紀元68年において、それまでの古い時代は『巻物が巻かれるように消えてなくなり』、新しい時代が到来することとなった。再臨が起きたということは、すなわち時代が古いバージョンから新しいバージョンへと切り替わることであるが、それは、ここまで読み進められた読者であればよく理解できるはずである。確かに、神の言葉も、再臨が起きると世界も刷新されるのだと明瞭に教えている(マタイ19:28、使徒行伝3:20~21)。しかしながら、紀元68年に起きたこの世界の刷新は、聖書に基づいて悟らなければ理解することができない。聖書に基づいて悟ってこそ、初めてこの刷新の事柄を理解できるようになる。ここにおいて、イザヤ書の『あなたがたは信じなければ知解しないであろう。』という聖句が重要となる。確かに、その時、世界は刷新された。御言葉がそのように教えているからである。この時以降の時代において、人々は信仰を持てば神の民となることができるようになり、世界の至る場所には教会が存在するようになり、もはやメシアの実体も隠されてはおらず不信者にさえ明らかにされており、明らかに旧約の時代とは違った状態の時代が到来したのだから、やはり再臨の日以降は新しい時代が始まったのだと考えなければいけない。天が刷新されるというこの預言は、次の箇所と対応している。『天の万象は朽ち果て、天は巻き物のように巻かれる。その万象は、枯れ落ちる。』(イザヤ34章4節)『…主の日は、盗人のようにやってきます。その日には、天は大きな響きをたてて消えうせ、天の万象は焼けてくずれ去り、地と地のいろいろなわざは焼き尽くされます。』(Ⅱペテロ3章10節)
『すべての山や島がその場所から移された。』
これは、キリストが再臨された際に、古いバーションの世界が取り除かれて新しくされるということである。これを象徴的な表現として捉えなければならないのは言うまでもない。確かに、再臨の時、古い世界は取り除かれて、まったく新しい世界が到来した。その古い世界の中には当然ながら『すべての山や島』が含まれている。だから、その刷新の出来事がこのように言い表わされたのは実に適切であった。それは、あたかも成人となった人に対して、「もう子どもとしての君たちは消えていなくなったのだ。」などと言うのと同じである。この部分は、すぐ前の『天は、巻物が巻かれるように消えてなくなり』という部分と、内容的に同じである。つまり、この14節目は二重表現がされていることになる。聖書において、このような二重表現は特に珍しいものではない。このような表現がされるのは、そこで言われていることを強調するためである。ルターも言うように、聖書において「同意反復は確かさのしるし」(『キリスト教神秘主義著作集11 シュタウピッツとルター』第二回詩篇講義 p411:教文館)である。この箇所の場合、「古い世界が取り去られて新しくなる。」ということが強調されつつ語られていることになる。
この部分は、16:20の『島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなった。』という箇所や、20:11の『地も天もその御前から逃げ去って、あとかたもなくなった。』という箇所と完全に対応している。20:11のほうでは「山と島」ではなく「地と天」になっているが、意味としては6:14や16:20の内容と何も変わらない。
【6:15~16】
『地上の王、高官、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が、ほら穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。「私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と子羊の怒りとから、私たちをかくまってくれ。』
これは、神とキリストにおけるその威光と御怒りの度合いが、実に凄まじいということを示している。その凄まじさは、あらゆる人たちが『ほら穴と山の岩間に隠れ』、山や岩にさえ自分たちを匿ってほしいと懇願するほどであった。実際、紀元68年に起きた再臨は、不信者たちにとって、そのようにしたくなるほどに恐るべき出来事であった。精神を張り割けんばかりにするこの喫驚すべき再臨については、既にキリストがこう言っておられた。『そのとき、人の子のしるしが天に現われます。すると、地上のあらゆる種族は、悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見るのです。』(マタイ24章30節)『そして、日と月と星には前兆が現われ、地上では、諸国の民が、海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩み、人々は、その住むすべての所を襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かされるからです。そのとき、人々は、人の子が力と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見るのです。』(ルカ21章26~27節)しかしながら、キリストの再臨をエルサレムにおいて見た不信者たちは、その凄まじい光景を見ていたにもかかわらず、その光景を記録として書き残すようなことはしなかった。何故なら、イザヤ29:1~8の箇所でも言われているように、その不信者たちにとって、再臨の出来事は『夢のよう』『夜の幻のよう』(29章7節)に感じられたからである。幻影に過ぎないと思われた非現実的な光景を、誰がいちいち書き記して、後の時代にまで伝わるようにするであろうか。彼らにとって、それはただの恐ろしい夢も同然だったのである。もちろん、中にはメモをとるぐらいのことをした人がいたかもしれないが、無名の一ローマ人に過ぎない者が書いたメモが、後世にまで残されることは当然ながらなかった。このことについては、既に第1部の中で論じられた通りである。なお、この箇所はイザヤ2章の箇所と完全に対応している。そこではこのように書かれていた。『岩の間にはいり、ちりの中に身を隠せ。主の恐るべき御顔を避け、そのご威光の輝きを避けて。その日には、高ぶる者の目も低くされ、高慢な者もかがめられ、主おひとりだけが高められる。』(2章10~11節)『主が立ち上がり、地をおののかせるとき、人々は主の恐るべき御顔を避け、ご威光の輝きを避けて、岩のほら穴や、土の穴にはいる。その日、人は、拝むために造った銀の偽りの神々と金の偽りの神々を、もぐらや、こうもりに投げやる。主が立ち上がり、地をおののかせるとき、人々は主の恐るべき御顔を避け、ご威光の輝きを避けて、岩の割れ目、巌の裂け目にはいる。鼻で息をする人間をたよりにするな。そんな者に、何の値打ちがあろうか。』(2章19~22節)またこの箇所は、ホセア10:8の箇所とも対応している。そこではこう書かれている。『彼らは山々に向かって、「私たちをおおえ。」と言い、丘に向かって、「私たちの上に落ちかかれ。」と言おう。』このホセア書の箇所では、イスラエル王国がアッシリアに滅ぼされる時の悲惨さを言い表している(紀元前720年)。つまり、我々が今見ている箇所で言われているのは、神とキリストによる御怒りはイスラエルがアッシリアに滅ぼされた時のような悲惨さを持っている、ということである。事実、イスラエル王国が滅ぼされる時にも、キリストが御怒りを発された時にも、山や岩や丘にかくまってもらいたくなるほどの恐怖が生じた。
【6:17】
『御怒りの大いなる日が来たのだ。だれがそれに耐えられよう。」』
再臨の起こる日は、『御怒りの大いなる日』であると共に、喜ばしい救いの日でもある。その日は、選ばれていなかった不幸な者にとっては災いの日だが、選ばれている幸いな者にとっては至福の日である。ここで山や岩にさえ助けを求めている哀れな者たちは、当然ながら不幸な者たちであった。もし彼らが不幸な者たちでなければ、このようなことは言っていなかったであろう。むしろ、詩篇に書かれているように『これは、主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。』(118篇24節)などと言っていたであろう。実際、幸いな者たちにとって、この日は正にこのように言うに相応しい日であった。
第9章 ⑥7章:間奏―神の配慮と耐え忍んだ者に与えられる天での恵み
このような挿入的な箇所が、ただでさえ難解な黙示録の難解さを更に増し加えている。何故なら、このような挿入がされているために、人間の理性は滑らかな解釈を妨げられ、より多角面からなされる考究を要求させるからである。文句を言っているわけではないのだが、もし黙示録が福音書や創世記のような記述の流れを持っていたとすれば、ここまで黙示録が難しく感じられることはなかったであろう。このような挿入によりこの文書の難解さが格段に増されているのは、やはりこの文書が、解読できる者にだけ解読されたらよいという文書だからである。神は、黙示録がほんの一部の者にだけ理解されたらよいと思っておられるのではないかと私には感じられる。だからこそ、このように恐ろしいほどの難解さがそこには見られるのではなかろうか。実際、今まで黙示録を十全に理解したことのある人間は、一人すらもいなかった(※)。しかし、黙示録を究めたいと願う者は、たとえこの文書が難解であったとしても、それを理解できるようにと神に求めなければいけない。そうすれば、その願いが聞かれ、この文書を理解できるようにもなるであろう。『求めよ。さすれば与えられん。』というキリストの御言葉は、無意味に語られたのではないのである。
(※)
それゆえ、この黙示録は相対性理論やその他の難しい理論などよりも遥かに難解である。それらの高度な理論は少なからぬ人が理解できているが、黙示録のほうは理解できている人がまったくいないからである。
[本文に戻る]
【7:1】
『この後、私は見た。4人の御使いが地の四隅に立って、地の四方の風を堅く押え、地にも海にもどんな木にも、吹きつけないようにしていた。』
『地の四隅に立って』いた『4人の御使い』とは、全世界に働きかけるべく定められていたある4人の御使いのことである。何故なら、この御使いが立っていた『地の四隅』とは、すなわち東西南北であり、全世界のことだからである。聖書において「4」とは世界を指しているのである。この4人の御使いは9:14でも出てくるが、恐らく良き御使いではないと思われる。何故なら、9:14の箇所でこの御使いは『つながれている』と言われているからである。繋がれている、つまり拘束されているというのであれば、どうしてそれが良き御使いなのであろうか。悪しき御使いが拘束されているというのであれば誰でも納得できるが、良き御使いが拘束されているというのはどういうことなのか。それはあり得ないことである。笑うべきことを我々は軽率にも考えるべきではない。また、この4人の御使いは、サタンという最高指揮官に従属する隊長的な御使いであったと思われる。何故なら、この4人の御使いは『2億』(9:16)の騎兵を指揮しているからである。そのような無数の騎兵を使って、この4人の御使いは多くの害をもたらすのであるから、この御使いが単なる並の御使いだったとは思えない。ところで、カルヴァンも言うように「神は、人間を罰するために、時に悪い天使のはたらきを利用され」(『新約聖書註解Ⅷ コリント前書』10:10 p232 新教出版社)る、ということを言っておきたい。この理解は黙示録の理解にためには、是非とも持っているべき理解である。
『地にも海にもどんな木にも』とは、全世界のことである。これは、地や海や木と言うことにより、何か別の存在を象徴的に表わしているのではない。つまり、これは文字的また物質的に捉えるべきものである。また、ここでは天が含まれていない。何故なら、この4人の御使いは天に害を与えることまでは許されていなかったからである。彼らが権能を有しているのは、この地上世界だけであった。御父と御子と御霊がおられる場所であり、長老たちと4つの生き物と無数の御使いたちが存在している場所が、これらの御使いたちによって損害を受けるなどということは、あり得ないことである。だから、この4人の御使いたちが地や海や木、すなわち世界に害を与えた時、天の場所は安泰であった。
『地の四方の風』とは、ユダヤが滅ぼされることを意味している。すなわち、ユダヤは滅びの風が吹きつけられることにより、神の御前から吹き払われ消し去られるのである。聖書において「風が吹きつける」とは、裁かれるべき悪しき者どもに害が与えられて滅亡することを意味している。それは次のように書かれていることから分かる。『悪者は、それとは違い、まさしく、風が吹き飛ばすもみがらのようだ。それゆえ、悪者は、さばきの中に立ちおおせず、罪人は、正しい者のつどいに立てない。…悪者の道は滅びうせる。』(詩篇1篇4~6節)『わが神よ。彼らを吹きころがされる枯れあざみのように、風の前の、わらのようにしてください。…彼らがはずかしめを受け、滅びますように。』(詩篇83篇13、17節)『彼らを風の前のもみがらのようにし、主の使いに押しのけさせてください。彼らの道をやみとし、また、すべるようにし、主の使いに彼らを追わせてください。』(詩篇35篇5~6節)『わたしは、彼らを、荒野の風に吹き飛ばされるわらのように散らす。』(エレミヤ13章24節)『東風のように、わたしは彼らを敵の前で散らす。彼らの災難の日に、わたしは彼らに背を向け、顔を向けない。』(エレミヤ18章17節)風=裁き、遺棄、滅び、散らされること。
この幻が示された時は、まだユダヤを神の御前から吹き払う風が『堅く押え』られていた。何故なら、この時はまだ「ユダヤが滅ぼされる時」が来ていなかったからである。だから、当時はユダヤがまだ存続している状態にあった。とはいっても、存続してはいるものの、死刑判決を受けて死刑を待つだけの囚人状態も同然だったのではあるが。しかし、その時に至ると、ユダヤに滅びの風が吹きつけるようになった。その時、ユダヤは地の四方から吹きつける裁きの風によって遂に滅亡してしまったのである。
【7:2~3】
『また私は見た。もうひとりの御使いが、生ける神の印を持って、日の出るほうから上って来た。彼は、地をも海をもそこなう権威を与えられた4人の御使いたちに、大声で叫んで言った。「私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはいけない。」』
『神のしもべたちの額に印を押してしまうまで』と言われているのは、つまり「定められた時が来るまで」という意味である。再臨の時までに救われるようにと決められている人々の数が達するまで、4人の御使いたちは、ユダヤの地を滅ぼすことが許されていなかった。その救われるようにと定められている人々の数が満ちることを指して、ここでは「印を押す」などと言われている。すなわち、この印というのは「選ばれた人たちに信仰が与えられるのを確認する」ということに他ならない。誰かが信仰を持ったのを御使いが確認したならば、その確認が「印」なのである。だから、この『生ける神の印』という言葉を、文字通り実際的に人々の額に印が押されることだと考えるべきではない。これは、黙示録の他の多くの箇所と同じように、象徴的に捉えるべき言葉である。黙示録の中には、このように人間の理性からすれば理解しがたい、しかし非常に高度で知的な言い回しが多く見られる。解読者が、神の御性質、聖書の性質、霊の性質、古代ユダヤ人の性質、象徴の性質を弁えていなければいないほど、そのような不可思議と言うべき言い回しを悟ることはそれだけ難しくなる。もし解読者が生きている時代の慣用によって黙示録の文章を悟ろうとするのであれば、それは無謀であり、お話しにならない。これは最近書かれた文書ではなく、いわゆる古文書なのである。黙示録を上手に解読したいと思う人は、このことをよく弁えなければいけない。
この4人の御使いによる損害の出来事は、紀元68年6月9日に実現された。すなわち、再臨により、ユダヤにおける地と海と木とは、ことごとく滅びの風によって滅ぼされることになった。その時、遂に神からの恐るべき風がユダヤに吹き付けたのである。そのようにして、ユダヤは神の御前から吹き払われ、永遠に遺棄され滅ぼされてしまった。それ以降、もはや、神の民としてのユダヤ人はどこにも存在しなくなった。その時に吹きつけられた滅びの風は、実に凄まじいものであった。それは、本当に文字通り全てが吹き払われたと言ってよいほどの悲惨さであった。我々が歴史の中で既に見ている通りである。
さて、どうしてこの箇所に出てくる御使いは『日の出るほうから』登場したのであろうか。この御使いが日の出るほうから出てきたのは、この御使いの登場が、キリストの再臨を暗示しているからである。聖書においてキリストは『太陽』(マラキ4章2節)として象徴されているが、この真の太陽であられるキリストがその再臨により人々の前に現われるのは、実際の太陽が日の出るほう、すなわち東の方角から上がって来るのに例えることができる。この御使いが登場したのは、地や海や木に害が与えられる時に起こるキリストの再臨を示すためであった。だからこそ、この御使いは、義の太陽なるキリストが人々の前に実際の太陽が現われるかのようにやがて現われることを示そうとして、太陽の出るほうから上がって来たわけである。つまり、この御使いの登場は、キリストの再臨を予表している。
【7:4~8】
『それから私が、印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されていて、14万4千人であった。ユダの部族で印を押された者が1万2千人、ルベンの部族で1万2千人、ガドの部族で1万2千人、アセルの部族で1万2千人、ナフタリの部族で1万2千人、マナセの部族で1万2千人、シメオンの部族で1万2千人、レビの部族で1万2千人、イッサカルの部族で1万2千人、ゼブルンの部族で1万2千人、ヨセフの部族で1万2千人、ベニヤミンの部族で1万2千人、印を押された者がいた。』
ここに出てくる『14万4千人』の『印を押された人々』とは、贖われるようにと定められていた人たちのことである。彼らこそ、真のイスラエル、影の本体である実体としてのイスラエル、すなわち『神のイスラエル』(ガラテヤ6章16節)である。というのも、ルターも言うように「イスラエルの民は信仰において集まる霊的な民の予表であった」(『ルター著作集 第一集 3』ローマの教皇制について p136:聖文舎)からである。肉のユダヤ人は、信仰を持たない限り、もはや神のイスラエルではなく、アブラハムの子孫でもない。『ですから、信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい。』(ガラテヤ3章7節)とパウロが言った通りである。霊的に言えば、彼らは神の民ではなく、サタンの民なのである。サタンの民であるからこそ、彼らはタルムードなどを信じ、律法に逆らい、愚かなことを考え、自分たちこそが世界を支配しようなどと無駄な計画を試みているのである。それゆえ今や、キリスト・イエスにつく者たちは、誰でも例外なくアブラハムの子どもたちであり、真の意味におけるイスラエル12部族である。影に過ぎなかったイスラエルの12部族は、既に神の御前から選民としての地位を奪われている。事柄は霊的に捉えなければいけない。
ここで各部族が『1万2千人』と言われているのは、「12」×「1000」(10×10×10)である。「12」は選ばれていることを示し(※)、「1000」は完全数10の3乗だから最高に完全であることを示す。つまり、この『1万2千人』とは、神が贖われるようにと定められた聖徒たちにおけるその選びが完全であって、その選びには少しの間違いや行き過ぎもないことを意味している。その数字が12集まった『14万4千』という数字を実際的な数字であると捉える人がいるが、それは誤っている。何故なら、再臨の際に天から降りて来る聖徒たちは『千万』(ユダ14節)だと言われているのだから、実際に14万ちょっとしかいないというのは少し無理があるからである。もし実際に14万4千人に聖徒の数が限定されていたとすれば(これはあまりにも愚かしい理解である)、エノクは『千万』などとは言わなかったであろう。また、この『14万4千』という数字が、贖われる者における多さあるいは少なさを示していると考える人もいるが、これも誤っている。というのも、この『14万4千』という数字からは、それが多いのか少ないのか判断できないからである。この数字から数の多さや少なさを判断する人は、判断の基準が聖書の御言葉にはなく、ただ感覚的に「多い」あるいは「少ない」と考えているに過ぎない。この数字は、やはり神の選びにおける完全性を象徴的に言い表わしていると考えるべきであろう。すなわち、私がこの節で述べた通りに考えるのが望ましい。何故なら、実際に神のその選びは完全であって、正に12(=選び)×1000(=最高に完全)と表現するに相応しいのだから。この『14万4千』という数字は、そのように神の選びにおける完全性を意味しているのだから、我々は、この数字を特別な数字として認識すべきであろう。これは明らかに単なる普通の数字ではない。まさか、この数字が取るに足らない普通の数字であると捉える人は読者の中にいないとは思うが。
(※)
この数字が「選び」を意味しているというのは、神の定められたイスラエルの部族が全部で12ということや、キリストに選ばれた使徒の数が12人であったということから、そのように言うことができる。神がヨルダン川の真中から取らせた石の数も12であった(ヨシュア記4:1~9)。大きな町ニネベにいた人間の数も『12万以上』(ヨナ書4章11節)いたと書かれているが、これも12だから、ニネベが救われるように選ばれていたということを示している。私の知る限り、「7」や「8」や「10」と違って、今までこの「12」という数字の意味に言及する人はあまり見られなかったが、これが神による定めや選びを意味する数字であるのは間違いない。カルヴァンのルカ10:1の註解を見ると、どうやら彼もこの数字は「選び」を意味していると考えていたらしく見える。
[本文に戻る]
ここでは、かつて12部族に属していたダン族は書かれていない。その代わりに、マナセの部族が12部族として書かれている。ダンが書かれていないのは、イスラエルから断ち切られたからである。同様にエフライム族もイスラエルから断ち切られた(※)。だから、ここでエフライム族は12部族の中に含まれていない。ここで記されているのが、イスラエルにおける永遠の12部族である。
(※)
聖書は言っている。『エフライムは打たれ、その根は枯れて、実を結ばない。』(ホセア9章16節)『エフライムは主の激しい怒りを引き起こした。』(同12章14節)『エフライムは、バアルにより罪を犯して死んだ。』(同13章1節)『エフライムの人々は、矢をつがえて弓を射る者であったが、戦いの日には退却した。彼らは、神の契約を守らず、神のおしえに従って歩むことを拒み、神の数々のみわざと、神が見せてくださった多くの奇しいこととを忘れてしまった。』(詩篇78篇9~11節)『わたしは、かつて、…エフライムのすべての子孫を追い払った』(エレミヤ7章15節)。これらの御言葉から、エフライム族は裁きとしてイスラエルから取り除かれたことが分かる。
[本文に戻る]
【7:9】
『その後、私は見た。見よ。あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから、だれにも数えきれぬほどの大ぜいの群集が、白い衣を着、しゅろの枝を手に持って、御座と子羊との前に立っていた。』
『大ぜいの群集』とは聖徒たちを指す。彼らが『白い衣を着』ていたということについては、今まで何度も述べられたことだから、もう説明しなくてよいであろう。彼らが『しゅろの枝を手に持って』いたのは、彼らの持つ権威と尊厳を象徴している。天上の聖徒たちは『永遠に王』(22:5)だから、権威と尊厳を示す棕櫚の枝がその手に握られていたのは、そのような存在に相応しいと言える。
天に入ることのできた贖われた聖徒たちは『だれにも数えきれぬほど』に多かった。つまり、天国に入るようにと定められている人たちは、数多いということが分かる。これはエノクが再臨の時には天から『千万』(ユダ14節)の聖徒がやって来ると預言したことと適合している。『千万』とは、すなわち『だれにも数えきれぬほどの大ぜいの群集』でなくて何であろうか。天国の聖徒の数が少ないなどと考えるのは誤っている。
天では『あらゆる国民、部族、民族、国語』の人たちが見られると、ここでは教えられている。天国にいる聖徒たちは、誰でも天国という同一の国籍を持っているのだが、しかし地上に生きていた時には、それぞれ異なる国籍を持っていた。すなわち天国には、元ギリシャ人も、元ローマ人も、元カルタゴ人も、元ユダヤ人も、元スパルタ人も、元エジプト人も、元エチオピア人も、存在している。つまり、天国においては一つの国籍しかないのだが、そこにいる人たちは実に多様性に満ちている。それはアメリカに住まうアメリカ人が、誰でもアメリカ国籍を持ってはいるものの、色々な人種の人が存在しているのと同じことである。このような天国の状態には、一と多の原理が表われており、そこには三位一体神の性質が豊かに反映されている。周知のように、我々の神は一人でありながらその中には三つの位格が存在し、一でありながら多でもあられるお方である。そのような神の性質を天国が反映していることは、実に喜ばしいことである(※)。天国において、このような神の三一性が反映されていないというのは、あり得ないことであった。すなわち、天国において単一もしくは少しだけの人種しか存在していないというのは、神の御心に適わないことであった。何故なら、その場合、天国はもっとも神の性質を反映すべき場所でありながら、神における一と多の性質を何も反映していない場所だということになっていたからである。
(※)
21世紀現在におけるアメリカにも、このような三一性があるが、それは喜ばしい状態であると言って良い。アメリカ人という一つの国民がそこにはいるものの、人間の内容は多様性に満ちている。これは日本のような単一民族の国家とは違い、神の性質がより豊かに表わされている。だからこそ、アメリカは世界でもっとも繁栄しているのであろう。
[本文に戻る]
このような天国の場面が示されたのは、聖徒たちに希望を抱かせるためであった。ここに示されている天国の場面は、地上にいる聖徒たちがやがて体験することになるものであった。このような場面を示されたならば、やはり聖徒たちはやがて自分が行くことになる天国を期待するようになり、その期待が信仰の忍耐へと繋がるようにもなる。ヨハネがこの文書を書き送った時の聖徒たちには、もう間もなく患難が到来することになっていた。それはキリストもマタイ24章の中で言っておられたユダヤ戦争の時期における苦難のことである。神は、このように天国の場面をあらかじめ示されることで、そのような苦難のために聖徒たちが霊的な「備え」をできるようにして下さったのである。
【7:10】
『彼らは、大声で叫んで言った。「救いは、御座にある私たちの神にあり、子羊にある。」』
人間が救われるのは、父なる神と子なるキリストによる。それは、キリストが救いにより与えられる永遠の生命について、次のように言われた通りである。『その永遠のいのちとは、彼らが唯一のまことの神であるあなたと、あなたの遣わされたイエス・キリストとを知ることです。』(ヨハネ17章3節)救いに選ばれていた地上の聖徒たちは、自分を救って下さった存在を口で言い表わしはするが、地上にいる間は、まだその存在の前にいるわけではない。しかし、天上の聖徒たちは地上の聖徒とは違い、自分の口で言い表わす救いを与える存在を、目の前でありのままに見る。ここで天上の聖徒たちが『御座と子羊との前に立っていた。』と書かれている通りである。
贖われた彼らが、このように大声で言うのは当然のことであった。何故なら、彼らが贖われて天に入れたのは、神とそのキリストが与えて下さった救いのゆえだからである。もしその救いが与えられていなければ、彼らは天でこのように言うこともできず、地獄の灼熱に投げ込まれて『泣いて歯ぎしり』(マタイ25章30節)するばかりであった。だから、もし彼らがこのように言わないとすれば、それはあまりにも大きな忘恩であった。彼らは、天において、永遠にこのように神とキリストによる救いを言い表わし続ける。それは、この世にいる誰かが自分を助けてくれた命の恩人のことを一生涯決して忘れず、いつも「今の私の命はあの人のゆえにあるのだ。」と口にするのと同じである。また、天にいる贖われた聖徒たちは、このように救いを言い表わし続けるのを苦とせず、むしろそれを喜びとする。何故なら、天の聖徒たちは『主をおのれの喜びと』(詩篇37篇4節)するからである。だから、この聖徒たちの場合、主の救いを口にして言い表わさないほうが、かえって苦しみをもたらす。天上の住民たちは、この世における肉的な人間とは、まったくその感覚が違うのである。
【7:11~12】
『御使いたちは、御座と長老たちと4つの生き物との回りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し、神を拝して、言った。「アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが、永遠に私たちの神にあるように。アーメン。」』
天では、御使いたちも、聖徒たちと同じように神を崇拝する。この御使いたちも、聖徒たちと同じように『主をおのれの喜びと』している。誰がこれを疑うであろうか。だから、彼らも神への崇拝を喜びつつ行なうのであって、それを行わないとかえって苦痛がもたらされることになる。ここでその御使いたちが神に帰しているのは全部で「7」であって、それは「7」だから、彼らが神に帰しているものが非常に良いものだということを意味している。この御使いたちは5:12の箇所でも神に7つの良きものを帰しているが、我々が今見ている箇所とは一つだけ良きものの内容が異なっている。すなわち、この箇所には『富』が語られていないが、5:12の箇所では『感謝』が語られていない。しかし、この2つのものがどちらも神に帰されねばならないものであるということは何も変わらない。この富と感謝以外については、どちらの箇所も同じ内容となっている。我々も、敬虔な心を持って神に全ての良きものを帰さねばならない。あらゆる良きものは全て神から出るのだ。『すべての良い贈り物、すべての完全な賜物は上から来るのであって、光を造られた父から下る』(ヤコブ1章17節)と使徒が言う通りである。そうであれば、どうしてその良きものの発出者であられるお方に、その良きものを帰さなくていいはずがあるであろうか。そのようにしない者は、鈍感であり、無知であり、道理を弁えていないと言わねばならない。
ところで、ここで御使いたちは天の場所において『立っていた』と書かれているが、天とは重力が存在する場所なのであろうか。というのも、『立っていた』のであれば、重力で下に引きつけられているということにもなるからである。宇宙空間のように重力がない場所であれば、宙にぷかぷかと浮かんでいるのだから、真っ直ぐな姿勢を取っていたとしても『立っていた』と言うことは難しいと感じられる。また御使いたちが立つ地面のような場所が、天にはあったのであろうか。もし彼らの立つ地面があったとすれば、天とは重力を持つ地球のような球体なのであろうか。すなわち、その重力を持つ球体に面している地面に御使いが立っていたのであろうか。また御使いは、その翼によって宙に浮かんでいるのではないのか。全ての御使いたちが、翼を休めて、天にある地面に立っていたのであろうか。私は言うが、このような疑問は、検討すべきものではない。何故なら、ここで示されているのは天上の世界のことであって我々には計り知れず、また神は言わば母親が幼児に片言で語りかけるようにして我々に天上のことを示しておられるからである。聖書において、人間が分かりやすいようにと、地上的また人間的な言い方や表現を持って語られている箇所は非常に多くあり、今までこのことについては多くの教師たちが教えてきたことである。そもそも地上に住む我々が、知ろうにも知りえない天上のことを知ろうとするのは、無理な話である。このようなことについて詳しく知れるというのであれば、確かに知れたほうがよいのは言うまでもないが、しかし我々にとってこのようなことは知り得ないことである。もし好奇心に突き動かされて無理にでも探ろうとするのであれば、その人はあのディオニシウスのような無謀を冒すことになろう。我々は、そのようにならないように注意すべきである。我々は自分が地上の人間であって、天上が測り知れない場所であるということを、よく弁えねばならない。
【7:13~14】
『長老のひとりが私に話しかけて、「白い衣を着ているこの人たちは、いったいだれですか。どこから来たのですか。」と言った。そこで、私は、「主よ。あなたこそ、ご存じです。」と言った』
このように長老がヨハネに話しかけたのは、自分の尋ねていることが分からなかったからではなく、ヨハネに教えるためであった。長老ともあろう存在が、『白い衣を着ているこの人たち』について知らないはずが、どうしてあるであろうか。これは、大人が10歳にもならない子どもに何かを指差して、「ねえ、あれは何なのかな?一体どういうものなんだろう?」などと、そのことを本当は知っているにもかかわらず、あたかも知らないかのように聞くふりをするのと同じことである。だから、我々はここで長老がヨハネにこのような仕方で尋ねているのを不思議がるべきではない。この長老にとって、ヨハネは小さな子どもも同然だったからである。もしこの長老のやり方を不思議がるべきだとすれば、どこかにいる大人が子どもにこのような仕方で尋ねることも同様に不思議がらなければいけないことになってしまうであろう。
ヨハネは、どうやら『白い衣を着ているこの人たち』のことをよく知らなかったように思われる。何故なら、ヨハネは長老の質問に対して『主よ。あなたこそ、ご存じです。』と言っているからである。しかし、本当は知っていながら、あえてこのように返答したということも考えられる。それは、せっかく教えようとして質問してくれた長老の面目を保つためである。使徒であるヨハネが、老人を敬えと命じる律法(※)を知っていたことは誰も疑えないことである。もしヨハネが白い衣を着ている人たちのことを知っているというので、「知っています。この人たちは云々」などと答えていたとしたら、せっかく教えようとして質問してくれた長老の善意に泥を塗ることになってしまうのである。それは明らかにレビ19:32の律法に違反することである。というのも、そこには老人である相手を立てる敬老の精神が見られないからである。しかし、この2つのうち、どちらが本当だったかということは、ヨハネ本人に直接聞かない限りは分からない。だが、別にどちらが本当だったとしても、黙示録の理解に重大な影響を及ぼすことはないから、その点について我々は心配しなくてもよい。
(※)
『あなたは白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない。』(レビ19章32節)
[本文に戻る]
ここでヨハネは長老を『主』と呼んでいる。はて、この長老は主なるキリストなのであろうか、それともヨハネがこのように長老を呼んだのは間違っていたのであろうか。まず、この長老はキリストではない。何故なら、この長老は、子羊なるキリストの前にひれ伏しているからである(4:8)。また、ヨハネがこのように長老を呼んだのも間違ってはいなかった。何故なら、この呼びかけに対し、長老は何も注意していないからである。ヨハネが御使いを拝もうとした時は注意されているが(22:8~9)、ここでは注意されていないのだから、ヨハネがこのように言ったのは何も問題なかったということである。ヨハネがここで『主よ。』と呼んだのは、単に長老を教え主として取り扱っているに過ぎない。つまり、この呼びかけは「あなたこそ私を教えてくださる教えの主体者です。」という意味に他ならない。もしヨハネがこの長老を本当の意味における主として取り扱っていたとすれば問題だったが、そうではない。だから、ヨハネはここで変なことを口にしたのではなかった。もしヨハネが被造物に過ぎない存在である長老を『主よ。』と言ったのが問題であるとすれば、あのサラをも問題とせねばならなくなってしまう。というのも、サラも人間に過ぎない『アブラハムを主と呼んで』(Ⅰペテロ3章6節)いたからである。
【7:14】
『すると、彼は私にこう言った。「彼らは、大きな患難から抜け出て来た者たちで、その衣を子羊の血で洗って、白くしたのです。』
『大きな患難』とは、ネロによる42ヶ月の苦難のことである。このいわゆる「大患難」が未だに起きていないと信じている聖徒は、あまりにも多い。あまりにも多いというより、全ての聖徒がそのように信じているといってよい。しかし、そのように信じるのは誤りである。それは聖書の否定に他ならない。何故なら、この大患難も含めて黙示録では『すぐに起こるはずの事』(1:1)が示されているからである。無知に基づく愚かしい誤謬は、聖徒の中から除き去られよ。つまり、ここでは大きな患難に続く再臨の後で起こることが示されている。要するに、この箇所では「大きな患難に耐えるならば、再臨が起こった後、やがて天国に至れるであろう。」ということが言われている。それは、先にも述べたように、大きな苦難が待ち受けている聖徒たちに天国を期待させるためであった。だから、このような光景が示されたのは無意味なことではなかった。
『その衣を子羊の血で洗って、白くした』とは、究極的な救い、すなわち身体の贖いのことを意味している。確かに天国に入れられた聖徒たちは、罪の残滓がまだある古い身体から解放されて、まったく罪を犯さない新しい御霊の身体に与かれるようになる。それはキリストの血による贖いが、究極的な意味において適用されることである。つまり、『その衣を子羊の血で洗って、白くした』とは簡単に言えば「身体の切り替え」のことである。
【7:15】
『だから彼らは神の御座の前にいて、聖所で昼も夜も、神に仕えているのです。』
『聖所』とは、神による天の住まいのことである。贖われて天に入れられた者たちは、この聖所で永遠に至るまでも主なる神に仕える。これは本当に素晴らしいことである。何故なら、人間は神に仕えて服従するためにこそ創造されたからである。それは、ソロモンが『神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。』(伝道者の書12章13節)と言った通りである。当然ながら、これは我々の未来のことでもある。聖徒であれば、誰でもやがて天に導き入れられ、そこにある聖所で神に仕えることになる。これはあまりにも大きな恵みである。だから、聖徒である者はこのことを覚えて喜び、主なる神の御前に日々、霊に燃えて歩んでいくべきであろう。我々の人生の行き着く先は、天にある神の聖所なのである。
『そして、御座に着いておられる方も、彼らの上に幕屋を張られるのです。』
神は、天にいる聖徒たちを、ご自身の聖なる幕屋、つまり永遠の住まいとされる。モーセたちが作った手作りの幕屋や、ソロモンによる石造りの神殿は、神の選ばれた永遠の住まいではなかった。神の御心は、聖徒たちをこそ永遠の幕屋また神殿とされることであった。だから、神は天において聖徒たちという幕屋また神殿のうちにとこしえに至るまでも歩み続けられる。このようにして、神が言われた『わたしの聖所を彼らのうちに永遠に置く。わたしの住まいは彼らとともにあり、わたしは彼らの神となり、彼らはわたしの民となる。わたしの聖所が永遠に彼らのうちにあるとき、』(エゼキエル37章26~28節)という言葉は、いついつまでも実現され続けることになる。手作りの幕屋と石による神殿が廃止されたのは、正にこれが理由であった。そのような理性なき神の住まいは、言わば「仮の住まい」のようなものであって、聖徒たちという真の幕屋、真の神殿を予表する「影」に過ぎなかったからである。今やもうその真の神の住まいが建てられているのだから、神は、かつての住まいをもはや必要としておられない。神がユダヤ人たちにエルサレム神殿の建設をお許しにならないのは、これが理由なのであって、それゆえこれからもそのような石造りの神殿が復活させられることはないであろう。それは、時間を無理矢理に捻じ曲げて逆行させるようなものである。イスラエル首相のデイヴィッド・ベン=グリオンは1962年に声明の中で、「イザヤの預言どおりエルサレムでは国連が寺院を建設し、…」などと言ったが、この言葉が実現されることは永遠にないのだ。
【7:16~17】
『彼らはもはや、飢えることもなく、渇くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら、御座の正面におられる子羊が、彼らの牧者となり、いのちの水の泉に導いてくださるからです。』
天にいる贖われた聖徒たちは、キリストにおいて生命の水を飲むことができ、永遠に生き続けることになる。これこそ、贖われるようにと選ばれていた聖徒たちに対する、キリストの御心であった。キリストは、このために、信じる者たちに永遠の生命をお与えになったのである。その永遠の生命を受けた聖徒たちは『もはや、飢えることもな』い。何故なら、彼らにとってキリストこそが永遠のパンだからである。それは、『わたしは、天から下って来た生けるパンです。だれでもこのパンを食べるなら、永遠に生きます。』(ヨハネ6章51節)とキリストが言われた通りである。また彼らは『渇くこともな』い。何故なら、天の聖徒たちは、永遠にキリストにおいて潤されるからである。また彼らは『太陽もどんな炎熱』にも打たれることがない。何故なら、天には『もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない』(黙示録21:4)からである。もし天が、飢え、渇き、太陽やその他の炎熱が害をもたらすような場所であったとすれば、そこは天国とは言えない。というのも、そのような場所は、我々が今現在生きているこの地上とほとんど大差ないからである。
天にいる贖われた聖徒たちについて言われているこの部分は、次の聖句と対応している。『彼らは飢えず、渇かず、熱も太陽も彼らを打たない。彼らをあわれむ者が彼らを導き、水のわく所に連れて行くからだ。』(イザヤ49章10節)『主は私の羊飼い。私は、乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、いこいの水のほとりに伴われます。』(詩篇23篇1~2節)
【7:17】
『また、神は彼らの目の涙をすっかりぬぐい取ってくださるのです。」』
神は、天に入れられた聖徒たちの涙を拭い取って下さる。そこには、神の慰めと恵みとが充満している。何故かと言えば、天国においては『以前のものが、もはや過ぎ去ったから』(黙示録21章4節)である。その天には、罪がなく、罪がないゆえに『のろわれるものは何もない。』(黙示録22章3節)というのも、罪があるからこそ、その罪に下されることになる呪いも存在するのだからである。罪がなければ、呪いも存在し得ない。また、そこにいる聖徒たちが本来であれば受けるべきであった罪に対する神の呪いは、既にキリストがご自身の上に背負って下さった。『キリストは、私たちのためにのろわれたものとなって、私たちを律法ののろいから贖い出してくださいました。』(ガラテヤ3章13節)とパウロが言っている通りである。つまり、天には神が不快とされるものが塵ほども存在していない。だからこそ、天国は神の慰めと恵みとに満ちているのである。そこは正に「パラダイス」と呼ぶべき場所であって、呪われるべきものが満ちているこの地上世界とはまったく違っている。
天における喜ばしい光景が描かれたこの部分は、次の聖句と対応している。『また、神ご自身が彼らとともにおられて、彼らの目の涙をすっかりぬぐい取ってくださる。』(黙示録21章4節)『わたしはエルサレムを喜び、わたしの民を楽しむ。そこにはもう、泣き声も叫び声も聞かれない。』(イザヤ65章19節)
第10章 ⑦8章1節:キリストによる7つ目の封印の解除
『子羊が第七の封印を解いたとき、天に半時間ばかり静けさがあった。』
これは一体どういうことであろう。第七の預言が欠如しているとでもいうのであろうか。それとも、神は、第七番目の預言だけ準備するのをお忘れになってしまったのであろうか。否、決してそのようなことはない。これは、天において静寂で平安に満ちた世界が永遠に続くという預言である。つまり、全ての預言が成就してから後、天では平和な世界が永遠に見られるようになるということである。そこには、もはや『私たちの兄弟たちの告発者』(12:10)が神の御前で聖徒たちを訴えることもなく、かつては存在していた悪霊どもも存在せず、ただ聖なる静寂が満ちている。その時間における永遠性が、ここでは『半時間』という言葉で言い表わされている。何故なら、永遠を言い表わすには半時間もあれば十分であるし、またそのぐらいの時間にしておくのが適切であったからである。ここで封印が解かれた際に何も起きていないのは、この預言において、全ての預言が完了済みとなったことを示すためであった。黙示録において最後に置かれている預言は、天国の場景である。それ以降の預言はない。だから、その場景に達したこの第7の預言においては、封印が解かれた際に何も起こることがなかったのである。
しかし、この第7の封印だけ、どうして他の6つの封印とは違った箇所に書かれているのか。それは、この7つ目の預言だけは、他の預言とは違っているということを、聖徒たちによく分からせるためでなくて何であろうか。確かに、7つある封印の預言の中で、この第7の預言だけが明らかに内容的な意味において異なっている。だから、このように一つだけ別の箇所に置かれたのは理に適っていたと言えよう。またそれは天における永遠の状態を特別扱いするという意味もあったと私には思える。そうすれば永遠の天に対して我々が特別な意識を持てるようにもなり、その特別な意識が、更なる天への憧れへと結びつくことにもなる。それは聖徒たちにとって間違いなく益である。そうであれば、このようにして第7の封印だけ別の箇所に置かれて特別扱いされているのは、聖徒たちが益を受けられるようになるためになされた神の配慮であったということになる。
さて、これにて封印が解かれることによる7つの預言は終わった。この封印による預言は、纏めるならば、一体どのようなものだったと言えるであろうか。これら7つの預言とは、すなわち、古い時代の終わりに起こる出来事が全体的・俯瞰的に語られた預言であったと考えればよい。そこでは古い時代の終わりの時期に起こる事柄が、全体的に記されているのであって、細部まで記されることに重きは置かれていない。それは、この7つの預言を見れば、誰でも分かることである。本で例えるならば、重厚な内容を持った本を短く纏めた「ダイジェスト版」のようなものだと思えばよい。だから、これらの預言を見ても、全体性は掴めるのだが、細かい部分まではよく分からない。しかし、それでも古い時代の終わりに起こる出来事の輪郭部分だけは明瞭に認識できるようにされている。神は、まずこのように大雑把に古い世の終焉を示されることから始められた。この封印における預言の箇所では、あたかも「これから大体こういうことが起こるのだよ。」とでも言われているかのようである。我々人間も、何か大きく衝撃的なことを語る際には、いきなり重厚であったり厳密であったりすることから始めるような語り方をせず、最初は大雑把に語ったり全体を把握させようとするものである。神も、預言の最初においてはそのようにされたのである。またそのようにされたのは、いきなり具体的な事柄を預言することにより、聖徒の心を最初から動揺させないという配慮の目的もあったのかもしれない。我々は『神は愛』(Ⅰヨハネ4章16節)であられることを知っている。
最後に、封印の解除による7つの預言がどのようなものであったか短く示すことにしたい。この黙示録という文書において、このような「おさらい」をするのは、より良い理解と認識のためには重要である。何故なら、この文書はただの文書ではなく、世界でもっとも難しい文書だからである。何かの学術書や教材において「おさらい」をする必要があるとすれば(そのようなことが必要な場合は少なくない)、尚更のこと、この黙示録ではそのような作業が必要である。私の経験から言わせてもらえば、ただでさえ難解なこの文書を、「おさらい」無しで豊かに理解できるようになると思ったら大間違いである。その人は黙示録をなめてかかっていると言われても文句はいえない。というわけで、これまでに見た封印解除による7つの預言は、纏めて示せば以下のようであった。
(Ⅰ:時間経過に則った記述)
【第一の封印】 キリストの再臨(6:1~2)/対応箇所…19:11~16
【第二の封印】 敵との戦い(6:3~4)/対応箇所…19:19~21
【第三の封印】 第一の復活(6:5~6)/対応箇所…20:1~6
【第四の封印】 ユダヤの破滅(6:7~8)/対応箇所…20:7~10
(Ⅱ:時間経過に則った記述)
【第五の封印】 天上における魂の復活(6:9~11)/対応箇所…20:1~6
【第六の封印】 旧約時代が終わる日の到来(6:12~17)/対応箇所…19:11~20:15
【第七の封印】 天における恒久的な平安の描写(8:1)/対応箇所…21:1~22:5
■期間:紀元68年6月9日~紀元70年
第11章 ⑧8章2節~9章21節:6つのラッパによる預言
この6つのラッパについての記述を章で区切ることだが、私だったら、8:2~9:21までを1章分として区切っていたであろう。このようにしたほうが、分かりやすいからである。こうした場合、1章分が長くなってしまうことになるが、分かりやすさのためであるから、仕方がない。この文書は、ただでさえ難解な内容を持っている。だから、現状のように章を短く区切るならば、より難解さが増し加わることにしかならない。何故なら、より細かく区切るのであれば、それだけ章に関して纏まった判断がしにくくなるからである。しかし、この6つのラッパを1章分として大きく区切るのであれば、それだけ纏まった判断が出来るようになり、難解さを無用にも増し加えることにはならない。もちろん、このようなことを言ったとしても、既に長い間保たれてきた現状の章分けを変えられることにはならないのではあるが。もし現状の区切りが変更されることにでもなれば、教会に大きな混乱と不便とが生じることになるのは間違いない。それゆえ、現状の区切りは、これからもずっと同じままに保たれることであろう。
それにしても、この7つのラッパについて記された箇所は、我々にとって実に驚くべき内容となっていると言わざるを得ない。そこには天上的な内容が満ちている。これは『人知をはるかに超え』(エペソ3章19節)ていると言うに相応しい内容である。このような内容になっているのは、もちろん、神がそれをお書きになられたからである。もし人間に過ぎない者がこれを書いたのであれば、このような天上性はそこに見られなかったであろう。実際、聖書の他の巻を除いて、このような内容を持つ文書は一つも書かれなかった。「シビュラの託宣」は黙示録と内容といい雰囲気といいかなり似てはいるものの、やはり黙示録とは霊性が天と地ほど違っているし、ニーチェの「ツァラストスゥラかく語りき」も意味深く神妙な内容ではあるが、これは単なる狂気の発露に過ぎないものである。アレスター・クロウリーの「おぼこ連のための物語」も黙示録を真似たかのようであり、そこには無数の比喩と象徴とが満ちているが、あまりにも人間的な匂いが感じられ、黙示録のような天上性は感じられない。彼の「霊視と幻聴」も実に秘儀的な文章が満ちているが、これは私の見るところではサタンの啓示以外ではない。何よりもクロウリーの作品は、バイセクシャルの男が書いたものに相応しく、低俗で下品である。だから、たとえそこに秘儀的な内容の文章が多く見られても、崇高で神聖な黙示録とは比べることさえできない。これら以外の文書でも、黙示録に比せられるべき文書は一つもない。これからも、神が何か新しい聖なる文書をお書きになられるというのでもなければ、このような文書が書かれることは恐らくないであろう。
【8:2】
『それから私は、神の御前に立つ7人の御使いを見た。彼らに7つのラッパが与えられた。』
『7人の御使い』に『7つのラッパ』が与えられたのは、神が示そうとしておられる預言のためであった。すなわち、この御使いが自分たちに与えられたラッパを吹き鳴らすと、神の預言が幻として啓示されるという仕組みになっていた。それは8:7からの箇所で、その啓示について記されている通りである。神は、今度はご自信の預言を示されるために「ラッパ」を用いられた。神は、何の楽器や現象も用いられることなく、ただ預言をそのまま幻として示されるようにもできたが、そのようにはなさらなかった。それは、ラッパを用いることで、預言を崇高また神聖たらしめるためであった。ラッパという楽器は、そのような目的のためには調度良い楽器だからである。また神は、既に7つの封印による預言をお示しになられたのに、その上更に7つのラッパによる預言をお示しになられた。つまり、これは預言の上に預言が重ねられていることになる。このラッパが吹き鳴らされると、全部で14の預言が示されたことになる。神がこんなにも多くの預言を示されたのは、ヨハネの時代の聖徒たちにやがて襲来することになる苦難の出来事があまりにも悲惨だったからであり、また神はご自身の聖徒たちが心の準備を行なえるように気遣っておられたからである。このように多くの預言が次々に重ねられるからこそ、これから襲来する苦難の悲惨さがよく理解されるようになり、また神の愛も豊かに感じられるようになるのだ。神はあらかじめ未来の出来事を啓示される方だから(アモス3:7)、このように預言を示さないということはあり得なかったし、また『神は愛』であるから、このように多くの預言を示すことで心の準備をさせないままでおくということもなさらなかった。もし神が再臨の直前に起こる出来事について少ししか預言されなかったとすれば、あまりその出来事における悲惨さが分からなかっただろうし、神もそのように大きな出来事が起こるにもかかわらず大いに予告されなかったのだから、「愛が少ないのでは」などと思われることになりかねなかった。
この『7人の御使い』がどのような御使いだったかということについては、よく分からない。しかし、この御使いがラッパを受けた御使いであると理解していれば、それだけで十分である。この御使いがガブリエルなのかラファエルなのかその他の御使いなのかと考察しても、分からないし、それを知れたとしても、あまり益にはならないであろう。もし益になったというのであれば、黙示録では、この御使いの詳細について、書き記されていたのではないかと思われる。
『7つのラッパ』も、詳細が何も書かれていないのだから、どのようなものだったかよく分からない。しかし、これも分からなかったとしても、特に問題にならない。私は分からないにもかかわらず無謀にも確定的なことを語って、好奇心の旺盛な詮索家を満足させるということはしたくない。
【8:3~4】
『また、もうひとりの御使いが出て来て、金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての聖徒の祈りとともに、御座の前にある金の祭壇の上にささげるためであった。香の煙は、聖徒たちの祈りとともに、御使いの手から神の御前に立ち上った。』
この御使いは、香と共に聖徒たちの祈りを神に捧げるようにと委任されていた。つまり、この御使いは聖徒たちの祈りを神に届ける媒介者であった。5:8の箇所では、長老たちが聖徒の祈りを神に届ける媒介者として描かれていた。つまり、神に祈りを届ける役割は、長老たちだけでなくここに出て来る御使いにも与えられていたのである。5:8のほうでは祈りそのものが香だと言われていたが、こちらのほうでは祈りと香とが別々に分けられている。これは一体どういうことか。これは、ただ表現だけ異なっており、どちらも、そこでは同一のことが言われていると考えるべきである。すなわち、5:8でもこの箇所でも、地上にいる聖徒たちの祈りは、神の前にとっては香のように喜ばしいものだということが示されている。5:8のほうでは祈りと香とが纏められて語られており、こちらのほうでは別々にされている。ただそれだけのことである。このようなことを考えると、黙示録が聖なる謎解きのように感じられてくるが、聖書に根ざし、よく考え、信仰による祈りを捧げるのであれば、この箇所であれ他の箇所であれ、必ずこの文書に隠された謎が分かるようになるということを読者には知ってほしい。黙示録の解明のために必要なのは、御言葉と信仰と祈りと、解明させて下さる神の恵みである。我々は、キリストが『だからあなたがたに言うのです。祈って求めるものは何でも、すでに受けたと信じなさい。そうすれば、そのとおりになります。』(マルコ11章24節)と言われたのを、よく心に留めるべきである。つまり、黙示録の解明を祈って求めるならば、必ず謎が解明されるようになるということである。
『祭壇』は既に6:9の箇所に出てきたが、そこを見る限りでは、その祭壇がどこの場所に位置しているのかよく分からなかった。しかし、この8:3では、この祭壇が天の神の御前に位置していたということが分かる。すなわち、これは地上に位置している祭壇ではない。
【8:5】
『それから、御使いは、その香炉を取り、祭壇の火でそれを満たしてから、地に投げつけた。すると、雷鳴と声といなずまと地震が起こった。』
『その香炉を取り、祭壇の火でそれを満たしてから、地に投げつけた』とは、聖徒たちの祈りが聞かれたがゆえに、神が地に働きかけられる、ということである。すなわち、聖徒の香しい祈りが祭壇を通して神に捧げられ、神がその香りを喜ばれるので、その祈りを地に実現させて下さるということが、ここでは言われている。ユダヤ戦争の際に起こる悲惨な出来事は、聖徒たちの祈りが聞き届けられたという一面もあったのである。ここで言われている『地に投げつけた』という言葉は、小さな言葉として軽んじられるべきではない。これは、よく認識されるべき言葉である。つまり、祈りが聞かれたことによるラッパの裁きは、地上において起こるのである。それは天において起こるのではない。もし天において起こるというのであれば、「天に投げつけた」と書かれていたことであろう。
ここで御使いが天の場所で捧げた聖徒たちの祈りは、前々から聖徒たちが捧げていた祈りであった。だから、ここでは遂に時至ってその祈りが実現させられることになる、と言われていることが分かる。聖徒たちが前々から大バビロンなるイスラエルに対する裁きのために祈り求めていた、というのはキリストが次のように言っておられた通りである。『まして神は、夜昼神を呼び求めている選民のためにさばきをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなたがたに言いますが、神は、すみやかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。』(ルカ18章7~8節)キリストがこう言われた通り、本当に神は聖徒たちの祈りを聞き入れられ、『すみやかに』ラッパにおいて預言された裁きをユダヤに注いで下さったのである。だから、これから見ることになる7つのラッパによる預言の出来事が、まだ実現していないなどと考えることはまったくできない。聖徒の香しい祈りが聞かれたからこそ、このラッパによる裁きが注がれることになる。つまり、まだ7つのラッパによる裁きが注がれていないというのであれば、聖徒たちがキリストの時代から捧げていた祈りは未だに聞き入れられていないということになってしまう。2千年間も祈りが聞き入れられていないと考えるのは、何と愚かしいことか。当然ながら、このラッパによる預言で示された出来事も、やはり『すぐに起こるべき事』(1章1節)であった。であれば、この預言が実現させられる原因となった聖徒たちの祈りは既に聞かれ、その預言はもうとっくの昔に実現していることになるのである。
『雷鳴と声といなずまと地震』とは、神の裁きと怒りを表わしている。聖書において、神の現臨と到来が起こる際には、このような事象が共に描かれるのが常である。これらの事象は、神の偉大な働きかけを崇高に演出するものである。神は、正に神らしく、神としての働きをなされるのである。もしこのような事象が伴っていなかったとすれば、神の働きが起こる際、何だか薄っぺらい出来事であると感じられることにもなっていた。『雷鳴』とは、神の裁きを示している。『声』とは、神の恐るべき御声を示している。『いなずま』とは、神の怒りを示している。『地震』とは、地が神に対して戦慄していることを、すなわち地さえも驚くような出来事が起こることを示している。ここではこれら4つの事象(雷鳴、御声、稲妻、地震)が描かれているが、『つむじ風』や『焼き尽くす火の炎』(イザヤ29章6節)などといった事象が描かれている箇所も存在する。それらのものも、もちろん、神の働きかけを大いに演出する事象である。
【8:6】
『すると、7つのラッパを持っていた7人の御使いはラッパを吹く用意をした。』
封印の解除によって示された預言と同じで、ラッパによる預言も一つ一つ順序正しく示される。もし7つのラッパを一挙に吹き鳴らすのであれば、預言が一挙に纏めて示されることになり、10人の話を同時に聞き分けたと言われる日本の聖徳太子でもない限り、明瞭に認識することはできなかったからである。神は、一つ一つしっかりとラッパによる預言が示されることを望まれた。それは分かりやすさのためであった。それは、Ⅰコリント14:33でも言われているように『神が混乱の神ではなく』、秩序の神だからである。
【8:7】
『第一の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、血の混じった雹と火とが現われ、地上に投げられた。』
まずラッパの吹き鳴らしについて記されている箇所(8:2~11:19)に多く出てくる『3分の1』という言葉の意味を、我々は知っておかねばならない。この『3分の1』とは、すなわちユダヤとその民を指している。何故ならゼカリヤ13:8~9では、次のように書かれているからである。『全地はこうなる。―主の御告げ。―その3分の2は断たれ、死に絶え、3分の1がそこに残る。わたしは、その3分の1を火の中に入れ、銀を練るように彼らを練り、金をためすように彼らをためす。彼らはわたしの名を呼び、わたしは彼らに答える。わたしは「これはわたしの民。」と言い、彼らは「主は私の神。」と言う。』火の苦しみにより試されると、その中にいる選ばれた者たちが『主は私の神。』と言うようになる人たち。それはユダヤ人でなくて誰であろうか。このゼカリヤ書の箇所では、ユダヤ人のことが『3分の1』と言われているのは間違いない。しかし、ユダヤが『3分の1』と言われるのは、どういった理由があるのか。何故、ユダヤは『3分の1』なのか。それは、アブラハムを通してユダヤ人に与えられると約束された地が『エジプトの川から、あの大川、ユーフラテス川まで』(創世記15章18節)だからである。まだ21世紀の今のようには世界の地形が知られていなかった古代において、エジプトの川(ナイル川)からユーフラテス川までの範囲は、世界の3分の1を占めると言ってよかった。これは今の時代では考えられないことだが、当時は認識されている世界の範囲が実に狭かったのだから、当時の感覚からすれば、この範囲を指して『3分の1』と言うのは何もおかしいことではない。我々は、古代人の地形認識が、今の我々のそれに比べて10分の1かそれ以下に過ぎなかったことを考慮する必要がある。だからこそ、その3分の1の地を約束されたユダヤ人たちが、黙示録では『3分の1』として言い表わされているのである。それゆえ、今の時代における一般的な地形認識に基づいて、この『3分の1』という言葉を理解しようとしても、それは出来ないことである。何故なら、今の感覚からすれば、アブラハムに約束された地は全世界の幾十分の1または幾百分の1の範囲としか思えないからである。このことからも分かるが、黙示録を理解したいと思われる方は、自分の時代の常識や知識を通して黙示録を解読しようとしてはいけない。そんなことをすれば、黙示録は永遠に解読できないままとなる。また、この第一のラッパの箇所を読んで、「これから人類の3分の1、つまり20億人ぐらいの人がやがて滅ぼされることになるのだ。終末は近い。」などと思う聖徒は多いはずである。私からすれば、このように思うのは愚かであり、何も黙示録を弁えていない。何故なら、この一つ目のラッパによる預言は2千年前に既に成就されており、『3分の1』とは文字通りの意味に捉えるべきではなくユダヤを指しているからである。だから、このような思い違いをしている聖徒は、自分の間違いを悟って、すぐにも悔い改めるべきである。もしパロのように強情になってこの預言が「すぐには起きない」預言なのだと言い張るのであれば、ヨハネがどうして黙示録で示されている幻は『すぐに起こるべき事』(22章6節)と言ったのか、私が納得できるように説明してほしいと思う。もちろん、強引に説明して私を納得させようとしても、ヨハネの言葉に歯向かうことになるだけなのは目に見えているのだが。私が今神の恵みにより述べたこと、すなわちこの『3分の1』という言葉がユダヤを意味しているということは、非常に重要であるから、もし読者が黙示録を解読したいと願うのであれば、必ずしっかりと覚え、忘れないようにせねばならない。そうしないと、黙示録を上手に理解できなくなってしまうであろう。
『血の混じった雹と火とが現われ、地上に投げられた。』とは、神の裁きにより、多くのユダヤ人が血を流すということである。『雹と火』により表示される神の裁きがユダヤの地に下されると、その裁きによりユダヤ人が大量に血を流すので、このように言われている。非常に難しく霊的な言い回しである。また、これは明らかにイザヤ28:2の預言と対応している。そこでは、こう書かれている。『見よ。主は強い。強いものを持っておられる。それは、刺し通して荒れ狂う雹のあらしのようだ。…主はこれを力いっぱい地に投げつける。』つまり、力強い主が裁きという名の雹をユダヤの地に投げつけると、そこにいるユダヤ人たちが裁きの雹に刺し通され、我々が今見ている箇所でも言われているように『血』が雹と結び合わされるということである。この『血の混じった雹と火』とは象徴的な表現だから、文字通りに捉えるべきではない。実際、ユダヤ戦争の時に、『血の混じった雹と火とが』天から落ちてきたということはなかった。しかし、神の裁きという雹と火であれば、本当に天から落ちてきたと言える。ここで言われている『雹や火』とは、神の裁きを象徴する言葉だから、黙示録を正しく解明したいと願う者にとっては覚えておくに値する。エゼキエル38:22の場合、雹や火の他に『豪雨』また『硫黄』も裁きを象徴する言葉として使われている。雹であれ火であれ豪雨であれ硫黄であれ、それらは神の裁きの恐ろしさと凄まじさを、物理的な現象や物体を通して示そうとしている。
『そして地上の3分の1が焼け、木の3分の1も焼け、青草が全部焼けてしまった。』
これはユダヤが裁きにより焼き尽くされるということである。既に説明されたように、この『3分の1』とはユダヤを指す言葉だから、地球全土における3分の1が焼かれることになるなどと考えてはいけない。ここでは『青草』だけが『3分の1』と言われておらず、『全部』と言われているが、この青草も『地上』や『木』と同じように『3分の1』であることは言うまでもない。この青草の部分では、単に『3分の1』という言葉が書かれていないだけに過ぎない。地上が『3分の1』で、木も『3分の1』であれば、それら2つのものに続く『青草』も同様に『3分の1』なのは確かである。つまり、これは言い方の問題である。語られる3つのもののうち、第3番目のものだけが『3分の1』と言われていないのは、第4のラッパの箇所でも同じである。そこでは、『3分の1は暗くなり、昼の3分の1は光を失い、また夜も同様であった。』(8:12)と書かれている。ここでも3番目に語られている夜だけが『3分の1』と言われていないが、夜も前の2つのものと同じように『3分の1』であったのは確かである。ただ、夜だけが『3分の1』と言われていないだけに過ぎない。神が、このように人間理性からすれば不思議な書き方をされたのは、黙示録の正しい解明を祈り求めない者たちを混乱させるためであった。黙示録を正しく悟れるようにと祈らない者は、祈らないから恵みを受けられず、どうしてここで『青草』だけが前の2つのものとは違う言い方をされているのか分からないので、大いに混乱してしまう。つまり、祈り求めなかったので、霊的な怠惰に対する報いとして正しい解明を得られないままに留められるのである。しかし、祈り求めるならば、神からの恵みをいただけるから、どうしてこのような言い方がされているのかがよく分かり、混乱に陥ることもない。祈るのである。そうすれば正しい解明が与えられる。私はルターと共にこう言おう。「あなたは自分の小さな部屋の中でひざまずき、正しい謙虚さと真剣さをもって神に祈願し、神があなたにその愛する御子によって聖霊を賜わるように祈りなさい。聖霊はあなたを照明し、導き、理解力を授けたもう。」(『キリスト教神秘主義著作集11 シュタウピッツとルター』(11)ルターのドイツ語全集版第一巻の序文 p192:教文館)
この預言は、既に成就している。確かにユダヤ戦争の際には、ユダヤにおける地も木も青草も、ことごとく焼き尽くされたと言ってよい。その恐るべき滅亡の光景は、今でもユダヤ人たちが忘れてはならぬ嘆きの日として思い返し続けるほどである。この惨状の度合いは、ヨセフスの書を読めば、よく分かる。彼は滅ぼされた後のユダヤについて、こう言っている。「こうして都を囲む城壁の他の部分はすべて徹底的に破壊されて平らにならされた。その結果、将来人がそこを訪ねても、かつてそこに人が住んでいたと信じられるような痕跡はもはや何も残されなかった。」(『ユダヤ戦記3』ⅤⅡ i1:3 p107:ちくま学芸文庫)このようにしてユダヤが滅ぼされ焼け野原とされたのは、神の裁きが下されたからであった。神の怒りが一挙に放出されると、このように一挙に滅ぼされてしまうことになるのである。あのソドムやゴモラも、そのようにして神の怒りの裁きにより滅ぼし尽くされてしまった。神の怒りと裁きは本当に恐ろしいものである。
ところで、パウロもこの第1のラッパの預言の内容と似たことをⅠコリント3章の中で言っているが、Ⅰコリント3章と第1のラッパの預言は対応しているのであろうか。確かにパウロも、第1のラッパの内容と同じように、火により木や草が焼かれてしまうと言っている。どちらも似たような内容のことが言われているので、この2つの箇所が対応していると理解する聖徒がいたとしても不思議ではない。そのパウロの言葉はこうである。『与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように、土台を据えました。そして、ほかの人がその上に家を建てています。しかし、どのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは、だれも、すでに据えられている土台のほかに、ほかの物を据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし、だれかがこの土台の上に、金、銀、宝石、木、草、わらなどで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現われ、この火がその力で各人の働きの真価をためすからです。もしだれかの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もしだれかの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自分は、火の中をくぐるようにして助かります。』(Ⅰコリント3章10~15節)結論を言えば、この2つの箇所は対応していない。確かにどちらも火で木や草が焼かれると言われており、非常に似通っているように感じられるのだが、そこで言われている内容は異なっている。何故そう言えるのか。まずパウロが言ったのは、火と共に来られる再臨のキリストにより聖徒たちの霊的な状態が試練にかけられる、ということであった。聖書は、キリストが火と共に天から再臨されると教えている(Ⅱテサロニケ1:7、イザヤ66:15)。その時に、『木、草』などといったこの世に属する思想や哲学などで自分の霊を養っていた聖徒たちは、キリストによる火の吟味により、それまでにしてきた苦労が全て台無しにされるものの、しかし天国には入ることが出来る。パウロが言いたいのは、こういうことであった。一方、第1のラッパの中で言われているのは、ユダヤの地が火で焼かれることについてである。またパウロが言っているのは、聖徒たちという人間だけを対象としている。場所のことは一切含まれていない。一方、第1のラッパでは、ユダヤの全体について言われている。すなわち、ユダヤの土地と民族全体、またそこにいる個人個人について言われている。それは単に人間だけを対象とした内容ではない。このように、この2つの箇所では、まったく異なることが言われている。少し記述の内容が似ているからといって、すぐ対応していると判断するのは、思慮なきことである。この2つの内容をよく考慮してみれば、その言われている内容が違っているということが、分かるはずである。黙示録には、このように聖書の他の巻の内容と似通っているものの実は内容的に異なっている、という箇所が少なくない。聖徒たちは判断を誤らないように注意せねばならない。
【8:8】
『第二の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、火の燃えている大きな山のようなものが、海に投げ込まれた。』
『火の燃えている大きな山のようなものが、海に投げ込まれた。』とは、ユダヤという山が神の怒りの炎に包まれ、神の国という高い場所にある崖から燃えながらにして突き落とされて下にある海に水没させられた、ということである。『山』はユダヤであり、『海』は異邦人である。つまり、神の怒りの攻撃によりユダヤという山は、異邦人という死の海の中へ棄てられたのである。そのようにして異邦人の中へ棄てられたユダヤ人は、異邦人と同一の地位に引き落とされてしまった。この預言は、明らかにエレミヤ書51:25~26の預言と対応している。そこには次のように書かれている。『全地を破壊する、破壊の山よ。見よ。わたしはおまえを攻める。―主の御告げ。―わたしはおまえに手を伸べ、おまえを岩から突き落とし、おまえを焼け山とする。だれもおまえから石を取って、隅の石とする者はなく、礎の石とする者もない。おまえは永遠に荒れ果てる。―主の御告げ。―』確かにユダヤという山は、神の御前と御国から追放されたので、今や神の御前において『永遠に荒れ果て』ており、霊的に言えば完全な異邦人である。それは、彼らが今に至るまで2千年もの間、呪われた状態で地の上を彷徨い続けている通りである。様々な国に散らされて彷徨い続けるとは、呪われているということでなくて何であろうか。律法の呪いについて記されている箇所で、『主は、地の果てから果てまでのすべての国々の民の中に、あなたを散らす。』(申命記28章64節)と書かれている通りである。この箇所は、エレミヤ書の預言を知らなければ、上手に理解することができない。もしエレミヤ書の聖句から助けを得ずにこの箇所を解釈しようとすれば、実際に天から燃える火の山が降ってくるとか、この火の山は巨大な隕石を象徴しているのではないかとか(これは、なかなか面白い解釈である)、おかしい解釈に陥りざるを得ない。聖句によらず、理性の感覚に基づいて解釈するから、そうなるのである。だから黙示録を正しく解釈したいと願う者は、聖書、特に旧約の預言に精通しておかねばならない。前にも述べたことだが、旧約の預言に精通していればいるほど、黙示録をより正しく解釈できるようになるであろう。
【8:8~9】
『そして海の3分の1が血となった。すると、海の中にいた、いのちのあるものの3分の1が死に、舟の3分の1も打ちこわされた。』
『海の3分の1が血となった。すると、海の中にいた、いのちのあるものの3分の1が死に』とは、ユダヤが、裁きによりその海においてさえ滅ぼされるということである。つまり、ユダヤに裁きが下されると、多くのユダヤ人が死に絶えるので、ユダヤは海から切り離されるという意味において海と共に滅ぼされるのである。この海とは、もちろんユダヤの西岸に面する地中海のことである。海にしては少し小さいと思えるかもしれないが、死海を含めてもいいかもしれない。裁きにより、ユダヤはこの地中海との関係性においても神の御前から消し去られたのである。
『舟の3分の1も打ちこわされた。』とは、再臨の際、ユダヤが低められるということである。『舟』とは、富や権威の象徴であって、傲慢な精神をも示している。キリストが再臨されると、ユダヤの高ぶった心は打ち砕かれて、萎れ、彼らは低められることになる。それは舟が打ち壊されるかのようである。このように彼らが低められてしまうのは、再臨されたキリストの威光が凄まじいからである。つまり、その威光の凄まじさに、ユダヤ人たちは圧倒されてしまうわけである。この再臨による舟の打ち壊しについて書かれている部分は、イザヤ2章の箇所と対応している。そこには次のように書かれている。『まことに、万軍の主の日は、すべておごり高ぶる者、すべて誇る者に襲いかかり、これを低くする。…タルシシュのすべての舟、すべての慕わしい舟に襲いかかる。その日には、高ぶる者はかがめられ、高慢な者は低くされ、主おひとりだけが高められる。』(2章12、16~17節)
この箇所も既に成就している。裁きの起きた際、ユダヤはその海と共に抹消されてしまったと言ってよい。無数のユダヤ人が死に絶え、その死んだユダヤ人たちは海との関係を失ったからである。彼らは海においても殺されたのである。また、再臨の際には、舟により表示されているユダヤ人の傲慢な心が打ち砕かれてしまった。というのは、キリストが再臨された時において、ユダヤの諸氏族は、キリストとその威光との前に嘆いたり泣いたりしたからである。ゼカリヤ12:10~14また黙示録1:7で、ユダヤ人はキリストを見て、皆嘆くであろうと言われている通りである。「嘆く」とは、すなわち『舟』において表示されるユダヤ人の高ぶった精神が打ち砕かれることでなくて何であろうか。
【8:10~11】
『第3の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、たいまつのように燃えている大きな星が天から落ちて来て、川々の3分の1とその水源に落ちた。この星の名は苦よもぎと呼ばれ、川の水の3分の1は苦よもぎのようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだ。』
『たいまつのように燃えている大きな星が天から落ちて来て』とは、御使いがユダヤに対する神の怒りの裁きを執行するということである。『星』とは、キリストも言っておられるように「御使い」を指す(1:20)。御使いは、神の裁きを召使いとして代行する役割を持った被造物である。イスラエルに対する疫病の裁きも、その執行が御使いに委任されていたのを、我々はⅡサムエル24:15~17の箇所で確認できる。神は、実際に下される裁きを、御使いを通して実現させられるのである。この御使いが『たいまつのように燃えている』状態だったのは、神の怒りの炎がこの御使いを通して、ユダヤを松明のように燃え上がらせるからであった。松明のように燃え上がるようにされるとは、ユダヤが神の燃える怒りで裁かれることでなくて何であろうか。これはゼカリヤ12:5の預言のことである。そこには次のように書かれている。『その日、わたしは、ユダの首長たちを、たきぎの中にある火鉢のようにし、麦束の中にあるたいまつのようにする。彼らは右も左も、回りのすべての国々の民を焼き尽くす。』つまり、ユダヤが神の燃える怒りで罰せられる時には、他の諸国も、ユダヤと同時に神の怒りを受けて燃え上がるようになるということである。この『たいまつのように燃えている大きな星』という言葉を、文字通りに捉えてはいけない。そのように捉えると、この箇所は永遠に理解できないであろう。月か火星が火で燃えながら地球に衝突するとでもいうのであろうか。それは、起こり得ないことである。
裁きを委任されたこの御使いが『苦よもぎ』と呼ばれているのは、この御使いを通して下される神の裁きが、あたかも苦よもぎでもあるかのような苦痛をもたらすからである。実際に苦よもぎが天から落ちてくるのではないから、注意しなければいけない。苦よもぎで汚染された水を飲んだかのような苦痛と死とをこの御使いがユダヤに裁きとして与えるとは、つまり、ユダヤが裁きにより滅ぼされて世界各地へと散らされるということである。これは霊的に捉えなければいけない。ここでは離散と滅亡のことが語られているのである。何故なら、この箇所と対応しているエレミヤ9:15~16の箇所では、次のように言われているからである。『それゆえ、イスラエルの神、万軍の主は、こう仰せられる。「見よ。わたしは、この民に、苦よもぎを食べさせ、毒の水を飲ませる。彼らも先祖たちも知らなかった国々に彼らを散らし、剣を彼らのうしろに送り、ついに彼らを絶滅させる。」』苦よもぎおよび悪い液体を口にするとは、すなわち『彼らも先祖たちも知らなかった国々に彼らを散らし、剣を彼らのうしろに送り、ついに彼らを絶滅させる。』ということだと、このエレミヤの預言の中では言われている。要するに、ここで言われているのは「ユダヤが殺され、散らされ、滅亡させられるのは、あたかもユダヤが苦よもぎで汚染させられた毒の水を飲んで多くの死と苦痛を味わうようなものだ。」ということに他ならない。
苦よもぎにより言い表わされているこの難しい預言も、既に成就している。紀元1世紀において、確かにユダヤの民はローマ軍によって大量に殺され、生き残った少数の者たちが世界各地へと散らされ、そのようにして神の御前から霊的な意味において絶滅させられたのだから、この裁きにおいて彼らは苦よもぎを口にするかのような死と苦しみを味わったといってよい。彼らは今も、この苦よもぎを食べ続けている。それは彼らが未だに2千年前に裁かれた時と変わらず世界各地に離散させられたままだからである。これからも、彼らは苦よもぎを食べ続けることであろう。つまり、相も変わらず彼らは離散の状態に留まり続けることであろう。
ここで出てくる『苦よもぎ』による苦しみと死は、チェルノブイリの大事件のことを指しているなどと言う人たちがいる。私は、今までにそのように言っている人たちを何人も見ている。何という盲目、何という愚かさ。このように言う者たちは、謙遜になってこの『苦よもぎ』が何を意味しているのか、神に祈り求めていない。だから、これがチェルノブイリのことだなどとおかしな解釈をするのである。ヨハネが、およそ2千年後に起こる大事件のことを、紀元1世紀のクリスチャンに向けて、ここで預言したとでもいうのか。馬鹿らしいことだ。あまりにも馬鹿らしいことだ。これはとてつもなく馬鹿らしいことなので、私はもうこれ以上、この狂った解釈については何も述べたくない。このような思い違いをしている人たちは、正しい解釈を神に祈り求め、そのように祈ったら、チェルノブイリのことなど忘れて、この箇所を一から解釈し直すべきである。
【8:12】
『第4の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、太陽の3分の1と、月の3分の1と、星の3分の1とが打たれたので、3分の1は暗くなり、昼の3分の1は光を失い、また夜も同様であった。』
これは、裁きにより、ユダヤ人からは太陽と月と星による光が奪われるということである。すなわち、これは多くのユダヤ人が死んで天にある灯りから切り離されるので、文字通り死という闇の中に移されることを言っている。死に移されるからこそ、もはや太陽と月と星の光が照らしてくれないという意味において暗くされるわけである。それゆえ、ここで言われている太陽と月と星という物体を、象徴的に捉えるべきではない。つまり、これは太陽がキリストを意味しており、星が御使いを意味しており、月が云々…、などというように捉えてはいけない。この箇所に出てくる物体は文字通りに捉えなければいけない。ここで『打たれた』と言われているのは、神の裁きが、太陽や月や星を通してユダヤに下されるという意味である。この言葉を読んで、太陽や月や星などの天体が神により物理的な衝撃を加えられるなどというふうに考えるのは誤っている。そのような物質的理解は肉的である。
実際、2千年前においてユダヤ人からは太陽と月と星による光が奪われて、この民は闇となってしまった。彼らの大部分はユダヤ戦争において死んだからである。その死んだユダヤ人から太陽と月と星の光が取り去られたと言うことは、実に正当な言い方である。死ぬとは、すなわち天にある光体が取られて闇になるということでなくて何であろうか。しかし、ユダヤ戦争で死なずに残された少数のユダヤ人と、そのユダヤ人の子孫である者たちには、この裁きが下されていないではないか、と思われる方がいるかもしれない。確かに彼ら残された者とその残された者の子孫においては、ユダヤ戦争が終わってからも、太陽と月と星が取り去られなかったのは明らかである。彼らは、今でもそれらの天体の光を享受し続けている。しかし、ここで言われているのは全体的なことだから、残されたユダヤ人とそのユダヤ人の子孫のことは問題にされるべきではない。その残されたユダヤ人は、肉におけるユダヤの民がどのような存在なのかということを全人類によく分からせるために生存させられているのであって、それは例えるならば日本の広島にある原爆ドームのような存在だから、彼らから天の光体が取り去られていなかったとしても問題にすべきではない。神は、かつてのご自身の民を、言わば遺物としてこの世に少しだけ残しておられるに過ぎないのである。しかし、ここで預言された出来事は、全体的に言えば、つまり細部まで徹底した厳密さをもって言うのでなければ、確かにその通りに実現されたことである。
【8:13】
『また私は見た。一羽のわしが中天を飛びながら、大声で言うのを聞いた。「わざわいが来る。わざわいが、わざわいが来る。地に住む人々に。あと3人の御使いがラッパを吹き鳴らそうとしている。」』
『わし』とは、すなわち「悪霊」のことである。これを実際の動物だと思ってはならない。そのように理解するのは、狂気に陥ることであり、御言葉を愚弄することである。しかし、どうしてこの『わし』が悪霊なのか。それは、この『わし』が19:17~21の箇所に出てくる『鳥』と同じだからである。19:17~21の箇所では、再臨のキリストによって裁かれた人々が、『鳥』の餌食にされてしまうことが書かれている。後に詳しく語られることになるが、これは再臨の時に裁かれた不信仰な人たちが、鳥として表示される悪霊どもに乗っ取られて惑わされるという、パウロがⅡテサロニケ2:10~12の箇所で預言した報復のことを言っている。この報復として送られる鳥すなわち悪霊どもと、我々が今見ている箇所に出てくる『わし』は同一の存在なのだから、この箇所で大声を出しているのは「悪霊」だということになる。この『わし』が悪霊だということは、キリストの例え話からも論証できる。マタイ13章における種蒔きの例えの中では、道端に落ちた種を鳥が取り去ってしまったことについて語られているが(13:4)、これはキリストの解き明かしから分かるように、『悪い者』すなわちサタンまたは悪霊どもが人の心に蒔かれた御言葉という種を奪い去ることである(13:19)。つまり、この例え話では、鳥がサタンまたは悪霊どもだとされていることが分かる。確かに彼らは、人の心に送られた御言葉を無効にすべく様々な働きかけをし、その御言葉がその人の中で実を結ばないようにする。このように聖書では鳥が悪い霊的な存在を象徴させる動物として語られているのだから、我々が今見ている箇所に出てくる『わし』も悪霊であると解釈すべきである。それだから、この『わし』が聖なる御使いのことだと捉えたり、または単なる裁きの象徴表現に過ぎないと考えたりしてはいけない。これは悪霊だと解するのが、もっとも理に適っており、そのように解するのが正解である。
『地に住む人々に。』すなわち、地上に災いが引き起こされるのであって、天に引き起こされるのではない。この言葉にも、我々は、よく注意し、「地上に災いが引き起こされる」という認識を強く持たなければいけない。何故なら、明瞭な認識は、よき理解の母だからである。明瞭に認識しなければしないほど、正しく良い理解を持ちにくくなってしまうのである。
ここでは『わざわい』という言葉が3回も繰り返して言われている。この3回の繰り返しは、つまり「本当に災いが来るのだ。」または「この災いはあまりにも重要なものなのだ。」ということである。この災いは、悪霊でさえも注目するべき出来事であったことが分かる。もし注目すべき出来事でなければ、この悪霊が、3回もこの言葉を繰り返して言ってはいなかった可能性も十分にあり得る。
この箇所で悪霊が災いの到来について叫んでいるのは、もう間もなく裁かれた者たちを『飽きるほどに食べ』(19:21)られるようになるからであった。つまり、この悪霊の叫びは、彼らにとっての食事に対する喜びと期待を示している。あと3つの災いが下されたならば、遂に美味しい食事にあり付けることが出来るのである。彼らにとっては、人間を惑わすことがその食事である。悪霊どもは人間を惑わすという食事をすることで生きるのである。だから、ここでその悪霊どもが興奮しながら災いについて大声で叫んだのは無理もないことであった。
【9:1】
『第5の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、私は一つの星が天から地上に落ちるのを見た。』
第5のラッパによる預言は、誰も解読できていない古代文字とほとんど同等の難解さを持つ。この預言を解読するよりは、相対性理論を理解するほうが遥かに容易い。というのも、相対性理論は多くの人が理解できているが、この預言は私の知る限り、正しく解き明かした人が今までに誰もいないからである。しかし、この預言も、正しく解き明かされねばならない。我々は、神の恵みを頂けるのであれば、この預言をも必ずや解読できるようになるということを堅く信じなければいけない。「黙示録の預言を理解することなんてとてもじゃないが出来やしないよ。」という言葉は、私にとって不快である。
『一つの星が天から地上に落ちる』とは、天の御使いが、裁きのために地上に送られたということである。これを文字通りに受け取り、巨大な天体が地球に向かってくるなどと考えるべきではない。この御使いは、もちろん聖なる御使いであって、悪しき御使いではない。というのも、この御使いは裁きのために遣わされたのであって、鍵の権能が与えられているからである。このようなことは、聖なる御使いにこそ相応しいことである。
『その星には底知れぬ穴を開くかぎが与えられた。』
『底知れぬ穴』とは、もちろん「地獄」を言っている。これは、この地上のどこかに存在する確認可能な場所ではない。また、これは単なる象徴として言われたものでもない。この箇所で、どうして地獄が出てくるかといえば、この第5のラッパの箇所では御使いが地獄に閉じ込められているサタンを解放させることについて語られているからである。20:1~3で書かれているように、紀元68年にキリストが再臨された際、サタンは『底知れぬ所』(20:1、3)に投げ込まれて千年において表示される短い間、完全に封じられた。そのようにして深い場所にある地獄へと投げ込まれたサタンが御使いにより解放されることについて、この第5のラッパによる預言の箇所では言われているのである。サタンがこの『底知れぬ穴』である地獄から解放されて再び活動できるようになったことについては、20:7~10の箇所で説明されている。
ここで御使いに与えられた『かぎ』とは、『底知れぬ穴』である地獄を開くことのできる権能を指す。すなわち、この御使いには、サタンが解放されるために地獄を開く許可が与えられたということである。この『かぎ』とは権能のことだから、これを文字通りに捉えて、この御使いに物理的な鍵が実際に与えられたなどと理解してはいけない。そのように異常な理解をした上、愚かな詮索家になって、その鍵がどのような形状や効果を持っていたのかなどと細かく無駄な思索をするのは、もっての外である。
【9:2】
『その星が、底知れぬ穴を開くと、穴から大きな炉の煙のような煙が立ち上り、太陽も空も、この穴の煙によって暗くなった。』
『煙』とは、神の怒りを示している。獰猛な性質の動物が怒り狂うならば、その鼻から荒々しい鼻息が吹き出るのは理の当然である。我々人間も、大いに怒った際、その鼻から息をフーフー激しく吹き出すことがある。ここでは、そのような被造物における怒りの状態から、神が怒っておられるということについて理解できるようになっている。つまり、神は、その鼻から煙を出すことでご自身の怒りを表わしておられるのである。神のユダヤに対する怒りは、紀元1世紀の時、遂に頂点に達した。だからこそ、その怒りの表れとして、あのように大きな悲惨がユダヤを襲ったわけである。それゆえ、あの悲惨を考えるならば、どれだけ神がユダヤに憤激しておられたかがよく分かる。
ここに出てくる『煙』を、ソドムとゴモラの地から立ち上っていた煙の記事において(※①)、解釈することができるであろうか。ソドムとゴモラから出ていた煙は、神がその地に刑罰として降らせた硫黄の火のためであって、それは神の怒りを物理的に表わしていたものである。だから、ソドムとゴモラの記事においてこの箇所を解釈することは間違っていない。それでは、シナイ山に満ちていた煙の記事において(※②)、この箇所を解釈することはどうであろうか。これも怒りを持たれる神の臨在を示す物理的な現象であったから、この記事において我々が今見ている箇所を解釈してよい。つまり、煙があるというのは、神の怒りがそこにあるとか、または怒られる神の働きがそこに見られるといった意味合いがあると我々は考えるべきなのである。
(※①)
『彼がソドムとゴモラのほう、それに低地の全地方を見おろすと、見よ、まるでかまどの煙のようにその地の煙が立ち上っていた。』(創世記19章28節)
[本文に戻る]
(※②)
『シナイ山は全山が煙っていた。それは主が火の中にあって、山の上に降りて来られたからである。その煙は、かまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えた。』(出エジプト19章18節)
[本文に戻る]
上空が煙において表わされている神の怒りにより暗くなったというのは、すなわち神の怒りにより、裁きとしてローマ軍が大いに招集されるということである。どうしてローマ軍が招集されたために上空が暗くなったかといえば、ローマ軍の数があまりにも多すぎて、すぐ次の節(9:3)でも言われているように『いなご』が全地を覆うほどだったからである。ユダヤを包囲するために招集されたローマ軍が数多かったということは、20:8の箇所でも『彼らの数は海べの砂のようである。』と言われている。同様に12:18の箇所でも、やはり『海べの砂』と言われている。つまり、煙で表示される神の怒りによって招集された彼らが海の砂のように多いからこそ、上空が彼らに覆われて暗くされてしまうというわけである。これは、もちろん実際のことを言ったのではなく、あくまでも比喩的に言ったに過ぎないものだから注意しなければいけない。実際は、ローマ軍が非常に多い数だったにしても、『いなご』のように全地が覆われて上空を覆いつくすということはなかった。しかし、比喩的に言えば、確かに彼らは上空を覆ってしまうと言えるほどの数であった。このこと、すなわち「上空が煙により暗くなった」ということが数えきれないぐらいの数のローマ軍の招集を表わしているということは、ヨエル書2:1~11を読めば明らかである。そこではユダヤを包囲して滅ぼすローマ軍の多さと力強さが語られているが、その兵士たちの凄まじさを語った後に『太陽も月も暗くなり、星もその光を失う。』(2:10)と言われている。つまり、ヨエルはローマ軍という存在のゆえに上空が暗くなると言っている。だから、このヨエル書の預言に基づいて言えば、「上空が覆い尽くされることによる暗黒の到来」とはすなわちローマ軍を暗示しているということが分かる。
【9:3】
『その煙の中から、いなごが地上に出て来た。』
『いなご』は、すなわち「ローマ軍」である。ローマ軍が『いなご』において表示されているのには、3つの理由がある。まず一つ目は、ローマ軍が、いなごのように無数にいたからである。二つ目は、ローマ軍が、いなごが地の上にある草を根こそぎにするかのように、ユダヤを根こそぎにするからである。実際、ヨセフスも記録しているように、ユダヤの地はローマ軍の攻撃により、あたかもいなごが草を食べつくして真っ平らになったかのように何もなくなってしまった。すぐ次の4節目で、この『いなご』が『地の草やすべての青草や、すべての木』にはまだ害を加えないことについて言われているのは、まだローマ軍がいなごのようにユダヤを食い尽くす時期ではなかったからである。三つ目は、『いなご』が裁きのために使われる昆虫だからである。神は、イスラエルがエジプトを出る直前に、エジプトをいなごの群れによって裁かれた(※①)。律法の呪いについて記されている箇所でも、いなごが呪いのために使われている(※②)。ローマ軍が、ユダヤに対する裁きのために動員されたのは疑えない。つまり、神は裁きとして、いなごの代わりにローマ軍を起こされたのである。このローマ軍は「霊的ないなご」だと言える。それだから、ここで出てくる『いなご』を実際の昆虫だと捉えることはできない。これは象徴として捉えるべき言葉である。もし象徴として捉えないと、この第5のラッパによる預言は永遠に理解できないままとなるであろう。なお、これは私の個人的な所感に過ぎないが、ローマ軍の兵士たちは外観的にどこか「いなご」のように感じられなくもない。
(※①)
『主はモーセに仰せられた。「あなたの手をエジプトの地の上に指し伸ばせ。いなごの大群がエジプトの地を襲い、その国のあらゆる草木、雹の残したすべてのものを食い尽くすようにせよ。」モーセはエジプトの地の上に杖を差し伸ばした。主は終日終夜その地の上に東風を吹かせた。朝になると東風がいなごの大群を運んで来た。いなごの大群はエジプト全土を襲い、エジプト全域にとどまった。実におびただしく、こんないなごの大群は、前にもなかったし、このあとにもないであろう。それらは全地の面をおおったので、地は暗くなった。それらは、地の草木も、雹を免れた木の実も、ことごとく食い尽くした。エジプト全土にわたって、緑色は木にも野の草にも少しも残らなかった。』(出エジプト10章12~15節)
[本文に戻る]
(※②)
『畑に多くの種を持って出ても、あなたは少ししか収穫できない。いなごが食い尽くすからである。』(申命記28章38節)
[本文に戻る]
聖書において、人が理性なき生命体に例えられるのは、何も珍しいことではない。例えば、主はヘロデを『狐』(ルカ13章32節)と呼ばれた。ネロは『獣』(黙示録13章1節)と言われている。聖徒は、多くの箇所で『羊』に例えられている。律法では、娼婦や男娼が『犬』(申命記23章18節)だとされている。アッシリヤの王は『はえ』また『蜂』(イザヤ7章18節)として言い表わされている。だから、ここでローマ軍が『いなご』だと言われていることを不思議に思うべきではない。
『彼らには、地のさそりの持つような力が与えられた。』
『彼ら』という言葉は、この言葉で言い表わされている存在が人格的存在だからでなくて何であろうか。すなわち、ここで言われているのが本物の昆虫ではなく、人間だからこそ『彼ら』と言われているわけである。もしこれが昆虫であったとすれば『彼ら』とは書かれていなかったことであろう。
ローマ軍に『地のさそりの持つような力が与えられた。』というのは、ローマ軍が、レハブアムが民衆を苦しめたかのようにユダヤを苦しめるからである。レハブアムが民衆に対して『私の父はおまえたちをむちで懲らしめたが、私はさそりを使うつもりだ。』(Ⅱ歴代誌10章14節)と荒々しく言ったのは、我々が既に知るところである。さそりが使われるというのは、実に苦しいことである。同様に、ローマ軍も、さそりが刺したかのような苦しみをユダヤに与えるので、彼らにさそりのような力が与えられたとここでは言われている。
【9:4】
『そして彼らは、地の草やすべての青草や、すべての木には害を加えないで、』
『地の草やすべての青草や、すべての木』とは、ユダヤの地を指す。これは、いくらか記述の違いが見られるものの、7:1~3の箇所で言われていた言葉と意味的には同じである。そこでは『地にも海にも木にも』と書かれていた。7章のほうでは『地の草やすべての青草』が書かれておらず、今我々が見ている箇所では『地にも海にも』という言葉が書かれていないという微妙な違いが見られる。これは、どちらもユダヤの地であるから、例えば木が信仰者を意味しており、海が異邦人を意味している、などというように別の存在を象徴させた表現だと捉えてはいけない。つまり、これはユダヤという地に範囲を限定させるのであれば、文字通りに捉えてよいものである。
ここでローマ軍がまだユダヤにおける『地の草やすべての青草や、すべての木には害を加えない』でいたのは、この第5のラッパによる預言が、まだローマ軍のユダヤに対する攻撃が開始される前の段階における預言だからである。これは大変重要な理解である。読者は覚えられたい、この第5のラッパによる預言は、ローマ軍がユダヤに対して戦陣を敷くことについて言われた預言であって、まだ攻撃は開始されていないのである。もしこの預言がユダヤに対する攻撃が開始されてからの預言だとすれば、『地の草やすべての青草や、すべての木には害を加えないで』などとは書かれていなかった。むしろ、「地の草やすべての青草や、すべての木に害を加えるようにした」などと書かれていたはずである。
『ただ、額に神の印を押されていない人間にだけ害を加えるように言い渡された。』
『額に神の印を押されていない人間』とは、ユダヤ人を指している。これは、ユダヤ人だけに限定されねばならない。というのも、この第5のラッパによる預言では、ローマ軍がユダヤ人を苦しめることについて言われているからである。文脈を考察するのであれば、この印を押されていない人間を、ユダヤ人以外も含まれると考えることはできない。もっとも、キリストを信じるクリスチャンとしてのユダヤ人であれば、話は別である。何故なら、彼らは神の子らであって「額に印を押されている」からである。そのような人間は当然ながら『額に神の印を押されていない人間』の中には含まれていない。
『いなご』のように無数のローマ軍が今にもユダヤ人を攻撃しようとして準備態勢を取っている。これは、正に『害を加える』ことでなくて何であろうか。彼らが突撃してきたら最後、ユダヤは目茶目茶にされてしまうのである。健全な感覚を持っているのであれば、これが災い以外ではないことが分かるはずである。試しに自分の国に他国軍がイナゴのように攻め入ってきたと考えてみるとよい。そうすれば、たとえ攻撃がまだ開始されていなかったとしても悲劇が起きたと感じられるはずである。だから、もしユダヤ人の中でローマ軍が戦闘態勢に入ったことについて悲惨だと感じない人がいたとすれば、その人は異常な信仰を持っていたか、痴呆だったか、泥酔していたに違いない。そのようにして戦陣を張るという間接的な―それは実際的ではない―害を与えることこそ、第5のラッパによる預言の内容なのである。
【9:5】
『しかし、人間を殺すことは許されず、ただ5ヶ月の間苦しめることだけが許された。』
この『5ヶ月』という言葉は、ローマ軍がユダヤに対して戦陣を張りはしたものの、しかしまだ攻撃が開始されていない期間のことである。その期間は、ただローマ軍がユダヤを攻撃しようとして陣を構えているだけに過ぎないから、ユダヤ人という人間が殺されることはまだ起きていない。それゆえ、『人間を殺すことは許されず』と言われている。つまり、これはユダヤ戦争の期間である紀元66~70年におけるある一定の期間のことを言っている。この『5ヶ月間』を、このように理解しない限り、正しい理解を得ることはできないから読者はよく注意せよ。この期間を文字通りに捉えるべきだとすれば、これは本当に5ヶ月間、すなわち150日間また20週間だったということになる。しかし象徴的に捉えるべきだとすれば、この期間は実際の期間ではなく、ただ「短い期間」であるということを言い表わしているに過ぎないことになる。その場合、『5ヶ月の間』というのは、ただの文字的な表示に過ぎないことになる。しかし、これは文字通りである可能性が高い。どうしてこう言えるかといえば、この期間は恐らく妊婦と関連があると思われるからである。妊婦の中にいる胎児は5ヶ月間は動かずにおとなしくしている。しかし6ヶ月目になると動き始める。同様にローマ軍も5ヶ月の間は胎児のように、その対象としている存在に戦陣を張って威圧するという苦しみは与えるものの―胎児も母親の身体に戦陣を張って「これから陣痛を起こすぞ」と威圧している―、まだ動くことはしなかった。しかし、6ヶ月目になると遂に攻撃すべく動き出す。つまりは、こういうことなのであろう。ローマ軍が『5ヶ月間』じっとしていたのは正に胎児のようではないか。
『その与えた苦痛は、さそりが人を刺したときのような苦痛であった。』
サソリのことについては、既に9:3で前もって語られていた。そのサソリとして言い表わされているローマ軍は、『さそりが人を刺したときのような苦痛』をユダヤにもたらすと、ここでは言われている。世界最強の軍隊がユダヤを滅ぼすべく構えていたのだから、まだユダヤ人に実際的な苦痛はもたらされていなかったにせよ、ユダヤ人があたかもサソリが刺した時のような苦しい精神状態になったのは間違いない。例えば、アメリカ軍が中東のある国を破壊しようとしてその国に乗り込んだとすれば、まだ攻撃が開始されていなかったとしても、つまり戦闘の準備をしているだけであったとしても、その国の住民は精神的にサソリに刺されたも同然の苦しみを感じるのではないか。特に女性など阿鼻叫喚してしまう人も中にはいるであろう。それと同じことが、攻撃を開始する直前のローマ軍とユダヤ人についても言えるのだ。だから、ここでローマ軍の恐るべき接近が『さそりが人を刺したときのような苦痛』と表現されているのは実に適切であった。確かにローマ軍は攻撃のために接近するだけでサソリの与えるような苦しみをもたらすほどに力強い軍隊であった。歴史を学んだ者であれば既に知っていると思うが、このローマ軍はあまりの強さのゆえに、無数の国や地域が戦うことすらせずに降伏したほどである。それは、戦っても勝ち目がないことを多くの支配者たちが悟ったからであった。このようにしてローマはその版図を広げていったのである。このようなローマ軍のことを知れば、この軍隊がサソリに例えられていることが、よく分かるはずである。
【9:6】
『その期間には、人々は死を求めるが、どうしても見いだせず、死を願うが、死が彼らから逃げて行くのである。』
これはヨブ記の聖句と対応している。そこでは、こう書かれている。『死を待ち望んでも、死は来ない。』(3章21節)我々が今見ているこの箇所では、ヘブル的な2重表現が使われている。すなわち、この箇所では「死を願うのだが死ぬことができない。」という意味のことが、違った言い方で2回繰り返されている。これはつまり、このことが非常に強調されているということを意味している。
ローマ軍がユダヤに対して陣を張っていた期間は、ユダヤ人にとって死にたくなるほどの苦しみがあったが、しかしまだ死は訪れなかった。何故なら、その期間は、まだローマ軍が攻撃をしようと立ち構えているだけであって、実際に攻撃を開始してはいなかったからである。またユダヤ人は、ローマ軍を前にした窒息しそうな状態において、みずから死ぬこともできなかった。つまり自殺することができなかった。何故なら、この期間に彼らが自殺することは、神の摂理により許可されていなかったからである。主の言われた『そんな雀の一羽でも、あなたがたの父のお許しなしには地に落ちることはありません。』(マタイ10章29節)という御言葉は普遍的な真理であって、あらゆる事柄に適用することができ、当然ながらユダヤ人もこの時に自殺することは許されていなかったのである。だから彼らがローマ軍を前にして死にたくなったのにもかかわらず、死を『どうしても見いだせず』、『死が彼らから逃げて行く』と言われている。
【9:7】
『そのいなごの形は、出陣の用意の整った馬に似ていた。』
この箇所から11節目まで、ローマ軍の詳細が記されている。
この箇所で言われているのは、ローマ軍が騎兵に乗って、ユダヤ戦争における出陣の用意を整えるということである。実際、ローマ軍は馬を用いてユダヤ戦争を遂行した。この箇所を見ても、やはりこの第5のラッパによる預言が、ユダヤに対してローマ軍が戦闘の陣を構えることについて語ったものだということがよく分かる。いやはや、黙示録は本当に謎解きゲームでもあるかのようである。その謎を解ける者は真理の美酒に酔えるが、解けない者は謎というサソリに刺されて理解不能の苦しみに悶える。我々に真理を悟らせて下さっておられる神に感謝。アーメン。
『頭に金の冠のようなものを着け、』
『金の冠』とは、ローマの権力を表わしている。当時のローマは「世界の支配者」と呼ばれており(※)、ユダヤもこのローマに屈従させられていたのだから、ローマの権力が『金の冠』として象徴させられたのは実に適切であった。これは象徴としての言葉だから、実際にローマ軍の兵士が『金の冠』を頭に着けていたなどと空想してはいけない。そのような光景はなかなか面白いとは思えるが、実際にはあり得ないことである。
(※)
例えばアウグストゥス帝は、ローマ人に向かって「ああ、ローマ人よ、世界の主よ」(スエトニウス『ローマ皇帝伝(上)』第2巻 アウグストゥス p137:岩波文庫)と言い、大祭司アナノスもローマ人を「世界の主人である者たち」(『ユダヤ戦記2』Ⅳ iii10:178 p165:ちくま学芸文庫)と言い、共和制末期の護民官ガイウス・メンミウスも「ローマ人民、この敵に敗れたことのない全民族の支配者」(サルスティウス『ユグルタ戦争 カティリーナの陰謀』ユグルタ戦争(第31章)p60/岩波文庫 青499-1)と言ったが、これは何も誇張したり偽って言ったわけではない。世界の主人と呼ばれたこのローマの圧倒的な支配力については、ヨセフスの「ユダヤ戦記」2巻:xvi/4/345~401の箇所も参照すべきである。そこではアグリッパ王がユダヤ人の群衆に対して、ローマがいかに世界の諸民族をコントロールしているか簡潔に語っている。このアグリッパ王の言説は長すぎるので、ここで引用することはできない。ひとまず、ここではこの王が「太陽の下のほとんどすべての民族がローマの武力の前にひれ伏している」とその言説の中で語っているとだけ書いておけばよいであろう。
[本文に戻る]
『顔は人間の顔のようであった。』
これは、『いなご』が実は人間であったということである。すなわち、第5のラッパによる預言の中では、人間の顔を持ったイナゴが実際に出てくるというのではない。ヨハネがここで伝えたいのは、「これは人間、すなわちローマ兵のことなのだ。本物の昆虫だと思ってはいけない。」ということである。
【9:8】
『また女の髪のような毛があり、』
これは、ローマ兵が着けている兜のことを指す。古代ローマ兵の画像や絵を見たことのある人であれば分かるだろうが、ローマ兵の兜には『女の髪のような毛』が付いていた(※)。だから、これはローマ兵における地毛のことを言っているのではない。それにしても、この9:7~9の箇所では、『いなご』がローマ軍であるということについて、いかに多くのことが示されていることか。これらの箇所では、正にローマ兵のことが示されており、それは明瞭過ぎて驚かされるほどである。それにもかかわらず、今まで全ての教会と聖徒たちが、ここで言われていることについてまったく理解できなかった。このことを考えると、恵みが与えられないのは何と悲惨なことかと思わされる。恵みが注がれていないので、こんなにも多くの目印が示されているのに、これがローマ兵のことだと分からないままに留められてしまうのである。つまり、恵みが注がれないと、こんな明瞭なことさえ分からなくなってしまうのである。よって、黙示録の理解においては、神の恵みに全てがかかっていると断言できる。私がこのように解明できているのも、もちろん恵みのゆえであって、私の知性によっているのではない。
(※)
https://www.google.com/search?q=ローマ兵%20イラスト&tb…
[本文に戻る]
『歯は、ししの歯のようであった。』
これは、ローマ兵が獅子のようだったということである。獅子は獰猛で力強い存在である。ここでは、ローマ兵の歯において獅子が表示されることにより、ローマ兵が獅子のような強さを持っているということが言われている。実際にローマ兵の歯が獅子のようだったという意味ではない。難しい表現であるが、神の恵みを頂きつつ解釈せねばならない。
【9:9】
『また、鉄の胸当てのような胸当てを着け、』
これはローマ兵の胸当てのことでなくて何であろうか。これについての説明は不要であろう。私が何かを説明するより、ネットや本でローマ兵の写真または絵を見たほうがよい。
『その翼の音は、多くの馬に引かれた戦車が、戦いに馳せつけるときの響きのようであった。』
これは、ローマ軍が戦車を率いて、ユダヤの地を滅ぼすために向かってくるということである。彼らがユダヤに来る際に出した音は、非常に大きな音であったと言える。何故なら、彼らは『いなご』のように数多かったのだから。聖書が同じことを何度も繰り返して言っているので、私も同じことを何度も説明しなければいけない。すなわち、この第5のラッパによる預言は、ローマ軍が『戦いに馳せつけ』て戦闘の準備をすることについて言われている預言である。つまり、この預言で言われているのは、彼らが攻撃をしようとはしているものの実際には攻撃を加えていなかった時のことである。ハンターが弓の弦を大きく引いて今にも矢を放とうとしている状態、木こりが斧を上にかざして今にも木に振り落とそうとしている状態、B-29が原爆を積んで日本に向かって飛んでいる状態。この第5のラッパで預言されたローマ軍は、ユダヤというターゲットに対して正にこのような状態を持っていた。
【9:10】
『そのうえ彼らは、さそりのような尾と針とを持っており、尾には、5ヶ月間人間に害を加える力があった。』
『針』とは、既に見たように、ローマ軍がユダヤに与える苦しみのことである。このローマ軍は、サソリの大群のようであった。いや、むしろローマ軍はサソリの大群よりも恐ろしかったと言えるかもしれない。何故なら、サソリの大群といえども数十万人もの人間を殺すことはないからである。そのような話は今までに聞かれたことがない。しかし、ローマ軍は数十万人ものユダヤ人を殺した。だから、このサソリの針を持っているローマ軍は、ユダヤにとって実に恐るべき存在であったと言える。
『尾』とは、すなわち頭(かしら)なるローマがユダヤを尾として屈従させ苦しめるということである。律法の中で、神に従わない反逆的な者は、異国の者たちに支配されて尾となると威嚇されている。『彼はかしらとなり、あなたは尾となる。』(申命記28章44節)と言われている通りである。これは、律法を守るならば『主はあなたをかしらとならせ、尾とはならせない。』(申命記28章13節)と言われていることからも分かる。つまり、これは神に従順に歩めば頭となれるが、もし従順でなければ呪いとして尾とされるということである。当時のユダヤ人は罪の中に歩んでいたために呪われており、頭なるローマの尾に、すなわち属国にされていた(ユダヤがローマの属国となったのは紀元6年である)。これは律法に背いていたためであるが、愚鈍な彼らはそのことを理解しておらず、その呪いによる屈従を神に対する従順抜きに、つまり力づくで覆そうとしていた。そのような尾の状態にあったユダヤを頭なるローマが5ヶ月の間、戦闘の準備をすることで苦しめるということが、ここでは言われているのである。この『尾』を、私が今説明した以外の意味において捉えることはできない。また、この言葉を律法の知識抜きに正しく理解することはできない。それゆえ、この『尾』という言葉を、読者は支配という観点から理解しなければいけない。これ以外の理解はどれも誤っていると私は断言する。
『さそり』について語られるのは、この第5のラッパの預言(9:1~12)の中では、これで3回目である。1回目は9:3で、2回目は9:5で語られていた。分かる者、すなわち神の恵みを受けた者にとっては、このような繰り返しは、認識と理解のために益となる。何故なら、繰り返しとは、認識と理解とを強める働きがあるからである。学校でも、よく覚え、よく学ぶために「反復」がなされるものである。しかし、分からない者、すなわち神の恵みを受けていない者の場合、このような繰り返しのために、ますます混乱が生じてしまう。何故なら、分からないことが繰り返されるので、謎に謎が積み重ねられることになるからである。分からない者にとっては、謎に謎が加えられても、分かるようになることはない。ますます謎が複合的になるばかりである。要するに、これは『持っている者は、与えられて豊かになり、持たない者は、持っているものまでも取り上げられる』(マタイ25章29節)ということである。理解できる者は繰り返されることで更によい解釈に至れるが、理解できない者は繰り返されることで無明の泥沼にますます引きずり込まれてしまう。この普遍的な原理は、黙示録において、いや全聖書において言えることである。つまり、これはこういうことである。「黙示録を理解できる者は更に理解できるようになりなさい。しかし理解できない者は更に理解の混乱に陥りなさい。」
【9:11】
『彼らは、底知れぬ所の御使いを王にいただいている。彼の名はヘブル語でアバドンといい、ギリシヤ語でアポリュオンという。』
『底知れぬ所の御使い』とはサタンである。この第5のラッパによる預言では、ローマ軍が、底知れぬ所に短い間封じられていたサタン(20:1~3)が解放されたことにより招集された出来事(20:7~9)について語られているので、底知れぬ所に封じられることになっていたサタンが出てきている。この御使いを、サタン以外の御使いだと捉えることはできない。このサタンは、『ヘブル語でアバドンといい、ギリシヤ語でアポリュオンと』呼ばれる。アバドンとは「破壊」を、アポリュオンとは「破壊者」と意味している(※)。なお、「アバドン」について言えば、これは旧約聖書の中では他にも「シェオル」(ヨブ26:6)や「死」や(同28:22)や「墓」を意味する言葉でもある。このように言われている通り、正にサタンは破壊する者に他ならない。彼は、己の善性を破壊し、人類の善性を破壊し、地上における全被造物を破壊に導いた。また彼は今に至るまで神の造られたあらゆる良き被造物を破壊したく願っている。何故なら、そうすることは神への攻撃となるからである。それは、ある芸術家の作品を無残にも破壊することが、その芸術家そのものを攻撃することに等しいのと同じである。彼から恵みを受けていると思えるサタン崇拝者たちも、実は破壊の対象であり、最後には破滅に至らせるという条件の下で、また自分に役立たせる限り利用するという制約の元で、破滅に至らされることもなく恵みを受けているに過ぎない。ベンジャミン・フルフォードというアユケナージのユダヤ人も言っているように、サタン崇拝者たちで「実はサタンは良いヤツなのかもしれない。」と思っている者は少なくないが、彼らは思い違いをしているのだ。何故なら、サタンとは『偽りの父』(ヨハネ8章44節)であって、彼らが自分の持つ破壊の願望に気付かないようにしているだけだからである。
(※)
「アバドン」は、聖書以外でも、その名前が使われているのをしばしば見かける。例えば、イルミナティカードの中ではアバドンという文字の書かれた絵が描かれているカードがあるし、エクスリーム・メタルの元祖と呼ばれるイギリスの「ヴェノム」というバンドにもアバドンという名のメンバーがいるし、世界的に有名なゲームである「ファイナルファンタジー」の8作目でもアバドンという名のモンスターが登場している。これらの名前が黙示録から取られたかどうかは定かではないが、もし黙示録から取られたとすれば、それは人々が黙示録に興味を持っているということの良い証拠である。「アバドン」以上に使われることの多い「666」や「ハルマゲドン」は間違いなく黙示録から取られているから(※666は13章18節、ハルマゲドンは15章16節)、恐らくこの「アバドン」も黙示録から取られているのではないかと思われる。私はこのように多くの人が注目している文書の解き明かしを神の恵みによりしているのだから、聖徒である方は、そのような文書の註解をぜひ忍耐を持って熟読してほしいものである。一方「アポリュオン」のほうは、その名前が使われているのを私の場合、今までに見たことがない。
[本文に戻る]
この箇所で、サタンがヘブル語とギリシャ語において語られているのは、サタンを豊かに強調しつつ語るためであった。このことの例証は、ローマ8:15でパウロが書いている『アバ、父。』という言葉である。この『アバ』とはヘブル語で「父」という意味であり、『父』とはギリシャ語であるから、つまりパウロはヘブル語とギリシャ語で「父、父。」と言ったことになる。パウロが父、父と違う言語で2回繰り返して強調させたのは、聖徒たちに、神が自分たちの父であるということを豊かに理解させるためであった。この箇所でも同様であって、ヨハネは聖徒たちがサタンのことを強く認識できるようにと、2つの言語でサタンの名を書き記したのである。そのようにすれば、一つの言語で一回だけ語られた場合よりも、より強いサタン認識が生じることになるのは確かである。このような言い方はヘブル人らしいと言える。既に説明したことだが、この民族は強調のために言葉を繰り返すということをよくしていた。今このような説明がされたのだから、聖徒たちは、このように2つの言語で2回もサタンが言い表わされていることを何か不思議であるかのように思うべきではない。
ローマ兵たちは、この破壊者であるサタンを『王にいただいている。』とヨハネは書いている。ローマ兵たちは、自分ではサタンが王だと認めないであろうが―むしろローマ皇帝やユピテルやアポロンが王だと彼らは言ったことであろう―、確かなところ彼らの王はサタンであった。何故なら、サタンは『この世の神』(Ⅱコリント4章4節)だからである。この世においては、キリストを王としないのであれば、意識しているのであれ意識していないのであれサタンというこの世の神を王とすることになる。霊的な世界において中間はあり得ない。よってローマ兵たちはキリストを王としていなかったのだから、サタンを王としていたことになる。キリストがパリサイ人たちに、『あなたがたは、あなたがたの父である悪魔から出た者であって』(ヨハネ8章44節)と言われたのも、このことを考えればよく分かる。すなわちパリサイ人たちはキリストを王としていなかったので、サタンが彼らの父つまり王だったわけである。パウロも言うように不信者たちは例外なく『暗やみの圧制』(コロサイ1章13節)の中に閉じこめられているのだから、不信者であったローマ兵たちが圧制者であるサタンの支配下にいたのは確かである。サタンの支配下にいるとは、サタンがその人の王であるということでなくて何であろうか。しかしながら、これはもちろん霊的なことを言ったものである。ローマ兵は、霊的に言えば確かにサタンを王としていた。しかし実際的に言えば、彼らの王は言うまでもなくローマ皇帝であった。
この箇所で言われているのは、すなわちローマ軍が自分たちの王であるサタンの霊に突き動かされてユダヤを破壊しにやって来るであろう、ということに他ならない。つまり、ユダヤに対する戦闘準備は他でもないサタンの働きかけによるものだったということである。彼らは破壊者であるサタンを王としていたからこそ、そのようなことを行なった。何故なら、人間とは、意識しているにせよ無意識であるにせよ自分の神の心に従って歩むようにと造られているからである。例えば、真の神を神としているキリスト者は真の神の御心に従って善を行なうものだし、邪悪な偽りの神を神とする邪宗の信者は邪悪なことを行なうものである。同様にローマ軍はサタンという破壊者を王すなわち神としていたので、サタンを支配者とする者に相応しく破壊の活動をするのである。実際、このローマ軍は、ユダヤを徹底的に破壊しつくした。もし彼らが『平和の神』(ローマ16章20節)であるキリストを自分たちの王としていたのであれば、このような破壊活動は行なわなかったであろう。
【9:12】
『第一のわざわいは過ぎ去った。見よ。この後なお二つのわざわいが来る。』
これはヨハネ自身の言葉であって、8:13で3つの災いについて叫んでいた悪霊の声を記したものではない。このヨハネは、8:13の箇所で悪霊の叫びが許可されたのを、神が自分にその悪霊の叫びを通して災いについて知らせて下さるためであったと悟った。ヨハネはこの悪霊の言葉が真実であると信じたからこそ、その悪霊の言葉に基づき、ここでその災いのことについて記しているのである。ヨハネが8:13の箇所で叫んでいる悪霊の声を聞かなかったとすれば、または聞いたとしてもそれを真実だと信じなかったとすれば、ヨハネはこのように書いていなかったはずである。確かに、悪霊が真実な言葉を口にした場合、我々はそれを信じるのが正しい。悪霊が口にしたからというので、真実なことまで受け入れないというのは間違っている。例えば、ゲラサの狂人の中に入っていた悪霊がキリストに向かって『いと高き神の子、イエスさま。』(マルコ5章7節)と言ったことを誰が疑っていいであろうか。この悪霊がキリストを『いと高き神の子』と言ったのは真実なことだったから、それは信じるべきものであった。それゆえ、ヨハネが8:13で叫んでいた悪霊の言葉を真実なものとして受け取った上でこのように災いについて書き記していることを、我々は問題にしてはいけない。
聖書は、ローマ軍がユダヤに対して戦陣を張ることこそ『第一のわざわい』だと教えている。であれば確かにそうである。何故なら、それは神の啓示だからである。神が示されたことに対して異論を唱えることはできない。もし啓示に文句を言ったりすれば、パウロによる『人よ。神に言い逆らうあなたは、いったい何ですか。』(ローマ9章19節)という御言葉がその人に突きつけられることになる。確かに、ローマ軍の戦闘準備は、ユダヤにとって災い以外ではなかった。サソリの大群が、世界最強の軍隊が、自分たちを滅ぼす裁きの使者たちが、目の前で戦いの準備をしていたのである。これが災いでなければ何を災いだと言えばよいであろうか。
7つあるラッパの預言では、第5番目から第7番目までの預言が『わざわい』だと言われている。すなわち、第5番目が『第一のわざわい』(9:12)であり、第6番目が『第二のわざわい』(11:14)であり、第7番目が『第三のわざわい』である。4番目までの預言は特に「わざわい」だと言われていない。それでは第4番目までの預言は「わざわい」ではなかったのであろうか。もちろん、第4番目までの預言も「わざわい」について示されたことであった。第4番目までの預言については既に確認した通りであって、そこではユダヤが滅ぼされることが語られていたが、ユダヤに破滅の裁きが下されることは正に「わざわい」そのものである。ではどうして第5番目からの預言が、特に名指しして『わざわい』と言われているのか。どうして第4番目までの預言は、それが災いであるにもかかわらず『わざわい』と言われていないのか。それは、第4番目までの預言と第5番目からの預言は、内容的に異なっているからである。我々が今見ている7つのラッパによる預言は、4番目までと5番目以降という2つの区分に分けることができる。4番目までは内容的に順序がなく、そこには時間の矢が流れていない。言わば無造作にそこでは預言が語られている。しかし5番目以降の預言では、明らかに内容が順序立てて語られており、そこには時間の矢が確認できる。つまり、第5番目以降の預言は4番目までの預言とは違って時間性が伴っている。だからこそ、第5番目以降の預言においては、流れの秩序をよく分からせるべく、災いが時間の流れに応じて3つに区切られているのである。だから、もし第4番目までの預言も時間性を伴ったものであったとすれば、第5番目~第7番目の預言は「第5~第7のわざわい」と言われていたはずである。その場合、第1番目~第4番目までの預言は「第1~第4のわざわい」と言われていたはずである。しかし、実際は第4番目までの預言に時間性が伴っていないので、災いの時間的な区分は第5番目の預言を基点として示されている。このようにラッパによる預言は2つに区分されているという理解を持たなければ、この謎を読み解くことは不可能である。これで、どうして第5番目以降の預言が3つの災いとして区切られているのか、思慮深い読者にはよく理解できたことであろう。
【9:13】
『第6の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、私は神の御前にある金の祭壇の四隅から出る声を聞いた。』
6番目のラッパによる預言は、5番目のラッパによる預言を理解していれば、それほど理解が難しい預言ではない。何故なら、6番目のラッパの内容は、5番目のラッパの内容の続きだからである。5番目のラッパにおいてユダヤが滅ぼされる直前の段階が示されていたということは…?―6番目のラッパがどのようなことを示しているかは誰の目にも明瞭であろう。
『金の祭壇の四隅から出る声』は、恐らく神の声だと思われる。何故なら、すぐ次の箇所(14節目)で、この声は第6の御使いに指令を出しているからである。もし神でなかったとすれば、声の主はセラフィムかその他の御使いである。この声が、悪しき存在のものだったということはあり得ない。どうしてこの声が『四隅』から出たかといえば、それはこの声が4つの方角である東西南北、すなわち「世界」を対象として指令を出しているからである。もっとも、世界と言っても、それは文字通りの世界ではなくユダヤにおける世界のことである。何故なら、この第6のラッパによる預言の箇所で言われているのは、ユダヤのことだからである。この『四隅』という言葉が文字通りの地球全土を意味していると捉えると誤りに陥ることになるから、よく注意せねばならない。このように黙示録では、そこで言われている対象が誰なのか、またどこの場所なのか、ということをよく考慮する必要がある。その対象を誤って理解すると、愚かで異常な理解に陥ることになるからである。
【9:14】
『その声がラッパを持っている第6の御使いに言った。「大川ユーフラテスのほとりにつながれている4人の御使いを解き放せ。」』
『4人の御使い』とは、既に7:1~3の箇所で出てきたあの御使いたちのことである。彼らは悪しき御使いであって、リーダー的な存在だが、その名前と性質の詳細は書かれていないので我々にはよく分からない。
『大川ユーフラテスのほとり』とは、すなわち「異邦人」のことである。神がアブラハムを通してユダヤに約束された土地の境界における一方は『ユーフラテス川』(創世記15章18節)であった(もう一方は『エジプトの川』)。この約束された範囲の土地は、既に説明されたように、霊的に言えばユダヤを指している。ユダヤを示すその約束の土地における境界線は『大川ユーフラテス』だが、その大川の『ほとり』とは、つまりユダヤを示す土地の外に位置しているのだから「異邦人」だということになる。この『大川ユーフラテスのほとり』という言葉を別の言い方で表わせば、「ユダヤ人ではない(=異邦人である)」ということである。ユダヤの土地でない領域とは、異邦人の領域でなくて何であろうか。この難しい言葉は、このように霊的に捉えなければ上手に理解できないであろう。もしこの言葉を実際的・物理的に捉えるとすれば、訳が分からなくなる。その場合、誤った捉え方をしているのだから、この言葉を上手に理解することは決してできない。
ここで言われているのは、つまり『大川ユーフラテスのほとり』である異邦人を動員することが4人の御使いに許されたので、その4人の御使いが行動するために束縛の状態から解放されたということである。その動員される異邦人とは、もちろんローマ兵たちのことである。つまり、ユダヤは、この4人の御使いに動かされたローマ兵たちにより攻撃され滅ぼされるということである。この4人の御使いたちは、7:1~3で書かれていたように、時が来るまではユダヤにおける地と海と木とを滅ぼさないようにと束縛されていた。しかし、サタンが底知れぬ穴から解放されると同時に時が満ち、この4人の御使いは『大川ユーフラテスのほとり』である異邦人に働きかけることが許可されることになった。だからこそ、束縛から解放されたこの4人の御使いはローマ兵という異邦人に働きかけ、ユダヤの地と海と木とを遂に滅ぼすことができるようになったわけである。これは、つまり地獄から解放されたサタンがこの4人の御使いを動員させることにより、ユダヤを滅ぼすようにさせたということである。サタンは根本的な律法の違反者であって、『盗んではならない。』という神の戒めに常に背いており、この戒めに従う気も毛頭ないので、盗む以外のことはできない。彼を別の名で言い表わせば「盗み」または「盗みの父」である。そのようにサタンは本質的に盗みをその性質としているから、常に神の行ないを真似る。このサタンは神が常に御使いたちを僕として何かをしておられるのを知っていたので、自分もそれを真似て、この4人の御使いを僕としてユダヤを破滅させたのである。つまり、この4人の御使いたちとは、サタンの忠実な『使いども』(12:9)だったのである。このように理解すると、ユダヤが滅ぼされた時の詳細が、ますます豊かに分かるようになってくる。また、この御使いの数が『4人』だったのは、この御使いがユダヤにおける四方すなわち東西南北(=世界)を滅ぼす役割を持っていたからであった。この4人の御使いがユダヤ世界を滅ぼす役割を持っていたというのは、7:1~3の箇所を見ても分かることである。この御使いにおける「4(人)」という数字は、象徴と共にある現実である。すなわち、この御使いが「4(人)」であったのは、その数字がユダヤ世界を象徴するためであったのと同時に、本当に現実的に4人の御使いが存在していたということである。
【9:15】
『すると、定められた時、日、月、年のために用意されていた4人の御使いが、人類の3分の1を殺すために解き放された。』
『人類の3分の1』とは、先に見たようにユダヤの民のことである。
『定められた時、日、月、年』とは、ユダヤが神の裁きにより滅ぼされる時のことを言っている。それまでは時が満ちていなかったが、遂に裁かれるべき時に至ったので、ユダヤは滅亡させられることになってしまったのである。この定めの時が、まだ訪れていないと全聖徒は当然のことのように思うであろう。しかし目を覚まし、心で悟ってほしい。黙示録の冒頭部分で言われているように、これもまた『すぐに起こるはずの事』(1:1)だったのである。つまり、この定めの時は、もうとっくの昔に過ぎ去っているということである。
『4人の御使いが、人類の3分の1を殺すために解き放された。』のは、神の裁きがユダヤに対して注がれるためであった。この裁きのために、本当に『人類の3分の1』であるユダヤ人が大いに殺されることになったのである。その破滅がどのようなものだったかということは、歴史が我々に教えている通りである。
【9:16】
『騎兵の軍勢の数は2億であった。私はその数を聞いた。』
『騎兵の軍勢』とは御使いたちのことであって、その数は『2億』と言われているが、これは実際の数字であろう。ユダヤが滅ぼされる際には、既に出てきた4人のリーダー的な御使いが動員した2億の御使いたちによってローマ軍が動かされ、そのローマ軍を通してあの滅亡が実現されることになった。つまり、ユダヤが滅亡する際に起きたのは、こういうことになる。すなわち、まず底知れぬ穴からサタンが解放され(20:7、9:1~11)、その解放されたサタンが4人の御使いを動かし(9:14~15)、その動かされた4人の御使いが2億の御使いたちを使ってローマ軍に働きかけた(9:16~19)。これは、キリストのやり方とまったく同じである。キリストも、ミカエルであれガブリエルであれ、まず力ある少数の御使いを動員され、その力ある少数の御使いが自分の配下にいる無数の御使いたちを動かしてキリストの御心を行なうように指示する。サタンは、キリストのようにするのが最善の方法だと弁えているのである。なお、この『2億』という数字を考察すれば、この騎兵が人間ではなかったことは明らかである。何故なら、既に第1部で説明されたように、当時の世界人口はだいたい2億ぐらいだったからである。もしこの2億の騎兵が人間だったと解するのであれば、当時生きていたあらゆる人間がユダヤを滅ぼすために馬に乗って戦いに臨んだということになる。しかし、このような馬鹿げた話は決して受け容れられないものである。実際の歴史を見ても、当時生きていた全ての人間がユダヤを攻めに向かったということは確認できない。紀元60年代にユダヤを攻めに向かったのは、ローマ兵だけであって、その数は300万にも満たなかった。このように『2億』という数字で表わされている騎兵を人間だと解すると異常な見解に陥ってしまうのだから、これは御使いのことだと解さなければいけない。これが御使いだったと解するのであれば、何かの問題が生じることもないのである。
それでは、ヨハネは誰からこの数を聞いたのか。それは神か、セラフィムか、セラフィム以外の御使いか、12人の長老であるかのいずれかだが、実際に誰だったかということは、何も書かれていないので分からない。しかし、たとえ分からなかったとしても重大な妨げが生じることはないから、これは騒ぎ立てるような問題ではない。
【9:17】
『私が幻の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子はこうであった。』
ヨハネは、自分の見たことを、聖徒たちにここで伝えている。それは、聖徒たちが、神の啓示をよく弁えられるようになるためである。何となれば、この文書は、聖徒たちに神の啓示が与えられるようになるためにこそ書かれたのである。だから、神がヨハネを通して、その示された幻の内容を聖徒たちにしっかりと伝えるようにされたのは当然であった。聖徒たちのために書かれた文書であるにもかかわらず、何も伝えられるべきことが伝えられていなかったとすれば、それは筋の通らないことであった。神は筋の通ったことをなされるお方だから、この黙示録では、ヨハネの記述を通して必要十分なだけの知識と情報とが聖徒たちに提供されているのである。
『騎兵は、火のような赤、くすぶった青、燃える硫黄の色の胸当てを着けており、』
2億もの御使いたちが着けていた胸当てには、2つのことが示されている。まず一つ目は、この胸当ての外観が、この御使いたちの口から出ているものがどのようなものかということを示しているということである。この節のすぐ後に書かれているように、この御使いたちの『口からは火と煙と硫黄とが出ていた』。この胸当ては、この御使いたちの口から出ている火が赤く、煙は青くて燻っており、硫黄は燃えているということを我々に教えている。要するに、この胸当ては、御使いの口から出ている3つのものと対応しており、それがどのようなものか説明したものである。だから、この御使いの口から出ている『火と煙と硫黄』は、単なる象徴ではなく実際的なものであったと考えなければいけない。二つ目は、この胸当てを着けた2億の御使いたちが、第5のラッパによる預言で出て来たローマ兵とは違うということを示すためである。既に見た第5のラッパによる預言で示されていたローマ兵も、第6のラッパによる預言で出てくる人たちと同じように胸当てを着けていた(9:9)。しかし、ローマ兵の着けている胸当ては、明らかに第6のラッパで出てくる人たちが着けている胸当てとは違う。何故なら、ローマ兵の胸当ての色は単調であって、我々が今見ている箇所で書かれている赤や青や硫黄の色はしていなかったからである。第5と第6のラッパでは騎兵が出てくるが、それぞれのラッパで出てくる騎兵は違う存在だから、両者の混合を避けるべく、このように胸当てに言及することで両者が異なっているということを示そうとしているわけである。つまり、この2つの胸当ての外観に着目すれば、第5と第6のラッパで出てくる騎兵は異なっていることが分かるようになっている。すなわち、この胸当てをよく考えれば、第5のラッパにおける騎兵はローマ兵だが、第6のラッパにおける騎兵は御使いであるということが、よく分かるようにされている。このように、この箇所で騎兵が着けている胸当てに言及されているのは、今述べられた2つのことを示す指標としての意味があった。
『馬の頭は、ししの頭のようで、』
これは、御使いたちが獅子のように力強い存在だったということを示している。獅子は「百獣の王」と呼ばれるように、獣の中では最強であって、どの獣もこの獅子に勝つことはできない。そのような獅子においてこの御使いが表示されているということは、この御使いが誰にも抵抗できないほどの力を持っていたということを意味する。実際、この御使いを通して下されたユダヤにおける破滅の出来事は回避不可能なものであった。それは、あたかも血に飢えた獅子が逃げ惑う鹿を骨まで喰らい尽くすかのようであった。9:8の箇所でローマ兵の歯において獅子が表示されていたのも、やはりローマ兵に対抗できる存在がこの地上にはどこにもいなかったからであった。13:2でネロが獅子において表示されているのも、やはりネロには誰も対抗したり逆らったりできなかったからである(これはネロについて記された古代の文書を読めば誰でも分かることである)。このように黙示録における「獅子」という言葉は、この言葉において表示されている存在が誰にも負けない獅子のごとき存在だったということを示している。これは黙示録を読み解くためには、是非とも覚えておかねばならない理解である。獅子の顔を持つ第一のセラフィムにより呼び出された再臨のキリスト(6:1~2)も同様であって、再臨されたキリストには誰一人として抵抗できなかった。つまり、獅子のセラフィムが再臨のキリストを呼びだしたのは、再臨されたキリストが獅子のように力強く、抵抗不可能だったからである。
『口からは火と煙と硫黄とが出ていた。』
これは御使いたちが、ユダヤに対する神の裁きを代行し、ユダヤを火炎の海とさせるということである。ユダヤ戦争の際、ユダヤの地は本当に文字通り火炎の海と化した。それは、神の裁きにより2億の御使いたちがローマ軍と共に働きかけたからであった。だから、我々はあの大炎上がローマ軍の仕業だったと考えるだけでなく、そこには御使いの働きかけもあったということを知らねばならない。確かに実際的に言えばあればローマ軍の仕業だったが、霊的に言えば御使いが神の裁きを下したから起きたことでもある。ここで『口から』と言われているのは、2億の御使いたちが、神の御口から出た判決に基づいて『火と煙と硫黄』とを下すからである。つまり、これは御使いたちが、神の御口による判決ゆえに『火と煙と硫黄』の裁きを下すという意味である。
【9:18】
『これらの3つの災害、すなわち、彼らの口から出ている火と煙と硫黄とのために、人類の3分の1は殺された。』
神がこの御使いたちを通してユダヤに災害を下されたので、ユダヤ人は大いに殺されてしまい、あの有名な都は滅ぼされてしまった。そのクライマックスは紀元70年9月である。ここで言われていることは、実際的に捉えられなければいけない。何故なら、実際にユダヤは『火と煙と硫黄』により燃え上がる火炎の海と化し、多くの死者が出たからである。実際にユダヤが燃やされて数えきれないほどの人が死んだのだから、ここで言われていることを文字通りに捉えるべきだというのは確かである。なお、ここでは『3つの災害』と言われているが、これは一つの災害を3つの災害として言い表したものに他ならない。つまり、ユダヤに注がれたのは大炎上という一つの災害であったが、それは位格的に言えば火と煙と硫黄という3つの災害に区分することができるということである。それは、どこかで起きた大地震が大地震という一つの災害でありながら、位格的に言えば「地割れの災害」「振動の災害」「建物が倒壊する災害」という3つの災害として語ることが出来るのと同じである。三位一体をよく弁えている人であれば、このような位格的表現を聞いても、あまり違和感を感じないと思う。一つの災害でありながら3つの災害。これがユダヤに下された神からの裁きであった。
【9:19】
『馬の力はその口とその尾とにあって、その尾は蛇のようであり、それに頭があって、その頭で害を加えるのである。』
『口』に力があるのは、神の御口の判決に基づいて、彼らがユダヤに火と煙と硫黄との災害を下すからである。これ以上に力あることが他にあろうか。神の御口に基づく恐るべき致命的な裁きよりも力強いものは他にあるまい。
尾が蛇のようであった、すなわちサタンのようであったというのは、サタンがこの2億の騎兵たちにより、ユダヤを尾として苦しめるということである。先に9:10の箇所で見た律法における支配と隷属の原理を我々は思い返すべきである。この原理についての知識がなければ、この箇所で言われている『尾』について上手に理解することはできない。また尾に付いている頭が害を加えるというのは、蛇であるサタンが頭として、尾であるユダヤに害を加えるということである。これも律法の知識抜きに正しく理解することはできない。当時のユダヤは罪のゆえに呪われており、尾である者に相応しく頭として定められた存在から裁かれるべき状態に陥っていた。その頭として定められたのは、もちろん蛇なるサタンであった。このようにユダヤは尾として裁かれるべき状態に陥っていたので、神の義なる裁きに基づく働きかけにより、サタンが頭として彼らに害を加えるようにされたわけである。
【9:20~21】
『これらの災害によって殺されずに残った人々は、その手のわざを悔い改めないで、悪霊どもや、金、銀、銅、石、木で造られた、見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を拝み続け、その殺人や、魔術や、不品行や、盗みを悔い改めなかった。』
御使いたちとローマ軍による攻撃で殺されなかったユダヤ人がいたが、この箇所では、そのようなユダヤ人のことが言われている。とはいっても、もちろん、ここで言われている生き残ったユダヤ人の中にはクリスチャンであるユダヤ人は一人すらも含まれていなかった。何故なら、ユダヤが破滅の裁きを受ける際には、既にクリスチャンであるユダヤ人たちは携挙されており地上には一人もいなかったからである。そのような選ばれたユダヤ人たちは、そもそも御使いたちとローマ軍による襲撃に遭うことさえなかった。すなわち、この箇所で言われているのは『額に神の印を押されていない』(9:4)ユダヤ人だけに限られている。
ユダヤに破滅の裁きが下された際に『殺されずに残った人々』は、悪に突き進み続け、悔い改めるということをしなかった。彼らが悔い改めなかったのは、彼らが悔い改めないようにと定められていたからであった。神の彼らに対する御心は、彼らの一人一人が悔い改めないで残され、それから永遠に滅びることであった。彼らが永遠に滅びるためには、彼らが悪を止めないことが必要である。よって、彼らは裁きがユダヤに下されてからも悔い改めることをしなかったのである。『悪霊どもや、金、銀、銅、石、木で造られた、見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を拝み続け』たとは、彼らがあくまでも神に反逆することで、偶像崇拝の罪を犯し続けたということである。確かにサムエルも言うように、『従わないことは偶像礼拝の罪』(Ⅰサムエル15章23節)である。つまり、ここで言われているのは、彼らの反逆は、神に対して偶像崇拝の罪を犯しているのも同然だったということに他ならない。実際には彼らが例えばゼウスとかアポロンとかミネルヴァとか、また悪霊を公然と拝むことはしなかったし、このようなものを拝んでいると言われたならば彼らは反発したであろう。しかし、彼らは悪を行なって神に反逆することで、このような存在を拝んでいたと言える。何故ならサムエルの言葉から分かるように、反逆とは偶像礼拝に他ならず、それは神以外の存在に付き従うことだからである。事柄は霊的に捉えねばならない。彼らがそのようにして事実上の偶像礼拝をしていたからこそ、黙示録では彼らが『不品行によって地を汚した大淫婦』(19:2)なのだと言われているのである。彼らは偶像崇拝により本来の夫であった神から離れてサタンの寝床に通っていたのだから、このように娼婦として取り扱われたのは当然であった。旧約聖書でも、イスラエルが娼婦として批判されている箇所を多く見かけるものである(※)。ヴァン・ティルの場合、この大淫婦が「この世」(『ヴァン・ティルの十戒』第七戒 p168:いのちのことば社)だなどと言っているが、大間違いである。彼は卓越した徹底的な有神論の信仰を持っていたが、黙示録においては一般信徒とほとんど変わらない理解しか持っていない。それゆえ、このような優れた神学者が大淫婦をこの世と解釈しているからといって、我々はその解釈を受け入れてはならない。特に権威者に従順な傾向を持つ日本人の牧師は注意せよ。この残されたユダヤ人たちが『その殺人や、魔術や、不品行や、盗みを悔い改めなかった』と書かれているのは、つまり纏めて言えば律法違反のことを指す。殺人や魔術や不品行や盗みが律法に反する邪悪な行ないだというのは誰の目にも明らかである。実際、彼らは多くの義人たちを殺し(マタイ23:34)、神に選ばれた民であるのに神から離れて偽りの神々に従うという魔術を行ない、真の夫である神に従わずにサタンに従うという霊的な不品行を犯し、神に服従という名の負債を払わないことで神に対して盗みを働いていた。このような悪事のためにユダヤには破滅的な裁きが下されたのだが、それにもかかわらず、この残されたユダヤ人たちは神の前に遜らなかったのである。なお、ここで言われている『殺されずに残った人々』がローマ人だと思われる方がもしかしたらいるのではないかと思う。それは、ここで言われていることがローマ人についてのことだと感じられるからである。しかし、この7つのラッパによる預言はユダヤを対象としたものであって、たとえこの第6のラッパの箇所で言われている『人類の3分の1』(9:18)をローマ人だと仮定したとしても、当時無数のローマ人が『殺された』(同)ということは確認できない。というのも、ユダヤ戦争の際、ローマ軍にはユダヤとは違ってあまり死者が出なかったからである。だから、ここで言われているのはローマの人たちではなくユダヤ人であったと考えなければならない。
(※)
『どうして、遊女になったのか、忠信な都が。公正があふれ、正義がそこに宿っていたのに。今は人殺しばかりだ。』(イザヤ1章21節)
『しかし、あなたがた、女卜者の子ら、姦夫と遊女のすえよ。ここに近寄れ。あなたがたは、だれをからかい、だれに向かって口を大きく開いて、舌を出すのか。』(イザヤ58章3~4節)
[本文に戻る]
この残されたユダヤ人たちは、自分たちの拝んでいた『金、銀、銅、石、木』であった。彼らは純粋な人間ではなかったと言ってよい。何故なら、偶像を造ったりそれに心を据える愚か者たちについて、詩篇ではこう言われているからである。『彼らの偶像は銀や金で、人の手のわざである。口があっても語れず、目があっても見えない。耳があっても聞こえず、鼻があってもかげない。手があってもさわれず、足があっても歩けない。のどがあっても声をたてることもできない。これを造る者も、これに信頼する者もみな、これと同じである。』(115篇4~8節)つまり人は、自分が崇拝する存在と同一の存在となる。金を崇拝する者は金も同然となり、石を拝む者は石に等しい者となる。ここでは『悪霊ども』とも書かれているから、彼らは物質であったと同時に悪霊どもだったと言っても間違いではない。実に、彼らが悪霊であり只の物質に過ぎない存在だったからこそ、彼らは神の命令を受け容れず、神に対して悔い改めることもしなかったのである。悪霊や只の物質が、どうしてそのようなことをするであろうか。彼らは悪霊が神に反逆するのと同じように神に反逆し、只の物質が神の言葉を聞かされても無反応なのと同じように神の言葉を聞いて心を引き裂くということをしなかった。だからこそ彼らは、悪霊どもが人の中から追い出されるように神の国から追い出され、消し去れない汚れに満ちた金や銀や銅や石や木が永久に捨てられてしまうように神の前から永久に捨てられてしまったのである。それらの刑罰が下されたのは、彼ら自身が持つ偶像崇拝の罪ゆえであった。
今の時代に生きているユダヤ人たちは、この残されたユダヤ人たちの子孫である。彼らの先祖は、キリストを否んで滅ぼされた者たちの生き残りなのである。つまり、彼らはキリストを信じた敬虔で幸いなユダヤ人たちの子らではない。今に至るまでユダヤ人たちが、キリストを否み続け(ユダヤ人で真のクリスチャンと言える者はほとんどいない)、愚かなことを考え、また耐え難いほどの高慢な精神を持っているのは、実にこれが理由である。彼らは邪悪で不敬虔な反逆者たちのDNAを受け継いでいるのだ。だから、今まで2千年の間に存在したユダヤ人たちが不敬虔で邪悪であったとしても驚くには値しない。今の時代に世界で陰謀を働かせているユダヤ人たちを見てみるがよい。紀元1世紀にキリストを否んだユダヤ人とそっくりではないか。これからも彼らは今のような状態を永遠に続けることであろう。他の民族の血が入らない限り、彼らの持つ「血」の性質は変わることがないからである。傾向としては弱まってきているものの、今でも彼らは同族結婚をする傾向を持つ。この傾向が無くならない限り、彼らは言わば呪われた標本としてこの地球上に存在し続けることになるであろう。
ここで一旦ラッパによる預言の流れが途切れ、すぐに挿入が加えられる。その挿入箇所は10:1~11:13までである。11:14になると、ラッパによる預言が再開される。その再開した箇所で語られているのは、6つ目のラッパについての末尾および7つ目のラッパによる預言のことである。聖書がこのように流れを中断させて挿入箇所を加えているのだから、私もそれに応じてラッパによる預言の解き明かしを中断させ、挿入箇所の解き明かしに取り組まなければいけない。
第12章 ⑨10章1節~11章13節:挿入―ネロによる大患難の前に起きる出来事から再臨の日に起こる携挙の出来事までについての預言
それにしても、このような突然の挿入は、誠に驚くべきものである。人間に過ぎない者がこの文書を書いたとすれば、このような理解を超えた挿入は決してしなかったであろう。誰がこのような挿入を企てるであろうか。人間であれば、このような挿入を加えず、そのまま第7のラッパによる預言を書き記していたに違いない。神は、その英知によりこのような挿入をなされることで、ご自身の造られた人間に与えられた理性を低く見てはおられないことを我々に示しておられる。つまり神は、人間の理性を低く見積もってはおられないからこそ、このように挿入を加えることで更に難解さを増し加えられたのである。このことからも言えるが、黙示録は知れば知るほど、それが神の手になるものだということが感じられるようになってくる。事実、黙示録は神がその手により書き記された文書に他ならない。だからこそ、黙示録はこれほどまでに知的で崇高で神聖で深遠で複雑で天的で難解なのである。神がその手で書かれたというのでなければ、このような黙示録の特異性を説明することは決してできない。これが人間の手になるものであったとすれば、それは矮小な人間によるものに過ぎないのだから、このような内容とはなっていなかったであろう。実際、人間の書いたもので、黙示録に匹敵するようなものは一つすらもないのである。
この挿入箇所は、2つに区切ることができる。一つ目は10:1~11までである。ここでは、一人の御使いが第7のラッパが鳴り響く前にヨハネに巻き物を渡している光景が描かれている。この巻き物の描写により、10:1~11:13の箇所が挿入箇所であって、それまでの流れには属さない箇所であるということが分かるようにされている。二つ目は11:1~13である。ここではヨハネが御使いから受けた巻き物の預言がどのような内容であったか書き記されている。この箇所は、第6と第7のラッパの中間に書かれてはいるものの、あくまでも特別な挿入箇所であるから、これがラッパの預言に含まれるものだと考えないように注意せねばならない。つまり、この挿入箇所で書かれている預言は、ラッパの預言とはまた分離して考えるべきものである。
【10:1】
『また私は、もうひとりの強い御使いが、雲に包まれて、天から降りて来るのを見た。』
これは聖なる御使いであって、悪しき御使いではない。何故なら、この御使いは10:6の箇所で神に向かって誓いをしているからである。このような行為をしている悪しき御使いが、神の示された幻の中で描かれることはあり得ない。それは、聖徒たちを侮辱するも同然の啓示である。神は、ご自身の聖徒たちに異常な幻を示すことで、ご自身の聖徒たちを弄ばれるお方ではない。しかし、この『強い御使い』の名前については、我々には何も分からない。ここでは、ただ『強い御使い』と言われているだけだからである。また聖書ではキリストも御使いとして語られることがあるが、この箇所で出てくるのは御使いとして表示されているキリストではない。というのは、先の場合と同じ理由であるが、この御使いが神に向かって誓いをしているからである。これがキリストであれば、このようなことはされなかったであろう。キリストは黙示録において『子羊』(5:6)また『人の子』(14:14)また『白い馬』(6:2、19:11)に乗る存在として出てくるのであって、御使いとしては描かれていないのだから、この箇所で言われているのは間違いなく真の御使いである。
この御使いが『雲に包まれて、天から降りて来』たのは、この御使いの持つ『巻き物』(10:2)に記されている預言の中では、キリストの再臨が内容的に含まれているからである。つまり、この御使いが雲と共に天から来たのは、キリストがそのようにして再臨されることを予表している。これは、あたかも次のように言っているかのようである。「私の持つ巻き物にはキリストの再臨の時期における出来事が預言されているが、その再臨は私が現われたごとくに起こるのだ。だから私はそれを示そうとして、キリストの再臨を私の現われにおいてあらかじめ予告したのだ。」7:2で出てきた『日の出るほうから上って来た』御使いも、太陽が現われるかのようにして現われる再臨のキリストを示していた。黙示録において、御使いはこのようにキリストそのものを影のように指し示す役割をも持っているのである。キリストが雲と共に天から再臨されるというのは、既に第2部の箇所で説明された。なお、この『雲』を御使いの権威を示すものとして捉える方がいるかもしれない。「雲」が権威を示すものであるというのはその通りだが、この見解よりは、私がたった今述べた見解を採用したほうがより良いと思う。何故なら、この御使いは、この箇所でキリストを予示していると捉えたほうがしっくりと来るからである。
『その頭上には虹があって、その顔は太陽のようであり、その足は火の柱のようであった。』
御使いの『頭上には虹があっ』たのは、この御使いが指し示している再臨のキリストが、大水をもって世界を裁かれることはされないからである。「虹」とは、神がもはや大洪水により人類を滅ぼされることはないということを示した、神と人類との間に結ばれた平和の契約の徴である(創世記9:8~17)。確かに、再臨の際に、キリストが大水の使用により裁きを下されることはなかった。ここでは次のように言いたいかのようである。「再臨の時にはノアの時のような大洪水が地を覆うことはない。神が虹を平和の契約の徴として創出されたのに、どうしてそのようなことが再び起こるだろうか。キリストが来られる時には、大水ではない他の事象により裁きが下されるのだ。」
御使いの『顔は太陽のよう』であったのは、再臨されたキリストの御顔が太陽のようであったことを示す。確かに再臨の際、キリストの御顔は太陽のように照り輝いていた。イザヤ2:10~22の箇所では、再臨されたキリストの御顔の輝きにおける凄まじさが教えられている。パウロがⅡテサロニケ2:8の箇所で、ネロは『来臨の輝き』により滅ぼされると言ったのも、再臨されたキリストの御顔が非常に照り輝いているということを我々に教えている。黙示録の場合、まだ再臨されていないのに既にキリストの御顔が『強く照り輝く太陽のようであった』(1:16)と書かれている。キリストは神であられるから、その御顔が太陽のように輝いておられるのは当然である。太陽を造られた方の御顔が、太陽のようにか、または太陽以上に照り輝いておられないということが、どうしてあるであろうか。
御使いの『足は火の柱のようであった』というのも、やはりキリストの再臨を予表している。これは、つまり『地はわたしの足台』(イザヤ66章1節)と言われるキリストが、その敵をご自分の足の下に従わせる再臨の時に(ヘブル10:12~13)、その足で敵をことごとく踏み砕かれるということを示している。足が『火の柱のようであった』のは、キリストが再臨される際には火が伴うからである(※)。この部分は次のように言っているかのようである。「御使いである私の足が火の柱のようであったのは、キリストが火と共に再臨され、その足で火と共に敵どもを踏み砕かれることを表わしているのだ。キリストが来られる際には、火と共に聖なる足が敵どもを粉砕されるということを知りなさい。」この表現は、正にキリストの再臨を表わすのには絶好の表現である。この幻を示されたのが神でなければ、このような幻を示すことはできなかった。人間の中で誰が再臨をここまで正確に、そして象徴的に表わせるであろうか。『足は火の柱のようであった』という表現は、再臨そのものであるとさえ言えるほどである。
(※)
『そのことは、主イエスが、炎の中に、力ある御使いたちを従えて天から現われるときに起こります。』(Ⅱテサロニケ1章7節)
[本文に戻る]
【10:2】
『その手には開かれた小さな巻き物を持ち、』
御使いがその手に『開かれた小さな巻き物』を持っていたのは何故か。それは、この巻き物に記されている預言が、7つのラッパによる預言とは異なった預言であるということ、すなわちこれまでのラッパの預言の流れに沿わない預言がこれから語られるということを我々に教えている。『巻き物』という言葉はそれが今までに語られていたラッパにによる預言ではないということを、『小さな』という言葉はそれが短い内容であるということを意味する。後者のほうについては、確かにこの巻き物による預言が書き記されているのは11:1~13の箇所だけであるから、「小さい」すなわち短いと言える。つまり、少しの文字しか書かれていないからこそ、この巻き物は小さかったということである。
この『小さな巻き物』が、視覚的にどのようなものであったのかと問う人が誰かいるのか。このような問いは、あまり重要でなく、知らなかったとしても問題は起こらない。もし無理に詮索しようとすれば、些細なことに拘る愚かな者にならざるを得ない。だから、我々はこの巻き物が『小さな』巻き物であり、そこにはラッパの預言に属さない預言が書き記されていたということなどを知るだけで満足すべきである。たとえこれだけ知っているだけでも十分だからである。この巻き物が、例えば何センチだったとか、色は何色だったとか、そこに記されている文字の筆跡はどのような感じだったか、などといった些細なことを知ったとして一体何になるであろうか。そのようなことを知れたとしても、単に好奇心が満足させられるだけに過ぎない。
このような巻き物による預言の箇所が急に挿入されたのは、黙示録が恵みを受けた者にだけ理解されるようになるためであった。恵みを受けていない者たちは、このような突然の挿入のゆえに、ただでさえ難しい黙示録が更に難しく感じられるようになり、ますます混乱してしまう。謎に謎が積み重ねられるので、ちょうど非常に多くの内容量を持つ大作を読もうとしてもなかなか気が向かないように、一つ一つ読み解こうとする意欲さえ削がれてしまう。つまり、そこに天にまで届くかと思えるほどに高い難解という名の壁がそびえ立っているので、黙示録を理解しようとする気さえ起こらなくなってしまう。今までほとんど全ての教師たちが―あのカルヴァンやアウグスティヌスさえもが―、この黙示録に手を出してこなかった、いや正確に言えば手を出そうにも出せなかったのは、このような挿入による難解さの増大も一役買っていたわけである。しかし恵みを受けた者たちは、このような挿入箇所を神の恵みによりあたかもサーファーが激しい荒波の上を走るかのように攻略することができ、そのように攻略できることを神に感謝するのである。たとえ一定の間は難解さに悩まされていたとしても、恵みを受けた者たちは、やがてその難解さを読み解けるようになるに至る。神は、福音と同じように黙示録が少しの者だけに悟られたならばそれよいと思われたので、あえてこのような挿入を加えて難解さを増大させることをよしとされた。何故なら、もしこのような挿入により黙示録が難しくならなければ、それだけ多くの者たちが黙示録を容易に悟れるようになってしまうからである。しかし、このようなことを聞くと「多くの人たちが理解できないほどに黙示録を難しくされた神は冷たいお方だ。もし神が愛であれば、どうして黙示録を多くの人が理解できるようにもっと簡単にされなかったのか。こんな挿入をされるのが愛の神なのか。」などと神を非難する人がいるかもしれない。私は言うが、このように文句をつける人は、黙示録以外に存在している少数の者にしか理解できないほどの難解さを持つ学問や書物や知識についても、黙示録のことで神を非難するようにそのことで神を非難せねばならくなるであろう。例えば、その人は「どうして神は相対性理論を多くの人が理解できるほどに簡単なものとされなかったのか。」とか「神は世界の創世から6千年経過してもまだ人間が理解できないほどに脳を複雑に造られたが(※)、どうして神は人間がすぐにも理解できるような簡単さを持った構造にしなかったのか。脳がもっと簡単な構造であったとすれば、もっと多くの人が脳について理解できていたではないか。」などと言って神を非難せねばならなくなる。何故なら、黙示録の難解さを通して神を非難するというのであれば、その他の難しいものにおいても神を非難しないというのは理に適っていないからである。世にある難解だと感じられるもののうち、黙示録だけを殊更に取り上げて神を非難するというのが道理に適っていないということは、まだ幼い小学生でも分かることである。もし黙示録の難解さに不満を持つがゆえ黙示録の著者であられる神を非難するのであれば、その人は、黙示録以外の難しいものにおいても神を非難するがよい。そのようなことをすれば、多くの人から気難しい異常な人間だと見做されるだけなのが落ちである。
(※)
スティーブン・ホーキングも言うように、人間の脳のことは21世紀になっても、あまりよく分かっていない。
[本文に戻る]
先にも述べたように、この『小さな巻き物』による預言は、7つのラッパによる預言には属しておらず、それゆえ7つのラッパとは別のものとして捉えることができる。たとえこの『小さな巻き物』による預言を単体的に認識し、把握したとしても問題はない。7つのラッパをより純粋に把捉したいと願われる方は、試しにこの挿入箇所である10:1~11:13の部分を抜きにして、7つのラッパが記されている箇所(8章~11章)を読んでみるとよい。そうすれば、この7つのラッパについて、より明瞭な認識を持てるようになるはずである。
この巻き物が『開かれ』ていたのは、この巻き物が元から封印されていなかったか、元は封印されていたがヨハネがこの幻を見ている時には既にキリストが解いておられた、ということである。どちらが真実であったかは何も書かれていないので分からない。しかし、いずれにせよ、この巻き物が『開かれ』ていたのは、キリストによる解除がされなくてもよい状態にあったということを教えている。これは7つのラッパの預言が語られている最中に挿入されるべき預言であったから、すぐにも開示されるように、あらかじめこの巻き物は開かれている必要があったのである。
『右足は海の上に、左足は地の上に置き、』
この箇所では、キリストが再臨される際には万物がその両の足で従わせられるということを、この御使いにより示そうとしている。確かに、キリストは万物がその足の下に従わせられた時に再臨されると聖書は教えている(Ⅰコリント15:23~28)。それは、つまり再臨されたキリストがここで御使いが両足を海と地との上に置くようにすることでなくて何であろうか。しかし、どうして『右足は海の上に、左足は地の上に置』いたのか。足の箇所(すなわち右か左か)と足を置く場所(すなわち海や地か)に何かの関係性があるのか。私は、そこには何の関係性もないと見る。すなわち、ここでは単にキリストの足が地と海とをその下に従わせるということが言われているだけだと考える。読者の中には、ここで言われている右足は再臨の際に幸いな者たちが右により分けられることを示し(マタイ25:34~40)、左足は左に分けられる不幸な者たちを示している(同25:41~45)、と考える人がいるかもしれない。しかし、これは完全な誤りである。何故なら、ここでは右足、すなわち右により分けられる幸いな者たちが、『海』として象徴される永遠に死すべき異邦人となっているからである。これがあの空中の審判の時における左右のことを示したものだとすれば、右足で表示される幸いな人たちが『海』に属していることになってしまうから、このように考えることは絶対にできない。もし右足の置かれている場所が『海』でなければ話は違っており、この見解はいくらかでも検討するに値したであろう。しかし、ここでは『右足は海の上に』置かれたと言われているのだから、この足がマタイ25:31~46で言われている内容と対応していると考えることはできない。なお、キリストが万物をその足の下に従わせることになる再臨は、既に何度も説明しているように、もう起きたということに注意しなければいけない。何故なら、聖書はキリストの御前に立っていた人たちとパウロから手紙を受けた紀元1世紀のテサロニケ人たちが生き残っている間に、つまり今から2千年前の時代にキリストの再臨が起きたと教えているからである(マタイ16:28、Ⅰテサロニケ4:15)。聖書が教えているように使徒の時代に再臨が起きたのだから、その時代に起きた再臨の際、万物はキリストの足の下に従わせられたのである。『信仰の薄い人たち』(マタイ6:30)に私は言いたい。不信仰な理性の思いに妨げられて御言葉が教えていることを素直に受け容れないのは、あまりにも巨大な罪である。私は聖徒たちに、御言葉が教えていることをそのまま純粋に受け容れるようにすることを要請する。そうしなければ、我々は神の御言葉に敵対し、理性のほうにこそ従うことになるからだ。
【10:3】
『ししがほえるときのように大声で叫んだ。』
これは、キリストが獅子の咆哮のごとき恐ろしさを伴わせつつ再臨されるということである。つまり、ここでも御使いが再臨のキリストを予表している。アモスは次のように言った。『獅子がほえる。だれが恐れないだろう。』(3:8)これと同様にキリストの再臨については次のように言える。「獅子であられるキリストが再臨される。だれが恐れないだろう。」確かにキリストが再臨された際、人々は獅子の咆哮を恐れるかのように、再臨されたキリストの前に恐れおののいた。それは、人々が『岩のほら穴や、土の穴に』(イザヤ2章19節)入って身を隠したくなるぐらいの恐ろしさであった。イザヤが言うように、再臨のキリストは『地をおののかせる』(イザヤ2章19節)のであるから、人々が恐れて隠れたくなったのは自然なことであった。また、ここで言われているのは、キリストが実際に獅子のような叫び声を出しながら再臨されたということではない。ここで言われているのは、キリストの再臨の際には、獅子が叫んだかのような巨大音が鳴り響くので人々が恐れおののくということである。それは、イザヤがキリストが再臨される時には『大きな音をもって』(イザヤ29章6節)現われると預言した通りである。
【10:3~4】
『彼が叫んだとき、7つの雷がおのおの声を出した。7つの雷が語ったとき、私は書き留めようとした。すると、天から声があって、「7つの雷が言ったことは封じて、書きしるすな。」と言うのを聞いた。』
『雷』とは、神の裁きについての預言である。何故なら、神が裁きのために来られる時には、雷が伴うからである。それはイザヤ29:6の箇所で、『万軍の主は、雷…をもって、…あなたを訪れる。』と預言されていた通りである。この『雷』が『7つ』であったのは、その預言の数を示している。すなわち、裁きの内容が7つに分割されて語られるべきだからこそ、その裁きを語る雷が7つ出てきたのである。それでは、どうしてこの雷は、御使いが地と海に立って叫んでから声を出したのか。それは、キリストが地上に再臨されてから裁きが下されることになるからであった。すなわち、雷を伴って来られる神の裁きは、神が来られるよりも前に起こるのではない。もし裁きが再臨よりも前に起こるのだとすれば、それは裁判が行なわれる前に刑罰が執行されるようなものである。なお、言うまでもなく、ここで『雷がおのおの声を出した』のは、神がこの幻の中で雷に声を出させた限りにおいてのことである。通常の場合、雷が我々に理解できるような言葉により声を出すということは起こらない。しかし、キリストが言われたように『神にはどんなことでもできます。』(マタイ19章26節)つまり全能の神が欲されたのであれば、今の時代でも、雷が我々に対して分かる言葉で声を出すということは起こり得るのである。信仰者の中で誰がこのことを疑うであろうか。
ヨハネはこの雷の声を書き記そうとしたのだが、天の声に制止させられた。これは雷による預言が開示されるべきではなかったということである。しかし、どうして雷の発した預言は開示されるべきでなかったのか。その理由は、神の聖徒たちに対する愛のためか、または単にこの文書が冗長にならないためである。聖徒たちに対する愛というのは、すなわち裁きの預言が詳しく語られることで、聖徒たちの精神が過度に緊張しないようにするためだということである。冗長にならないためというのは、すなわち神が裁きの時期に関する預言は「封印」と「ラッパ」と「鉢」における計21つがあればそれで十分だと判断されたということである。この雷の声が封じられた理由を、雷による預言がずっと後の時代に起こるためであったと考えることはできない。ダニエルに与えられた預言の場合、それがずっと後に起こる預言だからというので封じられることが命じられた(※)。何故なら、その預言は遥か未来に属することなので、ダニエルが生きていたその当時の段階で公にされても、ただ聖徒たちが悩まされ狼狽することになるだけだからであった。しかし、雷が言った再臨の際に起こる裁きは疑いもなく『すぐに起こるはずの事』(1:1)であって、ずっと後に起こることではない。だから、ここで雷の預言が封じられたのは、それが遥か未来に属するからではなかったということが分かる。もし雷の預言がずっと後に起こるからというので封印すべきだったとすれば、裁きを伴うキリストの再臨はずっと後に起こる出来事だったということになる。しかし、それでは『わたしは、すぐに来る。』(黙示録3章11節)と言われたキリストの御言葉を否定することになってしまうから、ずっと後に起こるからというので雷の預言が封印されたと考えるのは誤っている。
(※)
『先に告げられた夕と朝の幻、それは真実である。しかし、あなたはこの幻を秘めておけ。これはまだ、多くの日の後のことだから。』(8章26節)
『ダニエルよ。あなたは終わりの時まで、このことばを秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探り回ろう。』(12章4節)
『ダニエルよ。行け。このことばは、終わりの時まで、秘められ、封じられているからだ。』(12章9節)
[本文に戻る]
【10:5~7】
『それから、私の見た海と地との上に立つ御使いは、右手を天に上げて、永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方をさして、誓った。「もはや時が延ばされることはない。第7の御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は、神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就する。」』
ここで御使いが誓いつつ言っているのは、2つのことである。まず、ここでは古い世界の終わる時が、もう間もなく訪れるということについて言われている。『もはや時が延ばされることはない。』と御使いが言ったのは、つまり第6のラッパの出来事がユダヤ戦争の時に起きてから、すぐにも第7のラッパの箇所(11:15~19)で示されている古い世の終焉が到来するということである。つまり、この言葉はペテロが『万物の終わりが近づきました。』(Ⅰペテロ4章7節)と言った言葉における「終わりの時」についてのことである。実際、紀元66~70年のユダヤ戦争の時期には、第6のラッパ(9:13~21)で示されたユダヤの破滅が起きると、すぐにも第7のラッパで示されている古い世の終焉が訪れた。第7のラッパで示された出来事がユダヤ戦争においてユダヤが裁かれてから間もなく実現されるというのは、黙示録で示されていることは『すぐに起こるはずの事』(1:1)であったということと一致している。これが、ここで御使いが言っている一つ目のことである。二つ目は、諸々の預言が古い世界の終わりと共に何もかも成就されることになるということである。ここで言われている『神の奥義』とは、『神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就する』ものだから、つまり「旧約時代の預言」のことを意味している。その預言が『もはや時が延ばされることはない』と言われた旧約時代の終わる日に、ことごとく全うされたのである。実際、その日には、あらゆる預言が成就された。それはキリストもルカ21:22の箇所で、『これは、書かれているすべてのことが成就する報復の日』と言っている通りである。このルカ21章は既に説明されたようにユダヤ戦争の預言が記された箇所だから、ユダヤ戦争の起きた紀元66~70年の時に旧約聖書の預言は何もかも成就されたことになる。だから、21世紀の今において未だに成就されていない預言というものは一つもない。これが、ここで御使いが言っている2つ目のことである。
ここで御使いが『誓った』のは、その誓って言ったことが正にその通りに起こるということである。実際、ここで御使いが誓いつつ言った第7のラッパに関することは、ユダヤ戦争の時期に確かにここで御使いが言った通りになった。ただでさえ嘘をつくことのない御使いが、このように誓いつつ確言したのである。であれば、どうしてここで御使いが言ったことを疑ったり不思議に思ったりしていいであろうか。まさか、この御使いが、ここで嘘を信じこませるために誓いつつ言ったなどと考える人はいないはずである。
御使いが誓う際に『右手を天に上げ』たのは、『永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方』すなわち神において誓ったからである。これは、この御使いが『御名によって誓わなければならない。』(申命記6章13節)という戒めの通りにしていることを示すためであった。すなわち、この御使いは神を指して誓ったのであって、『天』や『地』や『エルサレム』や『頭』を指して誓ったのではないということである。このような神以外のものを指して誓うのは、キリストがマタイ5:33~37の箇所で禁止しておられた。だから、この御使いの誓いは、律法にもキリストの御言葉にも抵触していないということが分かる。また、この御使いが神に向けて『右手を天に上げた』のは、この誓いが軽々しくなされたものではないことを示している。聖書において「右」が重要であったり尊重していることを意味しているというのは、既に説明された通りである。この御使いが神を尊崇していたのは疑えない。だからこそ、この御使いは自分の崇めている神を指して誓う際、左手ではなく右手を上に上げたのである。もしこれが右手ではなく左手であったとすれば、ここで行なわれた誓いを信頼せよと言われても無理な話であったと言える。何故なら、その場合、より重要であることを示す右のほうの手が使われていないからである。右手を使わず、あえて左手を使ってなされる誓いが信頼するに値しない誓いだと見做されたとしても、何も不思議なことはない。
この箇所は、新約時代においては誓いが何もかも禁止されているという見解を粉砕する。あらゆる誓いを否認する者たちは、キリストが『決して誓ってはいけません。』(マタイ5章34節)と言われたからというので、どのような誓いもしてはならないと考える。彼らは、ヤコブの『何よりもまず、誓わないようにしなさい。』(ヤコブ5章12節)という言葉も、キリストの御言葉と同様に全ての誓いを禁じたものだと捉える。しかし、我々が今見ているこの箇所では、誰も疑えないほど明瞭に御使いが『誓った』ことについて記されている。もしこの御使いが誓いつつ言ったと考えない人がいれば、その人は知性の問題のある精神障害者として認定されるべきであろう。その人は、白を見て「真っ黒だ」と言っているようなものだからである。確かに、ここで御使いが『誓った』ことを否定することは誰にもできない。ここで御使いが誓いつつ言ったというのは、つまりキリストとヤコブの言葉が、あらゆる誓いを禁じたものではないということでなくて何であろうか。もしキリストとヤコブが全ての誓いを禁じていたのだとすれば、この御使いがこのように誓いつつ言うことはあり得なかった。聖なる神の御使いが、キリストとヤコブが禁じたことをあえて行なうはずが、どうしてあるであろうか。聖なる神の御使いであれば、キリストとヤコブの言葉に逆らうことは絶対にしないはずである。だから、これが聖なる御使いだと疑わないのであれば、この御使いが誓ったことにより、聖書ではあらゆる誓いが禁じられているのではないことが分かる。まさか、この御使いが聖なる御使いであることを疑う人は恐らくいないとは思うが…。つまり、キリストとヤコブが禁じたのは、神を指して誓うのではない律法に違反した誓いのことである。キリストとヤコブは、当時不法な誓いが横行していたからこそ、その不法な誓いを止めさせようとして、一見するとあらゆる誓いを否定しているかのような語り方で誓いを禁じたに過ぎない。パウロは実際に誓いをしているのだから(Ⅰコリント15:31)、もうこれだけでも誓いが全て否定されるべきではないことは明白である。この誓いの問題については、既に今まで多くの学者たちが論じてきたから(※)、これ以上の説明は不要である。私としては、ただ聖書ではあらゆる誓いが禁止されているのではないということが、この箇所からも論証できるということを言いたかっただけである。以上、やや脇道に逸れてしまった感があるが、誓いについていくらかのことを今書かせてもらった。
(※)
例えば、カルヴァンの『キリスト教綱要』やコーネリウス・ヴァン・ティルの『十戒』などで、このことについて論じられている。
[本文に戻る]
また、この箇所は、裁きの日がまだ到来していないという教会で一般的な見解をも粉砕する。何故なら、ここでは第5と第6のラッパにおいて示されているローマ軍の招集およびユダヤに対する裁きの出来事が起きたならば、それから第7のラッパで示されている裁きの日が到来する『時が延ばされることはない』と確言されているからである。第5と第6のラッパで示されている出来事はユダヤ戦争の時期のことであった。その第5と第6のラッパによる出来事が過ぎると、『もはや時が延ばされることはない』と御使いはここで言っている。『時が延ばされることはない』というのは、第7のラッパについてのことである。だから、第7のラッパで示されている裁きの日が到来したのは、ローマ軍が招集されてユダヤに裁きが下されてからすぐだったと考えなければいけない。裁きの日、すなわち『御怒りの日』(11:18)はユダヤ戦争の時期に起こる。これが聖書の教えていることである。思慮ある読者は、よく考え、よく理解し、私の述べたことを信じるべきである。反論する人があれば、その反論を聖句により打ち砕き、その人の口が封じられるようにしてやりたい。もし私に何か間違った見解があれば、その時は、私は自分の考えを改めることであろう。
なお、この10:5~7の箇所は、間違いなくダニエル書10:7の箇所と対応している。ダニエル書のほうでも、聖なる存在が天に向けて右手を上げ(こちらのほうでは左手も上げられている)、神に誓いつつ定められた時のことについて言っている。文章の内容も、骨格的な観点から見れば、よく似ている。このダニエル書10:7の箇所については、また後ほど第4部の中で語られることになる。
【10:8~9】
『それから、前に私が天から聞いた声が、また私に話しかけて言った。「さあ行って、海と地との上に立っている御使いの手にある、開かれた巻き物を受け取りなさい。」それで、私は御使いのところに行って、「その小さな巻き物を下さい。」と言った。』
『前に私が天から聞いた声』とは、10:4の箇所で『7つの雷が言ったことは封じて、書きしるすな。』と言ったあの声である。この声の主は、神か24人の長老か4人のセラフィムかその他の御使いのどれかである。この声の主が「無」であったということは、あり得ない。また悪い存在がこの声の主だったということもない。何故なら、そのようなことは実に不条理だからである。私としては、確信を持って言うことは出来ないのであるが、この声は恐らく神によるものではないかと感じられる。
天の声がヨハネに小さな巻き物を受け取るように命じたのは、ヨハネにその巻き物の預言を語らせるためであった。何故なら、この黙示録という文書は、聖徒たちに預言を与えるためにこそ記されたのであって、この小さな巻き物も聖徒たちが預言を知れるようになるために出てきたのだからである。もしヨハネにこの巻き物を受け取らせなかったならば、何のために巻き物がここで出てきたのか分からなくなってしまう。
このような天の声を聞いたヨハネは、誠に従順な態度で、御使いから巻き物を受け取りに行った。私の思うに、黙示録がヨハネにより記されたのは、恐らく、ヨハネが混じりけのない従順さを持つ聖徒だったからであろう。何故なら、そのような従順さを持っていたのであれば、預言の幻がありのままに書き記されることになるだろうからである。実際、我々が今見ている通り、ヨハネは自分の見た預言の幻をそのまま書き記してくれている。黙示録の預言は長く、無駄な記述抜きに、そのままの状態で聖徒たちに伝えられる必要があったのだから、キリストに関わることであれば何事にも従順な態度で臨むヨハネが筆記者として選ばれたのは誠に理に適っていると言えるのである。もしパウロであったら、自分に示された預言の中に哲学的なことや深遠な記述を織り交ぜていたかもしれない。パウロの書簡の中には、確かに哲学的なことや深遠な記述が満ちている。ペテロであれば、不信仰に妨げられたり、肉的な選択をするなどして、自分に示された預言をありのままに書き記すことはできなかったもしれない。実際、彼はキリストを3度も否み(マタイ26:69~75)、割礼派のユダヤ人を恐れて異邦人から遠ざかったりした(ガラテヤ2:11~14)。ヤコブであれば、預言を記すには記すものの、その中で、聖徒たちに叱責や訓導を大いに与えていたかもしれない。彼の手紙を見れば分かるように、彼はそのようにする使徒であった。ルカであれば、このように霊的な幻を書き記すのには適合していなかったかもしれない。彼は、福音書や使徒行伝を見れば分かるように、崇高で深遠な記述をするよりは、むしろ現実をそのまま記述するほうが適している。いずれにせよ、一つ確かに言えることは、黙示録を記すのにはヨハネがもっとも適任だったということである。もしそうでなければ、神は誰か他の聖徒に黙示録を記させていたことであろう。全知全能の神は、常に最善のことしかなさらない。黙示録をヨハネが記したということは、つまり、ヨハネに黙示録を記させるのが最善だったということでなくて何であろうか。
【10:9~10】
『すると、彼は言った。「それを取って食べなさい。それはあなたの腹には苦いが、あなたの口には蜜のように甘い。」そこで、私は御使いの手からその小さな巻き物を取って食べた。すると、それは口には蜜のように甘かった。それを食べてしまうと、わたしの腹は苦くなった。』
この箇所では、まず、「食べる」と「腹」ということの意味を理解せねばならない。まず巻き物を「食べる」というのは、つまり「巻き物に書かれている預言を聞くこと」である。すなわち「聞く」ことが、「食べる」という言葉で置き換えてここでは言われている。次に巻き物を「腹」に入れるとは、つまり「巻き物に書かれている預言を理解すること」である。すなわち「理解する」ことが、ここでは「腹」という言葉で置き換えられている。腹とは食べた食物を消化して自分の身体に取り込む場所だから、「理解」に替えて言い表わされるのには相応しい部位である。「理解」するとは、聞かされた言葉を心また脳において消化することで、理性的に自分に取り込むことに他ならないからである。このように、この箇所で言われていることは、霊的に捉えなければいけない。これを物質的に理解するのは愚の骨頂である。ヨハネが実際に預言の書かれた巻き物を食べて腹の中に入れたというのは、滑稽以外の何ものでもない。
しかし、どうしてこの巻き物を食べると『口には蜜のように甘かった』が、『腹は苦くなった』のか。すなわち、どうしてこの巻き物に書かれた預言は聞くには良かったが、理解することは悲痛に感じられたのか。それは、この巻き物の預言が、ネロの大患難について語ったものだからである。確かに、この巻き物の預言が記された11:1~13の箇所では、ネロが聖徒たちを迫害して苦しめることについて言われている。このような大患難についての預言は、聖徒たちを愛するヨハネにとっては、実に不快であり悲しむべきものとして感じられた。それはヨハネがこの預言について理解したからである。上で見たように、ここでは「理解」が「腹」に言い換えられている。だから、ヨハネがこの巻き物を食べた際に『腹は苦くなった』わけである。「苦い」というのは辛いとか悲しいという意味である。しかし、この預言を聞くこと自体については、ヨハネにとって喜ばしいことであった。何故なら、聖徒たちは誰でも神の御言葉を愛しており、それを蜜のように、また蜜以上に喜ぶからである。詩篇記者も御言葉について次のように言っている。『あなたのみことばは、私の上あごに、なんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。』(119篇103節)上で見たように、ここでは「聞く」=「食べる」であった。だから、ヨハネがこの巻き物を食べた時には『蜜のように甘い』ものとして感じられたわけである。つまり、ここで言われているのは、簡単に言ってしまえばこういうことである。「この巻き物に記されている大患難の預言においては、その預言を聞くこと自体は大変喜ばしいのであるが、その預言の内容を理解することは誠に辛い。」
この箇所は、明らかにエゼキエル書で書かれた内容と似通っている。そこでは次のように書かれていた。―これは神がエゼキエルに対して言われたことである。―『「…人の子よ。わたしがあなたに語ることを聞け。反逆の家のようにあなたは逆らってはならない。あなたの口を大きく開いて、わたしがあなたに与えるものを食べよ。」そこで私が見ると、なんと、私のほうに手が伸ばされていて、その中に一つの巻き物があった。それが私の前で広げられると、その表にも裏にも字が書いてあって、哀歌と、嘆きと、悲しみとがそれに書いてあった。その方は私に仰せられた。「人の子よ。あなたの前にあるものを食べよ。この巻き物を食べ、行って、イスラエルの家に告げよ。」そこで、私が口をあけると、その方は私にその巻き物を食べさせ、そして仰せられた。「人の子よ。わたしがあなたに与えるこの巻き物で腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせ。」そこで、私はそれを食べた。すると、それは私の口の中で蜜のように甘かった。」』(2章8節~3章3節)ここではヨハネと同じようにエゼキエルも巻き物を食べて蜜のような甘さを感じたことが書かれている。この両方の箇所が互いに似通っているのを疑う人はいないはずである。ヨハネは、このエゼキエル書の箇所を記憶していただろうから、今引用した箇所に基づいて我々が今見ている箇所を書き記したのではないかと思われる。いや、というよりは、むしろ神がエゼキエルに対してなされたのと類似した内容の幻をヨハネに示されたと捉えたほうがよいであろう。何故なら、ヨハネがエゼキエル書の記述に基づいてこの箇所を書いたと言ってしまうと、ただヨハネがエゼキエル書に基づいてこの箇所を書いただけであって、何だか神の示された啓示のゆえにこの箇所を書いたとは感じにくくなってしまうからである。もちろんヨハネがこのエゼキエル書の箇所を記憶しており、その箇所を記述の際に意識していたのは間違いないが、しかしそうではあっても、ヨハネは神がエゼキエルにされたのと類似した幻を啓示されたからこそ、このようにエゼキエル書の内容と類似したことを書くことになったのである。この2つの箇所は、巻き物を食べることだけでなく、巻き物を食べてから語るべきことを語れと命じられているという点まで同一の内容となっている。我々は、このような黙示録と旧約聖書の類似性に注目しなければいけない。何故なら、そのような類似性に注目することは、黙示録をよりよく理解するためには益となるからである。黙示録におけるこのような類似性を心に留めることなしに、黙示録を十全に把握することが可能だなどと考えてはならない。なお、この箇所はエゼキエル書だけでなくエレミヤ書の箇所ともいくらか類似している。エレミヤ書のほうでは次のように書かれている。『私はあなたのみことばを見つけ出し、それを食べました。あなたのみことばは、私にとって、楽しみとなり、心の喜びとなりました。』(15章16節)このエレミヤ書のほうの言い方はエゼキエル書ほどは似ていないが、御言葉を食べて幸いな感覚を味わうという点では、我々が今見ている黙示録の箇所と同一のことが言われている。
では、どうして神はヨハネにエゼキエル書の内容と類似した内容のことを、ここで書かせられたのか。その理由は2つある。第一の理由は、エゼキエル書の内容と類似させることで、黙示録の神聖性と権威とを高めるためである。長い間ユダヤ人の誰からも認められ尊重されてきたエゼキエル書の内容と類似しているというのであれば、黙示録がより霊的な意味において高く見られるようになるのは間違いない。何故なら、その場合、ヨハネがエゼキエルに働いておられたのと同一の霊によって、この黙示録を書き記していたということが分かるようになるからである。神は黙示録を崇高たらしめようと欲されたので、このようにエゼキエル書に類似した内容のことをヨハネに対して示され、それを書かせるようにされたのである。第二の理由は、これまでにも述べたことだが、この黙示録が更に難解にされるためである。ここで書かれているような書き方がされたならば、より多くの人が黙示録を理解できなくなることは目に見えている。霊的に鋭い人でも、この箇所を初めて読んだ時には、いくらかでも深い思考を要求される。何故なら、この箇所では、誰でも分かるような普通の語られ方はされていないからである。神は少数の者だけが黙示録を理解できればよいと欲されたので、このような知恵ある語り方をヨハネにさせることで、恵みを受けていない者が無明の闇に呑み込まれるようになされた。もしこの箇所がごく普通の語られ方、すなわち「ヨハネは神からの預言を聞けて喜びはしたものの、その内容を理解してからは心に深い悲しみを覚えた。」などという語られ方をしていたとすれば、より多くの人たちが黙示録をより容易に悟れるようになっていたはずである。しかし、そのようになることは神の御心ではなかった。これまでにいた無数の教師たちが黙示録をまったく悟れなかったのを我々が見ている通りである。
【10:11】
『そのとき、彼らは私に言った。「あなたは、もう一度、もろもろの民族、国民、国語、王たちについて預言しなければならない。」』
『彼ら』とは誰か。これは、ラッパを持った『神の御前に立つ7人の御使い』(8:2)および途中で介入してきた『もうひとりの強い御使い』(10:1)である。この計8人が『彼ら』なのである。すなわち、これは24人の長老やセラフィムやセラフィムおよび今述べた8人の御使い以外の御使いたちのことではない。
この小さな巻き物に書かれていた預言は『もろもろの民族、国民、国語、王たちについて』の預言であった。何故なら、ここでは小さな巻き物について、8人の御使いたちがそう言っているからである。実際にこの巻き物の預言について書かれている11:1~13の箇所を見ると、どうであろうか。この箇所では『異邦人』(11:2)や『もろもろの民族、部族、国語、国民に属する人々』(11:9)について書かれているから、確かにこの巻き物の預言は『もろもろの民族、国民、国語』についての預言だったことが分かる。また、この箇所では『底知れぬ所から上って来る獣』(11:7)すなわち皇帝ネロとネロにつく将来のローマ皇帝たちのことが語られているのだから、確かにこれは『王たち』についての預言であった。「皇帝」とはすなわち「王」でなくて何であろうか。
ここでヨハネに渡された小さな巻き物の預言が『もう一度』語られる預言だということは、つまり、この預言と同種の預言が既に語られていたということである。そうでなければ『もう一度』とは言われていなかっただろうからである。その既に語られいていた預言とは、既に我々が見た7つの巻き物による預言であった。この7つの巻き物による預言も、確かに『もろもろの民族、国民、国語、王たちについて』の預言であった。何故なら、この7つの巻き物による預言が記された箇所では『地上の王、高官、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人』(6:15)と書かれていたからである。この言葉が『もろもろの民族、国民、国語、王たち』に該当するのは確かである。つまり、既に『もろもろの民族、国民、国語、王たち』についての預言は語られていたのだが、それにもかかわらずヨハネに渡された巻き物により再び同じ種類の預言が語られることになったからこそ、ここでは『もう一度』語りなさいと言われているわけである。要するに、この『もう一度』という言葉は、7つの巻き物による預言に基点を置いた言葉である。この言葉を巻き物による預言ではなく、ラッパによる預言に基点を置いた言葉だと考えることはできない。何故なら、ラッパによる預言とは、『もろもろの民族、国民、国語、王たちについて』の預言ではなく「ユダヤ」についての預言だからである。ラッパの預言と封印の預言は種類が異なっている。だから、ラッパによる預言に基づかせて言ったのであれば『もう一度』という言葉をここで使うことはできなかった。その場合、この小さな巻き物による預言は『もう一度』される預言、すなわち「2度目」の預言とはならなかったからである。
それにしても、黙示録は本当にパズルのようである。黙示録は再臨の時期に起こる出来事を、複数の部分に切り分け、様々な配置により不思議な仕方で並べ、また色々な語り方で語っている。それでいながら、あらゆる箇所がよく調和している。これは神の組み立てられた霊のパズルであると言ってよいのではないかと思う。だから、黙示録は一つの部分が分かると自然と他の部分も分かるようになり、言わば解読の連鎖反応が起きる仕組みになっている。しかし、解読できないと、これは多くの者がそうなのだが、まったくどの部分も分からず、あまりにも難解なので諦めて解き明かしの作業から遠ざかってしまう。それゆえ、黙示録を豊かに解読できる聖徒は、神に感謝していただきたい。その人は神から恵みを受けているからである。恵みを与えられなければ、どうして黙示録を豊かに解読できるであろうか。ヨハネが『人は、天から与えられるのでなければ、何も受けることはできません。』(ヨハネ3章27節)と言っている通りである。神が、この作品において黙示録の解き明かしをさせて下さっておられることに感謝、感謝。アーメン。
【11:1~2】
『それから、私に杖のような測りざおが与えられた。すると、こう言う者があった。「立って、神の聖所と祭壇と、また、そこで礼拝している人を測れ。聖所の外の庭は、異邦人に与えられているゆえ、そのままに差し置きなさい。測ってはいけない。』
『こう言う者』とは、神のことである。何故なら、ここでヨハネに話している者は、すぐ後の箇所で2人の預言者を『わたしのふたりの証人』(11:3)と言っているからである。預言者を自分の証人として取り扱えるのは、当然ながら神だけである。神でもないのに、預言者を「私の証人」などと言える存在がどこにいるであろうか。もしいたとすれば、その存在は何と傲慢な思い違いをしていることか。また、この声の主は更に具体的に言えば「キリスト」である。というのは、この声の主が預言者を『証人』と言ったのは、つまりこの預言者が、イエスがキリストであるということの証人だという意味だからである。もしこれが人として来られた神の御子についての証人でないとすれば、一体何の証人だというのか。もしこれがキリストの証人以外ではないとすれば、この預言者を証人として取り扱っている声の主もキリスト以外ではないことになる(※)。
(※)
カルヴァンは、「預言者という語は、『コリント人への第一の手紙』から考えられるように、新約聖書では種々に解釈されている」(『新約聖書註解Ⅴ 使徒行伝 上』11:27 p349:新教出版社)と言っている。ここでの預言者は、実際に預言の賜物を持った無数のキリストの証人なる聖徒たちのことを言っている。これは単なる宣教者や教師という意味に過ぎないものではない。
[本文に戻る]
『杖のような測りざお』は、『神の聖所と祭壇と、また、そこで礼拝している人を』測るためのものである。それらのものを測るために、この測りざおがヨハネに与えられた。
ヨハネは、どうしてこれらのものを『測りざお』により測るようにと言われたのか。これは非常に難しいことであるから、分かるように説明されねばならない。ヨハネがこれらのものを測るように命じられたのは、つまり、『礼拝している人』である神の聖徒たちが測られることで、どの人も例外なく1デナリの救いを受けるようになることを示すためであった。すなわち、ここで測るように命じられたのは、先に見た第3の封印の預言で示された黒い馬の出来事と対応している。この黒い馬に乗っている者も、『量り』(6:5)を手に持っており、聖徒たちを計測する役割を委任されていた。ヨハネが『礼拝している人』を測ったのは、つまり聖徒たちが測られて1デナリの救いを受けるという預言である。ここでヨハネは、マタイ20:1~16の箇所におけるぶどう園の主人を演じさせられているわけである。もちろん、実際に聖徒たちを測るのはヨハネではない。どうしてヨハネがそのような行為をここで命じられたかといえば、それはすぐ後の箇所で、再臨の際に起こる1デナリの救いについて描かれているからである。確かにこの小さな巻き物の預言が記されている箇所(11:1~13)の中では、キリストが再臨されると起こる1デナリの救い、すなわち第一の復活のことについて記されている。『神から出たいのちの息が、彼らにはいり、彼らが足で立ち上がった』(11:11)と死んでしまった聖徒たちの復活について書かれている通りである。要するに、ここでヨハネに命じられた測りの行為は、11:11の箇所を実際の行ないにおいて説明したものである。つまり、小さな巻き物の中で1デナリの救いが記される前に、あらかじめヨハネの行為を通してそのことが示されたのである。よって、ここで言われている『神の聖所と祭壇と、また、そこで礼拝している人』とは、天上におけるそれではない。これは地上におけるそれである。何故なら、天上における聖所と祭壇の場所にいる聖徒たちは、既に贖われいてるので、もはや測られて1デナリの救いを受ける必要がないからである。その上、天上における聖所には異邦人も入場可能な『外の庭』がないのだから(※)、尚更のこと、これが天上におけるそれではないと言える。これを天上におけるそれだと考えると、何を言っているのか分からなくなるはずである。しかし、地上におけるそれだと考えると、誤った理解に陥ることもない。
(※)
旧約時代における石造りの神殿は、庭であれば異邦人も入ることができた。しかし聖所はユダヤ人しか入ることが許されていなかった。
[本文に戻る]
一方、『聖所の外の庭』を『測ってはいけない』と命じられたのは、そこにいる異邦人は異邦人であるゆえ、測られることがなく、それゆえ1デナリの救いを受けることもないからである。彼らは、聖徒たちとは違い、そもそも主のぶどう園に来てさえいない。だから、彼らに対しては測る行為をすべきではなかった。というのも、測るということは、つまり1デナリの救いを与えることを意味するからである。救いが与えられるからこそ測られるのであって、測られるのは救いを前提としている、ということは確かである。だから主のぶどう園に来ていない労務者が、計測を受けて、1デナリを貰ったとすれば、それは大変おかしな話である。もしヨハネがここで異邦人をも測っていたとすれば、測るのは救いのためであるのだから、救いを受けられない異邦人さえもが1デナリの救いを受けられるということになっていた。それは全くもってあり得ないこと、あってはならないことである。主のぶどう園に来ていない者も救われるというのは、万人救済論(ユニバーサリズム)であって、異端の教えである。それが言語道断なことだからこそ、神はここで異邦人について『そのままに差し置きなさい』と命じ、ヨハネが測ることを禁じられたわけである。
また、ここで神が『立って』とヨハネに言われたのは、ヨハネが恐らく座っていたからだと思われる。何故なら、通常の場合、話しかける対象が座っているからこそ、立ち上がらせようとして『立って』云々などと言われるものだからである。しかし、ただヨハネが真面目に事に当たるようになるために、このように『立って』と言われたということも考えられる。ヨハネは言うまでもなく心から、熱心に測る作業をしなければいけなかったのだから、そのようにさせるために『立って』と命じられたとしても何も不思議ではない。この場合、つまり身体的というよりは精神的な意味において『立って』などと言われたことになる。すなわち、その場合、『立って』という言葉は「真面目にやりなさいよ。」という意味だということである。とはいっても、ヨハネが実際にどのような状態で幻を見ていたのか分からないから、この言葉の意味について確定的なことを言うのはかなり難しい。もっとも、この言葉の意味について確定的なことが分からなかったとしても、黙示録の理解に重大な影響を及ぼすということはないのではあるが。
【11:2】
『彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじる。』
ここで言われている『聖なる都を42ヶ月の間踏みにじる』期間とは、いつか。この期間は、『底知れぬ所から上って来る獣』(11:7)が聖徒たちを迫害する『42ヶ月間』(13:5)の前に起きる聖徒たちの『1260日』(11:3)における活動期間よりも前の42ヵ月間であるから、『獣』(11:7)であるネロの迫害が始まった期間を知れば、すぐにも答えが出て来る。何故なら、簡単に言えば、この踏みにじりの期間はネロの迫害が始まる84ヶ月前に始まるからである。まず、これは後にも詳しく論じられることになるが、ネロが42ヶ月間活動する期間を、ここでは紀元64年12月~68年6月までとする。そうすると、ネロの迫害よりも前に起こる聖徒たちの活動期間である『1260日』(11:3)は、61年6月~64年11月までだったということになる。であれば、聖徒たちの活動期間よりも前に起きるこの「聖なる都の踏みにじり」の期間は、57年12月~61年5月までだったということになる。ここで言われている『42ヶ月間』を文字通りに、すなわち象徴として見ずに捉えるのであれば、このようになる。踏みにじりの始まったこの57年12月は、ネロが皇帝になった時(54年10月13日)から凡そ3年と2ヶ月後である。
具体的な期間が数字として出て来るのは、黙示録では、これで2度目である。1度目は第5のラッパによる預言が記された9:1~12の箇所であり、そこでは『5ヶ月』(9:5、10)と書かれていた。この『42ヶ月』という期間が出て来ることについて言えば、黙示録では、ここで最初に出て来る。これは第1部でも説明されたように、『1260日』(11:3)また『三日半』(11:9、11)すなわち「3年6ヶ月」また『一時と二時と半時』(12:14)でもあって、黙示録ではこれ以降の箇所でも繰り返し出て来る。また、この期間は明らかにダニエル書の記述に基づいている(ダニエル7:25、12:7、11)。しかし、神はどうしてある特定の期間を、このようにして複数の言い方で表現されたのか。すなわち、神はどうしてこの期間を一つの言い方だけに絞られなかったのか。それは、黙示録が更に難解になるためであった。神は、簡単には理解させないようにと、このようにあえてこの期間を複数の言い方で言われることにより、より黙示録が理解しにくい文書となるのを欲された。このような複数の言い方のゆえに、恵まれていない者たちは、黙示録の正しい理解から遠ざけられてしまうのである。つまり、理解しない者が永遠に理解しないようになるためにこそ、あえて複数に分けられた言い方がされているわけである。それゆえ、恵みを受けていない者たちは、この数字(42=1260=3.6=1/2/0.5)を目にして混乱してしまうので、いつまでも分からず、悟れず、無明の闇から抜け出ることができないままとされる。これが一つの言い方だけであれば、多くの者が黙示録を容易に理解できるようになっていたかもしれない。それではこの期間は、実際の期間を表わしているのか、それとも単なる象徴数に過ぎないものなのか。この『42ヶ月』という期間は、基本的には実際的な期間であると見做すべきであるが、しかしラフに捉える必要がある。というのも、これを厳密にその通りに捉えると、実際の歴史と調和しなくなってしまうからである。しかし、ラフに捉えると、実際の歴史と驚くほどに調和する。聖書では、ある数字を霊的な恣意に基づきラフに取り扱っている箇所が、いくらかある。例えばルターも指摘しているがキリストの系図を記したマタイ1:1~17の箇所ではいくらか代が恣意的に数えられているし、サウルの統治期間はⅠサムエル記13:1では『12年間』と書かれているがパウロは『40年間』(使徒行伝13章21節)としているし、創世記46:27と申命記10:22ではエジプトに行ったヤコブの家族が全部で『70人』と書いてあるがステパノは使徒行伝7:14の箇所で『75人』と言っている(※①)。我々が覚えねばならないのは、聖書は歴史書のように厳密な数字を提供することが目的とされているのではなく、神の聖なる意志が御民に告げ知らされることを至高の目的としているということである(※もちろん、だからといって聖書に出て来る数字が常に厳密性を欠いているというのではなく、聖書の多くの箇所では驚くほど正確に数字が書き記されているということを忘れてはならない)。だから、この『42ヶ月』をいくらかラフに捉えて理解したとしても何も問題は生じない。もしそのように捉えることを非難すべきだとすれば、数字を恣意的に捉えたマタイやパウロに対しても非難せねばならなくなってしまう。また、この数字は、驚くべきことだが、他の箇所で出て来る数字と同一の数字となっている。例えば、この数字はエリヤの祈りが聞かれた期間である『3年6ヶ月』(ヤコブ5章17節)と同じ数字であるし、すぐ後に見るキリストの系図における42代と同じ数字であるし、レビ人に与えられた『42の町』(民数記35章6節)と同じ数字である。。これは一体どういうことか。これは、つまり、この数字は「神の定め」であることが示されているということである。この数字が使われている期間や事象があれば、それは神が定められたからこそそのようになったということが強調されている。もちろん、全てのことは例外なく神の定めに基づいているのではあるが、この数字は特に神がそれを定めておられるということ、また神がその数字で表わされていることを強調しておられるということを我々に教えている(※②)。だから、この数字により表わされている何かが聖書に出てきたら、我々は神のことを思うべきである。すなわち「神が定められたからこそこのような期間となっているのだ。」とか「これは注目すべき期間なのだ。」などと思うべきである。それでは、この数字は分割可能であるのか。この数字を分割できるとすれば、24×2、7×6、14×3の3つが候補として出てくる。まず24×2であるが、これは意味がよく分からないので斥けられるべきである。次に7×6であるが、これも意味が分からないので、そのように分割するべきではない。では14×3はどうか。この42という数字は、明らかに14×3に分割されるべき数字である。何故なら、マタイがキリストの系図を記している箇所では、14(代)が3つ書き記されているからである(※③)。マタイが42を14×3に分割しているのだから、42ヶ月とは間違いなく14を3つ合わせて構成した期間である。バラムがバラクに用意させた動物も合計すると42頭であって、これは驚くべきことなのだが、バラクは1回分を14頭として3回用意させられることになった(民数記23:1~2―1回目、23:14―2回目、23:29~30―3回目)。これも間違いなく14(頭)が三つ分重なって42(頭)となっている数字である。これはつまり、それぞれ同一の本性であられる3つの位格を持つ神が定められた数字だということである。神を仮に「42」だとすれば、その3つの位格がどれも同質、すなわち14、14、14であられることを疑う聖徒はいないであろう。三位一体であるということは、つまり一人の神であり(42)、本質を同じくする3つの位格(14、14、14)だということでなくて何であろうか。このようにこの42という数字が三位一体神に関わっていると考えると明確に理解できるようになるのだから、この数字は14×3として分割されねばならない。つまり、この数字は特に神がその背後におられることを示す数字なのである(※④)。アレイスター・クロウリーの場合、この「42」を不毛の数だと言っているが、これは魔術上の意味においてであるから、聖書の数字においても同様のことを考えるべきではない。この『42ヶ月』という期間については本書においてこれからも繰り返し説明がなされるだろうから、これから読者は、その説明を読むことにより、ますますこの期間について理解を深められるようになるであろう。
(※①)
これについてはカルヴァンが筆写した者の誤りであったと見ているが、筆写者の誤りだった可能性以外にも、恣意的な言い換えであったか、または旧約聖書とは何か別の方法による数え方を採用したということも考えられる。いずれにせよ、旧約聖書の数とステパノの言った数が一致していないことは確かである。これを恣意的な言い換えであると捉えるならば、私が今述べていることにおける論証力が更に強められることになろう。
[本文に戻る]
(※②)
カエサルが終身独裁官だった期間は3年4ヶ月5日(前46年―前44年3月15日)であったが、これは2ヶ月ほど違うものの、聖書でよくされるように大まかに捉えれば「42ヶ月」とすることも出来なくない。カリグラの統治期間―統治というよりは暴虐を働いていただけのようにも感じられるが―も3年10ヶ月8日(37年3月16日―41年1月24日)であって、これも聖書の手法にかかれば「42ヶ月」として取り扱えないわけではない。キリストの公生涯の期間は「3年」と年のほうだけ言われ月のほうには言及されないことが多いが、キリストの期間を3年6ヶ月、つまり「42ヶ月」と捉えることも不可能ではないであろう。キリストほど特に神からその人生が定められたお方は他にいないのだから。
[本文に戻る]
(※③)
『それで、アブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代となる。』(マタイ1章17節)
[本文に戻る]
(※④)
Ⅱコリント12:2でパウロは自分が『14年前に』第三の天に引き上げられたと言っている。また使徒行伝27:33でもパウロは船にいた人たちが『14日』の間、何も食べなかったと言っている。この2つの箇所で言われている「14」と「42」には何か関わりがあるのだろうか。パウロが14年また14日と言ったのは、つまりそれが非常に短い期間、すなわち完全ではない期間だという意味である。何故なら、そこでは一つの位格分の数字しか言われていないからである。またアブラハムがイサクを産んだのはイシュマエルを産んでから14年後であったが(創世記16:16、21:5)、これもイシュマエルが産まれてからすぐにもイサクが産まれたと理解すべきことを要請している。実際、アブラハムにとってイサクが産まれるまでの14年間は矢のように素早く過ぎ去ったことであろう。ヤコブがラケルとレアのためラバンに仕えた年数も『14年間』(創世記31:41)だったが、これもヤコブが働いた年数はあっという間に過ぎてしまったということを意味している。実際、ヤコブがラケルのために仕えた7年間は『ほんの数日のように思われた』(創世記29:20)と書かれている。最初の7年間がほんの数日に思えたのであれば、残りの7年間も恐らく同様に思えたはずであり、それゆえ14年とはヤコブの場合においてもやはり「短い」ということを意味しているのだ。しかし、この「14」という数字が、ヘブル語のアルファベットが示す「魚」を意味しているのではないかと考える人も中にはいるかもしれない。確かにヘブル文字の14番目(נ=ヌン)は魚に由来していると考えられているが―蛇に由来すると考えている学者もいる―、私としては「14」に魚の意味はないと思う。この見解には、ややこじつけの感があるからだ。
[本文に戻る]
この箇所で言われているのは、異邦人たちが、エルサレム市を『42ヶ月の間』圧迫するということである。ここでは『踏みにじ』られるだけであって、まだ都が滅ぼされることはない。また、この『聖なる都』とは、文字通りに捉えるべきであって、これはつまり「エルサレム市」を指している。これを神の聖徒たちにおける集団のことだと考えてはいけない。というのは、聖書では『都』という言葉が、エルサレムを指してのみ使われているからである。例えば黙示録20:9では『聖徒たちの陣営と愛された都』と書いてあり、聖徒たちの集団とエルサレム市とが、しっかりと区分して取り扱われている。ヘブル書の著者が『生ける神の都』(ヘブル12章22節)と言っているのも天国のエルサレムことであって、聖徒たちそのもののことではない。マタイ4:5で『聖なる都』と言われているのも、間違いなくユダヤの首都である街のことを言っている。その他の箇所で『都』と言われているのも、皆同様である。よって、もしこれがエルサレム市ではなかったならば、『都』ではなく、何か別の言葉が使われていたことであろう。黙示録で『都』という言葉が出てきた際には、それが地上であれば「エルサレム市」であり、それが天上であれば「天国のエルサレム」であると理解せねばならない。
【11:3】
『それから、わたしがわたしのふたりの証人に許すと、彼らは荒布を着て1260日の間預言する。」』
『証人』とは、多くの聖徒たちを指す。何故なら、この小さな巻き物で記されている預言とは、ネロが聖徒たちを苦しめることについての出来事だからである。ネロが苦しめるこの『証人』は、つまり多くの聖徒たちだから、これはただ2人だけだったと考えるべきではない。読者である聖徒たちは文脈をよく弁えよ。そうすれば、これが多くの聖徒たちのことだと分かるであろう。また、この『証人』とは、先にも説明されたように「イエスがキリストであることを証言する人」という意味である。つまり、これは「キリストの証人」のことである。もしこれがキリストの証人でなければ何を証言する人たちだと言うのであろうか。言うまでもなく、これを福音の証し人として捉えるのがもっとも相応しいことは確かである。
彼らが『預言する』とは、文字通りに捉えてよく、彼らが福音においてキリストを証しすると共に将来の出来事を予告することである。例えば、間もなく実現されるキリストの再臨についてパウロのように『主は近いのです。』(ピリピ4章5節)と言ったり、すぐにも起こる旧約世界の終焉についてペテロのように『万物の終わりが近づきました。』(Ⅰペテロ4章7節)と言うのがそうであった。また彼らが『荒布を着て』いたのは、彼らの謙遜な精神を表わしている。聖徒たちが預言をする際には、神が示されたことを忠実に伝える必要があったのだから、彼らが謙遜であることを示す荒布を着ていたのは実に適切であった。というのも、謙遜でなければ忠実であることは出来ないからである。傲慢な者は、往々にして逆らったり、騒ぎを起こしたりするものである。謙遜な精神を持っていたバプテスマのヨハネとエリヤも、荒布を着て預言をしていた(Ⅱ列王記1:8、マタイ3:4)。もし彼らがローマ法王のように豪華な服装をして預言していたとしたら、それは傲慢な精神を持っていることの表われであると見做されても文句は言えなかった。
この証人たちが『1260日』(=42ヵ月=3年6ヵ月=一時と二時と半時)活動する期間は、61年6月~64年11月であった。
この箇所で証人たちが『ふたり』と言われているのは、この証人である聖徒たちがキリストに遣わされたからこそ預言の活動をするということを示している。つまり、これはキリストが伝道者たちを二人一組にして活動させに行かせた、あの時のような大規模の伝道がなされるということである。だからこそ、あの時に伝道者たちが主にあって奇跡をしたように、この証人たちも多くの奇跡をしたのである。この奇跡についてはすぐ後の箇所(11:5~6)で書かれており、もう間もなく説明されることになる。ここで書かれている多くの聖徒たちが、実際にあの時のように2人一組で活動をしたのか、それともそのようなことがなかったのかは、よく分からない。ここでは『ふたり』と書かれているから、実際にこの『1260日』活動する期間に、聖徒たちは二人一組で活動したということなのかもしれない。そうでなければ、ここではただキリストが『70人』(ルカ10章1節)の伝道者を遣わされたあの時のような伝道活動、すなわち多くの奇跡が行なわれる大々的な活動がなされるということだけが言われていることになる。この場合、2人組ではなかったということを除けば、聖徒たちが奇跡を行なうこと、またその規模が大々的であるという点において、あの時の伝道と非常によく似ていると言える。いずれにせよ、この箇所をヨハネが書いた時、ヨハネの頭にキリストの主宰によるあの伝道活動のことがあったのは間違いない。要するに、ここで『ふたり』と言われているのは、つまりこういうことを言いたいわけである。「これからあの時にキリストが行なわれたような大規模の伝道活動が行なわれるであろう。天におられるキリストが、再びあの時のようにして聖徒たちを人々に遣わされるのだ。その時にはあの時と同じように多くの奇跡が行なわれる。それはキリストの再臨がもう間もなく実現されるからである。」
【11:4】
『彼らは全地の主の御前にある2本のオリーブの木、また2つの燭台である。』
この箇所は、明らかにゼカリヤ書と対応している。ゼカリヤ書のほうでは次のように書いてある。『私と話していた御使いが戻って来て、私を呼びさましたので、私は眠りからさまされた人のようであった。彼は私に言った。「あなたは何を見ているのか。」そこで私は答えた。「私が見ますと、全体が金でできている一つの燭台があります。その上部には、鉢があり、その鉢の上には7つのともしび皿があり、この上部にあるともしび皿には、それぞれ7つの管がついています。また、そのそばには2本のオリーブの木があり、一本はこの鉢の右に、他の1本はその左にあります。」…私はまた、彼に尋ねて言った。「燭台の右左にある、この2本のオリーブ木は何ですか。」私は再び尋ねて言った。「2本の金の管によって油をそそぎ出すこのオリーブの2本の枝は何ですか。」すると彼は、私にこう言った。「あなたは、これらが何か知らないのか。」私は言った。「主よ。知りません。」彼は言った。「これらは、全地の主のそばに立つ、ふたりの油そそがれた者だ。」』(4章1~3、11~14節)ところで、タルムードの中ではこの2人の油注がれた者が「アロンとメシヤである」(『タルムード ネズィキーンの巻』アヴォード・デ・ラビ・ナタン 第34章 4 30b p119:三貴)と解釈されているが、このように解するべきではない。
『全地の主の御前にある』とは、証人である聖徒たちが地におられる主の御前に存在しているということである。つまり、これは地上の聖徒について言われているのであって、ここでは天上の聖徒のことが言われているのではないということを示す。主が『天にも地にも、わたしは満ちているではないか。』(エレミヤ23章24節)と言っておられる通り、神は天におられると共に、地にも目には見えないが常に満ちつつ存在しておられるのである。『オリーブの木』とは、聖徒である。ダビデが次のように言っている通り、聖書において聖徒は『オリーブの木』と言われている。『しかし、この私は、神の家にあるおおい茂るオリーブの木のようだ。』(詩篇52篇8節)『燭台』とは、キリストが1:20の箇所で言っておられたように『教会』を意味している。この『燭台』の上には、『世界の光』(マタイ5章14節)である聖徒たちが『あかり』(同5章15節)として置かれる。すなわち、この『燭台』である教会は、あかりである聖徒たちをその上に乗せて、『家にいる人々全部を照らす』(同)のである。つまり、教会にいる聖徒たちが世界中をキリストにあって照らす。要するに、ここでは地上における教会の聖徒たちが、主の御前において、世の人々を光として照らしつつ預言の活動をするということが教えられている。それゆえ、ここで言われている『オリーブの木』と『燭台』という2つのものを文字通りに捉えてはいけない。これら2つのものが実際に動き出して人間でもあるかのように何かの活動をするなどと考えるのは、愚かな妄想に他ならない。そのような肉的妄想は聖徒たちの頭から遠ざかれ。
【11:5】
『彼らに害を加えようとする者があれば、火が彼らの口から出て、敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとする者があれば、必ずこのように殺される。』
『火』とは御言葉のことである。何故なら、この火は聖徒たちの『口から出て』いるからである。とはいっても、聖徒たちの口から実際に本物の火が出るということではない。本物の火を口から出すのは人間で言えばピエロや魔術師や科学者ぐらいなものである。聖徒たちの口から出るのは、言うまでもなく「御言葉」である。この御言葉が、ここでは『火』と言われているのだ。確かに聖書では御言葉がすなわち「火」であると言われている(※)。それは、御言葉が裁かれるべき不敬虔な者たちに、火で焼かれた時のような苦しみと嘆きとをもたらすからである。先にも見たように御言葉とは聖徒たちにとっては『蜜のよう』だが、御言葉が断罪として送られる裁かれるべき者たちにとっては「焼き尽くす灼熱」に他ならない。だから、キリストの口から出ているのが実際の剣ではなく御言葉だったのと同様に(1:16)、この箇所で聖徒たちの口から出ている火も実際の火ではなく御言葉だったと考えなければいけない。聖徒たちが竜でもあるかのように口から本物の火を出すなどと思い浮かべるのは、空想に他ならない。そのような空想はアニメや漫画の中だけで十分である。この『火が彼らの口から出て』という部分は、肉的また物質的にではなく、霊的また象徴的に捉えなければいけない。
(※)
神はエレミヤを通して次のように言われた。『わたしのことばは火のようではないか。』(エレミヤ23章29節)『あなたがたが、このようなことを言ったので、見よ、わたしは、あなたの口にあるわたしのことばを火とし、この民をたきぎとする。火は彼らを焼き尽くす。』(同5章14節)神がご自身の御言葉を火と言っておられるのだから、聖書の中で御言葉が火として言い表わされていても驚いてはならない。
[本文に戻る]
『火が彼らの口から出て』敵を滅ぼし、殺すと言われているのは、つまり火である御言葉が聞かされることにより、断罪されることである。例えば、聖徒たちの伝えた福音に反発した敵どもが『信じない者は罪に定められます。』(マルコ16章16節)とか『信じない者は神のひとり子の御名を信じなかったので、すでにさばかれている。』(ヨハネ3章18節)などと聞かされるのが、そうである。これこそ正に霊的な殺害である。何故なら、このように御言葉により断罪されることで、断罪された人は永遠の滅びに定められるからである。よって、ここで言われていることを実際的に捉えてはいけない。当時の聖徒たちは、本当に実際の火でもって敵対者たちを殺害したのではない。ユダヤ戦争の頃の歴史を見ても、そのようなことは確認できない。しかし、霊的に言えば、確かに聖徒たちはその口から出る火により敵を滅ぼした。何故なら、御言葉により断罪するというのは、霊的な殺害をすることに他ならないからである。ここで言われていることを今述べたように霊的に捉えないと、上手に理解できないから、聖徒たちはよく注意しなければいけない。
この箇所もそうだが、黙示録で「滅ぼす」とか「殺す」などと言われていた場合、それはどれも御言葉による断罪、すなわち霊的な殺害と滅ぼしのことを意味している。例えば、後で詳しく解き明かされることになるからここでは少しだけ述べるに留めるが、19:21の箇所では『残りの者たちも、馬に乗った方の口から出る剣によって殺され』と書かれている。ここで殺されると言われているのは、実際的な殺害ではなく、御言葉により裁かれることを言っている。また20:9の箇所で『すると、天から火が降って来て、彼らを焼き尽くした。』と言われているのも同様である。これも御言葉という火により霊的な意味において滅ぼされることを言っている。しかし、「火の池に投げ込まれた」という表現の場合、「滅ぼす」とか「殺す」という言葉の場合と意味がかなり違う。こちらの場合、実際的に殺害されて永遠の地獄に投げ込まれるという意味になる。例えばネロについて19:20では『硫黄の燃えている火の池に、生きたままで投げ込まれた。』と書かれているが、これはまず殺されて生命を奪われ、そうして後に地獄へ放り込まれたという意味となる。つまり、こちらの場合、単に御言葉により霊的に殺害されるということだけが言われているのではない。すなわち、この2つの表現においては、実際的な死があるかないか、という点で大きく違っている。「滅ぼす・殺す」の場合は実際的な死がなく、「火の池に投げ込まれた」の場合は実際的な死がある。この2つの表現を明確に区別することは、黙示録の理解にとって非常に重要だから、黙示録をよく理解したいと願っている聖徒たちはよく覚えておかねばならない。
【11:6】
『この人たちは、預言をしている期間は雨が降らないように天を閉じる力を持っており、また、水を血に変え、そのうえ、思うままに、何度でも、あらゆる災害をもって地を打つ力を持っている。』
『1260日の』活動期間において、聖徒たちは、あのエリヤのように『天を閉じる力を持って』いた。ヤコブはこのエリヤが天を閉じたことについて、次のように手紙の中で書いている。『エリヤは、私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると、3年6ヶ月の間、地に雨が降りませんでした。そして、再び祈ると、天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。』(ヤコブ5章17~18節)つまり、この時の聖徒たちは祈るのであれば、たとえエリヤが願ったように天を閉じるというような壮大な願いであったとしても、神に聞き入れられることができた、ということである。我々は、当時の聖徒たちがそのように大きな願いを聞き入れてもらうことができたのを、何か不思議に思ってはならない。というのも既にキリストは、もし聖徒たちが祈るならば、山さえも自由に動かせると言っておられたからである。マルコ11:22~23。『イエスは答えて言われた。「まことに、あなたがたに告げます。だれでも、この山に向かって、『動いて、海にはいれ。』と言って、心の中で疑わず、ただ、自分の言ったとおりになると信じるなら、そのとおりになります。』主がこのように言われた通り、聖徒たちは山さえも海に動かせるのだから、我々が今見ているこの箇所で聖徒たちが『雨が降らないように天を閉じる力を持って』いたということを、どうして疑っていいはずがあるであろうか。というのは、もし山さえも海に動かせるぐらいであれば、『雨が降らないように天を閉じる』のは更に簡単なことだからである。雨が降らないようにするほうが、海の中に山を入れるよりも遥かに容易であるというのは誰でも分かることである。
また、この時の聖徒たちは『水を血に変え』ることも出来た。つまり、この時の聖徒たちは、ナイル川を血に変えたあのモーセのように力があり(出エジプト7:19~25)、それゆえ敵にとって恐るべき存在であった。『水を血に変え』られる者たちを恐れない者がどこにいるであろうか。この『水を血に変え』という言葉を書いている時のヨハネが、出エジプト記に書かれている話を頭に思い浮かべていただろうことは疑えない。黙示録では、これ以外の箇所でも、出エジプト記、ことにエジプトからイスラエルが脱出する際の記述を思わせる箇所が少なくない。黙示録は、明らかに聖徒たちが再臨の際に起こる携挙によりこの世から助け出される出来事を、イスラエル人がパロの圧制と『エジプトの国、奴隷の家』(出エジプト20章2節)から逃れでたあの聖なる解放劇になぞらえて語っている。つまり、聖徒たちが携挙によりこの世から救い出されたのは、あの出エジプトの出来事のようであったということである。この理解は誠に重要であって、黙示録を更に深く理解するためには絶対に知っておかねばならないことである。この理解無くして、黙示録をその深みにおいて究めることは決して出来ないであろう。
『思うままに、何度でも、あらゆる災害をもって地を打つ力を持っている』とは、つまり聖徒たちが、多くの奇跡を人々の前で行なえたということである。それは、そのような奇跡により、自分たちの伝えている福音と預言が確かなものであることを多くの人たちに論証するためであった。つまり、これは『みことばに伴うしるし』(マルコ16章20節)また『証拠としての奇跡』(ヨハネ2章11節)である。もちろん彼らは、自分たちの発する霊的な言葉を論証するためにこのような行為をしたのであって、恐怖の大王のようにただ人々を恐れさせるためにそのようにしたというのではない。もしただ恐れさせて反応を楽しむということであったならば、聖徒たちは何一つ奇跡を行なわなかったであろう。このような論証のための奇跡はキリストも多くされたことであって、それは既に我々が福音書を読んで知っている通りである。もう間もなく再臨が起こるこの重大な時期において、聖徒たちがこのような大きな奇跡を行なったのは、この時期に聖徒たちが語ることを多くの人々に受け容れさせるためであった。
【11:7】
『そして彼らがあかしを終えると、底知れぬ所から上って来る獣が、彼らと戦って勝ち、彼らを殺す。』
『底知れぬ所から上って来る獣』とは暴君ネロである。ネロが登場するのは、黙示録では、ここが最初となる。というのは、先に見た6:8の箇所における『地上の獣』とはネロを指した言葉ではなかったからである。このネロについては、彼について詳しく記されている13章の箇所で、再び説明されることになる。何故なら、そのようにしたほうが内容的に適切だからである。なお、言うまでもないが、この『獣』が実際の動物だと考えている人は愚かである。
ここではネロが聖徒たちを迫害して苦しめる出来事が書かれているが、この箇所は13:5~7の箇所と対応している。そこでは次のように書かれている。『この獣は、傲慢なことを言い、けがしごとを言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。そこで、彼はその口を開いて、神に対するけがしごとを言い始めた。すなわち、神の御名と、その幕屋、すなわち、天に住む者たちをののしった。彼はまた聖徒たちに戦いをいどんで打ち勝つことが許され』。また、この箇所は今まで幾度となく言及されてきた箇所であるⅡテサロニケ2:4とも対応している。パウロはそこでネロのことについて、こう言っていた。『彼は、すべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。』また、この箇所はダニエル書7:25の箇所とも対応している。そこではネロについて次のようなことが預言されていた。『彼は、いと高き方に逆らうことばを吐き、いと高き方の聖徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、聖徒たちは、ひと時とふた時と半時の間、彼の手にゆだねられる。』更に、この箇所はマタイ24:15~16の箇所とも対応している。この箇所でキリストはこう預言しておられた。『それゆえ、預言者ダニエルによって語られたあの『荒らす憎むべき者』が、聖なる所に立つのを見たならば、(読者はよく読み取るように。)そのときは、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。』これらは、どれもネロが聖徒たちを蹂躙する大患難について預言されたものである。―これらは本当にどれもこれもネロについて言われているのか?答え。本当に本当にそうである。
このネロによる大患難は神の定めによるものだったから、抵抗不可能なものであった。この大患難の出来事についてネロが『彼らと戦って勝ち』とか、『彼はまた聖徒たちに戦いをいどんで打ち勝つことが許され』(13:7)などと預言された通りである。ここではネロが『彼らを殺す』と書かれているが、この時に殺された聖徒たちの数については、人によっても見解が異なる。ある人は、実はあまり多くの死者が出なかったのではないかと見るが、私はそのようには見ない。何故なら、聖書はこの大迫害を巨大なもの、凄まじいものとして書いているからである。それにもかかわらず、少しの死者しか出なかったというのは考えにくいと私には思える。それでは、この時に殺された聖徒たちの数は、実際にはどれぐらいだったのか。これについては記録が残されていないので分からない。最高クラスに信頼できる歴史家であるタキトゥス(※①)の書では、この大患難そのものについては記されているが、しかしその際に生じた死者数については書かれていない(『年代記』第15巻 44)。また無数の本を読み漁ったギボンの有名な歴史書にも―彼の書庫には1万2000冊の本があったという―、この時に出た死者数は書かれていない(参照:『ローマ帝国衰亡史2 第11―16章』第16章:64年 p387~394:ちくま学芸文庫)。この2人の著名な大歴史家でさえ大患難により出た死者の数が分からなかったのだから、お手上げという他はない。カルヴァンの場合、この時の死者数を「幾千もの」と言っているが、これは非常に曖昧な言い方であって、この言い方では何も確定的なことが分からない(※②)。多くの本を読んでいたサドもネロは「信者をことごとく責め殺した」(『閨房の哲学』第5の対話 p209:講談社学術文庫)と言っているだけで、カルヴァンと同様、やはり実際的な数字を書くことは出来ていない。これ以外の著作家でも事は同様である。もしこれからこの死者数が分かることになるとすれば、それは我々がまだ知らなかった古代の文書が発見されることによるであろう。もっとも、そのような文書がこれから見つかるかどうかは誰にも分からないのではあるが。
(※①)
私は本書の中でタキトゥスについて多く言及しているが、このタキトゥスよりも高い評価を受けている歴史家は私の知る限り存在しない、ということをここで書いておきたい。タキトゥスについては、あのヒュームさえも「すぐれた歴史家」(『奇跡論・迷信論・自殺論 ヒューム宗教論集Ⅲ』奇跡について p19:法政大学出版局)と言っている。またヒュームはこの歴史家について「潔白さと信憑性で知られており、それに加えておそらく全古典時代を通じて最大かつ最も鋭敏な天才であり、軽信へのいかなる結果からもまったく免れていた」(前同)とも言っている。ギボンもこの歴史家の卓越性を認めている。
[本文に戻る]
(※②)
「あの恐ろしい人非人ネロは、ローマの町に火をつけさせるや民衆が彼を憎み、悪い評判を立てているのを知って、幾千ものクリスチャンや信じる者たちを殺させることによって、民衆の好意を取りもどす手段を見いだし、あるいは少なくとも、不平と中傷とをなだめようと努めた。」(『新約聖書註解Ⅴ 使徒行伝 上』12:3 p354:新教出版社)
[本文に戻る]
獣であるネロが『底知れぬ所から上がって来る』という部分は、非常に重要である。この部分は絶対に説明されなければいけない。ネロが『底知れぬ所から上って来る』とは一体どういう意味か。私は以前、このことについて次にように書いた。<我々は、黙示録においてネロという暴君が、アンティオコス・エピファネスという暴君において描かれていることを知る必要がある。このエピファネスという有名な暴君は、ユダヤの民を蹂躙し、迫害し、殺し、大いに苦しめた。それは悪魔的と言えるほどの凶暴さであった。このエピファネスは、ネロが皇帝になった紀元54年から200年ぐらい前に死んだ(前163年没)。すなわち、このエピファネスは死んでから、不信者である異邦人として相応しく『底知れぬ所』、つまり地獄へと投げ込まれた。黙示録では、暴君ネロが、あたかも既に死んで『底知れぬ所』にいたこの暴君エピファネスがそこから復活したかのような存在であるからこそ、そのネロについて『底知れぬ所から上って来る獣』などと言われている。このエピファネスもネロと同様に『獣』と呼ばれるに相応しい存在であった。確かに、ネロはエピファネスでもあるかのように神の民を蹂躙し、迫害し、殺し、大きな苦しみをもたらした。エルサレムの破壊の元凶となったという点でも、両者は一致している。ネロがすなわち再来したエピファネスだということは、既にダニエルにより預言されていた。ダニエル書7:25の箇所では、ネロがエピファネスをモチーフとして描かれている。読者は、私が今ここで新奇かつ非聖書的なことを言ったなどと考えはいけない。ネロがエピファネスにおいて預言されていたというのは、カルヴァンも述べていたことである(※①)。もっとも、カルヴァンは不法の人がネロであったということは悟れていなかったのであるが(また反キリストという言葉が特定の個人を指すために存在している言葉ではないということも彼は悟れていなかった ※参照―第1部・第3章)。この理解において注意しなければいけないのは、実際にエピファネスが地獄から復活したのではないということである。また地獄にいるエピファネスの霊が、地獄から出て来てネロの中に入ったということでもない。黙示録では、ただ単にネロはあたかもエピファネスが地獄から復活してきたかのような恐るべき存在である、ということだけが言われているに過ぎない。言うまでもなく、エピファネスとその霊は、ネロが暴君として出て来た時にも、地獄で永遠の苦しみを味わい続けていた。このこと、すなわち黙示録ではネロが地獄から再びやって来たエピファネスでもあるかのように語られているということは、誠に重要である。この理解は、黙示録を理解するためには最も持っていなければいけない理解の一つである。この理解がなければ、黙示録を、特に13章と17章の箇所を上手に読み解くことは不可能である。しかし、この理解があれば、黙示録をすんなりと読み解けるようになる。よって、黙示録を読み解きたいと願われる聖徒たちはこの理解を覚え、覚えたならばそれを決して忘れてはならない。>このようなことを私は書いたのであるが、確かなところ、ここで『底知れぬ所』から再来したかのような存在として描かれているのはエピファネスではなく、ネブカデレザルであった。何故なら、13章および17章で説明されているように、ネロは第1番目の頭が再来した存在だからである。この第1番目の頭とは、後ほど詳しく説明されるが「ネブカデレザル」である。だから、ここではネロがネブカデレザルの再来として描かれていると理解せねばならない。この存在がエピファネスだと考えていた以前の私は、酷い思い違いをしていた。私がこのように惨めな思い違いをしていたのは、神が解釈の恵みを私にお与え下さるまでは、まだ理解が十分なだけ進んでいなかったからである。恵みにより解釈が一段と進むより前の私は、ギリシャとそのエピファネスこそが第1番目の頭であると理解していた。だからこそ、ネロは私が1番目であると勘違いをしていたエピファネスの再来者だと考えてしまったのだ。しかし、ギリシャは実際は第3番目の頭であり、その上そもそもエピファネスは7つの頭の中に含まれてさえいない。ギリシャの王として対応しているのはエピファネスではなくアレクサンドロスである。ネロは3番目であるギリシャとその王の再来としては描かれていないから、エピフェネスこそがネロの再来者だと考えるのは無理があった。また私は告白するが、第1番目がエピファネスだと考えていた時の私には、何か違和感があった。「これはもしかしたら違うのではないか。別の解が正しいのではないか。もしかしたら今後更に理解が進む可能性がある。」などと感じていた。そうしたら、やはり間違っていたことが分かったのである。私を正しい解に導いて下さった神に感謝せねばならない。また私と同様に、この存在がエピファネスだと考えていたカルヴァンも、酷い思い違いをしていた。彼は、ただ『荒らす憎むべき者』と書かれているからというので、実際に教会を荒らしたエピファネスを思い浮かべただけであり、ネブカデレザルもエピファネスと同様に荒らす者だったということに思いを至らせられなかった(※②)。この秘儀は本当に難しく、エピファネスだと誤解したとしても不思議ではない。もしネブカデレザルが候補として思い浮かべられなければ、必然的にエピファネスしか答えがなくなってしまうからだ。私も以前はネブカデレザルが思い浮かべられなかったので、そのように誤解してしまっていた(※③)。だから、この誤解しやすい秘儀の解読に失敗した人がいたとしても、それほど強く非難されるべきではないと私は思う。
(※①)
「別の箇所で御霊は、アンティオコスなる人物において反キリストの姿を描き、彼の王国が大言壮語と神冒涜をもって立つであろうと示した(ダニエル7:25)。」(『キリスト教綱要 改訳版 第4篇』第4篇 第7章 第25節 p153~154:新教出版社)
[本文に戻る]
(※②)
ネブカデレザルもエピファネスと同様に「荒らす者」だったというのは、ユダヤが滅茶滅茶な状態にされたことについて『バビロンの王ネブカデレザルがその骨まで食らった。』(エレミヤ50章17節)と言われた通りである。だからこそ、ネブカデレザルは『雄獅子』(同)と言われたのだ。ユダヤを骨まで食らう雄獅子とは、つまり「ユダヤを荒らす者」でなくて何であろうか。
[本文に戻る]
(※③)
確かに、エピファネスとネロの類似性を考えれば、「荒らす憎むべき者」がエピファネスの再来だと理解したとしても無理はない。実際はネブカデレザルがネロの再来なのだが、しかし、ネブカデレザルが候補に出なければエピファネスに解を求めてしまうのは自然であると思える。参考までに、以下にエピファネスについて記された引用文を載せておく。これらの文章は外典のマカベア書に書かれているものだから、一度読んだことのある人も多いかもしれない。
彼らのうちから、アンティオコス王の息子、アンティオコス・エピファネスという罪深いひこばえがはえいでた。彼は最初ローマ人に人質となっていたが、137年にギリシア人の国の王となった。そのころイスラエルに律法にそむく輩が現われ、次のように言って多くの人々をそそのかした。「われわれはでかけて行ってわれわれの周囲の諸国民と契約を結ぼうではないか。彼らから離れて以来、われわれは数多くの禍いに見舞われているのだから」。この意見は人々の眼に善しと思われたので、国民のうちの熱心な者たちが王のもとへ出かけると、王は彼らに異邦人の定めを行なう権利を与えた。そこで彼らは異邦人の習慣に従ってエルサレムにギュムナシオンを建て、自分たちを無割礼の状態にもどし、聖なる契約を離れて異邦人とくびきをともにし、悪をなすことに身を委ねた。
アンティオコスのもとに王国が整ったので、彼はエジプトを征服して二つの王国に君臨しようと企て、戦車、象、大艦隊からなる大群を率いてエジプトに侵入し、エジプト王プトレマイオスに向かって戦いをおこした。するとプトレマイオスはアンティオコスに背を向けてのがれ、多くの者が傷つき倒れた。そこで、(アンティオコスの軍隊は)エジプトの堅固な街々を占領し、彼はエジプトの地から戦利品を奪い取った。アンティオコスは、143年にエジプトを征服すると、向きを変えてイスラエルへ向かい、大軍を率いてエルサレムへやって来た。そして驕慢にも聖所に侵入して、黄金の祭壇、燭台、および燭台のあらゆる装飾品、祭壇、灌祭の盃、酒盃、黄金の香炉、聖所の幕、冠、神殿の正面にあった黄金の飾りなどを奪い、(神殿の物を)すっかりはぎ取ってしまった。さらに、金、銀、すばらしい器具、秘蔵の財宝を見つけしだい奪い取り、かくして略奪をほしいままにすると、アンティオコスは自分の国へひきあげて行った。彼は民を殺戮し、高慢なことばを語った。そこでイスラエルの至る所に大いなる悲しみがわき起こった。
長らや長老たちは心をいため、
娘や若者たちは力衰え、
女たちの美しさは色あせた。
花婿は悲しみの歌を歌い、
花嫁は婚姻の床に伏して悲しんだ。
そして大地は、そこに住む者たちのためにふるえ、
ヤコブの全家は恥辱を身にまとった。
二年後、王はムシア人の頭をユダの街々に送った。彼は大軍を率いてエルサレムに入城し、詭計をめぐらして穏やかなことばで人々に語ったので、人々は彼を信用した。ところが彼は突然町(エルサレム)に襲いかかり、大打撃を与え、イスラエルの多くの民衆を滅ぼした。そして町(エルサレム)を略奪し、町に火を放ち、町の家々と周囲の城壁とを破壊し、(兵士たちは)女、子供を捕虜にし、家畜を奪い取った。そして、大きくて堅固な城壁と堅固な櫓とを備えたダビデの町を建設したので、これが彼らの要塞となった。彼らはそこに罪深い民、律法にそむく者たちを住まわせ、その町で彼らの力を強くした。すなわち彼らは武器と食糧とを備え、エルサレムから戦利品を運びこんでそこに貯え、恐るべきわなとなった。
要塞は聖所に対する妨げとなり、
常にイスラエルに対する憎むべき敵となった。
彼らは聖所の周囲で罪なき血を流し、
聖所を穢した。
エルサレムの住民たちは彼らを恐れて町から逃げ去り、
エルサレムは異邦人の植民地となった。
エルサレムの人々にとってエルサレムは異邦人のもののごとくになり、
エルサレムの子らはエルサレムを捨て去った。
その祭礼は悲しみに、その安息日は侮蔑(の的)に、
その栄誉はさげすみに変わり、
そのほまれに代わって恥辱が町を覆い、
その高貴は悲しみに変わった。
さて王は、全国土に向かって、「すべての者が一つの国民となって、各自が自分の習慣に固執することをやめるように」という布令を発した。そこですべての異邦人は王のことばに従った。そしてイスラエルの多くの者たちは、王を礼拝することをよしとし、偶像に犠牲を献げ、安息日を穢した。王は、さらに使者を遣わしてエルサレムとユダの町々に次のような布令を送った。「異邦人の習慣に従って生活し、はん祭といけにえと灌祭とを穢し、聖所と聖徒たちをはずかしめ、(異教の)祭壇、社、偶像を祀る神殿を建立し、豚および穢れた家畜を犠牲として献げ、子供たちに割礼を施さず、あらゆる不浄とけがしごとのゆえにその魂を穢すにまかせ、彼らに律法を忘れさせ、あらゆる(父祖伝来の)定めを捨てさせよ。王のことばに従わぬ者は処刑されるであろう」。王は、かくのごときことばをもって全国土に布令を発し、全国に監督官を任命し、ユダの町一つ一つに、犠牲を献げるように命令した。民の多くの者たちは律法を捨てて異邦人のもとに集り、各地で悪行を重ね、そのためイスラエルはのがれうる土地にはどこでも身を隠さねばならなかった。
そして145年のカセルの月の15日に、王は祭壇の上に荒らす憎むべきものを建て、(エルサレムの)周囲のユダの町々に(異教の)祭壇を築いた。そして家の戸口と通りでは香を焚き、律法の書を見つけしだい引き裂いて火を放ち、さらに家に契約の書を隠しているのを見つけだされた者や、律法を守っているのが知れた者は、王の布令に従って処刑された。彼らは毎月毎月町で見いだされるイスラエル人に対して乱暴を働いた。そしてその月(カセルの月)の25日には、(古い)祭壇の上に建てられた(異教の)祭壇の上に犠牲の獣を献げた。自分の子供たちに割礼を施した女たちを布令に従って処刑し、幼児を彼女らの首にかけ、その家族と、子供たちに割礼を施した者たちとを(処刑した)。しかし、イスラエルの多くの人々は堅く立って互いに強めあい、穢れた肉を食べなかった。食物のゆえに身を穢したり、聖なる契約を穢すよりは、むしろ死を選び、処刑されていったのである。こうして大いなる怒りが激しくイスラエルに臨んだ。
(『聖書外典偽典第一巻 旧約外典Ⅰ』Ⅰマカベア1:10~64 p80~83:教文館)
そのころアンティオコスはペルシア地方から無残な退却をなすはめにおちいっていた。というのは彼はペルセポリスといわれる町へはいって神殿のものをかすめ、町を占領しようとしたのだが、群集が騒ぎだし武器をとって立ち上がったため、アンティオコスは現地人たちに追われて恥ずべき退却を余儀なくされたのである。
ところが彼がエクバタナまで来たときにニカルノとティモテオスの敗戦の報が伝えられると、彼は激しく怒って、自分を敗走せしめた者たちから受けたはずかしめをユダヤ人に報いてやろうと考え、天からの裁きがわが身に臨んでいることも知らないで、戦車の御者に向かって、全行程を休みなく走り続けよと命じた。彼はおごり高ぶって言った。「エルサレムへ着いたらそこをユダヤ人の共同墓地にしてやろう」。
そこですべてをみそなわしたもうイスラエルの主なる神は彼に眼に見えない癒しがたい打撃を与えた。彼が語り終えるや否や内蔵の激しい痛みが彼を襲い、体の内部にするどい苦しみが生じた。他人の内臓をさまざまなつねならぬ災いをもって苦しめた男にはまことにふさわしい裁きであった。ところが彼は決して激しい心をおさえようとはせず、なお傲慢な思いに満たされてユダヤ人に対して激しく心を燃えたたせ、もっと急げと命じた。すると彼は疾走する戦車からころげ落ち、しかも落ち方が悪かったため全身にひどい傷を負った。今までは人間の分際をもわきまえず海の波を従わせ山の高さをものさしで測ろうと考えていたこの男は、地に倒れて担架で運ばれ、隠れもなき神の力を万人に示すに至ったのである。この不信仰な男の眼からは虫がわき、激しい苦痛にさいなまれつつ生きながらその肉がくずれてゆき、全軍は彼の体が腐敗してゆくために発する悪臭に悩まされた。彼はしばらく前には天の星に手を触れようとすら考えていたのだが、その耐えがたい悪臭のゆえにだれも彼を運ぶことができなかった。
(『聖書外典偽典第一巻 旧約外典Ⅰ』Ⅱマカベア9:1~10 p182~183:教文館)
[本文に戻る]
しかし、神はどうして聖徒たちが、このような大患難に苦しむのをお許しになられたのか。もし神がお許しにならなければ、確かに聖徒たちは、このような苦しみを味わわなかったはずである。神がこのような苦しみをお許しになられた理由は3つある。まず一つ目は、救い主であるキリストが再臨される時の栄光のためである。ネロにより悲惨な苦難を聖徒たちが味わった後で救い主であられるキリストの再臨が起こり、その再臨により苦難を与えたネロに滅びがもたらされる(Ⅱテサロニケ2:8)、という展開がもっとも再臨される救い主の栄光に相応しいのは確かである。もしこのような苦難に続いてキリストが再臨されなかったとすれば、再臨はどれだけ味気のない出来事となっていたであろうか。そこには何の感動も起こらなかったかもしれない。また有り難味もあまり感じられなくなっていたに違いない。そうすると、救い主の栄光があまり現わされなくなってしまう。苦難の後に救い主が再臨されるというのが、もっとも神の栄光となるのは明らかである。神は、あらゆることをご自身の栄光がもっとも現わされる形で実現させられる。だから、神の栄光がもっとも再臨の時に現わされるために、再臨の前に聖徒たちがネロのよる苦難を受けなければいけなかったのである。二つ目は、真の信仰者が誰なのか明らかにされるためである。神は、ご自身に属すると見做されている者たちの信仰を試されるお方である。アブラハムもそのようにして試みを受けた(創世記22章)。アブラハムがその試練によって、真の信仰を持っていたことを証明したのは、既に我々の知るところである。我々が今見ている箇所で言えば、ネロによる苦難が与えられるからこそ、その苦難に最後まで耐え忍ぶ真の信仰者が誰なのか分かるようになる。真の信仰を持っていなかった者、すなわち偽者の信者だった者は、ネロによる苦難に遭った際に棄教して自分が偽者の信者だったことを自らの振る舞いによって証明する。もしこのような苦難がなければ、誰が真の信仰者なのか明らかにならないのである。それゆえ、ネロによる苦難は神の御心に適ったことであった。これがネロによる苦難が許された二つ目の理由である。三つ目は、ネロによる苦難は、あらかじめ預言されていたからである。神の預言は、必ず実現されなければいけない(※)。預言が実現されないのは、あってはならないこと、あり得ないことである。何故なら、もし神が預言されたにもかかわらずその預言が実現されないとすれば、神が真実な方ではないということになり、神は偽りを愚かにも預言されるお方だということになってしまうからである。これが第三の理由であった。人間の理性からすれば、神がご自身の愛する民にこのような苦難を許可されたのは、少し考え難いと感じられるかもしれない。しかし、神には今書かれたようなことのゆえに、ネロの活動を許可される計画があった。だからこそ、聖徒たちはネロにより大きな苦しみを受けることになったわけである。神がそのようなご計画をお持ちであったというのに、どうしてそのご計画を塵に過ぎない我々が非難できようか。そのように非難する人は傲慢だと言わねばならない。
(※)
イザヤを通してヒゼキヤに与えられた預言のような小数の例外もあるが(イザヤ38:1~8)、そのような例外を除いて神の預言は常に100%の確率で実現されるものである。
[本文に戻る]
これで読者は、どうして小さな巻き物がヨハネの腹に苦く感じられたのか、よく分かったはずである。この小さな巻き物はネロによる大患難を預言していたのだから、その預言をヨハネが理解した際、腹が苦くなった、すなわち悲痛に感じられたのは当然であった。こんなにも辛く悲しむべき出来事が他に何かあろうか。これは誠に悲痛だと感じられる出来事である。だからこそ、ヨハネはこの巻き物を食べた際に、腹が苦くなったわけである。もしヨハネの腹がこの巻き物により苦くならなかったとすれば、ヨハネは神の民でなかったことになる。何故なら、その場合、ヨハネは神の民の苦しみを何とも思っていなかったからである。神の民の苦しみを苦しまない者が、どうして神の民と言えるであろうか。その者は、神の民の同胞ではないからこそ、神の民の苦しみを苦しまないのである。
【11:8】
『彼らの死体は、霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの主もその都で十字架につけられたのである。』
ここで言われている『都』とはエルサレムを指す。何故なら、『彼らの主もその都で十字架につけられた』と書かれているからである。主が十字架にかかられた場所がエルサレムであったことを疑う人はいない。よって、この都はエルサレム以外ではない。しかし、世の中には黙示録に出てくるこの『都』を、当時の世界首都であったローマだと見る人が少なくない。確かにローマも全世界の都であった。しかし、そのように見るのは誤っている。もしこれがローマだとすれば、『彼らの主もその都で十字架につけられた』のだから、キリストが十字架にかかられたのはローマの地だったということになる。誰がこのような馬鹿らしい見解を認められようか。
『彼らの主もその都で十字架につけられた』と書かれているが、これは聖徒たちも、キリストと同じように十字架につけられたと言っているのではない。これはキリストが十字架につけられて晒し者にされたように、聖徒たちも晒し者にされるということを言ったものである。つまり、ここに見られる類似性は「晒して酷い目に遭わされる」ということであって、「十字架につけられる」ということではない。もちろん、この迫害期において中には十字架につけられた聖徒たちもいたにはいたのであるが。
ここでエルサレムが『ソドムやエジプト』と呼ばれているのに、驚かれる方が多くいるのではないかと思う。しかし、このように呼ばれるのは、当時のユダヤを考えれば当然であったと言える。紀元1世紀のユダヤは、霊的に言えばソドムでもあるかのように真の神から離れて破廉恥な状態に染まっていたし、エジプトのように偶像崇拝をしているのも同然であった。当時のユダヤは、ソドムやエジプトと同等か、もしくはそれ以上に邪悪であった。というのも神に従うべき民が、神から離れて邪悪な状態に陥っていたからである。神に従う義務を持つ民が、神に反逆するという罪は、あまりにも重い。だからこそ、ユダヤはローマに攻められて滅びることになってしまったのである。あの時の滅びを考えれば、ユダヤがどれだけ神に忌み嫌われていたかがよく分かる。つまり、あの滅びの裁きは、ユダヤが神に非常に嫌われていたことのよい証拠なのである。だから、ここでエルサレムが邪悪な都市の名で呼ばれていることを、何か不思議に思うべきではない。我々は、神が既にイザヤの時代からユダヤをソドム扱いしておられたことを思い出すべきである。ユダヤがソドム扱いされるのは、これが初めてではなかった。神がイザヤを通して紀元前8世紀のユダヤに対して言われたことは、こうであった。『聞け。ソドムの首領たち。主のことばを。耳を傾けよ。ゴモラの民。』(イザヤ1章10節)このようにユダヤがソドム(またゴモラ)扱いされてから800年経過してもまだ同じように扱われてしまったということは、つまりユダヤがどうしようもない民であったということでなくて何であろうか。
『霊的な理解』と書かれているが、黙示録において、重要なのは霊的に理解することである。この『霊的な理解』を抜きにして、黙示録を正しく理解することはできない。黙示録の多くの箇所では、霊的な感覚で理解することが求められている。全聖書中、この黙示録ほど霊的な感覚が必要な文書はない。これは人間の書いた文書ではなく神の書かれた文書である。よって、黙示録は実に霊的である。だから、黙示録を十全に理解したいと願われる聖徒は神から『あらゆる霊的な知恵と理解力』(コロサイ1章9節)が与えられるように願うべきである。アインシュタインやJ・S・ミルのような高い知性を持っていたとしても、霊的な感覚がなければ、まったく黙示録を理解することはできない。黙示録を理解する何よりの鍵となるのは神の恵みによる『霊的な理解』なのである。
この箇所で書かれている出来事も、やはり例のごとく既に実現している。何故なら、この箇所で示されている出来事も『すぐに起こるべき事』(22:6)だったからである。ほとんど全ての聖徒たちは、まだこの出来事が起きていない、つまりこの出来事はヨハネがこの箇所を書いてからずっと後の時代に起こるなどと愚かにも考えている。しかし、御霊はこの箇所も含め、黙示録で示されていることは『すぐに起こるはずの事』(1:1)であると言われた。つまり、聖徒たちは、御霊の言われたことに逆らうことを考えていることになる。これは誠に大きな罪である。御霊がこの出来事も『すぐに』起こるであろうと言われたのに、聖徒たちはどうして素直になって御霊の言われた通りに信じないのか。御霊が多くの聖徒には与えられていないのか。だからこそ御霊の言われたことを信じることができないのか。ぜひ、これから多くの聖徒たちが素直になって御言葉で言われた通りに黙示録を理解してほしいものである。
【11:9】
『もろもろの民族、部族、国語、国民に属する人々が、三日半の間、彼らの死体をながめていて、その死体を墓に納めることを許さない。』
『三日半』という特徴的な数字で示されている期間は、すなわち「3年6ヶ月」である。何故なら、ここで言われているのはネロによる『42ヶ月間』(13:5)(=3年6ヶ月)の大迫害のことだからである。もしこの『三日半』という期間を、文字通りに理解すると、上手に黙示録を理解できなくなってしまう。もしこれが本当に三日半だとすれば、『三日半の後』(11:11)に起こる聖徒の復活は、ネロが迫害を開始してから数日で起こることになる。すなわち、紀元64年12月に大患難が始まったとすれば、それからすぐにもあの蘇えりが起こることになる。しかし、既に第1部で見た通り、聖徒の復活が起こるのはネロの命日である紀元68年6月9日である。この『三日半』という数字は、復活の起こる日であるネロの命日が『三日半の後』となるように理解せねばならない。もし『三日半』を文字通りに理解しなければいけないとすると、この期間はすなわち紀元68年6月5日~9日の間だったということになる。何故なら、ネロが迫害を開始してから三日半後に迫害が終わって、あの復活が起こるからである。その場合、ネロは紀元68年6月5日に迫害を開始したことになり、その迫害による大患難はたったの三日半(!)だけだったということになる。これはあり得ないことである。よって、この『三日半』は3年半だと理解しなければいけない。3年半を『三日半』と言い換えるのは、無理な話ではない。何故なら、どちらも「3と半分」であることには変わらないからである(※)。しかし、ヨハネはどうして3年6ヶ月を『三日半』と言い換えたのか。それは愛の知恵であった。ヨハネは、自分の愛する同胞たちに差し迫っている大迫害の期間が長く感じられないようにと、知恵を働かせて『三日半』と言い換えたのである。これは、あたかも「聖徒たちよ。君たちが受ける苦しみの期間は3日半も同然の期間なのだ。それほど短い期間も同然なのだから、このような苦しみが訪れるからといって絶望してはならない。」などと言っているかのようである。確かにモーセも詩篇で言っているように人間の人生が『ひと息のように』(90篇9節)終わるものだとすれば、3年6ヶ月が『三日半』も同然だったというのは確かである。いや、モーセが80年の人生を『ひと息』とさえ言ったことに比べれば、3年6ヶ月を『三日半』だと言うことはあまりにも長いとすら感じられるほどである。ヨハネがこのように苦しみの期間を『三日半』と短く表現したことは、これから苦難を受けることになっていた聖徒たちにどれだけ慰めとなったことであろうか。これを3年6ヶ月とそのまま言い表わすよりも、遥かに気持ちが楽になり、また忍耐の用意が容易に出来るようになったのは確かである。このようにヨハネが言って聖徒たちの精神に配慮したのは、御霊による愛と知恵に基づいている。
(※)
1年を1日として取り扱うのは、エゼキエル書にもその例が見られる。エゼキエル書では、イスラエルの390年の咎が『390日』に、ユダの40年の咎が『40日』に変換されている(4:4~6)。このようにエゼキエル書という根拠があるのだから、黙示録で3年半が『三日半』に変換されていたとしても、何もおかしなことはない。しかしながら、エゼキエル書のほうでは短縮された期間が実際に実効的な効力を持っていたのに対し、黙示録のほうでは短縮された期間は単に表現上における秘儀だったという相違点があることに我々は注意せねばならない。また我々はヘブル語において複数形で語られた「日」がしばしば「年」を表わす、ということも考慮に入れるべきであろう。例えば、アモス4:4の箇所では『3日』と言って「3年」を表わしている。ヨハネがヘブル語の語り方をここでギリシャ語において使用した、というのは十分に考えられる話である。
[本文に戻る]
ここで言われているのは、つまり3年6ヶ月の迫害期間においては、聖徒たちが人間らしく取り扱われないということである。人々が『彼らの死体をながめていて、その死体を墓に収めることを許さない。』とは、聖徒たちが酷く扱われるということでなくて何であろう。実際、この期間において、多くの聖徒たちは殺されても墓に入れてもらえなかったはずである。この期間における非人道的な虐殺行為が、どれだけ悲惨なものだったかということは、書き残された歴史の中で明瞭に示されている。この時、聖徒たちは、その切られた多くの首が松明代わりに燃やされるほどであった。
この箇所では、殺された聖徒たちの死体がテレビ中継で全世界に放映されることについて言われているなどという奇説を主張する教師がいるようである。このような見解は、お話しにならず、あえて反駁する値打ちさえない。ここまで読み進められた読者は、この見解がどれだけ馬鹿げているか、もうよく分かるのではないかと思う。このような異常な見解には、軽蔑の伴った微笑という無言の刑罰を与えておくのが相応しい。
【11:10】
『また地に住む人々は、彼らのことで喜び祝って、互いに贈り物を贈り合う。それは、このふたりの預言者が、地に住む人々を苦しめたからである。』
ここでは、人々が聖徒たちの死と苦しみを見て喜ばしく思うことが言われている。実際に、ここで書かれているように、当時の人々が贈り物を互いに贈り合ったというのではない。『互いに贈り物を贈り合う。』とは、つまり贈り物を贈り合う時のような喜びが生じたという意味である。『喜び祝って』というのも同様である。これも、人々が酒を飲みながら宴を開いたという意味ではなく、人々の持った大きな喜びを表現したものである。彼らが喜ばしく感じたのは、『このふたりの預言者が、地に住む人々を苦しめたから』であった。人は、自然の情として自分を苦しめた者の不幸を願うものだから、彼らが聖徒たちの不幸を喜ばしく感じたのは自然であったと言える。ギボンによると、この苦難が起きた際、当時のローマ人たちはネロに餌食とされた聖徒たちに同情の念を抱いたということである。いくらかでもネロの暴虐の犠牲とされた聖徒たちに同情を抱いたローマ人がいたということは、私も認める。だが全体的に言えば、当時の人々は聖徒たちの不幸を大いに喜んだと言わねばならない。何故なら、この箇所では、明らかにそのように言われているからである。自分が聖書に立つキリスト者だと思う者は、ここで聖書が教えている通りの理解を持たなければいけない。我々が立脚すべきは「ギボンの見解」ではなく「聖書の見解」である。聖書の見解よりも人の見解を優先させるとは、どのような聖徒なのか。もし聖書の見解を退けてギボンの見解を優先させる人がいたとすれば、私は言うが、その人は大いに呪われるであろう。
我々は、この時に聖徒たちが伝えた福音の真理が、滅びの子らにとっては『死から出て死に至らせるかおり』(Ⅱコリント2章16節)であったことを覚えるべきである。42ヶ月の活動期間の間に福音を聞かされた滅びの子らにとって、福音を聞かされるのは単なる苦痛でしかなかった。それは、少し例えが悪いのだが、デスメタルの嫌いな人が、悪魔的なギターと共に出されるデスヴォイスをずっと聞かされるようなものである。だから、『このふたりの預言者が、地に住む人々を苦しめた』と言われているのは適切であった。何せ42ヶ月もの間、滅ぶべき者たちはデスヴォイスを聞かされ続けていたのも同然なのだから。もちろん、福音は選ばれていた人たちにとっては『いのちから出ていのちに至らせるかおり』(Ⅱコリント2章16節)であって、また聖徒たちが福音を伝えたのは何も悪いことではなかったのではあるが。
【11:11】
『しかし、三日半の後、神から出たいのちの息が、彼らにはいり、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常な恐怖に襲われた。』
ネロによる『三日半』すなわち『42ヶ月』の苦難が終わると、聖徒たちの復活が起きた。紀元68年6月9日のことである。『神からでたいのちの息が、彼らにはいり』とは、死んでいた聖徒たちに御霊の身体が新しく与えられて復活したということである。『彼らが足で立ち上がった』とは、ここでは地上における死者の復活が描かれていることを示している。復活は天上でも起きたが、ここでは言われているのは地上の復活のことである。この箇所はⅠテサロニケ4:16~17と対応している。そこでパウロが言っているように、この復活はパウロと共にいたテサロニケ人たちが『生き残っている』時に起きた。また、この箇所は黙示録20:4~6とも対応している。この20章の箇所で言われているように、この復活こそ『
ここでは復活の直前に起こる再臨については、書くことが省かれている。実際には、復活が起こるすぐ前に、キリストが天から再臨しておられた。しかし、どうしてここでは復活だけが書かれており、再臨について書くことは省略されているのか。それは黙示録が謎解きだからである。ここで再臨について書かれなければ、それだけこの辺りに書かれている内容を解読するための手掛かりが少なくなるのは言うまでもない。神は、多くの者たちが黙示録の正しい理解から遠ざけられるために、あえてここで再臨のことについては書き記されなかった。もし再臨のことがここで書かれていたとすれば、それだけ解読のための手掛かりが増えるのだから、多くの者が黙示録をすんなりと読み解けるようになっていたかもしれない。しかし、神はそのようになるのを望まれなかった。無数の謎という洪水の前に多くの者たちが弾き飛ばされる。こうなることこそが神の御心であった。
この復活の出来事は、当時生きていた人たちに見られた。だからこそ、それを見た人たちは『非常な恐怖に襲われた』のである。この復活の出来事を見た人がどれぐらいたのかは、よく分からない。というのも、この時に復活した聖徒の数がよく分からないからである。言うまでもなく、復活の出来事を見た非キリスト者である人々の数は、復活した聖徒の数に比例する。すなわち、もし復活した聖徒が多くいれば、その復活を見た人々も多かっただろうし、もし復活した聖徒があまりいなかったとすれば、復活を見た人々もそこまで多くはいなかったかもしれない。しかし、実際にどのぐらいの聖徒が復活したか我々には分からないのだから、復活を見ていた人たちの数が多かったとか、少なかったとか、確定的なことは何も言うことができない。また、この復活を見ていた非キリスト者たちは、この復活をその目で見たにもかかわらず、その復活の出来事を何も記録として書き記さなかった。これについては、既に第1部で解説済みである。再臨に伴って起こる復活の出来事を見たのに当時の人々がそれを記録しなかったのは、それが夢や幻のように感じられたからであった。もし当時の人々が復活を見たにもかかわらず、それを記録しなかったことを問題にする聖徒がいたとすれば(こういう聖徒は多いかもしれない)、その聖徒は、キリストの奇跡についても問題にしなければいけなくなってしまう。何故なら、キリストの行なわれた多くの奇跡について紀元1世紀の異教徒たちが見たり聞いたりしていたのは間違いないが(誰がこのことを疑うであろうか)、異教徒の中でキリストの奇跡に言及した人は一人すらも見られないからである。キリストと同時代に生きていた異教徒たちは、キリストの奇跡について見たり知っていたのに、そのことについて書物や文書の中で何一つ言及していない。しかし、だからといって、キリストの奇跡を問題にする聖徒は一人もいないはずである。何故なら、聖書ではキリストが奇跡を行なわれたと書かれているからである。であれば、復活のことも、たとえ異教徒が誰一人としてそのことを記録していないからといって、問題にしてはならないことになる。何故なら、今までに語られてきた通り、聖書は明らかに復活がパウロの時代に起きたと教えているからである。それにしても、この復活を実際にその目で見た人々の恐れはどれほどであっただろうか。ヨハネは『それを見ていた人々は非常な恐怖に襲われた。』と書いている。この時に生じた恐れはさぞ大きいものだったに違いない。何せ墓の中から死んでいた者が出てきたのだから。しかも、その復活した者の数は一人や二人ではなく、何人もいたのである。
【11:12】
『そのときふたりは、天から大きな声がして、「ここに上れ。」と言うのを聞いた。そこで、彼らは雲に乗って天に上った。彼らの敵はそれを見た。』
復活が起こると、その後には携挙が起こる。この流れについてはⅠテサロニケ4:16~17の箇所でもパウロが言っている。復活が起きてから携挙が起こるまでの時間は、それほど差がなかったと思われる。何故なら、Ⅰテサロニケ4:16~17を見ると、この2つの出来事の間には時間的な差異がそれほどあるようには感じられないからである。この携挙の時に上に聖徒たちを挙げたのは、御使いたちであった。これはマタイ13章の箇所を見ても分かることである。このことについては既に第2部で説明された。聖徒たちは携挙される際に『雲に乗って』上へと挙げられた。これは、身体の贖いを受けた聖徒たちが『永遠に王』(22:5)だからである。つまり、贖われた聖徒たちが永遠の王だからこそ、権威を示す雲に乗って上へと挙げられたのである。雲と共に上に挙げられるというのは、キリストの昇天でも同様であった(使徒行伝1:9)。キリストが雲と共に挙げられたのも、やはりキリストが挙げられてから権威の座に着くことになるからであった。つまり、その雲は「これからキリストが権威の座に着くのだ。」ということを表わしていたのである。
この携挙の時に天から発せられた『声』の主は、キリストである。何故なら、復活は、キリストの声が発せられることにより起こるからである(※)。復活がキリストの声により起こるのであれば、復活の後に起こる携挙もキリストの声により起こるとすべきである。復活の主宰者がキリストであるがゆえにキリストの声により復活が起こるとすれば、携挙の主宰者もキリストであるからこそ、キリストの声により携挙が起こると考えるのは不合理なことではない。この『声』という言葉は、たったの一文字ではあるが、我々にとって重要な言葉である。何故なら、これは黙示録の中で非常に多く出て来る言葉だからである。この言葉の意味を理解するのであれば、それだけ黙示録をよりよく理解できるようになる。それは我々にとって幸いなことである。だから、このような小さな言葉であるからといって、それを軽んじたりすべきではない。これが小さな言葉だからといって蔑ろにする聖徒は、他の重大な言葉についても蔑ろにしてしまうことになる。このように私が書いたのを読んで、「いいや、そういうことはない。このような小さな言葉はあまり重視しないかもしれないが、重大な言葉であれば決して軽んじたりはしない。」などと言うことはできない。何故なら、キリストが言われたように『小さい事に不忠実な人は、大きい事にも不忠実』(ルカ16章10節)だからである。キリストの御言葉を否定できるものなら否定してみよ。そうすれば、自分がキリスト者でないことを露呈するだけである。
(※)
『このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者がみな、子の声を聞いて出て来る時が来ます。』(ヨハネ5章28節)
[本文に戻る]
この携挙も、復活の出来事と同じように人々により見られた。だが、やはりこれも記録として書き残されることはなかった。もし携挙に関する記録が何もないことに不満を持つ人がいれば、神に文句を言うがよい。神が、何も記録が残らないように定められたのである。それは、再臨の際に起こる諸々の出来事が、御言葉に拠り頼む聖徒たちにだけ確かな出来事として知らされるためであった。神は、御言葉よりも学問としての史実のほうを優先させる不信仰な者たちが再臨の際に起こる諸々の出来事を受け容れらないように、つまり真実な理解から遠ざけられるようにされた。だから、記録の有無のゆえに御言葉を蔑ろにする不信仰な者は、いつまで経っても再臨や携挙などについて悟ることができないままとなる。
【11:13】
『そのとき、大地震が起こって、都の10分の1が倒れた。この地震のために7000人が死に、生き残った人々は、恐怖に満たされ、天の神をあがめた。』
再臨と復活と携挙が起こる時期には『大地震』が生じるというのは、聖書の他の箇所でも言われていることである。あまりにも特異なことが起こるので、地でさえも大いに揺らいでしまうのである。大地震=地の驚愕。
『大地震が起こって、都の10分の1が倒れた。』とは、つまりユダヤの民の10分の1の人たちが、この時に救われ携挙されたということである。何故なら、聖書では、ユダヤにおける『10分の1』とはすなわち「ユダヤ人の中の救われる者たち」だと教えられているからである。すなわち、イザヤ書の中では次のように書かれている。『町々は荒れ果てて、住む者がなく、家々がいなくなり、土地も滅んで荒れ果て、主が人を遠くに移し、国の中に捨てられた所がふえるまで。そこにはなお、十分の一が残るが、…』(イザヤ6:11~13)。聖書の中で、ユダヤ人において10分の1と言われている箇所は、ここだけしかない。「10分の1」を捧げなければいけないと書かれている箇所もあるが、それは人についてではなく主への捧げ物についてのことだから、我々が今見ている黙示録の箇所とは関係がない。我々が今見ている箇所で言われているのは、捧げ物のことではなく人についてのことである。このイザヤ書の箇所では10分の1のユダヤ人が残されると言われているのだから、黙示録11:13で言われているのは、つまり霊的な理解をすれば「ユダヤ人で救われる人たちの割合」だということになる。これは、つまりこういうことである。携挙が起きた時、いくらかのユダヤ人たちは上に挙げられてしまうので、この地上から消えていなくなってしまう。その消えていなくなるユダヤ人が全ユダヤ人の『10分の1』だからこそ、ここでは『都の10分の1が倒れた』と言われているのである。これは「換喩表現」である。つまり、ここではユダヤ人の10分の1が携挙により地上から消え去ることを、ユダヤの都が倒れて消え去ることにより言い換えている。聖書には、このような換喩表現が少なくないから、このような言い方がされていてもそれほど驚くには値しない。それで、紀元68年の再臨の際に携挙されたユダヤ人が全ユダヤ人の1割だったというのは、どう考えるべきか。これは多かったと見るべきか、それとも少なかったと見るべきか。割合から言えば、これはかなり少なかったと見てもよいであろう。何故なら、たったの1割しか悔い改めてキリストに帰依したユダヤ人がいなかったからである。しかし、その総数から言えば、これはまあまあ多かったと言えるのはないかと私には思える。何故なら、当時のユダヤ人の総人口が200万人だとすれば、この時に携挙されたユダヤ人の数は20万人だったことになるからである。あれほど反抗的な民が20万人もキリストに帰依したというのは、私としてはかなり驚くべきことではないかと感じられる。しかし、この数と割合をどう感じるかは、人よってもそれぞれ違いがあるだろうから、私の主観をここで押し付けるべきではない。これは確かに換愈表現だから、実際的に、すなわち文字通りに捉えてはならない。もしこれを文字通りに捉えるとすれば、ユダヤ戦争の時に倒れた都の割合はたったの1割だけだったことになるからである。これはとんでもないことである。歴史を見れば分かるように、この戦争の時に倒れた都の割合は「10分の10」であった。だから、これを文字通りに捉えると大きな間違いを犯すことになるから注意せねばならない。なお読者の方は、ここでユダヤの1割が救われて携挙されたということは、すなわちユダヤの9割は救われず携挙もされなかったということを、よく覚えていてほしい。つまり、「10」であるユダヤからは「1」が取り除かれたので地上に残されたユダヤは「9」となった、ということである。「10ユダヤ-1ユダヤ=9ユダヤ」。この「9ユダヤ」という理解は重要であって、後の箇所を理解するために必要となる。その箇所の註解に来た時、この理解を失念していた場合、再び今見ているこの箇所に立ち戻ってどういうことだったのか読み返してほしい。
『この地震のために7000人が死に』と書かれているが、『7000人』とは、この箇所の前に書かれていたネロによる大患難の時に屈しなかった真の聖徒たちを指している。これは明らかに、神がエリヤに語られた『しかし、わたしはイスラエルの中に7000人を残しておく。これらの者はみな、バアルにひざをかがめず、バアルに口ずけしなかった者である。』(Ⅰ列王記19章18節)という御言葉に基づく(※)。つまり、地震で死んだ7000人とは、エリヤの時代にバアルに屈しなかった聖徒たちのような敬虔さを持った聖徒のことを言っている。我々が今見ているこの箇所の他に聖書の中で『7000人』と言われているのはエリヤに語られた神の御言葉だけだから、黙示録11:13に出てくる『7000人』という言葉は、エリヤに語られた神の御言葉において解釈すべきである。聖徒たちは、「聖書は聖書によって解釈する」という大原則を忘れないようにしてほしい。とはいっても、この地震が起きた際に存在していた敬虔な聖徒たちの数がたったの『7000人』しかいなかったというのではない。この黙示録の箇所では、地震の際にいた聖徒たちが、ただエリヤの時代にいた7000人の聖徒たちのような敬虔さを持っていたということが言われているに過ぎないからである。つまり、ここでは数における同一性が言われているのではない。ここでは敬虔における同一性が言われているのだ。言うまでもなく、地震が起きた時にいた聖徒の数は7000人よりも多かった。それで、この箇所で言われているのは、つまり地震と共に起きた携挙によりその時に生きていた聖徒たちが全て地上から消え去ったということである。その「消え去り」が、ここでは『死に』という言葉で言い換えられている。聖徒たちが携挙により地上から消え去ったのは、地震により死んで消え去ったということと、「消え去った」という点では全く同じである。このような共通性のゆえに、携挙を死として言い換えることが可能となっている。どちらもこの世から消えていることには変わらないのだから。これはつい先ほど見た「都の倒壊」でも同じであった。そこでも、救われたユダヤ人が携挙されて地上から消えたことを、都が倒れて消えたという言い方で表現していた。これも、やはり「消え去る」という点で共通性があるゆえに可能となった言い換えであった。だから、ここで地震が起きて人々が死んだと言われているのを、文字通りに捉えてはいけない。これは霊的に理解すべき部分である。もしこれを文字通りに捉えたとすれば、この部分を正しく理解することは永遠にできないであろう。実際、この部分を文字的に捉えようとしている悲惨な人たちは、この部分を正しく理解できていない。
(※)
パウロもこの御言葉をローマ11:4で引用している。―『「バアルにひざをかがめていない男子7000人が、わたしのために残してある。」』
[本文に戻る]
地震の伴う再臨と復活と携挙の出来事を見た人々が『恐怖に満たされ』たのは、当然であった。何故なら、これらの出来事は前代未聞の特異な出来事だったからである。その時人々に生じた恐れは、何かの事件で言えば、私の思うに911テロの時に人々が感じたような恐れだったと言ってよいであろう。この人々が『天の神をあがめた。』と書かれているのは、神の起こされた特異な出来事を見た人々が、神に対して敬虔な思いを抱いたということである。これは、人々が突発的な恐れに打ちのめされると、往々にして心に抱くものである。例えば、無宗教の人が自分の乗っている飛行機が墜落すると知ったならば、それまでは神のことなど何も思っていなかったのに、急に恐くなって「神さま。どうか。どうか。お助け下さいませ。お願いします。飛行機が落ちないようにして下さい。」などと心の中で叫び求めるのがそれである。実際、特に日本人がそうだが、非常な恐れが突如として襲い掛かって来た時に「神様!」などと心の中で叫ぶ人は少なくない。しかし、このような思いは一時的なものであって、危難が過ぎ去ったならば、即座に消えて無くなるような性質を持っている。もう安全になったと知れば、このように叫んだ無宗教の人は、神のことなどけろっと忘れてしまう。つまり、目の前に考えられないような状況が現れたので、言わばパニック状態になってしまい、何とかして苦しみや困難を逃れるべくこのような普段では思いもしないことを思うことになったわけである。だから、このような思いは一見すると敬虔そうに見えるが、そこには持続性がなく、真の敬虔が存在していない。というのも真の敬虔とは持続性があるものだからである。再臨や復活や携挙が起きた際に人々が恐れに打たれて『天の神をあがめた。』のも、このような性質を持った敬虔であった。よって、この人々が『天の神をあがめた。』からといって、彼らが回心したとかキリストの宗教に心を傾けるようになったというのではない。彼らは、時間が経過した後では、もはや『天の神をあがめ』ることを忘れてしまったであろう。それは飛行機が奇跡的に墜落しなかったので助かった人が、数日もしたら神のことなど考えもしなくなってしまうのと同じである。このような心に生じた敬虔を後の日にも持ち続ける人は、1000人に1人いるかいないかである。
ところで、この『大地震』が、紀元62年に起こった巨大地震のことではないかと考える人もいるかもしれない。紀元62年に非常に大きな地震が起きたのは確かである。これは歴史を調べれば誰でも分かることだ。しかし、これは紀元62年の巨大地震ではない。何故なら、この地震は11:7の箇所で『底知れぬ所から上って来る獣』であるネロが聖徒たちを迫害した後で起きた地震だからである。既に述べたように、ネロの迫害が起こるのは紀元62年よりも後である。であれば、どうして我々が今見ている箇所で書かれている地震が、紀元62年の地震なのであろうか。この地震について書かれている我々が今見ている箇所(11:13)は、ネロの迫害が書かれている11:7の箇所よりも、時間的に後のことが書かれている箇所なのである。もし11:7の箇所で言われているネロによる苦難が紀元62年よりも前に起きたとすれば、11:13の箇所で言われている地震は紀元62年の大地震だったかもしれない。何故なら、その場合、時間的に何も矛盾が生じないからである。しかしネロによる苦難は紀元62年よりも後に起こったのだから、11:13の箇所で書かれている地震は62年に起きた地震ではなかったと理解せねばならない。この地震は、紀元68年6月9日に起きたと理解すべきである。11:7の箇所で書かれているネロの迫害が紀元62年以降に起きたと理解しつつ、この11章の箇所を読んでみるとよい。そうすれば、どう考えてもこの箇所で言われているのが紀元62年の地震だとは思えなくなるはずである。それでは、この紀元62年に起きた巨大地震は、黙示録のどこに記されているのか。この地震は黙示録の中では全く記されていない。黙示録の中で記されている地震は2つ、すなわち紀元68年の再臨の時に起きた地震と、紀元70年のユダヤ滅亡の時に起きた地震の2つだけである。
ここで『小さな巻き物』による預言の記述は終わる。次の節からは、再びラッパによる預言の記述がなされる。読者は、この流れの区別をよく弁えなければいけない。ここで話を区切らないと、小さな巻き物による預言が、すぐ次の節から再開されている第6のラッパすなわち『第二のわざわい』(11:14)の内容に含まれていると誤解しかねない。
第13章 ⑩11章14節~19節:残された7つ目のラッパによる預言
一体どうして、6つ目のラッパによる預言の末尾部分が再開された箇所の冒頭に置かれており、小さな巻き物の預言が挿入される前の部分における末尾、すなわち9:21の後に置かれなかったのか。人間的な考えからすれば、6つ目のラッパにおける末尾部分は、挿入が始まる前の部分における末尾に置かれたほうがすっきりするし、分かりやすくなると感じられなくもない。しかし、神は挿入が終わってから、11:14の箇所で既に内容自体は語られ終わっていた6つ目のラッパにおける末尾部分をお書きになられた。この理由は一つであると思われる。すなわち、これはより分かりにくくするためであったということである。言うまでもなく、6つ目のラッパの末尾部分を9:21の後に置くよりも、11:13において挿入箇所が全て書き終わった後(すなわち11:14)に置いたほうが難解さが増すようになるのは確かである。神は、より難解にして恵まれていない者たちが正しい理解から遠ざけられるように、このようにあえて分かりにくくなるような書き方をされたのである。それゆえ恵まれていない者たちは、突然「小さな巻物」による挿入がなされた後に(10:1~11:13)、再びラッパに関する記述がその末尾部分から書かれているので混乱させられてしまうことになる。
今まで見てきたように、第6のラッパと第7のラッパの間には中間部分がある。このラッパにおける第6と第7の間に中間部分が存在しているのは誰の目にも明らかである。それでは、どうして第6と第7の間には、このような部分が挿入されているのか。その理由は2つ考えられる。まず一つ目は、例のごとく、より難解さを増し加えるためである。第6と第7の中間にこのような挿入が存在するほうが、より難しさが高まるのは確かである。二つ目は、記述の流れから単調さを取り除くためである。もし第6と第7のラッパの中間にこのような挿入がなかったとすれば、記述の流れが単調になっていたことは明らかである。記述の流れが単調になれば、それだけ黙示録が軽んじられることにもなる。何故なら、簡単なものは往々にして低く見られるものだからである。例えば、幼児向けのアニメ番組を低く見る大人は少なくないはずである。しかし、このような挿入が加えられて大きな中間箇所が創出されたら、記述が単調ではなくなるので、黙示録が軽んじられなくなるばかりか、その複雑性のために畏怖の念が抱かれることにさえなる。カントの文章はこの世で最も難解だと思われるが(特に3つの『批判』がそうである)、カントの文章が低いものとして軽んじられることはまずない。神はこのような理由のために、第6と第7の間に挿入を加え、黙示録が単調にならないようにされた。黙示録が畏怖されるべきもの、崇高さを感じられるものとなるためには、単調にならない必要があった。このような中間部分があるのは、神がこの黙示録をお書きになられがゆえである。もしこれが人間の書いた文書に過ぎなければ、このような中間部分を作ることはしなかったはずである。むしろ、人間は単純であって複雑なやり方をあまりしないものであるから、そのまま第6と第7の箇所を中間無しに繋げていたことであろう。また、第6と第7の預言の間に中間が存在するのは、このラッパだけでなく、巻き物および鉢の場合でも同様であるということは誠に注目に値する。これこそ神のやり方、これこそ神の書き方である。すなわち、ラッパの預言では第6の預言における末尾が書かれる直前に非常に長い挿入が入り(10:1~11:13)、巻き物の預言では第6の預言が全て開示し終わった時点で挿入が入り(7:1~17)、鉢の預言では第6の預言における末尾が書かれる直前に短い挿入が入っている(15:15)。6番目と7番目に挿入を加えることで複雑かつ難解にし、単調さを無くすと同時に聖徒たちの知性をその難しさによって試す―恵みによる霊的な知性を受けていない者は酷い混乱と無明に陥れられる。これは正に神の英知である。このような英知に基づく記述は、はっきり言って我々人間には測り知ることができないものである。神でなければ、一体どうしてこのような記述が思いつくのか。
たった今話された挿入の事柄について、もう少し詳しく説明をしてみたい。何故なら、この事柄は重要な事柄であって、大いに知るべき事柄だからである。神が、巻き物とラッパと鉢の中で、第6と第7の間に挿入を加えられたというのは、黙示録の理解における「奥義」である。どうしてこの理解が「奥義」なのか。それは、この事柄が非常に見出しにくく、あたかもピュタゴラスが自分の良しとした弟子にしか伝えなかった秘儀のようなものだからである。私も以前は、6番目に挿入がされているという認識を、明瞭には持っていなかった。その挿入が6番目の預言における最中か直後か、ということについては先に述べられた通りであるから、これ以上の説明はしない。それで、この挿入の内容は、その挿入が加えられる流れの内容に対し、明瞭に区別できるような内容となっていることに気付かされる。具体的にはこういうことである。すなわち7つの巻き物においては、諸国の民について語られている預言の流れの中において、天上における出来事の預言が挿入されている(7:1~17)。天上の出来事は第5の預言(6:9~11)および第7の預言(8:1)でも語られているが、それはほんの少し描かれているだけであって、挿入部分のように長々とした内容ではない。だから、巻き物における挿入は、巻き物の流れの内容とはだいぶ異なっていることが分かる。7つのラッパにおいては、ユダヤについて語られている預言の流れにおいて、聖徒たちの受ける苦難についての預言が挿入されている(10:1~11:13)。これも巻き物の場合と同じで、ラッパの流れとは、非常に異なった内容の挿入となっている。7つの鉢においては、ユダヤおよび異邦人についての預言がなされている中で、突如として聖徒たちに語りかけるキリストの声が預言として挿入されている(15:15)。これも先の2つの場合と同様に、その流れに乖離した内容の挿入である。これは、つまり神が7つの預言を6+1として構成しておられるということである。すなわち、神が7=6+1として7つの預言を組み立てておられるからこそ、6番目と7番目の中間にその流れとほとんど乖離している内容の挿入を加えることで、6と7に区別が見出せるようにされたということである。ほとんど全ての人は、6と7の間に区別が設けられていることに気付けない。何故なら、そもそも、そこで何が言われているのかさえ理解できていないからである。つまり「挿入がされている」という理解が生じる以前の段階にまだ留まっているということである。しかし、内容を理解しつつ考察する者には、この6:1という構成を察することができる。それは、神が恵みにより、そのことを悟れるように働きかけて下さるからである。しかし、どうして7つの預言が6と1という構成で組み立てられているのか。それは創造の7日間を考えてみれば分かる。地球が創世された最初の7日間において、神は6日目までを創造に使われ、7日目を完成の日とされた。つまり創造の7においては、まず6まで進んでから、その後に来る7において全てを完結させるという構成となっていた。7つの預言でも同じことが言える。つまり7の預言が6と1に構成されているのは、「6まで預言が進んだら遂に7の預言において全ての啓示が完結するのだ。7こそがクライマックスなのだ。創造の7日目が最後の日、つまり締めの日だったように。」という意味がこめられているわけである。このような挿入の事柄を考えても分かるが、黙示録は実に深く、あまりにも測り知りがたい。このような理解の奥義が、黙示録にはまだまだあるのではないかと私には思える。ぜひ神が、その奥義を、ご自身の民である聖徒たちに豊かに教えて下さらんことを。アーメン。
【11:14】
『第二のわざわいは過ぎ去った。見よ。第三のわざわいがすぐに来る。』
黙示録は繰り返しが多い文書だから(このことに気付いている聖徒はまったくいないのだが)、私も同じことを何度も繰り返して書かねばならないということを読者は理解してほしい(これが福音書や創世記であれば話は違ったことであろう)。もう既に語られたことではあるが、ここで言われている『第二のわざわい』には、『小さな巻き物』による預言(10:1~11:13)は含まれていない。確かに『小さな巻き物』に書かれている預言の内容も災いではあるのだが、それは『第二のわざわい』として規定されるべき災いではない。何故なら、『小さな巻き物』による預言とはラッパによる預言の流れを中断させる挿入に過ぎないのであって、この11:14は純粋な流れとして見れば9:21の続きだからである。
『見よ。』とは「これから書かれる預言の内容を注意して読みなさい。それを決して軽んじたりしてはいけない。」ということである。どうしてこう言われたのか。それは、これから書かれることになる第七のラッパによる預言が非常に重要なものだからである。だから、我々はこれから書かれる7つ目のラッパによる記述が重要なものであると認識せねばならない。それを軽んじるなど言語道断である。とはいっても重要なのは第7のラッパによる記述だけでなくて、当然ながら黙示録の他の全ての部分も重要なのであって、そればかりでなく聖書の全ての部分が我々にとっては重要なのではあるが。つまり、聖書はあらゆる部分が『見よ。』と言われるに相応しい書物であるということである。
『第二のわざわい』である第6のラッパにおける出来事が過ぎ去ると、すぐにも『第三のわざわい』である第7のラッパにおける出来事が起こるというのは、あの途中で介入してきた御使いが言っていたのと同じである。その御使いも、第6のラッパが吹き鳴らされた後で起こる第7のラッパの吹き鳴らしについて、『もはや時が延ばされることはない。』(10:7)と言っていた。ヨハネとこの御使いは明らかに同一のことを言っている。よって我々は、第6のラッパと第7のラッパにおける時間的な差異はほとんどなかったことを知らねばならない。つまり、第6のラッパで示されたユダヤの破滅が起こると(9:13~21および11:14)、それからすぐにも第7のラッパで示されている大審判の日が訪れるということである(11:15~19)。この第6と第7のラッパに大きな時間的差異があると考えるのは、今述べたことからも分かるように、聖書の啓示に反しているから、よく注意していただきたい。
【11:15】
『第7の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると、天に大きな声々が起こって言った。』
『大きな声々』の主は、セラフィムかセラフィム以外の御使いたちである。これはセラフィムだけかもしれないし、セラフィム以外の御使いたちだけかもしれないし、どちらの声でもあるかもしれない。これは24人の長老の声ではない。何故なら、すぐ後の箇所で『24人の長老たちも』(11:16)と書かれているからである。もし15節目における声の主が長老たちのものであれば、16節目でこう言われることはなかった。また、これは神の声でもない。というのは、この声は神を『主』として扱っているからである。この天で起こった声は実に大きかった。それは、この声が言うことは、素晴らしいことについてだからである。往々にして、素晴らしいことが語られる際には、声を大きくするのが望ましいものである。誰がこれを疑うであろうか。
『この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。』
『私たちの主およびそのキリスト』とは、父なる神とキリストである。キリストはそのまま書かれているが、父なる神は『私たちの主』などと書かれている。第一位格であられる御父および第二位格であられる御子だけを書いて、第三位格であられる聖霊を書かないのは、聖霊に対する不敬や罪のためではない。それは新約聖書の習わしである。パウロも多くの箇所で第一位格と第二位格しか書き記していないのを我々は確認する(ローマ1:7、Ⅰコリント1:3、Ⅱコリント1:2、ガラテヤ1:3、その他多数)。
『この世の国』とは、この世の国から贖い出されて天に住まうことになった聖徒たちを意味している。すなわち、これはこの地上における国家の意ではない。というのは、この第7のラッパの箇所ではキリストが『王となられた』(11:17)後に起こる大審判のことについて書かれているが、この箇所はマタイ25:31~46の箇所と対応しているからである。マタイ25章の箇所でもキリストが『王』と言われており(25:40、41、45)、王なるキリストがこの箇所でご自分のものとして獲得されるのは『羊』(25:32)、すなわちこの世から贖い出された聖徒たちである。それは、この地上における国家ではない。何故なら、このマタイ25章の中で言われているのは国家機構のことではなく、人のことだからである。それゆえ、第7のラッパの箇所と対応しているマタイ25章の箇所でキリストが獲得されるのが聖徒であるゆえ、我々が今見ている箇所に書かれている『この世の国』とは聖徒以外ではない。つまり、ここでは「この世の国から贖い出された聖徒たち」という言葉から「から贖い出された聖徒たち」という部分が除かれた上で『この世の国』と言われている。これは、ヨハネ3:16の箇所で「世の人々」という言葉から「の人々」という部分が除かれた上で『世』と言われているのと同じである。聖書ではこのような言葉の使われ方がされている箇所が少なくないが(※)、聖書を読み慣れた人であれば、そのことがよく分かるはずである。私は『この世の国』という部分が理解できなかったので、その意味が理解できるように祈り求めた。そうしたら、今述べたような見解に導かれた。よって私が今述べた見解は正しいと言える。我々に黙示録を教えて下さっておられる神に感謝。アーメン。『この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。』とここで言われているのは、つまり地上にいた聖徒たちが地上から解き放されて永遠に神とキリストの完全な支配の下に置かれるようになったということである。この出来事は第7のラッパが吹き鳴らされたユダヤ戦争の時期に実現された。その時に主の支配の下に置かれるようになった聖徒たちは、それ以降、永遠に天の場所で主の支配のうちに生き続けることになった。今この地上にいる聖徒たちも、この世を去った後に、天の場所で永遠に神とキリストの支配のうちに生き続けるようになる。それゆえ、聖徒たちは神とキリストとに感謝と賛美を捧げなければいけない。主が、こんなにも大きな恵みを我々に用意して下さっておられるのだから。
(※)
例えば、他にも「地」と書いて「地に住む人々」ということを意味している箇所がある。この場合、「に住む人々」という部分が省略されて「地」と書かれている。カルヴァンも、「「地」というのは、そこに住む者をさすのであって、…」(『旧約聖書註解 創世記Ⅰ』6:11 p160:新教出版社)と言っている通りである。ルターのように比喩的に「地」と書かれていると捉えても間違ってはいない。彼はこう言っている。「「地」が地上の人間たちを比喩的に表わしていることは、あらためて言うまでもないほど周知のことである。」(『キリスト教神秘主義著作集11 シュタウピッツとルター』第二回詩篇講義 p235:教文館)
[本文に戻る]
『主は永遠に支配される。』という部分は、もうお分かりであろう。これは、主が天で聖徒たちを永遠に至るまでも牧されるという意味である。その聖なる牧者の導きと守りは永遠に終わることがない。これこそ正にキリストが約束された『永遠のいのち』(ヨハネ6章47節)の内容である。すなわち『永遠のいのち』とは、キリストが永遠に支配されるということに他ならない。
【11:16~17】
『それから、神の御前で自分たちの座に着いている24人の長老たちも、地にひれ伏し、神を礼拝して、言った。』
御使いたちに続いて、『24人の長老たちも』神に崇拝を捧げた。長老たちが崇拝を捧げたのは、そのようにするのが彼らの本分だったからである。この長老たちの崇拝は、混じり気のない純粋そのものであった。というのは、天の住人は、まだ罪の残滓がある地上の聖徒たちとはその性質からして異なっているからである。天の住人には、地上に住まう聖徒たちとは違って、どのような思い煩いも、僅かの不信も、欠けた熱心もない。また、この際には『24人』の長老の全てが崇拝を神に捧げた。それは、神に反逆する者が、この長老の中には一人すらもいなかったからである。もしこの時に崇拝を捧げない長老がいたとすれば、その長老は天から追い出されていたことであろう。その長老は、自分の本分を弁えておらず、神を拝さないという罪を犯しているからである。
それにしても、天におけるこのような光景は、何と素晴らしいことであろうか。御使いに続いて長老たちが神に対して荘厳な崇拝を捧げる。これは実に神聖で厳かな光景である。天では、このような光景がいついつまでも続く。そのように行なわれるのが天国という場所だからである。神は、その場所において、永遠にご自身が当然受けるべき栄光をお受けになり給う。我々も、やがてこのような場所に行くことになるのを覚えるべきである。選ばれた聖徒であれば、誰でも天国に導き入れられることになる。しかも、その場所に行ったならば、このような光景を見ることができるだけなく、自分もその崇拝者の一員に加えられるので、大いなる喜びに満ちることになる。キリストが贖いとなられたのは、信じる者たちが、このような場所である天国に導き入れられるためであった。だから聖徒たちは、自分たちをこのような場所の住人として下さるために贖いとなられたキリスト・イエスに、大きな感謝と賛美とを捧げなければいけない。キリスト・イエスなくして、人に天国はないのである。
ここでは24人の長老たちが『地にひれ伏し』たと書かれているが、この『地』とは地上、すなわち地球世界における地面のことではない。これは天である。つまり、ここでは天における地面のことが言われている。何故なら、この長老たちは、天にいるからである。まさか、天にいるこの長老たちが、わざわざ地球の地面にまで降りて来て、その場所で神の前にひれ伏したとでもいうのか。『神の御前』で『座に着いている』のにもかかわらず、目の前にいる神から離れて、わざわざ地球の場所まで移動すると?こんな馬鹿らしい話は考えるのすら馬鹿らしいと言わねばならない。しかし、このように考えてしまう人も中にはいるに違いないから、私は今、あえてこのどうしようもない見解を取り上げておいた。それでは、天における『地』とは、一体どのようなものなのか。それは4:6の箇所でも言われているように『水晶に似たガラスの海のよう』な地面であった。長老たちは、この言わばクリスタルのような地面において身をかがめたのである。ここで、長老が『ひれ伏し』たのであれば重力がそこにはあったのかという疑問が出て来るが、重力の問題については詮索すべきではない。何故なら、天の世界は地上の世界とは原理が異なっており、その原理は今の我々の理性によっては把握できないものだからである。霊的な世界に関することを、どうして地上に住まう我々が理解できようか。それゆえ、我々は24人の長老たちが天の場所でクリスタルのような地面にひれ伏したということを知るだけで良しとすべきである。この重力について詮索するのは非常に危険である。これがどういうことなのかは、やがて我々が天に導き入れられた時に知ることができるようになるであろう。聖書では、今説明されたように『地』と書かれていながら実際は「天」である箇所もあるから、注意する必要がある。これとは逆に、聖書では「天」と書かれていながら地を意味している箇所もある。この場合、天と書かれているが、それは地球における大気圏、また大気圏を遥かに越えた宇宙空間のことを意味している。これにおいては、確かに「天」ではあるのだが、それは天国という意味における天ではない。
聖徒たちは、この箇所を通して、神に対する崇拝の重要性を弁えなければいけない。神とは、崇拝されるべき当然のお方である。また聖徒たちは、神に崇拝を捧げるようになるために救われ、聖徒とされた。だから、もし聖徒たちが神を拝さなかったとすれば、何のために救われて聖徒とされたのか分からなくなるし、それは大きな罪となる。それは、子が親を敬わず、弟子が師匠に仕えず、妻が夫に従わないようなものだからである。我々は、ここで『地にひれ伏し、神を礼拝して』いる24人の長老たちから良き刺激を受け、神を、ただ神だけを拝するようにますます邁進していかねばならない。神を拝さず、被造物に過ぎない存在を拝する愚か者どもには災いあれ。彼らは、罰として恥ずべき同性愛に引き渡される(ローマ1:21~27)(※)。
(※)
スエトニウスによればティベリウス帝は、偶像崇拝の儀式をしている最中に恥ずべき同性愛を実行してしまった。こう彼は記録している。「伝えるところによるとティベリウスは、ある日犠牲式をあげていたとき、香合を差し出した召使の顔に魅せられ、儀式がほとんど終るか終らぬうち、その場で直ちに別室に連れこみ、彼の兄弟の笛吹きも一緒に穢した。」(『ローマ皇帝伝(上)』第3巻 ティベリウス p272:岩波文庫)古代ギリシャ人と古代ローマ人は偶像崇拝を日常的にしており、彼らの社会全体に同性愛が普遍的に見られたことは周知の事実である。これは彼らが神を拝んでおらず、狂った崇拝行為にふけっていたことに対する罰だったのだ。同様にサタン崇拝をしている今の世界のリーダーたちも、その多くが恥ずべき同性愛に染まっているのである。
[本文に戻る]
【11:17】
『万物の支配者、常にいまし、昔います神である主。』
ここでは既に言われたことが言われている(1:4、1:8、4:8)。『万物の支配者』という部分は、既に説明されたから、ここで再び説明する必要はない。注目すべきは『常にいまし、昔います神である主。』という部分である。1:4、1:8、4:8の箇所とは違い、ここでは『後に来られる方』という言葉が省かれている。今挙げた3つの箇所では、この『後に来られる方』という言葉が『常にいまし、昔います神である主』という言葉と共に書かれていた。私は言うが、この違いはあまりにも重要である。どうして、この箇所では前の箇所では違って『後に来られる方』、つまり再臨されるキリストについては言われていないのか。それは、第7のラッパで示された出来事が起きた際には、既に再臨が起きているからである。キリストの再臨は、第5のラッパで示された出来事が起きた際には、既に起きている。つまり、実際の順序通りに記されている第5~第7のラッパにおいて示されている出来事は、再臨以降についての話が書かれている箇所だということである。この第5~第7のラッパの箇所は、―この理解は重要極まりないので是非頭に刻んでほしい―20:7~15の箇所と対応しているが、確かに20:7の時点では既にキリストの再臨が起こっており(19:11~21)、更には千年として表示されている42ヶ月の支配期間も過ぎ去っている(20:1~6)。恵みを受けた聖徒であれば、もうお分かりであろう。再臨は既に第5のラッパの時点で実現済みであるからこそ、この第5のラッパからいくらか経って後に起こる第7のラッパが吹き鳴らされた際には、もはや『後に来られる方』と言うことでキリストの再臨について語られてはいないわけである。第5のラッパの時点でもう既に再臨が起きているのだから、第7のラッパが鳴った際に長老たちが『後に来られる方』と言わなかったのは当然である。もし第7のラッパが鳴った際に再臨が起きていなかったとすれば、長老たちは1:4、1:8、4:8と同じようにキリストが再臨されることについて言っていたはずである。一方、この1:4、1:8、4:8の箇所では、まだ再臨が起きていなかったからこそ、『後に来られる方』と言って、これからキリストが再臨されることについて語っている。もしこの3つの箇所で既に再臨が起きていたとすれば、そこでは『後に来られる方』と言われることはなかった。我々が今見ている箇所で、キリストが再臨されることについてだけ省かれているのは、私の見解が正しいことを証明している。つまり、私が神の恵みにより既に説明したように、本当に第5のラッパから始まる出来事は再臨後に起こる出来事なのである。私の見解が正しいのは当然のことである。何故なら、神が私の祈りを聞いて下さり、私に黙示録の正しい見解を与えて下さっておられるからである。だから、これは私の見解と言うよりは、神の見解と言ったほうが正しいと言えよう。私以外の聖徒で黙示録における神の見解を知りたいと願われる方がいたとすれば、その人は、神にそのことを祈るとよい。そうすれば正しい見解が必ずや与えられることであろう。ヤコブが次のように言っている通りに。『あなたがたの中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は、だれにでも惜しげなく、とがめることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。』(ヤコブ1章5節)(※)
(※)
カシオドルスの言葉からも教えられるべきであろう。彼はこう言っている。「それゆえ、あらゆる有益な事柄の根源である神に祈ろう。たゆまず読み続け、熱心に繰り返しなさい。知恵の母は不断の集中的な黙想である。私はまた、雄弁なるカッシアヌスが『問答集』の第5巻において次のように述べていたのを見逃しはしない。彼によれば、教育のないある老人が聖書の非常に不可解な個所について問われ、繰り返し祈るうちに、上方からの光によってそれ以前に人間の教師からは教えられたことのない事柄を知り、突然神的な霊感に満たされて、問いを発した人々にその不可解な事柄を説明したという。聖アウグスティヌスが『キリスト教の教え』という書物において語っている話もこれと同様である。それによれば、学問の素養のないある異邦人の奴隷が繰り返し祈るうちに、まるで学校での長い訓練を通して学んだかのように、彼に手渡された書物を突然読んだという。聖アウグスティヌスはこれについて次のように述べている―これは驚嘆すべき奇跡であり、「信仰のある人々にとってはあらゆることが可能である」ことの証しとなるかもしれないが、われわれはそのようなことをしばしば望むべきではなく、われわれが大胆にも上方にあるものを探究しようとするときには、主の命令に背いて誘惑の罪へ向かうと思われないように、むしろ学問の通常の修練に耐えるべきである。主は「申命記」では「あなたがたの神、主を試みてはならない」と言い、また同様に「マタイによる福音書」では「よこしまで神に背いた時代の者たちはしるしを求める」と述べているのである。それゆえ、祈ろう。われわれに対して閉ざされた事柄が明らかにされるよう、そして読んで学ぶことからけっして切り離されることのないようにと。常に主の法に従っていたダビデですら「私に知恵を与えて、あなたの戒めを学ばせて下さい」と言って、主に呼びかけたからである。実際、この賜物は、受け取れば受け取るほどさらにいっそう求めたくなるような、このうえなく甘美なものである。」(『中世思想原典集成5 後期ラテン教父』綱要 第1巻序 p339~340:平凡社)ボエティウスも「哲学の慰め」5巻の中で、次のように言っている。「祈りがよくなされるとき、それが無力であることはありえない。」
[本文に戻る]
『あなたが、その偉大な力を働かせて、王となられたことを感謝します。』
ここで言われているのは、第7のラッパが鳴ると、キリストが正式な意味において天国と聖徒たちの『王となられた』ということである。キリストは、第7のラッパ
が鳴る前にも、天国と聖徒たちに対して王であられた。詩篇に『主は大いなる神であり、すべての神々にまさって、大いなる王である。』(詩篇95篇3節)また『主は、王だ。』(97篇1節)また『主は、王であられ、みいつをまとっておられます。』(93篇1節)と書かれていた通りである。しかし、天国の場所で正式に聖徒たちの王となられたのは、この時が初めてであった。これは、既に結婚しているのだが離れて暮らしている男女が、遂に結婚式を挙げて一緒に住まうようなものである。この時に正式な王として天国に君臨されたキリストは、それ以降、永遠に王として天国に君臨し続けられる。キリストという王に治められる御国は永遠に続くであろう、と聖書で言われたのは正にこのことであった。そのことについては例えば次のように書かれている。『その子はすぐれた者となり、いと高き方の子と呼ばれます。また、神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。』(ルカ1章32~33節)『この方こそ生ける神。永遠に堅く立つ方。その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。』(ダニエル6章26節)紀元1世紀に天の場所で王となられたキリストは、天国で王として永遠に統治を行なわれるのである。キリストが王となられたのは、父なる神の命令されたことであった。というのも、キリストは父の命令によらないでは何事もなさらないお方だからである。それはキリストご自身が、『わたしは、自分からは何事も行なうことができません。』(ヨハネ5章30節)と言っておられる通りである。また、その命令は御父の御心に適ったことであった。何故なら、御父は御心に適ったことしか御子に命じられないからである(※)。なお、ここでキリストが『王となられた』とあるのは、この世の国家機構に対してではなく、天国と聖徒たちに対してであるということを再び言っておきたい。何故なら、キリストが王として支配される国とは、この世の国家機構においてではなく、霊の国においてだからである。キリスト御自身が『わたしの国はこの世のものではありません。』(ヨハネ18章36節)と言われた通りである。また、このことは第7のラッパと対応しているダニエル書7章の箇所からも言える。そこでキリストが主権をもって統治されると言われているのは、明らかに天における霊の国のことだからである。もしそうでなければ、第7のラッパが鳴った紀元1世紀以降、この世の全ての国はキリストを実際に王とする体制となっていたであろう。何故なら、ここでキリストが『王となられた』と書かれているのは、明らかに実際的なことを言っているのだから。
(※)
詩篇115:3には、『私たちの神は、天におられ、その望むところをことごとく行なわれる。』と書かれてある。これは御子に対して命令を与えられることにおいても同じである。すなわち御父は、御子に対して『その望むところをことごとく』命じられるのである。
[本文に戻る]
キリストが天の王となられたのは『偉大な力』によるものであった。天国という神聖で崇高な場所の王となることほど、力ある業が他にあろうか。それは神のなされた誠に大きな御業であった。矮小な被造物であれば、このようなことは決して出来なかったであろう。
また、キリストが天で王となられたのは感謝すべきことであった。何故なら、それは大変に素晴らしいことだったからである。この時に感謝を捧げた24人の長老たちの感謝は、純粋そのものであった。それというのも、天国の住人たちは常に『心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛する』からである。地上にいる聖徒たちは、この長老たちの感謝を見習うべきである。神に対する感謝には偽りや欠けた熱心があってはならないのだ。そのようにして純粋な感謝を捧げるならば、それは神の栄光となる。この長老たちの感謝は我々の模範である。
【11:18】
『諸国の民は怒りました。』
人々は何に怒ったのか。その怒りの対象は何だったのか。人々が怒ったのは、聖なる福音に対してであった。つまり、ここで言われているのは小さな巻き物の中で示されていた『1260日』(11:3)の活動期間において聖徒たちが宣べ伝えた福音を聞いて、多くの人々が怒ったことについてである。11:10でも書かれているように、人々はその福音宣教により苦しめられたのだから、確かに『諸国の民は怒』ったことになる。何故なら、人間の自然な性質として、苦しめられるならば怒りが生じるものだからである。苦しめられたので怒りが生じた経験は、誰でも持っているはずである。確かに、この福音とは滅びるべき不信者らにとっては、怒りをもたらすものである。何故なら、それはパウロも言うように不信者にとっては『死から出て死に至らせるかおり』(Ⅱコリント2章16節)だからである。確かに福音は地獄の子らにとっては害毒でしかない。汚らわしいバイ菌にとって清浄な消毒剤が滅びをもたらす害毒であるのと同じことである。バイ菌である不信者たちは、バイ菌なのだから、自分に永遠の滅びを宣告する清浄な消毒剤なる福音に対して怒りを持つのが自然の理である。だから、当時において福音を聞かされた『諸国の民』が怒ったのは何もおかしいことではなかった。福音が怒りをもたらすというのは歴史も語ることであって、今に至るまで実に多くの人たちが福音を聞いてその心に怒りを持ったものである。16世紀のローマ・カトリック教徒も純正な福音の教えを聞いて怒り狂い、その怒りに任せて宗教改革者たちを大いに迫害したのであった。
『しかし、あなたの御怒りの日が来ました。死者のさばかれる時、あなたのしもべである預言者たち、聖徒たち、また小さい者も大きい者もすべてあなたの御名を恐れかしこむ者たちに報いの与えられる時、地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時です。』
『あなたの御怒りの日』とは、神が空中の審判を執行なさる時、またサタンとその使いたちが裁かれる時のことを言っている。この言葉は、裁かれるべき者たちを基点にした言葉である。というのも、この日には裁かれない義人もいるが、その義人を基点にすると『御怒りの日』とは言えないからである。彼らを基点にすると、むしろ「あなたの恵みの日」という言葉となる。この日は紀元70年であった。この言葉は黙示録で言えば、20:9の『すると、点から火が降って来て、…』から15節目までに該当している。この『御怒りの日』は、旧約聖書において昔から預言されてきた。例えば、ダニエル7:10の箇所では、この日に起こる審判について次のように書かれていた。『…幾万のものがその前に立っていた。さばく方が座に着き、幾つかの文書が開かれた。』ここでは、神の裁きの座の前に多くの者たちが集められることが言われている。なお、この部分も『すぐに起こるはずの事』(1:1)だったから、既に成就している。
ここで書かれている内容を詳しく見ていこう。ここでは3種類の存在について語られている。まず一つ目は『死者のさばかれる時』である。これは、こういうことである。まず『千年』として表わされている3年6ヶ月の支配期間が終わると、第二の復活が起こる(20:5)。第一の復活が『幸いな者、聖なる者』(20:6)に限定されていたのに対し、第二の復活においては悪しき者たちが復活させられる。この第二の復活により復活する悪しき者たちは、神の国に関わっていた者たちだけであった。神の国に関与していない者たちは、この第二の復活により復活してはいない。この第二の復活についての詳しい説明は、20章の註解が来た時に譲りたい。それで『死者のさばかれる時』とは、この第二の復活により復活した邪悪な死者たちが空中の座において裁きを受けることを言っている。黙示録では、20:12~15にこのことが書かれている。彼らは空中の座において裁かれた後に『火の池に投げ込まれた』(20:15)。マタイ25:31~46の箇所では、41~46節目と対応している。そこでも、やはり彼らは空中で裁かれてから『永遠の火』(25:41)に投げ込まれている。二つ目は『あなたのしもべである預言者たち、聖徒たち、また小さい者も大きい者もすべてあなたの御名を恐れかしこむ者たちに報いの与えられる時』である。これは、紀元70年の審判までに存在していたあらゆる聖徒たちが、空中の座においてキリストから永遠の命を宣言されることを言っている。これも黙示録では20:12~15で、そのことが言われている。この者たちのためには『いのちの書』(20:12)が開かれた。これは、つまり永遠の命がそこにおいて与えられるということである。マタイ25章では34~40節目が対応している。こちらのほうの人たちについては、もうこれ以上の説明をしなくても十分に分かるであろう。三つ目は『地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時』である。『地』とはユダヤの地のことであり、『滅ぼす者』とはユダヤの地を滅ぼすサタンとその使いたち及びローマ軍のことである。実際、これらの者たちは、紀元70年においてユダヤの地を容赦なく徹底的に滅ぼした。つまり、ここで言われているのは、ユダヤの地を滅ぼしたサタンどもとローマ軍たちに、神からの裁きが与えられるということに他ならない。サタンとその使いたちは『火と硫黄との池に投げ込まれ』(20:10)るという裁きを受け、ローマ軍たちは御言葉という火により裁かれた(20:9)。前者のほうは働きの停止という形での霊的な裁きを受け、後者のほうは霊的に滅ぼされたが肉体としては損害無しにそのまま保たれた。ローマ軍は、霊的に滅ぼされたのであって、肉体的なことがここで言われているのではないことに注意せねばならない。サタンが働きの停止に至らせられたというのは、既に第2部でいくらか触れておいた。そこでも言っておいたが、このことについては、20章を註解する時が来たら詳しく説明されることになる。『地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時』とは、20:9の『すると、天から火が降って来て、…』という部分から20:10の全部分までが対応している。この箇所は、最初の2つの存在を一纏めにし、残る3つ目の存在を前の2つの存在と区分すると把握しやすくなる。つまり、3つの存在を2:1という区分に分けると分かりやすくなる。黙示録は、このような区分をすれば非常に把握しやすくなる箇所が少なくない。
ここで言われている『御怒りの日』が未だに到来していないと考えるのは異常である。異常だからこそ、そのように考えるのである。何故なら、神はこの箇所で示されている出来事が『すぐに起こる』(1:1、22:6)と言われたのだから。神の言葉に明らかに沿わないことを考えるのは、正に異常であると言わずして何と言えばよいであろうか。しかし、多くの読者は「ここで言われている出来事が既に起きたとは考え難い。」などと思われるかもしれない。私は言うが、そのように考える人はキリスト者ではないのである。神から出たキリスト者ではないからこそ、自分の考えを神の言葉の上に置き、神が言っておられることに聞き従おうとしないわけである。キリストは神の言葉に聞き従わない邪悪なパリサイ人に次のように言われた。『あなたがたが聞き従わないのは、あなたがたが神から出た者でないからです。』(ヨハネ8章47節)もし神から出た真のキリスト者であれば、神が御言葉において言われたことに聞き従っていたはずだ。キリストが『神から出た者は、神のことばに聞き従います。』(同)と言われた通りである。それゆえ、もし私の説明を読んで理解しながら正しい見解を受け容れない人がいれば、その人は正しい見解を受け容れないことによって、自分がキリスト者ではないことをみずから証明していることになる。
この箇所を見るだけでも分かることだが、黙示録は、創世記や出エジプト記のように実際に起きた通りの順序で文章が書き記されている文書ではない。この文書は、創世記と似ているというよりは、むしろイザヤ書と同じである。イザヤ書のほうも、創世記などとは違って、そこでは時間の流れに則った記述がされているのではない。つまり、そこでは時間の順序がほとんど記述において考慮されていない。今に至るまであらゆる教師たち、あらゆる聖徒たちが、黙示録は時間の流れの通りに一本調子で書かれていると思い込んできた。―内容を理解していないにもかかわらず勝手にそのように思い込んでいた、否、というよりは内容を理解していないからこそ誤った思いを抱いてしまったと言ったほうが正しいかもしれない。―しかし実際は、黙示録に創世記のような「時間の矢」は流れていない。黙示録を理解したい聖徒は、このことをよく覚えてほしい。実際にこの箇所についていくらか考えるだけでも、今述べたことがよく分かる。何故なら、この箇所で書かれている「第7のラッパ」の内容は、後ほど書かれている20:9~15の箇所と同じ内容だからである。また、この7つ目のラッパは第7の鉢の内容(16:17~21)とも対応している。もうこれだけでも、黙示録には創世記のような時間の流れが存在していないことが明らかである。これは創世記で言えば、世界創世について記された1章目の内容が、再び繰り返して24章や45章の箇所に記されるのと同じことである。しかし、今まで教会は、このことにまったく気付けなかった。というのも、今まで教会は黙示録をそもそも何も理解できず、ほとんど全ての箇所に霧がかかっているも同然だったからである。つまり、黙示録の内容が何も分かっていなかったので、時間の流れがあるとかないなどといった理解を持つ以前の問題だったのである。黙示録の内容がほとんど濃い霧に包まれていたのであれば、そこに並んである木々の配列具合を知ることがどうしてできようか。それはできることではない。私がこのように理解できたのは、私が黙示録の奥義を神に願い求めたからである。神が、私にこのような理解の奥義を与えて下さったからこそ、私はこのような理解を持てるようになった。神の恵みがなくては、黙示録を正しく理解することは決してできない。神にこそ誉れが帰されんことを願うものである。アーメン。
【11:19】
『それから、天にある、神の神殿が開かれた。神殿の中に、契約の箱が見えた。』
『天にある、神の神殿が開かれた。』という部分は、少しばかり難しい。これは、他の箇所もそうであるが、神の恵みがなければ理解することも、説明することもできない。『神殿が開かれた』と書かれているのは、天国にある神の神殿に、聖徒たちが入って住めるようになったということである。聖徒たちがそこに導き入れられるようになったからこそ、神殿が『開かれた』と言われているのだ。第7のラッパが吹き鳴らされる前までは、聖徒たちの魂が神殿の存在する天に挙げられることはあっても、それはまだ魂だけの状態であり、しかもまだキリストは天において正式な王になっておられなかった。だから、第7のラッパが鳴らされるまでは、聖徒たちの住まうべき天の神殿が「閉じていた」と言わねばならない状態にあった。しかし、第7のラッパが鳴らされてからは、聖徒たちは御霊の身体において天にいられるようになり、しかも11:17で言われていたようにキリストが天において正式な『王となられた』のだから、天の神殿が『開かれた』と言われるに相応しい状態が現われたことになる。つまり、『神殿が開かれた』とは、遂に天国が正式な形でスタートすることになったという意味に捉えればよい。それまでには正式な形としてはスタートしていなかった。今や、天にある神殿が開かれた時代が到来している。だから聖徒たちは、この世を去ってから、その開かれた神殿に入れるようになっている。そのような方式は第7のラッパが吹き鳴らされた時から始まった。つまり天は、それ以前の状態とは違ったものになったわけである。しかし、この第7のラッパの吹き鳴らしにより天の神殿が開かれた正確な時期については、まだ詳しいことを書くことができない。私の理解が更に進めば、やがてこの部分を書き直すことになろう。ただ一つ言えることは、その時期は紀元1世紀におけるユダヤ戦争の時期であって、それは既に実現済みであるということである。何故なら、この第7のラッパの吹き鳴らしにより起こる出来事はユダヤ戦争の時期のことを言ったものであり、それは例のように『すぐに起こるはずの事』(1:1)だったのだから。なお、この天にある神殿については、21:1~22:5の箇所で詳しく書かれている。
『契約の箱』とは、神と聖徒との間に結ばれている聖なる契約を意味している。つまり、ここで言われているのは、天の神殿に住まう聖徒たちが、神との間に契約を結んだ状態にあるということに他ならない。天の神殿に住まう者が誰でも例外なく神と契約を結んでいるということを疑う聖徒はいないはずである。キリストを持たない不信者たちの場合、キリストを持たないがゆえに、神との契約も持っていない。だから、そのような者たちは天の神殿の中に住まうことがなく、憐みを受けることもなく地獄へと突き落とされてしまう。天の神殿とは、キリストにより神と契約を結んでいる聖徒たちだけが導かれて住まうことのできる場所なのである。また、この神殿の中にある『契約の箱』を我々は実際的に捉えるべきではない。この言葉は象徴的に捉えるべきものである。天の神殿の中に、物理的な実際の契約の箱は存在しない。何故なら、神と聖徒たちの間に結ばれているキリスト契約こそが、真の意味における契約の箱だからである。心にキリストの十字架を持っているキリスト者には実際の死刑道具としての十字架やアクセサリーとしての十字架がまったく不要であるのと同じように(※)、天の神殿に住まう聖徒たちは、真の契約の箱である神との契約を持っているので、実際的な目に見える契約の箱は必要ないのである。もし天の聖徒が実際の箱を求めるとしたら、それは地上に生きている聖徒が実際の十字架を愚かにも欲するようなものである。
(※)
残念なことに、異常な状態になっている今の教会では、キリスト者であるのに十字架のペンダントを着けていたり、十字架の刺青をしている者がしばしば見られる。心に十字架の信仰を持っているのであれば、どうして目に見える十字架を求める必要があるのか。このような物理的な十字架を今のキリスト者が持っているのは、キリスト教界が堕落しており、聖徒たちの信仰が弱く、また異常になってしまっている証拠である。
[本文に戻る]
『また、いなずま、声、雷鳴、地震が起こり、大きな雹が降った。』
これらのものは、神の怒りと裁きとを示している。聖書では、神の日が語られる際に、このようなものにより言い表わされている箇所が少なくない。『いなずま』とは、神の裁きを示す。神の裁きは、稲妻が落ちるかのように恐ろしい。『声』とは、裁きの日に鳴り響く声のことを言っている。『雷鳴』とは、神の怒りを示している。神の怒りは、雷鳴のように激しいのである。『地震』とは、神の裁きに対しては、地も戦慄するということである。『大きな雹が降った。』とは、神の裁きの凄まじさを言っている。すなわち、神の裁きは、巨大な雹の雨が耐え難いように、耐え難いということである。この『雹』は文字通りに捉えるべきではない。ユダヤ戦争の時期に『雹』が上から降って来たということは、実際にはなかったからである。これは、あくまでも神の裁きを象徴したものだと理解しなければいけない。この部分で言われていることを考えれば、神の怒りと裁きとがどれだけ凄まじいものであったかがよく分かる。
この部分は、黙示録の中では次に示す御言葉と対応している。『また、1タラントほどの大きな雹が、人々の上に天から降って来た。人々は、この雹の災害のため、神にけがしごとを言った。その災害が非常に激しかったからである。』(16:21)『すると、天から火が降って来て、彼らを焼き尽くした。』(20:9)この20:9の箇所では『火』しか書かれていないが、この箇所と対応しているエゼキエル38:22の箇所では『火』と共に『雹』も書かれているので、我々が今見ている11:19の箇所と対応していることになる。私は先に黙示録は繰り返しの多い文書であると述べたが、このように見てみると、本当に黙示録には繰り返しが多いということがよく分かるのではないかと思う。とはいっても、黙示録に繰り返しが多いというのは、神の恵みにより黙示録を研究してよく理解できるようになった者だけが、明瞭に認識できることである。よく理解するからこそ、何が言われているのか把握できるようになり、その結果、繰り返しが多いという認識も明瞭に持てるようになるからである。他方、黙示録を理解できていない人の場合、所々で似通った内容が言われていることは薄々と感じるのだが、黙示録には繰り返しが多いと明瞭に認識するまでには至らない。何故なら、その人は、そもそも内容自体があたかも霧に包まれてよく見えない物体のように理解できていないからである。そもそも内容を理解していないのだから、当然ながら繰り返しが多いという認識も強く持てない。すなわち、まだ内容がよく分かっていないので、繰り返しがあるとかないとかさえハッキリ言う段階にまで達していないということである。
これで7つのラッパによる預言は終わった。このラッパによる預言について良き理解を得られた聖徒は、神に感謝すべきである。神の恵みが無ければ、黙示録を正しく悟ることなどできないのだから。ヨハネ3:27。
この7つのラッパによる預言とは、「ユダヤおよびユダヤの裁きについての預言」であった。それは『もろもろの民族、国民、国語、王たちについて』(10:11)の預言ではなかった。これはユダヤに関する預言だから、ネロが聖徒たちを迫害する出来事は、その中に含まれておらず、それは挿入箇所(10:1~11:13)、つまり別枠において預言されている。このラッパの預言で示された出来事の期間は、ユダヤ戦争(66―70)の間であった。この預言の内容は、ユダヤ戦争の期間から、少したりともはみ出てはいないことを読者は覚えよ。しかし、どうしてユダヤの裁きに関するこの預言では、ラッパが用いられたのか。それは、この預言はユダヤの裁かれる時が到来したことについて語っているからである。ラッパは、何かの時が到来した時に使われるのが望ましい楽器である。誰でもラッパの大きな響きが鳴り渡れば、何かが起こり始めるのではないかと思うものだからである。「なんだ、なんだ、何が起こるのか」と。つまり、このラッパによる預言とは、こういうことなのである。「これから間もなくユダヤに裁きの与えられる時が訪れる。神は、その時の訪れをラッパの響きと共に告げ知らせておられる。何故ならラッパは時の訪れを合図するのには調度良いものだからだ。だから、読者はこのラッパが時の到来を示していることを知れ。」だから、もしこれがユダヤに関する時の訪れを知らせようとしたものでなければ、合図を出すのに相応しい楽器であるラッパは用いられていなかったであろう。『ただ、すべてのことを適切に…行ないなさい。』(Ⅰコリント14章40節)と言われた神は、あらゆることを適切に行なわれる。ユダヤに裁きが訪れる時のことについて預言する際にラッパを用いるのは、神にとって適切なことであった。
最後に、巻き物の箇所でなされたように、このラッパの箇所でも簡単な総復習をせねばならない。このような難しい文書において、多かれ少なかれ復習することなしに十全な理解が得られるなどと思ってはならない。もし復習なしによく理解できると思う人がいれば、その人は黙示録を侮っている。何故なら、その人は黙示録について、たとえ復習をしなくてもよく理解することが可能な文書であると考えているからである。それは、その人が黙示録を並の文書であると考えている証拠でなくて何であろうか。黙示録が高度な文書だと考えていたとすれば、復習しないでも十全な理解を得られるなどとは思わないはずである。事実、この文書は復習抜きには豊かな理解を得られない文書である。それは、この文書が、あまりにも深くて神妙な文書だからである。復習をすることにより、隠れていたことや分からなかったことが徐々に見出せるようになってくる、という性質をこの文書は持っている。特に心に留め忘れるべきでないのは、第5~第7のラッパの出来事が20:7~15の箇所と対応しているということである。この対応しあっている部分を実際に自分で読み比べて見れば、それぞれまったく同じことを同じ順序で言っているのに気付くはずである。また、7つの預言の内容が2つに大別できるという理解も重要である。というわけで、7つのラッパによる預言の内容は、短く纏めれば以下のごとくであった。
(Ⅰ:時間経過とは無関係な記述)
【第一のラッパ】 ユダヤの滅亡(8:7)/対応箇所…20:9
【第二のラッパ】 ユダヤの滅亡(8:8~9)/対応箇所…20:9
【第三のラッパ】 ユダヤの滅亡(8:10~11)/対応箇所…20:9
【第四のラッパ】 ユダヤの滅亡(8:12)/対応箇所…20:9
(Ⅱ:時間経過に則った記述)
【第五のラッパ】 災い①―解き放されたサタンが招集したローマ軍に取り囲まれるユダヤ(9:1~12)/対応箇所…20:7~9
【第六のラッパ】 災い②―御使いとローマ軍によるユダヤの滅び(9:13~21、11:14)/対応箇所…20:9
【第七のラッパ】 災い③―サタンの裁きと空中の大審判(11:15~19)/対応箇所…20:9~15、マタイ25:31~46
■期間:紀元68年6月9日以降~紀元70年
第14章 ⑪12章:ネロによる大患難からサタンがローマ軍を招集する出来事までについての預言
12章では、ネロによる大患難からサタンがローマ軍により『聖徒たちの陣営』(20:9)を取り囲ませる出来事までが示されている。時期は、紀元64年12月~70年までとなる。この章は、明確に2つに区切ることができる。一つ目は6節目までである。ここでは大患難の出来事から始まり、聖徒たちが復活して千年として表示される『1260日』(12:6)の完全な支配期間が始まるまでの出来事が書かれている。二つ目は7節目から18節目である。そこでは千年である『一時と二時と半時』(12:14)すなわち3年6ヶ月(=1260日)の支配期間が始まってから、その支配期間が終わってサタンによるローマ軍の包囲が起こる出来事までが書かれている。この章では、20章に出て来る『千年』が「3年6ヶ月」(=1260日)であると明確に規定されている。このことについては、これから説明されていくが、これは誠に誠に重要な理解である。
この18節分を1章分として区切ったのは、文句の付けようがない。黙示録の章区切りをした古代の人は、黙示録のことをまったく理解できていなかっただろうが、ここでの章区切りは完璧であった。神が私に黙示録の章区切りを委ねて下さったとすれば、私もこの18節分を1章分として区切ることであろう。
ここでも必要なのは、やはり信仰と祈りと聖句と思考と霊と恵みである。これらのものを持たないと、容易に誤謬に陥ったり、ひどく混乱したり、ずっと分からないままでいることになる。私は豊かに註解をしているつもりだが、もし私が書かなかったことで何か分からないことがあれば、その時は神に祈り、答えが何であるのか願い求めるようにしてほしい。純粋な心で祈れば、きっと分かるようになるはずである。
【12:1】
『また、巨大なしるしが天に現われた。』
『巨大な』とは、つまり非常に重要であるということを示す。何故なら、もし「小さな」徴であれば、あまり重要だとは感じられなかっただろうから。すなわち、神はその幻が非常に重要であるからこそ、その幻を巨大な視象によりお示しになられた。よって我々は、この『巨大なしるし』において語られていることを、それが重要であるがゆえに、よく心に留めなければいけない。
『ひとりの女が』
『ひとりの女』とは教会である。何故なら、この12章の箇所では、教会に起こる諸々の出来事が預言されているからである。新約聖書において、教会は「女」として取り扱われている。例えば、黙示録19:6~8の箇所では教会がキリストの『花嫁』としての女で描かれており、パウロもエペソ5:22~33の箇所で教会をキリストの妻である女として描いている。旧約聖書でも、やはり神の集団は女として取り扱われている。そこでは『おとめイスラエル』(アモス5章2節)とか『裏切る女、妹のユダ』(エレミヤ3章10節)というような言葉が頻繁に出てくる。だからこそ、古代の教父たちは、たびたび教会を指して「女」と言ったのである。聖書に堅く立てていない最近の教会では、聖書に堅く根ざしていないので、古代とは違って、あまり教会のことを「女」ということはないのであるが。それゆえ、ここで教会が『ひとりの女』として言い表わされているのを読んで、我々は何か不思議なことが言われているなどと思うべきではない。これをマリヤであると捉えてはならない。この女がマリヤだとすれば、ここではマリヤがキリストを生み(12:5)、そのキリストが昇天されること(12:5)について書かれていることになる。キリストが昇天されたのは紀元33年頃である。とすれば、ここではマリヤがキリストの昇天後に『1260日の間』(12:6)、すなわち紀元33年~36年の間に『彼女を養うために、神によって備えられた場所』(12:6)に逃げたことについて書かれていることになる。しかし、これは全く意味が分からない。そもそもマリヤは紀元33~36年の間に荒野に逃げたのか。それが本当だとすれば、一体どうしてそこに逃げたのか。またもしそれが本当であれば、一体どうしてヨハネ以外の使徒は、そのことについて何も書簡の中で触れていないのか。更に言えば、ヨハネがここでそのことについて記すのには、どのような意味が、どのような意義があったのか。このようにこれがマリヤだと捉えると、12章全体がよく分からないものとなってしまう。しかし、これを教会だと捉えるならば、この章では非常に意味と意義のある内容が記されていることを悟らされる。それゆえ、この『ひとりの女』をマリヤだと理解してはいけない。またこれはマリヤ以外の女でもない。何故なら、この女にもっとも該当すると思われる特定の女性はマリヤしかいないが、そのマリヤでさえもこの『ひとりの女』に該当しないのであれば、尚更のこと、他の女は除外されることになるからである。すなわち、この女は使徒ペテロの妻でも他の使徒の妻でもマグダラのマリヤでもその他の有名な女性でもない。
『太陽を着て、』
教会が『太陽を着て』いたとは、つまり教会がイエス・キリストをその身に纏っていたということである。何故なら、太陽とはマラキ4:2で言われているようにキリストだからである。『主イエス・キリストを着なさい。』(ローマ13章14節)と命じられているように、聖徒とはキリストをその身に着ている人たちである。教会とは、その聖徒たちが集った存在である。だから、キリストを着ている聖徒たちの集合体である教会はキリストをその身に着ていると言える。つまり、女である教会は太陽であるキリストを着ているわけである。もしこの女が教会ではなくマリヤであると解すると、ここではマリヤがキリストを着ていることについて言われていることになる。これは意味が分からないと言わねばならない。どうしてマリヤがキリストを着ていることについて、ここで言われているのか。それは何の意義も感じられないことである。マリヤがキリストを着ていたからと言って、我々にどのような意味があるのか。我々にマリヤ崇拝をさせるためだとでもいうのか。とんでもない話である。だから、やはり、ここに書かれている『ひとりの女』とはマリヤではないということになるのだ。
『月を足の下に踏み、』
教会が『月を足の下に踏み』つけていたとは、すなわち教会が聖徒たちを支配していたという意味である。というのは、聖徒とは太陽であるキリストに照らされて輝く存在だからである。周知のように、月は自ら光を放っているわけではなく、太陽からの光を反射しているからこそ光り輝くことができている。聖徒も、キリストという太陽に照らされてこそ輝くことのできる月に他ならない。聖徒たちは月であって、自分自身によっては光り輝けないからである。だから、この部分では、教会が月であるその聖徒たちを『踏み』つけている、つまり支配していることについて言われていることが分かる。ここで聖徒たちが『踏み』つけられていると言われているのを、悪い言い方だと思ってはならない。これは一見すると悪い言い方のように思えるが、単に教会が聖徒を支配していると言っているに過ぎないのだから、何か悪いことが言われているかのように思うべきではない。もしこの言い方が悪いとすれば、ペテロに対して『人間をとる漁師にしてあげよう。』(マタイ4章19節)と言われたキリストも悪い言われ方をされたことになってしまう。何故なら、ここでキリストは人間を魚という取るに足らない被造物に例えておられるのだから。悪いのは言い方ではなくて、むしろ聖徒たちを『踏み』つけない、つまり支配しない教会である。そのような教会は、つまりその教会の牧者が、羊たちをしっかりと牧していないことを意味するのだから。牧するとは、言い方は悪く聞こえるが『踏み』つけることでなくて何であろう。というのは、牧することにより、その足の下に従わせることになるからである。昔の牧者たちはしっかりと羊を牧さなかったからこそ、神から断罪されてしまったのである。
『頭には12の星の冠をかぶっていた。』
教会は『頭には12の星の冠をかぶっていた』が、これは教会が使徒の教えに立脚していることを示している。「12」は12使徒かイスラエル12部族以外にはないが、ここでは新約の教会について言われているのだから、これは12使徒のことを言っている。それで、パウロも言うように教会は『使徒…という土台の上に建てられて』(エペソ2章20節)いるし、またそのようでなければいけない。だから、ここでは教会が使徒を土台としていると言われていることが分かる。そのことが、ここでは『12の星の冠をかぶっていた』と言い表わされている。よって、この「12」をイスラエル12部族と捉えることは不可能である。また、ここでは使徒が『星』として表現されている。我々はこの表現を不思議に思うべきではない。何故なら、聖徒を星として例えるのは聖書的なことだからである。例えば、ダニエル12:3では多くの人を回心に導いた聖徒について次のように言われている。『多くの者を義とした者は、世々限りなく、星のようになる。』パウロもⅠコリント15章の箇所で、星を通して聖徒の復活体について論じている。だから、この箇所で使徒が星と表現されていても驚くには値しない。また、この12人の使徒は、キリストが直接お選びになった11人と、ユダの代わりに使徒となったマッテヤである。この中にパウロは含まれていない。何故なら、パウロ自身が次のように言っているからである。『私は使徒の中では最も小さい者であって、使徒と呼ばれる価値のない者です。なぜなら、私は神の教会を迫害したからです。』(Ⅰコリント15章9節)パウロが12人の誰か一人と入れ替わりにされたということは考えられない。というのは、使徒の中でパウロ以外の12人は教会を攻撃したことがなかったが、パウロは教会を滅亡させようとしていたからである。とはいっても、パウロも他の使徒と同じように、あくまでも使徒であったことには変わりないのではあるが。つまり私が言いたいのは、「12使徒」と言われたならば、その内訳にパウロは含まれていないということである。
【12:2】
『この女は、みごもっていたが、』
教会が『みごもっていた』のは何故か。これは、聖徒の復活のことである。大々的な聖徒の復活は、ネロによる42ヶ月間の迫害が終わった時に(11:7~11)、パウロと共にいた聖徒たちが『生き残っている』(Ⅰテサロニケ4章16~17節)時に、紀元1世紀の時に、つまり紀元68年6月9日に起こった。これが聖書の教えであり、それは私が既に説明した通りである。聖徒の復活が初代教会の時代に起きたことを疑うことはできない。それは聖書が教えていることなのだから。この箇所では、その復活する聖徒たちがこれから教会において多く現われることになるので、『この女は、みごもっていた』と言われている。つまり、黙示録では紀元68年に復活した聖徒たちが大勢教会において現われる現象を、女が多くの子を生むことに例えて言っている。何故なら、教会において多くの復活した聖徒たちが新しい存在として出現するのと、女が多くの子を生むのは、どちらも「新しい存在を生じさせる」という点でまったく一緒のことだからである。この理解は黙示録を解読するためには絶対に持っていなければいけない理解である。それで、ここで『この女は、みごもっていた』と書かれているのは、教会がこれから復活の聖徒たちを多く生み出すことになるからであった。だが、この時点ではまだその聖徒たちは生み出されていない。すなわち、まだ復活の出来事は起きていない。だから、『この女は、みごもっていた』などと言って、まだ復活は起きていないことがここで教えられているわけである。もし復活がもう起きた時のことを言っていたのであれば、ここでは『みごもっていた』とは書かれていなかったはずである。というのも、復活した聖徒たちが既に多く現われたのであれば、その時の教会はもはや妊娠している状態にあるとは言えないからである。この教会の妊娠期間は、ネロによる42ヶ月間の攻撃があった時期である。すなわち、それは紀元64年12月~68年6月である。何故なら、教会が復活した聖徒たちを生じさせる前における42ヶ月の期間には、ネロによる甚大な苦しみが教会にもたらされるからである。これは女が子を生む前においては、いくらかの期間、大いに苦しまねばならないのと同じことである。つまり、復活した多くの聖徒たちが現われる復活の日が人間の女で言えば出産日であり、教会において復活する聖徒たちが多く出る前の42ヶ月の期間が人間の女では10ヶ月ほどの妊娠期間に該当している。この箇所で教会が妊娠していたと言われているのは、復活の前に訪れるネロによる苦しみの期間以外のことではない。また例のごとく、黙示録で示されている出来事は『すぐに起こるはずの事』(1:1)なのだから、この妊娠期間における出来事は既に過ぎ去っている。聖徒たちは、このことをよく心に留め、決して忘れないようにしてほしい。ちなみに、この女をマリヤと捉えると、ここではとんでもなく無益なことが言われていることになるということも付け加えて言っておきたい。一体、マリヤが身ごもって苦しんでいたことをここで書き記して何の意味があるのか。それは聖徒たちにとって何の益にもならないことである。そもそもマリヤの妊娠は昔の出来事であって、未来の出来事について預言するという黙示録の目的に合致していないのだから、12章で出てくる女をマリヤだと捉えるのがどれだけ異常であるかということがよく分かる。この章に出てくる女をマリヤだとす解する者は、この章では意味も益もない無駄なことが書かれていると考えていることになるのだ。
『産みの苦しみと痛みのために、叫び声をあげた。』
これは、教会に対して遂にネロが攻撃を仕掛けて苦しめたということを言っている。その時の教会は、歴史家たちが伝え、神学者たちも語ってきたように、誠に大きな苦しみを受けた。それは、あたかも女が子を生む前に耐え難いほどの苦しみ、すなわち陣痛を味わうようなものであった。教会も女も、新しい存在を生じさせるためには、その前に大きな苦しみを受けなければいけないのである。だから、ここで復活者たちを生じさせる前の教会における苦しみが、新しい人間を生じさせる前の女における陣痛になぞらえられているのは、実に適切なことであった。
【12:3】
『また、別のしるしが天に現われた。』
この『別のしるし』は、12:1の『巨大なしるし』とはまた違った幻であるが、しかし12:1とセットにして捉えるべき幻である。これは、地球とセットとして捉えるべき地球の衛星―月―のようなものだと考えればよい。月も地球とは違うが、しかし地球とセットで捉えられるべきものである。この『別のしるし』と12:1の『巨大なしるし』をセットとして捉えるべき理由は、この二つの幻が互いに密接な関わり合いを持っているからである。それは、この『別のしるし』について書かれていることを読めば誰でも分かることである。
『見よ。大きな赤い竜である。』
『竜』とは、12:9でも言われているように『サタン』である。人それぞれ竜については自分なりのイメージを持っていると思うが、聖書が示しているサタンの像は、バジリスクやカメレオンやトカゲに翼の生えた生物ではないことに注意せよ。聖書におけるサタンの像は、長い身体を持った蛇に翼と手足が生えている生物である。世界中で人気のある「ドラゴンボール」という漫画に出てるシェンロン(神龍)が、聖書におけるサタンのイメージに近い。つまり、サタンは長いとぐろを巻くような身体を持っているということである。それというのも、聖書はサタンのことを『蛇』とも言っているからである。それでは、どうして聖書ではサタンが竜として描かれているのか。それはサタンが獰猛で、強大で、邪悪で、異常な存在だからである。そのような存在は、竜として描かれるのが相応しいのである。事実、霊的に言えば、確かにサタンは竜の形をしている。とはいっても、サタンは霊的な実体であるから、物質的な実体を実際に持っているというのではないのではあるが。ただ、物質的な視覚としては、竜として認識されるべきであるということである。世界中で竜の伝説や神話が多く見られるのは、元はと言えば、神の啓示に端を発している。すなわち、それらの伝説や神話は、聖書が書かれる前まではアダムとエバから伝えられた伝承から、聖書が書かれてからはその伝承および聖書の記述から取られている、もしくは影響を受けている。あのプラトンでさえユダヤ思想から貰い物をしていたのだから(これは『ティマイオス』を見れば明らかであろう)、世界中に見られる竜の概念が神の啓示を源流としていることを疑ってはならない。そうでなければ、どうしてこれだけ多くの竜に関する話が、世界各地に見られるのか説明できないと私には思われる。これは、世界各地で洪水伝説・神話が無数に見られるのと同じことである。こちらのほうも、元を辿ればノアの大洪水という一つの実話に源流を持っている。だから我々は、聖書に竜が書かれているのは、聖書が外部から竜の概念を吸収したからだなどと考えてはならない。世の中には、このように考える気の狂った馬鹿者が多くいる。しかし実際には話が逆である。すなわち、聖書が外部から取り入れたので聖書に竜が記されているのではなく、聖書以外の話や作品が聖書から取り入れたか関節的に影響を受けたからこそ、そこには竜が出てくるのである。もしアダムとエバが自分たちの前に現われた竜なるサタンのことを子孫たちに伝えず、聖書にも竜のことが記されず、神も預言者や聖徒たちに竜の幻を啓示されなかったとすれば、世界にはまったく竜の話や概念が存在していなかったはずである。また、我々は竜の絵やタトゥーなどを見て、それを格好良いなどとは思わないようにせねばならない。何故なら、竜とはサタンだからである。もし聖徒であるにもかかわらず竜を格好良いなどと思うのであれば、それは聖徒であるにもかかわらず敵であるサタンを格好良いなどと思っていることになる。こんな馬鹿なことがあっていいものであろうか…。サタンを神とするノンクリスチャンであればともかく、サタンを敵とする神の子らがサタンを良く思うのはいけない。ノンクリスチャンで竜を愛好する者は少なからず見られるが、彼らにはサタンが格好良いなどと思わせておけばよい。彼らは自分たちの支配者を良く思っているに過ぎないのだから。しかしサタンを敵とする我々は、竜の絵やタトゥーなどを見て、それを憎悪して厭うべきである。聖徒たちが良く思うべきなのは神に他ならない。
サタンが『赤い』外観だったのは、サタンがネロを通して聖徒たちを殺戮するからであった。実際、ネロはサタンに動かされて聖徒たちを大いに殺害した。またサタンが『赤』かったのは、血が流されることも意味している。確かに、サタンに動かされていたネロは42ヶ月の間に聖徒たちの血を多く流した。黙示録において『赤』が殺戮や血を示すというのは、『赤い馬』が呼び出された第二の封印の箇所(6:3~4)で既に説明された通りである。聖徒たちは、サタンが殺戮をする場合、サタンは『赤』の外観として認識されるべきだということを覚えてほしい。何故なら、サタンがそのような出来事を起こす場合、サタンは『赤』として肉的には認識されるのが相応しいからである。もちろん、サタンは霊的な存在だから、物質的には何の色も持っていないのではあるが。聖徒たちは、このような『赤い』という極めて短い語句でさえ、黙示録においては重視されるべきだということを知るべきである。というのも、黙示録においては、短い語句であっても、そこには多かれ少なかれ重要な意味が隠されているからである。この『赤い』という多くの人が無視してしまいそうな短い語句の場合、どうか。今説明されたように、この『赤い』という語句の中には「サタンが殺戮を引き起こして多くの血を流す。」という知っておくべき重要な意味が隠されていた。これは小さいことではない。たとい小さな語句だからといって軽んじたり無視したりするのは間違いである。取るに足りないように思える語句さえも重視するのでなければ、黙示録をマスターすることは決して出来ないであろう。「小を無視する者は小に泣く」と私は言いたい。
サタンが『大きな』身体であったのは、サタンが強く、激しく、抵抗し難かったということを示す。実際、ネロを通してサタンが聖徒たちを攻撃した際、聖徒たちはサタンに抵抗することができなかった。つまり、これはサタンが獰猛であったという意味を含んでいる。サタンが獰猛であるというのは、ペテロも次のように言っている通りである。『あなたがたの敵である悪魔が、ほえたけるししのように、食い尽くすべきものを捜し求めながら、歩き回っています。』(Ⅰペテロ5章8節)もしこの時に聖徒たちが抵抗できたとすれば、恐らく「小さな」と言われていたかもしれない。何故なら、抵抗できるということは、「小さな」と言い表わすに相応しいことだからである。つまり、抵抗できないから「大きい」のであり、抵抗できれば「小さい」というわけである。サタンが巨体だというのは、イザヤも『レビヤタン』(イザヤ27章1節)という巨獣によりサタンを言い表わしている通りである。サタンは大きな身体を持っているというのが聖書の啓示である。これは確実な知識だから、覚えておいて損にはならないであろう。何故なら、サタンが大きいと認識していれば、敵を見くびることがなくなり、それだけ我々の気が引き締まり、力を持って敵に打ち勝つことができるようになるからである。しかしサタンが小さいと誤認していれば、それは敵を見誤っているのだから、正しい戦いができなくなり、負けたり、本来であれば勝てるのに勝てなくなったり、悲惨なことになったりしかねない。敵を正しく認識していないのに、どうしてまともな戦いができるというのか。
『7つの頭と10本の角とを持ち、その頭には7つの冠をかぶっていた。』
サタンが『7つの頭と10本の角とを持』っていたのは、サタンがネロにおいて働いていたことを意味している。というのは、13:1の箇所で言われているように、ネロもこのサタンと同数の頭および角とを持っていたからである。この『7つの頭と10本の角』の詳細については、後ほど説明されることになる。ここでは、サタンがネロにおいて活動するがゆえに、サタンとネロが同数の頭および角とを持っていたのだと理解していればそれでよい。確かに、サタンはネロにおいて聖徒たちを攻撃し殺戮した。パウロがⅡテサロニケ2:9の箇所で『不法の人の到来は、サタンの働きによる』と言った通り、サタンが働きかけたからこそ、聖徒に暴虐を加えるネロが現われることになった。また黙示録13:2で『竜はこの獣に、自分の力と位と大きな権威とを与えた』と書かれている通り、ネロとその悪しき活動の背景にはサタンが存在していた。確かなところ、ネロはサタンに憑りつかれていた。だからこそ、あのような暴虐を聖徒たちになしたわけである。ネロに見られた邪悪な言葉、心の思い、振る舞い、その雰囲気、行ないはサタン抜きには考えられない。要するにサタンはネロにおいて自分の業をなしていたということである。だからこそ、ここではサタンの業とネロの業が結局は同一であることを示そうとして、サタンとネロにおける頭および角が同数として描かれているわけだ。ここで注意しなければいけないことが二つある。一つ目は、サタンは実際には、物資的な複数の頭や角は持っていなかったということである。というのも、サタンは物質存在ではないからである。二つ目は、サタンは常に『7つの頭と10本の角』とを持っているのではないということである。ここではサタンをネロにおいて示す目的があったので、ネロの持っていた頭と角に応じて、サタンもそれらのものを持っていたと書かれているに過ぎない。つまり、ネロにおいてサタンが示されるという目的がなければ、ここではサタンが『7つの頭と10本の角』を持っていたとは書かれていなかったということである。その場合は、サタンがそれにおいて示される存在に合わせた書き方がされていたことであろう。例えば、サタンがニムロデにおいて描かれていたとすれば、「竜は力ある猟師のようであり云々…」(参照―創世記10:9)などと書かれていたはずである。ユダの場合であれば、「竜は盗人のような姿をしており、その手には金入れを持っており云々…」(参照―ヨハネ12:6)などと書かれていたはずである。
サタンが『その頭には7つの冠をかぶっていた』のは、サタンが完全な権威を持っていたということを示す。キリストが6:2と19:12の箇所でその頭に冠をかぶっておられることから分かるように、黙示録において『冠』とは王権を意味している。その冠が『7つ』あるというのは、完全な王権を意味している。つまり、サタンが『7つの冠をかぶっていた』のは、サタンがその絶対的な権威によってネロを完全にコントロールしていたということを教えている。実際、ネロはサタンに憑依されていたといってよい。ネロの悪事について書かれたことを読むと、確かにネロは人間とは思えないようなことばかりをしていたのが分かる。これはネロがサタンに憑依されていたがゆえだと理解すれば、よく納得できる。ここでも、やはりサタンが実際に物質的な『7つの冠』を持っていたというのではないことに注意する必要がある。また、ここではネロにおいてサタンが示されているからこそ『7つの冠』をかぶっていたと書かれているに過ぎないのであって、サタンが常に『7つの冠』をかぶった存在として描かれるべきではないということも同様に注意する必要がある。ここではサタンの完全な権威を示す目的があるのだから、「7」ではなく「10」の冠でも問題なかったが、神は「7」の冠においてサタンをお示しになられた。それは「7」のほうが神の御心に適っていたからである。しかし、たとえ「10」だったとしても、ここで言われていることの意味は「7」の場合と何も変わらなかった。神が「10」よりも「7」のほうを選ばれたということは、2~3章の箇所で「7つ」の教会を描かれたことにおいても同様である。そこでも「10」が退けられて「7」が採用された。だから、我々も「10」と「7」を二者択一しなければいけない場合があれば、神を見習い、「7」のほうをこそ選択するのがよいかもしれない。もちろん「10」のほうを選択しても何も問題はないのではあるが。
【12:4】
『その尾は、天の星の3分の1を引き寄せると、それらを地上に投げた。』
この箇所では、サタンがネロの42ヶ月の期間の時に、聖徒たちを屈従させて苦しめることについて言われている。この箇所は、明らかにダニエル書の8:10~12の箇所と対応している。そこでは次のように書かれている。『それは大きくなって、天の軍勢に達し、星の軍勢のうちの幾つかを地に落として、これを踏みにじり、軍勢の長にまでのし上がった。それによって、常供のささげ物は取り上げられ、その聖所の基はくつがえされる。軍勢は渡され、常供のささげ物に代えてそむきの罪がささげられた。その角は真理を地に投げ捨て、ほしいままにふるまって、それを成し遂げた。』このダニエル書の聖句を解き明かすことはここではしないが、この聖句では、ネロが聖徒たちを蹂躙してその上に立つことについて書かれている。ネロが聖徒たちを屈従させて神でもあるかのような存在として君臨するというのは、Ⅱテサロニケ2:3の箇所でも言われている通りだ(※)。我々が今見ている箇所はこのダニエル書の聖句と対応しているのだから、この黙示録の箇所ではサタンがネロにおいて聖徒たちを蹂躙させる出来事について言われていることが分かる。聖徒たちが『星』と言われているのは、先に見たように聖書では珍しいことではないから、不思議に思ってはならない。その『星』である聖徒たちが『天』に位置していると言われているのは、聖徒たちは肉的には地上に存在していても、事実上は天にいる者たちだからである。それはパウロが、神は聖徒たちを『天の所にすわらせてくださいました。』(エペソ2章6節)と言った通りである。この天にいた星である聖徒たちをサタンが『地上に投げた』のは、つまり聖徒たちが不幸を味わうことになるという意味である。これは実際に聖徒たちが天から地に引きずり落とされるという意味ではない。確かなところ、天にいる聖徒たちが地に落とされるということ以上の不幸は考えられない。要するに、ここでは「サタンが聖徒たちをあたかも天から地へと落としたかのような不幸で満たすであろう。」ということが言われている。その不幸とは言うまでもなくネロの大迫害の期間についてのことである。もし本当にサタンが聖徒たちを天から地へ落とすことができたとすれば、それは世界がひっくり返ることである。そのようになるよりは全世界が破滅するほうが容易い。何故なら、神が定められたからこそ、聖徒たちは天へ引き上げられたのだから。神が引き上げられた存在を引きずり落とせるような者は一人すらもいないのである。サタンが『その尾』により聖徒たちを『引き寄せ』たのは、つまりサタンが聖徒たちを尾でもあるかのように屈従させるという意味である。『尾』が黙示録では屈従させられることを意味しているというのは、既に説明された通りである。実際、ネロにおいてサタンは42ヶ月の間、聖徒たちをまるで奴隷でもあるかのように苦しめた。聖徒たちが『3分の1』と言われているのは、サタンとネロが苦しめる聖徒の数が、地上にいる全ての聖徒たちの3分の1だったということを示している。つまり、サタンのネロが生じさせた大患難においては、あらゆる聖徒たちが苦難を味わったというのではない。しかし、当時における聖徒の総数およびネロの大患難の時に苦難を味わった聖徒たちの数が不明であるから、この『3分の1』という数字が具体的にどれほどなのかということは分からない。しかし『3分の1』だから、かなり苦しみを味わわされた聖徒たちの数は多かったと推測される。なお、この『3分の1』はユダヤではないことに注意されたい。先に見た第1~第4のラッパの箇所(8:7~12)で書かれていた『3分の1』はユダヤであったが、我々が今見ているこの箇所ではそうではない。何故なら、12章で示されているのは、ユダヤのことではなく、サタンがネロを通して聖徒たちを蹂躙し苦しめることについてだからである。この12:4の箇所は相当難しい箇所である。神の恵みがなければ、このように解き明かすことは決してできなかったであろう。
(※)
『彼は、すべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。』
[本文に戻る]
聖徒たちは、黙示録に出てくる『星』には幾つもの意味があることを覚えよ。この12:4の箇所における『星』は「聖徒」を指している。12:1の『星』は「12使徒」を指している。第4のラッパにおいて打たれた『星』(8:12)は、あくまでも象徴的に語られているのではあるが「実際の星」である。第5のラッパに出てくる天から落ちてきた『星』(9:1)は「御使い」である。この『星』という言葉に一通りの意味しかないと理解すると、黙示録を上手に理解できなくなるから注意せねばならない。その場合、その一通りしかないと思っている意味に適合する箇所であれば正しい理解を得られるが、その意味に適合しない全ての箇所では完全に誤ることになってしまう。
『また、竜は子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだとき、その子を食い尽くすためであった。』
この箇所では、サタンが教会において復活する聖徒たちを復活したらすぐにも殺してしまおうとして、教会に訪れる復活の時が来るのを注意深く監視していたということが言われている。というのも、サタンには、復活する聖徒たちが非常に脅威だと思えたからである。つまり、サタンはこう思っていたのである。「これから教会に復活が起こる。その時に復活した奴らは非常に危険だろうから、何を仕出かすか分かったもんじゃない。これは復活が起きたらすぐにも殺すに限る。その復活の時を見逃さないように教会をよく監視しておかねば。」サタンのことだから、もし神の許可があるのであれば、復活した聖徒たちを全て殺したかったことであろう。キリストを恐れて無数の幼児を殺させたヘロデと同じように(マタイ2:13~18)、サタンは自分にとって脅威に感じられる存在を殺そうとするのである。なお、ここでサタンが『食い尽くす』存在として描かれているのは、ペテロがその第一の手紙の5:8で描いているサタンの像と全く一緒である。また、それはイザヤがサタンを『レビヤタン』(イザヤ27章1節)として描いているのと同一のイメージでもある。何故なら、『レビヤタン』とは食い尽くす巨獣のことだからである。このことから、サタンと『食い尽くす』という要素は切っても切り離せない関係があることが分かる。『食い尽くす』とは、殺すとか滅ぼすとか、そういった類の意味である。ちなみに、この箇所を分かりやすく言い換えると次のようになる。「また、サタンは復活した聖徒たちを生じさせようとしている教会を注意深く監視していた。教会において復活の現象が起きた時、復活した聖徒たちを殺してしまうためであった。」
サタンが教会において起こる復活を待ち受けていたのは、あらかじめ、復活の出来事が起こることを知っていたからである。だからこそ、教会に復活が起こるのは今か今かと注意深く監視していたわけである。もしサタンが復活について何も知らなかったとすれば、このように『女の前に立っていた』ことはしなかったであろう。サタンは自分の知らないことについては、何も知らないからである。だから、サタン自身にとっても『何が起こるかを知っている者はいない。いつ起こるかを誰も告げることはできない。』(伝道者の書8章7節)という御言葉があてはまる。サタンは神のように多くの業を行なえるのではあるが、神に隠されている出来事については何も知らないし、また知っていたとしても、それをいつ神が実現させられるかまでは確言できない。だからこそ、サタンはいつか起こると知っていた復活が、いつ起きてもいいように教会を注視していたのであった。それで、サタンが復活について知っていたのは、キリストと使徒が復活のことについて語ったのを聞いたからである。キリストはやがて起こる復活について、次のように言っておられた。『このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者がみな、子の声を聞い出て来る時が来ます。』(ヨハネ5章28節)パウロも自分たちが生き残っている時に復活が起こることについて、次のように言っていた。『それからキリストにある死者が、まず初めによみがえり、次に、生き残っている私たちが、…』(Ⅰテサロニケ4章16~17節)サタンは、既に第2部で説明されたように世界各地に同時的に働くことができる普遍的な霊的存在であって、ゆえに全ての人間が話している言葉を聞き、知ることができる。サタンはキリストと使徒がこのように言ったのを聞いていたので、あらかじめ復活が起こることについて知っていたわけである。またサタンは、聖徒たちが世界を支配するようになるということも、キリストと使徒の言葉を聞いて、あらかじめ知っていた。キリストは聖徒の支配について、使徒たちにこう言っておられた。『わたしの父がわたしに王権を与えてくださったように、わたしもあなたがたに王権を与えます。それであなたがたは、わたしの国でわたしの食卓に着いて食事をし、王座に着いて、イスラエルの12の部族をさばくのです。』(ルカ22章29~30節)パウロも聖徒の支配について次のように言っていた。『あなたがたは、聖徒が世界をさばくようになることを知らないのですか。…私たちは御使いをもさばくべき者だということを、知らないのですか。』(Ⅰコリント6章2、3節)別にサタンでなくとも、復活が起きた後で聖徒の支配が実現されるだろうということは、少し考えれば誰でも容易に察することができる。だからこそ、サタンはその支配が実現される聖徒の復活を恐れて、教会に復活が起こるのを今か今かと注意深く待ち受けていたわけである。
サタンが色々な情報や推測に基づいて、世界各地を監視しているというのは、この箇所からだけでも十分に理解することができる。ペテロが『悪魔が、ほえたけるししのように、食い尽くすべきものを捜し求めながら、歩き回っています。』(Ⅰペテロ5章8節)と言ったのは、つまりサタンが餌食となるべき存在を見つけるために世界中を見回っているという意味に他ならない。ヨブ記1:7と2:2の箇所で、サタンが神に『地を行き巡り、そこを歩き回って来ました。』と言っているのも同じである。サタンは、監視のために、全世界を常に見回しているのである。サタンが世界を見回しているのは、事前に危険な存在を知り、素早く対処を講じることができるために他ならない。この箇所において教会を監視していたのも、それが理由であった。何故なら、そうしないと、監視不足という怠慢のゆえに大きなダメージを喰らうことになりかねないからである。21世紀の今においてサタンはユダヤ人やその道具としての組織であるイルミナティ、フリーメイソン、スカル・アンド・ボーンズなどを通して、世界中に監視の目を行き届かせている。その監視の事実は、いわゆる「プロビデンスの目」なるアイコンによって誇らしげに示されている。世の中の人々はそれが単にユダヤ人の陰謀に過ぎないと見ているが、それは実はサタンがユダヤ人を利用しているためなのだと理解されねばならないことである。世界に働きかけているユダヤ人とてサタンの道具に過ぎない。単に都合が良いからユダヤ人が用いられているだけだ。他の存在のほうが都合が良ければ、ユダヤ人が使われていることはなかったであろう。確かにサタンは全世界に監視の目を届かせているのだが、だからとって聖徒たちは恐れたり、不安になったりすべきではない。何故なら、聖徒たちとは『王』(Ⅰペテロ2:9)であり、全世界は聖徒のものであり(※)、聖徒はサタンよりも上に位置しているからである。たとえサタンが聖徒たちをも見ているからといって、聖徒たちを支配できているのではなく、支配されているのはサタンのほうなのである。聖徒たちはサタンに対する権力を持っているのだから、聖徒たちが動揺すべき理由は何もない。動揺すべきなのは、むしろサタンのほうであるし、実際、サタンは聖なる勢力に脅威を感じている。何故なら、我々には全世界の王であるイエス・キリストの権威がその背景にあるのだから。
(※)
『パウロであれ、アポロであれ、ケパであれ、また世界であれ、いのちであれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてあなたがたのものです。』(Ⅰコリント3章22節)
[本文に戻る]
【12:5】
『女は男の子を産んだ。』
遂に教会において復活の出来事が起こった。紀元68年6月9日のことである。教会という一人の女が、男の子である復活した聖徒たちをそこにおいて生じさせたのだ。これこそ正に今まで全ての聖徒たちがまだ起きていないと思い違いをしてきた、あの大復活の出来事であった。この出来事が紀元1世紀に起きたというのは、黙示録1:1、22:6およびⅠテサロニケ4:16~17の箇所のゆえに、決して疑えうことができない。もし紀元1世紀に復活が起きたことを否定するならば、御言葉を真っ向から否定することになるからである。この復活が起きてから、すぐにも教会は荒野へ逃げた(12:6)。第一の復活が起きてから荒野に逃げるこの期間が、黙示録20章に書かれた『千年』の期間である。何故なら、20章では復活が起き、千年の期間が終わってから、サタンがローマ軍を招集すると預言されているが、この12章では、復活が起き、教会が荒野に逃げてから、サタンがローマ軍を招集すると預言されているからである。つまり、20章とこの12章は対応しているのであって、荒野の部分はすなわち千年の部分と同一なのである。この荒野に逃げる期間は12:6によれば『1260日』である。よって、千年の期間は3年6ヶ月だったということになる。この期間については、後ほどまた詳しく説明されていくことであろう。また、この第一の復活の時に復活したのは『幸いな者、聖なる』(20:6)だけであった。すなわち、教会がこの時に産んだ男の子とは、本当に選ばれていた者たちだけであった。悪い者たちの復活のほうは、千年、すなわち3年6ヶ月の期間が終わってから起きた。それは20:5の箇所でこう言われている通りである。『そのほかの死者は、千年の終わるまでは、生き返らなかった。』ところで、この女がマリヤだとすると、ここではマリヤがキリストを産んだことについて書かれていることになるが、我々はそのように理解してはならない。一体、ここでキリストが産まれたことについて記して何になるのか。もしこれがキリストの生誕のことだとすれば、ここでは読者にとってあまり意義のないことが書かれていることになる。何故なら、キリストの生誕はもう周知の事実であり、何度も語られていることだったからである。
ここで言われていることは、間違いなくイザヤ書と対応している。そこでは次のように書かれている。『聞け。町からの騒ぎ、宮からの声、敵に報復しておられる主の御声を。彼女は産みの苦しみをする前に産み、陣痛の起こる前に男の子を産み落とした。だれが、このような事を聞き、だれが、これらの事を見たか。地は1日の陣痛で生み出されようか。国は一瞬にして生まれようか。ところがシオンは、陣痛を起こすと同時に子らを産んだのだ。「わたしが産み出させるようにしながら、産ませないだろうか。」と主は仰せられる。「わたしは産ませる者なのに、胎を閉ざすだろうか。」とあなたの神は仰せられる。」』(66章6~9節)イザヤ書で『シオン』と言われているのは、黙示録12章で出てくる『女』、つまり教会のことである。何故なら、『シオン』とは神の妻・花嫁のことを指すからである。イザヤ書のほうでは、妊娠期間であるネロの42ヶ月間、すなわち苦難が始まってから復活が起きるまでの期間が、非常に短いものとして書かれている。イザヤは、まるで一瞬にしてこの期間が過ぎ去るかのように言っている。これは、つまりネロが攻撃を始めてから復活が起こるまでの42ヶ月間は、あまりにも短いものなのだということを教えている。実際、この42ヶ月間は、あっという間に過ぎてしまった。70年ぐらいの人間の人生でさえ『しばらくの間現われて、それから消えてしまう霧』(ヤコブ4章14節)に過ぎないとすれば、確かに42ヶ月間は一瞬であると言っても誤ってはいない。事実、多くの人が数年間の期間を振り返って「あっという間であった。」などと溜め息をついているものである。ヨハネが小さな巻き物の箇所で、ネロの迫害期間を「3年6ヶ月」ではなく『三日半』(11:9、11)として言い表わしたのは、この期間を一瞬として描いている今見たイザヤ書の記述に触発されたからであろう。つまり、イザヤがネロの期間を一瞬も同然として描いているのに習って、ヨハネもその期間を大いに短く表現したということである。しかし、ヨハネはイザヤ書の記述をそのまま踏襲しなかった。ヨハネはイザヤ書の中で語られているように3年6ヶ月を「一瞬」として書くこともできたが、『三日半』と書いている。これは、この箇所と対応しているイザヤ書の部分を察知されにくいようにするためであり、またより黙示録を謎で包む目的があったと思われる。言うまでもなく「一瞬」と書いていればそれだけ対応しているイザヤ書66章の箇所を察知しやすくなるし、また『三日半』と書くよりも秘密らしさが薄くなってしまう。黙示録は秘密の書であるから、より秘密を込められるようにとイザヤ書の言い方をそのまま踏襲しなかったのであろう。このようにすることで、ますます黙示録は難解で不思議な文書とされたのである。またイザヤ書のほうでは、教会の産んだ男の子が複数であったと言われている。黙示録では『男の子』と単数形で言われているのに、イザヤ書のほうでは『子ら』と複数形で言われている。これは、つまり黙示録のほうでは、実際には無数にいた復活の聖徒たちを有機的統合体として単一的に描いたということである。それは無数にある砂粒を語る際に「砂々」などと複数形で言わないで、「砂」とあたかも一つの存在であるかのように言うのと同じことである。そのように「砂」と言っても、実際には1粒しか砂がないというのではなく、砂はこれでもかと言わんばかりにある。ここで「男の子たち」が『男の子』と言われているのも、それと同じである。このように復活した聖徒が今見ている黙示録の箇所と対応しているイザヤ書の箇所では複数形で語られているのだから、黙示録12章の女がマリヤだという見解は完全に否定されねばならない。何故なら、マリヤが産んだキリストは「一人」であって複数、すなわち『子ら』ではないからである。もしこの女がマリヤだとすれば、マリヤが産んだ子は複数だったということになるが、聖書の中で明確に啓示として語られているのはマリヤがキリストお一人を産んだということだけである。マリヤは啓示上においては複数の『子ら』を産んだのではないから、イザヤ書で女が『子ら』を産んだと言われていることにより、黙示録12章で出てくる女はマリヤではなかったということになる。
『この子は、鉄の杖をもって、すべての国々の民を牧するはずである。』
復活した聖徒たちは、復活してから携挙されて、『すべての国々の民を牧する』ことになった。これは20:4~6で言われている内容と同一である。そこでも、第一の復活にあずかった聖徒たちが、支配の業をなすことについて書かれている。サタンが恐れたのは、実にこの支配の業であった。この箇所は明らかに20:4~7の箇所と対応している。12章のほうでは、聖徒たちが復活して教会が荒野に逃げてから(12:6)、大いなる支配が起こると教えられている。教会が荒野に逃げる期間は、聖徒たちが支配する期間と同じであった。何故なら、復活した聖徒たちを生じさせた女なる教会が『1260日の間』荒野に逃げてから、サタンが聖徒たちの陣営に戦いを仕掛けるようになるからである。これは20章の箇所で、聖徒たちが復活して幾らかの期間―『千年』―が経過してから、サタンが『聖徒たちの陣営』(20:9)をローマ軍に取り囲ませたと言われているのと完全に対応している。よって、20章に書かれている『千年』とは、12章における『1260日』を言い換えたに過ぎない数字であることが分かる。何故なら、どちらのほうでも言われていることが一緒であり、それは①復活の実現およびサタンの無力化⇒②一定の期間の支配⇒③ローマ軍による包囲、という順序だからである。つまり、この②の部分を12章のほうでは『1260日』と言い、20章のほうでは『千年』と言っているわけである。このことがよく分からない人は、実際に12章と20章をそれぞれ読み比べ、よく考察するといい。そうすれば、この2つの章ではどちらも同一のことが語られているのが分かるはずだ。その読み比べをする際には、私が今書いた①~③の順序をよく頭の中に叩き込んでからするように。この②の期間について言えば、12章のほうが実際的な数字であり、20章のほうが象徴的な数字であることは疑えない。それゆえ、今まで全ての聖徒たちが『千年』という期間が非常に長大であると考えてきたのは、完全な誤りであった。彼らが黙示録をほとんど理解できていないにもかかわらず、『千年』の期間をさも理解しているかのように堂々と論じたのは、誠に異常なことであった!どうして何にも理解できていないにもかかわらず、『千年』という期間だけは確実に分かっているかのように今まで語られてきたのか、私は理解に苦しむ。もし聖徒たちに思慮があったとすれば、そのような愚を犯すことはなかったであろう。思慮とは、分からないことについては沈黙するか、たとえ語ったとしても推測に過ぎないことを伝えつつ語ることでなくて何であろうか。今までに聖徒たちがこの期間について堂々と論じてきたのは、例えて言えば野球について何にも知らないのに「ヤンキースは最高のチームだね。」などと、さも理解があるかのように言うようなものである。このように言う者は、「ところでお前は野球についてどれだけ知っているのか?」などと言われることで、その無知が暴かれてしまい撃沈させられるのである。そうして後、「お前は何にも知らないのによくも分かったかのように言えるな。」などと愚か者扱いされてしまうのである。さて、ここで復活した聖徒たちが『鉄の杖をもって』『牧する』と言われているのは、つまり聖徒たちが御言葉の杖をもって、土の器を打ち砕くかのようにして諸国民に裁きを下すという意味である。この千年で表示される42ヶ月の支配については、20章に達した時にまた詳しく述べられるであろう。というのも、これは20章で論じたほうが適切な事柄だからである。ソロモンも伝道者の書3:1で言っているように、『何事にも定まった時期が』あるものである。今の時点においては、取りあえず復活した聖徒たちが支配の業を行なう実際的な期間が42ヶ月であって、それは20章では『千年』として象徴されているということだけを理解していれば、それで十分である。
この箇所は、黙示録では20:4~6の他には、2:26~27、3:21、5:9~10と対応している。これらの箇所でも、やはり復活した聖徒たちによる42ヶ月間の支配のことが語られている。黙示録以外では、マタイ19:28、ルカ22:29~30、Ⅰコリント6:2~3と対応している。そこでも、復活の聖徒による支配について語られている。黙示録では、このように対応している他の箇所を見出すことが大切である。何故なら、対応している他の箇所と読み比べることで、より良い理解がもたらされるからである。黙示録には、聖書の他の箇所と対応している箇所が無数に存在している。だから黙示録を正しく理解したいと願う聖徒は、その対応している箇所を豊かに見出せるようにせねばならない。そうしなければ、黙示録を十全に理解することはできないであろうから。そのためにも、我々は聖書をよく読み、聖句を暗記し、聖書全体を手に取るかのように把握できるようにする必要がある。キケロも『弁論家について』という書物の中で言うように雄弁家には総合的な知識が必要不可欠だが、黙示録の理解にも聖書の総合的な理解が必要不可欠である。これほど聖書の全体的な理解が必要となる巻は他にないのではないかと私は思う。
この預言では『…はずである。』と書かれているが、「はず」と書かれているからといって、もしかしたらその預言が実現しない可能性も少しはあったということではない。何故なら神の預言は、絶対に実現させられなければいけないものだからだ。実際、ここで語られている預言は、紀元68年において成就されている。また、ここでは「未来形」の言い方で預言がなされている。どうしてこんな誰でも分かるようなことを書くかといえば、すぐ次の部分においては、いくらか違う言い方により預言がなされているからである。次の部分における註解を読めば、そのことがよく分かるはずである。
『その子は神のみもと、その御座に引き上げられた。』
ここでは「過去形」の言い方により預言がなされている。既に起きたかのように言われていても、これは過去についてのことではない。ヨハネがこの文章を書いている時には、まだここで言われている出来事は起きていなかった。黙示録ではこれからも過去形による預言が出てくるので、読者はこのような言い方の預言に慣れ、それを何か不思議な言い方でもあるかのように思うべきではない。
この部分では、復活した聖徒たちが携挙されることについて預言されている。聖徒たちが復活すると携挙されることになるというのは、パウロもⅠテサロニケ4:16~17の箇所で言っている通りである。この携挙が起きたのは紀元68年6月9日であった。聖徒たちは携挙されて後、天の『御座』へと引き上げられた。これは20:4で次のように言われているのと対応している。『また私は、多くの座を見た。彼らはその上にすわった。そしてさばきを行なう権威が彼らに与えられた。』すなわち、復活した聖徒たちは携挙されて天の座に着き、キリストと共に『千年の間』つまり42ヶ月の間、支配と裁きの業を執行した。このことは20:4~6の箇所で詳しく書かれている。このように考えると、ますますこの12章と20章とは対応しているということが、よく分かるはずである。つまり、どちらも同じことが言われているからこそ、同一の事柄が同一の順序で書き記されているわけである。
サタンは復活が起きたら復活した聖徒たちを食い尽くそうと待ち受けていたのであったが(12:4)、その願いは遂げられなかった。それは神が、この箇所で言われているように、復活した聖徒たちをサタンに襲わせることもなく上に引き上げられたからである。神が上に聖徒たちを上げられたのだから、サタンはどうすることもできなかった。この時におけるサタンの怒りと失望はどれほどだったであろうか。せっかく待ち受けていたのに、時が来たら、自分の思うように行かなくなってしまった。これは超人気アーティストのコンサートを楽しみに待っていたのに、公演当日になって急にコンサートが中止になってしまったようなものである。サタンはこの時、大いに歯ぎしりしたに違いないと私は思う。我々は、このことから、神が常にサタンの上を行かれるということを知るべきである。神は、一定の時期においては、サタンが悪事を行なうのをお許しになられる。サタンは悪事を行なっても平気でいられるので、調子に乗って悪事に突き進むことを止めようとはしない。しかし、最後になると神がサタンに裁きを与えられるので、今までに積み重ねてきたサタンの悪事は全て台無しにされてしまう。このようにして実は神のほうがサタンよりも大きくて強く、サタンはただ神の手の中で一定の期間、踊らせ続けられていたに過ぎないことが明らかにされる。ここにおいて神はサタンを通してご自身の栄光を現わされるのである。人々はこの大逆転の出来事を見て、神の御名とその御力とを褒め称えるのである。バベルにおいて計画が挫折させられたのも、このようにしてであった(創世記11章)。第2部でも説明されたように、神はこの地上において、このようにサタンを通していついつまでもご自身の栄光を現わされる。すなわち、サタンが悪事を行なったらそれを裁かれ、またサタンが悪事を行なったらそれを裁かれ、次にサタンが悪事を行なったらそれを裁かれ、…というサイクルを永遠に実現され続けられる。実にソロモンも言うように『神のなさることはみな永遠に変わらない』(伝道者の書3章14節)のであり、『神は、すでに追い求められたことをこれからも捜し求められる』(同)のである。だから、聖徒たちはサタンが暴れ回っていたとしても心配するべきではない。サタンが暴れているのは、やがて裁かれるためだからである。もしサタンが永遠に裁かれることもなく暴れ回るというのであれば心配すべきだったかもしれない。しかし実際はそうではない。よって我々はむしろ神に拠り頼み、恵みの力を受けられるように願い求めるべきである。そうすれば、ダビデがゴリアテを撃破したようなことが、またヨナタンと道具持ちが大勢の敵を撃滅したようなことが、きっと起こることであろう。それゆえサタンに対して恐れ戦いている聖徒たちは、今すぐ悔い改めなければいけない。そうしなければ敗北あるのみである。敗北を信仰している聖徒たちは、その信仰の通り、必ず敗北するであろう。
【12:6】
『女は荒野に逃げた。そこには、1260日の間彼女を養うために、神によって備えられた場所があった。』
『女は荒野に逃げた。』とは何か。これは、つまり女である教会が『荒野』同然の状態になってしまったということを言っている。何故なら、聖書において『荒野』とは<滅び>を意味しているからである。旧約聖書の中では、異邦人が『荒野』として象徴されている。例えばイザヤ43:19~21の箇所がそうである(※)。そこでは、やがて異邦人も聖霊を受けて神の民となる時代が到来するということについて預言されている。この『荒野』である異邦人は、そのような地に相応しく滅びる運命にあった。だから、異邦人とは、少なくとも旧約時代にあっては「滅びの子ら」であった。もうこれで賢明な読者は、この箇所で何が言われているか気付かれたかもしれない。つまり、ここでは復活した聖徒たちが全て携挙されて教会から消え去ってしまったので、教会が荒野として象徴される毒麦という滅びの子らしかいない場所になってしまったということが言われているのである。教会に荒野の子しかいなくなったのであれば、そこは荒野でなくて何であろうか。つまり、ここでは場所の移動ではなく、状態の移行が語られている。すなわち、ここでは教会が実際に荒野に行ったということではなく、荒野の状態のように変化した、ということが語られている。要するにヨハネは、ここで次のように言っているわけである。「教会から聖徒たちが携挙されて消えてしまったがゆえに、もうそこには荒野である滅びの子以外には見られなくなってしまった。これは教会が滅びの子らの場所である荒野に逃げたのも同然である。」もしこれを肉的に理解すると訳が分からなくなる。教会が本当に実際的にどこかの荒野に逃げたとでもいうのか。世界各地にある全ての教会が荒野に活動の場を移し、そこで礼拝や聖餐式を行なうことになったとでもいうのか。このように考えるのは愚かである。聖徒たちは、私が今述べたように考えるべきである。そうすれば何の問題もなく、ここで言われていることが理解できるのだから。また、ここで『逃げた』と言われているからといって、教会が敗北したとか臆病になったなどと考えるべきではない。この言葉は単に教会に変化がもたらされたことを意味しているに過ぎないからである。また、ここで教会が42ヶ月の間神により養われると言われているのは、教会がこの期間、あくまでも教会として保たれるという意味である。確かにこの時、教会は携挙された聖徒たちを失ったために毒麦しか見られなくなったのだが、それでも神はそこを教会として存続させておられた。このことから、たとい教会が毒麦だけになったにもかかわらず、世界から教会が失われることはなかったということが理解される。「毒麦だけになったのだから、そこは教会ではないだろう。」という指摘は容易に退けられる。何故なら、ここでは神が毒麦だけになった教会を養われたと教えられているからである。神が養われたのであれば、どのような状況になっていようとも、確かにそこには教会が教会としてあったのである。
(※)
『見よ。わたしは新しい事をする。今、もうそれが起ころうとしている。あなたがたは、それを知らないのか。確かに、わたしは荒野に道を、荒地に川を設ける。野の獣、ジャッカルや、だちょうも、わたしをあがめる。わたしが荒野に水をわき出させ、荒地に川を流し、わたしの民、わたしの選んだ者に飲ませるからだ。わたしのために造ったこの民は、わたしの栄誉を宣べ伝えよう。』
[本文に戻る]
たった今述べた『養う』ということについて、更に詳しく説明したい。先に述べたように、神により教会が養われるとは、教会があくまでも教会として保たれ続けるということである。それは、つまり聖徒たちが携挙されて荒野と化した教会に、神が新しい信者を言わば補給して下さったということである。何故なら、そのようにして荒野の子しかいなくなった教会に新しい潤いが注がれることこそ、養われていると言えるからである。もしそのようにして真の信者が新しく毒麦の中に加えられなかったとすれば、教会は荒野になった後、『1260日の間』ずっと荒野の状態だったことになる。もしその期間に教会が毒麦しかいない状態であれば、そこが教会であるとはもはや言えなくなる。というのも、教会とは麦たちの集合体だからである。だから、もし神が42ヶ月の間、教会を荒野の子、毒麦しかいないようにしておられたとすれば、そこはもはや教会であるとは言えず、神が養っておられたとも言えなかったことになる。毒麦だけしかいないのに、どうして神が教会を養われたと言えるのか?意味不明である。それは、むしろ教会を失わせておられたとか、飢え死にさせられた、などと言うべきことである。それで、神が教会を養って荒野に新しい信者を加えて下さったのは、教会が荒野と化してから即座にであった。私が「即座に」と言うのは、1分とか10分とか1時間とか、長くても10時間ほどである。10日間も信者が加えられないままだったということは考えられない。何故なら、この『1260日の間』とは神が教会を養われる期間だからである。自分の子を10日間も飢えたままにさせておく親がどこにいるであろうか。携挙の出来事により教会から聖徒たちが誰もいなくなって後、すぐにも新しい信者が加えられたという私の今論じたことは、確実なことだとすべきである。何故なら、この携挙とその前に起きた復活の出来事の際、それを見ていた信仰無き人々は『非常な恐怖に襲われ』(11:11)、『天の神をあがめた』(11:13)からである。11:12でも言われているように、確かに『敵はそれを見た。』のである。であれば、その恐怖と崇敬の念に基づき、携挙および復活を見ていた多くの人々が、ユダヤ教の分派としか思われていなかったクリストゥス派(当時のキリスト教はこう呼ばれた)にこそ真の宗教また真理があると悟ったとしても、何も驚くべきことはない。何故なら、異常としか思えない出来事が目の前で起こったのだから。とすれば、そのような悟りを持った人々が、すぐにも荒野となった空白状態の教会に来て、そこにあった聖書を読んだり、そこにいた毒麦やキリストについて知っている仲間から話を聞いたり、自分の脳に記憶されていたキリスト教の話を意識のうちに引き上げたりするなどして、信仰に入ったはずである。ちょうどエリヤの戦いの時に神の驚くべき働きかけを見たイスラエル人が、神への恐れと崇敬の念を持ちつつ、ひれ伏して『主こそ神です。主こそ神です。』(Ⅰ列王記18章39節)と言ったように。この時のように、多くの信仰無き人々が携挙と復活の出来事により「キリストこそ救い主です。キリストこそ救い主です。」などと思ったり言ったりして信仰に入ったと考えるのは、消して荒唐無稽ではない。というのも、神が教会を養われたと書かれているのだから、そのようなことが必ず起こったはずだからである。しかしながら、この時に教会に新しく加えられた人たちがどれぐらいだったかということについては、まったく不明である。私としては多くの人が信仰に入ったのではないかと思う。何故なら、この時に起きた復活や携挙は、あまりにも驚くべき出来事だったからだ。携挙の後に教会の中に加えられた新しい人たちは、既に携挙された人たちのように携挙されることがなく、『1260日の間』ずっと地上の教会に留まり続けた。彼らは『千年』の期間が終わるまでは地上に居続けたのであって、その期間が終わると第二の復活(※参照ー20:5)により生きたままの状態で復活に与かり、この時に同時に生き返った毒麦どもと共に携挙されて空中の大審判を受けることになった。この第二の復活については、20章の箇所が来たら詳しく論じられることになる。確かに12:17と20:9の箇所を見ると、『千年』である『1260日』の期間が終わってからも、地上に聖徒たちが残されていたことが分かる。これは、つまり神が教会を養われる間に信者となった者たちが、携挙されることなくずっと地上に居続けたことを意味している。もしそうでなければ、新しく信者となった者たちは携挙されて地上にはいなくなっていただろうから、サタンがローマ軍により地上の聖徒たちを取り囲ませることはできなかったであろう。地上にいない者を取り囲むことは原理的に不可能だからである。荒野の時期に加えられた新しい聖徒たちは、神の予定により、42ヶ月の間地上に居続けなければいけないことになっていた。だからこそ、この時に信者となった者たちは、42ヶ月間地上に居続けなければならず、救われてから即座に携挙されることがなかったわけである。以上、神が教会を『養う』ことについて必要十分なだけ説明されたことにしたい。
この教会における荒野の42ヶ月間は、20:1~6に書かれている『千年』の期間と同一である。この千年すなわち3年6ヶ月の時、携挙された聖徒たちは上からキリストと共に地を支配したのだが(20:4~6)、地上における教会は神から養われ、その守りを受けて保たれていた。その神の守りについては12:13~16の箇所で詳しく語られている。それだから、千年の期間は地上の教会が完全な支配を地上において遂行すると考えている夢想家たちの妄想は、容易に粉砕されることになる。何故なら、その期間に支配するのは上のほうに携挙された聖徒たちであって、地上における教会はただ神の守りを受けて滅ぼされないように保たれているに過ぎなかったからである。我々は、この千年で表示される42ヶ月の期間において、天上の教会と地上の教会における様子はかなり異なっていたということを知らなければならない。すなわち、天では支配し、地では守りを受ける。この区別がないと、千年の期間に地上の教会が地上においては支配しないと聞かされて、大いに戸惑うことになってしまう。しかし、この区別を弁えていれば、地上の教会においては支配を遂行しなかったと聞いても、それほど驚かなくて済むようになる。一体、聖徒たちの携挙により荒野の人たちしかいなくなった教会が、どうして地を支配できるというのか。荒野である毒麦たちが地をキリストと共に支配するとでもいうのか。馬鹿らしい。これは、とんでもない話である。だから、我々は千年の間支配したのが、天上の聖徒たちによったということをしっかりと覚える必要がある。理解不足の聖徒たちは、神から恵みを受けた私からしっかりと学べ。
『女は荒野に逃げた』42ヶ月の期間は、紀元68年6月9日~70年9月である。この42ヶ月間は、恣意的に捉えられなければいけない。期間を恣意的に捉えることについては、既に語られた通りである。たとい42ヶ月すなわち3年6ヶ月を2年と3ヶ月として捉えても、霊的に言えば、何も問題とはならない。何故なら、パウロがサウルの統治期間の『12年間』(Ⅰサムエル13:1)を『40年間』(使徒行伝13章21節)として恣意的に捉えているという聖書の例があるからである。この荒野の42ヶ月が過ぎると、すなわち紀元70年9月になると、あの第二の復活が起こり、悪者どもが復活することになった。何故なら、第二の復活は『千年』である荒野の42ヶ月が過ぎると起こるからである。このことについては20:5を参照せよ。その第二の復活により復活した悪者どもは、復活した後に携挙され、あの大審判を受けることになった。この出来事については20:11~15およびマタイ25:31~46を参照せよ。その審判が起こると、遂に天上において至福の天国が正式に開始されることになる。この天国の詳細については21:1~22:5を参照せよ。この時に天国が開始されて以降、地上にいる聖徒たちは、この世を去って後、正式に開始されたこの天国へと導き入れられることとなったのである。今や、もうそのような時代が到来しているのだ。
【12:7】
『さて、天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは、竜と戦った。』
ここからは、いくらか流れが変わる。7節目からは、サタンが天から追放された出来事を基点にして、話が書き記されている。1~6節目を「1話目」だとすれば、7節目以降は「2話目」だということになると考えればよい。この箇所の冒頭部分では『さて、』と書かれているから、確かに、7節目からは新しい流れが始まったことが分かる。この「1話目」と「2話目」は内容的には何も乖離していないが、流れの構成としては、しっかりと区別して把握すべきである。黙示録には、このように区別を把握することが、よき理解に繋がる部分が少なくないから心に留めておいてほしい。
『ミカエル』とは実際の御使いである。これは御使いではない別の存在を象徴させたものではない。先に見た5:2の箇所では『強い御使い』としか言われていなかったので、どの御使いであるのか断言できなかったが、この12:7の箇所ではしっかりと名前が書かれているので、どの御使いなのか断言することができる。我々は、断言すべきことを断言し、断言できないことについては沈黙するか話しても推測に過ぎないことを知らせるべきである。それが賢慮だというものだ。これは一般的なことだから、キケロやミルもうなずくことであろう。しかし、世の中には断言すべきことを断言せず、断言できないことを無謀にも断言する輩が多く見られる。こういう者は思慮がないか、もしくは、その語っている事柄に対して真剣な精神を持っていない。我々は、そのような愚を犯さないように注意せねばならない。特に聖書を取り扱う場合はそうである。何故なら、聖書とは間違うことの許されない神の神聖な文書なのだから。
この『戦い』は、何のためになされたのか。戦いがなされたのは、もう間もなく、神の王国が天上において正式に開始されることになるからであった。紀元68年6月9日までは、『竜』であるサタンは、天に自由に出入りすることができた。それはヨブ記1~2章を見れば明らかである。そこでは次のように書かれている。『ある日のこと、神の子らが主の前に来て立ったとき、サタンもいっしょに来て、主の前に立った。』(2:1)ここでは天上の出来事が言われているのである。しかし紀元68年6月9日が訪れると、神の王国が正式に天上でスタートされることになったために、状況が大いに変わった。すなわち、この日以降、もはやサタンが天に自由に出入りすることは許されなくなった。果たしてサタンが正式に始まった天国に、この至福かつ神聖に満ちた素晴らしい最高の場所に、自由に出入りするということがあっていいものであろうか。断じてそのようなことは許されない。サタンはこの正式に始まった天国にいてはならない存在なのだから、天国のある天上の場所から何としても追放されなければいけなかった。だからこそ紀元68年6月9日が訪れる直前において、『ミカエルと彼の使い立ち』は竜と戦うことで、その竜を天国から追い払おうとしたわけである。つまり、御使いたちが竜と戦ったのには、しっかりとした理由があったのだ。なお、この戦いは霊的なものではあったが、実際的なものであった。つまり、この戦いは単なる象徴また比喩として語られたものではない。これは実話としての戦いであったのである。
この箇所に書かれている『戦い』が、改革派の教会と異端との戦いだと考えている者がいる。すなわち、『ミカエルと彼の使いたち』が改革派教会であり、『竜』が異端であると見做すのである。このように考える者は黙示録を何も理解しておらず、ふざけている。この愚説を粉砕するのは容易いことである。すなわち、ヨハネは黙示録で示された出来事は『すぐに起こるはずの事』(1:1)だと断言した。もちろん、この12:7に書かれている出来事も『すぐに起こるはずの事』の中に含まれる。改革派教会は16世紀になって出てきたプロテスタントの派だから、ヨハネが黙示録を書いた時代を基点にして考えると、明らかに『すぐに起こるはずの事』ではない。1500年も経過してから生じる派がどうして『すぐに起こるはずの事』であろうか。それは「ずっと後に起こる事」である。つまりヨハネがここで言っているのは明らかに改革派教会のことではない。だから、彼の考えは完全な誤りであるということになる。もしこの戦いが本当に改革派と異端の戦いだとすれば、ヨハネは1500年後に登場する人たちが行なう戦いのことを、『すぐに起こる』などとあえて言い、それが紀元1世紀の人たちにあたかもすぐに起こるかのように語り伝えたということになる。もしそうだとすれば、一体当時の人たちには、どのような意義と益があったのか。遥か未来についての戦いを聞かされて、何か良いことがあったのか。ヨハネも改革派のプロテスタント教会が戦う戦いのことを当時の聖徒たちに伝えて、何かの意味があると思っていたのか。私にはさっぱり分からない。このような考えを披露した者は、明らかに黙示録を正しく理解できるように祈っていない。祈っていないからこそ、こんな出鱈目な奇説を披露するのだ。もし祈っていれば、神が正しい見解に導いて下さるだろうから、このような考えを愚かにも言い広めるようなことはしなかったであろう(※①)。我々は、このような奇説によく注意しなければいけない。今まで黙示録を論じてきた人たちは、実に多くの奇説を語ってきた。13章に出てくる666がロックフェラーだなどと言っている人たちの説も奇説に該当する。奇説には聖書の裏づけがないので、すぐに見分けられることが多い。今までに多くの聖徒たちが、20章に書かれている『千年』は非常に長い期間だと主張してきたのも、奇説に分類される。何故なら、彼らは『千年』が非常に長い期間だということを裏づける聖書の言葉を持っていないからである。今まで、この『千年』が長い期間だということを証拠づける聖句を提示した人がいたであろうか。そのような人は一人もいなかった。千年が長い期間だと思ったり言ったりする人たち自身も、自分の理解には聖句の裏づけがないことに気付いている。彼らは裏付けが聖書から見出せないものの、恐らく千年は長い期間に過ぎないだろうと感覚的に思っているに過ぎないのである。試しに『千年』が長い期間だと言っている人に、「聖書のどの箇所からそのように言えますか。証拠聖句はありますか。」と聞いてみるがよい。そうすれば証拠聖句を提示することはできないはずである(※②)。実際には私が既に神の恵みにより論じたように、この『千年』という言葉は12章の裏づけにより「3年6ヶ月」を言い換えたものであるという解を導きだせるのであるが、今までにこのことに気付いた人は誰もいなかったので、誰も彼もが自分の感覚に基づいて愚かにも『千年』は恐らく長い期間に違いないと思い違いをしてきたのであった。私の説には黙示録12章の裏づけがあるから奇説ではないが、彼らの説は感覚の裏づけしかないから奇説以外ではない。人間の感覚に基づいて解釈された説が奇説でなければ何を奇説と言えばよいであろうか。我々は、このような奇説に惑わされてしまわないように警戒すべきである。この箇所を改革派に関することだと考えている者の奇説もそうだが、そこには聖句が根拠として存在していない。つまり聖句を根拠としないからこそ、愚かな奇説が生まれてしまうのである。これは神の偉大な御言葉を矮小で堕落した不完全な人間理性によって解釈しようとする者に対する、神からの正当な罰である。ルターも言うように「神の言葉―その権威なしには何ものも主張されるべきでない―」(『後期スコラ神学批判文書集』『第2章C 罪の概念規定』9 要約、残存する罪は恩恵によって支配された罪である p248 知泉学術叢書6)のである。我々は次のカルヴァンの声に耳を傾けるべきであろう。「それというのも、神の言葉が先立ってわたしたちを導くのでなければ、わたしたちはめくらだからである。」(『新約聖書註解Ⅳ ヨハネ福音書 下』12:16 p409:新教出版社)
(※①)
この者は、このような考えを披露した書物―それは黙示録の註解書であった―を世に出すべきではなかった。というのは、このような愚説は糞便に等しいからである。黙示録を全体的な意味において間違って解釈した註解書を出す者は、世界に臭いゴミを蒔き散らしているのも同然なのである。そのような黙示録の註解書は、存在しないほうがましである。間違ったことばかり書かれている註解書に何の価値があるだろうか。
[本文に戻る]
(※②)
私と対論した黙示録を何も弁えていない教師も、この『千年』という期間について「この期間を裏づける聖書の聖句は存在しない。」などと、さも聖書の全てを知っているかのように堂々と言ったものである。この教師は黙示録をまったく把握できていなかった。だから、黙示録の聖句を詳しく解き明かすこともしていなかった。把握できていないのだから、詳しく説き明かせないのは当然である。もし把握していたとすれば、私のように神の恵みにより、今ここで書かれているような註解をしていたことであろう。多かれ少なかれ把握しているからこそ、このように多かれ少なかれ註解をすることができるわけである。無知は誤謬の母である。この教師は、無知であるにもかかわらず、よくも十全な理解を持っているかのように堂々と語ったものだ。
[本文に戻る]
【12:7~8】
『それで、竜とその使いたちは応戦したが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。』
ここではサタンだけでなく、サタンと共に『その使いたち』もいたと言われている。これはサタンを最高指揮官とするサタンの手下である悪しき御使いどものことである。今から6千年前にサタンが堕落した際、堕落したのはサタン一人だけでなく、サタン以外にも多くの御使いたちが堕落した。ここで『その使いたち』と言われているのは、その御使いのことである。この『使いたち』が、どれだけいたのかは、何も書かれていないので我々には不明である。私としては、この手下どもは、かなりいたのではないかと思う。このように思う人は、私の他にも多くいるはずである。賛美歌の中では「悪魔の手下どもの数は多し…」などと言われているが、これはこの賛美歌を作った人がサタンの使いたちの数が多かったと考えていたことを意味している。その数がどれだけであったにせよ、少なくとも一つ言えるのは、その数が2人とか3人ぐらいではなかったということである。というのも、いくらなんでも、まさかこれぐらいしかサタンの手下どもがいなかったなどとは思えないからである。
ここで言われているように、サタンの勢力はミカエルの勢力に打ち勝つことが出来なかったので、敗北した。というのは、根本的にミカエルの勢力のほうが強かったからである。恐らく、サタンがミカエルと戦いを交えたのは、これが初めてだったと思われる。聖書においてサタンがミカエルと戦ったという話は、この黙示録以外ではどこにも見られないからである。サタンがミカエルと言い争いをしたことであれば、ユダ9に書かれている(※)。しかし、これは単なる言い争いであって、実際的な戦いをしたというのではない。であれば、サタンはこの時に初めてミカエルと実際的な戦いをしたことになる。とすると、サタンはこの戦いの時に、初めてミカエルの強さを身をもって知ったことになる。この戦いがどのようなものであったかは、何も書き記されていないので、よく分からない。長かったのか短かったのか、また激戦だったのかそうでなかったのか、とにかく我々には何も分からない。しかし、たとい分からなかったとしても、黙示録の理解に致命的な妨げが生じることはないから安心すべきである。我々は、ただ「サタンどもがミカエルと戦って負けた」ということだけを知っていれば、それで十分である。この戦いの詳細が書き記されていないということは、つまり神が、聖徒たちにそのことを知らなくてもよいと判断されたということを意味する。何故なら、もし聖徒たちがこのことを知るべきだとすれば、詳細がしっかりと書き記されていただろうからである。知るべきであるにもかかわらず、神がそれを書き忘れたなどということはあり得ない。恐らく、この戦いについては今後、時代がかなり経過してから映画や小説として描かれることになるのではないかと私は予想する。何故なら、この戦いは良い題材となるからである。ダンテが『神曲』において煉獄の世界を長々と描き、ミルトンが『失楽園』において原初のエデンについて長いストーリーを空想したのだから、今後この戦いを作品化する人が現われたとしても不思議ではない。映画にでもすれば、非常に壮大なものとなるのではないか。もっとも、このような聖書が詳しく語っていない事柄を勝手にストーリー化して人々を楽しませようとするのは、実は大いに問題があるのではあるが。というのも、そのような作品は聖書が語っていない部分までも勝手に詳しく描写してしまうので、本来であれば聖書が語っていない事柄を、聖書が語ったものとして深層的に認識することへと繋がりかねないからである。
(※)
『御使いのかしらミカエルは、モーセのからだについて、悪魔と論じ、言い争ったとき、…』
[本文に戻る]
サタンどもはミカエルたちに敗北したので、天から追い出されることになった。これは当然であった。何故なら、これは戦争だったからである。イスラエルがカナンに侵攻した際、敗北を喫した民族がカナンの地から追い払われたように、サタンどももミカエルたちとの戦いに敗れたので、天の場所から追い払われねばならなくなったのである。戦争で負けた者たちは追放されて悲惨になる。この原理またルールは、地だけでなく天にもあったのである。それで、『天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。』と書いてあるということは追い出される前までは天にサタンどもの居場所があったということになるが、この居場所について無用な詮索をするのはよくない。何故なら、これは霊の世界に関することであって、聖書の中で何も語られていないからである。「サタンどもの居場所は御座に近かったのか、それとも遠かったのか。その居場所に聖なる御使いたちは近づくことができたのか。」などという問いを持ったとしても、どうして我々に分かるだろうか。どれだけ思索しても、確かなことは何も分からないままである。
【12:9】
『こうして、この巨大な竜、すなわち、悪魔とか、サタンとか呼ばれて、全世界を惑わす、あの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼とともに投げ落とされた。』
ここではサタンが多くの名で言い表わされている。多くの呼ばれ方をしていても、どれも同一のサタンであることに変わりはない。これは、ルターを「ルター」とか「博士」とか「修道士」とか「牧師」とか「異端者」とか「宗教改革者」とか「父」などと呼んでも、どれもルターを意味しているのと同じである。キリストも、聖書では様々な言われ方で言い表わされている。ここに書かれている『悪魔』とはギリシャ語では「ディアボロス」(反抗者)であり、『サタン』とはヘブル語であるがギリシャ語では「サタナス」である。ここでサタンが多くの呼び名でもって言い表わされているのは、聖徒たちにサタンを強く認識させるためであった。そのような例は、聖書の他の箇所でも見られる。例えば使徒行伝13:10の箇所がそうである。ここでパウロは魔術師エルマに対して次のように言っている。『ああ、あらゆる偽りとよこしまに満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵。』ここでパウロはエルマを3通りの言い方で言い表わしているが、どれもエルマであることには変わらない。またエレミヤ書23:36で『生ける神、万軍の主、私たちの神』と言われているのも、そうである。ここでも神が3通りの言い方で言われているが、どれも同一の神が言い表わされている。
サタンが天から『投げ落とされた』のは、聖徒たちの携挙と引き換えであった。すなわち、復活した聖徒たちが携挙されて天に導き入れられることになったので、その時にサタンは天から引き落とされねばならなくなった。何故なら、正式にスタートされた天上の王国において、サタンが居場所を持っていてはならないからである。果たして至福のパラダイスが正式に始まったというのに、サタンがそこにいてもいいものだろうか。サタンが存在しているパラダイスとは一体どのようなパラダイスなのか。もしサタンがいるような場所であれば、そこは真の意味においてはパラダイスとは言えない。だから、こういうことになる。すなわち、もしサタンが天から落とされることがなければ、聖徒たちも携挙されて天に入ることにはならなかった。何故なら、その場合、まだ天においてパラダイスが正式には始まっていないことになるからである。これとは逆に、もし聖徒たちが携挙されなかったならば、サタンもまだ天に居続けることができた。何故なら、その場合、まだ正式に天でパラダイスが始まってはいないので、サタンが地上に落とされる理由が生じていないからである。要するに、聖徒たちが天にいればサタンは天にいることができなくなり、聖徒たちが天にいなければサタンは天にいることができるというということである。聖徒たちが天にいるのにサタンも天にいるとか、聖徒たちが天にはいないのにサタンが天にいられないなどということはない。
敗北したサタンは天から投げ落とされて天の居場所を失ったので、それ以降、もはや天に出入りすることができなくなってしまった。紀元68年に天から投げ落とされて今に至るまでそうだったし、これからも彼は天に入ることができない。何故なら、居場所を失ったというのは、つまり天に入ることを禁止されたという意味に他ならないから。だから、我々がヨブ記1、2章で見るようなサタンの天への出入りは、もう2度と起こることがない。それは旧約時代にだけ限定されるべきことであった。聖徒たちの中には、今でもまだサタンがヨブ記に書かれているように、天の場所へと出入りしていると思っている人が多くいるはずである。しかし、今述べたことからも分かると思うが、そのように考えるのは誤っている。何故なら、天のパラダイスにいる聖徒たちの前に、突如としてサタンがぬっそりと現われ、聖徒たちを不快にさせるということは考えられないからである。至福のパラダイスにいる幸せな聖徒たちがサタンの現われにより、嫌な気持ちをその心に抱くとでもいうのか。これは考えられないことである。それは、あたかも天皇の誕生日パーティーが行なわれている最中に、極悪の犯罪者がニタニタと笑いつつ包丁を持って現われるようなものである。だから聖徒たちは、もはやサタンは天に対して入場不可能とされていると考えなければいけない。
キリストが言われた『わたしが見ていると、サタンが、いなずまのように天から落ちました。』(ルカ10章18節)という御言葉は、遥か昔の出来事であると今まで考えられてきた。すなわち、これはサタンが堕落した紀元前4000年頃の出来事について言われたものだと。しかし、そのように考えるのは誤っていると私は言いたい。これは、やがて起こるべき未来の出来事を預言した御言葉である。つまり、これは過去形の言い方で語られた預言だということである。聖書においては過去形の預言が普通に見られるということは、既に説明された。キリストは昔のことではなく、まだ起きていないことを、この御言葉において言われたのである。つまり、このルカ10:18の御言葉では、黙示録12:9で言われているサタンの追放のことが言われている。ルカ10:18と黙示録12:9は対応しているということだ。今まで聖徒たちは、これが過去形で言われているというだけの理由で、すっかりこれが昔の出来事について言われたものだと思ってきた。しかし、それは誤りであった。イザヤ14:12の有名な箇所も、同様にサタンが過去に堕落した出来事を語った箇所ではなく、未来に起こる預言が過去形で語られた箇所に他ならない。というのも、この箇所で言われているのがサタンの堕落であるという考えは、理性に基づいているからである。つまり理性がそう感じるからというので、誰も彼もイザヤのこの箇所では前4000年頃の出来事について言われているのだ、などと考えてしまった。しかし私の場合、誤ることの多い理性ではなく、黙示録12:9の箇所からこのイザヤの箇所を解釈する。そうすると、このイザヤの箇所でも、ルカ10:18の場合と同じで、やはり過去形の言い方による預言がされていたという見解に導かれる。私は言うが、サタンが前4000年頃に堕落した際、天から地に落とされたと考えるのには少し無理がある。というのも、もしサタンが天から地に落とされたのであれば、どうして紀元68年になるまでは天にサタンの居場所があったのか。確かに黙示録12:8の箇所では、それまで天にはサタンの『いる場所』があったということが示唆されている。また同じ黙示録の12:10でも、サタンが天から落とされるまで、サタンは天の場所で聖徒たちを『日夜』『私たちの神の御前で訴えて』いたと言われている。つまり、天からサタンが追放される前まで、サタンは天に居場所を持つことが許されていたことになる。もし本当にサタンが堕落時、すなわち前4000年頃に天から追放されたのであれば、どうしてあたかもサタンは天から追放されていないかのように、紀元68年になるまで天に居続けることができたのか。天から追放されて天の居場所を失ったのに、天にまだサタンの居場所があったというのか。これはおかしいことであると言わねばならない。しかし私の見解に従って考えれば何もおかしな点は生じない。だから、私の見解の通りに考えるのが望ましい。今まで聖徒たちは、過去形の預言に慣れていなかった上、黙示録をまったく理解できていなかったので、そのような知識と理解における不備が原因となり、このような思い違いをしてしまったのである。もし過去形の預言に精通しており、また黙示録をよく理解していたのであれば、つまり知識と理解に不備がなければ、このような思い違いをすることはなかったと思われる。しかし私がこのように言っても、大いに反発する人が多くいるのではないかと思う。だが私はその人たちに問いたい。あなたは黙示録を抜きにした上で聖書を理解しようとしているのではないか?すなわち黙示録を除いた65巻の知識の範囲内で聖書を理解しようとしているのではないか?黙示録を理解できていないのであれば、確かに65巻の範疇において聖書を理解せねばならなくなるのではないか?私のように黙示録も含めた66巻分の知識の範囲内において黙示録を理解できているのか?もし黙示録を理解できているというのであれば、黙示録を理解できていることを示す作品や文書を書いて私に見せることができるのか?その場合、私をうならせ、私の口を封じることができるのか?このように問われたならば、反発する人たちは口を閉ざすしかないはずである。何故なら、その人たちは私のように黙示録を多かれ少なかれ把握できていないだろうから。これは全く神の恵みによることなのだが、私は黙示録をも含めた上で啓示のことを考察しようとしているし、これからもそうするであろう。しかし多くの聖徒は、黙示録が分からないはずだから、どうしても黙示録の理解を前提としていない上で聖書の考察をせねばならない。つまり65巻だけで聖書を色々と考えなければいけないのであり、黙示録の理解を考察の助けとすることは不可能である。言うまでもなく、正しいのは私のように黙示録を含めた聖書理解に基づいて聖書の内容を考察することである。だから、私が今ここで述べたキリストの御言葉に関する見解を、聖徒たちは蔑ろにしてはいけない。もし反発を続けるのであれば、たとい黙示録を何も知らなかったとしても聖書の啓示を全て正しく理解することが可能だということを証明してほしい。そのような証明をするのが全く不可能であることは言うまでもない。黙示録を知らずに聖書の啓示、特に預言に関する啓示をことごとく正しく理解することは全くできないことである。それゆえ我々は黙示録の内容をも前提とした上で、冒頭に挙げたルカ10:18の御言葉を考察するようにせねばならない。ちなみに、このルカ10:18ではサタンが過去に天から落とされたと言われているのではないという見解は、カルヴァンも持っていたものである。彼のルカ10:18の註解箇所を参照。
【12:10】
『そのとき私は、天で大きな声が、こう言うのを聞いた。』
この『大きな声』の主は、セラフィムかセラフィム以外の御使いか24人の長老たちか、もしくはこの3つの者たちのうち2つの者か3つの者全てか、のどれかである。具体的なことは何も書かれていないので、実際はどうだったのかよく分からない。しかし、具体的なことを何も知らなかったとしても、大きな問題は何も生じない。この声の主が神でなかったのは間違いない。何故なら、この声の主は神を『私たちの神』と言っているからである。もし声の主が神であったとすれば、このようなことは言わなかったはずである。
『「今や、私たちの神の救いと力と国と、また、神のキリストの権威が現われた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。』
サタンが天から『投げ落とされた』ので、大きなことが起こった。4つのものが現われたのである。その4つとは、『神の救いと力と国と、また、神のキリストの権威』であった。神がサタンを天から追放されたのは、あまりにも大いなる出来事であった。何故なら、もはやサタンが天にいることができなくなったからである。そのような大いなる出来事が起きたからこそ、その出来事に応じて、素晴らしい4つのものが現われたわけである。それらのものを一つ一つ見ていきたい。
まず『神の救い』が現われたというのは、サタンが天から追放される時期に、再臨の出来事に伴って起こる復活という身体の贖いが聖徒たちに実現されたということである。滅びの子がキリスト者となるところの救いは紛れもない救いであるが、キリスト者が復活により身体の贖いを受けるのも救いである。この身体の贖いは究極的な意味における救いである。パウロも、ローマ13:11の箇所で、身体の贖いを指して『救い』と言っている。ここでは、その身体の贖いという救いが遂に現われたと言われている。つまり、ここで言われている『救い』とは新生のことではない。次に『力』が現われたというのは、神がその御力をもってサタンを天から追放されたということである。実際にサタンを追放したのはミカエルだったが(12:7~9)、ミカエルは神から受けた力により、そのようにしたのである。ヤコブがその手紙の1:17で言っているように『すべての良い贈り物、また、すべての完全な賜物は上から来るのであって、光を造られた父から下る』のだが、ミカエルが大きな力を受けたのも神がそれをお与えになったからであった。もし神が与えられなかったとすれば、ミカエルは力を持たず、それゆえにサタンに打ち勝つことはできなかったであろう。ここでは、神がこのミカエルを通してサタンを天から追い出され、そのミカエルにおいてご自身の力をお示しになられたということが言われている。力をお示しになられるとは、力が現われることでなくて何であろうか。そのミカエルを通して示された神の力は、全世界に働きかけていたサタンをさえも容易く屈服させるほどに大きな力であった。『国』が現われたというのは、サタンが天から追放されたことにより、遂に天において神の王国が正式に始められたということである。紀元1世紀の古代人たちが生き残っている間に、神の王国が再臨に伴って実現されるということについては、既にキリストがご自身の目の前にいる人たちに向かって次のように言っておられた。『まことに、あなたがたに告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が御国とともに来るのを見るまでは、決して死を味わわない人々がいます。』(マタイ16章28節)読者は、再臨と共に来るこの御国が地上的またこの世的なものではなく、天上的また霊的なものだったということを覚えられたい。何故なら、キリストの国とは既に述べられたように霊の国だからである。紀元68年にサタンが天からどかされたので、遂にキリストがマタイ16:28の箇所であらかじめ預言しておられた神の王国が天で始められることになった。だからこそ、サタンが追放された際、天では「神の国が現われた」と大きな声で言われたのである。『キリストの権威』が現われたというのは、サタンの追放により、キリストが世を3年6ヶ月の間裁かれる権威をお持ちになられたということである。その権威により裁かれる支配の出来事とは、20:1~6に記されている42ヶ月の支配のことである。なお、この権威にはサタンと入れ換えに上に引き上げられた聖徒たちにも与えられた。何故なら、20:4~6の箇所で書かれているように、この時には復活した後で携挙された聖徒たちもキリストと共に支配の業を遂行することになったからである。
このようなことが起きたのは神の御心であった。それが神の御心であったからこそ、このようなことが起きたのだ。もし神の御心でなければ、このようなことは起きなかったか、または起きたとしてもずっと後に起きていたことであろう。というのもパウロがローマ11:36の箇所で言っているように、『すべてのことが、神から発し、神によって成り、神に至る』からである。これら4つのものが現われたことを含め、この世の中に神から発せず、神によって成らず、神に至らない事象や出来事は存在していないのである。
この箇所の中で言われているように、サタンは『告発者』である。今の世の中を見ても分かるが、サタンは勝手な嘘をでっち上げたり隠された秘密を公にしてみせたり無罪の人に罪を押し付けるなどして、日々人々を告発することで世の中を荒らし回っている。サタンが天から追放される時まで、サタンは天において神の御前に聖徒たちの罪やその愚かさを『日夜』『訴えて』いた。それは神に聖徒たちの悪を告げ知らせることで神の怒りを燃え上がらせ、聖徒たちが神の裁きを受けるようにさせたいからであった。彼は聖徒たちを憎んでいたので、神の裁きを受けさせて聖徒たちが苦しむようにしたかったわけである。サタンが『地を行き巡り、そこを歩き回って』(ヨブ1章7節)いたのは、これが一つの理由であった。つまり、サタンは全世界にいる聖徒たちの悪を確認し、その悪を天にいる神に報告することで裁きを引き起こそうとするために地上を行き巡っていた。「どこかに罪を犯している聖徒がいたら天に行って裁く者に報告してやろう。そのような者は裁きを受けて苦しめばいいのだ。俺の目は少したりとも彼らの悪を見逃すまい。」というわけである。なお、サタンが告発する者だということについては、聖書ではこの箇所以外には語られていない。ヨブ記1、2章ではサタンがヨブのことについて神と話をしているが、これは告発ではない。パウロはローマ8:33の箇所で『神に選ばれた人々を訴えるのはだれですか。』と言っているが、これはサタンが聖徒たちを訴えると明白に言ったものではない。ヨハネはその手紙Ⅰの2:1で『もしだれかが罪を犯したなら、私たちには、御父の御前で弁護してくださる方があります。』と言ったが、ここでもサタンが聖徒の罪を御父の御前で訴えると言われたわけではない。しかし、この箇所(黙示録12:10)を見るだけでも、サタンが聖徒の告訴人だったということは十分に理解できる。何故なら、この箇所で『私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者』と言われているのは、そのようにしか理解できないからである。この箇所で言われていることを「サタンは聖徒を告訴する者であった。」という意味以外の意味に捉える人が誰かいるのであろうか…。
サタンが天から追放されたので、もはやサタンは天に行って、地上の聖徒たちの悪徳を神の御前で告発することが出来なくなった。ここでは彼が『投げ落とされた』と言われているのだから、どうして彼が天から追放されたにもかかわらず、再びその天に行くことができようか。入場禁止にされたのに、あいもかわらず入場できるとでもいうのか。それはあり得ないことである。それゆえ、聖徒たちは喜ぶべきである。我々がやがて行き着く天上のパラダイスにはサタンがもはや存在しておらず、そこでは永遠にサタンと出会うことがないだろうからである。
ところで、もはやサタンは天に存在していないと聞かされると、パウロの御言葉を問題として持ち出す人がいるのではないかと思う。その御言葉とはエペソ6:12のことである。そこでパウロはこう言っている。『私たちの格闘は血肉に対するものではなく、…天にいるもろもろの悪霊に対するものです。』さて、サタンが天にもう存在していないのであれば、この御言葉を我々は一体どのように理解したらよいのか。『もろもろの悪霊』とはすなわちサタンとその手下である悪しき御使いどものことだが、今でも彼らは天の場所に居続けているのではないのか。これまで聖徒たちは、このパウロの御言葉に基づき、今もまだ天にはサタンどもの勢力が存在していると信じ、論じてきた。私は言うが、これは今すなわちパウロの時代以降における「今」のことについて書かれた御言葉ではない。パウロがこのように書いたのは、紀元68年よりも前だから、まだサタンどもが天から追い払われていない時のことであった。つまり、パウロが生きていた時点ではまだ天にサタンが居続けていたからこそ、パウロはこのように「天には悪い者たちがいるのだ。」と書く必要があったのである。今の時代では、既に説明されたようにサタンどもは天から落とされているのだから、この御言葉が今の時代についてのことを言ったものだと考えることはできない。もはやサタンとその手下が天にいないにもかかわらず、パウロのこの御言葉に基づいて「今もまだ天ではサタンどもが存在しているのだ。」などと思ったり言ったりするのは愚かである。だから我々はパウロがこの御言葉を書いた時の状況と今現在の状況とは異なっていることを、よく弁える必要がある。その御言葉が語られた背景状況を弁えた上で御言葉を理解するというのは、聖書解釈の基本である。もしそうしなければ、どの御言葉で言われていることも我々が今生きている時代について言われたものであると理解することになってしまい、大変悲惨なことになってしまう。残念なことだが、今の教会においては、御言葉の語られた背景を無視して御言葉を理解するという看過できない無謀が多く見られるのである。
【12:11】
『兄弟たちは、子羊の血と、自分たちのあかしのことばのゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでもいのちを惜しまなかった。』
ここで言われているのは、ネロに取り憑いていたサタンによる42ヶ月間の大攻撃を受けた聖徒たちが、大いに忍耐したということである。ここで言われているのは、忍耐した聖徒たちだけであると考えなければいけない。何故なら、忍耐しない聖徒たちは、キリストの信仰に留まり続けなかったのだから、名ばかりの聖徒であって実際は聖徒でなかったからである。この忍耐の出来事はこれから未来に起こる事柄だと考えられているが、そうではない。というも、これは我々にとっては大昔のことだからである。キリストがマタイ24:13で言われた『最後まで耐え忍ぶ者は救われます。』という有名な御言葉は、この時に成就された。この御言葉でキリストは、「ネロにおいてサタンが聖徒たちを攻撃するので聖徒たちは耐え忍ばなければいけない。そのようにして耐え忍んだ者は紀元68年の時に携挙と復活に与かり、天に挙げられて救われることであろう。」と言われたのである。何故なら、この御言葉が書き記されているマタイ24章は、ネロの大患難について預言した箇所だからである。マタイ24章が紀元1世紀の出来事を預言した箇所だというのは、既に第1部で論じられた。私の言ったことが信じられないと感じる聖徒は、あのジョナサン・エドワーズという大物でさえ、マタイ24章では紀元1世紀の出来事が書かれているという理解を持っていたことをよく考えてみてほしい。
この時の聖徒たちは、『子羊の血と、自分たちのあかしのことばのゆえに』サタンに勝利した。子羊の血で洗い清められた状態に保たれ、キリストに関する信仰の証しを忠実に守り続けるのは、サタンに対する勝利に他ならない。何故なら、そのような聖徒たちを、サタンは屈服させることができなかったからである。サタンが屈服させられなかったということは、つまり打ち勝てなかったということだから、負けたことを意味する。サタンが打ち勝てなかったからこそ聖徒を屈服させることができず、また負けたからこそ聖徒は最後までキリストの血と純粋な証しの中に保たれ続けたのである。その場合、サタンは敗北したのだから、敗北した結果を自分の身に受けねばならない。つまり、その敗北の事実が現実の状態となって現われ、大いに悲惨と苦しみを味わわされることになるのである。要するに、ただ「敗北した。」という事実がそこにあるだけに過ぎないというのではなく、その事実には痛い結果が実際的に伴っているということである。ただ「敗北した。」という言わば情報的また認識的な事実がそこにあるだけでは、本当に敗北したとは言えないのだから。この箇所でもサタンが聖徒たちに敗北したからこそ、その敗北の結果として、実際に天から落とされるという痛みを受けることになったのが分かる。聖徒たちが忍耐することにより勝利するというのは、既に2~3章の箇所で論じられた通りである。
この時において、真の聖徒が誰なのかということが、如実に明らかにされた。聖徒たちが『死に至るまでもいのちを惜しまなかった』のは、その聖徒たちが選ばれていた明白な証拠であった。選ばれていたからこそ、キリスト信仰に立ち続け、『死に至るまでもいのちを惜しまなかった』わけである。選ばれている者は、『最後まで耐え忍ぶ』ようにと神の霊が働いて下さるので、必ず最後まで忍耐のうちに保たれ続ける。また、この時には、偽りの聖徒も明らかにされた。この時に信仰を捨てた者たちは、その無様な振る舞いによって、自分たちが本当は真の聖徒ではなかったことをみずから証明した。選ばれていないからこそ、その人たちは、信仰の忍耐に留まれなかったわけである。何故なら、選ばれていない人には神の霊が与えられていないので、神のために忍耐するなどということがどうしても出来ないからである。神の霊を受けていない人は神を愛することがないのだが、愛してもいない存在のために忍耐する人がどこにいるであろうか。選ばれていない人が神を愛さないのだとすれば、彼らが神のために忍耐できなかったとしても何も不思議ではない。要するに、忍耐とは、その人の選びを浮き彫りにさせる目に見える徴である。選ばれている人はその選びが忍耐という形で明瞭に現われるが、選ばれていない人は選ばれていないという事実が忍耐できないという形で明瞭に現われる。
【12:12】
『それゆえ、天とその中に住む者たち。喜びなさい。』
聖徒が天に導き入れられ、サタンが天から投げ落とされたのは喜ばしいことであった。それは、地上では『旅人であり寄留者』(ヘブル11章13節)に過ぎなかった聖徒たちが復活して『天の故郷』(同11章16節)へ挙げられた一方、サタンは自分の本来いるべきではない場所から落とされて消え去ったからである。義人が戻り、悪い存在が追い払われる。これは喜びそのものである。ここでは『天』に対しても『喜びなさい。』と言われているが、これは天全体に喜びがあるように、という意味である。『天』という場所が喜びの感情を持つ人格的な存在だと言っているわけではない。この箇所もそうだが、聖書の中で、ある場所を人格的な存在として取り扱っている箇所は少なくない。例えば、エレミヤ書22:29の箇所では、次に示すように、あたかも地という場所が聞く耳を持った人格的な存在であるかのように取り扱われている。『地よ、地よ、地よ。主のことばを聞け。』我々が今見ているこの箇所は、ルカ10:20から取られているのではないかと思われる。そこでキリストは聖徒たちに次のように言われた。『ただあなたがたの名が天に書きしるされていることを喜びなさい。』この2つの箇所は、その内容が完全に一致しているというのではないが、全体的に類似しているのは明白である。どちらも天における聖徒たちのゆえに喜ぶようにと言われているからだ。この12:12の箇所がルカ10:20の箇所と対応しているとすれば、私が先に12:9とルカ10:18は対応していると言ったのは、ますます確かなこととなる。何故なら、先に私が対応していると言ったルカ10:18の箇所は、私が今対応していると言ったルカ10:20の2節前の箇所であって、どちらも同じ場面で語られているからである。もしルカ10:18が黙示録12章と対応しているというのであれば、ルカ10:20のほうも黙示録12章と対応している可能性は高い。確かに黙示録12:9~12の箇所とルカ10:18~20の箇所は、言っていることが似ているのだから、ルカの箇所にある2つの部分(10:18と10:20)からヨハネが黙示録の御言葉を対応させたとしても不思議ではない。私としては、ヨハネが黙示録12:9~12の箇所を書いている時、その頭の中にはルカ10:18~20の内容があったのではないかと思う。
『しかし、地と海とには、わざわいが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒って、そこに下ったからである。』
まず『しかし、』と言われているのは、すぐ前までに語られていた出来事とは真逆の出来事が語られることになるからである。何故なら『しかし、』とは、それまでとは多かれ少なかれ異なった内容を切りだす際に使われる言葉だからである。すなわち、この箇所で言えば、すぐ前までは天における喜ばしい出来事が語られていたが、『しかし』今度は地における喜ばしくない出来事が語られることになる。その喜ばしくない出来事とは『わざわい』である。黙示録においては、このように小さいと思える言葉さえも重要であるということを読者は覚えられたい。何故なら、黙示録の場合、たとえこのような言葉であっても、謎に包まれた内容を紐解く原因となる場合が少なくないからである。だから黙示録を研究する際には、小さな言葉だからといって蔑ろにせず、神経質な態度を持って臨んでほしい。この文書は、明らかに他の聖書の巻とは性質が異なっている。黙示録は神経質になるからこそ、多くの箇所を把握できるようになる巻である。要するに、この文書は、神経質にならなければ把握できないほどに多くの部分が謎に包まれているというわけである。
『地と海とには、わざわいが来る。』とは、どのような意味なのか。これは、こういうことである。すなわち、サタンが天から落とされた後には3年6ヶ月(=千年)の封印期間が訪れるが(20:1~6)、それから後にサタンがユダヤの地をローマ軍を通して滅亡させる出来事(20:7~10)が、ここでは『わざわい』と言われている。つまり、『地と海』とはユダヤにおけるそれであり、ユダヤ全体を指している。これは7:2の箇所で『地をも海をもそこなう』と言われていたのが、ユダヤの世界についてのことだったのと同じである。確かに、20:7~10で書かれているように、サタンはローマ軍を動かしてユダヤの地に大きな『わざわい』をもたらした。その災いは、ユダヤが焼け野原と化すほどの悲惨であった。サタンが天から地に落とされて後でユダヤを滅ぼしたのは確かである。だからこそ、ここではサタンが落とされた際に、『地と海とには、わざわいが来る。』と言ってあらかじめユダヤの破滅が預言されたわけである。それゆえ、この『地と海』という言葉を地球全土におけるそれだと捉えてはいけない。そのように捉えるのは誤りである。何故なら、ここで書かれている出来事も『すぐに起こるはずの事』(1:1)だったからである。ヨハネがこの箇所における文章を書いてから、『すぐに』も起こった災いとして考えられるのはユダヤの陥落以外にはない。それ以外の地域でも災いを受けた場所がどこかあったかもしれないが、黙示録の内容とは無関係であるはずだから、考慮すべきではない。間違いなく言えるのは、ヨハネがこの文章を書いてから、全世界における『地と海と』が実際の災いを受けることはなかったということである。実際にすぐにも災いを受けたのはユダヤの地と海なのだから、ここではユダヤのことが言われていると考えなければいけない。この論に抗弁するというのであれば、その人は私のように神の恵みにより黙示録の註解を記して、まず黙示録を全体的にしっかりと把握していることを示していただきたい。それができないのであれば、黙示録を把握できていないということになるのだから、自分の無知を認め、無知であるにもかかわらず私の論に無闇にも抗弁するべきではない。それは学生が教授に学的なことで無謀にも抗弁するようなものだ。私には神の素晴らしい恵みにより黙示録についての多くの理解が与えられているのだから。もし私に抗弁するというのであれば、熟慮に熟慮を、研究に研究を、祈りに祈りを重ねてからにせよ。
ここで『悪魔が自分の時の短いことを知り』と言われているのは、何のことか。これは20:10に書かれていることである。サタンは天から落とされて3年6ヶ月が経過した後、ローマ軍を通してユダヤを滅亡させたのだが、それから後に『火と硫黄との池』に投げ込まれて裁かれると20:10の箇所では言われている。3年6ヶ月というのは、普通に考えて『時の短いこと』である。何故なら、モーセも言うように、人生の期間である70~80年でさえ『早く過ぎ去』(詩篇90篇10節)る『ひと息』(同90篇9節)のごとき時間なのだから。たとえ不信者たちが3年6ヶ月は長いと思ったり言ったりしても、聖書に自分の理解を一致させるべき聖徒たちは、聖書にしっかり立って3年6ヶ月という期間は実に短い期間であると思わなければいけない。つまり、ここでは、もう間もなくサタンがそのような裁きを受けることになるからこそ、『悪魔が自分の時の短いことを知』ったと言われているわけである。この火炎に投げ込まれるという20:10の裁きは、既に実現している。これを疑うことはできない。何故なら、この裁きも『すぐに起こるはずの事』だったからである。もし20:10の裁きがまだ起きていなかったとすれば、すなわちサタンが天から追放されてから遥か後に起こることだったとすれば、ここで悪魔がその裁きの時を間近だと知っていたとは言われなかったであろう。愚かな肉の心がどう思おうとも、神の言葉に逆らいたいというのでなければ、この裁きが既に起きたと信じなければいけない。この20:10の裁きを含め黙示録は大半がまだ起きていないと考えている者たちは、その考えを改める必要がある。何故なら、その者は、黙示録で記されている出来事はすぐに起こったということを知らないからである。また黙示録は20:6の箇所より後の出来事については未だに実現していないと思い違いをしている千年王国論者らも、自分の思い違いを改めなければいけない。彼らも、自分たちには理解があると表面的には見せかけているが、実のところ黙示録をよく弁えていないからだ。もし理解しているというのであれば、そのことを証明するために、黙示録のしっかりとした註解書を出せ。そして、しっかりと理解できているかどうか、その註解書を私に見てもらうべきである。しかしながら、彼らの中途半端な理解を示す文章を見る限りでは、黙示録の註解書を書くことはできないだろうと思う。それでは、その間近に迫っていたサタンの裁き、つまり20:10に書かれている火の中への投下とは、どのようなものであったか。それは、サタンがもはやそれ以降はかつてのようにユダヤに働きかけることが出来なくなったという裁きであった。これについては既に幾らか語られたが、20章の箇所が来たら再び詳しく説明されることになる。
サタンが裁きの近いことを知って怒りに燃えたのは自然であった。何故なら、もうその裁きを受けた後は、それまでのようにユダヤに働きかけることはできないからである。それまではユダヤに対して大いに働きかけ、神の聖なる民、選びの国民、唯一無二の存在を惑わして偶像崇拝をさせたり、神を怒らせる悪事に進ませたりして、大いに満足感を味わえたのだが、もはやそのようなことは出来なくなった。これではサタンが怒りに燃えたとしても無理はなかった。我々は、サタンが怒る存在であることを知るべきである。すぐ後の12:17の箇所でも、やはり悪しき働きかけが無効化されたがゆえにサタンは非常に怒っている。サタンは、言わば不良少年に似ているのだ。何か気に入らないことがあればすぐに激しい怒りを持つ矯正し難い不良少年のように、サタンも気に入らないことがあればすぐに怒りを持ち、しかもその怒りを抑えることができないのである。いや、むしろサタンが怒りやすいからこそ不良少年も怒りやすいと言ったほうが正しいであろう。何故なら、不良少年が怒りやすいのは、サタンがその少年に強く働きかけているからである。つまり、サタンが強く働きかけているからこそ、その少年はサタンのような怒りやすい性質を大いに持っているということである。だから我々は不良少年を見て、サタンを物質的・実際的に感じることが可能である。それで、この怒りは『激し』かったとここでは書かれている。サタンがこの時に大きな怒りを持ったのは、彼にとって只ならぬことが起きたからであった。サタンにとってユダヤに働きかけるのは、実に大きなこと、切に心を傾けるべきこと、何よりも優先させるべきことであった。というのも、ユダヤとは神に直接選ばれた聖なる民だったからである。神がもっとも重要とされたこの民は、サタンにとって見過ごしてはならない最高に重要なターゲットであったわけである。そのようなユダヤにもはやかつてのようには働きかけることが出来なくなったので、その変化の重大性に気付き、サタンは心に大きな怒りを持ったわけである。
さて、サタンが『自分の時の短いことを知』っていたのは何故か。どのようにしてサタンは天から落とされた際に、そのことを知れたのか。サタンは神のように予知ができず、何かを原因として知るのでなければ何事をもあらかじめ知ることはできない。彼は、『この世の神』ではあるものの、隠されている事柄については無知なのである。ということは、サタンは何らかの原因があったために、あらかじめ『自分の時の短いことを知』れたということになる。サタンが自分に裁きの与えられることの近いのを知っていたのは、イザヤの預言があったからである。イザヤは紀元前8世紀頃に、かつてこのようにサタンについて預言していた。『その日、主は天では天の大軍を、…罰せられる。彼らは囚人が地下牢に集められるように集められ、牢獄に閉じ込められ、それから何年かたって後、罰せられる。』(イザヤ24章21~22節)ここでイザヤは、神が『天の大軍』であるサタンどもを罰せられて後、『何年かたって後』に再びサタンどもを罰せられると預言している。これは12章と12章に対応している20章で言えば、まず『天の大軍』である『竜とその使いたち』(12:7)が天において『ミカエルと彼の使いたち』(12:7)に負けたがゆえに地へと投げ落とされて(12:9、10)『罰せられ』、そうして後に『地下牢』また『牢獄』である『底知れぬ所』(20:1~3)に封じられて全ての攻撃が無効化され(12:14~16、20:1~3)、『何年かたって後』すなわち『千年』(20:1~6)として象徴される『1260日』(12:6)(=3年6ヶ月)が経過してからローマ軍に聖徒たちの陣営を取り囲ませ(12:17~18、20:7~10)、再び『罰せられる』―つまり火の池に投げ込まれる―ということである(20:7~10)。サタンは天から投げ落とされた際、このイザヤの預言に基づき、神の裁きが始まったことに気付いた。何故なら、イザヤがかつて預言していたように、本当に『その日、主は天では天の大軍を、…罰せられる。』ということが起こったからである。「遂にイザヤの言っていたことが実現されてしまった。これから俺は牢獄に封じられて無効化され、『何年かたって後、罰せられる』のか。何てことだ。」サタンは、この時、このような精神状態になったわけである。既に説明されたがサタンはあらゆる人間の声を聞き、また覚えているので、このイザヤの預言も記憶として持っていた。だからこそ、天から落とされてイザヤの預言が成就し始めた際に、サタンは『自分の時の短いことを知』ったわけである。つまり、サタンが知ったというのはイザヤの預言した「2回目の罰」を指している。1回目の罰が起きたのだから、2回目の罰も必ず起こるだろうと察したということだ。ところで、このイザヤ24章の預言は、黙示録の理解にとって非常に重要な意味を持っている。何故なら、このイザヤ24:21~22の箇所は黙示録20章および12章と完全に対応しているからである。イザヤ書の箇所と黙示録の20章および12章を、よく比べつつ読んでみるとよい。そうすれば、どちらも全く同じことが言われていることに気付くであろう。すなわち、この3つの箇所では、どれも(1)まずサタンが天で悲惨なことになりそこから引き落とされ、(2)一定の期間だけ封じられて無効化され、(3)そうして後にローマ軍を招集してから再び悲惨なことになってしまう、ということが預言されている。つまり、イザヤ24:21~22=黙示録12章=黙示録20章、ということである。このように理解すれば、20章に書かれた『千年』という象徴数は『1260日』(=3年6ヶ月)だということが、ますます理解できるようになる。何故なら、この期間はイザヤ24:22の箇所では『何年か』と言われているからである。『何年か』とは、明らかに短い期間であることを示している。それは『1260日』が短く感じられる期間だということと、まったく合致している。もし『千年』が長大な期間だとすれば、黙示録では『1260日』とは言われていなかっただろうし、イザヤも『何年か』などとは言わなかったであろう。『1260日』また『何年か』が気の遠くなりそうな期間だとでもいうのか。気の狂ったことを考えるのは止めなさい。それゆえ、今や『千年』を長大な期間として見做す盲目的で愚劣な理解は、闇の中に葬り去られよ。このような理解は理性や人間の感覚に基づいたものであって聖句に基づいてはいない。そのように理解する者たち自身も、そのことを認めざるを得ないのである。このように理解する者らは、私は確かなことを言うが、黙示録を何も理解できていない。彼らは訳も分からず『千年』が長大であると感覚的に考えているに過ぎないのである。もし黙示録をしっかりと理解できていたのであれば、そのような誤謬には陥らなかったであろう。主が聖徒たちの目を開いて下さるように。アーメン。
この時には、サタンの手下どももサタンと共に、天から地へと投げ落とされた。それは12:9で『彼の使いどもも彼とともに投げ落とされた。』と書かれていた通りである。どうして再び既に語られたことを今言ったかといえば、読者に注意を促すためである。すなわち、この箇所ではサタンしか地上に落とされたことが書かれていないが、それはただ単にサタンだけしか落とされたとしか書かれていないだけであって、実際は彼と共に多くの悪しき御使いたちも落とされていたのだということを忘れないように、ということを私は言いたいのである。つまり、ここではサタン以外の悪しき御使いについては記述が省略されている、ということである。
ところで、先の箇所(12:9、10)ではサタンが天から投げ落とされたと書かれていたのに、この箇所では『悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒って、そこに下った』などと、あたかも自分から地に降下したかのように書かれているのは何故か。まず、サタンが自らによってではなく、天でミカエルから落とされたがゆえに落ちたということを確定しておかねばならない。何故なら、聖書にそう書かれているからである。それにもかかわらず、この箇所でサタンが自分の意思によって天から地に下ったかのように書かれているのは、この箇所が先の箇所とは違うことを言っているからである。すなわち、12:9、10の箇所では「サタンがどのようにして落とされたのか」ということが言われていたが、我々が今見ている箇所では「サタンが天から落とされてからどのようなことをしようとしたか」ということが言われている。つまり、確かにサタンは他の存在から働きかけられたがゆえに天から追放されたのだが、そのようにして追放された後は、サタンが怒りに燃えつつ自らの意志で教会を滅ぼすべく地へと突進していった、ということがここでは言われているのである。これは、あたかも強制的に追い出された悪い弟子を見ていた師匠が、「あいつは怒り狂って自分の家へと向かって行った。」などと言うようなものである。このように言われても追い出された弟子が自らの意思によって師匠の元から離れていったのではないのと同じで、サタンも『激しく怒って、そこに下った』などと言われているからといって、彼が自らの意思により天から地へと降下したというのではない。誰でも追い出された弟子が追い出されたからこそ遠くに行ったと思うように、サタンも追い出されたからこそ地へと降下することになったと思わなければいけない。しかし、追い出された後の行動について言えば、サタンの意志を基点としてその行動を語ることができる。つまり、ここでは、追い出された後のサタンの意志を基点とした行動について言われているわけである。黙示録では、このような難しい言い方をしている箇所が多いので、聖徒たちは、そのような箇所に出会った際、性急に判断したりせず、冷静になって熟慮するべきである。神の恵みをいただければ、それがどのようなことを言っているのか、よく分かるようになるであろう。もし分かった場合、その時は、神の恵みにキリストの御名において感謝すべきである。
【12:13】
『自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は、男の子を産んだ女を追いかけた。』
『自分が地上に投げ落とされたのを知った』という言葉の中には、「もはや天には出入りできなくなったのを知った」という意味も含まれている。何故なら、もし未だに天に出入りできたというのであれば、天から落とされたのは無意味になるからである。もし天から落とされたのにもかかわらず天に出入りできるのであれば、前と状態が何も変わっていないことは明白である。このこと、すなわち「もはや天に出入りできなくなった」ということも、サタンが激しく怒った理由の一つであった。何故なら、それは以前のように天に入って聖徒たちを告訴することが出来なくなったことを意味するからである。こんなにもサタンを苛立たせることは他になかったのではないか、と私には感じられる。傲慢なサタンにとって、そのようなことになるのは屈辱以外の何ものでもない。「サタン様である俺様が天に出入りできなくなるようにさせるとは何様のつもりだ?」というわけである。
復活した聖徒たちを生じさせた教会をサタンが『追いかけた』のは、つまりサタンが教会にいた復活者たちを『食い尽くすため』(12:4)である。「あの復活した奴らに支配されてたまるものか。奴らが何かをする前に食い尽くして滅ぼしてやろう。今が、今こそがチャンスだ。」このような精神状態に基づき、サタンは教会にいる復活者たちに向かって突進していったのである。この時に復活した栄光の聖徒たちは、サタンにとって誠に脅威であり、危険そのものであった。何故なら、この聖徒たちは支配の業をキリストと共に遂行することになっていたからである。そのような支配はサタンにとって望ましいものではない。だから、サタンが教会を『追いかけ』て聖徒たちを滅ぼそうとしたのは、彼にとっては自然なことであった。
このことを考えても、やはりサタンは正に『ほえたけるしし』(Ⅰペテロ5章8節)であったことが分かる。サタンは、どこかに『食い尽くすべきもの』(同)がいれば、それを獅子として喰い尽くそうとする。ここの箇所でも、サタンが獅子のように復活した聖徒たちを喰い尽くそうとしていたことが分かる。彼は、かつて蛇の中に入ってアダムとエバに罪を犯させることで、人類全体を食い尽くした。またネロに入ることで、多くの聖徒たちを食い尽くした。今の時代では、陰謀家たちの中に入って、人類全体を大いに喰い尽くそうとしている。我々は、サタンがそのような獅子であるからといって、恐れたり不安になったりすべきではない。何故なら、神の守りを受けている者は、その守りにより、サタンの鋭い牙から守られるからである。アウグスティヌスを、ルターを、カルヴァンを見よ。彼らはその時の時代においてサタンが最も憎悪した危険人物であったが、それにもかかわらずサタンに食い尽くされることなく、人生を最後まで全うさせた。すなわち彼らはサタンの暴虐を要因としてではなく、自分の内部からの要因、つまり病によってこの世の人生を終了させたのである。彼らの例を見れば分かるように、神の御手に守られている者は、サタンも手を出すことができないのである。
【12:14】
『しかし、女は大わしの翼を2つ与えられた。自分の場所である荒野に飛んで行って、そこで一時と二時と半時の間、蛇の前をのがれて養われるためであった。』
『女は大わしの翼を2つ与えられた。』とは何か。これは、教会にいた復活者たちがあたかも『大わしの翼を2つ』持って舞い上がったかのように上へ携挙された、という意味である。これは、今のプロテスタント教会、特にプレ・ミレニアリズムに立つ教会に属している聖徒であれば、誰でも知っていると思われるあの御言葉のことである。あの御言葉が実現されたことについて、ここでは言われているのだ。すなわち、その御言葉とはイザヤ40:31である。そこでイザヤは次のような預言をした。『主を待ち望む者は新しく力を得、鷲のように翼をかって上ることができる。』紀元68年6月9日に再臨が起き、聖徒たちが復活した際に、このイザヤ書の預言が成就されることとなった。まだこのイザヤ書の預言は未だに成就されていないと全ての聖徒たちが思い違いをしているのだが、実はこの預言は、既に成就されていたのである。何故なら、このイザヤ書の預言が成就されたことについて書かれているこの12:14の出来事は、黙示録の他の箇所と同じように『すぐに起こるはずの事』(1:1)だったからである。それゆえ、この箇所では「教会」が翼を受けたと言われているのだと考えてはいけない。そのように考えると、12章の箇所を上手に理解できなくなってしまう。紀元68年6月9日には確かに聖徒たちがあたかも翼を付けて飛ぶかのように上へ挙げられたのだから、ここで言われているのは「教会にいた聖徒たち」のことだと考えなければいけない。そうすれば12章の箇所を上手にスンナリと理解できるようになることであろう。また我々は、聖徒たちが実際に本物の翼を背中に受けたなどと考えるべきでもない。何故なら、聖徒たちとは人間であって、翼を持つ御使いではないからである。イザヤが『鷲のように翼をかって』と預言したのは、あくまでも象徴表現に過ぎない。キリストは復活した聖徒たちが『天の御使いたちのよう』(マタイ22章30節)になると言われたが、これも復活した聖徒たちに御使いが持っているかのような実際の翼が生えるという意味で言われたのではない。キリストが復活した聖徒たちは御使いのようになるだろうと言われたのは、外観のことではなく、その敬虔さのことである。もし本当に復活して天に入った聖徒たちの背中に翼が生えているのであれば、聖書のどこかにそのことが語られていてもいいはずだが、聖書にそのようなことは示唆されてさえいないのである。
なお、翼が『2つ』与えられたと書かれているのは、復活した聖徒たちが本当に上に舞い上がりつつ携挙されたことを示している。何故なら、もし「一つ」しか翼が与えられなかったとすれば、しっかりと舞い上がれないだろうから、本当に携挙したのかどうか分からなくなってしまうからである。また、この携挙は、御使いたちに委任された仕事であった。これについては既に第2部の中で論じられた通りである。
教会が『自分の場所である荒野に飛んで行っ』たとあるのは、復活した聖徒たちが翼を持って飛んだかのように携挙され教会から消えたので、その結果、毒麦しかいなくなった教会が荒野のごとき状態に移行したという意味である。既に述べたように、教会が荒野に行くとは場所の移動ではなく、状態の変化を言っている。この荒野が非再生者たちを意味しているというのは既に語られた通りである。他の箇所もそうだが、この箇所は肉的に解釈されるべきではない。私は聖徒たちに言いたい。事は霊的にこそ捉えねばならないと。聖書の他の巻が霊的に捉えられるべきだとすれば、尚更のこと、この巻は霊的に捉えられるべき必要がある。
教会が『一時と二時と半時の間』荒野の状態となったと、ここでは言われている。この『一時と二時と半時』と書かれたのはダニエル7:25、12:7の箇所からであって、『1260日』と『3年6ヶ月』と『42ヶ月』の言い換えである。黙示録では、この箇所でしか、この言い方は使われていない。他の箇所では別の言い方により当該の期間が示されている。この言い方は実に特徴的であると言える。さて、この言い方は、黙示録の理解にとって非常に重要である。何故なら、この言い方は、その期間をどのように捉えるべきかということを教えているからである。すなわち、この言い方は、それが非常に短いことを意味している。というのも、『一時と二時と半時』とは、すぐにも過ぎ去るということだからである。このように言われて、非常に長い期間を思い浮かべる人は恐らくいないはずだ。一時が経ち、もう二時が経った後、最後の半分の時が過ぎれば、もうこの期間が全うされるからである。ところで、この「一時」というのはカルヴァンもそう考えていたように「わずかの時間のあいだ」(『新約聖書註解ⅩⅠ ピリピ・コロサイ・テサロニケ書』Ⅰテサロニケ2:17 p196:新教出版社)という意味である。誰がこの意味に意義を唱えるであろうか。つまり、『一時と二時と半時』である『1260日』や『3年6ヶ月』や『42ヶ月』という期間は、それが非常に短いということを示している。ヨハネがこの期間を『三日半』(11:9、11)と極度に圧縮して表現したのも、この期間が非常に短かったからである。つまり、それが短いからこそ、このような圧縮が許された。何故なら、『3年6ヶ月』(=一時と二時と半時)も『3日半』も、程度の違いはあれ「短い」という点では何も変わらないからである。このことから、20章の『千年』という象徴数は非常に短かったということが、ますます確かとなる。何故なら、『千年』と同一の期間であることを示す『一時と二時と半時』という言い方は、既に述べたごとく非常に短いことを示しているからである。『一時と二時と半時』のイコール(=)表現である『千年』が長大な期間だったとでもいうのか。『一時と二時と半時』が何千年もの期間なのか?気の狂ったことを考えるのは止めなさい!この『千年』を今まで長大な期間だと間違って考えてきた人たちは、私が神の恵みにより述べたことを聞いて、悔い改めるべきである。さて、それにしてもこのような同一の期間の言い換えは、実に妙であり、素晴らしい。一つの期間を4つの言い方で表現し、その中には『一時と二時と半時』という実に特徴的な表現も含まれている。これは制限された知性しか持たない人間では考えられなかったことだ。実際、このように知的な言い換えは、聖書以外の書物では見られない。英知の神が聖書を書かれたからこそ、このように知的な言い方を思いつくことができたわけである。
『養われる』ということは、既に12:6の箇所で説明されたので、ここで再び書くことはしない。この箇所を見ても分かるが、黙示録には本当に繰り返しが多い。私のように恵みにより黙示録を多かれ少なかれ理解していれば繰り返しが多いことに気付くのだが、他の聖徒たちは黙示録をまったく理解できていないので、そもそも「繰り返しが多いのかどうか」という認識を持つ以前の段階に留まっている。この註解を読んだ聖徒であれば、既に繰り返しの多さに気付いているはずだ。しかし、たとえ繰り返しが多いからといって、黙示録を軽んじたり批判したりしてはならない。何故なら、黙示録とは神の言葉であって、神が欲されたからこそ、そこには繰り返しが多く出てくるのだから。神がそのようにヨハネを通して書かれたのだから、「どうしてこのような書き方をされたのですか。もっと繰り返しを少なくしたほうが良かったのではありませんか。」などと我々が言っていいはずがない。
ここで書かれているように教会は荒野状態となってから『蛇の前をのがれ』るのだが、これはサタンが封じられて無効化されたことを意味する。封じられて無効化されたからこそ、教会は『蛇の前をのがれ』ることが出来るのだから。これは20:1~6で書かれている内容と、完全に一致している。そこでもサタンがローマ軍により聖徒たちを取り囲むまでの間(『千年』=『一時と二時と半時』)、サタンは『底知れぬ所』に封じられるので無効化されると言われている。このことから、20章と12章は内容的に完全に一致しているということが、ますます確かに理解される。どちらも同じ出来事を取り扱っているからこそ、どちらにも同じことが書かれているわけである。これが分からない聖徒は、聖書を理解することにおいて裁きを受けているか、そうでなければ聖徒であると周りからは思われているものの実は神の霊を受けていない。でなければ、私の説明したことがよく分かるはずだからである。20章と12章をどれだけ読み比べても同じことが言われていると理解できない人は愚かであり、少しも似ていると思えない人は痴呆状態であるのも等しい。
【12:15】
『ところが、蛇はその口から水を川のように女のうしろへ吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。』
ここで言われている『大水』(=水=川)とは何か。『大水』とは、すなわち多くの非再生者たちを意味している。何故なら聖書において、非再生者たちは、大水とか海により象徴されているからである。神はイザヤを通して、次のように言われた。『ああ。多くの国々の民がざわめき、―海のとどろきのように、ざわめいている。ああ、国民の騒ぎ、―大水の騒ぐように、騒いでいる。国民は、大水が騒ぐように、騒いでいる。』(イザヤ17章12~13節)黙示録17:15の箇所でも、この大水が『もろもろの民族、群集、国民、国語』だと言われている。つまり、聖徒でない者たちだということである。聖徒でない者たち、すなわち非再生者たちは、神が心の土台に据えられておらず、ゆらゆらと揺らいでばかりいるので、定まりのない大水や海に例えられているわけである。だからイザヤの書では次のように彼らについて言われている。『しかし悪者どもは、荒れ狂う海のようだ。静まることができず、水が海草と泥を吐き出すからである。「悪者どもには平安がない。」と私の神は仰せられる。』(57章20~21節)確かに神の前に悪しき存在である彼らは、その心において海や大水そのものであると言ってよい。これとは逆に、神を土台としている聖徒たちは、聖書において山に例えられている。彼らは神を土台としているので、山のように揺らぐことがないからだ。イザヤ書ではこう書かれている。『主に信頼する人々はシオンの山のようだ。ゆるぐことなく、とこしえにながらえる。』(詩篇125篇1節)それだから、ここで言われている『大水』を実際的な意味において捉えてはいけない。サタンが、実際の液体をその口から大量に教会に対して吐き出したとでもいうのか。そのようなコミック的空想は子ども向けのアニメだけにしてもらいたいものである。
ここで言われているのは、サタンが『大水』である非再生者たちを多く動員させて、荒野状態となった教会を滅ぼそうとした、ということである。水により『押し流そうとした』とは、すなわち非再生者たちにより教会を滅ぼそうとした、呑み込もうとした、踏み潰そうとした、無効化させようとした、という意味である。サタンは、荒野になった教会を非再生者たちを用いることで滅亡させようとしたのであった。ところでサタンという存在は、この時だけではなく、いつの時代であっても教会を滅ぼすためには非再生者たちを使う。何故なら、彼らはサタンが自分の意のままに動かせる存在だからである。キリストも言われたように非再生者たちとは、すなわち『父である悪魔から出た者』(ヨハネ8章44節)であって、『父の欲望を成し遂げたいと願っている』(同)。彼らは意識していようとも意識していなかったとしても、また抵抗したとしても抵抗しなかったとしても、結局はサタンの心を行わざるを得ない。何故なら、彼らにはサタンの霊があるからだ(エペソ2:1~2)。サタンが教会を滅ぼすためには、自分の霊に動かされる存在が必要であるから、どうしても自分の子である非再生者たちを使うことになるわけである。聖徒たちは神の子であってサタンの霊にはもはや支配されていないから、サタンにとっては非常に動かしにくく、むしろ逆にサタンが振り回されることにさえなってしまうぐらいである。聖徒たちがサタンの願い通りに教会を滅ぼす結果を生み出してまうのは、罪を犯す場合しかない。その罪とは、例えば買収とか賄賂とか妥協とか欲望とか、そういった類の悪徳のことである。このような場合、サタンは聖徒たちにより教会を滅ぼすことが可能となる。例えば、ある牧師が金と女に負けてしまい、自分の管理している教会を霊的に明け渡すというケースが、そうである。神の子であったアダムが神の国を破壊したケースも、これにあたる。アダムはサタンの誘惑に乗ってしまったので、自らの意思により神の支配を断ち切ってしまったのであった。
サタンが『川のように』非再生者たちを教会の『うしろへ吐き出し』たとは、どういう意味か。すなわち『うしろ』という言葉は何を言っているのか。この言葉は、そのことの後に事が行なわれたという意味である。すなわち、ここでは教会が荒野の状態となった後に、つまり時間的な後で、サタンが教会に非再生者たちを送り込んだということが言われている。要するに、ここでは「時間の後続」を「場所の後続」に言い換えているということである。だから、我々は、サタンが教会の場所的な意味における後方部分に人々を送り込んだなどと考えてはいけない。それは意味が分からないことである。何故なら、教会とは聖徒たちの霊的な有機体であって、そこには前も後ろもないからである。つまり、この『うしろへ』というのも秘密の言い方の一つである。黙示録には、このような難しい言い方をしている箇所が少なくない。黙示録は本当に謎解きパズルのようである。
【12:16】
『しかし、地は女を助け、その口を開いて、竜が口から吐き出した川を飲み干した。』
この箇所は、かなり難しい。ここで地が『その口を開いて』、サタンが送り込んだ非再生者たちを『飲み干した』というのは、一体どういう意味なのか。これは、つまり教会を破滅させるべくサタンの送り込んだ非再生者たちが、口を開いた地に飲み干されたあのコラたちのように無効化されたという意味である。既に知られている通り、コラとその一味はモーセに逆らって罪を犯したのだが、神の裁きとしてその口を開いた地に飲み干されてしまった。つまり地割れにより殺されたのである。コラたちはその死により、もはや何一つ出来なくなったのだから「無効化」されたといってよい。それと同様に、サタンに動かされた非再生者たちも教会に送り込まれたのだが、結局はコラたちのように全ての計略が徒労に終わってしまった。この非再生者たちは『大水』であるから、彼らが無効化されたことは、つまり開いた地に飲み込まれたのも同然であった。何故なら、水が地に飲み込まれたならば、水は地の中に下っていってしまうので、もはや何事にも使えなくなるからである。要するに、ここではコラたちが地に飲み込まれて死んだのも、サタンの大水たちが封じられたのも、無効化されたという点ではどちらも変わらないということが言われているわけである。ここで言われているのは、あくまでも象徴表現であって、実際にサタンに送り込まれた非再生者たちがコラたちのように地に飲み込まれて死んだというわけではないから、そのことには注意しなければいけない。「大水である者たちはコラたちが地に飲み干されたように無効化された。」このように理解すれば、この箇所は上手に読み解けることができる。この箇所はコラの出来事が頭の中に入っていないと、解釈できない箇所である。また当然ながら、たといコラの出来事を知っていたとしても、もし神の恵みがなければ、そのコラの出来事をこの箇所に関連づけることができない。というのも、あらゆる正しい知性的な結びつけは、神の恵みによらねば頭の中に生じてこないものだからである。
サタンは、この時に、神の摂理により完全に封じられてしまった。その期間は『1260日』であった。すなわち、それは紀元68年6月9日から70年9月までの間である。サタンが一定の期間だけ完全に封じられたというのは、20:1~6の箇所で言われているのと、全く同じである。更には、サタンがこの期間の後で聖徒たちに戦いを挑もうとしたと記されていることも、この12章と20章は全く一緒である(12:17~18、20:7~9)。見よ、やはり12章と20章の箇所は対応しているのである。対応しているからこそ、どちらのほうでも、言い方や見方こそ違えど、同一のことが言われているわけである。もし対応していなかったとすれば、このような同一性は見られなかったであろう。これは大変に重要なことだから、私は何度も繰り返して述べることを差し控えない。重要なことは、重要であるがゆえに、その重要性をよく認識できるように、また忘れたりしないように、何度も繰り返すことが許されていると私は思うのである。神も聖書の中で、そのようにしておられる。
この箇所から分かるように、神はこの期間が過ぎ去るまで、教会をサタンの鋭い牙から守られた。何故なら、この期間は、教会が神により養われる期間だからである(12:6、14)。『養われる』とは、「守られる」ということを意味しているのでなくて何であろうか。守られなかったならば、養われているとは言い難いからである。神は、このようにして、ご自身の教会を守り保たれるお方である。聖徒たちが消え去って荒野の状態となった時も、神は教会をこの地上から失わせられなかった。今まで教会は幾度となく滅ぼされようとしてきたが、神はその度に、摂理の恵みにより教会を教会のままの状態として保ち続けられた。今でもサタンは教会を滅ぼそうとしているが、サタンの非常な努力にもかかわらず、教会が滅ぼされることはない。何故なら、教会とは全能者であられる『キリストのからだ』(エペソ1章23節)だからである。全能者を滅ぼすことが誰にもできないように、そのお方の身体を滅ぼすことも誰にもできないのである。もし教会を滅ぼせるとしたら、その者は、神をも滅ぼすことができるであろう。
【12:17~18】
『すると、竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち、神の戒めを守り、イエスのあかしを保っている者たちと戦おうとして出て行った。そして、彼は海べの砂の上に立った。』
サタンが『女に対して激しく怒り』狂ったのは、サタンにおいては当然であった。何故なら、せっかく大水を口から川のように吐き出したのに、全てが徒労に終わったからである。このようなサタンは、思い通りに行かないので頭に血が上った抑制の効かない不良少年のようである。これは呪われている存在に相応しい反応であった。サタンは呪われているから、至福の神のように怒りを抑えることができない。怒りを抑えられないとは、神の性質を反映していないのだから、呪いでなくて何であろうか。それが呪いであるからこそ、ソロモンは箴言の多くの箇所で、怒りについて悪く言っているのである。何故なら、悪く言ったということは、それが呪いである証拠に他ならないからである。サタンは呪われているので、これまで怒ってきたし、今も怒っているし、これからも怒ることを止めない。サタン=癇癪。
『女の子孫の残りの者』とは、携挙により聖徒たちが消え去った教会に、後ほど新しく加えられた聖徒たちのことである。つまり、荒野の『1260日の間』に新しく聖徒になった者である。それは携挙された古い聖徒たちではない。だから『残りの者』とは、すなわち「後に加えられた者」という意味となる。「これは携挙されたのではない聖徒たちだ。私は携挙されてからクリスチャンになった者のことを言っている。そのことをよく覚えなければいけない。」ヨハネは、ここでこのように言っているかのようである。この荒野の期間に新しく聖徒が加えられたということについては、既に説明された通りである。サタンはこの新しい聖徒たちに戦いを挑むべく『出て行った』のである。『出て行った』とは、つまりそうすることを許可されたという意味である。『千年』である『1260日』が終わるまでは、サタンは封じられており『底知れぬ所』(20:1~3)に縛られている状態であったから、聖徒たちに戦いを挑むことはまだ許されていなかった。しかしその期間が終わると、封印が解かれて牢獄から出されたので、聖徒たちに立ち向かうことが許されるようになった。だからこそ、サタンは封印から解放されて後、聖徒たちと戦おうとして突進して行ったわけである。この解放と許可については、20:7の箇所が対応している。そこで『千年の終わりに、サタンはその牢から解き放され』たと言われているのは、42ヶ月の期間が終わったので、封印状態が解かれて、聖徒たちに攻撃を仕掛ける許可が出されたということである。この時にサタンが戦いを仕掛けたのは、地上にいた聖徒たちを滅ぼすためであった。サタンはイザヤの預言から間もなく自分に2度目の罰が下されることを知っていたのだが、それにもかかわらず、聖徒たちを滅ぼそうと試みた。それは、もしかしたら聖徒たちを滅ぼせるかもしれないと考えたからである。私の経験からも言えるが、サタンは決して希望を失わず、たとい絶望するような時であっても何とかして勝機を見出そうとする。彼は負けたくないので絶対に諦めないのだ。「これから2度目の罰があるのは分かっている。だが、俺は奴らに攻撃を仕掛けねばならない。罰があるからといって何もしないでいいものか。もしかしたら奴らを滅ぼせるかもしれないのだ。だから攻撃を仕掛けよう。全力を尽くせば神の計画も超えられるはずだから。」サタンはこのような精神状態で聖徒の陣営に突進していったわけである。ところで以上の説明からも、この12章と20章とが対応していることが分かる。何故なら、一定の期間が経過したらサタンが聖徒たちに戦いを挑むということが、どちらのほうでも言われているからである(12:17~18、20:7~9)。そこでは言われ方や見方がいくらか異なっているに過ぎない。
この時にサタンが攻撃を仕掛けた対象は、携挙の後に教会に加えられた新しい聖徒だけであったということに、注意せねばならない。彼らは本当に救われていたから、『神の戒めを守り、イエスのあかしを保って』いた。『女の子孫の残りの者』とは、この者たちのことを、この者たちのことだけを言っている。サタンは彼らを対象として戦いを挑んだ。つまり、私が言いたいのは、携挙されないで地上に残された不幸な毒麦どもは(参照―マタイ24:40~41)、攻撃の対象としては認識されていなかったということだ。彼らは毒麦だから、イエスのあかしをそもそも持っておらず、本当の意味で律法を守ったことは一度もない。つまり彼らは『女の子孫の残りの者』ではなかった。彼らはむしろ「サタンの子」であった。それゆえ、サタンが攻撃する際には、彼らを滅ぼす対象とはしていなかったはずである。自分の陣営に属する子らを滅ぼそうとすることが一体どうしてあるだろうか。ヨハネは確かに、ここで『女の子孫の残りの者』に対して『戦おうとして出て行った』と書いているのであって、「荒野の子である毒麦ども」に対して『戦おうとして出て行った』とは書いていない。
サタンが聖徒たちと『戦おうとして出て行った。』というのは、復讐の意味もそこにはあった。サタンは教会に恥をかかせられたので、怒り狂って、教会を復讐しに行ったわけである。「畜生。あいつらに攻撃が無効化されたので大いに恥をかかされてしまった。これでは俺のプライドが許しておけない。何としても教会を目茶目茶にしてやらねば気がすまない。さあ、俺の怒りを彼らによって晴らそう。」このような精神状態に基づき、サタンは復讐すべく突撃して行ったのである。ところでサタンは根本的に復讐する者である。彼は『復讐してはならない。』(レビ19章18節)という神の戒めを守ろうとせず、それを守る気も持っていない。何故なら、ヨハネも言うように『神を愛するとは、神の命令を守ること』(ヨハネⅠ5章3節)だからである。サタンは神を憎悪しているので、それを守ることがすなわち神を愛することとなる律法を常に犯し、常に律法に違反したことをするのである。サタンが律法に適うようなことをしていたとしても、それは大局的に律法に違反したことをするために過ぎない。つまり、より豊かに、より完全に律法に反した行為をするために、その過程の中で律法に適った行ないを仕方なく含める。そうしないと、より高い罪悪に繋がらないからである。神はより高い善を実現させるために悪をその過程に含ませると第2部で説明されたが、サタンの場合はこの逆なのである。しかし当然ながら、その過程に含まれている律法遵守はあくまでも外面的な遵守に留まるのであって、そこには神への愛が何もないことは言うまでもない。これは人間で言えば、凶悪犯罪者が大きな事件を犯す前に、笑顔になりつつ善行をすることによって、人々の目を欺くのと同じである。人々はまだ事件を犯す前の悪人が善行をするものだから、その悪人が良い人だと誤って認識し、何も危険視することがなくなる。しかし、実はその善行は騙すために行われたに過ぎないのであって、確かなところ善行とは言えず、むしろ悪と言われなければいけないものである。何故なら、それは巨大な悪に貢献する善の見せ掛けを持った悪なのだから。
サタンがこの時に聖徒たちと戦うために使ったのは、ローマ軍であった。この箇所で『海べの砂』と言われているのはローマ軍を指している。これはローマ軍が、海べにある無数の砂でもあるかのように大人数だったからである。それゆえ、この『海べの砂』を文字通りに捉える人は非常に愚かである。その人はお笑い芸人になれるかもしれない。サタンが海の場所に立ったことを記して何の意味があるのか。サタンが『海べの砂の上に立った』と言われているのは、サタンのローマ軍に対する支配を意味する。サタンはローマ軍を動かす本当の支配者であったということである。というのも『立った』とは上に位置することであって、支配のことだからである。霊的に言えば確かにそういうことになる。人の目からすれば、ローマ軍を支配していたのは将軍であるティトゥスであった。しかし究極的に言えば、サタンこそがティトゥスによりローマ軍を動かしている真の将軍であった。なお、この無数のローマ軍については20:8の箇所でも言われている。そこでも、やはりローマ軍が『海べの砂のよう』だったと言われている。
12章のほうでは、このローマ軍が出てきたところで話が閉じられている。『そして、彼は海べの砂の上に立った。』と18節目で書かれてから、それまで見せられてきた幻の流れが終了している。そして13章に入ると別の幻が始まっているのだから、12:18で一区切りつけられていることは誰の目にも明らかである。すなわち、12章ではローマ軍がサタンにより集められてから後の出来事については何も述べていない。しかし12章と対応している20章のほうでは、ローマ軍が集められてから後に起こる出来事についても述べられている(20:9~10)。そこでは聖徒たちを『取り囲んだ』ローマ軍が御言葉という火で霊的に裁かれ(20:9)、ローマ軍を動かしたサタンが2度目の罰を受けたと書かれている(20:10)。要するに、12章の最後の箇所である12:18は、内容的に言えば20:9に続くということである。このように理解すると、ますます黙示録がよく把握できるようになる。もうお分かりであろう。本当に12章と20章とは対応しており、またよく繋がっているのである。
これにて12章目の註解が終えられた。この12章目は、黙示録の中でもっとも難しい箇所である。それは、この章に比べたら、13章や6章が優しく感じられるほどである。この章が難しいのは、そこに書かれている隠喩や比喩があまりにも高度で霊的だからである。ここでは、あらゆる部分が秘密の表現に満たされている。普通に読んだのであれば、この章は絶対に正しく読み解けない。このように恵みにより、この章を解き明かせたことを神に感謝。私が解き明かせるのは、ただただ神の恵みによる。この神にこそ栄光と誉れとが帰されんことを。アーメン。(※)
(※)
後になってこの12章に関して幾らかの不信仰が私を襲ったので、私は神に、今までに持っていた理解で間違っていないのか問い合わせた。「今までの理解が神の御心に適った理解なのでしょうか…」と。そうしたら、やはり今までの理解が正しかったことを即座に悟った。というのも、祈りが聞かれたことにより、すぐにも悟りを得たからである。すなわち、『産んだ』(12:5)とは復活のことであり、『牧する』(12:5)とは携挙の後に起こる裁きのことであり、『引き上げられた』(12:5)とは復活後に起こる携挙のことであり、荒野の『1260日』(12:6)とは20:1~6の期間のことであり、サタンが『戦おうとして出て行った』(12:17)とは20:7~10の出来事のことである、ということを。この悟りにより、やはりこの12章は20章と対応していることを悟らされた。どちらも全く同じ内容が書かれていることを再認識したからである。それゆえ、この祈りにより、12章の見解は私のうちにますます確かなものとされたのであった。読者も、私のように本当に具体的に祈ってみるとよい。それが真摯な思いに基づいてなされた祈りであれば、私のように必ず悟りが与えられることであろう。
[本文に戻る]
第15章 ⑫13章:ネロと偽預言者についての預言
この13章は前の12章と繋がりを持っていない。これは絶対に理解しておかねばならない。少し考えてみれば、このことがよく分かる。すなわち、ネロが死ぬのは再臨の起こる復活の日である。その復活の日は、12章で言えば12:5の箇所にあたる。そこで『女は男の子を産んだ。』と書かれているのは、教会が復活した聖徒たちを生じさせることだから、つまりその日がネロの命日であったということである。だから、13章が始まる直前の箇所である12:18の時点では、既にネロが死んでいたことになる。そして13章に入ると、ネロが秘密の表現に包まれながら登場する。これは明らかに12章と13章に繋がりがないことを意味している。何故なら、もしこの2つの章に繋がりがあったとすれば、既に12:5で死んでいるネロが、あたかも死んでいなかったかのように再び13:1で登場するのは意味不明だからである。もし繋がりがあったとすれば、13:1で死んだネロが再び出てくることはなかったはずである。それだから我々は、12章と13章を分離し、それぞれ独立した章として捉えるべきである。もしこの2つの章が連続していると捉えると、この2つの章の内容を正しく読み解けなくなってしまうであろう。
13章は2話に区切って考えられるべきである。1話目は1~10節目までである。ここではネロおよびネロの大患難について記されている。2話目は11~18節目である。そこでは偽預言者と偽預言者がネロを人々に崇拝させることについて記されている。このように2話に区切って考えることは我々に有益となる。何故なら、区別の把握は理解の増進を促すからである。区別が曖昧であれば、それだけ理解も乏しくなったり誤ったりすることに繋がりかねない。
13章の章における区切り方は適切である。この区切り方には言うべきことがない。何故なら、この18節分は内容的に纏まっており、一つのブロックとして捉えるのが相応しいからである。
【13:1】
『また私は見た。海から一匹の獣が上って来た。』
『獣』はネロである(※)。これがネロだということについては、ここまで本作品を読み進められた聖徒たちは、もう十分に分かっているのではないかと思う。これがネロだというのは13:18の箇所を見れば明らかである。そこで言われている666とはネロ以外ではあり得ないからだ。その箇所に来れば、この666という数字について私は詳細な説明をするつもりである。
(※)
本質的な事柄ではないが、スエトニウスによれば「ネロ」とはサビニ語で「勇敢」とか「剛毅」を意味しているという(『ローマ皇帝伝(上)』第3巻 ティベリウス p229:岩波文庫)。
[本文に戻る]
『一匹』と書かれているのは、つまり「複数者ではない」ということである。この獣は一者、単体者、一つの存在であったということだ。だから、この箇所(13:1~10)を名付けるとすれば「ネロという個人についての説明」というものになるであろう。
『海から一匹の獣が上って来た。』とは、明らかにダニエル書7:3に基づいている(※)。これは、つまり黙示録13章に出てくるこの第一の獣が、ダニエル書7:1~28の箇所に書かれている夜の幻と関連していることを示す。どちらのほうでも海から獣が上って来たと言われているからである。詳しく言えば、このネロは、ダニエル書7章に出てくる第4の獣に生えていた1本の角である。このダニエル書は、黙示録の中では、もっとも対応している箇所が多い巻の一つである。ここでは『海から』と書かれているが、同じネロについて書かれた11:7では『底知れぬ所から』と書かれている。つまり『海』とはハデスを意味している。先にも言ったが、ネロはネブカデレザルが再来したかのように感じられる存在である。つまり、ここでは「あの死んでハデスに行ったネブカデレザルが再びネロという存在において這い上がってきたかのようだ。」と言われていることになる。確かにネロは、その権威といい、異常性といい、知名度といい、ネブカデレザルと似ている点を大いに持っていた。註解を読み進めていけば、ますます、このネロがネブカデレザルの再来だということがよく分かるようになるであろう。この理解は絶対に忘れてはいけない。これを理解していないと黙示録を正しく読み解けなくなるからである。
(※)
『4頭の大きな獣が海から上がって来た。』
[本文に戻る]
『獣』という言葉は、あくまでも象徴表現である。これを実際の動物であると捉える人は愚かというか、知性に根本的な問題があると思われる。それではネロが『獣』という表現により象徴されているのは何故か。後にも説明されることになるが、『獣』とは世界帝国および世界帝国の統治者を現わしている。実際の獣は、強く、獰猛であり、恐ろしく、打ち勝ちがたい存在である。世界帝国とその統治者も、実際の獣であるかのように思える存在である。何故なら、その権威や力があたかも野にいる獣のように抵抗し難いものだからである。だからこそ、ここではヨハネが生きていた当時の世界帝国であるローマとその統治者であるネロを現わすために『獣』という言葉が用いられているわけである。これはダニエル書7:1~8の箇所でも同様である。21世紀の今で言えば、この『獣』はどの存在になるだろうか。それはアメリカとトランプであろう。何故なら、今の時代ではアメリカが最強の国家であり、そこで国の統治者とされているのはトランプだからである。とはいっても黙示録は『すぐに起こるはずの事』(1:1)を記した預言書だから、そこではアメリカについては何一つ言及されていないのではあるが。
『これには10本の角と7つの頭とがあった。その角には10の冠があり、その頭には神をけがす名があった。』
先に説明されたように、ネロの持つ角と頭とは、サタンの持つ角と頭と同一であった(12:3)。これはネロとサタンに大きな関連性があることを示している。すなわち、これはサタンがネロに取り憑いたということを我々に教えるものである。
この角と頭の『秘儀』は17章で語られているのだが、17章の箇所になるまで待つことをせず、この13章の時点でそのことを書くことにしたい。というのも、この秘儀を17章まで謎のままにしておき、その説明を留保しておくのは、読者の理解のためには適切ではないからである。この13章は、角と頭のことが分かっていないと上手に理解できない。13:1、3、12、14~15がそうである。だから、17章の箇所を待たずに今ここで獣の持つ角と頭とを解き明かしておくのが望ましい。そういうことだから、17章の註解のほうでは、繰り返しがいくらか多くなり、また註解の密度も薄くなるはずである。今そこで書くべき事柄を先に書いてしまうのだから、これは仕方がないことである。17章まで説明を留保しておけば、17章のほうでは豊かに説明されることになるが、この13章のほうは17章が来るまで分からないままとなってしまうのだ。そうすれば「もやもや」した感じが17章に来るまで残ることにもなってしまう。このことをあらかじめご了承いただきたい。
さて、この13章は17章およびダニエル書7章と対応している。もし13章に書かれている角と頭を理解したいのであれば、そちらのほうも詳しく考察せねばならない。そうしなければ13章の角と頭を理解することはできない。この13章の説明だけでは十全な理解を得るためには不十分だからである。それは日本だけしか知らないので、世界全体を理解できないのと同じことである。世界全体を理解するには日本だけでなく世界全体の知識を得なければいけないように、角と頭を理解するためには13章だけでなく17章およびダニエル書7章をも考察しなければいけないのだ。
まず最初に、ネロの持つ角と頭は、先に出てきた『獣』という言葉と同じように、あくまでも象徴表現だということを言っておく。これを実際的なものだとするのは愚かである。本物の獣が実際的な10本の角と7つの頭とを持って登場したとでもいうのか。馬鹿げた空想は止めてほしい。これは初歩中の初歩だから、もうこれ以上書くことはしない。
『7つの頭』のほうから先に見ていきたい。ネロが『7つの頭』を持っていたとは何を意味しているのか。これは、ネロが7人の王の後に帝位に就く王であるという意味である。つまり、ネロの前には7人の王が存在したということである。だからこそ、ネロの身体には『7つの頭』が生えていたわけである。確かに、この『7つの頭』とは17:9によれば「王」である。そこでは次のように言われている。『7つの頭とは、この女がすわっている7つの山で、7人の王たちのことです。』すなわち、『頭』というのは世界帝国における頭(かしら)ということだ。17:11によれば、未来に現われるはずのネロは『8番目でもありますが、先の7人のうちのひとり』であった。黙示録では8番目の頭には何も言及されていないが、これはネロが7番目の後で登場する8番目の王であるという意味である。確かに、ネロは8番目であると同時に最初の1番目でもあった。どうしてネロが最初の1番目でもあるかと言えば、ネロは13:12の箇所で『最初の獣』が復活したかのような存在として描かれているからである。つまり、こういうことになる。ネロが8番目また1番目でもあったのは、1番目であるバビロンのネブカデレザル王が復活したかのような存在だったからである。1番目がネブカデレザルだったということは、1番目の獣について書かれているダニエル書7:4を見れば分かる。ここで獣に『人間の心が与えられた』と書かれているのは、理性を失ったネブカデレザルが『理性を取り戻した』(ダニエル4:36)ことでなくて何であろうか。実際には1番目のネブカデレザルは8番目のネロではないのだが、8番目のネロは1番目の王ネブカデレザルと同一視されている。ネロがネブカデレザルの再来だということは既に語られた。これで8番目と1番目が誰なのか確定された。さて、17:10によればヨハネが黙示録を書いていた当時における王は6番目であった。つまり5番目までの王は既に亡くなっていた。確かにヨハネは『5人はすでに倒れたが、ひとりは今おり』と書いている。既に明らかにされたようにネロが8番目だったのだから、6番目の王とは、ネロの2代前の統治者であるカリグラ帝である。私は先に黙示録はカリグラの時に書かれたと言ったが、それはこの理解に基づく。この17:10を解読すれば、黙示録の筆記年代はカリグラ帝の37~41年だったことが間違いないこととして確定されるからだ。そして8番目と6番目が分かったのだから、その中間は明らかである。すなわち7番目はネロの前であり、カリグラの後であるクラウディウス帝である。ヨハネはこのクラウディウスが『まだ来ていません』(17:10)と言っているから、黙示録がクラウディウス帝の前の時代に書かれたのは、ますます確かとなる。このクラウディウスが『来れば、しばらくの間とどま』(17:10)り、そうして後、遂に8番目のネロが登場するというわけである。これで6番目と7番目の王についても確定された。さて、今説明されたように6番目はカリグラであるから、5番目はカリグラの1代前の皇帝であるティベリウス、4番目はカリグラの2代前の皇帝であるアウグストゥスだということになる。これは誰でもすぐに分かることである。これで5番目と4番目も確定された。ここで注意しておかねばならないのは、ユリウス・カエサルは『7つの頭』には含まれていないということである。何故なら、彼は正式には王とは言えないからである。世にはカエサルも王として含める人がいるものだが、少なくとも聖書はカエサルを王として含めていない。もしカエサルを『7つの頭』に含めると、黙示録13章および17章を正しく読み解けなくなる。私はカエサルを含めて考慮してみたが、どうしても上手にいかなかった。よってアウグストゥスの前の統治者であるカエサルは3番目の頭ではない。もしカエサルも含まれていたのであれば、彼は3番目の頭であったことであろう。それで残るは2番目と3番目である。この2人の王は誰なのか。これは歴史を知っていれば簡単に分かることである(とはいっても分かるのはあくまでも神の恵みによるのであるが)。すなわち2番目はペルシャ帝国のキュロス、3番目はマケドニア帝国のアレクサンドロスである。何故こう言えるのだろうか。それは1番目がバビロン、4番目がローマだからである。1番目がバビロンで4番目がローマだとすれば、2番目と3番目は必然的にペルシャとマケドニアであると確定されねばならない。ダニエル書7:4~7では4つの獣=世界帝国が順番に出てくるが、これは地球上に出てくる4つの強大な世界帝国を時間の流れに沿ってそのまま記したものである(※これについては第4部で更に詳しく解明される予定である)。すなわち、バビロンがまず出てくるがペルシャによって滅ぼされ、ペルシャが世界の覇権を握るのだがマケドニアにより滅ぼされ、そのマケドニアがローマに滅ぼされてしまうということである。確かに通俗の歴史においても、世に出てくる世界帝国はこの通りとなっている。このように理解しない限り、2番目と3番目がどの存在なのか知ることはできない。よって私が今述べたように読者は考えるべきである。これで2番目と3番目が誰なのかも分かった。読者は、4番目までは別々の国とされていることを、よく覚えられたい。しかし4番目以降はローマで統一されている。もし4番目以降もそれまでと同じように別々の国であると捉えると、上手に理解できなくなるから注意せねばならない。4番目以降も別々の国でなければいけないとは、直接的にも間接的にも聖書では指示されていない。もし4番目以降も別々の国でなければいけないとすれば、私今現在の知識に基づいて言えば、5番目はローマが滅んだ後に出てくる「プロイセン」、6番目は世界中に植民地を持った「イギリス」、そして7番目は今現在における超大国の「アメリカ」だということになる。そうだとすると、これから出てくる8番目の獣、すなわち666の獣は日本になるのか?陰謀について詳しい人であれば8番目は「ユダヤ」または「世界統一国家」だと考えるかもしれない。しかし馬鹿げたことを考えるのは止めたまえ。黙示録には『すぐに起こるはずの事』(1:1)が書かれているのだから。私の述べたように考えれば黙示録には本当に『すぐに起こるはずの事』が書かれていることになる。しかし、8番目が日本だのユダヤだのワンワールドだなどと考えるのであれば、黙示録には『すぐに起こるはずの事』が書かれていないことになる。そのように考えるのは聖霊の言われたことに反抗する罪である。私は忠告するが、聖霊の言われたことに反する理解を持つのは止めたほうがよい。繰り返すが、確かなところ、4番目以降の存在がそれまでと同様に別々の国でなければいけないということにはならない。私の説明したように理解すれば、すんなりと理解できるのだから、無理に変なことを考えたりしてみずから自分を誤謬の闇へと陥れるべきではない。私の述べた説明には何もおかしいところがないはずである。というわけで『7つの頭』とはネロの前にいた7人の大統治者だったということが解明されたが、それを書き並べてみると以下の通りとなる。
第一の頭 バビロン・ネブカデレザル
第二の頭 ペルシャ・キュロス
第三の頭 マケドニア・アレクサンドロス
第四の頭 ローマ・アウグストゥス
第五の頭 ローマ・ティベリウス
第六の頭 ローマ・カリグラ
第七の頭 ローマ・クラウディウス
(第八の頭 ローマ・ネロ)
7つの頭には『神をけがす名があった』とは、つまり頭により示される世界帝国が、どれも神に反する国家性を持っていたということである。それは、ダビデが治めていた時のイスラエル王国のようではなかったということである。第一の王であるネブカデレザルは神を賛美しはしたが(ダニエル書4:34~35、37)、バビロンそのものがダビデのイスラエルのように神に喜ばれる国だったということではないから、このバビロンも『神をけがす名』を持つ存在であったとせねばならない。
次は『10本の角』である。ネロに『10本の角』が生えていたとは、どういう意味なのか。まず『10本の角』とは、「10人の王」のことである。ヨハネは17:12の箇所で次のように言っている。『あなたが見た10本の角は、10人の王たちで、…』。この10人の王たちは、第4の獣であるローマから出る王である。すなわち、それは第一の獣であるバビロンから出る王ではなく、第二の獣であるペルシャから出る王でもなく、第三の獣であるマケドニアから出る王でもない。それは、ダニエル書7:23~24の箇所で『第四の獣は地に起こる第四の国。…10本の角は、この国から立つ10人の王。』と書かれているからである。また、この10人の王はネロが皇帝の時には、まだ皇帝の座に就いていない人たちである。ヨハネが17:12の箇所で『彼らは、まだ国を受けてはいませんが』と、この10人の王について言っている通りである。この10人の人たちは、ネロが皇帝であることに反発しておらず、むしろそのことに完全に同意している。このことが、17:13の箇所では次のように言い表わされている。『この者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威とをその獣に与えます。』つまり、この10人の人たちとは、これから皇帝になるのだがネロが皇帝の時にはまだ皇帝にはなっておらず、ネロが生きている時に存在しており、またネロが皇帝であることを多かれ少なかれ良く思っている人たちである。何故なら、ネロが生きている時に存在していなければ、ネロに『自分たちの力と権威とを』与えることは出来ないからである。これで、まず『10本の角』について大まかなことが分かった。さて、この『10本の角』とは誰のことだろうか。よく聞いていただきたい。この言葉には秘密が隠されている。ダニエル書によれば、ネロという11番目の角は、この10本の角のうち3本の角を打ち倒す。こう書かれている通りである。『私がその角を注意して見ていると、その間から、もう1本の小さな角が出て来たが、その角のために、初めの角のうち3本が引き抜かれた。』(ダニエル7:8)『その頭には10本の角があり、もう1本の角が出て来て、そのために3本の角が倒れた。』(同7:20)『彼は先の者たちと異なり、3人の王を打ち倒す。』(同7:24)ネロが3人の王を打ち倒すとは、つまりネロはそれよりも前にいた3人の皇帝を遥かに凌駕した存在だという意味である。確かにネロは、ネロよりも前の3人の皇帝、すなわちティベリウス(2代目)、カリグラ(3代目)、クラウディウス(4代目)よりも巨大な存在であった。これは誰も疑わないことである。だから、ネロが3人の皇帝を凌駕していることを『倒れた。』とか『打ち倒す。』という表現で言い表わしているのは実に適切である。凌駕するとは、すなわちその偉大さにおいて打ち倒すことに他ならないからである。1代目のアウグストゥスはネロに凌駕されていなかったので、この3人の王の中には含まれていない。ネロが「暴君」の代名詞であるのに対し、アウグストゥスは「神君」の代表的存在だから―彼は「国父」という尊称を全国民から一致賛成されつつ捧げられている(スエトニウス『ローマ皇帝伝(上)』第2巻 アウグストゥス p155:岩波文庫)―、その名の巨大さや知名度また後世の人たちに言及される度合いは両者とも同等程度であると言える。だから、もしネロがアウグストゥス帝をも凌駕していたとすれば、ダニエル書では『3本』ではなく「4本」が引き抜かれたと言われていたであろう。要するに、この『10本の角』という言葉には秘密が隠されているのであって、『10本』とは言われているが、これは実質的に言えば「7本の角」である。つまり、ネロが皇帝の時には『角』が7本あったということである。黙示録には秘密の表現が多いということは、既に読者もお分かりであろう。黙示録は普通の書き方で書き記された文書ではないのだ。だから、10本が実は7本だったということに驚いてはいけない。それでは、この7人の王たちとは誰なのか。先にも述べたように、この王たちとはネロと同時代の人であって、まだ皇帝にはなっていないが、ネロが皇帝であることには反発していない。これは確実に言えることなのだが、この7人とは次に示す8人の中の7人である。①ガルバ(6代目:前3年12月24日―69年1月15日)、②オト(7代目:32年4月25日―69年4月15日)、③ウッティリウス(8代目:15年9月7日―69年12月22日)、④ウェスパシアヌス(9代目:9年11月17日―79年6月23日)、⑤ティトゥス(10代目:39年12月30日―81年9月13日)、⑥ドミティアヌス(11代目:51年10月24日―96年9月18日)、⑦ネルウァ(12代目:35年11月8日―98年1月27日)、⑧トラヤヌス(13代目:53年9月18日―117年8月8日)。14代目のハドリアヌス以降の皇帝は、ネロが死んだ後で生まれてきた人であり、ネロと同時代には生きていなかったから、考慮する必要はまったくない。さて、この8人のうち除外されるべき1人は誰なのか。私としては、13代目のトラヤヌスだと感じられる。何故なら彼は「5賢帝」の一人であり、キリスト教徒に寛大であり、ネロが皇帝に就いていたことをあまりよく思っていなかったのではないかと推測するからである。ネルウァもキリスト教徒には寛大であったから、もしかしたらネルウァが除外されるべき人である可能性もあるが、彼はあの「5賢帝」の一人としては数えられていないから、やはりトラヤヌスのほうが可能性としては高いのではないかと思われる。ひとます、ここにおいては便宜上、トラヤヌスが除外されるべき一人だったということにしておきたい。これで7人の王が誰だったのかということが、ほとんど完全に確定された。そういうことだから、この箇所でネロが『10本の角』を持っていたというのは、つまりネロは自分よりも小さい名しか持たない皇帝をその前に3人抱えており、自分に精神的な心服感情を持っている将来の皇帝を7人抱えているという意味である。つまり3つの角は故人であり、7つの角は現存する人たちであった。このように、この箇所は神の言葉である聖書に基づいて解されねばならない。すなわち理性に基づいて好き勝手な解釈をしてはならない。神の言われたことに基づかず、むしろ理性に基づいて解釈するのであれば、いつまで経ってもこの箇所を誤って解するばかりとなるであろう。実際、全ての人たちはこの箇所を理性的に解しているので、一向にこの箇所で言われている『角』のことを悟ることができておらず、それゆえ正しく語ることができていないのである。ルターも言うように「聖書の範例なしには信仰(の問題)では何事も主張してはならない」(『後期スコラ神学批判文書集』『第3章 ローマの信徒への手紙第7章の講解』 p277 知泉学術叢書6)のであって、カルヴァンも言うように「なにびとも、主から聞いたこと以外、自分で勝手に語ってはならない」(『新約聖書註解Ⅲ ヨハネ福音書 上』3:11 p94:新教出版社)のである。
それで、『その角には10の冠があ』ったのは、角である存在が、実に大きな王権を持っていたことを意味する。『冠』は王権を、『10』はその絶対性を言い表わしている。実際、これらの皇帝たちは絶大な権威を持っていた。この『10の冠』を持っていたのは、『10本の角』の全てであったと考えるべきである。10本のうち1本しか持っていなかったとか、5本または6本しか持っていなかった、などとその数を限定すべきではない。何故なら、確かにこれら10人の皇帝たちには全て大きな権威―『10の冠』―があったのだから。これを疑うことは決してできない。
【13:2】
『私の見たその獣は、ひょうに似ており、足は熊の足のようで、口はししの口のようであった。』
これは一体どういうことか。これは説明されねば分からない。ここで言われていることは、ダニエル書7:4~8の箇所を見れば分かる。そこでは、第一の頭であるバビロンとそのネブカデレザルが『獅子』(7:4)、第二の頭であるペルシャとそのキュロスが『熊』(7:5)、第三の頭であるマケドニアとそのアレクサンドロスが『ひょう』(7:6)として描かれている。そして先にも述べたように第四以降の頭はローマである。このローマとそのネロは、これら3つの王国を頭としてその身体に生えさせている。つまり、こういうことになる。「第四以降の獣であるローマまたその首領であるネロは、『しし』である第一のバビロンのように口で獲物を砕き、『熊』である第二のペルシャのような足で敵を踏みつけ、『ひょう』である第三のマケドニアのように恐ろしく打ち勝ちがたい存在である。」つまり、ここではローマとそのネロが、バビロンやペルシャやマケドニアのような存在だと言われていることが分かる。実際、ローマはこれら3つの国のような世界帝国であった。それは獅子や熊や豹のように獰猛で強かった。だからこそ、ここではローマがこれら3つの国のようだったと言われているわけである。この箇所はダニエル書抜きでは解釈不可能である。
ここでも他の多くの箇所と同様に、動物が象徴として用いられている。このように動物を通してある存在を言い表わすのは、実に適切である。何故なら、動物で言い表わすことで、その存在がどのような性質を持っているのかよく分かるからである。人であれ国であれ、何かの存在をこれほどまでに動物の例えで言い表わしている書物や文書は、聖書以外には見られない。
『竜はこの獣に、自分の力と位と大きな権威とを与えた。』
この箇所から、ネロの背景にはサタンの存在があったことが分かる。暴虐を行なうネロはサタンの働きかけにより出てきたのである。ここではサタンがネロに3つのものを与えたことについて書かれている。まずサタンは『力』をネロに与えた。ネロがあれほどまでに強大な力を持っていたのは、サタンから力を受けたからであった。だからこそ、ネロに逆らえるような人間が誰一人として地球上には存在していなかったのである。その力は、ネロの師匠であったあのセネカさえ、ネロの命により自殺させられてしまったほどである。セネカほどの者ですらネロの意思に逆らえなかったのだ。往々にして皇帝といえども母には逆らえないものだが、母であってもこの暴君を抑制させることはできず、むしろ逆に殺されてしまった。またサタンは『位』をネロに与えた。つまり、ネロが帝位に就けたのはサタンが望んだからであった。「こいつは皇帝になるのに相応しい。俺が働きかけるには調度良い性質を持っているからだ。こいつに入れば好きなように活動できる。大昔の時に蛇に入ったようにな。そうすれば聖徒たちのヤツらを悲惨な目に遭わせることもできるようになる。どれ、こいつを皇帝に就かせてやるとしようか。」サタンはこのような精神状態を持って、ネロがクラウディウスの後の皇帝になるようにと、ローマ全体に、特に元老院をはじめとした皇帝の周辺に自分の使いどもである悪霊を動員させて働きかけた。神がこのサタンの企みを許可されたがゆえに、ネロはサタンの働きかけによって大きな位を持つことになったわけである。だから、サタンなくしてネロに帝位はなかった。更にサタンはネロに『大きな権威』をも与えた。皇帝と呼ばれる存在でありながら、欠けた権威しか持たない統治者が、歴史において少なからず見られる。このような統治者は、有効に働く権威を持っていないので、実質的に言えば権威を持っていないのも同じである。それは、誰かが多くのお札を持っていたとしても、その全てがボロボロの状態になって使えないために、実質的には何もお金を持っていないのと似ている。しかしサタンはネロに有効に働く権威を与えた。だからこそ、ネロはあらゆる人が平伏するほどの絶大な権威を持っていたわけである。このような権威を持ったネロは得意げに言ったものである。「かつての元首は誰も、私にいま許されているような権限を知らなかった」(スエトニウス『ローマ皇帝伝(下)』第6巻 ネロ p177:岩波文庫)と。ネロの治世に生きていた者であれ後世の者であれ、ネロがこれら3つのものを持っていたことを疑う人は誰もいない。聖書はこの3つのものが他でもないサタンから出たものだったと教えている。なお、ヴァン・ティルは「ネロは、なお地上で生きている間に本物の悪魔にまで成長したかもしれない」(『ヴァン・ティルの十戒』第一戒 p45:いのちのことば社)と言っているが、実際にネロが悪魔になることはないにしても、このように言いたくなるぐらいにネロが暴虐に満ちていたことは確かである。
ここでネロの登場がサタンの働きかけによったと教えられているのは、パウロの言葉と合致している。パウロはⅡテサロニケ2:9で『不法の人の到来は、サタンの働きによる』と書いたが、これはネロが暴虐を行なう者として出てくるその背景にはサタンの存在があったということである。何故なら、サタンによりネロが到来するということは、すなわちサタンがネロに『自分の力と位と大きな権威とを与えた』ということを意味しているからである。もしこれら3つのものが与えられなかったとすれば、どうしてネロがサタンの働きにより到来できるであろうか。このⅡテサロニケ2章と黙示録13章に出てくる人物が同一人物だということは、既に第1部で説明された通りである。もし未だにこの2つの箇所で出てくる人物が同一の人物だと理解していない聖徒がいれば、すぐにも理解できるようにすべきである。そうしないと再臨の時期に起こる出来事について正しく把握できなくなってしまうから。
ところで神は一体どうしてサタンがネロに働きかけて暴虐を行なわせることを許可されたのか。神はサタンがネロに働きかけるのを禁止されることもお出来になったが、そうはされなかった。つまり、神の御心はサタンがネロに働きかけることだったということになる。神がサタンに許可を出されたのは、聖徒たちの信仰を試すためであった。すなわちサタンがネロに暴虐を行なわせるのを許すことで、その暴虐の中にあって誰が真の聖徒であるかが明らかになるようにされた。その暴虐の期間において、『最後まで耐え忍ぶ者』(マタイ24:13)は真の聖徒であることが判明したのだが、耐え忍ばずに背教してしまった者は呪われし者だったことが暴露されてしまった。これはアブラハムの信仰が明らかにされるために、大きな試練がアブラハムを襲ったのと同じことである。神がサタンの邪悪な働きを許可されたからといって、我々は神を悪く思ったりすべきではない。何故なら、神がこのような許可を出されたのは、聖徒たちに大きな祝福をお与えになるためだったからである。実際、サタンに取り憑かれたネロによる42ヶ月の暴虐が終わった後に、聖徒たちは復活して携挙され、キリストと共に永遠に生きるようになったではないか。至福の前に苦難あり。女も子を産む前には大きな苦しみを味わうものである。
【13:3】
『その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も直ってしまった。』
これは死んでしまったと思われていたバビロンのネブカデレザルが、ネロにおいて再来したということである。『打ち殺された』とはネブカデレザルが死滅したことを言っており、『致命的な傷も直ってしまった』とは死んでしまったネブカデレザルがネロにおいて再び出現したことを言っている。これは一旦理解してしまうと、もう何も難しいことがなくなる。しかし理解できない者は、いつまで経っても何も分からないままである。またネブカデレザルがネロにおいて再来したというのは、黙示録において繰り返して言われていることである(11:7、13:1、3、12、14、17:8、11)。事情を神の恵みにより理解している人は、この繰り返しの多さに必ず気付かされる。しかし理解できていない人は、何だか似たようなことが言われているとは感じても、頭の中には「?」マークが出るばかりで延々と明瞭な気付きを得られないままである。
今の聖徒たちは、この箇所をどのように理解するか。決して正しく理解することはできない。たとえ理解できていたと思う人がいたとしても、その理解は誤っている。何故なら、今の聖徒たちは、この箇所が未だに起きていないと思い違いをしているのだから。この箇所は、ネブカデレザルがネロにおいて再来したか、またはエピファネスがネロにおいて再来したか、のどちらかしか解釈のしようがない。唯一正しいと思われるのは、この2つだけである。この2つのうち後者のほうは誤りであるということは、既に11:7の註解の部分で語られた通りである。私は、この箇所を正しく理解しているつもりでいる教師たちに言おう。もしその理解に自信があるというのであれば、それを私に知らせよ。そうしたら、ここでその理解が間違っていることを証明するから。私には、神に恵みにより、そのことが必ず出来るだろう。何故なら、この箇所はネブカデレザルとネロにおいて考える他は正しい解がなく、それ以外の解釈は全て間違っているからである。邪悪だが哲学的な真理を多く述べたアレスター・クロウリーは言っている。「真理はひとつあり、しかもひとつしかない。他の一切の思考は虚偽である。」(『アレスター・クロウリー著作集1 神秘主義と魔術』<第4の書>魔術 杯 p156:国書刊行会)これは正にその通りであり、我々が今取り扱っている事柄でも同様のことが言える。それだから、これをネブカデレザルとネロにおいて捉えない全ての人は、誤っている。この箇所を納得できるように正しく解き明かしている人は、私の知る限りでは全く見られない。誰もネブカデレザルとネロにおいて、この箇所を捉えてはいないからだ。
『そこで、全地は驚いて、その獣に従い、』
『全地』とは慣用である。すなわち、これはローマ世界における全地のことである。何故なら、この箇所ではローマの皇帝であったネロに関わる事柄が書かれているからである。つまり、これはローマの支配と影響が全く及んでいなかった紀元1世紀の中国や日本における地は含まれていない。これはルカ2:1で書かれている『全世界』という言葉が、誰がどう考えても文字通りの全世界、すなわち地球全土でないのと同じことである。これについては既に第2部で説明された通りである。また『全地』とは「全地に住んでいる人々」という意味である。ヨハネは、ここで「に住んでいる人々」という言葉を省いている。だから、『全地』と書かれているからといって、ここでは地そのものについて言われているとか、またヨハネは地に感情を伴う人格が存在していたと考えていたなどと思い違いをしてはならない。聖書においてこのように省略された言葉が出てくるのは珍しいことではないから、まだこのことを知らない聖徒は、よく覚えておくのが益となるであろう。我々も、このような言葉の使い方をよくするものである。例えば日本に住む人々を良いと言う際に「日本はいいね。」などと言うように。
ローマの支配と影響が及ぶ場所に住んでいた人々は、死んでしまったネブカデレザルがハデスから這い上がってきたかのような存在であるネロを見て、大きな驚きを持った。それはネロが、ネブカデレザルのような権威と力とを持っていたからである。それは誰もが驚かざるを得ないほどのものであった。最近で言えば、それはヒトラーや太陽王のルイ14世に例えることができよう。この2人は誠に大きな権威と力とを持っていた。とはいっても、やはりネロはこの2人よりも凄かった。ネロはヒトラーやルイ14世の10倍ぐらいの権威と力があったと言ってよいのではないかと私には思える。何せネロをはじめとしたローマの皇帝は「世界の支配者」とか「全地の主」などと言われるぐらいだったのだから(※)。また人々はこの強大な存在であったネロに服従せざるを得なかった。それは巨大隕石が落下した際に衝撃を避けられないようなものである。巨大隕石が降ってくれば近隣に住む人々は衝撃で吹き飛ばされてしまうように、ネロという巨大隕石がローマの皇帝として降ってきた際には、誰もがその権威という名の衝撃に吹き飛ばされてしまったのである。ネロには誰もが従わざるを得なかったということは、書き残された歴史書を読めば知ることができる。彼を治められるのは神とサタンしかいなかった。
(※)
例えばスエトニウスの言葉では、アウグストゥス帝は「世界のすみずみまで国家を統治してい」(『ローマ皇帝伝(上)』第2巻 アウグストゥス p157:岩波文庫)たと言われる。ヘロデの子アンティパトロスも、ローマ皇帝について「全世界の指導者」(『ユダヤ戦記Ⅰ』Ⅰ xxxii3:633 p230:ちくま学芸文庫)と言っている。タキトゥスも「人類の主」(『同時代史』第3巻 68 p178:筑摩書房)と言っている。ローマ皇帝に対してこういう言い方がされるのは当時において一般的であった。
[本文に戻る]
【13:4】
『そして、竜を拝んだ。獣に権威を与えたのが竜だったからである。また彼らは獣をも拝んで、「だれがこの獣に比べられよう。だれがこれと戦うことができよう。」と言った。』
『彼らは獣をも拝んで』とは、人々の皇帝崇拝を指す。当時のローマ皇帝は、人々から崇拝の念を持たれていた。だから、もし皇帝に忠誠を誓わない者があれば、ただでは済まなかった。これは当時のローマ皇帝が死んだ後に神の列に加えられたことからも、多かれ少なかれ察することができよう(※①)。死後に神とされるというのは、つまり生前から既に―どの皇帝かによっても度合いが違うが―いくらかでも神格を伴った認識が持たれていたことを意味するからだ。そうでなければ死後に神とされることはなかったであろう。紀元1世紀のローマ事情を知っている人であれば、人々が皇帝を崇拝したと聞かされても、何も驚くことはないはずである(※②)。ヨハネは、ここで当時の人々が持っていた皇帝(ネロ)に対する過度な尊崇のことを言っているのである。
(※①)
スエトニウスはカエサルが死んでから神格化されたことについて言っている。「行年56歳であった。カエサルは神々の列に加えられた。そのように元老院が議決したばかりでなく、一般市民もそう信じたのである。」(スエトニウス『ローマ皇帝伝(上)』第1巻 カエサル p91:岩波文庫)ユスティノスも、ローマの元老院に宛てて次のように言った。「皇帝は永遠に神化されてしかるべきだと考えるあなたがたは、証人を立てて、火葬の薪のなかで燃えていたカエサルが天に昇天するのを見たと誓わせています。」(『キリスト教教父著作集1 ユスティノス』『第一弁明』21:3 p38:教文館)
[本文に戻る]
(※②)
ローマで皇帝崇拝が行なわれていたのは歴史の事実である。だが、ここではその真偽性について説明することをしない。皇帝崇拝について知りたければ、各自が歴史を学ぶべである。
[本文に戻る]
また、この箇所では、人々がネロを崇拝したのは、すなわちサタンを崇拝したのも同然だということが言われている。何故なら、『獣に権威を与えたのが竜だったから』である。先にも述べたが、ネロの背景にはサタンがあり、サタンなくして崇拝されるべき皇帝としてのネロは存在していなかった。だから、ネロに対して皇帝崇拝をすることは、サタンを崇拝することになるのである。当時の人々はもちろん実際的なサタン崇拝はしていなかったし、「あなたは竜であるサタンを拝んでいるぞ。」などと言われたら反発したことであろう。しかし霊的に言えば、ネロ崇拝はサタン崇拝なのである。つまり、こういうことになる。「サタンが権威を与えて働きかけたのでネロが出てきたのだから、人々がネロを拝むのは、サタンを拝むのも等しい愚行である。それは、もしサタンの意でなければ崇拝されるべき存在としてのネロは全くあり得なかったからだ。人々はサタンの意志による皇帝を拝んでいるのだから、確かにそういうことになる。またネロはサタンの化身だったのだから、ますますネロ崇拝はすなわちサタン崇拝なのだと言わねばならない。」これはキリストを見ることが、すなわち父なる神を見ることであるのと同じである(ヨハネ14:9)。何故ならば、キリストとは神の目に見える現われだからである(ヘブル1:3、コロサイ1:15)。また、これは神の僕を受け入れることが、キリストを受け入れることであるのと同じでもある(マタイ10:40)。何故なら、キリストは父なる神と共に、ご自身の僕のうちにおいて歩まれるからである(ヨハネ14:23)。また、これは王の使いを快く受け入れることが、王を快く受け入れることになるのと同じである。何故なら、王の使いとは王の一部なのだから。それと同様に、ネロを崇拝することは、サタンを崇拝することなのである。何故なら、サタンはネロにおいて自己を目に見える形で実際に現わしていたのだから。
人々が『だれがこの獣に比べられよう。だれがこれと戦うことができよう。』と言ったのは、ネロに対抗できる存在が誰もいなかったからである。ユダヤ人の軍隊はどうだったか。ユダヤ戦争を見れば分かるように、ネロの軍隊に完全に滅ぼされてしまった。中国であれば、どうだったか。既に述べたように、紀元1世紀の中国とローマは全く接点を持っていなかったので、たとい巨大な国だった中国がローマの対抗勢力になり得たとしても、中国とローマを比較するのは虚しいと言える。「もしこうだったら…」などと想定してみても、我々が今取り組んでいる黙示録の解読には、あまり関係がないのだから。では、それ以外の国や軍隊はどうだったか。確かなところ、ローマとその皇帝に対抗できる存在は全くいなかった。だから、ネロというローマの獣は、世界に君臨する最強無敵の王者だったということになる。
【13:5】
『この獣は、傲慢なことを言い、けがしごとを言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。』
『42ヶ月』については、もう説明する必要がないと思われる。これについては既に十分な説明がされているからである。
ところで今の聖徒たちは、獣がロスチャイルドだとかロックフェラーだとかその他の同類の者だなどと考えているのだろうか。最近でも、この獣について多くの聖徒が色々なことを言っている。世の中でロスチャイルドなどと獣を結び合わせている人たちは少なくないと思われる。しかし、そのように考えるのは気が狂っていると言わねばならない。馬鹿げたことだが、仮にロスチャイルドが黙示録13章の獣だとしてみようか。だとすると、ロスチャイルドが活動する『42ヶ月間』とはいつのことなのか。彼の一族が世界支配の陰謀を働いてきた期間はもう100年以上にもなるが、この『42ヶ月』はいつにあたるのか。100年以上の期間が『42ヶ月』だとでもいうのか。この期間は別の言い換えでは『一時と二時と半時』であり、つまり非常に短いことを示すものであるのだが…。我々は100年以上もの活動期間を『42ヶ月』として捉えねばならないのか。このように言われたら、ロスチャイルドが獣だと言っている人たちは恐らく何も答えられないであろう。それとも、まだロスチャイルドの『42ヶ月間』は到来していないというのか。つまり、これからこの支配の期間が到来するというのだろうか。とすると、彼らの一族はたったの少しの間だけ支配するために今まで多くの陰謀を積み重ねてきたことになる。何故なら、獣は『42ヶ月』が過ぎれば再臨のキリストに殺されてしまうのだから。たったの1260日だけ支配するために多くの努力と犠牲を彼らは払っているのか?世界支配を達成したらすぐにも殺されることになるために、一心不乱に世界に陰謀を働かせていると?馬鹿らしいことだ。そんな儚く虚しい支配のために努力と犠牲を払うとは、異常としか言いようがない。それは死刑を受けるために一生懸命頑張るようなものだ。これはロスチャイルドだけでなく、その他にも獣であると見做されることのある人物でも同様のことが言える。実に多くの人が獣だ獣だ、666だ666だなどと言っているが、誰一人としてその支配が『42ヶ月間』しかないことに言及していない。皆、無知であり何も聖書を読んでいないのである!!!それゆえ盲目な者たち。これからこの獣が現われるなどと考えたり、この獣は今既に活動中だなどと考えるのを止めなさい。そうしないと、いつまで経っても目が見えないままとなるであろう。私が述べているように、これはネロが少しばかり活動する期間だということを理解しなさい。そうすれば霊の目が開けて、私のように黙示録を正しく捉えることができるようになるであろう。
ネロには『傲慢なことを言い、けがしごとを言う口』が与えられた。だからこそ、ネロの口からは数々の忌まわしい言葉が出てきたのであった。しかし、この悪しき口をネロに与えたのは誰なのか。それはサタンであった。何故なら、『不法の人の到来は、サタンの働きによる』(Ⅱテサロニケ2章9節)からである。サタンが『自分の力と位と大きな権威』(13:2)とをネロに与えたのだから、同じように悪しき口もサタンから与えられたとすべきである。また、この口をネロに与えたのは、神でもある。何故なら、ネロに邪悪な口を与えたいというサタンの願いを許可されたのは、神だからである。すなわち、ネロに邪悪な口が与えられるのは神の御心であったがゆえに、神がサタンにより悪しき口をネロに与えられたと言うこともできる。神は、ご自身の聖なる目的を遂行されるために、サタンを通して人々に邪悪な口または心が与えられるようにされる。それはエルサレムを壊滅させるという御心が実現されるために、ローマ人たちの心にその御心を遂行させるための思いを神が起こさせたと言われていることからも分かる(17:17)。サタンが『ユダの心に、イエスを売ろうとする思いを入れていた』(ヨハネ13:2)のも、やはり神がそのようにすることをサタンに許可されたからであった。つまり、神はキリストが売られるという計画が達成されるために、サタンがユダに悪しき思いを与えることを望まれたということである。そうでなければ、どうしてユダはキリストを売るという邪悪な思いを持てたであろうか。このローマ人とユダの場合は、心について言われているケースであるが、これは当然ながら口の場合でも同様のことが言える。我々は、神がサタンを通してネロに悪しき口を受けさせたことを非難してはならない。もしこのことが非難されるべきだというのであれば、神がユダに悪しき思いを与えられるようにされたことについても同様に非難されねばならないはずである。だが、神が悪い思いをユダが受けるように許可されたことを非難する聖徒がどこにいるであろうか。確かにユダが悪しき思いを持ったこと自体は非難されるべきことではあるが、しかし今まで神がそのような思いをユダが受けるようにされたのを非難したまともな聖徒は誰もいなかった。もし神が人間に悪しき口や心を持つことを許可されるのを非難する人がいれば、むしろその人自身のほうが非難されねばならない。何故なら、その人は神の御心を愚かにも非難する不敬な者なのだから。
良いことを話す口も、やはり神の御心により与えられる。しかし、こちらのほうは悪しき口とは違い、サタンを通して与えられるのではない。また、悪しき口が呪いのゆえに与えられるのに対し、良いことを話す口は恵みにより与えられる。何故なら良いものは全て恵みによらねば与えられることがないからである。ヨハネ3:27。キリストは『その口に何の偽りも見いだされ』(Ⅰペテロ2章22節)なかったが、人としてのキリストが正しい聖なる口を持っておられたのは、父なる神が人としてのキリストにそれをお与えになったからであった。悪しき口を与えられた者はネロのように悪しきことを話すが、良い口を与えられた者はキリストがそうされたように良いことを話す。悪しき口を受けた者は多くいるが、良いことを話す口を与えられた者はあまり見られない。良き口を与えられた者は、誠に幸いであり、非常に恵まれている。何故ならキリストがパリサイ人に対して言われたように、『あなたが正しいとされるのは、あなたのことばによるのであり、罪に定められるのも、あなたのことばによる』(マタイ12章37節)からであり、またソロモンも言うように『死と生は舌に支配される』(箴言18章21節)からである。ネロは『傲慢なことを言い、けがしごとを言う口を与えられ』たのだから、不幸の極みであった。
【13:6】
『そこで、彼はその口を開いて、神に対するけがしごとを言い始めた。すなわち、神の御名と、その幕屋、すなわち、天に住む者たちをののしった。』
これは『42ヶ月間』においてネロがなした邪悪なことである。すなわち、ここでは、あの大迫害の時に、神とその聖徒たちが大いに罵られたことを言っている。この大迫害は、既に言われたように、紀元64年のローマ大火の罪をキリスト者たちになすりつけることで始まった。その大迫害をネロが行っている際に、ネロが神とその聖徒たちに悪い言葉を吐いたということは、頭の悪い人でも容易に推測できることである。何故なら、罪を誰かになすりつける際には、往々にして罵りの言葉が伴うものだからである。それは、本当は罪を犯していない者たちを悪く言うことで、その者たちから名誉と尊厳を奪い、本当にその者たちが罪を犯したのだと周りの人たちに思わせるためである。この時の罵りが、どのような内容だったかは不明である。しかし不明であるからといって、ネロが聖徒たちを罵らなかったということにはならない。何故なら、この箇所ではネロが聖徒たちを『ののしった』と書かれているからである。我々は、ネロが聖徒たちを『ののしった』ということを知るだけで、よしとすべきであろう。これこそ正にネロに与えられたその悪しき口が愚かにもなしたことであった。
この箇所では、聖徒たちが二通りの言い方で言われている。一つ目は『幕屋』である。これは、聖徒たちが神の住まう幕屋だからである。パウロがⅠコリント3:16~17の箇所で聖徒たちを『神の神殿』と言ったのと同じ意味である。聖徒たちが神の幕屋また神殿であるということは、既に説明された。二つ目は『天に住む者たち』である。これは、聖徒たちが希望において、地上にいながら既に天の座に座っているからである(エペソ2:6)。しかしながら、ネロが大迫害をした際、天上にいる聖徒たちに向かって吠えかかったというのではない。ネロが意識していたのは、あくまでも地上にいる聖徒たちであった。恐らくネロは天にいる聖徒たちのことなど、まったく意識していなかっただろうと思われる。
この箇所と対応しているダニエル8:10の箇所では、聖徒たちが『星の軍勢』と言われている。我々が今見ている箇所では『天に住む者たち』と言われているが、聖徒たちとは希望において天に座しているのだから、地上にいても『星』と言い表わされるのは実に適切である。何故なら、天に位置しているというのは、つまり『星』に他ならないからである。ダニエル書のほうでは、この『星』である聖徒たちが地上に落とされるという表現で、その大迫害の凄まじさを語っている。というのも星が天から地に落ちるというのは、あり得ないことであって、正に悲惨そのものだからである。しかし実際には既に述べたように、聖徒たちが天上の地位から降下させられたということを言っているわけではない。
【13:7】
『彼はまた聖徒たちに戦いをいどんで打ち勝つことが許され、また、あらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。』
ネロが『聖徒たちに戦いをいどんで打ち勝つ』ことが出来たのは、神がそれを『許され』たからであった。神は、聖徒たちが苦しむこと自体を望まれたのではなかった。何故なら、『神は愛』だからである。パウロもローマ13:10の箇所で言うように、『愛は隣人に対して害を与えません』。神は愛なのだから、聖徒たちが単に害を受けることだけを求めてネロに許可を下されたのではない。神が許可を出されたのは、その苦しみの後に出てくるもののためであった。それは、大患難の苦しみが教会にもたらされることにより、真の聖徒が誰なのか明らかにされるという目的のことである。神はこの目的を見据えておられたからこそ、ネロが聖徒たちに勝つことをお許しになられた。もし単に聖徒たちが苦しむだけに過ぎないのであれば、神はネロに許可を出されなかったはずである。よって、我々は神がネロにこのような許可を出されたことについて、悪く思ったり言ったりしてはならない。神は、聖徒たちに対する憎しみのゆえに、このような大患難を許可されたわけではないのだから。
神の許可によるこのネロの苦難こそ、正に『「荒らす憎むべき者」が、聖なる所に立つのを見たならば』(マタイ24章15節)とか、『神の宮の中に座を設け』(Ⅱテサロニケ2章4節)とか、『彼は、…いと高き方の聖徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、聖徒たちは、ひと時とふた時と半時の間、彼の手にゆだねられる。』(ダニエル7章25節)などと預言されたことであった。これらの聖句は、どれもネロが42ヶ月間の間に、聖徒たちを蹂躙することを言っている。すなわち、そこではネロが聖徒たちに対する支配権を握って、あたかも奴隷であるかのように聖徒たちを苦しめると言われているのである。確かにこの期間において、ネロは神でもあるかのように聖徒たちの上に立って蹂躙の悪を行なった。誰がこのことを疑うであろうか。この出来事を題材とした多くの絵画でも、その蹂躙の様子が描かれているが、その描写は完全に現実と一致しているとまではいえないものの大体においては正しいのである。
『あらゆる部族、民族、国語、国民』とは慣用的な表現だと捉えねばならない。ネロの支配が、中国人や日本人にまで行き渡っていなかったことは明らかなのだから。
さて、ここで一つの疑問が生じるかもしれない。それは、こういう疑問である。「ネロは42ヶ月の蹂躙期間が始まる前までにも諸国の民を支配する権威を持っていたはずだが、42ヶ月が始まってから初めて諸国の民を支配する権威を持ったかのように、ここで言われているのは何故なのか。」この疑問を解決するのは容易い。我々は、ここではネロに初めて支配の権威が与えられたことが言われているのではなく、既にネロが持っていた支配の権威が更に強化されたと言われていると考えるべきである。つまり、ここで言われているのは「更に強力な権威が与えられた。」ということだと考えるべきである。こう考えれば、この箇所に何もおかしなことはなくなる。実際、ネロが聖徒たちを蹂躙したことにより、彼の持っていた『あらゆる部族、民族、国語、国民』に対する権威は更に強まったはずである。何故なら、蹂躙の出来事は聖徒たち以外の人々にとっても恐るべきものだかったからである。往々にして恐怖の増加は、支配の強まりに繋がるものである。何故なら、恐怖が増せば、それだけその存在が脅威的に感じられるようになるからである。聖書をよく読み慣れた人であれば、聖書には難しい言い方や誤解を招く言い方が満ちていることを既に知っているはずである。この箇所もその一つだ。それゆえ、ここで分かりにくい言い方がされていたとしても、問題ありとすべきではない。更に豊かな支配の権威が与えられたことを、『あらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。』と言ったとしても、何か間違ったことが言われているわけではないのだから。
【13:8】
『地に住む者で、ほふられた子羊のいのちの書に、世の初めからその名の書きしるされていない者はみな、彼を拝むようになる。』
ここで言われている『地』も、やはり慣用である。当時はローマ世界が「全世界」として見做されていたのだから、これはネロの支配が及ぶ範囲における『地』という意味である。もしこれを文字通りの地球全土として捉えたいのであれば、その人はルカ2:1に書かれている『全世界』という言葉も文字通りの地球全土だったと捉えたらよろしい。そんなことをすれば、自分が愚かであることをみずから言い表わすようなものである。
『ほふられた子羊のいのちの書』とは、キリストの贖いにより救われるようにと選ばれている者たちの定めのことである。すなわち、この子羊の書に名が書かれているとは、その人が永遠の昔からキリストにより救われるように定められているということである。逆に、この書に名が書かれていないとは、救われるように定められていないということである。この書は3:5の箇所でも出てきた。聖書でこの書は多くの箇所において語られている。この書は、あくまでも聖徒たちの救いの選びを象徴的に言ったものだとせねばならない。神が実際に物理的な書を持っておられるというのではない。何故なら、神はいちいちそのような書を参照しなくても、ご自身の選ばれた者たちを完全に知っておられるのだから。また、この書にその名が書き記されるのは、ただ神の御心による。誰かがこの書に名を書き込まれたのは、神がそのように望まれたという理由以上には我々に知らされていない。だから、聖徒たちの選びについて無用な詮索をして、自分を理解の闇へ陥れるのは望ましいことではない。これについては、カルヴァンの『キリスト教綱要』で詳しく論じられている。
この『いのちの書』に名が記されていなかった者たちは、大迫害の際、恐れを抱いて背教したので、教会の中にいる者でありながら『彼を拝む』に至った。この時の世界は、今のようにまだキリスト教が一般的な宗教とはなっておらず、「クリスチャン」という呼び名を持っていること自体が罪であった。すなわち、「クリスチャン」は罪そのものであった。だから当時の聖徒たちは、ネロにより差し向けられた刺客たちから、次のように二者択一を迫られたと推測される。「ネロか死か選べ。」もしネロを皇帝として崇拝するならば死は免れるがキリストを否まねばならない一方、ネロを崇拝しなければキリストを否まずに済むものの死を味わうこととなった。この時、『子羊のいのちの書』に名が書かれていた聖徒たちはキリストを告白してネロを崇拝しはしなかったが、その書に名が書き記されていなかった者はネロを拝んでしまったわけである。ああ、選ばれていない不幸な者たち!邪悪な被造物を万物の創造主よりも優先させるという、この忌まわしい惨めさ!彼らがこのような悲惨に陥ったのは、救われるようにと選ばれていなかったのがその理由であった。この時にネロを拝んだ者たちは、悔い改めることができなかったと思われる。つまり、あのペテロのように悔い改めて再び神に立ち帰ることは、もはやできなかったはずである。何故なら、ペテロはキリストを否んだだけだが、この時にキリストを否んだ者たちは、キリストを否んだ上にネロを崇めたからである。これは主権者をネロに鞍替えすることだから、致命的な罪である。確かに、この箇所では『いのちの書に、世の初めからその名の書きしるされていない者』が、実にこの者たちこそが、ネロを『拝むようになる』と言われている。つまり、『いのちの書』に名が書かれていれば、そもそもネロを拝むことはあり得なかったということだ。だから、この時の罪は、聖句から言っても許されない罪だったと考えるのが望ましいと私は思う。それで、この時にネロに対して皇帝崇拝をしてしまった偽善者たちは、すぐ後ほど起きたキリストの再臨の時に(これは68年6月9日のことである)、復活の恵みに与かれず、他の恵まれた人たちのように携挙されることもなく地上に情け容赦なく残されてしまった(参照―ルカ17:34~35)。彼らは地上に残されたので、再臨されたキリストとそこに集められた聖徒たちを見上げながら、大いに嘆き悲しんだのである(マタイ24:30)。この時にネロを崇拝した者たちは、自分がネロを崇拝したことについて、その責任を自分で負わねばならなかった。すなわち、彼らは次のように言って自分の悪を神に押し付けることができなかった。「私がネロを崇拝してしまったのは神が私を『いのちの書』に書き記しておられなかったからだ。だから私はネロを拝んでしまったのだ。全ては神の定めが実現させたことである。だから私がネロを拝んだことに責任はない。その責任は、私がそのようにすることを定めた神が負うべきである。」確かに彼らが『彼を拝むようになる』のは神が永遠の昔からお定めになったことだが、それでも不敬虔の罪を犯したのは当人たちなのだから、その責任を回避することは全くできない。それは殺人の罪を犯した者が、「私が殺人をしたのは神がそのように定められたからだ。だから私は罪の刑罰を受けるべきではない。」などと弁明しても刑罰を避けることができないのと同じである。
この大迫害の時に起きたことこそ、正にキリストが言っておられたことであった。すなわち、キリストはこのように、あらかじめ言っておられた。『ですから、わたしを人の前で認める者はみな、わたしも、天におられるわたしの父の前でその人を認めます。しかし、人の前でわたしを知らないと言うような者なら、わたしも天におられるわたしの父の前で、そんな者は知らないと言います。』(マタイ10章32~33節)つまり、この時に『彼を拝む』ことをしてキリストを否んだ者は、紀元70年9月に大審判が起きた際、自分も御父の前でキリストから否まれてしまった。しかしネロを拝まないでキリストの名を告白した者は、あの大審判の際、自分もキリストから御父の前でその名を口にしていただくことができた。この大審判とは、すなわちマタイ25:31~46また黙示録20:11~15に書かれている出来事のことである。この時、キリストを告白した者は羊として右により分けられ(マタイ25:34~40)、ネロを崇めた偽善者は山羊として左により分けられた(同25:41~45)。このことから、キリストは報いられるお方であるということが分かる。キリストは人がした通りの行ないを、その人にそのまま返される。オバデヤ15で、『あなたがしたように、あなたにもされる。あなたの報いは、あなたの頭上に返る。』と書かれている通りである。であるから、我々は、もしキリストを退けるならば、キリストからも退けられるであろう。その場合、我々が天とそこにおられるキリストに受け入れられることはない。しかし我々がキリストを拒まないのであれば、キリストも我々を拒まれないであろう。その場合、我々は天とそこにおられるキリストに快く受け入れていただくことができる。
【13:9】
『耳のある者は聞きなさい。』
あの言葉が再び出てきた。これは、つまり分からない人はそのまま分からないでいなさい、ということである。紀元1世紀における『アジヤにある7つの教会』(1:4)にいた聖徒たちのうち、『耳のある者』はこの13章で言われていることが、キリストの預言されたあの『荒らす憎むべき者』(マタイ24:15)についてだと悟ったはずだが、耳のない者は一体なにが言われているのか悟れなかった。耳のない者たちは恵みを受けていないので、恵みをいつまで経っても受けられず、分からないままの状態に留め置かれた。しかし彼らは恵みを受けないように定められていたのだから、たとえずっと分からないからといって、神に文句を言うことはできなかった。この語りかけは、21世紀に生きる我々に対しても言われていると考えるべきである。今の時代に生きる聖徒たちのうち、『耳のある者』はこの13章で言われているのはネロのことだということを悟るのだが、耳のない者たちは、この章ではロックフェラーだとかロスチャイルドだとかEUのトップだとか世界政府の首領について預言されていると思い違いをしてしまう。そのような人たちは恵みを受けていないので、いつまで経っても、この箇所が分からないままである。すなわち、既に起きた出来事が未だに起きていないと勘違いをし続けてしまう。しかし彼らは恵みを受けて黙示録を悟ることがないようにと定められているのだから、たとえずっと分からないままに留め置かれたとしても、神に文句を言うことはできない。この言葉が出てくるのは、黙示録ではこの箇所が最後となる。
ところで、どうしてヨハネは文章であるにもかかわらず『耳のある者は聞きなさい。』と言っているのか。これは文章であって読むものだから、「書かれたことを悟りなさい。」と言うべきではなかったのか。「読む」にもかかわらず「聞く」のだろうか。文章は音なのだろうか。これは全く問題にはならない。何故なら、ヨハネは1:3の箇所で、この文書を『朗読』するべきだと紀元1世紀当時の聖徒たちに対して言っているからである。『朗読』されたら口から出された声を耳で聞くのだから、ヨハネが『耳のある者は聞きなさい。』と書いたのは何も問題ではないことが分かる。またヨハネは、キリストの言葉をここでそのまま使っている。キリストもこの言葉をよくお語りになられた。これは聖徒たちに、より豊かにそこで書かれていることを注目させるためであった。何故なら、聖徒であれば誰でも、キリストの言葉がそのまま使われていたならば、より豊かに心を傾けることになるからである。だからヨハネがここでキリストの言葉をそのまま使用したのは、実に効果あることであった。よって、ヨハネがここで『耳のある者は聞きなさい。』と書いたのは、尚更のこと、全く問題にはならないことが分かる。
【13:10】
『とりこになるべき者は、とりこにされて行く。』
これは、ネロに殺されるようになるべき者が、全て例外なくネロの虜にされて殺されてしまうということである。それは、永遠の昔から、そのようになることが定まっていたからである。神の定めはこの世で最も強い力であり、誰もその定めに逆らうことができない。だから、ネロの虜にされるようにと定められていたが最後、その人にはネロによる死が運命として待ち受けていたのであった。先にも述べたが、この時にどれだけの人がネロに虐殺されたかは不明である。また、この時には、それぞれ人によって異なる仕方で虜にされたのは間違いない。ある人は歩いて死刑場まで連れて行かれただろうし、別の人は抵抗するのでズルズルと引かれただろうし、一旦気絶させられた者もいたに違いない。しかし、最後にはネロによる死が待ち受けているという点では、どの人も変わらなかった。その最終地点である死に引き行かれるまでの様子は、人それぞれその定めにより異なっていた。これとは逆に、『とりこになる』ようにと定められていない人は、どのようにしても『とりこになる』ことはなかった。何故なら、その人の場合、「とりこにされないこと」がその定めだったからである。だからネロに殺されないように定められている人は、たとえネロの兵士たちにどれだけ侮辱的な挑発行為をしたとしても、神の摂理が働き、決して死ぬことがなかった。その人がネロにより死ぬのは、神の定めのゆえに、あり得ないことだった。あのアントニウスも、聖徒たちが殺されるべく連行されていくのを引き止めようとして大胆に抗議活動をしたものだが、その激しい振る舞いにもかかわらず、少しの危害さえも加えられることなく生かされ続けた。要するに、このアントニウスであれネロの期間における聖徒たちであれ、「とりこにされない者は、とりこにされない。」ということになるのである。これは、この箇所で言われていることとは逆のパターンである。
この箇所からも分かるが、我々は、この世では全てが定めにかかっているということを再び思い返すべきであろう。あれも、これも、どれも、みな、この世では神の定めによって起こる。例外は一つさえもない。だから、パウロはこう言っている。『すべてのことが、神から発し、神によって成り、神に至る』(ローマ11章36節)。この世に偶然はないのである。当然ながら、ネロにより殺されるべく虜にされた人たちについても、このことが言える。
この箇所はエレミヤ15:2に基づいている。そこで神はこう言っておられる。『主はこう仰せられる。死に定められた者は死に、剣に定められた者は剣に、ききんに定められた者はききんに、とりこに定められた者はとりこに。』このエレミヤ書のほうでは堕落したイスラエル人について預言されたのに対し、我々が今見ている箇所は愛されたキリスト者たちについて預言されているから、内容的には取り扱っている対象が異なるが、しかし言い方は対応している。ヨハネがこのエレミヤ書の箇所に基づいて、『とりこになるべき者は、とりこにされて行く。』と書いたのは疑えない。また、ここで言われていることは、同じエレミヤ書の43:11の言葉ともよく似ている。そこでは次のように書かれている。『彼は来て、エジプトの国を打ち、死に定められた者を死に渡し、とりこに定められた者をとりこにし、剣に定められた者を剣に渡す。』
『剣で殺す者は、自分も剣で殺されなければならない。』
これはネロのことである。すなわち、ネロが紀元68年6月9日に剣で死んだことである。これについては既に第1部で見た。ネロは、剣により多くの者を殺したので、自分も自分の剣および解放奴隷の剣によって殺されるに至った。この箇所が、聖徒たちに言われたものだと考えるべきではない。すなわち、聖徒たちがネロの軍隊に反逆するのを阻止しようとして、「いいか、もしあなたがたが兵士たちに反逆して殺人をするなら、やがてあなたがたも同じように殺されることになるぞ。だから、そんなことをしては駄目だ。」などと言われたと考えるべきではない。何故なら、そのようなことは既に聖徒にとっては当たり前のことだからである。小プリニウスがトラヤヌス帝に宛てた手紙を見れば分かるように、紀元1世紀頃の聖徒たちは実に平和であり、正におとなしい羊と呼ぶべき存在であった。そのような聖徒たちに対し、あえて反逆による殺人行為を阻止すべく何かを言う必要はなかったはずである。
この箇所からも、神が報いられるお方だと我々は知ることができる。神は、その人の行ないを、鏡のようにその人に返される。そのように報いることで、神はご自身が公正な審判者であられることをお示しになられる。だから、ネロが剣で殺されたことについて、ネロは文句を言うことができなかった。何故なら、ネロは自分のした悪の実を、みずからの手で刈り取っているに過ぎないのだから。この神の報いは殺人以外の全てのことでも同様である。すなわち、盗んだ者はいずれ自分も盗まれ、騙した者はいつか自分も騙され、傷つけた者はやがて自分も傷つけられる。因果応報。これが神の原理であり、この世の法則である。だから、将来の悲惨を避けたいと思う聖徒たちは、悲惨という果実を実らせる悪の種を蒔かないようにすべきである。悪の種は、やがて時が経ってから実を結び、自分の身に帰ってくるのだ。アドニ・ベゼクが手足の親指を切り取られたのが良い例である(士師記1:5~7)。
この箇所で言われていることは、聖書の他の箇所でも多く言われていることである。その箇所は既に第1部で説明されているから、ここでは聖句箇所を挙げるだけに留めたい。すなわち、創世記9:6、レビ記24:17、マタイ26:52などがそうである。
『ここに聖徒の忍耐と信仰がある。』
このネロの大患難により、聖徒たちの『忍耐と信仰』が試された。真の信仰が与えられていた聖徒たちは、しっかりと忍耐し、最後まで信仰のうちに留まり続けた。彼らはそのようにして、自分たちに真の信仰が与えられていたことを、みずから証明した。他方、真の信仰を受けていなかった毒麦どもは、ネロの苦難に忍耐できず、信仰から離脱してしまった。彼らはそうすることで、自分には本当の信仰が与えられていなかったことを、みずから証明した。神は、このように聖徒たちを試されることで、聖徒たちの持つものを浮き彫りにさせるお方である。それは、あたかも金を精錬するようなものである。真の信仰が与えられた者たちは、その試みにより金が火で焼かれても朽ちないように堅固な信仰を持っていたことを明らかにするが、そうでない者たちは金を持っていなかったので、その試みにより自分たちが持っていたのは草やワラに過ぎなかったことを明らかにする。何故なら、もし金が与えられているのでなければ、草やワラを持っていることになるからである。
ここで言われている『忍耐と信仰』という2つのものは表裏一体である。すなわち、忍耐できるのは信仰があるからであり、また信仰があるならばしっかりと忍耐できる。一方、忍耐できないのは信仰がないからであり、また信仰がなければ忍耐することは原理的に難しい。つまり、忍耐なくして信仰なし、信仰なくして忍耐なし、というわけである。
【13:11】
『また、私は見た。もう一匹の獣が地から上って来た。それには子羊のような2本の角があり、竜のようにものを言った。』
ここから偽預言者が出てくる話に切り替わる。とはいっても、ネロが全く出てこなくなったというわけではない。ただ、この2話目では、偽預言者が基点として話が進められているだけである。こちらのほうでも、やはりネロは重要な位置を占めている。この2話目は1話目と量的には、あまり変わらない。最後の18節目では、誠に重要な理解をもたらす内容が書き記されている。この18節目は『獣』の存在を解読するための言わばキーである。
第2話目として認識されるべき話が始まったのは、『また、私は見た。もう一匹の獣が…云々』という文章を読めば明らかである。何故なら、この11節目からは、明らかに前とは違う獣についての話に切り替わっているのだから。
さて、『もう一匹の獣』とは誰を指すのか。これが既に出てきたネロでないことは確かである。もしこれがネロであれば、『もう一匹の獣』などとは言われていなかっただろうからである。まさか、ヨハネが気の狂った記述をしたというのでもあるまい。
この第二の獣が誰か知りたければ、『子羊のような2本の角』という言葉が、解読のキーとなる。このキーがあるからこそ、この獣が誰なのか知ることができるようにもなる。もしこの言葉が省かれていたならば、この獣の存在を解読するのは、かなり難しくなっていたであろう。この獣を解読するためには、ダニエル書8:1~14の箇所を見なければいけない。ダニエル書8:3~4では、我々が今見ている箇所に出てくるのと同じ『2本の角>』を持つ『雄羊』が出てくる。ダニエルはこう言っている。『私が目を上げて見ると、なんと一頭の雄羊が川岸に立っていた。それには2本の角があって、この2本の角は長かったが、一つはほかの角よりも長かった。その長いほうは、あとに出て来たのであった。』(ダニエル8:3)この羊の持つ2本の角は、少し後のダニエル8:20によれば『メディヤとペルシャ』である。この2つの国について8:4では、こう言われている。『どんな獣もそれに立ち向かうことができず、また、その手から救い出すことのできるものもいなかった。それは思いのままにふるまって、高ぶっていた。』これは正に歴史の教える通りである。確かにメディヤとペルシャは獰猛で非常に強かった。これで、ひとまずこの第二の獣は、二つの大国を表示しているということが分かった。しかし、メディヤとペルシャを示すこの羊はダニエル8:5~7によれば、『一頭の雄やぎ』により打ち殺されてしまう。ダニエル8:7ではこう書かれている。『見ていると、これは雄羊に近づき、怒り狂って、この雄羊を打ち殺し、その2本の角をへし折ったが、雄羊には、これに立ち向かう力がなかった。雄やぎは雄羊を地に打ち倒し、踏みにじった。雄羊を雄やぎの手から救い出すものは、いなかった。』この羊を殺した雄やぎは、ダニエル8:21によれば『ギリシャ』である。つまり、これはフィリッポス2世のギリシャすなわちマケドニアが、前4世紀にメディヤとペルシャを滅ぼしたということである。だから、この『子羊』は、実は『雄やぎ』だったということになる。何故なら、子羊なるメディアとペルシャは雄やぎなるマケドニアに滅ぼされて、世界帝国の座を奪われたからである。しかし、この雄やぎもダニエル書8:8によれば、その権勢を保てずに滅んでしまった。こう言われている。『この雄やぎは、非常に高ぶったが、その強くなったときに、あの大きな角が折れた。』これは詳細こそ書いていないが、ローマにマケドニアが滅ぼされたことを言っている。実際、紀元2世紀にマケドニアはローマに呑み込まれて属州とされるに至った。これは、どの辞典にも書かれていることだ。だから、この子羊とは、実はマケドニアですらなくローマだったことになる。そして、今度はこのローマから4本の角が生えた。ダニエル書8:8にはこうある。『そしてその代わりに、天の四方に向かって、著しく目立つ4本の角が生え出た。』8:22でも『その角が折れて、代わりに4本の角が生えた』と書かれている。既に説明されたように『角』とは世界帝国の首領を指す。つまり、この『4本の角』とはローマの皇帝であって、1本目が1代目のアウグストゥス帝を、2本目が2代目のティベリウス帝を、3本目が3代目のカリグラ帝を、4本目が4代目のクラウディウス帝を意味している。その後、第5の角がこのローマから出て来る。ダニエル書8:9。『そのうちの1本の角から、また1本の小さな角が芽を出して、南と、東と、麗しい国とに向かって、非常に大きくなっていった。』この5本目の角は、ダニエル書8:10によれば『星の軍勢のうちの幾つかを地に落と』すが、これは既に12:4の註解で見たように希望において天に位置している星なる聖徒たちが迫害されることだから、間違いなく5代目のネロ帝を指している。ダニエル書では、この5本目が最後の角である。5本目以降は何も書かれていない。つまり、この子羊とはメディアとペルシャでもなければ、マケドニアでもなく、ローマの4代目までの皇帝でさえなく、ネロだったということになる。ここに秘儀がある。すなわち、『子羊のような2本の角』を持つ第二の獣は、ネロをカモフラージュしているに過ぎなかったのである。子羊と見せかけているが、それはローマのネロであった。しかし、ここで疑問が起こる。この第二の獣はネロ以外の存在ではなかったのか。確かにこの第二の獣はネロではない。しかし、ダニエル書から読み解く限りでは、この第二の獣はネロだと解読せざるを得ない。これは一体どういうことなのか。
疑問を解決したい。この第二の獣はネロであるかのように思えるのだが、それは実はネロではなく、ネロと非常に近い関係にある人物であった。その人物とは、あまり歴史においては言及されることのない人物だが、ガイウス・オッフェウス・ティゲリヌス(10頃―69)というネロの近衛長官を務めた重要な人物である(※)。このティゲリヌスはネロの佞臣であり、ネロの最も重要なパートナーと言ってよい人であった。セネカさえ、この男に追い落とされて死に至らされた。彼はネロの暴政の手足となって、ネロに忠実に仕えた。彼はネロの身体の一部と言える人物だから、ネロにおいてその存在が描かれていたとしても何も不思議ではない。既にご理解していただけているとは思うが、黙示録は秘密の言い方に満ちているのだから、尚のこと、そのような描き方がされているのは不思議ではない。つまり、ティゲリヌスはネロも同然だからこそ、解読したらネロと一致してしまうというわけである。それでは、この第二の獣がティゲリヌスだという堅固な証拠はあるのか。証拠抜きにこの獣がティゲリヌスだと言っても、もちろん説得力はない。しかし、その証拠は「ある」。もし証拠がなければ、私もこれがティゲリヌスだなどとは言っていなかったであろう。その証拠は、黙示録においてこの第二の獣が『偽預言者』だと呼ばれているということである(19:20、16:13)。ティゲリヌスは、ネロの最も信頼する側近であり、それゆえネロは彼の進言を大いに聞き入れた。あのキリスト教徒迫害も、元はと言えばローマ大火の罪をキリスト教徒になすりつけたらどうか、というティゲリヌスの進言をネロが聞き入れたからこそ起きたことであった。つまり、ティゲリヌスが進言しなければ、ネロが大迫害を行なっていたかどうかは分からなかったということだ。それほどにネロはこの男を重要視していたのである。ユダヤにおける昔の王たちはたびたび預言者に何かを尋ねたりしたものだが、ネロにとって、ティゲリヌスは預言者も等しい存在であった。それはティゲリヌスが預言者たちのように、統治者を言葉でもって動かしたからである。しかし、ティゲリヌスは良いことを告げる真正な預言者のようではなく、むしろいい加減なことや悪いことばかりを告げる偽預言者のようであり、それゆえ忌まわしいことばかりを進言してネロを更に悪の道へと突き進ませた。それは偽預言者がユダヤの王を偽りの言葉により誤らせたのと一緒である。だからこそ、黙示録ではこのティゲリヌスをその類似性に基づいて『偽預言者』だと言っているわけである。事実、タキトゥスが言うようにネロという「元首が残忍になるときは、いつでも」ティゲリヌスが「内密の相談にあずかっていた」のである(『年代記(下)』第15巻 61 p288:岩波文庫33-408-3)。相談にあずかるというのだから、ティゲリヌスは正に偽預言者も同然なのである。このように第二の獣がティゲリヌスだという証拠を私は今、聖書から論証した。確かにティゲリヌスは統治者を誤らせるという点では偽預言者とよく似ていたのだから、『偽預言者』と言われても何もおかしなことはない。これから後の箇所を見ても、この第二の獣はティゲリヌス以外には考えられない。これ以降の註解を読めば、確かにこれはティリヌスだったということが、ますます分かるようになるであろう。それゆえ、この『2本の角』を持った獣がティゲリヌス以外だと考えてはならない。これは教会にいた悪しき預言者また毒麦の教職者やユダヤにおける王、祭司、長老、律法学者などではない。人間ではない存在を象徴させたものでもない。ローマやその他の国にいた異教の祭司でもない。私は神に祈ったら、この第二の獣が誰なのかすぐに分かるようになった。神が私に教えて下さったのである。これは感謝すべきことである。だから私はこの獣をティゲリヌス以外の存在だとする理解や考えを非とし、それを断罪する。
(※)
この人物は深く掘り下げられることのない人物だが、実のところ、大いに言及されるべき非常に重要な人物である。何故なら、この人物は黙示録に描かれている人物なのだから。もしこれがティゲリヌスだと多くの人が知っていれば、この人物は頻繁に言及されていたことであろう。しかし残念ながら、今まで黙示録は正しく解釈されてこなかったので、この人物はほとんどいないも同然の人物として無視され続けてきてしまった。
[本文に戻る]
しかしながら、第一の獣がネロであるならば第二の獣はセネカではないのか、と思う人も中にはいるかもしれない。この第二の獣は、第一の獣に対して明らかに従僕的である。その従僕性の度合いは、第一の獣を人々に崇拝させるほどであった(13:12)。セネカもネロに対して非常に従僕的な人であった。彼は、ネロに自殺を命じられて素直に従ったほどである。それだから、第一の獣がネロであるのに対し、第二の獣はセネカなのではないかと。確かに従僕的であるという点から考えれば、セネカはこの第二の獣のイメージと合致していることを私も認める。だが、これは明らかにセネカではない。何故かといえば、セネカは『人々の前で、火を天から地に降らせるような大きなしるし』(13:13)を行なっていないからである。しかし、ティゲリヌスであれば、このようなことを行なった。また、セネカはキリストの再臨が起こる紀元68年6月9日まで生きていなかったからである。19:19~20の箇所を見れば分かるが、第二の獣は第一の獣と共に、再臨が起こる時まで死んではいない。もしセネカが第二の獣であったとすれば、セネカはティゲリヌスのように、紀元68年6月9日までずっと生き続けていたことであろう。セネカが第二の獣ではないかと推測するのは、黙示録を真面目に考察できている証拠である。そのように推測する姿勢自体は好ましいと言える。しかし、残念ながら、今述べた2つの理由により、この第二の獣はセネカではなかったと結論せねばならない。
いったい、「666」とか「獣」とか「刻印」とか万人の心が引き付けられるような刺激のある部分だけを持ち出してきて、色々と自信ありげに論じている者たちは何なのか。私は言うが、このような者たちは、黙示録をまったく理解できていない。理解できていないのに堂々と語って、あたかも自分がよく知っているかのように見せかけている。彼らとて自分が黙示録を理解できていないことぐらい分かっているはずだ。もし理解しているのであれば、どうして人々の心を引き付ける少しの言葉だけに着目して、例えば「第二の獣は誰なのか」とか「致命的な傷を負った頭とは何か」とか「42か月とは何を意味しているか」などということには触れないのか。彼らは、こういうことについては実は何も知らないのである。もし知っているというのであれば、黙示録の註解をしてもらいたいものだ。出来たのならば私に見せて、どこが間違っているのか指摘してもらうべきである。しかし、そもそも注解書を書くことさえできないであろう。それにもかかわらず、自分が知りもしない内容を、分かっているかのように論じるというこの無謀さは一体なんなのか。世の中には黙示録を読めていないのに、黙示録のことを語りすぎている者があまりにも多過ぎる。盲目な者が光について語り、耳の聞こえない者が音について論じ、嗅覚のない者が匂いについて喋り立てている。黙示録を理解していないのに語るとは、つまりこういうことだ。悔い改めろ。もういい加減なことを好き放題に言うのを止め、世界に誤謬を撒き散らすな。私が恵みにより書いた註解を頭に叩きこめ。学べ。あなたがたはふざけているのだ。見えるようになってから光を語り、聞こえるようになってから音を論じ、嗅覚を持ってから匂いについて喋るようにせよ。
このティゲリヌスは『地から上って来た』。彼が、ネロのように『海から』(13:1)ではなく『地から』上って来たのは何故か。それは、この第二の獣が、ネブカデレザルの再来ではなかったということが示されるためである。第一の獣であるネロは、既に説明された通り、死んだネブカデレザルがハデスから這い上がってきたかのような存在であった。だからネロがハデスを表示する『海』(13:1)から上って来たと言われたのは適切であった。しかしティゲリヌスは、誰かが再来したかのように思える存在ではない。それゆえ、彼は『海から』上って来たと書かれるべきではなく、『地から』上って来たと書かれるのが適切であった。そうすれば、この第二の獣が第一の獣のようにハデスから這い上がったかのような存在でないことが、よく分かるからである。もしこの第二の獣も誰かの再来だとすれば、ネロと同じように『海から』上って来たと書かれていたであろう。この『地から上って来た。』という表現を、実際的に捉えてはいけない。これは象徴的に捉えるべきものである。今の人たちは、どうして第二の獣が第一の獣とは違い地から上って来たのか絶対に分からないはずだ。たとえ分かったかのように思っていても、その理解は間違っていると私は言おう。何故なら、これは、ネロとティゲリヌスとバビロンのネブカデレザルのことが悟れていなければ、決して読み解けない謎だからである。
『竜のようにものを言った。』と書かれているのは、つまりティゲリヌスが『竜』であるサタンに取り憑かれており、そのためサタンの心に適ったことばかりを口にしたということである。確かに彼は、忌まわしいことばかりを口にした。これは歴史の事実である。実際、この男はネロをその言葉によって更なる悪へと突き進ませ、あのキリスト教徒の迫害もティゲリヌスの進言に端を発したものであった。彼がサタンの喜ぶことばかりを口にしたということは、誰も疑えない。こんなにも悪しき言葉を発した者は、なかなか珍しいのではないかと私には思える。なお、ティゲリヌスがサタンに取り憑かれていたというのは、スエトニウスが彼について「ネロの放っていたあらゆる密偵のうちで最も極悪非道であった」(『ローマ皇帝伝(下)』第7巻 ガルバ p216:岩波文庫)と言っていることからも確かなこととしてよい。つまり、サタンに取り憑かれていたからこそ「極悪非道」だったということだ。また、彼についてはヨセフスも「もっとも悪しき2人の人物」の一人だと言っているが―もう一人は解放奴隷のニュムフィディオス・サビヌス―(『ユダヤ戦記2』Ⅳ ix2:492 p228:ちくま学芸文庫)、これは間違った言葉ではない。つまり、サタンに憑り憑かれていたからこそ「もっとも悪しき」者だったということだ。更にタキトゥスもティゲリヌスについて「罪に燃え狂った男」(『年代記(下)』第14巻 51 p216~217:岩波文庫33-408-3)と言っている。彼は「長年の鉄面皮と破廉恥ぶりをネロに見込まれた」(同)ほどの邪悪さを持っていたが、そのような邪悪さはサタンに憑り憑かれているのでなければ考えられないのである。
【13:12】
『この獣は、最初の獣が持っているすべての権威をその獣の前で働かせた。』
『最初の獣』とは、第一の頭であるバビロンのネブカデレザルのことである。つまり、これは文字通りの『最初の獣』であって、ローマにおける『最初の獣』すなわちアウグストゥス帝を指しているのではない。
この箇所で言われているのは、つまりティゲリヌスが、『最初の獣』であるあのネブカデレザルのような権威を、ネロの側近として持っていたということである。確かにティゲリヌスはネロの一部も同然であり、ネロを大いに動かしたのだから、このように言われるのは実に適切である。ネブカデレザルの再来であるネブカデレザルと同等の権威を持ったネロを容易に動かせるというのは、つまりネブカデレザルと同等の権威を持っていることでなくて何であろうか。
この箇所を分かりやすく言い換えれば次のようになる。「このティゲリヌスは、最初の獣であるバビロンのネブカデレザルが持っているような権威を、ネロの側近として行使した。」この箇所は、13章では何が言われているのか弁えていれば、自然と解読できるのであって、それほど難しい箇所ではない。とはいっても全ての解読は神の恵みによるのではあるが。それにしても、この箇所を今の人たちは、どのように解釈するだろうか。正しく解釈できないのは確かである。もしこの箇所における自分の見解が正しいと思うならば、その見解を私に教えてほしいものだ。もしその見解が本当に正しいのであれば、私の口を封じることができるだろうから。
『また、地と地に住む人々に、致命的な傷の直った最初の獣を拝ませた。』
例のごとく、『地と地に住む人々』という言葉はローマ世界のことである。これを文字通りに捉えると、しっかりとした理解ができなくなるから注意されたい。
ここで言われているのは、ティゲリヌスが復活したネブカデレザルなる皇帝ネロを、人々に崇拝させたということである。つまり、皇帝崇拝をしなかった人々は、ティゲリヌスの権力により断罪され処罰されたということである。彼はネロをも動かすほどの権力者だったのだから、彼がそのようにしたとするのは想像するに容易い。しかし、その様子がどのようだったかということは、よく分からない。というのも、先にも述べたように昔からこの男については、あまり多くのことが記録されてこなかったからである。彼のことについて辞書や辞典を読んでも、そこまで深く掘り下げられているというのではない。
このことから、ティゲリヌスがネロに非常な忠誠心を持っていたことが分かる。というのも、もし高い忠誠心を持っていなければ、このようなことはしないだろうからである。ネロもこの男を信頼しており、その功績のゆえに凱旋将軍顕彰を与え、中央広場に凱旋将軍像を、パラティウムに立像を作って置いてやるほどであった(タキトゥス『年代記(下)』第15巻 72 p298:岩波文庫33-408-3)。像が作られるというのは非常に名誉なことであり、ネロとティゲリヌスが非常に親密な関係を持っていたことが分かる。これを他の例で言えば、キリストとペテロ、釈迦とアーナンダ、ルターとメランヒトン、マルクスとエンゲルスといったところであろうか。それほどの関係だったからこそ、このティゲリヌスという者は、13章の中でネロと一緒にして語られているわけである。
【13:13】
『また、人々の前で、火を天から地に降らせるような大きなしるしを行なった。』
これはローマ大火のことである。紀元64年6月に起きたこの大火災は、自然に起きたのではなく、ネロにより引き起こされたと既に当時から言われていた。だから、民衆は、ネロが真犯人だと口を揃えて言ったものである(※①)。というのも、ネロは前からローマの市街模様を刷新したいと思っていたからである。ローマが全焼してしまえば、全てがリセットされるので、一から自分の好きなように市街をデザインできるというわけである。ネロは自分に対するこの非難を回避すべく、放火の罪を、本当は何もしていないキリスト者たちになすりつけた。このなすりつけから、あの大迫害が始まったのであった(※②)。しかし、この大火災を引き起こしたのは、実はティゲリヌスであった。何故なら、この大火災はティゲリヌスがアエリヌス街に持つ別荘からの出火を原因としていたからである。ローマは木造の建物が所狭しと密集した街であり、スエトニウスも言うように「火災をこうむりやす」(スエトニウス『ローマ皇帝伝(上)』第2巻 アウグストゥス p124:岩波文庫)く、前々からたびたび大きな火災が起きていたので、ティゲリヌスであれ他の人であれ、放火をすれば一体どういうことになるのかは目に見えていた。ティゲリヌスはネロの傲慢な願いを叶えさせるべく、自分の別荘に放火することで、このような大火災を引き起こしたわけである。この火災事件は悲惨な大患難と関わる大変重要な出来事だから―何故ならこの火災事件がきっかけとなりネロのキリスト教迫害が起こったのだから―、この火災事件についてタキトゥスが書いた記事を、ここで少し長いが引用しておきたい。タキトゥスはこのローマ大火の事件について言っている。「この後ですぐ災難が起った。偶然だったのか、元首の策略によるのか、不明である(両説あってそれぞれが信用のおける典拠をもっているので)。それはともかく、今度の火事は、それまで都を襲ったどの猛火よりも規模が大きく被害もはなはだしかった。火の手が最初にあがったのは、大競技場がパラティウム丘とエリウス丘に接する側である。そこには燃えやすい商品を陳列した店屋ばかりが並んでいた。それで、発生と同時に火勢は強く、おまけに風にあおられ、石瓶をめぐらした邸宅や外壁に囲まれた神殿などの延焼をおくらせるような障害物がまったくなかったためもあって、見る見るうちに大競技場をすっぽり包んでしまう。炎は狂暴な勢いでまず平地をなめつくすと、次には高台にのぼり、ふたたび低地を荒らした。どんな消化対策もおいつかぬくらい、災害の勢いは早かった。その頃のローマは、幅の狭い道があちこちと曲りくねって、家並も不規則だったから、被害を蒙りやすい都であった。それに加えて、恐れおののく女の悲鳴、もうろくした人、がんぜいな子。だれもが自分の安全を計り、他人の身を気遣い、弱い者を引き連れあるいは待ちながら、ある人はおくれ、ある者はあわて、みなお互いに邪魔し合う。多くの人が背後を気にしているまに、横から前から火の手にかこまれてしまう。近くまで逃れたと思うと、そこはもはや炎に包まれている。遠いと思っていた場所も、やはり同じ状態なのを見つける。ついにはどこを避け、どこへ逃げるか、見当もつかなくなる。人々は道路で押し合いへし合いし、地の上に転び倒れる。ある人は全財産を失い、1日分の食糧すらない。救ってやれなかった身内をいとおしがって、生きる手段を与えられながら、命を絶つ人もある。こうしてだれ一人として火を消しとめようとはしなかった。それどころか、消そうとするのを、多くの人はしばしばおどし邪魔をした。なかには、おおっぴらに松明を投げながら、「その筋の命令でやっているのだ」と叫んでいた。本当に命令を受けていたのか、それとも、いっそう図太く火事泥棒をやらかそうとしたためか。ちょうどこのとき、ネロはアンティウムに滞在していた。都に帰ってきたころには、パラティウム丘とマエケナス庭園を結ぶ「ネロの館」に今にも火が燃え移ろうとしていた。しかし、火を消し止めることができたのは、パラティウム丘が、カエサル家やその周囲の建築物を含めて、ことごとく灰儘に帰してしまったあとである。ネロは呆然自失の態でいる羅災者を元気づけるため、マルス公園やアグリッパ記念建築物を、さらには自分の庭園までも解放した。そして応急の掛け小屋を設け、そこに無一文となった群衆を収容する。オスティアや近郊の自治市から食料を運ばせ、穀物の市価を3セステルティウスまで下げさせた。このような処置は民衆のためにとられたはずなのだが、何の足しにもならなかった。というのも、次のような噂が拡がっていたからである。「ネロは都が燃えさかっている最中に、館内の私舞台に立ち、目の前の火災を見ながら、これを太古の不幸になぞらえて『トロイアの陥落』を歌っていた」と。6日目にやっと、火はエスクィリア丘の麓で鎮まった。広大な範囲にわたって建物が倒壊したので、これ以上猛火が続いたとしても、その火が出くわすのは、茫々たる地平線と原野しかなかったほどである。ところが、恐怖がまださめず、心に希望がたちかえらぬうちに、火がまた燃え上がった。今度は、市内の広々とした地域を襲ったので、人命の損傷は少なかったが、神殿や逍遥柱廊などは、もっと多く崩壊した。この出火はアエミリアヌス街のティゲッリヌスの所有地から起っていたため、先のよりも不名誉な噂が添えられた。「ネロは新しく都を建てなおし、それに自分の名前をつけようという野心を、日ごろから抱いていた」と。そして人々は本当にこれを信じていたのである。じっさい、ローマは14区に分れていたが、そのうち完全な姿で残ったのは、4区でしかない。3区は焼野原と化し、残りの7区は、倒壊したり半壊したりした家の残骸をわずかにとどめていた。ここで焼失した邸宅や共同住宅や神殿の数を明らかにすることは困難であろう。しかし、もっとも由緒の深い宗教記念物のなかから拾うと、セルウィウス・トゥッリウスが、「月の女神」に捧げた祠、アルカス・エウァンデルが目の前にあらわれたヘルクレスに捧げた大祭壇と神域。ロムルスが奉献を誓った擁護者ユピテルの神殿、ヌマの王宮とウェスタ神殿が、ローマ人の守護神とともに焼失した。それから幾多の勝利で獲得した他国の財宝、ギリシア芸術品の傑作、最後にローマの天才の手になる古い正真正銘の記念物。なるほど、その後で再建された現在の都は立派である。しかし、古老の記憶しているこれら多くの記念物は、もはや2度と復原できないのである。ある史家は、この大火の発生した日が7月19日で、セノネス族が都を占領して火をつけた日もやはりこの日であったことに注意を促している。別の人は、まことにたんねんな計算をして、これら2つの大火のあいだに、まったく同数の年と月と日が介在することを発見している。」(『年代記(下)』第15巻 38~41 p264~267:岩波文庫33-408-3)さて、ここでは実際にティゲリヌスが『天から』火を呼び寄せたかのように書かれているが、実際にそのようにしたわけではない。というのも『火を天から地に降らせるような』と書かれているからである。『ような』とは、例えとして言い表わす場合に使用される言葉である。また、ここで『火』と言われているのは、御言葉のことではない。これは実際の火である。11:4や20:9の箇所の場合、『火』は御言葉を意味している。しかし、この箇所の場合、この2つの箇所と同様に考えてはいけない。何故なら、神に逆らう不信者のティゲリヌスと御言葉に何の関係があるだろうか。彼のように邪悪な者が、御言葉という聖なる火を自分の武器また道具として使うというのは意味が分からないことである。さて、ここで、この大火災の出来事が書かれているのは、それが聖徒たちにとってあまりにも重要な意味を持つからであった。少し考えれば分かるように、この大火災が起きたからこそ、あの大迫害が起こることになった。すなわち、この大火災は大迫害に直結している。だから、ここでその出来事を取り立てて記すのは実に適切なことであった。これから聖徒たちには、その大迫害が襲い掛かることになっていたのだから。というわけで、この箇所は、私が今述べたように解釈すべきである。私の述べた解釈には無理がなく、文脈から考えても首尾一貫しており、歴史の出来事にもよく合致しているからである。私は黙示録を解読できるようにと心から願い求めているのだから、確かに私の述べた解釈を採用するのが望ましい。神が私に黙示録を恵みにより教えて下さっておられるからだ。
(※①)
スエトニウスもその例に漏れず、ネロこそが火災の犯人だったと思っていた。このことについて彼はこう書いている。「それどころか、ネロはローマ国民も祖国の城壁までも容赦しなかった。気のおけぬ座談の中で、ある者が「私が死ぬとき、大地は焔で焼きつくされよう」と言ったとき、「いや、私が生きているうちにだ」とネロは言った。まさしくそのとおりのことをやってのけた。というのもネロは、昔の古い醜悪な建物や狭く曲りくねった通路が我慢ならないと言って、首都に火をつけたのだ。あまりにおおっぴらにやったので、何人かの執政官級の人は、自分の敷地内でぼろ切れや燃え木を手にしたネロの寝室係を捕えても、これに手を下せなかったのである。そして黄金の館の周囲にあるいくつかの穀物倉を、これらの敷地を特にネロは欲しかったので、戦争に使う工作機械で焼き払った。というのも、その穀物倉は石の壁で造られていたのだ。6日と7晩、この猛火は荒れ狂った。民衆は記念建築物や墓地の中に追いこまれ、そこを宿とした。このとき灰燼に帰したのは、莫大な数の共同住宅に加えて、まだ敵の戦利品で飾られていた昔の将軍たちの屋敷、そして王たちが奉献した建物、ついでカルタゴやガリアとの戦争中に誓願し奉納されていた神殿、そして大昔からずっと保存され、見物や記録に価した一切の建造物である。この火災をネロは、遠くマエケナスの塔屋から展望していて―彼の言葉を使うと―「火炎の美しさ」に恍惚となり、いつもの舞台衣装をつけて『トロイアの掠奪』を全篇うたい終えた。この火災からもネロはまた、できるだけたくさんの掠奪物とその売上金をせしめるため、屍体や瓦礫を無償で取り除くと約束して、廃墟と化した敷地へ誰も入らせなかった。義援金を受け取ったばかりか、執拗にねだりさえして属州や個人の財産をほとんど枯渇させてしまった。…」(『ローマ皇帝伝(下)』第6巻 ネロ p177~179:岩波文庫)ネロの護衛隊副官スブリウス・フラウスも、ネロに処刑されることになった際、ネロの目の前でネロこそが「放火犯」だったと言った(タキトゥス『年代記(下)』第15巻 67 p293:岩波文庫33-408-3)。
[本文に戻る]
(※②)
このなすりつけによるネロの迫害について、タキトゥスはこう言っている。「しかし元首の慈悲深い援助も惜しみない施与も、神々に捧げた贖罪の儀式も、不名誉な噂を枯らせることができなかった。民衆は「ネロが大火を命じた」と信じて疑わなかった。そこでネロは、この風評をもみけそうとして、身代わりの被告をこしらえ、これに大変手のこんだ罰を加える。それは、日頃から忌まわしい行為で世人から恨み憎まれ、「クリストゥス信奉者」と呼ばれていた者たちである。この一派の呼び名の起因となったクリストゥスなる者は、ティベリウスの治世下に、元首属吏ポンティウス・ピラトゥスによって処刑されていた。その当座は、この有害きわまりない迷信も、一時鎮まっていたのだが、最近になってふたたび、この禍悪の発生地ユダヤにおいてのみならず、世界中からおぞましい破廉恥なものがことごとく流れ込んでもてはやされるこの都においてすら、猖獗をきわめていたのである。そこでまず、信仰を告白していた者が審問され、ついでその者らの情報に基づき、実におびただしい人が、放火の罪というよりはむしろ人類敵視の罪と結びつけられたのである。彼らは殺されるとき、なぶりものにされた。すなわち、野獣の毛皮をかぶされ、犬に噛み裂かれて倒れる。<あるいは十字架に縛りつけられ、あるいは燃えやすく仕組まれ、>そして日が落ちてから夜の灯火代わりにに燃やされたのである。ネロはこの見世物のため、カエサル家の庭園を提供し、そのうえ、戦車競技まで催して、その間中、戦車馭者のよそおいで民衆のあいだを歩きまわったり、自分でも戦車を走らせたりした。そこで人々は、不憫の念をいだきだした。なるほど彼らは罪人であり、どんなむごたらしい懲罰にも価する。しかし彼らが犠牲になったのは、国家の福祉のためではなく、ネロ一個人の残忍性を満足させるためであったように思われたからである。」(『年代記(下)』第15巻 44 p269~270:岩波文庫33-408-3)
[本文に戻る]
『人々の前で』と書かれているのは、この大火災を多くの人たちがその目で見て、聞き知ったからである。それゆえ、この言葉は文字通りに受け取ってよい。もしこれが小さな出来事だったとすれば、『人々の前で』とは恐らく書かれていなかったであろう。何故なら、その場合、多くの人たちが火災の出来事を見たり聞いたりすることはなかっただろうからである。その場合は例えば「密かに」とか「隠れながら」などと書かれていたに違いない。
この大火災は『しるし』であったとここでは言われている。確かにティゲリヌスにとって、この大火災とそのために行った放火は、正に『しるし』に他ならなかった。かつて預言者たちは、多くの徴を行なうことで、自分たちが本当に神から遣わされた使者であることを豊かに証明した。キリストもモーセも、多くの徴を行ない、自分こそ正に神からの使いであるということを力強く論証した。人々はそのような素晴らしい業を見たり聞いたりして、その人たちが本当に神の預言者だと悟ったのである。何故なら、神の預言者でもなければ、そのようなことは絶対に出来ないと感じたからである。それと同様に、このティゲリヌスという者も、大火災とそれに繋がる放火という言わば「悪しき徴」を行なうことで、自分が偽預言者のように忌まわしい者としてサタンから遣わされたことを、みずから証明した。人々はこのような徴と言うべき愚行を見て、ティゲリヌスが偽預言者のように忌まわしい存在だということを大いに悟った。このため、ティゲリヌスは民衆から大いに嫌悪されてしまったのである。スエトニウスは、ローマ国民が「ティゲリヌスの処罰をしきりに要求した」(『ローマ皇帝伝(下)』第7巻 ガルバ p216:岩波文庫)と書いている。この男は、多くの人から処罰を願われるほどに邪悪だったのである。だから、このティゲリヌスの放火は自分が悪い存在であるということを証明するための『しるし』に他ならないものであった。偽預言者がその悪しき行ないにより自分が偽預言者であることを示すのと同様に、ティゲリヌスも悪しき行ないにより自分がサタンからの使いであることを示した。ところで、このような英知ある記述は実に霊的であり神妙である。これこそ神の書き方である。霊的な恵みを受けていなければ、このような記述を読み解くことは決してできない。
今の人たちは、この箇所で言われていることを、よく理解できないはずである。塵ほどさえも察することができないはずである。ちょうど、ネコという動物を知らない未開民族の人が、ネコを想像することさえできないように。何故なら、今の人たちは、そもそもこの『しるし』を行なう第二の獣が誰なのかさえ理解していないのだから。つまり、『しるし』を理解する以前の段階さえ、まだクリアーしていないのである。先に理解すべき第二の獣さえ理解できていないのに、どうしてその第二の獣が行なう『しるし』を理解できるのであろうか。それゆえ、今の人たちがこの箇所を僅かでも理解できたとすれば、それは正に奇跡である。今の人たちは、私の言った通りに、この箇所を理解したらよい。そうすれば、この箇所をしっかりと無理なく理解できるようになる。目の前に黄金の美酒が置かれているのに、それを取って飲もうとしないのは勿体ないことだ。
【13:14】
『また、あの獣の前で行なうことを許されたしるしをもって地上に住む人々を惑わし、』
ここで書かれている『しるし』とは、前の節に書かれていた「大火災」また「放火」のことである。何故なら、文脈から考えれば、そのように理解するのが望ましいからである。聖書は聖書によってこそ解釈されねばならない。すぐ前の節で、この『しるし』について語られているのだ。だから、これは前の節で言われていたことだと考えるべきである。この言葉以外もそうだが、聖書で言われていることを聖句抜きに、すなわち人間理性の判断により好き勝手に解釈してはならない。聖書解釈は、聖書の明確な裏づけがあるべきである。私は今この『しるし』という言葉を前節により論証したのだから、愚かな者だと文句を言われるべき筋合いはまったくない。
『許された』とは、神の許可のことである。ティゲリヌスほどの者と言えども、神の許可がなくては、どのような悪も行なえなかった。しかし、ティゲリヌスには悪を行なう許可が神から出ていた。だからこそ、ティゲリヌスはネロの側近として様々な悪を行なうことができたのである。また、この『許された』という言葉は、ネロの許しのことだと理解することも可能である。しかし、神の許可だと捉えたほうが望ましいと私は思う。何故なら、そのほうがしっくりとくるからである。ティゲリヌスとネロは一身同体も同然の関係だったのだから、あえてティゲリヌスにネロの許しが出たということを書く必要はそこまでないのではないか。しかし、どちらの解釈を取ったとしても間違いだということにはならない。
ティゲリヌスは、大火災と放火という『しるし』を使って、偽預言者に似た者らしく『地上に住む人々を惑わし』た。これは、つまり放火により起きた大火災の罪がキリスト教徒たちになすりつけられて大きな苦難となったので、それを見た人々が恐くなり、真理の宗教に心が吸い寄せられないようにされた、ということである。キリスト教徒があのような苦しみをネロから受けたのを見たら、世の中の人々がキリスト教に向かわなくなったとしても何も不思議ではない。むしろ、キリスト教から意識的に遠ざかろうとするはずである。何故なら、自分もその宗教に行けば、大いに苦しむのではないかと感じられてしまうからである。これこそ、ティゲリヌスが人々に対して、大火災を通して仕掛けた『惑わし』である。人々が恐くなって真理に抵抗感を持ち、偽りの人生の中にますます根ざすようになったのだから、これを『惑わし』と言わずして何と言えばよいであろうか。真理から人々を引き離すのは『惑わし』と言うべきことである。その惑わしが、大火災による大迫害により引き起こされたのだ。このようにしてティゲリヌスは人々を真理から遠ざけたのだから、確かに『偽預言者』と言われてしかるべきである。何故なら、偽預言者とは人々を真理に向かわなくさせる輩だからである。またパウロがⅡテサロニケ2:9~11の箇所で、滅ぶべき人々に『惑わす力』が送られると預言したのは、このことを指している(※)。つまり、パウロが言ったのは、「ティゲリヌスはその悪しき徴により人々を恐れさせて真理に向かわないように惑わすが、それは神の裁きにより送られた『惑わす力』によるものである。」ということであった。このパウロの言葉は、キリストの再臨によりネロが殺されると預言される中で語られたのだから、私が今記した見解は誤っていない。何故なら、ティゲリヌスが人々をそのように惑わして42ヶ月が経過したら、キリストの再臨が起こってネロが殺されることになるからである。この惑わしが起こるまでに、全世界には福音が大いに宣教されていたから、人々がこのように裁きとして惑わされたのは自業自得であった。何故なら、多くの人々が福音を聞いても受け入れなかったために、遂にこのような裁きとしての惑わしが起こったからである。ところで、恐らくⅡテサロニケ2:9~12の箇所を、これほどまでに具体的に解釈したのは私が初めてではないかと思われる。今までこの箇所を具体的に解釈した人は誰もいなかった。このⅡテサロニケの箇所は非常に言及されることの多い箇所ではあるが、どの人も一般的なことを言うばかりであった。つまり、誰も彼もが「真理を受け入れなければ裁かれて惑わされる。」ということ以上には何も語らなかった。今まで聖徒たちは、再臨が既に起こったことも、第二の獣がティゲリヌスだということも、黙示録の詳しい内容もまったく弁えていなかったので、このⅡテサロニケの箇所を具体的に解釈しようにもできなかった。しかし、これらのことを弁えていれば、パウロの言葉がその細かい部分までくっきりと見えるようになってくる。そうだ。このⅡテサロニケの箇所は黙示録13:14の内容と対応しているのである。正にこの2つの箇所では同じことが言われているとしか考えられない。読者は、今までこのような解釈は少しも聞いたことがないから、多かれ少なかれ驚かれるかもしれない。しかし読者は、今まで聖徒たちが黙示録を抜きにして聖書を解釈してきたのに対し、私は神の恵みにより黙示録を通しても聖書を解釈しようとしているということを考えてほしい。黙示録を通しても解釈しようとしない限り、より完全に聖書を理解できないということぐらい、誰でも分かるであろう。それゆえ、読者が驚くのは仕方ないかもしれないが、その驚きのゆえに述べられたことを問答無用で拒絶するということはせず(こういうことは新しい見解が聞かれた際にはよく起こることだ)、いくらかでも興味深く考察したもらいたいものである。いったい黙示録を通してⅡテサロニケの箇所を解釈しようとすることの何がいけないのだ?いけないことはないであろう、否、むしろそのようにするのが望ましいであろう。であれば私が述べたことを真剣に考察してもらいたいものである。
(※)
『不法の人の到来は、サタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、しるし、不思議がそれに伴い、また、滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行なわれます。なぜなら、彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は、彼らが偽りを信じるように、惑わす力を送り込まれます。それは、真理を信じないで、悪を喜んでいたすべての者が、さばかれるためです。』
[本文に戻る]
【13:14~15】
『剣の傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像を造るように、地上に住む人々に命じた。それから、その獣の像に息を吹き込んで、獣の像がもの言うことさえもできるようにし、また、その獣の像を拝まない者をみな殺させた。』
ここに書かれている『剣』という言葉は滅ぼされるという意味である。旧約聖書では、ユダヤに滅びの預言が送られた際に、よく『剣』という言葉が用いられた。つまり『剣の傷を受けながらも』というのは、バビロンとそのネブカデレザルが滅ぼされたということを言っている。
この箇所は徹底的な霊的理解が求められる。ここで言われていることを理解したければ、ダニエル書3章に注目しなければいけない。周知のように、このダニエル書3章では、バビロンのネブカデレザルが『金の像』(ダニエル3:1)を造り、その像を『ひれ伏して拝まない者はだれでも、ただちに火の燃える炉の中に投げ込まれる』(ダニエル3:6)ようにした、すなわち殺されるようにしたということが記されている。我々が今見ている箇所でも、同様のことが記されている。すなわち、ティゲリヌスが『獣の像』を造り、それを『拝まない者をみな殺させた』と記されている。このダニエル書3章と黙示録13:14~15の箇所に見られる類似性に着目しない限り、ここで言われている出来事を正しく理解することは絶対にできない。黙示録を正しく理解したい聖徒は、私が今述べたことをよく心に刻まなければいけない。さて、我々が今見ているこの黙示録の箇所は、間違いなくダニエル書3章に基づいて記されている。つまり、ここではティゲリヌスがネブカデレザルにおいて、ネロが金の像において語られている。英知ある聖徒であれば、この時点で、もう何もかもが分かったはずである。しかしまだ分からない聖徒も多いだろうから、このまま説明を続けねばならない。ダニエル書を見れば分かるように、ネブカデレザルにとって金の像は非常に素晴らしく崇められるべきものであった。それと同様に、ティゲリヌスにとってネロは非常に尊くて崇められるべき人物であった。要するに、ヨハネはティゲリヌスにとってのネロは、あのネブカデレルにとっての金の像に対比させられるべき存在なのだ、と言いたいわけである。確かに、その対象としているのが崇められるべき存在であるという点(すなわち金の像およびネロ)、またもしそれを崇めない者がいればその者を殺すという点で、両者はまったく一致している。「あの時に金の像を崇めさせたネブカデレザルがネロという偶像を皇帝崇拝させるティゲリヌスにおいて再来した!」とヨハネは、ここで秘儀に包みつつ語っているということである。ティゲリヌスが『その獣の像に息を吹き込んで、獣の像がもの言うことさえできるようにし』たと書かれているのも、解決は容易い。これは、つまりネロというティゲリヌスにとっての生きた像と、金の像というネブカデレザルにとっての死んだ像の違いを示した記述である。ネブカデレザルの造った像は金に過ぎないから、息もなければ、何かを喋ることもできなかった。しかしティゲリヌスにとっての偶像であるネロは、息があった上、色々なことを喋った。この「生きているか生きていないか」また「喋るか喋らないか」という2つの偶像における相違点を示そうとして、ヨハネはここでこのように書いたわけである。だから、ここではティゲリヌスが本当に実際的な偶像を造り、その像に息を吹き込んで何かを喋れるようにしたと言われているのだと考えてはいけない。はっきりと言うが、そのように考えるのは誤っており、馬鹿げており、自分が何も黙示録を理解できていないことをみずから暴露するようなものである。また、ここでの記述はベースとなったダニエル書と内容的に完全に一致しているわけではないが、それも何ら問題とはならない。何故なら、ここではダニエル書の記述を引き合いにしてティゲリヌスのことが語られているに過ぎないからである。もし対応しているダニエル書との完全な一致を要求するというのであれば、キリストとダビデはどうなるのか。ダビデはキリストを予表させる人物であったが、キリストと何もかも一致しているのでないことは誰でも知っている。キリストとダビデが内容的に一致していないと言って不満を表明するまともな聖徒は誰もいない。そうであれば、ここでのティゲリヌスがダニエル書におけるネブカデレザルと完全に一致していなかったとしても、我々は問題ありとすべきではない。ここでは、あくまでもダニエル書の記述がベースとされているに過ぎないということに気付かない人が果たしているのであろうか。また実際、ティゲリヌスはここで言われているように、『その獣の像を拝まない者をみな殺させた』。これは歴史の事実である。つまり、これは聖徒たちのことを言っているのだ。すなわち、ヨハネがここで言っているのは、あの42ヶ月の迫害の際にネロという偶像を崇拝しないような聖徒たちはティゲリヌスの権力によって不敬な者として処刑に引き渡されるということである。確かにこのように考えるのであれば、ここで言われていることは本当に紀元64年12月~68年6月に起きたのだから、何も違和感がないし問題もそこには存在していない。これほどシックリくる解釈は他にない。正にパズルのピースを適切な箇所にぴったりとはめ込んだかのようである。それゆえ、この出来事をネロによるあの42ヶ月間の迫害の時期に起きたこととして捉えないのは、完全な誤りである。
ところでティゲリヌスがネブカデレザルの再来として描かれているのであれば、ネロもネブカデレザルの再来として描かれていたのだから、この2人は両方ともネブカデレザルの再来だということになるのであろうか。これはその通りである。ネロの場合はネブカデレザルの権威とその強大さにおいて、ティゲリヌスの場合はネブカデレザルの権威とその偶像崇拝の行為において、それぞれなぞらえられている。しかし、どちらも同じ対象がベースとされているからといって問題にはならない。何故なら、どちらか一人だけしかネブカデレザルになぞらえてはいけないというルールや制約は存在していないからである。聖書にそのような指示はどこにもない。どちらもネブカデレザルと似ている点を持つ存在だったから、どちらともネブカデレザルにおいて語って良かったのである。
このように2人の者はネブカデレザルにおいて描かれているのだが、誰かを他の人物において描くというのは、聖書の中で他にも例がある。それはバプテスマのヨハネである。彼はバプテスマのヨハネ以外の者ではないのだが、しかしエリヤにおいて描かれている。それは彼について次のように言われた通りである。『あなたがたが進んで受け入れるなら、実はこの人こそ、きたるべきエリヤなのです。』(マタイ11章14節)『そこで、弟子たちは、イエスに尋ねて言った。「すると、律法学者たちが、まずエリヤが来るはずだと言っているのは、どうしてでしょうか。」イエスは答えて言われた。「エリヤが来て、すべてのことを立て直すのです。しかし、わたしは言います。エリヤはもうすでに来たのです。ところが彼はエリヤを認めようとせず、彼に対して好き勝手なことをしたのです。人の子もまた、彼らから同じように苦しめられようとしています。」そのとき、弟子たちは、イエスがバプテスマのヨハネのことを言われたのだと気づいた。』(マタイ17章10~13節)バプテスマのヨハネは実際はエリヤではなかった。しかし、その職務と偉大さにおいてエリヤのようであるからこそ、彼がエリヤにおいて語られている。またキリストがダビデにおいて描かれているのも、そうである。ダビデはイスラエルを統導する偉大な王であるという点でキリストと一致しているので、聖書はキリストをダビデ王において語っているわけである。聖書には他にもこのような例があるのだから、ネロとティゲリヌスがネブカデレザルにおいて描かれていたとしても、驚いたり不思議に思ったりすべきではない。
さて、ここで言われていることを、今現在に見られるAIロボットのことだと考える人が多くいるのではないかと思われる。21世紀の現在において、科学技術は非常な発達を遂げており、少し昔の人たちからすればもはや魔術だと感じられる域に達しているほどである。そのような時代にあって高度なロボットが登場しているが、それは人間の造った人間そっくりの物質体にAIという息を吹き込んで喋れるようにしているのだから、ここで言われていることが実現していると思う人がいたとしても不思議ではないかもしれない。確かに見方によっては、そのAIロボットについて黙示録が述べていると考えないこともできないわけではない。しかし、そのように考えるのは間違っている。私はその考えを完全に非とする。もしそのAIを持ったロボットについてここで言われているとすれば、それを造った第二の獣とは誰なのか。この箇所を見るならば、そのロボットを造った『偽預言者』が必ず存在しなければいけないことになる。「それはユダヤの陰謀家たちだ。」と言うだろうか。「アメリカだ。」と言うだろうか。「それはCIAなのだ。」などと言うだろうか。どれもこれも誤っている。何故なら、偽預言者であるこの第二の獣は、明らかに単一の人物として描かれているからである。ユダヤの陰謀家とかアメリカとかCIAとは有機的な存在であって、個人ではない。また私は既にこの第二の獣がティゲリヌスだと聖書に基づき証明したのだから、その証明により、第二の獣はCIAだとかアメリカだなどと考える見解は退けられなければならない。更に言うが、読者は黙示録が『すぐに起こるはずの事』(1:1)を記した文書であることを忘れてはならない。もしここで言われているのがAIロボットのことだとすれば、ヨハネの記述に反することになる。何故なら、AIロボットの登場は明らかに『すぐに起こる事』ではないからである。いったい、紀元1世紀における『アジヤにある7つの教会』(1:4)にいる聖徒たちに、未来に登場するAIロボットのことを語って何の意味があるのか。ヨハネは気が狂ったとでもいうのか。しかし、これがティゲリヌスとネロという偶像について言われているとすれば、何も問題は起こらない。何故なら、それであれば本当に『すぐに起こる事』なのだから。それゆえ聖徒たちは科学技術の結晶であるAIロボットを見て、訳も分からず「遂に黙示録13章の出来事が実現し始めたか…」などと思い違いをしてはならない。そのような思い違いをしていたとすれば、すぐにもその考えを捨てて、この註解書で言われていることを受け入れるべきである。私は、神が私の祈りを聞いて下さり、私に黙示録の正しい理解を与えて下さっておられることを知っている。
【13:16~17】
『また、小さい者にも、大きい者にも、富んでいる者にも、貧しい者にも、自由人にも、奴隷にも、すべての人々にその右の手かその額かに、刻印を受けさせた。また、その刻印、すなわち、あの獣の名、またはその名の数字を持っている者以外は、だれも、買うことも、売ることもできないようにした。』
『小さい者にも、大きい者にも、富んでいる者にも、貧しい者にも、自由人にも、奴隷にも、全ての人々に』というのは、ローマ世界である。何故なら、ここではネロに関連したことが言われているからである。これはネロの支配が及ばない国や地域まで含まれているのではない。このように繰り返し同じことを言ってしつこいかもしれないが、繰り返して言わねばなかなか聖徒たちが誤った認識から遠ざかれないと私は思っているので、このように同じことを繰り返して言っている。つまり、それほどまでに今の聖徒たちが持つ黙示録への誤った思い込みは強いのである。読者は、このことを理解していただきたい。私がこのように言っても、この箇所やその他の箇所で言われている言葉がローマ世界に限られるということを認めようとしないのであろうか。よろしい。その人は、永遠に誤謬の闇の中に留まり続けることであろう。その人が黙示録を正しく解釈できることは永久的にあり得ない。
また、この箇所で言われている出来事は、間違いなく紀元1世紀のことである。何故なら、ここでは『奴隷にも』と書かれているからである。紀元1世紀に起こる出来事だからこそ、『奴隷』についても書かれているのである。この時代には、まだ奴隷が一般的に見られた。もしこれが21世紀の今か、またはそれ以降の時代について語られているとすれば『奴隷』については書かれていなかったであろう。というのも近代になってから奴隷という惨めな存在は、ほとんど全ての国ににおいて珍しくなっているからである。今でも奴隷が存在するのはアフリカにある一部の貧しい国ぐらいなものである。
この箇所では比喩が使われている。『その額』に『刻印を受けさせた』と書かれているのは、つまりネロに所有されるという意味である。既に3:12の箇所で説明されたように、聖徒たちは天国に行くと、その額に『神の御名』が刻まれることになる。これは聖徒たちが神の所有であるという徴である。我々が自分の所有する持ち物に自分の名前を書き記すのと同じことである。崇拝とは神に対してこそ相応しい行為であるから、ネロを崇拝してその前にひざまづくということは、すなわちネロを自分の神とすることも等しい行為であり、それは自分がネロの所有であるということを認めているのも同然である。ここでヨハネは、そのようにネロを崇拝する者は額にネロの名を示す刻印を刻み付けられて、彼の所有とされれるのも同然なのだ、と言っているのである。ネロを崇拝する人々が実際にそのような刻印を額に受けたという意味ではないから、その点に注意しなければいけない。また『その右の手』に『刻印を受けさせた』と書かれているのも、今語られたのとほとんど同じ意味であり、ネロの奴隷と化すことを言っている。昔の奴隷は、その手の甲の部分に、奴隷であることを証明する徴を焼き鏝により焼き付けられていた。人々は、その手に奴隷の徴が刻まれているのを見て、その者が奴隷であると認識したのであった。ネロの前にひざまずいて彼を崇拝することは、霊的に、また精神的にネロの奴隷となることを意味している。ヨハネは、ここでネロを崇拝する者は、ネロの奴隷としてその手にネロを示す刻印を刻み付けられるのも同然なのだ、と言っている。これも先の『額』の場合と同じで、人々の手に実際的な刻印が刻まれたというのではないことに注意すべきである。また、もし『その右の手かその額かに』刻印を受けていないような人がいれば、その人は売り買いができなくなったとヨハネはここで言っている。つまり、刻印を受けたも同然の人たちであれば、売り買いすることに支障は何もなかったということである。恐らくティゲリヌスは、ネロの42ヶ月の期間においてネロを崇拝しなかった者たちが売り買いを出来ないように布告したのだと思われる。この男は自分の放火により発生した大火災の罪をキリスト教徒になすりつけるような者だったのだから、そのような布告をしたとしても何も不思議ではない。ティゲリヌスであれば、そのようなことをするはずである。彼はサタンに取り憑かれていたのだから、そのようなことをしないほうが、かえっておかしいとさえ言える。それだから、ここで言われている出来事を文字通りに捉えるべきではない。もし本当に人々の額と手に刻印が刻まれると考えるならば、この箇所を理解することは永久に出来ないであろう。その人は誤謬の闇に留まり続ける。要するに、この箇所は霊的に捉えられるべきである。
今の人たちで、ユダヤ人の働く陰謀を見て、正にこの13:16~17の箇所が成就していると考えている人は実に多い。21世紀の今現在、ユダヤ人は人々の手と脳に電子チップを埋め込み、そのようにして自分たちが電子的にコントロールすることで人間を奴隷化しようと企んでいる。彼らの望むワンワールドが実現した際には、ユダヤ人がコンピューターを通じて、チップの埋め込まれた全ての人間を好きなように支配することになると考えられている。ニック・ロックフェラーも「俺たちの最終目標は人類に電子チップを埋め込むことだ。」と言っている。今現在、アメリカには手に電子チップを埋め込んだ人が50万人ほどいるという。私もネットで手にそのチップが埋め込まれている動画を見た。それは簡単な手術により行なわれ、手軽さから言えば整形手術のようであった。もう一方の脳にチップを埋め込むことについては、まだあまり事が進められていないようである。ユダヤ人がこのような陰謀をしているものだから、それを見た多くの人たちが「遂に黙示録13章の出来事が実現しつつある。」などと何の疑いもなく言っている。確かに、このようなチップの陰謀を見たならば、黙示録13章の箇所と結び付けたくなるのは、短絡的な思考に導かれやすい人間理性を考えれば自然と言えるかもしれない。私も、まったく黙示録について無知であれば、もしかしたらそのように理解していた可能性がある。しかし、そのように理解するのは間違っている。何故なら、この13:16~17の箇所で言われていることは『すぐに起こるべき事』(22:6)だからである。もうこれだけでも、まともな聖徒にとっては十分であろう。この一節だけでも、チップの陰謀はすなわち黙示録の実現であるという見解を容易く退けられる。しかし、そのように事を済ませられる聖徒ばかりではないだろうから、その他の反駁についても記しておかねばならない。まず、チップの陰謀を黙示録13章と結びつける人たちは、聖句を曲解していると言わねばならない。ヨハネが言っているのは、『右の手』に刻印を刻むということである。ここでヨハネは明らかにチップではなく、焼き鏝で押される形としての刻印のことを言っている。チップを手の中に入れ込むのは、刻印を手に刻むことではない。一体、誰がチップを手の中に入れることについて「刻む」と理解するのか。それは「入れる」と言われるべきことである。また『額』に刻印を刻むというのも同様であり、ヨハネはチップを脳に埋め込むことについて言っているのではない。ヨハネが言っているのは、明らかに「おでこ」の部分に外部から見える形としての刻印が刻まれるということである。ヨハネの記述を見て、聖徒たちの額に神の名が刻まれることになるという黙示録の記述を思わない人がいるのだろうか。つまり、ヨハネがここで言いたいのは、「あなたがたは神の名をこそ額に刻む者となれ。ネロにひざまづくのはネロの名を額に刻むことになるのも等しいことだ。」ということである。すぐ3節後の箇所でも、額に神とキリストの名が刻まれると言われているではないか(14:1)。ヨハネが天国で聖徒たちの額すなわち「おでこ」に名が記されることと関連付けているのは火を見るよりも明らかである。また、もし電子チップの陰謀がこの箇所のことであると考えるならば、致命的な問題が多く起こることになる。『刻印』すなわち多くの人たちが思い違いをしている電子チップを埋め込むのは「第二の獣」であるが、さて、その第二の獣とは誰のことを指すのであろうか。私はこの獣が「ティゲリヌス」であると聖書から論証した。黙示録について弁えていない者たちは、私に答えてほしい。それはロックフェラーであろうか、それともロスチャイルドなのか。もし仮にロックフェラーが「第二の獣」だとすれば、第一の獣は誰なのか。ロスチャイルドか。2匹の獣が『海から』(13:1)、また『地から』(13:11)上って来たというのはどう解釈するのか。また第一の獣が剣の傷を受けながらも回復したというのは何のことか。もし第一の獣がロスチャイルドだとすれば、ロスチャイルドに生えている『10本の角と7つの頭』(13:1)とは何を意味している?17章によれば角と頭は世界帝国またその統治者を指しているが、それを具体的に解き明かせるのか。ヨハネが黙示録を書いている紀元1世紀の時点では、5番目までの頭は既に倒れ、6番目の頭が現存している状態であった(17:10)。ロスチャイルドが第一の獣だとすれば、彼は8番目の頭でもあるが(17:11)、これはどういうことなのか。またティゲリヌスではなくロックフェラーが第二の獣だとすれば、彼には『子羊のような2本の角』(13:11)があるが、これは何を意味するのか。アメリカと中国だと言うのか?すなわち、ロックフェラーがアメリカと中国を支配していると?ダニエル書によれば、この2本の角は『メディアとペルシャ』(8:20)なのだが…。また第二の獣であるロックフェラーは、13:12で書かれているように第一の獣であるロスチャイルドを人々に拝ませるとでもいうのか?確かにヨハネの文章によれば、第二の獣は第一の獣を拝ませることになっている。そうして後、ロスチャイルドを拝まない人々を『みな殺させる』(13:15)とでも?ロスチャイルドが第一の獣だとすれば、その支配の期間は『42ヶ月間』(13:5)だけだが、そんな短い期間のためにロスチャイルドは努力奮迅しているのか?ということはロスチャイルドは大馬鹿者だということにならないか。そんな短い期間のために、大きな犠牲を払っているのだから。また電子チップを人々に埋め込む第二の獣であるロックフェラーは、大きな火の徴を行なうことになっているのだが(13:13)、これは一体何を意味しているのか。このように電子チップの陰謀が13章のことだと考えると、様々な問題が生じてしまう。恐らく、どれだけ思索力のある人であっても、その問題の全てを解決することはできないであろう。特に角と頭については絶対に解決できない。何故なら、既に見たように、これについては聖書に明瞭な指示があるのだから。つまり、電子チップの陰謀を見て黙示録13章が実現していると考えてしまうのは、黙示録がまったく分かっていないために、何かそれらしい出来事が目の前に現われたことにより、何も分からずおかしな理解に陥ってしまったということに他ならない。黙示録が分かっていないからこそ、何かそれらしい出来事を見て「もしかしたら、これこそがそうでは…」などと考えてしまうわけである。一方、私が述べた見解のほうには無理がないし、歴史の出来事とも合致しており、前後の箇所と首尾一貫性が完全に保たれている。しかもその上、聖書から論じられており、そこには確信が満ちている。これは神が私に色々と教えて下さっておられるからである。それゆえ、電子チップの陰謀をこの13:16~17の箇所と結びつけるのはよくないと私は言いたい。それは非とされるべき見解である。世の中の事象を見ることで黙示録を解釈してどうするのか?まず聖書は聖書によって解釈すべきである。そうした上で、世の事象を聖書に基づいて吟味・考察また評定していくのだ。そうすれば私のように電子チップの陰謀は黙示録とは何も関係がないことを悟ることができるだろう。今の教会が黙示録について、とんでもない出鱈目な解釈を持っているのは、確かなところ、聖書を聖書によって解釈しようとしていないからなのである。それだから、次のヴァン・ティルの言葉を、私は今の教会に突きつけたい。「もし信者たちが、聖書によって聖書を解釈することができず、したがって、神の御計画また御性質についての十分な洗練された概念を持つことができないならば、あらゆる種類の脇道へそれて行くことから、どうして守られるであろうか。」(『ヴァン・ティルの十戒』第三戒 p83:いのちのことば社)
【13:18】
『ここに知恵がある。思慮ある者はその獣の数字を数えなさい。その数字は人間をさしているからである。その数字は666である。』
この箇所は、黙示録の中で特に注目されることが多い箇所である。聖徒でない者たちでさえ、この箇所で言われていることには多かれ少なかれ興味を示す。そればかりでなく、ここで言われている『666』という数字を意識的に商品や何かのデザインなどに取り入れるほどである。エジソンの会社であるゼネラル・エレクトリックのロゴマークには「666」が描かれているし(※①)、ロックフェラーの所有するビルにも「666」の数字が記されている。日本のHYDEというロックミュージシャンのある作品のタイトル名は「666」である(※②)。イギリスのアイアン・メイデンというロックバンドの曲や映画のタイトルにも「666」が使われているし、メタリカというバンドの2000万枚以上も売れた有名なアルバムにも蛇において666が示されている(※③)。アメリカには「スリー・シックス・マフィア」というヒップホップグループがあるが、明らかに「666」である。カリスマ的なラッパーであるJAY―Zの曲には、逆再生すると「シックス、シックス、シックス、マーダー、マーダー、ジーザス」と言っている曲があるが(私はこの逆再生を聞いた)、彼はイルミナティであるから意図的に仕込んだものであると思われる。ディズニーやジョンソン・エンド・ジョンソンのロゴマークの中にも「666」が隠されている(※④)。有名なブラウザーであるグーグルクロームのアイコンも「666」の造形である(※⑤)。他にも探せばこのようなものはいくらでもある。世に見られるこのような「666」の使用は、元はと言えば、我々が今見ているこの箇所に基づいている。もし黙示録で『666』について語られていなければ、恐らくこの数字が、こんなにも世の中で使われることはなかったであろう。恐らく、この数字の使用は、これからも続くのではないかと私は思う。また、この箇所も引き続き注目され続けることになるであろう。それでは、この箇所が注目される理由は何であろうか。どうして人間はこの箇所とそこで言われている『666』に惹きつけられるのか。それは、この箇所で言われていることが、(1)非常に大きな事柄であり、(2)またその事柄が知的な秘儀に包まれて見えなくされているから、である。(1)について言えば、つまり人間とは、その自然な本性からして、大きなもの、偉大なもの、有名なものなどに心を傾けるということである。世の中を見ても分かるように、人間は巨大なものに惹かれやすい。それはヒトラーやスターリンのような悪人であっても、そうである。「有名」だと知っていれば、多くの人は耳を傾けたり、それを知ろうとする。あのアウグスティヌスも有名なものが好きだった。有名であるとはその名において巨大であるということでなくて何であろうか。この箇所でも何やら大きな存在が語られているらしく感じられるので、多くの人がこの箇所に心を向けるわけである。(2)について言えば、つまり人間とは知的な好奇心を持った存在であるということである。人間は、何か隠されたことがあればそれを知りたいと願うものだし、神の似像として造られたのだから自然と全てを知っておられる神に似ようとして知識を求める性質を持つ。この箇所では隠された存在について語られているので、多くの人がそれを知りたいという欲求を自然と持ってしまうわけである。この2つの理由がそこに存在するゆえ、多くの人がこの箇所に注目している。もしこの2つの理由がなければ、すなわちどうでもいいような取るに足りない存在について語られていたならば、また何も隠されていなかったならば、人々がこの箇所に注目することはなかったであろう。何故なら、そのようであれば、心を傾けるには値しないと自然に感じてしまうからである。この箇所が注目されるのは、ちょうど「宇宙の外側には何が存在しているのか?」と疑問を持つようなものである。宇宙の外側にあると思われるものは恐らく巨大な「何か」であるに違いないし、またその「何か」は少なくとも今現在の段階では全ての人に隠されている。ここには先に見た2つの理由があるので、宇宙の外側にある何かを知りたいと願う人は決して少なくない。この箇所で言われている『666』なる存在を知りたいと思うのも、正にそれと同じである。ところで隠された事柄を知ってしまうと、往々にして我々は急に興味を失ってしまうものである。「なんだ、こういうことか…、もう分かったからいいや」と。このような経験は誰でも持っているのではないかと思う。しかし、この箇所の場合、話が違う。この箇所は、そこで言われている存在が何かを知っても、興味が削がれるということがない。むしろ、「そういうことなのか…」などと思って、穏やかな知的喜悦が持続する。何故なら、ここで言われているのは神の啓示であって、『666』の秘儀をこの世に組み込まれたのは摂理に他ならないからである。つまり、『666』という秘儀は神の御心から発している。だからこそ、その秘儀が開示されても飽きたりすることがないわけである。神に属する霊的な事柄に飽きるということが、どうして起こり得るであろうか。
(※①)
https://www.ge.com/
[本文に戻る]
(※②)
https://ja.wikipedia.org/wiki/666_(HYDEのアルバム)
[本文に戻る]
(※③)
https://www.amazon.co.jp/フライト666-リミテッド・エディション-DVD-アイアン・メイデン/dp/B001VEH3JU
https://www.amazon.co.jp/METALLICA-メタリカ/dp/B000005RUG
[本文に戻る]
(※④)
https://www.disney.co.jp/
https://www.jnj.co.jp/
[本文に戻る]
(※⑤)
https://www.google.co.jp/intl/ja/chrome/
[本文に戻る]
また、この箇所は非常に重要な箇所である。何故なら、この箇所が解読できれば、13章に登場する『獣』が誰なのか分かるからである。黙示録において『獣』は重要な位置を占めている。この『獣』が誰なのか分からなければ、13章だけでなく、他にも11:7や16:13や17章や19:19~21の箇所が正しく理解できなくなってしまう。要するに、この『獣』の理解は、黙示録の多くの部分を読み解く言わば「キー」なのである。それゆえ、獣について解読することの出来るこの箇所は、あまりにも重要であると言わねばならない。しかし、この箇所が黙示録の中でもっとも重要な箇所かといえば、そうではない。他にも黙示録では非常に重要な箇所が幾つかある。それは、例えば20:1~6、3:11と22:20、1:1と22:6がそうである。その重要性から言えば、1:1と22:6のほうがこの箇所よりも勝っている。何故なら、この2つの箇所では、黙示録の全体部分を規定させ左右する内容が語られているからである。しかし、13:18の箇所は多くの箇所を左右させるものの、黙示録の全ての箇所を解釈的な意味において動かすというのではない。それだから、この13:18の箇所が最高度に重要であるとは言えない。しかし、それではあっても、この箇所があまりにも重要であるということには変わらない。
この箇所で示されている『666』の秘儀は、『知恵』と『思慮』がなければ読み解けないものであった。『知恵』が必要なのは、この秘儀が実に知的だからである。知的なパズルが、知的な人にしか解かれないのと同じである。『思慮』が必要なのは、もし思慮がなければ、短絡的な思考や愚かな考えに陥ってしまうからである。思慮のない子どもが、しっかりとした考えや解を持てないように、もし思慮がなければ666を読み解くことはできなかった。ヨハネが黙示録を書いた時代において、この2つのものを持ち合わせていた聖徒がどれだけいたかは分からない。だから、当時においてどれだけの人が、この『666』を解読できたか我々には分からない。もっとも、そのことが分からなくても、何か解釈上の大きな問題が生じるというのではないから安心すべきである。この2つのものを持ち合わせた紀元1世紀の人を誰か挙げるとすれば、パウロであろう。パウロという人は、『知恵』と『思慮』を共に持つ存在のうち最高の例の一人である。これを疑う人は恐らくいないと思う。
ここで一つの疑問を取り扱っておきたい。その疑問とは、こういうものである。すなわち、我々はこの数字を探ってもよいのであろうか。そのようにするのは恐れ多いことではないのか。また僭越なことではないのか。世の中には色々な人がいるものだから、もしかしたら、このような疑問を持つ人もいるかもしれない。そのような疑問を抱いてしまうならば、不安になって、恐る恐る『666』を探求してしまうことにもなる。しかし我々はこの数字を探求してよい。何故なら、ヨハネは『その獣の数字を数えなさい。』と言っているからだ。むしろ、我々は積極的にこの数字を探求せねばならない。何故なら、ヨハネは数字を探るようにと命令しているからである。上述した疑問を持つ人は、適切でない態度を取っていると言わねばならない。その人が敬虔であろうとするのは問題ないのだが、このケースの場合、少し行き過ぎである。ヨハネが数えよと命じているにもかかわらず、びくびくと恐れつつ探求するのは過度の敬虔である。このような人は、むしろヨハネの命令に動かされつつ、霊に燃えて力強く探求すべきであろう。それだから、我々はこのような疑問を持って恐れつつ数字を探求しないように注意すべきである。
さて、ここで示されている『666』とは、既に第1部で説明されたように「ネロ」である。既に何度も述べているが、黙示録で書かれている出来事は、この13章も含めて『すぐに起こるはずの事』である。それだから13章に書かれている666の獣は、既に出現している。それは『すぐに』現われたのである。『すぐに』現われた『666』を隠し持つ人間は、確かなところ、ネロ以外にはいない。一般の人々であれば「666」の数字が潜んでいる名前を持つ者もいたかもしれないが、黙示録13章で描かれている存在は明らかにビッグネームである。ビッグネームであるとすれば、それは確かにネロ以外にはいない。だから、この『666』がネロであることは明らかなのである。このことについては、もうこれ以上詳しい説明を書く必要はないであろう。何故なら第1部の箇所に戻れば、そのことが詳しく確認できるからである。ここでは第1部の中で語られなかったことに幾らか触れておきたい。ネロが、その名を数えるならば『666』となるようになっていたのは、神の摂理のゆえであった。つまり、神は世界の始まる前から、あらかじめネロという人物がその名を数えるならば666となるようにお定めになっておられたのである。だからこそ、我々の知っているネロという人物は、生まれた時に「ネロ」と名付けられることになったのである。それは、この皇帝が666として示されることにより、紀元1世紀の聖徒たちがその邪悪性を悟って警戒するにようになり、また後世に至るまでその邪悪性がよく認識されるようになるためであった。ネロ以降の時代に生まれてきた多くの人たちはこの666がネロだと気付いていないが、しかし気付いている者はネロが邪悪であるということを、その数字から更に豊かに感じさせられることになる。世界の全ての出来事は神の働きかけにより起こるが、ネロの命名においても、やはり神の働きかけがあったのである。
このネロについては、既に第1部で見たように、ギリシャ語名からヘブル語名に変換した後で、アルファベットを数値化して足し合わせるという調査法であった。しかし、ヘブル語を数値化するやり方ではなく、ギリシャ語を数値化するというやり方も、一つの可能な方法としてある。確かにギリシャ語にもヘブル語と同じようにアルファベットに数字が割り当てられており(※①)、ヘブル語に変換せずギリシャ語から直に数字に変換するという探り方も、試みるに値する。しかし、このようにして探ったとしても、意味はない。ギリシャ語の名前から666を引き出そうとしても、獣が現われることはないからだ。何故なら、正しい解が欲しいのであれば、まずヘブル語に変換するという手段を経なければいけないのであって、そのような手段を経て出てくる666の獣とはネロだからである。エイレナイオスは、愚かにも、このような方法で666を見つけ出そうとしていた。彼はそのようにすれば666の獣が見つけ出せるのだと信じきっていた。私は彼の頓珍漢ぶりを、読者の方に知っていただきたい。彼は『異端反駁』という本の中で、666をギリシャ語名から探ることについて、このように書いている。「加えて、前述の数字を持つ名前は多数見つかるのである。それでも、同じ問いは少しも減るわけではない。なぜなら、その数字を持つ名前が多数見つかれば、そのうちの一体どの名前で来るべき者はやって来るのか、という問いが残されるからである。われわれは以下で、同じ数字を持つ名前をいくつか上げてみるが、それは窮余の一策として行うわけではなく、神への畏れと真理に対する熱心ゆえのことである。例えば、ευανθασ(エウアンタス)(※②)という名前であるが、これは目下問題になっている数字を含んでいる。しかし、その点については私はここで確証を控えたい。ρατεινοσ(ラテイノス)も666の数字を持っているが(※③)、蓋然性は大きい。なぜなら、最後の王国はこの表記で示されているからである。ラテン人は今現に世界を支配している者たちである。しかし、われわれとしては、そのことを誇ったりしないだろう。さらにτειταν(テイタン)も同じである(※④)。第一音節に二つの母音εとιが書かれれば。そしてこの名前はわれわれの手元にあるものの中では最大の信憑性がある。なぜなら、この名前は前述の数字を内包しており、6文字から成り、二つの音節それぞれが3文字から成り、しかも古くからあるが馴染みのない名前であるからだ。われわれの時代の王たちの中でティタン(Titan)と呼ばれた王はいない。ギリシア人と野蛮人たちの間で公然と拝まれた偶像たちの中にも、この名を持つ者はいない。ところが、この名前は多くの民の間で神的なものと考えられている。そのため、太陽も現今優勢を張っている者たちの間で、ティタンと呼ばれているほどである。しかもこの名前には、いかほどか復讐を示唆するところ、また、処罰をもたらす者を示唆するところがある。そして、あの者も不当に扱われた者たちのために復讐するかのように装うからである。それとは別に、この名前は古くからあって、信頼に値し、王にふさわしい名前、そう、言わば専制君主に適した名前である。このように、このティタンという名前には、説得力があり蓋然性もあるので、われわれとしては、来るべき者はおそらくティタンと呼ばれるのではないかと結論づけることができよう。」(『キリスト教教父著作集3/Ⅲ エイレナイオス5』『異端反駁Ⅴ』第5巻1 30:3 p97~98 教文館)結局、この教父は真面目に考察した末に、「たぶんティタンが666の獣ではないかということだ。そうに違いないと思う。恐らくは…。」ぐらいのことしか思えず、我々のような確信を持つことはできなかった。この教父には申し訳ないが、666がティタンだなどと考えるのは、ふざけているとしか言いようがない。エイレナイオスの時代からもう2000年近く経過しているが、そのような者は現われていない。エイレナイオスよ。もしそのようにして簡単に666が探れるとすれば、ヨハネは666の秘儀が『知恵』だとか、思慮ある者はその数字を数えよなどとは言わなかったであろう。そんなにも簡単に分かるようであれば、それは知恵でも思慮ある者にしか探れないことでもないからである。一度ヘブル語にギリシャ語を変換するという必要があるからこそ―これは頭をひねらないと決してできない―、ヨハネは『知恵』とか『思慮ある者は云々』などと言ったのである。そもそもエイレナイオスが生きていた時点では、既に獣は現われ、殺され、滅ぼされていた。このことを知らなかったエイレナイオスは、勝負をする前から既に死んでいる者のように、根本的にお話しにならない状態であった。既に出現済みの獣を、まだ現われていないと断定し、しかもその存在を探ろうとして間違った探り方をするとは、愚かの極みと言わねばならない。ヨハネの言葉に基づいて言えば、少なくともこのことでは、エイレナイオスは『思慮ある者』ではなかった。666を探るということにおいて、彼は「愚かな者」であり、思慮がまったくなかった。もし『思慮』があれば、もう少し思考を深く働かせていたことであろう。読者は、彼のようにギリシャ語からそのまま666を探り出すという致命的な愚を犯さないように注意すべきである。そんな簡単に解が導き出せるようでは、『ここに知恵がある。』ということにはならないのである。
(※①)
α=1
β=2
γ=3
δ=4
ε=5
σ=6
ζ=7
η=8
θ=9
ι=10
κ=20
λ=30
μ=40
ν=50
ξ=60
ο=70
π=80
Q=90
ρ=100
σ=200
τ=300
υ=400
φ=500
χ=600
ψ=700
ω=800
□=900
,α=1000
,β=2000
αΜα=1000
βΜα=100000000
[本文に戻る]
(※②)
ε= 5
υ=400
α= 1
ν= 50
θ= 9
α= 1
σ=200
計 666
[本文に戻る]
(※③)
λ= 30
α= 1
τ=300
ε= 5
ι= 10
ν= 50
ο= 70
σ=200
計 666
[本文に戻る]
(※④)
τ=300
ε= 5
ι= 10
τ=300
α= 1
ν= 50
計 666
※この②~④の註は、上記の引用文が書かれている書物の訳注の部分による(註443~445 p143)。
[本文に戻る]
それでは「ローマ教皇」は、どうなのか。彼は『666』ではないのか?もしかしたら教皇を『666』だと考える人も読者の中にはいるかもしれないから、この教皇について、いくらか取り扱っておきたい。カルヴァンやルターをはじめとした宗教改革者たちは、教皇こそ正にパウロがⅡテサロニケ2章で預言した『不法の人』に違いないと考えていた。21世紀の今においては教皇をパウロの言った邪悪な者だと捉える人はかなり少なくなっているが、16世紀においては教皇をそのように捉えるのが一般的であった。確かにルターは、教皇こそが、Ⅱテサロニケ2章に出てくる邪悪な存在だと言っている。すなわち、彼は次のように書いている。「それはローマの怪物が教会の真中に座り込み(Ⅱテサロニケ2・4)、自らを神として売り込み、…」(『後期スコラ神学批判文書集』『スコラ神学者ラトムス批判』1521年 p109 知泉学術叢書6)これはルターが教皇を「不法の人」として捉えていた明らかな証拠である。カルヴァンも、教皇こそが正に『不法の人』だと確信していたが、それは彼の書いた次の文章を見るとよく分かる。「ローマ教皇を反キリストと呼ぶ時、我々は余りに口汚く、余りに厚顔だと見られてしまう。しかしそう感じる人は、我々が模範にしてそのように言い、また口ずからそのように語ったパウロを、慎みなき者と告白することになってしまうのを悟らない。また、パウロの言葉は他の人について語られたのに、我々が悪辣にもローマ教皇に転用していると反論する人がないように、この言葉が他ならぬ教皇制について言ったということを手短に示そう。パウロは「反キリストは神の宮の中に座を占めるであろう」と書いた(Ⅱテサロニケ2:4)。別の箇所で御霊は、アンティオコスなる人物において反キリストの姿を描き、彼の王国が大言壮語と神冒涜をもって立つであろうと示した(ダニエル7:25)。ここから我々は結論して、キリストの霊的王国に逆らって立ち上がる反キリストの専制は、身体に対するよりも霊魂に対するものであると言う。次に、これはキリストの名も教会の名も廃止することなく、むしろキリストの名を盾に取って濫用し、教会の名義の下に、謂わば仮面に隠れるようにして振る舞うのである。しかし、初め以来存在した異端と分派は全て反キリストの王国に関わるものではあるが、来たるべき背反を予告した時、あの憎むべき者の座は全世界的背教が教会を占有するに至って立てられ、それでも教会の多くの肢は散らされながら信仰の真の一致の内に耐え続ける、という有様であるとパウロは描き出したのである。更に付言して、後の世に明らかになる不法の業が今の時既に秘密の内に働き始めていると言っているところから、この禍いが一人物によって引き起こされるのでも、一人の人と共に終わるのでもないと理解される。更に、神から栄光を横領して自分の物とするのが反キリストの目印であると示すのだから、反キリストを探索するに当たって頼りになる突出した証拠はこれであり、とりわけこの種の傲慢によって教会を公然と四散させるに至る場合いよいよ顕著である。それ故ローマ教皇が、神にのみ属しキリストにこそ固有であるものを恥ずることなく己れのものに転用しているのは明らかであるから、彼が不敬虔と憎悪の王国の君でありまたその旗手であることは疑えない。」(『キリスト教綱要 改訳版 第4篇』第4篇 第7章 第25節 p153~154:新教出版社)「ダニエルも(ダニエル9:27)パウロも(Ⅱテサロニケ2:4)、反キリストは神の宮に座すであろうと預言したが、この反キリストの冒涜的で忌むべき王国の我々の内における指導者また旗手はローマ教皇であると、我々は断定する。反キリストの座を神の宮の内に置くのは、彼の王国がキリストの名と教会の名を廃絶するに至っていないと暗に言うことである。したがって、反キリストの専制の下でも、教会が残存することを我々が否定しないのは、ここから明らかである。」(『キリスト教綱要 改訳版 第4篇』第4篇 第2章 第12節 p52~53:新教出版社)教皇が『不法の人』であると捉える傾向は、17世紀に入っても続いた。17世紀に作成されたプロテスタントでは最も有名な信条である「ウェストミンスター信仰告白」の中では、教皇について次のように言われている(25:6)。「イエス・キリストの外に教会の首はなく、ローマの教皇もいかなる意味においても、その首ではあり得ず、彼こそキリストと神に召されたすべてのものとにそむき、教会において己れを高うする非キリストであり、不法の人、滅亡の子である。」(『新教セミナーブック4 信条集 後篇』p205:新教出版社)さて、教皇を『不法の人』だとすると、教皇は黙示録13章の『666』でもあるということになる。何故なら、既に第1部で説明されたように、Ⅱテサロニケ2章の『不法の人』はすなわち黙示録13章の『666』と同一人物だからである。もう読者にはお分かりだと思うのだが、Ⅱテサロニケ2章と黙示録13章は対応している箇所である。どちらのほうでも言わば「ボス的な存在」が登場しており、それはサタンをその背景として持っており、人々を惑わすことについても両方の箇所で同じことが言われており、更にどちらもその邪悪な者は再臨のキリストにより殺されることになっていると預言されている。ここまでの類似性が見られるのは、どちらも同じ人物について語られているからに他ならない。これは説明済みのことだから、これ以上の説明は控えたい。私は言うが、教皇は『666』ではない。というのも彼が666だとすると、様々な問題が起こるからである。例えば、666の人は再臨により殺されるのだが(Ⅱテサロニケ2:8、黙示録19:19~20)、教皇が再臨により殺されるとはどういうことなのか。もし再臨により教皇が殺されるとすれば、どの教皇なのか。これを説明できる人はいない。また666である『不法の人』は、パウロが生きていた時代に存命中の人物であったが(Ⅱテサロニケ2:5~7)、再臨により殺される教皇が当時から既に生きていたとでもいうのか。また、パウロはどうして遥か未来に現われる再臨により滅ぶべき教皇のことを、当時のテサロニケ人たちに『よく話しておいた』(Ⅱテサロニケ2:5)のか。パウロは当時の人たちには関係ない人のことをよく話すほど気が狂っていたのであろうか。また、『666』の出現は『すぐに起こるはずの事』(1:1)だから、再臨により教皇が殺されるというのはおかしな話である。というのは、21世紀の現在になっても、まだ教皇は再臨により殺されていないからだ。教皇がまだ再臨により殺されていないのを疑う人は誰もいない。であれば、もし教皇が666であり再臨により殺されるとすると、その出来事が『すぐに起こるはずの事』だと教えている神の御言葉と矛盾してしまうことになる。このように教皇を『666』だとすると、色々な問題点が出てきてしまう。それゆえ教皇を『666』だと捉えるのは、無知の現われであり、単なる「こじつけ」に過ぎないことが分かる。だから教皇を『666』とするのは非とされねばならない。もし教皇をそのように捉える人がいれば、その人は誤謬の罪を犯している。これから教皇が再臨により殺されることはないであろう。何故なら、もう既に再臨は実現しているのだから。また教皇は、その職務において既にユダヤ人に殺されているのだから。
では「ロックフェラー」また「ロスチャイルド」は、どうなのか。読者の中には、この2人か、この2人のどちらか一人が『666』ではないかと考えている人がいるかもしれない。確かにこの2人のことを考えるならば、この2人か、この2人のどちらかが『666』であると思えてしまうのは、自然なことであると言えるかもしれない。ロックフェラーは自分の所有する巨大ビルに666の数字を公然と刻んでいるし、ロスチャイルドも自分の関わるワインのロゴマークに666の数字を潜ませている。また、彼らは陰謀家らしく教会の滅亡を画策しており、多くの教会が既に彼らに骨抜きにされているが、それは13:7の箇所を思わせることである。そこでは666が『聖徒たちに戦いをいどんで打ち勝つことが許され』た、と書かれている。これから彼らが教会を公然と滅ぼすのだと考えている人が読者の中にはいるかもしれない。また、彼らは全人類に電子チップを埋め込もうとしているが、これも13:16~17の箇所を思わせると言えなくもない。既に述べたことだが、実際、チップの陰謀とこの箇所を結び付けている人は少なくない。この2人については、短く言えば、このような具合なのである。しかしロックフェラーもロスチャイルドも『666』ではない。何故なら、我々が今見ているこの13:18の箇所によれば『666』の存在には名前に邪悪な数字が隠されていなければいけないのだが、この2人の名前には666が隠されていないからである。もし隠されていたとすれば、誰かがそれを発見し、そのことがネットや本の中で大いに言い広められていただろうが、そのようなことはないし、私もまだそのような話は聞いたことがない。『666』の数字をこの2人が持っていない以上、この2人のどちらかが13章に出てくる獣だと考えることはまったくできない。もしこの2人のどちらかが666だと思えるならば、またそのように思いたいのであれば、まずその名前の中に潜んでいる『666』を見いだすことから始めなければならないであろう。もっとも、彼らの名前に邪悪な数字を見いだすことはしたくともできないと思うが。
上で述べたロックフェラーとロスチャイルドはユダヤ人である。つまり、この2人のどちらかが「666」であると考える人たちは、666である「獣」はユダヤ人だと考えていることになる。私は言うが、ある特定のユダヤ人か、またはユダヤ全体が「獣」だと考えるのはお話にならない。何故なら、17章を見れば分かるように、ユダヤは「獣」ではなくて「獣の上に乗っている女」だからである。いったい、ユダヤが「獣」だと考えている人たちは、何を言っているのか私にはよく分からない。そのように考える人たちは、聖書をよく読んでいないか、よく読んではいるがあまり深く考えていないか、のどちらかである。もし聖書をよく読んでいる上、深く考えていたら、間違ってもユダヤを「獣」として考えることはしなかっただろうからである。このようなとんでもない思い違いは、あまり聖書に通じていない人たちによく見られる。ただ興味本位で詮索するだけで、聖書本文に密着しないと、こんな愚かな妄想を抱くことになってしまうのだ。聖徒たちは、このような人たちと同類になってしまわないよう、よくよく注意せねばならないと私は思う。
この『666』が、すなわちコンピューターであると何の疑いもなく言っている人もいる。この見解によれば、「コンピューター」という単語のアルファベットを一つ一つ数字に変換して足し合わせると「666」になるという。すなわち、
C (18)
O (90)
M (78)
P (96)
U(126)
T(120)
E (30)
R(108)
=(666)
である。なるほど、確かに「コンピューター」は本当に「666」である。基礎教育を受けている者であれば、これは疑えない。しかし、この見解は完全に非とされねばならない。このような見解を取る人は、良いお笑い芸人になれる可能性が高い。何故なら、この見解はほとんどギャグも等しいからである。どうしてこの見解が間違いかと言うと、ヨハネは666が『人間をさしている』と言ったのであって、非生命体を数えよと言ったのではないからである。まさか、ヨハネは紀元1世紀の聖徒たちに対して、約1900年も経過しないと登場しないコンピューターという機械の名前を探って数値化せよと命じたとでもいうのか。当時はまだ英語など全く使われていなかったのに、英語の単語を探れと言ったとでもいうのか。ラテン語かギリシャ語を使っている人が大半だった紀元1世紀のローマ世界において、そのようにヨハネが命じたと?こんなふざけた見解に誰が我慢していられるであろうか。このような異常な見解には、石さえも怒り狂って叫び出すことであろう。お分かりであろうか。今の教会は、こんなことを言い出す人さえ出てしまうほどに、黙示録に対して盲目であり、霊的におかしくなっているのである。今の教会が黙示録に対して目を開けており、また霊的に研ぎ澄まされていたのであれば、間違ってもこんなことを言い出す人は出なかったはずである。このような見解を取る人は、ぜひ、その見解を捨てていただきたい。そして、この註解書の中で書かれていることをよく読み、しっかりと考えるべきである。そうすれば、神の恵みにより正しい見解を持てるようにもなるであろう。なお、陰謀研究で有名なジョン・コールマン博士は「ベルギーのブリュッセルのNATO本部」には「666と名づけられた巨大コンピューターの中に、ブレジンスキーが述べたあらゆる種類のデータを貯蔵している。」(『300人委員会』■2 ローマクラブの邪悪な謀略家たち p66:KKベストセラーズ)などと言っており、黙示録がよく分かっていない人たちにとっては興味深い情報かもしれないが、これはハッキリ言って黙示録の記述とは何の関係もないものである。何故なら、これはただ勝手に巨大コンピューターを666と名付けているに過ぎず、先にも述べたが666の数字は非生命体ではなく人間を指しているのでなければ意味はないからである。
再びコンピューター関連のことであるが、インターネット上で提供されているハイパーテキストシステムの「ワールド・ワイド・ウェブ」(World Wide Web)にも666が隠されている。これについては、もう既に知っておられる方も多いかもしれない。この言葉のどこに666が隠れているかといえば、「WWW」がそうである。第1部の註釈の中でも書いておいたが、ヘブル語の文字には数字が割り当てられており、英語アルファベットの「W」と対応している「ו」(ワウ)の文字は6を示している。つまり、「WWW」はすなわち「666」(ווו)だということである。確かにこれも「666」であることには間違いないが、これを黙示録の獣と結びつけるのは、ハッキリ言って馬鹿げている。「WWW」が666だから一体なんだというのか。ハイパーテキストシステムの名前の中に「666」が隠れていると、それが獣を意味するとでもいうのか。ヨハネはある『人間』において、その数字が隠れていると言ったのだ。これが特定の人間であれば話は別だったが(その場合は真剣な検討をする必要があった)、非生命体しかもただの表示名に過ぎない文字列の中に666が隠れているというのでは、まったくお話にならない。黙示録を研究している私からすれば、これは取るに足りないものである。サタンが聖徒および未信者たちの黙示録に対する無知を利用して、やりたい放題をしているとしか思えない。私には、サタンがニヤニヤとしているのが感じられる。あたかもサタンは次のように言いたいかのようである。「666を潜めさせても、どうせ多くの奴らは気付かねえんだろう?気付いた奴らには驚かせ、動じさせ、怖がらせておけばいいんだよ。」
では「バーコード」はどうなのか。バーコードのあの「線」の中に『666』が示されていることは、絶対に疑えない。もしこれを否定する人がいたとすれば、その人は知的な障害を持っているのだと思われる。つまり、それほど明瞭にバーコードからは『666』が読み取れるということだ。まだこのことを知らない人がいたら、ネットで調べてみてほしい。このバーコードに仕組まれた『666』の数字を見て、多くの人が「遂に黙示録の時代が来たか…」などと思ったり、不安になったり、絶望的になったり、喜んだり、興奮したりしている。それはクリスチャンであるかノンクリスチャンであるかを問わない。皆がこのバーコードの陰謀に動揺しているのである。しかし、このバーコードの陰謀を見て黙示録の記述が成就していると考えるのは馬鹿げている。何故なら、バーコードに666が隠されているのは間違いなのだが、そのバーコードを『刻印』として商品に刻んだ『獣』が誰なのかという点がまったく無視されているからである。ヨハネが言ったのは『刻印』から666を読み取れということではなく、その『刻印』を刻んだ『獣』の名から666の数字を読み取れということである。それなのに、多くの人が刻印のほうにしか目を向けないのは、どうしたことなのか。どうして刻印を刻んだ『獣』における666を探り出そうとしないのか。これは大変おかしいことである。ヨハネは獣の名から『666』を数えよと命じているではないか!陰謀の知識を多く持つ陰謀論者でさえ、バーコードに666が示されていることは説明するものの、しかしその提供者としての『獣』に666の数字が隠されていることについては何も語らない。つまり、そのような獣がどこにも見出されないのである。666の数字を潜ませているバーコードを刻ませた獣とその獣に隠されている666が分からない以上、バーコードの陰謀を見て黙示録の記述と結び合わせるのは、無知に基づく狂気と言わねばならないことになる。こういうのを狂信と言うのではないかと私は思う。バーコードを見て黙示録と関連付けている人たちは、少し思索力が足りないのではないか。バーコードを陰謀として商品に仕掛けたユダヤ人たちも思索力が足りない。私は人々にもう少し思考の努力をしてくれるように要請する。私がした説明から分かると思うが、バーコードを見てそれを黙示録13書の箇所と関わらせてしまうのは、ほとんど何も考えていない証拠である。
ヒトラーは『666』と思えるような存在であった。彼は、ドイツ教会を苦しめ、支配しようとした。これは黙示録13:7およびⅡテサロニケ2:4を思わせる愚行である。また彼は「大ボス的な存在」だから、黙示録13章とⅡテサロニケ2章で出てくるボス的な存在とイメージが合致している。しかし、このヒトラーは『666』ではなかった。何故なら、彼は再臨のキリストに殺されることなく歴史から姿を消したからである。彼はチャーチルの『第二次世界大戦』という本によれば愛人と結婚してから即座に銃で自殺したということだが(この説明には謎が多いと私には思えた)、陰謀論によれば潜水艦に乗って逃れて後、誰にも知られずに遠くの場所で余生を過ごしたということである。いずれにせよ彼は再臨により殺されなかったのだから、彼が『666』でなかったことは間違いない。かつてヒトラーこそが『666』だと信じていた人は、自分の間違いに気づき、恐らく「きょとん」としたのではないか。周りの人たちも、その人が間違ったことを言っていたということを知ったはずである。このように『666』である存在を間違って信じるとは、つまり自分の愚かさを後になって暴露することであり、周囲の人をも惑わすことであるから、我々はそのようなことにならないように注意せねばならない。先に述べたロックフェラーとロスチャイルドが『666』だと信じている人たちも、ヒトラーこそが『666』だと信じていた人のようになると私は思う。
アレイスター・クロウリーの場合、「418の書」の中で「カインの額のしるしは、黙示録に言及される野獣のしるしである」などと言っている。「霊視と幻聴」の中でも、彼は「カインの額の上の印は、『黙示録』に語られている<野獣>のそれで、…」(『アレイスター・クロウリー著作集4 霊視と幻聴』アルンと呼ばれる第二番目のアエティールの叫び p158:国書刊行会)などと言っている。つまり、カインに与えられた印は666だったということだ。これはどうなのか。本当に、カインの印は獣の印である666と一緒だったのか。これは気の狂った魔術師の無思慮なこじつけに他ならない。何故なら、カインに与えられた印が『666』であるなどとは、どこにも書かれていないからである。カインに666の印が与えられていたとすれば、確かにクロウリーの言説は正しかったかもしれない。しかし、聖書はカインに与えられたこの印がどのようなものだったか何も我々に伝えてはいない。それだから、カインの印が獣の印と同一のものだったと理解することは決して出来ない。不信者たちは、聖書理解において、こじつけが大の得意である。彼らは自分の心の思うままに好き勝手なことを、聖句の内容において夢想する。何故なら、彼らには神の御霊が与えられていないので、聖書を正しく解釈することができず、どうしてもこじつけをするしかないからである。クロウリーもその一人であった。彼は聖書の知識を多く持っていたが、神の御霊は持っていなかった。だからこそ、獣の印においても大変な思い違いをしてしまったのである。我々はこのようなこじつけに振り回されてはならない。もしこのようなこじつけに振り回されたならば、聖書に対する信仰が文字通りお終いになってしまいかねないのだから。
それでは、このアレイスター・クロウリー自体はどうなのであろうか。クロウリーは、よく本の紹介文などで黙示録の「獣666」と呼ばれている。彼自身も次のように自分のことを言っている。「まだ10代に届かぬ頃から、私は自分が666という数字を背負った<野獣>であると既に気づいていた。それが一体何を含意するのか私にはさっぱり合点がいかなかったが、このおぼろげな意識には血を騒がせる恍惚とした自己との一体感が伴っていた。」(『魔術 理論と実践』序 p17:国書刊行会)彼はこうも言っている。「私すなわち<野獣666>は、声を大にして誓って言う。この私自身は己れの<天使>によって此岸へ連れて来られたのだと。」(前同 p403)クロウリーは天使との交流について力説し勧めているが、これは私の見るところでは堕天使すなわちサタンのことである。また、彼は「世界で最も邪悪な男」と評された。これには私も同感である。彼に比べればニーチェが善人に思えるぐらいである。ニーチェが矯正不可能になった不良だとすれば、クロウリーは世界を悪くしてやろうと企んでいる新興宗教の創始者である。ニーチェはまだ社会の枠からギリギリで飛び出していないが、クロウリーは完全にあっちの世界へと行ってしまっている。こういう意味で、どちらも忌まわしいのではあるが、私としてはクロウリーのほうが危険度が高いと思うのである。また彼は反教会の人であり、キリスト教の全滅を願っていた。更に、彼はカリスマ的な大魔術師であって、180もの儀式殺人に関与していた。彼のもたらした負の影響はあまりにも大きく、彼の死後70年以上も経過した今でも世界中で見られるほどである(クロウリーの没年は1947年である)。音楽の分野で言えば、ジョン・レノンもマイケル・ジャクソンも彼の本から多くのことを学んでいるし、デイヴィッド・ボウイもクロウリーから大きな影響を受けていたし、オジー・オズボーンも「ミスター・クロウリー」というタイトルの曲を作った。このクロウリーは「私は<魔術>を<万人>の生活における不可欠な要因としなければならない。」(前同 p18)と言ったが、これは私の見るところでは、多くの人たちが彼から大きな影響を受けていることを考えれば、かなり成就していると思われる。私としてはクロウリーにはサタンが入っていたと思う。サタンにとって、彼のように知識が海のようにあり、知性が飛び抜けて高く―恐らくJ・S・ミルよりも高かったと思われる―、物事を俯瞰できる精神を持ち、既成概念に全く縛られず、霊的な事柄に不感症ではない人物は非常に相性が良いからである(このような卓越した頭脳を持った者が神に用いられていたとすればキリスト教に大いに役立っていたことであろう―残念ながらサタンに用いられてしまったが!)。クロウリーにサタンが入っていたということについては、彼自身が<悪魔>を自分の<主>だと言っていることや(「サメクの書」要点Ⅱ 項目J)、自分が「<サタン>の自負を抱いている」(『魔術 理論と実践』<聖杯>,<アブラハダブラ>~ p97:国書刊行会)と告白していることも考慮されるべきであろう。クロウリーとはこのような男だったのだから、彼のことを彼自身が言っているように「666という数字を背負った<野獣>」だと思う人がいたとしても不思議ではないと言えるかもしれない。しかし、彼は666の獣ではない。何故なら、まず第一にクロウリーの名前の中には「666」の数字が潜んでいないと思われるからである。もし彼が666だと主張するのであれば、彼の名前に666が潜んでいることを示さねばならない。第二に、ヨハネが紀元1世紀のクリスチャンに向かってクロウリーのことを示したとは考えられないからである。このように考えるのは馬鹿げていると私は言いたい。第三に、クロウリーは再臨のキリストによって殺されていないからである。666の獣はキリストの再臨により殺される、というのは既に説明済みのことである。以上の3点からクロウリーを666であると考えることはできない、と私は言う。私はこの3つの他にも彼が666でない理由を示せるが、手加減して3つの理由を示すだけにしておいた。要するにクロウリーを666だとするのは、聖書をよく弁えていない無知な者たちの自分勝手な思い込みに他ならない。もしクロウリーが666だとすれば、再臨の起きた年をクロウリーの死んだ1947年だとせねばならなくなる。いったい、誰がそんな説をまともに聞いていられるであろうか…。
他にも、この『666』について、とんでもないことを言っている人が世の中にはいる。これは私が最近になって知ったことである。どうか驚かないで聞いてほしい。この『666』は、何と実は「9・11」だというのだ!「9・11」とは、もちろん2001年9月11日に起こったユダヤ人の仕掛けた陰謀のことである。このように言っている人によれば、どうやら「9・11」が『666』に間違えられたのは、「印刷ミス」なのだという(!!!)。それゆえ、ネット上に満ちている陰謀関連の情報を集める際には真偽を見分ける眼識が必要だと、この人は力説していた。私は、このような奇論には反駁する必要性さえ感じられない。このような奇論であれば、コンピューターを666だとする見解のほうがまだマシである。世の中には、このような意味の分からないことを言い立てる人が、少なからず存在している。この『666』について言えば、先に見たクロウリーもそうであるが、特に未信者が破滅的に愚かなことを言い立てる傾向を持つと私は思う。彼らは聖書に真剣な態度を持てないので、何の躊躇もなく、平気でおかしなことを言えるのである。信者であれば、666を9・11だと言うほどには誤りたくても誤れない。今述べた「666=9・11説」もそうだが、この『666』には本当に多くの異常な見解が世の中には見られる。我々は、そのような訳の分からない奇論に惑わされてしまわないように注意する必要がある。
ところで、この『666』という数字には、どのような意味があるのか。この数字は誰もが邪悪であることを意味していると感じているが、それは間違っていない。確かにこの数字は邪悪であることを示す。しかし、この数字が邪悪であることは分かっていても、どうして邪悪であることを意味するのか具体的に説明している人は少ない。つまり、多くの人が「どうして666は邪悪なのか?」と聞かれたら、「そういえば、どうしてなのだろう?」と思ってしまう状態にあるということである。そこで、私はこの数字が邪悪であることの理由を、ここでいくらか書いておきたいと思う。まず聖書において「6」は人間を示す。何故なら、人間は創造の6日目に造られたからである。またこの数字には「不完全」という意味もある。それは完全数の「7」に「1」だけ足りないからである。『666』という数字は、この「6」が3つ繰り返して並べられた数字である。聖書において3回の繰り返しは「強調」のために用いられている。つまり、『666』とは人間また不完全性を示す「6」が大いに強調された数字だから、つまり「人間だけの状態」「理性の自律」、また「あまりにも不完全」ということになる。それは、言い換えれば「邪悪」ということに他ならない。確かに、神を抜きにした人間だけの状態が徹底的に不完全だということは、すなわち「邪悪」だということである。何故なら、そこでは万物の主権者が除外されているのだから。それは、神を捨てて人間だけでやって行こうとしたあのアダムのようである。敬虔な聖徒であれば、「人間だけ」すなわち「神を除外しよう」という思いまた精神性が、どれだけ邪悪であるかよく分かるはずだ。これとは逆に「777」であれば、それは「あまりにも完全」「徹底的に神聖」「付け加えたり減らしたりすべき部分がない」という意味となる。何故なら、「7」という数字は完全また神聖であることを示す数字であり、それが3つも並べられているからである。だから、スロットやゲームなどで大当たりが「777」に設定されているのは正しい。ちなみに「999」も『666』と見做すことが可能である。何故なら、「999」は逆さまにすると『666』だからである。サタンがアレスター・クロウリーに「逆向きに書かせよ、逆向きに読ませよ。」と言わせたことからも分かるように(※)、サタンにとっては逆さまであっても意味が通るのであれば正当とされるのである。何故なら、サタンとは<あべこべの主>であり<倒錯すなわち逆さまの主>だからである。とはいっても、聖書の中でそのような逆さまの判別方法が求められている箇所はないのではあるが。
(※)
11、「第一の方法」 まず被免達人は次に述べる方法によって、逆方向に考える訓練をする。
(a)左右いずれかの手で言葉を逆綴りにして書くようにすること。
(b)後ろ向きに歩くようにすること。
(c)できれば絶えず、映画やレコードを逆回転にして観聴きし、それがごく自然でそのまま評価できるように思えてくるまで馴染まなくてはいけない。
(d)言葉を逆綴りにして話す練習をすること。つまり「私はその男だ(I am He.)」と言うかわりに「エー・マ・アイ(Eh ma I)」と言わなくてはいけないのである。
(e)後ろから文字を読むようにすること。この場合なかなか自分をだますのは難しい。熟練した読者なら一目で一つの文章を見てしまうからである。そこで弟子を使って最初はゆっくり、次第に速く音読させる。
(f)自分自身の才能を使って、別の方法を案出すること。
(『魔術 理論と実践』附録Ⅶ ブドゥシスの書もしくはジスハルブの書 p537:国書刊行会)
[本文に戻る]
『666』という数字は、この箇所以外ではⅠ列王記10:14で記されている。そこでは、『1年間にソロモンのところにはいって来た金の重さは、金の目方で666タラントであった。』と言われている。こちらのほうは、黙示録13:18の箇所とは違い、ほとんど言及されることがない。しかし、こちらのほうの『666』もその数字の意味は黙示録の数字の意味と何も変わらない。ソロモンに邪悪であることを示す666タラントの金がもたらされて後、この王は律法に背き、忌まわしい行ないに歩み、そして遂には神から離れることになってしまった。つまり、ソロモンに『666タラント』の金が入ってきたのは、これからソロモンが堕落して邪悪になるということを預言した出来事だったわけである。確かにソモロンは神を無視した歩みをそれ以降してしまったのだから、この金の重量がソロモンの未来を予告していたことは疑えない。これは当該の箇所を読めば誰の目にも明らかである。ヨハネが『666』という数字を、このソロモンの記述から取ってきたのは間違いない。何故ならヨハネがⅠ列王記10章の記述を記憶していたことは明らかだからである。このⅠ列王記と黙示録に出てくる2人の統治者は、どちらも凄まじい権力を持つ王であるという点、非常に大きな知名度を持つという点、またある時点から急激に堕落してしまったという点で、完全に一致している。つまりヨハネは、ネロがソロモンのようにある時から急に邪悪になってしまう王だということを、この数字において教えているのだと思われる。確かにネロもソロモンも堕落して邪悪になるまでは、けっこう良い統治をしていたのである。またエイレナイオスは、黙示録13章の『666』は、ネブカデレザルの造った金の像が『高さは60キュビト、その幅は6キュビト』(ダニエル3章1節)だったのと関係があると言っている(『異端反駁』5巻)。この見解は非常に鋭いと思えるが、しかし、やや問題があると言わねばならない。何故なら、ダニエルが言っているのは高さが『60キュビト』、幅が『6キュビト』だということだけであって、長さが「600キュビト」だとまでは言っていないからである。つまり、ダニエル書からは「66」(60+6)の数字しか導き出せない。これが長さも含まれており、しかもその長さが「600キュビト」だと言われていたらエイレナイオスの見解は絶対に疑えないものであったが、残念ながら長さについては触れられていない。しかし、黙示録13章ではネロがこの『金の像』において描かれているのだから、たとえ高さと幅しか数値が書かれていないからといって、即座に愚かな見解として切り捨てるわけにはいかない。もしかしたら関連がある可能性は高いからである。例えばダニエルが、ネロという偶像の長さを600キュビトだと捉えるように求めていると考えることも不可能ではないのだ。霊的また象徴的に捉えるのであれば、このような捉え方は決して不可能ではない。いずれにせよ、この件については更に探求を深めねばならないと私は思う。それにしてもエイレナイオスがネロとネブカデレザルの造った『金の像』における深い関係性をまったく知らなかったにもかかわらず、このように黙示録13章の獣と金の像との関わりについて論じることが出来たのは非常に不思議である。今述べたこの2つの箇所以外で、『666』という数字の参照元になった箇所、また参照元になったと推測される箇所は、他に聖書の中には見られない。
最後に、『666』という数字の原語についていくらか論じて、この箇所の註解を終えることにしたい。多くの写本では、我々が今見ているように『666』(χξs)と書かれている。しかし、中には「616」(χιs)と書かれている写本もある。正しいのは明らかに前者の写本である。後者の写本は、写筆者が60を示す「ξ」を見間違えて10を示す「ι」としてしまったということは疑えない。このような誤写は聖書の写本では、よく見られることである。つまり、ヨハネがもともと書いたのは666だったが、誰かがそれを不注意から616にしてしまったというわけである。この逆の場合、すなわち本来は616だったが、間違えて666にしてしまったというのは非常に考えにくい。というのも、もし本来の数字が616であれば、10を示すιを60を示すξに見間違えたということになるが、それはあり得ないと思われるからである。それだから、主要な校訂本文でも、やはりこの数字は666とされている。先にも書いたように、聖書において666は他の箇所でも記されているが、616のほうはどこにも記されていない。ヨハネは明らかにソロモンに入ってきた『666タラント』からネロの数字を持ってきた。だから、やはり666こそが本来ヨハネの書いた数字だったとすべきである。
―【追記】―
もし『666』がその名前の中に隠されている『人間』が誰かいたのであれば、その人のことを私に教えてほしい。もちろん、それはもしかしたら13章における『獣』であると考えられなくもない、上記で紹介されていない著名な人間だけに限られる。上記で紹介されていたり、無名の人間であれば、あまり考察する意味がないからだ。私は、是非その人間が『666』なのか真面目に考察してみたい。とはいっても、考察する前から既にその人間が『666』でないことは分かりきっているのではあるが。
第16章 ⑬14章1~5節:天国の情景
この箇所は黙示録の中では非常に簡単な箇所である。その難しさを5段階で言えば「1」だと私には思える。とはいっても、もちろん全ての部分がことごとく簡単だというのではない。私が簡単だと言ったのは、あくまでも全体的な意味においてである。
【14:1】
『また私は見た。見よ。子羊がシオンの山の上に立っていた。』
『シオンの山』とは、ここでは天上の御国のことである。旧約聖書では、この言葉は主にエルサレムを指している。これは、神の臨在また神の臨在される場所というふうに捉えれば間違いではない。もともと『シオン』というのは、エルサレムにあった丘の名前であった。それが、いつからかエルサレムの都を呼ぶ名称として転用されるようになった。黙示録の中で『シオンの山』という言葉が書かれているのは、この箇所だけである。旧約聖書ではこの言葉が多く使われているが、新約聖書ではここ以外ではヘブル12:22しか使われていない。この言葉は実に喜ばしい意味内容を持っている。この箇所で言われているのは、つまりキリストが天国で立っておられたということである。ここで「キリストは神の右の座に座っておられるのではないか。どうしてヨハネはキリストが立っておられると言っているのか。」と疑問を持たれる方がいるかもしれないが、この疑問は既に解決済みであるから、ここで再び書くことはしないでおく。しかし、どうしてヨハネは単純に「天上において」とか「天国で」などと言わずに、『シオンの山』などとより分かりにくくなるように言ったのであろうか。それは更に黙示録が霊的・象徴的・ユダヤ的・秘儀的な性質を持つようになるためであった。このように書くからこそ、更に黙示録が難解で深遠な測り知り難い文書となるのである。神は、黙示録がそのような文書となるように望まれたのだ。
ヨハネは『見よ。』と呼びかけている。つまり、「天国にキリストが立っておられるのに注目せよ。」ということである。ヨハネはこの光景を見て、大きな感激を持ったのであろう。だからこそ『見よ。』と言ったのである。黙示録で『見よ。』と言われている場合、それが良い意味であれ悪い意味であれ、ヨハネの心が揺り動かされているということは間違いない。ところで、この箇所はバプテスマのヨハネが『見よ、世の罪を取り除く神の子羊。』(ヨハネ1章29節)と言ったのと似ている。
『また子羊とともに14万4千人の人たちがいて、その額には子羊の名と、子羊の父の名とがしるしてあった。』
『14万4千人』とは、7:4~8の註解で説明されたように、救いに選ばれていた全ての人たちを意味している。これは実際の人数を言ったものではなく、多いまたは少ないということを言ったものでもない。具体的に言えばこの『14万4千人』とは、紀元70年9月までに存在していたあらゆる聖徒のことである。何故なら、この14:1~5の箇所では天国が遂に開始された紀元70年9月のことが描かれているからである。これはネロの大患難について預言された13章のすぐ後に描かれているシーンであるから、あたかも「14万4千人として表示されている選びの民に含まれたければネロの大患難に耐え忍ばなければいけないぞ。そうしないと天国はない。」などと言っているかのようである。
この『14万4千人』の聖徒たちは、『子羊とともに』いた。キリストと共にいるというのが、天国の根本的な内容である。ある人はかつて「キリストと共にいるのであれば地獄に落ちても天国である。」と言ったが、この人は天国のことをよく悟れている。確かにキリストが共におられるのであれば、地獄も天国と化すであろう。もっとも、キリストと共にいるようにと定められている人が、地獄に落とされることは決してないのであるが。天国に導き入れられたいと思う人は、キリスト信仰に留まり続けなければいけない。ネロの時代の聖徒が受けた大患難のごとき災いは受けなくとも、この人生における大小様々な患難を耐え忍ばなければ、天国はない。もし忍耐が継続されなければ、紀元1世紀の聖徒もどきがネロの時に脱落したため天国から除外されたように、天国から除外されてしまうことになる。その人は天国で『子羊とともに』立つことがない。
また『14万4千人』の聖徒たちは、その額に神とキリストの名が刻まれていた。天国にいる聖徒たちの額には、誰でも神とキリストの名が書き記されるのである。これについては既に3:12の箇所で説明されたことだから、重複を避けるために再び説明することはしない。ここでは3:12とは違い、『新しいエルサレムの名』が刻まれることについては省かれているが、これは特に問題にはならない。何故なら、ここでは神と聖徒たちという人格的存在者に焦点があてられているのであって、ここは場所について焦点があてられた箇所ではないからである。この聖徒たちのようにやがて額に神とキリストの名を受けたいと思う聖徒は、キリストという岩に立ち続けなければいけない。主の所有物であることを示す名を額に刻まれるのは、主から離れなかった者だけに限定される。もし主から離れるというのであれば、その人はむしろ地獄に行ってサタンの名をその額に受けるであろう。そのような人はサタンの所有物に他ならないのだから。
【14:2】
『私は天からの声を聞いた。大水の音のようで、また、激しい雷鳴のようであった。また、私の聞いたその声は、立琴をひく人々が立琴をかき鳴らしている音のようでもあった。』
天から鳴り響いた『声』の主は、天にいる『14万4千人』の聖徒たちである。何故なら、ここは天上の聖徒について語られている個所だからである。つまり、これは4人のセラフィムやセラフィム以外の御使いたちが発した声ではない。この箇所は、彼らについて語られるべき箇所ではないのだ。この箇所は、13章でネロによる大患難が預言されてから後に記された箇所だから、つまり聖地たちがその大患難に耐えたならば天国に導き入れられると言われた箇所だから、確かにこのように言うことができる。聖書の他の箇所でもみなそうだが、黙示録においては、文脈をよく弁えつつ読まなければいけない。
この天の聖徒たちが『大水の音のよう』な声を出していたというのは、つまり大勢の人たちが声を同時的に発しているということを示す。12:15~16の箇所では『大水』という言葉で多くの非再生者たちが示されていたが、ここではその量的な多さを示すためにこの言葉が使われている。もしそうでなければ、天の聖徒たちが非再生者であるか、またはその心が実に騒がしいということになるが、それはあり得ないことである。また聖徒たちの声が『激しい雷鳴のよう』だったのも、その声の大きさを教えている。天の聖徒たちはたくさんいただろうから、その発された声が『激しい雷鳴のよう』に聞こえたというのは自然なことである。つまり、そこでは少しの声だけが発されていたのではない。『立琴をひく人々が立琴をかき鳴らしている音のよう』であったのは、天の聖徒たちが『立琴をかき鳴らして』神を賛美していたということである。天の聖徒が立琴により神を賛美していたということは決して疑えない。何故なら、詩篇では『十弦の琴と立琴をかなでて、神をほめたたえよ。』(150:3)と言われているからである。地上にいる聖徒にさえ立琴を用いて神を賛美することが命じられた。であれば、尚のこと、天の聖徒たちは立琴で神を賛美するはずである。実際、15:2の箇所では天国にいる聖徒たちが『神の立琴を手にして』いたと書かれている。このように、この箇所では天の聖徒たちが3通りの言い方により説明されていることが分かる。
【14:3】
『彼らは、御座の前と、4つの生き物および長老たちの前とで、新しい歌を歌った。しかし地上から贖われた14万4千人のほかには、だれもこの歌を学ぶことができなかった。』
天に導き入れられた『14万4千人』の聖徒たちは、天で『新しい歌を歌った』。この『新しい歌』については、5:9の箇所で既に説明されたから、ここで再び説明することは不要であろう。もし再び学びたければ、当該の箇所に戻って読み直せばよい。
しかし、どうして天の聖徒以外には、この『新しい歌』を『学ぶことができなかった』のか。それは、この歌が完全に霊的だったからである。完全に霊的なものは、完全に霊的な人間にしか捉えられない。完全に霊的な人間は天国に導き入れられた天国の聖徒の他にはいない。だから、この『新しい歌』は天の聖徒にしか悟り得なかったのである。もし地上の聖徒たちも完全に霊的であったとすれば、地上の聖徒もこの歌を学ぶことが出来たであろう。ところで、どうして完全な霊性を持っていなければ完全に霊的な歌を学べないかと言えば、まだ罪の残滓がある人間精神によっては、完全に霊的なものを把捉することが原理的に出来ないからである。それは悪魔的な人間が自己を犠牲にしてまで正義を追求する人間の善性をどうしても理解できないのと同じである。悪魔的な人間にとっては、そのような善性ははっきり言って馬鹿げたものである。それと同様に、地上の人間の持つ罪とは無関係ではない不完全な精神は、完全に霊的なものに多かれ少なかれ肉による抵抗感を抱いてしまうものなのである。それゆえ地上の人間が天で歌われる『新しい歌』を学ぼうとしても、完全に学んで十全な知解を持つことは決してできない。
【14:4】
『彼らは女によって汚されたことのない人々である。彼らは童貞なのである。』
ここでは『童貞』という表現により、天の聖徒たちがどれほど清らかであるか示されている。つまり、「天の聖徒たちはあたかも童貞であるかのように清純だ。彼らには一点の染みも汚れもない。」とここでは言われているのである。しかし、この言い方は精神の鈍い我々に理解させようとして言われた言い方であるということに、よく注意せねばならない。何故なら、天の聖徒たちは童貞という概念を超越しているからである。キリストも言われように、天の聖徒たちは『めとることも、とつぐこともなく、天の御使いたちのよう』(マタイ22章30節)である。彼らは結婚しようとか、離婚しようとか、子どもを生もうとか、そのような思いをそもそも持つことさえない。それゆえ彼らには童貞も何もない。彼らは根本的に超童貞的な神聖さを持った存在なのである。だから、この言い方は我々のためになされた言い方であることが分かる。
20世紀になるとユダヤ人が世界中にフリーセックスの概念を普遍化させたので、今や童貞は恥ずべき状態だとさえ思われるようになってしまった。私はネットや学校などで今まで「早く童貞を卒業せねば…」とか「やっと俺も童貞を卒業したぜ。これで一人前になった。」などとユダヤ人の陰謀など何も知らずに言っている男子を多く見てきた。童貞であれば、場合によっては苛められることさえある。これは20世紀になってユダヤ人が性的な腐敗を蔓延させるまでは、まったく考えられなかった現象である。20世紀になるまで、童貞は軽んじられるべきでない徳であった。近代になるまでは、少しでも卑猥なことを語るのさえ顔を赤らめるような傾向があった。同性愛を語ることについて言えば、それは「異常」の域に属することであった。ミシャエル・フーコーもこのことを述べている。近代になって性的な倫理観が破壊されるまではこのようなまともな傾向が世に満ちていたから、16世紀の人であるカルヴァンも、やはり童貞を称賛していた。彼はこう言っている。「わたしとしても、童貞がすぐれた賜物であることは、認める。」(『新約聖書註解Ⅷ コリント前書』7:7 p160 新教出版社)「もしお望みならば、童貞を「第三の天にいたるまで」ほめたたえることもよかろう。」(同 7:8 p161)―今ではこんなことを言う人はまず見られない。―このカルヴァンの声は、当時の一般的な傾向を反映させており、他の人たちもみなこのように思っていた。ヨハネの時代にあっては、更に童貞を賛美する傾向が強かった。そのため多くの人たちが童貞である者を清らかな者であると見做していた。その傾向は教父たちの時代になっても保たれ、そのためアウグスティヌスやアンブロシウスをはじめとした教父たちはほとんど例外なく独身であり、自分が童貞であることを誇りとしていたほどであった。ヨハネがこの箇所で、天の聖徒たちの清らかさを『童貞』という状態を用いて表現したのは、このような時代性が背景にあることを弁える必要がある。ヨハネの時代にあっては、『童貞』において清らかさを言い表わすのは実に適切であった。だから我々は、性的に狂った観念が普遍化してしまった今の時代性を通して、この箇所を捉えようとしてはいけない。もし今の時代性を通してこの箇所を捉えるならば、「童貞なんて情けないじゃないか。どうして天の聖徒たちは一人前の男になれなかったのだろうか…。」などと、とんでもない思いを抱いてしまうことにもなりかねないのだ。それゆえ、我々は今の時代性を無視して超越的になり、この箇所を読んで「天の聖徒たちは童貞として表現されるほどに清純な性質を持っていたのだ。」などというように思うのが望ましい。
この箇所を読んで、天の聖徒たちが、地上で『童貞』だったと考える人がもしかしたらいるかもしれない。童貞また独身を高く見ていたアウグスティヌスは、どうやらそのように考えていたように思われる。彼はこの箇所について次のように言っている。「それゆえに同じ使徒の黙示録に出ているあの14万4千人の聖徒は女に触れて身を汚していなかったし、実際、彼らは童貞にとどまっているのであるが、また彼らは咎められることがなかったがゆえに、彼らの口には偽りは見いだされなかった(黙14・3―5参照)。」(『アウグスティヌス著作集29 ペラギウス派駁論集(3)』罪の報いと赦し、および幼児洗礼 第2巻 第7章 第8節 p98:教文館)しかし先にも述べたように、ここでは『童貞』という表現で天の聖徒たちの清らかさが示されているに過ぎないのであって、彼らの地上での状態がどうだったか教えられているわけではない。この『14万4千人』の聖徒たちは、地上に生きている間、妻帯者だった人もいれば独身だった人もいたことであろう。もっとも、彼らにおける妻帯者と独身の比率がどれほどであったかは分からないのではあるが。ここで『童貞』と言われているからといって、この聖徒たちにおける地上での状態が実際にどうだったかは分からない。『童貞』でないからといって、地上では清らかな歩みをしていなかったということにはならない。妻帯者であっても、敬虔な人は敬虔である。例えばモーセやアブラハムやノアがそうである。彼らは女の経験を持っていた。これとは逆に童貞であるからといって、必ずしも清らかだということにはならない。童貞ではあるが、神の御前に邪悪である愚者など世の中にいくらでも存在しているからだ。それゆえ我々はここで言われている天の聖徒たちにおける地上での敬虔を判定する際、性交渉の有無に基づかせて判定しようとすべきではない。
ここでは性交渉について『女によって汚され』ることだと書かれているから、性交渉が邪悪なものとされているように見えなくもない。だから、この箇所を読んで、性交渉を悪く見做すようになる人も中にはいるかもしれない。「性交渉とは『女によって汚され』ることだから罪なのであって、避けるべきである」と。しかし、ここでは性交渉が汚れたものだとされているわけではない。この営みが邪悪なものでないことは、堕落前のアダムにさえ性交渉が命じられていたことから明らかである。また、神が性交渉を行なうようにと夫婦に言われたことからも、その営みが悪でないことは明らかである(出エジプト21:10、箴言5:18~19)。神は詩篇97:10で『悪を憎め。』と言われた。もし性交渉が憎むべき悪であれば、悪を憎まれる神は性交渉をすべきではないと人間に厳命しておられたであろう。しかし、神はそのようには命じておられない。この箇所では、天の聖徒たちの清らかさを示すために、このように言われたということを覚えねばならない。つまり『童貞』という状態がより清らかに感じられるように、あえて性交渉における交わりが汚れたものに仕立て上げられているに過ぎない。性交渉を引き下げれば、それだけ対極の概念である童貞がその清らかさにおいて高められることになるからである。性交渉自体について言えば、もしそれが夫婦間においてなされるものであったならば、それは神の定められたこと、良いこと、祝聖されたこと、である。それゆえ我々はこの箇所を読んで、正しく行なわれる性交渉まで邪悪視することになってはいけない。
『彼らは、子羊が行く所には、どこにでもついて行く。』
天にいる聖徒たちは、キリストの後について歩む。つまり、天の聖徒たちはキリストの意に徹底的に服従する。何故なら、『どこにでもついて行く。』とは、すなわち完全な服従を意味しているからである。天の場所でキリストについて行きたい、すなわち服従したい聖徒たちは、地上にいる今の時点から既にキリストに服従しつつ歩まねばならない。今の時点から既に服従するという小さなことさえ出来なければ、やがて天の場所でキリストに服従するという大きなことは、とてもではないが出来ないであろう。何故ならキリストが言われたように、『小さい事に忠実な人は、大きい事にも忠実であり、小さい事に不忠実な人は、大きい事にも不忠実』(ルカ16章10節)だからである。
この箇所は詩篇23篇と、かなり似ている。羊がキリストであるか聖徒であるか、という違いはあるものの、キリストが聖徒たちを牧者として導かれるという点ではどちらも同じことを言っている。
『彼らは、神および子羊にささげられる初穂として、人々の中から贖われたのである。』
贖われて天に導き入れられた聖徒たちは、神とキリストに捧げられた存在である。ゆえに彼らは完全に神とキリストの所有物とされている。だから、天の聖徒たちは、神に捧げられた存在に相応しく、自分の王であるお方にいついつまでも忠実に従い続ける。彼らは主に捧げられた存在なので、神とキリスト以外のために自分を使うことが許されていないのである。彼ら自身も、神とキリストにこそ幸いがあることを知っているので、喜びを持って服従する。要するに、天に導き入れられた聖徒たちには、次の御言葉が完全な意味において確かなものとされるのである。『私たちは主のも、主の民、その牧場の羊である。』(詩篇100:3)この御言葉は地上に生きる聖徒たちにおいてさえも既に確かなものであるから、天にいる聖徒たちには尚のこと、この御言葉が確かなものとされるのである。
紀元70年9月の時点で天に導き入れられた聖徒たちは『初穂』であると言われている。これは明らかに律法から取られた言葉である。律法では次のように言われている。『あなたの土地の初穂の最上のものを、あなたの神、主の家に持って来なければならない。』(出エジプト23章19節)この『初穂』とは、すなわち「最初」「それ以前にはなかった」「第一番目」などという意味で使われている。つまり紀元70年9月の時点で天に入れられた聖徒たちは、天国に御霊の身体を持って入った初めての人たちだったということが、ここでは言われている。彼らは言わば「初代組」だと考えればよい。他の例で例えるならば、彼らはピルグリムファーザーのようなものである。メイフラワー号に乗った人々が初代のアメリカ人と見做せるように、ここで書かれている聖徒たちも天国における初代―『初穂』―の人々であった。
この時よりも後の時代に天国に入る聖徒たちは、もちろん『初穂』ではない。彼らの場合、初代組のように大勢で一挙に天国に入場するということはない。初代組よりも後の時代に生きる聖徒が地上を去った場合、一人一人が個別的に天国へ入場することになる。だから、人それぞれ天国に入る時期がまったく違うということになる。しかし、ある一定の地域で多くの聖徒たちが同時的にこの世を去る場合は、この限りではない。その場合は、限られた一定の人数ではあるが、その時にこの世を去った聖徒たちが一挙に天に入場することになる。もっとも、そのようなケースは、例えば大虐殺や大事故が起きた場合など珍しい出来事が起きた時だけである。通常の場合、紀元70年9月以降に生きている聖徒たちは、ただ1人だけで天に召されることが多いというのは誰でも分かることであろう。それだから我々は、紀元1世紀における「初代組」は一挙に、それ以降の聖徒たちは個別的に、天に挙げられると考える必要がある。21世紀に生きる我々が、あの時の聖徒たちのように一挙に天に導き入れられるということはない。
【14:5】
『彼らの口には偽りがなかった。彼らは傷のない者である。』
天の聖徒たちは、キリストが『その口に何の偽りも見いだされなかった』(Ⅰペテロ2章22節)ように、その『口には偽りがなかった』とここでは言われている。彼らは『偽証してはならない。』という戒めを完全に守り行なう。永遠に至るまでも、である。また『彼らの口に偽りがなかった。』ということは、すなわちその心にも偽りがなかったことを意味している。何故なら、キリストが言われたように『人の口は心に満ちているものを話す』(ルカ6章45節)からである。つまり、天の聖徒たちは心が清らかなので、その心に基づいて口から出てくる言葉も清らかだったというわけである。御霊の身体を受けた天の聖徒たちは、このようである。彼らは口も心もみな清い。やがて、このようになりたいと願う聖徒は倒れないように気をつけねばならない。しっかりと立ち続ける聖徒たちだけが、清い口と心とを持つ御霊の身体をやがて受けることになるのだから。
天にいる聖徒たちは完全に『傷のない』状態となる。『傷』とは罪のことを言っている。つまり、天の聖徒たちは徹底的に神の律法を一点の落ち度もなく守り続ける。彼らが罪を犯して傷を負うことは決してない。この『傷』を、「あざ」とか「擦り傷」などといった身体的なものと捉えるべきではない。これは明らかに倫理的なもの、また神の御前における子としての清らかな状態について言われたものだからである。もちろん、天の聖徒たちは『太陽のように輝き』(マタイ13章43節)を持つことになるから、身体面においても何の傷も持たないようになると予想されるのではあるが。しかし、ここではあくまでも「義」に関して言われていることに留意しなければいけない。
第17章 ⑭14章6~13節:裁きの日に向けた色々な預言
この箇所は4つに区分できる。一つ目の預言は14:6~7であって第一の御使いにより、二つ目の預言は14:8であって第二の御使いにより、三つ目の預言は14:9~12であって第三の御使いにより、四つ目の預言は14:13であって天からの声と神の御霊による。神の御霊による預言が最後の第4番目に置かれているが、神であられる御霊が軽んじられているわけではない。ただ順序の関係上、神の御霊による預言が第4番目に置かれるべきだっただけである。黙示録を我々が十全に理解できるよう、一つ一つの預言が解き明かされなければいけない。
この14:6~13の箇所は、悟りを持ってさえいれば、それほど解釈するのが難しい箇所ではない。12章に比べれば簡単である。しかし、神の恵みがなければ、このような簡単な箇所であっても何ら解読できないことを我々は忘れてはいけない。あらゆる解読は神の恵みによる。神の恵みによらねば、我々はこのような簡単な箇所でも、誤ること以外にはまったく出来ないのだ。実際、今までにいた聖徒たちはこの箇所を、それが黙示録の中では簡単なほうに入るにもかかわらず、何も解読できていなかった。
【14:6】
『また私は、もうひとりの御使いが中天を飛ぶのを見た。彼は、地上に住む人々、すなわち、あらゆる国民、部族、国語、民族に宣べ伝えるために、永遠の福音を携えていた。』
『もうひとりの御使い』とは、どのような存在か。これは「今までには登場していなかった新しい御使い」という意味である。ヨハネはこれまでとは別の御使いであることを示そうとして『もうひとりの御使い』と言っている。この新しい御使いがどのような名を持っているのか、またどのような役割を本来的に持っている御使いなのか、我々には何も知らされていない。しかし、たとえ知らなかったとしても解釈上の問題が起こるというのではないから、好奇心の強い詮索好きな者でない限り、知らなかったとしても特に問題とはならない。
この御使いが人々に『宣べ伝えるために、永遠の福音を携えていた』とは、どのような意味か。これは、この御使いが、使徒をはじめとした多くの聖徒たちが行なう福音宣教の働きに共に参与していたという意味である。確かに御使いは、福音を宣べ伝える宣教者たちと共に働いているのだから、御使いも人々に宣べ伝えるために福音を携えていたと言われるのは間違っていない。もちろん、実際的な意味において直接的に御使いが、福音を人々に宣べ伝えるというのではない。それは人間がすることだからである。御使いは『仕える霊』(ヘブル1章14節)であって、肉体を持っていないのだから、そもそも実際的な意味において福音を伝えることはできない。しかし、霊的な意味において言えば、御使いも直接的に福音を人々に宣べ伝えている。この箇所は、私が今述べたようにしか解釈できないであろう。この解釈の他に、まともだと感じられるような解釈は恐らくないと私は思う。
『永遠の福音』とは、福音の永遠性について教えている言い方である。「永遠の救いをもたらす朽ちることのない福音」と言い換えれば分かりやすい。確かに、福音のもたらすキリストの救いは永遠の効力を持っているのであって、それは決して損なわれたり効力が減じたりすることがない。
『あらゆる国民、部族、国語、民族』とは、先に見た13:7とは違って、文字通りに捉えねばならない。何故なら、福音が宣べ伝えられ対象はローマ世界を越えているからである。外典によればトマスはインドにまで行ったという。中国や日本にも、紀元1世紀の聖徒たちが宣教に行ったはずである。この時に聖徒たちは、ピリポの例が示すように瞬間移動さえ出来たのだから(使徒行伝8:39~40)、確かにこのように言うことが出来る。これをローマ世界に限定すべきではない。しかし、この箇所と同じ言葉が使われている13:7の場合は、文字通りに捉えてはいけない。何故なら、その13:7の箇所で言われているネロの支配はローマ世界にだけしか及んでいなかったからだ。もしこちらのほうも文字通りに捉えなければいけないのであれば、ネロの支配がローマ世界を超えていたことを証明しなければいけない。もし証明できなければ、私の述べた通りに理解していただきたい。この世で私以上に黙示録のことを考えている人間は他にいないのだ。私は色々と考えた上で、このように言っている。だから、何ら考えもせず私の述べたことを問答無用に拒絶しないでほしいと思う。
【14:7】
『彼は大声で言った。「神を恐れ、神をあがめよ。神のさばきの時が来たからである。天と地と海と水の源を創造した方を拝め。」』
この御使いが『大声で言った』のは、その語られることが非常に重要だったからに他ならない。それが大いに告げ知らされるべきものだったからこそ、自然と『大声』で言われることになったのである。聖書において『大声』で語られている言葉は、どれもそれが重要であることを我々に教えている。
『神のさばきの時』とは、再臨の起こる紀元68年6月9日からエルサレムが陥落する紀元70年9月までの期間を言っている。これは、この期間が大まかに捉えられた言葉である。聖書において、このように大まかにある期間を捉えている箇所は少なくない。この箇所で、この御使いはもう間もなく裁きが到来するのだから『永遠の福音』を信じ、そして神を恐れ、崇め、その御前に大いにひれ伏すようにと警告している。何故なら、そうしないとキリストが再臨された時に救われなくなってしまうからである。実際、この『さばきの時』までに福音を受け入れなかった者たちは、救われることが出来なかった。繰り返しになるが、この『さばきの時』は既に起きたということを言っておきたい。何故なら、この出来事も含めて黙示録には『すぐに起こるはずの事』(1:1)が記されているからである。ヨハネが黙示録を書いている時点で『神のさばきの時が来た』と言われているのだから、まだその時が2000年経過しても来ていないと考えることはできない。なお、ここで『神を恐れ、神をあがめよ。』とか『拝め。』などと言われているのは、「救い」のことである。というのは救われなければ神を恐れたり、崇めたり、その御前にひれ伏したりすることはないからである。このような言葉が救いを意味しているというのは、ルターの見解でもある(これについては彼がマタイ5:16について解き明かした説教を見よ)。救われていない者が、真の意味において神を恐れたり崇拝したりすることは出来ない、ということは少し考えればすぐに分かるであろう。何故なら、救われていない者は神とまだ和解しておらず、敵対関係にあるのだから。敵である存在を、それが敵であるにもかかわらず、どうして敬虔な態度で恐れたり崇拝したり出来るであろうか。
ここで御使いが言っている『天と地と海』という言葉は、誰でも分かる。しかし『水の源』とは何か。これも『天と地と海』と同じように『創造』されたものだと言われている。これは、あの大洪水の時まで大気圏の場所にあった巨大な水の壁を指していると私は考える。この空にあった大水は、紀元前2300年ぐらいの時に大雨となって地に降り注いで大洪水を引き起こしたから、今となってはもう存在していないし、多くの人はその存在さえ知らない。しかしこの大水がかつて空に存在していたことは、創世記を見れば誰でも分かることである。この大水は大雨を生じさせた根源だったのだから、『水の源』と言われるのは適切である。それでは一体どうして、御使いはここで既に消失している『水の源』について言ったのか。それは、もう間もなく起こる「裁き」についての認識を強めさせるためである。この『水の源』があの巨大な水の壁だと分かれば、誰でもノアの大洪水という裁きを思い浮かべるように思考が導かれる。何故なら、その大水と大洪水の裁きは切っても切り離せない関係を持つからである。そのようにしてノアの大洪水という裁きを思い浮かべれば、もう間もなく実現される裁きに対する意識もより強められることになる。何故なら、もう間もなく実現される裁きと大洪水という裁きは、どちらも「大きな裁き」という点では一致しているからである。要するに、ここで御使いは潜在的に裁きへの意識が強められるようにこの言葉を使ったのだ。このような目的のために、ここでは『水の源』という既に存在していない被造物があえて言及されることになったのであろう。それだから、この言葉が、雨という水を生じさせる神という発生源を象徴させた言葉だと受け取るべきではない。確かに神は雨を生じさせるお方だから、象徴的に言えば、神も『水の源』だと言うことができる。しかし、ここではそのように捉えてはいけない。何故なら、ここでは被造物のことが言われているからだ。すなわち、ここで言われているのは比喩や象徴ではない。『天と地と海』と3つ続けて被造物が出て来たのだから、4つ目の『水の源』も前の3つと同様に被造物だと考えるべきである。
【14:8】
『また、第二の、別の御使いが続いてやって来て、言った。「大バビロンは倒れた。倒れた。激しい御怒りを引き起こすその不品行のぶどう酒を、すべての国々の民に飲ませた者。」』
『第二の、別の御使い』も、やはり新しく登場した御使いである。この第二の御使いは、ここでユダヤの陥落について預言している。それはウェスパシアヌスに遣わされていたティトゥスを通して紀元70年9月に起きたことである(※①)。なお、ユダヤはこの時、もしユダヤに来たウェスパシアヌスに恭順の印として矢を差し出せば、破滅を免れることが出来ていた。しかし、彼らは神の裁きを受けるべく定められていたから、そのようなことは決してしなかった(※②)。17章で詳説されるが、この『大バビロン』とは「ユダヤ」を意味している。これは「ローマ」ではないから注意されたい。また、この御使いはユダヤの裁きを2回も繰り返すことで強調している。それはユダヤの裁きが非常に大きな出来事だったからである。それが大きな出来事だからこそ、それを強く認識させるべく2回も『倒れた。』と繰り返したのである。18:2の箇所でもバビロン=ユダヤの裁きが、この箇所と同じように強調されている。
(※①)
このユダヤ制圧に関するスエトニウスの記述はこうである。「…ティトゥスはユダヤを完全に征服するために現地に残り、イェルサレムを最終的に包囲攻撃したとき、抵抗した敵を自らも12人、同数の矢で射殺した。この市をティトゥスは娘の誕生日に占領する(70年9月2日)。」(『ローマ皇帝伝(下)』第8巻(承前) ティトゥス p297:岩波文庫)
[本文に戻る]
(※②)
タルムードの中では次のように書かれている。「さて、ウェスパシアヌスはエルサレムを滅ぼすためにやって来た時(※紀元68年の春)、その住民に言った。「愚か者よ、なぜお前たちはこの町を滅ぼすことを求め、また神殿を焼くことを求めるのか。お前たちが一張の弓もしくは一本の矢をわたしに送ってよこせば、わたしはお前たちから立ち去るということ以外に、わたしはお前たちに何を求めているというのか。」」この言葉に対するユダヤ人の答えはこうであった。「わたしたちはあなたの前にいた最初の2人に立ち向かって行って彼らを殺したように、あなたにも向かって行ってあなたを殺すでしょう。」(『タルムード ネズィキーンの巻』アヴォード・デ・ラビ・ナタン 第4章 20a 5 p28:三貴)
[本文に戻る]
ここではユダヤに裁きが下された理由が語られている。ユダヤに裁きが下されたのは、ユダヤが霊的な不品行という名の罪深いぶどう酒を、他の国々の民と共に飲んで酔ったからであった。ここでは、そのことが『激しい御怒りを引き起こすその不品行のぶどう酒を、すべての国々の民に飲ませた者。』と言い表わされている。これは結果において語られている表現であることに注意すべきである。つまり、それはユダヤが他の民らと一緒に不品行という名のぶどう酒を飲んだという結果である。ユダヤが実際的な意味において、他の国々の民に対して神に背くようにと不品行を命じたり勧めたりしたというのではない。紀元1世紀までの歴史を見ても、ユダヤがそのような指示を他国民にしたということは確認できない。異邦の民は、そもそもユダヤが何も指示しなかったとしても、既に神に対する霊的な不品行を自主的に犯していた。つまり、この箇所を解読する際、我々は言い方をよく弁えなければいけない。また、ここでは神に背いて不品行に歩むという反逆の罪が『ぶどう酒』を飲むことだと書かれている。これは、つまりユダヤにとって神に反逆することは、あたかもぶどう酒を飲むかのように甘美だったということを示している。神に従わないという罪を喜ばしく感じるほどに当時のユダヤは堕落していたのだ。実際、この時のユダヤは本当に酷い状態にあった。キリストもその腐敗を大いに問題とされた。それは神の『激しい御怒りを引き起こす』ものであった。カルヴァンも言うように、この時のユダヤの時代は「ものごとが堕落のきわみに達し、ほとんど混沌としたありさまを呈していた」(『新約聖書註解Ⅲ ヨハネ福音書 上』5:3 p153:新教出版社)。だからこそ、罪に満ちていたユダヤは紀元70年9月に破滅してしまったのである。この箇所は私が今述べたように解するのが望ましい。なお、聖書では『ぶどう酒』を飲むという表現が使われている箇所が少なくないから、この表現を理解しておくことは有益である。この表現は、どこで使われていても、もしそこで言われている事柄が実現されたならば、あたかもぶどう酒を飲んだ時のように甘美な気持ちになったりフラフラして目茶目茶な状態になってしまうことを意味している。もちろん、これは実際にぶどう酒を飲んだということが言われているのではない。この表現が良い意味で使われることはない。
【14:9~10】
『また、第三の、別の御使いも、彼らに続いてやって来て、大声で言った。「もし、だれでも、獣とその像を拝み、自分の額か手かに刻印を受けるなら、そのような者は、神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのぶどう酒を飲む。』
『だれでも、獣とその像を拝み、自分の額か手かに刻印を受けるなら』とは、先に見たようにネロ崇拝を意味している。これは、今の人たちがやがて現われるだろうと思い違いをしている「滅びの子」―それがEUのリーダーであれ世界政府の首長であれ―に対する崇拝と服従のことではないから、よく注意していただきたい。そのように考えるのは誤りである。ぜひ聖徒たちの目が覚まされるのを願うものである。
ここではネロ崇拝をするならば、神の怒りに満ちた裁きを受けるということが言われている。何故なら、神の裁きを受けるというのは、すなわち『神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのぶどう酒を飲む。』ことも同然だからである。その裁きにおける怒りが『混ぜ物なし』なのは、つまり神の裁きに手加減が全くないということである。神はネロ崇拝をした偽の聖徒たちに、容赦なくその御怒りを注がれた。何故なら、その者たちはキリストよりもネロを上位に置いたからである。神がこのような者に手加減されることはない。また、この御怒りが激しかったことは間違いない。『混ぜ物なし』という言葉からも、そのことは分かる。また、この怒りが『ぶどう酒』を飲むことにおいて語られているのは、この怒りを受けて裁かれた者たちが、あたかもぶどう酒で泥酔したかのように目茶目茶な状態となってしまうからである。要するに、神のこの裁きは凄まじく悲惨な状態をもたらすということだ。この箇所の文章は、難しい表現が幾重にも組み合わされて書かれている。黙示録でこのような文章は少なくない。実に、これこそが黙示録を難解にしている理由の一つであり、また聖徒たちが今まで黙示録を敬遠してきた根本的な要因の一つである。このような難しい表現の組み合わせは、確かなところ、人間の知解におけるキャパシティを越えている。だからこそ、今に至るまで聖徒たちは黙示録の解読に、なかなか取り組めなかったのである。もし黙示録を解読したければ、私がこの註解でよくしているように、まず文章を細かく解体し、その解体した個々の部分を一つ一つジックリと読み解いていくという作業をしなければいけない。そうしたら、その理解できた個々の部分を繋ぎ合わせて全体的な解釈へと帰結させる。我々は、人間の脳が多くの事柄を同時的に処理できないことをよく覚えよう。このことを考えなかったからこそ、今までの聖徒たちは、そもそも最初から黙示録を解読しようともしてこなかった。何故なら、知解のキャパシティを越えた高度な文章が目の前に置かれているので、解読を始める前から既に諦めモードにさせられていたからである(※)。もしこのことを弁えていれば、黙示録は少しずつ読み解いていくべきものであるということが分かっただろうから、ほんの少しずつではあっても、徐々に一つ一つ読み解いていくという作業をすることも出来たであろうに。
(※)
人間の知解能力におけるキャパシティを1だとすると、黙示録の高度な複雑性は100ぐらいであると私は思う。これは目の前に100冊ぐらいの百科事典を置かれて全て理解せよと言うようなものである。そんなことを言われたら誰でも「無理だ」と思うであろう。黙示録に対する聖徒たちの態度もそれと同じであった。誰も彼も「無理だ」と解読を始める前から思っていたので、そもそも解読に取り組むことさえしてこなかった。それゆえ、聖徒たちは一つ一つ黙示録の事柄を根気よく習熟していくようにすべきである。そうすれば、徐々に黙示録の難解さに抵抗を持たなくなっていくであろう。次のポリュビオスの文章は、なかなか参考になるのではないかと思う。「実際、初めのうちは困難いやそれどころか不可能だと思われていたのに、時を経て慣れてくると、いとも簡単に実行できてしまうことは数多くある。この事実を証明する例はたくさんあるけれども、もっともわかりやすいのは文字を読むという行為であろう。いま仮に、文字を知らず読んだ経験もないが、それ以外のことでは利発な男を連れてきて、識字能力をもつ幼い少年のそばに立たせ、それから本を一冊与えて、それを読み上げるよう指示したとしよう。きっとその男は、読むためにはまず文字のひとつひとつの形態に注目し、次にその音価に、その次には文字どうしの結合に注意を払わねばならず、しかもそのいずれにもかなりの時間を要することに驚かされるであろう。それゆえ少年が5行か7行を立ち止まらずに一息ですらすらと読み上げるのを見たときには、少年がその本を読むのは初めてだということがにわかには信じがたいであろう。そして音の調子や区切り、さらに帯気音と無気音の区別まで正確に守れることにいたっては、とうてい信じられないはずだ。だからなんであれ有益なことは、一見したときの難しさに尻込みしてあきらめてしまうのではなく、習熟に努めるべきである。すぐれたものはすべて、それに習熟することによって人間の手に入るのであり、とりわけ安全を支える根幹になるようなことがらにおいては、習熟の度合いがしばしば大きく影響するものだ。」(『歴史3』第10巻:47、5~11 p144~145:京都大学学術出版会 西洋古典叢書 2011第4回配本)
[本文に戻る]
【14:10】
『また、聖なる御使いたちと子羊との前で、火と硫黄とで苦しめられる。』
キリストを否んでネロ崇拝に陥った偽善者たちは、地獄に投げ落とされてしまった。彼らは、紀元68年6月9日に再臨が起きた際、携挙されることなく地上に残され、42ヶ月が経過すると第二の復活に与かり、そうしてから携挙されて空中の大審判を受けて後、『のろわれた者ども。わたしから離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火にはいれ。』(マタイ25章41節)というキリストの宣告と共に地獄に投げ落とされた。この大審判については、マタイ25:31~46および黙示録20:11~15の箇所で詳しく描写されている。ここでは地獄が『火と硫黄』と言われている。地獄に投げ入れれた者たちは、この『火と硫黄』により裁きの苦しみを受けることになる。しかし、そのような苦しみを受けていても、彼らが神に文句を言い立てることはできない。何故なら、彼らは自分のした行ないに対する当然の罰を受けているに過ぎないのだから。また、地獄に投げ入れられた者たちは『聖なる御使いたちと子羊』とに、忌まわしい見世物とされる。とろこで、ここでは『聖なる御使いたち』と言われていることに注意せねばならない。つまり、これは地獄で苦しむ者たちを見物するのが、『聖なる』御使いであって「悪しき」御使いではないということを教えている。ヨハネは、明らかに『聖なる』と書いて、読者が勘違いをしないように、すなわちこれが悪しき御使いのことを言っていると思わないように配慮している。要するに、地獄に投げ込まれた悪者どもは、『火と硫黄とで苦しめられる』だけでなく「恥辱」の苦しみも味わうことになるのだ。彼らは永遠に恥に覆われて、不名誉な存在とさせられる。しかも、地獄での見物人は『聖なる御使いたちと子羊』だけでないと聖書は教えている。聖書によれば、贖われて天に入れられた聖徒たちも、地獄で苦しむ悪者を眺めることになるようである。それは、イザヤがこの地上という場所を出て天国に入れられた聖徒たちについて、次のように言った通りである。『彼らは出て行って、わたしにそむいた者たちのしかばねを見る。そのうじは死なず、その火も消えず、それはすべての人に、忌みきらわれる。』(イザヤ66章24節)地獄に投げ入れられた者たちは、無数の聖徒たちから軽蔑の眼差しで眺められることにより恥辱を味わわされるという刑罰も受けるわけである。なお、この地獄の刑罰は、紀元1世紀にネロを崇めて地獄に落ちた者たちだけでなく、紀元70年9月以降に不信仰なままで地上での人生を終えるあらゆる滅びの子らも同じように受けることになる。何故なら、ここで言われている地獄の刑罰は、当時の人たちだけに限定せず、普遍的に捉えるべきでもあるからである。つまり、ここで言われている刑罰の啓示は、永遠的なものとして拡大解釈してもよい、否、そのように解釈せねばならない。これを疑うまともな聖徒は恐らくいないであろう。
『火と硫黄』という言葉には、2通りの捉え方がある。一つ目は、これが実際的なことを言っていると考える捉え方である。この場合、地獄には本当に『火と硫黄』による裁きの苦しみがあると捉えることになる。多くの人たちは、このように捉えている。私もこの見解を取っている。二つ目は、これを単なる比喩に過ぎないと考える捉え方である。こちらの場合、『火と硫黄』という言葉は、地獄における神の裁きの凄まじさと恐ろしさとを象徴的に言い現わしたに過ぎないと捉え、実際に地獄にこのような物質および現象が見られるかどうかは定かではないと考えることになる。私の見る限り、こちらのほうの見解を持つ人は少ない。しかしながら、カルヴァンがこの見解を持っていたから(※)、やすやすとこの見解を斥けることはせず、斥けるならば大いに考えた上でそうするのが望ましいと私は思う。私としてはこの『火と硫黄』という言葉を実際的に捉えるのが正しいと思うが、これを比喩的に捉える人がいたとしても、それほど激しく非難されるべきではないと思う。何故なら、これを比喩的に捉えたとしても、許すべきでない致命的な誤謬に陥っているというわけではないからである。
(※)
「私たちは聖書の多くの箇所において、火というこの語は比喩的表現であると結論することができる。というのは、それが現実のもの、すなわち、「火」という物質だと信じるならば、イザヤによって共に述べられている「硫黄」や「息」(イザヤ33:33)も具体的なものと信じなければならないからである。そして、実際、見捨てられた者の永遠の苦痛を私たちに理解させるために聖書が語っている「火」と「うじ」は同じように解釈しなければならない。それ故、もしも「うじ」という語に比喩があることをみんなが一致して認めるならば、「火」に関しても同様に言わなければならない。従って、せんさく好きな者たちが何の益もなく心を悩ます思弁は放っておき、そして、聖書はこのような表現によって、私たちの弱い能力に適した仕方で、今は誰も表現できず、また、理解できない恐ろしい苦痛を、私たちに悟らせようとしているのを知ることで満足しよう。」(『新約聖書註解Ⅰ 共観福音書 上』マタイ3:12 p157:新教出版社)―この文章は説得力があるのだが、しかし神がソドムやユダ王国やエルサレム神殿を火の裁きで実際的に焼き尽くされたという事実から考えれば、神は地獄においても実際に火による裁きをお与えになると考えることが出来る、という反論をすることが可能である。いずれの解釈を取るにせよ、これは激しい論争をするほどの問題ではない。なお、参考情報であるが、カトリックの信仰を持っていた奇怪な人エリファス・レヴィもこの地獄の火を単なる比喩として理解していた。
[本文に戻る]
ところで、この箇所で書かれている順序を気にする人がいるかもしれない。すなわち、「どうしてキリストは御使いたちの主なのに、ここでは御使いたちの後ろに置かれているのだろうか…」と。確かにキリストは御使いたちの主であられるから、順序的に言えばキリストのほうが先に置かれるべきであるのは確かである。しかし、このような心配を持つ必要はない。何故なら、ここでは書き記される順序が何も考慮されていないからである。つまり、ヨハネはこの箇所で、ただ思いつくままに文章を書いているに過ぎない。ここではキリストと御使いたちの序列を教えることが目的とされているのではないから、別に順序が考慮されていなかったとしても問題にはならないのである。聖書において、その書かれる順序が、実際の序列を示している箇所は確かに多く見られる。例えばエペソ4:11では、明らかに書かれている順序が、実際に重要である順番通りとなっている。『こうして、キリストご自身が、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師として、お立てになったのです。』ガラテヤ2:9で『柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネが、…』と書かれているのも、恐らく重要な順を反映させている。カルヴァンもこのガラテヤ書の箇所は重要な順に書かれていると考えていた。しかし、我々が今見ている箇所のように、その書かれている順序がまったく重要性における序列を反映させていない箇所も聖書には多くあるから、我々はそのことをよく心に留めておくべきである。
【14:11】
『そして、彼らの苦しみの煙は、永遠にまでも立ち上る。』
地獄に落とされた悪者どもは、『永遠に』苦しめられると、ここでは言われている。『永遠』である。彼らに与えられる苦痛に終わりは来ないのである。それは、彼らがキリストではなくネロを己の主とし、その前に愚かにも屈服したからである。ここではその苦しみが『煙』として語られている。これは地獄では『火と硫黄』による苦しみが与えられるためである。確かに、地獄では燃える火炎がそこにいる滅びの子らを、あたかも燃えても燃え尽きない廃棄物でもあるかのように焼き尽くす。すなわち、そこにいる者たちは第二の復活により永遠に存続する性質を持つ苦しみを受けるために創造された新しい身体を持っているので、いつまで経っても一向に焼き尽くされることがない。そのように火が焼いても焼き尽くされないので、ここではその焼かれることにより生じる煙が『永遠にまでも立ち上る』と言われている。この新しい最悪の身体については既に第2部で触れられたが、再び20章の箇所で詳しく語られることになるはずである。この新しい身体は、聖書から分かる範囲で、よく理解されるべきである。このような永遠の苦しみを受けたくないと願う聖徒は、地獄に落ちないようキリスト信仰に立ち続けなければいけない。
この箇所で書かれている文章は、19:3で書かれている文章とよく似ている。すなわち、19章のほうではこう書かれている。『ハレルヤ。彼女の煙は永遠に立ち上る。』こちらのほうは、ユダヤの大炎上についてである。我々が今見ている14:11のほうは、ユダヤの地が炎に包まれることについて言われているのではなく、キリストを否んだ偽善者どもに対するあの世での裁きについて言われている。つまり、この14:11のほうでは、地上のある場所における大事件が言われているのではない。我々は、この違いを弁えなければいけない。どちらのほうも言われている文章が似ているからといって、一緒のことが言われていると考えたら誤りに陥る。黙示録の中で、文章はそっくりだが、その意味内容は異なっている箇所は少なくないから、我々は理解し間違えないように注意しなければいけない。これは先に見た14:6と13:7が良い例である。そこでは前者が文字通りの全ての民を、後者がローマ世界に限られた全ての民を、それぞれ意味していた。
『獣とその像とを拝む者、まただれでも獣の名の刻印を受ける者は、昼も夜も休みを得ない。』
地獄では、そこに投げ入れられた者たちが『昼も夜も休みを得ない。』とここでは言われている。地獄の住民には、一瞬の安息も与えられはしないのである。これこそ地獄という場所である。これは正に「地獄」と言うのに相応しい場所である。少し考えれば分かるが、これは考えただけでも戦慄する裁きである。存在する事象の中で、これ以上に恐るべきものは他に考えられないほどである。このような場所に不信者が投げ入れられると聞くと、神に対して不平や批判をぶちまける人がいるかもしれないが、彼らが地獄に投げ入れられるのは自業自得であるから、神を悪く言うことはできない。彼らは神とキリストよりもサタンを選択したのだから、その刑罰として『昼も夜も休みを得ない』苦痛を受けるのは当然なのである。神は、ご自身を否んだ者たちが、そのようにして苦しむことを望まれた。人間でさえ憎むべき者に対して「アイツは永遠に苦しんだらいいのに。」などと思うぐらいだから、尚のこと、神は憎むべき者に対してそのように思われるし、また実際そう思われた通りになされる。なお、地獄の住民が昼も夜も四六時中苦しめられるということについては、黙示録20:10やイザヤ66:24の箇所を読んでも分かる。
御使いは、このように言うことで、聖徒たちが苦難の中にあっても信仰に留まり続けるように働きかけている。ここでは次のように言われているかのようである。「いいかね、聖徒たちよ。君たちは、これから訪れるネロの大患難に耐え忍ばなければ『昼も夜も休みを得ない』刑罰を永遠に至るまでも受けることになる。だから、苦難が訪れた際にはよく忍耐しなければいけない。君たちが、そのような刑罰を受けることになるのは本当に悲惨なことだから。」将来に起こる恐ろしい出来事を想定することは、現状の姿勢や精神に大きな変化をもたらす。だから、御使いがこのようにネロの苦難についてあらかじめ警告しておくのは、それを聞いた聖徒たちが信仰を堅くするためには大きな益であったはずである。何故なら、もしネロの苦難に耐え忍ばなければ大きな破滅に至るということを悟るので、より忍耐できるように信仰が堅固になっただろうからである。これは例えるならば、やがて来ると言われている大地震に備えて色々な準備をするようなものである。このように御使いが聖徒に言ってくれたのは、信仰が堅くされることに結び付くのだから、神の恵みによることであった。
【14:12】
『神の戒めを守り、イエスに対する信仰を持ち続ける聖徒たちの忍耐はここにある。』
ネロの42ヶ月間の時に、聖徒たちの持つ信仰の真価が大いに試された。この時において聖徒たちがどのような存在だったのか、豊かに明らかにされた。ある者は非常に強い信仰を持っていたことが、別の者はまあまあの信仰を持っていたことが、他の者は見せ掛けの信仰しか持っていなかったことが、顕わとなった。この時に現われた真の姿は人それぞれ異なっていたが、それは神の恵みが注がれた度合いに応じていた。すなわち、大きな恵みを受けた者は苦しみの中にあっても勇気を失わず、それなりの恵みを受けた者は動揺しつつも信仰に留まり続け、実は恵みを受けていなかった者は完全に脱落した。神は、そのようにしてご自身の牧場にいる羊のような者たちが、振るい分けられることをお望みになった。神は査定人、ネロは査定を委ねられた雇い人、教会員たちは査定される羊たちであった。なお、この箇所では13:12で『ここに聖徒の忍耐と信仰がある。』と言われていたのと全く同じことが言われている。
先に見た12:17の箇所でも『神の戒めを守り、イエスのあかしを保っている者たち』という言葉が書かれていた。この言葉は我々が今見ている14:12に書かれている言葉と同じ内容のことを言っていると思える。しかし、この2つの箇所で言われているのは、実は同一存在ではないことに我々は注意せねばならない。12:17で言われていた人たちは、紀元68年6月9日に復活した聖徒たちが教会から消え去って後に新しく教会に加えられた新生したばかりの聖徒たちであった。この人たちが『女の子孫の残りの者』(12:17)と言われていたのは、つまり荒野の期間に救われた新しい聖徒たちのことである。この聖徒たちが救われた時には、既にネロは再臨により殺されていたから、もうこの世には存在していなかった。一方、今見ている14:12の箇所で言われているのは、これからネロの迫害を受けることになっている復活が起こる前に生きていた聖徒たちである。それは1節前の箇所で『獣とその像とを拝む者、まただれでも獣の名の刻印を受ける者は、…』と書かれていたことから分かる。これは、まだネロが迫害を開始していないということである。だから14:12で書かれている聖徒は、12:17の聖徒とは違い、ネロがまだ生きている間に生きている聖徒のことである。それだから、ほとんど同じ言葉で書かれているからといって、この2つの箇所で言われている人たちが、同一存在であると考えないようにすべきである。もしこの2つの箇所で同じ存在が語られていると考えると、黙示録をよく理解できなくなるであろう。我々は12:17のほうでは14:12に出てくる人たちと区別をつけるために、『女の子孫の残りの者』と言われていることを見なければいけない。もし14:12で出てくる人たちも荒野の期間に救われる聖徒たちのことだとすれば、14:12のほうでも『女の子孫の残りの者』と言われていたことであろう。やはり、本当に黙示録は相対性理論よりも難しい。このような言葉の謎が、読み解こうとする者たちを凄まじい混乱の渦に引き込むからだ。なるほど、これでは今まで聖徒たちが黙示録をまったく理解できてこなかったのも頷ける。
【14:13】
『また私は、天からこう言っている声を聞いた。「書きしるせ。『今から後、主にあって死ぬ死者は幸いである。』」』
ここで言われている『声』の主は誰なのか。これは、父なる神か、キリストか、4人のセラフィムか、セラフィム以外の御使いたちか、24人の長老のどれかである。これらの中の2つ以上の存在が、この声における共通の主だという可能性もなくはない。しかし実際にはどうなのか我々には不明である。この声の主が御霊でないことだけは確かである。これは小さな子どもでも分かるのではないかと思われる。何故なら、御霊は天から出たこの声が言っている言葉を聞かれて、『しかり。』と同意しておられるからである。まさか、御霊なる神がこの声も演じておられたということはないであろう。そのように考えるのは滑稽である。
『今』とは具体的にいつのことなのか。これは、ヨハネが幻を見ているその時における『今』である。すなわち、これは紀元37~41年のいつかにおける『今』である。このように捉えないと、この『今』という言葉を正しく理解することはできない。黙示録において『今』という言葉は、ヨハネが幻を見ているその時における『今』だということに気付くべきである。17:8、10~11で『今』と言われているのも、そうである。これを我々が生きている21世紀の『今』だと捉えることは愚かの極みである。
どうして『今から後、主にあって死ぬ死者は幸い』なのであろうか。それは、もう間もなく復活が実現されることになっていたからである。たといネロによる苦難を受けて死んだとしても、すぐにも聖徒たちには復活の恵みが与えられることになる。ネロによる苦難が始まる前に死んだ人も、もちろんそうである。その時間的な間隔は、もっとも長い人であっても約30年であった。何故なら、ヨハネがこの幻を見てから再臨に伴う復活が起こるまでの期間は約30年だからである。ヨハネがこの幻を書いている最中に聖徒たちが誰か死んでも、約30年後には復活できるのだ。これは実に短い期間である。一瞬と言っても誤りではない。このようにヨハネがこの幻を見た時には、もう間もなく復活が実現されることになっていたのであって、それはずっと後のことではなかった。つまり、ここでは「たとえ死んだとしても間もなく復活できるのだから、死ぬことがいったい何だと言うのか?間もなく復活できるのであれば死ぬことさえも幸いであると言えないだろうか。」と言われていることになる。だからこそ『今から後、主にあって死ぬ死者は幸い』なのである。この復活が紀元68年6月9日に起こって以降、地上に住む聖徒たちは、死んだらすぐにも復活できるようになった。もはや、彼らは旧約時代の時のように、死んでも魂だけの状態になることはないのだ。今や、既にそのような方式に変わった時代が到来している。聖徒である我々も、これからこの世を去ったら、即座に復活の恵みに与かるであろう。我々はもはやかつての聖徒たちのように、死んでも魂だけの状態に留め置かれることがない。というのは、パウロも言ったように、我々は死と共に『たちまち、一瞬のうちに』(Ⅰコリント15章52節)新しい身体に切り替えられつつ携挙されることになるのだから。だから、我々はこのことを、キリストにあって神に感謝すべきであろう。また、ここでは、死んでからまだ復活まで幾らかの待機期間が存在している聖徒たちでさえ、死ぬことは幸いであると言われている。であれば、死んだら待機期間など抜きに即座に復活の恵みに与かれる我々は、どれだけ幸いなのであろうか。この時の聖徒たちは死んだらまだ復活しないが、我々は死んだらすぐにも復活する。それゆえ、我々はこの時の聖徒たちよりも遥かに死における幸いの度合いが高いと言わねばならない。ところで、ここで『死者』と言われているのは、明らかに地上に生きる生身の聖徒たちを指している。これは霊的な死人である不信者のことではない。何故なら、彼らにとって死は幸いでないからである。死んだら地獄に投げ込まれる不信者たちが、どうして死において幸いを持っているであろうか。またこれは文字通りの死人のことでもない。何故なら、文字通りの死人は既に死んでいるので、もはや死ぬことができないからだ。それではどうしてここでは聖徒たちが『死者』などと言われているのか。ここでは復活した状態こそが「生命」だと定義されていることに注意しなければいけない。復活した状態こそが「生きていること」だと定義すれば、まだ復活していない状態は「死んでいること」として定義すべきことになる。聖徒たちは言うまでもなくまだ復活していない状態だったのだから、ここでは「まだ復活していない」という意味において『死者』と言われているわけである。要するに、この『死者』という言葉は言い換えれば「未復活の状態にある者」ということになる。
どうして、この言葉を『書きしる』すべきだったのか。その理由は何か。このように書かれるべきだったのは、聖徒たちが死んでから間もなく復活できるということを知って、その信仰に益がもたらされるためであった。間もなく復活できるのだから死さえも幸いであると聞かされたならば、やはり信仰が強まり、精神がより堅固になるのは目に見えている。黙示録を読んだ紀元1世紀の聖徒たちの中には死を軽んじたり、死を望みさえする聖徒も現われたであろう。そのような目的のために、ここではこのようなことが書かれた。もしこれが書かれなかったとすれば、より信仰が強められることにはならなかったはずである。何故なら、その場合、死んでもすぐに復活できるから幸いであるということが、強く感じられないままとなってしまうからである。その場合、希望が弱いままとなるのだから、必然的に信仰も強くなるようにならない。
ここで書き記すようにと言われている言葉は、恐らく詩篇116:15の『主の聖徒たちの死は主の目に尊い。』という御言葉と対応していると思われる。何故なら、どちらも言われていることが似通っているからである。黙示録は、旧約聖書と対応している箇所が無数に見られる文書である。だから、この箇所もその一つである可能性がいくらかでもある。
『御霊も言われる。「しかり。彼らはその労苦から解き放されて休むことができる。彼らの行ないは彼らについて行くからである。」』
御霊も『しかり。』と言われ、先に天の声が語ったことに同意しておられる。つまり、これは先に語られた言葉が強調されていることを意味する。御霊もこのように同意して下さったのだから、ここで言われていることを聞いた聖徒たちは大いに信仰の益を受けたはずである。というのも御霊とは神であられ、聖徒たちの主だからである。
ここで御霊が言っておられるのは、つまり「忍耐する敬虔な聖徒たちは、その労苦や信仰の振る舞いが、やがて永遠の安息となって自己自身に帰って来るであろう。」ということである。『行ない』また『労苦』とは、聖徒たちの忍耐や敬虔な言動を意味している。『ついて行く』また『解き放されて休むことができる。』とは、聖徒たちに永遠の安息が与えられる、また聖徒たちの苦労は無駄に終わらない、ということである。ここで御霊が言われたことは、あらゆる時代の聖徒たちにも言われていると理解されるべきである。紀元1世紀以降に生きる聖徒たちも、その人生における苦労や忍耐が無駄になることはなく、やがて天において永遠の報いとしてそれらの果実を受け取ることになるのだ。神は、聖徒たちの行ないや敬虔な歩みを忘れられず、それを必ず顧みて下さる。ヘブル6:10。しかし、滅びの子らはそうでない。汚れた彼らの地上における労苦や忍耐は、神の御前に根本的に忌まわしいものだから、祝福を持って報いられるどころか、永遠の苦しみとなってその果実を受け取らされることになるのだ。すなわち、彼らはその労苦から解き放されて休むことができず、彼らの行ないは悪い意味において彼らについて行く。このようになりたくない聖徒たちは、信仰から落ちてユダのようにならぬよう注意すべきだ。
それにしても御霊がこのように聖徒たちに言って下さったのだから、聖徒たちがそれを聞いて大いに励まされたのは間違いない。神なる御霊がこのように言って下さったのである。であれば、どうして聖徒たちの信仰に益がもたらされないはずがあるだろうか。なお、黙示録の中で、明瞭に御霊が語っておられることが分かるのはこの箇所だけである。それ以外の箇所では『御霊も言われる。』などというような文章は見られない。とはいっても、我々は、そもそも黙示録自体が御霊の御言葉であると理解すべきである。何故なら、これは黙示録以外の聖書の巻でも同じことが言えるのだが、黙示録という文書は全て、御霊がヨハネを通してお書きになったものだからである。御霊はご自身の御姿をこの黙示録の御言葉により現わしておられる。
最後に、この箇所(14:6~13)で書かれている内容をおさらいすることで、この箇所における註解を終わることにしたい。それは、そのようにおさらいすることで、我々がますます豊かにこの箇所を把捉できるようになるためである。私の経験からも確かに言えるのだが、黙示録の理解のためには復習が絶対に必要である。復習を抜きにすれば、より高次の理解に行き着くことは難しいであろう。というわけで、この箇所の内容を纏めると以下のごとくであった。
■第一の預言 第一の御使いからこの世の人々へ―「裁きの時が間近に迫っているから福音を受け入れるように」(14:6~7)
■第二の預言 第二の御使いからユダヤへ ―「もう間もなくお前たちには裁きが下されるであろう」(14:8)
■第三の預言 第三の御使いから聖徒たちへ ―「これからネロの苦難が訪れるからしっかりと忍耐するように」(14:9~12)
■第四の預言 天の声と御霊から聖徒たちへ ―「あなたがたは間もなく復活の恵みに与かれるようになる」(14:13)
第18章 ⑮14章14~20節:2度の携挙
それにしても、このように携挙の出来事が詳しく描写されたのは、本当に驚きである。というのも、ここでは携挙の出来事が実に精確に預言されているからである。この描写以外も黙示録では同じことが言えるのだが、黙示録を読み解けるようになると、どれだけ黙示録に書かれている預言の描写が精確であるかがよく分かるようになる。これは黙示録が神により書かれた文書だからに他ならない。もし神が記されたのでなければ、どうしてこんなにも精確に携挙やそれ以外の出来事について書き記せるであろうか。従って、それらの記述は神の霊による神聖で崇高な預言の記述だということになる。それだから、我々はダビデと声を合わせ、この黙示録における御言葉を主にあって賛美せねばならない。『神にあって、私はみことばをほめたたえます。主にあって、私はみことばをほめたたえます。』(詩篇56篇10節)
【14:14】
『また、私は見た。見よ。白い雲が起こり、その雲に人の子のような方が乗っておられた。』
『白い雲が起こり』とは、再臨のことである。キリストは、ご自身の前にいた人たちに向かって、次のように言われた。『なお、あなたがたに言っておきますが、今からのち、人の子が、力ある方の右の座に着き、天の雲に乗って来るのを、あなたがたは見ることになります。』(マタイ26章64節)ヨハネもキリストの再臨について言っている。『見よ。彼が、雲に乗って来られる。』(黙示録1章7節)再臨の際には『白い雲』が伴うということは、既に第二部で詳しく見た通りである。
『人の子』とは、もちろんキリストである。『のような』と書かれているが、これはヨハネに与えられた視像が、クッキリとした形を持っていなかったからである。つまり、やや「もやもや」していたということだ。この幻がそのようにやや曖昧に認識されてしまうものだったとしても、それがキリストであったことは間違いない。誰がこのことを疑うであろうか。それだから、もしこの幻が「もやもや」していなければ、ヨハネは『のような方』という言葉は省いていたであろう。
このように再臨の出来事が、ここで書かれたのも、やはり聖徒の信仰に益を与えるためである。先の箇所(14:6~13)で裁きの時に向けた預言がなされた後で、このように再臨の出来事が預言されたのだから、聖徒たちはこの再臨の出来事をより強く心の中で感じ、更に裁きの時に向けてその信仰を堅くすることが出来た。つまり、ここではこのように言われているかのようである。「聖徒たち。これから再臨が起こるのだから、あなたがたは、ますます裁きの時に向けて忍耐を強くしなさい。たとい苦難が降りかかって来ても、あなたがたの待ち望んでいる幸いな再臨がすぐに起こることになるのだから。その再臨の時、あなたがたは携挙されることになるのを知っているはずだ。」再臨と裁きの時という2つのものは、切っても切り離せない関係がある。それゆえ、裁きの時について預言がされた後に、再臨のことが預言されたのは実に適切であった。
『頭には金の冠をかぶり、手には鋭いかまを持っておられた。』
キリストが『金の冠をかぶ』っておられたのは、キリストの朽ちぬ王権を示している。キリストが『冠』をかぶっておられるというのは、6:2、19:12でも言われている。冠が『金』だったのは、キリストの王権が朽ちず、いつまでも保たれ、また輝かしいということである。要するに、キリストが『金の冠をかぶ』っておられたというのは、キリストが王として再臨されたということである。
『鋭いかま』がキリストの手に握られていたのは、携挙されるべき聖徒が地上から携挙されるからであった。すなわち、ここでは携挙される聖徒たちが地上から引き離されて上に引き上げられることが、『かま』で刈り取られるという象徴表現で語られている。農夫が鎌で穀物を刈り取って地面から引き離すように、『穀物』である聖徒たちも携挙の際には、農夫なるキリストにより地上から引き離されるのである。この『鋭いかま』とはあくまでも比喩であり、実際にキリストがその手に『かま』を握っておられたというのではないことに注意すべきである。しかし比喩としては実に適切な表現である。
【14:15】
『すると、もうひとりの御使いが聖所から出て来て、雲に乗っておられる方に向かって大声で叫んだ。』
『もうひとりの』という言葉は、つまり「今までに黙示録では姿を見せていなかった新登場の」という意味である。これは14:6で言われていたのと同じ意味である。
この新登場の御使いが『聖所から出て来』たのは、これから起こるのが地上を対象とした出来事だからである。というのも、『聖所』とは天国のことだからである。これから地上を対象として携挙の出来事が起こるからこそ、この御使いは天国の『聖所』から出て来ることになった。もしこれから起こる出来事が天上を対象としていたとすれば、この御使いが『聖所』から出て来る必要は全くなかった。というのも、一体どうして天上で何らかの出来事が起こるのに、わざわざ天上から離れなければいけないのであろうか。
この御使いが『大声で叫んだ』のは、これから起こる出来事が誠に重大な出来事だったからである。確かに彼の言ったこれから起こる出来事は、誠に重大な出来事であった。すなわち、それは次の言葉のことである。
『「かまを入れて刈り取ってください。地の穀物は実ったので、取り入れる時が来ましたから。」』
『かまを入れて刈り取ってください。』とは、言い換えれば「携挙されるべき聖徒たちを地上から携挙させて下さい。」である。ところで、どうしてここで御使いは、このようにキリストに聖徒たちが携挙されるようにと言っているのか。これではあたかも御使いが主権者で、キリストが言われたことを行なう召使いのようではないか。本来であれば、キリストが御使いに対して次のように言うべきではなかったのか。「かまを入れて刈り取りなさい。地の穀物は実ったから、取り入れる時が来たから。」しかし、これは何も問題にはならない。何故なら、ここでは御使いが主権者としてキリストを召使いのように扱っているのではなく、御使いが言わば忠実な大臣としてキリストを王のように扱っているからである。ここではキリストが御使いの要請に応じて何かを答えたことについては書かれていないが、もしここでキリストが何かを答えられたとすれば、それは次のようではなかった。「はい。分かりました。その通りに致します。」むしろ、キリストの答えは、次のようなものとなっていたであろう。「うむ、よくぞ言ってくれた。私もこの時を待ち望んでいたのだ。早速、あなたの言った通りに刈り取りをしてくることにしよう。」このように考えれば、ここで御使いがキリストを召使いのように扱っているのではないことが分かる。それでは、どうして御使いはここで携挙をするようにと、わざわざキリストに要請しているのか。別にこのように要請しなかったとしても、携挙を実施することができたのは確かである。御使いが要請しない限り、キリストが携挙の業を行なえなかったということはあり得ない。この疑問について私はこう答える。すなわち、これは「聖なる演出」なのだと。このように御使いが要請するからこそ、キリストの王としての尊厳が際立たせられることになる。何故なら、大臣が王に何かをすべきだと要請するかのように、ここでは御使いがキリストに携挙をなされるようにと要請しているからである。このような事例は、世の中や歴史を見れば、いくらでも存在している。例えば、何かの式で王が献花する際に、小さな子どもが献花をするための花を持ってきて王に「どうか捧げて下さい。」などとお願いするのがそれである。別に王はこんな演出がなくても献花できるのだが、その必要性あるいは王室の尊厳や国民に対するイメージなどのために、あえてこのような演出を自主的にするのである。ここで御使いがキリストにお願いしているのも、それと同じことである。
『地の穀物』とは、「地上にいる聖徒たち」という意味である。マタイ13章でも、聖徒たちは穀物において言い表わされている。これは、農夫が刈り取りにより穀物を上に引き上げるように、キリストという農夫が携挙という刈り取りにより聖徒という穀物を上に引き上げるからである。だから、『地の穀物』とは実に適切な表現であることが分かる。『地の穀物は実ったので、取り入れる時が来ましたから。』とは、もう聖徒たちが携挙されるべき時が訪れた、ということである。その時とは、再臨の起きた紀元68年6月9日である。農夫は、穀物を刈り取るべき時期が来たら「もう調度いいかな。」などと思う。同様に、キリストも携挙される時期が来たので「もう時が来た。」と思われたのである。『天の下では、何事にも定まった時期があ』(伝道者の書3章1節)る。携挙においても、その実現されるべき時期があったのである。
【14:16】
『そこで、雲に乗っておられる方が、地にかまを入れると地は刈り取られた。』
この箇所では携挙のことが言われている。それは紀元68年6月9日に起きた。この出来事が未だに起きていないと考えてはいけない。何故なら、ここで書かれている出来事も、例のごとく『すぐに起こるはずの事』(1:1)だったのだから。私は聖徒たちから誤謬の暗闇を何とか取り去ろうとして―取り去って下さるのは私ではなく神なのだが―、このように1:1と22:6の箇所をしつこいぐらいに引用している。これは実に実に重要だからこそしていることだ。読者はこの点に留意していただきたい。
『地は刈り取られた。』とは、つまり「地にいる聖徒たちは刈り取られた。」という意味である。「にいる聖徒たち」という言葉が省かれていることに注意せねばならない。それでは、どうしてこのような省略された言い方で携挙のことが書かれたのか。「地にいる聖徒たちは刈り取られた。」と書いたほうが、分かりやすかったのは言うまでもない。このような言い方で書かれたのは、黙示録に難解さと壮大さを増し加えるためであった。神は、黙示録が平易かつ矮小な文書になることは欲されなかった。このように少しの言葉を省略するからこそ、文章とその内容が、より難しくなり、より壮大に感じられるようになるのは確かである。同じようにキリストも、あえて難しい言い方で多くのことをお話しになられたのを、我々は知っている。それは、そのようにすることで崇高な特異性をその文章や言葉に伴わせるためである。聖書全体が、そのような文章で満ちている。アインシュタインなどの悪意ある死人どもは、このような言い方に触れて「誇張だ」「詩的に粉飾している」などと死人らしい腐敗した所感をよく述べるものだが、彼らは霊的な事柄がまったく分からない死人なのだから、特に気にすることもなく放っておけばよい(※)。豚が鼻息を荒々しくフーフーと鳴らしているに過ぎないのだから。我々はダビデと共に『神にあって、私はみことばをほめたたえます。主にあって、私はみことばをほめたたえます。』(詩篇56篇10節)と言おう。ルターも言うように、「神の言葉は崇められるべきであり、踏みにじられてはならない」(『後期スコラ神学批判文書集』『第3章 ローマの信徒への手紙第7章の講解』 p261 知泉学術叢書6)のである。また我々は、ここで言われている言葉を、文字通りに捉えてはいけない。すなわち、本当にキリストが地を刈り取られたと考えるべきではない。何故なら、地が刈り取られるというのは意味が分からないからである。地球の表面が刈り取られるとは何か?誰も事柄を弁えられないのは確かである。もし意味が分からないというのであれば、それは間違った捉え方である証拠である。よって、ここで『地は刈り取られた』と言われているのは、聖徒たちが携挙されることを比喩的に表現した言い方だと考えるべきである。
(※)
このアインシュタインは聖書に対して辛辣な所感を多く述べたが、彼が物理学以外の見解において驚くほど支離滅裂だったことは、よく知られている。それは聖書においても例外ではない。だから、彼ほどの有名な大巨人がこのようなことを言ったからといって、聖徒たちは動揺してはならない。
[本文に戻る]
また、この携挙は、第一の携挙だったことを弁えなければいけない。すなわち、これは第一の復活に与かった幸いな聖徒たちが上に引き上げられる再臨の際に起こる携挙のことを、言っている。この時には、まだ悪人も復活する第二の復活は起きていない。第二の携挙は、この第一の携挙が起きてから『42ヶ月間』経過してから実現されることになるのであって、それは14:17~20の箇所で説明されている。そちらのほうの携挙は紀元70年9月に起きた。この箇所(14:16)が第二の携挙を言っていると考えると、大きな混乱に引き込まれるから注意しなければいけない。
我々は、この節で一区切り付けるべきである。つまり、この節までを「第1話」として認識するのがよい。そして次の14:17からを「第2話目」として認識する。そうすれば、この14:14~20の箇所が、より良く把捉できるようになるはずだ。
【14:17】
『また、もうひとりの御使いが、天の聖所から出て来たが、この御使いも、鋭いかまを持っていた。』
この節から2回目の携挙が語られ始める。
この御使いが、キリストと同じように『鋭いかまを持っていた』のは何故か。それは、2回目の携挙は、御使いが代行するように定められていたからである。その時期は紀元70年9月、エルサレムが陥落した頃であった。黙示録では、20:11~15で書かれている内容に、この2回目の携挙が含まれている。そこでは文字としては2回目の携挙について何も書かれていないが、そこで言われている内容を見れば、またその周辺聖句における文脈を弁えれば、この20:11~15の箇所で2回目の携挙が起こるのは明らかである。それでは、どうして2回目の携挙はこの御使いに委ねられることになったのか。2回目も1回目と同じように、キリストご自身が刈り取りをすべきではなかったのか。我々の自然な感覚からすれば、やはり2回目もキリストに刈り取りの作業を行なって頂くのが良いと感じられるかもしれない。2回目の携挙が御使いに委ねられたのは、キリストが1回目の携挙により上に引き上げられた聖徒たちと共におられたからである。すなわち、キリストは空中に引き上げられた大勢の聖徒たちと親しく交わっておられたので、わざわざ自分が刈り取りの仕事をすることはせず、御使いにそれを行なわせることをお望みになられた。これは、どこかの国の王が、自分の兄弟姉妹を宮殿に招いて親しくしているようなものである。もしこの王が兄弟姉妹と仲良く過ごしているにもかかわらず、急に刈り取りの仕事があるからというので、「畑仕事があるからちょっと外に出て来るよ」などと言って席を外したらどうであろうか。それは仕方がないことかもしれないが、やはり兄弟姉妹たちはしんみりとしてしまい、多かれ少なかれ空虚な雰囲気がそこに流れてしまうことにもなる。蔑ろにされたと感じる兄弟姉妹も中にはいるかもしれない。キリストという王は聖徒たちという兄弟姉妹を愛しておられたので、あえて刈り取りの仕事のために席を外すことはせず、御使いにそれをやらせることにしたわけである。それだから、このような任務を委ねられた御使いは、本当に名誉ある仕事を与えられたと言えよう。キリストに代わって携挙の仕事を行なう。これ以上に名誉な仕事が他にあるであろうか。このような任務がこの御使いに与えられたのは、この御使いに対する神の恵みであった。しかし、この恵まれた御使いがどのような存在だったのかは、我々に何も知らされていない。
ところで、この御使いの持つ『鋭いかま』がどのようなものだったか気になる人がいるのだろうか。そのような人がいれば、「このかまについて知りたい」という好奇心を封じ込めるべきである。何故なら、14:14の箇所でも書いたように、これは単なる比喩表現に過ぎないのだから。我々は、好奇心から諸々の空想を生じさせることで、ディオニシオス化しないように注意しなければいけない。
【14:18】
『すると、火を支配する権威を持ったもうひとりの御使いが、祭壇から出て来て、鋭いかまを持つ御使いに大声で叫んで言った。』
『火を支配する権威を持ったもうひとりの御使い』とは、どのような存在か。これは、天の祭壇の場所で神に仕えていた聖なる御使いである。この御使いは、地上の聖徒たちが立ち上らせた祈りの『香』(5:8)を、祭壇において『祭壇の火』(8:5)と共にし、香しい香りを神にお捧げしていた御使いである。神は、祭壇で火と共に組み合わされた聖徒たちの祈りを、その嗅覚で嗅いでおられたのである。この御使いは、聖徒の祈りを火と合わせて神に届けるという名誉ある任務を与えられていた。この御使いについての名前と階級は、我々に知らされていない。ただ分かるのはその役目だけである。
この御使いが自分のいた『祭壇から出て来』たのは何故なのか。それは聖徒たちの捧げていた祈りが聞き入れられ、もう実現される時期が到来したからである。この御使いは聖徒の祈りを祭壇で火と共に合わせて神に届けていたので、どのようにしてかは我々に知らされていないが、もうその祈りが聞き届けられることになったのを知った。その祈りとは「裁きの時を来たらせて下さい。」という祈りであった。この空中の裁きは、第二の携挙が起こるのを前提としている。何故なら、この裁きが起こるのは、まず2回目の携挙が起きてから起こるからである。だからこそ、神は裁きのために第二の携挙を実現させるべく、祭壇の場所にいたこの御使いを遣わして、2回目の刈り取りを告げるようにされたわけである。なお、この御使いが『祭壇から出て来』たのは、これから起こる第二の携挙が、地上を対象としていることを意味している。だからこそ、彼は祭壇を離れて出て来たのである。というのも、この『祭壇』は天上にあるからである。これについては、第1回目の携挙が起こる際、御使いが『聖所から出て来』(14:15)たのと同じことである。『~~から出て来て』とは、すなわち「そこで行なわれるのではない」また「どこか別の場所を対象として実施される」という意味である。
この御使いが『大声で叫んで言った』のは、その語られる言葉が非常に重要なことだったからである。14:15の箇所で見たのと同じことである。その重要なことというのは、次の言葉のことである。
『「その鋭いかまを入れ、地のぶどうのふさを刈り集めよ。ぶどうはすでに熟しているのだから。」』
『ぶどうのふさ』とは聖徒である。何故なら、キリストが聖徒たちに対して、次のように言っておられたからである。『わたしはぶどうの木で、あなたがたは枝です。』(ヨハネ15章5節)ぶどうの枝が木にシッカリと繋がっていなければ実を実らせることは出来ないように、聖徒もキリストにシッカリと繋がっていなければ実を実らせることは出来ない。だから、聖徒が『ぶどうのふさ』また『枝』において言い表わされたのは実に適切であった。また、ここで言われている『ぶどうのふさ』には、「悪い実を実らせるふさ」も含まれていることに気付かねばならない。何故なら、14:17~20の箇所では、主にこの「悪いふさ」について書き記すことが目的とされているからである。その「悪いふさ」とは、言うまでもなくユダのごとき毒麦クリスチャンのことである。しかし、どうして第二の携挙においては、第一の携挙とは違い、携挙される者たちが『ぶどう』として描かれているのか。第一の携挙の時のように『穀物』では駄目だったのか。第二の携挙において携挙される者たちが『ぶどう』において描かれているのは、第二の携挙においては恐るべき裁きが実現されるからであった。それは、つまり悪いぶどうである毒麦どものことである。彼らは、携挙されて審判を受けて後、恐るべき裁きを受けることになる。その裁きの凄まじさを描写するのには、『穀物』ではなく『ぶどう』として彼らを描くのが適していた。それは後の箇所である14:19~20を見れば明瞭に分かる。もし裁きの凄まじさが描写されなかったとすれば、ここで書かれるのは別に『穀物』だったとしても問題なかったはずである。
『ぶどうはすでに熟している』とは、すなわち第二の携挙が起こるべき時期が到来したという意味である。ぶどう園の農夫は、自分の育てていたぶどうが熟したら「もう刈り入れてもいい頃かな。」などと思う。それと同じように、神という農夫も2回目の携挙が起こるべき時期が到来したので「もう刈り入れがなされるべきだ。」などと思われた。だからこそ、この御使いを遣わして、刈り入れをするようにと鎌を持った御使いに言わせたのである。神がキリストという名の葡萄の木を植えた農夫であられるということは、キリストも言っておられる通りである。ヨハネ15:1。『わたしはまことのぶどうの木であり、わたしの父は農夫です。』それだから、2回目の携挙が『ぶどう』により比喩的に語られたのは実に適切であった。
ところで、この御使いが天から出て来て携挙が実現されるように要請したのも、先に14:15で見た時と同じように、やはり「演出」であった。神は、聖なる携挙の出来事が、より難解で演劇的になるように望まれた。「演劇的」と私は書いたが、これはもちろん悪い意味ではない。もしこのような演出がなければ、第二の携挙に関する記述はどれだけ無味乾燥なものとなっていたであろうか。非常に味気なく感じられる記述となっていたのは間違いない。だから、神がこのように演劇的な描き方をされたのは、実に正しいことであった。死人どもはこのような演出を見て「詩的だ。装飾的に描き過ぎている。」などと批判するのだろうが、このような演出がされていなかった場合、逆に「無味乾燥だ。つまらない。平凡すぎる。」などと批判していたであろう。つまり、彼らは神を憎悪しているので、とにかく神の書かれたものを批判したいのだ。だから、もしカント的な難解さを持つ文章で書かれていたとすれば、「こんな難しい文章で書く神とは一体何なのか。これが愛の神だとでもいうのだろうか。」などと批判していたであろう。だから、いつの時代にも存在しているこのような者たちは放っておくに限る。彼らには、とにかく神を悪く言いたいという霊的な欲求が大前提としてあるからである。
【14:19】
『そこで御使いは地にかまを入れ、地のぶどうを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒ぶねに投げ入れた。』
遂に第二の携挙が実施された。この時に携挙されたのは、悪しき偽善者も含まれていた。第一の携挙との最大の相違点は、これである。第一の携挙においては、正しい者以外には誰も携挙されなかった。また、第二の携挙が起きた際には、教会の中にいた者だけが携挙されたということに注意せねばならない。つまり、これは第二部でも説明されたことだが、多くの人たちがそう思っているように、教会の外にいる不信者や異教徒まで第二の携挙の際に携挙されたというのではない。というのも、携挙されることになるのは、キリストの『脱穀場』(マタイ3章12節)また『御国』(マタイ13章41節)、すなわち教会という囲いの中にいるいわゆる「教会員」だけに限られるからである。だからこそ第二の携挙の後で起こる空中の大審判では、『羊と山羊』(マタイ25章32節)だけがキリストの前に立たせられるのである(マタイ25:31~46)。既に述べたごとく、そこに「狼」である教会外の者たちはいない。この空中の大審判については、20章になったら再び詳しく論じられるはずである。
『神の激しい怒りの大きな酒ぶね』とは、「地獄」である。『酒ぶね』は、足で非常に激しく踏まれるので、もし人格がそれにあったとすれば実に悲惨であることは確かである。21世紀の今で言えば、そんなことが誰かに行なわれたら「虐待」だなどと言われて、大きなニュースとなっても不思議ではない。地獄にはそのような凄まじい悲惨が満ちているため、ここでは地獄が『酒ぶね』を踏むことにおいて言い表わされている。『激しい』と言われているのも、地獄があまりにも恐ろしい場所だからである。酒ぶねが『激し』く踏まれたら、酒ぶねは目茶目茶になる。同様に、地獄にいる者たちも目茶目茶にさせられてしまうのだ。また、この地獄は空間的に『大き』かった。何故なら、地獄に投げ落とされる者の数が多いからである。地獄で苦しむ者が多くいるからこそ、その者たちを収容する地獄も『大き』かったというわけである。地獄に行く者が多いということは、次に示すキリストの御言葉からも分かる。『招待される者は多いが、選ばれる者は少ないのです。』(マタイ22章14節)『狭い門からはいりなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そして、そこからはいって行く者が多いのです。いのちに至る門は小さく、その道は狭く、それを見いだす者はまれです。』(マタイ7章13~14節)―では地獄に投げ込まれる者の数が少なければ地獄が「大きい」とは言われていなかったのか。答え。その可能性は高い。
このように、この箇所では第二の携挙により挙げられた滅びの子らが地獄に投げ込まれる出来事を描写しているが、これは他の多くの箇所と対応している。それは例えば次のような箇所がそうである。『しかし、その時、わたしは彼らにこう宣言します。『わたしはあなたがたを全然知らない。不法をなす者ども。わたしから離れて行け。』』(マタイ7章23節)『それから、王はまた、その左にいる者たちに言います。『のろわれた者ども。わたしから離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火にはいれ。』』(マタイ25章41節)『いのちの書に名のしるされていない者はみな、この火の池に投げ込まれた。』(黙示録20章15節)『人の子はその御使いたちを遣わします。彼らは、つまずきを与える者や不法を行なう者たちをみな、御国から取り集めて、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。』(マタイ13章41~42節)『御使いたちが来て、正しい者の中から悪い者をえり分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。』(マタイ13章49~50節)これらはどれも、第二の携挙により上に挙げられた第二の復活に与かった悪者どもが、空中の大審判を受けて後、地獄に投げ込まれて悲惨な状態になるということを言っている。我々が今見ている14:19の箇所について言えば、ここでは「第二の携挙」と「地獄への投下」という2つの事柄のみが記されている。ここで「第二の復活」と「空中の大審判」は完全に省かれている。というのも、この箇所は携挙と地獄に焦点があてられている箇所だからだ。だから復活と大審判の記述が省略されているからといって、この2つの出来事がこの箇所の内容に含まれていないというわけではない。ここではただ語られていないだけであって、この2つの出来事がこの記述における内容の中に実際は含まれているということは言うまでもないであろう。
【14:20】
『その酒ぶねは都の外で踏まれたが、血は、その酒ぶねから流れ出て、馬のくつわに届くほどになり、1600スタディオンに広がった。』
『都の外で踏まれた』とは、すなわち「地獄で裁かれた」という意味である。『都』とは天国を指す。その天国の『外』だから、それは地獄以外ではない。つまり、ここでは第二の携挙により空中の大審判に引き出された悪者どもが、天国の都に入れてもらえず、かえって地獄に投げ入れられて目茶目茶な状態に至らせられた、ということが言われいている。この『都』が天国を指すというのは、黙示録21:1~22:5やヘブル12:22を見ても分かることである。このことから、黙示録は20:6の箇所以降は未だに実現していないとする千年王国論者たちが、どれだけ大きな思い違いをしているかがよく分かる。少し考えれば分かるが、この14:17~20の箇所は第二の携挙により引き上げられた者が地獄に投げ込まれる出来事を預言しているのだから、この箇所は聖書啓示における最後の出来事である。先にも述べたように地獄よりも後に起こることを預言した預言は存在しない。地獄への投下(また天国への入場および天国の場景の示し)が最後の啓示である、ということは誰も疑わないであろう。もしこの箇所で啓示における最後の出来事が預言されているのであれば、どうして15章目以降もまだ色々な啓示が続いているのだろうか。黙示録が順序通りに書かれているとすれば、これはまったく説明できない。何故なら、もし順序通りだとすれば、黙示録14:17~20以降は預言することが何もないため、エピローグや教訓を除けばほとんど書くことがなかっただろうからである。千年王国論者たちは黙示録が創世記のように順序通りに書かれていると無知のため考えており、黙示録のことが何も分かっていない。従って私からすれば、彼らが黙示録は20:6までしか成就していないなどと言うのは、滑稽以外の何物でもない。これは、まるで「私たちは黙示録を何も理解できていないのです。」とでも言っているかのように聞こえてしまう。お話しにならない、というのが私の所感である。読者は、このような思い違いに陥らないように注意してほしい。もう一度言うが、この14:17~20に書かれている出来事よりも時間的に後で起こる啓示は何も存在していない。もし地獄さえも消滅して新しい「何か」が登場するというのであれば、まだ啓示は続いていただろうが、そのような「何か」はないのである。もし地獄よりも後で起こる出来事の啓示が何かあるとすれば、是非とも私に教えてほしいものだ。もちろん、そのようなことは出来ないであろうが。やれやれ、無知また研究不足とは実に惨めなものである!
さて、マタイ13:36~50の箇所は、この箇所(14:17~20)と完全に対応している。マタイ13章では、この箇所と同じように第二の携挙に関する出来事が書かれていたのである。それは、マタイ13章の内容をよく考えてみれば明らかである。マタイ13章でキリストが携挙を実施すべく『その御使いたちを遣わし』(マタイ13:41)たのは、このマタイ13章で書かれているのが2回目の刈り取りだったからに他ならない。もしこれが1回目の刈り取りだったとすれば、このマタイ13章では、キリストご自身が刈り取りをしておられるシーンが描写されていたであろう。というのも、先に14:14~16の箇所で見たように、第1回目の刈り取りはキリストご自身がなされるからである。またマタイ13章において『つまずきを与える者や不法を行なう者たち』(41節)が刈り取られたと書かれているのも、このマタイ13章の箇所で言われているのが2回目の携挙のことだからである。もしこれが一回目だとすれば、悪者どもの刈り取りはまったく記されていなかったはずだ。何故なら、1回目の刈り取りでは、聖徒たちだけが刈り取られるのだから。更に、マタイ13章で『火の燃える炉』(42、50節)について触れられているのも、このマタイ13章の箇所が2回目の刈り取りを描いていることの証拠である。何故なら、1回目の携挙ではまだ悪者どもが携挙されていないゆえ、地獄に誰かが投げ込まれるという出来事はまだ起こらないからである。それゆえ、このマタイ13章を1回目の携挙だと主張する者は、再臨の時期に起こる出来事をよく把握していないことを自ら示していることになる。把握していないからこそ、そのような間違いを犯すのだ。よって我々はこのマタイ13章が、第1回目の携挙について描いた箇所だなどと思い違いをしないようにすべきである。
『血は、その酒ぶねから流れ出て』とは、地獄における裁きの凄まじさを言った比喩表現である。つまり、地獄で裁かれる悪者どもは、あたかも酒ぶねが張り裂けるほどに激しく踏まれるかのように、神の怒りで目茶目茶にされたということである。ここでは『酒ぶね』が地獄を、『ぶどう』が悪者どもを、そしてぶどうから流れ出る果汁が『血』として表わされていることに注意せねばならない。つまり、地獄の悪者は、張り裂けて飛び散る葡萄のごとき悲惨な状態となったということだ。先にもいくらか述べたが、このような状態を比喩的に示すべく、第二の携挙においては『穀物』ではなく『ぶどう』という表現が用いられたのである。もし2回目の刈り取りでも1回目の刈り取りのように『穀物』という表現が用いられていたとすれば、飛び散る血(=ぶどうの汁)により地獄の恐ろしさを示すことは出来なかった。その流れ出た血が『馬のくつわに届くほどにな』ったのは、酒ぶねから出た血がどの高さまで達したかということを言っている。『くつわ』とは、馬の種類にもよるが、だいたい1,5~3mぐらいの高さである。要するに、これは、それほどまでの高さに達するぐらいに多くの悪者が血を流されたも同然だということを言い表わしている。こんなに高い場所にまで血が達するとは、考えただけでも恐ろしい。またその血が『1600スタディオンに広がった』というのは、血の広がった距離を言っている。1スタディオンは185mだから、『1600スタディオン』とは296kmである。地獄にいる者たちの血は『くつわ』の高さまで達しただけでなく、約300km離れた場所までも流れた。これはとんでもないことである。あたかも血の大洪水が起きたかのようだ。要するに、それだけ多くの者が地獄に投げ込まれ、血を流されまくるかのような恐るべき刑罰を受けたということが、ここでは言われている(※)。しかしながら、これはあくまでも地獄に投げ込まれて悲惨な状態となる者が多いことを教えるための比喩に過ぎないことを忘れてはならない。だから、この記述から地獄の物理的な大きさを計算したり、地獄に投げ入れられる悪者どもの実際的な数を推測したりすべきではない。我々は、この箇所で言われていることを読んで、「地獄には多くの者が投げ入れられて悲惨な裁きを受けた」という理解以上に進むべきではない。これから、この箇所に基づいて地獄について分かりもしないことを詳しく述べ立てるディオニシオスの徒が出現しないことを、願うものである。
(※)
この数字について、私は前に次のように書いた。<この「1600」という数字が、聖書の他の箇所から引き出されてきたのかどうか私は知らない。恐らく、これはどの箇所から持って来られた数字でもないと思われる。というのも、この数字の元となたった箇所が聖書のどこかにあるとは私には思われないからである。「42」という数字であれば聖書の他の箇所でも示されているが、「1600」という数字はそうではない。またこの数字の成り立ちも、よく分からない。「42」であれば<14+14+14>、「14万4000」であれば<1万2000×12>と分解することができる。しかしこの「1600」は分解するのが難しいと思われる。確かに言えることは、ヨハネは本当に大きいことを教えようとして、この数字を使ったということである。実際「1600スタディオン」(=296km)と聞いて大きいと思わない人はいないと思う。私は今現在の段階では、このようにこの数字について考えている。後ほどこの数字の元となった聖書の箇所が見つかったならば、またこの数字の成り立ちが分かったならば、その際にはこの箇所が書き換えられることになるであろう。>この数字が、聖書の他の箇所から引き出されたのかどうかは分からない、という点では私に何も変化はない。しかし、この数字の成り立ちについては、考えが進んだ。この「1600」の成り立ちは<40×40>である。我々は、エリヤが『40日40夜、歩いて神の山ホレブに着いた』(Ⅰ列王記19章8節)のを既に知っている。40日間も歩く距離が長いと思わない人はいない。つまり、「1600」という数字は、エリヤが40日間も歩き続けた距離を、更に40乗したぐらいの距離だということである。40乗もやはり「40」であるが、「40」とは聖書では<もう十分だ>とか<多くて豊かである>という意味である。すなわち、これはエリヤの歩行距離を40倍したぐらいに長く感じられる距離だという意味である。要するに、これは「とんでもなく長い距離」ということだ。他にも候補として<4×400>も挙がってきたが、こちらよりも<40×40>のほうが正しいように思われる。というのも<4×400>は、その成り立ちの意味が理解できないからである。しかし<40×40>ならば、いくつか意味を見出せるし、どのように捉えるにせよ、多かれ少なかれもっともらしく感じられるのである。
[本文に戻る]
このような地獄に投げ入れられたくないと思う聖徒は、父なる神との間に結ばれたキリスト契約に留まり続けるがよい。この契約を破って信仰から脱落するならば、その人は、地獄に投げ入れられて酒ぶねのように踏まれまくるであろう。そして目茶目茶にされて悲惨になるであろう。すべて御子にある生命の契約に留まらない者は、地獄における恐怖と苦しみを自分に対する永遠の分け前として受けるのだ。それゆえ全聖徒たちには次のような警告がなさればならない。「キリストに留まり続けよ。キリストに留まり続けよ。」と。
第19章 ⑯15~16章:7つの鉢による裁き
この箇所は、先の箇所(14:14~20)からの続きであると考えてはいけない。この箇所は、先の箇所と順序的に繋がっておらず、ゆえに先の箇所とは独立した箇所だと理解すべきである。それでは一体どうして、この箇所が先の箇所とは繋がっていないと言えるのか。その理由は何か。それは、先の箇所の最後のほうで第二の携挙の預言がされていたからである。この第二の携挙は、聖書啓示における最後から3番目の出来事である。すなわち啓示における最後の出来事が天国と地獄であり、最後から2番目が空中の大審判であり、最後から3番目がこの第二の携挙である(※第4番目は第二の復活である)。7つの鉢で描かれている出来事を見るとどうか。そこではユダヤの破滅(16:4~7)やローマ軍の招集(16:12~16)の出来事が預言されている。これらはどれも第二の携挙よりも前に起こることである。もし先の箇所(14:14~20)からの続きとして7つの鉢の預言が書かれているとすれば、これは非常におかしな話である。何故なら、そこでは明らかに順序通りのことが描かれていないからである。もし先の箇所からの続きとして描かれていると言うのであれば、どうして第二の携挙が先の箇所の最後で描かれてから、その後で第二の携挙よりも前に起こる出来事が7つの鉢による預言の中で描かれているのか説明できなければいけない。しかし、これを説明することは出来ない。何故なら、先の箇所とこの15~16章の箇所は分離して独立的に考えるべき箇所だからである。いったい、聖徒たちはいつまで黙示録には順序通りのことが書かれていると思い違いをしているのか。それとも、そもそも順序も何も内容自体がまだ分かっていないのだろうか。内容自体が理解できていないのであれば、その聖徒は、私の述べたことを学び、それを理解した上で受け入れたらよい。思い違いをしていた聖徒は、自分の考えを改めて、正しい考えに切り替えるがよい。私も、何か間違った理解があれば、それに気付き次第、その間違った理解を改めることにしよう。このようにするのは当然のことである。
また、この鉢の預言は、巻き物とラッパの預言に続く預言ではないということを、ここで再び言っておかねばならない。鉢と巻き物とラッパの預言は、先にも述べたように、それぞれ独立した預言である。これら3つのものは、再臨の時期に起こる諸々の出来事を、3つの福音書のように、それぞれ違う角度から違う語り方で預言したものに他ならない。それゆえ、これら3つのものを分かりやすく捉えたければ、巻き物の預言が「マタイの福音書」であり、ラッパの預言が「マルコの福音書」であり、鉢の預言が「ルカの福音書」であるというふうに捉えればよい。もしこれら3つのものが順序通りの預言だと言うのであれば、すなわち巻き物⇒ラッパ⇒鉢、という順で話が進むのだと言うのであれば、どうして巻き物における第6の預言で大審判の日が預言された後で(6:17)、大審判の日よりも前に起こる出来事であるローマ軍の包囲がラッパにおける第5の預言において預言されているのか(9:1~12)、説明してほしいものである。これは誰も上手に説明できないはずである。何故なら、これら3つのものが順序通りになっていないことは誰の目にも明らかだから。それとも大審判の日の後でローマ軍の包囲の出来事が起こるとでも言うのか?それはあり得ないことである。実際はローマ軍の包囲が起きてから大審判の日が訪れることになった。それだから、我々は、鉢と巻き物とラッパの預言が順序通りに記されてはいないことによく注意せねばならない。これら3つのものは、3つの福音書のように、同じ事柄を取り扱いながらも、どれもそれぞれ独立しているのだ。
【15:1】
『また私は、天にもう一つの巨大な驚くべきしるしを見た。』
まずヨハネは、ここでこれから示される幻が非常に注目すべきものだということを、読者たちに伝えようとしている。その幻は16:21までの箇所で示されている。確かにその幻についての記述を見てみると、それが『巨大』であり、『驚くべき』ものであり、また今までの幻と重複している部分はあるものの『もう一つの』、すなわち今までの幻とは異なった幻であるということが分かる。このような幻が示されたのは、聖徒たちに対する神の恵みであった。何故なら、この幻も、聖徒たちがあらかじめ未来の出来事を知って心の準備をしたり警戒できるようにと、示されたからである。もし聖徒たちのためというのでなければ、このような幻が啓示されることはなかったであろう。神は無意味に何かを行なわれるお方ではないのだから。
『7人の御使いが、最後の7つの災害を携えていた。神の激しい怒りはここに窮まるのである。』
『最後の7つの災害』とは、巻き物とラッパに続いて引き起こされる『最後の』裁きということではない。何故なら、既に述べたように、鉢と巻き物とラッパには順序的な繋がりがないからである。これは、つまり「最後の時に下されるであろう7つの災害」という意味である。もしこれが巻き物とラッパに続くという意味で『最後の』と言われていると捉えると、訳が分からなくなってしまうから注意しなければいけない。
『神の激しい怒り』が注がれるのは、ユダヤと異邦人である。何故なら、この『激しい怒り』を注ぐ鉢について記されている箇所では(15、16章)、ユダヤと異邦人について色々と言われているからである。ユダヤは多くの預言者たちをそれまでに殺した上に御子をさえも否認し、異邦人はせっかく御子の福音が宣べ伝えられたにもかかわらず不信仰を貫き通した。だからこそ、遂に『神の激しい怒り』が『窮まる』ことになったのである。その怒りの注ぎは、再臨後から紀元70年9月までの期間であった。神の怒りは、啓示と聖なる神の使いたちを蔑ろにした者どもに厳しい。神は正義の審判者であられるから、そのような者どもには容赦なく裁きが下されることになるのだ。
この『7人の御使い』とは、これまでに出てこなかった御使いたちである。すなわち、この御使いは、先に7つのラッパを吹き鳴らしたあの7人の御使いが、鉢の役目をも任されたということではない。これは7つのラッパの御使いとは別の御使いである。また7つのラッパの御使い以外の既に登場していた御使いが、ここで再び出て来たというのでもない。つまり、この御使いは黙示録の中では「ニューエンジェル」なのだ。
【15:2】
『私は、火の混じった、ガラスの海のようなものを見た。』
これは天国にある地面のことである。先に見た4:6で書かれている『御座の前は、水晶に似たガラスの海のようであった。』という文章と、やや表現は違うものの、一緒のことを言っている。天国におられる神の前には、このような神秘的な印象を与える地面が張り巡らされているのだ。これは実に恍惚とさせる場景であると私には感じられる。聖徒である者は、やがて天国に行けば、これが実際にどのような地面なのかまざまざとその目で見ることができる。それは大変素晴らしいものに違いないから、是非とも多くの人が天国でこのような地面を見れるようになってほしいものである。
『獣と、その像と、その名を示す数字とに打ち勝った人々が、神の立琴を手にして、このガラスの海のほとりに立っていた。』
この場景は、紀元68年6月9日に携挙された聖徒たちが天国で過ごしている場景である。この時には、第二の携挙はまだ起こっていない。第一の携挙が起きた直後の場面が、ここでは記されている。このような天国の場景があらかじめ示されたのは、紀元1世紀の聖徒たちに忍耐を持たせるためであった。何故なら、ここではネロの苦難に耐えるならば、やがてその者が天国に入れるということが示されているからである。つまり、これは当時の聖徒たちに間もなくやってくる未来の出来事であったから、聖徒たちの信仰に良い益を与えたはずである。このような場景を示されたら、やはり誰でも大いに忍耐する気になるだろうからである。黙示録とはネロの苦難に備えさせることを一つの目的とした文書であるゆえ、確かにこの記述は聖徒たちの益のために書かれたと言うことができる。
天国の聖徒たちは『神の立琴を手にして』いた。これは「神を賛美するための立琴」という意味である。天国の聖徒たちの全てが、この『神の立琴』を手にしていたかどうかは分からない。何故なら、詩篇150篇では『角笛』(3節)や『タンバリン』(4節)や『笛』(4節)や『シンバル』(5節)などでも神を賛美するようにと言われているからである。このように色々な楽器を使えと詩篇では命じられているのだから、天国で立琴以外の楽器を手に持っている聖徒たちがいる可能性はかなり高い。ここでは記述をシンプルにするために、あえて『立琴』のみを挙げたということなのかもしれない。すなわち、その他の楽器については記述を省いていると。いずれにせよ、聖徒である我々が天国に行けば、事情がどうだったのか明瞭に知れるようになるであろう。今の時点では、ただ天国の聖徒たちが『神の立琴を手にして』いたと大まかに捉えていれば、それで十分である。
この箇所は、ネロの時代以降に生きている聖徒たちも、自分に関わりのある箇所として見做すのが望ましい。何故なら、あらゆる聖徒たちには、この人生において、ネロほどの大患難は無かったとしても、大小様々な患難があるだろうからである。「患難がある」という点ではネロの時代の聖徒たちも、それ以降の時代に生きる聖徒たちも何も変わらない。その患難をくぐり抜ければ、全ての聖徒たちは『神の立琴を手にして、このガラスの海のほとりに立って』いる状態に至れる。例外はない。全ての聖徒たちがそうなるのだ。だから、この箇所をヨハネの時代に生きていた聖徒たちにしか関連していない箇所だと見做すのは、望ましくなく、勿体ないことである。
【15:3】
『彼らは、神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌って言った。』
『神のしもべモーセの歌』とは、明らかに出エジプト記15:1~18で記されている歌と対応している。この出エジプト記の歌と、黙示録15章の歌は、その量こそ違うが、内容的には非常に似通っている。また、この2つの歌が歌われた状況も、よく似ている。すなわち、モーセが主に歌を歌ったのはエジプトのもらたす苦しみから解放された時だったが、ここで天国にいる聖徒たちが主に歌を歌ったのも、彼らがネロのもたらす苦しみから解放されて天に挙げられた時であった。どちらも苦しみから救い出された後に、もはや敵のいない安全な場所で歌を歌っていることが分かる。黙示録の中で、出エジプト記と対応している箇所は多い。この15章で歌われている歌もそうであろう。ヨハネの頭の中に出エジプト記の記述が浮かんでいたのは、まず間違いないと思われる。要するに『モーセの歌』とは、「モーセの歌った歌のような歌」という意味である。『子羊の歌』とは、「子羊なるキリストに捧げる歌」という意味である。これは誰でも簡単に分かることだから、詳しく説明する必要はないであろう。この2つの言葉は、一つの歌を二通りの言い方で言っているということに注意しなければいけない。すなわち、ここでは『モーセの歌』と『子羊の歌』という2つの歌について言われているというのではない。これはどちらも同一の歌のことである。それは、バッハのある一曲を「神の栄光のための曲また素晴らしく芸術的な曲」などと言うようなものである。第一の携挙により天に引き上げられた聖徒たちは、あの時のモーセたちのように、天の場所でこのような歌を神に捧げたのであった。
この箇所から、賛美は不要だなどと主張する者たちの愚かしい見解は、完全に拒絶されることになるのが分かる。何故なら、この箇所は天でさえ賛美が行なわれていることを教えているからだ。天で賛美が行なわれるのであれば、地でも賛美をなすべきだということは確かである。天で行なわれる事柄は、基本的には地でも行なってよい、いや、ぜひとも行なうべき事柄だからである。もし天で賛美が禁止されていたとすれば、彼らの主張にも耳を傾けるべきだったが、この箇所で示されているように天では賛美があるのだから、彼らの言うことには耳を傾けるべきではない。賛美を毛嫌いする者たちは、いったい何を考えているのか。彼らは聖書に堅く立てていないからこそ、神の呪いを受けているとしか言いようがない。その呪いとは、聖書に堅く立てていないので聖書的ではない考えを愚かにも持ってしまうという呪いである。我々は、むしろこの箇所を読んで、尚のこと賛美を首肯すべきであろう。
『「あなたのみわざは偉大であり、驚くべきものです。主よ。万物の支配者である神よ。』
『みわざ』とは、第一の携挙の前に起きた復活のことである。何故なら、ここでは復活して携挙された聖徒たちが、復活した直後にこのような歌を神に捧げているからである。これが復活以外の『みわざ』だとすれば、例えば世界の創造とか様々な自然現象だとすれば、あまり状況にそぐわなくなる。しかし、これが復活だと捉えると、この歌が歌われている状況によく合致する。というのも、復活して天に挙げられた聖徒たちが、自分たちの与かった復活の御業について何かを言うのは自然なことだからである。よって、この『みわざ』とは復活のことだと理解するのが望ましい。
復活の『みわざ』は、誠に『偉大』であった。何故なら、この『みわざ』により、天にいる魂たちが新しい身体を受け、地上に生き残っている者たちは『たちまち、一瞬のうちに』(Ⅰコリント15章52節)身体の切り替えに与かり、墓の中に眠っていた骨たちは復活体として墓の中から出てきたからである。これを『偉大』と言わずして何を偉大と言うのであろうか。これは誠に偉大であるので、また『驚くべきもの』でもあった。しかしながら、神の『みわざ』の中で『偉大であり、驚くべきもの』であるのは、この復活だけだということが、ここで言われているのではない。神の業は、どれもこれも多かれ少なかれ偉大であり驚くべき性質を持っている。例えば、天地創造や、救いの御業や、使徒たちを通して実現された奇跡などがそうである。しかし、この復活の御業が、神の御業のうち、もっとも偉大で驚くべき部類に入るのは確かである。これと並ぶ御業ならば他にもあると言えるが、これ以上に素晴らしい御業はないと言ってよい。つまり、この復活の御業は、御業の巣晴らしさの極致であるということだ。
ここで『主よ。万物の支配者である神よ。』と言われているのは、その前の文である『あなたのみわざは偉大であり、驚くべきものです。』という文とセットであると私は考える。つまり、ここでは「神が全てを支配しておられる存在だからこそ、復活という大いなる御業を行なうことが出来るのだ。」と言われていることになる。確かに、この復活の御業は、神が『万物の支配者』であられる証拠である。全てを支配しておられるからこそ、人を復活させられることもお出来になるのだ。もし神が『万物の支配者』でなければ、人を復活させることなど出来なかったはずである。また、そのような存在は、そもそも神とは言えない。何故なら、復活を実現できないというのは、不完全な性質を持っているということに他ならないからである。不完全な性質を持っている不完全な存在であれば、そんな存在を神だとどうして言えるであろうか。なお、ここで言われている『万物の支配者』という言葉は、既に1:8の箇所で説明されたから、重複を避けるため、ここで再び繰り返して説明することはしない。
『あなたの道は正しく、真実です。もろもろの民の王よ。』
神の『道』とは、すなわち「神のなされる諸々の行ない」という意味である。つまり、これは「神のなされること」を、「神が歩まれる道」という表現で言い表わした言葉である。確かに神の『道は正しく、真実』である。これを言い換えれば、神がなされることは、ことごとくパーフェクトであって一点の欠けや愚かさもそこには含まれていないということである。それは聖書全体が教えていることである。例えば、聖書は神のなされることについて、次のように書かれている。『神、その道は完全。』(詩篇18篇3節)『神のなさることは、すべて時にかなって美しい。』(伝道者の書3章11節)『主は、その町の中にあって正しく、不正を行なわない。』(ゼパニヤ3章5節)『そのようにして神はお造りになったすべてのものをご覧になった。見よ。それは非常によかった。』(創世記1章31節)アウグスティヌスが「主のすべての道は真理なのである。」(『アウグスティヌス著作集20/Ⅰ 詩篇註解(5)』詩篇118篇 説教29 p584:教文館)と言っているのも、この意味に他ならない。ここに、神と人間との大きな相違点がある。人間は愚かなことや、不完全なことや、間違ったことばかりをする存在である。しかし、神はそのようなことは何もされない、いや、そのようなことはできない。何故ならば、もしそのようなことをすれば、神が神でなくなってしまうからである。聖なること、完全なこと、真理であること、正しいことだけをするからこそ、神は神であられる。
『もろもろの民の王よ。』という言葉は、すぐ前の文である『あなたの道は正しく、真実です。』という言葉に組み合わされていると私は捉える。つまり、ここでは「その『道は正しく、真実』である神こそが『もろもろの民の王』として相応しい存在なのである。」ということが言われていると私は考える。確かに、全ての行ないが正しく真実であられる神こそ、諸国の民を支配される王として相応しいお方である。というのも、ソロモンも言うように、王とは正しさをこそ持って統治すべきだからである。次のようにソロモンの書に書かれている通りである。『誠実をもって寄るべのない者をさばく王、その王座はとこしえまでも堅く立つ。』(箴言29章14節)『王座は義によって堅く立つからだ。』(箴言16章12節)『知恵のある王は悪者どもをふるいにかけ、彼らの上で車輪を引き回す。』(箴言20章26節)偽善と不正と高慢と洗脳により統治する王を待ち望んでいるユダヤ人たちは、完全な夢想に陥っている。パリサイ人の末裔である彼らは、キリストの時代と変わらず、何も聖書のことが分かっていない。王として相応しいのは、少しの偽善も不正も高慢も洗脳も喜び給わない神のような存在なのである。「支配は力のうちに宿る。」などと言う彼らは、全てを支配される神の大きな御力により報いを受けることになる。なお、実際に神が王として『もろもろの民』の上に君臨しておられるというのは、聖書が明瞭に教えていることである。すなわち聖書では次のように書かれている。『主は、王だ。』(詩篇97篇1節)『主は王である。国々の民は恐れおののけ。』(詩篇99篇1節)『わたしが大いなる王であり、わたしの名が諸国の民の間で、恐れられているからだ。』(マラキ1章14節)『地上の王たちの支配者であるイエス・キリスト』(黙示録1章5節)『キリストは天に上り、御使いたち、および、もろもろの権威と権力を従えて、神の右の座におられます。』(Ⅰペテロ3章22節)
【15:4】
『主よ。だれかあなたを恐れず、御名をほめたたえない者があるでしょうか。ただあなただけが、聖なる方です。』
主が『聖なる方』だというのは、聖書の他の箇所でも教えられていることである。すなわち、次のように聖書は神について語っている。『聖なる、聖なる、聖なる、万軍の主。』(イザヤ6章3節)『けれども、あなたは聖であられ、…』(詩篇22篇3節)『われらの神、主は聖である。』(詩篇99篇9節)『わたしが聖であるから、あなたがたも、聖でなければならない。』(Ⅰペテロ1章16節)ここで天上の聖徒たちは、聖であられる主を恐れもせず、その御名を賛美しない者が果たしているのであろうか、もしいたとすればそれはどのような馬鹿者なのであろうか、と言っている。というのも、正しい知性と感覚を持った者たちにとって、聖であられる主を恐れず、その御名を褒め称えないということは、考えられないことだからである。確かに主は『聖なる方』だから、『恐れ』られなければいけない。何故なら、聖であるとは、神聖不可侵であり、どれほどに小さな汚れさえも許容できないということだからである。もし御前に汚れた者がいたとすれば、そのような者は容赦なく斥けられて、永遠の死を受けるのみである。このような聖なる神は、恐れられるに相応しいお方である。また神が『聖なる方』だということは、神が『ほめたたえ』られるべきだということでもある。何故なら聖であられるというのは、すなわち素晴らしいということだからだ。人は小カトーの徳を聞いたら、その徳を賛美するであろう。その徳が素晴らしいからである。それと同様に神の神聖さも素晴らしいがゆえに、それは賛美されるべきものなのである。それゆえ、聖なる神を恐れず、その御名を褒め称えない者は、精神が狂っているか、邪悪に染まっているか、神が聖であられることをよく知らないか、のどれかに分類されることになる。何故なら、そうでなければ、神を恐れず、御名を褒め称えないということはあり得ないことだからである。
『ただあなただけが、聖なる方です。』とは、本来的な意味において、である。すなわち、これは「初めから自分自身によって根本的に聖であられるのは神だけしかおられない。」という意味である。根本的に、というのでなければ聖なる存在は神だけに限られない。贖われた聖徒たちも聖なる御使いたちも、神と同じように聖なる存在である。しかし、彼らの聖性は、神により付与されたがゆえの聖性であって、根本的に持っていた聖性というのではない。その聖性が根本的であるかないかという点で、聖徒および御使いの持つ聖性と、神の持つ聖性には、大きな違いがある。だから根本的な意味においてであれば、『ただあなただけが、聖なる方です。』という言葉は真実である。誰であれ、神のように生来的な聖を持つことはできない。それゆえ、自分も神のように生来的な聖性を持ちたいなどと願う傲慢な者がいてはいけない。
『すべての国々の民は来て、あなたの御前にひれ伏します。あなたの正しいさばきが、明らかにされたからです。』
これは空中の大審判が行なわれる際には、『すべての国々の民』が主の『御前にひれ伏』すことになるという意味である。この言葉が語られている時には、まだこの大審判は起きていない。それは、この言葉が語られてから『42ヶ月間』が経過して、第二の携挙が起きた後に実現された。つまり、これは預言である。確かに空中の大審判が起きた際には、『すべての国々の民』が主の御前にひざまづいた。ギリシャ人もユダヤ人もエジプト人もインド人もローマ人もブリタニア人も、そうである。何故なら、紀元70年9月に大審判が行なわれるまでに、福音が全世界に宣教されたからである。既に使徒の時代に世界中に宣教がなされていたということは、第1部で詳しく見た通りである。世界中に宣教がされたということは、すなわち、世界中の民族がクリスチャンとしてキリストの囲いの中に入れられたということを意味する。世界中の民族が麦であれ毒麦であれクリスチャンになったということは、つまり世界中の民族が空中の審判に呼ばれたということを意味する。何故なら、この審判に引き出されるのは、既に第2部で見たように、主の牧場で草を食べている羊と山羊たちだからである。この羊と山羊には実に多くの国籍が見られたのだ。だから、ここでその大審判について『すべての国々の民は来て、あなたの御前にひれ伏します。』と言われているのは、本当に真実であったことが分かる。
『正しいさばき』とこの箇所では書かれている。神は、『正しいさばき』しか行なわれないお方である。何故なら、神とは義なる存在だからである。「義」であるとは、、すなわち『不正な裁判』(レビ記19章15節)をせず、『正しくさば』(同)きをし、『わいろを取』(出エジプト23章8節)らず、『正義を、ただ正義を追い求め』(申命記16章20節)、『悪を憎』(詩篇97篇10節)む、ということを意味している。義なる神は、裁判においても不義を多く行なってしまう人間どもとは違うのだ。この箇所で言われている紀元70年9月の時の大審判においても、やはり神は義なる裁きをされた。その時、神は、贖われた者たちにはその善行に従って祝福の宣言を与えられ、呪われた滅びの子らにはその悪行に従って刑罰の宣言を与えられた。その裁きはどれもこれも、みな『正しい』ものであった。神はそのような審判により、ご自身の審判者としての御栄光を豊かに現わされたのである。この裁きはことごとく正しかったから、誰も意義を唱えることはできなかった。もし意義を唱える者がいたとすれば、その者は、次のように辛辣な言葉で排撃されていたであろう。『人よ。神に言い逆らうあなたは、いったい何ですか。』と。
【15:5~6】
『その後、また私は見た。天にある、あかしの幕屋の聖所が開いた。そしてその聖所から、7つの災害を携えた7人の御使いが出て来た。』
『天にある、あかしの幕屋の聖所』とは何か。言葉を分解して見てみよう。まず『あかしの幕屋』とは、「『イエスのあかし』(12:17)を持つ天上の聖徒たち」という意味である。『幕屋』は聖徒たちの比喩表現である。天上において神は聖徒たちを幕屋として歩まれる、ということについては7:15や13:6の箇所で説明された通りである。次に『聖所』とは、「『あかしの幕屋』である聖徒たちが住まう天の『都』(21:2)の中にある聖所」という意味である。簡単に言えば、これは「天国にある神と聖徒たちが一緒に住まう場所」ということである。それだから、この『あかしの幕屋の聖所』という言葉を、文字通りに捉えて、天国にはモーセたちの張ったような実際的な幕屋があったなどと理解してはいけない。この『幕屋の聖所』という言葉は、あくまでも比喩的な言葉だからである。この言葉はなかなか難しいと思えるのだが、神の恵みにより一つ一つの部分に分解して考察していけば、私が今解き明かしたことからも分かるように、解読がまったく不可能ということなのではない。黙示録を解読したいと願う聖徒たちは、黙示録の文章をこのように一つ一つ分解しつつ解読していくという作業を覚えていただきたい。必要なのは「丹念さ」である。黙示録の文章は秘儀と謎と象徴と隠喩から組み立てられており、その密度は人間の持つ知解の把握限度を越えているのだから、福音書や使徒行伝などのように、そこに書かれている文章を一挙に解読することは出来ない。タルムードの中で「たくさん掴もうとすると掴みきれないが、少し掴めば掴める。」(『タルムード モエードの巻』ローシュ・ハ・シャナー 第1章 4b p11:三貴)と言われているのは黙示録の解釈のことではないが、黙示録の解釈についても同じことが言える。すなわち、黙示録とは少しだけ掴んで解釈していくのが正しい解釈方法なのだ。従って、細かい部分を気にする傾向を持つ人や、神経質な人は、黙示録の解読に向いていると私は思う。私は日本人であるが、昔からアジア系の人間は繊細であると西洋の知識人から評されてきたから、私は民族的な意味において、黙示録の解読にはかなり向いていると言えるのかもしれない。より大雑把な傾向を持つ西洋人は、確かに黙示録の解読には今までほとんど取り組んで来なかったのだが(取り組んだ人も当然いるにはいるのだが、どれもこれもふざけた内容である)、それは民族的な性質がいくらかでも妨げになったという面もあったのではないか。
この『聖所』が『開いた』のは何故か。それには、どのような意味があったのか。『聖所』が開いたのは、そこにいた『7つの災害を携えた7人の御使い』たちが、裁きを与えるべく地に向かうためであった。というのも、天国の都における『聖所』から出ていかなければ、地に何かを行なうことはできないからだ。天の場所にいながら、神でもあるかのように、御使いが地に裁きを下すということはできない。御使いは全ての場所に遍在しておられる神ではないから、何かをする際には、その行なわれる場所に向かわなければいけない。それは、裁判官が家の中にいるため、裁判所の中で裁判をすることができないのと同じである。裁判官が裁判を裁判所の中で行なうためには家の中から出て行かなければいけないように、御使いが裁きを地において行なうためにも天の『聖所』から出て行かなければいけなかった。このようなことが描かれたのは、これを読んだ聖徒たちが、これから何が起こるのかよく弁えられるためである。
【15:6】
『彼らは、きよい光り輝く亜麻布を着て、胸には金の帯を締めていた。』
『きよい光り輝く亜麻布』とは、19:8で贖われた聖徒たちが着ることを許された『光り輝く、きよい麻布の衣』と同一の衣ではないかと思われる。聖徒たちが衣を着ることを許されたのは、すなわち聖徒たちが『正しい行ない』において歩むということであった。つまり、この聖徒たちが着る衣と同一の衣を着ている7人の御使いたちは、『正しい行ない』をする存在だということを示しているのであろう。そうだとすれば、ここでは、あたかも次のように言われていることになる。「これから7人の御使いたちが鉢をぶちまけることになるが、それは悪いことではないのだ。それは、むしろ彼らにとっては善でさえあるのだ。」確かに7つの鉢を彼らがぶちまけるのは、現象的には被害という悪をもたらすことであるが、倫理的な意味で言えば、それは神の意志を遂行していることなのだから、彼らにとっては善以外ではないことになる。
胸に『金の帯』が締められていたというのは、祭司が胸当てに着けていた『純金の鎖』(出エジプト28章22節)のことなのであろう。つまり、この7人の御使いたちは、アロンやアロンに連なる祭司たちのようだったということである。旧約の祭司たちは、良い意味で「異常」であり、その祭儀における忠実さは異邦人には理解できないぐらいのものであった。彼らが戦争の際に神殿の中に入ってきた兵士たちを前にしても、まったく通常のやりかたで動揺せず祭儀を続けたことは、よく知られている。彼らは兵士のことなど意に介さず、祭儀をしながら、そのまま殺されていった。これには異邦人も驚かされざるを得なかった。つまり、それほど彼らは神に忠実・熱心に仕えていたのである(※)。この御使いたちも、そのような祭司のように、神に忠実な態度で仕えていたということは疑えない。この『金の帯』については、祭司の胸当てに着けられていた鎖以外には思い当たるものがない。だからこそ、私は今、その胸当てに着けられていた鎖を助けとして、この『金の帯』を解釈したのだ。もし、もっと確からしく思える解釈が見つかったならば、この箇所を書き換える必要がある。もっとも、そのような解釈があるかどうかは定かではないが。今の時点では、これは旧約時代の祭司たちが着けていた『純金の鎖』と対応しているという解釈に立ちたい。ちなみに、偽ディオニシウス・アレオパギテースは、この帯について好き勝手なことを言っているが、それは今私が述べたように聖書に基づく考えではない。私は律法を提示しつつこの帯を説明した。しかし彼は、ただ自分の思うままに帯について説明している。すなわち彼はこう言っている。「そして帯は、彼らが自分たちの生産力を保持しうることを示しているし、またそれは、一つにまとまるという彼らの性質が彼ら自身においてただ一つに統一されることを示し、さらに秩序立った美しさをもって輪をなして彼ら自身の周りに不変の同一性によって集まるということを示している。」(『中世思想原典集成3 後期ギリシア教父・ビザンティン思想』天上位階論 第15章 第4節 p409~410:平凡社)我々は徹頭徹尾、理性ではなく聖書の根拠を求めつつ思索を進めるべきである。健全な聖徒たちは、このディオニシウスのようになるべきでない。
(※)
ヨセフスは、ポンペイウス率いるローマ軍がエルサレムを陥落させた時に見られた光景について、次のように書いている。「ローマ兵たちはここで非常に苦しめられたが、ポンペイオスはユダヤ人たちの不変の忍耐強さに、そしてとくに飛び道具の打ち込まれる中で宗教的儀式をひとつとして疎かにしないことに感嘆の声を上げた。あたかも都が深い平安の中に包まれているかのように、日々の犠牲と、罪の贖いの献げ物と、すべての礼拝儀式が落ち度なく神のためにささげられていたのである。そしてまさに都が陥落するときも祭壇の近くで同胞たちが殺されているときでさえ、彼らは宗教的儀式のための日々の細則の一項でも無視することがなかった。」(『ユダヤ戦記Ⅰ』Ⅰ 4:148 p067:ちくま学芸文庫)「このさなかにあって、祭司たちの多くは、帯剣した敵兵たちが向かって来るのを目にしても、冷静沈着に宗教的儀式を営みつづけ、神的なものへの宗教的儀式を命よりも優先させ、御神酒を注いでいる最中や香をたいている最中に虐殺された。」(同 5:150 p067~068)
[本文に戻る]
【15:7】
『また、4つの生き物の一つが、永遠に生きておられる神の御怒りの満ちた7つの金の鉢を、7人の御使いに渡した。』
『7つの金の鉢』が御使いたちに渡されたのは、神の裁きをこの御使いたちが代行することを意味している。神は御自身みずから裁きを直接的に下すこともお出来になられたが、この7人の御使いたちにその裁きを代行させられることを欲せられた。神が、御使いたちに裁きを代行させられるということについては、既に語られた通りである。神は、アッシリヤへの裁きとしてその陣営にいた『18万5000人』(Ⅱ列王記19章35節)を滅ぼされたが、その裁きを『主の使い』に代行させられたのを我々は既に知っている。そのように、この時も、やはり神は御自身の裁きを御使いたちに代行させたのであった。
『4つの生き物の一つが』7つの鉢を御使いたちに渡したのは、「演出」である。神は、別にセラフィムを通さずとも、この鉢を御使いたちに渡すことがお出来になったが、御自身の裁きの御業がより壮麗に感じられるように「演出」がなされるのを望まれた。もし、このような演出がなければ、この鉢による裁きについての記述は、どれだけ味気ないものとなっていたであろうか。非常に単調に感じられる記述となっていたのは確かである。神は全てを御自身の栄光のために行なわれるから、このような「演出」が加えられるのを良しとされた。というのも、そのような演出があってこそ、神の栄光がより豊かに現わされるようになるからである。
ところで、7人の御使いに7つの鉢を渡したこの『4つの生き物の一つ』とは、どのセラフィムのことなのか。この『4つの生き物』が4人のセラフィムだということについては、既に確認した通りである。これは4番目の『空飛ぶわしのよう』(4:7)なセラフィムである。一体どうしてそう言えるのか。まず、この7つの鉢の預言では再臨が挿入としては語られているが(16:15)、メインの内容としては語られていないから、この『4つの生き物の一つ』とは、明らかに再臨のキリストを呼び出した『ししのよう』(4:7)な第一のセラフィムではない(参照―6:1~2)。またこの7つの鉢の預言では、争いや殺戮が明瞭な記述でもって語られているのでもないから、争いや殺戮を引き起こす赤い馬を呼び出した『雄牛のよう』(4:7)な第二のセラフィムと考えるべきでもない(参照―6:3~4)。また、この7つの鉢においては、ユダヤと異邦人がその語られている対象だから―これは聖徒に関する預言ではない―、聖徒の復活をもたらす馬を呼び出した『人間のような顔を持』(4:7)っている第三のセラフィムであるとも考えるべきではない(参照―6:5~6)。さて、残るは4番目の『空飛ぶわしのような』(4:7)なセラフィムだけである。この7つの鉢では、ユダヤの致命的な破滅が預言されているのだから、ユダヤの破滅をもたらす馬を呼び出した第4のセラフィムが内容的に適合している(参照―6:7~8)。どちらでも、ユダヤの破滅が語られているからである。従って、この『4つの生き物の一つ』は、ハデスを従わせている死を乗せた馬を担当していた4番目のセラフィムだということになる。つまり、この4番目のセラフィムが7つの鉢を7人の御使いに渡したことには、「これからユダヤに死とハデスとが襲い掛かるのだ。」という暗黙のメッセージが込められていることになる。さて、私が今したように、神の恵みにより黙示録の記述を思索していけば、どれだけ難しいと思える箇所であっても、そこで書かれていることを究明することは不可能ではない。『求めよ。さすれば与えられん。』というキリストの御言葉は確かに真実である。黙示録の正しい解を求めて究明するならば、必ず正しい解が与えられることになるのだ。私はこのことを決して疑わない。聖徒たちは、「黙示録をマスターするなんて無理に決まっているじゃないか。」などという不信仰な思いを是非、捨て去ってほしいと私は思う。そのように不信仰な思いを持つ聖徒が、黙示録をマスターすることは絶対に出来ないであろう。必要なのは信仰なのである。
【15:8】
『聖所は神の栄光と神の大能から立ち上る煙で満たされ、7人の御使いたちの7つの災害が終わるまでは、だれもその聖所に、はいることができなかった。』
聖所に『神の栄光と神の大能から立ち上る煙』が満たされたので『はいることができなかった』というのは、明らかに出エジプト記40:34~45の箇所と対応している。我々が今見ている箇所では『煙』と書かれており、出エジプト記のほうでは『雲』と書かれている点で違っているものの、どちらも神の大いなる臨在のゆえに、そこに入ることが出来なかったと言われている。出エジプト記のほうでは、こう書かれている。『そのとき、雲は会見の天幕をおおい、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕にはいることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。』ヨハネがこの文章を書いていた時、この出エジプト記の箇所がその頭の中にあったことは間違いない。ここで7つの鉢の裁きが下される際に、聖所が『神の栄光と神の大能から立ち上る煙で満たされ』たのは、この裁きが『神の大能』により成し遂げられるということを、またそれが成し遂げられる時に神は『栄光』をお受けになられるということを、意味している。確かに『神の大能』によるのでなければ、このような裁きが実現されることはなかったであろう。またその裁きが実現されたならば、神の義なる審判者としての『栄光』がその裁きのうちに顕示されることになる。だからこそ、ここでは7つの裁きが下される際には、神のおられる聖所に『神の栄光と神の大能から立ち上る煙』が満たされたと書かれているわけである。
【16:1】
『また、私は、大きな声が聖所から出て、7人の御使いに言うのを聞いた。「行って、神の激しい怒りの7つの鉢を、地に向けてぶちまけよ。」』
この『大きな声』の主は、神か、15:7で出てきた『4つの生き物の一つ』か、それ以外の3人のセラフィムか、セラフィム以外の御使いか、のどれかである。この声は、2つ以上の存在が同時的に語ったものではないと思われる。すなわち、この声の主は一者だけに限定されると思われる。私としては先に出てきた『4つの生き物の一つ』がこの声を出したと考えるのが自然ではないかと思えるのだが、明白な根拠を示すことができないので、実際はどうだったのか確定的なことを言うことはできない。しかし、たとえこの声の主が分からなかったとしても、何か大きな問題が生じるというわけではないから、その点については心配する必要がない。
この声が『大き』かったのは、例のごとく、これから言われることが非常に重要だったからである。
『地に向けてぶちまけよ』と言われているが、この鉢の裁きは、地上を対象としている。すなわち、それは「天」が対象とされているのではない。この鉢による神の裁きとは、こういう仕組みとなっている。『鉢』の中には「神の怒りの裁き」という名の液体が入っている。その『鉢』に入っている裁きという名の液体を御使いが地に注ぐと、地に神の裁きが注がれることになる。つまり、この『鉢』とは、神の裁きが注がれるということを表わすための比喩表現である。また、この7つの鉢による裁きが注がれる際には、巻き物やラッパの場合と同じように、7つの事柄が一挙に実現されるというのではなく、一つ一つシッカリと順番に実現された。神は、秩序の神であられるので、この7つの裁きも秩序のうちに成し遂げられたのである。
繰り返し述べることになるのだが、この『7つの災害』も、『すぐに起こるはずの事』(1:1)だったと言っておかねばならない。確かに、この災害はヨハネが黙示録を書いてから『すぐに』実現された。というのも、『すぐに起こるはずの事』という言葉は真理だからである。真理である神の言葉を否定できるものならば、してみよ。もし否定するならば、その否定により、自分がキリスト者でないと暗に告白することになる。何故なら、神の御言葉を否定するのは、キリスト者ではないからである。キリスト者というのは、神の御言葉を『すなおに受け入れ』(ヤコブ1章21節)る人のことである。だから、真のキリスト者である人は、『すぐに起こるはずの事』という神の言葉を受け入れなければならない。すなわち、この『7つの災害』は本当にすぐに起こったと信じなければいけない。
【16:2】
『そこで、第一の御使いが出て行き、鉢を地に向けてぶちまけた。すると、獣の刻印を受けている人々と、獣の像を拝む人々に、ひどい悪性のはれものができた。』
まず我々が知っておくべきなのは、これから見ていく鉢における第1~第4までの預言は、先に見たラッパにおける第1~第4までの預言と、完全に対応しているということである。実際に、鉢とラッパの預言における4番目までの内容を見比べてみると、どうであろうか。驚くべきことだが、どちらも第1の預言が『地』(8:7=16:2)に対して、第二の預言が『海』(8:8~9=16:3)に対して、第3の預言が『川と水源』(8:10~11=16:4~7)に対して、第4の預言が『太陽』(8:12=16:8~9)に対して、という内容となっている。どの内容も、その対象としている被造物が同一であることが分かる。これは猿でも分かることではないかと思う。しかし、どうして鉢とラッパにおける4番目までの内容は同一なのか。それは、どちらもユダヤの破滅という同じ事柄について預言されているからである。ラッパにおける4番目までの内容は、すなわちユダヤに裁きが下されて遂に破滅に至る、というものであった。同様に鉢における4番目までの内容も、ユダヤに裁きが下されて破滅の悲惨を味わわされるというものである。「黙示録には繰り返しが多い。」と私が先に述べたことを、読者たちは覚えておられるであろう。今見た2つの箇所においても、このように繰り返しが見られる。それでは、どうしてどちらも同じ内容であるにもかかわらず、ラッパのほうではユダヤが『3分の1』と言われており、鉢のほうではユダヤについて『3分の1』とは言われていないのか。この疑問に、私は「ただ書かれていないだけだ。」と答える。鉢のほうでは、『3分の1』というユダヤを示すための指標がなくても構わなかった。何故なら、そのような指標を使わずとも、他の指標があるからである。その指標とは第3の鉢の預言である16:6の箇所に書かれていることである。そこではこう書かれている。『彼らは聖徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたは、その血を彼らに飲ませました。』これは、ルカ11:49~51の箇所を見れば分かるように、明らかにユダヤのことを言ったものである(※)。鉢の預言には、このようなラッパにはない指標があるので、別にラッパのように『3分の1』などと書くことでユダヤについて預言されていることを示さなくても問題なかったのである。私が今述べたこと、すなわち鉢とラッパにおける4番目までの預言はどれも同一の対象となっているということに気付くのは誠に重要である。聖徒たちは、もし黙示録を読み解けるようになりたいと思うのであれば、是非ともこのことを心に留めておくべきである。
(※)
『だから、神の知恵もこう言いました。『わたしは預言者たちや使徒たちを彼らに遣わすが、彼らは、そのうちのある者を殺し、ある者を迫害する。それは、アベルの血から、祭壇と神の家との間で殺されたザカリヤの血に至るまでの、世の初めから流されたすべての預言者の血の責任を、この時代が問われるためである。そうだ。わたしは言う。この時代はその責任を問われる。』』
[本文に戻る]
ここで書かれている『地』とはユダヤにおける地である。これを文字通りの地、すなわち地球全土という意味に捉えてはいけない。それは第一のラッパの箇所で書かれていた『地上』(8:7)という言葉が、ユダヤにおける地という意味であったのと同じである。
鉢における第一の裁きは、ユダヤがエジプトとパロのようになったという裁きであった。つまり、ユダヤがエジプトのように心を頑なにさせて悔い改めなかった、ということである。この箇所でユダヤに『ひどい悪性のはれものができた。』と書かれているのは、明らかに出エジプト記の記述と対応している。そこでは、悲惨な出来事が起きたにもかかわらず悔い改めようとしなかったエジプトとパロについて、次のように書かれている。『主はモーセとアロンに仰せられた。「あなたがたは、かまどのすすを両手いっぱいに取れ。モーセはパロの前で、それを天に向けてまき散らせ。それがエジプト全土にわたって、細かいほこりとなると、エジプト全土の人と獣につき、うみの出る腫物となる。」それで彼らはかまどのすすを取ってパロの前に立ち、モーセはそれを天に向けてまき散らした。すると、それは人と獣につき、うみの出る腫物となった。呪法師たちは、腫物のためにモーセの前に立つことができなかった。腫物が呪法師たちとすべてのエジプト人にできたからである。しかし、主はパロの心をかたくなにされ、彼らはふたりの言うことを聞き入れなかった。主がモーセに言われたとおりである。』(出エジプト9:8~12)ユダヤに対する裁きの場合、実際にエジプト人がそうなったように、『はれもの』が身体に生じたというわけではない。歴史を見ても、ユダヤにそのような災害が起こったことは確認できない。つまり、ここで言われているのは、「ユダヤ人たちは悪性の腫物による裁きが下されたのに頑なまま悔い改めようとしなかったエジプトのごとくになった。」ということなのである。すなわち、ここでは「悔い改めない」という結果においてユダヤがエジプトになぞらえられているわけである。少し理解するのが難しいが、このように考えるべきである。黙示録が普通の言い方で書かれている文書ではないということぐらい、読者も既に気付いているはずである。
悔い改めない、というのは霊的な災害に他ならない。何故なら、それは神の裁きにより、心が閉じられ、真理に盲目とさせられ、滅びに向かって突き進んでいくばかりとなる、ということだからである。出エジプト記には、神が不信仰なパロの心を閉じられたことについて、こう書かれている。『主はパロの心をかたくなにされた。』(10:27)このパロのように心が盲目とさせられてしまうのは、正に裁きそのものである。ヨハネも、心を頑なにさせるのは、既に神の裁きが注がれている証拠であると明白に述べている。『御子を信じる者はさばかれない。信じない者は神のひとり子の御名を信じなかったので、すでにさばかれている。』(ヨハネ3:18)肉の理解からすれば、心が盲目にさせられてしまうのは、実際的には裁きであると感じられないかもしれない。しかし霊的な理解においては、これは間違いなく裁きである。これこそが、正にユダヤに対する第一の裁きであった。彼らは、たびたび神が『悔い改める機会』(2:21)を提供して下さったのに、心を頑なにして悔い改めようとはしなかった。それは神の裁きが彼らに下されたからであった。
【16:3】
『第二の御使いが鉢を海にぶちまけた。すると、海は死者の血のような血になった。海の中のいのちあるものは、みな死んだ。』
『海』というのも、第一の鉢の場合と同じで、やはりユダヤにおける海である。つまり、これは単に「ユダヤ世界」もしくは「ユダヤ人全体」という意味である。
第2の裁きも、第1の裁きと同じように、ユダヤがエジプト人のように悔い改めなかったという裁きであった。今度のほうは、ユダヤが水を血に変えられてしまったにもかかわらず悔い改めなかったエジプトにおいて語られている。この箇所は、明らかに出エジプト記7:14~23の箇所と対応している。そこではナイルの水が血と化し、その水の中にいた生き物が死んでしまったことについて書かれている。これを我々が今見ている箇所と対応していないと考えることは出来ない。この出エジプト記の箇所を少し長いが引用する。『主はモーセに仰せられた。「パロの心は強情で民を行かせることを拒んでいる。あなたは朝、パロのところへ行け。見よ。彼は水のところに出て来る。あなたはナイルの岸に立って彼を向かえよ。そして、蛇に変わったあの杖を手に取って、彼に言わなければならない。ヘブル人の神、主が私をあなたに遣わして仰せられます。『わたしの民を行かせ、彼らに、荒野でわたしに仕えさせよ。』ああ、しかし、あなたは今までお聞きになりませんでした。主はこう仰せられます。『あなたは、次のことによって、わたしが主であることを知るようになる。』ご覧ください。私は手に持っている杖でナイルの水を打ちます。水は血に変わり、ナイルの魚は死に、ナイルは臭くなり、エジプト人はナイルの水をもう飲むことを忌みきらうようになります。」主はまたモーセに仰せられた。「あなたはアロンに言え。あなたの杖を取り、手をエジプトの水の上、その川、流れ、池、その他すべて水の集まっている所の上に差し伸ばしなさい。そうすれば、それは血となる。また、エジプト全土にわたって、木の器や石の器にも、血があるようになる。」モーセとアロンは主が命じられたとおりに行なった。彼はパロとその家臣の目の前で杖を上げ、ナイルの水を打った。すると、ナイルの水はことごとく血に変わった。ナイルの魚は死に、ナイルは臭くなり、エジプト人はナイルの水を飲むことができなくなった。エジプト全土にわたって血があった。しかしエジプトの呪法師たちも彼らの秘術を使って同じことをした。それで、パロの心はかたくなになり、彼らの言うことを聞こうとはしなかった。主の言われたとおりである。パロは身を返して自分の家にはいり、これを心に留めなかった。』これも第1の鉢の裁きと同じで、実際にユダヤの海が血に染まったということではない。ユダヤが破滅するに至ったユダヤ戦争の時期のユダヤを見ても、そのような記録は何も残されていない。これは、あくまでも例えとして語られているということに留意せねばならない。黙示録においてユダヤが『エジプト』(11:8)と呼ばれているのは、これが理由である。つまりユダヤが悔い改めなかったのは、モーセの時代に水が血に変えられても悔い改めなかったエジプトとまったく同じだということである。黙示録でユダヤがエジプトと同一視されているというこの理解は、黙示録の理解のためには非常に重要である。この理解なくして、黙示録の深みに達することは出来ない。
【16:4~6】
『第三の御使いが鉢を川と水の源にぶちまけた。すると、それらは血になった。また私は、水をつかさどる御使いがこう言うのを聞いた。「常にいまし、昔います聖なる方。あなたは正しい方です。なぜならあなたは、このようなさばきをなさったからです。彼らは聖徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたは、その血を彼らに飲ませました。彼らは、そうされるにふさわしい者たちです。」』
まず『川と水の源』とは、例のごとく「ユダヤ」という意味である。
この箇所で、『血になった』水をユダヤが飲ませられたと言われているのは、つまりユダヤが滅ぼされて、生き残った少数の者たちが散らされた、ということである。既に第3のラッパの箇所で見たが(8:10~11)、旧約聖書において「悪い液体を飲ませられる」というのは、ユダヤが滅ぼされて散らされることを意味している。エレミヤ9:15~16の箇所では、こう言われている。『それゆえ、イスラエルの神、万軍の主は、こう仰せられる。「見よ。わたしは、この民に、苦よもぎを食べさせ、毒の水を飲ませる。彼らも先祖たちも知らなかった国々に彼らを散らし、剣を彼らのうしろに送り、ついに彼らを絶滅させる。」』簡単なことである、すなわち「悪い水を飲む」=「裁きを飲む」である。エレミヤ書では『毒の水』と書かれており、我々が今見ている第三の鉢のほうでは『血』と書かれているという違いがあるが、これは全く問題にはならない。何故なら、『毒の水』であれ『血』であれ、飲用に適しない液体が書かれていれば比喩表現が成立するからである。それでは、どうしてこの比喩においては、悪い液体を飲ませられることが裁きという言葉の代わりとして言い表わされているのか。それは、川とは、そこから多くの人たちが液体を汲んで飲む場所だからである。その川が異常な液体に変化してしまえば、そこから汲んで飲む多くの人たちが死ぬことになってしまう。このために、川が異常な状態になるというのは、多くの人たちが滅ぼさるということを比喩として言い表わすには適切なのである。我々は、古代の世界においては、まだ多くの人たちが川から水を飲んでいたということを知る必要がある。古代は、水道設備が整えられている現代の社会とは違っていた。そのことを弁えれば、ここで川の水が変わるという比喩によりユダヤの滅びが示されていることを聞いても、それほど驚くことはなくなるであろう。なお、よく知られているようにユダヤの地に水はあまりなかった(※)。だから、ここで言われている表現を比喩的に捉えねばならないということは、ますます確かである。
(※)
「ユダヤには、それほど水は豊富にはなかった。」(カルヴァン)(『新約聖書註解Ⅲ ヨハネ福音書 上』3:22 p105:新教出版社)
[本文に戻る]
ここでユダヤの裁きが描かれている際に『水をつかさどる御使い』が登場したのは、水が変化するという比喩により表現されているユダヤの滅びの裁きを、御使いが代行して下すということを教えている。つまり、ここでは我々がよく事柄を理解できるようにと、この御使いが『水をつかさどる』と言われている。実際に、この御使いが水を支配していたと言われているのではない。もしこの御使いが本当に『水をつかさどる』役目を持っていたのであれば、ユダヤは実際に血に変えられた川の水を飲ませられたことになる。何故なら、『水をつかさどる』という言葉が比喩でなければ、「水が血に変えられた」ということも比喩ではないと理解せねばならないからだ。しかし、実際にユダヤが血に変わった水を飲んだということはない。だから、この『水をつかさどる』という言葉を文字通りに捉えるべきではない。
ユダヤに下されたこの裁きは「正しい」裁きであった。それは、この裁きを下された神が『正しい方』だったからである。正しくない存在は正しくない裁きを下すが、神は正しい存在だから正しく裁きをなされた。ユダヤがこのような滅びの裁きを受けたのは、彼らの行なった大きな悪のゆえである。彼らは『聖徒たちや預言者たちの血を流し』たのだ。だから彼らには滅びが与えられた。すなわち、彼らが神の使いたちを滅ぼしたので、神もそのようなことをしたユダヤを滅ぼされた。要するに、ユダヤの滅びは、理由なしに起きたことではなかったのである。だから、確かに神は彼らに対して正しい裁きを下されたことが分かる。また、神はこの裁きを通して、御自身の義を豊かに顕示された。聖徒たちと御使いたちは、このような裁きを見ることで、神が義であられ、神はその義に基づいて正しく裁かれるということを豊かに知ったのである。
ここではキリストについて『常にいまし、昔います聖なる方』とは言われているが、『後に来られる方』(4:8、1:8)という言葉は見られない。これは、つまりこの第三の鉢における出来事が「再臨後」に起こるということを教えている。もう再臨が起こったからこそ、ここでは『後に来られる方』と言われていないのである。これは確かにそうである。というのも、紀元68年6月9日に再臨が起き、それから42ヶ月経過した紀元70年9月にユダヤが血を飲ませられて滅びたからである。我々は、ここで『後に来られる方』という言葉が書かれていないことに注意すべきである。これは一見すると些細なことだと思えるかもしれないが、このような小さいと思える点が、黙示録の理解を助ける大きなキーとなるからである。実際、ここでは『後に来られる方』という言葉がないという点に着目することにより、ここで語られている預言が再臨後の出来事だという重要な理解が得られるようになっている。それゆえ、いかなる小さな点であっても気をつけないようであれば、それだけ黙示録を理解するのは難しくなってしまうであろう。
【16:7】
『また私は、祭壇がこう言うのを聞いた。「しかり。主よ。万物の支配者である神よ。あなたのさばきは真実な、正しいさばきです。」』
ここでは『祭壇』から声が聞こえたと書かれているが、これは「かつては祭壇の下にいたが今は復活して新しい身体を受けている魂だけの状態だった聖徒たち」が発した声である。これを『祭壇』そのものの声であると考えると誤りに陥る。何故なら、『祭壇』と言って、『祭壇の下にいる』『神のことばと、自分たちが立てたあかしとのために殺された人々のたましい』(6:9)を意味しているのは明らかだからである。祭壇そのものが声を出すということはない。また、これが祭壇の下にいる魂だけの状態となっている聖徒たちであると考えるのも、誤っている。何故ならば、この第3の裁き、すなわちユダヤの破滅が実現される時には、既に祭壇の下にいた魂たちは復活に与かっているからである。もしこれがまだ復活に与かっていない状態の聖徒たちであるとすれば、ユダヤが破滅する時にもまだ復活が起きていないことになるが、それはあり得ないことである。また、ここで祭壇の下にいた魂たちが声を発しているかのように書かれているのは、このかつては魂だった聖徒たちの切なる願いが遂に聞き入れられたことを我々に教えるためである。6:10でこの魂たちが『大声で叫んで言った』ように、魂たちはいち早くユダヤに滅びの裁きが行なわれることを待ち望んでいた。それが遂に紀元70年9月において実現されたのだ。だから、その願いが遂に実現されたことを示すべく、ここではあえてその時には既に魂だけの状態ではなくなっているにもかかわらず、あたかもまだ魂だけの状態で聖徒たちが祭壇の下にいるかのように思える描き方がされているのである。このような描き方がされたのは、『耳のある者たち』にとっては、このようにして描かれたほうがよく理解できるからである。ここで『祭壇がこう言うのを聞いた。』と書かれているのは、私が今言ったように理解するのが望ましいと思う。というのも、このように理解しない限り、上手に理解することが出来ないからである。もしそのように理解しないと、矛盾が起きてしまう。すなわち、「どうして再臨が起きてから後に起きた出来事が示されているのに、まだ魂たちが復活していないのか?魂たちは再臨が起きた際に復活したのではなかったのか?」という看過できない疑問が生じてしまう。
この箇所では既に復活している魂たちも、『あなたのさばきは真実な、正しいさばきです。』と言うことで、ユダヤに対する神の裁きが正しいことを強調している。何故なら、第三の御使いに続いて、この聖徒たちも、神の裁きが正しいと言っているからである。これは、神がユダヤを破滅させたからといって何か悪が行なわれたのではない、ということを教えるためである。つまり、「神はユダヤを滅ぼしたから悪を行なわれるお方なのだ。」という批判を避けるために、このように書かれた。世の中には、それが正しい裁きであっても、その裁きの痛々しさだけに目を留め、その裁きを下した主体者に非難をぶつける者が少なからず存在している。例えば、死刑執行人が死刑を執行したのを聞いて「人を殺すなど悪いことだ!」などと、その刑罰と死刑執行人に文句を言い立てる人が、それである。このような人は、裁きの背景にある正義を何も見ておらず、ただ裁きそのものを直視しているだけなので、その裁きの痛々しさに驚いたり怒ったりして、このように非難する。神のユダヤに対する裁きも、確かにそれそのものとしては誠に痛々しかったが、それはユダヤに対する報いの意味として実施されたのだから、その裁きを見て神が悪を行なわれたなどと考えてはいけないのである。我々も、この歴史的に有名な破滅の出来事を起こされた神に対して、愚かにも文句を言い立てたりしないように気をつけねばならない。聖書が教えるように、神は決して悪を行なわないのだから。
【16:8~9】
『第4の御使いが鉢を太陽に向けてぶちまけた。すると、太陽は火で人々を焼くことを許された。こうして、人々は激しい炎熱によって焼かれた。しかも、彼らは、これらの災害を支配する権威を持つ神の御名に対してけがしごとを言い、悔い改めて神をあがめることをしなかった。』
ここで言われている『太陽』というのも、やはり「ユダヤ」を指している。黙示録という文書の難解性を考えれば、このようにいちいち似たようなことを繰り返して言うのは許されるであろう、否、むしろ積極的にそのようにして少しの認識不足も生じないようにすべきであろう。この文書には、密度の高い文章が満ちており、隅から隅まで分からないことだらけなのだから。
第4の裁きは、ユダヤが、ソドムのように焼き尽くされ、悔い改めなかったという裁きであった。この箇所は、明らかにソドムの破滅について記している創世記19:23~28の箇所と対応している。そこでは次のように書かれている。『太陽が地上に上ったころ、ロトはツォアルに着いた。そのとき、主はソドムとゴモラの上に、硫黄の火を天の主のところから降らせ、これらの町々と低地全体と、その町々の住民と、その地の植物をみな滅ぼされた。…』(19:23~25)我々が今見ている箇所で『鉢を太陽に向けてぶちまけた』と書かれているのは、すなわちユダヤが「『太陽が地上に上ったころ』に滅ぼされたソドム」も同然であったということを示す。ヨハネがこの文章を書いている時、この創世記の記述が頭の中にあったことは間違いない。しかし、実際にユダヤが『太陽』により焼き尽くされたというのではない。ここで太陽がユダヤを焼いたと書かれているのは、あくまでも比喩である。歴史を見れば、誰でもユダヤが火の海と化したのが太陽によるのではなかったことぐらい容易に理解できる。実際にユダヤが火に包まれたのは、太陽がその地を焼いたからでなく、無名のローマ兵が何気なく都の中で火を放り投げたからであった。ここで太陽がユダヤの人々を焼くことの比喩として使われているのは、太陽が全ての人たちを照らす天体だからである。確かに太陽はユダヤのあらゆる人に熱を与えていた。だから、ユダヤの人々が『激しい炎熱によって焼かれた』ことを比喩により言い表わすために太陽という天体を使うのは、実に適切であったわけである。また、先に見た第一と第二の裁きにおいては、実際的な損害については、そのなぞらえられている対象と共通点が何もなかった。すなわち、第一と第二の裁きでは、そのなぞらえられているエジプトと「悔い改めなかった」という結果における共通点しか見られず、実際的な損害を受けたことについては何も類似していなかった。確かにユダヤは破滅する際、エジプトのように『悪性のはれもの』(16:2)が人々に出来たり、海が『死者の血のような血』(16:3)になる、という損害は受けなかった。しかしこの第4の裁きの場合、悔い改めないという点だけでなく、実際的な損害についても、そのなぞらえられている対象と共通している。すなわち、ユダヤはソドムのように悔い改めなかった上、激しい火で焼き尽くされた。実際的な損害においてもそのなぞらえられている対象と共通している、という点で、この第4の裁きは第一と第二の裁きと異なっている。だからこそ、第4の裁きは第一と第二の裁きとは連続していない場所に置かれているのかもしれない。また、黙示録においてユダヤが『ソドム』(11:8)と呼ばれているのは、これが理由である。ユダヤは、正にソドムとでも言わんばかりに心を頑なにさせ、そのためソドムのように焼き尽くされてしまった。確かに、当時のユダヤはソドムも同然であった。キリストがあれほどまでに激しくユダヤ人を非難されたのは、ユダヤがソドム化していたからに他ならない。だからこそ、彼らは遂にソドムと同じような裁きを受けるに至ったわけである。それは紀元70年9月のことであった。
このような火の裁きをユダヤが受けるに至ったのは、ユダヤの高慢がその理由であった。彼らは自分たちだけが他の民からより分けられたのを誇っていたが(※①)、その誇りが耐え難く見苦しい高ぶりを生み出し、彼らの精神と敬虔を改善不可能な段階にまで腐らせた。高慢は人が悔い改めるのを不可能にさせてしまう。何故なら、悔い改めとは精神を遜らせることに他ならないのだから。神は、高慢に満ちていたユダヤが悔い改めて自ら遜ろうとしなかったので、大いなる裁きを与え、強制的に彼らを下へ引き下げられた。このように神は、自ら謙遜になろうとしない高ぶった者どもを、強引に下へと引き下げられるお方である。サタンも「神のようになろう。」と言って高みに達しようとしたので引きずりおろされた、とイザヤ書では言われている。この時に裁きを受けたユダヤ人の末裔である今のユダヤ人たちも、やはり相も変わらず高慢を続けている。彼らは高慢なので、未だに自分たちこそが世界を支配するのに相応しい民族であると考え、何とかしてメシアによるユダヤ王国を実現させようとして、世界中で悪事を密かに行ない続けている。神は今はまだ彼らに対する裁きを留保しておられるので、彼らは恐れることもなく好き放題に振る舞っているが(※②)、いずれ神の裁きが下されることになるのは目に見えている。それは、旧約時代のユダヤが裁かれるまでは偶像崇拝にふけって平気でいたのだが、遂に時至って大いなる裁きを受けることになったのと同じである。なかなかその高慢が罰せられないのは、会心の一撃により最後の最後に破滅の刑罰を受けさせられるためなのである。
(※①)
「ユダヤ人たちが、どんなに傲慢な態度で、祖先のアブラハムにおいてみずからを誇り、また、どんなにうぬぼれてみずからの種族の神聖さを自負していたかは、周知のとおりである。」(カルヴァン)(『新約聖書註解Ⅲ ヨハネ福音書 上』1:47 p59:新教出版社)
[本文に戻る]
(※②)
次のソロモンの御言葉は、今のユダヤに対して言われているかのようである。『悪い行ないに対する宣告がすぐ下されないので、人の子らの心は悪を行なう思いで満ちている。』(伝道者の書8章11節)
[本文に戻る]
『これらの災害』とは何か。これは、第1から第4までの鉢における災害のことである。すなわち、心が頑なにされるという災害(第一および第二)、大量に人が殺されて生き残った者も散らされてしまうという災害(第三)、ソドムのように火で焼き尽くされて住む場所を消失させられてしまうという災害(第四)、である。これらの災害を下されたのは他でもない全能の神であった。だから、ここでは『これらの災害を支配する権威を持つ神』と書かれている。神は、あらゆる災害の主である。全ての災害は主が起こされたものである。それは、アモスが次のように言っていることから分かる。『街にわざわいが起これば、それは主が下されるのではないだろうか。』(アモス3:6)このアモスの言葉は、街だけでなく、街以外のあらゆる場所においても同じことが言える。だから、人間は神を恐れなければいけないのである。というのも、神を恐れない者には、その悪に対する当然の報いとして『災害』が送られるからだ。神は、御自身を恐れない「うなじのこわい者」に対しては容赦されないお方である。ユダヤもそのような者たちで満ちていたので、容赦のない『災害』が送られたのであった。
ここまでの4つの裁きは、一つの纏まった区分として把握すべきである。というのも第1から第4までの預言は、明らかに纏まっているからである。そこではユダヤに対する破滅の預言が、全体的に、時間の考量抜きに語られている。これは先に見たラッパにおける第1から第4までの預言でも同様である。
【16:10~11】
『第5の御使いが、鉢を獣の座にぶちまけた。すると、獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあまり舌をかんだ。そして、その苦しみと、はれものとのゆえに、天の神に対してけがしごとを言い、自分の行ないを悔い改めようとしなかった。』
第5の預言からは、実際に実現される順序通りの記述となっている。すなわち、まず第5の出来事が、次に第6の出来事が、最後に第7の出来事が、という時間の流れが記述における内容に伴うことになった。これは第4までの預言が、時間とまったく無関係に語られていたのとは大違いである。この鉢による7つの預言も、やはり<4:3>という方式で記されている。すなわち、最初の4つまでが時間経過と無関係に記され、後の3つは時間経過に則った記述となっている。それでは、4:3という方式には、どのような意味があるのか。それはこういうことである。まず「4」は、世界全体について網羅的にその起こる出来事を時間を何も考量せず記している。何故なら「4」とは聖書では世界を意味しているからだ。次に「3」は、その起こる出来事を時間ごとに3段階に区分して記すことで、その流れが完全に構築されたものであることを教えている。何故なら「3」とは完全な数字だからである。我々は、このように3段階で描かれることにより、その流れが完全に仕組まれたものであるということを知れる。この<4:3>の方式の意味は、私の今の考えでは、このように考えるのが望ましいと思われる。というのも、私が今述べた以外の意味は見いだせないように感じられるからである。しかし、神は一体どうして<4・3>の方式を採用されたのであろうか。その理由は何か。これについては分からないとしか言いようがない。神は、このような法式で記述されることを欲された。私に言えるのはこれぐらいである。あえて何かを言ってよいというのであれば、私は「神は数式を好まれる。」と言ってみたい。ロジャー・ペンロースという高名な物理学者―彼はホーキングの師である―は「世界は数式で成り立っている。」と言っている。確かに神が数式を好まれるというのは、この宇宙、ことに天体の動きが全て数式で読み解けるのを考えても分かる。つまり神は数式に基づいて世界を創造されたということだ。だから、ここでも4・3という数式めいた秩序を設定されたということなのかもしれない。
『獣の座』とは、「ネロ(=獣)の座」だからローマを指す。これはローマ以外の様々な国や地域も、もちろん含まれている。しかし、それはローマの支配と影響が及ぶ範囲に限られている。つまり、『獣の座』とは「ローマ帝国の世界」ということである。
第5の鉢による裁きは、ローマ世界の人々が、真っ暗闇にされたのに悔い改めようとしなかったエジプトのように心を頑なにさせた、という裁きであった。ここに書かれているのは、明らかに出エジプト記10:21~29の箇所と対応している。そこではこう書かれている。『主はモーセに仰せられた。「あなたの手を点に向けて差し伸べ、やみがエジプトの地に来て、やみにさわれるほどにせよ。」モーセが天に向けて手を差し伸ばしたとき、エジプト全土は3日間暗やみとなった。三日間、だれも互いに見ることも、自分の場所から立つこともできなかった。…しかし、主はパロの心をかたくなにされた。パロは彼らを行かせようとはしなかった。』(10:21~23、27)「国が暗くされた」という点でこの2つの箇所が一緒のことを、少なくとも文章においては言っていることを疑う人はいないはずである。実際には、ローマ世界がエジプトのように真っ暗闇になったというわけではない。歴史を見てもそのような現象は記録されていない。ここで言われているのは、先にも述べたように、ローマが暗くされたのに悔い改めなかったエジプトのごとくになった、ということに他ならない。つまり「悔い改めない」という結果においてどちらも同一だったということだ。これは、先に見た第一と第二の鉢における場合とまったく同じである。要するに、ローマもユダヤと同じような裁きを受けてしまったのである。ローマにいた人々の心の頑なさは正にパロそのものであった。実際にはローマ世界にもかなり悔い改めてクリスチャンになった人がいたようであるが、やはり悔い改めなかった人が断然に多かった。だから、多くの人たちが、ここで言われている不信仰という霊的な災害を受けたことが分かる。先にも述べたように、霊的な理解では、不信仰とは刑罰そのものである。だから、ここでローマの不信仰が明白な「災害」に分類されていたとしても不思議なことはない。
ここでは不信仰な異邦人だけが記述の対象とされていることに注意してほしい。すなわち、ここではユダヤおよび聖徒たちのことが言われているのではない。何故なら、ここではこの2つの存在については何も触れられていないからである。
【16:12】
『第6の御使いが鉢を大ユーフラテス川にぶちまけた。すると、水は、日の出るほうから来る王たちに道を備えるために、かれてしまった。』
6番目の裁きは何か。第6の裁きは、ネロがユダヤの鎮圧をウェスパシアヌスをはじめとした将来の『王たち』に命じた、という裁きである。先にも言ったように、霊的に言えば、ユダヤの地における境界線は『大ユーフラテス川』である。この境界線としての川に水が流れている限り、敵たちは、決してユダヤに攻め込むことができない。何故なら、その川の水が、敵たちの行く手を阻むからである。ここでは、その川の水が『かれてしまった』と言われている。つまり、これはユダヤにおける霊的な境界線である『大ユーフラテス』が『かれてしまった』ので、敵であるローマの『王たち』が遂にユダヤに攻め込むことができるようになった、ということである。これはユダヤにとっては正に『災害』そのものであった。それは、あの獰猛で力強いローマがユダヤを鎮圧することになったからである。ここでは霊的な言われ方がされているから、『大ユーフラテス川』という言葉を文字通りに解してはならない。もしこれを文字通りのユーフラテス川のことだと考えれば、正しい解はまったく得られなくなってしまう。実際的に、あの大川が枯れてしまったとは一体どういうことなのであろうか…。
ここで言われている『王たち』とは、将来のローマ皇帝のことであり、それはネロの頭に生えていた『10本の角』(13:1)すなわち7本の角を指している。具体的に言えば、それはガルバ、オト、ウッティリウス、ウェスパシアヌス、ティトゥス、ドミティアヌス、ネルウァもしくはトラヤヌスである。ここで「彼らは第6の裁きが注がれる時にはまだ『王たち』ではないではないか。」などと言って批判をする者がいてはならない。この『王たち』は17章で詳しく説明されているが、そこでは彼らが『まだ国を受けて』(17:12)おらず、『一時だけ王の権威を受け』(同)る、つまり少しの間だけ王として見做される、と言われているからである。つまり、彼らはこの第6の裁きが注がれる際には、まだ正式な王であってはいけなかった。だから、実際はまだこの『王たち』が第6の裁きが注がれる際に正式な王でなかったとしても問題にはならない。この『王たち』については、17章の註解に至れば再び説明されるであろう。
この将来の『王たち』が『日の出るほうから』ユダヤに攻め入ることになるというのを理解するには、キリストの再臨について考えなければいけない。先に7:2の箇所で説明されたように、キリストは『日のでるほうから』日が昇って来るかのように再臨された。この再臨の時期に、ローマの『王たち』もユダヤに攻め入ることになる。つまり、ここではローマの『王たち』が『日の出るほうから』来ると言うことで、彼らの出陣が再臨の起こる時期に起こるということを教えている。実際には、彼らが『日のでるほうから』、つまり東のほうからユダヤを攻めに行ったというのではない。実際は、東とは正反対の西のほうからユダヤが攻められた。だから、この『日のでるほうから』という言葉は、あくまでも象徴表現であると理解せねばならない。ローマが東のほうから攻め入るなど意味が分からない話である。ローマとはユダヤよりも西に位置していたのだから。
注意しておかねばならないことがある。それは、ここで言われている『ユーフラテス』という言葉が、先に見た第6のラッパの箇所でも出て来るということである。既に確認したようにラッパと鉢の預言は4番目までは同一の内容だから、『ユーフラテス』という同一の言葉が使用されているラッパと鉢における第6番目の預言も一緒の内容だと思われる方がいるかもしれない。私も一時期、そうかもしれないと感じていた。確かに4番目までがどちらも同一であるのは間違いないが、この6番目においては、同じ言葉が使われているからといって同一の内容が書かれているというのではない。確かなところ、ラッパと鉢における6番目の内容は、1番目~4番目までの内容とは違い、あまりにも違っている。それは火を見るよりも明らかである。まずラッパにおける第6番目の預言(9:13~21)は、もう既に再臨が起きている時期の出来事である。すなわち、そこでは再臨が起きて後に始まる42ヶ月の荒野期間が終わってから、解放された御使いたちに動かされたローマ軍がユダヤを殲滅させることについて預言されている。一方、鉢における第6番目の預言は、まだ再臨が起きていない時期について言われている出来事である。それは、後ほど見る16:13の箇所で書かれていることからも分かるが、この第6の預言における出来事の際には、まだネロが生きているからである。まだネロが生きているということは、つまりまだ再臨が起きていないことを意味している。何故なら、Ⅱテサロニケ2:8で言われたように、ネロは再臨が起こるまでは生きているからである。このようにラッパの第6番目ではもう再臨が起きており、鉢の第6番目ではまだ再臨が起きていないのだから、どちらのほうでも『ユーフラテス』という言葉が出て来るからといって、一緒の出来事が言われているというのではない。思考が足りない間は、「もしかしたらラッパと鉢の6番目は一緒の内容なのかもしれない。」と考えてしまう。しかし思考をすれば「一緒の言葉が使われているからといって一緒の内容が書かれているわけではなかった。」という理解を得られる。人間に理性という賜物を備えられた神は、我々に理性を使用することである「思考の努力」を求めておられる。神の恵みにより思考をするからこそ、黙示録の謎や難しい箇所が解明されるようになるのだ。それは、今私が書いた内容を見れば分かる通りである。
【16:13】
『また、私は竜の口と、獣の口と、にせ預言者の口とから、かえるのような汚れた霊どもが3つ出て来るのを見た。』
『にせ預言者』とはティゲリヌスのことである。何故なら、この『にせ預言者』は、19:20の箇所で、ネロに近い存在であり、また『しるし』により人々を『惑わ』したと書かれているからである。ネロに近い上に、『しるし』により多くの人を惑わす者とは誰か。それはティゲリヌス以外にはいない。これは13章の箇所を見れば明らかである。ティゲリヌスが『にせ預言者』と呼ばれているのは、黙示録では、この16:13が初めてである。ここ以外では、19:20および20:10の箇所で、このような呼ばれ方がされている。『竜』と『獣』についての説明は不要であろう。
ここで言われているのは、どういうことか。この箇所は密度が濃いので、一つ一つ解明していかねばならない。まず『霊』が口から出たとは、ある霊により言葉が語られるという意味である。何故なら「霊が口から出る」とは、「霊の働きにより何かを話す」という意味だからである。次にこの霊が『3つ』の口から出たとは、その霊による言葉が3者の口から出たということである。すなわち、『竜』と『獣』と『にせ預言者』がそれぞれ霊によりあることを語ったので、合計で3つの霊だというわけである。それでは、この3つの霊は3者に何を語らせたのか。それは、ユダヤにローマ軍を雪崩れ込ませる権能を持つローマの『王たち』を動員させるということであった。この霊が『かえるのよう』であったと書かれているのは、この3者により動かされたローマの指揮官たちが統率するローマ兵が『かえるのように』数多いからである。黙示録では、ローマ兵が『海べの砂』(12:18、20:8)のようだったと書かれているが、それは『かえるのよう』だということでなくて何であろうか。蛙のように無数のローマ兵が神の裁きによりユダヤに雪崩れ込むのは、明らかにエジプトに蛙が群がったあの出来事と対応している。もうお分かりであろう。ユダヤとユダヤに対するローマ軍を通しての裁きは、エジプトとエジプトに対する蛙を通しての裁きと、まったく対応しているのである。確かに、ユダヤにローマ軍が大量に雪崩れ込んだのは、エジプトに蛙の群れが入り込んだ時のようであった(※)。ユダヤにおけるローマ軍=エジプトにおける蛙。要するに、ここで言われていることを分かりやすく言えば、次のようになる。「サタンとネロとティゲリヌスは、悪しき霊の働きにより、蛙の群れでもあるかのようなローマ軍を統率する者たちがユダヤを攻め入るようにと布令を発した。」この箇所は非常に難しく、霊的である。文字通りに理解しようとしても、一向に正しい理解が得られることはないであろう。私が今神の恵みにより書いたように、ユダヤ戦争との関わりにおいて考察しない限り、しかも比喩的に解読しようとしない限り、この箇所を読み解くことはできない。
(※)
『主はモーセに仰せられた。「パロのもとに行って言え。主はこう仰せられます。『わたしの民を行かせ、彼らにわたしに仕えるようにせよ。もし、あなたが行かせることを拒むなら、見よ、わたしは、あなたの全領土を、かえるをもって、打つ。かえるがナイルに群がり、上って来て、あなたの家にはいる。あなたの寝室に、あなたの寝台に、あなたの家臣の家に、あなたの民の中に、あなたのかまどに、あなたのこね鉢に、はいる。こうしてかえるは、あなたとあなたの民とあなたの家臣の上に、はい上がる。』主はモーセに仰せられた。「アロンに言え。あなたの手に杖を持ち、川の上、流れの上、池の上に差し伸ばし、かえるをエジプトの地に、はい上がらせなさい。」アロンが手をエジプトの水の上に差し伸ばすと、かえるがはい上がって、エジプトの地をおおった。…』(出エジプト8:1~6)
[本文に戻る]
この箇所から第6番目の災害の時には、まだネロとティゲリヌスが生きていたことが分かる。何故なら、ここではネロとティゲリヌスが霊により語っているからである。もし彼らが既に死んでいたとすれば、彼らの口から霊が出て来ることはなかったはずだ。それというのも、霊とは生きている存在にこそ働きかけるのであって、動きもしない死者には働きかけないからである。霊にとっては、死体に入っても面白いことは何もない。それだから、もし既にこの2人が死んでいたとすれば、ここで、このような記述がされていることは無かったであろう。また、既に述べたように、まだネロおよびティゲリヌスが生きているということは、すなわちまだ再臨が起きていないということを意味する。
【16:14】
『彼らはしるしを行なう悪霊どもの霊である。』
ここでは、3者の口によりローマ軍を統率する者たちに布令が発せられたのは、『悪霊どもの霊』によったと教えられている。これは、第6のラッパの箇所で、悪しき御使いたちがローマ軍を動かしてユダヤを滅ぼさせたと教えられていたのと全く調和している。というのは、『悪霊』とはすなわち「悪しき御使い」のことだからである。つまり、悪しき御使いである悪霊たちがローマ軍を動かす指揮官たちに働きかけ、また指揮官たちと共にローマ軍をも動かしてユダヤを滅ぼした、ということである。悪霊どもが「悪しき御使い」だというのは聖書を見れば明瞭に分かる。ヘブル1:14によれば聖なる御使いとは『仕える霊』である。つまり、聖なる御使いたちが聖なる奉仕のために用いられる霊だというのであれば、悪しき御使いたちが悪に仕える霊だということも、必然的に結論されるのだ。
この『しるし』とは何なのか。これは、既に説明されたローマ大火における『しるし』のことであろう。何故こう言えるかといえば、『しるし』とは大火の事件しか考えられないからである。確かに13:13の箇所で、この大火は『しるし』であると言われている。つまり、サタンとサタンに取り憑かれていたティゲリヌスが起こし、そしてネロも大いに喜んだであろうあの大火事件は、究極的に言えば『悪霊どもの霊』が引き起こしたということだ。確かなところ、あのような忌まわしい事件は、悪霊どもでなければ引き起こせない。ちょうど2001年9月11日の自作自演テロが、悪霊に動かされた者たちにより計画され、実現されたのと同じである。この『しるし』を、この箇所(16:14)で書かれている『全世界の王たち』の招集であると捉えることはできない。何故なら、その招集の出来事は何も『しるし』などと言われていないが、大火事件のほうは明白に『しるし』と言われているからである。
『彼らは全世界の王たちのところに出て行く。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて、彼らを集めるためである。』
サタンに憑かれたネロとティゲリヌスはその悪霊の働きにより、『全世界の王たち』をユダヤ戦争に出向かわせるべく招集させた。これは象徴的な表現である。これを文字通りに捉えてはならない。何故ならば、先に見たこの7人の『王たち』の中には、ユダヤ戦争に参加していなかった者がいたからである。例えばドミティアヌスはユダヤ戦争には参戦しなかったし、トラヤヌスはユダヤ戦争の時にはまだ15歳ぐらいだから、彼が戦争に参戦したかどうかは疑わしい。つまり、ここではユダヤ戦争の時に起こる再臨を、より壮大に描くためにこのような「演出」がされている。キリストの再臨とはこれ以上ないほどに偉大な出来事である(映画化したらどれだけ壮大になるであろうか…)。その出来事は、やはり軽んじられるべきではないから、壮大に描かれる必要がある。ここで行なわれている演出のように再臨の際には、『全世界の王たち』が招集されると書かれたら、それだけ再臨が壮大に感じられるようになるのは確かである。だからこそ、ここでは『全世界の王たち』が再臨の際に戦いをすると演出的に言われているのである。事柄は霊的に捉えねばならない。聖書において、このように演出的な表現が多く見られるというのは、初信の聖徒でなければ既に知っておられるのではないかと思う。例えば、それは先にも引用した使徒行伝2:16~20の箇所がそうである。ここでは太陽と月に何も変化が見られなかったのに、『太陽はやみとなり、月は血に変わる』(20節)などと演出的な表現が使われていた。つまり霊的に言えば、このペンテコステの出来事が起きた際には、太陽と月が異常な状態になってしまったということである。我々が今見ている箇所で言われている事柄についても、それと同様に霊的な捉え方をせねばならない。もしこの箇所で言われているのが本当に文字通りの出来事だとすれば、今言及した使徒行伝2章の出来事も、本当に文字通りの出来事だったと捉えねばならないことになる。だが、使徒行伝2章の記述が演出的な性質を持っていることを疑う人はいないはずだ。―いったい誰が本当に当時、ペテロの上空にあった太陽が闇となり月が血に変わったと理解するのか???―それだから、我々が今見ている箇所における記述も演出的な性質を持っていると考えねばならないのだ。そもそも『全世界の王たち』という言葉からして演出的であることに注意すべきである。この人たちは17章で言われているように、実際上はまだ王ではない。それゆえ、これはあくまでも演出的に捉えねばならない言葉である。であれば、この『全世界の王たち』という演出表現が含まれているこの文章全体が演出的であったとしても、何も不思議なことはないではないか。
それでは、『万物の支配者である神の大いなる日の戦い』とは何か。これは、「再臨の日にキリストが戦う戦い」という意味である。再臨が起こるとは、すなわち再臨されたキリストが霊的な敵たちと戦われて裁きをなし、そして勝利されるということである。この再臨の日のことについてパウロはこう言っている。『そのとき主は、神を知らない人々や、私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は、主の御顔の前とその御力の栄光から退けられて、永遠の滅びの刑罰を受けるのです。』(Ⅱテサロニケ1章8~9節)この『大いなる日』は既に訪れたと理解しなければいけない。何故なら、もう既にしつこいぐらいに言っているが、再臨はパウロの仲間たちが『生き残っている』(Ⅰテサロニケ4章)間に実現したからである。既にパウロの時代に再臨が起きたと認めない者は、パウロを嘘つきに仕立て上げている。何故なら、そういう人たちの考えによれば、パウロは本当は当時の人たちが『生き残っている』間に再臨が起こるわけではないのにもかかわらず、『生き残っている』間に再臨が起こると言って偽証したことになるからである。こんなふざけた理解をしていいはずがどうしてあるのか!!確かにパウロも言ったように、再臨の起こる『大いなる日』はパウロの時代に既に来ている。これは今までに全く語られてこなかった解釈だが、しかし真に聖書的な解釈であるから、聖徒たちは勘違いをしないように注意してほしい。
【16:15】
『―見よ。わたしは盗人のように来る。目をさまして、身に着物を着け、裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。―』
これは例の挿入である。先に見たラッパと巻き物における挿入と同じで、ここでも7つの預言の内容には適合しない挿入がされている。すなわち、この7つの鉢による預言はユダヤと不信者たちについて言われているのだが、挿入における内容は聖徒たちのことである。ラッパの場合はユダヤに関する預言であったが挿入においては聖徒のことが語れており、巻き物の場合は地上に関する預言であったが挿入においては天上のことが語られていた。この挿入は6番目の預言が終わる一歩手前で書かれている。これはラッパにおける挿入と同じである。ラッパでも、第6番目の預言が終わる直前に挿入がされていた。しかし、挿入における内容量は、鉢とラッパでは、かなり違っている。鉢の挿入が極短めである一方、ラッパの挿入は非常に長い。この鉢の挿入は、第6番目の預言が終わって後に挿入が加えられる巻物における挿入とは、かなり違う。これが挿入であることは明らかであるが、このような挿入が、更に黙示録の密度を高めている。これは神が「解けるものなら解いてみよ。」とでも言っておられるかのようである。確かに黙示録は謎に満ちた難しい文書であるが、恵みを受けた者であれば、その複雑な謎を紐解くことができる。確かなところ、解ける者は解けてしまえるのだ。それだから、黙示録を解読できる者は、解読できる恵みを与えて下さった神に感謝せねばならない。
『わたしは盗人のように来る。』というのは、聖書の他の箇所でも書かれていることである。例えば、キリストはマタイ24:42~44の箇所でこう言っておられる。『だから、目をさましていなさい。あなたがたは、自分の主がいつ来られるか、知らないからです。しかし、このことは知っておきなさい。家の主人は、どろぼうが夜の何時に来ると知っていたら、目を見張っていたでしょうし、また、おめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だから、あなたがたも用心していなさい。なぜなら、人の子は思いがけない時に来るのですから。』ここでも、キリストが御自身を「盗人」に例えておられる。またパウロも似たようなことを言っている。すなわち彼はこう言っている。『兄弟たち。それらがいつなのか、またどういう時かについては、あなたがたは私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が盗人のように来るということは、あなたがた自身がよく承知しているからです。』(Ⅰテサロニケ5章1~2節)この言葉でキリストが言われたのは、つまり「再臨はいつ起こるか分からない。」ということであった。それゆえ次のソロモンの言葉は、正にこの再臨について言われているかのようである。『いつ起こるかをだれも告げることはできない。』(伝道者の書8章7節)確かに再臨は、紀元68年6月9日に『盗人のように』起こった。『盗人』が押し入ってきたら誰でもギョッとするであろうが、再臨もギョッとするようにして起こった。実際、再臨が起きた際には、多くの人たちがその唐突さに驚いたことであろう。いったい聖徒たちの中の誰が、再臨の実現する日が紀元68年6月9日だなどと思ったであろうか。誰もそのようなことは思っていなかったに違いない。今の聖徒たちは、まだ再臨が起きていないと勘違いをしているので、今にもキリストが『盗人のように来る』と本気で思っている。ある牧師は「私は私の生きている間に再臨が起こると信じている。」などと言っていた。このような非聖書的な信仰を持つに至ったのは、今まで教会が再臨について誤解してきたからである。だからこそ、私はこの作品を通して、その誤解を正そうと試みているわけである。私の言ったことを受け入れて、再臨は既に起きたと信じる人が、これから徐々に出て来るのではないかと私は期待している。実際、そのように信じている人は、既に何人かいるのだ。しかし多くの人は、私の言ったことがよく理解できても、ヨハネ福音書に出てくるパリサイ人たちのように周囲の目を恐れるだろうから、何も行動を起こさず、また何らそのことについて言及することをしないであろう。それについて指摘すれば絶対に相手の口を封じられると信じていても、である。アレイスター・クロウリーは邪悪な著作家だが、彼が次のように言ったのは正に至言であった。「堅固に見えながらも、子供が一突きするだけでひっくり返ってしまうようなものが、この世にはたくさんあるのだ。ところが、誰ひとりとして、この一突きをする勇気がないのである。」(『アレイスター・クロウリー著作集―1 神秘主義と魔術』<第4の書>神秘主義 p81~82 国書刊行会)クロウリーのこの言葉は、再臨についても同じことが言えるのである。
『目をさまして』とは、信仰の眠りを貪るなという意味である。キリストは聖徒たちが霊において生きることを望んでおられる。信仰的に考え、信仰的に語り、信仰的に行なう。これこそが『目をさまして』いるということである。現代のキリスト教は世俗化が大きな懸念事項だが、世俗化したクリスチャンは、はっきり言って『目をさまして』はいない。彼らは信仰を眠らせ、肉において目を覚ましている。というのも、彼らは肉的に考え、肉的に語り、肉的に行なう傾向を持っているからである。聡明なJ・S・ミルは、今のクリスチャンと初代教会のクリスチャンの違いを見て、大いに驚いているが、確かに世俗化した昨今の教会は初代教会に比べたら大変悲惨な状態になっていると言わざるを得ない。今の教会は『目をさまして』いなさいという命令を、忘れてしまったかのようだ。なお、この『目をさまして』という命令は、聖書の他の箇所でも多く見られる。例えば、Ⅰコリント15:34、Ⅰテサロニケ5:6などがそうである。
『身に着物を着け』とは、イエス・キリストという着物を着けたままでいなさい、という意味である。キリストを着るということについては、パウロも次のように言っている。『主イエス・キリストを着なさい。』(ローマ13章14節)『バプテスマを受けてキリストにつく者とされたあなたがたはみな、キリストをその身に着たのです。』(ガラテヤ3章27節)キリストという着物を着けていなければ、キリスト者ではない。キリストは、御自身の民が、御自身という着物を身に着けたままでいるのを望んでおられる。だからこそ、ここでキリストは『身に着物を着け』たままでいなさい、と御自身の聖徒たちに言われたのである。なお、こういう人は稀だと思うが、これが実際的な着物のことを言ったなどと考えるのは滑稽の極みである。いったいキリストは聖徒たちがヌーディストにならないようにと警告されたとでもいうのか。そのようなお笑いな解釈は、コントの中だけにしてもらいたいものである。
『裸で歩く恥を人に見られないようにする』とは、キリストという着物を脱ぎ捨てた状態のことである。これは、上で見た『身に着物を着け』という命令と、内容的に一緒である。霊的に言えば、キリストという着物を着けていない人は、『裸』の状態である。というのも霊的な理解では、神の御前における真の意味での着物とはイエス・キリストだけだからである。神は、キリストの他に、正しい服装を認めておられない。もし着物を着ていなければ、その人は裸の状態なのだから、栄光の天国
に入ることができず、神から『あれの手足を縛って、外の暗やみに放り出せ。そこで泣いて歯ぎしりするのだ。』(マタイ22章13節)と言われることになる。ユダは正に『裸で歩く恥を人に見られ』る者であった。すなわち、この邪悪な男は周りの人たちから見ればキリストという着物を着ていたかに思えたが、全てをご覧になっておられる神の御前では、キリストという着物を着ておらず、まったく裸の状態であった。不信者たちについて言えば、彼らはキリストという着物をその身に着けていないのだから、例外なく『裸』である。霊的なヌーディストである彼らは、神の前に忌まわしい存在である。この不信者については、詳しい説明は不要であろう。我々は、キリストという着物を万が一にも脱ぎ捨てたりしないように注意せねばならない。もし我々が裸の状態になれば、その行き着くことになる先は永遠の地獄である。
この箇所でキリストが言っておられるのは、つまりネロとティゲリヌスが『王たち』を招集する時期には再臨が起こるから、しっかりした信仰を持っていなければならない、ということであった。というのは、再臨の時に信仰が悲惨な状態だと、大変なことになってしまうからである。そのような人は再臨が起きた際に携挙されないで地に残され、それから42ヶ月経過した後で2回目の刈り取りが起きてから、空中の大審判で裁かれて地獄に投げ落とされてしまった。キリストは一人でも多くの人が、そのような悲惨を味わわないようにと願われた。だからこそ、ここで、このようなことを言って下さったのである。なお、ネロとティゲリヌスが『王たち』を招集するユダヤ戦争の時期に再臨が起こるというのは、福音書の中でも教えられていることである。確かにマタイ24章やルカ21章の箇所では、そのように教えられている。
【16:16】
『こうして彼らは、ヘブル語でハルマゲドンと呼ばれる所に王たちを集めた。』
『ハルマゲドン』(‘Αρμαγεδδων)とは、ヘブル語で「メギドの丘」という意味の言葉をギリシャ語化したものである。英語では「アルマゲドン」(Armageddon)と言われる。この丘は、古代では有名な戦場であった。これは今のパレスチナの地にあり、地中海から東に40km、ヨルダン川から西に60km、エルサレムから北に100kmほどの位置にある。この丘のあった町は通商路に面していた。再臨の際には激烈な戦いが起こることを教えようとして、ここでこの言葉が使われているのは疑えない。この「メギド」という言葉は、ファンタジー作品でも使われることがある。例えば、ファイナルファンタジーという世界的に有名なゲームの中では、モンスターの技名に「メギドフレイム」というものがある。この「メギド」という言葉は非常に響きが良く、いかにも戦いを思わせる勇ましい雰囲気がある。私も、この言葉そのものとしては嫌いではない。そうであれば、ファンタジー作品の中で使われたとしても不思議ではない。「アルマゲドン」という言葉も、何かの作品などで使われることがある。例えば、この言葉をタイトル名とした映画があるし、マジック・ザ・ギャザリングという有名なカードゲームの中でも、この言葉を使ったカード名がある。この言葉は、新約聖書では、黙示録の中に一箇所だけ出てくるだけである。旧約聖書の中では、この言葉すなわち「メギドの丘」について、次のように書かれている。『王たちはやって来て、戦った。そのときカナンの王たちは、メギドの流れのそばのタナクで戦って、銀の分捕り品を得なかった。』(士師記5章19節)『彼の時代に、エジプトの王パロ・ネコが、アッシリヤの王たちのもとに行こうとユーフラテス川のほうに上って来た。そこで、ヨシヤ王は彼を迎え撃ちに行ったが、パロ・ネコは彼を見つけてメギドで殺した。ヨシヤの家来たちは、彼の死体を戦車にのせ、メギドからエルサレムに運んで来て、彼の墓に葬った。』(Ⅱ列王記23章29~30節)『その日、エルサレムでの嘆きは、メギドの平地のハダデ・リモンのための嘆きのように大きいであろう。』(ゼカリヤ12章11節)『しかし、ヨシヤは身を引かず、かえって、彼と戦おうとして変装し、神の御口から出たネコのことばを聞かなかった。そして、メギドの平地で戦うために行った。』(Ⅱ歴代誌35章22節)今引用した御言葉では、どれも「戦い」や「悲惨さ」という要素において語られていることが分かる。
ここで言われているのは、再臨の時には、ネロと一時的に『王たち』だと見做された者たちが、『メギド』で悲惨な状態になった王たちのように悲惨になる、ということである。これは霊的に捉えねばならない箇所である。もしこの箇所を霊的に捉えないと、この箇所を正しく理解することはできない。これは「メギドの地において裁かれた王たちのようにローマの者たちが裁かれる―ただし霊的な意味において」というふうに捉えなければならない。世の中には、黙示録をよく理解していないにもかかわらず、この『ハルマゲドン』の戦いを文字通りに捉えている者たちが多くいる。その上、まだその戦いは実現していないと、その者たちは何の疑いもなく考えている。つまり、今のパレスチナの地域で巨大な戦争がこれから起こるなどという間違った理解を持っているのだ。もし本当にそうだとすれば、メギドの丘と呼ばれていた地域は、あまりにも重要なことになる。何故なら、文字通りに捉えるならば、そこにこそキリストが再臨されるのだから。しかし、それほど重要な地域であるにもかかわらず、あまり多くの人たちがこの地域について考究していないのはどうしたわけか。私は、この地域について徹底的に掘り下げて考えている教師たちを、ほとんど見ていない。もし本当にメギドの丘があった地域に再臨が起こるのであれば、これほどまでに考究せねばならない地域は他にないはずである。一体どうして、この地域が重要であるにもかかわらず、多くの者たちがこの地域について深い考究をしていないのか。それは自分の黙示録に対する理解に自信が持てていないからだと思われる。その上更に、この16:16の箇所を文字通りに捉えてよいものか無意識的に不安に感じている。というのも、少し黙示録を眺めれば黙示録が象徴的な表現に満ちていることに気付かされるからである。要するに、「本当に今の理解でよいのか…」という無意識の思いがあるゆえ、この箇所を力強く考究することができていないのであろう。もし黙示録を半分以上正しく理解できているという自信があれば、この16:16の箇所における理解についても自信を持てたかもしれないが、黙示録を半分以上も正しく理解できている人はほとんどいない。もし彼らの確信が本物であれば、当然ながらこの重要な地域は徹底的に探り調べられるべきであろう。しかし、徹底的に探り調べられていないのだから、もしくは探り調べられても深みが足りないのだから、多くの人たちが「これから『ハルマゲドン』で再臨の戦いが起こる。」と口では言っていても実のところ確信が足りていないのだ(※)。だが、ここまで神の恵みにより黙示録を註解している私は、彼らとは違ってこう言う。すなわち、「これは象徴的な表現であって、しかも既に実現された出来事である。」と。黙示録を解読したく願う聖徒たちは注意せよ。今のままこの箇所を文字通りに理解しようとするのであれば、永遠にこの箇所を正しく理解することはできないであろう。
(※)
もしあくまでもこのように言い続けることを止めないならば、私が恵みにより今しているように黙示録の註解を書いてみるがよい。そうしたら、その見解にかなり説得力が増すのではないかと思われる。もし黙示録の大半の部分が分からず、それゆえ註解を書けないのであれば、その人が持っている16:16の箇所に対する解釈も本当に正しいかどうか定かではないではないか。この16:16の箇所だけは特例的に正しく解釈できているというわけでも、あるまい。
[本文に戻る]
この箇所から分かる『ハルマゲドン』の戦いは、19:19~21の箇所と対応している。そこでは再臨のキリストが敵どもと戦われ(19:19)、ネロとティゲリヌスは裁かれて死んだ後に地獄へと投げ込まれ(19:20)、『王たち』とそれ以外の者たちは御言葉という『剣』により霊的に裁かれて悪霊どもの餌食となった(19:21)、と書かれている。これこそ正にハルマゲドンの戦いである。何故なら、ネロとティゲリヌスおよび『王たち』が、ハルマゲドンの場所で悲惨な状態になった王たちや指揮官たちのように悲惨な状態にさせられたからである。要するに、繰り返すが、ここで言われているのは再臨の際にはメギドの地で起きたようなことが霊的な意味において起こる、ということに他ならない。
【16:17】
『第7の御使いが鉢を空中にぶちまけた。』
『鉢を空中にぶちまけた。』とは、キリストが『空中』に再臨されたので、『空中』にいたサタンがそこから引き落とされ(12:7~9、20:1~3)、そうして後に『底知れぬ所』(20:3)で『1260日の間』(12:6)封じられたということである。この箇所では明瞭に再臨について語られているのではないが、鉢における預言の流れを考えるならば、ここで言われているのが再臨のことだというのは明らかである。黙示録には「事柄を明白に書き記さなければいけない。」というルールがない。むしろ、この文書のルールは「傾向として事柄を謎に包ませてより分かりにくくさせる。」というものである。それは、黙示録を読んでみれば誰でも分かることである。それだから、ここで明白に再臨について語られていなかったとしても、驚くべきではない。このように、第7の鉢の預言では再臨のことが語られている。先に見た第1の巻き物の預言でも再臨のことが語られていた(6:1~2)。この点について、読者は考察すべきである。巻き物とラッパと鉢が順序通りに繋がっていると間違って考えるならば、すなわち巻き物⇒ラッパ⇒鉢という順で事柄が書き記されていると誤解するのであれば、どうして1番最初の預言と最後の預言(すなわち21番目)で再臨のことが語られているのか、という致命的な疑問が起こることになる。もしこれら3つの預言が順序通りに繋がっているとすれば、最初と最後で再臨について語られていることは説明ができない。何故なら、誰がどう考えても、これら3つの預言が順序通りになっていないことは明らかだからである。もし順序通りであったならば、第1番目(すなわち第一の巻き物の預言)で再臨が語られた後は、再臨が起きて後に起こる出来事だけが書き記され、もはや再び再臨について書き記されることはなかったはずだ。従って、第1の巻き物と第7の鉢において再臨という同一の事柄が預言されているという点から、巻き物とラッパと鉢という3つの預言は、順序通りに繋がっていないことが分かる。
『すると、大きな声が御座を出て、聖所から出て来て、「事は成就した。」と言った。』
私は前に、ここで書かれている『大きな声』の主について、次のように書いた。<この『大きな声』の主は、神か、第4のセラフィムかそれ以外のセラフィムか、セラフィム以外の天使たちか、である。これは恐らく16:1で出てきた声と同一の声ではないかと思われる。これも16:1の場合と同じで、実際は誰の声なのか我々には不明である。私としては第4のセラフィムではないかと感じられるが、しかし第4のセラフィムだという根拠が何もないので、確かなことを言うことはできない。>このように私は以前書いたのであったが、この声の主は、確かなところ「神」であった。何故なら、ここでは『大きな声が御座を出て』と書かれているからである。『御座』とは神の座っておられる所であり、そこにこそ神はおられる。その『御座』から『大きな声』が出たと言われているのだ。だから、ここで書かれている『大きな声』の主は神だったことになる。16:1の箇所のほうは、声の主が神だったかどうか分からない。というのも、16:1では我々が今見ている16:17と同じように『聖所』から声が出てきたと言われてはいるが、『御座』から出てきたとは言われていないからである。もし16:1の箇所でも16:17の箇所と同じように『御座』から声が出てきたと言われていれば、16:1も16:17と同じようにそこで書かれている声の主は神だったことになる。しかし、16:1のほうでは『御座』については触れられていないのだ。だから、16:1の箇所における声の主は、16:17とは違い、もしかしたら神以外の存在だったという可能性が十分にある。
神による『大きな声』は、『御座を出て、聖所から出て来』た。つまり、その声は豊かに鳴り響いたということである。これは何か他の例で言えば、「王の大きな声が王座から出て、王宮の外にまで鳴り響いた。」と言うようなものである。再臨が起きた際に告げられた言葉は、大いに周知されるべき言葉であった。それは聖所の外にまで聞こえるべきものであった。だからこそ、聖所の外にまで出るほどに声が鳴り響いたと、ここでは言われているのだ。
『事は成就した。』とは、どういう意味か。ここでは何が成就したと言われているのか。それは「再臨」である。前々から、神は再臨が起こると聖徒たちに繰り返し預言しておられた。その再臨の預言が遂に成就したのだ。だからこそ、ここでは再臨の預言を指して『事は成就した。』と言われているのである。これを分かりやすく言い換えれば、「以前から預言されていた再臨の出来事が遂に今や成就したのだ。」となる。
【16:18】
『すると、いなずまと声と雷鳴があり、大きな地震があった。この地震は人間が地上に住んで以来、かつてなかったほどのもので、それほどに大きな、強い地震であった。』
ここに書かれている諸現象は、キリストが天から降りて来られたことを示している。神はシナイ山に降りて来られた時にも山の周囲に『雷』『いなずま』『角笛の音』(出エジプト19:16)などといったものを生じさせたが、神が来られる際には、このようなものが生じるものなのだ。それは、神の尊厳を、様々な諸現象により際立たせるためである。これを他の例で例えるならば、王が入場する際に楽器隊がシンバルやラッパを大きく鳴り響かせて王の尊厳を人々に告げ知らせるようなものである。そのような演出が王の入場には相応しいように、神の再臨もそのような演出を伴わせつつ実現されるのが相応しいのである。「栄光ある者にはその栄光に相応しい飾りを。」ということだ。ここでは4つの現象について書かれている。『いなずま』とは、神の恐ろしさを示している。そうでなければ、これはユダヤ人たちがローマ兵により剣で虐殺されるということを意味している。というのも、『いなずま』とは旧約聖書の中で、虐殺のために剣が稲妻でもあるかのように研ぎ澄まされることを示しているからである。エゼキエル21:28~32の箇所では、アモン人が残忍な者たちの剣で虐殺され滅ぼされてしまうことについて、次のように書かれている。『剣、一振りの剣が、虐殺のために抜き放たれた。いなずまのようにして、絶ち滅ぼすためにとぎすまされた。…彼らの日、最後の刑罰の時が来る。』確かに、神はローマ人たちの持つ稲妻のように煌めく剣により、ユダヤ人を滅びの裁きへとお渡しになった。だから、この『いなずま』をユダヤの破滅と捉える捉え方には、聖書的な根拠がある。『声』とは、再臨の際に発せられる『御使いのかしらの声』(Ⅰテサロニケ4章16節)を指す。『雷鳴』とは、神の御怒りを表示している。『大きな地震』とは、再臨という出来事は、地さえも震えるほどの出来事だったということである。この地震が前代未聞の大きさを持っていたと言われているのは、誇張表現である。ヨハネはキリストの再臨がどれだけ驚くべき出来事かということを示そうとして、このように誇張しつつ地震について語っている。このヨハネは、他の箇所でも誇張表現を使用している。例えば彼は、キリストが行なわれた御業について、こう書いた。『イエスが行なわれたことは、ほかにもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書きしるすなら、世界も、書かれた書物を入れることができまい、と私は思う。』(ヨハネ21章25節)この言葉が、キリストの御業の数多さを教えようとして記された誇張表現であることは確かである(※)。つまり、ここでは実際的なことが言われたのではなく、あくまでも「キリストの御業はあまりにも多かった。」ということが言われている。ヨハネはこのように誇張表現をすることがある人であった。それだから、我々が今見ているこの箇所で、ヨハネが再臨の際に起こる地震について誇張的に表現していたとしても何も不思議なことはない。
(※)
カルヴァンもこの聖句は誇張であると言っているから、私が何か自分勝手なことを言っていると思うべきではない。というのも、これは誇張でなくて何であろうか。カルヴァンはこの聖句について、こう言っている。「このところの誇張した言いかたを、ばかげたものだと考えてはならない。それというのも、世俗の作者たちにおいて、いたるところに見いだされるこの種の言いかたは、容認されているからである。わたしたちは、単に主イエス・キリストのわざの数を見るばかりでなく、また、それらのわざの重みと偉大さとを計量しなければならない。神の子の神的な威厳は、その無限性において、単にひとびとの感覚のすべてを圧倒し去るばかりでなく、(いわば)天地をのみこんでしまうものだが、まさにそこに、奇跡的にその光輝をあらわしているのである。いま、聖ヨハネが、かくもあがめるべきこの光輝に目を投じて、まるでまったく眩惑されたように、それらについてなし得る物語を全世界も容れることはできないだろう、と叫んでいるとしても、それを奇怪なことと思わなければならないだろうか。」(『新約聖書註解Ⅳ ヨハネ福音書 下』21:24 p655:新教出版社)なお、聖書では他にも誇張表現が使われている箇所が多く見られる。その一つは詩篇6:7の箇所である。ここでは、『わたしはわたしのうめきによって夜ごと寝台を洗うでしょう。わたしはわたしの涙でわたしの寝具をぬらすでしょう。』と書かれているが、これは誇張である。ルターは、この箇所についてこう言っている。「またわれわれは「涙」と「うめき」を誇張表現によって「寝台を洗い、ぬらす」として理解する。というのはある聖人がそれほど多量の涙を流したとは、けっしてどこでも聞かれたことがないからである。一夜でもそんなことはないのに、ましてや夜ごとにそんなことはありえない。それゆえ彼が寝台をぬらすことはなく、ましてや泳がせることはない。しかしわれわれは誇張表現を、涙のはたらきの外面だけを言ったものと理解しよう。…」(『キリスト教神秘主義著作集11 シュタウピッツとルター』第二回詩篇講義 p409:教文館)アモス6:14の箇所も、カルヴァンも言っているように「預言者は誇張して記している」(『アモス書講義』第6章 p260:新教出版社)。アモス9:2~4、13の箇所も同様である(同 第9章 p346/p376)。
[本文に戻る]
【16:19】
『また、あの大きな都は3つに裂かれ、諸国の民の町町は倒れた。』
『大きな都』であるユダヤは、『3つに裂かれ』る裁きを受けた。これは簡単に言えばユダヤ滅亡の出来事のことである。この『3つに裂かれ』るという言葉を、文字通りに捉えてはいけない。これは象徴的な言葉だと捉えるべきである。これは、要するにエゼキエルが髪の毛を3等分したことである。すなわち、ユダヤ戦争においてユダヤ人の『3分の1』は都の中で焼き殺され、『3分の1』は都の外で悲惨な状態となり(※)、『3分の1』は生き残りはしたものの散らされてしまった。神は、エゼキエルにユダヤを表示させる髪の毛を3つに裂かせることで、ユダヤが受ける3通りの刑罰がどのようなものなのかエゼキエルにお示しになられた。このことについては、エゼキエル書5:1~2で書かれている。神は、その箇所でエゼキエルにこう言っておられる。『人の子よ。あなたは鋭い剣を取り、それを床屋のかみそりのように使って、あなたの頭と、ひげをそり、その毛をはかりで量って等分せよ。その3分の1を、包囲の期間の終わるときに、町の中で焼き、またほかの3分の1を取り、町の周りでそれを剣で打ち、残りの3分の1を、風に吹き散らせ。わたしは剣を抜いて彼らのあとを追う。』このように3つに引き裂かれるとは、ユダヤに3つの仕方で裁きが下されることを示す。確かにユダヤが陥落した時期には、そのような3通りの悲惨がユダヤに降りかかった。この『3分の1』という比率が、実際的な比率であるかどうかは定かではない。これは霊的に捉えるべきであろう。つまり、神の御前においては、実際の比率がどうであれ、この3通りの裁きを受けた人々は、それぞれどの裁きを受けた人たちも『3分の1』として見做されたということだ。先にもいくらか触れたが、聖書の中で、このように恣意的な判定がされているのは特に珍しいことではない。ユダヤが『3つに裂かれ』たという裁きは、私が今述べたように考えるべきである。これはエゼキエル書の助けなしには、正しく解釈できない箇所である。理性の判断のみで解釈しようとしても、正しい解釈を得ることは決して出来ないであろう。一体どこの誰が、ただ理性の考察だけで、すなわち啓示の助けなしにこの『3つに裂かれ』たという裁きを正しく解釈できるであろうか。もしそのような人がいれば、その人は神に違いない。私も上に引用したエゼキエル書の聖句を知らなければ、この裁きを解することは、まったく出来なかった。
(※)
ヨセフスの「ユダヤ戦記」によれば、この時には都以外の街々でも多くの戦いが起こり、ローマ軍により次から次へと攻略され、数え切れないぐらいのユダヤ人が殺された。これは正にエゼキエル書の預言で言われていることと合致している。カイサレア市にいたユダヤ人などは「1時間のうちに2万以上の者が殺害された」(『ユダヤ戦記Ⅰ』Ⅱ xviii1:457 p366:ちくま学芸文庫)とヨセフスは記録している。ガリラヤの町ヨタパタは紀元67年7月に陥落させられた(『ユダヤ戦記』3:339~)。ギスカラとヤムニアとアゾトスの町は紀元67年11月以降に制圧させられた(『ユダヤ戦記』4・112~120、130)。タキトゥスも、ウェスパシアヌスがユダヤの「農村地帯を全部と、エルサレムを除きすべての町を征服し、軍隊で制圧した。」(『同時代史』第5巻 10 p274:筑摩書房)と言っている。また都以外の地方は、敵だけでなく同胞である者、すなわちユダヤ人の狂暴な野盗によっても荒らし回された。ヨセフスは彼らについてこう言っている。「ユダヤの他の地方でも、それまで鳴りをひそめていた野盗たちが活動しはじめた。ちょうど、体の場合、その主要な部分が腫れ上がると他の部分すべてが病に冒されるように、母なる都における抗争と騒ぎのために、地方のごろつきどもが何の恐れもなく略奪の限りを尽くした。野盗たちの各集団は自分たちの村を略奪し終わると荒れ野へ逃げ込んだ。そしてそこで勢力を糾合し誓いを交わすと、舞台ごとに―その勢力は軍隊よりも少なかったが、小さな野盗集団より大きかった―神殿や町々を襲った。野盗たちに襲撃された者たちには、捕まった者たちの受けるひどい扱いが待ち受けていたが、報復の機会はなかった。野盗たちが、略奪を終えるや遁走してしまうからである。ユダヤの中であの傑出した都と滅びを共有しなかった土地はひとつとしてなかった。」(『ユダヤ戦記2』Ⅳ vii2:406~409 p209:ちくま学芸文庫)ローマ人たちは、このようなユダヤ人の内部抗争を「天の賜物」(「ユダヤ戦記」第4巻/2:366)と考えた。
[本文に戻る]
先に11:13の箇所で、ユダヤの『10分の1』の人々が再臨の際には携挙されたということについて書いた。私はその時、「10ユダヤ-1ユダヤ=9ユダヤ」
という理解を心に留めておくべきだと述べておいた。もし失念している人がいれば、再び確認したいと思われる方は、当該の箇所に戻ってそこに書かれている文章を読み直してほしい。11:13の箇所で述べたように、再臨の際には『10分の1』のユダヤ人が携挙されたのだから、再臨後に残されたのは「10分の9」のユダヤ人であった。すなわち、ユダヤを「10」として見做すと、「1」のユダヤが取り除かれたのだから、残るは「9」になった。これは小さい子どもでも理解できる。この再臨後に残された「9」のユダヤ人たちが、再臨後に起こるユダヤの陥落において『3分の1』すなわち「3」「3」「3」に分けられ、裁きを受けることになったのだ。再臨の際には1のユダヤが除かれて残りが9となったのだから、このように考えるのは荒唐無稽なことではない。すなわち、『3分の1』に分けられたことをよく理解させるために、先の箇所で『10分の1』が除かれたと教えられていたのだ。もしユダヤが10のままだったとすれば、3で割り切れないから、一体どういう裁きをユダヤが受けたのか理解しにくくなっていた。「9」になったからこそ、我々が今見ている箇所で言われていることが、すんなり理解できるようにもなるのだ。これで私が先の箇所において、ユダヤの『10分の1』が地から除かれたことについて心に留めておいてほしいと言ったのがどういうわけなのか、よくお分かりいただけたのではないかと思う。要するに、ユダヤは10%が先に再臨の際に救われ、残りの90%が後でユダヤ陥落の際に裁かれたということである。救いがまず起こり、裁きはその後に起きた。また救われるユダヤは少なかったが、裁かれるユダヤは多かった。神は、このようにユダヤの救いと裁きにおけるその順序および比率を、黙示録の中でお示しになっておられる。それゆえ、黙示録を読み解ける恵みを受けた者たちは、ユダヤ戦争の際のユダヤに一体どのようなことが起きたのか、よく知ることが出来るのである。
『諸国の民の町町は倒れた。』とは、ユダヤが裁きを受ける際には、それと同時に『諸国の民の町々』も神の裁きを受けたという意味である。この『諸国の民』とは、ユダヤ以外の諸々の民族を指す。しかし、その中にキリストを信じる者たちが含まれていないのは明らかである。というのも、ここでは裁きを受ける者たちについて言われているからである。確かにユダヤ以外の民族もユダヤが裁き受ける時には裁きを受けたのであるが、この2つの存在に注がれた裁きの内容は、かなり異なっていた。すなわちユダヤには実際的な破滅という物理的刑罰が与えられた一方、ユダヤ以外の民族には霊的な刑罰しか下されなかったという違いがある。これは歴史を見ても明らかである。確かにユダヤは実際に滅亡させられたが、諸国の民は実際的には損害を受けなかった。ユダヤが実際的な悲惨を受けたのは、彼らが真理を受け入れる責任を持った民族だったからである。神に選ばれた彼らこそ、もっとも神の真理を受け入れなければいけない存在であるということに異を唱える人はいないであろう。その責任の大きさのゆえに、真理を受け入れなかった彼らは滅亡させられてしまったのだ。他方、諸国の民はユダヤに比べれば真理を受け入れるべき義務を負っていなかった存在だから、ユダヤのように物理的な破滅を受けることはなかった。責任が少ないから、受けることになる裁きもその責任に応じたものとなった。義務と責任が大きければ、より刑罰も大きくなるというのは、既に語られた通りである。『倒れた』とは、「裁きを受けたので、倒れて悲惨になってしまった人のように悲惨な状態となった」という意味である。つまり、この言葉は比喩表現である。
『そして、大バビロンは、神の前に覚えられて、神の激しい怒りのぶどう酒の杯を与えられた。』
『大バビロン』であるユダヤが『神の前に覚えられ』た、とはどのような意味か。これは、「ユダヤの罪が満ちたので遂に神は裁きの遂行を心において決定された。」という意味である。この『覚えられて』という言葉を文字通りに捉えてはいけない。これを文字通りに捉えると、ここでは神がこの時に初めてユダヤを心に記憶されたと言われていることになるが、それは明らかにおかしい。言うまでもなく、神はそれ以前からずっとユダヤのことを記憶しておられた。そもそも世界の始まる前から既に神はユダヤのことを、その予知のうちに記憶しておられた。だから、この言葉を思考抜きに正しく捉えることは難しいと言わねばならない。この『覚えられて』という表現は、聖書、特に旧約聖書を読み慣れた人にとっては、特に珍しい表現ではないはずだ。まだ聖書特有の言い方に通じていない人は、ぜひこの機会にこの表現を理解すべきである。これは古代のユダヤ人らしい特徴的な表現方法である。
ユダヤは『神の激しい怒りのぶどう酒の杯を与えられた』とは、ユダヤが滅亡する際には、葡萄酒により泥酔したかのような状態がそこに実現されたということである。確かに神がローマ軍を通してユダヤに怒りの裁きを与えられた際、ユダヤ人たちは酷く泥酔した悲惨な人のように目茶目茶な状態となった。そこには苦しみ、嘆き、悲しみ、混乱、号泣、狂気、嘔吐、暴力、略奪、不法、殺戮などがあった。これは歴史を見れば誰でも分かることである。このようになったのは、霊的に言えば、『神の激しい怒りのぶどう酒』を彼らが強制的に飲まされたからであった。
この箇所で言われているユダヤの裁きが、未だに起きていないと思い違いをしてはいけない。何故なら、繰り返すが、この箇所で言われている裁きも『すぐに起こるはずの事』だったからである。キリストが言われたように、それまでにユダヤが流した血に対する報いは当時における時代の上に下された、ということを我々は忘れるべきではない。確かに主は当時のユダヤに対して次のように言われたのだ。『それは、義人アベルの血からこのかた、神殿と祭壇との間で殺されたバラキヤの子ザカリヤの血に至るまで、地上で流されるすべての正しい血の報復があなたがたの上に来るためです。まことに、あなたがたに告げます。これらの報いはみな、この時代の上に来ます。』(マタイ23章35~36節)この『報復』が紀元70年9月のエルサレム陥落をもって全うされたというのは、健全な理解を持っている人であれば、疑い得ないことであろう。確かにその時には、明らかに神の報復がユダヤに下されたのだから。それゆえ、もしキリストの御言葉を否定したいというのでなければ、この箇所で言われている裁きがまだ実現していないなどと思うべきではない。しかし、ここで次のように思われる方がいるかもしれない。「それでは今のユダヤはやがて『神の激しい怒りのぶどう酒の杯』を飲ませられることにはならないのか?もうこの箇所が実現済みだと言うのであれば、もはやユダヤに杯が与えられることにはならないということなのであろうか…。」私は答えるが、今のユダヤは蛇の子どもらしく邪悪な陰謀を世界中で働かせているから、いずれ『怒りのぶどう酒の杯』を飲ませられることになるのは確かである。だが、この16:19の箇所では、今のユダヤにそのような裁きが下されることになると言われているのではない。これからユダヤに激怒の葡萄酒が与えられるのは、この箇所と直接的には無関係に起こる。つまり、これからユダヤに与えられる裁きについては、「黙示録16:19における既に実現済みの裁きのような裁きがユダヤに与えられるであろう。」としか言えない。すなわち、16:19の預言が実現したものとして、これからユダヤが裁かれるというわけではない。要するに、それは単に既に実現済みの裁きに似ているに過ぎないということだ。この点に我々は注意せねばならない。ちなみに私の意見を言わせてもらえば、これからユダヤに裁きが注がれる時には、恐らく全てのユダヤ人たちがその脳か右手かに電子チップを埋め込まれることになると思われる。つまり、彼らは自分たちがしようとしていることを、逆にされてしまうことになる。そうして自分たちがコントロールしようとしていた人たちから、逆にコントロールされ、監視され、行動を制御され、苦しみと悲しみを味わわされることになる。このような裁きが起こるのであれば、それはニューワールドオーダーが実現するその時か、またはその直前であると私は予想する。神は万人がアッと思うことをされるお方だから(※①)、神がこのようにされる可能性はかなり高い。一体どこの誰が、これからこのような裁きが下されるなどと思うであろうか?恐らく私以外は誰もこのようなことは考えていないのではないか。しかし、神はほとんど全ての人が僅かにさえ予想さえしないことを積極的に実現されるお方である。何故なら、神の名は『不思議』(士師記13章18節)だからである。しかも、これは非常に聖書的な推測である。というのも聖書の多くの箇所において、悪者どもは、自分たちの仕掛けた罠にみずから陥ると言われているからである。例えば詩篇9:15~16の箇所にはこう書かれている。『国々はおのれの作った穴に陥り、おのれの隠した網に、わが足をとられる。主はご自身を知らせ、さばきを行なわれた。悪者はおのれの手で作ったわなにかかった。』確かに神は、悪者どもにその企みを鏡のように返されるお方である。あの忌まわしいハマンも(その名の意味は「不正」である)、『モルテガイのために準備しておいた柱にかけら』(エステル記7章10節)れて殺されしまったではないか。神はハマンがしようとしていた悪を、ハマン自身に返されたのだ。彼がモルテガイを十字架にかけて殺そうとしていたのに自分がそうされてしまったように、今のユダヤ人も人類を電子チップによりコントロールしようとしていたのに自分たちがそうされることになる、という可能性は0%ではない。この裁きがこれから実現されるかどうかは、時間が明らかにしてくれることであろう。もしこの裁きが下されるのでなければ、考えられる裁きとしては、ユダヤ人だけに感染するウィルスが密かに作られて大量のユダヤ人が死滅させられるというものがある。ユダヤ人は今現在、人工的に生成されたウィルスにより人口削減を実現させようと企んでいるから、この陰謀に危機感を持った科学者が密かにユダヤ人だけを死なせるウィルスを作り上げる可能性は0%ではない。つまり、これも先に述べられた裁きの場合と同様、ユダヤ人たちは自分たちがしようとしていることを逆に自分たちで受けてしまうことになる。神は報いられるお方だから、このようにユダヤにされる可能性は、かなり高い。(※②)
(※①)
悲劇作家のエウリピデスは、異教徒でありながら神について次のように言っているが、これは誠に正しい。「神は多くのことを思いもよらぬ形で成し遂げられる。思いどおりに事は終わらず、思いがけないところに神は道を見つけられる。」(『悲劇全集1』アルケスティス 1160-1162 p90:西洋古典叢書2012 第1回配本/京都大学学術出版会)「成ると思われたことが成らず、まさかと思うようなことを成らしめるのが神の遣り口。」(同 メデイア 1417-1418 p202)
[本文に戻る]
(※②)
私がこの文章を書いてから1か月も経たないうちに、コロナウィルスが問題になり始めた。当然ながら、私がこの文章を書いた時には、まだコロナウイルス問題は起きていなかった。このコロナウイルスはイルミナティカードで予告されていたから、イルミナティの親分である陰謀家のユダヤ人が仕掛けたということになる。このような次第であるから、私はコロナウイルスがニュースになり始めてから、かなり驚いたものである。嘘を言うのではないが、私にはこのような出来事が多い。前兆めいた預言的な出来事がよく起こるのである。単なる思い込みに過ぎなければ、ここでこんなことを書いてはいなかったであろう。日本の有名な芸能人である志村けんが死ぬことについても預言的な出来事があったので、「彼は1年以内に死ぬだろうが、それは具体的には何月頃なのだろうか。」などと思っていたら、間もなくしてコロナウィルスに感染したとのニュースが流れ、「やっぱりか。」などと驚いていたら死去に至ったのである。これは本当のことである。神は私が嘘を言っていないことを御存じであられる。神が、これから起こる出来事を、事前に私に示して下さっておられるのだと思う。
[本文に戻る]
【16:20】
『島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなった。』
16:19で描かれたユダヤの陥落が起こると、第二の復活⇒第二の携挙⇒空中の大審判、という順序で事が進み、遂に世界が刷新されるに至った。『島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなった。』とは、この世界の刷新を言っている。つまり、島も山も一度消え失せて新しく再び据えられる、と教えることで世界の刷新を示している。この箇所は象徴的な表現として捉えるべきである。この箇所を文字的に捉えてはならない。ここで言われていることを文字的に捉えるのは、狂気に陥ることである。いったい、この箇所で霊的な言い方がされているということを理解しない人が誰かいるのであろうか。もっとも、このように霊的な言い方のために、心のひねくれた不信者からはその特徴的な表現が問題視されてしまうことになるのだが。
我々は、この世界の刷新が、紀元70年9月に空中の大審判が起きた際に実現されたことを疑うべきではない。多くの人たちは、紀元70年9月を振り返っても何ら世界に変革が起きたようには感じられないので、この時に世界が刷新されたなどとは理解できないかもしれない。しかし、聖書はこの時にこそ世界の刷新が起きたと教えているのだから、そのように信じなければいけない。事柄を霊的に捉えない限り、神の真理を理解することはできない。この世界の刷新は、他の例で言えば、ノンクリチャンがクリスチャンになるようなものである。誰かがクリスチャンになったからといって、天使のように輝いたり羽を持ったりするのではないから、その人がクリスチャンになったことを周囲の人が知らないままでいるというケースは珍しいものではない。実際、その人がクリスチャンになったという情報を耳にしたり、教会に実際に行ったりしているのを知ったりしない限り、なかなか誰かがクリスチャンになったことに気付けないものである。しかし、周りの人がどう思おうと、その人は確かに神の御前においてクリスチャンとなっている。それは、その人が神の御前でキリストによる贖いを受けたからである。問題なのは人からどう認識されるかではなく、神の御前で実際にどのような状態であるか、ということだ。紀元70年9月に世界が霊的な意味において刷新されたのも、これと同様である。多くの人がこの時に世界が刷新されたなどと思えなかったとしても、霊的に言えば、確かに世界はこの時に刷新されたのである。だからこそ、この時において、預言や異言や奇跡やその他無数の素晴らしい賜物が廃止されることになったのだ。また、この時期には世界中に福音を宣教する役目を与えられていた使徒たちや伝道者たちも、携挙されてことごとく世界から消えうせてしまっている。これは一度この時に世界がリセットされたことを示している。もしそうでなければ、紀元70年9月を経ても、未だに諸々の賜物が継続され、使徒や伝道者たちも活動を続けていたことであろう。聖書の教える世界刷新の出来事を、天国がこの地上に現出するかのように理解している人たちは、研究不足のため先入観を持っているのであって、あまりにも肉的に事を捉え過ぎている。そのような人たちは、人がクリスチャンになった際には神の子となったのだから即座に天使のように完全な聖性を持つことになるのであって罪を犯すことも一切無くなる、などと思い違いをしている人たちと似ている。
この箇所の言葉は、黙示録では次の箇所と対応している。―これから挙げる箇所は、どれも全て同じ時のことについて言われている― 20:11。『また私は、大きな白い御座と、そこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って、あとかたもなくなった。』6:14。『天は、巻き物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移された。』福音書の中では次の箇所が対応している。マタイ24:35。『この天地は滅び去ります。しかし、わたしのことばは決して滅びることがありません。』使徒書簡では次の箇所が対応している。Ⅰペテロ4:7。『万物の終わりが近づきました。』Ⅱペテロ3:12。『そのようにして、神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために、天は燃えてくずれ、天の万象は焼け溶けてしまいます。』我々が今見ている16:20以外の対応箇所では『島』『山々』ではなく『天』『地』『万物』などと言われている箇所もあるが、どれも世界刷新という同一の事柄について言われていることに変わりはない。
【16:21】
『また、1タラントほどの大きな雹が、人々の上に天から降って来た。人々は、この雹の災害のため、神にけがしごとを言った。その災害が非常に激しかったからである。』
この『雹』による裁きは、不信仰な異邦人をその対象としている。これはユダヤに対してではない。聖徒たちに対する裁きだとするのは、もっての他である。ここでは、福音を受け入れなかった全ての不信者たちが、あたかも『雹』の災害を受けたのに悔い改めようとしなかったエジプト人のように心を頑なにさせた、という裁きが語られている。確かに当時の不信者たちは、心を頑なにするという点で、雹の悲惨を受けたエジプト同然であった。この悲惨を受けたエジプトについて、出エジプト記では次のように書かれている。『そこで主はモーセに仰せられた。「あなたの手を天に向けて指し伸ばせ。そうすれば、エジプト全土にわたって、人、獣、またエジプトの地のすべての野の草の上に雹が降る。」モーセが杖を天に向けて指し伸ばすと、主は雷と雹を送り、火が地に向かって走った。主はエジプトの国に雹を降らせた。雹が降り、雹のただ中を火がひらめき渡った。建国以来エジプトの国中どこにもそのようなことのなかった、きわめて激しいものであった。雹はエジプト全土にわたって、人をはじめ獣に至るまで、野にいるすべてのものを打ち、また野の草をみな打った。野の木もことごとく打ち砕いた。…パロは雨と雹と雷がやんだのを見たとき、またも罪を犯し、彼とその家臣たちは強情になった。パロの心はかたくなになり、彼はイスラエル人を行かせなかった。』(9章22~25、34~35節)我々は次の点に注意すべきである。すなわち、エジプトに対する雹の裁きは実際的な出来事であった一方、我々が今見ている箇所で書かれている不信者に対する雹の裁きは霊的な出来事であった、ということである。雹が霊的な裁きであったというのは、つまり、この箇所で言われている雹が御言葉という名の雹だったということである。このユダヤ戦争の時期に不信者たちに注がれた『雹』を実際的な雹だと考えてはいけない。歴史を見ても、ユダヤ戦争の時期に上空から雹が降って来たなどという現象は記録されていない。どの古代人の書物にも、そのようなことは何も書かれていない。だから、これは霊的な意味としての雹なのである。しかし、我々は御言葉が『雹』という表現で表示されていたとしても不思議に思うべきではない。聖書は、他にも御言葉を『火』(エレミヤ23章29節)、『金槌』(同)、『剣』(黙示録19章21節)などと多様な表現で言い表わしている。そうであれば、御言葉が『雹』として言い表わされていたとしても何も驚くべきことではない。
この雹は『1タラント』の重さだったと言われているが、これは約35kgである。これは、小さな子どもや痩せている女性ぐらいの重さである。そのような重さを持つ雹が降って来たというのは、とてつもないことである。もっとも、先に述べたように、これは実際的な雹について言われたものではない。この重さは、御言葉という雹の裁きにおけるその凄まじさが、あまりにも大きかった、ということを教えている。実際に35kgの雹が天から降って来たとすれば、人々は神に対してこう言うに違いない。「いったい何故神はこんなことをするのか。あまりにもふざけている。私たちをこんな目に遭わせるとは!何が愛の神だ。ふざけやがって。俺たちを憎んでいるではないか。」それと同じように、御言葉という名の雹により霊的な悲惨を味わわされた不信者たちも、口で『神にけがしごとを言った』り、心の中で神を冒涜したりした。「何が救いの福音だ?何がイエス・キリストだ?ふざけやがって。俺たちにはそんなものはいらねえんだ。俺たちを救おうだなんて訳の分からないことを言うな。信仰を押し付けるつもりか。あの唾棄すべきキリスト信者にするつもりか。大きなお世話だ。放っておけ。うるさい。消えうせろ。」と。確かに御言葉である聖なる福音は不信者にとっては『死から出て死に至らせる香り』だから、その福音に反発して、不信者たちが、このように叫んだとしても何も不思議なことはない。死の匂いを嗅がせられて誰が神に文句を言わないであろうか、とさえ言うことも出来るぐらいである。この『雹』が『1タラント』として描かれているのは、実に適切であった。というのも、これぐらいであれば、御言葉という雹の凄まじさが誰でも理解できるからである。これは凄まじさを教えるためには、重すぎもせず軽すぎもしない調度良い重さである。また、この『1タラント』とは、言うまでもなく一粒の重さである。これは2粒以上とか全体で、ということではない。つまりヨハネは、その降って来た一粒一粒の雹がおのおの『1タラント』ぐらいだった、と言っているわけである。これは誠に恐ろしいことである。もちろん、これは実際的な現象を言ったものではないのではあるが。
この箇所で言われている出来事は、次の3つの箇所と対応している。①黙示録20:9。『彼らは、地上の広い平地に上って来て、聖徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ。すると、天から火が降って来て、彼らを焼き尽くした。』―ここで『火』と言われているのは御言葉を指すから、イコール『雹』でもある。②黙示録11:18。『諸国の民は怒りました。しかし、あなたの御怒りの日が来ました。…地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時です。』③エゼキエル38:22。『わたしは疫病と流血で彼に罰を下し、彼と、彼の部隊と、彼の率いる多くの国々の民の上に、豪雨や雹や火や硫黄を降り注がせる。』これら3つの箇所では、どれもユダヤ戦争の際にローマ人をはじめとした不信仰な異邦人たちが、御言葉という霊的な災害に、霊的な意味で苦しめられたということを教えている。
さて、ここまで見てきた7つ目の鉢は、3つの項目に区分することが出来る。一つ目は16:17~18で書かれており、「再臨とサタンの封印」である。これは紀元68年6月9日に起こった。二つ目は16:19~20で書かれており、「ユダヤと異邦人たちに対する裁き」および「その後で起こる世界の刷新」である。これは紀元70年9月に成就し終えられた。三つ目は16:21で書かれており、「異邦人に対する御言葉の裁き」である。これも2つ目と同じで紀元70年9月に成就し終えられた。ヨハネは19節目と21節目で『また』と言っているから、この言葉がある部分で区切りが付けられたと認識するのは適切である。何故なら『また』とは、いくらか違った話に進む際に使われる言葉なのだから。つまり、7つ目の鉢とは、再臨から紀元70年9月までの時期に起きた出来事を全体的に記した預言である。この箇所を、このように3つに区分すると、その書かれている内容が掴みやすくなる。しかし3つに区分しないと、この箇所で書かれていることについて、明瞭な認識を得ることは難しくなる。
例のごとく、この鉢における7つの預言も、最後に復習のために纏めてみたい。この鉢の預言の内容における期間は、紀元61年6月~紀元70年9月であった。また、巻き物とラッパと同じく、この鉢の預言も、やはり4・3という方式で預言が書かれていた。というわけで、7つの鉢による預言の内容は、以下の通りである。
(Ⅰ:時間経過とは無関係な記述)
【第一の鉢】 ユダヤにおける心の硬化(16:2)/対応箇所…8:7、出エジプト記9:8~12
【第二の鉢】 ユダヤにおける心の硬化(16:3)/対応箇所…8:8~9、出エジプト記7:14~23
【第三の鉢】 ユダヤ人の死滅と離散(16:4~7)/対応箇所…8:10~11
【第四の鉢】 ユダヤの大炎上(16:8~9)/対応箇所…8:12、創世記19:23~28
(Ⅱ:時間経過に則った記述)
【第五の鉢】 異邦人における心の硬化(16:10~11)/対応箇所…11:3~6<紀元61年6月~紀元64年12月>
【第六の鉢】 ユダヤ鎮圧の命令(16:12~16)/対応箇所…19:19~21
【第七の鉢】 サタンの封印・ユダヤの滅亡・異邦人への霊的な裁き(16:17~21)/対応箇所…19:11~20:11<紀元68年6月9日~紀元70年9月>
■期間:紀元61年6月~紀元70年9月
さて、これで巻き物もラッパも鉢も全て詳しく説明し終えられた。これら3つの預言で言われていた内容を、聖徒たちは、それぞれ相互に比較してみるがよい。そうすれば、この3つの預言が順序通りに繋がっているなどとは、とてもじゃないが思えなくなるであろう。この3つの預言には時間的な繋がりが何も無かった、という理解を得るのは、黙示録を解読するためには非常に重要である。
なお、巻き物とラッパと鉢の預言が、それぞれ「7つ」から成り立っているのは、再臨の時期に起こる出来事が非常に多いことを示しているのだと思われる。「7」とは聖書では、豊かであることを意味する数字だからである。しかし、もちろん、それは実際に起こる出来事の数を言い表したものではない。再臨の時期に起こる出来事が7つ以上あるのは明々白々である。再臨、第一の復活、第二の復活、携挙、ローマ軍の包囲、空中の大審判、ネロの大迫害―これだけで既に7つを数えている。しかし、これ以外にも再臨の時期に起こる出来事は多く存在している。また、巻き物もラッパも鉢も預言の内容が7つであるのは、再臨の時期に起こる出来事が多いことを強調しているのだと思われる。何故なら、7つの預言から成り立つ独立した預言が、黙示録では巻き物→ラッパ→鉢というように3回も繰り返されているからである。「3回」とは既に述べたように聖書では強調の意味を持っている。実際、確かに再臨の時期に起こる出来事は、非常に多かった。
第20章 ⑰17章:開示されるイスラエルとローマ皇帝ネロの秘儀
この章は、既に註解で語られた内容が、これでもかと言わんばかりに書かれている。この17章をざっと眺めて見れば、それはすぐにも分かる。私は、既にこの17章と関連している内容を、多く書いてしまった。それだから、この17章の註解の際には、既に語られたことと重複してしまう内容が多く書かれるだろうことを、読者は承知していただきたい。これは繰り返しの多い文書である黙示録の性質上、仕方がないと言わねばならない。私も、黙示録を読んで、こんなにも繰り返しが多いことに気付かされ、いくらか驚いている。しかし、だからといってこの文書を非難していいということにはならないのは言うまでもない。私は、この章では、なるべく簡潔に註解を記すように心がけたいと思う。それは、あまりにも重複部分が多くなったために、読者の心が不快にならないためである。神が、この章の註解において私に良き書き方を与えて下さることを願うものである。アーメン。
この章は、これまでの内容を理解できたのであれば、それほど難しい箇所ではない。この章の難しさをを5段階で表わせば「2」ではないかと私には感じられる。あの12章の難解さが「スパルタ」だとすれば、この17章は「南国の保養地」である。それゆえ、私もそれほど骨折らずにこの章を註解することができる。
【17:1】
『また、7つの鉢を持つ7人の御使いのひとりが来て、私に話して、こう言った。』
ユダヤとローマ皇帝ネロの秘儀をヨハネに教えようとして、『7つの鉢を持つ7人の御使いのひとり』がヨハネの前に現われた。この御使いが現われたのは、最後の鉢である7つ目の鉢による預言の幻が完全に示し終えられてからのことである。さて、ここで疑問が起こる。それは、この『7つの鉢を持つ7人の御使いのひとり』とは何番目の鉢を持っていた御使いなのか、という疑問である。ヨハネのように信仰深い聖徒であれば、これが何番目の御使いだったのか、非常に気になるのではないかと思う。私は言うが、これは「7番目の鉢を持つ御使い」であった。何故なら、17章で現われた御使いが示したのは、ユダヤの破滅とローマについての秘儀だったからである。このユダヤの破滅とローマについて示された鉢を担当していた御使いは、何番目の御使いだったか。それは再臨後の出来事を示した7番目の鉢を持つ御使いである。それ以外の御使いは、ユダヤかローマか、どちらか一つの存在についての幻しか示していなかった。すなわち第1から第4までの御使いは「ユダヤ」について、第5と第6の御使いは「ローマ」について、示していた。この2つをどちらも示した御使いは7番目の御使いだけであった。よって、17章で再び現われた御使いは、この2つの存在について示しているから、7番目の御使いだったことになる。この7番目の御使いが、この17章でユダヤとローマについて示したのは、彼こそがこの2つの存在について示すのが相応しかったからである。ユダヤとローマに関する預言の鉢を渡されたのは彼しかいなかったのだから、他の鉢を渡された御使いが、この2つの存在について示すのは相応しくなかった。世の中には「適任」というのがあるものである。これは御使いたちの世界でも同じことが言えるのだ。また、この章ではユダヤの裁きについて示されているが、それは7番目の御使いが持っていた7つ目の鉢と大きな関連がある。先に見たように7つ目の鉢では、ユダヤに対する裁きが預言されていた。つまり、17章で示されているユダヤの裁きは、先に示されていた7つ目の鉢による預言を更に詳しく説明しているということである。
この第7の御使いは、まずユダヤに関する秘儀をヨハネに教えようとして、ヨハネに『話して、こう言った。』。すなわち次の通りである。
『「ここに来なさい。大水の上にすわっている大淫婦へのさばきを見せましょう。』
まず御使いは『ここに来なさい。』とヨハネに言った。『ここ』とは、すなわち2節後に書かれている『荒野』である。何故なら、このように言われてからヨハネは『荒野』に連れて行かれたからである。つまり、これは「私が導こうとしている荒野の場所に一緒に来なさい。」という意味である。ここで御使い自身の所にヨハネが来るようにと言われたなどと思うべきではない。御使いがいる所にヨハネが行ったところで、何も意味はないからである。
『大水』とは、17:15で書かれているように『もろもろの民族、群集、国民、国語』である。これについては、12章の箇所で詳しく説明された。『大淫婦』とは、ユダヤを指す。これも説明済みである。この2つの言葉については、既に十分なだけ説明されているから、ここで再び説明をする必要はないだろう。
ここで御使いは、『大淫婦』であるユダヤが『大水』である諸国の『上にすわっている』と言っている。ここで次のような疑問をもたれる方がいるかもしれない。「ユダヤが諸国の上に位置しているとは一体どういうわけなのか。これは何を言っているのか。」確かに当時のユダヤは諸国の上に位置しているどころか、ローマの属国として奴隷的な地位にいたぐらいだから、ユダヤこそがローマを含めた全世界の上に位置していると言われているのを聞いて不思議に思う人がいたとしても不思議ではない。しかし、ここでは霊的なことが言われていることに注意せねばならない。霊的に理解すれば、確かに旧約時代においてユダヤは諸国の上に座っていたと言える。何故なら、ユダヤには神がおられたからである。神とは、諸国どころか万物を統べ治めておられる全ての上に立つ至高の王である。そのような神をユダヤは持っていたのであり、それ以外の国々はそうではなかった。つまり、ユダヤが全被造物の王であられる神に統御される国だったからこそ、ユダヤは神を持たない諸々の国家の上に立つ存在だったと、ここでは言われている。確かに霊的に言えば正にこの通りである。神がそこにおられるゆえ、それ以外の全ての存在の上に座っていると言われて、何か問題があるのであろうか。もちろん問題は全くない。このような理解は、実に霊的であって、ユダヤ人にとっては特に理解しがたいものではない。タルムードの中で次のように言われているのを見てほしい。「神殿はイスラエル全地より高い、そしてイスラエルの地は、(世界の)全地より高い」(『タルムード ナシームの巻』キドゥシーン 第4章 69a ミシュナ2/ゲマラ p260:三貴)。この文章では、人間的な見地からではなく霊的な見地から事柄が理解されている。すなわち、ラビたちにとっては、神のおられる神殿こそが世界で一番高い場所に位置しており、その神殿のあるイスラエルが国々の中で一番高い場所に位置しているのだ。ヨハネもユダヤ人であったから、そのような霊的見地から、ユダヤの位階について語ったわけである。それだから、ここでユダヤが諸国の上に座っていると言われているのを読んで、何かいぶかしく思うべきではない。しかしながら、今のユダヤは、もはやそのようなことはなくなっている。何故なら、ユダヤは紀元70年において、神の民としての地位から斥けられたからである。彼らには最早、かつてのような栄光の地位は何もない。今のユダヤは、その他の諸々の民族と同列の地位に引き下げられている。すなわち、今のユダヤは中国人やインド人やイギリス人やガーナ人などといった民族と、霊的な意味においては、まったく変わることがない。彼らは、もう神の前において異邦人なのである。それどころか、彼らはサタンに取り憑かれた者たちとさえ言える。というのも、彼らは世界中で陰謀を働き、邪悪な罪を犯して悔いることもしていないからである。もっとも、哀れな彼らはこの事実を知らず、その無知のゆえに未だに自分たちこそが選ばれた至高の民だなどと思い違いをしているのではあるが…。今の時代において、かつてのユダヤのように全世界の上に座っているのはキリスト者である。何故なら、神はキリスト者のうちにこそおられるからである。神は紀元1世紀において、ユダヤからキリスト者へと、御自身の住まいである地上の幕屋を移されたのだ。肉的な多くの人はキリスト者こそが諸国の上に座っていると聞いても、そうだとは思わないであろう。しかし霊的に言えば、確かにキリスト者こそが、全ての上に立っている存在なのである。だからこそ、我々キリスト者は『王』(Ⅰペテロ2:9、黙示録1:6)だと言われているのであり、また王であるがゆえに『すべては、あなたがたのものです。』(Ⅰコリント3章21節)と言われているのだ。神がキリスト者と共におられるからこそ、キリスト者は神において全ての存在の上に座る王であると言われて、何か問題があるのであろうか。もちろん問題は全くない。この事実に気付いていないキリスト者が多いのは実に残念である!なお、ここで言われている『大淫婦』という言葉をローマであると捉えている人が世の中には多いから、そのような誤謬に巻き込まれてしまわないよう注意せねばならない。これをローマと捉える人たちの多くは、これがユダヤについて言われているなどとは、とてもではないが考えられない。彼らは肉的な捉え方しか出来ないから、霊的な捉え方をすることが出来ないのである。だから、彼らはここでこの『大淫婦』が諸国の上に座っていると書かれているのを読んで、即座に「これはローマに違いない。何故ならローマは諸国の支配者だったから。」などと思ってしまう。これをローマだとする見解は、主に肉的な人たちが持つ見解だから、霊的な人たちが対象とされている本作品においては、詳しく反駁するに値しない見解だと私には感じられる。実に、このような肉的な見解しか持てない霊的でない人たちが真理を会得してしまわないために、黙示録はこんなにも分かりにくく書かれているのである。つまり、神は敬虔に物事を考えられないような人たちに真理が与えられるのは相応しくないと判断されたので、そのような人たちが極度の混乱に陥るようにと黙示録を凄まじいほどの難解さとされた。そのような人たちは、真理を愚弄する人たちだから、黙示録を読んでも誤る以外には導かれないような書き方で黙示録は書かれているのである。それは高級であったり高尚であったりする素晴らしいものを、貧乏であったり低俗であったりする道理の分からない人たちに汚されないようにと、どこかに隠しておくようなものである。また値の高い絵画を、小さな子どもに引き裂かれたり汚されたりしないようにと、秘密の部屋に置いておく人のようである。
ここで言われている『大淫婦へのさばき』とは、もちろん紀元70年9月にクライマックスを迎えるあの裁きのことである。
【17:2】
『地の王たちは、この女と不品行を行ない、地に住む人々も、この女の不品行のぶどう酒に酔ったのです。」』
『地の王たち』は文字通りに捉えるべきである。これはローマ世界に限られた範囲内における『王たち』ではない。つまり、インドの指導者も、中国の皇帝も、日本の天皇(スメラノミコト)も、この『王たち』の中には含まれている。また、これはネロがユダヤ鎮圧のために招集させた『王たち』(16:14)ではない。何故なら、その『王たち』は実際的には、まだ『地の王たち』ではなかったからである。
御使いは、『女』であるユダヤが、王たちと『不品行を行な』ったと言っている。『不品行』とは、霊的な不品行のことであり、つまりは神に対する反逆や不従順のことである。確かにユダヤは、世界中の王たちと共に、神に背くという不品行の罪を犯していた。神にとって、そのようなユダヤは諸国の王たちと共に不品行にふけっていたのも同然であった。何故なら、どちらも一緒になって神に背くという不品行を行なっていたからである。霊的に言えば、ユダヤと『地の王たち』は、同じ不品行を行なう者として「同類」だったわけである。だから、ここでは『地の王たちは、この女と不品行を行な』ったと言われているのである。
『地に住む人々』という言葉も、『地の王たち』という言葉と同様、文字的に捉えるべきである。すなわち『地に住む人々』とは、「地球全土に住んでいるあらゆる人々」という意味である。『地の王たち』という言葉を文字的に捉えるべきであれば、『地に住む人々』という言葉も文字的に捉えなければいけない。前者を文字的に捉えて後者を文字的には捉えない、または前者を文字的には捉えずに後者は文字的に捉える、という解釈をすることは出来ない。そのような解釈は「異常」と言わなければならないからだ。
ユダヤは、王だけでなく『地に住む人々』とも不品行にふけっていたと、ここでは言われている。確かにユダヤは、王だけでなく王以外の普通の人々とも同じようにして、神への反逆を重ね続けていた。この17:2の箇所は2つに区分できるが、後のほうの『地に住む人々も、この女の不品行のぶどう酒に酔ったのです。』という言葉は、そこで言われているのが王ではないという点を除けば先に言われていた『地の王たちは、この女と不品行を行ない』という言葉と、意味上においてほとんど異なることがない。しかし、後のほうでの箇所ではユダヤが『地に住む人々』と『不品行のぶどう酒に酔った』と言われている。つまり、ユダヤは地の人々が神に背いて喜び楽しみながら生を歩んでいるように、神への不従順に酔っていたということである。ユダヤにとって神に逆らうことは、酒に酔うことも同然の楽しみだったのである!!!これでは裁かれても文句は言えないのである。罪の酒に酔ったというのは、先のほうの箇所では書かれておらず、そこではただ『不品行を行な』ったとしか書かれていなかった。だが、もちろん『地の王たち』の場合も、やはり罪の酒に酔っていたという点では『地に住む人々』と何も変わることはない。ただ『地の王たち』について言われている箇所の場合は、『酒に酔った』などと書かれていないだけである。
御使いは、この箇所で、ユダヤが裁かれるのは彼らの霊的な不品行が原因だと聖徒たちに教えてくれている。それは文脈を考えれば誰でも分かることである。御使いはこのように言うことで、ユダヤは故無しに酷い目に遭わされたのではないことを理解させようとしている。それは、御使いが「配慮の霊」だからである。このようにしてユダヤが裁かれた原因を示さなければ、神は意味もなくユダヤを裁かれたと勘違いする聖徒が現われかねず、そのような聖徒が現われたら、神が非難されることにもなりかねない。「神は何の理由もないのにユダヤを破滅させた。一体どういうことなのか。」などと。御使いはそのような聖徒が出ないようにと、ここでユダヤが裁かれた原因を示さねばならなかった。それというのも、もしその原因を示せば、ユダヤが裁かれたことについて神を悪く思う人は出なくなるだろうからである。
【17:3】
『それから、御使いは、御霊に感じた私を荒野に連れて行った。』
『御霊に感じた』とは、「御霊が働きかけて下さった」という意味である。ヨハネは、御霊の働きかけがあったので、荒野へと移されたのである。このことは、御使いがヨハネを荒野に連れて行ったということと、何も矛盾していない。というのも、御使いは、御霊に感じたヨハネを荒野へと連れて行ったからである。つまり、御霊は、ヨハネが御使いに連れて行かれるために相応しい状態になるようにと働きかけて下さったわけである。従って、御霊に感じたからヨハネは荒野に移されたと考えるのは間違っておらず、御使いがヨハネを荒野に連れて行ったと考えても問題はない。『御霊に感じ』たというのは、他にも1:10、4:2で書かれており、また少し言い方は違うが21:10でも同じことが書かれている。特に21:10の箇所では、理解しやすい言い方となっている。これらは、どれも御霊の働きかけにより、ヨハネにこれまでとは違った内容の幻が示される場合に記されている。この『御霊に感じた』という言い方は、霊的な感覚を持たない人には解し難い言い方である。そのような者たちは、このような文章を書いたヨハネは気が狂っていたと考えるであろう。しかし、確かなところ、気が狂っているのは彼らのほうである。というのも、彼らは神の言葉で言われていることを聞いて、その文章を書くために用いられた筆記者ヨハネに対し「気が狂っている」などと言うからである。神聖な文章におけるその内容とそれを書き記した者を愚弄するとは、気が狂っていると言わなくて何と言えばよいであろうか。我々は、このような言い方を聞いて、そのような侮辱者たちに倣ったりしてはいけない。神の言葉は褒め称えられなければいけないのだから。
どうしてヨハネは『荒野』に移されたのか。ヨハネが他でもない『荒野』にこそ導かれたのは、12章で示されていた『荒野』の期間が終わってから、この17章で示されているユダヤの荒廃が起こるからであった。実際には、荒野の期間の間にユダヤの荒廃が起こるというのではない。その期間のユダヤはまだ健在な状態である。では、どうして荒野の場所で、荒野の期間が終わってから起こるユダヤ荒廃の出来事が示されたのか。それは、荒野の場所でこの出来事が示されるのが適切だったからである。この荒野の状態においては、まだユダヤの荒廃が実現されていない。17章で示されているユダヤの荒廃に関する記述は、その実現する当時の場面が描写されたというよりは、むしろ予告に過ぎないものである。だから、「荒野の期間が終わったらユダヤの荒廃が起こるのだぞ。」ということを示すべく、荒野の場所でこそユダヤに関する未来の出来事が示されたのである。だから、この荒野の場所以外の場所で、この幻が示されるのはあまり適切ではなかった。荒野の期間より後であることを示す場所に連れて行かれたとすれば少し遅かったし、荒野の期間より前であることを示す場所に連れて行かれたとすれば少し早かったことになる。
『すると私は、ひとりの女が緋色の獣に乗っているのを見た。その獣は神をけがす名で満ちており、7つの頭と10本の角を持っていた。』
ヨハネは、『女』であるユダヤが『獣』であるローマに乗っている光景を見せられた。これは霊的な現実に即した光景である。ヨハネはこの光景を見て、特に驚いていないように思われる。恐らく、霊的に優れた感性を持ったヨハネにとって、実はユダヤこそがローマの上に座っていたという現実は、それほど不思議に思うべきことではなかったのであろう。つまり、それはヨハネにとっては当たり前のようなことだったということである。もっとも、実際はヨハネに多かれ少なかれ動揺が生じていたのだが、ただそのことが何も書き記されていないだけであった、という可能性もないわけではないが。しかし、ヨハネはキリストに選ばれるぐらいの人物だったのだから、私としてはヨハネに何の驚きも生じていなかったと思いたい。何せこのような現実には、この文章を書いている私でさえ、それほど驚きを感じないのだから。私でさえ驚きをあまり感じないのに、ヨハネのほうは驚いていたというのはおかしい話である。何故なら、私よりもヨハネのほうが霊的な人だからである。私が驚かないのであれば、尚のこと、ヨハネは驚かないはずなのだ。
『獣』については、『緋色』をしていたと書かれている点を除けば、ほぼ13章における獣の記述と変わるところはない。「ほぼ」と言ったのは、13章のほうでは『その頭には神をけがす名があった。』(13:1)と書かれているのに対し、こちらのほうでは『頭』に何も言及することなしに『神をけがす名で満ちており、…』と書かれている、という記述上の些細な違いがあるからである。しかし、頭について書かれていても書かれていなくても、その言われていることはどちらも変わらない。『緋色』については13章では書かれていなかったが、獣が『緋色』だったのは、獣が実に罪深かったことを示している。何故なら、聖書で『緋色』とは罪を象徴する色だからである。神はイザヤ書の中で次のように言われた。『たとい、あなたがたの罪が緋のように赤くても、雪のように白くなる。』(1:18)律法によれば血は罪深い人間そのものだから(※)、血の色である緋色は人間における罪を象徴する色だということなのであろう。だから、もし人間の血が青色だったとすれば、聖書では青色が罪を象徴する色として書かれていたはずである。
(※)
『ただ、血は絶対に食べてはならない。血はいのちだからである。』(申命記12章23節)『なぜなら、肉のいのちは血の中にあるからである。』(レビ17章11節)『すべての肉のいのちは、その血が、そのいのちそのものである。』(レビ17章14節)
[本文に戻る]
【17:4】
『この女は紫と緋の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべきものや自分の不品行の汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っていた。』
ヨハネの見たユダヤは『紫と緋の衣を着てい』た。ユダヤが『緋』の衣を着ていたのは、その罪深さを示している。ユダヤは罪深いままの状態で歩み続け、御子を受け入れて神の御前に清められようとしなかった。だからこそ、ここでユダヤは『緋』の衣を着ているのである。もし御子によりユダヤが神に清められていたのであれば、ここでユダヤは「白」の衣を着ていたであろう。何故なら、聖書で「白」とは清められた状態を象徴する色だからである。神は聖書の中で、こう言っておられる。『たとい、あなたがたの罪が緋のように赤くても、雪のように白くなる。』(イザヤ1章18節)『ヒソプをもって私の罪を除いてきよめてください。そうすれば、私はきよくなりましょう。私を洗ってください。そうすれば、私は雪よりも白くなりましょう。』(詩篇51篇7節)またユダヤが『紫』の衣を着ていたのは、ユダヤの持つその高慢さを示している。聖書で「紫」の衣とか布などと書かれていたら、それは多くの箇所の場合、商人に関連していることを示している。ユダヤについて説明されている18章の箇所でも、ユダヤの商品として『紫布』(18:12)が挙げられている。あのルデヤも『紫布の商人』(使徒行伝16章14節)であった。商人という者たちは、その稼いだ多くの金のために、心を高ぶらせるものである。ソロモンも、『富む者は自分を知恵のある者と思い込む。』(箴言28章11節)と言っている。ユダヤも、神に選ばれて養われていたという霊的な富を多く持っていたがゆえに、この世の商人と同様に高ぶっていた。世の商人は、多くの金を持っているので言うであろう。「私ほどに知恵ある者はいない。こんなにも多くのお金を稼げるのだから。」などと。それと同じで、霊的な富を豊かに神から受けていたユダヤも、謙遜な精神を失い、高ぶっていたので、心の中で傲慢な思いを抱いていた。黙示録18:7ではユダヤが心の中で思っていた思いが次のように書かれている。曰く『わたしは女王の座に着いている者であり、やもめではないから、悲しみを知らない』。確かにユダヤは、自分たちこそが選民だと思っていい気になり、他の民族を見下して傲慢な者となっていた。だからこそ、ここでは高慢である商人を示す『紫』の衣をユダヤが着ていていたと言われているのだ。今説明されたこの2つの色をした衣は、もちろん象徴的に捉えられねばならないものである。これを実際的に捉えるのはナンセンスである。
またユダヤは『金と宝石と真珠とで身を飾り』立てていたが、これも先に見た衣と同じで、ユダヤの傲慢さを表示している。この世で富んでいる婦人が『金と宝石と真珠』を身につけて、多くの人たちを見下していたとしても、憤りを持つ人は多いだろうが、それほど驚くに値することだとは感じられないはずである。それというのも、そのような婦人は別に珍しくも何ともないからである。そのような高ぶった婦人と同じように、霊的な富を多く持っていたユダヤ婦人も、その富のゆえに諸国の民を見下して高慢な微笑をその口に浮かべていたのである。「ふふ、私こそが神に選ばれているんだわ。他の民族は違う。霊的な富をこんなにも持っている私のような民族が他にどこにいるっていうの?他の民族なんてどうでもいい。アイツらは皆クズ民族なんだから。」実際、こんなふうにユダヤ女は心で思っていた。この高価な金や宝石なども、先に
見た衣の場合と同様に象徴的な表現であることを弁えなければいけない。何故なら、実際的なことを言えば、ユダヤはあまり富んでいなかったからである。
またユダヤの手には『憎むべきものや自分の不品行の汚れでいっぱいになった金の杯』が握られていた。これは、ユダヤが汚れや霊的不品行という罪の酒を飲んで、大いに喜び楽しんでいたことを示している。ユダヤにとって罪を犯すことは、あたかも酒を飲んで酔い心地になるようなものであった。この時のユダヤのような悪者たちにとって、確かに罪を犯すことは酒を飲むことも同然である。何故なら、罪とは神に従わないことであって、それは自分が『神のようにな』(創世記3章5節)ることだからである。自分が神のようになって自分の人生を好きなように動かすのだから、酒を飲むかのように罪が気持ちいいのは、ユダヤのような堕落した人間どもにとっては理の当然であると言えるかもしれない。またこの罪の酒が『金の杯』に入っていたのは、ユダヤが金の杯でぶどう酒を飲んでいたあのベルシャツァル王のように傲慢になっていたことを示す(ダニエル5:1~4)。確かに、その傲慢性においてユダヤという女王は、ベルシャツァル王にそっくりであった。このベルシャツァルは金の杯で罪深いぶどう酒を飲んでから、間もなく神により殺されてしまった(ダニエル5:30)。それと同じように女王ユダヤも、金の杯で罪深い酒を飲んでいたら、間もなくローマ軍が襲い掛かってきて滅ぼされることになってしまった。ヨハネが、この箇所でベルシャツァル王になぞらえつつユダヤを描いているのは間違いない。彼の頭の中には、この箇所を書いている時、ダニエル書の記述が思い浮かべられていたに違いないと私は思う。
ヨハネは、この箇所で、このようにユダヤの3つの状態を描くことにより、この時のユダヤがどれだけ神の御前に傲慢になっていたかを聖徒たちに示そうとしている。こんなにも酷い状態になっていたというのが、紀元1世紀におけるユダヤの現実であった。だからこそユダヤには恐るべき破滅の裁きが下されることになったのである。
【17:5】
『その額には、意味の秘められた名が書かれていた。すなわち、「すべての淫婦と地の憎むべきものとの母、大バビロン。」という名であった。』
ユダヤの額には、ユダヤの本質すなわち真の姿を示す名が刻まれていた。それは、『意味の秘められた名』であった。つまり、思考により探り求めなければ、何が言われているのかちょっと分からないような名であった。その名は、この箇所で記されている通りである。このような秘密の名を記された女の幻が出てくるのは、実に象徴的である。神は象徴的に事を成したり言ったりしたりされるお方だから―それは聖書を見ればいくらでも例が見つかる―、このような象徴的な幻をヨハネにお見せになったわけである。また、このような幻はユダヤ人の性質とも、よく適合していた。ユダヤ人は象徴を好む民族だからだ。
『すべての淫婦と地の憎むべきものとの母、大バビロン』というユダヤの名は、非常に霊的で特徴的である。この言葉の意味が説明されなければいけない。まず『大バビロン』とは、すなわち「大きなバビロンのような存在」ということである。これはバビロンという言葉を強調しているのであって、「本当にバビロンのような存在だ。」もしくは「バビロンを越えるバビロンだ。」というほどの意味である。次に『すべての淫婦と地の憎むべきものとの母』とは、要するにユダヤがあらゆる邪悪な者たちを遥かに上回った邪悪な存在だということである。確かに、ユダヤの堕落の度合いは、その他の異邦人たちの堕落を遥かに凌駕していたと言ってよい。特に、彼らが破滅した時代である紀元1世紀においては、考えられないほどに腐敗した状態があった。つまり、この言葉は「その邪悪さにおいて他の邪悪な者たちよりも母のように大きな存在」という意味である。何故なら、母とはその他の者つまり子どもたちよりも、大きな存在だからである。それはアヒルの母が小さな子どもを何匹も連れ歩いているのを見れば誰でも分かるであろう。この言葉は、ユダヤが母としてその他の邪悪な異邦人たちを邪悪な存在として生じさせた、と言っているのではない。何故なら、別にユダヤ以外の邪悪な民族はユダヤを見習ったりユダヤから影響を受けたというので邪悪になったというのではないし(※)、そもそもユダヤ民族がアブラハムにおいて歴史の表舞台に出てくるより以前から既にユダヤ以外の多くの民族は根本的に腐りきっていたからである。例えば、ユダヤ人の祖アブラハムはカルデヤのウルから脱出したが、このウルという偶像崇拝の町は、アブラハムが生まれるより前の時代から既に偶像崇拝に染まっていた。それだから、これを「産む」という観点から『母』だと言われていると考えると、正しく解することができない。だから、これは「大きい」という観点から『母』だと言われていると考えるべきである。そうすれば、すんなりとこの『母』という言葉を解することができるのだから。ユダヤは、こんなにも不名誉な名をつけられてしまうほどに堕落してしまったいた。当然ながら、当時のユダヤ人がこのような名を聞かされたら、大いに反発したに違いない。「アブラハムの子たちである私たちユダヤにそんな言い方をしていいのか。」などと。しかし、彼らは神の預言者たちを前々から幾人も殺し、遂に来られた約束のお方さえも拒絶したのだから、このような名をつけられたとしても文句は言えなかった。彼らはその邪悪さのゆえにこんな名で呼ばれることになったのだから、確かなところ「自業自得」だったと言わねばならない。
(※)
中にはユダヤが原因となって邪悪に染まってしまった民族もいたかもしれない。しかし、そのような民族は少数に過ぎないだろうから、ここでは考慮されるべきではない。
[本文に戻る]
【17:6】
『そして、私はこの女が、聖徒たちの血とイエスの証人たちの血に酔っているのを見た。私はこの女を見たとき、非常に驚いた。』
『聖徒たち』と『イエスの証人たち』は、どちらも神の民である同一の人たちであるが、2種類に区別して考えられるべきである。この2つの存在は、神に選ばれていた贖われし者という点では何も変わらない。しかし、その存在していた時代に応じて、2つの種類に分けられる。まず『聖徒たち』とは、「ナザレのイエス」としてはキリストを知らずに死んだ神の子らである。簡単に言えば、これは旧約時代の聖徒たちを指す。例えば、アベル、イザヤ、エレミヤがそうである。次に『イエスの証人たち』とは、「ナザレのイエス」においてキリストを信じていた神の子らである。これは新約時代の聖徒たちのことである。例えばステパノや義人ヤコブがそうである。また、ここで言われているこの2つの存在は、どちらも殉教者であることに注意せねばならない。何故なら、ここでは殉教者のことが書かれているからである。ユダヤがこの2つの存在の流した『血に酔っている』と言われていることから、それは分かる。我々は、このような小さいと思える部分であっても、詳しい解読を蔑ろにしたり諦めたりすべきではない。何故なら、たとい小さいと思える部分であっても解読しなかったのであれば、重要な理解を見落としてしまうことに繋がりかねないからである。私の経験から言えば、そのような小さい部分の解読がキッカケとなり、重要な理解への扉を開くということが黙示録では少なくない。もっとも、たった今見た部分は、それほど重要な理解をもたらす部分とは言えないのではあるが。
ユダヤは、この聖徒たちの流された血に『酔ってい』た。彼らにとって、聖徒たちを殺すのは、葡萄酒を味わうことであった。葡萄酒を飲めば誰でも酔い心地になって気持よくなるように、彼らは聖徒たちの血を流して喜んでいたわけである。このように言われたのは、誇張でも中傷でもない。実際、ユダヤは聖徒たちを殺しても平気であり、何も後悔したり悲しんだりせず、むしろ邪魔者が消え去ったので満足していた。正に葡萄酒を飲むかのごとくにして聖徒たちを死に葬っていたのである。それだから、彼らはこのように言われても何も文句を言うことが出来なかった。というのも、このように言われるのは、彼らにとって当然のことだったからである。ヨハネは、ここで正しいことを書いているだけに過ぎない。それは、殺人を犯した者が、人々から悪く思われたり言われたりしても文句を言えないのと同じである。また、この箇所を実際的な意味として捉えてはいけない。つまり、ユダヤはここで言われているように、実際的に聖徒たちの流された血を飲んで酔っていたというわけではない。そのように考えるのは肉的である。ユダヤ人は堕落していても『血を食べてはならない。』という律法を守っていたから、恐らく殉教者たちの血を飲んだユダヤ人は一人もいなかったであろう。しかし、霊的に言えば、確かに彼らは聖徒たちの流された血を飲んで大いに満悦していたとせねばならない。事は霊的にこそ捉えられなければいけないのだ。
ヨハネは、ユダヤが殉教者たちの血に酔っているのを見て『非常に驚いた』ようである。つまり、ヨハネはこの時、次のような精神状態になったのだ。「あの神に選ばれたユダヤともあろう存在が遂に神の子らを殺して喜ぶほどまでに堕落してしまったとは…」。これは別の例で例えるならば、ユダヤ教から背教したパウロが熱烈に福音を宣べ伝えているのを見たパリサイ人たちに、大きな驚きと落胆の念が生じるようなものである。人は、そこに本来あるべき姿と真逆の状態が見られると、唖然としてしまう。それは、そこに普通では考えられない状態が見られるので、精神が衝撃を受けて正常に作動しなくなるからである。
我々は、ここでヨハネがユダヤの異常な状態を見て驚いていることから、彼の霊性を読み取ることができる。ヨハネは神の恵みにより、まともな霊性を持っていたので、ユダヤが殉教者たちの血に満足しているのを見て、それがどれだけ異常な状態であるのか察することができた。だからこそ、その異常性を見て『非常に驚いた』のだ。もしヨハネがどうしようもない霊性しか持っていなければ、このようなユダヤの状態を見ても驚くことはなかったであろう。何故なら、霊性がどうしようもないので、ユダヤが異常になっているのを見てもそれが異常であると思えないか、もしくは異常であると感じられたとしても別にどうでもいいと思えてしまうからである。霊的な不感症であれば、どうして霊的な事柄に接して大いに揺り動かされるということがあろうか。言うまでもなくヨハネは霊的な不感症ではなかった。だからこそ、このようなユダヤの状態を見せられて大いに驚いてしまったわけである。ヨハネのまともな霊性は、先に見た5:4の箇所からも読み取ることができる。そこでは、巻き物を誰も解けなかったので、ヨハネが激しく泣いてしまうほどに悲しんでしまっていた。既に述べたように、霊的に正常でなければ、このような号泣はまったくあり得なかった。このように、霊的な存在や事象や状態に対する態度を見れば、その人の持つ霊性がどのようなものであるか分かるものである。
【17:7】
『すると、御使いは私にこう言った。「なぜ驚くのですか。私は、あなたに、この女の秘儀と、この女を乗せた、7つの頭と10本の角とを持つ獣の秘儀とを話してあげましょう。」』
ヨハネがユダヤの異常な状態に驚いたのは彼の敬虔性の現れだったが、御使いは、やはりヨハネよりもその敬虔性において一段上であった。ユダヤに驚いているヨハネに対して、『なぜ驚くのですか。』と言ってたしなめたのである。御使いがヨハネをたしなめたのは、ユダヤの異常な姿を見た際には、驚くよりも、むしろ神の裁きに心の思いを向かわせるべきだったからである。そうしたほうが、神の働きかけについて思いを抱けるのだから、より敬虔である。驚くのも敬虔の現れかもしれないが、それはただ驚くだけであって、神の裁きについて思いを抱くことにはならない。ここで御使いは、次のように言っているかのようである。「ヨハネよ。確かにユダヤは異常な状態になってしまったから驚くに値するかもしれないが、驚いたからといって何になるだろうか。それよりも神の裁きが、これからどのようにユダヤに注がれるのか考えてみなさい。そうしたほうが、君の霊性のためにも良いだろうから。」他にもヨハネは、19:10や22:8~9の箇所で、ヨハネの至らなさをたしなめている。ヨハネは黙示録を記述させるために選ばれたほどに霊性の高い人間だったが、このヨハネといえども、不完全な性質を持った罪深い人間の一人だったのである。
このようにヨハネをたしなめた御使いは、『この女の秘儀と、この女を乗せた、7つの頭と10本の角とを持つ獣の秘儀』とを伝授してくれると言った。御使いは、このように言おうとしているかのようである。「ヨハネよ、驚いている場合ではない。あなたの驚いているユダヤ女は、もう間もなくローマ獣を通して裁かれるのだ。そのことに関する秘儀を知りたまえ。そうして秘儀について敬虔に考えよ。そのほうが君のためになるのだから。」この『秘儀』とは、「隠されている奥儀」という意味である。こは、単に「謎」であると理解したらよい。この秘儀は、まずローマから始まり、8節目から14節目までに書かれている。15節目からはユダヤに関する秘儀が始まり、18節目まで続いている。
【17:8】
『あなたの見た獣は、昔いたが、今はいません。しかし、やがて底知れぬ所から上って来ます。そして彼は、ついには滅びます。』
この箇所の内容は、今となっては、もう説明不要であろう。私は、ここでは重複を避けるべきだと判断する。もしここで言われている内容を再び学びたいと思う聖徒がいれば、13章の当該箇所に立ち戻り、どういうことだったのか読み返したらよい。13章の箇所でも述べたが、私はこの17章に記されている内容を、既に13章の個所で先駆けて説明してしまったのだ。だから、そのことをよく留意していただきたいと思う。私は、ここで何も楽をしようとしているわけではない。ここに至るまで私が神の恵みにより詳しく註解をしてきたのを知っている読者であれば、それは十分に理解できるはずである。私は今ここで面倒臭がっているというのではなく、単に重複を避けようとしているだけなのだ。私は今、くどくどと無用な弁明をし過ぎてしまったかもしれない。しかし、ただの一人さえも誤解しないために、あえてこのような弁明を書き記しておくことにしたい。
『地上に住む者たちで、世の初めからいのちの書に名を書きしるされていない者は、その獣が、昔はいたが、今はおらず、やがて現われるのを見て驚きます。』
『世の初めからいのちの書に名を書きしるされていない者』とは、要するに異邦人の不信者を指す。例えば、ローマ人、カルタゴ人、ブリタニア人、アジヤ人、ギリシャ人がそうである。ユダヤ人やキリスト者、また異邦人で不信者だが聖書に通じている者は、この言葉の中に含まれていない。
異邦人の不信者が、『獣』であるローマのネロが現れたのを見て驚いたのは、その現れが唐突であると感じられ、まったく予想していなかったからである。人は、急に何かが起きたり、予想していなかった出来事が生じると、驚いてしまう。これは誰でも経験があるはずだ。異邦人で不信者である者たちは、聖書に通じておらず、ネロという獣が現れることについて何もあらかじめ知らなかった。だからこそ、ネロが暴君として出てきた際、彼らは驚いてしまったわけである。これは例えるならば、ルターが「95か条の提題」を携えつつ急に出現したので、カトリック陣営が大いに慌てふためいたようなものである。カトリック陣営は、まさかルターのような衝撃を引き起こす人物が現れるだろうなどとは、予想すらしていなかった。暴君としてのネロの登場に当時の人たちが驚いたのも、これと同じことである。
一方、ユダヤ人やキリスト者や異邦人で不信者だが聖書に通じていた者は、ネロの現れを見ても、まったく驚かなかったか、驚いたとしても少し驚くだけであった。というのも、彼らは聖書をよく知っており、ネブカデレザルがやがて再来することをあらかじめ預言により知っていたからである。確かに、聖書では、いずれネブカデレザルのように獰猛な獣が再び現れて聖徒たちをかき乱すであろうと、明白に預言されていた。すなわち、ダニエルは次のように預言していた。『それから私は、第4の獣について確かめたいと思った。それは、ほかのすべての獣と異なっていて、非常に恐ろしく、きばは鉄、爪は青銅であって、食らって、かみ砕いて、その残りを足で踏みつけた。その頭には10本の角があり、もう1本の角が出て来て、そのために3本の角が倒れた。その角には目があり、大きなことを語る口があった。その角はほかの角よりも大きく見えた。私が見ていると、その角は、聖徒たちに戦いをいどんで、彼らに打ち勝った。』(ダニエル7章19~21節)『そのうちの1本の角から、また1本の角が芽を出して、南と、東と、麗しい国とに向かって、非常に大きくなっていった。それは大きくなって、天の軍勢に達し、星の軍勢のうちの幾つかを地に落として、これを踏みにじり、軍勢の長にまでのし上がった。それによって、常供のささげ物は取り上げられ、その聖所の基はくつがえされる。軍勢は渡され、常供のささげ物に代えてそむきの罪がささげられた。その角は真理を地に投げ捨て、ほしいままにふるまって、それを成し遂げた。』(同8章9~12節)この預言を知っていたのであれば、あらかじめ獰猛な獣が現れることが分かっていのだから、聖書を知らない不信者たちとは違い、ネロが現れた際に大いに驚くということはなかったわけである。それは、ちょうどカエサルが自分の暗殺を予想していたので、ブルートゥスら大勢の刺客が暗殺のために襲い掛かってきた時でも(※)平静な精神を貫き通せたのと同じである。歴史の記録を見れば分かるように、カエサルは暗殺される時にも全く動揺していなかった。事前に起こることが分かりきっているのであれば、それが起きた時に驚かないのは理の当然である。
(※)
「カエサルの暗殺を共謀した者は60名を越えた。首謀者はガイウス・カッシウス、マルクス・ブルトゥス、デキムス・ブルトゥスである。」(スエトニウス『ローマ皇帝伝(上)』第1巻 カエサル p82~83:岩波文庫)
[本文に戻る]
【17:9】
『ここに知恵の心があります。』
これは、知恵による秘儀だから『知恵の心』がなければ決して理解することはできない、という意味である。確かに7つの頭と10本の角とを持つ獣は知恵により秘儀的に描かれており、神の恵みによる知恵の心がない限り、決して正しい知解を得ることはできない。神は、黙示録が『知恵の心』を持つ者だけに解されたらそれでよいと思われた。だからこそ、黙示録には知恵で隠された秘儀が、これでもかといわんばかりに出てくるのだ。『知恵の心』を与えられていない者は、黙示録で書かれている秘儀を読み解くことができないので、黙示録を読んでも何も分からず盲目の状態に留め置かれるだけである。そのような状態が嫌だと思う聖徒は、『知恵』が与えられるよう神に祈るがよい(ヤコブ1:5~6)。13:18の箇所でも、我々が今見ている箇所と似たような言葉が書かれている。すなわち、『ここに知恵がある。』という言葉である。この13章の言葉は、17:9の個所とやや言い方が異なっているが、その意味していることはどちらも変わらない。
『7つの頭とは、この女がすわっている7つの山で、7人の王たちのことです。』
既に解明された『7つの頭』である7人の首領たちは『山』であったと、ここでは言われている。『山』とは、つまり「山のように大きな存在」だという意味である。確かに、あの7人の支配者たちは『山』のように巨大であった。バビロンのネブカデレザル然り、ペルシャのキュロス然り、ギリシャのアレクサンドロス然り、ローマにおける4人の皇帝然り。誰がこれを疑うであろうか。ここで『山』と言われているのは、聖徒たちについて言われているように「揺るがない」という意味でではない。そうではなく、ここでは「大きな存在」という意味において『山』と言われている。この箇所は、この『山』という言葉の他は説明する必要がない。それ以外は既に十分なだけ説明されているからである。
【17:10~12】
『5人はすでに倒れたが、ひとりは今おり、ほかのひとりは、まだ来ていません。しかし彼が来れば、しばらくの間とどまるはずです。また、昔いたが今はいない獣について言えば、彼は8番目でもありますが、先の7人のうちのひとりです。そして彼はついには滅びます。あなたが見た10本の角は、10人の王たちで、彼らは、まだ国を受けてはいませんが、獣とともに、一時だけ王の権威を受けます。』
ここで言われている内容は、もはや説明不要であろう。私は無意味な重複を避けるべきだと判断する。この箇所の内容を再び学び直したい人は、13章の当該箇所に立ち戻ってほしい。
【17:13】
『この者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威とをその獣に与えます。』
将来の皇帝である7人の者たちが『心を一つにして』いたというのは、彼らがユダヤを嫌う思いを共通して持っていたという意味である。これは、共に仲良く集まって、一つの思いを盗賊たちのように共有していたという意味ではない。つまり、ここでは象徴的なことが言われている。実際、この7人の者たちは、他のローマ人たちと同じように反乱ばかりしているユダヤに嫌悪感を持っていただろうから、ユダヤが憎いという思いを誰しもが抱いていたはずである。
また彼らが『自分たちの力と権威とをその獣に与え』たというのは、つまり彼らが、ネロが持っていたユダヤ鎮圧という意思に賛同していたという意味である。というのも、ネロが下したユダヤ鎮圧の決定に賛同したということは、その決定を何も妨げていないということだからである。妨げていないのであれば、ネロの決定には何も支障をもたらさないのだから、事実上『力と権威とをその獣に与え』ていることも等しいのだ。キリストは『わたしたちに反対しない者は、わたしたちの味方です。』(マルコ9章40節)と言われた。この御言葉からも分かるが、反対の行動を取らなければ、それは事実上、賛同しているのも同然となるのである。この部分も、先の部分と同じで、やはり実際的に捉えるべきではない。ここでは象徴的な言い方がされていると捉えるべきである。
【17:14】
『この者どもは子羊と戦いますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。』
ネロとその王たちは、再臨されたキリストと戦うのだが、キリストに打ち負かされてしまう、とここでは言われている。これは、あくまでも霊的また象徴的に捉えなければいけない。実際的に捉え、実際上の出来事として、ここで言われていることを理解すべきではない。そもそも『王たち』という言葉からして既に霊的また象徴的なのだから、ここで言われていることを実際的に捉えるべきではないというのは明らかであろう。この『王たち』という言葉が実際的な意味であったとすれば、ここで言われていることも実際的に捉えるべきであっただろうが、『王たち』という言葉は実際的な意味として捉えるべきものではないのだ。再臨により打ち負かされたこの敵どもは、2通りの仕方で裁きを受けた。すなわち、既に述べたようにネロとティゲリヌスは殺されて地獄に投げ落とされ、それ以外の者たちは御言葉により断罪されるという裁きを受けた。
この17:14の箇所で言われている戦いは、19:11~21および6:1~2(第1の巻物)と対応している。
『なぜならば、子羊は主の主、王の王だからです。また彼とともにいる者たちは、召された者、選ばれた者、忠実な者だからです。」』
ヨハネは、ここで再臨されたキリストが敵どもに打ち勝たれたその理由について説明している。
まずキリストが敵どもに打ち勝たれたのは、キリストが『主の主、王の王』だったからであると、ここでは言われている。つまり、キリストはネロとその王たちという支配者をも支配していた存在だったからこそ、彼らを打ち負かすことができたわけである。それはネロという王の王が、属国の王を上回る権威と権力とを持っているので、その属国の王たちを好きなように取り扱えるのと同じである。また警察が、悪者に対して、その権力を行使することができるのと同じである。この世界においては、より権威と権力を持っていれば、より権威と権力を持っていない存在を、自分の意のままに打ち負かすことが可能なのである。キリストが王をも超える王、主をも超える主としての権威と権力を持っておられるというのは、聖書が明白に教えている。このことについて聖書は次のように述べている。『地上の王たちの支配者であるイエス・キリスト』(黙示録1章5節)『キリストは天に上り、御使いたち、および、もろもろの権威と権力を従えて、神の右の座におられます。』(Ⅰペテロ3章22節)『神は、その全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座に着かせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また、今の世ばかりでなく、次に来る世においてもとなえられる、すべての名の上に高く置かれました。』(エペソ1章20~21節)『イエスは近づいて来て、彼らにこう言われた。「わたしには天においても、地においても、いっさいの権威が与えられています。』(マタイ28章18節)もしキリストが『主の主、王の王』でなければ、ネロとその王たちに打ち勝つことは出来なかったはずである。その場合、キリストが地上の王たちを打ち負かすのは合法でなかったからである。強大な権威と権力を持っていないのであれば、どうして世の支配者たちを罰せられるであろうか。
キリストが再臨された際には、無数の聖徒たちもキリストと共に、天から下って来た。『彼とともにいる者たち』とは、彼らのことを指す。この者たちはエノクによれば『千万』(ユダ14節)もいた。彼らについては、既に詳しく説明されている。ここでは、この無数の聖徒たちも、再臨のキリストと共に敵どもに対して勝利を得たと教えられている。キリストの獲得された義が聖徒たちに与えられたように、キリストが得られた勝利も聖徒たちに共有されたわけである。このようにキリストは寛大にご自身の獲得されたものを、聖徒たちに分け与えて下さるお方である。だからこそ、聖徒たちもネロとその王たちに対して勝利者となったのであった。キリストがご自身のものを聖徒たちに共有させて下さるというのは、2:26~27および3:21を見てもよく分かる。ここでは、その聖徒たちが3通りの言い方で言い表されている。まず聖徒たちは『召された者』である。聖徒たちは、神の民として召され、神の国を持つ者とされた。彼らは神の戦士たちである。また聖徒たちは『選ばれた者』でもある。聖徒たちは、『世界の基の置かれる前からキリストのうちに選び』(エペソ1章4節)を受けていた。彼らは恵まれた幸いな者たちである。また聖徒たちは『忠実な者』でもあった。天からキリストと共に下って来た聖徒たちは、もはや罪を犯さず、それゆえ呪いを受けることもない。彼らは神が聖くあられるように聖く歩む者たちである(Ⅰペテロ1:16)。ヨハネは要するに、ここでこう言いたいのである。このような聖徒たちがキリストと共に天から戦いにやって来たのであれば、一体どうしてネロとその王たちが彼らに対抗することができるであろうか、と。この箇所で聖徒たちも勝利の獲得者とされているのは、注目に値する。何故ならば、再臨の際に勝利されたのはただキリストお一人だけに限定されないということが、ここでは分かるからである。
【17:15】
『御使いはまた私に言った。「あなたが見た水、すなわち淫婦がすわっている所は、もろもろの民族、群衆、国民、国語です。』
ここから御使いは、ローマがユダヤを焼き尽くすことに関する秘儀について明らかにしている(~18)。
まず、ここで御使いは、ユダヤが諸々の国民よりも上に位置していたという、霊的な現実について語っている。これについては既に十分なだけ説明されているから、これ以上の説明は不要であろう。
世界の真実を悟っている陰謀論者であれば、ここで言われているのが「今のユダヤ」だと思うかもしれない。「今」とは西暦21世紀における「今」である。何故なら、今のユダヤは世界全体をその力と権力とお金によって支配しているように感じられるからである。確かに今のユダヤについて深い理解を持っている人であれば、ここで言われているのが今のユダヤのことだと考えても、それほど不思議ではない。だが、そのように考えるのは誤っている。ここで言われている『もろもろの民族、群衆、国民、国語』の上に立っている『淫婦』がユダヤであるというのは間違っていないが、それは「昔のユダヤ」あって、「今のユダヤ」では決してない。というのも、このユダヤという女は、17:16の個所で言われているようにローマという『獣』に焼き尽くされることになるからである。この出来事は、紀元70年に起きたユダヤ陥落の出来事でなくて何であろうか。正常な理性を持っていれば、これがあの有名な悲劇のことだと分からない人は恐らくいないはずである。しかも黙示録とはヨハネが同時代の仲間たちに対して書き送った文書であり、その上そこで書かれている内容は全て『すぐに起こるはずの事』(1:1)だったのだから、ここで言われているやがて焼き尽くされることになる『淫婦』が紀元1世紀のユダヤだったというのは火を見るよりも明らかである。もしこれが21世紀のユダヤだとすれば、ヨハネは同時代の仲間たちに2000年後に起こる出来事について先駆けて語ったことになり、しかも2000年という長い期間を指して『すぐに起こるはずの事』などと言ったことになる。これが紀元1世紀のユダヤだと考えれば、すんなりと解釈が進むのに、あえて21世紀のユダヤだと理解するというのはどういうわけなのか。より合理的な解釈を退けて、より無理のある解釈を採用するというのは、明らかにおかしいと言わねばならない。まあ、ここで言われている『淫婦』が21世紀現在のユダヤだと理解したい者たちには、そのように理解させておくことにしよう。私は断言するが、その者たちが、黙示録を十全に理解することは絶対にない。彼らは私の見解を聞きながら、あえて自分たちの誤った理解に固執するのであるから、確かなところ黙示録を十全に理解できなくても「自業自得」である。読者は、私がこの註解において述べている見解を受け入れたらよい。盲目的に受け入れるのが嫌だというのであれば、まず祈り、よく考え、十分に納得してから受け入れたらよい。私は、本当に黙示録を正しく理解できるようにと、いつも神に願いを捧げているのだから。
【17:16】
『あなたが見た10本の角と、あの獣とは、その淫婦を憎み、彼女を荒廃させ、裸にし、その肉を食い、彼女を火で焼き尽くすようになります。』
ここでは、ネロとその王たちが、ユダヤを滅ぼすということについて言われている。これも、やはり紀元70年の出来事である。ここでは『獣』であるネロもユダヤを滅ぼすと言われているが、これを実際的に捉えるべきではない。というのも、実際にユダヤを滅ぼしたのはローマ軍であり、ユダヤが滅ぼされる紀元70年の時にネロは既に他界していたからである。しかしネロはユダヤ滅亡の根本的な原因となった存在だから、ここでネロがユダヤを焼き尽くしたと言われていたとしても驚くべきではない。ここではローマのユダヤに対する態度と行動が5つ書かれている。まずローマはユダヤを『憎』んでいた。これはよく知られたことである。ローマ人で反抗的なユダヤ人が嫌いな人は多かった。ネロの師であったセネカの著作を見ると、彼もユダヤを嫌っていたことが分かる。またローマはユダヤを『荒廃させ』た。これは、ローマがユダヤ戦争においてユダヤを悲惨な状態にさせたという意味である。またローマはユダヤを『裸にし』た。これはローマがユダヤに大きな恥辱を与えたという意味である。実際、ローマ軍により神殿を奪われたユダヤは丸裸にされたといってよい。またローマはユダヤの『肉を食』った。これはローマが獰猛な雄獅子のようにユダヤをその骨まで食らい尽くしたということである。またローマはユダヤを『火で焼き尽く』した。これはローマの攻撃により、ユダヤが火の海と化したということである。黙示録がドミティニアヌスの治世に記されたと考える者たちは、どれだけ思索しても、この箇所を正しく理解することができない。何故なら、もしヨハネがドミティアヌスの治世に黙示録を書いたとすれば、ここでは約30年前に起きたユダヤ戦争の出来事が記されていると理解せねばならなくなるからである。しかし、まともな聖徒であれば、ヨハネが30年も昔の出来事を、未だに起きていない出来事として預言したなどとは絶対に考えないはずである。むしろ、これはドミティアヌスの治世よりも後の時代に起こる出来事であると捉えるはずである。これでは、どうしてこの箇所を正しく理解できようか。ここではユダヤ戦争のことが言われているのだ。彼らは、私のように黙示録の御言葉からではなく、エイレナイオスの記述や教会の一般的な見解に基づいて黙示録の記述年代を算定しているから、罰として黙示録を正しく理解できなくさせられている。だが、彼らが黙示録を正しく理解できなくなっているのは、彼らが御言葉よりも人間の記述や見解に基づいて、その筆記年代を考えようとしているのが原因だから、自業自得であって文句は言えない。神は、御言葉よりも人間を基準として考える者たちに、このような解釈上の罰をお与えになるのだ。神は妬まれるお方だから、ご自身の言葉よりも人間の言葉に信頼する者たちに、たとえそれが聖徒であっても、解釈的な盲目という罰をお与えになることに抵抗を持たれない。私がこの註解で書いていることを読んでも自説に拘るというのであれば、私はその人に問いたい。果たしてエイレナイオスや教会の見解は聖徒たちの規範である聖書と同等の権威を持っているのだろうか、我々は聖書の御言葉をこそ自己の見解における基礎また土台とせねばならないのではないだろうか、と。
この箇所で『7つの頭』について触れられていないのは、注目に値する。これは『7つの頭』である存在が、ユダヤの破滅と何も関連を持っていないことを示している。何故なら、もし関連があるとすれば、ここでは『7つの頭』についても触れられていただろうからである。ここで『7つの頭』が触れられていないのは当然である。というのも、それらの存在は、既に述べたようにネロの治世においては過去の存在だからである。それらの存在がもう消え去った過去の存在であれば、ここでユダヤの破滅に加担していると教えられてはいなかったとしても何もおかしなことはない。既に消え去っているのに、どうしてユダヤの破滅に加担できるのであろうか。それだから、もしここで『7つの頭』も出ていれば、それは異常であった。他方、『10本の角』のほうは、この箇所で触れられていないほうが異常である。何故なら、この角たちは、ネロの治世において存命している者たちだからである。だから、この角のほうは、ここで触れられていて当然であった。これは些細な点かもしれないが、黙示録の理解が更に深まるためには、是非とも一度は考察しておくべき事柄である。
【17:17】
『それは、神が、みことばの成就するときまで、神のみこころを行なう思いを彼らの心に起こさせ、彼らが心を一つにして、その支配権を獣に与えるようにされたからです。』
『みことばの成就』とは、どのような御言葉について言われているのか。これは、ユダヤの破滅に関する御言葉のことである。例えば、それは次のような御言葉である。『それゆえ、人の子よ。預言してゴグに言え。神である主はこう仰せられる。わたしの民イスラエルが安心して住んでいるとき、実に、その日、あなたは奮い立つのだ。あなたは、北の果てのあなたの国から、多くの国々の民を率いて来る。彼らはみな馬に乗る者で、大集団、大軍勢だ。あなたは、わたしの民イスラエルを攻めに上り、終わりの日に、あなたは地をおおう雲のようになる。ゴグよ。わたしはあなたに、わたしの地を攻めさせる。それは、わたしがあなたを使って諸国の民の目の前にわたしの聖なることを示し、彼らがわたしを知るためだ。』(エゼキエル38章14~16節)確かに、このエゼキエル書の預言は、ローマ軍によりユダヤ戦争において成就された。これ以外のユダヤの破滅に関する預言も、このエゼキエルの預言と同じことが言える。この17:17の箇所で言われている『みことば』とは、ただユダヤの裁きに関する御言葉に限定されるということに注意しなければならない。何故なら、ここではユダヤの破滅について取り扱われているのだからである。
この箇所では、ローマがユダヤの破滅に関する思いを抱いたのは、神がその思いを『彼らの心に起こさせ』たからであると、言われている。つまり、ローマ軍によるユダヤの破滅は、究極的に言えば神から出た出来事だったということである。すなわち、まず神がユダヤの破滅を願われたがゆえに―彼らは反逆的であったがゆえに破滅に値した―、神の働きかけによりローマがユダヤの破滅を願うようになり、それから後、ユダヤが実際にローマにより破滅させられることになった。では、もし神がユダヤの破滅を願われなければ、ローマがユダヤを破滅させることはなかったのであろうか。これは正にその通りである。その場合、ローマはそもそもユダヤの破滅に関する思いを心に抱かなかったか、もし抱いたとしても実際にユダヤを破滅させるには至らなかった。何故なら、その場合、ユダヤが存続されることを神は望んでおられるからである。神の御心でなければ何事も起こらないというのは、スズメの一羽さえも神の許しなしには地に落ちないと言われたキリストの御言葉から明らかである(マタイ10:29)。それだから、ユダヤの破滅はネロとそのローマが原因であった、と理解するのは間違っていない。それは歴史の現実だからである。またユダヤの破滅が神を原因として起きた、と理解するのも誤りではない。何故なら、霊的に考えれば、それも一つの現実だからである。しかしながら、ユダヤの破滅はネロが原因であったから神が原因ではなかったとか、神が原因であったからネロが原因ではなかった、などと理解するのは間違っている。何故なら、このように理解する場合、どちらか一方の現実を否定しているからである。実際的な現実も霊的な現実も肯定する、というのが正しい理解なのである。
ここでは神がローマの破滅に関する思いを王たちの心に起こさせたと教えられているが、聖書では、神が王たちの心を自由自在にコントロールされるお方であると教えられている。それはソロモンが次のように書いた通りである。『王の心は主の手の中にあって、水の流れのようだ。みこころのままに向きを変えられる。』(箴言21章1節)これは実際に王であったソロモンの言葉だから、深く考察すべき言葉である。神が王たちの心を好きなように動かされるというのは、あのパロを見ても分かる。神は、王であるパロの心を頑なにさせ、決して開かれることがないようにと常に働きかけておられた。『主はパロの心をかたくなにされた。』(出エジプト10章27節)と何度も繰り返して書かれている通りである。ネロとその王たちの心に、ローマを破滅させる思いが与えられたというのは、この「神が王の心に働きかけておられる」という観点から捉えるべきである。ネロとその王たちは、確かに王であった。だからこそ、神は、彼らに強く働きかけ、彼らがローマを破滅させるという御心に適ったことをするようにされたのである。神の王に対するこの働きかけは、非常に重要である。王とは、絶大な権力を持つ力強い存在である。聖書は、その王でさえ、神の意のままに動かされる言わば操り人形に過ぎないと教えているのだ。なお、ソロモンが王の心は神の支配のうちにあると言ったのは、もちろん王についての言及ではあるが、これは王だけでなく一般の人々にも同様のことが言える。カルヴァンも、そのように考えていた(「キリスト教綱要」)。つまり、ソロモンは神の卓越性を示そうとして、王だけに言及したのであり、あえて人々には言及していないだけであった。というのも、王だけについて言及したほうが、より神の卓越性が示されることになるからである。
【17:18】
『あなたが見たあの女は、地上の王たちを支配する大きな都のことです。」』
ここでも繰り返し、ユダヤこそが諸国の上に位置している存在だったと教えられている。黙示録では繰り返しが多いが、このように繰り返されるのは、それが重要であるということである。だから、我々はここで言われていることを、よく心に留めるべきである。
もう一度、この17章で言われている『女』は「今のユダヤ」ではないと言っておきたいと思う。このように繰り返すのは、これが重要なことだからである。ここではユダヤが『大きな都』と言われている。この都とは、もちろんヘロデの第2神殿が建設された昔のエルサレム市を指す。このエルサレムは紀元70年に火で焼き尽くされてしまった。今のパレスチナにあるエルサレムは、この箇所で言われている『大きな都』とは言えない。というのも、黙示録の中で『大きな都』と言われているのは、明らかに紀元1世紀におけるそれだからである。だから、ここで言われている都が、21世紀におけるユダヤであると考えるのは大きな誤りである。今の聖徒たちは、この註解を読んでも、自分たちの感覚に基づいた解釈を捨てようとしないのであろうか。私は、ぜひ黙示録が書かれた当時の時代背景をよく考慮しつつ、黙示録を解釈するようにしてほしいと思う。そうすれば、黙示録を正しく解釈できるようにもなるだろうからである。ヨハネという古代の人間が書いた古い文書を、ヨハネの生きていた時代を考慮せず、自分たちの時代性や感覚に基づいて解釈しようとしても問題ないと思っているのであろうか。そのように思っている人は、道理を弁えていないと言わねばならない。
17章の註解は、以上で終わりである。黙示録の内容は繰り返しが多いので、この章の註解でも繰り返しが多くなってしまったが、必要十分なだけ語られたのではないかと思う。また何か追加すべき内容が出てくれば、その時には、神の恵みにより、この章における註解を書き直すことになるであろう。
第21章 ⑱18章:ユダヤの裁きについて言われた霊的な預言
この章は、内容的に一本調子で語られ続けている。話の流れに起伏は見られない。この18章は、黙示録の中で最も単調な箇所である。また。この章は、霊的であり象徴的であり比喩的であり隠喩的であり詩的である。ここでも、やはり普通の書き方はされていない。それゆえ、我々はこの章を、黙示録の他の章と同様に、霊的な感覚で捉えつつ読み解くようにせねばならない。また、この章は、それほど難しい箇所ではない。ここまでの註解を理解できた人であれば、もちろん人によっても個人差があるだろうが、多かれ少なかれすんなりとこの章を理解することが出来るであろう。
【18:1】
『この後、私は、もうひとりの御使いが、大きな権威を帯びて、天から下って来るのを見た。地はその栄光のために明るくなった。』
この『もうひとりの御使い』が、どのような御使いなのかは何も知らされていない。だから、この御使いについて詳しいことを述べることはできない。しかし、これは7つの鉢を持つ御使いの一人ではなかったと思われる、ということだけは言える。何故なら、もしこれが鉢の御使いだったとすれば、17:1の箇所のように『7つの鉢を持つ7人の御使いのひとりが来て、…』などと明白に書かれていただろうからである。この18:1では、そのようなことは何も書かれていないのだから、これが少なくとも鉢の御使いではなかったことは確かである。とはいっても、これがどのような御使いだったかということは、それほど重要な問題ではないのだが。
この御使いが『大きな権威を帯びて』現れたのは、神の権威によりユダヤの破滅に関する預言を語るためであった。神は、この御使いに、ユダヤについての預言をするようにとお命じになり、そのためこの御使いは天から出てくることになった。だからこそ、この御使いは、神における権威をその身に帯びていたわけである。我々は、この権威が、御使い自身から生じた権威ではないことに注意すべきである。これは、あくまでも神により持たせられた権威に過ぎないものであった。だから我々は、この御使いが『大きな権威を帯びて』いたからといって、御使い崇拝へと傾いてはならない。この御使いの権威は、自己自身から出たものではないのだから。崇拝するのであれば、この御使いではなく、この御使いに大きな権威を与えられた神を崇拝せねばならない。
この御使いが天から地に下ってきた際に、地が『その栄光のために明るくなった』のは、この御使いに与えられていた神の権威が凄まじく素晴らしかったからである。言うまでもないことかもしれないが、これは霊的に捉えられねばならない。つまり、ここでは神による権威がどれだけ輝かしいものだったかを示そうとして、比喩的にこう語られているだけに過ぎない。それだから、これを文字通りに捉えるのは間違っている。御使いが地上に来て実際的な意味で巨大な輝きを生じさせたと考えるのは、いくらか肉的である。
この御使いが天から地に下って来たのは、この御使いの預言する出来事が、天ではなく地で起こることを示す。確かに、この御使いの預言したユダヤの破滅は地上における出来事であった。それが地上において起こるからこそ、この御使いはそれを示すべく地上に降りて来たのだ。もしこの御使いが天上で起こる出来事を預言するのだとすれば、わざわざ天から離れて地上に降りて来る必要はなかった。その場合、天の場所で、その預言を語ればよいからである。その起こる場所にまでわざわざ出向いて預言がなされるというのは、黙示録では通例のことである。そのようにして預言がなされるのは、非常に象徴的である。もし黙示録にアンドロメダで起こる出来事が預言されていたとすれば、ヨハネか御使いは、アンドロメダの場所にまで移動していたことであろう。象徴的であるとは、こういうことなのだ。
なお、この箇所は間違いなくエゼキエル書43:2の箇所に基づいて書かれている。というのも、言われていることが非常によく似ているからである。エゼキエル書の方では次のように書かれている。『すると、イスラエルの神の栄光が東のほうから現われた。その音は大水のとどろきのようであって、地はその栄光で輝いた。』
【18:2】
『彼は力強い声で叫んで言った。』
例のように、『力強い声で叫んで言った』のは、その語られる言葉が非常に重要だということである。その重要な言葉とは、こうである。
『「倒れた。大バビロンが倒れた。』
これは、ユダヤが陥落させられたということである。『倒れた』とは、すなわち「倒れて滅びたかのように滅びた」という意味である。ユダヤは、あたかもバビロンでもあるかのように壊滅させられた。黙示録でユダヤがバビロンになぞらえられているのは、その堕落性においてバビロンを凌駕しているだけでなく、バビロンのように他国の兵士たちに襲われて滅亡するからでもあった。この2つの事柄は、確かにどちらも似通っているから、黙示録の中でユダヤがバビロンと呼ばれていたとしても何も不思議ではない。
ここで『倒れた』と2回繰り返されているのは強調であり、その出来事が非常に重要だからである。このような2回の繰り返しによる強調は、古代のヘブル人らしい書き方である。14:8でも、ここと同様の表現が見られる。
この箇所は、明らかにイザヤ21:9の箇所と対応している。そこでも、我々が今見ている箇所と同じように『倒れた。バビロンは倒れた。』と言われている。イザヤ書のほうは実際のバビロンについての預言であり、黙示録のほうは霊的なバビロンについての預言であるという違いがあるものの、ヨハネがこの文章を書いていた時、イザヤ書の預言を頭に思い浮かべていただろうことは間違いないと思われる。それというのも、この18:2の文章はイザヤ21:9の文章と、ほとんど一緒だからである。
『そして、悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの巣くつ、あらゆる汚れた、憎むべき鳥どもの巣くつとなった。』
ここでは『悪霊』『あらゆる汚れた霊ども』『憎むべき鳥ども』という3つの言葉が書かれているが、これらは、どれも「悪霊」である。『鳥ども』も、悪霊以外ではない。鳥が悪霊であるというのは、キリストが語られたあの種蒔きの例えからも分かる。キリストの例え話から分かるように、この悪霊どもは、人の心に蒔かれた御言葉を取って食べてしまう霊的な意味での鳥なのである。聖書において、鳥とは悪霊の象徴である。それでは、ここでその悪霊について同じ事柄が3通りの言い方で言い表されているのは何故なのか。それは強調のためである。強調をしたい際に、まったく同一の事柄を3種類または2種類の言い方により表現するのが、古代ユダヤ人のやり方であった。もっとも今のユダヤ人は、そのようなやり方はあまりしなくなっている。
この箇所では、鳥により悪霊が表示されているから、8:13および19:17~21の箇所で書かれている鳥も、やはり悪霊であることが分かる。我々が今見ている箇所に書かれている鳥が悪霊の言い換えであるのと同様、それらの箇所で書かれている鳥も悪霊の言い換えである。この<鳥=悪霊>という理解は非常に重要であるから、聖徒たちは絶対に忘れないようにせねばならない。
ここでは、ユダヤが完全に神から見放されたということが教えられている。何故なら、悪霊どもの巣窟にさせられるとは、見放されることでなくて何であろうか。つまり、神から見放されたからこそ、ユダヤが悪霊どもの住居にさせられてしまったわけである。もし見放されなかったとすれば、見放されていないのだから、ユダヤが悪霊どもの巣とされることも無かったはずである。そのようにして悪霊どもに占領させることで、神はユダヤに対する裁きを下された。これはユダヤの悪い行ないに対する罰だったから、自業自得であって、文句を言うことはできなかった。ユダヤは自分たちの悪が結んだ滅びの果実を、自らの手で刈り取らされることになったのだ。なお、この箇所の内容は、イザヤ34:9~15の箇所と対応している。そこでは鳥を含めた色々な獣がユダヤを占領するだろうと預言されているが、それは、つまり悪霊どもがユダヤを占領するということに他ならない。そこでは、イザヤがユダヤの滅びについて次のように預言している。『エドムの川はピッチに、その土は硫黄に変わり、その地は燃えるピッチになる。それは夜も昼も消えず、いつまでもその煙は立ち上る。そこは代々にわたって、廃墟となり、だれも、もうそこを通る者はない。ペリカンと針ねずみがそこをわがものとし、みみずくと烏がそこに住む。主はその上に虚空の測りなわを張り、虚無のおもりを下げられる。そのおもだった人たちのうち、王権を宣言する人が、だれもそこにはいない。すべての首長たちもいなくなる。そこの宮殿にはいばらが生え、要塞にはいらくさやあざみが生え、ジャッカルの住みか、だちょうの住む所となる。荒野の獣は山犬に会い、野やぎはその友を呼ぶ。そこにはこうもりもいこい、自分の休み場を見つける。蛇もそこに巣を作って卵を産み、それをかえして、自分の陰に集める。とびもそれぞれ自分の連れ合いとそこに集まる。』なお、鳥を含めた色々な獣が占領するという表現で示される滅びの預言は、バビロンの滅亡における預言でも同様であった。バビロン滅亡の預言でも、ユダヤの滅亡が獣どもの占領により言い表されていたのと同様、やはり次のように言われていた。『カルデヤ人の誇らかな栄えであるバビロンは、神がソドム、ゴモラを滅ぼした時のようになる。そこには永久に住む者もなく、代々にわたり、住みつく者もなく、アラビヤ人も、そこには天幕を張らず、牧者たちも、そこには群れを伏させない。そこには荒野の獣が伏し、そこの家々にはみみずくが満ち、そこにはだちょうが住み、野やぎがそこにとびはねる。山犬は、そこのとりでで、ジャッカルは、豪華な宮殿で、ほえかわす。』(イザヤ13章19~22節)これは要するに、滅ぼされて人が誰もいなくなってしまうので、そこには獣どもが集まって住むようになろう、ということである。
【18:3】
『それは、すべての国々の民が、彼女の不品行に対する激しい御怒りのぶどう酒を飲み、地上の王たちは、彼女と不品行を行ない、地上の商人たちは、彼女の極度の好色によって富を得たからである。」』
ユダヤが神の裁きを受けて悪霊どもの住まいとされたのは、ユダヤが諸国の民族と同じように反逆的な歩みをしたからであると、ここでは言われている。この箇所は3つに区分できるが、どれも同一の事柄が言われていることに変わりはない。これも、やはり同一の事柄を複数の言い方で言い表すヘブル流の強調手法である。3つの区分を一つ一つ簡潔に見ていく。まず『すべての国々の民が、彼女の不品行に対する激しい御怒りのぶどう酒を飲』んだというのは、ユダヤがその他の国々の民と同様に神の御怒りを買う反逆に歩むことを止めなかった、という意味である。次に『地上の王たちは、彼女と不品行を行な』ったというのは、ユダヤが異邦人の国の王たちと同様に神に逆らっていた、という意味である。最後の『地上の商人たちは、彼女の極度の好色によって富を得た』というのは、ユダヤが異邦人の国における傲慢な商人たちのように神の御前で傲慢な態度であった、という意味である。要するに、ここではユダヤが不敬虔な異邦人たちと一緒に纏められることで、ユダヤの不敬虔が非難されているわけである。
この箇所は、黙示録の他の多くの箇所と同様、比喩的に捉えるべきである。この箇所を文字通りに捉えたとすれば、この箇所を正しく理解することは永遠に出来ないであろう。
ここでも、やはり繰り返しがされている。既に見た14:8や16:19でも、葡萄酒との関わりにおいてユダヤのことが語られていた。このことからも分かるが、黙示録を書いたヨハネは、どうやら、よく繰り返しをする人物だったようである。それは彼の書いた福音書や手紙を見ても分かる。しかし、繰り返しが多く見られるからといって、我々はヨハネを非難してはならない。何故なら、ヨハネの文書に繰り返しが多いのは、未熟ゆえの繰り返しではなく、重要であるがゆえの繰り返しだからである。ヨハネは、重要な事柄であれば何度でも繰り返すことに抵抗をあまり持たなかった。それは重要な事柄が、何度でも繰り返して聞かされるべきだからである。だからこそ、彼の黙示録と福音書と手紙の中では繰り返しがよく見られるのだ。
【18:4】
『それから、私は、天からのもう一つの声がこう言うのを聞いた。』
この声の主は、キリストが聖霊である。何故なら、この声は『わが民よ。』と言っているからである。神でなければ、聖徒たちに、このように言うことは出来ない。また、この声は父なる神を自分ではない他の存在として語っている。父なる神が、ご自身をまるで別の存在でもあるかのように語るというのはあり得ない。だから、父なる神を自分とは別の存在として語っているこの声の主は、キリストか聖霊であるということになる。つまり、この声の主は、セラフィムでもセラフィム以外の御使いでも24人の長老でもない。もし彼らが聖徒たちを指して『わが民よ。』と言ったとすれば、それはいくらか僭越で身分に不相応だったことになるからだ。この『天からのもう一つの声』が発した言葉は、18:20まで続いている。
『「わが民よ。この女から離れなさい。その罪にあずからないため、また、その災害を受けないためです。』
『わが民』とは「キリスト者」のことである。しかも、永遠の昔からキリストにあって選ばれていた麦また羊としてのキリスト者である。ユダのような独麦また山羊としてのキリスト者は、『わが民』という言葉の中に含まれていない。何故なら、そのような者たちは、『わが民』ではなく「サタンの民」だからである。また、この『わが民』とはユダヤ人でもない。何故なら、この18章においてユダヤ人は『わが民』ではなく『女』また『都』また『大バビロン』と呼ばれているからである。彼らは、預言されていたメシアが遂に到来されたのに、そのメシアを退け、迫害し、殺してしまった。だから彼らは『わが民』と呼ばれるべきではないのだ。もし彼らが『わが民』と神から呼ばれる存在なのであれば、彼らはメシアを受け入れていただろうから。
主はここで、ご自身の聖徒たちが、ユダヤ女から離れるようにと警告しておられる。これは、ユダヤ民族と一緒に歩んではならない、彼らと親しく交わってはならない、彼らに対して疎遠になれ、という命令である。そのようにすべき理由が、ここでは2つ挙げられている。一つ目は『その罪にあずからないため』である。極悪なユダヤと仲良くすれば、彼らの行ないに影響を受け、自分も悪い行ないに伝染してしまう可能性がある。主は、聖徒たちが悪に歩むことは望んでおられなかった。だからこそ、主はここでユダヤから離れるようにと言われたのだ。二つ目は『その災害を受けないため』である。もしユダヤと一緒に歩むのであれば、彼らと一緒に、彼らが受ける刑罰を聖徒たちも受けることになりかねない。ちょうどロトがソドム人と一緒にずっといたとすれば、ソドム人と共に火で焼かれることになってしまっていたように。主は聖徒たちが、ユダヤの受ける刑罰に巻き込まれることを望んではおられなかった。むしろロトのように、邪悪な人たちから離れるのを望んでおられた。だからこそ、主はユダヤと一緒に歩んではいけないと、ここで聖徒たちに言われたのである。主がこのような警告をされたのは、聖徒たちの対する愛ゆえであった。つまり、主は聖徒たちの幸せのために、このような警告をして下さった。この警告は理由無しに出されたものではなかったのである。
悪者と共に歩めば悪者の悪と裁きとに与ることになる。これが聖書の教えである。パウロは次のように言った。『思い違いをしてはいけません。友だちが悪ければ、良い習慣が損なわれます。』(Ⅰコリント15章33節)悪い者と親しく交われば、その悪い者から悪影響を受け、『良い習慣が損なわれ』てしまうのは避けられない。パウロはまた次のようにも言っている。『あなたがたは、ほんのわずかのパン種が、粉のかたまり全体をふくらませることを知らないのですか。』(同5章6節)たとい少数であっても悪者が仲間として集団の内部にいれば、その悪者の悪が集団全体に蔓延してしまう。だからこそパウロはコリントの教会にいた悪い者を対象として、『その悪い人をあなたがたの中から除きなさい。』(同5章13節)と言ったのである。ヨハネも次のように言っている。『あなたがたのところに来る人で、この教えを持って来ない者は、家に受け入れてはいけません。その人にあいさつのことばをかけてもいけません。そういう人にあいさつすれば、その悪い行ないをともにすることになります。』(Ⅱヨハネ10~11節)これは、つまり悪しき異端者どもと関わりを持てば異端者の悪に感染してしまうから、そういう者とは一切関わってはいけない、ということである。ソロモンも、次のように警告している。『わが子よ。主と王とを恐れよ。そむく者たちと交わってはならない。たちまち彼らに災難が起こるからだ。このふたりから来る滅びをだれが知りえようか。』(箴言24章21~22節)もし邪悪な者たちから離れなければ、邪悪な者たちに『たちまち』注がれる『災難』に巻き添えを食らうことになってしまう。だからソロモンは、邪悪な者たちから離れて、彼らの受ける災難を自分も受けることにならないようにせよ、と命じたのである。もしマフィアと仲良く歩んだとすれば、悪い影響と損害を避けられないことぐらいは誰でも分かるであろう。ここで主が聖徒たちにユダヤから離れるように警告しておられるのは、悪い影響と損害をもたらすマフィアとつるまないように警告しているようなものである。
この箇所で『わが民よ。この女から離れなさい。』と警告されたのは、エレミヤ書51:45の箇所と対応しているのであろう。そこでも『わたしの民よ。その中から出よ。』と似たような言葉が語られており、しかも、その語られた状況もよく似ている。すなわち、エレミヤ書のほうでは実際のバビロンからユダヤ人が逃げ出るようにと言われており、黙示録では霊的なバビロンであるユダヤからキリスト者が離れるように言われているという違いがあるものの、どちらもバビロンと呼ばれる存在から逃げて安全な状態を享受せよと言われている点では変わらない。ヨハネはこの18:4の文章を書いている時、恐らくこのエレミヤ書の言葉をその頭に思い浮かべていたのではないかと思われる。
【18:5】
『なぜなら、彼女の罪は積み重なって天にまで届き、神は彼女の不正を覚えておられるからです。』
ユダヤがそれまで行ない続けてきた罪は天にまで達するほどの量になっていた。それほどに、彼らの罪は重ね続けられていた。また神は、ユダヤの罪を、完全に記憶しておられた。神が見過ごされたり忘れたりされた罪は一つすらもなかった。それは、ちょうどコンピューターに記憶されているデータが、何も変化されないままで記憶され続けているようなものであった。だからこそ、ユダヤは遂に神の大いなる裁きを受けることになったわけである。つまり、「時が満ちた」のだ。ソロモンは『すべての営みには時がある。』(伝道者の書3章1節)と言った。ユダヤがその罪のゆえに裁かれるのにも、やはり『時』があったのである。その時とは、既に何度も述べているように紀元70年であった。
この箇所から、神は人間の『不正を覚えておられる』お方であるということが分かる。ここで言われているのは、当然ながらユダヤだけでなく、あらゆる民族、あらゆる人間でも同様である。世の中には、自分が悪を行なっているのを知っているのに、『神は忘れている。顔を隠している。彼は決して見はしないのだ。』(詩編10篇11節)とか『どうして神が知ろうか。いと高き方に知識があろうか。』(同73篇11節)などと心の中で意識的にであれ無意識的にであれ考えている人が多い。しかし聖書は、このような考えを否定している。ヘブル書によれば、神が見ておられないものは、この世に一つさえもない。『造られたもので、神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目には、すべてが裸であり、さらけ出されています。』(ヘブル4章13節)人間の罪は神の前で明らかに知られており、しかも神はそれらの罪をことごとく記憶し続けておられる。鈍感な悪者たちは、なかなか自分の悪に対する裁きが注がれないものだから、恐れることもなく、その悪に突き進み続けることを止めようとはしない。ソロモンが次のように言った通りである。『悪い行ないに対する宣告がすぐ下されないので、人の子らの心は悪を行なう思いで満ちている。』(伝道者の書8章11節)彼らは、裁きが注がれて痛い目を見るまでは、相も変わらず悪に突き進み続けている。悪に対する裁きが注がれて悲惨を味わってから、彼らは初めて神が自分たちの悪をご覧になっておられたことを明白に感じ取るに至る。ユダヤも正にその通りであった。ユダヤは、神が裁きを留保しておられたので、神に対して恐れを抱くこともせず、悪に突き進むことを止めようとはしなかった。そうして遂に注がれた紀元70年の裁きにおいて、彼らは自分たちの悪を神が直視しておられたことに気付かされたのだ。もっとも、それに気付いた時には既に遅く、大部分のユダヤ人が殺されることになってしまったのであるが。我々は、邪悪で鈍感な不信者たちのように『神は忘れている。顔を隠している。彼は決して見はしないのだ。』などと思わないようにしよう。そのような思いを抱いたら、我々は不信者たちと何も変わらなくなってしまうのだから。
これとは逆に、神は聖徒たちの善行をも、悪の場合と同じように完全に記憶しておられる。ヘブル書では聖徒たちの善行について次のように書かれている。『神は正しい方であって、あなたがたの行ないを忘れず、あなたがたがこれまで聖徒たちに仕え、また今も仕えて神の御名のために示したあの愛をお忘れにならないのです。』(6章10節)このことから、「神は善行をお忘れになっている。」などと心で思うのは誤りであることが分かる。神は聖徒の善行を記憶しておられるので、その善行に対して必ず報いをお与えになる。神が報いられない善行は一つすらもない。たった少しの善行にさえ報いが与えられることになる。だからパウロは次のように言ったのである。『思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種を蒔けば、その刈り取りもすることになります。』(ガラテヤ6章7節)要するに、神とは記憶そのものであられるお方である。神は、聖徒たちが過去に行なった善行を、それがまるで今行なわれたかのようにまざまざと記憶しておられる。それだから、我々は善行に励むことを疎かにしないようにすべきであろう。何故なら、神はあらゆる善行を記憶しておられ、いずれその善行に対する報いを必ずお与えになられるのだから。パウロも次に示すように同じことを言っている。『善を行なうのに飽いてはいけません。失望せずにいれば、時期が来て、刈り取ることになります。』(ガラテヤ6章9節)
【18:6】
『あなたがたは、彼女が支払ったものをそのまま彼女に返し、彼女の行ないに応じて2倍にして戻しなさい。彼女が混ぜ合わせた杯の中には、彼女のために2倍の量を混ぜ合わせなさい。』
神は、ユダヤの行なった悪を、彼らの上にそのままお返しになられた。というのも、神は、誰かの悪に対して、その悪をそのままその人にお返しになられるお方だからである。オバデヤ書では、神の報いについて次のように書かれている。『あなたがしたように、あなたにもされる。あなたの報いは、あなたの頭上に返る。』(オバデヤ15節)手足の親指を切り取られたアドニ・ベゼクも、次のように言った。『私の食卓の下で、手足の親指を切り取られた70人の王たちが、パンくずを集めていたものだ。神は私がしたとおりのことを、私に報いられた。』(士師記1章7節)またユダヤは、自分たちの行なった悪しき行ないに応じて、『2倍』の裁きを受けねばならなかった。これは神の怒りの現れである。神は、ユダヤに2倍の報復をされることで、彼らに思い知らせようとされたのだ。これは、つまり「悪い性質のために、ひどい報いを受ける」(プラウトゥス『ローマ喜劇集1』バッキス姉妹 546 p315:西洋古典叢書 京都大学学術出版会 文庫)ということである。我々人間も、全てのケースでそうるすというわけではないものの、往々にして復讐の際には、大いに思い知らせようとして2倍またはそれ以上の倍数の復讐をするものである。この復讐の内容は、ユダヤ戦争を見れば分かる。それを詳しく知りたい人は、ヨセフスの「ユダヤ戦記」を一度読むべきである。
このユダヤに対する神の裁きを考えても分かるが、神は、人間の悪に対して裁きをなされるお方である。神が、人間の悪で裁かれないまま見落とされるものは一つすらもない。何故なら、神とは全知全能である正義の審判者だからである。もし神が裁かれずに見落とされる悪が何か一つでもあるとすれば、それはもはや神とは言えない。というのは、たとえ一つであっても見落とすことのある存在は、不完全な存在であるから、そんな存在が神であると認めることは出来ないからである。聖書も教えるように、神とは『完全』(マタイ5章48節)な存在である。この神の裁きについては、霊的な人であればあるほど、よく知っている。何故なら、霊的な人は神の傍近くにおり、見放された悪者どもとは違って、ほんの小さな悪をしただけでも即座に神の裁きを受けてしまうので―これは彼らが即座に矯正されることで、より大きな悪に歩まないためだ―、神の裁きに非常に敏感だからである。この神の裁きに関する聖句を、ここで列挙する必要はないであろう。この註解を読んでいる読者は、そのような聖句が既に頭の中に入っているだろうからである。
神の悪に対する裁きを回避する方法は、確かなところ、一つしかない。その方法とは「悔い改め」である。もし悔い改めをするなら、神は今までに行われ続けてきた悪を寛大に許し、その悪を完全にお忘れになって下さる。それはイザヤ書の中で、神が次のように言われている通りである。『わたし、このわたしは、わたし自身のためにあなたのそむきの罪をぬぐい去り、もうあなたの罪を思い出さない。』(43章25節)そして悔い改めた存在は、もうその悪を神から忘れてもらったので、もはや悪に対する死の裁きを受けることもなくなり、生き続けることが出来るようになる。何故なら、悪が忘れ去られたということは、つまりその悪に対して裁きがもはや下されなくなったということを意味するからである。それだからエゼキエル書で、神は次のように言われた。『しかし、悪者でも、自分の犯したすべての罪から立ち返り、わたしのすべてのおきてを守り、公義と正義を行なうなら、彼は必ず生きて、死ぬことはない。彼が犯したすべてのそむきの罪は覚えられることはなく、彼が行なった正しいことのために、彼は生きる。』(18章21~22節)確かに、神は悔い改めた者たちの悪を、それがどのような悪であっても、もう2度と追及されようとはしない。あのような悪を行なったユダさえも、もし悔い改めていたのであれば、赦されて裁きを回避することが出来た。もっとも彼は引き戻せない領域に既に入っていたので、悔い改めようにも悔い改められなかったのではあるが。ユダヤも、もし悔い改めていたとすれば、神の裁きを受けずに済んだ。神は悔い改めた者に、相も変わらず裁きを受けさせるようなお方ではないからだ。しかし、ユダヤはパロのように頑なだったので、遂に悔い改めようとはしなかった。だからこそ彼らはあのような恐るべき裁きを受けて破滅させられることになったのである。それだから、悔い改めないということは、不幸であり、忌まわしく、悲惨である。悔い改めないからこそ、神の怒りをその身に受け、破滅させられてしまうことになるからだ。しかし悔い改める者は幸いである。その者は、キリストにおいて神から赦しを得、悪を忘れてもらうことができ、もはや裁かれなくて済むようになるからである。ユダヤは悔い改めなかったので、不幸であり、忌まわしく、悲惨であった。
【18:7】
『彼女が自分を誇り、好色にふけったと同じだけの苦しみと悲しみとを、彼女に与えなさい。彼女は心の中で『私は女王の座に着いている者であり、やもめではないから、悲しみを知らない。』と言うからです。』
ユダヤは自分たちだけが神から選ばれたというので心を高ぶらせ、自分たちだけが王である神の妻としての『女王』であり、自分たちだけが他の民族とは違って『やもめではない』から幸いである、と心の中で言っていた。これは本当のことである。実際、彼らは自分たちだけが選民であることを大いに誇って汚らわしい高慢に陥り、自分たち以外の民族である異邦人を腐敗した動物でもあるかのように考えていた。これはバプテスマのヨハネが、紀元1世紀のユダヤ人に対して『『われわれの先祖はアブラハムだ。』と心の中で言うような考えではいけません。』(マタイ3章9節)と言ったことからも分かる。つまり、当時のユダヤ人は、自分たちだけが神により選別されたアブラハムの子孫であるから特別な存在なのだ、と心の中で思っていた。だからこそ主が異邦人にも神の国を満ち広げよとの伝道命令を出された際、弟子たちは大いに戸惑ってしまったわけである。汚らわしい異邦人にも神の国が広まるようにするなどというのは、自分たちだけに神の国が与えられていると考えていた当時のユダヤ人には考えられないことだったのだ。この命令には使徒たちでさえも抵抗を持たざるを得なかった。今でもユダヤ人は、そのような高ぶった思いを心の中で抱き続けている。彼らは自分たちが既に神の国から追い出されたことに気付いておらず、相も変わらず自分たちだけが神から選ばれた民族であるなどと思い違いをして、恥ずかしいとも何とも思っていない。それだから、ここで『私は女王の座に…』とユダヤが心の中で言っている思いは、誇張ではない。その言われている内容の表現が比喩的であるという点を除けば、これは正にユダヤ人が心の中で思っていた思いそのものである。このような高ぶりの思いは罪であって、それが罪であるゆえ、神と御使いと聖徒たちと全ての異邦人たちから見苦しいと感じられてしまうものである。
このようにユダヤは高ぶっていたので、神は彼女に『苦しみと悲しみとを』お与えになった。その『苦しみ』は前代未聞の苦しみであった。キリストも、その時の苦しみについて『世の初めから、今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないような、ひどい苦難』(マタイ24章21節)と言われた。また、その『悲しみ』も実に凄まじい悲しみであった。その悲しみがあまりにも大きかったので、今現在になってもユダヤ人たちは、この出来事を思い返して嘆いているほどである。もしその悲しみが大きい悲しみでなければ、2千年経過しても、まだ嘆かれ続けるということはなかったであろう。
この箇所から、ユダヤが持ったような愚かな高ぶりには、恐るべき破滅が伴うということが分かる。もしユダヤのように誇り高ぶるならば、必ず破滅と滅びの報いを受けるようになる。ソロモンが『高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。』(箴言16章18節)と言った通りである。また、高ぶる者は神に忌み嫌われ、その御前から容赦なく退けられるようになる。それはペテロが『神は高ぶる者に敵対し』(Ⅰペテロ5章5節)と言い、ヤコブも『神は、高ぶる者を退け』(ヤコブ4章6節)ると言った通りである。確かなところ、高ぶる者は破滅を愛していると言える。何故なら、高ぶりの先には破滅が待ち受けているからだ。もちろん高ぶる者が実際に心の中で破滅を愛しているというのではないが、その高ぶりという振る舞いが事実上、破滅を愛しているのも同然だと見做せるということである。神の聖徒たちが、そのようであってはいけない。それゆえ我々は高ぶりから遠ざかり、謙遜になることを求めねばならない。もし高ぶらずに謙遜になれば、その謙遜が、我々一人一人を高め上げることになるであろう。ヤコブが次のように言った通りである。『主の御前でへりくだりなさい。そうすれば、主があなたがたを高くしてくださいます。』(ヤコブ4章10節)
【18:8】
『それゆえ1日のうちに、さまざまの災害、すなわち死病、悲しみ、飢えが彼女を襲い、彼女は火で焼き尽くされます。彼女をさばく神である主は力の強い方だからです。』
ユダヤは、その高慢に対する罰として、『さまざまの災害』に襲われ、『火で焼き尽くされ』てしまうことになった。『火で焼き尽くされ』る、というのは、もはや今となっては説明する必要がない。『さまざまの災害、すなわち死病、悲しみ、飢えが彼女を襲』ったというのは、つまりユダヤが裁きを受ける際には、彼らのうち多くの者が死に、悲しみに満たされ、食料不足のため飢えてしまった、ということである。これらの出来事はユダヤ戦争で実際に起こった。
ここではユダヤの裁きが『1日のうちに』起こると言われているが、これは「すぐさま」とか「短い間に」ということを示す比喩表現である。だから、これを文字通りの『1日』として解する必要はない。実際、ユダヤの裁きは短期間の間に実現された。だから比喩的に言えば『1日のうちに』、それは起きたと言える。しかし、その実際的な時間は『1日』すなわち24時間ではなかった。だから、文字通りの意味でユダヤの裁きが『1日のうちに』起きたと言うことはできない。黙示録に比喩が多く書かれているというのは、既に何度も論じられたから、読者はそのことについてよく弁えているものと思う。であれば、この箇所で『1日』という言葉が比喩として使われていたとしても、我々は何か不思議なことが書かれているかのように驚くべきではない。
神は『力の強い方』であるから、ユダヤを大いに裁くことの出来るお方であった、とこの箇所では言われている。実際、それはユダヤ陥落の出来事を見れば分かる。ここでは次のように言われているかのようである。ユダヤよ、神が裁きをなさる力を持っておられないなどと考えて侮りの心を持ってはならない、神の力ある裁きは必ず注がれることになるのだ、ただ今は裁きが留保されているので何も裁きが目に見える形で表れていないだけなのである、と。ここから我々は一般的な教訓を見出すべきである。すなわち聖徒である我々は、何事であれ、たとえ今は神の裁きがまだ注がれていなからといって、神を見くびるようなことがあってはならない。人間は目に見える形で何かが表れないと実際的な行動に出たり、真に恐れを抱いたりは、なかなかしない傾向を持つが、信仰によって歩むべき聖徒たちは、そうであってはならないのだ。何故ならば、今はまだ裁きが下されていなかったとしても、やがて必ず神の裁きが下されることになるからである。その裁きの時が訪れてから、「ああ、ずっと前から神を恐れていたらよかったのに。」などと気付いても既に遅い。それというのも、その時には既に裁きが下されているので、もう取り返しのつかない状態になってしまっているからだ。ちょうど大犯罪を犯した悪人が、「前から気を付けて止めていればよかったものを。」などと後悔しても、何にもならないのと同じである。
【18:9】
『彼女と不品行を行ない、好色にふけった地上の王たちは、彼女が火で焼かれる煙を見ると、彼女のことで泣き、悲しみます。』
ユダヤと同じように神に逆らうという霊的な不品行を楽しんでいた『地上の王たち』は、ユダヤが破滅させられたことを知った。その時、王たちはユダヤの破滅について『泣き、悲し』んだ。何故なら、自分の不品行仲間が、大変悲惨な状態になってしまったからである。人は誰でも、自分と同じようにして悪を行なう仲間たちが不幸になった際、大いに悲嘆させられるものである。「もうユダヤと一緒に神に逆らうという不品行を行なうことが出来なくなってしまった…。何という出来事が起こったことか…。」地上の王たちは、このような精神状態になったのであった。
とはいっても、ここで地上の王たちが悲嘆にくれたと書かれているのは、霊的に捉えなければいけない。つまり、この表現を実際的な意味において捉えてはいけない。何故なら、実際には、諸国の王たちがユダヤの破滅を見て、泣いたり悲しんだりするということは無かったからだ。実際はどうだったかと言えば、地上の王たちはユダヤの陥落に大きな衝撃を受けたものの、身内が死んだ時のように打ちひしがれたということは無かった。要するに、ここで言われているのは、黙示録の特有の演出である。ここでは、ユダヤの破滅がどれだけ大きな出来事だったかということを示そうとして、このような演出により効果を出そうとしているわけである。我々も、例えばラブレターを書く時や、社会的に特別な人が他界した際に追悼メッセージを語る際には、普段ではあり得ないような演出表現を多用することで効果が出るようにするものである。その際、そこでなされる演出が非難されることは、ほとんどない。何故なら、ラブレターや追悼メッセージには、そのような演出が付き物だということを、誰もが理解しているからである。ユダヤの破滅とは、すなわち霊的な意味における特別な存在が遂に滅びるという珍しい出来事であった。だから、社会的に特別な人が他界した際に語られる演出に満ちた表現が非難されるべきでないのと同様、ユダヤという霊的に特別な存在が神から捨てられる際に語られた表現に演出が見られたとしても、非難されるべきではない。もしこの箇所に見られる演出的な表現を悪く言うのであれば、その人は、大統領や首相や偉人などといった特別な人が死んだ際に語られる演出的なメッセージをも悪く言わねばならないことになる。
【18:10】
『彼らは、彼女の苦しみを恐れたために、遠く離れて立っていて、こう言います。『わざわいが来た。わざわいが来た。大きな都よ。力強い都、バビロンよ。あなたのさばきは、一瞬のうちに来た。』』
地上の王たちは、ユダヤが破滅している光景を遠くの場所から見て、感じ入っていた。それというのも、その破滅の出来事は、大きな出来事だったからである。この王たちは、ユダヤが受けた裁きによる『苦しみを恐れた』。王たちも、ユダヤが裁かれる原因となった神への反逆という悪を、ユダヤと同様に犯していたからである。つまり、王たちは自分たちもユダヤのように神からの裁きを受けはしないかと心配になったわけである。この箇所から、キリストの再臨の時期には、ユダヤだけが実際の破滅を受けたのであり、それ以外の国々は実際的な裁きを受けなかったことが分かる。何故なら、この箇所ではユダヤの破滅を、ユダヤ以外の国における王たちが遠くから眺めているからである。実際的な破滅の刑罰を受けなかったからこそ、諸国の国の王たちは、ユダヤの破滅を外から眺めることが出来たのだ。確かに、聖書はユダヤが裁かれる際には、その他の国々もユダヤと共に裁きを受けると教えている(黙示録14:8その他)。しかし、その裁きとはユダヤが実際的な破滅の刑罰を受け、それ以外の国々は単に御言葉により断罪されるという霊的な刑罰を受けるだけ、という2種類に区分できる内容の裁きであった。
この箇所では、『わざわい』と『都』という言葉が繰り返されている。ヨハネは、ここで2つの事柄を強調したいのである。すなわち、神の裁きが下されたということ、また神の裁きが下されたのはユダヤであったということ、の2つである。ここでこの2つの事柄が強調されつつ語られているのは自然であった。何故なら、ユダヤに対する神の裁きとは、黙示録の主題の一つだからである。つまり、黙示録がユダヤの裁きについて預言されるために記された書物であるからこそ、ここではその事柄について強調されているわけである。
また、この箇所で『わざわいが来た。』と言われているのは、18:16および18:19でも全く同様の言葉が見られる。8:13では悪霊である鳥が『わざわいが来る。わざわいが、わざわいが来る。』と言っていたが、これも、やはりユダヤに裁きが下されるという予告であった。この言葉が18:10以外の箇所で複数見られるのも、やはりユダヤに災いが下されることを強調するために他ならない。
【18:11~13】
『また、地上の商人たちは彼女のことで泣き悲しみます。もはや彼らの商品を買う者がだれもいないからです。商品とは、金、銀、宝石、真珠、麻布、紫布、絹、緋布、香木、さまざまの象牙細工、高価な木や銅や鉄や大理石で造ったあらゆる種類の器具、また、肉桂、香料、香、香油、乳香、ぶどう酒、オリーブ油、麦粉、麦、牛、羊、それに馬、車、奴隷、また人のいのちです。』
王だけでなく『地上の商人たち』も、ユダヤの滅びを見て、大いに嘆いた。もっとも、これも、やはり霊的に捉えなければいけない箇所である。すなわち、ここでは地上の商人たちのように傲慢な態度を持っていたユダヤが、もはや地上の商人たちと同じようにして神に不遜な態度を取り続けることが出来なくなった、ということが言われているのだ。
この箇所では、『地上の商人たち』がユダヤ女と取り引きしていたとされる商品のリストが、列挙されている。その挙げられている商品数は30である。「30」という数字は、聖書において、量であれば「十分なだけ」、時間であれば「時が満ちた」という意味があると私は見ている。キリストが公生涯に入られたのは『およそ30歳』(ルカ3章23節)であったし、ヨセフがパロに仕えるようになったのも『30歳』(創世記41章46節)であった。これは、時間における「30」だから、「もう大きな働きを本格的に行なっても問題ないだけの時間が満ちた」と受け取っていいのではないかと思う。我々が今見ている箇所では、量において「30」と書かれているのだから、これは「こんなにも豊かにある」と受け取っていいと思われる。確かに「30」も数があれば、その数が対象としている物品によっても違いはあるだろうが、多くの場合、誰でも豊かにあると思うものである。このように商品名が多く挙げられているのは、ユダヤと傲慢な商人たちにおける類似性を強く示すためである。つまり、こんなにも多くの商品を取り引きしていたと書くことで、ユダヤがどれだけこの世の傲慢な商人たちのように反逆的になっていたか、ということを言い表そうとしている。それだから、この箇所で挙げられている商品について、実際的な理解を持つべきではない。これらの商品を、一つ一つ個別的に考察しなったとしても問題はない。むしろ、これは全体的に、そして比喩的に理解すべきものである。
ここで次のような疑問を持たれる方がいるかもしれない。すなわち、「ここではユダヤがもう地上の商人たちのような振る舞いが出来なくなると言われているとすれば、今現在のユダヤが相も変わらず商人のように傲慢な振る舞いをしているのは一体どういうわけなのか。もし紀元1世紀にこの箇所が実現されたとすれば、もうその時点で、ユダヤは商人のような振る舞いが出来なくなっていたのではないか?」という疑問である。この疑問を解決するのは容易い。確かに、この箇所で言われているように、紀元70年の裁きにおいて、ユダヤはもはや商人のように振る舞うことが出来なくなった。我々は、この箇所で言われているのが、まだ捨てられる前のユダヤについてであったという点に注意すべきである。すなわち、ここで言われているのは捨てられた後のユダヤについでではない。紀元70年に捨てられてからのユダヤは、もはや神の民ではなく、御国を持たない異邦人と化したのであって、そのような存在としてのユダヤは黙示録で取り扱われている対象ではない。黙示録で取り扱っているのは、まだ捨てられる前のユダヤであり、我々はそのような存在としてのユダヤについて考えなければいけない。それだから、今のユダヤが商人のように傲慢だったとしても、何も問題ではない。この箇所で取り扱われているユダヤは、今のユダヤとは全く別物なのだから。
この箇所を読んで、これから『人のいのち』もその他の商品と同じように売買される時代が到来すると考えている人がいる。そのような悲惨な時代が来たら遂に世界が破滅すると。このように考えている人たちは、2つの点で思い違いをしている。まず一つ目の思い違いは、この箇所が未だに成就していないと考えている点である。この箇所も、既に述べたように『すぐに起こるべき事』(1:1)だったから、ここで言われている出来事は成就済みであるとせねばならない。神が『すぐに起こる』と明言されたことを否定できるならば否定してみよ。その人は地獄に行くであろう。また、この箇所が昔の出来事だというのは、商品リストの中に『奴隷』が含まれていることからも明らかである。この『奴隷』という言葉は、まだ奴隷が一般的な存在だった古代社会を背景とした言葉であるのは間違いない。二つ目の思い違いは、ここで書かれている商品のリストを文字通りに捉えているという点である。既に述べたように、このリストは比喩的に捉えねばならないものである。以上の説明により、これから、この箇所で書かれている『人のいのち』が売買される時代はやって来ないと考えるべきである。神は、人類に『人のいのち』が売り買いされるようになるのをお許しにはならないと私は思う。実際、これまでの時代において人間の生命が一般的に売買された時代は見られない。奴隷の売買であれば珍しくも何ともないが、ここでは明らかに奴隷ではない人間の売買について語られているのであって、そのような売買がされるようになるのは考えられない。今までにそのようなことが起こらなかったというのは、神がそのような売買を嫌っておられるということであるから、これからもそのような売買が起こることはないはずである。
【18:14】
『また、あなたの心の望みである熟したくだものは、あなたから遠ざかってしまい、』
これは、ユダヤから神の恵みが容赦なく取り上げられる、ということである。何故なら、神の恵みとは、『熟したくだもの』のように『心の望』むものであるから。これは霊的な人であれば決して疑わないことであろう。確かにユダヤは紀元70年に破滅させられて後、神の諸々の恵みから遠ざけられた。比喩的に言えば、そのようにして神の恵みが取り去られたのは「『心の望みである熟したくだもの』が『遠ざかって』しまった」と言われるべきことであった。
『あらゆるはでな物、はなやかな物は消えうせて、もはや、決してそれらの物を見いだすことができません。』
これは、ユダヤを高慢で膨れ上がらせていた神の諸々の霊的な恵みが完全に取り上げられてしまう、という意味である。実際、ユダヤが破滅させられてから、かつて与えられていたような素晴らしい霊的賜物は完全に除去されてしまった。例えば、もはやユダヤ人の生活の中心であった神殿が見られなくなり、犠牲の行為も行われなくなり、祭司も消え失せ、最高法院(サンヘドリン)が終止して4つの死刑方法も途絶え(※①)、預言者が一人さえも出なくなり、定住の地を奪われ離散させられ(※②)、絶えることなく迫害を受け続けるようになり、神の御前から捨てられたので悲惨極まりない状態へと至らせられた。タルムードの中でラビ・ピネハス・ベン・ヤイルは、ユダヤ破滅後の状態についてこう言っている。「神殿が破壊されてから、律法順守仲間は恥じるようになり、自由人もそうなった。そして奇跡を行う者は弱くなり、腕力の主や、口のうまい主どもが勢いをつけた。そして聖書の解釈者もなく、その探究者もなく、神に求める者もない」。ラビ・大エリエゼルも言っている。「神殿が破壊されてから、賢人たちは子供の教師のようになり、子供の教師は集金管理人のようになり、集金管理人は一般大衆のようになり、一般大衆はますます弱くなった。そしてだれも祈り求める者もなく、探究する者もない。」(『タルムード ナシームの巻 ソーター篇』第9章49a/b ミシュナ15 p240:三貴)このような当事者たちの言葉を聞けば、本当にユダヤからは霊的な恵みが取り上げられたことが分かる。アウグスティヌスも、次のように言っている。「神殿は倒され、祭司職は廃され、彼らの犠牲と捧げ物は滅び、これらはなくなってしまった。今はユダヤ人もそのようなものを持っていない。彼らは、アロンの位階に従う祭司職が既に滅びたのを見ている。」(『アウグスティヌス著作集20/Ⅰ 詩篇註解(5)』詩篇109篇 民衆への説教 p317:教文館)それゆえ、もう彼らは「私たちには神の神殿がある。」とか「神が私たちと共におられる。」などと言うことも出来なくなってしまった。要するにユダヤは裁きにより、霊的に無一文とされたのである。更に、その地はもはやレアの子ユダに基づく「ユダヤ」という名前ではなくなり、ユダヤの敵であったペリシテ人に基づく「シリア・パレスチナ」という名前へと変えられてしまった(名前を変えたのはハドリアヌス帝)。これは、例えるならば既にノックダウンされて床に倒れているのに、更に上から激しい打撃が加えられるようなものである。であるから、ラビたちが神殿崩壊後の自分たちの悲惨な状態を嘆いているのは、理由なきことでは無かったのである。彼らは次のように嘆きつつ言っている。「ラバン・シモン・ベン・ガマリエルは、ラビ・ヨシュアの名によって言う、「神殿が破壊されてから、呪いがない日はない。そして朝露は祝福としては降りなくなり、実のおいしさは取り去られた」と。ラビ・ヨセは言う、「脂肪のある実も取り去られた」と。」(『タルムード ナシームの巻 ソーター篇』第9章48b ミシュナ12 p233:三貴)
(※①)
タルムードの中でラビが嘆いてこう言っている。「ラヴ・ヨセフは言ったからである、そして、このようにラビ・ヒヤは教えている、「聖殿の破壊日以後、最高法院が終止したとはいえ、死刑の4つの方法は終止していない」と。しかし、やっぱり終止した。」(『タルムード ナシームの巻 ソーター篇』第1章8b p33:三貴)
[本文に戻る]
(※②)
ユスティノスも言うように、ユダヤ人はユダヤ陥落の後、そこに「一切居住が許可されないことに」(『キリスト教教父著作集1 ユスティノス』『第一弁明』47:5 p63:教文館)なってしまった。彼は紀元2世紀におけるローマの元老院に対して、次のように言った。「エルサレムに誰も立ち入らせぬためあなたがたローマ人が守備しており、また侵入して逮捕されたユダヤ人には死罪を定めていることは、詳しくご承知の事実です。」(同 47:6 p64)かつて住んでいた愛すべき土地に二度と入れなくなったというのは、神からの強烈な裁きでなくて何であろうか。
[本文に戻る]
【18:15~16】
『これらの物を商って彼女から富を得ていた商人たちは、彼女の苦しみを恐れたために、遠く離れて立っていて、泣き悲しんで、言います。』
地上の商人たちは、ユダヤが裁きにより受けた『苦しみを恐れた』。何故なら、この商人たちも、ユダヤが裁かれる原因となった傲慢な態度を、ユダヤと同様に持っていたからである。「我々もその傲慢を罰せられはしないか。」などと、商人たちが心の中で思い、心配したとしても不思議ではない。これは例えるならば、あるマフィアが警察により壊滅させられたのを聞いた別のマフィアが、自分たちもやがて警察により壊滅させられるのではないかと恐れ戦くようなものである。この箇所で言われている内容は、地上の王たちについて言われていた18:9~10の箇所と、ほとんど変わらない。このように繰り返すことで、ヨハネはユダヤの滅びを聖徒たちに印象付けようとしているのである。
【18:16~17】
『『わざわいが来た。わざわいが来た。麻布、紫布、緋布を着て、金、宝石、真珠を飾りにしていた大きな都よ。あれほどの富が、一瞬のうちに荒れすたれてしまった。』』
この箇所も、やはり18:10の箇所における内容と、ほとんど変わることがない。ただ言葉を語っている主体者が、地上の王であるか、商人であるか、という違いがあるだけである。これも強調の意味があり、このように繰り返すことで、ユダヤの破滅が大いに印象深いものとして描かれるようにされたのである。ここではユダヤが『麻布、紫布、緋布を着て』いたと言われている。17:4の箇所ではユダヤが『麻布』を着ているとは書かれておらず、『紫と緋の衣を着て』いたとしか書かれていなかったが、どちらも大した違いはない。どちらの箇所でも、ユダヤが良い着物を着た傲慢な女王のように振る舞っていたということが教えられている。またユダヤが『金、宝石、真珠を飾りにしていた』と書かれているのは、17:4の箇所と全く同じ内容である。これはユダヤの傲慢さが、高価な物品を通して比喩的に示された表現である。
【18:17~19】
『また、すべての船長、すべての船客、水夫、海で働く者たちも、遠く離れて立っていて、彼女が焼かれる煙を見て、叫んで言いました。『このすばらしい都のような所がほかにあろうか。』それから、彼らは、頭にちりをかぶって、泣き悲しみ、叫んで言いました。『わざわいが来た。わざわいが来た。大きな都よ。海に舟を持つ者はみな、この都のおごりによって富を得ていたのに、それが一瞬のうちに荒れすたれるとは。』』
海にいた者たちにとっても、ユダヤの荒廃の出来事は、心揺り動かされる出来事であった。ここでは海にいる者たちさえもユダヤの裁きに感じ入っているシーンを描くことで、ユダヤの裁きがより印象深いものとして感じられるようにされているのである。このような演出表現がなされたのは、その事柄からして自然なことであった。あの特別な民族が、遂に裁かれ、滅び、神の前から捨てられることになったのだ。であれば特徴的な演出により、その出来事が印象深いものとして言い表されるのは、当然のことであろう。この箇所で言われていることは、先に見た王と商人たちの嘆きと、それほど内容的に変わるところはない。それは先の箇所を見れば一目瞭然である。王と商人たちも、この箇所における海の者たちと、ほとんど同じことを言っていた。つまり、ここで海の者たちがユダヤの破滅について嘆いているのは、例のように「繰り返し」による強調である。
『わざわいが来た。わざわいが来た。』という言葉は、18章では、これで3回目である。しかも、それぞれの箇所では『わざわいが来た。』という言葉が2回も重ねられている。このことから、聖書がこの災いについてどれだけ強調しているかが、よく分かる。聖書がこんなにもユダヤの災いを強調しているのであれば、それに応じて聖徒である我々も、この災いについて大いに心を留めなければいけないというものである。私は早速、このように強調されているのに応じて、ユダヤの災いに対する意識を前よりも強めることにした。なお、この言葉は、エゼキエル書7:5の箇所から引かれていると思われる。そこでも『わざわいが、ただわざわいが来る。』と言われている。このエゼキエル書の言葉も、黙示録の言葉と同様、ユダヤの破滅について言われたものである。
ここでは海の者たちが、都について『このすばらしい都のような所がほかにあろうか。』と言っている。これは主に都にあったエルサレム神殿のことである。この賛辞は本当のことである。既に第2部でも説明されたが、ユダヤの神殿は、文字通り万人から素晴らしい建造物であると評された美しいものであった。福音書の中でも、弟子が神殿の素晴らしさに感嘆とさせられているシーンが描かれている(マタイ24:1~2、ルカ21:5~6、マルコ13:1~2)。その尋常でない美しさのゆえに、ユダヤ鎮圧を命じられたウェスパシアヌスも、果たしてこの神殿を壊滅させてよいものかどうか悩まされたほどであった。それというのも、もしこのような神殿を滅ぼしたとなれば、他国の人々から美しいものを平気で破壊する獰猛な野獣のごとき存在として評されてしまうのではないかと心配したからである。この神殿が古代で称賛されていたというのは、歴史を学んだ者ならば、既に知っているところである。タキトゥスも神殿のあるエルサレムのことを「この世に名高い都」と言っているが(『同時代史』第5巻 1:2 p268:筑摩書房)、この場所はタキトゥスさえも感嘆とさせられる場所だったのだ。それゆえ、この箇所で言われている都への賛辞は誇張ではなく、比喩や隠喩などでもない。これは文字通りに捉えてよい賛辞である。
【18:20】
『おお、天よ、聖徒たちよ、使徒たちよ、預言者たちよ。この都のことで喜びなさい。神は、あなたがたのために、この都にさばきを宣告されたからです。』
『天』とは「天にいる贖われた殉教者たち」のことである。これは天という場所そのものを言っているのではない。『聖徒たち』というのも、天にいる殉教者たちのことである。先には不明瞭な形で聖徒のことが言われたが、今度は明瞭な形で言われている。『使徒たち』とは、殉教した使徒のことである。例えば、ネロの迫害期に殉教したとされるペテロやパウロがそうである。『預言者たち』というのも、やはり殉教した預言者である。イザヤやエレミヤが、この言葉に該当する。ここでは4つの言葉が並んでいるが、その順序に意味はないと思われる。つまり、ここでは重要な順番で4つの言葉が並べられているというのではない。ヨハネは、ここで特に順番には注意せずに書いている。このヨハネという人は、黙示録を読んでいれば分かることだが、全体部分であれ個々の箇所であれ、あまり順番には意識を払わない人であった。彼がそのような人だったというのは、カルヴァンも気付いていたことである(※①)。これはマルコとマタイでも同じことが言えるが、古代ユダヤ人は、ヨハネだけでなく順序を気にしない人が多かったようである(※②)。
(※①)
「聖ヨハネは、物語を順序よく配列することに、あまり気をつけてはいない。かれにとっては、全体を簡潔にとりまとめるだけで十分なのである。」(『新約聖書註解Ⅳ ヨハネ福音書 下』18:15 p569:新教出版社)
[本文に戻る]
(※②)
ルターも言うようにマルコとマタイは福音書を書く際、ヨハネと同じように順序を気にしていなかった。このことについてのルターの説明はこうである。「マタイとマルコが順序に従っていないことは多くの箇所からも証明されることである。たとえばマタイが4章においてキリストの誘惑をしるし、また、キリストの復活後の顕現をしるしているところでは、マタイはけっして順序を問題にしていないのである。聖アウグスティヌスはde Consensu Euangelistarum(福音書記者間の一致について)の中で、これらの問題についてかなりの労苦をしている。マルコもまた順序を固執しない。そのことは聖餐に関する個所にも現われている。彼は、「一同はその杯から飲んだ」ということばを「そして彼は弟子たちに言われた、これは私のからだである」ということばの前に置いている。しかし、このことばは自然の順序や論理のすじみちに従えば、むしろあとに置かれるべきものである。このように、疑いもなくマタイとマルコは厳密な歴史的順序を踏まず、ただルカだけがその順序を踏み(※引用者註:ルカはユダヤ人ではない)、そのようにすることを自らに義務づけているので、マタイとマルコの説明は聖ルカの順序に従って判断され、おおよそ他の仕方で判断されてはならない。」(『ルター著作集 第一集8』キリストの聖餐について p253~254:聖文舎)
[本文に戻る]
この天にいた殉教者たちが喜ぶようにと、ここでは言われている。それは何故なのか。それは、神が『この都にさばきを宣告されたから』であった。多くの聖徒たちを殺したユダヤに対して、遂に神の復讐が果たされることになったのである。だからこそ、ここでは、そのような復讐について喜ぶようにと命じられている。復讐が果たされると、人の心には喜びが生じるものである。これは復讐の体験を持つ者であれば、よく分かるのではないかと思う。損なわれた部分が一挙に元通りになったような、また空のグラスに美味しい液体が目一杯注がれたような、何とも言えない満足がそこには生じる。ごく手短に言えば「解消感がある」ということになる。それだから、復讐が果たされた際に喜びが生じるのは、ごく自然なことであると言える。神は、そのような復讐における満足を味わってもよいと、この箇所で殉教者たちに言っておられる。
しかし、ここで疑問が起こる。果たして復讐が実現された際に、聖なる者たちは喜んでもいいのであろうか。復讐が実現された場合、聖徒たちは喜ぶべきではないのではないか。すなわち、神はソロモンを通して、次のように神の民を戒められたのではなかったか。『人の災害を喜ぶ者は罰を免れない。』(箴言17章5節)『あなたの敵が倒れるとき、喜んではならない。彼がつまずくとき、あなたは心から楽しんではならない。主がそれを見て、御心を痛め、彼への怒りをやめられるといけないから。』(同24章17~18節)ユダヤに対する復讐の出来事が、聖徒たちにとって『人の災害』であり、『敵が倒れるとき』また『彼がつまずくとき』という言葉に該当するのは明白である。それだから一見すると、この18:20の箇所でユダヤの不幸を喜べと言われているのは、箴言の聖句に反しているようにも思えなくない。しかし、ここでユダヤの不幸を喜べと言われているのは、何も問題なかった。それというのも、ソロモンが禁じているのは「過度に喜ぶこと」だからである。『心から』とソロモンは言っているが、これは「思う存分に」という意味である。神は『あはは』(エゼキエル書25章3節)と言って軽蔑しつつイスラエルの悲惨を喜んだアモン人について、『あなたは手を打ち、足を踏み鳴らし、イスラエルの地を心の底からあざけって喜んだ。』(同25章6節)と断罪しておられるが、このような侮蔑的な喜びが禁じられているのである。エジプト人たちが紅海で死滅した際にモーセたちが喜びの声を挙げたことからも分かるように、一定の限度を超えないのであれば、敵が破滅した際に喜ぶことは禁止されていない。つまり、アモン人のように侮蔑的に喜ぶのではなく、単に復讐が果たされたこと自体を節度を持って自然に喜ぶのであれば問題ない。そうでなければ、あのモーセたちの喜びも非難されねばならないことになるからだ。この18:20の箇所で『喜びなさい。』と命じられたのは、当然ながら、許容された範囲内における喜びを持てということであった。だから、天にいる殉教者たちが、ある一定の限度を超えないのであれば、自分たちを殺したユダヤに与えられた復讐の悲惨について喜ぶのは悪いことではなかった。もし、私が今説明したことが正しくないというのであれば、聖書には自己矛盾した箇所が存在することになる。つまり、ソロモンが誰かの悲惨を喜ぶなと言っている一方、ヨハネの黙示録ではユダヤの悲惨を喜べと言っている、という矛盾である。もし聖書に矛盾があるとすれば、聖書は信頼に値しない書物だということになる。そうであれば、聖書が信頼に値する書物だと信じている聖徒たちは、愚かな思い違いをしていることになってしまう。しかしながら、今説明されたことから分かるように、我々が今見ている箇所と箴言の箇所において矛盾は何も存在していない。だから、我々はこれからも、聖書を完全に首尾一貫した書物として信頼し続けなければならない。
18:4の箇所から続く『天からのもう一つの声』による言葉は、この18:20の箇所で終わりである。
【18:21】
『また、ひとりの強い御使いが、大きい、ひき臼のような石を取り上げ、海に投げ入れて言った。「大きな都バビロンは、このように激しく打ち倒されて、もはやなくなって消えうせてしまう。』
この『ひとりの強い御使い』とは、黙示録では新しく登場した御使いである。この御使いの名前と位階については、何も知らされていない。しかし、たといこの御使いについて知らなかったとしても、黙示録の理解において支障が生じることはない。もし支障が生じるということであれば、ここでは彼の詳細について触れられていたであろう。この御使いは『強い』御使いであった。というのも、彼は『大きい、ひき臼のような石を取り上げ、海に投げ入れ』るからである。もし強くなければ、決してこのような行為は出来ないのである。
ユダヤは、ここで御使いが『大きい、ひき臼のような石を』『海に投げ入れ』たかのようにして、神の御前から捨てられてしまった。神だけでなくユダヤ人自身も、シオンを見捨た(ヨセフス「ユダヤ戦記」2巻/xx1:556)。ここで言われている『大きい、ひき臼のような石』とは確かにユダヤ以外ではない。まずユダヤは『石』である。これは新約時代の神の民であるクリスチャンが『石』(Ⅰペテロ2章5節)であると言われていることから分かる。すなわち、ユダヤという旧約時代における神の民は、捨てられる前においては『石』と呼ばれるべき存在であった。またユダヤは『大き』かった。紀元1世紀のユダヤ人は数百万人もいたのだから、彼らが『大きい』と言われているのは何も不思議ではない。つまり、『大きい』とはユダヤ全体を指している。確かに、ユダヤは紀元70年において、神からまるで石が海に投げ込まれるかのようにして捨てられた。彼らはそのようにしてサタンという海底の暗闇に沈められたので、もはや海面に浮上して義なる太陽であるイエス・キリストの光に与ることが出来なくなってしまったのである。この18:21の箇所で言われている内容は、恐らくキリストの御言葉に基づいていると思われる。そのキリストの言葉とは、こうである。『つまずきが起こるのは避けられない。だが、つまずきを起こさせる者は、忌まわしいものです。この小さい者たちのひとりに、つまずきを与えるようであったら、そんな者は石臼を首にゆわえつけられて、海に投げ込まれたほうがましです。』(ルカ17章1~2節)ユダヤはイエスがキリストであることを否認したので、紛れもない『反キリスト』であり、それゆえ『人を惑わす者』(Ⅱヨハネ7節)であった。『人を惑わす者』とは、言うまでもなくキリストが言われた『つまずきを起こさせる者』である。何故なら、イエスがキリストでないと言って人を惑わす者は、まだ初信の聖徒やガラテヤ人のように未熟な聖徒たちを躓かせてしまうからだ。キリストの御言葉によれば、そのような反キリストであるユダヤは、『石臼を首にゆわえつけられて、海に投げ込まれたほうがまし』である。これは18:21の箇所の内容と、よく似通っている。このように、我々が今見ている箇所とキリストの御言葉の内容は類似しているのだから、黙示録18:21とルカ17:1~2の箇所が対応していたとしても不思議ではない。この箇所で、このような幻をヨハネに対して示されたのは、他でもないキリストである。黙示録という文書は、1:1で書かれているように『イエス・キリストの黙示』である。であれば、キリストがかつてご自身で言われた言葉の内容と似通った幻を、ここでヨハネに対してお示しになった可能性はかなり高い。
この箇所で御使いが行っている行為は、非常に象徴的である。神は、このように象徴的なやり方で物事を示されるのを好まれる。それは人間のためである。我々人間は誰であれ鈍くて悟るのに遅い性質を持っているから、神はなるべく人間が事柄を分かりやすいようにするため、象徴的なやり方で何かを啓示して理解しやすいようにして下さっておられるのだ。このような象徴的である預言が書かれている箇所は、聖書の中に多く見られる。例えば、神はご自身の帯としての民であったユダヤが腐ってしまうことを預言するために、エレミヤに帯を買わせて彼の腰に締めさせ、それから後、その帯を隠させ腐るようにされた(エレミヤ13:1~11)。つまり、これは「エレミヤの着けていた帯が腐ったように神の帯であったユダヤも腐るであろう。」という預言である。これは何という象徴的な預言であろうか。また聖霊なる神は、パウロがやがて縛られて人々の手に渡されることになるのを預言される際、アガボという預言者がパウロの帯を取って自分自身の手と足とを縛るようにされた(使徒行伝21:10~11)。これも、やはり「パウロはこのようにして縛られることになるであろう。」という預言であった。これも実に象徴的である。これ以外にも、聖書で象徴的な預言は数多い。神がユダヤを特別にお選びになったのは、私の推測では、恐らくユダヤが象徴の要素を好む、もしくは象徴に馴染みやすい民族だったからではないかと思う。何故なら、象徴に抵抗しないような民族であれば、神もその民族を通して象徴的な預言をそれだけしやすくなるから。しかし、象徴に抵抗感を持つような民族であれば、それだけ神はその民族を通して象徴的な預言をしにくくなってしまう。だからこそユダヤこそがアブラハムにおいて他の民族からより分けられたのではないか、と考えるのは荒唐無稽な推測ではない。事実、神は象徴的に何かをされることを好まれるし、ユダヤも象徴的な要素を非常に好む民族なのである。
ここではユダヤが紀元70年に捨てられて後、『もはやなくなって消えうせてしまう。』と言われているが、今でもユダヤは無くなっていないし、消え失せてもいない。実際、スファラディ系のユダヤ人について言えば、今のユダヤは紀元1世紀に捨てられたユダヤ人の子孫である。だから、ここでユダヤが消えてしまうと言われていることに問題を感じる人もいるかもしれないが、これは既に解決済みの問題である。すなわち、先にも述べたように、黙示録で取り扱われているユダヤとは「捨てられて異邦人と化す前のユダヤ」についてである。捨てられて神の国から除外された後のユダヤは、黙示録では何も語られていない。だから、ここでユダヤがヨハネの時代に『消えうせてしまう』と言われていたとしても、何も解釈上の問題は生じない。『消えうせてしまう』というのは、ユダヤ民族そのもののことではなく、「主の牧場で草を食べていた契約に属していた限りでのユダヤ民族」のことだからである。
【18:22~23】
『立琴をひく者、歌を歌う者、笛を吹く者、ラッパを鳴らす者の声は、もうおまえのうちに聞かれなくなる。あらゆる技術を持った職人たちも、もうおまえのうちに見られなくなる。ひき臼の音も、もうおまえのうちに聞かれなくなる。ともしびの光は、もうおまえのうちに輝かなくなる。花婿、花嫁の声も、もうおまえのうちに聞かれなくなる。』
ここで御使いは、ユダヤが裁かれて神から捨てられて後、どのような悲惨が彼らに降りかかるか預言している。その預言は5つに分けられている。それらの預言を一つ一つ簡潔に見ていきたい。
まず、『立琴をひく者、歌を歌う者、笛を吹く者、ラッパを鳴らす者の声は、もうおまえのうちに聞かれなくなる。』のであった。これは、ユダヤが裁かれてから、喜びが全て取り上げられることを言っている。何故なら、音楽とは、喜ばしいものだからである。これは実際その通りになった。また、『あらゆる技術を持った職人たちも、もうおまえのうちに見られなくなる。』のであった。これはユダヤにいる職人たちが全て殺されるので、社会的に悲惨な状態が訪れることを意味している。これも実際その通りになった。また、『ひき臼の音も、もうおまえのうちに聞かれなくなる。』のであった。これはユダヤから日常生活の恵みが奪われる、ということである。確かにユダヤは陥落させられてから、まともな日常生活は全く出来なくなった。また、『ともしびの光は、もうお前のうちに輝かなくなる。』のであった。ユダヤは裁かれてから、暗い場所がランプにより照らされるという恵みさえ受けることが出来なくなった。実際、ユダヤは裁かれて焼け野原とされたから、もはやランプで輝かされるという光景も見られなくなった。また、『花婿、花嫁の声も、もうおまえのうちに聞かれなくなる。』のであった。これはユダヤから、あらゆる幸せが取り除かれるということである。というのも、『花婿、花嫁の声』とは幸せの象徴だからである。確かにユダヤは裁かれてから、ほんの少しの幸せさえも味わえなくなってしまった。なお、ユダヤ戦争の時にラビたちから花婿と花嫁の装飾用具着用禁止令が出されたのは(※)、注目に値する。この禁止令は、もう間もなく花婿と花嫁の声がユダヤから完全に聞かれなくなるということの前兆として捉えることができる。以上が、ユダヤが裁かれた際に下された5つの悲惨である。
(※)
タルムードにはこう書かれている。「ヴェスパスィアヌスに対する戦争の時、彼ら(※ラビ)は花婿の花輪着用と婚席太鼓の禁令を出した。ティトゥスに対する戦争の時、彼らは花嫁の花輪着用の禁令を出した。」(『タルムード ナシームの巻 ソーター篇』第9章49b ミシュナ14 p239:三貴)なお、「ニッダー篇」によれば、ラビたちはこの時「染めた衣服についても禁じようと望んだ」(『タルムード トホロートの巻 ニッダー篇』第9章61b ミシュナ5/ゲマラ p270:三貴)ということである。
[本文に戻る]
要するに、これは簡単に言えば「恵みが除去される」ということである。何故なら、ここで御使いの預言している5つの悲惨は、どれも神の恵みに関わることだからである。
この箇所で言われている内容は、ソロモンの言葉と非常に似通っている。その箇所は、伝道者の書12:1~8である。そこでソロモンは次のように言っている。『あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えよ。わざわいの日が来ないうちに、また「何の喜びもない。」と言う年月が近づく前に。太陽と光、月と星が暗くなり、雨の後にまた雨雲がおおう前に。その日には、家を守る者は震え、力のある男たちは身をかがめ、粉ひき女たちは少なくなって仕事をやめ、窓からながめている女の目は暗くなる。通りのとびらは閉ざされ、臼をひく音も低くなり、人は鳥の声に起き上がり、歌を歌う娘たちはみなうなだれる。彼らはまた高い所を恐れ、道でおびえる。アーモンドの花は咲き、いなごはのろのろ歩き、ふうちょうぼくは花を開く、だが、人は永遠の家へと歩いて行き、嘆く者たちが通りを歩き回る。こうしてついに、銀のひもは切れ、金の器は打ち砕かれ、水がめは泉のかたわらで砕かれ、滑車が井戸のそばでこわされる。ちりはもとあった地に帰り、霊はこれを下さった神に帰る。空の空。伝道者は言う。すべては空。』恐らくソロモンは、ユダヤの終わりについて預言したのではないか。このユダヤにもやがて終わりが訪れるのだから、それを思って、人間の人生にも終わりが訪れることを知れ、と。ソロモンは、明らかにある世界の終焉について、この言葉の中で述べている。というのも、彼の言葉は、個別的な事柄ではなく全体的な事柄について言及しているからである。それゆえ、ソロモンがここでユダヤの滅びについて預言した可能性は、かなり高い。もちろん読者の中には、そのように思わない人もいるかもしれない。私はそのような人と言い争うつもりはない。ただ、その人も、このソロモンの言葉と我々が今見ている箇所の内容に豊かな類似性が見られることは、認めざるを得ないはずである。何故なら、どちらのほうでも終焉について、また臼を引く際に出る音や労働者たちや歌を歌う者のことについて言及しているからである。
それでは、このような裁きがユダヤに注がれた理由は何だったのか。その理由は、こうであった。すなわち、
【18:23~24】
『何故なら、おまえの商人たちは地上の力ある者どもで、すべての国々の民がおまえの魔術にだまされていたからだ。また、預言者や聖徒たちの血、および地上で殺されたすべての人々の血が、この都の中に見いだされたからだ。」』
という理由である。
ユダヤが裁きを受けたのは、まず『おまえの商人たちは地上の力ある者ども』だからであった。これは、ユダヤが『地上の力ある者ども』と商いをする商人のように傲慢だったということである。つまり、ここではユダヤが傲慢な商人と同類の徒として取り扱われている。確かに、ユダヤは金の霊に取りつかれた吝嗇な商人のように傲慢になっていた。彼らが傲慢だったからこそ、あたかも自分たちが神でもあるかのように、神の前で不遜な振る舞いばかりしていたのである。ユダヤは、そのような傲慢さを持っていたので、裁きを受けてしまった。なお、ここでユダヤが商人として取り扱われているのは実際的に捉えるべきではない。ユダヤは商売に強い関わりを持つ民族というよりは、宗教に強い関わりを民族として見做されていたからだ。それだから、ユダヤがこのように言われたのは、あくまでも比喩的に捉えるべきである。
また、ユダヤが裁かれたのは『すべての国々の民がおまえの魔術にだまされていたから』でもあった。ここでは、ユダヤの愚かしい反逆の振る舞いが『魔術』とされている。ユダヤの不敬虔が『魔術』として見做されていることに驚いてはいけない。魔術とは、すなわち神から離れたこと、サタン的なこと、通常の原理や性質や義務とは正反対のこと、である。ユダヤが神に反逆していたのは、正にこの魔術の概念に適合していたから、彼らの反逆は『魔術』と呼ぶに相応しかった。霊的に理解すれば、確かにそうである。神に従うべき選民が、自分たちを選んで下さった神に反逆して不敬虔な歩みをするというのは『魔術』でなくて何であろうか。ユダヤはその反逆の魔術により、異邦人たちに大きな誤解を与え、異邦人が神の選民であるユダヤ人たちを侮るようにしていた。「これが神の民であるとは!こんな反逆行為ばかりする民が神から選ばれた聖なる民だとは!」と。だから、ユダヤは反逆の魔術により、『すべての国々の民』を騙していたわけである。ユダヤはそのような魔術に凝っていたので、神の憤りにより大いなる裁きを受けてしまった。これは当然のことであった。というのも、神は魔術を忌み嫌っておられるからである(出エジプト22:18、申命記18:9~12)。
ユダヤに対して裁きが注がれた理由は、彼らが『預言者や聖徒たちの血』を大いに流したからでもあった。せっかく神がご自身の使いを彼らに送って下さったというのに、その使いたちを退けて殺してしまったのだから、彼らが破滅の裁きを受けるのは至極当然のことであった。もし彼らに裁きが与えられなかったとすれば、裁かれる神はこの世に存在しなかったことになるであろう。しかし、彼らは紀元70年に裁きを受けた。だから、この世界には裁きの神が働いておられることが分かる。この事柄については、もう既に十分なだけ説明されているから、これ以上の説明は不要であろう。
ユダヤに裁きが与えられたのは『地上で殺されたすべての人々の血』が彼らのうちに見出されたからでもある、と御使いは言っている。これは一体どういう意味であろうか。まず、これが実際的なことでないのは明らかである。何故なら、地上で殺された人が、全てユダヤ人の手により殺されたのではないからだ。カエサルはローマ人の手により殺されたし、アルキメデスも異邦人の兵士により殺された。サムソンもペリシテ人を通して殺された。セネカはネロにより殺された。それにもかかわらず、ここでは全ての殺された人の血が、ユダヤの罪として帰せられている。これは一体どういうわけなのか。これについて私はこう考える。ここではユダヤの殺人の罪が過重に責められているのだ。ユダヤの殺人は、あたかもユダヤが地上で殺された全ての人の加害者であったのも同然だと思えるぐらいに罪深いものである、と。このように過重な言い方で何かが表現されている箇所は聖書に少なくないから、ここでユダヤの罪が過重な言い方で責められていたとしても不思議ではない。確かに、ユダヤの殺人の罪は非常に重く、その罪の重さは彼らが全ての殺人による死亡者を殺した加害者であると感じられるぐらいの重さであった。というのも、『殺してはならない。』という聖なる戒めを受けた聖なる歩みをすべき聖なる民が、聖なる神から聖なる恵みにより遣わされた聖なる使いたちを、愚かにも退け、迫害し、殺したからである。このような彼らの愚行における罪深さは、どれだけ過重に責められたとしても過重過ぎることはないのだ。要するに、このようにここで言われたのは、ユダヤの罪がどのような罪の重さにも比べられないほどに大きかった、ということである。この難しい言葉は、私が今書いたように理解する以外にはないと思われる。私の見解の他に、何かもっともらしい見解があるのであろうか。そのような見解は恐らくないと思われる。もし今述べられた見解よりも正しいと思える見解が見つかったら、その時は、この箇所の内容を書き直すことになるであろう。しかし、今の時点では、今述べられた見解がもっとも正しい見解であることにしたい。
御使いは、このようにユダヤが裁かれた理由を明白に示した。それは、このようにして裁きの理由を示すことで、裁きを下された神に対して非難がされないようにするためである。このように理由をしっかりと示すからこそ、ユダヤが故なくして裁かれたのではないことが分かる。確かに、ユダヤが裁かれたのは彼らの悪ゆえであり、そのため彼らは裁かれても自業自得であり、文句は言えなかった。もしこのような裁きの理由が示されていなかったら、神が一方的にユダヤを無思慮にも痛めつけたなどと勘違いをする者が出ることになりかねないのだ。
さて、ここまでユダヤの裁きについて聖句から色々と述べたが、それにしても彼らは、誠に不真面目で不敬虔な子らであった。「救いようがない」という言葉は、正に彼らのために存在している言葉であるとさえ思えるほどである。この18章の箇所で、これほどまでユダヤについて厳しいことが言われているのは、理由なきことではなかった。つまり、それほどにユダヤは盲目で堕落しきっていたのだ。彼らは、ほとんど死んだも同然の状態であったといってよい。何故こう言えるかといえば、彼らは、ユダヤが破滅させられた理由を、まったく理解できていないからである。タルムードを見ると、どうであろうか。その中でラビたちは、ユダヤの破滅を思い返して、ただただ嘆くばかりである。エルサレム陥落の理由を、文字通りまったく考えようとさえしていない。彼らは、エルサレムの滅亡が神の裁きによりもたらされたなどということは、まったく思いつくことさえない。「ああ、エルサレムが滅ぼされて俺たちは最悪の状態になってしまった…。」ラビたちはこのように嘆いて涙を流すだけなのである。彼らは、これ以上に進まず、霊的な考察をしたり社会的な状況を顧みたりすることすらしていない。しかし確かなところ、エルサレムが破滅させられたその理由は、神の裁きが下されたからであった。すなわち、彼らが神から離れ、『人間の教え』(マタイ15章9節)により律法を蔑ろにし、頑なな心のままで悔い改めようともせず、神から送られた数々の預言者たちを殺し、遂には御子をさえ殺してしまったからこそ、その溢れるばかりの罪に対して巨大な遺棄すなわち民族的な断絶の刑罰を食らうことになったのである。これは、天の法廷により下されたカレット刑である。もし彼らが罪を犯していなかったとすれば、このような断絶の裁きを受けることはなかったであろう。何故なら、ソロモンも言うように『いわれのないのろいはやって来ない』(箴言26章2節)からだ。ユダヤ人であるヨセフス自身も、これは神の刑罰だったと認めている。彼はこう言っている。「ほかならぬ神ご自身が御自分の民全体を裁かれ、救いの道をことごとく滅びへと向けられたのである。」(『ユダヤ戦記2』Ⅴ xiii5:559 p387:ちくま学芸文庫)多くのラビたちは心が歪んでいたからどうして神が御自身の民を滅びに委ねられたのか全く理解できなかったが、ヨセフスのように物事を正しく見れる者からすれば、これは確かに神による報復以外の何物でもないことが分かったのである。しかし、彼らラビたちはマサダの要塞に立てこもっていたエレアザロスが演説の中で言ったように、「神がかつて愛したもうたユダヤ人種族が破滅に定められていたことを知るべきだった」(『ユダヤ戦記3』ⅤⅡ viii6:327 p177:ちくま学芸文庫)のである。また、もし彼らが罪を悔い改めていたとすれば、ニネベのように裁きを回避することができていたであろう。何故なら、神は悔い改めて御自身に立ち返る者には慈しみ深い御方だからである。マラキ3:7の箇所で、『わたしのところに帰れ。そうすれば、わたしもあなたがたのところに帰ろう。』と神が言っておられる通りである。彼らは、エルサレムが滅ぼされた後も、イエス・キリストが単なる裏切者の異端者だったとしか考えていなかった。これは今のユダヤ人(私がユダヤ人というのはスファラディ系のことを言っているのだが)も、そうである。この御方なのである。聖徒であればお分かりであろう。ご自分の民を救うために来て下さったこの救い主を退けたからこそ、遂にユダヤに裁きが下されることになったのである。それにもかかわらず、彼らはエルサレムの崩壊が、まさかキリストに関わっていたなどとは夢にも思わない。こういうことを聞かされたら、きっと昔のラビたちは反発し、このように言った者は煙たがれていたに違いない。これは、彼らがあまりにも鈍感で堕落していたことの明白な証拠である。彼らがそのように異常な状態にあったからこそ、紀元70年に神から断絶されることになったのだ。今でも彼らは神から断絶された状態で歩み続けている。
というわけで、18章の註解は以上で終わったが、この章は、あまりにも単調な内容であった。そこでは同一の事柄が、長々と繰り返して述べられていた。もっとも、単調だからというので、私は神の言葉を非難しているというのではないし、また神の言葉は非難されてはならない。神の言葉は、むしろ賛美されねばならないものである。しかし、18章は単調な内容だから、私も註解が単調にならないように、つまり多様性が感じられるように工夫したつもりである。私は今、必要十分なだけ18章の註解を書き終えたと思いたい。この18章の内容を解読できるのも、他の章の場合と同様に、やはり神の恵みによる。この章を解読できた者は、神の恵みに感謝せねばならない。
第22章 ⑲19章1~10節:ユダヤが陥落してから起きた天での出来事
黙示録の章を区分した人は、この19章の区分において「異常」な区切り方をした。この19:1~10と、19:11以降の箇所は内容的に言って明らかに区切られるべきだから、19:11以降の箇所から別の章として区切るべきであった。すなわち、19章11節目を〇〇章1節目とすべきであった。そして、我々がこれから見る19:1~10は独立した章として区分するか、もしくは18章の中に繋げるべきであった。私であれば、今見られるような19章の区分は絶対にしなかったであろう。このような区分をしてしまったのは、黙示録の内容をシッカリと把握できなかったからであろう。もし幾らかでもシッカリと把握できていたとすれば、このような区分はしなかったはずである。
【19:1】
『この後、私は、天に大群衆の大きい声のようなものが、こう言うのを聞いた。』
この『大群衆の大きい声』の主は、「無数の御使いたち」である。この声の主は、前の箇所で書かれていた声の主が多くの場合、不明瞭でよく分からなかったのとは違い、確言することが出来る。一体どうして、この声の主が御使いたちだと分かるのか。まず、この声の主は、『24人の長老と4つの生き物』(19:4)ではない。何故なら、この『大群衆の大きい声』が発した言葉に応じて、この2つの存在は『アーメン。ハレルヤ。』(19:4)と言っているからである。長老とセラフィムが『大群衆の大きい声』に呼応しているのに、『大群衆の大きい声』が長老とセラフィム自身だとでもいうのであろうか。それはあり得ないことだ。次に、この声の主は「神」でもない。何故なら、この声は神を賛美しているからである。神を賛美して良く言うのは、被造物であるのだから、これは神ではないことになる。最後に、この声は「天に上げられた贖われし聖徒たち」でもない。というのも、この声の主は後の19:6~8の箇所で、聖徒たちを他者として取り扱っているからである。聖徒たちが、自分たちのことを他者でもあるかのように取り扱うというのは、考えにくい。それは非常におかしいと思えるからだ。よって以上の考察から、消去法により、この声の主は「無数の御使いたち」以外には考えられないということが分かる。確かにこれは間違いなく御使いたちである。何故なら、『万の幾万倍、千の幾千倍』(5:11)もいる御使いが一斉に語ったからこそ、ここでは『大群衆の大きい声』が聞こえたと言われているからである。
ところで、ヨハネはどうして声の主について明白に語っていないのか。これまでに見た箇所でも、ヨハネは声の主が誰なのか、具体的に何も語ってはいなかった。私は今、聖書の内容に文句を言っているというのではない。単に素朴な疑問を取り上げているだけである。ヨハネが声の主を明白に語っていないのは、彼に見せられた幻における光景と音声が、あまり明瞭ではなかったからなのかもしれない。明瞭ではなかったからこそ、その声の主も明瞭には語られていないのではないか、ということである。もしそうでなく、幻が明瞭であったとすれば、あえてヨハネは声の主について具体的に書かなかったということなのであろう。それは黙示録をより難しくし、聞く耳を持たない者たちが、より黙示録の解読から遠ざけられるようにするためであったに違いない。何故なら、声の主をあえて書かないほうが、より秘儀的となり、解読が困難になるからだ。いずれにせよ、ヨハネが声の主について具体的に書かないようにしたのは、神の御心であった。これは間違いないことである。しかし、だからといって我々は「神は具体的に説明していないので不親切だ。」などと心の中で思わないようにしよう。神には、神の理由があるのだから。我々がその神の理由について注文を付けることが、どうして出来ようか。
【19:1~2】
『「ハレルヤ。救い、栄光、力は、われらの神のもの。神のさばきは真実で、正しいからである。神は不品行によって地を汚した大淫婦をさばき、ご自分のしもべたちの血の報復を彼女にされたからである。」』
『ハレルヤ。』とはヘブル語であり、「神を賛美せよ。」という意味である。『ヤ』(ia)とは、ヘブル人が神を呼ぶ時に使う言葉の一つである。響きが良いためか、「アーメン。」という言葉と同様、ヘブル語から翻訳されずにそのままの形で使われている。この言葉は、新約聖書では黙示録にしか使われていない。旧約聖書では「詩篇」で多く見られる。新約聖書では黙示録でしか使われておらず旧約聖書では多くの箇所で使われているという点で、この言葉は先に見た『ハルマゲドン』(15:16)という言葉と一緒である。この言葉は、教会だけでなく世俗においても、よく使われているのを見る。ポップスでも、この言葉を取り入れている曲が、いくつもある。もちろん、多くの場合、この言葉を曲の中に取り入れた作者がクリスチャンまたはユダヤ教徒であるというのではない。つまり、それだけ、この言葉は人間にとって耳障りが良いということだ。
神は『ご自分のしもべたちの血の報復を彼女にされた』と御使いは言っている。これは、言うまでもなく紀元70年におけるユダヤ壊滅の出来事のことである。その時に注がれた裁きは、『真実で、正しい』裁きであった。神は、ユダヤの悪に対し、正当なる裁きを注ぐことで復讐されたのである。またユダヤが裁かれたのは、ユダヤが『不品行によって地を汚した』からでもあった。『地』とはユダヤの地を指す。ユダヤは神に逆らうという霊的な不品行により自分たちに与えられた地を汚してしまったので、もはや、その地に住むには相応しくない存在となった。だからこそ、怒られた神は、ローマ人を使われ、ユダヤ人をその住んでいた地から一掃してしまわれたのである。これはカナン人が悪に染まってその地を汚していたために、ユダヤ人を通して、その住んでいた地から根こそぎにされたのと同じである。地は神の所有物であるから(申命記10:14)、ある地域に住んでいる者がそこに住むのに不適格だと判定されたならば、それがユダヤ人であれカナン人であれ、神により強制的に追い出されてしまうのだ。それはアパートの管理人が、邪悪な住人をその住んでいる部屋から強制的に退去させるのと、よく似ている。ユダヤ人という悪しき住人は、その住んでいる部屋を大いに腐敗させてしまったので、神という管理人から容赦なく追い払われてしまったのであった。彼らが不品行を行なって地を汚すことさえなければ、このような裁きが下されることは無かったであろうに。
紀元70年においてユダヤが神から裁きを受けると、その後に第二の復活が起こり、選ばれた者たちは遂に永遠の天国を相続する者とされた(マタイ25:34)。これこそ正に究極的な救いである。この救いは神により与えられる救いであった。また、それはユダヤに裁きが与えられてから実現される救いの出来事であった。だからこそ、ユダヤの裁きが起きた際、ここでは『救い…はわれらの神のもの。』と言われているのだ。また、ユダヤの裁きの時には、神の栄光が豊かに現わされた。すなわち、神はユダヤに正当なる裁きを下されることでご自身の審判者としての栄光を、またその後に選ばれた者たちに天の御国を相続させることでご自身の恵みの栄光を、現わされた。だからこそ、ここでは裁きが起きた際に『栄光…はわれらの神のもの。』と言われている。また、この裁きは神の御業であった。その御業は、神の御力の発露である。何故なら、神がその大きな力でもってユダヤを徹底的に粉砕されたからである。それゆえ、ここではその裁きが起きた際に『力は、われらの神のもの。』などと言われているのである。このように、ユダヤの裁きの際には、これら3つのものが顕現された。だからこそ、御使いは『救い、栄光、力は、われらの神のもの。』と言っているわけである。この裁きの際には、これら3つ以外にも、神の「恵み」「権威」「誉れ」が顕現された。これは少し考えれば、すぐに分かることである。しかし、ここではそれらのものは語られておらず、ただ救いと栄光と力という3つのみが書き記されるに留められている。恐らく、簡潔にするためにこの3つしか言われなかったと思われる。
聖徒である我々も、『救い、栄光、力』という3つのものを、神にこそ帰さねばならない。これは当然のことである。『救い』は、神の専有物である。何故なら、救いが実現したのは、御父が御子を救い主として世に遣わされ(ヨハネ3:16)、御子が自分から進んで十字架の贖いを実現され(Ⅰペテロ2:24)、御霊が選ばれていた人を新しい存在に変えて下さる(テトス3:5)、という方式によるからである。そこに人間の業や効力は一切、存在していない。つまり、救いとは全く人間には依存していないのだ。シューシューと音を鳴らす蛇どもの巣窟であるカトリックの輩がそう考えているように、救いがいくらかでも人間の力や功績にかかっているということはない。それだから、聖徒である者は『救いは神のもの。』と言わなければいけない。キリストの民は「アーメン。」と言うべきである。また『栄光』も神の専有物である。それは人間のものではない。だからダビデは次のように言っている。『私たちにではなく、主よ、私たちにではなく、あなたの恵みとまことのために、栄光を、ただあなたの御名にのみ帰してください。』(詩篇115篇1節)つまり、栄光は神のものだから人間には帰されてはいけない、とダビデは言うのだ。それゆえ、聖徒である者は『栄光は神のもの。』と言わなければいけない。キリストの民は「アーメン。」と言うべきである。また『力』も神の専有物、神から出るもの、神にこそ帰されるべきもの、である。だから詩篇においてダビデは次のように言っている。『力を主にささげよ。』(96:6、29:1)力も栄光と同様、神のものだから、人間のものとしてはならないのだ。よって、聖徒である者は『力は神のもの。』と言わなければいけない。キリストの民は「アーメン。」と言うべきである。これら3つの神の専有物を自分のものとするのは、冒涜的な強奪であり、罪であり、神の御心に適わない愚かな振る舞いである。神の民である聖徒たちが、そのような悪に陥ることがあってはならない。もし神の専有物を自己の所有物とし神に帰さないのであれば、ネブカデレザルのように動物のような状態に成り果てたり(ダニエル4:28~33)、ヘロデのように死の裁きを受けることになりかねない(使徒行伝12:20~23)。神のものを盗んで自分のものにするのは、実に恐ろしいことなのである。
【19:3】
『彼らは再び言った。「ハレルヤ。彼女の煙は永遠に立ち上る。」』
『彼女の煙は永遠に立ち上る。』とは、間違いなくイザヤ書34:9~10の箇所と対応している。そこでは次のように預言されていた。『エドムの川はピッチに、その土は硫黄に変わり、その地は燃えるピッチになる。それは夜も昼も消えず、いつまでもその煙は立ち上る。そこは代々にわたって、廃墟となり、だれも、もうそこを通る者はない。』我々が今見ている箇所も、イザヤ書の箇所も、どちらもユダヤの荒廃と破滅について預言されている。イザヤ書のほうで『エドム』と言われているのは、エドム=エサウであるから(創世記36章)、つまりユダヤがエサウのように神の御前から退けられてしまった状態にあることを示している。
『彼女の煙は永遠に立ち上る。』とは、やはりローマ軍によりユダヤが焼き尽くされる出来事を言っている。この出来事は、既に18:8、17:16、16:8~9、9:13~21(+11:14)で書き記されていた。つまり、これは既出の内容であり、繰り返しである。このことからも、黙示録では繰り返しが多いということが、よく分かるのではないかと思う。しかし、今まで聖徒たちは、黙示録を何も理解できなかったので、そのことに全く気付けなかった。解釈上における神の呪い。
ここでは焼き尽くされたユダヤから出る煙が『永遠に』上ると言われているが、これはどういう意味なのか。実際は、ユダヤが焼かれた煙が『永遠に』立ち上ったというのではない。ユダヤが大炎上した際に生じた煙は、短い期間に終息した。これは歴史を学べば誰でも分かることだ。ここで言われているのは、神がユダヤの荒廃におけるその煙を永遠に至るまでも記憶される、ということである。すなわち、神はユダヤが遺棄された際に立ち上った煙を、その遺棄と共に、いついつまでも忘れることがない、と。つまり、神は遺棄されたユダヤをその煙と一緒に永遠に記憶されたので、もはや2度とユダヤをかつてのように契約の民として復活させることはあり得ないということである。それだから、この『永遠に』という言葉を実際的に捉えるべきではない。ユダヤから出た煙は少しの間だけで消えてしまったのだから、もしこれを実際的に捉えるならば、意味が分からなくなってしまう。これは霊的に捉えるべき言葉である。
【19:4】
『すると、24人の長老と4つの生き物はひれ伏し、御座についておられる神を拝んで、「アーメン。ハレルヤ。」と言った。』
無数の御使いたちが神を賛美したのを見て、『24人の長老と4つの生き物』も、神に崇拝を捧げた。天国では、このように2重、3重、またそれ以上に重ねられた崇拝が、神に捧げられる。それというのも、神は幾重にも崇拝されるに相応しい御方だからである。神の栄光は無限であるため、たといどれだけ崇拝が重ねられたとしても、重ねられ過ぎるということはないのだ。無限の栄光を持っておられる神には、無限の崇拝が捧げられねばならない。それだから地上にいる我々も、神に対して大いに賛美と崇拝とを捧げなければいけない。言うまでもなく、神は地上の聖徒たちも、ご自身を崇拝することを望んでおられる。神の民である聖徒たちが、この地上で神を崇拝しないというのであれば、この地上において一体誰が神を崇拝するというのか。この地上において神を正しく崇拝できるのは、キリストの贖いを受けた聖徒たちしかいないのである。
ここでは長老とセラフィムが天の場所で『ひれ伏し』たと書かれているが、先に見た11:16の箇所と同様、重力については問題にすべきでない。天上の光景については実際の状態に相応しくない表現で示されている、ということを我々は覚えねばならない。聖書は、鈍くて愚かな我々人間が理解しやすいようにと、あえて我々の感覚に合わせた表現で天上の光景や神のことについて示している。神に右手や翼があるなどと詩篇で言われているのが、そうである。それだから、天国に重力があるかなどと考えるのはその疑問自体がナンセンスであり、たとえ思索したとしても答えを見出すことは決して出来ないであろう。事は霊的に捉えられなければいけない。我々は思慮を持ち、愚かにならないようにしよう。
この箇所から、天においては妬みも野心も虚栄も高慢も劣等感も競争心も存在しないことが分かる。何故なら、この箇所で、長老とセラフィムは、無数の御使いたちが捧げた礼拝の行為を見て「右へ倣え」をしているからだ。つまり、この2つの存在は、自分たちこそが神を最高に賛美しなければいけないのだなどという競争心を持っておらず、ペテロのように神の前では自分こそが第一とならねばならないなどという思いも抱かず、御使いたちに先駆けて礼拝の行為を捧げることが出来なかったからというので劣等感を感じたりしていることもないからだ。むしろ、ただ御使いたちに続いて『アーメン。ハレルヤ。』と言うだけで満足している。これは天国が全く罪の存在しない場所だからである。妬みや野心や虚栄といったものは、この世に属するものであって(Ⅰヨハネ2:16)、罪に他ならない。天国にそのような悪徳は一切無いので、長老とセラフィムは別に自分たちが二番手になったとしても、まったく不満を持たず、文句も言わないのである。聖徒である我々も、地上にいる今の時点から、このような天国の気質を身につけるべきであろう。確かに、キリスト者であっても、妬みや虚栄という悪徳から完全に放免されている人は誰もいない。特に、世俗化している弱小な今のキリスト教界は、そのような傾向がある。世俗化しているというのは、つまり妬みや虚栄に満ちたこの世的な感覚を、キリスト者が持っているということなのだから。しかし、やがて天国に導き入れられることになる聖徒が、そうであってはならないのだ。今から既に天国的な気質を身につけておくのが望ましいのは言うまでもない。これは言うまでもないことかもしれないが、この悪徳は聖徒たちの人生に常に付き纏う厄介なものだから、ここでこのように言っておかねばならない。
【19:5】
『また、御座から声が出て言った。「すべての、神のしもべたち。小さい者も大きい者も、神を恐れかしこむ者たちよ。われらの神を賛美せよ。」』
この声は『御座から』出ており、神を自分ではない他者として取り扱っているから、「4人のセラフィム」である。セラフィムたちが御座の場所にいたというのは、4:6で書かれていた。つまり、セラフィムたちは19:4で神をひれ伏して拝んだ後、他の存在にも神を賛美させようとして、ひれ伏した状態から立ち上がったのである。そうして後、この19:5で『すべての、…』などと言ったのだ。この声は『御座』から出ているが、これは御子また御霊がその声の主だというのではない。確かに御子と御霊も御座の場所にいたが、御子と御霊であれば、このようには言われなかった。御子と御霊が『われらの神を賛美せよ。』と言うのは考えられない。御子が聖徒たちに父なる神のことを言われる際には、『われらの神』とは言われず、『あなたがたの神』(ヨハネ20章17節)と言われた。御子が聖徒たちに「私たちの神」と言われたことはない。だから、これが御子の声だったとすれば、ここでは「あなたがたの神を賛美せよ。」という文章が書かれていたはずである。これは御霊の場合でも同様のことが言える。御子が父なる神について言われることは、御霊の場合でも同様だろうからである。
ここで『神のしもべたち』と言われているのは、天にいる贖われた聖徒たちのことである。何故なら、この19:1~10の箇所は、天のことが言われている箇所だからである。『小さい者も大きい者も』とは、すなわちパウロやアブラハムのように大いに輝いている者も、十字架上の強盗のような大いに輝いている者に比べればそれほど輝いてはいない者も、という意味である。天国において、小さい者と大きい者、また大いに輝いている者とそれほど輝いているのではない者がいるというのは、聖句が明瞭に教えていることである(ヘブル11:35、Ⅰコリント15:35~44、マタイ5:19)。「平等こそが至高である」などというユダヤ製の思想を植え付けられている人たちは、目を覚まし、よく注意してほしい。シオン賢者の議定書にも書かれているが、この世界に平等というものはないのだ(この文書ではユダヤにより蔓延させられた平等思想に毒された異邦人たちが嘲られている)。それは天国でも同様なのである。平等がこの世に存在しないというのは、自然を見れば明らかであり、聖書からも分かることである。現代人は思考力を全く削がれているので、こんな簡単なことすら分からなくなってしまった!(※)だから、我々は、天国においては人それぞれ差があるということを、よく弁えなければならない。「神様は天国で人を平等な状態にはしておられないなんて…」などと思うべきではないのである。また、ここで言われているように天国にいる聖徒たちは『神を恐れかしこむ者』である。というのも、彼らは地上において神への恐れのうちに保たれ続けたがゆえ、信仰から離れることもなく天国に挙げられることとなったからである。
(※)
私は現代人がジョン・ロックやジョナサン・エドワーズといった卓越した思考力を持った人物を見習うと良いのではないかと思う。
[本文に戻る]
セラフィムは『われらの神を賛美せよ。』と聖徒たちに命じている。これはユダヤが裁かれた時期に起きた諸々の出来事が、大いなる出来事だったからである。神はこの時、誠に賛美されるべき御業を実現なされた。だからこそ、聖徒たちに向かって『われらの神を賛美せよ。』と言われたわけである。もちろん、聖徒たちは、たといセラフィムからこのように命じられなくても、神を賛美していたであろう。しかし、それにもかかわらずセラフィムは、ここで聖徒たちにこのように命じている。これは言わば「指揮」である。御使いは、オーケストラの指揮者が楽器隊を指揮するように、聖徒たちに賛美をするようにと合図をしたのである。何も聖徒たちが言われなければ賛美しようとしない不敬虔で不真面目な人たちだから、このように命じて賛美するようにと促したというのではない。もし天の聖徒たちが命じられない限り神を賛美しないような存在だと考えるならば、それは彼らに対する侮辱である。天においては秩序や順序といった文化的な要素が、完全な形で見られるということを、我々はよく知るべきである。
【19:6】
『また、私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものが、こう言うのを聞いた。』
ここでは19:1でも出てきた『大群衆の声』が書き記されているから、この音の発生者は「無数の御使いたち」であった。つまり、再び御使いたちが語ることになったのだ。しかし、前に見た箇所が一つの言葉(『大群衆の大きい声』)しか書かれていなかったのとは違い、ここでは2つの言葉が更なる説明として付け加えられている。『大水の音』とは、御使いたちの声が大きな水のように聞こえたということである。それは、御使いたちが無数にいたからである。先にも述べたように、『大水』という言葉は、聖書において多くの人数がそこにいることを示している。これは異邦人また不信者を指して使われる場合が多いが、御使いにも適用可能な言葉である。『激しい雷鳴』とは、御使いたちの声が雷鳴のように聞こえたということである。御使いたちは無数におり、そのため彼らの発した声は幾重にも重なって重厚な音となっていた。だからこそ、御使いたちの声は『激しい雷鳴のよう』に聞こえたわけである。
『「ハレルヤ。』
この言葉が出てくるのは、19章では、これで4度目である。これは、神がユダヤを裁かれた時期には豊かに賛美されるに相応しい御業をなされた、ということである。確かに、ユダヤが正当なる復讐を受けて滅ぼされたのも、その後に起きた諸々の出来事も、賛美されるに相応しい御業であった。だからこそ、この19章では『ハレルヤ。』と何度も繰り返されているのだ。もしその起きた出来事が大したことではなかったのならば、このように何度も言われることはなかったであろう。
『万物の支配者である、われらの神である主は王となられた。』
紀元70年において、キリストは、天で正式に聖徒たちの王となられ、それから聖徒たちを永遠に統御されることになった。これは既に第7のラッパについて記された11:15~19の箇所で語られていたことである。つまり、この19:6の内容は、既に語られていたことの繰り返しである。前に見た第7のラッパの箇所でも、キリストが王となられ、この世から贖い出された聖徒たちを『永遠に支配される』(11:15)ことになったと言われていた。
ここでは『主は王となられた。』と書かれているが、これはキリストが紀元70年において、この地上世界における王になったと言っているのではない。これは、あくまでも天の王になられたということである。もしこれが地上世界について言われているとすれば、今頃この世界の諸国はキリストの御前に跪いていたことであろう。すなわち、全世界の国における政体が、コンスタンティヌス大帝のローマがそうだったように、キリストを最高の主権者として位置付けていたことであろう。キリストが言われた通り、キリストが王として君臨される世界は霊的な世界であって、この世の国ではない(ヨハネ18:36~37)。これについては既に第7のラッパの箇所で説明済みである。
【19:7】
『私たちは喜び楽しみ、神をほめたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。』
『子羊の婚姻の時』とは何か。これはキリストと教会の霊的な婚姻のことであり、つまりキリストと教会である聖徒たちが、夫婦のようにずっと一緒に歩むことになったという意味である。これはキリストと聖徒たちの結びつきを、この世の結婚に例えた表現である。この出来事はユダヤが裁かれた後、紀元70年9月において実現した。それ以降、キリストと聖徒たちは、永遠に夫婦でもあるかのように共に天で歩み続けることになった。この時から今まで2000年の間、キリストと教会は天で共に歩んでいる。これからも、その歩みは続くであろう。今はまだ地上にいる聖徒たち一人一人も、やがて天においてキリストと共に永遠に至るまでも歩むことになる。聖書が教会を妻に例えているのは、教会が妻のようにしてキリストに服従すべきだからである。だから、これは比喩的に捉えなければいけない。天国に行った聖徒たちが、男の聖徒まで女性化してしまうというわけではない。またキリストが夫に例えられているのは、キリストは教会に対して主人だからである。この夫も妻と同じように比喩的に言われたものとして捉えるべきである。
『花嫁はその用意ができた』とは、『花嫁』である聖徒たちがキリストと共に天で歩むようになる時が遂に到来した、という意味である。紀元70年9月までは、まだその時は来ていなかった。それというのも、神が予定しておられたのは、紀元70年9月に天でキリストと教会の結びつきが実現されるということだったからである。
この霊的な婚姻は『喜び楽し』むべきものだった。何故なら、キリストと教会の結びつきは、幸いであり、幸せなことだからである。この世における結婚が喜び楽しむべき出来事であるのと同様、キリストと教会の婚姻も喜び楽しむべき出来事であった。この世の男女における結婚に大きな喜悦が伴うとすれば、キリストと教会の結婚は、どれだけ喜悦に値する出来事であろうか。この結婚の出来事は、神の恵みにより実現されたことである。そのように恵みをお与えになられた神は、大いなることを実現して下さったのだから、清い口によって賛美されなければならない。だからこそ、ここでは『神をほめたたえよう。』と言われているわけである。
【19:8】
『花嫁は、光り輝く、きよい麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは、聖徒たちの正しい行ないである。」』
紀元70年9月において、天に挙げられた聖徒たちは、それ以降『正しい行ない』をし続ける者として歩むようになった。彼らは、もはや『正しい行ない』しかせず、悪しき行ないは全くしないようになった。というのも、彼らには御霊の身体が与えられたからである。御霊の身体は、その身体を持つ者に善を行なわせるだけであり、悪を行なわせることは絶対にない。その身体は、罪の残滓を持つ地上の身体とは、性質が根本的に異なっているのである。ここではその身体が『光り輝く、きよい麻布の衣』と呼ばれている。『光り輝く』とは、御霊の身体における栄光のことである。『きよい』とは、御霊の身体には罪の腐敗がまったく存在しないという意味である。『麻布』とは、恐らく御霊の身体が素晴らしいものであることを示している。何故なら『麻布』とは、良いものだからである。ユダヤもこの『麻布』(18:16)を着ていたが、ユダヤの場合、『麻布』を着ていたからといって何か良いことが言われているのではない。ユダヤが『麻布』を着ていると言われていた場合、それは単にユダヤが傲慢な女王だということを言っているに過ぎない。
今はまだ地上にいる聖徒たちも、やがて天に導き入れられ、『麻布の衣』を着て『正しい行ない』以外にはしなくなる。その時、聖徒たちは善しか行わなくなり、悪を行おうとは全く思わなくなる。これは大変に素晴らしいことである。それが素晴らしいので、パウロも、早くその衣を自分の身に着たいと大いに望んだ。彼はこう言っている。『私たちの住まいである地上の幕屋がこわれても、神の下さる幕屋があることを、私たちは知っています。それは、人の手によらない、天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを着たいと望んでいます。それを着たなら、私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にいる間は、私たちは重荷を負って、うめいています。それは、この幕屋を脱ぎたいと思うからでなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって、死ぬべきものがいのちにのまれてしまうためにです。』(Ⅱコリント5章1~4節)もし天に入れられて『麻布の衣』を着て『正しい行ない』だけをしたいと願うのであれば、聖徒たちは、キリストのうちに保たれ続けるがよい。『最後まで耐え忍』(マタイ24章13節)んでキリストから離れないのであれば、その願いがやがてか叶えられることになろう。しかし、キリストから脱落する者は、天に入れられず地獄へと投げ込まれる。その者には『麻布の衣』も『正しい行ない』も永遠にない。ただあるのは『うじ』と『火』(マルコ9章48節)のみである。
さて、この19:1~10の箇所で言われているのは、預言における最後の出来事である。何故なら、ユダヤが紀元70年9月に裁かれて天で正式に神の王国が始まるという預言よりも、時間的に後に位置する預言は何も存在していないからである。もしそのような預言があるという人がいれば、ぜひとも教えてもらいたい。その人は神から新しい啓示を受けた預言者に違いないから。それだから、この19:1~10の箇所は、時間的に言えば21:1~22:5の箇所と対応している。21:1~の箇所でも、遂に天国の開始が到来したことについて書かれている。このことから、黙示録は順序通りに預言が記された文書ではないということが、ますますよく理解される。というのも、19:1~10で最後の預言が啓示されてから後に書かれている19:11~20:15の箇所では、19:1~10よりも時間的に前の出来事が預言されているからである。この19:11~22:5は、天国が始まる前の出来事に関する預言である。もし黙示録が創世記や福音書のように順序通りに話が進められている文書だとすれば、19:1~10で天国について記された後、同じく天国について記されている21章目以降の内容に直結していたはずである。何故なら、それが実際の順序に適った記述だからである。もし順序通りに記されているというのであれば、19:1~10と21:1~22:5の間に、ひと昔前の預言(19:11~20:15)が記されているのは不適切な配置だったことになる。ヨハネが順序に無頓着だったというのは、既に説明した通りである。このことから、黙示録は順序通りに記されていると思っている教師たちは、すべて無知だということが判明する。彼らは黙示録を研究していない。もし研究していたとしても、研究が足りないか、その研究に神の恵みが注がれていない。だからこそ、黙示録の仕組みが正しく理解できない。それゆえ、黙示録について例えば「黙示録は〇〇章〇〇節までは成就している。」とか「〇〇章〇〇節以降はこれから実現する箇所だ。」などと言ったり思ったりしている教師たちは、自分が何も黙示録のことを知らないということをみずから堂々と告白していることになる。こういったことを言っている教師たちの活動を見るがよい。黙示録に関する註解書や神学書を何も書いていないか、たとい書いていたとしても出鱈目ばかりが満ちているはずだ。私からすれば、このような教師たちは、黙示録の分野においては完全な「盲人」である。私が今「盲人」と言ったことを、悪く受け取らないでいただきたい。というのも、今まで黙示録について「盲人」でなかった教師たちはいなかったからだ。私が「盲人」だと言ったのは、当然ながらアウグスティヌスやカルヴァンも含まれている。確かに、今まで誰も彼も黙示録においては、みな「盲人」であった。しかし、もし黙示録において自分が盲人であると気付いた教師や一般信徒の方がいれば、その人は、神の恵みにより私が書いているこの註解書から大いに学ぶべきである。私はそのような黙示録の分野における盲人たちが、シッカリと視力を持てるようになるため、この註解書を書いているのだ。だから、黙示録がよく分からない人たちは、この註解書を大いに利用すべきである。そうすれば、神の恵みにより、黙示録を正しく理解できるようになることであろう。どうか神が聖徒たちに黙示録を十全に理解させて下さるように。アーメン。
【19:9】
『御使いは私に「子羊の婚姻に招かれた者は幸いだ、と書きなさい。」と言い、また、「これは神の真実のことばです。」と言った。』
ここで御使いは『子羊の婚姻に招かれた者は幸いだ』、と言っている。キリストと教会の婚姻に招かれるとは、つまり、その招かれた者がキリストと共に永遠に歩み続けるようになるということだから、確かに『幸い』であった。この幸いについては、説明の必要がない。何故なら、読者は、この幸いについて、よく理解できるだろうからである。この幸いは、考えられる限り、最高の幸いであると言える。というも、永遠に天上においてキリストにおける幸いを享受し続けられるようになるからだ。これは幸いの極みである。
この幸いな事柄について御使いは『書きなさい。』と、ここで言っている。これを書き記すべきだったのは、聖徒たちが天国を期待し、より豊かに忍耐を持てるようになるためだった。既に述べたように、ヨハネが黙示録を書いている時代は、間もなく大きな危難がやって来る状態にあった。その危難が訪れた際、神の聖徒たちが、忍耐のうちに留まり続け、天国に至れるようになるべきだったのは言うまもでない。だから御使いは、聖徒たちの信仰を堅くするために、ここでこのように言って聖徒たちに信仰の益を与えようとしているのである。それというのも、このようにしてキリストと教会の婚姻について書き記されれば、それを読んだ聖徒たちが天国を求め、より忍耐強くなるだろうからである。それゆえ、ヨハネは、この幸いな事柄について絶対に書き記さなければならなかった。もしそうしなければ、ヨハネは聖徒たちを愛してはおらず、別にどうでもよいと思っていたことになるからだ。
御使いは『これは神の真実のことばです。』と言って、その示された幻を権威付けようとしている。それが『神の真実のことば』であるということほど、聖徒たちにとって神聖な権威はないからである。このように御使いがその幻を権威付けたのは、聖徒たちが、神の示されたことに堅く根差せるためであった。それというのも、もし神の言葉であると言われて権威が付与されなければ、それだけその示された事柄に根差すのは難しくなるからだ。ところで『これ』とは<どこからどこまでの箇所>を指しているのか。回答。それは19:1~8の箇所である。何故なら、『これ』とは『子羊の婚姻』という言葉にかかっているからである。『子羊の婚姻』については、19:1~8の箇所で書かれている。それゆえ『これ』とは19:1~8の箇所を指すことになる。
【19:10】
『そこで、私は彼を拝もうとして、その足もとにひれ伏した。すると、彼は私に言った。「いけません。私は、あなたや、イエスのあかしを堅く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を拝みなさい。イエスのあかしは預言の霊です。」』
ヨハネは、崇高な幻を示してくれた御使いの前にひれ伏して、御使いを崇拝しようとしてしまった。これはヨハネにとって致命的な誤りであった。というのも律法は、神以外の存在を神であるかのように取り扱うことを禁止しているからである。すなわち十戒にはこう書いてある。『あなたには、わたしのほかに、ほかの神々があってはならない。』(出エジプト20章3節)ヨハネの行為は、間違いなくこの戒めに違反していた。何故なら、崇拝が捧げられる対象とは、すなわち神に他ならないからである。『偶像を警戒しなさい。』(Ⅰヨハネ5章21節)と命じたヨハネ自身が、このような偶像崇拝に陥るとは実に驚きである。ヨハネも、やはり罪を持った一人の人間に過ぎなかったことが分かる。聖書は、このように聖書記者や神の使いたちや偉大な祖父たちなどが偶像視されないように、彼らの罪深い振る舞いを如実に示すのが通例である。あの義人ノアも、洪水後に恥ずべき醜態を演じてしまったことについて、創世記9:20~27で記されている。これはハム族、ことにカナン人に対する呪いが示される目的があったが、ノアが神のように取り扱われてしまわないためであった。記憶に値する聖なる人物であるにもかかわらず、その愚かさが隠されることもなく記録されていないのは、ステパノぐらいなものである。ヨハネがしたようなこのような振る舞いは、あらゆる人間と無関係なものではない。人間は、崇高な教えを持っていたり、神聖な職務に就いている者を、神のごとき存在であると見なしがちである。その人の持つ崇高な教えや、その神聖な職務が、その人に多かれ少なかれ神の匂いを分有させてしまうのだ。つまり、その人がその教えや職務から尊厳上における貰い物をしているので、神でもあるかのように思われてしまうことになる。コルネリオも、ペテロがまるで神でもあるかのように、その前にひれ伏してしまった(使徒行伝10:25)。これはペテロが神から遣わされた使徒というその職務ゆえに、神の栄光の匂いを帯びていたからである。今の世界でも、偉大であったり有名であったりする人が、その卓越した能力や輝かしい職務のゆえに神でもあるかのように取り扱われているのを、よく見かけるものである。このヨハネは後の箇所である22:8~9でも、ここで書かれているのと同じように御使いの前にひれ伏している。おお、ヨハネよ、神に選ばれた聖なる使徒よ。聖徒たちに見習われるべき偉大なあなたでさえ、このような悪徳に陥ってしまったとは……―。
愚かにも偶像崇拝に陥ったヨハネを、御使いは『いけません。』と言って、たしなめている。ここと同様の偶像崇拝が描かれている22:8~9の箇所でも、やはり『やめなさい。』とヨハネはたしなめられている。御使いが、このようにヨハネに言ったのは当然であった。何故なら、御使いは、『あなたや、イエスのあかしを堅く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべ』に過ぎないからである。聖徒たちと同じ被造物に過ぎない存在を拝んでどうするのか、と御使いは言いたいのである。確かに被造物は、ただの造られた存在に過ぎないのだから、拝まれるに値しない存在である。拝まねばならないのは、全ての被造物を造られた神である。だから御使いはヨハネにこう言っている。『神を拝みなさい。』このように御使いがヨハネをたしなめたのは、御使いが『救いの相続者となる人々に仕えるために遣わされた』(ヘブル1章14節)からであった。御使いは、ここでヨハネにそうしていることからも分かるように、聖徒の益になるようにと聖徒たちに働きかけてくれるのだ。ここでは御使いにたしなめられたヨハネの対応については、何も書かれていない。だからヨハネが実際にどう対応したかは不明だが、恐らく大いに恥じ入ったのではないかと推測される。ヨハネは、人間本性からすれば、このような醜態を演じたことを記録したくはなかったかもしれない。何故なら、このように書けば、多くの人たちに自分の罪が知られてしまうからである。実際、ヨハネがこのように書いたので、ヨハネのこの醜態は、古今東西あらゆるキリスト者たちに、またキリスト者以外の者らにも、周知されることになってしまった。このように書くのは、ヨハネの尊厳と評価に傷をつけることだから、ヨハネがこのような罪を記したくないと感じていたということは想像に難くない。しかし、それにもかかわらず、ヨハネはこのような醜態を、包み隠さずにそのまま記録した。これはヨハネが聖霊に導かれつつ記述の行為をしていたからである。モーセも聖霊に導かれつつ記述をしていたので、自分の部族の父祖であるレビの醜行を、ありのままに創世記の中で書き記している。もしヨハネが聖霊によりこの文書を書いたのでなければ、このような恥ずべき行為をしたことを、あえて書き記していたかどうかは定かではない。
御使いは最後に『イエスのあかしは預言の霊です。』と言っている。これは「イエスは預言の霊によって諸々の幻をお示しになられたのだ。」という意味である。ここで御使いは、こう言いたいかのようである。「ヨハネよ。これらの預言の幻は私が自分自身から預言したというのではなく、イエスが預言の霊によって預言したものだから、ただイエスの預言を媒介して君に伝えたに過ぎない私を拝んで一体どうするというのか。拝むというのであれば、媒介者としての私ではなく、これらの幻を預言の霊により示されたイエスをこそ拝まねばならないのではないか?」我々は、黙示録の幻が、ただ御使いにより示されたという理解だけを持つのではいけない。そうではなく、黙示録の幻は御使いだけが示した幻ではなく、イエスが示された幻であり、イエスも預言の霊によりそれを示された、という理解を持たなければいけない。つまり、これらの幻は、御使いとイエスと聖霊が示した幻であると理解すべきである。しかし、このうち御使いだけは単なる伝達役に過ぎないことに注意すべきである。
我々も、ヨハネのような偶像崇拝に陥らないように気を付けるべきであろう。我々人間は愚かで弱いので、このような悪徳には、しばしば陥りがちである。言うまでもなく神は、そのような悪徳を忌み嫌っておられる。だから、神はそのような悪徳に陥る者に、ご自身の怒りと嫌悪を示すため裁きを下される。その裁きとは具体的にどういうものか。それは、感覚ことに性倫理の倒錯、秩序の崩壊、悪しき思いの侵入、同性愛への接近、という裁きである。偶像崇拝とは、すなわち正しい秩序体系から自分の精神を逸脱させることに他ならないから、必然的に裁きとして異常性を持たざるを得なくさせられてしまう。公然と偶像崇拝をしている者、人間に過ぎない者に対して「神!」などと言っている人(こういう者は現今において無数に確認できる)を、鋭く観察してみるがよい。そうすれば、その者のうちにこれらのどれかを、多かれ少なかれ見出すであろう。世界の真実を知る陰謀論者には周知のことだが、ルシファー崇拝をしている世界の指導者どもは、その偶像崇拝への裁きとして同性愛や乱交や倒錯という悪徳が神から送られているのである。神の呪いが、偶像崇拝をする者を掴み損ねることは絶対にない。我々は偶像崇拝に決して陥らないため、この19:10の箇所を聖なる教訓とすべきであろう。
第23章 ⑳19章11~21節:再臨および再臨の際に起きた2つの裁き
ところで、この19:11から全ての幻が示し終わる22:5までの箇所は実際の順序通りに記されている、ということを知っておいてほしい。これは、19:11~22:5の箇所をジックリと考究してみれば、よく分かることである。少なくとも、この箇所の範囲内における内容には、順序のあべこべは見られない。これは非常に重要な認識であり、黙示録を理解するためには有益な認識である。それゆえ聖徒たちは、この認識を得、それを忘れるべきではない。19:11~22:5までが時間通りに書かれている、という認識は別に難しい認識でなく、小さい子供でさえも分かるようことであるから、私は何か難しいことを今言ったというのではないのだ。
この箇所は、これまでの内容を理解できたのであれば、それほど難しい箇所ではない。中には手強いと思える部分も人によって多かれ少なかれあるかもしれないが、それでも致命的な手強さというほどではないはずだ。12章や16章に比べたら、この箇所は簡単なほうである。この箇所を解読する場合もそうだが、黙示録を読み解く際には、「どうせ無理だ。」とか「知恵がなければ上手に出来やしない。」などと思うべきではない。このように思う人は、残念ではあるが、黙示録を永遠に読み解くことができないであろう。何故なら、神は不信仰な者を喜ばれないからだ。解読者は、「主の恵みがあれば必ず解読できる。」と思ったり、またそのような精神を持たなければいけない。そうすれば、必ずや、この箇所を含め黙示録の全ての箇所を、神の恵みにより正しく理解できるようになるであろう。何故なら、神は信仰をこそ喜ばれ、信仰を持つ者に恵みを与えて下さるからである。我々に必要なのは信仰であって、不信仰ではない。
それにしても、黙示録の章区分をした人は、どうしようもない区切りをしたものだ。どうして、この19:11から新しい章として区切らなかったのか。確かなところ19:11から始まる預言は、19:1~10の続きではない。それどころか19:1よりも前に起きた出来事についての預言である。だから本来であれば、19:11から新しい章が始まらなければおかしいことになる。私は、どうしてこのような区切りをしたのか、理解できない。黙示録の章区分をした人が誰なのかは分からないが、その人は黙示録を理解できていなかった。だからこそ、このような理解しがたい章区分をしてしまったのである。これは聖書の他の巻でも同様のことが言えるが、黙示録を理解していない人により、黙示録の章区分がされたのは実に残念なことであった。
【19:11】
『また、私は開かれた天を見た。』
いくらか時期を逸している感もあるが、ここにおいて、今まで多く記されていた『また』という言葉を取り扱っておきたいと思う。ヨハネは、黙示録において話を区切る際、この箇所で書かれている『また』と『この後』という2つの言葉を使っている。比率的に言えば、『また』のほうが圧倒的に多い。しかし、この2つの言葉は、どちらも話が区切られるという意味上においては、何も変わらない。すなわち、『また』とは『この後』という意味と同じであり、『この後』も『また』と同じ意味である。ヨハネは、話を区切る際、厳密な意味上の違いを考慮せずに、この2つの言葉を使用している。つまり、どちらの言葉も、単純に話が区切られるために使われていると考えれば、それで問題ない。よって、『また』と『この後』とは具体的にどう違うのか?などと疑問に思う必要はまったくない。
『開かれた天』とは、すなわちキリストの再臨についての預言が遂に開示されることになった、という意味である。これまで再臨の出来事は詳しく示されていなかったが、ここにおいて遂に詳しく示されることになった。それは天において、また天をその出来事の起点として実現される事柄であった。だからこそ、ここでは天から再臨されるキリストの預言が開示されることについて、「天が開かれた」などと言われている。それまでは、まだ再臨について詳しく預言されていなかったから、「天はまだ閉じていた」ということになる。何故なら、その時は、また再臨の預言が詳しくは開示されておらず、天に閉じ込められていたからだ。
『見よ。白い馬がいる。それに乗った方は、「忠実また真実。」と呼ばれる方であり、義をもってさばきをし、戦いをされる。』
この19:11~16の箇所は、間違いなく第一の封印における預言である6:1~2の箇所と対応している。というのは、どちらも『白い馬』に乗ったキリストが、霊の武器を持って敵どもと戦いに行かれることになったというシーンが描かれているからである。つまり、この19:11~16の箇所は、第一の封印を更に詳しく説明している箇所である。第一の封印ではごく手短に説明されたことが、こちらのほうでは詳しく説明されている。この理解に疑念を持つ人は、この2つの箇所を互いに見比べてみるとよい。そうすれば、それぞれ書かれている文章量の違いはあれど、どちらも同じシーンについて預言されていることに気付くはずだ。
キリストが『白い馬』に乗っていたのは、その馬においてキリストの清らかさを示すためである。キリストは、どのような白さも打ち勝てないほどに、清らかなお方であった。それは山上で変貌された際にも示されたことである(マルコ9:2~3)。この『白い馬』については、前に見た第一の封印の箇所で私は説明しておいたから、もうこれ以上の説明は不要であろう。
キリストが『義をもってさばきをし、戦いをされる。』とは、キリストが再臨の際に敵どもを正しく裁かれ、またその敵どもと戦って勝利を得られる、という意味である。何故なら、キリストは『主の主、王の王だから』(17:14)であり、『彼とともにいる者たちは、召された者、選ばれた者、忠実な者だから』(同)である。このようなキリストとその軍勢を前にしては、敵どもは裁かれ、打ち負ける以外にないのだ。この出来事は、先に16:16で語られていた『ハルマゲドン』の戦いに他ならない。この裁きと戦いは、少し後の箇所である19:19~21で詳しく描写されている。なお、この出来事は紀元68年に起きたということを、再び言っておきたい。ここまで読み進められた聖徒であれば、もうこれは十分に理解できることではないかと思う。しかし、これは誠に重要な事柄なので、私はこのように繰り返し言うわけである。もしこの理解、すなわち再臨と再臨の際に起こる戦いが紀元1世紀に起きたという理解を否認するのであれば、その人はキリストの御言葉をも否認することになるから、よくよく注意せねばならない。何故なら、キリストはご自身の目の前に立っている紀元1世紀のユダヤ人が生きている間に再臨が起こると、疑いもないほど明白に断言されたからである(マタイ16:28)。もしこの理解を否認するというのであれば、マタイ16:28で言われている言葉をどのように解釈するのが正しいのか、ぜひ私に教えていただきたい。既に第1部でも述べたが、この聖句箇所は、キリストの前にいた人たちが生存している間に再臨が起こると言われたという解釈以外には、まともな解釈をすることが出来ない。誰も彼もが、それを受け入れるかどうかは別として、この解釈の正しさ・合理性に口を慎まざるを得ないのだ。もしこの解釈以外に正しいと思えるような解釈があったとすれば、私はとっくの昔に、その解釈を真剣に検討し、この作品の中で取り扱っていたことであろう。
キリストが『忠実また真実』と呼ばれるのは、キリストが「忠実な方であり真実な方」だという意味である。これについては、既に3:14、3:7、1:5の箇所で言われていた。このお方は、『忠実また真実』に敵どもを裁かれた。すなわち、神の律法に従って忠実に、また何も曲げることなく真実に、敵どもを裁かれた。その裁きには一点の欠けもなかった。完全に正しく裁かれ、裁かれる時には何も誤らない。これが『忠実また真実』と呼ばれるキリストである。人は、このお方が『忠実また真実』であられることを知らねばならない。このお方には、不正も、賄賂も、買収も、言い訳も、通用しない。このお方は、すべての事柄を、ことごとく正しくお裁きになるのである。それは、『神は、善であれ悪であれ、すべての隠れたことについて、すべてのわざをさばかれる』(伝道者の書12章14節)と書かれている通りである。至高の審判者を欺けると考えている者たちは、実際にこのお方から裁きを受ける時、自分の考えが誤っていたことを思い知らされることになるであろう。
【19:12】
『その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほかだれも知らない名が書かれていた。』
キリストの『目は燃える炎であ』ったのは、既に説明されたように、キリストの目がレアのように弱弱しくはなかった、ということである。キリストの目が炎のようであったというのは、2:18と1:14で語られたことの繰り返しである。
キリストの『頭には多くの王冠があっ』たというのは、キリストの持っておられる絶対的な王権を示す。何故なら、キリストはただの王、ただの主ではなく、19:16でも言われているように『王の王、主の主』であられるからである。もしキリストの頭に、一つ、二つ、三つぐらいの王冠しかなければ、キリストの王権はそこまで大きくなかったということになる。何故なら、王権を示す王冠の数が少ないからである。だが、ここでは『多くの』王冠があったと言われている。だから、キリストは実に大きな王権を持っておられたことが分かる。12:3では、サタンが『7つの冠』をかぶっていたと書かれている。『7つ』とは明らかに多い数である。それは少ない数ではない。それゆえ、サタンもキリストと同じように大きな権力を持っていたことが分かる。実際、サタンには『世界の国々』が全て任されていたから(ルカ4:5~7)、大きな権力を彼が持っているのは明らかである。もっとも、サタンの場合は、その与えられた絶大な権力も、キリストというより高次の存在が許可される範囲内で行使できるに過ぎないのではあるが。
『ご自身のほかだれも知らない名が書かれていた』のは、もちろん『多くの王冠』にである。この『ご自身のほかだれも知らない名』とは何なのか。これは、「ただキリストお一人だけに固有の名」という意味である。つまり、これはキリスト以外には自身の名として知られることのない名前、ということである。それだから、これを次のように解してはいけない。すなわち、「キリストだけが知っている名前」とか「キリストにしか解読できない文字で記された名前」という理解がそれである。というのも、キリストの聖徒たちが、キリストの天における『新しい名』(3:12)を知らないというのは考えられないことだからである。キリストはご自身の命をさえ聖徒のために犠牲とされたお方である。そのお方が、天における新しいご自身の名を、ご自身の愛された聖徒たちに隠したままでいることが果たしてあるのであろうか。そのようなことは非常に考えにくい。もしキリストが聖徒たちを愛しておられるのであれば、ご自身の新しい名を聖徒たちに知らせるはずである。それゆえ、この名前は、単にキリストだけに専有された限定的また排他的な名前だという意味として捉えるべきである。
【19:13】
『その方は血に染まった衣を着ていて、その名は「神のことば」と呼ばれた。』
キリストが『血に染まった衣を着てい』たと書かれていることについて、少し前、私は次のように書いた。<キリストが『血に染まった衣を着てい』たのは、キリストが殉教者たちの証人であるということである。キリストは、殉教した聖徒たちが殉教した時、その殉教の出来事を傍近くで見ておられた。というのも神であられるキリストは、地のどこの場所にも存在しておられるからである(エレミヤ23:24)。そして、キリストは殉教者たちの流された血潮を、ご自身の衣に受けられた。だからこそ、ここではキリストが『血に染まった衣を着てい』たと言われているのだ。それだから、これは霊的に捉えるべきである。これを実際的に捉えてはいけない。何故なら、確かにキリストは霊的には殉教者の傍近くにおられたが、実際的な意味において殉教者たちの近くにおられたわけではなかったからである。よって、キリストの衣についていた血は、敵どもの血ではなかったことになる。キリストが『血に染まった衣』を身に着けておられたのは、2つのことを示す。一つ目は、キリストが殉教者たちの殉教を明白に記憶しておられる、ということである。キリストは殉教者たちの傍近くで殉教の出来事を見ていたのだから、これは間違いないことである。キリストはご自身の見た殉教の光景をお忘れになるお方ではない。二つ目は、キリストが殉教者たちの流された血に対して、敵どもに報復されるということである。キリストが殉教者たちの殉教を覚えておられるというのであれば、キリストがその血を流した敵どもに報復されるのは至極当然である。確かに、神であるキリストは悪しき行ないに対して報復されるお方である。神は次のように言っておられる。『復讐と報いとは、わたしのもの。』(申命記32章35節)エレミヤも次のよう言っている。『主は報復の神で、必ず報復される』(エレミヤ51章56節)。パウロも聖徒たちに次のように述べた。『愛する人たち。自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それは、こう書いてあるからです。「復讐はわたしのすることである。わたしが報いをする、と主は言われる。」』(ローマ12章19節)キリストがこのような衣を着ておられたと書かれているのは、かなり重要である。>この『血に染まった衣』が、敵どもへの報復を意味するという点に誤りはない。確かに、この衣は、キリストが敵どもに報復されることについて教えている。しかし、この衣に付けられた血が殉教者の血だという点は、誤りであった。この血は殉教者の血ではなく、敵どもが流した血である。敵とは、すなわちハルマゲドンの戦いの際にキリストと戦うローマ軍のことである。再臨の際、実際に敵どもがキリストにより血を流されたというのではない。しかし、彼らはキリストの口から出ている『剣によって殺され』(19:21)るのだから、霊的に理解すれば、ローマ軍の血が流されたと言うことができる。つまり、キリストにより執行される御言葉の剣による霊的な断罪が、実際的な殺傷行為として言い表されているということである。すなわち、それは霊的な現実を、実際的な現実に置き換えて表現しているということである。だからこそ、キリストの衣は敵の『血に染まった』わけである。この衣については、イザヤ63:1~6の箇所を参照しなければ正しく捉えられない。何故なら、この衣は、イザヤ書の箇所と対応しているからだ。私は少し前までは、このイザヤ書の箇所を何も考慮していなかったので、解釈を誤った。しかし後ほど、イザヤ書の箇所とこの衣が対応していることに気付いたので、このようにこの部分を書き直しているわけである。そのイザヤ書の箇所では次のように言われている。『「エドムから来る者、ボツラから深紅の衣を着て来るこの者は、だれか。その着物には威光があり、大いなる力をもって進んで来るこの者は。」「正義を語り、救うに力強い者、それがわたしだ。」「なぜ、あなたの着物は赤く、あなたの衣は酒ぶねを踏む者のようなのか。」「わたしはひとりで酒ぶねを踏んだ。国々の民のうちに、わたしと事を共にする者はいなかった。わたしは怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。それで、彼らの血のしたたりが、私の衣にふりかかり、わたしの着物を、すっかり汚してしまった。わたしの心のうちに復讐の日があり、わたしの贖いの年が来たからだ。わたしは見回したが、だれも助ける者はなく、いぶかったが、だれもささえる者はいなかった。そこで、わたしの腕で救いをもたらし、わたしの憤りを、わたしのささえとした。わたしは、怒って国々の民を踏みつけ、憤って彼らを踏みつぶし、彼らの血のしたたりを地に流した。」』
『神のことば』とは、その言われた言葉の通りであり、キリストのことである。ヨハネは、このように書くことで、この19:11~16で馬に乗っておられる方が正にキリストであるということを、我々に理解させようとしている。この言葉以外にも、この箇所では、それがキリストであることを示す「目印」としての言葉が多く書かれている。それだから、こんなにも多くの目印が置かれているのに、我々がこの馬に乗った方をキリストであると理解しないのは、愚かであり、恥ずべきことである。何故なら、それはあたかも、白の色を見ながら「これは白ではない」、また☆のマークを見ながら「これは☆のマークではない」などと言ったり考えたりするようなものだからである。この『神のことば』という言葉については、説明することをしないでおく。何故なら、本作品はキリスト論を本題として取り扱う作品ではないし、聖徒たちはこの言葉について、既によく理解しているだろうからである。もしキリストが『神のことば』であるという事柄を学びたければ、カルヴァンの「キリスト教綱要」や、アレクサンドリアのキュリロスまたアウグスティヌスをはじめとした教父たちの書物から学べばよい。この事柄については既に十分なだけ考究されてきたので、まだほとんど未開拓といってよい再臨論とは違って、この事柄を学ぼうと思えば幾らでも神学書は存在しているのだ。
【19:14】
『天にある軍勢はまっ白な、きよい麻布を着て、白い馬に乗って彼につき従った。』
『天にある軍勢』とは、すなわち天にいる聖徒たちの群れを指す。御使いたちも天の軍勢であるが(詩篇148:2、103:21、ネヘミヤ9:6)、ここで言われているのは御使いのことではない。というのも、この箇所で言われているのは、キリストに付き従う聖徒たちのことだからである。
『まっ白な、きよい麻布』とは、御霊の身体のことである。御霊の身体については先に見た19:8でも言われていた。キリストが再臨される紀元68年6月9日には、天にいた魂だけの状態だった聖徒たちが、御霊の身体を受けて復活することになった。その復活体が、ここでは『まっ白な、きよい麻布』と言われている。この御霊の身体については19:8でも言われていたが、どちらでも『きよい麻布』と言われているからといって、どちらとも同じ時期に起きた出来事が語られていると思ってはならない。この2つの箇所では、どちらも時期的に異なった出来事が記されている。すなわち我々が今見ている19:14の箇所では、紀元68年6月9日のことが書かれており、それは再臨の際に聖徒たちが御霊の身体を受けるという出来事についての事柄である。一方、19:8の箇所は紀元70年9月のことが書かれており、それはユダヤが陥落した後には聖徒たちが御霊の身体を持って永遠にキリストと共に歩むことになったという出来事についての事柄である。確かに、この19:8と19:14では、どちらも『きよい麻布』と言われているから、一見すると同じ時期について書かれていると思えるかもしれない。しかし黙示録を研究すれば、この2つの箇所で書かれている出来事は、時期的にかなり離れているということが分かるようになる。もしこの2つの箇所が同じ時期について書かれていると理解すると、黙示録の構造を正しく把握できなくなるから注意せねばならない。
キリストが再臨される際には、天で復活に与った聖徒たちも、キリストと共に天から降りて来た。これは聖書の他の箇所でも言われている(ユダ14、Ⅰテサロニケ4:14)。奇跡や福音宣教について考えれば分かるが、キリストは御自身の業を、聖徒たちにも為させて下さるお方である。キリストはそのようなお方であるから、再臨の際には、天にいた聖徒たちも御自身と同じように天から降りて来るようにされたのである。また、その再臨の際、天から降りて来た聖徒たちは『白い馬に乗って』いた。つまり、『白い馬』に乗っていたのはキリストお一人だけでなかった、ということが分かる。キリストは、馬に乗るという点でも、御自身が受けた恵みを聖徒たちに分有させて下さったのである。キリストは御自身の命さえも聖徒たちに分かち与えられたお方だから、キリストが聖徒たちと分かち合おうとされない業や恵みはないのである。それはキリストの聖徒たちに対する愛のゆえであった。もし愛がなければ、聖徒たちはキリストと同じようにして天から降りて来ることも、『白い馬』に乗ることも、なかったであろう。
ここで我々は、ゼカリヤ書6:1~8の預言が、この19:14の預言では、明白な形で示されていることに注目すべきである。ゼカリヤ書のほうでは、白い馬が戦車を引いているという預言がされていただけであった。これは、かなり大まかな内容の預言である。内容の細部まで知ることはできない。しかし、19:14の預言では、ゼカリヤ書の預言がかなり詳細に分かる形として示されることになった。つまり、ゼカリヤ書で書かれている馬が戦車を引いているという朧げな預言は、19:14で書かれている馬に乗ったキリストが馬に乗った聖徒たちを大勢率いられるという実体としての預言における言わば「影」のようなものであったということである。ゼカリヤ書の預言は影であったから、影に相応しく内容的には幾らか曖昧であった。ゼカリヤの時代は、まだ再臨の実現するのが遠かったから、ただ馬に引かれた戦車による戦いが起こるという簡単なことだけが示されれば、それで良かったのである。預言がその実現に近づくほど、その明瞭性を強めるというのは、神が預言をされる際に用いられるやり方である。
【19:15】
『この方の口からは諸国の民を打つために、鋭い剣が出ていた。』
キリストは再臨された際、『鋭い剣』である御言葉により、裁きとして『諸国の民を打』たれた。この出来事は19:21に書かれていることである。この点において諸国の民とユダヤの民に与えられた裁きは異なっている。すなわち、『諸国の民』に与えられたのは御言葉の剣による霊的な裁きだけであり、実際的な損害はもたらされなかった。一方、ユダヤの民には御言葉の剣による霊的な裁きが与えられただけでなく、実際的な損害も裁きとしてもたらされた。これは再臨の起きたユダヤ戦争の時期について思いを巡らせてみれば、すぐにも分かることである。神はユダヤと諸国の民に対する裁きを、それぞれ異なった内容のものとされた。キリストの口から『鋭い剣が出ていた』というのは、既に1:16や2:16で言われていたことである。
『この方は、鉄の杖をもって彼らを牧される。』
『鉄の杖』とは、既に説明されたように「御言葉」を指す。これを文字通りに捉えてはいけない。これを実際的な言葉だとして文字通りに捉えるならば、非常にコミカルな出来事が、ここでは言われていることになってしまう。
ここで言われているのは、キリストが『鉄の杖』である御言葉により、『諸国の民』を裁かれるということである。要するに、この箇所は前の句と内容的にほとんど変わらない。なお、この箇所は詩篇の箇所と対応している。詩篇の箇所でも、シオンの山に王として立てられたキリストが、鉄の杖で敵どもに働きかけることについて預言されている。それは次のように書かれている通りである。『天の御座に着いておられる方は笑う。主はその者どもをあざけられる。ここに主は、怒りをもって彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。「しかし、わたしは、わたしの王を立てた。わたしの聖なる山、シオンに。」「わたしは主の定めについて語ろう。主はわたしに言われた。『あなたは、わたしの子。きょう、わたしがあなたを生んだ。わたしに求めよ。わたしは国々をあなたへのゆずりとして与え、地をその果て果てまで、あなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。』」』(2篇4~9節)詩篇のほうでは、『牧される』ではなく『打ち砕き…粉々にする』となっているが、どちらも意味は変わらず、御言葉による断罪の裁きが下されることを言っている。
『この方はまた、万物の支配者である神の激しい怒りの酒ぶねを踏まれる。』
これは、キリストが『諸国の民』を『酒ぶねを踏まれる』かのようにして裁かれ、滅茶滅茶にさせる、という意味である。それは『神の激しい怒り』のゆえに注がれた裁きである。我々は、古代においては、酒が作られる際、酒ぶねが足で激しく踏まれていたという事情を弁えなければいけない。その激しさは凄まじいものであった。今では、そのようなやり方はされないから、酒ぶねについて知らない人も多いかもしれない。しかし、黙示録を豊かに理解するために、我々はこの酒ぶねを含めた古代の生活事情について精通しておく必要がある。聖書は、これは当然のことなのだが、その書かれた当時の時代事情を前提として書かれている。だから、当時の時代状況を知らなければ知らないほど、それだけ聖書を理解するのが困難になってしまう。この『酒ぶね』という言葉も、そのうちの一つである。
14:19~20の箇所でも『酒ぶね』について語られているが、この19:15とは内容的に違う。何故なら、14:19~20のほうでは、毒麦どもが第二の携挙により引き上げられた後で、地獄の刑罰を受けることについて語られているからである。そちらのほうでは、地獄で悪者どもが酒ぶねのように踏まれて悲惨になる、ということが言われている。しかし、こちらのほうでは、『諸国の民』である教会とは無関係の者たちが、酒ぶねで踏まれるかのような激しい裁きを受ける、ということが語られている。先にも述べたが、黙示録では、同じ言葉や似たような言葉が使用されていながら、まったく違う内容について語られているという部分が少なくない。この19:15の箇所も、そのうちの一つである。解読者たちは、この点によく注意する必要がある。同じ言葉や似たような言葉が使われているからといって、即「=(イコール)」で結び付けてしまうと、とんでもない誤りに陥りかねない。これは黙示録だけでなく、聖書の他の巻の内容でも同様のことが言える。
【19:16】
『その着物にも、ももにも、「王の王、主の主。」という名が書かれていた。』
キリストが『王の王、主の主』という名であったのは、キリストが再臨される際、キリストが主権者たちの主権者として敵を裁かれ、また敵と戦われるということである。『王の王』とは、すなわち『獣と地上の王たち』(19:19)をも超える王であられたという意味である。『主の主』とは、すなわちローマ人たちの主権者に対して主権を持っておられる主権者だという意味である。ローマ人たちは、自分たちの王であり主である存在はローマの主権者の他にはいないと思っていたことであろう。しかし、それは思い違いであった。この箇所でも言われているように、ローマの主権者の上には、キリストという更に高次の主権者が存在していたのである。キリストは『王の王、主の主』であられるので、『獣と地上の王たち』に勝利することができた。というのも、キリストはローマの主権者を遥かに超える権力と力とを持っておられたからである。それは、ちょうどローマの属国における王が、その王に対して支配権を持つローマ皇帝の前では手も足も出ない存在に過ぎなかったのと同じである。「大王」である者は、普通の王たちを凌駕して打ち負かせるものなのだ。
この『王の王、主の主』とは、17:14の箇所でも書かれている。そこでも、この19:16の箇所と同じで、キリストが最高の主権者であられるからこそ敵の王たちに勝利することができた、ということが言われている。この2つの箇所はどちらも同じ事柄について言われているから、両方の箇所を共に考察するならば、更に深い理解が得られるようになるであろう。
この名がキリストの『着物にも、ももにも』書かれていたのは、つまり無数にこの名が書かれていたということだから、すなわち「強調」である。たくさん書かれているというのは、強調以外でなくて何であろうか。ヨハネはここで、「キリストこそ正に王の王、主の主であられる存在だ。これは絶対に疑うことが出来ない。」と言いたいわけである。しかし、ここでキリストの『着物にも、ももにも』名が書かれていたというのは、あくまでも象徴的な表現として捉えるべきである。これを実際的に捉えるのは、あまり適切だとは言えない。我々は、黙示録の事柄は、多くの場合、霊的に弁えなければいけないということを忘れないようにすべきである。
ところで、この『王の王、主の主』という名が、どのような文字で書かれていたのか知りたい人がいるのであろうか。このような疑問はナンセンスである。何故なら、これは先にも述べたように、あくまでも象徴的な表現に過ぎず、実際的なことが言われているのではないからである。それに、このようなことは別に知らなくても、問題にはならない。しかし、あえてこの疑問に回答するとすれば、「それはギリシャ語で書かれていた。」と言うことができる。何故なら、黙示録を書いたヨハネはギリシャ語を使っていたからである。ヨハネがここで『王の王、主の主』という名を明白に書き記しているのは、つまりヨハネに解読できる文字として、この『王の王、主の主』という名が幻の中で示されたということである。だからこそ、ヨハネはここでキリストの名を精確に書き記しているのだ。もしヨハネが幻の中で見せられた文字を解読できなかったとすれば、ここでヨハネが『王の王、主の主』というキリストの名を書き記すことがどうして出来たであろうか。それは出来ないことである。だから、ヨハネの見たキリストの着物と腿とに書かれていた名前は、ギリシャ語により示されていたことになる。ヨハネがヘブル語かアラム語を使えたとすれば、ギリシャ語ではなくヘブル語かアラム語で示されていたという可能性もある。しかし、その場合「ヘブル語(またはアラム語)で王の王、主の主と書かれていた。」と記していたと思われる。ここではそのようには書かれていないから、やはりギリシャ語で示されていたのであろう。それではヨハネがギリシャ語を解読できなかったとすれば、ヨハネが解読できた言語により、この言葉が示されていたのであろうか。これはその通りである。例えばヨハネが中国語しか話せず読めなかったとすれば、『王の王、主の主』という言葉は、中国語で示されていたはずである。神は、ヨハネが解読できるようにして、この言葉を示された。だからこそ、ヨハネの使用している言語に合わせて、この言葉が示されたのである。もしヨハネの使用できない言語で『王の王、主の主』という言葉が示されたとすれば、どうしてヨハネはキリストの名について聖徒たちに知らせることが出来たであろうか。もしそのようであったとすれば、そのような幻を示された神は、会衆に対して自分以外には解せないラテン語でミサの式文を聞かせていた愚かな司祭どもと同類の存在となっていたことであろう。対象としている存在に何が書かれているか分からせようとして示そうとしているのに、その対象者が解読できないような文字で示すということぐらいに愚かなことが他にあるであろうか。
【19:17】
『また私は、太陽の中にひとりの御使いが立っているのを見た。』
この『ひとりの御使い』が誰で、どのような名を持っていたのかは何も知らされていないので、我々には分からない。ただ可能性として一つ考えられるのは、これはミカエルではないかということである。それというのも、ここでこの御使いは、再臨の際、悪霊どもに対して上に立って上の位置から言動をしているからである。つまり、この御使いは、悪霊どもを支配的に取り扱っている。12:7~9の箇所でも、再臨の際、御使いが悪霊どもを支配的に取り扱っていた。そこに出てきた御使いは、すなわち「ミカエル」であった。我々が今見ている19:17の箇所と、先に見た12:7~9の箇所とでは、そこに書き記されていることが再臨の際に起こるという点、また御使いが悪霊どもを支配的に取り扱っているという点で、共通している。それだから、この19:17で書かれている御使いは、12:7~9に出てきたミカエルであった可能性がある。しかし、確定的なことは言えない。これは、あくまでも推測に過ぎない見解だからである。もしかしたら、ミカエル以外の御使いであるという可能性も十分にある。いずれにせよ、この御使いが誰であったにしても、致命的な問題が何か生じるというのではないから、その点では安心できる。
『太陽』とは、もちろんイエス・キリストを指す。何故なら、この19:11~21の箇所では、キリストの再臨について書かれているからだ。つまり、ここで『太陽』と書かれているのは、「義なる太陽であるキリストが遂に再臨された。」ということである。よって、この『太陽』という言葉を文字通りに、すなわち太陽系の中心にあるあの大きな天体だというふうに捉えてはいけない。8:12や6:12や16:8~9の箇所で『太陽』と言われていたのは実際の天体であったが、この19:17は違う。
この箇所で言われているのは、再臨の際に御使いがした言動についてである。というのも『太陽の中に』とは、すなわち「太陽であるイエス・キリストが再臨された時において」という意味だからである。この言い方を、実際的な意味に捉えることはできない。何故なら、実際の『太陽の中にひとりの御使いが立っている』というのは、意味が分からないからである。仮に実際の太陽の中に御使いが立っていたとする場合、それは一体何を我々に教えようとしているのであろうか。誰も上手に説明できないはずである。しかし、私が今言ったように、これが再臨について言われた言葉だとすれば、すんなりと理解することが出来る。それゆえ、私が言ったように捉えるべきである。
『彼は大声で叫び、中天を飛ぶすべての鳥に言った。』
この御使いは、『大声で叫び』―すなわち重要で周知されるべき事柄を、『中天を飛ぶすべての鳥に』―すなわち空中にいた全部の悪霊どもに、『言った』―すなわち上からの立場で命じた。その命令とは、こうであった。
【19:17~18】
『「さあ、神の大宴会に集まり、王の肉、千人隊長の肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべての自由人と奴隷、小さい者と大きい者の肉を食べよ。」』
ここで言われている種類の人たちは、ローマ軍にいた人たちである。『王』とは、『10本の角』であるあの「王と見做された7人の者」である。『千人隊長』とは、説明するまでもない言葉である。『勇者』とは、ローマ軍にいた者のうち、「強者」と呼ぶべき優秀な兵士のことである。『馬とそれに乗る者』とは普通のローマ兵たちと彼らの乗っていた馬を指している。『すべての自由人と奴隷』とは、ローマ軍にいた自由人と奴隷のことである。これはローマ軍の全体を言っている。『小さい者と大きい者』というのもローマ軍の全体であって、ローマ軍にいた大小様々な者のことである。これらがローマ軍を言っているということは、決して疑えない。何故なら、我々が今見ている19:11~21の箇所は、再臨が起こる時の出来事について書かれている箇所だからである。第6の鉢が預言された16:12~16の箇所を見れば分かるように、再臨されたキリストは、ローマにおいて招集された『王たち』(16:14)と戦うことになっていた。その『王たち』とは、我々が今見ている箇所で書かれている『王』のことである。この『王たち』は、ローマ軍を統率する者たちである。彼らは将来的にはローマ軍を自己の意思により統御するのだから、霊的に捉えれば、当時はまだ大きな権力を持っていなかったとしても、確かにローマ軍の統率者であると言える。そのローマ軍について、ここでは言われているのだ。だから、この箇所で色々と言われているのはローマ軍の詳細だということになる。『千人隊長』とか『勇者』とか『馬とそれに乗る者』などと書かれているのだから、これがローマ軍についてのことであるのは確かである。
この箇所では『神の大宴会』と言われている。聖書において、再臨の際に起こる出来事は『大宴会』また『宴会』という言葉で譬えられている。再臨が起こる際には、天から降りて来る聖徒たちと、地上から空中に引き上げられた聖徒たちが、空中の場所で大勢集まることになった。そこでは、大宴会のような状態が見られた。天から降りて来る『千万』(ユダ14)の聖徒たちと、地上から挙げられた無数の聖徒たちが集って喜び合うということほど、大きくて聖なる宴会が他にあるであろうか。決してない。だから、聖徒たちにとって、再臨は『大宴会』であると言えるのだ。また、御使いたちにとっても、それは『大宴会』であった。というのも、再臨の際に起こる出来事は、非常に喜ばしいことだからである。それは、あたかも王の宴会で給仕している奉仕人が、そこに集まって喜んでいる客人たちを見て、喜ばしい感情で満たされているかのようである。また、それは悪霊どもにとっても『大宴会』であった。何故なら、再臨が起きた際、悪霊どもは多くの人々の肉を食べられたからである。それは悪霊どもにとっては「ごちそう」であった。だから悪霊どもにとっても、この『大宴会』は喜ばしい出来事であった。聖書の預言の中で『宴会』という言葉が書かれていれば、それが悪霊どもに関わる内容であった場合は、再臨の際の出来事について言われている。再臨の時の有様が、悪霊にとっては正に『宴会』のようだったからである。しかし、預言でない箇所で『宴会』と言われている場合は、この限りではない。例えば、Ⅰサムエル25:36でナバルが『王の宴会のような宴会を開いていた』と書かれているのは、明らかに再臨のことを言っているのではない。それは誰でも分かるように、再臨を言い表しているのではなく、ただの宴会に過ぎない。また、イザヤ25:6~8やルカ13:28~30などの箇所で『宴会』または『食卓』と言われている場合も、やはり再臨のことが言われているのではない。それは再臨ではなく世界中にいる者たちが御国の信仰のうちに差別なく招き寄せられることを言っている。だから、『宴会』と言われていた場合、聖書では3つの意味があることが分かる。すなわち、再臨と実際の食事会と信仰への招き、の3つである。この箇所では再臨の際に起こる『宴会』について言われているのだ。
この箇所で言われているのは、再臨の際、ローマ兵たちが悪霊どもに取り憑かれてしまう、ということである。御使いが悪霊どもに向かって「ローマ兵たちの肉を食べよ。」と言ったのは、つまり「ローマ兵たちを乗っ取っても良い。取り憑け。」という意味である。「食べる」という行為が悪霊どもにとっては「憑依」に該当する、という事柄については、後ほど再び論じられる。この憑依の悲惨は、再臨されたキリストにより与えられた裁きであった。ローマ兵たちは、福音を拒絶したので、悪霊どもに取り憑かれるのが相応しかった。だからこそ、キリストは、悪霊どもに食べさせるという裁きをお与えになったのである。だが、ローマ人たちは、自分たちが裁きを受けたことについて何も文句を言えなかった。というのも、彼らは福音を拒絶したからこそ、その報いとして悪霊どもに委ねられたからである。とはいっても、彼らは肉の人たちであり、霊的に死んでいたので、自分が悪霊どもに入られたなどとは夢にも思わなかっただろうが。もし彼らがこの裁きを受けた時に「君たちは悪霊どもに憑かれたのだ。」などと指摘されたとすれば、笑うか、反発するか、無視していたことであろう。なお、再臨の際に起きたこの裁きの出来事は、Ⅱテサロニケ2:9~12の箇所で預言された裁きのことである。そこで言われているのはティゲリヌスによる『しるし』のことだと前に述べたが、これは再臨の時に与えられた裁きのことでもある。というのも、このⅡテサロニケの箇所で人々が悪霊どもに惑わされると預言されているのは、正に再臨の際に起きた裁きのことだからである。つまり、この箇所ではティゲリヌスによる惑わしのことだけが言われているというのではない。誰であれ真理を拒絶するならば、裁きとして悪霊どもの餌食にさせられてしまう。しかし、そのようになるのは、真理を拒絶したことに対する当然の報いなのだから、自業自得であると言わねばならない。真理を受け入れないというのは、つまり惑わされることを望むというのでなくて何であろうか。真理を選択しなければ、必然的に惑わしの事柄を選択せざるを得ないからだ。それゆえ神が真理を退ける者たちに、惑わすための悪霊どもを送られて惑わされるのは、当然のことであり、またそれは正当な裁きである。
先に言っておいた悪霊どもの「食事」について、ここで書いておきたい。先に述べたように、悪霊どもにとって、人間の身体に憑依するのは、すなわち「食事」に他ならない。何故なら、彼らは霊的存在だからである。物質存在である我々人間が食事をしたら楽しくなり、元気を出すように、悪霊どもも人の中に入ることで楽しくなり、元気を出す。というのも、彼らはそのために存在しているからである。我々が食事をしないと飢えたり元気が無くなったりするように、悪霊どもも人に働きかけられないと飢えたり元気が無くなったりする。悪霊どもの場合、食事行為をずっとしなくても死ぬということにはならないが、食事をするかしないで喜んだり苦しんだりするという点で、悪霊どもと人間の食事は共通している。それだから、再臨が起きた際、悪霊どもには正に『大宴会』と呼ぶに相応しい状況が目の前に置かれたことになる。自分たちの前に、多くの食べるべき人間が、すなわち『海べの砂のよう』(20:8)に数多いローマ兵たちが「御馳走」のようにして用意されたのである。これを『大宴会』と言わずして何と言えばよいであろうか。ところで、悪霊どもが憑依するとは具体的に、どのような意味であるか。それは、悪霊どもが人の中に入って、自分たちの望む神の御心に適わない悪をその憑依した人間に行わせる、ということである。人間は霊の入れられる器である。聖霊を受けた聖なる器である人間は正しい行ないをして神を喜ばせるが、悪霊の入っている器は悪い行ないをして神の怒りを燃え上がらせる。これの良い例は、ガダラの狂人である。あの狂人は、汚れた霊に憑依されていたので、その霊の働きにより鎖や足かせを断ち切ったり、荒野に追いやられていたりした(ルカ8:26~39)。悪霊に憑かれると、イカれた振る舞いをしてしまうのである。ユダもまた、これの良い例である。彼にはサタンが入ったので(ヨハネ13:27)、サタンの働きにより、キリストを売るという忌まわしい悪を行なってしまった。我々が今見ている箇所で言われているローマ兵たちの場合、どうであったか。彼らは悪霊どもの餌食にされ憑依されたので、悪霊どもの働きにより、エルサレムを荒らして滅茶滅茶にさせた。確かに、ユダヤに対する彼らの攻撃は、彼らが悪霊どもに突き動かされたがゆであったのは間違いない。何故なら、かつては神から『愛された都』(20:9)であるエルサレムを無慈悲にも破壊し尽くすというのは、悪霊に動かされない限り決して出来ないことだからである。また我々は、悪霊どもが人間だけではなく動物をも食べる、すなわち憑依できる、ということを忘れてはならない。これは聖書から分かることである。創世記3章では蛇がエバを騙した話について記されているが、これはサタンが蛇に憑依してエバに語りかけた、ということである。ルカの福音書8:33でも、キリストの許しにより、悪霊どもが『豚にはいった。』と記されている。我々が今見ている箇所でも、悪霊どもが食べよと命じられている生命体の中には『馬』が含まれている。つまり、ここで御使いは悪霊どもに「馬にも取り憑け。」と命じていることになる。動物に憑依した場合も、人間に憑依した場合と同様のことが起こる。その動物が異常な振る舞いをしてしまうのだ。サタンに憑依された蛇は聖なる罪なきエバを惑わすという邪悪な行ないをし、キリストの許しにより悪霊に憑依された豚どもは『いきなりがけを駆け下って湖にはいり、おぼれ死』(ルカ8章33節)に、再臨の際に憑依された馬たちも馬と同じように憑依されていたローマ兵たちと共にエルサレムの破壊に加担した。ところで21世紀の今現在で言えば、どのような存在が悪霊どもに憑依されているのか。分かりやすい例を挙げれば、銃乱射により無差別殺人事件を起こして有名になろうとする名誉男や、自分がHIVに感染したからというので一人でも多くの男にHIVを広めようとする精魂の歪んだ気狂い女が、そうである。このような振る舞いは、悪霊どもがその人の中に入っていない限り、決して出来ない。もし悪霊どもが入っていなければ、良心の働きかけや将来受けるであろう刑罰への恐れにより、自己を制して悪に歩まなかっただろうからである。悪霊どもが入ると、良心や恐れという悪を妨げる働きとなっている精神的な防護壁を、容易に乗り越えられるようになってしまう。何故なら、悪霊どもはそのような壁は気にしないからである。だからこそ、悪霊に憑かれた者たちは、平気で悪に突き進むのである。なお、悪霊どもが入るのは、非キリスト者たちだけだと思ってはならない。これは注意が必要である。キリスト者にも悪霊どもが入ることがある。それはキリストの受難を妨げようとしたので『下がれ。サタン。』(マタイ16章23節)と言われてしまったペテロの例を見れば、分かる。この時、キリストの使命を妨害しようとしたペテロは、知らず知らずのうちにサタンの霊に入られていたのである。だからこそ、サタンの働きにより知らず知らずのうちにペテロはキリストに言うべきでないことを言ってしまったわけである。もっとも、ペテロ自身は単にキリストを思う心から言っただけであり、まさか自分がサタンの心に適ったことを言っているなどとは全く思っていなかったのではあるが。聖徒である者たちが、悪霊どもに入られるのを防ぐためには、より祈り、断食などをしてより豊かに敬虔な歩みをする以外にはないと思われる。それというのも、キリストによれば、悪霊どもは『祈りと断食によらなければ出て行かない。』(マタイ17章21節)からである。祈りと断食により悪霊どもが出て行くというのであれば、それらの行ないにより、悪霊どもが入るのを防げるということにもなるのだ。もちろん、聖徒たちが悪霊どもに入られたとしても、それは聖徒たちがサタンの子に逆戻りしてしまったというわけではない。何故なら、聖徒たちはあくまでもキリストにある神の子たちであって、彼らに悪霊どもが入るのは一時的なことか、または入られるのが長くても必ず解放される時が来るのだからである。神は、御自身の神殿である聖徒たちが(Ⅰコリント3:16)、ずっと悪霊に悩まされ続けるのをお許しにはならない。
ところで、この箇所で言われている種類の人たちの中に、『獣』と『にせ預言者』の名が含まれていないのは注目に値する。どうして、ここではこの2人について何も触れられていないのか。それは、この2人はキリストの再臨の際、殺されるからである。彼らは殺されるのであって、悪霊どもの餌食になるのではない。我々が今見ている19:17~18の箇所で言われているのは、悪霊どもに憑依される者たちについてのことである。だからこそ、ここでは『獣』と『にせ預言者』について何も言及されていないのだ。それでは、もしネロとティゲリヌスが殺されるのではなく、他のローマ兵たちと同様に憑依されたとすれば、この箇所では彼らについて言及されていたのであろうか。これは正にその通りであると言える。黙示録では、このように「どの名また存在が含まれていないか」という一見すると些細と感じられるような点も、重要な意味を持っていることに解釈者たちは注意すべきである。黙示録は、その内容における非常な正確性と密度ゆえに、どれだけ神経質になったとしても神経質になり過ぎるということはない。
【19:19】
『また私は、獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。』
これこそ正に第6の鉢における預言で語られていたハルマゲドンの戦いである(16:12~16)。その戦いは、『馬に乗った方とその軍勢』と『獣と地上の王たちとその軍勢』との戦いであった。前者が勝ち、後者は負けた。なお、ここでは『獣』であるネロがまだ生きていることに注意すべきである。確かに、ここでは『獣』と書かれているから、キリストが再臨された際、まだネロは死んでいなかったことが分かる。もし既にネロが死んでいたとすれば、再臨について書かれたこの箇所で彼の呼び名が書かれることは無かったであろう。ここでネロが生きている存在として出てくるのは当然であった。それというのも、ネロは正にこの再臨の出来事により死滅することになるからだ。ネロが再臨のキリストにより殺されるというのは、次の聖句(19:20)やⅡテサロニケ2:8の箇所を見ても分かる。
このハルマゲドンの戦いは、次のような内容であった。まずネロとローマ軍たちが、エルサレム上空に再臨されたキリストとその軍勢を見た。キリストはエルサレムにある『オリーブ山』(ゼカリヤ14章4節)に再臨されたのだから、彼らが再臨されたキリストを見上げただろうことは間違いない。ネロはローマにいただろうから再臨のキリストを明瞭に見たかどうか定かではないが、エルサレムにいたローマ軍たちは間違いなく明瞭にキリストの姿を見たはずである。そして、彼らは空中に現れたキリストとその軍勢に戦いを挑んだ。ローマ兵たちは獰猛で屈強な強者たちであったから、彼らがキリストの陣営に立ち向かっただろうことは想像に難くない。ローマにいたネロも、キリストの軍勢をローマの地から朧げに見て、敵意を抱くなどしたことであろう。すると、キリストは自分に対抗して戦いの姿勢を取っているローマの者たちに裁きを下された。すなわち、ネロとティゲリヌスを実際的に殺し、それ以外のローマ人たちを悪霊にエサとして喰い尽くさせた。前者のほうの裁きは19:20に、後者のほうの裁きは19:21に書かれている。このハルマゲドンの戦いは、一瞬の間に行なわれた。それは長くは続けられなかった。だから、ローマの者たちにとって、その戦いはあたかも幻想に感じられるものであった。それについては、注目すべき箇所であるイザヤ29:1~8の箇所を見れば、分かる。そこでは、キリストの陣営に戦いを挑んだローマの者たちが『夢のようになり、夜の幻のようになる。』(イザヤ29章7節)と書かれていた。つまり、彼らにとって、それが実際的な出来事であるとは感じられなかった。確かに、このような映画的とでも言うべき再臨の光景が上空に展開されていたとすれば、そのあまりの特異性ゆえに、それが現実の出来事であるとは思えなかったとしても無理はない。それは、ちょうど寝不足の人がぼうっとしてモヤモヤした幻を見るようなものである。寝不足の人が自分の見た幻を特に気に留めないように、ローマの者たちも自分たちの見たキリストの姿を、気には留めなかった。この見解は、私が何か個人の考えから勝手なことを言っているというのではなく、シッカリとイザヤ29:1~8が根拠としてあるのだから、聖徒たちは馬鹿にして退けたりすべきではない。それだから、キリストの再臨を実際に見た当時の兵士たちは、実際に再臨の光景を見たにもかかわらず、その出来事について何も記録することはしなかった。エルサレムにいたキリスト者たちも、携挙されたのだから、再臨についての記録を残すことは出来なかった。ユダヤ人たちも、エルサレムの地で徹底的に殺戮されたのだから、キリストの再臨について書き物をすることが出来なかった。ヨセフスは、投降したのでローマ軍と一緒にいて安全だったが、彼にとっても再臨は幻のように感じられたので、「ユダヤ戦記」の中には何も再臨のことが書かれていない。これらのことについては既に第1部の中で説明されている。
【19:20】
『すると、獣は捕えられた。また、獣の前でしるしを行ない、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを惑わしたあのにせ預言者も、彼といっしょに捕えられた。』
『捕えられた。』とは、どのような意味か。まず「捕える」主体者は再臨されたキリストである。そして「捕えられる」対象者は、『獣』であるネロと『にせ預言者』であるティゲリヌスである。これについて異論を唱える人はいないはずである。さて『捕えられた』とは、つまり再臨されたキリストがネロとティゲリヌスを裁かれることになった、という意味である。狩人は、獣たちを売ったり、殺したり、食べたり、丸裸にして皮を得るため、まずその獣を捕えることから始めるであろう。まず捕えるからこそ、酷い目に合わせることができるからである。それと同様に、再臨された狩人なるキリストは、『獣』(13:1、11)であるこの2人を裁いて酷い目に合わせるため、この2人をまず捕えたのである。だからこそ、この2人はキリストにより間もなく裁きを受けることになったわけである。それだから、この『捕えられた』という言葉を解する際には、今述べたように「狩」の光景を思い浮かべるとよい。そうすれば、この言葉をより理解しやすくなるはずである。
『そして、このふたりは、硫黄の燃えている火の池に、生きたままで投げ込まれた。』
『硫黄の燃えている火の池』とは「地獄」である。先にも述べたことだが、この地獄は、カルヴァンがそう考えていたように単なる象徴として捉えるべきではない。これは、実際的な場所について言われているのだと考えるべきである。この場所については、黙示録では14:10、20:10、20:14~15、21:8が対応している。マルコ9:43~48の箇所で言われているのも、この『火の池』についてである。空中の大審判において裁かれた者どもが投げ入れらる場所について言われているマタイ26:41の箇所も、やはり地獄のことを言っている。この刑罰の場所には、キリストがマルコ9:48で言われたように、『火』と『うじ』による苦しみがある。しかも、そこにいる者たちに与えられる苦しみは永遠に続く。これこそ神が悪しき滅びの子らに与えられる永遠の裁きである。『御子に聞き従わない者は、いのちを見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。』(ヨハネ3章36節)ので、このような場所で、永遠に苦しめられることになるのだ。なお、この箇所で言われている『火の池』また『ゲヘナ』(マルコ9:43~47)と、『ハデス』(シェオル)また『黄泉』は、違っているということを覚えねばならない。『ハデス』という場所は、ただ死んだ人間の魂だけが苦しめられる場所である。しかし『ゲヘナ』という場所では、魂だけでなく身体も魂と共に苦しめられる。この2つを混同してはならない。この2つの場所を同一視すると、地獄について語られている聖書の箇所が、上手に把握できなくなってしまう。確かに、この2つの場所は内容的に異なっている。しかし、その場所における「本質」はどちらも変わらない。つまり、この2つの場所は「外形」また「方式」が異なっている。すなわち、罪人たちが神からの刑罰により苦しみを受ける、という本質部分はどちらも一緒である。しかし、ハデスのほうでは魂だけが苦しめられ、ゲヘナのほうでは身体も苦しめられる、という方式の点では一緒ではない。これは、ちょうど古い契約と新しい契約が、どちらもキリストによる救いを与えるという本質部分では一緒であっても、その救いを与えるキリストが影において信じられるか実体において信じられるか、という方式の点では異なっているのと同じである。古い契約も新しい契約も同じ「救いの契約」であるように、ハデスとゲヘナも同じ「地獄」である。我々が今見ている箇所では、ハデスではなく『ゲヘナ』のほうが取り扱われている。
ネロとティゲリヌスは、ゲヘナであるこの『硫黄の燃えている火の池に、生きたままで投げ込まれた。』これは再臨されたキリストが、この2匹の獣どもを捕えて、裁きへと投げやったからである。この裁きほど恐ろしいものは、この世に存在しない。何故なら、キリストが避けられない突然の死を与え、そうして後に地獄へと容赦なく投げ込まれ、もう取り返しのつかないことになってしまうからである。獣に対するこの裁きについては、パウロが次のように預言していた。『その時になると、不法の人が現われますが、主は御口の息をもって彼を殺し、来臨の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。』(Ⅱテサロニケ2章8節)この預言の中ではネロだけが語られているように思えるが、この裁きの中には、ティゲリヌスも含まれている。というのも、黙示録19:20を読めば分かるように、再臨の際にはティゲリヌスもネロと一緒に裁きを受けたからである。パウロは単にネロのことだけしか言っていないだけである。またこの裁きは、ダニエル7:11と対応している。そこでは次のように預言されていた。『私は、あの角が語る大きなことばの声がするので、見ていると、そのとき、その獣は殺され、からだはそこなわれて、燃える火に投げ込まれるのを見た。』このダニエルの預言と19:20の箇所が対応しているのは、火を見るよりも明らかである。このダニエルの預言でも、やはり語られているのはネロだけに思えるかもしれないが、パウロの預言と同じように、そこで言われている裁きの中にはティゲリヌスも含まれている。確かにこの19:20の箇所では、火の池に投げ込まれるのが「ひとり」ではなく『ふたり』であると言われているのだ。
この箇所でネロとティゲリヌスが地獄へ『生きたままで投げ込まれた。』と書かれているのは、つまりこの2人が「実際の身体を持ちつつ地獄へ投げ込まれた。」という意味である。この2人が実際に肉体の死を経ず、そのまま地獄へと投げ移された、と言われているのではない。彼らは実際的な肉体の死を味わった。この19:20の箇所と対応しているダニエル書7:11の箇所では、確かにネロが『殺され』たと言われている。実際、ネロとティゲリヌスは肉体的に死んだことが、歴史を見ると分かる。よって、ここで『生きたままで』と言われているのを、文字通りに捉えるべきではない。つまり、彼らが肉体的に死なないでそのまま地獄に移されたなどと考えるべきではない。そのような考えは、ダニエル書7:11と実際の歴史から否定される。それでは、『生きたままで』地獄に投げ込まれたとは、どのような意味なのか。これは、つまり彼らが死んだ際には、即座に地獄専用の実際的な肉体が与えられて地獄へと投げ込まれた、ということである。彼らは、それまでの時代に死んだ人たちがそうだったように、死んだ際、霊と身体が分離されることが無かった。それまでの時代に死んだ人たちは、死んだら霊が身体から離され、その離された霊がハデスという地獄に投げ込まれていた。しかし、ネロとティゲリヌスはそうではない。彼らの場合、死んでも霊と身体が分離されず、朽ちた身体が新しい身体に切り替わりつつ地獄へと移された。それは、紀元68年6月9日に生きたままで復活した聖徒たちが、『たちまち、一瞬のうちに』(Ⅰコリント15章52節)新しい御霊の身体に切り替えられたのと同じことである。もちろん、聖徒たちが御霊の身体に変えられたのに対し、ネロとティゲリヌスは地獄用の身体に変えられたという相違点はある。つまり、この2人は死と共に即座に新しい肉体が付与されたわけだから、肉体の持続が断絶させられることなく、地獄へと移されたことになる。これはその現象面から見れば、死んだにもかかわらず死んだとは言い難い出来事であったと言える。何故なら、死んだのに身体がそのまま彼らの存在において以前と変わらず保たれているからである。確かに「身体を伴いつつ存在している。」という観点から言えば、彼らの身体はその持続において断絶させられなかったわけだから、この2人は死んだが死んでいない。だからこそ、ここでは彼らが地獄に『生きたままで投げ込まれた。』と言われているわけである。それは、彼らが死んだのに死んでいないのも同然だからである。この言葉は、かなり解釈の難しい言葉である。だが、歴史を調べ、御言葉に固執し、霊的に事を考察するのであれば、決して解釈できない言葉だというのではない。神の恵みが与えられるのであれば、神の恵みによる思索ゆえに、このような難しい言葉も正しく解釈できるようになるのである。それゆえ正しく解釈できた者は、その恵みを神に感謝すべきなのである。
この2人の死んだ時期とその死に方について、もう少し詳しい説明をしておかねばならない。というのは、この2人の死について詳しく知れば知るほど、それだけ黙示録をより正しく把握できるようになるからである。まずは彼らの死んだ時期についてだが、この2人は同時的に死を受けたというのではない。彼らの死には半年ほどの時間差があった。すなわち、ネロは紀元68年6月9日に死を受け、ティゲリヌスはその半年後の紀元69年1月に死を受けた。しかし、時間に差があったとしても、何も解釈上の問題は生じない。何故なら、この19:20の箇所では、時間については何も触れられていないからである。この箇所では、ただネロとティゲリヌスが死んだとだけしか示されておらず、時間についての教示はまったくない。この2人が『捕えられた』のは『いっしょ』であったと教示されている。だから、彼らが裁きを受けるようにと定められたのは『いっしょ』の時期であった。しかし、殺されて地獄に投げ込まれたことについては『いっしょ』になどと書かれていない。もしこの箇所で「この二人は一緒に殺されて地獄に投げ込まれた。」と書かれていたのであれば、それは実際の歴史に適合しないから、大いに問題であった。だが、裁きを受ける時期まで一緒だったなどとは書かれていないのだから、この2人が殺されて地獄に投げ込まれる時期が半年ほど違っていても特に問題にはならないのである。次は彼らの死に方についてだが、まずネロのほうから言えば、キリストは彼が自殺するという方法により死の裁きをお与えになった。キリストは再臨された際、『御口の息』(Ⅱテサロニケ2章8節)である御言葉によりネロを殺された。その御口の息とは『命には命』という御言葉であった。ネロはそれまでに多くの人たちを殺したので、キリストによる御言葉の裁きが発動され、自分も自分と解放奴隷の手により殺されることになったのである。キリストが御言葉により人を裁かれるとは、こういうやり方なのである。事柄は霊的にこそ捉えられるべきである。このネロの死に方については、既に第1部で詳しく語っておいた。ティゲリヌスの場合、オト帝から自殺を強要されるという形により、キリストの裁きを受けた。彼も多くの人をネロの元で殺してきたので、キリストはオト帝を通して自殺という形の死で彼が罰せられるようにされた(※)。世の人々はこの死をオト帝から出たに過ぎないものだと見るだろうが、霊的に言えば、キリストが『命には命』という御口の息によりオト帝を通してティゲリヌスを殺そうとされたからこそ、そうなったのである。それだから、我々はこの2人が同時的に死んだとか、キリストが霊的ではない仕方でこの2人を殺された、などと考えるべきではない。彼らが一緒の時期に死んだと考えるのは歴史から否定されるし、キリストが実際に物理的な鋭い剣を使って彼らを死に至らしめたなどと考えるのも滑稽であり間違っている。
(※)
タキトゥスは「オトがティゲッリヌスの破滅を命じた」と言って、この忌まわしい佞臣の死についてこう書き記している。「オフォニウス・ティゲッリヌスは無名の両親から生れ、荒んだ少年期と汚らわしい老年を過した。消防隊長、護衛隊長、その他美徳の褒賞を人より早く手に入れたのは悪徳の賜物であった。やがて男の悪行である冷酷無比と貪欲に徹し、ネロをあらゆる罪へと堕落させ、ネロの陰で鉄面皮を重ね、その揚句にネロを裏切り捨ててしまった。そこでネロを心の底から憎んでいた人も、ネロの死を惜しんでいた者も、それぞれ相反した感情からこのティゲッリヌスの処罰を他の誰よりも烈しく執拗に求めた。ガルバの下ではティトゥス・ウィニクスの勢力に庇護されていた。ウィニクスは、自分の娘が命をティゲッリヌスに助けられたからだ、と弁明していた。ティゲッリヌスは確かに彼女を救っていた。慈悲心からではない。彼はあれほど沢山の人を殺しているのだから。そうではなく、将来のため逃げ道を作っておいたのだ。というのも性悪な者は誰でも、現在に信を措かず運命の変化を用心し、公的な憎悪に私的な恩を売っておくものである。そこには清廉潔白への配慮はかけらもなく、あるのは無罪放免の取り引きだけである。ティゲッリヌスへの宿意にティトゥス・ウィニクスへの最近の憤怒も加わり、それだけ烈しく憎悪の念にかられ、人々は都全体からパラティウムの丘や広場へ駆けつけた。そして民衆の放埓が最も許される競争場や劇場は人で満ち溢れ、不穏な叫喚があたりに轟いた。ついにティゲッリヌスはシヌエッサの温泉上で、最期はもはや避けられないとの知らせを受けとる。しかし妾たちの淫らな抱擁や接吻の中に愚図愚図とみっともない時を過し、やっと剃刀で喉を切り、思い切りの悪い恥ずべき最期で不名誉な生涯を汚した。」(『同時代史』第1巻 72 p51~52:筑摩書房)
[本文に戻る]
このネロは、ゲヘナなる『火の池』に投げ込まれた人類初の人間であった。彼よりも前に、ゲヘナに投げ込まれ、ゲヘナの苦しみを味わった人間は存在しない。何故なら、このゲヘナはキリストの再臨と同時に言わば「開所」されたからである。ネロ以前の時代において、死んだ滅びの子たちは誰でもハデスへとその魂が投げ込まれていた。というのも、その時には、まだゲヘナが始まっていなかったからである。要するにネロはゲヘナの『初穂』であった。それは紀元68年6月9日に復活した聖徒たちが、天国の『初穂』(14:4)だったのと同じである。このようにネロはゲヘナに入った初めての人間だったが、それは非常に不名誉なことであった。しかしネロが文句を言うことは出来なかった。何故なら、彼は世界で初めて支配者としてキリスト教徒を迫害した者だからである。キリストは、そのようなネロを、世界で初めてゲヘナを味わう者とされたのである。だからネロが人類初のゲヘナ入場者となったのは、自業自得であった。神は、ネロがした通りに、ネロにもされた。神は人の行ないに応じて、その人に鏡のように報いられる御方なのである。オバデヤ15。『あなたがしたように、あなたにもされる。あなたの報いは、あなたの頭上に返る。』ところで、タキトゥスによれば紀元62年には「体育館が雷火に打たれて炎上」し、「その中にあったネロの像は、融けて見る影もない銅塊とな」ったが(『年代記(下)』第15巻 22 p251:岩波文庫33-408-3)、これはもしかするとネロが数年後に受ける永遠の刑罰を予表していたのかもしれない。プリニウスがネロについて言っている次のことも、もしかしたら同様の意味があったのかもしれない。「ネロ帝は自分の肖像を、120フィート(※引用者註:36メートル)の高さのリンネルに巨大な規模で描くよう命じた。前代未聞のことだ。この絵が完成してマイウス公園に掲げられたとき、それは雷に打たれ、公園のいちばんよい部分もろとも焼けてしまった。」(『プリニウスの博物誌Ⅲ』第35巻33<51> p1418:雄山閣)
今となっては、もうハデスに投げ込まれる人間はいない。今現在において、人は死んだら、かつてのようにハデスではなくゲヘナに投げ込まれるようになっている。再臨が起きてから、聖徒たちは、かつてのように魂だけの状態にはならなくなった。それは、死んだらすぐにも新しい身体が付与されるからである。それと同様に、滅びの子らも、再臨が起きてからは、かつてように魂だけの状態になることがなくなった。彼らは、死んだらすぐにも滅びの身体が付与されてゲヘナに投げ込まれるのである。もう今や、このような時代が到来してから2千年が経過しているのである。ほとんど全ての聖徒たちは、人は死んだら再臨が起こるまでは魂だけの状態に留め置かれる、と当然のように理解している。再臨が起こると、その魂だけの状態の聖徒たちが身体を持つようになると。しかし、このような理解は誤っている。何故なら、キリストの再臨は既に起こったからだ。再臨が既に起きたということは、すなわち聖徒たちが死んだらもはや魂だけの状態にはならなくなった、ということを意味している。聖徒たちは再臨理解を正しいものにせよ。そうすれば死後理解も正しいものとなるであろう。
ところで、この『火の池』が場所的にどこにあるのか知りたい人がいるのであろうか。まず、この刑罰のための場所が、実在するというのは確かなこととして確定されねばならない。何故なら、聖書がこの場所について明白に啓示しているからである。もし地獄の実在性を疑う人がいたとすれば、その人は啓示を信じていないわけだから、キリスト者ではない可能性が高い。しかし、この地獄が宇宙の外側の空間に位置しているのか、まったく我々には知覚し得ない霊的な空間にあるのか、この宇宙ではない別の宇宙に存在しているのか(これはマルチユニバース説が正しかったらの話だが)、我々にはよく分からない。というのも聖書では地獄の場所について何も記していないからである。いずれにせよ、我々は地獄が本当に存在すると信じるだけで、十分であるとすべきであろう。知り得ない事柄を決して知り得ないにもかからわず愚かにも詮索しようとするのは、傲慢の為せる業に他ならない。こういう事柄については無知なままで満足しているほうが、かえって利口なのだ。この件については、既に第2部の中で語っておいたことである。
この箇所の出来事も、やはり『すぐに起こるはずの事』であった。ヨハネが黙示録を書いたのが紀元37~41年の間であり、ネロの殺されたの
が紀元68年、ティゲリヌスの殺されたのが紀元69年だったから、この箇所の出来事が起きたのは、ヨハネが黙示録を書いてから約30年後のことであった。第1部でも説明されたように、その事柄が些細でなければないほど、感じられる時間の速度は比例的に短くなるが、この箇所の出来事は些細なことではなかったから、確かに約30年後という期間は『すぐに起こるはずの事』であった。今の聖徒たちは、御言葉が黙示録の出来事は『すぐに起こるはずの事』だと断言しているのに、黙示録に書かれている出来事が『すぐに』起きたと信じないのであろうか。この『すぐに』という言葉は、我々が日常的に用いている時間の尺度で捉えるべき言葉である。つまり、『すぐに』とは文字通りの「すぐに」という意味に他ならない。神の尺度で捉えようとする人が多くいるかもしれないが、それは誤っている。この文書は人間である者に対して書かれたものだからである。それだから聖徒たちは、この『すぐに』という言葉を正しく捉えるべきである。そうしないと、聖徒たちはツヴィングリの愚かさに陥ってしまうことになる。ツヴィングリはキリストが『これは私の身体である。』と言われた御言葉における『である。』という部分を、文字通りの意味には捉えず、「という意味である。」というふうに捉え、その理解から終生離れようとしはしなかった。だからこの男は、一生涯、聖餐のパンには単に象徴の意味だけしかないと考え続けていた(※注:私の聖餐論の立場は改革派のそれである)。これは大きな誤りであった。聖句を文字通りに捉えなかったからこそ、ツヴィングリという者は聖餐論において誤ったのである。黙示録における『すぐに』という言葉も、それと同様のことが言えるのであって、もしこの言葉を文字通りに捉えなければ、黙示録の解釈において大きな誤りに落ち込むことになってしまう。
【19:21】
『残りの者たちも、馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が、彼らの肉を飽きるほどに食べた。』
『残りの者たち』とは、ローマの軍隊に関わる者のうち、ネロとティゲリヌを除いた者たちである。すなわち、19:18で書かれている『王』『千人隊長』『勇者』『馬とそれに乗る者』『すべての自由人と奴隷』『小さい者と大きい者』が、そうである。この箇所は19:18と対応している。それゆえ、ここで言われているのは19:18で書かれていたローマの兵士たちだったということになる。
この『残りの者たち』は、『馬に乗った方の口から出る剣によって殺され』た。これは実際的な殺害のことではない。この箇所で言われているのは霊的な断罪のことだからである。もしこれが実際的な殺害のことだとすれば、キリストが再臨された時、キリストを見ていたローマ兵たちは、すぐにも大量に殺されていたはずである。しかし、歴史を見てもそのような出来事は確認できず、ローマ兵たちは再臨が起きてからも長く生き続けた。だから、ここで言われている殺害は、霊的な断罪のことだと理解せねばならない(※)。この19:20~21で語られている2つの裁きが実際の死による裁きか霊的な断罪に過ぎない裁きであるかということは、『火の池』という言葉の有無が目印となる。ネロとティゲリヌスについては『火の池』に投げ込まれたと書かれているから、実際に殺されたことになる。というのも、実際に殺されて死なない限り、『火の池』である地獄には入れないからである。他方、『残りの者たち』については『火の池』に投げ込まれたと言われていないから、実際に殺されたのではない。実際には殺されていないからこそ、『残りの者たち』のほうでは『火の池』に投げ込まれたと言われていないのである。もし彼らも実際に殺されていたとすれば、ネロとティゲリヌスについて書かれているのと同じように『火の池』に投げ込まれたと書かれていたことであろう。それゆえ、この『残りの者たち』のほうも実際的に殺されたと理解するのは誤っている。
(※)
ユスティノスも、剣で悲惨にさせられるという表現が、実際のことを言ったのではなく、霊的な火により焼かれることを言っていると考えていた。彼はこう言っている。「「剣があなたがたを食い滅す」と予言されているのは、不従順な者が剣によって殺されることを言っているのではありません。神の剣とは火であり、悪しき行為を選択する者はその餌食となるのです。このゆえに「剣があなたがたを食い滅す。これは主がその口で語られたことである」という表現になっています。そこでもし一瞬のうちに切り殺す剣について語ったのなら、「食い滅ぼす」という表現はとらなかったことでしょう。」(『キリスト教教父著作集1 ユスティノス』『第一弁明』44:5~7 p60:教文館)
[本文に戻る]
『すべての鳥が、彼らの肉を飽きるほどに食べた。』とは、ローマ兵たちが悪霊どもの餌食にされ完全に憑依されてしまった、という意味である。この出来事は19:17~18の箇所で言われていた内容と一緒である。この出来事は既に説明済みであるから、まだよく理解できていない人は、19:17~18の註解に立ち返って再び学び直してほしい。私はその箇所の註解で、説明すべき事柄を十分に説明しておいたのだから。
ネロの裁きについて預言されていた先の句である19:20の箇所は、ダニエル7:11の箇所と対応していた。我々が今見ている『残りの者たち』について預言された19:21の箇所は、そのダニエルの箇所の1節後の箇所と対応している。そこでは次のように書かれている。『残りの獣は、主権を奪われたが、いのちはその時と季節まで延ばされた。』(ダニエル7:12)このダニエル書7:12で言われている『残りの獣』とは、すなわち『王』(19:18)とその配下の兵士たちを指す。ヨハネはダニエル書におけるこの『残りの獣』を『残りの者たち』と言っている。この『残りの獣』とは、ダニエル7:4~6の箇所に出てくる第1から第3までの獣のことではない。何故なら、第4の獣であるネロの時代には、既に第3までの獣は滅ぼされているからである。すなわち、バビロンもペルシャもギリシャも既に、世界帝国という意味における獣としては死滅させられている。それだから、この『残りの獣』はネロにつく将来の7人の皇帝―獣―とその配下の兵士たちだったと考えるべきである。『いのちはその時と季節まで延ばされた。』と書かれているのは、つまりネロおよびティゲリヌス以外のローマ軍の者たちは、その定められた寿命を全うすることが出来た、という意味である。つまり、彼らは再臨の際に実際的に殺されなかったということである。実際、『残りの獣』たちは、再臨の際、ネロとティゲリヌスのようには殺されず、それ以降も長く生き続けている。先に見た19:20の箇所がダニエル7:11の箇所と対応しているとすれば、その次の句である19:21の箇所もダニエル7:11の次の句(7:12)と対応しているとすべきである。何故なら、この2節分の箇所は、明らかに同様の出来事について預言しているからである。つまり、どちらの箇所でも、獣のほうは殺されるのだが、その殺された獣でない獣どもは実際的には殺されない、ということが言われている。黙示録という文書は、ダニエル書と多くの箇所において対応している、という点も考慮すべきである。つまり、この19:20~21は、黙示録におけるその他の多くの箇所と同様、ダニエル書と対応しているということである。
ところで、どうしてネロ・ティゲリヌスと『残りの者たち』は、それぞれ裁きが異なっているのか。どうしてネロ・ティゲリヌスは実際的に殺され、『残りの者たち』は実際的には殺されず霊的な断罪だけで済まされたのか。この興味深い疑問は、逆に次のような質問をすることで解決できる。すなわち、どうして今まで多くの戦勝国は敗戦国における支配者だけを処刑し支配者でない多くの者たちを死なせなかったのか、という質問である。これは、支配者は特に罪の責任を負っているからである。一方、支配者でない者たちは、支配者ほどには罪の責任を負っていないから、断罪されても奴隷として酷使されたり、多くの制限が課されるだけだったり、無罪放免にされたのも同然にされたりするだけで済む。これは全ての戦争においてそうだというのではないが、確かに傾向としては、敗戦国の支配者だけのみ大きな刑罰を受けるという場合が多かったのは事実である。キリストの場合もそれと同様であった。すなわち、キリストという栄光の将軍は、敗北者であるネロ・ティゲリヌスという最高の立場にある支配者2人だけを厳しい裁きにより断罪し、それ以外の者どもは霊的に断罪するだけで良しとされたのである。もしこのキリストの裁きについて批判するというのであれば、今まで多くの戦勝国が敗戦国の支配者だけを罰してきたことも同様に批判せねばならなくなる。もし今まで多くの戦争においてトップの者だけが厳しい裁きを受けてきたことを批判すべきでないとすれば、再臨の際にキリストが下された裁きについても批判すべきではない。トップだけが厳しい裁きを受けるというのは、何も戦争だけに限ったことではない。
なお、この19:19~21の箇所は、イザヤ24:21~22の箇所、ことにイザヤ24:21の箇所で『その日、主は…地では地上の王たちを罰せられる。』と言われている部分と対応している。イザヤが預言していたのは、再臨の日に地上においてローマの者たちが戦いに打ち負ける、ということだったのだ。このイザヤ24章の箇所は、後ほど再び詳しく語られることになる。この箇所は黙示録19:19以降の箇所を理解する際において、非常に重要な箇所であるから、よく心に留めておくべきである。
第24章 2120章1~6節:復活と携挙と裁きと荒野の期間
この箇所でキーとなるのは、やはり何と言っても『千年』という期間である。この言葉は多様な解釈が可能な言葉であるが、解釈次第で、黙示録の理解およびその人の世界観が大幅に変化してしまう。『千年』の期間が未だに訪れていないとすると、黙示録で預言されている諸々の悲惨が、これから後の時代に実現すると考えることになる。『千年』の期間が正に今の時であると理解すれば、今が千年の期間であると考えるので、その期間においては聖徒たちがサタンに打ち勝てると思って闘士的な気質を持つようになる。『千年』の期間は既に実現済みである理解すれば、黙示録で預言されている出来事は既に成就したと考えることになる。この3つの立場のうち、真に正しい立場はただ一つだけである。3つとも、あるいは2つが正しいということはあり得ない。神は、これら3つの立場のどれか一つに対してだけ「それが正しい立場である。」と言われる(※)。それはキリスト教とイスラム教と仏教が、どれも正しい宗教とは決して言えないのと同じである。この3つの宗教のうち正しいのはキリスト教だけであるのと同様、これら3つの立場のうち正しいのはどれか一つだけである。神の恵みを受けた者は、正しい立場に立つことが出来る。しかし神の恵みを受けない者は、誤った立場に立つこと以外には出来ない。私は、この箇所で、この『千年』という言葉を、十分満足できるほど詳しく論じたいと思っている。神が私に正しく書ける力を与えて下さらんことを。また聖徒たちが、この期間についての正しい理解を、神の恵みにより得られるように。アーメン。
(※)
私はいつも祈りの中で、「あなたが<これこそ正しい理解である。>と言われる理解をこそ私に下さい。」と願い求めている。だから、私の述べる見解こそが正しいと私はここで言っておきたい。何故なら、私はキリストが言われたように、祈り求める物は既に受けたと信じつつこう祈っているからだ(マルコ11:22~24)。
[本文に戻る]
この箇所の註解をするにあたり、まず一つ注意しておきたいことがある。それは、この箇所で言われている『千年』という言葉を、聖句の根拠抜きに論じる者たちが、世の中にはいるということである。彼らは聖句が何も根拠として無いのに、この期間について、さも自分たちが真に正しい理解を獲得しているかのように堂々と語る。聖句が根拠としてあれば、別に問題は無かった。しかし、彼らは、ただ自分たちがそう思うからというだけで、聖句の助けが何も無いにもかかわらず、この期間について確定的なことを言うのである。彼らはこの期間について聞かれると、こう言う。「この『千年』という期間を確定できる聖書の他の箇所はありません。」―私は確かにこのように書かれていたのを見た。―なんなのだ、この言葉は。他の箇所に助けとなる聖句が無いのに堂々と語るとは何事か。これではいけないのは正しい信仰を持つ聖徒であれば、誰でも分かることである。もし堂々とこの期間について確定的なことを語るのであれば、まず聖書の他の箇所に根拠を見出していないといけない。もしそうでなければ、この期間に対する解釈は確固たるものではないはずだから、当然ながら堂々と語ることは出来ないのである。これは言うまでもないことであろう。それだから、我々はこの『千年』という言葉のように曖昧であったり分かりにくい部分があれば、必ず他の聖句箇所に根拠を求めつつ解を見出していかなければならない。もしシッカリと他の箇所から助けを得られたら、多くの場合、その解は正しいと見てよいであろう。しかし、他の箇所から助けを得れなければ、その人がその時に持っている解は解ではなく、単なる推測に過ぎないのだから、堂々と自分の考えこそが怜悧でもあるかのように他人に教えることは出来ないのである。私はルターと共にこう言おう。「われわれは聖書に基づく根拠を求めるのであって、想像に基づく怜悧さなどを求めはしないのである。」(『ルター著作集 第一集8』キリストの聖餐について p127:聖文舎)この事柄については、後ほど再び詳しく論じられることになるはずである。
【20:1】
『また私は、御使いが底知れぬ所のかぎと大きな鎖とを手に持って、天から下って来るのを見た。』
この『御使い』はミカエルではないかと考えられる。何故なら、先に詳しく述べたように、この20章は12章と対応しているからだ。12章では、天でミカエルたちがサタンに打ち勝ち、敗北したサタンが天から追放されて『1260日の間』(12:6)(=千年)封じられて力を失う、という出来事について預言されていた。この追放と封印の時における出来事が、20:1~3の箇所では預言されている。12章と20章の類似性を悟った人であれば、これはよく分かるはずである。確かにサタンの追放を実現させたのは12:7~9で書かれていたように『ミカエル』である。であれば、サタンを封印させたのも同様にミカエルの行為だったと思われる。サタンを追放させた張本人が、追放と共に封印もするというのは、実に適切なことであると私には感じられるのだ。もっとも、これがミカエルだと確言することはできない。もしかしたら、封印したのは別の御使いだったかもしれないからである。いずれにせよ、この御使いが誰なのか知らなくても解釈上における致命的な問題は何も起こらないから、その点では安心できる。ただ、ここでは『御使い』が単なる象徴として描かれているなどと考えさえしなければ、たといこれがミカエルと考えようがミカエルでない御使いであると考えようが、厳しく批判されるべきではないと私は思う。
この御使いが『天から下って来』たのは、この御使いが天ではない場所で事を為すからである。もし天において事を為すのだとすれば、ここでは『天から下って来る』とは書かれていなかったであろう。これは、18:1や10:1の箇所でも同じことが言える。それでは、この御使いは、どこで事を為すのか。それは天より下の場所である。この御使いは『底知れぬ所』を対象の場所として事を行なうのだ。だからこそ、この御使いは『天から下って来』たと言われているのだ。
この御使いが『底知れぬ所のかぎ』を持っていたのは、『底知れぬ所』を『封印』(20:3)するためであった。彼が、この鍵を封印のために使ったのは確かである。しかし、この鍵を使って『底知れぬ所』を開いたのかどうかは分からない。何故なら、20:3の箇所では『底知れぬ所』を閉じたり封印したりしたことについては書かれているが、そこが「開かれた」とは書かれていないからである。もしかしたら、『底知れぬ所』は元から開いていたという可能性もある。つまり、元々そこが開かれていたので、20:3の箇所では「開く」ことについては何も書かれていないと。また彼が『大きな鎖』を持っていたのは、言うまでもなくサタンを縛り付けるためであった。これはガダラの狂人が断ち切ったような鎖ではない(ルカ8:29)。この鎖は間違いなく、決して断ち切ることのできない堅固な鎖であった。というのも、サタンが鎖で縛られたのに、それを断ち切るなどというのは考えられないからである。サタンがガダラの狂人でもあるかのように御使いにより縛り付けられた鎖を断ち切って自由にされる、などという光景は考えるだけでも滑稽である。
ところで、この『かぎ』と『鎖』における形状が、どのようであったか問う人がいるのであろうか。このような問いはナンセンスである。これは詮索すべき事柄ではない。何故なら、ここでは御使いの持っている『かぎ』と『鎖』の形状が取り扱われているのではないからだ。つまり、ここでは、そこで言われている「出来事」にこそ心を向けるべきなのである。我々は、ただこの御使いが『かぎ』により底知れぬ所を封じ、『鎖』によりサタンを縛り付けた、とだけ理解していればそれで良い。もしこの2つのものの形状を問うべきだとすれば、4:2で言われている神の『御座』がどのような外観だったのかとか、12:7で言われているミカエルの『使いたち』はどのような者たちだったのか、などといったことも問わねばならなくなってしまう。こんなことを問うてばかりいれば、切りがなく、どれだけ時間があっても足りなくなり、註解書を無限に膨らませなくてはならなくなるであろう。
この箇所の出来事が起きたのは、紀元68年6月9日であった。何故なら、この出来事は、再臨(19:11~21)と復活および携挙(20:4~6)が起きた時に実現されたからである。再臨と復活と携挙が起きたのは、いつだったか。それは紀元68年6月9日であった。だから、この箇所の出来事が起きた年月は紀元68年6月9日であったことになる。それだから、この20:1の箇所で言われている出来事も、やはり『すぐに起こるはずの事』(1:1)だったことになる。私は、この事柄について何度でも繰り返して言わねばならないと思っている。何故なら、これは「超」が付くほどに重要な事柄だからである。私がこれだけ黙示録の出来事は『すぐに起こるはずの事』だったと言っているのに、未だにそれを信じようとしない聖徒がいるのであろうか。そのような聖徒は黙示録を自分の好きなように理解するがよい。私は断言するが、その聖徒は黙示録をいつまで経っても正しく理解できないままでいることになる。
【20:2】
『彼は、悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕え、』
ここでサタンが4つの言い方で言い表されているのは、サタンを聖徒たちに強く認識させたいからである。このサタンとは、人類を破滅と滅びへと陥れた究極の元凶である。もしサタンが存在しなければ、アダムとエバおよびこの2人に連なる全人類は、堕落していなかったかもしれない。しかしサタンがいたからこそ、人間は腐敗に陥れられることになった。つまり、サタンとは悪しき存在のうち、もっとも注目しなければいけない存在である。これを疑う人は恐らくいないはずである。だからこそ、ここでは4つもサタンの異なる呼び名を重ね合わせて、サタンを強く意識するようにさせているのである。12:9の箇所でも、この20:2の箇所と同じようにサタンの名が4通りの言い方で言い表されているが、これはこの2つの箇所が対応しているからである。同じ出来事が記されているからこそ、サタンも同じ4つの言い方で言い現わされている。すなわち、どちらの箇所でもサタンが敗北して、遂にある一定の期間(1260日=千年)だけ封じられることになったという出来事が預言されている。
御使いがサタンを『捕え』たのは、この御使いがサタンよりも力強かったからである。この御使いがサタンを捕えるのは神の御心であり、それはあたかも警官が泥棒を捕まえるようなものであった。だから、サタンはこの御使いによる捕縛に抵抗できなかった。この箇所を見ると、サタンを捕えるのは御使いの役目だったことが分かる。この時、キリストはネロとティゲリヌスという獣を捕え(19:20)、そのうえ多くのローマ兵たちを裁かれるという業に専心しておられた(19:21)。だから、サタンを捕えることは、御使いに委ねられたのである。この御使いがサタンを捕えたのは、キリストが2匹の獣を捕えたのと同様、その捕えた者を酷い目に合わせるためであった。すなわち縛り(20:2)、『底知れぬ所』に投げ入れて封じ込める(20:3)という目的のために、御使いはサタンを捕えたのであった。これは、狩人が「狩」で忌まわしい獣を容赦なく捕まえるようなものであった。このようにされるのは、サタンにとって、どれだけ屈辱だったことであろうか。
『これを千年の間縛って、』
御使いはサタンを捕えると、それを『縛って』しまった。そのようにしたのは、サタンを無力化させるためである。この時、御使いの手にあった『大きな鎖』が使用された。それは『大きな』ものであったから、『巨大』(12:9)な身体を持っていたサタンには調度良いものであった。もしこれが小さい鎖であれば、サタンの巨体を縛ることは出来なかったかもしれない。しかし、これは『大きな鎖』だったのだから、それで縛られたサタンは、完全に身動きが出来なくなってしまったと考えるべきである。
さて、『千年』という注目すべき言葉を見ていきたい。黙示録では、ここで初めて『千年』という言葉が出てくる。この箇所以降では、20:3~7までの箇所で、この言葉が使われている。それ以降には出てこない。つまり、これは20章のある部分にだけ使われている言葉である。この言葉は、既に述べたように実際的な期間を言っているのではない。この言葉が表示する実際的な期間は、12章を見れば分かるように『1260日』(12:6)また『一時と二時と半時』(12:14)(=3年6か月=42か月)である。この事柄が未だに理解できていない人は、12章の註解に立ち戻って再び学び直してほしい。私はそこで、既に十分なだけ、この期間について説明しておいたのだから。しかし、これは非常に重要な事柄だから、ここでも幾らかのことを語っておくことにしたい。ほとんど全ての聖徒たちは、この期間が非常に長い時間を意味すると何の根拠もなしに―聖句の根拠なしに(!)―、考えている。しかし、そのように理解するのは誤りである。何故なら、これはその期間における内容の十全性を表示する言葉に過ぎず、実際の期間を表示した言葉ではないからである。すなわち、『千年』とは完全数「10」の3乗であるが、聖書において「3」とは強調また証明を意味しているから、10の3乗年である『千年』とは、つまり「あまりにも完全」また「十全過ぎて少しの欠けもない」という意味になる。アウグスティヌスも「千という数は完全性を表す」(『アウグスティヌス著作集20/Ⅰ 詩篇註解(5)』詩篇104篇 p200:教文館)と言っている。その理由は「10の正方数は10の10倍であり、その10倍が千になるからである。」(同)と彼は言っている。このアウグスティヌスも千を10の3乗という成り立ちとして考えていたわけである。つまり、ここで御使いがサタンを『千年の間縛っ』たと言われているのは、サタンが42か月の間完全に無力化された、ということである。要するに、ここではサタンが完全に無力化されたということを、『千年』という象徴的な言葉により強調しているのだ。20章と対応している12章の中でも、この期間が過ぎるまではサタンが教会に対して完全に無力化される、と教えられている(12:13~16)。カルヴァンも、どうやらこの期間は非常に長い時間を表示しているのだと何の根拠もなしに考えていたようである。彼は『千年』の期間を文字通り「1000年」として規定している者たちを激しく批判している(※)。カルヴァンはその者たちが「千年を文字通りの千年として限定している。」と憤っている。これは、彼が『千年』という言葉を、千年以上の長い期間であると理解していた証拠である。それというのも、もし千年が長い期間だと理解していなければ、どうして千年を文字通りに規定する者たちに対して「千年に限定している。」などと批判をするのであろうか。つまり、彼は「千年を文字通りに規定するというのは何事か。それは文字通りの1000年として捉えるべきではなく、もっと長い年数として捉えるべきだ。それは<教会がなお地上で労する間>の期間を指しているのだから。」と言いたかったのである。中世においては、この期間を文字通りに捉えていた人たちが多かった。だから、西暦1000年頃の人たちは、遂に千年の期間が終わるなどと本気で考え、大いに慌てたものであった。その時に彼らは「世界の終末が遂に来る。」などと言って動揺し、中には絶望のあまり自殺する人さえいたほどである。私は言うが、この『千年』を非常に長い期間であると解するのは完全な間違いである。何故ならば、この期間を非常に長い期間であると考える見解には、聖句の根拠が何もないからだ。もし聖句の根拠があるというのであれば、それを私に示していただきたい。示せるものなら示せ。さあ、出来るのか。出来るのならばやってみよ!誰も出来ない。それどころか「この期間を規定する聖書の他の箇所は存在しない。」などとさえ言う始末である。実際、私は千年が長いと言いながらも、その根拠としての聖句を提示している人を誰も見たことがない。カルヴァンさえも、どうして千年が長いと言えるのか、聖句を根拠として説明していない。あれほど聖書の意味は聖句をこそ根拠として導き出されねばならない、と言っていた彼がである。つまり誰も彼も、ただ感覚的にそう思えるからというので「千年は長い」と思ったり言ったりしているに過ぎないのである。このように千年を長い期間だとする見解は、聖書に基づいた見解では全くない。それは人間理性に基づいた見解である。そんな見解にどうして信頼できるのか。私は、聖句の根拠なしにこの期間が長いと主張して堂々としている人たちが、よく理解できない。「どうして根拠もないのにこんな大胆になれるのか。」などと思わされるものである。それは藁で造られた台の上に立つようなものである。その台の上にシッカリ立とうとしても、すぐにフワフワと潰れてしまうので堅固に立脚できないのである。しかし、私の見解には聖句の根拠がある。すなわち、20章で言われている『千年』という期間は、12章で言われている『1260日』また『一時と二時と半時』という期間と、まったく同一の期間である。この12章の聖句こそが、『千年』という期間における私の見解の堅固な根拠である。よく聞いてほしい。12章と20章では、とちらも聖徒の復活が起きてからサタンが聖徒たちと戦おうとして『海辺の砂』(12:18、20:8)のごときローマ軍を動員させるまでの間には一定の期間があると教えられている。その一定の期間とは、12章のほうでは『1260日』(12:6)また『一時と二時と半時』(12:14)と言われており、20章のほうでは『千年』と言われている。つまり、『1260日』また『一時と二時と半時』=『千年』である。このうち、『千年』という言葉はその期間における内容の十全性を表示しており、『1260日』という言葉はその期間の実際的な年月を表示しており、『一時と二時と半時』という言葉はその期間の短さを表示している。このことから、『千年』という言葉は、その期間の具体的な年月を表示した言葉ではないことが分かる。これは単にその期間における「内容の質」を言ったものに過ぎない。それゆえ『千年』という期間は、実際的な年月としては『1260日』であったのだから、それは非常に短い期間だったことになるのだ。ここにおいて、千年を長い期間だと根拠もなしに主張する人たちの見解は完全に粉砕される。何故なら、その人たちは千年という期間を聖句の根拠と共に論じられないのに対し、私はシッカリと聖句の根拠と共に論じられるからである。私からすれば、千年を根拠なしに長い期間だと主張する人たちは、ちょうど聖餐論を何も聖句の根拠なしに論じていたカールシュタットのように見える。この愚か者は、聖句の根拠によらず自分の感覚に基づいて聖餐論を論じていたので、ルターからこっぴどく非難されたのであった(参照:「キリストの聖餐について」)。私に対して千年は長いなどと言って立ち向かう人たちは、正にルターに反発して喚き散らしていたカールシュタットも同然である。なお、私は今述べた見解を、イザヤ24:21~22の箇所からも証明することが出来る。千年が非常に長いと主張する者たちは、一つも明白な根拠を聖句から示せない。しかし私は2つも根拠聖句を示すことが出来る。要するに私の見解は完全・盤石なのである。これでは千年が長いと考えている者たちの敗北は明らかである。従って、千年が長いなどと根拠も示せずに主張する者たちは、御言葉にあって私とその見解を恐れるべきである。何故なら、私は本作品の中で御言葉にあって自分の見解を証明しているからである。私とその見解を恐れないというのは、つまり御言葉を恐れていないということでなくて何であろうか。このイザヤ書のほうについては、すぐ後ほど説明されることになる。
(※)
「…その後まもなく千年王国論者が続き、キリストの王国を千年に限定した。彼らの思いつきは子どもじみていて、反駁の必要もないほど無価値なものである。その誤謬を格好づけるために引かれた黙示録も、彼らを助ける証拠にならない。千年という数字(黙示録20:4)は教会の永遠の至福に関するものではなく、教会がなお地上で労する間に翻弄される様々の出来事を言うに過ぎない。これに対して全聖書は、選ばれた者の祝福にも遺棄された者の刑罰にも終わりはないのだと叫んでいる。ところで、我々の目には捉えられず我々の精神能力をも遥かに超える全ての事物については、信仰は神の確かな託宣によって達しようとするか、もしくは全く拒絶するしかない。来たるべきべき生の嗣業を神の子らが享受する期間として千年しか割り当てない者は、キリストとその王国にいかなる侮辱を加えているかに気づいていない。」(『キリスト教綱要 改訳版 第3篇』第3篇 第25章 第5節 p512~513:新教出版社)
[本文に戻る]
ここまで読み進められた聖徒たちに私は言いたい。20章と12章における同一性に気付くことが出来たであろうか、と。気付けた人は幸いである。その人は神からの恵みを受けている。しかし気付けない人は不幸である。神の恵みを受けていなからである。私は、まだ気付けていない人に、特に言おう。まず黙示録は、順序通りに話が進められている文書ではない。例えば、この文書の中では6:14の箇所で山と島が除かれたと書かれているのに、かなり後の箇所である16:20でも同様に山と島が消え去ったと書かれている。更に、この2つの箇所で言われていることは、その言われている言葉こそ違えど、20:11の箇所でも再び言われている。また6:1~2の箇所ではキリストの再臨のことが書かれているが、それは19:11~21の箇所でも再び言われている。これだけでも、黙示録が順序通りに記されたのではないのだと理解できる。何故なら、もし本当に順序通りに書かれているとすれば、どうして前の箇所に書かれていたのと同様の出来事が、再び後の箇所で繰り返して書かれているのか説明がつかないからである。もし順序通りに書かれていたとすれば、既に1回でも語られたことは、もう再び語られることは無かったはずである。創世記1章で語られた創造の詳しい描写が、もはや創世記における後の箇所では再び繰り返して書かれることが無かったように。しかし、黙示録ではそのようにはなっていない。そこでは、創世記1章で書かれていた出来事が、23章にも45章にも再び書かれている(これはあくまでも創世記の場合で言えば、の話である)。それだから、20章と12章という2つの箇所が対応していたとしても何も不思議なことはない。それゆえ、まだ悟りを得られていない聖徒は、20章で書かれている『千年』は12章で書かれている『1260日』であったという見解を受け入れるべきである。繰り返そう。『千年』=『1260日』である。黙示録が創世記のように順序通りに書かれている文書だと考えては駄目である。そんな理解を持っていれば、黙示録の仕組みがまったく分からないままとなる。それでは20章と12章が同一の出来事を述べているということも分からないままである。そうなると、『千年』がすなわち『1260日』だということも分からなくなる。
よくよく考えてみれば分かると思うが、『千年』というこれだけ聖徒の心を夢中にさせ動揺させ混乱させる言葉に、神が聖書の中で何の手掛かりも備えられなかったということは有り得ない。「この秘儀的な期間の手掛かりとなる箇所は聖書に存在しない。」だと!そんなことがあるはずないであろう。もしこの言葉に何の手掛かりも無かったとすれば、神は嫌がらせを聖徒にしておられるということになる。それは神の聖徒に対する憎しみである。しかし、そのようなことは無かった。何故なら、『神は愛』であり『愛は親切』だからである。親切なる愛そのものである神が、このような是非とも知るべき秘儀的な言葉の手掛かりを何も聖書の中に置かれなかったというのは、神が慈しみ深い存在でないと考えるのも同然である。もしそのようなことであれば、神は聖徒たちを愛してはおられなかったのだ、と言わねばならなくなる。何故なら、これだけ聖徒を悩ませ混乱させる言葉をヨハネを通して書いておきながら、ただ悩ませ混乱させるだけに留めさせ、どれだけ聖書の中を探し求めても絶対に手掛かりが見つからないようにさせたからである。これは一種の拷問に等しい。「一体この言葉はどういう意味なのであろう。他の箇所に何か助けとなる聖句はないものか。」と聖徒が聖書の中を探求するようにさせながら、「探したって無駄だ。」などという気持ちに基づいて答えをどこにも置いていないからである。全ての聖徒たちは、今までこの期間の手掛かりが聖書の他の箇所には存在しないと考えてきたが、それは黙示録を何も研究しなかったからである。黙示録を研究しないのであれば、この期間の手掛かりが聖書の他の箇所には存在しないと判断したとしても、何も不思議ではない。というのも、この期間の手掛かりは黙示録の中にだけ存在しているからである。今や、この期間には手掛かりが存在することが、シッカリと証明された。慈しみ深い神は、この期間がどのような意味なのか分かるように、黙示録の中に手掛かりを用意して下さっておられた。その手掛かりが、今私を通して、この註解の中で指し示された。それだから聖書信仰に立つ聖徒たちは、私が述べた見解を受け入れ、この『千年』という期間の意味を正しく捉えるようにすべきである。
この『千年』という言葉の原文χιλια ’ετη(a southand years)には何も問題がない(※)。これは13:18の『666』のように別の言葉(616)が書かれている写本が存在しているとか、複数の意味に解せるということもない。これは「千年」という言葉にしか解せないギリシャ語である。それゆえ、この『千年』という言葉を原文から考察したとしても特に意味はない。これはあくまでも補足的なことだが、気になる人もいるかと思い、今ここで短く取り扱っておいた。
(※)
χιλια(キリア):1000
’ετη (エーテ):年
[本文に戻る]
【20:3】
『底知れぬ所に投げ込んで、』
御使いが鎖で縛ったサタンを『底知れぬ所に投げ込ん』だのは、サタンを完全に無力化するためであった。サタンがそこに投げ込まれるのは神の定めであったから、サタンは抵抗することが出来なかった。この箇所で言われている『底知れぬ所』は、イザヤ24:22の箇所では『地下牢』また『牢獄』と言われている。これも、やはりサタンが完全に無力化されることについて言っている。それというのも、『地下牢』とか『牢獄』という場所は、動きを封じるためにあるものだからである。先にも述べたが、確かにこの20章および12章の箇所はイザヤ24:21~22の箇所と対応している。20章および12章とイザヤ24:21~22は、まったく同じ出来事について語られている。すなわち、再臨の際に天の場所でサタンが敗北した後、幾らかの間、封じられて無力化される、ということがこれら3つの箇所では言われている。これはこれら3つの箇所を読み比べれば一目瞭然である。さて、20章で言われているサタンの封じられる『千年』という期間は、イザヤ24:22の箇所では『何年か』と言われている。『何年か』とは、どう考えても長大な時間を意味するのではない。それは比較的短いと感じられる期間である、というのは誰でも理解できるはずだ。もし『千年』が1000年以上もの長い年月だったとすれば、イザヤ書のほうでは『何年か』などとは言われていなかったであろう。その場合、イザヤ24章では例えば「かなりの期間」とか「数千年」などと言われていたはずである。この『何年か』という言葉は、実際的な期間において言えば、明らかに『千年』という言葉には適合しておらず、むしろ『1260日』また『一時と二時と半時』という言葉のほうに適合している。健全な理性を持っていれば、これは決して疑えない。何故なら一体どこの誰が『何年か』という期間を、『1260日』また『一時と二時と半時』ではなく、むしろ文字通りの『千年』また『千年』以上の期間だと見做すのであろうか。そのような人がいたとすれば、精神がどうかしていると思われても仕方がない。従って、確かに『千年』という期間は、実際的な期間としては短い期間、すなわち『何年か』と言うべき期間に過ぎなかったことが分かるのである。ここにおいて、千年は長いなどと根拠も無しに主張する者たちの見解は、更に打ち砕かれることになる。何故なら、私は既に論証した自分の見解を今、更にイザヤ書を根拠としつつ論証したからである。このように私は聖句から根拠を示せるのだから、千年が長いなどと考える者たちが誤っていることは確かである。それゆえ千年が長いと言う者たちは、悔い改め、私が述べた見解を受け入れるがよい。もし私がこのような説明をしたのに頑なな心のままで自分の見解を捨てないというのであれば、その人の見解が正しいということを、私が今したように聖句を根拠としつつ明白に論じてもらおうではないか。私が求めているのは、「こじつけ」の論証ではなく、誰がどう考えても聖句を根拠としているとしか考えられない明白な論証である。私はそのような論証を黙示録12章とイザヤ24章に基づいて行なったが、千年が長いと勘違いしている者たちがそのような論証をすることは絶対に出来ないはずである。よって、ここにおいて私とその見解は勝利したことになるのだ。聖徒たちは聖句を根拠としていない不確かな見解を受け入れるな。そうではなく、聖句を根拠としている確かな見解をこそ受け入れよ。さて、ここでサタンが『底知れぬ所に投げ込』まれたと言われているのは、確かにサタンが完全に無力化されることであった。これは場所に関して言われているというよりは、むしろサタンの行動面に関して言われているものだと捉えるべきである。何故なら、ここでヨハネが言いたいのは場所というよりは、サタンの状態についてのことだからである。
『そこを閉じ、』
御使いは、底知れぬ所に投げ込まれたサタンが、そこから出て来れないように『そこを閉じ』た。これはサタンを無力化させるためであった。つまり、そこを閉じないとサタンが出てきて自由に活動しかねないので出て来れないようにシッカリと閉じた、というわけである。ところで、御使いの持っていた『底知れぬ所のかぎ』(20:1)は、この場所を閉じるために使われたのであろうか。私はそのようには考えない。私はこう考える。すなわち、その『かぎ』は『底知れぬ所』を閉じるために使われたのではなく、すぐ次の部分で言われているように『封印』するためにこそ使われたのだと。つまり、ここで言われているのは単に『底知れぬ所』の扉が閉められただけに過ぎないということである。この閉じた時に『かぎ』が使用されたと捉えるのは難しいと思われる。というのも『閉じ』るだけなら、鍵などなくても出来るからである。鍵とは封印するためにこそあるのだから、御使いの持っていた鍵は『底知れぬ所』を『封印』するためにこそ使われたのだと捉えるべきであろう。もっとも、私はこの鍵が閉じるために使われたと捉える人と言い争そうとは思わない。この問題は激しく言い争うような大きい問題ではないからである。
『その上に封印して、』
御使いは、サタンを『底知れぬ所』に投げ込んで、そこを閉じた後、『底知れぬ所のかぎ』を使って『封印し』た。サタンは捉えられ、縛られ、牢獄の中に入れられ、そこを閉じられた上、そこが封じられてしまうことにさえなった。我々は、ここまでサタンの無力化について強く語られていることを、よく注意すべきである。これは、つまりサタンの無力化が完全だったことを示している。その無力化が完全だったからこそ、『千年の間』サタンは封じられたと言われているのだ。しかし、サタンが封印されるのは『1260日』の間だけであった。その期間が終わると、封印が解除され、また再び教会に対して活動し始めるようになった。その出来事が、後ほど註解される20:7以降の箇所で語られている。
ある者らは、サタンが千年の間封じられている期間においても教会に害を与えられる、などと考えている。この期間においてサタンは犬のように鎖に繋がれているので、その鎖が伸びる範囲までは活動が出来るのであって、それゆえ教会に損害を加えることが出来ると。これは大変素晴らしい理解である。一体どう考えればサタンが、この期間において教会に害を加えられると思えるのか。20:1~3の箇所で言われているのは、千年の期間においてサタンは完全に無力となる、ということである。もしこの期間にもサタンが教会に害を加えられるというのであれば、それは最早『千年』の期間ではない。それというのは、そのようなことであれば、それは完全数10の3乗で示される『千年』の間サタンが封じられているとは言えなくなるからである。サタンが相も変わらず教会に害を加えられるというのに、『千年』つまり完全に封じられているとでもいうのか。この者たちが、千年の間にもサタンが教会に攻撃を加えてダメージを負わせられると考えているのは、本当にふざけている。彼らは、この20:1~3の箇所で、捕えられた、縛られた、底知れぬ所に投げ込まれた、閉じられた、封印された、千年の間、と言われていることが、よく理解できていないようである。このように言う彼らは、黙示録を何も理解できていない。だから、黙示録の聖句を詳しく解き明かすこともしていない。理解していないのだから、詳しく解き明かせないのは自然なことである。もし理解していたとすれば、私が神の恵みによりこの作品でしているように、詳しく解き明かせるはずなのだ。しかし彼らは、そのようなことはしていない。本当は理解しているが、あえて解き明かしていないだけ、というのではない。それというのも、彼らはもし理解していれば、必ずその理解していることを語るような者たちだからである。私は彼らのことをよく知っているのである。だから、かつて私が彼らの書いたものを読んでいた時、私は「黙示録のことを何も理解できていないのだな。」といつも思わされていたものである。また残念なことだが、どうやらカルヴァンも千年の期間には、サタンが封印されながらも教会を害せると理解していたようである。これでは、あたかもサタンが捕らえられておらず、縛られておらず、底知れぬ所に投げ込まれてもおらず、そこが閉じられてもおらず、封印されてもおらず、何だか『千年』の間、無力化されているのではないかのようである。カルヴァンも、やはり黙示録を何も理解できていなかった。だから黙示録については何も語ることが出来ていない。もし理解していたとしたら、私のように大いに語ることが出来ていたであろう。読者たちは、千年の期間にサタンが教会に打撃を加えられるなどとは考えないようにしてほしい。
『千年の終わるまでは、』
『千年の終わる』時とは、いつか。それは、ローマ軍がエルサレムを包囲するようになる時までである(20:9)。何故なら、『千年の終わる』時が到来するとサタンが解き放され(20:7)、その解き放されたサタンがローマ軍を動かしてエルサレムを包囲させるようにするからである。このことからも、千年は非常に短いという私の見解を証明することが出来る。それは、サタンが封じられて千年が始まってから(20:1~3)、千年が終わってエルサレムが包囲されるまでの期間は(20:7~)、非常に短いからである。その期間の終焉日時を決定するのは難しいが、2年3か月以内だったことは間違いない。何故なら、キリストの再臨が起きた紀元68年6月9日に千年の期間が開始され、その2年3か月後である紀元70年9月にエルサレムが完全崩壊させられたからである。どうであろうか。これは正に『千年』が『一時と二時と半時』の期間しかないということである。だから確かに『千年』という期間は短かったのである。
この『千年の終わる』時が未だに訪れていない、と考えている聖徒は多い。ほとんど全ての聖徒がそうであろう。彼らは、千年がまだ来ていないと信じているにせよ今が千年の時代であると信じているにせよ―信じていると言っても『千年』について述べている黙示録を何も理解していないのだが―、まだ20:7以降の箇所で記されている出来事が実現していないと考える点で共通している。つまり、彼らは未だに黙示録が完全に成就したとは考えていない。このような聖徒たちに、私は問いたいのである。①黙示録で書かれている出来事は、『すぐに起こるはずの事』(1:1)だったのではないのか。まだ黙示録の出来事が起きていないというのであれば、それらの出来事が『すぐに起こる』と言われた神は嘘を付かれたことにならないか。②20:9で書かれている『愛された都』が取り囲まれたという出来事は、ユダヤ戦争の際にエルサレムがローマ軍に包囲されることを言ったものではないのか。もしそうでなければ、これは何だというのか(※)。③黙示録の内容を十分に理解しているのか。もし理解していないのであれば、どうして理解できるように神に祈り求めないのか。どうせ理解できやしない、などと思うのは不信仰ではないのか。④私がこれまで神の恵みにより書いてきた註解の内容を受け入れようとしないのか。黙示録を正しく理解できるようにと、いつも私が信仰の祈りを捧げていることを知らないのか。ほとんど全ての聖徒は、これら4つの問いに毅然とした態度で答えられないはずである。もし堂々と答えられないというのであれば、私の述べた見解を受け入れるべきであろう。何故なら、堂々と答えられないというのは、つまり私の言ったことが正しいということを示しているからだ。ツヴィングリやエコランパディウスも、マールブルグの宗教会議においてルターから正論を言われると答えられずに沈黙してしまった、とオジアンダーは報告している。正しい意見や見解に対し、人は堂々と答えられないものなのだ。何故なら、真理や真実や理に適った意見といったものは、それ自体において非常に力があるから。もし私の問いや見解に沈黙させられてしまうにもかかわらず、あくまでも自分の誤謬のうちに留まり続けるというのであれば、その人はただでは済まず、やがて神からの霊的な裁きを受けることになるのを覚悟せねばならない。
(※)
ある人は、私がこれはエルサレム包囲のことだと言うと、一切このことに触れず、その場をやり抜けた。何も答えられなかったのである。確かに、これはエルサレムが包囲された出来事以外ではあり得ない。何故なら、普通に考えたら、これはあの包囲の出来事だと捉えるしかないからである。
[本文に戻る]
『それが諸国の民を惑わすことのないようにした。』
『諸国の民』とは誰か。これは「ローマ軍」である。何故なら、この『諸国の民』は20:9によれば『愛された都』であるエルサレムを『取り囲んだ』からである。『すぐに起こるはずの事』(1:1)であるエルサレム包囲の出来事(20:9)を実現させた『諸国の民』(20:3、8)について、考えるとどうであろうか。そのような存在はローマ軍しかいないのである。だから、この『諸国の民』はローマの兵士たちだったと考えなければいけない。実際、歴史が教えるように彼らはエルサレムを包囲したのである。どうして彼らが『諸国の民』と呼ばれているかという理由については、後ほど書かれる20:8の註解で説明したい。後ほど説明したほうが適切だからである。ひとまず今は、この『諸国の民』がローマ軍だったと理解していれば、それで問題はない。しかし、どうしてローマ軍が『諸国の民』と言われているのか一早く知りたくてならない人は、先駆けて20:8の註解を読んでしまうがよい。
それではサタンがローマ軍を『惑わす』とは何か。これは、サタンがローマ軍を突き動かしてエルサレムを包囲させる、ということである。聖書は、エルサレム包囲の出来事がサタンの霊により引き起こされたと教えている。つまり、ローマ軍がエルサレムを取り囲んだのは、彼らがサタンに惑わされて、狂暴な破壊の思いをエルサレムに対して向けたからこそ起きたのだと。確かに、神に『愛された都』(20:9)を取り囲んで滅ぼすというのは、サタンに惑わされなければ出来ないことだった。どれだけ堕落していても、それはあくまでも「神の都」だったのだから。悪い霊に動かされなければ、どうしてあのエルサレムを滅茶滅茶にしてやろうなどと思うのであろうか。実際、聖なる聖徒たちは、ローマ軍とは違ってサタンに惑わされていなかったから、エルサレムを取り囲もうとも、それを破壊しようとも思わなかった。それだから、この『惑わす』という言葉について、聖徒たちは次のように簡単に考えればよい。すなわち、「サタンがローマ軍を惑わす」=「ローマ軍がエルサレムを破壊しようとして本格的に取り囲むようになること」である。
要するに『千年』の期間とは、サタンが封じられてから、ローマ軍がエルサレムを本格的に包囲するようになるまでの、非常に短い期間である。まずサタンが封じられると千年が開始される。それはキリストの再臨された紀元68年6月9日である。そしてローマ軍がエルサレムを取り囲むようになると、千年が終わる。これは紀元68年6月9日から紀元70年9月の間の、いつかである。見てほしい。私の述べた見解は、どれだけ聖書の記述に則っていることであろうか。この見解であれば、黙示録20章をすんなりと読み解くことができる。だからこそ、ここまで豊かに論じることも出来ている。しかし、千年がまだ訪れていないと考える者たちや、今がその時代だと考えている者たちは、豊かに論じることが出来ないし、僅かばかり論じることがあっても非常にぎこちない。僅かばかり論じている者について言えば、今が千年の時代だからサタンに勝利できるなどと大胆に言いながら、時にはロスチャイルドやロックフェラーなどの金融資本家たちの陰謀に動揺して「もうサタンは牢から解放されたのか?彼らの存在こそサタンが解放された印なのか?もう何をしても駄目なのか?」などと言ったりする。一体これは何なのだ。今が千年の時代なのか。それとも、もう千年は終わったのか、または正に今終わろうとしているのか。まったく分からない。このように言っている者自身も、自分がどのように理解しているのか分かっていない。「今が千年だ」と力強く言いながら、今が千年なのかどうかさえ確固たる理解を持てていないとは!このように言う者が、理解においてさ迷っており、おかしいことを言っているのは、誰の目にも明らかである。カルヴァンは、こういう者たちについて、「神の言葉、あるいは命令をよそにして、自分だけの意見に導かれる時には、あてもなくさまようことしかできない」(『新約聖書註解Ⅲ ヨハネ福音書 上』4:22 p130:新教出版社)と言っている。確かに、このように言う者たちには、聖句の確固たる根拠が何も無いのである。それにもかかわらず、こういう者たちは、自分の理性により支えられた人間的な見解の上に、次々と新しい解釈を積み重ねている。こういう者たちについては、アウグスティヌスと共に次のように言うべきである。すなわち、「不確実なことの上に解釈を積み上げはならなない。」(『アウグスティヌス著作集20/Ⅰ 詩篇註解(5)』詩篇101篇 説教1 p26:教文館)と。聖句抜きに理性のみにより支えられた見解とは「不確実なこと」でなくて何であろうか。何も千年について論じられない人たちについて言えば、彼らは何も分かっていないからこそ、千年について何も論じることが出来ていない。こちらのほうの者について言えば、私はそれほど激しく責めるつもりはない。彼らは、黙示録の正しい見解について何も聞いていないからこそ、千年について何も知らないのだからだ。一方は間違ったことを語り、一方は何も語っていないが、どちらも千年をよく理解できていないという点では共通している。私はと言えば、黙示録の一節一節の箇所を、日々の研究に基づいてジックリと豊かに論じており、ここまで緻密に黙示録を論じた者はかつていなかったのではないかと思われる(もちろんそのように出来ているのはただ神の恵みによる)。これでは一体誰が黙示録について正しいことを言っているのか明白であろう。
未だにサタンが『諸国の民を惑わす』時が訪れていないと考えるのは、完全な誤りである。というのも、サタンが諸国の民を惑わすという出来事も含めて、黙示録に書かれている出来事は『すぐに起こるはずの事』なのだから。まさか、神の御言葉が偽りを述べているなどと考えるのか。まともな聖徒であれば、そのように考える人はいないだろうと思う。また、まだサタンが諸国の民を惑わしていないというのであれば、諸国の民がサタンに動かされて『愛された都』(20:9)を取り囲むというのは何を言っているのか。そもそも『愛された都』とは何のことなのか。これはエルサレムという都がローマ軍に取り囲まれることでなくて何であろうか。また、今が千年の時代だから『諸国の民』は惑わされないと考えている者たちについて言えば、彼らはまったくおかしなことを言っている。というのも、今の世の中を見れば、多くの国々の民がサタンに惑わされているのは火を見るよりも明らかだからである。もし今が千年の時代だとすれば、実に多くの人たちがサタンに惑わされて異常になっていることは説明がつかない。何故なら、その期間においてはサタンが完全に封じられているはずだからだ。今の時代に蔓延っている無神論・進化論・ビッグバン宇宙論・偽りの宗教や間違った諸々の思想および哲学の存在は、サタンの惑わし以外でなくて何なのか。繰り返すが、サタンが『諸国の民を惑わす』とは、すなわちローマ軍がサタンに動かされてエルサレムを破壊しようとする、ということに他ならない。私のこの註解を読んだ聖徒は、悔い改めて自分の見解を新たにすべきである。何故なら、ここで私は聖書の内容を聖書的に解き明かしているからである。それゆえ、もしこの惑わしの出来事がローマ軍について言われたものだと理解しないのであれば、その人は真理を受け入れなかったのだから、惑わしの霊が送られて黙示録をいつまで経っても理解できないようにと裁かれるであろう。
ところで、サタンが『諸国の民を惑わす』というのは、主なる神の御心に適ったことであった。何故なら、神は、ユダヤを裁こうとしておられたからである。神はそのユダヤの裁きを、サタンがローマ軍を惑わすことにより、そして惑わされたローマ軍がエルサレムを攻撃することにより、下そうとされたわけである。だからこそ、神はサタンがローマ軍を惑わすことに許可を出されたのである。もし神がユダヤを裁こうとしておられなければ、サタンの惑わしに許可が出されることも、ローマ軍がエルサレムを攻撃することも、無かったはずである。もちろん、だからといって、エルサレムが破壊されたことの悪を神に帰してはいけない。確かにローマ軍たちは悪しき心を持ってエルサレムを破壊した。だが、神はただユダヤに対する報復のために、サタンを通してローマ軍が野蛮なことをするようにさせた。つまり神は正義の復讐のためにこそ、この出来事を起こされた。神は何も悪を目的として事を実現させられたのではないのだ。だから、神がサタンにローマ軍を惑わすようにされたことで、神を責めることは許されない。この神の御心と許可の事柄については、既に17:17の註解でも私は説明しておいた。
『サタンは、そのあとでしばらくの間、解き放されなければならない。』
サタンが解き放されるのは、既に述べたように、ローマ軍を惑わし突き動かさせて、エルサレムを破壊させるようにするためであった。サタンが解き放されるまでは、まだローマ軍が惑わされることもないので、エルサレムが本格的に包囲されることもなかった。
サタンが解放されてから起こる出来事は、20:7~10の箇所で記されている。
【20:4】
『また私は、多くの座を見た。彼らはその上にすわった。そしてさばきを行なう権威が彼らに与えられた。』
『多くの座』とは、天にあり、裁きを執行する者たちが座る椅子また場所である。これは地上に置かれているものではない。この時、遂にサタンとユダヤ人と異邦人という3種類の者たちに対して裁きが下されることになった。この『座』が、再臨の時に天に現れたのか、それともそれよりも前に既に天に存在していたのかは定かではない。とはいっても、このようなことは、たとえ知らなくても何も問題にはならない。何故なら、ここでは座が現われた時のことについて取り扱われているのではないからだ。また、この『座』がどのような外形だったかということも、何も知らなくて問題ない。何故なら、それは本質的な事柄ではないからである。
『彼ら』とはどの者たちのことか。これは、19:19で言われていた『馬に乗った方とその軍勢』を指す。というのは、前の文章を遡って見ると、それ以外には考えられないからである。これが19:17で言われていた太陽の中に立つ『御使い』だったと考えることはできない。何故なら、この御使いは『ひとり』だったからだ。我々が今見ている箇所では、『彼ら』が『多くの座』に座ると書かれている。この御使いは『彼ら』ではないし、複数の存在ではないから『多くの座』に座るという表現も適合していないのである。この『彼ら』であるキリストとキリストに付き従う聖徒たちは、座に着いた後、サタンとユダヤ人と異邦人を裁くことになった。この座に着いた者たちは、実に多かった。何故なら、エノクが預言したように、再臨の際に天からやって来る聖徒たちは『千万』(ユダ14節)だったからである。この座に着いた者の中には、エノクやノアやアブラハムやモーセやダビデやエリヤもいた。12人の族長や数々の預言者たちもいた。また彼らは、例外なく誰でも御霊の身体を持っていた。何故なら、天上にいた魂だけの状態だった聖徒たちは、再臨が起こる際に御霊の身体を付与されて復活したからである。
この天から降りて来た聖徒たちによる『さばき』とは、どのようなものだったか。それは霊的な裁きであった。何故なら、それは『鋭い剣』(19:15)で打つという裁きだったからである。これは御言葉という剣で霊的な断罪を下すことでなくて何であろうか。それは実際的な損害を与えるものではなかった。実際、再臨が起きた際、サタンとユダヤ人と異邦人らには、実際的なダメージは何ももたらされなかった。例えば、巨人たちのように大洪水に飲み込まれたり、コラたちのように地面の中に落とされたり、ゴリアテのように撃ち殺されたりするということはなかった。それでは、その霊的な裁きとは具体的にはどのようなものだったか。それは、こういう裁きである。すなわち、天上で魂だけの状態だった聖徒たちが御言葉において復活して降りてくる、という現象そのものが霊的な断罪であった。天上の聖徒たちは御言葉の約束により遂に復活したわけだが、それが霊的な裁きとして働いたのである。というのも、天上の聖徒たちは御言葉において復活したから勝利したのに対し、地上にいる3種類の者たちは御言葉の恵みに与れなかったから復活できず、それゆえ天上の聖徒たちに対して敗北したことになるからである。これこそ正に御言葉において霊的に裁かれるということであった。これは例えるならば、カンニングを常習的に犯しているライバルを何とかして見下したいと思っている受験生のようなものである。この受験生は、ライバルを蹴落とすべく、トップの点数で受験を突破しようと考えた。後日、この受験生はトップの点数で受験を突破したが、ライバルはといえばカンニングをしたことが明るみに出て、受験に失敗してしまった。ここにおいて受験生は、自分の勝利を感じて喜び笑い、大いに満悦した。一方ライバルのほうは、その受験生と自分の対比において大いなる屈辱感を味わわされ、敗北を認めざるを得なかった。これは結果において受験生が自分のライバルを断罪し敗北させたと言ってよい出来事である。再臨の際に起きた裁きも、これと似たようなものである。地上にいたサタンとユダヤ人と異邦人らは、天上からやって来た御言葉における勝利者たちを見て、その結果において断罪され敗北させられたのである。
この裁きの出来事は、次に示す箇所で言われていたことである。マタイ19:28。『イエスは彼らに言われた。「まことに、あなたがたに告げます。世が改まって人の子がその栄光の座に着く時、わたしに従って来たあなたがたも12の座に着いて、イスラエルの12の部族をさばくのです。』―これは使徒たちが、復活して携挙された後、ユダヤ人たちを霊的に断罪するということである。Ⅰコリント6:2~3。『あなたがたは、聖徒が世界をさばくようになることを知らないのですか。…私たちは御使いをもさばくべき者だということを、知らないのですか。』―これは紀元1世紀の聖徒たちが、復活した後、サタンと異邦人たちを霊的に裁くということである。ここで言われている直接的な対象者はもちろんコリントの聖徒たちだが、それがコリントの聖徒たちだけに限られるのではないことは言うまでもない。黙示録2:26~27。『勝利を得る者、また最後までわたしのわざを守る者には、諸国の民を支配する権威を与えよう。彼は、鉄の杖をもって土の器を打ち砕くようにして彼らを治める。』―これも、やはり紀元1世紀の聖徒たちが復活した後で、異邦人たちを御言葉において罰するということである。彼らが罰を与えるのは、すなわち『千年』の期間の出来事だから、既に説明されたように『一時と二時と半時』である。だからこそ、ここでは『鉄の杖をもって土の器を打ち砕くようにして』と言われているのだ。土の器を打ち砕くのは、通常の場合、非常に短い期間しか要しない行為だから。『一時と二時と半時』とは、非常に短い期間を意味する言葉である。ローマ16:20。『平和の神は、すみやかに、あなたがたの足でサタンを踏み砕いてくださいます。』―これは紀元1世紀の聖徒たちが復活して空中に挙げられることにより、聖徒たちがその携挙の出来事において、高みからサタンを己の足の下に踏み置くということである。
『また私は、イエスのあかしと神のことばとのゆえに首をはねられた人たちのたましいと、獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。』
まず『イエスのあかしと神のことばとのゆえに首をはねられた人たちのたましい』とは、キリストを実体において信じた殉教者たちの魂のことである。彼らの魂は、死んだ後で天に挙げられることはなく、地上において自分の死んだ肉体と共に留め置かれていた。それというのも、彼らの魂は地上において復活するからである。パウロがⅠテサロニケ4:16の箇所で言った復活する聖徒たちとは、この者たちのことを言っている。一方、キリストを影において信じていた殉教者たちの魂は、死んだ後で地上に残されることなくハデスへと移されていた。そしてキリストが昇天されると同時に、ハデスから引き上げられて天の場所に移されることになった。天に置かれたこの魂は、天に置かれているゆえ地上で復活することはなかった。何故なら、彼らは天の場所で復活するのだからである。だから、パウロがⅠテサロニケ4:16の箇所で言っている復活する聖徒たちとは、この者たちのことではない。パウロは地上で復活する聖徒たちのことを言っているからだ。それゆえ、我々が今見ている箇所で言われている『イエスのあかしと神のことばとのゆえに首をはねられた人たちのたましい』とは、キリストを影において信じていた殉教者たちの魂のことではない。それは地上に置かれている地上で復活するようにと定められていた魂のことだからである。
次に『獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たち』とは、ネロの前に屈服してキリストを否むということをしなかった紀元1世紀の生きた聖徒たちである。この人たちは、先に見た人たちとは違い、殺されてはいない。何故なら、この人たちについては『首をはねられた』つまり殺された、とは書かれていないからである。『獣やその像』とは、どちらもネロを言っている。すなわち、『獣』とはネロそのもののことであり、『その像』とはティゲリヌスに媚びへつらわれる存在としてのネロのことである。ネロとその像について、まだ理解が足りていない人は、13章の註解に再び立ち戻ってほしい。当然ながら、この人たちも、地上にいる人たちである。それは天上にいる人たちではない。何故なら、この部分では地上にいる人たちのことが言われているのだから。
この2つの者たちは一体どうなったのか。ヨハネはこう言っている。
『彼らは生き返って、キリストとともに、千年の間王となった。』
これは『第一の復活』のことである。ここで言われている2種類の人のうち、『イエスのあかしと神のことばとのゆえに首をはねられた人たち』は地上において死体の状態から復活し(Ⅰテサロニケ4:16)、『獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たち』は地上において生きながらにして『たちまち、一瞬のうちに』(Ⅰコリント15章52節)御霊の身体に切り替えられて復活した。この第一の復活は、パウロもⅠテサロニケ4:16~17の箇所で言っているように、紀元1世紀の聖徒たちが『生き残っている』間に起きた。この復活の出来事は、次の箇所と対応している。すなわち、Ⅰテサロニケ4:16~17、Ⅰコリント15:51~52、ヨハネ6:39、40、44、54、黙示録11:11、12:5である。なお、ここで言われている復活は、地上における復活であるという点に注意すべきである。ここでは天上の聖徒たちの復活が言われているのではない。
この部分では「携挙」の出来事が省かれている。また、ここでは携挙された聖徒たちが空中にある『多くの座』(20:4)に着くことについても省かれている。従って、この部分に書かれている出来事を省略抜きに言い表すとすれば、次のようになる。「彼らは生き返り、携挙され、空中の座に着き、そしてキリストと共に千年間王となった。」ヨハネは、どうして携挙と座に着くことを省いたのか。それは、この2つの出来事は、別に書かなくても自明だったからである。聖書において、自明であるがゆえ何らかの事柄が省かれている箇所は少なくない。復活した聖徒たちが携挙されるというのは、Ⅰテサロニケ4:16~17や黙示録11:11~12や12:5を見れば明らかである。携挙された聖徒たちが空中の座に着くというのは、黙示録3:21を見れば分かる。
さて、ここでは聖徒たちが第一の復活に与ってから初めて『王』になったかのように書かれているが、聖徒たちは、この第一の復活が起こるよりも前から既に王ではなかったのか。確かに、聖徒たちは、この第一の復活が起こるよりも前から王であった。それは、黙示録1:5~6や2:9を見れば明らかである。復活よりも前から聖徒が王であったことを認めない者は、聖句で言われていることを認めていないわけだから、不信仰であり傲慢である。当然ながら、この20:4の箇所を書いている時のヨハネも、ほかの聖徒たちと同様、王であった。それでは、どうしてここでは再臨の時から初めて聖徒たちが王になり始めたかのように書かれているのか。それは、こういうことである。すなわち、復活前の聖徒たちが王と言われているのはその尊厳と法的な地位についてであり、この20:4の箇所で復活後に聖徒たちが王となると言われているのは実際的な王権を行使するということである。復活前の聖徒たちは、尊厳と法的な地位においては王だったものの、実際的にはまだ王でなかったので、実際的な王権を地上世界で行使することはできなかった。しかし、復活して携挙された聖徒たちは、キリストと共に実際的な王とされたので、実際的な王権を行使できるようになった。つまり、ここで言われているのは、遂に聖徒たちが実際的な王権を持つようになった、ということである。それよりも前には、いかなる意味においても王でなかった、ということがここでは言われているではない。それだから、ここでは他の箇所と矛盾した内容のことが言われているのではない。もし他の箇所と矛盾していると思う人がいれば、その人はただこの箇所の内容を正しく理解できていないだけである。すなわち、正しく内容を理解していないからこそ、「矛盾している。」などと感じてしまうのだ。
この部分で復活の出来事について言われたのは、紀元1世紀の聖徒たちに復活を期待させるためであった。やがて復活してキリストと共に裁きを執行できるようになるというのは、当時の聖徒たちにとって、どれだけ望ましいことだったであろうか。無数の金よりも望ましかったのは言うまでもない。当時の聖徒たちには、やがて大患難が訪れることになっていたのだから、その苦しみと悲惨とに耐えるべく心が強められるべきであった。だからこそ、ここで復活の出来事が語られ、聖徒たちが復活を期待できるようにと、神はヨハネを通してお書きになられたわけである。このように言われるのを聞いて、聖徒たちが復活を期待し、ますます心を強めただろうことは想像に難くない。つまり、ここでは次のように言いたいわけである。「聖徒たちよ。あなたがたはもう間もなく復活してキリストと共に裁きを行なえるようになるのだ。だから、今しばらくの間、心を強めつつ忍耐し続けるようにしなさい。耐え忍めば報いは大きいのだから。」
【20:5】
『そのほかの死者は、千年の終わるまでは、生き返らなかった。これが第一の復活である。』
『その他の死者』とは、第一の復活では復活しなかった人たちを指す。すなわち、これは前の聖句で言われていた『イエスのあかしと神のことばとのゆえに首をはねられた人たち』ではない死亡者を指す。つまり、真のキリスト者としては死ななかった既に死んだ死亡者たちである。その人たちが、文字通りの意味で全ての人たちであったと考えてはいけない。第一の復活で復活しなかった人たち、と言っても、それは主の羊園の中で草を食べていた羊と山羊、つまり麦と独麦に限定される。すなわち、そこには狼は含まれていない。それは何故なのか。それは復活して空中の大審判に招かれる者たちは、マタイ25:31~46を見れば分かるように、羊と山羊だけだからである。マタイ13章でも、御使いにより取り集められる復活者たちは、『御国から』(13:41)すなわち主の羊園の中から、と明言されている。更にバプテスマのヨハネも、主が復活した者たちに働きかけるのは、『ご自分の脱穀場』(マタイ3章12節)においてである、と言っている。『ご自分の脱穀場』とは、主の羊園である教会でなくて何であろうか。もし『その他の死者』が文字通り全ての人たちであるとすれば、地上にいる全ての人たちが大審判を受けるために携挙されることになるが、そうだとすれば主により携挙の際には地上に残される者がいると言われたのが理解できなくなってしまう(マタイ24:40~41)。この問題については、既に第2部の中で詳しく論じておいた。それだから、この『その他の死者』に該当する人たちが、教会に無関係の者たちも含めた「全ての人たち」と考えるのは誤っている。なお、この『その他の死者』は、「第二の復活において復活する者たち」と言い換えることが出来る。
この箇所で言われているのは、第二の復活で復活する人たちは千年すなわち『1260日』が経った後に復活する、ということである。千年で表示される短い期間が過ぎるまでは、まだ第一の復活しか起こらない。つまり、この千年の期間が終わるかどうかという点が、第二の復活の指標である。すなわち、千年の期間が終わらないうちは、まだ第二の復活が起こらない。しかし千年の期間が終わると、遂に第二の復活が実現することになる。事柄は至極明瞭である。
私は今「第二の復活」という言葉を使ったが、読者の中には、この言葉の使用に否定的な人がいるかもしれない。「第二の復活」という言葉は聖書に書かれていないのだから、そのような言葉を使うのはいかがなものか、と。確かに、この言葉が文字として聖書に記されていないことは私も認める。しかし、『第一の復活』があるのであれば、それに続く「第二の復活」が存在するのは誰の目にも明白である。次の箇所(20:6)では、『第二の死』という言葉が出てくるが、この言葉から「第一の死」が存在するというのは誰でも分かるはずだ。何故なら、もし「第一の死」が無ければ、どうして『第二の死』があるのであろうか。ところが、この「第一の死」という現象は、存在するものの文字としては聖書の中に記されていないのである。もし「第一の死」の存在を認めるというのであれば、同様に「第二の復活」の存在も認めねばならないことになる。この2つの存在は、存在するのが明白なのであるから、その言葉が聖書の中に書かれてはいなくても使用して差し支えない。もし聖書に書かれていないからというので使用してはいけないというのであれば、「三位一体」や「位格」や「受肉」という言葉はどうなるのであろうか。これらの言葉は、聖書の中に書かれていないのである。
ある者らは、この「第二の復活」は未だに起きていないと考え、主張している。何故なら、その者たちは何の根拠もないまま千年という期間が非常に長いのだと理解しているからである。つまり千年という彼らの理解するところの長い期間が未だに終わっていないので、千年が終わると起きる第二の復活もまだ実現していないというわけである。このような悟りの与えられていない者たちには、千年が非常に長いことを明白に示す根拠聖句を示せ、とだけ言っておけば十分である。彼らは、千年が非常に長いと理解していながら、何も根拠となる聖句を提示することができない。実際、彼らがそのような聖句を提示しているのを私は見たことがない(もしあれば私は本作品の中でその聖句を検討していたはずだ)。それどころか、私に向かって「千年を規定する聖書の他の箇所はありません。」などと堂々と言う。彼らは、ただ単に自分がそう思うからというので、千年が非常に長いと思っているに過ぎないのだ。彼らが根拠聖句を一つも示せないのに対し、私は2つも明白極まりない根拠聖句を示した。これでは私が正しいことを言っているのは明白である。それだから、聖徒たちは彼らが考えているように千年はまだ終わっていないとか、また千年が終わっていないがゆえに第二の復活も起きていない、などと考えないようにしてほしい。既に幾度となく述べたように、それらの出来事も『すぐに起こるはずの事』(1:1)だったのである。もし第二の復活が未だに起きておらず、今が千年の時代だと言うのであれば、千年が非常に長いことを示す根拠聖句を一つでも提示してほしいものだ。私が求めているのは、こじつけに思えるものではなく、明白な根拠となる聖句である。もしそのような聖句を一つでも示すことが出来れば、私は自分の今の立場を変えることを検討してもよい。
私と私の見解に対抗した人について再び書きたい。私が、この第二の復活と千年の期間を含めて黙示録で書かれている出来事は全て『すぐに起こるはずの事』(1:1)だったと言うと、ヨハネが書いたのは『この後に起こる事』(1:19)だった、などと言って防衛する人がある。この人は千年が非常に長いと信じている人の一人である。この人は単に聖句を挙げて手短に反論したに過ぎず、何か詳しい説明をしたのではなかったが、つまりこういうふうに言いたかったのである。「ヨハネが黙示録の中で書いたのは『この後に起こる事』だったから、黙示録で書かれている出来事はずっと後の時代に起こることなのだ。すなわち、千年の記されている20:6まではすぐに起こったが、それ以降の箇所はまだ起こっていない。それゆえ、あなたが提示した『すぐに起こるはずの事』という聖句は私に何の打撃も加えない。」これは一体なんなのか。私をからかっているとでもいうのか。この1:19の箇所に書かれている『この後に起こる事』という言葉は、少し考えれば10歳の子供でも分かるように、時間の長短について言った言葉ではない。これは単に「これから未来に起こること」という意味以外ではない。すなわち、この言葉の中では「ずっと後に起こる」とか「すぐに起こる」という長いか短いかという規定は何も含まれていない。この言葉だけでは、『この後に起こる事』が「ずっと後に起こる」のか「すぐに起こる」のか、まったく分からない。私は『すぐに起こるはずの事』という時間の長短が規定された言葉を提示したのに、この人は時間の長短とは無関係な言葉を提示して私の主張を無効化させようとしたのだ。だから、この人の反論はまったく無効であり、それは意味のない反論である。そもそも、それは反論として成り立っていない。もしこの人の提示した御言葉の本文が「ずっと後に起こる事」であったとすれば、私は本当に動揺して、「これは手強い反論がなされたぞ」などと感じていたはずである。何故なら、その場合、明らかに時間の規定がされており、私の主張に真っ向から反対する内容のことが言われているからである。しかし、1:19の聖句の内容は、そのような内容ではない。見てほしい。千年が長いと理解している人たちは、こんな貧弱な反論しか出来ないのだ。もしもっと強力な反論が出来たとすれば、こんな貧弱な反論などせず、むしろ力強い反論のほうをしていたであろう。何故なら、何かを議論したり論争が起きている際には、より強力な反論をしたほうが良いに決まっているからである。しかし、この人はこんな貧弱な反論しか出来なかった。つまり、そもそも強力な反論など何も持ち合わせていなかったのである。だから、私はこのような反論めいたことが言われた際、このように思ったものである。「ああ、何も理解できていないのか…」と。彼がこの1:19の聖句を挙げて防衛しようとしたのは、鋭い大剣を振り回されて襲われたのにもかかわらず―その大剣とは黙示録1:1および22:6の聖句である―、ハンカチ一枚を盾代わりにするようなものであった。私としては、もし私に反論してたじろがせたかったのであれば、千年が長いことを証明する明白な聖句をまざまざと提示すれば良かったと思う。そうすれば私の口を封じることが出来ていたかもしれない。しかし上で述べたように、そのような聖句は何も存在していないので、この人は千年が長いことを証明する明白な聖句をまざまざと提示することが出来なかった。これで読者は私が正しい見解を述べているということを、更によく知れたのではないかと思う。私のする聖句に基づいた主張に強力な反論をする人は、未だに一人すらも現れていない。
さて、『これが第一の復活である。』という言葉は、『その他の死者は…云々』というすぐ前の部分にかかっているのではない。これが前の部分にかかっていると捉えるのは誤っている。そのように捉えると、この20:4~6の箇所を上手に解釈できなくなってしまう。理解の闇の中に陥りたくなければ、そのような捉え方をしないよう注意すべきである。『その他の死者は…云々』という部分は、言うまでもなく「第二の復活」にかかわることである。
【20:6】
『この第一の復活にあずかる者は幸いな者、聖なる者である。』
『第一の復活』を受けるのは、『幸いな者、聖なる者』つまり永遠の昔から救われるようにと選ばれていた聖徒たちだけである。つまり、悪い者たちは「第二の復活」で復活することが分かる。何故なら、『第一の復活』で聖徒たちだけしか復活しないとすれば、第二の復活では悪い者たちが復活するのは確かだからだ。この『第一の復活』で復活した復活者として確実なのは、次の人たちである。すなわち、使徒たち、福音書記者ルカ、殉教者ステパノ、ヨハネの母マリヤ、キリストの愛されたラザロとマリヤとマルタ、及びその他の人々である。イスカリオテのユダやアナニヤ夫妻は、『第一の復活』に与ることが出来なかった。彼らは主の羊園の中にいたものの、山羊すなわち毒麦だったからである。彼らは、1260日が経過すると実現される「第二の復活」の時に復活させられることになった。
「第二の復活」のほうで復活するのは、ただ悪い者たちだけに限定されない。この復活では、聖徒たちも復活の対象として含まれている。つまり、「第二の復活」とは悪者と聖徒たちが共に復活する復活である。何故そう言えるのか。それは、携挙により教会が荒野状態になってから第二の復活が起こるまでの間に、新しい信者が教会に加えられていたからである。この信者たちは12:17の箇所で『女の子孫の残りの者』と呼ばれている。携挙が起きてから新しく信者が荒野状態になった教会に加えられたというのは、11章の註解で説明した通りである。この新しい聖徒たちが、悪者たちと共に第二の復活に与り、携挙されて空中の審判に招かれただろうことは間違いない。というのも、その時に悪者だけしか第二の復活に与らなかったというのは、考えにくいからである。もちろん、第二の復活の際に復活する仕方は、悪者と聖徒とでは異なっていた。すなわち悪者は滅びの身体として復活させられるのに対し、聖徒たちは御霊の身体が付与されることにより復活させられた。この「第二の復活」は、エルサレムが破滅する時期に実現された。すなわち、それは紀元70年9月である。
『この人々に対しては、第二の死は、なんの力も持っていない。』
『第二の死』とは何か。これは、地獄における永遠の死のことである。つまり、これは単純に「地獄」と考えれば問題ない。この『第二の死』については、19:20、20:10、20:15、21:8でも記されている。キリストが毒麦どもに対して『永遠の火にはいれ。』(マタイ25章41節)と言われたのも、この『第二の死』に該当する。この『第二の死』という言葉は、黙示録だけにしか出てこない。「第一の死」は、誰でも知っている普通の死を指す。これについては説明しなくてもよいであろう。
この箇所で言われているように、『第一の復活』に与った聖徒たちは、この『第二の死』である地獄を受けることが決してない。これは当然である。何故なら、『第一の復活』により御霊の身体に復活させられた聖徒たちは、もはや永遠に損なわれないからである。この復活した聖徒たちは、当然ながら「第一の死」も受けることがない。というのは、復活した聖徒たちは既に死に打ち勝っているからである。彼らには既に、『死は勝利にのまれた。』(Ⅰコリント15章54節)という御言葉が成就している。それゆえ彼らは死を見下して言うのである。『死よ。お前の勝利はどこにあるのか。死よ。おまえのとげはどこにあるのか。』(Ⅰコリント15章55節)と。
この恐るべき『第二の死』である地獄を受けたくない聖徒は、キリスト信仰に留まり続けねばならない。第二の死を免れるのは、ただキリストに保たれ続けた者のみである。もしキリストから落ちるならば、その人は必ず第一の死を受けた後、第二の死に投げ込まれることになる。その人は、人に『第二の死』を免れさせるべく永遠の救いを実現されたイエス・キリストを捨ててしまったので、『第二の死』を受けたとしても自業自得なのである。
『彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストとともに、千年の間王となる。』
先に見た20:4の箇所では、復活した聖徒たちがキリストと共に『王となった』と書かれていたが、今度はキリストの『祭司とな』ったと言われてもいる。先の箇所では祭司になったとは書かれていなかった。
第一の復活に与った聖徒たちは、キリストと共に王になるだけでなく、キリストの『祭司』にもなった。これも20:4の箇所の場合と同じで、この時に初めて聖徒たちが祭司になったというのではなく、聖徒たちが本当に祭司としての業を行なうようになった、ということである。聖書が教えるように、聖徒たちは第一の復活に与る前から既にキリストの祭司である。この時に聖徒たちは祭司として父なる神とキリストに、裁きの願いを捧げた。神とキリストは御自身の祭司たちの祈りを聞き入れられた。そのようにして、あの3種類の者たちに霊的な断罪が注がれることになったわけである。また、この約束も、やはり当時の聖徒たちに復活を期待させる目的があった。それというのも、やがてキリストの祭司になれると約束されたのであれば、復活を期待してより忍耐強くなるだろうからである。もしこのように言われていなければ、聖徒はそれだけ復活を期待して心を強めることが出来なかったであろう。
さて、この『千年』という秘儀的な言葉は、これまで実に多くの聖徒たちを悩ませ混乱させてきた。確固たる意味が聖書から導き出せないにもかかわらず、これほどまでに関心を持たれた言葉は、恐らく聖書の中で他にはないと思われる。更に、この言葉は、たとい実際的な意味は分からなくても、何か輝かしいことが言われていると感じさせる雰囲気がある。だから、この『千年』という言葉を、名前や制作物の中に取り入れている人が世の中にはいる。もし悪い印象しかなければ取り入れられることはなかっただろうが、この言葉は悪い印象を放っていないのだ。あるプロテスタント教徒の名前は「千年」である。キリスト者の親が、この人に黙示録20章から名前を取ったのは間違いない。聖霊の言葉に逆らったある教職者の運営するサイトの名前は「ミレニアム」である。これは「千年紀」という意味の言葉であり、運営者には恐らく今こそが千年の時代に違いないと感じられたのでサイト名に取り入れられたのである。以前の私も、千年が何となく長いのではないかと感じていたので、この言葉の輝かしさに惹きつけられ、よくこの言葉を何かに取り入れたものである。例えば、暗証番号の中に、この数字「1000」を取り入れていた。しかし、聖句からこの言葉の意味が精確に理解できるようになった今は、こう思う。「この言葉を何かに取り入れるのは、とんでもないことだ。」と。というのも、この『千年』という言葉は、非常に短い期間を指す言葉だからである。この言葉を取り入れるというのは、つまり、その取り入れたものが「一時と二時と半時も経てば終わりを迎える」と言っているのも等しい。この言葉には非常に強力な肯定的意味があるのと同時に、非常に刹那である虚無的意味もあるのだ。だから、この言葉を良かれと思って何かに取り入れた人は、この言葉の真の意味を知った際、愕然とするのではないかと思う。もしこの言葉の意味を事前に知っていたとしたら、この言葉を黙示録から取ることはしなかったはずだ。いったい誰が「すぐにも過ぎ去る期間」という意味の言葉を好き好んで、自分に関わりのある事物に取り入れるのであろうか。この言葉は言い換えれば「短時間」なのである。私が述べた『千年』についての見解は、信頼に値する正しい見解である。これは嘘でも偽りでもない。何故なら私は、この『千年』がどのような意味なのか、祈りにより神に問い合わせたからである。そうしたら間もなくこの言葉の意味が分かるようになったのだ。すなわち、神が私の祈りを聞かれ、これがどういう意味なのか聖書から教えて下さったのである。それゆえ、私のこの『千年』に関する見解は絶対に正しい。よって、これまでこの言葉が長いに違いないと理解してきた聖徒たちは、私の見解に耳を傾け、自分の理解を変えるべきである。恐らく、初代教会よりも後の時代に生きた聖徒たちにおいて、この『千年』という言葉を聖書から正しく悟れたのは私が最初ではないかと思われる。これまでの聖徒たちは、誰一人としてこの言葉が『1260日』であると気付けなかった。しかし私が悟れたのは、祈ったからであり、その祈りも元はと言えば神から出たのであり、要するに全ての原因は神にある。すなわち、神が私にこの言葉を悟らせようとされたからこそ、私はこの言葉を悟ることが出来たのだ。でなければ、どうして私がこの言葉を聖句に基づいて悟ることが出来たであろうか。それゆえ、誉れと栄光と賛美は神にこそ帰されるべきである。
ということで、千年の期間についての記述がなされた箇所は、ここで終わる。
第25章 2220章7~10節:解放されたサタンとローマ軍による都の包囲/サタンとローマ軍に対する裁き
この箇所では、解放されたサタンがローマ軍にエルサレムを取り囲ませ、そうしてからサタンとローマ軍に裁きが与えられる、ということが書かれている。この20:7~10の部分は20章の中では前後の部分と区切られていないが、私は20章における現行の章区分に不満を持っていない。しかし、この註解では20:7~10の部分を前後の部分と区切っておいた。何故なら、そうしたほうが内容が把握しやすくなるからである。
この箇所も、やはり『すぐに起こるはずの事』だったという前提に立ちつつ、読み解かれるべきである。これが昔の出来事だと理解するのであれば、この箇所を読み解くのは、それほど難しくはない。何故なら、正しい前提に立ちつつ読んでいるからである。しかし、これが昔の出来事だと理解しないと、この箇所を読み解くことは永遠に出来なくなる。何故なら、この箇所で言われているのは『すぐに起こるはずの事』であり、その人はそのことを何も弁えていないからである。かの有名な日本の長編小説「源氏物語」が―これは小説としてはドン・キホーテ並みに素晴らしい―、21世紀の日本のことだと思って読む無学で無知な人がいたとすれば、どうであろうか。その人は間違ないなく今の日本を誤解してしまうはずだ。というのも、この小説は今の日本についての話ではなく、中世の頃の日本を舞台とした話だからである。前提がおかしいのだから、理解においてもおかしさが生じてしまうのは必然である。この20:7~10の部分が昔の出来事だという前提に立たないで読み解こうとする人は、源氏物語を昔の日本だとは思わずに読む人のようである。
【20:7】
『しかし千年の終わりに、サタンはその牢から解き放され、』
これは、サタンがローマ軍を惑わし、ローマ軍が遂にエルサレムを包囲する時期となった、ということである。それまでは、まだサタンが解き放されてはいなかったので、ローマ軍がエルサレムを本格的に攻撃するということは起きていなかった。この20:7~10の箇所では、20:3の箇所で『サタンは、そのあとでしばらくの間、解き放されなければならない。』と言われていたことが詳しく展開されている。
【20:8】
『地の四方にある諸国の民、すなわち、ゴグとマゴグを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを招集する。彼らの数は海べの砂のようである。』
先に見た20:3の箇所で、『諸国の民』は「ローマ軍」であると私は書いておいた。しかし、そこでは『諸国の民』がどうしてローマの軍隊だと言われるのか説明しておらず、20:8の箇所が来たら説明すると言っておいた。20:8の箇所に来た今や、その説明をしよう。ローマ軍が『諸国の民』と言われているのは、ローマ軍における内訳の観点から言った言い方である。古代ローマの軍隊は多くの国籍の人たちから成り立っており、ローマはローマ以外の色々な国からローマ軍の兵士を募集・採用していた。カルヴァンは次のように正しく言っている。「ローマ人は非常にしばしば、兵士を属州や同盟市の住民から募集した」(『新約聖書註解Ⅴ 使徒行伝 上』10:1 p298:新教出版社)。それだからローマ軍は、その半分以上が外国人の兵士であった。これは歴史を学んだ者であれば、誰でも知っていることである。更に、この時は「近隣諸国の諸王から提供された多数の同盟軍兵士」(『ユダヤ戦記2』Ⅲ i3:8 p015:ちくま学芸文庫)もローマ軍に加わっていた。その中には「アラブ人の弓兵や、シリア出身の遠投兵」(同 vii18:211 p057)もいた。実に黙示録でローマ軍が『諸国の民』と言われているのは、これが理由である。それゆえ『諸国の民』とは、言い換えれば「諸国の民から採用された兵士たちにより成り立っているローマ軍」となる。黙示録で秘儀に包まれた言い方が無数に書かれているのは誰の目にも明らかなのだから、ローマ軍がこのような分かりにくい言い方で言われていたとしても、不思議に思ってはならない。ローマ軍が『地の地方にある(諸国の民)』と言われているのも、やはりローマ軍が世界各地から寄せ集められた兵士たちにより成り立っている、という意味である。この『諸国の民』とは私が今言ったように理解すべきである。というのも、それこそが唯一正しい理解だからである。もしそのように理解しなければ、いつまで経っても、この『諸国の民』という言葉を理解することは出来ない。実際、全ての聖徒たちは、私が今言ったように理解していないので、誰一人としてこの言葉を正しく捉えられていないのを私は見ている。それではローマ軍が『ゴグとマゴグ』と呼ばれているのは何故なのか。そもそも『ゴグとマゴグ』とは何なのか。まず、『マゴグ』とは創世記10:2で記録されているようにヤペテの子であり、スキュティア人の祖先である。『ゴグ』とはエゼキエル書38~39章によれば、『マゴグ』の地の大首長である。つまり、この『ゴグ』はスキュティア人の一人である。黙示録でローマ軍が『ゴグとマゴグ』と呼ばれているのは、ローマ軍が『ゴグとマゴグ』であるスキュティア人に類似していたからである。スキュティア人とは、有名な騎馬民族であり、非常に力強かったので周りの地に住む人々から恐れられ(※①)、その軍事力により次々と版図を拡大させていったことで知られている(※②)。トログスはこのスキュティア人について次のように言っている。「彼らは、アレクサンドロスの将軍ゾピュリオンを3万人の武装兵士と共に根絶したり、ペルシア王キュロスを20万人の兵士と共に殺したり、マケドニア王ピリッポスを敗走させたりした」(ポンペイウス・トログス/ユニアヌス・ユスティヌス抄録『地中海世界史』第37巻 3 p397:京都大学学術出版会 西洋古典叢書)。「彼らはアシアの支配を3度求めた。彼ら自身はずっと他国の支配に触れられることもなく、負かされることもないままであった。彼らはペルシア王ダレイオスを恥ずべき逃亡へと追い払い、キュロスを全軍と共に殲滅し、アレクサンドロス大王の将軍ゾピュリオンを、同じようにして、全軍勢と共に滅した。ローマ人の武器を彼らは耳にしたが、それを感じることはなかった。パルティア王国、バクトリア王国を彼ら自身が建てた。彼らの種族は労働と戦争とに際して粗暴で、身体は強壮である。彼らは、失うかも知れない物を獲得することはなく、勝者となっても、栄光以外の何物をも欲しがらない。」(同 第2巻 3 p62~63)莫大な知識を持っていたアウルス・ゲッリウスによれば、彼らは「人肉を喰らい、それを糧として暮らし」(『アッティカの夜1』第9巻 4:6 p427/京都大学学術出版会 西洋古典叢書 2015第6回配本)ていたと言っている人もいたようである。紀元1世紀のローマ軍も、馬に乗った兵士を多く有する有名な軍隊であり―その騎兵は無数にいた(※③)―、非常に強かったので周りの地に住む人々から恐れられ、その軍事力により次々と版図を拡大させていった。つまり、スキュティア人とローマ軍とは、単に人数や国籍やその言語といった細かい部分を除けば、兄弟でもあるかのように感じられる存在であった。だから、ローマ軍が『ゴグとマゴグ』と言われているのは、言い換えれば「ゴグとマゴグでもあるかのようなローマの兵士たち」となる。ゴグとマゴグがスキュティア人であると理解し、そのスキュティア人をローマ兵たちに重ね合わせてみよ。そうすれば事がよく理解できる。また『マゴグ』という場所が、ユーフラテス川の北側に位置していたという点にも注目すべきである(※④)。―これがエチオピアにあったという説もあるが、誤りである。―既に説明したように、霊的な理解において黙示録の中でユダヤの北の境界線は『ユーフラテス川』であった。黙示録では、この大きい川が枯れると、その枯れた川を通ってローマ軍がユダヤの地に侵攻してくると言われている(16:12、9:13~21)。もうお分かりであろう。黙示録では、ローマ軍がユダヤに攻めてくるというその侵攻の出来事を、マゴグの地にいたスキュティア人が枯れたユーフラテス川を通ってユダヤの地に侵攻することになぞらえているわけである。実際に、昔の時代においてスキュティア人がユーフラテス川を越えて南に位置していたユダヤを攻めたことがあるのかどうか、私は知らない。しかし、ローマ軍がユダヤを攻めるのは、あたかもそのようであると黙示録は教えているのである。このことを、イコール関係で示すと次のようになる。すなわち、「ローマ軍=スキュティア人」、「ローマの地=マゴグの地」、「ローマ軍がユダヤに侵攻する=スキュティア人がユーフラテス川を越えてユダヤに侵攻する」である。黙示録は『すぐに起こるはずの事』が書かれているという誠に聖書的な前提に立ち、それだけでなく古代の歴史的な知識を踏まえて考察すると、今私が言ったような解釈に導かれる。黙示録が『すぐに起こるはずの事』であるという前提に立たないと、また古代の知識を持っていないと、どうしてローマ軍が『地の四方にある諸国の民、すなわち、ゴグとマゴグ』と言われているのか全く分からないはずである。ヨハネから黙示録を届けられた紀元1世紀の聖徒たちは、マタイ24章とその並行箇所におけるキリストの預言により『愛された都』(20:9)であるエルサレムがローマ軍に包囲されることになるのを知っていたから、黙示録20:7~10の箇所に書かれている出来事は『すぐに起こるはずの事』だったと分かったはずだし、今の時代に生きる者たちとは違って多くの者が『ゴグとマゴグ』についての知識を持っていたはずだから、私が今述べたことがよく分かっていたに違いないと思う。しかし、今の聖徒たちは、黙示録が『すぐに起こるはずの事』だと理解していない上に、ゴグとマゴグについても知っている人はほとんどいないから、ここで言われているのがローマ軍だとは全く気付けないままでいる。
(※①)
トログスやタキトゥスによれば、このスキュティア人は「あのアレクサンドロス大王ですら避けてきた」とオロシウスは書いている(「世界史梗概」7・34・5)。つまり、それだけ力があったということだ。
[本文に戻る]
(※②)
<ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典>では、スキュティア人についてこう書かれている。「前6世紀から黒海北岸の草原地帯を支配したイラン系騎馬民族。前7世紀の後半にはすでに西南アジアや小アジアを荒し,クバン地方を中心として支配していたキンメリ人を征服して,南ロシアの草原に強力な支配体制を築き上げた。前6世紀の後半にはドナウ川下流,中流域に進出し,前513年にはペルシアのダレイオス1世の遠征軍を撃退している。前4世紀には統一的な大王国を形成,前339年にマケドニアのフィリッポス2世と戦ったアテアス王は最も著名なスキタイ王であった。しかし前300年以降はケルト人に圧迫されはじめ,前260年頃からは東のサルマート人がドン川を渡って侵入してきてその攻勢に押され,わずかの者がクリミア半島とドブルジャに避難したが,ローマ帝国のもとでスキタイ王国は崩壊した。馬具,武器,動物意匠(美術)において独特の発達をとげたが,これをスキタイ文化の3要素という。彼らの風俗,習慣についてはヘロドトスの『歴史』に詳しい。」また<デジタル大辞泉>ではこう書かれている。「前6世紀から前3世紀にかけて、カルパチア山脈とドン川との中間の草原地帯に強大な遊牧国家を建設したイラン系民族。黒海沿岸のギリシャ植民都市と交易。すぐれた馬具・武具・武器を発達させるなど、独自の騎馬遊牧民文化を形成し、ユーラシア各地から中国にまで大きな影響を与えた。装飾文様の動物意匠に特色がある。」今引用された文章を読むと、確かにスキュティア人はローマと多くの共通点を持っていたことが分かる。
[本文に戻る]
(※③)
ネロの時代には、ローマ軍が28箇軍団いた。1箇軍団は歩兵5000~6000人、騎兵120人から成り立っている(前3世紀では、1箇軍団につき歩兵4000~5200人、騎兵200~300人であって、危急の時になると増員されていた―ポリュビオス『歴史』第1巻:16、2/第2巻:24、3/第3巻:107、10~11)。つまり、ゴグとマゴグであるローマ軍に在籍していた騎兵の数は、ネロの時代のローマ軍において考えれば、単純計算で言えば3360騎であったことが分かる(28×120)。しかし、ローマ軍には他国や属州からの兵士たちも度々加えられていたから、実際的にはもっと多くの騎兵が見られたと考えるべきであろう。
[本文に戻る]
(※④)
エゼキエル書38:15の箇所でも、マゴグの地はユダヤから見て『北の果て』にあると書かれている。これはマゴグがユーフラテス川の北側に位置していたという見解と一致している。
[本文に戻る]
ところで、この黙示録20:7~10の箇所に出てくるゴグとマゴグは、周知の通り、エゼキエル38章・39章の箇所にも出てくる。このエゼキエル38章・39章に出てくるゴグとマゴグは、黙示録20:7~10の箇所とどのように関わっているのであろうか。また、エゼキエル38章・39章で言われているのは一体なんのことか。これは、再臨を理解するためには、絶対に知っておかねばならないことである。何故なら、再臨について教えられている黙示録の中で、ヨハネはエゼキエル38章・39章と同じ内容のことを語っているからである。もしエゼキエル38章・39章と黙示録20章との関わりについて関心を持とうとしなければ、その人は再臨の十全な理解を諦めているのも等しい。結論から言えば、ヨハネが黙示録20:7~10の箇所でゴグとマゴグについて語っているのは、それがエゼキエル38章・39章の内容と同一のことだからである。つまり、黙示録20:7~10とエゼキエル38章・39章とは対応している。これは大変に重要な理解である。ヨハネは、遂にエゼキエル38章・39章で書かれていた預言が成就することを示すべく、黙示録20:7~10の箇所でエゼキエルの預言に基づいた内容のことを語ったわけである。黙示録20章でもエゼキエル38章・39章でも、ゴグとマゴグという言葉は代喩法として語られている。すなわち、ヨハネもエゼキエルも、ゴグとマゴグと言ってローマを表示させている。だから、我々はこの2つの箇所で、本物のゴグとマゴグがユダヤを攻めたことについて言われていると考えてはならない。実際、歴史を見ても分かるように、そのような出来事は起こっていない。それゆえ、このゴグとマゴグという言葉を象徴として捉えないと酷い誤りに陥るから、我々は注意しなければならない。しかしながら、エゼキエル38章・39章のほうでは、ゴグとマゴグと言ってネブカデレザルもしくはアンティオコスを指しているのではないか、と考える読者もおられるかもしれない。確かに、ネブカデレザルもアンティオコスも多くの軍隊を率いてユダヤを包囲して攻撃した。これは歴史の事実である。だが、エゼキエル38章・39章で書かれているゴグとマゴグとは、ネブカデレザルまたはアンティオコスのことではない。何故なら、これをネブカデレザルと捉えるならば、エゼキエル38:7の箇所で書かれている『剣の災害』という言葉が何を言っているのか分からなくなるからである。この『剣の災害』という言葉はネブカデレザルの攻撃を指しているのであって、その災害から立ち直ったユダヤをゴグとマゴグが攻めるのである。だから、エゼキエル38章・39章でネブカデレザルの攻撃が預言されていると捉えるのは間違っている。またゴグとマゴグをアンティオコスと捉えると、今度はエゼキエル38:5の箇所が上手に理解できなくなってしまう。何故なら、アンティオコス4世がユダヤを攻めた時、アンティオコスのシリアはエジプトと敵対していたゆえ、『クシュとプテ』がアンティオコスの軍隊と共に戦いに向かうということは有り得ない話だったからである。だから、エゼキエル38章・39章で言われているのがアンティオコスの攻撃だと捉えるのも間違っている。であれば導き出される答えは一つしかない。すなわち、エゼキエル38章・39章で言われているゴグとマゴグとは、ローマを言っている。このエゼキエル38章・39章については、また後ほど、第4部の中で詳しく説明されることになる。このエゼキエルの預言を今にも熟知したいと思う良い意味で拙速な読者は、先にそちらのほうを読んでしまうがよい。だが今はまだいいと思う読者は、ひとまずエゼキエル38章・39章ではローマによるユダヤへの攻撃を言っているということを理解しておくべきである。また後ほどエゼキエル38章・39章の詳細を学ぶというのであれば、別にそれでも問題はないであろう。また、ここで私は黙示録とエゼキエル38章・39章を理解させて下さった神に感謝を奉げたい。私がこれらの箇所を理解できるようにと祈ったので、神が私に教えて下さったのである。全ての聖徒たちがこの黙示録とエゼキエル38章・39章をまったく理解できないままでいるのは、これらの箇所を理解できるようにと神に祈り求めていないからである。もし祈り求めていたら、私のようにこれらの箇所を理解できていたはずである。神が聖書の正しい理解を求める我々の切なる願いを聞いて下さらないということが、一体どうしてあるだろうか?だから、もし私も他の聖徒たちのようにこれらの箇所について神に祈り求めていなければ、これらの箇所をまったく理解できないままであったはずである。
ある者たちが今は黙示録20:1~6の時代であるなどと堂々と主張することを止めないという無思慮さには、あきれ果てるしかない。確かに彼らは、あたかも自分たちが黙示録をよく理解できているとでも言わんばかりに―私から見れば無知同然なのであるが―、「今は黙示録20:1~6の時代である。」などと言う。だが、彼らはそのように大胆に主張しているのにもかかわらず、そのすぐ後に書かれている20:7~10の箇所およびそこと対応しているエゼキエル38章・39章の箇所を、深く考究しようとはしていない。読者よ、彼らのことをよく考えてみてほしい。自分たちが堂々としている主張に大いに関わっているであろう他の箇所を解読しようとしないというのは、何という無思慮さ、何という怠惰さ、何という鈍感さであろうか。これが他の学問や分野だったとしたら、多くの人に苦笑されていたのは間違いない。ただ黙示録については他の全ての聖徒たちも彼らと同様無知なので、彼らがそのような無思慮さを持っていても、誰もおかしいとは思わないだけなのである。だから、黙示録を神の恵みにより考究することが出来た私から見れば、彼らが20:1~6に続く20:7~10の箇所およびそこと対応しているエゼキエル38章・39章の箇所を解き明かそうとしていないのは、誠におかしいと思わされるのである。彼らは一度でも次のように思ったことがあるのか。すなわち、「もし20:7~10の箇所とエゼキエル38章・39章を理解できたら、20:1~6の箇所をも真に正しく理解できるようになるに違いない。何故なら、これら2つの箇所は20:1~6のすぐ後で書かれている事柄なのだから。」などと。私は、今が20:1~6の時代だなどと主張している者に対し、次のように聞いてみた。「エゼキエル38章・39章はユダヤがローマ軍から包囲されることについて預言しており、黙示録20:7~10の箇所では明らかにそこと同じ内容のことが書かれているから、黙示録20:7~10は既に起きたユダヤ陥落について言われているのではないか。そうすると、そのすぐ前の箇所である黙示録20:1~6の箇所も既に終わっていることにならないか。」そして、次のようにも加えて尋ねてみた。「黙示録20:7~10の箇所でローマ軍によるユダヤへの攻撃が預言されているとすれば、黙示録20:7~10の箇所もヨハネが言ったように本当に『すぐに起こるはずの事』を書いていたことにならないであろうか。」この質問に彼は何と答えたか。何も答えなかった。何故なら、この者は今が黙示録20:1~6の時代であると力強く主張しているにもかかわらず(力強いというよりは無謀と言ったほうが正しい)、黙示録20:7~10の箇所とエゼキエル38章・39章についてはまったく考究していないからである。彼はこの2つの箇所(黙示録20:7~10の箇所とエゼキエル38章・39章)で何が言われているのか分からなかった。だから私の質問に何も答えられなかったのだ。もしこの2つの箇所を弁えていたとすれば、私に対して「確かにそうかもしれない。」とでも返答していたであろう。読者は、このように研究していないにもかかわらず黙示録についてさもよく理解しているかのように堂々と教えている教師に注意せよ。もし注意しなければ、そのような教師が語る間違った見解にやすやすと陥ることにもなりかねないからである。
さて、話がエゼキエル書のほうに飛んでしまったので、元の流れに戻したい。ここでローマ軍が『海べの砂のようである』と言われているのは、ローマ軍の数の多さを比喩的に言い表している。これは既に説明された通りである。12:18の箇所でもローマ軍について同様のことが言われている。16:13の箇所ではローマ軍が『かえる』と言われているが、これもローマ軍の数の多さを教える言葉であり、つまりエジプト全土が裁きにより蛙の群れに満たされたように、ユダヤも裁きにより蛙の群れのごときローマ兵たちに入り込まれてしまうという意味である。
ここではサタンが初めてローマ軍を招集したのだと言われているわけではない。ローマ軍は既に前から招集されていた。というのも、この20:8の箇所で言われているのは再臨が起きてネロが死んでから後の出来事についてだが、ネロがローマ軍を招集したのは再臨が起こる前の出来事だからである。ここで言われている『招集』とは、すなわち既にネロによって招集されていたローマ軍が、サタンの働きかけにより遂にエルサレムを本格的に攻め込むように動かされた、ということである。つまり、この箇所における『招集』とは「戦いの準備をさせる」ということに他ならない。この『招集』という言葉を、最初の招集のことだと考えると誤りに陥る。何故なら、最初の招集はまだ存命中のネロにより実現されたのであって、そのネロは既に19:20の箇所で殺されているからだ。既に19:20の箇所で殺されたネロが、どうして時間的に後の出来事が書かれている20:8の箇所でローマ軍を招集するというのであろうか。これは全く説明できないことである。
【20:9】
『彼らは地上の広い平地に上って来て、聖徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ。』
『地上の広い平地』とはユダヤを指す。既に説明されたように、霊的な理解において黙示録の中でのユダヤの領域は『エジプトの川から、あの大川、ユーフラテス川まで』(創世記15章18節)である。これは確かに『地上の広い平地』である。これをユダヤ以外だと考えることはできない。先に見た『ハルマゲドンと呼ばれる所』(16:16)すなわちメギドの丘だと考えることもできない。何故なら、メギドの丘は広い場所ではないからである。また後程述べるが、ここで言われているのはハルマゲドンの地における戦いのことではないのだ。
『愛された都』とは言うまでもなく「エルサレム」を指している。神は、かつてエルサレムを大いに愛しておられた。それは、そこに御自身の聖なる神殿を置かれるほどであった。ところが今や、堕落したエルサレムから神の愛は離れ去っていた。それゆえエルサレムは神の罰により、ローマ軍に包囲されるという悲惨を受ける羽目となった。だからこそ、ここでは『愛された都』が取り囲まれた、と言われているのだ。つまり、この言葉は言い換えれば「かつては神に愛された都エルサレム」となる。この都を、紀元1世紀におけるユダヤの首都としてのエルサレム以外だと考えることはできない。黙示録において『都』とは、地上におけるエルサレム市を指すか(11:8)、天国を指すか(21:1~22:5)、どちらかである。この言葉が聖徒たちを指す部分はない。我々が今見ている箇所で言われているのは、誰の目にも明らかなように『地上の広い平地』において起こる出来事である。それは天上において起こる出来事ではない。従って、ここで言われている『都』とは今のパレスチナにあったエルサレム市以外ではない。『聖徒たちの陣営』とは、再臨が起きた後の教会に新しく加えられたエルサレム市にいた聖徒を指している。再臨が起きて教会が荒野状態になってから、新しい信者が教会に加えられたというのは、既に説明された通りである。この新しい信者たちは、当然ながらローマ軍がエルサレムを包囲した際、そこにいた他の不信者また毒麦たちと共にローマ軍に取り囲まれることになった。だからこそ、ここでは『聖徒たちの陣営』もローマ軍に包囲されたと言われているのである。なお、ここで言われている取り囲まれた聖徒たちは、あくまでもエルサレム市にいた聖徒たちに限られる。何故なら、ローマ軍が実際に包囲したのはエルサレム市だけだからである。だから、エルサレム市以外にいた聖徒たちまでローマ軍に包囲されたと言うことはできない。もしエルサレム市以外にいた世界各地の聖徒たちもローマ軍に包囲されたなどと考える人がいたとすれば、そのような人は相手にせず放っておくに限る。
この箇所で言われているのは、単にローマ軍によるエルサレム包囲の出来事についてである。あまり難しく考える必要はない。この箇所をエルサレム包囲の出来事だと考えない聖徒たちは、一体どういうことなのか。どうして、これがエルサレム包囲の出来事だと気付かないのか。試しに、自分が紀元1世紀に生きているヨハネから黙示録を受け取ったエペソ教会の聖徒だったと仮定してみるがよい。今、我々は紀元1世紀のアジヤの地に住んでいる。まだその時の我々にとって、やがてローマ軍によりエルサレムが包囲されるであろうと預言されたキリストの発言は、少し前になされたものであり、それゆえ記憶に新しい。10年ぐらい前にキリストがそのように預言されたばかりなのだ。ヨハネから送られてきた黙示録の中では、明らかにそのキリストの預言としか考えられない出来事が預言されていた。すなわち、20:9の箇所で、『愛された都』であるエルサレムが『海べの砂』のように多い者たちに取り囲まれると言われていた。どうであろうか。我々は、これがエルサレム包囲のことだと理解しないであろうか。普通の感覚を持っていれば、誰でも「これはキリストが預言されたエルサレムの包囲の出来事に違いない。」と思うはずである。それだから、もしヨハネから黙示録を受け取った当時の聖徒たちの中で、これがエルサレム包囲の出来事だと悟れなかった者がいたとすれば、その者はキリストの預言を知らなかったか、信じていなかったか、または知っていたが痴呆状態だったか、のどれかに分類されるべきであった。今の聖徒たちは御言葉に密着し、紀元1世紀の時代についてよく考え、眠っているその目を豊かに覚ましてほしいものである。
先にも触れたが、ここではハルマゲドンの戦いについて言われているのではない。何故なら、ハルマゲドンの戦いとは再臨の際に起こる戦いのことであり、それは19:19~21の箇所で既に実現されているからだ。この20:9の箇所で言われているのは再臨の時の出来事ではなく、もう既に再臨から『1260日』が経過した後の出来事なのだから、ここでハルマゲドンの戦いが語られていると理解することはできない。
『すると、天から火が降って来て、彼らを焼き尽くした。』
『彼ら』とは、もちろん『諸国の民』であるローマ軍の兵士たちを指している。前後の文章を読めば、これは明らかである。これは、すぐ前に記されている『聖徒たち』のことではない。何故なら、聖徒たちが天からの火で焼き尽くされるというのは、考えられないからである。神は、御自身の聖徒たちに悲惨な滅亡を味わわせられるようなお方ではない。また、これを「ユダヤ人」と取ることもできない。確かにユダヤ人は、歴史が示すように、この時期に火で焼き尽くされた。しかし、ここではユダヤ人を指して『彼ら』と言われているのではない。というのも、前後の文章を読めば、これはユダヤ人と取るよりもローマ軍と取るほうが適当だからである。それに、前の箇所をずっと遡って見ても、『彼ら』という言葉の元となったユダヤ人に関する部分がどこにも見当たらない。19:10よりも前の箇所に遡れば、『彼ら』がユダヤ人を指している箇所に行き着くが(それは19:1~10の箇所である)、しかし19:10よりも前の箇所と19:11よりも後の箇所は内容的に断絶しているのだから、19:10よりも前の箇所まで遡ることはできない。もし19:19よりも前の箇所に遡ることができていれば、この『彼ら』がユダヤ人を指していると取ることも十分に可能であった。
『火』とは、ここでは「御言葉」を指している。これは本当の火ではない。実際、ローマ軍はユダヤ戦争の際、本当の火で焼き尽くされるということはなかった。もう少し後で見ることだが、エゼキエル書38章の箇所を見ても、やはり、ここで言われている『火』が御言葉であったことが分かる。聖書では御言葉が『火』により言い表されているということについては、既に説明された通りである。
この箇所では、ローマ軍が御言葉という火に焼き尽くされたということが言われている。これは、つまりローマ軍が霊的に断罪されたという意味である。これは、聖徒たちに敵対する者たちが、聖徒たちの口から出る火により殺されると言われていたのと同じである(11:5)。確かに、この時に聖徒たちに害を加えようとした者たちは聖徒たちの口から出た火により滅ぼされたのだが、それは霊的に断罪されるという意味における殺傷であった。また、これはローマ軍がキリストの口から出ている剣により殺されたと言われていたのと同じでもある(19:21)。確かに、この時にローマ軍たちはキリストの剣により殺されたのだが、それは霊的に断罪されるという意味における刺殺であった。ここで言われているのは、この2つの箇所で言われているのと同じ意味に捉えるべきである。黙示録では、このように霊的な断罪が、刺殺また焼殺において言い表されていることに留意すべきである。もっとも、黙示録の中で刺殺また焼殺について語られていた場合、その全てが例外なく霊的な断罪を言い表しているということではない。中には、実際的なことを言っている箇所もある。例えば、13:10で言われているのは明らかに実際的な刺殺のことだし、17:16で言われているのも実際的な大炎上のことである。だから、黙示録で刺殺また焼殺について語られていた際には、それが霊的な表現なのか、それとも実際的な出来事なのか、よく見極めなければならない。さて、確かにローマは、ユダヤ戦争において都を取り囲んだ。これは大きな悪であった。ローマ軍が御言葉により霊的に断罪されたのは、この悪が理由であった。彼らは神に『愛された都』であるエルサレムを攻撃するという悪を行なったので、彼らが霊的に断罪されるのは至極当然であった。神は、悪を行なう者を、その行なった悪に応じてお裁きになる。ここで、そもそもローマ軍がエルサレムを攻撃するようになったのは神から出たことではなかったか、と訝しく思う人がいるかもしれない。確かに、ローマ軍がエルサレムを攻撃するようになったのは神がローマの者たちの心に働きかけられたからであった(17:17)。神が働きかけられなければ、ローマ軍はエルサレムを攻撃していなかったはずである。だが、それにもかかわらず、ローマ軍は霊的な犯罪人として神からの霊的な裁きを受けることになった。これは、当然のことであったと言える。何故なら、究極的に言えば包囲と破壊の出来事は神から出たことであったものの(ローマ11:36)、実際にその行為を自らの意識でしたのはローマ軍の者たちに他ならなかったからである。だから、我々はローマ軍がしたことで神を責めることはできない。もしローマ軍が行なった悪がそもそも神の許しと働きかけのうちに起きたからというので神を非難してもよいというのであれば、アダムが罪を犯したことについても神を非難せねばならなくなる。何故なら、アダムが罪を犯すようになったのも、究極的に言えば神がそうなるようにと定められたからである。しかし、まともな聖徒であれば、いったい誰がアダムの堕落のことで全てを定められた神を非難するのであろうか。まともな聖徒の中で、そのようなことをする聖徒は一人もいないはずである。
ここでローマ軍が御言葉の火により断罪されると言われているのは、エゼキエル書38:22の箇所と対応している。エゼキエル書38章および39章では『ゴグとマゴグ』について言われているから、そこで言われているのは明らかにローマ軍のことである。そこでは神が次のように言っておられる。『わたしは…彼と、彼の部隊と、彼の率いる多くの国々の民の上に、豪雨や雹や火や硫黄を降り注がせる。』ここでは『火』に加えて『豪雨や雹や…硫黄』についても書かれている。実際の歴史を見れば分かるように、ユダヤ戦争の時期にローマ軍が『豪雨や雹や…硫黄』を受けたということはなかった。だから、これは実際的な現象や物体について言われた言葉ではない。これらは全て「御言葉による霊的な断罪」のことを言っているのだ。またこの出来事は、黙示録16:21の箇所とも対応している。そこでは『火』ではなく『1タラントほどの大きな雹』がローマ軍の上に天から降って来たと言われていた。これも、やはり御言葉の裁きを比喩的に言い表したものであった。なお、詩篇18:12~13の箇所で『雹と火』により神の怒りの裁きが表現されているということも、考慮に入れるべきである。また当然ながら、この16:21の箇所もエゼキエル書38:22の箇所と対応している。これらの箇所で注意せねばならないのは、どれも御言葉が自然現象や実際的な物体において表現されているということである。その表現を文字通りに受け取ると、誤るだけでなく、何が言われているのか上手に理解できなくなる。
また、この箇所はゼカリヤ書12:6の箇所とも対応している。そこでも、やはりローマ軍に対する霊的な断罪が、火で焼き尽くされるという比喩表現のもとに示されている。すなわち、次のように書かれている。『その日、わたしは、ユダの首長たちを、たきぎの中にある火鉢のようにし、麦束の中にある燃えているたいまつのようにする。彼らは右も左も、回りのすべての国々の民を焼き尽くす。』このゼカリヤ書12:6の箇所は、第4部の中で再び取り扱われることになる。
【20:10】
『そして、彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も、にせ預言者もいる所で、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。』
ここでは言われているのは、どういうことなのか。ここでは、サタンが最早ローマ軍においてユダヤに働きかけられなくなった、ということが言われている。ネロとティゲリヌスは『火の池に、生きたままで投げ込まれた』(19:20)ことにより、最早ローマ軍を通してユダヤに働きかけることが出来なくなった。そのようなネロとティゲリヌスのように、サタンもローマ軍を通してユダヤを弄ぶことが出来なくなった。つまり、これは言い方が問題である。ここではサタンのローマ軍による働きの終焉が、ネロとティゲリヌスが投げ入れられた『火の池』にサタンも投げ入れられるという言い方で言われているのだ。すなわち、これは「最早ローマ軍を通して働けなくなった。」という結果において同様のことが言われていると判断せねばならない。既に述べたように黙示録には常ならぬ言い方が満ち満ちているのだから、ここでこのような難しい言われ方がしていたとしても、何も不思議ではない。むしろ、そのような難しい言われ方が無数にあるからこそ、黙示録は黙示録であると言えるのだ。この見解を非とし断罪する者は、黙示録を理解するためにどれだけ神に祈り求めているのか私に教えてもらいたい。私よりも祈っていないことは確かである。私の場合、黙示録を理解するために、大いに神に祈りを捧げている。だからこそ、このように豊かな註解を書くことが出来ている。すなわち、この註解は、神が私に黙示録を教えて下さっておられることの紛れもない証拠である。もし私の見解に反論するというのであれば、まずは真摯な思いで黙示録を理解できるようにと祈ってからにせよ。ひとまず次のように祈ることをお勧めしたい。「この人の註解の内容が本当に正しいのかお示しください。もしそれが正しければ、私がその見解を受け入れられるように謙遜な心を持てますように。しかし、これが御心に適わない見解でしたら、そんなものを私が受け入れることはありませんように。私がこの箇所に対して誤った見解を持たないように憐れんで下さい。」私はこのような祈りを、自己を無にして、つまり心から純粋に祈るように要請する。私は言うが、聖書では、サタンの働きの終焉が、サタンが死ぬとか追い出されるとか牢に投げ込まれるといった表現で言い表されていることに留意せねばならない。例えば、キリストはヨハネ12:31の箇所で『今、この世を支配する者は追い出されるのです。』と言われた。これは、すなわちキリストを信じる者たちの心からサタンが支配権を失わせられ追い出されるようになるという意味であった。また、ヘブル2:14ではキリストが『悪魔という、死の力を持つ者を滅ぼし』たと言われている。これは、もはやキリストを信じる者たちには、サタンが死の支配を持って支配することは出来なくなった、という意味である。また、先に見た20:1~3の箇所では、サタンが牢に封じられたと言われていた。これは、サタンが荒野の期間において教会に害を与えられなくさせられる、という意味であった。また、イザヤ51:9では『竜』であるサタンが紅海が割かれる奇跡の時に『刺し殺』されたと言われている。これは、もはやサタンがエジプト王パロを通してはユダヤに苦しみを与えられなくなった、という意味である。この20:10の箇所の場合、どうであるか。ここではサタンがネロとティゲリヌスの投げ込まれた地獄に投げ込まれると言われている。これは、サタンが地獄に投げ込まれたネロとティゲリヌスのように最早ローマ軍を通してユダヤを苦しめられなくなった、という意味である。何故なら、この時にユダヤは滅ぼされたのだから、それ以降はローマ軍を通して働きかけたくても出来ないからである。聖書特有の言い方に慣れている人であれば、サタンの働きの終焉が、このような言われ方で言われていたとしても驚かないはずである。それというのも、その人は聖書が普通の書物でないことを、よく弁えているはずだからである。
全ての聖徒たちは、今まで、この箇所ではサタンの実際的な死滅のことが言われていると考えてきた。しかし、そのように考えるのは誤っている。何故なら、その考えは理性に基づくからである。ただ自分たちがそう感じるからというので、ここではサタンの実際的な滅びについて言われていると誰もが考えている。つまり、その考えには聖書の裏付けがない。聖書が根拠にないのに、自分の感覚に基づいて何かを考えるとは一体どういうことなのか。前から言っていることだが、この20:10の出来事も含めて黙示録に書かれていることは『すぐに起こるはずの事』である。すなわち、ここでサタンが火の池に投げ込まれると言われている出来事は、既に成就している。しかし、実際の世の中を見てみると、未だにサタンが滅んでいるようには感じられない。というのも、今の時代においてサタンがまだ生きており、活動を続けているのは誰の目にも明らかだからである。それゆえ、この20:10の箇所で言われていることは一見すると実際の状況と矛盾しているかのように感じられるが、実は矛盾していない。何故なら、ここで言われているのは単にサタンが地獄に投げ込まれたネロとティゲリヌスのようにローマ軍を通してユダヤを苦しめられなくなった、ということに過ぎないからである。黙示録の内容は全て成就しているという見解を拒絶する者たちは、「黙示録は全て成就したと言うがサタンは未だに滅んでおらず活動しているではないか。どういうことなのかね。」という反論をもって自分を武装する。つまり、このように反論できるのだから、私の見解は誤っており、受け入れなくても別に問題はない、と考えるわけである。だが、このように反論する者たちは、黙示録を半分以上も理解できていないのに、このように堂々と言っている。この箇所で言われているのが一体どういうことなのか分かりもせずに、このように反論している。このように反論するのは、私に対して反論しているのではなく、神の霊に対して反論しているのだ。何故なら、黙示録の出来事が全て『すぐに起こるはずの事』だと言ったのは、私ではなく神の霊なのだから。だから、私の示した見解を拒絶して反論する者たちは、神に次のようなことを言っているのも等しい。「黙示録を書かれた神よ。あなたは黙示録の出来事が『すぐに起こるはずの事』だと言うが、私はそんな理解を受け入れたくない。何故なら、サタンはまだ滅ぼされていないではないか。もし黙示録が『すぐに起こるはずの事』を記しているとすれば、どうしてサタンがまだ滅ぼされていないのか。説明してほしいものだ。」実際に彼らがこう言っているというのではないが、つまり彼らが人間である私に反論するのは、神にこう言っているのも同然なのである。私は問いたいのだが、もしこの20:10の箇所で言われているのをサタンの実際的な滅びだと理解せねばならないとすれば、どうしてその他の箇所でサタンが滅びたと言われているのを実際的に理解しようとしないのであろうか。例えば、ヘブル2:14ではサタンがキリストにより滅ぼされたと言われている。今まで多くの教師たちが、キリストはその贖いと復活によりサタンを滅ぼされた、と言ってきたのは事実であり聖書的な言説である。だが、サタンの滅びを実際的な滅びであると捉えた正統的な信仰を持つ教師は誰もいなかった。それは何故なのか。それは、聖書でキリストがサタンを滅ぼされたと言われているのは、実際的な滅びについてのことではないからである。これは誰もが認めざるを得ない。何故なら、サタンは今になってもまだ現実の世界に働きかけているのだから。もしヘブル2:14などでサタンが滅びたと言われているのを実際的に捉えなくてもよいとすれば、すなわち文字通りにサタンが死滅して全く何も行なえなくなったと捉えなくてもよいのであれば、どうして我々が今見ている20:10の箇所ではあくまでもサタンの滅びを実際的に捉えようとするのか。もしヘブル2:14の内容が実際的なサタンの滅びについてのことだと理解しなくてもよいのであれば、この20:10の箇所も実際的なサタンの滅びについてのことだと理解しなくてもよいことになる。もし20:10が実際的な滅びだと考えなければならないとすれば、他の箇所でサタンが滅びたと言われているのも、実際的な滅びのことだと考えなければいけないことになる。この箇所ではサタンが地獄に投げ込まれたと言われていながら、実際にはまだサタンが活動しており、また黙示録で書かれている出来事はこの箇所も含めて『すぐに起こるはずの事』だったのだから、この箇所は私が上で説明したように捉えなければいけない。
ここで言われている出来事については、サタンが肉の身体を与えられて地獄に投げ込まれた、という解釈も存在している。すなわち、サタンは受肉体としては地獄に投げ込まれたが、霊においては現世において活動が許され続けている、と考える捉え方である。この解釈については既に第2部で説明されている。私は以前、この解釈に立っていた。しかし、このように捉えるのは間違っている。どうして間違いなのか。それは堅固でないからである。この解釈は単なる「こじつけ」に過ぎない。これは根拠に乏しいと言わざるを得ない解釈である。しかし、上で述べたサタンがローマ軍においてユダヤを苦しめられなくなったという解釈は堅固である。というのは、サタンの働きの停止が刑罰の場所に投げ込まれるという言い方で表現されている箇所が、黙示録の中には他にもあるからだ。すなわち、既に見たように20:1~3の箇所では、サタンが教会に対して無力化された出来事を、『底知れぬ所』に投げ込まれるという言い方で表現していた。このようにサタンの働きの停止が刑罰の場所に投げ込まれるという言い方で表現されていると捉える解釈は、少し前の箇所で既に例証があったのだから、根拠がシッカリしているのだ。昔の私は、ある時まで、このことに気付けないでいた。神が、まだ私に正しい解を悟らせることを引き延ばしておられたのである。だから、私はある時が来るまで、このことが分からないでいた。しかし今や、時が来たので、私はこの箇所で言われている出来事を正しく解することが出来ている。神には、ある人に正しい解をお与えになる『時』(伝道者の書3:1)があるのである。サタンが実際的な身体を受けて地獄に投げ込まれるという解釈は、おかしい解釈である。聖徒たちは、堅固でない空想的な解釈に陥らないように注意すべきである。もっとも時が来るまでは、神の摂理により、そのような解釈に陥ったままでいなければいけない場合も、人や時によっては避けられないこともあるのではあるが。
この箇所で『そこは獣も、にせ預言者もいる所で』と言われているのは、黙示録における順序を教える指標である。ここでは既にネロとティゲリヌスが地獄に入っていると言われているからである。つまり、この20:10と彼らが地獄に投げ込まれた出来事について書かれている19:20の間にある箇所は繋がっており、そこでは時間の矢が流れている。それは私が既に説明したように、19:11から22:5までの箇所は順序通りに描かれているからである。
また、この箇所では地獄における永劫性が示されている。そこにいる者たちは、『永遠に昼も夜も苦しみを受ける』とここでは言われている。つまり、地獄の刑罰に終わりはないということだ。また『昼も夜も』という言葉は、一時さえも休みや中断が与えられないという意味である。これほどに恐ろしい場所と刑罰は、他にない。キリストが自分の身体を損なってでもゲヘナに行かないほうがよい、と言われたのは、誠にもっともなことであった(マルコ9:43~47)。
この地獄に投げ込まれたくない聖徒たちは、地獄における苦しみの光景を心に思い浮かべるがよい。そのように思い浮かべるのは、より明瞭であればあるほどよい。そうすれば、地獄に対する抵抗感を持つはずである。というのも、誰でも地獄に行きたくはないだろうからである。そのようにして聖徒は、自分の心が地獄を嫌うようにすべきである。そうすれば、自然と自分の信仰が堅固になるように導かれることであろう。地獄を忌避するならば、精神がそれだけ天国に固着するようになるのは必然である。
第26章 2320章11~15節:第二の復活、第二の携挙、空中の大審判について
しつこいようであるが、この箇所で書かれている出来事も『すぐに起こるはずの事』だったと理解すべきである。私は今、何か変なことを自分勝手に言ったのではない。これが『すぐに起こるはずの事』だというのは、私ではなく御言葉がそのように言っていることなのだ。それゆえ、読者は私の言ったことを愚かなことだと思うべきではない。もし愚かだと思う人がいたとすれば、それは私ではなく、御言葉の内容が愚かだと思っていることになる。聖徒である者はよく注意せねばならない。御言葉を愚かだと思うのは恐ろしいことである。
【20:11】
『また私は、大きな白い御座と、そこに着座しておられる方を見た。』
遂に、キリストが大審判を行なわれるために裁きの座に着かれる時がやって来た。時は紀元70年9月である。これも、やはり『すぐに起こるべき事』(22:6)であった。
『御座』が描かれているのは、そこに王であられるキリストが審判者として着座しておられるからである。これは、まだ王が裁判官の役割を果たしていた時代の裁判を思い浮かべればよい。御座が『大き』かったのは、キリストの審判者としての偉大さを示している。すなわち、キリストは大いなる審判者として裁きを下されるのだ。御座が『白い』色をしていたのは、そこに着座しておられるキリストの神聖性と純潔性を示している。つまりキリストは裁かれる時、決して不正をなさらない。『主には不正がありません。』(詩篇92:15)と書かれている通りである。
ところで、どうしてヨハネは、この箇所を含め黙示録の多くの箇所で、キリストをその名前で言い表していないのであろうか。ヨハネは、ここでもあそこでも、黙示録の中でキリストを「キリスト」と言っていない。ヨハネは、聖四文字を口にすることを大いに恐れたユダヤ人のように、キリストの御名をそのまま書くことを恐れたのであろうか。そうではない。ヨハネがキリストの名前をそのまま書いていないのは、黙示録をより秘儀的な記述で満たすためであった。黙示録には、より難しい記述にしなければいけない、という暗黙のルールがあったと考えてよい。それは、悟れる者だけが黙示録の内容を悟れるようになるためであった。だからこそ、ヨハネはキリストの名前さえ、そのまま書き記すことをしていないのである。そうすれば、それだけ黙示録を多くの人が読み解けなくなるからである。もしキリストを「キリスト」とそのまま書いていれば、それだけ黙示録は秘儀的な文書とはなっていなかったはずである。とはいっても、これは全ての部分がそうだというのではなく、キリストがその名前において書かれている部分もかなりある。しかし全体としては、やはりキリストの名前をそのまま書き記していない部分が圧倒的に多い。
この大審判の出来事と対応している聖書の他の箇所は次の通り。黙示録11:18、14:17~20、マタイ25:31~46、ダニエル書7:9~10。
『地も天もその御前から逃げ去って、あとかたもなくなった。』
これは世界が更新されるということである。何かを更新したい場合、既に置かれているものを一度取り去り、その上で新しいものを据える、というやり方が取られる場合は少なくない。キリストも、世界を更新される際、そのようにされたというわけである。ネロもローマ市街を一新させるため、何とかしてローマ市街を真っ新に出来はしないものかと日頃から思いめぐらしていた―その願いはティゲリヌスにより叶えられた。ここで言われているのは比喩的に捉えるべきである。何故なら、実際に地と天とが逃げ去るということは起こり得ないからである。また地と天に逃げ去ろうと思わせる人格が備えられているというのでもない。これはペンテコステの出来事の際に成就された『太陽はやみとなり、月は血に変わる。』(使徒行伝2章20節)という御言葉が、比喩的に捉えられるべきだったのと同じである。その時に太陽が闇とならず月も血に変わっていないように、この20:11の箇所で『地も天もその御前から逃げ去って…云々』と言われているのも実際的な現象について言ったものではない。
この箇所は次の箇所と対応している。6:14。『天は、巻き物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移された。』16:20。『島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなった。』これら3つの箇所がどれも同じことを言っているというのは、健全な感覚をもった聖徒であれば疑わないはずである。それだから私は黙示録が未だに全て成就しているのではないと考えている人たちの理解を、今ここで再び大いに粉砕したいと思う。ここで粉砕するのは2種類の人たちの見解である。一、黙示録は6:14までの箇所であれば既に実現済みであると無知であるにもかかわらず考えている人たちに、私は言おう。もし6:14の箇所が既に成就しているのであれば、確かなところ、20:11の箇所も成就していることになる。何故なら、6:14と20:11は同じことを言っているからだ。それで20:11が既に成就しているのであれば、黙示録は全ての箇所が既に成就していることになる。何故なら、20:11の箇所が成就すれば、後はすぐにも空中の大審判が起こり(20:12~15)、その後すぐにも21章目以降の箇所が成就されることになるからである。それだから、6:14までの箇所は実現済みだと考えるのは、すなわち黙示録の全てが実現済みだと考えていることになるのだ。まさか、6:14の箇所で言われているのが、再臨の時期に起こる世界更新の出来事についてだと分からないはずもないであろう。もしそれが世界更新の出来事について言われているとすれば、黙示録も全て成就したことになる。二、黙示録は16:20までの箇所であれば既に実現済みであると無知であるにもかかわらず考えている人たちに、私は言おう。もし16:20の箇所が既に成就しているのであれば、確かなところ、20:11の箇所も成就していることになる。何故なら、16:20と20:11は同じことを言っているからだ。それで20:11が既に成就しているのであれば、黙示録は全ての箇所が既に成就していることになる。何故なら、20:11の箇所が成就すれば、後はすぐにも空中の大審判が起こり(20:12~15)、その後すぐにも21章目以降の箇所が成就されることになるからである。それだから、16:20までの箇所は実現済みだと考えるのは、すなわち黙示録の全てが実現済みだと考えていることになるのだ。まさか、16:20の箇所で言われているのが、新しい世界が到来する時期のこといついて言われているのだと分からないはずもないであろう。もしそれが新世界到来の時期について言われているとすれば、黙示録も全て成就したことになる。見てほしい。私は6:14および16:20までの箇所が既に実現していると思っている者たちの理解を、適切な論法により打ち砕いてしまった。6:14までか16:20までであれば既に成就していると理解している人のうち、この論述に反論できる人はいないはずだ。これだけ強力な論証が他にあるであろうか。ない。黙示録は確かに、その全ての箇所が既に成就されているのだ。しかし、今までの聖徒たちは、そのことに気付けてこなかった。何故か。黙示録のことについて祈らず、考えず、研究しなかったからである。
【20:12】
『また私は、死んだ人々が、大きい者も、小さい者も御座の前に立っているのを見た。』
『死んだ人々』とは、20:5で言われていた『そのほかの死者』を指している。この人たちは霊的に死んでおり、肉体的にも死んでいた。しかし今や第二の復活の時が訪れたので、第二の復活に与り、空中の大審判においてキリストのおられる『御座の前に立っている』ようにされたのだ。だから、この『死んだ人々』という言葉は、言い換えれば「第二の復活により復活した死んだ人々」となる。
『大きい者も、小さい者も』キリストの前に立っていたというのは、第二の復活で復活する者たちには差別が与えられないことを教えている。王者や偉大な賢人であれ、無名の者や奴隷であれ、滅びに至らせる第二の復活から免除されることはない。神は『大きい者』だからといって第二の復活を受けなくてもよいとか、『小さい者』だからといって大目に見てやろう、などと言われる御方ではない。神は悪者どもに容赦されないからだ。それは神について『罰すべき者は必ず罰して報いる者』(出エジプト34章7節)と言われている通りである。
ここでは「第二の携挙」の出来事が省略されていることに気付くべきである。第二の復活により地上で復活した『死んだ人々』は、少し考えればすぐにも分かるように、空中の大審判に出頭させられるために携挙された。というのも、携挙されなければ大審判を受けられないからである。『死んだ人々』が第二の復活で復活はしたものの、携挙されず地上にいたままではどうして大審判を受けられようか。審判の御座は空中の場所にあったのだ。地上にいながらも空中の大審判を受けるのは十分に可能であった、などということは考えるべきでない。当時は今とは違って、テレビ会議ならぬ「テレビ審判」などという方法は実現できなかったのだから。この第二の携挙の出来事については、14:17~20の箇所で詳しく書かれていた。14:14~16および11:12の箇所も携挙について言われた箇所だが、これは再臨の時に起こる「第一の携挙」であって、再臨から『1260日』経って後に起こる「第二の携挙」ではないから注意されたい。
この箇所で言われている出来事は、マタイ25:32~33の箇所と対応している。そこでは次のように書かれていた。『そして、すべての国々の民が、その御前に集められます。彼は、羊飼いが羊と山羊とを分けるように、彼らをより分け、羊を自分の右に、山羊を左に置きます。』このマタイの箇所で言われている『すべての国々の民』という言葉が、御国の囲いの中にいる者に限定される、ということは既に第2部で語られている。我々が今見ている20:11~15の箇所では、マタイ25章で言われているところの『山羊』にのみ焦点が当てられている点に注意せねばならない。というのもこの20:11~15の箇所で取り扱われている『死んだ人々』とは『山羊』のことだからである。もちろん、マタイ25章の箇所が教えるように、大審判の際には、山羊と共に羊も審判の場に招かれることになる。しかし、ヨハネは我々が今見ている箇所で、羊のほうにはほとんど焦点を当てていない。それゆえ、20:11~15の箇所で山羊のことだけが言われているように感じても、実際に審判を受けるのは山羊だけに限られないという点を忘れないようにすべきである。
『そして、数々の書物が開かれた。また、別の一つの書物も開かれたが、それは、いのちの書であった。死んだ人々は、これらの書物に書きしるされているところに従って、自分の行ないに応じてさばかれた。』
『数々の書物』とは、神があらかじめ定めておられた悪者どもに対する裁きの予定のことを象徴している。第二の復活により復活した悪者どもは、空中の大審判を受けるべく携挙された後、永遠の昔から予定されていた神の裁きに基づいて裁きを受けた。その予定のことが、ここでは『数々の書物』と言い表されている。というのも、そのような多くの悪者に対する神の予定は、多くの書物になぞらえることが出来るからである。大裁判官が分厚い書物を開きつつ判決を犯罪人どもに下すように、神は御自身の予定に基づいて悪者どもに判決を下し給う。それだから、この箇所では第二の復活により復活した悪者どもについて、こう言われている。『死んだ人々は、これらの書物に書きしるされているところに従って、自分の行ないに応じてさばかれた。』この『数々の書物』という言葉を、文字通りに捉えてはならない。これは単なる比喩表現である。何故なら、地上の裁判官とは違って、神はそのような書物などなくても、悪者どもに対する裁きを正しく完全に下すことがお出来になるからである。
『いのちの書』とは、神が聖徒たちに定めておられた永遠の命を与えるという予定のことを象徴している。これについては、悪者たちは無関係である。この書については、先に見た3:5の箇所で説明しておいた。この書についての言及から、大審判の場においては、聖徒たちも招かれることが理解できる。しかし先にも述べたように、この20:11~15の箇所で聖徒たちの存在は、ほとんど無視されていると言ってよい。すなわち、この箇所は悪者どもに対する裁きだけを限定的に語る場所として設けられているのである。
この箇所で書かれている裁きの出来事は、マタイ25:34~46の箇所、ことに41~45節目の部分に詳しい。また、この出来事はダニエル書7:10の箇所と対応している。そこでは次のように言われていた。『さばく方が座に着き、幾つかの文書が開かれた。』
【20:13】
『海はその中にいる死者を出し、死もハデスも、その中にいる死者を出した。』
ヨハネは、先に裁きについて言わば梗概的なことを言った後、今度はその詳細について説明し始める。まず全体的に短く語り、そうしてから細かい部分を論じていく。このような語り方がされている箇所は、聖書に少なくない(例えばヨハネ3:18~21)。こうするのがヘブル人の語り方における特徴であった。ヘブル人という民族そのものは知性的にごく普通の民族であって、古代ではギリシャ人のほうが、現代では日本人のほうが卓越した知性を持っている(※)。しかし彼らには、聖なる神の法が与えられていたので、その法から得た知恵のゆえに、その他の民族よりも賢くなることが出来た。詩篇の記者も、「律法があるから私はどの人よりも賢い。」と言っている(詩篇119:98~100)。だからこそ、彼らは、このような賢い語り方が出来たわけである。
(※)
古代ギリシャ人については言うまでもない。日本人について言えば、日本人の平均IQが105であるのに対し、ユダヤ人が75%を占めるイスラエル(※日本の外務省の公式ホームページによる基礎データ:2019年9月2日現在)の平均IQは94である。筆者の感覚では、韓国人を見ると、知性の高い人が多いようにいつも思う。言葉の鋭さの裏側に高い知性が垣間見える。イザベラ・バードも「朝鮮紀行」の中で、彼らの知性が低くないと記録している(彼女によれば朝鮮人は学習能力が高く、外国語もすぐに覚えてしまうという)。実際、韓国人の平均IQは日本人のそれよりも1上である。しかし、ユダヤ人を見ても、あまり知性の高さを感じないことが多い。物を書いている人でさえ、ベンジャミン・フルフォードやアル・ゴアやジョージ・ブッシュやズグブニュー・ブレジンスキーやジョセフ・ナイやアシモフを見ても、そこまで知性が高いとは感じられないのである。日本のテレビに出てくるデープ・スペクターもそうだ。彼らの多くは考えられないぐらいに多量の知識を得るので、知識はやたらとあるものの知識に縛られて独創性を失う傾向があり(彼らが独創性を持っていないというのはヒトラーも「わが闘争」の中で言っている)、知性の自由な向上が妨げられてしまっている。ただ、アインシュタインなどごく一部の人たちはずば抜けて知性が高い。日本人や韓国人の場合、平均的には知性が高いのだが、ずば抜けた知性の持ち主はほとんど見られないのである。
[本文に戻る]
まず『死者』とは、20:5の箇所で言われていた『そのほかの死者』を指している。すなわち、これは第二の復活により復活した既に死んでいた死亡者どものことである。この人たちは、霊的な意味においても死者であった。何故なら、キリストにより新生していなかったからである。キリスト者でない者が死者であるというのは、キリストがヨハネ5:25の箇所で言っておられる通りである。しかし、ここで言われている『死者』とは、霊的な意味における死者ではないことに注意せねばならない。確かに彼らは霊的な死者であるが、ここでは単に実際に肉体の絶命を経験した死亡者たち、という意味においてのみ『死者』と言われている。すなわち、ヨハネはここで「霊的な死人」という意味も含めて『死者』という言葉を使っているのではない。もしこの言葉を霊的な死者という意味においてのみ捉えるならば、すなわち単にキリストを信じていない者たちという意味において捉え、肉体的に死亡してはいない者も含まれると考えるならば、上手な解釈が出来なくなってしまう。これは実際的な絶命者というふうに捉えないと駄目である。
次に『出した』とは、場所を移動させられることを示している。ヨハネは、この表現を律法から持ってきたと思われる。律法の中では、その場所からどかされることが「出す」という言い方で言われている。すなわち、レビ18:24~25ではこう言われている。『わたしがあなたがたの前から追い出そうとしている国々は、これらすべてのことによって汚れており、このように、その地も汚れており、それゆえ、わたしはその地の咎を罰するので、その地は、住民を吐き出すことになるからである。』黙示録のほうでは『出した』と言われ『吐き出す』とは言われていないが、これば些細な問題である。言葉が微妙に異なってはいるが、どちらでもそこからどかされて移動させられると言っていることに変わりはないからだ。
それでは、『海』また『死』『ハデス』とは何か。まず『死』は文字通りに捉えればよい。すなわち、これは実際的な肉体の死滅を意味している。『ハデス』という言葉も文字通りに捉えればよい。では『海』とは何であろうか。これは少し難しい。これは『底知れぬ所』である。つまり、これはハデスの言い換えである。ハデスが海として言い表されていることについては、既に例がある。すなわち、ネロは13:1で『海から』上って来たと言われていたが、少し前の11:7では『底知れぬ所から』上って来たと言われていた。海=底知れぬ所。この20:13でも、ハデスという意味において『海』と言われている。もっとも黙示録の中で『海』と書かれていたら、その全てがハデスを意味しているというのではない。中には文字通りの海を意味している箇所もある。例えば、8:8で言われているのは文字通りの『海』である。ところで、18:2の箇所で言われている3つの言葉は、その言われた方は違えど、どれも「悪霊」を意味していた。また8:7の箇所で言われていた3つの言葉も、全て地上の場所について言われていた。また8:12の箇所で言われていた3つの言葉も、例外なく天体について言われていた。それと同様に、この20:13で言われている3つの言葉も、全て死に関わることが言われている。すなわち、ここではハデス、死(=ハデス)、ハデス、と言われていることになる。もし『海』だけが地球上の場所について言われた言葉だとすれば、黙示録の規則に適合しなくなってしまう。黙示録で3つの言葉が連なっていた場合、それは明らかに強調の意味を持たせているのだから、そのどれもが同一の種類について言われているというのは明らかである(※)。だから、ここでもその規則が適用されていると考えるべきである。この箇所だけ規則にそぐわないというのは、おかしい。もし「海、死(=ハデス)、ハデス」と言われているとすれば、明らかに一つだけ仲間外れになるから、違和感が生じるのである。黙示録の他の箇所では、そのような語り方とはなっておらず、3つとも例外なく種類的に共通しているのだ。もし、この『海』という言葉を地球上の場所だと捉えると、この箇所で言われていることを正しく解釈出来なくなってしまう。注意が必要である。
(※)
つまり、黙示録で3つの連なる言葉が出てきた場合、正しい解釈は以下に示す通りとなる。「OK」は正しい解釈であり、「駄目」は間違った解釈である。また「A」と「B」は全く種類的に異なった内容の言葉である。
A・A・A =OK
A・A・B =駄目
A・B・A =駄目
A・B・B =駄目
B・A・A =駄目
B・A・B =駄目
B・B・A =駄目
B・B・B =OK
[本文に戻る]
要するに、ここでは第二の復活により復活した死亡者たちの復活が、大いに強調しつつ言われているのである。すなわち、「海で言い表されるハデスから悪者どもが復活した」「死んでハデスにいた悪者どもが復活した」「ハデスの中にいる悪者どもが復活した」と。ここでは『出した』と書かれているから、つまり悪者どもはハデスから復活して後、大審判の場に移されたことになる。黙示録の表現に慣れていないと、この箇所で言われていることを解釈するのは非常に難しいと思う。しかし、黙示録では他にも似たような表現方法が使われていることを知っていれば、この箇所の表現を読み解けるようにもなる。黙示録とは究極の言語パズルなのである。
『そして人々はおのおの自分の行ないに応じてさばかれた。』
第二の復活によりハデスの場所から復活した死んだ者たちは、御座に着いておられる方の御前で、『おのおの自分の行ないに応じてさばかれた。』これは前の聖句の中で『死んだ人々は、これらの書物に書きしるされているところに従って、自分の行ないに応じてさばかれた。』と言われていたことの繰り返しである。
【20:14】
『それから、死とハデスとは、火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。』
この箇所は、言い方が問題である。ここで言われているのは、つまり、こういうことである。「死んだ者、またハデスの中にいる者は火の池に投げ込まれた。」すなわち、ここでは単に「死んでハデスに行った者」という言葉が「死とハデス」という省略した形で言い表されているに過ぎない。このような省略した形で言われている箇所は聖書において珍しくない、というのは既に語られた通りである。だから、ここでそのような言い方がされていたとしても驚くべきではない。また、この20:11~15の箇所では、悪者と悪者が裁かれる出来事について語られているということを忘れてはならない。ここでは死という現象やハデスという場所について語られるのが主眼なのではない。それゆえ、文脈から考えても、これは死んでハデスの中に入れられていた悪者について言われているとすべきである。この『死とハデス』という言葉を文字通りに捉えるのは、すなわち省略されていない言葉として文字通りに捉えるのは誤りであって、そのように捉えると20:14の箇所を正しく解釈できなくなる。
それでは、どうしてこの箇所では『海』については触れられていないのか。先に見た20:13の箇所では、『死とハデス』だけでなく『海』についても書かれていたのだから、20:14でも『海』と書かれるべきではなかったのか。ここで『海』が書かれていない理由は何なのか。それはヨハネが、『海』については触れなくても十分だと考えたからである。何故なら、先にも述べたように『ハデス』という言葉は『海』と同じ意味だからである。この20:14の箇所では、20:13の箇所のように死に関する事柄を強調せねばならなかったというのでもなかった。だから、ここでは『海』を省いても良しとヨハネが判断したのだと考えるべきである。我々は、この回答だけで満足すべきである。これ以上の理由を求めるのは、僭越であると私には思われる。しかし、たとえ我々がこれ以上の理由を知らなかったとしても、何か致命的な問題が生じるというのでもないのだから、心配する必要はないと私は言いたい。
【20:15】
『いのちの書に名のしるされていない者はみな、この火の池に投げ込まれた。』
死んでハデスに投げ込まれたが第二の復活により復活した『いのちの書に名のしるされていない者』は、燃えるゲヘナへと投げ込まれてしまった。すなわち、大審判の際にキリストから『のろわれた者ども。わたしから離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火にはいれ。』(マタイ25章41節)と宣告されて、地獄へと入ることになった。これは前の聖句(20:14)の繰り返しである。このように同一の事柄を、異なった言い方で表現するのは古代ヘブル人の特徴である。
第27章 2421章1節~22章5節:天国について
とはいっても、黙示録では既に天国のことが、幾つかの箇所で啓示されていた。その箇所とは、7:9~17および14:1~5であった。黙示録が全て順序通りに書かれた文書だと無知と研究不足と神の呪いのゆえに考えている者たちは、黙示録の中で天国について語られているのは、この箇所だけであるという思い違いをしやすい。何故なら、その人たちは、黙示録が順序通りに書かれていると未熟さのため思い込んでおり、天国のことについては最後の部分で書かれているに違いないという盲目的な前提が頭の中にあるからである。しかし、そういうことはないのだ。豊かに天国のことが示されている部分は確かにこの箇所だけだが、豊かにというのでなければ既に天国のことは示されていたのである。
それにしても、黙示録の章区分をした人は、21章目以降においてとんでもない区分をしたものである。最初が21:1から始まるのに文句はない。私が章区分をしたとしても、こうしていたであろう。しかし最後の部分が問題である。章区分をした人は、どうして22:5までの部分を全て21章として纏めなかったのか。この21:1~22:5の箇所では天国のことが言われており、一緒の章に区分するのが適切なのだから、22:5までを21章とすべきであった。そして22:6の箇所から22章をスタートさせれば、実にスッキリした区分となっていた。私は、21章目以降の区分に納得ができない。黙示録の章区分をした人は、21章目以降の区分をする際に思慮を喪失していたとしか言いようがない。しかし今更になって嘆いても、一度決められた章区分はもう変更できないだろうから、実に残念だと思う。
【21:1】
『また私は、新しい天と新しい地とを見た。以前の天と、以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。』
この部分では、言わば前置きとしての序言的なことが言われている。すなわち、ここでは次のように言われているのである。「遂に天国が始まることになった。それは今までにはなかった出来事である。今から、この天国のことについて語られ始めるのだ。」これは創世記1章で言えば、『初めに、神が天と地を創造した。』(1:1)という序言的な部分に該当する。
『新しい天と新しい地』とは、すなわち「天国」のことを言っている。つまり、これは「天における新しい天と天における新しい地」という意味である。聖書において、「天と地」と書いてあった場合、いかなる箇所でも「神のおられる霊的な世界としての天と人間の住む地上世界」と捉えなければいけないということはない。中には、「天における天と天における天」(すなわち天国のみ)または「地における天と地における地」(すなわち地上のみ)というふうに捉えねばならない箇所も存在している。例えは創世記1:1がそうである。ここでは『初めに、神が天と地を創造した。』と書かれているが、この『天と地』とは「地上における天と地上における地」すなわち地上世界だけのことである。つまり、この箇所における『天』とは我々の地球上にある「大気圏」の意である。何故なら、創世記1:8の箇所では、『神は、その大空を天と名づけられた。』と書かれているからだ。『天』である『大空』とは地球の大気圏のことでなくて何であろうか。創世記1:1の『天と地』という言葉が、地上世界のことだけについて言われているというのは、アウグスティヌスやほかの教師たちも言っていることである。このように「天と地」と書かれていても、場所によっては天国のみか、または地上のみ、というふうに捉えねばならない箇所が聖書には幾つもある。この21:1もその一つである。「天と地」と書かれていたら絶対に神のおられる霊的な世界という意味の天と人間の住む世界という意味の地としか解釈できない人は、まだまだ聖書の精通度が足りないと言わねばならない。それでは、どうしてこの21:1の箇所では『新しい天と新しい地』という言葉が、すなわち「天国のみ」だと言えるのか。それは21:1~22:5の箇所とは、天国のことが言われている箇所だからである。この箇所をじっくりと見てみるがよい。そうすれば、この箇所が天国について説明されている箇所だということに気付くであろう。この箇所で言われているのは、天国、天国、天国、である。だから、『新しい天と新しい地』という言葉は「天国」に限定されるということになる。『以前の天と、以前の地』と言われているのも、同様に天国のことである。何故なら、それは『新しい天と新しい地』という言葉と、純粋に繋がっている意味でなければいけないからだ。それというのも、『新しい天と新しい地』とは『以前の天と、以前の地』という言葉よりも時間的に後の状態のことを言っただけの言葉であり、『以前の天と、以前の地』とは『新しい天と新しい地』という言葉よりも時間的に前の状態のことを言っただけの言葉だからである。この2つの言葉が、意味的に繋がっていない言葉として捉えるのは明らかに間違っている。
『もはや海もない。』とは、天国のことである。これは地上のことが言われた言葉ではない。というのも、21:1~22:5の箇所では、天国について説明されているからである。事実、天国には海など存在していないのである。これは、つまりこう言いたいのだ。すなわち、天国においてもはや海が見られることはないであろう。それゆえ、天国に導き入れられた聖徒たちは、そこで海を二度と見ることはないであろう、と。我々は、聖句が言っているように、『もはや海もない。』という出来事も『すぐに起こるはずの事』だったと理解せねばならない。つまり、海が無くなるという出来事は既に実現しているのだ。しかし、今の地上世界を見ると、海がまだ存在しているのは誰の目にも明らかである。それにもかかわらず、聖書は既に海が無くなる出来事は起きたと教えている。さて、これは一体どういうことであるか。解決は容易である。すなわち、それは地上のことを言っているのではない。これは天国におけることを言っているのだ。多くの人たちは、これが天国についてのことだと聞かされると、こう反論するかもしれない。「『もはや海もない。』という言葉は天国について言われているとあなたは言うが、『もはや』という言葉は、すなわち「かつては存在していた」ということを意味しているのだから、あなたは天国において海が存在していた時期があったとでも理解しているのか。」なるほど、この反論は、一見すると強力なように感じられなくもない。何故なら、確かに『もはや…ない』とは、換言すれば「以前はあった」ということになるからだ。だが私はこう反論する人に、逆に尋ねよう。すなわち、かつて天国には死や悲しみや叫びや苦しみ、また呪われる存在、また夜が存在していたのか、と。私がこう尋ねるのは、21:4で天国には『もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。』と書かれており、22:3でも天国には『もはや、のろわれるものは何もない。』と書かれており、22:5でもやはり天国には『もはや夜がない。』と書かれているからだ。もし『もはや』という言葉が「かつてはそこにあった。」という意味であるならば、例えば天ではかつて『夜』が存在していたのであろうか。確かに22:5では、天の場所について『もはや夜がない。』と言われている。また天ではかつて『呪われるもの』が存在していたのであろうか。確かに22:3では、天の場所について『もはや、のろわれるものは何もない。』と言われている。「否、そんなことは有り得ない。天に夜や呪いが存在していた時期は無かった。」と私に対して反論する人は答えるはずだ。何故か。何故ならば、22:5や22:3また21:4の箇所で言われているのは、天における昔の状態のことについてではなく、天に導き入れられた聖徒たちの「体験面」のことについてだからである。つまり、22:5では「もはや聖徒たちは天国で夜を見ることがない。」と言われており、22:3では「もはや聖徒たちは天国において呪いというものを見なくなる。」と言われているのだ。それと同じことが海についても言える。すなわち『もはや海もない。』というのは22:5や22:3の言葉と一緒の仕方で捉えるべきであって、それは「もはや聖徒たちは天国において海を見なくなる。」という意味として捉えるべきである。だから、もし『もはや海もない。』と書かれているので「かつてそこに海はあったのだ。」と理解するのであれば、『もはや夜がない。』と書かれているので「かつてそこに夜があったのだ。」とも理解せねばならなくなる。『もはや』という言葉を「かつてそこの場所に存在していた」と理解すべきであるとすれば、確かにそうである。しかし、天上の場所にかつて海や夜があったなどと誰が考えるであろうか。要するに、『もはや海もない。』とは、天国における聖徒たちの視点また感覚に基づいて言われた言葉である。黙示録において、このように難しい言い回しがされている箇所は多い。
ここで言われている出来事も、やはり『すぐに起こるはずの事』であった。それは空中の大審判が起きた直後であり、紀元70年9月である。自分の理性に立ち、神の言葉を拒絶するのであれば呪いを受けるがよい。逆らう者には呪いを発動させる神の言葉は、ここで言われている出来事も『すぐに起こる』と言っているのである。
この箇所で言われている出来事は、間違いなくイザヤ65:17~25の箇所と対応している。そこでは次のように書かれていた。『見よ。まことにわたしは新しい天と新しい地を創造する。先の事は思い出されず、心に上ることもない。だから、わたしの創造するものを、いついつまでも楽しみ喜べ。見よ。わたしはエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、わたしの民を楽しむ。そこにはもう、泣き声も叫び声も聞かれない。そこにはもう、数日しか生きない乳飲み子も、寿命の満ちない老人もない。百歳で死ぬ者は若かったとされ、百歳にならないで死ぬ者は、のろわれた者とされる。彼らは家を建てて住み、ぶどう畑を作って、その実を食べる。彼らが建てて他人が住むことはなく、彼らが植えて他人が食べることはない。わたしの民の寿命は、木の寿命に等しく、わたしの選んだ者は、自分の手で作った物を、存分に用いることができるからだ。彼らはむだに労することもなく、子を産んで、突然その子が死ぬこともない。彼らは主に祝福された者のすえであり、その子孫たちは彼らとともにいるからだ。彼らが呼ばないうちに、わたしは答え、彼らがまだ語っているうちに、わたしは聞く。狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように、わらを食べ、蛇は、ちりをその食べ物とし、わたしの聖なる山のどこにおいても、そこなわれることなく、滅ぼされることもない。」と主は仰せられる。』このイザヤ書の預言でも、やはり『新しい天と新しい地』と言われているのは天国のことに限られている。何故なら、『新しい天と新しい地』とは、すなわち新たに『創造』される『エルサレム』(65:18)であり『聖なる山』(65:25)だからである。新しいエルサレムと聖なる山とは、天国のことでなくて何であろうか。確かに、このイザヤ書の箇所を考察するならば、20:1で言われている『新しい天と新しい地』という言葉が天国のみを指すということは更に明らかとなる。何故なら、20:1とイザヤ65:17~25は対応しており、どちらも新天新地の創造について言われているからだ。黙示録のほうでは、イザヤ書のほうでも言われているその新天新地の創造が『すぐに起こる』と断言されている。つまり、新天新地の創造はヨハネが黙示録を書いてから『すぐに』も実現した。それゆえ、もう新天新地の創造は今の我々からすれば実現済みである。しかし今の地上世界を見渡しても、新天新地について書かれているイザヤ65:17~25の中で言われているような至福の状態は全く実現されていない。これは、新天新地という言葉が天国全体のことを意味しているからに他ならない。だからこそ、イザヤ65:17~25の預言は地上においては実現されていないのだ。これが実現されたのは天上の世界においてなのである。
【21:2】
『私はまた、聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神のみもとを出て、天から下って来るのを見た。』
『聖なる都、新しいエルサレム』とは、天上の教会である。何故なら、21:9の箇所では『聖なる都』が『子羊の妻である花嫁』と言われているからだ。『子羊』であるキリストの『花嫁』とは教会でなくて何であろうか。その花嫁なる教会が、ここでは『天から下って来る』と言われている。それゆえ、ここで言われている『聖なる都、新しいエルサレム』とは天上の教会であると結論すべきである。
天上の教会が、『夫のために飾られた花嫁のように整えられて』いたのは、天上の教会における完全性を示している。天上の教会は、愚かさや未熟さの見られる地上の教会とは違う。そこには少しの汚れさえも存在していない。もし僅かであっても汚れがあれば、それは最早、天上の教会とは言えない。だからこそ、ここでは完全な天上の教会が、完璧な状態として整えられていたと言われているのだ。また夫であるキリストは完全であられるから、妻である教会にも完全であることを欲しておられる。それは、『わたしが聖であるから、あなたがたも、聖でなければならない。』(Ⅰペテロ1章16節)と主が言っておられる通りである。『聖』とは完全であることである。だからこそ、ここでは教会が整えられて完全であると言われている。何故なら、教会とはキリストの妻だからである。もし教会が完全で無かったとすれば、キリストに相応しい存在では無かった。完全なキリストに、不完全な存在が、どうして相応しいであろうか。それは偉大で輝かしい皇帝に、卑しい奴隷の女が相応しくないのと同じことである。
それでは、その教会が『天から下って来る』とは、どういった意味なのか。これは言い方が問題である。これは、つまり聖徒たちにやがて神から天上の教会がその住まうべき場所として与えられる、という意味である。実際は、聖徒たちが天の場所に行き、そこにある教会に与かることになる。すなわち、実際は天から教会が聖徒たちのほうに下って来るというわけではない。それにもかかわらず、ここでは教会のほうが聖徒たちに下って来るかのように言われている。これは、天上の教会が神の恵みにより聖徒たちに与えられるということを、よく分からせるためであった。つまり、ここで言われているのは、天上の教会に住まうことが出来るのは、上から下される神の恵みに基づくということである。何故なら、天上の教会に与かれるという神の恵みは、聖徒たちに上から注がれるものだからである。神の恵みが上から注がれて下って来るということを疑う聖徒はいないはずだ。ヤコブもこう言っている。『すべての良い贈り物、また、すべての完全な賜物は上から来るのであって、光を造られた父から下るのです。』(ヤコブ1章17節)
21世紀のオジアンダーは、この箇所を読んで、この地上世界に天国が展開されるなどという珍奇な考えを軽率にも夢想している。というのも、ここでは天国が『天から下って来る』と書かれているからである。つまり、天国が天から下って来るので、その下って来た天国が地上に繰り広げられるというわけである。このような無知に基づく夢想は、はっきり言ってお話にならない。この21:2の箇所で言われている出来事は、『すぐに起こるはずの事』だったのだ。つまり、この21:2で言われている出来事は、既に実現されている。このオジアンダーは20章で言われている『千年』が非常に長い期間であると勝手に思い込んでおり、今の時代は20:1~6の箇所に該当していると誤って考えているので、私が21:2の箇所も含めて黙示録は既に全て成就していると言っても聞く耳を持たないで反発する。しかも、『千年』が長い期間であるという確固たる根拠聖句を持っているのかと思いきや、自分のほうから「そんな聖句は聖書にない。」などと躊躇することもせず言う始末である。普通であれば、根拠聖句があるからこそ『千年』について堂々と論じられるものであろう。だが、このオジアンダーは根拠聖句が無いのにもかかわらず堂々とこの期間について、さもどういう意味か分かっているかのように確言するのだ。読者は既に理解しておられると思うが、この期間は既に説明したように『1260日』という短い期間である。だから、21:2の箇所も『すぐに起こるはずの事』だったことになるのだ。何故なら、千年が非常に短い期間だとすれば、黙示録の出来事が『すぐに起こるはずの事』だったと考える際において、20:1~6の箇所が言わば「つっかえ棒」とはならなくなるからだ。千年が短ければ、『すぐに起こるはずの事』という神の言葉を、何の妨げもなく黙示録の全体に関わらせることが可能となる。千年は短いのだから、我々は実際に『すぐに起こるはずの事』という御言葉を黙示録の全ての部分に関わらせるべきである。ところが、このオジアンダーは千年を無知と研究不足と神の呪いのゆえに正しく解釈できていないので―彼の黙示録理解は非常に浅い―、この千年という言葉が妨げとなり、『すぐに起こるはずの事』という御言葉を20:1~6の箇所よりも前の部分にしか関わらせることが出来ていない。これではいけない。また、この21:2の箇所で天国が『天から下って来る』と言われているからといって、地上に天国が展開されるなどと考えるのは、一体どういうことであろうか。これは大変おかしい見解である。聖書は、この地上世界が天国になるなどとは教えていない。聖書が教えているのは、天上の世界に天国があるということである。これは未信者でさえ知っていることである。この天にこそ我々の永遠の住まいである天国があるのだ。実際、聖書は次のように言っている。『けれども、私たちの国籍は天にあります。』(ピリピ3:20)これは聖徒たちが自分の国籍のある天で永遠に住まうということである。『私たちは、この地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。』(ヘブル13:14)ここでは地上の場所に天国があるのではないことが教えられている。『これらの人々はみな、信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって、自分の故郷を求めていることを示しています。もし、出て来た故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし、事実、彼らは、さらにすぐれた故郷、すなわち天の故郷にあこがれていたのです。それゆえ、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。』(ヘブル11章13~16節)ここでは紛れもなく明瞭に天国が地上にあるという見解が否定されている。何故なら地上とは寄留の場に過ぎない場所だと教えられているからだ。『わたしの父の家には、住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなたがたに言っておいたことでしょう。あなたがたのために、わたしは場所を備えに行くのです。わたしが行って、あなたがたに場所を備えたら、また来て、あなたがたをわたしのもとに迎えます。わたしのいる所に、あなたがたをもおらせるためです。』(ヨハネ14章2~3節)ここでキリストは天上にこそ聖徒たちの住まう場所が備えられていると言っておられる。ここでは地上にその天の住まいが降りて来るなどとは少しも言われていない。オジアンダーは、21:2の箇所で『天から下って来る』と言われているのを文字通りに捉えるというミスを犯している。また、実際に降りて来ると思っている天国を地上世界に繰り広げるという二重のミスを犯している。更に『千年』を正しく理解していないために21:2の箇所を未だに実現していないと考えているという三重のミスを犯している。彼は黙示録をほとんど論じることが出来ていないのだから、黙示録について浅い理解しか持てていないのは明白である。その浅い理解が、このような3重のミスを生じさせてしまったのである。読者は、彼のようなミスに陥らないように注意してほしい。
これ以降、天国において教会はキリストと共に永遠に歩むことになった。それは結婚した夫婦に例えることができる。というのも、結婚したら一組みの男女は夫婦としてずっと共に歩むことになるからである。だからこそ、聖書では教会とキリストが一緒に天国で生きるようになる幸いを、男女が結婚して夫婦になる幸いになぞらえているわけである。この教会とキリストの結婚については、19:6~10の箇所でも語られていた。黙示録の中でこの結婚について語られているのは、我々が今見ている21章の箇所と19章の箇所の2つ以外にはない。
【21:3】
『そのとき私は、御座から出る大きな声がこう言うのを聞いた。』
『御座から出る大きな声』の主は、セラフィムである。何故そう言えるのか。それは、まず第一にセラフィムは御座の場所にいるからである。4:6ではセラフィムが『御座の中央』にいたと書かれている。第二に、この声は明らかに神を他者として取り扱っている。もしこの声が神御自身によるものだったとすれば、神を他者としては取り扱っていなかったはずである。第三に、この声が言っていることは、正にセラフィムが語ることに相応しい。それはイザヤ6:3の箇所を見れば分かることである。以上の3点から、これはセラフィムの声だったと結論できる。この声の主を神御自身だと捉えるのは非常に難しいと私には思われる。
『「見よ。神の幕屋が人とともにある。』
神は、天国において人である聖徒たちを永遠の幕屋として歩まれる。ここで言われている『幕屋』を、我々は『聖所』(エゼキエル書37:26、28)また『神殿』(Ⅰコリント3章16節)と読み替えることが出来る。何故なら、ここで言われているのは「神の住まい」のことだからである。幕屋であれ聖所であれ神殿であれ、それが神の住まいであることには変わらないのだ。なお、この箇所を読んで、我々は神の幕屋が聖徒たちと別々に存在するかのように理解してはならない。ここで言われているのは、聖徒たち自身が神の住まわれる幕屋であるということである。
聖徒たちという名の『幕屋』については、13:6の箇所でも言及されていた。私はその箇所でも、この『幕屋』について幾らかのことを語っておいた。
『神は彼らとともに住み、彼らはその民となる。』
天国において、神はそこに招かれた聖徒たちを、永遠に御自身の民とされる。その聖徒たちは、とこしえまでも自分たちの神と『ともに住』むようになる。何故なら、あらかじめ、そうなるようにと神が決定しておられたからである。そこにおいて、遂に神の決定が、定められた聖徒たちにおいて永遠の効力を発揮するのだ。なお、ここでは天国に招き入れられて初めて聖徒たちが『その民とな』ったと言われているのではないことに、注意せねばならない。言うまでもなく、聖徒たちは天国に入るよりも前から、既に『その民』であった。というのは、聖徒たちは救われた時点で、キリストにおいて神の民となったからである。では、どうしてここでは天国に入れられてから初めて聖徒たちが『その民』となったかのように言われているのか。これは、つまり希望が遂に現実のものとして実現されたということである。聖徒たちは、やがて天国で永遠に神の民として生きられるようになるという希望を、キリストにあって抱いていた。その希望が遂に天国に入れられることで実現された。そのような意味で、ここでは天国に入れられた聖徒たちが『その民となる』と言われているのだ。それだから、この箇所を読んで、もし天国に入るよりも前には聖徒たちが神の民では無かったと考えるのであれば、それは大きな間違いである。
この21:3の箇所は、明らかにレビ記26:11~12の箇所と対応している。そこでは次のように言われていた。『わたしはあなたがたの間にわたしの住まいを建てよう。わたしはあなたがたを忌みきらわない。わたしはあなたがたの間を歩もう。わたしはあなたがたの神となり、あなたがたはわたしの民となる。』
【21:3~4】
『また、神ご自身が彼らとともにおられて、彼らの目の涙をすっかりぬぐい取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものが、もはや過ぎ去ったからである。」』
天国では、神の祝福に満ちた慰めと幸いな臨在とが満ち満ちている。そこには良いもの以外には存在していない。その場所は、あたかも幸いな羊飼いに飼われた羊たちが、安心と喜びに満たされつつ草を食べているような場所である。それゆえ、そこにいる羊なる聖徒たちは、何も不満を感じない。ダビデも次のように言っている通りである。『主は私の羊飼い。私は、乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、いこいの水のほとりに伴われます。』(詩篇23:1~2)このような場所こそ正に天国である。
天国に導き入れられた聖徒たちには、『もはや死もな』い。何故なら、彼らには『キリスト・イエスにある永遠のいのち』(ローマ6章23節)が与えられているからである。もし死ぬことがあるとすれば、それは、もはや『永遠のいのち』ではない。また彼らは『悲しみ』を味わうこともない。何故なら、天国には『もはや、のろわれるものは何もない。』(22:3)からである。悲しみとは、全て呪いのゆえに生じるものである。天国には呪いが無いゆえ、悲しみも無いのだ。また彼らは『叫び』をあげることもない。これも、そこには呪いが無いからである。それと同様に『苦しみもない。』呪いが全く無ければ、苦しみが生じることも全く有り得ないのである。要するに、これらのことは次のようにまとめて言うことができる。すなわち、「天国には悪いものが塵ほどさえもない。」と。
それでは、どうして天国には悪いものが何も存在していないのか。どうして天国に招かれた聖徒たちは、そのような幸いを享受できるのか。それは、『以前のものが、もはや過ぎ去ったからである。』とヨハネは言っている。天国とは、この地上世界とは性質的に異なった聖なる場所である。その天国に聖徒たちが導き入れられるというのは、古い世界から脱離することを意味している。それは大いなる移行である。その移行が実現すると、もはや聖徒たちは過去の世界に住んでいたようではなくなる。だからこそ、ここでは悪の存在しない天国という場所について、『以前のものが、もはや過ぎ去った』と言われているのである。つまり、悪の存在しない天国に移されたゆえ、そこに移された聖徒たちは悪を味わうことがなくなった、ということである。
キリストの救いが目的としている点は、実にここにあった。すなわち、キリストは選ばれた者たちがこのような幸いを享受できるようにと、御自身を永遠の犠牲として父なる神にお捧げになった。それゆえ、キリストを信じて救われた者たちは、その救いのゆえに、このような場所である天国に導かれて幸いを受けられるようになるのだ。それは、そこにおいて聖徒たちが豊かな恵みを神に感謝し、神の栄光が顕されるためである。パウロが救われるようにと選ばれていた聖徒たちの定めにおける理由ついて、『神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が、ほめたたえられるため』(エペソ1:6)であったと言っている通りである。それだから、聖徒たちは天国において、永遠に神の恵みを感謝せねばならないのである。そうするからこそ、キリストの救いの目的としていた点―神の栄光の顕現―が、豊かに実現されることになるのだから。それゆえ、もし天国にいる聖徒たちが神に感謝しなかったとすれば、それは甚だしい忘恩であって、キリストの救いを蔑ろにしていることになるのだ。もっとも、天国で神に感謝しない聖徒たちは一人もいないのではあるが。
この箇所はイザヤ35:10(=51:11)と対応している。そこではこう言われていた。『主に贖われた者たちは帰って来る。彼らは喜び歌いながらシオンにはいり、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついて来、嘆きと悲しみとは逃げ去る。』シオンとは天上のパラダイスのことだから、正にイザヤの言ったのは黙示録21章のことである。
【21:5】
『すると、御座に着いておられる方が言われた。』
『御座に着いておられる方』とは、間違いなく父なる神である。黙示録の中で『御座に着いておられる』のは、父なる神か子なる神の他にはいない。21:5で御座に着いておられる方は、少し後の21:7で聖徒たちが『わたしの子となる。』と言っておられるのだから、間違いなく父なる神である。もしこれが子なる神であれば、聖徒たちを『子』としては取り扱わなかったであろう。何故なら、聖徒たちが子であるのは、父なる神に対してであって、子なる神に対してではないからである。聖徒たちは父なる神にとって『子』だが、子なる神にとっては『兄弟』(ローマ8章29節)また『友』(ヨハネ15章14~15節)である。だから、ここで言われている『御座に着いておられる方』とは、聖徒たちを子として取り扱っているがゆえ、父なる神であると理解せねばならない。ヨハネは、このように実名をあげないで言うことで、より難解さの度合いを高めている。それは、理解できない者がますます黙示録を理解できなくなるためであった。黙示録とは言わば「分かる者だけが分かればよい秘密の文書」なのだから。
ここで出てくるのが神だとすれば、前の箇所(21:3~4)に出てきた存在は神でないことになる。何故なら、ここで出てきたのが神なのに、どうして前の箇所に出てきたのも神なのであろうか。ここでも神が、前の箇所でも神が、などということが果たしてあるのか。10歳の子供でもないと分かるはずだ。であれば、前の箇所に出てきたのは神でないゆえ、やはりセラフィムだったということにもなる。もっとも、4人のセラフィムのうち、どのセラフィムだったかということについては不明であるが。
父なる神は、ここから20:8までの箇所で、3つのことを言っておられる。すなわち、第一に更新についての宣言が(20:5)、第二にヨハネに対する記述の命令が(20:5)、第三に約束と威嚇が(20:6~8)、語られている。ここではこのように3つの事柄が3つに区切られつつ言われており、非常に分かりやすくなっている。しかも驚くほど簡潔に書かれている。
『「見よ。わたしは、すべてを新しくする。」』
紀元70年9月に神は『すべてを新しく』された。だが、『すべて』とは一体どういう意味における『すべて』なのか。それは天上の世界における『すべて』である。何故なら、紀元70年9月になっても、地上世界は刷新されたように感じられないからである。しかし天はといえばどうか。そこでは正式に神の王国が始まり、遂に聖徒たちが新しい御霊の身体を持ちつつ生活するようになり、キリストがその聖徒たちを実際的に統御されるようになり、もはやサタンもかつてのようにその場所には見られなくなった。もうそこでは聖徒たちが霊だけの状態として留まり続けていることもなくなった。これは驚くべき変わり様であり、まったく以前の状態とは異なっている。あたかも別の世界に移行したかのようである。一方、地上のほうではこのように驚異的なリニューアルが確認できない。それだから、多くの人は紀元70年9月に地上が変わったと聞かされたとしても、それを不思議がって「何も変わっていないではないか。」と言うことになる。そうだ。確かに地上のほうは変わっていないのだ。よって、ここで言われているのは天についてだと理解すべきである。我々が今見ている21:1~22:5の箇所は天国について言われた箇所だから、この『すべて』という言葉が天を指しているというのは文脈にも適合している。聖書では『すべて』と書かれていても、その箇所によってそれぞれ色々な意味を持っているから注意が必要である。『すべて』と書かれていたからといって、即座に文字通りの意味で『すべて』と解するようでは駄目である。そのような人は、まだまだ未熟な解釈者だと言わねばならない。
『また言われた。「書きしるせ。これらのことばは、信ずべきものであり、真実である。」』
『これらのことば』とは、どの言葉なのか。これは、天国についての言葉であると思われる。すなわち、21:3~4の箇所で言われていた言葉がそうである。しかし、これをこれまでに語られてきた言葉であると解することも不可能ではない。すなわち、4:1の箇所からここまでの言葉が『これらのことば』であると解するのが、そうである。私としては、これは21:3~4の箇所が該当していると思うが、黙示録の全体を指していると考える人と言い争うつもりはない。それでは、どうして『これらのことば』をヨハネは書き記すべきであったのか。それは、それが『信ずべきものであり、真実であ』ったからである。つまり、ヨハネは黙示録で言われたことを読者たちに受け入れさせるために、こう書いたのだ。何故なら、このように言わなければ、言われていることが受け入れられなくなることにもなるからである。ヨハネは、福音書の19:35の箇所でも、似たようなことを言っている。ヨハネとは、このような書き方で、読者にそこで言われていることを受け入れさせようとする人であった。もっとも、この黙示録では福音書の場合と違って、ヨハネが自分からこう言ったというのではなく、キリストがそう言われたからというので、このように言ったのではあるが。ヨハネは『書きしるせ。』と言われたので、自分の聞いた言葉を実際に書き記した。我々が黙示録の中で、その書かれた文章を見ている通りである。
前に見た19:9の箇所でも、御使いがヨハネに『書きなさい。』と言っていた。また1:19の箇所でも、キリストが『書きしるせ。』とヨハネに言っておられた。このようにヨハネに命令されたのは当然であった。何故なら、ヨハネは黙示録という文書を書き記すためにこそ、御使いとキリストから多くの幻を見せられ、また様々な声や音を聞かされたのだからである。もしヨハネが黙示録を書き記すために選ばれていなかったとすれば、恐らくヨハネは幻を見なかっただろうし、また声や音も聞かされなかったであろう。
【21:6】
『また言われた。「事は成就した。』
『事』とは何か。第一に考えられるのは「天国に関する預言」である。すなわち、21:1~4で言われている天国の事柄が『事』であると考えるのだ。第二に考えられるのは「聖書にあるあらゆる預言」である。天上に神の国が実現するという出来事は、預言における最後の出来事である。ここでは、その天国の実現について啓示されている箇所(21:1~4)の中で、『事は成就した。』と言われている。だから、ここでは全ての啓示が成就したと言われていると捉えることもできる。この『事』という言葉は、今述べた2つの解釈のうち、どちらにも取れる。各人は自分の好きなほうを選べばよいと思う。どちらを選んでも誤ることにはならないから。私はといえば、2番目の捉え方のほうに傾いているが、1番目の捉え方も捨て去るべきではないと現時点では考えている。
『わたしはアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。』
この言葉は1:8、17、2:8で既出である。
『わたしは、渇く者には、いのちの水の泉から、価なしに飲ませる。』
この箇所では、霊的に渇いている者は、キリストにおいて『いのちの水の泉から』豊かに水を飲むようになれ、と勧められている。つまり、キリストを信じ、聖霊を受けて霊的に潤うようにせよ、ということである。もしキリストを信じて救われるのであれば、その人は『いのちの水の泉から』豊かに水を汲んで飲むことができる。何故なら、その人は聖霊を受けて潤うからだ。しかしキリストを信ぜず救われなければ、その人に『いのちの水の泉』はない。その人には聖霊が与えられていないからだ。ここでは、このように言われることで、聖徒たちがキリストの救いのうちに留まるようにされている。というのも、キリストの救いに留まるからこそ、永遠に至るまでも『いのちの水の泉』に与かれるようになるからである。もしキリストの救いから落ちるならば、その人から『いのちの水の泉』に与かる恵みは取り去られることになる。それゆえ、このように聞かされた聖徒たちは、ますますキリスト信仰に留まるようにと良き刺激を受けるのである。
この言葉は、明らかに福音書におけるキリストの御言葉と対応している。キリストは福音書の中でこう言われた。『だれでも渇いているなら、わたしのもとに来て飲みなさい。わたしを信じる者は、聖書が言っているとおりに、その人の心の奥底から、いける水の川が流れ出るようになる。』(ヨハネ7章37~38節)『わたしが与える水を飲む者はだれでも、決して渇くことがありません。わたしが与える水は、その人のうちで泉となり、永遠のいのちへの水がわき出ます。』(同4章14節)この21:6の箇所で言われているのは、このようにキリストの御言葉と対応しているのだが、だからといってこの箇所で言っておられるのがキリストであられるというわけではない。何故なら、先にも述べたように、もしこれがキリストであるとすれば、聖徒たちを『子』としては取り扱われなかったはずだからである。つまり、この箇所では父なる神がキリストの言われた言葉と同じ内容のことを言っておられるに過ぎないのだ。
先に見たすぐ前の句は、この箇所の内容に掛かっていると思われる。すなわち、こういうことになる。「神である私はアルファであり、オメガである。だから、渇いている者に永遠の潤いを与えることができる。よって、渇いている者は、私から命の水を飲ませてもらえるように求めよ。」しかし、すぐ前の句であるこの『わたしはアルファであり、云々』という言葉を、それよりも前の句である『事は成就した。』という部分にかからせる人もいるかもしれない。その場合、次のように言われていることになる。「神である私はアルファであり、オメガである。そのような存在である私が、全ての事を成就させたのだ。」このような見解を持つ人を、私は何も批判しない。この見解も不可能な見解ではないからだ。だが、この見解よりも私の述べた見解のほうが、よりもっとらしいと私としては感じられる。
【21:7】
『勝利を得る者は、これらのものを相続する。』
『勝利を得る者』とは、「最後までキリスト信仰に保たれて脱落しなかった者」という意味である。これについては2~3章の註解で十分に説明しておいた。
この勝利者が相続する『これらのもの』とは何か。これは、21:3~4の箇所で言われていた諸々の恵みを指していると思われる。というのも、そのように解するのが自然だからである。21:3~4の箇所で言われているのは複数の事柄だから、この箇所で言われている『これらのもの』という複数形の言葉と適合している。これをすぐ前の箇所である21:6に書いてある『いのちの水』だと解するのは、少し難しい。というのは、『いのちの水』とは複数の事柄ではないので、『これらのもの』という複数形の言葉と適合していないからだ。この『これらのもの』という言葉は、今述べた2つのうち、どちらかであると解する以外にはない。何故なら、これよりも前の箇所を遡ってみても、この2つ以外には『これらのもの』という言葉に該当するものは見出されないからである。
『わたしは彼の神となり、彼はわたしの子となる。』
最後までキリストに保たれて勝利した聖徒たちは、天において永遠に神を自分の神とし、神の子として生き続けるようになる。何故なら、その人は、そのような運命を持つようにと、永遠の昔から定められていたからである。このようになるのは恵みの極みである。このような恵みを受けられる者は、本当に幸いである。
ここで注意しなければならないのは、聖徒たちが神の子となるといっても、それは本来的な意味で神の子とされるというのではなく、あくまでも養子としての子とされるという点である。聖徒たちはパウロも言うように『生まれながら御怒りを受けるべき子ら』(エペソ2章3節)だったのであり、元から神の子らだったというわけではない。元からの子、すなわち生来的な意味での子は、ただイエス・キリストお一人だけである。このお方だけは、我々とは違って養子としての子なのではない。
21:3や20:4の箇所の場合と同じで、ここでも聖徒たちが勝利してから初めて神を神とし、神の子となった、というわけではない。言うまでもなく、聖徒たちは勝利する前から既に神を神とし、神の子として歩んでいた。ここで言われているのは、聖徒たちが勝利して天に招き入れられることで、遂に聖徒たちが神を神とする神の子であったという事実に確認の印が押されるということに他ならない。もし勝利するまで聖徒たちは神を神としておらず、また神の子でも無かったというのであれば、聖徒たちはサタンを神としており、またサタンの子であったということになる。これはふざけた理解である。これは全く有り得ないことだ。それが有り得ないというのであれば、聖徒たちは勝利する以前から既に神を神とし、また神の子として存在しているということになる。
天に挙げられて神を神とし、神の子として永遠に至るまでも生きたいと願う聖徒はキリストから離れるべきでない。キリストに保たれ続けるからこそ、その願いが天において現実となるのだ。もし救い主から脱落するのであれば、その人は失格者となり、火の池を己の永遠の住まいとすることになる。
【21:8】
『しかし、おくびょう者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不品行の者、魔術を行なう者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。」』
勝利を得ない者は、天国に招き入れられず、『火と硫黄との燃える池』に投げ込まれて『第二の死』を味わうことになる。このような者たちは勝利しなかったので、つまり「敗北者」である。敗北した者は、戦争の例を見れば分かるように、悲惨になるのが常である。戦争で敗北した者が悲惨になって苦しむように、人間として敗北した者たちも敗北者に相応しく悲惨になって苦しむのだ。
勝利を得ない者とは、次のような者たちである。『おくびょう者』。臆病な者たちは、人の目を恐れるので信仰の道に入ろうとはしない。ソロモンは、『人を恐れるとわなにかかる。』(箴言29章25節)と言っている。彼らは臆病になっているので不信仰という罠にかかっているのだ。信仰の道に入らなければ救いはない。それゆえ、『おくびょう者』は地獄に投げ込まれる。『不信仰の者』。不信仰な者についてキリストはこう言っておられる。『信じない者は罪に定められます。』(マルコ16章16節)不信仰の者は、不信仰に陥っているので、地獄に入れられて永遠にその不信仰に対する罰を受ける。神は不信仰な者に対して容赦されない。『憎むべき者』。これは神の前で忌まわしい存在のことである。裏切者のユダがこれに該当する。そのような者は『生まれなかったほうがよかった』(マタイ26章24節)ので、その忌まわしさに相応しく、火の池で永遠に焼き続けられることになる。『人を殺す者』。殺人を犯す者は、不法を行なう者である。不法者に神はこう宣言される。『不法をなす者ども。わたしから離れて行け。』(マタイ7章23節)人を殺す者は天国に相応しくないので、神から退けられて地獄に投げ落とされる。『不品行の者』。不品行な者は、ただでは済まない。ヘブル書では次のように言われている。『神は不品行な者と姦淫を行なう者とをさばかれる』(13章4節)。不品行な者は、裁かれるべき存在なので、地獄に入れられて永遠に裁かれることになる。『魔術を行なう者』。魔術とは神への公然たる反逆であり、神を無視した人間独自の体系を傲慢にも打ち立てることである。律法はこの魔術を死罪と定めている(出エジプト記22:18)。それだから、アレスター・クロウリーのような死罪を犯している者―彼は魔術のカリスマである―が天国に行くことは有り得ない。『偶像を拝む者』。偶像崇拝者どもは神を神としておらず、むしろサタンが彼らの神である。彼らはサタンと同類の徒なので、そのような存在に相応しく永遠の断罪を受ける。永遠の火は、偶像崇拝者どものために用意されているのだ。『偽りを言う者ども』。偽りを言う者どもには、真実がない。彼らには真実がないので、「偽り者」と呼ばれねばならない。そのような偽り者は永遠に滅ぼされることになる。ダビデが、『あなたは偽りを言う者どもを滅ぼされます。』(詩篇5:5)と言っている通りである。言うまでもなく、ここではこれらのような悪を犯した者が、少しでもそのような悪に陥ったならば火の池に投げ込まれねばならない、と言われているわけではない。もしそういうことであったとすれば、ダビデもモーセもペテロも永遠の火に入らなければならないことになる。何故なら、ダビデは殺人と不品行の罪を犯し、モーセは憎むべきことを行ない、ペテロは偽りを言ったり臆病になったからである。ここで言われているのは、このような悪を犯しながらあくまでも悔い改めようとしない不敬虔な者についてである。もし1回でもここで挙げられているような悪を犯したらアウトだというのであれば、誰一人として永遠の地獄を免れることは出来なかったであろう。なお、この箇所の内容は、Ⅰコリント6:9~10の内容と似通っている。そこでパウロは次のように言っている。『あなたがたは、正しくない者は神の国を相続できないことを、知らないのですか。だまされてはいけません。不品行な者、偶像を礼拝する者、姦淫をする者、男娼となる者、男色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者はみな、神の国を相続することができません。』パウロも黙示録21:8と同じように、ここで様々な悪を列挙し、そのような悪に歩む者は天国に入れない、すなわち地獄に投げ込まれるであろうと威嚇している。
要するに、ここで挙げられているような悪に陥っている者たちは、そもそも救われておらず、救われていないので御霊も持っていないのである。救われておらず、御霊も持っていないからこそ、ここで挙げられているような悪に陥るというわけだ。もし救われた御霊を持つ者であったとすれば、ここに挙げられているような悪に歩まなかっただろうし、たとえ歩んだとしても必ずいつかはそれから離れていたであろう。神の子たちが、ここで挙げられているような悪に歩み続けることはできないはずだからである。それゆえ、ここで言われているような者たちは、その行ないにより、自分たちが地獄の子どもであることをみずから証明している。だからこそ、ここでは様々な罪を犯している者たちが、勝利することもなく『火と硫黄との燃える池の中に』投げ込まれると言われているのだ。
【21:9】
『また、最後の7つの災害の満ちているあの7つの鉢を持っていた7人の御使いのひとりが来た。彼は私に話して、こう言った。』
『最後の』とは、「古い時代の最後の時に起こる」という意味である。これについては既に説明しておいた。今まで全ての人が、この『最後』という言葉を、巻き物とラッパと鉢という順序における3連弾に重ねられた預言の最終局面というふうに捉えてきた。しかし、そのような捉え方は間違っていた。何故なら、もうお分かりだと思うが、巻き物とラッパと鉢の預言に順序の繋がりはないからである。そのような間違った捉え方をしていたのが、今まで教会が黙示録を正しく解釈できなかった最大の理由の一つである。巻き物とラッパと鉢についての事柄を正しく捉えていないのであれば、黙示録の全体を正しく解釈できなくなるのは必然である。何故なら、これら3つの預言は、黙示録において大きな場所を占めているからである。黙示録を全て正しく解釈したいと思う人は、もし本当にそう思うのであれば、一度騙されたと思って私の言ったように巻き物とラッパと鉢を捉えてみなさい。すなわち、これら3つのものが、それぞれ独立した預言であると捉えるのだ。そうすれば、黙示録を正しく解釈できるための道が開かれるであろう。黙示録を分からないままでいたい人は、ずっと「巻き物→ラッパ→鉢」という順番で預言の話が進むという従来の誤った捉え方に固辞し続ければよいのだ。
ヨハネの前に来たのは『7つの鉢を持っていた7人の御使いのひとり』なのだが、これが何番目の鉢を持つ御使いだったかは分からない。というのも、この御使いについて何も詳しいことは書かれていないからである。この御使いが何番目かということについては、推測するのも出来ない。何故なら、この御使いがこれから示す天上の教会に関する事柄は、7つの鉢の内容のどれに適合しているか見当がつかないからである。もし天上について預言している鉢があれば、21章の内容と適合しているのだから、その鉢を持つ御使いこそが21:9の箇所でヨハネの前に来たことになるが、実際にはそのような鉢はなかった。だから、この御使いが何番目か確定することは難しい。とはいっても、それを知らなくても別に問題は生じないから、何か不安になったりする必要はない。
この御使いがこれから示す天上の教会に関する事柄は、先に書かれていた7つの鉢の続きとして見做されるべきである。つまり、こう言って許されるのであれば、これは「第八の鉢」なのである。何故なら、この御使いは鉢を持っていた御使いの一人だからである。その御使いが来て天上の幻を示したというのは、つまり、その幻の示す事柄が7つの鉢に結び付けて考えられるべきことを我々に要請している。
【21:9~10】
『「ここに来なさい。私はあなたに、子羊の妻である花嫁を見せましょう。」そして、御使いは御霊によって私を大きな高い山に連れて行って、聖なる都エルサレムが神のみもとを出て、天から下って来るのを見せた。』
『大きな高い山』とは、イザヤ65:17~25の箇所によれば『新しい天と新しい地』である。それというのも、イザヤ65:25では、この『新しい天と新しい地』がすなわち『わたしの聖なる山』と言われているからである。それで、この『新しい天と新しい地』とは「天国」のことである。何故なら、先にも述べたが、これは天国における天と地すなわち天上の世界全体のことを言っている言葉だからである。しかし、どうして天国が高い山として表現されているのか。それは、高い山は、位置的に高いので、いと高き場所にある天国を地球上で最も反映させる場所だからである。地球上で位置的に最も天国に近いのが高い山だというのは、誰も疑わないはずだ。キリストがよく山に登られたのも、山が神のおられる天をよく象徴しているからであった。旧約時代において異邦人たちがヤハウェ神を「山の神」と呼んだのも、ユダヤの神が山において象徴される天国を人に与えられる唯一真の神だったからに他ならない。それだから、神は異邦人たちから「山の神」と呼ばれるのを恥とはなさらなかったのである。
御使いは、御霊に導かれたヨハネを、天国であるこの『高い山に連れて行っ』た。それは天国にある天上の教会がこれから聖徒たちに与えられるようになるということを、幻においてヨハネに示すためであった。ここでその教会が『下って来る』と言われているのは、先にも述べたように、「与えられる」という意味である。つまり『下って来る』=「教会に与かれる恵みが上から下される」ということである。ここでは天上の教会が地上の場所に降りて来ると言われているのではないことに注意しなければいけない。
先に見た21:2の箇所では、天上のエルサレムが単に天から下って来ると言われていただけであった。しかし今度は、天上のエルサレムが天から下って来ると言われるだけでなく、その詳細が豊かに示されることになった。これからその詳細について言われている箇所を見ていく通りである。例のように、これはユダヤ人特有の書き方であって、まず最初に全体的なことを短く述べ、そうしてから後に詳しい描写へと入っていくわけである。
【21:11】
『都には神の栄光があった。』
『都』すなわち『子羊の妻である花嫁』(21:9)としての天上の教会には、神の栄光が満ち満ちている。何故なら、『その都を設計し建設されたのは神』(ヘブル11章10節)だからである。栄光の神が造られたのであれば、天上の都は栄光に満ちざるを得ない。何故なら、神は御自身の栄光を求めるお方であり、全てを御自身の栄光を表すために行われるからだ。だから、もし都が神の栄光に満ちていなかったとすれば、それはそもそも神の都ではないし、神が造られたものでもなかった。これは、ちょうど偉大な陶芸家が更に自分の名を上げようとして素晴らしい陶器を造り、人々が大いに関心するようなものである。この都にある神の栄光が、22:21の箇所まで詳しく示されている。
『その輝きは高価な宝石に似ており、透き通った碧玉のようであった。』
天上の教会にあった神の栄光の輝きは、『高価な宝石』が放つ輝きのように見えた。それは、いかなる宝石の輝きよりも輝かしかったと考えるべきである。何故なら、全ての宝石の元となる原石を創造された神が、それら全ての原石よりも遥かに上回る輝きを持っておられないということが、一体どうしてあるのであろうか。神が、全ての宝石と全ての原石を合わせた輝きよりも輝かしい輝きを有しておられることは疑い得ない。それだから、もし金持ちがこの栄光を見ることが出来たとすれば、その栄光の輝きをお金で買いたいと思うかもしれない。しかし、たとえ金持ちがその有り金を全て出しても、その輝きを買うことはできないであろう。聖徒たちは、天国の教会において、このような輝かしい神の栄光を見ることになる。それどころか、聖徒たちは、その栄光のうちに自分に与えられた永遠の人生を楽しむことになる。これこそ天国で与えられる大きな恵みなのである。
都にあった神の栄光の輝きは、『透き通った碧玉』のように見えた。それは、思わず息を呑んでしまうような美しさだったのである。この輝きの美しさが、至上の美しさだったことは間違いない。光の美しさも、自然の美しさも、女の美しさも、秩序の美しさも、清潔の美しさも、バランスの美しさも、組み合わせの美しさも、その元を辿れば神の創造に行き着く。あらゆる美しさの源であられる神が、それらの美しさを凌駕した輝きの美しさを有しておられるのは言うまでもないことである。要するに、神とは美の根源であって、美そのものである。ゆえに、その栄光の輝きも美しい。神が『人はわたしを見て、なお生きていることはできない』(出エジプト33章20節)と言われたのは、これが理由の一つである。というのも、神の美は人の把握力を遥かに超え出ているので、人がそれを見ると死なずにはおられないからである。ちょうどビックリし過ぎて誰かが死んでしまうようなものである。御座の前の場所にも、透き通った美しさが見られた(15:2、4:6)。これも、やはり神の栄光の現れの一つであった。つまり、このような透き通った美しさが、神の栄光の輝きにおける美しさなのである。天上の教会に導き入れられた聖徒たちは、このような神の栄光の輝きを見ることができる。それどころか、その輝きのうちにおいて永遠に生きることになる。これこそ天国における幸いな恵みである。
【21:12~13】
『都には大きな高い城壁と12の門があって、それらの門には12人の御使いがおり、イスラエルの子らの12部族の名が書いてあった。東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があった。』
神の都には『大きな高い城壁』があった。これは、都の中に不適格な者が入って来れないようにするための城壁である。この城壁があるので、都に悪しき者が侵入することは全く不可能である。既に天上から追放されたサタンも、この城壁を越えて都の中に入り込むことができない。何故なら、その城壁は『大きな高い』ものだからである。それゆえ、天の都にいる聖徒たちには安心と平和の幸いがある。21:4の箇所で『もはや悲しみも叫びもない。』と言われていた通りである。
この都には『12の門』があった。これは、都の中には選ばれた者以外には入れないことを示している。というのも『12』という数字は選びを意味しているからだ。選ばれていない者は、都に入るための門を開けてもらえないのである。「天国は選ばれた者にだけ与えられる」ということについては、キリストも次のように言っておられる。『さあ、わたしの父に祝福された人たち。世の初めから、あなたがたのために備えられた御国を継ぎなさい。』(マタイ25章34節)
その門には『12人の御使い』がいた。これは、都の中に不適格な者が入らないように警戒する門番としての御使いである。この御使いが門の場所にいるので、不適格な者は都の中にいっさい入れないのだ。この御使いは恐らくケルビムであろう。エデンの園の入り口にも、そこから追放されたアダムとエバが再び園に入れないようにと、門番としてのケルビムが置かれていたからである(創世記3:24)。それだから天国の中にいる聖徒たちは、誰か忌まわしい存在がそこに入って来るのではないかなどと心配する必要がまったくない。『12人の御使い』が、いつも都の門で番をしてくれているからである。
また、その門には『イスラエルの子らの12部族の名が書いてあった。』これは、神の民でなければその門を通って都の中に入れないことを示している。何故なら、『イスラエルの子らの12部族』とは、すなわち神の民を意味するからである。つまり、これは「旧約時代におけるイスラエル12部族のように神に属していないのであれば都の門をくぐることはできない。」ということになる。新約時代においてイスラエル12部族とはキリスト者のことである。というのも旧約時代においてイスラエル12部族に限定されていた神の国は、今や信仰を持つ全てのキリスト者に広げられているからである。先に見た7:4~8の箇所でも、イスラエル12部族において旧約と新約における神の民が表示されていた。
この『12部族の名』は、7:5~8で示されている通りである。すなわち、ユダ、ルベン、ガド、アセル、ナフタリ、マナセ、シメオン、レビ、イッサカル、ゼブルン、ヨセフ、ベニヤミンの12部族である。既に述べたようにダンとエフライムはユダヤから除外されたので、この中には含まれていない。
この都には、各方角に、それぞれ『3つの門』があった。これは都の中に、地上における全世界の場所から救われた聖徒たちが導き入れられる、ということを教えている。地上世界ではあらゆる地域にいる人々が日に日に救われており、その人たちは、地上での人生を終えた後に天の都へと招かれることになる。ロシアにいる聖徒も、ノルウェーにいる聖徒も、パレスチナにいる聖徒も、日本にいる聖徒も、オーストラリアにいる聖徒も、レソト王国にいる聖徒も、やがて天国の都に導かれる。だから、そのことが、ここでは都の各方角にそれぞれ3つの門があるという表現で示されているのだ。確かに天における神の王国には地の四方から救われた者たちが来る。福音宣教の対象は世界各地であり、救われた者は世界各地に存在しているので、その救われた者たちを受け入れるために天の都には12もの門が各方角に置かれているわけである。
この都の門における方角は、重要な順番で記されていると考えられる。まず『東』は、義なる太陽であるキリストが再臨において上って来られる『日の出るほう』(6:2)を示す方角だから、最も重要な方角だとすべきである。神殿も東のほうからでなければ入れなかったし、エデンの園も東にその入り口があった(創世記3:24)。東は第一の座を持つに相応しい方角である。『西』は、この東とは逆の方角だから、もっと重要でない方角だということになる。西からではキリストが上って来られないし、神殿とエデンの園も西からでは中に入れないのである。すると、『北』と『南』は2番目および3番目だということになる。『北』はすなわち上であって天国の場所を指し示すのに対し、『南』はすなわち下であって地獄の場所を指し示す。よって、『北』が2番目に重要であり、『南』は3番目だということになる。しかし、読者の中には、このようには考えない人がいるかもしれない。すなわち東ではなく北が1番重要だとし、西ではなく南が一番重要ではない、と考える人のことである。私は、東と北を3番目また4番目としないのであれば、また西と南を1番目また2番目だとしないのであれば、批判をするつもりはない。だが東が4番目だとか西が1番目だとか言うのであれば、それは受け入れられない。とはいっても、今述べている方角に関する順番は、本質的な事柄ではなく、それほど重要であるというわけでもない。私は今、事のついでに、ヨハネの書いている4つの方角の順番における重要性について書いただけである。
なお、この箇所で語られている『12の門』は、明らかにエゼキエル書48:30~34の箇所と対応している。我々が今見ている箇所で「ダンとエフライム」が書かれていないのに対し、エゼキエル書のほうでは「マナセとエフライム」が書かれていない。また、エゼキエル書では『町の門』と言われているが、この『町』とは要するに都のことであり、この点については言い方は違えど両方とも変わらない。またエゼキエル書のほうが黙示録よりも内容的に細かく書き記されている。そのエゼキエル書の箇所では次のように書かれている。『町の出口は次のとおりである。北側は4500キュビトの長さで、町の門にはイスラエルの部族の名がつけられている。北側の3つの門はルベンの門、ユダの門、レビの門である。東側も4500キュビトで、3つの門がある。ヨセフの門、ベニヤミンの門、ダンの門である。南側も4500キュビトの長さで、3つの門がある。シメオンの門、イッサカルの門、ゼブルンの門である。西側も4500キュビトで、3つの門がある。ガドの門、アシェルの門、ナフタリの門である。』このエゼキエル書の箇所は、また後ほど第4部でも再び見ることになる。
【21:14】
『また、都の城壁には12の土台石があり、それには、子羊の12使徒の12の名が書いてあった。』
都の城壁に12使徒の名が書かれた『12の土台石』が据えられていたのは、都の城壁が決して揺るがないことを教えている。地上の教会は使徒という土台に建てられているが(エペソ2:20)、天上の教会もそれと同じである。都の城壁は使徒という石がその土台であるから、完全に堅固である。というのも、使徒とは神の使いであって、真理の伝え人だからである。使徒というキリストに選ばれた者たちの名が記された土台に支えられるということほど、盤石なことが他にあろうか。ない。それだから『都の城壁』は、たとい土星がぶつかったとしても揺らぐことがないほどに堅固であったと、我々は考えるべきである。このような土台に支えられている城壁に囲まれて聖徒たちは生きているのだから、天上の聖徒たちは常に安心できるのである。これも天国における大きな恵みの一つである。
ところで、この『12使徒の12の名』とはどの名のことか。それは、キリストが直接お選びになった11人(ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、ピリポ、バルトロマイ、トマス、マタイ、ヤコブ、タダイ、シモン)と、ユダと入れ替わりに使徒とされたマッテヤである。パウロは使徒であるが、この中には入っていないと思われる。彼はこの中に入っていなくても、文句は言わないであろう。何故なら彼は次のように言ったからである。『私は使徒の中では最も小さい者であって、使徒と呼ばれる価値のない者です。なぜなら、私は神の教会を迫害したからです。』(Ⅰコリント15章9節)パウロは自分のことを『罪人のかしら』(Ⅰテモテ1章15節)とも言っている。しかし、もしパウロをこの中に含めなければいけないとすれば、先に挙げた12人の中から誰と入れ替えにしたらよいのか。最も入れ替えるのに相応しいのはマッテヤである。何故なら、マッテヤは他の11人とは違い、キリストから直接的には使徒として選ばれていないからである。しかし、マッテヤとパウロを入れ替えてもよいのかどうか私には判断がつかない。私としては、ただ単純にパウロ以外の12人の名だったとするのが無難だと思う。
【21:15】
『また、私と話していた者は都とその門とその城壁とを測る金の測りざおを持っていた。』
御使いが『測りざお』を持っていたのは、『都とその門とその城壁とを測る』ためであり、都の詳細を聖徒たちに伝えるためであった。神は、御自身の聖徒たちに、あらかじめ天国の都について、その詳細を知らせることを望まれた。つまり、神は聖徒たちに都の詳細を知らせることで、「あなたがたはこれからこういう都に行くのだよ。」と聖書の中で言おうとされたわけである。だからこそ、ここで神は御使いに都を測るための『測りざお』を持たせられたわけである。なお、都のサイズを測る出来事については、明らかにエゼキエル書40~42章と対応している。エゼキエル書のほうでは「キリスト」が「神殿」を測っているという相違点があるものの、どちらも『測りざお』で神聖な建造体を測定しているという点では変わらない。
この測り竿が『金』だったのは、都が尊かったからである。尊いものに、それに応じた良いものを使うのは理の当然である。例えば、病院に王が検診を受けに来たら、病院はどのようにするであろうか。そこで王を検診する医師は、よれよれの器具は使わず、むしろ新しかったり良かったり清潔だったりする器具を使うはずである。まともな感覚を持った医師であれば、そうするに違いない。何故なら、王には良いものこそが使われるべきだということが、人間の情として分かるからである。聖なる天の都に『金の測りざお』が使われたのは、これと同じことである。天の都は非常に尊かったのだから、それに金の竿が使われないというのは有り得ないことであった。それだから、もしこれが普通の家だったとすれば、別に金の竿を使わなくてもよかった。何故なら、それが普通のものであるゆえ、普通の竿を使えばそれで十分だからである。
【21:16】
『都は四角で、その長さと幅は同じである。彼がそのさおで都を測ると、1万2000スタディオンあった。長さも幅も高さも同じである。』
天上の都は『四角』であり、『長さも幅も高さも同じ』であったが、これは都には均整と秩序の栄光が満ちていることを示す。エゼキエル書45:2の箇所でも、聖所が『正方形』であったと書かれているが、これは我々が今見ている箇所と内容的に対応している。何故なら、『正方形』とは『四角』に他ならないのだから。現代物理学における最高の学者の一人であるロジャー・ペンローズは、世界は数式により成り立っていると言う。数に異常なこだわりを持っていたピュタゴラスも、この世界は数字で構成されていると言った。この2人がこう言ったのは間違っていない。天文学や化学をある程度知っていれば、確かに世界が数式により構成され作動させられているのは誰でも分かることである。つまり、神は均整と秩序に基づいて被造物を創造された。それは天上の都においても例外ではなかったのだ。そのことが、ここでは整った立方体として都が表現されることで示されている。この都における整ったサイズは、象徴的な表現である。これは実際的なサイズを言い表したものではない。というのも、ここではただ都が均整であったと分かれば、それで良いからである。それは、天上の聖徒たちが御使いのようになると言われたものの、それは単なる「たとえ」であって、実際に天上の聖徒たちが御使いになるのではないのと同じことである(マタイ22:30)。天の都にいる聖徒たちは、このような秩序に満ちた世界で永遠に生き続けることになる。そこには、もはや混乱や秩序の無さが全く見られない。そこでは秩序の神が十全に働いておられるので、『ただ、すべてのことを適切に、秩序をもって行ないなさい。』(Ⅰコリント14章40節)という御言葉が常に完全に実現される。これも天国における大きな恵みの一つである。なお、ここで示されている立方体すなわちキューブは魔術において「祭壇」の意味を持つ。そのためサタニストや魔術を好む者たちは、よくこのキューブを儀式や制作品の中で用いる。これが魔術に用いられていることからも分かるように、立方体とは霊的なものである。何故なら、魔術とは悪霊どもの創作物だからである。もちろん、この21:16の箇所では邪悪な意味として立方体が示されているというわけではない。読者は、この立方体が非常に霊性の強い形であるということを覚えておかれたい。ルターは黙示録におけるこの四角い立方体を「8」という数字において捉えているが(※)、私としては微妙に思える。また蛇足になるが、カバラにおいて「4」とは実際的なこと、知性的なこと、倫理的なことを示し、それは力・法・権威・抑制・保護といった概念を象徴させるものである。しかし当然ながら、この21:16の箇所に書かれている『四角』(4)は、カバラ的な意味において捉えるべきものではない。
(※)
「さらに8の数は聖書によく出て来る数でもあり、聖なる数でもある。(ヒエロニムスが述べているように)8日目に割礼が施され、ノアの箱舟には8種の生き物がいた。ダビデもまたエッサイの8番目の末子と言われ、ヨハネの父ザカリヤも8日目にことばを取り戻した。その他同様のことが言われている。さらに8は(立方体を表わす)3乗数であり、6つの側面によって正方形が対をなし、24の三角形の平面をもち、8つのさいころのような立方体をもつ。さいころの四角い形も聖書において用いられ(黙21・16)、また哲学者たちによって等しさと安定を表わすものと見なされた。」(『キリスト教神秘主義著作集11 シュタウピッツとルター』第二回詩篇講義 6:1 p389~390:教文館)
[本文に戻る]
この都は、長さと幅と高さが、それぞれ『1万2000スタディオン』あった。1スタディオンは185mだから、『1万2000スタディオン』とは「2220km」である。地球の半径は6371kmだから、これはその3分の1程度である。長さが地球の3分の1、幅も地球の3分の1、高さも地球の3分の1。これはとんでもないサイズである。地球上に、このような建造物は今までになかったし、これからも造られないであろう。とはいっても、先に述べたように、これは象徴表現としてのサイズである。これを文字通りに捉えてはいけない。ここでは「都は非常に大きい」ということが教えられているに過ぎないからである。『12000』という数字からしても、これが象徴数であることは明らかである。この数字は、明らかに「12×1000」に分解できる。これは、つまり選ばれた者たちが(=12)住むことになる大きく完全な空間(=1000)と解釈すべきである。これが象徴表現でなければ一体なんだというのか。これは霊的に捉えるべき数字である。20章に書かれていた『1000年』が実際の期間を示していたのではないのと同じで、ここで言われている『12000スタディオン』も実際のサイズを示しているのではない。
【21:17】
『また、彼がその城壁を測ると、人間の尺度で144ペーキュスあった。これが御使いの尺度でもあった。』
都を取り囲んでいる城壁の長さは『144ペーキュス』である。1ペーキュスは45cmだから、『144ペーキュス』とは「108m」である。これは高さだけで考えると、それほど大きいとは思えないかもしれない。何故なら、現代社会にはそのぐらいの高さを持つ建造物はいくらでもあるからである。ドバイにあるブルジュ・ハリファは828mもある。2001年に倒壊した世界貿易センタービル(WTC)は417mであった。しかし、我々は、これが『城壁』であったことを忘れるべきではない。これは塔やビルのようにある一か所にだけ位置しているというのではなく、横にずっと続いているのだ。108mもの高さを持つ壁が、巨大な都の周りをぐるりと途切れることもなく覆っている。これは誠に驚くべき大きさを持つ壁であると言わざるを得ない。こんな壁は今までになかったし、これからも造られないであろう。万里の長城も、この壁の壮大さにには全く及ばない。これも、やはり都の場合と同じで、あくまでも象徴的に捉えるべき数字である。ここでは実際的なサイズが教えられているのではなく、「城壁がとんでもなく大きい」と教えられているに過ぎないからだ。『144ペーキュス』という数字からしても、これが象徴数であることは明らかである。「144」を分解すれば「12×12」となるのは誰でも分かるはずである。これは、選ばれた者たち(=12)が大いに守られるための城壁、というふうに解するべきである。何故なら、それは選ばれていることを意味する「12」という数字を12回も重ねた数字だからである。この象徴的な数字の成り立ちは、我々に霊的な理解を持つことを要請している。都の中にいる聖徒たちは、このように巨大な城壁により守られているので、常に安心することができる。このような城壁を飛び越えたり破ったりして中に入れる者は誰もいないからである。これも天国で聖徒たちが受ける大きな恵みの一つである。
ここでは、この人間における尺度が御使いの使う尺度でもあったと言われている。これは、読者たちが、人間の尺度と御使いの尺度が違っているのではないかなどと心配しないためである。つまり、これは次のような疑問を持たないために書かれた。「御使いは人間の尺度で都を測っているが、御使いは人間の尺度を使うものなのか。御使いは人間ではないから御使いの尺度を使うのではないか。」―しかし、御使いは人間の尺度を用いる謙遜さを持っていた。―ヨハネは愛の霊によって文章を書いていたので、聖徒たちが尺度のことで何か不思議に思ったりしないように、このような配慮をしたわけである。
【21:18】
『その城壁は碧玉で造られ、都は混じりけのないガラスに似た純金でできていた。』
都の城壁が『碧玉で造られ』ていたのは、都はその城壁さえもが神の栄光を放っているということを示すためである。『碧玉』は、重厚で深淵な輝きを持つ宝石であるから、神の栄光を表すためには調度良い物質である。まだこの宝石を見たことがない人は、気になれば見てみるとよい。その色や雰囲気に好き嫌いがあるかもしれないが、少なくとも軽んじることはしないはずである。また、この碧玉を使ったお守りが多く見られることは、注目に値する。この物質が、元から神の栄光を豊かに現わす物質として創造されていたのは疑えない。だから、この物質からは何か神秘めいた印象を受けるのだ。多くの人がこの物質からお守りを作っているのは、この物質が神の栄光を豊かに現わしていることの証左である。人は、そこに何か神のような感じを受けない限り、そのようなものは作らないものだからである。
都は、その全体が神の栄光に満ちていた。それは『混じりけのないガラスに似た純金』のような輝きを持っていた。都にいる聖徒たちは、このような神の栄光のうちに永遠に至るまでも生き続けることになる。天国における恵みとは、このようなものである。
【21:19~20】
『都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は碧玉、第二はサファイア、第三は玉髄、第四は緑玉、第五は赤縞めのう、第六は赤めのう、第七は貴かんらん石、第八は緑柱石、第九は黄玉、第十は緑玉髄、第十一は青玉、第十二は紫水晶であった。』
都の『城壁の土台石』には、多くの宝石が組み込まれていた。つまり、都はその城壁の土台石においても、神の栄光が表わされている。『土台石』とは聖徒たちを守る城壁を支えるものだから、その『土台石』が『あらゆる宝石で飾られていた』というのは、つまり神がその栄光をもって聖徒たちを完全に守られる、ということを教えている。神が聖徒たちを守る際に、その栄光を表されるというのは、誰でも分かることである。その土台石に、それぞれ異なる12の宝石があったのは、神の栄光が多様であることを示す。つまり、神の栄光は豊かであって、単調で飽きたりするようなものではないということだ。
ここで列挙されている12の宝石は、一つ一つ詳しく説明する必要がない。何故なら、ここでは(1)都はその城壁の土台石さえもが神の栄光に満ちていたということ、(2)その栄光は豊かでありつまらないものではなかったということ、という2つの点を弁えていれば、それで十分だからである。ここで挙げられている宝石について一つ一つ掘り下げて探求するのは、暇な中世の修道士がやりそうなことであり、あまり本質的であるとは言えない。先に見た18:12~13の箇所で列挙されていた『商品』を一つ一つ掘り下げて見ていく必要がなかったのと同じことが、ここでも言える。また、ここに書かれている宝石を詳しく見る必要がないのは、マタイ1:1~17に書かれているキリストの系図の中の人物を一人ずつ詳しく見る必要がないのと同じでもある。(※)
(※)
もし、これらの宝石がどのようなものか知りたい人がいれば、次のリンクを参照すべきである。
1:「碧玉」
https://ja.wikipedia.org/wiki/碧玉
2:「サファイア」
https://ja.wikipedia.org/wiki/サファイア
3:「玉髄」
https://ja.wikipedia.org/wiki/玉髄
4:「緑玉」
https://ja.wikipedia.org/wiki/エメラルド
5:「赤縞めのう」
6:「赤めのう」
7:「貴かんらん石」
8:「緑柱石」
https://ja.wikipedia.org/wiki/緑柱石
9:「黄玉」
https://ja.wikipedia.org/wiki/トパーズ
10:「緑玉髄」
https://ja.wikipedia.org/wiki/クリソプレーズ
11:「青玉」
12:「紫水晶」
https://ja.wikipedia.org/wiki/アメシスト
※筆者註:「ダイヤモンド」が12の宝石の中に含まれていないのは、やはり飛び抜けた素晴らしさを持っており、不公平感が生じてしまうからなのであろうか。つまり、「あの有名なダイヤモンドに該当する使徒は誰か」などと詮索されないためだったのであろうか。その可能性は高い。しかしながら、ヨハネの時代にはダイヤモンドがあまり知られていなかったという事情があったということも考えられる。ヨハネと同時代の人であるプリニウス(23-79)によれば、ダイヤモンドは「長い間国王たちにだけ、それもその少数の者にだけしか知られていなかった。」(『プリニウスの博物誌Ⅲ』第37巻15<55> p1509:雄山閣)ということだから。そうであれば、ダイヤモンドについては書かれていなかったとしても、不思議なことはない。ところでヨハネの時代には、このダイヤモンドは「アダマス」と呼ばれていた。
[本文に戻る]
【21:21】
『また、12の門は12の真珠であった。どの門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大通りは、透き通ったガラスのような純金であった。』
都にある『12の門』は、それぞれ一つずつ真珠により出来ていた。これは門全体が真珠であるという意味である。はて、真珠とは小さな宝石ではなかったのか。それは最大級に大きいサイズでも手のひらに収まるほどではなかったのか。確かにそうである。それにもかかわらず、ここでは門が真珠であったと言われている。真珠で門が造られているなどとは今までに聞いたことがないし、そんなものは造られたことが全くないし、これからもこの地上では造られないであろう。しかし、天国の門は真珠により出来ている。これは誠に驚くべきことである。これは、つまり天国の門が神の栄光に満ちているということを示している。何故なら、そのような門は前代未聞であって、大変素晴らしいからである。(※)
(※)
ネットで真珠について調べていたところ、この21:21の箇所で言われていることを読んで、天国の門が本当に丸ごと真珠であると想像している牧師がいた。その牧師の作った画像には、巨大な真珠が天国の門としてポンと置かれており、あまりにもコミカルな光景に驚かされた。これは明らかに間違っている。ここでは真珠が丸い形のままで門そのものだと言われているのではない。ここで言われているのは「門が真珠製であった」という意味である。確かに、ここでは門が『真珠からできていた』と書かれているのである。これは、つまり門が「真珠により作られていた」ということに他ならない。
[本文に戻る]
天の都は、その『大通り』においても神の栄光が輝きを放っていた。その栄光の輝きは『透き通ったガラスのような純金』として言い表されている。天の聖徒たちは、このような栄光のうちに日々を歩むのである。これは誠に大きな恵みである。
【21:22】
『私は、この都の中に神殿を見なかった。それは、万物の支配者である、神であられる主と、子羊とが都の神殿だからである。』
天国における神殿は、神とキリストであった。神殿の本質と目的は、言うまでもなく神とキリストである。神とキリストがあればそれは神殿と言えるが、神とキリストがなければそれは神殿とは言えない。地上にいる聖徒たちは、まだ主と共にはいない。パウロが次のように言う通りである。『ただし、私たちが肉体にいる間は、主から離れているということも知っています。』(Ⅱコリント5章6節)しかし天国に行くと、神が実際に共におられるようになる。先に見た21:3の箇所で、『神ご自身が彼らとともにおられて』と言われていた通りである。天国にいる聖徒たちは、神およびキリストと実際的な意味において共に歩んでいる。聖徒たちと共におられる神とキリストは神殿の本質と目的なのだから、天国の聖徒たちは他に神殿を必要としないのである。もし天国の聖徒が神とキリストの他に、何か神殿を求めるということがあれば、それは冒涜の極みである。何故なら、神殿の本体としての存在が共にいて下さるのに、それを無視し、本体を表示する影に過ぎない別の神殿を求めているからである。それは、キリストの贖いが既に実現しているのに、それを無視して、旧約時代に行なわれていた動物犠牲を捧げるようなものである。もちろん、天国にはそのような悪に進もうとする愚か者は、一人もいないのではあるが。ところで、聖書ではキリストも聖徒も神殿だと言われているが、両者が共に神殿だというのは、どうして成り立つのか。キリストが神殿だというのは、ヨハネが福音書で書いている通りである(ヨハネ2:21)。聖徒たちが神殿だというのも、パウロがⅠコリント書3:16で言っている通りである。これの解決は容易である。すなわち、キリストも聖徒も、どちらも歴とした神殿なのである。キリストは聖徒たちの永遠の住まいであられる御方だから、紛れもなく神殿である。聖徒たちも神の永遠の住まいだから、紛れもなく神殿である。どちらも神殿だったとしても問題は生じない。というのは、神殿とは「聖なる存在が住まう聖なる存在」と定義すべきものだからである。
【21:23】
『都には、これを照らす太陽も月もいらない。というのは、神の栄光が都を照らし、子羊が都のあかりだからである。』
天国は、神とキリストという光により、全ての場所が照らされている。それだから、そこには『これを照らす太陽も月もいらない』のである。もし天国で神とキリストの他に光を求める人がいれば、それは馬鹿げたことである。何故なら、そこには神とキリストという十全な光が照らされているからである。そのようにするのは、例えるならば既に妻がいるのに妻を求めるようなものであり、既に国家資格を取ったのに同じ国家資格を再び取ろうとしたりするようなものであり、既にバプテスマを受けたのに何故かもう一度受けようとするようなものである。天国の都を照らすこの聖なる光は、都の全体を満遍なく照らしているので、光に不足するというのはまったく有り得ないことだ。なお、トマス・アクィナスによると、この太陽と月を「教会のより大いなる、またより小さな博士たち」(『中世思想原典集成 第Ⅱ期1 トマス・アクィナス 真理論 上』第9問題第1項 p619:平凡社)などと註釈している人がいるようだが、これはいい加減な解釈である。ここで言われているのは光り輝く実際の天体のことだからだ。
この箇所から、21章で言われているのは天国が地上に降りてきてそこに展開されることであるなどと考えている人たちの夢想は、完全に退けられる。というのも、ここでは『都には、これを照らす太陽も月もいらない。』と言われているからだ。そこに太陽も月もないというのは、そこが地球ではないことを教えている。何故なら、地球と太陽および月はセットとして考えられるべきであり、それは切っても切り離せない組み合わせだからだ。この2つの星があるから地球は地球と言えるのであって、もしこの2つの星がなければそれは地球とは言い難い。しかし、私がこう言うと、とんでもない夢想から離れようとしない黙示録に無知な人たちは次のように反論するであろう。「いやいや、ここではある時になれば地球の性質がまったく変わると教えられているのだ。その時には、私たちの知らないような原理が地球上に働くことになる。その時には太陽と月を必要としない地球が存在しているはずだ。だから天国がやがて地球に降りて来ると考えても差し支えない。」なるほど、確かに地球の性質が変わるならば、もはや地球が太陽と月を必要としなくなることも可能だということは、私も認める。何故なら、全能の神にはどんなことでもお出来になるからだ(ルカ1:37)。しかし、21章の箇所で書かれている出来事も『すぐに起こるはずの事』(1:1)だと神が言っておられるのは、どうするのか。この『すぐに』という言葉が、黙示録の全ての預言において文字通りに理解されるべきだということについては、既に何度も説明した通りである。冗長を恐れずに再び言うとすれば、例えば11:7~10の箇所で言われているのはネロの大迫害のことだから文字通り『すぐに起こるはずの事』だったし、13章で出てくる666の獣はネロだったから13章も文字通り『すぐに起こるはずの事』だったし、20:7~10の箇所で言われているのはローマ軍によるエルサレム陥落のことだからこれも文字通り『すぐに起こるはずの事』であった。更に言えば、この『すぐに』という言葉を文字通りに捉えている私が黙示録を豊かに理解できているのに対し、この言葉を文字通りには捉えていない人たちは黙示録を全く理解できていない、という事実もこの『すぐに』という言葉を文字通りに解釈すべきことを教えている。これは文字通りに捉えるのが正解であって、文字通りに捉えないのは間違いなのである。だからこそ、これを文字通りに正しく捉えている私は黙示録を豊かに理解できており、文字通りに捉えていない誤った捉え方をしている人たちは混乱と無知と誤解の海にいつまでも沈んでいるのだ。つまり、21章で言われている出来事は既に実現済みのことである。何故なら、それは『すぐに』起こったのだから。しかし、地球を見ても、そこで言われているような変化は何も起きていない。実際に太陽と月が、神とキリストに取って代わられたという変化も起きていない。これは21章の内容が地球について言われたことではなく、我々の知らない場所にある霊的な世界としての天国について言われているからに他ならない。もう一度言うが、21章で言われているの天国のことなのだ。それゆえ、天国が地上に降りて来て地上が大きく変化するなどという夢想は、黙示録に対する無知と思考の欠如および研究不足をその原因としているのだから、間違っている見解として退けられねばならない。
この箇所は、明らかにイザヤ書60:19~20の箇所と対応している。そこでは次のように書かれている。『太陽がもうあなたの昼の光とはならず、月の輝きもあなたを照らさず、主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの光栄となる。あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月はかげることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。』黙示録は、エゼキエル書とダニエル書と同様、イザヤ書とも対応している箇所が多い。このイザヤ60:19~20の箇所は、また後ほど第4部の中で取り扱われる。
【21:24】
『諸国の民が、都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る。』
『諸国の民』とは、天国にいる色々な国の聖徒たちを指す。何故なら、天国には、色々な国にいる救われた人が導き入れられているからである。そこにはアメリカ人もブラジル人も日本人も中国人もインド人もトルコ人もスペイン人もエジプト人もオーストラリア人もフィリピン人もいる。彼らは、神とキリストという『都の光』によって生き続ける。彼らは闇を照らす光を求めることがない。何故なら、彼らには神とキリストという光が十全に照らしているので、暗いところが何もないからだ。しかし地獄に落ちた者に光は与えられない。何故なら地獄に、神とキリストはおられないからである。だから、その場所は『まっ暗なやみ』(ユダ13)である。彼らは光に与かれず闇に包まれている。だから、彼らは『そこで泣いて歯ぎしりする』(マタイ25章30節)のである。
『地の王たち』とは何か。これは、地上の世界にいる救われた聖徒たちのことである。『地』とは、天上の世界における地のことではなく、地上の世界における地のことである。先に21:1~22:5の箇所では天上の世界を取り扱っていると述べた。ここでは『地』と言って地上の世界について触れられているが、ここで言われているのは地上の世界にいる聖徒たちが天上の世界に導かれるという話であって、何も地上に焦点を当てて取り扱っているわけではないから、『地』と書いてあってもこの21:1~22:5の箇所が地上のことを取り扱っていることにはならない。『王たち』とはキリスト者を指す。キリスト者が王であるというのは、Ⅰペテロ2:9や黙示録1:5~6の箇所で言われていることだ。これを地上世界における実際的な王だと捉えるのは間違っている。
ここで言われているのは、地上にいる聖徒たちが栄光のうちに天国の都へと導き入れられるようになった、ということである。地上の聖徒たちは、地上での人生を終えた後、パウロも言うように『たちまち、一瞬のうちに』(Ⅰコリント15章52節)復活に与かり、新しい身体に伴う栄光に満たされつつ都へと挙げられる。この復活は実際的な復活である。聖徒たちは、かつてのように、もはや地上での人生を終えた後に魂だけの状態になることは無くなった。かつては聖徒たちが人生を終えると、魂と肉体が分離されて、ある時まで魂のままに留め置かれていた。しかし、ある時が訪れると、もう復活が実際に実現される新しい時代となったので、地上にいる聖徒たちは即座に復活して『その栄光を携えて都に来る』ようになった。その時とは、再臨の時、すなわち紀元68年6月9日である。
ここでは、今述べたような新しい死後の方式が開始されたのだ、ということが教えられている。つまり、ここでは「これ以降、地上に生きる聖徒たちは人生を終えたらこのようになるのだ。」ということが教えられているのである。それは、未来永劫ずっとそうである。今の時代に生きる我々も、この地上での人生を終えたならば、『その栄光を携えて都に来る』であろう。実際、今までに生きていた新約時代における聖徒たちはそのようになったし、これからの未来に生きる聖徒たちもずっとそのような方式に与かることになる。未だに聖徒たちが地上での人生を終えた後には魂だけの状態になると考えている人たちは、非常に惨めである。何故なら、その人たちは、もうとっくの昔に御霊の身体により即座に復活して天の都に挙げられるようになる時代が到来したのにもかかわらず、それを知らず、まだ昔の方式が適用されていると考えているからである。聖徒たちは、ぜひ私が本作品の中で述べていることを無視せず、よく祈り、考究し、聖書の御言葉が何を言っているのか弁えてほしいものである。
【21:25】
『都の門は一日中決して閉じることがない。そこには夜がないからである。』
天国に『夜がない』のは、3つの要因のゆえである。一つ目は、神が天国に夜を望まれなかったからという要因である。天国とは、光の神(※Ⅰヨハネ1:5)が支配する『光の子ども』(エペソ5:8)の住まう光の王国である。そこには闇が何もない。何故なら、光の神と光の子と光の国に闇は相応しくないからである。それゆえ、神は天の都に闇をもたらす夜が来ないようにされた。二つ目は、21:23で言われていたように『神の栄光が都を照らし、子羊が都のあかり』だからである。天国では、神とキリストが、その全ての場所を満遍なく輝かしておられる。そこには暗い場所が少しもなく、闇が入り込む余地はまったくない。それゆえ、神とキリストという灯りのゆえに、天国には『夜がない』のである。三つ目は、天国が地球ではないという要因である。夜とは、地球が球体であり、その地球に太陽という光体が近くにあり、そして地球が自転をているために生じる地球上に見られる暗い部位のことである。天国は、恐らく球体ではなく、そのため恐らく自転もしておらず、自然現象として暗くなる部位がない。だから、天国は夜という自然現象が見られないのである。今述べられた要因のうち、第一は御心という要因であり、第二は神存在という要因であり、第三は原理的な要因である。
天国には、このように『夜がない』ので、その『都の門は一日中決して閉じることがない』。これは、地上世界にいる聖徒たちが、いつでも天国の門を通って至福の世界に入れるようになるためであった。天国の門は24時間ずっと開いているので、聖徒たちは、いつ地上の人生を終えても天国の門をくぐることができる。それゆえ、ある時に地上の人生を終えたので、ちょうど門が閉まっていて天国に入れなかった、ということも起こり得ない。これは、あたかも24時間営業のスーパーマーケットのようである。24時間営業のスーパーマーケットにいつでも我々が買い物をしにいけるように、天国もいつでも行けるのである。「今は閉まっているので少し後にまた来てください。」などと言われることもない。それだから、地上に生きている聖徒たちは、いつ天に召されることになっても常に安心できる。あなたが天の都に至る時には、そこにある門がずっと開かれているのを見ることであろう。
【21:26】
『こうして、人々は諸国の民の栄光と誉れとを、そこに携えて来る。』
天国に導き入れられた聖徒たちは、『諸国の民の栄光と誉れ』とを天国に持って来る。これは、つまり天国に導き入れられる聖徒たちが、地上世界で持っていた国民性すなわち民族の特質を天国まで保持・継続するという意味である。だから、天国にいる聖徒たちは、かつて自分が持っていた国民の性質をそのまま持ち続けている。例えば、天国でも日本人はおとなしいだろうし、中国人は細かい模様を作る傾向があるだあろうし、イギリス人は自由に振る舞う傾向があるだろう。何故そうなのか。それは、民族性というものは神の創造だからであり、神はその民族性を首肯しておられるからであり、その民族性のうちには神の栄光が鏡のように表わされているからである。もし天国に地上世界に見られた多様な民族性が持ち運ばれず、そこに住む人たちは一つの特性しか持っていないとすれば、天国はどれだけつまらない単調な世界になっていたであろうか。その場合、神の栄光も豊かには現わされなくなる。というのも、民族性が豊かにあるからこそ、そこに表される神の栄光も彩り豊かになるからである。神は人間の民族性においても、御自身の栄光を表すことを欲しておられる。それは地上世界だけでなく天国でも同様である。それゆえ、聖徒たちがかつて地上世界にいた時に持っていた民族性が、天国にまで保持・継続されることを神はお許しになられたわけである。その民族性における良き特質が、ここでは『諸国の民の栄光と誉れ』と言われているのだ。もちろん、天国に持ち運ばれる民族性は、神の創造された部分だけに限られる。神の創造されたのではない堕落した悪しき付加的部分としての民族性は、天国に入る際に全て切り捨てられる。例えば、日本人の持つ鎖国性、ラテン人の持つ狂暴性、朝鮮人の持つ妬み深さ、がそれである。何故なら、それは神の創造された特質ではないゆえ、神の栄光を表してはおらず、天国という栄光の場所には全く相応しくないものだからである。確かに、この聖句の中では『栄光と誉れ』が持ち運ばれると言われている。つまり、栄光と誉れでない部分は持ち運ばれて来ないということだ。既に述べたが、天国とはアメリカのような場所だと思えばよい。アメリカにはアメリカ人という一つの国民がいるものの、そこには様々な特質を持った民族が多く見られる。それと同様に天国にも神の民という一つの国民がいるのだが、そこには性質的にアメリカ的が人がいればインド的であったり北欧民族的な人もいるのだ。一でありながら多。天国がそのようであってこそ、神の三一性における栄光がそこの場所で豊かに顕現されるようになるのである。
【21:27】
『しかし、すべて汚れた者や、憎むべきことと偽りとを行なう者は、決して都にはいれない。子羊のいのちの書に名が書いてある者だけが、はいることができる。』
天国の都には正しい者だけが入れる。それは、『子羊のいのちの書に名が書いてある者』である。彼らは永遠の昔から神の選びにより救われるようにと定められているので、キリストの贖いによって正しい者とされ、天国へと導き入れられるに至る。しかし正しくない者たちは、天国の都に入れない。その者たちは、『子羊のいのちの書に名が書いてある者』ではないからである。彼らは、救われるようにと定められていないので、キリストの贖いによって正しい者とされず、容赦なく地獄へと落とされる。何故なら、彼らは『汚れた者』であり『憎むべきことと偽りとを行なう者』だからだ。『汚れた者』とは、罪の汚れをキリストの聖なる血によって洗い清めていない者を意味している。彼らは罪の汚れを持ったままなので、燃えないゴミが焼却場の中に入れられるかのように地獄へと投げ入れられ、永遠の刑罰を受ける。人が汚らわしいゴミを火に投げ入れるように、神も汚らわしい蛆虫たちを火に投げ入れられるのだ。『憎むべきことと偽りとを行なう者』とは、要するに聖なる神の法に従わない者を意味している。何故なら、律法に適わない行ないは『憎むべきこと』であり、それは神の前に真実な行ないではないからである。救いに選ばれていない者たちは、神とその御子であられるお方に従うことを拒むので、憎悪すべき偽りに満ちた歩みから決して離れようとしない。だから、ヨハネも言うように、『御子に聞き従わない者は、いのちを見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる』(ヨハネ3章36節)ことになるのだ。それゆえ、彼らは神の怒りの刑罰の場所である地獄に投げ込まれ、決して天の都に導き入れられることがない。
ヨハネは、このようにこの箇所で書くことで、聖徒たちを威嚇し、天の都に入れるように促しているのである。というのも、このように言われるのを聞けば、『汚れた者』や『憎むべきことと偽りとを行なう者』とにならないように気をつけるようになるのは明らかだからである。いったい、聖徒であるにもかかわらず、このように恐ろしいことを聞かされながら、何の刺激も感じず、堕落に自分の身を任せることに抵抗感を持たないままでいる者がいるであろうか。エサウのような近視眼的な愚者でない限り、ここで言われていることを聞いて、大いに自分を戒めることになるのは言うまでもない。また、ここでこのように言われているのは、神が聖徒たちに天国に入ってほしいと願っておられることを示している。だからこそ、神はヨハネを通して、このように言われたのだ。神が聖書の中でこのように言っておられる箇所は、他にもある。例えば、ヘブル3:12~14やⅠコリント10:12がそうである。
天の都に入れないようになりたくない聖徒たちは、『汚れた者』や『憎むべきことと偽りとを行なう者』とに堕さないように注意すべきである。そのような者に堕したならば、その者に天国はもはやなくなる。『子羊のいのちの書に名が書いてある者』であれば、そのようにならずに済むことであろう。しかし、命の書に名が書いていない者は、やがて堕落して天国に相応しくない者として正体を現わすであろう。全ては選びにかかっている。選ばれていれば堕落しないし、選ばれていなければ堕落する。我々としては、天国に相応しくない者とはならないように、力を尽くす以外にはない。というのも、もし選びが全てを決するからといって何もせず怠惰になるのであれば、そういう者は、天国に行けなかったとしても何も不思議ではないからである。実際、世の中には「選びが全てであるゆえ、選ばれている人は何をしても最終的には天国に入れるだろうし、選ばれていない人はどれだけ頑張っても地獄に行くことになるのだから、全ては選びに委ねて何もしないままでいたほうが得策ではないのか。」などと思って怠惰にふけるような人がいるのである。確かに選びが全てを決するのだが、こういう態度は不真面目であって、よくない。こういうような人たちは、恐らく選ばれていないのだと思われる。
これから22章目に入っていく。先にも述べたことだが、どうしてここで章の区切りを改めてしまったのか。まだ残りの5節分が天国に関する記述として続いているのだから、ここで章を新たにするのは明らかにおかしい。黙示録の章を区分した人は、いったい何を考えていたのであろうか。
【22:1~2】
『御使いはまた、私に水晶のように光るいのちの水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て、都の大通りの中央を流れていた。』
『いのちの水の川』とは、もちろん永遠の命を示している。天国に導き入れられた聖徒たちは、この『いのちの水の川』に永遠に与かり、とこしえまでもキリストにある生命を愉しみ喜ぶ。ここにこそキリストの救いにおける目的があった。このような恵みを受けた聖徒たちは、その恵みを覚えて、永遠に神に感謝と賛美とを捧げ続けるのである。
この川が『水晶のように光』っていたのは、永遠の命に見られる神の栄光を示す。神は、聖徒たちに与えられた永遠の命そのものにおいても、御自身の栄光を表わされる。何故なら、神は御自身の栄光のためにこそ、聖徒たちに永遠の命をお与えになるからである。その永劫の生命のうちに見られる栄光の輝きが、ここでは『水晶のように光る』という言葉で言い表されている。
この川が『都の大通りの中央を流れていた』のは、永遠の命こそ天国における本質的な要素だからである。この永遠の命があるからこそ、そこは天国なのだと言える。このことに疑いを持つ人はいないはずである。何故なら、もし永遠の命がなければ、そこは地上世界と何も変わらないのだから、天国とは言い難いからである。それゆえ、ここで天国の本質である永遠の命を示す『いのちの水の川』が『都の大通りの中央を流れていた』と書かれていたのは実に適切であった。
この川が『神と子羊との御座から出て』いたのは、永遠の命が神とキリストにかかっているからである。確かに聖書では、永遠の命を持つのは、神とキリストによると教えられている。つまり、永遠の命は神とキリストから出る。キリストはヨハネ17:3の箇所でこの永遠の命について、こう言われた。『その永遠のいのちとは、彼らが唯一まことの神であるあなたと、あなたの遣わされたイエス・キリストとを知ることです。』
【22:2】
『川の両岸には、いのちの木があって、12種の実がなり、毎月、実ができた。』
『いのちの木』というのも、やはり永遠の命を示す。人は最初、もし従順を貫き通したのであれば、園の中央にあった命の木から取って食べることで永遠に生き続けるようにと決められていた(創世記3:22)。ここで書かれている『いのちの木』については、創世記2~3章の箇所で書かれている。ここでは、明らかに読者がこの創世記の箇所を思い起こすように要請している。
この至福の木に『12種の実がな』ったのは、この木に出来る実を選ばれた者たちだけが食べられるということを示している。それは、先に見た『12の門』(21:12)が、選ばれていた者だけを通すことを示していたのと同じである。つまり、これは実際にこの木に生る実の種類を教えたものではないと私は考える。すなわち、これは単に象徴数として言われているということである。21章と22章には「12」という数字が幾つも出てくるのだから、それらは象徴数として言われていると考えるのが自然であると今の私は思う。
この木は『川の両岸』に、いくつも生えていたと理解すべきであろう。何故なら、この木が川の両岸にそれぞれ1本ずつしかなかったとは、考えにくいからである。天国には多くの贖われた聖徒たちがいるのだ。その聖徒たちの数多さを考えても、この木は多く生えていたとするのが自然である。それがどのぐらいの本数だったかということについては分からないが、とにかく全聖徒たちに不足することがないだけの量だったのは間違いない。もっとも、1本の木があまりにも巨大であり、考えられないぐらいに多くの実をつけるので、川の両岸にそれぞれ1本ずつしか生えていなかったという可能性もないわけではない。いずれにせよ、ここではこの木が永遠の命を示していると弁えていれば、それで十分である。というのも、ここでは永遠の命のことが主眼とされているからだ。
この木に『毎月、実ができた』のは、永遠の命の継続性を示している。すなわち、実が『毎月』出来たとは、「絶えず永遠の命の恵みが注がれ続ける」という意味である。もし永遠の命の恵みが途切れることでもあれば、それは永遠の命とは言い難い。それゆえ、永遠の命は常に神から恵みが注がれることで保たれている。だからこそ、そのことを教えようとして、ここでは永遠の命を示す木に『毎月、実ができた』と言われているわけである。このように天国にいる聖徒たちは途絶えることなく永遠の生命のうちに生かされているので、「もしこの命が失われたり停止されたりすることがあればどうしようか…」などと心配になることはまったく有り得ない。
ところで、この『いのちの木』とは実際的なものであろうか、それとも単に永遠の命を象徴する比喩表現に過ぎないものであろうか。これは、どちらにも捉え得る。もし実際的なものとして捉えるならば、天国にいる聖徒たちは実際にそこにある『いのちの木』から実を取って食べることで、永遠の命を保ち続けるということになる。アダムも、もし罪を犯さなかったとすれば、そのようにして永遠に生き続けることになっていたであろう(創世記3:22)。他方、もしこれが象徴的な表現に過ぎないとすれば、実際には天国に『いのちの木』なるものは無いことになる。私としては、今の時点ではまだ判断がつかないでいる。しかし、この木が永遠の命を示しているという点を弁えていれば、これが実際的なものであるのか象徴的なものであるのか知らなかったとしても、それほど問題にはならない。もしこの『いのちの木』が実際的なものか象徴的なものか確言するのであれば、聖句が根拠になければならない。聖句が根拠にないにもかかわらず、「こうだ!」などと確定的に言うことは許されない。何故なら、神聖なる聖句が証拠として挙げられないのであれば、それは矮小で信頼に値しない理性の考えを根拠としているということだから。聖徒たちは、明白な根拠聖句があるからこそ初めて確言してよい、ということをよく弁えなければならない。
『また、その葉は諸国の民をいやした。』
『諸国の民』とは、もちろん天国にいる諸々の民族のことである。これは地上世界にいる諸々の民族のことではない。何故なら、ここでは天国のことが語られているからである。
命の木に生えている『葉は諸国の民をいやした』のは、天国の聖徒たちが永遠に健康であり元気であることを教えている。つまり、この「癒す葉」とは聖徒たちにおける健康と元気を象徴している。というのも、『いのちの木』に生えている『葉』を使えば、ずっと壮健でいられるからである。
この『葉』における形状や数量や効能について詳しく知りたい人がいるのであろうか。そのような疑問はナンセンスである。ここでは、聖徒たちが無病息災でいられるということだけを知っていれば、それで十分だからである。たとえこの葉について詮索したところで、具体的なことは何も分からないであろう。このような神が明らかにしておられない知り得ない事柄については知らないままで満足しているのが、知恵である。カルヴァンも言うように、「神の御霊が明らかにしたまわないことは未解決のままに残したほうがよい」(『旧約聖書註解 創世記Ⅰ』19:12 p341:新教出版社)。
この『葉』も、『いのちの木』と同じように、やはり実際的なものなのか象徴的なものなのか判断がつかない。もし前出の木が実際的なものであればこの葉も同様に実際的なものであることになり、もし前出の木が象徴的なものであればこの葉も同様に象徴的なものであることになる。この件について私の理解が進んだ時には、この箇所の内容をより良いものにすべく更新することになるであろう。
なお、この22:1~2の箇所は、間違いなくエゼキエル書47:12の箇所と対応している。ヨハネは、エゼキエル書の箇所に基づいて、この箇所を書いたとしか思えない。というのも、この2つの箇所の内容は、あまりにも類似しているからである。エゼキエル書のほうでは次のように言われている。『川のほとり、その両岸には、あらゆる果樹が生長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月、新しい実をつける。その水が聖所から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。』聖なる所から流れている川、その川の両岸、そこにある木、その木が毎月実らせる実および癒しを与える葉、といった多くの類似点が、この2つの箇所に見られるのは明らかである。このエゼキエル書47:12の箇所については、第4部の中で詳しく説明されることになる。
【22:3】
『もはや、のろわれるものは何もない。』
天国では、『もはや、のろわれるものは何もない』という幸いがある。というのも、天国には罪が無いからである。呪いとは、罪に対して神が正当なる報復をなされることである。すなわち、呪いとは常に罪を前提としている。それゆえ、天国には呪いをもたらす罪がないので、呪いもまったく存在しないのである。もし天国に呪いが少しでもあったとすれば、最早そこは天国とは言えなくなる。それゆえ、我々は次のような定義を持つことができる。「天国とは呪いがまったく存在しない場所である。」
天国に呪いがまったく存在しないというのは、つまり天国には祝福だけしかないということを意味している。何故なら、呪いと呪いをもたらす罪が存在しないのであれば、それは祝福しかないということになるからである。天国にいる聖徒たちは罪を何も犯さず、ただただ『正しい行ない』(19:8)しかしない。神はそのような『民を楽しみとする』(イザヤ65章18節)ので、ただただそこにいる聖徒たちに祝福だけをお注ぎになられる。もし天国が祝福しかない場所では無かったとすれば、最早そこは天国とは言えなくなる。それゆえ、我々は次のような定義を持つことができる。「天国とは祝福しか存在しない場所である。」
ここで次のような疑問を持つ人がいるかもしれない。「まったく呪いがない世界など果たして存在し得るのであろうか。まったくそこにいる人たちが罪を犯さないということがあり得るのであろうか。」確かに、このように聖なる場所とそこに住む人の聖なる性質が驚くべきものであるということを、私は認める。何故なら、そのような場所と人の性質は、罪に満ちた世界に住む今の我々が持つ感覚からすれば、良い意味で「異常」だからである。いったい、誰がこのような場所と人の性質に驚かないであろうか。そこには僅かにさえも呪いが見られないとは…。そこに住む人たちは塵ほども呪いの原因となる罪を犯さないとは…。だが、天国とそこに住む人の性質とは、実際そのようである。何故なら、神が天国とそこに住む人たちについて、そのように啓示しておられるからである。それゆえ、聖徒である者たちは、これらのことを真実なることとして信じなければいけない。というのは、神の啓示を子どものように受け入れ信じる人が、聖徒なのだからである。キリストはそのような人こそが、神の国に入ると言っておられる(マタイ19:13~15)。神の啓示をそのまま信じようとしないのであれば、そのような人は聖徒とは言い難い。これらのことを信じようとしない人たちは、好きにさせておこう。その者たちは、恐らく天国に入るように選ばれていないのであろう。もし選ばれていたとすれば、神の啓示を拒絶することはなかっただろうから。そういう人たちについて、キリストは次のように言っておられる。『彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。』(マタイ15章14節)
【22:3~4】
『神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。』
天国には『神と子羊との御座が』その中にある。こここそが天国における中心である。何故なら、天国の本質とは神とキリストに他ならないからである。誰がこのことを疑うであろうか。これは、宮殿で言えば謁見の間がそれに当たると考えればよい。昔には、主の御座がある場所は複数ある天の階層における最上の階層であると考えていた人たちもいたが、この考えは無視しても差し支えない。何故なら、天に複数の階層があるかどうか我々には分からないのだから。とろこで、ここでキリストが御座に座っておられると教えられていることは誰の目にも問題ないはずだが、父なる神も御座に座っておられるとはどういうことであろうか。まさか、父なる神もキリストのように受肉された上で物理的な御座に実際的な意味において座られるとでもいうのであろうか。そのようなことはない。何故なら、神の三位格のうち、実際に受肉して物理的な身体を持たれたのは第二位格であられる御子だけだからである。では、ここで父なる神も御座に座っておられると言われているのは、どういうわけなのか。キリストのように肉において座っておられるというのでなければ、それはどのような状態における着座なのであろうか。これについては理解し得ない、と私は言おう。何故なら、ここで描かれている光景は天国という場所についてであって、事柄は徹底的に霊的だからである。我々は、ただ単純に『神と子羊との御座が都の中にあ』ったとだけ理解していれば、それで十分である。
天国にいる『しもべたちは神に仕え』る。何故なら、神に仕えることこそ人間の本来的な意味また目的であって、そのようにすることにこそ人間の幸いがあるからである。天国では人間の意味と目的が有効的に実践され、またそこにいる住民は神の恵みによる幸いを享受すべき存在なのだから、そこにいる者たちは永遠に至るまでも神に仕え続けるのである。そこにいる聖徒たちは祝福されているので、地上世界にいる堕落した人間たちとは違って、神に仕えることを大いに喜ぶ。このこと、すなわち天国においては聖徒たちが神に仕えるということについては、既に7:15の箇所でも書かれていた。
『神の御顔を仰ぎ見る。』とは、聖書で多く出てくる表現である。これは、人が神と不和の状態にはないということを意味している。何故なら、もし不和の状態にあれば、人は『神の御顔を仰ぎ見る』ことが出来ないからである。これは「神の御顔が隠される。」という表現と真逆の意味を持っている。こちらのほうは、人が罪のゆえに神と不和の状態にあることを意味している。何故なら、人が罪を犯していれば神の御顔に自分の顔を向けられないだろうし、神もそのような人からは御自身の御顔を隠されるからである。天国にいる聖徒たちは、神の御顔を仰ぎ見つつ神と共に親しく生き続ける。それは永遠の期間に及ぶ。というのも天国とは永遠に続く場所だからである。これも天国において聖徒たちに注がれる幸いな恵みの一つである。
【22:4】
『また、彼らの額には神の名がついている。』
天国の聖徒たちには、その額に3種類の名が刻まれている。それは、神とキリストと新しいエルサレムの名である。これについては既に3:12の箇所で説明しておいた。
【22:5】
『もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らにはともしびの光も太陽の光もいらない。』
神とキリストという光のゆえに天国には『夜がない』ということについては、既に説明された通りである。
『彼らは永遠に王である。』
天国に導き入れられた聖徒たちは、キリストの恵みのゆえに王として生き続ける。聖徒たちは使徒も言う通り、地上世界においても王だったが、それは実際的な意味においてではなかった。誰でも分かるように、地上にいる聖徒たちは霊的な意味においては王であるが、その多くが実際的な意味においては一般市民である。しかし、天国では全ての聖徒たちが実際的な意味における王とされる。それは、彼らが自分に与えられた領域を支配するからであり(マタイ25:14~30、ルカ19:11~27)、また王としての偉大な尊厳を持っているからである。しかも、それは『永遠に』までも及ぶ。というのも、神が聖徒たちを永遠に王として生かされるからである。そうなるのが神の御心だったのである。これは誠に大きな恵みである。キリストは、聖徒たちをこのような輝かしい状態に至らせるためにこそ、御自身を永遠の贖いとして神に捧げられた。それゆえ、聖徒たちは自分を贖って下さった救い主に永遠までも感謝と賛美を捧げねばならないのである。「聖徒たちは天国で人々を支配しないから王とは言えないではないか。」などと言うべきではない。確かに、天国において、その多くの聖徒たちは周りの人々を支配しないと思われる。何故なら、多くの聖徒たちが誰も彼も自分以外の聖徒たちを支配するというのは考えにくいからである。しかし、ここでは地上世界について言われているのではないことを弁えるべきである。ここで言われているのは天国のことだ。そこでは地上世界と比べ、多くの面において性質や概念が異なっている。それは聖書において啓示されている天国の事柄を考えてみれば分かることである。それだから、天国においては、たとえ周りの人々を支配しなかったとしても、そこにいる全ての人が実際に『王』であることが可能なのである。もしそうでなければ、この22:5の箇所では嘘が書かれていることになる。しかし、ここで嘘が書かれているなどと誰が考えるであろうか。
神が天国で聖徒たちを永遠に王とされるのは、御自身の栄光のためである。神は御自身の栄光を求める御方であり、そのためにこそ聖徒たちを王として生かされる。もし聖徒たちを王にしても神の栄光とならないとすれば、聖徒たちが天国で王になることはなかった。聖徒たちが天国で永遠の王となれば、「御自身の民を永遠の王にされた主は何と大いなる御方なのであろうか。」ということにもなる。そうすれば、そこにおいて神の栄光が表わされることにもなる。何故なら、神の聖徒たちに対する大きな恵みが豊かに表われ、認められ、感謝されるからである。これは、あたかもあるサッカーの監督が超大物スター選手だけを集めた夢のチームを作り、そのチームを通して更に名を上げようとするようなものである。その際に「この監督は粋なことをするものだ。」などと言われるように、神も天国において「神は素晴らしいことをして下さったものだ。」などと言われるのである。
天国で永遠の王になりたい者は、救い主であられるキリストから離れないでいるがよい。つまり、『死に至るまで忠実で』(2:10)いるがよい。そうすれば、キリストが天国で永遠の王として下さるであろう。あなたは、もはや一般市民ではなくなるのだ。しかし、キリストから離れる者は、天国で永遠の王となることができない。何故なら、その者は『いのちの水の泉、主を捨てたから』(エレミヤ17章13節)である。主を捨てる者が、どうして主により天国で永遠の王にしてもらえるであろうか。その者は天国の主宰者を退けたので、地獄にまで落とされる。その場合、あなたは一般市民どころか奴隷化の存在、すなわち極悪の霊的な大犯罪人となり、しかも永遠の苦しみを受けることになるので実に惨めである。
再び述べるが、どうして章を区分した人は、ここで章を改めなかったのか。現行の区切りである22:5の箇所で黙示録に書かれている預言が一通り終わるのだから、ここで章の区切りを付けるのが適切である。私は21章目以降の章の区切りに不満である。
第28章 2522章6~21節:エピローグ
この箇所は、これまでの箇所に比べると、そこまで難しいというわけでもない。何故なら、この箇所で言われているのは、これまでに語られてきたことの繰り返しが多いからである。とはいっても、難しいことに変わりはない。ただ黙示録の他の箇所と比較すれば、そこまで難しいとは言えないというだけである。また、たとえ難しくはなかったとしても、書かれている事柄を正しく解釈できるのは神の恵みによる以外ではない。この箇所では、多くの重要なことが記されている。それは解釈次第で、黙示録全体の理解を大幅に変動させてしまうほどの内容である。それゆえ、この箇所に書かれていることも、この箇所以外の箇所で書かれていることと同様、少しも甘く見ることは許されない。もし軽んじて挑むのならば、解釈を誤り、黙示録の全体を間違って捉えることになってしまう。
【22:6】
『御使いはまた私に、「これらのことばは、信ずべきものであり、真実なのです。」と言った。』
御使いがこのように言ったのは、聖徒たちが、黙示録で示された啓示の幻を受け入れないようなことがないためである。というのも、それは神による幻だからである。聖徒たちは神の啓示に立つべき存在なのだから、その聖徒たちが神の示された言葉を受け入れないというようなことがあってはならないのである。今の時代に生きる我々も、御使いが言ったように、『これらのことば』を『信ずべきものであり、真実』であると理解せねばならない。ところで『これらのことば』とは何のことか。これは、黙示録における全ての預言の言葉を指すと私は解する。何故なら、この箇所は、黙示録における全ての預言が一通り語り終えられた直後に書かれている箇所だからである。つまり、これはすぐ次の箇所(21:7)で言われている『この書の預言のことば』に該当するとすべきであろう。文脈から考えると、そう理解するのが自然である。しかし、これを21:9の箇所から始まる御使いの示した幻に基づく言葉であると解する人も、中にはいるかもしれない。私はその人の理解と争おうとは思わない。何故なら、これはとんでもなく本質的で重要な事柄であるというわけでもないからだ。しかし、次の聖句と黙示録全体の文脈を考慮するならば、これは黙示録の全ての預言の言葉を指していると解するのが、もっともらしい。
このような言い方による説得は、19:9や21:5の箇所でも見られる。またパウロも、このような言い方により真理を拒絶しないようと手紙の中で言っている。Ⅰテモテ1:15の箇所である。『「キリスト・イエスは、罪人を救うためにこの世に来られた。」ということばは、まことであり、そのまま受け入れるに値するものです。』これらの言い方は、つまり「これは真実で信じるべきものだから受け入れなかったら裁きを自分の身に招くであろう。」ということを言った、威嚇を伴う説得方法に他ならない。
『預言者たちのたましいの神である主は、その御使いを遣わし、すぐに起こるべき事を、そのしもべたちに示そうとされたのである。』
ここでは主が、『預言者たちのたましいの神』と言われている。この『預言者たち』とは、それまでに存在した全ての神の預言者を指す。ここでは、ヨハネを通して黙示録の預言を語られた神が、それまでにいた全ての預言者の神と同一の神であったということが言われている。これは、読者たちが、万一にもヨハネを通して預言をされた神が、それまでの預言者たちを通して預言をされた神とは別者であったなどと思い違いをしないためである。つまり、これも黙示録を読んだ聖徒たちが、そこで語られている預言を拒絶したりしないようにするために言われたものである。というのも、もしヨハネが今までの預言者を通して語られた神とは別の存在によって預言をしていたなどと思ったのであれば、聖徒たちが黙示録の預言を拒絶してしまうことになりかねないからである。神は、このようにヨハネに書かせることで、聖徒たちが勘違いをしないようにと配慮をされた。何となれば、神とは思慮そのものであられる御方だからである。なお、ヨハネが黙示録の中で記した預言は、聖書の全預言における終局であると言ってよい。何故なら、ヨハネの記した預言は、それまでにされてきた預言の総まとめのようなものだからだ。これは黙示録を読めば明らかである。
ここで明言されているように、黙示録で示されている出来事は『すぐに起こるべき事』であった。もう一度言う。黙示録で示されているのは、『すぐに起こるべき事』だったのである。例外の箇所はない。プロローグとエピローグの部分、すなわち預言が始まる冒頭の部分と預言が終わった最後の部分で「これらの預言はすぐに起こることなのだ。」と言われているのに注目しようとしないのであろうか(1:1、22:6)。当然ながら、これは本当に注目すべきことである。このように最初と最後の部分で、これらの預言は『すぐに起こる』と言われているのは、この文書で示されている出来事が全て例外なく『すぐに起こる』ということを意味している。ある者たちは、20:1~6の箇所までは『すぐに起こる』出来事が書かれていたと信じるが、20:7以降の箇所は『すぐに起こる』出来事ではないと考えている。というのも、彼らは今の時代が20:1~6の箇所に該当すると考えており、そこで言われている『千年』という言葉を非常に長いに違いないなどと聖句に基づかず印象により思い込んでいるからである。しかし、残念ながら、この期間が非常に短いということを私は明白な聖句の根拠に基づきつつ証明した。それだから、彼らは黙示録の出来事が『すぐに起こる』と言われた神の言葉に逆らっているのである。その他の多くの聖徒たちは、黙示録で書かれているほとんど全ての出来事は、まったく実現していないと考えている。何故なら、多くの聖徒たちは、そもそも黙示録の内容を何も理解できておらず、ただ何となくそこで言われている出来事がまだ未実現であって、これから起こるようにと感じているからである。つまり、印象により何の根拠もなく、ただ自分の思うままにそう考えている。例えば「チェルノブイリこそがあの『苦よもぎ』(8:11)なのだ。」などと言ったりする人は、ただ感覚的にそう思うからというので、このように言っているに過ぎない。しかし、黙示録には紀元1世紀に起こる出来事が書かれているということを、私はこれまで神の恵みにより豊かに論じた。それだから、多くの聖徒たちも、黙示録の出来事が『すぐに起こる』と言っておられる神の言葉に同意していないことになる。もっとも、多くの聖徒たちは何も知らないがゆえ、そのように神の言葉に反した思いを抱いているのだから、それほど強く責められるべきではないと私には思われる。この『すぐに』という言葉は、文字通りの意味として捉えるべき言葉である。読者は、私が神の恵みにより黙示録の内容を豊かに論じたのを見たであろう。それは、『すぐに』という言葉を文字通りに捉えたから出来たことである。もしこれを文字通りには捉えていなければ、私が黙示録をこんなにも豊かに論じることは出来ていなかった。それゆえ、この『すぐに』という言葉を、文字通りの意味として捉えないということがあってはならない。「ペテロによれば神にとって『千年は一日のよう』(Ⅱペテロ3章8節)だから、この『すぐに』という言葉は千年を一日とされる神の感覚により捉えられるべきものだ。」などと言って。私は断言するが、この言葉を文字通りに、すなわち人間の感覚に基づいた『すぐ』という意味として捉えない者は、黙示録を永遠に正しく理解できないままに留め置かれるであろう。
要するに、今まで聖徒たちは、黙示録をまったく何も理解できてこなかった。例外はないと言ってよい。昔の人が書いたものを読めば、それは明らかである。それでは、どうして今まで聖徒たちは、黙示録を正しく理解できなかったのか。それは、キリストの再臨を正しく捉えていなかった、というのが大きな原因であった。キリストの再臨が紀元68年6月9日に起きたと信じていないと、どうしても黙示録で書かれている出来事が『すぐに起こるべき事』であると理解することは出来なくなる。何故なら、再臨と黙示録の内容は全く調和しているので、再臨が遥か未来に起こる出来事だと理解すると、自然と黙示録の内容も遥か未来に起こる出来事だと理解することになるからである。それは誤った見解であるから、黙示録を正しく理解できないことに繋がってしまう。しかし私のようにキリストの再臨が紀元68年6月9日に起きたとパウロの聖句に基づいて信じると、黙示録で書かれている出来事は『すぐに起こるべき事』だったと考えることが可能となる。これも、やはり再臨と黙示録の内容が調和しているためである。そのように捉えるのは正しい見解であるから、その結果、黙示録を正しく理解できるようにもなるのである。ここで「そのような見解は今まで一度も聞かれたことがなかった。だから怪しいぞ。こんな珍奇な見解には警戒すべきだ。」などと言って抗弁することはできない。我々は、ルターもそのように言われて、カトリック陣営から激しく攻撃されたことを忘れてはならない。カルヴァンが「キリスト教綱要」の中で言っているように、当時のカトリックはルターの述べた真理を「珍奇」な見解として徹底的に退けた。そのため、ルターは異端者とされ、教皇の大勅書により破門されてしまうほどであった。しかし、ルターや彼に続く宗教改革者たちは何も珍奇な見解を主張したわけではなかった。何故なら、彼らは単に使徒や教父たちの言ったことを繰り返し、それを更に豊かに強調したに過ぎなかったからだ。私の場合でも同様のことが言える。私は何か目新しいことを言っているのではなく、単にキリストと使徒が語った預言を、既に成就したものとして繰り返しているに過ぎない。つまり、私はキリストと使徒による預言を、そのまま語っているのである。というのも、キリストと使徒による預言は既に成就しているがゆえ、今となっては成就したものとして語るのが本当の意味でそのまま語るということだからである。一方、キリストと使徒による預言を文字通りの意味でそのまま語っている教師たちは、実はその預言をそのまま語ってはいないことになる。何故なら、確かにそれは文字としてはそのまま語っているかもしれないが、既にそれが成就したことを理解していないので、内容の本質を弁えないで語っていることになるからである。文字としてはそのまま語るが、内容としては時代的な意味において無分別なことを語る。これが果たして「そのまま語っている」と言えるのであろうか。
詰まるところ、聖徒たちが今まで黙示録を理解できなかったのは、「裁き」という一語に帰結される。今まで教会は黙示録の研究を真剣にしてこなかった。それは、そもそも最初から諦めの精神があったからである。それは「どうせ分かるはずがない。」という精神のことである。これは明らかに不信仰である。神が、そのような不信仰に対して、解釈上の盲目という裁きをお与えになったとしても何も驚くには値しない。何故なら、神は不信仰の者に対しては、それ相応の裁きをもって報いられる御方だからである。私はといえば―自らを誇るのではなく全ては徹底的に神の恵みによるのであるが―、「不可能なき神が働かれたら黙示録は全て理解することができる」という精神をもって黙示録という霊的な迷宮に挑戦しているので、裁きを免れている。神は信仰を喜ばれる御方であり(ヘブル11:6)、信仰のある者にこそ恵みをお与えになる(ヤコブ1:5~6)。だからこそ、私は神の恵みにより裁きを免れ、このように豊かに黙示録を理解しまた論じることが出来ているわけである。もし聖徒たちにおける黙示録の誤解や無知が「裁き」でなければ一体なんだというのか。これは「解釈上の飢饉」でなくて何であろうか。
今、黙示録を間違って理解していた聖徒たちは、悔い改めて黙示録の正しい理解を会得すべきである。黙示録を誤解するというのは、確かに悔い改めなければならないことである。もし小さな嘘でさえも悔い改めなければいけないとすれば、尚のこと、黙示録の誤解については悔い改めなければいけないことになる。何故なら、小さな嘘よりも黙示録を誤解するということのほうが、大きい過ちだからである。これは特に黙示録を講壇から論じたことのある教師たちに言わねばならないことである。何故なら、その教師たちは、黙示録を間違って教えることで、多くの聖徒たちを惑わしたことになるのだから。もし悔い改めなければ、その人は悲惨な状態から抜け出せないままとなる。すなわち、黙示録をいつまで経っても誤解し続けるという悲惨に陥ったままとなる。これは霊的な災害であると言える。もしこの註解を全て読んだにもかかわらず悟らず心を頑ななままにする人がいたとすれば、そのような人は、神の存在を大いに感じさせられたにもかかわらず心を頑なにして延々と悔い改めなかったあのパロと似ている。「私の黙示録に対する理解は間違っていないから悔い改める必要もない。」などと言う人がいるのであろうか。こういう人はいないと思うが、もしいたとすれば、私はその人に問いたいものである。すなわち、私のように黙示録を十全に教えることができるのか、もしできるとすればその教えには自信があるのか、もし自信があるとすれば私と議論して私を言い負かすことができるのか、と。恐らくこの問いに堂々と答えられる人はいないと思われる。であれば、私の言った通り、黙示録のことで悔い改めなければいけないということにもなろう。何故なら、これらの問いに堂々と答えられない人は、この註解で語られていることを受け入れざるを得ないはずだからである。
【22:7】
『「見よ。わたしはすぐに来る。』
キリストは紀元68年6月9日にエルサレム上空の場所において再臨されたということを、私は既に聖書から論証した。それゆえ、ここでキリストが言っておられる『すぐ』とは、人間が感覚的に感じる通りの意味における『すぐ』であると捉えなければいけないことになる。もしそのように捉えなければ、ずっと黙示録とそれ以外の聖書の巻に書かれている再臨に関わる事柄を正しく解釈できないままとなるであろう。
『この書の預言のことばを堅く守る者は、幸いである。」』
『この書』とは黙示録を指す。これを聖書66巻であると捉えるべきではない。何故なら、ヨハネが黙示録を紀元37~41年の間に書いている時には、まだ今知られている形としての新約聖書は存在していなかったからである。その時には、まだⅡテサロニケ書さえも記されていなかった。それだから、これを聖書66巻だと理解するのは間違いである。もっとも、そのように理解するのは、より敬虔的であるとは言える。しかしながら、聖書の言葉は、それがより敬虔に感じられるかどうかという基準により解釈されるべきものではない。そうではなく、聖書の言葉は、それが本当に正しい解釈か、聖書的か、神の御心に適っているか、という点に基づいて解釈されるべきものである。もし敬虔に思えるかどうかという点が解釈の尺度だとすれば、写本の場合でも、例えば「主」としか書かれていない写本より、「神である主イエス・キリスト」と書いてある写本が常に原文の通りであると決めねばならないことになってしまう。何故なら、どう考えても「主」より「神である主イエス・キリスト」という言葉のほうが、より霊的に思われるからである。しかし、多くある写本においては、必ずしも我々の感覚がより霊的だと思える写本のほうが常に正しいというわけではないのである。これは写本だけではなく解釈においても同様である。よって、ここでは『この書』=「黙示録」だと捉えねばならない。
『堅く守る』とは、「信じて決して疑うことをしない」という意味である。これは実にヘブル的な言い回しである。
どうして、黙示録に書かれている預言の言葉を堅く守る者は、幸いなのか。それは『時が近づいているから』(1:3)であった。この時は、キリストの再臨やネロによる大患難が間近に迫っていた。それゆえ、この時代における聖徒たちは、そのような出来事に心を向け、信仰を強め、しっかりと霊的な備えをしなければいけなかった。つまり、のんびりしていたり、平和ボケしてはいけなかった。だからこそ、ここでは『この書の預言のことばを堅く守る者は、幸いである。』と言われたのである。というのも、そうしなければ、再臨や苦難が起きた際に、大いに慌ててしまうことになりかねないからである。この箇所は、明らかに1:3の箇所と内容的に同じことが言われている。これは、本当にこの文書で書かれている預言を心に留めなければいけなかったことを意味している。何故なら、冒頭と最後の箇所で、わざわざ2回も同じ内容のことが語られているからである。
今の時代の聖徒たちは、どのようにして黙示録の預言を『堅く守る』のであろうか。今の聖徒たちは、そもそも黙示録の預言がどのようなものか、よく把握できていない。把握していないのであれば、『堅く守る』こともできない。何故なら、よく弁えていない事柄を、しっかりと守ることは難しいからである。よく分かっていないにもかかわらず、堅固に固守することが一体どうしてできようか。それゆえ、今の聖徒たちは黙示録の預言を『堅く守る』ために、まずその預言をよく把握することから始めねばならない。そうしてこそ、黙示録の預言を固守できるようにもなるのだ。しかし、聖徒たちが黙示録の預言を本当に正しく把握したとすれば、その預言を固守すべき本来的な人々は、今の時代に生きる我々ではなく、ヨハネから手紙を貰い受けた紀元1世紀の聖徒たちだったということに気付かされるはずである。何故なら、ヨハネは紀元1世紀における『アジヤにある7つの教会』(1:4)へ黙示録を書いたのであって、その預言は『すぐに起こる』と言われていることからも分かるように、既に成就しているからである。このことに気付いた聖徒たちは、恐らく多かれ少なかれ動揺するのではないかと思う(もちろん人によってもそれぞれ感じ方は違うだろうが)。
【22:8】
『これらのことを聞き、また見たのは私ヨハネである。』
『これらのこと』とは、これまでに書かれた黙示録の全ての幻のことである。すなわち、1:10から22:5までに書かれていたあらゆる幻が、それである。
ヨハネは、ここで言わば署名をしているのである。それは、聖徒たちがこの文書を万が一にも拒絶したり、疑念を抱いたりしないためであった。何故なら、ヨハネがこれを書いたと分かれば、どうしても受け入れざるを得なくさせられるからである。キリストの使徒であるヨハネが書いた文書を、退けたりする人が、果たしてまともな聖徒の中で誰がいるのであろうか。まともな聖徒であれば、いないはずである。それだから、ヨハネがこのように自分の名を記したのは、自分の名を示して名声を得るためだというのではなかった。使徒である人が、どうしてそういうことをするであろうか。むしろ、ヨハネが自分の名を記したのは、自分のためではなく読者たちのためであった。つまり、ヨハネは愛のゆえに、聖徒たちがこの文書に否定的な態度を持ったりしないようにと、このように名を記したのである。すなわち、ヨハネは『私たちは、互いに愛し合いましょう。』(Ⅰヨハネ4章7節)と命じたことを、自分自身で守ったわけである。ヨハネは1:1、4、9でも、この文書を書いたのが自分であることを明白に示している。
この文書の著者が本当にヨハネかどうか疑うような人がいるのであろうか。例えば、「パウロの黙示録」や「ニコデモ福音書」のように、実際の著者はその作品名にある人物とは別の人物だったのと同じだと黙示録について考える人がいるのであろうか。この文書を書いたのは、間違いなくあのヨハネである。すなわち、ここで名を記したのは当の本人である。黙示録の文章とヨハネが書いた他の文書である福音書と3つの手紙の文書を比べてみると、秘儀的であるかどうかという1点だけを除けば、すべての点で共通していることが分かる。黙示録も福音書および3つの手紙と同じように、繰り返しが多く、文章が平易でありあまり洗練されておらず、内容が剥き出しであり、時間の順序にそれほど注意が払われておらず、非常に霊的であり、恐れのない大胆な書き方がされている、という特徴がある。試しに黙示録から文章の秘儀性という要素を取り除いた上で、黙示録を考えてみられるとよい。そうすれば、黙示録は福音書および3つの手紙における著者と同一の人物が書いたとしか考えられなくなるはずである。エイレナイオスの著書を読んでも分かるように、黙示録は既に古代からヨハネが書いた文書であると当然のように理解されてきた。アウグスティヌスも、これがヨハネによる文書だと思って疑うことをしなかった。中にはこれが真作であるかどうか疑った人もいたが、そういう人は少なかった。今更になって、黙示録を書いたのがヨハネであるのかどうか問題にするのは、いかがなものかと思われる。これは著者名が何も記されていない「ヘブル人への手紙」とは違うのだ。
『私が聞き、また見たとき、それらのことを示してくれた御使いの足もとに、ひれ伏して拝もうとした。』
ヨハネが御使いの前に『ひれ伏して拝もうとした』のは、これで2回目である。1回目は19:10の箇所で書かれている。
ヨハネは、御使いを通して示された神の預言を、あたかもそれが御使いから出たかのように感じてしまった。それは、その預言の幻を示したのが、直接的には御使いだったからである。それだから、ヨハネは御使いの前に『ひれ伏して拝もうと』してしまったのである。人間とは、表面上に表われた事物にだけ心を向ける傾向を持った生命体である。その背後にある本質的な事物には、なかなか心を向けようとはしない。それというのも人間いうは存在は弱く、目の前に表われた表面的な事物だけで精神が一杯になってしまうので、その背後にある事物にまで精神を超越させるのには少なからぬ知性の力が必要となるからである。この傾向は、特に女性のほうが強い。それは、ヒトラーや大スターなどといった表面的には非常に輝かしい人物を見て失神してしまう女性が昔から少なからず見られるのに対し、男性ではそのような人はまったく見られないことを考えても分かる。女性はより弱い性なので、男性よりも目の前に現れた表面上の事柄に心を奪われがちなのである。つまり、女性は男性に比べて「目の前の事物で心が一杯になりやすい」。男性は女性に比べると、より目の前にある表面上の事柄に心を吸い寄せられない傾向を持つ。しかし、男性も人間であって弱い存在だから、女性と同じように目の前に現れた事物に心が貼り付けにされてしまう傾向を持つ、という点では何も変わらない。ヨハネも使徒とはいうものの、あくまでも弱い人間の一人であった。それだから、ヨハネは神の預言を、背後に隠れてはいるものの本来的な発信者であられる神にではなく、現実的な発信者ではあるもののあくまでも間接的な発信者に過ぎなかった御使いに帰してしまったわけである。もしヨハネが自分に預言を示してくれた御使いの背後におられる真の発信者に心を吸着させていたとすれば、目の前にいる間接的な発信者である御使いを神でもあるかのように拝もうとはしなかったであろう。ここでのヨハネの悪徳は、神にまで精神を超越させなかったことに原因がある。
いったい、使徒ヨハネともあろう者が、このような悪徳に陥ってしまったとはどういうわけなのか。これは看過ならぬ悪徳である。しかも、2回も彼はこのような悪徳に陥ってしまった。これはヨハネの罪が明らかに知れ渡るようになるためであった。我々は、このような描写を見て、ヨハネも罪人の一人であったことを知るのである。また、この描写から、我々は人の悪徳はただでは消し去られないということも教えられる。古代の人の多くは「本性的な悪徳を改善するのは至難の業である」などと言ったものだが(※)、これは確かにその通りである。本性的な悪を消し去るのは、あたかもビッシリとこびりついた固い粘着物を、鋭い突起の付いた棒で一生懸命剥がそうとするようなものである。つまり、それはほとんど不可能にも等しい。それほど本性的な悪というものは、改善するのが困難なのだ。ソロモンも箴言27:22の箇所で、今述べたのと同じことを言っている。曰く、『愚か者を臼に入れ、きねでこれを麦といっしょについても、その愚かさは彼から離れない。』つまり、愚か者の持つ本性的な悪は、何をしたとしても除去することが出来ない、ということである。それだから、ヨハネも一度ばかりでなく2度も、このような悪徳に進んでしまったわけである。ヨハネが、何であれ崇高な存在や事物を拝みやすい性質を持っていたのは疑えない。もっとも、全能の神が働かれたのであれば、あらゆる悪徳が一瞬のうちに吹き飛ばされることになるものではあるが。神により回心した愚かな悪人が、瞬時に善だけを求める新しい人に変えられたのを、我々が昔から見ている通りである。
(※)
例えば紀元2世紀の人であるケルソスは、こう言っている。「いずれにしても、罪を犯す本性と習性を持つ人々を罰することによって、ましてや憐れみによって完全に変えることなど誰にもできないことは、まさしく万人に明らかである。本性を完全に変えることは非常に困難だからである。」(オリゲネス『キリスト教教父著作集9 オリゲネス4 ケルソス駁論Ⅱ』ケルソス駁論 第3巻 65 p62:教文館)
[本文に戻る]
【22:9】
『すると、彼は私に言った。「やめなさい。私は、あなたや、あなたの兄弟である預言者たちや、この書のことばを堅く守る人々と同じしもべです。神を拝みなさい。」』
ヨハネは、再び御使いから愚かな悪徳を諌められてしまった。御使いの言ったことは、先に見た19:10の箇所と言葉はやや違うものの、内容的にはほとんど同一である。ヨハネは使徒であり敬虔な人だったから、このように御使いから諌められて大いに恥じ入ったことは間違いない。もし恥じ入らなかったとすれば、ヨハネは敬虔な人でなかったことになるからである。
このように2回もヨハネの罪が記されたのは、神の御心であった。神が、このように書かれることを欲されたのだ。でなければ、このような記述がなされることはなかった。このようにヨハネの悪が赤裸々に描写されたのは、ヨハネが崇拝されないためである。このようにヨハネの罪が示されるからこそ、ヨハネに栄光が帰されないようにもなる。何故なら、黙示録という素晴らしい内容の文書を書いている一方で、御使いを拝もうとするという致命的な罪をも同時に犯しているからである。神は、栄光が御自分だけに帰されて、人間に帰されることは望んでおられない。何故なら、栄光とは神の専有物だからである。それゆえ神はイザヤ書の中でこう言っておられる。『わたしはわたしの栄光を他の者には与えない。』(48章11節)このゆえに、神はヨハネに自分のした悪を記すようにと、その聖なる霊によって働きかけられたのである。もしヨハネがこのように自分の悪をまざまざと書き記していなかったとすれば、ヨハネは偶像崇拝の対象となっていたかもしれない。それはヨハネを通して書かれた黙示録の内容が、神的であって人間的ではないからである。既に述べたように、人間的には偉大と見なされるような人たちの悪徳が隠されることもなく記されるというのは、聖書の通例である。ヨハネも、その例に漏れてはいなかったのだ。
【22:10】
『また、彼は私に言った。「この書の預言のことばを封じてはいけない。時が近づいているからである。』
『時が近づいている』ので、ヨハネは『この書の預言のことばを封じてはいけな』かった。『封じ』るとは、隠して秘密にするということである。ここでは「封じるな」と言われている。つまり、黙示録の預言は、大いに知れ渡るようにされるべきものであった。何故なら、もう間もなく再臨や大患難が起こることになっていたからだ。この文書が封じられず大いに知らされるからこそ、聖徒たちはやがて来る大いなる出来事に備え、霊と信仰とを整えることが出来る。もしこの文書が隠されていたとすれば、聖徒たちはほとんど何も警告や予告をされないことになるから、それだけ準備をするのは難しくなるのだ。神はあらかじめ聖徒たちが備えを出来るようにと、ここでこの預言を封じてはいけないと御使いに言わせたのだ。読者は、ここで黙示録の預言を封じてはならないと言われた理由が、『時が近づいている』からだったということを強く心に留めるべきである。すなわち、もし時が近づいていなければ、この文書を封じてはならないとは言われていなかったかもしれないということである。
この22:10の箇所から、黙示録に書かれている預言の出来事は『すぐ』(1:1、22:6)起こると言われていたところの『すぐ』という言葉を、文字通りの意味に捉えねばならないということを明白に論証することができる。それは、どのような論証であるか。まずダニエル書8:26の箇所を見ていただきたい。そこでは、『荒らす者』(ダニエル8:13)についての預言が遠い未来に起こるために、その預言を封じなければいけないと命じられている。すなわち、そこではダニエルにこう言われている。『先に告げられた夕と朝の幻、それは真実である。しかし、あなたはこの幻を秘めておけ。これはまだ、多くの日の後のことだから。』この箇所では「秘める」ようにと言われているが、同じことが語られているダニエル書12:4、9を見れば分かるように、これは「封じる」ということである。ダニエルが封じるようにと命じられた預言の中で語られている『荒らす者』とは、すなわち「ネロ」である。その預言の中では、ネロが聖徒たちを蹂躙する出来事について語られていた。これがネロだということは、既に第1部の中で詳しく語られている。ダニエルが預言を封じるようにと命じられたのは紀元前6世紀であり、ネロが聖徒たちを蹂躙したのは紀元60年代である。つまり、ダニエルに与えられた預言は、約600年後に起こる出来事についてであった。だから、ダニエルは約600年後に起こる出来事について語られた預言を、隠して人々に知られないようにせねばならなかったことになる。それは、同じく600年後に実現する喜ばしいキリストの預言とは異なり、悪しき出来事についての預言を600年前に聞かされても、あまり意味がなかったからである。キリスト出現の預言であれば、たとえ600年前に聞かされたとしても、霊に良い影響をもたらすであろう。しかしネロの大患難についての預言を600年前に聞かされても、意味もなくそわそわしてしまうだけである。それならば、かえって聞かないほうが霊のためには良いことになる。実際、ダニエルはこの預言を聞いたので、悩んで脅かされ(ダニエル7:15)、ひどく怯えて顔色が変わり(同7:28)、病気になって驚きすくまされた(同8:27)。最高の霊性を持っていたダニエルでさえこうなってしまうのであれば、ダニエル以外の者が知ったら一体どうなってしまうであろうか。これでは、預言が封じられるべきだったとしても、何も驚くべきことではない。これは、王位に就いた人に対して、民衆や側近の者がこれから起こる喜ばしい出来事だけを話し、やがて王位から退かねばならない日が訪れることについては何も口にしないのと似ている。喜ばしい出来事については遠い未来のことであっても喜ばしいものだが、王位から退けられるという出来事については聞いても何も意味がないどころか、かえって気持ちが暗くなるだけだからである。さて、ダニエルには悪しき出来事が約600年後に起こるからというので、その出来事について語られた預言を封じなければいけないと命じられた、ということをよく考えてもらいたい。これは、黙示録で言われている『すぐ』という言葉を、神の感覚を基準として捉え、2千年以上もの年月だと解してはならないことを我々に教えている。何故なら、600年後に起こる悪しき出来事でさえもダニエルが封じなければいけなかったとすれば、尚のこと、2千年以上も経過してから起こる悪しき出来事についての預言は封じられなければいけないことになるからである。これは10歳の子供でも分かるはずである。もしこの『すぐ』という言葉が本当に2千年以上もの年月として解されねばならないとすれば、ダニエル書のほうでは600年後の出来事でさえも封じられねばならないと言われているのに、黙示録のほうでは2千年以上も経過してから起こる出来事なのに封じるなと言われていることになる。つまり、より短いほうが封じるように言われており、より長いほうが封じるなと言われている。これは、どう考えてもおかしい。普通は明らかに逆であろう。すなわち、普通に考えれば2千年以上も経過してから起こる出来事のほうが封じろと言われ、600年後に起こる出来事のほうは封じるなと言われるはずである。何故なら、それが悪しき出来事であるがゆえに隠さねばならないとすれば、より長い年月が経過してから起こる預言のほうが隠すべき必要性が高いからである。誰がこれを疑うであろうか。このように、もし『すぐに』という黙示録の言葉を神の感覚を基準として捉えると、ダニエル書の記述と矛盾が生じてしまうことになる。これは『すぐに』という言葉を、本当に文字通りに捉えるべきことを教えている。私が既に説明したように『すぐ』という言葉を文字通りに理解すれば、50年も経たないうちに起こる悪しき出来事の預言が「封じるな」と警戒できるために言われているのに対し(これは黙示録のほうである)、600年後に起こる悪しき出来事の預言のほうは「封じよ」と心を無意味に騒がせないために言われている(これはダニエル書のほうである)、ということになるから、非常に理に適っている。こう考えれば論理的な矛盾も起こらない。だから、この22:10の箇所をダニエル書8:26の箇所により考察するのであれば、『すぐに』という言葉は文字通りの意味として捉えねばならないことが分かる。
今書かれた論証に反論できる人は、恐らくいないはずである。「ダニエルに与えられた預言は600年後に起こる出来事についてのことではない。」などと言っても無駄である。私が既に聖書から証明したように、ダニエルに与えられた預言の中で語られている荒らす者とはネロ以外ではないからだ。しかし、どうして今まで聖徒たちは、この22:10の箇所をダニエル書の箇所と比較しつつ真剣に考察してこなかったのであろうか。それは、22:10を考察するどころか、そもそも黙示録自体を研究しようとする気さえ起こらなかったからである。今までの聖徒たちは、黙示録に見られるその異常なほどに膨大な「謎」の海を目の前にして、圧倒されてしまったのである。ちょうど敵国の巨大な軍隊が凄まじい力を見せつけてきたので、兵士たちが戦う前から諦めモードになってしまうのと同じである。
【22:11】
『不正を行なう者はますます不正を行ない、汚れた者はますます汚れを行ないなさい。正しい者はいよいよ正しいことを行ない、聖徒はいよいよ聖なるものとされなさい。」』
この箇所では、間近に迫っている再臨と大審判の時に向けて、更に善と悪の存在が2分化するようにと言われている。人間がもやもやした曖昧な状態を嫌うように、神ももやもやした曖昧な状態を嫌われる。いや、むしろ神がそのような状態を嫌われるからこそ、人間もそのような状態を嫌うと言ったほうがより正しい。何故なら、人間とは『神に似せて』(創世記5章1節)造られたのだから。人間が明白な状態に区分されているのを喜ぶように、神も来たるべき時になるまでに善人と悪人の存在がますます明白化されるのを喜ばれるのである。なお、ここで命じられている2つの対象は、主の羊小屋の中にいる羊と山羊だけに限定して考えられなけれなならない。ここでは文字通りの意味としての全人類について言われているのではない。何故なら、ここで言われているのはマタイ13章のことであって、つまり主人の言った『収穫まで、両方とも育つままにしておきなさい。』(マタイ13章30節)という言葉についてだからである。すなわち、ここでは教会の内部にいる者たちが、麦である真のキリスト者たちは更に善行に進んでキリスト者としての姿を神の目の前に明らかにし、毒麦である偽キリスト者たちは更に不正なことをして偽キリスト者としての姿を神の目の前に明らかにすべきだ、ということが言われている。そのように麦が麦らしく成長し毒麦が毒麦らしく成長することで、遂にクライマックスとして両者が右と左により分けられるという結末の実現へと至るのだ(マタイ25:32~33)。
それにしても、「正しい者たちは正しいことを更にするように」という部分は別として、「悪しき者たちは悪しきことを更にするように」と言われている部分は他に類を見ない記述である。これは前代未聞の記述といってよい。今まで誰がこのようなことを命じたであろうか。誰がこんなことを大胆に命じられるであろうか。しかも、聖なる文書の中で、このような悪の命令が公然とされているのである。シビュラの託宣にも、シオンの議定書にも、ニーチェの作品にも、このような命令は見られない。ネロやヘリオガバルスも、このような命令はしなかった。はっきり言って、この命令の内容は人間の理性を超越している。悪を大いに行なうようにと公然の命令がなされるとは…。もし人間理性により黙示録が書かれたのだとすれば、このような命令は書けなかったであろう。というのも、これは人間の自然な感覚から乖離しているから。それだから、このような悪の命令は、正に神がこの黙示録という文書を書かれた明白な証拠であるとしてよい。神がヨハネを通してこの文書を書かれたからこそ、このような人間の感覚を越えた命令が書かれたのである。それゆえ、このような神的な記述を前にして、聖徒たちの霊は神に対して驚きつつ平伏させられるのである。
教師たちは、後ろの部分、すなわち「正しい者は更に正しくなれ」という部分については、大いに口にすべきである。何故なら、神は正しい者に対して、彼らが更に正しくなるのを望んでおられるからだ。『わたしが聖であるから、あなたがたも、聖でなければならない。』(Ⅰペテロ1章16節)と神が言われた通りである。今まで、キリスト教の教師たちは、実際にそのように口にしてきた。しかし、前の部分、すなわち「邪悪な者はますます邪悪になれ」という部分については、聖書でこう言われているからといって、自分もそのように言ったりすべきではない。何故なら、神は人々が邪悪になるのを望んではおられないからである。むしろ、神は人々が悪から立ち返るようにになるのを望んでおられる。次のように聖書で言われている通りである。『わたしは悪者の死を喜ぶだろうか。―神である主の御告げ。―彼がその態度を悔い改めて、生きることを喜ばないだろうか。』(エゼキエル18章23節)『悪者はおのれの道を捨て、不法者はおのれのはかりごとを捨て去れ。』(イザヤ55章7節)お分かりであろう。確かに神は聖書の中で、人々が悪において成長することがないようにと望んでおられるのだ。もしこの部分の通りに講壇の上から命じる教師がいたとすれば、どうなるであろうか。その教師は教職の立場から退けられても文句は言えない。ここで悪者が更に悪くなるようにと言われているのは、ただ裁きの時に向けて悪者が更に悪者としてその真の姿を明瞭に現わすように、という御心に関する願いのことが表明されているに過ぎない。もし教会が神の言葉の通りにこう言わねばならないとすれば、教会は悪の勧誘所となってしまうであろう。
我々は、この箇所で悪が勧められていることを読んで、神を悪の勧誘人であるなどと思ってはいけない。確かに神は、悪者が悪者として明確化することを望んではおられる。それは、彼らが永遠に滅ぼされるためであり、彼らの存在とその悪とが明らかになるためである。しかし神は、実際的な意味においては、悪者であっても悪に進むことを望んではおられない。何故なら、神は義であられ、悪そのものを憎んでおられるからだ。神が、むしろ悪者がその悪から離れるようになるのを望んでおられるというのは、聖書を読めば誰でも分かることである。そうでなければ、神は使徒たちを通して、邪悪のうちに歩んでいる者たちに次のように言われはしなかったであろう。『そういうわけですから、あなたがたの罪をぬぐい去っていただくために、悔い改めて、神に立ち返りなさい。』(使徒行伝3章19節)『神は、まずそのしもべを立てて、あなたがたにお遣わしになりました。それは、この方があなたがたを祝福して、ひとりひとりをその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなのです。』(同3章26節)つまり、こういうことである。神は、御計画の実現という観点からは悪を望んでおられるが、実際に実現するという観点からは悪を望んでおられない、ということである。例えば、神は御計画のゆえにアダムが悪に陥って堕落することを欲されたが、アダムが実際に堕落すること自体を欲されたわけではない。言うまでもなく、神は実際的にはアダムが堕落しないことを欲しておられた。しかし、御計画における御心は常に実際的な御心に優先されるので、神はあえてアダムが堕落するという実際的には御心に適わない出来事を許容された。この22:11の箇所で悪者どもが悪に歩むようにと言われているのも、それと同じである。すなわち、神は御計画の面からすれば悪者が更に悪者としてその真の姿を明瞭にするのを望んでおられるのだが、実際的に言えばむしろその悪者が出来るならば悔い改めて悪から離れるようになるのを望んでおられる。この場合も、やはり御計画における御心のほうが優先されるので、神はあえて悪者どもが悪に突き進むことを望まれたのである。このように聖書で言われていることは霊的であって、人間の理性では計り知れず、そのため難しい。それだから、この箇所は非常に誤解しやすく、よく考えないといけない箇所である。我々はよく祈り、このように霊的な事柄を上手に理解できるように注意を働かせねばならない。
【22:12】
『「見よ。わたしはすぐに来る。わたしはそれぞれのしわざに応じて報いるために、わたしの報いを携えて来る。』
ここで言われているのは、再臨の時期に起こる大審判についてのことである。何故なら、ここではキリストの再臨の時に報いが起こる、と言われているからだ。その報いとは何か。あの空中の大審判でなくて何であろうか。この報いについては、マタイ25:31~46、黙示録20:11~15の箇所で詳しく描写されている。
この箇所では、つまりこう言われているのである。「聖徒たちよ。私はもう間もなく再臨するのだから、怠惰にしていてはいけない。その時には、おのおのの行ないに応じて報いがなされることになる。その報いは永遠の状態を左右する重要なものである。それだから、あなたがたは良い報いを得られるように、気を引き締めてシッカリとしていなければいけない。そのような報いに心を向けないということがあってよいものであろうか。」つまり、ここでは滅びに定められている悪者どもに対して威嚇がなされたというのではなく、救いに定められている聖徒たちに対し、より敬虔になるようにと促しがされているのである。
【22:13】
『わたしはアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。初めであり、終わりである。」』
ここでは、つまり次のように言われていることになる。「聖徒たちよ。私がこのように言ったのだ。イザヤ書の中でかつて語っていた私が、である。そのような存在である私がこのように言ったのだから、どうしてその言葉を心に留めないでよいであろうか。そのような者がいたとすれば、どれだけ叱責を受けるに値するであろうか。」要するに、この22:13の箇所では前の箇所である22:12で言われたことが重厚になり尊厳を持つようになるため、神聖な署名がなされているのである。これは、ある国王が発布した文書の最後の部分で、「これは〇〇国の王である私が書いたものである。」などと書かれるようなものである。
このような署名は、特にレビ記の中で多く見られる。例えば次のような聖句がそうである。どれも最後に神の署名がされているのが分かる。『あなたがたは、わたしの名によって偽って誓ってはならない。あなたの神の御名を汚してはならない。わたしは主である。』(レビ記19章12節)『あなたがたは、わたしのすべてのおきてとすべての定めを守り、これらを行ないなさい。わたしは主である。』(同19章37節)
【22:14】
『自分の着物を洗って、いのちの木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都にはいれるようになる者は、幸いである。』
この箇所では、聖徒たちが天国にシッカリと入れるように促しの言葉が語られている。ここでは3つのことが語られているが、どれも本質的な事柄としては一緒の内容である。つまり、同一の事柄を3つの言い方で言うことで、よりその一つの事柄を強調し、豊かに語っているわけである。
『自分の着物を洗って』とは、イエス・キリストの聖なる血により自分を洗い清めるという意味である。ここでは罪の肉体が『着物』として言い表されている。創世記49:11の箇所でも、贖いを受ける者たちが『着物』(また『衣』)と言われている(※)。この部分で言われているのは、つまり「キリストの血により洗い清められて天国に入れるようになる者は幸いである。」ということである。
(※)
『彼はその着物を、ぶどう酒で洗い、その衣をぶどうの血で洗う。』
[本文に戻る]
『いのちの木の実を食べる権利』とは、天国に入って永遠の命を受けられるようになる、という意味である。22:2の箇所でも既に述べたように、この『いのちの木』という言葉を、実際的に捉えるか象徴的に捉えるか、という点には注意せねばならない。この木は、新約聖書では黙示録だけにしか書かれていない。これが黙示録だけにしか書かれておらず、新約聖書の他の巻ではそのまま『永遠の命』と言い表されていることから考えると、これは比喩表現として捉えるべきなのかもしれない。何故なら、もし本当に物質的な木から実を取って食べることで永遠の命が継続されるという仕組みになっているとすれば、新約聖書の他の巻でそのことが一切書かれていないのは、どういうわけなのか。もしそれが天国における実態だとすれば、少しぐらいは黙示録以外の新約聖書の巻でもそのことに言及されていてよかったはずではないか。しかし、誰も天国を見に行って戻って来た人はいないのだから、この件についてはこれ以上のことは言わないでおくことにしたい。この部分で言われているのは、つまり「天国に入って永遠の命を享受できるようになる者は幸いである。」ということである。
『門を通って都にはいれるようになる』とは、天国の門をくぐってそこに住まうようになる、という意味である。この『門』とは、キリストのことである(ヨハネ10:7、9)。この門は、キリストの羊である者だけしか通ることができない。この部分で言われているのは、つまり「イエス・キリストの物として天国に入れるようになる者は幸いである。」ということである。
当然ながら、ここで言われている促しの言葉は、今の時代に生きる我々に対しても向けられている。何故なら、この箇所の内容は、普遍的なことを言っているからである。もう間もなく再臨と大患難が起こるという点を除けば、今の聖徒たちも、やがて数十年後には天国に導き入れられるという点で紀元1世紀の聖徒たちと変わることがない。それゆえ、ここで書かれていることが自分に実現してほしいと望む者は、キリストから離れないでいるがよい。そのようにしてキリストに保ち続けられるのであれば、ここに書かれていることがやがて自分に実現されるであろう。
【22:15】
『犬ども、魔術を行なう者、不品行の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを行なう者はみな、外に出される。』
この箇所では、聖徒たちが地獄に行かないようにと威嚇の言葉が語られている。これは万が一にも聖徒たちが信仰から離れて地獄へ堕ちないようにするための、神の聖なる配慮である。真の聖徒たちは、このような威嚇の言葉を聞いて恐れ、ますます地獄に堕ちることがないようにと気を付けるようになるのである。このような威嚇は、既に21:8の箇所でも行なわれていた。
『外に出される』とは、「天国の外に出される」という意味である。「天国の外に出される」とは天国に入れないということだから、「地獄に堕ちる」ということである。つまり、ここでは省略した言葉が使われている。聖書の中で、このように省略した言葉が書かれるのは珍しいものではない。
この箇所では、地獄に堕ちる6種類の存在が挙げられている。『犬ども』以外の5つは、既に21:8の箇所で説明した通りだから、ここでは『犬ども』だけを説明すればよいであろう。この『犬ども』は、2通りの捉え方ができる。一つ目は『神殿男娼』である。申命記23:17~18の箇所では、神殿男娼が『犬』と呼ばれている。この箇所では、律法の違反者について取り扱われている。だから、この『犬ども』という存在も、律法の違反者としての神殿男娼を指していると捉えることができる。ここで、「しかし、そのような数の少ないであろう悪者が第一の位置に挙げられるなどということは有り得るのであろうか。」などと疑問に思う人がいるかもしれない。確かに神殿男娼は数が少なかったかもしれないが、同じく数が少なかったであろう『魔術を行なう者』も、より多く見られる他の4種類の者たちより前に置かれているのだから、別に第一の位置に置かれていたとしても問題にはならない。もし数の少なさのゆえに第一の位置に置かれることを問題にするならば、同じ理由から『魔術を行なう者』が第二の位置に置かれていることも問題にせねばならなくなる。恐らく、紀元1世紀のアジヤ教会には、このような者たちに関する問題があったのかもしれない。だからこそ、ヨハネはここで「そのような犬どもは地獄に堕ちるであろう。」と言ったと。アジヤの地域には異教やその神殿が多く満ちていたのだから、アジヤの教会が神殿男娼の存在に煩わされていたとしても不思議ではない。しかし実際はどうだったか、よく分からない。もしかしたら、そうだったかもしれないとしか言えない。それゆえ、これが神殿男娼だったという可能性を完全に切り捨てるべきではない。第二は、これを忌まわしい働き人と捉える捉え方である。パウロはピリピ3:2の箇所で、『悪い働き人』を『犬』と呼んでいる。パウロがアジヤの教会に書いた手紙を見ても分かるように、当時この地域には多くの邪悪な働き人がいたようである。それだから、ここでは、そのようなサタンの教師どもについて言われていると考えることができる。キリストがマタイ6:6の箇所で『犬』と言っておられるのも、このような偽教師であるとしてよい。彼らはサタンの霊に取り憑かれているので、聖なる真理を差し出してやると、犬でもあるかのように『それを足で踏みにじり、向き直って』『引き裂く』からである。要するに、ここでは真理を聞くと犬のようにキャンキャンと吠え立てる獣的な人間が言われていると考えるのが、第二の捉え方である。確かに彼らは、神聖なる真理を受け入れないでやかましく吠え立てるのだから、犬も同然である。いずれにせよ、ここで言われている『犬ども』という存在が、正気ではない忌まわしい存在であると捉えていれば、ひとまずのところは問題ない。これを男娼と捉えるか偽教師と捉えるかは、各自に任せたい。
言うまでもなく、ここでなされている威嚇の言葉は、今の時代に生きる我々に対しても向けられている。ここで言われている内容は普遍的だからである。この箇所の言葉を、ヨハネの時代の聖徒たちだけに向けられたものとして限定するのは、よくない。もし『外に出される』ことになりたくなければ、聖徒たちは堕落して『犬ども、魔術を行なう者、不品行の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを行なう者』にはならないがよい。もしそのような者に成り下がれば、天国は取り上げられ、地獄が与えられることになるのだ。
我々は、ここで言われているような威嚇を、世の人々に対してもしていかねばならない。我々の見習うべきキリストや使徒たちも、そのようにして世の人々を、地獄の恐怖で威嚇したのである。しかしながら、今の時代においては、人々の気持ちをはばかって、語るべきことを差し控える傾向が見られる。例えば、「罪」と言うと嫌がられるので「弱さ」と言い換えたり、「地獄」と言うと人が逃げて行くので地獄については何も語らない、という教会がそうである。こんな教会は現在において、いくらでもある。これは御言葉よりも人々の気持ちのほうを優先させたことによる。このように御言葉を大胆に語らないでいると、最終的にはティリッヒのように、人々は御言葉を嫌がるから語らないほうがよい、などと言い出すまでに落ちぶれてしまう。御言葉を差し控えるので、神の裁きにより、更に御言葉がその口や文章から取り去られてしまうのである。実際、ティリッヒの著書の中には、それがキリスト教の著書であるにもかかわらず、まったくといっていいほど御言葉が出てこなかったので、非常に驚かされたものである。我々は、そのようであってはならないのである。何にせよ、我々はここで言われているように罪と刑罰とについて、聖書の通りに伝えていかねばならない。神もそれを我々に望んでおられる。何故なら、そのように大胆に行なうからこそ、人々が真理を知れるようにもなるからである。もし真理を大胆に語らなければ、どうして聖書の真理を知ることができるのであろうか。まともに聞かされなければ、まともに知ることができないのは目に見えているのである。
【22:16】
『「わたし、イエスは御使いを遣わして、諸教会について、これらのことをあなたがたにあかしした。』
ここまでに示された預言の幻は、キリストから出たものであった。それはヨハネがした証しではなかった。御使いも、ただキリストの証しを媒介する役目を持っていただけである。この幻が与えられた『諸教会』とは、すなわち紀元1世紀における『アジヤにある7つの教会』(1:4)および当時あったその他の地における教会である。というのも、この文書で書かれている内容は、明らかに当時の教会に対して言われたものだからである。これは、ここまでの註解を読まれた人であれば、よく分かるはずである。今の聖徒たちは、この『諸教会』というのが、今までに至る2千年の間に存在してきた地球上の全ての教会であると解するかもしれない。しかし、それは誤っている。これは直接的には、再臨が起こるまでの時期に存在していた教会として限られるべきである。もちろん、これは神の文書であって、そこには普遍的な内容が多く含まれているのだから、間接的に言えば再臨が起きてから後の時代に存在している教会にも多くの言葉が向けられていると理解せねばならない。
それだから、この黙示録という文書を読んで何か良いことを感じたのであれば、ヨハネに対して称賛を送るべきではない。これはヨハネの証しではないのだから。これはキリストの証しだから、キリストにこそ栄誉が帰されねばならない。このキリストを差し置いて、単なる筆記人に過ぎないヨハネに栄誉を帰するのは、明らかに道理に反しているのである。同様の理由から、御使いにも、この文書にかかわる栄誉を帰したりすべきではない。御使いも、単にキリストの証しを取り次ぐ媒介者に過ぎなかったからである。別にヨハネと御使いは、たとえ自分に栄誉が帰されなかったとしても、何も文句は言わないはずである。何故なら、ヨハネと御使いは詩篇記者と共に、次のように言うはずだからである。『私たちにではなく、主よ、私たちにではなく、あなたの恵みとまことのために、栄光を、ただあなたの御名にのみ帰してください。』(詩篇115:1)
『わたしはダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。」』
これは、その言われた言葉に重みを持たせるための神的な署名である。ここでは、あたかも「このような存在である私がこのように言うのだから、その言われたことを心に留めねばならない。」とでも言われているかのようである。このような署名は、既に22:13の箇所でもされていた。
『ダビデの根』とは、人としてのキリストが、その源流をダビデに持っておられるという意味である。あらかじめ預言されていた通り、キリストはダビデを根として持つ存在として生まれなければならなかった。『子孫』とは、キリストが親を辿ればダビデに行き着く、という意味である。これは先の言葉と、意味としてはほとんど変わらない。マタイ1:1~17に書かれている系図を見れば、ダビデから発してキリストに至るまでの流れを確認することができる。このマタイの箇所で、どうしてマリヤではなく血の繋がっていないヨセフの系図が記されているのかという問題は、ここで取り扱うべきことではない。これについては今までに出た福音書の註解書を見ればよい。『輝かく明けの明星』とは、キリストが金星のように輝いておられるからである。1:13~16で示されているキリストの姿を見ると、確かにキリストが輝いておられたことが分かる。先に見た2:28の箇所でも、キリストは『明けの明星』と呼ばれていた。
ここではキリストが3つの言い方で言い表されているが、これも20:13の箇所で確認したのと同じで、やはり「3連弾の法則」が見られる。すなわち、ここでは色々な言い方がされているが、それはどれもキリストのことだから「キリスト、キリスト、キリスト」と言われていることになる。このように黙示録では、3連弾の言葉が出てきた際、その意味するのはどれも種類としては同一の事柄である。このような文章表現は実にヘブル的である。
【22:17】
『御霊も花嫁も言う。「来てください。」これを聞く者は、「来てください。」と言いなさい。』
『来てください。』とは、栄光の再臨を待望する敬虔な声のことである。当時の聖徒たちは、真にキリストの再臨を待ち望まなければいけなかった。何故なら、もう間もなくキリストが神の国と共に天から降りて来ることになっていたからである(マタイ16:28)。ルカ19:11~27の箇所から分かるように、キリストの再臨とは、すなわち「王の帰還」である。それだから、僕である聖徒たちは、僕である者に相応しく、自分の王がやがて帰還されるのを切に望まなければならないのである。当時の聖徒たちがキリストの再臨を待ち望んで『来てください。』と言わないのは、許されないことであった。というのも、もしキリストが自分たちの王となられるのを望んでいたのであれば、必ずキリストが王として帰還されるのを望んでいたはずだからである。王の帰還を望まないというのは、つまり、その王を事実上否認していることである。その者が王として自分たちの上に立つのを望まないからこそ、王の帰還を望まないからである。そのような者は王の僕として相応しくないので、王が帰還された際、皆殺しにされてしまった。すなわち、そのような偽クリスチャンは、キリストが紀元68年に再臨された際に携挙されず、1260日経過して第二の携挙に与かって後、大審判の場で王なるキリストの前に連れて来られ永遠に滅ぼされることとなった。『ただ、私が王になるのを望まなかったこの敵どもは、みなここに連れて来て、私の目の前で殺してしまえ。』(ルカ19章27節)と王が言っている通りである。我々は、この22:17を読んだ当時の聖徒たちが、皆揃って『来てください。』と言ったと信じるべきである。何故なら、まともな聖徒であれば、必ずキリストの再臨を大いに待望したに違いないからである。
『御霊も花嫁も言う。』とは、すなわち「教会が御霊において言う。」という意味である。教会が何か正しいことを言った際、それは御霊が言われたことでもある。何故なら、御霊は教会に正しいことを言わせて下さるからである。『来てください。』と教会が言うのは明らかに正しいことである。だからこそ、ここでは『御霊も花嫁も言う。』と言われているのである。もっとも、正しくないことを教会が言った場合、話は別である。その場合、その正しくないことを言ったのは教会だけであって、御霊がそのように言われたことには決してならない。
今の時代の聖徒たちは、この箇所を読んで、心から『来てください。』と言うであろう。実際、今の時代の聖徒たちの多くが、この箇所を読んで、そのように言っている。私も、あるバプテスト派の伝道師から、『アーメン。主イエスよ、来てください。』(22:20)という御言葉が大胆に書かれている年賀状を貰ったことがある。しかし私は言うが、今の聖徒たちは、この箇所を読んで『来てください。』と言うべきではない。何故なら、もう既にキリストは来られたからである。私がマタイ16:28やⅠテサロニケ4:15を提示しつつ「キリストは既に再臨した。」と言うと、牧師たちのうち誰一人として聖書から反論できないのだから、私の言うことは認められねばならない。再臨が既に起きたのであれば、確かにもうこのように言う必要はなくなったということになろう。今の聖徒たちが『来てください。』と言っても意味はない。何故なら、どれだけ再臨を待ち望んだとしても、もうそれは起こったので、いつまで経っても再臨が起こることはないからである。実際、この2千年間ずっと教会は『来てください。』と言い続けて来たが、キリストが来られることはなかった。確かなところ、もう間もなく再臨が起こると信じている牧師は本当に多い。遠くから巨大で不可解な音が聞こえた時に、「もしかしたら再臨が…」などと心の中で感じる牧師は多いはずだ。地震が頻発している時にも、「間もなく再臨が起こるのかもしれない」などと思う牧師は少なくないはずだ。しかし、残念ながらこれから再臨が起こることはないであろう。また、このように言って再臨を待ち望むのは、マイナスの効果さえもたらす。その待ち望む度合いが強ければ強いほど、マイナスの効果も大きくなる。何故なら、再臨を待ち望むと、再臨に全ての解決を求めるようになるから、非建設的になり、未来志向ではなくなり、力を大いに喪失させられるからである。切迫再臨信仰を持つプロテスタント教派を見てみられたい。そこには大成したり素晴らしいことを実現させようとする建設的な文化人があまり見られないことに気付くであろう。「これから再臨が起こるのに偉業などを求めて何になる…。」などと言うような人ばかりである。ロスチャイルドとそのイルミナティも、念願の世界支配のために、キリスト教に再臨を大いに待望させて軟弱にし、自分たちの邪魔にならないようにと仕掛け人を送っている。その仕掛け人とはダービーやスコフィールドである。他にもこのような仕掛け人は多くいることであろう。イルミナティカードの中にも、キリスト教に再臨を待ち望ませることを命じているカードがある。再臨がまだ起きていない時期に生きていた聖徒たちが、このように言うのは誠に正しかった。というより、このように言うのは義務であり、言わないのは咎められるべきことであった。何故なら、ここでは『来てください。』と言うように命じられているからである。しかし今となっては、そのように言うべきではないのだ。もし私に反論するのであれば、その人は再臨の内容を十全に理解しているとでもいうのか。もし再臨の内容を十全に理解しているのであれば、黙示録をも豊かに理解できるはずである。というのも、黙示録はその多くの箇所において再臨のことを教えているからである。再臨の理解と黙示録の理解は比例せざるを得ない。再臨を正しく理解しているのであればそれに応じて黙示録も正しく理解することができ、再臨を理解していないのであればそれに応じて黙示録も理解することができない。それゆえ、黙示録を理解できないということは、再臨をよく分かっていないということになるのである。もし私に反論するというのであれば、まずは再臨について教えている黙示録を豊かに理解してからにしていただきたい。再臨について大いに教えている黙示録を理解してもいないのに、堂々と私に反論するつもりなのか。それは知識のある大学教授に、知識のあまりない大学生が、さも知ったかぶって論戦を挑むようなものではないか。私の見解に反論するならば、まずは黙示録を豊かに理解してからにするのがマナーである。それとも、黙示録の理解無しに再臨を正しく理解できるとでも思うのか。黙示録を読んで、再臨に関する事柄が大いに示されていることに気付かないとでもいうのか。まさか、このように思う人はいないはずである。であれば、まずは黙示録を理解し、そこで再臨についてどういうことが言われているのか弁えるべきだということになる。そうすれば私の言ったことがよく分かるようになり、反論する気持ちも失せることになるであろう。
『渇く者は来なさい。いのちの水がほしい者は、それをただで受けなさい。』
ここでは次のようなことが言われている。すなわち、霊的に渇いている者は、信仰を持って救いの音信を受け入れ、イエス・キリストにおける永遠の生命に与かるようになりなさい、と。この箇所で言われているのは、あたかもまだ救いを受けていない者に対してであるかのようである。何故なら、ここではまだキリストにおける救いに与かっていない者が、その救いに与かるかのように言われていると感じられるからである。だが、ここで言われている対象は、既に救われている聖徒である。というのも、この文書は、聖徒たちを対象とした文書だからである。聖書において、このように既に救われた聖徒たちが、一見すると未だに救われていないかのように取り扱われている個所は、他にもある。パウロはコリント教会の聖徒に対して、そのような言い方で御言葉を語っている。すなわちパウロは、既に神と和解している聖徒たちに対して、次のように言った。『こういうわけで、私たちはキリストの使節なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちは、キリストに代わって、あなたがたに願います。神の和解を受け入れなさい。神は、罪を知らない方を、私たちの代わりに罪とされました。それは、私たちが、この方にあって、神の義となるためです。』(Ⅱコリント5章20~21節)このようなことをヨハネから言われた当時の聖徒たちは、ますますキリストの救いに心を据えたことであろう。キリストがヨハネを通して、永遠の救いを、信じる者たちにタダで与えて下さると言われたのだ。まともな聖徒たちのうちで、誰が、ますます救いについて思いを傾けずにいられるであろうか。今の時代に生きる我々も、このように言われたのを聞いて、ますます救いに自己の霊を据えるようにすべきだ。キリストの霊が、ヨハネを通して、このように喜ばしいことを言って下さったのだから。
この箇所は、明らかにイザヤ書55:1と対応している。そこでは次のように言われていた。『ああ。渇いている者はみな、水を求めて出て来い。金のない者も。さあ、穀物を買って食べよ。さあ、金を払わないで、穀物を買い、代価を払わないでぶどう酒と乳を買え。』パウロも、ローマ3:24の箇所で、キリストのよる救いは『価なしに』与えられると言っている。キリストの救いとは、無償の贖い、上から下される聖なる授与、徹底的に一方的である愛に満ちた恩恵なのである。神は、キリストによる救いを与えられる際、代価を要求されることはないのである。この22:18の箇所でも言われているように、それは『ただ』なのだから。
【22:18】
『私は、この書の預言のことばを聞くすべての者にあかしする。』
『すべての者』とは、再臨が起こるまでに生きていた紀元1世紀の聖徒たちである。これは、再臨が起きてから後に生きている聖徒たちは含んでいない。何故なら、この文書は、直接的には再臨がまだ起きていない時代に生きていた聖徒たちに対して書かれた文書だからである。確かに、ヨハネは冒頭の部分で紀元1世紀における『アジヤにある7つの教会へ』(1:4)書き送ったと明示しているのだ。重要なので繰り返すが、聖書で『すべて』と書かれていた場合、それが一体どういう意味における『すべて』なのか我々はよく考えなければいけない。『すべて』と書かれているからというので、即座に「全ての時代に生きている全ての聖徒たちだ」などと何も考えず結論するのは、思慮が足りない。この箇所(22:18~19)では、その聖徒たちに対し、黙示録をぞんざいに取り扱わないように警告するための強烈な威嚇がされている。それは2つの警告である。
『もし、これにつけ加える者があれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。』
まず『これにつけ加える』というのは、つまり黙示録の内容に付け足しを加えるということである。黙示録の言っていないようなことを、あたかも黙示録が明白に言っているかのように言ったり教えたりするのが、それである。例えば、再臨が2回起こるなどと言ったり教えたりするのが、それに該当する。再臨が1回だけ起こると言うのであれば何も問題はない。何故なら、黙示録はそう教えているからである。だが、再臨が2回起こるなどというのは黙示録の中では教えられておらず、キリストもヨハネ以外の使徒
もそのようなことは言っておらず、今まで2千年の間に存在したキリスト教徒たちもそのようなことは言わず、異教徒やユダヤ人たちもそのようなことは考えなかった。それだから、そのように言ったり教えたりする者は、黙示録に『つけ加える者』である。これはアメリカの憲法で例えて言えば、「アメリカの憲法ではプロテスタントを禁止している。」などと言うようなものである。実際はアメリカ憲法はプロテスタントを禁止してはいない。それどころか、そもそもアメリカはプロテスタントのピューリタンが入植して建国された国だし(もっとも、その大半はフリーメイソンであったのだが…)、大統領も就任式の際には聖書に手を置いて宣誓をしなければいけないぐらいにキリスト教の色合いを持つ国である。だから、このように言う者は、アメリカ憲法に『つけ加える者』と呼ばれねばならないのである。
そのように黙示録に付け足しをする者は、神が『この書に書いてある災害をその人に加えられる』ことになる。『この書に書いてある災害』とは、どういう意味であるか。これは、つまり黙示録で書かれている災害を受ける不信者およびユダヤ人と同じようにして断罪されることになる、という意味である。黙示録に付け加える者は、黙示録で書かれている災害を受ける不信者とユダヤ人と同等の者であり、それゆえ永遠の地獄に堕ちねばならないのだ。そのような者は、黙示録の御言葉を愛してはいない。黙示録の御言葉を愛してはいないからこそ、御言葉だけでは満足せず、好き勝手な付け足しをするのである。それは夫が自分の妻だけでは満足せず他の女性を求めたり、カトリックが2つの聖礼典だけでは駄目だと思って5つもの聖礼典を加えたり、パリサイ人が律法だけでは満足しないで数々の人間的な戒めを創出したのと同じことである。満足できなければ別のものを作り上げて満足を得ようとするのは必然である。そのような付け足しをする者たちが御言葉を愛して満足できないのは、そもそもキリストの御霊を受けていないからである。もし御霊を受けていれば、御言葉を愛して満足できるだろうからである。パウロも言うように『キリストの御霊を持たない人は、キリストのものではない』(ローマ8章9節)のだから、キリストの前から退けられて破滅せねばならないのである。我々も、黙示録に対して、いや、黙示録だけでなく聖書全巻に対して、何か付け足しをしないようにしよう。そのような愚行を神は大いに忌み嫌われる。そのようにしたことに対する罰は誠に大きい。
【22:19】
『また、この預言の書のことばを少しでも取り除く者があれば、神は、この書に書いてあるいのちの木と聖なる都から、その人の受ける分を取り除かれる。』
『少しでも取り除く』とは何のことであるか。これは、黙示録に明白に書かれていることを、それが黙示録の中に書かれていないかのように言ったり教えたりすることである。例えば、20:1~6の箇所で書かれている『千年』という期間が、実際には存在していないと言ったり教えたりするのが、それに該当する。既に説明されたように、この『千年』という期間は、『1260日』という非常に短い期間ではあるが、実際に存在する期間であった。だから、この期間が存在しないなどと言ったり教えたりする者は、黙示録から『取り除く者』である。これは日本の憲法で例えて言えば、「日本の憲法は日本国民に信教の自由を与えると書いていない。」などと言うようなものである。実際は、日本の憲法において日本国民が新教の自由を持っていると明白に記されている。それだから、このように言う者がいれば、日本の憲法から『取り除く者』と呼ばれねばならないのである。
そのように黙示録から『少しでも取り除く者』には、神が『この書に書いてあるいのちの木と聖なる都から、その人の受ける分を取り除かれる』ことになる。つまり、その者は『いのちの木と聖なる都』における恵みから排除されてしまう。地獄に堕ちなければいけないということだ。たとえ少しであっても黙示録から何かを取り除く者は、神を殺しているも同然である。何故なら、神は御言葉において御自身の存在を示しておられるからである。カルヴァンも言っているように、御霊はその御姿を御言葉において現わしておられる(『キリスト教綱要』)。神を殺す者は、確かにただでは済まない。だから、黙示録の御言葉から何かを取り除く者が、天国の恵みを奪われて地獄に投げ落とされたとしても、何も不思議なことはない。我々も、黙示録の御言葉から、いや聖書全巻にある御言葉から、何かを取り除くことがないようにしよう。もし我々の肉体から肉が勝手に切り落とされたとすれば、多くの人は怒るのではないだろうか。恐らく多くの人は平然とはしていないであろう。神も御自身の御言葉を勝手に切り落とす者には、御怒りを燃やされるのである。なお、ここで言われているのは『いのちの木と聖なる都』において受けられる恵みが単に減らされるという意味ではない、ということに注意せねばならない。ここで言われているのは天国における恵みの「減少」ではなく「消失」である。何故なら、神の御言葉を不遜にも損なう者に、永遠の命はないからである。
22:18~19の箇所で黙示録をぞんざいに取り扱わせないようにと強烈な威嚇がなされたのは、この文書で書かれている預言を決して軽んじさせないためであった。当時の聖徒たちには、黙示録に書かれている重大な出来事の到来が間近に迫っていた。それは、聖徒たちの地上および天上の運命を大きく左右させるほどの出来事である。そのため、黙示録で書かれている預言は改変されてはならず、そのまま受け取らねばならなかった。もし改変されて伝えられたことにより聖徒が誤解すれば、やがて来たるべき出来事が来た際、霊的に誤った対応をしてしまい、地上および天上における運命が大きく変わってしまうことにもなる。それだから、そのようなことにならないようにと、ここでは恐るべき威嚇がなされたわけである。これは他のことで例えるならば、拡散されたら一挙に数十万人もの人間が死ぬことになる猛毒の細菌が入った容器の外側に、<警告:以下に書かれている取り扱い方法を厳守しない者は法律により死刑または無期懲役に処せられる>などと書かれているようなものである。その細菌は人類の生命を大きく左右させるものなので、絶対に指示された通りに取り扱わなければいけない。それをぞんざいに取り扱うことは全く許されないことである。それゆえ、そのような細菌の入った容器には、誠に強烈な威嚇の言葉が書かれているわけである。もしこのような威嚇の言葉を持って警告されていなかったとすれば、黙示録にはそれほど重大なことが書かれていなかったことになる。何故なら、その場合、別にそのような警告をするほどでもないということになるからである。
この箇所の内容は、加えたり減らしたりするな、と言われている点では申命記の2つの箇所とよく似ている。しかし、ヨハネがこの申命記の箇所を元にして、この22:18~19の箇所を書いたのかどうかは分からない。というのも、申命記のほうでは、加えたり減らしたりするなとは言われているものの、罰則のことについては何も言及していないからである。その申命記の御言葉はこうである。『あなたがたは、私があなたがたに命じるすべてのことを、守り行わなければならない。これにつけ加えてはならない。減らしてはならない。』(12:32)『私があなたがたに命じることばに、つけ加えてはならない。また、減らしてはならない。私があなたがたに命じる、あなたがたの神、主の命令を、守らなければならない。』(4:2)
【22:20】
『これらのことをあかしする方がこう言われる。「しかり。』
キリストはここで『しかり。』と言われ、22:18~19の箇所でヨハネが言ったことに同意しておられる。このキリストの同意は何を意味しているのであろうか。それは22:18~19の箇所で言われていたことが、本当に守られなければいけないということである。それというのも、そこで言われていたことは、ヨハネだけでなくキリストも願っておられないことだからである。聖書において、2人または3人の同意は、その事柄をより確かにさせるということを我々は既に知っている(申命記19:15、Ⅱコリント13:1)。
『わたしはすぐに来る。」アーメン。主イエスよ。来てください。』
ここではキリストが再び御自身の再臨について宣言し、ヨハネがその宣言に応じて再臨を願い求めている。このヨハネの応答は、当時の聖徒たちを代表した応答だったと捉えるのが望ましい。何故なら、当時の聖徒たちがキリストの再臨宣言を聞いた際、ヨハネと同じような応答をして『アーメン。主イエスよ。来てください。』と言っただろうことは間違いないからである。
【22:21】
『主イエスの恵みがすべての者とともにあるように。アーメン。』
ヨハネは、読者に『主イエスの恵み』を願って、この文書を終わらせている。ヨハネは読者である聖徒たちが、キリストにあって恵まれ、幸せであるようにと願ったのである。また、このような締め方は、非常に適切であった。というのも、読者の幸いを願って何かの作品や手紙を閉じるのは、一般的なやり方であり、違和感がまったくないからである。このような文書の終わり方は、新約聖書の他の巻でも多く見られる。例えば、Ⅰコリント16:23、Ⅱコリント13:13、ガラテヤ6:18、エペソ6:24、ピリピ」4:23、コロサイ4:18、Ⅰテサロニケ5:28、Ⅱテサロニケ3:18、Ⅰテモテ6:21、Ⅱテモテ4:22、テトス3:15、ピレモン25、ヘブル13:25、Ⅰペテロ5:14がそうである。
『すべての者』とは、やはり再臨が起こるまでに生きていた紀元1世紀の聖徒たちを指している。ヨハネがこの文書を書いていた、という観点から言えば、確かにそうである。何故なら、ヨハネが紀元1世紀の聖徒たちを直接的な対象として書いていたのは確かだからである。しかし、御霊がこの文書をヨハネによりお書きになられた、という観点から言えば、この『すべての者』という言葉は、ヨハネの時代以降の時代に生きている全ての聖徒たちも含まれていると理解することができる。何故なら、神の御霊は、あらゆる時代に生きている聖徒たちに『主イエスの恵み』があるようにと願っておられるからである。誰がこのことを疑うであろうか。もっとも、だからといって、この文書で書かれている直接的な対象がヨハネの時代以降に生きている聖徒たちだったということにはならない。
最後に、基本的なことではあるが重要なことを書いておかねばならない。それは、この黙示録は、そこで示されている出来事が実際に実現されてから書き記されたのではない、ということである。不信仰な人であれば、黙示録はそこに書かれている出来事が起きてから作られた、つまり実際に起きた過去の出来事だったからこそ書くことが出来た、などと思うであろう。しかし、これはリベラルの考えであり、間違っている。我々は信仰的に考えなければならない。すなわち、ヨハネは黙示録に書かれた出来事が実現する前の時期に、神の霊によってその出来事を預言として書き記したのである。私は言うが、預言の真実性を疑う人は、確かなところクリスチャンではない。また、今の聖徒たちは、事実上、黙示録の理解においてリベラル的になっているということも言っておかねばならない。今の聖徒たちは、「我々は聖書にこそ立つ」というルター的精神を持っていると自負するかもしれないが、しかし聖書以外の文書や一般的な伝承に基づいて、黙示録が書かれたのはユダヤ戦争の凡そ30年後ぐらい、つまりだいたい紀元100年ぐらいであると理解している。このように理解するのは、リベラル的であり不信仰である。何故なら、既に示されたように、黙示録にはユダヤ戦争のことが預言されているからである。ヨハネはユダヤ戦争のことについて預言したのだから、黙示録がユダヤ戦争の起こる前に書かれたのは明らかである。聖書信仰に立ち続けたいのであれば、黙示録はユダヤ戦争よりも前の時期に書かれたと理解せねばならない。聖書以外の文書や伝承によって黙示録の筆記年代を算定する者は、私がこの第3部でやったように聖書に基づいて黙示録を考察していないので、神の裁きにより事実上リベラル的な考えを持つに至らされるのであるが、今の聖徒たちはそもそも黙示録についてまったく弁えていないから、自分たちがまさか神学的な裁きを受けているなどとは思いもよらないのである。
というわけで、これにて黙示録の註解は終えられた。この黙示録という聖なる文書の内容量について、考えるとどうであろうか。現行の章区分においては全22章あるが、これは長いのであろうか、短いのであろうか、それとも適切だったのであろうか。これは適切な量であったとせねばならない。何故なら、神が、この分量に決められたからである。神は、あらゆる点で、正しいことしかなさらない。それゆえ、ヨハネに全22章の量を持つこの文書を書かせるという点でも、神は正しいことをなされたのである。それだから、この文書の量が長すぎるとか短すぎるなどと言う者は、非常に傲慢である。何故なら、その者は正しいことしかなさらない神のされたことに文句を言っているからである。では、ここまで書かれた註解における量は、どうなのか。ある人は長かったと思い、ある人は適切な量だったと思うであろう。短いと思う人はいないはずだと思う。この註解は、一般的な註解書に比べると、かなりボリュームがあるからである。こちらのほうは、各人が好きなように思っていればよい。私はと言えば、人がどう思おうとも、ただ神の御心に適った理解を過不足なく記せたならば、それで良いと思っている。私がこの註解を書くにあたり、もっとも祈り求めたことの一つは、誤らずに十全な内容を記せるようということであった。というのも、誤るのは避けるべきことであるし、過剰であったり不十分であったりするのも良くないからである。何にせよ、このような註解を書けたことを、神に感謝せねばならない。もし神の恵みが無ければ、このような註解を書くことはできていなかったであろう。また、このような註解作品は、私の知る限りでは、今まで一度も書かれたことのなかったものである。黙示録の註解はいくつも書かれてはいるが、どれも内容がまともではなく、黙示録の異常なほどの密度と豊かな秘儀に応じた度合いの分量でもなく(つまり短すぎる)、どれもこれも読むに値しないものしかなかった。恐らく、神がこの註解を通して、教会に黙示録の正しい解釈を与えようとしておられるのではなかろうか。そうでなかったとすれば、どうしてこのような註解が書かれたのか説明できないように思われる。私が何か自分自身の意志に基づいて、このようなものを自分から作ったとでもいうのであろうか。そういうことはないのである。私は、神が働かれたからこそ、このようなものが作られたのだと思っている。すなわち、パウロがこう言っていることである。『神は、みこころのままに、あなたがたのうちに働いて志を立てさせ、事を行なわせてくださるのです。』(ピリピ2章13節)
第29章 ヨハネが黙示録を書いた理由
神がヨハネにこの文書を書かせた理由は、2つあると考えることができる。まず一つ目は、ヨハネだけ福音書の中でユダヤ戦争について書き記していないということである。マタイは24章で、マルコは13章で、ルカは21章で、やがて起こるユダヤ戦争のことについて書き記している。だが神は、ヨハネには福音書の中で、そのことについて書き記すことを欲されなかった。ヨハネは福音書の中でユダヤ戦争について書き記していないぶん、黙示録のほうでその出来事を書き記すことになった。つまり、ヨハネにとってのマタイ24章とマルコ13章とルカ21章は、黙示録において代替えされているのだ。それだから、ヨハネは福音書の中で、キリストという神人の人格性をより深淵かつ濃厚に書き記すことができた。というのも、ヨハネはユダヤ戦争について書かなかったぶん、キリストの人格描写に集中することができたからである。しかも、そのようにすれば、他の3つの福音書と違いが生じ、4つの福音書が単調だと思われなくなるという効果も生じる。つまり、そこに多様性が生じる。もしヨハネも他の3人の福音書記者と同じように福音書の中にユダヤ戦争についての箇所を置いていたとすれば、確かに福音書は彩り豊かではなくなっていたはずである。二つ目は、ヨハネが軽んじられないためであった、ということである。福音書と3つの手紙を見れば分かるように、ヨハネは『無学な、普通の人』(使徒行伝4章13節)らしい平易な文章を書く人であった。もしこの4つの文書しかヨハネが記していなかったとすれば、ヨハネは軽んじられていたかもしれない。というのもファーブルが『昆虫記』の中で不満げに言っているように、多くの人々は往々にして難解だったり修辞的だったりする文章つまり優秀な文章を好み、そのような文章に凄みを感じるものだからである(※ファーブルは平易な文章を書く人であった)。一方、簡単な文章を書く者は、低く見られがちである。しかし、ヨハネが黙示録を書いたのであれば、他の4つの文書で平易な文章を書いていたとしても、軽んじられることはなくなる。何故なら、福音書と3つの手紙の中で漁師らしい素朴な文章を書いている一方、黙示録のほうでは誰も書けないほどに難解で秘儀的な内容の文章を書いているからである。ヨハネは聖なる文書の筆記人だったのだから、決して軽んじられるべきではない人間である。というのも、彼の手が真理の言葉を文書の中で神から取り次いだのだからである。だからこそ、神はこの真理の言葉の媒介人であるヨハネが軽んじられないようにと、黙示録の中で前代未聞の難しさを持った内容の文章を書かせられたと考えることができる。つまり、黙示録は他の4つの文書における彼の文体を補うという意味もあったということである。
このヨハネという人は、キリストから特に愛された弟子であった。ヨハネは、キリストの『御胸のそばで身体を横にしていた』(ヨハネ13:23)ほどの弟子であった。このようにできたのは、キリストが特にヨハネを愛しておられたからである。心理学も教えるように、身体の接触の度合いは、親密さの度合いと比例している。例えば夫婦は結婚当初は身体の接触が多いが、年月が経つとどんどん接触の度合いが低くなるものである。また親しい人の身体についているゴミであれば普通に取ってやるものだが、嫌いな人の身体についているゴミであれば接触したくないのであまり取ってやりたいとは思わないものであろう。誰が嫌いな人に触れたいと思うであろうか。ヨハネはこのように大いに愛された弟子だったから、黙示録を書くように恵みを受けたのであろう。もし彼が黙示録を書かなかったとすれば、つまり福音書と3つの手紙しか書かなかったとすれば、その文体のゆえに大いに軽んじられていたかもしれない。しかし黙示録を書いたので、ヨハネを他の4つの文書に基づいて軽んじることは非常に難しくなった。これは神の愛の配慮であると言える。またヨハネが福音書の中でユダヤ戦争について書いていたとすれば、「どうして既に存在していた3つの福音書と同じような内容の福音書を書き記したのか。(※)」などと批判されることにもなっていたかもしれない。しかし、ヨハネはユダヤ戦争のことを黙示録のほうで書き記したので、4つの福音書には豊かな色彩が生じることになった。これも神の愛の配慮であると言える。ヨハネに黙示録を書かせられた神は『愛』(Ⅰヨハネ4章8節)である。そして愛とは『自分の利益を求め』(Ⅰコリント13章5節)ない。つまり神とは他の存在の利益を求められる御方である。またヨハネはこの神から特に愛されていた。だからこそ、ヨハネは、このような愛の配慮を神からいただくことが出来たのだと思われる。要するに、ヨハネが黙示録を書いたのは、神のヨハネに対する愛の証拠であるということだ。もしヨハネがそこまでは愛されていなかったとすれば、このように黙示録を書くために用いられていたかどうか定かではない。何故なら、愛の度合いが低まれば配慮の度合いも低まるというのは、人間だけではなく神の場合でも同様のことが言えるからである。愛が薄いのに、どうして豊かな愛の配慮が与えられるのであろうか。
(※)
一番最後に福音書を書いたのはヨハネである。
[本文に戻る]
第30章 黙示録の註解における真実―濃密な文章は正しい見解の証拠
このように私は黙示録の註解を豊かに書き記した。この註解こそ、私が黙示録を正しく理解できている証拠と言ってよい。正しく理解しているからこそ、このように豊かに解き明かすことができたのだからだ。もし正しい理解を持てなかったとすれば、このような註解を記すことはまったくできなかった。理解していないのに、どうして豊かに論じられるであろうか。
しかしながら、このように註解を書き記せたのは、ただ神の恵みによる。黙示録を人間の知性や力によって正しく理解したり正しく語ったりすることは、出来ないからである。人間が自分自身により黙示録を理解したり語ったりするよりは、天地が混同してしまうほうが容易い。だから、この註解における栄誉や力は、神にのみ帰されなければならない。恵み深い神であるイエス・キリストに栄光が永遠に至るまでもあるように。アーメン。
補章 マサダの要塞および第2次ユダヤ戦争における記述について
さて、まずはマサダの要塞にユダヤ人が立てこもって総自殺した出来事であるが、これについて黙示録は取り扱っていない。黙示録は、この出来事に少したりとも触れてさえいない。それだから、黙示録の中にこの出来事が書かれているかと思って調べたとしても、徒労に終わるだけである。
第二次ユダヤ戦争も、黙示録の中では書き記されていない。読者の中には、13章に出てくる第一の獣がバル・コクバであり、第二の獣がラビ・アキバではないのか、などと推測する人がもしかしたらいるかもしれない(このように推測できる人はかなり黙示録のことを真剣に考察できている)。第二の獣における推測について言えば、確かにアキバは第二次ユダヤ戦争の時期にバル・コクバに心酔してしまったのだから、13章に書かれている第二の獣のイメージに合致しており、一見すると真剣に考察すべき推測であるかのように感じられなくもない。だが、この推測は容易に打ち砕くことができる。何故なら、バル・コクバは聖徒たちを苦しめておらず、その名前にも666が恐らく含まれていないだろうから第一の獣ではあり得ず、バル・コクバが第一の獣でなければ必然的にラビ・アキバも第二の獣ではないことになるからだ。そもそも、この2人の狂ったユダヤ人による反逆はヨハネが黙示録を書いてから『すぐに起こるべき事』ではなかった。それだから、13章に出てくる2匹の獣がバル・コクバとラビ・アキバではないかという推測は退けられなければならない。もし第二次ユダヤ戦争の記述を黙示録の中に見出そうとしても、それは出来ないことである。そのようなことをしても、時間と労力を無駄に使うのみである。
結局のところ、黙示録の記述は、歴史的な出来事について言えば、第一次ユダヤ戦争における神殿崩壊の出来事で終わっている。これ以後の出来事について、黙示録は何一つとして記していない。黙示録とは、神の国を受けていた選民としてのユダヤ人が完全に遺棄されることについて記された文書である。だから、そこに記されているのが神殿崩壊の出来事までであったとしても何も不思議ではない。何故なら、神の住まいである神殿が滅ぼされるというのは、つまりユダヤ人が御前から完全に遺棄されたということを意味しているからである。
第4部 部分註解
第1章 十全な再臨理解のために必要な聖句の部分註解
再臨をより豊かに、より精確に、より主の御心に適った形として理解するためには、どうしても黙示録以外の聖書の巻から再臨について解き明かされねばならない。これまでの3部から学んだのであれば、再臨について75%ぐらいは理解できると私としては思う。しかし、これまでの内容から学ぶだけでは、どうしても100%の理解に至ることは有り得ない。何故か。それは黙示録以外の聖書の巻でも、多くの箇所で再臨について語られた御言葉があるからである。それらの御言葉からも学んでこそ、100%の理解に至ることが可能にもなる。「可能」とはいっても、もちろん人間が自身の知恵や力によってそのように出来るというのではなく、神がそのようにして下さるならば、ということである。既に述べたように、本作品はキリストの再臨に関する事柄を徹底的に考究することを目的としている。それゆえ、この第4部において、黙示録以外の巻からも、再臨について更に理解すべく再臨について語られた聖句を註解する必要があるのである。もしこの第4部が書かれないとすれば、本作品の読者が、黙示録以外の聖書の巻にある再臨に関した聖句を読んだ際、重大な問題や心を悩ます疑問が起こりかねない。それというのも、その場合、その読者は黙示録の註解しか読んでいないことになるからである。本作品以外から再臨について語られた御言葉を学ぶというわけにはいかない。何故なら、教会は今に至るまで再臨の分野において誤ってきたのであり、そのため誤ったことを論じた作品しか今までには出て来なかったからである。そのように問題や疑問が起きたら、再臨理解において大きな誤謬に陥るということにもなりかねない。「千年」という言葉が非常に長い期間を意味していると誤って理解している教師たちを見れば分かるように、無知は誤謬の母である。よく分かっていないからこそ、人は誤りに陥る。中世のカトリック教徒たちも、長い間司教たちから聖書の閲覧を禁止されていたものだから(司教たちは実に愚かなことをしたものである)、深い誤謬の闇に陥っていても何もそれに気づかなったものである。彼らが司教たちから聖書を読むことを許されていたとすれば、カトリックの腐敗はルターが現われるよりも前に既に糾弾され打ち砕かれていたかもしれない。再臨理解の場合も同じことが言えるのであって、黙示録の聖句を全て理解しただけでは、まだ十分ではない。私を含めた聖徒たちが再臨理解において誤るのは、是非とも避けられるべきである。だからこそ、黙示録以外の巻における再臨に関して語られた聖句の註解が、この第4部で書き記されなければいけないわけである。
この第4部も、これまでの3部と同様、重要である。何故なら、この第4部ではキリストの再臨のことが聖句から解き明かされるからである。聖徒である我々にとって、キリストの再臨は非常に重要である。その再臨について語られている御言葉も、我々にとって非常に重要である。というのも、その御言葉において再臨のことが啓示されているからである。第4部では、その再臨に関する御言葉が注解されることになる。それゆえ、この第4部は再臨に関わる御言葉について解き明かされるがゆえ、非常に重要だというわけである。それだから、この第4部を軽んじる者があってはならない。ここでは神の聖なる御言葉から、キリストの聖なる再臨のことが、天からの聖なる恵みにより豊かに解明されるのだから。
第2章 第4部の記述について
第4部では、黙示録以外の聖書の巻に書かれている再臨に関わる聖句が、一つ一つ解き明かされる。それは、我々が再臨を十全に理解できるようになるためである。少しも見落とされることなく再臨に関わる聖句が抽出され註解されねばならない。註解の際には、各巻ごとに章が改められることになる。当然ながら黙示録だけは第4部において除外される。
これまでに書かれた内容との重複は、それほど気にすることをしない。すなわち、第3部までの内容で語られた聖句であったとしても、それが間接的な言及であったのであれば、この第4部の中で取り扱うことを厭わない。何故なら、これまでは間接的な言及に過ぎなかったとしても、ここでは主体的に語られることになるのだから、再臨をより豊かに理解することに結びつくからである。もちろん、冗長になるのは、なるべく避けられるようにせねばならないが。
また、各巻の冒頭部分では、その巻が再臨を理解するためにどれだけ研究されるべきかという度合いが、10段階で示されている。これはあくまでも筆者の経験に基づいた主観的な度合いであるが、私は誰よりも再臨について考究していると言ってよい者なのだから、いくらかでも参考になるのではないかと思う。10の★がある巻は、もし再臨を十全に理解したいというのであれば、絶対に研究されなければいけない。1しか★がない巻は、別に研究しなかったとしても、恐らく問題が生じることはないであろう。なお、本作品の末尾にある【資料】の箇所で、各巻における研究すべき度合いを一覧として纏めておいた。
第3章 1:創世記
創世記は、再臨を更に良く理解するために研究しなかったとしても、問題は生じないであろう。何故なら、創世記には、再臨に直接的に関わる箇所が見られないからである。しかし、いくつか目を留めておかねばならない箇所がある。
教会の伝統的な理解に立てば、創世記を書いたのはモーセだということになるが、仮に創世記を書いたのが紀元前1300年頃に生きていたモーセだとすると、まだその時代には再臨について明らかに示される時期が来ていなかったと言わねばならない。というのも、その時はまだキリストの「初臨」を御民に示す段階にあったからである。確かにキリストの初臨を示す段階であったのならば、まだ再臨について示す段階が来ていなかったことは間違いないことである。それは、例えば古代人に核融合反応を教える場合に、まず原子のことから教え始めねばならないのと同じである。古代人に原子をすっ飛ばして、先に核融合反応から教える人は恐らくいないと思われる。何故なら、原子が分かっていなければ、核融合反応も分かるはずがないからである。原子をある程度理解してこそ、初めて核融合反応も多かれ少なかれ理解できるようになる。再臨の啓示もそれと同じであり、先にキリストの第一の到来を示してから、その第一の到来を踏まえた上で示されるべきだったのである。物事には順序というものがあるのだ。後に示されるべきことが先に示されるのでは、問題が生じかねない。再臨がしっかりと啓示されるようになるのは、ダビデ以降、ことに預言者の時代からである。ダビデが現われると、神が彼の口を通して、キリストの再臨について朧げに示され始めた。詩篇を見ると、キリストの再臨が薄いベールに隠されたようにして示されているのが分かる。そして預言者の時代になると、遂にキリストの再臨が明白に示されるようになる。もうその頃には、キリストの初臨がかなりの程度示されたので、再臨が豊かに示されてもよい時期となったのである。ソロモンは『何事にも定まった時期があ』(伝道者の書3章1節)ると言ったが、キリストの再臨が示されるに相応しくなる時期もあったのである。もしダビデ以前に再臨が示されていたとしたら、もしかしたら御民は分からなかったか、または混乱していたかもしれない。何故なら、もしダビデ以前の時代においても再臨のことが示されてよかったとすれば、既に神は再臨のことをお示しになっていただろうからである。しかし、ダビデ以前にはまだ相応しい時期となっていなかったので、ほとんど再臨については示されなかったのである。それからキリストと使徒の時代になると、まざまざと再臨について示されるようになった。それは、あたかも目の前で再臨の出来事を見ているかのようであった。これは、福音書や使徒書簡に書かれている再臨に関わる御言葉を読めば分かることである。もうその頃にはキリストの再臨が間近に迫っていたので、まざまざと再臨のことを示してよい、いや、示されなければいけない時期が訪れていたのである。
【3:1~15】
『蛇』
これは黙示録12:9、20:2の箇所で言われている『古い蛇』のことである。何故なら、この『古い蛇』とは、創世記3章に出てくる蛇の他には考えられないからである。この人間を惑わした蛇は、再臨が起きて天上で神の王国が始まるようになった時、天上の場所から落とされた(黙示録12:7~9)。それまでは、ヨブ記1~2章を見れば分かるように、まだ天へと出入りすることができた。まだその時には、天上でキリストによる神の王国が始まっていなかったからである。キリストがルカ10:18の箇所で、『わたしが見ていると、サタンが、いなずまのように天から落ちました。』と言われたのは、このことを過去形の形で語った預言である。それだから、聖徒たちは、もうサタンが天上に出入りできなくなっていると理解せねばならない。多くの聖徒たちは、まだサタンが天上にいられると考えているかもしれないが、もうそういうことはなくなったのだ。何故なら、蛇であるサタンが天上の居場所を失った黙示録12章における墜落の出来事は、ヨハネが黙示録を書いてから『すぐに』(黙示録1:1、22:6)起きたからである。この蛇については、既に第3部の中で十分に語られているから、もうこれ以上説明する必要はない。
【2:9、3:22】
『いのちの木』
これは、明らかに黙示録に出てくる『いのちの木』(黙示録22章2節)と対応している。創世記に書かれている『いのちの木』は、実際的・物理的な木である。これを単なる象徴としてしか見なさない人の考えは、受け入れられない。何故なら、神は『今、彼が、手を伸ばし、いのちの木からも取って食べ、永遠に生きないように。』(創世記3章22節)と、実際的なことを言っておられるからである。この木を象徴としてしか理解しない人は、何か思い違いをしている。他方、黙示録の『いのちの木』は、実際的な木なのか象徴的な表現に過ぎないのか、または実際的でありながら象徴的な意味も持つのか、非常に理解しにくい。黙示録のほうについては第3部で既に語っておいた。創世記に出てくるこの木は、再臨について教えている黙示録に出てくるのだから、無視されてはならないものである。
【3:24】
『こうして、神は人を追放して、いのちの木への道を守るために、エデンの園の東に、ケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。』
パラダイスの入口に御使いが置かれているというのは、パラダイスである天国の入口に御使いが置かれていると教えている黙示録21:12の記述と同じである。神は、至福の場所の入口に、警備者を置かれる。それは、そこに悪い者たちが入って来れないようにするためである。悪しき者は、アダムであれサタンであれ、この警備者としての御使いが至福の場所を見守っているので、そこに入ることができない。黙示録22:12で書かれている御使いがケルビムであったかどうかは、確言することができない。何故なら、黙示録のほうでは、その御使いがケルビムだとは明言されていないからである。ただ、我々が今見ている創世記3:24の記述を考慮するならば、黙示録に出てくる御使いはケルビムだった可能性があると言うことができる。創世記3:24で書かれている御使いが、黙示録22:12で書かれているのと同じように『12人』いたのかどうかは分からない。何故なら、創世記のほうでは、御使いの数について何も言及されていないからである。いずれにせよ、天国の門の所には、御使いが警備してくれているから、天国にいる聖徒たちはいついつまでも安心して生きることが出来るのである。
【19:23~29】
『ソドム』
黙示録では、堕落の極みに達していたユダヤが『ソドム』(黙示録11章8節)と呼ばれ、その大炎上の裁きもソドムの炎上になぞらえて語られている(黙示録15:8~9)。紀元1世紀のユダヤがソドムと同一視されてしまったのは、当然と言えば当然であった。当時のユダヤは、神の御子を拒絶して殺してしまうほどに、異常な状態になっていたのだから。もし異常ではなかったとすれば、ソドムのように裁かれて滅ぼされることもなかったはずである。確かに、ユダヤとその裁きは、ソドムとその裁きとよく似ている。ユダヤもソドムのように堕落しており、火で焼き尽くされて炎上し、周りの国民から脅威の目で見られ、裁かれてからその地には平和や繁栄がまったく無くなってしまった。この類似性に誰が気づかないであろうか。つまり、ソドムとその裁きは、ユダヤとその裁きを前もって示す予表であった。黙示録ではユダヤとその裁きがソドムとその裁きにおいて語られているのだから、この見解はおかしなものではない。すなわち、ソドムとは言わば紀元1世におけるユダヤの「型」だったのだ。それはダビデとアダムがキリストの、石造りの神殿が聖徒という神殿の、エリヤがバプテスマのヨハネの「型」だったのと同じである。だからこそ、ヨハネは黙示録の中で、創世記に出てくるソドムにおいてユダヤを描いたわけである。それだから、黙示録を通して再臨を理解する場合、創世記におけるソドムについての記述を忘れることはすべきでない。
【49:1~27】
『ヤコブはその子らを呼び寄せて言った。「集まりなさい。私は終わりの日に、あなたがたに起こることを告げよう。…』
ヤコブが死ぬ前に告げた12部族に対する『終わりの日』の預言とは、すなわち「ユダヤの終わり」のことである。これは、地球全土における終わりのことではない。もし、ここで言われている『終わりの日』が地球全土の終わりのことだとすれば、使徒がすぐにも世の終わりが来ると言ったのに、未だにそれが起きていないのは何故か。また、2千年経過してもまだ起こらないのに、自分の生きている時代が正に「終わりの時」であると教えたのは何故か。もし『終わりの日』を文字通りの意味としての全世界のことだと捉えると、事柄を正しく読み解くことができなくなる。しかし、これがユダヤ世界の終わりについて言われていると捉えると、何も問題はなくなる。何故なら、使徒が言った通り、本当にユダヤ世界の終わりは、すぐにも訪れたからだ。創世記49:1~27の箇所に書かれているヤコブの預言を、紀元1世紀におけるユダヤの終わりの時期について言われた預言だとして捉えてみるとよい。そうすれば、これが確かにユダヤについてのことだと理解できるはずである。この『終わり』がユダヤのことだと捉えると、ユダヤが終わる時期には、まだ預言の中で語られている12部族が識別できたので何も問題は起こらない。ヨセフもマリヤもキリストもユダ部族であることが知られていたし、パウロも自分が『ベニヤミンの別れの者』(ピリピ3章5節)だと言っている。この4人以外のユダヤ人も、自分の出自を知っていたはずである。何故なら、昔のユダヤ人は、キリストがユダ部族から出ることを知っていたから、部族について決して無頓着ではなかったからである。これはマタイとルカが福音書の中で、キリストの系図を詳しく書き記していることからも分かる。しかし、この『終わり』が文字通りの全世界のことであり、未だに終わりが到来していないと捉えると、ヤコブの語った12部族についての識別が全く出来なくなり、大きな問題が起きてしまう。今のユダヤ人は、自分たちと12部族との関連について、ほとんど意識していないからである。どのユダヤ人もただ「ユダヤ人」と言われるだけであり、どの部族をその出自としているかは全く言われることがない。「私はレビを先祖に持っている。」とか「私はユダ族なんだ。」などと言っているユダヤ人は今や誰もいない。ヤコブが『終わりの日』における12部族の状態を明白に預言したからには、その『終わりの日』が、まだ12部族の出自を識別できる時代のことを言っているのは明白である。その終わりが紀元70年のことを言っているとすれば、その時にはまだ12部族を識別できたのだから、これこそ正しい理解であると言わねばならない。この『終わりの日』が全世界についてのことだと捉えたい人は、そのように捉え続ければよい。その人は、いつまで経っても聖書を正しく理解することは出来ないであろう。事実、今まで教会はこの言葉について間違って捉えて来たので、聖書を正しく理解することが出来ていなかった。すなわち、終わりの時期に実現する再臨についての事柄が上手に把握できず、ずっと再臨の分野において解釈上の進展が見られなかった。だからこそ、この『終わりの日』という言葉について正しく捉えている私が、これまで未開発だった再臨の分野を、神の恵みによりせっせと耕しているわけである。
第4章 2:出エジプト記
この文書は、決して無視されるべきではない。ヨハネは黙示録の中で、この文書から多くのことを書き記している。黙示録で書かれている再臨の時期に起こる破滅や苦難が、出エジプトの出来事において預言されている、ということについては既に第3部の中で説明した通りである。この文書を考慮することなしに、黙示録を十全に理解することはできない。黙示録とは再臨について教えられている文書だから、もし黙示録を十全に理解できなければ、再臨も十全に理解することができない。それゆえ、再臨を理解するためには、この文書における黙示録と対応した部分に心を傾けなければならない。
【7:8~16:36】
この箇所は、決して無視されるべきではない。何故なら、ここでは黙示録の記述と対応している出来事が、非常に多く書かれているからである。この箇所を無視するならば、黙示録が理解できなくなり、再臨についても豊かな理解を得られなくなってしまう。蛙の裁きについて書かれている8:1~15の箇所は、黙示録15:13、12:18、20:8の箇所と対応している。既に述べたように、出エジプト記の蛙は、黙示録では『海べの砂のよう』なローマ軍である。腫物について書かれている9:8~12の箇所は、黙示録では16:2の箇所と対応している。水が血に変わって水の中にいた生物が死んでしまうという裁きについて書かれている7:14~23の箇所は、黙示録では8:8~9、16:3と対応している。雹の裁きについて書かれている9:22~35の箇所は、黙示録では8:7、16:21の箇所と対応している。黙示録20:9の箇所では『火』の裁きが書かれているが、これは雹と同じく御言葉を意味しているから、この箇所も対応している箇所として含めることができる。エジプトが真っ暗闇になった出来事が書かれている10:21~29の箇所は、黙示録では8:12の箇所と対応している。初子の死について書かれている11:4~12:36の箇所は、黙示録のほうでは対応している箇所がない。というのも、黙示録では、初子が死んだことについては書かれていないからである。しかし、この初子の死滅も、再臨の時期に起きたユダヤの破滅と対応していると考えることが可能である。というのは、死滅の裁きを受けたのが、初子かそうでないか、また一部の人間かほとんど全ての人間か、という違いを除けば、この死滅の裁きは似ていなくもないからである。この出エジプトの出来事は、その全体が、聖徒たちにおける苦難と携挙の出来事と対応していると言える。旧約の聖徒たちはエジプトとサタンおよびサタンに取り憑かれていたパロの圧制から抜け出し、新約の聖徒たちはこの世とサタンおよびサタンに取り憑かれていたネロの蹂躙から抜け出した。どちらも古い場所と悪しき者とその苦難から神により助け出されたという点で一致している。ヨハネは出エジプト記に基づいて黙示録の多くの箇所を書いたのだから、このように考えるのは荒唐無稽でないと思われる。12章で聖徒たちが携挙された後に教会が荒野へと移された、と書かれていることからも、これは確かな見解であると言える。旧約の聖徒たちも、エジプトから助け出された後で荒野へと移されたからである。この一致に誰が気付かないであろうか。もっとも、黙示録の記述の場合、携挙された聖徒たちは天に引き上げられたのだから、地上において荒野の状態となった教会にはもはやいなくなった、という点で出エジプト記の記述と異なっているのではあるが。出エジプト記のほうでは、携挙が無かったのだから、助け出された後に実際の荒野へとその住む場所が移されたのである。
第5章 3:レビ記
レビ記は、特に研究しなかったとしても問題は起こらないはずである。何故なら、この文書には、再臨に直接的に関わる重要な箇所が見られないからである。ただ、黙示録の聖句と重なっている箇所については、忘れないようにしておくのが望ましい。
第6章 4:民数記
民数記も、別に研究しなかったとしても問題にはならない。とはいっても、もちろん再臨をより豊かに理解するためには研究しなくても問題ないということに過ぎず、この文書の内容そのものは当然ながら弁えておかねばならない。これは言うまでもないことである。
第7章 5:申命記
申命記も、あまり研究する必要はない。しかし、この文書で書かれている律法を、十分に弁えていなければいけない。何故なら、再臨の時期に滅ぼされたユダヤは、律法に違反していたからこそ滅ぼされたからである。もし彼らが律法に違反していなければ、滅ぼされることもなかったであろう。それゆえ、申命記に書かれている律法を弁えていなければ、ユダヤの滅びについても十分な理解が得られなくなってしまう。特に、28章目で書かれている律法の呪いについての箇所を、心に留めておくべきである。紀元1世紀に破滅したユダヤは、正にこの箇所で書かれているような数々の呪いを、その堕落のゆえに受けることになったのだから。
28:15~68の箇所では、律法に違反した場合に注がれる数々の呪いについて、書き記されている。ユダヤは、律法に違反し続けていたので、ここで書かれているような呪いを紀元1世紀の時に受けることになった。確かに、この箇所で書かれている呪いは、正にユダヤについて言われていると感じられるものである。この箇所を一度ざっと眺めてみるだけでも、それは分かる。
ユダヤに対する呪いが書かれているとしか思えないこの箇所から、いくつか聖句を取り出して註解する。全ての箇所だと長いので、一部分だけである。以下は、呪いについて書かれたこの箇所の中で、特に紀元1世紀におけるユダヤの裁きが言われていると感じられる箇所の一つである。
【28:44】
『…あなたは尾となる。』
紀元1世紀のユダヤは、罪を犯し続けていたので、神からの呪いを受け、『尾』として位置することになってしまっていた。どのような存在の『尾』となっていたのか。それは、サタンとローマ帝国である。すなわち、サタンがローマ帝国を通してユダヤを支配し、好きなように弄んでいたのである。当時のユダヤがローマから屈辱的な扱いを受けていたのは、歴史を学んだ者には周知のことである。このようになったのは、ユダヤの犯している罪が、根本的な原因であった。もしユダヤが罪を犯していなければ、むしろサタンとローマのほうがユダヤの『尾』
となっていたであろう。何故なら、律法では、神に逆らわなければ尾とはならないと約束されているからである。申命記28:13の箇所では、こう言われている。『私が、きょう、あなたに命じるあなたの神、主の命令にあなたが聞き従い、守り行うなら、主はあなたをかしらとならせ、尾とはならせない。ただ上におらせ、下へは下されない。』しかしユダヤは、自分たちが屈辱的な立場に位置させられているのが、罪に対する呪いのためであることを全く理解していなかった。もしその立場を打破したいのであれば、律法を守って神に従い、『尾』にさせられるという呪いが取り除かれるようにすればよかった。つまり、ただ落ち着いて『主の子ども』(申命記14:1)らしく敬虔に歩んでいれば、それで良かった。それなのにユダヤは無知なものだったから、反逆をすれば力づくで今の屈辱的な状態から解放されると本気で思い込んでいた。だからこそ紀元60年代に、彼らはローマに対して反逆したのである。これは彼らが持つ傲慢な態度の現れであって、遂には神の裁きが下されて滅ぼされることになったのである。
黙示録では『尾』と言われている箇所がいくつかあるが、これは律法の原理をよく理解していないと、読み解くことができない。黙示録9:10の箇所ではユダヤがローマ軍に尾として『5か月間』苦しめられると言われており、9:16~19の箇所ではユダヤが悪しき御使いの軍勢から尾として滅ぼされてしまうと言われている。黙示録12:3~4の箇所では、サタンが聖徒たちを尾として悲惨な目に遭わせると言われている。こちらのほうの場合、確かに聖徒たちが尾として取り扱われているが、それはユダヤのように罪が原因で起こったことではなく、単に尾でもあるかのように取り扱われたと言われているに過ぎないことに注意せねばならない。今説明されたことからも分かるのではないかと思うが、この「尾とされる」という律法の呪いは、黙示録を理解するためによく覚えておかねばならない。
もし『尾となる』のが嫌であれば、聖徒たちは罪を犯さないでいるがよい。罪を犯さないでいれば、呪いが注がれないのだから、尾となることもないであろう。何となれば、罪を犯すからこそ屈従せねばならないことになるのだ。ルターとカルヴァンを見ると、どうであろうか。この2人は敬虔に歩んでいたから、罪に対する呪いが注がれることがなく、サタンとサタンの働いていたカトリックに尾とさせられることがなかった。ルターはカトリックに福音の真理を認めさせられる一歩手前の状態にまで至らせたし、カルヴァンも学識ある枢機卿サドレの口を完全に封じ込めることができた。この2人は、サタンとサタンのカトリックから攻撃こそ受けたものの、その改革運動における生涯の中で彼らに対して優位に立っていたと言ってよい。霊的に言えば確かにそうである。もしこの2人が罪を犯していたならば、サタンとそのカトリックに対して優位に立つことは出来なかったであろう。一方、カトリックはどうであろうか。この宗派は真理を退けて罪の歩みを止めようとしなかったので、神の前から捨てられ、今やロスチャイルドとそのイルミナティに乗っ取られてしまっている。今現在のカトリックは完全に『尾』とさせられてしまっていると言ってよい。現教皇のフランシスコも国際社会主義者の息のかかった人物である。私はこの教皇が、イルミナティであることを示す明白な徴を見た。彼は間違いなく向こう側の人間である。教皇がイルミナティであるということは、つまりカトリックが完全に攻略されて尾となっているということでなくて何であろうか。何故なら、教皇とはカトリックの顔であり支配者だからである。
【28:49】
『主は、遠く地の果てから、わしが飛びかかるように、一つの国民にあなたを襲わせる。その話すことばがあなたにはわからない国民である。』
ここで言われているのは、正に紀元1世紀におけるローマ軍であるかのようである。『わし』と書かれているが、確かにローマとローマ軍におけるシンボルは「わし」であった。これは古代ローマの歴史を学んだ者であれば、よく知っているはずである。
『遠く地の果てから』滅ぼすための裁きの使者がやって来ると、ここでは言われている。確かにローマはユダヤから遠く離れた場所にあった。
それでは、ローマの人たちは『その話すことばがあなたにはわからない国民』であったのか。これはその通りであった。紀元1世紀のローマ人はラテン語を話し、ユダヤ人はギリシャ語とヘブル語またはアラム語を話していたのだから、確かにユダヤ人にとってローマ人の話す言葉は分からなかった。もちろんユダヤ人の中にはラテン語を話せる者もいたはずだが、それは一部の者たちであって、民族全体で言えばそうではなかったのである。
確かにこの呪いの言葉の中で言われているように、ローマ軍は罪に染まりきっていたユダヤを攻め、襲い、最終的に滅ぼしてしまった。それは、あたかも『わしが飛びかかるよう』であった。正に御言葉で言われていることが紀元1世紀のユダヤに実現されたのである。
【28:50~51】
『その国民は横柄で、老人を顧みず、幼い者をあわれまず、あなたの家畜の産むものや、地の産物を食い尽くし、ついには、あなたを根絶やしにする。彼らは、穀物も、新しいぶどう酒も、油も、群れのうちの子牛も、群れのうちの雌羊も、あなたには少しも残さず、ついに、あなたを滅ぼしてしまう。』
ローマ兵たちは、確かに『横柄』であった。これはユダヤ戦争においてユダヤが受けた悲惨を考えれば分かる。ローマ兵は、ヨセフスをはじめ投降した者は別として、ユダヤに対して全く容赦しなかった。それは、あたかも苦しみ藻掻く小さな獲物が、大きい鷲に襲いかかられて無残にも切り裂かれるようなものであった。ローマという獰猛な鷲がユダヤという罪深い獲物にもたらしたのは、血と殺戮と荒廃であった。
確かに、ここで言われていることは、紀元70年9月2日に実現している。その時、ローマはユダヤにあるものを何もかも根こそぎにした。ヨセフスによれば、ローマが荒らした後のエルサレムには草1本さえも残されていなかった、ということである。このような呪いを受けたのは、ユダヤが神の御言葉を自分たちのうちから取り除いたからである。すなわち、ユダヤが御言葉を自分から取り除いたので、神もそれに報い、御自身の前からユダヤを完全に取り除かれた。
【28:52】
『その国民は、あなたの国中のすべての町囲みの中にあなたを包囲し、ついには、あなたが頼みとする高く堅固な城壁を打ち倒す。』
ユダヤがユダヤ戦争においてローマに包囲されたのは歴史の事実である。つまり、ここで言われている包囲の呪いも、実際にユダヤに実現されたことになる。
ローマ軍は、ユダヤ戦争においてユダヤ・エルサレムの城壁を打ち倒した。この箇所で言われているように、ユダヤの城壁は『あなたが頼みとする高く堅固な城壁』と言えるようなものであった。それだから、ヨセフスが記しているように、ローマ軍もなかなかこの城壁を打ち壊せず、かなり骨を折らされた。しかし、やはりローマ軍と言うべきか、遂にはこの城壁も強力な破城槌により打ち壊されてしまった。そうして後、ローマ軍がイナゴでもあるかのように都の中に雪崩込んだのである。そうしてからユダヤに見られたのは、殺戮、殺戮、殺戮、という有り様であった。これが罪に対する呪いであるというのでなければ、何を罪に対する呪いであると言えばよいであろうか。
この申命記の箇所と、ユダヤに対する呪いの出来事から、防御の役割を果たしている壁または壁に相当するものが打ち壊されるのは、呪いの一つであるということが理解できる。というのは、神の呪いが注がれるからこそ、防御壁が打ち壊されることになるからである。これは、神が守りを取り去られるということである。ローマがユダヤの城壁を打ち倒したのが、正にそれであった。とはいっても、壁の破壊が、すべて神の呪いというわけではない。壁の破壊が、むしろ祝福を意味する場合もある。例えば、不和のために置かれた仕切りの壁が、和解の出来事のゆえに取り去られた、という場合がそうである。エペソ2:14の箇所で、『キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ちこわし、…』と言われているのも、当然ながら呪いのゆえに起こったことではない。また、敵により包囲されるのも、呪いの一つであることが分かる。何故なら、神の呪いが注がれるからこそ、敵により包囲されるようになるからである。ユダヤがローマ軍に包囲されたのも正に呪いのゆえであった。しかし、これも敵の包囲が全ての場合において呪いを意味するというのではない。時には、神の計画が実現されるために、何の罪も犯していないのに敵から包囲されることになる場合もある。例えば、神の人エリシャがアラムの略奪隊に包囲された出来事がそうである(Ⅱ列王記6:8~23)。
【28:52~53】
『彼らが、あなたの神、主の与えられた国中のすべての町囲みの中にあなたを包囲するとき、あなたは、包囲と、敵がもたらす窮乏とのために、あなたの身から生まれた者、あなたの神、主が与えてくださった息子や娘の肉を食べるようになる。』
ローマ軍がユダヤを包囲した際には、極度の窮乏がユダヤに生じ、飢えのために自分の子を煮て食べる母親さえも現れたほどであった。その時、ユダヤ人は、草、木の皮、靴、また鳥の糞さえも食べるほどに窮乏させられた。正に、ここで言われていることがユダヤに実現されたのだ。これは呪いのゆえに起きた悲惨であった。もし呪いが注がれなければ、このようなことは起こらなかったであろう。
我々は、この箇所から、人間を食べなければならないほどの窮乏が、神の呪いにより齎されることを知らねばならない。すなわち、神の呪いが注がれるからこそ、遂には人間さえも食べることになるわけである。ユダヤは罪に罪を重ねていたので、遂に、このような呪いが注がれてしまった。つまり、当時のユダヤはそれほどまでに罪の深みにはまり込んでいたということである。
第8章 6:ヨシュア記
ヨシュア記は研究しなくても問題ない。
第9章 7:士師記
士師記も、研究のために心を向けなくても構わない。ただ、この文書では『メギド』について言及された箇所があるから、その箇所は忘れ去られるべきではない。この地は、黙示録においてキリストの再臨の際に起こる霊的な激動を描写するために用いられている場所である。もっとも、それはあくまでも描写のために用いられているに過ぎず、実際に再臨が起きた場所は『メギド』ではなく、エルサレムにおける「オリーブ山」だったのではあるが。
【5:19】
『王たちはやって来て、戦った。そのとき、カナンの王たちは、メギドの流れのそばのタナクで戦って、銀の分捕り品を得なかった。』
ここではメギドその地ではないが、メギドの近くにあるタナクという地で起きた戦いについて語られている。この箇所を見ても、メギドが戦いと関わりのある場所だったことが感じ取れるのではないかと思う。このメギドとは、古代では戦場として有名であった。だからこそ、ヨハネはキリストの再臨の際に起こる霊の戦いを示す際、この地を引き合いに出すことにしたわけである。もしメギドが有名な戦場ではなければ、メギドではなく、戦場として有名な別の場所が引き合いに出されていたことであろう。
第10章 8:ルツ記
ルツ記は、全く研究しなかったとしても問題ない。
第11章 9:Ⅰサムエル記
Ⅰサムエル記も、研究しなくてよい。何故なら、この文書には、再臨の理解を増進させる箇所が見られないからである。
第12章 10:Ⅱサムエル記
Ⅱサムエル記も研究しなくて問題ない。
第13章 11:Ⅰ列王記
Ⅰ列王記も研究しなくて大丈夫である。
第14章 12:Ⅱ列王記
Ⅱ列王記も、再臨について学べるような箇所は見られない。ただ、メギドについて記されている箇所は忘れ去られるべきでない。
【23:29~30】
『彼の時代に、エジプトの王パロ・ネコが、アッシリヤの王のもとに行こうとユーフラテス川のほうに上って来た。そこで、ヨシヤ王は彼を迎え撃ちに行ったが、パロ・ネコは彼を見つけてメギドで殺した。ヨシヤの家来たちは、彼の死体を戦車のせ、メギドからエルサレムに運んで来て、彼の墓に葬った。』
この箇所を読むと、黙示録では『ハルマゲドン』(16:16)と書かれているメギドという地が、戦場であったことがよく感じられる。先に見た士師記5:19の箇所では、メギドが付帯的にしか語られていなかったが、ここでは主体的に語られている。この箇所では、ヨシヤ王がメギドの地でパロ・ネコに殺されたことが書かれている。同様に黙示録19:19~21の箇所でも、王たちがキリストにより殺されたと書かれている。このことから、黙示録19:19~21の箇所はⅡ列王記23:29~30の箇所と対応していることが分かる。どちらも強い存在が、不信仰で不敬虔な王を、戦いにおいて殺しているからである。
第15章 13:Ⅰ歴代誌
Ⅰ歴代誌は、特に研究する必要がない。
第16章 14:Ⅱ歴代誌
Ⅱ歴代誌も、再臨について知るために研究する必要はない。しかし、この文書もⅡ列王記と同様、メギドについて記されている箇所を忘れるべきではない。
【35:22】
『しかし、ヨシヤは身を引かず、かえって、彼と戦おうとして変装し、神の御口から出たネコのことばを聞かなかった。そして、メギドの平地で戦うために行った。』
Ⅱ列王記23:29~3の箇所と同様、ここでもメギドが戦いの地であったことが分かる。黙示録におけるハルマゲドンの戦いを理解するためには、この箇所を参照しなければいけない。つまり、ヨハネは不敬虔なネロたちが、再臨のキリストによってメギドの地で悲惨になった王のように悲惨にさせられる、と言いたかったのである。
第17章 15:エズラ記
エズラ記は、研究しなくともよい。
第18章 16:ネヘミヤ記
ネヘミヤ記はどうであるか。この文書も、再臨を理解するために研究しなかったとしても問題ない。
第19章 17:エステル記
エステル記も研究しなくて問題ない。
第20章 18:ヨブ記
ヨブ記は、研究しなかったとしても、ほとんど問題にはならない。ただ1章と2章だけは、忘れないようにすべきである。何故なら、この2つの章では、まだサタンが天に出入りしていることが示されているからである。サタンが天に出入りするというのは、黙示録を見れば分かるように再臨の時期に大いに関わっているのだから、決して無視されてはならない。これ以外の箇所は、特に心を留めるべき箇所はない。
【1:6~7(=2:1~2)】
『ある日、神の子らが主の前に来て立ったとき、サタンも来てその中にいた。主はサタンに仰せられた。「おまえはどこから来たのか。」サタンは主に答えて言った。「地を行き巡り、そこを歩き回って来ました。」』
まず、この出来事が起きたのは、いつ頃であるか。この出来事が起きたのはヨブの時代であるから、ヨブがいつ頃の時代に生きたのか知ればよいことになる。それではヨブはいつ頃の人であったか。これは、よく分からない。紀元前1世紀頃に書かれたと思われるユダヤ教の文書にはヨブがヤコブの時代の人だったと示している文書があるが(※)、それは正典に含まれていない文書であるから、信頼に値する情報源とはならない。これについては、ただ「そういう可能性もある。」としか言えない。聖書66巻を読んでも、ヨブが生き正確な年代を知ることはできない。しかし、ヨブがいつ頃の人であったにせよ、旧約時代の人間だったということは間違いない。何故なら、ヨブ記が旧約時代に書かれたのは誰も疑わないことだからだ。ここでは、ヨブが旧約時代の人間だと分かっていれば、それでよい。
(※)
これは「ヨブの遺訓」という文書である。この文書の中でヨブは、自分がヤコブの娘ディナの夫であると言っている。この文書の中でヨブは子どもたちに対して次のように言っている。「子供たちよ、どうか、わたしを取り囲んでくれ、主がわたしになしてくださったことやわたしの身に起こったすべてのことを、お前たちに示したいのだ。わたしは忍耐強く振る舞ったお前たちの父ヨブであり、お前たちは母方の父ヤコブの末から出た、選ばれた栄誉ある種族なのだ。わたしはヤコブの兄弟エサウの子らの末であり、お前たちのお母さんディナはヤコブの娘なのだ。わたしは彼女を通してお前たちを生んだ。わたしの前妻はひどい死に方で、他の10人の子供たちといっしょに死んでしまったのだ。」(『聖書外典偽典 別巻 補遺Ⅰ』ヨブの遺訓 第1章4~6 p375:教文館)なお、ラビ伝承の中でもヨブの妻はディナであったと言われているが、これもあくまでも参考情報としてのみ捉えるべきである。
[本文に戻る]
ここで描かれている場所は天上の世界である。どうして、この箇所で天上の世界のことが言われていると分かるのか。それは、この箇所では神のおられる場所が描かれており、神がおられるのは天上の世界だからである。詩篇115:3の箇所で言われているように、『私たちの神は、天におられ』る。イザヤ66:1の箇所でも、こう言われている。『主はこう仰せられる。「天はわたしの王座、地はわたしの足台。…』 地は神の『足台』であって、そこに『王座』はない。だから、ここで描かれている場所は神のおられる天上の世界であることが分かる。
それでは、ここで言われている『神の子ら』とは、どのような存在であるか。これは御使いである。何故なら、これは御使いとしてしか理解できないからである。この時代において、まだ聖徒たちは天上の世界において神の御前に立つことが出来ていなかった。そのように出来るようになるのは、キリストが再臨された紀元68年以降である。それだから、ここで言われている『神の子ら』とは聖徒ではないことになる。であれば、これは御使いだということになる。というのも、『神の子ら』と呼ばれる存在は「御使い」と「聖徒」の2種類しかいないからである。
旧約時代において、サタンはまだ天上の世界に出入りすることが出来ていた。それは、この箇所を読めば分かることである。このことは、Ⅰ列王記22:19~23の箇所からも分かる。そこでは、偽りを言う惑わしの霊が、天上の世界にいることが書かれているからである。『偽りを言う霊』(Ⅰ列王記22:23)とは悪しき御使いでなくて何であろうか。聖なる御使いは、決して偽りを言わせるように働きかけはしないからである。それではサタンという悪しき霊は、天上に出入りすることで何をしようとしていたのか。それは地上にいる聖徒たちを苦しめるためであった。まずサタンは、地上を動き回って、そこにいる聖徒たちを観察した。彼が主に対して、『地を行き巡り、そこを歩き回って来ました。』と言った通りである。ペテロもまた同じようにこう言っている。『あなたがたの敵である悪魔が、ほえたけるししのように、喰い尽くすべきものを探し求めながら、歩き回っています。』(Ⅰペテロ5章8節)このサタンは地上の聖徒たちが犯している罪を見つけると、神のおられる天に行って、それを神に対して告発していた。だから、黙示録12:10の箇所では、サタンが『私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者』と言われている。このようにサタンが聖徒の罪を神に報告したのは、そのように報告することで、神の裁きを聖徒たちに発動させるためであった。サタンは、神が御自身の民であっても、そこに悪が見られるのであれば、容赦なく報いられることを知っていた。確かに神の民だからといって悪を犯しても報いが免除される、というのではなかった。つまり、サタンの思いはこうであった。「ねえねえ、神様。私は地上にいるあなたの民が罪を犯しているのを見ましたよ。私はそのことをあなたに報告いたします。あの者たちはあんなことをしているのだから、是非ともお裁きになって下さい。正義そのものであられる御方が、悪を処罰しないということがあってよいのでしょうか。御自身の民だからといって報いられないということがあってよいのでしょうか。それは正義であられる御方のご性質にそぐわないのではありませんか。さあ、彼らは悪を行なっているのですから、あなたの正義によって裁きを下して下さい。彼らが裁かれるのは当然ではないでしょうか。(早く裁かれて苦しんでしまえ。ぐふふ。)」しかしながら、ヨブの場合、神に告発できるような悪を見つけることが出来なかった。というのもヨブは『潔白で正しく、神を恐れ、悪から遠ざかっていた』(ヨブ1章1節)からである。だから神も彼についてこう言っている。『彼のように潔白で正しく、神を恐れ、悪から遠ざかっている者はひとりも地上にいない』(ヨブ1章8節)。それにもかかわらず、サタンはヨブを苦しめたかったので、神に対してヨブの罪を告発するのではなく―それは出来ないことだった―、ヨブを試すようにと提案した。つまり、ヨブが神から試されることで苦しむように取り図ったのである。この提案は神に受け入れられた。それゆえヨブは、神の試みにより、大きな苦難を受けることになった。これはヨブ記を見れば分かる通りである。旧約時代におけるサタンは、このように罪を犯している聖徒たちを天上で神に訴え、それどころか罪を犯してはいない聖徒さえをも苦しみを受けさせるべく神に狡猾に取り入っていたのである。
しかし今や、サタンはかつてのように天上で聖徒たちを訴えることが出来なくなっている。何故なら、もう既にサタンは天上から追放され、そこにいられなくなったからである。黙示録12章で書かれているサタンの天からの追放は、既に何度も述べたように『すぐに起こる』ことであった。サタンの追放が『すぐに起こる』ことだったのであれば、それはもう実現していることになる。黙示録に書かれている出来事は『すぐに起こるべき事』(黙示録1:1)だったと教えている神の御言葉を、故意に無視する者でなければ、サタンの追放はもう起きたのだと信じなければいけない。サタンが天にいられなくなったのは、再臨が起きて後、天上でキリストの王国が正式に開始されることになったからである。天のパラダイスにサタンという邪悪な存在がいてもよいのか。断じてそのようなことはあってはならない。それゆえ、サタンは紀元68年において天から居場所を失わなければならなくなったのである。今の聖徒たちは、まだサタンが天上にいるなどと考えているが、そのように考えるのは誤りである。何故なら、サタンは既に天から落とされているからである。サタンが天から落とされたというのであれば、どうして再び天に戻ることが出来るのであろうか。もし天に戻れるというのであれば、それは天から追放されたことにはならないのである。パウロがエペソ6:12の箇所で、天に『もろもろの悪霊』が存在していると言ったのも、まだエペソ書が書かれた時には再臨が起きていなかったからである。既に述べたように、再臨が起こる時になると、天からサタンとその他の悪霊どもは一掃されることになった。だから、このエペソ6:12の箇所に基づいて、まだ天には悪霊どもがいるなどと考えたり言ったりすることはできない。そのように考えたり言ったりするのは、黙示録をよく理解していない証拠である。というのも、もし黙示録をよく理解していれば、既に天からは悪しき霊が追い出されているということが分かるはずなのだから。
第21章 19:詩篇
詩篇は、再臨の理解を深めたいのであれば、心を傾ける必要がある。何故なら、この文書には、再臨の理解を増進させる箇所があるからである。とはいっても、詩編の全ての箇所を研究せねばならないというわけではない。ただ再臨に関わる重要な箇所に注意せねばならないということだけである。特に、有名な110篇は、最高に注目せねばならない。そこではキリストの再臨のことが大いに語られているからである。この箇所は再臨の理解を大いに増進させてくれる箇所である。この箇所は、本章の中で註解される。先にも述べたように、詩篇になってから、聖書では再臨の預言が本格的に語られるようになる。それまでは再臨のことはほとんど語られず、例外的なケースを除けば、まだ初臨についてしか示されていなかった。
【8:6】
『万物を彼の足の下に置かれました。』
パウロは、Ⅰコリント15章の箇所で、ここで言われているのはキリストのことだと示している。この詩篇の箇所は、ダビデについて言われたことかもしれない。すなわち、神はダビデを王とされ、彼に万物を統べ治めさせた、と。実際、ダビデは諸国を治める強大な王であった。しかし、これはキリストについての預言でもある。何故なら、このダビデとは、やがて来たるべきキリストを代表する人だったのだから。
この箇所については、後に書かれるⅠコリント15章の註解箇所で、再び取り上げられる。
【37篇】
『地を受け継ごう。』
この言葉を、今の聖徒たちの多くは、再臨に関わらせて理解するはずである。すなわち、こういう理解である。これからキリストが再臨される。その時には、無数の聖徒たちもキリストと一緒に天から降りてくる。そして、地上にいる悪人どもは容赦なく滅ぼされる。その時から、全ての聖徒たちがこの地球をキリストと共に相続するようになる。この地球は我々の物になるのだ。それは、詩篇37篇で『彼らは地を受け継ごう。』と書かれている通りである。だから、聖徒たちは地球を相続する者に相応しく、正しく、柔和に、敬虔な歩みをしていかねばならない。本書を読んでいないか、再臨成就説をまったく聞いたことのない聖徒の多くは、この見解に対して何の疑いもなく「アーメン。」と言うであろう。というのも、再臨未成就説に立つならば、その奉じている終末論が前であっても無であっても後であっても、このような見解を持つしかないからである。
しかし、この見解は間違っている。それは再臨未成就説の考えだからである。そもそも再臨が未だに実現していないと考えている時点で、教理的に敗北している。教理的な勝利は、既に再臨が起きたと考えるところにある。何故なら、もう再臨は起きているのだから。それでは、詩篇37篇で『地を受け継ごう。』と言われているのは、どういう意味か。これの正しい解釈は、どのようであるか。ここでは一般的なことが言われている。すなわち、聖徒たちがこの地上で正しく歩むならば、絶やされたり追い散らされたりすることもなく、その地にいつまでも住み続けられる、とここでは言われている。これは律法の教えていることである。律法にはこう書かれている。『きょう、私が命じておいた主のおきてと命令とを守りなさい。あなたも、あなたの後の子孫も、しあわせになり、あなたの神、主が永久にあなたに与えようとしておられる地で、あなたが長く生き続けるためである。』(申命記4章40節)箴言2:21の箇所でもこう書かれている。『正直な人は地に住みつき、潔白な人は地に生き残る。』カルヴァンも、詩篇37篇では一般的なことが言われているとしか考えていない。彼は、この箇所を全く再臨と関連付けていない。彼の詩篇註解における当該箇所を参照。つまり、ここで『地』と言われているのは、この地球のことである。しかも、それはどこか特定の地だけに限定されていない。それは、この地球の全土である。もし我々が御心に適った歩みをするならば、我々は今の地にずっと住み続けられるであろう。我々は、絶やされたり追い払われたりすることもない。子々孫々に至るまで安全である。何故なら、地とは神の所有物だから(出エジプト19:5)。神は、御自身の所有物である地を、御心に適った者にお与えになるのだ。しかし、御心に適わない歩みをしたならば、我々はその地に住み続けられない。我々の子孫も、今我々が住んでいる地に住み続けるということはありえない。紀元70年において祖国から滅ぼされて追放されたユダヤ人が、良い例である。彼らは神の御心に適わなかったので、絶やされ、散らされたのだ。この例を考えても分かるように、神は、御心に適わない者に、御自身の物である地を持たせ続けては下さらない。だから、ソロモンはこう言っている。『悪者どもは地から絶やされ、裏切り者は地から根こぎにされる。』(箴言2章22節)御心に適った歩みをして子々孫々までも地を受け継ぐようにするか、御心を損ねた歩みをして地から排除されるようにするか。どちらを選ぶかは我々の歩みにかかっている。私は前者のほうを選びたい。
アウグスティヌスは、この『地』が天国であると考えていた。つまり、詩篇37篇では、聖徒たちがやがて天国という場所にある地を受け継ぐようになる、と言われているとした。当たっているか間違っているかはともかく、これは霊的に高度な解釈である。霊的な素質がなければ、このような解釈は出来なかったであろう。まず天国を『地』と呼び表すのは、聖書の語法に反していない。何故なら、天の世界にも「天と地」があるからだ。我々が今住んでいるこの地の世界に「天と地」があるのと一緒である。黙示録21章とイザヤ65章で『新しい地』
と言われているのは、天国における地のことを言っている。このうち黙示録の箇所は既に註解したが、イザヤ書の箇所はこれから註解されることになる。また黙示録11:16の箇所では、明らかに天の場所が『地』と言われている。つまり、天にも<地>がしっかりとあるのだ。だから、天国を指して『地』と言うのは正しいことである。この黙示録11:16の箇所は既に註解された。だが、詩篇37篇で天国のことについて言われていると捉えるのは間違いである。文脈を考えれば分かるように、そこではこの地上における一般的なことが言われている。もちろん、確かに我々キリスト者は、やがて天国にある地を受け継ぐであろう。だが、ここでは天国について言われているわけではない。
事柄を纏める。詩篇37篇で『地を受け継ごう。』と言われているのには、3通りの解釈がある。すなわち、ここでは聖徒たちが永遠にこの地を実際的に相続すると言われているとするか、ごく一般的なことが言われているとするか、天国について言われているとするか、である。このうち第一のものは今の聖徒たちが一般的に考えるであろう見解であり、第二のものはカルヴァンの見解であり、第三のものはアウグスティヌスの見解である。第一の見解は根本的に誤っており、第三の見解は文脈を考慮しておらず、第二の見解は何も問題がなく自然である。だから、第二見解が正しいとせねばならない。
キリストの語られたマタイ5:5の箇所は、この詩篇37篇で『地を受け継ごう。』と言われているのと非常に似ている。キリストはこう言われた。『柔和な者は幸いです。その人は地を相続するからです。』主は、我々が今見ている詩篇の箇所に基づいて、お語りになったのであろう。何故なら、キリストが言われたことは詩篇の箇所と内容的に同一だからである。どちらでも正しい者が地に残されると言われている。
【110:1】
『主は、私の主に仰せられる。「わたしがあなたの敵をあなたの足台とするまでは、わたしの右の座に着いていよ。」』
詩篇110:1は、再臨について重要なことが言われている箇所である。本書は再臨について考究する使命を持っているのだから、この箇所を註解しないわけにはいかない。再臨について深い理解を持ちたい聖徒たちは、是非ともこの箇所を丸暗記しておくのが望ましい。
この箇所は、新約聖書の多くの箇所で引用されている。恐らく、新約聖書の中で最も対応している箇所の多い旧約聖書の聖句は、この詩篇110:1ではないかと思われる。実際、新約聖書では、次の箇所で詩篇110:1の内容と同じことが言われている。マタイ22:43~44、マルコ12:36、ルカ20:42~43、使徒行伝3:21、Ⅰコリント15:25、ヘブル1:13、10:13。旧約聖書の中では、この箇所と同じことが言われている他の箇所は見られない。
ダビデがこの預言を語った際、当時の人のどれだけが、この預言の中で言われていることを悟れたであろうか。実際に当時の人の身になって考えてみてほしい。果たして、この預言を聞いたり読んだりして、当時の人たちは再臨のことが悟れたであろうか。恐らく、悟れなかった人も多くいたのではないかと思われる。何故なら、ダビデの生きていた紀元前1000年頃の時代は、まだ初臨のことしか、ほとんど啓示されていなかったからである。だから、この預言を聞いたり読んだりして、多くの人が、メシアの到来、すなわち我々が理解するところの「第一の到来」しか悟れなかったのではないか。もっとも、ダビデがこの預言で言われている再臨のことを御霊により人々に説明し、その説明がイスラエル全体に知られていたので、当時のユダヤ人は誰でもこの預言で再臨のことが言われていると理解していた可能性も十分にある。もしダビデか、またはダビデ以外の人がこの預言について再臨のことを説明していなかったとすれば、この預言から初臨のことしか悟れなかったとしても不思議なことは何もない。今の時代のキリスト者の場合、この預言が再臨について言っていると理解しない者は誰もいない。すなわち、この預言から初臨のことを理解するキリスト者がいるなどとは、まったく考えられないことである。
『わたしがあなたの』と言われているのは、「父なる神が子なる神であるキリストの」という意味である。これは我々キリスト者にとっては明白である。何故なら、我々は、神の3位格について弁えているからである。一方、ユダヤ人たちは、これについて理解することができない。何故なら、彼らは神のペルソナについて何も弁えていないからである。これからも、彼らがここで言われている父なる神と子なる神のことについて理解することは出来ないであろう。もちろん、キリスト者になったユダヤ人であれば話は別であるが。
ここでは、キリストの再臨は、敵が足台となった時に実現されると言われている。つまり、敵が足台とならない限り、キリストの再臨も起こらないということである。キリストが昇天されて後、神の右の座に着かれたということについては、新約聖書の多くの箇所で言われている通りである。これについては、いちいち聖句を挙げる必要はないであろう。『足台とする』とは、つまり足の下に踏み砕く、裁きを与える、滅ぼす、殺す、その対象を下に置きつつ断罪する、という意味である。それでは、キリストは誰を、またはどのような存在を『足台とする』のであろうか。いかなる者を足台とすると、キリストが再臨されることになったのか。これは、キリストの再臨の時に足台として裁かれた者を知ればよい。何故なら、その者が足台になると、キリストが再臨されることになったからである。その『足台』となった『敵』とは、すなわちネロとネロにつく王たちである。黙示録19:19~21の箇所を見ると、キリストが再臨された際には、ネロとネロにつく王たちが足台として断罪され悲惨にさせられていることが分かる。要するに、ネロとネロにつく王たちが足台となるべき時が紀元68年6月9日に訪れたからこそ、遂にキリストが彼らを罰すべく再臨されたのである。これまで教会は、この足台となる敵について、よく理解できていなかった。敵が足台となるとキリストの再臨が起こることは分かっていたが、その敵が何かと言えば誰も具体的に説明することが出来ていなかった。これは当然であった。何故なら、この敵とは、再臨が既に起きたと理解していない限り、具体的に知ることが出来ないからである。紀元68年6月9日に再臨が起きたと理解して初めて、この敵が誰なのか知ることが出来るようにもなるのだ。
さて、今まで教会は、この詩篇110:1で言われていることが、未だに実現していないと信じてきた。すなわち、まだ敵が足台となっておらず、それゆえ再臨も起きていないと考えてきた。しかし、そのように考えるのは誤りであった。というのも、キリストもパウロも、自分と一緒にいた紀元1世紀の人たちが生き残っている間に、すなわち死ぬ前に再臨が起きると明白に言ったからである。これはあまりにも明白だから、決して疑うことはできない。しかし、私がこのように言っても、誰もが目を丸くするばかりである。聖書の御言葉が再臨は既に起きたと明白に示しているので、誰も彼も反論できず、ただ沈黙するばかりである。これは教会が今まで2千年間も持ってきた歴史的な理解を徹底的に打ち砕く理解だから、ほとんど全ての人が、なかなか受け入れようとはしない。というのも、もし受け入れると今まで教会は2千年間も誤ってきたことを認めなければいけなくなるからである。これが正しい理解だと分かっていても、今までとは違った見解を持つことによる孤立や迫害を恐れるので、立場を変えようとはしない人が何と多いことか。この聖書的な再臨の理解を受け入れない人が多いのは、実に残念なことである。これから多くの人が、聖書が教えている通り、既に再臨は起きたのだと信じるようになるのを願うものである。
【110:2】
『主は、あなたの力強い杖をシオンから伸ばされる。』
『力強い杖』とは、御言葉のことである。杖が御言葉だというのは、エレミヤ23:29の箇所から分かる。御言葉が『力強い』というのは、改めて説明するまでもないことである。当然ながら、これは実際的な杖のことを言っているのではない。つまり、これは比喩表現としての『杖』に他ならない。
『シオン』とは、キリストのおられる天上のことである。エルサレム市にあった丘もシオンと呼ばれる。すなわち、シオンという場所には、天上のそれを地上のそれという2つが存在している。この箇所では地上のシオンが言われているのではない。何故なら、我々が今見ている詩篇110篇の箇所は、キリストが天上のシオンから再臨されることについて語っているからだ。
『伸ばされる』とは、効力を及ぼす、その威力を発揮させる、周りにまで有効力を行使させる、というほどの意味である。つまり、ここでは杖である御言葉により働きかけがなされる、と言われていることになる。これが実際に物理的な杖を伸ばすことだと考えるのは、お笑いである。
『主は、あなたの』とあるが、これは「父なる神が子なる神であるキリストにあることを行なわせられる」という意味である。つまり、『主』=父なる神、『あなた』=子なる神であるキリスト、である。
この110:2の箇所で言われているのは、つまり天上の『シオン』から再臨されたキリストが、『力強い杖』である御言葉を使って敵どもを断罪し裁かれる、ということである。かなり難しい言い方がされているが、この箇所はこのように解されるべきである。
この箇所で言われている内容は、黙示録19:11~16の箇所と対応している。黙示録のほうでも、この詩篇の箇所と同じように、天のシオンから再臨されることになったキリストが『鉄の杖』(黙示録19:15)である御言葉を使って敵どもを霊的に処罰されることになった、ということが言われている。この黙示録の箇所も一緒に考察すれば、更に詩篇110:2の箇所における理解が豊かなものとなるであろう。
『「あなたの敵の真中で治めよ。」』
この言葉を誰が語っているのか、ここでは何も書き記されてはいない。しかし、これが御父の御子に対する命令の言葉であることは明らかである。詩篇には、他の箇所でも、このような書き方ををしている箇所が見られる。
『敵』とは、ネロとネロにつく王たちのことである。これは、明らかに110:1で言われていたのと同一の『敵』である。
『真中』とは、臆せずに、堂々と、真正面から、というほどの意味である。何故なら、隅からでないというのは、すなわちそういうことだからである。
『治めよ』とは霊的な裁きのことを言っている。すなわち、これはキリストが『力強い杖』である御言葉により敵どもを霊的に断罪し悲惨にさせられる、ということである。
この箇所で命じられているのは、キリストが再臨される際には御言葉の杖により敵どもが大いに断罪されるように、ということである。つまり、ここで言われているのは黙示録16:16の箇所で言われている『ハルマゲドン』における戦いのことであり、その戦いにおける断罪は同じ黙示録の19:19~21の箇所で詳しく示されている。ところで、ここで言われているのは、新約時代における「戦う教会」のことではないかと思われる方がいるかもしれない。すなわち、ここで言われているのは、新約時代における教会が主なるキリストに従いつつ敵の真中で歩んでいくことである、と。実際、多くの聖徒たちが今まで、そのように考えてきた。再臨が未だに起きていないと理解しているのであれば、この箇所をそのように理解したとしても不思議ではない。何故なら、再臨が未だに起きていないと理解していると、この箇所はそのように捉えるしかないと思えてしまうからである。しかし、詩篇110篇の全体をよく読んでほしい。ここで言われているのは、キリストが紀元68年6月9日に再臨されることについてである。すなわち、まず110:1の箇所でキリストは敵が足台となった時に再臨されるということが示されてから、最後の110:7の箇所まで再臨の詳細がどのようなものであるか示されている。黙示録19:11~21の箇所と併せて考慮してみると、このことはますます確かとなる。何故なら、その黙示録の箇所とこの詩篇110篇の箇所は、完全に調和しているからである。既に第3部の中で見たように、黙示録19:11~21の箇所では再臨のことが語られていた。それゆえ、その黙示録の箇所と対応している詩篇110篇の箇所でも再臨のことが語られているのである。この詩篇110篇が、再臨よりも前の出来事について語られていると考えると、この箇所を正しく理解できなくなってしまう。
【110:3】
『あなたの民は、あなたの戦いの日に、聖なる飾り物を着けて、夜明け前から喜んで仕える。』
『あなたの民』とは、天上の聖徒のことである。これは地上にいる聖徒のことではない。何故なら、詩篇110篇では、キリストの再臨における言わば発着地点である天を起点にしたことが語られているからである。文脈を考慮すれば、これは天上の聖徒のことだと解さざるを得ない。
『戦いの日』とは、黙示録16:16の箇所に書かれている『ハルマゲドン』の戦いが行なわれる日であり、それは再臨が起こる日である。聖書は、キリストの再臨の日を、霊的な戦いの起こる日として取り扱っている。その戦いは、黙示録19:19~21の箇所で詳しく描かれている。
ここでは天上の聖徒たちが『聖なる飾り物を着けて』いたと書かれているが、これは御霊の身体のことを言っている。聖徒たちが天上で復活すると新しい身体である御霊の身体を受けることになるが、ここではその身体が『聖なる飾り物』と言われている。これは詩篇110篇と対応している黙示録19:11~21の箇所では、『まっ白な、きよい麻布』(19:14)と言われている。『まっ白な、きよい麻布』が、すなわち『聖なる飾り物』であるということは確かである。つまり、この飾り物という言葉は、新しい身体を言い表した象徴表現である。
『夜明け前から』とは、言い換えれば「再臨が起こる前から」となる。キリストとは義なる太陽であり、その現れである再臨が起こる出来事は夜明けとして例えることが出来る。それだから、黙示録でもキリストの再臨が、太陽が東から上って来る夜明けとして語られている。同様に、ペテロもキリストの現れである再臨を夜明けとして取り扱っている。ペテロの場合、太陽ではなく明けの明星としてキリストを取り扱っているが、その意味するところは太陽の場合と何も変わらない。彼はⅡペテロ1:19の箇所でこう言っている。『夜明けとなって、明けの明星があなたがたの心の中に上るまでは、暗い所を照らすともしびとして、それに目を留めているとよいのです。』言うまでもないことかもしれないが、この夜明けという言葉を、実際的な自然現象としての夜明けとして捉えるのはナンセンスである。
この箇所では、天上の聖徒たちが、再臨の起こる前に天上で復活するということが教えられている。すなわち、天上にいて魂だけの状態だった聖徒たちは、再臨の起こる少し前に復活して新しい身体―『聖なる飾り物』―を受け、その後、キリストと共に天から降りて来る。どうして、この箇所から天上の聖徒たちの復活が再臨よりも前に起こると分かるのか。それは、『聖なる飾り物を着けて、夜明け前から喜んで仕える。』と書かれているからである。これは、つまり再臨という夜明けが起こる前から、聖なる飾り物という御霊の身体を天上の聖徒たちが受ける、ということを教えている。そのようにして再臨前に復活した天の聖徒たちは、早速、天において『夜明け前から喜んで仕える』ことになった。しかし、仕えると言っても何をしたのであろうか。それは、キリストと共に天から降り、裁きを行なうための準備である。天上の聖徒たちが復活すると天からキリストと共に降り、そうして後、裁きの座に着いて裁きを行なうこととなった(黙示録20:4)。そのようにするために、彼らは再臨が起こる前から、キリストの御前で聖なる仕度をしたのである。その仕度をしている時、天上の聖徒たちには喜びがあった。それは、『喜んで仕える。』とここで聖徒たちの仕度について書かれている通りである。ところで人間の造られた目的とは神である。この神に生きるようにと人間は造られたのだ。今や、天上で復活した聖徒たちの目の前には、人間の目的であるこの神がまざまざとおられるのである。であれば、どうしてその神に仕える天上の聖徒たちに喜びがないということがあるのであろうか。天上で復活した彼らが目の前におられる神に仕える際、喜びを持つことが出来たのは自然なことであった。
この箇所で、天上の聖徒たちが、再臨という『夜明け』が起こるよりも前に復活に与かったと示されているのは重要である。つまり、天上の聖徒たちは、再臨が起きた後に復活するのではない。これは是非とも覚えておかねばならない理解である。一方、地上にいた聖徒たちの場合、再臨が起きてから復活することになった。それはパウロが次のように聖徒たちに対して言ったことから分かる。『主は、号令と、御使いのかしらの声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者が、まず初めによみがえり、次に、生き残っている私たちが、たちまち彼らといっしょに雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。』(Ⅰテサロニケ4章16~17節)このⅠテサロニケ書の箇所で言われているのは、空中に携挙される者たちのことだから、明らかに地上の聖徒のことである。つまり、まず復活に与かるのは天上の聖徒たちであり、その次に地上の聖徒たちが復活に与かる。パウロが、天上にいる今はもう地上にいない聖徒たちの復活に自分たちが先んじることはない、と言ったのは正にこのような順序があったからである。彼はこのことについてⅠテサロニケ4:14~15の箇所で、こう言っている。『私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば、神はまたそのように、イエスにあって眠った人々をイエスといっしょに連れて来られるはずです。私たちは主のみことばのとおりに言いますが、主が再び来られるときまで生き残っている私たちが、死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。』もし地上にいる聖徒たちのほうが天上にいる聖徒たちよりも先に復活するか、または両者が同時に復活するというのであれば、パウロはこのように言っていなかったであろう。要するに、2つの復活と再臨の起こる順序を示せば、次の通りとなる。①天上の聖徒たちの復活⇒②再臨⇒③地上の聖徒たちの復活。
『あなたの若者は、あなたにとっては、朝露のようだ。』
ここでは天上で復活した聖徒たちが『若者』と言われている。これは、天上で復活した聖徒たちが、生き生きとした若者のようだからである。地上にいた時には老人だった聖徒も、また幼児の時に亡くなった選ばれた者たちも、天上で復活した際には『若者』のようになった。確かに、復活した聖徒たちについては、イザヤ書の中でこう言われている。『走ってもたゆまず、歩いても疲れない。』(40章31節)これは、つまり復活した聖徒たちが若者のような精力を持つようになるということでなくて何であろうか。天上で復活した聖徒たちは、非常に幸いな者たちであるから、『若者』のようになるのが相応しいのは確かである。せっかく栄光の身体に復活したのに、老人のようだったり幼児のようだったりするのは、考えられないことである。それは聖なる御使いたちの中に、老人や幼児が見られないのと同じことである。確かに聖書の中で出てくる御使いは、若者の姿をしているのである(マルコ16:5~6)。また当然ながら、地上にいて生きながらにして復活した紀元1世紀の聖徒たちも、天上で復活した聖徒たちと同じように若者のような状態として復活した。というのも、天上の聖徒たちと地上の聖徒たちの復活においては、その復活する場所は異なるものの、復活する状態においては何も変わらないはずだからである。天上で復活した聖徒たちは誰もが若者のようだが、地上で復活した聖徒たちの中には老人や幼児も含まれるというのは滑稽である。天上の聖徒たちが全て若者のような姿として復活したのであれば、地上の聖徒たちも同じようになったとすべきである。今の時に生きる我々も、この人生を終えて復活した際には『若者』のようになるであろう。今は壮年や老年であったとしても、必ず、誰もが若者のようになる。これは大変感謝すべきことである。
この天上で復活した聖徒たちが『朝露のようだ』と言われているのは、つまり再臨の際の降下のことである。『朝露』の明瞭な写像を脳内において思い描いてみるとよい。無数の透明な雫が木の葉っぱや建物の縁の部分から、ポタポタと下に滴り落ちている、そのような写像。天上で復活した聖徒たちがキリストの再臨の際、キリストと共に天から降りて来たのも正にこの『朝露』の滴りのようであった。というのも、エノクが預言したように、キリストの再臨の際に天から降下して来る聖徒たちは『千万』(ユダ14節)だからである。再臨の際に天から降りて来る復活体の聖徒たちは実に数が多いのだから、その降下が、無数の水滴が下に落ちて来る『朝露』に例えられているのは実に適切であった。この『朝露』というのは、私が今述べたように聖徒たちの降下のことだと理解しないと、正しい理解を持つことは出来ないであろう。なお、聖書の中で『朝露』と言われているのは、どれも下に水滴が落ちることについて言われている。例えば、ミカ5:7、申命記32:2、Ⅱサムエル17:12がそうである。これは覚えておいて損にはならない知識である。
ところで、ダビデがこの箇所の預言を書いたり語ったりした際、それを読んだり聞いたりした当時の聖徒のうち、一体どれだけの人が聖徒の降下について理解できたであろうか。もう既に全ての啓示が示し終えられた今の時代の聖徒でさえ、この箇所を読んで、十全な理解を得られないでいる。であれば、まだまだ多くの啓示が啓示されないままでいたこの時代に生きていた聖徒たちは、尚更のこと、この箇所で言われていることから聖徒の降下について悟れなかったのではないかと思われる。しかしながら、当時のイスラエルには先にも触れたあのエノクの預言が知れ渡っていただろうから、もしかするとこの箇所では聖徒の降下について言われているということが悟れていたかもしれない。何故なら、エノクが『千万』の聖徒の降下について預言したのは、正に『朝露』が滴り落ちる場面になぞらえることが出来るからである。当時の聖徒たちの霊性が鋭かったのであれば、またはダビデやその他の敬虔な聖徒たちが当時の人々にこの箇所について色々と教えていたのであれば、ここで聖徒の降下について言われていることが悟れていたであろう。いずれにせよ、ダビデの時代における人々の一般的な理解について我々はよく知らないから、このことについて何か確言することは難しいと言わねばならない。
【110:4】
『主は誓い、そしてみこころを変えない。「あなたは、メルキゼデクの例にならい、とこしえに祭司である。」』
この箇所は、ヘブル書の中で多く引用されている(5:6、10、6:20、7:17)。しかし、ヘブル書以外の巻では引用されていない。詩篇の中でも、このように言われているのは、この箇所だけである。
ここでも、先に見た110:1や110:2の箇所と同様に、父なる神が子なる神であるキリストに語っておられる。その言われたことは『誓い』であった。つまり、その言葉における内容は絶対であった。何故なら、神であられる方が誓われるということほどに堅固なものは他にないからである。それだから、その言われたことは『変え(られ)ない』内容であった。もしここで言われていることが変えられるぐらいならば、千の宇宙が一挙に消えてしまうほうが遥かに容易いであろう。
ここで言われているのは、つまりキリストが永遠にメルキゼデクのごとき祭司として存在される、ということである。このメルキゼデクとはシャレムにいた誠に偉大な祭司であって、アブラハムでさえも十分の一を捧げたぐらいの存在であった(創世記14:20)。ヘブル7:4の箇所で言われていることからも分かるように、このように偉大な祭司は他にいなかった。キリストは、このメルキゼデクのように偉大な祭司として永遠に存在し続けられるのだ。このメルキゼデクという祭司の詳細については、話が少々横に逸れてしまう上、長くなってしまうだろうから、ここではこれ以上の説明はしないでおく。さて、この箇所からは、キリストが再臨される際には、偉大な祭司としても再臨されるということが分かる。聖徒であれば誰でも、再臨の際にはキリストが王また裁き主として来られる、ということは分かるはずである。しかし、キリストは王や裁き主としてだけではなく祭司としても再臨されるということを我々は覚えるべきである。それではキリストが祭司として再臨されるとは、具体的に言えば一体どういうことなのか。それは、キリストが再臨される際には、祭司として地上にいた聖徒たちの身体を贖われる、ということである。何故なら、祭司とは、その犠牲の祭儀を通して人々に聖なる贖いを受けさせる存在だからである。実際、旧約時代の聖徒たちは、神殿にいた祭司に犠牲の動物を渡して犠牲の祭儀を執り行ってもらうことで、神からの贖いを受けていた。そのように、キリストも再臨された際には、祭司として聖徒たちに究極的な贖いをお与えになったのである。
【110:5】
『あなたの右にいます主は、御怒りの日に、王たちを打ち砕かれる。』
『御怒りの日』とは、再臨の起こる日である。それは既に何度も言われていることだが、紀元68年6月9日であった。この日にはキリストがその御怒りを発せられるので、怒りの日などと呼ばれている。またこの日は、怒りの日と呼ばれる一方、喜びの日でもあった。というのも、この日には聖徒たちが身体の贖いを受けて喜ぶことになるからである。このように、この日には2面性があるということを忘れないようにしたい。
ここで『王たち』と言われているのは、もちろん黙示録で言われていたネロにつくあの王たちのことである。私は言いたい、聖書は聖書によって解釈せよ、と。つまり、自分の感覚や印象によって聖書を解釈してはいけないということだ。詩篇110篇は明らかに黙示録19:11~21の箇所と対応しているのだから、この110:5の箇所で言われている『王たち』とは明らかに黙示録19:19の箇所で言われている『地上の王たち』のことである。ここで『王たち』と書かれているのを見て、今の時代のほとんど全ての聖徒たちは、聖句の根拠抜きに、すなわち理性が判断するままに解釈しようとするはずだ。「王たちと書かれているからイギリスとかサウジアラビアなどといった多くの国々のリーダーのことが言われれているのだろう。」と。しかし、このような解釈方法は、聖句を根拠とした解釈方法ではないから、よくない解釈方法である。また、この王たちが『打ち砕かれる』というのは、黙示録19:21の箇所で言われている御言葉による霊的な刺殺のことである。この『打ち砕かれる』という部分も、やはり聖書によって解釈せねばならない。つまり、自分の心が好き勝手に判断するままに解釈してはいけない。ペテロも『聖書の預言はみな、人の私的解釈を施してはならない』(Ⅱペテロ1章20節)と言っている。
【110:6】
『主は国々の間をさばき、それらをしかばねで満たし、』
主キリストが『国々の間をさば』かれると言われているのは、つまりキリストが国々の王に断罪を下される、ということである。その王たちが裁かれて『しかばね』になるとは、つまり黙示録19:21の箇所で言われていることである。そこでは、ネロにつく複数の王たちがキリストから殺され、その死体が鳥によりむしゃむしゃと食われてしまうと言われている。これは既に第3部の中で説明されたように、霊的に断罪されたネロにつく王たちが悪霊どもの餌食にされてしまう、という意味である。
『広い国を治めるかしらを打ち砕かれる。』
この部分は、キリストが紀元68年に再臨されたという前提に立ちつつ読み解くのであれば、理解するのはそう難しいことではない。まず、『広い国』とは、明らかにローマ帝国を指す。何故なら、古代のローマとは非常に大きい国だったから。次に、そのローマ帝国を『治めるかしら』とは、ネロを指している。何故なら、ネロとはローマにおける最高の首領だったから。そして、そのネロが『打ち砕かれる』とは、黙示録19:19~20やⅡテサロニケ2:8で言われているように、ネロが再臨されたキリストにより断罪され、殺され、滅ぼされてしまうという意味である。何故なら、ネロが『打ち砕かれる』とは、ネロが霊的な意味においても実際的な意味においても再臨されたキリストにより死滅させられるということだからである。
【110:7】
『主は道のほとりの流れから水を飲まれよう。それゆえ、その頭を高く上げられる。』
キリストが『道のほとりの流れから水を飲まれ』るとは、どういう意味なのか。これは、キリストが再臨される際には、あのギデオンの時の戦士のように戦いに望まれるということである(士師記7:4~8)。ギデオンが敵どもの陣営に戦いをしに行く時、ギデオンと共に戦うことになったのは『口に手を当てて水をなめた』(士師記7:6)300人だけであった。キリストは、水を手から汲んで飲んだあの300人の戦士たちのように敵どもと戦われたのである。出エジプト記15:3の箇所で言われているように『主はいくさびと』なのである。キリストが、ギデオンと共に戦いに行けなかった300人以外の者のようでなかったのは、言うまでもない。何故なら、もしキリストが300人以外の者のようであったならば、再臨の際に戦われることは無かったはずだからである。士師記で言われているように、そのような者たちは戦うことができず、自分の家に帰らなければいけなかったのである。
キリストが『その頭を高く上げられ』たのは、あの300人のように腰をかがめて水を飲み、そうしてから身を起こして出陣されることになったからである。腰をかがめたならば、水を飲んだ後、腰と一緒に下がった頭を高く上げるのはごく自然なことである。つまり、これはキリストが戦いに望まれる際の出陣表明である。「私はあの300人のように手で水を汲んで飲んだ。そして頭を高く上げた。それゆえ私は敵どもと戦うために出て行くであろう。」と。あの時に口に手を当てて水を飲んだ300人の者たちも、水を飲んでから下がった頭を高く上げたはずである。誰がこれを疑うであろうか。
このように、この110:7の部分は、ギデオンの話を参照してこそ正しく解せる。というのも、この詩篇の箇所はギデオンの話が書かれている箇所と対応しているからである。どちらも戦いに望もうとしているという点で共通しているのは明らかだ。しかし、この部分をギデオンの話により解そうとしなければ、何がここで言われているのか分からないままとなる。何故なら、ここではギデオンの話に基づいた記述がされているからである。このことからも、いかに聖書は聖書によって解されなければいけないかということが、よく分かるのではないかと思う。聖書によって聖書を解するからこそ、真に正しい解釈を得られる。もし聖書によって聖書を解さないと、いつまで経っても何が言われているのか分からないままである。それは、あたかも出口のない暗闇の迷宮を延々と悩みながら彷徨うようなものである。
第22章 20:箴言
箴言は、研究しなかったとしても問題はない。
第23章 21:伝道者の書
伝道者の書は、研究しなかったとしても、ほとんど問題はない。何故なら、この文書からは、あまり再臨のことが学べないからである。ただ、12:1~8の箇所は見ておく必要がある。この箇所では、どうやらユダヤの終焉について言われているように感じられるからである。本章では、この箇所について註解される。
【12:2】
『太陽と光、月と星が暗くなり、』
これから見ていく12章の前半部分は、恐らくユダヤの破滅について預言された箇所だと思われる。ユダヤの破滅について預言された黙示録18:22~23の箇所と、我々がこれから見る箇所をよく見比べてみてほしい。どちらも似たようなことが言われているのは明らかである。この伝道者の書の箇所と黙示録18:22~23の箇所が対応しているとすれば、確かに我々がこれから見ていく箇所はユダヤの破滅について預言された箇所だということになろう。というのも対応しているというのは、つまり一緒のことが言われているということだからである。
この部分で言われているのは、再臨が起こるユダヤ世界の終わりの頃についてであると思われる。というのも、その頃には太陽や月などが暗くなると多くの箇所で言われているからである(マタイ24:29、黙示録6:12、8:12、16:10など)。もちろん、これはあくまでも象徴的な表現に過ぎないのであって、実際に天体や空が暗くなると言われたというわけではない。
ラビたちの場合、タルムードの中で、この箇所について次のように言っている。「「太陽や光が暗くなる前に」。これは額や鼻(への言及)である。「や月」。これは魂(への言及)である。「や星」。これは頬(への言及)である。」(バビロニア・タルムード:シャバット篇 23章/ミシュナ6のゲマラ)これは検討してもよい見解だと思うが、少しこじつけの感があるように思われる。というのも、これらの見解には堅固さがないからである。やはり、これはユダヤの終末において使われた表現に関わる文章として見るべきではないかと私には思える。
『雨の後にまた雨雲がおおう前に。』
これは何か。これは、恐らく初臨と再臨のことなのであろう。キリストはその初臨によって全世界に救いの雨がもたらされるようにして下さったのだから、初臨は『雨』である。そして再臨においてキリストは雲に乗って来られるのだから、再臨は『雨雲がおおう』ことである。このように解するのは無理なことではない。しかし、私の感覚からすれば、この見解は、やや堅固でないように思われる。つまり、堅い基礎の上に立っている見解ではないように感じられてしまう。この部分については、これから理解が進むのを望みたい。なお、この部分はホセア6:3の箇所も考慮されるべきである。そこでは主の現われについて次のように言われている。『主は暁の光のように、確かに現われ、大雨のように、私たちのところに来、後の雨のように、地を潤される。』また、ヨエル書2:23の箇所も考慮されるべきである。そこでは次のように言われている。『シオンの子らよ。あなたがたの神、主にあって、楽しみ喜べ。主は、あなたがたを義とするために、初めの雨を賜わり、大雨を降らせ、前のように、初めの雨と後の雨とを降らせてくださるからだ。』
ラビたちの場合、これは「泣くことで失われる視力(への言及)である。」(バビロニア・タルムード:シャバット篇 23章/ミシュナ6のゲマラ)と言っている。つまり、目から生じる涙を雨また雨雲として捉えているわけだ。この見解は、もっともらしいと思われなくもない。しかし、これが初臨と再臨について言われているという見解も捨てるべきではないと私には思われる。
【12:3】
『その日には、』
『その日』とは、もちろんユダヤの終わりの日のことである。この日を、個人の人生における終わりの日だと捉えてはならない。というのも、この辺りの部分においては、個人的な終わりというよりは、明らかに全体的な終わりについて語られているからである。
『家を守る者は震え、力のある男たちは身をかがめ、粉ひき女たちは少なくなって仕事をやめ、窓からながめている女の目は暗くなる。』
『家を守る者は震え』とは何か。これは、ユダヤの終わりの時期には、ローマ軍が襲来するということだと思われる。何故なら、力強いローマ兵がユダヤに入り込んで来たら、家を守るように期待されている者は家を守ることが出来ず、ただ震えるしかないからである。ラビたちは、これを「脇腹と肋骨」(バビロニア・タルムード:シャバット篇 23章/ミシュナ6のゲマラ)と解しているが、これは検討すべき見解である。『力のある男たちは身をかがめ』とは何か。これは、力ある男でさえ、ユダヤ戦争の時期には堂々としていられなくなるということではないかと思われる。何故なら、その頃には『戦争や、戦争のうわさを聞く』(マタイ24章6節)うえ、『民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々にききんと地震が起こ』(同24章7節)るからである。ラビによれば、これは「脚」への言及である(前同)。これは、もっともらしい。『粉ひき女たちは少なくなって仕事をやめ』とは何か。これは、携挙によりある女たちがこの地上から取り去られるので、仕事のための働き手が少なくなるということではないかと思われる。キリストはユダヤ戦争の時期に起こる携挙のことについて、次のように言っておられる。『そのとき、…ふたりの女が臼をひいていると、ひとりは取られ、ひとりは残されます。』(マタイ24章40~41節)ラビはこれが「歯」であると理解している(前同)。つまり「臼=歯」ということなのだろうが、これは私が述べた理解のほうがもっともらしいと感じられる。『窓からながめている女の目は暗くなる』とは何か。これは、ユダヤの終わりの時期には、窓から眺めている女の目に喜ばしい光景が入ってこないということだと思われる。というのも、その時期には破滅へのカウントダウンが既に始まっているので、ユダヤ全体のムードが薄暗くなったからである。ラビの場合、これを「目」の衰えへの言及として理解しているが(前同)、私はこの理解を否定しはしない。
【12:4】
『通りのとびらは閉ざされ、臼をひく音も低くなり、人は鳥の声に起き上がり、歌を歌う娘たちはみなうなだれる。』
『通りのとびらは閉ざされ』とは何か。これは、ユダヤ戦争の時期に、ローマ兵に対する恐れからユダヤの家々が扉を閉ざすということなのであろう。恐るべきローマ兵がやって来るというのであれば、扉を閉ざすのは自然なことである。もっとも、どれだけ堅固に扉を閉めたとしても、ローマ兵の襲来にあっては、何の意味もなさなかったのではあるが。また、これはユダヤ戦争の時期に邪悪なテロリスト(スィカリーン)がエルサレム中を荒らし回っていたからでもあると思われる。つまり、人々がこのテロリストを恐れたから『通りのとびらは閉ざされ』だのだ。この狂った者たちについては、ヨセフスの書でも詳しく記されている。この者たちは、まったく抑制されていないマフィアや不良と言えば分かりやすいのではないかと思う。ラビはこれが「人体の開口部である」と言っているが(バビロニア・タルムード:シャバット篇 23章/ミシュナ6のゲマラ)、これはもっともらしく感じられる。『臼をひく音も低くなり』とは何か。これは前節でも書かれていたように、『粉ひき女たちは少なくなって仕事をやめ』たからである。女たちが粉ひきの仕事を止めるのであれば、臼をひく音が低くなるのは自然なことである。ユダヤの破滅について言われている黙示録18章の箇所でも、『ひき臼の音も、もうおまえのうちに聞かれなくなる。』(18:23)と言われている。ラビはこれが「轢かない胃袋」と言っているが(前同)、これはなかなか堅固に感じられるものの、私の述べた見解のほうが正しいと思われる。『人は鳥の声に起き上がり』とは何か。これは、当時のユダヤにいた人々は神の呪いのうちにあったので、鳥の声にさえ驚いて起き上がらせられてしまうということなのであろう。確かに律法違反により呪いを受けている状態にあると、『夜も昼もおびえて、自分が生きることさえおぼつかなくなる』(申命記28章66節)のだから、小さな鳥の声にさえ敏感にさせられるのは必然である。ラビたちは、私と同じで、これを文字通りに捉えている。『歌を歌う娘たちはみなうなだれる』とは何か。これは、ユダヤ戦争の時期には悲惨な状況が訪れるので、娘たちも歌を歌っている場合ではなくなるということなのであろう。戦争の時期に喜ばしい歌を歌って楽しもうとする者がどこにいるであろうか。この部分は、黙示録18:22の部分と対応していると思われる。そこでは次のように言われている。『立琴をひく者、歌を歌う者、笛を吹く者、ラッパを鳴らす者の声は、もうおまえのうちに聞かれなくなる。』ラビの場合、これは老衰のゆえに歌手の声が囁きのように聞こえるようになることだと言っている(前同)。
【12:5】
『彼らはまた高い所を恐れ、道でおびえる。』
『彼らはまた高い所を恐れ』るとは、つまり携挙されなかった者のことであろう。携挙されなかった者たちは、空中に現れたキリストの所に引き上げられなかったのだから、自分がそこに引き上げられるには不適格だった者であるということを知らされ、恐れざるを得なかったはずである。何故なら、携挙されず地上に残されたということは、地獄行きを宣言されたのも同然だからである。ラビは、これが老人には「小塚でさえ、山々のうちでもっとも高く見える」ことだと解釈しているが(バビロニア・タルムード:シャバット篇 23章/ミシュナ6のゲマラ)、この解釈にはもっともらしさがない。何故なら、老人でなくても高い所を恐れる者は少なくないからである。その者たちが『道でおびえる』とは、携挙されなかったために地上の場所で恐れを抱くからである。キリストもマタイ24:30の箇所で言っておられるように、再臨の際に携挙されなかった者たちは、携挙されなかったので『悲しみ』を持つことになったのである。悲しんだのであれば、怯えるということにもなったはずである。しかし、携挙された者たちは、そうではなかった。すなわち彼らの場合、携挙されたので、高い所を恐れることもなければ道で怯えることもなかった。彼らは空中の場所に携挙されて、『いつまでも主とともにいることにな』(Ⅰテサロニケ4章17節)ったのだから、むしろ大きな喜びと感激を持つことが出来た。ラビは、これについて「彼が道を歩く時、彼は恐れを抱かせられる。」と言っている(前同)。これは携挙について考慮していないという点を除けば、私の理解と同じである。
『アーモンドの花は咲き、いなごはのろのろ歩き、ふうちょうぼくは花を開く。』
この箇所で言われているのは、アーモンドやフウチョウボクが花を付けたり、蝗がノロノロと歩いたりするのとは異なり、ユダヤの破滅は唐突に訪れるということであろう。文脈から考察すれば、このように捉えることが出来る。確かにユダヤの破滅は、突如として襲いかかって来たのであって、それは植物が緩やかに花を付けたり、蝗が少しずつ進むようではなかった。実際、キリストもユダヤの破滅は突然訪れると言っておられる。『あなたがたの心が、放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日がわなのように、突然あなたがたに臨むことのないように、よく気をつけていなさい。』(ルカ21章34節)パウロも次のように言っている。『人々が「平和だ。安全だ。」と言っているそのようなときに、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが臨むようなもので、それをのがれることは決してできません。』(Ⅰテサロニケ5章3節)ラビの場合、「アーモンド」が尾骨、「いなご」が臀部、「ふうちょうぼく」が性欲であると解している(バビロニア・タルムード:シャバット篇 23章/ミシュナ6のゲマラ)。この解釈は、いかがなものかと私には思われる。
『だが、人は永遠の家へと歩いて行き、嘆く者たちが通りを歩き回る。』
『人は永遠の家へと歩いて行き』とは、携挙されて天で永遠に住まうようになった幸いな者たちのことであると思われる。キリストが天に昇られたのは、再臨の際に聖徒たちを天の『住まい』に導き入れるために、準備をしに行くためであった(ヨハネ14:2~4)。この『住まい』が、ここでは『永遠の家』と言われているのであろう。というのも、天の『住まい』とは、永遠に住むことになる家に他ならないからである。ラビはこれが「すべての義人が彼の栄誉にふさわしい住まいが与えられること」(バビロニア・タルムード:シャバット篇 23章/ミシュナ6のゲマラ)と解釈しているが、これは私の解釈と同じである。『嘆く者たちが通りを歩き回る』とは、携挙されなかった者たちが地上で狼狽えるということだと思われる。彼らが携挙されなかったので嘆いたのは想像するに容易い。そのように嘆いたのであれば、自然と通りを歩き回ることにもなる。何故なら、人は極度の嘆きに沈み込むと、混乱したり思考が働かなくなったりして、意味もなくうろつき回るものだからである。実際、大きな借金を負ってもうどうしようもなくなった人などは、どうしていいか分からず、街をとぼとぼと歩き回るものである。
【12:6】
『こうしてついに、銀のひもは切れ、金の器は打ち砕かれ、水がめは泉のかたわらで砕かれ、滑車が井戸のそばでこわされる。』
『こうしてついに』とは、遂にユダヤの終わりに至った、ということであろう。すなわち、これは紀元70年のことであると思われる。『銀のひもは切れ』とは何か。これは、少し後に書かれている『泉のかたわら』にある『水がめ』と関わっていると思われる。すなわち、泉の傍にある水瓶に繋がれている銀の紐が切れてしまう。これは、つまりユダヤからは水の恵みさえ取り去られるということなのであろう。実際、ユダヤ戦争の際には多くのユダヤ人が死んだので、彼らからは水の恵みが奪い去れらた。ラビたちは、この『銀のひも』を脊髄として解している(バビロニア・タルムード:シャバット篇 23章/ミシュナ5のゲマラ)。これはもっともらしく感じられなくもないが、大いに検討を要する。『金の器は打ち砕かれ』とは何か。先に見た『銀のひも』が『水がめ』に関わっているのであれば、この『金の器』は『滑車』に関わっていると考えられる。そのように考えると、これはユダヤからは井戸から『金の器』により汲み上げる水さえも取り去られるということなのだと思われる。つまり、これも先に見た『銀のひも』と同じことを言っているということである。ラビたちは、この『金の器』を陰茎として捉えている(前同)。この解釈は堅固なところがない。『水がめは泉のかたわらで砕かれ』とは、既に述べた説明から理解できる。その水瓶を砕いたのはローマ兵であった。ラビによれば、この水瓶は「胃」だが(前同)、この見解はいかがなものかと思われる。『滑車が井戸のそばでこわされる』という部分も、既に述べた説明から容易に理解できる。この滑車が壊されたのは、ローマ兵を通してもたらされた神の裁きによった。ラビの場合、これは「胃」また「排泄物」への言及として捉えるが(前同)、私はこの見解に賛成しない。
第24章 22:雅歌
雅歌は、考究しなくても問題はない。★は1つである。
第25章 23:イザヤ書
イザヤ書は大いに心を傾けられる必要がある。この文書を研究しないことは許されない。何故なら、イザヤ書の中では、再臨のことが豊かに啓示されているからである。この文書は「再臨について学ぶべき書」と言ってもよいぐらいである。ヨハネも、黙示録の中の多くの箇所で、この文書から表現や内容を引っ張ってきている。キリストも、イザヤ書に基づいて、御自身の再臨に関する事柄をお語りになった。ヨハネとキリストも、この文書を読んで、再臨について思いを傾けたのである。聖書では、このイザヤ書から、再臨の預言が惜しげもなく語られるようになる。先にも述べたように、再臨は詩篇、すなわちダビデの時期から啓示されるようになったが、預言者の時代になるまでは、まだ少しだけしか示されていなかった。我々人間は、何でも最初は少しずつ、ゆっくりと事を始めるものである。神も再臨を示される際には、そのように少しずつ始められたのである。
【2:2】
『終わりの日に、主の家の山は、山々の頂に堅く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れて来る。』
『終わりの日』とは、「ユダヤの終わる日が近づくと」という意味である。つまり、これは紀元1世紀のことを言っている。この『終わりの日』を、カルヴァンもアウグスティヌスも、新約時代の全体だと捉えていた。これはキリストが現われてから再臨までの全期間を言っていると。しかし、読者はもうお分かりであろう。この2人の理解は間違っていた。何故なら、もう既に再臨は起きているからだ。それゆえ、既に『終わりの日』は過ぎ去っている。確かに終わりの期間は、再臨が起きて新しい世界が始まるまでである。だから、この期間は既に終わっているのだ。だが、聖徒たちは注意せねばならない。ここで言われているのは、単にユダヤの終わる日が近づけば一体どうなるのか、ということに過ぎない。だから、終わりの日が終わったからといって、ここで言われていることが全て実現されなくなったというわけではない。言うまでもなく、ここで言われているのは、終わりの日が過ぎて新しい世界になってからも実現され続ける出来事である。というのも、この箇所では全ての時代に言える普遍的な事柄が示されているからである。
『主の家の山』とは、神の御国また教会を言っている。何故なら、神の家である聖所はシオンの山にあったからである。それゆえ、聖書では神の国を示すために「家」とか「山」といった言葉が使われている。多くの箇所では、このうち一つだけ使われている場合が多いが、ここでは2つとも使われている。
『山々の頂に堅く立ち、丘々よりもそびえ立ち』とは、どういった意味なのか。これは神の国が、全ての山々の頂点に位置していると言うことで、神の国の壮大さを示している。それというのも、神の国である山よりも優った山は存在しないからである。また、ここでは神の国があらゆる丘々よりもそびえ立つと言って、神の国の力強さ・雄々しさを示している。何故なら、神の国よりも猛々しい丘などは存在しないからである。要するに、この部分では比喩表現が使われている。神は御自身の国の圧倒的な素晴らしさを示すために、このようにして地上の事物を例えとして持ち出しておられる。それだから、この部分で言われているのが物理的なことだと考えないようにせねばならない。この部分は霊的に捉えるべきなのだ。我々が既に知っている通り、神の国とは物質的な国ではなく霊の国なのである。
つまり、この箇所で言われているのは、こういうことである。すなわち、ユダヤが終わる時期になると、諸国の民が、偉大なる神の国の中に入るようになる、と。『すべての国々』とは、ユダヤ人以外の異邦の民たちという意味である。『流れて来る』と書かれているのは、諸国の民が御国に入って来る様を川の流れに例えている。確かに使徒たちが全世界に伝道をすると、実際にその通りとなった。次から次へと異邦人が神の国の一員となったのである。
我々は、この箇所では携挙について言われているのではないという点に気を付けねばならない。ここでは、あらゆる国の民族が神のところに集まって来る、と言われている。だから、この箇所を読んで携挙の出来事が言われていると思う人もいるかもしれない。何故なら、携挙の出来事においても、あらゆる国の民族が神のところに集められるからである。だが、ここでは携挙の出来事ではなく救いのことが言われている。旧約聖書には、特に預言書がそうだが、携挙について言われているようにも救いのことについて言われているようにも感じられる箇所が少なからず見られる。そのような箇所に出会った際、そこで言われているのが携挙のことなのか救いが全世界に押し広げられることなのか、我々はよく見極めなければいけない。というのも、携挙について言われている箇所を御国が世界中に広まることについて言われていると理解したり、その逆に御国が世界中に広まることについて言われている箇所を携挙について言われていると理解するのは、悲惨だからである。
【2:3】
『多くの民が来て言う。「さあ、主の山、ヤコブの神の家に上ろう。』
ここでは、あらゆる国の民族が新約時代になると神の国を求めるようになる、ということが言われている。『多くの民』とは、旧約時代には御国から完全に除外されていた異邦人のことを指している。『来て』とは神の御許に行く、という意味である。
『主の山』とは、先に述べたように神の国を言っている。『ヤコブの神の家』も、神の国のことである。こちらのほうは、アブラハムにおいて与えられた神の契約が想起されるような言い方である。つまり、この箇所では、「神の国」と2回続けて言われていることになる。このような繰り返しは古代ユダヤ人の特性であった。
『主はご自分の道を、私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。」』
主が教えて下さる『ご自分の道』とは何なのか。これは、「天の教え」または「救いの教説」を指している。それというのも、神の道とは天的であって人を救いに至らせるものだからである。一言で言えば、これは<福音>のことを言っている。
選ばれていた者たちは、ここで『私たちはその小道を歩もう。』と言っている。「小道」と言われているのは、彼らの遜った姿勢を示している。何故なら、遜ることなしに神の道に歩むことは出来ないからである。高ぶっていれば強制的に神の道から弾き飛ばされる。聖書が「神は高ぶる者に敵対される。」と教えている通りである。これは、ちょうどダビデがアビガイルを妻として迎えようとした時に、アビガイルが『まあ。このはしためは、ご主人さまのしもべたちの足を洗う女奴隷となりましょう。』(Ⅰサムエル25章41節)と言ったのと似ている。アビガイルがこう言うことで、彼女の謙虚さが豊かに示されたのである。我々も偉大な王族から素晴らしい任務を任されたとしたら、たぶん「このように小さき者であるこの私などに、そのような任務を任せていだたくのは、誠に恐れ入るばかりでございます。しかし閣下が私めにお任せくださいました以上、つまらない僕である私めは命をかけて事に当たらせていただきたく思っております。」などと遜った態度で対応するかもしれない。この箇所で選ばれた者たちが『その小道を歩もう。』と言っているのは、我々が王族に対してこのように言うようなものである。このような謙遜さについて考えると、アウグスティヌスの言葉が思い出される。彼はキリスト者の要件は何かという問いに対して次のように言った。「それは第一に謙遜であり、第二に謙遜であり、第三に謙遜である」と。
この箇所で言われていることは実際に実現されている。今や異邦人たちは、神の道に導かれ、その小道を謙虚に歩んでいる。つまり、イエス・キリストという神に至る真の道であられる御方を(ヨハネ14:6)、素直に信じている。あの国の民族も、この国の民族も、どの国の民族も、である。古代ユダヤ人たちの場合はそうではなく、実に高慢であって、神に対して逆らってばかりいたのであった。
『それは、シオンからみおしえが出、エルサレムから主のことばが出るからだ。』
ここでは、エルサレムから福音が全世界に満ち広がる、ということを言っている。『シオン』と『エルサレム』という言葉の説明は不要である。『みおしえ』と『主のことば』とは、キリストの福音である。キリストも、昇天する前に、次のように言って、このことを確認なされた。『次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって、罪の赦しを得させる悔い改めが、エルサレムから始まってあらゆる国の人々に宣べ伝えられる。』(ルカ24章46~47節)これは既に実現されている。今から2千年前にエルサレムから福音が全世界に広がり、今も福音は世界中で宣べ伝えられている。我々が信じている福音は「エルサレム発」なのである。
この箇所では、同じことが2回繰り返して言われている。すなわち、「エルサレムから福音が拡がる」ということが2度言われている。これは強調であるから、かなり重要であることを示している。
しかし、どうして福音はエルサレムから発出せねばならなかったのか。それはエルサレムに神の聖所が置かれていたからである。聖所の置かれていた場所から聖なる福音が広まる、ということの合理性を疑う人がいるのか。恐らくいないはずである。例えば、アメリカ大統領の話は、大統領のいるアメリカから出るはずである。トヨタの最新ニュースは、トヨタの本社がある日本から出るはずである。ビートルズの音楽はそのメンバーの国であるイギリスから、マイケル・ジャクソンの音楽は彼の国であるアメリカから全世界に広がった。福音が聖所のあったエルサレムから広まったのも、これと同じである。だから、もし福音がエルサレムから発出しなかったとすれば、それはおかしい。何故なら、その場合、理に適っていないからである。もしそうだとすれば、それはアメリカ大統領の話が何故かインドから出たり、トヨタのニュースがいつもブラジルから流れてきたり、ビートルズやマイケル・ジャクソンの音楽が常にニュージーランドを基点にして発表・発売されるようなものだ。
【2:4】
『主は国々の間をさばき、多くの国々の民に、判決を下す。』
ここでは、神と人との間に霊的な和解が成立するということが言われている。その和解は、世界中に宣べ伝えられた福音において示されたイエス・キリストに基づく。このキリストによる和解は、あたかも裁判において致命的だった問題が一挙に解決されるかのようである。だから、ここでは裁判の例えが使われている。従って、ここで言われているのは良いことである。ここでは裁判について言われているものの、それは不幸なことを意味していない。
ここでも、2回の繰り返しがされている。すなわち、ここでは「主が諸国の民との間における裁判において霊的な問題に決着をつける。」ということが2度言われている。これも先の場合と同じで強調だから、かなり重要であるということを意味している。
この箇所では、裁判について言われているから、空中の大審判について言われていると思われる方もいるかもしれない。確かに空中の大審判でも、審判と判決とが行なわれた。だが、ここで言われているのは救いにおいて実現される問題解決と平和のことである。これは文脈を考えれば明らかであろう。我々は間違わないように注意せねばならない。
『彼らはその剣を鋤に、その槍をかまに打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。』
ここで言われているのは、神と人との間に平和が成立したことを示す比喩である。つまり、この箇所は霊的に捉えねばならない。キリストにおいて神と人とに和解が起こるまで、人は神に対して武器を取っており、神も人に対して武器を捨てることはなさらない。だが人がキリストにおいて神と平和を得ると、両者ともその手に持っている武器を放棄する。これは敵対し合っていた2つの国が、和解して同盟国となるようなものである。だから、ここでは『国は国に向かって剣を上げず』と言われている。我々には、この平和が既にキリストにおいて実現している。パウロが次のように言った通りである。『ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって、神との平和を持っています。』(ローマ5章1節)
神と和解していない全ての人間は、未だに神と交戦状態にあり、そのままでは御怒りによる滅びに至る。パウロは救われる以前のエペソ人について、こう言っている。『私たちもみな、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行ない、ほかの人たちと同じように、生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。』(エペソ2章3節)今でも、実に多くの人たちが、このような交戦状態を神に対して持っている。このため、彼らは、最後まで神と和解しないでいるならば、その生涯の終わりに滅ぼされて永遠の地獄へと投げ込まれるのである。それは、ある国が、自分と戦っている国を最後には打ち滅ぼしてしまうのと同じである。我々は、既にキリストにおいて神と和解しており、もはや神との交戦状態はない。それゆえ、我々は滅びの子らのように滅ぼされるということもない。我々は、このような救いを実現させて下さった神に、キリストにおいて永遠に感謝せねばならないのである。キリストは今から2千年前に永遠の贖いを実現され、あらゆる国の民族が神の国に入れるようにして下さった。このため、信じる者たちは、キリストにおいて神と和らぐことが出来るのである。教会は、この聖なる救いを豊かに宣べ伝えて行かねばならない。このような救いが宣べ伝えられなくても別によい、ということは絶対ないのである。
【2:5】
『来たれ。ヤコブの家よ。私たちも主の光に歩もう。』
『ヤコブの家』とはユダヤ人を指す。これは、ヤコブに連なる子孫たち、という意味である。『主の光』とは、「天の教え」また「救いの教理」を指す。それというのも、天から啓示される救いの教説は、我々人間を明るく照らす光だからである。この救いの光なしには、我々はただただ闇なのである。『歩もう』とは「信じよう」とか「受け入れようではないか」といった意味である。
つまり、ここで言われているのは、堕落していたユダヤ人たちがしっかりと御前に根差した歩みをして永遠の救いに至るように、ということである。これは文脈を考えても分かる。すぐに続く箇所(2:6~9)では、ユダヤ人たちの背教があからさまに指摘されている。そのすぐ前の箇所(2:5)で、我々が今見ている通り、ユダヤ人たちに主の光に来るようにと言われているのだ。それゆえ、この箇所では、愚かになっていたユダヤ人たちが神に立ち返って御民として相応しい歩みをするようにと言われていることになる。
【2:10】
『岩の間にはいり、ちりの中に身を隠せ。主の恐るべき御顔を避け、そのご威光の輝きを避けて。』
ここから2:22までの箇所で言われているのは再臨に関する預言である。それゆえ、この箇所を無視することは許されない。少なくとも本書においてはそうである。
キリストが再臨された時、その御顔は恐ろしく、その御威光は凄まじかった。それは人の精神の耐えうるものではなかった。ヨハネやダニエルも、キリストを見た際には耐えられずに気絶してしまった。イザヤも主の栄光を見た時に絶望してしまった。主の御顔と御威光とは、これほどまでに凄まじいのである。だから、再臨の際には『岩の間にはいり、ちりの中に身を隠』すようにと人々に対して言われている。そうでもしないと、耐えられず、精神がどうにかなってしまうからである。これは、陽が非常に強い時に日傘をさすように命じるのと似ている。もし日傘をささなければ、太陽の熱に耐えられず、熱中症で倒れてしまいかねないのである。
この箇所の内容は、明らかに黙示録6:15~17の箇所と対応している。そこでもキリストの再臨が起きた時には人々が岩などを隠れ場にしている様が語られている。すなわち、こうである。『地上の王、高官、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が、ほら穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。「私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と小羊の怒りとから、私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。だれがそれに耐えられよう。」』
【2:11】
『その日には、高ぶる者の目も低くされ、高慢な者もかがめられ、主おひとりだけが高められる。』
『その日』とは再臨が起こる日である。何故なら、ここでは再臨について語られているのだから。
再臨が起きた際には、キリストの凄まじさの前で、全ての高慢が無効とされた。何故なら、キリストの御顔と御威光があまりにも凄まじいので、その前で人の高ぶりが打ち砕かれてしまったからである。だから、再臨の起こる日には『高ぶる者の目も低くされ、高慢な者もかがめられ』ると言われている。これを何かに例えるならば、その地域で最強のボス的な不良少年である。この不良少年はその地域で最も強いので高ぶっており、誰も自分に勝てる者などいないと本気で思い込んでいる。ところが、この少年の前にマイク・タイソンやヒョードルが現われて威嚇でもするならば、少年の高ぶりは一挙に打ち砕かれ、大いに動揺して縮こまざるを得なくさせられるのである。この例えにおいてタイソンやヒョードルはキリストであり、不良少年は高ぶった人間である。つまりキリストが再臨された際、そのキリストを見た高慢な者たちは、自分などは何でもないと思わされた。そして、ここにおいて『主おひとりだけが高められる』ことになったのである。
【2:12】
『まことに、万軍の主の日は、すべておごり高ぶる者、すべて誇る者に襲いかかり、これを低くする。』
キリストの再臨は、高ぶる者たちの高ぶりをことごとく打ち砕いてしまった。これは既に説明されているから、再び説明する必要はない。
【2:13~16】
『高くそびえるレバノンのすべての杉の木と、バシャンのすべての樫の木、すべての高い山々と、すべてのそびえる峰々、すべてのそそり立つやぐらと、堅固な城壁、タルシシュのすべての船、すべての慕わしい船に襲いかかる。』
ここでは再臨されたキリストの凄まじさが全てを低めることについて、詳しく語られている。まず再臨の時には『高くそびえるレバノンのすべての杉の木と、バシャンのすべての樫の木』が低められた。これは、レバノンの杉の木とバシャンの樫の木のように力強い者たちも、キリストの御前で低められた、という意味である。つまり、これは木について何かが述べられているのではない。また『すべての高い山々と、すべてのそびえる峰々』も低められた。これは山々や峰々のように平常であれば揺るがされない者たちも、キリストの御前では揺るがされたことを示している。これも、山や峰について何かを述べているわけではない。また『すべてのそそり立つやぐらと、堅固な城壁』にもキリストの再臨は襲いかかった。つまり、再臨されたキリストの御前では、どのような櫓や城壁も拠り頼むべき誇りとするには全く足らなかった。どれだけ素晴らしい堅固な櫓や城壁があっても、人々はキリストの凄まじさに圧倒されるしかなったわけである。また『タルシシュのすべての船、すべての慕わしい船』にもキリストの再臨は襲いかかった。これは、船に乗る高ぶった商人たちも低められたことを言っている。
【2:17】
『その日には、高ぶる者はかがめられ、高慢な者は低くされ、主おひとりだけが高められる。』
これは先に見た2:11の箇所とほとんど一緒の内容だから、ここで再び註解する必要はない。
【2:18】
『偽りの神々は消えうせる。』
キリストが再臨された時、偽りの神々は無と化した。何故なら、その時、キリストこそ真の神に他ならないということが明らかに感じられたからである。キリストこそ真の神に他ならないというのであれば、必然的にこの世で神と呼ばれる神々は偽りの存在であるということになる。ここで『偽りの神々は消えうせる。』と言われているのは、このような意味である。また、この箇所は普遍的な意味として理解することもできる。つまり、この地上に見られる偽りの神々はどれも消え去る運命にある。実際、バビロンの神々もギリシャの神々も、今となっては完全に消え失せている。現在において見られる偽りの神々も、やがてこれから消え失せることになるであろう。つまり、歴史はこのようになるのだ。偽りの神々が現われては消え去り、現われては消え去り、現われては消え去る、と。神は、永遠に偽りの神々を消され続ける。それというのも神は永遠に同じことをなされるからである。それは、伝道者の書3:14~15の箇所を見れば分かることである。
【2:19】
『主が立ち上がり、地をおののかせるとき、人々は主の恐るべき御顔を避け、ご威光の輝きを避けて、岩のほら穴や、土の穴にはいる。』
キリストが再臨された時、その御顔の恐ろしさと御威光の輝きが凄まじかったので、人々は耐えられずに『岩のほら穴や、土の穴にはい』った。この神の御前では、セラフィムでさえ恥じ入って自分の身を隠さねばならないほどである(イザヤ6章)。であれば、罪深い人間は尚のこと、隠れねばならないと感じるのである。実際、キリストがオリーブ山の上空に降りて来られた際、そこにいたローマ兵たちは岩の穴や土の穴に逃げ込んだはずである。凄まじい力をもって到来されたキリストを前にして、どうして隠れないまま平気な状態でいられたということがあるだろうか。この箇所の内容は、先に見た2:10の箇所と共通している。
【2:20】
『その日、人は、拝むために造った銀の偽りの神々と金の偽りの神々を、もぐらや、こうもりに投げやる。』
『その日』とは再臨が起きた日である。
再臨が起こると、真の神であられるイエス・キリストが現われたので、偽りの神々は偽りの存在であることが明らかにされた。その時、人は偽りの神々を虚しく感じた。偽りの神々がモグラやコウモリに投げやられたとは、このような意味である。つまり、『もぐらや、こうもりに投げやる。』とは実際的なことを言っているのではない。これは表現である。なお、ここで言われている『こうもり』は申命記14:18の箇所で汚れた動物とされている。
ここで偽りの神々が価値のない動物に投げやられると言われているのは、前に見た2:18の箇所で『偽りの神々は消えうせる。』と言われていたのと対応している。つまり、その時に『人は、拝むために造った銀の偽りの神々と金の偽りの神々を、もぐらや、こうもりに投げやる』からこそ、『偽りの神々は消えうせる』ことになったのだ。確かに偽りの神々が動物に投げやられたのであれば、その存在は消え去ったも同然である。それというのも、モグラやコウモリに与えられる神々などは一体なんであろうか。ただの「無」、または糞以下の存在に過ぎないのではないか。
【2:21】
『主が立ち上がり、地をおののかせるとき、人々は主の恐るべき御顔を避け、ご威光の輝きを避けて、岩の割れ目、巌の裂け目にはいる。』
この箇所は、先に見た2:19の箇所とほとんど一緒の内容である。相違点は、人々が逃げ隠れる場所の表現だけである。それは些細な違いであって、どちらも言われていることは同じである。つまり、2:19では『岩のほら穴や、土の穴』と言われていたのが、こちらでは『岩の割れ目、巌の裂け目』と言われているだけに過ぎない。これは2:19から続く繰り返しの内容だから、要するに強調表現である。聖書は、このように同じ内容を繰り返すことで、事柄を大いに伝え知らせようとしているのだ。
【2:22】
『鼻で息をする人間をたよりにするな。そんな者に、何の値打うちがあろうか。』
再臨が起きた時、『鼻で息をする人間をたよりに』しても無意味であった。何故なら、人に頼っても、神の御怒りを回避することは出来ないからである。例えば、当時の人たちがローマ皇帝に頼ったとしよう。皇帝は人々を神の怒りから免れされることができたか。皇帝にそのような力はなかった。また、パウロに人々が頼ったとしよう。パウロも神の御怒りから人々を守ることは出来なかった。何故なら、パウロに救いはなく、パウロの宣べ伝えているイエス・キリストに救いがあるのだから。これは皇帝やパウロ以外の被造物でも一緒である。つまり、人に過ぎない存在に救いはないのである。だから、詩篇ではこう言われている。『君主たちにたよってはならない。救いのない人間の子に。その息が絶えると、その者はおのれの土に帰り、その日のうちに彼のもろもろの計画は滅びうせる。幸いなことよ。ヤコブの神を助けとし、その神、主に望みを置く者は。』(146:3~5)エレミヤ17:5~7の箇所でも次のように言われている。『主はこう仰せられる。「人間に信頼し、肉を自分の腕とし、心が主から離れる者はのろわれよ。そのような者は荒地のむろの木のように、しあわせが訪れても会うことはなく、荒野の溶岩地帯、住む者のない塩地に住む。主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように。』
ここで『そんな者に、何の値打ちがあろうか。』と言われているのは真実である。何故なら、人間とはただの被造物、しかも罪深い小さな被造物に過ぎないのだから。アブラハムは主の前で自分が『ちりや灰』(創世記18章27節)であると言った。人間とは土の塵により造られたに過ぎない矮小な存在なのである。ヨブ記25:6の箇所では、『うじである人間、虫けらの人の子』と言われている。我々は、蛆や虫と同然の価値しか持たない存在なのである。イザヤ40:6の箇所では『すべての人は草』と書かれている。だから、我々は無価値な草が枯れるように枯れるのである。ヤコブも人が『霧』(ヤコブ4章14節)に過ぎないと言っている。確かに我々は霧がすぐにも消え去るように、すぐに消え去るのである。このように、聖書全体が人間に価値はないと示している。しかし、イザヤ書43:4の箇所では神が聖徒たちにこう言っておられる。『わたしの目には、あなたは高価で尊い。』この御言葉は真理である。それは偽りではない。ではどういうことになるのか。人間には価値がないと言われている諸々の聖句と、このイザヤ43:4の聖句で言われていることは、どのように調和するのか。一方では人間に価値がないと言われ、一方では価値があると言われている。これは矛盾しているのではないのか。解決は簡単である。イザヤ43:4の箇所で聖徒が価値高いと言われているのは、聖徒たちの存在そのものに価値があるという意味ではない。つまり、神は、ただイエス・キリストのゆえに聖徒たちを価値ある存在として見做して下さっておられる、ということである。このイザヤ43:4の箇所は私が今言ったように解釈すべきである。何故なら、聖書の無数の箇所では人間に価値がないと明白に言われているからである。もし人間の存在が本当の意味で価値高いというのであれば、聖書の多くの箇所で人間が無価値であると言われてはいなかったはずである。
この箇所では救いにおいて人間に頼るな、と言われている。何故なら、既に述べたように、人間に過ぎない存在に救いはないからである。つまり、ここでは日常生活において人に頼ってはならないと言われているわけではない。もし日常生活でも人に頼るべきではないとすれば、我々の人生は滅茶滅茶になってしまう。例えば、上司が部下に何かの仕事を任せたり、配達員に配達をお願いしたり、子どもを買い物に行かせたりする、ということが全く出来なくなる。キリストも、弟子たちに何かを買いに行かせることは出来なかったであろう。もし日常でも人に頼ってはならないというのであれば、の話である。もしそのようにせねばならないとすれば、我々は人間ではなくなってしまう。つまり、理性のない獣も同然になる。だから、ここでは日常生活における規範が語られているというわけではないのだ。もし日常でも人に信頼すべきではないとすれば、我々は愛のない存在になってしまう。それというのも、パウロが言ったように愛とは『すべてを信じ、すべてを期待』(Ⅰコリント13:7)するということだから。
【6:1】
『ウジヤ王が死んだ年に、私は、高くあげられた王座に座しておられる主を見た。』
ユダ王国を統治していた『ウジヤ王が死んだ年』は紀元前740年頃である。この時にはまだイスラエル王国が陥落していなかった。
イザヤは『高くあげられた王座に座しておられる主を見た』。これはイエス・キリストである。キリストが高くされた王座に座しておられたのは、キリストの権威と卓越性を示すためである。何故なら、上とは下を凌駕した場所だからである。この理由から、昔の王たちは往々にしてその王座を一段と高い場所に設けたのである。エゼキエルも、キリストが高き場所におられる光景を見た(エゼキエル1:26~28)。このエゼキエル書に書かれていることについては、また後ほど註解される。
イザヤはどうして、このような神的光景を見せられたのか。それには2つの理由があった。一つ目は、聖徒たちへの啓示のためである。神は、このように御自身をイザヤに示されることで、聖徒たちが神についてより多くのことを知れるようにされた。二つ目はイザヤの権威を高めるためである。イザヤがこのような聖なる光景を見せられたとなれば、御民はイザヤが文書として書いたことを、またイザヤが自分の口で語った預言を蔑ろにするわけにはいかなくなるのだ。何故なら、このような光景を見せられる人は、神に祝福された預言者に違いないと分かるからである。
【6:1~2】
『そのすそは神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。』
『そのすそは神殿に満ち』。これはキリストが神殿の主・支配者であられることを示す。『すそ』とはキリストの一部であり、それが神殿を覆っているのだから。
『セラフィムがその上に立っていた』。『その上』とは「どの上」なのか。それは「神殿の上」である。つまり、これは「主の上」ではない。そうだとすれば、セラフィムがキリストよりも存在的に格上だということになるであろう。だが、セラフィムはキリストの御手により造られた単なる被造物に過ぎない。
このセラフィムは、既に第3部で見たように、黙示録に出てくる4つの生き物である。ヨハネは、このイザヤ書に出てくるのと同じ御使いについて書き記した。つまり、神がイザヤに見せられたセラフィムと同様のセラフィムをヨハネにも見せられたのである。しかしヨハネはこのセラフィムをそのままの名前で呼んでおらず、『4つの生き物』と曖昧な言い方で呼んだ。ヨハネがこのようにしたのは、黙示録を秘儀の書物たらしめんがためであった。ヨハネは、その生き物がセラフィムであることを知っていながら、あえてその名前を示さなかったのである。このセラフィムとは「熾天使」という意味である。聖書の中では、この箇所と黙示録にしか出て来ない。このセラフィムが書かれているからこそ、私はこのイザヤ6:1~7の箇所を註解せねばならないのである。何故なら、このセラフィムは黙示録を理解するためには是非とも深く知っておくべき存在だからである。もしセラフィムが書かれていなければ、私がこの箇所を註解していたかどうかは分からない。
このセラフィムはエゼキエル書に出てくる生き物ではないことに注意せねばならない。エゼキエル書に出てくるのはケルビムである。セラフィムとケルビムはよく似ているように感じられるが、色々な点で実はかなり異なっている。だから、この2種類の御使いを混同してしまわないようにすべきである。
【6:2】
『彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔をおおい、2つで両足をおおい、2つで飛んでおり、』
『それぞれ』と書かれているのは、セラフィムが複数いたからである。既に見た通り、黙示録では4人いたと教えられている。イザヤはここでセラフィムの数については触れていない。これは単に触れていないだけに過ぎない。イザヤが見ていたセラフィムも、ヨハネが見たのと同様、4人いたことは間違いない。では、どうして神はイザヤにセラフィムの数を書き記させなかったのか。これは御民の教育のためである。神は、黙示録と併せてイザヤ書を読むことにより、セラフィムについて深い知識を持てるようにされた。それは我々が霊的な怠惰を貪らないために役立つ。あれもこれも同じ一つの箇所に書かれていれば、我々はそれだけ聖書を調べなくなり、霊的に怠惰になるだろうからである。それゆえ、黙示録を読んで初めて、このイザヤ書に出てくるセラフィムが4人であったと分かるのである。では、セラフィムが「4」人であったことに何か象徴的な意味はあるのか。このセラフィムは神の『御座の回り』(黙示録4章6節)、すなわち東と西と北と南とにいた。4は聖書において世界また全体を意味している。つまり、セラフィムが4人いたのは、セラフィムが神の回りの全体部分に満遍なく位置していたことを意味している。
このセラフィムには『6つの翼があ』った。すなわち、右側と左側にそれぞれ3枚ずつの翼があった。この翼が生えていた部位は恐らく背中の上のほうである。何故なら、その部位が自然だからである。翼が肩の部位に生えていたというのは考えにくい。何故なら、それは不自然に思えるからである。我々人間の背中には、翼が生えるのには調度良い部位がある。肩甲骨のある部位である。肩もやや連動してしまうが、この部位はほとんど独立的に左右に動かすことが出来る。もしそこに翼が生えていたら、飛べそうな感じがする。一度、自分の身体で試してみるとよい。セラフィムの翼は、この部位に生えていたのであろう。セラフィムも我々人間と同様、神の似姿であり、神の子らである。だから、我々の身体で翼が生えていたら調度良い部位に、セラフィムの翼が生えていたとしても何も不思議ではない。そのうち2つは『顔をおお』っていた。これは、セラフィムでさえ神の御前では清くなく、矮小な存在だからである。聖書ではこう言われている。『見よ。神はご自分のしもべさえ信頼せず、その御使いたちにさえ誤りを認められる。』(ヨブ4章18節)つまり、セラフィムは神の御前で恥じ入っていたわけである。これは例えるならば、ゴルフのアマチュア王者が、タイガー・ウッズと出会うようなものである。アマチュアの世界では輝いていた王者も、タイガーの前ではうつむきがちになってしまう。何故なら、タイガーに比べれば自分など何でもないと思うからである。別の2つは『両足をおお』っていた。これも、顔を覆っていたのと同様の理由による。残りの2つは飛行用に使われていた。これは恐らく上か真ん中の翼であろう。何故なら、その位置が自然だと思えるからだ。一番下の2つの翼で飛んでいたとは考えにくい。それは、あまり自然ではないように思えるからである。ところで、4枚の翼で顔と両足を覆っていたのであれば、その真ん中の部分である胸と腹の部分はどうなっていたのか。その部分はがら空きになってしまわないのか。恐らく、顔と両足を覆うだけで胸と腹の部分も一緒に覆うことが出来たのだと思われる。つまり、それほど翼の面積が大きかったということだ。だが実際はどうであったか我々には分からない。もしかしたら胸と腹は覆われていなかったということもあり得る。この翼は、黙示録4:8の箇所によれば『その回りも内側も目で満ちていた』。これはセラフィムが大いに神の栄光を見て、大いに神の栄光を称えるためである。大いに神の栄光を見るからこそ、大いに神の栄光を称えられるようにもなるのだ。もし少ししか見なければ、少ししか称えられないであろう。セラフィムの持つこの「6」つの翼には、数字的な象徴の意味がこめられているのか。聖書において「6」は人間や不完全であることを意味している。セラフィムは人間ではないから、もし翼の枚数に意味があるとすれば「不完全」という意味である。つまり、セラフィムは神によらねば存在すら出来ず、また何一つ出来ない、ということである。だが、この翼の枚数に本当にこのような意味がこめられているのかどうかは定かでない。
ケルビムの場合、その翼の数は4つである。このケルビムの翼にも、目が多く付いていた(エゼキエル10:12)。このケルビムとその翼については、また後ほどエゼキエル書の註解において述べられる。
【6:3】
『互いに呼びかわして言っていた。「聖なる、聖なる、聖なる、万軍の主。その栄光は全地に満つ。」』
4人のセラフィムたちは、神の栄光を互いに呼び交わしつつ称えていた。口の本来的な意味は神の栄光をたたえることである。何故なら、この世界にある全ては神の栄光のために造られたからである。だから、セラフィムは自分に与えられた口を正しい目的のために使っていたことになる。我々も、自分に与えられている口を、神の栄光を称えるために使わねばならない。そうするのは神に喜ばれることである。何故なら、我々がキリストの血により贖われて神の子とされたのは、我々の口が神の大いなる栄光を称えるためだったからである。パウロがエペソ1:4~6の箇所で言っている通りである。
『聖なる、聖なる、聖なる、万軍の主』。セラフィムは神について3回『聖なる』と言った。3回は聖書において強調や確認を意味している。つまり、セラフィムは神が聖であられることを強調して称えている。読者の中には、この3回の繰り返しが、神の3位格について言われていると捉える人もいるかもしれない。すなわち、ここでは「御父は聖であり、御子も聖であり、御霊も聖である」と言われていると捉える人である。私はこの捉え方を否定しない。何故なら、確かに3位格は均しく聖であられるからである。そのように捉えたい人は、そのように捉えていればよい。だが、今の私としては、これが強調のための繰り返しであると捉えたい。黙示録に出てくるセラフィムも、やはり同様のことを言っている。曰く、『聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。神であられる主、…』(黙示録4章8節)。黙示録の4つの生き物はイザヤ書6章に出てくるセラフィムと同様のことを言っているのだから、間違いなくセラフィムである。神は、このようにイザヤ書6章と併せて読むことで、黙示録の生き物が何であるか知れるようにして下さった。もしイザヤ書6章でこのようにセラフィムが言っていなければ、それだけ我々は黙示録に出てくる生き物が何なのか知りにくくなっていた。ところで、世の中にはこの黙示録の生き物がセラフィムではなくケルビムであると捉える者がいる。この者は明らかに研究不足である。
『その栄光は全地に満つ』。神の栄光は、この全宇宙、ことに地球上に満ちている。この『全地』とは宇宙世界を指している。これはユダヤにおける全地という意味ではない。美しい自然や宇宙における銀河団の輝きを見よ。そこには神の美の栄光が現わされている。古代の哲学者によりミクロコスモス(小宇宙)と言われた我々人間の身体を見よ。そこには神の巧みな構造と知性における栄光が現わされている。いかにも食べるに好ましいと思える実をならせる無数の木を見よ。そこには神の人類に対する慈愛の栄光が現わされている。小さなタンポポや哀れな小動物が損なわれることも殺されることもなく保たれ続けている様を見よ。そこには神の憐れみの栄光が現わされている。日々絶えることなく行なわれている悪者どもに対する裁きを見よ。そこには神の義なる審判者としての栄光が現わされている。神が悪者どもの悪行と呟きとにずっと耐え続けて裁きを延ばして下さっておられることを見よ。そこには神の忍耐における栄光が現わされている。正しい理解によれば、この世界はただ神の栄光のためだけに造られた。だから、この世界には神の栄光が満たされねばならない。もし世界に神の栄光が満たされなければ、世界はその造られた意味を無くす。このため、神はこの世界に御自身の栄光を様々な手段と生命体および無生物を通して現わされるのである。
ケルビムは、このセラフィムとは違い、何事かを口にすることはないと思われる。何故なら、聖書にはケルビムが喋っている箇所がないからである。もしかしたら、ケルビムも喋るのかもしれない。だが、聖書には書かれていないから、定かなことは言えない。しかし、もしケルビムが喋る存在であれば恐らく聖書にはそのことが書かれていただろうから、ケルビムは恐らく喋らない可能性が高いと考えるのが妥当である。
【6:4】
『その叫ぶ者の声のために、敷居の基はゆるぎ、宮は煙で満たされた。』
セラフィムは、神の栄光を称える際、叫んでいた。つまり、セラフィムの声は普通の声量ではなかった。これは神の栄光が非常に重要だったからである。重要であるからこそ、大声で叫ぶ必要が出てくるのだ。これは、ちょうど王などの権威者のために歌を歌う歌手が、心のこもった身振りや姿勢と共に大声で熱唱するのと同じである。その権威者が重要な存在であればあるほど、歌手は真剣に歌うものである。もしセラフィムの声が小さければ、神の栄光はあまり重要でないということになってしまう。
この大声により『敷居の基はゆる』いだ。つまり、それほどに大きな声量だったということだ。この『敷居』とは神殿におけるそれのことである。また、その神殿とは、もちろん石造りの神殿を指している。ここではクリスチャンという新約時代の神殿について言われているわけではない。
セラフィムが神の栄光を称えると、『宮は煙で満たされた』。この『煙』は神の栄光を表示している。聖書では、神の栄光が他にも『雲』として表示されている。イスラエル人が荒野にいた時、神の栄光が雲において幕屋に満たされた。このため、モーセはその雲が満ちている幕屋の中に入れなくなってしまったのであった。次のように書かれている通りである。『そのとき、雲は会見の天幕をおおい、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕にはいることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。』(出エジプト40章34~35節)神の栄光が煙や雲などにより表示されるのは理に適っている。何故なら、神の栄光とは人間の理性を越えており、把握し難く、非常に抽象的・神秘的だからである。このような神の栄光が煙や雲により現わされるのは実にピッタリである。
【6:5】
『そこで、私は言った。「ああ。私は、もうだめだ。私はくちびるの汚れた者で、くちびるの汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王を、この目で見たのだから。」』
イザヤは『万軍の主である王を、この目で見た』。これはイエス・キリストである。イザヤはキリストの栄光をその目で見たのだ。これは、ヨハネが福音書の中で書いている通りである(ヨハネ12:39~41)。
このキリストの栄光は圧倒的であった。だから、イザヤは絶望的にさせられてしまった。イザヤがそのようになったのは、2つの理由からである。まず一つ目の理由は、『私はくちびるの汚れた者で、くちびるの汚れた民の間に住んでいる』からである。つまり、罪深い口を持つユダヤ人の一人である自分が一体どうして栄光の主の御前に立つことが出来ようか…、ということである。イザヤがここで「口」の部位を挙げているのは注目に値する。これは、口こそが我々の存在において本質的な部位であることを意味している。ソロモンは口の言葉が全てを決すると言った。『死と生は舌に支配される。どちらかを愛して、人はその実を食べる。』(箴言18章21節)キリストもこう言われた。『あなたが正しいとされるのは、あなたのことばによるのであり、罪に定められるのも、あなたのことばによるのです。』(マタイ12章37節)この唇こそが、我々の倫理状態を左右し決定させる。だから、この部位は我々の身体における最も本質的な部位なのである。あの金持ちも全ての身体の部位のうち「舌」だけを冷やすように地獄で懇願した(ルカ16:24)。これも私が今述べたことの根拠である。己そのものを表明するための器官であるこの舌は、我々の存在における本体部分と言っても間違いではない。二つ目の理由は、イザヤが『万軍の主である王を、この目で見た』からである。イザヤは、主の栄光の前では自分など無に等しいと感じていたはずである。だから、もうどうしようもなくなり、『私は、もうだめだ。』などと絶望してしまったのである。
栄光の主を見ると、聖徒たちは気絶したり絶望したりするのが常である。何故なら、その栄光があまりにも凄まじいからである。ヨハネは栄光のキリストを見た時、『その足もとに倒れて死者のようになった』(黙示録1章17節)。ダニエルもキリストを見た際に力を喪失してしまった(ダニエル10:8~9)。イザヤも、ここで主を見た際に絶望的にさせられてしまった。聖徒たちがこのようになったのは当然であった。つまり、それだけ主の栄光は凄まじいのである。有名人や大スターを間近で見て失神してしまう女性がいる。熱狂的な支持を受けていたヒトラーを見たあるドイツ人女性は、あまりの精神的衝撃により気を失ってしまった。そこに性的な要素がないという点で違いはあるが、聖徒たちが栄光の主を見て普通の状態でいられなくなるのは、これと似ている。どちらも、把握できないほどの衝動を魂に受けたので、気がおかしくなってしまうのである。
イザヤでさえ、栄光の主を見た際にはこうなった。であれば、我々が見た場合はどうなるであろうか。イザヤという聖なる預言者でさえこうなったのであれば、イザヤなどには到底及ばない我々が主を見た際にはどうなるのか想像することさえ出来ない。多分、気を失うか、そうでなければ主と自分とにある無限の倫理的隔たりを感じて発狂してしまうのだと思われる。
【6:6~7】
『すると、私のもとに、セラフィムのひとりが飛んで来たが、その手には、祭壇の上から火ばさみで取った燃えさかる炭があった。彼は、私の口に触れて言った。「見よ。これがあなたのくちびるに触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪も贖われた。」』
イザヤは自分の罪深い口を大いに嘆いたが、セラフィムがやって来て、嘆いているイザヤの口に『燃えさかる炭』を触れさせた。この炭はイエス・キリストである。何故か。それは、『これがあなたのくちびるに触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪も贖われた』からである。人の不義・罪が消し去られるのは、イエス・キリスト以外にはよらない。ただキリストこそが人間を救って罪の中から解放させて下さる。これを信じない者はキリスト者ではない。それはペテロがこう言った通りである。「この方以外には、だれによっても救いはありません。世界中でこの御名のほかには、私たちが救われるべき名としては、どのような名も、人間に与えられていないからです。」(使徒の働き4:12)だから、この炭はキリスト以外としては解せない。もしキリスト以外の存在として解せば、キリストの他にもう一つの救い主を捏造することになってしまう。もっとも、キリストが炭そのものであられるというわけではない。というのもキリストは炭ではなくて人間であられるからである。つまり、この炭とは単なる象徴に過ぎない。これが分からない人がいるのであろうか。誰もいないはずである。ところで、この炭の詳細、すなわち形状や印象や由来などについて知りたいと願う人がいるのであろうか。いるかどうかは分からないが、これは詮索すべき問題ではない。何故なら、これは単に象徴表現であり、実際的に何かを詳しく知ろうとすべき事柄ではないからである。そのようなことを探ろうとする人は、イソップ物語に出てくる動物の体重や趣味や生まれ故郷などについて知ろうとする者と一緒である。
セラフィムが、このようにキリストという炭をイザヤの口に触れさせたのは何故だったのか。それは、イザヤが自分の罪深い口を大いに嘆いたからである。このイザヤの口は、神の預言を取り次ぐ口として永遠の昔から定められていた。このため、イザヤは神の預言をどうしても語らねばならなかった。イザヤが自分の口について絶望していたままだと、神の預言を語れなくなりかねない。「こんな罪深い口を持った私が神の聖なる預言を語るなどとは…」とイザヤが心の中で思うはずだからである。これでは神の計画が達成されない。それは神の御心に適ったことではない。神は御自身の計画を絶対に達成される御方である。だから、神はセラフィムを通してイザヤの口にキリストを触れさせることで、イザヤの口を清めて聖別されたのである。そのようにすれば、たとえ罪深い口を持っていたとしても、それは聖別されているのだから、臆せずに神の預言を語り伝えることが出来るようになるのだ。実際、続く箇所を読めば分かるが、イザヤは口がキリストにより聖別されて後すぐ態度を変え、『ここに私がおります。私を遣わしてください。』(6:8)と自分から進んで神の預言を取り次ごうと申し出ている。
我々一人一人の口にも、イザヤにそうされたように、キリストという炭が触れられている。何故なら、キリスト者とはその全身がキリストにより聖別された者だからである。だから、我々もイザヤがそうしたように、神の言葉を語り伝えねばならない。実に、そのように我々がするためにこそ、我々はキリストの救いを受けて王また祭司である光の民とされたのである。ペテロが次のように言った通りである。『しかし、あなたがたは、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それは、あなたがたを、やみの中から、ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方のすばらしいみわざを、あなたがたが宣べ伝えるためなのです。』(Ⅰペテロ2章9節)
イザヤの所に飛んで来たこの『セラフィムのひとり』は、4人のうち何番目のセラフィムだったのであろうか。これはトマスの「神学大全」に書かれていそうな問題である。これについては探索すべき必要がない、と私は言おう。何故なら、これを知ろうとしても意味がないからである。聖書のどこを見ても、このセラフィムが何番目のセラフィムだったか何も書かれていないのである。分かりもしないことを探究してあの偽ディオニュソスのように空想世界に浸るとでもいうのか。そのようなことは避けるべきである。
【6:11~12】
『私が「主よ、いつまでですか。」と言うと、主は仰せられた。「町々は荒れ果てて、住む者がなく、家々も人がいなくなり、土地も滅んで荒れ果て、主が人を遠くに移し、国の中に捨てられた所がふえるまで。』
イザヤは、ユダヤ人に対する働きかけはいつまで続くのか、と神に質問している。これはイザヤが敬虔であり霊の人であったことを示している。何故なら、敬虔でなく霊の人でもなければ、神とその民のことなど気にかけないだろうから、このような質問はしないはずだからである。敬虔であればあるほど、霊の人であればあるほど、神とその民に心を傾けるものだ。
ここでは、つまりこのようなことが言われている。ユダヤに対する働きかけはユダヤが滅ぼされる時まで続く、と。ユダヤが滅ぼされるまでは、ユダヤに対する働きかけがなされるべきであった。何故なら、その時には猶予があったからである。しかし、ユダヤが滅ぼされると、もう働きかける必要はなくなった。もうユダヤに猶予が与えられる期間は過ぎ去ったからである。ここで言われている個々の語句を見ていきたい。『町々は荒れ果てて、住む者がなく』。これはユダヤの町々が荒廃させられたので、そこに住むユダヤ人がいなくなった、という意味である。『家々も人がいなくなり』。これも、ユダヤが荒廃するので、そこにあった家にはユダヤ人が消えていなくなる、という意味である。『土地も滅んで荒れ果て』。これはユダヤの地がローマ軍に滅ぼされて荒れ果てることを言っている。『主が人を遠くに移し』。これは、殺されずに生き残った少数のユダヤ人が、呪いとして世界の四方に散らされたことを言っている。『国の中に捨てられた所がふえる』。これはユダヤの国が全的に神から遺棄されてしまうことを言っている。
【6:13】
『そこにはなお、10分の1が残るが、それもまた、焼き払われる。テレビンの木や樫の木が切り倒されるときのように。』
ユダヤには、殺されずに済んだ者が『10分の1』いた。これは実際的な比率を示しているのではなく、僅かな数であることを示している。聖書の多くの箇所で、ユダヤには少数の者が残されるであろう、と言われているのと一緒の意味である。しかし、その者たちも『焼き払われる』ことになった。つまり、神から完全に遺棄されて異邦人のようになった。何故なら、ユダヤ人にとって神から退けられるのは、火で焼き払われるかのように苦しいからである。この考え方については、ユダ22~23の箇所から裏付けが取れる。そこでは、神から遠ざかっている非再生者たちが『火の中』にいると言われているからだ。神から離れた状態とは、霊的に言えば、火で焼かれることでなくて何であろうか。この残されたユダヤ人が捨てられたのは、『テレビンの木や樫の木が切り倒されるときのよう』であった。木が切り倒されたならば、惨めにも地面に横たわり、誰かが引き上げない限りそこに倒れたままである。残されたユダヤ人も、神からそのような引き起こされない木も同然の存在として取り扱われることになった。彼らがそのようになったのは、彼らの罪が原因であった。神が彼らの罪を罰せられた。だから、あのような悲惨が起きたのである。もし彼らが罪を犯していなければ、彼らは悲惨にならずに済んでいた。何故なら、聖書が言うように『命令を守る者はわざわいを知らない。』(伝道者の書8章5節)からである。
黙示録11:13の箇所でも『10分の1』という言葉が使われている。黙示録のほうでも、やはり僅かな度合いを示そうとして『10分の1』と言われている。この『10分の1』という言葉が使われているのは、我々が今見ているイザヤ書の箇所と黙示録の他には、10分の1の捧げ物について書かれている箇所だけである。10分の1の捧げ物については周知の事柄だから、ここでいちいち説明する必要はない。
『しかし、その中に切り株がある。聖なるすえこそ、その切り株。」』
これはイエス・キリストの預言である。『切り株』とはイエス・キリストを象徴している。何故なら、ユダヤ人が裁きにより『テレビンの木や樫の木が切り倒されるときのように』なっても、キリストは切り倒されなかったからである。実際、ユダヤは紀元70年において完全に神の前で切り倒された。しかしキリストは今に至るまでずっと存在し続けておられる。主は、これからも永遠に存在される。永遠に変わらない『切り株』として、である。ヘブル13:8の箇所でこう書かれている通りである。『イエス・キリストは、きのうもきょうも、いつまでも、同じです。』確かに神であられるキリストは永遠に変わられない。それは主御自身がこう言われた通りである。『主であるわたしは変わることがない。』(マラキ3章6節)この『切り株』をキリスト以外として捉えることはできない。というのも、この切り株とは『聖なるすえ』であって、それはキリスト以外ではないからである。聖徒であれば、聖書でキリストについて「子孫」つまり『すえ』と言われていることを既に知っているはずである。
【11:4】
『くちびるの息で悪者を殺す。』
キリストは、口から出る息により悪者どもを殺される。これは真理である。この『くちびるの息』とは御言葉である。キリストは、その御言葉により悪者を殺されるのである。その殺し方には、霊的な場合と実際的な場合との2つがある。御言葉が突き刺されても霊的に死ぬだけの場合、実際的には死なない。これはローマ兵たちがそうであった。キリストが再臨された際、ローマ兵たちは御言葉によりただ霊的に殺され、そして悪霊どもに憑依されただけであった(黙示録19:21)。それとは違い、御言葉により霊的にも実際的にも殺される場合もある。ネロがそうであった。ネロは再臨のキリストが発された御言葉という息により、霊的に殺されただけでなく、実際的にも殺されたのである。黙示録11:5の箇所でも、似たようなことが言われている。そこでも、御言葉―こちらのほうでは火において示されている―が口から出て悪者どもを殺す、と言われている。だが、この黙示録のほうでは単に霊的な殺しだけが言われているに過ぎない。何故なら、歴史を振り返っても、聖徒たちが御言葉により敵対者たちを焼殺したなどという記録は見出されないからである。なお、この箇所で言われている事柄を全く文字通りに捉えるのはナンセンスである。キリストがフッと息を口から敵に吹きかけて絶命させるとでもいうのか。これはコミカルな想像であり、キリストを侮辱していると見做されても仕方がない。このような違和感のある理解が許されるのは初学者だけに限られる。
パウロがⅡテサロニケ2:8の箇所で言っているのは、このイザヤ11:4の箇所と対応している。文章の相似具合を見れば、この2つの箇所が対応しているのは明らかである。パウロはこう言っている。『その時になると、不法の人が現われますが、主は御口の息をもって彼を殺し、来臨の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。』ネロは『悪者』であった。キリストは再臨された際、その聖なる御言葉という息によりネロを殺されたのである。それは霊的な殺害であると共に、実際的な殺害でもあった。このネロに対する裁きについては既に説明されている。ところで、我々が今見ている箇所では、直接的な意味においてネロのことが言われているのか。そうではない。ここで言われているのは普遍的な事柄である。すなわち、キリストは誰であれ悪者をその御言葉という息により殺されると。だが、この普遍的なことを言っているイザヤ11:4の箇所を、パウロはⅡテサロニケ2:8の箇所でネロという個別の場合に当てはめて語ったのである。このⅡテサロニケ2:8の箇所を深く理解したければ、そこと対応しているイザヤ11:4の箇所を忘れることがあってはならない。これは言うまでもないことであろう。
【24:1】
『見よ。主は地を荒れすたらせ、その面をくつがえして、その住民を散らされる。』
『地』とはユダヤの地である。これは地球全土という意味ではない。『その面』というのも、やはりユダヤを指している。『その住民』はユダヤ人である。つまり、ここでは徹底的にユダヤのことが言われている。
『見よ。』と書かれているのは、つまり「注目せよ。」という意味である。『主は地を荒れすたらせ』。これはユダヤの地がローマ軍により完全に荒廃させられることを言っている。つまり紀元70年のことだ。『その面をくつがえして』。これは、紀元70年においてユダヤの社会とその秩序が根底から覆されることを言っている。これを例えるならば、原爆により広島と長崎が破壊され尽くした出来事である。歴史が示す通り、ユダヤは正にそのような状態になったのである。『その住民を散らされる』。これは死ななかった少数のユダヤ人たちが呪いとして四方に散らされることである。
それにしても、約800年も前からこのような預言がされていたというのには驚かされる。全てをお定めになられた神が、預言においてこのように語られた。だから、大昔からこのように未来のことを語れたのである。もしこれを語ったのが人間に過ぎなかったとすれば、このような預言を語ることは出来なかった。人間に過ぎない者が、どうして800年後の出来事を正確に言い当てることが出来ようか。我々人間は、どれだけ知性と見識があっても、たかが数十年後の未来でさえ正確に言い当てられないのである。
【24:2】
『民は祭司と等しくなり、奴隷はその主人と、女奴隷はその女主人と、買い手は売り手と、貸す者は借りる者と、債権者は債務者と等しくなる。』
ここではユダヤ社会が根底から覆されると教えている。立場や地位や役目や呼称や関係といったものは、社会における基本要素である。社会はそのような要素の集合体だからである。ここでは、そのような要素が全て取り払われると示されている。だから、ここではユダヤが根本的に滅ぼされることについて言われているのである。それは紀元70年において実際に起こった。その時、ユダヤは完全に滅ぼされてしまった。それは、もう立場とか地位などといったものを考慮し得ないほどの滅びであった。
これは凄まじい呪いである。しかし、ユダヤが罪を犯し続けたのでこうなったのだから、ユダヤにとっては自業自得であった。神は、この呪いにおいてユダヤに対して正当な報いを下された。我々も、もしユダヤのように堕落してしまうならば、最終的にはユダヤのように滅ぼされてしまう。そのようになっても当然である。何故なら、聖書に書かれているように『主は報復の神で、必ず報復されるから』(エレミヤ51章56節)である。
【24:3】
『地は荒れに荒れ、全くかすめ奪われる。主がこのことばを語られたからである。』
紀元70年においてユダヤは完全に荒廃させられ、そこにあった財物は『全くかすめ奪われ』てしまった。ヨセフスの書を読んだことがあるだろうか。そこには、この荒廃がどのようであったか詳しく記録されている。ティトゥスの凱旋門に描かれているレリーフを見たことがあるだろうか。そこにはユダヤにあった財物をローマ兵たちが戦利品として持ち運んでいる様が描かれている。それゆえ、ここで言われている出来事は文字通りに捉えてよい。そこには誇張や象徴は一切ない。ただありのままのことが書かれている。
しかし、ユダヤの滅びる出来事が紀元70年に起きたのは何故だったのか。それは『主がこのことばを語られたから』であった。つまり、神が預言においてユダヤの滅びを語られたので、それは絶対に実現されるしかなかった、ということである。確かに神は語られたことを必ず実現される。だから、神の預言を真実なものとして信じる者は幸いなのである。ルカ1:45の箇所ではこう言われている。『主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は、なんと幸いでしょう。』神の預言とは、すなわち事前に未来のことが開示されることである。だから、神が預言の言葉を語られたならば、それは絶対に起こるのである。
【24:4】
『地は嘆き悲しみ、衰える。世界はしおれ、衰える。天も地とともにしおれる。』
紀元70年においてユダヤは完全に退廃してしまった。それは、かつては咲いていた花が、枯れてしまうようなものである。枯れた花を誰でも見たことがあるであろう。私は、あのような花を見て虚しいと思う。ユダヤという花も、正にそのように虚しい状態となったのである。ここで萎れるとか衰えると言われているのは、そういうことである。なお、この箇所で『地』また『世界』と言われているのは、ユダヤであるという点に注意せねばならない。イザヤ24章の文脈をよく考えるべきである。ここではユダヤのことが言われているのだ。
また、その時には『天も地とともにしおれ』た。天が萎れるとは一体どういう意味なのか。これは、天上が古い状態から新しい状態に様変わりした、ということである。その時には携挙された聖徒たちと入れ替わりに天上から悪霊どもが追放されることになった。それまで悪霊は天に居続けることが出来た。しかし、その時からはもうそういうことが出来なくなった。これは古い状態における天が萎れることに他ならない。何故なら、それは新しい状態へ移行するために古い状態が消え失せて過去のものとなるということだから。だから、ここでは『天も地とともにしおれ』ると言われている。つまり、ユダヤ戦争の時期に様変わりしたのは地上におけるユダヤだけではなかった。その時にはユダヤと共に天上の場所も様変わりしたのである。
【24:5】
『地はその住民によって汚された。彼らが律法を犯し、定めを変え、とこしえの契約を破ったからである。』
ユダヤは、ずっと―そう「ずっと」―神の命令に背き続けていた。彼らのすることと言えば、反逆、偶像崇拝、殺人、不品行、欺き、愛のない形式だけの安息日順守などばかりであった。これは真実である。だから、ステパノは不敬虔な彼らにこう言ったのである。『かたくなで、心と耳に割礼を受けていない人たち。あなたがたは、先祖たちと同様に、いつも聖霊に逆らっているのです。…あなたがたは、御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことはありません。』(使徒行伝7章51、53節)ステパノが聖霊に満たされてこう言ったのだ(使徒行伝7:54~55)。だから、ユダヤ人たちが律法を守ったことがなかったということを否定することは出来ない。『律法』とは文字通りに捉えればよい。『定め』とは、神に愛された特選の民として正しく歩むべきであるというユダヤにおける定めを言っている。『とこしえの契約』とは、神がユダヤ人と結んでおられた救いの契約である。つまり、これは古い契約のことである。それは初めアブラハムにおいて結ばれ、それから再びモーセの時に結ばれた。このようにユダヤが神に背き続けていたのは、実に恐るべきことであった。何故なら、本来であれば神に従うべき民が、神に従うどころかサタンや偽りの神々や自分の罪に従っていたからである。
このように律法に違反していたユダヤ人は、その罪により自分たちに与えられた『地』を汚した。2020年の今では世界的にコロナウィルスが流行している。このウィルスに感染した人がいる場所や触った部分は、洗浄して綺麗にしなければいけない。何故なら、その人によりそこが言わば汚されてしまったからである。ユダヤ人たちがユダヤの地を汚したのも、これと同じであった。我々も罪を犯すならば、自分の周りの人や場所を汚すことになる。罪は汚れを生じさせ、その汚れは伝染してしまう。聖書でパン種が広がると言われているは、このことである(Ⅰコリント5:6)。つまり、ほんの少しの罪であっても、それは周りの人や場所に波及せざるを得ないのである。だから、我々は気を付けなければならない。しかし、律法を行なうのであれば、逆に周りの人や場所に聖なる作用や伝染効果をもたらすことになる。例えば、律法に適った聖徒たちの良い行ないを見た人たちが、見習ったり恥じ入ったりして、自分たちも良い行ないに進むようになったりする。更に、キリストが言われたように、聖徒たちの良い行ないを見た人たちが救われて御名を崇めるようにさえなる(マタイ5:16)。罪が汚れを伝染させるように、律法順守も周りにある存在を感化させるのである。
【24:6】
『それゆえ、のろいは地を食い尽くし、その地の住民は罪ある者とされる。それゆえ、地の住民は減り、わずかな者が残される。』
ユダヤ人の罪のため、律法の呪いがユダヤの地を獅子でもあるかのようにして食い尽くした。『食い尽くし』と言われているのは、それがそこに満ちるという意味である。この呪いは申命記に記されている。それは非常に悲惨であって、是非とも避けたいと思わせる内容である。これは「呪い」だから当然である。もし避けたくないと思えるのであれば、それはもはや呪いとは言えないであろう。避けたいと思うからこそ、それは「呪い」なのだ。こうしてユダヤの地にいた『住民は罪ある者とされ』た。神が幾度となく彼らに悔い改めを促されたのに、悔い改めようとせず、ずっと罪のうちに歩み続けたからである。
この律法の呪いにより、ユダヤの地にいたユダヤ人は『わずか』だけになってしまった。これは律法の呪いの一つである。神が不敬虔なユダヤを忌み嫌われたので、ユダヤ人の大部分をこの世から消し去られたのである。我々は、もし家のどこかに大量のゴキブリが潜んでいたとすれば、是非とも駆逐したいと思うであろう。神がユダヤを駆逐されたのも、これと同じであった。ユダヤは神の御前に汚らわしいゴキブリのようになってしまっていたのだ。我々は、大量のゴキブリが駆逐されれば喜ぶ。神も、そのようにユダヤ人が駆逐されたのを喜ばれた。律法の呪いの中で次のように書かれている通りである。『主は、このみおしえの書にしるされていない、あらゆる病気、あらゆる災害をもあなたの上に臨ませ、ついにはあなたは根絶やしにされる。あなたがたは空の星のように多かったが、あなたの神、主の御声に聞き従わなかったので、少人数しか残されない。かつて主があなたをしあわせにし、あなたがたをふやすことを喜ばれたように、主は、あなたがたを滅ぼし、あなたがたを根絶やしにすることを喜ばれよう。あなたがたは、あなたがはいって行って、所有しようとしている地から引き抜かれる。』(申命記28章61~63節)しかし、今のユダヤ人は1500万人もいるではないか、ぜんぜんユダヤ人は僅かになってはいないではないか、などと疑問に思う人がいるかもしれない。確かにユダヤ人と呼ばれる者が2020年の今においてそのぐらい存在しているのは事実である。だが、そのうちからアブラハムの遺伝子を持ったスファラディ系のユダヤ人を抽出してみられよ。そうすれば、今の時代でも本物のユダヤ人は数少ないことに気付くであろう。イスラエルにいるスファラディ系ユダヤ人も、たったの1割程度に過ぎない。世の中で有名なユダヤ人も、そのほとんどはアシュケナージ系のユダヤ人である(例えばロックフェラー家、ロスチャイルド家、ウィトゲンシュタイン、フロイト、アインシュタイン、ノイマン、ガモフ、アドルノ、ドラッカー、バフェット、ソロス、マーク・ザッカーバーグはどれもアシュケナージ系であるが、これは有名なユダヤ人のごく一部だけに過ぎない)。「ユダヤ人」には2種類の存在があるということを前提にしないで考えると、このように思い違いをしてしまうことになる。
我々も、ユダヤ人のように堕落してしまうならば、彼らのように僅かな者しか残されなくなってしまう。神が、律法の違反者たちを憎悪されるからである。神に憎まれておきながら、神の民がその大部分において生き残ったままでいるというのは考えにくい。何故なら、神はそのような者たちに憤慨されるのだから。神に従う義務を負っていない者たちであれば話は別かも知れないが、神の民とは神に従うべき存在なのである。そのような存在が神に従わなかったために駆逐されても、文句は言えないであろう。我々は、ユダヤ人のように駆逐されたいだろうか。されたくはない。だったら、神の御怒りを燃やさないように、我々は御心に適った歩みをしていかねばならない。
【24:7】
『新しいぶどう酒は嘆き悲しみ、ぶどうの木はしおれ、心楽しむ者はみな、ため息をつく。』
この箇所では、呪いによりユダヤからあらゆる喜びが取り上げられると示されている。『新しいぶどう酒は嘆き悲しみ』。これは、本来であれば大きな喜びをもたらすはずの新しい葡萄酒も、嘆きと悲しみのうちに呑み込まれてしまうという意味である。原爆が投下された直後の広島にいた人たちは、素晴らしい御馳走を味わおうなどと考えただろうか。あまりにも大きい悲惨が起きたので、とてもじゃないが御馳走のことなど考えられもしなかったはずである。というのも、それどころではないからである。ユダヤが荒廃した時に新しい葡萄酒が嘆きと悲しみに呑み込まれてしまったのも、これと同じである。『ぶどうの木はしおれ』。これもユダヤから喜びが失われることを言っている。聖書で葡萄の木とは楽しみを示しているからだ。『心楽しむ者はみな、ため息をつく』。これはユダヤが荒れに荒れたからである。自分の故郷が滅茶滅茶にされたのに、溜め息をつかない者は人間らしい感覚を持っていないのである。
呪いが注がれると、このように喜びが取り上げられてしまう。これは律法が示している。神は、御自身に聞き従わない不敬虔な聖徒たちに、喜びをお与えにはならない。人間の親は、自分に逆らってばかりいる子どもに喜びを与えてやろうとは思わないであろう。神が不敬虔な聖徒たちに呪いとして喜びを与えられないのも、これと同じである。我々は、神から喜びが取り上げられるこを望まないはずである。だったら、イエス・キリストに従い続けねばならない。そうすれば、我々は神から与えられる喜びを期待してよい。
【24:8~9】
『陽気なタンバリンの音は終わり、はしゃぐ者の騒ぎもやみ、陽気な立琴の音も終わる。歌いながらぶどう酒を飲むこともなく、強い酒を飲んでも、それは苦い。』
ここでもユダヤから喜びが取り上げられると示されている。酒や音楽について言われているのは、分かりやすさのためである。
この箇所で言われている内容は、黙示録18:22~23の箇所と対応している。そこでも、ユダヤが滅びる際、あらゆる喜びが消し去られることについて言われている。この黙示録の箇所は既に註解された。また、この箇所は伝道者の書12:1~4の箇所と対応している。そこでも、やはりユダヤからあらゆる幸いが取り上げられると言われている。この伝道者の書の箇所も既に註解されている。聖徒たちは、今挙げた2つの箇所と共にこのイザヤ24:8~9の箇所を考察すべきである。そうすれば、より豊かな理解が得られるようになるであろう。
【24:10】
『乱れた都はこわされ、すべての家は閉ざされて、はいれない。』
ここでもユダヤに襲いかかった悲惨が語られている。『乱れた都はこわされ』。これはエルサレムが大いに揺り動かされ、遂には破壊されてしまうことを言っている。『すべての家は閉ざされて、はいれない』。これはユダヤ人が恐れを抱いて家の扉に鍵をかけたことを言っている。恐れを抱いた対象は何だったか。シモンとヨアンネスに従う叛徒どもとローマ兵たちである。これは「ユダヤ戦記」で詳しく書かれている。もっとも、この叛徒とローマ兵は鍵のかけられた扉をぶち破って中に侵入したのではあったが。
【24:11】
『ちまたには、ぶどう酒はなく、悲しみの叫び。すべての喜びは薄れ、地の楽しみは取り去られる。』
ここでも、やはりユダヤからあらゆる喜びが取り去られることについて語られている。神は、もうユダヤに恵みの喜びをお与えになろうとはされなかった。ユダヤ人が神に逆らい続けていたのだから、こうなったのは当然である。これこそ彼らの悪に対する正当な神の復讐なのだ。
【24:12~13】
『町はただ荒れ果てたままに残され、城門は打ち砕かれて荒れ果てる。それは、世界の真中で、国々の民の間で、オリーブの木を打つときのように、ぶどうの取り入れが終わって、取り残しの実を集めるときのようになるからだ。』
ユダヤは完全に荒廃させられ、その城門も打ち砕かれてしまった。これは歴史が示す通りである。ユダヤは、ローマ軍とかなり良い戦いをすることが出来た。しかし、やはりと言うべきだろうか、最終的にはローマ軍の経験と知略がユダヤの獣的な勢いに打ち勝った。こうなったのは、ユダヤの罪が原因である。神が、ユダヤの罪をローマ軍を通して罰されたからだ。それゆえ、もしユダヤが罪を犯していなかったとすれば、神がユダヤに味方しておられたので、ローマ軍に打ち負けることはなかった。罪が全ての勝敗を決定づけたのである。
その時の悲惨は『オリーブの木を打つときのように、ぶどうの取り入れが終わって、取り残しの実を集めるときのよう』であった。これは、つまり携挙が起こる時を言っている。聖書の中で、携挙は穀物の取り入れにおいて語られている。必要なものを引き上げるという点で、携挙と穀物の取り入れは一緒だからである。携挙を穀物の取り入れに例える以上によい例えはない。その時には携挙されるユダヤ人と携挙されないユダヤ人がいた(マタイ24:40~41)。後者のほうは、ユダヤの地に残され、エルサレム陥落と共に滅んだのである。この箇所の他でも、黙示録14:14~16やイザヤ27:12~13などで携挙が取り入れの例えにおいて語られている。
このようにユダヤが荒廃したのは、どこでであったのか。それは『世界の真中』である。幾らかの読者は、「ユダヤの地が世界の中心だったのか」などと思われるかもしれない。事柄は霊的にこそ捉えられなければならない。ユダヤには、全世界の支配者であられる万軍の王なる神が、その神殿に住んでおられた。だから、その神が住まわれるユダヤこそ『世界の真中』だったのである。ちょうど、天皇の住む東京が日本における中心であり、カルヴァンのいたジュネーヴ市がプロテスタント界の中軸地であったのと同じである。神のおられた場所が世界の中心だったということに、何もおかしな点はない。また、それは『国々の民の間』で起こった。これはローマ軍のことを言っている。既に述べた通り、ローマ軍は『国々の民』から構成されていたのだから。
【24:14~16】
『彼らは、声を張り上げて喜び歌い、海の向こうから主の威光をたたえて叫ぶ。それゆえ、東の国々で主をあがめ、西の島々で、イスラエルの神、主の御名をあがめよ。私たちは、「正しい者に誉れあれ。」という地の果てからのほめ歌を聞く。』
『彼ら』とは誰か。これはユダヤの民である。何故なら、ここではユダヤについて預言されているからである。文脈から考えるならば、これはユダヤだとするしかない。これをローマ軍だとするのは、難しいと私には思われる。
この箇所では、キリストが再臨された際、世界の各地にいたユダヤ人たちが御名を賛美することについて預言されている。どうして再臨の際には賛美が起こるのか。それは再臨の時には、ユダヤに回復の恵みが注がれるからである。それまでにユダヤが犯してきたあらゆる罪が、遂に御前から消し去られるのだ。それなのに、どうして御名を崇めないということがあるだろうか。ここで『正しい者』と言われているのはキリストである。キリストは真に正しい御方だからである。これをキリスト以外の存在として理解しないように注意せよ。
キリストも、このことについて語られた。主も、再臨が起こるとユダヤ人は御名を賛美するようになると言っておられた。すなわち、こうである。『あなたがたに告げます。『祝福あれ。主の御名によって来られる方に。』とあなたがたが言うときまで、あなたがたは今後決してわたしを見ることはありません。』(マタイ23章39節)このキリストの御言葉は既に紀元1世紀において実現している。我々が今見ているイザヤ書の箇所でキリストについて『正しい者』と言われているのは、マタイ23:39の箇所では『主の御名によって来られる方』と言われている。つまり、イザヤ書で『正しい者に誉れあれ。』と言われているのは、マタイ福音書では『祝福あれ。主の御名によって来られる方に。』と言われているのと対応している。
【24:16】
『しかし、私は言った。「私はだめだ、私はだめだ。なんと私は不幸なことか。裏切る者は裏切り、裏切り者は、裏切り、裏切った。」』
このようにユダヤの回復について語られたのに、イザヤは喜ぶどころか大いに嘆いている。どうしてイザヤは嘆いたのか。それは、ユダヤが裏切り者となり、神に裏切りを重ねていたからである。つまり、イザヤはこのように思ったのだ。「ああ、ユダヤが神に裏切りを重ねているというのに、どうして回復が実現されるというのか。私もそのようなユダヤに属する人間の一人である。だから私は非常に不幸だ。」イザヤは、酷い裏切り者となったユダヤに絶望していた。だから、そのユダヤが回復されるなどとは思えなかったのである。
この箇所を見れば分かるように、イザヤは、不幸を感じて大いに悲しむ人であった。他にもイザヤ6:5の箇所で、彼は絶望している。しかし、このように悲しむのは幸いであった。何故なら、キリストは悲しむ人についてこう言われたからである。『悲しむ人は幸いです。その人は慰められるからです。』(マタイ5章4節)パウロも大いに嘆く人であった。ローマ7:15~25の箇所を見れば分かる通りである。ダニエルも嘆く人であった。ダニエル書9:3~19の箇所を見れば分かる通りである。ダビデもそうであった。詩篇を見れば分かる通りである。
この箇所では『裏切る者は裏切り、裏切り者は、裏切り、裏切った。』などと非常に特徴的な文章が書かれている。聖書以外では、まずこのような文章は見られない。ホメロスやウェルギリウスもこのような語り方はできなかった。ニーチェやクロウリーの書物にも、このような文章は見られない。ここではユダヤが「裏切り者」であると2回言われている。これはユダヤが裏切り者になったことを強調しているのである。また、ここではユダヤが裏切ったと3回も言われている。これもユダヤが神に裏切りをしたことを強調している。
【24:17~18】
『地上の住民よ。恐れと、落とし穴と、わなとがあなたにかけられ、その恐れの叫びから逃げる者は、その落とし穴に落ち、落とし穴からはい上がる者は、そのわなに捕えられる。』
『地上の住民』とはユダヤ人である。ここではユダヤについて述べられているのだから。これを地球全土のあらゆる民族として捉えてはならない。聖書には、このように具体的な名称を書いていない箇所が非常に多くある。このため、往々にして人により解釈が違うということになる。だから聖書は難しい書物なのである。具体的な名称がそこら中で書かれていたら、ここまで解釈するのが難しいということはなかったはずである。
この『地上の住民』であるユダヤ人には、『恐れ』が生じさせられた。ローマ軍がユダヤを滅ぼそうとやって来たからである。それゆえ、彼らには『叫び』が起こった。しかし彼らが叫んでローマ軍から逃げようとしても、『その落とし穴に落ち』ることになった。つまり、災いを回避することが出来なかった。何故なら、逃げようにも周りにローマ軍という落とし穴が置かれていたからである。その『落とし穴からはい上がる者』も、結局は『わなに捕えられる』ことになった。神がローマ軍という罠をユダヤに仕掛けておられたからである。要するに、この箇所ではユダヤに大きな恐れが生じたが、どうあがいても災いを免れることは出来なかった、ということが言われている。
このように、神の裁きを回避することは絶対にできない。神が、その裁きを下すと永遠の昔から定めておられたからである。神がお定めになられたことを、誰が覆せるであろうか。次のように書かれている通りである。『万軍の主が立てられたことを、だれが破りえよう。御手が伸ばされた。だれがそれを引き戻しえよう。』(イザヤ14章27節)それゆえ、我々は神を恐れなければいけない。全てを定められた神を恐れるのは人にとって当然のことだからである。
【24:18】
『天の窓が開かれ、地の基が震えるからだ。』
ユダヤが裁かれる時には『天の窓が開かれ』た。これは、それまではまだ裁きが下されていなかったが、突如として裁きが下されることになった、という意味である。何故なら、その時、天におられる神が裁きの窓を開かれたからである。その開かれた窓から裁きという雨が猛烈に降ってきたのだ。創世記7:11の箇所でも、大洪水が起こる時に『天の水門が開かれた。』と書かれている。我々が今見ているイザヤ書の箇所で天の窓が開かれたと言われているのが象徴的な表現であるのに対し、この創世記の箇所では実際的な事柄が言われている。その時には、天の水を止めていた抑制の現象がなくなったからである(この現象が何であったか詳しいことは言えない)。しかし、神が天から裁きを下されたという点では、どちらも一緒である。また、その時には『地の基が震える』ことになった。これはユダヤ世界が根底から覆されるという意味である。
【24:19】
『地は裂けに裂け、地はゆるぎにゆるぎ、地はよろめきによろめく。』
ここではユダヤが大いに激震させられると強調して言われている。『地は…云々』と3回も言われている。これは<3回>であるから、誰の目にも明白な強調表現である。
【24:20】
『地は酔いどれのように、ふらふら、ふらつき、仮小屋のように揺り動かされる。そのそむきの罪が地の上に重くのしかかり、地は倒れて、再び起き上がれない。』
ユダヤはローマ軍を通して裁かれたので、酷い酔っ払いのように、また嵐に襲われた仮小屋のようになった。酔っ払いや揺れ動く仮小屋を見たことがあるだろうか。それらを頭に思い描くならば、ユダヤの悲惨がどれだけ大きかったかがよく分かる。つまり、もうどうしようもないぐらいに悲惨な状態になったということだ。
ユダヤがこうなったのは『そのそむきの罪が地の上に重くのしかか』っていたからである。大きな重りが何かの上にあれば、それはグラグラと揺れ動いてしまう。ユダヤもそれと同じであった。罪という重りがユダヤの地にのしかかっていたので、ユダヤは大いに激震したのである。
この時にユダヤの『地は倒れて、再び起き上がれな』くなった。これはユダヤの破滅を、倒れて絶命する人に例えている。倒れて死んだ人は、もう2度と起き上がらない。それと同じで、ユダヤも破滅してからは、もう2度とかつての状態に回復することがなくなった。実際、今に至るまでユダヤは昔の状態に戻っていない。倒れた人で言えば、起き上がって立っていた時の状態に戻っていない。「昔の状態」とは、つまり神と契約を結ぶことができていた時代を指す。これからもユダヤが起き上がることはない。何故なら、もう契約の民としてのユダヤ民族は終わってしまったのだから。
【24:21】
『その日、主は天では天の大軍を、地では地上の王たちを罰せられる。』
これから見ていくイザヤ24:21~23の箇所は、再臨の理解にとって非常に重要である。この箇所よりも重要な箇所が他にあるのかと思えてしまうほどに重要である。実際にこの箇所が第一に重要であるというわけではない。だが、この箇所は間違いなく最も重要な箇所の一つである。だから、この箇所を無視して通り過ぎることは決して出来ない。この箇所は、既に第3部の中で語られている。だが、それは主体的に語られたのではなく、あくまでも付随的に言及されたに過ぎなかった。ここにおいて今、その箇所を主体的に語らねばならない。つまり、この箇所を基点として註解をするのである。
『その日』とはキリストが再臨される時期を言っている。これは、ある特定の日だけを言っているのではない。それは、再臨が起きてから一定の時期について言っているからである。
再臨が起こると、『主は天では天の大軍を』罰せられた。『天の大軍』とは、それまで天にいたサタンの霊どもを言っている。神の軍勢も「天の大軍」である。だが、ここでは神の軍勢として『天の大軍』と言われているのではない。何故なら、神が御自身の聖なる軍隊を自ら罰せられるなどというのは有り得ないことだからである。つまり、ここでは再臨の際、天上にいた悪霊どもが追放されたことを言っている。その時、聖徒たちの携挙が起きた。そして、それ以降、聖徒たちは天上の世界に住まうことになった。その時に天の御国が天の場所で開始されたのである。再臨と共に御国が到来するとキリストがマタイ16:28の箇所で言っておられた通りである。そのようにして携挙により聖徒たちが天上にやって来ると、もはやそこに悪霊どもは住めなくなった。何故なら、天上で聖徒たちと悪霊どもは絶対に共存できないからである。だから、再臨が起きた時には天から悪霊どもが罰せられて追放されたのだ。大量の水と油があれば、どちらか一方が台の上からこぼれ落ちなければならない。それと同じで、聖徒たちが天に来た際には、天から悪霊どもがこぼれ落ちなければならなかった。どこへか。もちろん地上へ、である。この出来事は、黙示録12章の箇所と対応している。また黙示録20:1~3の箇所とも対応している。また、再臨が起きた時には、キリストが『地では地上の王たちを罰せられ』た。前の部分では霊的な世界で起きたことが言われていた。しかし、今度は我々が今住んでいるこの地上世界について言われている。その地上で罰せられる『王たち』とは、黙示録17:12の箇所に書かれている『10人の王たち』を指している。彼らは、再臨が起きた時にはまだ王ではなかったが、一時的に王として見做された。つまり、これは再臨のキリストによりローマ軍の兵士が裁かれ、霊的に殺され、悪霊どもの餌食にされることを言っている。これは黙示録19:19~21の箇所と対応している。確かに、そこでは『地上の王たちとその軍勢』(つまりローマ軍)が再臨されたキリストに裁かれ、悲惨な状態になったと教えられている。というわけで、この箇所では2つの場所で行なわれる裁きが言われている。すなわち、霊的な世界である天と我々が今住んでいる地上世界である。また、ここでは2種類の存在が裁かれると言われている。すなわち、天にいた悪霊どもと地上にいたローマ兵たちである。
【24:22】
『彼らは囚人が地下牢に集められるように集められ、牢獄に閉じ込められ、それから何年かたって後、罰せられる。』
再臨が起こると、天にいた悪霊どもと地上にいたローマ兵たちが、囚人でもあるかのように封じられた。この箇所で『地下牢』また『牢獄』と言われているのは、完全に封じられることを象徴している。何故なら、囚人が牢に閉じ込められると何も出来なくなるからである。つまり、その時、サタンとローマ兵たちは、天と地にいるキリストの勢力に手も足も出せなくなったということである。その封じられる期間は『何年か』であった。これは2年と3か月である。すなわち、紀元68年6月9日~70年9月がそうである。これは『何年か』だから、明らかに短い期間であることを示している。
イザヤ24:21~22の箇所は、黙示録20:1~10の箇所と対応している。黙示録のほうでも、サタンが封じられて、ある期間が経った後で罰せられると示されている。黙示録20:1~3の箇所で『底知れぬ所』と言われているのは、我々が今見ている箇所で『地下牢』また『牢獄』と言われているのと対応している。どちらも完全に働きが封じられることを教えている。黙示録で『千年』と言われているのは、イザヤ書のほうでは『何年か』と言われている。既に述べた通り、黙示録の『千年』という言葉は実際の期間の長さを示しているわけではなく、その期間における質を示している。だから『千年』(完全数10の三乗)という質を表示させた言葉は、実際の期間としては『何年か』であり、それは既に述べたように「2年と3か月」である。読者は黙示録20:1~10とイザヤ24:21~22を読み比べてみるとよい。そうすれば、どちらも同一の出来事を取り扱っていることが分かるはずである。このように私が教えても、その対応具合に気付かない人が果たしているのであろうか。もしいたとすれば、その人は認識不足・注意不足だと言わざるを得ない。
自分だけが最も聖書的な信仰を持っているかのように見せておきながら黙示録も預言者の書もほとんど研究していないある者は(※)、ほとんど研究していないにもかかわらず、黙示録20章に出てくる『千年』という言葉について次のように言った。「この言葉を規定する聖書の他の箇所はない。」だから、この者はこの言葉を自分の理性に基づいて勝手に解釈している。これは、とんでもない話である。神が、このような難解な言葉の意味を知ろうとして聖書を探る者たちに、答えとなる箇所を用意しておられないとでもいうのか。それは有り得ない話である。というのも、もしそうだとすれば、神は悪い虐めっ子のように聖徒たちを悩まして弄んでおられることになるからである。聖徒たちが「千年という言葉は一体どういう意味なのだろうか。」などと思って聖書を熱心に研究しても、神はどこにも解決となる箇所を備えてはおられないのだから。愛である神が、御子をさえも与えて下さるほどに愛しておられる聖徒たちに対し、そのようなことをするはずがないではないか。それなのに、あの者は、神が聖書の中に『千年』という言葉の解決となる聖句を用意しておられないと思っている。だから、「この言葉を規定する聖書の他の箇所はない。」などと言ったのである。何という不信仰、何という不敬虔か。しかも、黙示録や預言者の書をかなり研究した上でそのように思うのであればまだ話は分かるが、彼はそのような研究をほとんどしていないのである。彼はそのような研究(これはあまりにも重要な研究である!)を差し置いて、ロスチャイルドやロックフェラーなどの陰謀や、日ユ道祖論や、従軍慰安婦の問題や、世界大戦の出来事などについて研究していた。これでは聖書の研究よりも、今挙げたような事柄の研究のほうが大事だと言わんばかりである。なるほど、これでは聖書の事柄が分からないままでいるのは当然のことである。調べないのにどうして分かるのであろうか。言うまでもなく、聖書を探れば解決となる明白な箇所があるに違いない、と考えるのが信仰的な姿勢である。実際、我々が今見ているイザヤ24:21~22の箇所では『千年』と対応している『何年か』という言葉が記されている。聖徒たちは、聖書の箇所を徹底的に調べるようにするのが望ましい。そうすれば、それまではまったく分からなかった謎の箇所も、神の恵みにより明白に理解できていくようになる。聖書を調べる者には大きな素晴らしい恵みがあるのだ。
(※)
この者は自分が最も聖書的な信仰を持っていると自負しているものだから、「我々だけが残された。」などと言っていた。
[本文に戻る]
サタンとローマ人が幾らかの間、封じられると、その後、彼らは『罰せられる』ことになった。これは黙示録20:7~10の箇所で書かれている事柄である。まずサタンは、黙示録によれば、燃える火の池に投げ込まれることになった。これはサタンの働きが完全に封じられたことを言っている。つまり、それ以降、サタンはもうユダヤに働きかけられなくなった。それというのも、サタンが追放されたとか閉じ込められたなどと聖書で言われているのは、サタンの働きの停止を意味しているからである。例えば、キリストは、御自身の生きておられるその時期にこの世からサタンが追放されると言われた。『今がこの世のさばきです。今、この世を支配する者は追い出されるのです。』(ヨハネ12章31節)という御言葉がそうである。これはキリストの時代にこの世からサタンが完全に追い出されてもはや存在しなくなると教えられたのではなく、もうこれからは世の人々がキリストの支配に入るならばサタンはその人たちに干渉できなくなる、と教えているのだ。何故なら、世の人がキリストにつくならば、サタンはその人に対する暗黒の支配権を失うからである。パウロが言ったように、キリストの支配に入る前の状態にある人たちは、サタンの支配下の中に歩んでいるのである(エペソ2:1~2)。だから、黙示録20:7~10の箇所でサタンが火の池に投げ込まれると言われているのも、サタンがこの世から滅ぼされるというのではなく、サタンのユダヤに対する干渉と攻撃が完全に停止されるいうことなのだ。つまり、サタンが火に投げ込まれるとは、サタンの働きが停止されることの暗喩なのである。ローマ人のほうは、天から火が降って来て焼き尽くされると言われている。これは御言葉という火により霊的な裁きを受ける、という意味である。これについては既に説明がされている。学び直したいと思う人がいれば、第3部の当該箇所に立ち戻るがよい。このように、ユダヤ戦争の時には、サタンとローマ人という2種類の者たちが裁かれた。サタンはそれまでユダヤに働きかけてきたことに対する罰を、ローマ人たちはキリストの福音に聞き従おうとしなかったことに対する罰を受けた。このようにして神は御自身の審判者としての栄光を現わされたのである。
【24:23】
『月ははずかしめを受け、日も恥を見る。万軍の主がシオンの山、エルサレムで王となり、栄光がその長老たちの前に輝くからである。』
サタンとローマ人が罰せられると、キリストが天上において王となられた。何故なら、その時、遂に天上において天国が開始されたからである。ここで『万軍の主』と言われているのはキリストのことであり、『シオンの山、エルサレム』と言われているのは天国のことである。なお、ここで言われているのは、キリストが天国で正式な王になられるということである。ここではキリストが地上において正式な王になられると言われているわけではない。キリストが王になられたというこの出来事は、他の箇所ではマタイ19:28、25:31、黙示録20:11などでも示されている。こういった深く難しい事柄を理解するにあたり、我々は同じことが言われている他の箇所と併せて理解するようにせねばならない。そうすれば、より立体的で明瞭な理解が得られるようにもなるのだ。ある一つの箇所においてしか理解しないと、どうしても平面的で不十分な理解にならざるを得ないことが多いのである。
主が王になられた時、主は御自身の栄光を現わされた。これが物凄い栄光の輝きであったことは間違いない。『長老たち』は、その栄光を目の前で見た。この長老たちは、どこの場所にいたのか。それは『シオンの山、エルサレム』である天国である。彼らは黙示録に出てくる『24人の長老』である。この長老たちについては、既に第3部の中で説明しておいた。この時のキリストの栄光は、あまりにも輝かしかったので、太陽や月さえも輝いていないかのように思えるほどであった。もし太陽と月に人格があれば、「ああ、何ということか。万物の支配者であられる御方の栄光が現われたので、私たちは闇も同然になってしまった。」などと恥じ入っていたはずである。『月ははずかしめを受け、日も恥を見る。』とは、このような意味である。つまり、これはキリストの栄光の度合いを教えている。ここでは太陽よりも月のほうが先に書かれている。太陽のほうが栄光の度合いが大きいのだから太陽のほうを先に書くべきではなかったのか、などと疑問に感じる人がいるかもしれない。確かに太陽のほうがより輝かしい栄光を持っているが、ここでは特に順序が考慮されていないだけである。既に述べた通り、聖書において順序が気にされていない部分は少なくない。
【25:6】
『万軍の主はこの山の上で万民のために、あぶらの多い肉の宴会、良いぶどう酒の宴会、髄の多いあぶらみとよくこされたぶどう酒の宴会を催される。』
この箇所では、あらゆる国の民族が神の国に集められるようになる、ということが言われている。つまり、これは新約時代の預言である。『この山』とは、既に述べたように神の国を指す。『の上で』とは「そこにおいて」という意味である。『万民』とは、救われた諸々の国民のことである。
ここでは、神の国が魅力的な『宴会』に例えられている。これは、御国の素晴らしさ・喜ばしさを示すための比喩である。パウロが言ったように、神の国においては食物に意義があるというわけではない。『なぜなら、神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。』(ローマ14章17節)だが、このイザヤ書の箇所では、あたかも神の国が食物においてあるかのような言われ方がされている。これは御国が食物においてあると教えているわけではなく、ただ肉的な傾向を持つ我々に分りやすいようにと、あえて肉的な幸いを通して霊の事柄における幸いを悟らせようとしているのである。聖書で、このように肉的な事物において霊的な事物を知解させようとしている箇所は、決して少なくない。神の国に宴席のような素晴らしさがあるということについては、キリストも言っておられる。すなわち、こう主は言われた。『あなたがたに言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国で、アブラハム、イサク、ヤコブといっしょに食卓に着きます。』(マタイ8章11節)アブラハムやイサクやヤコブと食事の席に着くというのは、素晴らしく、あまりにも光栄を感じられることである。このように望ましい宴席は、恐らく他にないであろう。神の国に入れられるとは、肉的な感覚に合わせて例えるならば、このような宴席に参加できるようなものなのである。
この箇所では『宴会』という言葉が3回も繰り返して言われている。すなわち、肉の宴会、葡萄酒の宴会、肉と葡萄酒の宴会、と。3回は強調の意味を持つから、これは重要であることを示している。よって、我々は宴会のような素晴らしさを持つ御国の事柄を心に留めねばならない。神の国とは、キリストにおける神との共生また交わりなのだ。誰が、このような素晴らしい御国に心を留めないでいていいはずがあるであろうか。
この箇所では、あらゆる国の民族が招かれると教えられている。それにもかかわらず、ここでは携挙の出来事が言われているのではない。確かに携挙においてもあらゆる国の民族が招かれるが、ここではそのことについて言われているのではない。それは次の節を見ても分かるであろう。我々は間違えないように注意せねばならない。
【25:7~8】
『この山の上で、万民の上をおおっている顔おおいと、万国の上にかぶさっているおおいを取り除き、永久に死を滅ぼされる。』
イエス・キリストの王国が現われると、信じる人たちからはその顔に被さっている覆いが除去される。この『おおい』とは何か。これは、イエス・キリストに向かわないことによる霊的また神学的な盲目を意味している。誰であれ、イエス・キリストに向かわず、イエス・キリストにおいて捉えるのでなければ、聖書を正しく理解することは不可能である。何故なら、聖書とはイエス・キリストについて啓示された書物なのだから。それゆえ、キリストに向かわないで聖書を捉える人は、顔に覆いを付けている人と一緒である。すなわち、イエス・キリストにおいて聖書を捉えていないので、顔に覆いを付けている人が何も正しく認識できないように、聖書を正しく認識することができない。しかし、イエス・キリストにおいて聖書を捉えるならば、誰もが覆いを顔から外した人のように、聖書を正しく認識することができる。これについてはパウロがⅡコリント3章の箇所で詳しく論じている。キリストが現われたことにより、今や万民がこのキリストにおいて闇の覆いを外し、聖書をくっきりと把握することが出来ている。今やそういう時代になっているのだ。この箇所では、この事柄が繰り返して言われている。つまり、これは非常に重要であるということだ。また、ここで『万民』と『万国』と言われているのは一緒の意味であり、これは「あらゆる国の民族」を指している。『顔おおい』と『おおい』という言葉も一緒の意味である。
人がイエス・キリストの御国に入ると、その御国において、神はその人から『永久に死を滅ぼされる』。これは、つまり信じた者たちから、死の問題が完全に解決されるということである。何故なら、その人はキリストのゆえに、もはや死ぬことがなくなったからである。一見すると、地上にいる信仰者たちも、死んで消え去るかのように感じられる。確かに肉体的な意味において、信仰者たちはこの地上で死ぬことになる。しかし、それは単に肉体的な死を経験するだけであって、実際は即座に御霊の身体に復活され、永遠に生き続けるようになる。これは実質的には聖徒たちが死なないことを意味している。何故なら、死によってその人の生命が滅びに呑み込まれてしまうことにはならないのだから。それゆえ、御国に入れられた聖徒たちからは永久に死が滅ぼされていると言うことができる。これについてはキリストも次のように言われた。『わたしを信じる者は、死んでも生きるのです。また、生きていてわたしを信じる者は、決して死ぬことがありません。』(ヨハネ11章25~26節)イエス・キリストにおいて神の御国に入れられた者たちには、既に死が滅ぼされている。だから我々はキリストにあって永生の希望を持つことができるのである。
この『永久に死を滅ぼされる。』という御言葉は、復活のことについて言われているのではない。確かに復活の時にも死は永久に滅ぼされる。その時には、究極的な意味において死が敗北させられるからである。その時パウロが言ったように、『「死は勝利にのまれた。」としるされている、みことばが実現』(Ⅰコリント15章54節)するのである。だが、我々が今見ている箇所で言われているのは、復活の時に死が滅ぼされることについてではない。聖書では、救いの時にも復活の時にも死が滅ぼされると教えられている、ということを我々は知るべきである。すなわち、救いの時には希望また約束において死が滅ぼされ、復活の時には実際的に死が滅ぼされる。この2つの区別を弁えないと聖書理解に問題が起こることになるから注意されたい。
我々が今見ているこの箇所と対応している他の箇所は次の通り。Ⅱテモテ1:10。『キリストは死を滅ぼし、福音におって、いのちと不滅を明らかに示されました。』ヘブル2:14~15。『そこで、子たちはみな血と肉とを持っているので、主もまた同じように、これらのものをお持ちになりました。それは、その死によって、悪魔という、死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人人を解放してくださるためでした。』これらの聖句では、イエス・キリストがその贖いによって死を放逐して下さったことを教えている。一方、次に示す箇所は、我々が今見ているこの箇所と対応していない。黙示録21:4。『もはや死も…ない。』Ⅰコリント15:54~55。『しかし、朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、「死は勝利にのまれた。」としるされている、みことばが実現します。「死よ。おまえの勝利はどこにあるのか。死よ。おまえのとげはどこにあるのか。」』Ⅰコリント15:26。『最後の敵である死も滅ぼされます。』これらの聖句が我々が今見ているこの箇所と対応していないのは、これらがどれも復活の時に聖徒たちから死が駆逐されることを教えているからである。読者は、今示された聖句で死についてどのように言われているか、よく考えてみるがよい。そうすれば明白な違いに気付くであろう。すなわち、ある聖句では死が既に滅ぼされたと言われており、別の聖句では死が未だに滅ぼされていない事象として言われている、という違いをである。
【25:8】
『神である主はすべての顔から涙をぬぐい、』
イエス・キリストにおいて御国に入れられた聖徒たちの顔からは涙が全て拭い去られる。『すべての顔』とは、選ばれている全ての信仰者たちの顔、という意味である。ユダのような選ばれていない信仰者は当然ながら含められていない。何故なら、彼らの顔からは永遠に涙が流れ落ちるからである。では『涙をぬぐい』去るとは、どういった意味か。これは、聖徒たちから罪の呪いと不幸と悲しみとが、キリストにおいて除去されるという意味である。救われるまで我々は、罪の苦しみの中に喘いでいた。だが救われた際、我々は罪の問題からキリストにおいて助け出された。これは大いなる慰めである。要するに、顔から涙が拭い去られるとは、罪の赦しにおける比喩表現である。事柄は霊的に捉えねばならない。
この箇所は、黙示録21:3~4の箇所と対応しているのか。そこでは次のように言われている。『また、神ご自身が彼らとともにおられて、彼らの目の涙をすっかりぬぐい取ってくださる。』この2つの箇所では、言われていることが似ている。だから、両者が対応していると思う人がいたとしても不思議ではない。だが、これら2つの箇所は対応していない。確かにどちらでも、聖徒たちの顔から涙が拭い取られると言われている。この点ではどちらも一緒である。しかし、涙が拭い去られるその理由が、それぞれ違っている。それは、どのような違いなのか。まず我々が今見ているイザヤ書の箇所の場合、涙が聖徒たちから拭い取られるのは、イエス・キリストの御国において罪と死の問題が解決されるからである。これは既に地上において起こっている。一方、黙示録の箇所の場合、涙が聖徒たちから拭い取られるのは、『もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもな』く『以前のものが、もはや過ぎ去ったから』(黙示録21:4)からである。これは復活の時の至福を言っている。要するに、イザヤ書のほうは既に我々が経験している慰めであり、黙示録のほうはまだ我々が経験していない慰めである。それだから、この2つの箇所が対応しているとすることはできない。
『ご自分の民へのそしりを全地の上から除かれる。』
これは、新約時代には神の国が宣べ伝えられるようになるので全地において信仰者たちへの誹りが止むようになる、という意味である。何故なら、神の国の福音が伝えられると、あらゆる国の民族が神の国に入るようになるからだ。そうなると、かつては信仰者たちを誹っていた者たちも、もはや誹ることが出来なくなる。自分が誹っていた当の信仰に、自分が飲み込まれてしまったのである。であれば、どうしてその信仰を以前と同じように誹り続けることが出来るであろうか。もしそのようにするならば、それは自分自身を誹ることになってしまうのだ。こんなにも馬鹿げたことは他にない。なお、この箇所では一般的なことが言われているという点に注意せねばならない。すなわち、ここでは文字通りの意味で、全地からあらゆる誹りが終止させられると教えられているわけではない。
『主が語られたのだ。』
これは署名のような文言と考えればよい。これは次のように言っているようなものである。「これらは神が啓示して下さった事柄である。そのような事柄に、疑問を持ったり、異を唱えたりする者がいるのであろうか。まさか、そのような愚か者は一人もおるまい。何故なら、それは主が語られた真理なのだから。」このような文言は律法の書にも見られる。すなわち、レビ記で「私は主である。」と書かれているのがそうである。このような文言は、その啓示の公布者が神であることを明白に宣言しているのである。
【25:9】
『その日、人は言う。「見よ。この方こそ、私たちが救いを待ち望んだ私たちの神。この方こそ、私たちが待ち望んだ主。その御救いを楽しみ喜ぼう。」』
『その日』とは新約時代である。ここでは『その日』と言われているが、これはある特定の1日だけを言っているのではない。
『人』とは新約時代における救われた聖徒たちである。これは、当然ながら救われていない者は含まれていない。それは、この『人』が言っている言葉の内容を見れば明らかである。
『見よ。』とは、その語られる事柄の重要性を示している。それというのも、ここでは救いのことが言われているからである。
ここでは、遂に約束されていた救い主が現われて下さったことについて言われている。その救い主なる神とは、もちろんイエス・キリストである。アダムの時から、この救い主がずっと予告されてきた。その救い主が遂に紀元1世紀の時に現われて下さったのだ。これについて何かを言わないままでいるということは、あってはならないのである。これは、少し例えが適切ではないかもしれないが、ずっと探し続けていた物が遂に見つかった際、次のように喜びつつ言うようなものである。「やっとだ。遂に私の探していたあの物があった。どれだけこれが見つかることを待ち望んでいたことだろうか…。」
この箇所では、この救い主の現われについて2回繰り返して言われている。すなわち、『この方こそ、私たちが救いを待ち望んだ私たちの神。』という部分が1回目であり、『この方こそ、私たちが待ち望んだ主。』という部分が2回目である。これは、どれだけ約束されていた救い主の現われが待ち望ましかったか、ということを示している。
キリストのこの救いについて、この箇所では『楽しみ喜ぼう。』と言われている。キリストの救いとは、つまり罪の洗い清め、サタンの支配からの解放、地獄から天国へと行き先を変えること、神との和解、永生の獲得である。この救いにおける幸いは、あらゆる幸いを凌駕している。我々は、この地上における事柄において『楽しみ喜ぼう。』などとよく言うものである。例えば、ディズニーランドに来たから大いに楽しもうとか、今夜は宴会だからわいわい喜びましょうや、などと。であれば、どれだけキリストの救いについては『楽しみ喜ぼう。』と言わねばならないであろうか。
【25:10】
『主の御手がこの山にとどまるとき、わらが肥だめの水の中で踏みつけられるように、モアブはその所で踏みつけられる。』
『主の御手』とはイエス・キリストである。何故なら、我々人間が自分の手で何かを実現させるように、神は御自身の御子において救いを実現されたからである。イザヤ53:1の箇所でキリストが『御腕』と呼ばれているのも、これと一緒の理由からである。だが、聖霊の場合は違う呼び方がされている。聖霊は「指」である。「指」もキリストを意味しているのではないから、注意せねばならない。
『モアブ』とは、周知の通り、ユダヤ人にとって不俱戴天の敵であった。彼らは幾度となくユダヤを滅ぼそうとした。この言葉は、モアブ人として単体的に捉えてもよい。しかし、これを悪者の全体として捉えるならば、そちらのほうが遥かに望ましい。つまり、ここでは『モアブ』と言って全ての悪者を表示していると考えるのである。これは提喩法という聖書ではよく使われている語法である。それというのも、ここでモアブについて言われていることは、その他の悪者たちにおいても同じことが言えるからだ。
この箇所で言われているのは、イエス・キリストが現われた新約時代においては、福音を信じた聖徒たちに比して悪者どもが低められるということである。それまで悪者たちは、神の聖徒たちに対して高ぶり、軽蔑の念を持っていた。しかし福音が明らかにされると、もはやそのようなことは出来なくなる。何故なら、キリストの福音によって信じる者たちは天高く引き上げられるからである。そうして引き上げられた聖徒たちは、その足の下にモアブを始めとした悪者どもを踏み置くのである。このようにして悪者どもは、神の御前において大いに低められるのだ。
【25:11】
『泳ぐ者が泳ごうとして手を伸ばすように、モアブはその中で手を伸ばすが、その手を伸ばしてみるごとに、主はその高ぶりを低くされる。』
ここではモアブが、泳ごうとして手を振り回す者に例えられている。これはどういう意味か。イザヤが言っているのは、モアブが聖徒たちを引き裂こうとして腕を動かすことである。それは泳ぐ者に似ているのだ。だが、神はそのようなモアブの振る舞いを無意味なものとされる。何故なら、信じる者たちは福音において高められ、キリストにおいて守られるからである。だから、モアブは信仰者たちを攻撃しようとしても無様な振る舞いをするだけとなる。こうしてモアブたちは、神の御前において低められるのである。ただ意味もなく手を振り回すだけの状態ほど滑稽なものはないのである。
【25:12】
『主はあなたの城壁のそそり立つ要塞を引き倒して、低くし、地に投げつけて、ちりにされる。』
『あなた』とは文脈から考えるならばモアブを指している。これをイスラエルと捉えることは出来ないであろう。何故なら、ここではモアブの屈辱・悲惨について語られているのだから。
この箇所では、モアブの高ぶった誇りが『城壁のそそり立つ要塞』として描かれている。何故なら、誇りとは、人を屈辱や軟弱から守ってくれる精神的な要塞だからである。この誇りがあるからこそ、人は、要塞の中にいる人のように堂々としていられるのだ。しかし、聖徒たちに対するモアブのそのような誇りは、御前においてまったく打ち砕かれる。そのことが、ここでは『城壁のそそり立つ要塞を引き倒して、低くし、地に投げつけて、ちりにされる。』と言われている。それは、聖徒たちがキリストにおいて高められているのに、モアブはそのようなっていないからである。だから、御前においてモアブが聖徒たちよりも上にいる者であるかのように誇ることは出来ないのである。
【27:1】
『その日、主は、鋭い大きな強い剣で、逃げ惑う蛇レビヤタン、曲がりくねる蛇レビヤタンを罰し、海にいる竜を殺される。』
これから見ていくイザヤ書27章は非常に重要である。そこでは、再臨の時に起こるユダヤの救いが預言されているからだ。しかも、そこではパウロがローマ書で引用した重要な箇所も含まれている。それゆえ、この27章を無視することは決してできない。
ここでは『海にいる竜』また『レビヤタン』が主により裁かれ殺される、と言われている。これは何のことか。これは、エジプト王のパロが紅海の水に呑み込まれて滅ぼされたことを言っている。つまり、これはモーセがまだ生きていた昔の出来事である。しかし、どうしてこの竜がパロを指していると分かるのか。それはイザヤ51:9~10の箇所で次のように書かれているからである。『さめよ。さめよ。力をまとえ。主の御腕よ。さめよ。昔の日、いにしえの代のように。ラハブを切り刻み、竜を刺し殺したのは、あなたではないか。海と大いなる淵の水を干上がらせ、海の底に道を設けて、贖われた人々を通らせたのは、あなたではないか。』ここでは、確かに『主の御腕』であられるイエス・キリストにより、紅海のあの奇跡の時、竜であるパロが滅ぼされたと言われている。聖書の他の箇所でも、やはりパロが竜として語られている(エゼキエル29:3、32:2)。どうしてパロが竜と呼ばれているかと言えば、パロはナイル川を支配しているかのように感じられる傲慢な竜すなわち「鰐」のように振る舞っていたからである(※①)。主がパロに対して、『あなたは海の中の竜(または鰐)のようだ。』(エゼキエル32:2)と言われた通りである。なお、聖書においてナイル川は海と呼ばれている。このパロが『逃げ惑う蛇』と言われているのは、パロが紅海の水に呑まれた際、蛇のように逃げようとしたからである。また『曲がりくねる蛇』と言われているのは、パロが神の前で蛇のように曲がりくねった陰険な者だったからである。『レビヤタン』とは、ナイル川にいた鰐のことである。ホッブスがあの有名な著作を「リヴァイアサン」と名付けたのは、これから取られている。(※②)このパロを、主イエス・キリストは紅海における奇跡の際、『鋭い大きな強い剣で』殺された。この『剣』とは御言葉である。何故なら、聖書において御言葉は剣として象徴されているからである。つまり、主は御言葉においてパロに裁きを下される際、紅海の水を裁きの道具としてお用いになられたのである。だから、この剣は実際的な剣を意味しているわけではない。
(※①)
エゼキエル29:3、32:2の箇所でパロが『竜』と言われているのは『鰐』とも訳せる。
[本文に戻る]
(※②)
ヨブ記でも、このレビヤタンについて語られている(41:1)。ヨブ記でも、やはり『レビヤタン』ではなく『鰐』とも訳すことが出来る。この獣は、ヨブ記において有名である。何故なら、レビヤタンについてこれまで語ってきた人は、そのほとんどがヨブ記に基づいてレビヤタンを語ったからである。我々が今見ているイザヤ書27章に基づいてこの獣を語った人は、ほとんどいない。というのも、イザヤ書27章は難しいので、なかなか記憶されにくく、そのため想起されにくいからである。
[本文に戻る]
しかしながら、ここでは直接的な意味でパロの死滅について言われているのではない。これは当然である。何故なら、パロが殺されたのは昔のこと、既に起こったことだからである。もう起きた出来事と全く同様の出来事が再び起こるというのは有り得ない。それは意味が分からないからである。ここで言われているのは、つまりパロの出来事が起きた時のように、ユダヤ人たちは敵の手から救い出される、ということである。要するに、ここでは昔の話を引き合いに出して、未来に起こる出来事を預言しているわけである。だから、ここでパロについて言われているのは単なる例えに過ぎない。それで、その救いというのは、既に述べたように再臨の時に起こるユダヤの救いである。これについてイザヤ27章では語られている。このように理解していないと、この27章を正しく捉えることは出来ないであろう。
ここではパロが3通りの仕方で言い表されている。すなわち、『逃げ惑う蛇レビヤタン』と『曲がりくねる蛇レビヤタン』と『海にいる竜』の3つである。これはパロの存在を強調している。どうして神はパロを強調して語られたのか。それは、このイザヤ27章ではパロにおいて表示されている敵からの救いが預言されているのであって、その救いは非常に重大な事柄だからである。黙示録18:2の箇所でも、同じ仕方により悪霊の存在が強調されている。すなわち、そこでは『悪霊』また『あらゆる汚れた霊ども』また『あらゆる汚れた、憎むべき鳥ども』と言われている。これはどれも悪霊という一つの存在を、3つの異なる言葉で言い表すことにより、その悪霊を強調しているのである。
この27:1の箇所は、かなり解釈が難しい。だから、よく考えないと、ここでは何が言われているのか全く分からない。この箇所は、私が今述べたように解釈すべきである。
【27:2】
『その日、麗しいぶどう畑、これについて歌え。』
ここではユダヤの未来に起こる事柄を預言せよ、と言われている。『歌え』とは「預言せよ」という意味である。『麗しいぶどう畑』とはユダヤのことを言っている。神にとって、ユダヤは素晴らしい葡萄畑のように好ましかったからだ。我々が素晴らしい葡萄畑を持っていたとすれば、心楽しく、見るにも楽しいはずである。植物を眺めたり育てたりすることにより喜びが生じる性質は、誰の心にも備わっているものである。神の御前で、ユダヤはそのような葡萄畑のようであった。
ここで『歌え』と言われていることから、イザヤ書27章の預言は喜ばしい預言であることが分かる。何故なら、歌うとは喜ばしいことだからである。だから、もしここで悲しい預言が語られていたとすれば、この27:2の箇所では「これについて嘆け。」と言われていたはずである。
【27:3】
『わたし、主は、それを見守る者。絶えずこれに水を注ぎ、だれも、それをそこなわないように、夜も昼もこれを見守っている。』
神は、ユダヤという葡萄畑を見守り、養い、心にかけられる御方である。葡萄や葡萄酒の好きな葡萄畑の主人であれば、その葡萄畑を熱心に整備し、怠ることはないはずである。神も葡萄畑の主人も、愛しているから四六時中それを心にかけるのだ。というのも愛とは、犠牲を惜しまず、その対象に自己を集中させることだからである。愛してもいないのに、どうしてわざわざ心をそれに費やすことが出来るであろうか。神がユダヤを愛しておられたということについては、神がユダヤについて次のように言われたことから分かる。『永遠の愛をもって、わたしはあなたを愛した。それゆえ、わたしはあなたに、誠実を尽くし続けた。』(エレミヤ31章3節)『わたしはほんのしばらくの間、あなたを見捨てたが、大きなあわれみをもって、あなたを集める。怒りがあふれて、ほんのしばらく、わたしの顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛をもって、あなたをあわれむ。』(イザヤ54章8節)『わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛している。』(イザヤ43章4節)
ところで、神はどうしてユダヤを愛されたのか。これは、神がユダヤを愛されたからだ、としか言いようがない。私は次のような質問をしたい。私はどうして「私」として造られ、あなたはどうして「あなた」として造られたのか。これは、私が「私」として造られたから、またあなたが「あなた」として造られたから、としか言いようがないであろう。誰もそれ以外の理由を知りえないはずである。神がユダヤを愛されたのは神がユダヤを愛されたからであるというのも、それと同じことである。
【27:4】
『わたしはもう怒らない。』
神は、それまでずっとユダヤに怒ってこられた。すなわち、出エジプトからローマ軍によるユダヤ陥落の時までずっと、である。それは、ユダヤ人が神に従おうとしなかったからである。だが、神は『わたしはもう怒らない。』と言われた。これは、再臨の時にユダヤの罪が取り払われるからである。ゼカリヤ6:8の箇所でも、再臨の時には神の怒りが静まると言われている。これは当然である。何故なら、罪が抹消されるならば、その罪により生じていた怒りも消し去られるのは自然なことだからである。既に再臨は起きたので、もう既にユダヤに対する神の怒りも静められている。すなわち、再臨の時に救われたユダヤ人において既に神の怒りは静まったのである。これこそ真に聖書的な理解である。
『もしも、いばらとおどろが、わたしと戦えば、わたしはそれを踏みつぶし、それをみな焼き払う。』
『いばらとおどろ』とは邪悪な者を指している。それは次に示す聖句を見れば明らかである。『よこしまな者は、いばらのように、みな投げ捨てられる。手で取る値うちがないからだ。』(Ⅱサムエル23章6節)つまり、これは単なる象徴表現であって、文字通りの意味で植物が言われているのではない。
この茨とオドロで象徴されている邪悪な者が神と『戦えば』、つまり神に逆らって立ち向かうならば、神はその者どもを『踏みつぶし』、『焼き払う』、つまり殺して滅ぼされる。これは当然である。何故なら、その者たちが神に戦いを挑んでいるからである。無敵の神に立ち向かって滅ぼされずに済む者など誰もいない。我々人間は、蚊や蠅が自分に立ち向かって来たならば、容赦なく滅ぼすであろう。であれば尚のこと、神はご自分に立ち向かう邪な者を滅ぼされるのだ。
これは実際その通りになった。神に逆らい続けた茨とオドロであるユダヤ人たちは、紀元70年において容赦なく滅ぼされてしまった。神に踏み潰され、焼き尽くされてしまった。彼らの滅亡は、一般的に考えればローマ軍による侵攻のゆえだったと言えるかもしれない。だが、そのローマ軍による侵攻は、神の裁きを代行する意味として実現された。だから、ローマ軍によるユダヤの滅亡は、究極的に言えば神がその出来事の作成者であられる。つまりローマ軍は単なる神の報復の道具に過ぎなかった。これは既に註解された黙示録17:16~17の箇所を見れば明らかである。
【27:5】
『しかし、もし、わたしのとりでにたよりたければ、わたしと和を結ぶがよい。和をわたしと結ぶがよい。』
『とりで』とは神の救いのことである。人が砦の中に入れば物理的に安全であるように、神の救いという砦の中に入ればその人は霊的に安全なのである。箴言18:10の箇所でもこう言われている。『主の名は堅固なやぐら。正しい者はその中に走って行って安全である。』ここでは、神の救いの中に入りたければ神と和解せよ、と言われている。その和解の手段はイエス・キリストに対する信仰による。このキリストへの信仰なしに、人が神と和解し、神の尊い救いという砦の中に入ることは全くできない。何故なら、人が神と和解するための仲介者として定められているのは、このイエス・キリストお一人以外には存在しないからである。Ⅰテモテ2:4の箇所で、『神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリスト・イエスです。』と書かれている通りである。
ここでは和解をするようにと2回言われている。これは神が大いに和解を望んでおられることを意味している。
パウロがⅡコリント5:20の箇所で言ったことは、恐らくこの箇所に基づいているのではないかと思われる(パウロが旧約聖書に基づいて多くのことを語ったのは、聖書を読み慣れている者には周知のことである)。それというのも、パウロが言ったことはイザヤ27:5の箇所と内容的に似ているからだ。パウロはそこでこう言っている。『私たちは、キリストに代わって、あなたがたに願います。神の和解を受け入れなさい。』確かにパウロも神と和を結ぶようにと言っている。
【27:6】
『時が来れば、ヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出し、花を咲かせ、世界の面に実を満たす。』
『時が来れば』、つまりキリストの再臨が起これば、ユダヤは救われるようになる。ここではその救いが、植物の実りに例えられている。誰でも自分の蒔いた種が生長して地面を実で満たせば、やっぱり喜ぶものである。そのような幸いが、ユダヤの救いの時には起こった。だから、ここで言われている植物への言及は単なる象徴表現に過ぎない。この救いは未だに実現していないと、今の教会は考えている。だが、そのように考えるのは誤っている。ユダヤの回復をもたらす再臨は既に起こったのだから。これは、まだ天動説が主流だった時代の人たちが、地動説について聞かされるのと同じである。地動説という宇宙論の真実が語られた際、それが語られたにもかかわらず、多くの人はなかなか認めようとしなかったのである。非常に合理的で認めざるを得ないのに、である。私がユダヤの救いについて語ったのに、なかなか認めようとする人が出ないのも、これと同じである。
『ヤコブ』と『イスラエル』とは、どちらもユダヤの民である。これは「ヤコブを父祖として持つ者」また「イスラエルの家系に属する民族」というほどの意味である。これは、ちょうど「パパ」とか「キリストの代理者」とか「カトリック教会の首領」などと複数の異なる呼称があっても、一人の教皇だけを意味しているのと同じである。
【27:7】
『主は、イスラエルを打った者を打つように、イスラエルを打たれただろうか。あるいは、イスラエルを殺した者を殺すように、イスラエルを殺されただろうか。』
『イスラエルを打った者』また『イスラエルを殺した者』とは、イスラエル王国を滅ぼしたアッシリヤ帝国を指す。イスラエル王国の滅亡は、正に打たれること、殺されること、であった。その出来事が起きたのは紀元前720年である。イザヤがこの預言を語った時に、もう既にこの出来事は起きていた。
アッシリヤの場合、打たれたり殺されたりして滅びたら、それで終わりであり、神は彼らを顧みられない。それは、ちょうどゴミを捨てたならば、もう2度とそのゴミについて考えなくなるのと同じである。というのもゴミとは価値がなく忌まわしいとさえ思えるからだ。アッシリヤも、神の前ではそのようなゴミ同然であった。だから実際、アッシリヤはすぐ滅亡したが、神は彼らを全く惜しまれなかった。このためアッシリヤは歴史の途中で葬り去られ、過去の遺物と化したのである。しかし、イスラエルはそうでなかった。神はイスラエルが滅ぼされてからも、イスラエルを心にかけ続けられた。だから、イスラエルはアッシリアのように過去の遺物とはならなかった。それというのも、イスラエルはゴミであるかのごとくになったものの、ゴミではなかったからである。これは、ある夫の妻が不倫をしたにもかかわらず、夫がそれまでと変わらず妻を愛しているのと似ている。その妻はどうしようもない愚行を仕出かしたのだが、だからといって夫にとってその妻がどうでもよい存在になったわけではないのである。
【27:8】
『あなたは彼らを追い立て、追い出し、彼らと争い、東風の日、激しい風で彼らを追放された。』
ここで言われているのは、アッシリヤ捕囚によりイスラエルの人たちが四方に散らされたことである。その離散は、神がイスラエルを追放されたから起きたとここでは言われている。律法では、神に従わないならば罰として散らされると威嚇されていたが、それが現実となったのだ(申命記28:64~65)。この四方への離散を、ここでは風に吹き飛ばされる出来事として描いている。このように離散と追放を風に吹き飛ばされるという象徴において語るのが聖書の通例である。というのも、その出来事は風に塵や木の葉が吹き飛ばされるのとよく似ているからである。それゆえ、我々はここで言われていることを読んで、実際にイスラエル人が風に吹き飛ばされて四方に散らされたなどという幼稚な想像をしてはならない。そのような空想的出来事は、コミック雑誌の中だけに限定されなければならないのである。
【27:9】
『それゆえ、次のことによってヤコブの不義は赦される。祭壇のすべての石を粉々にされた石灰のようにし、アシェラ像と香の台をもう立てなくすること、これが、自分の罪を除いて得られる報酬のすべてだ。』
再臨の時、イスラエルが犯した偶像崇拝の罪は全て取り除かれた。イスラエルは、偽りの神々のための石の『祭壇』を持っていた。これは死と滅びを招く罪であった。また彼らは、『アシェラ像』という偶像とその偶像に煙を焚くための『香の台』を立てていた。これも死と滅びを招く恐るべき律法違反であった。神は、これらの罪に対して怒られ、それをずっと覚えておられた。だが、再臨の時にこれらの罪は全て抹消されることになった。何故なら、その時、神は救われたユダヤ人においてユダヤを完全に赦されたからである。
この箇所は、パウロが再臨について書かれたローマ書11:26~27の箇所で引用している(とは言っても、かなり自由な引用である)。そこではこう書かれている。『…こうして、イスラエルはみな救われる、ということです。こう書かれているとおりです。「救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬虔を取り払う。これこそ、彼らに与えたわたしの契約である。それは、わたしが彼らの罪を取り除く時である。」』このパウロの言葉が再臨について言っているということを疑う聖徒は絶対にいないはずである。だから、私はイザヤ27章が再臨の時のことについて言われた箇所だと言ったのだ。何故なら、パウロは再臨について語る際に、このイザヤ27章に書かれている箇所を引用したのだから。このローマ書の箇所については、また後ほど註解される。
この箇所は、直接的にはユダヤの救いについて言われている。だが、この箇所からは、ユダヤに限定されない普遍的な悟りを得ることが出来る。それは、<罪を除いて得られる報酬は、罪が除かれること自体にある>という悟りである。つまり、罪が除かれるということは、それ自体で本質的な事柄である。それは本来的に、何か別の目的を実現させるために、付随的な解決方法として為されるべき事柄ではない。それは、それ自体が、それ自体において目的とされるべき事柄なのである。だから、「罪を除いたとすれば私は何の益を得られるのだろうか。」などと思う人は、よく事を弁えていない。罪を除いて得られる益は、その罪が除かれることにあるのだから。それというのも罪とは存在するものの中で最悪のものだからである。この罪が、これこそが、我々に死と悲惨と呪いと地獄とを入らせた。もしこれさえなければ我々に不幸は塵ほどもなかった。つまり、罪とは不幸の母なのである。だから、罪が除かれることは、それ自体で既に幸せであり益なのである。この箇所でも言われている通り、ユダヤから偶像崇拝が排除されるのは、それ自体が『報酬のすべて』であった。我々は霊的な事の本質をよく弁えなければならない。
【27:10】
『城壁のある町は、ひとり寂しく、ほうっておかれる牧場のようになり、荒野のように見捨てられる。』
『城壁のある町』とはエルサレムである。そこには城壁が築かれていたから。このユダヤの城壁は、ポンペイウスに侵略された後で、より堅固にされていた。それはあまりにも堅固だったので、ユダヤ戦争の時にローマ軍を悩ませた。
ここではエルサレム陥落について預言されている。その時、エルサレムは『ひとり寂しく、ほうっておかれる牧場のようになり、荒野のように見捨てられ』てしまった。確かにローマ軍に滅ぼされたユダヤは悲しさの漂う牧場のようになった。ヨセフスは、かつてそこには何かがあったとは思えないほどに荒廃させられた、と言っている。また、そこは神から荒野のように見捨てられた。ユダヤ人が背きに背きを重ねて御子をさえも殺したので、彼らはもう神から飽きられ、顧みられなくなったのである。それだから、この箇所の預言は既に成就されている。我々は、この預言がまだ成就されていないかのように考えたりしないようにせねばならない。
『子牛はそこで草をはみ、そこに伏して、木の枝を食い尽くす。』
『子牛』とはローマ兵である。黙示録やダニエル書で言われているように、ローマとは「獣」なのだから。『木の枝』とはユダヤである。パウロはローマ11:24の箇所でユダヤを『栽培されたオリーブの木』と言っているし、ダビデも自分のことを『オリーブの木』(詩篇52:8)と言っている。
『子牛はそこで草をはみ』と書かれているのは、ローマ兵によりユダヤが真っ平らな牧場のようにされたことを言っている。だから、ローマという子牛がそこで草を食むようになったのだ。もちろん、ローマが草を食むというのは、あくまでも分かりやすさのための単なる表現である。この子牛が『木の枝を食い尽くす』と書かれているのは、ローマ兵がユダヤを滅ぼし尽くすことを言っている。子牛が木の枝を食い尽くせば、その木は滅茶滅茶になってしまう。ユダヤがローマに滅ぼされたのも、正にそのようであった。
【27:11】
『その大枝が枯れると、それは折られ、女たちが来てこれを燃やす。』
『大枝』とはユダヤである。何故なら、これは前の節で言われていた『木の枝』と同じ存在であるから。『女たち』とは、この箇所においては聖徒たちである。聖書は、聖徒たちをキリストの妻・配偶者・花嫁として取り扱っている。だから聖徒とは主と契約を結んでいる霊的な女なのである。だが、聖書の中で「女」と書かれていたら、その全てが聖徒を意味しているわけではない。これは言うまでもないことであろう。
この箇所では、再臨の際に起こるユダヤの裁きについて預言されている。『大枝が枯れると』。これはユダヤが神から飽きられたことを言っている。彼らがキリストを拒絶したので、神はもう彼らに愛想を尽かしてしまわれた。だから、神という根から切り離されたユダヤという大枝は枯れたわけである。『それは折られ』。これも神がユダヤを捨てられたことを言っている。パウロも、このような意味合いでユダヤが折られたと語っている(ローマ11章)。『女たちが来て』。これは再臨のキリストと一緒に天から聖徒たちが降りて来たことを言っている。ユダ14、Ⅰテサロニケ4:14。『これを燃やす』。これは、再臨のキリストと共に天から降りて来た聖徒たちが空中の座に着き(黙示録20:4)、審判を下してイスラエルの12部族を焼き尽くしたことを言っている(マタイマタイ19:28)。歴史が示している通り、その時、ユダヤは本当に文字通りの意味で燃やされてしまった。
『これは悟りのない民だからだ。』
ユダヤが神の裁きにより燃やされたのは、ユダヤに悟りが無かったからである。この世では、「悟り」と言えば、ノウハウや経験や知識に基づく一般的な知恵のことを意味している。例えば、古代中国の孫子は正に「悟りの人」であった。彼の書いた「孫子の兵法」を読むと、彼のように悟りを多く持っている人はなかなか珍しいと思わされる。だから、この書は今に至るまでずっと読み続けられている。しかし、聖書が教える悟りは、このようなものではない。聖書の教えている悟りとは、神を恐れ、罪から離れることを言う。聖書には次のように書かれている。『こうして、神は人に仰せられた。「見よ。主を恐れること、これが知恵である。悪から離れることは悟りである。」』(ヨブ28章28節)だから、孫子のように一般的な悟りを多く持っていても、霊的な悟りは持っていないのであれば、その人は真の意味において悟りある者ではない。むしろ、愚者である。何故なら、その人は最も恐れるべき存在である神を恐れず、あらゆる不幸の源泉である罪から離れようとしないからである。ユダヤには、この悟りが無かった。だから、ずっと神を恐れず、罪の道から遠ざかろうとしなかった。このため神はユダヤを滅ぼしてしまわれたのである。その滅びにおいて、『御言葉を蔑む者はその身を滅ぼす。』という箴言の御言葉が、ユダヤの上に実現された。もしユダヤが悟りを持ってれば、このような滅びは免れていたであろう。というのも、神は悟りのある民を滅ぼされるような御方ではないからである。
我々も悟りを失ってしまえば、ユダヤと同じ運命を辿ることになる。滅ぼされ、捨てられ、悲惨になってしまうのだ。我々がそのような不幸を味わいたくなければ、神の御前で悟りを持ち続けるようにしなければいけない。
『それゆえ、これを造った方は、これをあわれまず、これを形造った方は、これに恵みを与えない。』
神は、もうユダヤに憐れみと恵みをお与えにならなくなった。だから、紀元70年においてユダヤが滅ぼされてから、もうユダヤは神に顧みられることがなくなった。ここで、神が一方的にユダヤに酷いことをなされたなどと考える者があってはならない。つまり、ユダヤを捨てられた神を悪者扱いすることがあってはならない。何故なら、神がユダヤを捨てられたのは、まず先にユダヤのほうから神を蔑ろにしたからである。神の側では、キリストが殺されるまで1300年もの間、彼らが悔い改めるのを待ち望んで耐えておられた。長らく耐え忍んで来られた神が遂にユダヤを捨てられたのは、ユダヤの致命的と言うべき不遜な態度に相応しい態度で応じられただけに過ぎない。その致命的な態度とは、ユダヤがキリストを拒んだことである。御子をさえも拒絶されたというのに、神が相も変わらずユダヤに憐れみと恵みを注がれ続けるとでも思うのか。とんでもない話だ。我々が自分の子を容赦なく殺した悪人に対して我慢したり慈愛を注いでやることが出来るのかどうか、よく考えていただきたい。要するに、悪いのは全的にユダヤである。神の側に非は塵ほども無かった。
この箇所では、神がもはやユダヤを顧みられないということが2回述べられている。これは、神がユダヤに愛想を尽かされたことを強調して言っているのである。このような言い方は福音書の中でも見られる(ルカ13:1~5、マタイ24:40~41)。
【27:12】
『その日、主はユーフラテス川からエジプト川までの穀物の穂を打ち落とされる。イスラエルの子らよ。あなたがたは、ひとりひとり拾い上げられる。』
この箇所では『穀物の穂を打ち落とされる』と言われている。これは何を言っているのか。言うまでもなく穀物の取り入れのことである。聖書では、穀物の取り入れにおいて携挙の出来事が語られている。例えば黙示録14:14~16の箇所では、聖徒たちの携挙について次のように言われていた。『また、私は見た。白い雲が起こり、その雲に人の子のような方が乗っておられた。頭には金の冠をかぶり、手には鋭いかまを持っておられた。すると、もうひとりの御使いが聖所から出て来て、雲に乗っておられる方に向かって大声で叫んだ。「かまを入れて刈り取ってください。地の穀物は実ったので、取り入れる時が来ましたから。そこで、雲に乗っておられる方が、地にかまを入れると地は刈り取られた。」』(※)このように聖書で携挙が穀物の取り入れに例えられているのは、携挙が正に取り入れのようだからである。すなわち、農夫が穀物を取り入れるべく実を引き上げて集めるように、神も救われた者たちを地上から引き上げて御自身のもとに集められた。この取り入れ以上に携挙の出来事を象徴させることができる営みはないと思われる。それだから、この取り入れについての言及は、文字通りに捉えられるべきではない。これは、あくまでも象徴として言っているに過ぎないのだから。
(※)
この箇所がまだよく理解できていない人は、再び第3部の当該箇所に立ち戻って祈りつつ熟慮すべきである。
[本文に戻る]
『その日』とは再臨と携挙が起こる日である。ここで『その日』と言われているのは、ある特定の1日として捉えてよい。それは紀元68年6月9日である。
ここでは『穀物』が『ユーフラテス川からエジプト川まで』の場所にあると言われている。これは、この箇所で言われている対象がユダヤ人たちであることを示している。何故なら、この範囲の場所はアブラハムに神が約束された場所だからである(創世記15:18)。ユダヤに約束された場所にある穀物がここでは言われているのだ。だから、ここで『ユーフラテス川からエジプト川まで』と言われているのはユダヤ人についての言及であることを示しているとせねばならない。もちろん、ここでは携挙されるのがユダヤ人だけであると言われているわけではない。ここでは単にユダヤ人を対象として語られているだけである。実際、携挙されたのはユダヤ人だけに限られなかった。その時には、世界中にいた諸国の民がキリストのもとに携挙されたのである。これはマタイ24:31の箇所を見れば明らかである。
ここでは救われていたユダヤ人の携挙について言われているが、携挙されなかったユダヤ人はどうなったのか。確かに携挙が起きた際には、地上に残されたままの人がいた(マタイ24:40~41)。そのユダヤ人たちは、ユダヤの場所に残され、もう間もなく『女たちが来てこれを燃やす』(イザヤ27:11)ことになった。つまり、エルサレム陥落の際に悲惨な死に方で死んだ。これこそユダヤに対する神の正当な裁きであった。ヘブル12:29の箇所では『私たちの神は焼き尽くす火です。』と書かれている。その時、神は焼き尽くす火として不敬虔なユダヤ人に臨まれたのである。その他の携挙されなかった異邦人たちは、それぞれが自分のいた場所で、ただ霊的な断罪を受けただけであった。だから、再臨が起きた時に異邦人たちは実際的には死ななかったのである。だが異邦人の中でもネロとティゲリヌスだけは例外であった。彼らはキリストが来られると、間もなく実際的な意味で殺されてしまった。これは既に註解された黙示録19:19~20の箇所から分かる。
【27:13】
『その日、大きな角笛が鳴り渡り、アッシリヤの地に失われていた者や、エジプトの地に散らされていた者たちが来て、エルサレムの聖なる山で、主を礼拝する。』
『その日』とは前の節で言われていたのと同じ意味であり、再臨と携挙が起こる日である。
再臨の際に起きた携挙には、エルサレム以外の遠くの場所にいたユダヤ人たちも与かった。ここでは、その例としてアッシリアとエジプトが挙げられている。この2つの場所はあくまでも分かりやすさのための例である。ここではこの2つの場所を挙げることで、あらゆる遠くの場所を示している。だから、エルサレム以外の場所では、この2つの場所にいたユダヤ人だけしか携挙されなかったということではない。実際、携挙が起きた際には、あちらこちらにいるユダヤ人たちがキリストのもとに集められた。ブリタニアにいたユダヤ人も、エチオピアにいたユダヤ人も、インドにいたユダヤ人も、中国にいたユダヤ人も、である。エルサレム以外の場所では、アッシリアとエジプトにいたユダヤ人しか携挙されなかったというのは滑稽な理解である。それは有り得ない。
ここでは遠くの場所にいるユダヤ人が『エルサレムの聖なる山』に集められると言われているが、これはキリストの救いにユダヤ人たちが異邦人と共に招かれるようになったということではない。イザヤ25:6~8の箇所で言われている『山』の場合であれば、そのような意味である。つまり、遂に実現されたキリストの救いに人々が世界中から続々と招かれる、ということである。だが、この箇所で言われているのは、天国という『エルサレムの聖なる山』にユダヤ人が携挙において招かれることである。この27章が携挙について言われているということについては、ここまでイザヤ27章の註解を読み進めた読者であれば既に理解しているはずである。だから、ここで『エルサレムの聖なる山』と言われているのは天国を指している。それは、黙示録14:1の箇所で『シオンの山』と言われているのが、天国を指しているのと全く一緒である。だがイザヤ書25:6~8の箇所で『山』と言われているのは、天国のことではない。そこで言われているのは、遂に実現されたキリストの救いのことである。
『大きな角笛が鳴り渡り』と書かれているのは、再臨の際に響き渡る大きな音を鳴らす楽器のことについてである。再臨の際には大きな音が鳴った。キリストはこう言われた。『そのとき、人の子のしるしが天に現われます。すると、地上のあらゆる種族は、悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見るのです。人の子は大きなラッパの響きとともに、御使いたちを遣わします。』(マタイ24章30~31節)パウロもこう言っている。『主は、号令と、御使いのかしらの声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られます。』(Ⅰテサロニケ4章16節)イザヤ書29:6でも、『万軍の主は、…大きな音をもって、…あなたを訪れる。』と言われている。再臨の時に使われる楽器が角笛ともラッパとも言われているのは、大きな問題ではない。我々は、ただ再臨の際には大きな音を鳴らす楽器が使われたとだけ理解していれば、それでよい。もしどうしてもこの点について気になる人がいれば、その人はこの楽器が角笛ともラッパとも呼べるような天の楽器だったと理解したらよい。我々の思い描くような楽器としてその楽器を想像しても、正確に想像できていない可能性が高いのだ。何故なら、我々のうち誰が御使いの使う楽器を正確に思い描けるであろうか。我々はその楽器を実際にその目で見たわけではないのである。また、その楽器による音がどれだけ大きかったかということについては、全く分からない。ただ非常に大きかっただろうことは間違いないと思われる。というのも、もし楽器の音が小さければ、栄光の再臨に相応しくないからである。小さな音しか鳴り渡らなければ、その卑小な音により、キリストの再臨からはその尊厳と栄光とが減ぜられることになるのだから。それは王が凱旋した際に、ラッパやシンバルではなく、リコーダーやカスタネットしか使わないことにより凱旋の栄光を損ねるようなものである。このようなミニマムな楽器と音は、凱旋式に相応しくないのである。
【29:1】
『ああ。アリエル、アリエル。ダビデが陣を敷いた都よ。』
ここから29:8までの箇所は非常に重要である。何故なら、そこでは再臨とエルサレム包囲について預言されているからだ。また、ここでは再臨の時にローマ軍に起こったことについても語られている。これは、再臨の理解を十全に持つためには、どうしても知っておかねばならない。再臨の探究者にとって、この29:1~8の箇所を無視することは許されない。この箇所を無視するのは、経済学で言えば、共産主義を学ぶ際に「共産党宣言」を無視するのと一緒である。つまり、とんでもないということが分かる。
『アリエル』とはエルサレムである。何故なら、『ダビデが陣を敷いた都』がアリエルだからである。この都はエルサレム以外にはありえない。また、後の箇所である29:8では『シオンの山』がアリエルだと言われている。『シオンの山』とはエルサレムである。だから、やはり『アリエル』とはエルサレムであると理解せねばならない。この『シオンの山』がエルサレムだということを分かっていない人は、初学者か今までほとんど聖書を学んでこなかった者か霊的におかしい者である。このアリエルという名前は、聖書の中でこのイザヤ29章だけにしか出てこない。しかし、どうしてエルサレムが『アリエル』などと言われているのか。これは神が不思議な御方であって、不思議な言い方をなされるからである。聖徒であれば、聖書の中でどれだけ不思議に感じられる言い方が書かれているか知らぬ者はいないはずである。それは、雄弁家が雄弁の術を駆使するのと同じである。つまり、神が不思議な語り方をされるのは本来的なことなのである。雄弁術を使わない雄弁家など考えられないように、不思議な語り方をしない神も考えられない。なお、言うまでもないかもしれないが『アリエル』とはヘブル語である。
『ああ。』という短い言葉は、嘆きの感情を示している。エルサレムが包囲されて滅ぼされることについて預言されるのだ。誰が『ああ。』と言って嘆かずにいられるであろうか。皇居かホワイトハウスが破壊されて消え失せてしまったと考えてみよ。誰もが「ああ。」と言って嘆くであろう。ここでエルサレムについて『ああ。』と言われているのは、それと同じことである。
ここで『アリエル、アリエル。』と繰り返されているのは強調である。このように強調するのは、事が非常に重要だからである。もし重要でなければ「アリエル」と1回だけ言われていただけだったはずである。
キリストがマタイ23:37~39の箇所で言っておられるのは、このイザヤ29:1~8の箇所と対応している。キリストも『ああ、エルサレム、エルサレム。』(マタイ23:37)と言って、エルサレムの滅びを嘆いておられるからだ。キリストが嘆かれた時、このイザヤ書29章を念頭に置かれていたのは間違いない。
『年に年を加え、祭りを巡って来させよ。』
これは、この預言が遠い未来に実現されることを教えている。これは次のように言ったも等しい。「これは多くの年が流れ、多くの祭りが行なわれてから起こる預言である。」これも不思議な言い方である。だから、よく考えないと、ここで何が言われているのか理解することは出来ない。
【29:2】
『わたしはアリエルをしいたげるので、そこにはうめきと嘆きが起こり、そこはわたしにとっては祭壇の炉のようになる。』
神がエルサレムをローマ軍により攻撃させられたので、そこには大きな悲惨が起きた。その時、『そこにはうめきと嘆きが起こ』った。これは実際の歴史を見れば明らかである。ユダヤ人がこのようになったのは当然であった。何故なら、その時に『町は取られ、家々は略奪され、婦女は犯され』(ゼカリヤ14章2節)たからである。この悲惨について詳しく知りたい人は、ヨセフスの書を読むとよい。また、その時にエルサレムは『祭壇の炉のように』なった。これは、エルサレムが祭壇の炉のように火で満たされたということである。これも実際に起きた。あるローマ兵が何気なく火を神殿に投げ込むと―最大の悲惨はしばしば一見すると何でもないような些事から生じる―、それがキッカケとなり、都が火の海と化すに至ったのである。
ここでは、エルサレムへの攻撃が「神の虐げ」だと教えられている。つまり、これは神がエルサレムを処罰されたということである。神は、ローマ兵を使ってエルサレムを裁かれたのだ。この虐げには正当な理由があった。それは、ユダヤが神を捨てたからである。ユダヤが神を捨てたので、神もそれに報いてユダヤを捨てられた。神を捨てるならば、罰を受けて失せ果てるしかなくなる。こう書かれている通りである。『そむく者は罪人とともに破滅し、主を捨てる者は、うせ果てる。』(イザヤ1章28節)ユダヤは神を見失い、憎んでいたので、当然の報いとして大きな破滅を受けるに至ったのである。こう神が言っておられる通りである。『わたしを見失う者は自分自身をそこない、わたしを憎む者はみな、死を愛する。』(箴言8章36節)つまり、神は何の理由もなしにユダヤを滅ぼされたのではない。もし何も理由がないのにユダヤを裁かれたとすれば、神は悪いことをする虐めっ子とほとんど変わらなかったであろう。だが、神は決してそのようなことをなさる御方ではない。『主は、その町の中にあって正しく、不正を行なわない。』(ゼパニヤ3章5節)と書かれている通りである。
このように神とは復讐される御方である。世の中を見れば分かるように、我々人間も復讐をしようとする。であれば、尚のこと、神は復讐される存在である。何故なら、我々人間とは神の似像として創造されたのだから。似像よりも原型のほうが、より大きな情動を持っているということは論を待たない。ここに一つの明白な実例がある。確かにユダヤは神の復讐により滅ぼされてしまった。我々はこのユダヤのようになりたいであろうか。なりたくない。であれば、我々はこのユダヤの悲惨を大いに教訓として忘れず、神の御心を損ねないように歩まねばならない。そうすれば、滅ぶのは我々ではなくて敵のほうになろう。何故なら、神は聖徒たちが正しく歩む場合、大いに味方して下さり、勝利を得させて下さるからである。ユダヤももし神に背いていなければ、神の働きかけにより、ローマに勝利を得ていた。それは次のように書かれている通りである。『あなたがたの神、主の命令、主が命じられたさとしとおきてを忠実に守らなければならない。主が正しい、また良いと見られることをしなさい。そうすれば、あなたはしあわせになり、主があなたの先祖たちに誓われたあの良い地を所有することができる。そうして、主が告げられたように、あなたの敵は、ことごとくあなたの前から追い払われる。』(申命記6章17~19節)この申命記の言葉が、カナン侵攻の時だけに限定されるべき内容ではなく、普遍的なことを言っているのは明らかである。
【29:3】
『わたしは、あなたの回りに陣を敷き、あなたを前哨部隊で囲み、あなたに対して塁を築く。』
ここではローマ軍によるエルサレム包囲のことが預言されている。これは第一次ユダヤ戦争で成就された。しかし、今の教会は、どこもこのことについて何も語ろうとしない。牧師の頭の中には、ユダヤ戦争のことなどほとんど思い浮かびもしないほどである。だから、何もその戦争について言及していないのだ。何故なら、今の教会は霊的に少しおかしくなっているからである。霊のレベルが明らかに低くなっている。アウグスティヌスの時代であれば、一般信徒の女性でさえ「神の国」を読んでいた。つまり、全体的な霊のレベルが高かったので、普通の姉妹でさえそのような書物を読むぐらいだったのである。だが今の時代では、牧師でさえ、そのような本を読もうとはしていない。これは経済学の教授であれば、アダム・スミスやリカードやケインズやミーゼスを読んでいないのと一緒である。つまり、とんでもないということが分かる。この箇所に書かれている語句の内容はあまりにも明白なので、いちいち説明する必要はないであろう。
ここではエルサレム包囲という一つの出来事が、違った言い方で3回も言われている。これはエルサレム包囲が非常に重要な出来事だからである。それはキリストも教えられたように前代未聞の出来事だったから(マタイ24:21)、このように3回も繰り返されたのは相応しいことであった。
この箇所は、キリストがルカ19:42~44の箇所で言われた御言葉と内容的に対応している。そこでキリストはエルサレムについて次のように言われた。『おまえも、もし、この日のうちに、平和のことを知っていたのなら。しかし今は、そのことがおまえの目から隠されている。やがておまえの敵が、おまえに対して塁を築き、回りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしておまえとその中の子どもたちを地にたたきつけ、おまえの中で、一つの石もほかの石の上に積まれたままでは残されない日が、やって来る。』今引用した箇所もそうだが、キリストの御言葉は、その全てが旧約聖書に基づいていると思われる。これはよく考えると当然であることが分かる。何故なら、旧約聖書の全ての箇所はキリストの御霊により書かれたのだから、キリストが語られることはどれも必然的に旧約聖書の内容と一緒にならざるを得ないのである。だから、旧約聖書を読めば読むほど、我々はどれだけキリストが旧約聖書に基づいて語っておられたかということを知れる。そうすると、ますますキリストの御言葉における真理性を感じることになる。そこには霊的な喜びがある。これは神が与えて下さる恵みによる。
それにしても、およそ800年も未来の出来事がこのようにあらかじめ語られるというのには驚かされる。これは神が語られたから出来たことである。もしこれが人間から出た預言だったとすれば、このような預言は語れていなかった。300人委員会のメンバーの一人でありロスチャイルドのお気に入りであったH・G・ウェルズでさえ、「世界はこうなる」という計画本の中で、この本が書かれてから約170年間のことしか取り扱えなかった(すなわち2106年6月6日までである―666の数字を年月の中に含ませたのは明らかに意図的である)。しかも、それは預言ではなく単なる計画または願望に過ぎないうえ、その中にはいい加減な内容もかなり含まれている(※)。博識であり陰謀の見識も多分に持っていたウェルズでさえこの程度であれば、800年も先の出来事を正確に言い当てたこの文章は正に神が語られたとしか言いようがないのである。人間の中では最高クラスに預言めいた話を語れるウェルズでさえ、たった170年後の未来ですら正確に言い当てられていないのであるから。
(※)
例えば、ウェルズは2100年になってもまだ世界人口が20億人ぐらいだと言っている。だが、2100年までまだ80年もあるのに、世界人口は今やもう80億人に達しようとしている。また彼は、今(2020年)ではもう世界政府の思想が普遍的になっていると予想している。だが、今の世界を見れば分かるように、世界政府の思想などほとんど誰も心に思い浮かべさえしていない。それについて思い浮かべるのは、陰謀家と陰謀について学んでいる者ぐらいなものである。更に、ウェルズは服装を買い替えるスパンが非常に短くなり、ずっと同じ服を何回も洗って着続けることはなくなる、とも言っている。これは文化的であり洗練された習慣だと思えるが(何故なら、そうしたほうが衛生的であり長く着続けることで生じる服装の欠損が見られなくなり、何よりも「新鮮」だからである)、今の世界を見ると、まだまだ全然実現されそうにない。ベッカムが下着を1回しか使わないと聞いただけで多くの者が驚いているぐらいである。下着でさえこうであれば、服装をすぐに捨てると聞いたらどれだけ驚くだろうか。詰まるところ、ウェルズは聖書に疎い霊的な死人であって、ソロモンが次のように言ったことをよく弁えていなかった。『何が起こるかを知っている者はいない。いつ起こるかをだれも告げることはできない。』(伝道者の書8章7節)
[本文に戻る]
ここで言われている包囲をローマ軍によるそれではなく、ネブカデレザルによるそれだったと考える人がいるかもしれない。確かにネブカデレザルの軍隊もエルサレムを包囲した。だが、ここで言われているのはネブカデレザルの時の出来事ではない。何故なら、この箇所(イザヤ29:1~8)では、再臨のことが預言されているからである(29:6)。再臨と関わりのある包囲は、ネブカデレザルの包囲ではなく、ローマ軍による包囲である。ネブカデレザルがエルサレムを取り囲んだ時には、キリストが『雷と地震と大きな音をもって、つむじ風と暴風と焼き尽くす火の炎をもって』(29:6)エルサレムを訪れるということは起きなかった。それが起きたのはローマ軍がエルサレムを取り囲んだ紀元1世紀の時だから、このイザヤ29:1~8の箇所で言われているのは明らかにネブカデレザルの出来事についてではない。
【29:4】
『あなたは倒れて、地の中から語りかけるが、あなたの言うことは、ちりで打ち消される。あなたが地の中から出す声は、死人の霊の声のようになり、あなたの言うことは、ちりの中からのささやきのようになる。』
ユダヤはローマ軍により『倒れて』、そこにいたユダヤ人たちは死んだので何も語れなくなってしまう。この箇所では、このことが3通りの表現で語られている。まず死んだユダヤ人たちの『言うことは、ちりで打ち消される』。これは、塵にも打ち消されるほどの小さな声しか出せなくなる、という意味である。塵に打ち消される声とは、聞き取れない無にも等しい声である。つまり、これはユダヤ人が何も言えなくなるということである。またユダヤ人たちが『地の中から出す声は、死人の霊の声のように』なった。これも、ユダヤ人たちが死んだので、何も語れなくなったことを示す。またユダヤ人たちの『言うことは、ちりの中からのささやきのように』なった。これも先の場合と同様の意味である。ここでは3回の繰り返しが見られる。神がユダヤの死滅を強調しておられるのだ。
ここで言われているのは、あくまでも比喩である。つまり、ここではユダヤ人たちが死んでからも声を出せるなどと言われているのではない。それは文字通りの捉え方であり、間違っている。ここでは確かにユダヤが語ると言われてはいる。だが、確かにユダヤが語るとは言われていても、その事柄は文章の中で打ち消されて無にされている。だから、ここではユダヤが喋らなくなると言われているのだ。
【29:5】
『しかし、あなたの敵の群れも、細かいほこりのようになり、横暴な者の群れは、吹き飛ばすもみがらのようになる。』
『敵の群れ』とはローマ軍を指している。ローマ軍はユダヤと戦っているユダヤの敵だったから。『横暴な者の群れ』もローマ軍を指している。ローマ人は、降伏した敵には寛大であったが、そうでない敵には正に食らい尽くす横暴なライオンであった。だから、諸国の王たちはそのようなローマを大いに恐れたのである。このため、中には元老院議員たちの前に来た際、奴隷の恰好をして女々しく媚びへつらった「王」さえもいたほどである。
キリストが再臨された際には、ユダヤだけでなく、ローマ軍にも裁きが与えられた。だからローマ軍は『細かいほこりのようになり、』『吹き飛ばすもみがらのように』なった。これは一体どういう意味なのか。これは、再臨されたキリストの前でローマ兵たちが低められるという意味である。何故なら、キリストが再臨された時、人はその御前で無に等しい存在として見做されたからである(イザヤ2:10~22)。埃や籾殻とは捨てるべきものであって、全く価値がない。ローマ兵たちは再臨の時にキリストの御前でそのようになったのである。それだから、ここで言われているのは比喩表現であると考えなければならない。ここでは実際的な事柄が言われているのではない。これが分からない人は恐らくいないはずである。
ここでローマ兵たちが『吹き飛ばすもみがらのようになる』と言われているのは、詩篇1:4の箇所を思い起こさせる。そこではこう書かれている。『悪者は、それとは違い、まさく、風が吹き飛ばすもみがらのようだ。』この詩篇の箇所では普遍的なことが言われているのであって、直接的な意味においてローマ兵のことが言われているのではない。何故なら、いつの時代であれ、どこの場所であれ、悪者は籾殻のように吹き飛ばされるからである。だから、この2つの箇所に直接的な対応性はない。
『しかも、それはにわかに、急に起こる。』
再臨に伴うローマ軍への裁きは、唐突に起きた。それが起きたのは紀元68年6月9日である。ローマ軍にいた兵士の中で、誰がこの日に再臨が起こるなどと考えただろうか。誰一人としていなかったのは間違いない。キリストでさえ、人としては、その日がいつなのか知っておられなかったぐらいなのである(マタイ24:36)。再臨の際、敵に対する裁きが急に起こるというのは、新約聖書の多くの箇所で教えられている。例えば次に示す箇所がそうである。『人々が「平和だ。安全だ。」と言っているそのようなときに、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが臨むようなもので、それをのがれることは決してできません。』(Ⅰテサロニケ5章3節)『洪水前の日々は、ノアが箱舟にはいるその日まで、人々は、飲んだり、食べたり、めとったり、とついだりしていました。そして、洪水が来てすべての物をさらってしまうまで、彼らはわからなかったのです。人の子が来るのも、そのとおりです。』(マタイ24章38~39節)
聖書は、悪者に対する神の裁きが突如として下されると教えている。それは、次のように書かれている通りである。『わが子よ。主と王とを恐れよ。そむく者たちと交わってはならない。たちまち彼らに災難が起こるからだ。このふたりから来る滅びをだれが知りえようか。』(箴言24章21~22節)『しかも、人は自分の時を知らない。悪い網にかかった魚のように、わなにかかった魚のように、人の子らもまた、わざわいの時が突然彼らを襲うと、それにかかってしまう。』(伝道者の書9章12節)実際に聖書を見てみると、どうだろうか。確かに、ノアの大洪水も、ヘロデ王の死も、ナバルの死も、ソドムとゴモラの滅びも、突如として起こった。それらには事前の前触れなどはなかった。だから、確かに神は悪者どもが予想もしていなかった時に大いなる災いを下されるということが分かる。しかし、どうして神はいきなり裁きを下されるのか。それは神の主権を如実に現わすためである。裁きの起こる時は神に知られているが、人はその時を予想できないので知らない。ここにおいて神の人に対する優越が示されるのだ。これは、先生が先生であるために、生徒たちに抜き打ちテストを仕掛けることが出来るのと一緒である。このようにされると、多くの生徒たちは驚いたり、不満を持ったりする。そして、その生徒たちは自分たちが下のほうにおり、先生は自分たちよりも上に位置していることを感じさせられるのだ。神が悪者に言わば抜き打ちで災いを下されるのも、これと同じである。
【29:6】
『万軍の主は、雷と地震と大きな音をもって、つむじ風と暴風と焼き尽くす火の炎をもって、あなたを訪れる。』
明白な再臨の預言である。『あなたを訪れる』とは、言い換えれば「ユダヤの場所に天から再臨される」となる。先にも述べた通り、この節が含まれているイザヤ29:1~8の箇所は、ネブカデレザルの時に起きた出来事を預言しているのではない。何故なら、いったい誰がネブカデレザルの時に再臨が起きたなどと考えるのであろうか。そんな人は一人もいないはずである。であれば、このイザヤ29:1~8の箇所ではローマ軍による包囲について言われていることになる。
マラキ3:1の箇所でも『あなたがたが尋ね求めている主が、突然、その神殿に来る。』と言われている。どちらでも唐突に主が来られると言われている。だが、マラキ書のほうで言われているのは再臨ではなく初臨のことである。何故なら、マラキの箇所では、バプテスマのヨハネが遣わされると言われたすぐ直後にキリストが来られると言われているからである。これはキリストの公生涯のこと以外ではない。
ここで言われている語句について見て行かねばならない。ここでは全部で6つの事柄が挙げられている。ここでの「6」には特に象徴的な意味は込められていないと思われる。まず、キリストは『雷』において来られた。スエトニウスの書を見れば分かるように、確かに再臨が起きた日には雷光が空に生じている。キリストは再臨が雷の閃きのようにして起こると言っておられた。『人の子の来るのは、いなずまが東から出て、西にひらめくように、ちょうどそのように来るのです。』(マタイ24章27節)これは、単に再臨が突如として起こるということを雷に例えて言っただけでなく、文字通りの意味で言ったことでもあったのだ。またキリストは『地震』において来られた。これもスエトニウスの書に書かれている通りである。この地震は、再臨が地でさえも揺らいでしまうほどの衝撃を持つ出来事だったことを教えている。黙示録やエゼキエル書でも、再臨の時には地震が起こると教えられている(黙示録16:17~18、11:13、6:12、エゼキエル38:19)。またキリストは『大きな音』において来られた。これは再臨の時に鳴り響く様々な音である(Ⅰテサロニケ4:16)。どこかの王が大勝利を得て凱旋するならば、楽器隊が喇叭を吹き鳴らして迎えるであろう。キリストという王が再臨された時にも、これと同じことが起きたのである。またキリストは『つむじ風』において来られた。この旋毛風は実際上のことを言っていると共に、再臨の唐突性をも示している。私は小さい頃に運動場で旋毛風が起きたのを見たことがあるが、事前の前触れなしに生じたのを覚えている。またキリストは『暴風』において来られた。これはキリストが風を大いに従えて天から降りて来られたことを言っている。つまり、この風とはキリストに仕える家臣のようなものである。何故なら、風とは聖書が教えるように神の僕だからである(詩篇104:4)。またキリストは『焼き尽くす火の炎』において来られた。既に述べたようにカルヴァンはこの火を単なる象徴表現としか理解していないが、それは間違っている。もしこの火を象徴として捉えねばならないとすれば、ここで書かれている他の5つの現象も同様に象徴として捉えるべきだということになるが、その5つの現象は既に見たようにどれも文字通りに捉えるべきものだったのだから、この火だけを例外扱いとすべきではない。6番目だけ象徴に過ぎないというのは明らかに不自然である。ところで、どうして神はここで「7」の項目が挙げられるようにしなかったのか、と思う人がいるかもしれない。確かに7にしていれば、それはそれで良かったであろう。だが、神はここで数字的な象徴の意味を組み入れなくてもよしとしておられる。その理由が何なのかはよく分からないが、とにかくここでは別に「7」を示す必要はなかったのである。もし示す必要があったならば、ここでは何かもう一つの現象が付け加えられていたことであろう。
【29:7~8】
『アリエルに戦いをいどむすべての民の群れ、これを攻めて、これを取り囲み、これをしいたげる者たちはみな、夢のようになり、夜の幻のようになる。飢えた者が、夢の中で食べ、目がさめると、その腹はからであるように、渇いている者が、夢の中で飲み、目がさめると、なんとも疲れて、のどが干からびているように、シオンの山に戦いをいどむすべての民の群れも、そのようになる。』
この箇所はあまりにも重要である。何故なら、ここでは再臨の時にローマ兵たちがどのようになったかということを教えているからである。もしこの箇所を無視するならば、我々からは再臨に関わる重要な理解が一つ抜け落ちてしまう。だから、この箇所を無視することは絶対に許されない。
語句の説明。『すべての民の群れ』とはローマ兵を指す。彼らは多くの国民から成り立っていたから。『シオンの山』とはエルサレムである。『夢』また『幻』は、それが取るに足らない一時的な幻想として見做されたことを言っている。
ローマ兵たちにとって、キリストの再臨は夢また幻のようであった。すなわち、彼らはキリストとその軍勢を空中の場所に見たが、あたかも夢や幻を見ているかのように思った。『飢えた者』や『渇いている者』が夢の中で食べたり飲んだりしても、実質的には何も起こっていない。それと同じで、ローマ人たちにも再臨されたキリストとその軍勢は、実質なき事象として認識されたのである。これが再臨を見たローマ兵たちにおける真実である。しかし、どうしてローマ兵たちに再臨の出来事は幻想のように思えたのか。それは、再臨の出来事があまりにも非日常的だったので、現実の光景とは感じられなかったからである。今、我々が当時のローマ兵だったとしてみよう。きっと我々も再臨の光景を怪しんでいたはずである。なお、ここで『飢えた者』また『渇いている者』と言われているのは、ローマ兵たちを示している。また『夢』また『幻』と言われているのは、すぐ前の節で書かれていた再臨のことである。
実に、これこそローマ兵たちが誰一人として再臨についての記録を書き残さなかった理由である。確かなところ、ローマ人とは真面目で文化的で大人びた人たちであって、幻想などという取るに足りないものをいちいち記録するような人たちではなかった。もちろん、ローマ兵たちには幻想だと感じられたとしても、実際にキリストの再臨は幻想ではなく現実だったのであるが。そもそも、当時のローマ兵たちの中で文字を書ける人がどれだけいたのか。識字率がまだ低かった昔の時代だから、恐らく多くの兵士たちが文盲だったと思われる。しかも、この時のローマ兵たちはユダヤを制圧しに来たのであって、何かを記録するということを目的とはしていない。戦争とは記録のためではなく勝利と平和と解決のためになされるのである。であれば、再臨を見たローマ兵たちが何も記録を残していなかったとしても不思議なことではない。だが、有り難いことにヨセフスとタキトゥスが再臨に関する記録を残してくれている。特にタキトゥスの記述は強力である。何故なら、タキトゥスほどの歴史家が、取るに足らない出鱈目な空想話を記録して、わざわざ自分の歴史書を汚すなどということは考えられないからである。言うまでもなく、タキトゥスはそれが真実であると思ったからこそ、それについて臆することなく書き記したのである。ポリュビオスが言ったように、歴史家また歴史書の使命は真実を記録するという点にあるのだから(※)。タキトゥスがこのことを弁えていなかったということが、一体どうしてあるだろうか。再臨が起きた証拠としては、高名なこの2人の証言があるだけで十分である。
(※)
「歴史家というのはことさらに奇異な事を語って読者を驚かせようとしてはならないし、悲劇作家のように信憑性の不確かな弁論を作中に取り入れたり、主題に付随する事柄をすべて並べたりするべきではなく、むしろ現実に行なわれたことと言われたことを、たとえそれがどんなにありふれた事柄であっても、そのまま記録するのを第一の務めとすべきである。なぜなら歴史の目的と悲劇の目的は同じではなく、むしろ正反対だからである。すなわち悲劇は、魅力に富む言葉によって一時の間、聴衆の心をつかみ揺り動かすのを目標とするが、歴史は真実の行動と言葉により学徒を永遠にわたって教え諭すのを目的とする。悲劇を先導するのは魅力する力であり、たとえそれが偽りであっても観衆を幻惑できればそれでよいのだが、歴史は真実を導き手とし、学徒に利益をもたらすことをめざすのである。」(ポリュビオス『歴史1』第2巻:56、10~12 p210:京都大学学術出版会 西洋古典叢書 第Ⅲ期第8回配本)
[本文に戻る]
この箇所で言われていることは、聖書の中で他に対応している箇所がない。つまり、ローマ兵たちが再臨を幻想のように感じたと教えられているのは、聖書の中でここだけである。それゆえ、この箇所はあまりにも重要であることが分かる。この箇所では、この箇所を読まない限り決して分からないことが書かれているのだから。
イザヤ29章は、これ以降、註解する必要がない。これ以降の箇所そのものは註解されるべきなのだが、少なくとも本書においてはその必要がないということである。何故なら、本書は再臨について取り扱っているのであり、29:9以降の箇所はあまり再臨とは関係のない事柄が書かれているからである。実際にその箇所を見ると、ユダヤ人が頑なにされたことやキリストの救いなどについて預言されている。その箇所については、他の人の註解書で学べばよい。
【60:19~20】
『太陽がもうあなたの昼の光とはならず、月の輝きもあなたを照らさず、主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの光栄となる。あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月はかげることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。』
この箇所は、明らかに黙示録21:23の箇所と対応している。そこではこう書かれている。『都には、これを照らす太陽も月もいらない。というのは、神の栄光が都を照らし、子羊が都のあかりだからである。』この2つの箇所が同一の内容について預言しているのは明らかである。黙示録の中では、エゼキエル書やダニエル書と同様、イザヤ書と対応している箇所が非常に多くある。我々が今見ている箇所もその一つである。
この箇所では天国のことが言われている。天国には我々が今見ているような太陽や月はない。そこは天国であって、この地上世界とは異なる場所だからだ。天国と地上が一緒なわけが、どうしてあるだろうか。その天国では、御父と御子が聖徒たちの太陽また月となられる。天国の聖徒たちは、どこに行っても常に御父と御子により照らされるので、暗くて困惑することが決してない。それゆえ、この箇所ではこう言われている。『あなたの太陽はもう沈まず、あなたの月はかげることがない。』このような場所は、今の我々の感覚からすれば想像を絶している。だが、聖書はそのような場所が存在すると我々に教えている。だから、我々は太陽も月もない永遠の場所があると信じなければならない。何故なら、聖徒たちの規範はこの聖書だからである。
このような場所に入れる者は本当に幸いである。これ以上の幸いはないと言ってもよいであろう。だから、そのような場所に入れる聖徒たちは神に感謝すべきである。そして、その場所に導き入れられたならば、地上にいた時に捧げた感謝よりも更に大きな感謝を神に捧げなければならない。
【60:21】
『あなたの民はみな正しくなり、とこしえにその地を所有しよう。』
天国に導き入れられた聖徒たちは、全てにおいて正しくされる。もう聖徒たちからは、罪も不敬虔も愚かさも除外されるのだ。何故なら、その時、聖徒たちは『天の御使いたちのよう』(マタイ23章30節)になるのだから。ここで『あなたの民』と言われているのは直接的にはユダヤ人である。だが、これは当然ながら新約の異邦人クリスチャンのことでもある。何故なら、新約の異邦人クリスチャンは、旧約のユダヤ人と同じで神の民だからである。このように天国に入って正しくなりたい者は誰か。その者はキリスト信仰に留まり続けるがよい。そうすれば、やがて文字通りの意味で完全な正しさを獲得できるようになろう。
ここでは『とこしえにその地を所有しよう。』と言われているが、『その地』とはどこか。これは天国の地である。これは天国について預言されているエゼキエル書40~48章を見ても分かる。その箇所では、天国の聖徒たちにそれぞれ相続地が割り当てられている。つまり、我々は天国に行った際、それぞれに相応しい自分の相続地を所有できるようになる。ちょうどイスラエル人がカナンの地に住みついた際、おのおのに相続地が割り振られたように。なお、このエゼキエル書40~48章は、もう少ししたら註解されることになる。この『その地』
という言葉を、我々が今住んでいる地球のことだと考えてはならない。何故なら、この地球は聖徒たちが永遠に住まう場所ではないからである。パウロが言った通り、我々の国籍は天にある(ピリピ3:20)。我々の本国は天だから、我々は天において地を所有するのだ。それゆえ、ここで地球の土地を所有することについて言われていると考えるのは誤っている。
『彼らはわたしの栄光を現わす、わたしの植えた枝。わたしの手で造ったもの。』
天国の聖徒たちとは、神の栄光のために作られた製作品であって、神のために地上から天国へと植え替えられた枝である。神が御自身のために造られたからこそ、天国の聖徒たちは神の製作品である。また神が植え替えられたからこそ、天国の聖徒たちは天国に植えられている。その全ては神の栄光を目的としている。もし神が造られたのでなければ聖徒たちは天国の製作品ではなかったし、もし神が植え替えられたのでなければ聖徒たちは天国に植えられていなかった。このことから、天国の聖徒たちの存在目的が何かよく分かる。すなわち、天国の聖徒たちは、ただただ神の栄光のために存在している。それだから、そこにいる聖徒たちは、食べるにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を現わすためにするのである(Ⅰコリント10:31)。
この箇所から、我々は神の選びにおける主権を理解できる。神が選ばれたからこそ、聖徒たちは神の製作品、神の植えられた枝なのである。人が自分自身から神の製作品また枝になりたいと願っても、神が選んでおられなければ、その願いが実現することはない。それはパウロがこう言っている通りである。『したがって、事は人間の願いや努力によるのではなく、あわれんでくださる神によるのです。』(ローマ9章16節)例えば、ある俳優がある映画に出演したいと願っても、その映画の監督がその俳優を使ってくれない限り、願いは叶えられない。事は全て監督次第である。神が人を神聖な製作品また天国の枝として下さるのも、これと同じである。
【60:22】
『最も小さい者も氏族となり、最も弱い者も強国となる。』
ここで言われているのは、天国で聖徒たちは王になるということである。黙示録22:5の箇所では、天国の聖徒たちについて、こう言われている。『彼らは永遠に王である。』ここでは、『最も小さい者も氏族となり』と言われている。これは、地上にいた時には無名かつ取るに足らない者が、天国では氏族のごとき輝かしい名誉を持つという意味である。何故なら、彼らはキリストにより罪と死と悪魔に打ち勝って、天国へと凱旋したのだから。また、ここでは『最も弱い者も強国となる。』とも言われている。これは、地上にいた時には弱い者でも、天国では強国のような強さを持つという意味である。何故なら、彼らは強国にも働いているサタンを足の下に踏み砕いたのだから。弱さから強さへ、小から大へ、無から有へ。これが救いのもたらす結果また効果である。今現在、読者の中で小さかったり弱かったりするので嘆き悲しんでいる者がいるだろうか。その人は悲惨な状態だと自分のことを思うかもしれない。だが、未来を思って喜ぶべきである。我々は、やがて天国に行けば『氏族』また『強国』となるのだから。
この天国への移入において有るものが無へと引き下げられることになる。確かにパウロは次のように言った。『また、この世の取るに足りない者や見下されている者を、神は選ばれました。すなわち、有るものをない者のようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。』(Ⅰコリント1章28節)地上で無も同然だった者は、天国に入って有る者とされる。それなのに地上で有だった者は、地獄に投げ落とされて無も同然とされている。神は、我々人間とは違って、無に等しい者を天国に入れて栄誉ある者とされる。我々の場合は、通常の場合、神とは違って、既に栄誉ある者を栄誉ある場所に連れて行くのである。これについては、あのラザロと金持ちの話を読んでも分かる。ラザロは無だったのに有とされ、金持ちは有だったのに無とされたのである。この地上にいる今は、まだ聖徒たちの救いにおいて有る者が無にされているとは考えにくい面もあるかもしれない。だが、天国に行けば、そのことがよく分かるようになるであろう。実に神とは、このような配剤のゆえに『不思議』(士師記13:17~19)な御方なのである。
『時が来れば、わたし、主が、すみやかにそれをする。』
この時には、この天国についての言説は、まだ預言において語られるだけであった。というのも、まだこの時は天国が開始されていなかったからである。神は、時が来るまでは、まだここで言われている天国の実現を留保しておられた。
だが、何事にも『時期』がある(伝道者の書3:1)。ここで言われている天国の到来も、実現する『時期』があった。それは紀元70年9月である。
その『時期』が到来して以降、地上にいる聖徒たちは、地上を去ると即座に天国に入れるようになった。もはや、聖徒たちは地上を去っても魂だけの状態になることが無くなったのである。それは、紀元1世紀に復活が起こったからである(Ⅰテサロニケ4:16~17)。それまでは、聖徒たちが地上を離れると、魂だけの状態になっていた。だが、天国が到来してからは、地上の聖徒たちが地上を離れると同時に即座に復活体に切り替えられるようになった。もう今や、旧約時代とは違う新しい秩序が到来しているのである。なお、紀元1世紀に天国が到来したというのは、キリストが再臨の起きた時に天国は来ると言われた通りである。すなわち、キリストはこう言われた。『まことに、あなたがたに告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が御国とともに来るのを見るまでは、決して死を味わわない人々がいます。』(マタイ16章28節)
【65:17】
『見よ。まことにわたしは新しい天と新しい地を創造する。』
『新しい天と新しい地』とは天国を指す。これは「天国における天と地」という意味である。つまり、ここでは『新しい天と新しい地』と言って、一つの世界を表している。これは、神のおられる霊的な天上の世界と、我々が住んでいるこの地上の世界、という意味ではない。「天と地」と言って、天上世界だけを、あるいは地上世界だけを表すのは、聖書において特に珍しいことではない。それでは、どうしてここで言われている『新しい天と新しい地』が天国だと分かるのか。それは、黙示録において新天新地の現われは『すぐに起こるべき事』だと明言されているからである。ヨハネが言ったように、確かに新天新地は黙示録が書かれてから『すぐに』現われた。だが歴史を見れば分かるように、今でも世界はヨハネの時代から何も変わっていないように感じられる。これは、つまり『新天新地』という場所が、天国を指しているということを意味しているのだ。変化は地上において起こらなかったが、天上では起きていた。もしこう考えなければ、新天新地が『すぐに』現われると言われている黙示録を否定せねばならなくなる。それは許されないことである。
『創造する。』とは、新しく始められる、今までに無かったものが造られる、という意味である。確かに天国は神により『創造』された。この天国とは、聖徒たちが御霊の身体においてキリストと住まう永遠の場所である。このような場所は、それが造られるまでは、まったく存在していなかったのである。だから天国の始まりが『創造』という言葉で言い表されているのは、実に適切であった。
この『新しい天と新しい地』は、キリストが再臨された時に『創造』された。何故なら、キリストは御自身が御国を伴って再び天からやって来るであろう、と明言されたからである。後にも述べるが、この御国とはすなわち『新しい天と新しい地』である。では、新天新地が創造されたのは、いつか。それは紀元70年9月であった。何故なら、この時に第二の復活が起こり、空中の大審判が実施され、そうして天上において天国が言わばオープンされたからである。それだから、既に新天新地は開始されている。それは地上においてではなく天上においてである。
この箇所で言われている新天新地は、黙示録21:1~22:5の箇所と対応している。黙示録のほうでも、我々が今見ている箇所と同様、天国における至福の恵みについて預言されている。
また、Ⅱペテロ3:13の箇所で言われている『神の約束』とは、我々が今見ているこのイザヤ書の預言を指している。このⅡペテロのほうについては、後ほど詳しく註解されることになる。
ここでは『見よ。』と言われているが、これは新天新地の創造が注目されるべき事柄であるということを教えている。「これから新しい天と新しい地が創造されるのだ。この出来事について心を傾けないでいていいはずが、どうしてあるだろうか。」神は『見よ。』と言って、あたかもこのように言おうとしておられるかのようである。なお、聖書では他の箇所でも『見よ。』と書かれている箇所が非常に多くある。
この箇所から65:25までの箇所は、非常に重要である。何故なら、そこでは新天新地について語られており、それは我々の未来観に大きく関わっており、聖徒たちの霊と信仰とに少なからぬ影響を及ぼすからである。再臨研究において、この箇所を無視することは許されない。もし再臨研究の際にこの箇所を無視する人がいれば、その人は陰謀を研究しているのにフリーメイソンリーの考究を避ける人と似ている。そのようにしても十全な理解に達することはないのである。陰謀研究の際にフリーメイソンリーの考究が避けられないように、再臨研究の際にこの箇所の考究を避けることはできない。
『先の事は思い出されず、心に上ることもない。』
天国では、地上世界の人生における苦い記憶が呼び覚まされることがない。それは『心に上ること』さえない。どれだけ少しであっても、である。何故なら、そこは天国だからである。天国とは、黙示録21:4の箇所で言われているように、『もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない』場所である。もし天国において地上世界で生きていた時の悲惨な人生を思い起こしたとしたら、後悔や涙が生じることは避けられない。それは大変に惨めな人生であったからだ。そうなれば、そこはもはや天国ではなくなってしまう。後悔や涙が生じるような場所は、天国とは言えない。それゆえ、天国において『先の事は思い出されず、心に上ることもない』のである。
これは今の我々からすれば、想像し難いことである。前の時に属する悲惨な事柄が、まったく心の中に想起されないとは…。これは今の我々には、記憶喪失になるか何らかの精神障害を持つかしない限り、有りえないことである。だから、次のように思われる方もいるかもしれない。「天国で先の事柄が何も想起されなくなるというのは信じられないことだ。」しかし私はこう言おう。今の我々が想像し難いと感じても、聖書で啓示されていることであれば、天国において必ずそれが実現される。何故なら、神にはどんなことでも出来るからである。『主に不可能なことがあろうか。』(創世記18章14節)と言われている通りである。信仰を持て。そうしないと神に喜ばれることは出来ないであろう。『信仰がなくては、神に喜ばれることはできません。』(ヘブル11章6節)これを信じない人は、復活を信じようとしなかったサドカイ人のようである。我々はサドカイ人のようにならぬよう注意せねばならない。
この箇所で言われていることは、黙示録21:4の箇所で言われているのと一緒である。そこでは次のように言われている。『なぜなら、以前のものが、もはや過ぎ去ったからである。』黙示録のほうでも、天国では地上世界にいた時の事柄が全てシャットダウンされてしまうと教えられている。その時には、あらゆる事柄が一新され、前の事柄は過去として切り離されてしまうのである。
【65:18】
『だから、わたしの創造するものを、いついつまでも楽しみ喜べ。』
天国において聖徒たちは、神の恵みを永遠に楽しみ喜ぶ。その楽しみと喜びは、いつになっても終わることがない。何故なら、天国にいる聖徒たちは、キリストにより永遠の生命を持っているからである。
キリストを信じる聖徒たちは、天国でこのような至福の恵みを享受し続ける。それは彼らが永遠の昔から、そのようになるようにとキリストにおいて定められていたからである。それゆえ聖徒たちは感謝せねばならない。もし神がキリストにおいて我々を定めておられなかったとすれば、我々が天国で恵みを享受することはなかったからである。一方、キリストを信じない不信者たちは、この天国における恵みを享受することはない。何故なら、彼らは天国に導き入れられるようにと定められていないからである。それゆえ彼らは永遠に嘆くことになる。それは、彼らが選ばれておらず、いつまでも地獄で苦しみ続けることになるからだ。
【65:18~19】
『見よ。わたしはエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。わたしはエルサレムを喜び、わたしの民を楽しむ。』
神は、天上のエルサレムとそこにいる聖徒たちを、永遠に楽しみ喜ばれる。何故なら、その場所は祝福されており、そこに住んでいる人々は御心に適っているからである。これは繁栄している強大な国の王が、自分の国とそこに住んでいる人民を喜びとするようなものである。我々がそのような王になったと考えてみるとよい。そうすれば、天国とその民における神の楽しみと喜びが、どのようなものであるのか、いくらかであっても感じ取れるはずである。
神が天国の聖徒たちを楽しまれるということは、つまり天国の聖徒たちが完全な聖潔を持っているということを意味している。何故なら、もしそうでなければ、神が天国の聖徒たちを楽しまれることはないだろうからである。欠けた聖潔しか持たない聖徒たちを神が楽しまれるというのは、完全を求められる神には相応しくないのである(マタイ5:48)。だから我々は確信すべきである。天国の聖徒たちは常に少しの染みも汚れもない純潔さを持っていると。
18節目の後半部分と19節目はセットとして読まれるべきである。何故なら19節目は18節目の後半部分を繰り返したに過ぎないからである。この2つの部分を切り離して読むべきではない。このように繰り返されているのは、つまり強調である。だから我々は、ここで強調がされているゆえ、神が天国とそこにいる聖徒たちを喜び楽しまれるということを注目せねばならない。
【65:19】
『そこにはもう、泣き声も叫び声も聞かれない。』
天国には、祝福に満ちた幸せしかない。それが天国という場所である。これは大変に素晴らしいことである。このような至福の場所は今の我々からすれば想像し難いかもしれないが、それは真実の場所である。何故なら、神がそのように啓示しておられるからである。
この箇所は、明らかに黙示録21:4の箇所と対応している。そこでは次のように言われていた。『もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。』黙示録のほうが、より豊かに語られていることが分かる。それというのも、黙示録のほうが、より具体的で明瞭だからである。
【65:20】
『そこにはもう、数日しか生きない乳飲み子も、寿命の満ちない老人もない。』
天国には、赤子や老人は存在しない。何故なら、彼らは祝福を十全に受けるのに相応しくないからである。これは、少し考えればすぐにも分かる。何もできない赤子や、よぼよぼとした老人が、神の祝福を存分に受けるための器として相応しいと言えるであろうか。明らかに相応しくないと言わねばならない。それは、例えるならば5歳ぐらいの少女に、100億円をあげるようなものである。そのような少女に大金をあげても、その少女は力も知識も経験も乏しいのだから、多額のお金が活かされることはない。言うまでもなく、そのようなお金は、力と知識と経験に富んだ成人にあげてこそ、大いに活きるのである。これは100歳ぐらいの老人に100億円をあげることでも同じである。
つまり、天国には永遠の青春がある。そこにいる聖徒たちは全て成人であり、輝かしく、実に活き活きとしている。見よ、これこそが天国における住民の祝福された姿なのである。
『100歳で死ぬ者は若かったとされ、100歳にならないで死ぬ者は、のろわれた者とされる。』
ここで言われているのは、永遠の命の比喩である。ここでは聖徒たちの永生が、非常に特徴的な言い方で示されている。つまり、これは永生を逆の方向から語っている。非常に難しい部分であるが、これは私が今述べた通りに捉えるべきである。
ある者は、この箇所について、得意満面でここでは新天新地に「死ぬ者」が存在しているのだと恥ずかしげもなく喋々している。「新天新地には<死ぬ者>がいる!」と。あたかも、自分こそがこの箇所を正しく理解できていると言わんばかりの口ぶりなのである。このように言う者は、理解が浅く、イザヤ65:17~25の箇所を詳しく読み調べていない。それゆえ、私はこのような意見に対して失笑を禁じ得ない。このように言う者の意見を打ち砕くのは、簡単である。まず先に我々が見たように、天国においては『そこにはもう、泣き声も叫び声も聞かれない』ということであった。もし65:20の箇所で言われている内容を文字通りに解釈すべきだとすれば、確かにある者が臆面もなく言ったように「そこには<死ぬ者>がいる」であろう。しかし、もし『死ぬ者』が新天新地に存在しているのであれば、65:19の箇所で言われていたように『泣き声も叫び声も聞かれない』ということにはならないはずである。何故かと言えば、死ぬ者がいたとすれば、必ずや『泣き声も叫び声も』聞かれるだろうからである。まさか、新天新地で死ぬ者たちは泣きもせず叫びもせずに死ぬということはあるまい。その死んでしまった者のために、周囲の人たちが泣いたり叫んだりしない、ということもないはずである。また後の箇所である65:25の箇所では、主がこう言っておられる。『わたしの聖なる山のどこにおいても、そこなわれることなく、滅ぼされることもない。』もし新天新地に『死ぬ者』がいたとすれば、『そこなわれることなく、滅ぼされることもない』ということは有り得ないはずである。何故なら、死ぬというのは、損なわれたり滅ぼされたりすることだから。更に先に見た65:19の箇所では、このように主が言っておられた。『わたしはエルサレムを喜び、わたしの民を楽しむ。』もしそこに『死ぬ者』が本当にいたとすれば、神が天上のエルサレムとそこにいる者たちを喜び楽しむということにはならないであろう。エゼキエル書18:23の箇所でも言われているように、神は決して死を幸いに思われる御方ではないのだから。さて、少し考えれば誰でも分かるように、<死ぬ者がいるということ>(※これを前者とする)と<泣き声と叫び声が聞かれないということ><損なわれることも滅ぼされることもないということ><神がエルサレムとそこにいる人たちを喜び楽しまれるということ>(※これら3つを後者とする)は矛盾している。正しいのは、明らかに前者を肯定して後者を否定するか、後者を肯定して前者を否定するか、のどちらか一つである。それというのも死がありながら至福の世界と呼ぶことはできないし、至福の世界と呼べるのであれば死はそこにないはずだからである。我々が今見ているイザヤ65:17~25の箇所では至福の天国について預言されているのだから、文脈を考えれば、否定されるべきなのは間違いなく前者すなわち<死ぬ者がいるということ>のほうである。つまり、この箇所で言われているのは、先にも述べたように、永遠の命を比喩的に示していると解釈せねばならない。すなわち、この箇所で死ぬ者について語られているのは、実際のことを言っているのではなく、単なる比喩としてなのである。ここで言われているのは、要するに「新天新地の住民たちには素晴らしい永遠の生命がある。」ということである。このように部分だけを見て全体の文脈を考慮しないと、ある者のように誤りに陥ることになる。私がここで言及した者は、この部分(65:20)だけに目を留め、イザヤ65:17~25の箇所における文脈を考慮するのは疎かにしていた、という点で間違っていた。我々は、このようなミスに陥らないように、よく注意せねばならない。少しでも考えれば、我々はすぐにも、ここでは死ぬ者について言われていながら泣き声や叫び声が聞かれないとも言われているという点で矛盾しているかのように感じられる、ということに気付くはずなのである。
また、この者は、この箇所に基づいて、人間の寿命がこれから洪水前の程度にまで回復されるなどという愚かな夢想を抱いている。65:22の箇所でも『木の寿命』と書かれているので、この夢想的な見解は確かに違いないとこの者は感じている。すなわち、これから我々の寿命は木のごとき年数になると。この者の追従者たちも、この見解に惑わされており、自分自身により考える力を完全に奪われてしまっている(これはどの分野でも追従者たちにはよく見られることである)。彼らは、自分たちの見解に同調しない者は全て駄目だと言わんばかりである。私は言うが、このような妄想は、検討にも価しない。それというのも、このように考えるのは狂気に他ならないからである。このような玄妙さは、狂気と言わずして何と言えばよいであろうか。しかし、どうして彼らは狂気に陥っているのか。それは聖書をよく研究していないからである。研究不足だからこそ、訳の分からない空想にやすやすと落ち込むことになるのだ。これは霊的・神学的な怠惰に対する神からの裁きである。実際、彼らはこのイザヤ65:17~25の箇所をいつも部分的に論じるだけであって、しかもそこには何の深みもない。私の場合は、今こうして神の恵みにより註解を書いていることからも分かるように、この箇所の全体を論じており、しかも一つ一つの箇所を可能な限り詳しく考察している(私は一切手抜きはしていないつもりである)。それゆえ、私の註解を読めば、読者は、この者たちの異常性がよく分かるはずである。彼らは黙示録についても部分的に少し論じるだけであって、私が神の恵みによりしたように全体をその詳細に至るまで深く論じようとはしていない。私のように全体を徹底的に理解しようとしないにもかかわらず、ただ個別的な聖句だけに着目して、さも自分が何もかも正しいとばかりに吠え叫ぶのは、見ていて滑稽に感じられる。そんなにも自分たちの見解に自信があるならば、どうして他の箇所も詳しく考察し、註解書を出したりしようとしないのか!全体を徹底的に理解してこそ、個別的な箇所も正しく深く理解できるようになる、ということにいつまで気付かないのか!今述べた彼らの妄想については、次のように言っておくだけで事足りる。すなわち、このイザヤ65:17~25の箇所では何の損害も滅亡も見られない至福の場所について言われているのであって、たとえ木のような寿命であろうとも有限の寿命を想定するのであればこの箇所の文脈に反することになる、と。
【65:21~22】
『彼らは家を建てて住み、ぶどう畑を作って、その実を食べる。彼らが建てて他人が住むことはなく、彼らが植えて他人が食べることはない。』
この部分は、纏めて読まれるべきである。何故なら、ここで書かれている文章は、明らかに一繋がりになっているのだから。
この箇所で言われているのは、明らかに律法に基づいている。申命記28:30の箇所では、律法違反に対する呪いとして次のように言われていた。『家を建てても、その中に住むことができない。ぶどう畑を作っても、その収穫をすることができない。』神は、律法に違反する者が家や葡萄畑を作っても、他の者にそれをお与えになられる。何故なら、神は罪を憎んでおられ、罪を犯す者には報復をなされるからである。神はそのようにして、律法の違反者に対して御自身の怒りを実際的に注がれる。しかし天国には罪がなく、そのため罪に対して下される神の呪いも存在していない。それは黙示録22:3の箇所で、『もはや、のろわれるものは何もない。』と言われている通りである。つまり、新天新地である天国に住まう聖徒たちは、呪いを受けることがないので、家や葡萄畑を作ってもそれを自分自身で利用し喜ぶことができる。ここで言われているのは、そういうことである。何故なら、もしそうでなければ、そこが天国とは言い難くなってしまうからである。果たして、せっかく家や葡萄畑を作ったのに他人に使われたり奪われたりするような場所が天国すなわちパラダイスだと言えるであろうか。そのような場所は、我々が今住んでいるこの地上とさほど変わらないと言わねばならないであろう。
【65:22】
『わたしの民の寿命は、木の寿命に等しく、』
この箇所では、先に見た箇所と同様、永遠の命が比喩的に示されている。神はこの箇所で、聖徒たちの永生を、木の寿命を使って示しておられる。それというのも、永遠の生命を示すのに、末永く存命し続ける木ほど適切な被造物はないからである。ここでは肉的で粗野や我々人間の理解力に合わせ、永遠のものが、地上のものを通して言い表されている。これは、あたかも大人が幼児に対して幼児言葉で語りかけるようなものである。神は、聖書の他の箇所でも、そのような語り方で真理を啓示しておられる。それだから、この箇所では、新天新地に住まう住民の生命が木の寿命のように有限的であるということが言われているわけではない。すなわち、新天新地の住民は、木でもあるかのように1000歳近くの寿命を持っているということではない。もしそうだとすれば、新天新地の住民たちには限りある寿命と死が存在しているということになる。そのようであれば、新天新地には泣き声や叫び声が聞かれるはずである。死がありながら、泣き声も叫び声も聞かれないというのは、先にも述べたように有りえない。しかし、このように考えるのは我々が今見ている箇所の文意に明らかに反している。何故なら、数節前では、新天新地について『そこにはもう、泣き声も叫び声も聞かれない。』と言われていたのだから。要するに、この箇所で言われているのは、こういうことである。「新天新地にいる住民は木でもあるかのような永遠の生命を持っているので、朽ちて死ぬことにより、自分で作った家や葡萄畑が誰か他の人に相続されたり使われたりすることは決してない。」我々は新天新地において、自分の作った物を誰にも奪われることなく永遠に享受し続けられるのだ。これはキリストがルカ12:33の箇所で、天国にある宝は『盗人も近寄らず、しみもいためることがありません。』と教えられたのと完全に適合している。つまり、キリストは聖徒たちが天国において持つ財物は、いついつまでも安全かつ完璧に持ち続けることができる、と言われたのである。それというのも、そこにいる聖徒たちは、この地上においては『木の寿命』として比喩されるべき永遠の生命を恵みにより持っているからである。
『わたしの選んだ者は、自分の手で作った物を存分に用いることができるからだ。』
『わたしの選んだ者』とは、天国にいる聖徒たちを指している。彼らはキリストにおいて選ばれていた。彼らは、祝福されているので、自分自身で自分の作った物を十全に享受し利用することができる。利用権を奪われないこと、事が順調に進むこと、効率が良いこと。このようなことは、どれも祝福である。一方、呪われているとこのようにはならない。その場合、誰かに利用権が奪われたり、なかなか事が上手に進まなかったり、非効率になったりする。それは、そこに呪いがあるからだ。天国にそのような呪いはないのである。
【65:23】
『彼らはむだに労することもなく、』
これも祝福を示している。天国の住民は祝福されているので『むだに労すること』はない。呪われていると、呪われているので『むだに労すること』になってしまう。それは次のように律法の呪いで言われている通りである。『畑に多くの種を持って出ても、あなたは少ししか収穫できない。いなごが食い尽くすからである。ぶどう畑を作り、耕しても、あなたはそのぶどう酒を飲むことも、集めることもできない。虫がそれを食べるからである。』(申命記28章38~39節)例えばアメリカ人が仕事を効率よく行なうのは、アメリカ全体が祝福されているからである。日本人はよく非効率だと言われるが、それはアメリカよりは国家に祝福が注がれていないからである。
『子を産んで、突然その子が死ぬこともない。』
これも、やはり天国における祝福の比喩である。神は、我々人間の粗野な感覚に合わせ、天国における祝福がどのようなものであるか分からせるべく、このような比喩を用いておられる。それだから、これは新天新地に出産の営みがあると示しているわけではない。何故なら、天国ではキリストも言われたように『人はめとることも、とつぐこともな』(マタイ22章30節)いからである。天国に結婚がないというのであれば、出産もないと考えるべきであろう。それにもかかわらず、この箇所では天国に出産があるかのように語られている。これは、つまり祝福の隠喩表現だということである。それというのも、産まれた子がすぐに死ぬということほど呪いを象徴する呪いはないからである。これは呪いの極みであると言ってもいいであろう。ダビデも、このような呪いを蒙ったのを我々は知っている。だから、ここでは天国には物凄い祝福があるということを教えていると捉えるべきである。
『彼らは主に祝福された者のすえであり、その子孫たちは彼らとともにいるからだ。』
『主に祝福された者』とは、キリストを指していると思われる。何故なら、キリストほど神から祝福された御方は他に存在しないからである。『祝福された者のすえ』とは、キリストの聖徒たちであろう。つまり、『すえ』とは「キリストに連なっている」という意味であると私は考える。
ここで言われている御言葉を分かりやすく言い換えれば次のようになる。「新天新地にいる聖徒たちはキリストに連なる贖われた者たちであり、その新天新地にいる聖徒たちの地上にいる子孫たちも、やがては新天新地に導き入れられて皆で一緒になるように定められている。」この箇所は、他にも可能な解釈があるかもしれない。だが現在の私としては、今述べられた解釈が適切であると考えている。
【65:24】
『彼らが呼ばないうちに、わたしは答え、彼らがまだ語っているうちに、わたしは聞く。』
ここでは、神が天国の聖徒たちに先回りして願いを叶えられる、ということが教えられている。天国では、聖徒たちが願いを奉げるべく神に呼ばわる前に、既に神がその願いを叶えて下さる。『わたしは答え』とは、神が願いを聞いてくださるという意味である。また天国では聖徒たちが願いを奉げているうちに、その願いが叶えられる。『わたしは聞く』という言葉も、やはり、神が願いを聞いてくださるという意味である。要するに、天国において神は聖徒たちに先んじて事を遂げて下さる。これは天国にいる聖徒たちが全的に清く、御心に適った願いしか捧げることがないからだ。それゆえ、神は天国の聖徒たちが願いを奉げる前から、また願いを奉げている最中に、その願いを快く遂げて下さるのである。聖徒たちの御心に適った願いは必ず聞かれるということについては、聖書で明白に教えられている。それはキリストがこう言われた通りである。『あなたがたがわたしにとどまり、わたしのことばがあなたがたにとどまるなら、何でもあなたがたのほしいものを求めなさい。そうすれば、あなたがたのためにそれがかなえられます。』(ヨハネ15章7節)
聖徒たちが願いを奉げようと神を呼ぶ前から神が既に願いに答えて下さるというのは、アダムの堕落前の時が正にそうであった。創世記を見れば分かるように、アダムが飲食や生活に必要な物を求めるよりも前から、神は既にそれらを全て備えて下さっておられた。またアダムが助け手を求めて神に呼ばわる前に、神は先んじてエバを彼のもとに連れて来られた。またアダムがどのように生きればよいのか神に尋ねる前に、神はアダムに対して聖なる禁令をお与えになられた。このように、神はアダムがまだ神に『呼ばないうちに』彼の願いを叶えておられた。聖徒たちが願いを奉げている真っただ中に、神がその願いを聞いて叶えて下さるというのは、ダニエルの例がある。ダニエルは願いを奉げたが、神はその願いが捧げられている最中に、もうその願いを聞いて下さった。これについてはダニエル書9章で書かれている。神はダニエルが『まだ語っているうち』から既に、ダニエルに先んじておられたのである。
【65:25】
『狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように、わらを食べ、蛇は、ちりをその食べ物とし、』
狼と子羊が共になって草を食むというのは、想像し難い光景である。何故なら、狼と子羊が共にいれば、狼は子羊を食い尽くしてしまうだろうからである。獅子が牛のように藁を食べるというのも、考えにくい現象である。何故なら、獅子とは肉食であって、生きた獲物を食い殺すものだから。蛇が塵を食べて生きるというのも、イメージしにくい。何故なら、蛇とは生き物を丸呑みにして腹を満たすからである。しかし新天新地では、これらの光景が見られるかのように、ここでは言われている。これは新天新地には堕落が存在していないことを示している。それというのも、狼が子羊を食べたり、獅子が肉食になったり、蛇が他の生物を丸呑みするようになったのは、アダムの堕落に巻き込まれたのが原因だからである。また、これは新天新地に平和が満ちていることをも示している。それというのも、ここで言われているのは死も暴力もないということだから。神は、このような『正義の住む新しい天と新しい地』(Ⅱペテロ3章13節)を創造される。それは既に創造されている。この場所にこれから入ることの出来る者は本当に幸いである。
この箇所では、新天新地にも動物が堕落していない状態で生存しているかのように言われている。しかし、実際に天国に動物がいるのかどうかは分からない。何故なら、ここで言われているのは単に清らかさと平和が象徴されているに過ぎない可能性があるからである。先に見た木のような寿命と死ぬ者の存在が単なる比喩表現だったのと同様、ここで言われているのも比喩表現と捉えるのが適切かもしれない。実際、同じ新天新地について示されている黙示録21:1~22:5の箇所では、動物については全く触れられていない。それ以外の箇所でも、聖書は天国に動物がいるということについて何も語っていない。黙示録に出てくる4つの生き物は既に説明したようにセラフィムという御使いだから、これは動物ではない。もし新天新地に動物がいるのだとすれば、このイザヤ65:25の箇所以外の箇所で、そのことについて聖書で触れられていないのは不自然であると私には思われる。
『わたしの聖なる山のどこにおいても、そこなわれることなく、滅ぼされることもない。」と主は仰せられる。』
ここで言われているように、『聖なる山』である新天新地には、破壊と滅亡がまったく存在していない。これは天国という場所が完全な祝福に満ちた場所であって、そこにおいては『以前のものが、もはや過ぎ去っ』(黙示録21章4節)ているからである。天国とは、実にこのような場所である。これは今の我々が住んでいる地上世界とは、根本的に何もかもが異なっている。それゆえ、我々の理性によって、このような場所を把握することは、たとえしたくてもできないであろう。
ここで言われているように天国には破壊も滅亡もないのだから、先に述べたように、イザヤ65:17~25の箇所で言われている「木のような寿命」や「死ぬ者の存在」は永生の比喩だとして捉えねばならない。もう一度言うが、もし天国に有限の寿命と死が存在しているのであれば、『そこなわれることなく、滅ぼされることもない』ということにはならないからである。そこでは間違いなく『そこなわれることなく、滅ぼされることもない』のだから、言うまでもなく無限の寿命と不死が存在しているということになるのだ。我々は誤りに陥らないよう注意せねばならない。
ところで、カルヴァンの場合、このイザヤ65:17~25の箇所で言われているのが、新約時代の聖徒たちにおける霊的な幸いのことだと考えていた。65:20の箇所は、聖徒たちはたとえ老人であっても赤子のような生命性を持つ、というのが彼の解釈であった。65:25の箇所も、異邦人の召しについて言われていると理解していた。カルヴァンは最高に卓越した神学者の一人であるが、この箇所に対する彼の解釈は頓珍漢である。それゆえ彼の解釈は、じっくり考えるにも価しないと言わねばならない。何故なら、この箇所では、我々が今住んでいるこの世界の状態とは質的に異なった世界の状態について言われているのだから。つまり、この箇所では、まったく新しい世界について言われているのである。
【66:15】
『見よ。まことに、主は火の中を進んで来られる。』
ここから66:17までの箇所では、再臨について預言されている。再臨研究をする際において、この箇所を無視することは許されない。再臨を考究する者たちにとって、この箇所は非常に重要である。
キリストが再臨される時、キリストは燃える炎を伴って天から降りて来られた。パウロもⅡテサロニケ1:7の箇所で、キリストは炎において来られると預言している。『そのことは、主イエスが、炎の中に、力ある御使いたちを従えて天から現われるときに起こります。』イザヤ書でも同様に言われている。『万軍の主は、…焼き尽くす火の炎をもって、あなたを訪れる。』(29章6節)この火という言葉は、単なる象徴として捉えるべきではない。何故なら、再臨の時には実際の火が伴っていたと捉えるほうが、より再臨の栄光を際立たせるからである。これを疑う人は恐らくいないと思われる。
『見よ。まことに、』と言われているのは強調である。この言葉は、あたかも「この再臨の出来事に心を留めない者が果たしているのであろうか。」とでも言っているかのようである。それゆえ、我々は主が火において再臨されたということを心に留めるべきである。
『その戦車はつむじ風のようだ。』
キリストが再臨された時、キリストは戦車に乗っておられた。もしくは、戦車隊を率いておられた。いずれにせよ、再臨のキリストが馬に乗っておられたのは間違いない。再臨について預言された黙示録6:2の箇所でも、やはり再臨のキリストが馬に乗っておられたと言われている。『私は見た。見よ。白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出て行った。』我々は、再臨のキリストが、どのようなものにも乗らずに来られる光景をイメージしがちである。あたかも、これは少し例えが悪いが、クレーンで吊られながら徐々に下降してくるコンサート中のアーティストでもあるかのように。キリストの再臨について描いた絵画でも、やはりそのような光景が描かれている。だが聖書は、再臨のキリストは馬に乗っておられると教えている。だから、我々は再臨のキリストに対して持っている自分のイメージを変化させる、というよりは修正・刷新させなければならない。キリストは何にも乗らずに再臨されたわけではないのである。ところで、今までの教会はこのようなイメージさえも持たなかったほどに、キリストの再臨についてあまりにも知らなさ過ぎたと言わねばならない。このぐらい、しっかり調べれば神の恵みにより分かるものなのだ。しかし、今まで教会はキリストの再臨において馬や戦車を全くイメージしていなかった。また、再臨が起きる際には、キリストだけでなく聖徒たちも馬に乗って天から降りて来た。これについては再臨について預言されている黙示録19章における14節の箇所で、次のように言われている。『天にある軍勢はまっ白な、きよい麻布を着て、白い馬に乗って彼につき従った。』聖徒たちはキリストと契約的に一体なので、神は再臨が起こる際、聖徒たちをもキリストと同じように装って下さったのである。
またキリストの再臨は『つむじ風のよう』であった。これは、つまりキリストの再臨が唐突に起きたということである。我々は、つむじ風が起きた際、その急激性に驚かされるものである。キリストの再臨もそのようであった。実際のつむじ風が予測できないのと同じで、再臨も予測できなかった。再臨におけるこの唐突性については、次のキリストの言葉と内容的に一致している。『人の子の来るのは、いなずまが東から出て、西にひらめくように、ちょうどそのように来るのです。』(マタイ24章27節)『だから、あなたがたも用心していなさい。なぜなら、人の子は、思いがけない時に来るのですから。』(マタイ24章44節)実際はどうであったか。既に述べたように、再臨が起きたのは紀元68年6月9日であった。当時の人のうち誰もこの日にまさか再臨が起こるなどとは予測していなかったであろう。であれば、確かに再臨が起きたのは『つむじ風のようだ』ったことになる。
【66:15~16】
『その怒りを激しく燃やし、火の炎をもって責めたてる。実に、主は火をもってさばき、』
主が再臨された時、怒りを炎のように燃え上がらせて裁きをなされた。このため、主が再臨された直下の場所であるエルサレムは火の海になってしまった。これは歴史が示している通りである。
この裁きは実に恐ろしい。だが、この出来事は既に実現している。何故なら、既に何度も述べた通り、もうキリストは燃える火において天から再臨されたからである。
【66:16~17】
『その剣ですべての肉なる者をさばく。主に刺し殺される者は多い。おのが身を聖別し、身をきよめて、園に行き、その中にある一つのものに従って、豚の肉や、忌むべき物や、ねずみを食らう者たちはみな、絶ち滅ぼされる。―主の御告げ。―』
再臨されたキリストは『その剣ですべての肉なる者をさば』かれた。『その剣』とは御言葉の剣を指す。キリストの口からは御言葉という『鋭い両刃の剣』(黙示録1章16節)が出ているのだから。『刺し殺される』とは文字通り生命が絶たれるという意味である。すなわち、これは象徴的な意味ではない。再臨の主に殺される者は『多』かった。つまり、その時の死者数は決して少なくなかった。
ここでは『すべての肉なる者をさばく』と言われているが、これは我々の理性からすれば文字通りの意味であると感じられる。すなわち、これは地球全土にいる全人類のことだと。だが、これは聖書によれば文字通りに捉えるべき言葉ではない。66:17の箇所を見ると、どうであろうか。そこに書かれている『絶ち滅ぼされる』者とは、教会の中にいる偽善者である。つまり、再臨の時にキリストが殺されるのは、偽善者における『すべての肉なる者』である。このように聖書で「すべて」と書かれていながら、実際は範囲が限定されている箇所は、既に説明されたように多く見られる。この17節目に書かれている偽善者についての御言葉を解読せねばならない。まず『おのが身を聖別し、身をきよめて』とは、「清められて聖徒たちの群れに入れられて神の民と見做される者とされる」という意味である。何故なら、清められることなしに教会の中に入ることは出来ないからである。『園に行き』とは、神の民であるにもかかわらず、偶像崇拝をする場所に行くという意味である。古代イスラエル人は、園に行って偶像を礼拝していた。『その中にある一つのものに従って』とは、園にいるバアルやアシュタロテやミロクといった偶像の前に跪いて、という意味である。『豚の肉や、忌むべき物や、ねずみを食らう』とは、つまり律法で禁じられている汚れた生き物を食べることである。新約時代ではもう聖俗の規定はキリストにおいて撤廃されているが、旧約の時は聖と俗との区別をしっかり持たねばならななかった。その時代に汚れた生き物を食べるのは罪であり、神に背くことであった。『絶ち滅ぼされる』とは、教会の中にいる邪な偽善者たちが滅ぼされ殺されるという意味である。もうお分かりであろう。66:16の箇所でキリストにより殺されると言われていたのは、今述べたような輩、つまり教会の中に導き入れられていながら不法のうちに歩み続ける偽善者のことなのである。すなわち、キリストが再臨された時には、文字通り全ての人がキリストにより刺し殺されたというわけではなかった。これは66:16だけに目を留めて66:17を見過ごしているならば、決して分からない。何故なら、66:17では66:16で言われていた言葉の意味内容を更に詳しく規定しているからである。
【66:18】
『「わたしは、彼らのわざと、思い計りとを知っている。』
ここから66:21の箇所までは、御国が全ての国に押し広げられる新約時代について預言されている。神の国は、新約時代になるまではユダヤにだけ限定されていた。つまり、ここでは神が人々を集められることについて言われているが、キリストの再臨の時に起こる携挙について言われているわけではない。この箇所において携挙のことは全く触れられていない。それだから、この箇所は、我々が取り扱っている再臨と大いに関わっているということではない。だが、この箇所で言われているのが携挙の出来事ではないということを詳しく知るべく、私はこの箇所を註解しようと思う。この箇所の註解は飛ばそうとも考えたが、私は結局のところ書くことに決めた。
まず、この箇所で言われている『彼ら』とはユダヤ人のことだと思われる。何故なら、これをユダヤ人と解釈すれば、後に続く文章としっかり調和するからである。
この箇所を後に続く文章と調和させつつ言い換えれば、次のようになる。「神である私は、ユダヤの民における業と思い計りとを知っている。彼らはエジプトの牢獄から導き出された時から今日に至るまで、私に逆らい続けてきた。彼らは実にうなじのこわい民だ。彼らのうちに私に対する敬虔はない。だが、これから神の民とされる異邦人たちは、そのようではない。彼らは、このユダヤの民とは違い、私に対する敬虔を持って清く正しく仕えるであろう。ユダヤの民よ、あなたがたはこのことを知っておけ。」
『わたしは、すべての国々と種族とを集めに来る。彼らは来て、わたしの栄光を見る。』
ここで言われているのは、あらゆる国の人々が御国に入れられる新約時代についてのことである。キリストが贖いと復活を実現されて後、神は、異邦人も神の国に入るようにと招かれた。それゆえ、『彼らは来て、わたしの栄光を見る』ことになった。『わたしの栄光を見る』とは、神の栄光を明白に感じ、その栄光を褒めたたえ、それを語り伝える、という意味である。それまで神の国に招かれているのはユダヤ人だけに過ぎなかった。それだから、ここで言われているのはキリストが再臨される時の携挙ではないことが分かる。確かにキリストが再臨された時にも、神は人々を集めに来られた(Ⅱテサロニケ2:1)。だが、この箇所で『集めに来る』と言われたのは、そのような意味合いにおいてではない。我々は間違えないように注意すべきである。このように異邦人さえも神の国に入るというのは、古代ユダヤ人からすれば考え難いことであった。使徒でさえ、いざ神の国が世界中に広まる段階になった際、驚き惑ったほどである。それは前代未聞の出来事であった。これを何かに例えるならば、ある人が突然王家に迎え入れられて王族の一員となるようなものである。そのような出来事を知った知人や親族たちは、「えっ、あの人が。一体どうして…―。」などと非常に驚くのである。異邦人もが神の国に入れるようになるのは、神の御心であった。だから、ユダヤ人たちの思いに反し、遂にかつては神の国から除外されていた異邦人たちもそこに入れる時代が到来したのである。
この素晴らしい出来事は、キリストの宣教命令によって言わば始動された。それは、ちょうど車にエンジンをかけて遠くまで走り行くようなものである。その宣教命令とは、次に示す通りである。『全世界に出て行き、すべての造られた者に、福音を宣べ伝えなさい。』(マルコ16章15節)『それゆえ、あなたがたは行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。』(マタイ28章19節)この宣教命令が発されてから、御国の福音がエルサレムより世界中へと満ち広がったのである。イザヤ2:3の箇所で、『それは、シオンからみおしえが出、エルサレムから主のことばが出るからだ。』と預言されていた通りである。
【66:19】
『わたしは彼らの中にしるしを置き、彼らのうちののがれた者たちを諸国に遣わす。すなわち、タルシシュ、プル、ルデ、メシェク、ロシュ、トバル、ヤワン、遠い島々に。これらはわたしのうわさを聞いたこともなく、わたしの栄光を見たこともない。彼らはわたしの栄光を諸国の民に告げ知らせよう。』
神の国に導き入れられた異邦人である聖徒たちの中に置かれる『しるし』とは何か。これは、聖霊のことだと思われる。何故なら、そのように解するのが妥当だからである。パウロも、聖徒たちには証印として聖霊が与えられたと言っている。『神はまた、確認の印を私たちに押し、保証として、御霊を私たちの心に与えてくださいました。』(Ⅱコリント1章22節)
この者たちの『うちののがれた者たち』とは、どういう意味であるか。これは、つまり聖徒とされた者の中で、本当にこの世と汚れた者どもから霊的に分離された者たち、という意味である。何故なら、この世と汚れた者どもから霊的な意味で切り離されていなければ、真に神の支配のうちに歩む者とされたとは言い難いからである。つまり、これは真に贖われた聖徒たちを意味している。聖書では、「そこから出よ。」などと言われている箇所が多く見られるが、それらはどれもこの世また汚れた者たちから分離せよという意味である。それは例えば次に示す箇所がそうである。『わたしは彼らの間に住み、また歩む。わたしは彼らの神となり、彼らはわたしの民となる。それゆえ、彼らの中から出て行き、彼らと分離せよ、と主は言われる。汚れたものに触れないようにせよ。そうすれば、わたしはあなたがたを受け入れ、わたしはあなたがたの父となり、あなたがたはわたしの息子、娘となる、と全能の主が言われる。』(Ⅱコリント6章16~18節)『わが民よ。この女から離れなさい。その罪にあずからないため、また、その災害を受けないためです。』(黙示録18章4節)『去れよ。去れよ。そこを出よ。汚れたものに触れてはならない。その中から出て、身をきよめよ。』(イザヤ52章11節)
この救われて神の国に入れられた異邦人たちは、自分が受けた救いを、『諸国の民に告げ知らせ』るようになった。それは文字通りの意味での『諸国』である。それらの国々の民らは『わたしのうわさを聞いたこともなく、わたしの栄光を見たこともな』かった。つまり、それらは神から放置されていた御国を受けていない人々であった。御国が諸国に満ち広がるというこの出来事は、既に成就している。それは、パウロの時代から既に『世界中で実を結び広がり続けてい』(コロサイ1章6節)たという事実を考えても分かる。今の時代にも、神の国は全世界に満ち広がっており、諸国の民に御国の福音が宣べ伝えられている。これは古い時代には全く考えられないことであった。
この箇所では全部で「7つ」の国が具体的に挙げられているが、これは重要な点である。これは「7」であるから、つまり7つの国を挙げることで全世界の諸国を表示している。何故なら「7」とは聖書では無限または数が多いことを意味しているからである。黙示録でも、7つの教会において世界中の教会が表示されていた。これについては既に第3部で説明された通りである。『島々』という言葉は、ユダヤの場所から遠くに位置している諸々の国々を指す。古代ユダヤ人たちは、海を越えた遠くの国々を『島々』という言葉で纏めていた。これは文字通りに捉えてはならない言葉だから注意せねばならない。
この箇所で預言されている出来事は既に実現しているが、これから実現し続けることになる。今後も、救われた異邦人である神の民が、諸国へと聖なる御国の福音を宣べ伝えるのだ。何故なら、それが神の御心だからである。あらゆる国の民族は、神の摂理により形成された。だから、神はあらゆる国の人々を御自身の国に導き入れられる。それは多くの子を持つ親が、全ての子に例外なく食事を与え養うのと一緒である。
このような時代が到来するなどとは、古代のユダヤ人からすれば理解不可能だったであろう。実際、ユダヤ人の書いた旧約の外典と偽典を読んでも、異邦人の召しについては何も触れられていない。これは旧約のユダヤ人にとって異邦人の召しが理解し難かったことを示している。もしそうでなければ、幾らかでも異邦人に御国が広まることについて触れていただろうからである。しかし、神は異邦人をも聖徒として召しだされるというユダヤ人の心を遥かに超え出たことを実現された。このことからも分かるように、神がなされることは、人にとっては計り知りがたい。神は我々が考えてもいなかったようなことを、かえって積極的に実現させられる。だから我々にとって神のなされることは不思議に思えてしまうのである。このことについてはイザヤ55:8~9の箇所でこう言われている。『わたしの思いは、あなたがたの思いと異なり、わたしの道は、あなたがたの道と異なるからだ。―主の御告げ。―天が地よりも高いように、わたしの道は、あなたがたの道よりも高く、わたしの思いは、あなたがたの思いよりも高い。』
【66:20】
『彼らは、すべての国々から、あなたがたの同胞をみな、主への贈り物として、馬、車、かご、騾馬、らくだに乗せて、わたしの聖なる山、エルサレムに連れて来る。」と主は仰せられる。「それはちょうど、イスラエル人がささげ物をきよい器に入れて主の宮に携えて来るのと同じである。』
救われた異邦人の聖徒たちは、自分と同じ異邦人にも神の国を告げ知らせ、その異邦人たちを神の御前に連れて来るようになる。異邦人が異邦人に対する御国の運び人となる。ここにおいてユダヤ人の存在や介入は触れられていない。これはユダヤ人にとっては受け入れ難いことであったろう。何故なら、それはアブラハムにおけるユダヤ人の選びを超え出た出来事、つまりユダヤの選びが無視されたように感じられる出来事だからである。
救われた異邦人である聖徒たちが、自分の同胞である異邦人をも御国へと導くのは、主へ贈り物を持って行くようなものである。それは、例えるならばシェバの女王が、多くの贈り物を携えて偉大なソロモン王の宮殿まで訪ねて行くようなものである。シェバの女王とは既に救われた異邦人、多くの贈り物とは新しく救われた異邦人、ソロモン王とは神である。その贈り物は『馬、車、かご、騾馬、らくだに乗せて』王の場所にまで持っていかれる。この箇所ではシェバの女王とソロモン王について何も書かれていないが、私は分かりやすさのため、この2人の支配者を例えとして用いた。
また異邦人の聖徒が同じ異邦人を神の国に導くのは、ユダヤ人が捧げ物を持って神殿に上るのと同じであった。実に、神の国に入れられた異邦人とは、神に捧げられた物なのである。それというのは、聖徒とは神に全的に捧げられた存在だからである。パウロが次のように言ったのは、これがその理由であった。『そういうわけですから、兄弟たち。私は、神のあわれみのゆえに、あなたがたにお願いします。あなたがたのからだを、神に受け入れられる、聖い、生きた供え物としてささげなさい。それこそ、あなたがたの霊的な礼拝です。』(ローマ12章1節)
このような時代が到来してから今や2000年が経った。そのようになったからこそ、我々にも御国の福音が宣べ伝えられるようになり、我々は神の国に入ることになったのである。もし今も昔のような状態のままだったとすれば、我々が御国に入れられるようなことはなかったはずである。それゆえ御国の民とされた聖徒たちは、このような時代を到来させて下さった神に感謝せねばならない。聖徒である者たちは「アーメン。」と言うべきである。
【66:21】
『わたしは彼らの中からある者を選んで祭司とし、レビ人とする。」と主は仰せられる。』
神から選ばれる『ある者』とは、いったい誰なのか。これは新約時代に教会へ招かれた異邦人のうち真に聖徒とされている人である。教会の中には「聖徒」が存在しているが、その聖徒には<麦>と<毒麦>という2種類がある。これは既に我々の知るところである。この箇所で言われている『ある者』とは、このうち麦である聖徒を指している。これは毒麦のことでは決してない。この麦である聖徒は、この箇所で言われている通り、恵みにより神の祭司とされる。キリストが現われてから救われた聖徒たちは、誰もが祭司とされる。それはペテロが新約時代の聖徒たちに対してこういった通りである。『しかし、あなたがたは、…祭司…です。』(Ⅰペテロ2章9節)ヨハネも黙示録1:5~6の箇所で、同じことを教えている。新約時代になった今や、聖徒とされた我々は例外なくキリストにある祭司である。旧約の時代においてこのようなことはなく、その時に祭司となれるのはレビ人だけであった。
しかし、新約時代に全ての聖徒たちが祭司となるのは、どうしてなのか。その理由は何なのか。それは聖徒たちに対し、神がキリストにおける愛を注いでおられるからである。聖徒たちは、契約的にキリストと一体である。だから神は、キリストが永遠の祭司となられたように、そのキリストと契約的に一体である聖徒たちをも祭司として下さるのである。それゆえ、もし神が聖徒たちに愛を注がれないのであれば、また聖徒たちがキリストと契約的に一体でないのであれば、新約時代の聖徒たちが祭司とされることはなかったであろう。何故なら、その場合、聖徒たちが祭司とされる理由は何もないからである。
【66:22】
『「わたしの造る新しい天と新しい地が、わたしの前にいつまでも続くように、―主の御告げ。―』
ここで言われている『新しい天と新しい地』とは、65:17~25の箇所で言われていた新天新地と同じである。つまり、これは天国を指している。この言葉には、我々が今住んでいるこの地上世界は含まれていない。
この天国は、神の御前において、いついつまでも続く。それは100億年経っても、それ以上の時間が経っても、である。何故なら、そこは永遠の天国だからである。天国の存在年数が永遠であるとすれば、地獄の存在年数も永遠であるということになる。天国のほうは永遠に存在するのに、地獄のほうは永遠に存在しないというのは、考えられないからである。実際、黙示録20:10の箇所では、地獄における苦しみは『永遠』であると言われているが、これは地獄が永遠に存在することを意味しているのだ。
『あなたがたの子孫と、あなたがたの名もいつまでも続く。』
『あなたがたの子孫』とは、聖徒たちの子孫である聖徒たちのことである。これは、これから未来に現われる聖徒たちの全てを指している。これは、当然ながら霊的な子孫である。これを肉的な子孫のことであると捉えるのは間違っている。『あなたがたの名』とは聖徒たちを指している。何故なら、「名」とは本体そのものを表示する記号だからである。例えば、聖書ではキリストの御名が私たちを救うと教えられている。名=本体である。それゆえ、これはキリストが私たちを救うと言っているのと同じである。
この聖徒たちも、天国が永遠に続くのと同様、『いつまでも続く。』彼らは永遠に生きるようにと定められているからだ。それゆえ、彼らには永遠の命が与えられる。それはキリストにおける神の恵みによる。すなわち、それは聖徒たちの行ないや功績などにはよらない。
【66:23】
『毎月の新月の祭りに、毎週の安息日に、すべての人が、わたしの前に礼拝に来る。」と主は仰せられる。』
この箇所は新約時代のことを言っている。新約になると、あらゆる国の人々が、神を礼拝するようになった。それは神の国が世界の諸国に宣べ伝えられたからであった。それは既に紀元1世紀の時に実現しており、今も実現し続けている。これからも、それは実現され続けるであろう。なお、ここでは『毎月の新月の祭り』と『毎週の安息日』について言われているが、これは当時のユダヤ人に合わせた言い方であるという点に留意せねばならない。つまり、ここでは新約時代になっても新月の祭りや安息日が存在していると教えられているわけではない。何故なら、それらは本体であるキリストの影であって、本体であるキリストが現われた以上、もはや影としての役割を終えたからである。パウロはこう言っている。『こういうわけですから、…祭りや新月や安息日のことについて、だれにもあなたがたを批評させてはなりません。これらは、次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。』(コロサイ2章16~17節)新約時代において、新月の祭りは廃止されており、安息日は「主の日」へと置き換えられた、ということは既に我々の知るところである。
この箇所では地上のことが言われている。先の節(66:22)では、天国と天国に定められた聖徒たちの永遠性が示されていた。この66:23も先に見た66:22と同じように天上に関わる事柄が言われていると考えるのは誤りである。
【66:24】
『「彼らは出て行って、わたしにそむいた者たちのしかばねを見る。』
『彼ら』とは、新約時代における救われた聖徒たちを指す。彼らが『出て行』ったのは、どこから、どこへなのか。それは、この地上から新しい天と新しい地である天国へ、である。つまり、これは、この世と汚れた者たちからの究極的な分離を言っている。この分離は、聖徒たちがこの地上での人生を終える時に実現する。そのようにして天国に入った聖徒たちは、『わたしにそむいた者たちのしかばねを見る』。どのようにして見るのであろうか。天国から見下ろしつつ、である。その屍と化した背いた者たちは、一体どこにいるのか。それは地獄である。その者たちは、どうして地獄に屍として葬られているのか。それは、彼らが最後の最後まで悔い改めず頑ななままだったからである。ところで、天国に出て行った聖徒たちが地獄にいる滅びの子たちを見るのは何故なのか。それは、天国の聖徒たちが自分たちとの対比において神の愛を豊かに感じられるためである。自分たちは天国で祝福を受けているのに、滅びの子らは惨めにも地獄で屍と化している。この明白な違いにおいて、聖徒たちに対する神の愛が豊かに浮き彫りにされるのだ。
注意せねばならないが、この箇所で言われているのは、天国のことである。それは地上のことではない。すぐに続く部分も、やはり言われているのは地上のことである。我々が今見ている辺りの箇所では、その語られている場面が箇所ごとに異なっているので、よく注意せねばならない。
『そのうじは死なず、その火も消えず、それはすべての人に、忌みきらわれる。」』
地獄における刑罰は、『うじ』と『火』により与えられる。そこにいる滅びの子たちは、『火』によって苦しめられる。彼らは火で焼かれるのだが、焼かれるにもかかわらず、焼き尽くされて消失させられることがない。何故なら、彼らは焼き尽くされても消失しない身体に復活させられているからである。これについては第2部の中で説明された。また彼らには『うじ』も与えられる。彼らは、蛆によってもたらされる不快なおぞましさに戦慄させられる。彼らの精神的な苦痛は頂点にまで達するが、しかし誰も彼らを蛆から助ける者はいない。彼らはこの蛆に食い尽くされることにもなる。だが、彼らは新しい身体に復活させられているので、蛆に食われても身体が消失させられることがない。この2つのものによる刑罰の苦しみと嘆きは、何か他のものに例えることができない。それほどに、この刑罰は悲惨なのである。もし何かに例えられたのであれば、私はそれについて書いていたであろう。
地獄の子たちはまた、『すべての人に、忌みきらわれる』ことにもなる。『すべての人』とは、天国の聖徒たちにおける『すべての人』という意味である。天国の聖徒たちは、地獄で苦しんでいる者たちを憎み、見下し、決して憐みの念を持つことがない。地獄にいる者たちは、天国にいる者たちが良い思いをしているのを見て、妬み、悔しがり、苛立ちに満ちる。だから、地獄にいる彼らについて福音書では次のように言われている。『彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。』(マタイ13章50節)このように地獄の刑罰には「不名誉」または「恥辱」も含まれている。これは地獄の刑罰にはぴったりである。
この部分は、明らかにキリストの御言葉と対応している。主はマルコ9:48の箇所でこう言われた。『そこでは、彼らを食ううじは尽きることがなく、火は消えることがありません。』キリストが我々が今見ているイザヤ66:24の箇所に基づいてマルコ9:48の箇所を語られたのは間違いない。このキリストの御言葉とイザヤ書の御言葉は、どちらも文意が一緒である。すなわちイザヤ書で地獄のことが言われているように、キリストも地獄について言われた。新約聖書では、旧約聖書をその文意から離して用いている箇所もあるが、今取り上げたマルコ9:48の箇所はそうではない。キリストが地獄について言われたというのは、すぐ前の箇所であるマルコ9:43~47を見れば分かる。そこでは『ゲヘナ』について言われているからである。
第26章 24:エレミヤ書
エレミヤ書も無視されてはならない。この文書は、イザヤ書やエゼキエル書やダニエル書ほど研究すべきだというのではないが、しかし大いに心を傾けるべき文書である。ヨハネも、黙示録の幾つかの箇所で、このエレミヤ書の内容に基づいて文章を書いている。
【9:15~16】
『それゆえ、イスラエルの神、万軍の主は、こう仰せられる。「見よ。わたしは、この民に、苦よもぎを食べさせ、毒の水を飲ませる。彼らも先祖たちも知らなかった国々に彼らを散らし、剣を彼らのうしろに送り、ついに彼らを絶滅させる。」』
この箇所では、『苦よもぎを食べさせ、毒の水を飲ませる』という比喩表現において、ユダヤ人の滅亡と離散とが語られている。苦ヨモギを食べれば、その人は苦しむ。誰が苦ヨモギを食べたいと思うであろうか。誰も思わない。また毒の水を飲めば、その人は死ぬか苦しむであろう。誰が毒の水を飲みたいであろうか。誰も飲みたくはない。このように苦ヨモギと毒の水は、誰もが避けたいと思うものである。つまり、ユダヤ人が滅ぼされて生き残った者たちが散らされるのは、正に苦ヨモギと毒の水を口にするのも同然だったということである。それだから、ここでは実際的にユダヤ人に苦ヨモギと毒の水が与えられるなどと言われているわけではない。これが分からないほど愚鈍な人が果たしているのであろうか。
黙示録8:10~11の箇所でも『苦よもぎ』が出てくる。更に、その箇所では苦ヨモギの落ちた川から水を飲んだ人たちが死んだと言われている。これは我々が今見ている箇所で言われている『毒の水』と対応していると見てよい。何故なら、苦ヨモギにより苦くなった水を飲んで人が死ぬというのは、『毒の水』を飲んだということに他ならないからである。この黙示録のほうでも、やはりユダヤ人が滅ぼされて散らされることについて言われている。この黙示録の箇所で『苦よもぎ』と言われているのは、我々が今見ているエレミヤ書の箇所を参照しない限り、何が言われているのか決して分からないはずである。黙示録の箇所を単体的に理解しようとすれば、「苦ヨモギとはチェルノブイリのことを言っている。」などと馬鹿げた理解を持つようにさえなる。しかし、エレミヤ書と併せて読むのであれば、そこでは滅亡と離散について言われていることがよく分かる。この黙示録の箇所については既に第3部の中で註解された。そこで何が言われているのか忘れてしまった人は、第3部の当該箇所に戻り、再び学び直していただきたい。
第27章 25:哀歌
哀歌は考究しなかったとしても問題ない。何故なら、この文書からは再臨のことが学べないからである。それゆえ、この文書は★1つである。
第28章 26:エゼキエル書
エゼキエル書も絶対に考究されねばならない文書である。これは黙示録と非常に対応度の高い文書である。このエゼキエル書は黙示録と非常に似ているので、ヨハネはあたかも新しいエゼキエルとして黙示録という預言書を書いたかのように感じられるほどである。特に、エゼキエル書と黙示録における最後のほうの部分は、非常に類似性が高い。どちらも最後のほうになると、ゴグとマゴグからユダヤが攻撃される出来事について語られた後(エゼキエル38~39章、黙示録20章)、聖なる場所とそこの計測について語られてから(エゼキエル40~48章、黙示録21~22章)、預言が閉じられるという順序になっている。この類似性に気付かない人は誰もいないはずである。これほどまでに黙示録がエゼキエル書に似せられているというのは、つまりヨハネが祭司として黙示録を書いたということなのかもしれない。ヨハネは新約時代における祭司である(Ⅰペテロ2:9、黙示録1:5~6)。エゼキエルは旧約時代における祭司である(エゼキエル1:3)。この2つの文書はよく似ているのだから、ヨハネが新しいエゼキエルになったつもりで、またはエゼキエルの像に自分を置きつつ黙示録を書いていた可能性はかなり高いと私には思われる。
【1:4】
『私が見ていると、見よ、激しい風とともに、大きな雲と火が、ぐるぐるとひらめき渡りながら北から来た。』
このエゼキエル1章の中で言われているのは、ケルビムである(「ケルビム」は「ケルブ」の複数形)。これまで多くの人が黙示録に出てくる4つの生き物は、このエゼキエル書に出てくるケルビムだと考えてきた。だが、それは間違っていた。黙示録に出てくるのはケルビムではなくセラフィムである。今までどうしてこのような初歩的な事柄さえ、多くの人は弁えることができなかったのか。それは聖書をよく研究していなかったからである。このぐらい、いくらかでも研究すれば、神の恵みにより、すぐに分かるものである。確かなところ、黙示録や再臨に関わる事柄について今まで深く考究されて来なかったという現実が教会にはある。そういう次第であるから、私はこのエゼキエル1章を註解することにした。そうすれば、黙示録に出てくる生き物についての理解がより明瞭となるだろうからである。このケルビムの事柄については再臨とあまり関わりがないと思われる方もいるかもしれない。しかし、これは黙示録の内容と幾らかでも関わりがあるのだから、再臨とまったく無縁というわけでもないのだ。
エゼキエルは、ここで4つの生き物を見たと言っている。その生き物とはケルビムであるが、このケルビムの出てくる光景は、単なる幻に過ぎなかったのか、それともそれは霊的な現実を可視的に表わしたものだったのか。これは後者のほうが正しい。何故なら、ケルビムとは現実の存在であって、エゼキエルの見たケルビムは実際に存在するケルビムだったからである。この霊的な光景は神がエゼキエルにお示しになられた。すなわち、それはサタンが生じさせた幻だったのではない。また、それはエゼキエルが頭の中で勝手に空想した光景でもない。
それでは、どうして神はエゼキエルにこのような霊景をお見せになられたのか。これには2つの理由がある。まず第一の理由は、神がエゼキエルを愛し選んでおられたことを証示するためである。エゼキエルが神に愛され選ばれていたからこそ、このようなケルビムの光景が見せられた。もしエゼキエルが愛されもせず選ばれてもいなかったならば、このような光景は見せられていなかったであろう。我々は自分にとってどうでもいい人には素晴らしいものを与えようとはしないものだが、神の場合もそうなのである。第二の理由は、エゼキエルの権威を高めるためであった。エゼキエルがこのような光景を見たとなれば、エゼキエルの預言者としての権威は当然ながら高まり、そのため聖徒たちはエゼキエルの預言にますます信頼と尊敬の念を持つようになる。神はエゼキエルを通して重大な事柄を聖徒たちに示そうとしておられた。だからこそ、神はエゼキエルを聖徒たちに対して権威ある者とすべく、このような光景を見せられたのである。
『見よ』という小さな言葉は、これから示される事柄が重要であることを意味している。実際、ケルビムの事柄は聖徒たちにとって軽んじられるべき事柄ではなかった。それゆえ、我々はこれから示されるケルビムの事柄を真の意味で見なければいけない。これまで教会は、ケルビムの事柄を見てはいるが真に見てはいなかった。すなわち、ケルビムについて書かれたことを読みはしたが、深く把捉することはしていなかった。だからこそ、黙示録の生き物がケルビムだなどと愚かにも平気で言ったのである。
『激しい風』が起こったのは、神が風においてケルビムを送られたことを示す。何故なら、風とは神の用いられる道具だからである。詩篇104:4の箇所で、神は『風をご自分の使いとし』と書かれている通りである。
『雲』も、それが神により生じていることを示す。何故なら、雲も神が御自身のために使われる道具だからである。キリストが再臨された時にも、この雲が用いられた。またこれは、神の権威をも示している。『火』も、やはり神からそれが出たことを教えている。キリストも、再臨の際には火において来られた。この雲と火とが大きかったのは、その事柄において神が畏怖されるためであった。もしこれが小さかったのであれば、我々は事柄をそれほど重んじなかったかもしれないのである。
この現象が『ぐるぐるとひらめき渡りながら』来たのは、実に神秘的である。この不可思議さは、我々が神の事柄を軽んじないためである。もしこの雲と火が単調な仕方で来たとすれば、我々はこの現象を取るに足りないと感じていたかもしれない。カントのような難しい学者的な文章でなければ満足しない人が少なくないことを考えれても分かる通り、我々は往々にして簡単なものを低く見る傾向を持っているからである。しかし、複雑であったり霊妙であったりすれば、それほど見下したりすることもなくなる。
この現象が『北から来た』のは、これが神から生じていることを示す。何故なら、北とはすなわち上だからである。神のようになろうとしたサタンも、思い高ぶって神のおられる北の場所に座を据えようと心の中で思った(イザヤ14:13)。神のおられる場所が上=天すなわち『北』であることを疑う人がいるのか。誰もいないはずである。
『その回りには輝きがあり、火の中央には青銅の輝きのようなものがあった。』
この現象には、外側にも内側にも栄光の輝きが見られた。これは神から起こされた現象だから当然である。
なお、この箇所で言われている輝きが、ケルビムから生じたと考えないように注意せねばならない。もしこの輝きがケルビムから発していると考えるならば、それは神から栄光を奪い取ることになるからである。言うまでもなく、ケルビムはただ神から発された栄光のうちにいたに過ぎない。
【1:5】
『その中に何か4つの生き物のようなものが現われ、その姿はこうであった。彼らは何か人間のような姿をしていた。』
この箇所で、エゼキエルはケルビムを『何か4つの生き物のようなもの』と言い表している。ケルビムがこう言われているのは当然であった。何故なら、まだこの時にエゼキエルは、この生き物がケルビムであると気づいていなかったからである。彼がこの生き物をケルビムだと知るのは、10:20の箇所にまで進んでからである。
エゼキエルの前に現われたケルビムは、『人間のような姿をしていた』。これはケルビムが御使いの一種だったからである。御使いが人のような姿をしている、というのは不信者たちでさえも知っているところである。ケルビムも、人間と同様、神を鏡のような表わす像としての被造物であった。だから、ケルビムは神の像である人間と似たような姿をしていたのである。もっとも、羽や輪の有無といった多くの細かな点においてケルビムと人間は異なっているのではあるが。
ところでケルビムに「性別」はあるのか。この箇所では『彼ら』と言われているから、ケルビムは男なのか。これはトマス・アクィナスが非常な興味を持ちそうな疑問である。私は言うが、ケルビムにはっきりとした性はない。何故なら、彼らには性を持つ必要性がないからである。エゼキエルの前に現われたケルビムは、ただ女というよりは男のように見えたというだけに過ぎない。この疑問については、このぐらいに留め、もうこれ以上には考えないようにするのが望ましい。このような類の些細な問題を深く考究したからこそ、トマスは本質的とは言えない事柄を多く語ることになってしまったのである。
【1:6】
『彼らはおのおの4つの顔を持ち、4つの翼を持っていた。』
このケルビムは『おのおの4つの顔を』持っていた。つまり、4人のケルビムには総計16の顔があった。セラフィムの場合、おのおの1つの顔であった(黙示録4:7)。すなわち、4人のセラフィムには総計4つの顔しかなかった。これはケルビムとセラフィムにおける大きな相違点の一つである。この顔については、また後ほど語られる。
また、ケルビムにはそれぞれ『4つの翼』があった。セラフィムの場合、翼はそれぞれ6つである(黙示録4:8、イザヤ6:2)。この翼についても、また後ほど語られる。なお、ケルビムに翼が与えられていたのは、神の命令を速やかに遂行するためである。神が命令を発されると、ケルビムはその命令を遂行すべく、翼を使って迅速に移動をするのだ。これはケルビム以外の天使でも同じことが言える。
ところで、どうしてケルビムには4つの顔と翼があったのか。また、どうしてケルビムは4人いたのか。すなわち、なぜ「4」なのか。これについては分からないとしか言いようがない。それは、どうして聖書が「66」巻なのか分からないのと同じことである。
【1:7】
『その足はまっすぐで、足の裏は子牛の足の裏のようであり、みがかれた青銅のように輝いていた。』
ケルビムの『足はまっすぐ』だったが、これは彼らがその翼により宙に浮いていたからである。また、それは彼らの神に対する従順な精神をも示していると思われる。上官の命令を遂行すべく待ち構えている兵士たちが、足を緩めて楽にすることはしないのと同じである。また、ケルビムの『足の裏は子牛の足の裏のようであ』ったが、これは子牛のようにその振る舞いが勇んでいることを示しているのであろう。なお、足の裏が見えたのは、このケルビムがエゼキエルの上空に飛んでいたからである。その足が『みがかれた青銅のように輝いていた』のは、ケルビムが神の栄光をいくらかでも帯びていることを示す。ケルビムは神に仕える存在として遣わされているので、必然的に神の栄光を伴わずにはいられないのである。これはケルビム以外の御使いたちでも同様である。
【1:8】
『その翼の下から人間の手が四方に出ていた。』
ケルビムの翼からは人間の手が『四方に出ていた』が、これは2本の手を外側に伸ばしていたということであろう。『四方に出ていた』と書かれているから、ケルビムには4本の手があったと考える者もいるかもしれない。だが私の考えでは、ただ2本の手が出ていたとしたほうが無難である。しかしながら、ケルビムに手が4本あったという見解も完全に否定することはしないでおきたい。
『そして、その4つのものの顔と翼は次のようであった。』
エゼキエルは、自分の見たケルビムの顔と翼における詳細を示そうとしている。まずは翼のほうから説明されている。
【1:9】
『彼らの翼は互いに連なり、彼らが進むときには向きを変えず、おのおの正面に向かってまっすぐ進んだ。』
ケルビムの4枚の翼は、後の箇所を見ても分かるように上と下にそれぞれ2枚ずつあり、その2枚はくっつけられていた。セラフィムの場合、上と中央と下にそれぞれ2枚ずつの翼があった(イザヤ6:2)。
ケルビムが進む時に、この翼は向きを変えず、ケルビムと一緒に動いた。翼がケルビムと一緒に動いたのは、もちろん翼がケルビムの一部だったからである。移動の際に翼の向きが変わらなかったのは、ケルビムの精神における恒常性を示していると私には思われる。それは、シッカリとした大人が、子どものように落ち着きなくもじもじしないのと同じである。
ケルビムが動いていたのは、ケルビムが実際に生きていることを示すためであった。動いているからこそ、それが実際の生き物であると知れる。もしこれが止まっていたのであれば、そのケルビムは置き物か像だったと認識されていたかもしれないのである。
【1:10~11】
『彼らの顔かたちは、人間の顔であり、4つとも、右側に獅子の顔があり、4つとも、左側に牛の顔があり、4つとも、うしろに鷲の顔があった。これが彼らの顔であった。』
ケルビムの顔は、一人ずつ計4つあった。すなわち、どれも正面が人間の顔、右側が獅子の顔、左側が牛の顔、背面が鷲の顔であった。日本の阿修羅像は顔が3つだけであるが(正面と右側と左側)、この阿修羅像を考えるとケルビムの顔をイメージしやすくなるであろう(※)。セラフィムの場合、一人につき一つの異なる顔がある。すなわち、第一は獅子、第二は牛、第三は人間、第四は鷲である(黙示録4:7)。
(※)
阿修羅+顔
[本文に戻る]
この4つの生物の顔がケルビムにあることには何か意味があるのか。昔の教父たちは、黙示録に出てくる4つの顔を持つ生き物を4つの福音書として捉えていた。だが、これは強引なこじつけであり、単なる妄想に過ぎない。私としては、この4つの生物の顔には特に何か意味があるとは感じられない。あるとしたら、霊的な世界の不可思議さを示すためか、人間が神の生き物に対して畏怖の念を持つためである。
【1:11】
『彼らの翼は上方に広げられ、それぞれ、2つは互いに連なり、他の2つはおのおののからだをおおっていた。』
先に述べた通り、ケルビムの翼は上と下に2つずつあり、それらは2つとも左右に互いに連なっていた。そのうち上の2つは上空のほうに向けられていた。これはケルビムの精神が神に向いていたこと、またその神に忠実であったことを示している。これは、言わば敬礼のようなものだと思えばよい。例えはあまりよくないが、これは「ハイル・ヒトラー」と言って、ドイツ人が手を上に差し伸ばしたのとよく似ている。
下の2つは、ケルビムの身体を覆っていた。これはケルビムでさえ神の御前では完全でなく、そのため恥じ入るからであった。ヨブ記4:18の箇所ではこう言われている。『見よ。神はご自分のしもべさえ信頼せず、その御使いたちにさえ誤りを認められる。』ケルビムは罪のない存在であり、たとえ敬虔な聖徒であっても罪を犯さずにはいない我々人間とは違う。だが、その聖なるケルビムでさえ神の御前では身体を覆って恥じ入らねばならないほどなのである。セラフィムも4つの翼により自分の身体を覆っていたが(イザヤ6:2)、これもケルビムと同様の理由からである。セラフィムはケルビムよりも栄光において優っていたが、そのセラフィムでさえも神の御前においては身体を覆わねばならなかったのである。
【1:12】
『彼らはおのおの前を向いてまっすぐに行き、霊が行かせる所に彼らは行き、行くときには向きを変えなかった。』
この箇所で言われている『霊』とは、神の霊ではない。これは後の箇所である1:20~21で言われているように、『生きものの霊』であった。しかし、どうしてケルビムの霊とケルビムが別の存在でもあるかのように、この箇所では言われているのか。ケルビムの霊はケルビムそのものではないのか。確かにその通りである。ここでケルビムの霊がケルビムとは別でもあるかのように言われているのは、霊こそがケルビムの主体存在であることを示すためであった。ヘブル1:14の箇所で書かれているように御使いとは『仕える霊』であって、本来的に物質存在ではないのである。
この箇所で、その霊によりケルビムが真っ直ぐに移動していたと言われているのは、軽んじられるべきではない。何故なら、これはケルビムの忠義性を我々に示しているからである。すなわち、彼らは神に従うことにおいてふらふらしていないのである。
【1:13】
『それらの生きもののようなものは、燃える炭のように見え、たいまつのように見え、それが生きものの間を行き来していた。火が輝き、その火から、いなずまが出ていた。』
4人のケルビムには、それぞれ『燃える炭』また『たいまつ』のようなものが、そのうちを駆け巡っていた。これは恐ろしいと共に神秘的であり、なかなか想像するのが難しい。しかも、ケルビムには稲妻を発する輝かしい火が伴っていた。これは一体なんという光景また現象であろうか。ケルビムがこのようであったのは、人間が霊の事柄を軽んじないためである。我々は簡単な感じだと、すぐにも事柄を見下すものだからである。
【1:14】
『それらの生きものは、いなずまのひらめきのように走って行き来していた。』
先の箇所ではケルビムが移動をしていたと語られていたが、ここではその移動が稲妻の閃きのように速かったと言われている。ケルビムにこのような速さが与えられていたのは、神の命令を即座に遂行するためである。もしケルビムが遅い動きしかできなかったならば、神の命令をすぐさま行なうことは難しいのである。
【1:15】
『私が生きものを見ていると、地の上のそれら4つの生きもののそばに、それぞれ一つずつの輪があった。』
4人のケルビムの傍には、一人ずつ、それぞれ『一つずつの輪』が見られた。つまり、この輪は総計4セットあった。この輪は、ケルビムに神妙さを伴わせるための言わば装飾物である。これは、男に髭が備えられているのと似ている。
【1:16】
『それらの輪の形と作りは、緑柱石の輝きのようで、4つともよく似ていて、それらの形と作りは、ちょうど、一つの輪が他の輪の中にあるようであった。』
この4つある輪は『緑柱石の輝きのようで』あったが、これは輪においても神の栄光が伴っているからである。この緑柱石は、鮮やかさのうちに深みがあり、実に神秘的である。また、この4つの輪はどれも同じように見えた。それはセラフィムの顔が、4人ともそれぞれ違っていたようではなかった。また、この輪は、あたかも一つの小さな指輪がもう一つの大きな指輪の中にすっぽり収まっているかのようであった。この2つの指輪は、恐らく互いに接触してはいなかったと思われる。
【1:17】
『それらは四方に向かって行き、行くときには、それらは向きを変えなかった。』
この輪は『四方に向かって行』ったと書かれているが、これはどういうことか。4つの輪がそれぞれ四方に向かって行ったということなのか。それとも、これは一つの輪だけについて言われているのか。私としては、これは4つの輪の全体について言われていると考えたい。それというのも、一つの輪が四方に向かって動いたというのは、物理的に理解不可能だからである。
【1:18】
『その輪のわくは高くて、恐ろしく、その4つの輪のわくの回りには目がいっぱいついていた。』
この4つの輪は驚異的であり、我々の精神を戦慄させるような形状であった。我々は、これがどのような形状であったか、明瞭にイメージすることができない。もしイメージしたとしても、それがエゼキエルの見た通りの形状であるとは限らない。それゆえ、この形状については、それほど多くの事柄を述べることは難しい。しかし我々がやがて天に召されたならば、その時には、この輪の枠がどのような形状なのか明瞭に知れることになるであろう。というのも、我々は新しい人生に入ったならば、このケルビムを見ることが出来るだろうからである。
しかしながら、枠の目については幾らかのことを述べることが可能である。何故なら、それはエゼキエルにより語られているからである。この輪の『わくの回りには目がいっぱいついていた』とエゼキエルは書いている。このように輪の枠に目が沢山あったのは、2つの理由がある。それは、その無数の目により世界全体を見渡し、またその外観により畏怖を引き起こさせるためである。それというのも、このような目の集まりを見て、幾らかでも恐れを感じない者が果たしているのであろうか。この枠に付いている無数の目も、それがどのようであるか、やがて我々は明瞭に知れるようになるであろう。
我々は、この目のことで、黙示録に出てくる4つの生き物(すなわちセラフィム)とエゼキエル書に出てくるケルビムを混同しないように気を付けねばならない。確かに黙示録の生き物にも目があったと書かれているが、エゼキエル書の生き物にある目の記述とは、よく似ているようで実は違っている。それがよく似ているからこそ、今まで少なからぬ数の人たちが、黙示録に出てくる生き物をエゼキエル書に出てくる生き物だと思ってしまったのである。黙示録に出てくるセラフィムの場合、目がびっしりと満ちているのは『6つの翼』(4:8)である。一方、エゼキエル書に出てくるケルビムの場合、目がびっしりと満ちているのは『4つの輪のわくの回り』である。セラフィムには、そもそも輪が備えられてさえいなかった。このぐらいは少し調べればすぐにも分かるのに、今まで教会の多くの人たちは、このぐらいのことさえ区別してこなかった。これまで聖徒たちは誰でも福音書やパウロ書簡は詳しく調べるのに、黙示録やエゼキエル書になると、どうしてか研究の手を引っ込めてしまっていた。これは認めねばならないことだが、エリファス・レヴィが正しく指摘したように、これまで教会にはソロモンの秘儀を解く鍵が与えられてこなかったのである。黙示録やエゼキエル書にソロモンの秘儀が満ちているのは誰の目にも明らかである。だから今こそ我々は気付くべきである。黙示録の生き物とエゼキエル書の生き物は同一ではない、ということを。
【1:19】
『生きものが行くときには、輪もそのそばを行き、生きものが地の上に上がるときには、輪も上がった。』
ケルビムの動きに応じて、ケルビムの傍にあった輪も一緒に動いた。これは輪がケルビムの身体の一部分だったからに他ならない。「身体から離れているのにもかかわらず身体の部分である」ということを、我々の理性は理解できないかもしれない。だが、それは我々がこの地上の原理にはまった思考しかしていないからであって、霊の世界においてはそのようなこともある、ということを弁える必要がある。というのも、霊の世界の原理は、この地上の物質的な原理とはかなり異なっているからである。だからこそ、霊の世界に属するケルビムにおいては、身体から分離された輪も身体の部分であることが可能なのである。
【1:20】
『これらは霊が行かせる所に行き、霊が行かせる所には、輪もまたそれらとともに上がった。生きものの霊が輪の中にあったからである。』
ケルビムの霊がケルビムを動かすと、そのケルビムの動きに輪も同調した。その理由は、『生きものの霊が輪の中にあったからである』とエゼキエルは述べている。このことから、我々は、霊こそが生命体の基幹すなわちコントロールルームであることを知れる。霊こそが、その霊の入っている生命体を根本的に動かすのだ。つまり、身体は霊に動かされているだけに過ぎないのである。それゆえ、霊なき物体は、自意識を持つ霊により自由自在に動かされるということもないのである。
【1:21】
『生きものが行くときには、輪も行き、生きものが立ち止まるときには、輪も立ち止まり、生きものが地の上から上がるときには、輪も共に上がった。生きものの霊が輪の中にあったからである。』
この箇所では、既に述べられた内容が繰り返されている。非常に重要な事柄でもない限り、既に説明された事柄を繰り返して説明するのは冗長となろう。エゼキエルがこのように繰り返して書いたのは、彼が自分の見ていた光景を心の赴くままに記録していたからである。それは、ちょうど試合の成り行きに興奮したアナウンサーが、勢いはあるもののやや整序感に欠けた実況をするのと似ている。
【1:22】
『生きものの頭の上には、澄んだ水晶のように輝く大空のようなものがあり、彼らの頭の上のほうへ広がっていた。』
ケルビムの上方には、神秘的で美しい空間が広がっていた。これは神がケルビムの上に置かれた空間である。
この箇所からも分かる通り、ケルビムは下のほうに置かれている。アダムが楽園から追放された時にも、やはりケルビムは『エデンの園の東』(創世記3:24)すなわち地上に置かれた。一方、セラフィムの居場所は地上ではなく天上である。しかも、それは神の御座の近くであった。このことから、ケルビムよりもセラフィムのほうが栄光において優っているのは明らかである。何故なら、一方は御座の近くに置かれ、一方は地上に置かれているからである。それだから、我々はケルビムとセラフィムの栄光が同等であったと考えてはならない。星ごとにそれぞれ栄光の違いがあるのと同じで(Ⅰコリント15:41)、御使いにも栄光の度合いにおいて差があるのだ。
【1:23】
『その大空の下には、互いにまっすぐに伸ばし合った彼らの翼があり、それぞれ、ほかの2つの翼は、彼らのからだをおおっていた。』
この箇所は、大空の下にケルビムの上の部分における2つの翼が広げられていたと言われていることの他は、既に述べられたことの繰り返しである。この上下にあったそれぞれ2つの翼については、非常に重要であるというのでもないから、再び説明する必要はないであろう。
【1:24】
『彼らが進むとき、私は彼らの翼の音を聞いた。それは大水のとどろきのようであり、全能者の声のようであった。それは陣営の騒音のような大きな音で、』
ケルビムが移動をする際には、翼の音が鳴り響いた。これは鳥が飛ぶ時には羽ばたく音がするのと同じである。エゼキエルは、その音がどのようであったか3つの例えを述べている。それは『大水のとどろきのよう』であった。誰でも巨大な滝の鳴り響く轟音を聞いたことがあるであろう。それは会話の声を掻き消すほどに大きい音である。ケルビムが羽ばたく音は、正にそのようであった。この『大水』とは、この箇所では異邦人を意味してはいない。また、それは『全能者の声のよう』であった。それは稲妻のような野太い音である(ヨハネ12:28~29)。また、それは『陣営の騒音のような大きな音で』あった。この音については、戦争映画やファンタジー映画の戦闘シーンを思い返してみれば、よく分かる。エゼキエルは、このように3つの例えを示すことで、ケルビムの羽ばたく音がどのようであったか我々に知らせようとしてくれている。
【1:24~25】
『彼らが立ち止まるときには、その翼を垂れた。彼らの頭の上方の大空から声があると、彼らは立ち止まり、翼を垂れた。』
ケルビムが移動を止めると、上に伸ばされていた2枚の翼が下に下ろされた。つまり、こういうことである。ケルビムは上にあった2つの翼で移動をしていた。止まる時には、その2枚の翼を広げておく必要がなくなる。だから、移動が停止した際にはその翼も下ろされることになったのだ。
『上方の大空から声』が鳴ったのは、主の御声である。何故なら、これは主の御声以外には解せないからである。
ケルビムは、上のほうから神の声が発されると、立ち止まって翼を下ろした。これはケルビムの主に対する忠義性を示している。ちょうど忠実な兵士が、上官の声が発されると、即座に動きを止めてその声に耳を傾けるようなものである。ケルビムの忠義性は完全完璧である。それゆえ、ケルビムが主の御声を聞き漏らすことは決してない。
【1:26】
『彼らの頭の上、大空のはるか上のほうには、サファイアのような何か王座に似たものがあり、その王座に似たもののはるか上には、人間の姿に似たものがあった。』
上のほうにいたのは、もちろんキリストである。このキリストは、栄光の王であられる主である。それにもかかわらず、エゼキエルはここでキリストについて『人間の姿に似たもの』としか言っていない。これは、まだエゼキエルがそれをキリストであるとはっきり認識していなかったからである。この時点では、ただ見て感じた通りのことを淡々と書き記しているに過ぎない。もうこの時から既にそれがキリストであると分かっていたならば、このような言い方はせず、「それは主であった。」とでも書いていたはずである。
エゼキエルの見た光景においては、遥か上にキリストがおられ、その下に『王座に似たものがあり』、その下にケルビムが位置していた。この3層の構図は何を意味しているのか。ここで言われている『王座』とは支配・権威を示す。つまり、この箇所ではケルビムがキリストの支配・権威の下に服している、ということが示されている。これは実に象徴的であり印象深い構図である。正にユダヤ人にぴったりの示し方であると言える。
我々は、ここで想像を逞しくすべきではない。すなわち、この箇所ではキリストが下にある王座に着いて支配をするのだとか、まだキリストは王座に座っておられないからケルビムはキリストの支配のうちに服してはいなかった、などと空想を展開させるべきではない。この箇所で言われていることは、ただ単純に考えればよい。玄妙に解そうとすれば、シンプルな教えを理解し損ねないのである。このような一見すると知恵深そうに見える玄妙な解釈は、哲学を神学に混入させて愉しんでいるスコラ主義者やテュービンゲン学派の者のような人たちにやらせておけばよいのだ。
【1:27】
『私が見ると、その腰と見える所から上のほうは、その中と回りとが青銅のように輝き、火のように見えた。その腰と見える所から下のほうに、私は火のようなものを見た。』
キリストは、腰から上も下も、栄光に輝いておられた。その身体の全体が火のように見えたというのは、ヘブル12:29の箇所で『私たちの神は焼き尽くす火です。』と言われているのと一致している。キリストの上半身が『青銅のように輝』いていたのは、キリストの堅固さと栄誉を示している。
黙示録1:13~16とダニエル10:5~7で描かれているキリストは、このエゼキエル書1章で描かれているキリストと同じキリストである。どちらも、身体が輝かしい堅固な物質であり、また照り輝いている、という点で一致している。もちろん、記述上の違いがいくらかあるが、だからといって異なるキリストが描かれているというわけではない。これらの箇所で描かれているキリストを相互比較してみると理解がより一層増すことになるであろう。
【1:27~28】
『その方の回りには輝きがあった。その方の回りにある輝きのさまは、雨の日の雲の間にある虹のようであり、それは主の栄光のように見えた。』
キリストは輝かしい栄光を発しておられた。この栄光の輝きを見たエゼキエルは、大いに驚いていたに違いない。何故なら、このような栄光を見て驚かないのは、豚のように鈍感な愚か者だけだからである。エゼキエルが豚でなかったのは誰でも分かるはずである。
【1:28】
『私はこれを見て、ひれ伏した。』
エゼキエルは、神の栄光を感知したので、キリストの御前にひれ伏して崇拝を奉げた。これは当然であった。何故なら、神の輝かしい栄光を見ながら、崇拝を奉げないというのは、異常なことだからである。我々人間は、人間に過ぎない王に対してでさえ、ひれ伏すものである。であれば、尚のこと、神であられる王の御前においてはひれ伏さねばならないのだ。
エゼキエルがこのように崇拝を奉げたのは違法ではなかった。何故なら、その対象がキリストだったからである。ヨハネが御使いの前でひれ伏したのは違法であった(黙示録22:8)。何故なら、御使いを拝むのは偶像崇拝だからである。コルネリオがペテロの前にひれ伏したのも違法であった(使徒行伝10:25)。何故なら、ペテロは神ではなかったからである。
エゼキエルは、神の栄光を感知するや否や、すぐにも崇拝をした。そこに迷いや不信仰はなかった。アブラハムも、主が来られた際、非常に素早く動いた(創世記18章)。ペテロも主を感知するや否や、一目散にキリストの場所へと急いで行った(ヨハネ21:7~8)。お分かりであろう。神の御前において、為すべき従順な行為を問答無用に行なう。これこそ敬虔であるということなのだ。詩篇119:60の箇所でも次のように言われている。『私は急いで、ためらわずに、あなたの仰せを守りました。』このような速やかな従順さは、多くの場合、セム系が得意とするところである。それは古代ユダヤ人やイスラム教徒たちを見ても分かる。ヤペテ系は、まあまあである。彼らは理性が先に立つ傾向があり、セム系に比べると世俗的な波に呑まれやすいからである。ハム系は、まったく駄目なように感じられる。特に日本人などは(日本人がハム系であったと仮定した場合※)、本来的にまったく宗教と適合していないとさえ思えるほどである。
(※)
日ユ道祖論に従い、日本人が失われた10部族の子孫であったとしたら、日本人はセム系だということになる。とはいっても、先祖であるその10部族は反逆的であるがゆえに裁かれて散らされたわけだから、たとえ日本人がセム系だったとしても、そのことのゆえに喜んだり誇ったりすることは出来ないと私は思う。ここは民族の祖先について取り扱う場所ではないから、このことについてはこれ以上語るべきではないであろう。
[本文に戻る]
『そのとき、私は語る者の声を聞いた。』
この語る者の声は、もちろんキリストの声である。上におられるキリストがエゼキエルに語りかけた。それは、エゼキエルに啓示を与えるためであった。
1章は、この28節目でお終いである。本註解では、2章にまで突入することをしない。何故なら、私はケルビムをセラフィムと区別できるようにエゼキエル1章を註解したのであって、2章目に突入しても、本来の目的を実現させることはできないからである。2章目以降を見ると、10章目になるまではケルビムがもはや出て来ないことが分かる。そういうわけだから、すぐ続けて次は10章目の註解に進むことにしたい。
【10:20】
『彼らは、かつて私がケバル川のほとりで、イスラエルの神の下に見た生きものであった。私は彼らがケルビムであることを知った。』
1章に出てきた4つの生き物は、ケルビムであったことが、この箇所で明らかにされている。つまり、エゼキエルはこの箇所になるまで、あの生き物がケルビムであると気づいていなかった。我々も、1章を見るだけでは、そこに出てくる生き物がケルビムであるとは理解できないかもしれない。かえって、それがセラフィムであると勘違いをしてしまうかもしれない。実際、私はある時まで、エゼキエル書1章に出てくるのはもしかしたらセラフィムではないのか、などと思っていた。
【10:21】
『彼らはおのおの4つずつ顔を持ち、おのおの4つの翼を持っていた。その翼の下には、人間の手のようなものがあった。』
これは既に1章で説明されたことの繰り返しである。この繰り返しには、今エゼキエルが見ている生き物が第1章で見た生き物と変わらなかったということを確認する意味もある。
【10:22】
『彼らの顔かたちは、私がかつてケバル川のほとりでその容貌としるしを見たとおりの顔であった。』
この箇所でも、10章に出てくるケルビムが1章に出てきたケルビムと何も変わらなかったと確認されている。『容貌』とは、ケルビムの外形全体を指す。『しるし』とは、ケルビムにおいて見られた諸々の不可思議な現象を指している。
『彼らはみな、前のほうへまっすぐ進んで行った。』
ここでは、エゼキエルの見たケルビムが生きた実際のケルビムであったと示されている。これは既に第1章でも示されていた。エゼキエルがこう書いたのは当然であった。何故なら、律法の中では、ケルビムの像が契約の箱の部分に造られるようにと命じられていたからである(出エジプト25:18~22)。ユダヤ人は律法をよく知っていたから、ケルビムを生命のない像として認識してしまう恐れがあった。だから、エゼキエルはこのケルビムが動いていたと述べ、そのケルビムが像のケルビムでなかったと知らせているわけである。
【38:1】
『さらに、私に次のような主のことばがあった。』
エゼキエル38章と39章は、再臨を理解するにあたり、とつてもなく重要な箇所である。その重要性は、黙示録の重要性と同等である。何故なら、この箇所は、黙示録20:7~10の箇所と明らかに対応しているからである。これを疑うことはできない。どちらもゴグ・マゴグなる存在がユダヤを攻撃する出来事について預言されている。もしこの2つの箇所が対応していると理解できない人がいたとすれば、その人の理性は機能不全に陥っていると言わざるを得ない。この重要性ゆえ、本書において、このエゼキエル38章と39章は絶対に註解されねばならない。もし私がこの箇所の註解を拒むとすれば、それは私が自分の職務を放棄したことになってしまうであろう。
この38章・39章の箇所では、ユダヤが攻められると預言されているが、これは捕囚に至るネブカデレザルの攻撃のことではない。確かに、捕囚が起こる際に、ネブカデレザルはユダヤを攻撃し破壊した。だが、この箇所で言われているのは、その攻撃ではない。この箇所でネブカデレザルの時のことが言われていると理解している人は、私は言うが、研究不足である。これについては、後ほど註解の中で語られることになる。
それでは、この箇所で言われているのは、アンティオコス4世の時の攻撃であろうか。確かにあの時に、ユダヤはアンティオコス4世に攻撃され、酷い目に遭わされた。だが、ここで言われているのは、そのことではない。何故なら、ヨハネは、このエゼキエル38章・39章の預言を未だに実現していない出来事として黙示録20:7~10の箇所で語っているからである。アンティオコス4世によるユダヤの破壊は、ヨハネが黙示録を書いた時からおよそ200年前の出来事であり、ヨハネの時代からすればそれは過去の出来事であった。しかしながら、この38章・39章を読んで、これがアンティオコス4世の攻撃だと思われる探究者は少なくないかもしれない。これがネブカデレザルの攻撃だとするのは完全な間違いであるが、アンティオコス4世の攻撃だとする人がいるのは、この箇所における異常と思えるほどの難解さを考慮すれば、それほど不思議であるとは言えないかもしれない。だが、このアンティオコス説もネブカデレザル説と同じで間違っている。これについても、後ほど註解の中で語られることになるであろう。
では、この38章・39章で言われているのは何の出来事なのか。それは紀元1世紀に起きたローマ軍によるユダヤの滅亡である。この箇所では、ゴグがユダヤを攻めて破滅させると教えられている。実際、ゴグであるローマは紀元1世紀にユダヤを攻めて破滅させた。これはヨハネが、ゴグがユダヤを取り囲んで攻撃するのは『すぐに起こる』と言ったことからも裏付けが取れる。確かに、ゴグなるローマがユダヤを攻めたのは、ヨハネが黙示録を書いてからすぐにも起きた。この破滅の出来事こそ38章・39章の主題である。私は、このことについて詳しく論じなければいけない。
38章・39章が記された時期はいつなのか。それは捕囚の時期である。40:1以降の箇所は、捕囚から25年目に書かれたから、そのすぐ前の箇所である38章・39章もその年に書かれたか、もしくはそれよりも前に書かれたことになる。すなわち、38章・39章は紀元前560年に書かれたか、それよりも前に書かれた。この箇所が560年よりも後に書かれたと考えるのは、難しい。
この38章・39章が難しいと感じられる方は多いだろうと思われる。確かにこの箇所はかなり難しい。黙示録を全て註解した私でさえ、そのように思うほどである。私の感覚では、このエゼキエル38章・39章は、黙示録と同様、聖書の中で最も難しい箇所の一つである。たぶん、他の人もこの意見に同調してくれるであろう(※)。だが、本註解を読めば、この箇所の内容をよく理解できるようになるであろう。もちろん、理解できるのは我々の力によるのではなく、神の恵みによるのではあるが。
(※)
もし、もっと難しい箇所があるというのであれば、その箇所を知らせていただきたい。だが、そのような箇所はないはずである。この2つと同等程度の難しさを持つ箇所であればあるかもしれないが、この2つよりも更に難解な箇所はないはずである。
[本文に戻る]
エゼキエルは『次のような主のことばがあった。』と言って、自分が受けた預言を語り始めている。エゼキエルがこのように自分の受けた預言を公にするのは、義務であった。何故なら、神はエゼキエルを通して預言を公にするためにこそ、エゼキエルに預言をお与えになったからである。エゼキエルも、神の言葉を取り次ぐために召されていた。それゆえ、エゼキエルが愚かにも預言を隠したままでいたとすれば、エゼキエルは大きな罪に定められていたはずである。
ところで、どうして神はエゼキエルを通して、このような預言を公にされたのか。それは、御自身の民であるユダヤの滅びを、あらかじめ周知させるためであった。そのようにするのは神にとってよい。何故なら、遠い昔から未来の事柄が預言されたとなれば、人々は神に対して恐れや尊敬の念を抱いたりするので、それが神の栄光に繋がるからである。人間は、数年後・数十年後に起こる出来事を予言した人を見て、とてつもない人物だと思う。であれば尚のこと、600年後の出来事について預言された神はとてつもない存在だということにならないであろうか。なるであろう。神は御自身の栄光を求めておられる。だから、神は600年も前から、紀元1世紀に起こる出来事を預言されたのである。
【38:2】
『「人の子よ。』
『人の子』とはエゼキエルのことである。これは、エゼキエルが人間から生まれた者であるということを明白に示す呼びかけである。キリストも、よくこの言葉で御自身を呼ばれた。それは、キリストが御自身を人間から生まれた存在であると示されるためであった。実際、キリストは真の神でありながら人間から生まれた真の人間でもあられた。
『メシェクとトバルの大首長であるマゴグの地のゴグ』
『メシェクとトバル』とは、ヤペテの子である(創世記10:2)。だから、これはメシェクとトバルが入植した土地またはその場所にある国家を指している。これは、ここでは個人名を言っているのではない。
『マゴグ』とは、メシェクとトバルを支配する国である。このマゴグがエチオピアの方面にあったと考える人は間違っている。これはユーフラテス川の北側にあった場所である。実際、後ほど見ることになる38:15の箇所では、このマゴグがユダヤから見て『北の果て』にあると書かれている。ヨハネも、黙示録の中で、ユーフラテス川が枯れると北からマゴグの軍隊がユダヤを攻めに来ると語っている。既に述べた通り、黙示録ではユダヤを攻めて来るローマがユーフラテス川の北側にいたマゴグの民において言い表されている。このマゴグもヤペテの子どもである(創世記10:2)。つまり、これはマゴグが入植して始められた国家または地名を指している。これは元は人間の名前であったが、この箇所では人間を指しているのではない。
『ゴグ』とは、このマゴグの地における『大首長』である。これは地名または国家名でない点に注意せよ。この人物は、『大首長』などと呼ばれているから、恐らくルイ14世やチンギス・ハーンやニムロデのような支配者だったのではないかと推測される。
このゴグという大首長とは、すなわちローマの皇帝を指している。ゴグは、多くの国々を支配するマゴグの地における大首長であった。ローマ皇帝も、多くの国々を支配するローマ帝国における大首長であった。このように両者には明らかに共通点がある。だからこそ、エゼキエル書また黙示録の中では、ローマとその首長が、マゴグとその首長において言い表されているのだ。まだ強大な国家としてのローマがなかった紀元前6世紀の時代において、ローマとその首長をマゴグとその首長において表示するのは、実に適切であった。何故なら、マゴグとゴグ以外に、どのような存在がローマとその皇帝を表示するのに相応しかったであろうか。当時の覇権国家であるバビロンでさえも、ローマを表示するのには適していなかった。というのも、もしバビロンにおいてローマを表示していれば、紀元1世紀のあの悲劇を十全に伝え示すことは難しかっただろうからである。
『に顔を向け、』
これは、その対象に向けて行動を起こせという命令である。ここにおいては、ゴグに対して神が命じられた事柄を為せ、という意味となる。
【38:2~3】
『彼に預言して、言え。神である主はこう仰せられる。メシェクとトバルの大首長であるゴグよ。』
これは、ゴグにおいてローマに関する預言をせよ、ということである。これはゴグについて言われているが、実はゴグについての預言ではない。すなわち、これは「本物のゴグ」についての預言ではない。これは「ローマというゴグ」についての預言である。何故なら、38章・39章においてゴグとは単なるローマの表示物に過ぎないからである。
『神である主はこう仰せられる。』とは、預言の際の定型句であった。預言者は、神からの預言を取り次ぐ際、必ずこのように言わねばならなかった。それは、その預言が、本当に神から発されたことを示すためである。預言の際に、このように言わないのは許されなかった。何故なら、その場合、神からの預言が語られるのに、そこにはそれが神からの預言であることを示す署名がないことになるからである。それゆえ、このように言わない場合、その預言者は御心に適わないやり方で預言をすることになったのである。このような定型句には幾つかのパターンがあり、その定型句が語られる規則も特に見いだせない。つまり、このような定型句は、不規則だと思えるような仕方で所々に配置されていた。これは預言者の書を読めば分かる。愚かな偽預言者どもも、この定型句を用いて、自分から出た偽預言をあたかも神からの預言であると思い込ませようとした。このようにするのは死に値する罪であった。何故なら、そのようにするのは、本来は神から出たのでない偽預言を、神が発した預言であると偽って告げたからである。これは神について偽証することだから、その罪は非常に重い。もしどこかの阿呆者が、王や大統領がこれを語ったなどと言って、自分が捏造した言葉で民衆を惑わしたとすれば、国によっても違いはあるかもしれないが、恐らく罰せられるであろう。共産圏の国であれば死刑になるかもしれない。であれば尚のこと、偽預言者が『神である主はこう仰せられる。』と言って自分で作り上げた偽預言により人々を惑わした場合、罰せられることになる。
【38:3】
『今、わたしは、あなたに立ち向かう。』
神は、今からもう既にゴグにおいてローマの定めを開示された。『今』とは、もちろんエゼキエルがこの預言を受けた紀元前6世紀における『今』である。これは我々が生きている今のことではない。また、ここでは神が実際的にゴグに戦いを仕掛けることについて言われているわけではない。神がゴグに『立ち向かう』とは、神がゴグに対して働きかけをされるという意味である。
ここで言われていることが本物のゴグだと解すると、大変なことになる。その場合、実際のゴグが実際にユダヤを取り囲んで攻撃したことになってしまう。しかし、歴史を見ても実際のゴグがユダヤに攻撃をしたなどという記録はまったくない。そのようなことを言っている人も皆無である。だから、これを文字通りにゴグのことだと捉えるのは、愚かの極みであると言わねばならない。このゴグは、あたかもダビデがキリストを表象していたように、ローマを表象していると解さねばならない。そうすれば、全てがすんなりと理解できるようになる。だから、その解釈でよいのである。
【38:4】
『わたしはあなたを引き回し、あなたのあごに鉤をかけ、あなたと、あなたの全軍勢を出陣させる。』
神はゴグとして表象されたローマを、あたかもワニの顎に鉤をかけて引き回すかのように、ユダヤの討伐へと引き回された。つまり、ローマは、神の摂理により強制的にユダヤを破滅させるようにと動かされた。この神の摂理とは、神の鉤により万物の顎が引き回されることでなくて何であろうか。
黙示録の中でも、やはりローマがユダヤを滅ぼすために、神がローマの者たちの心を動かしてユダヤ戦争のために強制させると言われていた。すなわち、次のように書かれていた。『あなたが見た10本の角と、あの獣とは、その淫婦を憎み、彼女を荒廃させ、裸にし、その肉を食い、彼女を火で焼き尽くすようになります。それは、神が、みことばの成就するときまで、神のみこころを行なう思いを彼らの心に起こさせ、彼らが心を一つにして、その支配権を獣に与えるようにされたからです。』(17章16~17節)
先にも述べたが、ここで言われているのが本物のゴグのことだと考えてはならない。何故なら、本物のゴグは自分の軍勢を率いてユダヤを襲うことなどしなかったからである。もし本物のゴグがユダヤを攻撃していたとすれば、この38章・39章で言われているのはその出来事だったことになる。だが歴史を振り返ってみても、そのような出来事は起きていないから、この38章・39章ではゴグが単にローマの表示物として持ち出されているに過ぎないことになる。
『それはみな武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、みな剣を取る大集団だ。』
これはローマの軍隊を言っている。この箇所の記述内容は、正にローマ軍そのものである。
【38:5】
『ペルシヤとクシュとプテも彼らとともにおり、みな盾とかぶとを着けている。』
ローマ軍には、『ペルシヤとクシュとプテ』に属する兵士たちがいた。このローマ軍は、積極的に他国や他州から兵士を募集していた。だから、ローマ軍は言わば多国籍軍であった。それは、その半分以上がローマ人以外の兵士だったぐらいである。これは、ちょうどオリンピックの試合会場に行くと、多くの国の観衆や選手が見られるようなものである。このローマ軍の多国籍性については、もし詳しく知りたいというのであれば、古代ローマの歴史を学べばよい。『クシュ』とはエチオピアであり、これはハムの子クシュが建てた国である(創世記10:6)。『プテ』も同じくハムの子プテが建てた国であった(創世記10:6)。『ペルシヤ』については、詳しく説明しなくてもよいであろう。
この箇所から、38章・39章で言われているのはアンティオコス4世によるユダヤ攻撃ではないということが分かる。それは『クシュとプテも彼とともにおり』と書かれているからである。アンティオコス4世のシリア軍は、明らかに『クシュとプテ』と共にいなかった。むしろ、この2つの国と敵対していたはずである。この2つの国は、エジプトと親密な関係を持っている。聖書の他の箇所を見ても、エジプトとこの2つの国は兄弟でもあるかのように一緒に語られている(エゼキエル30:4~5、エレミヤ46:7~9)。これら3つの国は、元はと言えばどれもハムの子である兄弟だったのだから(創世記10:6)、これらの国の仲が良かったのは理の当然である。アンティオコス4世の時のシリアはエジプトと敵対し戦争状態にあったのだから、エジプトと近い関係を持つ『クシュとプテ』とも良い状態になかったのは容易に推測できることである。それゆえ、アンティオコス4世の軍隊と共に、この2つの国がいたというのは非常に考えにくい。エジプトと戦っていながら、クシュとプテと仲良くするということは、ほとんど有りえないように思える。しかしローマの軍隊であれば、『クシュとプテも彼らとともにおり』と言うことができる。何故なら、ローマはエジプトを支配していたのだから、そのエジプトと近い関係にあるこの2つの国と悪くない関係を持っていただろうからである。この38章・39章においてアンティオコス説を取る人は、シリアとエジプトが長らく争い合っているその時期において、シリア軍と共にクシュとプテが一緒にいたという証拠を提示していただきたい。そのような証拠は提示できないだろうから、やはり38章・39章で言われているのは紀元1世紀のローマだと結論するしかないのだ。
【38:6】
『ゴメルと、そのすべての軍隊、北の果てのベテ・トガルマと、そのすべての軍隊、それに多くの国々の民があなたとともにいる。』
ゴメルとベテ・トガルマの軍隊とは、多くの国々の軍隊を表示している。つまり、ここではローマ軍が他の多くの国の軍隊と連携を持っていたことを言っている。実際、ローマが戦争をする際は、他の同盟国や属国の王が自分の持つ軍隊を援軍として送ったりしていた。『ゴメル』とは、ヤペテの子ゴメルが建設した国である(創世記10:2)。『ベテ・トガルマ』とは、ゴメルの子トガルマが建設した国か、もしくは強い関わりを持っている国である(創世記10:3)。
『多くの国々の民があなたとともにいる』とは、ローマが他の多くの国々の民と共に歩んでいたことを示す。ローマとその他の多くの国は、主人と奴隷のような関係であった。すなわち、主人であるローマは自分の支配する国に容赦なく内政干渉し、支配される国はローマに貢物を献納せねばならなかった。この両者の関係は傾向として厳しかったが、問題や騒ぎでも起きない限りは、主従関係のうちに共に歩んでいたと言ってよい。
【38:7】
『備えをせよ。あなたも、あなたのところに集められた全集団も備えをせよ。あなたは彼らを監督せよ。』
神は、ゴグにおいてローマ軍がユダヤを征伐するための備えをするようにと語っている。この箇所では、戦闘の準備を整えよと3回も繰り返されている。これは「3回」であるから、ローマ軍によるユダヤの滅亡が非常に重要な出来事であることを示している。
それにしても、600年も前から紀元1世紀のローマに対してユダヤを滅ぼす準備をするようにと語られていたというのは、驚くべきことである。ここに神の預言における凄みがある。数年後、数十年後であれば、時には正確な予言をする者もいるであろう。しかし、どの人であれ、600年も未来の事柄を正確に預言するということは出来ないはずである。もし数年、数十年経過してから起こる出来事を予言した人に驚嘆すべきだとすれば、尚のこと、神には驚嘆せねばならないことになる。
【38:8】
『多くの日が過ぎて、あなたは命令を受け、終わりの年に、一つの国に侵入する。』
『多くの日が過ぎて』とは、「600年が経過してから」という意味である。先に見た38:3の箇所では、『今』から既に神が働きかけると言われていた。だが、この箇所では『多くの日が過ぎて』から神の働きかけが作動すると言われている。これは字義的に考えれば、相反しているように感じられる。というのも、『今』であれば『多くの日が過ぎて』からではなくなるし、『多くの日が過ぎて』からであれば『今』とは言えないからである。これの解決はそう難しくない。つまり、『今』から既に神は預言においてローマに定めを与えられるが、その定めが正式に実現されるのは『多くの日が過ぎて』から、ということである。『今』から既に定めが実現されているわけではないし、『多くの日が過ぎて』から預言が与えられるというわけでもない。間違えないように注意すべきである。
『あなたは命令を受け』とは、神の摂理により、ローマが神の計画のために強制的に動員させられることになる、という意味である。これは直接的な意味での命令を言っているのではない。すなわち、イザヤやエレミヤなどの預言者に対して神が命令を発されたかのように、神がローマに命令を発されたというのではない。そのように考えてはならない。何故なら、これは神の隠された衝動によりローマが知らず知らずのうちに御心のまま突き動かされるということだからである。
『終わりの年』とは、ユダヤが紀元1世紀に終わる時期を言っている。これは38章・39章の文脈を考慮すれば分からない者はいないはずだ。何故なら、この箇所ではユダヤが攻撃されて滅ぼされる出来事について預言されているからである。この『終わり』を世界の終わりとして解する者は、大いに間違っている。その人は、エゼキエル書38章・39章をしっかりと研究していない。その人は、複数回は38章・39章を読んだとしても、この箇所における御言葉を部分部分に至るまで詳しく研究していない(これは間違いないことである)。もし研究していれば、こういうことは決して言えないはずだからである。
『一つの国に侵入する』とは、ローマがユダヤに攻め入ることである。『侵入する』という言葉は、ローマの攻撃性・獰猛性を示している。
『その国は剣の災害から立ち直り、』
『剣の災害』とは何か。これはネブカデレザルによるエルサレム破壊のことである。剣の災害と呼べる出来事には3つある。すなわち、ローマ軍によるエルサレム滅亡、アンティオコス4世の暴虐、ネブカデレザルの破壊である。この箇所で言われている『災害』は、ローマ軍による攻撃ではない。何故なら、38章・39章で言われているのは、その『剣の災害』から立ち直ったユダヤがローマ軍により攻撃されることについてだからである。また、この『災害』とはアンティオコス4世の攻撃でもない。何故なら、38章・39章では捕囚からの回復と剣による災害が関係づけられているからである。捕囚からの回復と大きな関わりを持つ剣による災害は、ネブカデレザルの攻撃以外にはない。それゆえ、この箇所で言われている『剣の災害』とは紀元前6世紀の悲劇だったとせねばならない。この箇所では、そのネブカデレザルの攻撃による悲惨からユダヤが回復したことについて言われている。その回復は、ペルシャ王のキュロス2世によって実現された。それはエルサレムが破壊されてから70年後のことであった。
エゼキエル38章・39章がネブカデレザルの攻撃について言われていると考えている人は、この箇所に書かれている『剣の災害』という言葉をよく考えねばならない。仮に、38章・39章をネブカデレザルの攻撃について言われた箇所だとしてみよう。すなわち、ここで言われているマゴグとゴグをネブカデレザルとその軍隊であるとする。そのように考えた場合、この箇所に書かれている『剣の災害』とはどの出来事を指しているのか。エゼキエル38章・39章で言われている攻められる対象とは、『イスラエルの地』(38:18)である。ネブカデレザルがユダ王国を攻めるよりも前に、ユダ王国が『立ち直』らねばならないほどの『剣の災害』を受けたことがあったか。そのような災いは起きていない。ユダ王国がそのような致命的な災害を受けたのは、ネブカデレザルの侵攻の時が初めてであった。このように、38章・39章で言われているのがネブカデレザルの攻撃であると捉えると、『剣の災害』という出来事がまったく説明できなくなってしまう。実に、この『剣の災害』という言葉が、そのネブカデレザルの攻撃を指しているのである。だから、38章・39章で言われているのがネブカデレザルによる侵攻だったとすることは出来ない。冒頭でも述べたが、この箇所においてネブカデレザル説を取る人は研究不足である。
この箇所で言われている『剣の災害』が未だに起きていないと考えるのは、私は言うが、お話しにならない。そのように考える人は、シオニズムにより建設された現代のイスラエルが、これから『剣の災害』により悲惨にさせられるとでも考えているのか。そもそも現代のイスラエル国家が、正当なイスラエル国家とは言い難いことを理解していないのか。そこに住んでいるユダヤ人の約9割はアブラハムのDNAを持たない偽のユダヤ人(アシュケナージ)であり、アブラハムの血をその源流としている本物のユダヤ人(スファラディ)はシオニズム自体に反発しているという事実を知らないのか。また、その本物のユダヤ人がこれから『剣の災害』により再び破滅的な悲惨に陥らされるとでも考えているのか。再臨が起きた際、ユダヤ陥落の出来事において彼らに対する裁きは全うされたことを悟っていないのか。キリストが彼らに対する神の報いは、その時代のうちに与えられると言われたことを忘れてしまったのか(マタイ23:33~36)。私は言うが、まだ『剣の災害』が実現されていないと考えるのは、とんでもないことである。そのように考えている者は、聖書とユダヤ人のことをあまりにも知らなさすぎる。
『その民は多くの国々の民の中から集められ、』
これは、捕囚によって諸国に散らされていたユダヤ人たちが故郷であるユダヤの地に再び戻って来たことを言っている。これを、諸国から異邦人たちが御国の中に招かれることだと考えるのは、誤っている。何故なら、38章・39章ではユダヤ民族のことが言われているからである。
『久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。』
これは、捕囚から戻って来たユダヤ人が再びユダヤの地に住まうようになったということである。『イスラエルの山々』とはエルサレムを指す。エルサレムは多くの山に囲まれた場所だったから。『久しく廃墟であったイスラエル』とは、捕囚の時期のユダヤの地を言っている。その時のユダヤは荒れ果てたままの状態であった。
『その民は国々の民の中から連れ出され、彼らはみな安心して住んでいる。』
ダヤが滅ぼされる時期のユダヤは、平穏な状態であった。その時期には、カリグラによる神殿の問題や長らく続いているローマとの睨み合いなどといった幾らかの懸念事項があったが、全体的には平和な状態が見られたといってよい。それは、あと8年もすればユダヤが滅ぼされることになる終末の時期にもかかわらず、ユダヤの悲惨を預言したイエススという者が、まったく相手にされず気違い扱いされたことからも分かる。もし平和でなければ、このイエススという者の言った言葉に多くの人たちが心を傾けていたであろう。ヨセフスも、この時のユダヤは平和であったと言っている。(※)
(※)
このイエススの出来事についてヨセフスは次のように記録している。「しかし、これらの兆しよりももっと恐ろしかったのは次のものだった。戦争が起こる4年前(62年の秋)、都が平和と繁栄をとくに謳歌していたときのことである。アナニアスの子イエススと呼ばれるどこにでもいる田舎者が祭にやって来ると―この祭では神のために仮庵をつくるのが全ユダヤ人の習慣だった―、神殿の中で、突然、大声で、「東からの声、西からの声、4つの風からの声!エルサレムと聖所を告発する声、花婿と花嫁を告発する声、すべての民を告発する声!」と叫びはじめた。そしてイエススは日夜こう叫びながら、路地という路地を歩いてまわった。市民の中のその名の知られた者たちは、これらの不吉な言葉に苛立ち、この者を捕まえると何度も鞭打って懲らしめた。しかしイエススは自分のために弁解するわけでもなく、また自分を鞭打った者たちに密かに解き明かすわけでもなく、それまでと同じように大きな叫び声を上げつづけた。そこで指導者たちは、事実そうだったのだが、ダイモニオンか何かに憑かれていると考えて、イエススをローマ総督のもとへ引き出した。彼はそこで骨の髄まで鞭打たれたが、憐れみを乞うわけでも涙を流すわけでもなく、ただひどく悲しみに打ち震える調子で、鞭打たれるたびに、「エルサレムに呪いを!」と言った。アルビノスが―彼は総督だった―「いったいおまえは何者で、どこからやって来たのだ。何のためにこんなことを口にするのか」と尋問しても、それには答えず、都を呪う言葉を繰り返すだけだった。結局アルビノスは、気が触れていると宣告して男を放免した。以後この男は戦争の勃発まで、市民に接触することはなく、また話しているのを目撃されることもなく、毎日祈りでも唱えるかのように、「エルサレムに呪いを!」と悲しみの言葉を繰り返していた。イエススは連日自分を鞭打つ者を呪いもせず、また食べ物を恵んでくれる者を祝福もしなかった。男はすべての人にあの薄気味悪い呪いの言葉を口にするだけだった。とくに祭ともなれば、一段と声を張り上げて叫んだ。こうしてイエススは7年と5か月、相変わらずの調子で、倦むことなく嘆きの声を上げつづけた。しかし、都が包囲されて呪いの言葉が成就されたのを見ると安息を得た。というのも、そのときイエススは周囲を巡回しながら城壁から「都と民と聖所に再び呪いを!」と甲高い声を上げていたが、最後に「そしてわたしにも呪いを!」と口にしたとき、投石機から発射された石弾が命中して即死したからである。こうしてイエススは、呪いの言葉をまだ口の端にのせながら、その命を解き放ったのである。これらの数々の予兆の意味を考えると、人は次のことを、すなわち神は人間たちの保護者であり、ご自分の民にはあらゆる手段を用いて救いの道をあらかじめお示しになっていたことを、しかしまた人間というものは愚行と自らが選び取った悪とで滅びるものであることを知るのである。」(『ユダヤ戦記3』ⅤⅠ v3:300~4:310 p072~075:ちくま学芸文庫)
[本文に戻る]
【38:9】
『あなたは、あらしのように攻め上り、あなたと、あなたの全部隊、それに、あなたにつく多くの国々の民は、地をおおう雲のようになる。』
ゴグであるローマ軍は、ユダヤの地に『あらしのように攻め上』った。ヨセフスの歴史書を読むがよい。そこには、ローマ軍がまるで嵐でもあるかのように、ユダヤの各地を次々と制圧したことが描かれている。最後の最後に残ったエルサレム市も、竜巻が襲ったかのようにして破滅させられてしまった。巨大なハリケーンに抵抗できないように、ローマ軍の力と勢いにユダヤの地は抵抗することが出来なかった。
この時のローマ軍は『地をおおう雲のように』なった。すなわち、地を雲が覆うかのようにローマ軍がユダヤを取り囲んだ。エルサレム市には10箇軍団が配置されたから、そこには歩兵5万~6万、騎兵約1200が取り囲んでいたことになる。これは正に雲が囲んでいるかのようだと言ってよい。黙示録でも、やはりローマ軍がユダヤの地を雲でもあるかのように取り囲んだと示されている。すなわち、次のように黙示録では書かれている。『…彼らの数は海べの砂のようである。彼らは、地上の広い平地に上って来て、聖徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ。』(20章8~9節)
【38:10】
『神である主はこう仰せられる。その日には、あなたの心にさまざまな思いが浮かぶ。』
ユダヤが滅びる時期のローマは、ユダヤを制圧するために色々なことを考えていた。何故なら、ユダヤ人たちはローマに反逆的であって、言わば不良少年のようだったからである。だから、不良少年をどう取り扱おうかと考える校長のように、ローマはユダヤをどう取り扱ったものかと考えていたわけである。
『あなたは悪巧みを設け、』
ローマは、ユダヤの問題を解決すべく巧みに計略を練った。実際、当時の皇帝であったネロは、ユダヤ問題のために真剣に考えていた。そうして考えた末、軍隊を遣わしてユダヤを制圧させるという誠にネロらしい計画を実行させるに至ったのであった。
【38:11】
『こう言おう。『私は城壁のない町々の国に攻め上り、安心して住んでいる平和な国に侵入しよう。彼らはみな、城壁もかんぬきも門もない所に住んでいる。』』
これは、ユダヤを攻略してやろうというローマの精神である。ローマが実際にこのように言ったというわけではない。ここで言われているのは、単にローマのユダヤに対する精神状態を言葉として表現しているだけに過ぎない。
また、我々はここで言われていることを文字通りに捉えるべきではない。この箇所では、ユダヤには『城壁もかんぬきも門もない』と言われている。だが、実際にはこれらのものがユダヤにはあった。それでは、どうしてここでは実際とは違うことが言われているのか。これは、つまりユダヤがどれだけ平和な状態であったかということを比喩表現として言い表しているのである。だから、実際とは違ったことがここで言われていたとしても問題にはならない。ここでは、まるで『城壁もかんぬきも門も』備えていないかと思えるぐらいにユダヤが非常な平和を享受していたと教えられているのだ。というのも、これらのものを必要としないほどに平和だと言えることが他に何かあるであろうか。
【38:12】
『あなたは物を分捕り、獲物をかすめ奪い、今は人の住むようになった廃墟や、国々から集められ、その国の中心に住み、家畜と財産を持っている民に向かって、あなたの腕力をふるおうとする。』
ローマ軍は、まるで卓越したハンター集団が無数の獲物を仕留めるかのように、ユダヤを仕留めて強奪した。この箇所では『獲物』と言われている。正にローマのユダヤ侵攻とはハンティングだったのである。また、ここでは『あなたの腕力をふるおうとする。』とも言われている。これは熟練したハンター(=ローマ)が、獲物を前にして「どうら、いっちょ俺の狩の腕を振るってみるとすっかな。」などと自信満々に構えるようなものである。この箇所で言われているように、確かにユダヤは獲物でもあるかのように強奪の限りを尽くされた。家畜も財宝も祭儀用の道具も、全てがことごとく奪われてしまった。ユダヤは負けてしまったのだから、このようにされるのは当然であった。何故なら、昔から今に至るまで敗戦国が勝った国に好き放題されるのは常のことだからである。負けた側は何をされても文句を言えない。しかし、このようにユダヤが根こそぎ奪われたのは、彼らの罪がその原因であった。
この箇所では、特にエルサレム市にピントが当てられている。何故なら、ここでは<『その国の中心に住』んでいる民>と言われているからだ。『その国の中心』とは、もちろんエルサレム市である。だから、ここではエルサレム市を特に語っている。だが、だからといってローマに滅ぼされたのはエルサレム市だけだったというわけではない、という点に注意せねばならない。
【38:13】
『シェバやデダンやタルシシュの商人たち、およびそのすべての若い獅子たちは、あなたに聞こう。『あなたは物を分捕るために来たのか。獲物をかすめ奪うために集団を集め、銀や金を運び去り、家畜や財産を取り、大いに略奪をしようとするのか。』と。』
ローマによるユダヤの破滅は、諸国の『商人たち』や『すべての若い獅子たち』も注目した。注目していたからこそ、このように聞くのである。もし注目しておらず、別にどうでもいいと思っていたとすれば、わざわざ聞くこともなかったであろう。『商人たち』とは、商人だけでなく金持ちや有力者も含んでいるとすべきであろう。『若い獅子たち』とは、まだ若い王を指している。エゼキエル書32:2の箇所でも、まだ若かったエジプトの王パロを指して『若い獅子』と呼ばれている。実際、このユダヤの破滅は、大いに着目すべき出来事であった。何せ世界で最も卓越した建造物であったエルサレム神殿が破壊され、ユダヤの国が一挙に滅ぼされてしまったからである。もしこの出来事に着目しないとすれば、それは鈍感であるからに他ならないのであった。確かなところ、これは911の悲劇が小さく思えるぐらいの出来事であった。何故なら、911の悲劇では幾つかの建造物と約3000人の人が滅びたのに対し、我々が今見ている悲劇のほうではユダヤという国そのものが滅ぼされた上に最高で110万人とされる死者が出たからである。当時の世界観が今に比べて小さく、世界人口も少なかったことを考慮すれば、これがどれだけ衝撃的な出来事だったか分かるはずである。黙示録18章でも、王たちと商人たちがエルサレムの崩壊を見て、大いに驚き嘆いている様が描かれている。ところで、この黙示録18章であるが、この黙示録18は我々が今見ている箇所と対応しているとすべきである。
『銀や金を運び』という言葉は、成就された。『家畜や財産を取り』という言葉も、成就されている。『大いに略奪』するという出来事も既に起きた。ユダヤの陥落を歴史書から学んでいない者は、ユダヤ陥落後12年経ってから作られた有名な凱旋門におけるレリーフを見るとよい(※)。そうすれば、この箇所で言われているように、確かにローマがユダヤから諸々の物品を略奪したということが感覚的に分かるであろう。このレリーフの中では、ローマ兵たちがメノラーなどの道具を持ち運んでいる様子が描かれている。
(※)
ティトゥスの凱旋門 レリーフ
[本文に戻る]
【38:14】
『それゆえ、人の子よ、預言してゴグに言え。神である主はこう仰せられる。わたしの民イスラエルが安心して住んでいるとき、実に、その日、あなたは奮い立つのだ。』
この箇所で言われているように、『イスラエルが安心して住んでいるとき』に、急に悲劇がユダヤを襲った。この時が平和な状態だったということは、ヨセフスの証言がある。平和な状態の時に、突如として滅びがやって来るというのはキリストも言っておられたことである。すなわち次の通りである。『洪水前の日々は、ノアが箱舟にはいるその日まで、人々は、飲んだり、食べたり、めとったり、とついだりしていました。そして、洪水が来てすべての物をさらってしまうまで、彼らはわからなかったのです。』(マタイ24章38~39節)パウロもこう言っている。『人々が「平和だ。安全だ。」と言っているそのようなときに、突如として滅びが彼らに襲いかかります。』(Ⅰテサロニケ5章3節)
『実に』という言葉は強調である。それゆえ、我々はこのユダヤ陥落の出来事に大いに着目せねばならないのである。神が『実に』と言って強調しておられるのに、その事柄を無視したり軽んじたりしていいはずが、一体どうしてあるのか。
ところで、どうして神は平和な時に突如として悲劇をユダヤに下されたのであろうか。その理由は、神が我々の理性と常識を遥かに超え出た御方だからである。そのように我々の意表を突く仕方で事を実現されるからこそ、神が崇められたり恐れられたり認められたり感じられたりするのだ。試しに神がごく普通の仕方で事を実現されると考えてみよ。そうすると、どうか。その場合、我々はあまり驚いたり感じ入ったりしなくなるであろう。そうなれば、それだけ神が崇められたり恐れられたりすることもなくなる。むしろ、神を軽んじることにもなりかねなくなる。我々人間は、人から軽んじられることを好まない。我々人間でさえそうであれば、神は尚のこと、そうである。だからこそ、神は御自身の尊厳と栄光のため、人々が想定してもいなかったような平和な時に突如として悲劇的出来事を実現されたのである。
【38:15】
『あなたは、北の果てのあなたの国から、多くの国々の民を率いて来る。彼らはみな馬に乗る者で、大集団、大軍勢だ。』
ここでは、ローマ軍の大集団がユダヤを攻めにやって来るということが、マゴグとゴグの大集団において預言されている。確かにローマ軍は『大集団、大軍勢』であった。単純計算で言えば、ローマ軍は歩兵14万~16万8000、騎兵3360を有していたからである。
この箇所では、先にも述べた通り、マゴグの地がユダヤから見て『北の果て』にあったと言われている。これは黙示録でユーフラテス川の北側からマゴグなるローマがユダヤに攻めて来ると言われていたのと一致している。何故なら、ユーフラテス川の北側とは、ユダヤから見て北側だからである。
ここでマゴグの軍隊が『馬に乗る者』と言われているのは、正にその通りであった。マゴグに住む者とは騎馬民族であるスキュティア人だったからである。エゼキエルもヨハネも、このスキュティア人であるマゴグに、ローマの軍隊を重ね合わせている。そのようにするのは、正にピッタリであった。何故なら、マゴグの人たちが馬に乗る戦士だったように、ローマ軍も騎兵を大いに持つ軍隊だったからである。しかも、どちらも非常に力強く、周りの民族から恐れられていた。私は言うが、このマゴグにローマを重ねることなしに、黙示録とエゼキエル38章・39章を理解することはできない。聖徒たちは私が今言ったことをよく心に留めよ。
【38:16】
『あなたは、わたしの民イスラエルを攻めに上り、終わりの日に、あなたは地をおおう雲のようになる。』
『終わりの日』とは、もちろんユダヤが滅ぼされて終わる時のことである。それは、38章・39章の文脈を考えれば、分からない者はいないはずである。これが分からない人は、恐らく理性に欠陥があるのだと思われる。それだから、これが地球全土の終わりだなどと勘違いをしてはならない。38章・39章で言われているユダヤの地とは、局所的な場所に過ぎなかったのだから。
ここでローマ軍が『地をおおう雲のようになる。』と言われているのは、先に見た38:9の箇所と同じである。このように繰り返されるのは、ユダヤ陥落の出来事が非常に重要だったからに他ならない。
『ゴグよ、わたしはあなたに、わたしの地を攻めさせる。』
これは、ローマにユダヤを滅ぼさせるという神の堅い決意が表明された御言葉である。この計画は誠にとてつもないものであった。何故なら、これはちょうど勘当された邪悪な息子を、強力なヤクザまたはマフィアを雇って容赦なく殺させようとするのと同じだからである。確かなところ、ユダヤは勘当された邪悪な息子のようなものであり、ローマは誰も打ち勝てないヤクザまたはマフィアのようなものであった。
『それは、わたしがあなたを使って諸国の民の目の前にわたしの聖なることを示し、彼らがわたしを知るためだ。』
神がローマ軍によりユダヤを滅ぼされたのは、人々が神とその神聖性を認めるためであった。つまり、こういうことである。ユダヤが壊滅させられたのであれば、誰でもユダヤが罪悪を持っていたことを知るようになる。何故なら、神が御自身の民を、何の理由もなしにこんなにも酷い目に遭わせるなどということは考えにくいと思えるからである。そうだとしたら、ユダヤが滅ぼされたのは、神がユダヤをその罪ゆえ裁かれたからだということになる。であれば、神とは御自身の民に対してでさえ、容赦なく悪を罰せられる聖なる審判者だということになる。ここにおいて、諸国の民は、神の存在を、またこの神は悪を憎まれる聖なる御方であるということを感じ取るのである。『諸国の民の目の前にわたしの聖なることを示し、彼らがわたしを知るため』と言われているのは、今述べたような意味であった。これは、例えるならばキケロがカティリナの陰謀から国を救った際、「国父」などと呼ばれたようなものである。キケロがその勇敢な振る舞いによりローマを救ったからこそ、人々はキケロの言行を認め、「国父」という称号を彼に送らざるを得なくさせられた。これと同じで、神がユダヤを滅ぼされた際、その裁きの出来事を見た人々は神についてその存在と神聖性を認めざるを得なくさせられたのである。
この箇所では『使って』とローマについて言われている。これはローマが単に神の道具に過ぎなかったことを示している。ローマは、神がユダヤを滅ぼすために利用した剣に他ならなかった。このように神は、ある存在を御自身の計画が成就されるために道具として使われる。それは、ネブカデレザルもキュロスもアンティオコスもそうである。ローマ人がこのようなことを聞いたとすれば、彼らは「そんな見解はとんでもないことだ。」などと否定したかもしれない。だが実際は正にその通りであったというのが聖書から言えることである。
【38:17】
『神である主はこう仰せられる。あなたは、わたしが昔、わたしのしもべ、イスラエルの預言者たちを通して語った当の者ではないか。この預言者たちは、わたしがあなたに彼らを攻めさせると、長年にわたり預言していたのだ。』
ローマとその軍隊は、前もって預言されていた。つまり、それはエゼキエルにおいて初めて語られたというわけではなかった。神は、このようにあらかじめ未来の事柄を繰り返し告げ知らせる御方である。だが、人は鈍感なので、神の預言をなかなか悟ることができない。『神はある方法で語られ、また、ほかの方法で語られるが、人はそれに気づかない。』(ヨブ33章14節)と聖書では言われている。このローマの預言はどうだったか。ユダヤ人は、いずれユダヤが攻撃されるということは理解できたが、それが誰の手によるのか、すなわちマゴグとゴグというのが誰なのかまでは理解できなかった、と私には思える。中には、このマゴグとゴグが本物のマゴグとゴグだと理解した者もいたかもしれない。また、アンティオコス4世の暴虐がユダヤを襲った際に、このエゼキエルの預言が実現されたと感じた者もいたかもしれない。いずれにせよ、これがローマについて言われていると理解できた者は、エゼキエルの時代には一人もいなかったはずである。何故なら、その時代においては、まだローマなど取るに足りない存在だったからである。ローマが台頭して周りの国から一目置かれるようになったのは、紀元前3世紀以降の話である。
では、神が昔から語ってこられたローマ軍によるユダヤ攻撃の預言とは、具体的には聖書のどこに書かれているのか。神が、ここで聖書には書かれていない預言について言及しているとは考えにくい。確かにそうであった。神は、聖書に書き記された預言について、ここで言及しておられる。その預言とは次の通りである。『諸国の民の間で、こう叫べ。聖戦をふれよ。勇士たちを奮い立たせよ。すべての戦士たちを集めて上らせよ。』(ヨエル3章9節)
【38:18~19】
『ゴグがイスラエルの地を攻めるその日、―神である主の御告げ。―わたしは怒りを燃え上がらせる。わたしは、ねたみと激しい怒りの火を吹きつけて言う。その日には必ずイスラエルの地に大きな地震が起こる。』
神がローマ軍によりユダヤを滅ぼされる際、神はユダヤに大きな怒りを燃え上がらせた。これは当然のことであった。神の子イエス・キリストが拒絶され、迫害され、殺されたのである。これではユダヤが滅ぼされなかったほうが、かえって不思議なぐらいである。試しに自分の子が他の子どもたちのところに救助者として送られたのに、まったく相手にされず、それどころか肢体を引き裂かれて殺されてしまったと考えてみよ。その殺人者である他の子どもたちは、まったく反省する気持ちさえ見せていない。それどころか、子どもを送ったあなたを睨みつけて敵視している。このようにな状況を考えるとどうであろうか。神がユダヤを滅ぼされた気持ちが、よく分かるのではないかと思う。確かに神は、御自身の御子を殺害したユダヤに対して、猛烈な怒りの火を燃え上がらせた。実際、キリストはユダヤに裁きを与えるため、火をもって天から降りて来られた。そして、ユダヤは御言葉という火により霊的に断罪された。またユダヤは本当に本物の火で容赦なく焼き滅ぼされてしまった。これらの出来事を考えると、確かに神はユダヤに『激しい怒りの火を吹きつけて』裁かれたことが分かる。
ユダヤが裁かれる時、ユダヤには確かに『大きな地震が起こる』ことになった。それはユダヤ戦争まっただ中の紀元68年6月9日である。この日は荒らす者であるネロが死んだ日だが、ネロがこの日に死ぬ少し前に、大きな地震が起こった。その時にキリストが再臨されたので、地は揺るがざるを得なかったのである。このように地を揺るがされたのは、他でもない神であった。キリストが再臨されてユダヤが滅ぼされるのだから、地に大激震が起きて然るべきだったのである。この大地震の出来事は、黙示録では16:18の箇所と対応している。そこでは『この地震は人間が地上に住んで以来、かつてなかったほどのもので、それほどに大きな、強い地震であった。』と書かれている。
この箇所では『イスラエルの地』が攻められると預言されている。『イスラエルの地』!これは石造りの神殿があったあの地以外の地ではない。この言葉を文字通りに捉えるならば、その人はエゼキエル38章・39章を上手に解釈できるようになる。しかし、この言葉を霊的または玄妙に捉えるならば、その人は永遠にエゼキエル38章・39章を理解できないままとなる。それゆえ、黙示録20:7~10の箇所で言われているマゴグとゴグが都の場所を包囲するという出来事は、紀元1世紀のユダヤ包囲に他ならないことが分かる。何故なら、ヨハネはエゼキエル38章・39章のことを黙示録20:7~10の箇所で言っているのだからである。この理解は、黙示録に書かれている出来事は全て『すぐに起こるべき事』(黙示録22:6)だったと言われている神の御言葉と完全に調和している。何故なら、黙示録20:7~10の箇所で書かれているユダヤ包囲の出来事は、ヨハネが紀元1世紀に黙示録を書いてから本当に『すぐに』起こったからである。この『イスラエルの地』という言葉を文字通りに解そうとしない者は、永遠に無知の闇に陥るがよい。その者は、黙示録もエゼキエル38章・39章もずっと理解できないままとなるであろう。
【38:20】
『海の魚も、空の鳥も、野の獣も、地面をはうすべてのものも、地上のすべての人間も、わたしの前で震え上がり、山々はくつがえり、がけは落ち、すべての城壁は地に倒れる。』
『海の魚も、空の鳥も、野の獣も、地面をはうすべてのものも、地上のすべての人間も、わたしの前で震え上がり』とは、ユダヤの地について言っている。これはエゼキエル38章・39章の文脈を考えれば分からない人はいないであろう。この箇所では、ユダヤの地のことが預言されているのだから。地上における全てが悲惨になると言われながら、実はユダヤの地上についてだけを言っている箇所は、聖書の他の箇所にも存在している。それはゼパニヤ書1章である。ユダヤが破滅した時のことについてよく考えてみよ。その時にはユダヤにおける全てがことごとく破壊され尽くした。だから、この箇所でユダヤの地における全ての生命体が神の御前において戦慄すると言われているのは、誠にもっともなことであった。
『山々はくつがえり、がけは落ち、すべての城壁は地に倒れる。』とは、ユダヤの滅びを詩的に言い表している。つまり、これはユダヤの地に大異変が起こるということだ。これが詩的な表現であると分からない者が果たしているのか。しかし、『すべての城壁は地に倒れる。』という部分だけは、詩的表現であると共に、実際の出来事とも合致している。何故なら、ローマ軍はユダヤの各地における城壁をことごとく打ち破ったからである。ところで、この城壁が地に倒れるという出来事と、先に見た箇所で言われていたことが矛盾しているのではないかと思われる方がいるかもしれない。すなわち、我々が今見ている38:20の箇所ではユダヤに城壁があると言われているのに対し、前に見た38:11の箇所ではユダヤに城壁がないと言われている、という矛盾である。この解決は簡単である。先に述べた通り、38:11の箇所では、単にユダヤの平和を示そうとして城壁がないと言われたに過ぎない。すなわち、38:11の箇所では象徴的なことが言われている。我々が今見ている箇所のほうは、38:11の箇所とは逆であって、実際の状態から乖離していない。何故なら、ユダヤにあった町々は城壁を持っていたからである。特にエルサレム市においてはローマ軍さえ手こずらされた難攻不落の城壁があった。
【38:21】
『わたしは剣を呼び寄せて、わたしのすべての山々でゴグを攻めさせる。―神である主の御告げ。―』
『剣を呼び寄せて』とは、すなわち「剣による死の裁きを下して」という意味である。『剣』という言葉が虐殺を指しているということは、旧約聖書をよく読み慣れた者であれば、知っているはずである。つまり、神はここでこのように言っておられる。「私は剣による死の裁きをユダヤに下すが、それはゴグを用いて実現される。」
ゴグであるローマ軍は、自分たちの意志で、自主的にユダヤを陥落させたと感じていたはずである。確かに、表面的に言えば正にその通りであった。だが究極的に言えば、神が望まれたからこそ、ローマはユダヤに侵攻することになった。もし神が望んでおられなければ、ローマがユダヤを破滅させることもなかったであろう。つまり、ローマによるユダヤの破滅は神から出て、神によって成り、神に至る出来事であった。ローマ11:36の箇所で言われているように、この世界では『すべてのことが、神から発し、神によって成り、神に至る』のだから。
『彼らは剣で同士打ちをするようになる。』
これはユダヤ戦争の時期に起こったローマの激しい内戦を指す。これについてはタキトゥスが『同時代史』の中で詳しく記している。この内戦は、全部で3回も起こった。すなわち、1回目はガルバ軍とオト軍の戦い、2回目はオト軍とウッティリウス軍の戦い、3回目はウッティリウス軍とウェスパシアヌス軍の戦いである。この内戦によりローマは疲弊し、あやうく滅びてしまうところにまで行ったのであり、最終的な勝利者となったウェスパシアヌスによりローマが立ち直されたことがほとんど奇跡的だと言えるほどであった。このような悲惨な仲間争いは、神の裁きによった。それはどのような裁きであったのか。それは、ローマ人たちが福音を受け入れなかったことに対する裁きであった。
この出来事については、ハガイ2:22の箇所でも預言されている。すなわち次のように書かれている。『馬と騎兵は彼ら仲間同士の剣によって倒れる。』このハガイ書の預言については、また後ほど註解される。
【38:22】
『わたしは疫病と流血で彼に罰を下し、』
ローマに対して下される『疫病』の罰とは、ローマに起こった伝染病を指す。これは歴史が記録している通りである。黙示録の中では次のように言われている。『そこで、第一の御使いが出て行き、鉢を地に向けてぶちまけた。すると、獣の刻印を受けている人々と、獣の像を拝む人々に、ひどい悪性のはれものができた。』(16章2節)
『流血』の罰とは、内戦のことである。この内戦では、多くの血が流されたからだ。これは正にローマが受けるべき正当な罰であった。
『彼と、彼の部隊と、彼の率いる多くの国々の民の上に、豪雨や雹や火や硫黄を降り注がせる。』
ローマ軍の上に『豪雨や雹や火や硫黄』が降り注がれるとは、ローマに起こった内戦の悲惨さを言い表している。もし実際にこれらのものが地上に降り注いだとすれば、たまったものではない。苦しみと叫びとがそこら中に満ち渡るであろう。ローマの内戦も、そのような悲惨さを持っていたのである。だから、これらは文字通りに捉えるべきではない。この4つが降り注がれるとは単なる象徴なのである。また、これらの象徴表現が、昔の悲劇を念頭に置いていることは間違いない。すなわち、『豪雨』とはノアの大洪水の時に降り注いた大雨を、『雹』とは出エジプトの際にエジプトに降ってきた雹を、『火や硫黄』とはソドムとゴモラに降り注がれた火と硫黄に基づいて言われている。つまり、この箇所では、これらの悲劇を思い起こさせることで、どれだけ大きな悲惨がローマを襲うかということを悟らせようとしている。
このローマ内戦における悲惨は、黙示録の中では2つの箇所で記されている。一つ目は16:21である。『また、1タラントほどの大きな雹が、人々の上に天から降って来た。人々は、この雹の災害のため、神にけがしごとを言った。その災害が非常に激しかったからである。』二つ目は20:9である。『彼らは、地上の広い平地に上って来て、聖徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ。すると、天から火が降って来て、彼らを焼き尽くした。』この黙示録の2つの箇所で言われている出来事は、同一の出来事である。読者は、黙示録では時間の流れ通りに記述が進められているのではないという第3部で既に述べられたことを、再び思い返してほしい。
【38:23】
『わたしがわたしの大いなることを示し、わたしの聖なることを示して、多くの国々の見ている前で、わたしを知らせるとき、彼らは、わたしが主であることを知ろう。」』
ここで言われている内容は、先に見た38:16の箇所と、ほとんど同じである。38:16の箇所では、ローマ軍によりユダヤが滅ぼされることで神とその神聖性が人々に知らされる、と言われていた。この38:23の箇所では、ローマに裁きが下されることで神とその神聖性が人々に知らされる、と言われている。つまり、どちらの箇所でも神が御自身を知らされると言われている点では一緒だが、どの対象を用いて神が御自身を知らされたのかという点で異なっている。我々が今見ている箇所で神がローマに対する裁きを通して御自身を知らせると言われているのは、先に見た38:16の箇所における仕組みとまったく一緒である。すなわち、ユダヤの裁かれる時期にローマが裁かれると、人々はローマもユダヤと同じように神からの裁きを受けているのだと感じるようになる。すると、人々は神が悪を裁かれる神聖な存在であるということを、ローマの裁きを通して知るに至る。ここにおいて人々は裁きをなされる神の存在を認知するのである。このように神とは、裁きを通して御自身の存在を知らされる御方である。昔から誰でも非常に大きな災いが起きたり、長らく続く災いに苦しんでいると、次のように感じたりするものである。「もしやこれは神からの天罰なのではないか。」ここにおいて神は、人に裁きを下される御自身の存在を明白にお示しになるのである。
【39:1】
『「人の子よ。ゴグに向かって預言して言え。神である主はこう仰せられる。メシェクとトバルの大首長であるゴグよ。わたしはあなたに立ち向かう。』
この箇所で言われている内容は、既に書かれていたことの繰り返しであるから、再び説明する必要はない。
ここから新しい章として区切られているのは正しい区切りである。何故なら、神は再びゴグに対して預言をし始めておられるからである。38章が第1部だとすれば、この39章は第2部だということになる。39章は38章よりも解読が難しい。
【39:2】
『わたしはあなたを引き回し、あなたを押しやり、北の果てから上らせ、イスラエルの山々に連れて来る。』
神は、ローマ軍を言わば押し流すかのようにして、強制的にユダヤ討伐へと向かわせられた(もちろんローマは神から強制されているなどとは思っていなかっただろうが)。これは38:4の箇所でも言われていたことである。『イスラエルの山々』とは、先にも述べたようにエルサレム市を指している。
【39:3】
『あなたの左手から弓をたたき落とし、右手から矢を落とす。』
これはローマ軍が無力化されるという意味である。いったい誰に対して無力化されるのか。それはキリストと復活した聖徒たちに対して、である。この時には、キリストが再臨され、復活した聖徒たちと共に僅かの間だけ強力な支配を実現されたのだから、ローマ軍はキリストの勢力に対抗することができなかった。その時には『千年』として言い表される無敵の支配が実現されたのだから―この千年とは時間を示す言葉ではない―、ローマ軍が無力化されたとしても何の不思議なことがあるであろうか。
この箇所では、マゴグなるローマ軍の手に弓矢が握られていたと示されているが、ローマ軍の全ての兵士が弓矢を使っていたわけではないという点に注意すべきである。確かにローマ軍は弓矢を使用していたが、全ての兵士が常に弓矢を専門的に使用していたわけではなかった。だから、この箇所で弓矢が両手から落とされたと言われているのは、実際上のこととして捉えるよりは、むしろそこで教示されている事柄に注意を傾けるべきである。つまり、この箇所を読んで、我々は単にローマ軍が神の御前において無力化されたということだけを理解すれば、それでよい。ローマ軍が弓矢を使っていたことについては、少なくともこの箇所においては何も考えなくてもよい。
【39:4】
『あなたと、あなたのすべての部隊、あなたの率いる国々の民は、イスラエルの山々に倒れ、わたしはあなたをあらゆる種類の猛禽や野獣のえじきとする。』
ローマ軍は、『イスラエルの山々』であるエルサレムにおいて霊的に断罪された。何故なら、その時、そこにはキリストが再臨され霊的な裁きを下されたからである。この時のことについて、パウロはこう言っている。『そのとき主は、神を知らない人々や、私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は、主の御顔の前とその御力の栄光から退けられて、永遠の滅びの刑罰を受けるのです。』(Ⅱテサロニケ1章8~9節)それだから、ここでローマ軍がエルサレムの場所で倒れると言われているのは、実際的な意味ではない。ユダヤ戦争の時、ローマ軍が物理的な意味において倒れなかったのは確かである。その時に物理的に倒れたのはローマ軍ではなくユダヤ人である。ローマ軍は単に霊的な意味において裁きのうちに倒されただけに過ぎなかった。
ローマ軍が『あらゆる種類の猛禽や野獣のえじき』にされるとは、こういうことである。キリストが再臨されると、エルサレムにいたローマ兵たちは霊的に殺されて霊的な死体と化した。すると、その死体と化したローマ兵たちを、無数の悪霊どもが餌食とした。悪霊どもに餌食にされるとは、悪霊に憑りつかれることである。この箇所では、その悪霊が『あらゆる種類の猛禽や野獣』と言い表されている。この出来事は、黙示録19:17~18の箇所でも書かれている。『また私は、太陽の中にひとりの御使いが立っているのを見た。彼は大声で叫び、中天を飛ぶすべての鳥に言った。「さあ、神の大宴会に集まり、王の肉、千人隊長の肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべての自由人と奴隷、小さい者と大きい者の肉を食べよ。」』我々が今見ている箇所では悪霊が鳥や野獣として言い表されているのに対し、黙示録のほうでは鳥としか言い表されていないが(つまり野獣が省かれている)、どちらの箇所でも言われている内容は同一である。また、キリストがマタイ24:28の箇所で次のように言われたのも、この出来事についてであった。『死体のある所には、はげたかが集まります。』この箇所でキリストは、再臨により霊的に殺されたローマ兵の死体たちが『はげたか』である悪霊どもに憑依されると言われたのであった。このように聖書では悪霊が主に鳥類として言い表されているが、『はげたか』であれ『猛禽』であれ表記は違えど、どれも悪霊について言われていることに変わりはない。
【39:5】
『あなたは野に倒れる。わたしがこれを語るからだ。―神である主の御告げ。―』
ローマ軍が『野に倒れる。』とは、霊的なことを言っている。つまり、これは再臨のキリストにより神の御前で霊的に倒されるという意味である。
ここで神が『わたしがこれを語るからだ。』と言っておられるのは、次のように言われたのも同然である。「神である私がこのように語るのであれば、どうしてそのことが実現しないわけがあるであろうか。私は全能の神ではないのであろうか。」確かに神は約束されたことを絶対に実現される御方である。それはイザヤ14:24の箇所で、神御自身がこう言っておられる通りである。『必ず、わたしの考えたとおりに事は成り、わたしの計ったとおりに成就する。』それだから、神が約束された事柄が絶対に実現すると信じた者は幸いである。ルカ1:45の箇所でこう言われている通りである。『主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は、なんと幸いなことでしょう。』実際、ここで語られた出来事は、ユダヤ戦争の時に実現された。
【39:6】
『わたしはマゴグと、島々に安住している者たちとに火を放つ。彼らは、わたしが主であることを知ろう。』
『マゴグ』とはローマを指す。『島々』とは多くの国々を指す。『島々に安住している者たち』とは、多くの国々に住んでいる平和な人たちを指している。『火』とは御言葉を指している。つまり、この箇所では神が御言葉という火において、世界中の人々に御自身の存在を感知させる、ということが言われている。つまり、こういうことである。神がローマに御言葉という火に基づいて復讐されると、その復讐の出来事により、人々は神の存在を感じるようになる。何故なら、その復讐は御言葉において為された出来事だからである。この箇所で言われている『島々』また『火』という言葉を文字通りに捉えないよう注意していただきたい。どちらか一つであれ両方であれ、この言葉を文字通りに捉えるならば、この箇所を正しく理解できなくなってしまうからである。
【39:7】
『わたしは、わたしの聖なる名をわたしの民イスラエルの中に知らせ、2度とわたしの聖なる名を汚させない。諸国の民は、わたしが主であり、イスラエルの聖なる者であることを知ろう。』
ユダヤが裁かれると、それから後、ユダヤが神の『聖なる名』を軽んじることはなくなった。何故なら、その時にはキリストが再臨され、ユダヤが背きの罪から救われたからである。すると、ユダヤ人の救われた者たちは天上に引き上げられ、そこで神の御名を褒め歌うようになった。だから、それからはもうユダヤが神を蔑むことはなくなったのである。このユダヤの救いについては、聖書にこう書かれている。『救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬虔を取り払う。これこそ、彼らに与えたわたしの契約である。それは、わたしが彼らの罪を取り除く時である。』(ローマ11章26~27節)『それは、主の御前から回復の時が来て、あなたがたのためにメシヤと定められたイエスを、主が遣わしてくださるためなのです。』(使徒行伝3章20節)
また、この時には諸々の国の民族も、神存在を感知することになった。その時、ユダヤとローマに大きな裁きが下されたからである。現代とは違って非常に有神論的だった古代人たちは、これらの裁きを見て、大いに審判者なる神の存在を察知したに違いない。彼らは、あらゆる事象や概念を色々な神々と結びつけるぐらいだったのだから。裁きにより人々が神とその神聖性を感知する、ということについては既に語られた通りである。
【39:8】
『今、それは来、それは成就する。―神である主の御告げ。―それは、わたしが語った日である。』
この箇所では、38章・39章で言われているユダヤ侵攻の預言が『今』において『成就する。』と言われている。この『今』とは、もちろんエゼキエルが神から預言を受けた『今』すなわち紀元前6世紀である。しかし、ヨハネは黙示録の中で、まだマゴグなるローマの攻撃を成就していない出来事として語っていたのではなかったか。ローマ軍の攻撃が起こるのは、明らかにこの箇所で言われている『今』ではない。だが、この箇所ではマゴグの攻撃が『今』起こると言われている。この問題はどう解決すればよいか。これはこう解決すべきである。すなわち、この箇所では「この預言はもう今から成就しているのも同然だ。」と言っていると捉えねばならない。先にも述べた通り、神が語られたことは絶対に成就する。ゆえに、神の預言を、その預言が語られた時から既に成就していると言ったとしても間違いではない。この箇所は、私が今述べたように理解すべきである。何故なら、このように理解する以外に正しい理解はないからである。
それゆえ、この箇所を文字通りに捉えてはいけない。もしこれを文字通りに捉えるならば、エゼキエル38章・39章で言われているのはネブカデレザルの攻撃だったことになる。というのも、エゼキエルに預言が与えられている『今』の時点で預言が成就するとすれば、それはネブカデレザルの攻撃しかないことになるからである。だが、このように考えると多くの問題が出てくる。まず、この箇所を文字通りに捉えると、先に見た38:8の箇所で書かれていたユダ王国が立ち直らねばならなくさせられたほどの『剣の災害』という出来事が何なのか分からなくなってしまう。この問題については先にも語られた。また、この箇所を文字通りに捉えると、ヨハネがまだ成就していない出来事としてゴグの侵攻について語ったことが説明できなくなる。もしこのゴグの侵攻がネブカデレザルの侵攻だったとすれば、ヨハネが黙示録の中でゴグの侵攻について語っていたかどうかは定かではない。また、この箇所を文字通りに捉えると、38:8の箇所で『多くの日が過ぎて』からゴグが侵攻を実行すると言われているのと調和できなくなる。これは決定的である。何故なら、もし『今』から既に成就するというのであれば、『多くの日が過ぎて』から成就するということにはならないからである。この矛盾を解決するには、『今』という言葉を霊的に、『多くの日』という言葉を字義通りに解するしかない。そういうわけで、以上の考察から、この箇所で『今』から既に預言が成就されると言われているのは文字通りに解釈すべきではないと結論せねばならないことが分かる。
【39:9】
『イスラエルの町々の住民は出て来て、武器、すなわち、盾と大盾、弓と矢、手槍と槍を燃やして焼き、7年間、それらで火を燃やす。』
ユダヤ人が『出て来て』と言われているのは、どこからどこへ、なのか。それは「この地上から天国へ」である。この箇所から39:16までの箇所では天国のことが言われている。ゆえに、39:9~16の箇所は、天国という観点から読み解かれねばならない。この天国が再臨およびユダヤ滅亡の時に開始された、ということについては既に語られた通りである。
『武器』が燃やされて焼かれると言われているのは、天国における平和を示している。何故なら、天国とは平和そのものと言える場所であり、そこには144ペーキュスもある『大きな高い城壁』(黙示録21章12節)があるので、そこに住まう人々は武器を持つ必要がないからである。試しに天国にいる人々が武器を何か持っていたと考えてみよう。その場合、そこは天国とは言えない。何故なら武器を持つ必要のある場所は、天国と呼ぶに相応しくないからである。ここで『武器』として挙げられている6つのものは、説明する必要がない。というのも、武器の種類について色々と論じても、ここでは何の意味もないからである。
『7年間』とは永遠の時間を意味する。何故なら、天国において平和はいつまでも続くからである。この言葉を文字通りに捉えるのは愚かである。そのように捉える人は、霊的な秘儀を解くソロモンの鍵をその手に持っていない。
【39:10】
『彼らは野から木を取り、森からたきぎを集める必要はない。彼らは武器で火を燃やすからだ。』
ここでも天国における平和の祝福が示されている。武器を捨てるという行為により効率化の恵みが与えられる。これは正に祝福以外の何物でもない。確かに天国には平和と効率化の幸いがある。それはイザヤ65:22~23の箇所でも教えられている通りである。このことから言えるのは、平和には往々にして繁栄と効率化の益が伴うということである。平和のうちに歩めるからこそ、経済的な益がもたらされる。戦後の日本が経済大国になれたのは、軍事にそれほど意識を費やさずに済んだので経済活動に専念できたというのが、一つの要因であることは間違いない。アメリカが軍事にお金を費やしていなければ今よりも遥かに繁栄していただろうし、韓国にも徴兵制がなければより経済的に富んでいたはずである。個人においても、もし警備会社などと契約を結ばなくて済んだのであれば、それだけお金が浮くので(※)、重要な営利事業にますます資金を投入できるようにもなるのだ。
(※)
例えば日本の警備会社であるセコムを使うと、年額8万1600円(税別)の費用がかかってしまう。これは決して少ない額ではない。
[本文に戻る]
『彼らは略奪された物を略奪し返し、かすめ奪われた物をかすめ奪う。―神である主の御告げ。―』
これは一体どのような意味であるか。これは、つまりこういうことを言っている。すなわち、聖徒たちが地上において損失させられた所有物は、神により必ず補填されると。ただし、それは当然のことながら、敬虔を理由として損失を被った場合に限られる。言うまでもなく、聖徒たちの罪や過失により生じた損失には、補填がなされることはない。神は、御自身の聖徒たちにその奪われた所有物を返し、元通りにして下さる。神が、その損失を見過ごしにされたままでおられることは有り得ない。何故なら、神は真実で正しい御方だからである。キリストも、次に示すように、聖徒たちが神のために失った所有物を何倍にも増し加えて補填して下さると言われた。『また、わたしの名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべて、その幾倍もを受け、また永遠のいのちを受け継ぎます。』(マタイ19章29節)これは王が国のために戦って障害者となった兵士に対し、多額の慰安金と生涯年金を与えるのと似ている。この世の王でさえ自分のために苦しんだ者にこうするとすれば、尚のこと、神は御自身を理由として損失を被った者にはそうして下さる。このこと、すなわち神が聖徒たちから奪われた物を取り返して下さるというのは、出エジプトの際に起きた出来事が素晴らしい例としてある。この時、それまで苦しめられてきたユダヤ人たちは、自分たちを苦しめたエジプト人たちから大量の財物を剥ぎ取ったのである(出エジプト11:2~3、12:35~36)。これは400年もの間搾取され続けてきたユダヤ人が今までに略奪されてきた価値総量に値する物を取り返したのであって、神からの慰安であった。
この箇所では、同じ内容のことが2度言われている。すなわち、『略奪された物を略奪し返し』が1度目であり、『かすめ奪われた物をかすめ奪う』が2度目である。これは強調であって、神が聖徒たちに必ず報いて下さるということを大いに示している。
聖徒である者たちは、神のゆえに奪われた財物を、必ず自分の手元に取り返す。それは、この地上でそのようになるかもしれないし、天国に行ってからそのようになるかもしれない。人によって、この地上で取り返すか、天国で取り返すか、それぞれ異なっている。神は正義そのものであられ、それゆえ全ての事柄において正しい。だから、そのような御方であられる神が、聖徒たちに対してなされた略奪をそのままにしておかれるはずは絶対にない。人間の親が苦しんだ子どもに対して慰めを与えずにはいないのと同じで、神も略奪された聖徒たちに報いをもって慰めを与えずにはおかれないのである。
【39:11】
『その日、わたしは、イスラエルのうちに、ゴグのために墓場を設ける。それは海の東の旅人の谷である。そこは人が通れなくなる。そこにゴグと、そのすべての群衆が埋められ、そこはハモン・ゴグの谷と呼ばれる。』
ここから39:16までの箇所は、異常なほどに難しい。その難しさは絶望させられるほどである。これは嘘ではない。もしそうでなければ、私はこのように言っていなかったであろう。だが、私は神の恵みにより、この箇所を正しく捉えることができた。それゆえ、私は堂々とこの箇所について註解したい。正しく捉えているからこそ、自信をもって語れるのである。もし神の恵みにより悟っておらず、それゆえ自分の理解が足りなかったり怪しげだったりすれば、堂々と註解することはできなかったはずである。
これから見ていく39:11~16の箇所では、再臨されたキリストと聖徒たちがローマ兵たちに天からの裁きを下すことについて言われている。聖徒たちはよく弁えよ。この箇所は、黙示録20:1~6の箇所と対応している。この2つの箇所を見比べてみると、どうか。黙示録のほうでは、キリストの再臨について語られてから(19:11~21)、キリストと聖徒たちによる無敵の働きかけについて語られている(20:1~6)。エゼキエル書のほうでも、まず再臨の時にローマ軍たちが断罪されることについて語られてから(39:1~10)、黙示録20:1~6の箇所に対応している出来事が語られている(39:11~16)。どちらも話の順序が一緒である。我々は、この共通性によく注意すべきである。このように考えないと、この39:11~16の箇所を正しく解することはできない。聖徒たちはよく弁えねばならない。
『その日』とは、再臨されたキリストの勢力がローマに裁きを下す期間を言っている。これは『その日』と言われているが、ある特定の1日を意味しているのではない。何故なら、これは黙示録20:1~6における支配の期間についてのことだからである。『日』と言って、ある一定の期間を示すのは、聖書において珍しいことではない。例えば、聖書ではユダヤが終わる頃の時期を全体的に指して『終わりの日』と言われている。
『わたしは、イスラエルのうちに、ゴグのために墓場を設ける。』とは、エルサレムにおいてローマ兵たちが霊的に裁かれ死ぬことになるという意味である。『イスラエル』とはエルサレムを、『ゴグ』とはローマ軍とその兵士たちを指している。『墓場を設ける。』とは、裁きによりローマ兵たちが霊的な死体と化すことである。これは霊的な意味であって、実際のことを言っているのではない。何故なら、ユダヤ戦争の時、エルサレムに実際にローマ軍の墓場が設けられることはなかったからである。要するに、『墓場』とは霊的に殺されることの暗示である。霊的に死体とされるのは、悪霊どもの餌食とされることに他ならない。何故なら、霊的な死体となれば、霊的な死肉を好む悪霊どもがやってきて食事をするからである。悪霊どもが食事をするとは、食い尽くされるということであり、それは乗っ取られることを意味している。これについては、黙示録19:17~21の箇所を読んでも分かる。確かなところ、悪霊どもに憑りつかれて知らず知らずのうちに操縦されるというのは、神から霊的に殺されることでなくて何であろうか。というのも、悪霊どもに憑依されて生きたり何かをしたりするというのは、霊的な死のうちに歩むことに他ならないのだから。だからこそ、再臨のキリストとその聖徒たちにより裁かれて悪霊漬けにされたローマ兵たちは、神の都であるエルサレムを破壊し尽くすという凶行に走ったわけである。既に述べた通り、神の都を滅亡させるというのは、悪霊どもに突き動かされない限りは決して出来ないことであった。そういうわけだから、この部分を、地獄の創出のこととして捉えるのは誤っている。すなわち、この部分を次のように考えるのは誤っている。「『わたしは、イスラエルのうちに、ゴグのために墓場を設ける。』とは、地獄の創出のことを言っている。何故なら、ユダヤ戦争の時期に、地獄が創り出され開始されたからである。それは、悪者たちが生身の身体において永遠に苦しみを受ける裁きの場所である。この場所はゲヘナと呼ばれる場所であり、魂だけしか苦しみが与えられないハデスとは異なる。ユダヤ戦争の時期になるまで、このような場所はまだ存在していなかった。それまでは、まだハデスしか悪者が苦しむ場所は存在していなかったからである。だが、悪者たちの永遠の墓場であるゲヘナの創出と共にハデスはもうその役目を終えて、そこで苦しむ者は誰もいなくなったのである。」この誤った見解の中で言われているゲヘナの創出は、ローマ兵たちに対する裁きが終わってから、すなわちユダヤ戦争が終結してからの話である。
『海の東の旅人の谷』とは何か。これはエルサレムを指している。まず『海』とは、地中海である。これはエーゲ海、死海、またそれ以外の海のことではない。また、これは文字通りの意味における『海』である。すなわち、これは単に何かを象徴させているに過ぎない言葉ではない。その海の『東』とは、エルサレムのことである。何故なら、エルサレムは地中海の東にあったから。『旅人』とはローマ軍とその兵士である。何故なら、ローマ兵たちは、ローマから戦いのためにユダヤへ旅してきたからである。確かに彼らは『旅人』であった。それは「ユダヤ制圧のために戦いにやってきた旅人」という意味の旅人である。『谷』というのも、やはりエルサレムである。エルサレムは山々に囲まれた谷であったから。当時の世界のどこかに『海の東の旅人の谷』と実際に呼ばれていた場所があったと考えるのは間違っている。というのも、これはエルサレムのことを言っているからである。また、この谷がゲヘナを意味していると捉えて、次のように言うとすれば、それは誤りである。私は以前、そのように捉えていたのであった。「このゲヘナの墓場は、ここで『海の東の旅人の谷』と言われている。恐らく、ユダヤかユダヤ周辺の場所に、このように呼ばれている谷があったのだと思われる。『海の東』だから、その場所は地中海か死海の東側だったのかもしれない。またはエーゲ海の東側だったという可能性もある。その場所は、死体を投棄するのに調度良かったのではないかと推測される。それは、その谷が非常に深かったからである。それゆえ、戦争などで大量の死体が出た際には、その谷に死体が捨てられたと。ゲヘナが、ここではこの谷に例えられている。実際、ゲヘナとはそのような場所である。ゲヘナがどれだけ深い底を持っているかは分からないが、そこに大量の死者が投げ捨てられることは確かである。」―今読み返してみると、この理解はあまりにも玄妙過ぎて、どこかシックリとしないと感じられる。正しい理解をしていないと、このようにどこかスッキリしない文章となるのだ。―
『そこは人が通れなくなる。』とは、エルサレムにいたローマ兵たちが大量に死体と化す、という意味である。つまり、そこにローマ兵たちの死体が積み重ねられるので、『そこは人が通れなくなる。』と言いたいわけである。ただし、これはあくまでも霊的な話である。この部分を実際的に捉えることはできない。何故なら、実際にエルサレムの地に大量のローマ兵たちが葬られることはなかったからである。しかし、霊的な意味においては確かにローマ兵たちが死体としてエルサレムの場所に葬られた。では、このローマ兵たちは霊的な意味において実際にどれぐらい殺され死体となったのか。正確な数は分からないが、だいたい5万~20万ぐらいのローマ兵たちがエルサレムにおいて霊的な死体となった。なるほど、この数であれば、確かにエルサレムの地が通れなくなるぐらいに死体で満ちたと示されているのには納得できる。何故なら、実際にこのぐらいの数のローマ兵たちが葬られたならば、本当に通れなくなるだろうから。それだから、ここではゲヘナのことについて言われていると理解し、その理解に基づいて次のように言うのは間違っている。「『そこは人が通れなくなる。』とは、こういうことである。ゲヘナに死者が大量に積み重ねられるのは、あたかも『海の東の旅人の谷』に死体が積まれ過ぎて通れなくなったかのようである、と。かつて『海の東の旅人の谷』で、そのようなことは起こらなかった。だが地獄ではそういう状態が見られる、とこの箇所では言いたいのであろう。そのように言って、ここではゲヘナの恐ろしさを悟らせようとしているのである。」―確かにゲヘナの場所にも生きた死体が大量に投げ捨てられるのだから、人が通れなくなると言えるような場所ではあるが、この箇所ではゲヘナのことが言われているのではない。―
ローマ兵たちが裁きにより霊的な死体とさせられたエルサレムの場所は、新しく『ハモン・ゴグの谷』という名で呼ばれることになると神は言われる。これはヘブル語であって、ゴグとゴグにつく悪者たち(=ローマ兵たち)の死体がそこに大量に放置されることになるからこそ、こう呼ばれるのである。
【39:12】
『イスラエルの家は、その国をきよめるために、7か月かかって彼らを埋める。』
『イスラエルの家』とは聖徒たちの群れを言っている。『その国』とはユダヤの国を指す。これはユダヤ以外の国のことではない。何故なら、エゼキエル38章・39章の箇所では、ユダヤの国が攻撃されることについて預言しているからである。また、これは神の国のことでもない。何故なら、この38章・39章では実際の国家のことが言われているのだから。『埋める』とは、霊的な裁きの暗喩である。何故なら、聖徒たちが霊的な裁きを下すと、その裁きを下されたローマ兵たちは霊的な死体になるが、死体とは埋められるべき腐敗物だからである。
要するにこの箇所では、こういうことが言われている。すなわち、聖徒たちはローマ兵たちを裁き殺すことでユダヤの地を清らかな状態にさせる、と。キリストがエルサレムの上空に再臨されたのだ。だから、その直下にあるユダヤの地からは、ローマ兵たちという汚れた異物が霊的な意味において取り除かれねばならなかったのである。ここでは地上における霊的な裁きについて言っているのだから、地獄の中に埋められることについて言われているなどと考えてはならない。すなわち、この箇所について次のように言うのは間違っている。「地獄へと悪者が埋められるのは、すなわち天国が清められることに他ならない。何故なら、汚らわしい毒物が、天国へと入って来ないのだから。もし毒が天国に入ってくれば、天国が清い状態を保てなくなってしまう。子どもでも分かる通り、天国とは徹頭徹尾清い状態でなければいけない。それゆえ、天国には、そこを汚す悪者たちが入れないのである。彼らは、天国が清く保たれるために、地獄へ埋められるのだ。ちょうど我々がどこかの場所を清潔に保とうとして、腐敗物をゴミ捨て場に捨てるように。」
『7か月』とは、黙示録20:1~6の箇所に書かれている『千年』のことである。黙示録20章の『千年』が時間を表示させる言葉ではなかったように、我々が今見ている箇所で言われている『7か月』も時間を表示させる言葉ではない。これは『<7>か月』である。つまり、これはその期間において行なわれる事柄の完全性また神聖性を示している。黙示録に書かれていた『千年』を時間を表示させる言葉として捉える者たちは、研究不足かつ無知であって、まったく誤っている。それと同様に、この『7か月』という言葉を時間を表示させる言葉として捉えるならば、その人は自分の研究不足と無知を曝け出すことになる。それだから、この期間を文字通りに解釈してはならない。何故なら、裁きの期間は7か月ではなく、紀元68年6月9日~70年9月までの期間だったのだから。また、ここで地獄のことが言われていると捉えるならば、次のように考えることになる。「ここでは『7』か月と言われているから、つまり永遠に悪者どもは地獄に投げ捨てられることになると教えられている。しかり。確かに悪者どもは、いつの時代でも常に死んだ後で地獄に投げ捨てられることになる。これから2000年が経っても、2000万年が経っても、2000憶年が経っても、である。悪者たちは、永遠に地獄に投げ捨てられる運命を持っている。それは彼らが神の子イエス・キリストを信じないからである。」ここでいつの時代にも悪者は地獄に投棄されると理解されているのは正しいが、我々が今見ている箇所では地獄を対象として何かが語られているのではない。
【39:13】
『その国のすべての民が埋め、わたしの栄光が現わされるとき、彼らは有名になる。―神である主の御告げ。―』
聖徒たちによりローマ兵たちが全て『埋め』られてしまうと、すなわちローマ兵たちが全て裁かれてしまうと、神の『栄光が現わされる』ことになった。これは、神の義なる裁きが聖徒たちを通してローマ兵たちに下されたからである。つまり、この栄光とは「神の義なる審判者としての栄光」という意味である。
そのようになると、聖徒たちは『有名にな』った。これは、聖徒たちが天国に行って誉れを受けるという意味である。何故なら、ローマ兵たちに対する裁きが終わると、天国が始まり、そこに聖徒たちが入れられるようになったからである。
この『有名になる』という言葉は、実際的な意味として解されるべきではない。つまり、この言葉は、この時に聖徒たちが地上にいる人々からよく知られるようになった、という意味において解されるべきではない。そうではなく、これは天国に行った聖徒たちが、あたかも有名な人でもあるかのような誉れを受けるようになった、ということを教えている。天国に行った聖徒たちが有名人のような誉れを受けるようになるということを疑う人は、聖徒たちの中に誰もいないはずである。
【39:14】
『彼らは、常時、国を巡り歩く者たちを選び出す。』
再臨の際に携挙が起こると、その時に地上にいた聖徒たちは全て携挙された。その時には、キリストが言われたように『ひとりは取られ、ひとりは残され』(マタイ24章40~41節)た。だから、携挙が起きた際には、地上の教会に正しい聖徒たちが一人もいなくなってしまった。そこに残されたのは毒麦のクリスチャンだけであった。だが、携挙が起きてから始まった支配の期間、すなわち黙示録20:1~6の期間には、地上で救われることになった聖徒が現われた。その聖徒たちは、携挙により毒麦しかいなくなった教会に加えられた。これは既に本書の中で語られたことである。ここで『国を巡り歩く者たち』と言われているのは、この地上で救われた聖徒たちである。彼らは、救われたが携挙されず、そのまま地上に居続けたのでこう呼ばれている。『巡り歩く』とは、その聖徒たちが生きており、動いており、何かの活動をしていることを示している。
黙示録20:1~6の期間に救われたこの地上の聖徒たちは、携挙されて上に座している聖徒たちから『選び出』された。これは認識的に『選び出す』という意味である。つまり、地上の聖徒たちをローマ兵たちから区別して認識するということである。何故なら、地上の聖徒たちがローマ兵たちと一緒に認識され、彼らと共に霊的に断罪されるようなことがあってはいけないからである。神の聖なる聖徒たちが、裁かれるべき者たちと一緒にされていいはずが、どうしてあるであろうか。だから、この『選び出す』という言葉は、何か実際的な行為としての選びとして理解すべきではない。すなわち、言わば授賞式で選ばれるかのような選びとして理解すべきではない。これは単に認識における区別のことを言っているに過ぎない。
『常時』とは、「その期間中ずっと」という意味である。つまり、支配の期間中、上にいる聖徒たちはいつでも地上にいる聖徒たちを悪者たちから区別して認識していた。何故なら、そのようにしないと、ローマ兵たちと一緒に聖徒たちを裁くことになりかねないからである。この『常時』という言葉は、上にいる聖徒たちの識別における完全性を示している。その聖徒たちが怠惰になったり見過ごしたりして、下にいた聖徒たちを誤ってローマ兵たちと一緒に断罪してしまったなどということは起こらなかったのである。
『彼らは地の面に取り残されているもの、旅人たちを埋めて国をきよめる。』
上の場所で座に着いて裁いていた聖徒たちは、戦いの『旅人』としてローマからやって来た兵士たちを裁いてユダヤの地を清めた。『地の面に取り残されているもの』とは、『旅人』という言葉と同様にローマ兵を言っている。何故なら、彼らは再臨が起きた際に携挙されず、『地の面に取り残され』ていたからである。注意せねばならないが、これは支配の期間中に新しく信仰者になった地上の聖徒たちを言っているのではない。というのも、この『地の面に取り残されているもの』たちは、この箇所で埋められる、すなわち裁かれると言われているのだから。ローマ兵たちは埋められたが、聖徒たちが埋められることはなかったのである。
繰り返して言うが、この『埋めて』というのは実際的な意味として解釈されるべきではない。これは霊的に裁かれることの暗示だからである。
『彼らは7か月の終わりまで捜す。』
『7か月』である黙示録20:1~6の期間が終わるまで、上にいた聖徒たちは、地上にいた救われた聖徒たちを識別し続けた。この識別が、ここでは『捜す』と言われている。何故ならば、区別して認識するというのは、認識的に捜す過程を伴っているからである。それだから、この『捜す』という言葉を、何か実際的な行為がなされるかのような意味で捉えるべきではない。なお、この『捜す』という言葉が、先に見た『選び出す』という言葉と同義語であるのは言うまでもない。
我々は、この捜された地上の聖徒たちが、地上に居続けたということを忘れてはならない。つまり、彼らは地上で救われてから即座に携挙されるということはなかった。何故なら、彼らは『国を巡り歩く』と言われているからだ。もし携挙されて地上にいなくなったとすれば、どうして『国を巡り歩く』ことができようか。それゆえ、支配の期間に救われた地上の聖徒たちが即座に携挙されるなどと考えるのは誤っているとせねばならない。
【39:15】
『巡り歩く者たちは国中を巡り歩き、人間の骨を見ると、そのそばに標識を立て、埋める者たちがそれをハモン・ゴグの谷に埋めるようにする。』
『巡り歩く者たちは国中を巡り歩き』と言われているのは、地上にいる聖徒たちが地上に居続けたことを示している。彼らは携挙されてはいなかった。だから、このように言われているのである。
『人間の骨』とはローマ兵たちの暗喩である。この言葉は、生きているローマ兵たちが霊的に裁かれて死体の骨とされるべきだということである。何故なら、骨とは死体のことでなくて何であろうか。
この時期に地上にいた聖徒たちは、ローマ兵たちを見つけると『そのそばに標識を立て』、上にいる聖徒たちがそのローマ兵たちを裁いて死体にするようにさせた。この『標識』とは祈りのことだと思われる。つまり、こういうことである。まず地上の聖徒たちがエルサレムを今にも攻めようとしているローマ兵たちについて神に祈る。すると、祈りを聞かれた神が、上にいる聖徒たちを通してローマ兵たちを裁かれる。この霊的なやり取りが、ここでは『標識』と言われているのであろう。この『標識』という言葉を、文字通りの意味で捉えるのは愚かである。これは明らかに象徴として言われているからである。
もう一度繰り返すが、ここで『埋める』と言われているのは実際のことではない。もしこれが実際のことだと言うのであれば、ローマ兵たちがエルサレムに葬られたという証拠を出さねばならない。だが、そのような証拠を出すことは出来ないであろう。ローマ兵たちはエルサレムでほとんど死者とはならなかったのだから。
【39:16】
『そこの町の名はハモナとも言われる。』
エルサレムの場所は、その時以降『ハモナ』と呼ばれるようになった。ただし、これは、あくまでも霊の世界においての話である。すなわち、神と御使いと天上の聖徒たちから、エルサレムの場所が『ハモナ』と呼ばれることになった、ということである。だから、これは地上のこととして捉えるべきではない。実際、この地上においてエルサレムは『ハモナ』などと呼ばれるようにはなっていない。エルサレムの場所は、この地上において『ハモナ』ではなく「パレスチナ」と呼ばれることになったのである。
『彼らは国をきよめる。』
この部分は既に語られたことの繰り返しであって、再び説明する必要性も感じないので、再び説明することはしない。
【39:17】
『神である主はこう仰せられる。人の子よ。あらゆる種類の鳥と、あらゆる野の獣に言え。集まって来い。わたしがおまえたちのために切り殺した者、イスラエルの山々の上にある多くの切り殺された者に、四方から集まって来い。おまえたちはその肉を食べ、その血を飲め。』
ここから39:20までの箇所は、間違いなく黙示録19:17~21の箇所と対応している。これは確かなことである。ヨハネが黙示録の箇所を書いていた時、このエゼキエル書の箇所が頭の中にあったことは間違いない。神は、エゼキエル書に書かれているのと同じ内容の幻を、ヨハネに預言として示されたのである。
『あらゆる種類の鳥と、あらゆる野の獣』とは悪霊のことである。黙示録のほうでは鳥しか書かれていないが、単に獣については省かれているだけに過ぎない。この鳥と獣を文字通りの生き物として解するのは間違っている。これは明らかに比喩だからである。
この箇所では、霊的に裁かれたローマ兵たち―『多くの切り殺された者』―が、エルサレムの場所―『イスラエルの山々』―で無数の悪霊どもに憑依されるようになる、ということが預言されている。霊的に裁かれるとは、霊的に死体とさせられることである。霊的に死体とさせられることは、霊的な鳥・獣である悪霊どもに食われることである(悪霊どもは死肉が大の好物であるから)。悪霊どもに食われることは、悪霊どもに憑りつかれて操作されるということである。それゆえ、我々はここで言われている悪霊どもの食事を、「憑依」として捉えなければならない。
実に、この憑依こそ、ローマ兵たちがユダヤを壊滅させた根本的な理由であった。何故なら、『愛された都』であるエルサレムを滅茶滅茶に破壊するというのは、悪霊に突き動かされない限りは決して出来ないからである。実際、悪霊に憑りつかれていなかった聖徒たちは、都を破壊しようなどとは少したりとも思わなかったはずである。だからユダヤ陥落の真相はこうだったことになる。すなわち、ユダヤが滅びたのは神がローマ兵たちを悪霊どもに委ねたからだった、と。
では、悪霊どもにローマ兵たちを委ね、そしてユダヤを破壊するように仕向けられた神は、悪の創出者と言えることにならないであろうか。否。そのように言うことは決してできない。確かに、ローマ兵たちが悪霊に憑りつかれ、そうしてユダヤを攻撃するようにしたのは、神の御心であった。だが、だからといって神が悪の発出元だったということにはならない。事柄をよく考えてみよ。神は、単にユダヤの悪を裁かれるため、ローマ兵たちと悪霊どもの暴虐を用いられたに過ぎなかった。これは王が反乱分子を鎮圧するために軍隊を動員させるのと何ら変わらない。王がそのようにするのは悪でなく、むしろ正しいことである。だから、神という王がローマ軍を悪霊において動員させユダヤという反乱分子を罰されたからといって、神が悪の創出者だということにはならない。聖徒たちは、神が悪がそこから出てくる泉のような存在だと考えてはならない。今まで教会は、このような考えを徹底的に非難してきた。悪は、悪魔と人間から出てくる。それゆえ、神を悪の発生源だとして責める者は、その冒瀆のゆえに必ず神から断罪されるであろう。聖徒たちは間違えないように注意せねばらならない。
【39:18】
『勇士たちの肉を食べ、国の君主たちの血を飲め。雄羊、子羊、雄やぎ、雄牛、すべてバシャンの肥えたものをそうせよ。』
『勇士たち』とは、ローマ兵における強者である。『国の君主たち』とは、ローマ軍の中にいた将来のローマ皇帝である。これは既に第3部で説明されたことであり、黙示録17:12の箇所でも教えられている。聖書では、再臨の時期にローマ軍にいた将来の皇帝たちが、あたかもその時から既に皇帝であるかのように取り扱われている、ということを聖徒たちは良く理解すべきである。それだから、この『国の君主たち』という言葉を文字通りに解釈すべきではない。これは「将来国の君主になるべく定められている者たち」という意味である。
この箇所では、悪霊に食われるローマ兵たちが獣として取り扱われている。これは、悪霊どもが食事をするということを我々人間によく分からせるためである。というのも、悪霊どもが人間を食べると聞くと、一体どういうことなのかと思ってしまう人もいるだろうからである。つまり、これはこういうことを言っている。すなわち、「悪霊どもが人間に憑依するという食事をするのは、あなたがた人間が獣の肉を食べるのとまったく同じことである。」と。
【39:19】
『わたしがおまえたちのために切り殺したものの脂肪を飽きるほど食べ、その血を酔うほど飲むがよい。』
ここでは、悪霊どもがローマ兵たちに大いに憑りつくようにと命じられている。腹をすかせた人が肉をガツガツと食べ、酒飲みたちが酔い潰れるまで酒をガブガブと飲んでいるのを見たことがある人は少なくないはずである。悪霊どもがローマ兵たちを食べ、その血を飲むという憑依をしたのは、正にこのような人たちのようであったとここでは示されている。
【39:20】
『おまえたちはわたしの食卓で、馬や、騎手や、勇士や、すべての戦士に食べ飽きる。―神である主の御告げ。―』
『わたしの食卓』と言われているのは、神がローマ兵たちを悪霊どもにご馳走させて下さるからである。神はこう言われるのだ。「さあ、悪霊どもよ。私が用意してやったローマ兵たちの死肉を大いに食するがよい。」すると悪霊どもはこう応じる。「さあ、今、目の前にローマ兵たちが置かれた。これは是非とも大いに食さねばならない。」このことから、ローマ兵たちが悪霊どもに食われたのは、神から発したということが分かる。神が御自身の食卓にローマ兵たちを置かれなければ、どうして悪霊どもはローマ兵たちを食べることが出来たであろうか。
『食べ飽きる』とは、悪霊どもに憑りつかれたローマ兵たちが多かったことを示す。実際、エルサレムの場所にいたローマ兵たちは多かった。もし憑りつくべきローマ兵たちが少なければ、ここでは『食べたりない』などと言われていたはずである。
この箇所では『馬』にまで悪霊が憑依したと示されている。だからこそ、『馬』もローマ兵たちと一緒になってユダヤを攻撃しに行ったわけである。もし馬には悪霊が憑りつかなったとすれば、馬たちはローマ兵たちとは違って、ユダヤに攻め向かうことを拒絶していたかもしれない。ちょうど気違いのバラムが行こうとしていた方向に行くのを拒絶したあのロバのように(民数記22:21~35)。動物にも悪霊が入るというのは、聖書の他の箇所からも分かる。例えば、創世記には蛇にサタンが入ったことについて書かれている。福音書でも、キリストが『レギオン』という名の悪霊どもを豚の中に入ることを御許しになられたことが書かれている(マルコ5章)。悪霊どもは、ただ人間にだけ入るというわけではないのだ。『騎手』とは、ローマ兵における騎兵である。『勇士』とはローマ兵における強者である。『すべての戦士』とはローマ兵の全てを言っている。
【39:21】
『わたしが諸国の民の間にわたしの栄光を現わすとき、諸国の民はみな、わたしが行なうわたしのさばきと、わたしが彼らに置くわたしの手とを見る。』
これは一体いつのことを言っているのか。捕囚から解放された後のことか、それとも紀元1世紀にユダヤが陥落した後のことか。これは捕囚から解放された後のことであろう。何故なら、文脈を考えれば、そう解するしかないからである。後に続く箇所を考慮すれば、これは紀元前6世紀の時のことについて言われていると解するのが自然である。
『わたしが行なうわたしのさばき』とは、ネブカデレザルを通して下されたユダヤに対する神の裁きである。これは正に裁き以外の何物でもなかった。それは、間違いなく神の裁きの代表的な裁きとして挙げられるべき裁きであった。『わたしが彼らに置くわたしの手』とは、ユダヤに対して与えられる神の慈しみである。つまり、ここで言われている『手』とは、神が慈しみを与えるために差し伸ばされる恵みの手のことである。それは、もちろん捕囚からの回復のことである。ユダヤが捕囚から帰還すると、諸国の民は、神の裁きと手について感知するようになった。ここにおいて神の栄光が諸民族に対して現わされた。何故なら、その時、周りの国の人々は、神が至高の審判者としてユダヤ人を虐殺に委ねられたことを、また恵み深い神として散らされていたユダヤ人を故郷に帰らせて下さったことを、知るようになるからである。
【39:22】
『その日の後、イスラエルの家は、わたしが彼らの神、主であることを知ろう。』
『その日の後』とは、いつか。これは前の節で言われていた『わたしが諸国の民の間にわたしの栄光を現わすとき』の後、すなわち捕囚からの解放が実現された後である。つまり、これは紀元前6世紀のことを言っている。これを紀元前6世紀のことだと捉えないと、捕囚について言われている次の節が上手に理解できなくなってしまう。
捕囚からの解放が起きた後、ユダヤ人たちは、自分たちの神について知るに至った。何故なら、神が自分たちを捕囚から帰還させて下さったので、その取り計らいを通して神を感知したからである。もちろん、彼らが神を知るというのは、それまでよりも更に良く神を知るようになった、という意味である。すなわち、その時になって初めて彼らが神を知るに至ったということではない。捕囚からの解放よりも前に、ユダヤ人たちは神について知らないわけではなかった。これは捕囚以前のユダヤの歴史を考えれば誰でも分かることである。神は、アブラハムの時からユダヤに御自身を啓示しておられたのだから。
【39:23】
『諸国の民は、イスラエルの家が、わたしに不信の罪を犯したために咎を得て捕え移されたこと、それから、わたしが彼らにわたしの顔を隠し、彼らを敵の手に渡したので、彼らがみな剣に倒れたことを知ろう。』
『捕え移されたこと』とは、もちろんバビロン捕囚のことである。『みな剣に倒れたこと』とは、バビロン軍によるユダヤ人の大量虐殺である。つまり、この2つはどちらも紀元前585年のことを言っている。
ユダヤがこのような苦難を受けたのは、『イスラエルの家が、わたしに不信の罪を犯したため』に起きた。ユダヤは神の前に咎を得た。だからこそ、神はユダヤをこのような苦しみに引き渡されたのである。これは当然のことであり、ユダヤは文句を言うことができなかった。それは国が重犯罪を犯した反逆者を法により容赦なく罰したとしても、その反逆者が文句を言えないのと同じである。
ここで『顔』と言われているのは、神の恵みを意味する。我々人間は、自分が良くしてやりたいと思う人に、顔を向けるものである。神の場合も、それと同じである。もちろん神は物資存在ではないから、ここで神に顔があるかのように言われているのは比喩表現に過ぎないことを弁えるべきである。この箇所では『彼らにわたしの顔を隠し』と言われている。これは、つまり神がユダヤから御自身の恵みを取り上げた、という意味である。
もしユダヤが罪を犯さなければ、虐殺されることも散らされることも起きなかったであろう。罪を犯していないのに、どうしてそのような恐るべき刑罰を受けねばならないのか。ソロモンが『命令を守る者はわざわいを知らない。』(伝道者の書8章5節)また『正しい者は何の災害にも会わない。』(箴言12章21節)と言っている通りである。だがユダヤは邪悪な不信の罪を犯してしまった。それゆえ、当然のこととして裁かれ、あのような苦難を受けることになったわけである。
【39:24】
『わたしは、彼らの汚れとそむきの罪に応じて彼らを罰し、わたしの顔を彼らに隠した。』
ユダヤがあのような苦難を受けたのは、彼らの犯した罪悪がその原因であった。あの時に起きた捕囚と虐殺の裁きは、ユダヤの犯した罪がどれだけ大きかったかということを物語っている。我々は、誰かが死刑になったことを聞くと、その人がとてつもない重犯罪を犯したのだろうと感じる。それと同じで、ユダヤの苦難を見るならば、我々はユダヤがとてつもない不敬虔な歩みをしていたのだということを知れる。もしユダヤがほとんど罪を犯していなければ、あのような刑罰を受けはしなかったであろう。しかし、中には神がユダヤに受けさせた刑罰はあまりにも行き過ぎだったのではないかと思われる読者もいるかもしれない。だが私はこう言おう。あの刑罰に過不足はまったくなかったと。何故なら、神はあらゆる事柄を正しくなされるからである。それゆえ聖徒たちは、ユダヤが受けたあの刑罰に文句を付けたりしないように注意せねばならない。
神は、悪があれば、その悪に相応しい報いをなさる御方である。これは聖書の全体が教えている。神とは真実で正しい御方である。だから、神はその悪の度合いに応じた報いを与えられるのだ。我々は、この神の裁きを大いに恐れて日々歩むことが望まれる。というのも、もし我々が悪を行なえば、神の裁きが我々に下されることになるからである。
【39:25】
『それゆえ、神である主はこう仰せられる。今わたしはヤコブの捕われ人を帰らせ、イスラエルの全家をあわれむ。』
『ヤコブの捕われ人』とは、捕囚されていたユダヤ人を指している。『ヤコブ』という言葉が「父祖ヤコブに連なるイスラエルの人々」という意味であることは、あらためて詳しく説明する必要もなかろう。『イスラエルの全家』とは、ユダヤ人の全体のことである。
ここでは『ヤコブの捕われ人』と言われているが、やはりエゼキエル38章・39章は、ヤコブが捕われている時期に書かれたとすべきであろう。これは40章目以降の箇所を考えても明らかである。40章目から最後の48章目までは、イスラエルが捕囚となっている時期に書かれた。その直前の箇所が、この38章・39章なのだ。であれば、40章目以降と同様、38章・39章も捕囚の時期に書かれたと考えるのが自然である。もしこの38・39章が捕囚よりも前に書かれたとすれば、どうなるか。そのように捉えると、38章・39章を上手に理解できなくなってしまう。上手に理解できないのは、何かがおかしいということを意味する。それゆえ、もう一度繰り返して言うが、エゼキエル38章・39章は捕囚の時期に書かれたとすべきである。
この箇所では『今』から既に捕囚の解放が実現されると言われている。『今』とは、エゼキエルが預言を受けた『今』、すなわち紀元前6世紀における『今』である。これは、先に見た39:8の箇所と同様、文字通りに解釈すべきではない。これは、つまり「今から既にイスラエルは捕囚から解放されたのも同然である。」という意味である。試しに、この『今』という言葉を文字通りに解釈するとしてみようか。その場合、エゼキエルにこの言葉が語られてからすぐにもイスラエルは捕囚から帰還したことになる。しかし、それは実際の歴史に合致していない。捕囚からの帰還が起きたのは、もっと後の話である。つまり、この『今』を文字通りに捉えると、この箇所で何が言われているのか分からなくなる。だから、この『今』という言葉を文字通りに捉えるのは誤っているとせねばならない。
この捕囚からの帰還は、既に述べた通り、神がキュロス2世を通して実現して下さった。それは捕囚が起きてから70年後のことであった。それまでユダヤは、神殿も犠牲もない状態で、惨めなまま歩み続けていたのである。
『これは、わたしの聖なる名のための熱心による。』
神がユダヤ人たちを捕囚の地から帰らせて下ったのは、御自身の聖なる御名を重んじておられるからであった。神は、御自身の御名における名誉に熱心であられる。我々人間は自分の名声を大事にするものだが、神は尚のこと、御自身の名声を大事にされる。つまり、こういうことである。神は御自身の聖なる御名が蔑まれないために、ユダヤに回復の恵みを施して下さったのである。もし神がいつまでもユダヤを散らされたままでおられたとすれば、神の御名にとってマイナスになりかねなかった。ユダヤ人においては「神はいつまで私たちを放っておかれるのか…」と言われ、異邦人においては「ユダヤの神は自分の民を放っておかれたままにする残虐な神だ」と言われかねなかった。だが捕囚から回復されたのであれば、神の御名が賛美されるようになる。「ユダヤを故郷の地に帰らせて下さった神はほむべきかな。」と。この箇所で言われているように、神は御自身の御名に大変熱心であられる。だからこそ、神はユダヤの捕囚帰還を70年で終わらせられたのである。我々も、神がユダヤを捕囚から帰らせて下さったことのゆえに、神の御名を崇めねばならない。何故なら、神は御自身の御名のためにユダヤを元の場所に帰らせて下さったからである。
神は、御自身の御名の栄誉を何よりも第一に求めておられる。これは大変に重要なことであり、心に留められねばならない。何故なら、もし我々が神の御名を汚すようなことがあれば、一体我々はどうなるか。間違いなく裁きを受けて悲惨に陥らされるであろう。しかし御名を尊べば我々には幸いがある。神が『わたしは、わたしを尊ぶ者を尊ぶ。』(Ⅰサムエル2章30節)と言っておられる通りである。我々の幸せと不幸は、この神の聖なる御名にかかっていると言っても間違いではない。であれば、どうして我々が神の聖なる御名に心を寄せずにいていいということがあるであろうか。
【39:26】
『彼らは、自分たちの地に安心して住み、彼らを脅かす者がいなくなるとき、わたしに逆らった自分たちの恥とすべての不信の罪との責めを負おう。』
『自分たちの地に安心して住み』とは、捕囚から帰ってきたユダヤ人のことである。回復の恵みが注がれてから、ユダヤ人たちには平穏が与えられた。もっとも、もはや預言者たちを通して神が語りかけて下さることは起きなくなってしまったのではあるが。
『彼らを脅かす者がいなくなる』とは、捕囚が終わってから、ユダヤを苦しめる恐るべき者が現われなくなるという意味である。何故なら、ユダヤが回復してから、ユダヤはもうかつてのような偶像崇拝の罪を犯さなくなったからである。つまり、彼らは「良い子」になった。だから、神もユダヤに対し、彼らが太刀打ちできないような恐るべき『脅かす者』を、裁きまた懲らしめとして起こされることをしなかったのである。確かに、大きな邪悪を行なっていなければ、そのような強大な者が現われて脅威となるということは起こらないはずである。
そのようにして平和な状態が訪れると、ユダヤ人たちは『わたしに逆らった自分たちの恥とすべての不信の罪との責めを負』うことになった。これは、彼らが自分たちの罪深さを反省して大いに悲嘆するという意味である。これは実際的なことを言っているのではなく、単に精神的な後悔のことを言っている。つまり、これは神が何か実際的な言葉を天から鳴り響かせてユダヤ人たちを責めたという意味ではない。何故なら、神による実際的な責めは捕囚の時期において全うされたのだから。捕囚の苦しみそのものが神からの責めでなくて何であったろうか。
これらのことから、我々は教訓を得るべきであろう。我々は、将来に悲嘆することになるのが分かっていたとすれば、そもそも最初からそのような悲嘆をもたらす悪事を行なうべきではない。事前に将来の悲嘆を予測して、悪事を抑えるというのが知恵と思慮である。そうすれば、やがて苦しい目に遭うこともなくなるのだ。それを行なえば未来に嘆き悲しむことが分かっているにもかかわらず、何かの悪事に走るというのは、愚かであって無思慮であると言わざるを得ない。ユダヤの場合、偶像崇拝などをしていたらいずれ悲惨が訪れることになるのは、律法の宣言から分かりきっていたことなのだから、そもそも彼らは最初から偶像崇拝などすべきではなかった。
【39:27~28】
『わたしが彼らを国々の民の間から帰らせ、彼らの敵の地から集め、多くの国々が見ている前で、彼らのうちにわたしの聖なることを示すとき、彼らは、わたしが彼らの神、主であることを知ろう。』
ユダヤが捕われの状態から回復すると、ユダヤ人と異邦人たちは、神の存在を感知するようになった。当時の世界をよく考えるがよい。古代は非常に有神論的であった。だから、イスラエルの帰還を見た多くの人々が、その帰還のうちに神とその働きを感じ取ったのは間違いない。我々は、多くの人が心の中で神を殺してしまった近代社会の感覚により、エゼキエルの時代について判定すべきではない。すなわち、「たとえユダヤ人が故郷に帰れたからといって、当時の人々はその出来事のうちに神の存在を感じ取ることが出来たのであろうか。」などと言ってはならない。このように言うのは近代的な感覚に基づいており、当時の世界観をまったく考慮していない。もし有神論的であった当時の世界観をよく知りたいと思うならば、その人はホメロスやプラトンやヘロドトスといった古代人の著作を読むとよい。そうすれば、当時の人々にとって神はまったく当たり前の存在であったことを知れるであろう。
【39:28】
『わたしは彼らを国々に引いて行ったが、また彼らを彼らの地に集め、そこにひとりも残しておかないようにするからだ。』
『わたしは彼らを国々に引いて行ったが』。ユダヤが捕われの状態になったのは、神がそのようにされたからであった。実際的に言えば、ユダヤを捕囚に陥らせたのは、バビロンであったと言うべきかもしれない。だが、バビロンがユダヤを捕われの状態にさせたのは、神がそうなるように欲されたからであった。もし神の御心でなければ、バビロンがユダヤを捕われの身に陥らせることは起きなかった。それゆえ、捕囚の究極的な発出元は神だということになる。それは、パウロが『すべてのことが、神から発し、神によって成り、神に至る』(ローマ11章36節)と言った通りである。
『彼らを彼らの地に集め』。ユダヤ人を捕囚の地から故郷へ連れ戻したのも、やはり神がなされたことであった。実際的に言えば、ユダヤ人を捕われの状態から連れ戻したのは、キュロスだったとすべきかもしれない。だがキュロスがユダヤ人を連れ戻させたのは、神がキュロスにそのようにさせたからに他ならなかった。これについてはイザヤ書で書かれている通りである。だから、もし神の御心でなければ、キュロスがユダヤ人に良くしてやるということも起こらなかったであろう。キュロスが何かをユダヤ人に対して望んでも、神がそれを望まなければ、実現することはなかったのだから。
『そこにひとりも残しておかないようにする』。『そこ』とは、ユダヤ人が捕囚により引かれて行った『国々』を指している。これはユダヤの地ではない。これをユダヤの地だと解すると、この箇所の文意が不明瞭になってしまう。つまり、この箇所では、神がユダヤ人を捕囚の地から完全に故郷へ戻れるようにして下さる、と約束されている。しかし、ここで次のような疑問を持つ方がいるかもしれない。「神がキュロスを通して捕囚からの解放を実現させられた時、多くのユダヤ人たちは故郷に帰れるようになったにもかかわらず、捕囚の地に留まることを望んだのではなかったか?」これは確かにその通りであった。ユダヤ人たちはせっかく帰れるようになったのに、臆病のため故郷に帰ろうとしない者が多かった。だが、ここではユダヤ人が捕囚の地に『ひとりも』残されないようにする、と明白に約束されている。これは一体どういうことか。解決は簡単である。すなわち、神はここで実際的なことを言っておられるのではなく、単に状況の変化について言っておられるのだ。確かに神は、キュロスを通して、ユダヤ人たちの全てが捕囚の地から帰ろうと思えば帰れるようにして下った。ユダヤ人たちの全てが一人も残らずユダヤに帰ることは、もし彼らが望んでいたとすれば100%可能であった。だが彼らの多くは、それを嫌がったのだ。それというのは、故郷と言えども1度も住んだことのない地に移住するというのは気が引けたし(※捕囚からの解放が実現した時、捕囚時に生きていたユダヤ人はその多くが既にこの世からいなくなっていた)、今住んでいる地に住み続けたほうが気分的にも楽だったからである。神御自身としては、確かに『そこにひとりも残しておかないようにする』状況を作り出して下さった。つまり、単にユダヤ人たちがそのような状況の変化に乗らなかっただけなのである。だから、ここで言われていることには何も問題がない。
実に、このような出来事が起きたからこそ、ユダヤ人と異邦人たちは神の存在を強く感知するに至った。何故なら、その出来事において神が豊かに働きかけられたのは明白だからである。もし神がこのような出来事を起こされていなければ、ユダヤも異邦人も、神とその働きかけを豊かに感知していなかったかもしれない。働きかけによる何らかの動きがあるからこそ、人はその対象を認識する。何も働きかけがなければ、ずっと気づかないままである。これは当然のことである。
【39:29】
『わたしは二度とわたしの顔を彼らから隠さず、わたしの霊をイスラエルの家の上に注ぐ。―神である主の御告げ。―」』
ユダヤ人は、捕囚からの帰還が起きてから、神の恵みを失わなくなった。ここで『顔』と言われているのは、先にも述べた通り、神の恵みのことである。つまり、ここで『わたしは二度とわたしの顔を彼らから隠さず』と言われているのは、神がもう2度とユダヤから恵みを取り去らないという意味である。
とはいっても、これはあくまでも紀元70年までの話である。その時、ユダヤは滅ぼされて完全に神の恵みを失うに至ったからである。ここで言われているのは紀元1世紀になるまでに限られている。だから、紀元70年になって神の御顔が永遠にユダヤから隠されることになったとしても、この箇所で出鱈目が言われていることにはならない。これは割礼の命令でも同じである。神は、割礼が永遠に守られるべき命令であると言われた(創世記17章)。だが、割礼を守るべきなのは、あくまでもキリストが地上に来られるまでの話であった。だから新約時代になってから割礼が廃止されたとしても、神は何か出鱈目を言われたことにはならないのだ。
では、アンティオコスとポンペイウスの時に起きた悲惨は、どうなるのか。アンティオコスはユダヤを荒らし回り、ポンペイウスはユダヤを占領した。この2人により引き起こされた出来事は、正に悲劇そのものであった。これは神が御顔をユダヤから隠されたことだと言えないであろうか。確かに、この2人による悲惨は、神が御顔を隠されたから起きた出来事であるように感じられる。何故なら、神の恵みが注がれ続けていたとすれば、どうしてあのような災いが起きたであろうか。だが、この2つの出来事は、神が御顔をユダヤから隠されたことではなかった。もし本当に神が御顔を隠されていたとすれば、バビロン捕囚の時のように70年も散らされるなどという出来事に近似した悲惨が生じていたであろう。しかし、アンティオコスとポンペイウスによる悲惨は、そこまで酷い悲惨とは言えなかった。だから、この2人がユダヤを苦しめたのは、神が御顔を隠されたがゆえに起きた出来事だとは言えない。アンティオコスとポンペイウスの時にも、ユダヤからは神の御顔が隠されていなかった。というのも、この2人による悲惨は、教訓を得させるための単なる懲らしめとして起こされた出来事だったのだから。
捕囚から帰って来たユダヤ人に神の霊が注がれるというのは一体どういう意味なのか。これは、回復後のユダヤには神の霊が豊かに働きかけて下さるので、もはやユダヤはかつてのような偶像崇拝に陥らなくなる、という意味である。実際、捕囚から帰って来た後のユダヤ人たちは、確かにもう偶像崇拝を行なわなくなった。バアルやアシュタロテやアシュラやミルコムなどを崇拝しなくなった。それは、神がその霊によりユダヤに働きかけて下さっておられたからに他ならない。また、これは回復後に初めてユダヤに神の霊が注がれるようになる、という意味ではないことに注意せねばならない。言うまでもなく、それよりも前からユダヤには神の霊が注がれていた。それはダビデが自分から神の霊を取り去らないようにと神に懇願していることからも明らかである(詩篇51:11)。バアルに膝を屈めなかったあの『7千人』(Ⅰ列王記19章18節)も、神の霊を受けていたことは間違いない。もし回復の恵みが与えられるよりも前にはユダヤに神の霊が注がれていなかったとすれば、それまでユダヤは神の契約の民ではなかったことになる。だが、そのように本気で考える者が一体どこにいるであろうか。
【40:1~2】
『私たちが捕囚となって25年目の年の初め、その月の十日、町が占領されてから14年目のちょうどその日、主の御手が私の上にあり、私をそこへ連れて行った。すなわち、神々しい幻のうちに、私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。』
これから見ていくエゼキエル40~48章では、天国が地上のエルサレムにおいて示されている。この箇所で言われているのは、紀元70年に滅ぼされた第二神殿のことではない。何故なら、ここで言われているのが第二神殿だとするのは無理があるからだ。それは、この箇所を読み調べれば分かる(※)。また、ここで言われているのは、ユダヤ教徒やディスペンセーション主義者たちが考える神殿のことでもない。彼らは、これからエルサレムの地に石造りの神殿が再び建てられるなどという勝手な空想をしている。だが、これから石造りの神殿が建てられると考えるのは、聖書の真理に対する冒瀆である。そのような神殿は、これから建設されない。よって、エゼキエル40~48章では、これから作られるであろうと思われている神殿について言われているのではない。
(※)
ここで言われているのが第二神殿ではないということについては、また後ほど説明されることになる。
[本文に戻る]
ここで書かれている幻が示されたのは、『私たちが捕囚となって25年目の年の初め』だから、紀元前560年である。『町が占領されてから14年目のちょうどその日』と書かれているのは、捕囚が起きてから11年目にエルサレム市が占領されたからである。つまり、捕囚が起きた時にはまだエルサレム市は占領されていなかった。
ここではエゼキエルの上に『主の御手』があったと言われている。これは、神がエゼキエルに豊かに働いておられたという意味である。エゼキエルは、ここであたかも「これから主が私に何らかの働きかけをしようとしておられた。」とでも言っているかのようである。
このエゼキエルは、イスラエルの地にある非常に高い山の上に連れて行かれた。これは霊的に理解せねばならない。すなわち、エゼキエルは地上のエルサレムとそこにある山に連れて行かれたというのではなく、天国というエルサレムとそこにある霊の山に連れて行かれたと理解すべきである。
エゼキエルがその天へと連れて行かれたのは『神々しい幻のうちに』であった。これはエゼキエルに幻が示されていたことを示す。つまり、エゼキエルは幻の中でエルサレムへと霊的に連れて行かれたのであった。
ところで読者は、我々が今見ている箇所と黙示録との類似性に気付いているであろうか。霊的に鋭い読者であれば、既に気付いているかもしれない。第3部で見たように、黙示録ではゴグとマゴグがユダヤを包囲する出来事の後で、ヨハネが高い山に連れて行かれ天国について示されたのであった。このエゼキエル書でも、まずゴグとマゴグがユダヤを包囲する出来事について書かれ、その後でエゼキエルが高い山に連れて行かれ天国について示されている。黙示録19~22章とエゼキエル38~48章では、その内容と書かれている順序がまったく一緒である。つまり、これはこういうことである。神は、エゼキエル38~48章で書かれているのと同じ内容と順序を持った預言の幻を、ヨハネに示されたのである。ヨハネがエゼキエル38~48章をベースにして黙示録19~22章を書いたなどとは、考えないようがよい。そうではなく、我々は神がエゼキエル書と同じことを示されたからこそ、ヨハネは黙示録の中でエゼキエル書と同じことを書いたと考えるべきである。そのように考えるほうが、敬虔で信仰深く、正しい。
黙示録を十全に理解するためには、エゼキエル書38~48章と黙示録19~22章を相互比較しつつ調べる必要がある。そうしなければ黙示録を真の意味で知解することは出来ない。幾らかは理解できたとしても、「納得感」が100%に達しない。何故なら、黙示録と対応しているエゼキエル書のほうを理解していないので、解釈における不安が多かれ少なかれ残らざるを得ないからである。すなわち、その人は「もし黙示録と対応しているエゼキエル書のほうを理解したならば、聖書の知識が向上したことにより、黙示録の理解にも変更を強いられるのではないか…」という解釈上の不安から解放されることが出来ない。もしこのような不安を持たない人がいたとすれば、その人は聖書研究に適正があまりないのである。何故なら、その人は自分が今見ている箇所(すなわち黙示録)と対応しているであろう別の箇所(すなわちエゼキエル書)を理解していなくても、あまり気にしていないのだから。本書の読者は、これから書き記される註解を読んで、エゼキエル40~48章をよく学ぶがよかろう。そうすればその40~48章だけでなく、そこと対応している黙示録の箇所をも更に良く理解できるようになるであろう。
【40:2】
『その南のほうに町が建てられているようであった。』
『南』とはエルサレムの場所である。何故なら、エルサレムの場所は、イスラエルの南側に位置していたからだ。エゼキエルにこの幻が示された時には、まだエルサレムは荒れ果てたままの状態であった。しかし、ここではそのエルサレムが再建されていると言われている。これは一体どういうことであるか。事柄は簡単である。つまり、神は再建された地上のエルサレムにおいて天国を表象されたのである。もし荒れ果てたエルサレムの幻であれば、天国を表象させることは出来ない。だから、ここでは地上のエルサレムが再建された状態として示されている。なお、ここではネヘミヤを通してエルサレムが再建されることについて預言しているなどと理解してはならない。何故なら、先にも述べたが、ここでは天国について預言されているからである。
【40:3】
『主が私をそこに連れて行かれると、そこに、ひとりの人がいた。その姿は青銅でできているようであり、その手に麻のひもと測りざおとを持って門のところに立っていた。』
エゼキエルの見た『ひとりの人』とはキリストである。ここでキリストは『青銅』において示されている。ダニエル10:6の箇所でもキリストが青銅において示されている。これはキリストの力強さ・堅固さを象徴している。また、これは聖徒たちが主に信頼できるようになるためでもある。主が青銅であると示されたら、我々は安らかに主に信頼できるであろう。例えば主がコンニャクにおいて示されていたとすれば、聖徒たちは主に信頼しにくくなってしまうことにもなりかねないのだ。
キリストが『その手に麻のひもと測りざおとを持って』おられたのは、天国が表象されている地上のエルサレムを示すためである。計る道具を持っているからこそ、その道具で計ることにより、エルサレムを具体的に示すことが出来るのだ。主は理知ある御方である。
また、キリストが『門のところに立っていた』のは、まず門の場所から示し始められるからである。それゆえ、もし神殿から示し始められることになっていたとすれば、キリストは門ではなく神殿の場所に立っておられたことであろう。
黙示録21章では、キリストではなく御使いがエルサレムを測定している。黙示録では、御使いが話の流れを導くガイド役であった。だから、黙示録のほうでは御使いがエルサレムを計り示しているのである。というのも、そのようにしたほうが黙示録においては自然だからである。
【40:4】
『その人は私に話しかけた。「人の子よ。あなたの目で見、耳で聞き、わたしがあなたに見せるすべての事を心に留めよ。わたしがあなたを連れて来たのは、あなたにこれを見せるためだ。あなたが見ることをみな、イスラエルの家に告げよ。」』
エゼキエルが霊においてエルサレムへと連れ行かれたのは、天国についてユダヤ人たちに告げ知らせるためであった。それは、苦しみの最中にあったユダヤ人が希望を持てるようになるためである。たとえ苦しみの中にあっても、やがて来たるべき天国について知らされるならば、苦しみが和らぐことにもなるのである。
【40:5~16】
『そこに、神殿の外側を巡って取り囲んでいる壁があった。その人は手に6キュビトの測りざおを持っていた。その1キュビトは、普通の1キュビトに一手幅を足した長さであった。彼がその外壁の厚さを測ると、1さおであり、その高さも1さおであった。それから、彼が東向きの門に行き、その階段を上って、門の敷居を測ると、その幅は1さお、もう一つの門の敷居も幅は1さおであった。控え室は長さ1さお、幅1さおであり、控え室と控え室の間は5キュビトであった。門の内側の玄関の間に続く門の敷居は1さおであった。彼が門の内側の玄関の間を測ると、1さお、すなわち、門の玄関の間を測ると、8キュビト、その壁柱は2キュビトで、門の玄関の間は内側にあった。東のほうにある門の控え室は両側に3つずつあり、3つとも同じ寸法であった。壁柱も、両側とも、同じ寸法であった。彼が門の入口の幅を測ると、10キュビト、門の内のり幅の長さは13キュビトであった。控え室の前に出た仕切りは両側ともそれぞれ1キュビトであった。控え室は両側とも6キュビトであった。彼がその門を、片側の控え室の端から他の側の屋根の端まで測ると、一つの入口から他の入口までの幅は25キュビトであった。彼は壁柱を60キュビトとした。門の周囲を巡る壁柱は庭に面していた。入口の門の前から内側の門の玄関の間の前までは50キュビトであり、門の内側にある控え室と壁柱には格子窓が取りつけられ、玄関の間もそうであった。内側の回りには窓があり、壁柱には、なつめやしの木が彫刻してあった。』
まずは、神殿の外壁およびそこにある門や控え室について測り示されている。これらの造形や秩序は完全であった。これは、天国における外壁の完全さを表象させている。黙示録のほうでも御使いが都の壁を測っている。
ここで書かれている壁の詳細について、私は具体的な説明をしない。それについて説明しても、あまり意味がないからである。ここでは地上のエルサレムを通して示されている天国の外壁が完全であるということが分かれば、それでよい。これ以降の箇所でも、取り立てて説明する必要があるのでもない限り、エルサレムの形状について細かく説明することはしない。私がこのように測定された数値について細かく説明しないからといって、手間を省いているとか厳密性がないなどと言うべきではない。何故なら、ここで見るべきなのはエルサレムの具体的な形状ではなく、「測定されたエルサレムを通して何が示されているのか」という点にあるからである。もし具体的な説明をするのが望ましかったとすれば、私はたとえ面倒であってもそれについて説明する労を厭わなかったであろう。
【40:17~49】
『それから、彼は私を外庭に連れて行った。そこには部屋があり、庭の回りには石だたみが敷かれていた。石だたみの上に、30の部屋があった。石だたみは門のわきにあり、ちょうど門の長さと同じであった。これは下の石だたみである。彼が下の門の端から内庭の外の端までその幅を測ると、東も北も100キュビトであった。彼は外庭にある北向きの門の長さと幅を測った。それには両側に3つずつ控え室があり、壁柱も玄関の間も先の門と同じ寸法であった。その長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。その窓も玄関の間もなつめやしの木の彫刻も、東向きの門と同じ寸法であった。7段の階段を上って行くと、その先に玄関の間があった。東に面する門と同様に、北に面する門にも内庭の門が向かい合っており、彼が門から門まで測ると、100キュビトであった。次に、彼は私を南のほうへ連れて行った。すると、そこにも南向きの門があり、その壁柱と玄関の間を彼が測ると、それは、ほかの門と同じ寸法であった。壁柱と玄関の間の周囲に窓があり、それはほかの窓と同じであった。門の長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。そこに上るのに7段の階段があり、その先に玄関の間があった。その両側の壁柱には、なつめやしの木が彫刻してあった。内庭には南向きの門があり、彼がこの門から南のほうに他の門まで測ると、ほかの門と同じ寸法であった。その控え室も壁柱も玄関の間もほかのと同じ寸法で、壁柱と玄関の間の周囲に窓があった。門の長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。玄関の間の周囲は長さ25キュビト、幅5キュビトであった。その玄関の間は外庭に面し、その壁柱にはなつめやしの木が彫刻したあった。その階段は8段であった。次に、彼は私を内庭の東のほうに連れて行った。そこの門を測ると、ほかの門と同じ寸法であった。その控え室も壁柱も玄関の間もほかのと同じ寸法で、壁柱と玄関の間の周囲に窓があった。門の長さは50キュビト、、幅は25キュビトであった。その玄関の間は外庭に面し、両側の壁柱にはなつめやしの木が彫刻してあった。階段は8段であった。彼は私を着た門に連れて行った。それを測ると、ほかの門と同じ寸法であった。その控え室も壁柱玄関の間もほかのと同じ寸法で、その周囲に窓があった。門の長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。その玄関の間は外庭に面し、両側の壁柱にはなつめやしの木が彫刻してあった。階段は8段であった。門の壁柱のそばに戸のある階段があり、そこは全燃のいけにえ、罪のためのいけにえ、罪過のためのいけにえをほふるために、両側にそれぞれ2つずつの台があった。北の門の入口へ上って行くと、外側に2つの台があり、門の玄関の間の他の側にも2つの台があった。北の門の入口へ上って行くと、外側に2つの台があり、門の玄関の間の他の側にも2つの台があった。すなわち、門の片側に4つの台があり、他の側に4つの台があり、この8つの台でいけにえをほふるのである。また、全燃のいけにえのための4つの切り石の台があり、その長さは1キュビト半、幅は1キュビト半、その高さは1キュビトであった。その上に全燃のいけにえや、ほかのいけにえをほふるための道具が置かれていた。内側には、周囲に一手幅の縁が取りつけてあり、ささげ物の肉は台の上に置かれるようになっていた。彼は私を内庭に連れて行った。内庭には2つの部屋があり、北の門のわきにある部屋は南を向き、南の門のわきのは北を向いている。彼は私に言った。「この南向きの部屋は、宮の任務を果たす祭司たちのためであり、北向きの部屋は、祭壇の任務を果たす祭司たちのためである。彼らはツァドクの子孫であり、レビの子孫の中で主に近づいて仕える者たちである。」彼が庭を測ると、長さ100キュビト、幅100キュビトの正方形であった。神殿の前には祭壇があった。彼が私を神殿の玄関の間に連れて行って、玄関の間の壁柱を測ると、両側とも5キュビトであり、その門の幅は14キュビト、その門の両わきの壁は、それぞれ3キュビトであった。玄関の間の間口は20キュビト、奥行は12キュビトであった。そこへ上るのに階段があり、両側の壁柱のそばにはそれぞれ円柱が立っていた。』
次は、神殿の外庭・内庭について測り示されている。これも、やはり完全な形状と秩序になっている。つまり、ここでも天国の都にある外庭・内庭が完全であるということが示されている。
ここでは動物犠牲について言及されている。これは天上のエルサレムで動物犠牲が行なわれるという意味ではない。この動物犠牲は、イエス・キリストを表象している。つまり天上のエルサレムには、永遠の贖いを実現された神の子羊がおられるということである。また、ここで動物犠牲が出てくるからといって、第2神殿について預言されていると考えはならない。先にも述べた通り、エゼキエル40~48章では天国のことが預言されているのだから。
『ツァドクの子孫』とは天国にいる贖われた聖徒たちを象徴している。これについては後の箇所で詳しい説明がされているので、私もその箇所が来たら詳しく説明することにしたい。
まず初めに示されたのは外壁であった。そして次は庭である。外側から内側に向かって測定が進められているのが分かる。また、より重要でない場所からより重要な場所へと測定が進んでいるのが分かる。これは詳示の順番として理に適っている。ちょうどコンサートで、まず無名同然のバンドが登場し、次に中堅のバンドが登場し、最後にヘッドライナーが登場するのと一緒である。
【41:1~26】
『彼は私を本堂へ連れて行った。その壁柱を測ると、その幅は両側とも6キュビトであった。これが壁柱の幅であった。入口の幅は10キュビト、入口の両わきの壁はそれぞれ5キュビトであり、本堂の長さを測ると、40キュビト、幅は20キュビトであった。彼が奥にはいり、入口の壁柱を測ると、2キュビト、入口は6キュビト、入口の両わきの壁は7キュビトであった。彼はまた、本堂に面して長さ20キュビト、幅20キュビト、を測って、私に「これが至聖所だ。」と言った。彼が神殿の壁を測ると、6キュビト、神殿の周囲を囲む階段式の脇間の幅は4キュビトであった。階段式の脇間は3段に重なり、各段に30あった。神殿の周囲の階段式の脇間は壁に固定してささえられ、神殿の壁は梁でささえられていなかった。階段式の脇間の幅は階段を上るごとに広くなっていた。それは神殿の周囲にあるらせん階段を上るごとに、その段の幅も広くなり、その下の段から上の段へは中央の階段を通って上るのである。私は神殿の回りが高くなっているのを見た。階段式の脇間の土台は、長めの6キュビトの測りざおいっぱいであった。階段式の脇間の外側の壁の厚さは5キュビトであった。神殿の階段式の脇間と、部屋との間には空地があり、それが神殿の周囲を幅20キュビトで囲んでいた。階段式の脇間の入口は空地のほうに向き、一つの入口は北向きで、他の入口は南のほうに向き、その空地は幅5キュビトで周囲を囲んでいた。西側の聖域にある建物は、その奥行が70キュビト、その建物の回りの壁は、厚さ5キュビト、その間口は90キュビトであった。彼が神殿を測ると、長さは100キュビト、その聖域と建物とその壁とで、長さ100キュビトであった。また、東側の聖域と神殿に面する幅も100キュビトであった。彼が神殿の裏にある聖域に面した建物の長さと、両側の回廊とを測ると、100キュビトであった。本堂の内側と、庭の玄関の間、門口と格子窓と3段になった回廊とは、床から窓まで羽目板が張り巡らされていた。窓にはおおいがあった。入口の上部にも、神殿の内側にも外側にも、これを囲むすべての壁の内側にも外側にも彫刻がしてあり、ケルビムと、なつめやしの木とが彫刻してあった。なつめやしの木はケルブとケルブとの間にあり、おのおのケルブには2つの顔があった。人間の顔は一方のなつめやしの木に向かい、若い獅子の顔は他方のなつめやしの木に向かい、このように、神殿全体の回りに彫刻してあった。床から入口の上まで、本堂の壁にケルビムとなつめやしの木が彫刻してあった。本堂の戸口の柱は四角で、至聖所の前には何かに似たものがあった。それは木の祭壇のようであり、高さは3キュビト、長さは2キュビトで、その四隅も台も側面も木でできていた。彼は私に、「これが主の前にある机だ。」と言った。また、本堂の至聖所にそれぞれ2つのとびらがあり、それらのとびらにはそれぞれ2つの戸が折りたたむようになっていた。すなわち、一つのとびらには2つの戸があり、ほかのとびらにも2つの戸があった。本堂のとびらには、壁に彫刻されていたのと同じようなケルビムとなつめやしの木が彫刻してあった。外側の玄関の間の前には木のひさしがあった。玄関の間の両わきの壁には格子窓となつめやしの木があり、神殿の階段式の脇間とひさしも同様であった。』
次は神殿が測り示されている。これも当然ながら地上における石造りの神殿について言っているのではない。黙示録のほうでは、天上においては主が神殿であられると言われている(黙示録21:22)。つまり、聖徒たちは天国で神という神殿において生き、住まい、礼拝し、喜ぶのである。
前から『なつめやしの木』が彫刻してあったと言われており、ここでもそのように言われているが、この木は何を意味しているのか。これは天上のエルサレムが力強く、決して揺るがないことを示している。実際のナツメヤシを見よ。それは堂々としており、嵐が襲いかかっても打ち倒されてしまわない。天上のエルサレムも実にそのようなのだ。
ここではケルビムが彫刻してあったと書かれている。このケルビムは、ここでは『2つの顔があった』と言われている。すなわち、『人間の顔』と『若い獅子の顔』である。はて、ケルビムには4つの顔があるのではなかったか(エゼキエル1:10)。左にある牛の顔および後ろにある鷲の顔は、どうなってしまったのか。顔が2つしかないケルビムも存在するのであろうか。この解決は難しくない。つまり、エゼキエルが見たケルビムはあくまでも『彫刻』である。すなわち、この彫刻においては我々から見て左に身体を向けたケルビムが描かれているので、真正面と右にある顔しかないのである。だから、ここでは本物のケルビムの顔が2つだけしかなかったとか、顔が2つだけしかないケルビムも存在している、などということが示されているのではない。この彫刻上におけるケルビムには単に2つしか顔が描かれていなかっただけであり、実際のケルビムに4つの顔があることに変わりはない。例えば、我々の身体の上半身しか彫刻において描かれていなかったからといって、我々に下半身がないことになるか。そういうことにはならないであろう。ここでケルビムに2つの顔しか彫刻の中で描かれていないのも、これと同じことである。
【42:1~14】
『彼は私を北のほうの外庭に連れ出し、聖域に面し、北方の建物に面している部屋へ連れて行った。その長さは100キュビト、その端に北の入口があり、幅は50キュビトであった。20キュビトの内庭に面し、外庭の石だたみに面して、3階になった回廊があった。部屋の前には幅10キュビトの通路が内側にあり、その長さは100キュビトであった。その部屋の入口は北に向いていた。上の部屋は、回廊が場所を取ったので、建物の下の部屋よりも、また2階の部屋よりも狭かった。なぜなら、これらは3階建てであり、庭の柱のような柱がないためである。それで、上の部屋は下の部屋よりも、また2階の部屋よりも狭かった。部屋に沿った外側の石垣は、外庭のほうにあって、部屋に面し、その長さは50キュビトであった。したがって、外庭に面する部屋の長さは50キュビトであった。しかし、本堂に面する側は100キュビトであった。これらの部屋の下には、外庭からはいれるように、東側に出入口があった。聖域や建物に面している南側の庭の厚い石垣の中には、部屋があった。その部屋の通路は、北側の部屋と同じように見え、長さも同じ、幅も同じで、そのすべての出口も構造も入口も、同様であった。南側の部屋の入口も同様で、通路の先端に入口があり、東側の石垣に面し、そこからはいれる通路があった。彼は私に言った。「聖域に面している北の部屋と南の部屋は、聖なる部屋であって、主に近づく祭司たちが最も聖なるささげ物を食べる所である。その場所は神聖であるから、彼らはそこに最も聖なる物、すなわち穀物のささげ物、罪のためのいけにえ、罪過のためのいけにえを置く。祭司たちは聖所にはいったなら、そこから外庭に出てはならない。彼らが奉仕に用いる服は神聖だから、それを脱いで他の服に着替えてから民の所に近づかなければならない。」』
続いて聖域に面した建物とその部屋が詳示されている。これらも、やはり整った造形・秩序になっている。
ここでは祭司たちが一般人に近づく際には祭服を脱いでからにせねばならないと言われている。これは天国にいる聖徒たちの聖性を示している。確かに、そこにいる聖徒たちは完全な聖性を持っている。というのも、そこには『もはや、のろわれるものは何もない』(黙示録22章3節)からである。
【42:15~20】
『彼は、神殿の内側を測り終えると、東向きの門に私を連れ出し、神殿の周囲を測った。彼が測りざおで東側を測ると、測りざおで500さおであった。北側を測ると、測りざおで500さおであった。南側を測ると、測りざおで500さおであった。彼が西側に回って測りざおで測ると、500さおであった。彼が外壁の回りを巡って四方を測ると、その長さは500さお、幅も500さおで、聖なるものと俗なるものとを区別していた。』
次は神殿の周囲が測定されている。これも、天のエルサレムにおける完全性を示している。
ここでは神殿が周りの場所から区別されていると言われている。『聖なるものと俗なるものとを区別していた』と書かれている通りである。これは、天国がそこ以外の場所から断絶していることを示している。そこには『子羊のいのちの書に名が書いてある者だけが、はいることができる』(黙示録21章27節)からである。
【43:1】
『彼は私を東向きの門に連れて行った。』
今度は、エゼキエルが『東向きの門に』連れて行かれている。つまり、最初に連れて来られた場所に戻って来たわけだ。これも、もちろん幻において起きた出来事であることを忘れてはならない。
では、どうしてエゼキエルは『東向きの門に』連れて行かれたのか、その理由は何だったのか。それは、間もなく現われる東からの神の栄光を、エゼキエルがよく確認するためであった。神殿の中にいたのであれば神の栄光が見えなかっただろうし、庭にいても外壁に妨げられて完全な形としては視認できない。だから、神の栄光をまざまざと見れるように、エゼキエルは門の場所に連れて行かれたのである。そこであれば、栄光が丸ごと目に入って来るからである。
【43:2】
『すると、イスラエルの神の栄光が東のほうから現われた。その音は大水のとどろきのようであって、地はその栄光で輝いた。』
エゼキエルは門の場所に連れて行かれたので、東から現われた神の栄光をしっかりと見ることが出来た。ここでエゼキエルは神の栄光について豊かな描写をしていない。だから、この栄光がどのような感じだったのか細かく述べることは難しい。だが、これが非常に素晴らしい栄光だったことは間違いない。しかし、神の栄光はどうして『東のほうから現われた』のか。なぜ『東』からなのか。これは、我々の主なる神が真の太陽であられるからである(マラキ4:2、イザヤ60:19)。つまり太陽が東のほうから上ってくるように、真の太陽であられる神の栄光は東のほうから現われるべきだったのである。聖書の象徴的な文章表現に慣れている人であれば、このような表現は何も不思議だと感じないはずである。
その神の栄光における音は『大水のとどろきのよう』であった。黙示録19:6、1:15、14:2でも『大水』という表現が使われている。これは、滝の流れる轟音を考えればよい。
この箇所は、明らかに黙示録18:1の箇所と対応している。すなわち、神はエゼキエル43:2の内容に基づく啓示の幻をヨハネに黙示録18:1の箇所でお与えになった。そこでは次のように書かれている。『この後、私は、もうひとりの御使いが、大きな権威を帯びて、天から下って来るのを見た。地はその栄光のために明るくなった。』この2つの箇所における文章の相似具合に気づかない人は恐らくいないのではないか。この2つの箇所における違いは次の通り。①:黙示録のほうでは御使いが栄光を伴って天から降りて来たと言われているが、エゼキエル書のほうは神の栄光が現われたと言われている。②:黙示録ではヨハネに啓示が与えられているが、エゼキエル書のほうではエゼキエルが啓示を受けている。③:黙示録ではユダヤの終末において言われているが、エゼキエル書では天上のエルサレムについて言われている。
【43:3】
『私が見た幻の様子は、私がかつてこの町を滅ぼすために来たときに見た幻のようであり、またその幻は、かつて私はケバル川のほとりで見た幻のようでもあった。それで、私はひれ伏した。』
エゼキエルに示された幻は、かつてエゼキエルが見た2つの幻とよく似通っていた。その一つ目は『かつてこの町を滅ぼすために来たときに見た幻』であり、二つ目は『ケバル川のほとりで見た幻』である。前者はエゼキエル書9章に、後者はエゼキエル書1章に書かれている。このように以前に示された幻と同じような幻が再び示されたものだから、エゼキエルは神の栄光の前で即座に『ひれ伏した』。何故なら、そこに神の存在を豊かに感じたからである。このようにするのは彼にとっては当然のことであった。何故なら、エゼキエルは敬虔な人だったから。
我々も、神の栄光を感じ取ったならば、祈るのであれ賛美をするのであれ、即座に礼拝行為をすべきであろう。何故なら、そうするのが神に生きる聖徒たちに相応しいことだからである。世界全体が科学全能主義に毒されて宗教心が低下している昨今、我々はどうであろうか。もし全然エゼキエルのようではないと自分のことを思うならば、その人は反省する必要がある。何故なら、聖徒たちとは敬虔であるべきであって、敬虔とは宗教的な迅速に他ならないのだから。それは、詩篇119:60で『私は急いで、ためらわずに、あなたの仰せを守りました。』と敬虔な著者が言っていることからも分かる。
【43:4】
『主の栄光が東向きの門を通って宮にはいって来た。』
これは何という神秘的な光景であろうか…。このような光景を見れたエゼキエルは実に幸いであった。彼が恵まれた人であるということを誰が疑うであろうか。私も、この素晴らしい聖なる光景を見てみたかったものである。
【43:5】
『霊は私を引き上げ、私を内庭に連れて行った。なんと、主の栄光は神殿に満ちていた。』
エゼキエルが門の「外側」の場所に連れて行かれたというのは、この箇所を見ても分かる。つまり、エゼキエルは門の「内側」に連れて行かれたわけではない(43:1)。何故なら、もし門の内側に連れて行かれたのであれば、どうしてここで門の内側の場所である『内庭に連れて行った』と言われているのであろうか。エゼキエルが門の外側に連れて行かれたからこそ、ここで今度は『内庭に連れて行った』と言われているのである。
ここでは天上のエルサレムが栄光に満ちていたと示されている。何故なら、そこは神のパラダイスだからである。そこはパラダイスだから、神の栄光に満ちているのは当然のことである。もしそこが神の栄光に満ちていなかったとすれば、そこは天国だと言えなかったであろう。
【43:6】
『ある人が私のそばに立っているとき、私は、神殿からだれかが私に語りかけておられるのを聞いた。』
エゼキエルの傍に立っていた『ある人』とはキリストである。このキリストは、手に測る道具を持っておられ(40:3)、つい先ほどまで神殿のサイズを測っておられた。
神殿から語りかけておられる『だれか』とは聖霊なる神である。何故なら、この御方は聖徒たちのうちに住まわれると言っておられるから(43:9)。しかし、この『だれか』を父なる神だと解する人もいるかもしれない。私はその人の理解を否定しない。これが父なる神だという理解も間違っているとは言えないからである。確かに父なる神はその聖霊において聖徒たちのうちに住まわれるのである。だが、この『だれか』がキリストであると解するのは間違っている。何故なら、キリストは神殿の中にではなくエゼキエルの『そばに立ってい』たのだから。
【43:7】
『その方は私に言われた。「人の子よ。ここはわたしの玉座のある所、わたしの足の踏む所、わたしが永遠にイスラエルの子らの中で住む所である。イスラエルの家は、その民もその王たちも、もう2度と、淫行や高き所の王たちの死体で、わたしの聖なる名を汚さない。』
ここでは天上のエルサレムが3種類の意味を持っていると言われている。まずそこは『わたしの玉座のある所』である。つまり、これは神が天のエルサレムを支配されるということである。何故なら、『玉座』とは王が王として支配をする場所だから。次にそこは『わたしの足の踏む所』である。これは、天上のエルサレムが神に服しているという意味である。何故なら、足の下に踏まれるとは服従させられるということでなくて何であろうか。そしてそこは『わたしが永遠にイスラエルの子らの中で住む所』である。神は、天のエルサレムで聖徒たちのうちに永遠に至るまでも住まわれる。何故なら、天国において神の住まいは、そこにいる聖徒たちだからである。
捕囚が起こる前のユダヤには、『淫行や高き所の王たちの死体』による悪と汚れがあった。『淫行』とは偶像崇拝のことである。『高き所の王たちの死体』とは、王の死体を崇拝することである。これら2つは、どちらも律法で禁じられている。だから、このような罪に染まっていたユダヤは裁かれてしまったのである。だが、天上において聖徒たちはもはやそのような罪を犯さないと、ここでは言われている。何故なら、天上の聖徒たちは御霊の身体を与えられているからである。この身体において生きる聖徒たちは、絶対に罪を犯さないのである。
ここでは罪を犯すことが、すなわち神の聖なる名を汚すことであると言われている。どうして罪を犯すと神の御名が汚されることになるのか。これは世の中の出来事を考えてみればよい。例えば、日本の大使が駐留している外国でとんでもない凶悪犯罪を犯したとすれば、その大使により日本が悪く思われるから、その大使は日本の名声と信用を汚したことになる。またハンバーガーショップの社長が不祥事を起こせば、大きなニュースとなって悪いイメージを持たれるので、その社長が自分のハンバーガーショップを汚したことになる。聖徒たちが罪を犯すのも、これと同じである。聖徒たちにとって、神とは聖なる国であり、喜んで仕えるべきハンバーガーショップなのだから。
【43:8】
『彼らは、自分たちの門口をわたしの門口のそばに設け、自分たちの戸口の柱をわたしの戸口の柱のかたわらに立て、わたしと彼らとの間には、ただ壁があるだけとなり、彼らの忌みきらうべきわざによってわたしの聖なる名を汚した。そこでわたしは怒って、彼らを絶ち滅ぼした。』
ここで門口と戸口の柱について言われているのは、神とユダヤ人との距離の近さを比喩的に表現している。つまり、これは例えとして言われている。「ユダヤ人が神の傍近くにいたのは、あたかも2人の住民が壁一枚の距離で過ごしているかのようであった。」ここではこのように言いたいのである。実際、ユダヤ人たちは神の近くに位置していた。というのも、ユダヤ人とは養子として神に買い取られた特選の民だったのだから。
それにもかかわらず、ユダヤ人たちは『彼らの忌みきらうべきわざによって』神の御名を汚した。せっかく神の子どもとして他の民族から選出されたのに、自分たちを選出して下さった神に背くとは何という不敬虔であろうか。これは例えるならば、養子にされた子が、養子にしてくれた人の家を破壊したり燃やしたりして大恥をかかせるようなものである。
このように背いたユダヤ人たちは、当然ながら神の怒りにより滅ぼされてしまった。これは紀元前585年に起きたあの悲劇のことである。彼らがこのような裁きを受けたのは当然であった。何故なら、神とは報いられる御方だからである。エレミヤ書51:56の箇所でこう言われている通りである。『主は報復の神で、必ず報復されるからだ。』
【43:9】
『今、彼らにその淫行や王たちの死体をわたしから遠く取り除かせなければならない。わたしは永遠に彼らの中に住もう。』
主はあたかもこう言っておられるかのようである。「あなたがたはやがて天国で永遠に神の住まいとなるのだから、そのような存在に相応しく、地上にいる今から既に聖なる歩みをせねばならない。特に、あなたがたの滅びの原因となった『淫行や王たちの死体』から遠く離れ去らねばならない。」この箇所で『わたしは永遠に彼らの中に住もう。』と言われているのは、天国のことである。これは地上のことではない。何故なら、このエゼキエル書40~48章では天国について預言されているのだから。
我々も、天国に定められている者として、今から既に天国に入れられる者として相応しい歩みをすべきである。天国に定められているからといって、この地上ではいい加減に歩んでよいということにはならない。すなわち、「どのような歩みをしても結局は天国に入れられるのだから、この地上でいい加減な歩みをしても問題はない。」などと考えるべきではない。むしろ逆である。聖徒たちは、天国に定められているからこそ、そこに入る者としての歩みをせねばならない。何故なら、聖く歩もうと望まないどうしようもない者が天国に入って神を見ることはないからである。それはヘブル書12:14の箇所でこう言われている通りである。『…聖められることを追い求めなさい。聖くなければ、だれも主を見ることができません。』もし昔のユダヤ人たちのような歩みをするのであれば、その人は天国に入れなくなることにもなる。つまり、その人はそもそも最初から天国に入るようにと選ばれていなかったのである。パウロが次のように言ったのは真実である。『あなたがたは、正しくない者は神の国を相続できないことを、知らないのですか。だまされてはいけません。不品行な者、偶像を礼拝する者、姦淫をする者、男娼となる者、男色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者はみな、神の国を相続することができません。』救いは行ないによらないけども、聖徒たちはこの地上で聖なる歩みをする必要があるのだ。
【43:10~11】
『人の子よ。イスラエルの家が自分たちの不義を恥じるために、彼らに神殿を示し、彼らにその模型を測らせよ。もし彼らが、自分たちの行なったあらゆることを恥じるなら、あなたは彼らに神殿の構造とその模型、その出口と入口、すなわち、そのすべての構造、すべての定め、すべての構造、すべての律法を示し、彼らの目の前でそれを書きしるせ。彼らが、そのすべての構造と定めとを守って、これを造るためである。』
これは一体どういう意味であるか。ユダヤ人たちに神殿を示し、その模型を測らせるとは…。これは、こういうことである。当時のユダヤ人は、神の規定に違反し、いい加減な歩みをしていた。それは、別の事柄で例えるならば、設計図に従わないで好き勝手に家屋を建設するのと一緒であった。神は、このようなユダヤを教育されようとし、彼らに神殿が示され、彼らがその模型を忠実に作ったり測ったりするようにしようとされた。そうすれば、神殿の造形におけるその完全性と秩序をまざまざと感じ、自分たちの不完全性・異常性と比較して恥じ入ることになるからである。そうなれば次のように感じざるを得なくなるのだ。「私たちの目の前にある神の神殿はこのように完璧だが、それに比べて不敬虔に歩んでいる私たちのだらしなさといったら…。」実際に完全な造形を有する神殿を自分たちで作ったり測ったりするからこそ、このような恥辱を持つことにもなるのだ。この箇所は、よく考えないと、どうして神殿の模型を測ることでユダヤ人が恥じ入るのか理解できないはずである。だが、よく考えると、今説明されたように、確かに神殿の模型を測ればユダヤ人が恥じ入るようになるということが分かる。
要するに、神は実物教育をユダヤに与えようとしておられた。それはユダヤ人が、言葉で言うだけでは駄目であり、何らかの行ないを通して実感しないと反省しないからである。いや、これはユダヤ人だけでなく、他のあらゆる民族においてもそうである。というのもソロモンが次のように言うのは真実だからである。『しもべをことばだけで戒めることはできない。彼はそれがわかっても、反応がない。』(箴言29章19節)ユダヤは神の前にいる僕であった。だから神は御自身の僕であるユダヤを、このように言葉だけでなく感覚的に教育しようとされたのである。神は英知の御方である。
【43:12】
『宮に関する律法は次のとおりである。山の頂のその回りの全地域は最も神聖である。これが宮に関する律法である。』
『山』とは神殿が建てられていた場所である。『山の頂のその回りの全地域』とは神殿の建っていたエルサレム市の全体である。つまり、ここでは地上のエルサレムが神聖であると言われている。これは、地上のエルサレムの神聖性を通して天上のエルサレムの神聖性を示しているのである。
【43:13~17】
『キュビトによる祭壇の寸法は次のとおりである。―このキュビトは、普通のキュビトに一手幅足したものである。―その土台の深さは1キュビト、その回りの縁の幅は1キュビト、みぞは一あたりである。祭壇の高さは次のとおりである。この地面の土台から下の高台までは2キュビト、回りの幅は1キュビト。この低い台座から高い台座までは4キュビト、その回りの幅は1キュビト。祭壇の炉は高さ4キュビトであり、祭壇の炉から上のほうへ4本の角が出ていた。祭壇の炉は長さ20キュビト、幅12キュビトの正方形である。その台座は長さ14キュビト、幅14キュビトの正方形で、その回りのみぞは半キュビト、その縁は1キュビトであり、その階段は東に面している。」』
ここでは祭壇のサイズが示されている。このサイズについて細かい説明をする必要はない。
【43:18~27】
『彼は私に言った。「人の子よ。神である主はこう仰せられる。祭壇の上で全焼のいけにえをささげ、血をそれに注ぎかけるために祭壇を立てる日には、次のことが祭壇に関する定めとなる。わたしに仕えるために、わたしに近づくツァドクの子孫のレビ人の祭司たちに、あなたは、罪のためのいけにえとして若い雄牛1頭を与えよ。―神である主の御告げ。―あなたは、その血を取って、祭壇の4本の角と、台座の4隅と、回りのみぞにつけ、祭壇をきよめ、そのための贖いをしなければならない。またあなたは、罪のためのいけにえの雄牛を取り、これを聖所の外の宮の一定の所で焼かなければならない。二日目に、あなたは、傷のない雄やぎを罪のためのいけにえとしてささげ、雄牛できよめたように、祭壇をきよめよ。きよめ終えたら、あなたは、傷のない若い雄牛と群れのうちの傷のない雄羊とをささげよ。あなたは、それらを主の前にささげ、祭司たちがそれらの上に塩をまき、全焼のいけにえとして主に捧げなければならない。7日間、あなたは毎日、罪のためのいけにえとして雄やぎをささげ、傷のない若い雄牛と群れのうちの傷のない雄羊とをささげなければならない。7日間にわたって祭壇の贖いをし、それをきよめて使い始めなければならない。この期間が終わり、八日目と、その後は、祭司たちが祭壇の上で、あなたがたの全焼のいけにえと和解のいけにえとをささげなければならない。そうすれば、わたしはあなたがたを受け入れる。―神である主の御告げ。―」』
今度は『祭壇に関する定め』が教えられている。天上では祭壇により動物を犠牲として捧げることはないから、ここでは動物犠牲の本体であられるイエス・キリストのことが言われているとすべきであろう。つまり、天国では聖なる贖いを実現されたキリストが永遠の大祭司として、いつまでもおられるのである。また、ここでは再び聖徒たちの象徴である『ツァドクの子孫』が出てくる。この象徴存在については、もう少ししたら説明されることになる。
【44:1~2】
『彼が私を聖所の東向きの外の門に連れ戻ると、門は閉じていた。主は私に仰せられた。「この門は閉じたままにしておけ。あけてはならない。だれもここからはいってはならない。イスラエルの神、主がここからはいられたからだ。これは閉じたままにしておかなければならない。』
東向きの外の門は神が入られた場所なので、そこから誰も通ってはならなかった。何故なら、もしそこから誰かが通れば、神の至高性と神聖性を侵害するからである。これは、ちょうど厳かな玉座に一般人が勝手に座って王らしく振る舞うようなものである。誰かがそのようにすれば、間違いなく王の唯一性と尊厳が侮辱され汚されてしまう。誰かが神の入られた門に勝手に入るのも、これと同じことである。しかしながら、これはあくまでも平日に人がそこから入ってはならない、と言われているだけであることに注意されたい。何故なら、後の46:1の箇所では、この門を『安息日と、新月の祭の日にはあけなければならない。』と言われているからである。その日であれば話は別である。その日ならば、たとえそこから入っても、神の聖らかさを侵すことにはならない。
【44:3】
『ただ、君主だけが、君主として主の前でパンを食べるためにそこにすわることができる。彼は門の玄関の間を通ってはいり、またそこを通って出て行かなければならない。』
王たちは、一般人とは違って、主の御前でパンを食べることができた。聖書で王は神々と呼ばれている。彼らは神の支配と裁きを代行する天により立てられた使者である。だから、王たちは言わば神の同労者として神の御前でパンを食べることができたのだ。イスラエルの長老たちも、指導者であったので、やはり神の御前で食事をすることができた(出エジプト25:9~11)。『そこ』とは「神の御前」のことである。
また、王たちは自分が入って来た時と同じ場所を通って帰らなければならなかった。これについては後の46:8の箇所でも言われている。王たちも神の規定に従わねばならなかった。何故なら、彼らも神の御前では神に従うべき一人の人間に過ぎないからである。だから、テオドシウス帝も教会では司教アンブロシウスに服従していたのである。皇帝であっても、教会では教職者に教え導かれる一人の羊に他ならないのだから。
【44:4】
『彼は私を、北の門を通って神殿の前に連れて行った。私が見ると、なんと、主の栄光が主の神殿に満ちていた。そこで、私はひれ伏した。』
今度は、エゼキエルが北の門から神殿の前へと連れて行かれたが、やはり神殿は神の栄光に満ちていた。エゼキエルはまたも神の栄光の前でひれ伏した。神の栄光は、何度であっても崇拝されるべきである。それは、136篇で神の働きが語られるごとに崇拝の言葉―『その恵みはとこしえまで。』―を著者が発していることからも分かる。神の栄光は崇めすぎても崇めすぎることにはならない。だから、再びエゼキエルがこのように神の栄光の前で崇拝行為をしたのは適切であった。
【44:5】
『すると主は私に仰せられた。「人の子よ。主の宮のすべての定めとそのすべての律法について、わたしがあなたに告げていることをことごとく心に留め、それに目を注ぎ、耳を傾けよ。宮にはいれる者と、聖所にはいれないすべての者を心に留めよ。』
エゼキエルは、神殿とその全ての規定について、大いに注意せねばならなかった。この神殿は天国を表象している。つまり、エゼキエルは天国に心を留めるようにと言われたのである。天国とは、非常に重要な場所である。だからエゼキエルはそこについて心に留めるようにと言われたのだ。
またエゼキエルは『宮にはいれる者と、聖所にはいれないすべての者』も心に留めるように言われた。『宮にはいれる者』とは天国に入れる聖徒たちを指す。『聖所にはいれないすべての者』とは天国に入れない悪者を指す。どうしてエゼキエルは彼らについて心に留めるべきだったのか。それは、この2つの場所があまりにも重要だったからである。我々人間が永遠に住まう最終的な場所。それが天国と地獄である。そこについて心に留めよと言われているのを聞いて、何かおかしいことが言われていると思う者がいるのであろうか。霊的に愚鈍でないのであれば、誰も何もおかしいとは思わないはずである。
この天国と地獄が開始されたのは、紀元70年、すなわちエゼキエルの時代から約600年後である。エゼキエルは約600年も経過してから始まる場所について心に留めるようにと言われた。これはこの2つの場所の重要性をよく示している。つまり、あまりにも重要であるからこそ、600年も前から既にそこを心に留めるべきだったのである。もし重要でなかったとすれば、600年も前から心に留める必要はなかったであろう。この天国と地獄は今やもう始まっている。それが始まる前からエゼキエルはそれを心に留めよと言われた。であれば、もうそれが始まっている時代に生きている我々は一体どれだけ、その場所について心を留めねばならないであろうか。
【44:6~8】
『あなたは、反逆の家、イスラエルの家にこう言え。神である主はこう仰せられる。イスラエルの家よ。あなたがたのあらゆる忌みきらうべきわざは、もうたくさんだ。あなたがたは、心にも肉体にも割礼を受けていない外国人を連れて来て、わたしの聖所におらせ、わたしの宮を汚した。あなたがたは、わたしのパンと脂肪と血とをささげたが、あなたがたのすべての忌みきらうべきわざによって、わたしとの契約を破った。あなたがたは、わたしの聖所での任務も果たさず、かえって、自分たちの代わりにわたしの聖所で任務を果たす者たちを置いた。』
ユダヤは『反逆の家』と言われるまでに堕落してしまっていた。いや、というよりユダヤは前からずっと堕落し続けていた。エジプトから連れ出された時以降、彼らが「従順の家」だったことは一度もなかったのだ…。せっかく神に従って正しく歩むようにと選び出されたにもかかわらず、そのようにして下さった神に背き続けるというのは何ということか。
このようなユダヤに対して神はこう言われた。『あなたがたのあらゆる忌むべきわざは、もうたくさんだ。』神は忍耐の神であられる。だから、これまでずっとユダヤの罪深さを耐え忍んでおられた。だが、エゼキエルの時代において神の忍耐が限界に達した。もちろん神は耐えようと思えば永遠に耐えることもお出来になった。だが、神はそうされなかった。何故なら、これ以上耐え忍んでも、もう改善の見込みがないと判断されたからである。
ここではそのユダヤの極悪が3つ挙げられている。それらは、どれもとんでもない悪事である。
まずユダヤ人は、無割礼の汚れた異邦人を聖所の中に入らせていた。異邦人が入れる場所は、神殿の外にある「庭」までである。聖所には祭司たちしか入ってはいけなかった。それなのに、彼らは異邦人を聖所にまで入れていたのだ。彼らは御心などお構いなしであった。これは今の教会で言えば、聖餐をノンクリスチャンにまで受けさせている教会に該当する。このような教会は、異邦人を聖所に入れていたユダヤ人のように神の御心を重視していないのだ。
またユダヤ人は、神への『パンと脂肪と血とをささげ』て外面的には崇拝行為をしているかのように見えたが、日頃の忌むべき悪事によって神との契約を守っていなかった。これは最悪の不敬虔である。何故なら、捧げ物による外面的な崇拝行為の純粋性が、日頃の行ないによって立証されておらず、かえって否定されているからである。彼らは、神が求められるのは犠牲ではなく純粋な心に基づく服従だということを全く知らなかった。確かに聖書は次のように言っているのだ。『主は主の御声に聞き従うことほどに、全焼のいけにえや、その他のいけにえを喜ばれるだろうか。見よ。聞き従うことは、いけにえにまさり、耳を傾けることは、雄羊の脂肪にまさる。』(Ⅰサムエル15章22節)『たとい私がささげても、まことに、あなたはいけにえを喜ばれません。全焼のいけにえを、望まれません。神へのいけにえは、、砕かれたたましい。砕かれた、悔いた心。神よ。あなたは、それをさげすまれません。』(詩篇51:16~17)これは別の事柄で例えるならばフリーメイソンである。この団体は自分たちを慈善団体として見せかけているが、実のところ、ワンワールド実現のために工作活動をしている陰謀団体なのである。人々を欺くためだけに慈善という仮面を被っているのだから、たとえ慈善をしたとしても、それが一体なんになるのであろうか。
またユダヤ人は、聖所での任務を本来であればその役に任じられていない者に行なわせていた。これは聖所の任務を任されていた祭司すなわちレビ人たちが腐っていたことを示す。また、それはユダヤの民衆全体が腐っていたことを示してもいる。何故なら、大勢いる一般のユダヤ人たちは、レビ人たちにより教えられ導かれていたからである。言わば教師であるレビ人が腐敗しているのであれば、民衆も腐敗せざるを得ないのだ。これは自分そっくりのロボットを作って、自分の代わりに授業をさせる小学校の教師とよく似ている。この教師は自分では何も教えないのに、やすやすと賃金を得ることが出来るのだ。
ユダヤがこのような有り様であったから、神はユダヤを裁いて滅ぼされた。彼らが滅びたのは、その数々の罪に対する当然の結果であった。それは、国家にクーデターを企てた邪悪な反逆者どもが、容赦なく死の処罰を受けることになるのと同じである。
【44:9】
『神である主はこう仰せられる。心にも肉体にも割礼を受けていない外国人は、だれもわたしの聖所にはいってはならない。イスラエルの中にいる外国人はみなそうだ。』
無割礼の異邦人は、祭司だけが入るべき聖所に入れてはいけなかった。これは基本中の基本である。ユダヤは、このようなことさえ守れていなかった。聖餐をノンクリスチャンにも与えている教会は、このユダヤ人の不義を非難できない。何故なら、その教会も同様のことをしているからだ。その教会は、聖餐をクリスチャンだけに与えるというごく簡単なことさえ守れていない。
なお、ここでは異邦人が割礼を受ければ聖所に入れるようになる、と言われているわけではない。これは注意せねばならない。ここでは単に無割礼の外国人が聖所に入るべきではないとだけ言われているに過ぎない。
【44:10~14】
『レビ人でも、イスラエルが迷って自分たちの偶像を慕って、わたしから迷い出たとき、わたしを捨て去ったので、彼らは自分たちの咎を負わなければならない。彼らは宮の門で番をし、宮で奉仕をして、わたしの聖所で仕えるはずなのだ。彼らは民のために、全焼のいけにえや、ほかのいけにえをほふり、民に仕えて彼らに奉仕しなければならない。それなのにレビ人たちは、民の偶像の前で民に仕え、イスラエルの家を不義に引き込んだ。それゆえ、わたしは彼らに誓う。―神である主の御告げ。―彼らは自分たちの咎を負わなければならない。彼らは、祭司としてわたしに仕えるために、わたしに近づいてはならない。わたしのあらゆる聖なる物、または最も聖なる物に触れてはならない。彼らは自分たちの恥と自分たちの行なった忌みきらうべきわざの責めとを負わなければならない。わたしは彼らに、宮のあらゆる奉仕とそこで行なわれるすべての宮の任務を果たさせる。』
レビ人たちは、神の御前で熱烈に仕えるべきであった。彼らは宮の門で番をし、種々の犠牲を捧げ、民のために祈り、そのようにして神殿で神と人とに仕えるべきであった。そのようにするために彼らは召し出されたのだから。
それにもかかわらず、レビ人たちは神に従わずに歩んでいた。そればかりか、偶像を崇拝して、偶像の神に仕えていた。そして、そのことによって彼らは『イスラエルの家を不義に引き込んだ』のである。つまり、イスラエルの人々が偶像崇拝の深みに陥ったのは、レビ人たちの振る舞いが元凶であった。何故なら、下にいる者たちは常にトップにいる者たちからの影響を受けざるを得ないからである。率いる者が堕落していたのであれば、どうして率いられる者たちが堕落しないでいられようか。ソロモンも次のように言っている。『支配者が偽りのことばに聞き入るなら、従者たちもみな悪者になる。』(箴言29章12節)
神は、当然ながらこのようなレビ人を大いに罰された。その罰とは次のような内容であった。まず、彼らはもはや祭司として神に奉仕することが出来なくなった。また、神に属する聖なる物品に触れることが出来なくなった。そして、それらの罰を受けることにより、大いなる恥辱を味わうことになった。見よ、これが民を率いていたレビ人に対する報いである。これが彼らにとって痛々しい裁きであったことは間違いない。
しかし、レビ人に対するこのような罰は少し厳しすぎるのではないかと思われる人もいるかもしれない。だが、よく考えるべきである。彼らは、イスラエルを統導すべき立場にあった。それなのに彼らはイスラエルを統導するどころか、偶像崇拝へと陥らせた。これは実に大きなことである。彼らには大きな責任があったのだから。それゆえ、彼らがこのような罰を受けたとしても当然であったと考えるべきである。ヤコブも『教師は、格別きびしいさばきを受ける』(ヤコブ3章1節)と言っているではないか。レビ人たちはイスラエルの宗教的な教師であった。古代ローマ軍を見よ。彼らは軍の規律に少しでも違反した兵士を、非人道的に思えるぐらいの容赦なさで粛清していた。例えば、夜の見張りをしている時に居眠りを見つけられた兵士は、棒で打ちのめされて殺されねばならなかった。ローマ軍の強さと規律の秘訣はこのあまりの峻厳さにあった。またフリーメイソンを見よ。彼らは裏切り者を見せしめのために容赦なく殺すことで、他のメイソンリーたちが裏切り行為に走らないための抑止力を生じさせている。ある脱退者の言うところによれば、裏切り者は、会員たちの集まっている前でズタズタに刺されて殺される(この脱退者もこの秘密について書いた暴露本を出版した後ですぐ死んでしまった)。彼らが今に至るまでほとんどその陰謀を知られずに済んでいるのは、このように冷酷な粛清をすることで暴露を防止させる効果を出しているからである。このように人間でさえ組織の強さや規律や秘密主義を維持するために容赦なく粛清をするのであれば、神が御自身の組織を担っているレビ人たちに情け容赦のない罰を下されたからといって何の不思議があるであろうか。
この44:10~14の箇所では、レビ人たちがもはや祭司として仕えられなくなると言われた後、最後の部分で『わたしは彼らに、宮のあらゆる奉仕とそこで行なわれるすべての宮の任務を果たさせる。』と言われている。これが一体どういうことなのか疑問に感じないであろうか。多くの人が疑問に感じるのではないかと思う。だが、これはそう難しい問題ではない。つまり、ここでは内容の順序がほとんど考慮されていないのである。聖書で、内容の順序が整っていない箇所は珍しくない。最後の部分である44:14で言われている内容は、44:11と同一である。要するに最後の部分は、次のように言われていると考えるべきである。「『わたしは彼らに、宮のあらゆる奉仕とそこで行なわれるすべての宮の任務を果たさせる。』わたしはレビ人について確かにそのように定めた。だから、彼らはそのようにすべきであった。しかし、彼らはそのようにはしなかった。それゆえ、彼らはもう二度とわたしの前で祭司として仕えることが出来ない。」この問題は今解決されたように解決すべきである。何故なら、同一の箇所で、レビ人がもう神に仕えられなくなったと言われていると同時にこれからレビ人が神に仕えるようになる、などと矛盾したことがどうして言われているのであろうか。44:14を44:11の部分にくっつけて44:10~13を読んでみよ。そうすれば全てがシックリするであろう。
【44:15~16】
『しかし、イスラエル人が迷ってわたしから離れたときもわたしの聖所の任務を果たした、ツァドクの子孫のレビ人の祭司たちは、わたしに近づいてわたしに仕え、わたしに脂肪と血とをささげてわたしに仕えることができる。―神である主の御告げ。―彼らはわたしの聖所にはいり、わたしの机に近づいてわたしに仕え、わたしへの任務を果たすことができる。』
しかしながら、『ツァドクの子孫のレビ人の祭司たち』だけは例外であった。彼らは、他のレビ人たちとは違って、神への奉仕を続けることが出来た。何故なら、彼らの父祖であるツァドクは神を愛して神の命令を守り、他のレビ人たちが脱落した時にも脱落しなかったからである。だから、神はツァドクの子孫たちが、いつまでも御自分に仕えるように恵みを注がれる。それは、神が『わたしを愛し、わたしの命令を守る者には、恵みを千代にまで施す』(出エジプト20章6節)と言っておられる通りである。我々は、ここに神に従う者の幸いを見る。神に従う者の子孫には祝福が注がれるのだ。だから、我々が神に従うのは、子孫に幸せをもたらすことに他ならない。それゆえ、もし子孫の幸福を望むのであれば、我々は神に忠実になるべきなのである。もし神の前で堕落するならば、我々の子孫には幸福どころか呪いがもたらされることになるのだ。
先にも述べた通り、この『ツァドクの子孫のレビ人の祭司たち』とは、天国にいる聖徒たちを表示している。何故なら、天国の聖徒たちは、ツァドクの子孫のように従順で忠実な者たちだからである。私の記憶違いでなければ、世の中にはこれからエルサレムに建設されると思われている第3神殿の聖所で仕える『ツァドクの子孫』を探している者がいるという。これは馬鹿げており、お話しにならない。聖書の記述に基づいて愚かな妄想話を展開させる者たちには、うんざりである。
【44:17~31】
『彼らは内庭の門にはいるときには、亜麻布の服を着なければならない。内庭の門、および神殿の中で務めをするときは、毛織り物を身に着けてはならない。頭には亜麻布のかぶり物をかぶり、腰には亜麻布のももひきをはかなければならない。汗の出るような物を身に着けてはならない。彼らが外庭に出て、外庭の民のところに出て行くときは、務めのときに着ていた服を脱ぎ、それを聖所の部屋にしまい、ほかの服を着なければならない。その服によって民を聖なるものとしないためである。彼らは頭をそってはならない。髪を長く伸ばしすぎてもいけない。頭は適当に刈らなければならない。祭司はだれでも、内庭にはいるときには、ぶどう酒を飲んではならない。やもめや、離縁された女を妻にしてはならない。ただ、イスラエルの民のうちの処女をめとらなければならない。しかし、やもめでも、それが祭司のやもめであれば、めとってもよい。彼らは、わたしの民に、聖なるものと俗なるものとの違いを教え、汚れたものときよいものとの区別を教えなければならない。争いがあるときには、彼らは、わたしの定めに従ってさばきの座に着き、これをさばかなければならない。わたしのすべての例祭には、わたしの律法とおきてとを守り、わたしの安息日を聖別しなければならない。彼らは、死人に近づいて身を汚してはならない。ただし、自分の父、母、息子、娘、兄弟、未婚の姉妹のためには汚れてもよい。その場合、その人は、きよめられて後、さらに7日間待たなければならない。聖所で仕えるために聖所の内庭にはいる日には、彼は罪のためのいけにえをささげなければならない。―神である主の御告げ。―これが彼らの相続地となる。わたしが彼らの相続地である。あなたがたはイスラエルの中で彼らに所有地を与えてはならない。わたしが彼らの所有地である。彼らの食物は、穀物のささげ物、罪のためのいけにえ、罪過のためのいけにえである。イスラエルのうちのすべての献納物は彼らのものである。あらゆる種類の初物、あなたがたのあらゆる奉納物のうちの最上の奉納物は、すべて祭司たちのものであり、あなたがたの麦粉の初物も祭司に与えなければならない。あなたの家に祝福が宿るためである。祭司たちは、死んだものや裂き殺されたものはすべて、鳥であれ獣であれ、食べてはならない。』
ここでは聖徒たちを象徴している『ツァドクの子孫』に関する規定が述べられている。これらの規定はどれも律法に書かれている。それらは既によく知られていることだから、再びここで細かい説明をする必要はないと思う。この箇所では、ツァドクの子孫たちが律法に従って完全な行為と振る舞いをしなければならないと命じられている。これは、つまり天国にいる聖徒たちが完全であることを示している。何故なら、ツァドクの子孫とは天国の聖徒たちを象徴しているのであって、ここで言われている規定は全て完全だからである。
【45:1~6】
『あなたがたがその地を相続地として、くじで分けるとき、その地の聖なる区域を奉納地として主にささげなければならない。その長さは2万5千キュビト、幅は1万キュビト。その周囲の全域は聖なる地である。このうち、縦横500キュビトの正方形を聖所に当て、その回りを50キュビトの空地にしなければならない。先に測った区域から、長さ2万5千キュビト、幅1万キュビトを測れ。そして、その中に聖なる至聖所があるようにせよ。これは国の聖なる所である。これは、聖所で仕え、主に近づいて仕える祭司たちのものとしなければならない。ここを彼らの家の敷地とし、聖所のために聖別しなければならない。また、長さ2万5千キュビト、幅1万キュビトの地は、宮で奉仕をするレビ人のものとし、20の部屋を彼らの所有としなければならない。聖なる奉納地に沿って、幅5千キュビト、長さ2万5千キュビトを町の所有とし、これをイスラエルの全家のものとする。』
今度は、聖なる奉納地についての定めである。これは天国の地が聖別されていて聖いことを示している。
この箇所で、聖所が『正方形』と書かれているのは、注目に値する。何故なら、黙示録21:16の箇所でも『都は四角で』あったと書かれているからである。この2つの箇所は対応しているとすべきであろう。この『正方形』という言葉は、文字通りに捉えるべきではない。これは象徴表現として捉えるべきである。つまり、これは天国に少しの乱れもないことを示している。何故なら、正方形または四角の形状ほど整合性・秩序性を示している形状はないからである。この形状には、少しの乱れも不完全な釣り合いも見られない。この形状は非常に秩序だっているので、クロウリーをはじめとした魔術師たちでさえ魔術の中で祭壇として取り入れているぐらいである。
【45:7~8】
『君主の土地は、聖なる奉納地と町の所有地との両側にあり、聖なる奉納地と町の所有地に面し、西側は西のほうへ、東側は東のほうへ延びている。その長さは一つの部族の割り当て地と同じで、この国の西の境界線から東の境界線にまで及んでいる。これがイスラエルの中の彼の所有地である。わたしの君主たちは、二度とわたしの民をしいたげることなく、この地は部族ごとに、イスラエルの家に与えられる。』
ここでは君主に与えられる土地について述べられている。君主たちも、天国では土地を持つことが出来る。何故なら、君主も天国では他の人たちと同じように恵みを受けられるからである。しかし、天国にも君主という存在がこの地上のようにいるのであろうか。これは、いる可能性が高いと思われる。何故なら、神は地位や名誉や権威といった要素を重んじられるからである。もしかしたら、この地上で王だった聖徒が、天国でもそのまま王であるという可能性もある。しかし、実際はどうなのか確定的なことを言うことはできない。また、この『君主』とは文字通りの王として捉えるべきである。聖書では、聖徒たちも王であると言われている(Ⅰペテロ2:9)。だが、ここでは聖徒たちという意味で『君主』と言われているわけではない。
【45:9~17】
『神である主はこう仰せられる。イスラエルの君主たちよ。もうたくさんだ。暴虐と暴行を取り除き、公義と正義とを行なえ。わたしの民を重税で追い立てることをやめよ。―神である主の御告げ。―正しいはかり、正しいエパ、正しいバテを使え。エパとバテとを同一量にせよ。バテはホメルの十分の1、エパもホメルの十分の1とせよ。その量はホメルを単位とせよ。1シェケルは20ゲラである。20シェケルと25シェケルと15シェケルとで1ミナとせよ。あなたがたがささげる奉納物は次のとおりである。小麦1ホメルから6分の1エパ、大麦1ホメルから6分の1エパをささげ、油の単位により、油のバテで、1コルから10分の1バテをささげよ。1コルは1ホメルと同じく10バテである。また、イスラエルの潤った地の羊の群れから200頭ごとに1頭の羊を、ささげ物、全焼のいけにえ、和解のいけにえのためにささげ、彼らのための贖いとせよ。―神である主の御告げ。―国のすべての民に、この奉納物をイスラエルの君主に納めさせよ。君主は、祭りの日、新月の祭り、安息日、すなわちイスラエルの家のあらゆる例祭に、全焼のいけにえ、穀物のささげ物、注ぎのぶどう酒を供える義務がある。彼はイスラエルの家の贖いのため、罪のためのいけにえ、穀物のささげ物、全焼のいけにえ、和解のいけにえをささげなければならない。』
今度は、君主たちに守るべき規定が与えられている。地上におけるユダヤの君主たちは、神の規定に従って統治せず、罪深い歩みばかりをしていた。だが天国にいる君主たちは、そのようであってはならない。だから、ここでは天国の君主たちの守るべき規定が示されているのである。
【45:18~25】
『神である主はこう仰せられる。第一の月の第1日に、あなたは傷のない若い雄牛を取り、聖所をきよめなければならない。祭司は罪のためのいけにえから、血を取り、それを宮の戸口の柱や、祭壇の台座の四隅や、内庭の門の脇柱に塗らなければならない。その月の7日にも、あなたは、あやまって罪を犯した者やわきまえのない者のためにこのようにし、宮のために贖いをしなければならない。第一の月の14日に、あなたがたは過越の祭りを守り、その祭りの7日間、種を入れないパンを食べなければならない。その日に君主は、自分のためと国のすべての民のために、罪のためのいけにえとして雄牛をささげなければならない。その祭りの7日間、彼は全焼のいけにえとして傷のない7頭の雄牛と7頭の雄羊を、7日間、毎日、主にささげなければならない。また1頭の雄やぎを、罪のためのいけにえとして、毎日ささげなければならない。穀物のささげ物は、雄牛1頭に1エパ、雄羊1頭に1エパをささげなければならない。油は1エパごとに1ヒンとする。第7の月の15日の祭りにも、7日間、これと同じようにささげなければならない。すなわち、罪のためのいけにえ、全焼のいけにえ、穀物のささげ物、それに油を、同じようにささげなければならない。』
次は、色々な犠牲に関する定めである。先にも述べた通り、天国でここに書かれているような犠牲は行なわれない。もし天国でそんなことをすれば、イエス・キリストの永遠の贖いを否定することになるからだ。つまり、ここでは犠牲の本体であられるイエス・キリストが天国におられることを示している。
【46:1~15】
『神である主はこう仰せられる。内庭の東向きの門は、労働をする6日間は閉じておき、安息日と、新月の祭りの日にはあけておかなければならない。君主は外側の門の玄関の間を通ってはいり、門の戸口の柱のそばに立っていなければならない。祭司たちは彼の全焼のいけにえと、和解のいけにえをささげ、彼は門の敷居のところで礼拝して出て行かなければならない。門は夕暮れまで閉じてはならない。一般の人々も、安息日と新月の祭りの日には、その門の入口で、主の前に礼拝しなければならない。君主が安息日に主にささげる全焼のいけにえは、傷のない子羊6頭と、傷のない雄羊1頭である。また、穀物のささげ物は、雄羊1頭について1エパ。子羊のためには、彼が与えることのできるだけの穀物のささげ物。油は1エパごとに1ヒンである。新月の祭りの日には、傷のない若い雄牛1頭と、傷のない子羊6頭と雄羊1頭である。穀物のささげ物をするために、雄牛1頭に1エパ。雄羊1頭に1エパ。子羊のためには、手に入れることのできただけでよい。。油は1エパごとに1ヒンである。君主がはいるときには、門の玄関の間を通ってはいり、そこを通って出て行かなければならない。しかし、一般の人々が例祭の日に主の前にはいって来るとき、北の門を通って礼拝に来る者は南の門を通って出て行き、南の門を通ってはいって来る者は北の門を通って出て行かなければならない。自分のはいって来た門を通って帰ってはならない。その反対側から出て行かなければならない。君主は、彼らがはいるとき、いっしょにはいり、彼らが出るとき、いっしょに出なければならない。祭りと例祭には、穀物のささげ物は、雄牛1頭に1エパ、雄羊1頭に1エパ。子羊のためには与えることのできるだけのもの。油は1エパごとに1ヒンである。また、君主が、全焼のいけにえを、進んでささげるささげ物として、あるいは若いのいけにえを、進んでささげるささげ物として主にささげるときには、彼のために東向きの門をあけなければならない。彼は安息日にささげると同じように、全焼のいけにえと和解のいけにえとをささげなければならない。彼が出て行くなら、彼が出て行って後、その門は閉じられる。あなたは毎日、傷のない1歳の子羊1頭を全焼のいけにえとして、主にささげなければならない。これを毎朝ささげなければならない。それに添えて、毎朝、6分の1エパの穀物のささげ物、上等の小麦粉に振りかけるための油3分の1ヒンをささげなければならない。これが主への穀物のささげ物であり、永遠に続く定めである。こうして、子羊や穀物のささげ物や油を、常供の全焼のいけにえとして、毎朝ささげなければならない。』
次は、門に関わる規定と捧げ物について教えられている。門の事柄については先にも既に幾らかのことが教えられていた。捧げ物は、捧げ物の本体であられるイエス・キリストを示している。この捧げ物は、ここでは細かく説明する必要がない。
【46:16~18】
『神である主はこう仰せられる。もし、君主が、贈り物として自分の相続地を自分の息子たちに与えるなら、それは息子たちのものとなり、それは相続地として彼らの所有地となる。しかし、もし、彼が自分の相続地の一部を贈り物として奴隷のひとりに与えるなら、それは解放の年まで彼のものであるが、その後、それは君主に返される。ただ息子たちだけが、相続地を自分のものとすることができる。君主は、民の相続地を奪って彼らをその所有地から押しのけてはならない。彼は自分の所有地から自分の息子たちに相続地を与えなければならない。それは、わたしの民がひとりでも、その所有地から散らされないためである。」』
再び君主たちについて述べられている。ここでは君主たちが、民から不法に相続地を略奪してはならないと命じられている。天国の君主たちは、地上にいる罪深い君主たちとは違い、悪い性質を何一つとして持っていない。だから天国にいる君主たちは、いかなる度合いであっても他の住民の土地を奪い取るということが全くないのだ。
【46:19~24】
『それから、彼は私を、門のわきにある出入口から、北向きになっている祭司たちの聖所の部屋に連れて行った。すると、西のほうの隅に一つの場所があった。彼は私に言った。「ここは祭司たちが、罪過のためのいけにえや、罪のためのいけにえを煮たり、穀物のささげ物を焼いたりする場所である。これらの物を外庭に持ち出して民を聖なるものとしないためである。」彼は私を外庭に連れ出し、庭の四隅を通らせた。すると庭の隅には、それぞれまた、ほかの庭があった。庭の四隅に仕切られた庭があり、それは長さ40キュビト、幅30キュビトであって、4つともみな同じ寸法であった。その4つとも、回りは石の壁で囲まれ、石の壁の下のほうには料理場が作られていた。彼は私に言った。「これは、宮で奉仕をしている者が、民からのいけにえを煮る料理場である。」』
ここでは、聖所にある祭司たちの部屋および庭にある料理場が示されている。ここで書かれているのは、神殿に本来見られるべき完全な内容の規定である。これも、やはり天国の完全性を示している。なお、再び繰り返して言うが、天国ではここに書かれているような犠牲の制度は全く存在していない。この犠牲に関する記述は、あくまでも天国における完全性を象徴させていると考えなければならない。
【47:1】
『彼は私を神殿の入口に連れ戻した。』
キリストは、エゼキエルを再び神殿の門へと連れ戻された。これも、もちろん幻において起きた出来事である。では、どうしてエゼキエルは神殿の入口に移されたのか。それは、これから神殿で見られる現象をエゼキエルに示すためであった。それは神殿の中というよりは外で確認すべき現象である。もし神殿の中にいれば、その現象を確認するのは難しい。だから、主はその現象をよく見れるようにとエゼキエルを神殿の入口に戻されたのである。それゆえ、もしこれが神殿の内部で確認すべき現象であったとすれば、エゼキエルは神殿の内部へと移されていたであろう。
『見ると、水が神殿の敷居の下から東のほうへと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の右側の下から流れていた。』
ここで言われている『水』とは、すなわち聖霊である。聖書で聖霊が水において示されているということは、聖書研究を怠っていない聖徒であれば既に知っておられるであろう。ヨハネ7:37~39の箇所では、こう書かれている。『さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って、大声で言われた。「だれでも渇いているなら、わたしのもとに来て飲みなさい。わたしを信じる者は、聖書が言っているとおりに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。」これは、イエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。』しかし、どうして聖書は聖霊を水により表示しているのか。それは、人間が水なくして生きることは出来ないからである。それと同じで、神の子らも聖霊なしには神の御前に生きることが決して出来ない。だから、聖書では聖霊が水として語られているのである。このように聖霊が水により示されているからといって、実際に聖霊が水であられるなどとは考えるべきではない。それは、キリストが『門』(ヨハネ10章9節)であると言われているにもかかわらず、実際上はキリストが門であるわけではないのと同じである。
この箇所では、この聖霊を表示している水において、聖徒たちの永生が教示されている。何故なら、天国の聖徒たちは聖霊に潤されて永遠に至るまでも生き続けるからである。キリストが言われたように、聖霊はキリスト者にとって『生ける水の川』である。だから、ここでは水により聖徒たちが永遠に生きるということを示しているわけである。
では、この水が『神殿の敷居の下から』流れていたのは何故なのか。これは、天国では御父と御子が聖なる神殿だからである(黙示録21:22)。だから、ここでは神殿から聖霊を表示する水が流れていたと言われている。つまり、これは聖霊(=水)が御父と御子(=神殿)から出るということである。
【47:2】
『ついで、彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの外の門に行かせた。見ると、水は右側から流れ出ていた。』
ここでは、エゼキエルが北の門から東の門へと移されたと言われている。これは、47:1でエゼキエルが連れ戻されたのは『北の門』であったことを示している。その北の門から今度は東へと連れ出されたわけである。すなわち、47:1では東の門に連れ戻すと言われていたのではなかった。東の門に連れ戻されたのは、少し前の箇所である44:1でのことである。
それでは、どうしてエゼキエルは東の門へと移されたのか。それは、水が神殿の右側から流れ出ていることを再確認させるためであった。聖書思想によれば、全ての事柄は2回または3回確認されるべきである。それゆえ、エゼキエルは47:1の箇所で水が『宮の右側の下から流れて』いることを確認した後、再び47:2の箇所で同じことを東の場所において確認するようにされたのである。
【47:3~5】
『その人は手に測りなわを持って東へ出て行き、1000キュビトを測り、私にその水を渡らせると、それは足首まであった。彼がさらに1000キュビトを測り、私にその水を渡らせると、水はひざに達した。彼がさらに1000キュビトを測り、私を渡らせると、水は腰に達した。彼がさらに1000キュビトを測ると、渡ることのできない川となった。水かさは増し、泳げるほどの水となり、渡ることのできない川となった。』
実に印象的な箇所である。ここでは何が示されているのか。
ここでは、天国における聖霊の充満が示されている。すなわち、天国にいる聖徒たちは十全に聖霊が満たして下さっておられる、ということがここでは言われている。あたかも大きな川に我々が入ってすっぽり水で覆われてしまうかのように。ここでは「4」回の計測がされている。これは聖霊が聖徒たちを満たしておられることを、よく分からせるためである。何故なら、ここでは4回も計測が行なわれているのだから。『1000』とは完全数10の3乗だから、事柄における完全性を示している。この数字については既に説明された。つまり、ここでは『1000』と言って、聖霊の充満における完全性を教示している。
ここでは新約時代について言われていると考えている者がいる。すなわち、ここでは言われているのは4回の千年紀であり、1000年ごとに聖霊が世界にますます充満されていく様を描いている、と。なるほど、これは一見するともっともらしく思える見解である。何故なら、この見解は合理的かつ自然であるように感じられるからだ。だが、この見解は間違っている。何故なら、エゼキエル40~48章は天国について預言されている箇所だからである。これは黙示録との対応具合から考えても分かることである。黙示録の全聖句を神の恵みにより研究した私がこう言うのである。何よりも、この見解は非常に玄妙である。これは単なるこじつけに過ぎない。また、その見解は理性に基づいている。果たして、この世界が西暦4000年に終わるとでもいうのか。世界の始まりから8000年目にキリストが再臨されるとでもいうのか。一体なんなのか、この無知と研究不足に基づく初心者的な怪しい玄妙さは。このように考えている人たちには、どうかお願いしたい。もっと聖書の研究をし、キチンとした解釈をしてほしいものである。理性の感覚が赴くままに解釈するならば、どのような見解でも導き出せることになってしまうのだから。
【47:6】
『彼は私に、「人の子よ。あなたはこれを見たか。」と言って、私を川の岸に沿って連れ帰った。』
キリストは、水の計測を終えられると、エゼキエルに『人の子よ。あなたはこれを見たか。』と確認を促された。この言葉からは2つのことが分かる。まず一つ目は、たった今示されたのは心に留めるべき幻だったということである。二つ目は、その幻が非常に重要であるということである。
こうしてキリストは、エゼキエルを『川の岸に沿って連れ帰』られた。主がこのようにされたのは、今度は川の岸の情景がエゼキエルに示されるべきだったからである。
【47:7】
『私が帰って来て見ると、川の両岸に非常に多くの木があった。』
川の両岸に生えていた木とは何か。その中の一つは、天国の聖徒たちを永遠に生かす生命の木である。何故ならば、黙示録22:1の箇所では『川の両岸には、いのちの木があって、…』と書かれているからである。この生命の木は、すなわちイエス・キリストを象徴している。実際、聖徒たちはキリストという命の木なくして生きることは出来ないからである。では、その生命の木の他に、そこには何か木があったのか。あった。それは後の箇所である47:12で『両岸には、あらゆる果樹が生長し、…』と書かれている通りである。では、その木はどれぐらいの数だったのか。これは別に考えなくてもよい問題である。何故なら、この箇所では木の詳細な数を問題にしているわけではないからである。我々は、ただ川の両岸には木が多く生えていたと理解すれば、それでよい。この木については、また後ほど再び述べられることになる。
【47:8~10】
『彼は私に言った。「この水は東の地域に流れ、アラバに下り、海にはいる。海に注ぎ込むとそこの水は良くなる。この川が流れて行く所はどこででも、そこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水がはいると、そこの水が良くなるからである。この川がはいる所では、すべてのものが生きる。漁師たちはそのほとりに住みつき、エン・ゲディからエン・エグライムまで網を引く場所となる。そこの魚は大海の魚のように種類も数も非常に多くなる。』
この箇所では、聖徒たちが聖霊により永生のうちに生き続けるということを、良い水が海の魚を生かすという例えで示されている。海にいる魚は、良い水がなければ死んでしまう。魚には良い水がどうしても必要である。それと同様に、聖徒たちは聖霊が取り去られたら御前に生きていることが出来ない。聖徒という魚には聖霊という水がどうしても必要なのだ。
この箇所の内容は象徴的に捉えるようにせねばならない。ここで言われている内容を文字通りに捉えるのは間違っている。『水』とは聖霊である。『海』とは天国である。『魚』とは聖徒である。川の畔に住みついた『漁師たち』の存在は、聖霊を表示する水がどれだけ清らかであるかを示している。水が清らかでなければ、漁師たちがその水の畔に住みつくことはないからである。『エン・ゲディからエン・エグライムまで』という範囲は、天国の範囲を示している。魚が『種類も数も』非常に多いというのは、天国にいる聖徒たちの数および国籍や性や身長といった諸々の要素が非常に多いことを示している。
【47:11】
『しかし、その沼と沢とはその水が良くならないで、塩のままで残る。』
ここでは、聖霊が地獄とそこにいる悪者どもには充満されない、ということを教えている。何故なら、そこは呪われた場所であり、そこにいる者たちは呪われた者だからである。そのような忌まわしい場所と人間に聖霊が満たされるとでもいうのであろうか。とんでもない話である。『沼と沢』は地獄を意味している。何故なら、沢と沼とは汚くて不快な場所だからである。この場所は、地獄と完全に一致しているとは言えないが、地獄を象徴する場所として相応しい場所である。『塩のままで残る』とは、地獄を塩と化したソドムとゴモラの場所になぞらえている。ソドムとゴモラが裁きにより塩だらけになったのは周知のことである(申命記29:23)。つまり、ソドムとゴモラがずっと荒廃し続けたままだったように、地獄も荒廃し続けたままの場所だということである。
ここでは地獄とそこにいる者たちに恵みが全くないことを教えている。だから、間違っても地獄とそこにいる者たちには僅かばかりでも恵みが与えられるなどと考えてはならない。かつて、このように考えてしまった者がいるのだ。だが、それは全くの間違いである。何故なら、聖書は地獄では恵みが何もないと教えているからである。むしろ、聖書は地獄にいる者たちが昼も夜も永遠に休みを得ないと教えている。「しかし、それでは神が憐みのない残虐な存在だということにならないか」などと思う人がいるだろうか。口を慎みたまえ。地獄に投げ込まれた者たちは「滅びの器」なのである。神が、彼らを滅びの器として定められたのだ。一体、誰が神の定めに文句を言えるであろうか。一体、誰が神の定めを覆せるであろうか。
【47:12】
『川のほとり、その両岸には、あらゆる果樹が生長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月、新しい実をつける。その水が聖所から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。』
黙示録22:2の箇所を見ると、川の両岸には『いのちの木』だけがあるかのように書かれている。だが、実際はそうではない。我々が今見ている箇所で書かれているように、そこには『あらゆる果樹』が生えているのであって、『いのちの木』はそのうちの一つなのである。だから、黙示録22:2とエゼキエル47:12は、どちらも間違ったことを言っていない。つまり、黙示録のほうでは数ある木のうち生命の木だけを示しており、エゼキエル書のほうでは全ての木を示しているのだ。この箇所およびこの箇所と対応している黙示録22:2の内容は、明らかにエデンの園を思わせる。創世記2:7の箇所では、エデンの園についてこう書かれていた。『神である主は、その土地から、見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には、いのちの木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。』要するに、天国ではエデンの時に見られた原初の状態が回復されている。それゆえ、天国に生えている木々は、エデンの園に生えていた木々のように活き活きとしているはずである。また、天国に生えているこの木には、枯れない葉がついている。どうして枯れないかといえば、天国が祝福された場所だからである。この葉は『薬』として働き、聖徒たちを大いに幸いにさせる。この木には毎月、新しい実も生じる。聖徒たちはその実により養われるのである。ところで、この箇所で言われている木は、実際的に捉えるべきか、それとも象徴表現として捉えるべきか。既に第3部でも述べたが、これはどちらにも捉え得る。だが私としてはこれを象徴として捉えるのが適切ではないかという思いに傾いている。もちろん、これを実際的に捉える人がいても非難されるべきではない。何故なら、もしかしたら天国には本当にこのような木々が生えているかもしれないからである。なお、天国にこのような木が生えているのは、神の恵みによる。すなわち、この木々は、神の恵みを目に見える形で具現化している。それというのも、天国とは恵みに満ちた場所だからである。また、そこにいる者たちは恵まれた者たちだからである。このため、天国にいる聖徒たちは、このような木々を通して神の恵みを知り、味わい、それによって賛美と感謝を神に捧げ、そのようにして神に栄光を帰するのである。
この多くの木は、聖所から流れ出ている水により生長し保たれていた。これは実に象徴的である。つまり、木による生命と癒しは三位一体の神から与えられるのである。何故なら、ここにおいて『聖所』とは御父と御子、『水』とは聖霊であって、その水が聖所から流れているゆえ木が潤うからである。
この箇所は間違いなく黙示録22:1~2の箇所と対応している。そこではこう書かれている。『御使いはまた、私に水晶のように光るいのちの水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て、都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には、いのちの木があって、12種の実がなり、毎月、実ができた。また、その木の葉は諸国の民をいやした。』黙示録とエゼキエル書における主な違いは次の通り。①:黙示録では生命の木について書かれているだけだが、エゼキエル書では川の両岸にある全ての木々について書かれている。②:黙示録では『神と子羊との御座から』水が流れていると書かれているが、エゼキエル書では『聖所から』流れていると書かれている。『神と子羊』は天国における『聖所』だから、どちらの箇所も内容的には同様のことを述べている。③:黙示録では御使いが媒介者として幻を示しているが、エゼキエル書のほうでは神が直に幻を示しておられる。④:黙示録ではヨハネに幻が示されており、エゼキエル書ではエゼキエルに幻が示されている。
【47:13~48:35】
『神である主はこう仰せられる。あなたがたがイスラエルの12の部族にこの国を相続地として与える地域は次のとおりである。ヨセフには2つの分を与える。あなたがたはそれを等分に割り当てなければならない。それはわたしがかつてあなたがたの先祖に与えると誓ったものである。この地は相続地としてあなたがたのものである。その地の境界線は次のとおりである。北側は、大海からヘテロンの道を経て、ツェダデの入口に至り、ハマテ、ベロタ、およびダマスコの領土とハマテの領土の間にあるシブライム、さらにハウランの領土に面したハツェル・ハティコンに至る。海から始まる境界線はダマスコの境界のハツァル・エナンに至り、北は北のほうへ、ハマテの境界にまで至る。これが北側である。東側は、ハウランとダマスコの間と、ギルアデとイスラエルの地の間のヨルダン川が、東の海を経てタマルに至るまでの境界線である。これが東側である。南側は、タマルから南に向かってメリバテ・カデシュの水と川に至り、大海に至るまでである。これが南側である。西側は、大海が境界となり、レボ・ハマテにまで至る。これが西側である。あなたがたは、この地をイスラエルの部族ごとに割り当てなければならない。あなたがたと、あなたがたの間で子を生んだ、あなたがたの間の在留異国人とは、この地を自分たちの相続地として、くじで割り当てなければならない。あなたがたは彼らをイスラエル人のうちに生まれた者と同じように扱わなければならない。彼らはイスラエルの部族の中にあって、あなたがたといっしょに、くじで相続地の割り当てを受けなければならない。在留異国人には、その在留している部族の中で、その相続地を与えなければならない。―神である主の御告げ。―部族の名は次のとおりである。北の端からヘテロンの道を経てレボ・ハマテに至り、ハマテを経て北のほうへダマスコの境界のハツァル・エナンまで―東側から西側まで―これがダンの分である。ダンの地域に接して、東側から西側までがアシェルの分。アシェルの地域に接して、東側から西側までがナフタリの分。ナフタリの地域に接して、東側から西側までがエフライムの分。エフライムの地域に接して、東側から西側までがルベンの分。ルベンの地域に接して、東側から西側までがユダの分である。ユダの地域に接して、東側から西側までが、あなたがたのささげる奉納地となる。その幅は2万5千キュビト、その長さは東側から西側にかけて部族の割り当ての一つと同じである。聖所はその中央にある。あなたがたが主にささげる奉納地は、長さ2万5千キュビト、幅2万キュビトである。祭司たちへの聖なる奉納地は次のとおりである。北側は2万5千キュビト、西側は1万キュビトの幅、東側は1万キュビトの幅、南側は2万5千キュビトの長さである。主の聖所はその中央にある。この区域はツァドクの子孫の聖別された祭司たちのものである。彼らは、イスラエル人が迷い出たときいっしょに迷い込んだレビ人とは異なり、わたしへの任務を果たしている。彼らの地域はレビの部族の地域に接し、奉納地のうちで最も聖なる地である。レビの部族の分は、祭司たちの地域に接して、長さ2万5千キュビト、幅1万キュビトである。すなわち、全体の長さは2万5千キュビト、幅は1万キュビトである。彼らはそのどの部分も、売ったり取り替えたりしてはならない。その初めの土地を手放してはならない。主への聖なるものだからである。幅5千キュビト、長さ2万5千キュビトの残りの地所は、町の一般用であり、住まいと放牧地のためである。町はその中央に建てられなければならない。その大きさは次のとおりである。北側は4500キュビト、南側は4500キュビト、東側は4500キュビト、西側は4500キュビトである。また、町の放牧地は、北へ250キュビト、南へ250キュビト、東へ250キュビト、西へ250キュビトである。聖なる奉納地に接する残りの地所の長さは、東へ1万キュビト、西へ1万キュビトである。それは聖なる奉納地に接している。そこから収穫した物は町の働き人の食物となる。その街の働き人は、イスラエルの全部族から出て、これを耕す。奉納地の全体は2万5千キュビト四方であり、あなたがたは、聖なる奉納地と町の所有地とをささげることになる。聖なる奉納地と町の所有地の両側にある残りの地所は、君主のものである。これは2万5千キュビトの奉納地に面し、そこから東の境界までである。西のほうも、その2万5千キュビトに面し、そこから西の境界までである。これは部族の割り当て地にも接していて、君主のものである。聖なる奉納地と宮の聖所とは、その中央にある。君主の所有する地区の中にあるレビ人の所有地と、町の所有地を除いて、ユダの地域とベニヤミンの地域との間にある部分は、君主のものである。なお、残りの部族は、東側から西側までがベニヤミンの分。ベニヤミンの地域に接して、東側から西側までがシメオンの分。シメオンの地域に接して、東側から西側までがイッサカルの分。イッサカルの地域に接して、東側から西側までがゼブルンの分。ゼブルンの地域に接して、東側から西側までがガドの分。ガドの地域に接して、その南の境界線はタマルからメリバテ・カデシュの水、さらに川に沿って大海に至る。以上が、あなたがたがイスラエルの部族ごとに、くじで相続地として分ける土地であり、以上が彼らの割り当て地である。―神である主の御告げ。―町の出口は次のとおりである。北側は4500キュビトの長さで、町の門にはイスラエルの部族の名がつけられている。北側の3つの門はルベンの門、ユダの門、レビの門である。東側も4500キュビトで、3つの門がある。ヨセフの門、ベニヤミンの門、ダンの門である。南側も4500キュビトの長さで、3つの門がある。シメオンの門、イッサカルの門、ゼブルンの門である。西側も4500キュビトで、3つの門がある。ガドの門、アシェルの門、ナフタリの門である。町の周囲は1万8千キュビトあり、その日からこの町の名は、『主はここにおられる。』と呼ばれる。」』
エゼキエル書の最後の部分では、ユダヤの諸部族に割り当てられる相続地について言われている。これは、つまり天国の聖徒たちはおのおの自分の所有地を持つ、ということである。キリストは、天国には住まいが多くあると言われた(ヨハネ14:2)。これは、天国で聖徒たちがそれぞれ自分の地を持てるようになることを示している。何故なら、住まいとは地面の上に建てられるものだからである。天は共産主義の世界であると考える者たちは、思い違いをしている。たとえ彼らが使徒行伝の箇所を根拠として提示したとしても無駄である。聖書は、明らかに天国に私有財産があると教えているからだ。それは、つい先ほど言及したヨハネ福音書の箇所がそうである。また、キリストが『朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。』(ルカ12章33節)と言われたのも、そうである。この御言葉は、天国で報いとして私有財産が与えられることを示しているのだから。
先に私は、エゼキエル書40~48章では第二神殿について預言されているのではないということを後ほど説明すると約束した。その約束を今ここで果たすことにしたい。それというのも、我々が今見ているこの箇所からは、40~48章が第二神殿について預言されているのではないことがよく分かるからである。この箇所では、ユダヤの諸部族に相続地が割り当てられる、と言われている。それは当然ながら10部族も含まれている。もし40~48章が第二神殿について預言された箇所だったとすれば、そこで書かれている通り、第二神殿が建設された際には10部族を含めたユダヤの諸部族に土地の割り当てがされてはずである。実際はどうであったか。歴史を見れば分かる通り、そのようなことは起こらなかった。何故なら、10部族はアッシリヤ捕囚の際に散らされてしまっており、第二神殿が建設された時にはほとんど確認できなかったからである。その時、10部族に土地を割り当てようにも割り当てることは出来なかった。10部族がどこかに行ってしまっているというのに、どうして10部族に土地を割り当てることができようか。よって、この40~48章は第二神殿について預言されているのではないということが分かる。先にも述べた通り、ここでは天国について預言されているのだ。それは黙示録との関わりから考えても分かる。何故なら、我々が今見ているエゼキエル書40~48章は、天国について預言されている黙示録21:1~22:5の箇所と対応しているからである。
第3部でも書いたが、この箇所は黙示録21:12~13と対応している。この2つの箇所を読み比べてみれば、両者が対応しているのは明らかである。両者の箇所における相違点については、既に第3部で書いたから、ここで再び説明する必要はない。この2つの箇所における対応についても、やはり既に述べられたのと同様のことが言える。すなわち、神はエゼキエルに示されたのと同じ内容の幻を、ヨハネに黙示録21:12~13でお与えになった。神は、どれだけエゼキエルに示されたのと同じことをヨハネにも示されたことであろうか。これは、ヨハネが神からエゼキエルのように重んじられていたことを意味している。そうでなければ、こんなにも多くエゼキエルに与えられたのと同様の預言をヨハネが受けることはなかったはずだからである。ヨハネはキリストの使徒として選ばれたぐらいであるから、神はエゼキエルでもあるかのようにヨハネを重んじられたのである。
第29章 27:ダニエル書
ダニエル書を研究しないことは許されない。再臨について最も学べる文書である黙示録の中で、最も対応している部分の多い聖書の巻の一つが、このダニエル書である。キリストも、この文書から『荒らす憎むべき者』(マタイ24章15節)について預言しておられる。この文書を研究しないのは、再臨が豊かに理解できるようになることを諦めるのも同然である。
【2:28】
『しかし、天に秘密をあらわすひとりの神がおられ、この方が終わりの日に起こることをネブカデネザル王に示されたのです。あなたの夢と、寝床であなたの頭に浮かんだ幻はこれです。』
ネブカデネザル2世には、夢の中である幻が示された。その幻は、夢という形態により与えられた神の預言であった。これはいわゆる「正夢」のことである。正夢とは、これから起こる出来事を事前に示す夢だから、預言として捉えても差し支えないものである。実際、ダニエル2:45の箇所では、この夢が『正夢』であったと言われている。この正夢を見たことのある人は、けっこういると思われる。今の世界を見ても、歴史を見ても、正夢を見たことについて話している人がけっこう見られるからだ。カエサルも自分が死ぬことの前兆としての夢を見た。私も正夢を見たことが今までに何度もある。とはいっても、多くの人の場合、この正夢を預言として理解することはほとんどないのではあるが。ネブカデネザル王に示されたこの夢による預言は、ダニエル書2章に書かれている。本書は再臨に関わる事柄を考究するための作品だから、当然ながら再臨に関わっていない部分は取り上げず、本書において註解するに相応しい部分だけを抽出して註解することにしたい。次は2節分を飛ばして2:13の箇所から註解が進められる。
このように夢を通して預言の幻が与えられた人は、他にも聖書の中で見られる。それは、創世記におけるヨセフとパロである。ヨセフの見た正夢は、誰も解き明かすことがなかった。パロの正夢はヨセフに解き明かされている。また後ほど詳しく見ていくが、このダニエル書を書いたダニエル自身も、このような正夢を2回も見ている。その1回目は7章目で、2回目は8章目で書かれている。
ネブカデネザル王に示されたこの夢は、ヨセフが神の恵みにより鮮やかに解き明かした。それは、ちょうどヨセフがパロの見た秘儀的な夢の解き明かしを鮮やかに成し遂げたかのようであった。ここで不信仰の徒は次のような冒瀆の思いを心に持つかもしれない。「このネブカデネザルの夢を解き明かしたダニエルの話は、創世記に書かれているパロの夢を解き明かしたヨセフの話に基づいて書かれた創作話であって、実際にはそのような出来事は起きていなかった。」私は、神の御前でこのような見解を非とし断罪する。というのも、このダニエル書は明らかに神の書かれた神聖な文書だからである。このダニエル書にはキリストもマタイ24:15の箇所で言及しておられるし、他の預言者の書の中でもダニエルは神的な人として取り扱われているのだ。神の文書であるということは、そこに不信を抱かせるようないかがわしい文章が何も書かれていないということを意味する。それだから、ダニエル書に対するこのような冒瀆の思いは間違っていると言わねばならない。神の文書に、どうして小説のような創作話があたかも実話であるかのように書かれているのであろうか。聖書を信仰の規準とするまともな聖徒たちは、このような言説に惑わされないように注意すべきであろう。
ネブカデネザル王に示された夢は『終わりの日に起こること』であった。この『終わりの日』とは、エルサレム神殿の崩壊と共に訪れるユダヤにおける終焉の日またその時期を指す。ここで次のような疑問を持つ方がいるかもしれない。すなわち、「どうして神はネブカデネザルという異邦人に対し、ユダヤの終わりに関する預言の幻をお示しになられたのだろうか。」と。これに対して私はこう答える。この預言の幻は、ネブカデネザルに示されたというよりは、むしろユダヤという神の民に示されたものである。神は、最初からネブカデネザルの見た幻をダニエルに解き明かさせることで、その解き明かされたことを御自身の民に知らせようとして、ネブカデネザルに夢の中で幻を見せられた。つまり、ネブカデネザルに幻が示された目的は、ユダヤに預言を与えることにあった。キュロス2世を通してユダヤが捕囚から解放されたことを考えても分かるように、神は異邦人を通して神の民に恩恵を施される、ということを躊躇せずに行なわれる御方である。異邦人であっても、神の道具として用いられるのであれば、御民に恩恵を与える存在と化すのだ。それだから、ユダヤに知らせることを目的とされた幻が、まずネブカデネザルに与えられたとしても何も問題ではない。それゆえ、もしこの幻がユダヤには知らされず、ただネブカデネザルにだけ知らされるということであれば、この幻がネブカデネザルに示されることは無かったはずである。何故なら、異邦人に過ぎないネブカデネザルにだけユダヤの終焉の時期に関する幻が示されたとしても、一体なんの意味があるだろうか。そのようにしても、ただネブカデネザルという異邦人だけがユダヤの終わりについて知るに過ぎないのだ。また、もう一度繰り返して言っておくが、この『終わりの日』という言葉をユダヤの終わりではなく地球全土の終わりであると捉えるならば、再臨と再臨に関わる出来事について、いつまでも理解できないままとなってしまう。聖徒たちは解釈を誤らないように、すなわち人間精神の感覚によってこの言葉の意味を軽々しく捉えたりしないように、よくよく注意していただきたい。
この『終わりの日に起こること』について示された幻は、再臨に大きな関わりを持っているから、再臨について考究する本書において、その『終わりの日』について示された幻をこれから見ていく。その箇所は2:31~45である。
【2:31】
『王さま。あなたは一つの大きな像をご覧になりました。見よ。その像は巨大で、その輝きは常ならず、それがあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。』
ダニエルは、ネブカデネザルの夢に出てきた幻を、ネブカデネザルの前でまざまざと示すことが出来た。ネブカデネザルは、ダニエルに直接的にであれ間接的にであれ、自分の見た夢を知らせたわけではない。むしろ、この王はダニエルにそのことを言わないでおいた。というのも、ネブカデネザルは知らされていないにもかかわらず夢の内容を告げることが出来るぐらいでなければ、その夢を解き明かすことなど到底出来はしない、と考えていたからである(ダニエル2:5~9)。これは普通に考えれば無茶な話であった。しかしダニエルは自分からネブカデネザルの夢を間違いなく示すことが出来た。それはダニエルが神にその夢を知らせて下さるようにと祈ったからである(ダニエル2:18~23)。神がその願いを聞き入れ、ダニエルにネブカデネザルの夢を知らせて下さったのだ。神がこのようなダニエルの願いを聞き入れて下さったのは、ダニエルが『神に愛されている人』(ダニエル10章19節)だからであった。人は、自分の愛する子どもが何かを願えば、それを与えてやるものである。神がダニエルの願いを聞いて下さったのは、それと同じことであった。
ネブカデネザルの見た夢の中では、一つの像の前がこの王の前に立っていた。この像は、その各部分が、上から順に歴史において現われる帝国を示している。すなわち、この像は歴史の流れを示しており、下に行けば行くほど歴史が進むのである。
この像についてはここで3つのことが言われている。まず、この像は『巨大で』あった。これは、この像において示されている帝国が、その支配領域において非常に大きかったことを示す。またこの像は非常な『輝き』を放っていた。これは帝国における国家としての栄光を言っている。そして、この像は『恐ろしいもの』であった。これは帝国が非常に強くて打ち勝ち難かったことを示している。
【2:32~33】
『その像は、頭は純金、胸と両腕とは銀、腹とももとは青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。』
ここでは4つの帝国が示されている。まず『純金』の『頭』はバビロンである。何故なら、ダニエルがバビロンのネブカデレザル王に対して、『あなたはあの金の頭です。』(ダニエル2章38節)と言っているからである。バビロンが金で示されたのは、バビロンが非常に繁栄していたからに他ならない。その繁栄は凄まじく、当時の人たちから世界の7不思議に数えられるほどであった。ネブカデレザル王も、バビロンの繁栄が物凄かったので、高ぶって次のような言葉を吐いたほどである。『この大バビロンは、私の権力によって、王の家とするために、また、私の威光を輝かすために、私が建てたものではないか。』(ダニエル4章30節)2番目の『銀』である『胸と両腕』はペルシャである。このペルシャは、繁栄していたが、しかしバビロンほどではなかった。だからバビロンが純金であるのに対し、ペルシャは銀で表示されている。3番目の『青銅』である『腹ともも』はギリシャである。何故なら、バビロン・ペルシャと来れば、次に続くのはギリシャしか考えられないからである。ギリシャが『青銅』だったのは、バビロンとペルシャよりも国としての輝きが劣っていたからに他ならない。青銅が金と銀よりも劣っていることを疑う人はおるまい。なお、後の箇所で再び見ることになるが、夜の幻で現われた第4の獣であるローマの『爪は青銅』(ダニエル7:19)であったのは、このギリシャに関わりがある。これは、つまりローマが、ギリシャという豹の持つ爪を使って国々という獲物を引き裂くという意味なのだ。実際、ローマはギリシャでもあるかのように諸国を巡り回って征服した。第4の『鉄』である『すね』は、これまでの順序から考えれば、間違いなくローマである。ローマが『鉄』で示されているのは、ダニエル2:40の箇所でも書かれているように『鉄のように強い』からであった。実際、ローマは鉄が何かを打ち砕くかのように、諸国を打ち砕いた。最後の足には、鉄と一緒に粘土が見られた。鉄はローマだが、粘土はユダヤを指している。これは、つまり、ユダヤがローマ帝国と共に有りながら、ローマに決して服属しようとしなかったことを示している。何故なら、ダニエル2:43の箇所で言われている通り、鉄と粘土は一緒に混じり合うことをしないからである。実際、ユダヤという粘土は、ローマという鉄と一体になるのを頑なに拒んでいた。それは、ちょうど粘土が鉄と一緒になるのを拒んでいるかのようであった。ローマはユダヤを自分と一体化させようと頻りに奮闘するのだが、ユダヤは粘土であるから、鉄であるローマに吸収されることなど出来なかったのである。なお、このユダヤだけは例外的に帝国ではない。
ところで、これらの国が、人間の像において有機的に示されたのは何故だったのか。それは、これらの国が、どれも、人間の像が打ち砕かれるかのようにして打ち砕かれるからであった。人間の像が打ち砕かれる時、それは大きな音を出しながら勢いよく崩れ去ってしまう。これら4つの国、5つの国が打ち砕かれるのも、そのようであった。それだから、ここでこれらの国が人間の像において示されているのは実に適切であった。この表現は非常に分かりやすいのだ。神が、他でもないこの神が、このような表現を選ばれたのだ。それなのに、その表現に異を唱えたり疑問に感じたりすることがあってもよいものであろうか。この表現が気に入らない人は、霊感が鈍いと言わざるを得ない。
【2:34】
『あなたが見ておられるうちに、一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。』
これは、『一つの石』であるイエス・キリストが現われ、鉄であるローマと粘土であるユダヤを打ち砕かれた、ということである。確かにキリストが現われたのは、ローマとユダヤがあたかも鉄と粘土でもあるかのように混ざり合えないでいた、あまり穏やかではない時代であった。それは金や銀や青銅の時代ではなかった。
ここではキリストが2つの国を打ち砕かれると言われているが、「打つ」とは、すなわち「滅ぼす」という意味である。実際、粘土であるユダヤはキリストにより滅ぼされた。ユダヤはキリストという石を退けたので、怒りを燃え上がらせた神の裁きにより容赦なく滅ぼされてしまった。それは紀元70年9月に起きたことである。同様に鉄であるローマもキリストにより滅ぼされた。すなわち、ローマ帝国は、キリストの建てられた宗教であるキリスト教により滅ぼされてしまった。この理解は、ギボンやモンテスキューやサドやヒトラーなどといった人たちが持っていた理解であり、それは間違っていない(※)。今述べられた理解、すなわちローマとユダヤはキリストにより打ち砕かれたという理解を受け入れない人は、教会の中でも受け入れられない。何故なら、教会とは聖書に立つ人たちの霊的な集まりだからである。その聖書が、このダニエル書2:34の箇所において、ローマとユダヤが打ち砕かれた原因はイエス・キリストであったと教えているのだ。だから、そのように理解しない人は、教会に相応しくないと言わねばならないのである。
(※)
サドの場合、こう言っている。「ローマ帝国は、キリスト教が布教を始めるや滅んだ。キリスト教を畏敬するかぎり、フランスもまた滅びることになる。」(『閨房の哲学』第5の対話 p198:講談社学術文庫)
[本文に戻る]
このキリストという石によりローマとユダヤが打ち砕かれたのは、神によった。神がそのようになるのを望まれたのである。つまり、それは自然に起きたことでは無かった。もしそのようになるのを神が望まれなかったとすれば、このようなことは起きていなかったであろう。その場合、ローマとユダヤは別の方法により滅ぼされていたか、そうでなければ、そもそもこの2つの国が滅ぼされるということはなかったはずである。我々は、神の御計画と働きについて、深く心を傾けるべきである。この世においては、神の御計画と働きかけなくしては、何一つしとして起こりはしないのだ。ローマとユダヤの滅びにおいても、それは例外では無かった。
【2:35】
『そのとき、鉄も粘土も青銅も銀も金もみな共に砕けて、夏の麦打ち場のもみがらのようになり、風がそれを吹き払って、あとかたもなくなりました。そして、その像を打った石は大きな山となって全土に満ちました。』
ここでは、イエス・キリストという石が、これらの国を表示する人間の像を打ち砕かれ、全世界に満ち広がるようになる、ということが言われている。キリストという石が『大きな山となって全土に満ち』たと言われているのは、つまりキリストの御国が世界中に拡大されるという意味である。実際、キリストが現われた紀元1世紀に、そのことが実現された。パウロはコロサイ1:6の箇所でこう言っている。『この福音は、あなたがたが神の恵みを聞き、それをほんとうに理解したとき以来、あなたがたの間でも見られるとおりの勢いをもって、世界中で、実を結び広がり続けています。』マルコも「別の追加文」の中でこう言っている。『その後、イエスご自身、彼らによって、きよく、朽ちることのない、永遠の救いのおとずれを、東の果てから、西の果てまで送り届けられた。』キリストという石が大きな山として全世界に拡がったのは、福音の伝道によった。神は、聖徒たちが福音を宣べ伝えるようにと命じられた。聖徒たちは、その命令を大いに実践した。そのようにして、ここで言われている『その像を打った石は大きな山となって全土に満ちました。』という御言葉が成就したのである。
ここで次のような疑問を持たれる方がいるかもしれない。「キリストが鉄と粘土を打ち砕かれたのは分かるが、青銅と銀と金も打ち砕かれたというのは一体どういうわけなのか。キリストは鉄と粘土の時代にはおられたが、青銅と銀と金の時代にはまだこの世におられなかったはずである。」確かにキリストがこの世におられた時代は、鉄と粘土すなわちローマとユダヤの時代であって、まだ青銅と銀と金すなわちギリシャとペルシャとバビロンの時代には来ておられなかった。だから、ここでこれら3つの国をもキリストが打ち砕かれたと書かれているのを読んで、疑問に思った人がいたとしても無理はないかもしれない。しかし、御言葉に偽りはない。ここで書かれている通り、キリストは鉄と粘土だけでなく青銅と銀と金も打ち砕かれたと言うことが出来る。それは何故なのか。それはキリストがローマを打ち砕かれたからである。このローマは、バビロンを打ち砕いたペルシャを打ち砕いたギリシャを打ち砕いた存在である。だから、このローマを打ち砕くことは、ローマだけではなく、そのローマが打ち砕いだギリシャと、そのギリシャが打ち砕いたペルシャと、そのペルシャが打ち砕いたバビロンをも同時に打ち砕いたことになるのだ。例えば、他の多くのボクサーに打ち勝ったチャンピオンのボクサーに打ち勝ったボクサーがいたとすれば、そのボクサーがチャンピオンに打ち勝つことで、そのチャンピオンがそれまでに打ち負かした多くのボクサーをも同時に打ち負かしたと言うことが出来る。何故なら、チャンピオンに打ち勝てば、自然とそのチャンピオンが打ち負かした多くのボクサーよりも強いということが証明されるからである。つまり、実際的には打ち負かしていないのだが、事実上は打ち負かしたも同然なのである。それと同じで、ローマという諸国のチャンピオンを打ち砕いたキリストは、ローマを打ち砕くことで、ローマにより打ち砕かれた国がそれまでに打ち砕いた国をも打ち砕いたと言うことが出来るのだ。それだから、ここでキリストが4つの帝国・5つの国を打ち砕かれたと言われていたとしても何も問題ではない。
【2:36】
『これがその夢でした。私たちはその解き明かしを王さまの前に申し上げましょう。』
これが、ダニエルの示したネブカデレザルの見た夢であった。先にも述べたように、神がダニエルに示されたからこそ、ダニエルはこのようにしてネブカデレザルに夢の内容を示すことが出来た。しかし、神がダニエルにその夢を示されたのは、どのようにしてであったのか。例えば、ネブカデレザルが側近の一人に夢のことを話しているのをダニエルが隠れた場所で密かに聞いた、という方法で神はその夢をダニエルに示されたのか。そうではない。このように考えるのは間違っている。ダニエルに夢が示されたのは、ダニエル2:19の箇所で書かれているように、『夜の幻のうちに』啓示として示されたのであった。つまり、ダニエルは超自然的な方法でネブカデレザルの夢を知った。不可能のない神は、人知を超えた不思議な方法で、その夢をダニエルに教えて下さったのである。
これからダニエルは夢の解き明かしに取り掛かった。この解き明かしも当然ながら神の恵みによった。ダニエル自身も言っているように、ダニエルが他のどの人よりも知恵深かったので、この秘密がダニエルに現わされたというのではなかった(ダニエル2:30)。―全ての良きことは神にこそ帰されなばならない。―なお、この夢の解き明かしについては、既にその大部分がこれまでの註解において説明されてしまっているから、冗長になるのを避けるため、出来るだけ簡潔に済ますことを心がけたい。
【2:37~38】
『王の王である王さま。天の神はあなたに国と権威と力と光栄とを賜い、また人の子ら、野の獣、空の鳥がどこに住んでいても、これをことごとく治めるようにあなたの手に与えられました。』
ネブカデネザルは『王の王である王さま。』であった。彼は「世界の王」と呼ばれた。それは、彼が諸国を支配するバビロンの王だったからである。同じく世界帝国であったペルシャのキュロス2世やダリウス1世も、このように呼ばれた。西暦21世紀の今において、このように呼ばれている支配者は存在していない。このような名称に最も近いのは、イギリスの女王である。イギリスの女王は、今でもカナダやオーストラリアをはじめとした多くの国の主君であるから。
この大王ネブカデネザルには、神が『国と権威と力と光栄とを賜』わった。それは神から与えられた賜物であって、ネブカデネザルが自分の力により獲得したのではない。『国』とはバビロン帝国を指す。これは非常に大きな帝国であった。『権威』とは、バビロン帝国における王としての権威である。これも絶大な度合いであった。『力』とは、王として諸事物を好きなように統御できる自由性のことである。実際、この王には多くの事物を思いのままに取り扱うことの出来る力が与えられていた。『光栄』とは、王としての栄光のことである。これもまた非常に凄まじかった。その光栄の度合いは、恐らくルイ14世と同等か、またはそれ以上であったと思われる。
またこのネブカデネザルには、神が万物を支配するようにと、それを彼の手に委ねておられた。実際、ネブカデネザルはそのようにした。彼は万物を支配しており、彼に逆らえる者は誰一人としていなかった。このような支配権をネブカデネザルが持てたのは、ただ神の恵みによる。神が、他でもない神が、ネブカデネザルに万物を支配させることを望まれたのだ。だからこそ、この時のバビロン帝国ではネブカデネザルが諸物を治めていたのである。もし彼が神の御心では無かったのならば、他の人物がバビロン帝国を治めていたことであろう。
ここで次のような疑問を持つ方がおられるかもしれない。「神はどうして御自身の聖なる民ユダヤを差し置いて、異邦人に過ぎないネブカデネザルに世界の覇権をお与えになったのか。これは親が自分の相続財産を、自分の子どもではなく、他人の子どもに与えるのも同然ではないのか。」これは簡単である。この時のユダヤは堕落しており、神の恵みを受けるに相応しい状態には無かったのである。ただこれだけである。それだから、もしユダヤが神に喜ばれる状態にあれば、バビロンのネブカデレザルに覇権が与えられてはおらず、ユダヤにこそ覇権が与えられていたことであろう。ちょうど周りの諸国を支配していたダビデとソロモンの時のイスラエル王国のように。また、神がユダヤを差し置いて異邦人に覇権を握らせたのは、ユダヤに自分たちが祝福を受けられない惨めな状態であることを悟らせ、神の御前に大いに反省できるようになるためであった。「ああ、我々がかつてのように諸国を凌駕できなくなっているのは我々の罪が原因なのだ…。」と。要するに、ユダヤを差し置いてネブカデネザルに世界の覇権が与えられていたことは、ユダヤにとって懲らしめの意味があった。
『あなたはあの金の頭です。』
ネブカデネザルとそのバビロン帝国は、最も上にある『金の頭』であった。これについては既に説明されている。なお、このように言われたネブカデネザル王は、悪い気はしなかったであろう。何故なら、この王は栄光と繁栄と権勢を重視し好んでいたのだから。
【2:39】
『あなたの後に、あなたより劣るもう一つの国が起こります。次に青銅の第三の国が起こって、全土を治めるようになります。』
第2の帝国はキュロス2世のペルシャであった。これはバビロンよりも劣っていた。なお、この第2番目のペルシャのことも、ネブカデネザル王にとっては悪い気のすることではなかったはずである。何故なら、第2の国よりも自分のほうが格上であると聞かされたのだから。
第3の帝国は青銅のギリシャである。このギリシャは先の2つの国よりも劣っている。何故なら、バビロンが金・ペルシャが銀であるのに対し、ギリシャは青銅に過ぎなかったからである。このギリシャは、紀元前330年に銀のペルシャを打ち砕いて『全土を治めるように』なった。これは一般的に「アレクサンドロス帝国」と言われている。
【2:40】
『第4の国は鉄のように強い国です。鉄はすべてのものを打ち砕いて粉々にするからです。その国は鉄が打ち砕くように、先の国々を粉々に打ち砕いてしまいます。』
4番目の帝国はローマである。ローマは『鉄のように強い国』であった。実際、ローマは「最強」などと言われたものである。
このローマは『先の国々を粉々に打ち砕いてしま』った。つまり、ギリシャもペルシャもバビロンも滅ぼしてしまった。しかし実際の歴史を見ると、ローマが打ち砕いたのはギリシャだけである。ペルシャはギリシャが、バビロンはペルシャが打ち砕いた。この2つの帝国を打ち砕いたのはローマではない。それにももかわらず、ここではローマがこの2つの帝国をも打ち砕いたと言われている。これは一体どういうわけなのか。これは、先の箇所でキリストがローマもギリシャもペルシャもバビロンも打ち砕かれたと言われていたのと同じである。ローマがギリシャを打ち砕いたのは確かである。そのギリシャは、バビロンを打ち砕いたペルシャを打ち砕いた。だから、ローマがギリシャを打ち砕いたのは、ギリシャを打ち砕いたのと同時にペルシャとバビロンをも打ち砕いたことになるのだ。よって、ここでローマがギリシャだけでなくペルシャもバビロンも打ち砕いたと言われているのは、何もおかしくはない。
ここでは鉄が全てのものを打ち砕くと言われているが、これは科学的には正確でない。鉄は確かにほとんど全ての物質を打ち砕くが、ダイヤモンドは打ち砕けないからである。ダイヤモンドは最強の物質であり、鉄がダイヤモンドを打ち砕こうとしても、逆に打ち砕かれてしまう。それではどうなのか。聖書には偽りが書かれているとでもいうのか。否、決してそのようなことはない。何故なら、ここでは科学的なことが言われているのではなく、ただ一般的なことが言われているに過ぎないからだ。この箇所が科学的な事柄を説明する個所でないことぐらい誰でも分かるはずである。我々も、実際の現象とは違っているのにもかかわらず、「太陽が上って来た。」などと普通に口にするが、それが科学的に正確な言説ではないからといって、問題にすることはしない。もし太陽について問題にしないのであれば、この箇所で言われている事柄についても同じように問題にすべきではない。なお、ダニエルの時代においては、今の時代とは違って、まだダイヤモンドが一般的には知られていなかった、ということも考慮すべきである。当時にあってダイヤモンドの存在を知っているのは一握りの人に限られていた。ダニエルもダイヤモンドを知っていたかどうか定かではない。
【2:41~43】
『あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国のことです。その国には鉄の強さがあるでしょうが、あなたがご覧になったように、その鉄はどろどろの粘土と混じり合っているのです。その足の指が一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部が強く、一部はもろいでしょう。鉄とどろどろの粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、それらは人間の種によって、互いに混じり合うでしょう。しかし鉄が粘土と混じり合わないように、それらが互いに団結することはありません。』
最後の部位には、鉄であるローマと一緒に粘土であるユダヤが見られた。
このローマは先に見たように鉄のように強かったが、その支配領域のうちにはユダヤという粘土を抱え持っていた。つまり、ローマはユダヤを属国として抱えていた。
この2つの国のうち、ローマは強かったが、ユダヤは脆い存在であった。それは正に鉄と粘土のようであった。ローマは鉄のようにどのような存在にも打ち負かされないのだが、ユダヤは粘土のように少しでも突かれたら即座にぶよぶよと揺らいでしまうのである。
このローマとユダヤは、ここでダニエルが言っている通り、同じローマ帝国という領域の中に一緒になって住んではいたが、しかし決して同体化することはなかった。それは鉄と粘土が一緒になっているのだが同一化していないのと同じであった。ローマという鉄は頻りに「粘土であるユダヤは私たちと一つになりなさい。」と言うのだが、ユダヤという粘土は「いや、そんなことは絶対にできないことだ。」と言って抵抗してばかりいたのである。
ところで、ローマとユダヤよりも下に何も無かったのはどうしてなのか、すなわちどうしてこの像の最も下の部位はローマとユダヤだったのか。それは、このローマとユダヤの時代に起こる出来事を、ここでは示そうとしているからである。それはその時代にキリストが退けられて御国が打ち立てられるようになる、という出来事である。ローマとユダヤの時代よりも先の時代まで進んでしまえば、このことを示すのは難しくなるか出来なくなる。だから、ここでは像の最も下の部位がローマとユダヤなのである。それゆえ、もしここでローマとユダヤの時代よりも先の時代に起こることを示すのが目的とされていたのであれば、この像の足とその指の部分では他の国が表示されていたはずである。例えば、ここで20世紀におけるアメリカとロシアを表示することが目的だったとすれば、この像の足の部分はプラチナと鋼鉄になっていたはずである。
また、これはトマスが興味を示しそうな問題であるが、この像の足における鉄と粘土の比率はどのようであったのか。これは何も書かれていないから分からないが、些細な問題であるから、たとえ分からなかったとしても問題にはならない。どうしてもこのことを知りたいと願う人がいれば、その人はローマ鉄が8割、ユダヤ粘土が2割だったと考えればよい。何故なら、この時代の情勢を考えれば、このぐらいの比率だったと考えるのが相応しいと思われるからである。この比率をローマが9割、ユダヤが1割だったと考える人がいても、私は否定したり批判したりしようとは思わない。いずれにせよ、我々はこんな比率の問題に頭の力を費やすべきではない。
【2:44】
『この王たちの時代に、天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて、絶滅してしまいます。しかし、この国は永遠に立ち続けます。』
神は『一つの国を起こされ』た。それは天上の国であって、地上の国ではない。また、それは霊の国であって、肉の国ではない。これは一般的に言われる「天国」のことである。
この天国はいつ起こされたのか。それは『この王たちの時代に』である。すなわち、この夢に出てきた人間の像において示されている帝国が存在している時代において、である。この言い方は、全体的・俯瞰的な言い方であって、詳しい時期には言及されていない。しかし、それは具体的にはいつだったのか。それはキリストが紀元68年に再臨されてから42か月の支配が終わってからであり、紀元70年9月である。何故なら、天の御国は、キリストが再臨されると起こされることになっていたからである。キリストはマタイ16:28の箇所でこう言われた。『まことに、あなたがたに告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が御国とともに来るのを見るまでは、決して死を味わわない人々がいます。』つまり、キリストの再臨と御国の到来は相互に関連しているのであって、キリストの再臨が起こると御国も天上において実現されることになるのだが、再臨が起こらない限り御国が始まることはないのである。今の時代の聖徒たちの中には、まだこの天国が起こされていないと思っている人がいるかもしれない。その人たちは、聖書の理解と研究が大いに不足しており、それゆえまだ天国が起きていないと思っている。そのような人はよく考え、よく学ぶようにしていただきたいものである。
天国は『永遠に滅ぼされることがな』い。何故なら、そこはキリストという王が治めておられる場所だからである。キリストが統治しておられる国を、誰が滅ぼすことなど出来ようか。たとえサタンが1000万人に分身したとしても、この天国を滅ぼすことは出来ない。聖書が教えている通り、キリストという神は力の強い御方なのであるから。また、その国は『他の民に渡され』ることがない。何故なら、聖徒でない国民は、そこに入ることさえ出来ないからである。入ることさえ不可能な国を、どうして奪い取ることが出来るであろうか。このように、天上の王国とは、この地上の王国とはまったく異なっている。この地上の王国の場合、滅ぼされたり奪い取られてしまう運命から逃れ得ないものである。
また、この天国に人を導き入れる聖なる宗教は、どのような存在によっても打ち砕かれず、かえって打ち砕こうとした存在を打ち砕いてしまう。今まで、どれだけ多くの国や民族や勢力がこのキリスト教を打ち砕こうとしたことか。ローマはキリスト教を憎んで大いに絶滅しようとした。しかし逆に、ローマは自分たちが絶滅しようとしていた宗教に滅ぼされてしまったのだ。またアメリカの先住民族であるインディアンはソドミーで頑なだったので、建国の父たちの信仰を決して受け入れようとはしなかった。このインディアンは、聖なる理念を退けた結果、自分たちにその理念を宣べ伝えた人たちに呑み込まれてしまった。また日本の江戸幕府はキリスト教を弾圧し、キリスト教徒たちを迫害し苦しめた。江戸幕府が危険視したこのキリスト教は日本において滅びることが無かったが、江戸幕府のほうは最終的に滅びて無くなってしまった。これからも聖なる宗教は敵視され滅ぼされようとするであろう。しかし、ここで言われているように、キリスト教は滅ぼされないで、かえって滅ぼそうとした者たちが滅ぼされてしまうのである。何故なら、そのようになるのが神の定めであり運命なのだから。
要するに、ここでは地上の王国と対比しつつ天上の王国が語られており、そうすることで天国が高められて推奨されている。この箇所では次のように言われているかのようである。「この地上の王国はどれだけ強大で繁栄していたとしても、結局は滅ぼされたり誰かに渡されたりしてしまう。そこに永遠性はない。しかし、天上の王国はそうではない。その国は滅ぼされたり誰かの手に奪われたりすることが決してない。天国とはこんなにも素晴らしいのである。だから、聖徒たちはこの国のことを心に留め、そこに入れるようになるのを希求すべきなのである。」なお、このように対比しつつ天上の国が語られているのは、また後ほど見ることになるダニエル7:17~18の箇所でも同じである。
【2:45】
『あなたがご覧になったとおり、一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神が、これから後に起こることを王に知らされたのです。』
先にも述べたように、この夢がネブカデネザルに示されたのは、ネブカデネザルに益が与えられるためであった。すなわち、この夢が示されたのは、ネブカデネザルが神を崇め、恐れ、より神に対して謙遜になるためであった。神は、この夢を通してネブカデネザルに良くして下さったのである。しかし、それではどうなのか。この王はユダヤの民と同じように救われるようにと定められていたのか。これについては分からないとしか言えない。確かにネブカデネザルはユダヤの神すなわち天地万物を造られた唯一の神を崇め、賛美し、恐れ、その御前に高ぶることをしなかった。だが、その一方で、ネブカデネザルは他の神々をも信じており、偶像を崇拝していた。聖書が明確に教えるように、他の神々を信じるのは大罪であり(出エジプト20:3)、偶像崇拝をする者が天国を相続することは決してない(Ⅰコリント6:9~10、黙示録21:8、22:15)。それだから、ネブカデネザルは真の神を崇めてはいたものの、地獄の子だったと考えるのが正しいのかもしれない。つまり、この王はサタンの子でありながら、真の神を信じて崇めていたということである。これは、ちょうどアレイスター・クロウリーというサタンの子が、滅びるべきサタンの子でありながら、イエス・キリストを<我らの主><救い主>などと大胆に言っていたのと同じである(「愛の書」)。
また、この夢がネブカデネザルに示されたのは、聖徒たちの益のためでもあった。すなわち、ダニエルがこの夢を解き明かし、その解き明かしを聖徒たちが知ることで、霊的な知識を増し加えるためであった。そのようにして聖徒たちは、ますます神に対する愛と信頼を深めるのである。この夢のことから、我々は、神が一つの行ないで複数の目的を実現させる御方であるということを知るべきである。神は、往々にして、幾つかの目的を成し遂げるために一つの行ないを為される。つまり、一つの行ないに複数の目的を組み込ませる。この夢の場合もそうであった。キリストの贖罪も同様である。この贖いには幾つかの目的があり、それは「神の栄光が褒めたたえられるようになるため」「選ばれていた者たちが救われるようになるため」「万物が神と和解するようになるため」「サタンとユダの罪深さが発露されるようになるため」「滅びに定められている者たちが贖いに躓くことで滅びるようになるため」などといった目的であった。神はこのように一つのことで複数の目的を達成されるので、矮小な理性を持つ我々人間にとって、神の御業は非常に測り知りがたい。それは我々にとっては超越的なのだ。だからこそ、ソロモンは神の霊により次のように言ったのである。『そのように、あなたはいっさいを行なわれる神のみわざを知らない。』(伝道者の書11章3節)『人は日の下で行なわれるみわざを見きわめることはできない。』(同8章17節)『人は、神が行なわれるみわざを、初めから終わりまで見きわめることができない。』(同3章11節)人がこのような神の御業を見極めるのは、もしそれが出来たとすれば、顔に付いている両の目で360度のパノラマ写真のように一挙に東西南北の全ての方角を見渡すようなものである。そんなことは出来っこないのである。
『その夢は正夢であり、その解き明かしも確かです。」』
ネブカデネザルの見たこの夢は『正夢』であった。実際、この夢は実現している。神が、ネブカデネザルの見た夢の中で、これから後に起こることを預言されたのである。ネブカデネザルの見た正夢以外の正夢も、みな例外なく預言である。我々は、正夢という夢が、神の預言として与えられるものだということを心に留めるべきである。神がその夢において未来のことを預言されるのでなければ、そもそも正夢など見るはずがないのである。正夢における驚異性を考えれば、その夢をフロイトの言うところの「無意識の現われ」や「性的な願望またはコンプレックスの表出」として捉えることは出来ない。
この夢の解き明かしは『確か』であった。ダニエルは、このように確信しつつ言うことが出来た。何故なら、この夢の意味は、神が示して下さったからこそダニエルに知られることになったからである。この夢の解き明かしを聞かされたネブカデネザルは、戦慄するほどに驚き、また感動したに違いないと私は思う。夢を知らせていないにもかかわらず示され、その解き明かしまで示される、などという驚異的なことが他にあるであろうか。実際、この夢とその解き明かしを示されたネブカデネザルは、この後、ダニエルの前に平伏し、ダニエルに多くの恵みを施している(ダニエル2:46~49)。
【7:1】
『バビロンの王ベルシャツァルの元年に、ダニエルは寝床で、一つの夢、頭に浮かんだ幻を見て、その夢を書きしるし、そのあらましを語った。』
ここに出てくる『ベルシャツァル』の治世は、紀元前555~539年であったとされる。つまり、ダニエルがここで言っている『元年』とは紀元前555年である。この王について、我々は3つの点について注意せねばならない。まず第一は、一般的にこの王は自分で王と名乗ったことはないと言われている点である。しかし、ダニエル書では、明らかにベルシャツァルが『王』として取り扱われている。だから、ベルシャツァルは明白な王であって、自分自身でも王と名乗っていたと考えるべきである。第二は、一般的にこのベルシャツァルは新バビロニア王国の最後の王だったと言われているという点である。しかし、聖書はベルシャツァルの次にも新バビロニアには王がいたと述べている。ダニエル書5:30~31ではこう書かれている。『その夜、カルデヤ人の王ベルシャツァルは殺され、メディヤ人ダリヨスが、およそ62歳でその国を受け継いだ。』それだから、ベルシャツァルが新バビロニアの最後の王だったと考えることはできない。第三は、一般的にこのベルシャツァルはナボニドゥスの子だったと言われているという点である。しかし聖書は、ベルシャツァルがナボニドゥスの子ではなく、ネブカデレザル2世の子だったと言っている。これは明白である(ダニエル書5:18、22)。一般的な見解よりも、ダニエルの言っている言葉のほうを正しいとすべきであるのは言うまでもない。それだから、我々はベルシャツァルがネブカデレザル2世の子だったと捉えなければならない。今までの歴史が示すように、単なる学問としての史実は往々にして誤るが、聖書には誤りがないのである。聖書に書かれていたことが新たな考古学的発見により正しいと認められた、ということが今までどれだけあったことか!聖書よりも考古学のほうを優先させる自由主義神学は消え去れ!最近ではナボニドゥスの書いたものとされる円筒型碑文が発掘され、そこではナボニドゥスがベルシャツァルを自分の息子として取り扱っている文章が見られるが(※①)、これはあの有名なディオニシウス文書と同様に巧妙に偽造されたものだと考えるべきである。つまり、古代の誰かがフザけてか、または人々を惑わそうとして、あのようなものを造ったのである。この円筒型碑文の内容は明らかに聖書の記述に反しているのだから、聖書信仰を持つまともなクリスチャンは、このように考えなければならない。(※②)このベルシャツァル王が大宴会の後に殺されてしまったあの出来事については、ここで詳しく説明すべきではない。何故なら、あの出来事を語ると、この第4部の内容の筋から大きく逸れてしまうからである。
(※①)
「私ナボニドゥス、バビロンの王について、その神性に対する罪から我を救い給いますように。私に永きにわたる人生を贈り物として授け給いますように。そしてベルシャザル、私の一番上の息子については、あなたの偉大な神性への畏敬の念を彼の心に注ぎ給いますように。そして彼が宗教的な過ちを犯しませんように。彼が豊かな人生で満たされますように。」(ウル出土のナボニドゥスの円筒形碑文―ポール・アレン・ボーリューによる翻訳)
[本文に戻る]
(※②)
近代におけるユダヤの陰謀家が働いている可能性も排除すべきではない。マイケル・ジャクソンも言っていたが、陰謀家たちは、歴史を改竄して人々が正しい歴史認識を持てないようにしている。陰謀家であるユダヤ人は、人々から聖書の正しい理解をなるべく遠ざけたいと思っている。何故なら、そこには真実なことが書かれているのを知っているからである。彼らが間違いであることを知っていながら進化論を世に撒き散らしているのも、聖書の正しい歴史認識を人々に持たせたくないからである。「豚どもには汚らわしい偽りの認識こそが相応しい。」というわけである。それだから近代になって発掘された古代の文書や碑文などは、陰謀家であるユダヤ人の手にかかっていないかよく注意する必要がある。現代の発達した技術力を持ってすれば、古代に造られたかのように感じられる文書や碑文を偽造することなど容易いのだ。サタンだったら、人々が聖書を信じないようにさせたいのだから、こういうことをある者たちにやらせるに決まっているではないか。
[本文に戻る]
ダニエルは夢の中で、非常に特徴的な幻を見た。それは夢である幻であった。これは神がダニエルに与えられた啓示である。ダニエルはその啓示を文章にして記したが、それはダニエル書7:1~28の箇所に書かれている。なお、この箇所ではヘブル特有の二重表現が使われている。ダニエルに啓示が与えられたことについては、『一つの夢』という部分が一度目であり、『頭に浮かんだ幻』という部分が繰り返しの2度目である。ダニエルがこの啓示を記したことについては、『その夢を書きしるし』という部分が一度目であり、『そのあらましを語った。』という部分が繰り返しの2度目である。
神が、ダニエルにこのような幻を示されたのは何故だったのか。それは、聖徒たちに未来に起こることを予め知らせるためであった。アモスはこう言っている。『まことに、神である主は、そのはかりごとを、ご自分のしもべ、預言者たちに示さないでは、何事もなさらない。』(アモス3章7節)神は、寛大な御方であるから、やがて起こるべき出来事を、事前に聖徒たちに知らせておこうと思われた。だから、ダニエルという『しもべ、預言者』に預言としての幻を与え、このダニエルがそれを書き記すようにされたのである。このゆえに、古代ユダヤ人たちは、他の民族とは違い、未来に起こる事柄を知ることが出来ていた。これは非常に感謝すべきことであったと言えよう。
【7:2~3】
『ダニエルは言った。「私が夜、幻を見ていると、突然、天の四方の風が大海をかき立て、4頭の大きな獣が海から上がって来た。その4頭はそれぞれ異なっていた。』
この『4頭の大きな獣』とは、強大な力を持った大帝国を示している。大帝国が獣として表示されているのは何故か。それは大帝国という存在が、獣のように貪欲で獰猛で強いからである。獅子や熊や豹がいれば、サムソンやゴリアテのような男でもない限り、誰でも恐れるはずである。これらの大帝国もそのような獣のごとき存在であった。この獣が『大き』いと言われているのは、これらの大帝国がその領土において非常に大きかったからである。
それではこの4頭の獣が『海から上がって来た』のは何故なのか。これは、これらの大帝国が異邦人の国だったことを示す。聖書では、既に述べたように、異邦人が海として表示されている。その海から獣が上って来たのだから、獣である大帝国は異邦人の国だったことになるのである。実際、これらの大帝国はどれも異邦人の国であって、ユダヤ人の国ではなかった。なお、黙示録13章に出てくる第一の獣も『海から』(13章1節)上って来たと書かれているが、これもこの第一の獣であるローマが異邦人の国だったからである。
では『天の四方の風が大海をかき立て』と書かれているのは、どういう意味か。聖書において『天の四方』とは全世界を意味している。何故なら、それは東西南北だからである。その全世界を意味している天の四方の風により掻き立てられた海から獣が上がって来たのであるが、これはこの獣たちが全世界を支配していたことを示す。実際、当時の狭かった世界観に基づいて言えば、これら4つの大帝国は全世界を支配していたと言ってよい。もちろん、今現在の世界観からすれば、この4つの大帝国と言えども全世界を支配していたとは言えないのだが、ここでは当時の状況を今現在の世界観によって解釈すべきではないのだから、この4つの大帝国が全世界を支配していたということを聞いて、ああだこうだと愚かにも文句を言い立てるべきではない。つまり、我々はこの当時における古代的な世界観を弁えつつ、ここで言われている事柄を把握すべきなのである。今現在の世界観に基づいて古代に書かれた聖書の記述を捉えようとしても、上手に捉えることは出来ないであろう。
【7:4】
『第一のものは獅子のようで、鷲の翼をつけていた。見ていると、その翼は抜き取られ、地から起こされ、人間のように2本の足で立たされて、人間の心が与えられた。』
この第一の獣は、バビロン帝国である。何故そう言えるのか。それは、ここではヒントが書かれているからである。ここではこの獣が、動物のように地に伏していたが、2本足で立たされて人間の心を持つようになった、と言われている。これはネブカデレザル2世のことである。実際、ダニエル書4:28~37の箇所では、ネブカデレザルが地面に伏して動物のようになり、いくらか経つと理性つまり人間の心が回復されて再び立ち上がることになったと言われている。このネブカデレザル王とは、バビロンを象徴する王である。だから、ここではネブカデレザルにおいて獅子がバビロンとして表示されていることになる。これがバビロンだということは、後に出てくる3匹の獣との関連からも分かることである。この第一の獣をバビロン以外だとすることは絶対に出来ない。
ではこのバビロンが『獅子のようで』あったのは何故なのか。これはバビロンが獅子のように強かったからである。獅子とは獣の王であって、他にこの獣に打ち勝てるような獣はいない。それと同じで、バビロンも諸国の王としての国家であって、他にこの国に打ち勝てるような国はなかった。つまり、バビロンは「百獣の王」ならぬ「百国の王」だったわけである。
バビロンが『鷲の翼をつけていた』のは何故だったのか。これはネブカデレザル王が鷲のように傲慢だったことを示している。鷲とは鳥の王者であって、非常に誇り高い。同様にネブカデレザル王も王の王であって、非常に誇り高かった。しかし彼の誇りが頂点に達したので、彼は罰を受けて地に伏させられ、神の裁きを受けて実際に鷲のようになってしまった。それは、『彼の髪の毛は鷲の羽のようになり、爪は鳥の爪のようになった。』(ダニエル4章33節)と彼が罰せられていた時のことについて書かれている通りである。そのように実際に鷲のようにされてから、ネブカデレザル王は再び立ち上がって人間としての自分を取り戻した。その時には、彼はもう鷲のような高慢さを持ってはいなくなっていた。
【7:5】
『また突然、熊に似たほかの第二の獣が現われた。その獣は横ざまに寝ていて、その口のきばの間には3本の肋骨があった。するとそれに、『起き上がって、多くの肉を食らえ。』との声がかかった。』
続いて現われた第二の獣はペルシャ帝国である。何故これがペルシャ帝国だと言えるのか。それには2つの理由がある。まず第一に、これがバビロン帝国に続く2番目の帝国だからである。バビロンの次に覇権を握る国家はぺルシャ以外ではない。このペルシャは紀元前539年にバビロンを滅ぼして、世界を支配する国家となった(※)。だから、この獣はペルシャを表示していることになる。第二の理由は、この獣の『口のきばの間には3本の肋骨があった』からである。これはペルシャが3つの獣を喰い尽くしたことを示している。すなわち、ペルシャは前550年にメディヤを、前547年にリュディアを、前539年にバビロンを滅ぼした。だからこそ、その食い滅ぼされた3つの獣の肋骨がペルシャの牙に付いていたのである。これは実に象徴的な表現である。この描写は、我々が魚を食べた際、その骨が歯ぐきの間に突き刺さった時のことを考えれば分かりやすい。このように2つの理由があるゆえ、この第二の獣をペルシャ以外の国だとすることは出来ない。もしこれがペルシャ以外の国ではないのかと思って調べたり考えたりしても、徒労に終わるだけである。
(※)
この後、バビロンは「市の城壁のほかにもはや何もなく、アルゴリス地方のティリュンス同然」(パウサニアス『ギリシア記』第8巻 アルカディア地方 第4章 メガロポリス p554:龍渓書舎)になってしまった。
[本文に戻る]
このペルシャは『熊』に例えられている。これはペルシャが熊のように強くて獰猛だったからである。熊が現れたら、その弱点が頭部にあることを知っているので倒せる自信を持った強者でもない限り、誰でも恐れるはずである。熊は死体を好まないので、死んだフリをする人もいるに違いない。ペルシャもそのような熊のごとき存在であった。
ではこのペルシャが『横ざまに寝てい』たのは何故だったのか。これはペルシャに『起き上がって、多くの肉を食らえ。』という摂理の声が与えられる時までは、すなわちペルシャが3つの国家を滅ぼすようになる時までは、存在してはいたものの寝ていて何もしていない状態にあったからである。その時が来ると、ペルシャは急に起き上がって3つの国を食い滅ぼし、世界の覇権を握ることになった。それは、あたかも寝ていた熊が急に起き上がって喰い尽くすべき獲物を容赦なく喰い尽くすようであった。
【7:6】
『この後、見ていると、また突然、ひょうのようなほかの獣が現われた。その背には4つの鳥の翼があり、その獣には4つの頭があった。そしてそれに主権が与えられた。』
3番目に現われた獣はマケドニアである。話の流れと歴史の流れを共に見れば、これがマケドニアであることは明らかである。『そしてそれに主権が与えられた。』と書かれていることからも、これがマケドニアであるのは間違いない。これは、つまりマケドニアが紀元前330年にペルシャを滅ぼして、世界の主権を握る覇権国家となったことを意味しているのだから。
このマケドニアは『ひょうのよう』であったと言われている。これも、やはりマケドニアが豹のように強くて恐ろしかったからである。ここでマケドニアが豹に例えられているのは、実に適切であった。何故なら、このマケドニアのアレクサンドロスは、豹がサバンナを走り回って獲物を食い滅ぼすかのように、全世界を走り回って諸国を次々に征服したからである。「彼は、どんな敵とぶつかってもそれを倒したし、どんな都市を攻囲してもそれを征服したし、どんな種族を攻めてもそれを踏みつけにした。」(ポンペイウス・トログス/ユニアヌス・ユスティヌス抄録『地中海世界史』第12巻 16 p211:京都大学学術出版会 西洋古典叢書)このアレクサンドロスの凄まじい征服事業を考えると、確かに彼は豹のようであったと言えるのだ。
マケドニアの『背には4つの鳥の翼があ』ったが、これはマケドニアのアレクサンドロスにおけるその移動性・機動性を示している。実際、アレクサンドロスは鳥の翼を持っているかのように世界中を移動し回った。4つの翼を持った恐るべき豹、これがマケドニアなのである。ダニエル8:1~12の箇所で語られている朝の幻のほうでは、マケドニアが雄山羊として描かれているが、そこでもやはりマケドニアは翼を持っているかのような存在として示されている(ダニエル8:5)。なお、この翼が『4つ』あったのは、マケドニアという獣が全世界を移動し回ることを示している。何故なら、聖書において「4」という数字は、東西南北すなわち全世界を意味しているからである。
また、このマケドニアに『4つの頭があった』のは、アレクサンドロスの死後、大帝国が4つに分けられて4人の王により統治されることになったからである。その4つの国とは、マケドニア、トラキア・小アジア、シリア、エジプトである。聖書において『頭』とは、国家また王を示している。黙示録13章に出てくる第一の獣が『7つの頭』(13:1)を持っていたのも、やはり同様であり、これは既に第3部で説明されたようにローマのネロが『7人の王たち』(黙示録17章9節)の後に来る王であったということを示していた。
【7:7】
『その後また、私が夜の幻を見ていると、突然、第4の獣が現われた。それは恐ろしく、ものすごく、非常に強くて、大きな鉄のきばを持っており、食らって、かみ砕いて、その残りを足で踏みつけた。』
この恐るべき狂獣の正体は、もちろんローマ帝国である。何故なら、流れから考えればマケドニアの次はローマ以外ではないからである。
この第4の獣においては、前の3匹の獣とは違い、具体的にどのような獣なのか示されていない。『大きな鉄のきばを持って』いたとは書かれているが、これだけではローマという獣が、どのような獣に該当するのか不明である。ローマは実際にどのような獣に該当していたのだろうか。これについては黙示録13:2の箇所で説明されている。そこではローマという獣についてこう書かれている。『私の見たその獣は、ひょうに似ており、足は熊の足のようで、口はししの口のようであった。』ここでヨハネはローマが混合獣、一般に言われるキマイラのような獣だったと言っている。つまり、ヨハネが言っているローマの獣とは、こういう獣である。まずローマは、豹であったマケドニアのように世界中を走り回って獲物を喰い尽くす獣であった。実際、ローマは世界の各地に軍隊を送り込んで、次々と攻略し征服して行った。またローマは、熊であったペルシャのように多くの獣を『足で踏みつけた』獣であった。実際、ローマは世界中の国々を攻めて踏みにじった。またローマは獅子であったバビロンのように他の多くの獣たちを喰い尽くした。実際、ローマは他の地域にいた民族を次々と滅ぼして行ったのであり、例えばユリウス・カエサルなどはガリアに乗り込んでガリア人を70万人も殺戮した。これについては彼の書いた「ガリア戦記」を見るべきである。要するに、ローマとはバビロンやペルシャやマケドニアのような獣である大帝国であったということだ。ローマにおいて、この3つの大帝国が再来したのである。いや、このローマはかつての大帝国よりも強くて獰猛であり、その帝国としての威光も優っていたと言うべきである。
ここで言われているローマの狂暴性、残忍性は文字通りに捉えてよいであろう。実際、このローマは本当に物凄い力を持つ国家であった。ローマがあまりにも強かったので、多くの国は戦うことを避けて降伏するのを選んだほどである。紀元1世紀のローマ人であった大プリニウスはローマが「世界を征服し、全世界を従わせ、多くの民族や王国をあちこちに配置し、外国の国民たちに自分たちの命令を発し、いわば人類の間で天の代理者であ」(『プリニウスの博物誌Ⅲ』第36巻24<118> p1477:雄山閣)ったと言っているが、この言葉からもローマの強大さが分かるはずである。もしローマが真に強大で無かったならば、このように言われはしなかっただろうからである。当時の狭い世界観の範疇において語られているという点を無視しなければ、この大プリニウスの言葉に誇張はまったく無かったと言える。
【7:7~8】
『これは前に現われたすべての獣と異なり、10本の角を持っていた。私がその角を注意して見ていると、その間から、もう1本の小さな角が出て来たが、その角のために、初めの角のうち3本が引き抜かれた。よく見ると、この角には、人間の目のような目があり、大きなことを語る口があった。』
第4の獣が『10本の角を持っていた』のは、ローマ帝国における10人の王を示している。この第4の獣は黙示録13章に出てくる第一の獣と対応しているが、その獣に生えていた10本の角について黙示録17:12の箇所ではこう書かれている。『あなたが見た10本の角は、10人の王たちで、彼らは、まだ国を受けてはいませんが、獣とともに、一時だけ王の権威を受けます。』ここでは『王たち』と言われているが、これは皇帝のことである。しかし、どうしてこの第4の獣にだけ角が生えていたのか。ダニエルも、この第4の獣に角が生えていたのは『前に現われたすべての獣と異な』っていたと書いている。これは、第4の獣だけが、その帝国における複数の支配者たちを考察すべき存在だったからである。すなわち、第4の獣であるローマはキリストの再臨と密接な関係を持っているので、そこに現われる皇帝たちのことを詳しく知るべきであった。何故なら、ローマの皇帝たちを知れば、より再臨のことを知れるようになるからである。一方、3番目までの獣は再臨と直接的な関係を持っていないので、そこにおける複数の支配者たちについて知る必要はなかった。もしこの3つの帝国も再臨と直接的な関わりを持っていたとすれば、それらの帝国においても角がしっかりと描かれていたことであろう。
それでは、ここで言われているのは一体どういうことなのか。11本目の角が初めの3本の角を引き抜いたとは何を言っているのか。これについては既に第3部で説明済みだから、簡潔に述べればよいであろう。まず新しく出てきた『もう1本の小さな角』とはネロである。このネロという『角のために、初めの角のうち3本が引き抜かれた』と書かれているのは、ネロの前に皇帝に就いていたネロよりも皇帝として小さな3人の者たちであって、それはティベリウス(2代目)とカリグラ(3代目)とクラウディウス(4代目)である。1代目のアウグストゥスはネロと同等か、もしくはそれ以上に大きい皇帝だったから、ネロにより凌駕されておらず、それゆえ引き抜かれた皇帝とは言えなかった。残る7本の角である皇帝は、ネロがいた時には『まだ国を受けてはい』(黙示録17章12節)なかったが、これから国を受けることになっていたのだから、明らかにネロの存命中に生きていた未来のローマ皇帝たちである。その7人とは、ガルバ、オト、ウッティリウス、ウェスパシアヌス、ティトゥス、ドミティアヌス、ネルウァもしくはトラヤヌスである。この7人はネロの死後、順々に一人一人が国を受けることになった。この10本の角についての描写は、このように解釈する以外に正しい解釈は見いだせない。私は他にも正しい解釈がないかと探ってみたが、どのように考えてみても上手に行かなかった。例えば、11人目をドミティアヌスだと想定してみると引き抜かれた3人はアウウグストゥスとティベリウスとカリグラということになるが、これでは意味が分からない。また取るに足りない3人の皇帝(ガルバ、オト、ウッティリウス)を除外して考えてみると、ハドリアヌスが11本目の角だったということなるが、5賢帝の一人であるハドリアヌスは明らかに11本目の角とされる存在の邪悪なイメージに合致していないし、彼が3代目までの皇帝を引き抜いたと言われているのも意味が分からない。今述べたこの2つ以外にも他に正しい解釈は有りそうにない。しかし、これがネロだと考えれば、全てがすんなりと読み解けるようになる。それだから、この10本の角については、私が述べたように考えるのが最もよい。
この11本目の角に『人間の目のような目があ』ったのは、これがネロという目を持った人間だったからである。この言葉は、この角が国家や集団などといった有機的な存在であると考えないようにすることを、つまり単一者である人間であると考えるにようにすることを、我々に要請している。また、この角に『大きなことを語る口があった』のは、ネロが傲慢なことばかり言う人だったからである。実際、歴史書を見れば分かるように、ネロほど凶悪で尊大な口を持った人間は他にいなかったと言える。黙示録13:5~6の箇所でも、このネロについて『この獣は、傲慢なことを言い、けがしごとを言う口を与えられ、…彼はその口を開いて、神に対する汚しごとを言い始めた。すなわち、神の御名と、その幕屋、すなわち、天に住む者たちをののしった。』と書かれている。ネロがこのように言ったのは、彼が『大きなことを語る口』を持っていたからでなくて何であろうか。尊大なことを語る口を持っていなければ、神を罵ることなど出来ないのである。
【7:9】
『私が見ていると、幾つかの御座が備えられ、年を経た方が座に着かれた。』
ここで言われているのは、11本目の角であるネロが殺されてから起こるキリストと聖徒たちによる支配についての出来事である。ネロが再臨のキリストによって殺されると、備えられた『幾つかの御座』に、キリストと聖徒たちが着く。そうすると、サタンとユダヤ人と異邦人に対する支配の業が執行されるのだ。ここで御座が『幾つか』と言われているのは、御座が複数あったことを示す。何故なら、この御座にはキリストの他にも多くの聖徒たちが座るのだからである。この支配の業については、キリストも次のように言っておられた。『まことに、あなたがたに告げます。世が改まって人の子がその栄光の座に着く時、わたしに従って来たあなたがたも12の座に着いて、イスラエルの12の部族をさばくのです。』(マタイ19章28節)
『年を経た方』とは、イエス・キリストである。人間精神の感覚からすれば、これは御父のことではないかと思えてしまう。何故なら、これは誰も否定しないと思うが、老人のイメージは、明らかに御子よりも御父のほうに合致していると感じられるからである。だが、我々は聖書の内容に自分の精神を服属させねばならない。後の箇所であるダニエル書7:22を見るとよい。そこでは再臨されるキリストが『年を経た方』と言われている。このように7:22の箇所では再臨のキリストが老人として描写されているのだから、我々が今見ている箇所でキリストが老人として描写されていたとしても何も問題はない。しかも、キリストが『年を経た方』と言われているのは、聖書の教えによく合致している。何故なら、聖書は、キリストが永遠に生きておられると教えているからである。そのキリストの永遠性が、「若者」よりも「老人」においてより相応しく象徴できることは誰でも分かるはずである。何故なら、老人とは若者よりも長く生きており、より永遠の時間に近いからである。
この箇所で言われている出来事については、黙示録20:4~6の箇所と対応している。次に示す通り、そこでもキリストと聖徒たちが備えられた御座に座ったと書かれている。『また私は、多くの座を見た。彼らはその上にすわった。そしてさばきを行なう権威が彼らに与えられた。』(黙示録20章4節)この支配の出来事については既に第2部と第3部の中で説明されている。
『その衣は雪のように白く、頭の毛は混じりけのない羊の毛のようであった。』
キリストの『衣は雪のように白』かったが、これはキリストの清らかさを示している。純粋な白の色が黒く思えてしまうぐらいに、キリストは清らかであった。これは理性に反する言い方であるが、キリストの清さをを示すためであれば許されるであろう。山上の変貌においても、キリストの衣が白くなったことを我々は知っている(マタイ17:2)。また、キリストの『頭の毛は混じりけのない羊の毛のようであった』が、これはキリストの光栄性を示している。キリストは光栄であられた。何故なら、我々の罪のために、御自身の清い御身体を父なる神に自ら捧げられたからである。だから、光栄であられるキリストの髪が白かったのは当然である。邪悪な愚者や病気の時を除けば、通常の場合、白い毛とは人の光栄を表わす印となる。それはソロモンがこう書いている通りである。『しらがは光栄の冠、それは正義の道に見いだされる。』(箴言16章31節)だから、聖徒たちはキリストの髪が白いのを見て、キリストが光栄と正義の御方であることを知れるのである。なお、ここで『羊』と書かれているからというので、これがキリストを示していると考える人も中にはいるかもしれない。何故なら、聖書において羊はキリストを示しているからである。黙示録13:11の箇所ではティゲリヌスについても『子羊』と書かれているから、「羊」と書かれていたら全てがキリストを示していることにはならないが、我々が今見ている箇所の場合、「羊」と書かれているのでキリストであると考えても問題ないと私は思う。
【7:9~10】
『御座は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から流れ出ていた。』
このキリストの『御座は火の炎』であった。金製や銀製の御座が火に包まれていたというのではない。ここでは御座そのものが火であったと言われているのだ。これは、キリストの栄光を際立たせるための火であった。キリストが火の御座に座っておられるのを見たら、聖徒たちは誰でも驚いたり、感動したり、キリストを崇めたりするはずである。そのようになれば、そこにおいてキリストの栄光が豊かに表わされるようにもなるのである。神は御自身の栄光を表わすことを欲しておられるから、御自身の御座を炎とされた。
また、この御座には『車輪』が付いていたことが、この箇所から分かる。この車輪が御座のどこの部分に、どのようにして付いていたのかは分からない。我々は、無用な詮索をせず、ただ御座に車輪が付いていたと理解するだけで十分とすべきであろう。この車輪も、先の御座と同じで火そのものであった。これも、やはりその車輪を通して、キリストの栄光がより豊かに示されるためである。しかし、どうしてキリストの座られた御座には車輪が付いていたのか。これはキリストが恐るべき裁きを行なわれるということである。古代には「車裂きの刑」という刑罰があった。これは回る車輪で人を轢かせることにより殺害する恐ろしい極刑である。ソロモン王はこの刑罰についてこう書いている。『知恵のある王は悪者どもをふるいにかけ、彼らの上で車輪を引き回す。』(箴言20章26節)再臨されたキリストは御座に着かれてから、その御座において、サタンとユダヤ人と異邦人たちとをお裁きになった。それは、あたかも車裂きの刑が行なわれるかのような悲惨な裁きであった。その裁きを示そうとして、ここでは御座に車輪が付いていたと教えられているのだ。しかも、その車輪は『燃える火』であった。これは、つまりキリストが火をもって、車裂きの刑のごとき苛酷な刑罰を下されるということである。次に示す通り、イザヤもキリストが再臨された時には、火をもって裁きをお与えになると言っている。『見よ。まことに、主は火の中を進んで来られる。…その怒りを激しく燃やし、火の炎をもって責めたてる。実に、主は火をもってさばき、…云々』(66章15、16節)。このように、この車輪は裁きと関連させて考えられるべきものである。
また、キリストの前からは『火の流れが』『流れ出ていた』。これは、キリストが火を持って裁きを与えられるということ、また火によりキリストの栄光が際立つようにされること、という2つの意味を持っている。このようにキリストに火が伴っているのは実に適切であった。何故なら、ヘブル12:29の箇所で言われている通り、『私たちの神は焼き尽くす火』だからである。つまり、火により象徴される神には、火こそがその従者としては相応しいのである。
【7:10】
『幾千のものがこの方に仕え、幾万のものがその前に立っていた。』
ここで言われているのは聖なる御使いのことである。ここでは『幾千』また『幾万』と御使いの数について書かれているが、これを実際の数として捉えるべきではない。これは「非常に多かった」ということを示した象徴表現だと捉えるべきである。何故なら、もし実際の数を言い表すならばこのような曖昧な言い方はせず、例えば黙示録9:16の箇所のように『2億』などと具体的に言っていたはずだからである。また、御使いがここで言われてる通りにたったの数千・数万しかいなかったというのは、有り得ないことだからである。この御使いたちはキリストに『仕え』ていた。これはキリストに仕えることが御使いたちの造られた意味と目的であり、そのようにするのが御使いたちの本分だからである。この御使いの中にはキリストの『前に立っていた』者たちもいた。これは何もせず怠惰になっていたのではなく、神の命令が発される時まで謙遜に待機していたのである。ちょうど従順な兵士たちが将軍の命令が出るまでは直立不動の姿で構えているように。既に第3部でも述べたが、ヨハネはこの箇所に基づき、黙示録5:11の箇所で御使いについて書いている。
『さばく方が座に着き、幾つかの文書が開かれた。』
ここで言われているのは空中の大審判のことである。キリストは座に着かれて42か月の支配をなされた後、今度は審判をなされるために座へと着かれた。そうして聖徒たちと毒麦たちが空中において審判を受けることになった。それは紀元70年9月に起きている。なお、1節前の7:9の箇所でもキリストが座に着かれたと書かれていたが、そこは、我々が今見ている箇所とはまた違った出来事について言われている、という点に注意せねばならない。7:9の箇所で言われていたのは、空中の大審判のためにキリストが座に着かれることではなく、42か月間の支配をされるためにキリストが座に着かれることであった。これら2つの箇所で言われていることは、時間的にも内容的にもかなり異なっている。先に42か月の支配が行なわれてから、次に大審判が起こる。すなわち、7:9の出来事が実現したら、そうして後に7:10の出来事が実現される。要するに、ダニエル書7:9~10の箇所で書かれている出来事は、その起こる順序に準拠しているのである。また、ここで『幾つかの文書』と言われているのは、聖徒たちに永遠の天国を宣言する宣言書としての「命の書」および毒麦たちに裁きを宣言するための「裁きの書」のことである。
この箇所で言われている大審判の出来事は、黙示録では20:11~15の箇所と、マタイ福音書では25:31~46の箇所と対応している。これら3つの箇所の一致具合に心を留めるべきである。どうしてこの3つの箇所が一致しているかと言えば、それはどれも皆、同じ出来事について語っているからである。ダニエル7:9の箇所で言われている42か月の支配の出来事は、今挙げた黙示録とマタイ福音書の箇所とは対応していない、という点に気を付けねばならない。その支配の出来事は、黙示録では20:4~6の箇所と、マタイ福音書では19:28の箇所と対応しているからだ。聖徒たちはこれらの箇所を相互によく参照して、あべこべな勘違いをしないように注意すべきである。
この大審判の出来事は、もう既に実現されていることを忘れるべきではない。何故なら、その出来事は黙示録20:11~15の箇所と対応しているのであって、その黙示録の箇所では『すぐに起こるはずの事』(黙示録1:1)が書かれているのだからである。この理解を否認する者は、私の理解ではなく、聖書の教えを否認していることになる。聖徒たちは注意せねばならない。
【7:11】
『私は、あの角が語る大きなことばの声がするので、見ていると、そのとき、その獣は殺され、からだはそこなわれて、燃える火に投げ込まれるのを見た。』
ここで言われているように、ネロという角は『大きなことば』すなわち傲慢な言説により神を罵っていたが、遂に彼の時が来たので、殺されることになった。どのようにしてか。Ⅱテサロニケ2:8の箇所で書かれているように、再臨されたキリストの御口の息によって、である。
そうして後、このネロは地獄へと投げ込まれた。そのことが、ここでは『からだはそこなわれて、燃える火に投げ込まれる』と書かれている。これは、つまり滅びるための新しい身体を受け(その身体は恐らく最初から損なわれた状態だと思われる)、その新しい身体において地獄に投げ入れられる、ということである。そのようにしてネロは永遠に至るまでも地獄で身体が損なわれてしまうことになった。身体が損なわれる、というのが地獄の刑罰における本質の一つなのである。
この箇所は、間違いなく黙示録19:20の箇所と対応している。そこでは次のように書かれている。『すると、獣は捕えられた。また、獣の前でしるしを行ない、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを惑わしたあのにせ預言者も、彼といっしょに捕えられた。そして、このふたりは、硫黄の燃えている火の池に、生きたままで投げ込まれた。』ダニエル書のほうでは第二の獣である『にせ預言者』(ティゲリヌス)は書かれていないが、それ以外については、言われている内容が同じである。すなわち、どちらも傲慢なことを口にするネロがキリストにより殺され、それから地獄に投げ込まれる、ということが示されている。この2つの箇所における前後の御言葉を確認すれば、この類似性をますます感じることが出来るようになる。このようにこの2つの箇所が類似しているのは、ヨハネがダニエル書7:11の箇所をベースにして黙示録19:20の箇所を書いたからなのであろう。いや、というよりは神がダニエルに示されたのと類似した内容の幻をヨハネに示されたと考えるべきであろう。だからこの2つの御言葉では一緒のことが言われているのだ。
【7:12】
『残りの獣は、主権を奪われたが、いのちはその時と季節まで延ばされた。』
『残りの獣』とは、先に出てきた10本の角、すなわち未来において皇帝となる7人の者たちのことである。これは、黙示録19:19の箇所では『地上の王たち』と書かれている。これをダニエル7:4~6の箇所に出てきた3匹の獣(バビロン、ペルシャ、マケドニア)だと解してはならない。何故なら、この第4の獣が現われた時には、それまでに現われた3匹の獣は既に滅ぼされてしまっているからだ。既に滅ぼされているにもかかわらず、『いのちはその時と季節まで延ばされた』などと言われるのは有り得ないことである。では、この7人の者たちが『主権を奪われた』と書かれているのは、どういった意味か。これは、再臨されたキリストが天の御国において永遠の主権を獲得されたということである。キリストに与えられた御国の主権を考えれば、未来に皇帝となるこの7人の者たちがやがて受ける地上の主権などは何でもないものである。何故なら、そのような地上の主権は過ぎゆくものであって、そこには永遠の輝きが欠如しているからである。そのことが、ここでは『主権を奪われた』と言われている。つまり、これは比較における言い方である。すなわち、ここではキリストに与えられた主権のゆえに、残りの獣が受けるべき主権は取り去られたも同然だ、それは意味を持たないものなのだ、ということが言われている。この部分は、このように解釈しなければ、正しい解釈は得られないと思われる。どうしてそのように言えるのだろうか。それは2節後のダニエル7:14の箇所では、キリストに永遠の主権が付与されたと言われているからである。つまり、文脈から考えれば、私が今言ったように解釈するしかないということだ。
次に、『いのちはその時と季節まで延ばされた。』とは、どのような意味か。これはやや難しい部分である。まず『いのち』とは文字通りに捉えればよい。これは地上における肉体の生命のことである。その次に書かれている『その時と季節まで延ばされた』とは、どういうことか。『その時』とは、この残りの獣たちが、キリストの再臨されたその時には殺されずに済んだ、ということである。既に説明済みであるが、キリストが再臨された時に肉体的に殺されたのはネロ(およびティゲリヌス)だけであって、ネロ以外の王たちは霊的な断罪は受けたものの肉体において生きることは許された。すなわち、彼らは断罪されて悪霊どもに喰い尽くされるだけで済んだ。『季節』とは、この7人の王たちにおける「残りの生涯」のことである。この者たちは、キリストの再臨後も、すぐに殺されたネロとは違って、そのまま自分の生涯を全うすることが許された。それは、この7人の者たちが実際に再臨後も生き続けたのを考えれば誰でも分かることである。しかし、その残りの生涯は実に短い期間であった。その生涯における短さが、ここでは『季節』と言われている。というのも、彼らに残された残りの生涯は、ある季節がすぐに過ぎ去ってしまうかのように短かったからである。我々の生涯が季節でもあるかのように即座に過ぎ去ってしまうと聖書で教えられているということについては、本書の読者であれば既に知っているはずである。
この箇所で言われている出来事は、明らかに黙示録19:21の箇所と対応している。そこでは次のように言われている。『残りの者たちも、馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が、彼らの肉を飽きるほどに食べた。』どちらの箇所を読んでも、キリストが再臨された際に、ネロ以外の王たちが断罪されはしたものの、それは霊的な断罪であって実際的には生かされ続けた、ということが分かる。このダニエル7:12の箇所とその1節前の箇所(7:11)を、黙示録19:20~21の箇所と比較してみよ。そうすれば、その類似性を感じずにはいられないはずである。ダニエル7:11はイコール黙示録19:20であり、ダニエル7:12はイコール黙示録19:21である。
【7:13】
『私がまた、夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。』
ここでは再臨のことが言われている、というのは聖徒であれば誰でも分かるであろう。この箇所にはほとんど難しい部分はない。『人の子』とはイエス・キリストである。『年を経た方』とは父なる神である。ダニエル7:22の箇所を見るとキリストも『年を経た方』と言われているが、父なる神もキリストと共に永遠に生きておられるのでキリストと同じように『年を経た方』と言われるのである。『天の雲に乗って来られ』と書かれているのは、再臨が起きたことを示す。聖書が教えている通り、キリストは天の雲に乗って再臨されるからである。そのキリストが父なる神の御前に進まれたと書かれているのは、キリストが父から御国を貰い受け永遠の主権を頂くためである。このことについては1節後のダニエル7:14の箇所で書かれている。また、ここでキリストが『年を経た方のもとに進み、その前に導かれた』と書かれているのは、この出来事における双方性を示している。つまり、キリストは御父の御心によって御父の前に『導かれた』のだが―これは御父が主体となっている―、キリストも御自身みずからの意志により自発的に御父の『もとに進』まれた―これはキリストが主体となっている―。
【7:14】
『この方に、主権と光栄と国が与えられ、諸民、諸国、諸国語の者たちがことごとく、彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。』
キリストが再臨されてから、キリストには『主権と光栄と国が与えられ』ることになった。まず『主権』とは、天上における聖徒たちに対する支配権のことである。この時、キリストは天上で正式に聖徒たちの主権者となられた。それから聖徒たちは天で実際的にキリストの前で仕え続けることになったのである。次に『光栄』とは、キリストが王として受けられるべき誉れのことである。キリストはこの時に正式な王となられたのだから、光栄をお受けになられるのは当然であった。ちょうど凱旋した王が当然のように民衆から誉れを受けるべきであるのと同じである。また、この時にキリストは聖徒たちからも光栄をお受けになられた。それは、パウロがⅡテサロニケ1:10の箇所で言っていることを読めば分かる。そして『国』とは、天上における御国すなわち天国のことである。マタイ16:28の箇所で示されている通り、神の御国はキリストが再臨された時に天上で正式に開始されることになった。それは、父なる神がキリストに天上の王国をお与えになったからである。それというのも、キリストは御父において何事かを受けられる御方だからである。キリストは御父の子であって、第二位格であられるキリストの存在は第一位格であられる御父の存在に負っているのだから、キリストは全てを御父において受けられるのである。キリストが御霊を限りなく持っておられたのも、『神が御霊を無限に与えられ』(ヨハネ3章34節)たからであった。我々は、天上の御国とは父なる神がキリストにお与えになったものである、ということを見落とすべきではない。
この時から、天上の御国において聖徒たちがキリストに実際的な意味において仕えるようになった。「実際的」と言ったのは、聖徒たちが地上においてはまだキリストから離れて仕えていたので、御前において直接的に仕えていたというのではなかったからである。ここで『諸民、諸国、諸国語の者たち』と言われているのは、この天上の聖徒たちを指している。これは、つまりどの民族の聖徒であっても、どの国に属していた聖徒であっても、どの国語を話していた聖徒であっても、という意味である。既に語られたが、天国にはどのような種類の聖徒たちも存在している。天国には日本人もエジプト人もインド人もいれば、ギリシャ語を話していた人もラテン語を話していた人も中国語を話していた人もいる。天国とはほとんど一つの民族しか見られない日本のような場所ではなく、多様な人たちが見られるアメリカのような場所なのである。なお、この『諸民、諸国、諸国語の者たち』とは天上の聖徒たちについてのことであって、地上の聖徒たちについてのことではない、という点に注意すべきである。というのも、ここでは天国のことが語られているのだから。
キリストがお受けになられたこの『主権』は永遠である。つまり、キリストは天国において、いついつまでも聖徒たちの支配者であられる。その主権は万が一にも『過ぎ去ることがな』い。それが神の御心だからである。またその御国も永遠である。その国は1億年が経っても1兆年が経っても1京年が経っても、それ以上の年月が経っても、終わることがない。この地上に存在している国であれば、いつかは滅びてしまうものである。ユダもニネベもバビロンもローマも結局は滅びてしまった。現在における最も長寿の国は日本であって、この国は2500年も続いているが、この国も未来にどうなっているかは分からず、もしかしたら数千年後には滅びてしまっているという可能性も十分にある。しかし、天国はまったくそのようなことがないのである。このように、天国という国ではキリストという一人の王が永遠に聖徒たちを従えつつ統治を行なわれ続ける。これは地上の国ではあり得ないことである。
我々が今見たこのダニエル7:14の箇所は、紀元70年9月に大審判が起きてから実現された出来事である。その時から今に至るまで、キリストは天で御自身の聖徒たちを従えて支配し続けておられる。これからもキリストは、いついつまでも天上でそのようにされ続ける。我々も、この地上での人生を終えたら、この天国に導き入れられるようになる。そうしたら、我々は永遠に至るまでキリストの御前に仕え続けることになる。何故なら、そのようになるのが選ばれた聖徒たちに対する神の御心だからである。
【7:15】
『私、ダニエルの心は、私のうちで悩み、頭に浮かんだ幻は、私を脅かした。』
この幻を見たダニエルの精神が動揺したのは何故だったのか。それは、その幻が非常に分かりにくかったからであり、またその内容が恐ろしく感じられたからである。人は、何だかよく分からないモヤモヤとした状態や現象などに多かれ少なかれ恐怖を持つ。エリファス・レヴィが「人間の無知はつねに未知なるものにおびえる」(『高等魔術の教理と祭儀 教理篇』序章 p10:人文書院)と言っているのは正しい。それは、それを把握することが出来ず、把握できないと対処や判別の仕方も分からないままなので、心が不安に感じてしまうからである。しかも、その把握できない事柄が恐ろしい内容を持っていればいるほど、恐怖の度合いも倍加される。ダニエルに示された幻が正にそれであった。それだから、ダニエルが幻を見て大いに動揺したのは無理もなかったと言える。ダニエルが臆病だったので、この幻を見て恐れ戦いたと考えることは出来ない。何故なら、もしこの幻を見て恐れないようであれば、ダニエルは非常に鈍感であったか、霊的な事柄に無頓着だったか、とんでもない馬鹿者だったか、ということになるからである。事実、この幻の内容は恐れを抱いて当然のものであった。鉄の牙を持った大きな獣が現われて滅茶滅茶なことを行ない、火の御座と天の雲に乗った人の子のような方と無数の御使いたちが現われたのだ。誰がこのような幻を見せられて動揺しないであろうか。要するに、ダニエルは健全な感覚を持っていたので、この幻に心を揺るがされたのである。
【7:16】
『私は、かたわらに立つ者のひとりに近づき、このことのすべてについて、彼に願って確かめようとした。』
ここでは『かたわらに立つ者』が出てくるが、これは誰なのか。これは難しい疑問である。何故なら、この者は、7:1の箇所から語られている夜の幻についての話の中で、初めて登場したからである。何の前触れもなく、いきなり、である。私の考えでは、これは御使いであると思う。というのも、そのように考えるのが自然だと感じられるからだ。しかし、この考えには聖書の明白な根拠があるわけではない。そうでなければ、これはキリストである。つまり、複数いる御使いたちのうち、その一人は御使いのペルソナを取って現われたキリストであった。アブラハムの前に複数の人が現われたが、その一人はキリストであり、それ以外の人は御使いだったのと、同じである。また、この者たちはダニエルの『かたわらに立』っていたのであり、遠く離れて立っていたのではない。何故か。それは、ダニエルに真理を告げるためである。遠くに立っていたとすれば、たとえ何かを告げたとしても、聞こえないか、または聞こえにくいのである。我々が何かを告げる際には、それを告げる人のいる場所まで近づくものである。この者たちがダニエルの近くにいたのは、それと同じことである。
ダニエルは自分に示された幻の内容について、『かたわらに立つ者のひとりに』尋ねようとした。それは、この幻の内容をよく知りたかったからであり、尋ねれば答えてくれるだろうと期待したからであり、その内容をよく知れば動揺も鎮まるだろうと思ったからである。また、ダニエルが真面目であり、敬虔であり、勤勉であり、知識欲が旺盛であった、ということも言っておくべきである。何故なら、真面目でなければ、敬虔でなければ、怠惰であれば、知識欲が無ければ、あえて幻の内容について尋ねるようなことも無かっただろうからである。ダニエルがこのような人であったということは、ダニエル1:3~4の箇所を見れば容易に分かることである。
しかし、どうしてダニエルは『かたわらに立つ者のひとりに近づ』いて尋ねたのか。すなわち、どうして一人だけに尋ね、2人または2人以上の人には尋ねなかったのか。これについては分からない。ちょうど1人が自分の傍近くにいたのでその者に近づいただけという理由だったのかもしれないし、複数いる者のうちその人だけが話しかけやすかったということなのかもしれないし、霊に導かれるままにその1一人に近づいたということも考えられる。いずれにせよ、この問題はトマス・アクィナスが非常な興味を持ちそうな些細な疑問であって、別に知らなかったとしても問題は起こらないので、これ以上のことは無理に探らないでおこうと思う。
『すると彼は、私に答え、そのことの解き明かしを知らせてくれた。』
ダニエルの問いに対して、この者は、その解き明かしを知らせてくれた。実に親切である。しかし、この者がダニエルの問いに答えてくれたのは何故だったのか。それは、その解き明かしをダニエルが書き記すことで、当時の聖徒たちが未来に起こる出来事を予め知るためであり、それが実現した後の時代に生きる聖徒たちがますます聖書を信頼するようになるためである。要するに、この者は聖徒たちの益のためにダニエルの問いに答えてくれたのである。
我々も、このダニエルのように啓示に関することを神に尋ねるのであれば、その答えを頂くことが出来る。何故なら、神は求める者にはお与えになられる御方だからである。その良い例は、本作品の第3部である「黙示録註解」である。私は、黙示録を正しく理解できるようにと神に祈り求めた。だから、神の恵みにより、このような註解書が作られることになったのである。今の聖徒たちはどうであるか。黙示録を正しく理解できるようになどと何も祈り求めていない。だから、いつまで経っても黙示録をまったく理解できないままでいる。今の聖徒たちがダニエルのように黙示録について祈り求めないのは、私の見るところ、黙示録を豊かに理解できるようになれば恐ろしさが生じるのではないかと感じているか、そうでなければ黙示録の正しい理解など別にどうでもいいと思っているか、である。または怠惰であったり、霊的な眠りを貪っている、ということも原因として考えられる。今の聖徒たちも、私のように祈れば、必ずや黙示録の正しい理解を獲得することが出来るのだが…。祈れば必ず与えられると聖書が教えているのに、黙示録が難しい難しい難しいとばかり言うだけで、何も黙示録の正しい理解について祈り求めようとしていないのは実に不思議な光景であると私は思う。何であれ、我々はダニエルのように、どうしても啓示について分からない事柄があれば、神に『願って確かめようと』すべきである。そうすれば、もはや分からないままの状態でいることは無くなるであろう。神は、ダニエルのような「霊の人」に慈しみ深くして下さるのだ。
さて、この者はダニエルに対して次のような回答をしてくれた。すなわち、
【7:17】
『『これら4頭の大きな獣は、地から起こる4人の王である。』
という回答である。
先に出て来た『4頭の大きな獣』は大帝国であったが、それは『4人の王』も表示していた。その王とは、第一のバビロン獣においてはネブカデレザル2世、第二のペルシャ獣においてはキュロス2世、第三のマケドニア獣においては大王アレクサンドロス、そして第四のローマ獣においては暴君ネロである。我々は次のように思い違いをしないように注意すべきである。すなわち、この獣は帝国であるから王ではない、またはこの獣は王であるから帝国ではない、という思い違いである。この獣は、帝国であるが同時に王でもあり、また王であるが同時に帝国でもあるのだ。
また、この者は、
【7:18】
『しかし、いと高き方の聖徒たちが、国を受け継ぎ、永遠に、その国を保って世々限りなく続く。』』
とも回答してくれた。
これは、つまりこういうことを言っている。地上の王たちと王たちの治める国は、儚いものであって、いつかは必ず滅び去ってしまう。そこに永遠性は存在していない。しかし、聖徒たちという王と聖徒たちの相続する天の御国は、そのようなものではない。そこには永遠性が存在している、と。実際、これはその通りであった。これまでに現われた4頭の獣は、バビロンとそのネブカデレザルも、ペルシャとそのキュロスも、マケドニアとそのアレクサンドロスも、ローマとそのネロも、消えていなくなった。今はもうこれらの国と王は存在していない。これは歴史の事実である。一方、聖徒たちはキリストが再臨されてから天の御国を受け継ぎ、その御国をいついつまでも享受できるようになった。これは啓示が我々に教えている通りである。つまり、地上の国とその王たちはどれだけ偉大であっても滅び失せるが、天上の国とその王たちは滅び失せることがまったくない。これは実に対照的である。このことからも分かるが、この節とすぐ前の節は、その内容をセットにして捉えなければならない。
要するに、ここでは地上の王国との対比において、天の御国が高められ、推奨されている。この対比において、天の御国のほうが優位に置かれているのは言うまでもない。何故なら、どう考えても地上の王国よりも天上の王国のほうが優っているからである。もしそうでなかったら、ここでは地上の王国と比較することにより天上の王国が持ち上げられていることが無かったであろう。ここでは次のように言われているかのようである。「この地上の王国はどれだけ大きく有名であったとしても、やがて草のように消えて無くなってしまう。しかし、天国という国は、永遠に続くのであって、それは絶対に滅びない。それは草のようなものではない。あなたがた聖徒たちは、やがてこの天国を永遠に相続できるようになるのだ。たといバビロンやペルシャやマケドニアやローマであったとしても、この天国にはまったく及ばない。」
聖徒たちが天上の御国を受け継ぐようになったのは、紀元70年9月であった。その時、選ばれていた聖徒たちは、キリストから次のように言われて天国へと入ることになった。マタイ25:34。『さあ、わたしの父に祝福された人たち。世の初めから、あなたがたのために備えられた御国を継ぎなさい。』これ以降、地上にいる聖徒たちは、地上での人生を終わらせてから、一人一人が順々にこの天国へと導き入れられるようになった。今の時代に生きる我々も、この地上での人生を終えたら、やがてこの天国へと入れられることになる。今やもう、天上においてはキリストの御国が開始されているからである。
【7:19】
『それから私は、第4の獣について確かめたいと思った。それは、ほかのすべての獣と異なっていて、非常に恐ろしく、きばは鉄、爪は青銅であって、食らって、かみ砕いて、その残りを足で踏みつけた。』
ダニエルが第4の獣について深く知りたいと思ったのは、この獣だけ『ほかのすべての獣と異なっていて』、しかも『非常に恐ろし』かったからである。もしこの第4の獣も他の獣と同じような獣であったとすれば、恐らくダニエルはあえてこの第4の獣について更に知ろうとはしていなかったと思われる。何故なら、その場合、この第4の獣は特別に注意を惹くような存在ではないからである。
ここで言われている獣の内容は、先に見たダニエル7:7の箇所と、ほとんど変わらない。ただ、こちらのほうでは『爪は青銅であって』と書かれている。これについては先の箇所では書かれていなかった。これは、つまりローマという獣が『青銅』すなわちマケドニアである豹のような『爪』を持って(参照:ダニエル2:11、39)、周りにいる獲物を引き裂いたということを教えている。実際、ローマ獣はそのようにして諸国を征服した。だから、この爪における描写も、やはりローマという獣の凄まじさを示していることになる。
【7:20】
『その頭には10本の角があり、もう1本の角が出て来て、そのために3本の角が倒れた。その角には目があり、大きなことを語る口があった。その角はほかの角よりも大きく見えた。』
ここで言われている角の描写も、先に見たダニエル7:7~8の箇所と、ほとんど変わらない。ただ、こちらのほうでは『その角はほかの角よりも大きく見えた。』と11本目の角について書かれている。これは先の箇所では書かれていなかった。これは、つまり11本目の角であるネロが、それ以外の10本の角である皇帝たちよりも強大だったということを教えている。実際、この11本の角すなわちローマ皇帝の中で、もっとも大きい皇帝はネロであった。この11人の中にアウグストゥスが含まれていたら話はまた別だったが、先にも述べたように、アウグストゥスは11人の中には含まれていない。
【7:21】
『私が見ていると、その角は、聖徒たちに戦いをいどんで、彼らに打ち勝った。』
この箇所ではネロという角が、聖徒たちを迫害し蹂躙することについて言われている。これについて黙示録では次のように言われている(ダニエル書と黙示録における文章の類似性に注目すべきである)。『彼はまた聖徒たちに戦いをいどんで打ち勝つことが許され、…』(13章7節)『そして彼らがあかしを終えると、底知れぬ所から上って来る獣が、彼らと戦って勝ち、彼らを殺す。』(11章7節)マタイ24:15やⅡテサロニケ2:4の箇所で邪悪な者が聖なる場所に立つと言われているのも、ネロが聖徒たちを攻撃し打ち勝つことを言っている。何故なら、後ほど説明されるが、そこで言われている聖なる場所とはクリスチャンのことを意味するからである。確かに、聖徒たちはネロという大きな角に敗北させられてしまった。つまり、ダビデという聖徒がゴリアテという滅びの子を打ち倒したようにはならなかった。しかし、そのようになったのは、ネロが再臨のキリストにより裁かれ、殺され、滅ぼされるためであった。
【7:22】
『しかし、それは年を経た方が来られるまでのことであって、いと高き方の聖徒たちのために、さばきが行なわれ、聖徒たちが国を受け継ぐ時が来た。』
聖徒たちはネロから迫害されたが、それはキリストが再臨されるまでのことだった。何故なら、キリストが再臨されるその時、ネロは殺されて消え失せるからである。
また再臨のキリストによりネロが裁かれると、遂に『聖徒たちが国を受け継ぐ時が来た』。それはネロが殺される時になると、再臨されたキリストの元に聖徒たちが携挙され、その聖徒たちが天国へと招き入れられるようになるからである。この裁きは『いと高き方の聖徒たちのために』行なわれた。というのは、この時、聖徒たちを苦しめていた者が裁かれ、苦しめられていた聖徒たちは報いとして安息に引き入れられることになったからである。
【7:23】
『彼はこう言った。『第4の獣は地から起こる第4の国。これは、ほかのすべての国と異なり、全土を食いつくし、これを踏みつけ、かみ砕く。』
この者は、ダニエルの知りたがっている事柄を、ダニエルに再び教えてくれた。
ここで言われているのは、ローマとその凄まじい強大さについてのことである。第4の獣が国家であったと明らかにされている点を除けば、特に目新しいことは語られていない。
【7:24】
『10本の角は、この国から立つ10人の王。彼らのあとに、もうひとりの王が立つ。彼は先の者たちと異なり、3人の王を打ち倒す。』
ここで言われているのは、ローマの皇帝たちとそのうち一人の皇帝であるネロについてのことである。ここでも10本の角が王であったと明らかにされている点を除けば、特に目新しいことは語られていない。
【7:25】
『彼は、いと高き方に逆らうことばを吐き、いと高き方の聖徒たちを滅ぼし尽くそうとする。』
ネロという角は、神に『逆らうことばを吐』いた。これについて黙示録では次のように言われている。―この2つの箇所における内容の類似性によく注目していただきたい。―『この獣は、傲慢なことを言い、けがしごとを言う口を与えられ、42か月間活動する権威を与えられた。そこで、彼はその口を開いて、神に対するけがしごとを言い始めた。すなわち、神の御名と、その幕屋、すなわち天に住む者たちをののしった。』(黙示録13章5~6節)この2つの箇所が対応しているのは誰の目にも明らかである。それでは、ネロは実際にどのような冒瀆の言葉を神に対して口にしたのか。これについては知る術がない。何故なら、ネロが実際にどのようなことを言って神を罵ったのか、聖書では具体的に何も書かれていないからである。また、ネロについて書き記されている古代の文書を見ても、それは分からない。セネカも大プリニウスもタキトゥスも、ネロが言った冒瀆の言葉について詳しく書き記していない。ただネロは神と呼ばれるあらゆる存在を見下しており、唯一信じていた女神シュリアの像をも小便によって汚したぐらいだから、この世界を造られた真の神に対しても、とんでもない冒瀆の言葉を口にしただろうことは間違いない。しかし、ネロがそのようにして神を罵った理由は何だったのか。それはネロが傲慢だったからであり、またサタンに憑りつかれていたからである。ネロは永遠の昔から地獄に投げ込まれて刑罰を受けるようにと定められていた。ネロは、神を冒涜したので、定められた通りに地獄に投げ込まれたとしても文句を何も言うことが出来ないのである。神は、ネロが永遠に滅ぼされるために、ネロが『いと高き方に逆らうことばを吐』くことをお許しになられた。最近の時代でも、ネロのように神に対して不遜なことを言う呪われた輩が、幾らか見られる。その代表的な例としては、ニーチェやホーキングを挙げることが出来る。だがこのような者はごく少数であって、一般的には神を公然と冒涜する者はほとんど見られない。
また、このネロは『いと高き方の聖徒たちを滅ぼし尽くそうと』した。これはネロの迫害の時のことを言っている。ネロはキリスト教徒たちを憎悪していたのである。彼が聖徒たちを滅ぼし尽くそうとしたのは、彼の行なった迫害の内容を見ればよく分かる。ネロは、聖徒たちを十字架に付けて殺し、その頭を松明代わりとし、大いに愚弄して飽きることがなかった。このような迫害は、彼が聖徒たちを絶滅させようとしていたことの表れでなくて何であろうか。
『彼は時と法則を変えようとし、聖徒たちは、ひと時とふた時と半時の間、彼の手にゆだねられる。』
ネロは『時と法則を変えようとし』たが、これは何を言っているのか。まず『時』を変えるとは、キリスト者という存在が存在している時を変えようとする、という意味である。ローマ人の言い方によれば「一派の首領であるユダヤ人クリストゥス」という御方が現われた時から、この世にはキリスト者という存在が存在する時代となった。ネロはそのキリスト者を『滅ぼし尽くそうとする』ことで、そのような時を覆そうとしたのである。次に『法則』を変えるとは、キリスト者こそが王であるという霊的な法則に対する反抗である。霊の世界において、キリスト者は万物の支配者である。何故なら、キリスト者は万物の支配者であるキリストと契約的に一体だからである。ネロは、そのキリスト者を絶滅させることで、その霊の法則を覆そうとしたのである。であるから、この『時と法則』という言葉を物理的な概念として捉えてはならない。すなわち、ここで言われているのは4つ目の次元である時間およびこの地上に働く科学的な法則のことだと捉えてはならない。ここで言われているのは、あくまでも霊的なことである。それゆえ、この角をヴォルデモート的な人物だと考えることは出来ない。今の聖徒たちは、ここで『時と法則を変えようと』すると書かれているので、この角が本当の意味における魔術師のような存在だと感じがちである。しかし、そのように考えるのは間違っている。これは魔術師でなく邪悪な皇帝に過ぎないなのだから。
このネロに聖徒たちは『ひと時とふた時と半時の間』委ねられ、迫害を受けた。既に第3部でも説明された通り、この期間は「非常に短い」ことを意味している。何故なら、これは一つの時が経って、もう2つの時が経ち、その後に半分の時が経つ、ということだからである。これを長い期間だと捉えるのは愚かである。具体的に言えば、これは「42か月」である。つまり『ひと時とふた時と半時』とは、「1年と2年と半年」の言い換え表現である。黙示録でもネロが42か月の間聖徒たちを蹂躙すると言われている。『この獣は、傲慢なことを言い、けがしごとを言う口を与えられ、42か月間活動する権威を与えられた。』(黙示録13章5節)ところで、この「42」という数字は聖書に頻出し、それは実に秘儀的な意味を持っている。これは既に述べたように、3つの「14」から成り立っている。この「14」とは非常に短い、または非常に少ない、という意味である。この42および14は聖書において無意味に出てくるのではないから、聖徒たちはこの数字の意味を忘れないようにすべきである。また、ここで言われている通り、実際にネロが聖徒たちを蹂躙した期間は42か月であった。ネロが聖徒たちを迫害し始めたのは紀元64年の後半もしくは65年の初頭である。そうしてから42か月ぐらい経過すると、ネロは遂にキリストの再臨によって裁かれ滅ぼされることになった。それ以降、もうネロは聖徒たちを蹂躙することが出来なくなったのである。しかし、聖徒たちが42か月という短い間、ネロの手に委ねられ苦しめられたのは何故だったのか。それは神がネロを通して聖徒たちを試すためであった。金は火にかけられ精錬されることで、それが本物であったと初めて証明される。何故なら、金は火で焼かれることにより自分が金であることを明らかにするが、金で無ければ焦げて灰になってしまうからである。それと同様に、聖徒という金もネロの迫害という火にかけられて試されることで、彼らが本当の神の子たちであったということが明らにされたのである。
【7:26】
『しかし、さばきが行なわれ、彼の主権は奪われて、彼は永久に絶やされ、滅ぼされる。』
ネロは、再臨されたキリストにより裁かれ、その主権を取り上げられた。この『主権』とは、ローマ皇帝としての主権であり、聖徒たちに対して許された蹂躙における主権のことである。その主権は神により奪われた。だからこそ、ネロからは主権が取り除かれたのだ。何故なら、あらゆる主権は、神がお与えになられるからこそ持てるようになるものだからである。つまり、神は主権を好きなようにお与えになる権限と自由を持っておられ、その与えられた主権を好きなように取り去られる権限と自由をも持っておられる、ということである。要するに、ネロは、結局のところ一時的に神から大きな主権を借り受けていたに過ぎなかったのである。神はこの時、貸し与えておられたその主権をネロから取り上げられた。
このネロは裁かれて殺されたので、『永久に絶やされ、滅ぼされる』ことになった。ここにおいて彼が聖徒たちを踏みにじることは最早できなくなった。死んで滅ぼされたのであれば、どうしてそれまでと同じように踏みにじることが出来るであろうか。滅ぼされたあとで地獄から這い上がって攻撃しに戻った、というわけでもなかったのだ。つまり、神は、キリストが再臨された時点で、聖徒たちをネロによる苦しみと困難とから救い出されたのである。
【7:27】
『国と、主権と、天下の国々の権威とは、いと高き方の聖徒である民に与えられる。』
聖徒たちは、キリストが再臨されてネロを滅ぼされてから、ここで言われている3つのものを貰い受けた。誰からなのか。それは、あらゆる良きものがそこから発出する存在である神から、である。まず『国』とは、天上の王国を指している。この時、天に挙げられた聖徒たちは、天国を受け、そこで永遠にキリストと共に住まうことになったのである。これについてはマタイ25:34の箇所でも言われている。次に『主権』とは、聖徒たちの持つ王としての権威である。黙示録22:5の箇所でも言われている通り、天国に導き入れられた聖徒たちは主にあって『永遠に王』とされる。その王としての主権が、ここでは言われているのだ。そして『天下の国々の権威』とは、聖徒たちが42か月の間、全世界の国々を霊的に断罪する際における巨大な権威を指している。既に述べられた通り、ネロが殺されるとキリストが座に着かれて幾らかの間、悪者どもを裁かれることになったが、その時には聖徒たちもキリストと共に裁きを行なった。この巨大な権威による裁きの出来事については黙示録20:4~6やマタイ19:28の箇所を参照すべきである。これら3つのものは、神の恵みによって、再臨が起きた時に携挙された聖徒たちに与えられた。つまり、これらのものが聖徒たちに与えられたのは、聖徒たちがそれに値する行ないを何かしたからとか十分な功績を持っていたからとかいうのではない。何となれば、あらゆる良きものは神から与えられるのであって、人が己の力によって自分自身から出たかのように得ることは出来ないのである。それは箴言10:22の箇所で『主の祝福そのものが人を富ませ、人の労苦は何もそれに加えない。』と書かれている通りである。
『その御国は永遠の国。』
天の御国は永遠であって決して滅びることがない。何故なら、そこは永遠の命を受けた聖徒たちが永遠に住まう国だからである。もしそこが永遠に続くのでなかったら、そこは天国とは言えなかった。この天国の永遠性については、先に見たダニエル7:14の箇所でも言われていた。
『すべての主権は彼らに仕え、服従する。』』
これは何を言っているのか。これはこういうことである。すなわち、聖徒たちはキリストの再臨が起きた際に携挙されたが、その時、あらゆる主権を凌駕する存在になった、と。何故なら、その時に聖徒たちはキリストと共に王となったからである。王というのは全ての主権の上に立つ存在である。その主権が、ここでは言われているのだ。この主権に基づく支配の期間については、黙示録20:4~6の箇所に書かれている。
【7:28】
『ここでこの話は終わる。私、ダニエルは、ひどくおびえ、顔色が変わった。しかし、私はこのことを心に留めていた。」』
夜に示された預言の幻における内容は、以上であった。これ以上の幻はダニエルに示されていない。何故なら、神がこれぐらいの幻を示せばそれで良しとされたからである。もしもっと示すのが御心であったとすれば、ダニエルにはもっと多くの幻が示されていたであろう。
この幻を見たダニエルは、心に大きな衝撃を受け、すっかり参ってしまった。何故なら、その幻がよく悟れなかった上に、非常に恐ろしい内容だったからである。確かに、この幻のことを考えれば、ダニエルが動揺したのは無理もなかったと言える。先に見た7:15の箇所でも、ダニエルが幻を見て恐れ戦いたことについて書かれていた。
人間は、恐ろしい事柄を、意識的であれ無意識的にであれ、脳内から消す、すなわち忘れ去ろうとすることが往々にしてある。戦場で恐ろしい思いをした兵士が、その恐ろしい記憶を自然と忘れてしまう、という話を私は聞いたことがある。それというのも、人間の脳は恐るべき事柄を自動で消し去ってしまう機能を持っているからということであった。しかし、ダニエルは、自分に示された恐るべき幻を決して忘れることがなかった。これはダニエルが敬虔で真面目であったからであろう。ダニエルは、せっかく神が自分に示して下さった幻を、忘れることにより蔑ろにしたくはなかった。だから、そのことを『心に留めていた』のだ。例えば、我々にどこかの国の王が貴重な話をしてくれたとしたら、恐らく我々はその話を忘れないようにするのではないか。何故なら、王がせっかく自分に貴重な話をしてくれたからである。ダニエルが神に示された幻を忘れようとしなかったのは、これとよく似ている。
【8:3】
『私が目を上げて見ると、なんと一頭の雄羊が川岸に立っていた。』
ダニエルは、角を持った獣の幻を見たことについて書き記している。これは神から与えられた幻の預言であった。神は、このように幻を通しても預言を御語りになった。我々は、預言がただ言葉で伝えられる方式しかなかったとは考えないようにすべきである。不信の者であれば、このような幻の預言が書かれているを読んで、ダニエルは妄想をしていたとか麻薬で幻覚を見ていたのだなどと言って、神の言葉を愚弄するかもしれない。実際、モーセは麻薬を使用していたので神々しい幻を見たのだなどと言って聖書を侮辱している者が、世の中にはいる。こういう者は、恐らくダニエルの場合でも同じようなことを言うのであろう。しかしダニエルの見た幻が、神から与えられた預言だったことは明白である。聖徒たちは不信の者と同じようにならないように注意せねばならない。
ここでは『なんと』と言われている。ダニエルは獣の幻を見て驚いたのである。『神に愛されている人』(ダニエル10章19節)であるダニエルでさえ驚いたということは、つまり、この幻に大いに着目せねばならないということである。よって、我々はこの幻についての記述を蔑ろにしないようにすべきである。ダニエルさえも驚いたことを、我々が注目しなくていいはずはないのだから。
これから見ていく角を持った獣の幻は、明らかに黙示録の内容と類似している。既に第3部でも見たように、黙示録でも角を持った獣が出てきた。これは一体どういうことであるか。こういうことである。すなわち、神はダニエルに見せたのと同じような内容の幻をヨハネにも見せられた。だからこそ、黙示録ではダニエル書のように角を持った獣が出てくるのである。ヨハネはダニエル書に似せようとしてダニエル書に書かれている獣を黙示録にも登場させたなどと考える人もいるかもしれないが、私が今述べたように考えたほうが望ましい。このようにダニエル書と黙示録は類似しているのだから、黙示録を理解するためにはダニエル書を理解することが大きな益となる。それというのも、ダニエル書を理解すればするほど、それだけ黙示録を豊かに理解できるようになるからである。要するに「急がば回れ」である。黙示録を理解したければ、ダニエル書に回り道をしてみるのが良いのだ。実際、私はそのようにしている。
『それには2本の角があって、この2本の角は長かったが、1つはほかの角よりも長かった。その長いほうは、あとに出て来たのであった。』
雄羊の持つ『2本の角』とは、ダニエル8:20の箇所で言われているように『メディヤとペルシャの王』である。これは聖書が教えていることだから、確定事項とせねばならない。この『2本の角は長かった』が、これは角における力と権力が大きかったことを示している。実際、メディヤとペルシャは実に強大な国であった。ところで、黙示録のほうでは角については書かれているが、角の長さについては何も書かれていない。また、この2本の角のうち『1つはほかの角よりも長かった』が、長かったのはペルシャのほうである。何故なら、ペルシャは紀元前550年にメディアを打ち倒したからである。打ち倒したほうが、打ち倒されたほうよりも角が長かったというのは誰でも分かることであろう。また、『その長いほうは、あとに出て来たのであった』が、これもやはりペルシャのことを言っている。何故なら、ペルシャのほうがメディアよりも遅く台頭したからである。これは歴史を見れば明らかである。注意せねばならないのは、この幻の中ではメディヤ帝国とペルシャ帝国があたかも同時に世の帝王として並び立っていたかのように書かれているということである。実際は、ペルシャがメディヤを打ち倒したのだから、両者が同時に世の帝王として並び立っているということはなかった。つまり、この幻の中では単にペルシャとメディアが一緒にして描かれているだけに過ぎないということである。
黙示録では、第二の獣であるティゲリヌスに『子羊のような二本の角があ』(13:11)ったと言われている。これは、明らかにダニエル書に出てくる雄羊の持つ『2本の角』と対応している。既に第3部で述べたように、黙示録はダニエル書と多くの点で対応しているが、この羊の2本の角もその一つである。それでは、ティゲリヌスが二本の羊のような角を持っていたというのは、どういうことなのか。ティゲリヌスがメディヤとペルシャだというのか。それともティゲリヌスがメディヤ人とペルシャ人を祖先に持っているというのか。そうではない。ティゲリヌスが二本の角を持っていたというのは、つまり彼がメディヤとペルシャのように傲慢で罪深かったということである。次の節に書かれているメディヤとペルシャについての言葉は、ティゲリヌスにも当てはまる。『それは思いのままにふるまって、高ぶっていた。』実際、多くの人が証言しているように、ティゲリヌスほど悪に染まっていた者はいなかった。つまり、ヨハネはメディヤとペルシャの傲慢さがティゲリヌスにも見られるということを示そうとして、ティゲリヌスという第二の獣に『子羊のような二本の角があ』ったと書いたわけである。なお、ダニエル書に出てくるこの2本の角を持つ雄羊は、やがて雄山羊に打ち殺され、その雄山羊も4つに分裂してしまうが、黙示録に出てくる第二の獣を解釈する時は、そこまで考える必要はない。そこまで考えるのは行き過ぎである。何故なら、ヨハネは単にティゲリヌスがメディヤ王とペルシャ王のようだと言いたかったに過ぎないからである。
【8:4】
『私はその雄羊が、西や、北や、南のほうへ突き進んでいるのを見た。』
これはメディヤとペルシャの支配また侵攻における方角を示している。確認できる者は、この2つの帝国のあった場所を地図で確認してみるとよい。確かに、この2つの帝国が身体を向けていたのは西と北と南の方角であった。
『どんな獣もそれに立ち向かうことができず、また、その手から救い出すことのできるものもいなかった。』
これは、メディヤとペルシャが最強の帝国だったということである。確かに、この2つの帝国にはどんな国も打ち勝つことが出来ず、この2つの帝国に捕えられたら助け出すことの出来る国も存在していなかった。今の時代で言えば、これはアメリカとその軍隊に当たると考えればよい。誰でも知っているように、アメリカにはどの国も対抗できず、イラク戦争を見れば分かるようにアメリカに目を付けられたら誰にも助けてもらうことは出来ないのである。
『それは思いのままにふるまって、高ぶっていた。』
これは言葉の通りに捉えればよい。メディヤとペルシャは非常に傲慢であった。何でもそうだが大きな存在になると、自分のやりたいように何でも出来ると思うようになる。自分があまりにも巨大なので、自分よりも小さい存在に対して心が高ぶるのである。その高ぶりが傲慢で異常な振る舞いを生み出す。そのようになると、多くの人たちから嫌われたり批判されたりするようになる。これはネロがよい例である。ネロは今まで誰にも与えられなかったほどの権力を持ったので高ぶり、考えられないぐらいに傲慢な振る舞いを幾度となくしたものである。メディヤとペルシャも、傲慢であるという点ではネロと同じであった。ところで、J・S・ミルも言っているように、もし完全な人間が統治するとすれば、最も理想的な政体は絶対王権制である。何故なら、そこにおいて統治する王は間違いを犯すことがないからである。しかし現実にはそのような人間はおらず、人間は愚かで弱いので、大きな権力を持つと必ず高ぶりメディヤとペルシャのようにならざるを得ない。だからこそ人間の国には三権分立の原理が採用されるべきなのである。シオン議定書の中では、絶対王政こそが真に正しいなどと言って、あたかも自分たちだけが知恵者だなどと言わんばかりであるが、これはただ夢を見ているだけに過ぎない。もし彼らの言うところの「ユダヤ王」が完全に正しければ確かに議定書に書かれていることは誤りではなかったが、たとい幼少の頃から徹底的な教育を受けたとしても、人間は堕落しているのだから完全を望むことは不可能である。メディヤとペルシャやその他の王国を見てみるがよい。高ぶって愚かなことをしなかった王国や王など誰もいなかった。あのダビデでさえも驚くべき悪を行なったのである。あのダビデが、である。ダビデ王さえも愚かなことを仕出かしたということは、つまり王として愚かなことをしない者は存在し得ないということを意味している。何故なら、この地上ではダビデ王よりも優った王など存在し得ないからである。アクトン卿も言ったように「絶対権力は絶対に腐敗する。」それゆえ、王制であったメディヤとペルシャが『思いのままにふるまって、高ぶっていた』のは特に驚くべきことではなかったと言えよう。
【8:5】
『私が注意して見ていると、見よ、一頭の雄やぎが、地には触れずに、全土を飛び回って、西からやって来た。その雄やぎには、目と目の間に、著しく目だつ一本の角があった。』
次にダニエルの前に現われた幻は、『一頭の雄やぎ』であった。これは先に出てきた『一頭の雄羊』とは区別せねばならない。何故なら、雄山羊と雄羊は明らかに別の存在だからである。では、この『雄やぎ』とは一体なんなのか。これはダニエル8:21の箇所で言われているように『ギリシャの王』である。もっと正確に言えばギリシャにあるマケドニアの王である。この雄山羊には『目と目の間に、著しく目だつ一本の角があった』。これはダニエル8:21で書かれているようにギリシャ・マケドニアにおける『第一の王』である。これが『著しく目だつ一本の角』だったと言われているのは、この王が有名で強大だったからである。つまり、もしこの王が無名であまり強くもなければ、このようには言われていなかったということである。それで、この雄山羊の角である王は、続く箇所に書かれているようにペルシャ帝国という雄羊を打ち滅ぼすのだから(ダニエル8:6~7)、明らかに大王アレクサンドロスを指している。この有名な大王が紀元前330年にペルシャを攻め破ったのは歴史の事実である(※)。このマケドニア・アレクサンドロス王が雄山羊と言われているのに対し、ペルシャが雄羊と言われているのは、力の差を示すためである。マケドニアはペルシャを打ち破ったから、明らかにマケドニアのほうがペルシャよりも強い。だから、ここではマケドニアが雄山羊に、ペルシャが雄羊に例えられているのである。というのも、雄山羊のほうが雄羊よりも強いからである。雄羊は臆病であって、この雄羊の群れは100匹いようとも一匹の雄山羊に率いられる。どちらが優位に立っているかは一目瞭然だ。聖書は、マケドニアとペルシャを、例えば獅子と雄山羊として描くこともできた。何故なら、獅子と雄山羊でも、マケドニアのほうがペルシャよりも強いという意味は伝わるからである。しかし、聖書は雄山羊と雄羊という例えを用いている。
(※)
この王について知りたければ、クルティウス・ルフスの『アレクサンドロス大王伝』という書物を読むとよい。
[本文に戻る]
このアレクサンドロスが『西からやって来た。』と言われているのは、ペルシャを基点とした言い方である。アレクサンドロスのマケドニアは、ペルシャよりも西の場所に位置している。その西のほうからアレクサンドロスがペルシャを滅ぼしにやって来た。だから、ここでは彼が『西からやって来た。』と言われている。
また、このアレクサンドロスは『地には触れずに、全土を飛び回って』ペルシャのほうにやって来た。これはアレクサンドロスの機動性の高さを示している。古代人の中でアレクサンドロスほどに多くの距離を移動した人間は珍しい。彼はインドのほうまで行ったが、それは考えられないぐらいに遠い場所であった。つまり、ここではアレクサンドロスという雄山羊が、あたかも雄山羊でありながら翼を持って飛び回りつつ移動しているかのように言われているのだ。確かに、彼は翼を持った生物でもあるかのように遠い場所まで行った。
ダニエルは、ここで『見よ』と雄山羊の幻について言っている。それゆえ、我々は、この雄山羊の幻について大いに着目せねばならない。『神に愛されている人』であるダニエルが御霊によって、『見よ』と言っているのだ。そうであれば、聖徒である者がこの雄山羊の幻を軽んじたり無視したりすることは霊的な義務に反していると言わねばならないのである。ダニエルは、どうでもいいようなことであれば『見よ』などとは言っていなかっただろうから。
【8:6~7】
『この雄やぎは、川岸に立っているのを私が見たあの2本の角を持つ雄羊に向かって来て、勢い激しく、これに走り寄った。見ていると、これは雄羊に近づき、怒り狂って、この雄羊を打ち殺し、その2本の角をへし折ったが、雄羊には、これに立ち向かう力がなかった。雄やぎは雄羊を地に打ち倒し、踏みにじった。雄羊を雄やぎの手から救い出すものは、いなかった。』
これは、マケドニアのアレクサンドロスがペルシャ帝国を打ち滅ぼすことについての預言である。ダニエルは、雄羊を打ち殺した雄山羊がギリシャの王だということは理解していたが(ダニエル8:21)、その王がアレクサンドロスだということまでは知らなかった。神は、ダニエルがアレクサンドロスのことまでは知らなくてもよいと判断されたのである。それは、神がキリストの預言を語られたものの、御民にそのキリストがナザレのイエスという存在だということまでは知らされていなかったのと同じである。不信仰なリベラルの者は、ここでアレクサンドロスがペルシャ帝国を打ち滅ぼすと言われているのを読んで、これは後世に書かれたものだと愚かにも考えている。何故なら、彼らは預言のことなど信じていないからだ。つまり、この箇所は、アレクサンドロスがペルシャ帝国を打ち滅してから書き記されたのだと彼らは理解している。だからこそ、そのことについて書くことが出来た、と。それゆえ彼らは、これがダニエルの書いた文章ではないと考えているばかりか、ダニエル書の書かれた年代を前2世紀頃に設定している。参考までに言えば、ダニエルが活動したのは紀元前600年頃~540年頃であり、ペルシャ帝国が打ち倒されたのは既に述べたように前330年である。聖徒である我々は、このような不信仰に毒されてしまってはならない。これは神がアレクサンドロスの生まれる前の時代にダニエルに語られた預言であると、我々は信じなければいけない。御霊を受けている者たちは「アーメン。」と言うべきである。実際のところ、リベラルのキリスト教はキリスト教ではない。彼らは御霊を受けておらず、それゆえ我々の兄弟ではないのである。このリベラルのキリスト教は、ニーチェもキリスト教の中で最も忌み嫌っていたほどである(『反キリスト』)。リベラルのキリスト教は世界から消えて無くなれ。
この箇所を読むと、ペルシャ帝国の滅亡が凄まじかったことが感じられる。実際、アレクサンドロスは容赦なくペルシャ帝国を滅ぼした。ペルシャのダレイオス3世はマケドニアの勢力に勝てないと思い講和を申し出たのだが、アレクサンドロスはそれを断固として拒絶し、すぐさまペルシャを徹底的に攻めたのである。このダレイオス3世は前333年にイッソスの戦いで、前311年にガウガメラの戦いで、アレクサンドロスに敗北を喫した。それは正に狂暴な雄山羊が弱弱しい雄羊を噛み裂いて殺すようなものであった。この戦いを描いた有名なモザイク画があるが、それを見ると、正に山羊と羊であるかのようである。そのようにして、ダニエルに語られたこの預言は紀元前330年に成就されたのである。なお、ここでは『怒り狂って、』とアレクサンドロスについて言われているが、これは彼が「怒りっぽい気質」(『プリニウスの博物誌Ⅲ』第35巻36<86> p1425:雄山閣)を持っていたという事実と調和している。
【8:8】
『この雄やぎは、非常に高ぶったが、その強くなったときに、あの大きな角が折れた。』
アレクサンドロスという雄やぎは『非常に高ぶった』。これは、彼が自分を神として取り扱うようにと要求したことからも、よく分かる。自己を神とするのは、紛れもなく高慢の現われである。もし高慢でなければ、自分を神とすることは無かっただろうし、むしろ自分が神として取り扱われることを拒んだはずである。歴史が示すように、物凄い権力を持った王や支配者は、往々にして、このような高慢に取りつかれる。アレクサンドロスもその一人であった。
このアレクサンドロスは、『強くなったときに』『折れた』。強くなった時というのは、かなりの地域を征服していた時ということである。角が折れたというのは、つまり死んだということである。実際、彼はインドの辺りまで征服した後、バビロンに行った際、33歳の若さで死んだ。それは紀元前323年の時である。ポンペイウス・トログスの『ピリッポス史』第12巻・第14節によれば、復讐欲に突き動かされたアンティパトロスにより容赦なく毒殺されてしまったという(※)。彼の遺骨は、この後、プトレマイオス朝のエジプトに運ばれ安置された。
(※)
マラリアによる恐ろしい熱病が彼の命を容赦なく奪ったと言っている人もいるが、私としてはトログスの記述に従いたい。パウサニアスの場合、この毒殺について「ピリッポスの子アレクサンドロスも、この毒のせいで最期をとげることになったのかどうか、わたしははっきりとは知らないが、この種の話のあることは知っている。」(『ギリシア記』第8巻 アルカディア地方 第3章 アルカディア北部 p530:龍渓書舎)と言うだけに留めている。なお、この大王の死因には、他にもウエストナイル脳炎、癲癇の発作、過剰飲酒など、多くのもっともらしい説が存在していることを忘れるべきではない。
[本文に戻る]
彼が死んだのは、確かなところ、神の裁きによった。彼が異常なほどに高ぶって自分を神としたので、神が怒られ、罰として毒殺による死を下されたのである。これは聖書的な理解である。何故なら、箴言では『高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。』と言われているからだ。神は、御自身と並び立とうとする者に裁きを下さずにはおかれない御方である。というのも、神は御自身と並び立つ存在を許容してはおかれない御方だからである。ヘロデも演説をしている時に民衆から『神の声だ。人間の声ではない。』(使徒行伝12章22節)と叫ばれたが、彼はこの民衆の言葉を否定しなかったので、すぐさま裁きにより『虫にかまれて息が絶えた』(使徒行伝12章23節)のである。これはヘロデが民衆の言葉を否定しなかったことにより、自己を神と見做したからに他ならない。というのも否定しないということは、首肯したということになるからである。我々は、自分の名誉を横取りする酷い奴が現れた際、何か行動を起こさないだろうか。多くの場合、多くの人が行動を起こすはずである。神も、御自身の神としての名誉を横取りする酷い人間が現れた際、その人間に対して行動を起こされる。それは、死の裁きを与えるという行動である。我々は、自己を神としないようにしよう。我々は神ではなく、ただの小さな被造物に過ぎないのだから。むしろ我々は次のように言うべきである。『知れ。主こそ神。主が、私たちを造られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。』(詩篇100:3)
『そしてその代わりに、天の四方に向かって、著しく目だつ4本の角が生え出た。』
これは、アレクサンドロスの死後、彼に従っていた4人の遺将たちが、アレクサンドロスの帝国をそれぞれ4つの国に分割して統治することになるという預言である。すなわち、それはマケドニア、トラキア・小アジア、シリア、エジプトの4つの国である。このうちトラキア・小アジアは短命に終わった。この4つの国は確かに『著しく目だつ』ものであった。何故なら、それらは誰からも例外なく認識されたからである。
このような分裂は、神の裁きにより引き起こされる。罪を犯すならば呪いとして分散させられてしまうと律法の中でも言われている(申命記28:64)。アレクサンドロスの死んだ後に彼の帝国が4つに分かれたのも、彼が高ぶりの罪を犯したからであった。これは他の例を見ても分かる。例えば、人々はバベルの塔を建てていたので無数の民族と言語に分けられてしまったが(創世記11:1~9)、これは自己神化願望の罪に対する刑罰であった。彼らは『さあ、われわれは町を建て、頂が天に届く塔を建て、名をあげよう。』(創世記11章4節)と言って、天におられる神に対抗しようとしたのだから。また1054年に東方教会が西方教会から分離させられたのも同様である。東方教会が三位一体について忌まわしい理解を持っていたので、その教理的な罪に対する罰により、この異端の教会は西方教会から切り離されてしまったのである。また宗教改革も同様である。カトリックは腐敗し切っていたので、その罪悪に対する裁きとして、新しく生まれた教派から区別されることになった。もし罪が犯されなかったとすれば、神の裁きが下されることもないのだから、アレクサンドロスの帝国もバベルの時代の人間も教会も多くの部分に分けられることは無かったであろう。このように分裂は罪に対する神の裁きが原因となって引き起こされるが、しかし、その分裂は神の御心に適った現象でもある。何故なら、神は多様性を好まれる御方だからである。ノアとその3人の子供から実に多くの民族が生まれたことや、教会が多くの教派に分かれたことを考えてみられよ。神は、多くの部分が地上に見られることをその御心としておられるのだ。もしそのようになるのが神の御心で無かったとすれば、民族も教会もここまで多くの部分に分けられることは無かったはずである。つまり、神は裁きを通して、多様性が満ちるようになるという御自身の御心を実現させておられる。このような仕方は、人間である我々からすれば不思議なことである。
それでは、このような分裂を避ける方法は何かあるのであろうか。今現在自分の属している団体や集団が出来るならば分裂しないでそのままに保たれてほしい、と願う人は多いだろうと思う。もし分裂を回避できる方法があれば、それを是非とも知りたい。このように思う人は少なくないはずだ。私は言うが、残念ながら、そのような方法は存在していない。何故なら、人間は堕落しており罪深いからである。もし人間が天使のように完全で聖なる存在であれば、罪を何も犯さないのだから、裁きも下されることがなく、それゆえ分裂が起こるということも無い。しかし、人間は天使のように完全で聖なる存在ではなく、必ず罪を犯してしまう。ソロモンも言うように、『罪を犯さない人間はひとりもいない』(Ⅰ列王記8章46節)のだ。だから、罪を犯してしまう人間が属する団体や集団は、分裂してしまうことから絶対に免れ得ない。これは今までの歴史を見てみれば分かることである。ただ、そこにいる者たちが心を一つに合わせて祈り、本当に敬虔に歩むのであれば、分裂の起こる時期を多かれ少なかれ遅らせることが可能であると私は考える。何故なら、そのような団体や集団は神の御心に適った歩みをしているからだ。しかし、そのような団体や集団であっても、最終的にはやがて分裂が起こることにならざるを得ない。いつか罪を犯す人が必ず、そこにおいて現われるだろうから。これは今までの教会の歴史を見れば分かることである。その一つの例としては、リベラルに染まってしまったプリンストン大学から、メイチェンにより新しい正統的な神学校が生まれ出ることになったことを挙げることが出来る。このプリンストンは昔はリベラルに染まってなどいなかったのである。
【8:9】
『そのうちの1本の角から、また1本の小さな角が芽を出して、』
これは、シリアという『そのうちの1本の角』から、アンティオコス・エピファネスという『角』が現れるという預言である。このエピファネスという王は、最初は小さかったが、徐々に大きくなった。この王は、我々にとって重要である。何故なら、この王は、霊的に言えば、あの不法の人と関係を持っている王だからである。
『南と、東と、麗しい国とに向かって、非常に大きくなっていった。』
これは、エピファネス王が、彼の国であるシリアから見て南と東の地域に、また『麗しい国』に支配の手を伸ばして行ったということである。地図を確認できる人は、シリアの位置を確認してみるとよい。『麗しい国』とは、もちろんユダヤとそのエルサレムを指している。これは、かつてエデンの園があった場所や日ユ同祖論で言われるところの失われた10部族が向かったとされる日本のことではない。ユダヤ人の国が『麗しい』と言われているのは、神がユダヤ人と共におられたからである。神が共に歩んでおられる聖なる民の住まう国を『麗しいと言わずして何と言えばよいであろうか。旧約時代において『麗しい国』と呼ぶことが出来たのはユダヤ人の国だけであった。それ以外の国は全て「荒野」である。
【8:10~11】
『それは大きくなって、天の軍勢に達し、星の軍勢のうちの幾つかを地に投げ落として、これを踏みにじり、軍勢の長にまでのし上がった。』
エピファネスという角は、『大きくなって、天の軍勢に達し』た。これは、この王がユダヤを自分の支配化に置こうとして攻め入ったということである。『天の軍勢』とは、もちろんユダヤを指している。しかし、どうしてユダヤが『天の軍勢』と言われているのか。それは、ヘブル書11:13~16の箇所から分かるように、旧約時代のユダヤ人たちは天を自分の故郷として持つ人たちだったからである。彼らの本国、また国籍は天であった。だから、ここでユダヤが『天の軍勢』などと言われているのを我々はいぶかるべきでない。また、この『天の軍勢』とは先の箇所に書いてあった『麗しい国』に属している。それでは、どうしてエピファネスはユダヤにまで支配の手を伸ばそうとしたのか。それは彼の傲慢が原因であった。エピファネスは自分が神であると思っていた。だからこそ、神でもあるかのようにユダヤを征服して自己の支配化に置こうとしたわけである。これはアレクサンドロスも同様であった。彼は自分が本当に神であると思っていたので、神でもあるかのように諸々の地域を征服しようとしたのである。歴史が示すように、強大な権力を持つ支配者の傲慢な精神は、往々にしてこのような征服の欲望を持つものである。ローマ然り、チンギス・ハーン然り、ヒトラー然り、である。
またエピファネスは、『星の軍勢のうちの幾つかを地に投げ落とし』た。この『星の軍勢』とは、先に見た『天の軍勢』と一緒の意味を持つ。これも、やはりユダヤ人の本来的な住まいが天に定められているからである。つまり、ここで言われているのは、エピファネスがユダヤ人のうちの幾らかを酷い目に遭わせた、ということである。何故なら、天にある星が地に投げ落とされるというのは、非常に悲惨なことだからである。彼が『踏みにじり』と書かれているのは、ユダヤ人が激しく蹂躙されたことを言っている。これは歴史が我々に教えている通りである。また彼が『軍勢の長にまでのし上がった』と書かれているのは、エピファネスがあたかもユダヤ人たちの長であるかのように振る舞ったということを言っている。これも実際に起きたことである。
【8:11~12】
『それによって、常供のささげ物は取り上げられ、その聖所の基はくつがえされる。軍勢は渡され、常供のささげ物に代えてそむきの罪がささげられた。』
エピファネスにより、『常供のささげ物は取り上げられ』ることになった。つまり、これは動物犠牲が禁止されたことを言っている。そのように禁止されたからこそ、いつものように常供の捧げ物を奉げることが出来なくなったのである。とはいっても、この忌まわしい禁止命令など気にせずに犠牲を捧げるユダヤ人も中にはいた。当然ながら、このようなユダヤ人は捕らえられて殺されてしまった。しかし、彼らはその行ないにより、自分たちがアブラハムと同じ信仰を持っているということを証明した。一方、この禁止命令に従い、犠牲を全く捧げなくなったユダヤ人も、もちろんいた。彼らは命を失わずに済んだ。だが、彼らはその行ないにより、自分たちがアブラハムのような信仰を持っていないことを証明してしまった。キリストは『木はその実によって知られる。』と言われた。この御言葉からも分かる通り、この時、それぞれのユダヤ人がどのような木であるのか判明することになったのである。禁止命令を守らないという実を結んだユダヤ人は良い木であることを示し、禁止命令を守るという実を結んだユダヤ人は悪い木であることを示した。
またエピファネスによって、『そむきの罪がささげられ』ることにもなった。これは、この暴君がユダヤ人に対して豚を奉げるように働きかけたことを言っている。これは実際に起きたことである。エピファネスはどうしてユダヤ人たちが命を捨てることになってまで豚を奉げようとしないのか非常に不思議に思っていた(このように思っていたのは彼以外の異邦人も同じであった)。それだから、エピファネスは、もし豚を捧げるのであれば命を助けてやろう、それどころかシリアで高い地位に就けて幸いな状態を享受させてやろう、とユダヤ人に脅迫しつつ誘惑したのである。このように律法で禁じられている豚が捧げられるようにさせるというのは、正に『そむきの罪がささげられ』ることであった。何故なら、豚を捧げるというのは、明らかに神に背く行ないだったからである。それは神への背信抜きには絶対に出来ない行為であった。このようにユダヤ人に働きかけたエピファネスは、実に忌まわしい存在である。だから、彼は正に『忌むべき者』(ダニエル12章11節)と呼ばれるに相応しい暴君であった。
【8:12】
『その角は真理を地に投げ捨て、ほしいままにふるまって、それを成し遂げた。』
エピファネスは『真理を地に投げ捨て』ていた。『真理』とはトーラーを意味している。つまり、この王は神の律法など別にどうでもよいと思っていた。もしそのように思っていなければ、ユダヤ人に常供の捧げ物を禁止させたり、豚を奉げるように働きかけるなどということは決してしなかった、いや、出来なかったことであろう。何故なら、律法では神に捧げ物を奉げるようにと、また豚は決して捧げないようにと、命じられているからである。
また彼は『ほしいままにふるまって、それを成し遂げた』。これは文字通りに捉えればよい。彼は、本当に傲慢に振る舞い、暴虐の限りを尽くした。これは彼について書き残された文書を読めば分かる通りである。
【8:13】
『私は、ひとりの聖なる者が語っているのを聞いた。すると、もうひとりの聖なる者が、その語っている者に言った。』
ここで言われている『聖なる者』とは、御使いのことであろう。これが主であると考える人もいるかもしれない。しかし、この箇所において最も重要なのは、この『聖なる者』が誰なのかということではなく、そこで語られている内容が何なのかということである。それゆえ、この者についての解釈は、最高に重要であるというわけではない。我々は、事柄の本質を見分ける能力を求めるべきである。
『「常供のささげ物や、あの荒らす者のするそむきの罪、および、聖所と軍勢が踏みにじられるという幻は、いつまでのことだろう。」』
ここでは、荒らす者が現われ、犠牲が停止させられ、エルサレムが蹂躙される期間はどれぐらいなのか、という問いがなされている。我々は、単に聖なる者がこのことについて無知だったから、このような問いをした、などと考えるべきではない。そうではなく、むしろ、このような質問がなされたのは聖徒たちに知識を与える目的があったのだと考えるべきである。何故なら、全ての預言は聖徒に聖なる知識を与えることを目的としているのだから。もしこの聖なる者が単に知識欲を満たしたいという願望のゆえにこのような質問をしているだけだったとすれば、ここでは、このような質問が書き記されていたのかどうか我々には定かではない。
【8:14】
『すると彼は答えて言った。「2300の夕と朝が過ぎるまで。』
エピファネスがエルサレムを荒らす期間は、1150日間であった。この『2300の夕と朝』という期間を、我々は2300日すなわち24時間が2300回繰り返される時間だと捉えるべきではない。ここで言われているのは、夕と朝が過ぎるその合計回数に基づく日数である。何故こう言えるかといえば、ダニエル12:11の箇所では『常供のささげ物が取り除かれ、荒らす忌むべきものが据えられる時から1290日がある。』と書かれているからである。ダニエル12:11のほうで『1290日』と言われているのは堅固であって、一つの解釈しかできない。すなわち、これは24時間が1290回続くという意味にしか解せない。もしダニエル8:14の箇所で言われている期間が2300日であると捉えると、このダニエル12:11の箇所で『1290日』と言われているのと明らかに調和しない。しかし、ダニエル8:14の箇所では1150日と言われていると捉えると、ダニエル12:11の期間と調和する。しかし、どうして我々が今見ている箇所では1150日と教えられているのに、ダニエル12:11の箇所では『1290日』と言われているのか、と疑問に感じる人がいるはずである。この2つの箇所で言われている期間には、140日の違いがあるではないか、と。この問題はなかなか難しい。このことについては、また後程、私の理解が進んでから、この箇所を書き直すことになるであろう。しかし、我々はこのような僅かな違いが見られる箇所が、他にも聖書には多くあるということを知っておくべきである。例えば、マタイ17:1の箇所ではキリストが御国の到来について語られてから『6日たって』弟子たちを高い山に導いて行かれたと書かれているが、ルカ9:28の箇所では『8日ほどして』高い山に行かれたと書かれている。つまり、明らかに2日の違いがある。これは見方の違いによって記述における日数の違いが生じているのだが、このように日数において記述上の違いがあったからといって、キリストが10日以内に高い山に登られたということは確かな事実なのである。それと同じで、我々が今見ている2つの箇所で日数の違いが見られるのも、恐らく見方の違いが原因となっているのであろう。すなわち、ある観点から見れば『1290日』だが、別の観点から見れば『2300の夕と朝』すなわち1150日なのだ。それだから、この2つの箇所で140日の違いが見られるからといって、我々は不信を抱いたり慌てたりしてはならない。
『そのとき聖所はその権利を取り戻す。」』
エピファネスが不幸な病により死ぬと、エルサレムにはかつての日常が戻った。それは、もはや荒らす者が消え失せたからである。そうして後、神殿では供犠が自由に捧げられるようになった。それゆえ、ここでは『そのとき聖所はその権利を取り戻す。』などと言われているのである。これ以降、終わりの日がユダヤに訪れるまでの間、聖所がその権利を失うことになったのは2回起きた。1回目はポンペイウスがユダヤを侵略した時であり、2回目はユダヤ戦争の時に大祭司エレアザロスが叛徒ヨアンネスにより殺された時である。そして紀元70年に終わりの日が到来して以降、ユダヤは永遠にその聖所の権利を失うことになった。彼らは再びエルサレムに聖所を建ててその権利を取り戻したいと切願しているが、その願望が成就されることは絶対に有り得ない。
【8:19】
『そして言った。「見よ。私は、終わりの憤りの時に起こることを、あなたに知らせる。それは、終わりの定めの時にかかわるからだ。』
ダニエルに示されたのは、『終わりの定めの時にかかわる』幻であった。この『終わりの定めの時』とは、もちろんユダヤが紀元70年に終わりを迎えることである。しかし、ここで疑問が生じる。すなわち、ダニエルに示された幻は確かに終わりの時に関わる幻であったが、エピファネスという明らかに終わりの時に現われるのではない人物が、どうしてユダヤの終わりの時に関わっていると言えるのか、という疑問である。これは、次のように考えれば解決できる。つまり、エピファネスとその暴虐は、ユダヤの終わりの時に現われるネロとその暴虐を予表していたのである。エピファネスとその暴虐そのものがユダヤの終わりと直接的な関係を持っているというのではないが、それがユダヤの終わりを予表しているという意味では大いに関わりがあった。要するに、ここで言われているのは、これから現われるエピファネスと彼が行なう暴虐を見て、その後に現われるネロとネロが行なう暴虐を知ることが出来る、ということである。だからこそ、エピファネスの出てくる幻は『終わりの定めの時にかかわる』幻だったのである。聖徒たちは、ここで『終わりの定めの時にかかわる』と書かれており、「終わりの定めの時のこと」とは言われていないことに着目すべきである。『かかわる』という言葉は、つまり<間接的な意味を持っている>ということである。また、それはダニエルを通して聖徒たちに知らされるべきものであった。というのも、聖徒たちにとってユダヤの終わりに関する事柄は非常に重要なことだからである。
【8:20】
『あなたが見た雄羊の持つあの2本の角は、メディヤとペルシャの王である。』
ここでは雄羊の秘儀が開示されている。雄羊の持つ2本の角が『メディヤとペルシャの王』であるということ自体は、あまりにも明白だから、何も説明する必要がない。注意せねばならないのは、ここではメディヤとペルシャがセットにされているということである。ペルシャはある時まではメディヤに服していた状態にあった。しかし、紀元前550年になるとペルシャが自分の服していたメディヤを打ち倒したので、その時からペルシャだけが角として保たれ続けることになった。それにもかかわらず、この幻ではメディヤとペルシャが一緒にして取り扱われている。さて、どうしてこの幻の中ではこの2つの国がセットにして語られているのか。歴史を見れば、ペルシャという角がメディヤという角を打ち砕いたのだから、ペルシャという1本の角だけが描かれるべきではなかったのか。これの解決は容易である。つまり、この雄羊の幻がダニエルに与えられたのは、メディヤが滅ぼされる紀元前550年よりも前だったのである。その時には、まだメディヤは滅ぼされておらず、ペルシャはメディヤに服属している状態だったから、この2つの国はセットとして取り扱われるべきであった。だからこそ、ここではペルシャだけでなくメディヤも含められた状態の雄羊が描かれているのである。だから、もしこの幻の示された年が紀元前550年以降だったとすれば、もうその時にはメディヤという角は滅ぼされているのだから、ここではペルシャという1本の角だけを持った雄羊が描かれていたはずである。実際、この幻がダニエルに与えられたのは『ベルシャツァル王の治世の第3年』(ダニエル8章1節)すなわち紀元前552年だったが、それは、まだメディヤが紀元前550年にペルシャにより打ち滅ぼされる前であった。
【8:21】
『毛深い雄やぎはギリシャの王であって、その目と目の間にある大きな角は、その第一の王である。』
続いて雄山羊の秘儀が開示されている。この雄山羊がギリシャとその王であるということ自体には、何ら不明瞭な点はなく、特に何かを説明する必要もない。この雄山羊が『毛深い』と言われているのは、つまりギリシャの王が非常に獰猛・野蛮だったことを教えている。角が『目と目の間にあ』ったのは、角が頭の部分に付いていたことを聖徒たちによく認識させるためである。この雄山羊の角は大きかったが、この角は、雄羊に付いているペルシャの角よりも大きかったと考えるべきである。何故なら、ギリシャの角はペルシャの角を打ち滅ぼしたからである。打ち滅ぼしたということは、つまり打ち滅ぼした側のほうが大きいということである。つまり、この幻における角の長さとは「強さ」を示しているのだ。雄羊に付いている2本の角においても、ペルシャという角がメディヤという角を打ち倒したのだから、やはりペルシャという角のほうがより巨大であった(ダニエル8:3)。
【8:22】
『その角が折れて、代わりに4本の角が生えたが、それは、その国から4つの国が起こることである。しかし、第一の王のような勢力はない。』
『その角が折れて』とは、アレクサンドロスが死ぬことを言っている。この王が死んで後、先に見た『4つの国が起こること』になった。この4つの国は『著しく目だつ』(ダニエル8章8節)国ではあったものの、『第一の王のような勢力はな』かった。これはアレクサンドロスおよびその帝国における強大さと、この4つの国を比較してみれば、よく分かる。確かにアレクサンドロスに比べて、この4つの国とその王は、知名度も力も権威も支配力も遥かに劣っていたのである。
【8:23】
『彼らの治世の終わりに、彼らのそむきが窮まるとき、横柄で狡猾なひとりの王が立つ。』
『彼らの治世の終わり』とは、「4つの国が全て終焉を迎える時期が近づいてくると」というほどの意味である。実際、ここで言われている『横柄で狡猾なひとりの王』は、紀元前146年にまだ滅ぼされていなかった最後の国であるマケドニアが滅ぼされる少し前に出現した。この王が現われてから少し経つと、遂に4つに分けられた国の全てがその独立国家としての治世を終わらせることになった。だから、正にここに書かれていることは歴史が示している通りであって、真実である。『彼らのそむきが窮まるとき』とは、「4つの国における罪悪が看過ならない領域にまで神の御前に積み重ねられるようになると」というほどの意味である。
『横柄で狡猾なひとりの王』とは、もちろんエピファネスを指す。書き残された歴史が示しているように、この王は本当に傲慢であり手の付けようがない暴君であった。
【8:24】
『彼の力は強くなるが、彼自身の力によるのではない。』
このエピファネスは強くなっていったが、それは彼の自力によるのではなかった。では誰によりエピファネスは強くされたのか。それは、他でもないサタンである。我々は、先に第3部の中で、ネロが邪悪な暴君として台頭したのはサタンの働きかけがあったからであるということを確認した(黙示録13:2、4)。すなわち、サタンがネロに『力と位と大きな権威を与えた』
からこそ、ネロは暴君として現われ、とんでもないことを幾度となく仕出かしたのであった。つまり、もしサタンが働きかけていなければ、邪悪な暴君としてのネロは現われていなかった。これと同じことがエピファネスについても言える。エピファネスもサタンにより力と位と大きな権威を受けたからこそ邪悪な暴君として台頭したのであり、もしサタンの働きかけが無ければ邪悪な暴君としてのエピファネスはいなかったであろう。確かに、サタンの働きかけについて考慮することなしに、あのような邪悪さは説明がつかない。というのも、サタンがアダムとエバに罪を犯させて堕落させた出来事を考えれば分かるように、極度の邪悪というものはサタンが第一原因となって人間に引き起こされるものだからである。ユダがキリストを売り渡したのも、やはりサタンがユダに働きかけたからであった。もしサタンの働きかけがなければ、つまり人間だけであれば、とんでもない邪悪さにまで突き進むことは難しいのである。
『彼は、あきれ果てるような破壊を行ない、事をなして成功し、有力者たちと聖徒の民を滅ぼす。』
エピファネスは『あきれ果てるような破壊を行な』ったが、これはエルサレムの破壊のことを言っている。それは実に凄まじいものであった。なお、この箇所で言われている破壊を行なったのが、ネブカデレザルだったと考える者があってはならない。確かにネブカデレザルもエルサレムを破壊したのではあるが、ここで言われている破壊者はネブカデレザルではない。何故なら、ネブカデレザルのバビロンは先に見た雄羊であるメディアの角と一緒に、雄山羊であるペルシャの角により打ち滅ぼされているからである。つまり、この箇所で言われている破壊の出来事が起きた時には、既にネブカデレザルは死んでいるし、世の覇者としてのバビロンも消え失せている。それゆえ、この箇所に出てくる破壊者をネブカデレザルだと捉える者は、この獣の幻について全く理解していないか、または理解があまりにも浅いと言わねばならない。
エピファネスは『事をなして成功し』たが、これは神がエピファネスの悪を抑制されなかったことを言っている。全てを動かしておられる神は、エピファネスの悪が大いに発露されるのをお望みになった。だからこそ、彼はとんでもない暴虐を阻まれることもなく繰り返し繰り返し重ねたのである。しかし、神が彼の悪を抑制されなかったのは何故なのか。それは、この王が、豊かに裁かれるようになるためであった。このように神は、ある者の悪が発露されるのを、あえて許可されることがある。それは神が御自身の望んでおられる目的を達成されるためである。その目的の達成されるために抑制の恵みが取り上げられた悪人は、どうしても自発的に悪に進まざるを得ない。彼は自分が悪を行なうことを抑えることが出来なくなる。何故なら、神がその人から恵みを取り上げられたからである。
この邪悪な王は『有力者たちと聖徒の民を滅ぼ』すこともした。これは実際の歴史が示している通りである。このような愚行をしたエピファネスは実に忌まわしい存在であった。だから、彼は確かに「憎むべき者」と呼ばれるに相応しい王である。
【8:25】
『彼は悪巧みによって欺きをその手で成功させ、心は高ぶり、不意に多くの人を滅ぼし、君の君に向かって立ち上がる。』
エピファネスは『悪巧みによって欺きをその手で成功させ』たが、これは彼の悪が神により抑制されなかったので恣に振る舞うことが出来た、という意味である。これは前の聖句で『事をなして成功し』たと言われているのと同じ意味である。このように邪悪な振る舞いが何も制御されないことは、確かなところ、実に恐ろしい。何故なら、それは、その人が完全に神から見放されたことを意味しているからだ。すなわち、見放されたからこそ、悪に委ねられてしまうわけである。
エピファネスの『心は高ぶ』っていたが、これは文字通りに捉えればよい。しかし、彼の心が高ぶっていたのは何故なのか。それは、彼が堕落していたからである。堕落しているからこそ、人の心は高ぶる。もし堕落していなければ、人は誰も高ぶりの心を持たなかったであろう。実際、聖なる御使いたちは堕落していないので、常に謙遜な心で神と人とに仕え、決して高ぶりを持つことがない。このエピファネスは堕落の性向が抑えられていなかったので、多かれ少なかれ抑制の恵みを受けている他の人たちよりも大いに高ぶっていた。
またエピファネスは『不意に多くの人を滅ぼし』た。これは歴史が示している通りである。サタンが彼に強く働きかけていたので、このような悪を行なったのだ。これはネロの場合でも同様であった。ネロの精神はサタンによって完全に駄目にされていたので、ネロは不意に多くの人たちを殺した。ネロはサタンに取り憑かれていたから、自分の母や師までも不意に殺したほどであった。
エピファネスは『君の君に向かって立ち上が』った。これは神のことである。何故なら、神とは人間の君に権威を与えた(ローマ13:1)、君をも支配する神なる君だからである。この『君の君』を、サタンであると捉える者があってはならない。確かに多くの不信仰な王たちの父はサタンだから、その意味でサタンは「君の君」と言うことが出来る。しかし、ここではそのような意味で『君の君』と言われているのではない。それでは、どうしてエピファネスは神にまで立ち向かうという大それた愚行を為すに至ったのか。これには確かな理由があった。まず、彼が神に対抗したのは、彼にサタンが強く働きかけていたからである。このサタンは、神に立ち向かい、出来るならば神を屈服させてやりたいと願っているのである。つまり、サタンはエピファネスを通して、ユダヤ人たちの信じていた真の神に戦いを挑んだわけである。また、彼が神に対抗したのは、彼の精神が傲慢だからであった。極度の傲慢は、神にも打ち勝つことが出来ると思うものである。この2つの理由、すなわちエピファネスにサタンが働いており、エピファネスが傲慢な精神を持っていたということを考えると、彼が神に向かって対抗しないほうが、かえって異常・不思議であったと言える。
『しかし、人手によらずに、彼は砕かれる。』
この呪われた暴君は、『人手によらずに』『砕かれ』た。これは、彼が地上にいる誰かの働きかけによらず神により砕かれた、という意味である。『砕かれる』とは、つまり死ぬことである。聖書においては人間が「器」として取り扱われていることを思い出すべきである(ローマ9:21)。すなわち、救いに定められていた人間は「良い器」であり、滅びに定められていた悪者は「悪い器」である。エピファネスは明らかに「悪い器」であった。人間は「器」なのだから、聖書において、その死は「砕かれる」という表現で示されるのだ。それでは、彼はどのようにして死んだのか。それは恐ろしい病であった。神が裁きによりエピファネスに不幸な病による死をお与えになったのである。彼は耐え難い腐臭を周囲に撒き散らしながら死んだ。
我々は、この暴君だけでなく、ネロも人手によらずに砕かれたことを知るべきであろう。ネロも、誰かの手によるというよりは、自分の手で自殺することにより死んだ。これは再臨されたキリストの『御口の息』(Ⅱテサロニケ2章8節)により自殺という死をネロが受けたからであった。この再臨によるネロの死については、既に十分に語られた通りである。神は、このようにして『人手によらずに』悪者を殺される。
【8:26】
『先に告げられた夕と朝の幻、それは真実である。』
これまでにダニエルに示された獣の幻における預言は、偽りのないものであったと、ここでは言われている。つまり、その幻における預言は拒絶されてはならず、受け入れられなければならないものであったということである。
聖書では、何か非常に重要な事柄が知らされる際、このようにして御言葉の真実性が伝えられている箇所が多く見られる。例えば、キリストは神の国の到来について告げられた際に、このように言われた。『しかし、わたしは真実をあなたがに告げます。』(ルカ9章27節)黙示録でも、キリストと教会の婚姻について知らされた際、御使いが次のように言っている。『これは神の真実のことばです。』(黙示録19章9節)聖書でこのように御言葉の真実性が伝えられるのは、御言葉というものが神の言われたことであって、それは絶対に信じられなければいけないものだからである。我々も絶対に守られなければいけない約束や規則などを告げる際、例えば「これは絶対に疑ってはならないものだ。」などと言うことが往々にしてある。聖書で『それは真実である。』などと言われているのは、つまりは、我々が「これは絶対に疑ってはならないものだ。」などと言うようなものである。
ところで、ここで言われている『夕と朝の幻』とは具体的には何のことを言っているのか。これは、ダニエル書をよく読み、少し考えれば、神の恵みにより分かる。まず「夕の幻」とは、ダニエル7:1~27の箇所に書かれている『ベルシャツァルの元年に』(ダニエル7章1節)示された幻のことである。これは『夕』に示された。何故なら、ダニエル7:1の箇所では、ダニエルが『寝床で、一つの夢、頭に浮かんだ幻を見て、その夢を書きしるし、そのあらましを語った』と書かれているからである。寝床で夢を見たというのだから、これは「夕」であるとすべきである。実際、ダニエルは『私が夜、幻を見ていると、…』(ダニエル7章2節)と言っている。次に「朝の幻」とは、ダニエル8:1~25の箇所に書かれている『ベルシャツァル王の治世の第三年』(ダニエル8章1節)に示された幻のことである。こちらのほうは『朝』に示された。というのも、ダニエルはこの預言を示されてから『起きて王の事務をとった』(ダニエル8章27節)と書かれているからである。その幻が示されてから起きて仕事に取り組んだというのであれば、その幻が示されたのは夕ではなく朝だったはずである。というのも普通に考えて、夕の時間帯に起きて仕事に取り組むというのは、あまり自然なことではないからである。
『しかし、あなたはこの幻を秘めておけ。これはまだ、多くの日の後のことだから。」』
ダニエルに示された獣の幻による預言は、『秘めてお』く、すなわち隠しておかねばならなかった。何故なら、その預言が実現されるのは『多くの日の後のことだから』である。ただこの理由のゆえに、ダニエルは自分に示された幻を隠しておかねばならなかった。つまり、もしその預言が近い未来に実現されるのであれば、その預言を隠す必要はなかった。それでは、『多くの日の後』とは具体的にどれぐらいの期間だったのか。まず7:1~28の箇所で示された夕の幻は、ユダヤの終わりについての預言だったから、その預言が全て実現されるのはダニエルの時代から600年以上も後のことである。次に8:1~25の箇所で示された朝の幻は、エピファネスがユダヤを荒らすことについての預言だったから、それが全て成就されるのはダニエルが預言を受けてから凡そ400年後であった。確かに、これは『多くの日の後のこと』である。それだから、ダニエルは自分について示された幻が実現されるのを、その目で見ることが出来なかった。朝の幻で示された獅子のような獣であるバビロンが熊のような獣であるペルシャに打ち滅ぼされるという出来事(ダニエル7:4~5)については見た可能性もあるが、それ以外はどう考えてもダニエルが見ることは不可能であった。しかし、どうして『多くの日の後』に実現されるからというので、その預言を封じておかねばならなかったのか。それは、まだまだ後の未来に実現される預言を聖徒たちが事前に聞いても、あまり意味がないばかりか、心に良くない影響が及ぼされるからであった。要するに、そのような預言を聞いても、ただネガティブになる以外の作用は生じなかった。これとは逆に、キリストの預言の場合、たとえ『多くの日の後』に起こる預言であったとしても、それを事前に知ることは非常に益であった。というのも、キリスト預言は、それが実現されるずっと前の時期に聞いたとしても、聖徒たちに喜びと希望を抱かせる作用を引き起こすものだからである。このゆえに、キリスト預言については封じられるようにと命じられはしなかった。だから、もしキリスト預言が聞いて害をもたらすものだったとすれば、キリスト預言も我々が今見ている預言と同様に隠されねばならないことになっていたであろう。その場合、預言を聞いても無意味であり害が生じるだけだからである。
黙示録の場合、こことは全く反対のことが言われている。そちらのほうでは、預言を『封じてはいけない。』(黙示録22章10節)と命じられている。つまり、黙示録の預言のほうは、絶対に隠されてはいけなかった。何故なら、その預言の実現される『時が近づいている』(同)からである。当時は預言された大きな患難が間近に迫っていたのだから、その患難が不意に襲いかかって来ることのないように、つまりあらかじめ心の準備をすることができるために、語られた預言を大いに周知拡散しなければいけなかった。これについては既に第3部の中で説明されたから、もうこれ以上の説明は必要ないであろう。なお、我々が今見ているダニエル書の箇所を考察すれば、黙示録で示されている預言が2千年経過しても未だに起きていないと理解することは絶対に出来ない、ということは明らかである。我々が今見ているダニエル書の箇所では、1000年以内に起こる預言でさえ、それが恐ろしく遥か前の時代に知っても意味が無いからというので、隠しておくように命じられている。であれば、もし黙示録で示されている預言が2千年以上経過してから実現されるとすれば、それはダニエル書の預言と同じで恐ろしい出来事に関する預言なのだから、尚のこと、隠しておくべきだったはずである。その場合、普通に考えれば、隠しておかねばならない必要性は明らかにダニエル書よりも黙示録のほうが優っている。何故なら、ダニエル書の預言は1000年以内に起こるのに対し、黙示録の預言のほうは2000年経過しても起こらないと理解されているからである。ところが、黙示録の預言は、それが恐ろしい預言であるにもかかわらず、隠してはならないと言われている。このことから、黙示録の預言が2000年経過しても起きていないと理解するのは間違っているとせねばならない。もし2千年経過しても黙示録の預言が成就しないというのであれば、黙示録のほうでも『あなたはこの幻を秘めておけ。』とヨハネに命じられていたはずだ。何故なら、ダニエル書によれば、遥か未来の時代に起こる恐るべき出来事に関する預言は隠されねばならないものだからである。しかし、そのような命令はヨハネに与えられなかった。だから、私が前から言っているように、確かに黙示録の預言とは『すぐに起こるはずの事』(黙示録1:1)であって、その『すぐに』とは文字通りの意味として捉えねばならないものなのである。
【8:27】
『私、ダニエルは、幾日かの間、病気になったままでいた。その後、起きて王の事務をとった。しかし、私はこの幻のことで、驚きすくんでいた。それを悟れなかったのである。』
ダニエルが病気になったのは、恐らく神から示された幻における預言が、あまりにもショッキングな内容だったからであると思われる。2年前に示された夕の幻を見た際、ダニエルは、その驚くべき内容にショックを受けた。『私、ダニエルは、ひどくおびえ、顔色が変わった。』(ダニエル7章28節)と書かれている通りである。我々が今見ている箇所に書かれている朝の幻も、やはりショッキングな内容であった。だから、その精神に対する衝撃が、ダニエルの身体に病を生じさせたのだと考えられる。例えば身近な人が死んでしまったので精神が塞ぎ込み、自分まで病気になってしまった、という話はそこまで珍しいものではない。このよう例からも分かるように、精神と健康には、明らかに関係がある。それだからダニエルが幻を見て病気になったのは、要するに「病は気から」ということなのであろう。つまり、ダニエルの身体に病を引き起こすほどに、この幻は衝撃的だったということである。しかし、その病がどのような種類のものだったか我々は知らない。風邪だったのかもしれないし胃炎だったのかもしれないし頭痛だったのかもしれない。いずれにせよ、ダニエルの身体に起きた病が何なのかということは些細な問題であるから、我々はただダニエルが『病気になったままでいた』ということだけを知っていれば十分である。
この幻をダニエルは『悟れなかった』と、ここでは言われている。これは当然であった。夕に示された幻について言えば、ダニエルが第3の獣であるマケドニアの台頭(ダニエル7:6)や暴君ネロの出現について悟ることは、絶対に出来なかった。朝に示された幻について言えば、ダニエルがアレクサンドロスの死とその死に引き続く帝国の分割(ダニエル8:8)やエピファネスの出現(ダニエル8:9)について悟ることは、どのようにしても出来なかった。神は、この幻を抽象的に示されたのであって、『メディアとペルシヤ』また『ギリシャ』(ダニエル8章20~21節)を除けば具体的な名を挙げてダニエルに示されることはされなかったのである。これではダニエルが幻の内容をよく悟れなかったとしても無理はなかった。
神は、その預言を示された人がその内容を悟れないにもかかわらず、預言を示される御方である。このダニエルの場合、神はダニエルがエピファネスやネロのことを悟れないにもかかわらず、この2人の暴君についてダニエルに預言をお与えになった。神は、具体的な名を示して悟らせることもお出来になられたが、幾つかのことを除けば、ここではそのようにされていない。つまり、ダニエルは「分かり得ないこと」を聞いた。神が、このように悟れない内容であっても預言をある人に示されるのは何故なのか。それは、まず神とは絶対的な主権者であられるからである。絶対的な主権には、当然ながら「黙秘権」も含まれている。だから、黙秘権をお持ちである神は人が悟れるように預言を示す義務を負わされていないのである。これは、ちょうど国王が「私にはこれから行きたい場所があります。」とだけ言って、どこに何をしに行くのかまでは説明する義務を負っていないのと同じである。国民は、この国王に向かって「王様。どこに何をしに行くのか説明しないのはどういうわけですか。」などと問う権利は持っていないのである。また、悟れないにもかかわらず預言が示されるのは、かえって悟れないほうが良い場合が多いからである。このダニエルの場合もそうであって、エピファネスやネロの暴虐について具体的に悟れないほうが、かえってダニエルには良かった。何故なら、それについて知っても、ますます恐怖が増し悲観的になるだけだからである。物事には何でも適切さがあるものだが、これは神が与えられる預言の内容においても同様のことが言えるのだ。
【9:24】
『あなたの民とあなたの聖なる都については、70週が定められている。』
これから見る9:24~27の箇所では、聖所について捧げられた願いに答えられる形で、ダニエルに預言が与えられている。神は、その預言をガブリエルを通してダニエルに示された。御使いを通して預言が示されるというのは、黙示録の場合と同じである。
これから見る箇所は非常に難しい。何が言われているのか全く分からない、と思われる方も少なくないはずである。この難しさは、ここで語られている期間の霊的性質に由来している。我々は、ここで語られている期間を肉的に捉えようとしてしまう。だが、ここで語られている期間は霊的に捉えるべきものである。霊的に捉えるべき期間を、肉的に捉えようとしても、正しい理解を得られるはずがない。だから、この箇所は難しく感じられるのである。また、この箇所における文章表現も難しさを生じさせている一つの要因である。この箇所では、あまり具体的な表現がされていない。例えば、ローマの邪悪な皇帝が御民の勢力を迫害する、などとは言われていない。全体的に抽象的なのである。このため、この箇所はその抽象性ゆえ難しく感じられるのだ。だが、神の恵みをいただくならば、この箇所を上手に理解できるようになる。それは神がその人に教えて下さるからである。
それでは早速、この箇所を見て行くことにしたい。まず『あなたの民とあなたの聖なる都』に『70週』が定められているとは、どういう意味であるか。『あなたの民とあなたの聖なる都』とは、もちろんユダヤ人と都エルサレムを指す。『70週』とは霊的な数字である。注意せよ。これを文字通りに捉えてはならない。文字通りに捉えるならば、何が言われているのか分からなくなってしまう。これは「70」だから、その期間が大いに神聖であることを意味している。つまり、これは期間の時間を教えているのではなく、期間の性質または概念を教えている。何故なら、「70」とは聖なることを示す7に完全数10をかけた数字だからである。要するに、これはユダヤの回復までの期間を『70週』と表現することでその期間を聖別している。この箇所でユダヤの回復について語られているということは、続く箇所を読めば明らかである。
『それは、そむきをやめさせ、罪を終わらせ、咎を贖い、永遠の義をもたらし、幻と預言とを確証し、至聖所に油を注ぐためである。』
ここでは全部で6つの事柄が語られている。内容的に重なり合っている点も幾つかあるが、一つずつ簡潔に見て行きたい。『そむきをやめさせ』。これは、キリストが現われたら、ユダヤ人たちは背きから離れるという意味である。何故なら、ユダヤ人がキリストを信じるならば、神への背きを止めることになるから。ペテロはそうなるようにとユダヤ人にこう言ったのである。『神は、まずそのしもべを立て、あなたがたにお遣わしになりました。それは、この方があなたがたを祝福して、ひとりひとりをその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなのです。』(使徒行伝3章26節)『罪を終わらせ』。これはキリストがユダヤ人の罪を赦されるということである。何故なら、キリストはユダヤ人をはじめ全ての民族の罪が赦されるようにと来られたのだから。『咎を贖い』。これは簡単である。イエス・キリストが永遠の贖罪を実現させられたことを言っている。『永遠の義をもたらし』。これもキリストが聖なる救いを成し遂げられたことを言っている。『幻と預言とを確証し』。これは、キリストについての幻と預言が、ナザレのイエスにおいて成就されるという意味である。旧約の幻と預言はキリストを指し示していたのだから、これは当然である。キリスト御自身もこう言われた。『わたしについてモーセの律法と預言者と詩篇とに書いてあることは、必ず全部成就する』(ルカ24章44節)。『至聖所に油を注ぐ』。これはキリストという神殿の至聖所が聖別されるという意味である。神殿が建てられる際には、その至聖所が油注ぎにより聖別されなければならない。キリストが言われた通り、新約時代の神殿とその至聖所はキリスト御自身であられる(ヨハネ2:19~21)。その新しい神殿の現われについて、ここでは言われているのだ。ところで、ここで言われている6つの項目に数字的な意味は秘められていないと思われる。何故なら、それは「6」だからである。「6」は聖書で人間の意味を持つが、ここではそのような意味が6つの項目に隠されているとは感じられない。これが「7」であれば話はまた違っていたのだが。
今語られたようなことが『70週』の後に実現されると、ここでは言われているのである。この『70週』を文字通りに解すると、もうすぐにもキリストの到来が実現されるということになるから、そのような解釈が間違っているのは明らかである。
【9:25】
『それゆえ、知れ、悟れ。』
ダニエルは、神が語られる預言を知り、そして悟らねばならなかった。何故なら、それは非常に重要なことだからである。このように神から言われたダニエルは、間違いなく知り、悟ろうとしたはずである。何故なら、ダニエルは神に忠実な人だったから。
しかし、9:24~27の箇所で書かれている預言を、ダニエルは細かく悟れなかった。ナザレのイエスという存在が十字架にかけられて人々の前で処刑される。このように具体的なことをダニエルが悟ることは出来なかった。神は、そこまで詳しいことをダニエルに啓示されなかったからである。つまり、ここでは大まかに悟るようにとだけ言われたに過ぎない。ダニエルが細部まで悟ろうとしても、時代の制約があるので、悟ろうにも悟れなかったのだから。
『引き揚げてエルサレムを再建せよ、との命令が出てから、油そそがれた者、君主の来るまでが7週。』
エルサレム再建の命令が出たのは、『アルタシャスタ王の第20年』(ネヘミヤ2章1節)である。それは紀元前445年であった。アルタシャスタの治世の始まりは紀元前465年だったから。この再建命令についてはネヘミヤ2:1~10の箇所に書かれている。周知の通り、この時のエルサレムはネブカデレザルにより荒廃させられたままだったので、再建せねばならない状態であった。
『油そそがれた者、君主』とはイエス・キリストである。これを『大祭司エルヤシブ』(ネヘミヤ3章1節)と解する人がもしかしたらいるかもしれない。すなわち、再建の命令がアルタシャスタ王から出てから、『7週』後に大祭司エルヤシブが再建事業を行なうためにやって来た、と。確かにエルヤシブは大祭司であったから、『油そそがれた者』であった。だが、この解釈は強引であり、粗っぽく、間違っている。何故なら、エルヤシブは『油そそがれた者』ではあったが、『君主』ではなかったからである。またエルヤシブが再建命令の時から『7週』後にやって来たなどとは、聖書のどこにも書かれていない。更にこの存在はやって来てから『62週の後』(ダニエル9:26)に断たれると言われているが、エルヤシブが62週間後に死んだなどと一体どうして分かるのか。このように多くの問題があるゆえ、これをエルヤシブと解することは出来ない。これは間違いなくキリストである。
ここでは再建の命令が発されてからキリストの到来まで『7週』と言われている。実際の期間は約450年である。450年が『7週』だというのは一体どういうわけなのか。これは、つまり再建命令からキリストの到来までの期間を『7週』と言い表すことで、その期間を聖別している。何故なら、7とは聖なることを示す数字だからである。古代のユダヤ人は、キリストの到来を聖い思いで切に待ち望んでいた。それは神の御心に適った待望であった。だから、ここではその待望の期間が「7」という数字により神聖視されているわけである。キリストが到来するまでの待望期間を「7」と神聖視することについて、異を唱える聖徒が果たしているのであろうか。いないであろう。
【9:25~26】
『また62週の間、その苦しみの時代に再び広場とほりが建て直される。その62週の後、油そそがれた者は断たれ、彼には何も残らない。』
『その苦しみの時代に再び広場とほりが建て直される』とは、キリストが聖所を回復されることを言っている。『広場とほり』とはエルサレムを指している。そこには広場と堀があったのだから。『苦しみの時代』とは主の受難の期間である。このキリストの苦しみについてはイザヤ53章でも言われている。要するに、神は、荒れ果てたままの聖所に御顔を輝かせて下さいというダニエルの願いに対して、キリストにおいて聖所が回復されるという誠に霊的な預言をもって回答とされたわけである。ダニエルは物質的な聖所の回復については聞かされなかったが、真の意味における回復については知ることが出来たのである。神がこのような回答をされたのは、たとえ地上の聖所が回復されたとしても、キリストという真の聖所が現われなければ何の意味もないからである。また、ここで言われている内容を、肉的に捉えることがあってはならない。これを肉的に捉えると、たったの『62週』で地上のエルサレムが再建されたことになってしまう。だが、それは有り得ない。ネヘミヤ5:14の箇所を見ても分かるように、再建の事業は明らかに10年以上かかっているのだから。ヨハネ2:20の箇所では、再建に『46年』かかったと言われている。このように肉的に捉えると、訳が分からなくなる。間違った仕方で捉えているから訳が分からなくなるのだ。それゆえ、ここで言われている内容は霊的にこそ捉えなければならない。
ここではキリストの苦しみの期間が『62週』と言われている。実際は約3年であった。3年が『62週』だというのは、どういう意味なのか。これはキリストの苦しみが長いことを示している。何故なら、この箇所に書かれている他の期間は『7週』、『1週』『半周』だからである。これら3つの期間に比べて『62週』は非常に長いのである。
その期間が終わると『油そそがれた者は断たれ、彼には何も残らない』。これはキリストが十字架で死なれてから葬られたことを言っている。これについてはイザヤ53:8、9の箇所でも次のように言われている。『しいたげと、さばきによって、彼は取り去られた。…彼の墓は悪者どもとともに設けられ、彼は富む者とともに葬られた。』
この箇所で言われているのはキリストとその受難としか解しようがない。何故なら、それが正しい理解だからである。ここでキリスト以外について言われていると試しに考えてみよ。そうしても上手に行かないはずである。
【9:26】
『やがて来たるべき君主の民が町と聖所を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて、荒廃が定められている。』
『やがて来たるべき君主』とはサタンである。何故なら、サタンはキリストの時に策略を持ってやって来たからである。キリスト御自身が捕らえられる前にこう言われた通りである。『わたしは、もう、あなたがたに多くは話すまい。この世を支配する者が来るからです。…』(ヨハネ14章30節)そのサタンの『民』とはローマ人を指す。これは文脈から考えるならばローマ兵のことを言っている。
そのローマ兵たちが『町と聖所を破壊する』ことになった、とここでは言われている。これは、もちろんユダヤ戦争のことである。
『洪水』と言われているのは、ローマ軍の象徴表現である。これはユダヤに雪崩れ込んだ数多くのローマ兵たちを、洪水が押し流す出来事になぞらえている。実に巧みな象徴の仕方である。この言葉はダニエル書の後の箇所でも使用されている。
『その終わりまで戦いが続いて、荒廃が定められている』。これはユダヤの終わりの時までローマ軍との戦争が続いて、遂に定められた破滅がユダヤに降りかかるという意味である。その破滅は神の意志に基づいていた。何故なら、ユダヤ人たちは堕落しており、神に背き続け、遂には御子イエス・キリストを拒絶して殺したからである。神がユダヤ人たちに恐るべき荒廃をお与えになったのは、誠に正当なことであった。何故なら、ユダヤ人たちは神に対してこれ以上ないほどの極悪を行なったからである。
【9:27】
『彼は1週の間、多くの者と堅い契約を結び、半週の間、いけにえとささげ物とをやめさせる。』
『彼』とは9:26の『やがて来たるべき君主』を指す。これは9:25~26に書かれていた『油そそがれた者、君主』すなわちキリストではない。
『彼』すなわちサタンは、『1週の間、多くの者と堅い契約を結』んだ。これはサタンがネロを通して多くのローマ人たちを強力にコントロールしたことを示す。『1週』とは期間の短さを示す。何故なら、それは70週の70分の1に過ぎない期間だからである。
またサタンはユダヤに対して、『半週の間、いけにえとささげ物とをやめさせ』た。これはサタンがアンティオコス4世を通してユダヤ人に犠牲を止めさせたように、再びネロを通してユダヤに苦しみを与えるということである。アンティオコス4世の時、ユダヤは犠牲を取り上げられたので大いに悩み苦しんだ。その時のような苦難が、サタンによりネロを通して紀元1世紀のユダヤに降りかかったのである。『半週』とは、ネロの治世のある一定の期間を示している。何故なら、それはネロの治世を示す『1週』のある部分に過ぎないからである。つまり、これはネロの治世の全期間においてユダヤが苦しめられたわけではないことを我々に教えている。実際、ネロがユダヤを苦しめたのは、その治世のある期間だけに過ぎなかった。
ところで、この9:27の箇所ではアンティオコス4世について言われているのではないか、と思う人がいるかもしれない。何故なら、ここでは『いけにえとささげ物とをやめさせる。』と書かれているからである。確かにアンティオコス4世は生贄の儀式をユダヤ人から奪い取った。だが、ネロはユダヤを苦しめただけであって、犠牲を取り去ることまではしなかった。だから、この箇所では確かにアンティオコス4世について言われているとも解せる。しかしながら、これはアンティオコス4世というよりは、むしろネロとして捉えるべきである。つまり、ここではアンティオコス4世においてネロのことが言われていると解すべきである。それというのも、ダビデがキリストの影であったように、アンティオコス4世とはネロの影だったのだから。だから、ダビデについて言われている箇所をキリストのこととして捉えることが可能なように、アンティオコス4世について言われていると感じられるこの箇所もネロとして捉えることが可能なのである。実際、キリストはマタイ24章でアンティオコス4世においてネロのことを預言しておられる(24:15)。また、もう間もなく見ることになるダニエル書11~12章の箇所でも―特に11章の最後と12書の前半がそうだが―、やはりアンティオコス4世を影としてネロという実体について預言されている。
『荒らす忌むべき者が翼に現われる。ついに、定められた絶滅が、荒らす者の上にふりかかる。」』
『荒らす忌むべき者』とはアンティオコス4世とネロである。『翼』とは聖所を指す。アンティオコス4世の時は石造りの聖所、ネロの時は聖徒という聖所である。70人訳では『神殿』となっている。言うまでもなく、この『翼』とは象徴表現だから、文字通りの意味に捉えてはならない。
ここでは、荒らす者が聖所に『現われる』と言われている。これは荒らす者が聖所を蹂躙し悲惨にさせる、という意味である。何故なら、ただ単に現われただけで何もしなかったとすれば、それは取り立てて書くほどのことでもないからである。アンティオコス4世という荒らす者の場合、石造りの神殿を荒らし回った。ネロという荒らす者の場合、聖徒という神殿を荒らし回った。旧約と新約では神殿が異なっているから、荒らす者が荒らす対象も異なっている。もっとも、聖所そのものを荒らすという本質部分では、どちらも行なったことは変わらないのではあるが。
また、ここでは荒らす者が滅ぼされるとも言われている。アンティオコス4世は、後にも書かれるが、恐らく裁きにより与えられたと思われる病により死んだ。ネロは、Ⅱテサロニケ2章で書かれているように、再臨されたキリストにより死んだ。この2人の死滅は、永遠の昔からあらかじめ『定められた』出来事であった。何故なら、この世界では定められた出来事しか起こらないからである。
ここで言われている『荒らす忌むべき者』を、神殿再建を邪魔した妨害者どもだと解釈する人がいるかもしれない。この妨害者どもについては、ネヘミヤ記に書かれている。だが、この見解は初心者的な誤謬である。何故なら、確かに彼らは妨害をしたかもしれないが、『町と聖所を破壊する』(9:26)ことまではしなかったからである。もし彼らについてここでは言われているとすれば、あまりにも大げさな言い方がされていることになる。我々は、キリストと紀元1世紀の時代に心の目を傾けなければならない。そうすれば、ここで言われていることが上手に理解できるようになる。
【11:2】
『今、私は、あなたに真理を示す。』
これから、この箇所よりダニエル書12:13の箇所まで註解がなされる。やや長い箇所だが、ここは見ておかねばならない箇所である。
これから見ていく箇所は、本書において註解に値する箇所なのか、と思われる方がいるかもしれない。というのも再臨の際に起こる復活が書かれている12章はともかく、11章の部分は再臨とはあまり関わりがないように思えてしまうからである。確かに11章を眺めて見ると、そこだけでは再臨と関連があるかのようには思えにくい。もし11章だけに限られていたとすれば、私はここで註解のために11章を取り上げていなかった。だが、12章も含めるならば、11章を註解しなければならない。何故なら復活について書かれている12章をシッカリと理解するためには、そこに至るまでの一連の流れを11章の箇所から把握しておくべきだからである。つまり、11章から続く流れとして12章を把握してこそ、12章が真に豊かに理解できるのである。総合的
な理解が、全体に内包されている個々の部分をより深く・より確かに理解できることに繋がるのは改めて言う必要もないであろう。もし11章を理解しなかったならば、11章と繋がっている12章の内容に確信が持てなくなることにもなるのだ。更に11章の内容を知ることは、歴史的な知識を増すことにもなる。つまり11章の部分から註解をするのは一石二鳥なのである。さあ、それでは註解を始めていこう。
ここで書かれているように、ダニエルは『真理』を示された。この真理とは、ここでは「真実なこと」という意味である。これからダニエルに嘘も偽りもない確かな話が語られるのである。
その真理が示された時期はいつか。それは、キュロス2世の時代、すなわち紀元前547年である。何故こう言えるかといえば、ダニエル書10:1の箇所では、この話が『ペルシャの王クロスの第3年に』語られたと書かれているからである。これはキュロス2世のことであり、その治世は紀元前550~529年であった。これが語られたのはネブカデレザル2世の時代でもダリウス1世の時代でもない。
これから示される真理の預言は、歴史の出来事とまったく一致している。その一致具合は驚異的である。ここで霊的に愚かな死人である不信者たちは、次のようにベチャクチャと喋り立てるに違いない。「ダニエル書11章に書かれているのは、そこに書かれている出来事が全て起きてから書かれたのだ。既に起きている出来事だからこそ、つまり過去の出来事だからこそ、ここまで正確に書くことが出来た。そうでなければ、どうしてまだ起きていない出来事を事前にここまで詳細に正しく書くことが出来るのか。」彼らがこのように言うのは(また心の中で考えるのは)、不信仰のゆえに預言を信じていないからである。確かに預言を信じていなければ、必然的にこのように言わざるを得なくなる。だが、預言は確かにある。これは間違いないことである。だから聖徒である我々は預言を絶対に疑わない。それゆえ、我々は、これから示される事柄がその起きた後で書かれたなどと不信仰な思いを抱かないようにせねばならない。預言における真実性を信じているのであれば、リベラルの理解に陥らなくて済む。何故なら、その人は信仰によって聖書の記述を素直に受け入れることが出来るからである。信仰ある者にとって、預言が正確に書かれているのは、何もおかしなことではないのである。
『見よ。なお3人の王がペルシヤに起こり、第4の者は、ほかのだれよりも、はるかに富む者となる。』
キュロス2世(前550-529)に続く『3人の王』とは、カンビュセス2世(前529-522)、スメルディス(前522)、ダリウス1世(前522-486)である。『第4の者』であるダリウスは、大いに富んでいた。彼は「大王」と呼ばれ、ペルシアの建国者としてキュロス2世と並び称されるほどである。アレクサンドロスも、ダリウスの墓に行った際には、大いに心を打たれた。ここで言われている通り、このダリウスは他の誰よりも富において優っていた。
『この者がその富によって強力になったとき、すべてのものを扇動してギリシヤの国に立ち向かわせる。』
ダリウスが大いに富んで強くなると、ギリシャ遠征を大胆にも企てた。ペルシヤ帝国の支配領域をギリシャのほうまで押し広げようというのである。この企ては上手に行かなかった。息子のクセルクセスも、父のギリシャ征服を継続して行なったが、やはり徒労に終わってしまった。全てを支配される神が、この企てが成就されることを御許しにならなかったのである。ここではダリウスが『その富によって強力になったとき』にギリシャに侵攻した、と言われている。これは、この企てが高慢に基づいていたことを教えている。何故なら、多くの富は人を高ぶらせるからである。そうして高ぶった者は、自分こそが至高の知者であると無謀にも思い込み、とんでもないことを平気で言ったり仕出かすようになる。これはネロがその良い例である。カルヴァンは言う。「人間というものは、豊かさに満ち溢れますと、あるいは、高い権力の座に着きますと、自分というものを見失い、さらには神を誹謗するようになるのです。自分たちが全ての危険の外にいるものと思い込んで。」(『アモス書講義』第4章 p121:新教出版社)富が自己を知者であると錯覚させるということについては、ソロモンが次のように言っている。『富む者は自分を知恵のある者と思い込む。』(箴言28章11節)『ほかのだれよりも、はるかに富む者』であったダリウスが、正にこれであった。つまり、彼は自分が知者であると富のゆえに思い込んでいたからこそ、ギリシャも征服できるに決まっていると考えたのである。ところで、この『第4の者』がダリウスではなく、ダリウスの子であり次の王であったクセルクセス1世(前485-465)ではないのかと疑問に感じる方がいるかもしれない。それというのも、スメルディスは王としてカウントしていいものかどうか悩ましい存在であるからである。もしスメルディスが第3の王としてカウントされるべきではないとすれば、確かにクセルクセスが『第4の者』だったことになる。だが、この『第4の者』はダリウスである。何故なら、我々が今見ている箇所では、第4の王が初めてギリシャ遠征を企てると教えられているからである。クセルクセスもギリシャに立ち向かったが、それは父の企てを引き継いだだけであって、ギリシャへの侵攻を始めたのはダリウスである。だから、我々はスメルディスを第3の王としてカウントし、第4の王をダリウスとして認識せねばならない。
【11:3】
『ひとりの勇敢な王が起こり、大きな権力をもって治め、思いのままにふるまう。』
これはアレクサンドロス大王のことである。アレクサンドロスは『勇敢な王』であった。これは驚くべきことだが、この王はたった一人で、1000人もの敵に臆することなく向かって行くことさえした。しかも他の兵士たちが救援に来るまで、多くの敵を殺し、打ち負けることが無かった(※①)。また彼はインドの辺りまで猛烈な勢いで征服しつつ進んで行った。もし彼の部隊に老兵が多くいたのでなければ、恐らく中国や日本までも征服していたかもしれない。彼は父ピリッポス2世の頃から戦争に従事している老兵のことを気遣って―老兵たちは体力の限界に達していた―、インドで引き返すことにしたのである。私の思うに、父譲りの獰猛さとギリシャ人によく見られた名誉を愛する心―単なる虚栄であると見做すことも出来るが…―と師であったアリストテレスの感化による「偉大さへの熱心」とサタンの働きによる支配への傾倒(※②)が、あのような勇敢さを生じさせたのであろう。とにかくあの勇敢さは普通ではなかった。これは誰もが認めるところであろう。またアレクサンドロスは『大きな権力をもって治め』た。これは歴史が示す通りである。アレクサンドロスの名が持つ偉大性のゆえに、多くの国や民族が、自発的にこの王に服属した。またアレクサンドロスは『思いのままにふるま』った。これも歴史の示す通りである。彼は手が付けられない王であり、怒りに任せて最も大切な友人を槍で刺し殺すことさえした。特に酒宴の席では振る舞いが酷く、酔った勢いで人を殺すことも珍しくなかった。このため、酒宴の後に死人が出るのは普通のことであった。この王の傍若無人な振る舞いを抑制できる者は誰一人としていなかった。
(※①)
トログスは、アレクサンドロスの軍隊がマンドリ族とスドラカェ族に打ち勝った時の出来事について、こう書いている。「彼は戦闘で勝者となって、軍隊を彼らの市へと導いた。城壁に1番によじ登って、そこから眺め渡して、防衛していた者たちが市を見捨てたことを知ると、彼は一人の護衛もつけずに市の表面に飛び降りた。そこで敵は彼が一人であるのを見て、叫び声をあげ、そしてアレクサンドロス一人の首をとれば、世界中の戦争を終わらせ、多くの種族に仇をとってやれると思って、四方から馳せ集まって来た。一方、アレクサンドロスも同様に辛抱強く抵抗し、一人で何千人の者に対して戦った。言っても信じがたいことだが、敵の大群も、投槍の大きな力も、挑んで来る者たちの大きな叫び声も彼を恐れさせることはなく、彼は一人で何千人をも倒し、逃亡させた。しかし彼は自分が大群に圧せられているのを見ると、城壁の前にその時立っていた木の幹にもたれかかって、その助けのお蔭で、長い間敵の一団の攻撃に耐えた。しかし、彼の危険を知って、幕僚たちが城壁から飛び降りて彼の所へやって来たが、それらのうちの多くの者が倒された。そして戦闘は、城壁を毀して前軍隊が救援にやって来るまで、長い間決着がつかなかった。彼はその戦闘で乳の下を矢で打ち抜かれ、血を流して弱り果てたが、傷を負わせたその男を倒すまで、膝をついて、長い間戦った。」(ポンペイウス・トログス/ユニアヌス・ユスティヌス抄録『地中海世界史』第12巻 9 p202:京都大学学術出版会 西洋古典叢書)
[本文に戻る]
(※②)
母オリュンピアは、アレクサンドロスを身籠った日に蛇と交わった夢を見たが、それ以降、アレクサンドロスが自分と蛇の間に生まれた子だと言って止まなかった。子のアレクサンドロスは、母の言ったことを真に受けていた。父のピリッポスも晩年になって、アレクサンドロスが蛇との間に生まれた子だと信じてしまった。これは母の狂った思い込みに過ぎなかったが、蛇と交わってアレクサンドロスが生まれたというのは、つまり蛇であるサタンがアレクサンドロスに憑りつくということを意味していたのであろう。
[本文に戻る]
この11:3の箇所は、すぐ前の節である11:2の箇所から、かなり時間が隔たっている。11:2に出てくるダリウス1世が死んだのは前486年であり、アレクサンドロスが王となったのは前336年だから、11:2と11:3の間には150年ほどの時間が経過していることが分かる。この11:2と11:3が時間的に隔たっていないと理解すると、11:2は上手に理解できても、11:3のほうは理解不可能となってしまうから気を付けねばならない。
【11:4】
『しかし、彼が起こったとき、その国は破れ、天の四方に向けて分割される。それは彼の子孫のものにはならず、また、彼が支配したほどの権力もなく、彼の国は根こぎにされて、その子孫以外のものとなる。』
これは、アレクサンドロスが前323年に死んでから、彼の大帝国がディアドコイと呼ばれる遺将たちにより4分割されて治められたことを言っている。『天の四方に向けて分割される。』と書かれているのは、その分割された4つの国が世界的な規模を持っていたからである。その4つの国とは、既に述べたように、シリア(アンティパトロス朝)、トラキア・小アジア(リュシマコス朝・カッサンドロス朝)、マゲドニア(セレウコス朝)、エジプト(プトレマイオス朝)であった。この箇所で言われているように、この4つの国は、それぞれアレクサンドロスほどの支配力を持ってはいなかった。アレクサンドロスの権力が100だとすれば、私の思うに、これら4つの国はそれぞれ40~60ぐらいの権力だったのではないか。この時において、アレクサンドロスの大帝国は『根こぎにされて』しまった。もうその大帝国は、それ以降、復活することが無かった。栄枯盛衰。アレクサンドロスは急速に台頭したが、その没落も速やかに訪れた。これら分割された4つの国は、この箇所で言われている通り、アレクサンドロスの『子孫以外のものと』された。アレクサンドロスの子どもが、その国を支配することはなかった。何故なら、アレクサンドロスは死ぬ直前に、部下たちから帝国の後継者が誰になるのかと尋ねられた時、賢明にも「もっとも相応しい者を。」と言ったからである(※)。つまり、後継者の要件を「血」ではなく「適切さ」に求めた。彼は、冷徹性が求められる支配者に相応しく―支配者は情に振り回されるようであってはいけない―、情よりも理知のほうを優先させたのである。これは正しいことであった。しかしながら、このために彼の将軍たちが壮絶な後継者争いをしたのであった。それというのもアレクサンドロスの将軍たちは、トログスも言っているように誰もがみな「王クラス」の傑物ばかりであって、王になるに相応しい素質と力を持ち合わせていたからである。
(※)
「彼の力が尽き果てると幕僚たちが見た時、彼らは誰を帝国の後継者にするか、と尋ねた。彼は、最もふさわしい者を、と答えた。」(ポンペイウス・トログス/ユニアヌス・ユスティヌス抄録『地中海世界史』第12巻 p210:京都大学学術出版会 西洋古典叢書)
[本文に戻る]
この箇所以降、11章では4つに分割された国のうち2つの国、すなわちエジプトとシリアだけしか出てこない。そこでは、エジプトが『南』の王国として、シリアが『北』の王国として語られている。この南王国と北王国が色々と争っているのは、シリア戦争のことである。そこにおいてもう2つの国、すなわちマゲドニアとトラキア・小アジアはまったく出てこない。何故なのか。それは、北王国であるシリアから出てくる「荒らす憎むべき者」を通じて、12章に書かれている復活の事柄へと話を繋げるためである。このシリアの暴君は、12章における復活の出来事と大いに関わりを持っている。だから、この11章では、荒らす憎むべき者の国である北王国シリアとこの北王国シリアと深い関係のある南王国エジプトのことが詳しく語られているのである。
【11:5】
『南の王が強くなる。しかし、その将軍のひとりが彼よりも強くなり、彼の権力よりも大きな権力をもって治める。』
『南の王』とはエジプトのプトレマイオス1世(前305-282)である。彼はアレクサンドロスの死後にエジプトの王であるファラオとなり、プトレマイオス朝エジプトを創建し、大いに強くなった。なお、ここではエジプトの王について語られているが、エジプトだからといって、マトリックスに出てくるモーフィアスのような黒人系の王を想像してはならない。プトレマイオスはギリシャ人だったから、恐らくヤペテ系であって、やや中東系の印象を持つ白色人種の人間であった。彼の胸像を見ても、彼が白人系の人間だったことが分かる。
『その将軍のひとり』とは、アレクサンドロス大王に仕えていた将軍の一人、という意味である。次の6節目を見ると、この将軍は『北の王』だったことが分かる。つまり、これはセレウコス朝のシリアを創建したアレクサンドロスの遺将の一人セレウコス1世(前312-281)である。この箇所で言われている通り、セレウコス1世はプトレマイオス1世よりも強大であった。この時代以降の勢力範囲においても、やはりセレウコス朝シリアのほうがプトレマイオス朝エジプトよりも優っていた。
この『将軍のひとり』は、『南の王』プトレマイオスに従う将軍ではない、ということを言っておかねばならない。これは間違いやすい点である。何故なら、この11:5の箇所を見ると、この将軍が『南の王』に従属する将軍であるかのように感じられてしまうからである。私は、ある時までは、これがプトレマイオスに付くエジプトの将軍だと認識していたので、一体どういうことなのかと思い悩まされた。何故なら、プトレマイオスを凌駕したエジプトの将軍などという存在はいないからである。これは次の節を見ても分かるように、『北の王』となった将軍である。そのように理解しないと、11:6の箇所で同盟を結んだと言われているのが何のことがよく分からなくなってしまう。もしこれがエジプトの将軍だったとすれば、11:6で同盟を結んだのはプトレマイオスとその将軍だったということになるのだ。これは意味不明である。読者はこの点を誤って理解しないように注意すべきである。
【11:6】
『何年かの後、彼らは同盟を結び、和睦をするために南の王の娘が北の王にとつぐが、彼女は勢力をとどめておくことができず、彼の力もとどまらない。』
紀元前253年に、エジプトのプトレマイオス2世とシリアのアンティオコス2世は『同盟を結』んだ。その時、『南の王の娘』であるベレニケ・フェルノフォラスが、『北の王』であるアンティオコス2世の妻として与えられた。このベレニケは、両国における和睦の印また手段であった。なお、この箇所で出てくるベレニケ(ベレニケ・フェルノフォラス)は、他のベレニケ(ベレニケ2世)とはまた違う人間だという点に注意せねばならない。ベレニケ2世はこの箇所で出てくるベレニケではなく、プトレマイオス3世の妻だった人間である。一方、ここに出てくるベレニケ・フェルノフォラスはプトレマイオス2世の娘であり、プトレマイオス3世の姉妹だった女である。この時期の中東事情に疎い人には少し分かりにくいとは思うが、この両者を区別しないと、まったく訳が分からなくなってしまうから注意せねばならない。
このベレニケ・フェルノフォラスという者はアンティオコス2世の妻となったものの、和解の道具としての使命を果たすことが出来ず、そのためシリアの勢力を和解の道具として留めておくことが出来なかった。それというのも、紀元前246年にプトレマイオス2世が死んだのを期にアンティオコス2世と復縁した前の妻であるラオディケ1世が、ベレニケを邪魔に思って殺したからである。だから、ここでは『彼女は勢力をとどめておくことができ』なかったと言われている。また『彼』すなわちベレニケの夫であるアンティオコス2世もその力を留めておくことが出来なかった。何故なら、復縁して再びアンティオコス2世の妻となったラオディケに毒殺されてしまったからである。それゆえ、ここでは『彼の力もとどまらない。』と言われている。ところで、この毒殺は離婚に対する神からの刑罰であった。というのも神は離婚を憎んでおられるからである。今の世の中を見ても、離婚者は不幸な状態となっているケースが非常に多く見られる。法廷沙汰になっている事例も珍しくない。最近になって離婚したアマゾンのジェフ・ベゾスは、妻に対する慰謝料として株式4兆円を支払わされた。このように離婚者たちが不幸になるのは、せっかく『神が結び合わせたもの』を、愚かにも勝手に引き裂くからなのである(マタイ19:6)。神の定めによる聖なる結びつきを自ら無謀にも破棄する離婚者たちに呪いが注がれないはずがどうしてあるだろうか。
『この女と、彼女を連れて来た者、彼女を生んだ者、そのころ彼女を力づけた者は、死に渡される。』
『この女』とはベレニケ・フェルノフォラスである。『彼女を連れて来た者』とは、ベレニケの父であるプトレマイオス2世だと思われる。何故なら、アンティオコス2世の所にベレニケを連れて行ったのはプトレマイオス2世だったからである。『彼女を生んだ者』とはベレニケの母なのであろう。『彼女を力づけた者』は恐らくアンティオコス2世である。というのも、妻であるベレニケを、夫であるアンティオコス2世が力づけるのはごく自然なことだからである。
これら4人の者は、それぞれ短い期間のうちに『死に渡され』た。ベレニケはラオディケの手で、ベレニケの父は恐らく病気で、母も恐らく病気で、アンティオコス2世はラオディケによる毒殺で。悲しい事柄は往々にして一挙に引き起こされるものである。
【11:7】
『しかし、この女の根から一つの芽が起こって、彼に代わり、軍隊を率いて北の王のとりでに攻め入ろうとし、これと戦って勝つ。』
『この女』であるベレニケの『根』であるプトレマイオス2世から起きた『芽』であったプトレマイオス3世(前246―222)は、自分の姉妹であったベレニケが殺されたことにより、『彼』すなわちプトレマイオス2世に『代わり』、『軍隊を率いて北の王のとりでに攻め入ろうとし、これと戦って勝』った。要するに、これは第3次シリア戦争(前246-241)のことである。この戦争で、殺されたアンティオコス2世の次に王となったセレウコス2世(前246―225)は、エジプトのプトレマイオス3世に打ち負けることになった。シリアがプトレマイオス3世に敗北した理由は、間違いなくシリアがベレニケを殺したからである。神は殺人に対しては厳しい処置を為される。つまり、シリアはベレニケ殺害に対する刑罰として、エジプトから徹底的に打ち負かされることになったのである。ユダヤも、キリストを殺したので、神の裁きとしてローマ軍との戦いに負けて完全に滅ぼされることになった。もしシリアがベレニケを殺していなければ、―他に神の刑罰を引き起こす罪が犯されていなかったとすれば―、シリアがエジプトに敗北させられることは無かったであろう。ユダヤも、もしキリストを殺していなければ、ローマ軍に滅ぼされるという裁きを受けることは無かったはずである。
【11:8】
『なお、彼は彼らの神々や彼らの鋳た像、および金銀の尊い器を分捕り品としてエジプトに運び去る。彼は何年かの間、北の王から遠ざかっている。』
神の裁きにより、エジプトはシリアに圧勝することが出来た。プトレマイオス3世は、シリアの首都アンティオケを占拠したほどである。その時、このエジプト王は『彼らの神々や彼らの鋳た像、および金銀の尊い器を分捕り品としてエジプトに運び去』った。
そうして後、プトレマイオス3世は、『何年かの間、北の王から遠ざかってい』た。これは何故だったのか。それは、神がプトレマイオスの心に、北の王の国に攻め入ろうという意志を抱かせられなかったからである。これについては黙示録17:17の箇所を読んで悟るべきである。あの王たちがユダヤを滅ぼそうという思いを心の中に抱いたのは、神が御心のままに、この王たちの心に働きかけられたからであった。もし神が働きかけられていなければ、この王たちは、我々が今見ている箇所に出てくるプトレマイオス3世のように、ユダヤから遠ざかったままでいたことであろう。実に、『すべてのことが、神から発し、神によって成り、神に至る』(ローマ11章36節)のである。
【11:9】
『しかし、北の王は南の王の国に侵入し、また、自分の地に帰る。』
シリアの王はエジプトに侵入したが、侵略することは出来ず、『自分の地に帰る』ことになった。この『北の王』とは、アンティオコス2世の次にシリア王となったセレウコス2世である。こう言える理由は二つある。まずアンティオコス2世は、11:7~8の箇所に書かれている第3次シリア戦争の時点で、既にこの世からいなくなっているからである。とすれば、この箇所で言われているのはアンティオコス2世の次の王として解するのが自然である。また、次の節(11:10)では『その息子たち』と書かれている、という点もこれがセレウコス2世であることの理由である。この『息子たち』とは話の流れから考えると、セレウコス2世の息子であったセレウコス3世(前225-223)とアンティオコス3世(前223-187)である。これを、アンティオコス3世の息子であったセレウコス4世(前187-175)とアンティオコス4世(前175-164)と考えるのは、あまりにも時期が早過ぎる。しかも、この『北の王』という者をセレウコス2世と考えれば、ダニエル書11章の全体が実際の歴史における流れと合致することになり、それゆえ滑らかな理解が出来るようになる。それだから、ここで出てくるシリア王はセレウコス2世だったとせねばならない。『南の王』とは、もちろんプトレマイオス3世である。
【11:10】
『しかし、その息子たちは、戦いをしかけて、強力なおびただしい大軍を集め、進みに進んで押し流して越えて行き、そうしてまた敵のとりでに戦いをしかける。』
先に述べたように『その息子たち』とはセレウコス3世とアンティオコス3世であるが、この2人の子どもは、父であるアンティオコス2世と同様、『強力なおびただしい大軍を集め、進みに進んで押し流して越えて行き、そうしてまた敵のとりで戦いをしかけ』た。シリアの王は、これほどまでにエジプトとの領土争いに熱心だったのである。既に知られているように、このコイレ・シリアを巡るエジプトとシリアの戦争は第6次まで続いた。今の時代で例えれば、これは中東においてイスラエル人とアラブ人たちがずっと争い、いがみ合っているようなものである。日本における尖閣問題や竹島問題を見ても分かるが、このような国家における領土争いは、なかなか解決が付かないのが通例である。
【11:11~12】
『それで、南の王は大いに怒り、出て来て、彼、すなわち北の王と戦う。北の王はおびただしい大軍を起こすが、その大軍は敵の手に渡される。その大軍を連れ去ると、南の王の心は高ぶり、数万人を倒す。しかし、勝利を得ない。』
これは第4次シリア戦争(前219-217)のことである。『北の王』であるアンティオコス3世は『おびただしい大軍を起こ』してエジプトに攻め入った。これに対し、『南の王』であるプトレマイオス4世(前221-205)は『大いに怒り、出て来て、彼、すなわち北の王と戦う』ことにした。その結果、シリアの大軍がプトレマイオス4世に打ちのめされてしまった。『北の王はおびただしい大軍を起こすが、その大軍は敵の手に渡される。』と書かれている通りである。これはアンティオコス3世にとっては酷い痛手となった。この4度目の戦争は短く、2年ほどで終わった。
3度目に引き続き4度目もシリアが悲惨な目に遭ったのは、やはりシリアがベレニケを殺害したからである。シリアは国家において殺人という罪を犯したのである。そのような存在が裁かれ、敵に打ち負けてしまうのは当然のことなのである。もっとも、これ以降はもうベレニケ殺害に対する呪いがシリアに注がれることは無くなったようであるが。つまり、これはベレニケ殺害の罪に対する罰が2回の敗北により全うされた、ということなのであろう。
この第4次シリア戦争では、エジプト側が圧勝したと一般的には見做されている。それというのも、エジプトはシリアの軍隊を大いに撃退したからである。この箇所でも、エジプト王がシリアの軍隊の『数万人を倒す』と書かれているから、一見するとエジプト側が勝ったのだと感覚的には思えてしまう。しかし聖書は、この戦いにおいてシリアが『勝利を得ない。』と言っている。これは次のような理由があったからである。
【11:13】
『北の王がまた、初めより大きなおびただしい大軍を起こし、何年かの後、大軍勢と多くの武器をもって必ず攻めて来るからである。』
つまり、こういうことである。『北の王』であるアンティオコス3世は、『何年かの後』すなわち15年後に、『初めより大きなおびただしい大軍を起こし』てエジプトに攻め入り第5次シリア戦争(前202-195)を引き起こした。この5度目の戦争においては、シリア側がエジプトに圧勝した。このように最終的にアンティオコス3世はエジプトに打ち勝つに至ったので、たとえ第4次シリア戦争では撃退されたとしても、それは過渡期における一時的な状態に過ぎないのであって、究極的には敗北したことにはならないのだ、と。確かにアンティオコス3世は結果的にエジプトに対する勝利者となったのだから、部分的また一時的には敗者であったとしても、全体的また長期的には勝者であった。それゆえ、もしアンティオコス3世が第4次シリア戦争の時に負けて死んでいたとすれば、11:11~12の箇所ではエジプトが「勝利を得た。」と書かれていたであろう。その場合、アンティオコス3世は究極的な意味においてエジプトに対する敗者となっていたのだから。つまり、前の箇所で『勝利を得ない。』と言われていたのは、「北の王アンティオコス3世を殺すことが出来なかった。」ということである。なお、ここでは『必ず攻めて来る』と言われているが、この『必ず』という言葉は、読者に預言の真実性を強く確信させるために書かれている。つまり、この言葉は預言の内容を強調しているのである。実際、アンティオコス3世は、1回目の侵攻は上手に行かなかったので、数年後に気を引き締めて再び侵攻を行なったのである。これは歴史が示している通りである。
【11:14】
『そのころ、多くの者が南の王に反抗して立ち上がり、あなたの民の暴徒たちもまた、高ぶってその幻を実現させようとするが、失敗する。』
第4次シリア戦争において、プトレマイオス4世は、シリアのアンティオコス3世に打ち勝つために、エジプトの先住民を兵士として大いに起用した。何故なら、シリアと戦うためには戦力が不足していたからである。この先住民は卑しい者たちであり、本来的には兵士では無かった。しかし、この先住民はシリアに打ち勝つために大いに力を発揮した。このためエジプトはシリアに対して、またも圧勝することが出来た。しなしながら、この先住民が勝利に大いに貢献したので、その価値と尊厳とが大いに高まり、以前よりも力を持つようになった。プトレマイオスも、彼らの重要性を認めざるを得なくなった。彼らがいなければエジプトはシリアに打ち負けていたかもしれないからである。要するに、彼らは言わば「先住民ども」から「先住民様」になった。このゆえにエジプト先住民はプトレマイオス4世に『反抗して立ち上が』るようになった。簡単に言えば「いい気になった」のである。そのため反逆したこのエジプト先住民は、それから20年の間、プトレマイオスの支配から逃れて独自の王を持つに至った(※)。この反乱は次のエジプト王であるプトレマイオス5世の時代になっても続き、王を大いに悩ませた。これは、妻が夫の命を救ったので、それ以降、夫を支配するようになるのと似ている。またチームにいた弱小者が大勝利に貢献したので、チームのリーダーさえも一目置かざるを得なくさせられるのと似ている。この例からも分かるが、実績や成果は力の大きな印また証明である。それは王でさえも認めざるを得ないものである。往々にして人間はこの実績や成果により物事を判断する。それまでは無名であっても実績や成果を出すと急に注目されもてはやされるようになる。これは古代から今に至るまで何も変わっていない。もしエジプトの先住民が勝利に寄与しなかったならば、何も実績や成果が無いままなのだから、価値と尊厳も高まらず、彼らが叛乱を起こすようになることも無かったであろう。
(※)
この反逆の出来事についてポリュビオスはこう記している。「この王(※プトレマイオス4世―引用者註)はアンティオコスとの戦争に備えてエジプト人に武器を与えていたのだが、これはその場面に限っていえば首肯できる方法であっても、将来のためにはつまずきの石となった。というのもラビアの勝利によって自信をふくらませたエジプト人たちは、もはやおとなしく命令に忍従するのをいさぎよしとせず、自分の力で身を守ることのできる人間として、それにふさわしい指導役の人物を求めるようになったのである。この要求はしばらくのちに実現することになる。」(『歴史2』第5巻:107、2~3 p276:京都大学学術出版会 西洋古典叢書 第Ⅳ期第3回配本)
[本文に戻る]
この時期には、ユダヤ人の『暴徒たち』も、プトレマイオス4世を排除しようと企んだ。何故なら彼らは『高ぶって』いたからである。この暴徒たちは自分勝手な思いを持っていたので、プトレマイオス4世が消え、アンティオコス3世が勝利すればよいと考えていた。ここでは彼らが『その幻を実現させようとする』と書かれているが、『その幻』とは、無茶な願望に基づく夢想的な企みという意味である。確かに暴徒たちの企てたことは、幻想とでも言うべき企てであった。これは「預言」や「律法」のことではないから注意すべきである。この暴徒たちの企みは、エジプト先住民の叛乱と同様、『失敗する』ことになった。何故なら、神がエジプト先住民とユダヤの暴徒が抱いた企てを成功させられなかったからである。
プトレマイオス4世が良い結果を出したのにエジプト人から叛乱されて悩まされたのは、この王が犯した罪に対する裁きであった。この王は罪深い放蕩者であって、日々遊んで暮らしており、遊女に囲まれて怠けていた。この王は自分の母と姉妹も殺した。だから、その犯した悪に対する裁きとして、エジプト人により苦しめられることになったのである。つまり、プトレマイオス4世は神と人とに逆らったので、自分もエジプト人に逆らわれることになった。この事例を見ても分かる通り、『あなたがしたように、あなたにもされる。』という神の言葉は誠に真実なのである。この王は、かつてアドニ・ベゼク王が嘆いて言ったように『神は私がしたとおりのことを、私に報いられた。』(士師記1章7節)とでも言いたかったのではないかと私には思われる。
【11:15】
『しかし、北の王が来て塁を築き、城壁のある町を攻め取ると、南の軍勢は立ち向かうことができず、精兵たちも対抗する力がない。』
これは第5次シリア戦争(前202-195)のことである。アンティオコス3世にとっては、第4次シリア戦争の次に行なった復讐戦となる。この戦争については、既に2節前の11:13の箇所で語られていた。事の次第はこうである。アンティオコス3世は、第4次シリア戦争での屈辱を晴らすべく、エジプトに攻め入ろうとしていたが、なかなかその機会を見出すことが出来なかった。そのような中、プトレマイオス4世が紀元前205年に死に、彼の子であるプトレマイオス5世(前204-181)が5歳の若さでエジプトのファラオとなった(※)。これを好機として捉えたアンティオコス3世は、マケドニアのピリッポス5世と手を組み、2年の準備期間を設け、前202年にエジプトに攻め込んで第5次シリア戦争を引き起こした。この時、シリアは『大軍勢と多くの武器をもって』エジプトに侵攻した。シリア王は、以前の屈辱を晴らすべく準備万端で臨んだのである。その結果、シリアはエジプトに圧勝した。それは、シリアの攻撃を受けたエジプトについて、この箇所で『南の軍勢は立ち向かうことができず、精兵たちも対抗する力がない。』と書かれている通りである。もうこの時には、ベレニケ殺害に対するシリアへの刑罰は全うされていたから、裁きにより敗北することは無かったのである。
(※)
参考情報だが、このプトレマイオス5世もプトレマイオス4世と同様、どうしようもない支配者であった。ポリュビオスはこう書いている。「プトレマイオス(5世)は、人々を裸にして荷車に縛り付け、引きずったあとで、拷問に加えて殺した…。」(ポリュビオス『歴史4』第22巻:16、4 p27:京都大学学術出版会 西洋古典叢書 2012第8回配本)
[本文に戻る]
【11:16】
『そのようにして、これを攻めて来る者は、思うままにふるまう。彼に立ち向かう者はいない。』
この時のアンティオコス3世は、非常に強かった。だから『彼に立ち向かう者はいな』かった。これは神がこうなるように定められたからである。それは、この箇所における預言が、実際の歴史において成就するためであった。
『彼は麗しい国にとどまり、彼の手で絶滅しようとする。』
アンティオコス3世は、第5次シリア戦争の時、『麗しい国』であるユダヤをも征服した。彼はユダヤを『絶滅しようと』した。何故なら、彼はサタンに突き動かされていたからである。しかし、神はユダヤがアンティオコス3世に絶滅されることを御許しにはならなかった。それというのも、この時は、まだユダヤの終わる時では無かったからである。ユダヤの終わりは紀元70年に訪れるのであって、その時にユダヤはローマ軍により神の御前において絶滅されたのである。
【11:17】
『彼は自分の国の総力をあげて攻め入ろうと決意し、まず相手と和睦をし、娘のひとりを与えて、その国を滅ぼそうとする。しかし、そのことは成功せず、彼のためにもならない。』
前193年にエジプトとシリアは『和睦を』結び、アンティオコス3世は『娘のひとり』であるクレオパトラ1世(在位:前193-176)をプトレマイオス5世に妻として与えた。彼女は和解の道具であり、両国が和解したことを示す印また証拠であった。これは、事はひとまず一件落着したかに見えた。しかし、この結婚は、この箇所でも言われている通り、エジプトを『滅ぼそうとする』シリアの政略であった。要するに、シリアはエジプト王の妻として与えられたクレオパトラ1世を通してエジプトを内部から破壊しようとしたのである。このクレオパトラ1世はコイレ・シリアの支配権という魅力的な持参金付きでプトレマイオス5世に与えられたが、これは名目上の持参金に過ぎず、実際にエジプト王がコイレ・シリアを支配することは出来なかった。これ以降、エジプトはクレオパトラ1世を通してシリアから内政干渉を受けることになる。エジプトはまんまとシリアにはめられてしまったわけだ。だが、これは驚くには値しない。何故なら、国家間においてこのような欺瞞は特に珍しいものではないからである。
しかし、この政略はアンティオコス3世の思惑とは裏腹に、あまり上手に行かなかった。シリアがエジプトに内政干渉できるようにはなったが、エジプトを屈服させるという段階にまでは至らなかった。何でもそうだが事柄は往々にして上手く進まないものである。だから、この箇所では、この政略結婚を実現させたシリア王についてこう言われている。『しかし、そのことは成功せず、彼のためにもならない。』
【11:18】
『それで、彼は島々に目を向けて、その多くを攻め取る。』
アンティオコス3世は、多くの国々を次々と征服して行った。そのため、シリアはこの王の治世の時に最も大きな支配領域を持った。この征服事業は、あのアレクサンドロスの征服を感じさせるものであった。だからアンティオコス3世は「大王」と呼ばれることになった。ここでは『島々』と書かれているが、これは「国々」の言い換えである。何故なら、アンティオコス3世が征服したのは島々ではなく国々だからである。どうして国々が島々と表現されているのか。それは、この王の征服した国々が、島々のように多く、また広大な場所に散らばっていたからである。
『しかし、ひとりの首領が、彼にそしりをやめさせるばかりか、かえってそのそしりを彼の上に返す。』
アンティオコス3世はギリシャの方面も征服しようとしたが、この方針は東側への進出を企んでいたローマの方針と真っ向から対立した。ローマもギリシャの方面を征服したかったのである。ここではアンティオコス3世が『そしりを』したと示されている。これはギリシャを我が物にしようとしていたローマをそしるという意味である。「ローマよ。あなたがたはギリシャを狙っているが、そんな馬鹿なことは止めたまえ。ギリシャを攻め取るのはこの私たちなのだから。あなたがたは素直に引っ込んでいればよい。」と。これに対してローマの『ひとりの首領が、彼にそしりをやめさせるばかりか、かえってそのそしりを彼の上に返』した。すわなち、こういうことである。「シリアよ。馬鹿なことを言っているのは君たちのほうだ。君たちがギリシャを攻め取ることは絶対に出来ない。何故なら、ギリシャを攻め取るのはこの私たちなのだから。」このローマの『首領』とは、あの大スキピオ(前236―183)を指す。彼はローマ軍における首領である将軍であった。
【11:19】
『それで、彼は自分の国のとりでに引き返して行くが、つまずき、倒れ、いなくなる。』
前188年にこのシリア王は、「120頭の象、騎兵、戦車、および大軍を率いてローマ人に対抗した」(『聖書外典偽典1 旧約外典Ⅰ』Ⅰマカベア書7:6 p111:教文館)ものの、ローマの頭領であった大スキピオに撃退され、敗者が負うことを常とする賠償金を課されることになった。その額はあまりにも巨大であった(※①)。このローマは敗戦国にその国の支払い能力を超えた耐え難いほどの賠償金を課すのが常であった。だから、憤激してローマに立ち向かい、再び打ち負かされる羽目になった国も少なからずあったほどである。このようにして悲嘆しつつ『自分の国のとりでに引き返して行』ったアンティオコス3世は、酷い状態に陥る羽目になった。そして、この王は巨大過ぎる賠償金を支払えなかったので、スサ(※②)の神殿から財宝を略奪して、賠償金を確保しようとした。そのため神殿に祀られている女神と結婚し、巧みに神殿の財宝を奪おうとしたのである。これに現地人は怒り狂い、この王は現地人により暗殺されてしまった。こうしてアンティオコス3世は『つまずき、倒れ、いなくなる』ことになった。前187年のことである。これは正に歴史が示している通りである。この王の治世は全部で36年であった。他の王たちに比べるとかなり長い年数である。
(※①)
ポリュビオスによれば、この時、大スキピオがアンティオコス3世に突き付けた通告はこうであった。「ローマ人は戦いに勝ったからといって圧力を強めるわけではなく、(また敗れたからといって弱めるわけでもない)。それゆえローマ人がいま与える返答は、戦いの前にヘレスポントスで会談したときに与えた返答と同じである。すなわち、アンティオコスはヨーロッパから、そしてタウロス山脈のこちら側のアジア全土から撤退すること。戦争費用の賠償として、1万5000エウボイア・タラントンをローマに支払うこと。ただしそのうち500タラントンは即時に、2500タラントンはこのあと民会が講和条約を批准したときに、そして残りは毎年1000タラントンの年賦で12年間かけて弁済するものとする。またエウメネスにも、父王とのあいだに結んだ協定に従って、未済の400タラントンと未納の穀物を償還すること。さらにカルタゴ人ハンニバル、アイトリア人トアス、アカルナニア人ムナシコロス、カルキス人ピロンとエウブリダス、以上の5人を引き渡すこと。そしてこれらすべての義務の担保とするため、別記の20人を人質としてただちに供出すること。」(『歴史3』第21巻:17、1~8 p539~540:京都大学学術出版会 西洋古典叢書 2011第4回配本)ローマによる正式な条約には次のように書かれている。「アンティオコスが最上質のアッティカ銀で1万2000タラントンを、毎年1000タラントンずつ12年間で支払う。1タラントンは80ローマ・リブラを下回らないものとする。加えてアンティオコスは穀物54万モディウスを提供する。アンティオコスはエウメネス王に350タラントンを、毎年70タラントンずつ今後すぐの5年間に、ローマへの支払いと同時期に支払う。穀物についてはアンティオコス王の換算査定に従い、127タラントンと1208ドラクマを支払う。…」(同 43、19~21 p581~582)
[本文に戻る]
(※②)
この場所は、ペルシャの方面、バビロンの周辺に位置している。
[本文に戻る]
私の思うに、この時はもうローマに覇権が移りつつある段階にあった。つまり、もうローマの時代になりつつあった。だから、シリアはローマに打ち勝つことができなかったのである。実際、この頃のローマには、スキピオ兄弟の他にも大カトーをはじめとした傑物が出始めるようになっていた。これはローマが全体的に強まっていたことを意味している。というのも、素地が全体的にしっかりしているからこそ、優秀な人間も生じてくるようになるからである。戦前のドイツは、素地がきちんとしていたので、偉大な人物が次から次へと登場した。しかし素地がしっかりしていないと、総合的な力が弱いことを意味するので、優れた人はなかなか出てきにくい。今で言えばポルトガルやギリシャがそうである。不本意ながらノーベル賞受賞者を全く出せないでいる韓国もそうである。
【11:20】
『彼に代わって、ひとりの人が起こる。彼は輝かしい国に、税を取り立てる者を行き巡らすが、数日のうちに、怒りにもよらず、戦いにもよらないで、破られる。』
次にシリア王となったのはセレウコス4世(前187-175)である。彼はアンティオコス3世の子であり、アンティオコス4世とクレオパトラ1世の兄弟である。彼について語るべきことは、あまり多くはない。
この王は、父がローマから負わされた賠償金を支払わねばならなくなった。彼は、この支払いのために、大いに悩まされた。それは、その額があまりにも大きく、とてもじゃないがシリアには支払えなかったからである。何とかして踏み倒すこともできない。相手はあの力強いローマだからである。もし踏み倒したらローマから酷い目に遭わされることは目に見えているのだ。このため、セレウコス4世は『輝かしい国』であるユダヤに『税を取り立てる者』すなわち財務長官・大臣であるヘリオドロスを遣わし、神殿の財物を奪い取ろうとした。その財物を奪えば、賠償金の支配いを確保できるからである。ユダヤの神殿に莫大な財物があるということは、神殿長官であったシモンという悪しきユダヤ人により、少し前に報告されていた。そこには「総額にして銀400タラント、金200タラント」(『聖書外典偽典1 旧約外典Ⅰ』Ⅱマカベア書3:11 p163:教文館)があった。しかし、このヘリオドロスは神殿の中に入りはしたものの、熱心に祈り求めるユダヤ人に動かされた神の働きかけにより死人のような状態にさせられたので、財物を略奪することが出来なかった。この出来事はマカベア書に詳しく書かれている(Ⅱ第3章/Ⅳ第4章)。そうして後、セレウコス4世はすぐにも殺されることになった。自分の遣わしたヘリオドロスにより殺害されたのである。この大臣は前々から王位を簒奪したいと心の中で願っていた。こうしてセレウコス4世は『税を取り立てる者を行き巡ら』して後、『数日のうちに、怒りにもよらず、戦いにもよらないで、破られる』ことになった。これが起きたのは紀元前175年である。
神の組織における財物を略奪することは、神に強奪を働くことである。それは王の物を盗むよりも悪い。神は王よりも尊い御方だからである。誰かが王の物を盗んだならば酷い刑罰を受けるであろう。であれば、尚のこと、神の物を盗んだならば酷い刑罰を受けることになる。要するに、ここで語られているセレウコス4世は神の物を盗もうとしたので死の罰を受けたのである。最近は、宗教に課税すべきだなどとほざいている者がいるが、思慮に欠けており、宗教のことがよく分かっておらず、馬鹿げている。これは、つまり神に税を課そうと言っているのだ。このように言う者は、自分に裁きが降りかかることを願っているも同然である。しかし、私がこう言うと、宗教課税を主張する者は「宗教がマネーロンダリングに利用されたままでいいのか。税金逃れをしたお金が愚かな国に渡ってしまうのを阻止すべきではなのか。」などと反発するであろう。確かに、マネーロンダリングのために利用されている宗教があるのは事実である。それはいけないことである。しかし、神に税を課すのはもっといけないことである。だから、税を課すというのであれば、プロテスタント教会を除いた宗教だけにすべきである。プロテスタントに税を課すと、神から金銭を徴収することになるから、あまりにも危険である。その場合、ここで言われているセレウコス4世のように裁かれかねない。だが他の宗教に税を課すのは、神から金銭を強奪することにはならない。何故なら、プロテスタント教会でない宗教また宗派は、カトリックであれユダヤ教であれ仏教であれ、神に属する宗教ではないから。例えば異教における神像を破壊しても神から裁きを受けることにはならないのと同じで、プロテスタント教会でない宗教また宗派から税を取っても裁きを受けることにはならないであろう。しかし、そのようにした場合、今度はプロテスタント教会を隠れ蓑にして税金逃れの悪が為されるのではないか。そのようなことがあったら、見つけ次第、対処していくしかない。もしマネーロンダリングに加担している教会があれば、法律により莫大な罰金―例えば1000万円ぐらい―を支払わせるようにすればよい。そうすれば、プロテスタント教会がマネーロンダリングのために使われることも無くなる、または少なくなっていくことであろう。
【11:21】
『彼に代わって、ひとりの卑劣な者が起こる。彼には国の尊厳は与えられないが、彼は不意にやって来て、巧言を使って国を堅く握る。』
次にシリアの王となったのは、エピファネスと呼ばれるアンティオコス4世(前175-164)である。この王はアンティオコス3世の子であり、セレウコス4世とクレオパトラ1世の兄弟であった。後にも語られることになるが、我々にとって、この王は非常に重要な意味を持っている。アンティオコス4世に関する記述が11章の半分以上を占めている、ということからも、この王の重要性が分かる。彼以外の王は、11章の中でここまで多く語られてはいない。
この王には『国の尊厳は与えられな』かった。つまり、キュロス2世やダリウス1世やアレクサンドロス大王のような偉大性は、彼に無かった。彼の功績と言えば、エジプトに打ち勝ったことぐらいである。また聖徒たちにとって、彼はただの暴君に過ぎなかった。
またこの王は、『巧言を使って』シリアを大いに支配した。これは彼がサタンに憑かれていたことを意味している。サタンは律法の本質的な違反者であり、『欺いてはならない。』という神の戒めを常に犯したいと思っている。だから、アンティオコス4世が巧言を使うようにと、サタンは彼の心に働きかけた。何故なら、そうすれば、サタンはアンティオコス4世
においてアンティオコス4世と共に悪を為せるからである。ちょうどエデンの園でサタンが蛇において蛇と共に欺きの言葉をエバに語ったのと同じである。
【11:22】
『洪水のような軍勢も、彼によって一掃され、打ち砕かれ、契約の君主もまた、打ち砕かれる。』
アンティオコス4世は、『洪水のよう』に多いシリアの軍隊を大いに支配した。それは彼がシリアの最高権力者となったからである。
また彼は『契約の君主』も打ち砕いた。『契約』とは何を指すのか。これは聖なる宗教すなわち古代ユダヤ教のことである。では、その『君主』とは何か。これはユダヤ人における統治者である。つまり、『契約の君主もまた、打ち砕かれる。』とは、アンティオコス4世がユダヤの王家を大いに蹂躙するという意味である。実際、アンティオコス4世は、ユダヤの王家も含めてユダヤ全体を荒らしに荒らし回った。
【11:23】
『彼は、同盟しては、これを欺き、ますます小国の間で勢力を得る。』
この王は、欺瞞により『小国の間で勢力を得』た。この箇所では『欺き』と書かれている。これは明らかに『偽証してはならない。』という戒めに違反している。律法違反という罪により勢力を得ること。これは正にサタンに憑かれた者の為すことである。
【11:24】
『彼は、不意に州の肥沃な地域に侵入し、彼の父たちも、父の父たちもしなかったことを行なう。彼は、そのかすめ奪った物、分捕り物、財宝を、彼らの間で分け合う。彼はたくらみを設けて、要塞を攻めるが、それは、時が来るまでのことである。』
アンティオコス4世は、『不意に州の肥沃な地域に侵入し』、その『要塞を攻め』、金目の物を大いに強奪した。ここで言われている『州』とは、どこの場所を言っているのか。これはユダヤではないかと思われる。何故なら、この州は『肥沃な地域』と言われているからだ。ダニエル書11章では、ユダヤが『麗しい国』(11:16)また『輝かしい国』(11:20)と言い表されている。これは、ユダヤが霊的に麗しく・輝かしい国だという意味である。だから、ここでもユダヤが霊的に肥沃であるという意味で『肥沃な地域』と言われていると考えられる。実際、霊的に言えば、旧約時代においてユダヤは霊的に肥沃であった。しかしそれ以外の国や地域は、荒れ果てた砂漠であった。というのも当時において神の国があったのはユダヤだけだからだ。しかし、これがシリアやエジプトを指している可能性はないのか。まずシリアという想定は完全に退けられる。何故なら、アンティオコス4世が自分の国に侵入したというのは意味が分からないからだ。エジプトであれば可能性としては有り得る解釈である。何故なら、古代においてエジプトは非常に豊穣な国だったから。だが私としては、これはユダヤを指していると思われる。その理由は既に述べられた。
この王は『州の肥沃な地域に』攻め入るが、『それは、時が来るまでのこと』あった。これは、つまりアンティオコス4世が死ぬ時までのこと、という意味である。実際、アンティオコス4世が紀元前164年に死ぬとほとんど同時期に、ユダヤは汚れと悲惨から回復され、もはやこの暴君に攻め入られることが無くなったからである。しかし、それまではこの暴君による苦しみが続いたのである。
【11:25】
『彼は勢力と勇気を駆り立て、大軍勢を率いて南の王に立ち向かう。南の王もまた、非常に強い大軍勢を率い、奮い立ってこれと戦う。』
これは第6次シリア戦争(前170-168)のことである。この戦争で、アンティオコス4世は2度エジプトに侵攻する。この11:25~28の箇所では、1度目のエジプト侵攻が語られている。それは前169年に起こった。その時、シリア王は『大軍勢を率いて南の王に立ち向』かった。既に前176年の時にエジプト王に妻として与えられていたアンティオコス4世の姉妹であるクレオパトラ1世が死んでいたので、シリア王は自分の姉妹に気兼ねせずに侵攻することが出来た。これに対し、『南の王』であるプトレマイオス6世(前180-145)も『非常に強い大軍勢を率い』てシリアに立ち向かった。なお、この6度目でシリア戦争は終わる。
『しかし、彼は抵抗することができなくなる。彼に対してたくらみを設ける者たちがあるからである。』
猛烈な勢いで侵攻してきたアンティオコス4世に、プトレマイオス6世は『抵抗することができなくな』り、大敗北を喫した。その時、このエジプト王は、アンティオコス4世の捕虜にされてしまった。そうして、プトレマイオス6世はシリアの操り人形として首都であるアレクサンドリアを除くエジプト全域を支配するようになった。この際、アレクサンドリアには統治者が不在となったので、プトレマイオス6世の弟であったプトレマイオス8世がアレクサンドリアの統治者として据えられた。こうしてエジプトには2人の王による共同統治体制が敷かれたのである。ところで、この侵攻の時にエジプト王が対抗できなかったのは何故か。それは『彼に対してたくらみを設ける者たちがあるから』であった。この陰謀者たちは、自然に考えるならば、恐らくプトレマイオス6世の臣下たちであったと思われる。
【11:26】
『彼のごちそうを食べる者たちが彼を滅ぼし、彼の軍勢は押し流され、多くの者が刺し殺されて倒れる。』
プトレマイオス6世は『彼のごちそうを食べる者たち』である臣下たちにより、シリア王に打ち負けることになった。この場合もそうだが、往々にして敗北や破滅や悲惨は内部から生じる。あの聖なる12人の集まりを離散させたのは内部にいたイスカリオテ・ユダであったし、カトリック教会が大混乱に陥ったのもカトリックの修道士であったルターによったし、アレクサンドロス大王が死んだのも大王と近い関係にあったアンティパトロスが密かに毒を仕込んだからであった。今の時代における教会勢力にも、内部から破壊するための工作員が侵入している。私はそのような工作員を何度も見ている。内部にいる者は言わば癌細胞のようにその身体全体を打ち壊してしまう力があるのだ。要するに、『ごちそうを食べる者たち』が最大の敵に変貌するというわけである。
ここではエジプトの軍隊が『押し流され』ると書かれているが、これは相手の軍隊の多さを押し流す洪水に例えているのである。つまり、エジプト軍は、洪水のように多いシリア軍の攻撃により、あたかも洪水が全ての物をなぎ倒すかのように打ち倒されてしまった、ということである。実際、この時にエジプト軍は洪水にでも流されたかのように一挙に死者を出した。
【11:27】
『このふたりの王は、心では悪事を計りながら、一つ食卓につき、まやかしを言うが、成功しない。その終わりは、まだ定めの時にかかっているからだ。』
『ふたりの王』とは、アンティオコス4世とプトレマイオス6世を指す。この『ふたり』の中には、プトレマイオス6世と共同統治を行なったもう一人の王であるプトレマイオス8世は含まれていないので注意せねばならない。何故なら、この辺りの文脈を見ると、どうやらこの辺りではプトレマイオス8世については言及されていないように思えるからである。これはアンティオコス4世とプトレマイオス6世と捉えるのが自然である。
シリア王は、捕虜にされたエジプト王と『一つ食卓につ』いた。エジプト王は、シリア王に従うより他なかった。敗者が勝者の言いなりになるのは当然のことだからである。この時に、両者は『まやかしを言』った。これは『心では悪事を計りながら』本心とは異なる事柄を述べることである。要するに、これは「口先だけの言葉」である。恐らく、アンティオコス4世は、プトレマイオス6世にアレクサンドリアを除いた全エジプトの支配について語りながら、心の中では最終的にエジプトを屈服させることを企んでいたはずである。一方、プトレマイオス6世のほうは、外面的にはアンティオコス4世に従う姿勢を見せておきながら、心の中ではシリアの圧力を排除することを目論んでいたはずである。国家間の駆け引きとは、こういうものである。
この『まやかし』は『成功しな』かった。それは、『その終わりは、まだ定めの時にかかっているから』である。『その終わり』とは、アンティオコス4世の生命が終わる時である。『定めの時』とは、アンティオコス4世が死ぬようにと定められている時である。つまり、アンティオコス4世の死期がまだ訪れていなかったので、この時に何を企んでも上手に発展することは無かった、ということである。実際、アンティオコス4世が死ぬのはこれから6年後であり、時間はまだまだ残っていた。その時が来るまでに『まやかし』が成功し、アンティオコス4世の命が失われることになるのは、神の定めではなかった。
【11:28】
『彼は多くの財宝を携えて自分の国に帰るが、彼の心は聖なる契約を敵視して、ほしいままにふるまい、自分の国に帰る。』
シリア王は、自分が占領したエジプトから財宝を強奪し、その戦利品を自分の国に持ち帰った(※)。これは、第3次シリア戦争の際にエジプト王がシリアから戦利品を奪い取って持ち帰ったのとは、まったく逆である(ダニエル11:7~8)。この世には報いの法則が働いている。かつてエジプトはシリアから戦利品を獲たので、今度は自分がシリアから財物を奪われることになったのだ。
(※)
「そこで、(アンティオコスの軍隊は)エジプトの堅固な町々を占領し、彼はエジプトの地から戦利品を奪い取った。」(『聖書外典偽典1 旧約外典Ⅰ』Ⅰマカベア書1:19 p80:教文館)
[本文に戻る]
アンティオコス4世は、エジプトから帰る途中、帰り道に位置していたユダヤを激しく侵略した。その侵略は酷かった。このシリア王が『ほしいままにふるま』ったからである。この時、ユダヤ人の多くが殺され、その財物を奪われ、エルサレムは大いに踏み荒らされた(※)。アンティオコス4世がこのような迫害を為したのは、彼が『聖なる契約を敵視して』いたからである。この『聖なる契約』とは、ユダヤ教とユダヤ教に属するユダヤ人を指している。どうして彼はユダヤの共同体を敵視していたのか。それは、ユダヤ人が独自の文化・法則・神また思想体系を持っており、そのうえ信仰堅固だったからである。つまり、アンティオコス4世は、自分の望んでいるヘレニズム化やゼウス崇拝を頑なに拒み続けるこのユダヤ人が反抗的に思えたので、気に食わなかったのである。ちょうど、ナチスの方針に従おうとしなかったドイツ教会にヒトラーが激しく憤ったのと同じである。ところで、この時、ユダヤはアンティオコス4世の支配下にあった。ポリュビオスはこう書いている。「当時コイレ・シリアとフェニキアの両地域を支配していたのはアンティオコスだった。現王の父アンティオコス(3世)がパニオン近郊の戦いでプトレマイオス(5世)の将軍たちを打ち破って以来、これらの地域は例外なくシリアの王に服属していたのである。それゆえアンティオコス(4世)は、戦争による獲得という事実が何にもまさる重みと誉れを有するという信念から、これをあくまでも自分の所有財産として守りとおすべく力を傾けていた。」(ポリュビオス『歴史4』第28巻:1、2~5 p126:京都大学学術出版会 西洋古典叢書 2012第8回配本)
(※)
この時のアンティオコス4世の暴虐はこうであった。「そして驕慢にも聖所に侵入して、黄金の祭壇、燭台、および燭台のあらゆる装飾品、祭壇、灌祭の盃、酒盃、黄金の香炉、聖所の幕、冠、神殿の正面にあった黄金の飾りなどを奪い、(神殿の物を)すっかりはぎ取ってしまった。さらに、金、銀、すばらしい器具、秘蔵の財宝を見つけしだい奪い取り、かくして略奪をほしいままにすると、アンティオコスは自分の国へひきあげて行った。彼は民を殺戮し、高慢なことばを語った。」(『聖書外典偽典1 旧約外典Ⅰ』Ⅰマカベア書1:21~24 p80:教文館)
[本文に戻る]
【11:29~30】
『定めの時になって、彼は再び南へ攻めて行くが、この2度目は、初めのときのようではない。キティムの船が彼に立ち向かって来るので、彼は落胆して引き返し、』
アンティオコス4世は、前168年に2度目のエジプト侵攻を為した。シリアは、どうしてもエジプトとの戦いに勝ちたかったのである。この2度目の侵攻は、勝利したいというシリアの願望が実際の行ないとして現われ出たものである。
この2度目のエジプト侵攻は、『初めのときのようではな』かった。つまり上手に行かなかった。何故なのか。それはエジプトがローマに助けを求めたからである。エジプトからの要請を受けてローマからやって来た大使は、アンティオコス4世に会い、このシリア王の周りの地面に円を描いてこう言った。「あなたがこの円から外に出るまでに、エジプトから撤退するか、ローマと戦いをするのか選んでいただきたい。」この大使が円を描いて急かしたのは、回答を留保させないためであった。エジプトを侵攻し続けるならばローマと戦わねばならなくなり、エジプトから退けばローマとは戦わずに済む。このように言われたアンティオコス4世は、止むを得ずエジプトから撤退することを決定した。何故ならローマが怖かったからである(※)。この時のローマはどんどんと力を付けている時期であり、先にも述べた通り、覇権がこのローマに移り始めていた。一方、シリアにはハンニバルやエピメイノンダスやピロポイメンやアリストメネスやヨシュアのようなローマに対抗することが期待できる恵まれた強者が誰もいなかった。だから、このシリア王の決定は間違ったものではなかった。これは今の時代で例えるならば、中国が日本を攻めたのだが、アメリカが日本の味方をしたので、中国は仕方なく撤退せざるを得なくさせられるようなものである。この結果、アンティオコス4世は『落胆して引き返』さねばならなくなった。この時、彼は相当悔しかったろう。だがローマが相手ではどうにもならなかった。ところで、ここでは『キティムの船が彼に立ち向かって来る』と書かれている。『キティム』とはキプロスのことである。だが実際にキプロスからの船がアンティオコス4世の所にやって来るということは起こっていない。これはどういうことかと言えば、『キティムの船』が立ち向かって来るとは、ローマから使節がやって来ることを示している。つまり、これは象徴としての言い方である。実際の歴史を考えるならば、これはローマのことだと解さざるを得ない。これはローマから使節が船で訪れることを言っているのであろう。どうしてキプロスからその使節が来ると象徴的に言われているかといえば、それはその使節がさほど遠くない場所からやって来ることを示すためである。
(※)
この有名な出来事についてポリュビオスはこう書いている。「…アンティオコスがペルシオン奪取をめざして、プトレマイオスめがけて攻め寄せてきたときのことである。ローマ軍司令官ポピリウスは、アンティオコスが遠くから声をかけて右手を差し出してきたとき、元老院決議の刻まれた書板を手に持ったまま相手の方に突き出して、まずこれを読めと命じた。たぶん、先に右手を差し出してきた相手の真意が、友好と敵対のいずれにあるのかを確認してからでないと、友好のしぐさを返すわけにはいかないと考えたのであろう。そして王が決議に目を通したあと、この件については廷友たちに相談したいと答えたとき、それを聞いてポピリウスのとった行動は、きわめて峻厳でしかも尊大なものだった。手に持っていた葡萄の木の枝を使って、アンティオコスの回りの地面に円を描いたうえで、書状への回答を示すまではこの円から出るのを許さないと言い渡したのである。王はこの居丈高な言動に虚を突かれ、しばらくのあいだためらったあと、ローマ人の命令にはすべて服すると返答した。するとポピリウスの一行はこぞってアンティオコスの右手を取り、次々に親愛のこもったあいさつを交わした。書状の内容は、そくざにプトレマイオスとの戦争をやめるべし、というものだった。そこで一定の日数の猶予が与えられたあと、アンティオコスは憤怒と苦悶を胸に秘めながら、当面は現実への譲歩もやむなしとあきらめて、軍勢とともにシリアへ引き上げた。」(ポリュビオス『歴史4』第29巻:27、1~8 p184~185:京都大学学術出版会 西洋古典叢書 2012第8回配本)
[本文に戻る]
『聖なる契約にいきりたち、ほしいままにふるまう。』
彼は、2度目のエジプト侵攻から帰る際にも、帰り際にユダヤを侵略した。この時の侵略も酷かった。この時もアンティオコス4世は『ほしいままにふるま』ったからである。Ⅰマカベア書の記述はこうなっている。「彼は大軍を率いてエルサレムに入城し、詭計をめぐらして穏やかなことばで人々に語ったので、人々は彼を信用した。ところが彼は突然町に襲いかかり、大打撃を与え、イスラエルの多くの民衆を滅ぼした。そして町を略奪し、町に火を放ち、町の家々と周囲の城壁とを破壊し、女、子供を捕虜にし、家畜を奪い取った。」(『聖書外典偽典1 旧約外典Ⅰ』Ⅰマカベア書1:30~32 p80:教文館)Ⅱマカベア書ではこう書かれている。「若者も老人も女も子供も殺戮の手をのがれることはできなかった。3日間に8万人が殺され、戦闘で殺された者は4万人に及び、死者に劣らぬ多数の者たちが売りとばされた。王はしかしこれに満足せず、律法と祖国の裏切り者メネラオスを案内に立てて世界中で最も聖なる神殿に踏み入り、穢れた手で聖なる器をとり、神殿の繁栄と栄光と栄誉のためにほかの王たちから送られた品々を穢れた手で奪い去った。」(『聖書外典偽典1 旧約外典Ⅰ』Ⅱマカベア書4:13~16 p171:教文館)
【11:30】
『彼は帰って行って、その聖なる契約を捨てた者たちを重く取り立てるようになる。』
このシリア王は自分の国に帰ると、『その聖なる契約を捨てた者たち』すなわち背教者のユダヤ人を『重く取り立てるように』した。これは、背教したユダヤ人が、ますます霊的に堕落させられるという意味である。何故なら、そのように捉えるしかないからだ。実際の歴史を見ると、アンティオコス4世は背教者たちに酷い取り扱いをするどころか、かえって厚遇している。それは彼らが自分の宗教を捨ててアンティオコス4世に服従したからである。中には、魅力的な地位と権力とを約束された者たちもいたぐらいである。よって、『重く取り立てる』というのは、背教者たちがあたかも重税を課されるかのように霊的な意味において悲惨を味わわされるということである。
【11:31】
『彼の軍隊は立ち上がり、聖所ととりでを汚し、常供のささげ物を取り除き、荒らす忌むべきものを据える。』
アンティオコス4世のシリア軍は、エルサレムにおける『聖所ととりで』を汚し、大いに荒らし回った。これはユダヤ人たちに対する迫害を神が許可されたために起こった。つまり、神は彼らに対する懲らしめの意味としてアンティオコス4世がエルサレムを汚すのをお許しになられたのだ。この時のユダヤ人たちは敬虔な状態にあるとは言えなかった(※)。もし当時のユダヤ人が敬虔に歩んでいたとすれば、このような迫害は決して起こらなかったであろう。
(※)
Ⅰマカベア書では、この時の状況について次のように書かれているが、これでは懲らしめを受けて当然であったと言えよう。「そのころイスラエルに律法にそむく輩が現われ、次のように言って多くの人々をそそのかした。「われわれはでかけて行ってわれわれの周囲の諸国民と契約を結ぼうではないか。彼らから離れて以来、われわれは数多くの禍いに見舞われているのだから」。この意見は人々の眼に善しと思われたので、国民のうちの熱心な者たちが王のもとに出かけると、王は彼らに異邦人の定めを行なう権利を与えた。そこで彼らは異邦人の習慣に従ってエルサレムにギュムナシオンを建て、自分たちを無割礼の状態にもどし、聖なる契約を離れて異邦人と軛をともにし、悪をなすことに身を委ねた。」(『聖書外典偽典1 旧約外典Ⅰ』Ⅰマカベア書1:11~15 p80:教文館)
[本文に戻る]
この時の迫害により、エルサレムでは律法の命じる『常供のささげ物』が捧げられなくなってしまった。アンティオコス4世が、通常の犠牲行為を禁止したのである。それというのも、この王はユダヤの犠牲を忌み嫌っており、奇異に感じていたからである。これ以降、いつも通りに犠牲を捧げるユダヤ人は全て殺されることになった。これは彼らにもたらされた大きな悲劇であった。そればかりか、この王は神殿に『荒らす忌むべきものを据える』ことさえした。これは異教の祭壇とゼウス像を指している。こうしてユダヤの神殿はゼウス神殿とされてしまった。アンティオコス4世は、これほどまでにユダヤをヘレニズムに染めたかったのである。当然ながら、このゼウス像を拝まないユダヤ人は殺されてしまった。
この『荒らす忌むべきもの』だが、これをアンティオコス4世として捉えないように注意せねばならない。ダニエル書では、この王も『荒らす忌まわしいもの』として取り扱われている。先に見たように、ダニエル8:13の箇所ではアンティオコス4世が『荒らす者』と言われていた。しかし、ここで言われているのは、異教の祭壇またゼウス像としての『荒らす忌むべきもの』である。これは人間ではなく偶像のことなのだ。これをアンティオコス4世という人間として捉えると、非常に理解がしにくくなる。その場合、この時にシリア軍がシリア王をエルサレムに据えたことになるが、これは意味が分からない。何故なら、このシリア王は既にエルサレムにおいて神の摂理により荒らす者として据えられていたからである。
【11:32】
『彼は契約を犯す者たちを巧言をもって堕落させるが、自分の神を知る人たちは、堅く立って事を行なう。』
神との契約を蔑ろにした背教者のユダヤ人たちは、アンティオコス4世の『巧言』により大いに堕落させられた。一般民衆だけでなく、多くの祭司たちや貴族たちも、アンティオコス4世の背教的な命令に屈服した。そうしなければ命を失うからである(※)。彼らは大いに堕落し、異邦人も同然となり、ゼウスを拝み、豚を犠牲として捧げ、道徳的な戒めに背くようになった。「民の多くの者たちは律法を捨てて異邦人のもとに集まり、各地で悪行を重ね」たとⅠマカベア書では書かれている(『聖書外典偽典1 旧約外典Ⅰ』Ⅰマカベア書1:52 p83:教文館)。「イスラエルの多くの者たちは、王を礼拝することをよしとし、偶像に犠牲を献げ、安息日を穢した。」とも書かれている(同1:43 p82)。Ⅱマカベア書ではこう書かれている。「災いはすべての人々の上に重苦しくのしかかってきた。すなわち神殿は娼婦とたわむれる異邦人の放縦と騒乱に満ち、彼らは聖なる内殿で女と交わり、そのような場所にふさわしくない物を神殿の中へ持ち込んだ。祭壇は律法に禁じられている不法な品々に満ちあふれた。もはや安息日を守ることも父祖伝来の祭儀を執り行うこともなく、ユダヤ人であることを公然と名乗ることもできなかった。月々王の誕生日には犠牲の獣の内臓を食べることが厳しく強制せられた。デュオニュソスの祭りの時にはきずたを持ってデュオニュソスを祝う行列に加わらねばならなかった。」(『聖書外典偽典1 旧約外典Ⅰ』Ⅱマカベア書5:3~7 p173:教文館)このような状況を見たアンティオコス4世は、さぞかし気分上々だったのではないかと思われる。何故なら、ユダヤ人たちの多くが自分の宗教を捨てて、ギリシャ化したからである。このようになることが、この王の望みであった。
(※)
この時に発せられたアンティオコス4世の命令はこうであった。「異邦人の習慣に従って生活し、燔祭といけにえと灌祭とを穢し、聖所と聖徒たちをはずかしめ、祭壇、社、偶像を祀る神殿を建立し、豚および穢れた家畜を犠牲として献げ、子供たちに割礼を施さず、あらゆる不浄とけがしごとのゆえにその魂を穢すにまかせ、彼らに律法を忘れさせ、あらゆる定めを捨てさせよ。王のことばに従わぬ者は処刑されるであろう。」(『聖書外典偽典1 旧約外典Ⅰ』Ⅰマカベア書1:44~50 p82~83:教文館)「すべての者が一つの国民となって、各自が自分の習慣に固執することをやめるように」(同1:41、42 p82)。
[本文に戻る]
しかし、『自分の神を知る人たちは、堅く立って事を行な』った。つまり、真の信仰者たちは、アンティオコス4世に屈服することをせず、信仰のうちに保たれ続けた。彼らは、神殿が汚されてしまっていたから犠牲は捧げられなかったが、割礼を怠らず、安息日を守り、神を礼拝し、豚も食べず、道徳的な戒めに背くようなこともなかった。Ⅰマカベア書の記述はこうなっている。「しかし、イスラエルの多くの人々は堅く立って互いに強めあい、穢れた肉を食べなかった。食物のゆえに身を穢したり、聖なる契約を穢すよりは、むしろ死を選び、処刑されていったのである。」(『聖書外典偽典1 旧約外典Ⅰ』Ⅰマカベア書1:62~63 p83:教文館)
ここにおいて両者の違いが明瞭に現われ出た。この時、背教者たちは、真の信仰を持っていなかったことを自ら示した。彼らは『神を知る人たち』ではなかった。つまり、神が御自身に背く者には大いに報いられる御方であるということを真の意味で知ってはいなかった。だからこそ、神よりもアンティオコス4世のほうを上に置いたわけである。もし彼らが神を本当の意味において知っていたとすれば、信仰に背きはしなかったはずである。これとは逆に、真の信仰者たちは、この時、自分たちが真の信仰を持っていたことを自ら示した。彼らは『神を知る人たち』であった。つまり、神こそが最も恐れられるべき御方であるということを真の意味において知っていた。だからこそ、彼らはアンティオコス4世に従わないで、神に従い続けたのである。彼らが神について知らなかったのであれば、彼らも背教者たちのようになっていたはずである。我々は、この出来事から、苦難こそが真の姿を明らかにするということを覚えよう。
【11:33】
『民の中の思慮深い人たちは、多くの人を悟らせる。彼らは、長い間、剣にかかり、火に焼かれ、とりことなり、かすめ奪われて倒れる。』
『思慮深い人たち』とは、神を恐れて神に従い続けた人たちのことである。神を恐れることが真の思慮深さである。だから、彼らは本当の意味において『思慮深い人たち』であった。世の中において思慮深いと思われている人がいても、神を恐れていなければ、本当の意味において思慮深いとは言えない。その人は最も恐れられるべき神を恐れていないからだ。それゆえ、その人は究極的に言えば「無思慮な人」に分類される。例えば、ヒュームとアダム・スミスは一般的には思慮深い人たちだと見做されるだろうが、無神論者だったので、究極的には愚か者であったと言われなければならないのだ。この世において思慮深くても、この世を造られた神を無視して蔑ろにしているのであれば、そのような思慮深さが一体何の意味を持つのであろうか。
この思慮深い真の信仰者たちは『多くの人を悟らせ』た。つまり、自分が敬虔の模範となることで、他のユダヤ人たちが神こそ重視されねばならない存在であるということを悟るようにさせた。「そうだ。あの人のように神こそを第一にせねばならない。ここで屈してはならない。そんなことをしては駄目だ。」と。このように悟らされた人はどれぐらいいたのか。具体的な数字を挙げることは出来ない。しかし、相当の数のユダヤ人が悟らされたのは間違いない。何故なら、この箇所では『多くの人』が悟らされると書かれているのだから。
しかし、この『思慮深い人たち』は、その敬虔のゆえに大いに苦しみを受けることになった。敬虔に歩めば苦難は避けられない(参照:Ⅱテモテ3:12)。これは、いつの時代にも言えることである。このユダヤ人たちは『剣にかかり』死刑に処せられた。また『火に焼かれ』断罪されてしまった。また『とりことな』って連れて行かれ、処罰を受けることになった。また所有物を『かすめ奪われて』酷い目に遭わされて『倒れる』ことになった。要するに、彼らはあまりにも大きな悲惨を味わうことになった。これは歴史を調べれば分かる通りである。この苦難の出来事は、ヒトラーがドイツにいたユダヤ人を大いに苦しめたのと、よく似ている。もっとも、アンティオコス4世の時の苦難は懲らしめのために起こり、ヒトラーの時の苦難は陰謀を企む者たちとして危険視されたために起こった(これについては「我が闘争」を読むべきである)、という背景要素の大きな違いがあるのではあるが。
ここで言われている『長い間』とは、42か月間=3年6か月である。というのもダニエル書では、アンティオコス4世の迫害する期間が『ひと時とふた時と半時』(12:7)また『1290日』(12:11)と言われているからである。その期間を具体的に言えば、前167年の夏から前164年の冬までである。すなわち、167年の夏になるとアンティオコス4世の大迫害が始まり、164年の冬になるとユダヤに回復の恵みが注がれた。
【11:34】
『彼らが倒れるとき、彼らへの助けは少ないが、多くの人は、巧言を使って思慮深い人につく。』
真の信仰者たちが殉教した時、彼らを弁護したり、救い出そうとする人は少なかった。これは自然なことであったと言えるかもしれない。何故なら、もし思慮深い人たちを助ければ、仲間と見做され、自分も苦しみに引きずり込まれることになるのは目に見えているからだ。
しかしながら、思慮深い人たちに同調するユダヤ人は多かった。彼らは迫害の中にあっても『巧言を使って思慮深い人につく』ようにした。つまり、口の巧みさにより敵対者たちの攻撃と憎悪とをかわしつつ、あくまでも殉教者たちと同じようにユダヤ教の信仰に留まり続けることを止めなかった。真の信仰者であれば、このようにするものである。何故なら、キリストも言っておられるが、聖徒たちは鳩のように素直でありつつ蛇のように聡くあらねばならないからである。
【11:35】
『思慮深い人のうちのある者は、終わりの時までに彼らを練り、清め、白くするために倒れるが、それは、定めの時がまだ来ないからである。』
ここで『終わりの時』と言われているのは、アンティオコス4世の生命が終わる時のことである。このように解さないと、この箇所をよく理解できなくなる。注意せねばならない。
ここで言われているように、『思慮深い人のうちのある者』は、アンティオコス4世の生命が終わる時までに、多くのユダヤ人を『練り、清め、白くするために倒れ』た。『練り、清め、白くする』とは、要するに復活のことである。何故なら、復活とは、新しい身体に練られ、罪のない肉体へと清められ、キリストの血により白い純粋な状態になることだからである。この復活のために真の信仰者たちが『倒れ』たというのは、つまり真の信仰者たちがユダヤ人たちを復活に至らせる信仰のうちに留まらせるために殉教した、という意味である。先にも述べた通り、彼らが殉教を通して信仰の模範を示すことで、多くの者たちは感化されるので、それだけ既に持っていた信仰から離れなくなるのだ。「我々もこの信仰に踏みとどまらなければ」と。実際、この迫害の時に殉教した7人の子どもたちが見せた信仰の模範により、感化されたユダヤ人たちは次のように言ったとマカベア書では書かれている。「兄弟よ、われわれは律法のためにお互いの兄弟たるにふさわしく死のうではないか。」「兄弟よ、勇気をもて」「立派に耐え忍べ」「魂をお与えになった神に、われわれ自身を心から聖めて献げ、律法を守るためにわれわれの肉体を用いようではないか。われわれを殺そうとしている者(王)を恐れるな、魂の闘いは激しく、神のいましめに背く者には恐ろしい永遠の責め苦が待ちかまえているのだから。神に与えられた理性による情念の支配をわれわれの武具としようではないか。このようにして死ぬわれわれを、アブラハム、イサク、ヤコブなどすべての父祖たちは受け容れ、称賛するであろう。」(『聖書外典偽典第3巻 旧約偽典Ⅰ』第4マカベア書 第13章8~17 p128:教文館)もし7人の子どもたちが信仰の模範となって『倒れ』ていなければ、ユダヤ人たちがこのように奮い立つことは決してなかったであろう。サドも言っていたが、このアンティオコス4世の時を含め、今までに行なわれた聖徒たちに対する迫害と攻撃は、ことごとく無意味であった。それは、かえって反対の効果をもたらした。筋肉が痛めつけられれば痛めつけられるほどかえって強さを増すように、神の勢力も苦しみを受ければ受けるほどその力と範囲を増し加えたのである。苦しみによって進むのが聖徒たちの集団である。そのようにして今に至るまで聖なる陣営はどんどんと世界に拡がってきたのである。サタンはこのことに気付いたので、もう今となってはかつてのような苦難を与えることをしていない。そのようにすることは神の陣営に結果的に益を与えることになるからである。だから、今となってはサタンはやり方を巧みに変えている。
アンティオコス4世の『定めの時』が来るまで、真の信仰者たちは殉教しなければいけない状況に置かれていた。しかし『定めの時』が来て、アンティオコス4世が『終わりの時』を迎えると、もう彼らが殉教をせねばならないような状況は消え失せた。何故なら、その時にはもう迫害を引き起こした暴君はこの世からいなくなっているのだから。
【11:36】
『この王は、思いのままにふるまい、すべての神よりも自分を高め、大いなるものとし、神の神に向かってあきれ果てるようなことを語り、憤りが終わるまで栄える。』
アンティオコス4世は『思いのままにふるま』った。Ⅰマカベア書1:10では「罪深いひこばえ」と適切に表現されている。これは歴史を見れば明らかである。この王は、多くの者を殺し、多くの略奪を為し、多くの欺瞞を働いた。正に彼は「忌まわしい者」であった。
彼はまた『すべての神よりも自分を高め、大いなるものとし』た。異教の神々はもちろんのことである。そればかりでなく、彼は古代ユダヤ教の神すなわち唯一真の神をも自分の下に位置づけさせた。これは彼について記されたことを読めば容易に分かることである。
また彼は『神の神に向かってあきれ果てるようなことを語』った。『神の神』とは、ヤハウェ神のことである。『あきれ果てるようなこと』とは、冒瀆の言葉、不遜な蔑み、邪悪な批判のことである。このシリア王は、サタンからこのような悪しき口を与えられた。つまり、神は、サタンがアンティオコス4世に悪しき口を授けることを御許しになられた。そうでなければ、この王が神に向かって愚かなことを語ることはなかったであろう。ネロも、このようにしてサタンから悪しき口を受けたのである(黙示録13:5~6)。このシリアの暴君は、ユダヤ人に偶像に捧げられた豚肉を無理やり食べさせようとしていた時、エレアザルという老人に次のように言ったが、これは『あきれ果てるようなこと』だと言ってよいであろう。「考えてもみるがよい。もしお前たちのこの宗教を見張っているある力が存在するとしても、その力はやむをえず犯した律法違反に対してはお前をとがめはしないだろう。」(『聖書外典偽典第3巻 旧約偽典Ⅰ』第4マカベア書 第5章13 p111:教文館)(※)この思い違いは何というイカレ具合であろうか…。
(※)
この老人についての話は、Ⅱマカベア書6:18~31でも記されている。
[本文に戻る]
このアンティオコス4世は『憤りが終わるまで栄える』ことになった。これは、つまりユダヤに対する神の懲らしめの憤りが全うされる時まで、アンティオコス4世は妨げられることなく活発に迫害を行なった、という意味である。その憤りが終わったのは前164年であった。我々は、この悲惨な迫害が、懲らしめのために起きたということを知らねばならない。この時のユダヤは酷い状態にあった。だからこそ、神が憤られ、懲らしめとしてアンティオコス4世の暴虐をユダヤに対して発揮させられたのである。もしユダヤが敬虔に歩んでいたとすれば、このようにしてアンティオコス4世が迫害を行なうことは出来なかったはずである。つまり、この苦難は、神の愛から出ていた。要するに、神は父として子であるユダヤ人たちをお叱りになられた。それだから、このような苦しみを受けたユダヤ人たちは、その苦しみを許可された神に対して文句を言うことが出来なかった。それは箴言3:11~12の箇所で次のように書かれている通りである。『わが子よ。主の懲らしめをないがしろにするな。その叱責をいとうな。父がかわいがる子をしかるように、主は愛する者をしかる。』なお、ヨブの受けた苦難は、この時の苦難とは異なっており、ヨブに対する試練と教訓のために与えられた。それは罪に対する懲らしめとしての苦難ではなかった。何故なら、ヨブは敬虔な人であって、罪から離れて歩んでいたからである。それだから、アンティオコス4世の時の苦難とヨブに与えられた苦難を、同一の意味を持った苦難として混同しないようにすべきである。
『定められていることが、なされるからである。』
このようにしてアンティオコス4世がユダヤを迫害したのは、永遠の昔から『定められていること』であった。だからこそ、このシリア王はユダヤを苦しめたのである。あらゆる出来事は神の定めに基づいて起こる。この世では、神が定めておられない出来事が起こることは絶対にない。だから、もし神がアンティオコス4世の迫害を定めておられなかったとすれば、この王がユダヤを苦しめることは起きていなかった。これは間違いないことである。このように私が言うと、神の定めについてブツブツと不平を鳴らす心に割礼を受けていない輩が出てくるものである。この定めの問題については既に本書の中で解決しておいたし、カルヴァンをはじめとした多くの神学者たちも十分に論じているし、パウロもローマ書の中で彼らに対して語っているのだから、ここで再び説明をするのは冗長であり、あまり適切でないと私は判断する。
【11:37】
『彼は、先祖の神々を心にかけず、女たちの慕うものも、どんな神々も心にかけない。すべてにまさって自分を大きいものとするからだ。』
アンティオコス4世は、自分を全てに勝る至高の存在であると考えていた。マカベア書では彼が「高慢な恐るべき人物」(『聖書外典偽典第3巻 旧約偽典Ⅰ』第4マカベア書 第4章15 p109:教文館)だったと正しく言われている。これはネロもその通りであった。Ⅱテサロニケ2:4の箇所でネロについて、『彼は、すべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ』と書かれている通りである。このシリア王はその傲慢のために、『どんな神々も心にかけな』かった。何故なら、この高慢な王にとって、自分よりも上に位置する神がいるなどというのは、まったく耐え難いことだったからである。極度の傲慢は、神さえをも凌駕してナンバー1になりたいと願わせるのである。また、ここでは『女たちの慕うもの』と書かれているが、これは恐らく偶像のことではないかと思われる。それというのも、女の慕う物と言えば、文脈から考えれば偶像ぐらいしか思い当たるものがないからである。もし偶像でないとすれば、名将やスター兵士また人気のある劇作家や俳優を指しているのであろう。
この王のように自分を全ての神に勝る存在だと考えるのは、傲慢の極致である。これ以上の傲慢を考えることはできない。何故なら、神よりも高い存在はいないからである。数百年前には、ヨーロッパに神の創造を指導するかのような言葉を吐いた啓蒙主義者が現われたものである。この者曰く「もし私が創造の前に存在していたとすれば、神にどのように創造すればよいか助言を与えてやっていたであろう。」この者は間違いなく最高に高ぶっていた。いつの時代にも、このような者が少しぐらいは、どこかにいるものである。
【11:38】
『その代わりに、彼はとりでの神をあがめ、金、銀、宝石、宝物で、彼の先祖たちの知らなかった神をあがめる。』
しかしながら、これには例外が一つだけあった。それは『とりでの神』である。アンティオコス4世は、砦の神だけは例外的に崇拝していた。しかも熱心に、である。何故なら、ここでは『金、銀、宝石、宝物で』その神を崇めると言われているから。本当に熱心でなければ、自分の財物を犠牲にしてまで崇拝することは難しい。この『とりでの神』だが、これがどのような神だったのかはよく分からない。アンティオコス4世について記された古代の文書を読んでも、その神については何も言及されていない。その神は『彼の先祖たち』も『知らなかった』ようである。このアンティオコス4世は、ユダヤを占拠すると、そこに要塞(アクラ)すなわち砦を建設した。そして、その要塞を拠点にして、侵略行為を更に続けて行なった(※)。これは彼が『とりでの神をあがめ』ていたのと関係があるかもしれない。つまり、彼は自分の崇拝する砦の神のために、敵地に砦を打ち立てたのではないかと考えられる。そうして、その砦の神の力を借りて、ますます敵地を荒廃させていったと。要するに、彼が砦を建設したのは自分の神に対する礼拝行為の意味があったのではないかと思われる。しかし、この見解については、確かな資料が欠如しているのだから、あくまでも推測に過ぎないものであることを忘れないようにしていただきたい。
(※)
Ⅰマカベア書にはこうある。「そして、大きくて堅固な城壁と堅固な櫓とを備えたダビデの町を建設したので、これが彼らの要塞となった。彼らはそこに罪深い民、律法にそむく者たちを住まわせ、その町で彼らの力を強くした。すなわち彼らは武器と食糧とを備え、エルサレムから戦利品を運びこんでそこに貯え、恐るべきわなとなった。要塞は聖所に対する妨げとなり、常にイスラエルに対する憎むべき敵となった。」(『聖書外典偽典1 旧約外典Ⅰ』Ⅰマカベア書1:33~36 p81:教文館)
[本文に戻る]
【11:39】
『彼は外国の神の助けによって、城壁のあるとりでを取り、彼が認める者には、栄誉を増し加え、多くのものを治めさせ、代価として国土を分け与える。』
この王は『外国の神』(=『とりでの神』)に助けられ、『城壁のあるとりでを取』ることができた。これは実際の歴史を見れば分かる。彼は確かに諸国に遠征し、その国の要塞を打ち破り、そこを占拠した。このように出来たのは彼の崇拝していた『外国の神』に助けられたからであった。これは偽りの神であって、その正体は悪霊であった。悪霊どもは、この砦の神であれアシュタロテであれバアルであれゼウスであれアポロンであれシヴァであれカーリーであれ、「神」という仮面を実に巧妙に付け、人間どもが己を崇めるようにさせている。それは人間をもてあそぶためである。「くくく、あいつら人間は愚かだから実は俺たちであると知らずに偽りの神を崇拝していやがる、本当の神はただ一人しかいないというのにな。どうせ何も気づかないのだから愚かな状態のままに留めておいてやろう!」と。
アンティオコス4世は『彼が認める者には』大いに恩恵を与えた。これは、アンティオコス4世に聞き従って背教した一部のユダヤ人のことである。すなわち、背教した全てのユダヤ人が王から恩恵を受けられたというわけではない。恩恵を受けたのは、あくまでもアンティオコス4世から直接的に話しかけられて背教した一握りの者たちだけである。この王は、そのようにして背教した者には『栄誉を増し加え』た。王が大いに誉れを与えたのである。また、その背教者に王は『多くのものを治めさせ』た。つまり、強大な支配権を持つ総督や大臣にさせた。また、その背教者に王は『代価として国土を分け与え』た。国土というこの大きな贈り物は背教に対する報酬であり、王による親愛の印であった。実際、この暴君は7人の子どもたちに脅迫しつつこう持ちかけている。「…わたしの言うとおりにしてわたしの友情を楽しむように勧める。わたしはわたしの命令に従わない者をこらしめることも、またわたしに心から従う者に恩恵を与えることもできるのだ。だからもしお前たちの父祖伝来の生活規定を捨てるならば、わたしの国事に関して指導的な地位を得るであろうということを信ずるがよい。お前たちの生活をギリシアふうに改め、お前の国の若者たちの間で豪華な生活をしてはどうか。」(『聖書外典偽典第3巻 旧約偽典Ⅰ』第4マカベア書 第8章5~8 p118:教文館)「…もし服従するならばわたしの友となって王国の国事をつかさどることになるであろう。」(同 第12章4 p126)つまりアンティオコス4世は「もし父祖伝来の慣習から離れるならば金持ち、最も幸福な者、王の友とし、国事を委ねようと誓って約束した」(Ⅱマカベア7:24)のである。この7人の子どもたちは、もしアンティオコス4世に従うならば『彼が認める者』となり、多くの恩恵を受けることができていた―実際は従わなかった。アンティオコス4世の側近も、マッタティアスに対して「王の命令に従え。」と言って、こう持ちかけた。「さらば汝も、汝の息子たちも王の友となり、汝も汝の息子たちも、金、銀やさまざまなの賜物をもって栄えを受くるであろう。」(『聖書外典偽典1 旧約外典Ⅰ』Ⅰマカベア書2:18 p85:教文館)このマッタティアスも、もし王の命令に従うならば、大きな栄誉を受けることができた―実際は従わなかった。このことからも分かるが、往々にして不敬虔の報酬は物質的な幸福である。悪しきことをすれば繁栄したり幸福になることが出来る。この世はそういう仕組みになっているのだ。これは今までの歴史および現在の社会をよく見て考えれば分かることである。<石油王>ジョン・D・ロックフェラーは、どれだけ懸命な悪の策略を働かせて、石油利権を獲得し保持したことであろうか。もし彼が真面目な道徳坊やでいたとすれば、あのように莫大な富を得ることはできなかったであろう。キリストも、もしサタンの前にひざまづいて服従するならば全世界の支配権を受けられるようになる、とサタンから誘惑を受けた。これは不敬虔になればこの世において幸いになれる、ということである。もっとも、そのようにして得た繁栄や幸福は、なかなか長続きしないことが多いのではあるが。
【11:40】
『終わりの時に、南の王が彼と戦いを交える。北の王は戦車、騎兵、および大船団を率いて、彼を襲撃し、国々に侵入し、押し流して越えて行く。』
『終わりの時』とは「アンティオコス4世の生命が終わりに近づく時」という意味である。これをユダヤの終わりの時(紀元1世紀)であると捉えると、この箇所を上手に理解できなくなってしまう。注意しなければいけない。
アンティオコス4世が生命を終わらせる時に近づくと、彼はエジプト王と戦いを交えた。それは『戦車、騎兵、および大船団を率いて』行なわれた大規模な戦いであった。その結果、エジプト王は打ち負け、エジプトは悲惨な状態にさせられてしまった。つまり、これは第6次シリア戦争のことである。何故なら、アンティオコス4世がエジプトと戦った出来事といえば、それ以外にはないからである。ここで、どうして既に語られていた出来事が再び語られているのか、と疑問を持つ人がいるに違いない。確かに第6次シリア戦争については既に語られていた。答えは簡単である。この箇所では、アンティオコス4世の晩年という観点から、再びこの戦争のことが語り直されているのだ。つまり、ここで言われている出来事は、11:35の箇所に時間的に後続する内容として語られているわけではない。前の箇所とこの箇所とは時間的な繋がりがない。だから、ここで再び既に語られた戦争について語られていたとしても問題にはならない。第3部でも述べたが、ユダヤ人はこのようにあまり時間を考慮しない書き方をよくしたものである。
またこの王は、多くの『国々に侵入し』てシリアの支配領域を拡張しようとした。実際はどうだったか分からないが、彼は自分の父アンティオコス3世のように豊かな征服を為したいと願っていたのかもしれない。この侵入の際に彼は『押し流して越えて行』った。これはシリア軍があたかも洪水のように敵たちを薙ぎ倒して敵地を進んで行った、という意味である。実にユダヤらしい象徴的な表現である。
【11:41】
『彼は麗しい国に攻め入り、多くの国々が倒れる。』
また彼は、既に述べたが『麗しい国』であるユダヤにも侵攻した。それは前169年と前168年の2回であった。これらは、どちらもエジプト遠征の帰り際に行なわれた。
彼はユダヤだけでなく、その他の多くの国々にも攻め入った。彼は第6次シリア戦争が終わると、東のほうに心を向け、そちらのほうに突き進んで行った。そしてアルメニアやペルシャの大部分を支配下に治めることが出来た。11:39の箇所でも言われていたようにアンティオコス4世は砦の神つまり悪霊が化けた偽りの神に助けられていたので、多くの国を獲得することが出来たのである。その際には『多くの国々が倒れた』と、この箇所では言われている。『倒れた』とは「征服された」という意味である。
『しかし、エドムとモアブ、またアモン人のおもだった人々は、彼の手から逃げる。』
『エドムとモアブ、またアモン人のおもだった人々』は、アンティオコス4世に打ち取られることがなかった。これらの国は、どれもイスラエルの敵であり、呪われた者の子孫である。すなわち、エドムはエサウの子孫たちであり(創世記36章)、モアブまたアモンは近親相姦者の子孫である(創世記19:30~38)。どうしてこれらの国のある人たちは、アンティオコス4世から逃れたのか。これは、よく分からない。ただ一つ言えるのは、神が許可されたからこそ、彼らはこの王から逃げることが出来たということである。キリストも言われたように、スズメの一羽でさえも神の許しなしには地に落下することがないのだから。
【11:42】
『彼は国々に手を伸ばし、エジプトの国ものがれることはない。』
この王は諸国に攻め入り、そこを占領した。それは彼が砦の神に助けられていたからであった。彼はエジプトにも侵入して荒らし回った。これらの侵略は既に語られていたが、ここでは再び総括的に語られているのである。
【11:43】
『彼は金銀の秘蔵物と、エジプトのすべての宝物を手に入れ、ルブ人とクシュ人が彼につき従う。』
アンティオコス4世は多くの財物を手に入れた。諸国に攻め入った際、そこから金目の物を強奪したのである。支配者が高価な物に目が無いのは常のことだが、この王もその一人であった。
このシリア王には『ルブ人とクシュ人』も付き従った。『クシュ』とはエチオピアである。これはエジプトの近くにある。『ルブ』という地もエジプトの近くに位置している。他の箇所を見ると、このルブ人はエジプトと一緒に語られており(※)、エジプト人の仲間だったことが分かる。つまり、アンティオコス4世はエジプトを侵略した際、その周りにいた民族をも自分に従わせたのである。なお、この3つの民族はどれもハム系である。
(※)
『クシュとエジプトはその力。それは限りがない。プテ人、ルブ人もその助け手。』(ナホム3章9節)
『また、彼とともにエジプトから出陣した民、すなわちルブ人、スキ人、クシュ人の人数は数えきれないほどであった。』(Ⅱ歴代誌12章3節)
[本文に戻る]
【11:44】
『しかし、東と北からの知らせが彼を脅かす。彼は、多くのものを絶滅しようとして、激しく怒って出て行く。』
アンティオコス4世はエジプトとの戦争を終えると、『東と北からの知らせ』に脅かされた。『東』からの知らせとは、シリア軍がペルセポリスで敗北したという知らせのことである。アンティオコス4世は第6次シリア戦争の後、東方に侵略のため出向いて行った。その時にペルセポリスを彼の軍隊が征服しようとしたのだが、大群衆の抵抗を受けて、撤退せざるを得なくさせられた。この報告はアンティオコス4世を脅かした。『北からの知らせ』とは、北王国シリアがユダヤに打ち負かされたことである。アンティオコス4世がユダヤにいない時、彼の僕であったニカノルとティモテオスがユダヤの地において敗北させられて追い返されてしまった。こ敗北の知らせもアンティオコス4世を脅かした。王という者は勝敗に敏感であるから、敗北の知らせには人一倍動揺させられるものである。その勝敗には、国と国民と自分の命および運命そして更には名誉とがかかっているのだから。
アンティオコス4世はペルセポリスでの敗北を聞いて動じていた時にユダヤでの敗北を聞かされたので、大いに混乱してしまった。そして彼の怒りは頂点に達した。何故なら自分の思うように事が進んでいないからである。そのため彼は『激しく怒って出て行』った。それは『多くのものを絶滅しようとして』であった。その『多くのもの』とはエルサレムにいたユダヤ人のことである。つまり、彼はうっ憤を晴らそうとして、ユダヤ人を滅ぼしてやろうといきり立ったわけである。何という子どもじみた狂気の愚行であることか。彼は聖書に『短気な者は愚かなことをする。』(箴言14章17節)と書かれているのを知らなかった。
【11:45】
『彼は、海と聖なる麗しい山との間に、本営の天幕を張る。』
『海』とは地中海である。これを死海として理解すべきではない。『聖なる麗しい山』とは、もうお分かりだろうが、エルサレムである。ダニエル9:16の箇所ではエルサレムが『聖なる山』と言われているからである。『本営の天幕を張る』とは、間もなく本格的な戦いを仕掛けることを示す。何故なら、本格的な戦いをしないのにもかかわらず、わざわざ『本営の天幕を張る』ことはしないからである。
つまり、ここではアンティオコス4世が地中海とエルサレムとの中間の地域に戦いのための天幕を張る、と言われていることになる。これは、この王がもうすぐにもエルサレムに攻め入ろうと準備態勢を取ったことを教えている。何故なら、地中海とエルサレムに挟まれた地域とエルサレムは、距離的にごく近いからである。実際、この王はユダヤを絶滅しようと決意すると、即座にエルサレムへと向かって行こうとした。
『しかし、ついに彼の終わりが来て、彼を助ける者はひとりもいない。』
そのようにしてエルサレムに突き進もうとしていた正にその時、アンティオコス4世は倒れてしまった。恐らく病かと思われる悲惨な苦痛が神の裁きにより彼に与えられ、それから間もなくこの暴君は絶命してしまったのである。これは絶妙なタイミングであった。もうこの王がユダヤを荒らし回らないようにと、神がちょうどよく働きかけられたのである。この王が倒れた時、『彼を助ける者はひとりもいな』かった。何故なら、病気か何らかの異常により生じた酷い腐臭のために近づき難かったうえ、神が身体の内部から激しい打撃を彼に加えておられたので、何かをしようにもどうにもならなかったからである。このことについてⅡマカベア書では次のように書かれている。「そのころアンティオコスはペルシア地方から無残な退却をなすはめにおちいっていた。というのは彼はペルセポリスといわれる町へはいって神殿のものをかすめ、町を占領しようとしたのだが、群集が騒ぎだし武器をとって立ち上がったため、アンティオコスは現地人たちに追われて恥ずべき退却を余儀なくされたのである。ところが彼がエクバタナまで来たときにニカルノとティモテオスの敗戦の報が伝えられると、彼は激しく怒って、自分を敗走せしめた者たちから受けたはずかしめをユダヤ人に報いてやろうと考え、天からの裁きがわが身に臨んでいることも知らないで、戦車の御者に向かって、全行程を休みなく走り続けよと命じた。彼はおごり高ぶって言った。「エルサレムへ着いたらそこをユダヤ人の共同墓地にしてやろう」。そこですべてをみそなわしたもうイスラエルの主なる神は彼に眼に見えない癒しがたい打撃を与えた。彼が語り終えるや否や内蔵の激しい痛みが彼を襲い、体の内部にするどい苦しみが生じた。他人の内臓をさまざまなつねならぬ災いをもって苦しめた男にはまことにふさわしい裁きであった。ところが彼は決して激しい心をおさえようとはせず、なお傲慢な思いに満たされてユダヤ人に対して激しく心を燃えたたせ、もっと急げと命じた。すると彼は疾走する戦車からころげ落ち、しかも落ち方が悪かったため全身にひどい傷を負った。今までは人間の分際をもわきまえず海の波を従わせ山の高さをものさしで測ろうと考えていたこの男は、地に倒れて担架で運ばれ、隠れもなき神の力を万人に示すに至ったのである。この不信仰な男の眼からは虫がわき、激しい苦痛にさいなまれつつ生きながらその肉がくずれてゆき、全軍は彼の体が腐敗してゆくために発する悪臭に悩まされた。彼はしばらく前には天の星に手を触れようとすら考えていたのだが、その耐えがたい悪臭のゆえにだれも彼を運ぶことができなかった。」(『聖書外典偽典第一巻 旧約外典Ⅰ』Ⅱマカベア9:1~10 p182~183:教文館)これは外典に過ぎないが、この引用文の内容は信頼してもよいものだと私は思う。何故なら、ここで言われていることは、我々が今見ているダニエル書11章の箇所の内容とまったく一致しているからである(※)。この暴君の終わりの時であるが、大英博物館の持つBM35603というテキストによれば、アンティオコス4世の死についての報せがバビロンで確認されたのが前164年11月20~12月18日の間だったという。つまり、このテキストによれば、彼はこの期間のある日に死んだということになる。また、ポリュビオスによれば、彼は「ペルシスのタバイで生を終えた」(『歴史4』第31巻:9、3 p238:京都大学学術出版会 西洋古典叢書 2012第8回配本)という。このタバイという町がどこにあるかは不明である。
(※)
この後、アンティオコス4世はこのように言ったとⅠマカベア書では書かれている。「わたしは今やなんと大きな患難に出会い、なんと大きな荒波にもまれていることだろう。権勢のうちにある時にはわたしは憐み深く、また愛されていたのに、今わたしはエルサレムでなしたさまざまの悪事を思い起こす。わたしはエルサレムにあったあらゆる金銀の飾りを奪い、ゆえなくユダの住民を滅ぼさんと軍を遣わした。わたしはそのためにかかる不幸にみまわれたのだということを知っている。見よ、わたしは大いなる苦しみのうちに異国の地で死のうとしているのだ。」(『聖書外典偽典1 旧約外典Ⅰ』Ⅰマカベア書5:11~13 p103:教文館)―この暴君がこのように本当に言ったのかどうかは定かではない。聖書から裏付けることもできない。
[本文に戻る]
というわけで、ここまでがアンティオコス4世についての記述であった。先にも述べた通り、この王についての記述は、ダニエル書11章の半分以上を占めている。これはアンティオコス4世という王が、聖徒たちにとって非常に重要な意味を持っていることを示している。この王は、キリストさえも言及されたほどの存在である。そのことからも、この王がどれだけ重要であるのか察することが出来るはずである。もし彼がそこまで重要ではなかったとすれば、ダニエル書11章でこんなにも彼について書かれていることも、キリストにより言及されることも、無かったはずである。
【12:1】
『その時、』
この箇所から、我々は視点を変革させなければならない。その変革とは、時間を先にずらすということである。すなわち、この12:1~3の箇所では、これまでに語られていたアンティオコス4世をネロに、その記述における時代を紀元前170年代から紀元60年代に置き換えなければならない。これに刮目すべきである。これは理解の奥義である。この奥義を採用してこそ、12:1~3の箇所を正しく読み解けるようになる。この3節分の箇所では復活の出来事が語られている。この復活がネロの時代に起こったということについては、既に本書の中で聖書から論証された。つまり、ここで言われている『その時』とはアンティオコス4世の時代として理解されるべきではない。これは視点を未来に置き変えたうえでの『その時』として理解されねばならない。何故なら、実際に復活が起きたのはネロの時代だったのだから。このような読み方がこの箇所で要求されているのは、神がこの文書をお書きになられたからに他ならない。私はこの奥義を悟った時、非常に驚かされ、脳がひねくれるかのようであった。何故なら、その奥義は人間の理性を超え出ているからである。もし人間がこの文書を書いたというのであれば、このような書き方はできていなかったであろう。実際、このような読み方を要求するような書物や文書を、私は聖書以外において今まで見たことがない。
この奥義を悟ることなしに、この12:1~3の箇所を上手に理解することは絶対にできない。仮に、この箇所をそのまま単純に解釈してみよう。するどどうか。その場合、前の箇所である11:45ではアンティオコス4世が死んでいるが、この王が死んだ『その時』に、12:1~3で書かれている善人と悪人の復活が起きたと教えられていることになる。それは紀元前164年である。紀元前2世紀に復活が起きた!これはとんでもない話である。何故なら、紀元1世紀に生きていたキリストとパウロは、まだ復活が起きていないと認識していたのだから(ヨハネ6:39~40、Ⅰテサロニケ4:16、使徒行伝24:15)。このように奥義を抜きにして「普通に」解釈しようとすると、とんでもない考えを持たねばならなくなる。だから、この12:1~3の箇所は私が言った通り、時間と人物を未来にずらしつつ解さなければいけないことになる。そうすれば無理もなくすんなりと事が理解できるようになるのだ。これを私は「視点の変革による解釈手法」と呼びたい。
要するに、このアンティオコス4世とはネロのモチーフ・予表としての暴君であった。それはダビデがキリストの影としての王であったのと同じである。ネロを中心として見れば、ネロはアンティオコス4世の再来した暴君だったということになる。それはバプテスマのヨハネがエリヤの再来した者だったのと同じである。キリストがマタイ24章15節でダニエル書に触れつつ『荒らす憎むべき者』について語られたのも、つまりはネロをアンティオコス4世において語られたのである。キリストはそこでこのように言われたのだ。「これからアンティオコス4世でもあるかのようなネロという暴君が聖なる所に立つであろう。」キリストが、この『荒らす憎むべき者』をアンティオコス4世その人自身として語ったと考えてはいけない。あくまでもキリストはこのシリアの暴君をモチーフとして語られたに過ぎない。そうでなかったとすれば、キリストは聖書も歴史もまったく理解しておられなかったことになる。何故なら、このシリア王は、キリストがおられた時代には既に死んでこの世にいなくなっているのだから。既に死んだ者が再び暴君として現われると言うことほど愚かなことはないのである。
『あなたの国の人々を守る大いなる君、ミカエルが立ち上がる。』
ユダヤの共同体は『ミカエル』により守られていた。このミカエルはユダ9の箇所で言われているように『御使いのかしら』である。その高い誉れのゆえに、ここでは『大いなる』者であると言われている。ユダヤ人たちは、自分たちを守護するミカエルを君として意識していたわけではなかった。しかし、この箇所ではミカエルがユダヤにおける『君』と呼ばれている。これは神が、この御使いをユダヤを守護・管理・統導する存在として任命されたからである。キリストが言われた通り、聖徒たちにはそれぞれ守護者としての御使いが割り当てられている(マタイ18:10)。それと同じように、聖徒たちの国家にもそれぞれ守護者としての御使いが割り当てられていた。守護者は、聖徒たちだけでなく国家も持っているのだ。聖徒に割り当てられている御使いは、その任されている聖徒たちを導き、守り、危ない目に遭わないようにする。それは詩篇で次のように言われている通りである。『まことに主は、あなたのために、御使いたちに命じて、すべての道で、あなたを守るようにされる。彼らは、その手で、あなたをささえ、あなたの足が、石に打ち当たることのないようにする。』(91:11~12)このようにするのが聖徒たちに付いている御使いの役目であり意味である。これと同じで、聖徒たちの国家に付いていたミカエルも、国家を導き、守り、危ない目に遭わないようにする役目と意味を持っていた。つまり、ミカエルはただ何となくユダヤの国家に付いていたわけではなかったのだ。
ユダヤ以外の国にも、守護者としての御使いが割り当てられている。それは、いかに小さな国であっても、どれだけ忌まわしい国であっても、そうである。それぞれの国は固有の御使いを持っているのだ。しかし、どうしてそのように言えるのか。なぜ守護の役割を持つ御使いが割り当てられているのはユダヤだけではないのか。神の敵である国にも御使いがいるというのは、本当なのか。私は言うが、ダニエル書10:20の箇所では『ペルシャの君』また『ギリシャの君』と書かれているのだから、この箇所からユダヤ以外の国にも御使いが割り当てられているのは明らかである。もしユダヤにだけしか『君』がいないのだとすれば、ペルシャとギリシャにも君がいるなどとは言われていなかったはずである。それでは西暦21世紀の今の時代にも国家には、それぞれ御使いが割り当てられているのか?―もちろん、そうである。アメリカにはそのような御使いがいるのか?―いる。ではルクセンブルクのような小さな国には?―そこにも守護天使が割り当てられている。このことから、300人委員会が推進しているワンワールド計画は、この守護者としての御使いを一人だけに限定しようとする企みであることが分かる。その企みが実現した際には、存在する守護者としての御使いはワンワールド国に割り当てられているサタン一人だけとなる。というのも、その時には、諸国家は廃止され、単なる一つの行政地域に過ぎなくなるからである。この守護者を諸国家から排除する企みが、聖書に適っているとは思われない。全能者なる神は、この企みをどのように見ておられるであろうか。神は、御心には適わないけれども、何らかの目的を実現させるために一度だけはその企みの実現を許可されるのであろうか。全ては御心次第である。このワンワールド計画がどうなるかは今後の歴史が明らかに示してくれるであろう。
さて、アンティオコス4世の再来者として認識すべきネロが死んだ『その時』(12:1)、この『ミカエルが立ち上がる』ことになった。これはミカエルが、再臨されるキリストを先導するために立ち上がったことを言っている。王が凱旋する際には、将軍や高官たちが王の前を先導することで、王の威光を更に増し加えようとする。それと同じで、ミカエルという天使長も、再臨のキリストの威光を高めるべく先導者として立ち上がったのである。再臨の際にミカエルがキリストの前に進むというのは、Ⅰテサロニケ4:16の箇所から分かる。そこでは次のように言われている。『主は、号令と、御使いのかしらの声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られます。』また、この時にミカエルはサタンと戦って勝利した。何故なら、我々が今見ているこの箇所で言われている出来事は、黙示録12:7~9の箇所と対応しているからである。このミカエルとサタンの戦いについては既に第3部の中で述べられている。読者は、この箇所で言われている出来事が、再臨の時のことであるという点に注目すべきである。
『国が始まって以来、その時まで、かつてなかったほどの苦難の時が来る。』
『国が始まって』とは、いつなのか。これはイスラエル国家が建設された時であると私は考える。つまり紀元前1000年頃である。しかし、これを神が御自身の国をアブラハムのうちに打ち立てられた時だと理解する人がいたとしても、私はその人の見解を否定しようとは思わない。この見解のほうが気に入る人は、そのように理解していればよい。
ここで言われているように、ネロの時代には『苦難の時が来る』ことになったが、これはユダヤ戦争およびネロによるキリスト教迫害を指している。この『苦難の時』が未だに訪れていないなどと考えないように注意せよ。
この苦難は、ユダヤの国が始まって以降、もっとも厳しい出来事であった。それはネブカデレザル2世によるエルサレムの破壊よりも酷い出来事であった。何故なら、ローマの軍隊はバビロンの軍隊よりも激しくユダヤを荒らしたし、紀元1世紀の時には捕囚という情けも与えられなかったし、その時にはユダヤ人だけでなくキリスト教徒たちも大量に虐殺されたからである。しかも、この苦難はユダヤ史上というだけでなく人類史上もっとも厳しい苦難であった。キリストはこの時の苦難についてこう言われた。『そのときには、世の初めから、今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないような、ひどい苦難があるからです。』(マタイ24章21節)この時の苦難における悲惨さについては、既に第2部の中で述べられている。今引用されたマタイ24:21の箇所については、また後ほど註解がされることになる。
『しかし、その時、あなたの民で、あの書にしるされている者はすべて救われる。』
『あなたの民』とは、神の民であるアブラハムの子たちというユダヤ人のことである。しかし、『その時』には信仰を持った異邦人も神の民に加えられていたことを忘れてはならない。何故ならパウロも言っているように、新約時代になってからは『信仰による人々こそアブラハムの子孫』(ガラテヤ3:7)なのだからである。
『あの書』とは、もちろん「命の書」を指している。これは神の選びを書物という物体により象徴的に言い表した言葉である。この象徴表現については、既に第3部の中で十分に論じておいたので、どういうことだったのか忘れた人は当該箇所に戻って学び直してほしい。
『その時』に、永遠の昔から選ばれていた聖徒たちは『すべて救われる』ことになった。すなわち、紀元68年6月9日までに死んでしまった聖徒たちは魂だけの状態から新しい身体を付与された状態に切り替えられ、その時に生きていた聖徒たちは生きながらにして復活の救いに与かることになった。このように復活は複数の仕方によって実現された。全ての聖徒たちが同一の仕方で復活に与かったわけではない。しかし、どのようにして復活したにせよ、それが究極的な救いをもたらす復活であったことには変わりない。この復活の出来事は既に起きた。今の教会の聖徒たちは、聖書の研究不足のため、まだこの復活が起きていないと考えているが、それは間違っている。何故なら、パウロは紀元1世紀のテサロニケ人たちが『生き残っている』間に復活が実現すると明白に言っているからだ(Ⅰテサロニケ4:16~17)。読者は思い違いをしないようにしてほしい。今の教会は、特に教理面において異常なものが多く満ちており、聖書に真っ直ぐ立てていない状態にある。高名な神学者と見做されている教師が、普通に進化論やディスペンセーショナリズムを信じているが、キリスト教界のトップに立つと認識されている教師たちがこんなようでは、その他の無数の教師および教会が酷い状態にあったとしても特に驚くには値しないのかもしれない。
【12:2】
『地のちりの中に眠っている者のうち、多くの者が目をさます。ある者は永遠のいのちに、ある者はそしりと永遠の忌みに。』
この時には、『地のちりの中に眠っている者のうち、多くの者が目をさます』ことになった。『目をさます』とは復活である。つまり、「死」=「眠り」という見方がこの箇所ではされている。キリストとパウロも、死んだ聖徒たちを眠っている聖徒として取り扱った。これは死から復活するのが、あたかも眠りから目覚めるようだからである。なお、この箇所で言われているのは、地上で復活した聖徒たちのことである。何故なら、この箇所では『地のちりの中に眠っている者のうち』と書かれているから。これは天上のことではない。しかし、この時には当然ながら天上に魂だけの状態で居続けていた聖徒たちも、その天上の場所で復活することになった。ただこの箇所では、地上で復活する聖徒たちにだけ触れられているに過ぎない。
この箇所で言われていることは、キリストがヨハネ5:28~29の箇所で言われたことである。そこではこう言われている。『墓の中にいる者がみな、子の声を聞いて出て来る時が来ます。善を行なった者は、よみがえっていのちを受け、悪を行なった者は、よみがえってさばきを受けるのです。』このキリストの御言葉が、我々が今見ている箇所と対応しているのは明らかである。キリストが『墓のなかにいる者』と言われたのは、我々が今見ている箇所で言われている『地のちりの中に眠っている者』のことである。
この時に復活した聖徒たちは『永遠のいのち』に入った。つまり、復活してから携挙され、キリストから幸いな言葉を受け、そうして天国へと引き上げられた。それ以降、彼らは永遠の至福を受け続けることになった。『もはや、死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。』(黙示録21章4節)と書かれている通りである。この時に復活した悪者どもは、聖徒たちとは反対に『そしりと永遠の忌み』に入った。つまり、復活して携挙され、大審判において恐るべき宣告を受け、そうして地獄へと投げ込まれた。これ以降、彼らは今に至るまで、―そして今後も永遠に―『そしりと永遠の忌み』を受け続けることになった。『それはすべての人に、忌みきらわれる。』(イザヤ66章24節)と書かれている通りである。
ここで言われている聖徒たちと悪人の復活は、まったく一緒の時に起こるというのではない。この箇所を読むと、両者が一挙に纏めて復活するかのように感じられる。だが実際、この2種類の復活には順番と区別とがある。これについては既に述べられた内容であるが、重要なので、再び述べることにしたい。まず再臨の起きた紀元68年6月9日には、聖徒たちだけが復活した。これは第一の復活である。この時には悪者は復活しなかった。何故なら、悪者は、聖徒たちが復活してから千年として象徴される短い期間が経った後に復活するからである。それは黙示録20:5の箇所で次のように言われている通りである。『そのほかの死者は、千年の終わるまでは、生き返らなかった。これが第一の復活である。』この『千年』である短い期間が終わると、初めて悪者が復活するようになる。これが第二の復活である。このように復活は2度あり、そこには順序と区別とが存在している。これは黙示録20章を読むならば疑うことが出来ない。だから、我々は復活を考える際、第一と第二の復活を、つまり聖徒と悪者の復活を、一緒に纏めて理解するなどということがあってはならない。
頑なで研究不足の千年王国論者たちは、このうち第一の復活のほうについては、既に実現されたと理解している。何故なら、パウロによるⅠテサロニケ4章の御言葉が、我々にそのように教えているからだ。この点について彼らの見解は間違っていない。だが彼らは研究があまりにも足りていないので、第二の復活のほうについては、まだ実現していないと見ている。それは、彼らが『千年』という期間に私的解釈を施しており、それを非常に長い期間―2千年以上の期間―として捉えているからである。黙示録20:5の箇所を見れば分かる通り、第二の復活は、この千年の期間が終わってから起こる。その時に初めて悪者が復活する。それゆえ、この千年王国論者たちは、千年がまだ終わっていないからというので、第二の復活も未だに起きていないと見ているのである。しかしながら既に説明済みのことだが、この『千年』とは、イザヤ書24:22によれば『何年か』であり、黙示録12:6および14によれば『1260日』(=42か月)『一時と二時と半時』である。つまり『千年』という言葉は単に期間内における質の完全性を示しているだけであり、実際にはごく短い期間なのである。よって、この短い期間が終わってから起こる第二の復活は、第一の復活が起きてから間もなく起きたと考えなければいけない。第二の復活は既に起きたのである。そもそも、ダニエル書12:2およびヨハネ5:28~29の中で言われている事柄を、一方は既に成就したとし、もう一方はまだ成就していないと考えること自体が間違っている。第一と第二の復活に時間差があるのは間違いない。しかし時間差といっても、たかだが42か月間である。このぐらいの差であれば、第一も第二もほとんど同時期に起こったと捉えることができる。だからこそ、ダニエル書12:2でもヨハネ5:28~29でも、2回の復活があたかも一挙に起こるかのように言われているのである。私がこのように言うと、彼らは「この2つの箇所では時間の詳細な順序が教示されているのではない。」などと言い、実は問題を回避しているに過ぎないのだが、巧みに対処できたかのように振る舞う。なるほど、確かにこの2つの箇所において時間に関する細かい教示がされていないことは私も認める。だが、この2つの箇所で時間の順序について教示がされていなかったとしても、復活の出来事そのものに時間の順序があることに変わりはない。彼らがこの2つの箇所では時間の順序が何ら語られていないと言っても、復活における時間の問題が解決されたことには全くならない。それゆえ、彼らが私にこのように対処したとしても、その対処は何ら意味を持たないことが分かる。詰まる所、彼らは『千年』に対する自分たちの好き勝手な解釈に固執するあまり(彼らのこの解釈には彼らも認める通り根拠聖句が何もない!)、キリストとダニエル書の御言葉に解釈上の不正を働いているのである。
【12:3】
『思慮深い人々は大空の輝きのように輝き、多くの者を義とした者は、世々限りなく、星のようになる。』
『思慮深い人々』とは、既に見たように信仰に留まり続ける聖徒たちのことである。彼らは霊的に思慮深いので、神に従い続けることを止めようとはしない。『多くの者を義とした者』とは、『思慮深い人々』のうち、他の聖徒たちをも敬虔に歩ませた人たちのことである。つまり彼らは敬虔の模範になった信仰者である。このような人たちは、マカベア書に書かれているエレアザルや7人の息子とその母が良い例である。彼らはその敬虔さによって、他の聖徒たちの手本となり、『多くの者を義とした』。この2種類のうち前者は『大空の輝きのように輝』くことになった。彼らは天国に行ってから、かなりの輝きを持つようになったのである。後者のほうは『世々限りなく、星のようにな』った。彼らは天国で、あまりにも素晴らしい輝きを持つことになったのである。こちらのほうが前者よりも大きな恵みを受けている。後者のほうが前者よりも幸いな歩みをしたのだから、天国での状態がより幸いになったのは理の当然である。というのも神はそれぞれに対して報いられる方だからである。天国の状態において聖徒たちに輝きの差があるというのは、Ⅰコリント15:40~41の箇所を見ても分かる。この時に復活した聖徒たちは、それぞれの歩みに応じて、それぞれに相応しい輝きを獲得するようになったのである。
この復活した聖徒たちの持つ輝きについてはキリストも次のように言われた。『そのとき、正しい者たちは、天の父の御国で太陽のように輝きます。』(マタイ13章43節)ここでキリストが言っておられるのは、『思慮深い人々』ではなく『多くの者を義とした者』のほうである。何故なら、ここでキリストは『星』すなわち太陽の輝きについて言っておられるのであって、『大空の輝き』については言及しておられないからである。
ここで言われているのは普遍的なことである。この箇所では、昔の聖徒たちに対してだけ言われているなどと考えないようにすべきである。いつの時代であれ、敬虔に歩んだ聖徒は大空の輝きを持つようになるし、他の聖徒たちをも敬虔にさせた聖徒は星の輝きを持つ。パウロのような聖徒は間違いなく星のように輝くようになる。あまり大きな働きをしていない普通の聖徒たちは、大空のような輝きを持つことになる。今の時代の聖徒たちは、どのように思うであろうか。やがて星のように輝きたいと思うであろうか。であれば『多くの者を義とした者』になれるようにするがよい。別に大空のように輝けるのであればそれで構わない、と思うであろうか。であれば『思慮深い人々』である今の状態から堕落しないように信仰に保たれ続けるがよい。
要するに、ここで言われているのは聖徒に対する励ましと薦めである。既に努力と忍耐のうちに歩んでいる聖徒にとって、この箇所は「励まし」となる。何故なら、彼らがこの箇所を読めば、自分の労苦が無駄にはならないことをよく理解するだろうからである。信仰が弱かったりスランプ状態に陥っている聖徒の場合、この箇所は「薦め」となる。何故なら、この箇所を読めば、よく歩むことにより、よい報いが与えられるようになることを知れるからである。それだから、この箇所を聖徒たちが心に深く留めるようにするのは非常に望ましい。私は断言するが、そうすれば益がもたらされないことは絶対にないであろう。
蛇どものカトリックの場合、この箇所を読んで行為義認の裏付けとするに違いない。次のように言って。「この箇所では思慮深くしたり多くの者を義としたならば輝けるようになると言われているから、人は自分の努力や功績によって永遠の救いに値する者となれるのだ!」と。私は言うが、このように考えるのは間違っている。何故なら、聖書は行為義認を明白に否定しているからである。パウロは救いは行ないによらない、と言っている。もし行ないによらなければ、それは恵みであるということになる。恵みでありながら行ないにもよる、というのは矛盾しており、有り得ないことである。よってカトリックの愚かな妄想は斥けられなければならない。ところで、最近のカトリックはややプロテスタントに妥協した姿勢を見せる時もあるが、この際、思い切って一挙にプロテスタントへと総改宗してしまえばよいのだ。そうすれば計り知れないほどの祝福がキリスト教界に注がれるはずである。こんなにもサタンが嫌がることはない、と私は思う。
【12:4】
『ダニエルよ。あなたは終わりの時まで、このことばを秘めておき、この書を封じておけ。』
ダニエルは『終わりの時まで』、11:2の箇所から書かれている預言の内容を全て隠しておかねばならなかった。ここで『終わりの時』と言われているのは、ダニエルの人生が終わりを迎える時である。ここではユダヤの終わりが言われているのではない。ダニエルがこの命令の通りにしたことは疑えない。何故なら、ダニエルは神を恐れる敬虔な聖徒だったからである。つまり彼は自分の死ぬ時まで、この預言を文書として書き記しはしたものの、その文書を誰かに見せたり、またその内容を口で伝えたりするようなことはしなかった。ここでは隠しておかねばならないことを、「秘めておけ」「封じておけ」と2回繰り返して命じている。これは絶対に隠しておかねばならないことを分からせようとして為されたユダヤ的な強調表現である。
この預言の内容を隠しておかねばならなかったのは何故なのか。それは既に述べた通り、その預言を周知させてもあまり意味がなく、かえって精神に良くない作用がもたらされるからであった。例えば、これから200年後に巨大隕石が地球のどこかに落ちてくるということを啓示により誰かが知ったとしたら、どうか。それは神の定めであり、どれだけ対処しても被害者数に変わりがない。この場合、今からこの出来事を周知させても、あまり意味がない。伝えないほうが、かえって人々の精神にとっては良い。伝えたとしても意味もなく怯えてしまうだけだからである。預言を隠すようにとダニエルに命じられたのも、これと同じことであった。つまり、神は聖徒たちの精神的な健康を思って、こう命じられたのだ。何となれば『神は愛』だからである。
この箇所は、黙示録22:10の箇所と、よく見比べるべきである。黙示録のほうでは啓示された預言が『封じてはいけない。』と命じられている。我々が今見ている箇所で言われているのとは全く逆である。黙示録における預言の場合、どうして封じてはならなかったかと言えば、それは『時が近づいているから』であった。ヨハネに示された預言は、もう30年もすれば実現されることになっていた。もしヨハネがダニエルのように預言を隠したとすれば、紀元1世紀の聖徒たちは突如として起こる悲惨な出来事に不意打ちを食らわされることになってしまうのだ。そのようなことにならないようにと、黙示録では秘匿することが禁止されたのである。一方、ダニエル書の預言はおよそ600年後に起こる出来事だったから、隠しておかねばならなかった。先にも述べた通り、それを先駆けて知ったとしても、メリットはほとんどないからである。実際、我々が既に見たように、ダニエルは遥か未来の出来事を先駆けて知らされたので、酷く怯え、混乱し、病気にさえなってしまった。だから、こういうことになる。もしヨハネに示された預言が遥か未来に起こる出来事だったとすれば、ヨハネにはダニエル書で言われているように『封じておけ。』と命じられていたであろう。また、もしダニエルに示された預言が数十年後に起こる出来事だったとすれば、ダニエルには黙示録で言われているように『封じてはいけない。』と命じられていたであろう。
『多くの者は知識を増そうと探り回ろう。」』
これは、こういうことである。もしここまでに告げられた預言が隠されるならば、多くの者たちは未来の知識を増し加えようとして躍起になるであろう。そして、探し出されるのであれば、この預言が探し出されることになるであろう。このような仕方でこの預言が公になればそれでよい。この預言は、現段階では積極的に周知されるべきものではない。何故なら、これは今から知ってもあまり良い作用をもたらさない内容なのだから、と。この部分は、内容的に短いので、何が言われているのか非常に理解しにくい。だがこの部分は私が今述べたように理解すべきであると私には思われる。
【12:5】
『私、ダニエルが見ていると、見よ、ふたりの人が立っていて、ひとりは川のこちら岸に、ほかのひとりは川の向こう岸にいた。』
この『川』とは、『ヒデケル』(10:4)すなわちティグリス川である。これは8:2の箇所で書かれている『ウライ川』のことではない。『ふたりの人』とは、恐らく御使いではないかと思われる。というのも、これは御使い以外には考えられないからである。
【12:6】
『それで私は、川の水の上にいる、あの亜麻布の衣を着た人に言った。「この不思議なことは、いつになって終わるのですか。」』
ここに出てくる亜麻布の衣を着た人はキリストである。何故なら、この人は10:16および12:8の箇所でダニエルから『わが主よ。』と呼ばれているからである。『主』とは誰か。イエス・キリストである。このキリストが『亜麻布の衣を着』ておられたのは、キリストが永遠の大祭司であられることを示している。旧約時代においてアロンに連なる祭司たちは亜麻布の衣を身に着けていたからである(出エジプト28章)。
ダニエルは、この預言された悲惨な出来事について更に知りたかったので、それがいつ終わるのかキリストに尋ねている。これはその出来事が『不思議なこと』だったからである。その不思議さが、もっとよく知りたいというダニエルの知的欲求を刺激したのである。また、ダニエルがこの出来事について尋ねたのは、それが非常に恐るべき内容を持っていたからでもある。つまりダニエルは、この出来事を更に知って正しい判断を持てるようにし、そのようにして自分の心に生じた動揺を少しでも落ち着かせようとしたのである。よく知れば、より理知的な判断が可能となり、前と比べて冷静な状態になれるようにもなるのだ。
【12:7】
『すると私は、川の水の上にいる、あの亜麻布の衣を着た人が語るのを聞いた。彼は、その右手と左手を天に向けて上げ、永遠に生きる方をさして誓って言った。「それは、ひと時とふた時と半時である。聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わったとき、これらすべてのことが成就する。」』
預言の中で示された悲惨な出来事が起こる期間は『ひと時とふた時と半時』であった。すなわち、これは1年と2年と半年(=3年6か月=42か月=1260日)である。この期間が、『聖なる民の勢力を打ち砕くこと』が行なわれる期間であった。『聖なる民』とはユダヤの共同体を指す。『打ち砕く』とは、神の懲らしめとして苦難が下される、という意味である。これは懲らしめとしての打ち砕きであるから、神の敵に対して与えられる刑罰としての打ち砕きとは、意味合いが全く異なる。この懲らしめの出来事が終わると、『これらすべてのことが成就する』ことになる。『これらすべてのこと』とは11:2の箇所から言われてきた諸々の預言を指す。それが終わるのは紀元前164年の12月であった。
既に第3部で触れておいたが、この箇所で言われている内容は、間違いなく黙示録10:5~7の箇所と対応している。この2つの箇所を見比べてみれば、それは明らかである。この2つの箇所における相違点は次の通り。①天に上げている手の本数の違い。黙示録のほうでは右手だけが上げられているが、ダニエル書では左手も上げられている。②手を上げている者の違い。黙示録のほうでは御使いが手を上げているが、ダニエル書のほうではキリストである。③神の言い表し方の違い。黙示録のほうでは神が永遠者および創造者として言い表されているが、ダニエル書のほうでは永遠者としてしか言い表されていない。④誓いの内容における違い。黙示録のほうでは第7のラッパに関する内容だが、ダニエル書のほうではユダヤにおける苦難の期間について言われている。黙示録が書かれた時には既にダニエル書が書かれており、ダニエル書が書かれた時にはまだ黙示録は書かれていなかった。それゆえ、黙示録における預言また記述が、ダニエル書をベースとしていることは疑う余地がない。つまり、こううことになる。神は前にダニエルに示されたのと類似した幻を、ヨハネにも示されたのである。だから、我々が今見比べた2つの箇所はよく似ている。この2つの箇所で誓われている事柄は、どちらもユダヤの終末に関する事柄であった。だから、この2つの箇所が内容的に類似しているのは理に適っている。我々はこのような類似を見て、この2つの箇所が、また聖書全体が、同じ一人の神によって書き記されたことを知るのである。
既に語られたことだが、ここではキリストが誓っておられるので、誓いは全て禁止されるべきだという考えは否定されねばならないことが分かる。何故なら、もし全ての誓いが禁止されるべきだとすれば、我々はこの箇所で誓っておられるキリストをも批判せねばならなくなるからである。我々は、ここでキリストがしておられるように、誓ってもよい。ただし、それは「神を指して」でなければならない。申命記6:13の箇所で『御名によって誓わなければならない。』と言われている通りである。キリストが誓いを禁止されたのは、あくまでもキリストの時代に蔓延っていた不敬虔な誓いに限られている。当時の人たちは、神でない存在を指して、しかも純粋さや慎重さをほとんど持たずに誓いをしていたが、キリストはそのような誓いを禁じられたのである。我々は、この点を再びよく弁えるべきであろう。
【12:8】
『私はこれを聞いたが、悟ることができなかった。そこで、私は尋ねた。「我が主よ。この終わりは、どうなるのでしょう。」』
ダニエルは、自分に与えられた回答を聞いても、何だかよく分からなかった。それは、ダニエルにとって時代が早過ぎたからである。例えば、ルネサンス期の人間に400年以上も経過してから登場する核兵器について知らせたとしたら、知解できるか。絶対にできない。何故なら、ルネサンスの時代では、まだデモクリトスやエピクロスの主張した原子論が夢想話として認識されていたからである。原子の存在を否定するのであれば、核爆発について理解することは非常に困難である。それと同じように、ダニエルに告げられた遥か未来に関する預言も、ダニエルが理解するのは非常に困難であった。ダニエルの時代には、まだアンティオコス4世の出るセレウコス朝シリアも、ネロの出る帝政期のローマも存在していなかったのだから。つまり、ダニエルが預言の内容を悟れなかったのは、時代の壁に阻まれたからであった。ダニエルの知性や知識量に問題があったので、『悟ることができなかった』というわけではない。となると、神はダニエルが悟り得ない事柄を、ダニエルに示されたということになる。それは一体どうしてなのか。それは、聖徒たちが聖書により信頼できるようになるためであった。もしダニエルの頃から遥か未来についての事柄が正確に預言されていたとすれば、それだけ聖徒たちが聖書に信頼するようになるのは間違いない。何故なら、そんなにも早くから、未来のことが告げられていたことを知れるからである。これが数年前や数十年前であれば、聖書の信頼性を高めることにはならなかった。何故なら、数年後や数十年後に起こる事柄であれば、それを正確に示す人が、世の中には少なからず見られるからである。だからこそ、神はダニエルが悟れないにもかかわらず、ダニエルに対して遥か未来についての預言を与えられたのである。
ダニエルは、語られた事柄をどうしても知りたかったので、更に尋ねることにした。といっても、この箇所における質問は12:6で為された質問とほとんど変わらず、内容的に雑然としている感は否めない。これはダニエルが自分に語られた事柄をよく理解できていなかったことを示す。我々も事柄を十分に理解していない時には、このような質問をしがちである。
【12:9】
『彼は言った。「ダニエルよ。行け。このことばは、終わりの時まで、秘められ、封じられているからだ。』
『行け。』とは「もうこれ以上に示されることはない。」ということである。つまり、これは話を終止させる言葉である。
では、どうしてもうこれ以上に何かが示されることがなかったのか。それは『このことばは、終わりの時まで、秘められ、封じられているから』である。つまり、もう十分なだけ示し終えられたので、後はユダヤの終わりが来る時まで隠し続けておかれなければならない、ということである。ここでは「もうこんなにも示されたのだから十分としなさい。」とでも言いたいかのようである。あらゆる事柄には「時」がある。ダニエルに示された啓示にも「それが終止される時」があったのである。
【12:10】
『多くの者は、身を清め、白くし、こうして練られる。悪者どもは悪を行ない、ひとりも悟る者がいない。しかし、思慮深い人々は悟る。』
多くの聖徒たちは、最終的に救われ、『身を清め、白くし、こうして練られる』ことになった。これは先にも述べた通り、復活の救いについて言われている。この箇所では『多くの』聖徒たちが救われると言われているが、これはその総数に着目した言い方であるという点に注意せなばならない。つまり、これは絶対的な観点から見た言い方である。比率的に言えば、救われる聖徒の数はごく少ない。それは世の中を見ても分かる。いつの時代であれ、真に救われているクリスチャンの数は多くない。我が日本でも、総人口1億2千万に対し、私の見るところによれば真に救われている聖徒の数は多く見積もって35万人ぐらいである。救いを人に与えるキリストご自身も、救われる者の数は、相対的にはあまりにも少ないと言っておられる。『狭い門からはいりなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そして、そこからはいって行く者が多いのです。いのちに至る門は小さく、その道は狭く、それを見いだす者はまれです。』(マタイ7章13~14節)我々としては、最終的に『身を清め、白くし、こうして練られる』ようにならねばいけない。何故なら、それこそ人間の人生において最も重要な事案だからである。
一方、悪者どもは『ひとりも悟る者がいな』かった。何故なら、彼らは『悪を行ない』続けるからである。救いとは、悪を打ち砕くことである。だから悪を行なう者は、救いのことについて悟ることが出来ない。救いに与かれば、悪が失われ、全てが光に照らされ、恥ずかしがり恐れるようになるのだ。それゆえ、彼らは自分の悪のゆえに救いをもたらす光のほうに決して行こうとはしない。それは彼らが既に裁きを受けているからである。ヨハネはこう言っている。『そのさばきというのは、こうである。光が世に来ているのに、人々は光よりもやみを愛した。その行ないが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行ないが明るみに出されることを恐れて、光のほうに来ない。』(ヨハネ3章19~20節)この箇所では、悪者どもの数については何も触れられていない。実際、悪者どもの数は多いのであろうか、それとも少ないのであろうか。この悪者どもは絶対的に言って非常に多い。それは世の中を見れば明らかであろう。また比率的に言っても非常に多い。先に挙げたキリストの御言葉の中では、救われる者に対して滅びに至る者が多いと言われていたからである。
霊的に『思慮深い人々』は、救いについて『悟る』ことができる。彼らは思慮深いので、救いをもたらす信仰に留まり続ける。というのも、彼らは、もし救いから脱落したら最終的にあまりにも悲惨な状態に至ってしまうということが、よく理解できるからである。このような霊的思慮深さは、恵みにより神の御霊が生じせてくださる。この思慮深さを、我々人間が自分自身の力や素質によって持つことは絶対にできない。何故なら、我々人間は、それ自身としては、つまり神の恵みが無い状態においては、まったく霊的に死んだ存在だからである。そのような霊的死人がみずから霊的な思慮深さを持つということは、死人が起き上がって理知的な振る舞いをするようなものである。
【12:11~12】
『常供のささげ物が取り除かれ、荒らす忌むべきものが据えられる時から1290日がある。幸いなことよ。忍んで待ち、1335日に達する者は。』
『常供のささげ物が取り除かれ、荒らす忌むべきものが据えられる』という出来事は、既に説明済みである。これはユダヤの神殿が汚されることであった。『1290日』とは、聖所が汚されてから、聖所を汚した張本人であるアンティオコス4世が死ぬ時までの期間である。それは前167年の夏から前164年の冬であった。『1335日』とは、聖所が汚されてから完全に回復されるまでの期間である。つまり、アンティオコス4世が死んでから45日が経過すると神殿が元通りとなる。12:11~12の箇所に見られる45日間の差には、このような意味があったのである。これは実際の歴史が示している通りである。調べれば分かるが、アンティオコス4世が死んでから少し経つと神殿も回復されることになった。この2つの期間を、今述べられたのと真逆に考えてはならない。すなわち、『1290日』を神殿の回復までの期間とし、『1335日』をアンティオコス4世の死として捉えるべきではない。何故なら、それは歴史とは異なっているからである。しかも、そのように考えるのは普通に考えてもおかしいと言わねばならない。この暴君が死んでから幾らか経ってから神殿が回復したとするほうが自然である。神殿が回復してからアンティオコス4世が死んだというのは、少し考えにくい。何故なら、この暴君が神殿回復の実現を許すことなど有り得ないからである。ところで、この45日という数字には何か象徴的な意味が隠されているのか。例えば、これは15+15+15で構成されており、三位一体の神が関わっていることを象徴しているのであろうか。この数字に象徴的な意味は何もない。これは、ただ単に実際の期間を表わしているに過ぎない。しかし、聖徒たちは、このような数字が聖書に出てきた際、そこに何かの意味が秘められていないかどうか注意深く考えてみるべきである。アウグスティヌスのように何かの数字が出てくれば即座に強引なこじつけをするのは行き過ぎであるが(※)、象徴性についてほとんど無頓着になっている現今の聖徒たちにとっては、少し神経質になるぐらいが調度よい。何かの数字が出てきたら「この数字は何だ。何かの意味があるのか。」などと思索してみるのである。この箇所の「45(日)」のように象徴的な意味がない数字も多いが、意味のある数字も多いのである。
(※)
例えば彼は「3」で構成されるものが出てくると、すぐに3つの位格に結びつける癖があった。「信仰、希望、愛」とあれば、御父は愛に、御子は希望に、御霊は信仰に対応している、などと。
[本文に戻る]
ここで言われているように、神殿が汚されてから1335日の間、耐え忍ぶ者は『幸い』であった。何故なら、その時になると神殿が回復されるのだから。それ以降はもう神殿でいつものように神聖な儀式を執り行なうことが出来るのだ。しかし、この期間の間、耐え忍ばなかった者は災いであった。何故なら、1335日間忍耐しなかったということは、つまり背教してしまったということを意味するからである。背教して神の国から落ちるということ以上に酷い災いは有り得ないのである。
この「45日」について考慮すべきなのは、アンティオコス4世においてだけである。これをアンティオコス4世をその影とするネロにおいて考える必要はない。何故なら、この期間は、アンティオコス4世の時代にだけ関わっているからだ。試しにネロの死における前後45日間のことを考えてみられたい。そうすれば、この期間がネロの時代においては考慮されるべきでないことがよく分かるであろう。アンティオコス4世の事柄を、何でもそのままネロの場合に移植して当てはめればよいというわけではないのである。
【12:13】
『あなたは終わりまで歩み、休みに入れ。あなたは時の終わりに、あなたの割り当ての地に立つ。」』
『あなたは終わりまで歩み、休みに入れ。』とは何か。これは、ダニエルが人生の終わりまで歩んだら死んで永遠の安息に入る、という意味である。『終わり』とはダニエルの死のこと、『歩み』とはダニエルが自分に定められた人生のコースを歩むこと、『休み』とは死後の安息のことである。この部分における『終わり』をユダヤの終わりだと解するべきではない。そのように解すると、意味が分からなくなってしまう。何故ならダニエルが歩むべきなのは、ユダヤの終わりまでではなく、自分が死ぬ時までだからである。
『あなたは時の終わりに、あなたの割り当ての地に立つ。』とは何か。これは、ダニエルはユダヤの終わりが来ると復活して天国に入れられる、という意味である。『時の終わり』とは神の国を持つ存在としてのユダヤ民族が終焉を迎える時のことである。それは紀元70年9月であった。この部分における終わりを、ダニエルの人生における終わりだと解してはならない。そのように解すると、この部分がよく分からなくなってしまう。『割り当ての地』とは天国である。何故なら、聖徒たちには神と神の統治される天国が割り当てられているのだから。悪者たちに、このような割り当てはない。彼らに割り当てられているのは地獄だからである。実際、ダニエルはユダヤの終わりになると復活した。そしてキリストと共に座に着いて幾らかの間裁きの業を遂行した。そうしてからキリストと共に天国という『割り当ての地に立つ』ことになった。このユダヤの終わりにおける一連の流れは既に十分なだけ説明されているので、再び説明する必要はないであろう。
さて、アンティオコス4世の話が始まってからこの箇所に至るまで『終わり』という言葉が多く使われていたのを、我々は見た。この言葉はどれも一様の意味を持っているのではなく、4通りの意味を持っている。この言葉の意味における複数性について説明することで、11:2の箇所から続いてきたダニエル書の註解を終わることとしたい。まず一つ目は、アンティオコス4世の『終わり』である。これは、この暴君が前164年に死ぬことである。11:45がそうである。二つ目はダニエルの『終わり』である。これはダニエルの死を意味している。12:13がそうである。三つ目は神殿に関する『終わり』である。つまり、神殿の汚染が遂に終わることである(前164年)。これは11:36や12:6がそうである。4つ目はユダヤの『終わり』である。これは紀元70年9月にユダヤが終わりを迎えることである。12:9や12:13がこれに該当する。
第30章 28:ホセア書
ホセア書は、無視されるべきではない。ホセアは、前720年に起こるイスラエル陥落について色々と預言をしている。しかし、ホセアはイザヤと同じように、遥か未来の出来事についても預言をしている。その預言を以下で見ていくことにする。というのも、それは本作品にとって重要なことを言った預言だからである。
第31章 29:ヨエル書
ヨエル書は絶対に無視されてはならない。この文書には、紀元1世紀に起こる出来事が多く預言されているからだ。以下で見るべき箇所を見ておくことにしたい。★は10である。
第32章 30:アモス書
アモス書には心を傾けなかったとしても問題ない。何故なら、この文書はイスラエル王国の終焉について預言した文書だからである。『わたしの民イスラエルに、終わりが来た。』(8章2節)と預言されている通りである。歴史が示すように、イスラエル王国は紀元前720年に滅ぼされ、アッシリアに捕囚された。一方、我々が本書の中で取り扱っている事柄は紀元1世紀のことである。それだからアモス書は考究しなくても構わない。
第33章 31:オバデヤ書
オバデヤ書では、紀元前585年に起きたエルサレム陥落を平然と傍観していたエドム人たちが、再びエルサレム陥落が紀元70年に起こる時が来ると、神の怒りの裁きにより罰せられる、ということが言われている。エサウの子孫であるエドム人たちは、ヤコブの子らであるイスラエル人たちが苦しんだ時、本当に無関心で傍観的であった。自分の兄弟が苦しんでいるのに憐みの心を持とうとしないのは酷いことである。だから、神もそのようなエドムに報いられたのである。このオバデヤ書では、紀元70年におけるユダヤの破滅について述べている。それゆえ、この文書は絶対に考究されなければならない。★は10である。
第34章 32:ヨナ書
ヨナ書は、特に見るべき箇所がないと思われる。
しかしながら、このヨナ書からは、次のことを言っておかねばならない。すなわち、もしユダヤがニネベのように心を変えて悔い改めていたとすれば、決してあのような裁きを受けることはなったであろう、と。何故なら、『主のあわれみは尽きない』(哀歌3章22節)からだ。神は、もしユダヤが悔い改めていたとすれば、ユダヤに下そうと思っておられた破滅の裁きを思い直しておられた。それはニネベが悔い改めたので、破滅の裁きを免れることが出来たのと同じである。神は、悪者どもが破滅することは望まず、むしろ悔い改めて生きるようになるのを望んでおられる(エゼキエル18:23)。しかし、ユダヤは最後の最後まで、まったく心を引き裂こうとはしなかった。だからこそ、ユダヤは、紀元70年にあのような大破滅を受けることになったわけである。神は、悔い改めようとしない心の頑なな者たちにまで憐れみを注がれる御方ではないのである。そういった者たちは、怒りの対象となるので、憐れみが注がれることなく滅ぼされるに至る。
第35章 33:ミカ書
ミカ書は難しい。というのも、そこに書かれている預言がバビロン捕囚の時の悲惨を言っているのか、ユダヤ戦争の時の悲惨を言っているのか、見分けにくいからである。この文書には、ざっと読んだだけでは何が言われているのか分からない部分が非常に多い。それゆえ、慎重で緻密な思索が求められている。とはいっても、黙示録に比べれば、そこまで難しいとは思えない。以下で、この文書から註解するべき箇所をいくつか註解していきたいと思う。
第36章 34:ナホム書
ナホム書は特に考慮しなくてもよい。何故なら、これは『ニネベに対する宣告』(1章1節)が記された預言書だからである。この文書は再臨やユダヤの崩壊について書き記されたものではない。
第37章 35:ハバクク書
ハバクク書は、別に考究しなかったとしても問題ない。ハバククは、自分を苦しめるユダ王国とそこにいる人々が、やがて神からの裁きを受けることになるであろう、と預言している。この預言は、紀元前585年に実現された。暴虐を行なっていたユダの人々は、その報いとして、自分たちも暴虐を受けて悲惨にさせられた。我々が本書で取り扱っているユダヤの悲惨は、紀元前585年の悲惨ではなく、紀元1世紀の悲惨である。だから、この預言書は心に傾けなかったとしても別に構わない。
第38章 36:ゼパニヤ書
ゼパニヤ書は無視されるべきではない。ゼパニヤは、もう間もなく訪れるバビロン捕囚の際のユダヤ滅亡について預言しているのだが、その中では紀元1世紀に起こる福音の世界的な普及と天国の到来についても預言されている。バビロン捕囚の際のユダヤ滅亡はさておき、紀元1世紀における福音の伝播および天国のことについては見ておかねばならない。以下で、この2つの事柄について言われている箇所を見ていく。
【1:2~3】
『わたしは必ず地の面から、すべてのものを取り除く。―主の御告げ。―わたしは人と獣を取り除き、空の鳥と海の鳥を取り除く。わたしは、悪者どもをつまずかせ、人を地の面から断ち滅ぼす。―主の御告げ。―』
これから見ていく箇所は、キリストの再臨と関係がない。何故なら、そこでは紀元前6世紀にユダ王国が滅ぼされることについて預言されているからだ。だが、この箇所からは、聖書について重要な理解を得られる。その理解を持てば、再臨を研究するために大いに益となる。それどころか、再臨以外のことで聖書を研究する時にも益が生じる。それだから、再臨には関係がない箇所でありながら、この箇所を第4部の中で取り上げることにした。
この箇所では、『地の面』から『すべてのもの』が『断ち滅ぼ(される)』と書かれているから、地球全土にいるあらゆる生物が死滅させられると言われているかのように感じられる。字義通りに捉えるならば、確かにこの箇所では地球全世界に起こる究極的な破滅が示されていると解されねばならないであろう。私はそのことを認める。
だが、続く箇所を見るならば、ここで地から全ての生物が滅ぼされると言われている内容の詳細が明瞭となる。その続く箇所を順々に見て行きたい。
【1:4】
『わたしの手を、ユダの上に、エルサレムのすべての住民の上に伸ばす。』
先の箇所で全ての生物が地から断ち滅ぼされると言われていたのは、実はユダヤのことだったと明らかにされている。つまり、神は確かに『すべて』と言われたが、それはユダヤにおける『すべて』であった。1:2~3の箇所だけを見れば、世界全土の破滅として捉えるしかなかったかもしれない。だが、そのように解するのは愚かであることが分かる。個々の聖句にだけ着目して文脈は考慮しないという傾向が、今も昔も教会には往々にして見られる。だが、それでは駄目である。文脈を弁えたうえで個々の聖句を解読する、という作業が重要なのだ。
ここで神の御手が伸ばされると言われているのは、裁きが下されるという意味である。これは我々が裁きを与えようとして誰かに自分の手を伸ばす時のことを考えれば、分かりやすくなる。実際、ユダヤはネブカデレザルを通して神の裁きを受けた。紀元前585年、ネブカデレザル率いるバビロン軍が、ユダ王国を破壊して滅茶滅茶な状態とした。この破壊は実に痛ましかった。当時の王であったゼデキヤも捕獲されて両眼を抉り取られてしまった(Ⅱ列王記25:6~7)。
聖書で『すべて』などと書かれていながら、実は限定された『すべて』という意味である場合、『すべて』と書かれたすぐ後に説明を加えているのが常である。例えば、我々が今見ているゼパニヤ書がそうである。ここでは地から全ての生物が取り除かれると言われた直後に、それはユダ王国における話だということが明らかにされている。イザヤ66:16~17の箇所もそうである。そこでは、主が全ての者を殺して裁くと言われた直後に、その裁かれる者とは神の家に住まう偽善者どもにおける全てであると示されている。マタイ25:32~33の箇所もそうである。そこでは『すべての国々の民』が御前に集められると言った直後に、それは教会の『羊と山羊』における全ての者たちであると言われている。このように誤解を防ぐためにすぐさま『すべて』という言葉の範囲が限定されているのは、神の配慮である。これは覚えておいて損にはならないこと、いやむしろ覚えておくべきことである。もし聖書に『すべて』などといった言葉が書かれていたら、その言葉の前後の部分を調べてみよ。そうすれば、その『すべて』の範囲を規定している部分があるかもしれない。もしそのような部分があれば、その『すべて』という言葉は字義通りの意味において理解されるべきではない。
『わたしはこの場所から、バアルの残りの者と、偶像に仕える祭司たちの名とを、その祭司たちとともに断ち滅ぼす。』
この時のユダヤにはバアル崇拝が見られた。エリヤの時でさえ、既にユダヤには『450人のバアルの預言者』(Ⅰ列王記18章19節)がいた。預言者でさえこれだけいたとすれば、一般人のバアル崇拝者はどれだけいたであろうか。これはイスラエル王国についての話だからゼパニヤ書で言われているユダ王国の場合にもそのまま当てはめることは出来ないが、ユダ王国にも相当多くのバアル崇拝者がいたのは間違いない。バアル崇拝をしていたこのユダヤ人たちは、ユダの国において滅ぼされてしまった。これは文字通りに理解してよい。それは歴史が示していることだからである。
バアル崇拝に歩んでいたユダがあのように滅ぼされたのは、その偶像崇拝の罪が原因であった。これは誠に大きな罪である。だから、彼らが滅ぼされたのは当然であった。夫が妻の不倫現場に遭遇したとしたら、その夫は猥らな振る舞いをしている不貞な妻をどうするであろうか。怒りに燃えて不倫相手と共に殺してしまったとしても何も不思議ではない。実際、今までに不倫をした配偶者が殺された出来事は少なくない。神という夫も妻であるユダの不貞に対して、そのような罰を下されたのである。もっとも、神の場合は、妻の不貞が続いていても長らく忍耐し続けておられたのではあるが。
それだから、神がユダを滅ぼされたからと言って、神を残虐だなどと非難してはならない。ユダは自分の罪の実を刈り取ったに過ぎない。神も、正義の審判者としての役割を果たされたに過ぎない。例えば、大量殺人犯が死刑にされたからといって、その死刑を執行した人が残酷だなどと非難する人がいるであろうか。また、重犯罪人に死刑の宣告を下した裁判官が非道だなどと非難する人がいるであろうか。死刑廃止論者でなければ、誰も非難はしないのではないか。神もそれと同じである。神は、ただ裁判官また死刑執行人として霊的な重犯罪者であったユダを罰されたに過ぎないのだから。
【1:5~6】
『また、屋上で天の万象を拝む者ども、また主に誓いを立てて礼拝しながら、ミルコムに誓いを立てる者ども、また、主に従うことをやめ、主を尋ね求めず、主を求めない者どもを断ち滅ぼす。』
この箇所では、当時のユダの住民がどのようであったか分かる。ここでは3種類の人たちが示されている。まず、当時のユダ王国には、『屋上で天の万象を拝む者ども』がいた。『屋上』とは偶像礼拝をする場所、『天の万象』とは太陽や月といった諸々の天体である。律法では明らかに天体崇拝が禁じられている(申命記4:19)。それにもかかわらず、当時のユダには天体を崇拝する輩がいたのだ。また当時のユダには『主に誓いを立てて礼拝しながら、ミルコムに誓いを立てる者ども』もいた。これは夫に愛と服従を誓っておきながら、別の男にも同じことを誓う女と一緒である。律法は、御民がただ神において誓いを立てるようにと命じている。それなのに当時のユダにはミルコムなどという人が勝手に作り出した偽りの神々に誓いを立てる愚か者がいた。更に当時のユダには『主に従うことをやめ、主を尋ね求めず、主を求めない者ども』もいた。神の民が神に仕えることを拒んでいたとは何という不敬虔であろうか。律法では、御民が神に熱烈に奉仕するようにと命じられている。それなのに当時のユダには神を無視した輩がいたのである。これら3種類のユダヤ人たちがユダにどれぐらいいたのかは不明である。しかし、当時のユダは滅ぼされるまでに堕落していたのだから、このような輩がかなり沢山いただろうことは間違いない。
なお、これまで見てきたゼパニヤ書の箇所では、ユダ王国における全てが滅ぼされると言われていたが、これは字義通りに捉えるべきではない。すなわち、本当にユダ王国の住民が絶滅させられるという意味に捉えるべきではない。何故なら、ネブカデレザルによりユダが滅ぼされた時、少数ではあるが生き残った者たちがいたからである。ダニエルやエゼキエルがそのよい例である。もしこれが字義通りの意味であったとすれば、紀元前585年においてユダ王国にいたユダヤ人は一人も残らず消え失せていたはずである。だが、ここではそのような意味で「全ての者が滅ぼされる。」と言われているのではない。そのようになるのは神の御心ではなかった。何故ならば、キリストがユダヤ人の中から現われると神はお定めになっておられたからである。もしこの時にユダヤ人が絶滅してしまったとすれば、キリストがユダヤ人として生誕されることもなくなる。そうなれば我々人間の救いも実現されなくなっていた。それゆえ、我々は神がユダの住民を完全には死滅させられなかったことについて感謝すべきである。
我々は、ここで言われているユダヤ人のようにならないよう注意すべきであろう。何故なら、聖徒たちとは聖徒として相応しく歩むべきだからである。パウロが次のように命じた通りである。『召されたあなたがたは、その召しにふさわしく歩みなさい。』(エペソ4章1節)もし我々がこの時のユダヤ人のように酷い堕落に陥ってしまえば、悲惨になるのは避けられない。神が、我々の堕落に対して怒られ、裁きまたは懲らしめをお与えになるだろうからである。
第39章 37:ハガイ書
ハガイ書は、研究しなかったとしても問題は起こらないであろう。この文書は、神殿が廃墟となっている時代に再び神殿を建設し始めることについて記録された文書だからである。この神殿はいわゆる第二神殿のことであり、紀元前520年に建設が完了された。ただ、この文書にはユダの総督ゼルバベルの復活について預言された部分があるので、そこは見ておかねばならない。というのも、復活とは本書における主要概念の一つであって、再臨の出来事とは切っても切り離せない事象だからである。
【2:6】
『まことに、万軍の主はこう仰せられる。しばらくして、もう一度、わたしは天と地と、海と陸とを揺り動かす。』
『しばらくして』という言葉は、文字通りに捉えてよい。すなわち、これは「もう間もなくしたら」という意味である。数百年・数千年といった長い時間ではない。
この箇所では、神が全世界に働きかけるので、もう間もなく大きく素晴らしい出来事が実現される、と言われている。その出来事は2:7~9の箇所で言われている。『もう一度』と言われているのは、シナイ山に神が降りて来られた時の大激動に続く第二の大激動がこれから起こるからである。
ヘブル書12章では、この箇所の預言が引用されている。ヘブル書のほうでは、再臨の際の大激動を示すために、このハガイ書の預言が示されている。だが、そのハガイ書の預言そのものは、直接的には紀元前6世紀の神殿に起こることについて言われている。つまり、ハガイ書の預言は昔の神殿について言われた言葉ではあるが、それは再臨の時にも当てはめることが出来た、ということである。このような預言の引用例は聖書に他にも見られる。例えばマタイ24:15の箇所がそうである。そこでキリストは、間もなくダニエル書に書かれている『荒らす憎むべき者』であるネロが現われるであろう、と預言された。だが実際、その『荒らす憎むべき者』は直接的に言えばネロではなくアンティオコス4世を指していた。つまり、キリストは本来的にはアンティオコス4世を示す言葉を、ネロに転用させてお語りになったわけである。これは別に間違ったことではなかった。何故なら、ネロとは本当にアンティオコス4世でもあるかのような酷い暴君だったのだから。
【2:7】
『わたしは、すべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、わたしはこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。』
神が『すべての国々を揺り動かす』ので、すなわち多くの国々に働きかけるので、これから建設される神殿には多くの財物が運ばれて神殿が輝かんばかりとなる、とこの箇所では預言されている。ユダヤの神殿は、非常に有名であり、誰もが注目するような建物であった。それだから王たちでさえも献納物を持って神殿に足を運んだほどである。これは、この神殿にとっては当然であった。何故なら、それは「神の神殿」だったのだから。神がそこに住んでおられたのだ。であれば、王たちでさえもそこに引き付けられることになったのは、自然であったと言えるのである。なお、この箇所では『すべての国々』と書かれているが、これは文字通りに捉えるべきではない。これは「周囲にある諸々の国」という意味であって、ラフに捉えてよい言葉である。何故なら、この当時において、日本やアメリカ大陸にある国までもがユダヤの神殿まで宝物を携えてきたのではないということは明らかだからである。これを文字通りに捉えねばならないとすれば、紀元前6世紀の日本やアメリカ大陸の国までもが、ユダヤの国に使者を遣わすか支配者が自ら赴いたということになってしまうであろう。これは例えるならば、我々が「ビートルズであれば誰だって知っている。」と言うようなものである。この言葉はラフに捉えれば確かにその通りだが、厳密に文字通りに捉えるならば、世の中にはビートルズを知らない人たちだっているのだから、正しくないことになるのだ。
それでは実際にはどうなったか。神殿が再建されてから、そこには『すべての国々の宝物がもたらされ』たのか。これは実際その通りになった。それは歴史が示している通りである。
【2:8】
『銀はわたしのもの。金もわたしのもの。―万軍の主の御告げ。―』
ここでは神の主権と所有権が宣言されている。ここでは次のように言われているかのようである。「ユダヤ人よ。今は神殿が悲惨な状態になっているが、これから銀や金といった宝物が再び神殿にもたらさることなど有りえない、などと考えているのか。世界中にある全ての銀や金は神である私の所有物である。それだから、銀や金がどこの国にあっても、私の主権によりそれらを再び神殿にもたらされるようにする。自分の所有物を自分の好きなように動かしてはならない法があるであろうか。あなたがた人間も自分の持っている所有物を望みの場所に自由自在に移動させているではないか。であれば、尚のこと、神である私は諸国にある銀や金を神殿に移させることができる。」
【2:9】
『この宮のこれから後の栄光は、先のものよりもまさろう。万軍の主は仰せられる。』
これから建てられようとしていた第二神殿は、その栄光においてソロモンの建てた第一神殿よりも優っていた。これは実際の歴史を見れば分かる。ヘロデが神殿を更に立派にしてからは、ますますその素晴らしさが増された。ヘロデは金で外壁を覆いたかったのだが、ラビたちがそのままのほうがよいからと言って、ヘロデの思惑を阻止させた。もしヘロデの願い通りに金が外壁に満ちていたとすれば、神殿は銀河団のように輝いていたに違いない。
『わたしはまた、この所に平和を与える。―万軍の主の御告げ。―」』
第二神殿には平和があるであろうと神は約束された。アンティオコス4世による蹂躙やポンペイウスの占領、またカリグラによるゼウス像の設置など、平穏とは言えない時期もあったが、その全体においては平和がそこにあったと言える。もちろん、神殿に平和があるというのは、紀元60年代までの話である。紀元60年代になるとローマ軍が神殿を包囲し、間もなく神殿は壊滅させられることになったからである。神はこのように平和を神殿に約束されることで、当時のユダヤ人に喜びと希望と平安をお与えになった。それは彼らが気落ちしないためであった。愛なる神は、このようにして聖徒たちに取り図って下さったのである。
【2:21~22】
『わたしは天と地とを揺り動かし、もろもろの王国の王座をくつがえし、異邦の民の王国の力を滅ぼし、戦車と、それに乗る者をくつがえす。馬と騎兵は彼ら仲間同士の剣によって倒れる。』
先に見た箇所では、紀元前6世紀に再建された第二神殿の幸いについて言われていた。すなわち、それは紀元1世紀に起こる再臨の出来事についてではなかった。今見ている箇所でも、先に見た箇所と同様、天地が揺り動かされると言われている。だが、今見ている箇所で言われているのは、紀元1世紀に起こる再臨に関することである。この箇所は前とは違って、神殿にもたらされる物質的な祝福のことが述べられているのではない。我々は、この2つの箇所における違いをよく弁えるべきである。
この箇所では、全部で5つの事柄が預言されている。その一つ一つを見ていかねばならない。『わたしは天と地とを揺り動かし』。これはキリストが再臨された際、天地に大きな激動が起こることを言っている。すなわち、地には大きな地震が起きて聖徒たちの携挙が起こり、天では戦いが起こってサタンとその勢力がそこから追放された(黙示録12章)。この2つの出来事については、既に説明済みである。『もろもろの王国の王座をくつがえし』。これは、王の王であられるイエス・キリストが再臨されるならば、ただの王に過ぎない王たちは取るに足りない存在と見なされる、という意味である。何故なら、キリストは本質的な意味において王であられるが、この地上の王たちはキリストから権威を与えられ王にされたに過ぎないからである。『異邦の民の王国の力を滅ぼし』。これはキリストが再臨されたならば、諸国の持つ力はその御前において無に等しく見なされる、という意味である。『戦車と、それに乗る者をくつがえす』。この戦車とはローマ軍を指す。キリストが紀元68年に再臨された際、エルサレムにいたローマ軍は上空に来られたキリストを見たはずだが、それにもかかわらず、ローマ軍はまったくどうすることもできなかった、とこの部分では教えられている。何故なら、既にイザヤ書29章で見たように、その時のローマ軍たちにとって上空に現れたキリストの軍勢は幻想だと感じられたのだから。『馬と騎兵は彼ら仲間同士の剣によって倒れる』。これはユダヤ戦争の間に起きたローマの内乱である。キリストが紀元68年に再臨されると、間もなくローマには仲間争いが生じた。それは誠に凄まじい流血沙汰であり、この戦いによってローマは疲弊しきってしまった。すなわち、まずガルバ軍とオト軍が仲間打ちをし、その戦いに勝ったオト軍がウッティリウス軍と仲間打ちをし、その戦いに勝ったウッティリウス軍がウェスパシアヌス軍と仲間打ちをし、最後にはウェスパシアヌス軍が勝利したのである。これは古代ローマの歴史を学んだ者であればよく知っているはずである。確かに聖書は、キリストが再臨されると軍隊が同士討ちをすると預言しているが、それは紀元60年代後半に起きたローマの内乱のことだったのである。このハガイ書2:22の他にもエゼキエル書38:21の箇所で、そのことが預言されている。
【2:23】
『その日、―万軍の主の御告げ。―』
『その日』とは、復活が起こる日、すなわち紀元68年6月9日である。これは、多くの日々や、ある一定の時期を指しているのではない。少なくとも、この箇所ではそうである。何故なら、復活の起こる日は明確に決まっているからだ。だが、だからといって、他の箇所で『その日』と言われていた場合、我々が今見ている箇所のように、必ずしもその全てがある特定の1日を指しているということにはならない。
『シェアルティエルの子、わたしのしもべゼルバベルよ、わたしはあなたを選び取る。―主の御告げ。―わたしはあなたを印形のようにする。わたしがあなたを選んだからだ。―万軍の主の御告げ。―」』
ここで言われているのは、そう難しいことではない。この箇所では、再臨の起こる日にゼルバベルが選ばれた者として復活し、『印形のように』神と一緒に歩むようになる、と預言されている。『印形』を考えてみよ。それは指輪や器と正に一体化している。復活する者も、神の聖なる印形となるのである。実際にゼルバベルは紀元68年に復活し、それ以降、印形でもあるかのように神と共に歩み続けることになった。これについては黙示録21:3の箇所でも、『神ご自身が彼らとともにおられて』と言われている。
ゼルバベルをはじめとした聖徒たちが復活する理由は、神がその者たちを選ばれたからである。ただそれだけである。神が、永遠の昔から、ある者たちをキリストにおいて復活するようにと選ばれた。だからこそゼルバベルのような聖徒たちは、キリストにあって復活することになる。これ以外の理由は存在していない。だから神は、このように言っておられる。『わたしは自分のあわれむ者をあわれみ、自分のいつくしむ者をいつくしむ。』(ローマ9:15)それでは選ばれていない者は、どうなるのか。その者たちは、復活はするが、滅びの身体においてであって、永遠に裁きを受け続けることになる。どうして神は彼らにそうされるのであろうか。それは彼らが滅びるようにと選ばれていたからである。我々人間は、自分にとって不快な汚いゴミは容赦なくゴミ箱に捨てるであろう。いったい、どこの誰が汚らわしいゴミを大切に保っておくのか!狂気に陥っている人や障害者でもなければ誰もいない。神も、そのように御自身にとって汚らわしい滅びの子らを、容赦なく地獄という焼却場に送って廃棄されるのである。
第40章 38:ゼカリヤ書
ゼカリヤ書は絶対に考究されなければならない。何故なら、この文書からは、再臨に関することが豊かに学べるからである。この文書を考究しなければ、再臨について十全な理解を持つことは難しい。また、黙示録も理解できなくなる。何故なら、黙示録には、このゼカリヤ書と対応している箇所が多くあるからである。ゼカリヤ書を十全に理解してこそ、黙示録も十全に理解できるようになるのだ。なお、ゼカリヤの預言は、問題なく紀元70年頃の出来事と結びつけて考えることが出来る。何故なら、ゼカリヤという預言者は前520~440年頃に活動したのであって、完全にバビロン捕囚の後の人だったからである。これはイザヤやエゼキエルとは違う点である。イザヤやエゼキエルの場合、彼らを通して語られた預言を例外なく紀元70年頃の出来事と結びつけることは出来ない。何故なら、イザヤは完全にバビロン捕囚の前に生きた預言者であり、エゼキエルはバビロン捕囚の前と最中と後に生きた預言者だったからである。彼らの場合は、エルサレムの破滅について預言していても、それがバビロン捕囚の時に起きた破滅だったのか、それとも紀元70年頃のユダヤ戦争の時に起きた破滅だったのか、見極める必要がある。すなわち彼らの場合、その預言がバビロン捕囚の時の破滅を言っている場合もあれば、ユダヤ戦争の時の破滅を言っている場合もあるのである。ゼカリヤの預言において、このように見極める必要はない。
なお、このゼカリヤという預言者の活動期間は前520~440年頃であって、彼はハガイ、マラキまたエズラとネヘミヤの同時代人である。このゼカリヤは旧約時代における最後から2番目の預言者であった。彼はバビロン捕囚の時にはまだこの世に生まれていない。
強調して言いたいが、このゼカリヤ書は、再臨の理解にとって本当に重要な文書である。それゆえ、再臨の探究者たちは、この文書を何度も読むようにするのが望ましい。1回か2回か3回か4回ぐらい読んだだけで理解の深みに達することが出来るなどと思うな。聖書の真理は万物の支配者である神の大いなる真理であるが、その真理を理解しようとする我々人間は矮小でつまらない惨めな存在だからである。
【1:7】
『ダリヨスの第二年のシェバテの月である第11の月の24日に、イドの子ベレクヤの子、預言者ゼカリヤに、次のような主のことばがあった。』
これから見ていく預言が与えられたのは、『ダリヨスの第二年』すなわち紀元前520年である。ダリヨスの治世は紀元前522~486年だったからである。この箇所は、月日の違いを除けば、1:1の箇所と言われていることが同一である。これから見ていく箇所は非常に霊的であって、是非とも心に留められるのが望ましい。
これから見るゼカリヤ1章は、黙示録の理解向上のために是非とも学んでおかねばならない。特に、黙示録6章の箇所のために学ぶ必要がある。何故なら、このゼカリヤ1章では、黙示録6章に出てくるのと同一の馬たちが出てくるからである。再臨を考究する者にとって、再臨を取り扱っている黙示録に出てくるのと同一の馬が出てくるこのゼカリヤ1章は、絶対に弁えておかねばならない。もしそうしないのであれば、怠慢の誹りを覚悟せねばならないであろう。真理を考究することに怠惰であっても責められずに済むと思っているのか。キリストは、真理に関して鈍かったり愚かだったりする者たちを容赦なく叱責されたではないか。であれば、再臨の考究者たちがこの箇所を把握しようとしなかった場合、多かれ少なかれ非難されねばならないのは確かである。
【1:8】
『夜、私が見ると、なんと、ひとりの人が赤い馬に乗っていた。その人は谷底にあるミルトスの木の間に立っていた。彼のうしろに、赤や、栗毛や、白い馬がいた。』
馬に乗っている『ひとりの人』とは、御使いである。それは後に続く箇所を見れば分かる。
この御使いが『赤い馬に乗っていた』のは何故なのか。赤い馬は、黙示録6:3~4の箇所を見ても分かる通り、「争い」を表す。つまり、赤い馬に乗っていたこの御使いは、争いをもたらすための使者である。
この御使いの後ろには3種類の馬がいた。『赤』い馬は、今述べたように「争い」を示す。これは、まだこの時には争いが投じられていないことを意味している。何故なら、この赤い馬は後ろに控えていたからである。『栗毛』の馬は、ゼカリヤ6:3の箇所では『まだら毛の強い馬』と言われており、黙示録6章では第4の馬である『青ざめた馬』(6:7~8)と対応している。この馬は黙示録によれば「死」をもたらす使者である。つまり、ここでは、まだ死の破滅がもたらされていないことを意味している。何故なら、この栗毛の馬は後ろに控えていたからである。『白い馬』は、黙示録6:1~2の箇所から分かる通り、再臨のキリストが乗られる馬である。これは、まだ再臨が起きていないことを示している。何故なら、この白い馬は後ろに控えていたからである。
この御使いが『谷底』にいたのは、そこがエルサレムであったことを示している。エルサレムとは山々に囲まれた谷の場所だったから。彼が『ミルトスの木の間に立っていた』のは、エルサレムに神の恵みがあったことを意味している。イザヤ41:19、55:13を見ても分かるが、ミルトスの木は恵みの象徴である。神の恵みがそこにあるから、ミルトスの木が生えるわけである。呪われていたら、そこは荒地の場所であったことであろう。
【1:9~10】
『私が、「主よ。これらは何ですか。」と尋ねると、私と話していた御使いが、「これらが何か、あなたに示そう。」と私に言った。ミルトスの木の間に立っていた人が答えて言った。「これらは、地を行き巡るために主が遣わされたものだ。」』
ゼカリヤは神とその真理を愛していたので、これらの馬が何を意味しているのか知ろうとして尋ねた。すると、御使いはゼカリヤに答えてくれた。
御使いによれば、これらは主が地に行き巡らせるための馬であった。つまり、これは神の働きかけがどのようなものであるか示している。赤い馬であれば、神が地上に争いを送られるということである。栗毛の馬であれば、神により死の裁きが地へと送られるということである。白い馬であれば、神が再臨のためキリストを天から遣わされるということである。
【1:11】
『すると、これらは、ミルトスの木の間に立っている主の使いに答えて言った。「私たちは地を行き巡りましたが、まさに、全地は安らかで、穏やかでした。」』
これらの馬たちは、地上を行き巡ったことによる調査結果を報告している。確かに、ここで言われている通り、この時に全地は平穏な状態であった。これは、まだ赤も栗毛も白も出動される時期ではないことを示している。何故なら、マタイ24章とその並行箇所からも分かる通り、地上に恐れと不安と激動とが生じない限り、これらの馬は出動しないからである。セネカやタキトゥスやヨセフスを読めば分かる通り、紀元40年頃~70年9月までの間には、普通ではない状態が地上に見られた。その時期には本当に多くの異常現象が各地で起こっていた。だからこそ、その時期に馬が神から出動され、遂にキリストが再臨されることになったのである。
【1:12】
『主の使いは答えて言った。「万軍の主よ。いつまで、あなたはエルサレムとユダの町々に、あわれみを施されないのですか。あなたがのろって、70年になります。」』
ここで御使いは、ネブカデレザルにより荒廃させられたままのエルサレムが70年もの間放置され続けている、と不満を露わにしている。これは一見すると不遜なようにも感じられる。主に対して文句めいたことを言っているからだ。だが、これは不遜ではなかった。何故なら、御使いは聖所への愛からこう言ったのだからである。これを他の例で言えば、夫が10年間も家を留守にしているので妻が「いつになったら一緒に生活できるの」などと涙ながらに言うようなものである。この妻の発言はもっともであって、夫にこう言ったからといって非難されるべきではないであろう。それと同様に、ここで御使いが主に言っていることも非難されるべきではない。
ここで言われている『70年』とは、捕囚が起きてから再びユダヤ人たちがエルサレムに戻って来るまでの期間である。神が捕囚の期間を70年として定められたからだ。エレミヤ25:11~12、29:10、ダニエル9:2の箇所でも、ユダヤ人たちがエルサレムに戻るまでの期間が70年と言われている。つまり、捕囚からの解放が実現される年に、この箇所で書かれているやり取りが起きたのである。
【1:13】
『すると主は、私と話していた御使いに、良いことば、慰めのことばで答えられた。』
一見すると文句のようにも感じられる御使いの言葉に対し、主は慈しみ深く返答された。これは私が述べた通り、この御使いが非難されるべきことを言ったわけではないからである。然り、確かにそうである。聖なる御使いが非難されるべきことを言うわけはない。これは、ちょうど10年間も家を留守にしていた夫が妻に対して、幸いなことを優しく語りかけるようなものである。
【1:14】
『私と話していた御使いは私に言った。「叫んで言え。万軍の主はこう仰せられる。『わたしは、エルサレムとシオンを、ねたむほど激しく愛した。』
ここで御使いはゼカリヤに『叫んで言え。』と命じている。これは、これから語られる神の言葉が非常に重要だったからである。第3部でも述べたが、キリストも重要なことを言われる際には、大いに叫ばれた。
神がここで言っておられるように、神はイスラエルを激烈に愛された。これは旧約聖書の全体で示されている。その愛は、イスラエルが幾度となく偽りの神々に不倫をしたのに幾度となく立ち帰るように求め、ずっと改悛の余地を残したままでおられたほどである。いったい、これほどの愛があるであろうか。いったい、これほどの忍耐と憐れみがあるであろうか。しかし一体どうして神はイスラエルをそこまで強く愛されたのか、と問う人がいるかもしれない。イスラエルに良い部分があるので神から特別に愛されたのであろうか。違う。それは神御自身が否定しておられる(申命記7:7~8)。神がイスラエルを特別に愛されたのは、神がイスラエルを特別に愛されたからだと言うより他はない。神の愛における選びの理由は、我々の知り得るところではない。これは、知らないままでいるのが正解である。探っても分からないことを無謀にも探るのは、知恵と思慮がないことの表れである。
【1:15】
『しかし、安逸をむさぼっている諸国の民に対しては大いに怒る。わたしが少ししか怒らないでいると、彼らはほしいままに悪事を行なった。』』
しかし、ユダヤ以外の異邦人は別であった。神は異邦人に対しては大いに怒られた。何故なら、彼らは霊的に『安逸をむさぼって』おり、神の怒りがあまり注がれないのでほしいままに悪事をしていたからである。彼らが幾らかでも反省の色を見せていれば話は別であった。だが、彼らはそのようにはしなかったのだ。これは、ちょうど改善の余地のない不良の子どもを父が家から容赦なく追い出すのと似ている。改善の見込みがあれば悲惨にされることもないが、矯正不可能であれば厳しい処罰を受けるのである。今に至るまで非再生者たちは、神が彼らにあまり怒られないので、神の前で遜ることがまったくない。一方、再生者たちは、誰でも多かれ少なかれ必ず神の前で遜った精神を持つ。何故なら、再生者たちには神の霊が住んでおられるからである。
この箇所は、伝道者の書8:11の箇所を思い出させる。そこでは次のように言われている。『悪い行ないに対する宣告がすぐ下されないので、人の子らの心は悪を行なう思いで満ちている。』非再生者たちに、すぐにも大いに報いが下されていたとすれば、彼らは今よりもっと正しい霊と精神を持っていたはずである。何故なら、悪をすればすぐに天罰が襲いかかってくるのだから。だが、神は彼らに対して、通常の場合そのようになさらない。それは、彼らがほしいままに振る舞い、悪に突き進み、癒されることもなく、最終的に破滅して地獄をその住まいとするためである。要するに彼らは神から放置されているのだ。何故なら、彼らは神の子らではないから。いったい、自分の子でもない子たちを、頻りに叱責したり矯正しようとしたりする親がどこにいるのか。このように神の子らでない者たちは、あまり神から叱られないので―『わたしが少ししか怒らないでいると』と神は彼らについて言っておられる―、今日も明日も調子に乗って最終的な破滅へと突き進むのである。
【1:16】
『それゆえ、主はこう仰せられる。『わたしは、あわれみをもってエルサレムに帰る。そこにわたしの宮が建て直される。―万軍の主の御告げ。―測りなわはエルサレムの上に張られる。』』
ここでは次のように言われている。「異邦人たちは、反省の色も見せず悪に突き進むばかりであって、悲惨である。一方、ユダヤ人たちは捕囚の苦しみを味わい、神から憐れまれるようにと願っている。それゆえ、神である主は、ユダヤ人たちに大きな恵みをお与えになる。」どうしてこう言われていると分かるのか。それは1:14~15に続いて『それゆえ』と1:16が始まっているからである。つまり、話の流れからこのように言われていると分かる。
その恵みとは、神がエルサレムに再び元の状態を回復して下さることであった。神は、もう一度エルサレムの地に住まわれることにした。だから、そこにユダヤ人たちが戻って住むようになったわけである。この約束は、ゼカリヤにこの約束が語られてから間もなく実現された。すなわち、捕囚からの解放はキュロス2世を通して前6世紀に、宮の再建はエズラやネヘミヤたちを通して前5世紀に。
『測りなわはエルサレムの上に張られる。』とは、エルサレム再建の真実性を示している。つまり、これは「エルサレムは絶対に建て直される。」ということを教えている。何故なら、エルサレムが実際に再建されるからこそ、そこに測りの縄を張れるようになるのだから。再建されもしない存在を、一体どうして測り縄で測れるのであろうか。ないものを測ることは出来ないのである。
以上の説明から、このゼカリヤ1章ではゼカリヤの時代におけるエルサレム再建について言われていることが分かる。つまり、ここでは天国や再臨について言われているのではない。これを知るだけでも再臨の探究には益が生じる。何故なら、このゼカリヤ1章が天国や再臨について言われている箇所ではないと分かるからである。そうすれば、もはや「この箇所では黙示録に出てくる馬が出てくるが、ここで言われている内容は何か再臨やユダヤの終末と関わりがあるのだろうか…」などと研究的な悩みを持つこともなくなる。もしこのような学的悩みが頭の中にあるのであれば、どうして確固とした理解に基づく力強い信仰を持てるであろうか。持てないであろう。だからこそ、私はこのように再臨に関わる全聖句を註解する第4部を書いて、聖徒たちが十全で多角的で総合的な再臨理解を持てるようにしているのである。
【1:17】
『もう一度叫んで言え。万軍の主はこう仰せられる。『わたしの町々には、再び良いものが散り乱れる。主は、再びシオンを慰め、エルサレムを再び選ぶ。』」』
御使いは、再びゼカリヤが叫ぶように命じている。これから語られる神の言葉が非常に重要だからである。
ここでも神がユダヤを回復させて下さることについて預言されている。70年も離れていた故郷に再びユダヤ人たちが帰れるようになるのだ。それなのに、どうして叫ばずにいていいものであろうか。新しい王が王位に就いた時に公に周知させないのが有りえないように、エルサレムが回復されるというのに叫ばないのは有りえないことだった。ここでは3つのことが言われている。1:ユダヤに良い物が満たされるようになる。これはユダヤに霊的・精神的・物質的を問わず幸いが与えられるようになる、という意味である。例えば霊的なことであればユダヤ人が犠牲を捧げられるようになり、精神的なことであれば平和の楽しみを享受できるようになり、物質的なことであれば家を建てたり油を身に濡れるようになる、というのがそうである。2:神がイスラエルを慰めて下さる。これはユダヤ人たちから悲しみが消え失せるという意味である。何故なら、神が彼らを元の場所に戻らせて下さるからである。3:神がエルサレムをお選びになる。これは難しくない。すなわち、神がもう一度エルサレムを御自分の住まいとして選択される、という意味である。このため、エルサレムには再び神の住まいである神殿が建てられることになったのだ。
【6:1】
『私が再び目を上げて見ると、なんと、4台の戦車が2つの山の間から出て来ていた。山は青銅の山であった。』
これから見るゼカリヤ書6:1~8の箇所は、再臨理解にとって非常に重要である。何故なら、ここでは、再臨を取り扱っている黙示録の第6章に出てくるのと同一の馬が出てくるからである。私は既に黙示録註解の中で、このゼカリヤ6章について幾らか取り扱っておいた。同じ事柄を、あたかもまだ説明していないかのように再び説明する必要はない。だから、既に説明された事柄については、出来るだけ簡略に説明して済ませたいと思っている。再臨の探究者は、黙示録だけを探究して、その黙示録と対応しているゼカリヤ書のほうを無視するということではいけない。そのようにするのは、キリストを知るために、福音書だけを調べて使徒書簡のほうは調べないようなものである。だから、再臨の探究者は、黙示録と同様このゼカリヤ書も知解しておかねばならない。
ここに出てくる『4台の戦車』は明らかに黙示録6章に出てくる4匹の馬と対応している。つまり、神はゼカリヤ書の幻と対応している幻を、黙示録の中でヨハネにお与えになったのである。黙示録では、このゼカリヤ書と対応している箇所が非常に多く見られる。これは、神がヨハネにゼカリヤ書と対応している幻を多く示されたからに他ならない。
ここで出てくる『青銅の山』とはイエス・キリストである。これがキリストであると言える理由は2つ。まず第一に、聖書ではキリストが『山』(ダニエル2章35節)として示されているからである。第二は、聖書でキリストの身体は青銅において示されているからである(ダニエル10:6)。この山は『2つ』あった。これは、キリストという山から戦車が出て来ることを示している。つまり、ユダヤの終末の時に出て来るこの戦車はキリストが遣わされたということである。
【6:2~3】
『第一の戦車は赤い馬が、第二の戦車は黒い馬が、第三の戦車は白い馬が、第四の戦車はまだら毛の強い馬が引いていた。』
この4匹の馬たちは、それぞれ神の働きかけがどのようなものであるか示している。神は象徴的な御方である。だから、このように象徴的な仕方で事柄を御示しになられる。
この馬たちを一つ一つ簡潔に説明して行きたい。「簡潔に」というのは、この馬たちについては既に第3部の中で説明されているからである。まず『赤』は、黙示録6:3~4の箇所から分かるように「争い」が投じられることを示す。争いが起これば血が流れるので「赤」なのだ。次に『黒』は、黙示録6:5~6の箇所から分かるように「救い」を示している。この黒は、非常に解読が難しいが、まだ究極的な救いが与えられていない状態にある聖徒たちを暗示している。『白』は、黙示録6:1~2の箇所から分かるようにキリストの再臨を示している。この色はキリストの聖らかさを表示するのには相応しいからだ。『まだら毛』は、黙示録6:7~8の箇所から分かるように「死」を示している。何故なら、死とは斑毛のように不気味で気色が悪いからである。黙示録のほうでは『青ざめた』と言われている。これも、やはり死を表示している。何故なら、死により生命体は青ざめるからである。
誰でもすぐに気付くと思うが、『戦車』はゼカリヤ書のほうでしか語られていない。黙示録のほうでは馬だけしか語られていない。戦車が黙示録のほうで語られていない理由は何なのか。答え。黙示録では、ただ単に戦車について触れていないだけである。つまり、黙示録で書かれている馬も、実際には戦車を引いていた。ある事柄が書かれていないからといって、即その事柄の否定を意味するのではないことぐらい、誰でも少し考えれば分かるはずである。実際、イザヤ66:15の箇所では、再臨のキリストが『戦車』において来られると言われているではないか。つまり、キリストは馬に引かれた戦車に乗って再臨されたのである。再臨のキリストに割り当てられているこの白の馬がそうであれば、赤も黒も斑毛の場合もそうであるのは自明であろう。また、ヨセフスとタキトゥスは、ユダヤ戦争の際に天空に戦車部隊が駆け巡っていたと書き記しているではないか。だから、馬は馬単体として現われたわけでなく、戦車を引いている状態として現われたことが分かる。それゆえ、戦車がゼカリヤ書においては示されているのに黙示録では示されていない、ということのうちに矛盾は全く存在していない。もしこのことに矛盾を感じる人がいたとすれば、その人は単にこの2つの箇所をよく理解できていないだけである。
既に第3部で述べた通り、このゼカリヤ書6章では、馬の現われる順序を実際通りに示していない。既に見たように、黙示録での順番は「白、赤、黒、第4の馬」、ゼカリヤ書での順番は「赤、黒、白、第4の馬」であった。毀損されていない理性を持つ者であれば、どちらとも実際通りの順番を言っているのではない、ということぐらいすぐにも分かるはずである。というのも、どちらも実際の通りの順序を言っているというのは意味が分からないからである。つまり、どちらか一方だけが実際の順序を示していると結論せねばならない。正しい順序が示されているのは黙示録のほうである。ゼカリヤ書では順序の啓示を含んでいないのだから。これについては既に第3部で十分に説明されたから、もうこれ以上の説明はしなくてもよいであろう。
【6:4】
『私は、私と話していた御使いに尋ねて言った。「主よ。これらは何ですか。」』
ゼカリヤは、この馬の幻が何を意味しているのか知りたく思い、御使いに尋ねた。このように尋ねるのは、神を愛する敬虔な人であれば当然である。何故なら、その人にとって神の啓示は何よりも重要なものだから。神を愛さない敬虔でない人は、何か特別な理由でもない限り、このように尋ねたりはしない。何故なら、その人にとって神の啓示などは別にどうでもよいからである。彼らにとって重要なのは、地上のことだけなのである。『彼らの思いは地上のことだけです。』(ピリピ3章19節)とパウロが言う通りである。
【6:5】
『御使いは答えて言った。「これらは、全地の主の前に立って後、天の四方に出て行くものだ。』
御使いは、ゼカリヤの質問に答えてくれた。何故なら、この馬の幻は聖徒たちが知ってもよいもの、いや、是非とも知るべきものだったからである。
この馬たちは主の前に立ってから世界へと遣わされる、と御使いは言っている。『全地の主の前に』とは、馬たちが地上を対象として遣わされることを示している。何故なら、ここでは「天におられる主の前に」とは言われていないからだ。もし「天におられる主の前に」であれば、馬たちは天の場所へと遣わされていたはずである。『主の前に立って後』とは、「神の前で出陣する用意が整ったら」という意味である。つまり、これは神の定められた時が来たら、という意味である。その定めの時とは紀元68年であった。
【6:6】
『そのうち、黒い馬は北の地へ出て行き、白い馬はそのあとに出て行き、まだら毛の馬は南の地へ出て行く。』
ここでは馬たちの現われる順序が示されている。その順序には、北と南の2パターンがあった。『北の地』へ行くのは、黒、白という順である。『南の地』へ行くのは、赤、斑毛という順である。赤についてはこの箇所で何も書かれていないが、この赤が南の第一番目であるのは、少し考えれば明らかである。
繰り返すが、ここでは馬が実際に出て行く順序を示しているわけではない。ゼカリヤ書で示されている順序は、実際上の順序と異なるからである。実際の順序が啓示されているのは黙示録6章のほうだけであって、このゼカリヤ書で言われているのは単に啓示上の順序であるだけに過ぎない。私がこう言ったことに反論する人がいるのであろうか。黙示録の順序もゼカリヤ書の順序も、共に実際上の順序を示していると?理性の崩壊した哀れな者よ…。
ここで書かれている『北の地』と『南の地』には、どういった意味があるのか。まず『北の地』とは、恵みが与えられる対象を示している。それは聖徒たちのことである。彼らには黒と白が遣わされる。つまり、聖徒たちは、救われるために量りで量られ(黒)、再臨のキリストに出会うことが出来る(白)。次に『南の地』とは、不幸が与えられる対象を示している。それは裁かれるべき者たちのことである。彼らには赤と斑毛が遣わされる。つまり、悪い者たちは、互いに争いあうことになり(赤)、死滅させられる(斑毛)。しかし、どうして北が恵みにおける地であり、南が不幸における地なのか。それは、北が神のおられる天上を象徴しており、南が地獄のある下の場所を象徴しているからである。黙示録6章のほうでは、全く方角については触れられていないと感じられるかもしれない。だが、黙示録のほうでも一応方角が示されている。「一応」と言ったのは、そのまま方角が示されているのではなく暗示されているに過ぎないからである。それは第4の馬が示されている第4の封印の箇所で書かれている『地上の4分の1』(黙示録6章8節)という言葉である。これは明らかに南を示している。何故なら、南とは地上にある4つの方角のうち4分の1の部分なのだから。この黙示録では4分の1の部分が明白に南とは書かれていないが、ゼカリヤ書6:6の箇所を読めば、これが南であることは絶対に疑えない。
【6:7】
『この強い馬が出て行き、地を駆け巡ろうとしているのだ。」』
4匹の馬は『強い馬』であった。これは、馬の出陣を誰も阻めない、という意味である。どうしてそう言えるのか。それは、この馬は神の働きかけを示しているからである。神の働きかけを阻めるような人が誰かいるのか。誰もいない。聖書で次のように言われている通りである。『これが、全地に対して立てられたはかりごと、これが、万国に対して伸ばされた御手。万軍の主が立てられたことを、だれが破りえよう。御手が伸ばされた。だれがそれを引き戻しえよう。』(イザヤ13章26~27節)
この馬の出陣は、ゼカリヤの時代から500年以上も後の出来事であった。つまり、ゼカリヤは遥か未来の出来事について示されたわけだ。こんなにも早い時期から、どうして神は未来のことを預言されたのであろうか。それは、神がより恐れられ、より信頼され、より崇められるためであった。500年も前から預言がされたのであれば、聖徒たちは神の凄みを感じずにはいなくさせられる。そうなれば、聖徒たちがより豊かに神を恐れ、信頼し、崇めるようにもなるのだ。
『そこで彼が、「行って、地を駆け巡れ。」と言うと、それらは地を駆け巡った。』
ここでは既に4匹の馬が地を駆け巡らされている。これは単なる予告である。つまり、ここでは「やがてこのような出来事が起こるのだ。」と言いたいのである。だから、この箇所を読んで、既にゼカリヤの時代から馬の預言が成就されていたなどと考えないように注意せねばならない。
【6:8】
『そのとき、彼は私にこう告げた。「見よ。北の地へ出て行ったものを。それらは北の地で、わたしの怒りを静める。」』
ここで言われているように、『北の地へ出て行ったもの』は注目すべきであった。何故なら、北の地へ出て行く馬は、幸いをもたらす役目があるからである。それゆえ、その馬たちは『わたしの怒りを静める』のである。黒い馬は、聖徒たちを量って救いに与からせることで、神の怒りを静める。聖徒たちが救われたならば、そこにおいて神の怒りはもはや完全に停止されるからである。また斑毛の馬は、再臨を示しているが、この再臨により神の怒りが静められる。何故なら、再臨が起こるとユダヤから罪が取り除かれるからである(ローマ11:26~27)。一方、南の地へ出て行った馬については注目するようにと言われていない。これは、南の馬は聖徒たちにとって別に喜ばしい出来事をもたらす存在ではなかったからである。
【11:1】
『レバノンよ。おまえの門をあけよ。火が、おまえの杉の木を焼き尽くそう。』
これから見る11:1~6の箇所では、紀元70年のエルサレム陥落が預言されている。ここで言われているのは、ネブカデレザルによる荒廃についてではない。何故なら、ゼカリヤ書が書かれたのは捕囚よりも後だったから。また、ここで言われているのはアンティオコス4世の蹂躙についてでもない。何故なら、ここではユダヤが焼き尽くされると言われているが、アンティオコス4世はユダヤを焼き尽くさなかったからである。であれば、ここではローマ軍によるユダヤ滅亡が言われていることになる。消去法で考えれば、確かにそうなる。
『レバノン』とはアッシリヤの地域を指す。聖書では、レバノンとアッシリヤが結び付けられているからである(エゼキエル書31:3)。『杉の木』はユダヤを指す。『門』は、レバノンとユダヤの境界を指す。つまり、レバノンの境界を越えるとユダヤに至るというわけである。ちょうど王宮の門を通って中に入るのと同じである。
ここではレバノンの視点から、ユダヤが焼き滅ぼされることについて預言されている。レバノンよ、お前の門のあちら側にあるユダヤを見よ。彼らはやがて焼き滅ぼされてしまうのだ。ここでは、あたかもこう言われているかのようである。
【11:2】
『もみの木よ。泣きわめけ。杉の木は倒れ、みごとな木々が荒らされたからだ。』
『もみの木』とは異邦人を指す。『みごとな木々』とはユダヤを指す。何故なら、ユダヤとは神に愛された特選の民・宝の国民だったのだから。
ここでは『もみの木』である異邦人たちが、『杉の木』また『みごとな木々』であるユダヤの破滅を嘆くようにと言われている。何故なら、神の民が神の前から捨てられてしまうからである。異邦人もその破滅を悲しまなければいけない、ということのうちにユダヤの破滅における悲劇性がよく示されている。黙示録18章の中でも、異邦人たちがユダヤの破滅を嘆いている。この共通性は決して無視されるべきではない。何故なら、複数の箇所で異邦人たちがユダヤの破滅を嘆いているのは、その出来事における悲惨さをよく示しているからである。
『バシャンの樫の木よ。泣きわめけ。深い森が倒れたからだ。』
『バシャンの樫の木』とは強者を指す。この木は堅固で力強いからである。『深い森』とはユダヤを指す。ユダヤ人は森のように多く、群がっていたから。
ここでは強者たちもユダヤの破滅を嘆くようにと言われている。このことのうちにも、やはりユダヤの破滅における悲惨さがよく示されている。子であった者が父から完全に勘当されてしまうのだ。誰がこれを見て悲しまずにいられるであろうか。
【11:3】
『聞け。牧者たちの嘆きを。彼らのみごとな木々が荒らされたからだ。』
『牧者』とは、ユダヤの指導者・教師・祭司たちを指す。彼らは、牧者が羊を飼うように、ユダヤを統導していたからである。
この牧者たちも、ユダヤが荒廃した際には大いに嘆いた。実際、タルムードの中では、ラビたちがエルサレム陥落を思って大いに悲嘆している。愛すべき都が壊滅してしまったのだ。それなのに、どうしてラビたちが嘆かずにいられるのであろうか。『聞け。』とは「聞かれるようになるであろう」という意味である。何故なら、これは預言であって、ゼカリヤが生きていた時にはまだ『牧者たちの嘆き』は聞かれなかったからである。
『聞け。若い獅子のほえる声を。ヨルダンの茂みが荒らされたからだ。』
『若い獅子』とは異邦人の国の若い王を指す。黙示録やダニエル書でも、王が獣において言い表されている。『ヨルダンの茂み』とはユダヤを指している。
この若い王たちは、『ヨルダンの茂み』であるユダヤの破滅を見て『ほえる声』を出した。『ほえる』とは、驚き、恐れ、嘆く、という意味である。彼らが吠えたのは、ユダヤの破滅がとんでもない出来事だったからである。黙示録18:9~10の箇所でも、王たちがエルサレム陥落を見て悲嘆すると書かれている。次の通りである。『彼女と不品行を行ない、好色にふけった地上の王たちは、彼女が火で焼かれる煙を見ると、彼女のことで泣き、悲しみます。彼らは、彼女の苦しみを恐れたために、遠く離れて立っていて、こう言います。『わざわいが来た。わざわいが来た。大きな都よ。力強い都、バビロンよ。あなたのさばきは、一瞬のうちに来た。』』
【11:4~5】
『私の神、主は、こう仰せられる。「ほふるための羊の群れを養え。これを買った者が、これをほふっても、罪にならない。これを売る者は、『主はほむべきかな。私も富みますように。』と言っている。その牧者たちは、これを惜しまない。』
誰かが羊の群れを買ったり売ったりしても、それはその人の自由である。また、当然ながら買って自分の所有となった羊を『ほふっても、罪にならない』。これは所有権には支配権も伴っているからである。すなわち、持っているから好きなように取り扱える。キリストの例え話に出てくる主人も、こう言っている。『自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか。』(マタイ20章15節)ここで『牧者たちは、これを惜しまない。』と言われているのは、牧者たちが羊を躊躇せず平気で屠るという意味である。
神はゼカリヤに『ほふるための羊の群れを養』わせることで、このことをゼカリヤに良く分からせようとされた。何故なら、実際に体験すれば、実感として事柄の内容が明確に理解できるようになるからである。すなわち、ゼカリヤが羊の群れを飼えば、ゼカリヤは羊の支配権が羊の所有者にあるということをよく理解できる。神は実際的な御方である。神は、ただ主知主義に徹して実践はほとんどしないような哲学者のようではない。だから、ゼカリヤに実際的に体験の知を得させようとされたのだ。
【11:6】
『わたしが、もう、この地の住民を惜しまないからだ。―主の御告げ。―』
牧者たちが自分の所有する羊を惜しまずに屠るのと同じで、もはや神もユダヤを惜しまれなかった。だから、神はユダヤを滅びに引き渡された。そのため、ユダヤはローマ軍により荒廃させられてしまった。もし神がユダヤを惜しんでおられたとすれば、このような荒廃は起こらなかったであろう。だが、もう神の慈愛心はユダヤから完全に遠ざかってしまっていた。もう神がユダヤを惜しまれる時期は過ぎたのである。
しかし、ここで「もしかすると神とは愛のない御方ではないのか。」などと言う人がいるかもしれない。何故なら、神はユダヤを敵の手に渡されたからである。このように言うのは間違っている。というのも、神はそれまで1000年以上もの間、ユダヤが逆らい続けているにもかかわらず、彼らに忍耐しておられたからである。この長い忍耐のうちに神のユダヤに対する愛を見ない人がいるのであろうか。しかも、ユダヤが滅ぼされたのは、ユダヤが神の子キリストを拒絶するという極悪を行なったからである。彼らがキリストを殺したのは、すなわち神との関係を断ち切ることであった。何故なら、御子を殺しておいて、どうして相も変わらず神との関係を保ったままでいられようか。それは絶対に有りえないことである。つまり、ユダヤはまず自分たちから進んで神との縁を切ったのである。だから、そのような極悪ユダヤが神の裁きにより滅ぼされたとしても、神に愛がないということにはならない。
『見よ。わたしは、人をそれぞれ隣人の手に渡し、王の手に渡す。彼らはこの地を打ち砕くが、わたしは彼らの手からこれを救い出さない。」』
神はユダヤを捨てられたので、惜しまないでユダヤを『隣人』と『王』に引き渡された。『隣人』とはローマ兵たちを指す。何故なら、この11:1~6の箇所では、ローマがユダヤを滅ぼすことについて預言されているのだから。この『隣人』をシモンおよびヨアンネスとして解する人も中にはいるかもしれない。確かに、ユダヤがこの2人の叛徒に引き渡されたのは間違いない。私はそれを認める。そして、この2人は、ローマ軍と同様に、ユダヤが滅ぶ直接的な要因となった。これはヨセフスの書を読めば分かる。だから、ここで言われている『隣人』がシモンとヨアンネスを指していると解するのは、間違っているとは言えない。だが、私はこれがあの2人のユダヤ人というよりは、むしろローマ兵であるという見解に立ちたいと思う。何故なら、そのほうが無難だからである。『王』とは黙示録17:12の箇所に書かれている『10人の王たち』を指している。彼らはまだ実際の王でなかったが、ユダヤ戦争においては王として見做されている。この王たちに引き渡されたので、ユダヤは破滅してしまったのである。この王については既に第3部の中で述べておいた。
神は、もはやローマの手からユダヤを救い出されなかった。もうユダヤが聖徒として神の前に歩む時代は終わったからである。もし神がまだユダヤを惜しんでおられたとすれば、ローマから救い出されていた可能性も十分にあり得た。たとえローマに滅ぼされたとしても、昔のように再び元の状態へと回復させられていたはずである。しかし、神はもうユダヤを惜しまれなかった。今、彼らはどうなっているか。今のユダヤ人は非常に数が少ないうえ、本来はユダヤ人ではないアシュケナージ系のユダヤ人が真正なユダヤ人でもあるかのように思われている始末。未だにキリストの到来を待ち望んでいるが(※)、彼らの願い通りにキリストが来られるはずもなく、ただ無意味な待望を抱いて無駄に精神力を疲弊させるばかり。もはや捨てられているので、これから再び神の御前に立ち帰るということも起こらない。昔に比べるとだいぶ良くなったかもしれないが、今でも続けられている悲惨な迫害の運命。このように今のユダヤ人たちは実に絶望的な境遇に置かれている。これこそ、彼らが神を裏切りキリストを殺したことに対する、恐るべき呪いなのである。
(※)
ニューヨーク・タイムズに掲載された「ネトゥレイ・カルタ(エルサレムの友)」の全面広告の中で、スファラディ系のユダヤ人たちはこう述べた。「しかし、わたしたちとユダヤの同胞はいまも待ち続けています。救世主はまだ現われてはいないのです。」※ジョン・コールマン博士著『石油の戦争とパレスチナの闇』日本民族が知らされないパレスチナ、その怨磋の歴史 p114:成甲書房より
[本文に戻る]
【12:1】
『宣告。イスラエルについての主のことば。―天を張り、地の基を定め、人の霊をその中に造られた方、主の御告げ。―』
これから見るゼカリヤ12:1~8の箇所では、第一次ユダヤ戦争について預言されている。この箇所は非常に重要である。何故なら、第一次ユダヤ戦争は再臨と大いに関わりがあるからである。
この12:1の箇所では、まず全体の序言的な内容が語られている。『宣告。』これは、これから語られることが絶対的な力を持つ宣言文であることを示している。ナホム1:1やハバクク1:1やマラキ1:1の箇所でも、同じようなことが言われている。『イスラエルについての主のことば。』これはユダヤに関わる内容がこれから告げられる、という意味である。『天を張り』。この『天』とは大気圏の場所としての天である。すなわち、これは24人の長老や御使いたちが住まう霊的な世界としての天ではない。ここでは、神による天の創造が、擬人的に言い表されている。『地の基を定め』。これは神が地球の大地を創造された、という意味である。『人の霊をその中に造られた』。これは、我々のうちにある霊が神の創造により生じたということである。我々の持つ霊は被造物なのである。それは、ある人たちが考えたように「神の部分」ではない。しかし、この12:1の箇所では、どうしてこのような序文的文言が語られているのか。それは、これから語られる事柄が、権威ある存在の宣言文であることを示すためであった。古代の碑文を見ても分かるが、古代で権威者の宣言に前置きが書かれるのは一般的であった。十戒でも、やはり最初に権威者である神の前置きが書かれている。『わたしは、あなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出した、あなたの神、主である。』(出エジプト20章2節)と。
【12:2】
『見よ。わたしはエルサレムを、その回りのすべての国々の民をよろめかす杯とする。ユダについてもそうなる。エルサレムの包囲されるときに。』
ユダヤ戦争の時、ユダヤは回りの国民を酔わす杯となった。これはどういう意味なのか。これは、つまりユダヤの破滅に回りの地域にいた者たちが巻き込まれる、という意味である。ユダヤの破滅は非常に巨大な出来事であった。その規模は、回りの地域にいた者たちも平穏でいられなかったほどである。だから、異邦人たちは、ユダヤの悲惨を見て大いに身震いしたはずである。その動揺が、ここでは「ユダヤという酔わす杯」として言われているのだ。確かに、この戦争の時、ユダヤは諸国の民に対して戦慄という酔いを与える杯となった。この箇所の表現は、なかなか理解するのが難しい。だが、この箇所は私が今述べたように理解すべきである。
黙示録の中でも、ユダヤと酔わす杯のことについて言われている。黙示録でも、やはりユダヤの悲惨に回りの者たちが巻き添えにされる、ということが言われていた。あの時、回りの国民はユダヤのせいで大いに酔わされたのであった。黙示録で言われている杯については既に第3部の中で述べておいた。
ここで『エルサレムの包囲されるときに。』と言われているのは決定的である。すなわち、この言葉は、ゼカリヤ12:1~8が紀元1世紀のユダヤ戦争について言われている箇所であるということを我々によく教えている。何故なら、『エルサレムの包囲されるとき』とは第一次ユダヤ戦争の他には全く考えられないからである。誰か私に反論する人がいるのか。誰も反論できないはずである。
【12:3】
『その日、わたしはエルサレムを、すべての国々の民にとって重い石とする。すべてそれをかつぐ者は、ひどく傷を受ける。地のすべての国々は、それに向かって集まって来よう。』
ユダヤ戦争の時、ユダヤは諸国の民にとって『重い石』となった。これは難なく理解できる。これは、ユダヤ戦争の時にユダヤと一緒にいたりユダヤに近づいたりする国民は、ユダヤの破滅に巻き添えを食らう、という意味である。実際、あの戦争の時にユダヤの地にいた者たちは、ローマ軍の攻撃に巻き込まれたはずである。何故なら、ローマ軍は、いちいちユダヤの地にいる外国人をユダヤ人と区別するようなことはしなかったからである。それは、あたかも非常に重い石を背中に背負わされたので倒れ、大ダメージを受けるようなものであった。だから、ユダヤ戦争の時にユダヤが諸国民にとって『重い石』になるという例えは、実に適切である。我々人間は、このように知的な比喩表現をなかなか思いつけない。人間の知性は矮小であり、広がりがあまりないからである。しかし、神の知性は無限である。だから、聖書にはこのように知的な比喩表現が無数に書かれているのである。
『地のすべての国々は、それに向かって集まって来よう。』これは、ローマ軍がユダヤを包囲すべく集まって来る、という意味である。『地のすべての国々』とはローマ軍とその兵士たちを指している。既に述べた通り、ローマ軍は様々な国の民族から構成されていたからである。黙示録20:8の箇所でローマ軍が『地の四方にある諸国の民』と呼ばれているのも、これと同じ理由による。聖徒たちは、この『国々』という言葉をローマの軍隊として理解せよ。そうしなければ、永遠に正しい理解は得られないであろう。教会の中には、この『国々』という言葉を、最終戦争の時に集結される無数の国々であると考える人が多くいるはずである。これは何という玄妙さ、何という研究不足、何という霊的な盲目性であることか!このように考えてしまう人は、本書をよく読み、大いに祈りを捧げ、思考と神学的な改善の努力をせねばならない。ここでは最終戦争についてではなく第一次ユダヤ戦争について教えられているのである。『それ』とは、ユダヤ・エルサレムを指す。
【12:4】
『その日、―主の御告げ。―わたしは、すべての馬を打って驚かせ、その乗り手を打って狂わせる。しかし、わたしは、ユダの家の上に目を開き、国々の民のすべての馬を打って盲にする。』
ユダヤ戦争の際、神はローマ軍の馬とその乗り手たちを打って異常にされた。これはどういう意味なのか。これは、彼らが御言葉の剣により殺されて霊的な死体となり、悪霊どもに食われて支配されてしまった、という意味である。つまり、ここでは再臨が起きた時のことについて言われている。この出来事は、黙示録の19:11~21の箇所と対応している。霊的に殺されて悪霊どもに憑りつかれるというのは、打たれること、驚かされること、狂わされること、盲目にされること、でなくて何であろうか。そのようにして悪霊どもに憑依されたからこそ、ローマ軍の兵士たちは神に『愛された都』(黙示録20:9)であるエルサレムを破壊したのである。既に述べたが、悪霊に憑かれることなしに、そのような恐るべきことは出来ないのである。なお、この時に打たれた馬の数は約1200匹ぐらいであった。何故なら、ローマ軍の一箇軍隊には騎兵が120おり、エルサレム包囲の時には10箇の軍隊が出動していたからである。だが、この戦争には他国からの援軍もやって来ていたから、実際にはもう少し多かったはずである。
一方、神はユダの家の上には目を開かれた。『ユダの家』とは、ここでは再臨が起こるまでに死んでいた聖徒たち、すなわち天上からキリストと共に降りて来ることになっていた聖徒たちを指している。この言葉をこのように理解しないと、続く箇所で何が言われているのか珍紛漢紛になってしまう。その死んでいた聖徒たちに神の目が開かれるとは、すなわち彼らが再臨の際に復活させられるという意味である。再臨の際に死んでいた聖徒たちが復活するというのは、既に説明された通りである。これはⅠテサロニケ4章を読むならば、疑うことが出来ない。
【12:5】
『ユダの首長たちは心の中で言おう。エルサレムの住民の力は彼らの神、万軍の主にある、と。』
『エルサレムの住民』とは、地上のエルサレムにいた生きた聖徒たちを指している。これは『ユダの家』と明白に区別されなければならない。すなわち、ここにおいて『ユダの家』とは天上の聖徒たちであり、『エルサレムの住民』とは地上にいた聖徒たちである。この天上にいた聖徒たちは、心の中で『エルサレムの住民の力は彼らの神、万軍の主にある』と言った。これは、地上のエルサレムにいる聖徒たちには神が共にいて下さるのでユダヤ人たちのように断ち滅ぼされることはない、という意味である。実際、神を自分の力とする彼らは再臨の際に復活して携挙されたので、ユダヤの滅亡に巻き込まれるということがなかった。つまり、神を力としていたので滅亡から免れることが出来たのである。再臨を待ち望んでいた聖徒たちが携挙されるというのは、イザヤ40:31の箇所でこう言われていた通りである。『主を待ち望む者は新しく力を得、鷲のように翼をかって上ることができる。』
【12:6】
『その日、わたしは、ユダの首長たちを、たきぎの中にある火鉢のようにし、麦束の中にある燃えているたいまつのようにする。彼らは右も左も、回りのすべての国々の民を焼き尽くす。しかし、エルサレムは、エルサレムのもとの所にそのまま残る。』
ユダヤ戦争の時、『ユダヤの首長たち』である天上の聖徒たちは、『たきぎの中にある火鉢のように』また『麦束の中にある燃えているたいまつのように』なり、『すべての国々の民』であるローマ兵たちを焼き尽くした。これは、天上の聖徒たちがローマ兵たちに怒りの裁きを下す、という意味である。その裁きが、ここでは火による燃焼として表現されている。聖書で怒りの裁きが燃える火として言い表されているのは、周知のことである。だから、ここで『焼き尽くす』と言われているのは実際的な意味ではない。これは、あくまでも霊的な裁きの比喩である。我々は日常の中で「あの人の怒りの火が燃え上がった。」などと言われているのを聞いても、違和感を持たない。ここで焼き尽くすと言われているのも、それと同じ意味合いにおいてである。また、この箇所は黙示録20:9の箇所と対応している。そこでも、やはりローマ兵たちが天上の聖徒たちによる火のごとき裁きを受ける、と言われている。すなわち、このように書かれている。『彼らは、地上の広い平地に上って来て、聖徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ。すると、天から火が降って来て、彼らを焼き尽くした。』我々が今見ているゼカリヤ12:6とこの黙示録20:9が対応しているのは、ここまで読み進められた聖徒たちであれば難なく分かるであろう。
この箇所では繰り返しによる強調表現が使われている。すなわち、『たきぎの中にある火鉢のようにし、/麦束の中にある燃えているたいまつのようにする。』という部分がそうである。この強調は、裁きの事柄における重要性をよく示している。
『しかし、エルサレムは、エルサレムのもとの所にそのまま残る。』これは、ローマ兵たちが霊的な裁きを受けている中にあって、エルサレムにいた聖徒たちはそのような裁きを受けないままの状態に保たれる、という意味である。ここで『エルサレム』と言われているのは、場所ではなく、そこにいた聖徒たちを指している。これは続く箇所を読めば明らかである。エルサレムにいた聖徒たちは救われるように定められていたので、ローマ兵たちのように裁かれるべきではなかったのだ。これを場所として理解すると誤る。何故なら、ここではエルサレムが『そのまま残る』と言われているが、ユダヤ戦争の時にエルサレムはそのまま残らなかったからである。あの時、エルサレムは残されるどころか、完全に荒廃させられてしまった。だから、これを場所として理解すると、ここで何が言われているのか分からなくなる。あの時に『そのまま残る』ことになったのは、その場所ではなくその場所にいた聖徒たちであった。
【12:7】
『主は初めに、ユダの天幕を救われる。それは、ダビデの家の栄えと、エルサレムの住民の栄えとが、ユダ以上に大きくならないためである。』
『ユダの天幕』とは、先に『ユダの家』と言われていたのと同じ意味であり、天上の聖徒たちを指す。『エルサレムの住民』も、先に見た通り、エルサレムにいた地上の
聖徒たちを指す。『ダビデの家』とは、この『エルサレムの住民』のうちダビデに連なるユダ族のユダヤ人を指す。つまり、『エルサレムの住民』と『ダビデの家』とは、どちらもエルサレムにいた地上の聖徒たちという点で一緒である。ややこしいと感じる方もいるかもしれないが、これら3つの語句はしっかりと区別せねばならない。
神は再臨が起きた際、まず『初めに、ユダの天幕を救われ』た、すなわち最初に天上の聖徒たちを復活させられた。復活するとは、すなわち救われることに他ならない。その次に復活させられたのが、地上にいた聖徒たち、すなわち『ダビデの家』と『エルサレムの住民』であった。つまり、天上の聖徒たちと地上の聖徒たちは、一緒の時に復活させられたのではない。両者の復活には時間差があった。天上の聖徒たちのほうが先に死んだので先に復活する優先権を持っていたのである。ここでは先に天上の聖徒たちが復活する理由について、こう言われている。『それは、ダビデの家の栄えと、エルサレムの住民の栄えとが、ユダ以上に大きくならないためである。』先に地上にいた聖徒たちが復活するのは理に適わないことであった。それは、大学で1年生のほうが4年生よりも先に卒業してしまうようなものである。先に4年生のほうが卒業すべきなのは言うまでもない。もし先に1年生が卒業させられたら、4年生が侮辱されることになる。先輩が先んじるのは物事の道理である。だから、先に死んだ聖徒たちが侮辱されないため、先に死んだ聖徒たち―『ユダの天幕』
―のほうが先に復活することになったわけである。
パウロがⅠテサロニケ4:13~17の箇所で、先に天上の聖徒たちが優先的に復活すると言ったのは、このことであった。Ⅰテサロニケ4:15の箇所で、パウロは地上にいた聖徒たちが先に死んだ天上にいる聖徒たちよりも復活において先んじることはない、と言っている。『私たちは主のみことばのとおりに言いますが、主が再び来られるときまで生き残っている私たちが、死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。』これは既に述べたように、先に死んだ聖徒たちが先に復活の栄誉に与かるべきだったからである。1年生のほうが4年生よりも先に卒業して祝福されるのは明らかに自然ではないのである。聖徒たちは心に銘記されたい、我々が今見ているゼカリヤ12:7とⅠテサロニケ4:15は対応している。じっくり読んでよく考えれば、どちらも地上の聖徒が天上の聖徒に復活のことで優先されるべきではないと言われているのが分かるはずである。
【12:8】
『その日、主は、エルサレムの住民をかばわれる。その日、彼らのうちのよろめき倒れた者もダビデのようになり、ダビデの家は神のようになり、彼らの先頭に立つ主の使いのようになる。』
『その日』すなわち再臨の起きたユダヤ戦争の時、神はエルサレムにいた聖徒たちを庇われた。『かばわれる』とは、神が地上の聖徒たちをユダヤの破滅から免れさせて下さった、という意味である。その時に地上の聖徒たちは携挙された。その携挙された聖徒たちをローマ兵が攻撃することは出来ない。だから、ここでは神が聖徒たちを庇って下さると言われている。これこそ正に神の御翼の影に匿われるということである。鳥がその羽で自分の子を守るように、神は御自分の子らを守られるのだ。この鳥の羽による例えは、旧約聖書の中で多く使われている。黙示録3:10の箇所でもここと同様のことが言われている。そこでも、神が聖徒たちをユダヤ戦争における悲惨から免れさせて下さると約束されていた。つまり、ゼカリヤ書12:8と黙示録3:10は内容的に対応している。その黙示録の箇所ではこう言われていた。『あなたが、わたしの忍耐について言ったことばを守ったから、わたしも、地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時には、あなたがたを守ろう。』
このユダヤ戦争の時、神は聖徒たちを復活させて幸いな状態にして下さった。ここでは、そのことについて3通りの仕方で言われている。まず、エルサレムにいた聖徒たちは『よろめき倒れた者もダビデのようにな』った。すなわち、聖徒たちは、たとえ倒れてしまうほどの弱い者も復活によりダビデのように強くされた。イザヤ40:31の箇所では、復活した聖徒についてこう言われている。『走ってもたゆまず、歩いても疲れない。』これはダビデのように力強くなるということでなくて何であろうか。また、聖徒たちは『神のようにな』った。すなわち、復活した聖徒たちは神の性質を帯びるに至った。それは、永遠に生きたり、完全に聖い状態となったり、全く罪を犯さなくなる、という性質がそうである。これは聖徒たちが神になると言っているわけではない。そうではなく、これはあくまでも「神のようになる」ということに過ぎない。復活した聖徒がこのように神に似た者となるのは御心に適うことであった。何故なら、人間とは神に似ることを目的として創造された被造物なのだから(創世記1:26)。また聖徒たちは『彼らの先頭に立つ主の使いのようにな』った。この『主の使い』とはミカエルである。復活した聖徒が御使いのようになるというのは、キリストもマタイ22:30の箇所で言っておられる。これは聖徒たちが御使いのように純粋で聖くなるということである。すなわち、これは聖徒たちが御使いそのものになる、ということではない。
【12:9】
『その日、わたしは、エルサレムに攻めて来るすべての国々を捜して滅ぼそう。』
『その日』とは、ユダヤ戦争の時期を言っている。これは『その日』と言われているが、ある特定の1日について言われているわけではない。それは『終わりの日』と言って、ユダヤが終わるある特定の1日を指しているのではないのと同じである。ここで言われている預言は、ゼカリヤの時代から約500年後のことである。まだローマが無名だった頃から既にローマの侵攻について預言するというのは、正に全知の神がなせる業に他ならない。
この12:9の箇所で言われているのは、ユダヤを取り囲むローマ軍に対する神の裁きである。『滅ぼそう』とは、ローマ軍が霊的に裁かれることを意味している。ローマ兵たちは、御言葉の剣によって霊的に殺され、その死体が悪霊どもという鳥に食い尽くされたのである。この裁きについては黙示録19:17~21およびエゼキエル書39章の箇所でも言われている。これについては、黙示録註解(第3部)とエゼキエル書註解(第4部)の当該部分を見ていただきたい。『捜して』とは裁きの不可避性を示している。何故なら、神が捜されるならば仕留められずに済むことは絶対に出来ないからである。『すべての国々』とはローマ軍を意味する。何故なら、ローマ軍は様々な国の兵士から構成されていたから。黙示録20:7~10の箇所でも、やはりローマ軍が『諸国の民』と言い表されている。これはなかなか難しい表現だが、ローマ軍として解さなければならない。
この預言が未だに成就していないと考えている聖徒は多いはずである。だが、この預言は既に成就されている。ここまで読み進められた聖徒であれば、もう分かるはずである。この預言がこれから成就すると考えてしまうのは、聖書をよく学んでいるからそう考えるというのではなく、無知と研究不足が原因でそう考えてしまうのである。ちなみに、マタイ24章がまだ成就していないと考えてしまうのも、これと同じである。多くの牧師たちはまだマタイ24章が成就していないと言うけども、私から既にマタイ24章が成就したことを聖句と実際の歴史において示されると、すっかり黙ってしまう。それは、今までにそのようなことを考えたことが無かったからである。
【12:10】
『わたしは、ダビデの家とエルサレムの住民の上に、恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは、自分たちが突き刺した者、わたしを仰ぎ見、ひとり子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣く。』
この箇所ではキリストの再臨について預言されている。ここは重要な箇所であるから、是非とも心に留めて置きたいところである。出来るならば暗記するのが望ましい。
再臨のキリストを見たユダヤ人たちは、その時、恵みを受け、大いに嘆いた。何故なら、神がその時、彼らに『恵みと哀願の霊を注』がれたからである。『恵み』とは、再臨の時にユダヤが救われることを言っている。それは、ローマ11:26~27の箇所で、『救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬虔を取り払う。これこそ、彼らに与えたわたしの契約である。それは、わたしが彼らの罪を取り除く時である。』と言われている通りである。『哀願の霊を注ぐ』とは、ユダヤ人たちが哀願の霊においてキリストのことを思うという意味である。キリストに関する事柄はどれも霊的であるので、霊によらなければ心を突き動かされることがないのである。この再臨を見て嘆いたのはユダヤ人であったことに注意せねばならない。何故なら、ここでは『ダビデの家とエルサレムの住民』について預言されているからだ。『ダビデの家』とはダビデに連なるユダ族を指す。『エルサレムの住民』とは紀元1世紀におけるエルサレム市民を指す。既に述べたように、再臨はエルサレム上空で起こった。ゼカリヤ14:4の箇所に書かれている通りである。この再臨を見たのは、物理的にエルサレムおよびエルサレム近郊にいた者だけに限られた。これは小学生でも分かる。何故なら、この地球上は曲面になっており、幾らか遠ざかると近くにいた時には見えた物体が見えなくなるからである。実際、スエトニウスが書いているようにネロは再臨の時に生じた雷光は目にしたが、再臨されたキリストの御姿は見なかった。これはネロがローマの近隣にいたので、エルサレムからは離れ過ぎていたからである。つまり、再臨の時の雷光だけがローマにまで届いたというわけだ。また、この箇所で言われているのはユダヤ人のことである。何故なら、ここでは『自分たちが突き刺した者』と書かれているからである。この『自分たち』とはユダヤ人であって、異邦人ではない。ペテロも言ったように、キリストを突き刺して殺したのはユダヤ人である(使徒行伝2:23、36、3:13~15)。だから、ここではユダヤ人について言われていると理解せねばならない。このユダヤ人たちは、キリストが再臨された際、キリストを見て大いに嘆いた。誰でも自分の初子また独り子を喪失すれば大いに悲嘆するだろうが、再臨されたキリストを見たユダヤ人が悲嘆したのは、正にそのようであった。これはユダヤ人たちが突き刺してはならない御方を突き刺したのだから当然であった。何故なら、キリストとは彼らにとって主人なのだから。自分たちが突き刺した主人を再びその目で見たのに、悲嘆しない者が果たしているのか。普通の精神を持っているのであれば、そのような者は誰もいないであろう。なお、ここで『ひとり子』また『初子』と書かれているのは、キリストを暗示しているとも解せる。何故なら、キリストとは御父の『初子』である『ひとり子』だったのだから。
ここでは再臨のキリストを見たユダヤ人たちの嘆きが、繰り返しの表現により強調されている。すなわち、『ひとり子を失って嘆くように、その者のために嘆き』という部分が1度目であり、『初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣く』という部分が1度目の繰り返しである。この強調は、その時に起こった事柄の大きさを、またユダヤ人たちの嘆きの大きさをよく示している。確かに、自分たちが殺した御方を再びその目で見て嘆くというのは、只事ではない。
この箇所は、間違いなく黙示録1:7の箇所と対応している。そこでは次のように書かれている。『見よ。彼が、雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが、彼を見る。地上の諸族はみな、彼のゆえに嘆く。しかり。アーメン。』ヨハネがゼカリヤ12章に基づいて黙示録1:7の箇所を書いたのは間違いない。この黙示録のほうについては、第3部の当該箇所を見ていただきたい。
この箇所も、やはり既に成就している。何故なら、この箇所は今述べたように黙示録1:7の箇所と対応しているからである。黙示録1:7の箇所では、『すぐに起こるはずの事』(黙示録1章1節)が預言されていた。だからゼカリヤ12:10の箇所も、ヨハネが黙示録を書いてから『すぐに起こるはずの事』だったことになる。『すぐに』とは「人間的な感覚において間もなく」という意味でしかない。『すぐに』と言われながら数百年、数千年も成就していないというのは有りえない。だから、黙示録1:7が既に成就しているようにゼカリヤ12:10も既に成就しているのだ。
【12:11~14】
『その日、エルサレムでの嘆きは、メギドの平地のハダデ・リモンのための嘆きのように大きいであろう。この地はあの氏族もこの氏族もひとり嘆く。ダビデの家の氏族はひとり嘆き、その妻たちもひとり嘆く。ナタンの家の氏族はひとり嘆き、その妻たちもひとり嘆く。レビの家の氏族はひとり嘆き、その妻たちもひとり嘆く。シムイの氏族はひとり嘆き、その妻たちもひとり嘆く。残りのすべての氏族はあの氏族もこの氏族もひとり嘆き、その妻たちもひとり嘆く。』
ここでは、再臨が起きた時のユダヤ人たちの嘆きの凄まじさが教えられている。それは『メギドの平地のハダデ・リモンのための嘆きのよう』であった。『メギド』とは、既に述べたように、古代では戦場として名高かった場所である。『ハダデ・リモンのための嘆き』とは、ヨシヤ王がメギドでパロ・ネコと戦った際、悲惨な死に方をしたことについてであろう。その時、ユダ王国全体が大きな喪に服した。再臨の時にはそのような悲しみがユダヤ人に起こったと。このメギドでの話は、Ⅱ列王記23:29~30、Ⅱ歴代誌35:20~24に書かれている。また、この箇所から分かるように、再臨の時に嘆きが起こるのは『エルサレム』において、である。それは、再臨がエルサレム上空で起こったからである。この箇所も重要であるから、聖徒たちは心に留めて置くのが望ましい。
ここでは再臨の時に多くの者たちが嘆くと言われている。ここでは色々な者たちが挙げられているが、それらは無造作に挙げられているわけではない。これらの者たちには、それぞれ明白な意味がこめられている。まず『ダビデの家の氏族』とは王家に属する者である。ダビデとは王だったから。『ナタンの家の氏族』とは預言者たちである。ナタンは預言者だったから。『レビの家の氏族』とは祭司たちである。レビ人とは祭司の種族だったから。『シムイの氏族』とは悪い者たちである。シムイは反逆の子だったから。それ以外のユダヤ人たちは『残りのすべての氏族』という言葉で一括されている。つまり、この箇所では「王族も預言者たちも祭司たちも悪い者たちもそれ以外の者たちも」と言われているのである。
キリストがマタイ24:30の箇所で再臨の時に『地上のあらゆる種族は、悲し』むと言われたのは、明らかにこのゼカリヤ書12:10~14の箇所に基づく。これは文章の相似具合から明らかである。つまり、キリストは再臨の時にエルサレム市にいる全てのユダヤ諸氏族が悲しむと言われたのである。キリストが『地上』と言われたのは、ユダヤの地上を意味している。「そのような言い方があるのだろうか。これは地球全土という意味ではないのか。」などと疑問に感じてはならない。既に述べたが、ゼパニヤ1:2~6の箇所では『地の面』と言ってただユダヤの場所だけを意味していたではないか。また『あらゆる種族』とは、エルサレムにいるユダヤ人の『あらゆる種族』という意味である。これも既に述べたように、聖書では普通の言い方である。もう一度繰り返すが、聖書では「全て」とか「あらゆる人」などと言って、限定された範囲内における「全て」また「あらゆる人」を意味している箇所が多くある。例えば、使徒行伝2:17の箇所では『わたしの霊をすべての人に注ぐ。』と言われているが、これは信仰者たちにおける『全ての人』であって、地球全土に住む悪人も含めた『全ての人』ではない。だから、マタイ24:30に書かれている『地上のあらゆる種族』という言葉をエルサレム市にいたユダヤ人の諸氏族と解するのは、聖書の語法から何も逸れていないので合法であり、おかしいということは全くない。それゆえ、マタイ24:30の箇所では文字通りの意味で地球全土に住む全ての種族が悲しむと言われているのではない。そのように捉えるのは間違っている。ただマタイ24:30にだけ心を留めて、そのマタイ24:30のベースとなったゼカリヤ書12:10~14を考慮しないと、正しい再臨理解を得られなくなってしまう。聖徒たちは注意せねばならない。
【13:7】
『剣よ。目をさましてわたしの牧者を攻め、わたしの仲間の者を攻めよ。―万軍の主の御告げ。―牧者を打ち殺せ。』
『剣』とは虐殺を意味する。旧約聖書では、他にも多くの箇所で虐殺がこのように表現されている。
ここでは剣に対して目覚めるようにと命じられている。剣が眠っている状態は、虐殺が行なわれていないことを示す。だから、剣が目覚めるとは、虐殺が行なわれることを示す。
ここで神はユダヤの指導者たちに対して虐殺を指示しておられる。『わたしの牧者』とはユダヤの指導者を指している。何故なら、彼らは霊的な羊であるユダヤ人を飼う霊的な牧者だったから。『わたしの仲間の者』も、やはりユダヤの指導者を指している。彼らは、パウロがそうだったのと同じで、神の仲間である共同労働人だったからである(Ⅰコリント3:9)。この指導者たちの虐殺はユダヤ戦争の時に実現した。神がローマ軍の剣を用いて彼らを滅ぼされたのである。
この箇所では誠に驚くべきことが言われている。このような言葉である。『牧者を打ち殺せ。』これは、親が子を皆殺しにせよと言ったり、師匠が弟子を敵の手に渡したり、王が親しい臣下を全て処刑するようなものである。だから、この言葉が本当に神の言われたことなのかと疑ってしまう人も中にはいるかもしれない。また、ここで言われている『牧者』は本当にユダヤの指導者なのかと疑問に感じる人もいるかもしれない。しかし、これは確かに神の言われたことである。何故なら、ここでは『万軍の主の御告げ。』と言われているから。また、この『牧者』とは確かにユダヤの指導者たちを指している。何故なら、彼らについてここでは『わたしの仲間の者』と言われているからである。もしこの『牧者』がユダヤの指導者でなければ、つまり敵のことであるならば、『わたしの仲間の者』とは言われていなかったはずである。ここで神が御自分の牧者たちを虐殺せよと命じておられるのは、確かに驚くべきことである。だが、彼らに虐殺が命じられたのは仕方ないことであった。それというのも、紀元1世紀の指導者たちは完全に堕落していたからである。主が、ユダヤを指導していたパリサイ人どもを非常に激しく責められたことを思い出してほしい。当時の牧者たちが滅びに値するほどに堕落していたからこそ、主はあのように厳しい非難を彼らにお与えになったのである。だから、ここで神が牧者たちを殺すように命じられたのは、驚かされることではあるものの、何も間違ったことではなかった。
『そうすれば、羊は散って行き、わたしは、この手を子どもたちに向ける。』
ここで言われている『羊』とはユダヤ人を指している。聖書では基本的に「羊」と言えば純正な神の子らを指しているが、ここで言われている『羊』は単なる民族としてのユダヤ人という意味である。この箇所において純正な神の子らは『子どもたち』という言葉で示されている。ユダヤ人であっても救われてキリスト者になっていた者であれば、もちろんこの『子どもたち』という言葉の中に含まれている。
ここではユダヤ戦争において『羊』であるユダヤ人が虐殺されてから四方へと散らされ、『子どもたち』である純正な神の子らが救われる、と言われている。ここで『手を…向ける』と言われているのは救いを意味している。我々は、水の中で溺れている人を見かければ、たぶん手を向けて救おうとするはずである。ここで救いが『手を…向ける』と言われているのは、このような救出の場合を考えればよく分かるのではないかと思う。
【13:8~9】
『全地はこうなる。――主の御告げ。―その3分の2は断たれ、死に絶え、3分の1がそこに残る。わたしは、その3分の1を火の中に入れ、銀を練るように彼らを練り、金をためすように彼らをためす。彼らはわたしの名を呼び、わたしは彼らに答える。わたしは「これはわたしの民。」と言い、彼らは「主は私の神。」と言う。』
『全地』とはユダヤの地を指している。何故なら、ここではユダヤについて語られているからである。先に註解されたゼパニヤ1章でも『地の面』と言って、ただユダヤの土地だけを言い表していた。このような例がゼパニヤ書に見られるのだから、この箇所で『全地』と言ってユダヤだけを指しているのは何もおかしいことではない。
ここでは『3分の1がそこに残る』と言われている。これは聖徒たちを指している。何故なら、彼らは『主は私の神』と言う者たちだからである。神も彼らについて『これはわたしの民。』と言われる。これは聖徒以外ではありえない。聖徒でなければ『主は私の神』とは言わないだろうし、神もそのような者について『これはわたしの民。』とは言われない。『3分の2』とは聖徒でないユダヤ人を指している。彼らは『断たれ、死に絶え』る。つまり、再臨が起きた際、救われることなく断罪され滅びに至らされる。『そのような人々は、主の御顔の前とその御力の栄光から退けられて、永遠の滅びの刑罰を受けるのです。』(Ⅱテサロニケ1章9節)とパウロが彼らについて言った通りである。それでは、どうして聖徒たちが『3分の1』であり、救われない者たちが『3分の2』なのか。この割合には、それぞれどういった意味があるのか。まず聖徒たちが『3分の1』であるのは、救われる者たちが比率的に少ないからである。いつの時代でも真に救われている者は比率的に少ないものである。次に救われない者たちが『3分の2』であるのは、救われない者たちが比率的に多いからである。いつの時代でも真に救われている者よりも救われていない者のほうが比率的に多いのである。
『3分の1』である聖徒たちは、火にかけられて試されることになった。主はこう言っておられる。『わたしは、その3分の1を火の中に入れ、銀を練るように彼らを練り、金をためすように彼らをためす。』再臨が起きた際、聖徒たちは火の試練により、尊い金属として御前に受け入れられることになった。それは金または銀が火にかけられて、精錬された状態で所有者の持ち物に加えられるようなものである。これは信仰における試練であった。ペテロはこのように言っている。『信仰の試練は、火を通して精錬されてもなお朽ちて行く金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現われのときに称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。』(Ⅰペテロ1章7節)この火による精錬としての試練については、パウロも次のように言った。『もし、だれかがこの土台の上に、金、銀、宝石、木、草、わらなどで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現われ、この火がその力で各人の働きの真価をためすからです。もしだれかの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もしだれかの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は、火の中をくぐるようにして助かります。』(Ⅰコリント3章12~15節)このⅠコリント書の箇所は、また後ほど説明されることになる。
黙示録8章の中で『3分の1』と何度も言われているのは、間違いなくこの箇所で『3分の1』と言われているのと関わりがある。どちらのほうでも、『3分の1』が火に入れられると言われているからである。この一致具合に気付かないほどに鈍い人が果たしているのか。多分いないはずである。黙示録8章の『3分の1』という言葉は、我々が今見ているゼカリヤ書13:8~9の箇所の助けを借りない限りは正しく解釈できない。聖書は聖書によって解釈する。これが聖書解釈の原則である。旧約聖書との関わりにおいて解釈することが求められている黙示録では、特にこの原則を固辞することが必要である。聖徒たちは、このことを決して忘れるべきではない。
【14:1】
『見よ。主の日が来る。』
『主の日』とは再臨の日である。新約聖書の多くの箇所でも、そのような意味で『主の日』と書かれている。
『その日、あなたから分捕った物が、あなたの中で分けられる。』
これは、聖徒たちの略奪された所有物を、神が補償して下さるという意味である。それは、もちろんキリストのゆえに略奪された物に限られる。神は、キリストを理由として損失された物を、必ず補って下さる。だが管理ミスなど非宗教的な理由により略奪された場合は、その限りではない。何故なら、その場合、その人の不手際が悪いのだからである。なお、この損失は、迫害や除名などといった霊的・精神的な略奪も含まれているとすべきである。何故なら、それも一種の略奪だからである。だから、そのような目に見えぬ損失にも神は必ず報いて下さる。それはキリストがこう言われた通りである。『人の子のために、人々があなたがたを憎むとき、また、あなたがたを除名し、はずかしめ、あなたがたの名をあしざまにけなすとき、あなたがたは幸いです。その日には、喜びなさい。おどり上がって喜びなさい。天ではあなたがたの報いは大きいからです。』(ルカ6章22~23節)
聖徒たちが分捕られた物は、結局のところ神により取り戻される。その損失は永遠の報酬となってやがて返って来るのだ(人や場合によっては地上において既に返って来ることもある)。だから、聖徒たちに対する略奪とは、究極的に言えば利益に他ならないことになる。だからこそ、昔の聖徒たちは略奪や苦難を勇敢に、そして喜びつつ耐え忍んだのである(ヘブル10:34、11:35)。我々も、神の報いを期待するのであれば、諸々の略奪に耐えることが出来るであろう。それは、その人が地上にではなく天に目を置いているからである。
【14:2】
『わたしは、すべての国々を集めて、エルサレムを攻めさせる。町は取られ、家々は略奪され、婦女は犯される。町の半分は捕囚となって出て行く。』
ここではローマ軍がエルサレムを攻撃することについて言われている。『すべての国々』がローマ軍を意味しているということは、読者にもう説明する必要はないであろう。
『町は取られ』。これはエルサレム市がローマに攻略されることである。これは神からの呪いであった。『家々は略奪され』。これはユダヤ人の家々が荒廃させられ、その中にあった財物が強奪される、という意味である。これはユダヤ戦争の時に起こった。これも神の呪いである。『婦女は犯される』。古代人の歴史書を読んでも、ユダヤ戦争の時にこのような出来事が起きたとは記されていない。だが単に記されていないだけであって、あの戦争の時には婦女の凌辱が行なわれたのであろう。キリストの奇跡も聖書以外の本では何も記されていないが、実際にキリストは奇跡を大いに行なわれたのである。これも呪いであった。『町の半分は捕囚となって出て行く』。これも実際に起こった。ユダヤにいた多くの者は、ローマ軍が攻撃した後、四方へと散らされたのである。神の呪いによりこのような悲惨が彼らに与えられた。
この箇所で言われていることが、これから起こる出来事であると考えてはならない。例えば、この箇所ではやがて中東で起こるハルマゲドンの戦いについて預言されているのだ、などと考えてはならない。何故なら、ここで言われている出来事は既に成就しているからである。実際、ここで言われている通りのことがユダヤ戦争の時に起きたではないか。どうしてそれを認めないのか。「あの戦争の時に『すべての国々』は結集されなかった。」とでも言うのか。何という無知か!既に述べた通り、『すべての国々』とはローマ軍を表示する言葉に過ぎない。もしこの『すべての国々』を文字通りの意味で理解すべきだとすれば、黙示録13章に書かれている『獣』も文字通りの獣として理解せねばならないということになる。黙示録13章の獣が比喩ではなく実際の動物だとでも言うのか。お笑いな捉え方は謹んでいただきたい。目を覚ませ。ここで言われているのは紀元1世紀に起きたエルサレム包囲のことなのである。
『しかし、残りの民は町から断ち滅ぼされない。』
『残りの民』とは聖徒たちである。何故なら、これが聖徒でなければ誰だというのか。
この『残りの民』である聖徒たちは、ユダヤの破滅から免れ、ユダヤ人と共に断ち滅ぼされることがなかった。何故なら、ユダヤ戦争の時、彼らは携挙されて地上から取り去られたからである(マタイ24:40~41)。黙示録3:10の箇所からも分かる通り、主の御心は、聖徒たちがユダヤに降りかかる患難から助け出されることであった。
【14:3】
『主が出て来られる。』
これは再臨である。この箇所は、ごく簡単な箇所であるが非常に重要である。
これは受肉という到来のことではない。それは文脈を考えれば明らかである。ここではキリストが再臨されるユダヤ戦争の時について語られているのである。
『決戦の日に戦うように、それらの国々と戦われる。』
再臨されたキリストは『国々』であるローマ軍と戦われた。それは正に『決戦』のようであった。これは何に例えたらよいであろうか。アレクサンドロスとダレイオスの決戦がよいであろう。あの時の戦いは正に決戦と呼ぶに相応しかったから。このキリストとローマ軍の戦いは霊的であった。それは物質的な戦いではなかった。その戦いの勝者はどちらであったか。それはキリストとその軍勢であった。その時、キリストは御言葉の剣によってローマ兵たちを殺し、霊的な死体とし、悪霊どもの餌食となるようにされたのである。
この戦いは、黙示録では19:11~21の箇所で描かれている。そこではキリストとローマ軍が戦いをし、その結果、ローマ軍たちが負けてしまうことについて書かれている(19:19~21)。また、この戦いは黙示録6:1~4の箇所で書かれている白および赤の馬における預言とも対応している。何故なら、白の馬と赤の馬の出来事は、黙示録19:11~21の箇所と対応しているからである。
【14:4】
『その日、主の足は、エルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。』
キリストは、『エルサレムの東に面するオリーブ山の上』に再臨された。これが聖書の教えである。このオリーブ山は、キリストが昇天された場所である(使徒行伝1:12)。キリストの再臨は昇天と同様の有様において実現された(使徒行伝1:11)。何と、再臨された場所まで昇天の時と同様であった。また、このオリーブ山は、キリストがマタイ24章の預言をお語りになった場所でもある(マタイ24:3)。つまり、キリストは御自身が再臨について語られた当の場所に再臨された。この共同性には非常に感じさせられるものがある。更に、このオリーブ山はローマ軍がエルサレム包囲の時に駐留していた場所でもあった。つまり、キリストはローマ軍の真上に再臨されたことになる。ローマ兵たちは、再臨のキリストを見て、さぞ驚いたであろう。このローマ兵たちは、上空に降りて来られたキリストの軍勢に立ち向かおうとした。だが、それは束の間の出来事であって、彼らには幻想のごとき出来事に思えたのであった。これはイザヤ29:1~8の箇所に書かれている通りである。これこそタキトゥスを除きローマ人たちが誰もキリストの再臨に触れていない理由である。幻想にしか思われないような夢のごとき情景を、ローマ人という律儀な者たちが真面目に記録していなかったとしても、特に不思議には思われないのである。我々も、心理学者や脳科学者でもない限り、誰がいちいち夢や夢のような情景を書き記すだろうか。
キリストはオリーブ山の地面に降りて来られたのではない。この点を誤解しないようにすべきである。ここで『主の足は…オリーブ山の上に立つ。』と言われているのは、単にキリストがオリーブ山の上空に降りて来られたと言っているだけに過ぎない。パウロがⅠテサロニケ4:16~17の箇所で言った通り、キリストが降りて来られたのは地面ではなく空中の場所だったのである。つまり、キリストの足がオリーブ山の地面に触れるということはなかった。
『オリーブ山は、その真中で2つに裂け、東西に延びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。』
ここでは何が言われているのか。ここで言われているのは、再臨の際に人が2種類に分けられることである。すなわち、救われる者と断罪される者である。前者は『北』と対応し、後者は『南』と対応している。読者は、先に6:1~8の箇所で『北の地』と『南の地』について語られていたのを覚えておられるであろう。このうち北は恵みと救いを、南は呪いと断罪を示していた。つまり、ここでは北に移される地が救われる者を表しており、南に移される地が断罪される者を表しているのだ。このような表現は我々の理解を越えている。だから、よく考えないと、ここで何が言われているのか決して理解することは出来ない。
言うまでもないことかもしれないが、ここでオリーブ山が2つに裂けると言われているのは、文字通りの意味として捉えられてはいけない。これは単なる比喩に過ぎないからである。これを文字通りに捉える人は、聖書解釈の訓練が足りていない。
【14:5】
『山々の谷がアツァルにまで達するので、あなたがたは、わたしの山々へ逃げよう。ユダの王ウジヤの時、地震を避けて逃げたように、あなたがたは逃げよう。』
ここで『逃げよう』と言われているのは携挙のことである。再臨が起こると聖徒たちは携挙された(Ⅰテサロニケ4:16~17)。この携挙は、サタンに動かされているローマ軍から逃げることであった。この携挙という逃走を、敗北の逃走として理解してはならない。これは勝利の逃走であった。例えば、気の狂った男に襲われた女性が武装した軍隊のいる場所に逃げたと考えてみよ。この女性が軍隊のもとへ逃げたことにより、変な男に対する勝利を得たことになる。何故なら、この女性はその時から軍隊に守られるだろうからである。だから、これは勝利の逃走であったと言える。聖徒たちが神のもとに携挙され逃れたのも、これと同じである。ここで『わたしの山々』と言われているのは、神の御許のことである。ウジヤ王の時に起きた地震が言われているのは、一つの事例として示すためである。
黙示録12章の箇所でも、やはり携挙が逃走として語られている。これはサタンからしても正に逃走であった。サタンは聖徒たちが携挙された際、「くっそー、あいつら俺の前から神のところへと逃げやがった!」などと思ったはずである。この黙示録12章については既に説明済みだから、何が言われているのか忘れてしまった人は、第3部の当該箇所に立ち戻ってほしい。
『私の神、主が来られる。すべての聖徒たちも主とともに来る。』
ここでは明らかに再臨のことが言われている。
先に見た14:3の箇所とは違い、この14:5の箇所では、キリストが再臨される時には聖徒たちも一緒に来ると言われている。『すべての聖徒たちも主とともに来る。』という言葉は、明らかにエノクの預言に基づく、ゼカリヤの時代には、このエノクの預言がユダヤ人の間に一般的に知られていたのだと思われる。聖徒たちもキリストと共にやって来るというこの出来事については、Ⅰテサロニケ3:13、4:14、ユダ14の箇所でも語られている。
【14:6】
『その日には、光も、寒さも、霜もなくなる。』
この箇所から14:11までの箇所では、天国について言われている。『その日』とは「天国が始まったその日、その天国において」という意味である。だから、14:6~11までの箇所で地上のことが言われていると考えてはならない。そのように考えると正しい理解は得られない。
ここでは3つのことが言われている。まず天国には『光』がない。だが、次の節で明白に言われているように、天国には『光がある』。では、ここで天国に光がないと言われているのは、どういう意味なのか。ここで言われている『光』とは、すなわち太陽と月の照らす光である。黙示録21:23の箇所でも天国には『これを照らす太陽も月もいらない。』と書かれている。その理由は『神の栄光が都を照らし、子羊が都のあかりだからである』。『寒さ』と『霜』が地上的な事柄について言っているように、『光』も地上的な事柄としての光として捉えるべきである。それゆえ、この箇所を読んで天国に光そのものが存在しないと考えるのは間違っている。また天国には『寒さ』がない。何故なら、そこは祝福に満ちた快適な場所だからである。更に天国には『霜』もない。何故なら、そこにはガチガチ震えねばならない冬という季節がないからである。
【14:7】
『これはただ一つの日であって、これは主に知られている。』
『これはただ一つの日であって』。これは、天国の到来が1回限りであることを示している。何故なら、天国は1回到来するだけで十分だからである。それは2回も3回も繰り返される必要がない。天国が一度始まれば、後はもうずっと継続されるようになるのだから。これは、我々人間が一度生まれたら、もう一度生まれる必要がないのと同じである。この部分は、再臨を中途半端に理解しているある者たちを完全に反駁している。この者たちは、再臨が既に起きたと信じるものの、完全な形としての天国はまだ到来しておらず、それは2度目の再臨が起きた時に実現されると考えている。だが、この部分はそれを否定している。何故なら、ここでは天国の到来をもたらす再臨が1回限りの出来事として示されているからである。また、ここでは再臨が起こると完全な形としての天国が到来すると示されている。だから、彼らの盲目的な見解は、この箇所からも退けられねばならないのだ。もし再臨が2度あるのであれば、ここでは『これはただ一つの日であって』とは言われていなかったであろう。この者たちは、聖書、特に黙示録やその他の重要な箇所を研究していない分、政治・経済や社会情勢、陰謀論などの研究に意識を費やしている。もちろん、私もこのような分野の研究自体は否定しないし、それは否定されるべきでもない。だが、我々にとって最も重要なのは聖書の研究である。誰がこれを疑うのであろうか。彼らはカトリックが神学的に高尚で純粋なものを持っていない反動として会堂や儀式といった外面的な要素ばかり発達しているのと同じで、聖書を研究していない反動として聖書以外の分野に意識を向けてしまうのである。つまり、カトリックが外面的な要素で内面の不足を本能的にカバーしているように、彼らも聖書の研究不足による神学的な貧困を聖書以外の分野を考究し熟練することによりカバーしているのだ。だから、彼らが流暢に聖書以外の分野を語っているのを見た人たちは、目の前に立派な考究成果を見せつけられているので、それで幾らかの知的満足を覚えてしまい、別に聖書の御言葉そのものがあまり解説されなかったとしても不満には思わないのである(※)。これでは彼らが再臨について正しい理解を持てていないのも無理はない。実際、彼らをよく見てみよ。黙示録もエゼキエル書もゼカリヤ書も熱心に考究していないではないか。これらはどれも再臨と大いに関わりのある文書なのであるが…。要するに、彼らには恵みが注がれていないのである。もし本当に恵みが注がれていたとすれば、私がそうしているように黙示録やその他の重要な箇所を徹底的に考究しようとしていたはずである。何故なら、恵みが注がれると人の目と心は必ず聖書に傾けられるようになるからである。アウグスティヌスやルターやカルヴァンを見よ。彼らはどれだけ聖書に意識を傾けていたであろうか。だから、彼らは聖書そのものを大いに解説したのである。アウグスティヌスは聖書を毎日講解していた。ルターも日々聖書の解き明かしをしており、あまりにも忙しいので、いちいち説教の準備をしている暇もないぐらいであった。このルターはまた年に3回聖書を全巻読み通していた。カルヴァンも膨大な聖書註解を書いている。私には神が恵みを注いで下さっておられる。だから、このように聖書そのものから再臨を考究することが出来ているのだ。どうか、この神に栄光が永遠に至るまでもありますように。アーメン。
(※)
私のように聖書そのものを考究していると、どれだけ聖書に専心しなければいけないかということが、よく分かる。というのも調べねばならない箇所が、あまりにも多いからである。再臨について理解しておかねばならない箇所は、本当に無数にある。だから、聖書そのものに本気で取り組むならば、彼らのように聖書以外の分野に意識を費やすのは、時間の制約もあり(1日は24時間しかないから)、なかなか難しくなるのである。
[本文に戻る]
『これは主に知られている』。これは、天国の始まる時が主に予知されている、という意味である。何故なら、その時を定めたのは他でもない主であられるのだから。恐らくキリストがマタイ24:36の箇所で言われた御言葉は、この箇所に基づいていると思われる。何故なら、マタイ24:36とこの箇所は内容的また文章的に似通っているからである。そこでキリストはこう言われた。『ただし、その日、その時がいつであるかは、だれも知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。』
『昼も夜もない。』
天国には昼夜の区別というものが全くない。何故なら、そこは常に明るく昼のようだからである。それゆえ、天国には昼や夜という概念そのものがない。試しに、男または女しかこの世界にいなかったとしてみよ。その場合、我々は性すなわち男女の概念を持ち得ない。またこの世界に青年しかいなかったとしてみよ。この場合も、やはり我々は老人や子どもといった概念を持ち得ない。天国に昼夜の概念がないのは、これと同じである。天国にあるのはただ昼のみ。だから、そこには『昼も夜もない』のである。
天国に昼夜の区別そのものがないというのは、黙示録22:5の箇所を見ても分かる。そこでは『もはや夜がない。』と言われている。これは天国には昼しかないという意味である。昼しかないのであれば、実際に昼しかないのだから、昼とか夜などといった区別の認識もないのである。
『夕暮れ時に、光がある。』
天国には、夕の時にも光が至る所を照らしている。ここでは天国に『夕暮れ時』があると教えているのではない。これは我々の感覚に合わせてこう言われているだけである。つまり、ここではこう言われているのである。「天国には、あなたがたが夕暮れ時だと認識している時間帯にも光が照らされている。だから、天国には実質的に夕暮れ時などという時間帯はないのである。」
恐らく、天国には「睡眠」もないであろう。何故なら、そこは昼の場所であり(黙示録22:5)、そこにいる者たちは『光の子ども、昼の子ども』(Ⅰテサロニケ5章5節)だからである。昼の場所で寝る者がいるのであろうか。また光の子・昼の子どもが寝るということがあるのであろうか。これは、どちらも有りえないことである。だから天国では睡眠がない可能性が非常に高い。そもそも、睡眠とは神の栄光を大いに表わすような状態とは程遠いと思える。また、寝ている状態は死人と見分けがつかない。だから、栄光と生命の場所である天国に睡眠という生理現象はあまり相応しいと言えないのである。
このような場所である天国は、我々の理解を越えている。我々がどれだけこの場所を想像してみても、実際にそこがどのような場所であるのか真に実感することは出来ない。だが、実際にこのような場所はあり、その場所は既に再臨と共に開始されている。聖徒たちは、イエス・キリストの信仰に留まり続けよ。そうすれば、やがてこの場所に至るであろう。そして、その場所がどのような場所であるのか真に実感するようになるであろう。
地獄は、この天国とはまったく正反対である。つまり、地獄には「朝にも闇がある」。そこは闇の場所だからである。ユダは、この地獄に行く者たちについて、こう言っている。『まっ暗なやみが、彼らのために永遠に用意されています。』(ユダ13節)キリストの例え話の中でも、地獄に行く者について次のように命じられている。『役に立たぬしもべは、外の暗やみに追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのです。』(マタイ25章30節)地獄とは神の恵みがまったくない場所である。「光」とは神の恵みによる被造物である。それゆえ、恵みのない地獄には光もないわけである。
【14:8】
『その日には、エルサレムから湧き水が流れ出て、その半分は東の海に、他の半分は西の海に流れ、夏にも冬にも、それは流れる。』
この箇所では何が言われているのか。ここでは、天国に聖霊が満ちておられることについて言われている。エルサレムから流れ出る『湧き水』とは聖霊である。聖書で聖霊が水として示されているというのは、周知のことである。この聖霊を表示する水が、『東の海』と『西の海』にエルサレムから流れ出ている。『東の海』とは死海を、『西の海』とは地中海を指している。つまり、ここでは死海と地中海までの地域とその真ん中にあるエルサレムを、天国の全地域とその中心にある神とキリストという聖所(黙示録21:22)に見立てているのである。ここで『半分』の水が東と西の海に流れているのは、聖霊が天国に均しく満ち渡っておられることを教えている。聖霊なる神は無限の御方である。無限者であられる神が満ちるならば、その場所には神がどこでも均しくおられることになるのだ。何故なら、無限が充満すれば各部分は均一に充満されるしかないからである。
この箇所で言われていることは、黙示録では22:1~2の箇所と、エゼキエル書では47:1~12の箇所と対応している。そちらのほうの箇所でも、やはり天上のエルサレムに聖霊が満ちておられることを示している。しかし、この箇所はヨハネ7:38の箇所とは対応していない。そこでキリストはこう言われた。『わたしを信じる者は、聖書が言っているとおりに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。』どうしてこのヨハネ7:38とゼカリヤ14:8は対応していないのか。それは、キリストが言われたのは、人とその心についてだからである。我々が今見ているゼカリヤ14:8の箇所で言われているのは、人とその心についてではなく、天国という場所についてである。この2つの箇所では、語られている対象が違う。だから、この2つの箇所は対応していないとせねばならない。
この箇所では地上のことが言われていると捉えてはならない。何故なら、ここは再臨により始まる天国について言われている箇所だからである。この再臨は既に起きた。だから、この箇所の預言は既に成就している。しかし、ここで言われていることは地上において実現されていない。それゆえ、ここでは地上のことが言われていると理解すべきではない。ここでは天上について言われているとしないと正しい理解が持てなくなる。
ここでは水が『夏にも冬にも』流れると言われているが、これは天国に夏や冬があるという意味ではない。天国に冬があるというのは先に見た14:6の箇所から否定される。『寒さも、霜もなくなる』とは、つまり冬がなくなるということに他ならないからだ。天国に冬がないのであれば、同様に夏もないとすべきである。ここで『夏にも冬にも、それは流れる』と言われているのは、こう言っているのも同じである。「天国では水が夏のように枯れることはないし、冬のように凍ってしまうこともない。」つまり、天国ではいつも水が滞りなく流れている。それは、天国ではいつも聖霊が満ち渡っておられるということである。
【14:9】
『主は地のすべての王となられる。その日には、主はただひとり、御名もただ一つとなる。』
『地』とは天国の地を指している。何故なら、ここでは天国について語っているからである。既に第3部でも見たように、黙示録でも天国が『地』と言われている(11:16)。だから、黙示録11:16と同じように、ここで天国が『地』と言われているのは何もおかしくない。天国にも人の立つ地面があるのだから。
再臨後、キリストは天国で『王となられ』た。何故なら、キリストこそ天国の支配者であり主宰者であられるからである。キリストが王として君臨しておられない天国は考えられない。キリストが再臨後に天国で王となられるということについては、他にも黙示録11:17、19:6などの箇所で言われている。
天国では『主はただひとり』となった。これは、天国には『唯一の主なるイエス・キリスト』(Ⅰコリント8章6節)だけが「主」としておられる、という意味である。この地上世界には昔も今も『多くの主がある』(Ⅰコリント8章5節)。だが、天国にはそのような偶像は少したりとも存在しないのである。また天国では『御名もただ一つとなる』。これも、天国では神の御名だけが唯一の御名として存在することになる、という意味である。この地上世界では例えば「ゼウス様」とか「御釈迦様」とか「バフォメット様」といった無数の御名がある。だが、天国ではそのような御名は完全に排除されるのである。
【14:10】
『全土はゲバからエルサレムの南リモンまで、アラバのように変わる。エルサレムは高められ、もとの所にあって、ベニヤミンの門から第一の門まで、隅の門まで、またハナヌエルのやぐらから王の酒ぶねのところまで、そのまま残る。』
再臨が起こると、エルサレムは『アラバのように』変えられた。『アラバ』とは平地である。エルサレムは山々に属する地域である。そこがアラバのような平地となってしまう。これは、天上のエルサレムに多くの人たちが住まうことを暗示している。何故なら、平地とは人が住むのに適している場所だからである。実際、天国とは多くの人が住まう場所である。キリストが『わたしの父の家には、住まいがたくさんあります。』(ヨハネ14章1節)と言われたのは、天国に多くの人が住まうことを教えている。何故なら、人が多く住まうのでなければ、どうして住まいが多くそこにあるのであろうか。また、これも地上のエルサレムについて言われていると考えてはならない。何故なら、再臨が起きてから今に至るまで、エルサレムは何もアラバのように変わっていないからである。エルサレムがアラバのようになると言われているのを聞いて地上のエルサレムのことだと考える人は、キリストが神殿を3日で再建されると言われたのを聞いて、実際の神殿について言われていると勘違いをしてしまったユダヤ人と一緒である(ヨハネ2:18~21)。ヨハネ2:18~21の箇所もそうだが、聖書で一見すると実際のエルサレムについて言われていると感じるものの、実は霊的なエルサレム、または天上のエルサレムについて言われている箇所は少なくない。この箇所もそうである。
キリストの再臨により『エルサレムは高められ』た。これは天上のエルサレムが輝かしい名声を持つことを言っている。何故なら、『そのとき、正しい者たちは、天の父の御国で太陽のように輝』(マタイ13章43節)くからである。また、そこにいる聖徒たちは『永遠に王』(黙示録22章5節)だからである。再臨後には、天上の世界に太陽のような王たちが多く住まうようになった。これでは、どうしてエルサレムが名声において高められないままでいるはずがあるだろうか。
またこのエルサレムは『そのまま残る』ことになった。これも、やはり地上のエルサレムを通して天上のエルサレムを表示させている。すなわち、ここでは地上のエルサレムがそのまま保持されると示すことにより、天上のエルサレムが傷も損害もないままの状態に保たれることを教えているのである。これも、やはり地上のエルサレムについて言われていると考えることは出来ない。何故なら、紀元70年においてエルサレムは『そのまま残る』ことがなかったからである。歴史が示している通り、エルサレムは残るどころか、完全に荒廃させられてしまったのである。
【14:11】
『そこには人々が住み、もはや絶滅されることはなく、エルサレムは安らかに住む。』
天国において『そこには人々が住み』つくようになった。『そこ』とは天国、『人々』とは天国に住まう聖徒たちである。ここでも地上のエルサレムを天上のエルサレムに見立てている。これを地上のエルサレムとして捉えると誤ってしまう。何故なら、紀元70年以降、エルサレムにユダヤ人たちが住まうことは出来なくなったからである。ラビたちがタルムードの中で、エルサレムに戻れなくなったことを嘆いている通りである。「しかし、20世紀になってエルサレムにはユダヤ人たちが住まうようになったではないか。その時にここで言われている預言が成就したのではないか。」と言う人がいるかもしれない。残念であった。今現在あの国に住んでいるユダヤ人の90%はアブラハムの血を持たないアシュケナージ系のユダヤ人である。しかも、スファラディ系の正当派ユダヤ人たちは、そもそも現代のイスラエル国家そのものに抵抗感を持っている。このような状態を見て、イスラエルの地にユダヤ人たちが戻って住むようになった、などと考えることは出来ない。今のイスラエル国家の大部分を占めるアシュケナージ系ユダヤ人の祖先を辿ってみよ。そうしてもキリストやモーセの時代のユダヤ人には行き着かないのである。キリストやモーセの時代のユダヤ人を祖先に持たないのであれば、どうしてイスラエルの地に「戻って来た」などと言えるのか。理性を崩壊させなければ、このように荒唐無稽な発言は決して認められないであろう。だから、今のイスラエル国家を見て、ここで言われている預言が成就したなどと考えることは全くできない。
またエルサレムは『もはや絶滅されることはなく』なった。これは、天上のエルサレムが永遠に完全なままの状態として保たれることを示している。何故なら、そこは巨大な城壁により守られているからである(黙示録21章)。この城壁のため、天国にはいかなる敵も侵入できない。つまり、天上のエルサレムとは絶対無敵の状態にあるのだ。だから、そこが絶滅されるなどということは万一にも起こりえないのである。
また『エルサレムは安らかに住む』ようになった。これは天国における平和と安心を示している。それというのも、『そこにはもう、泣き声も叫び声も聞かれない』(イザヤ65章19節)からである。この部分も、やはり地上のエルサレムとして理解してはならない。再臨から今に至るまで地上のエルサレムには一時も安らかさがなかったからである。中世においては何回か神殿再建が試みられたが全て失敗し、忌まわしい十字軍の貪欲な対象地とされ、現代においてはロスチャイルドの陰謀のために偽イスラエル国家が築き上げられ、アラブ人との対立が絶えず、今でもずっと禍々しい岩のドームがかつて神殿のあった場所を陣取っている。これからも、地上のエルサレムに安らかさがもたらされることは有り得ない。何故なら、黙示録19:3の箇所でも言われているように『彼女の煙は永遠に立ち上る』からである。これはエルサレムという大淫婦がソドムとゴモラのように永遠に呪われ続けるという意味である。だから、いかなる意味においても、この『エルサレムは安らかに住む』という部分を地上のエルサレムのこととして理解することは出来ない。
繰り返して言うが、この14:11の箇所も既に成就している。これは繰り返して言わねばならない。何故なら、今の教会の多くの人たちは、この箇所が未だに成就していないと考えているはずだからである。つまり、今の教会にとって非常に重要なことであるから繰り返して私は言うのである。もっとも、どれだけ私が言ったとしても、多くの教会は見解を変えるよりも誤謬の中に安住し続けるのを望むことであろうが。教会に進化論が満ち、聖書で禁じられている女性牧師が普通に見られる時代である。こんな状態では、痛みを伴う見解の変更に多くの教会が進もうとしないのは、目に見えているのだ。
【14:12】
『主は、エルサレムを攻めに来るすべての国々の民にこの災害を加えられる。彼らの肉をまだ足で立っているうちに腐らせる。彼らの目はまぶたの中で腐り、彼らの舌は口の中で腐る。』
再臨されたキリストは、『エルサレムを攻めに来るすべての国々の民』であるローマ兵たちに裁きを下された。その裁きとは彼らを腐らせることであった。この腐敗は霊的に捉えねばならない。それは、黙示録11:5の箇所で二人の証人から火が出て敵を殺すと言われていたのが、霊的に捉えるべきであるのと同じである。この裁きは既に本書の中で説明済みである。すなわち、腐った死体にされたローマ兵たちが悪霊どもという鳥に食われたのである。腐った死肉をむしゃむしゃと食べ漁っているハゲタカをイメージしてみよ。ローマ兵たちに悪霊が憑依するというのは、そのようなものである。なお、この裁きの出来事は、黙示録では19:17~21と、マタイ福音書では24:28と、エゼキエル書では39:4~5、17~20と対応している。
ここで言われている出来事は文字通りに捉えられるべきではない。もしこの出来事を文字通りに捉えねばならないとすれば、例えば黙示録19:17~18の箇所で言われている『鳥』も文字通りに捉えねばならないことになる。だが、黙示録で言われている鳥を文字通りに捉えるのは明らかにおかしい。だから、我々が今見ているゼカリヤ書の箇所で言われている出来事も文字通りに捉えるべきではない。
【14:13】
『その日、主は、彼らの間に大恐慌を起こさせる。彼らは互いに手でつかみ合い、互いになぐりかかる。』
ここで言われているのは、ユダヤ戦争の時に起きたローマの内戦である。『互いに手でつかみ合い、互いになぐりかかる』とは、ローマ人が互いに戦うようになることを言っている。これは実に壮絶な仲間割れであり、多くの血が流されたが、これは主が下された裁きである。何故なら、ローマ人たちはイエス・キリストの福音を受け入れなかったからである。つまりキリストは、彼らの不信仰に対して、内乱という悲惨をもって報いられたのである。その結果、短期間の間に3人もの皇帝(ガルバ、オト、ウッティリウス)が剣に倒れるという悲劇が生じてしまった。この内乱について詳しく知りたい人は、タキトゥスの『同時代史』という本を読むがよい。
この内乱の出来事は、ハガイ書2:22またエゼキエル書38:21の箇所でも言われている。それらの箇所でも、やはりローマ人たちが仲間割れをすることについて預言されている。
【14:14】
『ユダもエルサレムに戦いをしかけ、回りのすべての国々の財宝は、金、銀、衣服など非常に多く集められる。』
語句の説明。『ユダ』とは、ここでは再臨のキリストと共に降りて来た聖徒たちである。どうして彼らがユダと言われるかといえば、彼らがイエス・キリストという『獅子の子』(創世記49:9)であるユダに属する者たちだからである。『エルサレム』とはエルサレム市にいたユダヤ人を指している。『回りのすべての国々』とはローマ兵たちを指している。
再臨が起こると、『ユダ』である天上の聖徒たちは『エルサレム』にいたユダヤ人たちを裁いた。この裁きには、その時に地上から携挙された聖徒たちも参加している。彼らが『エルサレム』すなわちイスラエルの12部族を天から裁くということについては、キリストも使徒たちにこう言っておられた。『まことに、あなたがたに告げます。世が改まって人の子がその栄光の座に着く時、わたしに従って来たあなたがたも12の座に着いて、イスラエルの12部族をさばくのです。』(マタイ19章28節)この出来事は黙示録20:1~6の箇所でも書かれている。その時、それまでに存在していた聖徒たちは『座』に着いて、審判の業を遂行したのである。この審判がここでは『戦いをしかけ』ると言われている。というのも、審判とは法的な意味において戦いを仕掛けることに他ならないからである。
また、天から降りて来た聖徒たちは、『回りのすべての国々の財宝』を略奪した。これは天上の聖徒たちがローマ軍に勝利を得たことを示している。ある軍隊が戦いに勝てば、その軍隊は敗北した敵の財宝をことごとく奪い尽くすであろう。だから、略奪した財宝とは言わば勝利の印である。この箇所では、そのような地上的な勝利により、天上の聖徒たちが獲得した霊的な勝利を示している。だから、ここでは実際に天上の聖徒たちがローマ軍から物質的な財宝を略奪したと言われているわけではない。ここで言われている略奪は、あくまでも勝利の比喩である。
【14:15】
『馬、騾馬、らくだ、ろば、彼らの宿営にいるすべての家畜のこうむる災害は、先の災害と同じである。』
キリストが再臨された時には、ローマ軍の動物たちも裁きを受けた。その裁きとは、動物たちが霊的に腐らされて悪霊どもに憑依されるという裁きであった。これは『先の災害と同じ』である。すなわち、それは14:12の箇所で言われていた災害、つまりローマ兵たちが腐らされて悪霊どもに憑依されるという災害と同じである。悪霊どもに憑依されるという点で、ローマ兵たちとローマ軍の動物たちは一緒の裁きを受けたわけだ。また、この箇所では動物たちに対する裁きのほうがローマ兵たちに対する裁きよりも順序的に後だったと示されている。何故なら、ここでは『先の災害と同じである』と書かれているからである。しかし、この言葉を「先に書かれていた災害と同じである」という意味として、すなわち単なる記述上の意味として捉える人がいるかもしれない。だが、私はそのように捉えない。つまり、こういうことである。まず第一にローマ兵たちが悪霊どもに憑依され、すぐ続けてローマ軍の持つ動物たちが悪霊どもに憑依されたのである。
この箇所で言われている動物がユダヤ人たちの動物であると考えないように注意せねばならない。何故なら、ここでは『彼らの宿営にいるすべての家畜』について語られているからである。この『宿営』とはローマ軍のそれであって、ユダヤ軍のそれではない。何故なら、ユダヤ側はただ単に責められただけであって、元々いた場所から何も離れていなかったのだから、宿営を張るということもなかったからである。だから、ここではローマ軍の動物について言われていると解さなければならない。これは14:14の箇所からの続き具合を考慮してみても分かる。明らかに、この14:15の箇所では14:14の箇所で言われていた『すべての国々』に関することが言われているのだから。
【14:16】
『エルサレムに攻めて来るすべての民のうち、生き残った者はみな、毎年、万軍の主である王を礼拝し、仮庵の祭りを祝うために上って来る。』
再臨が起きた際、『エルサレムに攻めて来るすべての民』すなわちローマ兵たちで、キリストを信じた人がいた。何故なら、先に述べたように、キリストはローマ軍の宿営の真上に降りて来られたからである。輝かんばかりの威光を伴って降りて来られたキリストとその軍勢を見たのであれば、ローマ人でありながらキリストを信じるようになったというのは、何も不思議なことではない。そのローマ兵は『生き残った』。つまり、御言葉の剣により霊的に殺されず、霊的な死肉として悪霊どもに食われるということがなかった。再臨の起きた時に救われて御名を崇めるようになった人がいたということは、黙示録11:11~13の箇所でも示されている。この黙示録の箇所については既に第3部で註解された。
この時に救われたローマ人たちは、神を礼拝するようになった。何故なら、クリスチャンとは神を礼拝する者たちだからである。ここで彼らが『仮庵の祭りを祝いに上って来る』と言われているのは、神を礼拝するというだけの意味でしかない。これは文字通りの意味、すなわち実際に仮庵の祭りを祝いに上りに行くという意味ではない。何故なら、新約時代において仮庵の祭りは廃止されたからである。つまり、ここではゼカリヤの時代のユダヤ人に合わせた言い方がされているだけに過ぎない。この時のユダヤ人にとって仮庵の祭りを祝うのは当たり前のことだったから。要するに、これはこう言ったも同じである。「あなたがたユダヤ人たちは仮庵の祭りを祝う神の崇拝者であるが、やがて幾らかのローマ人たちも仮庵の祭りを祝っているあなたがたのような神の崇拝者に変えられるであろう。」この仮庵の祭りに関する記述を文字通りに捉え、新約時代になってもこの祭りが行なわれるなどと考えるのは、明らかにおかしいと言わねばならない。
つまり、ここでは新約時代における異邦人の召しが示唆されている。それは当時のユダヤ人にとっては驚愕すべきことであった。何故なら、昔のユダヤ人にとって、『すべての民』すなわち異邦人がユダヤ人のように真の神を礼拝するようになるなどということは、ほとんど考えられなかったからである。だが、神の考えは人の考えを遥かに超えている(イザヤ55:8~9)。異邦人の召しは、昔のユダヤ人には想定し難かったが、神にとっては必ず実現されるべきことであった。だから、信じるならばどの民族でも神の民になれるという昔のユダヤ人には信じ難かった救いのパラダイムが、今となっては実現されているのである。
【14:17~19】
『地上の諸氏族のうち、万軍の主である王を礼拝しにエルサレムへ上って来ない氏族の上には、雨が降らない。もし、エジプトの氏族が上って来ないなら、雨は彼らの上に降らず、仮庵の祭りを祝いに上って来ない諸国の民を主が打つその災害が彼らに下る。これが、エジプトへの刑罰となり、仮庵の祭りを祝いに上って来ないすべての国々への刑罰となる。』
ここでも新約時代について言われている。
新約時代において主を礼拝しない民族には、律法の呪いが注がれる。ここではその呪いが『雨が降らない』という言葉で示されている。これは、律法の呪いの全体を、ある一つの律法の呪いにより言い表している。確かに律法では、雨の降らないことが呪いの一つとして教えられている(申命記28:23~24)。つまり、主を礼拝しない民族は祝福をいただくことが出来ない。実際に新約時代を見てみると、どうか。我々は、確かにキリスト教の信徒が多い欧米諸国が傾向として大いに栄え、キリスト教とは無縁である国ほど傾向として繁栄していない現状を見ている。特に、最も高度で洗練されたキリスト教であるカルヴァン主義を受け入れている国は、繁栄の度合いが凄まじかった。オランダとイギリスとアメリカがそうである。これらの国は世界に先駆けて近代化と繁栄の恵みに与かり、全世界に大きな影響を及ぼし、誰もが認める強大な覇権国家になったのである。しかしながら、日本はキリスト教がほとんど浸透していないにもかかわらず、欧米諸国と同等の繁栄を享受している。この日本は例外である。日本という国は、私の考えでは、欧米諸国が高ぶらないための防衛手段として栄えることが許されている。もし日本が栄えていなければ、ただ白人の住む欧米だけが栄えている状態となり、そのような状態は白人が白人以外の国や民族を大いに見下す大きな要因として作用していたであろう。だが、日本が欧米と肩を並べているゆえ、欧米諸国はそのような高ぶりを持つことに多かれ少なかれ抵抗をかけられているわけである。つまり、神は欧米人のために日本を繁栄させておられるのだ。何故なら、箴言でも言われているように『高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ』のだから。だから、日本が非キリスト教国であるにもかかわらず栄えているのは、我々が今取り扱っている事柄において何ら問題にはならない。
ここでは主を礼拝しなければ呪われるということの一例としてエジプト人が挙げられている。このエジプト人は、最も真の神に近づきそうにない民族である。だが、そのようなエジプト人でも神に近づくことが出来るようになると、ここでは示唆されている。真の神から遠く離れているように思えるエジプト人でさえ神を礼拝するようになるのであれば、尚のこと、その他の民族は神を礼拝するようになるであろう。だから、ここでエジプト人を例として挙げているのは、世界中の民族が例外なく神の前に召されるようになるということを示している。それゆえ、ここでエジプト人が挙げられているのは実に適切であったことが分かる。
【14:20~21】
『その日、馬の鈴の上には、「主への聖なるもの」と刻まれ、主の宮の中のなべは、祭壇の前の鉢のようになる。エルサレムとユダのすべてのなべは、万軍の主への聖なるものとなる。いけにえをささげる者はみな来て、その中から取り、それで煮るようになる。その日、万軍の主の宮にはもう商人がいなくなる。』
ここでは3つのことが言われている。一つ目は馬の鈴のこと、二つ目は鍋のこと、三つ目は神殿の商人のことである。一つ一つ見て行きたい。
【1:馬の鈴のこと】新約時代において『馬の鈴の上には、「主への聖なるもの」と刻まれ』るようになった。これが何を意味しているのか分からないと感じる人は多いはずである。これは律法の定めを知らねばならない。律法では、祭司であるアロンの衣装に『鈴』が付けられねばならないと命じられている(出エジプト28:33~35)。またアロンは、『主への聖なるもの』と彫られた札を、その被り物に付けておかねばならなかった(出エジプト28:36~38)。このような祭司の定めが、ここでは馬にも適用されている。旧約時代において馬にこのような鈴を付けるのは有りえないこと、絶対にしてはならないことであった。一般のユダヤ人でさえ、そのような大それたことをすべきではなかったからである。しかし、新約時代にはそのようなことが起こるようになる。これは何を意味しているのか。答えは一つ、新約時代には全ての聖徒がアロンのような祭司となるということである。この箇所では、新約時代において馬がアロンのような祭司になると言っているのではない。ここでは単に記述上においてだけ馬に祭司の定めが適用されると示すことにより、新約時代には全ての聖徒たちがアロンのようになると教えているのである。何故なら、馬でさえ祭司のようになると言われているからだ。馬という理性のない動物さえも祭司になれるのであれば、祭司になれない聖徒が誰かいるのであろうか。一人もいないはずである。もしいたとすれば、その人は馬以下の存在だということになる。実際、新約聖書では聖徒が全て祭司であると教えられている(黙示録1:5~6、Ⅰペテロ2:9)。今やもう我々はアロンのような祭司なのである。我々新約時代の聖徒たちは、旧約時代で言えば『主への聖なるもの』と刻まれた札や鈴を付けているアロンのような祭司なのである。
【2:鍋のこと】新約時代において『主の宮の中のなべは、祭壇の前の鉢のようにな』った。これは新約時代において、旧約時代に宮で仕えていた祭司たちは更に主の前に近づけるようになる、という意味である。何故なら、鉢は鍋よりも祭壇の場所に近いからである。また新約時代において『エルサレムとユダのすべてのなべは、万軍の主への聖なるものとな』った。これは、ユダヤ中にあった鍋が俗用から儀式用へと聖別されるということである。つまり、これは新約時代において旧約時代では俗人であった聖徒たちが祭司として聖別されるようになる、という意味である。また、その時に『いけにえをささげる者はみな来て、その中から取り、それで煮るようにな』った。これは新約時代において聖徒たちは、一人一人がそれぞれ宗教行為を自分から行なうようになるという意味である。何故なら、新約時代において聖徒たちは誰もが祭司だからである。祭司は自分から宗教行為を行なってもよいのである。旧約時代では、犠牲などの宗教行為をしたい場合、神殿にいる祭司の所まで行って、その宗教行為を代行してもらわねばならなかったのである。聖徒たちが一人一人自分から祭司としての行為をするというのは、旧約時代からすれば驚くべきことであった。
【3:神殿の商人のこと】旧約時代では、神殿の中に犠牲用の動物を売る商人たちがいた。キリストにより神殿から追い払われたのが、この商人たちである(ヨハネ2:13~16)。旧約時代のユダヤ人は、その時に動物を持っていなかったならば、この商人たちから動物を買い、それを祭司に渡して犠牲行為をしていたわけである。だが、新約時代において『万軍の主の宮にはもう商人がいなくな』った。何故なら、新約時代にはキリストが御自身という永遠の犠牲を父なる神に捧げて下さっておられるからである。だから、聖徒たちはもはや神殿にいる商人から犠牲用の動物を買って祭司に渡す必要がない。もし新約時代になってもそのようにして商人から犠牲用の動物を買う人がいたとすれば、その人はキリストの実現された1回限りの永遠なる贖罪を真っ向から否定している。そのような人は絶対に罰を免れない。なお、ここで『商人』と言われているのは『カナン人』と訳すことも出来る。
第41章 39:マラキ書
マラキ書は、あまり心を傾けなかったとしても、そこまで大きな問題にはならないであろう。しかし、だからといって、この文書にまったく無頓着になってもいいかといえば、そうではない。この文書にも、幾らか見ておくべき箇所がある。本章では、その箇所について註解される。
【3:17~4:1】
『「彼らは、わたしのものとなる。―万軍の主は仰せられる。―わたしが事を行なう日に、わたしの宝となる。人が自分に仕える子をあわれむように、わたしは彼らをあわれむ。あなたがたは再び、正しい人と悪者、神に仕える者と仕えない者との違いを見るようになる。見よ。その日が来る。かまどのように燃えながら。その日、すべて高ぶる者、すべて悪を行なう者は、わらとなる。来ようとしているその日は、彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。―万軍の主は仰せられる。―』
ここでマラキが預言しているのは、ユダヤの終わる日についてである。マラキが活動したのは紀元前420年頃であり、ユダヤの終わりは紀元70年に起きたから、マラキは約500年後の時代について預言したことになる。これは神の御霊によられば絶対に出来ないことである。人間に過ぎない者が、どうしてそのようなことを出来るであろうか。マラキの預言は、その預言がバビロン捕囚の時のエルサレム崩壊なのか、それともユダヤ戦争の時のエルサレム崩壊なのか、という点を見極める必要がまったくない。何故なら、マラキはバビロン捕囚が完全に終わった時代に生まれた人だったから、バビロン捕囚の時のエルサレム崩壊について預言するはずがないからである。一方、エゼキエルはバビロン捕囚が起こる前にも後にも活動した預言者だったから、その預言がバビロン捕囚の時の悲惨なのかユダヤ戦争の時の悲惨なのか見極めねばならない、という難しさがそこにはある。マラキの預言で難しいのは、その預言がキリストの初臨について言われているのか、再臨について言われているのか、という点である。マラキの預言の幾つかは、初臨について言われているのか再臨について言われているのか、一見すると判断ができない。これから見ていく箇所は、初臨ではなく再臨について預言された部分として解き明かしをしていきたい。この部分は再臨についての記述だと理解すべきである。何故なら、これから見る部分は、再臨として捉えたほうがシックリするからである。
まずユダヤが終わる時、神に従う選ばれた者たちは、救われて永遠の安息に導き入れられ、神の子として永遠に神と共に歩むようになった。『彼らは、わたしのものとなる。―万軍の主は仰せられる。―わたしが事を行なう日に、わたしの宝となる。』と神が彼らについて言われた通りである。どうして彼らは神の子として永遠の安息を享受できるのであろうか。それは、『人が自分に仕える子をあわれむように、わたしは彼らをあわれむ。』からである。つまり、彼らはキリストにあって神に聞き従う従順な子らだから、彼らの父である神も、彼らを子として迎え入れて下さるのだ。自分に熱心に仕える子どもを憐れもうとしない親がどこにいるであろうか。なお、ここで彼らが神に仕える者たちだから神から憐れみを受けられると言われているからといって、聖書が行為義認を教えていると捉えてはならない。何故なら、神が選ばれた者たちを受け入れられるのは、彼らが神に仕えているというその行ないにおける功績が見られるからではなく、彼らがキリストにより救われて神に仕えることを喜びとする回心した状態となっているからである。パウロもエペソ2:9の箇所で言っているように、神に救われて受け容れられるようになるのは『行ないによるのではない』。行ないではなく信仰が人を救う、というのが聖書の教えである。それゆえ行為義認という異端の教理は、聖徒たちの心の中から永遠に遠ざかれ。
他方、神に選ばれていない邪悪な者どもは、ユダヤが終わる時に救われず、永遠の安息に導き入れられなかった。むしろ彼らは焼かれた。『その日、すべて高ぶる者、すべて悪を行なう者は、わらとなる。来ようとしているその日は、彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。』と彼らについて言われた通りである。しかし、どうして彼らは藁のように焼かれて滅ぼされたのか。それは、彼らが『高ぶる者』であり『悪を行なう者』だったからである。義なる神にとって、御自身に従わない不敬虔な者たちは、ただただ忌み嫌うべき存在に他ならない。そのような者どもが永遠の安息に導き入れられないのは何もおかしいことではない。それだから、彼らはユダヤの終わりが到来した時、全能者から次のように言われ御前から退けられてしまった。『わたしはあなたがたを全然知らない。不法をなす者ども。わたしから離れて行け。』(マタイ7章23節)神に従わない邪悪な者たちがユダヤの終わる時に火で焼き尽くされるというのは、バプテスマのヨハネも言ったことである。彼はマタイの福音書の中でこう言っている。『斧もすでに木の根元に置かれています。だから、良い実を結ばない木は、みな切り倒されて、火に投げ込まれます。…手に箕を持っておられ、ご自分の脱穀場をすみずみまできよめられます。…殻を消えない火で焼き尽くされます。』(3章10、12節)つまり、もう間もなくユダヤの終わりが来るので、悪を行なう実を結ばない者たちは速やかに裁かれて焼き尽くされてしまう、ということである。マラキは500年後における出来事について言ったが、バプテスマのヨハネはもう間もなくしたら起こる出来事について言った。実際、神に従わない悪者どもは紀元70年にユダヤが終わる際、木やその根また枝でもあるかのようにして焼殺されてしまった。ユダヤ戦争について書き残された記録を見れば分かる通りである。
この預言の中で、『見よ。その日が来る。』と言われている部分に注目すべきである。ペテロの場合、ユダヤ世界の終わりを預言する際、『万物の終わりが近づきました。』(Ⅰペテロ4:7)と言った。ペテロが『近づきました』と言ったのは、もう間もなくユダヤにおける万物の終わりが実現するからであった。しかし、我々が今見ているマラキの預言の中では、「近い」などとは言われていない。これは、マラキの預言が、マラキの時代には実現されなかったからである。それは約500年後の出来事だったから、ペテロのように「近づいている」などと言うことは出来なかったのである。またマラキの預言では、マラキの時代にいた人々が生き残っている間に預言の出来事が起こるなどとは言われていない。これは、マラキと同時代の人間が生きている間において、預言は実現されないからである。しかし、キリストとパウロは、その時にいた人々が生き残っている間に預言が実現されると言った(マタイ16:28、Ⅰテサロニケ4:15)。これは、本当にその預言が語られた当時の人間が存命中に、その預言が実現されるからであった。それだから、もしマラキの預言がマラキの時代に実現されるとすれば、マラキはその預言がすぐにも実現され、またそれはマラキと同時代の人が生きている間に実現されるなどと言っていたはずである。
ユダヤが終わる時には、神に選ばれた子らと見放された者どもの違いが明らかにされた。すなわち、選ばれていた者は滅びに定められていた者たちが捨てられてしまったのを見、捨てられた者たちは選ばれている者たちが救われているのを見た。だから、この箇所では次のように言われている。『あなたがたは再び、正しい人と悪者、神に仕える者と仕えない者との違いを見るようになる。』神の子らは全能者に受け入れられているのに、捨てられた者たちは火で焼き尽くされて永遠の滅びへと投げ込まれた。ここにおいて両者の違いが明確化するのだ。この正しい人と悪者の明確化については、イザヤも次のように言っている。『彼らは出て行って、わたしにそむいた者たちのしかばねを見る。そのうじは死なず、その火も消えず、それはすべての人に、忌みきらわれる。』(イザヤ66章24節)永遠の安息へと導き入れられた神の子らは刑罰を受けていないが、それとは違って悪者どもは刑罰を受けている。これは、あまりにも大きな『違い』である。
このマラキ以降、キリストの時代になるまで約400年の間、ユダヤの終末に関する預言は停止された。この400年間は、ユダヤ人にまったく預言が与えられなかった。つまり、マラキはキリストの時代になるまでの間における最後の預言者であった。マラキ以降、ユダヤ人に預言が語られなくなったのは、ユダヤに対する呪いである。何故なら、預言が無くなったということは、つまり神がお語りになられず沈黙の状態に入られたということを意味しているからである。我々人間が往々にして不満を持っている人に対して口を閉ざすように、神も罪を犯してばかりいたユダヤに口を閉ざされたのだ。確かに預言とは神の人間に対する「語り」である。アモスが、『神である主が語られる。だれが預言しないでいられよう。』(アモス3章8節)と言った通りである。マラキにおいて預言が止むようになってから暫くすると、ユダヤ人はハラハ―(口伝律法)に固執し始めるようになった(前300年頃)。周知のように、タルムードのミシュナにおけるハラハ―が規定化され始めたのは、だいたいこの頃である。はて、これは一体なにを意味しているのか。これは、預言の停止が神からの呪いであることを証明している。何故なら、ユダヤ人が神からの預言を失ったからこそ、ハラハ―という人間の教えを求めるようになったからである。これは例えるならば、美味しい食事を取り去られた人が、飢えを満たそうとして泥や葉っぱを食べるようなものである。もしマラキ以降も預言が続いていたとすれば、ユダヤ人がハラハ―に固執するようなことは恐らく無かったであろう。その場合、預言という美味しい食事があるのだから、どうして敢えて泥や葉っぱで飢えを満たす必要があるであろうか。
なお、ここで『わたしが事を行なう日』と言われているのは、黙示録16:17と21:6で『事は成就した。』と言われているのと対応している。これはどちらも同一のことを言っている。すなわち、『事』というのは「神の国を持っていた民族という意味におけるユダヤが終わる事」という意味である。ユダヤが神の御前から退けられて終わってしまう出来事こそ、正に『事』である。
【4:2】
『しかし、わたしの名を恐れるあなたがたには、義の太陽が上り、その翼には、癒しがある。』
ここで言われているのも、ユダヤが終わる時、神を恐れる選ばれた者たちは救われて永遠の安息へ入れられた、ということである。彼らは神を恐れて御子の救いを信じたのだから、神もそのような彼らを御自身のもとに受け入れられるのを拒まれないのだ。ソロモンは、『主を恐れることの報いは、…いのちである。』(箴言22章4節)と言っている。つまり、イエス・キリストを信じて神を恐れる存在となっている神の子たちには、あたかも報酬であるかのようにして永遠の生命が恵みにより与えられる。実際、ユダヤが終わる際に、神を恐れる聖徒たちは滅ぼされることなく神に受け入れられた。これは、神を恐れない者たちが携挙されず、救いから除外されたのとはまったく別である。それでは、ここで言われている『義の太陽が上り』とは、どういう意味か。『義の太陽』はイエス・キリストを意味している。『上り』とは、義なる太陽であるキリストが再臨されることを言っている。すなわち、ここではキリストが輝かしい光をもって再臨により現われる出来事を、太陽が東のほうから現われる夜明けの出来事になぞらえている。この時に選ばれていた者たちの究極的な救いが実現されたというのは、既に説明されている通りである。『その翼には、癒しがある。』とは、どういう意味か。これは、神がイスラエルをその御翼に乗せて助け出され、彼らに大いなる救いをお与えになったことを考えてみればよい(出エジプト19:4)。つまり、この部分では、聖徒たちが神の御翼によって地上から助け出され、イスラエルがエジプトから移動させられたように天上へと移動させられて癒された、ということが言われている。要するに、これは携挙の時の贖いである。これを、聖徒たちが神の御翼に乗せられて上に引き上げられると捉えるのではなく、聖徒たちが携挙する際に『鷲のように翼をかって上る』(イザヤ40章31節)ことであると捉えるのも可能である。だが、私としては、これは聖徒たちにおける翼ではなく、神における御翼について言われていると捉えるほうがより正しいように思われる。
『あなたがたは外に出て、牛舎の子牛のようにはね回る。』
『あなたがたは外に出て』と書かれている。これは一体どういう意味か。これは、聖徒たちが汚らわしい邪悪な者どものいる世界から出る、という意味である。何故なら、聖書の他の箇所では、どこから外に出るのか明白に書き記されているからである。Ⅱコリント6:17の箇所ではこう書かれている。『それゆえ、彼らの中から出て行き、彼らと分離せよ、と主は言われる。汚れたものに触れないようにせよ。』これは、汚らわしい者から離れるという意味である。イザヤ52:11の箇所でもこう書かれている。『去れよ。去れよ。そこを出よ。汚れたものに触れてはならない。その中から出て、身をきよめよ。主の器をになう者たち。』これも、汚れた者たちの世界から出なさい、という意味である。つまり、この箇所で『外に出て』と言われているのは、ユダヤの終わりに携挙が起きた際、聖徒たちが汚らわしい者たちの住むこの地上世界から出るということを言っている。すなわち、これは地上から地上への移動ではなく、地上から天上への移動のことである。イザヤ66:24の箇所で、『彼らは出て行って、わたしにそむいた者たちのしかばねを見る。』と言われたのも、どこから出て行くのか明示されてはいないが、たった今述べたような意味において出ることを言っている。つまりイザヤが言ったのは、選ばれていた聖徒たちがこの地上から出て行って天国に至り、その天国から地獄に落ちた『そむいた者たちのしかばね』を軽蔑しつつ眺める、ということであった。このすぐ後で『それはすべての人に、忌みきらわれる。』と書かれているように、天国へと出て行った『すべての』聖徒たちは、地獄に落ちた者たちを憎悪しつつ見下すのである。
『牛舎の子牛のようにはね回る。』とは、つまり天国へと出て行った聖徒たちが、その天国で味わう大きな喜びを示している。天国に行った彼らは、あたかも跳ね回る子牛のように幸せそうなのである。天国がそのような場所であるというのは、聖書全体が教えていることだ。そこにおいて聖徒たちは、キリストおよび他の多くの聖徒たちと永遠に共に住まうようになるのだ。誰がこのような状態を子牛のように喜ばないであろうか。ダビデもこのような聖なる者たちの楽園について次のように言っている。『見よ。兄弟たちが一つになって共に住むことは、なんというしあわせ、なんという楽しさであろう。』(詩篇133:1)そこにはもう悪しき者どもがおらず、それゆえ彼らに悩まされることもない。また、そこには『もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。』(黙示録21章4節)これでは、そこにいる聖徒たちが『牛舎の子牛のようにはね回』るようになるのは自然なことである。
【4:3】
『あなたがたはまた、悪者どもを踏みつける。彼らは、わたしが事を行なう日に、あなたがたの足の下で灰となるからだ。―万軍の主は仰せられる。―』
神が『事を行なう日』すなわち神の国を持つ存在としてのユダヤが御前から退けられて滅ぼされる時、選ばれていた聖徒たちは上に引き上げられ、自分の足の下にいる悪者どもを踏みつけた。これは、つまり携挙された選ばれし者たちが上の場所で栄光に輝いているのに対し、彼らの足の下にいた不敬虔なユダヤ人たちは焼き尽くされて灰となった、ということである。実際、歴史が示す通り、エルサレムにいたユダヤ人たちは燃える炎で殺されて灰となった。
神が、このように言われたのは、御自身の聖徒たちがより敬虔になれるためであった。何故なら、このような約束を聞かされたら、より神に聞き従う姿勢が養われるようになるのは明らかだからである。これから悪者どもを足の下に踏み置けると言われながら、それを望まない者が果たしているであろうか。まともな聖徒であれば、誰でもそれを望むであろう。それを望むのであれば、その望みを実現させて下さる神に対して、よりよく仕えるようにもなる。であるから、神がこのような約束をあらかじめ聖徒たちに聞かせたのは、聖徒たちにとって大きな益であった。
第42章 40:マタイの福音書
4つの福音書は、どれも研究する必要がある。これらの文書を無視することはできない。何故なら、福音書では、再臨のことが大いに語られているからである。特に、マタイ24章、ルカ21章、マルコ13章は、絶対に研究せねばならない。では、この4つの福音書のうち、最も研究する必要性の高い文書はどれであるか。これには答えられない。というのも、4つの福音書は、どれも等しく研究されるべき文書だからである。
【4:17】
『悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。』
キリストは宣教を開始された際、人々に『悔い改めなさい。』と言われることから始められた。それは何故か。『天の御国が近づいたから』である。この『天の御国』は、マタイ16:28の箇所からも分かるように、当時の人々が生き残っている間に、再臨と共にやって来ることになっていた。それは数十年後の出来事であった。つまり、キリストはもう天国がすぐにも開始されることになるのだから、そこに入れるように悔い改めなさい、とこの箇所で言われたのだ。我々は、このことをよく考えるべきである。キリストは、天国がすぐにも始まるからこそ、このように悔い改めを命じられた。何故なら、天国が開始されるまでに悔い改めないと、数十年後に再臨が起きた際、天国に入れなくなってしまうからである。そうなれば、再臨の際に携挙されないで地上に残され、最後には地獄に行くことになってしまう。これは大変に悲惨なことである。キリストは一人でも多くの人が悔い改めて、御自身が再臨される時、天国に入れるようになるのを望んでおられた。だからこそ、ここで人々が悔い改めて天国に入れるようにと言われたのである。これは、例えるならば、もう5年もすればエルビス・プレスリーとチャック・ベリーとバディ・ホリーとボ・ディドリーとビル・ヘイリーとジェリー・リー・ルイスとリトル・リチャードが合同コンサートでやって来るから売り切れないうちにチケットを買うべきだ、とロックンロールの愛好者に言うようなものである。このコンサートにはジョン・レノンもゲストとして参加する。チケットを買えた人はこの豪華なコンサートに行けるが、買えなかった人はコンサートに行けない。我々が今見ている箇所で言われているのも同じである。悔い改めた者は数十年後にやって来る天国に再臨が起きた際、入ることが出来たが、悔い改めなかった者は天国に入場できなかった。
ここで言われている『御国』とは、天国のことであって、神が支配されるキリスト者という王国のことではない。というのも、神の支配王国としての意味であれば、それは既にモーセの頃からユダヤ人の中にあったからである(出エジプト19:6)。モーセ率いるイスラエルのうちに神の御国があったことを疑う人はいないはずである。しかし、この箇所ではまだ御国が到来していないものとして語られているから、そのような意味において『御国』と言われているのではない。この『御国』という言葉に2種類の意味があるということについては、後ほど、また論じられる。
【5:3】
『心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。』
ここでは『心の貧しい者』とその者が『幸い』である理由について取り扱うことをしない。それについては他の人の註解書を読めばよい。私がここで取り扱うのは、心の貧しい人の持つ『天の御国』についてである。何故なら、再臨を理解するにあたり、これは知っておかねばならないことだからである。
さて、ここで言われている『天の御国』とはどのような意味か。これは場所としての天国なのか、それとも聖徒たちのうちにある神の支配のことなのか。これは、どちらにも捉え得る。もし天国として捉えるならば、ここでは心の貧しい人がこの世では救われて天国に入れるようになる、と言われていることになる。これは聖書が教えていることである。もし神の支配として捉えるならば、ここでは心の貧しい人こそが救われて神の支配に導き入れられる、と言われていることになる。これも聖書が教えていることである。読者は各自、好きなほうの立場に立つとよい。私はどちらの立場をも否定しない。その私はと言えば、これはどちらにも捉え得るのだから、別にどちらの捉え方でもよいと思っている。
【5:5】
『柔和な者は幸いです。その人は地を相続するからです。』
この箇所も先の箇所と同様、『柔和な者』とその者が『幸い』である理由については取り扱わない。ここで見ておくのは『地を相続する』という部分である。何故なら、これは再臨を理解するためには、是非とも知っておくべき部分だからである。
さて、柔和な者が『地を相続する』とは一体どういう意味なのか。この『地』とは何なのか。これは地球の全土のことである。つまり、ここでは神に従う柔和な者は祝福されるので絶やされたり散らされたりすることもなく地を所有し続けられる、と教えられているのだ。これは律法が示している通りである。要するに、ここではごく一般的なことが言われている。しかしながら、この箇所では、今は天にいる聖徒たちやこれから天に引き上げられる聖徒たちがやがて地上に降りて来て、この地球全土を相続するようになり、祝福に満ちた世界が地球上に展開される、と教えられているなどと考える読者は少なくないはずだ。だが、それは再臨未成就説の考えだから、誤っている。聖書の多くの箇所で明白に教えられているように、我々の祖国また国籍は「天」であって、我々はこの地上ではなく天国に永遠までも住まうのだからである。また、読者の中には、この『地』が天国を指していると理解する人もいるかもしれない。このように理解できる人は、よく聖書を学んでいる。天国を「地」と言い表すのは間違っていない。だから、ここでは柔和な者が天国という地を相続することについて言われている、と捉えるのも可能である。何故なら、確かに聖徒たちは天国にある地を永遠に相続するのだから。このように捉える人は、そのように捉えていればよい。私は何も否定しない。
聖徒たちが地を相続するということについては、詩篇でも多く言われている。例えば次に示す箇所がそうである。『しかし、主を待ち望む者、彼らは地を受け継ごう。』(37:9)『しかし、貧しい人は地を受け継ごう。』(37:11)『正しい者は地を受け継ごう。そして、そこにいつまでも住みつこう。』(37:29)キリストは、このマタイ5:5の箇所を、御自身の御霊により書かれた詩篇に基づいてお語りになったに違いないと私は思う。というのも、キリストがここで言われたことは、詩篇の御言葉と内容的に一致しているからである。
【5:10】
『義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。』
この箇所では、どういうことが言われているのか。先に見た5:3の箇所と同じで『天の御国はその人のものだからです。』と言われているが、5:3の箇所と言われているのは同じなのか。それとも違うのか。まず、ここで『義』と言われているのは、イエス・キリストを信じることにより与えられる神からの義である。つまり、キリストを信じるならば、その信仰が神から義と見做される、ということである。創世記15:6の箇所で『彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。』と書かれている通りである。この義は、世の人も持っている一般的な義ではない。例えば、徳の行ないとか正義に適った判断のことではない。そのような義であれば、ほとんど全ての人が、多かれ少なかれ持っている。だが、ここで言われているのは信仰者のことである。要するに、これは救いにおける義のことである。この箇所では、キリストを信じて義と認められた者について取り扱われている。そのような者たちはキリスト信仰における義のゆえに迫害されるような存在であるが、『天の御国』が与えられるとキリストは言っておられる。この『天の御国』という言葉が問題である。これは一体何を意味しているのか。これは続く5:11~12の箇所を見るならば、天国のことであると分かる。つまり、この箇所でキリストはこう教えておられることになる。「信仰を持つ義人たちは迫害されるような存在であるが、彼らには天国が約束されている。」それだから、この『天の御国』とは別の世界にある<場所>のことである。これは聖徒たちに敷かれる神の支配という意味における「天の御国」のことではない。文脈を考慮すれば、このように考えざるを得ない。
【6:10】
『御国が来ますように。』
この『御国』という言葉を「天国」として捉えるのであれば、それは既に来ている。それが来たのは再臨の時、すなわち紀元1世紀であった。つまり、もうこの祈りは、天国の到来として捉えるのであれば、既に叶えられている。そのことは、マタイ16:28の箇所を見れば分かる。そこでは、キリストが再臨すると共に御国も到来すると言われている。我々は、キリストの再臨が起きた際には天国が天上において正式に開始されたということを忘れるべきではない。
このように『御国』を天国として捉えるとすれば、もはや、この祈りを唱える必要はない。何故なら、この祈りは既に叶えられており、天国は始まっているからだ。既に叶えられた祈りを、どうして未だに叶えられていないかのように祈る必要があるであろうか。私がこう言うのを聞いて、驚く者があってはならない。何故なら、私は異常なことは何も言っていないからである。思考を眠らせずシッカリと考察するならば、私が合理的な論述をしていることが誰でも分かるはずである。むしろ、問題視されねばならないのは、今の聖徒たちのほうである。もし主がこう祈れと言われたからといって問答無用にこう祈らねばならないとすれば、どうしてマタイ24章の中で祈れと言われた祈りについて、今の聖徒たちは問答無用に祈っていないのであろうか。キリストはマタイ24章の中で、聖徒たちに『ただ、あなたがたの逃げるのが、冬や安息日にならぬよう祈りなさい。』(24章20節)と命じられた。このような祈りを捧げている教会や聖徒たちは、全く見られない。私は、こう祈っている教会や聖徒たちを、今まで見たことがない。今の聖徒たちは、どうして主がマタイ24章の中で祈れと聖徒たちに言われた祈りをシッカリと祈っていないのか説明していただきたい。主が祈れと言われたのだから、シッカリと次のように祈らねばならないのではないのか。「どうか私たちの逃げるのが冬や主の日にならないように憐れんで働きかけて下さい。」などと。マタイ24章の出来事がこれからすぐにも実現されると信じているのであれば、もしくは今が正にマタイ24章の時代であると考えているのであれば、どうしてこのように心から祈らないのか。まさか、実はマタイ24章の出来事がこれから実現されるなどとは思っていない、ということではあるまい。あなたが教団に属しているのであれば、その教団に属する教会が一緒になってこの祈りを捧げるべきであろう。何故なら、これからマタイ24章の出来事が起こるのであれば、マタイ24章に書かれている悲惨な出来事を回避できなくなると困ってしまうだろうから。しかし、私がこう言っても、恐らく真面目にこの祈りを唱える教会や聖徒はあまりいないと思われる。何故なら、今までの教会の歴史を見れば、このように祈っても徒労に終わるだろうことを推察するだろうからである。この祈りを捧げていないほうこそ、問題である。何故なら、マタイ24章がこれから起こると本気で考えているのに、このマタイ24章の中で祈れと言われた祈りについては祈っていないからである。他方、私がこの祈りは天国の到来を祈るというのであれば最早祈らなくてもよいと言っているのは、何も問題がない。何故なら、私がこう言っているのには、合理的な説明がシッカリとされているからだ。
しかしながら、この『御国』を神がキリスト者たちを祭司の王国として支配されるという意味として捉えるのであれば、今も祈る必要がある。何故なら、そのように祈るのであれば、何も問題ないからである。その場合、この『御国が来ますように。』という祈りは、「神がキリスト者という御自身の支配領域を全地に満ち広げて下さいますように。」という意味となる。簡単に言えば、クリスチャンが全世界において日に日に増え広がるようにということである。ルターは、この意味において『御国が来ますように。』と祈っていた。私もこの意味においてであれば、いつも『御国が来ますように。』と主が命じられた通りに祈っている。
【6:33】
『神の国とその義とをまず第一に求めなさい。』
この聖句は、最近のプロテスタント界において、最も引用されることの多い聖句の一つである。私は今まで、この聖句を引用している教師や一般の聖徒たちを多く見てきた。聖公会の信徒であった自動車王のフォードも、この聖句を引用している。しかし、古代や中世の時代においては、今ほどにこの聖句が引用されることはなかった。
ここでキリストが命じておられるのは、天国と天国に住む者として相応しい義の生き方を何よりも第一に求めなさい、ということである。『神の国』とは、紀元70年9月に開始された天上における神の支配される王国を言っている。つまり、一般的に「天国」と言われる場所である。聖徒たちは、この天国に入れるようになるために、全てを犠牲に出来なければならない。何故なら、そのように出来なかったならば、天国に入れないで地獄へと落とされることになるからである。イスカリオテのユダはどうであったか。彼は神の国を第一に求めず、金を第一に求めたので、地獄へと投げ落とされてしまった。『その義』とは、天国に入る者として持つべき義なる歩みのことを言っている。聖徒たちが不義の歩みをすることがあってはならない。何故なら、不義の歩みをする不敬虔な者たちは、決して天国に入れないからである。それはヨハネが『御子に聞き従わない者は、いのちを見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。』(ヨハネ3章36節)と言い、パウロが『正しくない者は神の国を相続できない』(Ⅰコリント6章9節)と言い、キリストが『不法をなす者ども。わたしから離れて行け。』(マタイ7章23節)と言われた通りである。アナニヤとその妻はどうであったか。この夫婦は、神の義を求めず不義を傲慢にも行なったので、たちまち死んでしまい、永遠の地獄に落ちて行った(使徒行伝5:1~11)。とはいっても、もちろん聖書が行為義認を説いているのではないということには、よくよく注意せねばならない。聖書の中で不義の歩みをしていれば天国には入れないと言われているからといって、それは行ないによる救いを教えたものではない。パウロも言うように救いは『行ないによるのではない。』(エペソ2章9節)聖書が教えているのは、明らかに行為義認ではなく信仰義認である。
この箇所で『神の国』と言われているのは、聖徒の中にある神の支配としての王国という意味ではない。そのように解すると、意味が分かりにくくなるからだ。しかし、これを天国として解すると、すんなりと意味が分かるようになる。これが天国という意味における『神の国』であるというのは、ルカ12:31~34の箇所を見れば明らかである。そこで言われているのは、明らかに天国のことである。すなわちキリストはその箇所で、神の国を求める聖徒たちにはやがてそれが与えられるであろう、と言っておられる。これは間違いなく天国という意味以外ではないのだ。それだから、このルカの箇所と対応しているマタイ6:33の箇所で言われているのも天国についてであるということになる。
我々も、神の国を第一に求めなければならない。確かなところ、そのようにする人生こそが、最も幸いな人生である。「しかし、そうはいってもそのようにしたら日々の生活に困ることにはならないのか。」などと言われるであろうか。このように言う人に対し、キリストはこう言っておられる。『そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、などと言って心配するのはやめなさい。こういうものはみな、異邦人が切に求めているものなのです。』(マタイ6章31~32節)神の国を第一に求めていれば、必要は全て備えられることであろう。次のキリストの御言葉は真実である。『そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。』(マタイ6章33節)それゆえ、神の国を求めるならば日々における雑多な心配は不要となる。キリストはこう言っておられる。『だから、あすのための心配は無用です。あすのことはあすが心配します。労苦はその日その日に、十分あります。』(マタイ6章34節)そのようにして神の国を求める聖徒たちは、やがて天上に導き入れられて永遠の至福を享受するようになるのだ。その時、彼らには次の御言葉が実現されることになる。『もはや、死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。』(黙示録21章4節)要するに、キリストの御言葉の通りに神の国を第一に求める聖徒たちは、本当に幸いな恵みを神から受けていることになる。人間の心が何と思おうとも、これが聖書的に言えば最も良い人生なのである。
【8:11~12】
『あなたがたに言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国で、アブラハム、イサク、ヤコブといっしょに食卓に着きます。しかし、御国の子らは外の暗やみに放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。』
この箇所は、ルカ13:28~30の箇所と同じ内容である。二つとも註解してもあまり意味がない。ルカの箇所のほうが前後に見るべき聖句が書かれているから、ルカのほうを註解するのが好ましい。よって、このマタイ8:11~12の箇所は、後に書かれるルカの註解の場所で学んでいただきたい。この箇所では、ルカの箇所との相違点を述べるに留める。
ルカ13:28~30の箇所との相違点は以下の通りである。①:ルカのほうでは東西南北全ての方角が言われているが、マタイのほうでは東と西の方角しか言われていない。これは些細な違いである。②:マタイのほうではアブラハムとイサクとヤコブの名しか出て来ないが、ルカのほうでは『すべての預言者たち』も加えられている。これも些細な違いである。③:ルカのほうには『今しんがりの者があとで先頭になり、…』(13:30)という文章が書かれているが、マタイのほうでは書かれていない。つまりルカのほうが内容が豊かなのだが、しかし言われていることはどちらも一緒である。④:聖なる救いが、ルカのほうでは『神の国』と、マタイのほうでは『天の御国』と言い表されている。これは言葉の言い方が違うだけであって、どちらも内容的には同一の意味である。⑤:マタイのほうでは『御国の子ら』という言葉が見られるが、ルカのほうでは見られない。これは、もちろんユダヤ人のことを言っている。⑥:ルカのほうでは『外』と言われているが、マタイのほうでは『外の暗やみ』と言われている。マタイのほうが恐怖を起こさせる言い方だが、言われていることはどちらも一緒である。⑦:ルカのほうでは女がサタンから解放されて後に御国の事柄が語られているが、マタイのほうでは百人隊長とのやり取りの中で語られている。聖書に偽りや矛盾は一つもないが、2つの箇所におけるこの記述上の違いについては、ここで謎解くことをしない。それというのも、今は再臨に関わる事柄に注目しているのであって、福音書の話について専門的な詳細を語っているわけではないからである。
【10:23】
『彼らがこの町であなたがたを迫害するなら、次の町にのがれなさい。というわけは、確かなことをあなたがたに告げるのですが、人の子が来るときまでに、あなたがたは決してイスラエルの町々を巡り尽くせないからです。』
この箇所は、聖書の中で、もっとも理解するのが難しい箇所の一つである。私は、今までに、この箇所を正しく解釈している人を見たことがない。
まず、『人の子が来るとき』とは再臨のことである。何故なら、これは再臨としてしか捉えられないからだ。これを再臨ではない出来事として捉えるのは難しい。この言葉が、復活後にキリストが多くの聖徒たちの前に現われることだと捉える人が、もしかしたら読者の中にはいるかもしれない。しかし、そのように捉えるのは誤っている。聖書において、『人の子が来る』とキリストが言われたのは、どれも再臨についてのことである。実際にキリストの御言葉を見てみるがよい。例えば、マタイ16:28やマタイ26:64やヨハネ21:22が、そうである。これらの箇所で言われているのは、どれもキリストの再臨のことである。この箇所でも再臨のことが言われている。もっとも、この箇所で言われているのが復活後の現われであるなどと捉える人は、ほとんどいないとは思うが。
この箇所でキリストは、再臨が起こるまでは聖徒たちが『イスラエルの町々を巡り尽くせない』と言っておられる。これは深く考察されねばならない。これまで述べてきたように、再臨が起こるのは紀元68年6月9日であった。我々が今見ている10:23の箇所でキリストがお語りになられたのは、だいたい紀元33年頃である。つまり、キリストがお語りになってから再臨までの期間は、残り35年。35年ぐらいであれば、『イスラエルの町々』を巡り尽くすことが出来たのは間違いない。何故なら、また後ほど詳しく見ることになるが、パウロは自分がまだ生きている時に既に福音は世界中で実を結び広がり続けていると述べたからである(コロサイ1:6)。マルコも、キリストが昇天された後で、聖徒たちが『至る所で福音を宣べ伝えた』(マルコ16章20節)と書いており、その福音は『東の果てから、西の果てまで送り届けられた』(マルコの福音書/別の追加文)のである。使徒の時代に既に福音が全世界に満ち広げられていたのであれば、当時の聖徒たちは世界中に伝道に行ったわけだから、ユダヤの町々を聖徒たちが満遍なく行き巡ることが出来たのは明らかである。世界中にさえ伝道に行ったのに、ユダヤという一つの地域、しかも非常に近い地域を満遍なく巡り尽くせなかったというのは考えにくい。キリスト御自身が、聖徒たちは『ユダヤ、エルサレム…の全土』にまで『わたしの証人となります』(使徒行伝1章8節)と言われた。であれば、やはりイスラエルの町々が再臨よりも前の段階において行き巡らされていたのは間違いないことである。つまり、キリストがここで言われたことは文字通りに捉えるべきではない。もし文字通りに捉えると、キリストが偽りを言われたことになるし、他の聖句箇所で言われている内容と矛盾してしまうからだ。とはいっても、キリストが文字通りには捉えるべきでない内容のことを言われるのは、別に珍しいことではない。例えば、『誓ってはならない。』と言われたことや、『裁いてはならない。』と言われたのが、そうである。この命令が文字通りに受け取られるべきではないということは、カルヴァンやルターやその他の教師たちも、これまでに述べてきたことだ。このように、キリストの御言葉には、普通に理解すべきではないものが多くある。それだから、この箇所でキリストが文字通りには捉えるべきでない内容のことを言っていると理解したとしても、何も問題にはならない。
それでは、ここでキリストは一体どういったことを言われたのか。キリストがこう言われた理由は2つある。まず一つ目は、いかに再臨がすぐに起こるのか聖徒たちに教えるためであった。黙示録でキリストが『わたしは、すぐに来る。』と言っておられるように、キリストは本当にすぐに再臨された。その再臨における迅速性が、ここでは示されている。これは、つまり「再臨は弟子たちがイスラエルの町々を巡り尽くせない間に起こるとさえ言えるほどに速やかに起こるのだ。」ということである。これは、あくまでも表現上の例えであるから、実際は再臨が起こる前にイスラエルの町々を万遍なく巡り尽くすことが出来た。二つ目は、聖徒たちを怠惰にさせないためである。主は、聖徒たちが福音伝道を一生懸命に行なうのを望んでおられる。『万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。』(イザヤ9章7節)と言われている主は、御自身の似姿として造られた人間である聖徒たちが、御自身と同じように聖なる事柄において『熱心』であるのを求められる。だからこそ、ここでは、このように言われた。何故なら、再臨がイスラエルの町々を行き尽くすよりも前に起こるなどと聞かされたら、聖徒たちが良い意味で急かされて熱心になるのは明らかだからである。ここでのキリストの御言葉は、例えるならば、親が小さな子どもに対して「早く寝ないと大人になれないよ。」などと言うようなものである。別に早く寝なかったとしても大人になれるのは確かである。しかし、このように言うことで子どもが早く寝るようになるから、親は子どもにこう言う。実際、こう言われた子どもの多くは、まだ人間に関する知識が浅いので、親の言ったことを本当だと思って早く寝るはずである。このように実際とは違うことを言った親は、罪を犯したのではない。つまり、偽りを言うという悪を行なったわけではない。何故なら、親がこう言ったのは愛から出ているからだ。同様に、キリストが聖徒たちに、このように実際とは違うことを言われたのも罪ではない。つまり、キリストは偽りの言葉を口から出されたわけではない。何故なら、キリストがこう言われたのは神と人への愛から出ているからだ。すなわち、キリストがこう言われたのは、急かされた聖徒たちにより福音が迅速に広められることで多くの人が聖なる救いを聞けるようになるためであり、その福音伝道により救われた人たちを通して神の恵みの栄光が豊かに褒めたたえられるようになるためであった(エペソ1:6)。それだから、ここでキリストがこのように実際とは異なることを言われたからといって、我々は問題視してはならない。もしこのキリストの御言葉を問題視するのであれば、子どもに対して実際とは違ったことを言う親たちの教育的な発言も問題視しなければいけなくなるであろう。しかし、いったい誰がそんなことを問題視するであろうか。
今の聖徒たちは、この箇所を絶対に正しく理解することができない。何故なら、今の聖徒たちは、再臨が2千年経過しても未だに起きていないと思い違いをしているからだ。2千年またはそれ以上の年月があれば、余裕で『イスラエルの町々を巡り尽くせ』るのは、10歳の小さな子どもでも分かる。2千年どころか、200年もあれば十分である。いや、200年でも多すぎるかもしれない。ここでキリストは再臨が起こるまで聖徒たちがイスラエルの町々を巡り尽くせないと言っておられる。ここにおいて、2千年経過しても再臨が起きていないと理解している今の聖徒たちは、いったい何が言われているのかまったく分からなくなってしまう。つまり、次のように思わざるを得なくさせられる。「2千年もあればイスラエルの町々を巡り尽くすことは簡単に出来るはずなのに、どうして主はここで再臨が起こるまでそのようなことは出来ないと言われたのだろうか。」それゆえ、今の聖徒たちは、この箇所の正しい理解を諦める以外にはない。この箇所は、再臨が本当にすぐに起こるという前提で臨んで初めて上手に理解できるようになるからだ。
【13:37】
『イエスは答えてこう言われた。』
キリストは、毒麦の例えが理解できなかった弟子たちに、その例えの意味が分かるようにと一つ一つ詳しく説明してくださった。すなわち、弟子たちが例えの意味について説明を求めると、主は弟子たちに対してその答えを知らせて下さった。その答えが、これから見ていく13:37~50の箇所で書き記されている。神は、『求めなさい。そうすれば与えられます。』と言われた。この言葉の通り、確かに神は求める者たちには必ずお与えになられる御方である。それは教えについても例外ではない。すなわち、神は聖徒たちが聖書の教えについて求めるならば、必ずその求めに応じて下さる。この13:37~50の箇所にその実例があるのだ。それだから、聖徒である我々は聖書の中で分からないことがあれば、神に尋ね、謙遜になって答えを求めなければならない。そうすれば必ずや解が恵みにより与えられることであろう。
【13:37~39】
『「良い種を蒔く者は人の子です。畑はこの世界のことで、良い種とは御国の子どもたち、毒麦とは悪い者の子どもたちのことです。毒麦を蒔いた敵は悪魔であり、収穫とはこの世の終わりのことです。そして、刈り手とは御使いたちのことです。』
キリストは、この箇所で、ユダヤの終わりの時について預言しておられる。ここでキリストが『この世の終わり』と言っておられるのを、文字通りの意味として捉えてはならない。これは、ユダヤ世界について言われたものとして捉えるべきである。何故なら、マタイ24章の中ではエルサレム神殿の崩壊する時が正に『世の終わり』(24章3節)だと示されているからである。これは紀元70年におけるユダヤ世界の終焉のことでなくて何であろうか。これが理解できない人は、マタイ24章の箇所を、特に冒頭の3節分を、理解できるようになるまで何度でも繰り返し読むべきである。この『世の終わり』を紀元70年のユダヤ崩壊のこととして捉えると、聖書の他の箇所と上手に調和することが分かる。それだから、これはユダヤについて言われた言葉として解されなければならない。
キリストはまた、ここでユダヤが終わる際には『収穫』が行なわれると預言された。これは、つまり携挙のことである。人々が携挙されるのは地上から抜き去られて上のほうへと引き上げられる出来事だから、農作物の収穫に例えられる。農作物も、地上から抜き去られて上のほうへと引き上げられるからだ。
『良い種』とは、キリストが言っておられるように『御国の子どもたち』すなわち永遠の昔から救われるようにと選ばれていたキリスト者のことである。テモテやテトスやピレモンやオネシモがそうである。彼らは正しい人たちだから、正しい麦を生じさせる『良い種』に例えられる。この種を蒔かれたのは『人の子』であるキリストであった。キリストが、ある人に信仰を与えて救いが実現されると、その人は麦として教会に加えられる。つまり、キリストが良い麦を生じさせる良い種を蒔かれることで、教会の中には麦が増えていくわけである。すなわち、誰かが救われて教会の一員になるというのは、キリストが教会に良い種を蒔かれて良い麦を生じさせて下さるということなのだ。
『毒麦』とは偽キリスト者のことである。これは、つまり、教会に籍を置いておりキリスト者だと見做されているのだが、実は神の御前において救われていない滅びの子、サタンの弟子のことである。使徒のユダが、このような者に該当する。ユダは誰からもキリストの弟子だと見做されていたのだが、実はそうではなく、サタンの子どもなのであった。このような『毒麦を蒔いた敵は悪魔であ』るとキリストは言っておられる。サタンが教会の中に毒麦を蒔くと、教会にはキリスト者ならぬキリスト者が現れ出るようになる。サタンは毒麦を実に巧妙に投下するので、周りの人たちはその人が毒麦であることにしばしば気付けない。ユダも毒麦であるのに周りの人から何も気づかれなかった。使徒たちもユダの正体を全く見抜けなかった。それどころか、毒麦である本人さえも、自分が毒麦であることに気付けていない場合も多い。彼らは多くの場合、自分も真のキリスト者だと信じて疑わない。それだから、このような毒麦たちはキリストの御前に出た際、自分がキリストに属する存在だと思い込んでいたので『主よ、主よ。私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名におって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行なったではありませんか。』(マタイ7章22節)などとキリストに向かってあたかも自分がキリストの真の弟子なのだと言わんばかりに言ったのである。しかし彼らは実際、キリスト者ではなかった。だからキリストは彼らに対して次のような言葉を返された。『わたしはあなたがたを全然知らない。不法をなす者ども。わたしから離れて行け。』(マタイ7章23節)
『収穫』すなわち携挙を行なうのは、『刈り手』である御使いたちであった。すなわち、携挙された人々は、自然に身体が引き上げられたというのではなかった。そうではなく御使いに持ち上げられたからこそ、上の場所へと移動させられたのである。これについては、後ほど見る13:41~42の箇所でも書かれている。
この携挙の出来事が未だに起きていないなどと考えてはならない。もし『世の終わり』という言葉を文字通りの意味として捉えるべきだとすれば、携挙は未だに起きていないと考えるべきであった。何故なら、携挙とは世の終わりの時に起こる出来事なのだから。しかし、既に述べたように『世の終わり』とは紀元70年に起きたユダヤ世界の終焉を意味する。それだから、ユダヤの終わりが起きた紀元1世紀に携挙は起きたのである。
【13:40】
『ですから、毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。』
ユダヤが終わる紀元70年になると、教会の中にいた偽キリスト者どもは、あたかも『毒麦が集められて火で焼かれるように』して火で焼かれることになった。つまり、彼らは携挙されて空中の大審判を受けた後、永遠の火に投げ入れられて焼き尽くされることになった。その時、キリストが彼らに言われた恐るべき言葉はこうであった。『のろわれた者ども。わたしから離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火にはいれ。』(マタイ25章41節)なお、ここで『火で焼かれる』と言われているのは、エルサレムにいた人々が物理的な火により焼殺されるということについてではない。そうではなく、これは地獄における火の苦しみのことである。何故なら、我々が今見ている13:37~50の箇所では、携挙のことが語られているからである。携挙という名の刈り取りが起こってから御使いにより火に投げ込まれる。これは明らかにエルサレムにおける火の苦しみではなく、地獄における刑罰のことである。我々は、これがエルサレム炎上について言われているなどと思い違いをしないようにせねばならない。
【13:41~42】
『人の子はその御使いたちを遣わします。彼らは、つまずきを与える者や不法を行なう者たちをみな、御国から取り集めて、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。』
携挙という刈り取りには2回あると既に述べた。すなわち、再臨の時に起こるのが第1回目の携挙であり、再臨から42か月後に起こるのが第2回目の携挙である。黙示録では、第1回目の携挙が14:14~16で、第2回目の携挙が14:17~20で書かれていた。我々が今見ている箇所で書かれているのは、2回目のほうである。何故そう言えるのか。それは、2つの理由からである。まず一つ目は、我々が今見ている箇所では、御使いたちにより刈り取りが行なわれているからである。黙示録14:14~20の箇所を見ると、1回目の携挙はキリストによってなされ、2回目の携挙は御使いによってなされたことが分かる。よって、ここで書かれている携挙の出来事は御使いたちによりなされているので、2回目のほうである。二つ目は、この箇所では、悪者どもが携挙されているということである。既に説明したように、1回目の携挙では聖なる者たちしか携挙されず、悪者が携挙されるのは2回目の携挙である。よって、ここでは悪者どもが引き上げられているので、2回目の携挙について言われていることが分かる。この箇所で、1回目の携挙が言われていると解することはできない。そのように解すると、キリストの再臨された時に悪者が聖徒たちと共に蘇って携挙され、そうしてすぐに空中の大審判が行なわれることになるからである。しかし既に論じられているように、聖書はこのように教えてはいない。
この2回目の携挙により引き上げられる悪者どもは偽キリスト者という悪者のみに限られた、という点に注意せねばならない。何故なら、ここでは悪者どもが『御国から取り集め』られると書かれているからだ。これは「御国の子らの中から取り集められる」という意味である。つまり、携挙される悪者とは、御国の相続者である聖徒たちと共にいた偽善者どものこと以外ではない。だからこそ『御国から取り集め』られると言われたのである。悪者ではあっても偽キリスト者でない悪者は、偽キリスト者という悪者とは異なり、御国の子らと共にいるわけではない。それだから、偽キリスト者以外の悪者は第2の携挙における対象ではなかった。これはマタイ25:31~46の箇所を見ても分かることである。そこで描かれている者たちの中に「狼」は見られない。もし「狼」も第2の携挙により携挙されて大審判に出頭させられたというのであれば、このマタイ25:31~46の箇所では「狼」も描かれていたであろう。「狼」とは、もちろん偽キリスト者ではない悪者のことである。
それでは、この時に刈り取りを任された『御使いたち』とは、どのような存在だったのであろうか。黙示録14:17の箇所によれば、この御使いは『鋭いかまを持っていた』。また『御使い<たち>』と言われている通り、一人ではなく複数であった。しかし、この御使いの階級や能力については、何も分からない。この御使いについて書けるのは、これぐらいである。我々は、この御使いが、携挙を任されていた複数の御使いたちであったとだけ単純に理解していれば、それで問題ない。
選ばれた聖徒たちと共にいたキリスト者もどきの悪者ども、すなわち『つまずきを与える者や不法を行なう者たち』は、携挙されて後、『火の燃える炉に投げ込』まれた。これは、もちろん地獄のことである。地上のエルサレムもローマ軍に焼き尽くされて火の燃える炉になった。これも、ある意味では地獄と言うことが可能である。しかし、この箇所では炎上するエルサレムという炉の中に投げ込まれることが言われているのではない。思い違いをしないように注意すべきである。
悪者どもが投げ込まれたこの地獄とは、誠に恐るべき場所である。そこには火と蛆があり(マルコ9:48)、そこにいる者たちは永遠に苦しみを受ける(黙示録20:10)。また、彼らは天国にいる正しい敬虔な聖徒たちから眺められ忌み嫌われるという屈辱の苦しみも受けねばならない(イザヤ66:24)。更に、その場所はユダも言うように『まっ暗なやみ』(ユダ13節)が満ちている。地獄とはこのように悲惨で恐ろしい場所なので、そこにいる者たちは『そこで泣いて歯ぎしりする』ことになる。苦しみと悲しみと涙と嘆きと後悔。これが彼らに与えられる永遠の相続財産なのだ。これは、天国の聖徒たちが良きものを永遠に相続するのとはまったく正反対である。
この箇所では、携挙および地獄への投下しか語られていないことに注意すべきである。すなわち、復活および空中の大審判は、我々が今見ている13:37~50の箇所で語られていない。この2つの出来事は、ここにおいて省かれているのだ。しかし、我々はこのように省略されていることを驚くべきではない。何故なら、聖書において、このようにある事柄が省かれつつ語られている箇所は他にも多く見られるからである。要するに、この箇所では、携挙および地獄への投下という2つの出来事にだけ精神を集中させることが要請されている。だからこそ、復活および空中の大審判については記述が省かれているのである。
【13:43】
『そのとき、正しい者たちは、天の父の御国で太陽のように輝きます。』
『そのとき』とは、すなわち紀元70年9月である。これは正確に時期を特定することが出来る。
紀元70年9月になると、選ばれていた者たちは『天の父の御国』に導き入れられた。これは、この時に天上で正式に開始された父なる神の統御される偉大で聖なる王国のことである。聖徒たちがこの御国に入る時、キリストは彼らにこう言われた。『さあ、わたしの父に祝福された人たち。世の初めから、あなたがたのために備えられた御国を継ぎなさい。』(マタイ25章34節)
この天の御国に入れられた聖徒たちは『太陽のように輝』くことになった。これは、そこにおられる神とキリストという光が、聖徒たちを照らすからである(黙示録22:5)。ちょうど月が太陽に照らされて輝きを放っているのと同じである。また、もしかしたら聖徒たちも自分自身により光を輝き放っているということも考えられる。何故なら、天国にいる聖徒たちは、栄光の身体を持っているからである。ちょうどモーセが自分自身により光を輝き放ったように。聖徒たちが太陽のように輝くということについては、既に第2部と第3部の中で説明されている。このように聖徒が太陽のように輝くことになるのは、聖徒たちに対する誠に大きな恵みである。神は、御自身の選ばれた者たちに、このようにして良くして下さるのだ。天国の聖徒たちは、このような神の恵みを永遠に喜び楽しむのである。
『耳のある者は聞きなさい。』
これは、つまり悟れる者だけが悟れたらそれで良い、ということである。真理の教えは、それが分かるようにと定められている者にだけ正しい理解が恵みにより与えられる。何故なら、真理とは貴重であり大変素晴らしいものだからだ。神は、御自身の定められた者にだけ、そのような良きものをお与え下さる。ちょうど、夫が自分の愛しい妻にだけ、他の人にはあげない豪華で貴重な贈り物をするように。またピュタゴラス教団やフリーメイソンが、長年の観察と吟味により認められた僅かな構成員にだけ特別な秘密を伝授するように。神が、真理をごく一部の者にだけ与えられるのも、それと同じである。だから、真理とは、本当に僅かな者にだけ知解され得るものなのだ。聞く耳の与えられた者にだけ、それは与えられる。聞く耳の与えられていない全ての者は、たとえ真理をその耳で聞いたとしても、決して悟ることができない。神がその人に聞く耳を与えておられないからである。それだから、『耳のある者は聞きなさい。』とキリストが言われたのは、非常に排他的な言葉である。
【13:44】
『天の御国は、畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて、大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。』
キリストは、天国は『畑に隠された宝のようなもの』だと言われる。この宝とは、人を天国に至らせるキリストの福音のことである。
この福音とは地球世界という『畑』に隠されているものである。これは、つまり福音というものが、ほとんど全ての人から、それが宝であると気づかれないということを意味している。多くの人は、世界にあるこの尊い宝に気付くことがない。そもそも、この福音が宝であるということにさえ気づいていない。それは、ある畑に隠されている宝に誰一人として気づいていないようなものである。実際、今の世の中を見てみると、どうであろうか。ほとんど全ての人は、この福音という宝の存在にまったく気づいていない。つまり、福音という宝を見つけ出すことができていない。キリスト者と呼ばれている人たちの中でも、真にこの宝を見出せている人は、そこまで多くはない。何故なら、今のキリスト教界は世俗化しているからだ。もし多くのキリスト者が真にこの宝を見つけていたとすれば、ここまで多くの人たちが世俗的になり、福音に相応しくない振る舞いや精神を持っていることは無かったであろう。福音を世俗により抑制させているというのは、つまり福音を真に見つけられていないということを意味しているのだ。
それでは、福音を見つけた人が、その福音を『隠してお』くのは何故なのか。これは、福音が決して奪われてはならないものであるということを教えている。何故なら、もし福音が失われたりでもすれば、その人に救いと永遠の命は無くなるからである。それだから福音をこの世界という畑の中で見つけた人は、畑に隠されている宝を隠しておいて誰にも奪われないようにする人のように、誰からも、どのような出来事によっても、失われないようにシッカリ守っていなければならないのだ。真に大切なものを保持して失われないようにせねばならないということについては、黙示録3:11の箇所でもこう言われている。『あなたの冠をだれにも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。』
この例えに出てくる人は、福音という天国に至らせる宝を『持ち物を全部売り払って』まで手に入れている。これは、つまり福音というものは、あらゆる所有物を犠牲にしてまでも手に入れ保持すべきものだということである。何故なら、もし福音を獲得せず保持しないのであれば、人は地獄に投げ込まれるからである。自分の持ち物を売り払わなかったために福音を取り損ねたのであれば、そのために永遠の苦しみを受けることになるのだ。それだから、たとえ全財産を放棄したとしても福音という一つの宝を取り損ねないほうが遥かによい。パウロは、正に福音のために『持ち物を全部売り払っ』た人だと言える。何故なら、パウロはキリストという福音の主体者であられる御方のために『すべてのものを捨てて、それをちりあくたと思ってい』(ピリピ3章8節)たからである。彼は畑に福音という宝を見つけたので、持ち物を全部売り払ってその畑を買ったのだ。11人の使徒たちも、そうであった。何故なら、彼らもキリストという福音の本体であられる御方に『何もかも捨てて』(マタイ19章27節)自分を委ねたからである。11人の使徒も畑に宝を見つけたので、全ての物を売り払ってその畑を買ったのである。他方、イスカリオテのユダは、そのようではなかった。このユダは福音という宝のために全ての物を売り払っておらず、畑に埋まっている宝が宝であると気づけなかったので、その畑のために持ち物を全て売り払うどころか、自分の持ち物を増し加えるためにその宝を売り払うようなことさえした。つまり、キリストという福音の本体であられる御方を敵に売り渡してしまった。このような者は、キリストがこの箇所で言っておられる種類の人間ではない。とはいっても、福音という宝を獲得し保持するためには、全ての人が全ての財産を必ず放棄せねばならないということがここで言われているのではない。何故なら、あらゆる真のクリスチャンが自分の持ち物を全て放棄しなければいけなかったというわけではないからだ。多くの財物を持ちながら天へと召された聖徒など探せば幾らでも見つかることであろう。アブラハムやダビデもそのような聖徒であった。しかしながら、福音という宝を手放さないために、自分の持ち物を文字通り全て放棄するに至らさた聖徒たちは今までの歴史の中で少なからず見られる。
この地球世界という畑に隠されている福音という宝を真に見つけ、それを保持している人は、あまりにも幸いである。その人は、永遠の命を享受できるからである。教会に属している人の中で、まだこの福音を真に見いだせていない人がいれば、その人は福音を真に見いだせるようにするがよい。そうすれば永遠に喜べるようになるであろう。また既にこの宝を真に獲得し真に保持できている人は、その宝を誰にも、どのような出来事にも失わされないようにシッカリと隠し続けているがよい。そうすれば永遠に喜べるようになるであろう。福音という宝を見つけられない人は、永遠に喜ぶことができない。また福音という宝を見つけはしたが、それを見失ったり放棄してしまう人も、永遠に喜ぶことができない。
【13:45~46】
『また、天の御国は、良い真珠を探している商人のようなものです。すばらしい値うちの真珠を一つ見つけた者は、行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。』
人を天国へと至らせるキリストの福音は、あまりにも良質な真珠のようなものである。それは、商人が自分の『持ち物を全部売り払って』まで手に入れたいと願うほどのものである。つまり、商人の持つ持ち物の全てよりも、福音という一つの真珠のほうが重く、素晴らしく、価値が高いということである。それだから、パウロや11人の使徒たちが、この真珠のために持ち物の全てを捨てたのは賢明な選択であった。―それではこの地球上の財物を全て所有できたとして、その財物を全て売り払ったとしても、この福音という真珠は手に入れるべきものなのであろうか。答え。これはその通りである。この地球にある財物を全て合算しても、福音という一つの真珠のほうが遥かに卓越しているからである。
しかしながら、ほとんど全ての人は、この真珠の価値を知らず、それを見つけることさえ出来ていない。これは、彼らがこの真珠を獲得せず、この真珠により与えられる恵みによって癒されることがないためである。彼らはこの真珠を獲得するようにと定められていない。だからこそ、彼らはこの真珠とは無関係なままで自分の人生を終わらせる。むしろ彼らは、この真珠により癒されないで滅ぼされるために、この地上に生まれてきた。それだから、神は彼らがこの真珠を見出さないようにと定められている理由について、こう言っておられる。『それは、彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って、立ち返り、わたしにいやされることのないためである。』(使徒行伝28章27節)だが、この真珠を見つけて自分の持ち物を売り払ってまでそれを買うようにと定められている人たちもいる。このような人たちは定めを受けているからこそ、この真珠に気付き、その真珠のために自分の持ち物を売り払うことさえ厭わない。というのも、この世においては神の定めが全てを動かし、決定させるからである。世界で起こる全ての出来事は、神の定めに基づいている。それゆえ、定めを受けている人は、神の摂理により、どのようにしてもこの真珠を求めるようにさせられるのである。
【13:47~50】
『また、天の御国は、海におろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引き上げ、すわり込んで、良いものは器に入れ、悪いものは捨てるのです。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て、正しい者の中から悪い者をえり分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。』
この箇所では、携挙の出来事が漁に例えられている。漁においては、海に下ろした網を引き上げると、その網の中にいる魚を分け、良い魚は器に入れ、悪い魚は捨ててしまう。携挙もこれと同じであった。第2の復活によって復活した聖徒たちと悪者どもが第二の携挙により引き上げられると、漁の時のように「選別」が実施され、聖徒たちは天国という良い器の中に取り入れられ、悪者どもは地獄へと投げ捨てられた。この例えには特に難しい部分はない。この例えは、使徒たちにとって非常に理解しやすかったと思われる。何故なら、使徒の多くは漁をしていた漁師だったからだ。我々の経験も証しするように、その人のよく知っている事柄に関わらせて語られるということほど、人にとって理解しやすいことは、他にないのである。
【16:27~28】
『人の子は父の栄光を帯びて、御使いたちとともに、やがて来ようとしているのです。その時には、おのおのその行ないに応じて報いをします。まことに、あなたがたに告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が御国とともに来るのを見るまでは、決して死を味わわない人々がいます。』
この箇所、特に16:28の箇所は、再臨の正しい理解のためには、もっとも重要な箇所の一つである。そこでは、再臨に関する誠に重要で決定的なことが言われている。私は、この作品の主題聖句としてこの16:28の箇所を掲げようとも考えたほどである。再臨を正しく理解したい聖徒は、是非とも、この箇所を暗記しておくべきである。
ここでキリストは、御自身の目の前に『立っている人々』が生き残っている間に、再臨が起こると明白に言っておられる。この箇所は、このように捉える以外に、正しい解釈は存在していない。他に可能な解釈としてはアウグスティヌとグレゴリオス・パラヌスの解釈があるが、これは第1部でも述べたように、間違った解釈である。彼らの解釈は一見すると何だかもっともらしく感じられなくもないのだが、よく考えると多くの問題を抱えていることが分かり、それゆえ無理がある。この16:28の箇所は、私が述べた解釈とこの2人の解釈以外の解釈をほどこすことはできない。アウグスティヌとパラヌスのほうは明らかに間違っているから、私が述べた解釈のほうが正しいということになる。しかし、どうして今まで教会は、この聖句について正しい解釈を持つことが出来なかったのであろうか。それは、まだ再臨の真理が明らかにされる時期が来ていなかったからだ。これについては第1部の当該箇所を見てほしい。私は、そこでこのことについて詳しく書いておいた。私が述べたこの箇所に対する正しい解釈を受け入れるために必要なのは、常識を超越できる黄金の信仰である。そのような信仰があれば、神の恵みにより、この箇所の正しい解釈を獲得することが出来るであろう。何故なら、その人は常識よりも御言葉のほうを上に位置させる人だからである。もっとも残念ながら、バルト主義やエキュメニズムや世俗化といった無数の問題が蔓延している現今のプロテスタント界には、そのような信仰を持った人はほとんど見られないのではあるが…。
実際、キリストの目の前に『立っている人々』は、生き残っている間にキリストが再臨されるのを、その目で見た。何故こう言えるかといえば、御言葉がそのように教えているからである。それゆえ、聖徒たちのうちで誰も私が今言ったことを批判する者があってはならない。もしこの理解に批判をするのであれば、それは私の理解を批判しているのではなく、御言葉が言っていることを批判していることになるからだ。それでは、キリストの前に立っていた人々のうち、再臨の光景をその目で見た人は具体的にはどのくらいいたのか。このようにキリストが語られてから再臨が起こるまでは約35年である。35年ぐらいであれば、それなりに多くの人が再臨の時まで生き残っていたのではないかと考えられる。何故なら、キリストがこのように語られた時に20歳だった人は再臨が起こる時には55歳になっており、30歳であった人は65歳になっており、40歳であった人は75歳になっているからである。普通に考えて、55歳、65歳、75歳であれば、まだ死なないでいられた人も多くいたはずである。もちろん紀元1世紀の人間はまだ平均寿命が今よりも短かったという点を考慮せねばならないが、それを考慮したとしても、少なくともキリストの前に立っていた人々のうち10分の1ぐらいの人は35年後まで生き残っていたのではないかと私は思う。もしかしたら10分の3ぐらいだったという可能性もなくはない。とはいっても、実際にどれぐらいの人が再臨の時まで生き残っていたのかは分からない。我々は、ただ御言葉で言われている通りに、「キリストの前にいた人々のうちキリストの再臨まで生き残っている人がいた。」とだけ単純に理解していればそれで十分である。また再臨の時まで生き残っていた人たちは、再臨を見たものの何も文章として記録を書き残すことはしなかった、ということも言っておかねばならない。それというのも、再臨を見た麦たちは携挙されて地上から取り去られたし、毒麦たちは再臨が起きてから42か月後に起きた第二の携挙により地上から取り去られたし、エルサレムにいて再臨を見たユダヤ人たちはローマ軍の襲来によって即座に殲滅されたし、再臨を見たローマ軍の兵士たちには再臨が夢や幻であるかのように感じられたからである。これでは再臨の出来事が書き記されなかったとしても不思議ではない。これについては第1部の当該箇所を見てほしい。私は、そこでこのことについて詳しく論じておいた。
また再臨の時まで生き残っていた紀元1世紀の人々は、キリストが再臨されると共に御国も力をもってやって来るのを見た。何故こう言えるかといえば、御言葉がそう教えているからだ。もし聖徒であることを止めたいというのであれば、御言葉が教えていることを拒絶するがよい。しかし聖徒であり続けたいというのであれば、御言葉が教えていることを素直に受け入れるがよい。この『御国』というのは、言うまでもなく「天国」である。これは、神が聖徒たちを支配されるその王国という意味ではない。そのような意味としての『御国』であれば、再臨が起きるよりも前に既に聖徒たちのうちにあったからである。つまり、ここでキリストが言われたのは、再臨と共に天上において天国が正式に開始されるということである。この時以降、地上にいる聖徒たちが地上から去ったならば、再臨の時に開始されたこの天国へと導き入れられるようになった。だからこそ、キリストは宣教を開始された時に『天の御国が近づいた』(マタイ4章17節)などと言われたのである。というのも、キリストが宣教を始められてから再臨と共に『天の御国』が到来するようになるのは、40年以内だったからである。40年もしない間に御国が再臨と共に来るのであれば、確かにその到来を『近づいた』などと言うのは適切なことであった。
キリストが再臨された際には、『御使いたちととも』にやって来られた。キリストと共に天から降りて来たこの御使いたちは、実に多かった。何故なら、キリストが再臨される時には『すべての御使いたちを伴って来る』からである。御使いの数は黙示録5:11の箇所によれば『万の幾万倍、千の幾千倍』だったから、御使いたちと一緒に来られたキリストの再臨は、さぞ驚くべき光景だったに違いない。しかし、全ての御使いたちが再臨のキリストと共に降りて来たのは何故だったのか。それは演出と尊厳のためであった。演出というのは、キリストの再臨を際立たせるためである。キリストは『栄光の王』(詩篇24:8)であられるから、無数の御使いたちが言わばお伴をするのが相応しいのである。これは、ちょうど偉大な王が特別な儀式をする際には、横にずらっと並んだ儀仗兵の間を堂々と歩くようなものである。尊厳というのは、無数の御使いが共にやって来たほうが、キリストの尊厳に相応しいからである。多くの御使いが一緒に来るからこそ、キリストの尊厳が豊かに強調される。もしキリストがお一人で来られたとすれば、再臨はあまりキリストの尊厳に相応しくない出来事になっていたであろう。また、この無数の御使いたちはミカエルに率いられてキリストと共にやって来たと思われる。というのもミカエルとはユダも言うように『御使いのかしら』(ユダ9節)だからである。このミカエルが大きな声を響かせると、キリストの再臨が起きた。『主は、…御使いのかしらの声…のうちに、ご自身天から下って来られます。』(Ⅰテサロニケ4章16節)と書かれている通りである。
またキリストは再臨の際、『父の栄光を帯びて』天から降りて来られた。これは、つまりキリストが父なる神において再臨されたということである。すなわち、父なる神の御心ゆえに、キリストは遂に再臨されることになった。だからこそ、キリストは父の栄光を持って天から来られたのだ。これは、王に遣わされてある国に行った皇太子が、王の権威と名声とをもってその国に訪れるのと同じである。また大使がある場所を訪れる時、自分の国の名前と力と評判とにおいてその場所を訪れるのと同じである。それだから、我々は再臨を考える際、父なる神の栄光についても考えることを忘れないようにせねばならない。我々は再臨を考える時、どうしてもキリストの栄光だけしか考えない傾向がある。というのも、再臨とは主にキリストにかかわることだから、どうしてもキリストにだけ精神が集中されてしまうからである。しかし、キリストは再臨される時、御自身の栄光だけで来られたのではなかった。そうではなく、キリストは御自身の栄光に加えて御父の栄光をも伴って再臨されたのである。それでは再臨の時、キリストは御霊の栄光を帯びてはおられなかったのであろうか。もちろん、キリストは御霊の栄光をも帯びておられた。何故なら、『神が御霊を無限に与えられ』(ヨハネ3章34節)ておられるキリストが、その御霊において再臨されたのは明らかだからである。キリストが御自身と御父の栄光において再臨されただけで、御霊の栄光は例外的に帯びておられなかったなどというのは有り得ない話である。また、ルカ9:27の箇所を見ると、キリストが再臨された際には『御使い…の栄光』も帯びて来られたことが分かる。これは、つまり御使いの持っていた聖なる栄光が、キリストとその再臨における輝かしさを更に際立たせ強調させたということである。
キリストが再臨された時には、『報い』も行なわれた。それは人々に対する報いである。これは、具体的に言えば、あの空中の大審判のことを言っている。キリストは、ここでマタイ25:31~46や黙示録20:11~15に書かれている審判の出来事について言われたのだ。この空中の大審判が未だに起きていないなどと勘違いをしてはいけない。そのように考えるのは聖書否定である。何故なら、キリストはここで明らかに御自身の目の前に立っている人々が生き残っている間に、再臨に伴う報いが行なわれると言っておられるからだ。キリストの御言葉を否定できるものならばしてみよ。その場合、その人はキリスト者であることを放棄しているのも同然である。また、再臨の時に起こるこの審判には、あらゆる人たちが出頭したというわけではなかった。そうではなく、審判の場に出たのは、教会に属している羊と山羊だけであった。すなわち、キリストに対して「主よ。」と言うような人たちがそうである。これはマタイ25:31~46の箇所を見れば明らかである。そこでは「狼」が見られないのである。実際、再臨が起きた時期には教会に属する者以外は地上に居続けたわけだから、審判の場に文字通り全ての人間が出頭したと考えることはできない。つまり、この報いとは限定的なものだったのだ。これについては既に第2部の中で詳しく論じられている。
さて、ここでキリストは聖徒たちに何を言いたかったのであろうか。これは文脈を考えれば分かる。キリストは少し前の部分で、弟子たちが御自身に自分の人生を据えない限り、真の幸いは有り得ないと言われた(16:24~26)。そのように言われた後で、キリストは弟子たちが生きている間に再臨と御国と審判がすぐにも起こるであろう、と言っておられる(16:27~28)。つまり、これはこういうことである。すなわち、もう間もなくキリストの再臨と共に御国が起こり審判が行なわれるようになるのだから、当時の聖徒たちはその時に幸いな結果を掴めるようキリストにこそ自己の人生を据えて歩まなければならない、ということである。キリストはこう言われることで、聖徒たちが再臨が起こる際、悲惨なことにならないようにされたわけである。これは例えるならば、マイク・タイソンとモハメド・アリの試合がすぐにも行なわれるからその試合を見れるようにチケットを早く買わなければいけない、などと宣伝するようなものである。チケットを買えた人はこの歴史的な試合を見ることが出来るが、買えなかった人は試合の会場に入ることができず悔しい思いをする。この例えは言うまでもなく、タイソンとアリの試合が天国を、チケットがイエス・キリストと対応している。
【20:1】
『天の御国は、自分のぶどう園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。』
キリストは、天の御国を、葡萄園で働く人を次々と雇って働きに行かせる主人に例えておられる。この例え話もそうだが、キリストの話は、まったくのオリジナルである。世の中にある他の話であれば、必ず、直接的にであれ間接的にであれ、どこか他の話から引っ張ってきた痕跡が僅かであっても感じられるものだ。例えば、ギリシャ神話中のヘラクレス伝説は明らかに怪力サムソンの話から影響を受けているし、デウカリオンの洪水伝説は間違いなくノアの大洪水が歪められて伝承されたものだし、パンドラの箱についての話もその源流は創世記に書かれているエバを原因とする堕落の話である。キリストの話の場合、聖書に書かれている話を除けば、このような痕跡はまったく認められない。これはキリストの話が、聖書を除けば、どこからも引っ張られて来ていないことを示している。キリストは創造者なる神なのだから、純粋にオリジナルな話を作ることがお出来になったのである。
『天の御国』とは、紀元70年に開始された天上の王国を指している。『主人』とはキリストのことである。『労務者』とは聖徒のことである。『ぶどう園』とは、聖徒たちが神のために働く場としてのこの地上世界である。『雇(う)』とは、聖徒たちが神に仕える聖徒としてこの地上に召されることである。主人が『朝早く出かけた』のは、キリストがこの地上に聖徒たちを召される時間帯が、聖徒一人一人においてそれぞれ違っているからである。すなわち、ある人は早い段階に召されてキリストの労務者となるが、別の人は遅い段階に召される。例えば、ペテロは紀元30年頃に労務者として雇われたが、パウロはその3年後の紀元33年頃に雇われた。ペテロのほうが時間的に早く雇われたのは火を見るよりも明らかである。キリストは、全ての聖徒たちを一挙に地上に召されるわけではないのだ。
【20:2】
『彼は、労務者たちと1日1デナリの約束ができると、彼らをぶどう園にやった。』
「デナリ」とはローマのお金の単位であり、1デナリとは、だいたい1日分の給与に該当するお金である。日本で言えば1万円ぐらいだと捉えれば問題ない。ただ、これは2千前の世界におけるお金の単位だから、その価値を今の時代の価値に正確に換算することは難しいと言わねばならない。だから、1デナリが1万円だというのは、かなりラフに捉えるべきである。
この例え話では、この1デナリは「復活における救い」を示している。つまり、労務者たちが主人から1デナリの報酬を貰うというのは、聖徒たちが神から身体を復活させてもらう、ということである。ここではその復活がたったの1デナリとして示されているが、キリストが復活の価値を低く見積もっておられるのではないということに注意せねばならない。というのは、ここでは復活の価値が1デナリということが教えられているわけではないからである。この例え話の中では、復活の価値について何も示していない。また後ほど見るが、ここでは復活における平等性を示そうとして復活が1デナリとして示されているに過ぎない。もしここで復活の価値が教えられていたとすれば、復活が1デナリなどとは言われていなかったであろう。その場合、6000億タラントとか7兆タラントとか言われていたはずである。何故なら、栄光の身体への復活とは、たとえこの世の全てのお金を集めたとしても買うことが出来ないほどのものだからである。
【20:3~5】
『それから、9時ごろに出かけてみると、別の人たちが市場に立っており、何もしないでいた。そこで、彼はその人たちに言った。『あなたがたも、ぶどう園に行きなさい。相当のものを上げるから。』彼らは出て行った。それからまた、12時ごろと3時ごろに出かけて行って、同じようにした。』
この主人が最初に労務者を雇ったのは、20:1の箇所で『朝早く出かけた』と書かれているから、だいたい7時頃と見てよいであろう。もしかしたら5時とか6時だった可能性もある。しかし、この主人が出かけた時間は、我々にとって問題ではない。この主人は9時と12時と3時になってからも、葡萄園で働く労務者たちを新規に雇っている。主人が遅い時間になってから新規に労務者を雇ったその理由は何だったのか。これについては、我々は知らなくてもよい。というのも、この例え話においては、ただより時間的に遅くに雇われた労務者もいたということだけを知っていれば、それで十分だからである。ところで、ここで書かれている9時と12時と3時とは、原文では3時と6時と9時である。古代ユダヤの社会では、朝の7時を第1時として一日の始まりとし、夕方の6時すなわち現代で言えば18時を第12時として一日の終わりとしていた(※)。21世紀の時代では、ほとんどの国において、このような1日の始まりと終わりを規定してはいない。それだから、我々はこの例え話で語られている時間の概念を、当時の文化背景をよく弁えつつ理解すべきである。
(※)
つまり、こういうことである。
現代の時間概念 古代ユダヤの時間概念
0時 ―
1時 ―
2時 ―
3時 ―
4時 ―
5時 ―
6時 ―
7時 第1時(1日の始まり)
8時 第2時
9時 第3時
10時 第4時
11時 第5時
12時 第6時
13時 第7時
14時 第8時
15時 第9時
16時 第10時
17時 第11時
18時 第12時(1日の終わり)
19時 ―
20時 ―
21時 ―
22時 ―
23時 ―
[本文に戻る]
【20:6~7】
『また、5時ごろに出かけてみると、別の人たちが立っていたので、彼らに言った。『なぜ、1日中仕事もしないでここにいるのですか。』彼らは言った。『だれも雇ってくれないからです。』彼は言った。『あなたがたも、ぶどう園に行きなさい。』』
主人は、5時頃になってからも新しく労務者たちを雇用した。仕事が終わるのは6時である。つまり、この5時に雇われた労務者は、たったの1時間しか働かなかった。しかし、それでも働いていることには変わらないのだから、この労務者もれっきとした労働者である。先の箇所で言ったことから分かるように、ここで『5時』と言われているのは、ユダヤ社会では第11時である。もう1時間もすれば、ユダヤの1日が終わりを迎えるのだ。
【20:8~10】
『こうして、夕方になったので、ぶどう園の主人は、監督に言った。『労務者たちを呼んで、最後に来た者たちから順に、最初に来た者たちにまで、賃金を払ってやりなさい。』そこで、5時ごろに雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつもらった。最初の者たちがもらいに来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らもやはりひとり1デナリずつであった。』
夕方になり仕事が終わったが、労務者たちに与えられた報酬は、多く働いた者も少ししか働かなかった者も例外なく1デナリずつであった。この出来事から、我々は2つの事柄に着目すべきである。第一に、労務者たちは労働の度合いに関係なく誰もが1デナリの報酬を貰ったということである。先にも述べたが、ここで言われている1デナリとは、復活の救いを示している。つまり、聖徒たちはこの地上で主のために多く働いても少ししか働かなくても、誰もが例外なく復活の救いに与るということである。例えば、使徒パウロはどの聖徒たちよりも多く働き、キリストと共に十字架上で死んだ強盗はほとんど何も働かなかったが、どちらも栄光の身体へと甦らされた。神から復活させていただくという恵みを受けた、という点でこの2人はまったく一緒である。つまり、パウロも十字架上の強盗も、その働きの度合いに関係なく1デナリを貰ったわけである。パウロのほうが遥かに多く労働をしたからといって、十字架上の強盗よりも復活の恵みを多く受けられることになった、ということはなかった。第二は、より遅い時間に雇用された労務者のほうが、より早い時間に雇用された労務者よりも、時間的に早く報酬を受けたということである。これは、つまりより時間的に遅く主の聖徒となったほうが、より時間的に早く復活して天国に入れるということを教えている。次に示す2人の人について考えてほしい。(1)2100年に70歳の年齢で救われた後、5年後の2105年に75歳の年齢で天に召された人。(2)2070年に20歳の年齢で救われた後、60年後の2130年に80歳の年齢で天に召された人。この2人の場合、明らかに(1)の人のほうが、より後で主の労務者として雇われたのにもかかわらず、より先に天国における報酬を受けることになっている。(2)の人は、(1)の人よりも早く雇われたのに、(1)の人よりも後で報酬を受けることになっている。要するに、歳を取ってから救われたほうが、若いうちに救われた人よりも率先して天国に導き入れられるということである。神の定められた秩序とは、このようなものである。復活して天国に入ることについて言えば、より先に雇われた人のほうがより早く報酬を受けるというのではないのだ。
ここで書かれている出来事は、我々の理性に反している。いったい、多く働いた者も少ししか働かなかった者も同一の報酬を受けるというのは、どういうわけであろうか。また、より後に来た者のほうがより優先されるとは、どういうわけなのであろうか。これは普通では考えられないことである。このようなことをする主人は、今の世の中を見回しても恐らく見つからないであろう。しかし、この例え話に出てくる主人は、そのような主人であった。それは、我々の神である主人が、実際にこのような御方だからである。聖書が教えるように、我々の神とは不思議なことを為される御方なのである。
【20:11~12】
『そこで、彼らはそれを受け取ると、主人に文句をつけて、言った。『この最後の連中は1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは1日中、労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。』』
この労務者が主人に文句を言ったのは、人間の感覚からすれば自然なことだったと言えるかもしれない。何故なら、ここで主人がしていることは明らかに公平ではないと感じられるからだ。人間の心は公平であることを求めるものである。それは、公平であることこそが理に適っており、正義だと感じるからである。それだから、この文句を言った労務者は、心の中で「こんなおかしな話があるだろうか?」などと腹立たしく思っていたに違いない。
しかしながら、この労務者は、1デナリである復活の救いが誰にでも平等に与えられるものだということを知らないという点で、非難されるべきであった。彼は愚かである。何故なら、彼が主人に文句を付けたのは、次のように言っているのも同然だからである。「私たちは5時頃に雇われた者たちよりも多く働いたのだから、その者たちよりも多く復活の救いに与るべきなのだ。」読者は、この例え話で言われている『1デナリ』という言葉を、「1復活」または「一つの復活」と読み替えてみるとよい。そうすれば、この労務者がどれだけ愚かなことを言っているのか、よく分かることであろう。要するに、この1デナリを一回の復活として解釈しつつ読むと、この労務者たちは自分たちを何回も復活させてくれと言っていることになるのだ。
【20:13~15】
『しかし、彼はそのひとりに答えて言った。『私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と1デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としては、この最後の人にも、あなたと同じだけ上げたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか。それとも、私が気前がいいので、あなたの目にはねたましく思われるのですか。』』
文句を言った労務者に対して、この主人はこう答えた。『自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか。』つまり、この主人は自分の所有財産における裁量権を自由に行使したに過ぎないということだ。確かに、この主人のお金はこの主人の好きなように取り扱えるお金だから、この主人がどのように取り扱おうと主人の勝手であり、誰も文句を言うことはできない。だから、この労務者が主人に対して文句を言う権利はまったくなかった。彼が文句を付けたのは違法であり、主人の裁量権に対する侵害であった。それゆえ、この主人が全ての労務者たちに同一の報酬を与えたからといって、この主人は何も愚かなことをしたのではなかった。もっとも、今の時代でこのようなことをする雇い主がいれば、高い確率で騒ぎ出す者が現われたり話題やニュースになったりすることだろうが。
神は、この主人のように為される御方である。神は被造物である矮小な人間とは違っている。それゆえ、神が為されるやり方は、我々人間にとっては「不思議」に感じられる。士師記13:19の箇所でも、『主はマノアとその妻が見ているところで、不思議なことをされた。』と書かれている。神が不思議なやり方をされるのは、それを見たり知ったりした人間が驚いたり感嘆とさせられたりすることで、神の栄光が現わされるようになるためである。神が人間のように普通のことしかされないとすれば、まったく、またはほとんど神の栄光が現わされることもくなってしまうのだ。
この例え話では注意せねばならないことがある。それは、ここでは復活の救いがどの聖徒にも公平に与えられるということだけが教えられているということである。ここでは、それ以上のこと、それ以外のことは教えられていない。つまり、この例え話の中では、復活した後に与えられる聖徒の生活上における報酬については一切触れられていない。ここでは言われていないが、復活後の状態において受ける報酬は、聖徒によりそれぞれ異なっている。パウロはⅠコリント書の中で、星の輝きにはそれぞれ違いがあると言っている。つまり、天国に導き入れられた聖徒たちの持つ輝きは、一人一人異なっているということである。またキリストは『朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。』(ルカ12章33節)と言われた。つまり、天に宝を積み上げれば積み上げるほど、聖徒が受けることになる天国での報酬は増し加えられるということである。具体的に言えば、誰よりも働いたパウロは、間違いなくほとんど働かなかった十字架上の強盗よりも、天国における生活上の報酬を多く受けた。何故なら、パウロのほうが十字架上の強盗よりも、主のために多く労苦したからである。『少しだけ蒔く者は、少しだけ刈り取り、豊かに蒔く者は、豊かに刈り取ります。』(Ⅱコリント9章6節)と言われていることからも、このことは分かる。しかし、この天国における生活上の報酬について、この例え話の中では取り扱われていない。それが取り扱われているのは、後ほど見るマタイ25:14~30の箇所における例え話である。キリストの例え話は、今述べたことからも分かるように、思慮を持って理解されなければならない。キリストは、ある一つの例え話の中で、あれもこれも何かも教えておられるのではない。その例え話の中では、ある事柄の一面だけにいつも視点が絞られているのである。
【20:16】
『このように、あとの者が先になり、先の者があとになるものです。」』
人間が天上の御国へと入ることになる原理は、この通りである。これは地上世界の原理とは根本的に異なっている。だから、これは実に霊的な原理である。それゆえ、このことについて我々は事柄を霊的に捉えねばならないのである。
確かに、ここで言われている原理は、地上世界にはほとんど見られない原理である。具体的に考えると、どうか。例えば、病院であれば、王族や死にかけている人が運び込まれるのでもない限り、より後に来た人がより先に来た人よりも早く診療してもらえるということは有り得ない。そのような病院があれば、多くの人から非難されてしまうであろう。また大学であれば、飛び級や賄賂でも使わない限り、また留年を考慮しなければ、遅く入学した者が早く入学した者よりも先に卒業するということはない。1年生の者が3年生の者よりも先に卒業したなどという話は、今までに聞かれたことがないのである。それだから、この世の原理を言えば、こういうことになる。「先の者が先になり、後の者が後になる。」
【21:33】
『もう一つのたとえを聞きなさい。ひとりの、家の主人がいた。彼はぶどう園を造って、垣を巡らし、その中に酒ぶねを掘り、やぐらを建て、それを農夫たちに貸して、旅に出かけた。』
キリストは、ユダヤ人から神の国が取り上げられることを、農夫たちとその農夫たちに次々と僕たちを遣わした葡萄園の主人において語っておられる。この例えの内容は実に適切であった。これ以上の例えは考えつくことが出来ない。人となられた神が、このような例えをお語りになったからである。いったい、神よりも巧みに例えを考えつくような人間がどこかにいるのであろうか。
語句の説明がなされねばならない。まず『主人』とは父なる神である。『ぶどう園』とは神の国である。『農夫たち』とは旧約時代のユダヤ人である。主人が『旅に出かけた』のは、この地上において神が直接的にはユダヤ人と共におられないことを示している。葡萄園が『農夫たちに貸し』出されたというのは、ユダヤ人が神の国に入れられたことを示している。その葡萄園に主人が『垣を巡らし』たのは、旧約時代において神の国がユダヤ人のうちに限定・制限されているということである。実際、旧約時代においては神の国に垣が巡らされていたので、ユダヤ人でない民族は改宗してユダヤ人にでもならない限りは神の国に入ることが出来なかった。葡萄園に『酒ぶね』が掘られたというのは、神の国が素晴らしく望ましい場所だということである。そこに『やぐら』が建てられたのは、神の国が堅固で揺るがされないことを教えている。主人がこの『ぶどう園を造っ』たのは、つまり神がユダヤ人の中に葡萄園である神の国を打ち立てられたということを示している。
【21:34】
『さて、収穫の時が近づいたので、主人は自分の分を受け取ろうとして、農夫たちのところへしもべたちを遣わした。』
これは、つまり神がユダヤ人のところに御自身の使いたち、すなわち『預言者、知者、律法学者たち』(マタイ23章34節)を遣わされたということである。どうして、神である主人はそのようにされたのか。それは主人が『自分の分を受け取ろうとし』たからである。つまり、神はユダヤ人たちに御自身と結んでいる契約に相応しいシッカリとした対応をするようにと求めた。何故こう言えるかといえば、葡萄園の主人が農夫たちに自分の分を受け取ろうとして僕たちを遣わしたというのは、つまり神という主人がユダヤ人という農夫たちに為すべきことをするようにと求めたことを意味しているからである。この主人は恐らく「おい、農夫たちよ。シッカリと私の分を渡しなさいよ。君たちは約束を私と結んでいるのだからな。」などと言ったであろう。それと同様に、神も「ユダヤ人たちよ。シッカリと私の民として相応しく歩みなさい。あなたがたは私と契約を結んだ聖なる民なのだから。」などと御自身の使いを通して言われたのである。神がこのようなことを言われたのは、旧約聖書を読めば分かる通りである。また、この主人が『収穫の時が近づいた』から僕たちを遣わしたというのは、つまり神がちょうど良いと思われた時に御自身の使いをユダヤ人たちのところへ遣わされたということを示している。何故なら、『収穫の時が近づ』くというのは「ちょうど良い」ということだからである。
【21:35~36】
『すると、農夫たちは、そのしもべたちをつかまえて、ひとりは袋だたきにし、もうひとりは殺し、もうひとりは石で打った。そこでもう一度、前よりももっと多くの別のしもべたちを遣わしたが、やはり同じような扱いをした。』
農夫であるユダヤ人たちは、神がせっかく御自身の使いを遣わして下さったのに、その使いたちを拒絶したどころか、迫害して酷い目に遭わせた。しかも、それは繰り返して行なわれ続けた。ユダヤ人が神の使いたちに忌まわしい対応をしたのは、1度や2度どころではなかった。それは、旧約聖書を見れば分かる通りである。
我々は、ここに神の忍耐強さを見て取ることができる。神は御自身の使いが拒絶されたのを、まざまざと御覧になっておられた。しかし、それにもかかわらず、神は諦めることなく使いたちを延々とユダヤ人たちのためにお遣わしになった。ヨハネも言うように『神は愛』であり、神はユダヤ人らを愛しておられた。だからこそ、このように忍耐しつつ使いたちを遣わすことを御止めにはならなかったのである。何故なら、パウロも言うように、愛とは『すべてをがまんし、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍』(Ⅰコリント13章7節)ぶことだからである。もし神が愛でなかったか、または神がユダヤ人を愛しておられなかったのであれば、このように延々と使いたちが遣わされることはなかったはずである。何故なら、愛がないとは、すなわち「全てを我慢せず、全てを信ぜず、全てを期待せず、全てを耐え忍ばない」ことだからである。これが人間だったら、どうなっていたか。その場合、ユダヤ人たちは、1人か2人の使者を拒絶した時点で即座に滅ぼされていたことであろう。というのも、人間は神のように忍耐深くないし、すぐに怒って暴力的な手段に出るものだからである。
【21:37~39】
『しかし、そのあと、その主人は、『私の息子なら、敬ってくれるだろう。』と言って、息子を遣わした。すると、農夫たちは、その子を見て、こう話し合った。『あれはあと取りだ。さあ、あれを殺して、あれのものになるはずの財産を手に入れようではないか。』そして、彼をつかまえて、ぶどう園の外に追い出して殺してしまった。』
ここで言われている『息子』とは、イエス・キリストである。神は、それまでに遣わされた使者たちが全て拒絶されたので、遂に最後の手段として最後の使者である御子イエス・キリストを、ユダヤ人のところに遣わされた。それは、ユダヤ人の主人である神が『私の息子なら、敬ってくれるだろう。』と思われたからである。つまり、単なる人間に過ぎない使者であれば酷い仕打ちを受けてしまったが神の子であればそうはならないだろう、と。しかしながら、ユダヤ人たちは、この息子イエス・キリストさえも拒絶した。この例え話の中で農夫たちが言っているように、ユダヤ人たちはキリストを捕まえて殺してしまった。これは福音書の中で書かれているのを我々が見ている通りである。
こんなにも酷いことが他にあるだろうか。それまでに何度も善意から使いたちが遣わされたのにその使いたちを退け、遂に遣わされた神の御子をさえも退けてしまったとは…。これ以上の愚行は他に考えることができない。しかし、ユダヤ人たちは、そのようなことをしたのだ。つまり、ユダヤ人たちは、それほどまでに神に従いたくなかったのである。だからこそ、神に従うようにと告げに来た使者たちを迫害したり殺したりしたわけである。彼らの心の思いは、このようなものであった。「神が我々に使いなる者を遣わしているようだが、それが一体なんだというのか。我々は神になど従わずに自分たちだけで好きなようにやりたい。何故なら、それがもっとも良いと思えるのだから。」
【21:40~41】
『このばあい、ぶどう園の主人が帰って来たら、その農夫たちをどうするでしょう。」彼らはイエスに言った。「その悪党どもを情け容赦なく殺して、そのぶどう園を、季節にはきちんと収穫を納める別の農夫たちに貸すに違いありません。」』
酷いことをした農夫たちは主人からどのようにされるかというキリストの質問に対し、弟子たちはこのように答えた。この弟子たちは、我々の目からすれば正しく答えたように思われる。この弟子たちが言っているのは、つまり農夫であるユダヤ人たちから葡萄園である神の国が取り上げられ、別の農夫である異邦人たちに任せられるようになる、ということであった。もちろん、弟子たちが、この答えを神の国に関わらせて語ったのかどうかは定かではない。恐らく、この弟子たちは、こう答えた際、神の国とユダヤ人のことなどまったく考えていなかったであろう。何故なら、当時の弟子たちにとって、ユダヤから神の国が取り上げられるなどというのは想定さえ出来ないことだったからである。しかし、彼らが答えたのは、つまりそういうことであった。
実際、ユダヤ人という農夫から神の国という葡萄園は取り上げられ、別の農夫である異邦人にそれが与えられることになった。それはユダヤ人たちが、多くの使者たちを、神の子であるイエス・キリストを、酷い目に遭わせたからであった。今や神の国は異邦人のうちに打ち立てられている。もはやユダヤ人のうちに神の国は見られなくなった。これは今の世界を考えてみればよく分かるであろう。このようになったのは、2千年前からであった。
神は、このように神の国を取り上げて別の民族に与えるというやり方で、ユダヤ人に裁きをお与えになった。ユダヤが神に酷いことをしたので、神もユダヤに酷いことをされたのである。ユダヤ人は自分たちの神を捨てた。だから神もユダヤ人たちを捨てた。『主を捨てる者は、うせ果てる。』(イザヤ2:28)と言われている通りである。もしユダヤが神を捨てなければ、神もユダヤを捨てられはしなかったであろう。というのも神とは人間にその行ないに応じて報いられる御方だからである。それは神について次のように言われている通りである。『あなたは、恵み深い者には、恵み深く、全き者には、全くあられ、きよい者には、きよく、曲がった者には、ねじ曲げる方。』(詩篇18:25~26)
【21:42】
『イエスは彼らに言われた。「あなたがたは、次の聖書のことばを読んだことがないのですか。『家を建てる者たちの見捨てた石。それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には、不思議なことである。』』
キリストは、この詩篇の御言葉は、御自身について言われたものだと、ここで言っていられる。つまり、この御言葉は、『家を建てる者たち』であるユダヤ人が『石』であるキリストを『見捨てた』が、そのキリストが『礎の石』となり信じる者たちの土台となるであろう、と言われているのだと。キリストが『石』であるというのは、Ⅰペテロ2:4の箇所でも言われている。ペテロも、この詩篇の御言葉に基づいて、キリストが捨てられることについて語っている(Ⅰペテロ2:4~8)。キリストが『礎の石』つまり信じる者たちの土台であるというのは、パウロもⅠコリント3:11の箇所で言っている。『家を建てる者たち』がユダヤ人を指しているというのは、実際にユダヤ人がキリストという石を見捨てたのだから、誰でも分かることである。キリストは、この詩篇の御言葉が御自身について言われているということを知っておられた。何故なら、この詩篇の御言葉は、キリストの霊により書かれたのだからである。だからこそ、キリストはここで詩篇の御言葉について弟子たちに悟らせようとしておられるのだ。
要するに、ここでキリストは弟子たちが葡萄園の例え話を聞いて詩篇の御言葉を思い返さなかったのか、と幾らか責めるようにして言っておられるのである。この例え話から詩篇の御言葉を思い返さない君たちは一体どれだけ鈍感なのか、と。弟子たちのキリストに対する答えは(21:41)、一見すると正しく答えられているかのように感じられる。しかし、キリストは弟子たちの答えを良しとはされなかった。弟子たちは詩篇の御言葉を心に思い浮かべるべきだった。そして、次のようにキリストに答えるべきであった。「主よ。私たちは詩篇であなたが御自身の民から捨てられるが、やがて礎の石となられると書かれているのを思い出しました。」このように答えればキリストから次のように言われたことであろう。「その通りです。あなたがたに言うが、これから人の子は捨てられます。しかし信じる全ての民族の礎となるために蘇えります。」つまり、弟子たちの返答は100点満点中80点といったところであったと言える。100点になるためには詩篇のことを言わねばならなかった。
【21:43】
『だから、わたしはあなたがたに言います。神の国はあなたがたから取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。』
この御言葉の通り、ユダヤ人からは神の国が取り去られ、『神の国の実を結ぶ国民』に与えられることになった。それは、ユダヤ人ではない全ての民族、つまり異邦人たちである。彼らは『神の国の実を結ぶ国民』であった。それは、キリスト教の2千年間の歴史を見れば分かる通りである。もう今やユダヤ人たちからは神の国が取り去られているので、彼らに神の国はなく、それゆえ神の国の実を結びたいと思っても出来なくなってしまった。これからも、この状態は変わらないであろう。
要するに、神はユダヤ人が神の国に相応しくないと判断された。だからこそ、神の国が他の民族に移されたわけである。これは、何度も不倫を重ねる妻を夫が離縁したり、幾度となく反抗するどうしようもない子どもが家から追い出されるようなものであった。それだからユダヤ人は神の国を取り去られても文句を言うことが出来なかった。彼らから神の国が取り去られたのは自業自得だったのだから。しかし、ここで次のような疑問を持たれる方がいるかもしれない。すなわち、もしこれから異邦人がユダヤ人のように反逆を重ねるようになれば、異邦人もユダヤ人のようにやがて神の国が取り去られてしまうことになるのではないか、と。私は言うが、確かにもし異邦人が背信を重ね続ければユダヤ人の二の舞となることは避けられないものの、異邦人がそのようになることは決してないであろう。何故なら、聖書には異邦人がそのようになるなどとは教えられていないからである。聖書は、神が異邦人の中に永遠に聖所を置かれ続けると教えている。それだから、我々は異邦人の未来について心配すべきでない。神は、いついつまでも異邦人のうちに神の国を据え続けられるであろうから。
【21:44】
『また、この石の上に落ちる者は、粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛ばしてしまいます。」』
これは一体どういう意味であるか。まず『この石の上に落ちる者は、粉々に砕かれ』るとは、石であるキリストの福音に落とし穴に落ちるかのようにして不意に落ちる者は霊的に断罪される、ということだと思われる。つまり、これは思いがけず福音を聞くことになった者である。信じない者は、福音を聞いて断罪されるのだから、霊的に粉々にされてしまうのである。信じるようになる者の場合、そのように砕かれることはなく、キリストという石の上に立つことが出来る。この部分は難しいが、今の私としては、このように捉えるのがよいと思う。また更に良い解釈が与えられたならば、その時には、この箇所を書き直すことになるであろう。次に『この石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛ばしてしま』うというのも、石であるキリストの福音を誰かから聞かされた者は、霊的に断罪されるという意味なのであろう。その福音を聞いて信じる者は、福音を聞かされても粉微塵に吹き飛ばされることはない。何故なら、その人の場合、キリストを天から降って来る命のパンとして食べるからである(ヨハネ6:50~51)。この部分も難しい。これもまた更に良い解釈が与えられたならば、書き直されることになるであろう。
キリストは、この言葉をパリサイ人たちを指して言っておられる。パリサイ人たちは痴呆や精神障害者ではなかったから、キリストが自分たちのことについて言っておられるのに気付いた(マタイ21:45)。当然ながらパリサイ人たちは憤り、このように言ったキリストに対して殺意を抱いた。そういうわけで、やがてキリストは捕えられて殺されてしまうことになったのである。キリスト御自身は、このように言えばパリサイ人たちが怒りを持つようになることを予め知っておられた。それにもかかわらず、キリストはパリサイ人を指してこのように言われるのを憚らなかった。それはキリストが御父の御心に従い、十字架の贖いが実現されるようにするためであった。というのは、もしパリサイ人たちが発憤しなかったのであれば、キリストが捕えられることもないままだから、十字架刑が実施されることもなかったからである。
【22:1~2】
『イエスはもう一度たとえをもって彼らに話された。「天の御国は、王子のために結婚の披露宴を設けた王にたとえることができます。』
キリストは、天国を、王子のために設けられた結婚の披露宴になぞらえておられる。他の箇所でもキリストは、天国について何かの例えを用いて語っておられる。キリストがそのように何回も天国について例えをもって話されたのは何故だったのか。それは天国が非常に重要だからである。もし天国がどうでもよいものであれば、ここまで色々と弟子たちに語られることもなかったであろう。
『天の御国』とは、紀元70年に開始された天上の聖なる王国のことである。披露宴を設けた『王』とは父なる神である。『王子』とはキリストである。『結婚』とは、すなわち再臨が起きてからキリストと聖徒たちが夫婦のようにいついつまでも一緒に歩むようになることを言っている。『披露宴』と言われているのは、実際の結婚披露宴に多くの人々が招かれるように、再臨が起きてから天上の御国へと招かれる人が多いことを教えている。実際、人々が携挙されて神の御許に集められたのは、結婚の披露宴に多くの人々が集って賑やかにしている時の喜びと似ていたのである。
【22:3】
『王は、招待しておいたお客を呼びに、しもべたちを遣わしたが、彼らは来たがらなかった。』
『招待しておいたお客』とは、旧約時代のユダヤ人のことである。彼らは、アブラハムの時から、やがて来たるべき天上の王国に入れるようにと神からの招きを受けていた。この客たちに遣わされた『しもべたち』とは、神が遣わされた使者たち、すなわちキリストが言っておられる『預言者、知者、律法学者たち』(マタイ23章34節)のことである。その使者たちは、お客であるユダヤ人たちが、やがて天上の王国に入る者として相応しい歩みをするようにと、ユダヤ人たちを教え、導き、勧め、断罪した。エリヤやエレミヤが、その代表的な人である。そのような使者たちがせっかく遣わされたのに、『彼らは来たがらなかった。』とここでは言われている。これは、旧約のユダヤ人たちが、神から遣わされた使者たちを拒絶したということを教えている。彼らの背信と不敬虔と偶像崇拝を考えれば分かるが、彼らが求めているのは天上の王国というよりは、むしろサタンの王国、人間の王国、罪と背信の王国であった。彼らはその行ないによって、暗黙のうちにこう言っていた。「私たちには天上の王国など必要ありません。私たちは私たちの好きなようにしていたいのです。神はどうか私たちに御自身の使いなどをもうお送りにならないように。」と。
【22:4】
『それで、もう一度、次のように言いつけて、別のしもべたちを遣わした。『お客に招いておいた人たちにこう言いなさい。「さあ、食事の用意ができました。雄牛も太った家畜もほふって、何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。」』』
僕たちを遣わしても駄目だったので、王は『別のしもべたち』を遣わすことにした。つまり、ユダヤ人たちが神から遣わされた預言者などの使者たちを拒絶したので、更に神が使者たちを遣わして、彼らが天上の王国に入る存在として相応しい歩みをするようにと働きかけられた。1回目は駄目でも2回目またはそれ以降であれば上手にいった、というケースが世の中には往々にして見られる。例えば、日本の有名な漫画家である鳥山明は漫画のネーム(簡単な下書きのようなもの)を担当の編集者に見せたところ、即「ボツ」と言われて退けられたのだが、いくらか経ってから再び同じネームを恐る恐る見せたところ、今度は何故か「良し」と言われたという。このようなケースは、世の中にはいくらでもあることであろう。また、ここで言われている王の言葉から、天上の王国には大きな幸いがあることが分かる。『食事』とか『雄牛も太った家畜もほふって』とか『宴会』などという言葉を読んで、幸いなイメージを持たない者がいるのであろうか。恐らくいないのではないかと思われる。これは天国における喜びを示しているのだ。キリストは他の箇所でも、天上に人々が集う際における幸いを宴会という出来事において語っておられる(マタイ8:11)。我々が今見ている箇所の例え話では、たったの2回しか使者が客に遣わされていないが、実際は幾度となく客であるユダヤ人の所に使者たちが遣わされたことに注意せねばならない。この箇所で言われているのは例え話であるが、例えというのは細部まで一致していることを必ずしも要求されていない。実際の出来事と例え話を細部まで一致させることは不可能に近いから、通常の場合、例え話は大まかに理解できるのあれば、それで問題はない。それだから、実際は何回も使者が遣わされているのにここでは2回しか使者が遣わされていなかったとしても、我々はいぶかるべきではない。
【22:5~6】
『ところが、彼らは気にもかけず、ある者は畑に、別の者は商売に出て行き、そのほかの者たちは、王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。』
せっかく使者が遣わされたのに、招待されていた者たちは、その使者を拒絶しただけでなく、酷い目に遭わせることさえした。『彼らは気にもかけず、ある者は畑に、別の者は商売に出て行き』とは、つまり使者たちをユダヤ人が蔑ろにし無視したということである。ちょうど聖なる話を聞かせてくれたパウロに対して、アテネ人たちが『あざ笑』ったり、「このことについては、またいつか聞くことにしよう。」(使徒行伝17:32)などと残念な応対をしたように。『捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。』とは、つまり使者たちをユダヤ人が大いに迫害したということである。いったい、ユダヤ人たちはどれだけ多くの使者たちを捕えたり恥ずかしめたり殺したりしたことであろうか。
【22:7】
『王は怒って、兵隊を出して、その人殺しどもを滅ぼし、彼らの町を焼き払った。』
せっかく遣わされた使者たちが酷い取り扱いを受けたので、怒った王は兵士を出して、招いておいた客たちを滅ぼした。これはユダヤ戦争においてユダヤ人たちが、ローマ兵により攻め滅ぼされたことである。ユダヤ人たちはそれまで何度も遣わされていた使者たちを退け、最後の使者でありそれ以上の存在が考えられない使者であるキリストをさえも退けてしまった。これでは神の怒りが燃え上がって当然である。だからこそ、神はローマ兵を動かしてユダヤが破滅するようにされたのだ。神はこのように復讐される御方である。聖書はこう言っている。『主は報復の神で、必ず報復される』(エレミヤ51章56節)。つまり、ユダヤが滅ぼされたのは裁きによったのであり、何ら理由なくして滅ぼされたというのではなかった。それゆえ、もしユダヤが使者たちを受け入れて神に従順になっていたとすれば、このような滅びの刑罰を受けることはなかったであろう。
このユダヤ人たちは、自分たちが滅ぼされたことについて、何も文句を言えなかった。何故なら、彼らは自分たちの罪に対する当然の報いを受けたのだからである。罪の種を蒔けば、やがて刈り取ることになるのは「裁き」という名の果実である。「自業自得」という言葉は仏教用語であるが、この言葉が言っていることは誠に正しい。
【22:8~9】
『そのとき、王はしもべたちに言った。『宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちは、それにふさわしくなかった。だから、大通りに行って、出会った者をみな宴会に招きなさい。』』
ユダヤ人たちは、天上の王国に入るには相応しくない人たちであった。何故なら、彼らは邪悪な性質を持っており、神からの使いを飽きることもせず拒絶し続けたからである。このような者たちが天国に導き入れられないのは当然であった。もしこのような者たちが聖なる天国に入ってきたのであれば、天国は即座に汚されて悲惨な場所になってしまうだろうからである。それは、清らかな水の満ちたプールに、考えられないぐらいに毒性の強い液体を混ぜるようなものである。
神は、ユダヤ人たちが天上の王国に相応しくなかったので、他の民族を招くようにと指示した。神は、何とかして結婚の披露宴に多くの人が集まってほしいと願われた。それというのも、それは王子の結婚披露宴だからである。このような神聖な披露宴が無観客であっていいはずはない。だから、神は元来であれば招かれていなかった者たちである異邦人が天国に招かれるのを良しとされたわけである。誰も王子の披露宴に来ないよりは、たとえ異邦人であっても多くの人たちが招かれたほうが遥かに良かったのだ。
【22:10】
『それで、しもべたちは、通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った者をみな集めたので、宴会場は客でいっぱいになった。』
この僕たちは指示された通りに善人であれ悪人であれ披露宴に来るようにと招いたので、『宴会場は客でいっぱいになった』のであった。これは、紀元70年に起きた第二の携挙である。この箇所では、本来的に招かれていた客たちが滅ぼされて後、すぐにもかつては招かれていなかった人たちが宴会場へと招かれている。実際の歴史でも、アブラハムの時からずっと招かれ続けていたユダヤ人たちがユダヤ戦争で滅ぼされて後、すぐにもかつては神の国を持っていなかった異邦人たちが上に引き上げられた。ここで言われている出来事を、第一の携挙として捉えないようにせねばならない。第一の携挙は、ユダヤ人たちが滅ぼされる前に起きたのであって、その時に携挙されたのはただ救いに定められていた聖なる者たちだけであった。しかし我々が今見ている箇所に書かれている招きの出来事は、客たちが滅ぼされた後で起きており、しかも良い人だけでなく悪い人も招かれている。これは明らかに第二の携挙である。もしこの箇所で言われているのが第一の携挙であったとすれば、客が滅ぼされることについて書かれている22:7の箇所よりも前で、そのことが書かれていたことであろう。
ここで言われている『通り』とは、全世界のことである。つまり、第二の携挙が起こる際には、世界中から人々が上に引き上げられるということだ。とはいっても、その時に引き上げられたのは、あくまでも教会という牧場に属する羊(クリスチャン)と山羊(偽クリスチャン)だけであったことに注意せねばならない。狼すなわち教会と関係を持たない不信者や異教徒たちまで上に引き上げられたなどと考えるのは誤りである。
【22:11~12】
『ところで、王が客を見ようとしてはいって来ると、そこに婚礼の礼服を着ていない者がひとりいた。そこで、王は言った。『あなたは、どうして礼服を着ないで、ここにはいって来たのですか。』しかし、彼は黙っていた。』
宴会場には多くの人が集まったが、その中には『婚礼の礼服を着ていない者がひとりいた』。これは山羊のことであり、この山羊は『婚礼の礼服』であるイエス・キリストを着ていないのである。人がイエス・キリストという衣服を着ることについて、パウロは次のように言っている。『バプテスマを受けてキリストにつく者とされたあなたがたはみな、キリストをその身に着たのです。』(ガラテヤ3章27節)つまり、羊であるクリスチャンとはキリストという衣をその身に着た者であり、山羊である偽クリスチャンとはキリストという衣を身に着けていない者だということである。この箇所では、この山羊が、第二の携挙によりキリストの御前に羊たちと一緒に集められるということが言われている。ここではこの山羊が『ひとりいた』と書かれているが、『ひとり』と書かれているからといって、上に集められた山羊が少ししかいないということを言っているのではない。これは、単に一人の山羊が例え話の中でピックアップされているだけに過ぎない。実際には、実に多くの山羊たちが礼服を着ていない状態で上に引き上げられた。それは、第二の携挙によって人々が集められた際には、山羊たちも『大ぜい』(マタイ7:22)キリストの御前に立たせられたと山上の説教の中で示されている通りである。
この者は礼服を着ていないので王から礼服を着ていない理由を聞かれたが、何も答えずに黙っていた。この者が黙っていた理由は何だったのか。答えられなかったのか、それとも答えたくなかったのか。詳細は分からないが、とにかくこの者が気まずい思いを持ったことだけは間違いない。それと同じように、第二の携挙によりキリストの御前に集められた山羊たちは、キリストの御前において大いに気まずい思いを持つことになったであろう。それというのも、キリストの御前にキリストという礼服を着ずに立つのは、あまりにも恥ずかしいことだからである。それは、ちょうど園遊会に参加して天皇が自分の目の前に来た時、全裸姿の状態で立っているようなものである。こんなにも見苦しい醜態は他に考えられないが、キリストの御前に礼服無しで立った山羊たちもこれと同様だったのである。
【22:13】
『そこで、王はしもべたちに、『あれの手足を縛って、外の暗やみに放り出せ。そこで泣いて歯ぎしりするのだ。』と言った。』
キリストという礼服を着ていなかった邪悪な山羊どもは、第二の携挙によりキリストの前に集められはしたものの、『外の暗やみ』である地獄へと投げ込まれた。というのも、キリストに属していない者たちは、すべて地獄に行かねばならないというのが神の定めだからである。それゆえ、この山羊どもが地獄に投げ込まれるように命じられたのは、何もおかしなことではなかった。『あれの手足を縛って』と王は言っているが、これは地獄には何の自由もないことを教えている。自由とは恵みにより与えられる制限のない状態のことであるが、地獄にはまったく恵みがないので、自由がそこには存在しないのである。『外』というのは「天国の外」という意味であり、それは地獄を意味している。『暗やみ』とは地獄に光がまったく存在しないことを教えている。ユダ13の箇所で『まっ暗なやみが、彼らのために永遠に用意されています。』と言われているのも、この箇所と同じで、地獄にはいっさい光が存在していないことを教えている。キリストを着ていないと、このような場所に投げ込まれることになるのだ。彼らは『そこで泣いて歯ぎしりする』ことになる。
礼服を着ていなかった者が地獄に投げ落とされることになった出来事は、マタイ25:41の箇所と対応している。そこでも、山羊たちが地獄へと投げ込まれることになったシーンが描かれている。また、この箇所の出来事は黙示録20:15の箇所とも対応している。そこでも、山羊たちが地獄に投げ込まれることについて書かれている。
【22:14】
『招待される者は多いが、選ばれる者は少ないのです。」』
キリストは結論を述べられた。これは、つまり救いと天上の王国へと招かれる者たちは多いのだが、実際に救われて天上の王国へと導き入れられるようにと選ばれている者は僅かである、ということである。この例え話で言えば、どうか。最初のお客は招待されたものの、結局は誰一人として宴会場に行くことがなかった。つまり、多くの者たちが招待されていたが、その中に選ばれていた者は一人すらもいなかった。続いて招待された者たちは実際に宴会場に行ったのだが、その中には礼服を着ていない者がいた。その者は招かれて宴会場にまで行くことができたが、実は選ばれていなかった。招待される者が多いように選ばれる者も多いと考えるのは、ここでのキリストの言葉から間違いであると断言できる。我々は間違った考えを持たないように注意せねばならない。
実際の世界を見ると、どうであるか。実際の世界を見ても、確かにここでキリストが言っておられる通り、招待される者が多いのに選ばれている者は少ないということが分かる。世の中にキリスト教徒と呼ばれる者は約20億人も存在しており、彼らの多くは一応は招待されていると言える者たちであるが、その中で真に選ばれている者はどれぐらいいるであろうか。私の推測では、招待されていると共に選ばれてもいる者たちは2億人である。まず聖書的である真のキリスト教は4億人の信徒数を有するプロテスタント派だけに見られるから、それ以外の教派の者は、腐りきったローマ・カトリック教会の信徒であれ東方正教会の異端者たちであれ、招待されているだけで選ばれてはいないということになる。プロテスタント派について言えば、恐らく2億人ぐらいの人たちが真に選ばれていると予測される。というのは、プロテスタント教徒といっても、名ばかりの信徒だったり、万人救済主義を信じていたり、日曜日に教会に行っていなかったり、平気で偶像崇拝をしている者がそれなりに見られるからである。だから、実際にはキリスト教徒と呼ばれている者のうち10分の1が選ばれていることになり、10分の9は招待されているだけだということになる。実際は、もっと選ばれている者の数は少ないかもしれない。このように推測するのは、ここでのキリストの言葉の内容に反していない。キリストがマタイ7:14の箇所で、命に至る門を見出す者は『稀』であると言っておられることも心に留めるべきである。『稀』というのは、つまり僅かしかいないということである。それでは、招待されている者は多いのに選ばれている者が少ないのは、どうしてなのか。それは親というのは少しだけいる自分の子しか愛さないものだからである。人間の親が愛を注ぐのは自分の子らだけである。その数は少なく、もっとも多い親でも20人ぐらいである。通常の場合、自分の子らでない他の子らには愛を注ぐことはない。何故なら、それは他所の子だからである。それと同様に、神という聖徒たちの親も、御自分のお選びになった少数の子らだけに愛を注がれるのだ。人間の親が自分の子らでない他の子らに愛を注がないように、神という聖徒の親も御自身の選ばれた子らでない他の子らには愛を注がれることがない。人間の親が自分の子でないよく知らない子らを気にかけないように、神も聖徒という御自身の子らでない子らは愛の対象として気にかけられないのである。要するに、人間の親の持つ子が少しだけなように、神の持つ子らも少しだけなのである。だからこそ、選ばれて神の子らとして歩む者たちの数は『少ない』のである。
【23:33】
『おまえたち蛇ども、まむしのすえども。おまえたちは、ゲヘナの刑罰をどうしてのがれることができよう。』
実に辛辣な内容の御言葉である。これは、警官が取調室に連れて来られた重犯罪人に激しく怒りつつ怒鳴りつけるようなものである。パリサイ人どもの背信と堕落は、もう行き着く所まで行ってしまっていた。彼らは、もはや悔い改める余地のない状態に陥っていた。だからこそ、キリストはここでこのように厳しいことを言われたのである。もし彼らが酷い状態になっていなければ、ここまで厳しいことは言われていなかったであろう。
ここでキリストはパリサイ人どもに対して、『蛇ども』また『まむしのすえども』と言っておられる。『蛇ども』とは、パリサイ人どもが実際の蛇だと言っているのではない。そうではなく、これは彼らがサタンも同然だということである。サタンは蛇の中に入って人類を堕落させたので(創世記3章)、聖書はしばしばサタンを蛇として取り扱っている(黙示録12:9、20:2、Ⅱコリント11:3)。『まむしのすえども』というのも、パリサイ人どもが実際のマムシにより生まれた子どもだと言われているのはない。これは、彼らがマムシすなわちサタンの子どもであるということである。パリサイ人どもはサタンに属する存在だったのだから、サタンの子と言われたとしても何もおかしなことはない。キリストは、他にもヨハネ8:44の箇所で、彼らがサタンの子らであると示しておられる。確かに彼らはサタンを自分の親とする者たちであり、父であるサタンの望みを行ないたいといつも願っているのである。注意が必要だが、ここでキリストがこのように辛辣な言葉を言っておられるからというので、「何もここまで厳しく言われなくても…」などと思う聖徒があってはならない。他でもないキリスト御自身が、彼らはこのように言われるに相応しいと判断されたのである。我々人間に過ぎない者が、神の判断に文句を付けるようなことがあってはならない。
ここで言われているように、当時のパリサイ人どもは地獄に投げ落とされる運命にあった。ここでの厳しい御言葉は、彼らに対する最後通告のようなものであった。実際、このようにキリストが言われてから、彼らユダヤ人からは神の国が取り上げられ、それから数十年後に民族全体が裁きにより滅ぼされることになってしまった。その時、ここでキリストが相対しておられるパリサイ人どもを含めた多くのユダヤ人たちが、ゲヘナへと投げ落とされることになったのである。それだから、ここで言われているのは脅しではなく、脅しにより改善されるようになるのが目的とされているのでもない。ここで言われているのは、それ以上のこと、つまり「裁きの宣告」である。
【23:34】
『だから、わたしが預言者、知者、律法学者たちを遣わすと、おまえたちはそのうちのある者を殺し、十字架につけ、またある者を会堂でむち打ち、町から町へと迫害して行くのです。』
キリストが、ユダヤ人たちの悔い改めのために『預言者、知者、律法学者たち』を遣わしても、ユダヤ人たちは頑なに拒絶した。キリストは幾度となくこのような使いたちを遣わされたが、まったく駄目であった。これについては旧約聖書を読めば分かる通りである。ユダヤ人が神からの使いに対して取った振る舞いは、ここで2つに分けられている。それは「殺害」と「迫害」である。殺されたのは、イザヤやエレミヤなどが該当する。迫害されるだけで殺されなかったのはエリヤがそうである。中にはダニエルのような、ほとんど苛酷な苦難を味わいはしなかった預言者もいたが、そのような者はそこまで多くはいなかった。要するにキリストの時代に至るまでユダヤ人たちは酷い状態だったのであり、どうしようもない者たちであった。だからこそ、改善のために遣わされた神の使いたちを何度も何度も受け入れなかったのである。それは、ちょうど矯正不可能なほどに不道徳な不良少年を何度も何度も叱責しても何ら効果が生じないようなものである。なお、ここで言われている『預言者』とは、神からの直接的な託宣を受けた霊的なメッセンジャーである。『知者』とは、神によりユダヤ人たちが改善するようにと働きかける者のことである。『律法学者たち』とは、敬虔なラビたちを指している。
彼らユダヤ人たちは、永遠の昔から、このように神からの使者を受け入れることがないようにと定められていた。だからこそ、彼らは『預言者、知者、律法学者たち』を退けた。というのも、そのようになるのが神の御心だったからである。それでは、神がそのように定められたのは、一体どのような理由があったからなのか。その理由についてキリストは次のように言っておられる。
【23:35】
『それは、義人アベルの血からこのかた、神殿と祭壇との間で殺されたバラキヤの子ザカリヤの血に至るまで、地上で流されるすべての正しい血の報復があなたがたの上に来るためです。』
神からの使者たちが退けられ続けたのは、その使者たちを苦しめたことに対して与えられる裁きが、紀元1世紀の時のユダヤ人の上に注がれるためであった。神は、紀元1世紀になる時まで、それまでに犯されてきた正しい者たちに対する殺人と暴虐の罪を、ずっと裁かないままでおられた。何故なら、神は忍耐深い御方だからである。神は、それまで、ずっとユダヤ人たちが犯し続けた罪を耐え忍んでおられた。しかし、神は犯された罪を、いつかは必ず罰せられる御方である。それはナホム書1:3の箇所で、『主は決して罰せずにおくことはしない方。』と書かれている通りである。神は、紀元1世紀になると、もう耐え忍ぶべき時は過ぎ去ったと判断された。というのも、ユダヤ人はいつまで経っても悔い改めず、それ以上忍耐しつつ待っても無駄だということが確認されたからである。だからこそ、紀元1世紀において一挙に、これまでに犯され続けてきた悪に対する裁きが下されることになったわけである。これは伝道者の書3:1~8の表現を使って言えば、こういうことである。「耐え忍ぶのに時があり、裁きを与えるのに時がある。」神は、御自身に背いたユダヤ人たちを、長い間待つことなく即座に裁くこともおできになった。しかし、神の御心は、彼らの罪をずっと耐え忍ぶことであった。それは、彼らに悔い改めの機会を十分なだけ備えるためであった。
ここで言われている正しい人とは、神の子である者たちに限定して理解されなければならない。キリストは、ここでその正しい人たちを2人挙げておられるが、それはアベルとザカリヤである。彼らは永遠の昔から救いに定められていた神の子らであった。人間の目からすれば正しい人と言えるが、神の子ではない者たちは、当然ながらここで言われている正しい人の中に含まれてはいない。例えば、カミッルルスや小カトーやマザーテレサのような者たちは、ここで言われている人の中に該当しない。何故なら、このような者たちは人間の目からすれば正しいと見做されるかもしれないが、神の御前では正しくないからである。
既に第2部でも説明されたが、神は犯された罪に対して即座に罰を下されるのではなく、最後の時点になって初めて一挙に纏めて罰を下される御方である。多くの場合、神はそのようにして裁きを下される。それが神のやり方だからである。ユダヤが紀元70年に裁きを受けたのも、正にその通りであった。それというのも、そのようにするほうが、より神にとって良いやり方だからである。そのようにして最後に裁きを纏めて下すと、神の忍耐深さが豊かに示されるようになるし、悪者どもがずっと罪を犯し続けるので裁かれた際に弁解の余地がなくなるし、悔い改めることのできる機会も増し加えられて神の寛大さが明らかになるし、裁きが最大限にまで膨れ上がるので神に対する畏れや抑止力が生じたりするし、なかなか裁きが下されないものだから不敬虔な者たちが更に神の裁きを侮って霊的に盲目な状態になる。もし裁きが即座に注がれたとすれば、このような種々のメリットは生じなくなるのだ。『急ぎ足の者はつまづく。』と言われた神は、拙速が禁物であることを完全に弁えておられるのである。
【23:36】
『まことに、あなたがたに告げます。これらの報いはみな、この時代の上に来ます。』
このユダヤ人に対する裁きは『この時代』において実現されると、キリストは言っておられる。これは、その時に生きていた人々が生き残っている間に裁きが実現される、ということである。何故なら、その時に生きていた人々が全て死んでから後で裁きが実現されるとすれば、『この時代』と言うことは出来ないからである。その場合、例えば「続く時代」とか「後の時代」などと言われねばならなかったであろう。要するに、ここで言われている『この時代』という言葉は、我々が日常的に『この時代』と口にする場合の意味と同様の意味を持つ言葉として使われている。
実際、それまでに流されてきた血に対する神の報復は、『この時代』に実現された。これは紀元70年のエルサレム崩壊を見れば分かる通りである。この時、このキリストの御言葉を聞いたユダヤ人の多くは、キリストが愚かなことを言っていると感じたかもしれない。しかし愚かなのは彼らユダヤ人のほうであった。何故なら、キリストの真理の御言葉を愚かであると思うことほどに愚かなことは他にないからである。
【23:37】
『ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に遣わされた人たちを石で打つ者。わたしは、めんどりがひなを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾たび集めようとしたことか。それなのに、あなたがたはそれを好まなかった。』
キリストは、これまで実に多くの使者たちをユダヤに遣わし、ユダヤ人たちが改善されるように取り図られた。それは『めんどりがひなを翼の下に集めるように』してであった。しかし、ユダヤ人たちは、その遣わされた使者たちを常に拒み続けた。それは、雌鶏が雛を翼の下に集めようとしているのに、その雛が抵抗したり逃げ去ったりするようなものであった。これは誠に由々しきことである。だからこそ、キリストはここで『ああ、エルサレム、エルサレム。』などと言って彼らについて嘆いておられるのだ。せっかく神が善意から使者たちを遣わして下さったというのに、それを拒むというのは、愚かさの極みであり見苦しい礼節違反であると言わねばならない。
そのようにユダヤ人が使者たちを拒んだのは、彼ら自身の意志によった。『それなのに、あなたがたはそれを好まなかった。』とキリストが言っておられる通りである。だから、ユダヤ人たちに報いが与えられることについて弁解の余地はまったく無かった。もし彼らが嫌々ながら使者たちを拒んでいたとすれば、つまりそうせざるを得ない何か強制的な力や要因があったとすれば、裁きを免れることの出来る余地が幾らかはあったかもしれない。しかし、彼らは嫌々ながら拒んだのではなかった。よって、彼らが裁きにより滅ぼされることについて、彼らは文句を言うことが許されていなかった。
【23:38】
『見なさい。あなたがたの家は荒れ果てたままに残される。』
これは、ユダヤが滅ぼされて神から永遠に遺棄された状態になってしまう、ということである。つまり、これは物理的な荒廃について言われたというよりは、むしろ契約的なことが言われている。もはや神とユダヤとの契約関係は永遠に破棄されてしまう、と。ここで言われているのは預言である。それは紀元70年9月に実現されている。キリストがこのように言われた時には、まだユダヤの家は荒廃していなかった。『見なさい。』と言われたのは、つまり「よく心に留めなさい。」というほどの意味である。何故なら、ここで言われているのは預言であって、その預言はこの時にはまだ実現されていなかったからである。まだ実現されていない事柄を、どうして既に実現されたかのように眼球により視認できるのであろうか。
【23:39】
『あなたがたに告げます。『祝福あれ。主の御名によって来られる方に。』とあなたがたが言うときまで、あなたがたは今後決してわたしを見ることはありません。」』
これは、つまり再臨が起こるまでユダヤ人たちはもはやキリストを見ることがない、という意味である。「『祝福あれ。主の御名によって来られる方に。』とあなたがたが言うとき」とは、すなわち再臨の時である。再臨が起こると、回復するようにと定められていたユダヤ人たちは、再臨されたキリストにこう言ったのである。遺棄されているユダヤ人たちが、このように言ったというわけではない。『祝福あれ。主の御名によって来られる方に。』とは、「再臨されたキリストに御栄があるように。」というほどの意味として捉えればよい。実際、ここでキリストがこのように言われてから、間もなくユダヤ人たちは再臨の起こる時までキリストの姿をまったく見ないようになった。その期間を具体的に言えば、昇天の起きた紀元33年頃から再臨の起きた紀元68年までの間である。その期間には、あの使徒たちでさえキリストを見ることがなかった。
今の教会は、この箇所で書かれている出来事が未だに実現していないと考えている。しかし、それは既に実現している。何故なら、この箇所で言われているのは再臨のことであって、その再臨は既に起きているからである。ここまでの内容を読んだ人であればもう分かると思うが、再臨が未だに起きていないと考えるのは聖書否定である。聖徒たちは思い違いをしないように注意せねばならない。
【24:1~2】
『イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄って来て、イエスに宮の建物をさし示した。そこで、イエスは彼らに答えて言われた。「このすべての物に目をみはっているのでしょう。』
マタイ24章は、再臨を理解するためには、あまりにも重要な箇所である。何故なら、この箇所では、再臨と再臨に関わる諸々の出来事が詳しく預言されているからである。それゆえ、再臨を十全に理解したければ、この箇所は絶対に考究されなければならない。これはマタイ24章との並行箇所であるルカ21章とマルコ13章も同じである。
この箇所の出来事が起きたのは、だいたい紀元30~33年頃であった。この年代理解については人によっても数年の違いがあるが、紀元70年9月にユダヤが破滅する1世代前、すなわち約40年以内の間に起きたと理解していれば問題ない。何故なら、この箇所でキリストが預言されてから1世代が経過する間にユダヤの破滅が起こることになったからである(マタイ24:34)。
神殿から出て行かれたキリストに『弟子たちが近寄って来』る前、この弟子たちは神殿のことについて話し合っていた。ルカ21:5の箇所を見れば分かる通りである。彼らは、『宮がすばらしい石や奉納物で飾ってあると話していた』。そして、話し合っていたその弟子たちは、神殿から出て行かれたキリストに話しをしようとして、キリストのもとに近寄って行った。この時に話しかけたのは一人だけであった。それはマルコ13:1の箇所を見れば分かる通りである。つまり、この一人の弟子は周りの弟子たちを代表してキリストに話しかけたのだ。しかし、この時にキリストに話しかけた弟子が誰だったのかは分からない。マタイ16:13~16の箇所ではペテロが弟子たちの代表としてキリストの質問に答えているから、ここでもペテロが代表者として話しかけた可能性は高い。また、この時にキリストに近寄った弟子がどれぐらいいたのかは分からない。
この弟子たちは、キリストに対し、すぐ近くにあった神殿を指し示した。ルカ21:5~6の箇所では神殿を指し示したとは書かれていないが、ルカのほうでは単に指し示したと書かれていないだけに過ぎない。では、どうして弟子たちはキリストに神殿を指し示したのか。それは、キリストが神殿についてどのように思っておられるのか、また何と言われるのか知りたかったからである。我々も、何か気になる事柄があれば、専門家や識見の高い人に質問したり意見を求めるものであるが、それと同じである。ここで弟子たちはあたかも次のように言っているかのようである。「先生はこの神殿についてどう思われるのでしょうか、この神殿について何と言われるのでしょうか。」
【24:2】
『まことに、あなたがたに告げます。ここでは、石がくずされずに、積まれたまま残ることは決してありません。」』
キリストは『まことに、あなたがたに告げます。』と言われた。これはキリスト特有の強調語法である。これは次のように言っているのも等しい。「これから私が語ることは非常に重要であって真実なことだから、あなたがたはよく聞き、シッカリと心に留めなければならない。」このような前置きは、非常に権威ある言い方である。
ここでキリストが言われたのは、もちろんエルサレム神殿の崩壊についての預言である。これは誠に重大なことであった。だからこそ、キリストは『まことに、あなたがたに告げます。』などと前置きの言葉を口にされたのである。
このキリストの預言の通り、確かに弟子たちの指し示した神殿は、石が崩されずに積まれたままで残ることはなかった。紀元70年9月2日に、この神殿は文字通り跡形も無くなってしまった。ユダヤの罪に対して神の恐るべき怒りが注がれたために、このような悲劇が起きてしまった。オイディプスの悲劇も、ルクレティアの悲劇も、エルサレム神殿崩壊の悲劇に比べれば小さな悲劇である。とはいっても、この神殿崩壊は、ユダヤ以外の民族にとっては特に重大であるとは感じられない出来事であった。何故なら、彼らは霊的な事柄を正しく理解できないからである。しかし、霊的な事柄を理解できるユダヤ人にとって、これほどまでに大きな悲惨は考えられないものであった。それは今に至るまでもそうである。今でもユダヤ人は、この時に残されたあの「嘆きの壁」の前に行って、祈りを捧げたりこの悲劇について心に思い返したりしているのである。
このような預言をキリストがされたのは、預言の霊によった。キリストが預言される時は、いつも預言の霊において預言をされる。黙示録でも、キリストにより示された預言は、『預言の霊』(黙示録19章10節)によったと言われている。つまり、キリストは霊においてこのように未来のことを語られたのであって、単なる予測をされたり、思いついたままにこのように言われたというのではなかった。
ところで、自由主義神学の豚や異端者や不信仰な者であれば、この箇所の記述が宗教に熱心な者による創作であると言うに違いない。すなわち、神殿崩壊について書かれているこの24:2の箇所は神殿崩壊の前に起きた出来事が記されたのではなく、神殿が崩壊してから後で作り話として記されたのだと。彼らは神的な預言など信じていないし、信じたくもないので、どうしてもこのように解さざるを得ない。というのも、これが創作だと解さなければ、必然的に預言について書かれた出来事として解さなければならなくなるからである。しかし、ここで書かれている出来事が紀元30年頃に起きた出来事であり、またマタイもこの24:2の箇所を紀元70年に神殿が崩壊する前に書き記したということは確かであるとせねばならない。何故なら、ここで書かれているのが紀元30年頃の出来事ではないと解するのであれば、聖書には偽りが書かれていると理解せねばならないことになり、もはや聖書を信じるキリスト者ではなくなってしまうからである。またマタイは神殿崩壊の起こる時期、すなわち再臨が起きた時に携挙されて地上から取り去られたのだから、それが起こる前に我々が今見ている24:2の箇所が含まれているこの福音書を書き記したということは確かである。それだから、我々は不信仰な人たちの死んだ見解に感化されてしまわないように注意せねばならない。ニーチェも言ったように現代人は神を抹殺してしまっているが、目に見える証拠を見ない限り事柄を信じようとはしない実証主義的な時代精神が普遍的となっている近代社会においては、このような死んだ見解を持った者は、いくらでも見られる。だが教会には、そのような不信仰は要らない。そういう不信仰な者たちは聖徒の集いから遠ざかれ。聖書信仰を持った者たちこそが、聖徒の集いに集うべきなのだ。
【24:3】
『イエスがオリーブ山ですわっておられると、弟子たちが、ひそかにみもとに来て言った。』
時間が幾らか経過している。キリストは神殿から出て行かれた後、オリーブ山へと向かわれた。そして、そのオリーブ山で『宮に向かってすわっておられ』(マルコ13章3節)た。そうすると弟子たちがキリストのもとに来た。この山は、神殿からあまり遠くない場所にあった。使徒行伝1:12の箇所によれば、キリストが行かれたこの山は『安息日の道のりほどの距離』であった。それだから、24:2と24:3の間には、時間的な差がある。しかし、その時間差がどれだけだったのかは分からない。24時間以内であったことは確かである。なお、ルカ21:5~7の箇所のほうでは、我々が今見ているマタイの箇所とは異なり、まったく時間差がないかのように書かれているが、実際には時間差があったことは明らかである。
このオリーブ山とは、キリストが昇天された場所であり、キリストの再臨において直下地となった場所である。またこの山には、タルムードによれば汚れを清めるための水溜めがあったようであり、エルサレム包囲の時にはローマの10箇軍団が駐留拠点とした場所であった(※)。今まで教会は、この山について心を傾けず、ほとんどこの山について語ってこなかった。何故なら、今まで教会は再臨について、まともな考究をしてこなかったからである。この山は、再臨と深い関わりを持つ山である。それゆえ、再臨についてまともな考究をしてこなかった今までの教会は、この山についてもあまり重要視しなかったわけである。しかし、私のように再臨を深く思索するのであれば、必然的にこの山に注目せざるを得なくさせられる。
(※)
1箇軍団は歩兵5000~6000人、騎兵120騎から構成されていた。
[本文に戻る]
ここでキリストのもとに行った『弟子たち』は、マルコ13:3の箇所によれば『ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレ』の4人であった。マタイも、ペテロから話を聞いて福音書を書き記したマルコと同じように、この弟子たちが誰だったのか詳しく書き記すことができた。しかしマタイはそのようにしなかった。恐らく、マタイには何か思うところがあったので、あえてこの4人の弟子について書かなかったのであろう。その理由が何だったのか我々には分からないのではあるが。
この4人の弟子たちは、『ひそかにみもとに来て』神殿崩壊のことについてキリストに尋ねた。『ひそかに』とは、すなわち「堂々とではない」という意味である。弟子たちがひっそりとキリストに尋ねたのは、周りの人の目を気にしたからであろう。何故なら、神殿崩壊とは、あまりにもショッキングな出来事だからである。この神殿とは、言うなればユダヤ人の生命また身体も同然の建築物であった。しかも、この神殿は、全地の神が住まわれる神の家である。神が、この神殿の至聖所の中におられたのだ。そのような神殿がまったく消失してしまうなどという衝撃的な話は、出来れば他の誰にも聞かれないで済むように話されるのが望ましいと弟子たちは思ったのであろう。こんな話がされたら物議を醸すのは目に見えているからである。それだから、この4人の弟子たちは騒ぎになることを恐れて、『ひそかにみもとに来』たのだと考えられる。ニコデモも人目を憚るようにして、夜の時間帯にキリストを訪ねた(ヨハネ3:1~2)。ニコデモも当時の使徒たちも霊的にまだ未熟であったが、霊的に未熟な人たちは、往々にして人の目を大いに気にして小心な振る舞いをするものである。要するに、この『ひそかに』という短い言葉は、当時の使徒たちの霊性を如実に示している言葉として捉えることができる。
『「お話しください。いつ、そのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりには、どんな前兆があるのでしょう。」』
弟子たちは、神殿崩壊の出来事について詳しく知りたかったので、ここでキリストに対してそのことを尋ねている。何故なら、神殿崩壊とは非常に重大な事柄だったからである。例えば、これからイギリスがアトランティスのように沈没させられるなどと聞かされたら、多くの人が一体どういうことなのかと尋ねないであろうか。恐らく、多くの人が尋ねることであろう。何故なら、イギリスがアトランティス化するなどという話は、事柄があまりにも重大だからである。ここで弟子たちが神殿崩壊についてキリストに質問したのは、現代人がイギリスの沈没について質問するようなものであった。
ここで弟子たちは『いつ』と言い、神殿崩壊が起こる時期がいつなのかキリストに尋ねている。神殿が跡形も無くなるというのは、あまりにも重大である。それだから、弟子たちはそれがいつ起こるのか知りたいと思ったのだ。これに対するキリストの返答は、非常に曖昧であった。主は、ただその時期を大まかに告げられるだけで、正確な年月については一切知らせておられない。それどころか、主御自身でさえもその時期は知らないとまで言われた。すなわち、マタイ24:36の箇所ではこう言われている。『ただし、その日、その時がいつであるかは、だれも知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。』キリストは、もちろん神としては神殿崩壊がいつ起こるのか完全に知っておられた。だから、弟子たちにその年月を告げようと思えば告げることがおできになった。しかし、キリストはそうされなかった。どうしてなのか。その理由は、聖徒たちがいい加減にならないためであった。もし神殿が崩壊する時期が正確に告げられると、それを聞いた聖徒たちに怠惰が忍び込む可能性があった。「神殿が崩壊するまでは時間があるから、今はまだ気を引き締めておかなくてもよいだろう。また時期が近づいてきたらシッカリとすればいいのだから。」私が怠惰と言ったのは、このような安楽を求める心となることである。キリストの血により清められた聖徒たちといえども、この地上において罪人であることには変わらないから、もし神殿崩壊の時期が正確に告げられたとすれば、このような思いが心の中に入り込んだとしても不思議なことはない。しかし、神殿崩壊の時期が告げられなければ、常に気を引き締めておかねばならない必要性が生じる。何故なら、いつ定められた時が来るのか分からないのだから、いつその時が来てもいいように準備をしておかねばならないからである。キリストは、聖徒たちの心に安楽への欲求を忍び込ませることは望まれなかった。だからこそ、キリストは神殿崩壊の時期については、弟子たちに何も知らせないでおかれたのである。
また弟子たちは、ここで神殿が崩壊する『前兆』について尋ねている。この4人の弟子たちは、神殿崩壊という誠に衝撃的な出来事が起こる前には、何らかの前触れが見られるのではないかと考えた(その考えは当たっていた)。だからこそ、ここで彼らはその前兆が一体どういったものなのか、キリストに質問したのである。つまり、この弟子たちは、神殿崩壊という出来事を、その出来事の前兆となる出来事を通しても捉えようとしたわけである。事物をより多角的に捉えようとするのは、人間の持つ自然な傾向である。
さて、この箇所では、誠に誠に注目すべきことが書かれている。エルサレムにあった神殿が崩壊する時期に、『あなたの来られる時や世の終わり』が実現するというのだ。つまり、紀元70年9月に神殿が崩壊する時期に、再臨が起こり、ユダヤ世界に終わりが訪れるということだ。この2つの出来事については、これまでに豊かに論じられている。今まで教会は、私が今述べたこのことに、まったく注意してこなかった。今まで誰一人として、この24:3の箇所から神殿崩壊の時に再臨とユダヤの終焉が起こるなどとは言ってこなかった。もしそのようなことを言った人が誰かいたとすれば、もう既に本書の中で紹介していたであろう。それでは、どうして今まで聖徒たちは、このことに注意してこなかったのであろうか。それは、この24:3の箇所を読んでも、確かなところ、よく事柄が分からなかったからである。すなわち、まだ再臨について正しい理解を持つ時代ではなかったので、神の摂理により、聖徒たちはこの箇所を読んでも深く考究することが出来なかったのである。しかし今や再臨について正しい理解を持つことが許される時代が到来している。それゆえ、聖徒たちはこの箇所で言われていることを素直に受け入れ、紀元70年において神殿が崩壊した時期に再臨とユダヤ世界の終わりが実現されたと信じるべきである。素直になって聖句を直視すれば、我々には真理の正しい理解が与えられるのだ。どうして心を頑なにさせたままでいるのか?周りの目が怖いのか。間違っていても皆と一緒の理解を持っていたいのか。孤独になりたくないのか。実は聖句の正しい理解など別にどうでもいいのか。
これから続く聖句を見れば分かる通りだが、キリストは、この弟子たちの質問をまったく問題視しておられない。キリストは、何か質問の内容に問題があれば、それを容赦なく指摘される御方であった。これは福音書を見れば分かる通りである。しかし、我々が今見ているマタイ24章の箇所では、キリストはそのようにしておられない。つまり、この弟子たちが神殿崩壊の時期にこそ再臨とユダヤの終わりが起こると理解していたのは、正しい理解だった。
聖徒たちは、このマタイ24章において、2つのことを弁えるべきである。一、マタイ24章は、神殿崩壊が起こるユダヤ戦争について預言されている箇所だということ。これはマタイ24章を真面目に考察すれば、すぐにも分かることである。エドワーズも、この箇所はユダヤ戦争について言われた箇所だと理解していた。もしこれがユダヤ戦争について書かれた箇所だと理解できなければ、その人は知性に問題があると思われる。二、その神殿崩壊が起こる時期にこそ、キリストが再び来られ、ユダヤの世が終わりを迎えた、ということ。これもマタイ24章を真面目に考えれば、容易に理解できることである。この2つの事柄を弁えなければ、聖書、特に再臨について十全に理解することはできない。この2つの事柄を弁えるのは、言わば再臨を理解するためのキーである。このキーを獲得すれば、再臨を大いに理解できるための扉が開かれるのだ。今まで教会は、このキーを獲得していなかったので、いつまで経っても再臨について正しい理解を持つことが出来なかった。
ところで、ルカのほうでは弟子たちがキリストに対して『先生。』(ルカ21:7)と呼んでいる。我々が今見ているマタイのほうでは、『先生。』という呼びかけの言葉は書かれていない。本当は言われていないにもかかわらず、ルカのほうで『先生。』と弟子たちが言ったと記しているということは有り得ない。つまり、ルカが記しているように本当は『先生。』と弟子たちが言ったのだが、マタイはあえてその呼びかけについて書くことを省略したということである。それだから、我々は、この箇所で実際には弟子たちが『先生。』などとキリストに呼びかけたことを知るべきである。それでは、どうしてマタイは、キリストに対するこの呼びかけの言葉を省いたのか。それは、マタイがキリストと弟子たちの関係にではなく、ユダヤの終末についての事柄にこそ読者の心を向けさせたかったからであると思われる。『先生。』などという呼びかけの言葉が書かれていなければ、それだけ読者の心がキリストと弟子たちの関係にではなく、やがて来たるべき悲惨な出来事のほうに集中されるようになるのは確かである。マタイ24章の主題は人ではなく出来事にあるのだから、マタイはこのような呼びかけを記すことは不要であると判断したのであろう。マタイがこの4人の弟子たちの名前を詳しく書き記さなかったのも、恐らく同じ理由からだと思われる。
【24:4】
『そこで、イエスは彼らに答えて言われた。』
主は、この弟子たちの質問に対し、快く返答をしておられる。その返答は非常に詳しく、25:46の箇所まで続いている。
我々は、キリストの返答から3つのことを知るべきであろう。まず、キリストは寛大な御方であられたということである。キリストは非常に恵み深い御方であった。だからこそ、ここまで豊かに弟子たちにお語りになられたのだ。二つ目は、弟子たちがキリストにした質問の内容は間違いのないものであったということである。既に述べたように、もし間違った内容のことを弟子たちが質問していたとすれば、キリストはそのことについて多かれ少なかれ何かを言っておられたはずである。三つ目は、キリストの返答内容は、どれも皆、真実だったということである。何故なら、キリストは預言の霊によって、これらのことを返答されたからである。預言の霊とはすなわち神の霊だから、決して誤ることがないのである。
【24:4~5】
『「人に惑わされないように気をつけなさい。わたしの名を名のる者が大ぜい現われ、『私こそキリストだ。』と言って、多くの人を惑わすでしょう。』
神殿が崩壊する前兆となるのは、「偽キリスト」の大量出現である。その時には、『『私こそキリストだ。』と言って、多くの人を惑わす』馬鹿者が多く現われると、キリストはここで言っておられる。つまり、そのような愚かな者たちが現われたならば、もう神殿の崩壊は間近に迫っているということである。このような者たちが、自分こそキリストだと言う理由は何なのか。それは、彼らの持つ野心と虚栄心が理由である。人々に自分がキリストであると認めさせられたのであれば、人々からの崇拝と賛美と称賛とを我が物にすることができる。こんなにも野心家の虚栄心を満足させる状態は他にないであろう。もし失敗すれば大きな恥をかくが、上手に行けば最高の喜びが味わえる。それゆえ野心に動かされた者たちは、一か八かの思いで、『私こそキリストだ。』と言って人々を自分に引き付けようとするのである。このような者は、忌まわしい者である。最近の時代で言えば、あのダーウィンも、この種の人間に該当する。ダーウィンは、自伝の中で臆せず告白しているように、強い虚栄心を持っていた。何とかして人々から評価されたい、ビッグになりたい、という思いが彼の心にはあった。シオン議定書によれば、ダーウィン理論は「ユダヤの仕掛け」である。つまり、これはダーウィンが自己の虚栄心を満たすために、ユダヤの陰謀家の前に膝をつき、彼らに従って偽りの理論を体系化するという大事業を成し遂げたことを意味している。その結果生まれたのが、あの「種の起源」というわけだ。ユダヤの陰謀家は、成功したい人間の下心に上手につけ込む手法をよく使うので、有名になりたくてたまらなかったダーウィンにも働きかけたということなのであろう。近頃よく話題になることの多いレディー・ガガという女性歌手もイルミナティであるが、彼女もこのような手法によりイルミナティに取り込まれた(無名時代の頃からずっと成功したいと願っていたが成功できなかったので、その悩みにイルミナティがつけ込んだのである)。ダーウィンの父がフリーメイソンだったという事実も(これも自伝の中で記されている)、私が今言ったことをますます確かなことだと感じさせる要素の一つである。少し話がダーウィンの事柄に逸れてしまったが、自分こそが人々から注目される者になりたいと願っている点で、このダーウィンと偽キリストは一緒である。実に野心こそが、偽メシア、偽預言者、偽偉人を作り出すのだ。実際、神殿が崩壊する前の時期には、このような偽キリストが大量に現われたと我々は信じるべきである。何故なら、御言葉がそのように言っているからである。
キリストは、このような偽キリストに惑わされてはならないと言っておられる。何故なら、このような者は嘘つきであって、本当のキリストではないからである。しかも、このような邪悪な野心家が、正しい福音の教えを持っていることはまずない。何故なら、彼らには聖霊が与えられていないからである。聖霊が与えられていないからこそ、『私こそキリストだ。』などと言って人々を惑わすのである。そんな者が、福音を誤らずに信じていることが一体どうしてあるであろうか。そのような者に取り込まれてしまえば、聖徒たちの信仰が異常になり、最後には地獄に落ちることにもなりかねない。そのようになるのはキリストの御心ではない。だからこそ、キリストはここで、聖徒たちがそのような偽キリストに惑わされないようにと、あらかじめ注意させておかれたのである。つまり、キリストは愛ゆえに、このようなことを聖徒たちに言われた。もし愛がなければ、わざわざこのようなことを言われはしなかったであろう。愛があるからこそ、大変な状態にならないようにと注意を促すのだ。親も自分の子どもに対し、「変なオジサンに付いていったら駄目だよ。いいね。」などと言ったりするものである。
もう今の時代となっては、『私こそキリストだ。』などと言う者が多く出現することはないかもしれない。たとえ出現したとしてもごく一部の者だけだろうし、今の聖徒たちはそんな者に誰一人として惑わされたりはしないであろう。だが我々は、偽キリストではなくても、愚かにも人に惑わされてしまったりしないように気をつけねばならない。というのも、「人に惑わされないようにする」というのは、あらゆる時代の聖徒に対する神の御心だからである。それゆえ、ここでキリストが『人に惑わされないように気をつけなさい。』と命じられたのは、今の時代に生きる聖徒たちにも向けられているのだ。もし愚かな人に惑わされたりすれば、大変なことになりかねない。信仰が異常な内容になるということもあるであろう。中には永遠の地獄に投げ込まれることになってしまったという人もいるであろう。このようなことは絶対にあってはならないのである。しかしながら、今の時代のキリスト教徒には、自分は絶対に人に惑わされてはいないと確信していながら、実は人に惑わされてしまっている人たちが少なくない。例えば、バルト主義者たちは自分は誰にも惑わされていないと思っているだろうが、実はバルトという人に惑わされている。進化論を受容しているクリスチャンは、ダーウィンという人に惑わされている。最近のプロテスタント界において代表的な神学者だと言われているミラード・エリクソンは進化論を受容しているから、彼もダーウィンに知らず知らずのうちに惑わされている。アルミニウス主義者たちは、アルミニウスという人に惑わされている。カトリック教徒たちは、教皇という人に惑わされている。切迫再臨信仰を持っている人たちは、ダービーという人に惑わされている。他にも、自分は惑わされていないと思っているのだが実は惑わされていることに気付いていない人が、少なからず存在している。全ての聖徒たちは、『人に惑わされないように気をつけなさい。』というキリストの命令に従い、愚かな教理や異常な信仰を持っている人から遠ざかり、そのような人に惑わされてしまわぬよう警戒すべきである。
【24:6】
『また、戦争のことや、戦争のうわさを聞くでしょうが、気をつけて、あわてないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし、終わりが来たのではありません。』
神殿崩壊が起こる時期には、『戦争のことや、戦争のうわさ』が耳に入ってきた。これはユダヤとローマの戦いのことである。当時のユダヤには、ローマの支配を打ち砕こうという反逆的な精神が最高潮に高まっていた。それは、怒りという名の雨水が今にもユダヤという巨大な民族ダムを決壊させんばかりであった。だから、この時期に戦争に関することが耳に入ってくるのは、何もおかしくはなかった。むしろ、そのようなことが耳に入ってこないほうが、かえっておかしいといえる状況がそこにはあった。ヨセフスの「ユダヤ戦記」を見ると、正にキリストの言われたことが紀元60年ぐらいの時期に実現していたことが確認できる。この時には、ユダヤ中に戦争の匂いがプンプンと漂っていた。なお、ここで『戦争のこと』と言われているのは戦争が既に起きた時のことであり、『戦争のうわさ』と言われているのは戦争がまだ起きていなかった時のことである。また少し時期は前になるが、このような戦争の噂は、カリグラが神殿の中に自分の像を立てさせようとした紀元40年の時にもユダヤ全体に広まった(ヨセフス『ユダヤ戦記』2巻/x1)。
キリストは、そのような戦争についての話を聞いても動揺しないようにと言っておられる。これは、聖徒たちが堅く信仰を保ち続けられるためであった。神の御心は、聖徒たちが決して揺るがされないということである。パウロも『堅く立って、動かされることなく…』(Ⅰコリント15章58節)などと聖徒たちに命じている。もし聖徒たちが戦争の話を聞いて揺らいでしまったとすれば、信仰に堅く立てず、悲惨になったり無様な振る舞いをしたりすることになりかねない。これはキリストの喜ばれないことである。だからこそ、そのようなことにならないようにと、ここでキリストは戦争の話を聞いても揺らいではならないと命じられたのであった。
ここでは『終わり』と言われているが、これは、もちろんユダヤ世界の終焉のことである。何故なら、このマタイ24章とはエルサレム神殿崩壊により起こるユダヤの破滅について預言された箇所だからである。その破滅は紀元70年9月に起きた。だから、この『終わり』というのを文字通りの意味における世界全体の終わりだと捉えてはならない。聖徒たちは、なるべく早くこのことに気付くべきだ。タルムードの中では「老人は理性を働かせられない。」と言われているが、これは間違っていない。私の考えでは、55歳を過ぎるともう理性を強力に働かせることが出来なくなる。多くの人を見てきたリークワンユーも、50歳ぐらいまでは人を変えられるが、それ以降はもう駄目だと言っている。50代後半になると、女性の生理が終わってもはや新しい生命を産み出せなくなるように、理性もその力ある使用が不可能となり新しい概念に適応できなくなってしまうのだ。老人が頑固と言われるのは、もはや理性を働かせて、今までに吸収しなかった事柄を吸収することが出来なくなるからだ。それだから聖徒たちは、出来る限り早いうちに、聖書で言われている『終わり』とはユダヤ世界について言われた言葉だということを、柔和になって受け入れたほうがよい。出産に期限があるように、理性の力ある働きにも期限があるのだから。今の時点で壮年の人であれば、これから年数が経てば経つほど、ますます今までに持ってこなかった概念を吸収することが難しくなるであろう。そうしたら、今私がここで言っていることを聞いても「馬の耳に念仏」となってしまう。中には70代以降になってから信仰を持って新しい人となる良い意味で普通ではない者もいるが、そのような人はごく稀なのである。
今の時代の聖徒たちは、世界中で起きている戦争の話を聞いて、マタイ24章に書かれている終末の時代が近づいたなどと夢想している。今の聖徒たちは、漏れなく皆、そのように夢想している。例外はほぼないと言ってよい。聖徒たちは、どこかで戦争が起きているのを耳にすると、すぐ平気で「遂に終末の時代となったか…」とか「再臨は近い。」などと口にする。しかしながら、この箇所で言われているのは、エルサレム神殿崩壊の前兆として戦争に関する話が聞かれるようになる、ということであった。このエルサレム神殿崩壊の出来事は紀元70年9月に起きた。いったい、どこに目がついているのであろうか。エルサレム神殿が未だに崩壊していないとでもいうのか。またはエルサレム神殿崩壊の前兆として起こる戦争が、未だに起きていないとでもいうのか。馬鹿馬鹿しいことである。どうしてこんなにも簡単なことさえ分からないのか、私は理解に苦しむ。今の聖徒たちが、このようなあまり難しくない事柄を悟れないのは、誠に驚くべきことである。今の時代の聖徒たちが、早くマタイ24章に書かれている事柄は昔のことだったという正しい見解を持てるようになってほしいものだ。もし今の時代に多くの戦争について話が聞かれるというので、今が正にマタイ24章の時代だというのであれば、これまでの2千年の間ずっとマタイ24章の時代だったということになる。何故なら、これまでの2千年間にも戦争は多く起きたからである。戦争についての話が多く聞かれるのは、何も今に限った話ではない。昔から、いつの時代にも戦争の話は多くされている。むしろ、今の時代は、昔に比べればやや戦争が少なくなっている時代である。中東とその周辺であれば多くの戦争が起こっているが、世界全体で言えば、かつてほどに戦争が多く起きているというわけではない。私の住んでいるこの日本で言えば、どこにも戦争は起きていない。アメリカやカナダでもそうである。それにもかかわらず、今の聖徒たちは戦争についての話を少しでも聞くと、すぐにマタイ24章の時代が来たなどと思う。戦争があまり起こらなくなっている今の時代でさえそのように思うのであれば、今よりも戦争が多かった昔の時代には、どれだけそのように思わねばならなかったであろうか。
【24:7】
『民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々にききんと地震が起こります。』
『民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり』とは何のことか。これは、ユダヤとローマのことである。すなわち、これは「ユダヤ民族がローマ民族に、ユダヤの国がローマの国に反発する」という意味である。実際、神殿崩壊が起こる前兆として、このような出来事が当時のユダヤに起きた。ユダヤ人がローマに反逆したというのは、歴史が示している通りである。今の聖徒たちは、この箇所の内容を、非常に漠然と理解している。すなわち、ここでは世界中の民族と国家が互いに対立し合うようになると言われれている、というふうに捉えている。そこには何の具体性も見らない。しかも、まだその出来事は起きていないと考えている。既に述べたことから分かるように、そのような理解は大きな誤りである。
この箇所は、イザヤ19:2の箇所と似ている。そこでは次のように書かれている。『わたしは、エジプト人を駆り立てて、エジプト人にはむかわせる。兄弟は兄弟と、友人は友人と、町は町と、王国は王国と、相逆らって争う。』
キリストはまた『方々にききんと地震が起こります。』とも言っておられる。神殿が崩壊する前の時期には、飢饉と地震も起こった。『ききん』とは、ユダヤ戦争の時に起きた酷い窮乏を言っている。その時、ユダヤには飢饉が起こり、多くのユダヤ人が飢え、その飢えのために大量の死者が出た。このような飢饉が起こると、間もなく神殿が壊滅させられることになった。だから、キリストはここで本当に確かなことを預言されたのである。なお、このような飢饉は紀元45年頃にも起きている(『ユダヤ古代誌』20:49~53、101)。『地震』とは紀元51頃から頻発した地震のことを言っている。タキトゥスは紀元51年には地震が起きただけでなく、飢饉も起こり、そのうえ不吉な鳥も出現したと記録している。「この年、奇怪な現象があいついで起った。不吉な鳥が、カピトリウムに巣くう。地震がしきりと発生し、家々が崩れる。地震の恐怖はますますつのり、群衆は周章狼狽し、弱い者が誰彼となくおし潰される。収穫物も不作だった。そのため人々は飢えに苦しむ。これすら、不吉な前兆と受けとられた。」(『年代記(下)』第12巻 43 p91:岩波文庫33-408-3)紀元59~60年頃には、「アシアの有名な町ラオディケイアが、地震で壊滅する。」という出来事も起こった(『年代記(下)』第14巻 27 p196:岩波文庫33-408-3)。紀元62年にも非常に巨大な地震がカンパニアの町ポンペイで起きた。歴史書を見ていると、確かに神殿崩壊の前の時期には不思議なぐらいに地震が多く起きていたことが分かる。そして、このような地震が起こると、やがて神殿が焼き尽くされて消失させられることになった。それだから、キリストはこの預言の中で本当に真実なことを言われたのである。今の聖徒たちは、大きな地震のニュースを聞くと、すぐにマタイ24章のことを思い浮かべる傾向がある。「最近は巨大な地震が多く起こっているから、これから終末の時代に入り、もう間もなく再臨が起こるのかもしれない…。」などと心の中で思うのだ。しかし、このように思うのは誤っている。既に述べているが、この箇所で言われているのはエルサレム神殿崩壊の前兆として起こる出来事である。すなわち、紀元70年に神殿が崩壊する前に地震が各地で起こると言われているのだ。聖徒たちには、いい加減に目を覚ましてもらいたいものである。2千年前のことについて言われた事柄を、今の時代のこととして理解して一体どうするのか。そのような理解は明らかにおかしいと言わねばならない。私はこのことを繰り返して言うことを憚らない。何故なら、教会が2千年もの間抱いてきた間違ってはいるが伝統的な理解を打破するためには、少しぐらい言うだけでは恐らく効果が弱いだろうからである。私の考えでは、2千年分もの理解を覆すためには、やはり強力で鋭い言説を何度も何度も繰り返さねばならない。
【24:8】
『しかし、そのようなことはみな、産みの苦しみの初めなのです。』
『産み』とは何か。これは、すなわち「復活」のことである。キリストが再臨されると、この地上において聖徒たちの復活が起きた。母なる教会が復活の聖徒という新しい存在を生じさせるのは、人間の母が子という新しい存在を生むのと、よく似ている。どちらも新しい存在を生じさせるという点で一致している。それゆえ、聖書では復活が出産に例えられているのである。黙示録12:5やイザヤ66:6~9でも、復活が出産として語られている。
それでは『産みの苦しみの初め』とは何か。まず、復活という母なる教会の出産が起こる前には、非常に大きな苦難が起こるということを知らねばならない。それは、実際の母親が、子を産む前に陣痛という大きな苦しみを受けるのと同じである。教会の場合、復活という出産の前に起こるこの陣痛は「ネロによる大患難」であった。すなわち、この大患難という陣痛を経ると、遂に教会に出産が起こり、復活した聖徒たちが多く生じることになった。それは紀元68年6月9日のことである。これについては、ここまで読み進められた聖徒であれば、もう十分に理解しておられるのではないかと思う。つまりキリストがここで『産みの苦しみの初め』と言っておられるのは、偽キリストの出現や国と国との対立や地震の頻発などといった諸々の出来事は、復活という出産の前に起こる大患難という陣痛における前触れとしての出来事に過ぎないのだ、ということである。つまり、それらの出来事が前触れとして起きたならば、それから後、やがてネロによる大患難がやって来るであろう、ということである。キリストはあたかも次のように言っておられるかのようである。「これから偽キリストが現われたり民族が民族に敵対したりするであろうが、そのようなことが起きても驚いてはならない。そのようなことは序の口に過ぎないものだからだ。それらの出来事が前触れとして起きれば、もっと大きな出来事があなたがたに襲いかかることになる、ということをよく知っておくがよい。」
【24:9】
『そのとき、人々は、あなたがたを苦しいめに会わせ、殺します。また、わたしの名のために、あなたがたはすべての国の人々に憎まれます。』
これはネロの大患難のことである。その時、聖徒たちは捕えられ、迫害され、苦しめられ、殺された。殺された聖徒たちの頭が松明代わりとして使用されるという侮辱も受けた。伝承によれば、ペテロは逆さ十字架にされ、パウロは斬首された。また黙示録11:9の箇所によれば、この時に殺された聖徒たちの死体は墓に納めることが許されなかった。この時にキリスト者の死体を埋葬すれば自分もキリスト者の一員であると周りの人から見做されて迫害されることになっただろうから、多くの人がキリスト者の死体を埋葬したくても出来なかっただろうことは想像に難くない。何故なら、この時にキリスト者を埋葬することは、すなわち「死」を意味していたからである。このような苦難は、キリスト者の犯した罪のゆえに下された裁きではなかった。というのも、当時のキリスト者は、このような巨大な苦難を受けるほどに堕落していたのではなかったからである。このような苦難が起きたのは、罪のためではなく、預言が実現されるためであった。ダニエルの頃から、聖徒たちが復活の前には邪悪な者から苦しみを受けるということがハッキリと預言されていた。『その角は、聖徒たちに戦いをいどんで、彼らに打ち勝った。』(7章21節)とか『彼は、いと高き方に逆らうことばを吐き、いと高き方の聖徒たちを滅ぼし尽くそうとする。』(7章25節)などと書かれていた通りである。預言が成就されないということはあってはならないことだから、聖徒たちが苦難を受けねばならないと預言されていたがゆえに、聖徒たちはネロにより『産みの苦しみ』を受けることになったのである。ところで、このような預言がされたのは、聖徒たちが苦難を受けることにより、キリストによる救いと荒らす憎むべき者に対する義なる報復がより際立ちドラマティックになるためであった。聖徒たちが苦難を受けた末にキリストが再臨されることで、より再臨と敵に対する裁きが感動的で壮大な事象となるのである。この世の全ては神の栄光のために組み立てられているのだから、神は救いと裁きがよりドラマティックになるために、聖徒たちが苦難を受けるようにとお定めになったのである。
この時、聖徒たちは『すべての国の人々に憎まれ』た。それは何故なのか。それは、当時の聖徒たちが、世界中の人々にキリストの福音を宣べ伝えたからである。信じない人々にとって、福音は『死から出て死に至らせるかおり』(Ⅱコリント2章16節)である。人々は福音という死の香りを大いに嗅がせられ苦しめられたのだから、彼らがその福音の伝達者である聖徒たちを憎んだのは自然なことであった。黙示録11:10の箇所でも、福音を宣べ伝えた聖徒たちが『地に住む人々を苦しめた』と書かれている。苦しめられたのであれば、憎しみが起こるのは必然である。実際、紀元1世紀の人々は、聖徒たちのことを大いに憎んだ。それは、聖徒たちが福音を宣べ伝えただけでなく、イエス・キリストの御名を拝んでいるからでもあった。主が『わたしの名のために』憎まれると言っておられる通りである。当時の人々にとって、イエス・キリストを拝んでいるということ自体が、聖徒たちに憎しみを持つ十分な理由であった。何故なら、聖徒たちはイエス・キリストなどという訳の分からない存在を拝んでおり、その存在を拝めと力強く説き、従来の神々をまったく拝もうとしなかったからである。当時の異教徒たちにとって、昔からの神々を拝まないで今までに聞いたこともないような存在を拝めなどと言ってくるキリスト教徒は、ただの狂った異端者以外ではなかった。当時は、信仰を持っていないのに十字架のアクセサリーを身に着ける人さえ多く見られる今の時代とは違い、まだキリスト教は一般的な存在ではなかったのである。とはいっても、彼らがキリスト教徒たちを憎みはしても、そのキリスト教徒たちにキリストを拝んでいるということ以外には何一つとして批判すべき罪状は見つけられなかったのではあるが。小プリニウスも、ただキリスト教徒がキリストを拝んでいるというだけで毛嫌いしたが、その毛嫌いしているキリスト教徒が悪しき振る舞いをしているということは全く認められなかったのである。
【24:10】
『また、そのときは、人々が大ぜいつまずき、互いに裏切り、憎み合います。』
これは、ネロによる大迫害が起きたからであった。その時、聖徒たちの多くは処刑されるために捕えられてしまった。誰に捕えられたのか。それは、ネロの命令によりやって来た役人や兵士たちに、である。この時、『人々が大ぜいつまず』いた。何故なら、処刑に対する恐れが精神を圧倒したからである。そのため、この時に真の信仰を持っていなかった者は、処刑への恐れが生じたので躓き、キリストを3度も否んだあのペテロのように無様な振る舞いを演じることになった。また、この時には人々が『互いに裏切り、憎み合』った。何故なら、捕えられ処刑場に連行されたら間違いなく死んでしまうので、多くの人が自分の命を守ろうとして逃げたり仲間を告発したり偽りの仮面を被ったりしたからである。マルコ13:13の箇所では、この時の悲惨についてこう言われている。『また兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち、彼らを死に至らせます。』日本における江戸幕府の元でキリシタン刈りが行なわれた時にも、このような状況が見られた。つまり、キリシタンである者が自分だけは助かろうとして幕府から遣わされた役人に対し自分はキリシタンではないと偽って言ったりして、キリシタンの仲間や家族を裏切ったのである。キリストがあらかじめこのように言われたのは、聖徒たちが事前にこれから起こるべき出来事を知ることで、心の準備を豊かにできるようにするためであった。未来の出来事を知っていれば、その出来事が起きた時、知らなかった場合よりも良い振る舞いができるようになるのは確かだからである。このことについては、キケロの『トゥスクルム荘対談集』第3巻で有益な学びが出来るから、気になった人は読むと良い。そこでキケロはこう言っている。「それゆえ、将来の悪を前もって考えておくことは、それが訪れた時の衝撃を和らげる。はるか以前から、やって来ることを準備しておけるからだ。」「悪とみなされる出来事は、突然であればあるほど悲惨なものになることは疑いない。予想外であることだけが苦悩を最大にする原因ではないものの、心づもりと準備は苦痛を和らげるために大いに役立つ。」(『キケロ―選集12 哲学Ⅴ』トゥスクルム荘対談集(第3巻)14:29、30 p179、180/岩波書店)このようなことのゆえ、神は聖徒たちへの配慮から、やがて起こるべき多くの悲惨な出来事を事前にキリストや使徒たちにより伝え知らせて下さったのである。
今の聖徒たちは、この出来事が、これから実現されるなどと本気で考えている。それは、マタイ24章がユダヤ戦争の時期について言われた箇所だということを知らないからだ。既に述べたように、このマタイ24章とは2千年前の時代について預言された箇所だから、これから教会に躓きや裏切りや憎悪が起こるなどと恐れるには及ばない。多くの聖徒たちが、この箇所で言われていることを心配し、多かれ少なかれ不安になっているのは、非常に残念であると思う。聖書を間違って解釈しているからこそ、そのような無意味と言うべき恐れや心配に悩まされることになるのだ。
【24:11】
『また、にせ預言者が多く起こって、多くの人々を惑わします。』
ユダヤが崩壊する前には、『にせ預言が多く起こっ』た。これは、聖書で預言されていないことを勝手に預言したり、聖書で預言されてはいるものの聖書が預言している通りには預言しない愚か者のことである。この者たちも、先に見た偽キリストと同じで、やはり名誉や野心のために偽りを預言していたはずである。というのも、そのようにすれば多くの人たちを取り込める可能性があるからだ。そうしたら自分こそが英雄のように認められることにもなる。また、このような者の中には、単にフザけて偽りの預言をしていた者もいたのではないかと思われる。ヨセフスの書に出てくる惑わす者たちは、恐らくキリストが言っておられた偽預言者のことだと思われる。ヨセフスは次のように書いている。「ぺてん師やいかさま師どもが、神の霊感を受けたと称して大きな変革をつくりだそうとして、人びとを説き伏せ、ダイモンに憑かれたかのようにさせて、荒れ野の中に導き出した。神がそこで彼らに解放のしるしを示してくれる、というのである。」(『ユダヤ戦記Ⅰ』Ⅱ xiii4:259 p314:ちくま学芸文庫)これは、もしかしたら偽預言者ではなかった可能性もある。しかしヨセフスの次の記述は、間違いなくキリストの言われた偽預言者のことである。「エジプト人の偽預言者は、これよりも大きな一撃でユダヤ人たちに悪事を働いた。このいかさま師はユダヤの土地に現われると、自分を預言者だと信じ込ませ、騙された約3万もの者たちを集めると、彼らを荒れ野からオリーブ山と呼ばれる所まで引きまわし、そこからエルサレムへ押し入る構えを見せた。彼は、ローマの守備兵たちを制圧した後、自分と一緒に踏み込む者たちを警護の者として使い、暴君として市民を支配するつもりだった。」(同5:261~262 p314)次の記述も、生々しい偽預言者についての記述である。「彼らユダヤ人たちの滅びの原因であるが、それは彼らがひとりの偽預言者にたぶらかされたためだった。その日偽預言者は、都の中にいる者たちに向かって、神はユダヤ人たちが神殿に登り、救いのしるしを受けるように命令されたと告げた。実際そのころ、多くの偽預言者が暴君たちによって雇われていた。この偽預言者たちは神の助けがあるからそれを待つようにと告げて市民をたぶらかしていた。その目的は投降する者をひとりでも少なくし、恐怖や不安の虜になっている者たちの肩を希望で叩いてやることにあった。」(「ユダヤ戦記」第6巻/v2:285~286)キリストは、このような偽預言者がユダヤの終末の時には多く出てくると言っておられる。しかし、具体的にどれぐらいの数の偽預言者が出たのかは不明である。500人ぐらいだったかもしれないし、もしかしたら1万人もいたのかもしれない。いずれにせよ、『多く』と感じられるほどの偽預言者が現れたことは間違いない。何故なら、キリストがそのように言っておられるからである。ヨセフスの書によれば、この偽預言者たちは紀元54年以降に多く現われた。
この箇所では、『にせ預言者』に惑わされないように注意せよとは明白に言われていないが、たとえそのように言われていなくても、聖徒たちが偽預言者に注意すべきであったことは言うまでもない。つまり、24:4の箇所で『人に惑わされないように気をつけなさい。』と命じられた命令は、偽預言者についても対象とされていたとすべきである。実際、主は他の箇所で、偽預言者に注意せよと明白に言っておられる。すなわち、主はマタイ7:15の箇所でこう言われた。『にせ預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやって来るが、うちは貪欲な狼です。』また、キリストのこの御言葉は、偽預言者に惑わされてしまう人が幾らかでもいる、ということを含意している。何故なら、多くの偽預言者が惑わすのであれば、一人さえも惑わされないままで済むなどということは有り得ないことだからである。確かに幾らかの人は偽預言者に惑わされてしまっただろうが、そのようになったのは神の定めであり、その惑わされた人が信仰を堅く保っていなかったからである。今の時代にも変なことを預言したりする人が少なからず存在しているから、我々も惑わされたりしないように注意せねばならない。
【24:12】
『不法がはびこるので、多くの人たちの愛は冷たくなります。』
これはパウロがⅡテモテ3:1~5の箇所で言っていることである。ユダヤの終末が近づくと、その前兆として、多くの人たちが不法をするようになった。その時には、ユダヤを荒らし回る狂暴な野盗も現れた。この野盗は不法を行なう邪悪な輩であって、ヨセフスは次のように記録している。「新手の野党がエルサレムで増殖した。シカリオイと呼ばれる者たちで、彼らは日中都の中で人びとを殺害した。彼らはとくに祭のときに衣服の下に短剣を隠し持って群衆に紛れ込み、敵対する者たちをその剣で殺した。そして、相手が倒れると、暗殺者たちは憤激する群衆のひとりになりすました。このもっともらしい素振りのために、彼らが見破られることはなかった。大祭司のヨナテスは彼らに殺害された第1号だったが、彼以後は、連日、多くの者が殺された。暗殺そのものよりもそれに伴う恐怖のほうが厄介なものだった。誰も彼れもが戦場にいるかのように、時々刻々死を覚悟した。人びとは遠方から敵対する者たちを見張り、友人たちでさえも近づいてくるときには警戒した。しかし人びとは、これほど疑い深くなって警戒しても殺された。この陰謀家たちはそれほど素早く、姿をくらますのがうまかった。」(『ユダヤ戦記Ⅰ』Ⅱ xiii3:254~257 p313~314:ちくま学芸文庫)この野盗たちは、エルサレムが陥落するまで人々を悩ませ続けた。紀元62年には、この野盗をあえて取り締まろうとはしない邪悪な総督(アルビノス)がユダヤに着任した(「ユダヤ戦記」2巻/xiv1)。64年には「強奪と拷問のかぎりを尽くし、」「町々全体を丸裸にし、全市民を虐待した」(同xiv2)フロロスという総督が着任することにもなった。このフロロスは、とんでもないことをやらかした。それは恐ろしい大虐殺であったが、このことについてヨセフスはこう書いている。「フロロスはこれらの言葉に一段と激昂し、兵士たちに向かって、「上のアゴラ(※)と呼ばれる所を略取し、出会いがしらの者を皆殺しにせよ」と怒鳴りつけた。略奪物への渇望と相俟って指揮官の激励を得たので、兵士たちは遣わされた場所で略奪を働いたばかりか、人家という人家に押し入って家人たちを虐殺した。人びとは狭い路地の中を逃げまどい、捕まった者たちは殺された。やり残された略奪はなかった。多くの穏健な者たちが捕らえられ、フロロスのもとへ引き出された。彼はこの者たちを鞭打ちの刑で苦しめた後、十字架にかけた。その日滅んだ者たちの数は全部で、女と子供たちを入れて―幼児がお目こぼしに与ることはなかった―、約3600に達した。ローマ兵たちの前例のない残忍さが災禍を一段と重苦しいものにした。というのは、その日フロロスはかつて誰もしたことのない大胆な所業、つまり、騎士階級に属する者を審判の座の前で鞭打ちし、十字架に釘打ちするという所業をやってのけたからである。たとえ生まれがユダヤ人だったとしても、少なくともローマ人としての地位のある者たちをである。」(『ユダヤ戦記Ⅰ』Ⅱ xiv9:305~308 p324~325:ちくま学芸文庫)この出来事は紀元66年6月3日に起こった。更に、ユダヤの終末の頃には、次のような不法もはびこった。ヨセフスはこう書いている。「いかさま師や野党たちが結託し、大ぜいの者たちを叛乱へ駆り立て、自由のために立ち上がるよう呼びかけた。ローマ人たちの支配に唯々諾々としたがっている者たちには死で報いると脅し、自らの意志で隷従の道を選んでいる者たちを力でもって押さえつけると言った。彼らは部隊ごとに分かれて国中に散り、有力者たちの家を略奪し、その持ち主を殺し、村々に火をかけた。こうして彼らの狂気はユダヤ全土に満ち溢れた。戦いの炎は日ほとに激しく燃え上がった。」(同xiii6:264~265 p315)シモンというユダヤ人が同胞のユダヤ人を殺しまくるという出来事も起こった(『ユダヤ戦記』第2巻/xviii4)。また同胞同士による見苦しい争いも起こった。ヨセフスはこう書いている。「どの町も騒ぎや同じ種族の者同士の争いで揺れ動いていた。そしてローマ軍が立ち去りひと息つけるようになると、彼らは攻撃の手をお互い同士に向けはじめた。抗戦派の者たちと和睦を熱望する者たちとの間の抗争は熾烈だった。家庭にはじまった争いは、旧知の友人たちを巻き込み、ついでもっとも親しい者たちでさえ互いの関係を断ち切り、それぞれが同じ考えを持っている者たちと徒党を組んで反目し合った。騒ぎは各所で発生したが、変革をもとめ武装している者たちが若さと大胆さにものを言わせて、年長の冷静な者たちを制した。土地の者たちから成るそれぞれのグループは最初は略奪に走り、次には他のグループの者たちと一緒に部隊をつくり地方を略奪して回った。災禍をこうむった者たちにとっては、同じ種族の者たちの残忍さと無法ぶりはローマ兵たちのそれと変わるものではなかったが、略奪された者たちにとっては、ローマ兵たちの手に落ちる方がはるかに軽い損害でるように思われた。」(『ユダヤ戦記2』Ⅳ iii2:131~134 p156:ちくま学芸文庫)この時期にはカイサレア市でも大きな騒擾が起こり、見苦しい不法が見られた(「ユダヤ戦記」2巻/xiii7)。またガリラヤ市でも小さからぬ騒ぎが起こった(同 xxii1:647)。要するに、ユダヤが破滅を迎える前の時期は、ユダヤが不法のパラダイスとでも呼ぶべきような状態になっていた。ところで『不法』とは、神の律法に違反することである。それだから、キリストが言っておられるように、この時には人々から愛が失われた。パウロも言うように律法の本質とは人への愛だから(ローマ13:9、ガラテヤ5:14)、人々が律法を守らなくなれば愛が減退してしまうのは当然である。愛の律法を無視して不法に歩んでいる人が多いのに、どうして愛がそこに見られるであろうか。『不法がはびこるので』あれば、そこに見られるのは冷たさ、憎しみ、嫌悪、妬み、暴力、殺意、淫乱、無関心、不和、憤り、不信、不敬などといった好ましくないものばかりである。不法があれば愛が減退するというのは、ソドムを見ても分かることである。ソドムの人々は不法をする人々であったが、たとえ自分の損にはならなくても他人の益をまったく求めようとしない人々であった。実際、この時期にはユダヤ人が「血縁関係よりも自分たち自身の安全を優先させ、同胞の者たちに立ち向かった」(『ユダヤ戦記Ⅰ』Ⅱ xviii3:466 p368:ちくま学芸文庫)のだから、キリストの言葉の通り人々から愛の熱が冷めてしまったと言える。
(※)
これは都にある広場を持つ市場であり、上と下に分かれている。
[本文に戻る]
【24:13】
『しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われます。』
この聖句は、今まで教会において幾度となく引用されてきた聖句である。
『最後まで』とは、「再臨が起きる時まで」という意味である。当時の人たちは、もし紀元68年に再臨が起こるまで耐え忍んだのであれば、救われて天国に導き入れられた。というのも、その人は最後まで耐え忍んだので、真の信仰を持っていたということが確かとなったからである。これは、ある試験を受けた人が、高い能力を持っているためにその試験に合格して資格を得られるようになるのと似ている。とはいっても、聖徒たちの場合、能力も資格も全ては神からの恵みによってしか持てなかったのではあるが。一方、再臨の時まで耐え忍ばなかった人たちは、天国に導き入れられなかった。何故なら、その人たちは耐え忍ばなかったので、真の信仰を持っていなかったことが確かとなったからである。これは、ある試合のチケットを買わなかった人が、試合の当日になってチケットを持っていなかったために試合会場に入れなかったのと似ている。チケットを持っていなければ会場に入れないように、信仰というチケットを持っていない人は天国という会場に決して入れない。
「最後まで脱落しなければ幸いな状態を享受できる」ということについては、聖書の他の箇所でも多く言われている。例えば、黙示録2:11の箇所がそうである。『勝利を得る者は、決して第二の死によってそこなわれることはない。』黙示録3:11~12の箇所もそうである。『あなたの冠をだれにも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。勝利を得る者を、わたしの神の聖所の柱としよう。』ヘブル10:35~36の箇所でも、忍耐を保つならば幸いが聖徒たちに与えられるであろう、と言われている。『ですから、あなたがたの確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなたがたが神のみこころを行なって、約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。』使徒行伝14:22の箇所も、忍耐の末に得られる最終的な恵みのことについて言われている。『私たちが神の国にはいるには、多くの苦しみを経なければならない。』
このキリストの言葉は、直接的には当時の人たちに対して向けられた言葉である。しかし、この言葉は、紀元1世紀より後の時代に生きる全ての聖徒たちに対しても向けられていると捉えるべきである。というのも、「最後まで忍耐を保たなければならない。」というのは何も紀元1世紀の聖徒たちだけでなく、あらゆる時代の聖徒たちがその通りにせねばならないことだからである。誰がこれを疑うであろうか。我々も最後まで耐え忍ぶのであれば、やがて天国へと導き入れられることであろう。しかし耐え忍ばなければ、待ち受けるのは地獄の苦しみである。神は耐え忍ぶ者を天国から退けられないが、耐え忍ばない者には天国を与えられない。我々が、どちらのほうの人間として生涯を全うすべきかは火を見るよりも明らかである。どうか、憐れみ深い神が、聖徒たちが豊かに忍耐できるように恵みを与えて下さいますように。
【24:14】
『この御国の福音は全世界に宣べ伝えられて、すべての国民にあかしされ、それから、終わりの日が来ます。』
信じる者を御国へと導き入れるキリストの福音が世界中に宣教されると、ユダヤの終わりが実現される。これが神の定めであった。つまり、福音が世界の国々に満ち渡らない限り、ユダヤが終わる日はやって来なかった。また、ユダヤが終わるということは、つまり、その時には既に福音が十分に世界中に浸透していたことを意味する。それでは、どうして神は福音が世界に満ちるとユダヤの終わりが訪れるというふうに定められたのか。それは、そうするのが神の御心だったからである。神は、遂に異邦人さえもが神の国の中に入れる時代が到来したことを明らかにするため、ユダヤが終わるまでの短い間に福音が世界中に満ち渡ることを望まれた。そのようにして短期間で世界中に福音が満ち渡れば、新たな時代が来たことが確証されるからである。神がそのようにして福音が世界に満ちない限りユダヤの終わりは来ないと定められたのだから、どうして人間に過ぎない我々が、その定めに文句を言うことができようか。では、神は福音が全世界に浸透しない間にキリストの再臨を実現させることも可能であったのか。これはその通りであると私は答える。もっとも、そのように定めるのは神の御心ではなかったが。なお、福音が世界中に満ちるとユダヤの終わりが訪れると明白に言われているのは、聖書の中でこの箇所だけである。
聖書は、使徒の時代において既に福音が全世界に宣べ伝えられていたと、疑いもなく明瞭に教えている。だからこそ、使徒の時代にユダヤの終わりが訪れたのである。また、その時期にはキリストの再臨も起こった。パウロがⅠテサロニケ4:15の箇所で、当時の聖徒たちが『生き残っている』間に主の再臨が起こると言った通りである。私が今述べたこの理解は、非常に聖書的であり、首尾一貫している。それだから、この理解を聖徒たちは受け入れるべきである。私の述べた理解をシッカリと考慮することもせず、ただ感覚の導くまま問答無用に否定するということがあってはならない。
ユダヤの終わりの前には宣教が十分に成し遂げられるということについては、本書の中で、これまでに既に語られてきたし、これからも何回か再び語られることになる。これは重要な理解だから、どれだけ語っても語り過ぎるということにはならない。私は、今まで2千年もの間、教会が見過ごしていたことを率直に語っている。つまり、2千年分の歴史を打破しようとしている。そうであれば、少しだけ語るというのでは、あまり適切ではないと思われる。これは繰り返し聞かされるべきことだ。よって、私はこの理解について今後も繰り返して語ることを憚りはしない。世の知者たちも、重要なことは何度も何度も語ったものである。
【24:15】
『それゆえ、預言者ダニエルによって語られたあの『荒らす憎むべき者』が、聖なる所に立つのを見たならば、(読者はよく読み取るように。)』
ダニエルが預言した『荒らす憎むべき者』とは「ネロ」のことである。これについては、第1部の当該箇所を見てほしい。『聖なる所』とは「聖徒」のことである。マルコ13:14のほうでは『『荒らす憎むべき者』が自分の立ってはならない所』と言われている。ルカ21章では、この荒らす者と聖なる所については何も記されていない。Ⅱテサロニケ2:4の箇所では『神の宮』と書かれている。キリストが現われてから、キリスト者こそが神の正式な神殿となった。パウロも、キリスト者こそが神殿であるとコリント書の中で言っている。それだから、聖書の中で聖徒たちが神の宮であると言われていても、何か不思議なことが書かれているかのように思うべきではない。我々が今見ている箇所でも、聖徒という神殿を指して『聖なる所』などと言われている。この『聖なる所』という言葉を、文字通りに、すなわち石造りのエルサレム神殿のことだと解してはならない。何故なら、『荒らす憎むべき者』であるネロは、建造物としての神殿のほうには立たなかったからである。石造りの神殿のほうに立ったのは、ネロではなくティトスであった。しかし、ティトスは『荒らす憎むべき者』ではない。何故なら、この荒らす者はキリストの再臨により殺されることになっていたが(Ⅱテサロニケ2:8)、その時に殺されたのはネロであって、ティトスはキリストが再臨された時に死ななかったからである。さて、ここでキリストが言っておられるのは、つまりネロがキリスト者の上に立って苦しみを与えるということである。主がここで言われた言葉を分かりやすく言い換えれば、「ダニエルによって預言されたネロがキリスト者を蹂躙し迫害する時が来たのを見たならば」となる。確かにネロは聖徒たちという神殿の中に立ち(マタイ24:15)、そこに『座を設け』(Ⅱテサロニケ2:4)た。蹂躙し迫害するとは、霊的に言えば、そういうことである。何故なら、聖徒たちの上に立って傲慢に支配権を行使しなかったのであれば、どうして蹂躙し迫害することが出来るであろうか。
今の教会は、この『荒らす憎むべき者』が、まだ現われていないと考えている。宗教改革の頃は、この荒らす者がローマの教皇だと理解された。ルターもカルヴァンもそう言っている。しかし、その理解は誤りであった。何故なら、この荒らす者はⅡテサロニケ書2:8の箇所によれば再臨のキリストによって殺される定めとなっているが、教皇は今に至るまでキリストにより殺されていないからである。教皇が再臨のキリストに殺されていない以上、この荒らす者を教皇だと解する理解は拒絶されなければならない。また、これはヒトラーやEUの大統領や世界単一政府の王でもない。何故なら、マタイ24章をよく読めば分かるように、マタイ24章とはエルサレム神殿が崩壊する前に起こる事柄を書き記した箇所だからである。紀元1世紀について書き記されたのがこの箇所だというのに、どうして2千年後の人物がこの箇所で預言されているのであろうか。今の聖徒たちは驚くかもしれないが、これからこの『荒らす憎むべき者』が現われることは有り得ない。何故なら、これはネロのことであって、彼はもう既に登場したのだから。
『読者はよく読み取るように。』という挿入の言葉はどういう意味なのか。これは、「荒らす者が聖なる所に立つ」という言葉の意味を誤らずに悟りなさい、という意味である。マタイの福音書を読んだ当時の読者たちは、この言葉を読んで、荒らすようにと定められている邪悪な者が聖徒という聖所ではなく建造物としての聖所に立つと理解する恐れがあった。これが実際的な聖所のことだと解するのは間違っている。そのような思い違いをしないようにと、マタイはここで『読者はよく読み取るように。』と注意を促したのである。ダニエル書を読むならば、確かにこの聖所が聖徒という聖所のことを意味しているというのは明らかである。何故なら、ダニエル書では荒らす者が力を振るう対象は、建造物などではなく聖徒たちであると言われているからである。実際、ネロが力を振るったのは聖徒という『聖なる所』であった。当時の聖徒たちはダニエル書をよく知っていただろうから、マタイが何を言いたいのかよく分かったはずである。この挿入の言葉は、マルコのほうでも書かれている(マルコ13:14)。マルコのほうが先に福音書を書いたのだから、マタイはマルコの書いた福音書を読んで、自分も同じ文章を書くことにしたのであろう。一方、ルカ21章のほうでは、そもそも『荒らす憎むべき者』についての言及が省かれているから、このような挿入の言葉も当然ながら書き記されてはいない。
【24:16~19】
『そのときは、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。屋上にいる者は家の中の物を持ち出そうと下に降りてはいけません。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だが、その日、悲惨なのは身重の女と乳飲み子を持つ女です。』
ネロによる迫害が始まったならば、ユダヤにいた人々はとにかく大急ぎで逃げねばならなかった。何故なら、そのようにしないとネロによる魔の手に陥ってしまうからである。その時、『ユダヤにいる人々は山へ逃げな』ければならなかった。それは、山に逃げることで、ネロから送られた者たちに捕えられないようにすべきだったからだ。山に逃げるのであれば、追手たちも聖徒を捕えるのが難しくなる。また、『屋上にいる者は家の中の物を持ち出そうと下に降りてはいけ』なかった。これは、持ち物に気を取られたばかりに、命を失うことにならないためである。つまり、持ち物を犠牲にしてでも捕えられないように逃げ去りなさい、ということである。また、『畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけ』なかった。これも着物などというものに気を取られている場合ではないからである。みすぼらしい作業着のままだが逃げることを第一に優先させたので助かるということのほうが、着物を取りに戻ったのできちんとした服装になれたが命を失う、ということよりも遥かによい。キリストがこのように言われたのは人々に対する愛ゆえであった。つまり、ただ人々が助かるようになるためにこそ、キリストはこう言われた。そこに自己の利益を求める下心はまったくなかった。このキリストの命令に従って逃げた人々は、全速力で逃げたので命を失わずに済んだあのロトのように(創世記19章)、自分の命を保つことができた。しかしキリストの命令に従わなかった人は、町を振り向いたために塩の柱となってしまったロトの妻のように(創世記19:26)、最後には命を失ってしまった。実に、神を恐れてその命令に従う謙遜な者には、恵みとして命の守りが与えられるのである。ソロモンが『謙遜と、主を恐れることの報いは、…いのちである。』(箴言22章4節)と言った通りである。
この箇所からも、マタイ24章は紀元1世紀の出来事について言われた箇所だということが理解できる。何故なら、ここでは明らかに当時のことが言われているからだ。キリストは、『ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。』と言っておられる。つまり、ユダヤにいた人が山へ逃げたら救われるということだ。これは当時のことを言った言葉でなくて何であろうか。まともにマタイ24章を読むのであれば、これは決して疑えない。この箇所を読んで考えても、まだマタイ24章はこれから起こること、しかも文字通りの意味の全世界において起こることについて預言された箇所だと解釈することを止めないのであろうか。もしそういう人がいたとすれば、私はその人の思考回路がまったく理解できず、ただただ驚くしかない。そのような人は、ただ自分の好きなように聖書を解釈したいという気持ちに占領されてしまっているのであろう。
またネロによる苦難が起こった時、『悲惨なのは身重の女と乳飲み子を持つ女』であった。『乳飲み子を持つ女』は小さな子どもを持っているので、急いで逃げようにも逃げられない。子どもを捨てれば全速力で逃げることができるが、そのようにする女はほとんどいなかったと思われる。『身重の女』は、身体が重くて動きにくいのだから、もうどうしようもなかった。この2種類の女性たちは、ネロにより遣わされた役人や兵士たちがやって来た際、その多くが捕らえられてしまったはずである。だからこそ、キリストは彼女らについて『悲惨』などと言われたのだ。「幸が不幸に変わる。」とは正にこのことである。このような女性たちは、子どもにおける幸いと喜びが、不幸と苦しみをもたらす原因に変わってしまった。この時、彼女らが子どもを胸か腹の中に持っていなかったのであれば、どれだけ幸いだったことであろうか。
パウロが独身の者はそのままでいるがよいと言ったのは、これが理由であった(Ⅰコリント7:7~8)。もし結婚により妊娠したり子を持つことになれば、すぐにも訪れる苦難の時に逃げることが非常に難しくなってしまう。間もなくネロによる苦難が待ち受けているというのであれば、結婚して妊娠したり子を持ったりしなかったほうがかえってよかった、ということにもなるのだ。だからこそパウロは独身者は独身のままでいられるならばそうするがよい、と言ったのである。それだから我々は、Ⅰコリント7章におけるパウロの言葉を、その時代性を考慮しつつ理解しなければいけない。すなわち、パウロは『時は縮まってい』(Ⅰコリント7章29節)るからというので、独身者に独身であることを勧めたのである。先にも述べたように、この時代は、結婚したらすぐにも大変なことになってしまうという大変な時代であった。それゆえ、もし苦難の時が近づいていなかったとすれば、パウロはこのように言っていなかったであろう。むしろ、結婚を大いに推奨していたはずである。何故なら、その場合、結婚して妊娠したり子を持ったりしたとしても、個々人に降りかかる個別的な災いを除けば、何も困難は起こらないだろうからである。今まで教会は、このパウロによる言葉を、時代性をまったく考慮せず徹底的に普遍的な内容を持った言葉として理解してきた。つまり、パウロが言ったことはどの時代においても例外なく通用するものとして捉えられてきた。これは特に教父たちがそうであった。教父たちはパウロの言葉を時代性を考慮せずにではあるが真摯に受け取ったので、パウロのように独身であるのが最も良いと当然のように考えた。ヒエロニムスなどは独身を尊重するあまり結婚を貶すことさえした。それだから、教父たちはそのほとんどが独身だったわけである。もし教父たちがパウロの言葉を時代性を考慮しつつ読んでいたのであれば、その多くが結婚していたはずだと思われる。今でも、このパウロの言葉をいつの時代にも通用する内容として捉えている人は少なくない。しかし私は言うが、今やもう結婚したいと思う者は、躊躇せず大いに結婚するがよい。パウロは、時代が時代だったからこそ、独身を最もよい状態として勧めたということに気付くがよい。もう危急の時は2千年前にとっくに過ぎ去ったのだから、どうして悲惨になることを恐れて結婚しないままでいるという選択をするのか。まさか、これからローマからネロの使いたちが自分を捕えにやって来るなどと考えているのでもあるまい。
【24:20】
『ただ、あなたがたの逃げるのが、冬や安息日にならぬよう祈りなさい。』
ネロによる迫害が始まった時は、逃げるのが『冬や安息日になら』ないのが望ましかった。『冬』には逃げないのが望ましかったのは、季節的に厳しいからである。凍える寒さの中、いったい誰がネロの魔の手から逃れたいと願うであろうか。まともな精神を持つ者であれば、誰も冬に逃げたいなどとは思わないはずである。つまり、ネロの迫害が起きた際には、春か夏か秋に逃げるのが望ましかった。『安息日』に逃げることにはならないのが望ましかったのは、休みの日に苦しみと困難とを味わうのは、あまり相応しくないからである。例えば、仕事が休日の日に大きな苦しみと困難とを味わいたいと思う人がどこにいるであろうか。恐らく誰もいないと思われる。そのようなことがあれば、休みの日が休みではなくなってしまう。安息日に逃げることになるのも、それと同じである。このように、冬や安息日に逃げることになるのは実に悲惨である。だからこそ、そのような悲惨が起こらないように祈れとキリストはここで言われたのである。
それでは実際はどうだったのか。当時の聖徒たちは、キリストが命じられた通り、冬や安息日に逃げることにならないようにと祈ったはずである。彼らは実際、冬や安息日には逃げずに済んだのであろうか。それとも冬や安息日に逃げることになってしまったのであろうか。まず冬であるが、これについて確かなことは何も言えない。何故なら、ネロによる苦難がいつ始まったのかは確定できないからである。本作品の中では、紀元64年12月にネロの迫害が開始されたという設定にしているが、これはあくまでも推定上の設定に過ぎない。キリスト教迫害の原因となったティゲリヌスによるローマ大火は紀元64年6月に起きたが、この事件が起きてから11月までに迫害が起きたとすれば、当時の聖徒たちは冬には逃げずに済んだことになる。しかし、11月から65年の2月頃までの間に迫害が起きたとすれば、残念ながら聖徒たちは冬に逃げたということになる。これは可能性としては低いが、もし65年の3月以降に迫害が起きていたとしたら、聖徒たちは冬に逃げずに済んだことになる。ネロが迫害を開始した正確な時期については、更に深い思索と研究を要する。その正確な時期が確定されたならば、聖徒たちが冬に逃げたのかそうでなかったのか分かるようになる。安息日のほうについては、まったく何も分からない。というのも記録が何も残されていないからである。これについては、もしかしたら安息日に逃げずに済んだかもしれないが、安息日に逃げることになった可能性もある、としか言えない。
【24:21】
『そのときには、世の初めから、今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないような、ひどい苦難があるからです。』
この時期に起きた苦難、ことにユダヤ戦争における苦難は、史上もっとも悲惨な出来事であった。それは、ノアの大洪水よりも酷い苦難であった。何故なら、あの大洪水の時に死んだ人間の総数よりも、この時期に死んだ人間の総数のほうが多かっただろうから。また、それは2度の世界大戦における苦難よりも酷い苦難であった。これは既に第2部の中で論じた通りである。これからも、この時の悲惨を越える悲惨な出来事は起こらないであろう。しかし、これから核による破滅が起きたら、例えば日本が核で全滅するという破滅が起きたらどうなのか、と質問したい人がいるかもしれない。私は答えるが、そのような破滅は決して起きないであろう。何故なら、この時の苦難を越える苦難が起きたとすれば、キリストの言われたことから真実性が減じてしまうからである。キリストの御言葉が真実なものであり続けるためにも、この世において、この時以上の苦難は決して起こらないと考えるべきである。もしそのような苦難が起こるとすれば、ここでキリストが言われた言葉は我々が今見ているのとはやや違ったものとなっていたはずである。なお、ジョナサン・エドワーズもこの時の苦難こそがあらゆる苦難の中で最も酷い苦難であったと考えていた、ということを言っておきたい。彼は、キリストの言われたことを真正面から受け取っていたのであり、それは正しい態度であった。
これからあまりにも大きな苦難が起こるからこそ、キリストはあらかじめ、このように言われたのである。事柄が大きくなればなるほど、それだけ事前に伝え知らせるべき必要性の度合いも大きくなるのは確かである。この時の苦難は実に大きかったので、キリストはそれを知らせておかないままではおられなかった。ノアも大洪水が起こる前には、人々に対して来るべき事柄をあらかじめ宣べ伝えたものである(Ⅱペテロ2:5)。もしこの苦難がそれほど大きな苦難でなかったとすれば、キリストがこのようにあらかじめ大いに事前通告されていたのかどうか、私は知らない。
【24:22】
『もし、その日数が少なくされなかったら、ひとりとして救われる者はないでしょう。しかし、選ばれた者のために、その日数は少なくされます。』
この箇所は、理解するのがなかなか難しい箇所である。
まず『もし、その日数が少なくされなかったら、ひとりとして救われる者はないでしょう。』とは、どういう意味か。これは、「いつまでも引き延ばされるのであれば」という意味である。すなわち、ここでは「もしその時の到来が少なくされず、永遠に延期され続けるのであれば、誰一人として救われて天国に入ることはないであろう。」と言われているのだ。これは、キリスト特有の難しい言い回しである。しかし、我々はこのような言い回しに驚くべきではない。何故なら、キリストがこのような言い回しをされるのは、福音書の他の箇所を見ても分かるように、何も珍しくはないからである。この部分は私が今言ったように解されるべきである。そうしないと、この部分を正しく解することは出来ないであろう。
では『しかし、選ばれた者のために、その日数は少なくされます。』とは、どういう意味か。これは、つまり「選ばれている者たちが天国に入れるようになるために、定めの時は伸ばされず、むしろすぐにも到来させられることになろう。」ということである。定めの時に至るまでの日数が『少なくされ』るのは、聖徒たちのためであった。もしその日数が短くされなかったのであれば、いつまでも選ばれた者たちは天国に入れないままに留め置かれていた。なお、Ⅱペテロ3:12の箇所で『そのようにして、神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。』とペテロが言ったのは、我々が今見ている箇所で言われた言葉と対応している。つまりペテロは、キリストの言われた通りに、速やかに定めの時が来ることを切に願っていたのである。それは、選ばれた者たちが待たされることなく天国に入れるようになるためであった。
この定めの時は、既に到来している。それは紀元68年6月9日であった。この時、選ばれていた者たちは再臨されたキリストの所に携挙され、そうして天国に導き入れられるようになったのである。神は、選ばれている者たちが遅れずに天国に入れるようにと、その定めの時をすぐにも到来させて下さったのである。今の教会は、この定めの時が未だに到来していないと当然のように理解している。しかし、その理解は間違っている。何故なら、ここでキリストは『その日数は少なくされます。』と言っておられるからである。このようにキリストが言われたのだから、2千年経過しても未だにその日が到来していないと理解するのは、明らかにおかしいと言わなければならない。2千年という期間は、明らかに縮められた期間ではない。むしろ、それは縮められていない期間である。それは「引き延ばされた期間」であると言わねばならない。それだから、今の教会がそう考えているように、本当にもし未だに定めの時が来ていないとすれば、ここでキリストが『その日数は少なくされます。』などと言われることはなかったであろう。むしろ、「その日数は引き延ばされることになります。」などと言っておられたであろう。
【24:23~24】
『そのとき、『そら、キリストがここにいる。』とか、『そこにいる。』とか言う者があっても、信じてはいけません。にせキリスト、にせ預言者たちが現われて、できれば選民をも惑わそうとして、大きなしるしや不思議なことをして見せます。』
この時には、再臨詐欺が見られた。これは、再臨されたキリストがそこにおられないにもかかわらず、『そこにいる。』などと出鱈目を言う詐欺であった。こういった者たちは、野心によりこのようなことをするのである。キリストは、そういった者たちに耳を傾けてはならないと言われた。何故なら、彼らの言うことは嘘だからである。たとい、この詐欺師たちの示す場所を探しても、決して本物のキリストはそこにおられない。というのは、キリストはこの地上に再臨されるのではなく、空中に再臨されるからである(Ⅰテサロニケ4:16~17)。だから、キリストがここでそのよう詐欺を信じてはならないと言われたのは、誠にもっともなことであった。
また、この時には『にせキリスト、にせ預言者たち』も現われ、出来るならば選ばれた者をも惑わそうとして、多くの人々を惑わした。彼らは、選ばれていない者たちをますます『暗やみの圧制』(コロサイ1章13節)に閉じ込め、選ばれている者たちが何とかして滅びの穴に転落するようにしたかった。これは、今の時代で言えばエホバの証人とよく似ている。エホバの証人どもは、非キリスト教徒たちを更にサタンの闇へと引きずり込もうとし、キリスト教徒たちに対しては何とかして異端の教理を信奉するようにさせたく願っている。この時に現われた偽キリストと偽預言者たちは、サタンに取りつかれているか、もしくはサタンの働きを多かれ少なかれ受けていた。というのも、神の霊によって歩む者であれば、決して人々を惑わそうとすることなど出来ないからである。サタンは、人々を、特に聖徒たちを、何とかして自分の闇へと引きずり込みたかった。だからこそ、偽キリストや偽預言者に相応しい者を巧妙に用いて、人々を惑わした
わけである。今の時代に見られるキリスト教以外の宗教においても、サタンは働いている。サタンはその宗教を通して、更に人々がサタンの闇の中へと入り込むようになるのを望んでいるのだ。その意味において、今の時代に見られるキリスト教以外の宗教に属する者と『にせキリスト、にせ預言者たち』は同種の存在である。
ところで、この『にせキリスト』と『にせ預言者』は、それぞれ別の存在である。『にせキリスト』とは、僭越にも自分こそがキリストであると主張する者を指す。『にせ預言者』とは、偽りの預言をする者を指す。しかし、『にせキリスト』でありつつ『にせ預言者』でもあった者が、いくらかでもいたのではないかと思われる。というのも、自分がキリストであると主張するほどの野心家であれば、偽りの預言もせずにはいられないだろうからである。自分をキリストと主張する者が、自分がキリストであると主張するだけで満足していられるとは思えないのだ。また、この2種類の者たちは、どちらもそれぞれ死に値する罪を犯していた。『にせ預言者』について言えば、律法の中では偽りの預言をすることが死に定められている。それは申命記18:20の箇所で、『わたしが告げよと命じていないことを、不遜にもわたしの名によって告げたり…する預言者があるなら、その預言者は死ななければならない。』と神が言われた通りである。『にせキリスト』について言えば、自分がキリストであるなどと偽りを口にする者は明らかに死の裁きを受ける対象である。それはダビデが神に向かって次のように言っている通りである。『あなたは偽りを言う者どもを滅ぼされます。』(詩篇5:6)このダビデの言葉は、明らかに偽証が死の罰に値することを教えている。この2種類の者たちは、悔い改めなかったとすれば、天国に入ることは無かったであろう。
【24:25】
『さあ、わたしは、あなたがたに前もって話しました。』
キリストは、目の前にいた弟子たちにユダヤ崩壊の時期に起こる諸々の出来事について『前もって話し』ておかれた。これには2つの理由があった。まず一つ目は、弟子たちがそのことについて質問したからである。キリストは、その質問に対して快くお答えになられた。二つ目は、これから起こる悲惨な出来事を聖徒たちにあらかじめ知らせ、そうすることで心の準備が出来るようにさせるためであった。つまり、突如として予期していなかった悲劇が襲いかかってきたので大いに狼狽してしまう、という悲惨な事態を避けさせるために、このようにあらかじめ未来の出来事を弟子たちにお伝えになった。前にも述べたが、事前に何が起こるか知っているからこそ、それがいざ起きた時に混乱したり動揺したりせずに済むのである。もしこのようにあらかじめ未来の出来事が知らされていなかったとすれば、当時の聖徒たちは危機が訪れた際、大いに驚き揺るがされて無様な振る舞いをすることになっていたかもしれない。
【24:26~27】
『だから、たとい、『そら、荒野にいらっしゃる。』と言っても、飛び出して行ってはいけません。『そら、へやにいらっしゃる。』と聞いても、信じてはいけません。人の子の来るのは、いなずまが東から出て、西にひらめくように、ちょうどそのように来るのです。』
再臨の起こるのが近くなった時期には、再臨されたキリストの居場所を詳しく告げ知らせる者たちが現われた。キリストは、そのような者に耳を傾けてはならないと言っておられる。というのも、その者たちの言ったことは全て真実でないからである。主は、彼らが嘘を言う者たちであるということを、あらかじめ知っておられた。キリストが再臨されるのは、『いなずまが東から出て、西にひらめくように』して起こった。それだから、再臨されたキリストがこの地上のどこかにおられるなどとは決して言えなかった。それは稲妻の場合を考えてみればよく分かる。稲妻が起きた時、「稲妻が街の中で閃いている。」とか「部屋に稲妻がある。」などという人は誰もいない。それと同じで、再臨されたキリストについて『それ、荒野にいらっしゃる。』とか『そら、へやにいらっしゃる。』などと言うのは、明らかにおかしいことなのである。
ここで言われていることは、先に見た24:23の箇所の繰り返しである。先の箇所でも、再臨されたキリストが地上のどこかにいると告げ知らせる者のことについて語られていた。しかし、こちらのほうでは、先の箇所と比べてより詳しい内容となっている。キリストは、聖徒たちが惑わす者たちに惑わされないのを切に望んでおられた。だからこそ、このようにここで繰り返して語られたのである。繰り返すのは、それが重要であるからに他ならないからだ。
【24:28】
『死体のある所には、はげたかが集まります。』
この聖句は、聖書の中で最も解釈するのが難しい箇所の一つである。この箇所は、聖書全体と再臨の事柄についてよく弁えていなければ、正しく解釈することができない。
これは一体どういう意味であるか。この聖句は、再臨が起きた時のことを言っている。まず、再臨が起こると、選ばれていなかった滅びの子たちは再臨されたキリストにより殺されて死体と化した。イザヤはキリストの再臨について次のように預言した。『見よ。まことに、主は火の中を進んで来られる。その戦車はつむじ風のようだ。その怒りを激しく燃やし、火の炎をもって責めたてる。実に、主は火をもってさばき、その剣ですべての肉なる者をさばく。主に刺し殺される者は多い。』(66章15~16節)ここではキリストが多くの者を刺し殺されると言われているが、それはつまり多くの者が死体になるということを意味している。殺されたら死体になるというのを疑う人はいないはずである。もちろん、これは実際的なことではなく、あくまでも霊的なことである。すなわち、これは再臨されたキリストが御言葉という剣により滅びの子らを霊的に断罪し、彼らに対して永遠の滅びの宣告を下されたということである。そのようにして霊的な『死体』と化した人々に、多くの『はげたかが集ま』った。この『はげたか』とは悪霊どもである。つまり、再臨により霊的な死体となった人々は悪霊どもに憑りつかれ、惑わされ、完全に占領されてしまった。何故なら、悪霊というハゲタカのする食事は、霊的な死体となった人々を喜んで占領することに他ならないからである。つまり、ここで言われているのは、こういうことである。「再臨の際には霊的に殺されて死体となった人々が裁きとして悪霊どもに憑りつかれることになるが、それはあたかもハゲタカが殺された人間の死体に群がるようなものである。」なお、この聖句はルカ17:37の箇所でも同じことが言われている。
ここまで読み進められた読者であれば既に気付いているかもしれないが、この箇所は黙示録19:21の箇所と完全に対応している。そこでも、再臨されたキリストの口から出る御言葉という剣で殺され死体となった人々に悪霊という鳥が大いに群がった、ということについて預言されている。すなわち、ヨハネはそこでこう言っている。『残りの者たちも、馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が、彼らの肉を飽きるほどに食べた。』この黙示録の箇所とマタイ24:28の箇所の対応具合に気付かないほどに鈍感な人が誰かいるのであろうか。
【24:29】
『だが、これらの日の苦難に続いてすぐに、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。』
『これらの日の苦難』とは、ネロによりもたらされた聖徒たちの受けた苦難である。それは紀元68年6月9日までにおける苦難を指している。この箇所に続く聖句を読めば分かるように、この苦難が起こるとキリストの再臨が実現される。それゆえ、『これらの日の苦難』とは再臨の起きた紀元68年6月よりも後の苦難ではあり得ない。
『太陽は暗くなり、月は光を放たず』とは、再臨が起こることを示している。この言葉は実際的なこととして捉えるべきではなく、象徴的なこととして捉えるべきである。つまり、キリストの再臨は太陽と月さえも輝きを失ったかと思えるほどに輝かしい出来事だったということである。この表現は、他にもイザヤ13:10の箇所で使われている。『星は天から落ち』というのも、再臨を示している。これは再臨の特異性を表現した言葉である。つまり、再臨とはあたかも星が天から落下するかのように特別な出来事なのだ、ということをこれは言っている。ところで、この言葉は明らかに天動説に基づいた言い方である。というのも地動説を奉じていれば、とてもじゃないが、こんなことは口に出来ないだろうからである。キリストは地動説こそが真実な見解であると知っておられたが、ここでは天動説を奉じている者であるかのように振る舞っておられる。それというのも、キリストは16~17世紀が来ないうちは、まだ天動説が打破される時代は来ないことを知っておられたからである。また、キリストはコペルニクスやケプラーのように天動説を粉砕する役割を持ってこの地上に来られたわけではなかった。それゆえ、キリストはこのように天動説を奉じているかのような言い方をされることを恥とはなさならかった。簡単に言えば、キリストは無用な議論を巻き起こして御自身の使命が妨げられないようにと、あえて当時の常識であった天動説に御自身を適合させておられたのである。だから、もしキリストが天動説を打破する役目も持っておられたとすれば、キリストがここでこのような天動説に基づいた言い方をされることはされなかったであろう。他の箇所からも分かるが、聖書ではその時代の慣用が無視されていないという点に我々は注意すべきである。『天の万象は揺り動かされます。』というのも、やはり再臨のことを言っている。これは、つまり再臨はあたかも天の万象が動乱してしまうかのような驚異性を持った出来事なのだ、ということである。なお、ヨセフスの次の言葉は、ここでキリストが言っておられる出来事が実際に起きたことを我々に示してくれるものとして見てよいであろう。彼はユダヤ戦争の時期のある日についてこう言っている。「その夜、恐ろしい冬の季節風が突発的に発生した。土砂降りの雨と一緒に強風が吹き荒れ、稲妻が絶えず走り、身の毛のよだつ雷鳴と大地の揺れ動く大音響がそれにともなった。このような天変地異は人類の破滅を予示するものであり、人はこれらを決して小さくはない災禍の予兆と考えるであろう。」(『ユダヤ戦記2』Ⅳ iv5:286~287 p187:ちくま学芸文庫)タキトゥスも紀元59年に起きた異常な現象について次のように書いている。「そのあいだにも奇怪な現象がひんぱんに起っていた。ある女は蛇を生む。別な女は夫の腕に抱かれているとき雷に打たれて死ぬ。さらに、太陽がにわかに暗くなって、首都の14区全部に雷がおちる。」(『年代記(下)』第14巻 12 p183:岩波文庫33-408-3)またセネカの書いた著書を読んでも、この時期には異常な現象が多く確認されていたことが分かる。ストア派のセネカでさえ、そのように書いているのだから、そのような現象が起きたことは間違いない。何故なら、セネカがあえて本当は起きていないことを書いたとして、それが彼にとって何の意味と益を持つのであろうか。
【24:30】
『そのとき、人の子のしるしが天に現われます。すると、地上のあらゆる種族は、悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見るのです。』
『天に現われ』る『人の子のしるし』とは何であるか。再臨が起きた際に、『人の子のしるし』が現われたのは絶対に確かである。しかし、それがどのような徴だったかということについては、よく分からない。シッカリと確認できる形としての徴であったことは間違いないが、その詳細となると我々は再臨を見た当事者ではないのだから、詳しいことは何も語れない。この点について我々は、ただ<再臨の際には目に見える徴が天に現われた>ということを知るだけで良しとすべきであろう。なお、今の教会はこの『しるし』が未だに天に現われていないと当然のように考えているが、その考えは間違っている。何故なら、マタイ24章とは神殿が崩壊する時期に起こる出来事について預言された箇所だからである。どうか聖徒たちは、思い違いをしないでいただきたいものである。
キリストの再臨は、その時にいた『地上のあらゆる種族』が見た。これは、文字通りの意味における『地上のあらゆる種族』ではない。そうではなく、これはユダヤ人、しかもエルサレムにいるユダヤ人における『地上のあらゆる種族』である。何故なら、預言書では、ユダヤ人の諸部族がキリストの再臨を見て悲しみ嘆くと書かれているからである。すなわち、ゼカリヤ書12:10~14の箇所では再臨が起こる時について次のように預言されていた。『わたしは、ダビデの家とエルサレムの住民の上に、恵みと哀願を注ぐ。彼らは、自分たちが突き刺した者、わたしを仰ぎ見、ひとり子を失って嘆くように、その者のために嘆き、初子を失って激しく泣くように、その者のために激しく泣く。その日、エルサレムでの嘆きは、メギドの平地のハダデ・リモンのための嘆きのように大きいであろう。この地はあの氏族もこの氏族もひとり嘆く。ダビデの家の氏族はひとり嘆き、その妻たちもひとり嘆く。ナタンの家の氏族はひとり嘆き、その妻たちもひとり嘆く。レビの家の氏族はひとり嘆き、その妻たちもひとり嘆く。シムイの氏族はひとり嘆き、その妻たちもひとり嘆く。残りのすべての氏族はあの氏族もこの氏族もひとり嘆き、その妻たちもひとり嘆く。』ゼカリヤの預言の中で、『エルサレムの住民』がキリストを見て嘆くことになると言われているのは明らかである。今の教会は、我々が今見ている箇所で言われている『地上のあらゆる種族』という言葉を、文字通り地球全土に住んでいる全ての種族という意味で理解している。しかし、その理解は間違っている。何故なら、それは「感覚により」そう理解しているだけに過ぎないからである。一方、私は感覚には自分の理解を委ねておらず、むしろゼカリヤ書の預言に自分の理解を立脚させている。つまり、私の理解は霊的であり学問的である。今の教会の理解と私の理解のうち、どちらのほうが正しいかは火を見るよりも明らかであろう。何故なら、聖書は感覚ではなく聖書によって理解すべきものだからである。それゆえ、聖徒たちは、私が今言ったようにこの『地上のあらゆる種族』という言葉を理解せねばならない。実際、この時にエルサレムにいたユダヤ人は、この氏族もあの氏族も、キリストの再臨を見たはずである。というのも、キリストはエルサレムの上空、正確にはオリーブ山の上空に再臨されたからだ。当時のエルサレムには多くのユダヤ人がいたのだから、そこにはユダヤ人における全ての種族がいたはずなのである。だから、キリストのこの預言は、本当に現実となったことが分かる。また、この時に再臨を見たユダヤ人たちは『悲し』んだ。それは何故なのか。それは、再臨の出来事を見たことにより、あのナザレのイエスこそがキリストだったということを真に悟ったからである。既に第2部で論じたように、キリストの再臨とは実に偉大で感動的な素晴らしい光景であった。その光景は、否が応でもキリストが天から降りて来られたと悟らざるを得なくさせられるものであった。それゆえ、当時のユダヤ人たちが再臨を見て『悲し』んだのは、自然なことであった。もしその光景を見ても悟らず悲しみもしないような人がいたとすれば、その人は狂っているか精神的な病気を持った人だったに違いない。とはいっても、当時のユダヤ人が再臨のキリストを見て悟ったとしても、既にもうどうしようもなかった。何故なら、彼らの心は神に対して堅く閉ざされていたので、悲しみはしたものの悔い改めることが出来ない状態だったからである。それは、エサウが大いに嘆いて後悔したにもかかわらず、もはや『心を変えてもらう余地が』(ヘブル12章17節)なかったのと同じである。真実を悟っているのに悔い改められないのは、神から下された恐るべき呪いである。
この時に再臨されたキリストは『大能と輝かしい栄光を帯びて』おられた。『大能』とは、キリストの全能性のことである。あまりにも大きい能力性、と言えば分かりやすいであろうか。この言葉はパウロもエペソ6:10の箇所で使っている。『輝かしい栄光』とは、キリストの栄光である。キリストは神であられるから、無限の栄光をお持ちであった。再臨のキリストは、その栄光を伴って来られたのである。再臨が起きた時、人々はその栄光をまざまざと見た。かつては荒野にいたイスラエル人たちも、神の栄光をその目でまざまざと見たものである(出エジプト記24:17)。
【24:31】
『人の子は大きなラッパの響きとともに、御使いたちを遣わします。すると御使いたちは、天の果てから果てまで、四方からその選びの民を集めます。』
この箇所で言われているのは携挙のことである。キリストが再臨されてから、『大きなラッパの響きとともに』御使いたちが遣わされた。それは、御使いたちが多くの者たちを地上から刈り取るためであった。つまり、キリストは携挙を御使いに実施させられた。その出来事については、マタイ13章や黙示録14章でも語られている。読者の中には、御使いたちがこんなにも重要な事柄を任せられていることに驚く方がいるかもしれない。私は言うが、重要だからこそ神は御使いにそれをお任せになられる。というのも、御使いとは重要な事柄を任せられるために創造された存在だからである。黙示録の預言も、モーセの律法も、多くの民に災いが下されたのも、全て御使いを通してであった(黙示録1:1、ガラテヤ3:19、Ⅱサムエル記24:16)。神は、このように重要な事柄であっても、御使いにその執行や授与を任せられるのだ。それだから、携挙が御使いにより実施されたと教えられていても驚くべきではない。それでは、ここで言われている携挙は第一の携挙なのか、それとも第二の携挙なのか。これは簡単である。すなわち、ここで言われているのは第二の携挙である。つまり、それは紀元68年6月9日に起きた携挙ではなく、紀元70年9月に起きた携挙である。何故なら、ここで言われている携挙では、御使いが刈り取りをさせられているからである。マタイ13章や黙示録14章の註解でも述べたことだが、御使いが刈り取りをするのは1回目の携挙ではなく2回目の携挙である。1回目の携挙では、キリスト御自身が人々を刈り取られるのである(黙示録14:14~16)。
この箇所で言われている携挙の出来事は、既にとっくの昔に実現している。繰り返し述べるが、この箇所で言われている出来事も、神殿崩壊の時期に起こる出来事の一つである。聖徒たちは、シェイクスピアのように深く考えるべきである。私の述べている見解が正しいにもかかわらず受け入れられていないのは、正確に言えばその見解が直視されていないのは、ただ単に今まで誰もそのような見解を主張したことがなかったからなのである。私の見解は、ただそれだけの理由で相手にされていない。実際、私の述べた見解に真正面から向き合っている人は、私の見解こそが真に正しい見解だと認めている(というか認めざるを得ないのだ)。目を逸らさなければ、私の述べた見解は本当に正しいと思えるものなのだ。これはコペルニクスやケプラーやガリレオもそうであった。この3人は正しい理論を主張したのだったが、単に今まで誰もそのような理論を主張してこなかったというだけの理由で受け入れられず、迫害をさえ受けたのである。それゆえ聖徒たちは気をつけていただきたい。常識や伝統的な理解を超越できないのであれば、その報いとして、愚かな誤謬のガラクタにいつまでも埋没したままである。
ところで、ここで言われている『御使い』が使徒を指しているのではないか、などと推測をしている者がいたが、この推測について幾らか述べておきたいと思う。この推測は完全な誤りである。この御使いとは、明らかに人ではなく『仕える霊』(ヘブル1章14節)としての存在である。何故なら、この御使いとは間違いなくマタイ13章で出てくる御使いと同一の存在であって、その御使いは悪者どもを地獄へと投げ入れているからである(マタイ13:41~42、49~50)。悪者を刈り取って地獄に投げ込む役割を持った存在は、明らかに使徒ではない。このような推測は、馬鹿げていると言わねばならない。というのも再臨が起きると使徒たちは一挙に携挙されたからである。その携挙された使徒たちが、大きなラッパの響きと共に遣わされて四方から選ばれた聖徒たちを集めるとは一体どういうことなのか。それは御使いのすることではないのか。聖書のどこに使徒たちが携挙における刈り取りを委任されたなどと教えられているのか。これは明らかにおかしい推測である。私はどうして、このような推測が出来るのか不思議でならない。確かなところ、これは狂った推測であると言われねばならないものである。読者は、このような推測に惑わされないように注意していただきたい。
【24:32~33】
『いちじくの木から、たとえを学びなさい。枝が柔らかになって、葉が出て来ると、夏の近いことがわかります。そのように、これらのことのすべてを見たら、あなたがたは、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。』
イチジクの木を見れば夏の接近が知れるように、再臨もその前兆により知ることができた。その前兆とは何であったか。それは、ここまでに語られてきた諸々の悲惨な出来事である。その前兆は非常に分かりやすいものであった。それは誰でも分かるようなものである。それだから、当時の人たちは誰もが再臨の接近について大いに知ることができた。ここで『人の子が戸口まで近づいている』と言われているのは、再臨が間近に迫っていることを述べた表現である。つまり、扉を開けたら扉の向こうにいる人がすぐにもこちらに来れるかのように再臨が間もなく起こる、という意味である。この表現は、ヤコブ5:9の箇所でも使われている。
実際、『これらのことのすべて』が見られる時期になると、すぐにもキリストが天の戸口を開いて再臨された。それが起きたのは紀元68年6月9日であった。
イチジクの木による例えは、聖書の他の箇所でも、この時期について預言される際に用いられている。例えば、イザヤ34:4ではこう言われている。『天の万象は朽ち果て、天は巻き物のように巻かれる。その万象は、枯れ落ちる。ぶどうの木から葉が枯れ落ちるように。いじちくの木から葉が枯れ落ちるように。』これは、イチジクの木から葉が枯れ落ちるように、ユダヤにおける万物が神の御前から消え失せてしまう、ということである。黙示録6:13ではこう言われている。『そして天の星が地上に落ちた。それは、いちじくが、大風に揺られて、青い実を振り落とすようであった。』これも、ユダヤがイチジクから振り落とされた青い実のように、神の御前から振り落とされる、ということである。では、どうして聖書ではイチジクの例えが使われているのか。それはユダヤ人にとって分かりやすいからであろう。このイチジクとは、ユダヤ人には非常に身近な植物だからである。
【24:34】
『まことに、あなたがたに告げます。これらのことが全部起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。』
『時代』とは、原文ではゲネアーであり、既に第1部の中でも説明されたように「世代」すなわち30~40年ぐらいの期間である。キリストは、ここでこれまでにオリーブ山で語られた諸々の事柄が一世代(ゲネアー)の間に実現されると言っておられる。再臨も携挙もそうなのであろうか。もちろん、そうである。というのも、キリストの御言葉には偽りがないからである。ペテロが、キリストは『その口に何の偽りも見いだされませんでした。』(Ⅰペテロ2章22節)と書いた通りである。
実際、ここまでキリストがオリーブ山で語られた事柄は、本当に1世代の間に実現した。それは、既に本書で書かれた内容から明らかである。具体的に考えてみたい。キリストがオリーブ山で4人の弟子たちに返答された時期を、紀元33年だとする。ユダヤ戦争はそれから37年後の紀元70年9月2日に終わった―これはキリストが語られてから40年以内である。ネロが聖徒たちの上に立って蹂躙の不法を為すのは、31年後の紀元64年に始まり、それから3年6か月すると終わった―これもキリストが語られてから40年以内である。再臨と再臨の際に起こる携挙は35年後の紀元68年に起こった―これもキリストが語られてから40年以内である。どうであろうか。このように見ると、確かにキリストが言われたのは真実だったということが分かる。もし1世代すなわち40年の間にこれらのことが起こるのでなければ、恐らくキリストはここでこれらのことについて預言してはおられなかったと思われる。
聖徒たちは、マタイ24章が紀元1世紀に起こる出来事について預言された箇所だということを、よく理解すべきである。この箇所が今から2千年前のことについて言われているのは明らかである。この理解を受け入れない人は、理性の働きが弱いか、孤独になりたくないか、迫害を避けたいか、小心なので伝統的な解釈にしがみついたままでいたいか、今までに登場した偉大な教師たちの再臨に関する理解が誤っていたことを認めたくないか、まだ本書で言われている事柄がよく理解できていないか、気の合う仲間たちと一緒の見解をいつまでも持っていたいか、実は真理など別にどうでもいいと思っているか、プライドが高いので私の述べた見解に自分の見解を適合させたくない、という人である。確かに私が理知的に説明しても、それを受け入れる人は多くはいない。これは、世界的な陰謀を研究していたり否定していなかったりする人であれば、よく分かることではないかと思う。多くの人たちは、例えば300人委員会やCFRやスカル・アンド・ボーンズやイルミナティといった陰謀組織が巨大な陰謀を世界で実施していると聞かされても、なかなか受け入れようとはしない。その人たちは、陰謀を認めたくない何らかの理由を持っているので、明白な証拠の伴った理知的な説明がされても絶対に受け入れることをしない。彼らは言うのだ、「そんなことは信じられないよ。」などと。私がマタイ24章は2千年前の時代のことを預言した箇所だと説明してもなかなか受け入れられないのは、これと非常によく似ている。
【24:35】
『この天地は滅び去ります。しかし、わたしのことばは決して滅びることがありません。』
『この天地』とはユダヤのことである。すなわち、これはユダヤにおける『天地』を意味している。今の教会では、ここでキリストが言われた『天地』という言葉を、文字通り地球全土という意味において捉えるであろう。しかし、そのように捉えるのは間違いである。何故なら、マタイ24章で言われている『世の終わり』とは、神殿崩壊の時に起きたユダヤの終焉のことだからである。確かにユダヤ王国は紀元70年に滅び去った。無学か痴呆でなければ、これを疑う者は一人もいない。それゆえ、マタイ24章の文脈を考慮するならば、ここで言われている『天地』とはユダヤ世界を意味していると捉えねばならない。このように言われても読者は驚くべきではない。言葉を文字通りに捉えるべきでない箇所は、聖書に幾らでも見られるからである。例えば、創世記1:1で『天と地』と言われているのは、この世界における天と地であり、この言葉に霊的な世界という意味における「天」は含まれていない。ルカ2:1で『全世界』と言われているのも、ローマ帝国の領域における全世界であって、当然ながら中国や日本は含まれていない。黙示録13:7で『あらゆる部族、民族、国語、国民』と言われているのも、やはりローマの影響が及ぶ範囲内のことであって、そこには中国人や日本人は含まれていない。ゼパニヤ書1:2で『わたしは必ず地の面から、すべてのものを取り除く。』と言われたのも、『ユダの上に、エルサレムのすべての住民の上に』(ゼパニヤ1:4)いる全てのものであって、『地の面』また『すべて』とは言われているもののユダヤ以外の地は何も含まれていない。我々が今見ている箇所で『天地』と言われているのも同様であって、これはユダヤのことだけを意味している。聖徒たちは、よく思考し、思い違いをしないでいただきたい。これは聖書研究以外でも言えるのだが、神の恵みにより思考をするからこそ、人は愚かな思い違いから免れることが出来るのだ。
ここでキリストは、ユダヤはやがて滅びるであろうが御自身の御言葉は滅びない、と言っておられる。確かにユダヤは紀元70年に終わりを迎えた。しかし、キリストの御言葉は終わることがなかった。もしユダヤの終焉と共にキリストの御言葉も終焉を迎えていたとすれば、ここでキリストがこのように言われることは無かったであろう。神の言葉が永遠に続くということについては、イザヤ40:8の箇所でも次のように言われている。『草は枯れ、花はしぼむ。だが、私たちの神のことばは永遠に立つ。』このイザヤの言葉は真理である。実に、神の言葉が滅ぶようなことがあれば、この全宇宙が1億回も滅びるほうが遥かに容易い。
要するに、ここでキリストは聖徒たちが思い違いをしないようにしておられる。当時の聖徒たちはユダヤが滅茶滅茶になって終わりを迎えると聞いて、ユダヤの終わりと共にキリストの御言葉も終わるのではないかと考える恐れが多かれ少なかれあった。キリストは、そのような思い違いをさせないために、ここでこのように御自身の御言葉が永遠に続くと言われたのである。
【24:36】
『ただし、その日、その時がいつであるかは、だれも知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。』
この聖句は、今までの教会の歴史において、たびたび引用されたり言及されたりしてきた聖句である。
キリストの再臨が起こる正確な日時は、誰も知らなかった。知ることが許されているのは、ただ再臨が間近に迫っているということだけであった。それは、マタイ24:32~33の箇所を見れば分かる通りである。再臨の起こる日が知らされていないのは、聖徒たちが安逸を貪らないためである。もし再臨の起こる正確な日時を知ってしまえば、人間とは怠惰に向かいやすい性質を持っているから、どうしても怠ける心が起こりやすくなってしまう。「再臨は20年後に起こるのだから、まだまだ気を緩めていても大丈夫だ。」などと思って。そうなれば、引き締まった霊と信仰を持てなくなってしまうことにもなる。そうであれば、再臨の日が知らされないのは、かえって聖徒たちには良いことになる。つまり、神は聖徒たちのことを思って、あえて再臨の起こる日を知らせることはなさらなかったのだ。もし知らせたほうが益になっていたとすれば、神は聖徒たちにその日がいつであるのかシッカリと知らせておかれたはずである。
その再臨の日は、紀元68年6月9日であった。これは既に起きている。それゆえ、今となってはもうその日がいつであるのか隠されてはいないのである。
ところで、ここではキリストさえも再臨の起こる日を知らないと言われているが、これはあくまでも人としてのキリストについて言われたことである。つまり、ここで言われているのはキリストの人性についてである。当然ながら、キリストは神としては再臨がいつ起こるのか正確に知っておられた。キリストは神であられるのだから、どうして神としてその日を知らないということがあるであろうか。もしキリストが神であるにもかかわらず、その日を知らなかったとすれば、キリストは神でなかったことになってしまう。
トマスが好みそうなことであるが、この箇所から、御使いたちは未来の事柄を知らないことが分かる。何故なら、ここでは御使いたちがやがて起こる再臨の日がいつか知らない、と言われているからだ。再臨の日を御使いが知らないというのであれば、再臨以外の未来に起こる事柄も同様に知らないはずである。もちろん、神が事前に未来の事柄を御使いたちに知らせておかれた場合は、話は別である。つまり、御使いたちは何もかも知っているというわけではないのだ。また御使いが未来について知らされていないのであれば、同じようにサタンも未来について知らされていないことになる。というのも、御使いには未来のことが知らされていないのに、サタンには未来のことが知らされている、というのは考えにくいからである。御使いが未来について知らされていないのであれば、それはサタンでも同じはずである。もちろん、サタンの場合も、神からあらかじめ未来の事柄を知らされていた場合は、話は別である。つまり、『何が起こるかを知っている者はいない。いつ起こるかをだれも告げることはできない。』(伝道者の書8章7節)というソロモンの言葉は、人間だけでなく、御使いとサタンにとっても真実な言葉なのだ。このソロモンの言葉に適合していない唯一の存在は、ただ三位一体の神だけであられる。全ての事象をあらかじめ定められた神だけは、何が起こるのか細部まで全て知っておられるし、またそれを1秒のずれもなく予告することがお出来になる。
【24:37~39】
『人の子が来るのは、ちょうど、ノアの日のようだからです。洪水前の日々は、ノアが箱舟にはいるその日まで、人々は、飲んだり、食べたり、めとったり、とついだりしていました。そして、洪水が来てすべての物をさらってしまうまで、彼らはわからなかったのです。人の子が来るのも、そのとおりです。』
あの大洪水が起こるまで、ノアの時代の人々はごく普通に生活していた。彼らにとって、巨大な洪水が起こるなどとは想定外のことであった。まさか、当時の人間は世界的な大洪水がやがて起こるなどとは思いもしなかったであろう。ノアが人々に警告していただろうから、洪水のことを聞いていないわけではなかったが、そんなものはただの夢想に過ぎないものとして退けたはずだ。しかし、人々の思惑に反し、それは突然起きてしまったのである。
キリストが再臨されるのも、正にそれと同じであった。当時のエルサレムにいた人たちは、まさか再臨が起こるなどとは思っていなかったはずである。それは、単なる異端者の戯言にしか思えなかったはずだ。しかし、突如としてそれは起こった。広島と長崎の原爆および2001年ニューヨークのテロが起きた際、誰が事前にそれを察知できたであろうか。ほとんど全ての人には出来なかったはずである。つまり、多くの人にとって、この2つの事件は思いがけないものであった。キリストが再臨されたのも、正にそのようにして起きたのである。再臨が突如として起こるということは、聖書の他の箇所でも教えられている。例えば、ペテロは『主の日は、盗人のようにやって来ます。』(Ⅱペテロ3章10節)と言っている。これは、再臨は盗人が押し入るかのように急に起こるということである。キリストもサルデス教会の聖徒たちに対し、次のようにペテロと同じことを言っている。『もし、目をさまさなければ、わたしは盗人のように来る。あなたには、わたしがいつあなたのところに来るか、決してわからない。』(黙示録3章3節)パウロも同じことをテサロニケ人に書いている。『主の日が盗人のように来るということは、あなたがた自身がよく承知しているからです。人々が「平和だ。安全だ。」と言っているそのようなときに、突如として滅びが彼らに襲いかかります。』(Ⅰテサロニケ5章3節)
キリストがここで再臨を大洪水の日になぞらえているのは、聖徒たちが警戒して気を引き締めるようになるためであった。「再臨がいつ起こるか分からないのだから常に用心していなければならない。」これこそマタイ24章における主要なメッセージの一つなのである。
この箇所から分かるのは、神とは人には思いもよらないことを為される御方である、ということである。これは他の例を見ると、更によく分かる。例えば、神はキリストを突然、ユダヤ人の元に送られた。それはマラキが、『あなたがたが尋ね求めている主が、突然、その神殿に来る。』(3章1節)と言った通りである。ユダヤ人にとって、キリストの登場は、意表をつくものであった。神がルターを突如として台頭させられたのも、そうである。いったい誰がこのような無名の修道士が大いに活躍するなどと思ったであろうか。誰一人として思わなかったに違いない。ダビデが王になったのもそうである。末っ子の平民に過ぎなかったダビデが王になるなどとは誰一人として思わなかったが、神はそのダビデをこそ王にされたのだ。キリストの再臨が起きたのも、人々の思いもよらないことであった。では、どうして神は人間の意表をついたやり方で事を為されるのであろうか。それは人間が神の偉大さと驚異性とを知るためである。何故なら、そうすれば人は神を崇めるようにもなるので、神の栄光が現われるようになるからである。「このようなことをなされる神はなんという大いなる存在なのだろうか。」などと言うことによって。神は御自身の栄光が現わされるのを望んでおられる。だからこそ、神は人の驚くようなやり方で、事を実現させられるわけである。もし人間が驚かないようなごく普通のやり方であれば、誰も神のことを驚いたり崇めたりしなくなるから、神の栄光も現わされなくなってしまうのだ。また、神が驚異的また予想外の方法で事を起こされるのは、神の道と思いとが人の道と思いとを遥かに上回っているからでもある。つまり神は人間のやり方や精神を無限に超越しておられるので、どうしても人は神の為されることに驚かされてしまうのである。これは、天才の天才的なやり方や生き方を見て、凡人が唖然とするようなものである。凡人が天才の手法に吃驚するのは、人間が神の手法に吃驚するのと同じことである。神の道と思いが人のそれを越えているというのは、イザヤ55:8~9の箇所でこう言われている。『わたしの思いは、あなたがたの思いと異なり、わたしの道は、あなたがたの道と異なるからだ。―主の御告げ。―天が地よりも高いように、わたしの道は、あなたがたの道よりも高く、わたしの思いは、あなたがたの思いよりも高い。』
【24:40~41】
『そのとき、畑にふたりいると、ひとりは取られ、ひとりは残されます。ふたりの女が臼をひいていると、ひとりは取られ、ひとりは残されます。』
ここでは携挙について言われている。ここで言われているのは、第一の携挙のほうであるか、それとも第二の携挙のほうなのか。この箇所では、第一のほうが言われている。というのも、文脈を見れば、そのようにしか考えられないからである。キリストがここで言われた通り、携挙された人は、急にこの世から『取られ』ていなくなった。これは前代未聞の現象だから、携挙された人の傍近くにいた携挙されなかった人が、急に近くにいた人物が消えたのを見て驚いたのは間違いない。エノクが神から取り去られて地上からいなくなったのも、このようにしてであった(ヘブル11:5)。
このように携挙の事柄が2回も繰り返されているのは、携挙が非常に重要な事柄だからである。もし携挙がそれほど重要でなかったとすれば、このように繰り返して言われることはなかったかもしれない。
2回目に言われている部分で、臼を引いている二人の女が出て来るのは、恐らく伝道者の書12:3の箇所と関わりがあると思われる。伝道者の書のほうでは、『粉ひき女たちは少なくなって仕事をやめ』ると書かれているが、これはつまりキリストの言われたことなのであろう。すなわち、携挙が起こり粉ひき女がいなくなると、働き手が少なくなるので、携挙されなかった粉ひき女たちは仕事を止めてしまうことになる、と。これについては第4部の第23章で既に書いておいた。『臼』については黙示録18:22の箇所でも書かれている。そこでは、もはやユダヤにおいて臼を引く音が聞かれなくなってしまう、ということが言われている。我々が今見ている箇所では携挙により粉ひき女たちが少なくなると言われているのに対し、黙示録18:22の箇所ではユダヤが破滅するので全ての粉ひき女たちが消え失せてしまうということが言われている。
聖徒たちの中で、この箇所について次のような疑問を持たれる人がいるかもしれない。「ここで言われている携挙がもし既に起きたとすれば、どうしてそのことが何も書き残されていないのか。もし携挙が起きていたとすれば、幾らかでも、そのことについて書かれた文書が残されているはずではないのか。」このような疑問を持つ人に対して、私は次のように質問したい。「主の行なわれた奇跡は多くの人々に見られたり知られたりしていたはずだが、どうしてその奇跡について書き記された文書が、聖書以外にはまったくないのか。キリストの奇跡が多くの人たちに知られていたのであれば、キリストの時代に生きていた人たちが書いた文書のうち、幾らかでもそのことについて書かれた文書が残っていてもいいはずではないのか。」キリストの奇跡のほうは聖書記者が明白に書き記しているのに対し、この携挙のほうは誰一人として書き記していない、という違いがあるのは確かである。しかし、キリストの奇跡における驚異性を考えれば、聖書記者以外にもその奇跡について書き記した人が少しぐらいはいてもいいはずである。いや、むしろそれを書き記した人がいないと考えるほうが難しいぐらいである。だが、聖書以外でキリストの奇跡について書き記した文書は何もない。それにもかかわらず、キリストが奇跡を行なわれたのは確かである。何故なら、聖書がキリストは奇跡を行なわれたと教えているからである。そうであれば、携挙も実際に起きたことは確かである。何故なら、聖書は既に携挙が使徒の時代に起きたと今の時代に生きる我々に教えているからである。聖書で教えられていることを受け入れず、歴史的な記録を問題にするとはいったいどういうことなのか。聖徒であれば、ただ聖書がそう教えているからというだけで、たとえ書き残された文章が聖書の他には残っていなかったとしても、それを受け入れ信じるべきである。そうしなければ、神からの裁きとして、考古学的な史料や考察に基づいて聖書を読み解こうとする自由主義神学の徒に成り下がったとしても文句は言えない。神には、御言葉をそのまま受け入れない者たちを、裁きとして強引に自由主義神学へと引きずり込む力があるのだ。人間的な感覚を捨てよ。ただ御言葉だけに自己の精神を密着させよ。必要なのは聖書に対する信仰なのだ。
【24:42~44】
『だから、目をさましていなさい。あなたがたは、自分の主がいつ来られるか、知らないからです。しかし、このことは知っておきなさい。家の主人は、どろぼうが夜の何時に来ると知っていたら、目を見張っていたでしょうし、また、おめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だから、あなたがたも用心していなさい。なぜなら、人の子は、思いがけない時に来るのですから。』
ここでキリストは、家の主人が泥棒を警戒して心を引き締めるがごとくに、再臨が起こるのを心を引き締めて待機していなさい、と命じておられる。この箇所で、キリストの日が泥棒の侵入に例えられていることに、やや違和感を持たれる方もいるかもしれない。しかし、この例えは何も不適切なものではない。何故なら、ここではキリストが泥棒そのものに例えられているわけではないからだ。ここでは、あくまでもキリストの再臨が泥棒の侵入のように突如として起こる、ということが言われているに過ぎない。つまり、ここでは泥棒の侵入という出来事における<倫理性>が持ち出されているのではなく、<現象性>が持ち出されているのだ。だから、ここでキリストの来られるのが泥棒に例えられているのは、まったく問題にはならない。しかし、もしここでキリストが悪しき泥棒のようだなどと言われていたとすれば、それは大いに問題であった。とはいっても、キリストがそのようなことを言われることは絶対になかったのではあるが。また我々は、この箇所から神の英知について感じ取ることが出来る。神は、何かが起こる時期を告げないほうがかえって益となる場合も多いことを知っておられる。神は英知そのものであられるから、この箇所でそうされているように、伝えないほうが良いことについては一切伝えることをされないのである。というのも、英知とは最も益になることを最高のやり方で知らせたり(また知らせなかったり)実現させたりする能力のことだからである。ところで、この英知がどのようなものか実際に知りたければ、「孫子の兵法」という古代中国の有名な戦術書を読むとよい。
ここでも、やはり再臨がいつ起こるか分からないのだから警戒し続けていなさい、ということが命じられている。これは、マタイ24章の中で繰り返して言われている命令である。このような繰り返しは、再臨まで警戒しつつ待機することが非常に重要だったからである。もし重要でなければ、ここまで繰り返して言われることはなかったであろう。
この箇所では、再臨がいつ起こるか分からないのだから気を引き締めているようにということが、泥棒の話の前後において語られている。すなわち、ここで言われているのは次のようになっている。再臨がいつ起こるか分からないのだから気を引き締めているように⇒家の主人は泥棒の侵入を待機して気を引き締めている⇒そのように聖徒たちも再臨がいつ起こるか分からないのだから気を引き締めているように。
【24:45】
『主人から、その家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実で思慮深いしもべとは、いったいだれでしょうか。』
この箇所からマタイ24章の終わりの部分までは、教会の監督者に対して言われている。それは、一般信徒に対して言われているのではない。
この箇所における個々の語句はどのような意味となっているのか。まず『主人』とはキリストである。『家』とは地上におけるキリストの教会である。『家のしもべたち』とは教会にいる一般信徒である。『任されて』とは教会の監督者に与えられた一般信徒に対する監督権である。『食事』とは監督者が一般信徒たちを教育と指導とパン裂きによって霊的に生育させることである。『きちんと』また『忠実で思慮深い』とは監督者がシッカリと職務を遂行することである。『忠実で思慮深いしもべ』とは言うまでもなく教会の監督者である。
ここでキリストは、教会の監督者たちがシッカリと自分に与えられた職務を遂行するようにと促しておられる。何故なら、監督とは教会において監督の職務を果たすためにこそ、監督として立てられたのだからである。もし監督が名ばかりで職務を果たそうとしないのであれば、何のために監督として立てられたのか分からなくなってしまう。キリストが監督に対して真面目さを求めておられることは言うまでもない。
【24:46~47】
『主人が帰ってきたときに、そのようにしているのを見られるしもべは幸いです。まことに、あなたがたに告げます。その主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。』
『主人が帰ってきたとき』とは再臨が起こる時である。というのも、再臨とは、キリストが再び教会という聖徒たちのいる家に戻って来られる出来事だからである。
キリストが家に戻って来られた時、監督として忠実に仕事をしている者は、実に幸いであった。何故なら、その監督はキリストの御心に適ったことをしているからである。聖徒たちにとって、キリストの御心に適うことは、それそのものが幸いである。また、そのような監督が幸いなのは、天国で大きな祝福を得られるようにもなるからであった。ここでそのような監督に『全財産を任せるようにな』ると言われているのは、つまり天国において与えられる祝福の度合いがあまりにも大きいということを教えている。また、ここでキリストが監督に忠実さを求めておられるのは、教会にいる一般信徒のためでもあったことは言うまでもない。というのも、監督とは信徒たちの霊と信仰に大きな影響を及ぼす存在だからである。もし監督が駄目になれば、監督が駄目になると同時に、その監督の下で教えられ指導されている10人、100人、1000人の信徒たちも一挙に駄目になってしまう。これは、国や企業の指導者が異常になれば、一挙に国民や従業員もその異常さに毒されてしまうのと同じである。ルーズベルトのことを考えてみるがよい。フーバー元大統領は彼のことを「狂気の男」と言ったが、もしルーズベルトが大統領でなければ、真珠湾の悲劇は起こらなかったかもしれず、アメリカが第二次世界大戦に参戦することもなかったかもしれない。この大統領が陰謀を働かせたからこそ、真珠湾の悲劇が起こり、怒り狂ったアメリカ人が一挙に世界大戦に参戦せねばならないという気持ちを持つに至ったのだ。これは黙示録的に言えば、ルーズベルトの狂った葡萄酒に、無数のアメリカ人たちが酔わされたということになる。このことからだけでも、いかにトップの存在が多くの人たちにとって重要な意味をもつかが分かるであろう。私はディドロも百科全書も嫌いだが、彼が百科全書の中で次のように言っているのは、間違っていない。「主権者にあっては、ただ一人の意志の堕落だけで、人民を危険におとしいれたり、あるいは、臣民の最大の幸福を破壊したりすることができる。」(『百科全書―序論および代表項目―』主権者 p231:岩波文庫33-624-1)つまり、リーダーの意志一つで、そのリーダーに服させられている領域の全てが大いに変化させられてしまうということだ。この原理は、程度の違いはあれど、あらゆるトップの人物において当てはまる。それだから、教会におけるトップである監督がきちんと己の職務を遂行するのは、多くの一般信徒にとっても非常に重要なことなのである。
もう今となっては再臨が起こることはなくなった。それゆえ、最早いつ起こるか定かではない再臨を待機しつつ監督が努力粉塵する必要もなくなった。この箇所では、あくまでも再臨がこれから起こることを前提としているという点に注意すべきである。つまり、ここで直接的に言われている対象は、再臨が起こるまでの時代に生きていた監督者たちだけである。しかしながら、再臨がもはや起こらなかったとしても、相も変わらず監督者たちが努力粉塵しなければいけないことは確かである。何故なら、再臨が起こっても起こらなくても、監督者たちに対するキリストの御心は、彼らが問答無用に努力粉塵することだからである。誰がこのことを疑うであろうか。もし再臨がもはや起きないからといって監督者たちは忠実に職務を遂行しなくてもよくなったなどと考える人がいれば、その人は大きな思い違いをしている。
【24:48~51】
『ところが、それが悪いしもべで、『主人はまだまだ帰るまい。』と心の中で思い、その仲間を打ちたたき、酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めていると、そのしもべの主人は、思いがけない日の思わぬ時間に帰って来ます。そして、彼をきびしく罰して、その報いを偽善者たちと同じにするに違いありません。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです。』
ここで言われているのは、つまり監督者たちが自分に与えられた職務を果たさないようなことがあってはならない、ということである。何故なら、そのような監督者は監督者として相応しくないからである。また、そのような監督がいれば、その監督に教えられる一般信徒たちも悲惨になってしまいかねない。だから、ここでキリストが、監督者に対してこのような威嚇をされたのは当然のことであった。
再臨が起きる日にシッカリと仕事をしていなかった悪しき監督者は、どのようなことになったのか。その監督は、厳しい罰を受け、偽善者たちと同じように地獄へ投げ込まれることになった。そして、その地獄の場所で『泣いて歯ぎしりする』ことになった。この箇所では、彼らが地獄に投げ込まれるという文章はないが、文意を見るならば、そのような監督者が地獄に投げ込まれると教えられているのは明らかである。そのような監督者とは、『仲間を打ちたた』くような監督者である。これは、一般信徒という仲間を蔑ろにして正しく牧そうとはしない、ということである。これは今の時代で言えば、部下に酷い苛めをする上司また部長とよく似ている。そのような上司また部長が罰せられたり会社から追い出されてしまうように、一般信徒に対して正しい振る舞いをしない監督者には罰が与えられ御国からも排除されてしまう。また、そのような監督者は『酒飲みたちと飲んだり食べたり』するような監督者である。これは、悪い者と一緒になって仕事を怠けるような振る舞いを言っている。このような監督者は、サルダナパロスやヘリオガバルスとよく似ている。この2人の異常な統治者は、国民のことなどお構いなしで、自分の欲求を満たすことしか考えていなかった。このような愚かな監督者たちには、キリストがここで言っておられるように、不意に主の日が襲いかかった。それは歩いていたら急に落とし穴に落ちるようなものである。その時、その監督者たちは自分のそれまでの歩みを後悔したかもしれない。しかし、その時にはもう既に取り返しがつかないことになっていた。何故なら、その時、彼らの滅びが確定されてしまったからである。それゆえ、もうその監督者たちは、もはやエサウのように泣いて嘆いても地獄の運命を免れることが出来ない状態になっていた。
もはや今となっては再臨が起こることはなくなったから、もう再臨が起こることを念頭に置いて悪しき監督にならないように注意する必要はなくなった。しかし、再臨がもう起こらないからと言って、監督者たちが悪しき振る舞いを避けなくてもよくなったというわけではない。もし再臨が起きないからといって邪悪な監督者となるようであれば、その監督者は、この人生を終えてから地獄に容赦なく投げ込まれるであろう。再臨が起こっても起こらなくても、監督者に対する主の御心は、彼らが悪しき監督者にならないことである。誰がこのことを疑うであろうか。
【25:1】
『そこで、天の御国は、たとえて言えば、それぞれがともしびを持って、花婿を出迎える10人の娘のようです。』
キリストは、今度は、全ての聖徒たちに関わる天国についての例えを語っておられる。これは先の箇所とは違い、監督者たちにだけ言われているのではない。ここで言われているのは、つまり「キリストはいつ来られるか分からないから気を引き締めて悲惨なことにならないようにせよ。」ということである。この例え話は25:13の箇所まで続いている。
ところで、どうしてキリストは例えをもって語られたのか。それは次の預言が成就されるためであった。『わたしはたとえ話をもって口を開き、世の初めから隠されていることどもを物語ろう。』(マタイ13章35節)神の名は士師記13:18の箇所で言われているように『不思議』である。キリストは神であられるから、不思議という名を持たれる存在として、例え話で語られるのが相応しかったのである。というのも、例えにより話すと不思議な感情が聞く者の心の中に起こるものだからである。
ここで言われている個々の語句は、それほど難しいものではない。まず『天の御国』とは、紀元1世紀に開始された天上の国である。『花婿』とは、もちろんキリストである。黙示録19:7~8の箇所でも、キリストが教会という花嫁に対する花婿として描かれている。『娘』とは聖徒のことである。『花婿を出迎える』と書かれているのは、再臨されたキリストを地上の聖徒たちが出迎えることである。娘が『10人』いたのは、娘である聖徒たちの数が豊かであることを示している。10とは完全であったり豊かであったりすることを象徴させる数字だからである。『ともしび』とは聖徒たちの生命である。この『ともしび』とは聖書の多くの箇所において「生命の灯」という意味で使われている(箴言13:9、20:20、24:20、ヨブ21:17)。命を『ともしび』という言い方でもって表現するのは、世の人々も時折している。例えば「社長の灯も後僅かとなってしまった…。」などと言われるのがそうである。
【25:2~4】
『そのうち5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは、ともしびは持っていたが、油を用意しておかなかった。賢い娘たちは、自分のともしびといっしょに、入れ物に油を入れて持っていた。』
ここでは10人の娘たちが2種類に分けられている。すなわち、一方の5人は『愚かな娘』であり、もう一方の5人は『賢い娘』である。『愚かな娘』とは、再臨が起きた時に携挙されなかった不幸な聖徒のことである。この人たちは、永遠の昔から救われるようにと定められてはいなかった。『賢い娘』とは、再臨が起きた時に携挙されて天国に入れられることになった聖徒である。この人たちは、永遠の昔から救われるように定められていた。この10=5:5という比率が、実際の比率と同じだったかどうかは我々には分からない。もしかしたら、これは単に分かりやすさのために分けられた比率に過ぎないのかもしれない。実際には、例えば8:2とか7:3という比率だった可能性も十分にある。しかし、この5:5という比率が実際通りだったということもありえる。だが、やはり私としては、実際には愚かな娘のほうが圧倒的に多かったと考えるほうがよいのではないかと思う。それというのも、キリストが次のように言われたからである。『招待される者は多いが、選ばれる者は少ないのです。』(マタイ22章14節)すなわち招待されて教会に籍を置くようなった人は多くいるのだが、実際に真の信仰を持っている選ばれた者となるとその数は本当に少ないのだから―これはルターも度々述べたことである―、やはり賢い娘に分類されるような聖徒は愚かな娘よりも比率的に少なかったと考えるのがいいのかもしれない、と私は思うのだ。
ここで言われている『油』とは「聖霊」である。ヨハネも聖霊を『油』(Ⅰヨハネ2:20、27)と言っている。愚かな娘たちは、生命の灯は持っていたが、神の霊は与えられていなかった。彼女たちは、真の信仰を持とうとしなかったので、神の霊も彼女たちのうちにはおられない。彼女たちは真の信仰を持たなかったので、『愚か』であると言われている。というのも真に正しい信仰を持とうとしないのは、愚かそのもの、愚かの極みだからである。それは、白い色を見てそれが白い色だと認めようとしなかったり、自分が明らかに生きているのに自分が生きていることを否定するようなものである。これを愚かであると見做さない人がいるのであろうか。神の真理を否定してそれを認めようとしない者たちも、これと同じことをしているのだ。他方、賢い娘たちは、生命の灯を持っているだけなく、神の霊も受けていた。彼女たちは真の信仰を持っていたので、神の霊も彼女たちのうちにおられた。それゆえ彼女たちは『賢い』と言われている。というのも、真理を正しく信じるというのは正に知恵そのもの、知恵の極みだからである。詩篇では『主を恐れることは、知恵の初め。これを行う人はみな、良い明察を得る。』(111:10)と書かれている。知恵者は神を恐れるが、神を恐れるとは真理を正しく信じることである。というのも、知恵者とは神が人に真理を正しく信じるように望んでおられることを知っており、神の望み通りに真理を正しく信じようと願うものだからである。なお、この2種類のどちらにも該当する娘あるいはどちらにも該当しない娘は存在しないということを言っておかねばならない。確かなところ、愚かであると同時に賢くもあったり、または愚かではないが賢くもない、という娘は誰もいない。人は、必ずこの2種類のどちらかの存在に該当している。というのも神の御前に中間はないからである。神の御前において人は必ず2種類のうちどちらかに区分されている。すなわち、救われる人であるか救われない人であるか、のどちらかである。それは、「白であるが黒でもある」とか「有であるが無でもある」というのがあり得ないのと全く同じことである。
【25:5】
『花婿が来るのが遅れたので、みな、うとうとして眠り始めた。』
ここでは花婿であられるキリストの再臨が遅れることについて言われている。とはいっても、その遅延の度合いは、そう長いものではない。それは5年、もう少し長くて15年、最長で25年ぐらいである。
今現在の聖徒たちは、この箇所で再臨が遅れたと言われていることを、再臨が未だに起きていないという見解の根拠としてはならない。すなわち、次のように言ってはならない。「この箇所では再臨が遅れると言われているから、2千年前からずっとキリストの再臨は遅らされているのだ。だから、未だにキリストの再臨が実現されていなかったとしても不思議ではない。」どうか、よく考えてもらいたいものである。キリストはマタイ24:34の箇所で、再臨が1世代すなわち40年の間に起こると言われたのだ。つまり、再臨が遅れるといっても、その遅れる年数が40年を超えることは絶対にありえない。もしその遅延の年数が40年以上だったとすれば、キリストの御言葉が偽りだったことになるからである。しかし、キリストは偽りを言われたのではない。であれば、どうして2千年間も再臨が遅延しているということがあるのであろうか。もし再臨が2千年も遅れるとすれば、キリストはマタイ24:34の箇所で「再臨が起こらない限りこの世代は過ぎ去らない。」などとは言われず、むしろ「再臨が起こるまではまだ50世代かかる。」などと言っておられたはずである。2000年とは50世代分の年月だからである。しかし、キリストが言われたのは、キリストがオリーブ山で弟子たちの質問に答えられてから1世代の間に再臨が起こるということであった。それだから、再臨が2千年間も引き延ばされているなどと考えることは絶対にできない。また、もし2千年も再臨が遅らされているとすれば、この例えの中に出てくる娘たちは花婿が来る時までに死んでしまっていたはずである。何故なら、この娘たちが2千年も死なないままでいることはないからである。しかし、この例えの中では、娘たちが生きているその間に花婿が来ている。だから、再臨が遅れるといっても、ほんの少し遅れるだけであったと理解せねばならないことになる。
【25:6】
『ところが、夜中になって、『そら、花婿だ。迎えに出よ。』と叫ぶ声がした。』
夜になって再臨が起きたことを叫ぶ声が聞こえたのは、キリストの再臨が唐突に起こるということを教えている。我々が夜に寝ている時、急に陛下が大勢の政治家や知識人と一緒に自分の家に訪れたとすれば、どうであろうか。恐らく、ほとんど全ての人がその唐突な訪問に吃驚仰天するのではないか。キリストが突如として天から降りて来られるのは、正にそのようなものであった。
ここで再臨の起きたことが大きな声で叫ばれているのは、つまり再臨が非常に重要な出来事だったからに他ならない。重要だからこそ大声で叫ばれたのである。もし重要でなければ叫ばれることもなかったであろう。キリストも御使いも、重要なことを言う際には大声で叫んでいる(ヨハネ7:37、黙示録14:7、9)。
ところで、ここで大声で叫んでいる者は誰なのであろうか。キリストは、この声の主が誰であるのか示しておられない。トマスのような詮索好きの者にとっては残念かもしれないが、この声の主が誰であるのかということについては、別に知らなくてもよいことである。我々は、ただここで再臨について大声で叫ばれているということだけを知っていれば、それで十分とすべきである。もしこの声の主について知らねばならないと言うのであれば、他にも「この声はどのような響きが感じられたのか」とか、「この声の主はこれ以外にも何かを言ったのか」などといったことも知らねばならないということになってしまうであろう。こういう知らなくてもよい些細な事柄をいちいち問題にするからこそ、「神学大全」のような冗長な作品が生まれてしまうのだ。重要な事柄にこそ時間と精神と思考とを集中させるべき我々は、無益な詮索を避けるべきである。
【25:7】
『娘たちは、みな起きて、自分のともしびを整えた。』
聖徒である『娘たち』が『自分のともしびを整えた』とは、つまり再臨されたキリストの御前に出られるように自分で自分自身を整えた、ということである。陛下が家の扉の前で待っておられると聞かされたら、陛下の前にシッカリとした状態で出るために、誰でも自分で自分を整えるはずである。まさか、パジャマ姿のままで出るという人はいないであろう。それと同じで、再臨のキリストの御前に出るために、聖徒たちは自分で自分を整えるべきであったのである。もし再臨のキリストの御前に出るのに自分自身を整えない者がいたとすれば、それは陛下の前に出るのに全く何も整えないで行く者と同じである。そのような者は世の中にほとんどいないと思われるが、もしいたとすれば恥知らずと言われねばならない者である。なお、ペテロもこれからユダヤの終わりに伴い再臨が起こるからというので、聖徒たちが自分で自分自身を整えるようにと命じている。すなわち彼はⅠペテロ4:7の箇所で次のように言っている。『万物の終わりが近づきました。ですから、祈りのために、心を整え身を慎みなさい。』
【25:8】
『ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。『油を少し私たちに分けてください。私たちのともしびは消えそうです。』』
花婿が来た時、油を持っていなかった愚かな娘たちは、油を持っている賢い娘たちに、その油を分け与えるようにと求めている。というのも、油を持っていない娘たちは、再臨が起きた時に救われず断罪され、やがて生命の灯が消されることになるからである。これは、油を持っている娘たちが再臨の時に救われて永遠に生命の灯を保てるようになるのとは正反対である。この箇所で注目すべきなのは、愚かな娘たちが聖霊を分け与えてもらえると思っているということである。しかし、聖霊はただ神から一方的に与えられるのであって、聖霊を与えられている人から貰い受けるということはできない。この娘たちは、こんなことさえ分からなかった。だから、彼女らは確かに『愚か』と言われて然るべきであったと言えよう。
【25:9】
『しかし、賢い娘たちは答えて言った。『いいえ、あなたがたに分けてあげるにはとうてい足りません。それよりも店に行って、自分のをお買いなさい。』』
愚かな娘たちの愚かな要求を受けて、賢い娘たちはその要求をきっぱりと断っている。というよりは、断る以外の選択肢はなかった。それというのは、既に述べたように聖霊を他人に分与することは原理的にできないからである。ここでは『分けてあげるにはとうてい足りません。』と言われているから、聖霊が豊かに与えられていれば分与することも可能だと教えられていると捉える方もいるかもしれない。しかし、ここでは豊かに与えられていれば分与可能ということが言われているわけではない。ここで言われているのは、あくまでもその人に与えられた聖霊はその人に対して特有的に与えられているのだから、それを他の人に分けることは出来ない、ということであって「量」が問題とされているのではない。また、我々はここで愚かな娘たちの要求を断っている賢い娘たちの対応を見て、冷酷だなどと思うべきではない。何故なら、この娘たちは自分に与えられた聖霊をたとえ分けてあげたいと思っても、それは絶対に出来ないことだったからである。原理的に不可能だからというので断ったからといって、どうして冷酷な性質を持っていることになるのであろうか。
この賢い娘たちは聖霊という油を分けることがどうしても出来なかったので、愚かな娘たちに『店に行って、自分のをお買いなさい。』と勧めている。この『店』とは神であり、『お買いなさい。』とは「聖霊を受けるようにしなさい。」ということである。つまり、この賢い娘たちは、愚かな娘たちが神から聖霊をいただけるようにしなさい、とここで言っている。何故なら、そのようにして聖霊を受けるのであれば、愚かな娘たちも救われて生命の灯を永遠に保てるようになるからである。
【25:10~12】
『そこで、買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは、彼といっしょに婚礼の祝宴に行き、戸がしめられた。そのあとで、ほかの娘たちも来て、『ご主人さま、ご主人さま。あけてください。』と言った。しかし、彼は答えて、『確かなところ、私はあなたがたを知りません。』と言った。』
この箇所で言われているのは、再臨が起きてからでは既に時は遅くなってしまっている、ということである。キリストが来られたのを見たことにより聖霊と受けようと願っても、神はその人に聖霊をお与えにはならない。何故なら、もうその時には時間制限が切れてしまっているからだ。
この箇所を読んで、神が厳しく冷たい御方であるなどと考えてはならない。すなわち次のように心の中で考えるべきではない。「再臨が起きたのを見て聖霊を受けようと願った人も救われたらいいではないか。どうして再臨が起きたならば、もうその時点で救いの期限が終わりになるのか。そのように定めた神は酷い御方であると言えないだろうか。」しかし、考えてもらいたいのである。この世の社会を見回すとどうであろうか。あるタイトル戦の試合が開催される日にその試合会場へ足を運べなかった人は、当然ながらその試合を見ることはできない。ある特定の日にだけ限定的に売られる掘り出し物を買いそびれた人は、もうその掘り出し物を買うことはできない。ある人の誕生日をその日に祝えなかった人は、もう1年経過しない限り、その誕生日にその人を祝うことはできない。他にもこんな例は考えればいくらでも見つかる。このような事例の場合、その日に事を為せなかったり締め切りの日に間に合わなかったりした人のために融通を利かせる人はほとんどいないであろう。誰が遅れた一人のために定めておいた期日を引き延ばすのか。タイムセールに間に合わない可愛そうな人がいたからといって、そのタイムセールを実施した主催者を責める人がどこにいるのか。誕生日当日に祝えなかった人が怒り狂ったところで、いったい何になるであろうか。再臨が起きた時に、愚かな娘たちがもう時間切れで永遠の滅びに定められてしまったのも、これと同じである。再臨が起きた時に油を持っていなかった娘たちは、彼女たちに問題があったのであり、再臨が起こることをお定めになった神に問題があったのではない。それだから、この箇所を読んで神が冷酷であるなどと思う人は、何か思い違いをしているのである。そのような人は、あたかも試合当日に試合会場に足を運べなかった人に味方して、その試合の主催者たちを冷酷だなどと言って非難する人のようである。
【25:13】
『だから、目をさましていなさい。あなたがたは、その日、その時を知らないからです。』
ここまで例えを話された後、キリストは聖徒たちがいつ起こるのか定かではない再臨を気を引き締めつつ待機していなさい、と言っておられる。何故なら、もし例えの中に出てきた愚かな娘たちのようになってしまえば、その人は再臨が突如として起きた際に悲惨なことになってしまうからである。キリストは、聖徒たちが愚かな娘のようにならないのを望んでおられるのだ。この箇所で言われているのは、先に見たマタイ24:42の箇所の繰り返しである。このように繰り返して言われるのは、その事柄が非常に重要だからである。
もはや今となっては再臨を待機する必要はなくなった。もうキリストは既に再臨されたからである。しかし、今の時代に生きる我々も、昔の聖徒たちと同じように、常に目を覚ましていなければならない。何故なら、我々は自分がいつ死ぬのか知らないからである。中には、長く生きるようにと約束されている恵まれた人もいるかもしれない。しかし、そういう人ばかりではないのである。いつ天に召されるか定かではない、という点で今の時代に生きる我々と再臨を待望していた昔の聖徒たちは一緒である。ただ異なっているのは、再臨が起こるのか起こらないのか、また再臨により天に召されるのか再臨以外の事象により天に召されるのか、という点だけである。それだから、今の時代に生きる我々も昔の聖徒たちと同様に怠惰になっていてはならないのである。ところが今の聖徒たちは、長い時間であれ短い時間であれ、霊的な眠りの中に沈み込んでいた自分にハッと気づく時が往々にしてあるのではないかと思う。このようになるのを避けるのは、なかなか難しいと思われる。世俗化の進んでいる現今のプロテスタント教徒にあっては、特にそうである。いったい、どれだけ多くのプロテスタント教徒たちが、霊的な眠りに日々沈み込んでしまっていることであろうか。しかし、これは言うまでもないことかもしれないが、聖徒である者たちがそのような事態に陥ることは極力避けられるべきである。
【25:14】
『天の御国は、しもべたちを呼んで、自分の財産を預け、旅に出て行く人のようです。』
今度は、再び監督者たちに対する例えが語られている。この例えが一般信徒も含めた全ての聖徒たちに対する例えであると捉える人もいるだろうが、少なくとも今現在の私は、そのように捉えてはいない。私はここでは24:45~51の箇所と同じで、監督者を対象としていると考える。この例えでは、監督者たちが再臨の起きた際、天国に入るようになった時のことについて語られている。この例えは25:30の箇所まで続いている。
『天の御国』とは、紀元1世紀に開始された天上の王国のことである。これは、もうとっくの昔に到来している。『しもべたち』とは教会の監督者である。『財産』とは神から与えられる賜物である。『旅に出て行く人』とはもちろんキリストである。これは続く箇所を見れば分かるように『しもべたちの主人』である。『旅』とは、すなわちキリストが昇天されてから再臨されるまでの期間のことを言っている。つまり、キリストはオリーブ山から天に上って行かれたが、それこそ『旅』である。
【25:15】
『彼は、おのおのその能力に応じて、ひとりには5タラント、ひとりには2タラント、もうひとりには1タラントを渡し、それから旅に出かけた。』
神は、監督者たちに、それぞれ異なった度合いの賜物をお与えになる。ここで、『ひとりには5タラント、ひとりには2タラント、もうひとりには1タラントを渡し』と書かれている通りである。具体的に言えば、5タラントを与えられた者とはパウロやアウグスティヌスのような人であり、2タラントを与えられた者とは最高に有名であったり飛びぬけて優秀というわけではないもののよく頑張っている監督者であり、1タラントを与えられた者とは怠けてばかりいる未熟な監督者である。私の見るところ、5タラントを与えられている監督者はほとんど見られない。2タラントと1タラントのほうについては、どちらの人のほうが多いのか私には判断がつかない。それでは、どうして神は監督者たちにそれぞれ異なった度合いの賜物を与えられるのか。つまり、どうして神は差異をつけられるのか。これは、「神がそのように望まれたから。」としか言いようがない。例えば、どうしてウェスパシアヌスはティトゥスにはティトゥスという名を付け、ドミティアヌスにはドミティアヌスという名を付けたのか。これは、「ウェスパシアヌスがそう望んだから。」としか言いようがないであろう。神がある人に5タラントを与え、ある人には2タラントを、別の人には1タラントをお与えになるのも、それと同じである。
このことから、「人間は全て平等なんだ。」などと言っている者たちが、どれだけ間違ったことを言っているかがよく分かる。この箇所では、神が人に応じて5タラント、2タラント、1タラントという区別を付けつつ賜物をお与えになっておられることが書かれている。また神はアインシュタインには高い知性をお与えになったが、ジョージ・ブッシュ(子)にはあまり高い知性をお与えにはならず、これは数としては少ないが知性をまったく与えられていない者もいる(例えば山で獣に育てられた者など)。見よ、実に自然に平等など存在しないのである。「存在している」ということであれば全ての人が平等であるが、存在者にとって存在とは根本的な前提要件なので、これは考量の中に入れられるべきではない。つまり、人間は全て平等だなどと言っている人たちは、何も考えていないだけである。「シオン賢者の議定書」の中ではこのように言う人たちが嘲られているが、彼らは嘲られても文句を言えないと思う。何故なら、何も考えないのに間違ったことを堂々と言っており、世界と人々に対して誤謬という害を撒き散らしているからである。もし彼らの言っていることが本当だったとすれば、この箇所では全ての監督者たちに同一のタラントが与えられていただろうし、アインシュタインもブッシュも山で育てられた者も全て同一の知性を持っていたことであろう。しかし、自然を見ても平等などというものは決して見られない。このことから、神の御心は「差異」を付けられることだったということが分かるのだ。我々は思い違いをしないようにすべきである。
【25:16~17】
『5タラント預かった者は、すぐに行って、それで商売をして、さらに5タラントもうけた。同様に、2タラント預かった者も、さらに2タラントもうけた。』
5タラントを預かった監督者は、自分に求められている分のタラントを稼いだ。神から与えられた賜物に相応しい働きを為したのである。『すぐに行って』と書かれているのは、5タラントを受けた監督者の高い忠実さを示している。同様に2タラントを預かった監督者も、自分に求められている分のタラントを稼いだ。彼もその与えられた賜物に応じた働きを為したのである。
いつの時代であれ、監督者たちには、神から与えられた恵みに応じた働きが求められている。すなわち、5タラントを受けた者は5タラントを稼がねばならず、2タラントを受けた者は2タラントを稼がねばならない。5タラントを受けた者が10タラント稼がねばならないことはなく、2タラントを受けた者が5タラント稼がねばならないということもない。しかし、5タラントを受けた者が2タラントしか稼がなかったり、2タラントを受けた者が1タラントしか稼がない、というのではいけない。というのも、キリストが言っておられるように『多く与えられた者は多く求められ、多く任された者は多く要求される。』(ルカ12章48節)からである。このキリストの御言葉では多く与えられた者のことしか言われていないが、多く与えられた者が多く求められるというのであれば、少しだけ与えられた者は少しだけしか求められていないということは明らかである。それだから、5タラントの者が5タラント以上稼げなくても悲観すべきではないし、2タラントの者が5タラントの者のような働きが出来なかったとしても問題にはならない。事は、他の者との比較によって測られるのではなく、神から求められている度合いによって測られるのだ。つまり、監督者の働きにとって重要なのは「分相応」ということである。今の監督者たちは、自分自身の働きをよく考えてみるべきであろう。果たして、今の監督者たちは自分に与えられた賜物に応じた働きを為しているであろうか。為しているのであれば、それは結構な話である。しかし為せていないようであれば、その監督者には努力と労苦が不足しているということになる。求められている度合いのタラントを稼げていない監督者は、祈りと勤勉が必要である。
【25:18】
『ところが、1タラント預かった者は、出て行くと、地を掘って、その主人の金を隠した。』
1タラント預かった監督者は、自分に渡されたタラントを使って商売をしようとはしなかった。それどころか、犬でもあるかのように地中に主人の金を埋めて眠らせておいた。彼は5タラントおよび2タラントの者とは違い、自分に求められている分のタラントを稼いではいない。この監督者は、賜物に応じた働きをしなかった。
【25:19】
『さて、よほどたってから、しもべたちの主人が帰って来て、彼らと清算をした。』
『主人が帰って来て』とは、キリストの再臨のことである。キリストは昇天により天の場所へと旅に出られたのだが、その天から再び来られる出来事が、ここでは「帰還」として語られている。
再臨が起きた際には『清算』が行われた。これは、つまり空中の大審判のことである。その時には、監督者たちがその与えられた賜物に相応しい働きを為したのかどうか精査されるので、それが『清算』と言われているのだ。これはあらゆる清算を越えた清算である。というのも、それは神が直接的に査定をされ、その査定により監督者たちの永遠の境遇が確定されることになるからである。これ以上の清算は有り得ない。それゆえ、これは「清算の中の清算」と言うことが出来る。
【25:20~23】
『すると、5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出して言った。『ご主人さま。私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください。私はさらに5タラントもうけました。』その主人は彼に言った。『よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたは、わずかな物に忠実だったから、私はあなたにたくさんの物を任せよう。主人の喜びをともに喜んでくれ。』2タラントの者も来て言った。『ご主人さま。私は2タラント預かりましたが、ご覧ください。さらに2タラントもうけました。』その主人は彼に言った。『よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたは、わずかな物に忠実だったから、私はあなたにたくさんの物を任せよう。主人の喜びをともに喜んでくれ。』』
5タラントと2タラントの者は、自分に求められている分の働きをしたので、主人から褒められ、大きな報いを受けられた。5タラントの者は5タラント以上は稼げなかったし、2タラントの者は5タラントの者のような働きは出来なかったが、神はそれを何も問題視されず、むしろこの2人の者の働きを大いに喜んでおられる。つまり、先にも述べたように、監督者は分相応の働きをすれば、それでよいのだ。もしそうでなければ、この箇所では2タラント預かった者に対して「どうして5タラントの者のような働きをしなかったのか。」などと言われていたはずである。我々は、例えばジェフ・ベゾスといった大企業の社長やジョージ・ルーカスといった有名な映画監督が大きな成果をあげない限りは認めたり称賛したりしようとしないが、幼児であれば積木を上手に積み上げただけで大拍手をしたり大きな声をあげたりする。つまり、多く与えられている者には多くの物を求め、少ししか与えられていない者には少しの物しか求めない。神が人に対して取られる態度も、それと同じである。
監督者たちは、自分に求められている分のタラントを稼ぐ必要がある。5タラント与えられた者は5タラントの稼ぎを報告できるように、2タラント与えられた者は2タラントの稼ぎを報告できるようにせねばならない。監督者たちは、ただそうすれば、それだけでよい。そうすれば、ここで言われていることから分かるように、神からの称賛と報奨をいただくことが出来るからだ。自分に求められている分よりも多くのタラントを無理に稼ごうとしなくても問題はない。何故なら、神は、その人が自分に期待されている分のタラントを稼げばそれで良しとされるからだ。そもそも、自分に与えられている分よりも多くのタラントを稼ぐことは原理的に出来ないのではないかと思われる。例えば2タラント与えられている者は、2タラントであれば稼げるだろうが、5タラントの稼ぎを得ることはできないであろう。何故なら、その人には2タラント分の稼ぎを得る恵みしか与えられていないからである。
【25:24~25】
『ところが、1タラント預かった者も来て、言った。『ご主人さま。あなたは、蒔かない所から刈り取り、散らさない所から集めるひどい方だとわかっていました。私はこわくなり、出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたの物です。』』
1タラント預かった者は、何も働かず何も稼がなかったので、主人のタラントをそのまま主人に返却した。怠けて商売をしなかったのだから、これは当然であった。これは、怠けることなく商売をしてシッカリと稼いだ5タラントおよび2タラントの者とは、まったく異なっている。この監督者が怠惰になり何も商売をしなかったのは、主人が『蒔かない所から刈り取り、散らさない所から集める』からであった。このような主人であれば、もし商売に失敗して預けられたタラントを失った場合、僕を大いに叱責したり罰したりするのは目に見えている。それゆえ、1タラント預かった監督者は、この主人を恐れたのだ。この者は、稼ぐのに失敗して主人から怒られるよりは、稼ぎはしなくても主人の金を変化なく安全なまま保っていたほうがよいと考えた。何故なら、その場合、預けられたタラントが増えることはないが、しかし減ることもあり得ないからである。つまり、この監督者はリスクを避けようとして、何も商売をしようとはしなかった。だからこそ、最後には主人のタラントをそのまま差し出すことになったのだ。もしこの監督者が恐れを抱いていなければ、自分に与えられたタラントを用いて商売していたことであろう。実際、5タラントと2タラントの者は恐れを抱かなったので、商売をしてシッカリと儲けを得た。
確かなところ、臆病は怠惰の母である。臆病と怠惰は密接に繋がっており、この2つは表裏一体であると言ってよい。すなわち、臆病になればその人は怠惰になり、怠惰になればその人は臆病になる。これは世の中を見渡せば確認できる。例えば、ニートは社会に出るのが怖いので家に閉じこもって怠惰な生活をしている。また怠惰になって自分を磨こうとしない者は、いつまでも未熟なままなので他人の上に立つことが出来ず、それゆえ一向に強くならないので小物の地位に甘んじるままとなる。臆病と怠惰に大きな関係があるというこの原理については、ソロモンの次の言葉からも分かる。『なまけ者は言う。「獅子が外にいる。私はちまたで殺される。」と。』(箴言22章13節)『なまけ者は「道に獅子がいる。ちまたに雄獅子がいる。」と言う。』(箴言26章13節)つまり、獅子に八つ裂きにされてしまうと恐れている人は、実際にそのようにならないようにと外に出ることもせず怠惰になってしまうのである。もしこの人が獅子のことなど考えないか、または獅子のことを恐れなかったとすれば、怠惰にはならなかったことであろう。この箇所に出てくる監督者も、主人およびリスクという獅子を恐れたので、怠惰になってしまった。それだから我々は次のことを知るべきである。すなわち、臆病のもたらす負の報酬は怠惰である、と。このことから次のように言える。もし臆病を殺したければ怠惰を殺したらよい。そうすれば、臆病は無くなるか抑えられるであろう。何故なら、勤勉になると自然と臆病は失せるか減退してしまうものだからである。これは我々の経験も教えるところである。またもし怠惰を殺したければ臆病を殺したらよい。そうすれば、怠惰は無くなるか抑えられるであろう。何故なら、勇気のある者は、何も恐れないか、もしくは恐れがあってもそれを気にしなかったり無理矢理にでも乗り越えようとするからである。恐れないのであれば、つまり歩みを妨げる壁がないのも同然なわけだから、躊躇することもなく勢いよく進めるようにもなるのだ。このように、もし恐れが生じれば怠惰が生じ、もし怠惰が生じれば恐れが生じてしまう。我々は注意しなければいけない。
【25:26~27】
『ところが、主人は彼に答えて言った。『悪いなまけ者のしもべだ。私が蒔かない所から刈り取り、散らさない所から集めることを知っていたというのか。だったら、おまえはその私の金を、銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰って来たときに、利息がついて返してもらえたのだ。』
まず、ここで主人は自分が『蒔かない所から刈り取り、散らさない所から集める』存在だということを否定しはしなかった。否定しないということは認めていることを意味する。つまり、主人すなわち神とは、かつては生じていなかったものをお求めになる御方であるということが分かる。
この1タラントの者は、主人が言っているように銀行にタラントを預けておくということさえしなかった。この監督は、せめて銀行にタラントを預けるぐらいのことはすべきであった。何故なら、そうすれば、たとえ僅かではあっても主人に増えたタラントを返せるからである。ここで主人は何か難しい仕事を求めているのではない。ただ銀行に預けよと言っているだけである。しかし、この監督はそれさえしなかった。というのも、もし銀行に預ければ、その銀行が預かったお金を無くしたり奪ったりすることを恐れたからである。つまり、この監督者はどうしようもないぐらいに酷い怠け者であった。それだから、彼がここで『悪いなまけのしもべ』などと言われたとしても文句は言えなかった。この監督の問題点は、まったく何もしようとはしなかったという点にある。この監督が何一つとして主人のための仕事を思いつかなかったということは有り得ない。少ししかタラントが増えなくても、必ず何か一つは行なうことの可能な仕事があったはずである。この箇所では、その一つとして「銀行に預ける」ということが書かれている。しかし、この監督者の臆病と怠惰の度合いは実に甚だしかったので、彼はそれさえもしなかったのだ。それゆえ、主人は彼に怒りを発せられたのである。もし彼がせめて銀行にタラントを預けることさえすれば、たとえそれが小さなことであったとしても、主人の怒りを買うことはなかったであろう。
今の監督者たちはどうであろうか。『悪いなまけ者のしもべ』になっていないだろうか。何も出来ない、何をしても駄目だ、などと思ったり言ったりしていないだろうか。リスクに過剰なまでに敏感になっていないだろうか。たとえ怠ける傾向を持っていたとしても、リスクのあることばかりしか思い浮かばなかったとしても、状況が悪かったとしても、まったく何一つとして御心に適った働きを行なうことが出来ないということはないはずである。頭をひねって考えれば、必ず何か良きことが思い浮かぶはずである。この箇所から分かるように、主なる神は、たとえタラントを銀行に預けておくということだけでも「良し」とされる。我々が「そんなことだけでもいいのか…」などと感じたとしても、主なる神はそれを御旨に適うこととして認めて下さる。そうすれば、僅かでもタラントが増えるからだ。怠惰な監督者たちは、そのぐらいのことさえ出来ないのであろうか。まさか、そんなことはないであろう。だから、監督者たちは自分の出来る御心に適ったことを、それがたとえ小さなことではあったとしても、精一杯に行なうべきである。そうすれば、やがて主から『悪いなまけ者のしもべだ。』などと言われることはないであろう。
【25:28~30】
『だから、そのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っている者にやりなさい。』だれでも持っている者は、与えられて豊かになり、持たない者は、持っているものまでも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは、外の暗やみに追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのです。』
1タラント預かった監督者は、怠けて何も働かなかったので、報いを受けることが出来なかった。その分、10タラント持っている監督者が、より多くの報いを受けることになった。そればかりでなく、この10タラントの者は地獄に投げ込まれることにさえなった。何故なら、主人のためにタラントを用いて稼ごうとしなかったからだ。『役に立たぬしもべは、外の暗やみに追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのです。』と言われている通りである。この語句の説明をすれば、『外の暗やみ』とは天国の外すなわち地獄であり、『追い出しなさい。』とは地獄に入れられることであり、『泣いて歯ぎしりする』とは苦しみと嘆きと妬みと後悔のことである。この監督者は怠惰のゆえに、このような結末を迎えることになった。もしこの監督者が銀行にタラントを預けるということだけでもしていれば、最終的にこのような悲惨を受けることにはならなかったであろう。
監督者が怠けていても永遠の報いが少なくなるだけで天国には入れるだろう、と思っている人がいるかもしれない。何故なら、たとえ怠けていてもキリストを信じてはいるのだから、と。この考えは誤っている。この箇所を読めば分かるように、怠けている監督者は報いを受けられないだけでなく地獄に投げ落とされる。そのような監督者は、実はキリストを信じてはいなかったのである。何故なら、もしキリストを信じていたとすれば、その人のうちには神の霊がおられるのだから、幾らかでも神のために努力しただろうからである。キリストを信じていないというのであれば、怠け者の監督者が地獄に行ったとしても当然である。また、ここでは怠けずにシッカリと仕えることが救いをもたらす、ということが教えられているわけではない。それだと聖書が行為義認を教えているということになってしまう。ここで言われているのは、あくまでも主人に仕えないような監督者は天国に入れない、ということに過ぎない。つまり、この箇所では義認の方法が教えられているというのではない。我々は知るべきである。監督者が怠けて何もしていないのであれば、その監督者は地獄に行くということを。ヤコブはこう言っている。『私の兄弟たち。多くの物が教師になってはいけません。ご承知のように、私たち教師は、格別きびしいさばきを受けるのです。』(ヤコブ3章1節)人を教える監督者たちには、その歩みに対して峻厳な報いが与えられることになるのだ。それゆえ、もし怠惰になっているのであれば、その監督者に対する報いは実に厳しいものとなる。
ここで『だれでも持っている者は、与えられて豊かになり、持たない者は、持っているものまでも取り上げられるのです。』と言われているのは普遍的な真理であり、心に留めるべき御言葉である。世の中を見てみるとどうか。キリストの言っておられる通りの状態が見られる。例えば、富を多く持っている者はますます富を増し加えて行くが、貧しい者は更に貧しくなって段々と悲惨の度合いを増し加えていく。アブラハムやアウグスティヌスなど霊的に恵まれた者たちは信仰や聖書の理解が時間と共に更に増し加えられたが、信仰のない異教徒たちは信仰の閃きのようなものさえ最初は持っていたとしても徐々に失っていく。他にもこのような事例が、世の中を見渡せば見つかる。この原理を心に留めることは我々にとって益となる。何故なら、そうすれば我々はより上手に何かを行なえるようになったり、よりこの世界の物事を鋭く見れるようになるからである。正しい原理を知って益にならぬことは、確かにない。
【25:31】
『人の子が、その栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴って来るとき、人の子はその栄光の位に着きます。』
今度は、監督者だけでなく全ての聖徒たちについてのことが言われている。これから言われているのは、空中の大審判の出来事についてである。この出来事については、今まで教会において幾度となく語られてきた。もう今や再臨が既に起きていると解明された以上、他の箇所と同様、この大審判についても再解釈が必要である。この出来事に関する記述は25:46の箇所まで続いている。
キリストは再臨されると、『その栄光の位に着』かれた。何故か。それは王として裁きを執行されるためであった。それでは、その裁きが執行されたのはいつか。それは紀元70年9月であった。この箇所で、キリストは時間をほとんど考慮せずにお語りになっておられる。つまり、ここでは再臨の時期に起こる出来事が大雑把に語られている。ここでは大まかに語られているが、実際には次のような順序で事が起きた。①紀元68年6月9日にキリストが再臨される。⇒②聖徒たちによる42か月の支配期間。⇒③紀元70年9月に空中の大審判が実施される。キリストは、ここで、この①と③の出来事を一緒にして語っておられる(②については無視されている)。それだから、この箇所で言われている出来事を、時間の考慮を抜きにして把握すると誤りに陥る。その場合、キリストが再臨されると即座に大審判が行なわれたと理解することになる。しかし、そのように理解するのは間違いである。何故なら、空中の大審判は再臨が起きてから幾年か経過してから実施されたからである。
キリストが再臨された時、そこには栄光が見られた。王が凱旋する際にはそこに栄光があるべきなのと同じように、キリストが再臨された際にもそこに栄光が見られるべきであった。これについては、マタイ24:30の箇所でも書かれている。またキリストが再臨された時には、『すべての御使いたち』も一緒に天から降りて来た。主人が式典に出る際には全ての僕たちが一緒に参加すべきなのと同じで、キリストが再臨された際には全ての御使いたちが一緒に来た。再臨の際に御使いたちがどれだけキリストと共に降りて来るのか教えているのは、聖書の中でこの箇所だけである。他の箇所では、ただ御使いたちがキリストと共に来るとだけしか言われておらず、数については言及されていない。
ここで言われている審判の出来事は、黙示録20:11~15とダニエル7:9~10、またすぐ後ほど見るエゼキエル34:17~24と対応している。
【25:32~33】
『そして、すべての国々の民が、その御前に集められます。彼は、羊飼いが羊と山羊とを分けるように、彼らをより分け、羊を自分の右に、山羊を左に置きます。』
審判の際には『すべての国々の民が』キリストの御前に引き出された。この『すべての国々の民』という言葉を文字通りに捉えるべきではない。これは既に見たように、主の牧場にいる羊と山羊における『すべての国々の民』という意味である。つまり、「地球全土に住んでいる全ての人間」という意味ではない。このマタイ25:31~46の箇所と対応しているエゼキエル34:17~24の箇所を見ると、どうか。そこに出てくるのは羊と山羊だけである。もしこの審判に狼すなわちキリスト教徒ではない不信者たちも引き出されるとすれば、この箇所では第3の存在として狼が出てきたはずである。しかし、この箇所に狼は出ていない。つまり、空中の大審判に狼は出頭させられないのである。また、この審判に出てくるのは『主よ。』とキリストに向かって言う人たちだけである。狼たちは間違ってもキリストにそのような言葉を言わないのだから、この審判に狼が引き出されなかったのは確かである。聖書で『すべて』と書かれていながら、それを文字通りに解釈すべきではない箇所は多い。これについては既に第2部の中で説明しておいた。ここで『すべての国々の民』と言われているのも同様であり、それは文字通りあらゆる人間を意味しているのではない。今に至るまで教会はこの箇所を、ただ感覚的に捉えるだけであった。しかし今やもう再臨と再臨に伴う出来事について正しい理解が開示される時代が到来している。それゆえ、我々はこの箇所を感覚によってではなく、徹底的に聖書に基づいて捉えようとすべきである。そうすれば、我々には再臨に関する真理が恵みにより与えられることであろう。
それでは、どうして羊と山羊とが両側に分けられたのか。それは区別を付けるためであった。男女共学の学校では、全生徒を集める時、男と女をシッカリと分けて並ばせる。何かの授賞式が行なわれる時には、受賞者とそれ以外の一般の参加者は違う席に座らせられる。家の中や工場では、必要な物とゴミが区別して置かれる。審判の際に羊と山羊とが区別して置かれたのは、今述べたのと同じ意味合いを持っている。もし羊と山羊とが一緒にして置かれたのであれば、まったく区別が付かなくなり、カオスな状態が生じてしまうのである。そのような秩序のない状態は、選ばれた者たちと滅びるべき者たちに対する審判が行われる時には相応しくなかった。
【25:34】
『そうして、王は、その右にいる者たちに言います。』
まずは『右にいる者たち』に対して審判者キリストが言葉を語られた。聖書において、良い事柄と悪い事柄が語られる際、先に良いほうから語られている箇所は多い。例えば、先に見たタラントの例えの中では(マタイ25:14~30)、先に幸いな監督者について、次に悪い監督者について語られていた。詩篇1篇でも、先に幸いな者が、次に悪しき者が書かれている。申命記28章の中でも、まず祝福について語られてから次に呪いについて語られている。我々が今見ているマタイ25:31~46の箇所も、そのうちの一つである。すなわち、先に神の子らについて書かれてから、次にサタンの子らについて書かれている。どうして聖書の多くの箇所において良いほうが先に置かれているかと言えば、そうしたほうが自然だからである。良いほうが悪いほうよりも優先されるべきだということは誰の目にも明らかではないだろうか。
『『さあ、わたしの父に祝福された人たち。世の初めから、あなたがたのために備えられた御国を継ぎなさい。』
『羊』である選ばれた聖徒たちは、『祝福された人たち』である。彼らは祝福されているので、主イエス・キリストを信じ、天国に入ることになるのだ。これこそ彼らが祝福されている紛れもない証拠である。というのも、もし祝福されていなかったとすれば、キリストを信じることも、天国に入ることもなかっただろうからである。たといこの地上世界において富み栄えているので神からの祝福を受けているかのように思える人がいたとしても、キリストを信じておらず、天国に入れないようであれば、確かなところ、その人は『祝福された人』ではない。何故なら、その人は祝福されていると多くの人たちから見做される地上での人生を終えた後、永遠の地獄に投げ込まれるからである。地獄で焼き尽くされるのであれば、どうして『祝福された人』なのであろうか。
この選ばれていた聖徒たちは、永遠の昔から天国に入るようにと定められていた。ここで『御国を継ぎなさい。』と言われているのは、つまり「天国に入り、そこで永遠に過ごしなさい。」というほどの意味である。聖徒たちは、そのようにして天国を相続するのである。この御国を相続するという言い方は、パウロもⅠコリント6:9の箇所で使っている。では、聖徒たちが天国に入るのは何が理由だったのか。それは「神の選び」である。すなわち、神に選ばれている者は天国を相続することになるが、選ばれていない者は天国を相続することがない。ただ、これだけである。天国に入るか入らないかは「選び」が全てなのだ。
【25:35~36】
『あなたがたは、わたしが空腹であったとき、わたしに食べる物を与え、わたしが渇いていたとき、わたしに飲ませ、わたしが旅人であったとき、わたしに宿を貸し、わたしが裸のとき、わたしに着る物を与え、わたしが病気をしたとき、わたしを見舞い、わたしが牢にいたとき、わたしをたずねてくれたからです。』』
キリストは、ここで聖徒たちが天国に入れる理由を説明しておられる。その理由とは、聖徒たちがキリストに対して愛の善行をしたからである。すなわち、聖徒たちがキリストに食べさせ、飲ませ、宿を貸し、着させ、見舞いをし、訪問をしたからこそ、聖徒たちは天国に入れる、とキリストは言っておられる。つまり、聖徒たちがキリストに対してこのような善を為さなかったのであれば、聖徒たちが天国を相続することはなかったということである。
言うまでもなく、ここで挙げられている善行の内容は一部分だけが挙げられているに過ぎない。ここに挙げられている善以外でも、当然ながらここで言われている内容に含まれているとすべきである。例えば、キリストが訴えられた時に弁護したり、困っていた時に助けたり、遠くへ行こうとしていた時に馬車を貸したり、などといった善行もここで言われている内容に含まれている。
【25:37】
『すると、その正しい人たちは、答えて言います。』
キリストは、聖徒たちを『正しい人たち』と言っておられる。これは、聖徒たちが自分自身により正しい存在であるということを言っているのではない。聖徒たち自身は罪深い存在である。もっとも敬虔であったと言えるパウロでさえ、自分の罪深さを嘆いているのである。またソロモンの次の言葉は、聖徒たちについて言われた言葉でもある。『この地上には、善を行ない、罪を犯さない正しい人はひとりもいない』(伝道者の書7章20節)。聖徒たちが『正しい人』であるのは、聖徒たち自身によってではなく、神からキリストにある恵みを受けて新しい人にされたからである。だから、聖徒たちが正しいのは聖徒たちにその原因が帰されるべきではない。しかし、それにもかかわらず神は聖徒たちがあたかも自分自身から正しい存在であるかのように見做して下さる。だからこそ、ここでは聖徒たちが自らにより正しい存在でもあるかのように『正しい人たち』と言われているのだ。それだから、聖徒たちは自分が『正しい』ことを決して誇れない。何故なら、もし神が聖徒たちをキリストにより御前に正しい存在にして下さらなかったとすれば、聖徒たちは相も変わらず御前に悪しき存在のままだったからである。
【25:37~39】
『『主よ。いつ、私たちは、あなたが空腹なのを見て、食べる物を差し上げ、渇いておられるのを見て、飲ませてあげましたか。いつ、あなたが旅をしておられるときに、泊まらせてあげ、裸なのを見て、着る物を差し上げましたか。また、いつ、私たちは、あなたのご病気やあなたが牢におられるのを見て、おたずねしましたか。』』
聖徒たちは、キリストの言われたことが、よく理解できなかった。何故なら、聖徒たちはキリストに対して直接的には善行をしていなかったからである。十字架の出来事が起こる前にキリストと共にいてキリストに善を行なう機会があった幾らかの聖徒たちを除けば、誰もキリストに直接的な善を為せなかったのは確かである。それにもかかわらず、ここでキリストは聖徒たちがあたかも直接的に御自身に善を為したかのように言われた。だから、聖徒たちがこの箇所で、このように質問したのは自然なことであったと言える。ここで言われていることもそうだが、キリストの御言葉には、矮小な人間理性によっては捉えることの難しい内容の言説が少なくない。我々が今見ている箇所の他では、例えばヨハネ6章における『生けるパン』についての話がそうである。しかし、キリストの言葉が人間にとって分かりにくかったとしても驚くべきではない。キリストは人であると同時に神でもあられるので、その話されることが人間に過ぎない者たちにとって難しかったとしても不思議ではないのだから。
ここで聖徒たちが、分からないことを質問しているのは何も問題なかった。このように質問をするのは罪ではない。何故なら、分からないことは、どうしても分からないのだから、分からなかったとしても仕方がないからである。神は、聖徒たちが分からないことを知れるよう求めることを望んでおられる。というのも神は聖徒たちが知恵と知識とを持つのを願っておられるからだ。悪いのは、分かっているのに、それを頑なに拒絶することである。我々も、何か分からないことがあれば、もし調べたり考えたりしても分からないのであれば、それがどういうことなのか神に尋ねるべきである。もし真摯な心から我々が求めるのであれば、必ずやそれが分かるようになるであろう。キリストが『求めよ。そうすれば与えられん。』と言われた通りである。
【25:40】
『すると、王は彼らに答えて言います。『まことに、あなたがたに告げます。あなたがたが、これらのわたしの兄弟たち、しかも最も小さい者たちのひとりにしたのは、わたしにしたのです。』』
キリストの聖徒に善を行なうのは、キリスト自身に善を行なうことである。それは何故か。それは、聖徒たちとはキリストの身体だからである。パウロはⅠコリント12:27の箇所で、聖徒たちに次のように言っている。『あなたがたはキリストのからだであって、ひとりひとりは各器官なのです。』キリストは身体における『頭』であり、聖徒たちは身体における肢体である。だから、肢体である聖徒に善を行なうのは、頭であるキリストに善をすることになるのだ。というのは、我々自身のことを考えれば分かるように、肢体の受ける感覚は頭において知覚されるものだからだ。キリストと聖徒が一体だというのであれば、確かに聖徒に為されたことはキリストに為されたことにならざるを得ない。これは、ちょうど妻か子に対して誰かが行なった善を、夫また親である者が自分にされたかのように感じるのとよく似ている。それは、男にとって妻および子とは自分の身体も同然の存在だからである。その男が妻か子に対して行なわれた善を自分に対して行なわれたかのように感じるように、キリストも聖徒たちに対して行なわれた善を御自分に行なわれた善として見做されるのである。
要するに、この審判においては、聖徒たちに善を行なったからというので正しい人たちが天国を相続できると言われているのだ。キリストは御自身の肢体である聖徒たちに良くしてくれた正しい者を、天国に導き入れて下さる。そのような者が救いを受けず天国に入れない、ということは確かにない。キリストが次のように言われた通りである。『わたしの弟子だというので、この小さい者たちのひとりに、水一杯でも飲ませるなら、まことに、あなたがたに告げます。その人は決して報いに漏れることはありません。』(マタイ10章42節)キリストの聖徒たちに善を為す者は、まずキリストを尊重したり信じたりしているからこそ、そのキリストに属する聖徒たちに善を為すのだ。だから、そのような者が救いから除外されるということは有り得ないのである。もしキリストなどどうでもよいと思っていたとすれば、そもそもキリストの聖徒たちによくしてやろうとは全く思わなかっただろうから。サタンに属する滅ぶべき子たちが、どうしてキリストに属する聖徒に良くしてやろうなどと思うのか。これは、ちょうど王が王子に対して良くしてくれた者を、宮殿に招いて一緒に食事をさせるようなものである。王は、ある者が自分の子に対して善を行なった際、それがあたかも自分に対して行なわれたかのように感じるので、その者に報いを与えてやるのだ。そのようにキリストも、御自身の聖徒に良くしてくれた正しい人に、大きな報いをお与えになられるのである。
とはいっても、ここでは聖徒たちに善を行なうので、その行為が人の救いの原因となる、ということが言われているわけではない。そうだとすれば、聖書は行為義認を教えていることになってしまう。しかし、聖書は「人が救われるのは行ないによるのではない。」と教えている。神の子らであるプロテスタント教徒たちはアーメンと言うべきである。ここでは単に「聖徒たちに善を為すような者は天国に入る人たちである」と言われているに過ぎず、救いの手段が教えられているのではない。我々は、この点によく注意すべきである。忌まわしい行為義認の教理は永遠に滅び去れ。
我々は、聖徒たちに善を為す際、本当に注意すべきである。我々が聖徒たちに為す善は、キリストに対する善でもあるのだ。我々は日頃からこのことについて気付いているであろうか。実際に聖徒に善を行なう際、このことを明確に意識しているであろうか。恐らく多くの聖徒たちは、このことをそれほど意識していないと思われる。我々は、聖徒たちに善を為す際、どれだけ心から為さねばならないであろうか。その善の対象は、その聖徒たちだけでなくその聖徒の主であるキリストも含まれているのである。よって、聖徒に善を行なう場合、どれだけ注意したとしても注意し過ぎることにはならない。既に聖徒たちに心から善を行なっている人は幸いである。何故なら、その人はキリストに対して心から善を行なっているからだ。だが聖徒たちに心からは善を行なえていない人は震えるべきである。何故なら、その人はキリストに対して中途半端な心により善を行なっているからだ。
【25:41】
『それから、王はまた、その左にいる者たちに言います。』
今度は、『左にいる』悪しき毒麦どもにキリストが語りかけておられる。彼らは滅ぶべき害虫であった。それゆえ、彼らは正しい者たちよりも後に置かれた。もし悪しき者のほうが正しい者よりも先に置かれたとすれば、それは自然に適っていないのである。そのようにするのは、例えるならば綺麗な貴重品よりも汚らわしい粗大ゴミのほうを重要視するようなものである。こんな趣味の悪い下劣なことが他にあるであろうか。
『『のろわれた者ども。わたしから離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火にはいれ。』
山羊であり毒麦である悪者どもは、呪われていた。つまり神の祝福を受けてはいなかった。だからこそ、彼らは祝福された者とは違って、左のほうに置かれたのである。彼らが呪われていたのは、神が永遠の昔から彼らが呪われるようになるのを欲しておられたからである。だから、彼らは自分たちが呪いに定められていたからといって文句を言うことはできない。それゆえ、もし彼らが『だれが神のご計画に逆らうことができましょう。』(ローマ9章19節)などと自分が呪われていることについて公然と文句を言うのであれば、次のように言われて断罪されてしまうであろう。『人よ。神に言い逆らうあなたは、いったい何ですか。形造られた者が形造った者に対して、「あなたはなぜ、私をこのようなものにしたのですか。」と言えるでしょうか。陶器を作る者は、同じ土のかたまりから、尊いことに用いる器でも、また、つまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないのでしょうか。』(ローマ9章20~21節)要するに、呪われた者たちが自分の呪いについて抗議するのは、神の主権を侵害することであり、永遠の定めを愚かにも冒涜することなのである。
左に置かれた山羊たちは呪われた存在だったので、恐るべき地獄に投げ込まれることになった。この地獄が、ここでは『永遠の火』と言われている。また、これは他の箇所で『ゲヘナ』(マタイ23章33節)とも言われている。悪者たちが神の怒りを火において受ける阿鼻叫喚の場所が、ここである。ごく一部のキリスト教徒は、この地獄が存在しないなどという考えを持っているが、そのような考えは受け入れられない。この箇所でキリストが言っておられるのは、つまり悪者たちが悪魔のように働きを停止させられ、悪魔の子どもとして地獄で焼き尽くされる、ということである。サタンが火の池に投げ込まれるという表現は、聖書の意味では、サタンが封じられる、その働きや支配が停止させられる、ということである。これについては、既に黙示録20章の註解で説明しておいた通りである。少し考えればすぐに分かるが、実際の身体を持たないサタンが実際の火に投げ込まれると言われているのは、明らかに文字通りに捉えるべきことではなく、霊的に捉えるべきことである。この表現について忘れてしまった人は、第3部の当該箇所に戻って再び学び直していただきたい。『悪魔の使いたち』とは、もちろん左に置かれた山羊を指している。この箇所は黙示録20:15と対応しているから、この山羊たちが地獄に投げ込まれる時には、既にネロとティゲリヌスが地獄に先駆けて投げ込まれていたことが分かる(黙示録19:19~20)。また、ここで『わたしから離れて』とキリストが言われたのは、明らかに詩篇6:8、119:115に基づいている。そこでも、忌まわしい不法者どもが離れていくようにと言われているからだ。すなわち、その詩篇の箇所ではこう言われている。『不法を行なう者ども。みな私から離れて行け。』(6:8)『悪を行なう者どもよ。私から離れて行け。』(119:115)キリストは汚れと罪を受け入れられない御方だから、左に置かれた汚らわしい悪者どもは、容赦なくキリストの御前から退けられるのである。
【25:42~43】
『おまえたちは、わたしが空腹であったとき、食べる物をくれず、渇いていたときにも飲ませず、わたしが旅人であったときにも泊まらせず、裸であったときにも着る物をくれず、病気のときや牢にいたときにもたずねてくれなかった。』』
ここでキリストは毒麦どもが地獄に投げ込まれる理由について語っておられる。彼らが地獄に投げ込まれるのは、キリストに対して善を行なわなかったからである。彼らはキリストに良くしなかった。だから、キリストも彼らに良くして下さらないのだ。キリストは人の行ないに報いられる方なのである。もし彼らがキリストに善をしていたとすれば、決して地獄に投げ込まれることにはならなかったであろう。彼らが地獄に投げ込まれる理由は、先に見た正しい人たちが天国に入れる理由とはまったく正反対である。
この箇所で言われている善の内容は、先に見た正しい人たちに対して言われた善の内容と一緒である。ここでも、やはり一例だけが列挙されている。つまり、ここで挙げられている非善行為以外にも、毒麦たちが地獄に投げ込まれる原因となった非善行為は無数に存在している。つまり、ここでキリストが言われたのは要約すれば「私に対して良くしてくれなかった」ということに他ならない。ここではその例として6つの非善が挙げられているというわけである。それゆえ、この箇所について、我々はあまり文字に拘泥し過ぎないように注意せねばならない。
【25:44】
『そのとき、彼らも答えて言います。『主よ。いつ、私たちは、あなたが空腹であり、渇き、旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見て、お世話をしなかったのでしょうか。』』
この山羊たちも、キリストが何を言っておられるのか、よく理解できなかった。というのも、彼らの大部分は、そもそもキリストに直接的な善を行なう機会が無かっただろうからである。キリストが十字架に架かられる前にキリストと共にいた者であれば別だが、そのような者はこの審判に引き出された者の中であまりいなかったと思われる。それだから、この偽善者たちが、ここでこのような質問をしたのは自然なことであった。
注意すべきなのは、ここで山羊たちがキリストに向かって『主よ。』と言っていることである。これから2つのことが分かる。まず第一に、空中の大審判に引き出された悪者たちは『主よ。』と言う悪者だったということである。つまり、山羊また毒麦である偽クリスチャンだけが審判の場に引き出された。そもそも教会とは無関係に生きている悪者たちは『主よ。』とは言わないから、空中の大審判には引き出されなかった。彼らがキリストに『主よ。』と言わないのは、キリストが自分の主だなどとは思っていないからである。つまり、あらゆる悪者がこの審判の場に集められたと考えるのは間違っている。既に説明されたように、そこに集められる悪者は、主の牧場の中に羊と共にいる山羊だけなのである。第二は、偽クリスチャンも『主よ。』と口にするということである。マタイ8:22の箇所でも、本当は神の子でない偽物のクリスチャンたちがキリストに対して『主よ。主よ。』と言っている。つまり、たとえ『主よ。』と言っているからといって、必ずしもその者が神の子であるとは限らない。『木はどれでも、その実によってわかる』(ルカ6章44節)とキリストが言われたように、このような偽善者は、その行ないにより真の姿を見極めることが可能である。そのような者たちは口先では『主よ。』と言っているのだが、しかし行ないの内容においてはイエスが主であることを否定しているのだ。我々が今見ている箇所に出てくる偽善者たちも、やはり行ないにおいてはイエスを主としていなかった。何故なら、すぐ前の25:42~43の箇所で言われていた通り、彼らはキリストに対して良いことをしていなかったからである。それゆえ我々は注意すべきである。人は誰でも口先では何とでも言えるのだ。サタンでさえ光の御使いに変装して『主よ。』などと平気で言うであろう。重要なのは、どうにでも欺ける口ではなく、その行ないなのである。
【25:45】
『すると、王は彼らに答えて言います。『まことに、おまえたちに告げます。おまえたちが、この最も小さい者たちのひとりにしなかったのは、わたしにしなかったのです。』』
彼らが聖徒たちに善を行なわなかったのは、キリストに善を行なわなかったことであると、ここでキリストは言っておられる。これは先に正しい人たちに対して言われていたのと同じことである。すなわち、聖徒という身体の肢体に良くしなかったというのであれば、それはキリストという身体の顔に良くしなかったも同然である。我々自身の身体を考えても分かるが、肢体と顔は切っても切り離すことができない。それはセットだからである。肢体は顔なくして存在できず、顔は肢体を動かす基礎装置のようなものであり、この2つは繋がっているのだ。聖徒とキリストの関係も、正にこれと同じである。
毒麦たちは聖徒たちにおいてキリストに良くしなかったので地獄に投げ込まれることになった。つまり、彼らは聖徒とキリストに対する愛を持っていなかった。愛を持っていないからこそ、良くしなかったのである。もし彼らが聖徒とキリストに愛を持っていたとすれば、善をしていたことであろう。彼らは聖徒とキリストに対する愛を持っていないのだから、地獄に投げ込まれて当然である。何故なら、それはすなわち聖徒とキリストを憎んでいるということだから。聖徒とキリストを憎んでいる者が、どうして天国に入れるのだろうか。
我々は注意せねばならない。聖徒たちに善をしないような者は、キリストの御前から退けられて、地獄に投げ落とされてしまうのだ。これは単なる脅しではない。これは脅しであると同時に真実なことでもある。ヨハネも聖徒たちを愛さず善をしないような者に永遠の命はない、と断言している。すなわち、Ⅰヨハネ3:15、17の箇所では次のように書かれている。『兄弟を憎む者はみな、人殺しです。いうまでもなく、だれでも人を殺す者のうちに、永遠のいのちがとどまっていることはないのです。』『世の富を持ちながら、兄弟が困っているのを見ても、あわれみの心を閉ざような者に、どうして神の愛がとどまっているでしょう。』それだから「聖徒たちに善をしないということのために地獄に落とされるというのは厳しすぎるのではないか。」などと言うことはできない。何故なら、聖書がキリストの左に立たされるような愛なき者に天国の恵みは与えられない、と教えているからである。聖書の教えに異を唱えるとは一体どういうことであるか。神の聖なる教えに文句を付けるような恥知らずの犬は立ち去れ。我々は細心の注意を払い、聖徒たちに善を行なわないようなことがないようにせねばならない。それは我々がここで言われているような左に立たされた山羊のごとき者にはならないためである。救われた者は右に立たされた羊の仲間である者たちなのだから、そのような者として相応しく、聖徒たちに善を行なうべきである。
【25:46】
『こうして、この人たちは永遠の刑罰にはいり、正しい人たちは永遠のいのちにはいるのです。」』
左に置かれた山羊である偽善者たちは、地獄に投げ込まれ、『永遠の刑罰』を受けることになった。黙示録20:15の箇所では次のように書かれている。『いのちの書に名のしるされていな者はみな、この火の池に投げ込まれた。』彼らは主に従おうとしない新しくされていない人たちだったから、大いなる御怒りを受けるのだ。それは、ヨハネ3:36の箇所で『御子に聞き従わない者は、いのちを見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。』と書かれている通りである。一方、右に置かれた羊である選ばれた者たちは、天国に導き入れられ、『永遠のいのち』に与ることになった。彼らはそうなるようにと、永遠の昔から定められていた。キリストにある神の憐みと恵みとが、彼らを天国の至福へと招いて下さったのである。
この出来事が未だに起きていないと考えている人たちは多い。だが、そのように考えるのは間違っている。というのも、このマタイ25:31~46の箇所は、黙示録20:11~15の箇所と対応しているからである。その黙示録の箇所は、既に第3部の中で見たように『すぐに起こる』事柄が書かれている。であれば、その黙示録20:11~15の箇所と対応しているマタイ25:31~46の箇所も『すぐに起こる』事柄が書かれていることになる。だから、私が述べたように、この審判の出来事は既に紀元1世紀において起きたと考えなければならない。そう考えないと『すぐに起こる』ということにはならなくなってしまうからである。
それでは、これ以降の時代に生まれてくる人たちは、死んだら一体どうなるのか。これは簡単である。すなわち、この審判の出来事が起きて以降、正しい人たちは死んだら即座に天国に入れられ、悪い人たちは死んだら即座に火の池に投げ込まれる。ただ、これだけである。もはや再臨が起きて、そうしてから大審判が実施され、それから人々が一斉に天国か地獄に移される、ということは起こらない。何故なら、それは紀元1世紀に起きたことだから。もう既に再臨と大審判は起きたのだから、聖徒たちは私が今述べたように考えなければならない。
【26:64】
『イエスは彼に言われた。「あなたの言うとおりです。なお、あなたがたに言っておきますが、今からのち、人の子が、力ある方の右の座に着き、天の雲に乗って来るのを、あなたがたは見ることになります。」』
ここでキリストが言われた通り、キリストの前にいた紀元1世紀の者たちは、キリストの再臨をその目で見た。この箇所でキリストが語られたのは、紀元33年頃である。仮に、キリストの前にいた者たちの平均年齢を50歳とする。というのも、キリストの前にいた者たちは、大祭司や律法学者や長老たちだったのだから(マタイ26:57)、高齢の者が多くいたと推測されるからである。再臨はこの箇所における出来事が起きてから35年後の紀元68年に起きたのだから、再臨が起きた時、キリストの前にいた者たちの平均年齢は85歳になっている。その平均年齢が85歳であれば、その中の幾らかの者が、再臨の時まで死なずに生き残っていたはずである。もちろん、大部分の者は、病気や事故や寿命により死んでいたはずである。しかし、紀元68年になるまでの間に、キリストの前にいた全ての者が死んでしまったということは考えられない。そこには老人だけではなく、まだ壮年の者や、20代・30代の若造もいたに違いないからである。その者たちが、紀元68年に『天の雲に乗って来』られたキリストを見たことは疑い得ない。であるから、ここでキリストは真実なことを言われたことになる。今まで教会がそう考えてきたように、すぐにはキリストの再臨が起こらなかったとすれば、キリストはここでこのように言っておられなかったはずである。というのも、2千年経過しても起こらないような遥か未来の出来事を、どうして当時の人たちが生きている間に見るかのように言うということがあるであろうか。キリストの前にいた人たちが、2千年以上経過しても起きないような出来事を『見ることにな』れないのは確かである。誰がこれを疑うであろうか。言うまでもなく、キリストがこう言われたのは、本当に当時の人たちが再臨をその目で見ることになるからであった。
それでは、およそ35年後に再臨されたキリストを見た議会にいた人たちは、どのようになったのか。これには2種類の人たちがいる。1種類目は、再臨が起こるまでの間にキリストを受け入れた人たちである。彼らは再臨が起きた際、生きたままで復活し、再臨されたキリストのおられる空中の場所へと携挙されることになった(Ⅰテサロニケ4:16~17)。2種類目は、再臨が起こるまでの間にキリストを受け入れないままでいた人たちである。彼らは再臨が起きた際に嘆き悲しみ(マタイ24:30)、携挙されることもなく地上に残され(マタイ24:40~41)、その時にエルサレムにいたのであればローマ軍の襲来によって殺されてしまった。前者は幸いな者であり、後者は不幸な者である。キリストの前にいた議会の者たちは、本当に紀元68年にキリストが言われた通りに再臨が起きたのを見て、大いに驚いたはずである。というのも、その時に彼らは『嘆く』(黙示録1章7節)ことになったからである。しかし、再臨のキリストを見て大いに驚いても、時は既に遅かった。何故なら、その時には、もはや悔い改める余地が残されていなかったからである。それは、ちょうど涙を流すほどに後悔したにもかかわらず、結局は悔い改めることの出来なかったエサウの場合と同じである(ヘブル12:17)。もし再臨のキリストを見た時に悔い改めることが出来ていたとすれば、とうの昔に悔い改めてキリストを受け入れていたことであろう。
ここでキリストが『天の雲に乗って来る』と言われているのは、実際的な意味と象徴的な意味という2つの意味がある。これについては既に第2部の中で論じられている。キリストが『力ある方の右の座に着』かれたというのは、紀元33年頃の昇天のことである。これについてはマルコ16:19やその他の箇所でも明白に語られている。
【28:19】
『それゆえ、あなたがたは行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。』
また後にも見ることになるが、既に、この宣教命令は成就されている。何故なら、聖書がそう教えているからだ。聖書がそう教えているにもかかわらず、「否!」と言うことはできない。聖徒とは、聖書の教えに立つべき者たちなのだから。しかし私がどれだけ聖書から言おうとも、世俗化している時代における今の聖徒たちは、なかなか既に宣教命令が成就しているという聖書の教えを受け入れないであろう。私はそのような聖徒たちに言いたい。自分の感覚を捨てよ。そうすれば聖書の教えに堅く立てるようになるであろう。
しかしながら、この宣教命令が既に成就されたからといって、もはや聖徒たちはあらゆる国の人々を弟子としていかなくてもよくなった、ということには全然ならない。むしろ、我々は、今でもあらゆる国の人々を弟子としていかねばならない。というのは、この宣教命令が成就されてからも聖徒たちが変わらずにこの宣教命令の通りに伝道をしていくというのが、主の御心だからである。誰がこれを疑うであろうか。ただ、再臨後の時代に生きる我々は、この宣教命令が未だに成就されていないかのように宣教をしてはならない。つまり、この宣教命令が未だに成就されていないので速やかに成就させなければならない、という姿勢で伝道をすべきではない。何故なら、この宣教命令は再臨前の聖徒たちにより既に成就されているからだ。そのような姿勢で伝道すべきなのは当時の聖徒たちだけであって、我々はこの宣教命令が既に成就された命令だという前提でもってこの宣教命令を実行していかねばならないのだ。
【28:20】
『見よ。わたしは、世の終わりまで、いつも、あなたがたとともにいます。』
この聖句は、これまで多くの教師たちに何度も引用されてきた。例えば、アウグスティヌスがそうである。彼は、特に講解説教などで、この聖句を幾度となく引用している。
ここで言われているのは、キリストがユダヤ世界の終焉まで聖徒たちと共におられる、ということである。この『世の終わり』という言葉を、文字通りの意味において捉えてはならない。聖書を調べた者にとっては、この言葉が紀元70年におけるユダヤの終わりを意味しているということは明らかである。だからこそ、使徒たちは紀元1世紀の時代に「世の終わりは近い。」などと言ったのである。実際、キリストはユダヤの終わる時まで、聖徒たちと共におられた。マルコは、当時の聖徒たちには『みことばに伴うしるし』(マルコ16章20節)が見られたと書いている。つまり、キリストが共におられたからこそ、彼らを通して奇跡という徴が御言葉に伴っていたのだ。もしキリストが彼らと共におられなかったとすれば、このような奇跡は御言葉に伴っていなかったであろう。
ところで、ここでキリストが『あなたがたとともいいます。』と言われたのは、あくまでも臨在においてである。すなわち、ここでキリストが言っておられるのは、肉体において聖徒たちと共にいるということではなかった。これは明白なことである。何故なら、キリストはこう言われた後、すぐにも昇天されたからである。キリストが肉体において天に上げられたのであれば、どうしてキリストが聖徒たちと肉体において共にいることが出来るのであろうか。「いや、そうはいっても確かにキリストは肉体において聖徒たちと共におられたのだ。」などと言うことはできない。というのも、キリスト御自身が、昇天により御自身は聖徒たちから離れるであろう、と言われたからだ(ヨハネ16:7)。これは、つまりキリストが肉体としては聖徒たちと一緒にいなくなるということでなくて何であろうか。パウロも、今はまだ自分がキリストと共にいない、と言っている(Ⅱコリント5:6)。もしキリストが肉体において共にいて下さったのであれば、パウロはこのように言っていなかったであろう。しかし、主が肉体においては共におられなかったとしても、聖徒たちと共におられないということにはならない。何故なら、霊的な臨在であっても、神が我々と共におられることになるからである。肉体において共におられなければキリストが聖徒たちと共におられることにはならない、という考えは聖徒たちに相応しくない。まともな聖徒のうち、誰がこのような考えを持つであろうか。
キリストがこのように言われたのは、聖徒たちを励まし力強くするためであった。何故なら、このように全能者から言われたら、聖徒たちが力を受けるのは明らかだからである。このように聞かされて力を増し加えない聖徒は恐らく一人もおるまい。キリストは、御自身こそ諸力の源であられるということを知っておられた。だからこそ、このように言うことで、聖徒たちが心を強められるようにされたのだ。なお、旧約聖書においても、神はこのようなことを言って聖徒たちを強めておられる。例えば、昔において神は次のように聖徒たちに言われた。『強くあれ。雄々しくあれ。恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神、主が、あなたの行く所どこにでも、あなたとともにあるからである。』(ヨシュア1章9節)『勇士よ。主があなたといっしょにおられる。』(士師記6章12節)『恐れるな。わたしはあなたとともにいる。たじろぐな。わたしがあなたの神だから。』(イザヤ41章10節)これは例えるならば、親が子どもに「お父さんが一緒にいるんだから安心しなさい。」などと言うようなものである。このように言われた小さな子どもは、このように言われて安心できるようになるのだ。
それでは、ユダヤ世界が紀元70年に終わってからは、もうキリストは聖徒たちと共におられないのであろうか。決してそのようなことはない。紀元70年以降も、キリストが聖徒たちと共におられるのは明らかである。アウグスティヌスを考えると、どうであろうか。彼には、キリストが共におられた。だからアウグスティヌスは守られ、残虐なドナティストどもの剣から免れることができた。ルターを考えると、どうであろうか。彼にもキリストが共におられた。だから彼は気の狂ったカトリックの連中から完全に守られていた。21世紀の今に生きる聖徒たちにも、主が共にいて下さる。誰がこのことを疑うであろうか。もし紀元70年以降には聖徒たちと共に主がおられないというのであれば、聖徒たちは絶望するしかなかったであろう。もっとも、再臨前の聖徒たちは共におられるキリストにおいて多くの奇跡を行なえたのに対し、再臨後の聖徒たちは、主が共にいては下さるものの、、そのほとんどが奇跡を行なえなくなっているという相違点がある。再臨後の時代にも奇跡を行なえるのは、日本人伝道師の森など少数の者しか見られない。しかし、それにもかかわらず、主は聖徒たちと共にいて下さる。ノアやアブラハムやヨブやバプテスマのヨハネを考えてみてほしい。彼らは奇跡を何も行わなかったが、それでも主が彼らと共におられたのは明らかである。彼らと共に主がおられたことを疑う人はいないはずだ。つまり、たとえ奇跡を行なわないからといって主が共におられないということにはならないのである。主は、その人が奇跡を行なおうが行なわなかろうが、共にいて下さる人には共にいて下さる。
第43章 41:マルコの福音書
【9:1】
『まことに、あなたがたに告げます。ここに立っている人々の中には、神の国が力をもって到来しているのを見るまでは、決して死を味わわない者がいます。』
この箇所で言われている内容は、先に見たマタイ16:28の箇所と同じである。ただマタイの箇所と異なるのは、マルコのほうではキリストの再臨について明確な言及がされていないという点である。すなわち、マルコは御国の到来についてしか書き記していない。これは何故なのか。私はこう考える。まずペテロを通してマルコが福音書を記した際、ペテロはマルコ9:1の箇所においてキリストの再臨についてマルコに聞かせるのを忘れてしまっていた。そうして後、マタイがマルコの福音書を読んで自分も福音書を書こうとしたのだが、マタイはマルコが9:1の箇所で再臨について書き記していないことに気付き、自分の書いた福音書のほうではシッカリと再臨についての文章を書き記した。マタイは、マタイ16:28の箇所で書かれている出来事が起きた際、キリストの目の前に立っていたのだから、キリストが人々に何を言われたのか記憶していたはずである。それだから、マルコ9:1の箇所で再臨について言及されていないことに気付けたわけである。ペテロは熱心ではあったがミスの多い人だったから、マルコにキリストについての話を聞かせる際、つい語り忘れてしまったということは十分にあり得る。もちろん、ペテロがマルコに話を聞かせていた時、ペテロには聖霊が完全に働いておられたから、マルコに対して語り忘れた(または敢えて語らなかった)ことはあっても、間違ったことは一つも語らなかったというのは確かである。誰がこのことについて疑うであろうか。また、マルコの箇所では『力をもって』御国が到来すると書かれている。マタイのほうでは、この言葉は書かれておらず、単に御国が到来するとしか書かれていない。後ほど見るルカ9:37の箇所でも、神の国について『力をもって』などとは書かれていない。どうしてマルコの箇所だけ御国の到来について『力をもって』と書かれているのかは分からない。しかし、マルコは何か間違ったことを書いたのではない。確かに、マルコが記したように神の国は『力をもって』到来したのだ。つまり、御国が到来したのは「弱弱しく」または「隠れてコソコソと」ではなかった。すなわち、御国は再臨をその目で見ていた人たちの全てが明らかに確認できるようにして、キリストの再臨と共に到来した。当時の人たちは、キリストが無数の聖徒たちと御使いとを引き連れてエルサレムの上空に天から降りて来られたのを見た。そのような光景を見たら、誰でも遂に御国が到来したことを感じずにはいられなかったはずである。だから、確かに御国の到来とは女々しい仕方ではなく非常に力のある仕方で実現されたのであった。
【16:19】
『主イエスは、彼らにこう話されて後、天に上げられて神の右の座に着かれた。』
昇天の出来事は再臨と結びついた出来事なので、再臨を考究する目的を持つ本書においては、決して無視できない出来事である。とはいっても、この出来事は、再臨とは異なり、それほど難しい神学的な考察をする必要はない。何故なら、昇天のほうは、従来の見解を何も変える必要がないからである。既に書かれた内容から分かると思うが、本書における昇天の見解は、今までの教会が持っていた見解と同じである。
【16:20/別の追加文】
『そこで、彼らは出て行って、至る所で福音を宣べ伝えた。主は彼らとともに働き、みことばに伴うしるしをもって、みことばを確かなものとされた。<さて、女たちは、命じられたすべてのことを、ペテロとその仲間の人々にさっそく知らせた。その後、イエスご自身、彼らによって、きよく、朽ちることのない、永遠の救いのおとずれを、東の果てから、西の果てまで送り届けられた。>』
この箇所で言われているように、福音は紀元1世紀において、既に『東の果てから、西の果てまで送り届けられ』ていた。この理解は非常に重要である。何故なら、この理解は再臨の理解に大きな影響をもたらすからである。福音が当時において既に世界中に満ち広がっていたというのは、パウロも述べていることである。
福音が当時において世界中に満ち広がっていたからこそ、当時において再臨が起きた。というのも、福音宣教の成就と再臨の実現は、密接に結びついているからである。すなわち、福音宣教が成就されると再臨が実現する。また再臨が実現したということは、つまりその時には既に福音宣教が成就されているということである。これらについては、また後ほど詳しく語られる。
この福音は、『きよく、朽ちることのない、永遠の救いのおとずれ』であった。まず福音は『きよ』かった。キリストは、弟子たちに『あなたがたは、わたしがあなたがたに話したことばによって、もうきよいのです。』(ヨハネ15章3節)と言われた。人がキリストの言葉によって清められるのであれば、そのキリストの救いを告げた福音の言葉が清いのは明らかである。また、福音は『朽ちることのない』ものであった。イザヤ40:8の箇所で言われているように、『神のことばは永遠に立つ』。福音の言葉とは、すなわち『神のことば』に他ならない。それゆえ、福音とは永遠であるゆえ決して『朽ちることのない』ものである。そして、福音とは『永遠の救いのおとずれ』であった。キリストは十字架において『永遠の贖いを成し遂げられた』(ヘブル9章12節)のであり、その救いの効力は永遠に続く。もし救いの効力が消失することがあるとすれば、それは『永遠の救い』とは
言えないからである。だからこそ、ここでは福音が『永遠の救いのおとずれ』と言われているのだ。
福音が世界中で宣教された際には、『みことばに伴うしるし』があった。それは一体どういう『しるし』だったのか。それは奇跡という徴であった。では、どうしてそのような徴が当時は御言葉に伴っていたのか。それは、主が『みことばを確かなものとされ』るためであった。つまり、当時の人々が福音の言葉を信じるようになるために、『証拠としての奇跡』(ヨハネ2章11節)として御言葉に徴が伴っていた。既に第1部でも述べたが、御言葉に奇跡という徴が伴っていれば、それだけ人々が救いを受け入れやすくなるのは明らかである。無神論的な時代の精神が世界中に蔓延している今の時代でさえ、福音に奇跡が伴っていたら多くの人たちがクリスチャンになると思われる。であれば、まだ無神論者などほとんどいなかった紀元1世紀の人たちは、奇跡という徴と共に宣教された福音を聞いた際、どれだけ容易に救いへ導かれていたことであろうか。すぐにも多くの人たちがキリスト者になっただろうことは間違いないと私には感じられる。神は、キリスト教の始めにおいて、福音がビッグバンのように爆発的な広がりを持つようになるのを望まれた。何故なら、最初の時点で力ある伝播がなされていなければ、最初から勢いがないのだから、後が続かないからである。インフレーション理論でも、宇宙は最初においては物凄い急激な拡張をしたとされるが、それと同じことである。それだからこそ、神は、当時においては、福音が急激に満ち広がって実を結ぶようにと福音に徴を伴わせておられたのである。では、その奇跡とは具体的にはどういったものだったのか。それは、例えば足に障害を持った者が癒されたり(使徒行伝3:1~4:22)、邪悪な者が盲目にされたりする(使徒行伝13:8~12)、というのがそうであった。ルカが記しているように、このような奇跡を見て、多くの人たちは福音を受け入れたのである。このような御言葉に伴う奇跡は、アウグスティヌスの時代まで続いていた。しかし、ローマにキリスト教が完全に浸透すると、このような徴は、まったくといっていいほど見られなくなった。これは、神がキリスト教を世界に一般化させるまでは、御言葉に徴という補助手段を備えておられたということを意味する。アウグスティヌスの頃になるまでは、福音は多くの抵抗を受ける運命にあったので、その抵抗を潜り抜けて世界に浸透するためにはどうしても徴という補助手段が必要だったのである。キリスト教が普遍的になると、もう補助手段は無くてもよくなったので、御言葉に徴が伴うことは稀になったのだ。これは、ちょうど子どもが自転車を普通に乗れるようになるまでは倒れないように補助輪を両側に付けて走るようなものである。もう立派に自転車に乗れるようになれば、そのような補助輪はもう必要なくなるのだ。
ところで、神が御自身では直接的に福音を全世界に満ち広げられなかったのは何故なのか。すなわち、どうして神は、御自身の聖徒たちを通して福音を全世界に広げられたのか。確かなところ、神は、御自身により直接、福音を世界に伝播させることがお出来になった。例えば、天から御声を発せられ、諸国の人々に福音を聞かせるということが神には出来た。不可能のない神にとって(ルカ1:37)、そのようなことは朝飯前である。しかし、神は、そうされず、むしろ聖徒たちに福音を宣べ伝えさせるという手法を選ばれた。この手法をこそ神が選ばれた理由は何だったのか。これは、幼稚園を考えてみれば分かる。幼稚園において、トップの座にいる園長が、自分の目の前で直接園児たちを教育しないのは何故か。園長が事務や管理の仕事に取り組み、実際の教育は資格を持った多くの職員たちに分担して任せるのは何故か。私がまだ園児の時には、多くの「先生たち」が分担して園児たちを教育し、園長先生はなかなか見かけなかったものである。これは、こうしたほうが都合がよいからである。園児にしても、高齢で威厳があるものの少し近寄りがたい園長に教育してもらうよりは、まだ若い20代、30代の先生たちに相手をしてもらったほうが良いに決まっている。福音宣教でも同じである。その御声を直接聞いたならば震え上がらざるを得ない神が御自身お一人により福音を説き聞かせるよりは(出エジプト記20:19、申命記5:22~27)、人間を通して福音が語られるほうが、人間にとっては良いことなのである。もしそうでなければ、神は御自身により福音を説き聞かせておられたことであろう。しかし、神はそうされなかった。つまり、人間が人間に福音を語ったほうが良いのである。もし神が直接我々に福音を語っておられたとすれば、我々は、あの時のイスラエル人のように次のように言っていたであろう。『神が私たちにお話にならないように。私たちが死ぬといけませんから。』(出エジプト記20章19節)―神の御声はこのように言わねばならないほどに恐るべきものなのだ。もし神が我々にお語りになっていたとすれば、我々は福音を受け入れるどころではなかったはずである。というのも、神の恐るべき御声に精神が圧倒され委縮してしまうので、精神の能力が正常に機能せず、福音の内容を知解するどころではなかっただろうから。要するに、神は人間のためを思って、人間を通して福音を告知するようにして下さった。これは神の愛の配慮であった。すなわち神は、人間に相応しいやり方を取られたのである。だからこそ、我々は福音を人間を通して親しく聞き知ることが出来る。我々は、人間にこのようにして下さった神に感謝すべきであろう。
第44章 42:ルカの福音書
【9:37】
『しかし、わたしは真実をあなたがたに告げます。ここに立っている人々の中には、神の国を見るまでは、決して死を味わわない者たちがいます。』
この箇所で言われている内容は、マタイ16:28の箇所と同じである。マタイの箇所と違うのは、ルカのほうではキリストの再臨について明確に言及されてはいない、ということである。すなわち、ルカのほうでは、ただ御国の到来についてしか言われていない。これは先に見たマルコ9:1の箇所でも同じであった。
【13:18】
『そこで、イエスはこう言われた。「神の国は、何に似ているでしょう。何に比べたらよいでしょう。』
キリストは、ここで『神の国』について語っておられる。これは人が救われた時に入れられる神の支配を言っている。すなわち、これは神と御使いたちの住まう天国という『神の国』のことではない。もちろん、天国も『神の国』として語られ得るが、少なくともこの箇所ではそのような意味としては語られていない。これを天国として捉えると、13:18~30の箇所が上手に理解できなくなる。注意せねばならない。
キリストは、この『神の国』を例えにより説明しようとされた。これには2つの理由があった。一つ目は、御自身が預言されていたメシアであることを証明するためである。何故なら、旧約聖書ではメシアが例えによって何かを語ると預言されていたから。二つ目は、分かりやすく理解できるようになるためである。別の事柄において説明をすれば理解しやすくなるということは、誰でも分かるであろう。主は、ここ以外の多くの箇所でも、この2つの理由から例えにより何かの事柄を説明しておられる。
【13:19】
『それは、からし種のようなものです。それを取って庭に蒔いたところ、生長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。」』
キリストは、御国を『からし種』に例えておられる。からし種が大きくなるように神の国も大きくなると。<あんなにも小さかった種が大きな木になるのだ>とでも主は言っておられるかのようである。なお、これは人の内面における神の国の拡大という意味で捉えるべきではない。すなわち、人のうちに神の支配が満ち広がっていくという意味で捉えるべきではない。確かに、神の国は信仰者のうちにおいて増大されていく。パウロが聖徒たちは『栄光から栄光へと、主と同じかたちに姿を変えられて行』(Ⅱコリント3章18節)くと言った通りである。だが、ここでは人の内面における神の支配の増長について言われているのではない。ここでは、『庭』すなわちこの地上世界に御国が大きくなることについて言われている。すなわち、神の国がより多くの人たちに満ち広がっていくということが言われている。もっと厳密に言えば、ここでは新約時代になって全ての異邦人に神の国が押し広げられるようになる、ということが言われている。というのも、後に続く箇所を見れば分かる通り、ここでは異邦人の召しにより御国が世界中に拡がることについて教えられているからだ。これについては、ダニエル書2:34~35の箇所でも示されている。実際、ここでキリストが言われたことは既に実現している。それは今の世界を見てみれば明らかである。かつて神の国はユダヤにだけ限定されていたのに、今や全世界の民族に広まっている。
ここで言われている『空の鳥』をサタンとして解せるだろうか。これをサタンとして捉える人も中にはいるかもしれない。だが私としては、これをサタンとして解するのは、やや強引であるように思える。何故なら、ここでキリストは単に御国が大きくなるというだけのことを言っているからだ。この『空の鳥』が枝に巣を作ったというのは、御国が大きくなることを示す装飾としての説明に過ぎないと捉えるのがよいと私は考える。
【13:20~21】
『またこう言われた。「神の国を何に比べましょう。パン種のようなものです。女がパン種を取って、3サトンの粉に混ぜたところ、全体がふくれました。」』
キリストは再び神の国を例えにおいて説明しておられる。このように繰り返すのは、神の国が非常に重要な事柄であり、またその事柄をよく分からせるためであった。もし神の国があまり重要でなかったとすれば、このように繰り返されはしなかったと思われる。
神の国は『パン種のようなもの』でもある。パン種が拡がるように、御国も拡がるのだ。実際、旧約時代には御国がパン種のように小さかったが、新約時代になった今や全世界へと膨らんでいるのを我々は見ている。パン種はその性質上、膨らまざるを得ない。それと同様、御国というパン種もその性質上、膨らまざるを得なかったのである。
【13:22~23】
『イエスは、町々村々を次々に教えながら通り、エルサレムへの旅を続けられた。すると、「主よ。救われる者は少ないのですか。」と言う人があった。』
ここでこのようにキリストに尋ねた者が、どうして尋ねたのかは全く不明である。本当に知りたかったのかもしれないし、単に好奇心に動かされただけだったのかもしれないし、キリストの力量をその返答において見極めようとしたのかもしれないし、誰かに聞いてくれと要請されたのかもしれないし、自分の信心深さを周りの人たちに示したかっただけかもしれないし、論争を仕掛けようとしたのかもしれないし、蠅でもあるかのようにキリストの邪魔をしようとしたのかもしれない。しかし、聖書にはこの者が尋ねた思惑について何も語っていない。いずれにせよ、この者がこのように尋ねた理由は我々にとって重要ではない。我々にとって重要なのは、この者の質問にキリストが何とお答えになったか、という点にある。
【13:23~24】
『イエスは、人々に言われた。「努力して狭い門からはいりなさい。なぜなら、あなたがたに言いますが、はいろうとしても、はいれなくなる人が多いのですから。』
キリストは、救われる者の数や比率については、何もお答えにならなかった。ここではその事柄について知らせるべきでないと判断されたのだ。もしそれを知らせるべきだったとすれば、主はここでその事柄について知らせておられたはずである。キリストに質問した者は、望み通りに答えてもらえなかったと思ったかもしれない。だが、この者に望み通りの答えを与えないのが主の御心であった。
実際はどうなのか。救われる者は多いのか、少ないのか。救われる者の数は非常に少ないと言わねばならない。何故なら、キリストが次のように言われたからである。『いのちに至る門は小さく、その道は狭く、それを見いだす者はまれです。』(マタイ7章14節)キリストはここで救われるに至る者は『まれ』と言っておられる。実際、これまでの歴史と今現在の世界を見れば、これは明らかである。いつの時代でも信仰者の数はごく少ない。ルターも「真の信仰者は少ない。」と正しく言った。だが天国にいる者たちの総数の場合、話は別であって、そこにいる者たちは非常に多い。何故なら、そこには時間が経つにつれて住民が増加していくからである。天国に入った者たちは決して死ぬことがない。またそこにいる者たちは天国から退場させられることもない。今や天国が始まってから2千年が経っている。だから、もう今では天国にいる人の総数は数え切れないほどに増し加えられていることであろう。
キリストは、救われる者の数を気にするのではなく、とにもかくにも第一に狭い門から入れるようにせよ、と命じられた。これは人々にとって狭い門から入れるようになるのが、何よりも大事だからである。もし救われる者は多いのか少ないのかなどと考えていたがゆえに、狭い門から入れなくなってしまったとすれば、その人は地獄に行くので悲惨になってしまう。そうなるぐらいであれば、別に救われる者の数など気にしなかったとしても、第一に狭い門に入れるようにして救われたほうが遥かによいのだ。ここで『狭い門』と言われているのはキリストである。人は、イエス・キリストという唯一の門を通ってこそ神の救いに入れるのである。キリストはヨハネ10:9の箇所で、御自身こそが救いに至る門だと言っておられる。『わたしは門です。だれでも、わたしを通ってはいるなら、救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。』また、今我々が見ている箇所で『はいりなさい』と言われているのは、信仰を持つことの比喩である。これを文字通りに捉えるべきではない。『努力して』とは、<頑張って><怠惰にならずに>という意味である。堕落している我々は、力を尽くさないと霊的な事柄に無頓着になりがちだからである。
ここでキリストは『努力して』御自身という救いの門に入るように命じられたが、これは我々のした努力が救いの手段になるという意味ではない。それだと救いの功績が人間に帰されてしまうことになるからだ。それでは行為義認の異端になってしまう。聖書は行為による救いを否定している。確かに人は救われるために努力すべきである。だが、だからといって、その努力における功績が我々に救いをもたらすというわけではない。何故なら、その努力も神の与えて下さった賜物だからである。もし神が恵みを与えて下さらなければ、我々は努力など全く出来ないのである。パウロも言っている通り、努力であれ何であれ、我々が持つもので神から与えられたのでないものは一つもない。『あなたには、何か、もらったものでないものがあるのですか。もしもらったのなら、なぜ、もらっていないかのように誇るのですか。』(Ⅰコリント4章7節)と書かれている通りである。
それでは、どうして『努力して狭い門からはい』るべきだったのか。その理由は『はいろうとしても、はいれなくなる人が多い』からである。我々は、ここでキリストが紀元1世紀のユダヤ人に対して言葉を述べておられることに注意せねばならない。これは当時のユダヤ人に語られているのだ。もう間もなく当時のユダヤ人は、神から捨てられ、滅ぼされることになっていた。彼らは御心に適わなかったので、神は御自身の国を彼らから取り上げようとしておられた。そのようになってからでは、キリストという門をくぐって救いに入るのは難しくなる。だからこそ、そのようになる前に、速やかに狭い門から入るようにとキリストは命じられたのであった。実際、捨てられてからのユダヤ人は、キリストを通して神の国に入れなくなってしまった。それは歴史を見れば分かる通りである。歴史を見ても、真正なユダヤ人で(※)クリスチャンになる者はほとんどいないのである。
(※)
すなわち、スファラディ系のユダヤ人。イギリスの有名な首相であるベンジャミン・ディズレーリはスファラディ系であり、洗礼も受けたようであるが、彼が本物のクリスチャンであったかどうか私には疑問に感じられる。
[本文に戻る]
ここで直接的に言われている対象は紀元1世紀のユダヤ人であるが、ここで言われている内容は全ての未信者たちにも応用して考えることが出来る。すなわち、未信者たちにも、紀元1世紀のユダヤ人たちと同じように神の救いに入れるための「期限」が定められている。その期限とは<死>である。死が訪れたならば、もうキリストという門がその人に完全に閉ざされてしまうので、ユダヤ人たちと同じように神の救いに入ることは不可能となる。地獄に行ってから、「どうして地上にいた時にキリストという門をくぐらなかったのか…」などと後悔しても、時は既に遅い。だからこそ、我々は未信者たちに大いに伝道せねばならないのである。未信者たちは、もう数十年もしくは数年もすれば、キリストという門にどうあがいても入れなくなってしまうのである。高齢化の問題を抱える先進諸国において、これからすぐにも死に至ることになる人たちが一体どれだけいるであろうか。多くの先進国には老人が多いから、これからすぐにも多くの人が墓に入るようになるのは目に見えている。日に日に多くの人が倒れて死んでいく。であれば、どうして我々が未信者にキリストという門をくぐるように宣べ伝えていかなくていいということがあるであろうか。
【13:25】
『家の主人が、立ち上がって、戸をしめてしまってからでは、外に立って、『ご主人さま。あけてください。』と言って、戸をいくらたたいても、もう主人は、『あなたがたがどこの者か、私は知らない。』と答えるでしょう。』
『家の主人が、立ち上がって、戸をしめてしまってからでは』とは、ユダヤ人たちが神の国から追い出されることである。具体的に言えば、キリストを殺して退けた時である。彼らが自分たちの主人を拒絶したので、彼らの主人も彼らを拒絶し、イエス・キリストという戸を閉じてしまわれたのである。
これ以降、ユダヤ人たちは何を言っても神の国に入ることが出来なくなった。彼らがどれだけ神に懇願しても、神はこう言われるのである。『あなたがたがどこの者か、私は知らない。』神がこう言われるのは当然であった。何故なら、ユダヤ人たちはイエス・キリストという門を拒否したからである。門を拒否したのに、どうして神の国へと入場できるのか。それは出来ないことである。というのも、神の支配される国に入場できるための門はただ一つだけ、すなわちイエス・キリストしか存在していないからである。
【13:26】
『すると、あなたがたは、こう言い始めるでしょう。『私たちは、ごいっしょに、食べたり飲んだりいたしましたし、私たちの大通りで教えていただきました。』』
『あなたがた』は、紀元1世紀のユダヤ人を指している。これは文脈を考えれば明らかである。何故なら、ここでキリストは、紀元1世紀のユダヤ人たちが神の国から除外されることについて教えておられるのだから。それゆえ、この『あなたがた』を今の時代に生きる我々のことだなどと考えてはいけない。
神の国から追い出されてからのユダヤ人たちがここで神に言っている抗弁めいたことは、あたかも次のように言わんばかりである。「私たちはナザレのイエスと一緒に飲み食いしたり、この方から色々と直接的に教えていただいたのに、どうして神の国に入れなくなってしまったのですか。」このような抗弁が愚かであり子供じみているのは、誰でも分かるであろう。たとえキリストと飲み食いしたりキリストから直に教えてもらったというだけでは、神の国に入れるようにはならないからである。キリストと一緒に飲み食いをしようが、直に聖なる教えを聞いていようが、キリストという救い主を心から受け入れないかぎり神の国に入れないのは言うまでもない。だから、ここでユダヤ人たちは無意味なことを神に対して吠え叫んでいることになる。
【13:27】
『だが、主人はこう言うでしょう。『私はあなたがたがどこの者だか知りません。不正を行なう者たち。みな出て行きなさい。』』
御国から除外されたユダヤ人は、もう何を言っても御国に戻れることはなくなった。何故なら、彼らはキリストを殺して退けるという『不正』をしたからである。自分の子を殺した者どもを、相も変わらず厚遇してやる親がどこにいるであろうか。どこにもいないはずである。神という御子の親も、その例に漏れる御方ではない。いや、むしろ神はこの世の親よりも上である。この世の親でさえ子を殺した者に憤激するのであれば、尚のこと、神は御自分の御子を殺したユダヤ人に憤激されるのだ。
これ以降、ユダヤ人たちは神の御許に帰れなくなってしまった。それは、これまでの2000年の歴史を見れば分かる。これからも彼らが神の御許に帰ることはない。しかしながら、私がこのように書くと、「いや、パウロはキリストが再臨されたならば彼らも神の御許に帰るようになると言っているではないか?」などという感覚主義者たちの声が聞こえてきそうである(※)。然り、確かにそうである。キリストが再臨されたらユダヤ人が神の御許に回復することを私は認める。だが、その再臨は既に起きた。だから、もうユダヤ人は神の御許に立ち帰った。その立ち帰ったユダヤ人たちは、神の子らとして天上の王国に導き入れられた。ここにおいてユダヤ人の問題は完全に決着がつけられた。それゆえ、もはやユダヤ人が再び神の御許に立ち帰ることはない。現在、世界中に散らされているスファラディ系のユダヤ人たちは、あくまでも標本として少しだけこの世に残されているに過ぎない。それは、聖書に書かれているユダヤ人という民族を人々が忘れてしまわないためである。人々が聖書の救いに導かれるためには、その聖書に書かれているユダヤ人が少数でも標本として残されていたほうが益になるのだ。考えてもみよ。もしユダヤ人が全く世界にいなかったとしたら、どうか。人々は聖書に書かれているユダヤ人という存在を強く認識できなくなってしまうであろう。しかし彼らは標本に過ぎないのだから、もはや神に戻るなどということは有り得ないのである。実際、今に至るまでユダヤ人たちはキリストにおいて神に立ち帰る兆しさえ見せていない。これは彼らがもう神に立ち帰ることがなくなったからである。標本に過ぎない化石のごとき民族が、再び神の御前に生命を回復するなどということが一体どうして起こるのか。勘違いも甚だしいのである。
(※)
「感覚主義者」とは、ただ御言葉による啓示を認識の前提とせず、自分の理性による感覚を認識の前提とするクリスチャンを指す。現代のプロテスタント教会にいる牧師たちは、残念ながら、そのほとんどが感覚主義者である。もしそうでなければ、今頃もっと多くの牧師たちが再臨成就説を受け入れていたことであろう。
[本文に戻る]
【13:28】
『神の国にアブラハムやイサクやヤコブや、すべての預言者たちがはいっているのに、あなたがたは外に投げ出されることになったとき、そこで泣き叫んだり、歯ぎしりしたりするのです。』
『神の国にアブラハムやイサクやヤコブや、すべての預言者たちがはいっている』とは、どういった意味か。これは旧約の父祖たちが、遂に露わにされたイエス・キリストにおいて神の国に入る、という意味である。それまでも父祖たちがキリストにおいて神の国に入っていたことは確かである。だが、それはあくまでも影としてのキリストにおいて、であった。何故なら、昔はまだイエス・キリストが実体としては露わにされていなかったのだから。だが、今やもうイエス・キリストが実体として出現された。その実体としてのキリストにおける御国に父祖たちは入ることになった。だから、ここでは『神の国に、アブラハムやイサクやヤコブや、すべての預言者たちがはいっているのに』などと言われているのだ。
『あなたがたは外に投げ出されることになったとき』とは、ユダヤ人たちが神の国から追放される時を言っている。それは、彼らがキリストを殺した時である。彼らは契約の主を殺したのだから、もう神の国にいることが出来なくなってしまった。自分の主人を殺す者が、どうしてその主人の国にいられるであろうか。
ユダヤ人たちが御国から除外されて以降、彼らは非常に悲惨となった。何故なら、もはやかつてのように神の前で子として歩めなくなったからである。その霊的な悲惨が、ここでは『そこで泣き叫んだり、歯ぎしりしたりする』と言い表されている。よって、これは文字通りの意味に解するべきではない。
この箇所で言われている内容は、マタイ8:11~12の箇所と同じである。マタイの箇所とは言葉において幾らかの違いが見られるが、その違いは既に述べられた通りである。
【13:29】
『人々は、東からも西からも、また南からも北からも来て、神の国で食卓に着きます。』
この箇所では、異邦人の召しについて預言されている。ユダヤ人から御国が取り上げられると、その代わりに異邦人にそれが与えられることになった。キリストがユダヤ人に対して、『神の国はあなたがたから取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。』(マタイ21章43節)と言われた通りである。すると、東西南北あらゆる場所にいる民族が、続々と神の国へと入って来ることになった。だから、『東からも西からも、また南からも北からも』という言葉は文字通りの意味に捉えるべきである。実際、ユダヤ人が捨てられてから、本当に世界各地にいる人々が神の国に導かれるようになったのだから。
また、ここでは、召された異邦人が救いに入ることが『食卓』に例えられている。異邦人が神の救いの中に入るのは、すなわち神が用意された食卓の饗宴に参加することなのである。その饗宴の主宰者は神であられる。しかも、そこには『アブラハムやイサクやヤコブや、すべての預言者たち』もいる。こんな素晴らしい食卓の饗宴が他にあるであろうか。天皇が催される愛餐会も、この饗宴には比べられない。つまり、異邦人が救いに入って神と交わるのは大変素晴らしいということを、この『食卓』という言葉は示している。イザヤ25:6~12の箇所でも、異邦人の召しが神の催される食事会として示されている。このイザヤ書の箇所は既に註解された。
ここで言われているのが携挙の出来事だと理解しないように注意せよ。ここでは人々が東西南北から神の所へ集まって来ると言われている。携挙も、人々が東西南北から神の所へ集まって来る出来事である(マタイマタイ24:31)。だから、ここで携挙について言われていると理解する人がいたとしても不思議ではない。だが、ここでは携挙について言われているのではない。それは文脈を考えれば分かる。ここでキリストは、ユダヤ人が退けられる代わりに異邦人が召される新しい時代について教えておられるのだから。初学者が特にこの点について誤りやすいのではないかと思う。よく注意せねばならない。
この『食卓』という言葉には解釈の奥義がある。それは、『食卓』という言葉が何の存在に結び付けられているかによって区別される、という奥義である。すなわち、人に結び付けられているか、悪霊どもに結び付けられているか、という違いである。この『食卓』が人に関連付けられている場合、そこでは人が神の国に入れられること、すなわち新生のことが語られている。何故なら、人が救われて神との交わりに入るのは、正に神の食卓に参加することだからである。我々が今見ている箇所やイザヤ25:6~12の箇所では、この意味合いで『食卓』と語られている。一方、この『食卓』が悪霊に関連付けられている場合、そこでは再臨の出来事について語られている。何故なら、再臨が起こるとローマ兵たちが殺されて死体になり、その死体を悪霊どもが御馳走としてムシャムシャ食べ尽くすからである。黙示録19:17~18およびエゼキエル39:17~20では、この意味合いで食卓について語られている。要するに、人において食卓が語られていたら、それは再臨のことについて示されているのではない。また悪霊において食卓が語られていたら、それは人の新生について示されているのではない。この解釈の奥義は知っておいて益になるはずである。
【13:30】
『いいですか、今しんがりの者があとで先頭になり、いま先頭の者がしんがりになるのです。」』
『今しんがりの者』とは異邦人である。彼らは、この時はまだ神から遠く離されていたからである。『いま先頭の者』とはユダヤ人である。彼らは、まだこの時には神の傍近くに子として歩んでいたからである。この箇所では、異邦人とユダヤ人の立場・境遇が丸っきり逆になると言われている。すなわち、異邦人が神の傍近くにいる神の民となり、ユダヤ人は異邦人のように神から遠く離される、と言われている。これは我々が今世界で見ている通りである。
実に驚くべきことが起こった。一体誰が考えたであろうか。神の救いを切に求めていたユダヤ人が救いから除外され、神の救いなど全く求めてもいなかった異邦人にそれが与えられるようになるとは…。当時生きている人たちのうち、誰一人としてこのようなことは考えなかったに違いない。何故なら、これは想像を絶することだからである。だが、神はこのように人の意表をつくやり方をなされる。そうすれば、神は人を遥かに超越しているということが豊かに示されるからである。そのようなことが示されれば、驚きと恐れと賛美と感動が人に生じるので、神の栄光が現わされるようにもなるのだ。
【13:34】
『ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に遣わされた人たちを石で打つ者、わたしは、めんどりがひなを翼の下にかばうように、あなたの子らを幾たび集めようとしたことか。それなのに、あなたがたはそれを好まなかった。』
キリストは、エルサレムを嘆いておられる。その嘆きは非常に大きかった。『エルサレム、エルサレム』という繰り返しが、そのことをよく示している。この『エルサレム』とは狭義の意味ではエルサレム市にいたユダヤ民族であり、広義の意味では神の国を持つ民族としてのユダヤである。
主がエルサレムを嘆かれたのは、ユダヤ人たちが『預言者たちを殺し、自分に遣わされた人たちを石で打』ったからである。神であられるキリストは、堕落した歩みをし続けていたユダヤ人たちが正しい道に進むようにと、幾度となく御自身の使者を遣わされた。イザヤやエレミヤやアモスなどがそうである。それなのに、ユダヤ人たちはその使者たちを受け入れず、かえって殺すことさえしてしまった。これではキリストが嘆かれたのも無理はない。好意に基づいて遣わした使者が何人も殺されたのに、嘆かない人がこの世のどこにいるのであろうか。
この箇所では、神が『めんどり』として、ユダヤ人たちが『ひな』として、神がユダヤ人たちを改悛させて立ち直らせることが『翼の下にかばう』という行為として例えられている。これは実に適切な例えである。これ以上の例えは思いつくことが出来ない。旧約聖書でも、多くの箇所で、神が翼を持つ鳥として語られている。例えば、申命記32:10~11の箇所ではこう書かれている。『主は荒野で、獣のほえる荒地で彼を見つけ、これをいだき、世話をして、ご自分のひとみのように、これを守られた。わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞いかけり、翼を広げてこれを取り、羽に乗せて行くように。』
ユダヤ人が神から遣わされた使者たちを拒んだ理由は何だったのか。それは神の目的が実現されるためであった。それは、異邦人に神の国が展開されるという目的である。ユダヤ人たちが堕落した歩みをしてどうしようもない状態になったからこそ、神はユダヤ人たちから神の国を異邦人に移すことが出来るようになった。もしユダヤ人たちが堕落していなかったとすれば、もしくは堕落していたが悔い改めて正しい者たちになっていたとすれば、神の国がいつまでもユダヤ人たちのうちに留まっていただろうから、異邦人に神の国が移されるということは実現されなかった。神は、絶対に神の国を異邦人にもお与えになるお積もりであった。何故なら、そのように永遠の昔から計画しておられたからである。だからこそ、ユダヤ人たちは堕落することが神により許されたのである。
【13:35】
『見なさい。あなたがたの家は荒れ果てたままに残される。』
ここでは、ユダヤ人たちから神の国が取り上げられて霊的に荒廃してしまうことが預言されている。確かに神の国が失われたならば、そこにはただ霊的な荒廃があるのみである。イエス・キリストにおける神の国こそが我々人間を霊的に潤った地とさせるのだからである。この部分を、紀元70年におけるユダヤ都市の物質的な崩壊として捉える人もいるであろう。確かに、その時、ユダヤは都市としても荒廃させられるに至った。だが、これは既に語ったように、都市の荒廃というよりは、むしろ霊的な荒廃として捉えるほうがよい。
『わたしはあなたがたに言います。『祝福あれ。主の御名によって来られる方に。』とあなたがたの言うときが来るまでは、あなたがたは決してわたしを見ることができません。」』
<『祝福あれ。主の御名によって来られる方に。』とあなたがたの言うとき>とは、再臨が起こる時である。その時、選ばれていた少数のユダヤ人クリスチャンは、このように言った。この時に、ユダヤの罪は、この選ばれていたユダヤ人において全て抹消された。ローマ11:27の箇所で、『それは、わたしが彼らの罪を取り除く時である。』と言われていた通りである。一方、選ばれていない多くのユダヤ人たちは、再臨が起きた時、このように言わなかった。何故なら、彼らはキリストを憎悪していたからである。憎悪しているのに、こんなことを言うはずはない。むしろ、「本当に来やがったとは、、。まさか、あの異端者が…。」などと呟いたはずである。『祝福あれ。主の御名によって来られる方に。』という言葉は、再び来られたキリストに相応しい言葉であった。何故なら、これはキリストの幸いを願っている言葉だからである。ちょうど王が凱旋した際に「王さま。万歳。」などと言うようなものである。
キリストが再臨されるまで、ユダヤ人たちはもうキリストをその目で見ることがなかった。それは、いつからだったのか。キリストが墓に葬られてからである。キリストが葬られてからも、幾らかの聖徒たちだけは、復活されたキリストを幾日かの間、その目で見ることが出来た。だが、信仰を持たないユダヤ人たちに、キリストはその姿を現わされなかった。だから、ユダヤ人たちはキリストが葬られて以降、キリストをずっと見ないままでいた。これは当然であった。キリストは葬られ、復活され、昇天され、天の父の右の座に着かれたのだから。
しかし、再臨が起きた時、ユダヤ人たちは再臨されたキリストをその目で見た。何故なら、既にゼカリヤ書の註解でも見た通り、キリストはエルサレムにあるオリーブ山の真上に降りて来られたからである。キリスト御自身が、紀元1世紀のユダヤ人たちに対し、彼らが再臨の主をその目で見ると預言しておられた。すなわち、こうである。『なお、あなたがたに言っておきますが、今からのち、人の子が、力ある方の右の座に着き、天の雲に乗って来るのを、あなたがたは見ることになります。』(マタイ26章64節)
この部分で言われている出来事は既に成就している。何故なら、再臨は既に実現したからである。ここまで本書を読んだにもかかわらず、再臨が既に起きたと信じない聖徒がいれば、その聖徒の信仰は明らかに問題がある。何故なら、その聖徒は御言葉を聞いても素直に受け入れていないからである。あなたの信仰が問題ないかどうか、一つ試してみようか。次に示す御言葉に心を傾けよ。キリストは御自身の目の前に立っている紀元1世紀のユダヤ人たちに対して、こう言われた。『まことに、あなたがたに告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が御国とともに来るのを見るまでは、決して死を味わわない人々がいます。』(マタイ16:28)さて、あなたはキリストがこのように言われた御言葉を読んで、素直に、即座に、確信しつつ「アーメン。」と言えるだろうか?………―
【17:20~21】
『さて、神の国はいつ来るのか、とパリサイ人たちに尋ねられたとき、イエスは答えて言われた。「神の国は、人の目で認められるようにして来るものではありません。『そら、ここにある。』とか、『あそこにある。』とか言えるようなものではありません。いいですか。神の国は、あなたがたのただ中にあるのです。」』
パリサイ人たちは、神の国について誤解していた。どういうことかと言えば、彼らは神の国を肉的に捉えていた。すなわち、彼らは神の国が無敵の支配力を持つ地上の国であると思っていた。これから神の国がユダヤに来れば、王なるメシアがそこにおいて支配をし、ユダヤをローマの軛から解放して助け出してくれる、と。パリサイ人たちは神の国を言わばスーパーマンとして捉えていたわけである。彼らはローマの支配から抜け出したいと思っていたから、早くメシアの支配する強大な国がユダヤに到来してほしいと願っていた。しかし、このように神の国を捉えていたのは何もパリサイ人だけではない。一般のユダヤ人たちもパリサイ人と同じように考えていた。つまり、普通のユダヤ人も何か神の国がスーパーマンでもあるかのように感じていた。そればかりでなく、使徒さえもそのように捉えていたぐらいである。使徒たちは、キリストが復活してからも、未だにキリストが神の国をユダヤの地に打ち立ててローマの支配から助けてくれるだろう、などと思っていた(使徒行伝1:6)。キリストから色々と教えを受けていた使徒でさえこのようであったのだから、他のユダヤ人たちが神の国について誤解していたとしても不思議なことはない。我々は、当時のユダヤ人たちを馬鹿に出来ない。何故なら、我々も当時のユダヤ人だったならば、神の国について正しい理解を持てなかっただろうから。使徒でさえ誤解していたのに、どうして我々が正しい理解を持てるというのか。有り得ない話である。我々が彼らの誤解に苦笑することも出来るのは、その時から既に2千年も経過しており、今となっては聖書の理解と神学が大いに発達しているからに他ならない。今の時代に生きる我々だって、1万年後の時代の人たちから見れば、あまりにも無知なので苦笑せざるを得ないはずである。しかし、時代には知的な制約が必ずある。その制約を突破できるのは、次の時代を切り開く一握りの天才だけにしか許されていない。それ以外の全ての人はその制約という言わば「檻」の中に閉じ込められたままである。アドルノが「現代意識の囲いの外に脱出することは不可能である。」(『不協和音 管理社会における音楽』Ⅴ 伝統 p249 平凡社)と述べたのは、一般大衆について言えば完全に正しい。認識的な牢獄の中にずっと留め置かれたままでいるということ、これはハッキリ言ってどうしようもない。だから、昔の時代の人々の無知を笑うことは適切とは言えないのである(※)。
(※)
キリストも、パリサイ人たちの誤解を叱責されず、むしろ心優しく正しい理解へと導いておられる。これは、この誤解がもうどうしようもない類のものだかったからである。もしこれが探りでもするならば見いだせることであれば、キリストは彼らの怠慢と無知を責め、例えば『信仰の薄い人たち』とか『心の鈍い人たち』などと厳しい言葉を発しておられたはずである。
[本文に戻る]
キリストは、神の国がすなわち一人一人の中にある神の支配であるとパリサイ人たちを教えられた。つまり、聖徒とは、神という王に統治される王国また領土なのである。確かに聖書では聖徒が『王国』(黙示録1:6、出エジプト19:6)と明白に言われている。だから、聖徒たちは神に治められる霊的な国として、神に従うのである。このように神の国を持つのは聖徒だけに限られる。何故なら、神が王として聖なる統治を敷かれるのは聖徒たちだけだからである。非再生者たちには「悪魔の国」がある。何故なら、彼らは知っているにせよ知らないにせよ、悪魔の支配のうちに生きているからである(エペソ2:2:1~2)。キリストはこのように答えることで、パリサイ人たちに神の国の正しい理解を教えられた。これに対するパリサイ人の応答は何も書かれていない。恐らく、福音書の他の箇所でも書かれているように、何も答えられなくなってしまったのだと思われる。そうでなければ、わざわざ取り上げるまでもないことしか言い返せなかったのであろう。
つまり、キリストはここで神の支配という意味における『神の国』のことを教えられた。それは、場所における神の国ではない。パリサイ人は、この神の国を場所的に捉えていた。もちろん、場所としての神の国も存在する。それは天国のことである。しかし、パリサイ人たちは、神の国を場所的には地上に定めていたのだ。これは大きな間違いであった。もし彼らが場所としての神の国を天上に求めていれば、何も問題はなかった。昔の聖徒たちはその天上にある場所としての神の国を求めていたとヘブル書でも書かれている(11:13~16)。だが、パリサイ人たちは天上の場所に神の国を定めることをしていなかった。そのようなパリサイ人に対し、キリストは天上の事柄をもって返答なさらなかった。「あなたがたの求めている神の国は、この地上ではなく天の場所にあるのだ。」などと。そうではなくキリストは神の国をあくまでもこの地上における事柄として語られた。つまり、主は、地上の事柄を尋ねてきたパリサイ人たちの視点に御自身の視点を合わされたのである。すなわち、主は地上の事柄に応じて天上の事柄では答えられなかった。そうではなく地上の事柄に応じて地上の事柄で答えられたのである。我々は、キリストのこの返答から、神の国が神の支配であるということを覚えよう。また、神の国は場所としては天国にあるということも覚えよう。
第45章 43:ヨハネの福音書
【3:14】
『モーセが荒野で蛇を上げたように、人の子もまた上げられなければなりません。』
この箇所では、キリストが上げられると言われている。これはキリストの携挙について言われているのではない。何故なら、ここではモーセが蛇を上げたことについて言及されているから。つまり、これは十字架において上げられることを言っている。これは実に初歩的なことであるが、もしかしたら読者の中にはこれについて理解していない人もいるかと思い、このように書いておくことにした。
【6:40(39、44、54)】
『わたしはその人たちをひとりひとり終わりの日によみがえらせます。』
ここで言われているのは、ユダヤの終わる時期に、復活の出来事が起こるということである。この『終わりの日』が未だに来ていないなどと考えてはならない。マタイ24章を読めば分かるように、『終わり』とは神殿崩壊の時に起こるユダヤ世界の終わりのことだからである。この復活は、第一の復活であり、それは再臨の起きた紀元68年6月9日に起こった。つまり、ここで言われているのは悪者どもが復活する2回目のほうの復活ではない。というのも、ここでは明らかに聖徒たちだけが復活することについて言われているからである。キリストは、同じ場面でこの復活についてのことを総計4回も言っておられる。このように復活のことが何度も言われたのは、ユダヤの終わりの時期に起こる復活の出来事が、あまりにも重要だったからである。
今まで教会は、この終わりの日と復活の出来事について、大いに間違いを犯してきた。すなわち今まで教会は、聖書が「世の終わり」はユダヤ世界の終わりのことだと教えているにもかかわらず地球全土のことを言っていると理解し、パウロが復活はパウロと共にいたテサロニケ人たちが『生き残っている』(Ⅰテサロニケ4:17)時に起こると教えたにもかかわらず未だに起きていないと考えてきた。私は、この2つの事柄について、正しい理解をこれまで示してきた。今こそ教会は悔い改めるべき時である。私は現代の教会が、色々な意味において異常になってしまっているのを見ている。もし悔い改めないというのであれば、これから教会はますます酷い状態に陥ることになるであろう。何故なら、私の述べたことを聞いて悔い改めないというのは、つまりその教会が聖書に忠実な態度を持っていないということを意味しているのであり、そのような教会は聖書に忠実でない態度に対する当然の報いとして誤謬と堕落に呑み込まれざるを得ないからである。私は言う、悔い改めこそが全てを解決すると。何故なら、もし悔い改めるのであれば、もはや神からの裁きはそれ以降注がれなくなるからである。しかし悔い改めないのであれば、神がその悔い改めない教会や聖徒たちに怒りを持たれ続けるので、ますます裁きを受けて悲惨になってしまう。
この箇所から、復活の出来事はキリストの御業であったことが分かる。何故なら、ここではキリスト御自身が聖徒たちを『よみがえらせます。』と言っておられるからだ。つまり、復活とは単なる自然現象のような出来事として起きたのではない。そうではなく、それはキリストの働きにより起きた人為的な現象であった。注意が必要であるが、この復活の出来事について、御父と御霊は何も関わっていないと考えてはならない。キリストは御父の御心に従って復活の御業を行なわれたのであり、御霊の御力において聖徒たちを復活させられた。それだから復活の御業を行なわれたのはキリストだけでなく、御父と御霊も行なわれたと理解せねばならない。
【12:32】
『わたしが地上から上げられるなら、わたしはすべての人を自分のところに引き寄せます。』
この箇所で、キリストは御自身が『地上から上げられる』と言っておられる。これも先に見た3:14の箇所と同様、携挙について言われているのではない。何故なら、すぐ次の節を見れば分かる通り、これは十字架の救いのことだからである。つまり、ここではキリストが十字架の贖いを成し遂げられると、信じる全ての者がキリストの肢体に加えられるようになる、と教えられている。これも初歩的なことだが、念のため書いておくことにした。「一切を徹底的に行なう。」というのが本作品のスタンスである。初学者でない方にとっては説明の必要がない内容だったかもしれないが、煩わしいと思わないでほしい。
なお、この箇所では『すべての人』と書かれているが、これは文字通りに捉えるべきではない。何故なら、キリストが贖いを実現させられたからといって、文字通りの意味で『すべての人』がキリストの肢体に集められるわけではないからである。言うまでもなく、ここで言われているのは選ばれている者たちにおける『すべての人』という意味である。もしこれを文字通りの意味で捉えるとすれば、万人救済主義の異端となる。この箇所の内容は、聖書の中で『すべて』と書かれているからといって、必ずしも文字通りの意味の『すべて』と解するべきではないということにおける良い例である。
【14:2】
『わたしの父の家には、住まいがたくさんあります。』
キリストが言っておられる『わたしの父の家』とは、父なる神のおられる天上の世界のことである。これがキリストの父だと誤解されていたヨセフの家だったのではないことは、言うまでもない。キリストとヨセフには血の繋がりが全くなかったのだから。
天上の世界には『住まい』が存在している。これは聖徒たちの住まいのことである。この地上世界において、人間は一軒家であれマンションであれホテルであれ王宮であれ簡易的な小屋であれ、何らかの住まいを持っている。人は、その住まいを生活の拠点として生きている。天上にいる聖徒たちにも、そのような住まいが与えられるのだ。それでは、この天上世界の住まいとは、どのようなものか?これについてはよく分からない。ただ、それが栄光に満ちた非常に素晴らしい住まいであるということは間違いない。誰がこれを疑うであろうか。
この天上世界の住まいは『たくさん』ある。これは天上にいる聖徒の数が多いことを示している。つまり、天上にいる聖徒が多いからこそ、そこにある住まいも『たくさん』あるというわけである。もし天上の聖徒が少なければ、キリストはこのように言われなかったであろう。ただし、『たくさん』というのはあくまでも天上にいる聖徒たちの数の多さについてだけ言われている、という点を我々は弁えなければならない。つまり、これは天上にいる聖徒たちのことを考えれば、その数は多い、という意味である。この地上にいる聖徒の数について言えば、それは絶対的な意味においても比率的な意味においても、多くはいない。いつの時代も、真に救われている聖徒の数は、この地上に少ないものだからである。イザヤ書66:16の箇所では、主が再臨される時のことについて『主に刺し殺される者は多い。』と言われている。これは「救われていない者の数は多い。」と言っているのも同然である。だから、やはり地上においては真の聖徒の数は少ないのである。もしそうでなければ、イザヤ66:16の箇所では『主に刺し殺される者は少ない。』と言われていたはずである。
『もしなかったら、あなたがたに言っておいたでしょう。』
これは、前に言われたことの強調である。キリストは、こう言っておられるかのようである。「あなたがたは、父の家に住まいが沢山ないにもかかわらず、父の家に住まいが沢山ある、などと私が言ったとでも思うのか。もちろん、私は父の家に住まいが沢山あるのを知っているからこそ、父の家には住まいが沢山あると言ったのだ。だから、そのことを疑わないようにしなさい。」信ずべき重要な事柄が述べられる際に強調表現を使われるのは、キリストのよく為されたことであった。話の前置きとして『まことに、まことに、あなたがたに告げます。』と言われたのも、そうである。
『あなたがたのために、わたしは場所を備えに行くのです。』
キリストは、聖徒たちに住まいを用意されるため、天上の世界へと昇天された。それは聖徒たちが天上に導かれたら、そこで住まうことが出来るためであった。もう40年もすれば、紀元70年に天上で天国が開始されるのだ。だからこそ、キリストは聖徒たちのために準備をしに行かれたのである。というのも準備が為されなければ、どうして聖徒たちがそこに住まうことが出来るであろうか。今に至るまで聖徒たちは「昇天」と聞くと、「キリストが御父の右の座に座られた」というだけのことしか考えない。もちろん、このように考えるのは間違っていない。しかし、もう一つ私が今述べたことも昇天においては考えなければならない。すなわち、キリストが天に行かれたのは、ただ御父の右の座に座られるためだけでなく、聖徒たちのために場所を備えに行くというためでもあったのである。
主は、聖徒たちにあらかじめ全てを備えて下さる御方である。『神は愛』(Ⅰヨハネ)である。だからこそ、神は親切に全てを事前に用意して下さるのだ。それは恵みを受ける者たちが、最初から準備万端の状態を享受できるためである。天国の場合が正にそれであった。聖徒たちは、キリストがあらかじめ天に行かれ場所を準備して下さったのだから、天国に導かれた時は何も不満を持つことがなかった。最初から全てが整っていたからである。アダムの場合もそうであった。神は、あらかじめ一切の被造物を創造されてから、最後の最後に人間を創造された。だからアダムが創られた時、彼の目の前には最初から何もかもが用意され整えられていた。このためアダムが神に文句を言ったり不満をもつことはなかった。「どうして神は創造の途中で私を造られたのだろうか。まだ出来ていない被造物もあるではないか。」などと不快に感じることがなかった。このようにするのが、神のやり方である。何故なら、そのようにすれば、人が神に感謝と賛美をするようになるからである。全てを準備万端にして下さっておられた神に崇拝を奉げない者が果たしているであろうか。神は御自身の栄光を求めておられる。だからこそ、神は御自身の恵みの栄光を現わされるために、あらかじめ全てを備えて聖徒たちに与えて下さるのである。我々が天国に行った時にも、そこには全てが既に備えられているであろう。そこはもう既にキリストによって豊かに備えられている場所なのだから。
主は、一瞬にして天上の世界に場所を備えることもお出来になった。しかし、主はそうされず、準備に数十年の歳月をおかけになられた。これは何故なのか。これは聖徒たちが、なかなかキリストが再臨されないからというので待ち疲れしてしまわないためである。当時の聖徒たちにとって再臨が遅いと感じられたとしても、キリストが天上で準備をしておられると分かっていれば、「そうだ、今はまだ天上で私たちの住まいが準備されている期間なのだ。その準備期間が終わるまでは再臨が起こらないのだから、待ち続けることにしよう。」などと思えるようにもなる。このように思えるならば、それだけ心も疲れずに済む。これは創造の出来事もそうであった。神は、創造を一瞬のうちに完了させることがお出来になられたが、そのようにはせず、6日の時間をかけられた。これは聖徒たちが神のやり方を真似るためである。すなわち、我々は神が6日働かれて1日休まれたように、週の6日で仕事をし残りの1日で自分を休ませるのである。これについては出エジプト20:8~11に書かれている。神は、このように人間のために時間をかけて仕事をなされる、ということをされる御方である。神が、一瞬にして何事かを前準備抜きで実現させられることは非常に珍しい。我々は、このことをよく弁えるべきであろう。
【14:3】
『わたしが行って、』
これは昇天のことを言っている。キリストは天へと行かれたのだ。それは紀元30年頃に起こった。
『あなたがたに場所を備えたら、』
これは、天上で準備が整えられて再臨が起こる時期に至ったならば、という意味である。天で住まいの準備が整ったのであれば、もはやキリストが天に留まり続ける必要はなくなる。会場の準備が整ったのに、招待客を招こうとしない主宰者はいない。キリストは天国という会場の主宰者であられる。だから、約40年の間準備をされた末、遂に準備が整ったので、キリストは紀元68年6月9日に聖徒たちを招くべく天から降りて来られたのである。
『また来て、』
これは再臨のことである。それは既に起こった。「いや、まだ起こってはいない。」などと読者の方々は言うであろうか。その場合、我々は聖書を否定せねばならなくなってしまうであろう。何故なら、キリストもパウロも紀元1世紀の人たちが生き残っている間に再臨は起こると明言したのだから。
『あなたがたをわたしのもとに迎えます。』
キリストが再臨されると、聖徒たちは第一の復活に与かり、空中におられるキリストの『もとに迎え』られた。その時、墓の中に眠っていた聖徒たちは墓の中から出てきて、生き残っていた聖徒たちは生きながらにして復活体に切り替えられた。これは恵みに満ちた、喜ばしい、大いなる出来事であった。これが起きたのは紀元68年6月9日である。当時の聖徒たちは、このようにしてキリストに迎えられることを切に待ち望んでいた。何故なら、キリストの迎えが来れば、聖徒たちはパラダイスに至れるからである。もう一度言うが、これは既に起きている。我々は、この出来事が未だに起きていないと考えるべきではない。
『わたしのいる所に、あなたがたをもおらせるためです。』
キリストと教会が永遠に共に居続ける、というのが神の御心である。何故なら、パウロも言うように、キリストと教会は夫婦だからである(エペソ5:22~32)。夫婦がずっと共に歩むというのは、理に適っており、ごく自然なことである。キリストは夫である。だから、妻である教会と永遠に共に居続けたいと思っておられる。教会は妻である。だから、夫であるキリストと永遠に共に居続けたいと思っている。キリストと教会には、このような相互愛が存在しているのである。
紀元1世紀にキリストに迎えられた聖徒たちは、それ以降、ずっとキリストと共に生きるようになった。パウロが『このようにして、私たちは、いつまでも主とともにいることになります。』(Ⅰテサロニケ4章17節)と言った通りである。これ以降、彼らがキリストから離れることはなくなった。神は離婚を憎んでおられるからである(マラキ2:16)。
我々も、やがて天に召されたならば、それ以降、キリストと共に生きるようになる。何故なら、キリストこそ聖徒たちにとって命だからである。それ以降、我々は、もはやキリストから離れることがなくなる。我々がキリストから離れるぐらいであれば、この全宇宙が真っ二つに引き裂かれるほうが遥かに容易いであろう。
【21:21~22】
『ペテロは彼を見て、イエスに言った。「主よ。この人はどうですか。」イエスはペテロに言われた。』
『この人』とは、使徒であり黙示録を書いたヨハネである。ヨハネは、福音書の中で、自分のことについて明瞭には書き記していない。そこでは、『イエスが愛された弟子』(ヨハネ21章20節)とか『「主よ。あなたを裏切る者はだれですか。」と言った者』(同)などと自分について言い表しているだけである。だが黙示録のほうでは、ちゃんと自分のことを書き記している(黙示録1:4、9、22:8)。
ペテロはキリストから『わたしの羊を飼いなさい。』(ヨハネ21章17節)と言われたが、ヨハネについてはキリストがどのような取り扱いをされるのか知りたいと思った。だからこそ、ここでは『主よ。この人はどうですか。』などとヨハネについて質問している。ペテロがこのように尋ねたのは、キリストが自分よりもヨハネを大事にしているかそうではないか気になったからである。この時のペテロはまだまだ未熟だったので、自分こそがキリストから最も重要な存在であると思われたく願っていた。これは、ちょうどマイケル・ジャクソンを崇拝する熱狂的なファンが、誰よりもマイケルから関心されるファンであり続けたいと願うようなものである。このようなファンはナンバー1のファンであることを求め、そのようなファンであることを気持ちよく感じるのだ。ペテロであれマイケルのファンであれ、このような願望はその対象に対する愛の反映などでは決してなく、それはむしろ自己愛の反映である。というのも、ペテロもマイケルのファンも、その対象の利益を自分を犠牲にして求めているというのではなく、自分が最高に良い状態であることだけを求めているに過ぎないからである。そこにあるのは、ただ自分を喜ばせたいという欲求であって、愛の精神が欠如していると言わねばならない。何故なら、愛とは相手のことしか考えない心の働きだからである。もし自分の利益を求めたら相手の利益をそれだけ求められなくなるので、自分を求めれば求めるほど愛の度合いは弱まってしまうのだ。それだから、もしペテロが愛において成熟していたとすれば、キリストにここでこのような質問をすることはなかったであろう。何故なら、その場合、ペテロは自分のことを考えないで、ただキリストのことだけを考えていただろうからである。要するに、ここでペテロが『この人はどうですか。』と言ったのは、言い換えれば「私こそが最も愛されている弟子なのか。」ということである。これはマイケルのファンの場合で言えば、そのファンがマイケルに対して「ねえ、マイケル。あなたにとって私こそが最高のファンよね?」などと聞くようなものである。こんなはしたない質問が他にあるであろうか…。
このようなペテロの幼稚な質問に対してキリストは次のように答えられた。
【21:22】
『「わたしの来るまで彼が生きながらえるのをわたしが望むとしても、それがあなたに何のかかわりがありますか。あなたは、わたしに従いなさい。」』
これは、つまりヨハネが再臨の起こる時まで生存していることを望まれるほどにキリストに愛されていたとしても、それはペテロにはまったく関係のないことだから、ヨハネのことなどに気を取られずペテロは自分の主に仕えなければならない、ということである。キリストは、ペテロの未熟な精神を完全に見抜いておられた。だからこそ、このように短い言葉の一撃で、ペテロの愚かさを打ち砕かれたのである。『知恵ある者のことばは突き棒のようなもの』(伝道者の書12章11節)と書いてある通り、このキリストの御言葉は、ペテロにとっては相当痛かったことであろう。というのも、キリストはここで突き棒により突くかのようにして、ペテロの愚かさを真正面から突いておられるからである。ペテロから愚かさが洗い落とされるためには、このような痛い言葉が必要であった。何故なら、痛みを受けるからこそ、喜ばしくない性質が除き去られることにもなるからである。これはソロモンが次のように言った通りである。『打って傷つけるのは悪を洗い落とすため。腹の底まで打ちたたけ。』(箴言20章30節)
ここでは、明らかにキリストの再臨が当時において起こるという前提で、御言葉が語られている。実際、紀元68年に再臨が起きたのだから、再臨がヨハネの生きている時代に起きるという前提で御言葉が語られたのは自然なことであった。しかし、今まで教会は再臨がまさか紀元1世紀に起きたとは想定さえしなかったので、どうしてここで当時において再臨が起こるという前提で御言葉が語られているのかまったく理解できなかった。第1部でも書いたが、アウグスティヌスもこの箇所を読んで、どうしてキリストがヨハネの生きている間に再臨が起こるという前提で語られたのかまったく理解できず、大いに慌てふためいてしまった。それだからこの高名な教父は、最後までこの箇所を正しく解釈できないままであった。霊的に最も鋭いと言ってよいアウグスティヌスでさえ、こうである。そうであれば、アウグスティヌス以外の聖徒たちは、どれだけこの箇所を読んで混乱に陥らなければいけないであろうか。言うまでもなく、この箇所は再臨が使徒の時代に起きたという前提で解釈しようとしないと、何が言われているのかまったく不明瞭なままである。それゆえ、このまま教会が再臨について従来の見解を変えないのであれば、永遠にこの箇所を理解できないままとなるであろう。
我々は、この箇所におけるキリストの御言葉からよく学んで、他の人がどうであれ、とにかくキリストにこそ仕えていくようにせねばならない。聖徒たちの多くは、ここでのペテロのように、自分以外の聖徒たちがキリストからどのような評価をされているのか気になるかもしれない。しかし、他の聖徒が神からどのように思われているのか気にしたところで、一体なんになるというのか。そのようなことを気にしても、卑屈に基づく妬みや優越感が起こるだけであり、かえって害になりかねない。ちょうど、ヨセフが父から最も愛されているのを見て不快の念を持ったイスラエルの子らのように(創世記37:3~4)。そのようになるぐらいであれば、他人が神からどう思われているのかということを、知らないままのほうがむしろ良いことになる。イスラエルの子らも、もしヨセフのことをまったく気にしていなかったとすれば、どれだけ穏やかでいられたことであろうか。はっきりと言うが、重要なのは他人が神からどのような評価を受けているのかということではなく、自分の神にシッカリと仕えることである。我々は未熟なペテロのようにならないようにしよう。
【21:23】
『そこで、その弟子は死なないという話が兄弟たちの間に行き渡った。』
キリストの言葉を聞いた弟子たちは、キリストがヨハネは再臨の時まで生き残っていると言われたと思った。つまり、主が御自身の目の前に立っている者の中のうち再臨の時まで生き残っている者がいると言われたのは(マタイ16:28)、ヨハネのことを指していたのだ、と思った。それは、ここでキリストが『わたしの来るまで彼が生きながらえるのをわたしが望むとしても』とヨハネについて言われたからである。ヨハネはこの『話が兄弟たちの間に行き渡った』と書いているが、どのぐらいの数の兄弟たちに言い広まったかは不明である。ここにいた少数の兄弟たちの間だけに言い広まったのかもしれないし、ユダヤの全土にいる多くの兄弟たちの間に言い広まったのかもしれない。
『しかし、イエスはペテロに、その弟子が死なないと言われたのでなく、「わたしの来るまで彼が生きながらえるのをわたしが望むとしても、それがあなたに何のかかわりがありますか。」と言われたのである。』
弟子たちがキリストの言葉を聞いてこのように考えたのは、間違っていた。彼らは思い違いをしていた。だからこそ、ヨハネはここでその間違いを指摘している。ヨハネがここで言っているように、キリストはヨハネの生きている間に再臨が起こると言われたわけではなかった。つまり、キリストはここで再臨がいつ起こるかということを教えておられるのではない。そうではなく、ここで言われているのはどれだけヨハネがキリストから愛されているのか、ということである。すなわち、ここでは先にも述べたように「ヨハネが再臨まで生き残っているのを望まれるほどにキリストから愛されていたとしても、」ということが言われている。それだから我々が今見ている箇所から、ヨハネはキリストの再臨の時まで生きていたのか生きていなかったのか、という重要なことを知ろうとしても無駄である。というのも、ここでキリストは再臨の起こる時期について何かを教えられたのではないからである。
この箇所の場合もそうだが、キリストの御言葉は本当に難しい。使徒でさえ正しく解釈できなかったほどである。今に至るまで、実に多くの人たちがキリストの御言葉を誤解したり、また理解したくても理解できずに悩まされてきた。これはキリストの御言葉が、人間理性では計り知れないものだからである。これからも多くの人々は、キリストの御言葉を間違って理解したり、理解したくでも理解できないままでいることであろう。聖徒である我々は真摯に祈るべきである。そうすれば神がキリストの御言葉を必ず正しく理解できるようにして下さるからである。もし真摯に祈るというのであれば確かにそのようになる。真摯に祈らない場合は、いつまで経ってもキリストの御言葉を理解できないままである。神は信仰をこそ喜ばれ、信仰のある者にこそ恵みを注いでくださる。。次のように書いてある通りである。『信仰がなくては、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを、信じなければならないのです。』(ヘブル11章6節)
実際はどうだったのか。紀元68年6月9日にキリストが再臨される時まで、ヨハネは生き残っていたのか、それとも生き残ってはいなかったのか。今の時代の聖徒たちであれば、ヨハネは再臨の時まで生き残っていたと考えるかもしれない。何故なら、伝承によればヨハネはトラヤヌス帝の治世(98年1月27日―117年8月8日)まで生きていたと言われているから。しかし、既に第3部でも書かれたように、この伝承はいかがわしく、聖書から容易に打ち砕くことのできるものである。私としては、ヨハネが再臨の時まで生きていたかどうかは「分からない。」と言う。何故なら、ヨハネが再臨の時まで生きていたのかどうか、聖書は何も教えていないからである。聖書から分からない事柄については「分からない。」というのが正解である。聖書で明白に教えられていないにもかかわらず、あたかも聖書で明白に教えられているかのように堂々と何かを語ることを、私は憎む。それでは、ヨハネは再臨が起きる時まで生き残っていることを望まれるほどにキリストから愛されていたのか。これについては「然り」と言うことができる。何故なら、ヨハネは『イエスが愛された弟子』(ヨハネ21章20節)だと書かれているからである。ヨハネが愛されていたのであれば、当然ながら再臨の起こる時まで生きているのを望まれていたはずである。しかし、そのように望まれていたからといって、再臨が起こる時までヨハネが生きていたと結論することはできない。何故なら、主からある事柄を望まれていたからといって、必ずしもその望み通りになるということではないからである。実際、神はイスラエルの子らが敬虔に歩むことを望んでおられたのに彼らは幾度となく堕落したのである。これは旧約聖書を読めば誰でも分かることだ。もし神の望まれたことを神が必ず実現されるというのであれば、敬虔であることを望まれていたイスラエルの子らが堕落することは決して無かったであろうし、人類を破滅させたアダムの堕落も起こらなかったであろう。何故なら神はアダムが御自身の御前に正しく歩み続けるのを望んでおられたからである。
第46章 44:使徒の働き
この文書には、見ておくべき箇所が幾つかある。再臨の理解を深めたいならば、この文書に書かれている再臨に関する箇所を無視することはできない。本章では、その箇所について註解される。
【1:8】
『しかし、聖霊があなたがたの上に臨まれるとき、あなたがたは力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、および地の果てにまで、わたしの証人となります。」』
『聖霊があなたがたの上に臨まれるとき』とは、この文書の2:1~21の箇所で記されているペンテコステの出来事を指す。これは紀元33年頃の出来事だから、既に実現されている。ここで次のような疑問を持たれる方がいるかもしれない。すなわち、ペンテコステの時に聖霊が注がれたのであれば以前は聖徒たちに聖霊がまだ与えられていなかったのであろうか、という疑問である。この時にならないと聖霊が聖徒たちに与えられない、というのはキリストも述べておられたことである。キリストはヨハネ16:7の箇所でこう言われた。『しかし、わたしは真実を言います。わたしが去って行くことは、あなたがたにとって益なのです。それは、もしわたしが去って行かなければ、助け主があなたがたのところに来ないからです。しかし、もし行けば、わたしは助け主をあなたがたのところに遣わします。』これは、つまりキリストが昇天して聖徒たちから離れられた後に、助け主であられる聖霊がペンテコステの日に聖徒たちに与えられることになる、という意味である。しかしながら、このペンテコステの日よりも前に、既に聖徒たちが聖霊を受けていたのは確かである。というのも、聖霊を受けていない限り、旧約時代の聖徒であれ新約時代の聖徒であれ、キリストを信じることは絶対に出来ないからである。キリストに対する信仰が聖霊によるものであるということに異を唱えるクリスチャンは一人もいないはずだ。実際、旧約時代の預言者たちは『キリストの御霊』を受けていたとペテロは言っている(Ⅰペテロ1:10~11)。詩篇51:11の箇所を見ると、ダビデも聖霊を受けていたことが分かる。ペテロがキリストに対して『あなたは、生ける神の御子キリストです。』(マタイ16章16節)と言ったのも、聖霊によらねば言えなかったはずである。確かに、ペンテコステの日よりも前から既に聖徒たちが聖霊を持っていたのは、今述べたことから明らかである。それでは、ペンテコステの日に初めて聖霊が聖徒たちに注がれるかのように言われたのは、一体どういうわけなのか。これは、つまりこういうことである。ペンテコステの日に聖霊が注がれると言われたのは、信仰を持つために初めて聖霊が与えられるということではなく、聖霊の豊かな現われがその時に初めて与えられるようになる、ということであった。そのような意味合いにおいて、キリストは聖霊が昇天後に注がれるであろう、と言われたのだ。この理解はカルヴァンの理解と同じ理解だから、私が何か自分勝手なことを独自に言っているなどとは思わないでいただきたい。確かに、ペンテコステの日になるまでは、御霊が目に見える形としては聖徒たちに現われていなかった。この日になると、聖霊とその御力が誰の目にも疑えないほど明瞭な形として、聖徒たちに現われることになった。これについては、この文書の2:1~21の箇所を見れば、すぐにも分かるであろう。
このように聖霊が臨まれると聖徒たちは『力を受け』る、とキリストはここで言っておられる。それは、例えば異言を語ったり、死者を蘇らせたり、障害者や病人を癒したり、瞬間移動をしたり、毒を飲んでも害を受けない、というのが正にそれであった。これが聖霊の力の現われでなかったとすれば、何がそれであると言えるであろうか。聖霊がその御力を聖徒たちのうちに発揮して下さるからこそ、このような素晴らしい業や出来事が聖徒たちを通して実現されることになるのである。
聖徒たちはペンテコステの日に聖霊を受けると、『地の果てにまで』キリストの証人となった。これはどういう意味か。これは、つまりイエスがキリストであるということの証し人となる、という意味である。簡単に言えば「ナザレのイエスこそ正に神が人として来られたキリストなのである。」という福音を伝えることが、そうである。当時の聖徒たちは、文字通り『地の果てにまで』キリストの証人となったと理解すべきである。何故なら、マルコ福音書の追加文では、福音が『東の果てから、西の果てまで送り届けられた』と言われているからだ。これは、つまり福音の宣教された地域が、単にユダヤ世界やローマ世界だけに留まらなかったことを教えている。「トマス行伝」によれば、トマスはキリストにインドまで送られて、インド人にキリストを宣べ伝えたという。この文書は外典に過ぎないから信頼には値しないものだが、しかしトマスによってであれその他の弟子によってであれ、インドにも伝道はなされたことであろう。インドよりも東の地域にある中国や日本にも福音は宣べ伝えられたことであろう。『地の果てにまで』聖徒たちがキリストの証人となったというのは、そういうことである。確固たる史実的・考古学的な証拠が無ければ、インドや中国や日本にまで伝道がされたことを信じないという人は、いっそのこと自由主義神学でも奉じるがよかろう。実際の証拠が無ければ御言葉で言われていることを信じないというのは、リベラルの人たちと一緒である。彼らは考古学の知識に基づいて聖書を解釈しており、愚かにも御言葉を世俗の学問の下に位置させている。我々はよく弁えるべきであろう。キリスト者とは、御言葉で言われていることを素直に受け入れて信じる人たちであるということを。
【1:9~10】
『こう言ってから、イエスは彼らが見ている間に上げられ、雲に包まれて、見えなくなられた。イエスが上って行かれるとき、弟子たちは天を見つめていた。』
ここでは紀元33年頃に起きた昇天のことが言われている。この出来事が起きたのは『オリーブという山』であった。その山は『エルサレムの近くにあって、安息日の道のりほどの距離で』(使徒行伝1章12節)であった。この昇天の出来事を見ていたのは、11人の使徒たちである。それは、この文書の中で言われているように、『ペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダ』(1章13節)である。つまり、使徒の全員がこの昇天を見ていた。この出来事については、マルコも福音書の最後の箇所(16:19)で書いている。マタイとヨハネは、その福音書の中の最後のほうで、キリストの昇天について何も書いてはいない。ルカの福音書の最後のほうの部分で言われているのは、文脈を考えれば、昇天のことだと思われる(24:51)。この24:51の箇所に、「そして、天に上げられた。」という文章が加えられている異本もある。旧約聖書では、詩篇24:7~10の箇所で、昇天のことが言われていると思われる。そこでは次のように書かれている。『門よ。おまえたちのかしらを上げよ。永遠の戸よ。上がれ。栄光の王がはいって来られる。栄光の王とは、だれか。強く、力ある主。戦いに力ある主。門よ。おまたちのかしらを上げよ。永遠の戸よ。上がれ。栄光の王がはいって来られる。その栄光の王とはだれか。万軍の主。これぞ、栄光の王。』これは、つまりキリストが昇天された際、天国にある門を通って父なる神のおられる天上の世界に入られた、ということであろう。その時、キリストは『王』として天国の門を通られた。キリストが王であられるというのは、キリストが『わたしには天においても、地においても、いっさいの権威が与えられています。』(マタイ28章18節)と言っておられることから分かる。天地における全ての権威を持っておられるというのは、つまり王でなくて何であろうか。キリストは、ピラトに対してもご自身が『王である』(ヨハネ18章37節)と言っておられる。このキリストが昇天の際に『雲に包まれ』たのは、キリストの権威を示している。既に述べたように、雲とは聖書では権威の象徴である。キリストは王であられるので、昇天の際には権威を示す雲の中へと上げられるのが相応しかったのである。
キリストは上げられる際、天のほうに上昇して行かれたのだが、天のほうに行かれたからといって、大気圏に行かれたというわけではない。キリストが行かれたのは、もちろん、この宇宙には属していない空間にある天上の世界であった。もしキリストが大気圏という意味における天に行かれたのであれば、地上から大空を見上げれば、その大空に座しておられるキリストが見えたかもしれない。しかし、そのようなことはなかった。だから、キリストは大気圏ではなく霊的な世界へと行かれたことになるのだ。我々は、聖書において天と書かれていた場合、その言葉には2通りの意味があることを忘れるべきではない。すなわち、大気圏という意味における天と、天上の世界という意味における天の2つである。もし前者の意味であれば後者の意味ではなく、もし後者の意味であれば前者の意味ではない。この箇所で言われているのは、言うまでもなく後者の意味においてである。
使徒たちは、キリストが上って行かれた天をその目で見つめていた。これは、キリストが再臨される際には、昇天された時と同じ有り様でやって来られるからであった。これについては11節目の箇所でまた後ほど論じる。
【1:10】
『すると、見よ、白い衣を着た人がふたり、彼らのそばに立っていた。』
この『ふたり』の人は、もちろん御使いである。しかし、読者の中には、これが御使いであるとは認めない人もいるかもしれない。「ここでは『人』と書かれているから、これは御使いではなく人間なのだ。」などと言って。だが、よく考えてみてほしい。この2人の人は、1:11の箇所を見れば分かる通り、使徒たちにそれまでは知らされていなかった再臨の詳細について伝えるために姿を見せたのだ。そのために現われた人は、御使いであると考えるのが自然である。しかも、この人たちの使徒に対する物の言い様は、普通の人間のそれではない。それだから、この2人の人は御使いであるとせねばならない。ルカ24:4~7の箇所でも、二人の御使いが『人』と呼ばれているから、我々が今見ているこの箇所で御使いが『人』と呼ばれていることを何か奇異に思うべきではない。この御使いたちが現われたのは、ただ再臨について使徒たちに伝えるためだけであった。もしそのような任務を持っていなければ、この御使いたちが現われていたのかどうか定かではない。
この御使いたちが『白い衣を着』ていたのは何故か。これは彼らの清らかさを示すためである。マルコ9:2~3の箇所では、キリストが山上で変貌された際、その御衣が非常に白くなったことが書かれている。これもキリストの清らかさを示している。また黙示録3:5の箇所でも、勝利した聖徒たちが『白い衣を着せられる』と約束されている。これも、やがて聖徒たちが完全な清らかさを持つようになる、という意味である。
では、この御使いたちが『ふたり』いたのは何故か。これは、今現在の私の考えでは、創世記の記述と関係があるのではないかと思われる。創世記では、アブラハムの前に3人の人が現われたことについて書かれている(18:2)。創世記19:1の箇所を見ると、この3人のうち、1人は主であり、他の2人は御使いであったことが分かる。この2人の御使いは、アブラハムと会見した後で、1人であった主から離れてロトのほうに行った。この2人の御使いが1人の主から遠ざかると、それから後、ソドムが火で焼き尽くされることになった(創世記19章)。それと同様に、使徒たちからキリストが離れて行かれると2人の御使いが彼らの前に現われ、それから後、ユダヤが火で焼き尽くされることになった(※)。主から離れた2人の御使いがロトという聖徒に会うとソドムが滅ぼされ、主が地上から去られた後で2人の御使いが11人の使徒という聖徒に会うとユダヤが滅ぼされた。ヨハネは、黙示録11:8の箇所でユダヤをソドムとして取り扱っている。このように、我々が今見ている箇所は創世記の記述と、よく似通っているように感じられる。それだから、我々が今見ている箇所で2人の御使いがキリストの昇天の後に姿を見せたのは、創世記の記述と関係している可能性がある。
(※)
ところで、アレイスター・クロウリーは、この火による破壊の悲劇が「キリスト紀元の1904年に実現した。」などと言っている(『アレイスター・クロウリー著作集 トートの書』アテュ ⅩⅩ.永劫 p129:国書刊行会)。彼は世界の終末について2つの思い違いをしている。一つ目は聖書が啓示している火を通しての終末は文字通りの全世界について言われていると考えている点、二つ目はその終末が1904年に訪れたと考えている点である。それだから彼の世界観にとっては1904年以降が、新しい世界、新しい時代、新しいパラダイムである。しかし既に説明されているように、聖書の啓示している終末とはユダヤ世界のことであり、それは紀元70年に実現している。読者は、クロウリーが述べたような類の見解に惑わされないように注意すべきである。
[本文に戻る]
【1:11】
『そして、こう言った。「ガリラヤの人たち。』
御使いたちは、使徒たちを『ガリラヤの人たち』と呼んでいる。これは使徒たちが、元はガリラヤの湖で漁師をしていたからである。しかし、定めの時が来るとキリストが彼らを選ばれたので、彼らは漁師の仕事を止めて使徒となった。これはマタイ4:18~22の箇所に書かれている通りである。だからこそ、彼らは『ガリラヤの人たち』などと呼ばれたのである。彼らはペンテコステの日に集まって来た人々からも、『この人たちは、みなガリラヤの人ではありませんか。』(使徒行伝2章7節)と言われている。それでは、もし使徒たちが例えばエルサレムで働いていたとすれば、ここで御使いは「エルサレムの人たち。」などと呼んでいたのであろうか。これはその通りである。いかなる地域で働いていたにせよ、御使いは、使徒たちが前に働いていた地域の名において使徒たちに話しかけていたことであろう。
『なぜ天を見上げて立っているのですか。』
ここで御使いは次のように言いたいかのようである。「おや、一体どうしたというのか。君たちは昇天されたキリストを見ているが、ただぼうっとして見ていたに過ぎないのではないのか。その昇天が再臨とどのように関わっているのか悟っていないのではないのか。恐らく、君たちのことだから、悟ることはできていないことであろう。よろしい。今、私たちがそのことについて君たちに示そう。君たちは、そのことを聞いて、それを信じるべきである。」御使いはこのように言いたかったと私は推測するが、このすぐ後、御使いは再臨について今まで知らされていなかったことを使徒たちに伝えている。すなわち、次のように御使いは再臨について言った。
『あなたがたを離れて天に上げられたこのイエスは、天に上って行かれるのをあなたがたが見たときと同じ有様で、またおいでになります。」』
ここで御使いが言っているのは、キリストは昇天されたのと同様の状態で再臨されるという預言であった。これは今までに知らされたことのない再臨の様子であった。つまり、この時、聖徒たちには更に再臨に関する詳細が開示されたことになる。使徒たちがキリストの昇天をその目で見るようにされたのは、実に、これが理由であった。すなわち、当時の使徒たちが再臨をシッカリと確認するためにこそ、使徒たちは昇天の光景を見せられた。使徒たちが昇天の光景を見るからこそ、再臨されたキリストが昇天されたのと同一のキリストであったことが確認されることになる。もし昇天を見せられた者がいなければ、キリストが再臨された時、そのキリストが昇天されたのと同一のキリストであるかどうか誰一人として確認できない。「あれは本当に昇天されたキリストなのか。」などと言い出す人も現れかねない。それは神の御心に適わないことであった。何故なら、聖書が示しているように、神とは事柄がシッカリと確認されることを好まれる御方だから(創世記6:5、12、11:5、18:21)。この時の場合、神がご自身で確認されるのではなく、使徒たちに確認をさせたのである。というのも、これが神の側から実現される現象だから、人間が確認するのが理に適っているからである。それだから、この昇天の出来事を見た使徒たちのうち、最低でも2人または3人の使徒が、紀元68年6月9日に起きた再臨の光景をその目で見たはずである。何故なら、律法やパウロが言っているように、全ての事柄は2人または3人の目によって確認されなければいけないからだ(申命記19:15、Ⅱコリント13:1)。すなわち、2人か3人の目で確認されなければ、確認されたとは見做されないのである。タルムードの中で「3人の証言は1000人の証言と同等の意味を持つ。」と言われているのは、間違っていない(ネズィキーンの巻:シュヴオート篇)。昇天を見たこの11人の使徒のうち、どの使徒が実際に再臨を見たのかは分からないが、恐らくパウロとペテロとヤコブは見なかったと思われる。というのも、この3人は再臨の起こる紀元68年までに殉教したと考えられるからである。パウロとペテロは伝統的にネロの迫害時に殉教したと言われてきたし、ヤコブはネロの迫害が起こる前に殉教したとエウセビオスの本には書かれている。このことから、やはり再臨は紀元1世紀に起きていたことが分かる。何故なら、使徒たちに対して再臨のキリストは昇天された時と同様の状態で来られると言われたのだから、そのように言われた使徒たちは実際に再臨の光景をその目で見たはずだからである。もし使徒の時代において使徒たちが再臨を見なかったとすれば、いったい誰が、再臨されたキリストは昇天された時と同じ姿だったと証明できるのか。誰も出来ない。何故なら、昇天をその目で確認したのは11人の使徒だけだったのだから。使徒が再臨を見たというこの理解は、再臨は紀元1世紀に起きたと教えている聖書の内容と適合しているから、何もおかしい理解ではない。ここまで読み進められた読者であれば、もうこのこと、すなわち再臨は紀元1世紀に起きたと教えている聖書の内容のことは十分に分っているはずだ。
我々は、キリストが、実際に昇天されたのと同一の状態で再臨されたと信じるべきである。スピノザのように、キリストは幻影のような状態であったと考えてはならない。確かなところ、キリストは幻影としてではなく、物理的な生命体としての状態により再臨された。キリストが昇天時と同様の状態で再臨されたことを受け入れない人は、神に喜ばれない。神は御言葉で言われていることを拒絶する人を、嫌われるからである。
キリストが再臨された場所も、昇天されたのと同じ場所、すなわちオリーブ山であった(※)。これはゼカリヤ書14:4の箇所を見れば分かる。再臨と昇天が一緒の場所に定められたのは、神の誠実さがよく現われていると私には思える。なお、キリストが再臨された場所は、黙示録16:16で書かれている『ハルマゲドン』ではなかったことに注意せねばならない。この場所は、再臨が起こる場所ではなかった。この場所は、単にキリストの再臨が起こる際には霊的な戦いが起こるということを示すために引き合いに出されたに過ぎない場所である。
(※)
このオリーブという名の山は使徒行伝1:12の箇所によれば、『エルサレムの近くにあって、安息日の道のりほどの距離であった』。タルムードでは、この場所について次のように書かれている。「イスラエルの長老たちは、オリーブ山へ徒歩で先立った。そして、そこには浸水礼の家があった。」(『タルムード トホロートの巻』パラー 第3章 34b ミシュナ7 p171:三貴)この浸水礼の家は、死体の汚れを受けないように空洞の上に建てられていた。ラビたちや一般のユダヤ人が、この山に行って自分の汚れを洗い清めていたのである。
[本文に戻る]
多くの教師たちは、このこと、すなわちキリストが既に昇天時と同様の状態で再臨されたという理解に、躓いてしまう。何故か。それは、そのようなことは考えられないからである。どうして考えられないのか。それは今までに誰一人として、そのようなことを言ってはいなかったからである。ここに驚くべき、そして嘆くべきキリスト教界の状況が見られる。今の教師たちは、御言葉がどう教えているかということではなく、今までにどう言われてきたかということを心配してしまっている。教師たちは、聖書が再臨は紀元1世紀の時に起きたと教えているということ自体を認めはする。何故なら、確かに聖書の言葉では、そのように教えられているからだ。もしこれを認めなければ、聖書の言葉に立ち向かわねばならなくなる。しかし、教師たちは御言葉で言われていることを認めはするものの、結局は今までにそんなことは言われてこなかったという理由から、御言葉で教えられていることを受け入れないという結末に至る。彼らはこう言うのだ。「もしそれが本当のことだとすれば一体どうして今まで誰もそのことについて言ってこなかったのか。」などと。ところが彼らはルターに対しても、このように言われたことを忘れてしまっている。ルターも正しいことを聖書から教えたのに、「それが真理ならばどうして今まで何もそのことについて教えられてこなかったのか。神が今まで教会に聖書の真理を隠して来られたとでもいうのであろうか…。」などとカトリック陣営から言われたものである。私の思うところでは、今の教会は御言葉など別にどうでもよいというような状態になっているのではないか。そうでなければ、どうして女性牧師のいる教会が多く見られたり、少なからぬ数の教会がディスペンセーショナリズムや進化論やバルト主義やエキュメニズムなどを受容しているのか。もし御言葉を切に希求していたとすれば、女性牧師のいる教会など見られなかっただろうし、おかしな教義や思想を受け入れている教会も無かったことであろう(※)。今の教会が御言葉を切に希求できていないというのは、今の教会が世俗化の悩みを抱えていることからも分かる。この世俗化は今の教会における最大の問題の一つと言ってよいと私は思うが、世俗化しているというのは、つまり御言葉に密着できていないということでなくて何であろうか。何故なら、御言葉に密着できていたとすれば、世俗の波に呑まれることなど起こらないはずだからだ。私が神の恵みにより述べている再臨の真理を受け入れようとしないのも同じである。すなわち、今の教会は御言葉が再臨についてどのように教えているのかということよりも、周りの教会の目や教会における常識のほうが大事なのである。もしそうでなければ、今頃もっと多くの人が、この作品の中で教えられている再臨の事柄を喜んで受容していたことであろう。
(※)
<このうちエキュメニズムについて>:昨今においては近代主義が猛威を振るっているのだから、反エキュメニズムの姿勢に立ち、教派間における離別を堅持している場合ではない、などと思われるであろうか。皆で一緒に共闘しなければ一体どうして近代主義の攻撃に対処できるのか、と。少なからぬ数の牧師がこう思うかもしれない。実際、今現在は多くの教会がカトリック陣営に前ほどには抵抗を抱かなくなっており、多くの教会が使用している新共同訳聖書がその証拠の一つである。近代主義を打ち砕くためにはカトリックとの協力体制も辞すべきではない、というのは一見するともっともらしく感じられなくもない。アブラハム・カイパーもこのような意見を持っていた。だが口を慎むがよい。何としてもカトリックと肩を組んで協同するわけにはいかない。たとえ近代主義と対抗する目的があっても、である。エキュメニズムを受容している牧師は、カトリックにフリーメイソンが多く巣くっていることを恐らく知らないのであろう。歴代の教皇であれば知っているように、カトリックの上位層には多くのフリーメイソンが忍び込んでいる。教皇ヨハネ・パウロはこの上位層にいるフリーメイソンたちを排除しようとしたので、陰謀により殺された。最近では、彼らの息のかかった者が教皇になったほどである。驚くなかれ、イルミナティカードで描かれていたのと同様の人物が教皇になったのである。教皇の位階でさえユダヤの陰謀家が攻略できているというのは、カトリックの全体が既に乗っ取られていることを意味している。何故なら、教皇の位階ほど攻略が困難なカトリックの場所はないからである。私が前々から言っているように、このグループは宗教改革の時に捨てられて、教会ではなくなったのである。ルターがカトリックを「サタンのシナゴーグ」と言ったその時には既にカトリックは捨てられていたのである。だからこそ、サタンの手下に乗っ取られることが許されたのである。何故なら、教会ではないということは、すなわちサタンの陣営に属しているということを意味するからである。そのようなサタンの陣営におけるトップに、サタンの手下によって定められた教皇が就いたとしても何の不思議があろうか。このようなことを知っていれば、とてもじゃないがカトリックと協同することなど出来ないのである。私は言うが、もしカトリックと協同すれば、必ずや霊がその純粋さを保てなくなるであろう。ソロモンも言うように『鉄は鉄によってとがれ、人はその友によってとがれる』(箴言27章17節)のであり、パウロも言うように『友だちが悪ければ、良い習慣がそこなわれ』(Ⅰコリント15章33節)るのだから。また私は疑問に感じるのだが、「カトリックと協同しなければどうして敵に打ち勝てようか」とか「今はこのような時期なのだからカトリックを毛嫌いしている場合ではない」などと言う人たちは神の力を知らないのであろうか。ぜひ口を慎んでもらいたい。神は、我々がたった一人しかいなかったとしても、敵の勢力を一撃で粉砕できる御方であられる。いや、我々がたとい0人しかいなかったとしても、神は敵を造作なく打ち負かすことがお出来になる。神が『くまばち』か何かで敵の陣営をかき乱されたならば、我々が何もしなかったとしても、敵の陣営は自然と勝手に追い払われるのだ(出エジプト23:28)。ヨナタンとその道具持ちは、たったの2人だけで敵の大軍勢を打ち破ったのではなかったか。その時、ヨナタンは『大人数によるのであっても、少人数によるのであっても、主がお救いになるのに妨げとなるものは何もない。』(Ⅰサムエル14章6節)と信仰の声を出したのではなかったか。それなのに、今の教会がカトリックの力を借りてまで数の強さに頼るとは一体どうしたのか。カトリックがいないと近代主義は打ち砕けないのか。神こそが問題を解決して下さる御方なのではないか。偽物の教会と手を組んで神の力が我々に与えられるとでも思っているのか。エキュメニズムに賛成の牧師には少し考えてもらいたい。エキュメニズムなどに力を求めても、意味はない。現にエキュメニズムを首肯している教会が多く見られる今の時代においても、近代主義はぜんぜん打ち砕かれていないではないか。むしろ、こんな思想を多くの牧師たちが受容しているゆえ、今の教会の霊性はどんどんと引き下げられていくばかりである。
[本文に戻る]
今の教会はこのような状況であるが、もしこれから多くの教師たちが再臨の真理を受け入れたならば、プロテスタント界は新しいステージに入ることであろう。天動説が地動説に切り替わったようなパラダイムの変革が起こる。その時、私の予測では、教会がかつて古代教会や宗教改革時代の教会の持っていたような霊性を取り戻すはずである。そうなれば、教会が大いに活発になり、豊かに栄えるようになるに違いない。何故なら、御言葉が受容されるところにこそ、全能の神は豊かに働いて下さるからである。とはいっても、これからプロテスタント界がどうなるかは、神だけが知っておられる。私としては、多くの教師たちが、この再臨の真理を理解し受け入れるようになってほしいと願っている。どうか神が、多くの教会に再臨の真理を豊かに悟らせて下さるように。アーメン。
【3:20~21】
『それは、主の御前から回復の時が来て、あなたがたのためにメシヤと定められたイエスを、主が遣わしてくださるためなのです。このイエスは、神が昔から、聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られた、あの万物の改まる時まで、天にとどまっていなければなりません。』
ここでは『主の御前から回復の時が来』ると、キリストが天から再臨されると言われている。これについては、パウロもローマ11:25~27の箇所で言っている。この再臨は、紀元68年に起きた。それゆえ、再臨の際に実現されるユダヤの回復も既に実現されている。この『回復』されるユダヤとは、すなわち再臨の際に救われた少数のユダヤ人を指している。彼らは救われて天国に導き入れられたが、そこにおいてユダヤが回復されたのである。それでは今現在のユダヤ人はどういう存在なのか。彼らは、再臨の際に遺棄されたユダヤ人の子孫である。彼らの先祖たちは、再臨の際に神に不適格な者と見なされたので、裁きを受けて完全に捨てられてしまった。彼らは遺棄される種類のユダヤ人たちであった。聖書は、明らかに再臨の際には救われるユダヤ人と捨てられるユダヤ人の2種類が存在すると教えている。これはルターも述べていることだ。この箇所で言われているのは救われるほうのユダヤ人のことである。それだから読者は、再臨が起きた際には全てのユダヤ人が回復されるなどという空想を持たないように気をつけるべきである。
これまで多くの教師たちが、これからユダヤは再臨が起こる時期に民族的な大回心の恵みを受けるようになるなどと考えてきた。もし再臨がまだ起きていなかったとすれば、このような考えは退けられるべきではなかった。何故なら、我々が今見ている箇所もそうだが、確かに聖書は再臨が起こる時か再臨の起こる前の時期にはユダヤの回復が起こると教えているからである。だが、既に再臨は起きている。よって、これからユダヤの民族的な大回心が起こるなどと考えるのは大きな間違いであることが分かる。ユダヤの回復は既に紀元1世紀の時に実現されたのだから。紀元1世紀にユダヤが捨てられた際には、天で『ハレルヤ。彼女の煙は永遠に立ち上る。』(黙示録19章3節)などと言われた。これは、つまりユダヤはもう神の御前から完全に断絶されたままの状態でい続けるということだ。何故なら、捨てられたユダヤの煙は永遠に立ち上るのだから。そのようなユダヤにおける生き残りの者たちが、これから回復の恵みに与かるようになるはずが、一体どうしてあるのであろうか。
それでは、ここで『神が昔から、聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られた、あの万物の改まる時』というのは、旧約聖書のどこの箇所に書かれていることなのか。それは、例えば次に挙げる箇所がそうである。イザヤ65:17~25。―この箇所では再臨が起こると天において新しい世界が到来するということが言われている。エゼキエル40~48章。―ここでも天上において創生される神聖な世界についてのことが書かれている。マラキ4:1~3。―ここでは再臨の時には巨大な変革が起こるということが預言されている。
【14:22】
『私たちが神の国にはいるには、多くの苦しみを経なければならない。』
ここで言われている『神の国』とは天国のことである。すなわち、これは地上世界のことではない。この場所については、既に見た黙示録21:1~22:5の箇所で詳しく描かれている。
パウロは、ここで聖徒たちが天国に入るためには『多くの苦しみを経なければならない』と言っている。我々は、紀元68年にキリストが再臨されてから天国が開始される、ということを弁えねばならない。この再臨が起こる前には、ネロの大患難という苦しみが聖徒たちに襲いかかることになっていた。この苦しみに耐えないと、その人は天国に入ることができなかった。何故なら、ネロの暴虐に屈した人は、すなわち信仰から脱落したことを意味するので、キリストが再臨された際に携挙されなかったからである。携挙されない、というのは、つまり天国に入れない、ということに他ならない。当然ながら、この苦しみに耐えた聖徒たちだけが、再臨の際に携挙され、その後、天国に導き入れられることになる。だからこそ、パウロはここで天国に入るまでには多くの苦しみがある、と言ったわけである。つまり、ここでパウロが言っているのは、やがて実現されるキリスト教徒に対する大迫害を念頭に置いている。パウロはダニエル書7:25~27の箇所を読んで、天国が開始される前には荒らす憎むべき者が『いと高き方の聖徒たちを滅ぼし尽くそうとする』(7章25節)のを知っていたので、その苦しみについて、ここでこのように予め言ったのである。
ここでパウロが言っていることの直接的な対象は紀元1世紀の聖徒たちであったが、ここで言われていることは、我々に対しても言われていると捉えるべきである。何故なら、あらゆる聖徒たちは、多かれ少なかれ信仰の苦難を受けるからである。我々のうちの多くは、紀元1世紀の聖徒たちが受けたような大迫害は受けないかもしれない。中には紀元1世紀の聖徒が受けたのに匹敵するほどの迫害を受ける聖徒もいるかもしれないが、キリスト教が一般的な宗教となっている今の時代において、そのような聖徒はそこまで多くはいない。だが、小さな苦難であれば、どの聖徒も必ず受けることは確かである。というのも、神の子たちには、例外なく信仰の苦難が神から与えられるものだからである。ヘブル書ではこう言われている。『訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなたがたを子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなたがたが、だれでも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生子であって、ほんとうの子ではないのです。』(12章7~8節)だから、もし信仰の苦難を受けない聖徒がいたとすれば、その人は多分、神の子ではないのであろう。このようにどの聖徒であっても必ず信仰に伴う苦しみを受けるものだから、ここでパウロが言っていることは、今の我々に対しても向けられていると捉えねばならない。
『神の国』という言葉について、注意しておかねばならないことがある。これまで多くの教師たちは、この『神の国』という言葉を、神が支配される王国としてのクリスチャンという意味を持つ言葉として度々使ってきた。これはカルヴァンが特にそうである。彼が『神の国』と述べているのは、そのほとんどが「神の支配」という意味合いにおいてであった。彼がこの言葉を「天国」という意味で使うことは、あまりない。ルターが「キリスト者は御国が広がることを喜ぶ。」と言ったのも、そのような意味においてである。これは、つまり神が御国として治められるキリスト者の数が地上に満ち広がる、ということである。このような意味として『神の国』という言葉を理解したり使用したりするのは、誤りではない。何故なら、確かに聖徒たちとは、聖書が教えているように神の『王国』(黙示録1章6節、出エジプト19章6節)なのだから。しかし、我々が今見ているこの箇所では、そのような意味においてこの言葉が使われているのではない。ここでは徹底的に天国という意味で、この言葉が使われている。何故なら、ここではまだ聖徒たちが神の国に入っておらず、これから入るということが言われているからだ。これは、ここでは天国について言われているからに他ならない。つまり、これから天国に入ることについて言ったからこそ、ここではこう言われている。もしこの箇所で『神の国』という言葉が神の支配という意味で使われていたとすれば、ここではこのようなことが言われてはいなかったであろう。何故か。それは、神の支配という意味における『神の国』であれば、聖徒たちは既に救われた時点で神の国に入っているからである。
【24:15】
『また、義人も悪人も必ず復活するという、この人たち自身も抱いている望みを、神にあって抱いております。』
パウロがここで言っている復活は、もう既に起きている。この復活は、義人と悪人において、それぞれ順序が異なっている。まず第一に復活したのは義人である。これは紀元68年6月9日に起こった。悪人の復活は、義人が復活してから後ほど経って起きた。それは紀元70年9月のことである。
ここで言われている復活が、未だに起きていないと理解することはできない。何故なら、パウロはⅠテサロニケ4:16~17の箇所で、紀元1世紀のテサロニケ人が『生き残っている』間に死者の復活が起こると言ったからである。私がこのように言うと、誰も反論できない。というのも、確かにパウロは紀元1世紀のテサロニケ人が存命中に復活が起こると言っているからである。それだから、私がこのように言っても、自分の考えを捨てず、未だに復活は起きていないと考え続けるのであれば、その人はパウロとパウロを通して語られた聖霊に逆らうことになる。思慮ある読者は、御言葉の明白な教えを拒絶しないように注意せよ。御言葉で言われている教えを素直に受け入れることこそ真の信仰を持っている印だからである。私の言ったことを無視する人たちは、自分が御言葉に対する信仰を持っていないと暗黙のうちに告白しているのだ。
ある者は、ここで言われている復活のうち、『義人』の復活が既に起きたことは認めている。何故なら、パウロがⅠテサロニケ4:16~17で、既に聖徒の復活は起きたと我々に教えているからである。また、この者が既に義人の復活は起きたと考えているのは、今が黙示録20:1~6の時代であると勘違いしているからでもある。確かに、黙示録20:1~6の箇所では聖徒の復活について語られている。しかし、この者は、『悪人』の復活については未だに起きていないとする。何故なら、悪人の復活とは第二の復活であって、それは黙示録20章によれば『千年』の期間が終わらない限り実現しないからである。確かに、今が黙示録20:1~6の時代だとするならば、このように考えるしかない。この立場の場合、悪者の復活が既に起きたと考えるのは絶対に不可能である。私はそのことを認める。だが、この者の見解は聖書そのものから否定される。何故なら、既に述べた通り、黙示録に書かれている出来事は全て『すぐに起こるべき事』であって、『千年』というのはその期間における質の完全性を示す言葉に過ぎないからである。だから、我々は既に『義人』の復活が起きたのと同様、『悪者』の復活も起きたとせねばならない。この者がまだ悪者の復活は起きていないと考えているのは、無知と研究不足に基づく誤りである。この者とその追従者たちは、聖句に対する密着度がまだまだ足りないと私には思われる。アウグスティヌスやカルヴァンといった昔の優秀な神学者たちは、もっと聖句に密着し、徹底的に聖句の正しい解明に心を傾けたものである。
第47章 45:ローマ人への手紙
ローマ人への手紙は、幾つか見ておくべき箇所がある。とはいっても、この文書全体は、それほど心を向ける必要がない。
【1:8】
『まず第一に、あなたがたすべてのために、私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。それは、あなたがたの信仰が全世界に言い伝えられているからです。』
ここでパウロが言っているローマ人の持つ信仰とは何か。これは、もちろんキリストの福音に対する信仰に他ならない。この信仰が、『全世界に言い伝えられている』とパウロは明白に言っている。つまり、パウロがこの手紙を書いた時代に既にキリストの福音は全世界に満ち広がっていた。というのも、ローマ人の持つ信仰が世界中に知れ渡るというのは、つまりキリストの福音が世界中に知れ渡るということを意味しているからである。なお、ここで言われている『全世界』という言葉は文字通りに捉えるべきである。何故なら、聖霊を受けた紀元1世紀の弟子たちは、キリストが言われたように『エルサレム、ユダヤとサマリヤの全土、および地の果てにまで、わたしの証人とな』(使徒行伝1章8節)ったからである。キリストは『地の果てにまで』弟子たちがキリストの証人となると言われたのだから、当時においてキリストの福音が満ち広がっていたその範囲はローマ世界やユダヤ世界にだけ限定されるべきではない。
パウロは、ローマ人の信仰が世界中に知れ渡っていることを、神に感謝していた。何故なら、ローマ人の信仰が世界中に知れ渡るのは、福音の前進にとって大きな宣伝の効果を果たすからである。ローマ人がキリスト信仰を持っているということほど、当時にあってキリスト教のPRとなるような事柄は、他に無かったと言ってよい。というのも、ローマ人とは当時の西洋社会にとって最も有名で力がある国民だったからである。これは今の時代で例えるならば、最高クラスに有名で影響力のある支配者や芸能人の多くが、キリスト教徒になったようなものである。もしそのような者が多くキリスト信仰を持ったのであれば、それだけ一般大衆がキリスト教に心を靡かせるようになるのは間違いない。何故なら、「あのような人たち」がキリストを信じているからである。日本で言うのであれば、天皇とその一族がそうである。そうなれば、多かれ少なかれ信者の数が増えるようになるのは確かだと思われる。昔から一般大衆とは偉大であったり素晴らしかったり大きな支配力を持っている者に影響を受けやすいからである。このようになるのは、大変に良いことである。何故なら、そのようになれば、それだけキリストの勢力が繁栄することになるからだ。パウロは言うまでもなくキリストの勢力が繁栄することを望んでいた。それゆえ、このパウロは、純粋な動機からでなく福音が宣べ伝えられることさえ喜んだほどであった(ピリピ1:15~18)。だからこそ、パウロは最もキリストをPRする効果を持った国民であるローマ人の信仰が、『全世界に言い伝えられている』ことを喜び、神に感謝していたのである。実際、パウロはローマ人の信仰が世界中に知れ渡ることの効果と益を、経験的に感じ知っていたのであろう。だからこそ、パウロは神にそのことを感謝していたのであろう。パウロがローマ人にだけこう言ったのは、これが理由であった。彼は他の手紙では、このようなことを何も言っていない。今の時代においても、力のある人たちがキリスト教信仰を持っていると知れ渡るのは、福音の前進にとって間接的な効果をもたらす。その人が力を持っていれば持っているほど、またそのような人が多くいれば多くいるほど、そうである。何故なら、人が力のある人たちから影響を受けるというのは、今も昔と変わらないからである。とはいっても、そのような力のある人たちは、なかなかキリストの救いに招かれることがない傾向を持っているのではあるが…。
既にパウロの時代において世界中にキリストの福音が知れ渡っていたからこそ、パウロの時代にユダヤの終わりの日が訪れ、再臨が起こることになったのである。というのも、福音が世界中に満ち広がるとユダヤの終わりと再臨が実現されるというのが、神の決定だったからである。これについてはコロサイ1:6の註解箇所で再び論じられる。
【8:18】
『今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに啓示されようとしている栄光に比べれば、取るに足りないものと私は考えます。』
ここでは、この地上における諸々の苦しみは、やがて天国にて与えられる素晴らしい幸いを考えるならば、ぜんぜん何でもない、ということが言われている。どうしてそうなのか。それは、天国の幸いが、あまりにも巨大だからである。この天国における幸いを海だとすれば、地上における苦難は砂粒一つぐらいなものである。それゆえ、天国の幸いに目を留めるならば、この地上での苦しみは無に等しいということになるのだ。これは難関大学に入ろうと必死に勉学に励む受験生に似ている。彼にとって、憧れの大学で生活できることを考えれば、今の時の苦しみなどは取るに足りないと感じられるのである。ここで『今の時のいろいろの苦しみ』と言われているのは、地上における苦しみの全てを指す。『将来私たちに啓示されようとしている栄光』とは、天国で受ける輝かしい至福を指す。なお、この箇所ではパウロが自分個人の考えを表明しているように感じられる。それはパウロが『…と私は考えます。』と言っているからだ。確かにパウロは、この箇所で自分の考えを示している。しかし、我々はこのパウロ個人の見解を、真理に適った見解として受容すべきである。何故なら、ここでパウロが言っていることは確かにその通りであり、明らかに御心に適った考えだからである。
【8:19】
『被造物も、切実な思いで神の子どもたちの現われを待ち望んでいるのです。』
『被造物』とは、諸々の創造物を言っている。もちろん、この箇所においては、聖徒たちはこの言葉の中に含められていない。それは、後に続く箇所を見れば明らかである。昔の教父らは、この『被造物』という言葉が聖徒たちだけを指していると捉えていた。これは明らかに間違っている。
『神の子どもたち』とは、パウロやテモテやローマ人といった地上における聖徒たちである。これは、少し前の箇所を見れば分かる。8:14の箇所ではこう言われている。『神の御霊に導かれる人は、だれでも神の子どもです。』8:16の箇所でもこう言われている。『私たちが神の子どもであることは、御霊ご自身が、私たちの霊とともに、あかししてくださいます。』この2つの箇所で言われているのは、明らかに地上にいる聖徒たちのことである。だから、我々が今見ている箇所で言われているのも、地上にいる聖徒たちとせねばならない。もちろん、天上にいる聖徒たちも『神の子どもたち』ではある。これは言うまでもないことだ。しかし、この箇所においては、『神の子どもたち』と言って地上にいる聖徒たちだけを指している。つまり、ここで天上の聖徒たちは念頭に置かれていない。それだから、我々は、ここで天上の聖徒のことが言われているなどと間違って理解しないように注意せねばならない。
『現われ』るとは何か。これは、そう難しいことではない。これは、つまりこの地上において真の聖徒たちが現われ、増えることを言っている。例えば、ある人がノンクリスチャンから真のクリスチャンに変えられたとする。ここにおいて、この地上には一人の神の子どもが『現われ』たことになる。どうだ、シンプルで分かりやすいであろう。
さて、どうして被造物たちは地上において聖徒たちが現われるのを待ち望んでいるのか。聖徒たちが増えると、被造物にとって何がよいのか。その理由は、聖徒たちが増えると、被造物が善用されるので神のために大いに活かされるようになるからである。これは神のためにこそ創造された被造物にとって誠に喜ばしい。だから、ここでは聖徒たちの現われを被造物が待ち望んでいると言われている。このことについては、また後ほど説明される。
【8:20】
『それは、被造物が虚無に服したのが自分の意志ではなく、服従させた方によるのであって、望みがあるからです。』
『被造物が虚無に服した』とは、つまり被造物がアダムの堕落に巻き込まれた、という意味である。それは被造物にとって虚しさに陥ることであった。何故なら、神の栄光のために活かされないのであれば、被造物からは本質が抜け落ちることになるからである。周知の通り、被造物は神の栄光のために活かされるためにこそ創造されたのだ。これを何かに例えるとすれば、中に入っていた大量の財貨が既にことごとく抜き取られてすっからかんとなった宝箱である。被造物がこのように堕落に巻き込まれたのは、神の摂理によった。つまり、被造物は強制的に知らず知らずのうちに虚無に服せしめられた。パウロがこの箇所で言うように、被造物自身は、堕落する意思などまったく持ち合わせてはいなかった。これは、道端に咲いているタンポポが、歩行者の足によって強制的に踏み折られてしまうようなものである。
確かに被造物は自然とアダムの堕落に呑み込まれてしまった。このため、神は被造物に対して寛大な態度を取られる。すなわち、被造物は神の栄光のために再び活かされることが出来るという望みを大いに持つことができる。これは、原爆の被害を受けた日本人が、無償で国から治療の援助を受けられるようなものである。サタンの場合、自らの意志によって堕ちたので、回復の望みはまったくない。それゆえ、神はサタンに対して塵ほどの憐れみも持たれない。同様に人間も自らの意志により神から背いたので、選ばれたごく一部の者を除いては、救われる望みがない。これこそ、いつの時代にも救われるようにと選ばれている人がごく少ない理由である。人間は、神から背いたので、滅びるのが当然なのだ。それだから、「神は信じる者しか救われず、不信仰な者は全て地獄に投げ落とされるという話だが、こんな酷い話が他にあるだろうか。」などと喋り散らす愚か者は、まったく事柄を弁えていない。そもそも人間はアダムにおいて自ら神から離れ去ったのだから、地獄に投げ落とされるのが当然なのであって、本来であれば救われるなどというのはまったく考えられないぐらいのことだったからである。自分で神から離れたにもかかわらず、このような批判を神にぶつける者は、正に狂気沙汰に陥っているとしか言いようがない。
【8:21】
『被造物自体も、滅びの束縛から解放され、神の子どもたちの栄光の自由の中に入れられます。』
先に述べたように、地上に聖徒たちが現われると、被造物は聖徒たちを通して神の栄光にうちに活かされるようになる。それは、食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を現わすためにすべき聖徒たちが(Ⅰコリント10:31)、被造物を神のために用いるからである。それは被造物にとっては『滅びの束縛から解放され』ることに他ならない。何故なら、それは被造物が原初の幸いを取り戻すことだからである。不信者たちの場合、被造物はどのようにしても滅びの束縛から解放されない。不信者は霊的に死んでおり、未だに神と敵対しているからである。そのような者たちが、被造物を神のために用いることなど天地が逆さまになっても出来ないことである。被造物は、聖徒が用いてこそ、神の栄光のうちに活かされ回復されるようになる。だから、この地上に現われた神の子どもたちである我々は、被造物が回復するようにと、大いに神の栄光を求めて被造物を善用せねばならない。これこそ聖徒たちのこの地上における使命の一つである。そのようにするのは主に喜ばれることである。
今まで多くの教会が、ここで言われているのは再臨の時に万物が回復されることだと考えてきた。すなわち、キリストが再臨されると全てが回復し、被造物は滅びに至る運命から解き放されると。私はこの見解をよく知っている。だが、この見解は間違っている。何故なら、もうキリストの再臨は既に起きたからである。この箇所では、ただ地上に聖徒たちが現われると、それに伴って被造物が神の栄光のために活かされる、ということが言われているに過ぎない。つまり、ここでは地上のことが言われている。この私の見解のほうが、これまでの見解よりも正しい。何故なら、この辺りの箇所をよく読んで考えて見るとよい。ここでパウロは、この地上において『神の子どもたちの現われ』が起こると一体どうなるのか、ということを言っているのだ。
【8:22】
『私たちは、被造物全体が今に至るまで、ともにうめきともに産みの苦しみをしていることを知っています。』
被造物は、新約時代になるまで4000年の間、妊婦のように苦しみ悩んできた。何故なら、本来は神のために使われるようにと創造されたにもかかわらず、そのような状態から遠ざけられていたからである。これは被造物にとっては大変に辛いことであった。それは例えるならば、願っていた家や車が遂に手に入ったのに、それを使用することがまったくできないようなものである。新約時代になるまで、被造物が神の栄光のために用いられるのは、ユダヤ人と彼らの地においてだけであった。だが、新約時代になると、被造物は回復の望みを抱けるようになった。それは新約時代になると、あらゆる地域に住んでいる民族が神の民となれるようになったからである。それ以降、被造物は地球の全土において聖徒たちの栄光の自由に入れられることになった。すなわち、どこかの地に聖徒が存在していれば、その地において被造物は回復の期待を大いに持つことが出来るのである。真の聖徒であれば、被造物を神の栄光を目的として用いるだろうからである。この期待は、妊婦がやがて子どもの誕生を期待するのと一緒である。
【8:23】
『そればかりでなく、御霊の初穂をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら、子にしていただくこと、すなわち、私たちのからだの贖われることを待ち望んでいます。』
『御霊の初穂をいただいている』とは、どういった意味か。これは、御霊を受けているので復活の約束が与えられている、という意味である。何故なら、御霊が与えられたということは、やがて復活の恵みに与かれるということに他ならないからである。我々は、農作物の初穂を見て、これからますます穂が出てくるだろうと確信する。パウロが言っているのは、これと同じことである。これを、パウロたちこそが御霊の身体において復活する第一の人たちであった、と捉えることはできない。確かにパウロをはじめとした紀元1世紀の聖徒たちは、復活する聖徒たちの初穂であった(黙示録14:4)。既に述べたように、彼らは天国に入った者たちの初代なのである。だが、この箇所では、そういった意味合いにおいて『初穂』という言葉が使われているのではない。それは、この辺りにおける文脈を考えれば分かる。
パウロは、この箇所で、被造物を引き合いに出して、聖徒たちの復活を語っている。すなわち、被造物が原初の状態に回復することを切に望んでいるように、聖徒たちも復活して本来あるべき状態に至ることを望んでいる、と。幸いな状態への復帰を求めているという点で、聖徒たちと被造物は変わらない。どちらも、現段階の状態においては呻き苦しんでいる。
パウロがここで言っている身体の贖い、すなわち復活は既に起きた。それはⅠテサロニケ4章から明らかである。しかしながら私がこう言っても、今の教会はシッカリと考察しようとせず、背を向けて無視するばかりである。どうしてか、今の教会は再臨に関わる事柄については不信仰なのだ。だが、再臨成就説における新規性を考えれば、このような教会の態度はある意味において仕方がないと言えるかもしれない。コペルニクスの地動説を考えても分かる通り、真理というものは、その出た当初は冷遇されるのが宿命だからである。
この箇所でパウロは、あたかも復活が起きるまでは、聖徒たちが神の子ではないかと言っているかのように語っている。つまり、復活が起きてから我々は神の子に初めてなると。だが、我々がこの地上にいる時から既に神の子らであるのは明らかである。すなわち、我々は復活に至らないと神の子らにならない、というわけではない。これは聖書の教えから明白である。Ⅰヨハネ3:1ではこう言われている。『事実、いま私たちは神の子どもです。』パウロも復活する前から既に聖徒たちは神の子らであると述べている。では、パウロは一体どういうことを、この箇所で言っているのか。パウロが言っているのは、つまり、復活により我々が真に神の子らであったことが確証されるように、ということである。何故なら、御霊の身体において復活できるのは本当の神の子どもたち以外には存在しないからである。だから、復活するということは、その人が真に神の子らであったということを公に証明することに他ならない。つまり、パウロはここで復活の時における追証について言っているに過ぎない。すなわち、この箇所においては、今はまだ我々が神の子とされていない、ということを言っているわけではない。
【11:25】
『兄弟たち。私はあなたがたに、ぜひこの奥義を知っていただきたい。それは、あなたがたが自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。』
パウロは、ローマ人たちに再臨に関わる『奥義』を知らせようとしている。『奥義』とは、「真理に関する非常に重大な秘められていた事柄」というほどの意味である。この言葉は、他にも黙示録10:7やローマ16:25やⅠテモテ3:16などの箇所で使われている。これは今の世界で例えて言えば、パール・ハーバーの真実を告げるようなものである。その真実を聞いた人は、本当に悪かったのは日本軍というよりは鬼畜のルーズベルトであったことを知るに至る。だから、それはパール・ハーバーにおける奥義を知らせることであると言えるのである。
パウロがこのような奥義をローマ人に知らせるのは、ローマ人たちが高ぶらないようにするためであった。高ぶりは破滅の母だからである。高ぶるからこそ、全てが駄目になる。ビル・ゲイツも最も気を付けねばならないのは成功であると言っている。成功すれば調子に乗って馬鹿なことをし易くなるからである。つまり、パウロはローマ人たちのことを思って、彼らに奥義を知らせようとしたわけである。
【11:25~26】
『その奥義とは、イスラエル人の一部がかたくなになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルはみな救われる、ということです。』
『イスラエル人の一部がかたくなになった』とは、ユダヤ人がキリストを斥けたことを言っている。つまり、ユダヤ人がキリストを殺した時、彼らの頑なさが神の御前に確定的なものとされた、ということである。実際の歴史を見ると、ユダヤ人たちの中で頑なになったのは、その大部分であった。だが、パウロはここであたかも頑なになったユダヤ人があまりいなかったかのように、『一部』という言葉を使っている。ユダヤ人が『一部』だけ頑なになったというのは、新約聖書を読んでも当たっていないように感じられる。どうしてパウロはこのような言葉を使ったのであろうか。これは、パウロが悲しみを抑えようとして行なった修辞上の縮小表現である。パウロにとって同胞であるユダヤ人の多くがキリストを斥けたままでいるのは耐え難い状態であったので、このように実際よりも小さく事柄を表現したわけである。縮小表現ではないが、ヨハネもキリストの御業について誇張して語っている(ヨハネ21:25)。聖書の中で、このように事柄を誇張したり縮小したりするのは、特に珍しいことではない。世の中の人でさえ著作や日常の中でそのようにしているのだから(※)、聖書にそのような書かれ方がされていても不思議がるべきではない。
(※)
これの最も顕著なのは、近頃他界した人の業績や人生を公の場で語る時である。その時、語る者は良い事柄を強調し、悪い事柄を抑えたり美のベールに包み隠すのである。
[本文に戻る]
『異邦人の完成のなる時』とは、異邦人の全体に伝道が一通りされることを言っている。つまり、これは大宣教命令が成就することである。大宣教命令が成就されると、異邦人が『完成』される。何故なら、既に世界中に福音が宣べ伝えられたので、もう異邦人にそれ以上の状態はないからである。この言葉は、なかなか理解するのが難しい。だが私が今言った通りに理解すべきである。
そのようにして大宣教命令が成就されると、『イスラエルはみな救われる』ことになった。何故なら、大宣教命令が成就すると、キリストの再臨されるユダヤの終わりの日が到来するからである。それはキリストがこう言われた通りである。『この御国の福音は全世界に宣べ伝えられて、すべての国民にあかしされ、それから、終わりの日が来ます。』(マタイ24章14節)ユダヤが終わる時期にキリストが再臨されると、その時に信仰を持っていたユダヤ人クリスチャンは携挙されて救われることになった。だから、その時に『イスラエルはみな救われる』のである。
再臨は既に実現しているから、この箇所で言われているイスラエルの救いも既に実現している。信仰ある聖徒たちは、このことを受け入れなければいけない。
【11:26~27】
『こう書かれているとおりです。「救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬虔を取り払う。これこそ、彼らに与えたわたしの契約である。それは、わたしが彼らの罪を取り除く時である。」』
パウロは、再臨が起こるとユダヤ人が回復するようになるということを、旧約聖書の御言葉により根拠付けている。『救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬虔を取り払う。これこそ、彼らに与えたわたしの契約である。』という部分は、イザヤ59:20~21の箇所に基づく。こう書かれている。『「しかし、シオンには贖い主として来る。ヤコブの中のそむきの罪を悔い改める者のところに来る。」―主の御告げ。―「これは、彼らと結ぶわたしの契約である。」と主は仰せられる。』次に『それは、わたしが彼らの罪を取り除く時である。』という部分は、イザヤ27:9の箇所であろう。こう書かれている。『それゆえ、次のことによってヤコブの罪は赦される。…』他にもローマ3:10~18の箇所がそうだが、パウロは幾つかの箇所で、旧約聖書の御言葉を纏めて一つの御言葉にしている。パウロがそうしているのだから、我々もそのようなことをしてよいのである。
『救う者』とはイエス・キリストである。『シオン』とは、キリストのおられる天である。『出て』とはキリストの再臨である。『ヤコブ』とは父祖ヤコブに連なるユダヤ人である。つまり、ここではキリストが再臨されるとユダヤから背きの罪が取り去られる、と言われている。何故なら、再臨が起こる時には選ばれたユダヤ人においてユダヤの罪が抹消されるからである。選ばれていないユダヤ人においてユダヤの罪が抹消されたというわけではない。何故なら、そのユダヤ人たちは再臨の時に滅ぼされることになったからである。あくまでもユダヤが赦されたのは選ばれたユダヤ人においてであった。
この時、アブラハムにおいてユダヤ人に与えられた救いの契約が完成された。何故なら、その時に究極的な救いがユダヤ人に与えられたからである。その救いとは、もちろん身体の贖い、すなわち天国に入れられることである。だから、こう言われている。『これこそ、彼らに与えたわたしの契約である。』ここでは、再臨が起きた時に初めてユダヤ人と契約が結ばれたと言われているのではない。契約であればアブラハムの時からあった。ここで言われているのは、ただ既に結ばれていた契約が真の意味において全うされた、ということである。それというのも、その契約の目指すところは信仰者たちが贖われた身体をもって天国に入るようになる、という点にあったからである。
パウロはこのように言うことで、ローマ人たちが高ぶらないように取り図らった。これはローマ人たちが『自分で自分を賢いと思うことがないようにするため』には、どうしても言っておかねばならないことであった。このように言われたら、ローマ人たちはユダヤ人たちが捨てられて惨めになっているのは異邦人が救われるための一時的な処置に過ぎない、ということに気付くようになる。そうしたらローマ人たちは自分たちに与えられた救いにより、ユダヤ人に優越感を持てなくなる。何故なら、やがてユダヤ人も再臨が起これば救いに与かるようになるからである。これは、ある人が成人になって酒を飲めるようになったので、まだ未成年である者に対して誇り高ぶるようなものである。この人は、未成年も間もなくすれば成人になり酒を飲めるようになることを忘れている。だから、やがて未成年も自分と同じように成人になるということを気付かされた時、その高ぶりが打ち砕かれてしまう。何故なら、未成年に対して優越を得られるのはほんの束の間だということを知るからである。そして、自分が虚しい誇りを抱いていたことを悟るのだ。もしこの人が永遠に成人であり、未成年である者も永遠に未成年であれば話は別だったが、そのようなことはないのである。この例えにおいて、成人はローマ人に、未成年はユダヤ人に対応している。
第48章 46:コリント人への手紙Ⅰ
1番目のコリント人への手紙は、心を傾ける必要がある。聖徒が裁きを行なうことについて言われている6:2~3、復活について言われている15章は、絶対に研究されねばならない。特に15章は、無視することが許されない。何故なら、この章からは、再臨の際に起こる復活のことが豊かに学べるからである。この章を無視するならば、再臨の理解に大きな欠けが生じざるを得ない。
【10:11】
『この私たちに世の終わりが来ています。』
例のように、ここで言われている『世の終わり』とは、ユダヤ世界の終焉のことである。これは、地球全土の終わりという意味ではなく、また未だに実現していない終わりについて言っているのでもない。これについては既に何度も語られているが、これはあまりにも重要なことなので、私はこのように繰り返して述べることを差し控えようとは思わない。この言葉がこれほどまでに重要であるというのでなければ、こんなにも何度も述べることはしていなかったであろう。
この箇所で『私たち』と言われているのは、パウロとその仲間たちのことである。すなわち、これは紀元1世紀の聖徒たち、しかもユダヤの終わりが訪れるよりも前に生きていた聖徒たちのことである。今の教会では、この『私たち』という言葉を21世紀に生きる我々も含んでいると理解するだろうが、そのような理解は間違っている。そのように理解するのは聖書の研究不足であって、人間理性を弄ぶことである。何故なら、この『世の終わり』とはユダヤのことであり、それは既に実現しているのだから。
これまで教会ではこの『世の終わり』という言葉を、根本から考察してこなかった。誰も彼もが、これは地球全土の終わりを意味している言葉だと信じ、そのように信じるのが当たり前となっていたから、誰も根本から考察しようなどとは思いつきもしなかった。その理解が感覚に基づいており、聖書に基づく理解ではないにもかかわらず、である。これは教会が認めなければならないことである。三位一体論や原罪論であれば、話は違っていた。これらの場合、もし正統派の理解を持っているというのであれば、その理解を堅持し疑ったりすべきではない。そのように疑うのは許しがたいことである。何故なら、三位一体や原罪の神学はこれまで幾度となく吟味・論争されてきたのであって、これらは言わば完全に開発済みの神学だからである。だが、『世の終わり』について言えば、これは根本的な意味においては、まだまだ未開発の神学分野であると言ってよい。もちろん「終末論」ではこの終わりについて色々と考察されはするが、現在の「終末論」はそもそも前提からして完全に誤っているので、そこでの『世の終わり』における考察は、まったくもって不毛である。再臨について正しい理解を持って初めて、この『世の終わり』についても正しい理解を持てるようになる。それゆえ、真に正しい再臨の理解を求める本書で取り扱われているこの『世の終わり』に関する諸考察を、聖徒たちは大いに聞き、吟味し、そして受け入れるべきである。本書で『世の終わり』について取り扱っているのは、終末論でそれを取り扱っているのとは前提からして異なっているが、正しい前提に基づいて取り扱っているのは言うまでもなく本書すなわち<再臨論>のほうなのである。
【15:20】
『しかし、今やキリストは、眠った者の初穂として死者の中からよみがえられました。』
ここから15:28までの箇所は非常に大切である。何故なら、そこでは再臨と復活について重要なことが語られているからである。再臨の研究において、この箇所を無視することは許されない。そうだ、私はこの箇所を決して無視するまい。他の多くのプロテスタント牧師たちのように、御言葉に背を向けるならば、真理は決して与えられないだろうから。言うまでもなく、御言葉に大胆に密着するからこそ、神はその人に真理を悟らせて下さる。それというのも、真理は御言葉において、この御言葉においてこそ啓示されているからである。
パウロは、キリストが死から復活した人の第一号であったと述べている。『初穂』とは、最初の、それ以前にはなかった、という意味である。既に第3部でも述べたように、この言葉は黙示録14:4の箇所でも使われており、律法から取られている。『眠った者』とは、つまり死のことである。これは生理的な睡眠のことではない。要するに、『眠った』とは死の暗喩表現である。キリストが『死者の中からよみがえられ』たのは、父なる神がキリストを肉体的に復活させて下さった、という意味である。すなわち、それはスピノザが夢想したような幽霊的な復活ではない。このキリストの復活は、非常に基本的な事柄なので、本書において詳しく説明しなかったとしても問題はないであろう。
単に復活したということであれば、キリストよりも前に、いくらかの例があった。例えば、預言者に復活させられたあの子供や、キリストに復活させてもらったラザロがそうである。だから、単に復活したというのであれば、キリストは復活者の初穂ではなかった。精神が狂っているのでもなければ、これは誰の目にも明らかであろう。だが、御霊の身体において復活したということであれば、正にキリストが初穂であられた。何故なら、キリストよりも前に御霊の身体で復活した人は誰一人としていないからである。パウロがこの箇所で言っているのは、この意味においてである。我々は勘違いをしないようにせねばならない。キリスト以前に復活させられた人は、やがてすぐにも再び死ぬことになった。何故なら、その復活は御霊の身体による復活ではなかったからである。つまり、それは単にこの地上の生命における復活に過ぎない復活であった。
【15:21~22】
『というのは、死がひとりの人を通して来たように、死者の復活もひとりの人を通して来たからです。すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからです。』
人は、アダムの罪過により、死ぬことになった。他の箇所でもパウロはこう言っている。『そういうわけで、ちょうどひとりの人によって罪が世界にはいり、罪によって死がはいり、こうして死が全人類に広がった』(ローマ5章12節)。アダムはその堕罪により、死すべき存在となった。このアダムという人類の根が腐ったので、その根から出てくる全人類も、アダムのように死すべき存在になったのである。根が腐れば、その根と共に、根から生えてくる枝も駄目になるのは自然なことである。それゆえ、もしアダムが堕罪していなかったとすれば、人類が死ぬことにはならなかったであろう。神は契約的に物事を御覧になられる。だから、アダムが死ぬようになったことで、アダムに連なる全人類も死に定められたのである。聖書に契約の教理を見いだせない人は、このことを弁えるのがなかなか難しいかもしれない。
一方、キリストにより、信じる全ての聖徒たちは神の御前に生きるようになった。パウロは他の箇所でもこう言っている。『こういうわけで、ちょうど一つの違反によってすべての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によってすべての人が義と認められて、いのちを与えられるのです。すなわち、ちょうどひとりの人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、ひとりの従順によって多くの人が義人とされるのです。』(ローマ5章18~19節)キリストは御父の召命に従われ、十字架の贖いを成し遂げられ、永遠の命を獲得された。だから、キリストに属する者は、キリストのゆえに神の御前に生きれるようになった。先に述べたように、神とは契約的な御方であられる。それゆえ、神はキリストに属する民に、キリストと同様の恵みを注いで下さるのだ。神の御前に生きるようになるためには、このキリストによる以外にはない。他に救いを求めても無駄なことである。
15:22の箇所で『アダムにあってすべての人が死んでいる』と言われている『すべて』とは、文字通りの意味での全ての人である。すなわち、全ての人間は、キリストという例外を除けば誰もがアダムにあって死んでいる。だが『キリストによってすべての人が生かされる』と言われている『すべて』とは、文字通りの意味での全てではない。何故なら、たとえキリストが贖いを成し遂げられたからといって、全ての人間が神の御前に生かされるわけではないからである。言うまでもなく、神の御前に生きるようになるのは、キリストを信じる聖徒たちだけである。それゆえ、この『すべて』とは聖徒たちにおける『すべて』という意味である。15:22の箇所で言われている2つの『すべて』という言葉を、どちらも同様の意味に捉えてはならない。アダムのほうは文字通りの意味において、キリストのほうは限定された意味において解されねばならない。
【15:23】
『しかし、おのおのにその順番があります。まず初穂であるキリスト、次にキリストの再臨のときキリストに属している者です。』
パウロは、復活にはそれぞれ順番が定められていると述べる。すなわち、キリストも聖徒たちも一緒にして復活が起こるというのではない。伝道者の書のように言えば、「キリストが復活されるのに時があり、聖徒たちが復活するのに時がある。」ということになる。まず初めに復活したのはキリストであった。それは紀元30年頃に起こった。これはパウロたちにとって、既に起きていた。このキリストの復活は、既に述べたように復活の『初穂』であった。キリスト以降に復活する者たちは、初穂であられるこのキリストのようにして復活するのだ。
キリストの次に復活するのが『キリストに属している者』であった。これは例えば、ノアやアブラハムやサムエルやダニエルやバプテスマのヨハネがそうである。彼らが復活したのは『キリストの再臨のとき』であった。つまり紀元68年6月9日である。キリストが再臨されると同時に復活が起こるというのは、Ⅰテサロニケ4:16~17の箇所でも教えられている。こちらのほうは、パウロたちにとっては、まだ起きていなかった。
パウロはこのように言って、まだ聖徒たちの復活が起きていないことを示している。何故なら、パウロがこの手紙を書いた時に再臨が起きていなかったのは誰の目にも明らかだったからである。再臨がまだ起きていないというのであれば、復活も起きていないということになるのである。
【15:24】
『それから終わりが来ます。』
『それから』とは、『キリストの再臨のときキリストに属している者』が復活してから、という意味である。これは文章の続き具合を考えれば明らかである。この『それから』という言葉は、時間の順序を教えているので非常に重要である。
『終わり』とは、例のようにユダヤが滅亡して終わることである。実際、聖徒たちが再臨の時に復活してから、ユダヤは滅亡して終わった。すなわち、紀元68年6月9日に復活が起きると、もう間もなく紀元70年9月にユダヤが『終わり』を迎えることになった。
この『終わり』を全地球的な滅亡と考えている人には、先入観がある。彼らは再臨のことで聖書をよく研究していない。ただ感覚的にこの言葉を捉えている。「これは地球の終わりのことを言っているのだ」と。つまり、釈義が全然なっていない。彼らの理解の基準はイメージやキリスト教における常識であって、残念ながら「聖書」には基準が置かれてはいない。しかし、聖書にこそ基準を据え、再臨のことで聖書をよく調べて考えるならば、この言葉はユダヤについて言われているということが分かる。研究不足は、先入観に基づく誤解をそのままに放置してしまう。注意せねばならない。研究してこそ色々と正しく理解できるようになるのだ。
『そのとき、キリストはあらゆる支配と、あらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。』
再臨されたキリストが『あらゆる支配と、あらゆる権威、権力を滅ぼし』と書かれているのは、ユダヤのことである。キリストが再臨された時期を考えてみよ。その時、ユダヤは滅ぼされ、支配と権威と権力をことごとく失った。もうユダヤには王も総督も見られなくなった。これは誰も疑えないことである。だから、ここで言われているのは、ユダヤから全ての支配、権威、権力が滅ぼされることなのである。これを地球全土的に捉えることはできない。何故なら、キリストが再臨された時、諸国における支配と権威と権力は滅ぼされなかったからである。今に至るまで、地球における支配と権威と権力はずっと保持されている。しかし、パウロはこの箇所で、キリストが再臨された時に『あらゆる支配と、あらゆる権威、権力』が滅ぼされると教えている。だから、これを地球に存在する全ての支配・権威・権力として捉えるべきではない。これは、キリストがマタイ24章の並行箇所であるルカ21章の中で、ユダヤが滅ぼされる時のことについて、『しかし、エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、そのときには、その滅亡が近づいたことを悟りなさい。』(ルカ21章20節)と言われた御言葉と適合している。ユダヤがローマの軍隊に囲まれて滅ぼされるというのは、つまりキリストがユダヤの『あらゆる支配と、あらゆる権威、権力を滅ぼ』されるということである。何故なら、ユダヤがローマ軍により滅ぼされたのは、キリストの裁きだったからである。それゆえ、この箇所で言われている支配と権威と権力の滅びは、ユダヤについて言われたこととして限定せねばならない。
『国を父なる神にお渡しになります。』とは、どのような意味であるか。『国』とは御国を指す。つまり、この部分で言われているのは、キリストが御国の民である聖徒たちを父なる神の御許に委ねられるということである。キリストの再臨と共に復活が起こると、ユダヤがローマ軍により滅ぼされ、紀元70年に天国が開始された。この天国は、父なる神が統べ治める国である。この天国が始まった時に、御国を持つ聖徒たちは天国におられる父なる神の御許に引き渡されたのである。だから、その時には『神は彼らとともに住み、彼らはその民となる』(黙示録21:3)ことになった。父なる神に聖徒が委ねられるとは、つまり聖徒が神と共に歩むようになるということなのである。この『国』を、ローマやエジプトやインドといった地上の諸国として解するべきではない。そのように解すると、意味が分からなくなってしまう。キリストが地上の国を父なる神に委ねられるというのは、理解し難いことである。しかし、これが御国の民を言い表していると考えれば、難なく理解ができる。
【15:25】
『キリストの支配は、すべての敵をその足の下に置くまで、と定められているからです。』
パウロが言っている『定め』とは、聖書のどこに記されているのか。それは詩篇110:1の箇所である。そこではこう書かれている。『主は、私の主に仰せられる。「わたしがあなたの敵をあなたの足台とするまでは、わたしの右の座に着いていよ。」』この預言は、キリストも福音書の中で引用しておられる。
キリストが再臨された時、『すべての敵をその足の下に置く』ことが実現した。それは紀元1世紀のことである。何故なら、既に述べたように、再臨と敵を足台とするという出来事は、セットだからである。すなわち、再臨が起きたということは、つまり敵がその時には足台になっていたということを意味している。また、敵が足台になるからこそ、キリストが再臨される。私の経験から言うが、マタイ16:28やⅠテサロニケ4:15の箇所ではキリストが紀元1世紀に再臨されたと教えられているという理解を聞いて、その理解を否定できる牧師や一般信徒は誰一人としていない。何故なら、その理解は正しく、そのように理解するしかないからである。つまり、キリストの再臨は既に起きている。であれば、その再臨が起きた時に、敵が足台になるという出来事も実現したのである。これは我々の理性にとっては受け入れ難いかもしれない。だが我々は、自分の理性がどう思おうとも、聖書が教えている通りのことを受け入れるべきである。
『すべての敵』とは何を意味しているのか。これはキリストと神の秩序に逆らい立つ諸々の存在である。例えば、ネロのような忌まわしい悪者どもや次の節で言われている『死』がそうである。それではこの敵を『足の下に置く』とは何を意味しているのか。これはキリストが敵をその足の下に踏み置いて屈服させる、その尊厳や威勢を奪い取る、それに対して光輝な勝利を収められる、という意味である。我々は、これが比喩的な表現であることに注意せねばならない。つまり、これはキリストがプロレスラーのように実際に御自分の足で物理的に敵を踏みつける、という意味ではない。
パウロが言っている『キリストの支配』とは、キリストの明白かつ強力な支配のことを言っている。その支配の期間は、キリストが昇天されてから再臨されるまでの間である。すなわち、紀元30年頃~紀元68年頃までである。確かに、この期間には、キリストの力強い支配が見られた。この時期のことを考えてみるがよい。その時、聖徒たちは死者を蘇らせ、悪霊を追い出し、病人を癒し、障害者を健常者にし、瞬間移動をし、預言を語り、異言を話し、異言を解き明かし、蛇を掴み、毒が体内に入っても死ぬことがなかった。これはキリストが聖徒たちを通して為された御業であった。当時は、このような奇跡を聖徒たちが行なっていたので、多くの人々が信仰に入り、神の国が豊かに満ち広がった。それというのも、これは『みことばに伴うしるし』(マルコ16章20節)だったからである。見よ、これこそが『キリストの支配』である。このような数々の奇跡を見たら、誰でもキリストが聖徒たちを通して支配しておられると感じずにはいられなかった。しかしながら、このような強力な支配は、再臨が起こるまでに限定されていた。パウロがこの箇所で言っている通りである。既に何度も述べている通り、その再臨は紀元1世紀に起きたのである。だから、このような支配も再臨と共に終わったのである。
パウロがここで言っている強力な『キリストの支配』は、今の時代にはもう見られない。それは特別的な支配だったからである。だから、キリストが再臨されてからは、もう聖徒たちが奇跡を行なうことはなくなったのである。使徒時代よりも後の時代には奇跡の賜物が廃止されたというのは、教会の一般的な見解である。もし今の時代にもまだ『キリストの支配』が続いているというのであれば、どうして今は使徒時代のようにキリストが聖徒たちを通して素晴らしい諸々の奇跡を行なわれないのか、という重大な問題が生じる。もしキリストの支配が今も続いていたとすれば、今も聖徒たちはキリストにおいて驚嘆すべき奇跡を行ない続けていたことであろう。それというのも強力な『キリストの支配』とは、聖徒たちを通じて為されるものだから。だが、再臨以降の時代でも、キリストのこの世界における支配そのものは続いている。つまり、使徒時代のような強力な支配ではないものの、今でもキリストの支配が世界に働きかけている。だからこそ、キリストに逆らう勢力は、ローマのように滅ぼされてしまうのである。つまり、今は緩やかで長期的なスパンで為される支配になっているというだけである。使徒時代の支配は、急激的で短期間に集約された支配であった。
【15:26】
『最後の敵である死も滅ぼされます。』
死が主により滅ぼされたのは、いつなのか。それは再臨の際に復活と携挙が起きた時である。何故なら、パウロはキリストが再臨されると、死もキリストにより足台とされる、と言っているからだ。そうだ。パウロが死の滅びについて言っているのは、天上のこと、天上における聖徒たちのことである。それは天上に集められた聖徒たちにおいて死が駆逐されるという意味なのである。すなわち、それはこの地上のこと、地上における人々のことではない。確かに、キリストは復活と携挙の出来事が起きた際、聖徒たちにおいて死を滅ぼされた。だから、聖徒たちはそれ以降、死に屈服させられることなく永遠に生き続けるようになった。このようにして「主は死を滅ぼされる。」という御言葉が成就したのである。
それだから、再臨成就説を反駁するための武器として、この箇所を利用することはできない。すなわち、人は私に向かって次のように言うことができない。「あなたは再臨が既に起きたと説いているが、パウロは再臨が起こると死が滅ぼされるとⅠコリント15章で教えている。しかし今の時代を見ても死がまだ滅ぼされていないのは誰の目にも明らかである。もし再臨が本当に起きていたとすれば、もう死も見られなくなっていたであろう。それゆえ、あなたの説く再臨成就説は受け容れられない。」このように言う人は理解が浅い。パウロが死の滅びについて言っているのは、再臨が起きた時期に実現される。その再臨は既に実現されたのだ。それは、ここまで何度も説明した通りである。再臨が起きたというのであれば、確かに死もその時に滅ぼされたのだが、今の地上を見てもまだ死は残っているのだから、パウロが言った死の滅びとは天上のことであったと理解せねばならないのである。もしパウロの言った死の滅びが、地上のことであったならば、今はもう死がこの世界において見られなくなっていたであろう。しかし、それは天上のことであった。それゆえ、キリストが既に再臨されたにもかかわらず、この地上にまだ死が残っていたとしても問題は生じないのである。天上においては実際に死が滅ぼされたのだから。
【15:27】
『「彼は万物をその足の下に従わせた。」からです。』
パウロは、ここで詩篇8:6の箇所から引用している。そこではこう書かれている。『万物を彼の足の下に置かれました。』パウロは、ほとんどそのまま引用していることが分かる。パウロが示すように、詩篇8:6の箇所で言われていたのは、キリストについてであった。他の箇所でもそうだが、詩篇では、多くの箇所でキリストのことが預言されている。
キリストが再臨された時、キリストは万物を足台にされた。詩篇8:6の箇所に続く箇所を読むと、この『万物』がどのような意味であるかが分かる。それは、すなわち『すべて、羊も牛も、また、野の獣も、空の鳥、海の魚、海路を通うものも』(詩篇8:7~8)である。つまり、『万物』とは文字通りの意味での『万物』である。前節でも言われていたように、それには『死』さえも含まれている。キリストは、紀元68年に万物の上に立つ支配者として天から降りて来られた。だから、その時にはキリストの足の下に万物が置かれたのである。
キリストが再臨された時、確かに『彼は万物をその足の下に従わせた』のである。そのようにしてキリストは、御自身が万物の支配者であられるということを、明白に示された。これは言わば支配者としての公的な宣言である。その時、あらゆる被造物は、聖書が述べる通り、再臨されたキリストの威光の輝きの前に恥じ入ることになったのである。それは『地も天もその御前から逃げ去って、あとかたもなくな』(黙示録20章11節)るほとであった。
『ところで、万物が従わせられた、と言うとき、万物を従わせたその方がそれに含められていないことは明らかです。』
これは、例えば次のように言うのと似ている。「王は、あの宮殿の中にいる全ての人をコントロールし支配下に置いておられる。もっとも、当然ながら王自身は、その「全ての人」の中に含められてはいないが。」つまり、パウロはここで当たり前のことを言っている。パウロは、別にこのようなことは言わずに済ますこともできた。それというのも、これは自明のことだからである。パウロ自身が『…は明らかです。』と言っている通りである。だがパウロはこのことについて、あえてコリント人に対して言った。それはコリント人が『まだ肉に属して』(Ⅰコリント3章5節)おり、非常に鈍かったからである。つまり、このようなことでさえ言われないと分からないほどに、コリント人は鈍感であった。教える者は、このパウロのように別に言わなくて構わないことであっても、相手によっては言わねばならないことがある。それは語る相手が、その鈍さのゆえに誤解してしまわないためである。教師たちは、相手の聞く力に応じて語らねばならないのである。
【15:28】
『しかし、万物が御子に従うとき、御子自身も、ご自分に万物を従わせた方に従われます。これは、神が、すべてにおいてすべてとなられるためです。』
パウロが言うように、万物がキリストに従う時、キリストも父なる神の御前に服従された。つまり、その時、キリストは至高の支配者になられたわけではなかった。これはキリストに万物を従わせたのが父なる神だったからである。キリストが御自身に万物を従わせた方に従われるのは、非常に理に適っている。というのも、もし父なる神が御子に万物を従わせておられなかったとすれば、万物は御子に従っていなかったはずだからである。そえゆえ、もしキリストが父なる神に万物を従わせられたのにもかかわらず、父なる神に服従されなかったとすれば、キリストは忘恩の愚を犯すことになるのだ。
このようにキリストも父なる神に服従されたのは、『神が、すべてにおいてすべてとなられるため』であった。つまり、父なる神が、キリストをも含めてあらゆる存在の上に位置されるためであった。しかし、どうして父なる神はキリストをも含めた万物の上に位置されるべきなのか。それは、父なる神から全てが出たのであって、全てはこの父なる神の下に置かれるのが相応しいからである。それは一家の頂点に立つべきなのが、妻でも子でもなく父であるのと同じである。
【15:35】
『ところが、ある人はこう言うでしょう。「死者は、どのようにしてよみがえるのか。どのようなからだで来るのか。」』
紀元1世紀のコリント教会には、復活についてよく弁えていなかった信徒がいた。この『ある人』とは教会の外部にいる人のことではない。何故なら、パウロはコリント教会にいた復活をよく理解できていなかった信徒たちを念頭に置いて書いているからである(Ⅰコリント15:12)。
彼らは復活について無知であった。だからこそ、このような疑問を抱いたのである。これは不信に基づく疑問であった。何故なら、不信仰だからこそ、このような疑い深いことを思わせる質問
をするのだから。
今となっては、もうこのような信徒は見られなくなった。それというのも、もう既に教会には、復活が当たり前の教義として定着したからである。プロテスタントにもカトリックにも正教会にも、もはやこのように頓珍漢な疑問を発する信徒はいない。
【15:36】
『愚かな人だ。』
彼らは『愚か』であった。というのも、聖なる復活について正しい理解を持っていなかったからである。復活とは、何よりも大いに知るべき重要な事項である。それを彼らは正しく知っていなかったのである。未信者であれば話は別だったが、彼らは教会に属しているキリスト教徒と見做されている者であった。だから、彼らが『愚かな人』と呼ばれたのは当然であった。もし彼らを愚かと呼ぶべきでないとすれば、いったい誰を愚かだと呼べばよいであろうか。
パウロはここで『愚か』と裁いているが、これはキリストが言われた『さばいてはいけません。』(ルカ6章37節)という御言葉に違反していないのか。パウロが言ったことは、キリストの御言葉に違反していない。何故なら、パウロがこのように愚かな人たちを裁かなければ、復活についてコリント教会の聖徒たちがおかしな理解を持ちかねないからである。愚かな人の見解に他の聖徒たちが惑わされたら、コリント教会の全体が復活信仰から外れることにもなりかねない。そうしたらコリント教会は神学的に神の呪いを受けることにもなる。そうなったら大変である。だから、パウロは『愚かな人』を裁かないわけにはいかなかったのである。我々はキリストも『忌わしいものだ。』(マタイ23章15節)とか『信仰の薄い人たち。』(マタイ6章30節)などと言って、容赦なく裁かれたのを忘れるべきではない。もし『さばいてはいけません。』という御言葉が例外抜きに全ての裁きについて言われているのだとすれば、キリストとパウロはこのように裁いていなかったはずである。当時は不当な裁きが横行していた。キリストは、そのような良くない裁きを指して『さばいてはいけません。』と言われたのである。我々は、正しい裁きであれば、裁いてもよい。それはキリストが『うわべによって人をさばかないで、正しいさばきをしなさい。』(ヨハネ7章24節)と言われた通りである。なお、パウロはガラテヤ人に対しても『ああ愚かなガラテヤ人。』(ガラテヤ3章1節)と言って裁いている。
『あなたの蒔く物は、死ななければ、生かされません。』
つまりパウロはこう言っている。「あなたが蒔く穀物の種は、落ちて死んでから、始めて芽を出して生きるようになる。復活もこれと同じである。あなたは、どうして種蒔きのことから、復活のことを悟らなかったのか。こんなことは、少しぐらい考えれば誰でも分かることであろう。」
【15:37】
『あなたが蒔く物は、後にできるからだではなく、麦やそのほかの穀物の種粒です。』
パウロは、15:36の箇所で述べられたことについて、それが身体についてではなく穀物について言われたことであるということの確認をさせている。「あなたは種を蒔くかもしれないが、それは穀物の種に過ぎない。私があくまでも例えとして穀物の種蒔きを示したことぐらい君には分かるはずだ。何故なら、どうして君に身体を蒔くことなど出来ようか?」と。
【15:38】
『しかし神は、みこころに従って、それにからだを与え、おのおのの種にそれぞれのからだをお与えになります。』
しかし、神が蒔かれる種は、人間の種蒔きとは異なっている。人間が穀物の種を蒔く場合、それが落ちて死んでから、始めて芽を出して生きるようになる。神の場合はそうではない。すなわち、神が蒔かれる人間という種は、死んでから後、復活体という新しい人間が生じるようになる。作物を蒔いて作物を生じさせるか、人間を蒔いて人間を生じさせるか。どちらも死なせて生かすという本質部分では一緒であるが、その内容が異なっているのだ。
この人間という種に与えられる死後の身体は、それぞれ人ごとに異なっているとパウロは述べる。種がその種ごとに違った作物を生じさせるように、人間という種もその人ごとに違った身体を生じさせる。それは、この世で我々一人一人の身体がそれぞれ異なっているのと同じである。もし復活体が誰も皆クローンのように一緒だったとすれば、パウロはここでこのように言っていなかったであろう。神は多様性を好まれるゆえ、『おのおのの種にそれぞれのからだをお与えにな』るのだ。
【15:39~40】
『すべての肉が同じではなく、人間の肉もあり、獣の肉もあり、鳥の肉もあり、魚の肉もあります。また、天上のからだもあり、地上のからだもあり、』
この地上世界には、様々な肉が存在している。それは決して一様ではない。人間や獣や鳥や魚など、肉には多様性がある。どれも肉という点では一致しているが、その種がそれぞれ異なっている。
それと同じで、人間の身体にも違いがあるとパウロは述べている。すなわち、人間の身体には『天上のからだ』と『地上のからだ』という2種類がある。どちらも人間の身体であるが、その種類が異なっている。パウロはここで、地上において様々な肉が存在しているということから、人間の身体にも場所によって違う身体があるということを分からせようとしている。復活を信じないサドカイ人であれば、このようなことを聞いて、愚かだと思ったであろう。不信者や異教徒たちも、それと同様に愚かだと思ったであろう。しかし、愚かなのは彼らのほうである。何故なら、彼らは神の全能を信じていないからである。神の全能を信じていれば、神が天上の身体をも用意しておられるということを聞いても、荒唐無稽だとは思わないはずなのである。
【15:40~41】
『天上のからだの栄光と地上のからだの栄光とは異なっており、太陽の栄光もあり、月の栄光もあり、星の栄光もあります。個々の星によって栄光が違います。』
星は、星ごとに、それぞれ異なる輝きの栄光を持っている。太陽の栄光は月の栄光よりも優っており、月の栄光は地球から見る限りではその他の星々の栄光よりも優っている。木星と土星の栄光は、金星・火星・水星の栄光よりも優っている。太陽よりも更に栄光に輝いている星が、この宇宙には非常に多く存在している。星により栄光の度合いの差があるのは、神がそうされたからである。神は多様性を好まれるのだ。
星の栄光に違いがあるように、『天上のからだの栄光と地上のからだの栄光とは異なって』いるとパウロは述べる。地上の身体の栄光がどのようなものかということについては、誰でも理解できるはずである。天上の身体の栄光のほうは、一体どのようなものであるか。キリストは、天上に至った聖徒たちが『太陽のように輝き』を持つと言っておられる(マタイ13:43)。ダニエル書12:3の箇所でも、天上の聖徒たちは大いなる輝きを持つと言われている。これらの聖句から、天上の身体の栄光はかなり凄いということが分かる。私の推測では、恐らく地上の身体よりも1000倍の栄光を持つのではないかと思う。何故なら、天上の聖徒たちは太陽のように輝くのだからである。
【15:42~44】
『死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので蒔かれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいもので蒔かれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いもので蒔かれ、強いものによみがえらされ、血肉のからだで蒔かれ、御霊に属するからだによみがえらされるのです。』
パウロは、死者の復活が、劣れるものから優れたるものへの移行であると教えている。弱から強へ、下から上へ、無から有へ。これが復活である。我々は『朽ちるもので』この地上に蒔かれた。だから我々はやがて死ぬ。しかし聖徒たちは、やがて『朽ちない』身体において復活できる。また我々は『卑しいもの』として地上に生えてきた。だから、ヨブ記25:6の箇所で言われているように、地上にいる我々は『うじ』であり『虫けら』も同然である。しかし聖徒たちは、やがて『栄光ある』復活体において新しい生命のうちに歩むことになる。また我々は『弱いもの』として生まれてきた。我々人間の弱さは、あまりにも悲惨である。しかし聖徒たちは、やがて『強い』存在となって復活させられる。また我々は現在においては『血肉のからだ』を持っている。まだ御霊の身体を我々が持っていないというのは誰の目にも明らかである。しかし我々はやがて『御霊に属するからだによみがえらされる』ことになる。
これらのことから、復活の素晴らしさが理解できる。キリストを信じる者は、このような恵みにやがて与かれるのだ。これは大変に魅力的な約束である。それだから、聖徒たちは復活の信仰から外れないようにしなければならない。もし復活の信仰から落ちたならば、聖なる復活に与かれなくなってしまうという残念な結末を迎えるからである。
【15:44】
『血肉のからだがあるのですから、御霊のからだもあるのです。』
パウロは、血肉の身体が存在しているのであれば当然ながら御霊の身体も存在していると結論する。これは逆にこう言うこともできる。「もし御霊の身体が存在していなければ血肉の身体も存在していないであろう。」ここでパウロが言っていることは、次のように言うのと似ている。「あの人は今生きているのだから、あの人の先祖もかつてはあの人のように生きていたのだ。」「人類が今までずっと存在し続けてきたのだから、これからも存在し続けることだろう。」神の子らは、パウロのこの御言葉に対し「アーメン。」と言わなければならない。
ある人は、このパウロの言葉を聞いて、次のように言うかもしれない。すなわち、血肉の身体に基づいて御霊の身体を導き出すというのは論理的に堅固とは言えないのではないか。血肉の身体が存在しているからといって、御霊の身体が存在すると帰結することが果たしてできるのだろうか、と。私はこう答えよう。神を前提とした世界観を持っているのであれば、血肉の身体に基づいて御霊の身体が存在することを確信するのは十分に可能である。何故なら、神とは全能者であって、神は聖徒たちに永遠の生命を約束しておられるからである。それだから神の存在を前提とする聖徒たちにとっては、パウロの言ったことだけで十分に満足できる。信仰を持つ我々の場合、御霊の身体を血肉の身体から論証できるのだ。しかしパウロの言葉に満足できない人は、神を前提とした世界観を持っていない人か、神を前提としているのだが非常に疑い深い人である。
【15:45】
『聖書に「最初の人アダムは生きた者となった。」と書いてありますが、最後のアダムは、生かす御霊となりました。』
パウロが引用している聖書の箇所は、創世記2:7である。その箇所を見ると分かるが、パウロはかなり自由な引用をしている。すなわち、このように書かれている。『その後、神である主は、土地のちりで人を形造り、その鼻にいのちの息を吹き込まれた。そこで、人は、生きものとなった。』昨今の教会の中には、聖句を逐語的に引用せねばならないと考える過度に潔癖な牧師や一般信徒が、数は少ないがいくらか見られる。彼らは、聖句をそのまま引用しなければ心が平安にならない。何故なら、「それは神の言葉だから。」である。確かに、聖書は神の言葉である。また彼らのこのような聖句に拘る態度は、傾向として悪くはないと思える。だが我々は、その文意さえ変えてしまうのでなければ、聖句をそのまま引用しなかったとしても咎められるべきではない。何故なら、この箇所を見れば分かるように、あのパウロがそのようにしているからである。まさか、逐語引用主義者たちは、パウロをも批判するというのであろうか。「パウロはそのまま聖書の言葉を引用していない。」などと言って。いくらなんでも、そんなことはしないだろうと私は思う。であれば、我々も聖句を文意を損ねない限りで自由に引用しても差し支えないのである。
創世記を読めば分かる通り、人間が造られた当初にはまだ生命がなかった。それは単なる人形に過ぎない物質体であった。しかし神が命の魂をお与えになったので、人形に過ぎなかった人間は、生きた者となった。もし神が魂を人間に与えられなかったならば、今も我々は人形のように動かずにいたことであろう。それゆえ我々は、我々に魂を与えて生きるようにして下さった神に感謝せねばならない。
『最後のアダム』とはキリストである。これはキリストが、最初の人アダムの為すべきだった従順の使命を成し遂げられて全うされた、という意味である。この言葉はなかなか難しいが、私が今述べたように捉えるべきである。ここではキリストが『アダム』において象徴されているが、これはキリストがアダムのように不従順だったという意味ではない。何故なら、キリストは罪を何も犯されなかったからである(Ⅰペテロ2:22)。また『最後の』と言われているのは「終わりの時の」という意味ではない。何故なら、この箇所で言われているのは歴史のことではなく、使命のことだからである。
キリストが『生かす御霊』となられた、とはどのような意味なのか。これは、キリストがその御霊において人間を神の御前に生かす御方になられた、という意味である。つまり、こういうことである。キリストは御霊において御父の御業を成し遂げ、永遠の救いを実現させられた。だから、人間はこのキリストによって神の御前に回復されるようになった。それゆえ、このような救いを実現させられたキリストは人を生かす御霊なのだ、と。この部分もなかなか難しいが、私が今述べたように捉えるべきであろう。
【15:46】
『最初にあったのは血肉のものであり、御霊のものではありません。御霊のものはあとに来るのです。』
最初に出てきたのは『血肉』の身体であった。それは御霊の身体ではない。パウロが言うように『御霊のものはあとに来る』。御霊の身体は第二なのである。ノアは神の御心に適った義人であった。それにもかかわらず、ノアは血肉の身体において出てきた。バプテスマのヨハネは、『母の胎内にあるときから聖霊に満たされ』(ルカ1章15節)ていた。それにもかかわらず、ヨハネは血肉において生まれてきた。この2人でさえ、最初は血肉の身体において出てきた。であれば、その他の全ての者も、この2人と同様に最初は血肉において出てきたということは確かである。
何事にも順序というものがある。人間の場合、第一が血肉、第二が御霊である。御霊が先んじるということはない。それは、あべこべだからである。医者も、最初から縫合することはしない。糸で縫うのは最後だからである。最初から縫合して「手術完了。」などと言う医者は、頭がイカれているのだ。我々も順序を弁えるべきである。そうしないと、順序を誤ったことにより、破滅や不幸に陥りかねないのだから。
【15:47】
『第一の人は地から出て、土で造られた者ですが、第二の人は天から出た者です。』
第一の人は、地から出たアダムに連なる人たちである。今の地上にいる人たちは、この第一の人であって、『土で造られた者』である。それは、葡萄の木に生え出てくる枝が、どれも葡萄の木の枝であるのと一緒である。第二の人は天からの者である。これは天上に住まう聖徒たちである。
キリストの場合は、どうなのか。キリストは御自身のことについて、『天から下った者』(ヨハネ3章13節)と言っておられる。それゆえ、キリストは『天から出た』『第二の人』であられる。しかし、パウロがローマ1:3の箇所で言っているように『御子は、肉によればダビデの子孫として生まれ』た。すなわち、ダビデの子孫であったマリヤからキリストはお生まれになった。これは誰でも知っていることである。それでは、キリストは肉においては『第一の人』だったのであろうか。私は言うが、そのようなことはない。何故なら、パウロはここで、第一の人であるアダムに対置されるべき存在としての第二の人であるキリストを語っているからである。15:45の箇所を見れば、キリストがアダムのような第一の人でなかったことは明らかである。そこでは、明らかにキリストがアダムと区別されているからだ。しかし、キリストが地上において真の人でなかったということではない。キリストは、ヘブル書でも教えられているように、罪を除けば我々と同じような人であられた。
【15:48】
『土で造られた者はみな、この土で造られた者に似ており、天からの者はみな、この天から出た者に似ているのです。』
土で造られた第一の者は、土で造られたアダムに似ている。何故なら、地上にいる人間は全てアダムの遺伝子を持っているからである。だから、第一の者は誰でもアダムのように罪を犯す。キリストの予表であったダビデでさえアダムのように罪を犯した。第一の者においては、アダムのように罪を犯さない人は誰一人としていない。
第二の者である天の住人たちは、天から出られたキリストに似ている。何故なら、彼らはキリストと同じように御霊の身体を受けているからである。だから、彼らはキリストのように何も罪を犯さない。心の中に少しでも悪の思いがかすめることさえない。キリストに似ているとは、そういうことだからである。
【15:49】
『私たちは土で造られた者のかたちを持っていたように、天上のかたちをも持つのです。』
地上にいる第一の者は、『土で造られた者のかたち』を持っている。それは、アダムと一緒の性質を持っているということである。だから、全人類はアダムのように弱く、卑しく、罪深く、最後には死ぬ。このようでない者は、地上にいる者のうち誰もいない。もしいたとすれば、その者はアダムの遺伝子を持っていないのである。
天国に住まう者たちは、『天上のかたち』を持っている。これはキリストの形を持っているということである。だから、彼らはキリストのように強く、誉れを持ち、罪を犯さず、決して死ぬことがない。キリストにおいて天上の形を持つというのは、そういうことである。聖徒でない者たちは、この『天上のかたち』を持つことがない。彼らには永遠の恵みが注がれないからである。むしろ、彼らはサタンの形を持つことになる。何故なら、彼らはサタンの子であって、サタンから生まれたのだからである。
【15:50】
『兄弟たちよ。私はこのことを言っておきます。』
パウロは重要なことを伝えようとしている。ここでパウロは「いいかね、これから語ることによく心を留めるように。」とでも言っているかのようである。これはキリストが、『まことに、まことに、あなたがたに告げます。』と言われたのと同じである。キリストも重要なことを伝える際には、それをよく心に留めるようにと、前もって一言を語られたのであった。
『血肉のからだは神の国を相続できません。朽ちるものは、朽ちないものを相続できません。』
パウロは言う。今の我々が持つ朽ちる血肉の身体は、朽ちることのない永遠の天国に相応しくないと。パウロはこう言って、復活の必要性を説いている。先にも述べたように、コリント教会には復活についてよく弁えていない人たちがいた。パウロは、そのような人たちがいたコリント教会が、より正しい復活の理解に導かれるようにしているのだ。
しかし、どうして血肉の身体では御国を相続できないのか。これは簡単に分かる。つまり、血肉の身体がすぐに朽ちるのに対し、御国は永遠に朽ちないからである。血肉の身体は80年もすれば滅びに至る。これでは永遠に朽ちない御国を担えないのは誰の目にも明白である。もし血肉の身体が永遠に朽ちなかったとすれば話は別だったが、残念ながら血肉の身体は滅びる運命にあるゆえ、永遠の御国を相続することができない。
【15:51】
『聞きなさい。私はあなたがたに奥義を告げましょう。』
パウロは再び重要な事柄を知らせようとしている。その重要な事柄とは『奥義』である。これは、知るに価値ある霊妙な神の真理を指している。
『私たちはみなが眠ってしまうのではなく、みな変えられるのです。』
パウロは、コリント人たちが死ぬことはないと言っている。『眠ってしまう』とは死のことである。何故、コリント人たちは死なないのか。それは、もう間もなくキリストの再臨が起こるからである。再臨が起こると、Ⅰテサロニケ4章や黙示録20章を見れば分かるように、その時に生きていた聖徒たちは生きながらにして復活した。だから、パウロはテサロニケ人たちが眠る、すなわち死ぬことがないと言っているのだ。その復活とは、『みな変えられる』ことであった。その復活の時の変化について、次の節では語られている。
【15:52】
『終わりのラッパとともに、たちまち、一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。』
『終わりのラッパ』とは再臨の時に鳴ったラッパである。キリストが再臨される時には、ユダヤの終わりを告げ知らせるラッパが鳴らされた。再臨の時にラッパが鳴るというのは、Ⅰテサロニケ4:16の箇所でも言われている。
この終わりのラッパが鳴り、再臨が起こると、その時に生きていたコリント人をはじめとした聖徒たちは生きながらにして復活体に変えられた。それは『たちまち、一瞬のうちに』してなされた。この時代に超高性能のビデオカメラがあったとしても、復活の変化における成り行きを捉えることは出来なかったであろう。それほどに急激な身体の変化が起きたのである。このようにして当時の聖徒たちは復活に与かることになっていたのだから、パウロは15:51の箇所でコリント人たちが死ぬことはないと言ったのであった。なお、我々は、この時の復活を科学的に解明しようとすべきではない。それはキリストの復活を科学的に解明するべきでないのと同じである。何故なら、復活とは理性を超え出た事象だからである。復活に科学というメスを入れるのは、明らかに違法である。そのようにするのは、制限のある矮小な理性という道具により、復活という神の超越的な事象を把握しようとすることだからである。有限なるものにより、無限なる神の計り知れない事柄を把握できるはずがないのは確かである。
ここで言われている『死者』とは、地上に生きていた聖徒たちを指している。これは既に絶命して墓の中に横たわっている聖徒ではない。それは、文脈を考えれば分かる。パウロがここで言っているのは、聖徒たちが生きながらにして生き返ることについてである。前節でパウロは、生きているコリント人たちが死ぬことはないと言った。すなわち、死ぬのではなく復活体に切り替えられると。それだから、パウロはここで生きている者を指して『死者』と言っているのである。この箇所でパウロは、復活した状態を生命として定義している。それゆえ、復活していない状態は『死者』なのである。他にもパウロは、Ⅰコリント15:22の箇所で、生きている人たちを死んでいる存在として取り扱っている。『アダムにあってすべての人が死んでいる』と書かれている通りである。このように生きている者を死人と言い表すのは、キリストもしておられる。主は、ヨハネ5:25の箇所で、地上に生きている人を『死人』と言われた。それは墓の中にいる既に絶命した人のことではなかった。このようなキリストの例があるのだから、パウロが生きている者を『死者』と言い表していたとしても問題にはならない。もっとも、パウロが聖徒たちを死人として取り扱っているのに対し、キリストはまだ信仰を持っていない人を死人として取り扱っている、という点では両者に違いがある。
【15:53】
『朽ちるものは、必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは、必ず不死を着なければならないからです。』
パウロが言いたいのは、こういうことである。すなわち、朽ちて死ぬことになる我々は朽ちない不死の身体を着ない限り神の国を相続できない、と。つまり、復活体を得ない限りは天国は有り得ないということである。ここでパウロは当たり前のことを言っている。
この復活体を着ることにこそ真の幸いと大いなる希望がある。今の我々の身体は朽ちて死ぬことになる。これは実に悲惨である。しかし、復活体は朽ちることも死ぬこともない。それは非常に素晴らしいことである。我々は、この復活に至らせる信仰に留まり続け、それを決して捨ててはならない。それを捨てるのは、幸いと希望とを捨てることである。そのようになれば、我々には不幸と絶望しかなくなるであろう。何故なら、そのようになった場合、我々の行き着く先は恐るべき永遠の死となるのだから。
【15:54】
『しかし、朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を切るとき、「死は勝利にのまれた。」としるされている、みことばが実現します。』
聖徒たちが復活体を着る時、死は敗北のうちに屈服させられた。何故なら、その時、死は復活した聖徒たちの前に無力化されたからである。聖徒たちが復活するより前にも、聖徒たちは既にキリスト信仰のゆえに死に勝利していた。しかし、その勝利は約束においてであって、まだその勝利は効力を発揮していなかった。聖徒たちが復活した時、その勝利は目に見える形で効力を発揮した。だから、その時には『「死は勝利にのまれた。」としるされている、みことばが実現』するのである。
死に対する勝利の飲み込みは、パウロがこの箇所を書いた時には、まだ実現していなかった。何故なら、パウロはそれをまだ実現していない出来事として取り扱っているからである。もし既にそれが実現していたとすれば、パウロはこの箇所でこのように言ってはいなかったであろう。むしろ、こう言っていたであろう。「あなたがたが知っているように、「死は勝利にのまれた。」と記されている御言葉は既に実現しました。」
それでは、パウロが引用しているこの聖句は、どこから引用されたのか。イザヤ書25:8の箇所であろうか。そこではこう書かれている。『(万軍の主は)永久に死を滅ぼされる。』それとも、すぐ次の箇所で引用されているホセア13:14の箇所であろうか。新改訳聖書における註釈では、イザヤ25:8が指示されている。これは、つまりⅠコリント書を訳した訳者がパウロはイザヤ25:8から引用していたと理解していたということになるのであろうか。それとも単に似ている聖句だから註釈において指示したのであろうか。それとも註釈は誰か別の人が作ったのであろうか。いずれにせよ、聖書を訳した人または註釈を作った人が必ずしも霊的また神学的に卓越しているということはないのだから、この註釈は強力な参考情報にはならないであろう。この註釈を作った人が、かなりの権威者であるというのであれば話は別であるが。解答を述べよう。これは文章の続き具合から考慮すれば、ホセア13:14の箇所から引用されたとするのが正しい。続く15:55の箇所で書かれている御言葉をパウロがどこから引用したのか考えてみよ。それはホセア13:14の箇所でしかない。だから、その前の場所である15:54で引用されている御言葉もホセア13:14の箇所からだと考えねばならない。何故なら、パウロは『「死は勝利にのまれた。」としるされている、みことば』がどのようなものであるか、続く15:55の箇所で指し示しているからである。これをイザヤ25:8の箇所から引用されたとするのは間違いである。何故なら、そこでは天国において実現する究極的な不死について言われているのではなく、御国の信仰における世界的な招きについて言われているのだからである。このイザヤ25:8の箇所については、既に書かれた註解箇所を参照してほしい。
ここでパウロが言っている「勝利による死の飲み込み」は、黙示録ではどこに対応しているのか。パウロが言っているのは、聖徒たちが復活して、永遠の命のうちに死を敗北させることについてである。これは黙示録の21:1~22:5、14:1~5、7:9~17と対応している。これら3つの箇所では、既に第3部で述べられたように、天国と天国に導き入れられた聖徒たちについて示されているからである。黙示録の構造をよく弁えていない人は―それは非常に複雑で難しい―、第3部を読みつつ黙示録を学び直すべきである。
【15:55~56】
『「死よ。おまえの勝利はどこにあるのか。死よ。おまえのとげはどこにあるのか。」死のとげは罪であり、罪の力は律法です。』
パウロが引用しているのはホセア13:14の箇所である。パウロはいくらか自由な引用をしている。すなわち、ホセア書では『針』となっている部分を、パウロは『勝利』と言っている。これはどういうことなのか。これは、つまり死はその針で刺すことにより人を殺して勝利するからである。それゆえ、『針』を『勝利』という言葉に置き換えるのは何も不適切ではない。
聖徒たちが復活する時、一人一人において、このホセア書の御言葉が実現される。確かに復活するよりも前に、既に聖徒たちにはキリスト信仰のゆえに、このホセア書の御言葉が実現されているとある意味において言える。何故なら、聖徒たちはキリストのゆえに、復活するよりも前から既に死に打ち勝っており、もはや死ぬことがなくなったからだ。しかし、本当の意味においてこの御言葉が実現されるのは、復活が起きた時である。何故なら、キリストにより聖徒たちが死に打ち勝ったという事実は、復活が起きた際に目に見える形で明らかとなるからである。
『死のとげは罪であり、罪の力は律法です。』とは、どのような意味であるか。これは、よく考えないと意味を弁えることが難しい。それというのも、パウロは事柄を凝縮して箴言のように語っているからである。まず『死のとげは罪であり』とは何か。これは、死がその棘によって人を刺し殺すという意味である。我々は、死をハリセンボンのようなものだと思えばよい。このハリセンボンには鋭い棘が無数に生えている。死というハリセンボンは、この棘により人を刺し殺して死に至らすのである。パウロは、この棘が『罪』であると言う。これは、罪を犯すことにより、人は死の恐るべき棘に刺し殺されるようになる、ということである。罪を犯すことにより死が棘で人を死なせるというのは、聖書で次のように言われている通りである。『罪から来る報酬は死です。』(ローマ6章23節)『罪を犯した者は、その者が死ぬ。』(エゼキエル書18章4節)次に『罪の力は律法です。』とは何か。これは、死が罪により人を殺す力は律法による、という意味である。というのも、ヨハネが第一の手紙の3:4の箇所で言っているように、『罪とは律法に逆らうこと』だからである。確かに罪とは、何らかの律法に違反した言行のことである。だから、人は律法違反という罪により、死の力ある棘で刺し殺されることになるのである。要するにパウロが言っているのを分かりやすく言い換えれば、次のようになる。「死は罪という名の棘によって人を死なせるが、その罪は律法により殺す力を得る。」
それにしてもこのパウロの言葉は実に深遠である。昔からパウロは哲学的に深いと言われてきたが、これは正にその通りである。パウロよりも深遠に真理を語れる人は、恐らくいないのではないか。神は、このようなパウロを教会のために用いられた。それは教会が、パウロを通して語られた神の言葉を聞いて、豊かに霊的な知恵を得るためであった。すなわち、教会はパウロの深遠な言葉から、神の真理を豊かに汲みだすのである。
【15:57】
『しかし、神に感謝すべきです。神は、私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。』
すべて聖徒たちは、キリスト信仰のゆえに、死に対して勝利している。それゆえ、死は聖徒たちを死なせて屈服させることができない。それは不可能である。何故なら、聖徒たちの犯した罪は、ことごとくキリストにより赦されているからである。それだから、死は罪の恐るべき棘を聖徒たちに突き刺すことが出来ない。死がその罪という名の棘で聖徒を刺そうと思っても、既にキリストの贖罪によりその棘が無効化されているので、どうしても刺せないのである。それゆえ、死は聖徒たちにとって、全ての針が取り除かれた惨めなハリセンボンのようなものである。だから、聖徒たちは、救い主イエス・キリストを与えて下さった神に感謝すべきなのである。
死の刺し殺す棘を無効化できるのは、ただイエス・キリストのみである。キリスト以外の存在に、死からの救いを求めても、救いを得ることはできない。そのようにするのは、病気を治療したいと願っている人が、病院や医者に助けを求めず、他の存在に助けを求めるようなものである。ただキリストこそが死の棘から聖徒たちを救うのだ。それゆえ、ペテロはこう言っている。『この方以外には、だれによっても救いはありません。世界中でこの御名のほかには、私たちが救われるべき名としては、どのような名も、人間に与えられていないからです。』(使徒の働き4章12節)
【15:58】
『ですから、私の愛する兄弟たちよ。堅く立って、動かされることなく、いつも主のわざに励みなさい。あなたがたは自分たちの労苦が、主にあってむだでないことを知っているのですから。』
パウロは、コリント人たちが揺るがぬ信仰を持ち、いつも主の御前に敬虔な精神で奉仕をするようにと命じている。『堅く立って、動かされることなく』とは、信仰において揺るがず、決して疑わず、真の確信を持ち続ける、という意味である。『いつも主のわざに励みなさい。』とは、神に喜ばれる霊の実をいつも結ぶように、という意味である。この2つの事柄は、パウロ書簡の他の箇所でも多く語られている。つまり、これは非常に重要であって、それゆえに何度も語られたということである。
どうしてコリント人たちは、信仰に立ちつつ常に主の御前に奉仕し続けるべきだったのか。それはコリント人たちの業には、報いが伴っているからであった。コリント人たちが敬虔に歩めば歩むほど、やがて天で与えられるようになる報いもそれだけ増し加えられる。敬虔に歩まなければ歩まないほど、それだけ天で受けることになる報いも少ない。コリント人たちは、このことについて知っていた。だから、パウロはコリント人たちが、良き歩みをして多くの報いを受けられるようにと命じたのである。良き歩みをすればそれだけ良き報いを受けられるようになると知っていながら、あえて良き歩みを願い求めないというのは、自分の愚かさと霊的な鈍さを露呈することに他ならないのである。
パウロがこのように命じたのは、コリント人たちに対する愛のゆえであった。『ですから、私の愛する兄弟たちよ。』と書いてある通りである。愛とは他者の益を求めることである(Ⅰコリント13:5)。パウロはコリント人たちを愛していた。その愛には偽りがなかった。だから、パウロはコリント人たちが天国においても地上においても幸いになれるようにと、ここでこのように命じたのである。もしパウロがコリント人たちに対する愛を持っていなかったとすれば、彼らにこのように命じていたかどうか定かではない。愛が無ければ、他者の益を求めるのは、ただ面倒なだけだからである。
我々も、『堅く立って、動かされることなく、いつも主のわざに励』まねばならない。何故か。それは、我々も『自分たちの労苦が、主にあってむだでないことを知っている』からである。我々が主の御前に奉仕をすればするほど、得られることになる報いの度合いも大きい。であれば、我々が主の御前に仕えようとしなくてもよい、ということがどうしてあるであろうか。別に報いの度合いが大きくなくても構わない、などと思う人がいるのであろうか。まさか、聖徒たちの中でそんな人は一人もいないはずである。
【16:22】
『主よ、来てください。』
パウロは、ここで再臨が起こるようにと願っている。つまり、これは臨在において主が近くにいて下さるようにと願っているのではない。「主の再臨がすぐにも起こりますように。」とパウロは言っているのだ。パウロがこのように言ったのは、悪に染まっていたコリント人たちを抑制させるためであった。パウロは『主を愛さない者はだれでも、のろわれよ。』と言ったすぐ後で、『主よ、来てください。』と言っている。つまり、主を愛さないで悪に歩み続ける不敬虔な者たちは呪われ、主が再臨された際にはその振る舞いに対する当然の報いを受けるように、ということである。パウロはこのように再臨について言って、コリント人たちが再臨が起きた際、キリストの御前に幸いな状態で出られるように計らっている。というのも、ここでパウロが言っているのは矯正のための威嚇に他ならないからである。つまり、パウロはコリント人のためを思って、ここで再臨について言ったのである。
パウロがこう願った願いの通り、主の再臨は紀元68年に起こった。『わたしは、すぐに来る。』とキリストが言われたように、キリストは本当にすぐに来られたのである。その時、悪に歩み続けていた呪われるべきコリント人たちは再臨が起きた際に御前から退けられたが、悪を止めて悔い改めたコリント人たちは再臨されたキリストの御前に快く受け入れられた。
第49章 47:コリント人への手紙Ⅱ
2番目のコリント人への手紙は、心を傾けなくても問題にはならない。何故なら、この文書からは、再臨のことがほとんど学べないからである。
第50章 48:ガラテヤ人への手紙
ガラテヤ書は、研究しなくしてもよい。
第51章 49:エペソ人への手紙
エペソ書には、見ておくべき箇所がある。それは、聖徒たちが天に座っていると言われている2:6や、天に悪霊がいることについて言われている6:12などが、そうである。しかし、この文書そのものは、それほど重要であるとは言えない。
【1:10】
『時がついに満ちて、この時のためのみこころが実行に移され、天にあるものも地にあるものも、いっさいのものが、キリストにあって一つに集められることなのです。』
パウロは、他の箇所で携挙とは聖徒たちがキリストの御許に集められることであると述べている。すなわち、こうである。『さて兄弟たちよ。私たちの主イエス・キリストが再び来られることと、私たちが主のみもとに集められることに関して、あなたがたにお願いすることがあります。』(Ⅱテサロニケ2章1節)確かに、キリストが再臨された際、聖徒たちは世界各地からエルサレムの上空に再臨されたキリストの場所へと集められた(マタイ24:31)。我々が今見ているエペソ1:10の箇所でも、聖徒たちが集められると言われている。だが、ここでは携挙のことが言われているのではない。ここで言われているのは、人々が贖いを実現されたイエス・キリストの救いに信仰において集められる、ということである。つまり、聖書で『集められる』と書かれていた場合、それには2通りの意味がある。すなわち、携挙か新生における契約か、である。携挙について書かれている箇所で新生のことが言われていると理解してはならないし、逆に新生について書かれている箇所で携挙のことが言われていると理解してはならない。この箇所では新生について書かれているから、ここでは携挙という意味において『集められる』と言われているなどと考えるべきではない。この箇所で新生という意味で集められると言われているということについては、まともな神学者のエペソ書註解を確認してみるとよい。どの人も、ここで携挙について言われているとは説明していないはずである。
【2:6】
『ともに天の所にすわらせてくださいました。』
聖徒たちは、地上にいる時から既に『天の所』に座っている。救われた時、我々は天に座ったのである。これは確かである。何故なら、パウロがここでそう教えているからである。だから、これを書いている私は今現在、天の所に座っている。これを読んでいる聖徒である読者も、もちろんそうである。
しかし、我々は今、実際的には天の所に座っていない。自分の回りを見てみよ。神や24人の長老や4人のセラフィムやセラフィム以外の御使いたちが、そこにはいるか。いない。もし我々が天にいたのであれば、このような聖なる存在が、回りには見られたはずである。パウロも、自分たちは今、この地上にいると述べている(Ⅱコリント5:1)。また、パウロはピリピ3:20の箇所で『私たちの国籍は天にあります。』と言っているが、これは我々が今地上にいるということでなくて何であろうか。それでは、ここで聖徒たちが天に座っていると言われているのは、どういう意味なのか。これはアウグスティヌスも言ったように、聖徒たちは希望において既に天にいるという意味である。もしくは、これは霊的な意味において天にいるという意味として捉えるべきである。霊においてであれば、実際的には天に身を置いていなかったとしても、我々が天にいることは出来る。それはパウロが実際的にはコリント人たちの場所にいなかったのに、霊においてはそこにいたのと同じである(Ⅰコリント5:3~5)。要するに、ここで天に座っていると言われているのは文字通りの意味においてではない。
我々が実際的に天に座るのは、我々がこの人生を終えた後である。何故なら、その時に我々は天の場所へと引き上げられるからである。今はまだ、地上にいる状態を続けなければならない。だが、我々はあっという間に天に座っていることになるであろう。すなわち、気がついたら、もう天に座っているであろう。というのは、モーセも言ったように、我々の70年、80年ぐらいの人生など『ひと息』(詩篇90:9~10)に過ぎず、それは『早く過ぎ去』(同)るのだから。
【6:12】
『私たちの格闘は血肉に対するものではなく、…天にいるもろもろの悪霊に対するものです。』
ここでパウロは、天に『もろもろの悪霊』がいると言っている。パウロがこの文章を書いている時は、確かにまだ天に悪霊がいた。何故なら、その時はまだ再臨が起きていなかったからである。再臨以前の時代は、悪霊どもが天に居続けることが出来た。それは聖書の御言葉そのものから分かる。例えば、ヨブ記1、2章では、サタンが天におられる神の御許に来たことについて書かれている。サタンとは、堕落した悪しき霊である。だから、ヨブの時代には、天に悪霊がいたことが分かる。またⅠ列王記22:19~23の箇所では、天におられる神が『偽りを言う霊』(22章23節)とやり取りをしているシーンが描かれている。『偽りを言う霊』とは間違いなく悪霊である。何故なら、『偽証してはならない。』と仰せられた神の御霊が一体どうして偽りを言われるのであろうか。罪ある偽りの言説を口にするのは悪霊以外ではない。だから、このやり取りが起きたアハブの時代にも天に悪霊がいたことが分かる。再臨が起こるまでは、まだ天にパラダイスが構築されていなかったから、そこに悪霊がいることが出来たのである。その時はまだ天の本来的な住民である聖徒たちが天に言わば入居していなかったから、悪霊どもがそこに居座ることが出来た。ちょうど、公園に子供たちが誰も来ないので、猫たちが大勢集まってゴロゴロしているようなものである。
しかし、再臨が起こると、それまで天にいた悪霊どもは遂にそこから落とされることになった。これは黙示録12章で書かれている。その時から天に聖徒たちが住まうようになったので、もう悪霊どもはそこにいられなくなったのである。これは、公園に多くの子供たちがやって来たので、そこにいた猫たちが一目散に逃げ出すようなものである。公園内で突如として総入れ替えが起こった。天で悪霊どもと聖徒たちとの総入れ替えが起こったのも、それと同じことである。それだから、今でもまだ天に悪霊どもがいると考えるのは誤っている。このように考える者は、聖書をもっと確認し研究すべきである。そうすれば、霊的な事柄がより明瞭になり、天に関する知識が深まるようになるであろう。もう再臨は既に起きたのだから―これは聖句の明白な根拠があるゆえ絶対に疑えない―、もう悪霊どもは既に天から追放されているのだ。天でパラダイスが開始されたというのに、未だにそこに悪霊どもがいていいものであろうか。それは有り得ないことである。
このように今やもう天に悪霊どもはいなくなっているが、この地上には相も変わらず居続けている。だから、我々はこの悪霊どもと格闘をせねばならない。つまり、パウロがこの箇所で言っていることは、もはや天に悪霊はいなくなっているという時代的な変化を除けば、今現在の我々にも適用されるべきである。要するに、我々は今となっては地上にしかいない悪霊と格闘をせねばならない。今現在、悪霊が地上で働きかけているのは間違いないのだから、どうしてその悪霊どもと格闘をしなくてもいいはずがあろうか。目の前に蚊が飛んで来たら、追い払ったり、強烈な一撃のもとに殺したりしないであろうか。するであろう。我々が悪霊と戦うべきなのは、蚊が飛んで来た際に無視してはいないのと同じである。というのも、もし悪霊と戦わずに無視していたら、蚊を無視していた場合と同じで大変なことになってしまうのだから。
第52章 50:ピリピ人への手紙
ピリピ人への手紙には、見ておかねばならない箇所が幾つかある。特に、聖徒たちの国籍が天にあると言われている3:20の箇所は、無視されてはならない。
【3:20~21】
『けれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを、私たちは待ち望んでいます。キリストは、万物をご自身に従わせることのできる御力によって、私たちの卑しいからだを、ご自身の栄光のからだと同じ姿に変えてくださるのです。』
ここでは、聖徒たちの本来いるべき場所が『天』であると教えられている。つまり、この地上の世界は、本来的には聖徒たちのいるべき場所ではない。何故なら、聖徒たちは、この地上では『旅人であり寄留者』(ヘブル11章13節)だからである。聖徒たちは天という本国から離れて、一時的に地上の世界に行かされているに過ぎない。それは、例えるならばアメリカにいるアメリカ軍の兵士が、戦争のために一時的に中東に行かされ、そこで幾らかの期間生活するようなものである。また、この箇所で聖徒たちの国籍が天にあると言われていることから、やがて天国が地上に降りて来るなどと考えている者たちの非聖書的な妄言は退けられる。黙示録21章の中で天の都が降りて来ると言われているのは、天国が地上に降りて来るという意味ではない。そこでは、天国という恵みが上から聖徒たちに降り注がれるようにして与えられる、ということを言っているに過ぎない。これについては既に第3部の中で論じておいた。キリストは、天上に聖徒たちを住まわせるべく、その天上へ住まいの準備をしに行かれたのである(ヨハネ14:2~3)。であれば、どうしてその天上の住まいが、わざわざ地上に降りて来るということがあるのであろうか。聖徒たちが永遠に天で住まうべきだからこそ、キリストは天の場所に住まいを備えに行かれたのだ。もしその住まいが地上に降りて来るというのであれば、キリストはそのことについて多かれ少なかれ言っておられたであろう。しかし、キリストはそのことについては何も言っておられないのである。なお、この箇所は、再臨を豊かに理解したければ、決して無視されてはならない箇所である。
パウロはここで、当時の聖徒たちがキリストの栄光の再臨を待望している、と言っている。ここで注意しなければならないのは、これは当時の聖徒たちについて言われた内容だということである。パウロがピリピ人に手紙を書いた時点では、まだキリストの再臨は起きていなかった。だからこそ、当時の聖徒たちはキリストの再臨を切に希求する必要があったのである。今の聖徒たちは、この御言葉を読んで、自分たちもパウロとピリピ人たちのように再臨を待望せねばならないと思っている。しかし、そのように思うのは誤っている。何故なら、再臨は紀元68年6月に起きたからである。既に再臨は起きたのだから、もう今となっては、キリストの再臨を待ち望む必要はなくなっている。今の聖徒たちには、分かりやすい例で理解をしていただきたいと思う。例えば、旧約聖書にこれからメシアが降誕されると書いてあるからというので、西暦21世紀に生きる我々はメシアの降誕を待ち望まなければいけないなどと思ったり言ったりする人がいたとすれば、どうであろうか。そのような人は笑われても文句は言えない。何故なら、もうとっくの昔にメシアの降誕は実現されたからである。それでは、新約聖書にこれからキリストが再臨されると書いてあるからというので、西暦21世紀に生きる我々はキリストの再臨を待ち望まなければいけないと思ったり言ったりする聖徒の場合はどうか。これも、やはりおかしいのである。何故なら、既にとっくの昔にキリストの再臨は実現したのだから。
パウロはまた、キリストの再臨が起きる際には、聖徒たちの身体が新しい身体へと切り替えられるだろうと言っている。この身体の切り替えについては、Ⅰコリント15章の中でも語られている。パウロは今の古い身体が『卑しい』と言っている。これは、この地上の身体が滅びゆく不完全なものだからである。他方、新しい身体には『栄光』があると言っている。これは天上の身体が決して滅びない完全で素晴らしいものだからである。またパウロは、聖徒たちがキリストの『栄光のからだと同じ姿に変え』られる、とここで言っている。このように彼が言ったのは、聖徒たちに身体の切り替え、すなわち復活を期待させるためであった。というのも、キリストと同じ身体に変えられると聞かされて、誰がそれを待ち望まないであろうか。まともな聖徒であれば、誰でも早くそのようになるのを待ち望むのは目に見えている。聖徒たちがキリストと同じ姿に切り替えられるというのは、ローマ6:5の箇所でも言われている。またパウロは、その身体の切り替えが、キリストの『万物をご自身に従わせることのできる御力』によると言っている。キリストは、ヘブル1:3の箇所でも言われているように、『その力あるみことばによって万物を保っておられ』る。そのような御方が、聖徒たちの身体を新しい身体に切り替えるというのは、いとも容易いことである。何故なら、キリストは万物をさえ支配し保っておられるのだから。パウロはこのように言うことで、聖徒たちが「キリストはもしかしたら私たちの身体を変えることが出来ないのではないだろうか…」などと不信仰な思いを持たないように、あらかじめ予防をしておいたのである。
古い身体から新しい身体に変えられるということであれば、この箇所で言われていることは、今の聖徒たちにも言われていることである。すなわち、紀元1世紀のピリピ人たちが再臨の際に新しい身体に与かったのと同様、今の聖徒たちもやがて新しい身体に与かれるようになる。その時から、聖徒たちは、もはや古い身体には戻らなくなる。何故なら、新しい身体を受けてからは、その新しい身体において永遠に生き続けるようになるからだ。しかし、再臨が起こるということであれば、この箇所で言われていることは、もはや今の時代の聖徒たちには当てはまらない。すなわち、今となっては、この箇所を読んで、当時のピリピ人たちが再臨を待ち望んだように再臨を待ち望むべきだということにはならない。何故なら、既に何度も述べているように、キリストの再臨は既に起きているからである。聖徒たちは、聖書で言われている再臨の事柄を、よく弁えなければならない。
【4:5】
『あなたがたの寛容な心を、すべての人に知らせなさい。主は近いのです。』
ピリピ人に手紙が送られたのは紀元60年頃であった。キリストの再臨は、この手紙が書かれてから10年以内に、すなわち紀元68年6月9日に起こった。10年以内に再臨が起こるというのは、正に「すぐ」だと言える。だからこそ、パウロはここで『主は近い』と言ったのである。注意せねばならないのは、ここで言われているのはキリストの再臨についてであるということである。つまり、ここでは「主の再臨は近いのです。」と言われているのである。すなわち、パウロの言葉からは本来であればあるべき「の再臨」という言葉が、『主』という言葉の後で書かれないで省略されている。このような省略は、聖書では何も珍しいことではない。ヤコブの場合、主の再臨が近いとハッキリとした言葉で言っている(ヤコブ5:8)。カルヴァンは、ここで言われているのは神の臨在における近さのことだと捉えている。すなわち、パウロは主が聖徒たちの傍近くにおられるという意味で『主は近い』と言ったのだと。私も、聖書の多くの箇所において、主の臨在の近さがこのような言い方で言われているのを知らないわけではない。しかし、ここの箇所では、再臨が近いという意味でこのように言われている、と私は言おう。何故なら、パウロがこの手紙を書いていた時は、本当に主の再臨が近かったからである。つまり、この『近い』という言葉は、臨在における距離的な近さと捉えるよりは再臨における時間的な近さと捉えるほうが、当時の差し迫った状況を考えるならば、より相応しいということである。
またパウロは、再臨が間もなく実現されるからというので、聖徒たちが自分の寛容さを周りの人々に知らせるようにと命じている。どうしてパウロは、再臨が近いので聖徒たちの寛容さを人々に知らせるようにと命じたのか。それには2つの理由がある。まず一つ目は、周りにいる未信者たちが、聖徒たちの寛容さを知ることで、キリスト信仰に導かれるようになるためである。人は、聖徒たちの寛容さを知ると、それをキッカケとして、キリストの救いに導かれるようになるものである。キリストも、人々が聖徒たちの善良さを知るようになると天の神を崇めるようになると、マタイ5:16の箇所で言っておられる。もう数年もすればキリストが再臨されるので、パウロはこのように一人でも多くの未信者がキリストに贖われるようにと図らったのである。二つ目は、聖徒たちが再臨の起きた際、より多くの報いを受けられるようになるためである。聖徒たちが、寛容さを示せば示すほど、再臨の際に受けられるようになる報いが増すことは確かである。何故なら、御心に適ったことをすればするほど、キリストから多くの報いを受けられるようになるのは明白だからである。パウロは、間もなく訪れるキリストの前に、当時の聖徒たちがより良い状態で臨めるようにと図らったのである。我々は、もう主の再臨が間近に迫っていたからというので、パウロがこのように言ったということをよく弁え知るべきである。つまり、再臨が近かったので、パウロはこのように言うべき必要性に迫られたわけである。これは、あたかも地震がもう間もなく起こるので、すぐにも備えをせよと命じるようなものである。それだから、もし再臨がすぐには起こらなかったとすれば、パウロはこのように言うべき必要性をそれほど感じていなかっただろうから、あえてこのようにピリピ人に対して言っていたかどうかは分からない。
第53章 51:コロサイ人への手紙
コロサイ書にも、幾つか見ておくべき箇所がある。とはいっても、コロサイ書の全体は、それほど心を傾ける必要がない。
【1:6】
『この福音は、あなたがたが神の恵みを聞き、それをほんとうに理解したとき以来、あなたがたの間でも見られるとおりの勢いをもって、世界中で、実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなたがたに届いたのです。』
パウロがコロサイ人に手紙を書いた時点で、既に福音は世界中に満ち広げられていた。つまり、キリストの宣教命令は、既に今から2千年前に成就されていた。キリストは、『全世界に出て行き、すべての造られた者に、福音を宣べ伝えなさい。』(マルコ16章15節)と命じられた。これは、もう既に成就されている。何故なら、パウロの時代に、福音は『世界中で、…広がり続けてい』たからだ。またキリストは『あらゆる国の人々を弟子としなさい。』(マタイ28章19節)とも言われた。これも既に成就されている。何故なら、パウロがコロサイ人に手紙を書いていた時、既に福音は『世界中で、実を結』んでいたからだ。これは、つまり世界中にキリストの弟子がいたということを教えている。何故なら、福音が『実を結』ぶとは、多くの人たちがキリストの弟子となるということでなくて何であろうか。ところで、パウロがここで言っている『世界中』とは、文字通りの意味として捉えるべきである。これはローマ世界またはユダヤ世界だけに限定されるべき言葉ではない。何故なら、マルコ福音書の追加文の中では、キリストが使徒たちにより福音を『東の果てから、西の果てまで送り届けられた』と書かれているからである。これは、使徒たちにより福音が宣べ伝えられた範囲が、文字通りの地球全土だったことを意味している。既に第1部でも書いたが、使徒の時代の世界人口は2億人ぐらいであった。つまり、2020年現在に存在しているアメリカ人の総数よりも、当時の人間は数が少なかった。また、この時代には、今では見られないような数々の奇跡や不思議な業を、神が弟子たちを通して為しておられた。このようなことを考慮するならば、キリストが宣教命令を出されてから短期間の間に全世界に福音が満ち広げられるということは、十分に可能だったことが分かる。我々は思い違いをしてはならない。この時代は、今のように70億人も人口があったのではなく、ほとんど奇跡らしいものが見られなかったというのでもないのだ。
パウロの時代に既に福音が世界中に満ち広がっていたからこそ、パウロの時代に再臨が起きたのである。というのも、福音が世界中に満ち広げられるとユダヤの終わりが訪れ、キリストが再臨されることに決まっていたからである。このことについてキリストはこう言っておられた。『この御国の福音は全世界に宣べ伝えられて、すべての国民にあかしされ、それから、終わりの日が来ます。』(マタイ24章14節)もしまだ再臨が起きていなかったとすれば、まだ福音も世界中で実を結び広がってはいなかったであろう。しかし、パウロはこの箇所で、紀元1世紀の時に福音が『世界中で、実を結び広がり続けてい』ると明白に述べている。それだから、もう既に紀元1世紀の時に再臨は起きたのである。
古代教会の教師たちは、アウグスティヌスであれエウセビオスであれその他の者であれ、そのほとんどが既に福音は全世界に宣教されていると考え、そのように述べてきた。これは誠に正しかった。何故なら、聖書がそのように我々に教えているからである。ところが最近の教師たちは、そのように考えたり述べたりしていない。むしろ、これから宣教命令が成就されなければならない、まだ福音は世界中に宣教されていないのだから、などと考えたり述べたりする。私は思うのだが、最近の教会は御言葉を真っ直ぐに見ていない。私が聖書に基づいて既に福音は全世界に宣教されていると言っても、聞く耳を持とうとはしない。私が古代教会の教師たちが言ったのと同じことを言っても、真正面から対峙しようとせず、ただ自分の勝手な理解を一方的に主張するのみなのである。「御言葉がこう言っている。」と言っても、不思議なぐらいに御言葉に注意を傾けようとはしない。私が何かおかしいのであろうか。そうではない。私は正しいことをしているだけである。何故なら、私は御言葉から真っ直ぐに語っているに過ぎないのだから。おかしいのは明らかに最近の教会のほうである。そこら中に女性や同性愛の牧師が牧会をしている教会があったり、ディスペンセーション主義や進化論やバルト主義を受けて入れている教会が無数に見られる現今の状態を考えても、それは明らかである。要するに、今現在の教会が御言葉を真っ直ぐに見ていないからこそ、女性や同性愛の牧師がいる教会が普通に見られたり(※)、異端や間違った見解を平気で受け入れたりすること出来ているのだ。もし御言葉を真っ直ぐに見ていたならば、このような教会は何も見られなかったことであろう。だから、聖書が既に福音は全世界に宣教されていると教えているのに、それとは違うことを考えたり述べたりしている今の教会は、非常に霊性が衰えていると言わざるを得ない。今の教会は、初代教会や教父時代の教会における霊性を取り戻す必要がある。そのためにも、まずは私が今ここで言ったことを受け入れるということから始めるべきだ。というのも、このようなことさえ受け入れられないようであれば、どうして昔の教会のような高い霊性を再び持てるようになるのか。このぐらいのことさえ受け入れられないのであれば、その衰えた霊性は何も回復されないままに留まらざるを得ないであろう。
(※)
最悪なのは女性かつ同性愛の牧師である。実際にこのような牧師が治めている教会は存在している。これは大変驚くべきことだが、今の教会の現状はこのような牧師が出てきてしまうほどに異常になっているのである。すなわち、このような怪物とでも呼ぶべき者が普通に教会を治められているというのは、今の教会におけるその堕落性をよく象徴している。
[本文に戻る]
第54章 52:テサロニケ人への手紙Ⅰ
Ⅰテサロニケ書は、絶対に研究されなければならない。何故なら、この文書からは、再臨のことが大いに学べるからである。特に4:13~17の箇所は、どれだけ注目したとしても注目し過ぎるということはない。これほどまでに再臨について理解を深められる箇所も珍しいと思われる。この箇所は、再臨の理解を深めたいならば、是非とも丸暗記しておくことが望ましい。
【2:19~20】
『私たちの主イエスが再び来られるとき、御前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのはだれでしょう。あなたがたではありませんか。あなたがたこそ私たちの誉れであり、また喜びなのです。』
ここで言われているのは、こうである。キリストが再臨される時、テサロニケ人たちはパウロたちの信仰と働きを示す証明としての存在になる、と。何故なら、クリスチャンとしてのテサロニケ人たちは、パウロたちの信仰深い宣教によって誕生したのだからである。このテサロニケ人とは、パウロたちの敬虔さが目に見える形で現われ出た存在なのである。それだから、再臨が起きた時、彼らはパウロたちの『望み』となった。これはテサロニケ人たちが、その存在により、パウロたちの敬虔さをキリストに推奨するからである。また彼らはパウロたちの『喜び』となった。これはテサロニケ人たちにより、パウロたちの行なった活動が無益で無かったことが明らかになるからである。また彼らはパウロたちの『誇りの冠』となった。これはテサロニケ人たちが、彼らを誕生させたパウロたちを高めてくれるからである。このため、パウロはテサロニケ人たちにこう言っている。『あなたがたこそ私たちの誉れであり、また喜びなのです。』この箇所でパウロは有りのままのことを語っている。パウロの心に欺瞞や誇張また狂気はまったくなかった。
ここでパウロはあまりにも自己本位的に語り過ぎているのではないか、と思われる方がもしかしたらいるかもしれない。ここではテサロニケ人たちがパウロたちの単なる付属物またアクセサリーとしてしか取り扱われていないではないか、と。確かにパウロはここで自分たちを中心にしてテサロニケ人たちを取り扱っている。だが、これには何の問題もない。何故なら、キリストも聖徒たちをご自身に付属する存在として取り扱っておられるからだ。『わたしはぶどうの木で、あなたがたは枝です。』(ヨハネ15章5節)と。例えば、王が臣下に次のように言ったとしたら、どうか。「あなたがたはその優秀な働きによって、私の威信を高めてくれている。あなたがたは私の喜ばしい誉れである。」王がこのように言うのは非難されるべきか。非難されるべきだとは思えない。そうであればパウロがこの箇所で言っていることも、この王の発言のように非難されるべきではない。何故なら、パウロもこの王とまったく同じように、自分を主体として対象の存在について語っているからである。先にも述べたが、パウロはこの箇所で事柄をただそのまま語っているだけである。そこには利己心、すなわちテサロニケ人たちを自分たちの栄誉の踏み台として利用するなどという気持ちは塵ほどもなかった。
教職者たちは喜ぶがよい。多くの信徒を生じさせた教職者たちは、特に喜ぶがよい。これから再臨が起こるというのではない。しかし、今の時代に生きる教職者たちも、やがてパウロたちと同じように自分たちが生じさせた信徒たちにより喜ばされることになる。それは、その教職者が天に召される時である。パウロたちの場合、自分たちの生じさせた信徒たちによる誉れを、天上において直接的に受けた。何故なら、その時には、一挙に全ての信徒たちが携挙されたからである。今の時代に生きる教職者たちの場合、既に自分よりも前に天に召されていた信徒たちからは直接的な誉れを受けるが、まだ地上に生きている信徒たちからは間接的な誉れを受けることになる。何故なら、再臨以降の時代においては、あらゆる信徒たちが一挙に天国へと引き上げられるわけではないからである。では、教職者でない一般信徒たちは、パウロたちが受けるような誉れを受けることはないのか。一般信徒であっても、多かれ少なかれ他の人を信仰に導いたのであれば、その人からの誉れを受けるようになる。それというのも、この箇所では、子どもが信仰における親に対して与える誉れについて言われているのであって、パウロたちのような教職者以外の人にも当てはめることができるからである。事実、テサロニケ人たちは、信仰的に言えばパウロたちを自分たちの親としていた。要するに、霊的に生んだ子がいれば、誰でもやがて天上においてその子を通して誉れを受けることになるのである。
【3:13】
『また、あなたがたの心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒とともに再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で、聖く、責められるところのない者としてくださいますように。』
パウロは、キリストが再臨される時に、テサロニケ人たちが相応しい状態で御前に出られるようにと願っていた。何故なら、そのようにならなければ、キリストから悲惨な言葉を受けることになるからである。「あなたがたはどうして不敬虔な状態のままでいたのか?」と。もしテサロニケ人たちが再臨の起きた際に『聖く、責められるところのない者』でいられるならば、それは幸いなことであった。その場合、キリストから良い言葉を受けることになるからである。それだから、パウロはそのことを神に祈り求めていた。ここで『聖く』と言われているのは、「神に従って敬虔な歩みをしている状態で」という意味である。『責められるところのない』と言われているのは、「キリストに贖われて清められたままの状態で」という意味である。
このために、パウロは神に『あなたがたの心を強め』て下さるようにと願った。―心の強さとは、心における意志の強さ、忍耐力、不動性のことである。―何故なら、心が強くなければ『聖く、責められるところのない者』となるのは難しいからである。心が弱ければ、容易に悪や不信仰に陥る。そうなれば、それだけ『聖く、責められるところのない者』にはなれなくなってしまうのだ。聖書は、多くの箇所で、聖徒たちが心を強めるようにと命じている。それは聖徒たちが敬虔に歩むためである。実に神の御心は、聖徒たちが心を強くし、敬虔に歩むことにある。もっとも、そのようにできるのは全て神の恵みによる。
ここで言われているように、キリストは『ご自分のすべての聖徒とともに』再臨された。エノクの預言では『千万の聖徒』がキリストと共に降りて来ると言われていたが、これはつまり『すべての聖徒』のことを言っている。すなわち、『すべての聖徒』は、『千万』にも感じられるほどに多いということである。この聖徒たちは、キリストがこの世に現われるよりも前に死んだ全ての聖徒を指している。彼らの魂は、死んでからハデスに留め置かれた。そしてキリストが復活されてから昇天される時に、キリストと共に天へと引き上げられた。その後、紀元68年6月になると天上において復活し、キリストと共に天から降りて来ることになった。それだから、ここで言われている聖徒は、キリストの出現以降に生きていた聖徒のことではない。その聖徒たちの場合、死んだら一時的にその魂が地上に留め置かれ、紀元68年になると地上において復活し、そうしてから携挙され上のほうへと導かれて行ったのである。再び言うが、我々は、上で復活する聖徒と下で復活する聖徒の2種類があることを心に留めなければならない。
【4:13】
『眠った人々のことについては、兄弟たち、あなたがたに知らないでいてもらいたくありません。あなたがたが他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。』
『眠った人々』とは、既に亡くなった聖徒たちを指す。これは我々がほとんど例外なく毎日1回はするあの眠りのことを言っているのではない。これは、キリストがラザロの死を日常的な眠りとして言い表したのと同じである(ヨハネ11:11~13)。キリストもパウロも、死んだが間もなく復活して目を覚ますからというので、死を眠りのようであると言い表したのである。何故なら、死んだ人が間もなく復活するのであれば、それは意識を失っても間もなく意識を取り戻す日常の眠りとさほど変わることはないからである。だから、ここで言われているのがあの日常の眠りのことだと解する人がいれば、その人は聖書をフザけたことが書かれている書物に、パウロを少し頭のおかしい人間に仕立て上げることになってしまう。我々はこのような思い違いをしないように注意せねばならない。
パウロはこの箇所から、死んでしまった聖徒たちのことについてテサロニケ人たちを教えるべく語っている。それはテサロニケ人たちが『他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないため』であった。恐らくテサロニケ教会の中には、既に死んでしまった聖徒たちのことで、あたかも世の人々でもあるかのように悲しみに満ちていた人が幾らかいたのではないかと思われる。聖徒たちがそのようであっていいはずはない。何故なら聖徒たちには望みがあるからである。だからこそ、パウロはそのような人たちが世の人々のように悲観しないようにと、ここでテサロニケ人たちに対して教えているのであろう。
ここでパウロも言っているが、往々にして世の人々は、死んでしまった人のことで『悲しみに沈む』ものである。世の人々の中には、ある人が死んでしまったので、わざわざ自分まで死のうとする人もいる。日本で60年も天皇の座に就いていた天皇が崩御した際には、少なからぬ数の日本人が死んだ天皇の後に付いていくかのように自殺したものである。歴史を見ると、愛する人が死んでしまったので一生の間ずっと悲しみ続けた女性もいたことが分かる。その女性は一生の間髪を切らないことで自己の深い悲しみを表明していた。死により生じた悲しみがストレスになり、自分まで病気になったりして、すぐにも死んだ人の後に続いて死んでしまう人もよく見られる。彼らがこのように死人のことで悲しむのは、復活の信仰が無いためである。彼らにとっては、死後の復活のことなど頭の中にない。彼らの人生観は「この世の間だけ」に限られている。彼らはこの地上での人生が全てなのだ。だからこそ、地上での人生を終えた人のことで、あんなにも悲しみに打ちひしがれてしまう。彼らにとってはこの地上での人生が全てなのだから、その人生が消えてしまった際に大いに悲しむのは、理屈で考えれば当然である。しかし、もし世の人々が復活のことを少しでも考えていたとすれば、このように悲しみに沈むことは無かったはずである。何故なら、その場合、やがて死んでしまった人と会えるようになることを確信するだろうからである。かつてアンブロシウスは死んだ人について次のようにいみじくも言った。「死者に対し人間として為すべき当然の義務を果たしたら、後はそれ以上悲しみに打ちひしがれることのないようにしよう。」このようにこの司教が言ったのは、死んだその人とやがて再開できるようになることを知っていたからである。世の人々は来世における確信を持てないので、このように本気で言うことは、ほとんどない。もし彼らが本気でこのように言ったとしても、周りの人から心の冷たい者だと思われるのが落ちである。
【4:14】
『私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば、神はまたそのように、イエスにあって眠った人々をイエスといっしょに連れて来られるはずです。』
キリストは贖いのために死なれ、その3日後に復活された。このことについて、パウロはローマ4:25の箇所でもこう言っている。『主イエスは、私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために、よみがえられた』。これこそ我々の信ずる救いの真理である。
ここでパウロは、既に死んでしまった聖徒たちが、死なれはしたものの復活されたキリストと同じように死から復活した状態において、やがてキリストと共にやって来る、と言っている。―その聖徒たちの復活は一体どのようなものであるか。答え。それはスピノザが理解していたように霊魂だけの状態による復活ではない復活、である(※)。―それでは、その復活した聖徒たちはどのようにしてやって来るのか。答え。それはキリストの再臨と一緒に、天から、である。―その出来事はいつ起きたのか。答え。もう既に何度も言われたように紀元68年6月9日である。
(※)
スピノザはキリストの復活を信じていたが、それは実際の肉体を伴わないと考える限りにおいて、であった。つまり彼は復活を正しく信じていなかった。
[本文に戻る]
ここでパウロは聖徒たちが復活してキリストと共に来ると言っているが、これは明らかにエノク書の預言に基づいて言っている。ユダも引用したエノク書の預言はこうである。『見よ。主は千万の聖徒を引き連れて来られる。』(ユダ14節)このエノクの預言は、ここでパウロが言っている内容と何も矛盾していない。ユダがエノクの預言を知っていたのだから、学識豊かだったパウロもその預言を知っていたことは間違いない。このエノク書は今では偽書とされているが、そこに書かれている再臨の預言については、心を傾ける必要がある。それというのも、その預言はユダさえも神の霊によって正典の中で引用しているほどだからである。これはその預言が実際にエノクの語った預言だということを意味しているのだ。なお、このエノク書はエリファス・レヴィをはじめとした多くの人たちがモーセ5書よりも古いと言っているが、確言できないものの、その可能性は十分にあると私も思う。
要するに、ここでパウロは思い違いをしていたテサロニケ人たちを慰めようとしているのだ。「これから死んだ聖徒たちが間もなく現われるというのに、一体どうしてあなたがたは悲しみに沈んでいるのか?」と。確かに、すぐにも死んだ聖徒たちが復活するのであれば、悲しむ必要などないのは明らかである。何故なら、もう間もなくしたら再開の喜びを得られるのだから。それにもかかわらず、テサロニケ人たちは死んだ聖徒のことで悲しみに満ちていた。それは、あたかもテサロニケ人たちが復活のことなど知らないかのようであった。だからこそ、パウロは理解の足りていないテサロニケ人たちに、ここでこのように教えたのである。
【4:15】
『私たちは主のみことばのとおりに言いますが、主が再び来られるときまで生き残っている私たちが、死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。』
ここでパウロが言っている『主のみことば』とは、どの聖句を指すのか。本書の読者であれば、もうお分かりであろう。それはマタイ16:28の聖句である。そこでキリストは次のように聖徒たちに対して言われた。『まことに、あなたがたに告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が御国とともに来るのを見るまでは、決して死を味わわない人々がいます。』しかし、どうしてパウロが言及している主の御言葉が、このマタイ16:28の御言葉だと分かるのか。それは、マタイ16:28以外には考えられないからである。パウロがここで言っている内容と、キリストがマタイ16:28の箇所で言っておられる内容は、完全に一致している。すなわち、どちらの箇所でも、その時に生きている人々が生きている間に再臨が起こるであろう、と言われている。言葉の言い方はやや違っているが、その内容はまったく一緒である。だから、パウロが言及したキリストの聖句はマタイ16:28の箇所だと考える以外にはない。今まで聖徒たちは、パウロがここで言及しているキリストの聖句がどのようなものなのか、今私がしたように真剣に考察してこなかった。それは、まだ教会に再臨の真理が開示されていない時代だからであった。まだ時代が時代だったので、神の摂理により、ここでパウロが言及しているキリストの聖句に着目することが出来なかったのである。それというのも、もしその聖句を真面目に探り求めれば、色々と考察することにより、再臨の真理が明らかになってしまうからである。今やもう再臨の真理が明らかになる時代が来ている。もう今は昔のようではないのだ。それゆえ、聖徒たちはここでパウロが言っている『主のみことば』について臆することなく真面目に考察すべきである。
パウロと共に生きていたテサロニケ人たちが『生き残っている』間に、キリストは『再び来られ』た。パウロがここでそのように言っているのだから、これを疑うことは絶対に出来ない。更にキリストのマタイ16:28の箇所における御言葉でも、同じことが言われている。どうか考えてもらいたい。聖書は、再臨が紀元1世紀の時代において実現されたと教えているのだ。これこそ聖書に真正面から向き合って得られる解なのである。今の聖徒たちに必要なのは、聖句に対する純粋な信仰である。聖句を真正面から受容するのであれば、本書で述べられている再臨の見解をよく理解できるようになるであろう。
ここでパウロは、この時に生きていた紀元1世紀のテサロニケ人たちにおける復活が、既に死んでしまっている聖徒たちにおける復活よりも先んじることは無いであろう、と言っている。すなわち、復活はその時に生きていたテサロニケ人たちが、まず第一に与かるというのではない。また両者が同時に復活に与かるというのでもない。そうではなく、まず第一に死んだ聖徒たちが復活に与かるのだ。再臨が起きた際に起こる復活において、地上に生きている聖徒たちと既に死んだ聖徒たちのどちらが先に復活するのか、または同時的に復活するのか、などと思い悩んだことのある聖徒が読者の中にはいるに違いないと思う。しかし、もう頭を疲れさせることはない。ここでパウロが、先に復活するのは死んだ聖徒たちのほうだ、と言っているのだから。この死んだ聖徒たちのほうが地上に生きている聖徒たちよりも率先して復活するというのは、適切であった。何故なら、死んで魂だけの状態になった彼らは、いつ身体の復活が起こるのかと切に待ち望んでいたからである。なお、ここで既に死んでいる聖徒たちのほうが先に復活すると言われているのは、ゼカリヤ12:7の箇所と対応している。そこでも、やはり既に死んだ聖徒たちが先んじて復活する、と言われていた。このゼカリヤ書12:7の箇所は既に註解された。
ところで、どうしてこの箇所では死んだ聖徒たちが『死んでいる人々』という言われ方に切り替えられたのか。これまでの箇所(4:13、14)では、死んだ聖徒たちについて『眠った人々』と言われていた。この突然の切り替えは、我々の心を大いに引き付ける。この謎は、パウロが死んだ聖徒たちを単に眠っている存在も同然なのだと強く伝えたかった、ということにより説明できる。実際、死んでいた聖徒たちはすぐにも復活して目を覚ますことになるのだから、死んでいたというよりは眠っていると形容したほうが相応しい。だから、パウロはまず彼ら死んだ者たちについて『眠った人々』と言ったのだ。しかし、彼らは眠っていると言われるに相応しい存在であるが、実際のところ死んでいる。だから彼らが本当の意味において眠っていると理解されてはならない。それゆえ、パウロはテサロニケ人たちが勘違いをしないように、途中から死んだ聖徒たちの言い方を切り替えたのである。つまりこういうことである。「私パウロはこれまで死んだ聖徒たちについて眠っていると形容していたが、それはあくまでも比喩的な表現であって、実際は死んでいることを忘れてはならない。」もしこのような言葉の切り替えが為されず、ただ死んだ聖徒たちが『眠った人々』とだけ言われていたとすれば、テサロニケ人たちは死んだ聖徒たちが実際は死んだのではなく単に眠っているに過ぎないと勘違いすることにもなっていたはずである。それだから我々は、この『眠った人々』と『死んでいる人々』という2つの表現が、それぞれ異なった種類の存在を指しているのだと考えないようにせねばならない。これら2つの言葉は、どちらも同一の存在を指している。つまり、死んでしまった聖徒という一つの存在について、一方では『眠った人々』と恣意的な言葉で言い表しており、一方では『死んでいる人々』と実際の状態に則した言葉で言い表しているのである。それゆえ、我々は「ここでは眠った人々と死んだ人々という、それぞれ異なった2種類の存在が語られている。」などと考えたり言ったりしてはならない。
【4:16】
『主は、号令と、御使いのかしらの声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られます。』
この箇所では、キリストの再臨について幾つかのことが語られている。再臨の際には『号令』がかかった。これは誰による号令なのか。これについては分からない。それというのも、これは判断が難しいからである。もしかしたら父なる神なのかもしれないし、御子なのかもしれないし、神の御霊なのかもしれないし、24人の長老なのかもしれないし、4人のセラフィムなのかもしれない。ただ御使いではない可能性が高い。何故なら、この号令が御使いによるのだとすれば、すぐ次の部分で書かれている『御使いのかしらの声』という言葉と重複してしまうからである。いずれにせよ、我々は再臨の際には誰かによる『号令』がかかった、ということを知っていれば、それでよい。また再臨の際には『御使いのかしらの声』が発せられる。これはミカエルのことを言っている。これの目的は演出である。すなわち、ミカエルがキリストの再臨をより栄光に満ちた出来事にするために、大きな声を発してその場の雰囲気を高めたのである。また再臨の際には『神のラッパの響き』も聞かれた。これも演出がその目的である。再臨されたキリストの栄光には、ラッパの響きこそが相応しい。その音色や振動させる音波は、神の栄光を際立たせるからである。シナイ山に神が降りて来られた時にも、ラッパに似た楽器すなわち『角笛』の音が響き渡った(出エジプト19:16、19)。これらのことから分かるように、主が再臨された際には、複数の大きな音が伴っていた。既に第2部でも述べたが、この時の光景は実に凄まじく感動的に感じられたに違いない。またキリストは、再臨される時、『ご自身天から下って来られ』た。つまり、キリストは強制されて天から降りて来られたのではない。この再臨が父なる神の発された御子に対する命令だったのは確かである。キリストはその命令に自ら従い、自発的な意思によって天から降りて来られたのである。だから再臨が御父の命令だったからといって強制されたことにはならないし、キリストが自発的に天から降りて行かれたのではないということでもなかった。
『それからキリストにある死者が、まず初めによみがえり、』
ここで言われている通り、まず最初に復活するのは『キリストにある死者』である。この死んだ聖徒たちの復活は、天と地において起こった。それというのも、キリストが現われる前に死んだ聖徒たちの魂はその時に天に置かれており、キリストが現われてから死んだ聖徒たちの魂はその時に地に置かれていたからである。再臨が起きた際、天にいた魂たちは復活して再臨のキリストと一緒に降りて来た。地上にいた魂たちは復活して、キリストの再臨された場所である空中へと携挙された。これらの出来事は既に本書の中で語られている。聖徒たちは、この箇所とすぐ次の箇所の中で、『まず初めに』・『次に』と言われていることに注目せねばならない。何故なら、これは時間の流れ、出来事の順序を如実に示しているからである。
この時に復活したのはキリスト者だけであった。何故なら、これは「第一の復活」だからである。読者は覚えておられるであろう。悪者どもは、この第一の復活においては復活することがない。彼らは第二の復活の時に初めて復活するのだから。つまり、彼ら悪者どもは第一の復活が起きてから、42か月後の紀元70年に復活するのである。
ここで言われている復活は「第一の復活」だから、この箇所は黙示録20:1~6の箇所と対応している。黙示録20:4の箇所で『イエスのあかしと神のことばとのゆえに首をはねられた人たちのたましい』と書かれているのが、我々が今見ている箇所で書かれている『キリストにある死者』に該当する。何故なら、これはどちらもキリストにあって既に死んでいる聖徒のことだからである。しかし黙示録20:4の箇所で『獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たち』と書かれているのは、我々が今見ている箇所で書かれている『キリストにある死者』に該当しない。何故なら、『獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たち』とは、死んではいない聖徒たち、すなわちまだ地上で生き続けていた聖徒たちのことだからである。読者は、我々が今見ている箇所とこの黙示録20:1~6の箇所(およびその付近の箇所)を互いに参照しつつ考究するがよい。そうすれば、この2つの箇所は互いに対応しているので、再臨および復活の事柄が更によく理解できるようになるはずである。
【4:17】
『次に、生き残っている私たちが、たちまち彼らといっしょに雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。』
次に復活したのは、その時に地上で生きている死んでいなかった聖徒たちである。この時、地上で生きていた聖徒たちは、少し不思議に聞こえるかもしれないが、生きながらにして生き返った。これは、つまり、生きている状態で罪の残滓がある古い身体から新しい御霊の身体に切り替えられた、ということである。驚く方もいるかもしれないが、このような復活の仕方もあるのだ。このようにして復活した聖徒たちは、肉体の死を経験することがなかった。この生きつつ生き返る復活について、パウロはコリント人に対して次のように言っている。『聞きなさい。私はあなたがたに奥義を告げましょう。私たちはみなが眠ってしまうのではなく、みな変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち、一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。』(Ⅰコリント15章51~52節)この復活は、パウロと一緒に生きていた紀元1世紀のテサロニケ人たちが『生き残っている』間に起きた。何故なら、パウロが御霊により、そのように書いているからである。御言葉と真っ直ぐ向き合う聖徒たちは、このことを純粋に信じる。真面目な聖徒たちは「アーメン。」と言わなければならない。その復活は再臨の時、すなわち紀元68年6月9日に起こった。しかし、恐らくパウロは生きながらにして生き返る人たちの中に含まれてはいなかったと考えられる。何故なら、伝承で言われているように、どうやらパウロは紀元68年6月9日よりも前にネロの手により殉教したようだからである。だが、ここではテサロニケ人たちの全体に対して語られているのだから、パウロがその中に含まれていなかったとしても特に問題とはならない。
この時に生きながらにして生き返った聖徒たちは、すぐ前に復活した死んでいた地上にいる聖徒たちと一緒に、携挙された。その携挙は一瞬の間になされた。『たちまち彼らといっしょに雲の中に一挙に引き上げられ』と書かれている通りである。そのようにして携挙された聖徒たちは、空中の場所で、再臨されたキリストと会ったのである。この時の再会ほど感動的な光景は他に無かったと思われる。何故なら、この出来事のように心を揺り動かす出来事は非常に珍しいからである。
そのようにして『空中で主と会』った聖徒たちは、キリストと共に空中に備えられた座に就いて、42か月の支配を遂行することになった。これは黙示録20:4~6の箇所で言われている出来事である。そうして42か月が終わると、第二の復活が起こり、空中の大審判が実施されることになった。これは黙示録20:11~15およびマタイ25:31~46で言われている出来事である。読者である聖徒たちは、この復活した聖徒たちが携挙されて空中で主と会うことになった、というだけの理解に留まらないようにするのが望ましい。我々は、その時に何が起こったのか、それからどういう展開になったのか、ということまで考えるべきである。そうしないと更に深い理解には達せない。必要なのは探究心と思考の努力である。我々は、エジソンのように、また「考える人」のようにならなければいけないのだ(※)。探らず考えない者に知識の広がりは与えられないであろう。
(※)
あのロダンの像があれほどまでに注目されるのは、明らかに忙しくて思考の余裕を持てない現代人にとって、あのような人が過去の遺物になってしまったからに他ならない。つまり、珍しいので注意を惹くわけである。ニーチェも「愉しい学問」の中で嘆いていたが、ソクラテスをはじめ、昔はあのような人が多くいたのである。現代人はほとんど思考をしない傾向を持つので、非常に表面的であり、やすやすと情報操作・プロパガンダの餌食になっているが、自分が騙されていることにさえ気付いていないのである。これは致命的な現代病であると言えるから、我々は思考の力を付けねばならない。私の経験から言えば、教会・神学界でも傾向として思考の力が衰えているように感じられる。とはいっても、これも私の経験から言えることだが、しっかりと思考するというのは生来的な性質に多くを負っている面もあると思われる。私は思考の人間であるが、それは何か意識して自発的に思考をしているというのではなく、小さい頃から自然と無意識的に深く考える性質を持っていたからである。エジソンもそのようであった。だから、生来的に深い思考にあまり傾かないような人、しかも日々の忙しさにより思考する余暇がなかなかとれないような人にとって、ロックのように思考する習慣を持つのは少々難しい部分もあるのかもしれない。深い思考をするのがなかなか難しいと思える人には、ひとまず次のようにしてみるのをお勧めしたい。何かの待ち時間がある際にスマートフォンを見るのではなく幾らかでもある事柄を集中して考えるようにしたり、寝る前に5分ほど思考する専用の時間を設け、気になっていることを集中的な思考により完全な解決へと至らせる、というのがそれである。とにもかくにも思考の効力は侮れない。思考をしなければ必ず表面的になり、常識や流行にただ流されるだけとなるのだ。
[本文に戻る]
なお、この箇所で言われている引き上げの出来事は、マタイ13章で言われている引き上げの出来事とは対応していない、という点に注意せねばならない。何故なら、我々が今見ている箇所で言われているのが第一の携挙であるのに対し、マタイ13章で言われているのは第二の携挙だからである。よくマタイ13章を見ていただきたい。そこでは明らかに聖徒たちだけでなく悪者も携挙されている。既に説明した通り、我々が今見ている箇所で携挙されるのは聖徒たちだけである。よって、この2つの箇所は携挙の内容がそれぞれ異なっているゆえ、対応していないことが分かるのだ。マタイ13章で書かれているのは、我々が今見ている箇所で書かれている出来事から42か月が経過してから起きた出来事である。
『このようにして、私たちは、いつまでも主とともにいることになります。』
携挙された聖徒たちは、それ以降、キリストから離れることがない。何故なら、天上におけるキリストと教会は、黙示録19章でも言われている通り、結婚した夫婦だからである。この地上における夫婦がずっと共に歩むように、天上におけるキリストと聖徒たちもずっと共に歩むのだ。この地上において離婚があるべきではない出来事であるのと同様、キリストと聖徒たちも天上において離れ離れになることは決してない。これ以降、今に至るまで、天上では聖徒たちがキリストと共に歩んでいる。これからもキリストと聖徒たちは共に歩むことになる。だから、この地上における夫婦は、天上における夫婦の影であると捉えることが出来る。何故なら、両者はよく似ており、地上におけるそれは天上におけるそれを鏡のように反映しているからである。もっとも、地上の夫婦においては多くの腐敗が常に付き物ではあるが。我々も、やがて天に挙げられたならば、そこでキリストと共に永遠に歩むようになる。それは、そのようになるのが聖徒たちに対する神の定めだからである。
【4:18】
『こういうわけですから、このことばをもって互いに慰め合いなさい。』
パウロは、もうテサロニケ人たちが死者のことで悲しみに沈まないようにと言っている。何故なら、パウロがここまで言った言葉により、テサロニケ人たちは間もなく死んだ聖徒たちと再会できるようになることを理解しただろうからである。ここでパウロはこう言いたいかのようである。「あなたがたテサロニケ人たちは間もなく再会できる死者たちのことで、どうして悲しんだりしているのか。そのようであってはいけない。あながたはもうすぐにも再会の喜びを得られるようになるのだから。」
このような慰めの言葉を、パウロは自信を持って告げることが出来た。何故なら、パウロは自分が神の霊によって語っていることをよく知っていたからである。神の霊により語るのであれば、自信を持たないようなことは起こりえない。というのも神の霊は全てを知っており、誤りを絶対に犯されない御方だからである。
我々も、既に死んだ聖徒たちのことで悲しみに沈まないようにすべきである。紀元1世紀のテサロニケ人たちでさえも悲しみに沈むべきではないとすれば、尚のこと、我々は悲しみに沈むべきではない。何故なら、もう今の時代において、死んだ聖徒たちは即座に新しい身体に切り替えられて天国に導き入れられるようになっているからである。我々も、これから即座に身体が切り替えられると同時に天国へと導き入れられるようになる。そうしたら、既に天国に入っていた聖徒たちと会えるようになるのだ。だから、我々は死んだ聖徒たちのことで悲しみに満ちる必要がない。もし我々が世の人のように死者のことで悲嘆するのであれば、それは我々が死者の復活と再会の喜びとを信じていないということを意味している。つまり、それらを信じていないからこそ、死者のことで大いに悲しみ嘆くわけである。私がある教会の葬式を見たところ、それはこの世の葬式とはまったく似ていなかった。そこでは、棺桶に入っている死者の顔を見た信徒たちが、顔に微笑みを浮べているほどであった。これは非常に理に適っている。もし本当に復活と再会のことを信じていたとすれば、このようになるのが自然だからである。復活と再会について確信していながら顔色を暗くするほうが、かえっておかしいのである。
【5:1~2】
『兄弟たち。それらがいつなのか、またどういう時かについては、あなたがたは私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなたがた自身がよく承知しているからです。』
テサロニケ人たちは再臨の起こる日である『主の日』の到来について、パウロたちから何かを知らされる必要が無かった。テサロニケ人たちはその日について、既によく知っていたからである。よく承知しているにもかかわらず、あたかも承知していないかのように何かを語るのは、一種の愚弄である。パウロは愛を追い求める人だったから(Ⅰコリント14:1)、そのようなことをしようとはしなかった。愛とは「礼儀に反することをしない」(参照:Ⅰコリント13:5)ことだからである。
この主の来られる日は、あたかも『夜中の盗人』が来るかのようであった。つまり、それは予期していない時に、突如として訪れた。これは実際その通りであった。一体どこの誰が紀元68年6月9日に主が来られるなどと思っただろうか。誰もそのようなことは思わなかったに違いない。誰もそのように思わなかったとすれば、再臨は予期していない時に実現したことになる。それは、ちょうど911のテロが唐突に起きて多くの人たちを驚愕させた時のようであった。
【5:3】
『人々が「平和だ。安全だ。」と言っているそのようなときに、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが臨むようなもので、それをのがれることは決してできません。』
主の再臨される日は、人々が安全にしている何事も無いような時に訪れた。それが神のやり方であった。このようにして再臨の日が来れば、人々は神を崇め、恐れ、敬い、軽んじることもそれだけなくなる。神はそのようにして御自身の栄光を表わされるのだ。もしこれが普通のやり方であれば、どうだったか。もし平凡な感じで主の日が訪れたとすれば、それだけ人々が神を崇めたり、恐れたり、軽んじたりすることもなくなる。そうすれば、それだけ神の栄光も表れなくなってしまうのだ。このように神は、人間の意表を突くような特異な手法で、事を実現させられる。これこそ神が『不思議』と言われる理由である。このようして事を為される神を嘲る者も世の中には少なからず見られる。我々は、そのような霊的事柄を弁えられない知恵の無い愚か者たちを放っておくべきである。彼らは死んでいるゆえ、神について何を聞かされても理解することが出来ないのだから。
ここでパウロが言っている内容は、キリストが福音書の中で言われた内容と対応している。キリストも、人々が普通に生活している時に、突如として再臨が起こると言っておられた。すなわちこうである。『人の子が来るのは、ちょうど、ノアの日のようだからです。洪水前の日々は、ノアが箱舟にはいるその日まで、人々は、飲んだり、食べたり、めとったり、とついだりしていました。そして、洪水が来てすべての物をさらってしまうまで、彼らはわからなかったのです。人の子が来るのも、そのとおりです。』(マタイ24章37~39節)『しかし、このことは知っておきなさい。家の主人は、どろぼうが夜の何時に来ると知っていたら、目を見張っていたでしょうし、また、おめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だから、あなたがたも用心していなさい。なぜなら、人の子は、思いがけない時に来るのですから。』(同24章43~44節)パウロがこのキリストの御言葉をよく知っていたということは間違いない。つまり、パウロはキリストの御言葉をベースとして、この箇所を書いたのである。
【5:4】
『しかし、兄弟たち。あなたがたは暗やみの中にはいないのですから、その日が、盗人のようにあなたがたを襲うことはありません。』
聖徒たちに、この主の日が盗人のように襲いかかることはなかった。つまり、聖徒たちにとって、その日は盗人に押し入られるかのように悲惨な日ではなかった。何故なら、聖徒たちにとって、この日は幸いをもたらす日だからである。一方、聖徒でない者たちにとって、この日は盗人が夜中に押し入るかのように襲いかかった。つまり、彼らにとって、この日は実に悲惨であった。何故なら、彼らはこの日、永遠の断罪を受け、滅びの宣告を下されたからである。この霊的な裁きについてはパウロがⅡテサロニケ1:8~9の箇所で語っている。彼らの場合、救われていない状態で主の日を迎えるよりは、盗人に押し入られて全財産を奪われたほうが遥かにましであった。
しかし、どうして聖徒たちには主の日が盗人のように襲いかかることが無かったのか。それは、次の節でも書かれているように、聖徒たちは『光の子ども、昼の子ども』だからである。盗人は、光が照らされている所や、昼の時間帯には、何かを盗もうとして家の中に侵入しないものである。だから、主の日は、輝かしい子らである聖徒たちに盗人のように襲いかかることが無かったのである。つまり、主の日は、聖徒たちを襲おうとも襲いかかることが出来なかった。それは盗人が光や昼のゆえに家の中に押し入ることが出来ないのと同じである。この盗人という存在は、誰かに犯行が見られることを恐れているので、闇の満ちている場所や、夜の時間帯に活動するものである。だから、暗黒の子たちには、主の日が盗人のようにして襲いかかった。彼らは『夜や暗やみの者』(Ⅰテサロニケ5:5)だったので、彼らに対して主の日は盗人のように襲いかかるしか無かった。要するに「信仰」である。信仰を持っているかどうかが、この時に主の日が盗人のように襲いかかるか襲いかからないかを決定づけた。信仰を持つ光の子たちにはこの日が救いの光をもたらし、信仰を持たない闇の子たちにはこの日が滅びの闇をもたらした。
【5:23】
『主イエス・キリストの来臨のとき、責められるところのないように、あなたがたの霊、たましい、からだが完全に守られますように。』
パウロの言っている『来臨』は既に起きた。これについては既に証明済みであるから、ここで再び証明する必要はないであろう。私はここで言いたい。再臨における真理を認め受け入れることに臆病になってはならない、と。聖書では強くあるようにと聖徒たちに命じられている。強くあらねばならないのは、聖書の真理を考究する学問である神学の領域においても同様である。聖徒たちは主の強者として、再臨の真理を受容すべきなのである。臆病になっていれば、いつまでも再臨の真理を獲得することは出来ない。本書における再臨の見解を受け入れないことは臆病がその原因ではない、などと抗弁することは出来ない。何故なら、これまでに本書の見解に対して真正面から真面目に反論できた人は誰もいないからである。もしこの見解を反論するならば、その見解を反論すると同時に御言葉をも否定せねばならなくなってしまう。聖徒たちのうちに住んでおられる神の霊は、聖徒たちがそのようにすることを御許しにはならない。何故なら、御言葉とは神の霊がお書きになったものだからである。だからこそ、聖徒たちは誰も彼も私が再臨の正しい見解を示すと何も反論できず黙り込んでしまうのである。もし反論したら御言葉を攻撃せねばならなくなるのだから、反論しようにも反論できるはずがないではないか!!
ここでパウロは、紀元1世紀の聖徒たちが再臨の時に『責められるところのないように』と願っている。何故なら、再臨の時に責められるというのは実に悲惨なことだからである。いったい、どこの誰が再臨されたキリストから次のように言われたいであろうか。『わたしはあなたがたを全然知らない。不法をなす者ども。わたしから離れて行け。』(マタイ7章23節)
『役に立たぬしもべは、外の暗やみに追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのです。』(マタイ25章30節)要するに「責められる」とは、責められて地獄に投げ入れられることを意味している。これは、あまりにも恐ろしいことである。だから、パウロが再臨のキリストから責められないようにと聖徒たちのために願っていたのは、当然のことであった。
またパウロは、聖徒たちの『霊、たましい、からだが完全に守られますように』とも願っていた。聖書において、多くの場合、人間のことは「魂と身体」とだけ言われている。これは人間における目に見えない部分と目に見える部分という意味である。プラトンやアリストテレスといった世の哲学者たちも、人間がこの2つから成り立っていると理解していた。しかし、ここでは3種類のことが言われている。つまり、普通に言われる場合に比べて、ここでは「霊」が加えられている。これは、人間の魂における霊を司る部位のことを指している。これは聖徒たちに与えられた神の霊のことではない。何故なら、これは『あなたがたの霊』と言われているからである。もしこれが神の霊だとすれば、『あなたがたの霊』とは書かれていなかったであろう。これを神の霊として解するのは、神の霊を愚弄することである。何故なら、神の霊は守られるようにと願われるような御方ではないからである。神の霊が弱く、あたかも被造物でもあるかのように守られるという保護を必要としているとでもいうのか。とんでもないことである。
『来臨』は最早起こらない。聖書を正しく読み解くのであれば、確かにこのように考えねばならない。しかし、ここでパウロが願っていることは、今でも願われるべきことである。すなわち、周りの聖徒たちが最終的に神の怒りを受けて責められることがないように、また彼らの霊と魂と身体が完全に守られるように、と願うことである。再臨がもう起きないからといって、ここでパウロが願っていることを我々も願わなくてよい、ということには全然ならない。ここでパウロが願っている2つの事柄は、明らかに神の御心に適った願いである。それゆえ、我々は今でも地上に生きている仲間たちのために、ここでパウロが願っている事柄を再臨後の時代に相応しい内容に言い換えて願うべきなのである。そうすれば祈りが聞かれて、より多くの仲間たちがキリストから脱落することなく、キリストのおられる天国に無事入れるようになることであろう。
第55章 53:テサロニケ人への手紙Ⅱ
Ⅱテサロニケ書も、Ⅰテサロニケ書と同様、絶対に研究すべきである。この文書からも再臨のことが大いに学べるからである。特に2:1~12の箇所は、大いに注目せねばならない。そこでは再臨されたキリストが不法の人であるネロを裁かれることについて預言されているからだ。
【1:5】
『このことは、あなたがたを神の国にふさわしい者とするため、神の正しいさばきを示すしるしであって、あなたがたが苦しみを受けているのは、この神の国のためです。』
テサロニケの聖徒たちは、『迫害』(Ⅱテサロニケ1:4)による苦しみを受けていた。これは、テサロニケ人たちが、神の御前に正しく歩んでいる証拠であった。何故なら、『確かに、キリスト・イエスにあって敬虔に生きようと願う者はみな、迫害を受け』(Ⅱテモテ3章12節)るからである。それゆえ、迫害を受けているかどうかということは、敬虔であるかそうではないかということの指標である。基本的に、迫害を受けていればキリストにおいて敬虔に歩んでおり、迫害を受けていなければ敬虔に歩めてはいない。「基本的に」と言ったのは、アリウスやエホバの証人たちのような異端者であっても迫害を受けることがあるからである。このような異端者どもの場合、たとい迫害を受けて苦しんでいたとしても、キリストにあって敬虔に歩んでいることにはならないのだ。
このテサロニケ人たちが迫害の苦しみを受けていたのは、神が彼らを『神の国にふさわしい者とするため』であった。この『神の国』とは、天上における神の国すなわち天国のことを言っている。つまり、これは使徒行伝14:22やマタイ25:34の箇所における「神の国」と同一の意味である。それで、テサロニケ人たちは、どうしても天国に入る者として相応しくなるために苦しまねばならなかった。つまり、彼らは天国の住民となるのだから、この地上にいる時から既に研ぎ澄まされなければいけなかった。それは、ちょうど第1級の演劇の舞台に出演することになったダンサーが、非常な努力と苦しみをもって自己を鍛錬しなければならないのと同じである。そうしなければ、舞台に出演した際に恥を見たり失敗したりすることになるからである。もし聖徒たちが信仰に伴う苦しみを耐え忍ぶのであれば、その聖徒たちは完全になる。ヤコブが次のように言う通りである。『私の兄弟たち。さまざまな試練に会うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰がためされると忍耐が生じるということを、あなたがたは知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば、あなたがたは、何一つ欠けたところのない、成長を遂げた、完全な者となります。』(ヤコブ1章2~4節)天国とは完全な場所だから、そこに入ることになっていたテサロニケ人たちは苦しみを耐えて『完全な者』とならねばならなかった。とはいっても、我々はこの箇所を読んで、苦しみを耐えるというその行ないがテサロニケ人たちが天国に入るための方法となっていたのではない、という点に注意せねばならない。というのも、そのような方法によって天国に入ると考えるのは行為義認であって、もしそのような行ないが人を天国に入れるための要件であれば、もはや神の恵みによる救いなど必要なくなるからである。言うまでもなく、人が天国に入るのは恵みによるのであって、それはイエス・キリストを信じることによる。
一方、滅びに定められていた迫害者たちにとって、テサロニケ人たちを迫害することは『神の正しいさばきを示すしるし』であった。パウロは、迫害者たちの迫害が「裁きの印」であると言う。これは、つまりその迫害行為が、あらかじめ彼らが裁かれるということを預言的に示しているという意味である。このような迫害者たちは、永遠の昔から、神の恐るべき裁きを受けるようにと定められていた。だからこそ、その定めの通りに裁かれるべき者となるために、テサロニケ人たちを迫害するという悪を行なったのである。何故なら、そのように迫害をすれば、やがて定められた通りに神の裁きを受けたとしても弁解の余地が無くなるからである。だから、当時のテサロニケ人たちは自分たちを苦しめる者たちの迫害行為を見て、「ああ、この者たちはやがて裁きを受けるために、このようなことをしているのだ。」と知ることが出来た。というのも、その迫害行為は「さばきを示すしるし」だからである。
【1:6~7】
『つまり、あなたがたを苦しめる者には、報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなたがたには、私たちとともに、報いとして安息を与えてくださることは、神にとって正しいことなのです。』
テサロニケ教会の聖徒たちを苦しめる迫害者たちには、『報いとして苦しみ』が与えられることになった。この『苦しみ』とは、地獄での永遠の刑罰を指す。彼らは神の聖徒たちを苦しめたので、当然の報いとして、自分たちも神から苦しめられるのだ。というのも、聖徒たちを苦しめるのは、「あなたに触れる者は私の瞳に触れる者だ。」と神が言われた通り、神を苦しめることだからである。神は報いられる御方だから、聖徒たちを通して御自身を苦しめる迫害者たちに、苦しみの刑罰をお与えになることで報いられる。それは箴言24:12の箇所で、ソロモンが『この方はおのおの、人の行ないに応じて報いないだろうか。』と言った通りである。人は自分の蒔いた種を刈り取らねばならない(ガラテヤ6:7)。それゆえ、テサロニケ人たちを迫害していた者たちは、非常に悲惨であった。何故なら、その迫害者たちは、裁きという名の実を刈り取るために、迫害という名の種をせっせと撒いていたのだから。
テサロニケ人たちは、この迫害者たちとは逆で、その受けた苦しみに対して『報いとして安息を』受けることになった。それは『私たちとともに、』すなわち『パウロ、シルワノ、テモテ』(Ⅱテサロニケ1章1節)と共にであった。この『安息』とは、もちろん天国のことを言っている。この箇所では、このように天国の安息が『報いとして』与えられると言われているが、これは本当の意味で報酬として天国が与えられるという意味ではないことに注意せねばならない。聖書では、他にも、このように言われている箇所が見られる。今に至るまでカトリック教会は、このような聖句を、行為義認という異端の教理の根拠としてきた。何故なら、そこでは救いや天国に入ることが、あたかも行為に対する報酬として与えられるかのように言われているからである。だが、天国に入ることについて『報いとして』と言われているからといって、聖徒たちの行為が天国に入る功績を作り出すなどと考えるのはまったく誤っている。何故なら、パウロがⅠコリント4:7の箇所で言っていることからも分かるように、あらゆる幸いは報酬ではなく恵みとして与えられるからである。聖書は、恩寵によって与えられる幸いを、あたかも聖徒たちがそれに値するかのような行為をしたかのごとくに『報い』と言っているだけに過ぎない。つまり、単に言い方が問題なのである。これについては、今までに多くの正統的な教師たちが十分に論じていることである。さて、このテサロニケ人たちにとって、迫害者たちから与えられていた迫害の苦しみは、これからテサロニケ人たちが安息の報いを受けるようになる言わば前触れとしての印であったと言ってよい。それだから、テサロニケ人たちは自分たちが苦しめられているのを見て、「ああ、私たちが苦しめられているのは、やがて安息を受けるようになるからなのだ。」と知ることが出来た。これは、先に見た迫害者たちの場合とは、まったく正反対である。
神が、このように両者に対してそれぞれ相応しい報いを与えられるのは、『神にとって正しいこと』であった。それというのは、神とは義なる完全な審判者であられるからである。神は完全に正しい審判者だから、キリストによって清められた者たちには幸いな報いを、悪い者たちには悲惨な報いを与えられる。神なる審判者は、往々にして間違った審判をしがちな人間の審判者とは、まったく違った審判者である。それだから、神がテサロニケ人たちには良い報いを与えて迫害者たちには悪い報いを与えられるのは、神にとって誠に当然のこと、自然なことであった。何故なら、そのようにするのが正義に適っているからだ。もし神がこの両者にこのような報いを与えられなかったとすれば、神は義なる審判者であられることを放棄されたことになっていた。
【1:7】
『そのことは、主イエスが、炎の中に、力ある御使いたちを従えて天から現われるときに起こります。』
この2つの種類の人たちに対する報いは、キリストが再臨される時に与えられることになった。それは間近に迫っていた。だからこそ、パウロは他の箇所で『主は近いのです。』(ピリピ4章5節)と言い、ヤコブも『主の来られるのが近い』(ヤコブ5章8節)と言ったのである。その時、テサロニケ人たちは携挙され、キリストと共に天国に住まうようになった。しかしテサロニケ人たちを苦しめていた迫害者たちは、そのようにならなかった。彼らに対する裁きについては続く箇所(1:8~9)で詳しく語られている。
既に述べられている通り、この再臨が起きたのは紀元68年6月9日であった。聖徒たちは、再臨が起きた時期について、誤って考えないように注意せねばならない。もし再臨の時期を正しく理解できないと、必然的に再臨と再臨の時期に起こる諸々の出来事についての理解も不完全なものとならざるを得ないからである。
この箇所では、キリストの再臨について幾らかのことが語られている。まず、キリストは再臨の際に『天から現われ』た。これは、キリストが昇天により天におられたからである。また、キリストが再臨されるのは『炎の中に』であった。これは再臨の栄光がより際立つようになるための演出的な御業である。カルヴァンは、この『炎』を単なる象徴表現に過ぎないと見る。だが、これは実際的な物理現象について言われていると捉えるべきであろう。何故なら、実際の炎に包まれて再臨が起きるほうが、より再臨の栄光が引き立つのは誰の目にも明らかだからである。キリストが『炎の中に』再臨されるというのは、イザヤ66:15の箇所でも言われていた。そこでは、『見よ。まことに、主は火の中を進んで来られる。』と書かれている。またキリストが再臨される際には『力ある御使いたち』が一緒に現われた。この御使いの数はマタイ25:31の箇所では『すべて』と書かれている。つまり、キリストの再臨がより壮大な出来事となるように、あらゆる御使いたちが動員された。この御使いたちは『力ある』者たちであった。御使いに力があるというのは詩篇103:20の箇所でも言われている。御使いたちは、神の御心を豊かに遂行するために、大きな力が付与されている。大きな力があってこそ、神の御心を力強く成し遂げることが出来るからである。もし御使いに力が無かったならば、何も出来ない小さな子どものように、御使いが神の御心を成し遂げるのは困難であった。
【1:8~9】
『そのとき主は、神を知らない人々や、私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は、主の御顔の前とその御力の栄光から退けられて、永遠の滅びの刑罰を受けるのです。』
この箇所では、2つの人たちが挙げられている。まず『神を知らない人々』とは、世界の創造主である三位一体の神を知らない人たちを指している。たとえゼウスやアポロンなどといった神々を信じていても、三位一体神を信じていないのであれば、その人は『神を知らない人々』に数えられる。何故なら、三位一体の神以外の神は偽物の神であり、実際には存在しない神だからである。ガラテヤ教会の聖徒たちは、かつて異教徒だった時には、神を知らない人々であった(ガラテヤ4:8)。これはエペソ教会の聖徒たちも同様であった(エペソ2:11~12)。次に『主イエスの福音に従わない人々』とは、三位一体の神を知ってはいるものの、キリストの福音には服従していない偽善者たちである。つまり、これは毒麦・山羊のことを言っている。具体的に言えば、これはあのアナニヤがそうである。この者は三位一体の神を知ってはいたが、実は偽善者であって、福音の前に謙虚にひざまづいてはいなかった。要するに、この2つの人たちは「滅びの子ら」という言葉で一括りにすることが出来る。
キリストが再臨された際、この滅びの子たちは、永遠の裁きを受ける者たちとして霊的な断罪を受けた。『永遠の滅びの刑罰を受ける』とは、そういう意味である。それは彼らが再臨の起こる時までにキリストを信じ救われていなかったからである。また彼らは再臨の際に『主の御顔の前とその御力の栄光から退けられ』たが、これは「御力の栄光を持って再臨されたキリストの御顔の前において受容されなかった。」というほどの意味である。というのも、彼らはキリストとその救いを受け入れることが無かったからである。彼らがキリストとその救いを拒絶したので、キリストも報いられて彼らを拒絶されたわけである。これは戦いから凱旋した王が、かつてから王を憎んでいた裏切者の臣下や民衆にこう言うようなものであった。「君たちは前々から私のことを苦々しく思っていたのだから、この喜ばしい時に私の前に立つことは決して許されない。速やかに私の前から消え失せるがよい。」
この箇所で言われていることは、イザヤ66:15~16の箇所と対応している。そこでは次のように書かれている。『見よ。まことに、主は火の中を進んで来られる。その戦車はつむじ風のようだ。その怒りを激しく燃やし、火の炎をもって責めたてる。実に、主は火をもってさばき、その剣ですべての肉なる者をさばく。主に刺し殺される者は多い。』ここでも、キリストが再臨されると、多くの者たちが霊的な断罪を受けることになると言われている。また、マタイ16:27の箇所とも対応している。キリストはそこでこう言っておられる。『人の子は父の栄光を帯びて、御使いたちとともに、やがて来ようとしているのです。その時には、おのおのその行ないに応じて報いをします。』ここでも再臨の時には報復が為されると言われている。また、黙示録19:11~21の箇所とも対応している。そこでも、キリストの再臨が起きると多くの者に御言葉による裁きが下されると預言されていた。
【1:10】
『その日に、主イエスは来られて、ご自分の聖徒たちによって栄光を受け、信じたすべての者の―そうです。あなたがたに対する私たちの証言は、信じられたのです。―感嘆の的となられます。』
『その日』は既に訪れた。この日が未だに訪れていないと考えている人は、パウロがⅠテサロニケ4:15の箇所で当時の聖徒たちの存命中に主は再び来られると言っていることを、何も考えていない。もしそのことを考えていれば、この日が未だに訪れていないなどとは考えず、私が本書の中で述べた見解を受け入れていただろうからである。
キリストは再臨された際、聖徒たちによって誉れをお受けになられた。ここでは、そのことが異なる言い方で繰り返して言われている。すなわち、『ご自分の聖徒たちによって栄光を受け』という部分が1回目であり、『感嘆の的となられます。』という部分が2回目である。これはヘブル特有の強調表現である。つまり、パウロはキリストが聖徒たちを通して誉れを受けられるということを、テサロニケ人たちに豊かに伝えようとしているのである。また、我々は再臨が起きた時、キリストは2重の栄光に包まれたということを知るべきであろう。つまり、キリストは再臨された時から既に栄光に包まれていた上、更に『ご自分の聖徒たちによって栄光を受け』られた。これは栄光をもって凱旋した王が、王の帰りを待ち構えていた民衆の称賛によって更に栄光を受けるのと同じである。
この箇所で難しいのは、「パウロたちの証言が信じられた」と言われている部分である。これは一体どういう意味であるか。私はこう考える。パウロは、やがてキリストは再臨された際に聖徒たちによって誉れをお受けになられるということを、前々からテサロニケ人たちに証言していた。その証言は実際に再臨の時に実現されることになったが、それはその証言がその証言の通りに信じられた通りであった。こういうことを、パウロはここで言っているのであろう。
【1:11】
『そのためにも、私たちはいつも、あなたがたのために祈っています。』
パウロたちは、キリストがテサロニケ人たちによって誉れをお受けになられるようにと、いつも祈っていた。これはキリストのための祈りであった。何故なら、パウロたちはキリストの誉れを求めていたからである。また、これはテサロニケ人たちのための祈りでもあった。何故なら、テサロニケ人たちによってキリストが誉れをお受けになられるのは、キリストを主とするテサロニケ人たちにとっても喜ばしいことだからである。テサロニケ人たちをはじめキリストの僕とは、キリストを己の喜びとする者たちである。要するに、パウロたちは神への愛と隣人への愛を、祈りの中で実践していた。我々もパウロたちに倣って、キリストと他の聖徒たちのために祈るべきであろう。
『どうか、私たちの神が、あなたがたをお召しにふさわしい者にし、また御力によって、善を慕うあらゆる願いと信仰の働きとを全うしてくださいますように。』
パウロたちは、テサロニケ人たちが『召しにふさわしいものに』なるようにと祈っていた。これは、テサロニケ人たちが神の召しに相応しく歩むことで、キリストが大いに誉れをお受けになられるためであった。弟子や臣下や部下が上に立つ者の意志に従って歩むならば、それはその上に立つ者の名誉が増し加えられることに繋がる、というのはこの世において自然なことである。テサロニケ人たちという弟子とキリストという主においても、これは同様であった。
またパウロたちは、テサロニケ人たちに神が『善を慕うあらゆる願いと信仰の働きとを全うしてくださ』るように祈っていた。これは、「神がテサロニケ人たちの善をしたいと思う願いおよび良く歩むための信仰の熱心を全うして下さることで、テサロニケ人たちが善の実に満ちた敬虔な人生を送れるように。」というほどの意味である。簡単に言えば、これは「テサロニケ人たちが良い行ないと敬虔に富むように。」ということである。これも先の場合と同様、テサロニケ人たちが幸いな行ないをしたり敬虔に歩んだりすることで、キリストが豊かに誉れを受けられるようになるためであった。
パウロたちのこの祈りは、神に聞き入れられたに違いない。何故なら、これは明らかに御心に適った祈りだからである。ヨハネは次のように言っている。『何事でも神のみこころにかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願う事を神が聞いてくださると知れば、神に願ったその事は、すでにかなえられたと知るのです。』(Ⅰヨハネ5章14~15節)もしパウロたちが不敬虔な悪者であったとすれば、この祈りが聞き入れられていたかどうかは分からない。何故なら、『神は、罪人の言うことはお聞きになりません。』(ヨハネ9章31節)と言われているからである。しかし、言うまでもなくパウロたちは敬虔に歩む幸いな者たちであった。だから、神はパウロたちのテサロニケ人たちに関する願いを叶えて下さったことであろう。次のようにヨハネ9:31では言われている。『だれでも神を敬い、そのみこころを行なうなら、神はその人の言うことを聞いてくださる』。我々も、パウロたちが祈ったように、聖徒たちに神が『善を慕うあらゆる願いと信仰の働きとを全うしてくださ』るようにと祈るのが望ましい。そうすれば、それは御心に適った祈りであるから、神は必ずやその祈りを聞き入れて下さるはずである。
【1:12】
『それは、私たちの神であり主であるイエス・キリストの恵みによって、主イエスの御名があなたがたの間であがめられ、あなたがたも主にあって栄光を受けるためです。』
パウロたちがテサロニケ人たちのために祈っていたのは、テサロニケ人たちの間でキリストの御名が崇められるようになるためでもあった。というのも、聖徒たちが敬虔に歩むようになれば、自然とキリストを崇めるようにもなるからである。聖徒たちは敬虔に歩んでいる時、その敬虔な歩みが神の恵みにより与えられていることを知っている。そのことを知れば、やはり当然ながら神への感謝が生じるようにもなる。何故なら、神の恵み抜きに敬虔な歩みは有り得ないからである。そのようにして感謝が生じるようになれば、必然的にキリストの御名を崇めることにもなるのである。
またパウロたちがテサロニケ人たちのために祈っていたのは、テサロニケ人たちも『主にあって栄光を受けるため』であった。ここで、いくら聖徒たちといっても栄光を受けていいのだろうか、栄光とは神にこそ相応しいものではないのか、などと疑問を持つ方がいるかもしれない。このような疑問は、不信や悪意からではなく、敬虔な思いから出たのだと思う。確かに、聖書は栄光が神だけのものであると教えている。例えば、詩篇115:1ではこう書かれている。『私たちにではなく、主よ、私たちにではなく、あなたの恵みとまことにために、栄光を、ただあなたの御名にのみ帰してください。』神御自身もイザヤ48:11で、『わたしはわたしの栄光を他の者には与えない。』と言っておられる。だから、このような聖句を知っている聖徒であれば、ここでパウロが言っていることを読んで、少し戸惑ったりしたとしても無理はないと言えるかもしれない。しかし、ここでテサロニケ人たちが『栄光を受ける』と言われているのは、何も問題がない。何故なら、ここでは神にだけ帰されるべき神に特有の栄光がテサロニケ人たちにも与えられるように、ということが言われているのではないからである。ここで言われているのは、神に帰されるべき栄光ではなく「僕としての栄光」である。つまり、ここでは単に「キリストの僕として敬虔に歩んだことでキリストにおいて神から褒めていただけるような者となるように。」ということが言われているに過ぎない。ちょうど大人が子どもに対して「よくやったね。お利口さんだ。」と言えば、そこにおいてその子どもは子どもとしての栄光を受けることになるが、ここで言われているのはそれと同様のことである。もしここで神に帰されるべき栄光がテサロニケ人たちにも付与されるようにと言われていたとすれば、それは冒涜的なことであった。我々も、キリスト・イエスにおいて敬虔に歩むべきであろう。そうすれば我々も『主にあって栄光を受ける』ことが出来るのである。
ところで、この箇所では、明白にキリストが『神』であると言われている。世の中には、キリストを神と信じていない異端者・異教徒・不信者たちが多くいる。彼らは言う。「キリストが神であるとは信じない。」または「キリストが神であるかどうかは分からない。」と。しかし、この箇所で、パウロはキリストが神であると断言している。我々は、彼らが何と言おうとも、彼らの不信仰な認識に惑わされることがあってはならない。もし聖徒たちがキリストを神と信じなくなったのであれば、その聖徒は正しい信仰から逸れたのであって、やがて地獄に投げ込まれることになるであろう。キリストが神であられるというこのことについては、他にもヨハネ20:28、ローマ9:5、テトス2:13、Ⅱペテロ1:1、Ⅰヨハネ5:20の箇所を忘れるべきではない。
【2:1】
『さて兄弟たちよ。私たちの主イエス・キリストが再び来られることと、私たちが主のみもとに集められることに関して、あなたがたにお願いすることがあります。』
『さて』と言って、パウロは新しい話に切り替えている。これまでは、テサロニケ人たちと迫害者たちがキリストの再臨の際に報いを受ける、ということについて語られていた。これからは、再臨の前に現われる不法の人のことについて語られることになる。話を項目ごとに秩序立てて書き記す、というのが聖書の常とするところである。我々が今見ている箇所もその通りである。
『私たちの主イエス・キリストが再び来られること』とは、もちろん再臨を言っている。これは既に起こった。『私たちが主のみもとに集められること』とは、携挙を言っている。これも既に起こっている。ここで『私たちが』と言われているのは、パウロと共にいた紀元1世紀の聖徒たちであったことに、今の教会の聖徒たちは注意すべきである。つまり、これは21世紀に生きる我々まで含んだ『私たちが』という意味ではない。もちろん、21世紀に生きる我々も、やがてこの人生を終えた後に個別的に天に引き上げられ、そこにおられるキリストの御許に導かれるようになる。しかし、この箇所で言われている直接的な対象は、紀元1世紀の聖徒たち、つまり携挙が起こる時までに生きていた聖徒たちだけである。ここまでの内容を弁えることの出来た聖徒であれば、このことは容易に理解できることであろう。
【2:2】
『霊によってでも、あるいはことばによってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり、心を騒がせたりしないでください。』
当時のテサロニケ教会には、『主の日がすでに来たかのように言われ』ている話が聞かれた。もちろん、テサロニケ教会にいた全ての聖徒たちが、そのような話に迎合していたというわけではない。これは多くの人の心を引き寄せる強力な噂話のようなものだったと考えればよい。ちょうど、ネロが死んだという話がローマ人の間に広がったが、実はまだ死んでいなかった、というあの時のような状態があったのだと思われる。キリストは、このような話が拡がるようになることを、あらかじめ知っておられた。だからこそキリストはマタイ24:23の箇所で次のように言われたのであった。『そのとき、『そら、キリストがここにいる。』とか、『そこにいる。』とか言う者があっても、信じてはいけません。』ここでキリストが言っておられる者たちは、要するに「『主の日がすでに来た』」と言う者たちのことである。『霊によって』とは、その人自身の霊によって、既に主の日が来たと思うことである。これは肉体に対する霊の部分のことを言っている。これを神の霊または悪霊と理解してはならない。『ことばによって』とは、誰かの言葉を通して、既に主の日が来たと思うことである。テサロニケ教会の聖徒たちの中には、ある人たちが『主の日がすでに来た』と言っている言葉を聞いて真に受けていた人たちがいたのだ。このように言う者たちは、かなりいたのだと思われる。だからこそ、ここでパウロはその人たちの言っていることを問題にしているのだ。『私たちから出たかのような手紙によって』とは、つまり偽使徒の手紙を読んで、既に主の日が来たと思うことである。パウロは偽使徒たちに悩まされていたが、この偽使徒たちは実際の使徒が書いたかのような手紙を当時の教会に送って読ませていた。彼らがそのようにしたのは、選ばれた聖徒たちを惑わして信仰を歪めるためであった。それでは、当時のテサロニケ教会に『主の日がすでに来た』かのように思ったり言ったりしていた人たちは、実際にどれぐらい存在していたのか。これについては知る術がないから、かなり存在していたとは思われるが、実際にはどれぐらい存在していたのか分からないと言うしかない。なお、ここで『主の日』と言われているのは、キリストが再臨される日のことである。ヨハネも黙示録1:10の箇所で『主の日』と言っているが、こちらのほうはまた意味が異なっている。ヨハネが『主の日』と言ったのは、既に説明した通り、皆で集まって一緒に礼拝を捧げる日曜日のことである。
パウロは、このような話が見られた当時のテサロニケ教会の聖徒たちに対して、動揺してはならないと要請している。何故なら、そのような話はまったくの出鱈目だったからである。出鱈目な話を聞いてアタフタしてしまうほどに惨めなことはない。キリストがマタイ24:23の箇所で聖徒たちに注意を促されたのも、やはり同様の理由からであった。
21世紀の時代となった今でも、出鱈目な話が、霊的であるか世俗的であるかを問わず、どの分野・どの場所でも聞こえてくるものである。その代表的な例は、「キリストはもう間もなく来られる。」というキリスト教会でよく聞かれる話である。これは聖書の研究不足と無知に基づくとんでもない出鱈目話であって、既にここまで読み進められた読者であれば分かると思うが実に非聖書的であり、更にはイルミナティでさえキリスト教徒たちがこのような話を熱心に受け入れてほしいと願っているほどである。我々は、このような類の出鱈目話を聞いて、『すぐに落ち着きを失ったり、心を騒がせたりし』てはならない。何となれば、信仰とは決して揺るがないことだからである。もし出鱈目な話を聞いて揺らいでしまうのであれば、我々の信仰はまだまだ堅固でないということを意味しているのである。
【2:3】
『だれにも、どのようにも、だまされないようにしなさい。なぜなら、まず背教が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現われなければ、主の日は来ないからです。』
このような出鱈目な話に騙されないようにと、パウロはテサロニケ教会の聖徒たちに命じている。
どうして、そのような出鱈目な話に騙されるべきではなかったのか。それは、先にも述べた通り、出鱈目な話に騙されるのは馬鹿げているからである。確かにテサロニケ教会には、『主の日がすでに来た』のではないかと思っている聖徒たちがいた。しかしパウロは、『不法の人』が現われ『背教が起こ』らない限りは、主の日が訪れないとここで言っている。まず『不法の人』とは、既に説明されているように「ネロ」を指している。それは、この不法の人が『神の宮の中に座を設け』るのでキリストがマタイ24:15の箇所で言っておられる『荒らす憎むべき者』と同一の人物であり、その『荒らす憎むべき者』はダニエル書によれば42か月の活動をするから黙示録13章の獣と同一の人物であり(ダニエル書12:11、黙示録13:5)、この黙示録13章の獣とは『666』(黙示録13章18節)の数字をその名前の中に潜めているのだから「ネロ・カエサル」を指している、という説明により証明することが出来る。この『不法の人』は、私が今した説明によらなければ、正しく理解することが出来ない。というのも、この説明こそが唯一の正しい説明だからである。他にこの『不法の人』についての聖書的な説明があるのであれば、是非とも私に知らせ、私を唸らせ悩ませてほしいものだ!!!このネロが『不法の人』と言われているのは、ネロが神の律法に違反してばかりいたからである。これはネロについて記された歴史書を読めば分かることである。またネロが『滅びの子』とも言われているのは、ネロが聖徒たちとユダヤに滅びをもたらす者だったからである。実際、この暴君は聖徒たちを滅ぼそうとしたし、ネロがユダヤを鎮圧せよと命じたからこそユダヤの滅亡を引き起こしたユダヤ戦争が勃発することになったのである。『背教』と言われているのは、ネロの迫害により、教会にいた多くの者たちが離教してしまったことを言っている。ネロの迫害が起こった際、多くの人たちは信仰よりも自分の命のほうを選んだ。何故なら、彼らには真の信仰が与えられていなかったからである。もし真の信仰を与えられていたならば、迫害が起きた際、自分の命よりも信仰のほうを選んでいたことであろう。この背教についてはキリストもこう言っておられた。『兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子どもたちは両親に立ち逆らって、彼らを死なせます。』(マタイ10章21節)『そのとき、人々は、あなたがたを苦しいめに会わせ、殺します。また、わたしの名のために、あなたがたはすべての国の人々に憎まれます。また、そのときは、人々が大ぜいつまずき、互いに裏切り、憎み合います。』(マタイ24章9~10節)このようにネロが現われ迫害と背教が起こると、それから『主の日が』訪れ、遂にキリストが再臨された。それは紀元68年6月9日であった。ネロの迫害が始まったのは紀元64年、または可能性としては低いが65年の初頭である。パウロがテサロニケ人たちにこの手紙を書いている時には、まだネロが皇帝にさえなっておらず、それゆえネロの迫害も起きていなかった。つまり、主の日が訪れるのは、もう少し経ってからのことだった。それにもかかわらず、テサロニケ教会の聖徒たちには、既に主の日が訪れたなどと考えている人がいた。だからこそ、パウロは「いやいや、そうではないのだ。テサロニケ人たちよ。あなたがたは誤った考えを持っている。」と言って、彼らに正しいことを教えたのである。
この箇所でのパウロの言葉は、明らかにマタイ24章の内容に基づいて言われている。マタイ24章を見るとどうであろうか。そこでも、やはり背教が起こり(24:9~10)、ネロが現れると(24:15)、それから後に再臨が起こる(24:29~31)、という順番で語られている。パウロはマタイの福音書の中で言われているキリストの言葉から、どのような出来事の後に再臨が起こるのかよく知っていた。だからこそ、パウロはテサロニケ教会の中に見られた誤りに気付き、彼らが正しい考えを持つようにとここで教えているのである。
【2:4】
『彼は、すべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。』
ここでパウロが言っているように、ネロは、神と呼ばれる存在を徹底的に見下し、その上に自分を高めていた。ネロの治世に生きていた大プリニウス(23-79)は、ネロのことをよく知っていたが、ネロについてこう言っている。「人間の幸運の絶頂に登ったことが、彼の邪悪な心の底に欲望を掻き立てた。彼の最大の欲求は神々に命令を下すことであった。彼はこれ以上高貴な野望を懐くことはできなかった。どんな他の術でも、これくらい熱狂的な後援者をもったものはなかった。」(『プリニウスの博物誌Ⅲ』第30巻5<14> p1244~1245:雄山閣)ここでプリニウスが「神々に命令を下すこと」と言っているのは、つまり神々の『上に自分を高く上げ』るということでなくて何であろうか。ネロの時代から幾らか後に生まれたローマ人である歴史家のスエトニウス(70頃―140頃)もネロについてこう言っている。「(ネロは)宗教はどの土地のものであれ、軽蔑した。ただ一つシュリアの女神の信仰は例外であった。しかしまもなくこの女神も、その像に小便をかけて穢すまでに、いやしめてしまった。」(『ローマ皇帝伝(下)』第6巻 ネロ p197:岩波文庫)ネロが「シュリアの女神」だけは信仰したが、その女神も後になって卑しめてしまったというのは、つまりあらゆる神々の『上に自分を高く上げ』たということに他ならない。またパウサニアスによればネロは「アポロンの許からブロンズ神像や人像を取りまぜて500体も奪い去るという、神をまるで問題にしないやり方」(『ギリシア記』第10巻 第1章 p671~672:龍渓書舎)で略奪の悪を為したが、これもネロが自己を全ての神の上に置いていたことを示していると見てよいであろう。このネロは高ぶりの極みに満ちており、サタンに取り憑かれていたのだから、神と呼ばれる存在を見下していたのは何も不思議ではなかった。むしろ、ネロがこのような者でありながら、全ての神々を蔑ろにしないほうが、かえって不思議であったと言えよう。パウロは、キリストがマタイ24:15の箇所で、ネロを『荒らす憎むべき者』であるエピファネスの再来として語っておられるのを知っていた。確かに、ネロは再びやって来たエピファネスでもあるかのようであった。だからこそ、パウロはここでネロが神と呼ばれる存在の上に自分を高めるようになると預言できたのである。というのも、ネロの言わば予表としての暴君であったエピファネスについて、ダニエル書の中では次のように書かれていたからである。『この王は、思いのままにふるまい、すべての神よりも自分を高め、大いなるものとし、神の神に向かってあきれ果てるようなことを語り、憤りが終わるまで栄える。定められていることが、なされるからである。彼は、先祖の神々を心にかけず、女たちの慕うものも、どんな神々も心にかけない。すべてにまさって自分を大きいものとするからだ。』(ダニエル11:36~37)つまり、ネロが全ての神々の上に自分を高く上げたのは、エピファネスが全ての神々の上に自分を高く上げたのと同じであったということである。ここまでは、『彼は、すべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ』という部分についての註解である。
次は『神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。』という部分についてである。これは、つまりネロが聖徒たちを蹂躙し、聖徒たちにローマ皇帝であるネロをこそ神として認めさせるよう強要させた、ということである。これは実際に起きたことである。すなわち、ローマ大火の罪が聖徒たちに擦り付けられることにより大規模な迫害が起こり、ネロを神と告白しない聖徒は次々と殺されていったのである。このようにして聖徒たちが踏みにじられることで、あの大患難が起きたのであった。これについては既に本書の中で十分に語られている。さて、この箇所では『神の宮』と言われているが、これは聖徒のことであると理解せねばならない。キリストがマタイ24:15の箇所で『聖なる所』と言われたのも、同じく聖徒のことである。このように断言できるということは聖書の聖句に根拠があるのであろう、と読者は思われるに違いない。その通りである。パウロは、手紙の中で、聖徒たちこそが神の宮なのであると言っている。それは次に示す通りである。『あなたがたは神の神殿であり、神の御霊があなたがたに宿っておられることを知らないのですか。』(Ⅰコリント3章16節)『この方にあって、組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあって、あなたがたもともに建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。』(エペソ2章21~22節)パウロは石造りのエルサレム神殿を神殿とは見做していない。それゆえ、ここで『神の宮』と言われているのは、聖徒という神殿のことであると解さねばならない。ペテロも聖徒たちこそが、神の住まいであると理解していたことを覚えるべきである。彼はこう言っている。『あなたがたも生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。』(Ⅰペテロ2章4節)更にこのことはダニエル書を見れば、ますます確かとなる。それというのも、ダニエル書ではネロの攻撃する対象が石造りのエルサレム神殿ではなく、明らかに聖徒という神殿であると預言されているからである(ダニエル7:21、25)。我々は、キリストが復活して以降、神の神殿が移り変わったことを知るべきである。それ以降、もはや石造りのエルサレム神殿は神の神殿ではなくなった。何故なら、キリストが復活されてから、神は預言されていた通り、聖徒たちという宮の中を歩まれるようにされたのだからである。このように理解しないと、我々は聖徒こそが神殿であると言っているパウロの言葉を否定せねばならなくなるから、注意せねばならない。なお、この『神の宮』という言葉の意味が聖徒という神殿なのか石造りのエルサレム神殿なのか知ろうとして、原語を調べてみても無駄である。何故なら、この『神の宮』という言葉の原語は「ναον」(ナオン)であるが、これは聖書の他の箇所を見ると、聖徒という神殿という意味で使われている箇所もあるし(Ⅰコリント3:16―ναοs)、石造りのエルサレム神殿という意味で使われている箇所もあるからである(マタイ23:21―ναω、23:35―ναου)。それだから、この原語「ナオン」を見ただけでは、どちらのほうの神殿を指しているのかまったく判別することができない。
この不法の人が、未だに現われていないと理解することは決してできない。何故なら、ここまで説明されたように、この不法の人とはネロ以外ではないからである。宗教改革者たちは、この不法の人がローマ教皇のことだと本気で思っていたが、これは完全な間違いであった。不法の人が踏みにじる『神の宮』という場所が、クリスチャンであったと理解している点では、宗教改革者たちに間違いはなかった。彼らはこの言葉が石造りのエルサレム神殿を指しているなどとは少しも考えていなかった。しかし、彼らはこの不法の人が再臨によって殺されるということ、666の獣でもあるということ、また後にも語られるがパウロの生きていた時から既に生存していたということを、まったく考慮していなかった。ただ教会を専制的な権力を振り回して支配しているというだけで教皇が不法の人だと理解するのは、あまりにも短絡過ぎたと言わねばならない。ヒトラーが不法の人だと考えた人たちも同様に短絡的過ぎた。教会を苦しめるボス的な存在だからというだけで、すぐに不法の人と結びつけるのは、いかがなものかと私は思う。何故なら、そこには聖書に対する厳密な解釈がまったく欠如しているからだ。
聖徒たちは、私が述べた見解を受け入れ、ネロこそが『不法の人』だったと知るがよい。そうすれば、聖書が教えている再臨および終末に関する事柄が、非常によく理解できるようになるであろう。それは目から鱗が落ちるかのようである。
さて、ここで、既に第1部(第3章)の註釈の箇所で予告しておいたことを取り扱うことにしたい。それは、ここで言われている『不法の人』がシモンおよびヨアンネスではないのか、という真面目な疑問である。これについては是非とも解決しておかねばならない。それは聖徒たちが、この2人の人物のことで解釈上の悩みを持たないためである。ユダヤ戦争について深い知識を持っている人であれば、この『不法の人』がシモンおよびヨアンネスではないのかと思うかもしれない。何故なら、この2人の叛徒は、聖書が述べている『不法の人』の人物像と合致しているように感じられるからである。その合致具合はどのようなものであるか。まず、パウロはこの箇所において邪悪な者が『神の宮の中に座を設け』る、と言っている。この2人の叛徒のうちヨアンネスは、実際にエルサレム神殿の中に文字通りの意味で座を設けた(※①)。しかも、ダニエル書によれば、既に見た通り、この邪悪な者が忌まわしい振る舞いをする期間は3年6か月であった。驚くべきことである、ヨアンネスがエルサレムにおいて暴虐をほしいままにしたのもだいたい3年6か月ぐらいである(※②)。また我々が今見ている箇所で、不法の人はあらゆる神々の上に自分を位置づけると言われている。この2人の叛徒は神々などどうでもよいと思っていたのだから、彼らはあらゆる神々の上に自分を位置づけていたと言ってよい。更に、我々が今取り扱っている人物は、不法を行ない荒らし回る、ということをする者である。この2人も、殺人や強奪などといった多くの不法を行ない、文字通りエルサレムとその神殿を荒らしに荒らした。これについてはヨセフスの書を読めば分かる。またこの不法の人はキリストとダニエルが言っているように「憎むべき者」である。歴史を知っている者であれば、シモンおよびヨアンネスが憎むべき者であったということは決して疑えない。更に付け加えれば、この2人の叛徒は、聖書が述べている不法の人のイメージに反していない、いや、むしろ完全に一致している。このようにシモンとヨアンネスは、聖書に書かれている邪悪な者と多くの点において適合しているように感じられる。だが、不法の人はシモンまたはヨアンネスではない。そのように言える理由がいくつかある。まず、既に述べたように、不法の人が座を設ける『神の宮』とは石造りの宮のことではなくクリスチャンという宮のことである。ネロは間違いなくクリスチャンという宮を蹂躙したが、シモンおよびヨアンネスはそのようにしたかどうか定かではない。もしかしたら、この2人もクリスチャンを蹂躙したかもしれないが、そのようにしたと確言することはできない。また、不法の人はアンティオコス4世の再来として現われる、という点も考慮されねばならない。ダニエル書からも分かるように不法の人はこのシリアの暴君が再び現れたかのような存在なのだから、ただの反逆児に過ぎない一般平民ではなく、ネロという帝位に就いている者だったと考えるほうが自然である。更に、この不法の人は黙示録13章の獣666でもあるが、ネロの場合は確実に666が導き出せるのに対し、シモンおよびヨアンネスの名前からはこの数字が出せるかどうか定かではない。ネロから666が出せることは間違いないのだから、この2人の叛徒から666が出てこないかどうか調べる必要はないと私には思われる。このように、幾つかの理由により、不法の人はネロだったとするほうが聖書的であり理に適っている。これをネロだと捉えれば、聖書の全体が驚くほど調和的に読み解けるようになるのだ。だったら、これはもうネロだと確定する以外にはないことになる。そうすれば自然とこれがシモンおよびヨアンネスだったのではないかという疑問は排除されることになるのだ。私は言うが、これを強引にこの2人だと理解すれば、聖書が何を言っているのかよく分からなくなってしまう。
(※①)
タキトゥスはヨアンネスの神殿占拠についてこう言っている。「3人の将軍と同数の軍隊がいた。一番外の最も長大な城壁をシモンが、真中の町をヨアンネスが<―彼はバルギオラとも呼ばれていた―>、神殿をエレアザルスが守っていた。ヨアンネスとシモンは大勢の兵士と武器を恃み、エレアザルスは地の利をあてにしていた。しかし彼らの間に確執と裏切りと放火が起り、多量の穀物が焼失した。やがてヨアンネスは犠牲を捧げると見せかけ、エレアザルスと彼の手勢を殺すため兵を送り込み、神殿を占拠した。こうして市民は二つの党派に分裂したが、ローマ人が接近してやっと外敵との戦争のため和解を余儀なくされた。」(『同時代史』第5巻 1:12 p267:筑摩書房)
[本文に戻る]
(※②)
ヨアンネスは紀元67年11月以降にエルサレムに逃げ込み、それからエルサレムで暴虐な振る舞いをし始めた。神殿が崩壊してユダヤ戦争が終わるのは既に述べたように紀元70年9月であった。ユダヤ的な年月の計算法により捉えれば、これは3年6か月ぐらいとすることが十分に可能である。
[本文に戻る]
【2:5】
『私がまだあなたがたのところにいたとき、これらのことをよく話しておいたのを思い出しませんか。』
パウロはテサロニケ教会にいた時、このことについてテサロニケ人たちによく話していた。しかし『よく』というのは、具体的にどれぐらいの程度を言っているのか。これについては分からないと言うしかない。ただ我々はパウロが『よく』話していたと大まかに捉えていれば、それでよい。
ではパウロがこのことについてよく話しておいたのは、何故だったのか。それは、この事柄が当時の聖徒たちにとって非常に重要なことだったからである。ここで注意せねばならないのは、パウロが話しておいたのは紀元1世紀のテサロニケ人たちだったということである。つまり、それは21世紀に生きる私たちにも話されているというのではない。どうして私はこんな誰でも分かるようなことを、今いちいち書いたのか。それは、今の教会は全体的に聖書の理解が弱くなっており(※)、この箇所で言われているのは21世紀に生きる聖徒たちも含まれているのだなどと思い違いをする人が多くいるはずだからである。だが、パウロがここで言っているのは、当時の聖徒たちにだけ直接的な意味を持っている。何故なら、パウロが言っているのは暴君ネロのことだからである。
(※)
これはアウグスティヌスの時代の教会と今の教会を比較してみれば一目瞭然である。アウグスティヌスの時代には、女性でさえ「神の国」を読んでいるほどであった。今の時代では教師でさえ「神の国」を読まないような人がいるぐらいである。私の思うところでは、今の聖徒たちは教師も一般信徒もあまり難しい本は読んでいないが、それは霊性の低下を意味している。
[本文に戻る]
パウロはここでかつて話された『不法の人』について思い返すように促している。パウロはテサロニケ人たちにそのことを思い返させることで、彼らの記憶が薄れないようにし、やがて来たるべき悲惨な出来事のために心の備えをさせているかのようである。
【2:6】
『あなたがたが知っている通り、彼がその定められた時に現われるようにと、いま引き止めているものがあるのです。』
これは現在4代目のローマ皇帝であるクラウディウスが帝位に就いているので、まだ5代目のローマ皇帝であるネロが暴君として現われる時は来ていない、という意味である。『引き止めているもの』とはクラウディウスであり、このクラウディウスに引き止められている者が「ネロ」なのである。私はこれまで、この引き止める者と引き止められている者について、まともな見解を示している人を見たことがない。どの人も、この2人の存在について何も詳しく語ろうとしない。分からないのである。しかし、それは当然と言えば当然と言えるかもしれない。というのも、この2人はクラウディウスとネロと捉える以外に正しい解釈は存在していないからである。すなわち、これをクラウディウスとネロと捉えた場合に限り、この箇所を確固たる精神を持って堂々と語れるようになるのである。
我々はパウロがここで『いま』と言っていることに注意せねばならない。この『いま』とはパウロたちが生きていた紀元1世紀における『いま』である。これは21世紀に生きる我々にとっての『いま』ではない。つまり、この不法の人がパウロの生きている時代に生きていた人物だったことは明らかである。パウロは『いま』不法の人が引き止められていると言っているのだから。パウロの時代における『いま』の時に既に引き止められていた不法の人が、2千年経過しても未だに引き止める者から解放されておらず、それゆえまだ現われていないなどとでも言うのか。とんでもないことを言うのはやめていただきたい。
この引き止められている者と引き止めている者について、テサロニケ人たちは知っていた。何故なら、パウロがあらかじめ、彼らにそのことについて話しておいたからである。しかし、『知っている』とは言っても、この2人の人物が具体的に誰なのか知っていたという意味ではない。彼らが知っていたのは、あくまでも全体的なことについてであった。つまり、「不法の人が今の時点で引き止める者に引き止められているのだ。」という大まかな理解を持っているだけであった。もっとも、鋭い人であれば、ネロのほうについてはともかく、その当時の皇帝であったクラウディウスのほうについては具体的に悟ることが出来ていた可能性もある。
【2:7】
『不法の秘密はすでに働いています。』
これは一体どういう意味であるか。ここでパウロはこう言っているのである。すなわち、不法の人であるネロは既に生きておりこの世に存在しているが人々には彼が不法の人であるということはまだ秘密にされている、と。この部分は非常に理解が難しいが、私が今言ったように理解するのが正しい。というのも、その理解の他にこの部分を正しく理解することは出来ないからである。実際、この手紙をパウロが書いていた時には既にネロがローマにいたのであるが、その時にはまだ皇帝とはなっておらず、ネロが次の皇帝となるかどうか誰も断言は出来なかったのだから、確かにネロが不法の人として現われることは神の摂理によって秘密にされていた。このことが、ここでは『不法の秘密はすでに働いています。』という秘儀的な言葉で語られているのである。私は神の恵みにより、この箇所を上手に理解することが出来た。今の説明を読んでこの難しい部分を正しく悟れた聖徒たちは、ぜひ主なる神に感謝していただきたい。
もう一度、私は言いたい。パウロはここで不法の人の秘密がすでに働いていると言っている。これを疑うことは誰にもできない。それにもかかわらず、まだこの不法の人が出現していないなどと考えているのは、一体どういうわけなのか。今の聖徒たちはパウロが言っていることを真っ直ぐに見ていないのか。兄弟たちよ、それはいけないことである。我々は、聖書の子として、パウロがここで言っていることを直視しなければならない。それとも、ここでパウロが言っていることを直視してはいるものの、それにもかかわらず未だに不法の人が現われていないなどと考えているとでもいうのか。もしそのように考えているとすれば、それはとんでもないことである。何故なら、その場合、不法の人はパウロの時代から2千年もの間ずっと引き止められているということになり、今はだいたい2000歳ぐらいだということになるからである。「いや、そうではない。パウロが言っているのは個人としての人間ではなく、概念的な人間のことなのだ。だから不法の人がパウロの時代から2千年もの間ずっと引き止められていると考えても問題にはならない。」などと抗弁するつもりであろうか。私は言うが、パウロがここで言っているのは、明らかに個人としての人間である。それはパウロの言葉を読めば一目瞭然であるし、これを個人としての人間すなわち皇帝ネロであると捉えて初めてパウロがⅡテサロニケ2章で言っていることが正しく読み解けるようになるのである。もしこれが概念的な人間としての不法の人であって個人を指しているのではないということであれば、このⅡテサロニケ2章を正しく読み解くことは永遠に出来ないままとなる。要するに、ここでパウロが言っていることは、私が説明したように理解しない限り、決して正しく理解することが出来ない。健全な感覚を持った聖徒であれば、今私が言ったことに頷いてくれるはずである。
『しかし今は引き止める者があって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。』
これを分かりやすく言い換えれば、このようになる。「しかし私パウロがこの手紙を書いている今の時点では4代目のローマ皇帝であるクラウディウスのゆえに5代目のローマ皇帝であるネロが帝位に就くのは妨げられているのだから、このクラウディウスが皇帝でなくなる時までネロが皇帝になる時はまだ来ない。」これは、先の箇所(2:6)で言われていたことの繰り返しである。どうして繰り返されたかと言えば、これは非常に重要なことだからである。なお、ここではクラウディウスがネロを『引き止めている』と言われているが、実際にクラウディウスがネロを意図的に皇帝にさせないようにしていた、という意味ではないことに注意すべきである。クラウディウスは「ネロが次の皇帝になったら暴君になるだろうからネロを次の皇帝にしてはならない。」と思って、ネロが次の皇帝になるのを阻止していたというわけではない。ここでは、クラウディウスのせいでネロが皇帝になれていなかったという当時の状態を、その現象面から見て『引き止めている』と言っているに過ぎない。つまり、パウロはここで「クラウディウスが皇帝だからネロが皇帝になれないでいるのだ。クラウディウスはネロが皇帝にならないようにするための言わば仕切り板のような存在なのだ。」と言っているだけに過ぎない。この部分を正しく理解できた聖徒たちは、恵み深い主なる神に感謝していただきたい。
それにしても、この箇所におけるパウロの言い方は何と巧みであろうか。ここでは実に秘儀的な言い方がされている。ここでパウロが言っていることを正しく悟れた瞬間、我々の精神は力動させられる。それというのは、その言い方があまりにも秘儀的だからである。パウロはよく深淵な人だったと言われるけども、このような点からも我々はパウロの深淵さを、よく知ることができる。ところでクロウリーの場合、キリストを卓越した存在として見てはいたが、パウロのほうはやや物足りないと感じていた。確かに、キリストのほうがパウロよりも卓越しているのは誰の目にも明らかである。しかし、このパウロは、クロウリーよりも遥かに卓越していた。それは、ここでのパウロの言い方を見ただけでも分かる。またこのパウロは、クロウリーが妬みを感じるぐらいの霊性を持った―クロウリー的に言えば魔術師的であった―人物である。それだから、彼がパウロをどこか見下したような感じで取り扱ったのは間違いであった。パウロは彼よりも卓越していたのだから、貶したりせず、もっと高く評価すべきだったのである。もしパウロがクロウリーと同じ時代にいたとすれば、パウロは魔術師エルマに言ったのと同じようにして、この現代の魔術師にこう言っていたことであろう。すなわち、『ああ、あらゆる偽りとよこしまに満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵。おまえは、主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。』(使徒行伝13章10節)と。
【2:8】
『その時になると、不法の人が現われますが、主は御口の息をもって彼を殺し、来臨の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。』
不法の人であるネロが現われる『その時』とは、いつか。まずネロが皇帝として現われるのは紀元54年である。次にネロが暴君として現われるようになるのは、皇帝に就いてから数年後である。それというのも、ネロは最初の数年間はセネカの助けにより善政を為していたから。そして聖徒たちに対する暴虐者として現われたのは、紀元64年の6月以降である。さて、この箇所では、ネロの現われについて、ほとんど時間が考慮されずに語られている。つまり、パウロはただ「ネロが現われるのだ。」ということを大まかに言っているだけに過ぎない。だから、我々は、「ここではネロが現われることについて言われているのだ。」というシンプルな認識を持つだけで充分とすべきである。
この箇所で言われているように、ネロはキリストの『御口の息』により、またその『来臨の輝き』により、死ぬことになった。『御口の息』とは、キリストの御言葉である。これを文字通りキリストの喉から出る空気のことだと解するのは、キリストを卑しめることであるから、そのように解さないよう注意せねばならない。『来臨の輝き』とは、キリストの再臨における栄光を言っている。つまり、これはキリストが輝かしく再臨された際、その輝かしい栄光に満たされつつネロを殺される、という意味である。確かにキリストはその栄光をもってネロを殺された。ネロが再臨のキリストにより死滅させられてしまうというこの出来事については、既に十分なだけ説明されているのだから、もうこれ以上ここで改めて説明する必要はないであろう。
この箇所ではヘブル特有の二重表現が使われている。すなわち、ここでは「ネロがキリストによって死んでしまう」ということが違う言い方で2回言われている。『主は御口の息をもって彼を殺し』という部分が1回目であり、『来臨の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。』という部分が2回目である。このように繰り返されたのは、例のように、ネロがキリストにより殺されるという事柄が非常に重要なことだったからである。このパウロが『きっすいのヘブル人』(ピリピ3章5節)であったことは、既に我々の知っていることである。
この箇所で言われていることは、明らかにイザヤ11:4の箇所と対応している。そこではこう言われていた。『くちびるの息で悪者を殺す。』これは、キリストが『くちびるの息』である御言葉によって『悪者』であるネロを殺す、という意味である。言葉の使い方が非常に似ていることから、パウロがこのイザヤ書に基づいて、この箇所を書いていたことは間違いない。またこの箇所は詩篇110:6の箇所とも対応している。そこではこう言われている。『広い国を治めるかしらを打ち砕かれる。』これも、やはりキリストが『広い国』であるローマを『治めるかしら』であるネロを『打ち砕かれる』、つまり殺される、ということを言っている。牧師であれば既に理解していると思うが、聖書は一人の著者であられる神がお書きになられた文書であるゆえ、あらゆる箇所が調和している。我々が今見た3つの箇所も、そのうちの一つである。
この箇所は、私が今述べたように理解しない限り、永遠に正しく理解することが出来ない。というのも、この箇所ではネロがキリストにより殺されると言われていると捉えるのが、唯一の正しい捉え方だからである。無知の穴と誤謬の闇に閉じ込められたくない聖徒は、私の述べた理解をしっかりと受け入れるがよい。
【2:9】
『不法の人の到来は、サタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、しるし、不思議がそれに伴い、』
ネロが現われたのは『サタンの働きによ』った。つまり、サタンが望んだからこそ、ネロが邪悪な皇帝として現われることになった。これは黙示録13:2の箇所を見ても分かる。そこではネロにサタンが『自分の力と位と大きな権威とを与えた』と書かれている。これは、サタンが働きかけなかったら、ネロが邪悪で強大な皇帝とはなっていなかったということを意味している。またこれはダニエル書8:24の箇所を見ても分かる。そこではネロの予表であるエピファネスについて、『彼の力は強くなるが、彼自身によるのではない。』と書かれている。これは、エピファネスがサタンの力により台頭できたのと同様に、ネロもサタンの力により邪悪な暴君として現われたということを意味している。確かに、サタンの働きなくして、我々が知っているあのネロは存在し得なかった。何故なら、サタンの働きかけを考えなければ、ネロがした諸々の愚行は説明がつかないからである。言うまでもなく、サタンが働きかけていたからこそ、ネロはとんでもない振る舞いを幾度となく平気で行なったのである。
ここで疑問が生じる。すなわち、支配者は神によってこそ現われるのではないのか、神が権威を与えられるからこそある者が支配者として到来するのではないのか、という疑問である。ここでは明らかにネロという支配者がサタンにより到来すると言われている。確かに聖書は、権威が神により与えられるものであり、支配者は神により立てられる、と教えている。神が王を立てることについて言えば、ダニエル書2:21の箇所を見ればよい。そこでは『神は…王を廃し、王を立て』られると言われている。神が権威を支配者に与えられることについて言えば、パウロがローマ13:1の箇所でこう言っている。『神によらない権威はなく、存在している権威はすべて、神によって立てられたものです。』当然ながら、ネロに権威を与え、ネロを皇帝として立てられたのも神である。それでは、ここでサタンによりネロが現われたと言われていることは、どう解決すればよいのか。ネロはサタンの働きにより立てられたのだから、神によっては立てられていなかったのか。この問題については、こういうふうに考えるべきである。すなわち、神はサタンの願望に沿ってネロを皇帝とされたのである。つまり、サタンはヨブ記1、2章で見られるように、まず神に対して「どうかあのネロを次の皇帝とし、私の働きによりネロが皇帝として立てられるようにして下さい。そうして私がその中に入れるようにして下さい。そうすればネロを通してあなたの聖徒たちが迫害されるようにもなるでしょう。」と願いを述べた。神はこのサタンの願いを聞き入れられた。それは、サタンに取り憑かれたネロを通して御自身の民を試されるためであった。だからこそ、ネロが聖徒たちを苦しめる暴君として現われることになった。そのことが、ここでは『不法の人の到来は、サタンの働きによる』と言われているのだ。それゆえ、サタンがネロを到来させたことは、神がネロを皇帝として立てられたことと矛盾していない。この2つの事柄は、まったく問題なく調和している。何故なら、ネロを皇帝として立てられたのは神であるが、神がネロを立てられたのはネロを皇帝にして欲しいというサタンの願いを聞き入れられたからである。だから、サタンがネロを到来させたからといってネロが神により立てられていないということにはならず、ネロが神により立てられたからといってサタンがネロを到来させてはいないということにもならない。
ここで言われているネロに伴う『あらゆる偽りの力、しるし、不思議』とは何であるか。まず『偽りの力』とは、ネロが自分に与えられた力すなわち権力を不正に行使することを言っている。確かにネロは権力を不当に振り回して飽きることがなかった。これは正に偽りにおいて力を行使することである。これについては歴史書を見れば分かる通りである。次に『しるし』とは、ネロが不法の人また荒らす憎むべき者であることを示す印のことを言っている。それは、ネロのしていた数々の愚かな振る舞いのことである。それだから、その振る舞いを見れば、聖徒たちはネロこそが預言されていた邪悪な者であるということを知れた。というのも、その振る舞いそのものが印として「この者こそがあの邪悪な者なのだ。」と叫んでいたから。最後の『不思議』とは、ネロの行なった諸々の不思議なことである。実際、ネロは普通の感覚からすれば『不思議』だと感じられることを幾度となく行なった。例えば親や妻や師を殺したり、120フィートもの肖像画を書かせて展示させたり、去勢された少年と結婚したり、戦車競技に騎手として参加したり、今で言うところのアーティストである歌手になって歌を歌ったり、有名な「黄金宮」を造って人々を驚かせたり、商店街を皇帝だと分からないようにして歩き回り置いてあった商品を盗んだりした。このネロほどに『不思議』だと思えるようなことをした支配者は、恐らく存在しないと思われる。要するに、ここで『あらゆる偽り力、しるし、不思議』と書かれているのは、ネロの愚行を総体的に言い表している言葉である。今の聖徒たちは、この言葉を読んで、ファンタジー作品で描かれている魔法のような現象や振る舞いを想像している。例えば、火を指から放ったり、魔力を発散させて人々を眩惑させたり、竜や悪霊どもを召喚して危害を与える、などといった類のことである。それだから、今の聖徒たちはこの『あらゆる偽りの力、しるし、不思議』を行なう不法の人を、ハリー・ポッターに出てくるヴォルデモート卿のような存在として認識しがちである。つまり、魔法使いのようなイメージを持っているわけである。しかし、私のこれまでの説明を読めば分かるように、不法の人をそのように捉えるのは聖書の考究不足であって、まったく間違っている。
【2:10】
『また、滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行なわれます。なぜなら、彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。』
ネロの時代において、滅びに定められていた人たちには『あらゆる悪の欺きが行なわれ』た。聖書を批判しているわけではないのだが(聖書を批判するなどとんでもないことである)、ここでパウロが言っていることは、非常に抽象的である。パウロがここで言っていることは、具体的には一体どういうことなのか。それは、こうである。すなわち、ここで言われているのは、ネロの時代における諸々の惑わしのことである。例えば、ネロがキリスト教徒を迫害した際、多くの人々が恐れを抱いてキリスト教に近寄らなくなったことは間違いない。何故なら、ネロの迫害したキリスト教に近づけば、自分も迫害されると予測するからである。これは一つの悪い欺きであったと言える。また、当時の時代性も『悪の欺き』として働いた。この時は、キリスト教徒というだけで罪に問われる時代であった。それだから、人々は時代の常識に妨げられて、なかなかキリスト教に近づくことが出来なかった。更にサタンの働きもあったことを忘れるべきではない。このサタンは、いつの時代、どの場所であっても、常に人々がキリスト教の真理に行かないようにと『悪の欺き』を抜かりなく働かせている。それは、ネロの時代においても例外ではなかった。このようにして、当時に生きていた滅びの子たちは、『悪の欺き』に呑み込まれてしまったのである。少し世の中を見回せば分かる通り、西暦21世紀の今でも、これは同じことである。どこもかしこも世界は『悪の欺き』に満ちている。それゆえソロモンが言うように、『知識を増す者は悲しみを増す。』(伝道者の書1章18節)ということになるのである。
この滅びる人たちが欺きに呑み込まれたのは、彼らが『救われるために真理への愛を受け入れなかったから』である。つまり、イエス・キリストの救いを信じて受け入れようとしなかったので、当然の裁きとして、悪い欺きに陥ることになったのである。突き当りに2本の道が分かれていた場合、右に行けば左に行くことはなく、左に行けば右に行くことはない。それと同様で、キリストの救いを受け入れなければ、必然的に欺きに陥らざるを得ない。だから、彼らが欺かれたのは本来的に自己自身がその原因なのであって、自業自得であった。それゆえ、彼らが「どうして神は我々が欺かれるようにされたのか。」などと文句を言うことは出来なかった。何故なら、もし彼らが欺かれたくなければ、イエス・キリストの真理を受け入れたら良かったのだからである。そうすれば、欺かれるようなことも無かったのである。我々は、真理を受け入れないことは、すなわち悪の欺きに引き込まれることであるのをよく弁えよう。そのようになるのは非常に悲惨なことである。
【2:11~12】
『それゆえ神は、彼らが偽りを信じるように、惑わす力を送り込まれます。それは、真理を信じないで、悪を喜んでいたすべての者が、さばかれるためです。』
滅びる人たちには、神により『惑わす力』が送り込まれた。これは悪霊のことを言っている。つまり、悪霊を送られた人は、その悪霊に惑わされてしまうので、『偽りを信じるように』なるのである。このようにして悪霊に入り込まれると、抵抗はまったく出来なくなる。というのも、その人は悪霊の意志を自分の意志とするようになるからである。イスカリオテのユダにもサタンという霊が入ったので、キリストを売り渡したいというサタンの意志をユダが自分の意志として実行することになった(ヨハネ13:26~30)。ヨハネは、サタンがユダに入ると、『すぐ』にユダは行動を起こしたと記している。この出来事からも分かるように、霊とは実に強力なのである。
このように彼らに悪霊が送り込まれたのは、『真理を信じないで、悪を喜んでいたすべての者が、さばかれるため』だった。つまり、イエス・キリストの救いを受け入れて悔い改めることをせず、あくまでも神から離れた悪の人生に歩み続けることを望んだので、裁きとして悪い霊に引き渡されたということである。これは、あたかも神がこう言っておられるかのようである。「あなたがたは真理を拒絶したのだから、悪霊に惑わされて偽りの道に歩み続けなさい。何故なら、あなたがたがそれを自ら望んだのだから。さあ、好きにするがよい。しかし、あなたがたの『最後は滅び』(ピリピ3章19節)であることをよく知っておきなさい。」なお、ここで言われている出来事は、黙示録19:17~18、21の箇所と対応している。そこではキリストが再臨された際、悪者どもが悪霊どもの餌食にされてしまうと言われている。これは、つまり惑わす霊が送り込まれたので惑わされてしまったということである。このように悪霊に入られて惑わされてしまうのは、すなわち悪霊に喰い尽くされることである。何故なら、悪霊にとっての食事とは、人間の中に入ってその者を好き放題に動かすことなのだから。今の時代にはレディーガガなどという女性アーティストがいるが、これは最も分かりやすい例であり、彼女は完全に悪霊に占拠されている。つまり、彼女は悪霊に隅々に至るまで喰い尽くされているのだ。
神は、真理を拒絶する者たちに、このようにして裁きを下される。これが神のやり方である。ローマ・カトリックも、宗教改革者たちの述べた真理を拒絶したので、裁きとして誤謬の霊に引き渡されてしまった。彼らは今に至るまで誤謬のガラクタに取り囲まれて歩んでいる。しかし、このように裁きとして悪霊に委ねられても、文句を言うことは出来ない。何故なら、悪霊を招いた原因はその人の頑なな心にあるからである。誘惑に打ち負けた人がソープランドにひょろりと吸い込まれるかのように入っていったとすれば、少なからぬ額を財布から失い、そのうえ更に病気まで貰ったとしても自業自得であると言わねばならない。真理を拒絶した人が悪霊に委ねられて裁かれるのも、これと同じで自業自得なのである。我々は真理に堅く立って、悪霊どもの餌食にならないようにせねばならない。真理を蔑ろにすることは悪霊に惑わされることであるから、よく気を付けねばならない。
第56章 54:テモテへの手紙Ⅰ
一番目のテモテへの手紙は、それほど心を向ける必要はない。
第57章 55:テモテへの手紙Ⅱ
二番目のテモテへの手紙も、それほど心を向ける必要はない。
【3:1】
『終わりの日には困難な時代がやって来ることをよく承知しておきなさい。……』
ここでパウロが言っている『終わりの日』とは、「ユダヤの終わる頃の日々」または「ユダヤの終わる日が近くなると」というほどの意味である。この言葉は非常に大まかである。それだから、この言葉が示している実際の年月や期間が具体的にいつなのかということについて書くのは、難しい。我々は、この言葉が、ただユダヤの終わりの時期を大まかに意味しているとだけ捉えていれば、それで十分である。
ここでパウロは、これからユダヤの終わる日が近づくと忌まわしい者たちが多く見られるようになるから、そういう者たちに警戒せよとテモテに警告している。その忌まわしい者たちが、3:2~5の箇所で列挙されている。そこでは全部で19の種類の者が挙げられている。パウロが、こういった者たちに警戒するようにと警告したのは、何故なのか。それは、テモテがそのような者たちに惑わされてしまわないためであった。そのような者たちに惑わされてしまえば、テモテは堕落し、キリストにある敬虔な姿勢が失われてしまうことにもなりかねない。そうすれば、再臨されたキリストの前に良い状態で立てなくなることにもなる。パウロはテモテが良い状態でキリストの前に出られるようになるのを願っていた。だからこそ、パウロはユダヤの終わりの時期に蔓延る忌まわしい者どもに注意するようにとテモテに命じたわけである。キリストもマタイ24:4の箇所で、ユダヤの終わりの時期に現われる邪悪な者に惑わされないようにと、弟子たちに命じておられる。解釈の面で注意せねばならないのは、ここでパウロは列挙されているような忌まわしい者たちが、ユダヤの終末に向けてこれから増えてくるであろうと言ったに過ぎない、ということである。つまり、パウロがテモテに対してこのように書いている時に、このような忌まわしい者たちが、まったく存在していなかったというのではなかった。言うまでもなく、パウロがこのように書いている時にも、3:2~5の箇所で列挙されているような者たちはテモテの周りに存在していた。ただ、そのような者たちは、今はまだ大いに蔓延ってはいなかったというだけのことである。だから、パウロは既にいたそのような者どものことについて、3:6~9の箇所で色々と語っている。今の時代に生きる我々も、そのような忌まわしい者どもに警戒せねばならない。もしそのような者たちに惑わされて堕落したとすれば、本当に大変なことになってしまいかねないのだから。
我々は、ここでパウロがテモテに言っているのは、紀元1世紀におけるユダヤの終わりの時期についてのことだったと理解せねばならない。今まで教会は、この箇所で言われている『終わりの日』が未だに訪れていないか、正に自分の生きている今の時代にその日が近づいている、と理解してきた。前者にはアウグスティヌスやカルヴァンがおり、後者にはルターがいる。しかし、そのように理解するのは間違っている。よく考えてみていただきたい。パウロは、これからユダヤの終わりと共に忌まわしい者どもが続々と出てくるようになるからというので、テモテにそういった者どもを避けるようにと警告したのである。テモテに対してパウロがそう言ったのであれば、それはテモテの生きていた紀元1世紀の時代についてのことだったと理解するのが自然である。だが今まで教会はそのようには理解してこなかった。驚くべきことだが、今まで教会は直接的な読者であるテモテに対して警告された状況がテモテの生きている間には実現されておらず、直接的な読者ではない遥か未来の読者が生きている時代にそれが実現されると理解してきた。テモテに対して言われたことがテモテの人生においては実現されず、遥か未来の聖徒たちに実現されるとは一体どういうことであろうか。そのように理解するのは、おかしいと言わねばならない。信仰に基づいて理性を働かせていただきたい。言うまでもなく、パウロはテモテがやがて数十年後に経験することになる状況について、テモテに知らせたのである。というのも、この手紙の本来的な読者は明らかに『愛する子テモテ』(1章2節)以外ではないからである。今の聖徒たちは、よく祈り、御言葉で言われている再臨と再臨の時期に関する事柄を深く考究すべきだ。そうすれば、憐れみ深い神が、聖徒たちに再臨の真理を悟らせて下さるようにもしてくれるであろう。
第58章 56:テトスへの手紙
テトスへの手紙は、心を傾けなかったとしても問題は起こらないであろう。この文書からは、再臨のことがほとんど学べないからである。
第59章 57:ピレモンへの手紙
ピレモン書は、特に心に留めなかったとしても問題は生じない。
第60章 58:ヘブル人への手紙
ヘブル書は、是非とも考究しておかねばならない文書である。この文書からは再臨のことが豊かに学べるからだ。それゆえ★は9である。
【1:1~2】
『神は、むかし先祖たちに、預言者たちを通して、多くの部分に分け、また、いろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には、御子によって、私たちに語られました。』
ここで言われている『終わりの時』とは、既に何度も述べているように、ユダヤが終わる時期という意味である。具体的に言えば、キリストの生まれた紀元前4年からユダヤが神から完全に見捨てられて終わりを迎えた紀元70年までとすべきである。新約聖書の中で「終わりの時」について言われている箇所は、どれも、この期間を意味していると考えねばならない。嘆かわしいことであるが、今に至るまで教会は、この『終わりの時』について、ほとんど考究してこなかった。これは予定の教理や自由意志や原罪が非常に深く考察されてきたのとは異なっている。歴史を思い返してもらいたい。これまで終わりの時について、アウウグストゥスの「三位一体論」のように考究した書物があっただろうか、またそのように考究した神学者がいただろうか。そのような書物や神学者は、今までに見られなかった。それだから、今まで教会はこの『終わりの時』における「終わり」の概念を、地球世界の終わりであると捉えてきた。これは感覚的・イメージ的な解釈である。すなわち、それは聖書の研究に基づく解釈ではない。このため、これまでこの『終わりの時』について言われてきたことは、実にまちまちであって、誰も彼も一貫していなかったと言わねばならない。ある人は正に今こそが終わりの時だと言い、別の人はもう間もなく終わりの時が来ると言い、終わりの時はまだまだ先のことだと言っている人もいる。何なのだ?これは。―明らかに普通ではないと言わねばならない。―しかし、私が述べたように、これは地球全土の終わりのことではなく、単にユダヤ世界が終わることを言っている。聖徒たちは、私が言ったように、これをユダヤ世界の終わりであると捉えつつ、聖書で『終わりの時』について書かれている箇所を読んでみるとよい。そうすれば聖書をすんなりと読み解けるようになるであろう。聖書を正しく解釈したいと願う聖徒は、私の言った解釈を受け入れるがよい。しかし聖書を正しく解釈したくないと思う聖徒は、私の言ったことを無視すればよい。
この『終わりの時』が来るまで、神は『預言者たちを通して』御子キリストのことを御語りになった。その預言者とは、イザヤやゼカリヤやマラキなどが、そうである。しかも、それは『多くの部分に分け』て語られた。つまり、神はキリストについての預言を、一挙に語られはせず言わば小刻みに語られた。また、それは『いろいろな方法で語られ』た。例えばイザヤは言葉によりキリストの到来を預言し、ダビデはその王位により王なるキリストを預言し、ヨナは3日間魚の中に閉じ込められることでキリストの3日目の復活を預言した。また、そのキリスト預言は、直接的にはユダヤ人だけを対象として語られた。ここでは『先祖たちに』キリスト預言が語られた、と書かれているからである。この『先祖たち』とは、「ユダヤ人の先祖たち」という意味であって「異邦人の先祖たち」という意味ではないのである。『終わりの時』が来るまで、神はこのようなやり方でキリストのことを預言されたのであった。
しかし、ユダヤ世界の『終わりの時』が来ると、神は御子により御子のことを御語りになった。それは、もう御子が地上に現われたからである。もう地上に御子が現れたのだから、あたかも未だに御子が地上に現われていないかのように預言者たちを通して御子のことを語る必要は無くなったのだ。もし御子がユダヤの『終わりの時』に現われたにもかかわらず、まだ預言者を通して御子のことが語られたとすれば、それは例えるならば王子が既に皆の集まっている場所に来ているのに未だに来ていないかのように「王子はこれから来られますよ。」などと言うようなものである。このように言うのは、王子に対する侮辱であり、王子から名誉を奪うことである。
何度でも言わねばならないが、多くの教会は、この『終わりの時』が正に今であると考えている。カルケドン信条でもそう書かれているし、このように考える傾向は今まで何も変わっていない。つまり、多くの教会は、新約時代の全ての時が『終わりの時』だと捉えている。その時はキリストが再臨される時まで続くと。このように考えるのは、明らかに聖書研究の不足のゆえだと言わねばならない。このように考えるのは、聖書に根差しておらず、それどころか理性にも反している。今まで教会はこの『終わりの時』について深く考えてこなかったことを反省しなければいけない。もう一度言うが、これを紀元70年に起こったユダヤの終わりであると捉えるべきである。そうすれば、全てが上手に理解できるようになるのだ。
【11:10】
『彼は、堅い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。』
『都』とは天国である。すなわち、これは霊的な世界におけるパラダイスを指している。これは地上にあるのではない。それがあるのは、天上である。都が天にあるということについては、ヘブル11:13~16や13:14の箇所を読めば分かる。そこでは、明らかに都が天上にあると示されている。また、この都の設計者また建設者は神であられる。これは、天国が神によって構想され創始された、と言っているに等しい。つまり、神の御心なしに天国という存在は有りえなかった。また、この天国は『堅い基礎の上に建てられ』ている。この基礎とは、すなわち神とキリストである。これ以上に堅固な土台は他に考えられない。それゆえ、天国はその基礎のゆえに絶対に揺らぐことがない。
この都は、黙示録21:1~22:5の箇所で描かれている神の都と一緒である。黙示録のほうでも、天上における神の王国について言われている。それだから、黙示録21章、22章では天国が地上に降りて来て展開されるなどと考えている者たちの狂気は、退けられねばならない。このように考えるのは、明らかに無理がある。聖書は、神の都が天上にあると教えているのであって、それが地上に降りて来るなどとは教えられていない。黙示録で天上から都が降りて来ているのは、単なる比喩であって、地上にその都が展開されるなどとは示されていない。この考えの誤りについては、既に第3部で説明しておいた。
我々の父であるアブラハムは、地上にいた時、この天上における都を切に求めていた。つまり、そこに入って至福の生を歩めるようにと望んでいた。人は、自分の出てきた故郷を求めるものである。アブラハムの故郷は、実に天上であった。だからこそ、彼は自分の本国である天上を願い求めていたのだ。このことからも分かるように、天上を求めるというのは、その人が真の信仰者であるという証である。何故なら、その人が本当に天を自分の祖国としているからこそ、その天を求めるのだからである。もし天が祖国でなければ、わざわざそのような場所を求めることもないはずである。現に、既に滅びた滅びの子たちは、生きている間、別に天上の世界など何も求めていなかったのである。
この都は、既に到来している。それは今から2千年前のことである。何故なら、その到来の出来事は黙示録に書かれているからである。既に述べた通り、黙示録に書かれている預言は、全て『すぐに起こるはずの事』であった。また、既に都が到来したと言えるのは、再臨が既に起きたからでもある。キリストはマタイ16:28の箇所で、御自身が再臨されると天の都も到来すると教えられた。それだから、もう既に再臨が起きた以上、この都も既に到来したとせねばならないのである。未だに都が到来していないと考えている者は、聖書の理解が浅いか、聖書の研究がまだまだ足りていない。というのも、そうでなければ、私が今述べたように既に都は来たという理解を持っていたはずだからである。
【11:13】
『これらの人々はみな、信仰の人々として死にました。』
『これらの人々』とは、11章の中でこれまでに書かれてきた箇所に出てきた信仰者たち、すなわちアベルやノアやアブラハムやサラを言っている。もちろん、これにはヘブル書の著者がこれまでに挙げなかった全ての敬虔な聖徒たちも含まれている。何故なら、この11章の箇所で言われているのは、一握りの聖徒のことではなく、あらゆる真の聖徒たちのことだからである。その信仰者たちは、『信仰の人々として死に』至った。信仰の人々であった彼らとて罪人に過ぎなかったのは確かである。ノアは、彼以上に偉大で敬虔な人間が他に誰もいないと言えるほどの人物だったのにもかかわらず(いったい誰が彼よりも敬神において優っていると言えるであろうか)、愚かにも泥酔して耐え難い醜態を晒した(創世記9:20~25)。アブラハムも、老女になっていたサラから子が生まれると言われた神の宣言を、素直に信じることができなかった(創世記17:15~21)。だが、彼らは欠けがありはしたものの最期に至るまでその信仰から遠ざかることなく、その人生を終えたのである。それは神が彼らを信仰のうちに保って下さったからであった。
聖徒たちは、『これらの人々はみな、信仰の人々として死にました。』とやがて言われるように人生を終えなければならない。つまり、最後までキリスト信仰のうちに留まらなければならない。我々は、ソロモンやテルトゥリアヌスのようであったはいけない。この2人は晩年になって正統的な信仰から逸れたが、最後に悔い改めて再び正統信仰に戻ったかどうかは我々には不明であるから、『これらの人々はみな、信仰の人々として死にました。』と言うことはできない。聖徒たちは、キリストという真の道から堕ちることがあってはならない。もしそうでもなれば、その行き着く最後は地獄での滅びだからである。アウグスティヌスは信仰の人として死んだ。ルターも信仰の人として死んだ。スポルジョンも信仰の人として死んだ。聖徒たちは、そのようでなければいけないのである。
ところで話がやや横にずれるが、再建主義者たちは、次のように言っている。「神の民は清められた者たちなのであるから、そのような存在に相応しく、「死」という呪いのゆえにもたらされた事象については口にさえすべきではない。聖徒たちとは生命に定められた民なのだから。」確かに彼らは「死」について真正面から、あまり語ってはいないように思える。なるほど、これは一見すると、もっともらしく、また非常に敬虔であるかのように思える。だが私は言うが、この主張には無理がある。何故なら、聖書は実に多くの箇所で死について大胆に論じているからである。キリストも使徒も、何も妨げられることなく、何度も死について口にした。我々が今見ているこの箇所でも、やはり死について普通に語られている。再建主義者たちは、果たして聖書に、またキリストや使徒やヘブル書の著者に対しても「生命を約束している書物は、また永遠の生命に定められている者たちは、死について口にすべきではない。」などとでも言うのであろうか。とんでもない話である。再建主義者たちは、自分たちこそが主導権を握りたいという隠された野心のゆえであろうが、今挙げた意見以外にも野心に基づいていると思われる理性的な意見を語っていることが多い。
『約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、』
『約束のもの』とは、天国における永生を指している。つまり、これは霊的な約束のことである。地上における人間的な約束ではないということである。
昔の信仰者たちは、自分たちに約束されていた至福の生命を、この地上においては『手に入れることはありませんでした』。何故なら、それは天上の世界において与えられるものだからである。それだから、神が信仰者たちに約束された生命を地上において獲得させられなかったとしても、神が意地悪な御方だということにはならない。もし地上においてそれが与えられたとしたら、かえっておかしいのである。
しかしながら、昔の信仰者たちは、その約束における永遠の生命を大いに期待し、心の中で聖い喜びを抱いていた。『はるかに』とは、「やがて来たるべき時において」という意味である。『見て』とは、「あたかも今それが目の前にあるかのごとくに確信して」という意味である。『喜び迎え』とは、「それを受けられることを快く思いつつ信じていた」という意味である。
『地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。』
彼ら信仰者たちが天における永生を希求していたのは、つまり彼らが天からやって来た『旅人であり寄留者』であるということを如実に示していた。これは、少し例えがよくないが、どこか遠い星から地球にやって来た宇宙人のようである。この宇宙人は、地球には争いが多く人間が罪に満ちているのを見て、一刻も早く自分の星に帰りたいとうずうずしている。地球にいる我々は、この宇宙人を見て、彼らはただ一時的にこの地球に寄ったに過ぎないことを知るのである。振る舞いや行ないといったものは、その人の心理を反映している。つまり信仰者たちは、天の国をこそ求めているという態度により、自分たちが天を祖国としていることを証ししていたのである。
【11:14】
『彼らはこのように言うことによって、自分の故郷を求めていることを示しています。』
この箇所でも、先に見た箇所と同じことが言われている。信仰者たちが天から来た旅人であり寄留者に過ぎないと自己を示しているのは、つまり彼らが自分の本国である天を求めている証拠であった。もし彼らの本国が天でなければ、自分がそこから来た旅人であり寄留者であることを告白してはいなかったであろう。何故なら、その場合、その人は天のことなど全く希求しないだろうからである。天を希求しないのであれば、自己を天からの旅人であり寄留者であることを告白することもない。
【11:15~16】
『もし、出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし、事実、彼らはさらにすぐれた故郷、すなわち天の故郷にあこがれていたのです。』
信仰者たちは、地上における故郷に帰ろうと思えば、帰ることができた。何故なら、それは物理的に可能だからである。自分の故郷が異世界にあるとか、足に障害があるので移動できなかった、ということもなかったのである。
彼らにとって、この地上の故郷などは取るに足りないものであった。というのも、彼らは天国の素晴らしさを信仰により知っていたからである。確かに天国の幸いを本当に知っているのであれば、それがあまりにも素晴らしいゆえ、この地上の故郷などはほとんど魅力のない場所となってしまう。それだから、もし彼らが地上の故郷を慕い求めていたとすれば、それは彼らが天国のことを何も考えていなかったということを意味していた。つまり、天国の素晴らしさを知らないからこそ、地上の故郷などというちっぽけな場所を求めることになるのである。これは、プラトンの『国家』に書かれている有名なあの地底人が、太陽の光をまったく知らないばかりに、地底こそが真に明るく素晴らしい場所だとばかり思い込んでいたのと似ている。
【11:16】
『それゆえ、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。』
どうして神は信仰者たちの神と呼ばれることを恥とされなかったのか。それは、信仰者たちが都を期待していた通り、神は実際にその都を用意しておられたからである。つまり、神は信仰者たちに対して真実な御方であった。これは神が正しく慈しみ深い存在であることを証示している。だから、神は信仰者たちの神と呼ばれることを嫌悪なさらなかったのである。もし神が都を用意しておられなかったとすれば、どうだったか。その場合、ただ聖徒たちが一方的に神は都を用意しておられると思い込んでいたに過ぎないことになる。そのようだと、神は御自身を信じる聖徒たちに対して誠実でないということになる。これでは神が誠をもって聖徒たちに応じられない御方だということを証示してしまう。だから、もし神が都を用意しておられなかったとすれば、神は聖徒たちの神と呼ばれることを恥としておられたはずである。もちろん神に「もしも」は有りえないから、神が都を用意しておられなかったということは万が一にも考えられないことなのではあるが。
この都は、再臨に伴って到来または開始された。それは紀元70年である。これは、都における出来事が『すぐに起こるはずの事』だと断言している黙示録と完全に一致している。既に見た通り、確かに黙示録21章と22章では都に関する出来事が預言されていたが、それは本当にすぐさま実現されたのであった。見よ、再臨成就説に立つと、これほどまでに一致した聖書の理解が得られるようになる。これは再臨成就説が真に聖書的な見解だからに他ならない。まだ都は到来していないと考える既存の見解に立つと、どうしても黙示録に書かれている預言は即座に実現されることであるという聖書の主張とそぐわなくなってしまう。これは、既存の見解が間違っているからに他ならない。というわけで、このようにして遂に聖徒たちは切に待ち望んでいた都に入れるようになったのである。
教会の使命の一つは、今から2千年前に到来したこの都に、世の始まる前から選ばれていた人たちが入れるようにすることにある。すなわち、選ばれた人たちが都に入れるように宣教をすることにある。何故なら、選ばれている人たちは、都の住民として定められているからである。もし教会が宣教をしなければ、選ばれている人たちがイエス・キリストについて知るのは難しい。もしイエス・キリストを知れないのであれば、この御方を信じることはできない。もしこの御方を信じることができなければ、都に入ることはできない。選ばれている人たちが都に入らないというのは、有りえないことである。それゆえ、教会が宣教をしないというのはあってはならないことだということになる。だから、教会がキリストを宣教するというのは、非常に大切なことなのだ。
【12:18~19】
『あなたがたは、手でさわれる山、燃える火、黒雲、暗やみ、あらし、ラッパの響き、ことばのとどろきに近づいているのではありません。』
この箇所で言われているのは、もうお分かりであろう。シナイ山の出来事である。
ここに書かれている語句を一つ一つ説明していく。これらは、どれもそう難しいものではない。『手でさわれる山』。これはシナイ山を指している。どうして、わざわざ『手でさわれる』と言われたのか。それは後の箇所である12:22で出てくる『シオンの山』と対比させるためである。『燃える火』。これはシナイ山に満ち広がった神の臨在を示す火を指している(出エジプト19:18)。これは実際の火であった。『焼き尽くす火』(ヘブル12章29節)であられる神は、火において御自身を示されたのである。『黒雲』。これはシナイ山に満ちた密雲のことである(出エジプト19:16)。この雲は、神の権威を表示していた。キリストも至高の権威者として再臨された際には、天の雲に乗って来られたのであった。『暗やみ』。これは神が闇において降りて来られたことを言っている(出エジプト20:21)。『あらし』。これは神が山に降りて来られた際に生じた諸々の激動を指している。『ラッパの響き』。これはシナイ山に鳴り響いた大きなラッパの音である(出エジプト19:16)。このようなラッパの巨大音により、神は御自身の威厳を際立たせられたのである。キリストが再臨された際にも、その威厳に相応しく、やはりラッパの音が鳴り響いた(Ⅰテサロニケ4:16)。『ことばのとどろき』。これは神の恐るべき御声である。これは実際の音声であった。これについては、続く箇所で更なる説明がされている。
この箇所で、7つの項目が挙げられているのは興味深い。恐らく、ヘブル書の著者は意図的に7つにしたのではないかと思われる。もし本当にそうだとすれば、ここではシナイ山の出来事における十全性が示されていることになる。何故なら、聖書において「7」とは、欠けがないことを表示するからである。
ヘブル書の著者は、この箇所で、聖徒たちにあのシナイ山の出来事のような恐るべき出来事がこれから訪れるのではないと言っている。『近づいているのではありません。』と書かれている通りである。これは、つまり「間近に迫っている出来事はそのようなものではない。」という意味である。もしあの時のような出来事が再び聖徒たちに訪れるのだとしたら、この箇所では「近づいています。」と言われていたはずである。後に見ることになるが、聖徒たちに迫っていたのは喜ぶべき幸いな出来事であった。
確かに、聖徒たちにとっては、このような恐るべき出来事が訪れることにはなっていなかった。しかし、ユダヤ人の不信者たちは、そうではなかった。彼らの場合、再臨がもう間もなく起きると、それからすぐにも恐るべき状態へと投げ込まれることになった。すなわち、彼らは神の裁きにより、恐れと戦きのうちに滅亡せねばならなくなったのである。それだから、この箇所では、ユダヤ人にではなく聖徒たちに対して語られているという点に注意せねばならない。もしこの箇所でユダヤ人に対して語られているとしたら、ここではあの時のような出来事が再びユダヤ人を襲うであろうと言われていたはずである。
【12:19~20】
『このとどろきは、これを聞いた者たちが、それ以上一言も加えてもらいたくないと願ったものです。彼らは、「たとい、獣でも、山に触れるものは石で打ち殺されなければならない。」という命令に耐えることができなかったのです。』
あの時にシナイ山に鳴り響いた神の御声は、そこにいた者たちにとって耐え難いものであった。それが、あまりにも恐ろしかったからである。恐らく、それは巨大な雷の音と響きが可愛く思えるぐらいの凄まじさだったのではないかと推測される。それだから彼らはモーセ一人だけが神の声を取り次いでくれるようにと懇願したのであった(出エジプト20:18~21)。
【12:21】
『また、その光景があまり恐ろしかったので、モーセは、「私は恐れて、震える。」と言いました。』
このシナイ山の出来事は、モーセでさえも戦慄させられた。『私は恐れて、震える。』とは彼の本当の思いであった。モーセでさえ恐れたのであれば、この時の光景を恐れずにいられる者が果たしていたであろうか。もちろん、そのような者はいなかったはずである。
ところで、キリストが地上におられた時にも御声が天から鳴り響いたが(ヨハネ12:27~33)、その時にいた人々は、御声を聞いても特に戦慄したようには思われない。というのも福音書の当該箇所を読んでも、「恐れた。」とか「動じた。」などとは書かれていないからである。むしろ、その時そこにいた人々は、これといって動揺しなかったように感じられる。ここでささやかな疑問が生じる。どうしてシナイ山の時には人々が御声に動じたのに、キリストの時には人々が御声に動じなかったのか。この疑問の解決は簡単である。つまり、シナイ山の時には人々を恐れさせるために神が御自身を顕現されたのであって、キリストの時にはそのような目的はなかったのである。シナイ山の時に民が大いに恐れたのは、民が従順になるために恐れを抱かねばならないからであった(出エジプト20:20)。一方、キリストの時には、神は御自身を慈しみ深い御方として示されたのであった。それだから、この2つの出来事における違いを見て、シナイ山の時の神とキリストの時の神は異なっているなどと考えるのは、大いに間違っている。言うまでもなく神は常に同一であられる永遠者だから、シナイ山の時の神もキリストの時の神も同じ神が語っておられたのである。
【12:22~24】
『しかし、あなたがたはシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また、天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに、新しい契約の仲介者イエス、それに、アベルの血よりもすぐれたことを語る注ぎかけの血に近づいています。』
ヘブル書の著者は、この箇所でこう言いたいのである。すなわち、「あなたがたにはこれからあのシナイ山の時のような恐るべき出来事が訪れるのではなく、非常に幸いな喜ぶべき出来事が訪れることになるのだ。」と。確かに、もう間もなく実現された再臨の出来事は、当時の聖徒たちにとって良い出来事であった。何故なら、聖徒たちにとって、それは救いをもたらす出来事だったのだから。
語句を一つ一つ説明していかねばならない。この箇所で言われている語句は、先に見た箇所とは違い、いくらか難しい。『シオンの山』。これは天上の聖所である。これは先に見た箇所で『手でさわれる山』と書かれていたのと対照的である。こちらのほうでは、手では触れない霊的な山について言われているのだ。『生ける神の都』。これは天国の都を指している。これは地上にあるのではない。黙示録21章、22章で書かれている神の都と、ここで言われている都は同一である。『天にあるエルサレム』。これは天国である。『天にある』と書かれているのは軽んじるべきでない。これは地上にあるのではないということである。『無数の御使いたちの大祝会』。これは、天国で皆が集う際における御使いたちの大饗宴を言っている。『御使いたち』とは文字通りの意味の御使いである。『無数』とは、御使いの数が凄まじかったことを示している。『天に登録されている長子たちの教会』。天上には長子であるユダヤ人の教会が登録されていた。この『長子』とは、異邦人の兄としての長子であるユダヤ人という意味以外には解せない。著者は、聖徒たちが間もなくこの天上の教会の一員に加えられるのだと言っている。『万民の審判者である神』。これは再臨の後で教会にいる万民がキリストにより審判を受けることを言っている。この審判は、マタイ25章や黙示録20章で書かれているあの審判を指す。それは紀元70年に実現している。『全うされた義人たちの霊』。これは紀元1世紀の聖徒たちが、今は霊だけの状態となっている昔の義人たちに間もなく会えるということである。とはいっても、その時には霊だけの状態だった昔の義人たちは新しい身体を受けて復活しているので、実際は霊だけの状態の聖徒と会うというわけではなかった。つまり、ここで言われているのは「今は霊だけだがやがて復活して実際の身体を持つことになる昔の義人たち」ということである。『新しい契約の仲介者イエス』。これは、間もなく聖徒たちが再臨されたキリストに会うことになる、という意味である。著者は『新しい契約の仲介者』と言って、ここまでヘブル書の中で論じられた内容を読者に想起させようとしている。著者はこのようにキリストについて言うことで、キリストを新しい契約の仲介者として称揚しているのだ。『アベルの血よりもすぐれたことを語る注ぎかけの血』。これは勿論キリストの血を指している。カインに殺されたアベルの血は、悪者に対する報復を求めて神に叫ぶに過ぎなかった(創世記4:10~12)。だがキリストの血は、そのアベルの血よりも更に優れたこと、すなわち人間の贖いについて実効的に語るのである。
この箇所では、全部で9の項目が挙げられている。「9」であるから、この箇所は前に見た箇所とは違い、特に数字に意味は込められていないと思われる。何故なら、聖書において「9」という数字は特に何の意味も持っていないからである。もっとも、魔術師であれば、完全数10に1足りないからというので不完全な数だとするかもしれないが。
これまで教会は、ここで言われている『生ける神の都』が未だに到来していないと思い込んできた。それというのも、その都の到来は黙示録21章、22章に記されている出来事であって、その箇所は恐らくまだ成就していないに違いないと感じていたからである。だが、今見ているこの箇所をじっくり見るがよい。そして、そこで言われていることをよく考えるがよい。この箇所では、今まで教会がまだ訪れていないと思ってきた『生ける神の都』が紀元1世紀の聖徒たちにとって『近づいている』と断言されている。これは、つまり、もう間もなく紀元1世紀の聖徒たちが神の都に住めるようになるということである。『近づいている』とは文字通りの意味である。すなわち、これは数年・数十年の時間単位である。この箇所で書かれている『生ける神の都』とは、当然ながら黙示録21章、22章に出てくる神の都と同一の都である。それだから、黙示録21章、22章で書かれている都は、紀元1世紀の聖徒たちにとってすぐにも到来したのである。このことを考えても分かるように、やはりヨハネが言った通り、黙示録に記されている出来事は21章、22章も含めて『すぐに起こるはずの事』であった。もしその都が間もなく訪れなかったとすれば、黙示録とヘブル書で、その都がすぐにも訪れると言われているのは間違いだったことになる。だが、神の聖書に間違いがどうして書かれているであろうか。そのようなことは絶対に有り得ない。私は、聖書には間違いがないと信じる。不信仰な者は誤謬の中に埋没するがよい。ある者は、私がこのように言うと、大いに反発した。すなわち、黙示録21章、22章で書かれている都は未だに訪れていないとした。黙示録やヘブル12:22~24の箇所で、それが紀元1世紀の聖徒たちにとって間もなく実現されると教えられているにもかかわらず、である。この者は、私だけに反発したと思っているかもしれないが、実は私ではなく聖霊に反発したのである。何故なら、私は聖書に書かれている通りのことを言ったに過ぎないのだから。聖霊に逆らう者は、もうどうしようもない。それだから、私はこの者が変化することを諦め、即座にこの者から離れることにした。このようにして御言葉の明白な教えを拒絶する者は、何を言っても無駄だと判断したからである。この者は黙示録21章で書かれている『千年』が非常に長い期間であると堂々と主張しておきながら、この言葉について尋ねられると「この言葉を定義する他の聖書の箇所はない。」などと平気で言ったり(つまり何の聖句根拠もなしに千年が長いと勝手に思い込んでいるのだ)、また黙示録20章で解放されたサタンが動員すると言われているのはロスチャイルドのことであるなどと空想を語ったりしていたが(これはこじつけもいいところである)、黙示録をよく研究していないにもかかわらず黙示録を豊かに理解できているかのように語っていたのは誠に不思議であった、と今にして思うのである。ほとんど研究らしい研究もしないくせに堂々と熟知しているかのように語るのは、普通に考えれば誰でも分かるように、非常な軽率であって正しい教師の振る舞いとは言えないのである。私の場合、既に神の恵みによって黙示録の註解書を全力で書き上げたが、それにもかかわらず、今になってもまだより深く・より正しい黙示録の理解に至れるようにと日々祈っているぐらいである。このようである私は読者諸氏に注意していただきたいのだが、この世には黙示録を研究しないにもかかわらず堂々と語る者があまりにも多いから、そのような者の語る黙示録の教えは十分に思慮を持って聞くようにしていただきたい。実際、そのような者たちが語る黙示録の教えには、間違いや不十分性が非常に多いのである。これは研究していないのだから当然のことだ。
【12:25】
『語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら、地上においても、警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが、処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。』
『語っておられる方』とは誰か。これは天の神である。
その天の神が『語っておられる』こととは何か。それは、次の箇所である12:26で言われていること、すなわち間もなく全世界が大いに揺り動かされる、ということである。
あのシナイ山の時に御声に聞き従わなかったならば、たとえ獣であっても、処罰されねばならなかった。であれば、今度の場合は、尚のこと、御声に聞き従わなかったら処罰に遭うであろう、とこの箇所では言われている。一体どうしてそうなのか。それは、前の時は地上から御声が発されたのに対し、今度の場合は天から御声が発されているからである。地上で発された御声に聞き従わないのは重大だが、天上から発された御声に聞き従わないのは更に重大である。前者よりも後者のほうが責任は重い。だからこそ、間もなく天地が揺るがされるから敬虔に歩まねばならないという天からの御声に従わない人たちは、大いに処罰に値したわけである。実際はどうだったのか。確かに、ここで言われている通りであった。すなわち、紀元68年に再臨が起きた際、不敬虔な者たちは大いに断罪されたのであった。ユダヤ人においては、そのほとんど全てが死に絶えた。
これらのことから、我々は、神の御声に聞き従わないことの悲惨さを学ぶべきである。天からの御声に聞き従わないからこそ、人は苦難に遭うのである。『御言葉を蔑む者は身を滅ぼす』と箴言で言われている通りである。もし御声に聞き従うならば幸いがある。何故なら、神がその人を喜ばれるからである。『謹んで御言葉を行なう者は栄える』と箴言で言われているのは真実である。
【12:26】
『あのときは、その声が地を揺り動かしましたが、このたびは約束をもって、こう言われます。「わたしは、もう一度、地だけではなく、天も揺り動かす。」』
シナイ山の時には、御声が地を揺り動かしたに過ぎなかった。つまり、神が降りて来られたシナイ山の場所が激動させられただけであった。この時に地が揺るがされたとは、文字通りの地球全土という意味ではない点に注意すべきである。この時に起きた振動は、『地が揺り動かされた』と書かれてはいるものの、それはただユダヤ人のいたあの場所に限定される。というのも、神がシナイ山に降りて来られた時、他の場所にいた諸々の民族は普通にいつも通りの生活をし続けていただろうから。これは出エジプト記19章の当該箇所を見ても分かる。そこで書かれているのは、明らかにユダヤ人の群れが遭遇した出来事についてであって、それは世界的な規模だったわけではない。
だが間もなく、今度は地だけでなく天も揺り動かされることになっていた。それはキリストが再臨される際の大激動である。ここに大きな違いがある。シナイ山の時に、神は地だけにしか働きかけられなかった。キリストの時には、神は地だけでなく天にも働きかけられた。この違いに着目するのは有益である。何故なら、この違いに着目すれば、これら2つの時の出来事がより明瞭に識別できるようになるからである。
この再臨の時の揺り動かしは、既に紀元前520年の時から預言者ハガイによって預言されていた。ヘブル書の著者は、この箇所でハガイ2:6から、その預言を引用している。既に500年以上も前から、キリストの再臨の際に起こる激動が約束されていたというのには大変驚かされる。
【12:27】
『この「もう一度」ということばは、決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての造られた、揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。』
ハガイ書で書かれていた『もう一度』という短い言葉には、この箇所で言われているような意味があると著者は教えている。これはヘブル書の著者が、ハガイ書を本当の意味で読み悟っていたことを示している。何故なら、もし真にハガイ書を知解していなかったとすれば、このように短い言葉から、このような解き明かしをすることは出来ないはずだからである。
では、この箇所で言われているのは具体的にどういった意味なのか。これは説明がされなければ、意味を明白に掴むのは難しいかもしれない。ここで言われているのは、つまり再臨の時に起こる大変動のことである。キリストが再臨されると、地が篩いにかけられ、決して揺り動かされない存在である真の聖徒たちだけが神の御前に抽出されることになった。これについてはパウロもⅠコリント3章の箇所で語っている。キリストがマタイ13章で語っておられる漁の例えも、この出来事と対応している。またその時には天にも篩いとしての大激動が起こり、それまでずっと天にいたサタンとサタンの手下どもが、遂に地に落とされることになった。これについては黙示録12章で書かれている。要するにこういうことになる。再臨が起こると、地が篩いとして揺り動かされたので聖徒たちが天上に引き上げられることになり、天も篩いとして揺り動かされたのでサタンどもが地へと追放されることになった。シナイ山の時には、天にこのような変動は起こらなかった。その時、大激動が起きたのは地だけであった。天にいたサタンどもは、地が揺るがされた時にも、天にずっと居続けることができた。それだから、シナイ山の時の激動と再臨の時の激動には、実に大きな違いがあったということが分かる。
【12:28】
『こういうわけで、私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。』
聖徒たちは、不動の御国を貰い受けていた。この『御国』とは、この箇所では、神の永遠の支配とも天国を相続する権利とも解せる。いずれにせよ、聖徒たちは御国を受けていたから、再臨が起きた際、揺り動かされて神の御前から取り落とされるということにはならなかった。むしろ、その時、聖徒たちは神に救い上げられた。それゆえ、聖徒たちは神に感謝するように、と著者は言う。これは当然である。何故なら、『揺り動かされない御国を受けている』というのは、つまり決して処罰を受けることがないということを意味しているのだから。今やもうこの大激動が天と地とを篩いにかけることはない。それは紀元1世紀に起きた出来事だからである。だが我々も、自分が御国を受けていることを神に感謝せねばならない。何故なら、我々も御国を受けているので、もはや天地の大激動に遭遇することはないにしても、最後の最後まで揺り動かされることは有りえないのだから。
『こうして私たちは、慎みと恐れとをもって、神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。』
自分が御国を受けていると知ったならば、その御国を与えて下さった神の慈しみを知ることができる。そうすれば、神がどれだけ素晴らしい御方であるかがよく分かるようになる。そのようになると、その人はより敬虔に神に仕えるようにもなる。何故なら、誰でも自分に良くしてくれる存在に対しては、多かれ少なかれ従順な精神を持つものだからである。だから、この箇所では、御国を受けている聖徒たちが、御国を受けているという事実により、より神に喜ばれる人生を歩めると教えている。例えば、我々を命がけで助けてくれた人がいたとすれば、どうか。我々は、出来るだけその人の願い通りにしたいと思わないだろうか。恐らく、普通の感覚を持っていれば、その恩により、その人の願い通りにしたいと思うはずである。我々が御国を受けているので神に従順に奉仕するようになるのも、これと同じである。
【12:29】
『私たちの神は焼き尽くす火です。』
突如として書かれたこの言葉は、どういう意味なのか。これは威嚇である。著者は、この部分で、つまり次のように言いたいのである。「私たちの神は火であって、逆らう者には火の刑罰をお与えになる。あなたがたも、もし敬虔な歩みをしないのであれば、この神により火の刑罰を受けることになる。そのような結末をあなたがたは迎えたいのか。もちろん、迎えたくないはずだ。だったら、この神に火で焼き尽くされることがないように、今後ますます敬虔に歩むようにしていただきたい。」聖書の中で、このように省略的で極端に短い言葉が使われている箇所は、少なくない。例えばマタイ24:28の箇所がそうである。『死体のある所には、はげたかが集まります。』これは既に説明されたように、再臨が起こると霊的に殺された人たちが、悪霊どもに食われて惑わされるようになる、という出来事を省略的に語った言葉である。レビ記19:18の箇所もそうである。『わたしは主である。』これは、「神がこのように語ったのに従わないのであれば罰せずに済まされるであろうか。」という威嚇を省略的に述べている。
【13:14】
『私たちは、この地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。』
この箇所では、我々の今住んでいる地上に都があるのではないと示されている。何故なら、ここでは明らかに都が地上のものとされていないからである。パウロも、ピリピ3:20の箇所でこう言っている。『けれども、私たちの国籍は天にあります。』これは都が天にあるということである。キリストも、聖徒たちが迎え入れられるのは天上の世界であると言われた(ヨハネ14:2~3)。ある者たちが、この都は天上から降りて来て地上で展開されるなどと思い違いをしてしまったのは、どういう理由からだったのであろうか。それは彼らが黙示録をよく弁えておらず、黙示録21章で言われているのが比喩表現であることに気付かなかったからである。
この都は既に天上において実現されている。何故なら、この都とは天国のことであり、その天国は再臨に伴って訪れたからである。今の教会は、どうしてこのぐらいのことさえ、分からないのか。私は理解に苦しむ。
我々は、既に到来したこの都に入れるようにならねばならない。もしこの都に入れないとすれば、我々が信仰を持っている意味はなくなる。何故なら、その場合、我々は地獄に投げ落とされることになるからである。そうだとすれば、今我々が信仰を持っていても持っていなかったとしても、どちらも結局は変わらないことになる。いや、その場合であれば、むしろ信仰を持っていなかったほうがよいことにすらなる。というのも、信仰というものは、この地上において往々にして苦しみや困難が伴うものだから。
第61章 59:ヤコブの手紙
ヤコブの手紙には、幾つか見ておかねばならない箇所がある。しかし、この文書そのものは、それほど心に留めなかったとしても問題はないであろう。
【5:7~8】
『こういうわけですから、兄弟たち。主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい。農夫は、大地の貴重な実りを、秋の雨や春の雨が降るまで、耐え忍んで待っています。あなたがたも耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。』
ここでヤコブがキリストはすぐに来られると言っているのは、文字通りの意味として捉えねばならない。
我々は、ここでヤコブが『耐え忍びなさい。』と命じているのは、もうすぐにも再臨が起こるがゆえであったということをよく弁え知るべきである。というのも、もし耐え忍んで信仰に立ち続けていなかったとすれば、間もなく起こる再臨の際、聖徒たちが本当に大変なことになってしまうからである。聖徒が耐え忍ばなかったために堕落したり信仰から脱落したとすれば、神の前に不適格な者となるから、再臨の際に携挙されなくなるということにもなりかねないのだ。ヤコブはそういう人が聖徒たちの中から出ないようにと、ここで耐え忍ぶように命じたのである。今の聖徒たちは未だに再臨が起こっていないと思い違いをしているが、もしヤコブがこの手紙を書いてから2千年経過してもまだ再臨が起こらないのだとすれば、ヤコブはここでこのように命じてはいなかったかもしれない。何故なら、その場合、再臨のために耐え忍んだとしても何の意味もないからである。これから再臨が起こるからというので再臨のために耐え忍んでも、一向に再臨は起こらないので、当時の聖徒たちは何のために耐え忍んだのか分からなくなってしまう。ヤコブが再臨のために耐え忍ぶようにとここで当時の聖徒たちに命じている以上、再臨は既に起きたと考えなければいけない。ところで私が聞いた話によれば、今の時代においては、精神病院に多くのクリスチャンがいるという。今の時代において再臨についてとんでもない理解を多くの聖徒たちが持っていることから考えても、また教会の世俗化と霊性の衰えを考えても、この話はあながち出鱈目であるとは思えない。つまり、この話には、根拠となるファクターがしっかりとあるのだ。どうか、今の聖徒たちには、しっかりと理性を働かせつつ信仰において聖句で言われていることを考察してもらいたいものだ。
ヤコブは、この箇所で農夫の例えを出して、聖徒たちが豊かに耐え忍べるようにと促している。ここでヤコブは次のように言っているかのようである。「聖徒たちよ。農夫は、刈り取りという地上的な事柄のためにさえ心を強くして耐え忍んでいる。であれば、これから再臨という霊的な事柄が起こることを知っているあなたがたは、尚のこと、心を強くして耐え忍ぶべきではないか。まさか、霊的な事柄を待ち望むべきあなたがたが、地上的な事柄を待ち望んでいる農夫よりも忍耐において劣っているということは万が一にもあるまい。」
第62章 60:ペテロの手紙Ⅰ
一番目のペテロの手紙は、幾つか見ておくべき箇所がある。本章では、その箇所について註解される。とはいっても、この文書自体は、黙示録や2つのテサロニケ書とは違い、心に留めなかったとしてもそれほど問題にはならないであろう。
【1:20】
『キリストは、世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時に、あなたがたのために、現われてくださいました。』
まず見るのは、前半の『キリストは、世の始まる前から知られていましたが、』という部分である。これは、この世が創られる前からキリストがこの世に現われるようになることが予め予知されていた、という意味である。誰によって予知されていたのか。もちろん父なる神によって、である。どうして父なる神は、キリストの出現を前もって予知しておられたのか。それは、父なる神が全知の御方であり、そもそもキリストが出現するようにと定められたのはこの御方だったからである。では、どうしてペテロはこの父なる神の予知について知ることが出来たのか。それはペテロが、キリストの現われについて、ミカ5:2の箇所で『その出ることは、昔から、永遠の昔からの定めである。』と言われていたのを知っていたからである。我々は、ここでキリストが世の始まる前から知られていたと言われていることを、聖徒たちや御使いたちのことだと考えないようにすべきである。聖徒たちや御使いたちは、世の始まる前からキリストの現われを知ってはいなかった。これは明らかなことである。何故なら、彼らは世の始まる前は、まだ存在すらしていなかったからである。なお、このペテロは、Ⅰペテロ1:2の箇所でも神の予知について語っている。
v
次は後半の『この終わりの時に、あなたがたのために、現われてくださいました。』という部分である。ここでペテロはこう言いたいのである。今やユダヤの終わる時期が訪れた。それゆえ、キリストが遂に現われて下さった。それというのもキリストはユダヤの終わりの時期に現われるようにと預言されていたのだから。実際、キリストはユダヤがもう間もなく終わる時期になって現われた。それは聖書がそのように教えている通りである。ところで、この「現われる」とは、「キリストが贖いを実現させるために人としてこの世に来て下さった」という意味である。
このキリストの現われは、『あなたがたのため』であったとペテロは言う。これは聖徒たちの全てのことである。これを紀元1世紀にいた聖徒たちだけに限って考えるのは誤っている。実際、キリストはあらゆる時代の選ばれた者たちのために、人として現われ、永遠の贖いを成し遂げて下さった。これが聖書の教えであり、我々もそのように信じている。世の人々は、キリストがただの人、普通の人であり、その十字架の死には何の意味も無かったと理解しているが、それは完全に誤っている。もしキリストがそのような存在であったとすれば、また十字架の死には何の意味も無かったとすれば、あらゆる人は例外なく地獄に投げ込まれることになっていたであろう。何故なら、その場合、贖い主がこの世に存在しないことになるのだから。
ここで言われている『終わりの時』とは、マタイ24:1~3の箇所を読むのであれば、どう考えてもユダヤの終わり以外だとは理解できない。然り。これは、もう間もなくユダヤが滅びる時期のことを言っているのだ。紀元70年にユダヤが滅ぼされたというのは誰もが認める。然り。この時、ユダヤは、神の御前における聖なる御民として完全にその存在を終えたのである。神の民が神の民としてその存在を終焉させる―これこそが『終わりの時』なのである。それにもかかわらず、今の聖徒たちは、これがユダヤの終わりだと考えていない。それは聖書と真っ直ぐに向き合っていないからである。私は前々からずっと思っていたが、今の教会にはそのような姿勢があるのだ。だからこそ、今の教会には数々の見苦しいことがあるのである。例えば、今の教会はその多くが進化論に妥協し、イルミナティのダービー卿により蒔かれたディスペンセーショナリズムにまんまと騙され、フリーメイソンであったジョン・ウェスレーやビリー・グラハムを多くの人が親愛しており、最近ではキリスト教の大手出版社が悪魔の格言から教訓を日々学ぶという誠に耐え難い異常な書物を出版したが(どうやら人気があるようなのだ…)、これらはどれも聖書にシッカリと立脚できていないからである。もし聖書に固執していたならば、教会は今のような状態では無かったはずである。つまり、古代教会や宗教改革時代の教会に見られた純粋さが多かれ少なかれ見られたはずである。今の聖徒たちは目を覚まし、聖句に真正面から向き合うべきである。この『終わりの時』という言葉についても、ぜひ正しい理解を持てるようにしていただきたい。
【4:7】
『万物の終わりが近づきました。ですから、祈りのために、心を整え身を慎みなさい。』
『万物の終わり』とは、ユダヤ世界のことである。何故なら、マタイ24章の中では、神殿の徹底的な崩壊と共に訪れるユダヤの破滅の時こそが、『世の終わり』(マタイ24章3節)だと明白に言われているからである。『世の終わり』と『万物の終わり』とは、同一の意味を持つ言葉である。この『万物の終わり』という言葉を、感覚的に捉えてはいけない。今まで教会は、まだ再臨の領域において目が開かれていなかったので、この言葉を感覚的に捉え続けてきた。すなわち、『万物の終わり』と言われているのを聞いて、本当に文字通りの意味で全世界つまり地球の全地が滅び失せるなどと捉えてきた。しかし、このように捉えるのは誤っている。何故なら、この言葉は聖書の他の箇所によってこそ解読されるべき言葉だからである。まともな派であれば、どこの神学校でも「聖書は聖書によって解釈しなければいけない。」と教えているはずだ。それなのに、どうして多くの教師たちが、この言葉を感覚によって捉えているのか。どうして感覚的な解読を退けて他の聖句箇所から捉えようとしないのか。私は疑問に思うのである。
ユダヤ世界における『万物の終わりが近づ』いたというのは、本当にユダヤの終わりが近かったからである。これは10歳の子どもでも理解できることである。実際的に考えてみると、どうか。ヤコブがこの手紙を書いた時期を紀元55年だとすれば、ユダヤが破滅するのはその15年後の紀元70年である。既に第1部でも説明されたように時間的に近いと感じられる度合いはその迫り来る出来事の大きさに比例しているから、確かにユダヤの破滅という大きな出来事が15年後に訪れるというのは「すぐに」と感じられる期間である。だからこそ、ヤコブはここでユダヤ世界における『万物の終わりが近づきました』などと言っているのである。
ヤコブはユダヤの終わりがすぐにもやって来るからというので、ここで『祈りのために、心を整え身を慎みなさい』と聖徒たちに命じている。このように命じたのは、もし聖徒たちが敬虔に歩んでいないと、間もなく訪れる大きな出来事がやって来た際、大変なことになりかねないからである。その時には再臨も起こったが、敬虔に歩んでいない者たちは、携挙されず地上に残されてしまったのである。ヤコブはそのような人が一人も出ないために、ここで予め準備をしておくようにと命じたわけである。すなわち、ここで命じられているのは、心と身を清く保ちつつ祈りに励むことで来たるべき時のために準備をするように、ということである。というのも、祈ることで霊的な準備が豊かに出来るようになるからである。
【4:17】
『なぜなら、さばきが神の家から始まる時が来ているからです。』
神の家から始められる裁きとは何か。まず『神の家』とは教会を指している。これはⅠテモテ3:15の箇所から明らかである。教会には神の臨在があるゆえ、神の家と呼ばれている。この神の家である教会から裁きが始まるとは、つまりネロの大迫害のことを言っている。これこそ正に教会に対する裁きであった。すなわち、神はネロを通して教会に大きな苦難をお与えになった。この裁きとは、この出来事以外ではない。
この箇所から分かるように、神は、まず御自身の群れから裁きをされる御方である。これは旧約聖書でも教えられている。すなわち、旧約聖書には次のように書かれている。『また、私が聞いていると、ほかの者たちに、こう仰せられた。「彼のあとについて町の中を行き巡って、打ち殺せ。惜しんではならない、あわれんではならない。年寄りも、若い男も、若い女も、子どもも、女たちも殺して滅ぼせ。しかし、あのしるしのついた者にはだれにも近づいてはならない。まずわたしの聖所から始めよ。」そこで、彼らは神殿の前にいた老人たちから始めた。』(エゼキエル9章5~6節)御自身の民からまず裁きをなされるというのは、我々の感覚からすれば、考えにくいことかもしれない。しかし、これこそが神のやり方である。神はこうして事を行なわれるのだ。では、どうして神はまず最初に、御自身の民から裁きを行なわれるのか。その理由は何か。聖書でその理由は明白に示されてはいない。だが、その理由は難なく分かる。神が御自身の民から裁きをなされる理由は、大きく分けて2つある。まず第一に、聖徒たちほど神の近くにいる存在はいないからである。我々が仕事をする際、まず身近にある案件から始めるように、神も御自身の近くにいる民から裁きをなされるのだ。第二は、他の全ての人々に対する証示のためである。すなわち、神はまず聖徒から裁きをなされることで、全ての人々に「神の群れである聖徒でさえ裁きを免れなかったとすれば、それ以外の人々は尚更のこと裁きを免れないであろう。」と暗黙のうちに語られるのだ。これは、警察がまず代表的な犯罪集団に強力に働きかけることで、全ての人々に威嚇をするのと似ている。もっとも警察の場合は威嚇だけで済む場合が多いのに対し、神の場合は威嚇と共に必ずや裁きもお与えになる、という違いがある。つまり、神は御自身の民だからといって裁きを容赦されない。むしろ、御自身の民だからこそ、神は積極的に裁きをお与えになる。それは聖なる民が、神の子らだからである。人の親は、まず自分の子をこそ叱るものである。往々にして親たちは自分の子を第一に叱り、その他の子たちは次に叱るものである。神も、そのようにまず第一に聖徒たちから事をし始められる。
これまで教会は、この箇所で言われている神の家から始まる裁きが、未だに実現していないと考えてきた。だから、無思慮にもペテロがここで言っている御言葉を引用し、これから神の家から裁きが始まることになるであろう、などと語ってきた。私はそのように語っている人を、これまで何度も見てきた。だが、ここでペテロが言っている裁きを未だに起きていない出来事として捉えるのは間違っている。何故なら、この箇所でペテロは、明らかに自分の時代にその裁きが実現すると語っているからである。ペテロが裁きの時はもう来ていると言ったのは、西暦21世紀の今ではなく、紀元1世紀の今である。つまり、ペテロはこの箇所で、もう間もなく神の家から裁きが始まるのだ、と言っているのである。それゆえ、この箇所で言われていることは、紀元1世紀の出来事についてであると理解せねばならない。このぐらい少し考えれば分かるものである。それなのに、今まで教会は、このぐらいのことさえ弁えてこなかった。これは、これまで教会には再臨に関わる悟りが与えられてこなかったからである。すなわち、悟りが与えられていなかったからこそ、再臨に関わる事柄において頓珍漢な考えを持つことになってしまったのだ。もし悟りが与えられていたとすれば、このⅠペテロ4:17の箇所を含め、再臨に関わる事柄を正しく把捉することが出来ていたであろう。
【4:17~18】
『さばきが、まず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりは、どうなることでしょう。義人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは、いったいどうなるのでしょう。』
教会でさえ裁きを免れないとしたら、『神の福音に従わない人たち』は尚のこと裁きを免れない。それは、神とは御自身の民にさえ裁きをお与えになる御方だからである。では実際はどうだったか。教会に裁きが下されてから、『神の福音に従わない人たち』には裁きが与えられたのか。これは実際にその通りとなった。すなわち、ユダヤの滅亡のことである。紀元1世紀の歴史を考えてみよ。教会が紀元64年頃からネロによる苦難を受けると、すぐにもユダヤに苦難が訪れ、もう間もなくユダヤは滅ぼされることになった。このユダヤに対する裁きは、教会に対する裁きよりも重く悲惨なものであった。このようにして、『さばきが、まず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりは、どうなることでしょう。』というペテロの言葉が、現実となったのである。確かに教会でさえ苦難を免れなかったのだから、ユダヤも苦難を受けて当然であった。このような例は、最近の歴史においても見られる。教会は18~19世紀の間、啓蒙主義、進化論、悲観的終末論、自由主義神学をはじめ諸々の苦難に悩まされた。これは実に悲惨な打撃であった。この打撃による負傷は21世紀になった今に至るまで、まだ癒されていないほどである。例えば、今でも実に多くの教会が進化論を受容したままの状態である。このような打撃があった後、20世紀に入ると、2度の世界大戦が起こり、全世界が滅茶滅茶な状態となった。これはどちらも裁きであると言ってよい。20世紀における世界に対する裁きは、18~19世紀における教会に対する裁きに続いて起きたと言える。また世界に対する裁きは、教会に対する裁きよりも遥かに重く悲惨であった。見よ。確かに神はまず教会から裁きを始められるのだ。近代の歴史が示す通り、教会でさえ裁きを免れなかったのだから、その後に引き続いて全世界も裁きを受けることになったのである!
18節目では、17節目と似たようなことが言われている。18節目でペテロはこう言っている。すなわち、真の聖徒たちでさえギリギリで救われるのだとすれば、それ以外の者たちは滅びの裁きを受ける以外にはないのではないか、と。実際にはどうだったか。確かに実際、ペテロの言葉の通りとなった。再臨が起こると、真の聖徒たちは救われたが、それ以外の者たちは裁きを受けた。すなわち、ユダヤ人たちはほとんど全滅と言ってよいほどの虐殺を受け、それ以外の不信者たちは永遠の滅びを宣言されるという霊的な裁きを受けた。この2つの裁きについては、本作品の中で既に語られた。
ペテロはこの箇所を、間違いなく箴言11:31の箇所に基づいて語っている。ペテロはこの箇所でギリシャ語訳(70人訳)をそのまま用いている。ヘブル語の旧約聖書ではやや違った言葉となっており、次のように書かれている。『もし正しい者がこの世で報いを受けるなら、悪者や罪人は、なおさら、その報いを受けよう。』
第63章 61:ペテロの手紙Ⅱ
2番目のペテロの手紙は、絶対に考究されるべきである。特に、ユダヤの終末について語られている3章の箇所は、無視することが許されない。この箇所からは再臨のことが豊かに学べるからである。
【1:11】
『このようにあなたがたは、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国にはいる恵みを豊かに加えられるのです。』
ここで言われている『御国』とは天国を指している。神の働かれる支配という意味でも確かに『御国』と聖書では言われている。この御国は、地上の聖徒たちのうちにも存在している。だが、この箇所で言われている『御国』は、そういう意味合いではない。ここでは地上の聖徒たちがまだ入っていない場所という意味合いにおける『御国』が語られているのだ。
この御国は『永遠』である。その場所に終わりは決して来ない。『永遠の命』に与かった聖徒たちは、この場所で永遠に生き続けるのである。天国が永遠であるということについては、ダニエル書でもこう言われている。『その御国は永遠の国。』(7章27節)『その国は滅びることがない。』(7章14節)神と聖徒たちは御国の永遠性にやがて飽きてしまうことにはならないのか、などと心配するには及ばない。何故なら、御国とは永遠でありつつ飽きないような場所だからである。「この時間がずっと続けばどれだけよいことか。」このように感じたことのある人が読者の中には多かれ少なかれいるはずである。天国とは、常にこのように感じられるほどに幸いな場所なのである。我々は、天国に満ちている神の至福の恵みを侮ってはならない。
【2:4】
『神は、罪を犯した御使いたちを、容赦せず、地獄に引き渡し、さばきの時まで暗やみの穴の中に閉じ込めてしまわれました。』
この箇所で言われている『御使いたち』とは、創世記6:1~4の箇所で書かれている『神の子ら』のことである。これは本当の御使いのことではない。これは、神の言葉を受けた少数の者たちを指している。つまり、もし不敬虔にならなければ天国に入れるような人間である。これを昔の教父たちのように文字通りの意味での御使いだと妄想するのは、自分を狂気に陥れることである。注意せねばならない。
この御使いたちは非常に堕落していたので、ノアの時代に滅ぼされ、『容赦せず、地獄に引き渡』されることになった。これは即座に地獄へと投げ込まれるという意味ではない。そうではなく、これは地獄行きを確定された、または地獄に定められていたという永遠の定めに確認の印が押された、という意味である。何故なら、この時にはまだ本当の意味での地獄は存在していなかったからである。既に第2部で述べたように、キリストが再臨されてから、真の意味における地獄すなわちゲヘナが開始されることになった。これは本当の地獄であるから、そこにいる者たちは身体においても魂においても苦しみが与えられる。しかし、再臨が起こるまでは、まだゲヘナが開始されていなかったから、地獄の前段階とでも言うべきハデスしか存在していなかった。これは「地獄の準備場所」と呼べばよいであろう。これは本格的な地獄ではないので、そこにいる者たちは身体を持っておらず、ただ魂だけの苦しみを受けるのである。我々が今見ている箇所で『地獄』と書かれているのは、このハデスではなくゲヘナであるということを弁えるべきである。また、ここでは堕落していた御使いたちについて『容赦せず、地獄に引き渡し』と書かれている。このことから、神の言葉を受けた者たちがどれだけ重い責任を負っているかがよく分かる。神の言葉における恵みを受けていれば受けているほど、神の言葉における責任もそれだけ重くなる。ヤコブが教師について次のように言ったのは、これが理由である。『私の兄弟たち。多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように、私たち教師は、格別きびしいさばきを受けるのです。』(ヤコブ3章1節)つまり、教師とはそのほとんどが他の人たちよりも神の言葉における恵みを受けているゆえ、堕落した際には裁きの度合いも他の人たちに比べて厳しくなるのだ。この箇所で言われている『御使いたち』も正にそのような存在であった。だからこそ、神は堕落したこの御使いたちを『容赦せず、地獄に引き渡』されたのである。この御使いたちは、暴虐に満ちたノアの時代における堕落性を最高に象徴していた。それゆえ、神はこの御使いたちの堕落をご覧になり、それから120年後に大洪水により世界を滅ぼされることに決められたのである(創世記6:1~3)。それというのも、神の子である御使いたちでさえ堕落していたぐらいなのだから、世界全体がもうどうしようもなくなっていたということは明らだかったからである。神の子らである御使いたちでさえ回復不能な状態に陥っていたのであれば、尚のこと、その他の者たちが回復不能であったのは確かである。
地獄に定められたこの御使いたちは、裁きが行なわれる再臨の時まで、ハデスである『暗やみの穴の中に閉じ込めてしまわれ』た。裁きの時が紀元1世紀に訪れると、彼らは第二の復活により、ハデスの中から出された(黙示録20:13)。この時、魂だけの状態になっていた彼らは、裁きを受け物質的な滅びに至るために復活の身体を付与された。そして、復活してから携挙され、キリストによる空中の大審判を受けた(マタイ25:31~46)。その後、裁かれた彼らは永遠の地獄へと投げ込まれることになった(マタイ25:41、黙示録20:15)。見よ。これこそ神の言葉を受けていたが堕落した者たちの恐るべき最終的結末である。もし彼らが堕落せずに歩んでいたとすれば、このようになることはなかったであろうに。
この箇所で言われている内容は、ユダがその手紙の6節目で繰り返している。ユダがペテロの書いたことをベースとしているのは間違いない。このユダ書の箇所については、また後ほど詳しく論じられることになる。
【2:9】
『これらのことでわかるように、主は、敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを、さばきの日まで、懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。』
神は、必ず『敬虔な者たちを誘惑から救い出し』て下さる。ノアを見よ。彼は敬虔だったので、罪深い世と共に滅びることがなかった。ロトを見よ。彼も敬虔だったので、忌まわしい街の堕落に呑み込まれることなく助け出された。ヨセフを見よ。彼も敬虔のゆえに、女のなまめかしい誘惑から逃れて大権威者とさせられるに至った。神は、敬虔な者たちに慈しみ深くして下さる。それは、彼らが謙遜な態度で神を恐れているからである。ソロモンは言う。『謙遜と、主を恐れることの報いは、富と誉れといのちである。』(箴言22章4節)ノアとロトとヨセフは、謙遜で主を恐れる敬虔な人たちであった。だから、彼らは『誘惑から救い出』され、『富と誉れといのち』を受けることができた。すなわち、この3人は滅びから免れて生き延び、長期的な意味において富を取り去られることもなく、後世に至るまで語り継がれる誉れ高き人となった。もし彼らが高慢で主を恐れることもなければ、つまり不敬虔な人たちであれば、滅ぼされ、富も誉れも命も取り上げられていたかもしれない。ペテロの時代に生きていた『敬虔な者たち』も、この3人と同じであった。この紀元1世紀にいた敬虔な聖徒たちは、ユダヤの滅びに巻き込まれることなく助け出され、永遠の『いのち』と朽ちることのない『富』と天上における輝かしい『誉れ』とに与かることになった。彼らは今に至るまで、そしてこれからも、これらの賜物を享受することが許されている。このように神は『敬虔な者たち』を喜ばれ、彼らに良くして下さる。我々は、このことをよく心に留めるべきであろう。
一方、『不義な者ども』は、裁きが行なわれる再臨の時まで、ハデスに投げ込まれて『懲罰のもとに置』かれることになった。彼らは再臨の時が来ると、第二の復活によりハデスから出され、空中の審判を受けた。そして裁かれて後に地獄へと投げ込まれた。それ以降、彼らは永遠に苦しみを受けることになった。つまり、これは先に見た2:4で言われていた内容とほとんど変わらない。違うのは、前の箇所では『罪を犯した御使いたち』だけについて言われており、我々が今見ている箇所ではその御使いたちをも含めた再臨の時までに存在していた全ての悪者どもについて言われている、という点である。この『不義な者ども』は、自分の不義のために、このような悲惨に陥ることになった。だから彼らは自分の運命について文句を言うことができなかった。それは、殺人罪を犯した犯罪人が死刑に処せられたとしても、自業自得であって、文句を言えないのと同じである。
それでは再臨以降に生まれてきた『不義な者ども』は、どうなるのか。これは簡単に分かる。すなわち、彼らの場合、この地上での人生を終えて後、即座に地獄へと投げ込まれる。再臨以降の悪者は、もはや死んでからハデスに投げ込まれ、魂だけの状態で地獄が始まるのを待つ、ということにはならない。何故なら、再臨の出来事が起きた際に、ハデスはその役目を終え、ゲヘナが新しく開始されたからである。このゲヘナは本当の意味での地獄であり、ハデスは地獄の前段階である。既に第2部でも述べられた通り、再臨を境として、悪者たちにおける死後の苦しみの場所の様相は一変したのである。
このように『敬虔な者たち』を助け出し、『不義な者ども』には悲惨な裁きを下される、というのは神の御心であった。それは神に適っている。何故なら、神とは正義を愛され悪を憎まれる王なる審判者だからである。今まで多くの王たちは、正しい者たちには恩恵を賜わり、悪い者たちには容赦せずに罰を与えてきた。神という至高の王も、そのようにされるのである。もし神がそのようにされなかったとすれば、神は神とは言えなかったであろう。その場合、神は正義を愛しておらず、悪を憎んでいないからである。そのような存在が果たして神と言えるのであろうか…。正義と悪に対して正しい態度を取らない存在が神などと言えるのであろうか…。
【3:3~4】
『まず第一に、次のことを知っておきなさい。終わりの日に、あざける者どもがやって来てあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。「キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこのかた、何事も創造の初めからのままではないか。」』
この箇所から3:14までの箇所は、非常に大切である。何故なら、そこでは古い世界の終末について重要なことが語られているからである。本書で、これらの箇所を無視することは許されない。我々がこれから見ていく箇所は、非常に霊的であって、簡単には正しい解釈を得ることができない。それゆえ、聖徒たちは霊を研ぎ澄ませつつ、これから書かれる註解を読み進めてほしい。
『終わりの日』とは、ユダヤが終わりに近づいた日々のことである。これはユダヤ終焉における直近の日々を指している。ペテロがこの手紙を書いている時には、まだこの時期は訪れていない。というのも、この箇所でペテロはその時期をまだ訪れていない時期として示しているからである。もし既にその時期が訪れていたとすれば、ここでペテロは『あざける者どもがやって来てあざけり、…次のように言うでしょう。』などとは言わず、「あのあざける者どもはこう言っている。」などと言っていたであろう。しかし、ユダヤが終わりを迎える時期そのものは、この時にも既に訪れていた。何故なら、前の手紙においてペテロは『キリストは、世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時に、あなたがたのために、現われてくださいました。』(1章20節)と言っているからである。この「終わりの日」とか「終わりの時」といった言葉は、その箇所ごとに意味を見極めなければならない。それというのも、これらの言葉は、その書かれている箇所によりそれぞれそ意味している内容が違っているからである。この意味の多様性が解釈者たちを混乱させてしまうのである。
ユダヤの終焉が近づいてくると、聖徒たちの前には『あざける者ども』が出現した。この者どもは「嘲り」を愚かにもした。ユダ16の箇所では、『ぶつぶつ言』い、『不平を鳴らす』と書かれている。この嘲りがどのような内容だったのかは、何も書かれていないので、詳しくはよく分からない。しかし、忌まわしい内容だったことは間違いない。また、彼らは『自分たちの欲望に従って生活し』ていた。ユダ4の箇所では『私たちの神の恵みを放縦に変え』たと書かれている。つまり、彼らは自分たちの酷い悪徳の口実として神の恵みを好き勝手に利用していた。この者どもは、ユダがその手紙の中で取り扱っている者と同一の存在である。何故なら、ユダは、自分の問題としている者が、ペテロの予告した者だったと言っているからである(ユダ18)。この者どもは、教会とは関わりを何も持たない単なる不信者・異教徒であったと考えてはならない。そうではなく、これは教会の中にいた偽クリスチャンすなわち山羊のことを言っている。というのも、彼らは『キリストの来臨の約束はどこにあるのか。』と嘲笑しつつ言うからである。このように言うのは、教会に関わりを持つ者だったとしか考えられない。当時の世界を考えても分かるが、教会の外部の者にとっては来臨のことなど、そもそも注意が向かなかったはずだからである。ユダも、この者どもは聖徒たちの共同体に『ひそかに忍び込んで来た』(ユダ4)と言っている。つまり、これは教会に撒かれたサタンの毒麦なのである。感覚的に捉えれば、この『あざける者ども』は一般的な悪者であると思えなくもない。しかし、聖書を調べると、実はそうでないことが分かる。
この『あざける者ども』は、ペテロがこの手紙を書いている時には、まだ現われていなかった。先にも述べた通り、ペテロはこの箇所における内容を、まだ起きていない事柄として記しているからである。しかし、ユダが手紙を書いている時には、この者どもが現われていた。だからこそ、ユダはこの者どもに注意を促そうとして、聖徒たちに手紙を書き送ったのである。このことから2つのことが分かる。一つ目は、ユダの手紙はペテロの第二の手紙よりも時間的に後で作られたということである。二つ目は、ユダがペテロの第二の手紙を読んだか、もしくはペテロの言葉を直接的にであれ間接的にであれ自分の耳で聞いた、ということである。この2つのことは絶対に疑えない。
この『あざける者ども』は、このように喚き散らしていた。「おいおい、一体どうなっているのか。キリストの再臨があるなどと多くの者は言っているが、ぜんぜんそんな出来事は起こらないではないか。そんな約束なんて嘘だったんじゃないのか?今の世界を見てみろ。世界が始まった時から何も変わっていないではないか。キリストが再臨されたら世界が劇的に変わるんじゃないのか?そんなことなど全く起きていないではないか。どうせ、これからも起きることはないのだろう。」この箇所で『キリストの来臨』と言われているのは、再臨すなわち第二の到来のことである。これは初臨すなわち第一の到来のことではない。どうしてこのように言うかといえば、今まで多くの学者たちが、キリストの初臨を指して「来臨」と言ってきたからである。つまり勉強に熱心な読書家の聖徒たちが勘違いをしないように、今このように私は言ったのである。学者たちは第一の到来も「来臨」と言うが、聖書で第一の到来を指して「来臨」と言われている箇所はない。聖書で「来臨」と言われた場合、それはどれも第二の到来を指している。神学書をよく読む聖徒は、誤解しないようにせねばならない。『先祖たち』とは、ノアやアブラハムやモーセやダビデといった聖なる歴史における聖なる父祖たちを指す。その父祖たちが『眠った』とは、つまり「死」のことである。『創造の初めから』とは「この世界が前4000年頃に創造されてから」という意味である。
この者どもは、どうしてこのように言ったのか。それは、不敬虔な欲望に従って生活するのを止めたくなかったからである。キリストが再臨されたならば、自分たちの悪徳に満ちた歩みが容赦なく断罪されてしまうのは明らかである。キリストご自身が、再臨の際には『おのおのその行ないに応じて報いをします。』(マタイ16章27節)と言っておられた。この『あざける者ども』は、そのことを知らなかったわけではないはずである。彼らはいついつまでも好き勝手に生き続けたかった。だからこそ、自分たちに裁きをもたらすキリストの再臨を故意に否定したのである。「これまでキリストは再臨されなかったから、どうせこれからも再臨されないんだろう。」―このような根拠の乏しい稚拙極まりない理由を作り出すことによって。このようにして再臨を否定しないと、つまり再臨がこれから本当に起こると考えていれば、再臨が起こるという予測に妨げられて悪を抵抗なく行なうことが出来なくなってしまうのだ。これは例えるならば、プロを目指しているアマチュアのアーティストが自分と同じようにプロを目指しているライバルについて、「どうせアイツはプロになんかなれやしない。何故なら今に至るまでオーディションに落ちてばかりいるからだ。精一杯修行しているがどうせ無駄なことだ。これからも落ち続けるだろう。」などと妬みと競争心に基づいて思うようなものである。確かに、このライバルは今現在においてはまだプロになれていない。「今は」である。だが、神の定めにより、このライバルはやがてプロの道に入ることになるのである。これと同じで、この『あざける者ども』が嘲っていたその時はまだ再臨が起きていなかったのだが、神の定めにより、これから間もなく再臨が起こることになっていたのである。
【3:5~6】
『こう言い張る彼らは、次のことを見落としています。すなわち、天は古い昔からあり、地は神のことばによって水から出て、水によって成ったのであって、当時の世界は、その水により、洪水におおわれて滅びました。』
この忌まわしい者どもは、致命的な見落としをしていた。それはノアの大洪水のことである。この大洪水が起きた時、我々が既に知っているように、『当時の世界は、その水により、洪水におおわれて滅び』た。それにもかかわらず、この者どもは、この大きな出来事を思い返さなかった。だからこそ、前節で書かれていたように、彼らは『先祖たちが眠った時からこのかた、何事も創造の初めからのままではないか。』などとほざいていたのである。もしこの大洪水について思い返していたとすれば、彼らがこのように言うことはなかったであろう。何故なら、この時に世界は大いなる変革を迎えたのだから。注意しなければならないのは、彼らはこの大洪水について知らなかったのではないということである。彼らは知っていたのに思い返すことがなかった。何故なら、ペテロはこの箇所で「彼らは次のことを知らないでいます。」とは言わず、『彼らは、次のことを見落としています。』と言っているからである。なお、この言葉は『彼らは次のことを故意に忘れようとしているのです。』とも訳すことができる。この嘲る者どもは、世界は創造された時から何も変わっていないと考えていたが、これは大きな間違いであった。確かなところ、ノアの大洪水を境にして世界は別の姿に変わっている。例えば、大洪水の前には大巨人や恐竜がまだ存在していた。恐らく我々が知らない動物も多くいたと思われる。しかし大洪水が起きてからは、大巨人も恐竜も見られなくなった。また大洪水の前は、寿命が1000歳近くあった。洪水後の寿命は、短期間のうちに徐々に引き下がり、今のように長くても100歳ほどになった。また水力学の博士であるヘンリー・モリスによれば、洪水前の世界には虹だけでなく雲や雨もまだ見られなかった。この博士はこの見解を科学的に合理的に説明しているが、これは聖書からも裏付けが取れるから、洪水前の時代は自然の環境が今とは異なっていたと考えるのが妥当である。このようなことを考えれば、とてもじゃないが世界はその創造された時から紀元1世紀の時代までそのままの状態だったなどとは言えないのである。この嘲る者どもは、欲望が人の精神能力を歪めてしまうことの良い例である。人は欲望に夢中になると、多くのことを忘れがちとなる。それは欲望という楽しみに心を奪われるので、他のことを考えたり注意したりすることが難しくなるからである。誰でも一度はそのようになった経験を持っているはずである。この嘲る者どもは、自分たちの欲望に拘るあまり、昔のことを思い返して吟味するという想起の能力が制限されてしまっていたのである。
【3:7】
『しかし、今の天と地は、同じみことばによって、火に焼かれるためにとっておかれ、不敬虔な者どものさばきと滅びとの日まで、保たれているのです。』
今現在の天地は火により焼かれて滅ぼされる、とここでペテロは言っている。3:5~6の箇所で言われていた天地の滅びは、世界的な規模であった。世の中にはあの大洪水が局所的な規模に過ぎなかったなどと考えている者たちがいるが、それは間違っている。このような考えはぜんぜん受け入れることができない。何故なら、創世記8:4の箇所では『箱舟は、第七の月の17日に、アララテの山の上にとどまった。』と書かれているからである。この山の標高は5137mである。この山に箱舟が漂着したということは、大水が地球全土を覆ったことを教えている。またダーウィンは高い山に貝殻や魚の化石を見つけて不思議がっているが(「ピーグル号航海記」)、これも洪水が世界的な規模だったことを意味している。ジェファーソンの「ヴァージニア覚え書き」にも、山に貝殻が見られたことについて書かれている。つまり、洪水が地球を丸ごと覆ったからこそ、最近になっても高い山で本来であれば海にしかないようなものが見つかるのである。それゆえ、私はノアの大洪水が地域的な規模に過ぎなかったとする意見を拒絶し断罪する。だが、この3:7の箇所で言われている『天と地』とは地球全世界を意味しているのではない。これはユダヤ世界を指している。つまり、ここで言われている『天と地』とは<ユダヤにおける天と地>という意味である。どうして、この箇所では『天と地』がユダヤ世界を意味しているのか。それは実際の歴史を見れば分かる。ユダヤは紀元70年に文字通りの意味で火に焼かれて完膚なきまでに滅ぼされた。これは誰も疑うことのできない歴史の事実である。ペテロは、ここでこの出来事について言っているのである。3:7の箇所における『天と地』を地球全土という意味で捉えると、聖書を正しく理解できなくなってしまう。何故なのか。それは、マタイ24章の中では、キリストがお語りになってから一世代(ゲネアー)が経過するまでに(マタイ24:34)、エルサレム神殿の崩壊に伴ってユダヤ世界が滅ぼされると預言されていたからである。その時に、ユダヤにおける天地が滅び去るとキリストは言っておられる(マタイ24:35)。確かにマタイ24:1~3の箇所では、神殿が崩壊する時に世界が終わると示されている。既に説明した通り、この世界とはユダヤのことを言っている。これこそ正に我々が今見ている箇所でペテロの言っている「天地の焼滅」なのである。このように『天と地』がユダヤ世界のことを意味しているからといって、聖徒たちは動揺したりすべきではない。ゼパニヤ書1:2~3の箇所を見るがよい。そこで神はこう言われた。『わたしは必ず地の面から、すべてのものを取り除く。―主の御告げ。―わたしは人と獣を取り除き、空の鳥と海の魚を取り除く。わたしは、悪者どもをつまずかせ、人を地の面から断ち滅ぼす。』ここでは地上から全てが滅ぼされると言われているが、これは地球全世界のことではない。一見すると、ここでは『地の面』と書かれているから、地球全土について言われていると感じられなくもない。しかし実際はそうではなく、ここで言われているのはユダヤにおける地上のことである。何故なら、続く1:4~6の箇所を見ると、ここではユダヤを対象として預言されていることが分かるからである。このような根拠が存在しているのだから、我々が今見ている箇所で『天と地』がユダヤ世界だけを意味していたとしても、問題ではないのである。聖書の語法に通じていない人であれば、この箇所で『天と地』と言われているのを文字通りの意味として捉えてしまうはずである。だが、私が今言ったことを理解するならば、この言葉をユダヤにだけ限定して捉えることが出来るようになるであろう。
要するにペテロは、3:5~7の箇所でこう言っているのだ。「あの忌まわしい者どもは、世界が創造された時から何も変わっていないなどとほざいているが、実際はそうではなかった。ノアの大洪水が起きた時にこの世界は一度滅ぼされて刷新されている。彼らはこのことについて故意に見落としている。また、これから、ノアの時に世界が滅ぼされたのと同じように、ユダヤの世界は滅ぼされるようになる。ノアの時は水によって滅ぼされたが、今後は火によって滅びがもたらされる。それは、あの忌まわしい者どもが、ユダヤの滅びる時に滅ぼされるようになるためなのである。その時はまだ来ていないが、彼らはこのことにまったく気付いていない。」ペテロは、このように言って、激しい憎悪の伴った批判を彼らに与えている。ペテロのうちに彼らに対する憐れみの念は少しもなかった。何故なら、ユダ4の箇所でも書かれているように、『彼らは、このようなさばきに会うと昔から前もってしるされている人々』だったからである。もし彼らが滅びに定められているのかどうか分からなければ、つまり彼らが麦か毒麦か分からなければ、ペテロは麦を毒麦と一緒に処分また断罪することを恐れて、ここまで辛辣な批判をすることはなかったかもしれない。だが、彼らは預言により既に滅びに定められていることが分かりきっていたのだから、ペテロは容赦しなかったのである。というのも滅びに定められている者に憐れみをかけても意味はなく、悔い改めの余地はまったくないからである。キリストもイスカリオテのユダに対しては、憐れみのない強烈な言葉を放たれた。
【3:8】
『しかし、愛する人たち。あなたがたは、この一事を見落としてはいけません。すなわち、主の御前では、1日は千年のようであり、千年は1日のようです。』
ペテロは、神の持つ時間感覚について述べている。すなわち『主の御前では、1日は千年のようであり、千年は1日のよう』である。これは間違いなく詩篇90:4の箇所に基づいている。そこでモーセは神にこう言っている。『まことに、あなたの目には、千年も、きのうのように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。』ここでモーセは、千年が1日も同然であると言っているだけである。しかしペテロはこれに加えて、神にとって1日も千年に等しいのだと言っている。ペテロがモーセの言ったことに加えて1日を基点とした言い方もここでしているのは、詩篇90:4の御言葉を読んで神の霊により悟りを得たか、キリストから教えられたか、他の聖徒により気付かされたか、のどれかである。このように聖書で教えられている通り、神にとって1日は千年にも感じられる。これは神にとって、諸々の出来事が起こる1日は非常に意義深いからである。我々も特別な日は、非常に長く感じられるものである。また神にとって千年は1日も同然に感じられる。これも我々のことを考えればよく分かる。我々は往々にして例えば「10年なんかあっという間だったな。」などと言うものである。神にとって1日も千年も同じであるということは、このように我々の経験を考えてみれば、それほど苦も無く理解することができる。それというのも人間とは神の似像だからである。神の感覚と人間の感覚が似ているのは、ごく自然なことなのである。
この箇所でペテロが言いたいのは、つまりこういうことである。「今に至るまでまだ再臨が起きていないのは確かである。ある人たちは、再臨がまだ起きていないので、その遅延が非常に長いと感じている。だが神にとっては、そのぐらいの遅延など何でもない。何故なら、神にとっては千年でさえ1日も同然なのだから。」ペテロはこのように言って、ある聖徒たちのそそっかしい短気な精神をなだめようとしているのである。ペテロは、この箇所で「神の時間感覚を知れ。」とでも言いたいかのようである。
ところで、この箇所を再臨成就論の反論における武器として使うことは出来るだろうか。筆者である私が「聖書では再臨がすぐに起こると言われているから、再臨はすぐに起こった。すなわち紀元1世紀に起きた。」と言うと、次のようにこの箇所を用いて反論する人がいるのだ。「いやいや、確かに聖書はすぐに再臨が起こると言っているが、たとえ2千年も再臨が起きていないからといって、再臨がすぐに起きていないということにはならない。何故なら神にとって千年は1日も同然なのだから。つまり2千年間という期間は神にとっては2日も一緒なのである。」このように反論する人は、どうやらこれが非常に強力な反論だと思っているようである。確かに神にとって千年が1日も同然だというのは絶対に疑えない。それは聖書の啓示していることだからである。だが、このような反論をしたところで、私の述べる再臨成就論はまったく揺るぎはしない。何故なら、キリストとパウロは再臨の起こる時期を明白に限定しているからである。それは、紀元1世紀の人たちが生き残っている間に、である(マタイ16:28、Ⅰテサロニケ4:15)。更にマタイ24:34の箇所でも、再臨の起こる時期が指定されている。それはキリストがマタイ24章の内容をお語りになられてから1世代(ゲネアー)が経過するまでの間に、である。もしこのように聖書が再臨の起こる時期を限定また指定していなかったとすれば、この反論は私を大いに動揺させていたかもしれない。その場合、この反論は非常に強力な鋭さを持つことになっていたからである。だが聖書は再臨が起こる時期を大まかにではあるが明白に教えているのだから、このような反論がされたとしても私はまったく恐れることをしない。このような反論は取るに足りず、お話にならないものである。もし反論するというのであれば、このような即席で作った軟弱な反論ではなく、もっと私の述べている見解を入念に研究して、「これならば。」と言えるような強力極まりない反論を用意してほしいものだ。今に至るまでそのような反論はまだ登場していない。登場していれば私は大いにたじろいでいたであろう。恐らく、これからもそのような反論は登場しないのではないかと私には思える。それというのも私は聖書の再臨を聖書的に理解しているからである。真に正しい理解を打ち砕ける反論など有りはしないのだ。
【3:9】
『主は、ある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえって、あなたがたに対して忍耐深くあられるのであって、ひとりでも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。』
ペテロの時代には、再臨がなかなか起こらないので、心に不満を持つ人が見られた。その人たちには、再臨が大いに遅延しているように感じたので、神に弄ばれているのではないかと思えた。「どうしてこんなにも長い間再臨が起こっていないのだ。もしや神は我々をじらそうと意地悪をしておられるのではないのか…」と。人は、何か良いことが遅らされると、往々にして不満を持つものである。例えば、宝くじに当選した人が、なかなか当選金が貰えないので次のように言うのがそうである。「どうしてまだ当選金が振り込まれないのか。運営者たちは、もしや私に悪意を持っているのではないのか。私が金持ちになるのを妬んでいるのではないのか。」人の精神はこのようにして、自分の持つ落ち着きのない不満を、相手側に非を作り出すことで、ぶつけて発散させようとしたがるのである。このような経験を持つ人は世の中に多いはずである。だが、このようなことは一方的な思い込みに過ぎないのが常である。真相はどうなのかと思って問い合わせたりすると、単に自分が妄想にふけっていたことに気付かされるのだ。
しかし、神は聖徒たちに意地悪をしようとして再臨が起こらないようにしておられたわけではなかった。神は、愛のゆえに、再臨を遅延させておられた。つまり、神は『ひとりでも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられる』からこそ、再臨がまだ起きないようにしておられた。ここで言われている悔い改めに進むことが望まれている人とは、選ばれている人たちのことを指す。何故なら、ここでは『あなたがたに対して忍耐深くあられる』と言われているからだ。つまり、ここで言われていることに選ばれていない人たちは含まれていない。ところでリンネも言うように「自然は飛躍しない」。それは植物や動物の成長を見れば分かる。自然はいつもゆっくりである。悔い改めもそれと同じである。悔い改めるのは、前々から多かれ少なかれ罪悪感を持っており、遂に時至って為されるようになる、というのがほとんどである。その時は、何かの出来事がきっかけとなったり、心の罪悪感が頂点に達した時などに訪れる。つまり、悔い改めるのには時間がかかるのだ。だからこそ、神は選ばれていた人たちが全て悔い改めるようになるまで、再臨を起こされなかったのである。もし彼らが悔い改めるよりも前に再臨が起きれば、その人たちは救われることなく滅んでしまうからである。そのようになるのは神の御心ではなかった。このことから、我々は『神は愛』だということを再び認識すべきであろう。パウロも言うように愛は『すべてを耐え忍ぶ』(Ⅰコリント13章7節)。神は愛だから、忍耐そのものであられる。それゆえ、神は聖徒たちが悔い改めるようになるまで待っていて下さるのである。神は、ユダヤに対しても、キリストが来られるまで約1300年もの間、彼らが悔い改めるようになるのを忍耐しつつずっと待っておられた。神のこの忍耐深さは、我々人間の感覚を遥かに超え出ている。
ペテロは、ここで再臨の時を念頭に置いて語っている。その時には、地上の教会にいる者たちが、一挙に救われるか滅びるかする。再臨が起こるまでがタイムリミットだった。だからこそ、ここでは、その時までに選ばれた者たちが悔い改めるようになるのを神は望んでおられる、と言われているのだ。それだから、ここで言われていることは、直接的には当時の人たちにだけ関わっている。この箇所を我々にそのまま語られた言葉をして捉えることはできない。つまり、我々はこの箇所で言われている言葉を時代的に読み解かねばならない。何故なら、もう既に再臨は起こり、その時に羊と山羊が一挙に最終的な結末を迎えることになったからである。だが、神が選ばれている者たちの救いを望んでおられる、ということについては、いつの時代であっても同じである。その人たちは選ばれているので、必ず救われなければならないからである。
【3:10】
『しかし、主の日は、盗人のようにやって来ます。』
キリストの再臨は、突如として実現された。それは、あたかも夜中に盗人が急に入り込んで来るかのようであった。聖書では、このように再臨を盗人の侵入という例えで語っている箇所が多く見られる(マタイ24:43~44、Ⅰテサロニケ5:2、黙示録3:3、16:15)。既に述べたが、これはキリストが盗人のように悪いことをされるという意味ではないから、その点は間違えないように注意すべきである。
『その日には、天は大きな響きをたてて消えうせ、天の万象は焼けてくずれ去り、地と地のいろいろなわざは焼き尽くされます。』
この箇所で言われているのは、要するにユダヤ世界が完全に焼き滅ぼされるということである。ここでは3つのことが言われているが、どれもユダヤの滅亡を意味している。確かに、紀元70年にユダヤは文字通りに焼き尽くされたと言ってよい。僅かに残されたものといえば、神殿城壁における残骸ぐらいなものである。この時にペテロの言ったことが成就されたのだ。
【3:11】
『このように、これらのものはみな、くずれ落ちるものだとすれば、あなたがたは、どれほど聖い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。』
ペテロは、ここでこう言っている。「今述べたようにユダヤはやがて滅びて『くずれ落ちる』ことになるが、もしあなたがたが敬虔に歩んでいなければ一体どうなるであろうか。あなたがたも一緒にユダヤの滅びと同じ運命を辿ることにならないだろうか。ユダヤが不敬虔をその理由として滅ぼされるのに、あなたがたは不敬虔に歩んでいても滅ぼされずに済むとでも思っているのか。とんでもない話である。」確かにユダヤが不敬虔のせいで滅亡させられるのであれば、同じく不敬虔に歩んでいる聖徒たちもユダヤの滅びと一緒に滅ぼされることになるのは目に見えている。『神にはえこひいきなどはない』(ローマ2章11節)から、ユダヤが不敬虔なので捨てられるとすれば、教会の中にいる信者も不敬虔であれば捨てられることになる。だから、ペテロがここで言っていることは至極もっともである。
要するに、ペテロはここでこのように言って脅迫し、聖徒たちが敬虔に歩むように働きかけている。それというのも、もし聖徒たちが敬虔に歩まないと、ユダヤの滅びが到来する際、本当に大変なことになってしまうからである。それでは実際はどうだったのか。この手紙を読んだ聖徒たちは、この箇所を読んで以降、敬虔に歩むことができたのか。この手紙が書かれた後で書かれたユダの手紙を読むと、どうやら聖徒たちは、ペテロの願い通りに敬虔に歩めていたように思われる。何故なら、ユダは手紙の中で、嘲る者どもについてだけ非難しているのであって、聖徒たちの素行については何も問題にしていないからである。もし聖徒たちが不敬虔に歩んでいたとすれば、ユダはその不敬虔を幾らかでも問題にしていたと想定するのが妥当である。しかし、ユダの手紙からは、そのような問題があったようには感じられない。神の恵みが、ペテロの手紙を読んだ聖徒たちに注がれたということなのであろう。
【3:12】
『そのようにして、神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。』
ペテロは、聖徒たちが敬虔に歩むことにより、それだけ再臨の日が早まるようになると考えていた。これはペテロが言ったことであるから、誰かが反対の意見を持ったとしても、確かにその通りなのである。だが、どうしてそうなのか。それは、聖徒たちが敬虔に歩めば、良い作用が起こり、それだけ選ばれている人たちが悔い改めに進みやすくなるからである。聖徒たちの敬虔は、まだ救われていない選ばれている人たちをキリストの救いに導くための補助手段として働く。聖徒たちが善をすればそれだけ多くの選ばれた人たちが救いに入れるようになる、というのは聖書の他の箇所でも示されていることだ(マタイ5:16、Ⅰペテロ2:12)。それというのも、聖徒たちの敬虔を選ばれている人たちが見れば、その敬虔さが心に働きかけ、自分もキリストにおいて変わりたいと決心できるように繋がるからである。そのようになれば、選ばれている人たちがより早く全て信仰に入ることにもなる。そうすれば再臨も早く起こるようになる。だからこそ、ペテロはこの箇所で、聖徒たちが敬虔に歩めば速やかに再臨が起こるようになる、と言っているのである。またペテロは、聖徒たちがキリストの再臨を待ち望むようにと求めている。これは再臨が起これば、聖徒たちがキリストと会えるようになるからである。聖徒であるにもかかわらず、キリストと会えるようになるのを望まない人などいるのであろうか。決していない。キリストの到来を待ち望めという要請は、黙示録22:17の箇所でも書かれている。それだから、既に知られているように、紀元1世紀の聖徒たちは非常に熱烈にキリストの再臨を待望していた。これはリベラルの学者たちでさえ認めるところである。その期待は、間もなく満足させられることになった。すなわち紀元68年6月9日である。
ペテロは、どうしてキリストの再臨が速やかに起こるようにさせたかったのか。それには2つの理由がある。まず一つ目は、再臨が起これば、聖徒たちはキリストと会えるようになるからである。これについては既に語られた。二つ目は、忌まわしい者どもの嘲りを、なるべく早く終止させるためであった。より早く再臨が起これば、再臨の際に嘲る者どもは滅ぼされるのだから、より早く彼らの無駄口が封じられることになる。これは変な言い掛かりをつけてくる不審者を封じるために、なるべく早く通報して警察に来てもらうようにするのと似ている。その不審者は警察が来るまでは調子に乗ってヘラヘラしているのだが、警察が来れば押し黙らされるか逃げ隠れるか逮捕されるかして、もう言い掛かりをつけることが出来なくなってしまうのだ。この例えにおいて、警察とはキリストのこと、不審者とは嘲る者どものことである。このように聖徒たちにとって再臨が速やかに起こるのはメリットしかなかった。再臨が起これば、キリストに会えるうえ嘲る者どもが封じられるのだから、一石二鳥なのである。それゆえ、このようなことを知りながら当時の聖徒たちが速やかな再臨の実現を願わないのは、有り得ないことであった。
ペテロがこの箇所でこのように言っていることから、キリストの再臨はペテロの時代に起きたということが分かる。何故なら、ペテロは、この箇所で明らかに再臨を自分の時代に起きる出来事として前提しているからである。「敬虔に歩んで再臨の日が早まるようにせねばならない!」ペテロはここでこう言っている。当時は、誰も彼もがキリストの再臨を大いに希求していた。であれば、どうして2千年経過してもまだ再臨が起きていないなどということがあるのであろうか。ペテロはここで再臨を近いうちに起こる出来事して取り扱っている。再臨が2千年以上も起きていないという理解は、明らかにペテロがここで前提としている理解とそぐわない。確かなところ、再臨が紀元1世紀に起こるからこそ、ペテロはここでこのように語った。もし再臨が2千年経っても起きないというのであれば、ペテロはこのように言っていなかったであろう。2千年経過しても起きない出来事を念頭に置いて、聖なるキリストの使徒が「再臨の起こる日を早めなければならない!」などと言ったと考えるのは、明らかにおかしいと言わねばならない。誇るのではないが、今までこのように再臨が深く考究されたことがあったであろうか。そのようなことはなかった。今まで教会は、再臨について考究しなさ過ぎた。ただ伝統的な理解に安住するだけであり、再臨について述べている御言葉を細かい部分までじっくり直視していなかった。カルヴァンであれエドワーズであれカイパーであれ、皆そうであった。だから、私が御言葉に根差した鋭い問題を提示しても、牧師たちは背を向けて沈黙してしまう。誰も私と議論しようとしないので、無視されていると感じられる。私の述べていることが正しく強烈であり既存の見解を根本から覆してしまうので、反論しようにもできず、最善の解決方法として意識的にであれ無意識的にであれ「沈黙」という選択をするのである。沈黙すれば逃げることができるから、私と不利な議論をせずに済むのである。私を取り巻く状況は、このようである。だが、だからといって私は悲観することをしない。まだ現われていなかった真理が現われた時にこのような状況が生じるのは、歴史を振り返っても分かるように、別に珍しいことではないからである。そのような場合、最初から歓迎されることのほうが珍しいのである。それというのも、人間という存在は、なかなか自分の立場を変えたり既存の見解を否定することに対して勇気を持てないものだから。
『その日が来れば、そのために、天は燃えてくずれ、天の万象は焼け溶けてしまいます。』
これはユダヤの焼滅のことである。ここでは天にしか触れられていないが、ユダヤの滅びは当然ながら地にも降り注がれた。つまり、ここでは単に地が意図的に省かれているだけである。確かに、紀元70年の時にユダヤの天は焼き滅ぼされた。その時にはユダヤの地も焼き滅ぼされた。ここにおいてユダヤに対する神の怒りは全うされたのであった。
この箇所で言われているのは、既に見た3:7および3:10の繰り返しである。我々が今見ている箇所と前の2つの箇所とは、やや文章の内容が異なっているが、その言われている内容自体はどちらも一緒である。すなわちユダヤの滅びである。
【3:13】
『しかし、私たちは、神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。』
ペテロの言っている『神の約束』とは、間違いなくイザヤ65:17~25の箇所における新天新地の預言である。これは議論が不要なほどに明白である。それでは、この『新しい天と新しい地』とは何を意味しているのか。これは天国のことである。すなわち、『新しい天と新しい地』とは「天国における天と地」という意味である。『新しい』と言われているのは、紀元70年9月に天国が新しく始まるからであり、聖徒たちにとってその場所は新しい場所だからである。つまり、これは「地上における天と地」という意味ではない。また「神のおられる霊的な世界としての天と我々の住んでいる宇宙という世界における地」という意味でもない。「天と地」と言って、霊的な世界における天あるいは宇宙という世界における地だけを意味するというのは、ぜんぜん聖書の語法に反していない。創世記1:1を見てほしい。そこでは『天と地』と書かれているが、この『天』とは明らかに地球における大気圏のことである。何故なら、7節後の1:8の箇所を見ると、天とは『大空』を意味していることが分かるからである。『地』のほうについては説明の必要がない。つまり、創世記1:1で『天と地』と言われているのは、ただ地上のことだけであって、そこには天上世界のことは含まれていない。このように『天と地』と言って天だけか地だけを指している箇所が、聖書には多く見られる。我々が今見ているⅡペテロ3:13の箇所も、そのうちの一つである。今の聖徒たちは、この箇所で『天と地』と言われているのを、神のおられる天と人間の住んでいる地という意味において捉えている。このように考えるのは誤っている。何故なら、キリストが言われた通り、聖なる御国は再臨が実現された時に現われたからである(マタイ16:28)。つまり、神の国は既にやって来た。これは真に聖書的な理解である。だからこそ、この見解に誰も反論することができないのである。神学の領域において、今まで聖徒たちから手厳しい反論を受けなかった誤謬などというものはない。どの誤謬も、必ず誰かによって徹底的に反駁されている。これは神の子どもである聖徒たちが真理を愛する人たちであって、誤謬を嫌っているからである。ゴミが落ちていれば誰かが拾って捨てるように、誤謬があればある聖徒が反駁して非とする。私が述べている再臨成就説は真理である。それは誤謬ではない。だからこそ、誰も私に反論しようとはしないのである。確かに、御言葉が示す通り、キリストの再臨は既に起きた。そして、その時に御国すなわち『新しい天と新しい地』もキリストの再臨と共に現われた。だが、キリストが再臨された紀元1世紀を見ても、この地上世界の様相が何か変化したようには感じられない。御国がその時に来たにもかかわらず、である。私はこのことを認める。これは一体どういうことなのか。これは、つまり新天新地である神の王国とは、地上のことではなく天国のことを意味しているのである。だからこそ、キリストが御国と共に再臨された時には、この地上に何の変化も見られなかった。その時には、ただ天上において新しい世界が現われただけだからである。このマタイ16:28の箇所で言われている内容は、私が今言ったように理解するしかない。誰一人として反論できないという事実を考えても分かるように、マタイ16:28の箇所で、紀元1世紀に再臨が起こると教えられていることは絶対に疑えない(※)。紀元1世紀に再臨が起きたとすれば、その時には新天新地(=御国)も到来したことになるが、しかしこの地上世界には何の変化も無かったのだから、その新天新地とは天上世界のことだったと考えなければいけないことになる。それゆえ、我々が今見ているⅡペテロ3:13の箇所で言われている『新しい天と新しい地』を天国という意味において捉えない人たちは、考察不足であって誤りを犯していることが分かる。もし、この『新しい天と新しい地』という言葉が地上世界だけのことか、または地上世界をも含む言葉だったとすれば、再臨が起きた時に我々が今住んでいる世界は大いに様変わりしていたはずなのである。
(※)
この見解は、本当に誰にも反論されない。誰も彼も、この見解を示されると、無視し、黙り、逃げる。問題に真正面から向き合うことを拒まない人は、逃げたり無視したりせず、私の言ったことをそのまま認める。「確かにこの御言葉では再臨が当時に起きたと教えられています。」と。これは何を意味するのか。マタイ16:28の箇所における私の見解が本当に正しいということだ。
[本文に戻る]
この箇所でペテロが言おうとしているのは、こうである。「聖徒たちよ。これからユダヤ世界における天地が滅びる時には、キリストの再臨と共に、聖なる御国が現われる。この御国が、かつてイザヤの預言で約束されていた『新しい天と新しい地』なのである。この御国こそ正に我々が切に求めるべき場所である。いったい、あなたがたのうちに、この場所を求めない者がいるのか。もちろん、そのような者は一人もいないはずである。」ペテロがこの天の御国を求めていたのは、そこがキリストの統治される正義に満ちた場所だったからである。そこには何一つとして悪が存在しない。『もはや、のろわれるものは何もない。』(黙示録22章3節)と黙示録では言われている。そこには、ただただ正義あるのみである。御霊により正義を愛する心を持つようにされていたペテロにとって、このような場所を求めないというのは有りえないことであった。確かに正義を愛する者であれば、このような場所を求めるはずである。これは、少し例えが悪いが、小さな子どもがお菓子で作られた世界を、女好きの者が女だけしかいない世界を、ディズニー好きな人が夢の現実化した世界を願うようなものである。このような例を考えれば、ペテロがどれだけ天国という場所を希求していたかが、よく分かるのではないかと思う。
今の聖徒たちは、この『新しい天と新しい地』が未だに現われていないと考えている。だが、この新天新地は既に到来している。その証拠となる聖句はマタイ16:28、ルカ9:27、マルコ9:1である。そこでは、キリストの前に立っていた紀元1世紀のユダヤ人たちが生きている間に、聖なる御国がやって来る、と断言されている。先にも述べた通り、この御国は『新しい天と新しい地』である。これは一般的な理解である。だから、御国である『新しい天と新しい地』は紀元1世紀に現われたことになる。また黙示録も証拠として挙げねばならない。黙示録21章では新天新地の現われについて預言されているが、それは既に第3部で繰り返し述べた通り、『すぐに起こるはずの事』(黙示録1章1節)であった。『すぐに起こる』とヨハネが言っているのは、黙示録の預言の全てについてだから、当然ながら21章の箇所でも『すぐに起こるはずの事』が記されている。その新天新地の現われが『すぐに起こる』というのは、マタイ16:28、ルカ9:27、マルコ9:1で紀元1世紀のユダヤ人たちが存命中に御国を見ることになると断言されていたのと完全に調和している。何故なら、紀元1世紀の人が生きている間に御国すなわち新天新地が現われるようになるというのは、正にヨハネが黙示録を書いた時を基点にして『すぐに起こるはずの事』だからである。それゆえ、この新天新地は今から2千年前に現われたのだと我々は考えなければならない。我々は次のことをよく考えるべきである。すなわち、紀元1世紀の聖徒たちは切に新天新地を待ち望んでいた。これは確かなことである。そうであれば、神が2千年以上もその現われを遅延させられるなどということが一体どうしてあるのであろうか。
このように新天新地は既に実現されている。再臨以後の時代に生きる我々にとって、この新天新地は、再臨以前の時代に生きていた聖徒たちとは違い、まだ現われていないものではない。我々は既に新天新地が開始された時代に生きているのだ。我々は、この新天新地を求めねばならない。何故なら、その場所は、聖徒たちの最終地点また本国だからである。ヘブル書で言われているように、この地上世界に生きる今の我々は単なる『旅人であり寄留者』(ヘブル11:13)に過ぎない。この地上世界は、聖徒たちにとって過渡期に過ぎない場所なのである。それだから、既に新天新地が現われたか未だに現われていないかという点で違いはあっても、この素晴らしい幸いな場所を切に求めねばならないということ自体は、ペテロの時代の聖徒たちも今の時代に生きる我々も変わらない。もし聖徒であるにもかかわらず、この場所を求めないのであれば、その聖徒は聖徒らしくないと言わねばならない。何故なら、その聖徒は、天国という完全な場所を求めていないからである。その聖徒は、まるで正義に満ちた天国よりも、悪に満ちたこの地上世界のほうが望ましいと感じているかのようである。
【3:14】
『そういうわけで、愛する人たち。このようなことを待ち望んでいるあなたがたですから、しみも傷もない者として、平安をもって御前に出られるように、励みなさい。』
ペテロは、御国と共にキリストが再臨される際、聖徒たちが御前に幸いな状態として出られるようになるのを求めている。その時には、『平安をもって御前に出られる』ようにせねばならなかった。何故なら、平安を持って御前に出られないということは、すなわち御怒りを受けるような状態にあるということだからである。その場合、その人はキリストからお叱りの言葉を受けることになる。そんなことになるのは、あまりにも悲惨である。だから、そのような結末に至らないように、ペテロはここで聖徒たちが正しい状態で御前に臨めるようにと要請しているのだ。そのためには一体どうしたらよかったのか。それは罪を犯さないことである。罪を犯すからこそ、聖徒たちには『しみ』や『傷』が付けられるようになる。罪である。この罪が、全てを悪くしてしまうのだ。よって、罪を犯し続けていた者たちは、キリストが新天新地と一緒に再臨された際、『しみも傷もない者として、平安をもって御前に出られる』ことができなかったはずである。罪に歩み続けながら、どうしてキリストの御前に喜ばしい状態で臨めるというのか。
キリストの再臨の際に幸いな状態で御前に出られるようにということは、新約聖書の他の箇所でも書かれている。例えばⅠテサロニケ5:23。『主イエス・キリストの来臨のとき、責められるところのないように、あなたがたの霊、たましい、からだが完全に守られますように。』Ⅰテサロニケ3:13もそうである。『私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒とともに再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で、聖く、責められるところのない者としてくださいますように。』Ⅰテモテ6:14も。『私たちの主イエス・キリストの現われの時まで、あなたは命令を守り、傷のない、非難されるところのない者でありなさい。』
第64章 62:ヨハネの手紙Ⅰ
1番目のヨハネの手紙には、心を傾けるべき箇所がある。再臨や反キリストやユダヤの終わりの時期について語られている箇所が、そうである。本章では、それらの箇所が注解される。
【2:18~19】
『小さい者たちよ。今は終わりの時です。あなたがたが反キリストの来ることを聞いていたとおり、今や多くの反キリストが現われています。それによって、今が終わりの時であることがわかります。彼らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちといっしょにとどまっていたことでしょう。しかし、そうなったのは、彼らがみな、私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。』
ヨハネはここで『小さい者たちよ。』と言って、聖徒たちに呼びかけている。このようにヨハネが呼びかけたからといって、聖徒たちを蔑ろにしたり低く見たりしているというわけではない。『互いに愛し合うべきである』(Ⅰヨハネ3章11節)と言ったヨハネが、どうして聖徒たちをぞんざいに取り扱うであろうか。愛とは、すなわちぞんざいに取り扱わないことである。ヨハネがここでこう呼びかけたのは、聖徒たちの心を低く保たせるためであった。高慢とは、聖徒たちにとって最大の悪徳である。シラ書は正典ではないが、この文書の中で「あらゆる罪の始まりは高慢である。」と書かれているのは正しい。サタンもアダムも、この高慢によって堕落したのである。ヨハネは、この高慢の危険性をよく知っていた。だからこそ、ここでは『小さい者たちよ。』と呼びかけることで、聖徒たちが何か自分を優れたものであるなどと思わないようにされているわけである。
『終わりの時』とは、もちろん「ユダヤ世界における終わりの時」という意味である。この言葉を感覚的に捉え、文字通りの地球全土の終わりだと解釈してはならない。何故なら、この言葉は聖書の他の箇所から捉え、紀元70年に訪れたあのユダヤ世界の終焉のことだと解釈すべきものだからである。今まで教会は、再臨について正しく理解できてこなかったので、再臨の時期に起こるこの『終わりの時』という概念についても正しく理解できていなかった。再臨について正しい見解を持てていなかったのであれば、この言葉についてまともな考察が出来なかったのは何も不思議なことではない。しかし今や再臨のことが正しく解き明かされる時が到来している。よって、聖徒たちはこの『終わりの時』という言葉を、徹底的に聖書の記述に基づいて考究しなければいけない。再臨について御言葉から正しい理解を持つのであれば、自然とこの言葉も正しく理解できるようになるであろう。
ヨハネは、この手紙を書いていた当時が『終わりの時』であるということの目印は、『多くの反キリストが現われてい』ることであると言う。ここで、もしこの作品がタルムードであれば、または筆者がトマスであったとすれば、「どの程度の数の反キリストが現われたら終わりの時であると判定できるのか、その具体的な数はどのぐらいか。」などと問うていたであろう。このような疑問は本質的ではない。我々は、ここでヨハネが「今や多くの反キリストが現われているから既に終わりの時が来ているのだ。」と言っていることだけで、十分とすべきである。無用な詮索は信仰と霊性を毀損させる元となる、ということを我々は弁えるべきだ。
ヨハネは『今』が終わりの時であると言っているが、この『今』とはいつか。これは紀元33年~68年の間における『今』である。何故なら、『終わりの時』とは、すなわちユダヤ世界に関する終わりのことだから。これまで教会は、この『今』という時を、正に自分たちが生きている時代における「今」だと捉えてきた。例えば、ルターの場合、自分が生きている16世紀の時代こそが正に終わりの時である「今」だと理解していた。カルケドン信条の作成者たちの場合、この信条が作成された5世紀が正に終わりの時である「今」だと思っていた。しかし、このように捉えるのは間違っている。何故なら、マタイ24章を見れば、この『終わりの時』というのが、ユダヤ世界の終焉が実現される紀元1世紀を指していると分かるからである。確かにマタイ24章の中では、ユダヤ世界の終わる日がこれから1世代の間(30~40年)にやって来ると教えられているのである(24:14、34)。実際、歴史が示すように、ユダヤの終わりは本当にキリストがマタイ24章で預言を語られてから1世代の間に起きたのである。
さて、これまで教会は、ここで言われている『反キリスト』という存在を、ある特定の邪悪な大ボス的存在として捉え、語ってきた。例えば、今までにはローマ教皇やEUの大統領が反キリストであるなどと言われてきた。最近では、ロスチャイルドやロックフェラーこそが反キリストではないかと考える人もいることであろう。教会の終末観が変わらない限り、これからも反キリストという言葉が、大ボス的な存在を指す言葉として使われ続けるであろう。しかしながら、ヨハネがここで言っている言葉を読むと、この『反キリスト』とは特定の邪悪な者を指すために使われるべき言葉ではないことが分かる。ヨハネは、ここで反キリストが『多く』現われていると言っている。つまり、反キリストとは特定の者を指す言葉ではなく、不特定多数を指す言葉である。またヨハネは、この反キリストが、かつてはヨハネたちの『仲間』である人たちであったとさえ言っている。これは、つまり反キリストという存在が、どこにでもいるような人たちであるということを意味する。何故なら、これはつまり反キリストが、以前はヨハネの仲間であったキリスト教徒だったということだからである。多くの離教者が反キリストだというのであれば、反キリストが普通の人たちだということは明らかである。それでは今まで教会が、反キリストという言葉を正しく捉えて来なかった理由は何なのか。それは、ほとんど全ての教師たちが風潮の力に流されるままだったからである。すなわち、今まで教師たちは反キリストが特定の大ボスを指す言葉であるという常識を大前提として思考を働かせていたので、そもそも反キリストという言葉の意味を聖書から深く考察するということさえ頭の中に思い浮かばなかったのである。確かに、この言葉が大ボスを意味しているという当たり前の前提が教会にはあったので(この前提は恐らくオリゲネスあたりから始まったと思われる)、今まで誰も反キリストという言葉の意味について深く考察していなかったのを、私は書物の中で見ている。人間とは常識を、それが間違ったものであったとしてもほとんど疑おうとしないものだから、こういう事例は探せば他にも世の中に幾らでもあることであろう。
この『反キリスト』という存在については、Ⅰヨハネ2:22、4:3、Ⅱヨハネ7も参照すべきである。ヨハネの2つの手紙以外に、『反キリスト』という言葉が使われている聖書の他の巻はない。この『反キリスト』とは、簡単に言えば「キリストを明確な意思を持って否認する者」を意味している。つまり、既に第1部でも述べたように、公然とキリストを否認しているのであれば、誰でも立派な反キリストなのである。これを読んでいるあなたの家族や親戚の中にも、きっと多くの反キリストがいることであろう。
ところで、今の時代にも多くの反キリストがいるからというので今の時代も終わりの時と呼ぶべきではないか、などと疑問に思う方がいるかもしれない。確かに、今の時代にも反キリストが多くいるのは事実である。誰がこれを認めないであろうか。しかし、だからといって、今が終わりの時であるということにはならない。何故かといえば、ヨハネが言っている終わりとはユダヤ世界のことだからである。我々は、ヨハネが言っている『終わりの時』という言葉の意味を聖書からシッカリと理解せねばならない。そうすれば、このような疑問は容易に解決されることになるであろう。
【2:28】
『そこで、子どもたちよ。キリストのうちにとどまっていなさい。それは、キリストが現われるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のとき、御前で恥じ入るということのないためです。』
ヨハネは、ここで『子どもたちよ。』と聖徒たちに呼びかけている。これは、ヨハネが聖徒たちを従順な子どものように取り扱っているからである。先に見た2:18の箇所で『小さい者たちよ。』と言われていたのと同様、ここでもやはり聖徒たちが謙遜な精神を保てるように、こう呼びかけられている。子どものようでなくなるからこそ、傲慢になり、神とキリストから離れるようになってしまう。確かに、キリストが言われた通り、天の国に入れるのは子どものような者たちだけである。だから、ヨハネがここで聖徒たちを子どもとして取り扱ったのは、実に適切であった。今の時代に生きる我々も、神の御前に従順な子どものように歩まなければならない。それこそ、主が我々に望んでおられることである。
またヨハネは、ここで聖徒たちがキリストに保たれ続けるようにと命じている。つまり、これはユダのようになるな、ということである。イスカリオテのユダは、ある時が来るまでは、キリストを除く全ての人からキリストに留まっている者であると思われていた。11人の使徒でさえ、まさかユダがキリストに留まっている者ではないなどとは思いもしなかった。しかし、定めの時が来ると、ユダはその金の欲によりキリストを裏切り、キリストから遂に脱落してしまった。これこそ正にキリストのうちに留まっていない、ということである。何故なら、ユダのような者は、一時的にはキリストに保たれていたかと思われていたものの、結局はキリストから永久に遠ざかってしまったからである。こういう者は、そもそも最初からキリスト信仰など持っていなかった。ヨハネは真に選ばれている者たちがキリストから離れることは万一にもあり得ないと分かっていたが、それでも、このように聖徒たちにキリストに留まり続けるようにと命じた。それは、こう命じることで、聖徒たちがより豊かに堅くキリスト信仰に根差せるようになるためであった。
それではヨハネがキリストに保たれ続けるようにと命じているその理由は一体なにか。その理由は2つである。まず一つ目は、キリストの再臨の時に『信頼を持』てるようになるためである。もしキリストに保たれるようであれば、再臨されたキリストの前に立った際、安心の精神を持てる。その安心の精神が、ここでは『信頼』などと言われている。二つ目は、再臨が起きた際に『御前で恥じ入るということのないため』である。もしキリスト信仰に堅く根差し続けていたのであれば、再臨のキリストの前に立った際、キリストから良い言葉をいただくことができる。そうなれば、キリストに喜ばれるのだから、『御前で恥じ入る』ということは決して起こらないのである。要するに、ヨハネは聖徒たちがキリストの前に幸いな状態で出られるようになるために、ここでキリストに保たれるようにと命じたのである。
ここでヨハネは、同一の事柄を繰り返して言っている。すなわち、再臨が起きた際には良い状態でいられるようにということを、2回繰り返している。1回目は『キリストが現われるとき、私たちが信頼を持ち、』という部分であり、2回目は『その来臨のとき、御前で恥じ入るということのないためです。』という部分である。これは古代のヘブル人らしい言い方である。
既に述べたようにキリストの再臨は既に起きている。それゆえ、ここで言われている内容は、直接的には紀元1世紀の聖徒たちに対してだけ言われていると理解せねばならない。というのも、ここで言われている御言葉は、明らかに再臨を前提とした内容となっているからだ。しかし、再臨以降に生きる聖徒たちも再臨以前に生きていた聖徒たちと同じように、『キリストのうちにとどまってい』る必要がある。今の時代に生きる我々も当然ながら例外ではない。何故なら、我々もやがてキリストに出会うことになるからである。その時、我々がキリストに保たれ続けていたのであれば、キリストの面前に出た時、『信頼を持ち、』『御前で恥じ入るということ』が無くなるであろう。再臨以前の聖徒たちは再臨の時に携挙されることでキリストに出会い、再臨以後の聖徒たちは地上の人生を終えてから天国にある門を通って都に入ることでキリストに出会う(黙示録21:24~26)、という点で再臨以前の聖徒たちと再臨以後の聖徒たちには相違点がある。しかし、どちらもキリストにやがて出会うという点では共通している。それゆえ、ここで言われている命令は、間接的には我々にも言われていることだと受け取らなければならない。ここで直接的には再臨以前に生きていた聖徒たちにだけ言われているからといって、再臨以後に生きる聖徒たちには全く無関係なことが言われていると捉えるのは、良くないことであり、勿体ないことである。
【3:2】
『愛する者たち。私たちは、今すでに神の子どもです。後の状態はまだ明らかにされていません。しかし、キリストが現われたなら、私たちはキリストに似た者となることがわかっています。なぜならそのとき、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。』
ヨハネが言っているように、聖徒たちは、この地上にいる時から既に『神の子ども』である。旧約時代の聖徒たちも、この地上にいる時から既に神の子らであった。彼らに対して、『あなたがたは、あなたがたの神、主の子どもである。』(申命記14章1節)とモーセが言った通りである。かつて神の子ともであったユダヤ人の場合、今や神の子どもではなくなっている。というのも、彼らはキリストを退けたことで、神の前から退けられたからだ。彼らは、もはや神の子としての地位を持っていない。キリストも言われたように、ユダヤ人からは神の国が取り去られてしまったのである(マタイ21:43)。彼らは御子を否認する反キリストの霊を持っているのだから、彼らは確かにもう神の子どもたちではない。御子を否認する反キリストの霊とはすなわちサタンの霊だから、彼らはむしろサタンの子らと呼ばれるべきなのである。もし彼らに御子を告白する神の霊があったとすれば、神の子として相応しく御子を受け入れていたことであろう!既に神の子らである聖徒たちは、今は神の子らだが、かつてはそうではなかった。すなわち、我々もかつては他の人たちと同じようにサタンの支配に属する『生れながら御怒りを受けるべき子ら』(エペソ2章3節)であった。そのようなサタンの子どもたちであった我々を、神はサタンの暗闇の圧制から、キリストの光の支配のうちへと移して下さった(コロサイ1:13)。これは神が子として我々を受容されたことを意味している。それゆえ、聖徒たちは神の子と呼ばれるのである。注意せねばならないのは、聖徒たちが『神の子ども』であると言っても、それは生来的な意味における子ではないということである。我々が神の子であるのは、キリストにおいて「養子」とされた限りにおいてである。養子ではない子、つまり生来的な子であるのは、キリストお一人以外には存在していない。我々もキリストと同様に生来的な意味における神の子であると考えるのは間違っている。
ここでヨハネが言っているように、聖徒たちは再臨が起こるまでは、自分たちの『後の状態』を知らなかった。というのも、それは、再臨が起こらない限り知り得ない事柄だったからである。行ったことのない場所や会ったことのない人間や未だに明らかにされていない理論やシステムについて知るのは難しく、まったく知ることが出来ない場合も多くある。聖徒たちが『後の状態』について知らなかったのも、これと同じであった。
しかし、再臨が起こると、聖徒たちは自分たちがかつては知らなかった『後の状態』について知ることになった。何故なら、再臨が起こると、その事柄について知るべき時が来たからである。ソロモンも言うように、何事にも『時期』(伝道者の書3章1節)というものがある。聖徒たちが永遠の状態について知ることについても、やはり『時期』があったのである。それまでは、まだその時期が到来してはいなかった。
キリストが再臨により現われると、聖徒たちは『キリストに似た者となること』になった。これは、つまり復活されたキリストと同じような状態として聖徒たちも復活した、という意味である。パウロもピリピ3:20~21の箇所で、我々が今見ている箇所で言われているの同じことを言っている。「キリストに似る」とは、すなわち「復活する」ということに他ならない。それでは、どうして再臨のキリストが現われると、聖徒たちはキリストと同じように復活体となったのであろうか。それは、『そのとき、私たちはキリストのありのままの姿を見るから』であった。つまり、栄光のキリストを見るのだから聖徒たちもそのキリストを見るのに相応しい状態になるべく復活させられる、ということである。栄光のキリストを見るのであれば、確かに聖徒たちは復活してキリストと同じように栄光の身体を持っていなければならない。ちょうど、高貴な人の前に出る時には、スーツやドレスなどといった高貴な人に適合した服装を身に着けているべきであるのと同じである。高貴な人の前にボロボロのTシャツと短パンで出るのが相応しくないのと同じように、キリストの前に罪の残る古い身体を持ったままで出るのは相応しくないことなのである。
ヨハネは、ここでこのように言うことで、聖徒たちに再臨を期待させようとしている。何故なら、このように言えば、聖徒たちが再臨を求めるようになるのは明らかだからである。再臨の際には『キリストに似た者となる』と聞かされて、速やかな再臨の到来を切に希求しないような聖徒が果たしているであろうか。まともな聖徒であればいないと思われる。そのように再臨を希求すれば、聖徒たちがより敬虔になり、更に豊かに忍耐の精神を持てるようにもなる。これから良いことが起きると知っていれば、往々にして人の心は強まるものだからである。聖徒たちがそのようになるのは非常に幸いである。だからこそ、ヨハネはここで再臨の際には聖徒がキリストと同じようになると、あらかじめ伝えたわけである。これは黙示録でも同じである。既に第3部で見たが、この文書の中でも、聖徒たちが近い将来のことを知って更に敬虔な姿勢を持てるようになることが書かれている。
第65章 63:ヨハネの手紙Ⅱ
2番目のヨハネの手紙は、別に心を傾けなかったとしても問題にはならない。ただ、反キリストについて語られている箇所は忘れ去られるべきではない。
第66章 64:ヨハネの手紙Ⅲ
3番目のヨハネの手紙も、特に見る必要はない。何故なら、この文書から再臨のことは学べないからである。しかし、著者であるヨハネの人間的な性質について知るというのであれば、この文書を考察するのも無益ではない。何故なら、ヨハネとは、再臨について多くのことを語っている黙示録を書き記した人だからである。ヨハネの性質を知れば、ヨハネの書いた黙示録を、それだけ理解しやすくなる。つまり、この手紙を読んでヨハネの性質を理解することは、間接的に再臨の理解を増進させることに結びつく。とはいっても、その増進の度合いは、ほんの僅かなものでしかないのではあるが。また、これはヨハネの書いた第2番目の手紙についても、同様のことが言える。
第67章 65:ユダの手紙
ユダの手紙は、心を大いに傾けるべき文書である。特にエノクの預言について記された箇所は、無視することが許されない。この文書は、それ以外の箇所でも、考察されるべき箇所が多い。
【6】
『また、主は、自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを、大いなる日のさばきのために、永遠の束縛をもって、暗やみの下に閉じ込められました。』
これは、やや難しい箇所である。結論から言えば、この箇所で言われているのは創世記6:1~4のことである。そこでは『神の子ら』が、結婚の際に美貌をその最大の基準として位置づけていたという酷い堕落ぶりを示していたことが記されている。それは主の御心には適わないことであった。この創世記6章自体については既によく知られている箇所である。この『神の子』が我々が今見ている箇所では『御使いたち』と言われているのだが、これは人間のことである。すなわち、これは神信仰に導かれてはいたが酷く堕落してしまっていた者を言っている。この『神の子ら』が、人間ではなく『仕える霊』(ヘブル1章14節)としての御使いであると今まで多くの人たちが理解してきたことを、私は当然ながら知っている。だが、これを霊としての御使いとして捉えるのは間違っている。私はその見解をカルヴァンと共に退けよう(※)。というのも、これが御使いであると捉えるのは自然ではないからである。御使いという霊が、物質の身体をとって人間の娘たちと生殖行為をするというのは、明らかに神の創造の仕組みに反している。聖書では、他にも聖徒たちが御使いとして言われている箇所が見られる。だから、我々が今見ている箇所で聖徒が御使いとして取り扱われていたとしても問題ではない。
(※)
「昔の人の考えた天使と女たちとの交合という説は、それ自体の不合理性によって、十分に反駁される。そして、いにしえの学問ある人たちが、かくも粗野でまた奇怪な妄想に魅せられていたとは、驚くべきことなのである。」(『旧約聖書註解 創世記Ⅰ』6:1 p149~150:新教出版社)
[本文に戻る]
この『御使いたち』を本当の意味での御使いだと捉える人が、読者の中にはいるに違いない。仮に、これが本当の意味での御使いだとしてみよう。そうすると、この御使いが束縛されて暗闇の下に閉じ込められたのがいつだったにせよ、封じられたにもかかわらず、ずっと活動し続けていたのはどう説明するのか。罪を犯して暗闇に閉じ込められたはずの御使いたちが、ユダがこの箇所を記すまでの間において、いつの時代にも働いていたのは明らかである。ここで言われている御使いが封じられたのが、原初におけるサタンの堕罪のことだったと仮定してみる。その場合、サタンという『自分のおるべきところを捨てた御使い』が束縛されて闇に封じられたにもかかわらず、アダムとエバとを罪に陥れることが出来たのはどうしてなのか。もし彼が『永遠の束縛をもって、暗やみの下に閉じ込められ』たのであれば、人間を堕落させるために誘惑することは出来なかったはずである。また、ここで言われているのが、創世記6章のことだったと仮定してみる。その場合、大洪水の時に束縛されて闇に封じられたにもかかわらず、あたかも束縛されたり闇に封じられたりしていないかのようにヨブやキリストやユダに働きかけることが出来たのはなぜなのか。これは我々が今見ている箇所で言われている事柄に明らかに反している。「いや、御使いたちは永遠の束縛をもって闇の中に閉じ込められたとしても活動することが許されていたのだ。」などと言い返すのであろうか。私は問いたいが、そのように言える根拠が聖書の他の箇所にあるのであろうか。それは、つまり御使いが封じられたにもかかわらず動くことができる、という見解を証明できる箇所のことである。もしそのような箇所があれば、御使いが封じられているのに活動できるという見解を認めることは十分に可能となる。しかし、そのような箇所は、私の見るところでは聖書にはない。だから、ここで『御使いたち』と言われているのは魂と身体を持った我々と同じような人間だったと解さねばならない。
この箇所のように難解な箇所があれば、分からなかった場合、我々は神に尋ね求めるべきなのだ。私は、ある時まで、この箇所を正しく理解できなかったので、正しく理解できるようにと神に願い求めた。そうしたら、すぐにも正しい理解が得られるようになった。私は聖書の正しい理解を願い求めるならば、必ずそれが与えられると信じている。何故なら、『祈りを聞かれる方』である神は我々に対して『求めなさい。そうすれば与えられます。』と約束されたのだから。
要するに、この箇所ではこういうことが言われている。神信仰に導かれたのに極度の堕落に陥ってしまっていた神の子らは、『自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた』(つまり神の御前に正しく歩むという本分を放棄して守らなかった)ので、大洪水の時に『永遠の束縛をもって、暗やみの下に閉じ込められ』てしまった。―この『暗やみ』とはハデスを指している。―彼らは、裁きをもたらす再臨が起こる『大いなる日』まで、そのハデスの中に閉じ込められている。しかし、再臨が起こる日になれば、彼らは神の裁きを受けるために、ハデスの中から出されて復活することになる(黙示録20:13)。だから、今の時点において彼らはハデスの中で恐れつつ裁きの時を待っているのだ、と。見ただろうか。この『御使い』を人間だと捉えると、こんなにもすんなりと読み解くことができるようになる。これは『御使い』という言葉を正しく捉えている証拠である。正しく捉えているからこそ、この箇所を読み解く際にギクシャクしないですむわけである。
この箇所でユダが言いたいのは、こうである。大洪水の時に、不敬虔になって堕落していた神の子たちは、滅ぼされてハデスの中に閉じ込められた。それ以降、彼らは再臨の日の裁きが起こるまで、そこに封じられ続けている。このような前例が既に我々にはある。つまり、あの大洪水の時の話は我々にとって教訓なのである。それにもかかわらず、最近になって教会に忍び込んできたあの忌まわしい輩は、このような前例などあたかもなかったかのように、好き放題に振る舞っている。これは実に由々しきことである、と。しかし、ユダがこの箇所でこのように言っているということが、どうして分かるのか。それは2節後の8節目で『それなのに、…』と我々が今見ている箇所に続けてこう言われているからである。『(それなのに、)この人たちもまた同じように、夢見る者であり、肉体を汚し、権威ある者を軽んじ、栄えある者をそしっています。』要するにユダは、このような前例を心に留めない彼らの愚かさぶりを辛辣に非難しているのである。
【13】
『まっ暗なやみが、彼らのために永遠に用意されています。』
この箇所では、不敬虔な滅びの子たちが地獄における永遠の闇に呑み込まれる、ということが教えられている。神が、滅びの子たちのために恐るべき闇を用意された。それは、彼らが永遠に闇において裁きを受けるようになるためである。キリストも、悪者たちが闇に捨て置かれることについて語っておられる。すなわち主は、例え話の中で、主人に『役に立たないしもべは、外の暗やみに追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのです。』(マタイ25:30)と言わせておられる。悪者たちの居場所は永遠の闇の中なのである。なお、この箇所は間違いなくⅡペテロ2:17の箇所をなぞっている(※)。
(※)
『彼らに用意されているものは、まっ暗なやみです。』
[本文に戻る]
第2部でも言ったが、地獄とは暗闇の場所である。そこには闇しかなく、闇が幾重にも満ちている。これは、地獄には神の恵みがまったくないからである。光とは神の恵みによるものである。何故なら、それは神を象徴させるものだから。ヨハネが述べている通り、『神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない』(Ⅰヨハネ1章5節)。地獄に対して神は恵みを塵ほども注がれない。だから、そこには恵みによる光も存在していない。しかし、地獄に光が存在していないとすると、そこにある『うじ』や『火』(マルコ9章48節)は一体どうなるのか。すなわち、地獄の虫と火炎とを、そこにいる者たちはどのようにして視認するのか。これに対して私はこう答えよう。それらのものを、地獄の住人たちは、恐らく精神によって、つまり観念によってまざまざと見るのだ。もしそうでなければ、地獄に特有の光で、それらのものを見るのであろう。その光とは光ではあるのだが、恵みにより与えられる光ではなく、呪いとして与えられる光であって、光というよりはむしろ闇というべきものである。人は暗闇に恐怖を感じる。何故なら、闇とは神の恵みがないことを示したり思わせたりするからである。地獄にいる者たちは、蛆や火による刑罰だけでなく、この暗闇による刑罰をも受けることになる。それゆえ、彼らは『そこで泣いて歯ぎしりする』ことになるのである。
これとは逆に、天国には闇がなく、光だけが幾重にも満ちている。何故なら天国とは恵みしかない場所だからである。もし天国に闇が少しでもあれば、そこは天国とは言えないであろう。というのも、それは神による至福の場所として相応しくないからである。天国には光が満ちている、というのは次の御言葉を見ても察することができる。『都には、これを照らす太陽も月もいらない。というのは、神の栄光が都を照らし、子羊が都のあかりだからである。』(黙示録21章23節)『もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らにはともしびの光も太陽の光もいらない。』(同22章5節)『そのとき、正しい者たちは、天の父の御国で太陽のように輝きます。』(マタイ13章43節)地獄が「暗闇の場所」であるのに対し、この天国は「光の場所」である。
我々は、このユダの言葉を心に留め、永遠の暗闇に落ちないようにすべきである。地獄の暗闇を真剣に考えるのだ。そうすれば、我々の霊は、より地獄とその刑罰に抵抗を感じるように導かれる。地獄の闇を真剣に考えれば考えるほど、抵抗を持つ度合いも強くなる。というのも、いったい誰が自分から進んで、地獄の暗闇の中に進んで行きたいと思うのであろうか…。
【14】
『アダムから7代目のエノクも、彼らについて預言してこう言っています。「見よ。主は千万の聖徒を引き連れて来られる。』
この預言はエノク書からの引用である。その当該箇所は既に第2部の中で引用したが、もう一度、ここで引用することにしたい。「見よ、彼は1万人の聖者をひきつれて来られた。それは彼らに審きを行なうためである。彼は不敬虔な者たちを滅ぼし、すべて肉なる者、すなわち罪人たちと不敬虔な者たちが彼に対して働いたいっさいの不義を告発されるであろう。」(『聖書外典偽典4 旧約偽典Ⅱ』エチオピア語エノク書 第1章9節 p172:教文館)所々において僅かな言葉の違いが見られるが、全体的には同じ内容である。多くの人の意見によれば、このエノク書は古い時代に書かれた。ある人は創世記よりも前に書かれたと考えている。この文書がいつ書かれたのか、正確に知るのは恐らくできない。しかし、これが相当に古い時代に書かれたのは間違いなさそうである。
ユダは、神の霊により、このエノクの預言を正典の中に引用した。つまり、神はこの預言を真実であるとしておられる。それゆえ、我々はこの預言の真実性を疑ってはならない。エノクは、まだ洪水が起こるよりも前に、このような預言を実際にしたのである。確かにこのエノクの預言は絶対に信じなければいけないものである。だが、だからといってこの預言が含まれているエノク書を正典として見做すことはできない。この文書は全体としては信頼に値しない。何故なら、この文書には、怪しげな記述が幾つも見られるのだから。ただ我々はこの文書の中でユダが引用した部分だけは絶対確実な部分として信頼しなければならない、というだけのことである。
ここでユダはエノクが『アダムから7代目』であったと言っている。ユダは、アダムからの代数について示さないでおくことも出来た。どうしてユダはここでアダムからの代数を示しているのか。これは私の考えでは、エノクの権威と聖性とを高めるためである。既に述べたように「7」とは完全または神聖性を示す数字だから、エノクが『7代目』であると示すのは、エノクを立場的に称揚させることである。そうすればエノクの預言が、より力強く聖徒たちの心に入ってくるようにもなる。というのも、権威が高ければ高いほど、人の発言や理念はそれだけ受け入れやすくなるからである。これは我々がどこかの王の発言を語って説得したい時、ただ「王があのように言った。」と言うのではなく、「あんなにも偉大で優れた王があのように言った。」などと装飾を施しつつ言うようなものである。ユダがエノクの代数に触れた理由は、これ以外には考えにくいと私には感じられる。
このエノクは預言の中で『見よ。』と言っている。これは「私の言うことをよく聞け、そしてそれを心に留めよ。」という意味である。つまり、これはより真に迫った内容とするために使われている言葉である。確かにエノクの預言は『見よ。』と言われるに相応しい内容であった。
この預言の中で言われているように、キリストは再臨が起きた際、『千万の聖徒を引き連れて来られ』た。これは天上において復活の恵みに与かった全ての聖徒である。つまり、キリスト以前の時代に死んだ全ての聖徒である。これには、キリストが現われてから死んだ聖徒および再臨が起きた時に地上で生きていた聖徒は含まれていない。何故なら、彼らは地上から携挙される人たちであって、天からキリストと共に降りて来るのではないからである。ここでは『千万』と言われているが、これは天上にいた『すべての聖徒』(Ⅰテサロニケ3章13節)のことを言っている。つまり、これは<千万もいるのではないかと思われる全ての聖徒たち>という意味である。既に述べた通り、これは実際の数字を示したものではない。エチオピア語エノク書のほうでは「1万人」となっている。読者の中には『千万』であれば全聖徒たちを表示するのに適切な言葉だが、「1万」ぐらいでは全ての聖徒を表示するには乏しいのではないか、と思う方がいるかもしれない。これはもっともらしい疑問に感じられなくもないが、エノクの時代のことを考えれば、「1万」でも問題はなかったことが分かる。何故なら、まだエノクの時代には世界の総人口が少なかったはずだから、たとえ「1万」とだけ言っても全ての聖徒を表示するのには十分であったのである。つまり、その当時においては人類の母数が僅かであったから1万人だけでも莫大な人数として認識することが出来たのである。なお、聖徒たちが天からキリストと共に降りて来るというのは、先に挙げたⅠテサロニケ3:13の他にⅠテサロニケ4:14の箇所でも語られている。
それにしても驚きである。この預言をエノクが語ったのは紀元前3200年頃であった。その頃にはまだアダムも生きていたし、まだノアも生まれていなかった。当時の世界には、20mぐらいの身長を持つ巨人もいたし(※実際、そのぐらいの身長を持つ人間の骨や棺桶が各地において出土している)、今では化石としてしか見られない恐竜も沢山いたはずである。そんなにも昔から、既にメシアの第二の到来のことが語られていたのである。とはいっても、エノクの時代に第二の到来が預言されていたからといって、エノクやその他の古代人たちが、メシアの第二の到来をはっきり認識していたかどうかといえば、それは非常に疑わしいと言わねばならない。何故なら、この時にはメシアについての認識がまだまだ曖昧であり、ほとんど雲に包まれている状態だったからである。だから、エノクも他の人も、この預言を第二の到来についての預言だと認識することは恐らく出来ていなかったであろう。当時においては、メシアが2度も到来するなどという理解はされていなかったはずだからである。キリストの時代に生きていたパリサイ人でさえ、メシアは1度だけ到来するという認識しか持っていなかった。つまり、彼らはメシアが2度も到来するなどということを、そもそも想像することさえなかった。キリストの時代でさえこうであった。であれば、尚のこと、エノクの時代には2度目の到来について認識されていなかったはずである。
【15】
『すべての者にさばきを行ない、不敬虔な者たちの、神を恐れずに犯した行為のいっさいと、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼のいっさいとについて、彼らを罪に定めるためである。」』
ここで言われているように、キリストが再臨されたのは、悪者どもに裁きを与えるためであった。つまり、再臨の目的は「報復」であった。神は報いられる御方である。エレミヤ51:56の箇所ではこう言われている。『主は報復の神で、必ず報復される』。もちろん、再臨の目的は、この報復だけだというわけではない。再臨には救済という目的もあった。ただし、それは聖徒たちだけに限定される目的であって、悪者どもはこの目的に関わっていない。
ここではキリストが『すべての者に』裁きを行なわれると言われているが、文脈を考えれば、これは教会の内部にいた邪悪な者である。これはユダ書をよく読めば、明らかである。何故なら、この『すべての者』とは14節目で言われている『彼ら』を指しているからである。『彼ら』とは誰であるか。これは14節目よりも前の箇所を読めば誰でも分かる。すなわち、これは聖徒たちの中に『ひそかに忍び込んで来た』『神の恵みを放縦に変え』(4節)るキリスト者のなりをした山羊である。ユダ書の中で取り扱われているのは、この不遜な異端者のことである。つまり、『すべての者』とは、「教会に忍び込んで来た邪悪な者における全ての者」という意味である。これは使徒行伝2:17の箇所で『すべての人』と言われたのが、文字通りの全ての人ではなくて、限定された意味における全ての人であったのと同じである。この「すべて」という言葉について第2部で書かれた説明を、ここで今再び思い返してほしい。聖書の中では、たとい「すべて」と言われていても、ある一定の範囲内における存在だけを指している場合が多いのである。我々が今見ている箇所もそうである。もしこれを文字通りに捉えると、この箇所および聖書全体を上手に理解できなくなってしまうから注意せねばならない。それは、聖書を感覚的に捉えているからである。いい加減に聖徒たちは、聖句を感覚的に捉えるという解釈を止めるべきである。聖句は他の聖句の助けを借りてこそ正しく捉えられるようになるものなのだから。この忌まわしい山羊どもは、ここで言われている通り、再臨の時にその不敬虔な言葉と振る舞いとが罰せられた。すなわち、紀元68年6月9日に再臨が起きた際に携挙されず、42か月が経過してから第二の復活によって空中の大審判を受けた後、永遠の地獄へと投げ込まれることになった。これが当時の悪者どもに与えられたキリストの裁きであった。
今の聖徒たちは、この預言が未だに成就していないと思うであろう。だが、そのように考えるべきではない。これは既に成就した預言である。それは2000年前のことである。今の牧師たちは、私と再臨や終末のことについて、まったく議論できない。どの牧師も私と議論しようとはしない。私が土俵で構えて待っているのに、誰もその土俵に上がって来ないのだ。これは、今の牧師たちの持つ再臨や終末についての理解があまりにも浅すぎるからである。というよりは根本的に誤っている。ぜんぜん研究が足りていないのだ。私からすればほとんど盲人も同然なのである。だから、私が問題を提起したり何かを教えたりしても、議論しようとする人がいないのである。誰も彼も再臨の真理を理解できていない。それゆえ、聖徒である読者たちは、特に牧師たちは、今言われたことや本書で教えられていることを、真剣に考えるべきである。時間がかかってもよい。そうすれば、やがて再臨の真理を悟れるようにもなることであろう。神の恵みがあれば、確かにそうなることであろう。
【18】
『終わりの時には、自分の不敬虔な欲望のままにふるまう、あざける者どもが現われる。』
『終わりの時』とは、<ユダヤが終わりを迎える時代の日々>という意味である。この言葉を、今に至るまでの日々すなわち新約時代の全ての日々だと捉えるのは、あまりにも強引である。この理解は、聖書理解の不足に基づいた誤謬である。我々は、マタイ24章の中で『終わりの時』がどのように教えられているのか、よく弁えなければならない。
ユダヤが神に捨てられて終わりそうになっている時期には、聖徒たちの前に忌まわしい者どもが出現した。彼らは、既にキリストの聖なる福音が明らかに宣べ伝えられているにもかかわらず、しかもその福音の内容をよく認識していたのにもかかわらず、それを受け入れず、不敬虔な振る舞いをしたり冒涜的な言葉を吐いたりしていた。コリント教会の聖徒たちは、『不敬虔な欲望のままにふるまう』ことをしていたが、しかしここで言われている者には該当しない。何故なら、コリント人たちは確かに不敬虔な歩みをしてはいたが、あくまでもキリストの民であったからである。またヒメナオとアレキサンデルは、冒瀆の罪を犯していたが、彼らもここで言われている者には該当しない。何故なら、パウロの言葉を見ると、どうやらこの2人には回復の望みがあったようだからである(Ⅰテモテ1:19~20)。この箇所で言われている『あざける者ども』を、世の中で一般的に見られる悪者たち、つまり不信者たちだったと捉えてはならない。これは不信者たちではなく、教会の中にいた毒麦(つまり偽クリスチャン)のことを言っている。これはユダ書における文脈を考えれば明らかである。ユダがこの手紙の中で取り扱っているのは、教会の中に『ひそかに忍び込んで来た』(4節)、『神の恵みを放縦に変え』(4節)てしまう、正しい信仰者たちと『恐れげもなくともに宴を張』(12節)る人々だからである。これは、どう考えても教会の内部にいる偽クリスチャン以外では有りえない。そうでなければ彼らが『あなたがたの愛餐のしみ』(12節)などと言われることはなかったであろう。これは、つまり彼らが『あなたがたの愛餐』(つまり聖餐式)に『しみ』としてではあるが本物の信者でもあるかのように参加していたことを意味しているのだから。これが偽クリスチャンだと分からない人は、ユダ書をじっくりと読んでいないのだと私は思う。また、この『あざける者ども』は、これまでに現われたことのなかった者たちであった。彼らは新種の毒物だったのである。何故なら、この時代になるまでは、まだキリストの福音も現われておらず、新約時代のような形としての教会もまだ存在していなかったからである。
この箇所で言われている出来事が、いまだに実現されていないなどと考える者があってはならない。そのように考える者は、ユダ書も終わりの時の事柄についても、理解がまだまだ浅い。この箇所がいまだに実現されていないと考えている者に、私は問いたい。ユダは、自分が生きている時に見られた不敬虔な侵入者である毒麦のことを語っているのではないのか、と。また『終わりの時』がユダヤ世界について言われた言葉であるということをどうして考えてみないのか、と。
ユダが言っているように、この箇所における言葉は『使徒たちが、前もって語ったことば』(17節)であった。その言葉とは、Ⅱペテロ3:3~4やⅡテモテ3:1~5で言われた言葉である(※)。
(※)
このことから、ユダ書はⅠ・Ⅱペテロ書およびⅠ・Ⅱテモテ書よりも後に書かれたということが分かる。
[本文に戻る]
【21】
『永遠のいのちに至らせる、私たちの主イエス・キリストのあわれみを待ち望みなさい。』
これは、キリストの再臨が起これば永遠の命に導き入れる大いなる憐みを受けられるのだから、その時になるまで不敬虔な悪者たちの中にあって希望を持ち続けなさい、という意味である。当時の聖徒たちにとって、キリストの再臨は間近に迫っていた。その時が来れば、聖徒たちは『主イエス・キリストのあわれみ』を受けるようになる。そうすれば、邪悪な輩が生じさせる忌まわしい状況からも解き放されるようになる。だからこそ、ここでユダはキリストの再臨の時まで忍耐しつつ待ち望むようにと命じているのである。既に述べた通り、このキリストの再臨は、既に起きている。マタイ16:28の箇所を読めば、そのことは決して疑えない。つまり、ここでは、直接的には紀元1世紀の聖徒たちに向かって命令が為されているということが分かる。
再臨以後の時代に生きる聖徒たちにとって、ここで言われていることは、天に召される日に起こる。我々が天に召される日に、我々は『永遠のいのちに至らせる、私たちの主イエス・キリストのあわれみ』に与かるようになる。その時、聖徒たちは真にキリストの憐れみを知るようになる。何故なら、その時、聖徒たちは身体の復活に与かるからである。キリストの憐れみは、この身体の復活において極みに至るのである。その時、聖徒たちはこう思うであろう。「これこそ正にキリストの憐れみによる至福の救いである」と。今において聖徒たちは諸々の悩みや問題を抱えているかもしれない。だが、ここでユダが言っているように、我々はキリストの憐れみを切に期待すべきである。そうすれば、心が和らぎ、やがてすぐにもそれらの悩みや問題から解き放されるようになるであろう。
第68章 第4部の最後に
第69章 聖書に書かれているユダヤ戦争について
聖書がこのようにユダヤ戦争について大いに語っているのは何故なのか。その理由は何か。それは、ユダヤ戦争がユダヤにとって非常に重大だからである。どうして重大なのか。それは、このユダヤ戦争においてユダヤが神の御前から完全に遺棄されるからである。その時、遂にユダヤが神から捨てられるというのだから、これほどまで大いに聖書でユダヤ戦争について語られていたとしても不思議ではない。つまり、ユダヤ戦争とはユダヤにおけるクライマックスなのだ。だから、聖書でその出来事について大いに語られていなければ、それはおかしいことであった。映画でも小説でも、クライマックスは例外なく強調されるものだが、それと一緒である。ところが、今まで教会はこのユダヤ戦争という重要な戦争について、ほとんど心を傾けることをしてこなかった。『キリスト教綱要』の中でも、この戦争にはまったく注意が払われていない。これは、今まで教会が再臨について盲目状態にあったからである。ちょうど、16世紀になるまで人々が宇宙観において盲目状態のうちに閉じ込められていたのと同じである。もし盲目状態でなかったとすれば、教会はもっとユダヤ戦争について語っていたはずである。それというのも、盲目状態ではなかったとすれば、再臨に関わるユダヤ戦争の重大さをよく弁えていただろうから、そのあまりの重大さゆえ、語らずにはいられないからである。現に、私はその重大さをよく理解しているので、この戦争について大いに語っている。
しかしながら、ユダヤの荒廃について書かれている箇所では、それがユダヤ戦争について言われているのかどうか解釈が難しい場所もある。ある箇所においては、ネブカデレザルによるエルサレム陥落の出来事を言っていると思える場合もあるはずである。というのも、ローマ軍によるユダヤの破壊とネブカデレザルによるユダヤの破壊は、非常に似通っているからである。その類似性を具体的に示せば、こうである。どちらもエルサレムが多くの軍勢により四方から包囲された。そして、そこにあった神殿が完全に破壊され尽くした。その時、ユダヤ人の多くが虐殺された。虐殺されずに生き延びた者たちは世界の各地へと散らされた。それらの悲惨は彼らの罪に対する裁きであった。そこには神の燃える怒りがあった。このようにこの2つの出来事は、そっくりな内容を持っている。だから、ユダヤの破滅について書かれている箇所を読んで、どちらの出来事を言っているのか悩まされる人は多いはずである。ユダヤ戦争について言われている箇所をネブカデレザルによる破壊の出来事として理解したり、それとは逆にネブカデレザルによる破壊について言われている箇所をユダヤ戦争として理解したりする。こういった間違いを犯す人が必ずいるはずだ。例えば、ゼパニヤ書1章では紀元1世紀の時に起きたユダヤの破滅について言われていると考える人がいるかもしれない。しかし、そこで言われているのはネブカデレザルによる破壊のことである。エゼキエル書38・39章も難しい箇所である。この箇所を読んで、そこで言われているのがユダヤ戦争のことなのか、それともネブカデレザルによる破壊のことなのか、思い悩む人は多いはずである。この箇所は、この箇所および聖書の全体を研究しない限り、決して正しい判断に至れない。調べれば分かるが、そこで言われているのはネブカデレザルによる破壊のことではなく、ローマ軍による破壊のことである。再臨の探究者たちは、ユダヤの破壊について言われている箇所を理解する際、どちらの出来事が言われているのかよく弁えるようにすべきである。
ユダヤ戦争について言われている箇所を、今の教会はまだ実現されていない箇所として理解するかもしれない。それは、これから未来に起こる出来事が言われている箇所だと。このように理解するのは、とんでもないことである。再臨に関して聖書を研究していないから、そのような理解を持つことになる。知れ。その箇所で言われているのは、ユダヤ戦争のことであるから、その箇所で言われていることは既に成就されているのだ。私が今言った通りにその箇所を捉えようとしてみよ。そうすれば、その箇所だけでなく聖書の多くの箇所が真に正しく理解できるようになるであろう。
【後記】
当作品から霊的な益を受けられた方には、以下のことをぜひお願いしたく思う。
もし読者が祈ってもよいというのであれば、この作品の筆者である私が聖書の真理を更に豊かに悟れるようにと、また私のうちにある誤謬を神が慈しみ深く取り除いて下さるようにと、祈ってほしい。このようにお願いしている私自身も、毎日、聖徒たちが聖書の真理を悟れるようにと祈りを捧げている。以前、この箇所で私は「特に黙示録を完全に理解できるように祈ってほしい。」と書いたが、私が黙示録を理解できるようにと祈って下さった聖徒たちには感謝したい。既に公開されているが、第3部において私は、神の恵みにより黙示録の註解を豊かに書き記すことができた。このような註解が書けたのは、読者の誰かが、このことについて祈ってくれたその祈りを主が聞いて下さったのも一つの要因であると私は思っている。
もし可能であれば、この作品で書かれていることが聖書の真理であると思われた方は、この作品を広めてほしい。その方法は、ツイッターでもフェイスブックでも印刷するのでも口で誰かに紹介するのでも、どのような形でも構わない。作品の中でも書かれたが、真理が広まるようになるのは神の御心である。また真理とは、その絶対的また排他的な性質からして、満ち広まり信じられるべきものである。だからこそ、私もこのようにして聖書の真理における正しい解釈を求めて、それを皆が見られるようにと公開しているのである。
[2]
何かの質問や問い合わせがあれば、私の所属している教会のメールアドレス<mail@sbkcc.net>かこちらのフォームまで、お願いしたい。なお、送られてきた内容は、これから書かれることになる続きの部分や既に書かれた内容の追加・訂正・削除をする時のために、実名を伏せて使わせていただく可能性もあるので、あらかじめ了承していただきたい。カルヴァンも「キリスト教綱要」の中で、ある医者からの質問をその内容の中に組み込んだし、そのような例は世の学者たちの著書においても枚挙にいとまがないのである。
[3]
当作品は、多くの改訂が行なわれることになると予想される。これを書いている時点で、既に改訂は行なわれている。というのも、私はアウグスティヌスと同様に、次のように告白する者の一人だからである。「私は進歩しつつ書き、書きつつ進歩する人の一人であることを告白する。」(書簡第七)アウグスティヌスという人は、自分が間違いを信じていたと悟ったならば、すぐにも容赦なく自分の考えを変える人であった。彼の書物を読み慣れた人であれば、このことをよく知っているはずである。例えば、彼は真理に気付いた際、かつて持っていた誤謬を破棄したがゆえに、その誤謬について「私はこの考えを捨てざるを得なくなった。」(『アウグスティヌス著作集29 ペラギウス派駁論集(3)』ペラギウス派の2書簡駁論 第1巻 第10章 第22節 p319:教文館)などといった内容のことを多くの箇所で言っている。私もそのようでありたいと思っている。もし誤謬が判明したならば、その誤謬が記されている箇所を正して誤謬が拡散されないようすることは、真理のためにはどうしても必要である。また追加すべき内容を追加して書いたり、細かな文章上のミスや不十分性を直すということも必要である。それゆえ、恐らく多くの改訂が行なわれるだろうということを、ここであらかじめ読者の方に伝えておきたいと思う。改訂をした際には、下のほうにある【作品情報】の箇所でそのことが書かれることになる。
【資料】
終身独裁官 カエサル(前100―前44)
前46年―前44年3月15日(3年4ヶ月5日)
1代目 アウグストゥス(前63―14)
前27年1月16日―14年8月19日(46年4ヵ月1日)
2代目 ティベリウス(前42―37)
14年9月18日―37年3月16日(26年6ヶ月19日)
3代目 カリグラ(12―41)
37年3月16日―41年1月24日(3年10ヶ月8日)
4代目 クラウディウス(前10―54)
41年1月24日―54年10月13日(13年8ヵ月28日)
5代目 ネロ(37年12月15日―68年6月9日)
54年10月13日―68年6月9日(13年8ヶ月28日)
6代目 ガルバ(前3年12月24日―69年1月15日)
68年6月8日―69年1月15日(7ヶ月6日)
7代目 オト(32年4月25日―69年4月15日)
69年1月15日―4月15日(5ヶ月1日)
8代目 ウッティリウス(15年9月7日―69年12月22日)
69年4月16日―12月22日(7ヶ月1日)
9代目 ウェスパシアヌス(9年11月17日―79年6月23日)
69年7月1日―79年6月23日(11年11ヶ月22日)
10代目 ティトゥス(39年12月30日―81年9月13日)
79年6月23日―81年9月13日(2年2ヶ月)
11代目 ドミティアヌス(51年10月24日―96年9月18日)
81年9月14日―96年9月18日(15年8ヶ月5日)
12代目 ネルウァ(35年11月8日―98年1月27日)
96年9月18日―98年1月27日(1年4カ月10日)
13代目 トラヤヌス(53年9月18日―117年8月8日)
98年1月27日―117年8月8日(19年7月15日)
※ネロ以降の皇帝については黙示録解読のキーとなるネロの生存中に生きていた人物だけを記した
※在位年数はアレクサンドリアのクレメンス『ストロマテイス』第1巻による
※カエサルは皇帝の起源であるために記しておいた
[聖書における度量衡とお金の単位]
<長さ>
キュビト 44cm
ペーキュス 45cm
スタディオン 185m
<お金>
デナリ 平均的な労働者の1日分の給与
タラント 6000デナリ
[聖書の諸巻が書かれた年代]
創世記 紀元前14世紀~南北朝時代の間※
出エジプト記 紀元前14世紀~南北朝時代の間※
レビ記 紀元前14世紀~南北朝時代の間※
民数記 紀元前14世紀~南北朝時代の間※
申命記 紀元前14世紀~南北朝時代の間※
ヨシュア記 紀元前14世紀~南北朝時代の間
ヨブ記 正確な時期は不明
詩篇 紀元前10世紀頃~紀元前6世紀頃
箴言 紀元前10世紀
エゼキエル書 紀元前6世紀
ダニエル書 紀元前6世紀
オバデヤ書 紀元前600~585年
ハガイ書 紀元前520年
ゼカリヤ書 紀元前520年
マラキ書 紀元前440~410年
70人訳聖書 紀元前2世紀
ピリピ書 紀元61~62年
Ⅱテサロニケ書 紀元41~54年
ヤコブ書 紀元50年代前半?
黙示録 紀元37~41年
※モーセが著者であるという伝統的な理解は聖書から証明できない
[再臨理解の向上のために読んでおくべき聖書以外の書物]
ヨセフス『ユダヤ戦記』(これは是非とも読むべきである)
タキトゥス『同時代史』『年代記』
スエトニウス『ローマ皇帝伝』
『スラブ語エノク書』
『エチオピア語エノク書』
フィロン『ガイウスへの使節』
セネカ全作品(紀元1世紀の状態や古代ローマ人のことを知るために)
『Ⅰ・Ⅱ・Ⅳマカベア書』(ダニエル書の理解向上のために)
[世界創世の年代に関する諸々の見解]
以下に、今までに聖書から世界創世の年を算出してきた人たちが、いつ頃の年代を算出したかということについて記す。これは再臨を徹底的に深く理解したければ、知っておいたほうがいい知識である。
ヨセフス 前5555年
ケプラー 前3993年
メランヒトン 前3964年
ルター 前3961年
ライトフット 前3960年
ヘイルス 前5402年
プレイフェア 前4008年
リップマン 前3916年
七十人訳聖書 前5270年
ユダヤ年代記 前3760年
■ヘンリー・M・モリス『創世記の記録』Ⅱ 世界の創造 p63(創造科学研究会)より
アイザック・ニュートン 前4000年
ジョナサン・エドワーズ 前4000年頃
ジェームズ・アッシャー(※①) 前4004年/10月27日/午前9時(※②)
ユリウス周期(※③) 前4713年
カルヴァン(※④) 前4000年頃
(※①)アイルランドの大主教
(※②)タルムードのゲマラの中ではラビ・エリエゼルも10月に世界が創造されたと言っている(モエードの巻 ローシュ・ハ・シャナー篇 10b)
(※③)ユリウス・カエサル・スカリゲル(1484―1558)による
(※④)『キリスト教綱要』3:24:12/3:21:4 『新約聖書註解―使徒行伝』17:30
―本書の筆者である私も世界創世の年を前4000年頃とする立場に立つ
[世界創世からユダヤの終焉に至るまでの歴史]
紀元前4000年 世界創世
紀元前3900年? エデンからの追放(正確な時期は不明)(※)
紀元前3200年 エノクの時代
紀元前3070年 アダムの死去
紀元前2900年 ノアの生誕
紀元前2300年 ノアの大洪水
紀元前2100年 バベルの塔の建設
紀元前1800年 アブラハムの時代
紀元前1300年 出エジプト
紀元前1000年 ダビデ王の治世
紀元前 720年 イスラエル王国の陥落/アッシリア捕囚
紀元前 585年 エルサレム滅亡/バビロン捕囚
紀元前 550年 メディア滅亡
紀元前 547年 リュディア滅亡
紀元前 539年 新バビロニア滅亡
紀元前 330年 ペルシャ滅亡
紀元前 323年 アレクサンドロスの死/大帝国の4分割
紀元前 146年 マケドニア滅亡
紀元前 27年 ローマ帝政期の始まり
紀元前 4年 キリストの受肉
紀元 30年 キリストの受難
紀元32~33年 パウロの回心
紀元 54年 ネロの治世(~68年)
紀元 66年 第一次ユダヤ戦争(~70年)
紀元 68年 キリストの再臨(6月9日)
紀元 70年 ユダヤの終焉(9月2日)
(※)アダムが追放されたのは創造後130年以内である。しかし、いつ追放されたのかは全く分からない。アウグスティヌスはアダムが造られたその日に堕落して追放されたと考えているが、この見解は間違っている。
[預言者たちの活動した期間(仮)]
エリヤ 前870~850
エリシャ 前850~790
ヨエル 前820~790
ヨナ 前790~770
アモス 前780~740
ホセア 前780~700
イザヤ 前770~680
ミカ 前740~700
ナホム 前690~630
ゼパニヤ 前640~610
エレミヤ 前640~590
ハバクク 前620~600
ダニエル 前610~522以降
オバデヤ 前600~560
エゼキエル 前590~570
ハガイ 前530~460
ゼカリヤ 前520~440
マラキ 前440~410―これ以降キリストの時代まで預言者の現われが途絶する
[聖書における数字の意味]
【2/3】―――確認・確証・強調(Ⅱコリント12:8、13:1、申命記19:15、
エレミヤ22:29、エゼキエル21:27、使徒行伝10:16、
イザヤ6:3、黙示録4:8、ヨハネ21:14、17)
【4】―――――世界・地の四隅(使徒行伝10:11、黙示録7:1、マタイ24:31、
マルコ13:27)
【6】―――――人間(創世記1:26~31)
※昔の時代では「6」は完全数とされていた。ケプラーも6を完全数として捉
えていたので、太陽の周りには6の惑星しか存在しないと思い込んでいた。だ
が聖書においてこの「6」は完全数ではない。
【7】―――――完全・完璧・完成・神聖・安息・無限・永遠(創世記2:1~3、4:24、
ユダ14、黙示録5:1、6、8:2、15:7、
ルカ17:4、箴言9:1、詩篇12:6
エゼキエル39:9、12、14、ゼカリヤ3:9
イザヤ30:26、ヨブ5:19)
【8】―――――新生・新しい状態への移行(創世記17:12、ヨハネ20:26)
【10】――――完全・完璧(出エジプト34:28、申命記4:13)
※ピュタゴラス学派でも「10」を完全数として捉えていた。
これは恐らくこの学派の祖であるピュタゴラスがユダヤ思想
に触れて感化されたからだと思われる。
【12】――――選び(マタイ10:1~4)
※この数字は古代ローマ人にも特別視されていた。
【14】――――少しの数ー42の3分の1(Ⅱコリント12:2、マタイ1:17、
民数記21:1、14、29、使徒行伝27:27、33、
創世記31:41、16:16+21:5、エゼキエル40:1)
※これはヘブル文字の14番目である 】(ヌン)=魚の意味ではない
【24】――――旧約の民と新約の民(黙示録4:4)
【30】――――充分なだけの時間や数量(ルカ3:23、創世記41:46、
民数記18:16、Ⅱサムエル5:4、Ⅰサムエル9:22)
【33】――――清め(レビ記12:4)
【40】――――充分なだけの時間や数量(マタイ4:2、Ⅰ列王記19:8、ヘブル3:9、
出エジプト34:28、申命記25:3、使徒行伝7:36、
創世記7:4、25:20、26:34、Ⅱサムエル5:4)
【42】――――神の定め/少しの数―14+14+14(マタイ1:17、
民数記21:1、14、29、黙示録13:5)
※A・クロウリーはこの数字を「不毛」と解するが、やや意味合いが違う
【66】――――清め(レビ記12:5)
【70】――――充分なだけの時間や数量(ダニエル9:2、24、エレミヤ25:11~12、
詩篇90:10、マタイ18:22)
【77】――――充分なだけの度合い(創世記4:24)
【120】―――選ばれた存在に関わる完全で十分な時間や数量―12×10(申命記34:7、
創世記6:3)
【144】―――選ばれた存在に関わる大きな数値―12×12(黙示録21:17)
【153】―――たくさん―1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+
14+15+16+17※(ヨハネ21:11)
※この数字の成立ちはアウグスティヌスの見解である(ヨハネ福音書講解説教)
【666】―――徹底的に人間主義・神の除外・理性の自立・堕落・邪悪・サタン
(黙示録13:18、Ⅰ列王記10:14)
【777】―――「幸い」(※推定)―ノアの父レメクの生きた年数(創世記5:31)
【1000】――徹底的に完全完璧―10×10×10(黙示録20:1~6)
【1600】――とにかく十分なだけの距離―40×40(黙示録14:20)
【12000】―選ばれた存在に関わる大きな数値―12×1000(黙示録21:16)
■<補足>:「13」は世の中では不吉な数字と見做されることがあり(特に有名なのは「13」日の金曜日である)、ユダヤ教においては聖なる数字である。だが、聖書においてこの数字は何の意味も持っていない。
[聖書における象徴の一覧]
<神>
盾(詩篇3:3、84:11)/翼を持つ鳥(詩篇17:8)/巌、砦、岩、櫓(詩篇18:2)/取り囲む火の城壁(ゼカリヤ2:5)/太陽(詩篇84:11)/隠れ場(詩篇119:114)
<キリスト>
子羊(黙示録5:6)/獅子(黙示録5:5)/蛇(ヨハネ3:14、民数記21:9)/太陽(マラキ4:2)/岩(Ⅰコリント10:4)/石(Ⅰペテロ2:4、黙示録2:17、ゼカリヤ3:9)/マナ(黙示録2:17)/パン(ヨハネ6:48)/門(ヨハネ10:9)/光(ヨハネ8:12)/葡萄の木(ヨハネ15:1)/若枝、新芽(ゼカリヤ3:8、6:12、イザヤ11:1)/切り株(イザヤ6:13)/ダビデ(エゼキエル34:23)/アダム(Ⅰコリント15:45)/輝く明けの明星(黙示録22:16)/神の御腕(イザヤ53:1)/神の御手(イザヤ25:10)/燃え盛る炭(イザヤ6:6)/棘の付いた棒(使徒行伝26:14)/衣(ローマ13:14、ガラテヤ3:27)
<聖霊>
鳩(ルカ3:22)/炎の舌(使徒行伝2:3~4)/水また水の川(ヨハネ7:37~39、エゼキエル47:1~12)/風(ヨハネ3:8)/息(ヨハネ20:22)/油(Ⅰヨハネ2:20)
<御言葉>
火(エレミヤ23:29)/杖(黙示録19:15)/乳(Ⅰペテロ2:2)/灯、光(詩篇119:105)/銀(詩篇12:6)/雹(黙示録16:21)/剣(エペソ6:17)/息(Ⅱテサロニケ2:8、イザヤ11:4)/種(Ⅰペテロ1:23、Ⅰヨハネ3:9)
<聖徒>
羊(ヨハネ21:17)/麦(マタイ13:26)/塩(マタイ5:13)/光(5:14)/葡萄の枝(ヨハネ15:5)/オリーブの木(詩篇52:8)/尊いことに用いる器(ローマ9:21)/星(黙示録12:4、ダニエル8:10、12:3)/山の上にある町(マタイ5:14)/山(詩篇125:1)/神(ヨハネ10:35)/神々(詩篇82:6)/水路の傍に植わった木(詩篇1:3)/畠(詩篇129:3)/女(イザヤ27:11)
<悪者>
狼(マタイ10:16)/毒麦(マタイ13:38)/海(イザヤ57:20)/大水(詩篇124:4)/海の荒波(ユダ13)/荒野、砂漠(ホセア2:3)/つまらないことに用いる器(ローマ9:21)/蛇(マタイ23:33)/彷徨う星(ユダ13)/風に吹き飛ばされる水のない雲(ユダ12)/枯れた秋の木(ユダ12)/荒地のむろの木(エレミヤ17:6)/風が吹き飛ばす籾殻(詩篇1:4、イザヤ29:5)/生い茂る野生の木、レバノンの杉(詩篇37:35)/獅子(詩篇17:12、22:13、35:17)/雄牛(詩篇22:12)/犬ども(詩篇22:16)/金かす(詩篇119:119)/牧場の青草(詩篇37:20)/煙(詩篇37:20)/茨、おどろ(イザヤ27:4、Ⅱサムエル23:6)
<教会>
真理の柱また土台(Ⅰテモテ3:15)/花嫁(黙示録19:7)/燭台(黙示録1:20)/山鳩(詩篇74:19)
<祭司/教師/伝道者>
御使い(ユダ6、Ⅱペテロ2:4、マラキ2:7)
<預言者>
ユダヤ人たちの目また頭(イザヤ29:10)
<神殿/聖所>
翼(ダニエル9:27)
<ユダヤ>
大バビロン(黙示録17:5)/淫婦(黙示録17:16)/ソドム、エジプト(黙示録11:8)/遊女(イザヤ1:21)/麗しい国(ダニエル8:9)/輝かしい国(ダニエル11:20)/天の軍勢、星の軍勢(ダニエル8:10)/聖なる山(ダニエル9:16)/麗しい山(ダニエル11:45)/多くの実を結ぶ葡萄の木(ホセア10:1)/麗しい葡萄畑(イザヤ27:3)/杉の木、見事な木々、深い森(ゼカリヤ11:1~2)/木の枝、大枝(イザヤ27:10~11)/栽培されたオリーブの木(ローマ11:24)
<異邦人>
野生種であるオリーブの木(ローマ11:24)
<人間>
塵、灰(創世記18:27)/蛆、虫けら(ヨブ25:6)/草(イザヤ40:6)/霧(ヤコブ4:14)/風(詩篇78:39)
<人生>
影(伝道者の書6:12)
<命>
ともしび(マタイ25:1、箴言13:9、20:20、24:20、ヨブ21:17)/霧(ヤコブ4:14)
<サタン>
竜、蛇(黙示録12:9)/明けの明星(イザヤ14:12)/鳥(マタイ13:4、19)
<悪霊>
猛禽、野獣(エゼキエル39:4)/禿鷹(マタイ24:28)/鳥ども(黙示録19:17、21、18:2、マタイ13:4、19)
<王>
雄羊、雄山羊、角(ダニエル8:20~21、黙示録17:12)/頭(黙示録17:9)/獣(黙示録17:11)/獅子(エゼキエル38:13、32:2)/神(詩篇45:6)
<大帝国>
大きな獣(ダニエル7:3)
<国々>
島々(ダニエル11:18、イザヤ24:15、66:19、詩篇97:1)
<支配>
枷、綱(詩篇1:3)
<軍勢>
洪水(ダニエル11:22、9:26)/海辺の砂(黙示録12:18、20:8)
<ローマ軍>
いなご(黙示録9:3、7)/マゴグとゴグ(黙示録20章、エゼキエル38章・39章)/子牛(イザヤ27:10)
<エジプト>
ラハブ(詩篇87:4)
<パロ(エジプト王)>
川に横たわる鰐(レビヤタン)また竜(エゼキエル29:3、32:2、詩篇74:14)/獅子(エゼキエル32:2)
<狡猾な者>
狐(ルカ13:32)
<良い妻>
商人の舟(箴言31:14)/豊かに実を結ぶ葡萄の木(詩篇128:3)
<妻としての女性>
愛らしい雌鹿、愛しい羚羊(箴言5:19)
<嗜みのない女>
豚(箴言11:22)
<若い子ども>
勇士の手にある矢(詩篇127:4)
<祝福された多くの子ら>
オリーブの木を囲む若木(詩篇128:3)
<母の胎>
地の深い所(詩篇139:15)
<怠け者>
回転する蝶番(箴言26:14)
<預言>
巻き物、ラッパ、鉢(黙示録)
<再臨>
盗人(マタイ24:43~44、Ⅱペテロ3:10、黙示録3:3、16:15、Ⅰテサロニケ5:2)
<携挙>
穀物の取り入れ(イザヤ24:13、27:12~13、黙示録14:14~16)
<権威>
雲(イザヤ19:1、マタイ26:64、黙示録1:7)
<神の義>
高くそびえる山(詩篇36:6)
<神の栄光>
煙(イザヤ6:4)/雲(出エジプト40:34~35)
<神の国>
主の家の山(イザヤ2:2)/山、家(イザヤ2:3)/魅力的な宴会(イザヤ25:6)/父祖たちとの宴席(マタイ8:11)
<神の裁き>
深い海(詩篇36:6)
<命の選び>
いのちの書(黙示録20:12)
<信仰>
大盾(エペソ6:16)
<数の多さ>
海の砂(ホセア1:10、ヘブル11:12)/天の星(ヘブル11:12)
<絶滅/離散>
毒の水(エレミヤ9:15)/苦よもぎ(エレミヤ9:15、黙示録8:10~11)
<雪>
羊毛(詩篇147:16)
<霜>
灰(詩篇147:16)
<雹>
投げつけられるパンくず(詩篇147:17)
<慈しみ>
神の顔(エゼキエル39:24その他多数)
<父の訓戒・母の教え>
頭の麗しい花輪、首飾り(箴言1:9)
<死>
眠り(Ⅰテサロニケ4:13~14、ヨハネ11:11~13、Ⅰコリント15:18)
<神殿男娼>
犬(申命記23:17~18)
■これらの象徴表現を見ると、あくまでも傾向としてではあるが、重要な存在であればあるほどそれだけ多く象徴されていることが分かる。重要でないほどに、象徴表現も多様ではない傾向が見られるのだ。
[聖書の各巻における再臨を理解するために研究すべき必要性の度合い](10段階表記)
1:創世記 ★★★☆☆☆☆☆☆☆ (3/10)
2:出エジプト記 ★★★★★★★☆☆☆ (7/10)
3:レビ記 ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ (2/10)
4:民数記 ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ (2/10)
5:申命記 ★★★☆☆☆☆☆☆☆ (3/10)
6:ヨシュア記 ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ (1/10)
7:士師記 ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ (2/10)
8:ルツ記 ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ (1/10)
9:Ⅰサムエル記 ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ (1/10)
10:Ⅱサムエル記 ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ (1/10)
11:Ⅰ列王記 ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ (1/10)
12:Ⅱ列王記 ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ (2/10)
13:Ⅰ歴代誌 ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ (1/10)
14:Ⅱ歴代誌 ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ (2/10)
15:エズラ記 ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ (1/10)
16:ネヘミヤ記 ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ (1/10)
17:エステル記 ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ (1/10)
18:ヨブ記 ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ (2/10)
19:詩篇 ★★★★★★★★☆☆ (8/10)
20:箴言 ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ (1/10)
21:伝道者の書 ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ (2/10)
22:雅歌 ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ (1/10)
23:イザヤ書 ★★★★★★★★★★(10/10)
24:エレミヤ書 ★★★★★★★★★★(10/10)
25:哀歌 ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ (1/10)
26:エゼキエル書 ★★★★★★★★★★(10/10)
27:ダニエル書 ★★★★★★★★★★(10/10)
28:ホセア書 ★★★★★★★☆☆☆ (7/10)
29:ヨエル書 ★★★★★★★★★★(10/10)
30:アモス書 ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ (1/10)
31:オバデヤ書 ★★★★★★★★★★(10/10)
32:ヨナ書 ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ (1/10)
33:ミカ書 ★★★★★★★☆☆☆ (7/10)
34:ナホム書 ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ (1/10)
35:ハバクク書 ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ (1/10)
36:ゼパニヤ書 ★★★★★★★☆☆☆ (7/10)
37:ハガイ書 ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ (1/10)
38:ゼカリヤ書 ★★★★★★★★★★(10/10)
39:マラキ書 ★★★☆☆☆☆☆☆☆ (3/10)
40:マタイ福音書 ★★★★★★★★★★(10/10)
41:マルコ福音書 ★★★★★★★★★★(10/10)
42:ルカの福音書 ★★★★★★★★★★(10/10)
43:ヨハネ福音書 ★★★★★★★★★★(10/10)
44:使徒の働き ★★★★★★★★☆☆ (8/10)
45:ローマ書 ★★★★★☆☆☆☆☆ (5/10)
46:コリント書Ⅰ ★★★★★★★★★☆ (9/10)
47:コリント書Ⅱ ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ (1/10)
48:ガラテヤ書 ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ (1/10)
49:エペソ書 ★★★★★☆☆☆☆☆ (5/10)
50:ピリピ書 ★★★★★★☆☆☆☆ (6/10)
51:コロサイ書 ★★★☆☆☆☆☆☆☆ (3/10)
52:テサロニケ書Ⅰ★★★★★★★★★★(10/10)
53:テサロニケ書Ⅱ★★★★★★★★★★(10/10)
54:テモテ書Ⅰ ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ (2/10)
55:テモテ書Ⅱ ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ (2/10)
56:テトス書 ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ (2/10)
57:ピレモン書 ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ (1/10)
58:ヘブル書 ★★★★★★★★★☆ (9/10)
59:ヤコブ書 ★★★★★☆☆☆☆☆ (5/10)
60:ペテロ書Ⅰ ★★★★★☆☆☆☆☆ (5/10)
61:ペテロ書Ⅱ ★★★★★★★★☆☆ (8/10)
62:ヨハネの手紙Ⅰ★★★★★☆☆☆☆☆ (5/10)
63:ヨハネの手紙Ⅱ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ (2/10)
64:ヨハネの手紙Ⅲ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ (2/10)
65:ユダ書 ★★★★★★★★☆☆ (8/10)
66:黙示録 ★★★★★★★★★★(10/10)―最も研究されねばならない巻
[セラフィムとケルビムの違い]
以下にセラフィムとケルビムの違いを示す。黙示録に出てくる4つの生き物はエゼキエル書に出てくるケルビムだと思っている人が多いが、黙示録の生き物はセラフィムであってケルビムではない。このぐらいのことさえ分からないほど、多くの人たちは黙示録を理解できていない。聖書の探究者たちは、間違えないようによく注意していただきたい。
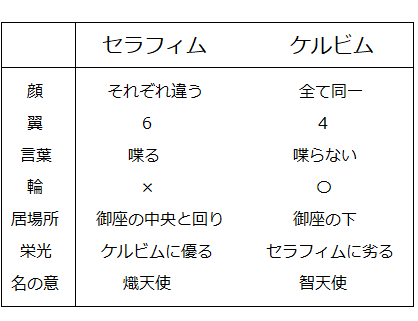
[聖書で使われている語法の一覧]
<反復>
同一の内容の文章や単語を繰り返すことで強調の意味を持たせる語法。(例)『主よ。私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。』(詩篇130篇2節)『倒れた。大バビロンが倒れた。』(黙示録18章2節)『地よ、地よ、地よ。主のことばを聞け。』(エレミヤ22章29節)
<提喩法>
ある一つの事柄や存在を挙げるだけで全体を表示させる語法。例えば、次の聖句では、「エフライム」と言ってイスラエルの全体を言い表している。『エフライムの人々は、矢をつがえて弓を射る者であったが、戦いの日には退却した。』(詩篇78:9)次の聖句では「ギリシャ人」と言って全ての異邦人を言い表している。『ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜなら、あなたがたはみな、キリスト・イエスにあって、一つだからです。』(ガラテヤ3章28節)
<誇張>
ある事柄の内容を大いに伝えるために本来それが持っている度合いを何倍にも拡大・膨張させて言い表す語法。(例)『イエスが行なわれたことは、ほかにもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書きしるすなら、世界も、書かれた書物を入れることができまい、と私は思う。』(ヨハネ21章25節)
<比喩>
ある事柄を異なる事柄によって言い表す語法。例えば、次の聖句では「鳥」と言われているが、これは実際の鳥ではなくサタンを表示させているに過ぎない。『蒔いているとき、道ばたに落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。』(マタイ13章4節)また次の聖句では「獣」と言われているが、これも実際の獣ではなく単にネロを表示させているだけである。『また私は見た。海から一匹の獣が上って来た。』(黙示録13章1節)
<省略>
語る相手には自明であるために、あえて多くを述べず省略的に短く述べる語法。これは、その部分だけを見るならば、何が言われているのか非常に分かりにくい。(例)『私たちの神は焼き尽くす火です。』(ヘブル12章29節)『死体のある所には、はげたかが集まります。』(マタイ24章28節)
<数による意味の創出>
ある事柄を複数挙げることで、その事柄に特定の意味を持たせる語法。例えば次の聖句では、7つの教会が挙げられているが、これは7つの教会を示すことで、教会の完全性また神聖性を示している。『あなたの見ることを巻き物にしるして、7つの教会、すなわち、エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィヤ、ラオデキヤに送りなさい。』(黙示録1章11節)十戒も、10の項目であるから、法の完全性がそこに示されている。何故なら、聖書において7と10は完全であることを表すからである。
<「数」の変化>
ヘブル語旧約聖書では、同一の文章の中で「数」の格が急激に変化している箇所が少なくない。すなわち、それまでは複数形で述べられていたのに急に単数形になったり、それまでは単数形で述べられていたのに急に複数形になったりする。これは、本来的には全体を対象として述べられているが途中から個別者にピントをあてたり、文脈的には個人を対象として語っているのに全体にもその語られている事柄が適用されるべきことを示すために使われる語法である。
[ギリシャ語アルファベットに割り当てられている数字の一覧]
これは獣の数字<666>を探るためには知っておかねばならないものである。
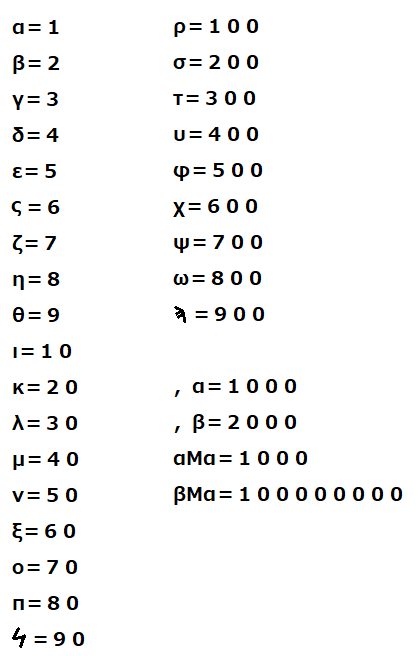
[666の利用リスト]
第3部で述べられた通り、黙示録13:18に書かれている666の数字を利用している企業や商品は非常に多く見られる。その利用の理由には、サタンが教会や人々を威圧し弱める、聖書の知識があることを示す、邪悪な雰囲気を出す、魔術的な作用で働きかける、など諸々の理由がある。しかし、どれもこれもそれは無知に基づく不正な利用である。何故なら、この数字が示しているのはネロだからである。ネロという人間を示す数字を、何の弁えもなく人でもない企業や商品の中に取り入れるとは何事か。以下に、この数字を不正に利用した例を簡単な説明付きで纏める。それを見れば、どれだけこの数字が多くの人たちの心に働きかける力を持っているか、よく分かるであろう。誰も彼もこの数字に心を留めざるを得なくさせられるのであって、だからこそこの数字を何かに取り入れるわけだ。もちろん、以下に示すのは私の知っている例だけに限られる。しかし、これからも私の知識が増えるのと同時に、以下のリストは拡充されていくはずである。
■<バーコードの右端と中間と左端の線に示された666>―これは間違いなく陰謀家の仕組んだものである。
■<日本の硬貨を全て足し合わせると666(円)>―これは陰謀家による仕掛けである可能性がいくらかでもある。「そんなのは偶然に過ぎない。ありえない。」などと断定する人は卑小で女々しい精神の持ち主なのであろう。そのようにして否定してしまえば、巨大な世界的陰謀に自分の精神を対峙させなくて済むのだから。
■<メタリカの「ブラックアルバム」に描かれた蛇の666>―このバンドのヴォーカリストであるジェイムズ・ヘッドフィールドは「ルシファーから力を貰っている。」と発言している。このことを考慮するならば、このアルバムジャケットの蛇に見られる666は意図的に仕組まれたものだとすべきであろう。ルシファーから力を受けているのであれば、666をジャケットに示したとしても何の不思議なことがあるだろうか。⇒https://www.amazon.co.jp/METALLICA-メタリカ/dp/B000005RUG
■<ロックフェラービルの入口に公然と書かれた666>―これは間違いなく意図的である。
■<アイアン・メイデンの作品名にある666>―このメタルバンドのイメージと666の数字が適合しているのは確かであるが、だからといって彼らが666の獣だというわけではない。⇒https://www.amazon.co.jp/フライト666-リミテッド・エディション-DVD-アイアン・メイデン/dp/B001VEH3JU
■<アイアン・メイデンの曲に出てくる666>―このバンドの「ナンバー・オブ・ザ・ビースト」という曲には、「その数字は666である。」という黙示録の文言が使われている。他の人たちもそうだが、彼らは黙示録を何も理解していないのに黙示録を利用している。これは、日本人が洋楽の曲を何かカッコいいからというので歌詞の意味も分からず口ずさむようなものである。⇒https://www.google.com/search?client=opera&q=iron+maiden+number+of+the+beast+lyrics&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
■<HYDEのアルバム名である666>―これほどまであからさまに666の数字を利用するケースは珍しい。宗教と霊の事柄における感性が欠如している日本人ならでは、ということなのであろう。欧米の人の多くはここまで大胆にはこの数字を利用していない。⇒https://ja.wikipedia.org/wiki/666_(HYDEのアルバム)
■<OKサインに示された666>―よく使われるOKサインで666の数字を表示できる。確かな証拠はないが、これは陰謀家が発明し広めたものである可能性がある。何故なら、サタン崇拝者であれば、自己を神のように啓示したいと思っているサタンの霊に動かされているわけだから、サタンのためにこのようなサインを世に広める、というのは彼らにとって当然なすべきことだと言えるからである。
■<コンピューターという単語に秘められた666>―COMPUTERという単語のアルファベットを一つ一つ数字に変換し、それを足し合わせると666になる。コンピューターはユダヤ人により作られた。陰謀家のユダヤ人が、邪悪である自分たちの存在を示そうとして、この近代的な利器を666が秘められたコンピューターという名前ににしたのであろう。これを偶然だと決めつける人は、陰謀家たちに牧されることから決して免れ得ないか弱き羊の一匹である。
■<グーグルクロームのアイコンに示された666>―デイヴィッド・ボウイが言ったように「グーグルはイルミナティ、イルミナティはグーグル」である。このイルミナティはルシファーによる霊的な有機体である。ルシファーは自分の存在を示すために666を使用する。それゆえ、イルミナティであるグーグルの作ったこのブラウザーに示された666は、意図的であると結論すべきである。⇒https://www.google.co.jp/intl/ja/chrome/
■<ワールドワイドウェブ(www)=666>―URLにあるwwwを数字に変換すると666となる。これは陰謀家の仕掛けたものである可能性がある。
■<jay―zの曲を逆再生すると聞こえる666>―アメリカのカリスマラッパーであるjay―zの曲を逆再生すると「シックス、シックス、シックス」という声が聞こえる。これはアレイスター・クロウリーの魔術なのであろう。これが意図的であるのは間違いない。何故なら、この後ですぐに「マーダー、マーダー、ジーザス」と続いているからである。偶然にこんな声が聞こえるなどとはとてもじゃないが考えられない。jay-zはイルミナティなのだから、こういうことをしても何もおかしくはない。
■<GEのロゴマークに見られる666>―世界的な大企業であるゼネラル・エレクトリックのロゴマークには666が示されている。世界の動向がNWOの実現に向けて進められている今の時代において、GEほどの大企業が陰謀家に乗っ取られていないと考えるほうが変である。イルミナティカードでも示されているように、企業を乗っ取って支配することは、ワンワールド計画の一つなのである。⇒https://www.ge.com/
■<QRコードに見られる666>―QRコードにある3つの【回】を666と見做すことが可能である。バーコードには間違いなく666が意図的に仕組まれているのだから、このQRコードにも意図的に666が仕組まれた可能性がある。
■<初代マッキントッシュに付けられた価格が666ドル>―アップル社の有名な林檎のマークは、アダムとエバが食べた善悪の知識の木の実(林檎ではない)を示しているのであろう。つまり、これは「私たちはアダムとエバのような神への反逆者なのだ。」というメッセージを隠しているのであろう。偶然に、何の意味もなく、こんなマークを採用するはずがないのだ。であれば、初代マッキントッシュに付けられた666(ドル)の数字は、邪悪な意図がその背景にあると考えるべきであろう。
■<東京オリンピックの公式マークに秘められた666>―東京オリンピックの公式マークを構成している正方形と長方形は、それぞれ18個ずつある。「18」は6たす6たす6なので、666を表示できる数字である。オリンピックは既にフリーメイソンに乗っ取られている。それゆえ、666が2つも秘められたこのマークは、悪しき意図に基づいて作成・採用されたと考えるのが妥当である。
■<岸本聖史の漫画作品である「666~サタン~」>―あまりにも大胆過ぎるので驚くほどである。先に述べたHYDEのように日本人だから、また日本だから、このような666の利用が出来るのであろう。宗教に疎い日本でこのようなことをしても、誰も何も騒いだりしないからである。日本であれば、このようなことをしても、真理の番人である教会でさえ騒ぐことはないのである!このようなあからさまな666の利用は、もしこの作者がサタニストでなかったのであれば、知らず知らずのうちにサタンの霊に動かされて行なったのである。⇒https://www.amazon.co.jp/666-サタン-1-ガンガンコミックス-岸本-聖史/dp/4757505973
■<ディズニーのマークに見られる666>―周知の通り、ウォルト・ディズニーはフリーメイソンであった。このフリーメイソンとはルシファーの組織である。であれば、フリーメイソンが作った会社におけるマークに666の数字が意図的に仕組まれたとしても、それほど驚くには及ばない。むしろ、そのようにするのは自然であるとさえ言えるのだ。⇒https://www.disney.co.jp/
■<2020年6月30日に成立した中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持法が6章66条=666>―陰謀家は、アジアを中国を中心としてコントロールしようとしている。それは日本ではない。ロックフェラーは中国をアメリカに続く覇権国家にしようとしているという情報もある。であれば、この法律により陰謀家たちが自分の邪悪な存在を示していたとしても、それほど驚くには値しない。これについてはまだ推測の領域を出ないが、法律が全6章66条というのを単なる偶然として片付けるのは、注意深さと詮索力が弱いと言わねばならない。今は陰謀がそこら中に蔓延っている時代なのだから、このような数字があれば、最初から思慮深さを持ちつつ疑ってかかるのが正しい姿勢である。⇒https://zh.wikisource.org/wiki/中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法?uselang=ja
■<ジョンソン・エンド・ジョンソンのマークに見られる666>―ジョンソン・エンド・ジョンソンはイルミナティ企業である。⇒https://www.jnj.co.jp/
■<freeeに見られる666>―会計ソフトで知られる日本のfreeeという企業における社名およびソフト名には666が確認できる。これは意図的である可能性がある。有名であったり大きな力を持っている企業や商品で怪しいものがあれば、常にその背景を見抜くべく、疑ってかかるべきである。のほほんとしていれば騙されるだけだ。⇒https://www.freee.co.jp/index3.html?utm_expid=.rYJebn1ZS6mHhbxi2PLFVQ.2&u…
■<ロスチャイルド家のワインに見られる666>―ロスチャイルド家の所有する葡萄園のワインには明らかに666が確認できる。6が全部で9個あるので、666が3つあると見做すことが可能である。ロスチャイルド家には間違いなくサタンの働きがある。よって、これは悪意に基づいて作られたマークである可能性が高い。⇒https://ja.wikipedia.org/wiki/ファイル:Mouton_Cadet_detail.JPG
■<「NARUTO」の登場人物における666>―2億部以上も売り上げた日本の漫画「NARUTO」の登場人物には666とも見做せる目の術を使う者がいる。この漫画を掲載していた少年漫画雑誌は、そのマークを見ても分かるように、陰謀家に乗っ取られている。この漫画雑誌に掲載されていた「ジョジョの奇妙な冒険」において、911が事前に予告されていたという事実からも(これはかなり有名な話である)、これを裏付けることができる。であれば、そのような雑誌に掲載されていたこの漫画において、意図的に666と見做せる瞳術を登場人物に使用させたということは可能性としては有りえる話である。もっとも、これについては確言をすることができない。もしかしたら、たまたま666に似ただけであるという可能性もある。ただ、NWOに向けて計画が推し進められている今のこの時代において、「目」に「666」とくれば、当然詮索されて然るべきなのである。⇒https://www.google.com/search?q=ナルト+写輪眼&client=opera&hs=i0d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2a…
■<サバタイ・ツヴィの改宗した年が1666年>―偽メシアとして有名なサバタイ派ユダヤ教の祖であるサバタイ・ツヴィがイスラム教に改宗したのは、1666年であった。彼にサタンが働いていたことは火を見るよりも明らかである。であれば、サタンが自分の働きかけを示そうとして666の数字が含まれている年に大騒動を引き起こさせた、というのは可能性としては考えられない話ではない。これはあくまでも推測の域を出ないが、サタンであれば、そういうことをしても何も不思議ではないのである。サタンだったら666の数字が含まれている年を無視するはずがないではないか。
■<コメダ珈琲店のマークに見られる666>―有名な日本のコーヒーチェーン店であるコメダ珈琲店のマークには、明らかに666が確認できる。しかも、そこにいる一人の紳士は、ユダヤ人の帽子とも見做せる帽子をかぶっている。それゆえ、この666は陰謀の意図に基づいて描かれた可能性がある。このチェーン店は大きくて有名な企業である。であればユダヤの陰謀家が働きかけたとしても不思議ではない。イルミナティカードの「企業の支配者」を思い起こせ。⇒http://www.komeda.co.jp/index.php
■<アレイスター・クロウリーと666>―クロウリーが自分で言っているように、彼は子供の頃から自分が666だと思っていた。この意識は大人になってからも、ずっと持ち続けていた。他の人たちもクロウリーが666であると認識した。この666とは、もちろん黙示録における獣のことである。
■<エナジードリンク「モンスター」に示された大胆な666>―どこでも売られているエナジードリンクの「モンスター」に表示されている|||は、ヘブル文字のヴァヴであり、数字に変換すると666である。ヘブル語に無知でない人であれば、これはすぐにも理解できることだ。「モンスター(怪物)」で「666」だから、これは間違いなく意図的である。疑いもなく、どこかにいる陰謀家が、このようなものを考え出したのである。これを偶然として片付けるような人がいれば、単に臆病であるか、既に相当な洗脳にかかっていると言わざるを得ない。⇒https://www.monsterenergy.com
■<「ちゃんみな」の名前表記に見られる666>―日本の女性ラッパ―である「ちゃんみな」の名前表記には、666が潜んでいる。彼女の音楽作品のジャケットを見れば分かるが、彼女は100%イルミナティのアーティストである。X―JAPANのHIDEと同様、彼女は陰謀家のペットである。とすれば、意図的に名前表記の中に666を潜ませた可能性は、かなり高い。「ゃ」の横棒と縦棒を繋げない限り、「ちゃんみな」という表記で666は示せないのだ。繋げてこそ666が示せる。それゆえ「ゃ」の横棒と縦棒を繋げたのは、かなり怪しいと見るべきであろう。たとえ、これが666を意図的に表示させているのではなかったとしても、彼女がイルミナティのアーティストであることに変わりはない。⇒https://chanmina.com/discography/detail/3/
■<パラリンピックのマークに見られる666>―パラリンピックのマークには666が隠されている。すなわち、そのマークにある|||は、先に述べたように、ヘブル語であって666である。ロンドン2012のマンデヴィルを見ても分かるように、パラリンピックは陰謀家に乗っ取られている。それゆえ、このマークは悪しき意図に基づいていると考えるのが妥当であろう。世界の裏側には、人々の深層に働きかける魔術師たちがいるのである。⇒https://ja.wikipedia.org/wiki/パラリンピックシンボル
■<「Spotify」における666>―世界最大の定額制音楽配信サイト「Spotify」におけるマークには、やや曲がった棒が3本あるが、これはヘブル文字で666を示していると見做すことができる。これは意図的に666として仕組まれた可能性がある。何故なら、イルミナティカードで示されているように、音楽に現実逃避をさせることで本当に重要な事柄に人々の意識が向かないようにする、というのが陰謀家たちの計画だからである。我々は、多くの定額制音楽配信サイトにおいて、イルミナティカードで音楽を聞いて陶酔している女性が描かれているのに気付くべきである。グーグルミュージックなどは、ほとんどそのままイルミナティカードの女性を描いている。⇒https://www.spotify.com/jp/
■<東京スカイツリーにおける666>―東京スカイツリーの高さは634mであるが、地下部分を32mだとすると、合計666mとなる。問題なのは地下部分をどう定めるかであるが、これは「都市伝説に過ぎない。」などと簡単に退けるべきではなく、真面目に考慮すべき事柄であって、今の時代を考えるならば意図的である可能性が高いとすべきである。というのも大きな放送事業者は、どこも陰謀家の支配下にあるからである。ウィキペディアを見ると、最初は666mにする計画だったようである。
■<「Paypay」に見られる666>―日本の有名な電子決済アプリである「Paypay」のマークには666が見られる。陰謀家たちは全ての領域をコントロールしたいので、出来る限り早急に全ての領域が電子機器によって動かされることを望んでいる。それは最近のデジタル化の流れを見ても分かる。何故なら、我々が使っている電子機器は、かなり古い機器でもない限り、どれも陰謀家が遠隔操作できる仕組みになっているからである。だから、この有名な電子決済アプリは出来るならば使わず、なるべく現金決済で買い物をしたほうが私としては良いと思う。⇒https://paypay.ne.jp
■<ホンダのマークに見られる666>―ホンダの有名な翼のマークには、ヘブル語のヴァヴが3つ見られるが、これは上で述べたように666である。以前のマークには、このような666が示されていなかった。これは陰謀家の働きかけによる可能性がある。何故なら、陰謀家は、トヨタや日本銀行やCBSなどのマークを見れば分かるように、マークにおいて自分たちの存在を示すからである。⇒https://www.google.com/search?q=ホンダ+バイク+マーク&tbm=isch&c…
■<CERNのマークに見られる666>―欧州原子核機構のマークには明らかに666が含まれている。これは意図的に仕組んだと見るべきであろう。この見解を都市伝説だなどと即座に切り捨てる人は、この世界のことをよく知っていない。ディズレーリが言ったように、この世界の舞台裏には一般大衆が思いもよらないような者たちが隠れ潜んでいるのだから。この研究所の知名度と規模を考えてみたまえ。悪魔と陰謀家たちが何も手を付けないままでいると思うのか。⇒https://home.cern
■<「WOWOW」には666が含まれているのか>―「WOWOW」という名前には、Wが3つあるから、ヘブル語において捉えれば666が含まれていることになる。ネットでは、これを意図的であると捉えている人が少なからず見られる。私も、これが意図的である可能性は幾らかでもあると思う。⇒https://www.wowow.co.jp
■<新潮文庫の葡萄に見られる666>―新潮文庫に描かれている葡萄のマークにおける蔓には、666が見いだされる。新潮社は巨大な出版社である。であれば、陰謀家が働きかけていないと考えるほうが逆におかしいことになる。そうならば、この葡萄のマークに見いだされる666は意図的である可能性があるとすべきであろう。しかも、この葡萄のマークには2パターンあるが、どちらのパターンでもそこに描かれている実は「13個」である。新潮文庫を持っている人は、自分で数えてみるとよい。我々は、ロスチャイルド家のワインのマークにも葡萄に666が示されていたことを忘れるべきではない。
[ネロ語録]
暴君ネロとは、荒らす憎むべき者であり不法の人である666の獣であった。また彼には『大きなことを語る口』(ダニエル書7章8節)が与えられていた。このネロが実際に口にした言葉を以下に纏める。この忌まわしい暴君は、再臨の理解にとって非常に重要な意味を持つ。それゆえネロの言説について知り、ネロの理解を深めておくことは、再臨を考究する聖徒たちにとって、決して無益とはならないであろう。この語録は、これからも追加していく予定である。
■「貧乏とは、いったい何のことだ。」―ネロは「貧乏」という観念を持っていなかった
■「これはネロの蒸留水だ。」―逃亡中に見つけた足元の水溜まりについて
■「そうするともう私には、敵も味方もいないのか」―誰も死ぬ助けを与えてくれなかった時に
■「生きているうちに土の中にはいるのはいやだ。」―死ぬ前に
■「ネロにふさわしくない、まったくネロらしくないぞ。こんな時こそ、しっかりとしなくては。さあ、奮起一番だ。」―死ぬ前に
■「この世から、なんと素晴らしい芸能人が消えることか。」―もう間もなく死のうとしていた時に言った言葉
■「おそかった。でもそれが忠義か。」―死ぬ数分前にやって来た百人隊長に言った最後の言葉
[各終末論における著名な信奉者および教派・団体]
<ディスペンセーション的前千年王国論>(ディスペンセーショナリズム・プレミレニアリズム)
ジョン・ダービー、サイラス・スコフィールド、ムーディー、ティム・ラヘイ、ハル・リンゼイ
<歴史的前千年王国論>(ヒストリカル・プレミレニアリズム)
ジョージ・ラッド
<無千年王国論>(アミレニアリズム)
ヴァン・ティル、アブラハム・カイパー、改革派/長老派、ルター派
<後千年王国論>(ポストミレニアリズム)
アウグスティヌス、ジョン・ノックス、ジョナサン・エドワーズ、ジョージ・ホィットフィールド、B・B・ウォーフィールド、スポルジョン、ヘルマン・ドーイウェールト、ローマ・カトリック、再建主義、エホバの証人、コロンブス
【リンク】
■Η Αγία Γραφή
https://el.wikisource.org/wiki/Η_Αγία_Γραφή
■Αγία Γραφή - Ελληνική Εβδομήκοντα εκδοχή (LXX)
http://lxx.ibibles.net
<聖書研究>
■The HTML Bible
http://www.greeknewtestament.com/index.htm
■Bible Hub
https://biblehub.com/
<世界的な陰謀についての重要なページ/本の紹介/トラクト>
■シオン賢者の議定書
https://sites.google.com/site/shionkenjanogiteisho/
■「ロックフェラーの友は、911を事前に予告した」 アーロン・ルッソ(1of2)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=EeWqlJHzcSo&feature=emb_title
■ロスチャイルドの密謀(日本語)単行本
https://www.amazon.co.jp/ロスチャイルドの密謀-ジョン・コールマン/…
■300人委員会―「世界人間牧場計画」の準備はととのった!!(日本語)単行本
https://www.amazon.co.jp/300人委員会―…
■ユダヤ人の陰謀に気付いて下さい!(プロテスタント教会のトラクト)
表(A4)
裏(A4)
【付録】
1.
再臨は、キリストが言われたように、キリストの御前に立っている人たちが生きている間に起きたと信ずべきである。(マタイ16:28)
2.
パウロも、主の御言葉に基づき、紀元1世紀当時のテサロニケ教会にいた聖徒たちが生き残っている間に、キリストが再び来られると言った。(Ⅰテサロニケ4:15)
3.
再臨が紀元1世紀に起こるからこそ、キリストも使徒も、再臨は速やかに起こると言ったのである。(黙示録3:11、ヤコブ5:8、ピリピ4:5)
4.
紀元66~70年に起こるユダヤ戦争およびエルサレム神殿の崩壊について預言されたマタイ24章とその並行箇所であるルカ21章とマルコ13章の中で、再臨のことが預言されているのだから、再臨は紀元66~70年の間に起きたと信じなければいけない。
5.
再臨により殺される不法の人とは暴君ネロのことだから(Ⅱテサロニケ2:8)、再臨が起きたのは、ネロの命日である紀元68年6月9日である。
6.
キリストが再臨された有様は、キリストが天に昇って行かれるのと同じ有様であった。(使徒行伝1:9~11)
7.
キリストが再臨された場所は、昇天された場所と同じであり、エルサレムの近くにあるオリーブ山であった。(ゼカリヤ14:4)
8.
ユダヤ戦争の際に再臨をその目で見たローマ兵たちには、再臨があたかも夢や幻のように感じられたので(イザヤ29:1~8)、誰一人として再臨のことを記録として残さなかった。
9.
再臨の日に地上に残されず空中へと携挙された者たちは(マタイ24:40~41)、右により分けられた者たちは天国に移され(マタイ25:34~40)、左により分けられた者たちは地獄に投げ込まれたので(マタイ25:41~45)、自分たちの見た再臨を記録として残そうにも残せなかった。
10.
パウロから手紙を受け取ったテサロニケ教会の聖徒たちが生きながらにして携挙される直前に、死者の復活が起きた。(Ⅰテサロニケ4:15~17)
11.
これこそ、キリストが終わりの日に起こると預言された復活だったのである。(ヨハネ6:39~40、44、54)
12.
実に、古い世の終わる日が紀元68年6月9日だったからこそ、ペテロは世界の終焉が間近に迫っていると書いたのである。(Ⅰペテロ4:7)
13.
再臨のキリストがその栄光の御座に着かれた時をもって、古い世は終わりを告げ、全く新しい世へと改められた。(マタイ19:28、使徒行伝3:21)
14.
再臨の起こる日に旧約聖書の預言が全て成就し尽されるのだから(ルカ21:22)、再臨の起きたその日に、新天新地が創造されると言われた預言は成就された(イザヤ65:17)。
15.
黙示録は人間一般の感覚から乖離しない意味合いにおいて速やかに実現される出来事を示しているのだから(黙示録1:1、22:6)、新天新地について示されている黙示録21章および22章の箇所は、既に成就しているのであって、未だに成就していないということはあり得ない。
16.
再臨の日に創造された新しい天と地は、すなわち今現在の世界であり、それは終わることもなく永遠に続く。(イザヤ66:22~23)
17.
神は永遠に続く全被造世界において、天国では贖われた聖徒たちを祝福されることでその恵みの栄光を、地獄では呪われた者たちを正しく裁かれることで義の審判者としての栄光を(マルコ9:48)、そしてこの地上では人々に祝福と裁きを与えられることで恵み主と裁き主としての栄光を、その本質的には変わらない事象の繰り返しを通して永遠に至るまでも顕示され続ける。(伝道者の書3:14~15)
18.
永遠に続くこの地上において、死ぬまでに福音を信じた者は死んでから天国に移され、信じなかった者は罪に定められるので死んでから地獄に移される(マルコ16:16)。
19.
聖書は明らかにキリストの到来が2度あり(ヘブル9:26~28)、また栄光の再臨が1度あると教えており(ピリピ3:20、Ⅰテサロニケ4:15、黙示録16:15、マタイ26:64その他多数)、到来が3度あるとか再臨が2度あるなどとは教えていないので、これから再びキリストが来られると考えることはできない。
20.
再臨の前に達成されると言われた全世界に対する宣教は(マタイ24:14)、再臨が紀元68年に起こるまでに達成されていたのだから(マルコ16:20および別の追加文、ローマ1:8、コロサイ1:6)、未だに達成されていないなどと思い違いをしてはならない。
21.
再臨が紀元1世紀に起きた際にユダヤは回復されたのだから(使徒行伝3:20~21)、ユダヤの霊的な問題は既に解決済みであって、多くの人がユダヤの民族的な大回心を待ち望んでいるのは聖書の理解不足に基づく病的な妄想に他ならない。
22.
不法の人とはネロを指しており、彼はパウロが証言しているように使徒時代の人物であるから(Ⅱテサロニケ2:5~7)、これから不法の人が現われると信じるのは誤っている。(Ⅱテサロニケ2:3~10)
23.
聖書が再臨は紀元1世紀の人たちが生きている間に起こると教えているにもかかわらず、史実的な証拠が存在しないからというので既に再臨が起きたと信じようとしない人は、見なければ信じようとしなかった不信仰なトマスの罪を犯しており(ヨハネ20:24~29)、他に誰もそのような意見を主張していないからというので既に再臨が起きたと信じようとしない臆病な日和見主義者は、神からの評価よりも人からの評価を愛するパリサイ人のようである(ヨハネ12:43)。
24.
再臨について御言葉が教えていることを子供のように素直になって受け容れようとしないのは(ルカ18:15~17)、明らかに不信仰の罪であって神に喜ばれないから(ヘブル11:6)、悔い改めなければいけない(マタイ4:17)。
25.
再臨が既に起きたと信じない心の頑なな者は、その不信仰に対する裁きとして神から惑わしの力が送り込まれるので、再臨の真理を買うことができず(箴言23:23)、偽りの信仰に陥ることになるであろう。(Ⅱテサロニケ2:11~12)
◇この項目集は、恐らく500ぐらいのプロテスタント教会に伝えられた(正確な数は記録していないので定かではなく、500という数はあくまでも私の不完全な記憶に基づく推定に過ぎない)。
[プロテスタントの牧師先生に対する通知と勧め(1)]
教会で教えておられる牧師先生の皆様へ
黙示録の註解書が記されましたので、皆様に是非読んでいただきたく思い、このように連絡させていただきました。これを書きました私は、霊感されていない書物の中ではカルヴァンの『キリスト教綱要』に勝るものはないと思っている、改革派の教会で教えていますプロテスタントの者です。聖徒である兄弟姉妹の方々が、黙示録を正しく理解できるようにと書かれたのが、この註解書です。この註解書では、一節一節が聖書から豊かに解き明かされており、そこに手抜きは一切ありません。私はこれを十分なものに仕上げるべく、神の恵みにより出来る限りの力を尽くしました。私の知る限りでは、今までこのような内容を持った黙示録の註解書は出たことがありませんでした。今までにも黙示録の註解書は書かれていますが、そのどれもが内容的に短く十全性に欠けており、そのうえ更に聖書に基づいていない曖昧かつ推測に過ぎない内容がそこには満ちていました。私からすれば、今までに書かれた黙示録の註解書で役に立つものは一つも見られません。
この註解書は、『再臨論』という作品の第3部として位置づけられているものです。この『再臨論』とは、キリストの栄光ある再臨に関わる事柄を徹底的に聖書から考究することが目的とされた神学作品です。この作品は、「聖書のみ」というプロテスタントの伝統的な原理に徹底的に固執して書かれています。ですから、この作品は人間理性による理解や常識的な見解や伝統的な解釈ではなく、徹頭徹尾「聖書」を根拠とした理解・見解・解釈が何よりも求められています。これはルターやカルヴァンも持っていた姿勢です。第1部では、既にキリストの再臨が起きたということが、聖書から論証されています。第2部では、第1部の内容を踏まえた上で、再臨と再臨に関わる諸々の出来事における詳細およびその順序について聖書から論証されています。そして、この第1部と第2部に続く第3部が「黙示録註解」です。これは、聖書に基づいて記された黙示録の徹底的な註解を通して、主の再臨を豊かに理解できるようになることを目指したものです。それがどのような内容であるかは、一度本註解書をざっと眺めていただければ、よくお分かりいただけるのではないかと思います。
これまで教会が黙示録を正しく理解できなかったのは、キリストの再臨を聖書から正しく理解していなかったからです。何故なら、黙示録とは再臨について教えている文書だからです。ですから再臨を正しく理解して初めて、黙示録も正しく理解できるようになるということです。その再臨についての正しい理解というのは、つまりキリストが使徒の時代に既に再臨されたと理解することです。これは出鱈目や誤謬ではなく、聖書的な理解です。キリストは、御自身の目の前に立っている紀元30年頃のユダヤ人たちが生きている間に、再臨が起こると言われました。マタイ16:28でキリストは、当時(つまり紀元1世紀)のユダヤ人に対してこう言っておられます。『まことに、あなたがたに告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が御国とともに来るのを見るまでは、決して死を味わわない人々がいます。』これほど明白な内容の御言葉が他にあるのでしょうか。この聖句の中で、確かにキリストは、目の前に立っているユダヤ人たちが生きている間に再臨が起こると言われたのです。このように考えるのをおかしいとは思わないでほしいと思います。といいますのも、この聖句は、私が今書いたように理解するのが正しい理解だからです。実際、この理解を示されて聖書から反論できる先生方は、今まで一人さえもいませんでした。どの先生も、何も反論できず沈黙してしまうのです。これは私の述べた理解を認めざるを得ないからでなくて何でしょうか。実際、私と議論したバプテスト派(JBBF)の牧師も、この聖句を読んで「これは2千年前のことだ。ここでは2千年前の人についてだけ語られている。」と言いました。アウグスティヌスや東方教会で「博士」と呼ばれるグレゴリオス・パラヌスのように、この聖句の中で言われたのが、すぐ後ほど書かれている17:1~8の山上の変貌についてのことだと考える解釈もありますが、これは『再臨論』第1部第2章の中で説明されていますように、完全な誤りです。何故なら、17:1~8で言われている山上の変貌が起きた時には、16:27で書かれている「報い」や「御使い」が確認できませんし、アウグスティヌスも疑問に感じていたようにその山上における変貌の出来事には「御国」が感じられにくく、どうして6日後に起こる出来事を告げられた際に「それが起こるまでこの中には死なない者がいるであろう。」とキリストが言われたのかよく分からなくなってしまうからです。普通に考えれば、マタイ16:28の聖句が、続く17:1~8の聖句のことを言ったものだと解することは出来ないでしょう。そうであれば、やはりマタイ16:28では、再臨のことが言われているとせねばならないことになります。パウロもこのキリストの御言葉に基づき、テサロニケ教会の聖徒たちに『私たちは主のみことばのとおりに言いますが、主が再び来られるときまで生き残っている私たちが、…』(Ⅰテサロニケ4:15)と言いました。この聖句からも、既に再臨は起きたことが分かります。何故なら、パウロは自分と一緒にいた紀元1世紀のテサロニケ人たちが『生き残っている』間に、キリストが再び来られると断言しているからです。この理解についても、聖書から反論できる人はいません。何故なら、パウロの言ったことは、私が今言ったように理解する以外に正しい理解はないからです。カルヴァンも、この聖句は当時の人について言われていると考えていました。彼はこの聖句の註解箇所で、「彼は最後の日まで生きるであろうひとびとのなかに、自分自身をおいている。」(『新約聖書註解ⅩⅠ ピリピ・コロサイ・テサロニケ書』Ⅰテサロニケ4:15 p216:新教出版社)と言っています。今までの教会は、再臨について今私が述べたようには理解していませんでした。つまり、今まで教会は再臨を正しく理解できていませんでした。だからこそ、再臨について語られている黙示録も分からなかったのです。前提となる理解が誤っていたとすれば、黙示録を上手に読み解けなかったとしても、何も不思議なことはありません。しかし、もし再臨を正しく理解するならば、黙示録も正しく理解できるようになります。ぜひ私が今言いましたように、既に再臨は起きていると理解されるのをお勧めいたします。そうすれば、黙示録をすんなりと理解できる道が開かれるようになるはずです。
まずは、有名な666の獣について書かれている13章か、気になっている箇所から読み始められるのがよいのではないかと思います。1章1節目から読むのは、やや骨が折れるという方もおられるかもしれません。とはいっても、御言葉を真に愛し求める方であれば、何の苦にもならないことでしょう。聖徒たちにとって「蜜よりも甘い」(詩篇119:103)御言葉に関する註解を読むことが、どうして苦痛になるのでしょうか。
また、この註解書は、信仰の祈りが積み重ねられて書き記された註解書です。確かに主は、黙示録を正しく理解させていただきたいという私の信仰による祈りを、聞いて下さったのです。この註解書こそ、神が恵みにより私の祈りを聞いて下さったことの証拠です。ヤコブ1:5では、信じて願うのであれば、必ず知恵が与えられると言われています。『あなたがたの中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は、だれにでも惜しげなく、とがめることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし、少しも疑わずに、信じて願いなさい。』ですから、この註解書の内容は、読むに値するものとなっていると私は信じます。もしそのように信じないとすれば、私はほとんど祈っていないか、もしくは確信を持って祈っていないことになるからです。しかし、私は黙示録を十全に、そして正しく理解できるようにと神に大いに祈りました。それゆえ、私はこの註解書の内容を、祈りが聞かれたと確信しているゆえ、読むに値すると皆様に対して言わないわけにはいかないのです。
教会は、これまで再臨について正しく理解してこなかったと認めなければいけません。確かに、御言葉は、再臨が既に起きたと私たちに教えているのです。『まことに、あなたがたに告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が御国とともに来るのを見るまでは、決して死を味わわない人々がいます。』(マタイ16:28)これは、目の前でキリストを見ていた紀元1世紀のユダヤ人が再臨をしっかりと見たということでなくて何でしょうか。『私たちは主のみことばのとおりに言いますが、主が再び来られるときまで生き残っている私たちが、…』(Ⅰテサロニケ4:15)これは、パウロと一緒にいた紀元1世紀のテサロニケ人が生きている間にキリストの再臨が起こるということでなくて何でしょうか。『まことに、あなたがたに告げます。これらのことが全部起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。』(マタイ24:34)これは、再臨について語られているマタイ24章の預言が、その『時代』すなわち一世代(γενεα:ゲネアー=30~40年)の間に実現するということでなくて何でしょうか。『わたしは、すぐに来る。』(黙示録3:11、22:7、12、20)これは、キリストが本当にすぐに、つまり紀元1世紀の聖徒たちが再臨を待ち望んでいる間に天から来られるということでなくて何でしょうか。御言葉が既に再臨は実現済みだと教えているのに、そのように理解しないのは恐ろしいことです。というのも、御言葉に聞き従わないからこそ、人間は神からの罰を受けることになるからです。実際、私がこのように聖書から説明したにもかかわらず、その説明を最終的には受け入れなかったある教会は、裁かれて悲惨になってしまいました。その教会の牧師は、一旦は私の言ったことを認めたのですが(認めざるを得なかったのです)、周りの教会の目を恐れ、また今までに教会が持ってきた再臨の理解から離れることを心配したので、結局は私の言ったことを強情に拒絶したのでした。カトリックも宗教改革者たちが論じた聖書の真理を拒絶しましたから、もう今では完全に裁かれた状態として歩み続けています。今のカトリックは既にユダヤ人の陰謀家に攻略されており、現在の教皇フランシスコも彼らの息のかかった人物です。御言葉で教えられていることを受け入れない教会が裁かれたとしても不思議ではありません。教会とは、御言葉に聞き従うべき存在だからです。イエス・キリストは、御言葉とその正しい見解を拒絶する教会を嫌われます。ですから、ぜひ御言葉で言われている再臨のことを、しっかりと考察し真に受け入れられるようにされるのをお勧めいたします。
御教会に主の恵みが豊かにありますように。
恵み深い神であるイエス・キリストの名において
黙示録註解(『再臨論』)
http://sbkcc.net/sairin.html
稲野晴也
-------------@yahoo.co.jp
静岡県静岡市駿河区小鹿@@@-@ @@@@@@@@
【追伸】
2021年6月11日にイルミナティが横浜で核テロ攻撃を行なう可能性があります。イルミナティは2001年9月11日、2011年3月11日と10年ごとに巨大な破壊を実施していますから、3:11から10年後の2021年に再び前の2回と同規模の破壊が実施される可能性は非常に高いと言えます。9:11と3:11がイルミナティカードの中で事前に予告されていたように、今度の6:11もこのカードの中で予告されています。9:11も3:11も起きた時刻は「46分」ですが、46とはイルミナティが好んで使用する数字ですから、6:11も46分に起こそうとしていることでしょう。これは本当に重大なことです。事件が起きてからでは取り返しがつかなくなってしまいます。悲惨なことが起きないようにお祈りください。
◇この通知と勧めは1318のプロテスタント教会に伝えられた。
[プロテスタントの牧師先生に対する通知と勧め(2)]
教会で教えておられる牧師先生の皆様へ
静岡聖書神の国キリスト教会で教師をしています稲野晴也と申します。先日メールを送らせていただきましたが、再臨のことについて幾らかでも考察して下さっておられるでしょうか。
先日のメールにも書きました再臨の解釈についてですが、未だに私の述べた再臨の解釈は真正面から反論されていません。これは、私の述べた解釈が聖書的であり、真に正しい解釈だからです。もしその解釈が誤っていたとすれば、とっくの昔に私は幾度となく反論されていたでしょう。ちょうど、イザヤがイスラエルを断罪したように、キリストがパリサイ人を責められたように、アウグスティヌスがユリアヌスを徹底的に打ち砕いたように、ルターが教皇主義者たちを非難したように、カルヴァンがセルベトゥスを論駁したように、です。しかし私の場合はどうでしょうか。イザヤやキリストやアウグスティヌスやルターやカルヴァンのように指摘したり勧告したり非難したりしているのは、私のほうなのです。私が聖書から論じると、どの方も真正面から応対することができず、黙るか、質問の内容には答えず自己の見解をただ表明するか、中傷するか、のどれかの応対をするしかないのです。真正面から応対する方は、私の述べたことが否定できないものですから、私の述べたことを認めて受け入れますが、そのような方は多くはいません。それで、あまりにも重要なことなので再びお伝えしますが、先日のメールにも書きましたように再臨は既に起きたと聖書は教えています。煩わしいと思われずに、再びキリストの次の御言葉をご覧になって下さい。『それから、イエスは弟子たちに言われた。…まことに、あなたがたに告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が御国とともに来るのを見るまでは、決して死を味わわない人々がいます。』(マタイ16:24、28)この聖句の中で、明らかにキリストは御自身の前に立っている紀元1世紀のユダヤ人たちが死ぬ前までに再臨が起こると教えておられます。痴呆か精神障害者でなければ、私が今述べた解釈がどういった意味なのか理解できるはずです。ほとんど全てのプロテスタント教会は、「私たちは聖書にこそ立つ。」と言うものです。これは教会の正しい姿勢です。それならば、どうして多くの方々が、私の述べたこの解釈に「アーメン。」と言えないのでしょうか。もし「アーメン。」と言って私の述べた解釈を受け入れてしまうと、あの指導者たちが恐れたように会堂から追放されてしまうと予測するからではないでしょうか(ヨハネ12:42~43)。確かに、私が述べた解釈を受け入れたならば、恐らく今の教派に居続けることは難しいでしょう。テレンティウスも言うように、「真実は憎しみを生む」(アンドロス島の女 68)からです。問題となっているのは神の神聖な御言葉です。しかも私がお話ししている対象は、一般信徒ではなく、神の言葉を取り次ぐようにと召されている先生方です。先生方とは、言わば「御言葉の専門家」です。そのような方々が、私の述べた真剣な聖書解釈を聞き流してよいはずはありません。もし私が今述べた解釈に「アーメン。」と言えないようであれば、他に正しいと思われる解釈を示していただきたい。しかし、そのようなことは恐らく出来ないと思われます。というのも、私はもう10年もマタイ16:28の聖句についてずっと考え続けていますが他に正しいと思われる解釈はまったく思いつきませんし、他の方々に聞いてみても誰も何も答えてくれない、というより答えられないからです。アウグスティヌスとパラヌスの解釈だけが私が述べた解釈以外では検討に値する唯一の解釈ですが、これは先日もお話ししましたように誤りです。そうであれば、やはりマタイ16:28の聖句は、私が述べたように解釈すべきだということになります。であれば、どうして私の述べた解釈に対して「アーメン。」と言えないのでしょうか。更に、再びパウロの語った言葉にも着目していただきたいと思います。パウロは明らかにマタイ16:28の聖句に基づいて、次のように言っています。『私たちは主のみことばのとおりに言いますが、主が再び来られるときまで生き残っている私たちが、…』(Ⅰテサロニケ4章15節) ここでパウロは自分と一緒にいた紀元1世紀のテサロニケ人たちが『生き残っている』間に『主が再び来られる』と言っています。カルヴァンも、パウロは自分を再臨の起こる日まで生き残っている者のうちに数えている、と註解書の中で述べています。つまり、このパウロによる聖句は、テサロニケ人たちが生きている紀元1世紀の時に再臨が起こると教えていることになります。これはキリストによるマタイ16:28の聖句で言われているのと同じことです。このⅠテサロニケ4:15の箇所も、マタイ16:28の箇所と同様、私が今述べた解釈以外の解釈をすることはまったく出来ません。ほとんど全ての先生方は、「キリストの再臨はこれから起こるであろう。」と言われるでしょう。つまり、再臨は未だに起きてはいないと。私は確かなことを言いますが、このように理解するのは、キリストとパウロの言葉に反しています。何故なら、キリストとパウロは、どちらも再臨は紀元1世紀の時に生きている人々が生きている間に起こると言っているからです。ですから、再臨がまだ起きていないと言うことは、キリストとパウロを偽証者に仕立てることになってしまいます。何故なら、そのように言うことは、キリストとパウロに対して「あなたがたが言っていることは違っている。あなたがたは再臨が自分と一緒にいた当時の人たちが生きている間に起こると言ったが(マタイ16:28、Ⅰテサロニケ4:15)、そのようなことがどうしてあるのだろうか。」と言っているのも同然だからです。今私が述べた通りに再臨が紀元1世紀に起きたと理解しますと、どうして使徒たちが繰り返し再臨はすぐに起こると言ったのか分かるようになります。すなわち、本当に間もなく再臨が起こることになっていたからこそ、再臨はすぐにも起こると使徒たちは繰り返して言ったわけです。もし2千年経過しても再臨がまだ起きていないというのが本当だとすれば、使徒たちは再臨がすぐに起こるなどとは言っていなかったはずです。何故なら、2千年という期間は明らかに「すぐに」と言えるような期間ではないからです。またマタイ24章の箇所についても、よく考えていただきたいと思います。この有名な箇所は、明らかに第二神殿の崩壊が起こるユダヤ戦争(66-70)について預言された箇所です。マタイ24章がユダヤ戦争について預言された箇所だというのは私だけでなくジョナサン・エドワーズやオリゲネスもそう理解していましたし、私と議論した学者肌の牧師も「これは確かにユダヤ戦争のことを言っている箇所だ。」と言いました。これはマタイ24章の並行箇所であるルカ21章やマルコ13章を読めば、更に明らかとなるでしょう。例えばルカ21:20で『しかし、エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、そのときには、その滅亡が近づいたことを悟りなさい。』と言われているのは、ユダヤ戦争においてティトゥス率いるローマ軍がエルサレムを包囲することでなくて何でしょうか。これがユダヤ戦争のことだと分からない方がいれば、その方は明らかに勉強不足です。確かにキリストはマタイ24:34でマタイ24章に書かれている出来事は『この時代』すなわち1世代(γενεαゲネアー=1世代=30~40年=ジェネレーション※KJV)の間に起こると言われたのですから、マタイ24章はユダヤ戦争について書かれた箇所だと結論せねばなりません。実際、キリストが語られてから1世代(ゲネアー)が経過する前にユダヤ戦争が起きています。それで、このマタイ24章がユダヤ戦争のことを書いているとすれば、マタイ24章の中では再臨のことについても書かれているのですから、ユダヤ戦争が1世代の間に起きたのと同様、再臨も1世代の間に起きたことになります。実際、マタイ24:1~3の箇所を読むと、弟子たちが目を見張っていた神殿が崩壊する時期に再臨が起こるということが分かります。更に、Ⅱテサロニケ2章の箇所についても、よく考えていただきたいと思います。そこに出てくる有名な「不法の人」は、改革派の著名な神学者であるB・B・ウォーフィールドがそう考えていたようにパウロと同時代の人であって、それは暴君ネロのことです。この不法の人はパウロが生きていた時、既に引き止める者に引き止められていたのですから(Ⅱテサロニケ2:6~7)、明らかに紀元1世紀に存命していた人物であり、この人物が2千年経過してもまだ現われていないと考えることはまったく出来ません。それで、この不法の人はパウロの時代に引き止められている生きていた人物だったのですから、再臨もパウロの生きていた紀元1世紀に起きたことになります。何故なら、パウロが、この不法の人はキリストの再臨により滅ぼされるであろうと明白に言っているからです(Ⅱテサロニケ2:8)。この見解は、再臨が紀元1世紀に起こると教えているマタイ16:28とⅠテサロニケ4:15で言われていることと、完全に調和しています。というわけで、ここまで色々と書きましたが、このメールでは、もうこれで十分でしょう。更に詳しいことは下記のリンク先にある「再臨論」をお読みになって下さい。多くの先生方が、真に聖書的な再臨理解に導かれるように願っています。
恵み深い神が、私たち一人一人に、聖書をますます深く理解させて下さるように祈ります。
聖なる贖い主イエス・キリストの御名において
黙示録註解(『再臨論』)
http://sbkcc.net/sairin.html
稲野晴也
-------------@yahoo.co.jp
静岡県静岡市駿河区小鹿@@@-@ @@@@@@@@
【追伸】
これも大変重要なことですが、イルミナティは日本を駄目にしようとしています。イルミナティは、イルミナティカードの中で予告しているように、これから2つの大事件を引き起こすつもりです。すなわち、横浜における大規模な核攻撃と、東京における複合災害です。リチャードコシミズやベンジャミンフルフォードといった工作員たちがやたらと「日本の未来は明るい」とか「日本こそ世界のリーダーになれる」などと日本について希望を持たせることを言うのは、彼らが日本の将来についての悲惨な計画を知っているからであり、わざと真逆のことを言って大衆を惑わしているのです。第二次世界大戦の時にはチャーチルさえも日本軍の力と勇敢さに震え上がったことからも分かるように、日本人という民族は本気になったり覚醒したりすると厄介な存在でして、だからこそ世界支配を目論む陰謀家たちは何とかして日本と日本人を無力で無害な存在にさせたいわけです。そのためにこそ、大規模な破壊的事件により我々の国を痛めて衰弱させると。いずれにせよ、日本人が力を持って立ち上がるためには、まず王(Ⅰペテロ2:9)である教会勢力が率先して聖書に基づく改進的な姿勢を持たねばならないでしょう。真理の柱また土台(Ⅰテモテ3:15)であり世の光・地の塩(マタイ5:13~14)であり王(Ⅰペテロ2:9)である教会勢力が弱々しければ、どうして世の中の人々が力を持って立ち上がることができましょうか。ひとまず、これから横浜と東京において悲惨な出来事が起きないようお祈りください。イルミナティカード(82年に発売)で予告されていた9・11と3・11のカードは、既に実現されております。このイルミナティカードについてご存じない方は、ネット上でいくらでも情報が出ていますから、ぜひお調べになってください。未信者の方々の多くは、このカードで予告されていたことと実際に実現された出来事との一致具合を見て、無理もないことかもしれませんが、怖がったり驚いたり興奮したりしています。
◇この通知と勧めは766のプロテスタント教会に伝えられた。
[子供の教育に携わっている兄弟姉妹への伝達と勧め]
子供たちの教育に携わっておられる兄弟姉妹の皆様へ
こんにちは。静岡聖書神の国キリスト教会の稲野晴也と申します。再臨の真に聖書的な理解を兄弟姉妹の皆様に伝えるべく、このようにメールをさせていただきました。私の述べる再臨の見解は真に聖書的であり、その見解は既に多くの牧師先生に伝えられましたが、これまで一度も反駁されたことがありません。何故なら、その見解が聖書的であって、誰も聖書から反論することが出来ないからです。以下に書かれているのは、再臨と再臨に関わる事柄についての真に聖書的な5つの理解です。プロテスタント教徒である私たちにとって、聖書の正しい理解は、あまりにも大切なものです。是非、以下の文章をお読み下さり、再臨についての正しい理解を受け入れられるようにされるのをお勧めいたします。
【1:再臨について】
キリストの再臨は、もう既に起きています。主は、御自身の目の前に立っている紀元1世紀のユダヤ人たちに対して、次のように言われました。『まことに、あなたがたに告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が御国とともに来るのを見るまでは、決して死を味わわない人々がいます。』(マタイ16:28)つまり、これはキリストの前に立っていた紀元1世紀のユダヤ人が死ぬ前までに再臨が起こるということです。再臨が紀元1世紀に起こるというのは、パウロの言葉からも分かります。パウロは、自分と一緒にいた紀元1世紀のテサロニケ人たちが生きている間に、キリストの再臨が起こると言っています。『私たちは主のみことばのとおりに言いますが、主が再び来られるときまで生き残っている私たちが、…』(Ⅰテサロニケ4章15節)。これも、パウロと共に生きていた聖徒たちが死ぬ前までに再臨が起こるということを教えています。このキリストとパウロの言葉は、私が今言ったように解釈する以外にはありません。他の解釈をすることは、出来ないでしょう。私は10年もこのキリストとパウロの聖句について考え続けていますが、他に正しいと思える解釈は思い浮かんだことがありません。キリストの再臨が紀元1世紀に起こるからこそ、ヤコブは再臨がすぐにも起こると言ったのです。彼はこう言っています。『あなたがたも耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。』(ヤコブ5章8節)キリストが『わたしはすぐに来る。』(黙示録22章7節)と言われたのも、再臨がすぐに起こることになっていたからに他なりません。もし2千年経過しても未だに再臨が起こらないようであれば、つまり紀元1世紀には起こらなかったのであれば、ヤコブもキリストも再臨がすぐに起こるなどとは言っていなかったことでしょう。
【2:マタイ24章について】
マタイ24章は、紀元66~70年に起きた第一次ユダヤ戦争について預言された箇所です。これは、キリストがエルサレムの神殿の崩壊について語られてから(マタイ24:2)、弟子たちがその崩壊の前兆についてキリストに質問をし(マタイ24:3)、その質問についてキリストがマタイ24:4から色々とお答えになっておられるのを考えれば容易に分かることです。このマタイ24章と同じことが書かれているルカ21章の20節目では、『しかし、エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、そのときには、その滅亡が近づいたことを悟りなさい。』とキリストが言っておられます。これは、ティトス率いるローマ軍がユダヤ戦争においてエルサレムを包囲することでなくて何でしょうか。その包囲が実際に起きたことは歴史を見れば明らかです。確かにキリストはマタイ24章に書かれている出来事は、すぐにも実現されると言われました。マタイ24:34ではキリストがこう言っておられます。『まことに、あなたがたに告げます。これらのことが全部起ってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。』ここでキリストが言っておられる『時代』とは、原語ではγενεα(ゲネアー)であり、英訳聖書では「ジェネレーション」と訳されています。このゲネアーという言葉の意味は「世代」であって、それはおよそ30~40年ぐらいの期間を指す言葉です。つまり、キリストはこれから30~40年の間(ゲネアー)に、マタイ24章の出来事が起こると言われたのです。実際、キリストが紀元33年頃にマタイ24章のことを話されてから、だいたい30~40年ぐらい経つとユダヤ戦争が起きています。その時には、キリストがマタイ24:2で言われたように、エルサレムの神殿が完全に破壊されてしまっています。ですから、確かにマタイ24章はユダヤ戦争のことについて言われた箇所だということが分かります。それゆえ、マタイ24章に書かれている出来事が未だに起きていないと考えるのは間違っています。
【3:黙示録について】
黙示録は、『すぐに起こるはずの事』(黙示録1章1節)・『すぐに起こるべき事』(黙示録22章6節)が書かれている文書です。この文書は、紀元1世紀の『アジヤにある7つの教会へ』(黙示録1章4節)送られたものです。ですから、紀元1世紀の聖徒たちにとって『すぐに起こる』ことが黙示録の中では預言されているということが分かります。つまり、黙示録に書かれている預言は、既に実現されているということです。具体的に見てみるとどうでしょうか。まず黙示録13章に出てくる獣は「666」の数字を持っているとヨハネは言っています。『ここに知恵がある。思慮ある者はその獣の数字を数えなさい。その数字は人間をさしているからである。その数字は666である。』(黙示録13章18節)この666の数字を持っている獣とは、あの暴君ネロのことです。すなわち、「ネロ・カエサル」というギリシャ語をヘブル語に訳し、その訳されたヘブル語を数値化して足し合わせると「666」となります。このネロは紀元68年6月9日に死にました。それは、ヨハネから黙示録を届けられた紀元1世紀の人たちにとって正に『すぐに』起こる出来事でした。ですから、黙示録13章で書かれている出来事は『すぐに起こる』ことだったということが分かります。また黙示録18章ではエルサレムが焼き尽くされることについて書かれています。このエルサレム滅亡のことについては、主もマタイ23:33~38の箇所で言っておられます。エルサレムが焼き尽くされたのは、紀元70年9月2日でした。ですから、黙示録18章も『すぐに起こるべき事』が書かれているということが分かります。また黙示録20:9では『愛された都』が取り囲まれる出来事について預言されています。これはローマ軍がユダヤの都エルサレムを取り囲んだ出来事を言っています。それは紀元66~70年のユダヤ戦争の時に起きたことです。ですから黙示録20章に書かれている出来事も既に実現されているということが分かります。そういうわけですから、黙示録に書かれている預言が、未だに成就していないと考えるのは間違っています。神が御使いを通してヨハネに示された幻は、どれも全て『すぐに起こるべき事』(黙示録22章6節)だったのですから。
【4:不法の人について】
Ⅱテサロニケ2章で言われている有名なあの『不法の人』とは、使徒パウロと同時代の人物でした。何故なら、この不法の人は、パウロが生きている時に『引き止める者』(Ⅱテサロニケ2章7節)により引き止められていたからです。パウロは『不法の秘密はすでに働いています。』(Ⅱテサロニケ2章7節)と言っています。つまり、不法の人の秘密はパウロがテサロニケ人に手紙を書いていた時から既に働いていたということです。ですから、この不法の人が2千年経過した今でも未だに現われていないと考えることは絶対に出来ません。いったい、パウロの時に『引き止める者』(Ⅱテサロニケ2章7節)により引き止められていた人物が2千年もの間ずっと引き止められ生き続けていたなどということが、どうしてあるのでしょうか。それでは、この「不法の人」とは誰でしょうか。これは暴君ネロのことです。この「不法の人」は『神の宮の中に座を設け』(Ⅱテサロニケ2章4節)ますから、キリストがマタイ24:15で言われた『荒らす憎むべき者』と一緒の人物だということが分かります。何故なら、キリストの言われた荒らす憎むべき者も、『聖なる所に立つ』(マタイ24章15節)と言われているからです。この『荒らす憎むべき者』はダニエル書12:11によれば『1290日』の期間が定められていますから、黙示録13章の獣(666)と一緒の人物であることが分かります。何故なら、黙示録13章の獣にも『42か月間』(黙示録13章5節)の期間が定めらているからです。『1290日』とは約『42か月間』です。この黙示録13章の獣は先にも述べましたが、666ですから暴君ネロのことです。ですから、黙示録13章の獣であり荒らす憎むべき者であるⅡテサロニケ2章に出てくる『不法の人』とはネロのことだったことが分かります。パウロが不法の人は『引き止める者』により引き止められていると言ったのは、つまりパウロがテサロニケ人に手紙を書いていた時の皇帝であるクラウディウスが帝位に就いているので、まだネロは暴君として世に現われることが出来ない、ということを言っているのです。何故なら、クラウディウス帝の『取り除かれる時』すなわち死ぬ時が来ない限り、ネロが皇帝になるのは引き止められている状態にあるからです。このクラウディウス帝が死により取り除かれるからこそ、新しい皇帝がローマに必要となりますから、ネロが皇帝として出てくることが出来るのです。この引き止める者に引き止められている不法の人のことについては、私が今言ったように考える以外に正しい理解をすることは出来ません。
【5:世の終わりについて】
聖書で言われている「世の終わり」とは、ユダヤ世界が終わりを迎えることです。これはマタイ24章を丹念に読み解くならば、分かることです。主は、マタイ24:2でエルサレム神殿が徹底的に破壊され尽くしてしまうことについて預言しておられます。『まことに、あなたがたに告げます。ここでは、石がくずされずに、積まれたまま残ることは決してありません。』この神殿崩壊について弟子たちは質問していますが、その質問を見ると、神殿崩壊の起こる時期が「世の終わり」(また再臨の起こる時)であると言われていることが分かります。弟子たちはマタイ24:3でキリストに対してこう言っています。『お話しください。いつ、そのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりには、どんな前兆があるのでしょう。』ご覧ください。ここでは、明らかに弟子たちが神殿崩壊の起こる時期に『世の終わり』(および再臨)が起こると考えていたことが示されています。後の続く箇所を見てみると、その弟子の理解をキリストはまったく否定したり批判したりしておられません。つまり、この弟子たちの持っていた『世の終わり』に関する理解は正しかったということです。それで、キリストが言われたエルサレム神殿の崩壊は、紀元70年9月に起こっています。誰もが認めるように、この時、ユダヤは滅ぼされてしまいました。ですから、『世の終わり』とはユダヤ世界のことについて言っているということが分かります。だからこそ、ペテロは『万物の終わりが近づきました。』(Ⅰペテロ4章7節)と言ったのです。ユダヤにおける万物の終わりが紀元70年に実現するのですから、ペテロがこのように終わりが近いと言ったのは自然なことでした。またパウロが『この私たちに世の終わりが来ています。』(Ⅰコリント10章11節)と言ったのも同じことです。何故なら、パウロはユダヤ世界の終わりがもう間もなく訪れるからというので、こう言ったからです。聖書では他の箇所でも『世の終わり』について語られている部分が多く見られますが、それらは紀元70年にユダヤ世界の終わりが訪れることについて言っています。それゆえ、この『世の終わり』を地球全土の終わりとして捉えたり、またその終わりが未だに訪れていないなどと考えるのは、完全に間違っています。今まで教会はこの『世の終わり』という言葉を、ただ感覚的・イメージ的に捉えていただけでした。しかし、聖書を研究すると、これはユダヤ世界について言われた言葉だということが分かるようになるのです。
ここまで5つの項目について書かれましたが、更に詳しいことは以下のリンク先にある『再臨論』という作品を御覧ください。これは、再臨について聖書から徹底的に考究することを目的とした作品です。ここまで深く再臨について掘り下げられた作品は、恐らく今までに無かったのではないかと思います。兄弟姉妹の皆様が、聖書について更に深い理解を持てるようになれば幸いです。
■『再臨論』(現在第3部まで制作完了)
http://sbkcc.net/sairin.html
神が、私たち一人一人に聖書を更に豊かに理解させて下さるように祈ります。
神の御子イエス・キリストの御名において
稲野晴也
-------------@yahoo.co.jp
静岡県静岡市駿河区小鹿@@@-@ @@@@@@@@
◇この伝達と勧めは54の教育機関に伝えられた。
[プロテスタントの牧師先生に対する通知と勧め(3)]
教会で教えておられる牧師の皆様へ
先日、再臨のことでメールをいたしました静岡聖書神の国キリスト教会の稲野晴也と申します。
非常に重要な再臨の話ですが、再臨の正しい理解について日本国内にある1300の教会にメールで伝えましたところ、未だに異論を唱える人が現われていません。これは私が前に述べました再臨の解釈が、真に正しいことを証明しているのではないかと思います。何故なら、私が述べた解釈は、正にその通りだと言わざるを得ないからです。すなわち、マタイ16:28とⅠテサロニケ4:15の御言葉は、「再臨が紀元1世紀の人たちの生きている間に起こると示している」という解釈です。このように解釈する以外にどのように解釈するのでしょうか。私がこのように言うと、「確かにあなたの言う通りだ。」と言う牧師も今までおりました。確かにマタイ16:28とⅠテサロニケ4:15の御言葉は、私が言ったように解釈するしかありません。だからこそ、1300もの教会にメールがされたのに、誰一人として「それは違う」と言う人が出ないのです。といいますのも、もし私の解釈に異を唱えるならば、それはキリストとパウロに文句をつけることになるからです。例えば、誰かが私に対して「再臨が紀元1世紀の人たちの生きている間に起こったなどとは、一体なにを言っているのか。」などと言ったとしましょう。このように言うと、私にではなく、キリストに文句を言っていることになります。何故なら、主は御自身の前に立っている紀元1世紀のユダヤ人に対して、こう言われたからです。「まことに、あなたがたに告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が御国とともに来るのを見るまでは、決して死を味わわない人々がいます。」(マタイ16:28)
私が述べた解釈を認めざるを得ないにもかかわらず、どの牧師先生も、私に対して沈黙を保ったままでおられます。どうしてそうなのでしょうか。それは、キリストの再臨はまだ起きていないのではないかと感じているからです。自分の心の中では再臨はまだ起きていないと感じているのに、マタイ16:28とⅠテサロニケ4:15の御言葉では紀元1世紀の時に再臨が起きたと示されている。また他の牧師たちも既に再臨は起きたなどとは言っていない。これまでキリスト教では、そんなことを言う人はいなかった。誰も彼も再臨がこれから起こると考え、言ってきた。ここにおいて混乱が起こるのです。その混乱ゆえに、訳が分からなくなり沈黙するに至る、ということです。
ですが、このように誰もあえて何も私に言ってこないのは、無難な判断ではないかと思えます。何故なら、どの人も事柄をよく弁えていないからです。分からないなら、分からないのですから、僭越にも堂々と何かを語らない、というのは一つの思慮です。この再臨の件について、あえて無理に何かを言えば、聖書に反したことを言ってしまうことにもなりかねませんから。
多くの牧師先生におかれましては、この再臨の問題が分からないと思われるかもしれません。しかし解決はそう難しいことではありません。まず、私たちは、キリストの再臨が既に紀元1世紀の時において起こったと考えねばなりません。それはマタイ16:28とⅠテサロニケ4:15の御言葉を考えればすぐにも分かります。再臨について預言されたマタイ24章も、キリストが言われた通り「ゲネア」(マタイ24:34)すなわち1世代の間に実現することが書かれている章です。新約聖書において再臨がすぐに起こると言われているのも、やはり再臨が紀元1世紀の時に起こることになっていたからです。再臨のキリストにより殺されることになっている「不法の人」も(Ⅱテサロニケ2:8)、パウロがⅡテサロニケ2章で明白に言っているように、パウロの存命時に既にこの世界に存在していた人物でした(これは改革派の有名な神学者であるB・B・ウォーフィールドもそう考えていました)。この他にも、新約聖書の多くの箇所で、再臨が紀元1世紀に起こるということが示されています。
大きな問題となっているのは、まだ再臨が起きていないと感じられるということです。私たちは、再臨が今まで言われてきたような規模を持った出来事ではなかったということを、聖書から知らねばなりません。つまり、今まで再臨の内容については、間違って理解されてきたということです。例えば、キリストは再臨の出来事が「地上のあらゆる種族」(マタイ24:30)に見られると言っておられます。ですから、今まで教会は、再臨が地球全土に住む文字通りの意味での万民に見られると考えてきました。しかし、ゼカリヤ書12:9~14を見ると、「地上のあらゆる種族」とは「ダビデの家とエルサレムの住民」(ゼカリヤ12:10)、すなわちユダヤ人における「あらゆる種族」であったことが分かります。このゼカリヤ書の箇所では、間違いなく再臨のことが言われています。これだけでも、再臨がエルサレムにおいて起こった地域的な規模の出来事だったと理解するには十分です。またキリストが再臨される際には、「世の終わり」が来ると聖書は教えています。ですから、今まで教会は、「世の終わり」が地球全土の終わりのことを言っていると考えてきました。しかしマタイ24:1~3を見ると、「世の終わり」とは神殿崩壊に伴って実現するユダヤ王国の終焉であったということが分かります。それは紀元70年9月に起こりました。だからこそ、新約聖書では世の終わりがすぐに来ると、切迫した面持ちで言われているのです。世界や地上に破滅が訪れると言われていながら、実はユダヤにおける世界や地上のことについて言っている箇所は、他にもゼパニヤ書1:2~6があります。ここでは「わたしは必ず地の面から、すべてのものを取り除く。」(1:2)と言われていますが、これは「ユダヤにおける地の面」のことを言っています。聖書で「世界」とか「全て」とか言われていながら、実は限定された範囲内における「世界」また「全て」について語られているというのは、珍しいことではありません。聖書を読み慣れた牧師の方であれば、このぐらいのことは知っておられるでしょう。また、再臨が起こると人間の全てが主の御前において裁きを受ける、と聖書は教えています。ですから、今まで教会はキリストの審判に出頭するのが文字通りの意味における全人類だと考えてきました。しかしながら、聖書を調べてみますと、審判のために出頭させられるのは「御国」すなわち教会に属している者たちであって(マタイ13:41~42)、審判の場にいるのは教会の中にいる「羊と山羊」(マタイ25:32~33)すなわちクリスチャンと偽クリスチャンだけであり、審判のために空中へと引き上げられない人もいると教えられていることが分かります(マタイ24:40~41)。もし今まで教会が考えてきたように、審判の場にあらゆる人類が出頭させられるとすれば、キリストはマタイ24:40~41でこのように言っておられたでしょう。「そのとき、畑にふたりいると、ふたりとも取られます。残される人はいません。」と。ですから、再臨に伴って起こる審判の規模も、今まで教会は誤解してきたということになります。このように再臨の規模についての理解を修正すれば、マタイ16:28やⅠテサロニケ4:15の御言葉で再臨が紀元1世紀において起こると言われているのを、理解できなくなるということはなくなります。つまり、聖句で既に再臨が起きたと教えられているのにもかかわらず、私たちの心ではまだ再臨が起きていないと感じられるのは、私たちが再臨の規模を誤解しているからに他なりません。再臨が世界的な規模で起こると考えているからこそ、もう既に再臨が起きたと言われているのを聞いても、よく理解できないのです。私は言いますが、再臨の規模について理解を修正しない限り、マタイ16:28でキリストが言っておられることに対して「アーメン。主よ。正にあなたが言われたことは本当です。」と言うことは出来ないでしょう。ですから、先生方は私の言ったことを受け入れ、再臨認識を聖句に基づいて修正せねばなりません。もしそのようにすれば、再臨は紀元1世紀に起こるという聖書の明白な教えを、すんなりと受け入れられるようになるでしょう。
もう一度言いますが、私が述べたことについて反論する人が現われないのは、私が述べたことが正しいからです。もし私が間違ったことを言っていたとすれば、これまで多くの批判が私にされていたはずです。何故なら、御言葉を専門とする牧師たちが、誤謬を攻撃しないということは、今までの歴史を見ても分かるように、有りえないことだからです。しかし、私に対しては「聖霊に導かれている。」と言う人もいるぐらいです。これは私が正しいことを言っている一つの証拠と言えるのではないでしょうか。私は、再臨の真理を悟るべく、聖書を研究し続けております。これを読んでおられる牧師先生におかれましては、ぜひ再臨について正しい解釈を持っていただきたいと思います。これまで教会は再臨について、ただ伝統的な見解に安住するだけで、あまりにも研究していませんでした。研究していないのですから、今まで教会が再臨の神学において間違ってきたのは当然のことです。今まで教会は再臨についてこのようでしたが、これから、ぜひ多くの聖徒たちが、再臨の真理を悟れるようになるのを願っています。
主の恵みと平安が豊かにありますように。
静岡聖書神の国キリスト教会 稲野晴也
メール -------------@yahoo.co.jp
▼「黙示録註解」をぜひ御覧ください。
http://sbkcc.net/sairin.html
【追伸1】
再臨が起きた歴史的な証拠ですが、ヨセフスとタキトゥスが、ユダヤ戦争の時に、空中に戦車部隊が見られたと記録しています。ヨセフスはこう書いています。「またその後、祭が終わって何日もたたないアルテミシオスの月の第21日にも、信じがたい、ダイモニオンか何かが起こした現象が認められた。実際わたしがこれから語ろうとする事柄は、それを見た者が語ったり、その後で凶兆どおりの不幸が起こらなかったら、面妖奇怪な作り話として一笑に付されるのではないかと思われる。日没前に、国中の各地で、戦車が天空に現れ、武装した密集隊形の兵士たちが雲の中を疾走し、町々を包囲していたのである。」(『ユダヤ戦記3』ⅤⅠ v3:288~300 p070~072:ちくま学芸文庫)タキトゥスもこう書いています。「不思議な現象が起っていた。迷信にとらわれ、ローマの宗教儀式に敵意を抱くユダエア人は、犠牲や祈願でこれらの現象の汚れを祓い清めることを是認しなかった。天空で戦列が衝突し、武器が火花を散らすのが見られた。」(『同時代史』第5巻 13 p276:筑摩書房)これらの記述はマタイ24章でキリストの再臨は神殿崩壊に至るユダヤ戦争の時に起こると教えているのとまったく一致しています(※マタイ24章はジョナサン・エドワーズもそう理解していたように、ユダヤ戦争の時のことを預言した箇所です。)。また、再臨されたキリストと聖徒たちは、戦車また馬に乗って降りて来ると聖書で教えられているのとも一致しています(イザヤ66:15、黙示録6:2、19:11~16)。この上空に現われた戦列は、天から降りて来たキリストとその聖徒たちではないかと思われます。それは聖書の教えと一致していますし、そう考えるしかないと感じられるからです。また、ヨセフスとタキトゥスが、わざわざこのような空想話をでっち上げたとも思えません。というのも、あえてこのような妄想を作り上げて書き記すのは、歴史家としての名声と信用にかかわるリスクが大きすぎますし、何よりも馬鹿げているとしか言いようがないからです。ヨセフスならばともかくタキトゥスともあろう卓越した高名な歴史家が、そんな愚行をするなどとは考えにくいことです。
【追伸2】
キリストは既に再臨されたと言われても、まだマタイ24章の預言が成就したとは感じられないと思われるかもしれません。しかし、そのマタイ24章の預言は既に成就されています。これは明らかです。では、どうして既にマタイ24章は成就していると言えるのでしょうか。まず、マタイ24章とは、マタイ24:34でも言われているように「この時代」(ゲネア/γενεα)が過ぎ去る前に起こる出来事が預言された箇所です。このゲネアという言葉は、新約聖書の中で15回使用されていますが、どの箇所でも「今のその時代」という意味で使われています(マタイ12:39、45、16:4、17:17、24:34、マルコ8:12、38、9:19、13:30、ルカ9:41、11:29、30、21:32、使徒行伝13:36、ヘブル3:10)。このゲネアという言葉の言語的な意味は「世代」であって、それはおよそ30~40年ぐらいの期間を意味しています(英訳聖書ではどれも「ジェネレーション」と訳されています)。アウグスティヌスも、この言葉が非常に短い期間を意味していると教えています。「「代」をギリシア人はゲネアと言っている。これは一番短く考えると15年で終わるとされ、それは人が子孫を残すことのできる歳である。」(『アウグスティヌス著作集20/Ⅰ 詩篇註解(5)』詩篇104篇 p199:教文館)実際、キリストがマタイ24章の預言を語られてから1世代ぐらいが経つ頃になると、「荒らす憎むべき者」(マタイ24:15)であるネロが現われて聖徒たちを蹂躙・虐殺し、エルサレム神殿は紀元70年に文字通り完全に滅ぼされてしまいました(マタイ24:1~2)。キリストがマタイ24章の預言を語られたのが紀元30年だとしましょう。それからユダヤ戦争が起きたのは36年後、神殿が滅ぼされたのは40年後です。ですから正に「ゲネア」(=1世代)の間にマタイ24章の預言が成就したことになります。また、マタイ24章の並行箇所であるルカ21章の20節目を見るならば、ますますマタイ24章は紀元1世紀の出来事を預言しているということが分かります。そこでキリストはこう言われました。「しかし、エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、そのときには、その滅亡が近づいたことを悟りなさい。」これは、ティトゥス率いるローマ軍がユダヤの都エルサレムを包囲し攻撃するあの出来事でなくて何でしょうか。これは確かに「この時代」(=30~40年)の間に起きたことです。誰がこれを疑うのでしょうか。また、キリストはユダヤに悲惨が近づいてきたならば、その時そこにいる人は山に逃げるようにと命じられました(マタイ24:16)。歴史が教えている通り、ユダヤにいた紀元1世紀の人たちは、ユダヤ戦争の時期にキリストの御言葉に従ってペラという山へと逃げています。またキリストは「にせ預言者たち」(マタイ24:24)が現われて人々を惑わそうとすると預言されましたが、これも既に起きています。実際、ヨセフスはユダヤ戦争の時期に多くの偽預言者たちが出現したことについて、次のように記録しています。「ぺてん師やいかさま師どもが、神の霊感を受けたと称して大きな変革をつくりだそうとして、人びとを説き伏せ、ダイモンに憑かれたかのようにさせて、荒れ野の中に導き出した。神がそこで彼らに解放のしるしを示してくれる、というのである。」(『ユダヤ戦記Ⅰ』Ⅱ xiii4:259 p314:ちくま学芸文庫)「エジプト人の偽預言者は、これよりも大きな一撃でユダヤ人たちに悪事を働いた。このいかさま師はユダヤの土地に現われると、自分を預言者だと信じ込ませ、騙された約3万もの者たちを集めると、彼らを荒れ野からオリーブ山と呼ばれる所まで引きまわし、そこからエルサレムへ押し入る構えを見せた。彼は、ローマの守備兵たちを制圧した後、自分と一緒に踏み込む者たちを警護の者として使い、暴君として市民を支配するつもりだった。」(同5:261~262 p314)「彼らユダヤ人たちの滅びの原因であるが、それは彼らがひとりの偽預言者にたぶらかされたためだった。その日偽預言者は、都の中にいる者たちに向かって、神はユダヤ人たちが神殿に登り、救いのしるしを受けるように命令されたと告げた。実際そのころ、多くの偽預言者が暴君たちによって雇われていた。この偽預言者たちは神の助けがあるからそれを待つようにと告げて市民をたぶらかしていた。その目的は投降する者をひとりでも少なくし、恐怖や不安の虜になっている者たちの肩を希望で叩いてやることにあった。」(「ユダヤ戦記」第6巻/v2:285~286)また再臨が起こる時期には、様々な異常現象が起こると聖書は教えています。セネカやタキトゥスの書を読めば分かる通り、確かにキリストが再臨された紀元60~70年の時期には、不思議なぐらい多くの異常現象が各地で生じました。セネカは、空から武器が降って来たとか、炎の竜巻が突如として平野に巻き起こった、などと書いています。タキトゥスもこの時期には、異常な現象が多く起きていたと書いています。例えば次のようにタキトゥスは言っています。「そのあいだにも奇怪な現象がひんぱんに起っていた。ある女は蛇を生む。別な女は夫の腕に抱かれているとき雷に打たれて死ぬ。さらに、太陽がにわかに暗くなって、首都の14区全部に雷がおちる。」(『年代記(下)』第14巻 12 p183:岩波文庫33-408-3)「この年の終り頃、奇怪な現象が起る。近く不幸の訪れる前兆と取沙汰された。かつてなかったほどのひんぱんな落雷。そのたびにネロが名士の血しぶきでもって罪滅ぼしをしていた彗星の出現。頭の2つある赤子が路上に捨てられていたり、犠牲の中に(ある神々には孕んだ生贄を奉げることを習慣としたので)両頭の動物の胎児が発見される。さらにプラケンティア地方の街道筋では、頭が股の間についていたという仔牛が生れたりする。」(『年代記(下)』第15巻 47 p272:岩波文庫33-408-3)「さらに深く市民を不安の中に落し入れたのが、あちこちで発生し喧伝される奇怪な現象であった。カピトリウム神殿の前庭で、二輪戦車に立っている勝利の女神の手から馬の手綱がずれ落ちた。女神ユーノの内陣から人の姿より大きな幻影が飛び出した。ティベリス川の神君ユリウス・カエサルの像が、風のない晴れた日に西から東へ向きを変えた。エトルリアで牛が物を言った。いろいろの動物が奇形を生んだ。その他に、未開時代は無地平穏な時でも注目され、いまは不穏な時にしか噂されない現象も多く起った。しかし市民が現在と共に将来の破滅まで恐れた特別な異変は、ティベリス川の突然の氾濫であった。著しい増水で杭橋が崩壊し、その残骸の山に流れが塞ぎ止められ、両岸に溢れて首都の川岸に近い地域や低地帯ばかりでなく、それまでこのような水害から安全であった地域まで流れに浸った。路上から多くの人が攫れ、さらに多くの人が店舗や仕事場や寝台から不意に奪い去られた。大衆は日雇職がなく食料供給も不足し餓に苦しむ。水が澱み共同住宅の根底が腐り、水が引いたあと倒壊した。この恐怖から解放され人々が安堵した途端、オトが遠征の準備を始めた。マルス公園もフラミニア街道も、戦場へ向う道が塞っていたこと自体、市民は偶然とか自然の結果としてよりも、縁起の悪い兆しや目前に迫った凶事の前触れと受けとめた。」(『同時代史』第1巻 86 p61:筑摩書房)「ちょうどこの頃、カムロドゥヌムの勝利の女神像が、はっきりした原因もないのに、ぶっ倒れた。それも、まるで敵から退却したように、後に向けてひっくりかえったのだ。気違いじみた妄想にとりつかれた女らが「ローマ人の破滅が近いぞ」と触れ廻った。「カムロドゥヌムの義会場で、奇怪な叫び声がきかれた。劇場は金切声でこだました。タメサ河の河口附近で水面に、壊れたこの植民市の光景が反映した。さらに、北海は血の色に染り、潮のひいた海岸に、人間の骸をかたどった跡が残っている」と。こうした現象は、ブリタンニア人に吉兆と、老兵らに凶兆と解釈された。」(『年代記(下)』第14巻 32 p200~201:岩波文庫33-408-3)紀元61年)気になる方は、ぜひセネカとタキトゥスの書を読んで下さい。どうしてこの時期にだけこんなにも異常な現象が多く起きたのか不思議に思われるでしょう。しかし、このような異常現象が多く起きたのは、マタイ24章でユダヤ戦争の時期に再臨が起こると預言されているのと完全に調和しています。つまり、ユダヤ戦争の時期に再臨が起こることになったからこそ、その時期には多くの異常現象が起きたのです。マタイ24:30で言われている再臨も、既に起きています。何故なら、マタイ16:28とⅠテサロニケ4:15では、紀元1世紀の人たちが存命中に再臨が起こると言われているからです。神の言葉は至高の権威であって認識の前提にせねばならない聖なる啓示です。それを疑うことは許されません。また、マタイ24:31で言われている携挙も既に起こっています。何故なら、パウロは紀元1世紀のテサロニケ人たちが「生き残っている」(Ⅰテサロニケ4:16~17)時に携挙が起こると言ったからです。キリストも使徒たちも、再臨は「すぐに」起こると言いました。それは本当に再臨がすぐに起こることになっていたからです。これはマタイ24章の中で、再臨がユダヤ戦争の時期に起こると言われているのと調和しています。何故なら、ユダヤ戦争の時期に再臨が起こるのであれば、確かにキリストと使徒たちの時代において「すぐに」再臨が起こると言えるからです。ですから、もし再臨が2千年経過してもまだ起きないというのであれば、マタイ24章の中では再臨について預言されていなかったでしょう。繰り返しますが、マタイ24章とは「この時代」(γενεα=1世代=30~40年)(※マタイ24:34)に起こる出来事が預言されている箇所なのです。
【追伸3】
Ⅱテサロニケ2章も、再臨を正しく理解するためには考究すべきです。この箇所は、再臨が既に起きたことを私たちに示しています。パウロの記述によれば、不法の人はパウロの生きている時から既に「引き止める者」が「引き止めてい」(2:7)ました。パウロは2:7で言っています。「不法の秘密はすでに働いています。」お分かりでしょうか。不法の人は、パウロがテサロニケ人たちに第二の手紙を書いている時に存命していたのです。すなわち、不法の人とは紀元1世紀の人物です。それでは、それは一体誰だったのでしょうか。改革派の人間であればその名を知らぬ者はいないB・B・ウォーフィールドという聖書信仰の神学者は、<これはローマ皇帝ではないかと思われる>と註解書の中で述べています。これは当たっています。しかし、この神学者は、そのローマ皇帝が誰なのかということまでは明らかにしていません。では、そのローマ皇帝とは、実際誰なのでしょうか。それは、あの暴君ネロです。確かにパウロが語った不法の人の詳細は、ネロと完全に一致しています。2:4では、不法の人はあらゆる神の上に自分を高める、と言われています。ネロは実際そのような皇帝でした。彼は全ての神々を見下しており、ある女神像に小便をかけて貶したぐらいです。これについてプリニウスはこう書いています。「人間の幸運の絶頂に登ったことが、彼の邪悪な心の底に欲望を掻き立てた。彼の最大の欲求は神々に命令を下すことであった。彼はこれ以上高貴な野望を懐くことはできなかった。どんな他の術でも、これくらい熱狂的な後援者をもったものはなかった。」(『プリニウスの博物誌Ⅲ』第30巻5<14> p1244~1245:雄山閣)ここでプリニウスが「神々に命令を下すこと」と言っているのは、つまり神々の「上に自分を高く上げ」(2:4)るということでなくて何でしょうか。ネロの時代から幾らか後に生まれたローマ人である歴史家のスエトニウス(70頃―140頃)もネロについてこう言っています。「(ネロは)宗教はどの土地のものであれ、軽蔑した。ただ一つシュリアの女神の信仰は例外であった。しかしまもなくこの女神も、その像に小便をかけて穢すまでに、いやしめてしまった。」(『ローマ皇帝伝(下)』第6巻 ネロ p197:岩波文庫)ネロが「シュリアの女神」だけは信仰したが、その女神も後になって卑しめてしまったというのは、つまりあらゆる神々の「上に自分を高く上げ」たということに他なりません。またパウロは、不法の人が「神の宮の中に座を設け」(2:4)るとも言っています。ネロが、新約時代の神の宮である聖徒たち(Ⅰコリント3:16~17、Ⅱコリント6:16)を大いに迫害し蹂躙したのは、歴史が示している通りです。彼はアンティオコス4世がユダヤ人を蹂躙したように聖徒たちを蹂躙しました。それでは、不法の人であるネロが「引き止める者」の「取り除かれる時まで」(2:7)引き止められているというのは、どういう意味なのでしょうか。これは、クラウディウス帝が帝位に就いているのでネロが引き止められており、暴君としてまだ世の中に現われていないということです。パウロがテサロニケ人たちへの第二の手紙を書いている時には、まだネロの前の皇帝であるクラウディウスが帝位に就いていました。ですから、このクラウディウスが帝位から取り除かれない限り、ネロは聖徒たちを苦しめる暴君として世に姿を現わせないでいました。ですから、パウロはネロが暴君として現われるのはクラウディウス帝が生存している今はまだ起こらないでいる、と言ったわけです。このネロが再臨されたキリストにより殺されたのです(2:8)。その再臨の時には、地震と雷が起こると聖書は言っています(イザヤ29:6)。スエトニウスが書いているように、ネロが死ぬすぐ前の時には、確かに突発的な地震と雷が起きています(『ローマ皇帝伝(下)』第6巻 ネロ p189~194:岩波文庫)。そして、その地震と雷が起こると、もう間もなくネロは死んでしまいました。これは聖書の記述とまったく一致しています。ですから、確かにネロが死ぬその日にキリストは再臨されたことが分かるのです(2:8)。
◇この通知と勧めは1110のプロテスタント教会に伝えられた。
[用語辞典]
【666】
黙示録13:18で探るようにと言われているネロの名前に隠された邪悪さを示す数字。「ネロ・カエサル」というギリシャ語をヘブル語に訳し、そのヘブル語のアルファベットを一つ一つ数値化して合計するとこの数字になる。紀元1世紀の時代において、どれだけの人がこの数字をネロの名前から読み解けたかは不明である。ヨハネが黙示録を書いてから21世紀の今になるまでの期間で、邪悪な著名人のうち、その名前の中にこの数字が見いだせるのはネロ以外には存在しない。
【作品情報】
これは、キリストの再臨と再臨に関わる諸々の事柄を、聖書から徹底的に考究し解き明かすことが目的とされた作品である。神の御心であれば、再臨の真理は密やかに世に浸透していくことであろう。
[本書の教理について]
本書における目的の一つは、キリストの再臨が既に成就したということを聖書から証明することであるが、この教理を「再臨成就説」と呼ぶことにしたい。既存の再臨教理、すなわち再臨はまだ成就していないという教理は「再臨未成就説」とする。このように教理を命名する理由は2つ、すなわち「認識の強化また明白化」と「忘却の防止」である。教理というのは名前がなければ、なかなか頭の中に入ってこないものである。
[公開日]
2019年 6月 4日(火) : 公開
2019年 6月 7日(金) : 改訂
2019年 6月16日(日) : 改訂
2019年 7月 7日(日) : 改訂
2019年 7月10日(水) : 第二部公開
2019年 7月11日(木) : 一部訂正
2019年 7月21日(日) : 改訂
2019年 8月13日(火) : 改訂
2019年 9月17日(火) : 改訂
2019年 9月23日(月) : 改訂
2019年 9月28日(土) : 改訂
2019年10月02日(水) : 改訂
2019年10月06日(日) : 改訂
2019年10月29日(火) : 改訂
2019年11月30日(土) : 改訂
2020年 1月30日(木) : 改訂
2020年 2月 5日(水) : 改訂
2020年 2月23日(日) : 第三部公開
2020年 2月29日(土) : 改訂
2020年 3月 7日(土) : 改訂
2020年 3月12日(木) : 改訂
2020年 3月18日(水) : 改訂
2020年 4月 4日(土) : 改訂
2020年 5月 2日(土) : 改訂
2020年 5月 8日(金) : 改訂
2020年 5月19日(火) : 改訂
2020年 6月 3日(水) : 改訂
2020年 7月12日(日) : 改訂
2020年 9月 2日(水) : 改訂
2020年 9月12日(土) : 改訂
2020年10月19日(月) : 改訂
2020年11月13日(金) : 改訂
2020年12月30日(水) : 第四部公開
2022年 1月13日(木) : 改訂※この日以降、改訂箇所を以下に示すこととした
⇒3箇所増補(註解文書における増補箇所は下線と赤文字の部分)
■■■■■①■■■■■
【第3部 黙示録註解】【9:7】
『頭に金の冠のようなものを着け、』
『金の冠』とは、ローマの権力を表わしている。当時のローマは「世界の支配者」と呼ばれており(※)、ユダヤもこのローマに屈従させられていたのだから、ローマの権力が『金の冠』として象徴させられたのは実に適切であった。これは象徴としての言葉だから、実際にローマ軍の兵士が『金の冠』を頭に着けていたなどと空想してはいけない。そのような光景はなかなか面白いとは思えるが、実際にはあり得ないことである。
(※)
例えばアウグストゥス帝は、ローマ人に向かって「ああ、ローマ人よ、世界の主よ」(スエトニウス『ローマ皇帝伝(上)』第2巻 アウグストゥス p137:岩波文庫)と言い、大祭司アナノスもローマ人を「世界の主人である者たち」(『ユダヤ戦記2』Ⅳ iii10:178 p165:ちくま学芸文庫)と言い、共和制末期の護民官ガイウス・メンミウスも「ローマ人民、この敵に敗れたことのない全民族の支配者」(サルスティウス『ユグルタ戦争 カティリーナの陰謀』ユグルタ戦争(第31章)p60/岩波文庫 青499-1)と言ったが、これは何も誇張したり偽って言ったわけではない。世界の主人と呼ばれたこのローマの圧倒的な支配力については、ヨセフスの「ユダヤ戦記」2巻:xvi/4/345~401の箇所も参照すべきである。そこではアグリッパ王がユダヤ人の群衆に対して、ローマがいかに世界の諸民族をコントロールしているか簡潔に語っている。このアグリッパ王の言説は長すぎるので、ここで引用することはできない。ひとまず、ここではこの王が「太陽の下のほとんどすべての民族がローマの武力の前にひれ伏している」とその言説の中で語っているとだけ書いておけばよいであろう。
[本文に戻る]
■■■■■②■■■■■
【第4部 部分註解】第42章 40:マタイの福音書【24:10】
『また、そのときは、人々が大ぜいつまずき、互いに裏切り、憎み合います。』
これは、ネロによる大迫害が起きたからであった。その時、聖徒たちの多くは処刑されるために捕えられてしまった。誰に捕えられたのか。それは、ネロの命令によりやって来た役人や兵士たちに、である。この時、『人々が大ぜいつまず』いた。何故なら、処刑に対する恐れが精神を圧倒したからである。そのため、この時に真の信仰を持っていなかった者は、処刑への恐れが生じたので躓き、キリストを3度も否んだあのペテロのように無様な振る舞いを演じることになった。また、この時には人々が『互いに裏切り、憎み合』った。何故なら、捕えられ処刑場に連行されたら間違いなく死んでしまうので、多くの人が自分の命を守ろうとして逃げたり仲間を告発したり偽りの仮面を被ったりしたからである。マルコ13:13の箇所では、この時の悲惨についてこう言われている。『また兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち、彼らを死に至らせます。』日本における江戸幕府の元でキリシタン刈りが行なわれた時にも、このような状況が見られた。つまり、キリシタンである者が自分だけは助かろうとして幕府から遣わされた役人に対し自分はキリシタンではないと偽って言ったりして、キリシタンの仲間や家族を裏切ったのである。キリストがあらかじめこのように言われたのは、聖徒たちが事前にこれから起こるべき出来事を知ることで、心の準備を豊かにできるようにするためであった。未来の出来事を知っていれば、その出来事が起きた時、知らなかった場合よりも良い振る舞いができるようになるのは確かだからである。このことについては、キケロの『トゥスクルム荘対談集』第3巻で有益な学びが出来るから、気になった人は読むと良い。そこでキケロはこう言っている。「それゆえ、将来の悪を前もって考えておくことは、それが訪れた時の衝撃を和らげる。はるか以前から、やって来ることを準備しておけるからだ。」「悪とみなされる出来事は、突然であればあるほど悲惨なものになることは疑いない。予想外であることだけが苦悩を最大にする原因ではないものの、心づもりと準備は苦痛を和らげるために大いに役立つ。」(『キケロ―選集12 哲学Ⅴ』トゥスクルム荘対談集(第3巻)14:29、30 p179、180/岩波書店)このようなことのゆえ、神は聖徒たちへの配慮から、やがて起こるべき多くの悲惨な出来事を事前にキリストや使徒たちにより伝え知らせて下さったのである。
■■■■■③■■■■■
[聖書における数字の意味]
【33】――――清め(レビ記12:4)
【66】――――清め(レビ記12:5)
※「改訂」といっても、そのほとんどは、文章の強化、典拠の追加、書き忘れていた内容の挿入、資料の拡張といった大小様々な増補である。ここまで多くの改訂がされているのは、教義上の揺らぎ・不十分性に基づく根本的な修正をその理由としているのではないから、読者諸氏は安心していただきたい。本書の内容における教理面は、神の恵みにより、そのほとんどが既に盤石な状態にあるから、教理的な修正は細かい点を除けばほとんどされていない。
[作成期間]
第一部 : 2019年4月頃(?)~ 2019年 6月 4日
第二部 : 2019年6月 4日 ~ 2019年 7月10日
第三部 : 2019年7月10日 ~ 2020年 2月23日
第四部 : 2020年2月23日 ~ 2020年12月30日
[著者の紹介]
■著者名
稲野晴也
■居住地
静岡県静岡市駿河区小鹿
■信仰・神学
三位一体/信仰義認/二性一人格/6日創造説/前提主義/契約主義/反アルミニウス/二重予定説/全的堕落/限定的贖罪/不可抗的恩恵/聖徒の永遠堅持/反エキュメニズム/非バルト主義/反禁酒・反禁煙/特殊恩恵・一般恩恵/非神秘主義/反共産主義/神律主義/原罪/反スコラ/領域主権/反カトリシズム/反シオニズム/反テュービンゲン学派/再臨成就説/律法の三用法/二種陪餐/反人工妊娠中絶
■影響
ソロモン
アウグスティヌス
ルター
カルヴァン
■純粋に尊敬できる人
J・S・ミル
■好きな言葉
栄枯盛衰
「ゆっくり急げ」(古代ローマの格言)
■嫌いなもの
自由主義神学
進化論
無神論
同性愛/同性愛者―呪われた汚らわしいソドムの子たち
女性牧師―聖書否定の違法な牧師/パウロへの挑戦※
聖書に関する誤謬
※女性牧師のいる教会がある教派は、彼女らを辞めさせるべきである。教派ごとにそれぞれ都合や状況があるかもしれないが、なるべく早いうちにこの問題を処理しておいたほうがよい。私は聖書によって、またパウロと共に、このことをその教派のために勧告する(Ⅰコリント14:33~35、Ⅰテモテ2:11~12)。もしこの勧告を読んでも女性牧師を辞めさせないのであれば、その教派の未来は決して明るくない。何故なら、その教派は聖書に立っていないからである。牧師からして聖書に違反している教派が一体どうして祝福されるだろうか。
■私の耐え難い者
サルダナパロス
ヘリオガバルス
セルベトゥス
マルキ・ド・サド
■嫌いな著述家
◇ニーチェ ― 腐りきった反キリストである病的な狂気の哲学者
◇アレイスター・クロウリー ― 優れた知性の使い道を誤った邪悪な大魔術師
◇ジョージ・バークリー ― 思い違いをした徹底的な観念論者
◇アイリアノス ― 低能な剽窃野郎
◇マルキ・ド・サド ― 軽蔑すべき有害な腐敗物/悪魔の糞尿
■嫌いな著書
◇「愉しい学問」(ニーチェ)
◇「古代ユダヤ教」(マックス・ヴェーバー)
◇「動物奇譚集」(アイリアノス)
◇「人間の由来」(ダーウィン)
■現代の日本人が読んでおくべきだと個人的に感じられる書物
1. 聖書
2. 人間知性論(ジョン・ロック)
3. 人間知性新論(ライプニッツ)
4. 論理学体系(J・S・ミル)
5. 随想集(F・ベーコン)
6 自由論(J・S・ミル)
7. 感覚の分析(マッハ)
8. 人間本性論(ヒューム)
9 ローマ帝国衰亡史(エドワード・ギボン)
10.哲学史講義(ヘーゲル)
11.イノベーションと企業家精神(ピーター・ドラッカー)
12.認識の分析(マッハ)
13.国家活動の限界(フンボルト)
■聖書以外で重要かつ意義が高いと思われる書物または文書
1. 95か条の提題(ルター)
2. キリスト教綱要(カルヴァン)
3. 自然哲学の数学的緒原理(ニュートン)
4. 天球の回転について(コペルニクス)
5. 運動物体の電気力学について(アインシュタイン:1905年)
6. イリアスおよびオデュッセイア(ホメロス)
7. 国富論(アダム・スミス)
8. 法の精神(モンテスキュー)
9. 統治二論(ロック)
10.ドン・キホーテ(セルバンテス)
11.プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神(マックス・ウェーバー)
12.ローマ帝国衰亡史(エドワード・ギボン)
13.ルターの諸著作
14.聖書註解(カルヴァン)
15.アウグスティヌスの著書
16.原論(ユークリッド)
17.ジョン・フォン・ノイマンの諸論文
18.孫子の兵法(孫子)
19.論語
20.ユダヤ戦記(ヨセフス)
21.シェイクスピア作品
22.歴史(ヘロドトス)
23.歴史(トゥキディデス)
24.源氏物語(紫式部)
25.イソップ物語(イソップ)
26.概念記法(フレーゲ)
27.ガラテヤ書大講解(ルター)
※私が進化論者であれば間違いなくダーウィンの『種の起源』を上の中に入れていたであろう。
※プラトンおよびアリストテレスの著書は上の中に入れられない。この2人の著書は学問的・文化的には計り知れない影響を世界に及ぼしたが、それと同じぐらいキリスト教・教会にも悪い影響を及ぼしたからである。
※フーゴー・グロティウスの有名な『戦争と平和の法』も上の中に入れられない。この著書では自然律法に国際法を基づかせており、聖書からも多くの根拠を示してはいるものの、徹底的に聖書律法から規則の内容を構築しようとしているのではないからである。国際法も聖書律法に基づかせねばならないのは言うまでもない。
■今現在の理解において有害だと思われる書物または文書
1. シラ書およびソロモンの知恵
2. シオン賢者の議定書
3. タルムード
4. 種の起源(ダーウィン)
5. コーラン
6. 純粋理性批判(カント)
7. 銀河の世界(エドウィン・ハッブル)
8. 百科全書
9. ハリー・ポッター(J・K・ローリング)
10.反キリスト(ニーチェ―サタンの犬、ユダヤの仕掛け、毒、呪われた哲学者、気狂い)
11.古代ユダヤ教(マックス・ウェーバー)
12.ディオニシウス文書
13.アレイスター・クロウリーの著書―盲人、狂人、愚人、悪人、怪人、変人、死人、魔人
14.スティーヴン・ホーキングの著書
15.人間の由来(ダーウィン)
[連絡先]
mail@sbkcc.net